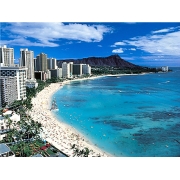PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
まだ登録されていません
カテゴリ: 「京」ものがたり
「ちょっと言いたくなる京都通」として奥深い京都の良さや
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
さて、今回は独特の世界観を持ち数多くの仏教美術を残した、
堂本印象画伯の作品を多く所蔵する
『京都府立堂本印象美術館』をご紹介いたします。
今回のテーマは
・外観も内観もインパクトがおますんえ。
・宗派を超えた信仰どす。
■ 外観も内観もインパクトがおますんえ。
京都の神社仏閣を訪ねていると、建築物、庭園などの美しさに出会うとともに、京都ならではの日本美術にも触れることができます。
今回ご紹介するのは、「京都府立堂本印象美術館」。
近代日本画家の大家、堂本印象画伯(1891年?1975年)は絵画、彫刻、スケッチなどを含め、生涯で数多くの作品を残しました。
こちらでは、その作品約2100点を所蔵しています。
生涯を通して多くの仏教美術も制作した堂本印象。
東寺・小子房や智積院・宸殿(しんでん)のふすま絵などが有名です。
以前、この京都通で東福寺を取り上げましたが、本堂のダイナミックな龍の天井画が印象の作品です。
また画伯制作による釘抜き地蔵のユニークなモニュメントもご紹介しました。
衣笠山を背景に、金閣寺、龍安寺、仁和寺へと続く「きぬかけの路」に、ひときわ斬新なたたずまいを見せているのが「京都府立堂本印象美術館」です。
1966年に開館したこちらの美術館は、堂本印象が構想に構想を重ねて、自ら外観・内観の全てをデザインしました。
エントランスの柱からドアノブまで画伯のデザイン。
ランプの傘やさりげなく置かれたイスも似かよっているようでいて、ひとつずつ異なるデザインが施されており、ディテールに至るまで印象のこだわりと情熱が伝わってきます。
目を引く外壁とエントランスの白い柱は、印象が構想段階の細やかなスケッチなどを描き残しており、いかに美術館の建築にエネルギーを費やしていたのかがうかがえます。
当時、画伯はすでに75歳でしたが、年齢を超越したパワフルな創造への意欲には驚かされます。
1952年に印象は初めて海外を訪れました。
約6ヶ月をかけてイタリア、西ドイツ、スペイン、フランス、スイスなどを遊学します。
風景のスケッチをする傍ら、あちこちのアトリエや美術館などを精力的に訪ねたそうです。
その時、強く受けたインスピレーションがこの美術館に表れています。海外遊学後、印象が一番変わった点は、彫刻、陶芸、染色への関心だそうです。
そこから、建築などの空間美術を手がけるようになり、平面から立体へと世界が広がったと考えられています。
■ 京都画壇の花形え。
堂本印象は、1891年(明治24年)京都市上京区の造り酒屋で生まれました。
敬虔な信仰心のある両親のもとで育ったと言われています。
同時に、父親は家業を営みながら、富岡鉄斎を始めとする芸術家たちとの親交もあり、歌、俳句、茶道、花道、書画、骨董などへ造詣の深い趣味人でもありました。
一方、母親は沢山の子どもを育てながら、いつも忙しく一生懸命、家業に明け暮れていたと言います。
これらの家庭環境、両親への想いは、印象の画家としての作風に強い影響を与えました。
印象が20歳の時に、父親はこの世を去り、その追想とも言える絵画を『故父』という作品で表しています。
また母親への想いを表すエピソードは数々ありますが、こちらの美術館の外壁のレリーフに、母を思わせる顔が刻んであるそうです。
美術館に設けられたスローブや一部バリアフリーな建築は、高齢であった母親を思いやる気持ちからだと言われています。
印象は、京都市立工芸学校を卒業後、西陣織の図案を描いていましたが、日本画を志すようになり、27歳で現在の京都市立芸術大学の前身である京都市立絵画専門学校に入学します。
1919年、28歳で第1回帝展に『深草』で初入選を果たしました。
それは決して早い方ではなく、遅咲きの大器でした。
その後、精力的に作品の創作に取り組み、第3回帝展では『調鞠図』で特選、第6回帝展では『華厳』で帝国美術院賞を次々と受賞。時代の寵児として一躍注目を集め、日本画壇において確固たる地位を築いてゆきます。
創作に加えて、絵画専門学校の教授として、また私塾東丘の主宰者としても多くの後進の育成に努め、1944年、上村松園らとともに帝室技芸員になりました。
印象の作風は、初期の頃からそのモチーフも描き方もインパクトがあるものでした。
日本画でありながら、どこか西欧風のモダンな雰囲気が感じられるのです。
『木華開耶媛』では、イタリアのボッティチェリを、『故父』や『坂』では、フランスのアンリ・ルソーを思わせると評されています。
これは、大正時代という、海外の趣味が取り入れられ始めた、独特のモダンな空気感が漂っていた時代背景と関連しているようです。
時代と共に少しずつ変化してゆくというより、奥行きが広がってゆく印象の作風。早い時期から仏教絵画を描き始め、「祈りの表現」は、多彩なテーマを持つ印象の大きなひとつの主題であり、生涯のライフワークとなります。
■ 宗派を超えた信仰どす。
多くの人がそうであったように、印象もまた、戦争を体験することでひとつのターニングポイントを迎えます。
戦後、戦争体験から生まれた悲しみや絶望、社会の混沌とした状況を絵で表現するようになりました。
1952年の海外遊学で印象の作風が大きく変わったと思われがちですが、実はそうではなく、戦後に少しずつ変化の兆しがありました。
助走段階であったその感覚を確認するかのように、海外へ渡った印象。
ヨーロッパで、日本とは全く違う風景や建物を懸命にスケッチしたと言われています。
そこでの感銘は深く、風土・芸術など多くのことを吸収したそうです。
帰国後、1953年にパリの地下鉄をモチーフに描いた作品『メトロ』を発表。
モダンな作品は油絵のような感じを受けますが、筆の線、立体表現は日本画の技法に徹底的にこだわっています。
日本画の画材でどこまでできるか、一種のチャレンジだったのでしょうか。
この『メトロ』を皮切りに様々な試みを始めたと言われています。
70歳にして発表した『交響』は、最も前衛的であると絶賛されました。
「日本画の枠を超えた自らの美への模索」が、この『交響』でした。従来の日本画では表現しきれない心象風景を新しい手法で表現したと言われています。
一方、ライフワークであった仏教絵画も意欲的に制作します。
若い頃から、仏教への造詣が深く、晩年に仏教をテーマにした作品を多く生み出しました。
印象にとって信仰とは、何かひとつの宗教というのではなく、宗派を超えたものでした。
「祈りの形」のひとつとして、教会のステンドグラスなども手がけています。
仏教を主題に描かれた、観音菩薩像、阿弥陀如来などをはじめ、寺院空間に放つ、ふすま絵や天井画なども数多く残しました。
1963年、高知市の五台山竹林寺書院のふすま絵を発表。
当時、この作品は大きな反響を呼び起こしました。
なぜならば、「風神」「雷神」「太平洋」「瀬戸内海」の4題24面からなるこのふすま絵は、日本画家による抽象画という、これまでには決してなかった作風だったのです。
日本画にとらわれず、また宗派を超えて、自由な感性で創作を続けた堂本印象。
その作品には多くのメッセージがこめられています。
伝統と革新、東洋と西洋、仏教とキリスト教…そして「祈りの形」。
日本の伝統がしみ込んだ芸術的感性の奥行きを一段と広げた印象ならではの世界観-…日本画壇に強烈な刺激を与え続けた偉大な存在であったことに改めて気づかされます。
こちらの美術館では、年間5回の企画展が行われます。
本来、一人の画家だけの作品でこれだけの企画展を開催するのは難しいことです。
印象が多彩であり色々な切り口を持っているからこそ、その多様性のある表現や様々な作品のプレゼンテーションが成り立ちます。
建物そのものが作品である「京都府立堂本印象美術館」で、印象の世界観を感じてみませんか。
※11月30(木)まで、特別企画展を開催中です。
「超『日本画』モダニズム -堂本印象・児玉希望・山口蓬春」
この機会にぜひ、ご来館してみませんか。
また、「土曜美術茶論(サロン)」では、学芸員やスペシャリストの興味深い話が聞けます。
11月18日(土)「戦争と美術---画家たちの戦争協力」
京都府立堂本印象美術館館長/立命館大学文学部長 木村一信さん
参加は自由ですので興味のある方は、詳細を美術館までお問い合わせください。
取材協力:京都府立堂本印象美術館
京都市北区平野上柳町26-3
電話 (075)463-0007
京都の人も知らない情報などをおりまぜながら、
わかりやすく紐解いていきたいと思います。
ぜひ身近に京都を感じてください。
さて、今回は独特の世界観を持ち数多くの仏教美術を残した、
堂本印象画伯の作品を多く所蔵する
『京都府立堂本印象美術館』をご紹介いたします。
今回のテーマは
・外観も内観もインパクトがおますんえ。
・宗派を超えた信仰どす。
■ 外観も内観もインパクトがおますんえ。
京都の神社仏閣を訪ねていると、建築物、庭園などの美しさに出会うとともに、京都ならではの日本美術にも触れることができます。
今回ご紹介するのは、「京都府立堂本印象美術館」。
近代日本画家の大家、堂本印象画伯(1891年?1975年)は絵画、彫刻、スケッチなどを含め、生涯で数多くの作品を残しました。
こちらでは、その作品約2100点を所蔵しています。
生涯を通して多くの仏教美術も制作した堂本印象。
東寺・小子房や智積院・宸殿(しんでん)のふすま絵などが有名です。
以前、この京都通で東福寺を取り上げましたが、本堂のダイナミックな龍の天井画が印象の作品です。
また画伯制作による釘抜き地蔵のユニークなモニュメントもご紹介しました。
衣笠山を背景に、金閣寺、龍安寺、仁和寺へと続く「きぬかけの路」に、ひときわ斬新なたたずまいを見せているのが「京都府立堂本印象美術館」です。
1966年に開館したこちらの美術館は、堂本印象が構想に構想を重ねて、自ら外観・内観の全てをデザインしました。
エントランスの柱からドアノブまで画伯のデザイン。
ランプの傘やさりげなく置かれたイスも似かよっているようでいて、ひとつずつ異なるデザインが施されており、ディテールに至るまで印象のこだわりと情熱が伝わってきます。
目を引く外壁とエントランスの白い柱は、印象が構想段階の細やかなスケッチなどを描き残しており、いかに美術館の建築にエネルギーを費やしていたのかがうかがえます。
当時、画伯はすでに75歳でしたが、年齢を超越したパワフルな創造への意欲には驚かされます。
1952年に印象は初めて海外を訪れました。
約6ヶ月をかけてイタリア、西ドイツ、スペイン、フランス、スイスなどを遊学します。
風景のスケッチをする傍ら、あちこちのアトリエや美術館などを精力的に訪ねたそうです。
その時、強く受けたインスピレーションがこの美術館に表れています。海外遊学後、印象が一番変わった点は、彫刻、陶芸、染色への関心だそうです。
そこから、建築などの空間美術を手がけるようになり、平面から立体へと世界が広がったと考えられています。
■ 京都画壇の花形え。
堂本印象は、1891年(明治24年)京都市上京区の造り酒屋で生まれました。
敬虔な信仰心のある両親のもとで育ったと言われています。
同時に、父親は家業を営みながら、富岡鉄斎を始めとする芸術家たちとの親交もあり、歌、俳句、茶道、花道、書画、骨董などへ造詣の深い趣味人でもありました。
一方、母親は沢山の子どもを育てながら、いつも忙しく一生懸命、家業に明け暮れていたと言います。
これらの家庭環境、両親への想いは、印象の画家としての作風に強い影響を与えました。
印象が20歳の時に、父親はこの世を去り、その追想とも言える絵画を『故父』という作品で表しています。
また母親への想いを表すエピソードは数々ありますが、こちらの美術館の外壁のレリーフに、母を思わせる顔が刻んであるそうです。
美術館に設けられたスローブや一部バリアフリーな建築は、高齢であった母親を思いやる気持ちからだと言われています。
印象は、京都市立工芸学校を卒業後、西陣織の図案を描いていましたが、日本画を志すようになり、27歳で現在の京都市立芸術大学の前身である京都市立絵画専門学校に入学します。
1919年、28歳で第1回帝展に『深草』で初入選を果たしました。
それは決して早い方ではなく、遅咲きの大器でした。
その後、精力的に作品の創作に取り組み、第3回帝展では『調鞠図』で特選、第6回帝展では『華厳』で帝国美術院賞を次々と受賞。時代の寵児として一躍注目を集め、日本画壇において確固たる地位を築いてゆきます。
創作に加えて、絵画専門学校の教授として、また私塾東丘の主宰者としても多くの後進の育成に努め、1944年、上村松園らとともに帝室技芸員になりました。
印象の作風は、初期の頃からそのモチーフも描き方もインパクトがあるものでした。
日本画でありながら、どこか西欧風のモダンな雰囲気が感じられるのです。
『木華開耶媛』では、イタリアのボッティチェリを、『故父』や『坂』では、フランスのアンリ・ルソーを思わせると評されています。
これは、大正時代という、海外の趣味が取り入れられ始めた、独特のモダンな空気感が漂っていた時代背景と関連しているようです。
時代と共に少しずつ変化してゆくというより、奥行きが広がってゆく印象の作風。早い時期から仏教絵画を描き始め、「祈りの表現」は、多彩なテーマを持つ印象の大きなひとつの主題であり、生涯のライフワークとなります。
■ 宗派を超えた信仰どす。
多くの人がそうであったように、印象もまた、戦争を体験することでひとつのターニングポイントを迎えます。
戦後、戦争体験から生まれた悲しみや絶望、社会の混沌とした状況を絵で表現するようになりました。
1952年の海外遊学で印象の作風が大きく変わったと思われがちですが、実はそうではなく、戦後に少しずつ変化の兆しがありました。
助走段階であったその感覚を確認するかのように、海外へ渡った印象。
ヨーロッパで、日本とは全く違う風景や建物を懸命にスケッチしたと言われています。
そこでの感銘は深く、風土・芸術など多くのことを吸収したそうです。
帰国後、1953年にパリの地下鉄をモチーフに描いた作品『メトロ』を発表。
モダンな作品は油絵のような感じを受けますが、筆の線、立体表現は日本画の技法に徹底的にこだわっています。
日本画の画材でどこまでできるか、一種のチャレンジだったのでしょうか。
この『メトロ』を皮切りに様々な試みを始めたと言われています。
70歳にして発表した『交響』は、最も前衛的であると絶賛されました。
「日本画の枠を超えた自らの美への模索」が、この『交響』でした。従来の日本画では表現しきれない心象風景を新しい手法で表現したと言われています。
一方、ライフワークであった仏教絵画も意欲的に制作します。
若い頃から、仏教への造詣が深く、晩年に仏教をテーマにした作品を多く生み出しました。
印象にとって信仰とは、何かひとつの宗教というのではなく、宗派を超えたものでした。
「祈りの形」のひとつとして、教会のステンドグラスなども手がけています。
仏教を主題に描かれた、観音菩薩像、阿弥陀如来などをはじめ、寺院空間に放つ、ふすま絵や天井画なども数多く残しました。
1963年、高知市の五台山竹林寺書院のふすま絵を発表。
当時、この作品は大きな反響を呼び起こしました。
なぜならば、「風神」「雷神」「太平洋」「瀬戸内海」の4題24面からなるこのふすま絵は、日本画家による抽象画という、これまでには決してなかった作風だったのです。
日本画にとらわれず、また宗派を超えて、自由な感性で創作を続けた堂本印象。
その作品には多くのメッセージがこめられています。
伝統と革新、東洋と西洋、仏教とキリスト教…そして「祈りの形」。
日本の伝統がしみ込んだ芸術的感性の奥行きを一段と広げた印象ならではの世界観-…日本画壇に強烈な刺激を与え続けた偉大な存在であったことに改めて気づかされます。
こちらの美術館では、年間5回の企画展が行われます。
本来、一人の画家だけの作品でこれだけの企画展を開催するのは難しいことです。
印象が多彩であり色々な切り口を持っているからこそ、その多様性のある表現や様々な作品のプレゼンテーションが成り立ちます。
建物そのものが作品である「京都府立堂本印象美術館」で、印象の世界観を感じてみませんか。
※11月30(木)まで、特別企画展を開催中です。
「超『日本画』モダニズム -堂本印象・児玉希望・山口蓬春」
この機会にぜひ、ご来館してみませんか。
また、「土曜美術茶論(サロン)」では、学芸員やスペシャリストの興味深い話が聞けます。
11月18日(土)「戦争と美術---画家たちの戦争協力」
京都府立堂本印象美術館館長/立命館大学文学部長 木村一信さん
参加は自由ですので興味のある方は、詳細を美術館までお問い合わせください。
取材協力:京都府立堂本印象美術館
京都市北区平野上柳町26-3
電話 (075)463-0007
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[「京」ものがたり] カテゴリの最新記事
-
★「京都の祭・時代祭り」 2025.10.22
-
★「五山の送り火」 2025.08.16
-
★祇園祭 毎年7月1日… 2025.07.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.