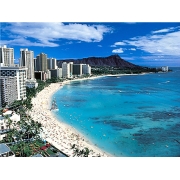PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
今日は「土用の丑」の日です。
夏バテ予防の代名詞「うなぎ」
江戸時代に花開いたうなぎ料理の歴史
香ばしい匂いが食欲をそそる夏のスタミナ源、うなぎ。
奈良時代に編纂された「万葉集」にも夏バテの予防食として登場する程、その効用は古くから知られていました。実際、うなぎには疲労回復に効くとされているビタミンやたんぱく質が豊富に含まれており、厳しい暑さを乗り切るには最適な食材なのです。
土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代に始まったといわれています。その起源には諸説ありますが、最も有名なのは、発明家としても名を馳せた蘭学者・平賀源内を仕掛け人とする説だ。近所のうなぎ屋から「夏場は客が少なくて困っている」との相談を受け、源内が「本日、土用の丑の日」と書いた紙を店先に張り出すように助言したところ店は大繁盛。他のうなぎ屋も真似をしたことで、「土用の丑と言えばうなぎ」と言う意識が定着したと言います
ちなみに土用と言いますと、立春・立夏・立秋・立冬前のおよそ18日間のこと。12日周期で割り当てられる十二支の「丑」に当たるのが「土用の丑の日」となるが、立秋前の夏の土用(7月20日頃〜8 月6日頃)は二十四節気の大暑に重なるため、身体によいものを食べて精をつける風習があった。さらに、土用の丑の日に「う」のつく食べ物を食すと夏バテしないという俗信もあり、平賀源内もこれにヒントを得たようだ。
うなぎ料理の代表格である蒲焼きが初めて文献に登場したのは、室町時代に京都で書かれた「鈴鹿記」だとされている。当時は丸々一匹またはぶつ切りにしたうなぎを串に刺して焼き、塩や酢みそなどをつけて食べていたようで、その姿形が植物の蒲の穂に似ていたことから「蒲焼き」と呼ばれるようになったとの説もある。
うなぎの蒲焼きが今のようなスタイルになったのは、江戸時代後期。濃口醤油やみりんの普及に合わせて甘辛のタレをつけて焼く調理法が生まれた。うなぎを割いてから焼くようになったのはこの頃で関東では背中から、関西では腹から開く方法が定着した。
一説では、武士の町江戸では腹びらきは切腹に通じると背開きに、商人の町上方では腹を割って話せるように腹びらきとなった、といわれている。
さらに、関東ではうなぎの頭を落とし、一度素焼きしてから蒸してタレをつけて焼くのに対し、頭をつけたまま串を打ち、タレをつけて焼く。そのため関東のかば焼きは、ふっくら柔らかめ、関西はパリッと香ばしく仕上がるのが特徴です。
国産うなぎの危機 !!!
日本人が愛してやまないうなぎ。
国内にはニホンウナギとオキナワウナギの二種類が生息しているが食用として出回っているのはニホンウナギで、その 99 %が養殖物が占めている。農林水産省の統計によると、現在養殖うなぎの生産量は鹿児島県が最も多く、次いで愛知県、宮崎県、静岡県の順となっている。
ニホンウナギは西太平洋のマリアナ諸島付近で生まれ、黒潮に乗って日本沿岸に来遊するその後、シラスウナギと呼ばれる稚魚に変態し、冬になると河川を遡上、上流で成長したうなぎは、産卵の時期が近づくと再び海へと下っていく。うなぎの養殖では河口付近でとれた天然のシラスウナギを種苗としているが、環境汚染や乱獲などによってその数は年々減少し、価格が高騰。近年はうなぎ料理が高根の花になってしまったのはこうした事情によるものだ。 一方で、環境省や国際自然保護連合によってニホンウナギが絶減危惧種に指定されるなど、資源保護への取り組みも進んでいる。
この日ばかりは少し奮発して、うなぎ料理で英気を養いたいものですね。
-
立 冬(りっとう) 2025.11.07
-
霜 降(そうこう) 2025.10.23
-
寒 露(か ん ろ) 2025.10.08