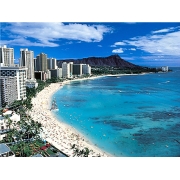PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
今日は節分です、節分とは雑節のひとつで、立春の前日で、旧暦の年の暮れ、年頭にあたります。
豆まきは、中国から伝わった「 追難
」の儀式に由来。旧暦大晦日に宮中で行われる「 鬼遣
い」の儀式として始まりました。これが現代の豆まきの元になった行事です。
「まめ」は魔目。鬼の目をめがけて豆を打ちます。
「焼い嗅がし」は柊の小枝に焼いた鰯の頭を刺した魔除け。鰯の悪臭が鬼を寄せつけないと考えられていました。他には大蒜や葱、焼いた髪の毛を吊るす地方もあります。
節分は冬季か春季かの正解は冬季。しかし、翌日が立春だから、すでに春の匂いの濃い冬季といえる。
この辺の事情をみごとに語っているのが、芝居好きならお馴染みの 河竹黙阿
弥
(文化 13
〜明治 26
〈 1816
〜 92
›)快心の歌舞伎狂言『 三人吉三
廓
初買
』
の「 大川端
庚申塚
の場」のお嬢吉三の 名科白
だろう。
月も 朧
に白魚の 篝
も 霞
む春の空、つめてえ風もほろ酔いに 心持
よくうかうかと、
浮かれ 烏
のたゞ一羽 塒
へ帰る川端で、 棹
の 雫
か 濡
手
で泡、思いがけなく手に入る百両。
ほんに今夜は節分か、西の海より川のなか落ちた 夜
鷹
は厄落とし、 豆
沢山
に 一文
の 銭
と
違って 金包
み、こいつあ春から 延喜
がいヽわえ。
止めの「春から延喜(=縁起)がいゝ」の春は翌朝からとも夜のうちからとも受け取れる。
本来節分とは文字どおり季節の分かれ目の意味で、立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前日をさし、したがって一年に四回あった。平安後期、摂政藤原道長の栄華を中心に書かれた歴史物語『栄華物語』峰の月に「秋の節分にいと 疾
く入りぬべければとて、 七月
三日内
に帰らせ 給
」とあります。
旧暦七月三日だから、「秋の節分」とは云うものの、正確には立秋前日すなわち夏の最後の日なのだ。
「三人吉三」のお嬢吉三は直後、登場したお坊吉三にゆすられて女から男に変身、ここには八百屋お七のパロディーということを含めて、冬が春に変身することと重ねた趣向もあるのかもしれません。
今回は昨今話題の恵方巻についてもちょっと触れておきたいと思います。
恵方巻の由来や起源とは?
毎年、 2
月に入るとスーパーには数多くの恵方巻きが並びますが、子供のころから食べているという方も少なくないでしょう。恵方巻きを食べる文化は、現在は日本全国で知られており、節分の習慣の一つとなりつつあります。ここでは、恵方巻きの由来や起源について見ていきましょう。
★起源や由来
恵方巻きを食べる起源は、江戸時代から明治時代に始まったといわれています。商売繁盛や節分をお祝いすることが恵方巻きを食べる目的であり、芸子や商人たちが食べていたようです。
当時は、恵方巻きではなく、「太巻き寿司」や「丸かぶり寿司」と呼ばれることが多く、「七福」にかけて「 7
つの具」を入れて食べていました。しかし近年になるまで、この習慣は日本の中でも一部の地域のものだったといわれています。
1989
年に、某コンビニエンスストアが節分に食べる太巻き寿司の販売を開始しました。広島県で恵方巻きと名付けられたことが、今日の呼び名の由来とされています。それから、一気に恵方巻きが広がり、コンビニ以外のスーパーやデパートでの販売が開始されました。
★ 1
本まるごと食べる理由
今では、全国で地域性豊かな恵方巻きが食べられていますが、なぜ 1
本まるごと食べるのでしょうか。食べやすい大きさにカットして、家族と一緒に分けあいながら食べたのでは、いけないのでしょうか。
1
口サイズにカットすることなく 1
本まるごと食べる理由は、商売繁盛や幸福を一気にいただくという意味合いが大きいそうです。「一気に食べなければ運を逃してしまう」ということから、その年の幸運を手に入れるために、無言で 1
本まるごと食べていたようです。
恵方巻きが全国に広がったきっかけは、これを取り扱うコンビニやスーパーの影響が大きいのですが、「 1
本まるごと食べる習慣」は、それ以前からずっと続いていたのですね。
★食べ方のルール
恵方巻きには、食べ方のルールがあります。ここで、昔から大切にされているルールについて確認していきます。
◆
ルール 1
:恵方巻きの本数は、家族の人数分用意する。
◆
ルール 2
:今年の恵方を確認する。
◆
ルール 3
:恵方の方角を向き、願い事を考えながら無言で恵方巻きを食べる。
◆
ルール 4
:途中でカットすることなく、そのまま一気に食べていく。
これらのルールを守ると、自分の願い事が叶うといわれています。しかし、恵方巻きを家族分用意するというのは、非常に大変だと思います。お子さんに、大きな恵方巻きを用意しても食べきることはできないでしょう。その場合は、小さい海苔を購入して、細く短いコンパクトな恵方巻きを作ると、最後まで余すことなく食べられると思います。
★食べるタイミング
恵方巻きは、いつでも食べれば良いというわけではありません。もちろん、食べるタイミングがあります。毎年、節分である 2 月 3 日に恵方巻きを食べます。尚、方角は、その年の恵方です。その年によって、恵方の方角や日付が変わるため、毎年チェックする必要があります。
なお、節分は、立春の前日のことで、冬と春の分かれ目を意味しています。そして、節分はずっと 2 月 3 日というイメージがありますが、実はその年によって変わります。
例えば、 2025 年は、立春が 2 月 3 日なので、節分の日は 2 月 2 日になります。
そのほか「太巻き・細牧」「恵方巻と巻きづ氏の違い」等々いろいろとございますが永くなりますので、それらはまたの機会に譲ります。
最後にご参考マテに、今年の恵方は「西南西」です。
-
立 冬(りっとう) 2025.11.07
-
霜 降(そうこう) 2025.10.23
-
寒 露(か ん ろ) 2025.10.08