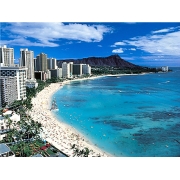PR
キーワードサーチ
カレンダー
フリーページ
HAWAII 情報いろいろ是非覗いて見て下さい

「ALOHAの起源」

「覚えておきたいハワイ語講座」

「ハワイの花 プルメリア」

「ハワイのアンティークショップ」

「Coconut Palm」

「火の女神ペレ」

「ハワイの神話」

「サワーサップ」

「心と体を癒やすヒーリング」

「ハワイ島3つの砂浜」

「マウナケア天文台」

「カメハメハ1世のお話」

ハワイの定番「アロハシャツ」

ハワイの定番「アロハシャツ」No.2

ハワイのレイについて(No.1)

ハワイのレイについて(No.2)

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」

メイド・イン・ハワイ「ウクレレ」No.2

ハワイアン・ミュージック

フラの起源と歴史

ハワイの花「ピカケ」

オアフの聖なる湾 Hanauma Bay ハナウマ湾

ダイヤモンド・ヘッド(ハワイ州自然記念公園)

「ハワイの島々の地形や地質について」

ハワイの自然で暮らす様々な動物たち

ハワイ観は三つのキーワードで

ハワイの風景が見える音楽〜 アロハ・オエ

ハワイの教え~与える人
オアフ島の癒やしの写真集
HAWAIIの基礎知識

HAWAIIの簡単歴史

ハワイの神話

ハワイ版創世記

「HAWAIIの基本情報-1」

「HAWAIIの基本情報-2」

「HAWAIIの基本情報-3」

ハワイの歴史のはじまり
コメント新着
★夏バテ予防の代名詞「うなぎ」
今日 7
月 30
日は今年の夏の「土用の丑の日」です。
・江戸時代に花開いたうなぎ料理の歴史
立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前18日間を土用と言います。
現代では、夏の土用を「土用の丑」と捉え、表現されていることが多いです。
そして、この立秋前の夏の土用、この期間が一年の中で最も暑く、暑い時期を乗り切るために栄養価が高く、体に精のつくものを食べる習慣があります。
鰻を食べるという風習について、色々な説がありますが、中でもよく知られているのは、江戸時代に平賀源内が「土用の丑の日に〝う〟のつく〝鰻〟を食べるとよい」と鰻屋の宣伝に一役買ったことにより広まったと言う説です。 そのほかにも諸説あるようです。
この夏負けしないように精のつくものを食べるという考え方は、和菓子では土用餅という餡餅があり、暑気あたりをしないよう、やはりこの期間に食べられたということです。お餅は力餅、小豆は厄除けに通じるということから、土用餅を食べると暑さに負けず無病息災で過ごせると言われています。
土用には、そのほかしじみや卵を食べたり、慣わしとして、「虫干し」や「丑湯」の風習があるといいます。
土用の虫干しとは、梅雨で湿った室内調度などに風をあてて、陰干しします。
丑湯は土用の丑の日に薬草を入れたお風呂に入ることで、疲労回復と無病息災を祈ります。
暑い日本の夏を乗り切るさまざまな知恵が風習として、今も生きているのです。
★ 関西・関東 鰻の蒲焼 調理方法の違いとは
土用の丑の日に食べられる鰻ですが、関西と関東では、調理方法が異なります。
一般的に、関西の蒲焼は鰻の腹から包丁を入れる〝腹開き〟をし、頭と尾をつけたまま串を打ち、身の方から白焼きにして照りがつくまでタレをつけながら焼きます。
対して、関東の蒲焼は鰻を〝背開き〟にして頭と尾を切り取り、2つ切りにして串を刺し、両面を白焼きにした後に蒸し、最後にタレをつけながら焼きます。
関東の鰻の焼き方は、蒸すことによって脂肪分が抜けてさっぱりとした味わいになり、皮や肉も柔らかくなります。
<鰻の裂き方>
この関東で〝背開き〟にする理由は、鰻を腹から割くことが、武士社会であった江戸では切腹という行為につながり好まれなかったと言われ、一方、商人の町関西は〝腹を割って話す〟気風であり、〝腹開き〟になったと言われています。
<蒸す・蒸さない>
関西風は蒸すことなく焼き上げることによって、表面はこんがりと、中身はジューシーに。
脂が香ばしく焼けた香りと、じゅわっと口の中に広がる鰻の脂を楽しめます。
関東風は蒸すステップが加わることで、柔らかくふんわりとし、箸ですっと切れるような仕上がりになります。
口の中で、ふわっとする柔らかさでさっぱりといただけます。

-
立 冬(りっとう) 2025.11.07
-
霜 降(そうこう) 2025.10.23
-
寒 露(か ん ろ) 2025.10.08