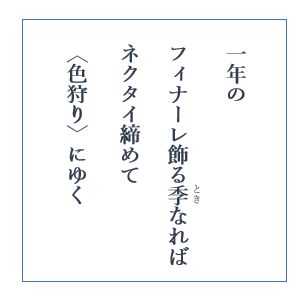2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2011年08月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
浴衣会
今年も、京都で浴衣会に参加することができました。私には貴重な経験です。今を去ること数年前に、名前(芸名)だけいただいて、外国に逃げかえっていた”もらい逃げ名取”のワタクシは、なんと、御流儀の浴衣さえ持っていなかったのです。で、今年は、御流儀の浴衣を一枚ぐらい欲しいなあと思っていたら、なんと、師匠が”ちょうどいただいたものがあるから”と、真新しい”おさがり”を下さいました。(T_T) それを、今日は、ありがたく着させていただきました。子供が寝てから、ちょこちょことお浚いしていた「岸の柳」。今回は、芸者の立ち方を随分直していただき、少しはそれらしくなったのか...。(-_-)曲と間だけはは、しっかり頭に入っていた、というか、マッスルメモリーで、半分寝てても身体が動いているハズ.....だったのですが、さて、前に出て、テープが鳴りだすと、「あり.....?!」 これ、いつものとバージョンが違う。ミュージシャンが違う。当然、間が違う。いつもネバるところが、さささっと進んだり、その逆だったり。そんな、違うテープなんて、聞いてませんぞ。違うバージョンで、いきなり本番ですか?!!! 私は、曲を裏から表まぜ一音一音全部憶えてフリを憶える、という習慣がついていまして、また、地方さんの生演奏なんてのも、経験もないのです。かなり動揺しました。なんじゃ、こりゃ。と、少なくとも最初は相当慌てました。曲に乗らねば...と思いつつ、つかめない。「え、ここまだ延びるの」「え、ここもう次いくの」。曲に乗る余裕がありません。後半、動揺にも少し慣れ、なんとか無事(?)終わりました。優しいお稽古場のおばさま方は、「え、そうやったん? 全然そんな風にはみえなかったけど」などとおっしゃって下さいましたが、でも、うらめしやー。せめて、一度ぐらいこのバージョンで通しておきたかった。これは、師匠がたまたまいつものテープがなくて、「ま、これでいいか」と、持ってこられたのか、それとも、“親心”による故意のイケズ(イジワルともいう)か...。どちらもあり得る。いや、後者は自意識過剰か。師匠に直接聞く勇気はありませんです。「先生、唄が違いました(ひくひく...)」「うフフ...違いましね。同じ唄ですよ。うフフ..」だけで終わりました。いずれにしろ、いい経験になりました。ありがたいことです。(いや、ほんとにそう思っている.....と思う..)
2011年08月26日
コメント(2)
-

お祭シーズン その後の復習
まず、昨日の日曜日の話から。盆踊りにいってまいりました。でも、盆踊りといっても、なんと花街、上七軒の盆踊りでございます。だから、普通の”地域のお祭”とは、ちょっと雰囲気が違います。出店なども、ちょっとでてました。ヨーヨー釣りとボールすくいが一つずつ。この街の人っぽい兄さん達が、商売抜きの値段でやらせてくれました。雰囲気作りのためでしょうね。食べ物だと、せいぜい、わらび餅。たこ焼きや、焼きトウモロコシなんてのは、ありません。だから、臭いもしません。また、格子のついた、それっぽいお店の前で、お姐さんが冷たい飲み物を売っていて、緋もうせんのかかった床几の上で飲ます、という、品のいいもんです。”看板娘”みたいに、舞妓さんも立ってたりします。京都の花街にはいっぱいいる、”舞妓さんおっかけカメラマン”もいっぱいいるけど、そういう人は、始まったばかりの明るいうちにほとんど帰ってしまうので、薄暗くなりかけたころは、上七軒の玄人さん達に混じって、誰でも踊れるという、なかなかの機会です。独特の雰囲気がありますしね。で、時はさかのぼり、先週の日曜日。まず、朝、南座での舞踊会に出かけたら、四条通りを祇園祭の花笠巡行と子供御輿が通るところでした。そして、夕方からは幼稚園の夏祭。部屋に戻ると、ちょうど、これまた祇園祭の還幸祭の御神輿が神泉苑に向かうところ。で、私は、御神輿とは逆方向。舞踊会の最後の長~い演目に間に合うように南座へとってかえしました。で、舞踊会が終わってでてくると、なんと、ちょうどその御神輿達がかえってくるところ。還幸祭の御稚児さん達も、馬で石段下にむかうところ。宵の宮や山鉾巡行と違って観光客は少ないので、よくみえます。そのまま八坂神社までついていきたいところだけど、ガマンして帰りました。で、さらに遡り先々週の日曜日。巡行の日です。今年は週末に巡行だったので、人出の多さについては、言わずもがな。炎天下の中、先頭の長刀鉾をみるのは、相当の覚悟が必要です。でも、最後の北観音山が帰っていくところについていきました。このころになると、群衆の数も、多いとはいえ、まあ、なんとかいけます。で、その残っている群衆のなか、なにしろ最後の最後なので、新町通りに入る最後の辻回しの辺りから、たいへん盛り上がりました。御囃子も、四条通りを通るときの粛々とした調子と違い、テンポも速いですしね。かけ声も、最後の盛り上がり。会所に帰ってきたところで、見物人も一緒に全員で手打ちが。シャシャシャシャシャン結局、「おまけ」「念のため」が入って、4回ぐらいやったかな。で、上から兄さん達が、飾りの笹を投げて、それを下の群衆がとりあいっこします。縁起ものなんでしょうね。最後は、兄さんが自分の茅巻まで投げたりして、いい雰囲気でした。すぐ後で、近所のおばあさんが「ああ、無事に終わってよかった。よかった。」と。祇園祭は、最大の京都観光イベントだけど、基本的にはここの町衆のお祭ですものね。京都の暑い夏は、まだまだ続きます。
2011年08月01日
コメント(4)
全2件 (2件中 1-2件目)
1