2015年03月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

種ショウガ 保存成功
2月5日の日記で紹介した種ショウガの保存法、あれから2ヵ月近くが経った現在、どうやら成功したと言えそうだ。現在の姿はこちら。 昨年の10月24日に収穫したショウガは、5か月の時を経て水分が飛んでシワシワになっていて、部分的に腐ったりカビが生えたりしたものがあるが、完全に腐ったものは1つもない。で、実はこの画像の右半分が昨年の新ショウガ、左半分が「昨年の種ショウガ」なのだ。前々から興味があったのは、前年の種ショウガが果たして翌年も種ショウガとして使えるのかということ。この様子だと、問題なく使えそうだ。 ちなみに、品種は赤生姜である。珍しい品種だけに種ショウガもちょっとお高め。それだけに、保存のし甲斐があるというものだ。さあ、今年も豊作を目指そう。表皮が赤くなる生姜。冷え性にも効果的!【赤生姜】【種生姜】【ショウガ】【赤ショウガ】【アカ...価格:810円(税込、送料別)
2015.03.31
コメント(0)
-

モモ ボンファイヤー 開花 2015
矮性桃のボンファイヤーが開花した。前回開花を紹介したのは昨年4月6日の日記でのこと。が、昨年はカイガラムシが幹にびっしり付いて壊滅的な被害を受けてしまい、衰弱してしまった。いちおう2月から3月にかけてマシン油乳剤を2回散布はしたが、すでにカイガラムシに侵された枝は大半が枯れてしまった。 というわけで、今年は枝の大半が枯れ込んだために、非常にみすぼらしい姿になったのが残念。ただ、マシン油乳剤を散布してカイガラムシそのものはほとんど駆除できているはずなので、今年の生育に期待したい。 それから、例の実生2代目だが、前回は3本発芽と紹介したが、実は落下して腐った果実から採取した種子があと1個発芽に成功していて、合計で4本の実生苗がある。いずれも濃く赤い葉を展開している。今後、それぞれの個体差がどのように現れるのかが興味深い。上手く結実までこぎつけたら、食味の良い個体を選抜してみたい。親のボンファイヤーは、2013年に収穫した実を3個食べた限りでは、果実が小さく糖度がやや物足りない。 ところでこのボンファイヤー、国内で初めて売り出されたときは「ボナンザ紫葉」と、あたかもボナンザピーチの赤葉種であるかのような品種名で売られていた。が、ボナンザピーチと同時に育ててみた限りでは、別系統の品種のようだ。花も、ボナンザピーチは八重咲きだが、ボナンザ紫葉ことボンファイヤーは一重咲きである。ちなみに下の画像は3月21日にも登場したボナンザピーチである。 で、ずっと気になっていたのがボンファイヤーの由来。もしかして外国由来の品種かと思いきや、意外な事実が判明。英語で検索したところ、アメリカのサイトがヒットした。それによると、何と「筑波2号」という、日本で接木の台木用に育成された品種の自然交雑実生が由来だという。種子が採取されたのが1984年、播種されたのが翌年1985年、そして1988年にこの個体が選抜されたのだとか。実生が行われたのが日本なのかアメリカなのか定かではないが、ともかく意外だった。 さらにそのボンファイヤーの親の「筑波2号」がどういう品種なのか調べたところ、「赤芽」×「寿星桃ピンク一重」の実生から選抜されたもので、食用モモの矮化台木として使用されるらしい。寿星桃とは、極矮性のハナモモで、ピンク一重のほかに赤、ピンク、白、咲き分けの八重咲き品種がある。そうかあ、ボンファイヤーにはハナモモの血が入っていたわけか。どおりで果実が小さくて甘くないわけだ(笑)。 そして、現在育てているボンファイヤーの2代目は、今のところ4本とも矮性で葉が赤い。筑波2号から数えて3代目になるこの実生苗、それぞれ形質の違いがどのように現れるのか、ますます興味深くなってきた。あと、昨年の春に川中島白桃にボンファイヤーを交配し、収穫した種子を4個庭に埋めておいたはずだが、現在のところ発芽が確認できていない。大丈夫か?
2015.03.29
コメント(0)
-

Bc. Princess Patricia 'Falstaff' 開花 2015
1919年に登録された古典的名花、Bc. Princess Patricia 'Falstaff'(Bc. プリンセス・パトリシア ’ファルスタッフ’)が今年も開花した。昨年の4月16日以来2回目の登場。今回は2花茎3輪咲きである。が、前回も今回も窮屈な貸温室の中での開花で、きれいに咲いてくれなかったのがちと残念。。。 毎年、晩秋から春にかけて、手持ちのランを貸温室に預けるのだが、狭い場所に多くの株をギュウギュウに詰め込むものだから、この時期にカトレアをきれいに咲かせるのが一苦労だ。花が他の株に接触しないように位置を変えたりするのだが、1鉢移動させるだけでも至難の業で(笑)、鉢を移動するどころか方向を回転させるだけでも四苦八苦する(笑)。 で、このプリンセス・パトリシア、6号鉢に植わっていてバルブが鉢から飛び出すほどの大株になっていて、鉢を移動するのが困難だったため、その窮屈な体勢のまま開花させたのがこの花。来年こそは伸び伸びと咲かせてこの個体の実力を発揮させたいところだが、これ以上大株にするのが困難なので、今年は株分けせざるを得なくなりそうだ。本領を発揮できるのはいつの日か。。。
2015.03.22
コメント(0)
-

モモ ボナンザピーチ 開花
モモの矮性品種、ボナンザ・ピーチが開花した。私が小学生の頃から興味を持っていた品種で、ようやく入手したのは一昨年の秋にこと。今まで他のモモの品種を紹介した時にボナンザの名前を出したことがあったが、単独でこの品種をブログで紹介するのは初めて。この品種は節と節の間が極めて短く、背丈が高くならないのが特徴。2013年7月28日に紹介した「ボンファイヤー」(ボナンザ紫葉)よりもさらに節と節の間が短く小型になるようだ。昨年は1個だけ結実したのだが、収穫時期を逃して実が落下してしまった。。。 で、今年こそはしっかり収穫してのそのお味を賞味したいと思っていたのだが、開花したのはわずかに5輪。軒下のやや日当たりの悪いところに植えていることと、カイガラムシにやられたことが原因ではないかと見ている。また、例の川中島白桃と交配し、もっと実が甘い矮性品種が作出できないものかと思っていたのだが、開花のタイミングが見事にずれてしまい(笑)、交配が不可能になってしまった。現在、ボナンザピーチ、ボンファイヤー、川中島白桃、白秋、倉方早生を栽培している中では、ボナンザが最も開花が早かった。しかし、昨年は確かボナンザとボンファイヤーと川中島白桃が同時に開花したと記憶している。ともかく、ボナンザの5輪咲いたうちの1個でも結実してくれるといいのだが。。。
2015.03.21
コメント(0)
-

Bc. Amabilis 'Inter' 開花 2015
往年のカトレア交配種の中でも初期に登録された品種、Bc. Amabilis 'Inter'(Bc. アマビリス ’インター’)が開花した。昨年の11月7日に続いて2回目の登場。前回紹介した時の花は、実際には5月31日に撮影したもの。前回は自然の温度下で伸び伸びと咲いてくれたが、今回は窮屈な貸温室の中での開花なので、ちょっと今一つな咲き映え。 画像では花が小さく見えるが、実物は案外大きい。そして甘い香りもある。この品種(個体)は、開花時期がいつなのか今一つ良く分からない。もしかして不定期咲きなのかもしれない。株そのものは大きくなってきているので、また今年の初夏の自然の温度条件で開花してくれるといいが。
2015.03.14
コメント(0)
-
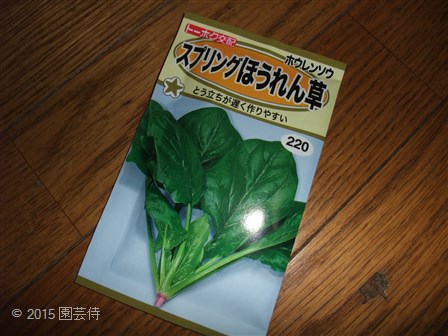
スプリングほうれん草に挑戦
2月8日に紹介した日本ホウレンソウ、播種時期が遅くて大きくならなかった上に、ヒヨドリの食害に遭ってしまったため、すべて処分することにした。ちょっともったいないが、これ以上ヒヨドリの腹を肥やさせるわけにはいかないので、収穫できないものは潔く処分した方が良い。今年の秋はもう少し早く種子を蒔いてみたいと思う。 で、春も近づいてきた今日この頃、今度はホウレンソウの別の品種に挑戦しようと思い、選んだのがトーホク交配の「スプリングほうれん草」だ。その名の通り、バネのように伸び縮みするという、非常に珍しい品種だ。・・・違うがな(笑)。その名の通り、春蒔き専用の品種である。 ホウレンソウは一般に長日性が強く、日が長いととうが立ってしまう。また、日が短い季節でも、街灯に反応してとうが立つことがある。それぐらい日長に敏感なので、春に蒔くには春蒔き専用の品種でなければならない。今まで、ホウレンソウを春蒔きで育てたことがないので、どんな風に育つか楽しみだ。この品種は西洋ホウレンソウの系統と思われる。私はホウレンソウでは日本ホウレンソウが一番好きなのだが、これは春に蒔くととうが立ってしまう。誰か春蒔きしてもとうが立たない日本ホウレンソウを育種してくれないだろうか?
2015.03.10
コメント(0)
-

フクジュソウ 開花 2015
自宅アパートの北側の庭に植えておいたフクジュソウが開花した。品種名は「福寿海」である。昨年の3月23日に続いて2回目の登場。 早春の寒々とした庭に、この黄色い花はよく目立つ。前回ブログに紹介した、成田から転居するときに移植してきたフクジュソウは、現在のところその存在が確認できていない。枯れてしまったのか、それともただ単に今年は開花しないだけなのか? 今回咲いたものは、昨年の1月に購入して植えておいたもの。で、実は今年の1月にも、さらにもう1株植えていて、それも開花している。 フクジュソウは、お正月の寄せ植えの素材として園芸店やホームセンターに出回るが、活着させるのがちょっと難しい。もともと、フクジュソウの根は長くて量も多いのだが、寄せ植えではそれを極端に切り詰めているために、根が弱っていて枯れてしまうことが多い。なので、こんなデリケートなものを寄せ植えに使ってもすぐ枯れてしまうはずなので、お正月というおめでたい場には、むしろ縁起が悪いような気もするのだが・・・。また、暑さと乾燥に非常に弱いため、夏越しに失敗することが多い。ちなみに、フクジュソウは早春の開花の後に葉を茂らせるが、梅雨時の6月頃には早くも地上部が枯れ、長い休眠期に入ってしまう。つまり、葉を茂らせている時期が短いため、いかにこの時期に良い環境を作るかがカギとなる。 現在フクジュソウが植わっている場所のそばにはアジサイが植わっているため、夏はうまい具合に日陰になってくれる。今年も上手く夏を越して来年もまた開花してくれるのを楽しみにしている。
2015.03.08
コメント(0)
-

C. lueddemanniana 'Stanleyi' FCC/RHS 開花
セミアルバのカトレア原種、C. lueddemanniana 'Stanleyi' FCC/RHS(C. ルデマニアナ ’スタンレー’)が開花した。2年前に購入したオリジナル株で、ブログでは初登場。2花茎3輪咲き。 小さな小さな分け株を購入しての初花なので、あまりきれいに咲いてはいないが、確かに紛れもなく’スタンレー’の花だ。私がこの個体の存在を知ったのは1990年(平成2年)前後に発売された某洋蘭雑誌だった。まさに原種のルデマニアナをそのままセミアルバにした個体で、20世紀初頭にはすでに知られていた個体だとか。私はその本に載っている写真にほれ込んでしまい、いつか欲しいと思っていた。 ちょうどその頃だったと思うが、国内でこの’スタンレー’のメリクロン苗が出回り始めた。しかし、洋蘭業者のカタログに載っている写真と洋蘭雑誌で見た写真がどうも違うことに違和感を持っていた。また、間もなく花の実物を見る機会があったが、やはり本で見たそれとは違うような気がしていた。後で判明したことだが、メリクロンの’スタンレー’はアメリカから入ってきたもので、どうやら偽物だということ。また、'Cerro Verde'(’セロ・ベルデ’)という個体に酷似しているため、メリクロンの’スタンレー’は’セロ・ベルデ’と同一個体だと言われているのは趣味家なら周知の通り。また、本来のルデマニアナの開花期は春なのに対し、メリクロンのスタンレー=セロ・ベルデ?は開花期が夏であることから、趣味家の間では、ワーセウィッチーとの交配種ではないかとも言われている。 で、本物のスタンレーなのだが、実は10年ほど前に趣味家の方から小さな小さなオリジナル分け株と称するものを入手したことがある。ところがこの株、私の育て方が悪いのか、なかなか大きくなってくれない。私は、ルデマニアナは木が大きくなると思っていたので、その分け株が本当に本物なのか疑いの目で見るようになってしまった(譲ってくれた方、申し訳ない。。。)。そして数年ほど育てたが、一向に大きくなる様子がなく、栽培面積に限りがあるため、処分してしまった。 そして2年前、とある洋蘭業者に置かれているのを発見。そこの社長さんに、それが間違いなく本物のスタンレーであるということを確認し、大枚はたいて購入した。それから2年、生育が遅いものの徐々に大きくはなっているが、まだまだミニカトレアサイズ。開花するまで何年かかるのだろうと思いきや、今年の2月ごろから小さなシースの中につぼみが上がっているのを発見。しかも、リードが2本あり、その両方につぼみが上がっている。ルデマニアナはこんなに小さな株に花が付くのか? もしやまた偽物? と、疑心暗鬼になっていたところ、めでたく開花し、本物であることを確認できた。 これが株全体の画像だが、非常に小さな株に開花しているのが分かる。そう、あの時趣味家の方から譲ってもらった小さな株はやはり本物だったのだ。「短気は損気」とはこのことだわ。。。私はルデマニアナのスタンレーがこんな小さな株だとは知らなかったのだ。そう言えば、15年ほど前だったが、ルデマニアナの小さな実生苗を開花させたことがあり、その時もこれぐらいのサイズで大きな花が咲いた。というわけで、やっと手に入れた本物の’スタンレー’、大株に仕立ててもっと良い花を咲かせてみたい。
2015.03.07
コメント(0)
-

意外と強い!?ナゴランの耐寒性
私はナゴラン(名護蘭)を2鉢育てている。いずれも昨年2月の東京ドームの世界らん展で購入したもの。おそらく実生苗と思われ、価格も1鉢800円と野生ランとしてはお手頃。で、2鉢買ったのは、実は耐寒テストをしてみたかったからというのもある。神奈川県内陸部でナゴランは屋外越冬が可能なのか? ナゴランは日本原産とはいえ南方系のランなので、寒さには弱いとされる。ただ、なんとなく直感的に、少しずつ寒さに慣らせば屋外で越冬できるのではないかと思い、アパートの北側に面した軒下にセッコク、フウランと共に置いておいた。水やりはかなり控えめ。昨年の晩秋から数えるほどしかやっていない。ただし、風向きによっては自然の雨が当たる場所である。厳寒期は葉にしわが入るほどに水やりを控えたが、寒さも峠を越えた現在、実に生き生きとした姿をしている。 ご覧の通り、ほとんど葉に傷みが見られない。これなら初夏の開花も期待できそうだ。今回、屋外で越冬できたのは、軒下の雨風がしのげる場所に置いていたからであって、霜が降りる吹きさらしの場所ではこうはいかないはずだ。今後も大事に育てて大株にして楽しみたい。
2015.03.03
コメント(4)
-
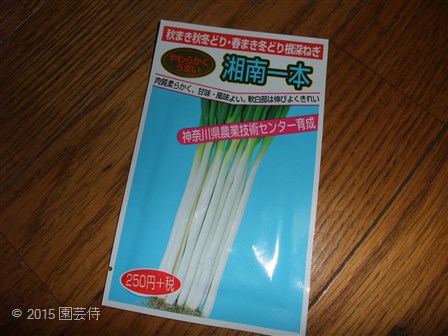
ネギ「湘南一本」に挑戦
2006年(平成18年)にブログを開始して以来、毎年下仁田ネギを栽培するのが恒例となっていた。昨年の秋にも種子を蒔いて苗を育てるはずだったのが、実は今回は失敗してしまった(笑)。種子を蒔いたのは10月だったが、もともと種子が古くて発芽率が低かったうえに、発芽直後にネキリムシの被害を受けてしまい、急遽蒔き直すことに。しかし、播種時期が遅かったがために、苗が大きくならないままに冬を迎え、霜柱で苗が浮き上がってしまって壊滅状態となった(笑)。 で、今年の下仁田ネギはあきらめて何か違うものに挑戦しようと思い、選んだ品種が神奈川県のご当地品種の「湘南一本」である。私はかつて平塚市に住んでいたが、平塚市は実は根深ネギの産地でもあり、平塚市北部にはネギ畑が多い。いつか私も根深ネギに挑戦したいと思っていたが、下仁田ネギに比べて場所が必要なため、なかなか栽培する機会がなかった。この機会に湘南一本の宣伝も兼ねて?ブログで紹介することにした。なお、私は回し者ではない(笑)。
2015.03.01
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 花のある暮らし・・・
- 小菊・ユーチューブで誤送信ラインの…
- (2025-11-25 11:00:16)
-
-
-

- 花のある暮らし、宿根草
- またガーベラが咲いています。
- (2025-11-23 14:37:34)
-
-
-

- バラがすき!
- Florence Delattre フローレンス・デ…
- (2025-11-25 06:41:54)
-






