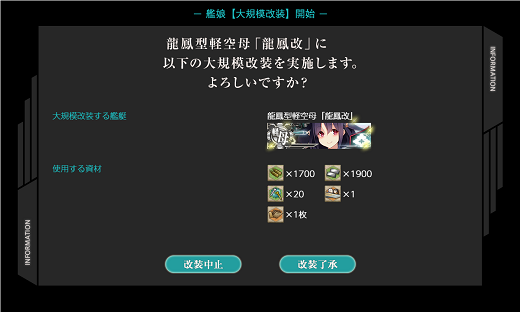2011年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

岡本太郎展 東京国立近代美術館
万博の太陽の塔が岡本太郎の作品だと知ったのは、学生の頃だろうか。ロバート・ブラウンのグラスが、我が家にあったことを思い出す。そして、やはり強烈な印象が残っているのは、日立マクセルのビデオテープのCMだ。あの「芸術は爆発だ!」という言葉がが一世を風靡した。しかし、肝心の岡本太郎の絵画には、当時はほとんど出会うことが無く、著作も読んだことが無かった。リアルタイムで岡本太郎を知りながら、今回の展覧会、そして地震で中断中のNHKドラマ「TAROの塔」で、はじめて岡本太郎という人物の人となりを知ったのである。再開した近代美術館は、常設展は公開されておらず、1階の岡本太郎展のみの公開となっていた。それでも、多くのギャラリーで展示会場はあふれかえっていた。みんなアートに飢えていたのだろうか。芸術はうまくあってはならない。きれいであってはならない。心地よくあってはならない。と唱えた岡本太郎だが、多くの作品は、見ていて楽しい。作品によっては、楽しいという表現は、不謹慎といわれるものもあるのかもしれないが、それぞれの画面からは、無意識のうちに身体を震わせる太鼓の響きのような、色彩と形が感じられるのである。オブジェにいたっては、まさに自由奔放。伸びやかでユーモアにもあふれ、子ども達に優しい。そういえば、我が家の近くの公園にも岡本太郎のオブジェが置かれていた。今回の展覧会でのいちばんは、「痛ましき腕」だ。この人物は男性か女性か。赤いリボンと髪の毛からは女性だとも思えるのだが、筋骨隆々とした腕は男性のもの。悲嘆にくれているのか、怒りに身を震わせているのか。会場を出ると海洋堂のガチャガチャ。後で開けてみると、座ることを拒否する椅子の2点セットだった。
2011年03月20日
コメント(2)
-
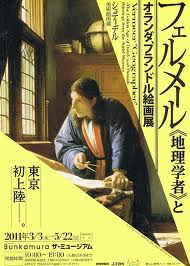
フェルメール《地理学者》とオランダ・フランドル絵画展
最初に展示されている「音楽で動物を魅了するオルフェウス」から目が釘付けになってしまう。象がいて駱駝がいて馬がいて虎がいて・・・深い森の中でオルフェウスが竪琴を弾くそばに、多くの動物が集まっている。この幻想的なシーンに心を奪われた。同じ趣向の「楽園でのエヴァの創造」もステキ!あとは、オランダ・フランドル絵画では、おなじみの細やかな静物画や、人々の暮らしを描いた風俗画。そして深い森、都市や海を描いた風景画などそれぞれに見所のある作品ばかり。フェルメールの「地理学者」には、唸ってしまう。フェルメールの定番、室内に差し込む光の表現の見事さ。地理学者の着ている服が、日本の着物だとは驚き。この地「理学者」の前だけは、柵があって接近して見ることはできないのだが、さほどの混雑ではなく、最前列でじっくり見ることができた。「地理学者」以外にも、すばらしい絵が多く、十二分に楽しむことができた。
2011年03月05日
コメント(4)
-

鏑木清方と東西の美人画 そごう美術館
昨年、サントリー美術館の「清方ノスタルジア」で、清方の魅力を満喫したのだが、今回も清方の「道成寺・鷺娘」「妖魚」「刺青の女」など鬼気迫る作品に圧倒される。この絵をコレクションした福富太郎が最初に清方と出会った「薄雪」の切なさ。見れば見るほど、知れば知るほど、清方の魅力にはまる。驚いたのは菊池容斎の「塩谷高貞妻出浴之図」である。1842年の作。この時代の伝統的な日本画で、このようなヌードがあったことをはじめて知った。山川秀峰の「春雨の宵」、小早川清の「唐人お吉」もいい絵だ。「西の美人画」の中では、島成園の描く「おんな」は、怖い。能面の柄の着物を着た黒髪をとかす。鬼気迫る目つき。甲斐庄楠音の「横櫛」は、いつもの楠音らしくない清楚な美人画に見えたのだが、よく見ると目つきが普通ではない。楕円形の瞳がどこを見つめているのか分からず、不気味である。近代美人画の魅力にますます惹かれていく。
2011年03月04日
コメント(2)
-
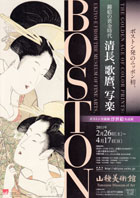
ボストン美術館 浮世絵名品展 山種美術館
錦絵の黄金時代と銘打って、清長、歌麿、写楽の3人の名品をメインにした展覧会。山種の狭い会場にどれだけ展示できるのかと思ったのだが、140枚の浮世絵がぎっしりと展示されており、見応えも十二分で、まったく文句なし。開館前に出かけたのだが、美術館を出たのは12時をまわっていた。第1章は鳥居清長。まずは、「仲之町の牡丹」がオープニングを飾る。江戸のヴィーナス、八頭身美人の三枚続き。咲き誇る牡丹見物に来た女性たち。美しい色彩は元より、中央の女性の着物の白地のから摺りまで、しっかりと味わう。その他、晩の「美の巨人たち」で特集された「美南見十二候」の三月・九月。また「雛形若菜の初模様」や「子宝五節遊」。そして役者絵など、次々と美しい浮世絵が登場。今回のいちばんの見どころは、歌麿でも写楽でもなく、この清長であると思う。第2章は喜多川歌麿。清長の健康的な美人像に比べると、歌麿のそれは、秘められた感情が感じられるとはよく言われる。何年か浮世絵を見てきて、ようやくこのあたりのことが分かるようになったが、まだまだ歌麿が描く難波屋おきた、高島おひさ、富本豊ひなの違いが認識できない。ボストンの歌麿は、紫や藍色、黄色、朱色などきれいに残っていて、目を見張る絵が多い。「金魚」の紫色の着物、「夏衣装当世美人 伊豆蔵仕入のもやう向き」のピンクなど見とれてしまうほど美しい色が残る。この時代の遊女の着物は、着物の絵柄に人工的なオブジェをつけているのが、清長や歌麿の絵を見て分かった。第3章は東洲斎写楽。役者絵は、美人画に比べるとテンションが下がるので、写楽の大首絵以外はあまり興味が沸かない。大首絵の「宮城野」とか「けはい坂の少将、実はしのぶ」など正面から見ると背景の雲母もはげているが、絵の下にしゃがんでみると照明に反射して、背景が一面に光り輝き、人物が浮き上がって見える。これが雲母刷りの魅力。後の北尾重政の摺物でもこの方法で金銀に光り輝く絵を楽しんだ。春信ファンとしては、春信の作品が一枚も無いのは少々残念であったが、それはそれ。鮮やかな色彩が残る浮世絵が次々と現われ、興奮しっぱなしの展覧会であった。
2011年03月01日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1