2022年10月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
ブラジル大統領選決選投票
ブラジル大統領選、ルラ元大統領が決選投票で勝利30日に行われたブラジル大統領選挙の決選投票で、左派のルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバ元大統領が勝利した。開票率98%超の時点でルラ氏は50.83%の票を獲得して接戦を制した。現職のジャイル・ボルソナーロ大統領の得票率は49.17%だった。今月2日に行われた1回目の投票では両氏とも過半数を獲得できなかった。政策が大きく異なる両氏の一騎打ちは、実質的な国民投票となっていた。今回の選挙の有権者は約1億5600万人。---この週末は他にも大きなニュースがありますが、先に第1回投票について記事を書いたので、最終結果についても記事を書くことにしました。第1回投票では、事前予測で決選投票を待たずにルーラ当選の可能性(第1回で得票率5割を超える候補者がいれば当選、いない場合は上位2名の決選投票となります)も取り沙汰されていましたが、蓋を開けたら意外な接戦で、ボルソナロ大統領が予測よりかなり支持を伸ばしており、米国のトランプ当選時と同様に、選挙予測の精度が問題視されました。ただ、予測よりは僅差だったとはいえ、ルーラが首位であり、それも得票率48.5%で、過半数まであと一歩、という状態だったことから、決選投票もルーラが多分勝つだろうとは踏んでいました。とはいえ、絶対ということはないのでどうなるかと思いましたが、ともかくルーラが勝利したことにホッとしています。もっとも、ルーラの決選投票での得票率は第1回投票から2ポイント余の上積みなので、支持を表明していた3位と4位の候補者の票の取り込みは、あまりできなかったということになります。一方、ボルソナロ大統領は第1回投票から6ポイントほどの上積みに成功しています。前回の記事で、「決選投票でボルソナロに流れそうな支持票は、第1回投票ですでに流れてしまっているので、もうこれ以上流れる票はほとんどないでしょう。」と書いたのですが、この見通しは少々甘かったようです。ボルソナロ票の上積み部分は、3位・4位の支持票と考えるのが妥当だと思われます。第1回投票より決選投票の方が投票率※は0.4%上がっていますが、それだけでは6%分の上積みにはならないので。※ブラジルは投票が義務とされており、病気など正当な理由なく棄権すると罰金が科せられます。が、その割には投票率は100%近いわけではなく、今回の大統領選の投票率は第1回が79.05%、決選投票が79.42%となっています。もちろん、日本の投票率よりはずっと高いですが。ともかく、ボルソナロという南米のトランプが政権を降りることは喜ばしいことです。ルーラは、2002年から2010年まで2期大統領を務めており、今回が3期目となります。かつての急進的労働組合指導者の姿はもはやなく、穏健な中道左派政治家ですが、政治的手腕には問題なくボルソナロが捻じ曲げた政策の修正を図っていくことになるでしょう。
2022.10.31
コメント(0)
-

第2回AYNIコンサート
2年半ほど前に、AYNI春を呼ぶコンサートが開催されましたが開催されました。今回、その第2回が開催されたので見に行きました。前回の記事を書いた際、あまり大っぴらに書いていいのかどうか分からなかったので、コンサートが開かれるに至った経緯等は書かなかったのですが、実は日本を代表するケーナ奏者である福田一弘さんが大きな病気をされたため、なんとか励まそうという趣旨で行われたものでした。それから2年半、長い闘病生活の末、どうにか寛解となって、福田さんがフォルクローレの世界に戻ってきました。正直なところ、病名を聞いたときには厳しいなと思ったし、手術していったん治った後、再発して再手術という話を聞いたときは、今度こそは、と半ば覚悟したのですが、よく戻ってきてくださいました。というわけで、前回のコンサートは「主役」は抜きだったのですが、今回は主役の入った、本当に素晴らしいコンサートになりました。なお、遅刻して行ったので、最初のグループだけ写真を撮っていません。福田さんが主宰されているケーナ教室の演奏だったと思います。ルセリート先々週一緒に演奏しました。今日はメンバー1人欠場でしたが。アルトゥーラ結成44年と言っていたかな。リーダーの長田さんの演奏を、多分30年ぶりくらいに聞いたように思います。グルーポ・マニャーナ、秩父を中心に活動しているグループです。福田さんが登場!福田さんと言えばケーナですが、ギターも上手いんです。ただ、やはり長い闘病生活のためか、少しパワーが落ちたかなという気はします。名古屋から参加のチャスカ+福田さん+イリチさん。私がサンポーニャの音で「この人にはかなわない」と思う人が日本で(プロを除いて)二人いまして、その一人がゆなさん。今日もバキバキとサンポーニャ吹いてました。マリネーラ・ミ・アルマペルー海岸地方の踊り。この時はマリネーラではなく、トンデーロだったかな。キント・スーヨペルー山岳地帯の踊りリベラル・ラティン・コンパニオンズ私がサンポーニャの音で「かなわない」と思う(プロを除く)日本人のもう一人が、左端の彼なのです。ちなみに、チャランゴの名手でもあり、ハーディガーディ奏者でもあったり。ラス・パキータスここで初めて、私が知らないグループが登場しました!ただし、グループとして知らないだけで、メンバーは全員知り合いですけど。ミスティフォルクローレ、あるいはアンデス音楽、コンドルは飛んでいくと言えば、世間一般的にはペルーの印象が強いですが、実際には世界的に知られているアンデスのフォルクローレ音楽は基本的にボリビアのスタイルです。私が演奏しているのも、ほぼボリビアとアルゼンチンです。正統的なペルースタイルの演奏するグループは数少なく、ミスティは日本におけるペルー音楽の第一人者です。福田さんと言えばミスティというのが私のイメージ。そして、このグループには福田さんのケーナとみゆくまさんのボーカルという2枚の看板がある、凄いグループなのです。UKS前回は3人でしたがUさんが急逝されてお二人になってしまいました。アコ・イ・チミチュリ福田さんまた登場。福田さんのケーナはもちろん、アコさんの歌が素晴らしかったです。お子さんを連れてのステージでした。ロス・アピオネス2週間前に一緒に演奏しました。こちらも1970年代から続く超ベテランです。チョコ&サエミによるマリネーラ・ノルテーニャマリネラ・ミ・アルマ+チョコ&サエミによるマリネーラ・ノルテーニャダイジート・イ・ホセ+福田さん福田大治さんとホセ犬伏さんのデュオに福田さんが参加したのでW福田になりました。ロス・ボラーチョス名は体を表す。Tシャツには生ビールのイラストが印刷されていました。グループ名は「酔っ払い」の意味です。平均年齢70歳だそうです。サボール・アンターニョここでも福田さん登場。ボンボ奏者(さる大学の研究者)は1年間ボリビアに滞在中だそうで、助っ人のボンボ奏者が小林さん。直接お会いしたのは何年ぶりでしょうか。20年は経っているかな。イリチ・イ・ポクラトリを飾ったのはイリチ・モンテシーノスさんと福田さんのデュオ素晴らしかったです。福田さん、だいぶ回復されました。ちょっと音がかすれているかな、というところは何か所かありましたけど、全般的にすごくよかったです。吸い込まれるような素晴らしいビブラートが帰ってきた、音に酔いしれました。福田さんケーナの音はどんなものか、今から10年前、もちろん発病前の演奏動画がYouTubeに上がっています。
2022.10.30
コメント(0)
-
思い当たるところはある
不登校、いじめとも過去最多 コロナ影響か 文科省、21年度調査文部科学省は27日、全国の学校を対象に2021年度実施した「問題行動・不登校調査」の結果を公表した。病気や経済的理由などとは異なる要因で30日以上登校せず「不登校」と判断された小中学生は24万4940人、小中高と特別支援学校のいじめの認知件数は61万5351件で、ともに過去最多だった。文科省は、新型コロナウイルス禍による行動制限などで、人間関係や生活環境が変化したことが影響したとみており、「心のケアを中心とした早期の対策が必要だ」としている。~不登校と判断された小中の児童生徒数は9年連続で増えた。今回の増え幅は特に顕著で、過去最多だった前年度から24・9%増加した。一方、高校の不登校は18・4%増の5万985人だが、過去10年でみるとほぼ横ばいで推移している。小中の不登校の主な要因で最多なのが「無気力、不安」(49.7%)で、「生活リズムの乱れ、遊び、非行」(11.7%)、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」(9.7%)が続いた。小中学校で1000人当たりの不登校の児童生徒数は平均25・7人となり、都道府県でばらつきもあった。~不登校とは別に病気や経済的理由などによる長期欠席者数も調べた。コロナの感染回避を理由に登校を控えた小中学生は、初集計だった前年度の約3倍となる5万9316人となった。いじめの認知件数は全校種合わせ61万5351件で、新型コロナによる影響などで大幅減少した前年度の51万7163件から一転し過去最多になった。(以下略)---これは、色々と思い当たる節があります。うちの子が、高校生でもろにコロナ禍の影響を受けました。うちの子は、中学から高校1年にかけてはそれほど問題なく登校しており、特に高校生活は非常に楽しそうな様子でした。ところが、2020年2月末に、都内の高校は臨時休校となり、それが5月まで続きました。この臨時休校は、明らかに子どもの生活リズムを乱しました。後日、子どもが自分で「あのときはヤバいと思った」と言っていましたが、毎日自宅にこもるだけの日々は、生活リズムを乱すばかりだったのです。途中、家族旅行で九州に行ったのですが、それがなかったら、どうなっていたかと思います。結局、5月に授業が再開されて以降も(しばらくは分散授業で登校が一日おきだったり半日だったりした)、リズムは完全には元に戻らず、やや休みがちな高校生活になってしまいました。不登校の定義に入るようなレベルではなく、進級や卒業にも問題はありませんでしたが(そして、高校では学校生活自体は楽しそうだったので、そこまで深刻な問題ではありませんでしたが)ちょっと気になったことは確かです。コロナによる緊急事態宣言や外出「自粛」は、あの時点での判断としてはやむを得ないものだったと思いますが、学校の休校はあまりに長すぎたと言わざるを得ません。うちの子のような例は多かったのではないかと思いますし、中には不登校の範疇にいたる場合も少なくなかったことは容易に推察できます。その影響は、多かれ少なかれ、今後に残っていくのではないかと思ってしまいます。あちらを立てればこちらが立たず、不登校の解消とコロナ対策は両立し難い面はあります。2020年3月頃の状況では、学校の休校やむを得ない部分はあったと思いますが、緊急事態宣言と比しても休校は早すぎたし、終了も遅すぎました。子どもにとっての学校は、決して不要でも不急でもありませんから。思えば、うちの子は充実した高校生活と呼べるものは1年弱だけで、あとの2年あまりは不自由だらけの高校生活でした。修学旅行はなし、文化祭は1年の時だけ、体育祭は学年別の「分散開催」だったとか。部活もコロナ以降は大幅に制約があったようです。これらはうちの子だけに限ったことではありませんし、小学生から大学生までの全児童生徒学生が同じ状況だったわけですが、人生のもっとも多感な時期が制約だらけの生活になってしまったことは、可哀想と思わざるを得ません。願わくば、このような事態が今後はもう起こらないでほしいものです。
2022.10.28
コメント(0)
-
函館本線の未来
新幹線延伸の陰で北海道物流の大動脈が存続危機 在来線が赤字見込みで協議難航北海道新幹線の札幌延伸の陰で、貨物の大動脈である並行在来線が廃線になる可能性が高まっている。北海道発の物流危機は回避できるのか。札幌市内のJR貨物の札幌貨物ターミナル駅には毎日、本州との間で約40本の貨物列車が発着する。1日平均6464トンのコンテナ輸送量は東京貨物ターミナル駅につぎ、全国2番目に多い。貨物列車はペットボトルや宅配便、書籍など道民の生活に欠かせない物資を運んでくる一方、道内から集まるタマネギやジャガイモ、食料工業品を本州に向けて送り出している。札幌ドーム10個分に相当するこの広大な物流拠点が「無用の長物」になるかもしれない。札幌発着の貨物列車は、北海道の「玄関口」である道南のJR函館線を通り、本州と行き来する。要所である函館-長万部間の路線が、廃線の瀬戸際にある。物流の大動脈が危機に直面するのは、貨物が走る旅客線の存廃問題がからんでいる。北海道新幹線が2030年度末に札幌まで延びる予定だ。延伸区間と並行して走る函館線は、函館-小樽間がJR北海道から分離され、存廃は北海道と沿線市町の協議にゆだねられている。今年3月、長万部-小樽間の廃線・バス転換が固まった。残る函館-長万部間は協議が続く。「はこだてライナーは存続をお願いしたい」。函館市長が発言すると、近隣の北斗市長や七飯町長も同調した。新幹線の新函館北斗駅と函館駅間を結ぶライナーは、観光が売り物の函館圏にとっては生命線だ。しかし、他の区間の存続を望む声は沿線から聞こえてこない。地元自治体が及び腰になるのは、沿線人口は減る一方で、新幹線が開業すれば観光客の利用も見こめなくなるからだ。北海道の試算によると、函館-長万部間を第三セクター方式で維持した場合、開業後30年間の累計赤字は816億円に達する。沿線からは「住民に多大な負担を強いることはできない」と、「バス転換やむなし」という声が強まっている。(要旨)---記事は、おそらく途中までしか掲載されていないようです。結局、JR北海道は新幹線が開業したら並行在来線である函館本線は(採算が見込める小樽-札幌間を除き)手放すし、大赤字が見込まれるので沿線自治体も第3セクターで引き受ける気がない、ということです。通称山線と呼ばれる函館本線の長万部-札幌間は、遠い昔、確か大学生の時に各駅停車で通ったことがあります。気動車の単行だったか2両編成だったかは記憶がありませんが、通学の高校生で超満員だった記憶があります。前日、各駅停車で上野から青森まで行き、当時あった青函連絡船の深夜便で北海道に渡りました。夜を徹して列車と船に乗っていたので、寝不足で途中かなり寝ていた記憶がありますが、所々おぼろげな記憶では、かなり景色がきれいだったように思います。この区間の廃止についても、鉄道ファン(元)としては、思うところは色々ありますが、そこは言っても仕方がないので、今回の記事では取り上げません。問題は函館-長万部間です。ここは、現在は函館-札幌間の特急「北斗」が1日11往復走る大幹線ですが、北海道新幹線が札幌まで延伸すると、旅客需要が激減することは明白で、一気にローカル線となってしまいます。が、旅客需要が激減しても、貨物需要はそうではありません。新幹線は貨物列車が走らないからです。函館本線を走る貨物列車は1日21往復と、特急「北斗」より本数が多いのです。かつ、これらの貨物列車はすべて本州からの直通便です。札幌貨物ターミナル駅のコンテナ輸送量が全国で東京貨物ターミナル駅に次いで第2位というところから見ても、JR貨物にとっては北海道路線は最重要路線の一つであることは明らかです。東北本線、羽越線-信越線-北陸本線を走る貨物列車も、北海道と東京、大阪を結ぶものが相当ありますから、それらを失うことはJR貨物にとっては死活問題でしょう。一方、日本全国の貨物輸送から見ると、鉄道輸送のシェアは1%しかありません。しかし、鉄道輸送の特性上、近距離、少量の輸送は不得手であり、長距離、大量の輸送に適しています。そのため、北海道-本州間の輸送に占める鉄道のシェアは約1割であり、中でも本州への農産物の輸送に占めるシェアは3割程度に達します。本州との鉄道輸送は、北海道経済にとっても無視できるようなものではないのです。鉄道の貨物輸送は既にシェアを落とすだけ落としており、それでも存続している貨物輸送には、それなりの理由と必然性があります。青函トンネルは鉄道専用です。つまり現状では貨物列車は本州まで直通できるけれど、トラック輸送は途中で船を使わなければならないわけです。だから、北海道本州間のトラック輸送は船の輸送力の上限にも左右されます。もちろん、天候にも左右されます。鉄道もどんな悪天候でも走れるわけではありませんが、船に比べれば運航率は高いですから。それに、物流業界は常に人手不足です。北海道もその例外ではありません。前述のとおり農産品の輸送では鉄道のシェアがかなり高いのですが、農産品は手荷役作業を伴うため、一部地域で輸送の受託制限が始まっている、本州の主要港から先のトラック輸送が断られる状況が現れ始めている、という指摘があります。したがって、函館本線の貨物輸送を廃止してそれをトラック輸送に切り替え、というのも簡単なことではありません。ここまで考えれば、函館本線の函館-長万部間は新幹線札幌延伸後も、貨物用としては必要不可欠であることは明白です。にも拘わらず、誰も存続を言い出さないという異常事態です。要するに、誰も赤字を被りたくない(かぶれる額ではない)のです。沿線自治体もそうですし、貨物列車を運行するJR貨物もそうです。JR貨物が路線の譲渡を受けて、自ら函館本線を維持、運営する、というは現実的には不可能です。何故なら、現状JR貨物が貨物列車運行のためにJR旅客各社に払っている線路使用料は、経営がギリギリのJR貨物を救済するため、国策で格安に設定されているからです。アボイダブルコストと言って、JR貨物の列車が走ることによって線路保守等の費用が増加する、その増加した差額分だけを支払うことになっています。それでJR貨物は何とか経営を維持しています。自社で全長130km以上の長大な路線を自社で保有してしまうと、アボイダブルコストでJR北海道に払っている線路使用料よりはるかに高額の費用が掛かります。JR貨物にはとてもその額を負担できないのです。もちろん、沿線の市町村が自力で鉄道を維持できるはずもなく、またJR北海道自体も厳しい経営状態であり、大赤字の函館本線を維持し続けることができません。結局、必要なのに誰も費用を出せない、ということで、函館本線廃止へ、という最悪の方向に向かいつつある状況のようです。本州との物流網の維持は沿線市町村だけの問題であるはずがなく、むしろ札幌をはじめとした沿線以外の市町村の問題です。ならば、それは全北海道の問題であって、道が中心になるべき(経営基盤としても、都道府県でなければその負担に耐えられないのは明白ですし)と思われますが、現在の北海道知事にその確固たる意志があるようには見えません。結局、新幹線の作りすぎ、というところに問題があったように思います。新幹線が本当に必要な路線は既に作られているわけです。衰退しつつある今の日本で、既存の新幹線ほどの需要がない路線に新しい新幹線の路線を建設しようとするところから、色々な無理が生じています。長崎新幹線の佐賀県通過をめぐる迷走も同根の問題でしょう。それに加えて、物流は経済の血流であるにもかかわらず、その重要性を世間一般が軽視していること、さらにJRグループ発足時に、明らかに経営基盤の弱い北海道四国九州を独立会社とし、本州も3つに分割してしまったことの先見の明のなさ(民営化するにしても分割する必要性があったのか、せいぜいNTTのように東西2社に分割程度にすべきだったのでは)など、これらの負の遺産の積み重ねに、日本全体の少子高齢化、地方の過疎化が加わって、北海道本州間の物流の危機、事態を招いているのではないでしょうか。
2022.10.26
コメント(2)
-
往生際が悪すぎる
山際大臣が辞任の意向固める “急転直下”舞台裏で何が旧統一教会を巡る問題を受けて24日午後、山際経済再生担当大臣が辞任の意向を固めました。国会記者会館から報告です。24日の国会の質疑でも岸田総理大臣は続投させる意向を示していましたが、最終的には山際大臣本人が辞任を申し出て、官邸がそれを受け入れる形となりました。岸田総理は、この臨時国会が始まる前から「説明ができないのであれば交代もあり得る」という認識を周辺に対して示していました。そして当初は山際大臣本人も含めて続投の意向を示していましたが、ここにきて答弁についても非常に評判が悪いということもあり、本人が申し出て辞任という形になったということです。当初、旧統一教会との関係を理由に閣僚が1人辞任すれば他の閣僚で関係が明らかになった場合、ドミノ辞任になってしまうのではないかという懸念もあったのですが、ここにきて辞任という形になりました。(以下略)---統一教会とズブズブの山際大臣の辞任は、当然ですが、あまりに遅きに失したというしかありません。「続投させる」と言った直後の辞任も印象はよろしくありません。岸田政権は、安倍元首相の国葬という、やる必要のない政治決断はあっという間に決めてしまうのに、当然やるべき決断はしない、という悪癖があるようです。統一教会との関係についての調査にもきわめて後ろ向きでした。引用記事に「1人辞任すれば他の閣僚で関係が明らかになった場合、ドミノ辞任」とありますが、他にも寺田総務相、秋葉復興相についても統一教会との関係が指摘されています。この二人についてもズルズルと決断を先延ばしにするのでしょう。もっとも、岸田が優柔不断で思い切った決断ができないから、ということももちろんありますが、それだけがこの煮え切らない対応の理由のすべてでもないのだろうと思います。端的に、統一教会と関係のある議員が自民党にあまりに多すぎて、もっと言い換えるなら自民党と統一教会の関係が深すぎて、切るに切れない、ということでしょう。ならば国民が自民党を切るべきです。と、言っても、どうもこの国の国民は、この期に及んでも自民党にNoを突き付けそうな気配は感じられないのが現状ではあります。岸田の優柔不断ぶりも、どれほど右往左往の醜態をさらしたところで、万が一にも自民党が野に下る恐れはない(岸田自身の退陣はあるかもしれませんが)、というところもあるのではないかと思ってしまいます。
2022.10.25
コメント(2)
-

2022年10月の鳥 9月に続いてエゾビタキまつり開催
10月の鳥第2弾があるかどうかは分かりませんが・・・・・・10月2日葛西臨海公園チョウゲンボウ。ちょっと遠かったです。チョウゲンボウ。ハヤブサ科です。同じ仲間のハヤブサは2回しか遭遇していませんが、2回ともそれなりの写真が撮れています。ところが、チョウゲンボウはハヤブサよのも遭遇しているのに、写真は撮れなかったり、撮れてもボケボケだったり、この小さな写真でも、今まで撮影できた中では一番マトモな写真です。10月9日東京港野鳥公園エゾビタキ。9月にも撮影しましたが、10月になってももまだいました。この日は3~4羽いたようです。いずれもトリミングながら、かなり近くから撮影できました。エゾビタキ。見返り美人です。(オスかメスか知らないですけど)エゾビタキ。名前はエゾビタキですが、北海道に多いわけではありません。もっと北のシベリア、サハリン、カムチャツカで繁殖し、北海道は本州と同様に、秋の渡りの際に通過するだけで、その数もむしろ東京近辺より少ないようです。エゾビタキ。エゾビタキは背中から見ると茶褐色の背中に白いラインできれいですが、お腹から見ると茶色い斑点で、それほどきれいな鳥には見えません。ただ、お腹の方から見ると、何とも言えない愛嬌が私には感じられて好きです。エゾビタキ。ヒタキ類を英語でフライキャッチャー(蠅取り鳥)と言いますが、その名のとおり、枝の先に止まって、パッと飛んだと思うと蠅あるいは他の虫を捕まえて元の枝に戻る、という動作を繰り返していました。カモの渡り第一陣。ホシハジロとキンクロハジロ空飛ぶモフモフくん。みんなの人気者、エナガ。エナガ。エゾビタキが脇にいてさえ、みんなエナガにカメラを向けるんだから、その人気はなかなかのものです。(エゾビタキも9月末から10月初めの時期は珍しい鳥ではないとはいえ、それでも観察できる機会はエナガよりはずっとまれですが)ノスリノスリセグロセキレイがいました。セグロセキレイ左奥セグロセキレイ、右手前ハクセキレイ。セグロセキレイはほぼ日本にしか分布しません。一方ハクセキレイはユーラシア大陸に広く分布します。ハクセキレイは近年都市鳥化しており、都心でもよく見かけます。セグロセキレイも、日本では珍しい鳥ではありませんが、都会で見かけることは極めて稀です。10月23日東京港野鳥公園まだエゾビタキいるかな、他のヒタキもいないかな、と思って行ったのですが、一日違いで何もいませんでした。昨日まではエゾビタキとキビタキが観察されていたようですが。(他に東京近辺で越冬するジョウビタキも記録されていますが、これも今日は見られず)コゲラ今日も空飛ぶモフモフくんのエナガに遊んでもらいました。エナガ
2022.10.23
コメント(0)
-
現在の兵器は総力戦に耐えられない
ロシアのミサイル在庫は危機的な低水準に ウクライナ国防情報総局ウクライナ国防省の情報総局は、ロシアの複数種のミサイルの在庫が危機的な少なさになっているとみている。ウクライナ国防省のブダノフ情報総局長は「ロシアの防衛産業は新しいミサイルを十分に製造できず、2月24日に戦争に突入した際に有していたミサイルはすでに底をつきつつある」と声明で述べた。「多くの品目の在庫はすでに危機的なレベル、つまり30%を下回っている」とブダノフ氏は指摘した。例えば巡航ミサイル「イスカンダル」の在庫は通常の13%に落ち込んでいるという。ロシアのミサイルの在庫は推測だ。ウクライナのゼレンスキー大統領は5月、ロシアは2154発のミサイルを発射し、おそらく精密誘導ミサイルの60%を使い切ったと述べた。しかしこれは希望的観測のようだ。米国防総省は同月、ロシア保有の兵器のうち「巡航ミサイル、特に空中発射のものが最も少なくなっている」としながらも、ロシアには戦前の在庫の50%超が残っているとの見方を示した。ブダノフ氏は「ミサイル不足でロシアは何らかの選択肢を探さざるを得なくなった。そしてイラン製の無人機を使い始めるに至った」と述べた。さらに、ロシアがイランの無人機を「徐々に使い果たしており」、注文し続けていると述べ、イランの製造は「即座に行われるものではない」と語った。(以下略)---前回の記事で、ロシアに何十年も総力戦の経験がなかった、という趣旨のことを書いたところですが、そもそも現代の戦いで総力戦というものが可能なのか、という面で、示唆に富んだ話です。総力戦の定義は百科事典やWikipediaに譲るとして、兵站や生産の面に限定すると、総力戦とは果てしない消耗戦であり、大量生産を行いながらの戦争であることが基本的な定義となるでしょう。戦前からの兵器や物資のストックだけで戦っている間は、総力戦とは言えません。総力戦であった第二次大戦では、各国とも戦前に持っていた兵器よりも、戦時中に生産した兵器の方がはるかに多いのです。例えば、ゼロ戦(零式艦戦)は日本海軍の開戦時の主力戦闘機でしたが、総数1万機以上が生産されましたうち開戦前に完成していたのは500機あまりで、大半は戦時中に完成しています。また、パイロットの養成も同じで、開戦前の日本陸海軍の航空機搭乗員の総数は1万人に達しませんが、戦時中の搭乗員の戦死者は3万4千人にもなります。つまり、戦前の搭乗員の人数の3倍以上が戦死した=それ以上の搭乗員が戦時中に養成された、ということになります。ところが、現在では新兵器の開発にははるかに長い期間と巨額の費用を要するようになっています。ゼロ戦は1937年に開発が開始されて1940年に制式採用されましたが、1943年には旧式機となっていました。戦争後期の最優秀戦闘機であった米国のP51は、わずか9ヶ月で開発されましたが、ジェット戦闘機が実用化されたことによって数年で旧式機となりました。しかし現在では、米国製の最新鋭戦闘機であるF35は、原型機の初飛行は2000年ですから22年も前です。ゼロ戦にしてもP51にしても、初飛行の22年後には超音速ジェット戦闘機の時代になっていました。価格的にも、F35は1機170億円ほどもします。物価の差を考慮しても、第二次大戦当時の軍用機と比べて、きわめて高価なものとなっています。機械としての複雑さ、特に第二次大戦当時は存在しなかったコンピューターが操縦や火気管制をつかさどるようになり、機体よりも制御するコンピュータのソフト開発に膨大な時間を要するようになっています。そして、世界のどの国でも、自国だけで部品のすべてを生産することはできなくなっています。ある国がいくら国家の総力をつぎ込んで新兵器を開発しようとしても、部品を輸出する国が国家の総力を挙げて輸出してくれるわけではありません。パイロットの養成も同様です。第二次大戦当時の単発レシプロ機と現在のジェット機では操縦の難易度が違い、従って養成に要する飛行時間もまったく違います。戦争末期の予科練(海軍飛行予科練習生)は訓練期間半年で実用機過程へ、実用機過程3か月で(つまり合計9か月で)実戦配備されたようです。もちろん、それでは飛行技量は最低限度に過ぎず、夜間飛行もできない、航法もあやふやで先導機についていくことしかできない、「離着陸がやっと」の状態だったわけですが、それでもともかく何とか実用機で単独飛行はできた(させられた)わけです。しかし、現代においてはそのようなパイロットが戦場に出ることなど有り得ません。結局、戦争が始まってからパイロットの養成を始めても、とうてい間に合わないのです。引用記事では、ロシア軍がこの侵略戦争で大量のミサイルを使ってしまい、その補充が容易にはできない状態に触れています。しかし、この状況は他国でも全く同じです。軍用機の開発に第二次大戦頃よりはるかに時間がかかることに触れましたが、それは製造に要する期間でも同じことですし、ミサイルでも同じことです。半導体など電子機器の取引制限があろうがなかろうが、現代のミサイルは高価であり、そう易々と増産は出来ないものです。ミサイルとしてはもっとも軽量小型の部類である、携帯式対空ミサイルのスティンガーミサイル(米国製)ですら、その製造には約1年半から2年かかるとされています。当然、それより大型の巡航ミサイルや弾道弾の製造には、もっと時間がかかります。戦車や戦闘機ならなおさらです。世界的な半導体不足が、その状況に更に拍車をかけているはずです。スティンガーなら戦争には間に合うかも知れませんが(1年半から2年も戦争が続いてほしくはありませんけれど)、それ以上の兵器は、増産を始めてそれが戦場に届く頃には戦争が終わっています。そういう意味で、現代において、別にロシアに限らず、大量の兵器の開発、生産を伴う総力戦というものは、もはや成り立たなくなっていると思われます。ただし、それは生産、戦争経済という側面での話です。その面で総力戦が成り立たなくなっている分だけ、むしろしゃかりきになって国論の統一、社会の統制、そのための少数意見の圧迫という側面に力を入れている傾向が、現状のロシアには見られます。これもまた、ロシアに限ったことではないでしょう。
2022.10.21
コメント(2)
-
いきなり太平洋戦争末期と同じ
ロシアの動員、悲惨な実態 「これはやばいよ」新兵SNSで訴え次々穴の開いた防弾チョッキやさびた自動小銃――。ウクライナへの侵攻を続けるロシアで、9月に始まった部分的動員の悲惨な現状を伝えるSNSの投稿が続いている。「(配置前の)訓練はないと告げられた」と涙ながらに訴える人までいる。プーチン政権は動員で侵攻の劣勢を覆す考えだが、早くも動員による戦死者が出ており、士気の低下は深刻だ。黒い目出し帽をかぶった軍服姿の男性が、穴が開き、テープで補修された防弾チョッキを見せている。今月にSNSで広まった、動員されたとみられる男性の写真だ。男性はロシアが支配するウクライナ南部クリミア半島出身で、写真を投稿した男性の親族は、投稿の中でこうつづった。どんな装備で人々を戦いに送るつもりなのか」---太平洋戦争末期、旧「満洲」で、かつて日本陸軍の中ても最精鋭とうたわれた関東軍は、主力を次々と太平洋の激戦地に引き抜かれていき(もっとも、その少なくない部分は戦場に着く前に輸送船が撃沈されて、戦う前に海の藻屑と消えていますが)、1945年3月には、太平洋戦争開戦時に関東軍に属していた13個師団がすべて移動してしまいます。その穴埋めをすべく、45年6月から「満洲」在住邦人25万人の「根こそぎ動員」が行われました。形の上では関東軍の兵力は急増して、24個師団、9個混成旅団、1個戦車旅団で太平洋戦争直前の「関特演」当時の規模を回復しますが、言うまでもなく、その実態は、兵士の頭数だけを揃えたにすぎない惨憺たるものでした。何しろ、小銃すら持たない丸腰の兵隊が10万人もいたというのです。関東軍は、実質的には「案山子の兵団」と化したのです。「満洲」ではなく本土での話ですが、敗戦直前に召集された補充兵の中には、本当に火縄銃や竹槍を持たされた兵隊もいるくらいです。1945年8月9日、ソ連軍が対日宣戦布告して「満洲」に攻め込んだ時、関東軍の額面上の兵力は上述のとおり24個師団、9個混成旅団、1個戦車旅団でしたが、実戦力としては8個師団相当だったと言われます。当然、ソ連軍には全く歯が立たず、あっという間に敗北しました。それから77年がたち、歴史は繰り返す、今度はソ連の末裔であるロシアが旧関東軍とおなじ状態に追い込まれています。ある意味関東軍よりひどいのは、当時、日本は太平洋戦争敗北直前であり、動員兵力は700万人にも達し、B29の空襲と潜水艦等による輸送網の寸断で、本土は焼け野原、国民は総飢餓状態に陥っていました。もう絞り切った雑巾からまだ水を絞り出すような状態だったわけです。(もちろん、その状態で手を上げなかった戦争指導者たちには大いに非がありますが)しかし、今のロシアはそうではありません。ウクライナ側はともかく、ロシア側は別に総力戦を戦っているわけではないし、空襲で国内が焼け野原になっていいるわけでも、国民が飢餓地獄に陥っているわけでもありません(この先はどうか分かりませんが、今の時点では)。太平洋戦争末期の日本よりは明らかに余力のある状態です。それなのにこの状態というのは、すべてが泥縄式に、後手後手のやっつけ仕事で計画されているからでしょう。もっとも、この点に関してはロシアだけが酷いのかどうかは分かりません。米軍も、イラク戦争の際に、第一線の戦闘部隊はともかく、あとから急遽召集された予備役兵には、まともな戦闘訓練もなくイラクに送り込まれた例が多々あったように記憶しています。先進国、主要国とされる国はどこも、最近数十年間、総力戦なんて経験はなく、そのための準備もしていないのでしょう。それは、ある意味「どんな総力戦でも何年でも耐えられる」という状態よりは多くの国民にとっては幸せなことではないかと思います。それにしても、プーチンが専制的な政治体制を敷くロシアと言えども、今や軍での滅茶苦茶な対応はそのままSNSに流出する、そういう時代になっているのですね。
2022.10.19
コメント(2)
-

フォルクローレ交流演奏会in Zushi その2
昨日写真だけアップしましたが、動画もアップしました。4曲演奏したうちの2曲です。峡谷のカーニバルこの曲は20年前から何度も演奏しています。スリキこちらは人前で演奏したのはまだ2回目の曲です。少し前から練習していたのですが、難易度高く、なかなかモノになりませんでした。えっ、この演奏はモノになっているのかって?さてさて・・・・・・。それにしても、昨日は練習で4曲、本番の演奏も同じ4曲を演奏しただけで、それ以外の時間はほとんど椅子に座って人の演奏を聞き、あとは待機していただけなのですが、今朝はドーンとすごい疲労感でした。山登りの翌日でもあんなに疲れないのに。経験則では、人前での演奏って練習の5倍くらい疲れます。同じ曲を同じ息の強さで吹いているのにね。やはり緊張度のなせる業でしょうか。
2022.10.17
コメント(0)
-
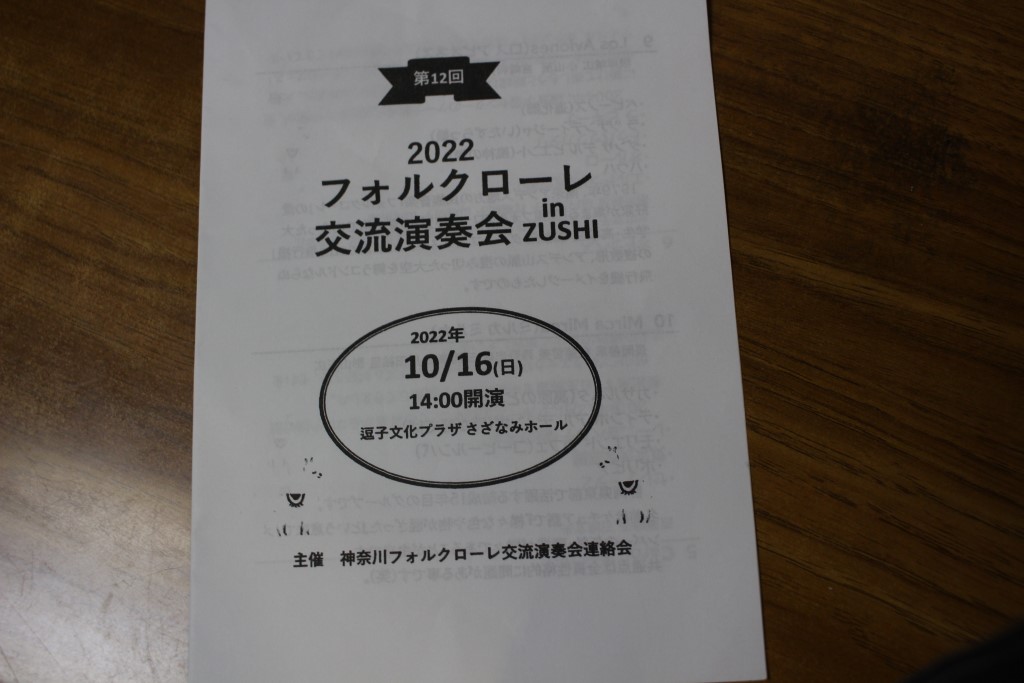
フォルクローレ交流演奏会in Zushi
神奈川県の逗子で演奏してきました。昨年も演奏したのですが、その時はギタリストが急に参加できなくなり、急遽私がギターに回りました。今回はフルメンバーそれって演奏できました。音源をアップしたいのですが、まだ編集できていないので後日アップすることにして、今日は写真のみ。キラ・ウィルカヨコハマ・ブリサ・アンディーナシエラ・ベルデ青と碧ビエントス・アル・マールキャロルオトラベスブランカ・ロサルセリートロス・アピオネスミルカ・ミルカ本日のトリ、カパック・ニャン2時から6時半までという長丁場のコンサートでした。
2022.10.16
コメント(0)
-
日本アムウェイ
「日本アムウェイ」に6カ月の取引停止命令 社名や目的言わず勧誘消費者庁は14日、「日本アムウェイ合同会社」に対し、連鎖販売取引(マルチ商法)について社名や目的を言わずに勧誘したことなどが特定商取引法違反に当たるとして、6カ月の取引停止命令と、再発防止策を講じることなどを求める「指示処分」を出した。同社への行政処分は初めて。同庁によると、社名や目的を言わずに勧誘した▽目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した▽相手の意向を無視して一方的に勧誘した▽契約締結前に書面を交付しなかった――という4種類の違反を確認したという。同社は、会員が勧誘により別の会員を増やすことで報酬を得るネットワークビジネスが主事業。同社のホームページによると、1979年5月の創業で資本金は50億円。2021年6月時点で373人の従業員を抱えている。日用品から健康食品など幅広いジャンルを取り扱い、21年の売上高は984億5700万円に上った。同庁によると、全国の消費生活センターに寄せられたアムウェイに関する苦情相談件数は、19年度317件▽20年度257件▽21年度270件▽22年度(9月15日時点)109件。(以下略)---日本アムウェイといえば、マルチ商法の総本山のようなものですが、その昔、そうとは知らず、アムウェイの会員の集まりみたいなところで頼まれて演奏してしまったことがあります。20世紀の話です。おそらく1996年か7年頃のことではなかったかと思います。詳細は覚えていないのですが、当時参加していたアルゼンチンの踊りの伴奏グループのメンバーの誰かの親戚の家の新年会ということで呼ばれたように思います。当時アムウェイという名を事前に知っていたわけではなく、行ってみたら十数人の人が集まっていて、自己紹介で次々と「アムウェイをやっています」「アムウェイやっていてよかったです」などという言葉が出てきて、つまりアムウェイ会員の新年会だったのです。結構、誰もが名を知るような超一流大企業に勤めている、という人が多かったように思います(もちろん、自己紹介ですからそれが事実という保証はありませんが)こちらも一人ではなく、グループ数人だったこともあって、演奏しただけで勧誘されたりはしなかったように思います(うろ覚え)。ただ、遠い記憶の中て、かなり保守的な考えを前面に出す人たちという印象があります(もちろん、サンプルはその場にいた十人前後だけですから、アムウェイ会員一般がどうかはまったく分かりません)。そして、「アムウェイって何だろう?」とも思いましたが、同時に何か危険な匂いを感じたように記憶しています。普通だったらそのまま忘れてしまっても不思議はないところでしたが、やはり気になって、後日調べたのでしょう。当時、まだパソコンを所持しておらず、調べるのに時間はかかったような記憶はあります。ともかくほどなく「日本アムウェイ」の正体を知り、「なるほど、危ない危ない」と思ったのでした。一歩間違えたら私も被害者、だったかもしれません。実は、職場にもアムウェイにはまっている人はいる、という話を聞いたことがあります。それにしても、世の多くのマルチ商法は、短期間のうちに摘発して消滅しますが、日本アムウェイはその当時から、少なくとも四半世紀存続しています。何故あんな典型的なマルチ商法が法の網をかぶせられずに存続できるのか、不思議に思っていましたが、とうとう法の網をかぶせられたのは、喜ぶべきことでしょう。
2022.10.14
コメント(5)
-
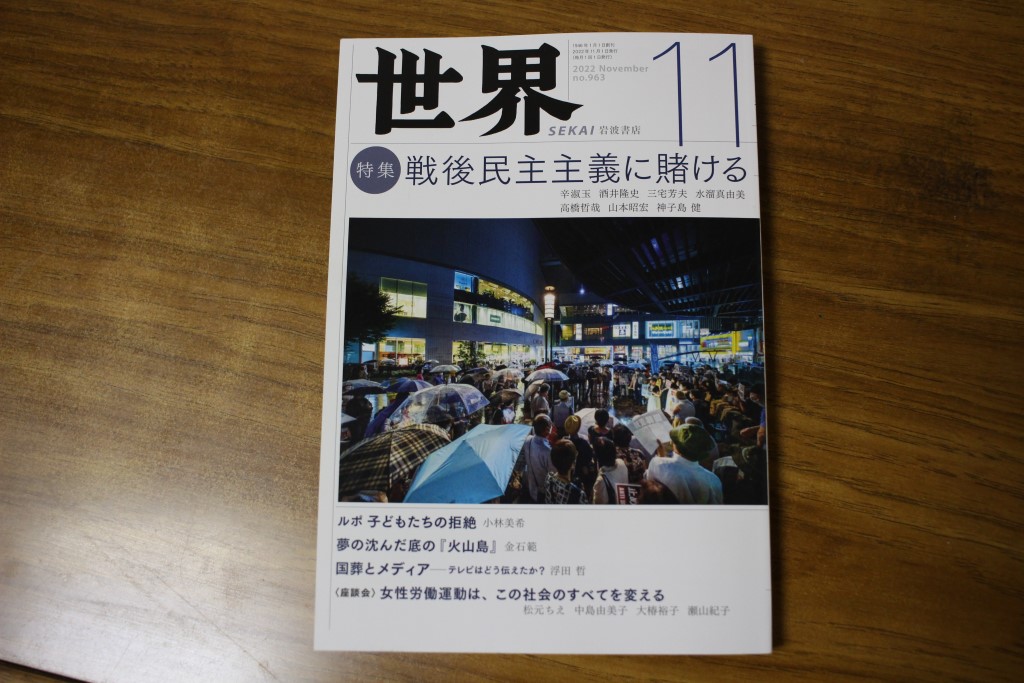
お疲れ様でした
岩波書店の「世界」と言えば、編集長であるクマさんこと熊谷伸一郎さんは私の古い仲間でありました。いや、過去形ではなく今も仲間なのですが、あまりにビッグな存在かつ超多忙な雑誌編集者という職で、もう昔のように徹夜で飲み明かして議論する、というような機会はなくなってしまいました。さて、そのクマさんが「世界」編集長を退任すると聞いて、慌てて彼の担当最終号である2022年11月号の「世界」を購入しました。確かに、編集後記に退任の報告が書いてありました。編集長として4年、編集長となる以前も含めると15年以上「世界」の編集に携わってきたそうです。ともかくも、お疲れさまでした!!しかし、彼はまだ40代、まさか今後はバイク三昧の日々、というわけにもいかないでしょうし(いや、もちろんそれもやるでしょうけど)、絶対この先また何か新しいことに打って出るのだろうと思いますが、それが何かは私も知りませんけど。次の道筋も、応援しますよ。
2022.10.13
コメント(2)
-
そう簡単には行かないでしょう
保険証廃止、24年秋にも 厚労省調整、マイナカード一本化 交付率5割届かず、対応課題厚生労働省は、健康保険証を2024年秋にも原則廃止する方向で調整に入った。保険証を廃止した後の事務対応はマイナンバーカードを基本とする。ただマイナカードの交付率は9月末時点でも人口の5割に届いておらず、カードを持たない人への対応が課題となりそうだ。---マイナンバーカードの普及率は今年9月時点で49%。まだ5割に届いていません。それで政府は普及に躍起になり、あの手この手の策を繰り出しているわけです。保険証をマイナンバーカードに統合してしまえば(マイナ保険証)、否応なく全国民がマイナンバーカードを持たざるを得なくなるからです。ただ、ことはそう簡単にはいかないはずです。マイナンバーカードを保険証として利用するには、医療機関側の機器整備が必要です。厚労省は来年度から「マイナ保険証」のシステム導入を各医療機関に義務付けるそうですが、費用の問題が絡むだけに、そう簡単に行くのかどうかというところです。とは言え、国にも面子があるので、最後は補助金漬けにしてもやるんでしょうけど。すでに、マイナンバーカードを持てば2万円分のポイントを付与が行われています。1億人が応募すれば(全国民にマイナンバーカードを持たせようというのだから、最終的にそうなります)2兆円です。たかがあのカードひとつのために、2兆円とはびっくりです。それに比べれば、全国の医療機関に対応機器を入れさせる費用の方が、おそらく安くあがるでしょうから。私も、今のところマイナンバーカードは持っていません。2万円のポイントのために魂を売る気はない(笑)ですが、保険証がマイナンバーカードに統合されたら命と社会生活維持の問題になってくるので、マイナンバーカードを持つしかなくなります。仕方がないので、それまでにはマイナンバーカードをつくるしかないか、とあきらめ気味です。ただ、国のお金の使い方としてどうなの、という疑問はつきません。保険証、将来的には免許証?更にもっと将来は他のカード類も統合されていくのでしょうか?それは一見便利なように見えますが、なくしたときのリスクがどんどん大きくなるということを意味します。カード類をなくしたりしないと自信を持って言えるような管理能力高い系の人なら困らないでしょうが、世の中そういう人ばかりじゃないですからね。私自身も、保険証と免許証をなくしたことはないのですが、定期券を何回かなくしたことがあるのでね。気をつけなくては。
2022.10.11
コメント(2)
-

中尊寺と毛越寺(栗駒山付録)
先の記事で栗駒山登山の写真を紹介しましたが、下山した時間はまだお昼前で、その後、高校同期の山仲間と二人で中尊寺と毛越寺に行きました。中尊寺は、昨年、家族旅行でも行ったので2回目になります。中尊寺本堂。金色堂は、友人だけが観覧し、私は昨年見たので今回はパスしました。能楽堂。これは、昨年来た時は見ていなかったので、友人が金色堂を見ている間にこちらを見物。実際にここで能を上演することはあるのかな?と思ってちょっと検索したら、「中尊寺薪能」というものが演じられているそうです。能楽堂の奥にあるのは白山神社。中尊寺の境内に神社があるのですね。江戸時代には神仏習合で神社と仏閣が同じ境内にあるのは普通でしたが、明治初めの廃仏毀釈で神仏が分離されたものと思っていましたが、多少の例外もあったということでしょうか。このステージで演奏してみたい、という不埒なことを考えてしまいました。考えてみれば、キリスト教会で2回演奏したことがあるし、実は四半世紀以上前、お寺で演奏したこともあるのです。だったら能楽堂でもぜひ・・・・といっても、古さ(歴史的価値)が違いますけど。昼食後は毛越寺へ。こちらは昨年の家族旅行では行っていないので、私としてはむしろこちらが行きたかったのです。本堂は新しそうです。開山堂これ以外は多くの建物が戦国時代~江戸時代に焼失してしまったようで、「跡」という表示しかありません。これは何だったかな。鑓水の遺構だそうです。栗駒山の紅葉は真っ盛りでしたが、人里の紅葉はまだまだこれからです。庭園は素晴らしかったです。これだけでも見る価値はありました。一ノ関駅に帰ってきました。カーシェアの車を返却し、駅前の居酒屋で二人で一杯やって、帰路はめいめいで新幹線を予約したら、色々あって別々の列車になってしまい、私だけ一足先に新幹線に乗ったのでした。仙台までは起きていたのですが、仙台から大宮までは爆睡でした。東北の山もいいなあ。鳥海山、秋田駒ケ岳、早池峰山など、他にも登りたい山はあります。いつかまた。
2022.10.09
コメント(0)
-
ブラジル大統領選
ブラジル大統領選の各種世論調査、ルラ氏大勝との見誤りに波紋拡大2日のブラジル大統領選は複数の世論調査の事前予想を裏切って右派の現職ボルソナロ大統領が善戦し、第1回投票での左派ルラ元大統領勝利とはならず、対決は30日の決選投票に持ち越される。2016年米大統領選や英国のEU離脱を問う国民投票で保守派の強さを見誤った世論調査の「失敗」が再び繰り返された形だ。事前の各種世論調査では、ルラ氏は7~17ポイントのリードと予想されていたが、蓋を開けると5ポイント差の接戦だった。ボルソナロ氏は女性や少数派向けの発言で批判される右翼の人物で、支持者の多くは世論調査に支持を明かしたがらない。トランプが勝利した16年米大統領選にもあてはまった現象だ。コロナ禍の影響で同国では2010年を最後に国勢調査が実施されておらず、世論調査会社の母集団無作為層化抽出がやりにくかったという。移民の多いブラジル社会の変化は早く、例えば右寄りの福音派キリスト教徒の票は急激に伸長している。今回の選挙直前の数週間で一部の世論調査がルラ氏のリード拡大と1回目投票での当選確定を示す結果になったことで、保守派有権者がびっくりし、他のより中道な候補者の支持をやめてボルソナロ氏支持に回った可能性もある。ルラ氏はこうした展開を警戒し、あえて直前の世論調査結果にコメントするのを避けてきたが、その甲斐はなかったようだ。ブラジルの保守派が、これはブラジル以外でも言えることだが、単純に世論調査会社を信頼していないようにみえることもある。保守派が回答に応じないことで調査結果が保守派支持の候補者の強さを過小評価し、これが保守派有権者の世論調査への不信をさらに強めるという悪循環になっている可能性がある。---この結果は私もびっくりしましたが、とはいえ事前の予測より僅差ではあるものの、ルーラが最多得票であることは間違いありません。得票率48.5%は、過半数には足りないものの、あと1.5%でしかありません。選挙は終わるまで分からないので、決選投票の結果を確実に予想することはできませんが、おおむねルーラが優勢であることは否定できません。ボルソナロが予想外に健闘したといっても、潜在的支持層の票をすべて掘り起こした結果であり、これ以上の伸びしろがあるようには見えないからです。引用記事にあるように、ルーラ大勝の事前報道に、第3位以下の候補を支持していた保守層の票が「ルーラ当選阻止」のためにボルソナロに流れたという側面もあるようです。ただ、それは言い換えれば、決選投票で新たに獲得できそうな票を第1回投票で先食いした、ということでもあります。つまり、第1回投票で第3位以下の候補に投じられた票が、決選投票でボルソナロに流れる可能性はほとんど期待できないわけです。実際、第3位となったシモーネ・テベチ(ブラジル社会民主党)、4位のシロ・ゴメス(民主労働党)は相次いで決選投票でのルーラ支持を表明しています。元々シロ・ゴメスを擁する民主労働党はルーラの前政権期の与党でした。それに対してブラジル社会民主党は、その名前とは裏腹に、実質的には保守政党で、ルーラ率いるPT(労働者党)とは常に敵対関係にあります。それでもボルソナロよりはルーラの方が「まだマシ」と判断したのでしょう。その支持層も、ボルソナロよりはルーラに親和性がありそうです。また前述のとおり決選投票でボルソナロに流れそうな支持票は、第1回投票ですでに流れてしまっているので、もうこれ以上流れる票はほとんどないでしょう。というわけで、決選投票ではルーラが勝利できる可能性がかなり高いと思いますが、絶対ではありません。こればかりは終わるまでは分かりませんから。それに、僅差での勝利の場合、米国でトランプ支持者が暴動を起こしたのと同様、ボルソナロ支持者が納得せずに暴動を起こす可能性が指摘されています。すでに、現状でもルーラのPT党員がボルソナロ支持者に射殺されたという事件も起こっていするようです。残念ながらブラジルにおける民主政治の歴史はそう確固たるものではなく、1964年から85年まで20年以上軍政下にありました。その時代に戻るような事態があってはならないと思いますが。色々な意味で、今後のブラジルの動きには注目する必要がありそうです。
2022.10.08
コメント(0)
-
言っているでしょう
臆測広がる「大陸8割」発言 識者「高市氏、事実関係の説明を」国葬反対を巡る「大陸8割」発言はあったのか、なかったのか――。渦中にいる高市早苗・経済安全保障担当相が明言せず、SNSを中心に臆測が広がっている。~騒動の発端は、三重県の小林貴虎県議=自民=のツイッターだ。<国葬反対のSNS発信の8割が隣の大陸からだったという分析が出ているという。今日の講演で伺った話。ソースは以前三重の政治大学院でもご講演頂いた事のある現職。>投稿は拡散し、「いいね」は1万1000件以上。これに対し、SNSでは「どこからそんな情報を手に入れたのですか?」「その方のお名前は?」などといった反応が相次いだ。小林氏は4日、「誰が話したかって話ね。高市早苗さんです」と報道陣の取材に答えた。「日本会議」の会合が2日に名古屋市内であり、高市氏が安全保障問題について講演した際に「政府の調査結果」として話した内容を基に投稿したと説明した。また小林氏はツイッターにも次のように投稿した。<さて皆さん非常に関心が高い様なのでお答えすることにしました。私が総理大臣になって頂きたいと強く願っている高市早苗先生が、政府の調査結果としてお伝えいただいた内容です。ウクライナ戦争で明らかになった様に情報戦争の時代です。我が国も安全保障上取り組むべき課題だと言うお話でした。>これを受けて毎日新聞は高市氏の事務所に質問状を送り、高市氏が日本会議の会合で講演した事実はあるのか▽「国葬反対のSNS発信の8割が隣の大陸からだったという分析が出ているという」という趣旨の発言をしたのか▽発言をしたのであれば、その根拠は何か――について尋ねた。高市氏はメールで「日本には、情報操作(偽情報)に対応する法律が無いので、政府は調査することができません。政府が出来るのは、海外の情報機関や企業による調査結果の収集くらいです」と回答し、小林氏が言及した「政府調査」について否定した。しかし、高市氏が日本会議の会合で講演したかや、その際「国葬反対のSNS発信の8割が隣の大陸から」という趣旨の発言があったのか、については説明がなかった。また高市氏はツイッターに「不正確な情報」と投稿したが、ここでも発言そのものの有無には触れなかった。(要旨・以下略)---高市は、「政府調査」という発言についてだけ否定していますが、「国葬反対のSNS発信の8割が隣の大陸からだったという分析」という発言そのものについては肯定も否定もしていません。が、しかし、これだけ騒ぎになっている状況で、その発言をしていないなら全力で否定しているに決まっているので、それは事実上「そのように発言しました」と言外に認めているも同然です。つまり、高市が「投稿の8割が大陸から」と発言し、そこにこの県議が「政府調査」という尾鰭をくっつけた、そういうことであろうと推察できます。あきれ果てた話です。それは「分析」ではなく、もちろん「政府の調査」でもなく、ただの「妄想」です。ネトウヨ連中が、自分たちの気に入らない発言、主張を「韓国の手先」「中国の手先」と叫ぶ、いつものアレです。お仲間の間で言いたい放題の放言をしたら、それを嬉々として満天下に開陳する支持者がいた、という話です。安倍元首相が生きている間の政策の是非ということであれば、諸外国にとっても関心の高いところでしょう。しかし、すでに亡くなってしまった安倍元首相の国葬の是非というのは、純然に日本の国内問題にに過ぎません。国葬がいいか内閣自民党合同葬がいいか、なんて、日本人以外にとっては、どう考えたって関心の外でしょう。それに、世論調査であれだけ国葬に対する反対が多いのに、ネット空間だけ反対論がない、などということがあり得るかどうか、ちょっと考えれば分かりそうなものです。人間は事実ではなく、見たいものしか目に入らない、と言われますが、その究極の姿がここにある、というわけです。国葬反対論、という見たくない事実があれば、それは「外国人の捏造である、日本人の世論ではない」と信じたい、ということでしょう。この種のバイアスは、程度を問わなければどんな人にも見られるものではありますが、このレベルにまで達すると、さすがに「マトモじゃない」としか言いようがありません。
2022.10.06
コメント(2)
-

神の絨毯・栗駒山の紅葉 その2
前回の続きです。今度はナナカマド(おそらくウラジロナナカマド)の紅葉。ウラジロナナカマド。栗駒山山頂が近づいてきました。草紅葉も素晴らしいです。咲き始めたリンドウ。山頂に近付いてきました。いわかがみ平からの直登コースと合流するあたりからは登山者の行列です。山頂までもう少し。山頂に到着!おお、秋田県の文字がある。と、思ったのですが、秋田県の県境はここから西に30分ほどのところになるようです。(秋田県と山形県は、まだ行ったことがありません)いわかがみ平を7時に出発して、9時過ぎに到着、所要時間は2時間余でした。昭文社の登山地図の標準コースタイムが2時間なので、丁度コースタイムどおりです。登山口からの標高差520m余なので、実は体力的には案外楽な山です。これが正真正銘の鳥海山です。前回記事で鳥海山と書いたのは間違いで、どうも月山だったようです。さて、何山でしょう。鳥海山よりだいぶ右方向なので、焼石岳のようです。山頂も登山者でごった返していました。紅葉の一番の見ごろ、快晴、土曜日、そりゃもう一番人出が多い日でしょう。下山にかかったら、ますます多くの人が登ってきました。往路の東栗駒山経由の登山道より、道は整備されています。下山時の紅葉もため息が出るくらいきれいでした。モミジの向こうの山頂。山頂を振り返って。やはり山頂近くの方が紅葉はきれいですね。山頂のアップ。整備された登山道で、下りは速い速い。9時20分過ぎに下山開始で、あちこちで写真を撮りながら下ったけれど、いわかがみ平まで1時間かかりませんでした。もちろん笛一式を持って行ったのですが、ちょっと人が多くて、登山道では吹けませんでした。なので、下山後車で少し下ったところにある、車が2~3台しか止まっていない小さな駐車場で存分に吹きました。途中で、シャトルバスがやってきたのはびっくりでしたが。(運転手が休憩に来たようです)というわけで、実はまだ午前中。この後中尊寺と毛越寺に立ち寄りましたが、その写真はまた機会があれば別の記事にて。栗駒山の写真は以上となります。
2022.10.04
コメント(2)
-

神の絨毯・栗駒山の紅葉 その1
高校同期の山仲間と二人で、金曜の夜東京を出発して、夜行日帰りで宮城県・岩手県境の山、栗駒山に行ってきました。池袋発の夜行バス、けせんライナーで岩手県の一ノ関に向かいました。この夜行バスを使うのは初めてではありません。3年前、宮城県の伊豆沼にガン、ハクチョウの写真を撮りに行ったときに使って以来となります。一ノ関に着くと、山仲間が予約をしていたカーシェアの車に乗り、栗駒山登山口に向かって出発です。駅に着いたときには、かなり霧が立ち込めていて、あまり視界がなかったのですが、しばらく走ると晴れてきました。これから登る栗駒山の山容が一望できます。朝焼け+紅葉で赤く輝いているじゃないですか。素晴らしい景色が期待できそうです。登山口はいわかがみ平ですが、駐車場はあまり広くないため、紅葉の時期にはその手前で通行止めとなり、いわかがみ平まではシャトルバスで行くことになります。6時過ぎにはシャトルバスの発車場に着いたのですが、すでにこのとおりの行列でした。マイクロバスを待つ間。山腹は紅葉に染まっています。結局、マイクロバスの順番が回ってきて、いわかがみ平に着いたのは7時少し前でした。東栗駒コースを登り始めます。足元の土がツルツルで、やや滑りやすい登山道です。東北地方の山は、豪雪のため亜高山帯針葉樹林を欠き、山地帯(落葉広葉樹林帯)の上が高山帯になっている例が多いです。栗駒山も同様です。ただ、実際には、亜高山帯の典型的な針葉樹であるシラビソやコメツガはありませんが、ヒノキ科のクロベ(おそらくそうだと思います。あるいはアスナロかもしれません。私には識別できませんでした)は数多く自生していました。近くから見ると、木々の1本1本は、必ずしもきれいに真っ赤になっているわけではありません。あるいは、東北の長雨の影響もあるのでしょうか。秋の花の代表、リンドウがもうじき咲きそうです。途中からは沢の脇を登っていきます。沢といっても水の中を歩くところはありませんが、増水時はおそらくその限りではないでしょう。稜線に出て、視界が一気に広がります。正面に栗駒山山頂が鎮座しています。栗駒山のアップ。前述のとおり、木々の1本1本は、必ずしもきれいに真っ赤になっているわけではないのですが、全体としては素晴らしい紅葉になります。晴天のおかげもあるのでしょうが。ハイマツの緑とカエデ、ナナカマド等の赤の組み合わせが絶妙です。同じアングルのアップです。ボヤっとして分かりにくいですが、鳥海山が見えます。※追記 鳥海山ではありませんでした。栗駒山から南西方面の山です。月山でしょうか?眼下に車を止めた駐車場が見えます。東栗駒山に到着。ここから栗駒山までの山頂は標高差200mほどです。似たような写真ばかりになってしまいますが、栗駒山山頂です。登りはじめから下山まで、常時アキアカネがたくさん飛んでおり、同行者の腕にも止まってきました。先の写真にも写っていましたが、噴火口のアップです。栗駒山は活火山です。有史以降の噴火は1744年と1944年の2回のようです。ただし、これら近年の噴火はこの噴火口からではなく山頂北側の噴火口からのようです。紅葉するカエデと栗駒山。この辺りは木々の1本1本の紅葉もかなりきれいになってきました。以下次回に続きます。
2022.10.02
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1










