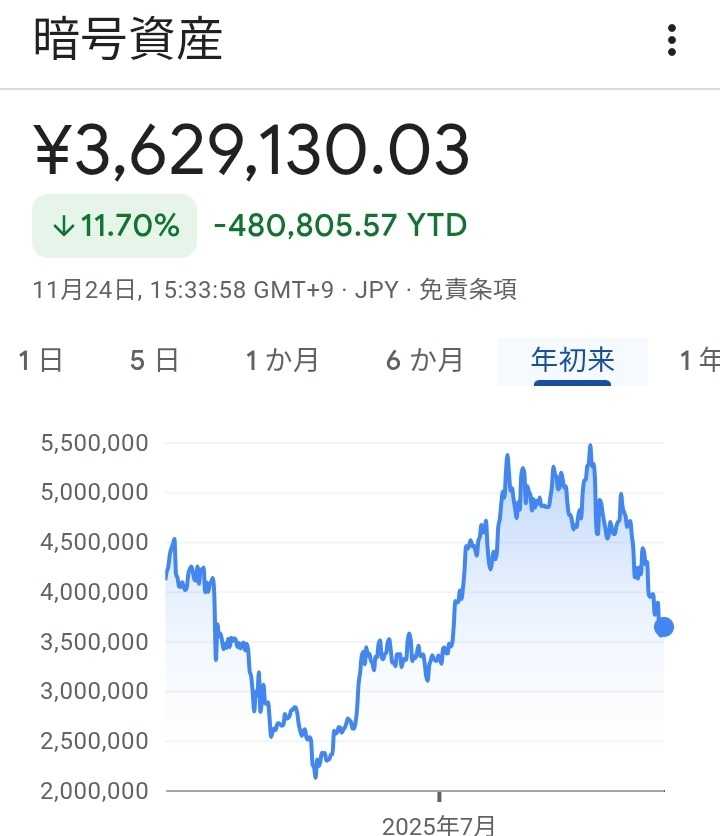2015年01月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
まったくどうしようもない
田母神氏、ネット情報うのみ? 「人質事件」で不確かな情報連発これまで何度となく物議をかもしてきた元航空幕僚長の田母神俊雄氏のツイッターが、またしても批判の的となっている。イスラム国に拘束されているジャーナリスト後藤健二さんと母・石堂順子さん親子について、名字が違うことから、「ネットでは在日の方で通名を使っているからだという情報がながれています」と書くなど、真偽不明の投稿を繰り返しているためだ。石堂さん会見に「少し違和感を感じます」渦中のツイートは2つ。2015年1月29日に投稿され、いずれも真偽不明、または事実誤認にもとづく内容で批判を集めている。1つ目のツイートは、「イスラム国に拉致されている後藤健二さんと、その母親の石堂順子さんは姓が違いますが、どうなっているのでしょうか。ネットでは在日の方で通名を使っているからだという情報が流れていますが、真偽のほどは分かりません。マスコミにも後藤健二さんの経歴なども調べて流して欲しいと思います」と書いたもので、9時46分に投稿された。名字が違うことに関して、石堂さんは週刊新潮の取材に対し、後藤さんが学生のころに離婚したためと答えている。2人が在日外国人だとする根拠は現段階で全くない。日本政府が後藤さんを在日外国人だと発表したことももちろんない。(以下略)---問題のツイートはこれです。田母神俊雄臆面もなく、まだ削除もしていないようです。(2015.1.31現在)親子で苗字が違うなんてことは、いくらでも起こりうることです。親の離婚や再婚、子の結婚(妻が姓を変えることが多いけれど、夫が変えることだってある)、養子縁組、などなど。後藤さんの場合は母親の離婚が原因だそうです。そういう可能性を全部すっ飛び超えて、「親子で苗字が違う、だから在日だ」って、どれだけバカなんだ、としか言いようがありません。ちなみに、韓国朝鮮は夫婦別姓ですが、私の経験上では、日本での通名は夫婦同姓にしている人が多いです。さらに言えば、ニュース等で後藤さんが日本を出国する際の映像が流されており、そこには日本国の旅券を手にした姿が写っています。つまり、後藤さんは100%確実に日本国籍があり、在日とかっていうのはデマであることが完全に確定しています。後藤氏のパスポートについて検証しているブログ日本国のパスポートを手にしている映像が確認できます。それにしても、です。もう一人の、殺害された(らしい)湯川氏は、自称「民間軍事会社CEO」で、田母神とツーショットで写っている写真が残されています。彼の会社の「顧問」という人物も自民党の元政治家。湯川氏のブログによれば、田母神が都知事選に出馬した際は選挙演説の手伝いにいったとか。ある種典型的なネトウヨです。さらに、田母神と湯川氏は双方ともアメーバーブログを使っており、アメンバー登録(アメーバーブログ利用者相互の友達登録)もしています。ところが、誘拐が発覚すると、田母神は、面識がない、いつ会ったかも覚えていない、だそうです。田母神が覚えていないのは、事実なのかも知れませんが(選挙運動の手伝いも、大勢参加しているんだろうし、田母神のアメンバーは1500人もいる)、自分の主義主張に賛同して選挙運動も手伝っていた人物が誘拐されたことについて、言うことはそれだけ?と思ってしまいます。湯川氏の行動には、落ち度はあったと私も思います。しかし、犯罪を犯したわけではないでしょうし、少なくとも誘拐されたり、殺されたりしてよいわけではないでしょう。それなのに、子の態度。そして、その湯川氏を助けようとして巻き添えを食ったと言われているのが後藤氏。田母神が湯川氏と面識があるからと言って、助けに行く義務があるわけではないし、そんな能力もないだろうから、お前が助けに行け、とは言いません。それにしたって、自分を信奉していた人物をわざわざ助けに行った人に対して、これが言うべき言葉なのか?呆れはてた話です。人としての信義というものがなさすぎます。湯川氏の最大の失敗は、こんな田母神を信奉してしまったこと、なのかもしれません。ところで、そんなネトウヨ系の湯川氏を助けに行った後藤健二氏。彼がどんな思想信条の持ち主だったかは知りませんが、取材の方向性、著作や人脈から考えると、どちらかというとリベラル系で、少なくともネトウヨ系でないことは間違いありません。でも、ネトウヨ系の湯川氏を助けに行った。以前にも一度助けたことが会って、面識はあったようですが、人のつながりは政治的主義主張だけでは決まらない、ということですね。
2015.01.31
コメント(5)
-

2月11日 フォルクローレコンサートのお知らせ
東京からは若干遠いですが、神奈川県の大和市で、2月11日にフォルクローレ・コンサートを開催します。2月11日(祝)午後1時半開場 2時開演場所 大和市渋谷学習センター小田急江ノ島線高座渋谷駅下車すぐ入場 無料対象は一応大和市在住在勤者となっています。(一応、です)出演 ルミ・マユ・オルコ/エストレージャ・アンデイーナ/森の風人/キント・スーヨ終演 午後4時ころ私は、エストレージャ・アンディーナのメンバーとして出演予定です。エストレージャ・アンディーナキント・スーヨ森の風人※曲名が?となっていますが、Camino de llama(リャマの道)という曲です。
2015.01.30
コメント(12)
-
積極的破滅主義
スカイマーク:破綻 民亊再生申請、支援協議不調経営不振が続く国内航空3位のスカイマークは28日、自力での再建を断念し、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理された。負債総額は710億8800万円だが、欧州航空機大手エアバスとの違約金交渉次第で増える可能性がある。西久保慎一社長は退任し、後任に有森正和取締役が就いた。国内27路線の運航は継続する。国内航空会社の破綻は、2010年1月に会社更生法の適用を申請した日本航空以来。スカイマークはLCCとの競争などで搭乗率が低迷した上、円安で燃料費が膨らみ、収益が悪化した。さらに、エアバスから超大型機A380の発注見送りを巡り、多額の違約金を求められたことを受け、14年9月中間決算で57億円の最終(当期)損失を計上していた。---A380発注キャンセル騒動と同様に、「まさか」というよりは「やっぱり」というのが正直な感想です。そして、破綻に至った要因は様々あるにしても、A380キャンセル騒動が、かなり大きな要因を占めていることは明らかです。私は、いち飛行機ファンとしては日本にA380を導入する航空会社があることをうれしく思ったけど、あの規模の新興航空会社がA380という巨人機を6機も購入って、大丈夫なの?思っていました。別に私だけが思ったことではないはずで、誰だってそう思ったはずです。もちろん、社内にだって、身の丈にあっていないのでは、と考えた従業員、役員がいなかったはずがない。でも、ワンマン社長が鶴の一声で決めたA380導入に、「無理でしょう」とストップをかけられる人はいなかった、ということなのでしょう。元々、西久保社長は経営不振でいつ倒産してもおかしくなかったスカイマークの経営を引き受けて、一度は立て直した実績があります。だから、経営手腕はある人だったのでしょう。その時は、おそらくこんなイケイケドンドンで無謀な大型機購入に走るようなやり方ではなかったはずです。そんなことをやっていたら、スカイマークはとっくに倒産していたでしょうから。ところが、経営立て直しに成功した途端に、それを過信したのかどうかは分かりませんが、無謀な方向に走り始めた。報じられているところによると、スカイマークは、元々エアバスとは別の機種の購入交渉をする予定だったのに、社長がエアバス社に出向いて直接交渉した際、A380を勧められたら、その気になってしまって、導入を決めてしまったとのことです。慎重な経営判断の末の決定ではなかった。元々、購入予定だった機種は、おそらくA330じゃないかと思うのですが、それも導入を見送ったわけではなく、結局A330もA380も導入を進めています。スカイマークは、西久保社長が就任した当時はB767という中型機を保有していましたが、それを手放して小型のB737に一本化することで経営を立て直したのに、ちょっと経営が上向きになったからと、中型機のみならず超大型機まで導入は、経営規模から見ても無謀過ぎたのでしょう。しかし、威勢の良い積極拡大論に対して、慎重な意見はかき消されるだけだったのでしょう。その、イケイケドンドンの末に待っていたのが経営破綻です。個人でも組織でも国家でも、右肩上がりのときは多少の無理も効くし、積極論がうまくいくときもあるでしょう。しかし、それも限界はある。それに、永遠に成長し続けられる人も組織も国家も、存在するはずがないのです。限界が見えている時ほど、慎重であらねばならないのに、そういう時ほど人は冒険したがるのでしょう。問題なのは、そういう時にストップをかけられる人がいるか、ということです。威勢が良くて勇ましい積極論に、慎重な意見が吹き飛ばされる、というのは、必ずしもスカイマークだけの話でもないでしょう。橋下市長、都構想で職員に「できないと言うな」橋下徹・大阪市長は大阪都構想の準備作業に関し、市役所で記者団に「個々の職員が『(目標までに)できない』などとメディアに向けて個人の感想を言うことは許されない」と述べ、職員に対して発言を控えるよう「情報統制」する考えを示した。都構想は、5月17日に大阪市民による住民投票で成否が決まる見通し。橋下市長は市内部から構想に否定的な意見が出され、住民投票に影響することに神経をとがらせている。市は今後、組織再編を想定した準備を始めるが、橋下市長は「市役所を一から作り直すのだから、無理な理由はいくらでも挙げられる。責任も権限もない職員が、あれやこれやと発言するのは組織としてあり得ない」と述べ、今後は自身が説明するとした。橋下市長は20日の幹部会議でも「職員は『できるように努力します』以上の発言はしないように」と求めたという。---これなんかも典型的だな、と思ってしまいます。「出来るように努力します」以外はいうな、と。ブレーキはいらない、アクセルだけだというわけです。アクセルだけあってブレーキがない車は、スカイマーク同様、どこかで事故を起こして止まるしかないわけですが。責任も権限もない職員って、臨時雇用のアルバイトですか?正規職員なら、職責による程度の差はあれ、責任も権限もあるはずですが。それに、実際に実務を行うのは、一般職員でしょう。ソフト工藤監督3禁 ガム×ツバ×弱音×ソフトバンク工藤公康監督が3つの禁止事項を掲げた。「試合中のガム」「ツバ吐き」「言葉の禁止」で、23日に行われた監督・コーチ会議で全スタッフに通達。これから選手に徹底していく方針だ。~「言葉の禁止」では、3つのNGワードを設定した。「できません」「分かりません」「しようがない」の禁止だ。工藤監督は現役時代から向上心を大切にしてきた。その気持ちを阻害する言葉は不要。自分自身をより高めていく姿勢を選手に期待している。---これも同様の匂いを感じます。現役時代の工藤投手は割と好きだったんですけどねえ・・・・・・。もちろん、いくらなんでも「中二日で先発完投を一年通せ」みたいなことは言わないだろうと思いますけどね。
2015.01.29
コメント(6)
-
意見が一致しているなら結束もできるが
自民・山本一太氏、人質事件で与野党結束訴え自民党の山本一太前沖縄・北方相と学習院大の野中尚人教授が27日、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、イスラム過激派組織「イスラム国」によるとみられる日本人人質事件への国会の対応について議論した。山本氏は、国会審議について「今のタイミングで政府の対応をただされても、外に明かせないことがある。(事件を)攻撃の材料として野党が使うことは控えてほしい」と述べ、与野党の結束を訴えた。野中氏も「事件が一段落するまでは(国会は)あまり余計なことはしなくていい。後でしっかり論戦をしてほしい」と語った。---与野党の結束、というけれど、国会内の各党のこの件についての主張はよく知らないけど、世間一般には自己責任だから放っておけという論から、身代金を払うべしという意見まで、いろんな論が満ち溢れています。全国民の意思がひとつになっている、という状況でもないのに口を出さずに黙って見ておれ、的な言い分は、まったく承服しがたいものです。黙って見ていられるほど、安倍政権のやることなすことに安心感が感じられません。今回の件だって、二人の日本人がイスラム国の拘束されている事実を政府は把握していたと報じられています。にもかかわらず、安倍はイスラム諸国と敵対的な関係のイスラエルを訪問し、またイスラム国を名指しで、それに対する対策のためとして2億ドルの援助をぶち上げたのです。要するに、イスラム国に人質を取られている、という事実の価値判断(言い換えるなら、人質を利用するイスラム国の凶悪性、狡猾さについての判断)を誤った結果がこの事態だったわけです。あとでしっかり論戦、と言っても、現に今、人質の命がかかっています。すでに1人は殺されてしまったようですが。殺されてしまった後で論戦しても、命は返って来ません。もちろん、最善を尽くして、それでも救えなかったのであればそれは仕方がないとは思います。安倍政権は、最大限の努力は払うだろうとは思います。問題は、その努力が、最善最善の結果をもたらす方向に向かうのかどうか、です。ずれた方向に努力を集中しそうな不安感を私は感じるのです。外に明かせないことがある、と。そりゃもちろんそうでしょう。何でもかんでも明らかにしていたら、交渉になりませんから。問題は、明かせないことについて、政府に任せよう、という信頼感があるかないか、です。少なくとも私は、そういう信頼感を安倍政権に対して持ちえません。あえて言うなら、「外の明かせないこともある」ということは分かった、と。ならばその代わり、限られた情報から(ひょっとしたら)的外れな批判が生じたとしても、それは許容せよ、ということに尽きます。話は変わりますが、少し前に、二人の人質のコラージュ画像をイスラム国関係者のツイッターアカウントに送りつける日本のネットユーザーが批判を浴びている、という話を記事で紹介したことがあります。それに対して、テロリストを挑発して日本をテロの標的にしたらどうしてくれる、という批判がかなり起こっているようです。でも、日本政府のトップ自身が、イスラエル訪問とイスラム国敵対宣言という、思いっきりの挑発行為に及んでいます。首相がイスラム国を挑発するのはよくて、ネット民が挑発するのは悪いのでしょうか。テロリストに屈するのは悪だ、というのであれば、ネット民によるコラ画像送りつけという挑発行為を控えることも、テロリストに屈すいることになるでしょうし、そもそも「危ないからシリアには渡航しない」ということもテロに屈っした、ということになってしまいます。「テロリストに屈するな」という言葉は簡単だけど、何が「テロに屈する」ことなのか、という評価は、なかなか難しいものです。
2015.01.28
コメント(0)
-
パソコン対タブレット
パソコン国内出荷3%減…タブレット右肩上がり電子情報技術産業協会(JEITA)が22日に発表した2014年のパソコン国内出荷台数は、前年比3%減の1085万台だった。1~5月は前年同月比で2けたの伸びを記録したが、6月以降は7か月連続で前年割れとなった。出荷台数が大きく増減したのは〈1〉14年4月に米マイクロソフトの基本ソフト「ウィンドウズXP」のサポートが終了したことに伴う買い替え需要が増えた後、一段落した〈2〉消費税率引き上げ前の駆け込み需要と、その反動減―が要因だ。JEITAは「反動減は当面続く」とみている。一方、パソコンと競合する形のタブレット端末は右肩上がりだ。調査会社のMM総研によると、14年度上半期(14年4~9月)の国内出荷台数は、前年同期比20%増の413万台。14年度の1年間では前年度比21%増の910万台を見込んでいる。---1年間トータルの数字で、販売台数がパソコン3%減の1085万台対タブレット21%増の910万台だそうです。仮にこのままの伸び率と仮定すると、2015年の販売台数はパソコン1052万台、タブレットは1101万台となり、販売台数が逆転することになります。実際に、去年6月の時点で、2015年にはパソコンとタブレットの販売台数が逆転するだろう、という報道があります。2015年度にはタブレットとノートPCの出荷数が逆転、スマートデバイス需要調査なるほどね、と思います。販売台数が逆転しても、すでに世の中に出回っている台数はすぐには逆転しないでしょうが、時代の趨勢としてはパソコンよりタブレットの方が優位になりつつあるようです。私の場合は、デスクトップパソコンとiPad miniの両方を持っています。で、どちらも頻繁に使っていますが、自宅では、基本的にはパソコンをメインに使っています。iPad miniを買った当初は、自宅でもiPad miniを使うことが多くなり、パソコンを使う機会が激減したのですが、次第にパソコンが勢力を盛り返してきました。決定的だったのは、11月に新しいパソコンを組んだことです。それまでのパソコンは起動に1分以上の時間を要していましたが、新しいパソコンは起動時間が20秒ちょっとしかかからない。パソコンの欠点は起動に時間がかかることだったのですが、その欠点がほとんど解消されてしまいました。一方、iPad miniのほうは、本体の起動は一瞬ですが、無線LANの起動と接続に時間がかかる。外で使っているモバイルルータは起動は割合速いのですが、自宅の無線LANはパソコンの起動より時間がかかります。最近は、子どもが3DSのために自宅の無線LANをつけっ放しにしていることが多いのですが、夜間などはやっぱり電源を落としています。で、起動時間以外のことでいうと、まずタッチパネル式のタブレットより、マウスを使うパソコンのほうが私には使いやすいです。タッチパネルでコピー&ペーストは、結構面倒なことがあります。これは、iPad miniが7インチクラスで画面が小さいせいもあるでしょう。10インチのでかいタブレットなら、ひょっとしたら話は変わってくるかもしれません。だけど、10インチクラスの馬鹿でかいタブレットを家の外に持ち歩く気にはなれませんけど。そして、パワーが違う。iPad miniはデスクトップパソコンに比べると、いかにも非力です。iPad miniに動画編集アプリなんてあるのかどうかは知りませんけど、あったとしてもとても使おうとは思いません。写真編集アプリは入れてあるのですが、今ひとつ使いにくいのと、動作が重いので、ほとんど使っていません。そういう重い作業は、明らかにパソコンのほうが快適です。文章を書くこと自体は、外付けのキーボード(自宅ではBluetuthのキーボードをパソコンとiPad mini兼用で使っています)を使えば、優劣はあまりありません。ただ、前述のようにコピペがiPad miniだと若干面倒なので、ブログを書くときはどうしてもパソコンのほうが楽です。※若干の余談ですが、パソコンはWindows上ではBluetuthのキーボードを認識しますが、BIOS上では認識しません。だから、BIOSの設定を動かすときだけUSB接続のキーボードを引っ張り出しています。普段はキーボードを2台も並べるのは邪魔なので、引き出しの中に放り込んでありますが。いろいろ考えると、パソコンが使える条件のときはパソコンのほうが使いやすい、というのが私の感覚です。ただ、デスクトップパソコンは家の外には持ち出せません。ノートパソコンなら持ち歩けますけど、タブレットほど軽くはありません。だから、家の中でも家の外でも使う、パソコンかタブレットかどちらか1台だけ、ということになると、タブレットになってしまうのかもしれませんね。両方持っているのが一番いいのですが。
2015.01.27
コメント(0)
-
生活保護費をプリペイドカードで?
生活保護のプリカ支給「当たり前」か「権利侵害」か大阪市の橋下徹市長が、生活保護費の一部をプリペイドカードで支給するモデル事業を発表し、波紋が広がっています。橋下氏は「記録化が一番重要」と意義を強調していますが、受給者の権利を侵害するとして、中止を求める声も出ています。橋下市長は経済的な自立のためには、「支給と支出を管理するのは当たり前」と語り、支出管理による自立支援の意義を強調しています。 「プライバシー権を侵害する」「使う店が限定され不便」「カード会社が儲かるだけ」など反対の声も出ています。 法律家らによる団体は「金銭給付の原則に反し違法」として、要望書を提出する構えです。---福祉事務所に関係する知人に言わせると、プリペイドカードなんて無駄なことだそうです。生活保護受給者の大半は高齢者ですが、その多くは日常生活には特に問題がなく、保護費の範囲内で自律的に生活できる人だそうです。そういう人たちにプリペイドカードなど必要ない。一方、比較的若い世代の生活保護受給者には、さまざまな精神疾患、人格障害、アルコールその他の依存症などなど、いろいろな問題を抱えている人が少なくないようです。金銭の自己管理ができない、お金があればあるだけ使ってしまう人に対しては、福祉事務所は生活保護費を毎週、場合によっては毎日小分けして渡すこともあるそうです。しかし、それは担当職員にとっては大変な負担です。全身から臭気を漂わせている人、かばんの中にゴキブリが潜んでいる人、やたらと攻撃的な人・・・・・・そんなタイプの人たちと、毎週、まして毎日顔をあわせるのは、いくら仕事だって辛いですよね。知人の場合は、週2回までは経験があるそうですが、それはそれは大変だったとのこと。ならば、そういう人たちの金銭管理にプリペイドカードは役に立つか、というと、あまり役には立たないだろうということです。そもそも、そんな状態に陥った人間が長期間安定して居宅生活なんかできるわけがないのです。生活保護費を小分けして渡すような対応を取らざるを得ない受給者が、そのままの状態で長く居宅生活を続けることは、ますほとんどないようです。多くの場合は、遠からず入院か施設に入る、またはそれが嫌で姿をくらまして生活保護が打ち切りになる、という結末になるようです。橋下市長は経済的な自立のためには、「支給と支出を管理するのは当たり前」と語ったそうですが、金銭を自分で管理できずに生活保護になったような人が、経済的な自立などできるわけがありません。報道によれば、保護費(家賃を除く生活費)のうち、プリペイドカードの分は約3万円だそうです。大阪を含む大都市の生活保護基準は、年齢によりますが一人世帯で7万5千円から8万円くらいなので、結局現金で手にする部分が半分以上になります。金銭管理ができないからプリペイドカード、という状況の人なら、この、プリペイドではない部分に手をつけてしまうであろうことは、火を見るより明らかです。かといって、全額をプリペイドカードにするのはできない相談です。どう考えても、すべての支払いをプリペードカードで行うことは不可能だからです。光熱費や電話代の引き落としとか、交通費(電車やバスの切符代)など、現金または銀行の預金の状態でなければ対応できないものは、日常生活の中で少なくありません。そこを福祉事務所で金銭管理するなら、結局全部金銭管理するのも同じことです。つまり、生活保護受給者にプリペイドカードというのは、一見もっともらしく見えるけれど、それに要するであろう事務コストと、それによって得られるメリットの釣り合いがまったく取れないことが容易に予想できるわけです。カード会社を儲けさせるだけで、たいして役にも立たないプリペイドカードなんて、導入する意味はないと思われます。
2015.01.26
コメント(2)
-
これはどう評価すべきか・・・・・・
「イスラム国」新たな映像、写真持つ後藤さん「彼ら(イスラム国)はもう、金銭を要求しません」などとし、ヨルダンで拘束されているとみられる女死刑囚の釈放を求めた。この死刑囚は、2005年11月にヨルダンの首都アンマンで起きた同時爆破テロ事件の実行犯の一人として生き残ったとされる。安倍首相は25日未明、首相官邸で記者団に対し、「湯川氏が殺害されたとみられる写真がインターネットに配信された」と述べた。さらに「このようなテロ行為は言語道断。許し難い暴挙だ。強い憤りを覚える。断固として非難する」と語った。---日本政府が手をこまねいているうちに、どうも人質の一人が殺害されてしまったようです。そして、イスラム国側の要求が、身代金要求からヨルダンで拘束されている死刑囚の釈放に変化した、ということです。これは、きわめて難しい局面になってしまったと言わざるを得ません。身代金なら払うことはできますが、ヨルダンで死刑判決を受けている死刑囚の釈放を日本政府が決める権限などないからです。それを決めるのはヨルダン政府です。日本政府としては、ヨルダンにお願いすることくらいしかできません。それすら、安倍政権がやるかどうかは分かりませんけど。いろいろ調べると、この死刑囚は、イスラム国の捕虜となっているヨルダンのパイロットとの捕虜交換の動きもあったそうで、釈放がまるっきり不可能、ということでもないようですけどね。ただ、この死刑囚は夫と一緒に自爆テロを試み、夫は自爆、本人だけ生き残ってしまった、という経緯だったようです。ということは、釈放されてどうなるの?結局また自爆テロをやるだけだとしたら、死刑でも釈放でも何も変わらない(死刑なら本人が死ぬだけだが自爆テロなら多くの死者が出る)、むなしい、実にむなしい選択肢としか言いようがありません。それはともかくとして、話は変わりますが、今回の人質騒動を契機に、イスラム国対日本のネットユーザーの場外バトルまで発生している、との報があります。ISISメンバーが日本人人質コラ画像に激怒か?ネット上からも厳しい批判の声邦人男性2人の殺害予告映像を公開したISISの関係者に対し、その後、twitter上でハッシュタグをつけ、コラ画像を投稿するという、実に不可解なムーブメントが巻き起こっていることについて、その後、ISISの関係者が、こうした日本人の行為に対して激怒。2人の安否を気にする日本のユーザーからも、批判が相次いでいる。~こうしたユーザーの中には、ISIS関係者宛にこれらの画像を送り、そのリアクションを楽しむという、にわかに信じがたい行為を行う者まで出る始末であった。当初は、こうした日本人の行動に対し、さほど敵意を見せなかったISIS関係者であったが、その後、あまりにこうしたユーザーが続出したことに腹を据えかねたのか、日本在住の日本人に対しても、危害を与える可能性について言及。ネット上で強く警告を発するメンバーも出現したことから、一部の心無いユーザーに対し、ネット上では厳しい批判の声が相次いでいる。---最初、この報道を見たとき、何という狂気の沙汰としか思えなかったのですが、いや、今もそう思っていますが、もともとイスラム国という狂気に対抗するのに、別種の狂気をもってするのも、案外有効な手段かもしれない、という気がしなくもありません。イスラム国には、欧米からも相当の戦闘員が流入しているといわれます。二人の日本人と一緒に動画に写っていたイスラム国のテロリストも、イギリス出身の人物らしいという話もあります。イスラム国は、インターネットを駆使して世界に発信してリクルートをしているわけですが、それらのツイッターアカウントがそういう種類の画像が殺到すれば・・・・・・、今回、問題となったイスラム国関係者のアカウントは、早々に削除されてしまったそうです。イスラム国による情報発信がやりにくくなる、という効果はある程度期待できそうです。もっとも、アカウントを削除してもまた別のアカウントを作るだけでしょうから、いたちごっこではありますけど。ただし、それだけで済むかどうかは分かりません。イスラム国側関係者が、アカウント削除前に「日本人よ、なんて楽観的なんだ。5800kmも離れて、安全地帯にいると思っているからか。我々はどこにだって軍隊を持っているぞ」「二人の顔を切った後にお前の顔を見てみたい」などと捨て台詞を残しているので、ひょっとすると今度は日本をテロの標的にしてしまうかもしれない。そうなると、この行為は最悪の挑発行為だった、ということになります。イスラム国側にどれだけ日本語を解する人材がいるかにもよりますが、個人情報を抜かれて直接攻撃を受けるリスクもある。とはいえ、インターネットで世界がつながっています。テロリスト側もまたインターネットを駆使しているとなると、良し悪しの問題はともかく、現実の問題としてこういう事態が起こるのは避けがたいでしょう。インターネット上に立ち入り禁止も非常線もありませんから。とりわけ、ツィッターやFacebookは、本当に世界中の誰とでも直接のやり取りができてしまいます。言語の問題はありますが、音楽や画像、映像は言語の違いをある程度は超えられます。「バカッター」騒動と根の部分は同じかもしれませんが、いくら相手がテロリストであっても、会話すること自体が禁じられたり、非難されたりするわけではないですからね。
2015.01.25
コメント(0)
-
またぞろ自己責任論
身代金、自分で払わせれば良い」「危険承知していた」 拘束された2人にネットで吹き荒れる「自己責任論」「イスラム国」を名乗る集団から殺害が警告されている湯川遥菜さんと後藤健二さんに対し、ネットでは「自己責任論」が噴出している。2004年、紛争地だったイラクで日本人3人が武装勢力の人質となった当時を思い起こさせる状況だ。2人がイスラム国に拘束されるまでの経緯は2015年1月21日現在はっきりしないが、これまでの報道をまとめるとシリア入りの目的が少しずつ明らかになってきた。北部アレッポで拘束された動画が8月に公開されて以降、消息が分からなくなっていた湯川さんに関して、軍事会社の関係者は「実績が作りたかったのではないか」などと各紙の取材に答えている。一方の後藤さんは、知人で現地ガイドの男性が「友人の湯川さんの情報を得るために行った」と話しているとし、救助のために現地入りしたと各紙が報じている。2人は現地での危険を認識していなかった訳ではない。湯川さんは最後の更新となった7月21日のブログで「今までの中で一番危険かもしれない」と書いた。後藤さんも、ガイドの男性が撮影したという動画の中で「これからラッカに向かいます。どうかこの内戦が早く終わってほしいと思っています。何が起こっても、責任は私自身にあります」と話している。しかし結果は人質として拘束され、日本政府には計2億ドルという法外な身代金が要求されることとなった。ツイッターをはじめ、ネットでは「そもそも行くなって言われてんのに行ったのは自己責任でしょ」「もし払うなら自己責任は明白なので自分で払わせれば良い。危険地帯を承知で出かけているのだから」と「自己責任論」が吹き荒れている。「拘束された奴の命がどうなろうと、現地へ行った奴の自己責任なんだからほっときなよ」という書き込みや、「そもそも後藤、湯川両氏はイスラム国と意を同じくしているのではないか?とすら思う」「捕まったやつはイスラム国の仲間で日本から資金得るため演技してんだよ」とイスラム国と共謀した自作自演を疑う人までいる。同様の見解をする著名人もいる。タレントのフィフィさんは「この時期にあの地域に入るのには、それなりの覚悟が必要で自己責任」とツイート。元衆院議員の渡部篤氏は、2人について「日本政府が要請してシリアに行ったのではない」と突き放す。「冷酷かもしれないけど、イスラム国のテロに屈してはならない。ここで妥協すれば、世界中の日本人がテロに狙われることになる」と持論を書いた。(以下略)---引用記事にも指摘されていますが、2004年のイラクでの人質事件の際の騒動を思い出させるような状況になっているようです。政府として人質を救出するためにできることには、おのずと限界はあり、何でもできるわけでもないとは思います。私は、身代金を払うことはあり、だと思っていますけど、それを政府や関係者が公然と口にできないということはわかります。2億ドルという金額も、さすがにそれは、というところでしょう。それらの限界はあるにしても、危機に陥った人を救助するために関係機関が努力を払う、危機に陥った理由は問わない、というのは、公的機関として当然のことです。たとえば、少し前にスキー場で滑走禁止の場所で滑走して遭難した人がいました。救助された際に、救助隊に相当叱られた様子でしたが、それは救助したあとの話であって、「自分から滑走禁止の場所に入っていったんだから救助しない」などという対応がとられることはありませんでした。世の病気や怪我の中には、たとえば食事の嗜好とか飲酒に起因する成人病や依存症、無謀な行動に起因する怪我、果ては自殺未遂まで、「身から出たさび」のものが相当数含まれます。だからと言って、好き好んで高塩分高カロリーの食事を取り酒を飲んだせいで脳出血になったんだから治療しない、とか、自殺を図ったんだから、治療の必要はない、などということはありえないわけです。そりゃ、治療しても治らないものは治らない、という現実はありますし、個別には家族や医療関係者、福祉関係者などのいろいろな心情は渦巻いていることは確かでしょうが。二人の人質のいろいろな経緯を見ると、自称「民間軍事会社CEO」のほうは、確かに本人の行動に無謀な点、問題がありすぎると私も感じます。一方、ジャーナリストのほうは、最初に人質になった「民間軍事会社CEO」を救助しようとして、言ってみれば二重遭難をしてしまったような状態です。同情の余地は大いにあり、と思います。政府が何もやらないから、彼が赴いた、という側面もあるのでしょうし、救出云々は別に考えても、ジャーナリストである以上、危険地域であるからこそ、取材の必要があることもまた事実です。いずれにしても、これらの点について経緯をただし、批判すべき点があれば批判するのは、彼らが救出された後でも遅くはない。「ここで妥協すれば、世界中の日本人がテロに狙われることになる」という渡部篤の発言が紹介されています。こういう言い方で、まるで、一銭も払わずに二人が殺されることこそが正義であるかのような言い方をする人が他にも大勢いますが、本当にそうなのでしょうか。先日の記事で過激派「イスラム国」がシリアで人質にした外国人のうち23人について過酷な監禁の実態や、身代金支払いの有無が人質の殺害か解放かを左右している状況を報じた。身代金支払いを拒む米英の人質で解放された事例はない。~米英人は7人いたが、4人が殺害され、ほかも拘束されたまま。殺害されたロシア人1人を除くフランス人やスペイン人など残りは全員解放され、1人当たり平均200万ユーロ以上が支払われたとされる。という報道を紹介しました。米英は身代金を払わず、イスラム国に一切妥協しない「毅然とした態度」の結果、人質はみんな殺され、あるいは誰も解放されていないわけですが、そういう態度にもかかわらず、イスラム国は米英人を人質にとることをやめてはいません。引用記事には身代金を払った例としてフランスとスペインが紹介されていますが、それ以外にもドイツとイタリアも身代金を払っているようですが、身代金を取れるフランス・イペイン・ドイツ・イタリア人が、身代金を取れない米英人より優先的に狙われている、としいうような証拠はまったくないのが現実ですから、「身代金を払えば日本人は世界中で狙われる」という話は相当に怪しいと考えるしかありません。
2015.01.24
コメント(0)
-
無償アップグレードはいいが・・・・・・
マイクロソフト:ウィンドウズ10を無償提供…戦略転換米マイクロソフトは21日、今年後半に発売する次期OS「ウィンドウズ10」を発売から1年以内に限り「7」以降の利用者に無償提供すると発表した。新OSを有料としていた従来の戦略を転換し、既に無償化している米アップルや米グーグルに対抗する。MSは、パソコンのOSでは圧倒的なシェアを持っているが、普及が加速しているスマートフォンではアップルやグーグルに出遅れている。パソコンとスマートフォンとの連動性を高めた新OSを無償提供することで、シェア拡大を目指す。「10」には新たな閲覧ソフト「スパルタン」(仮称)も搭載した。---それはすごい、最新のOSにタダでアップグレードできるのなら、喜んでアップグレードします、と、言いたいところですが、実際のところはかなり躊躇しますね。まず、新しいOSというのは、まだどこにバグが潜んでいるか分からないし、周辺機器の対応ドライバなどもまだ未整備、ということも多いのです。そもそも、古い周辺機器はサポートされないかもしれないし、ソフトも同様の可能性があります。だから、私は新しいOSを入れるときは、しばらくの間古いOSと並行使用しています。Windows98からXPに移行したときは、2台のパソコンをしばらく並行して使用したし、XPから7に移行したときも、パソコンは1台でしたが、両方のOSどちらでも起動できるデュアルブートの状態にして、しばらくの間は使っていました。私のパソコンからは、今はXPは消してしまいましたが、実は相棒のパソコンは今もXPを削除しておらず、デュアルブートが可能な状態になっています。実際には、もうXPで起動することはないのですが、削除するのが面倒で、まだやっていません。というわけで、無償提供はいいのですが、問題は、新規のクリーンインストールが可能なのか、上書きインストールしかできないのか、という点です。2020年まで使えるウィンドウズ7をわざわざ消して、新しいOSに乗り換えようとは思いません。新規のクリーンインストールが可能なら、既存のウィンドウズ7は消さずに、デュアルブートで2つのOSを並行して使えますから、無償提供を利用するのも悪くないですが。もうひとつの問題は、発売開始から1年間のみ、というところです。提供がオンラインのみだとすると、結局1年後にインストールしようと思ったら、やっぱり購入するしかありません。と、いうのは、私は自作機を使っている関係で、パソコンを新しくするタイミングとOSを新しくするタイミングが、まったく一致しないのです。パソコン本体を変える(実際は、中身を入れ替えるだけで、ケースはそのままですが)ときはOSは前のパソコンからの流用で、OSを変えるときは、パソコン本体は前のまま、ということがほとんどです。つまり、無償アップグレードを利用してタダでOSを手に入れたとしても、結局その後パソコンを新調する時点で、やっぱりお金を払ってOSを買わなければならなくなる、わけです。そう考えると、私のようなパソコン自作派にとって、無償アップグレードのメリットは、それほど大きくもないなあ、というのが正直なところです。それに、タブレットも、私が使っているのはiPad miniなので、Windiowsは入れられないですし。
2015.01.22
コメント(0)
-
なぜイスラエルなどに行ったのか
イスラム国邦人人質:日本人2人殺害を警告 ネットに映像内戦が続くシリアと、イラクの一部地域を勢力下に置くイスラム教スンニ派の過激派組織「イスラム国」とみられるグループが20日、日本人男性2人を拘束している映像と共に、日本政府に72時間以内に身代金2億ドル(約236億円)を支払わなければ殺害すると警告するビデオ声明をインターネット上に公開した。菅義偉官房長官は、ビデオが公開された直後の午後2時50分ごろに政府として確認したと説明しており、身代金の支払期限は日本時間23日午後とみられる。ビデオは約1分40秒。男は安倍晋三首相に呼びかける形で「私たちの女性や子どもを殺し、イスラム教徒の家を壊すために1億ドルを拠出した」と日本を一方的に非難。さらに「イスラム国の拡大を止めるためにムジャヒディンと戦う背教者の訓練に1億ドルを拠出した」として要求額を1億ドル上乗せした。ナイフをかざしながら身代金支払いの期限を「72時間」と指定し「もしそうでなければ、このナイフがお前たちの悪夢になる」と警告した。---人質をとって身代金を要求する、つまり営利誘拐ですが、これは言うまでもなく言語道断の暴挙です。ただ、イスラム国というテロ集団が言語道断の存在であることは、今に始まった話ではありません。問題は、なぜ今2人の日本人の身代金要求が飛び出したのか、ということです。声明ビデオによれば、日本がが「私たちの女性や子どもを殺し、イスラム教徒の家を壊すために1億ドルを拠出した」「イスラム国の拡大を止めるためにムジャヒディンと戦う背教者の訓練に1億ドルを拠出した」からだそうです。これ自体は、まったく事実無根の話です。2億ドルというのは、イラク・シリアとその周辺諸国の難民・避難民支援のための費用ですから。だけど、とにかくイスラム国対策として、日本が2億ドルを拠出すると発表したことは事実です。それに、アラブ諸国(もちろんイスラム国も)が敵視するイスラエルを訪問した。安倍は、なぜ今、このタイミングでイスラエルを訪問したのでしょう。今回殺害予告の出ているうちの一人は、「イスラム国に拘束されている」という報道は事前にはなかったように思いますが、もう一人の、自称民間軍事会社CEOの方は、昨年イスラム国に捉えられた際に盛んに報道されていましたし、当然日本政府もその事実を認識していたはずです。にもかかわらず、あえてイスラム国対策として2億ドル拠出を表明し、またイスラエル(この国がパレスチナでやってきたこともまた、ある種のテロのようなものであろうと私は思います)を訪問する、いってみれば、人質のことなど眼中になかったわけです。人質のことなどより、安倍の外遊が国際的に注目を集めることのほうが大事だったのでしょう。ことは、二人の人質だけの問題にはとどまりません。日本国外で日本人がイスラム過激派に拘束されたり、その結果殺害された事例は過去にもありましたけど、日本が名指しで直接イスラム過激派の標的にされたことは、今までになかったように思います。これからは、日本が直接イスラム過激派の攻撃目標にされることを警戒しなければならないとすれば、安倍のイスラエル訪問の影響は重大です。そういえば、日本の右翼には、イスラエルが大好きな人たちがいます。以前に、は田母神俊雄元航空幕僚長が率いて、イスラエル国防視察ツアーという企画があり、それを批判する記事を書いたことがあります。田母神と行くイスラエル国防視察団だそうで「キリストの幕屋」という、イスラエルべったりの右翼系宗教団体もあります。いくら何でもそんなことはないと思うけど、まさか安倍はネトウヨ支持層へのサービスとしてイスラエルを訪問先に入れた、なんてことはないでしょうね。それにしても、二人の人質を、日本政府はどうするのでしょうか。なんだか、身代金を払って救出することは、「テロに屈した」みたいな、一銭も払わずに二人が殺されるのが正義であるかのような議論がまかり通っていますが、本当にそうでしょうか。人質解放は身代金が左右? 米紙報道米紙ニューヨーク・タイムズは(10月)26日、過激派「イスラム国」がシリアで人質にした外国人のうち23人について過酷な監禁の実態や、身代金支払いの有無が人質の殺害か解放かを左右している状況を報じた。身代金支払いを拒む米英の人質で解放された事例はない。~米英人は7人いたが、4人が殺害され、ほかも拘束されたまま。殺害されたロシア人1人を除くフランス人やスペイン人など残りは全員解放され、1人当たり平均200万ユーロ以上が支払われたとされる。---これを読む限り、身代金を払わずに人質を見殺しにするのは米国とイギリスだけで、フランス・スペインその他の国々は、身代金を払って人質を取り戻しているようです。米国とイギリス以外の世界の大勢としては、身代金を払う選択肢もあり、ということです。もちろん、払った事実を外部に公表することは絶対にないでしょうが。それでも、日本は身代金を一切払わずに見捨てるのでしょうか。
2015.01.21
コメント(2)
-
あまりに根の深い問題
仏スーパー:射殺容疑者育ちの街 偏見と貧困、渦巻く憎悪「今すぐ出て行け」「これ以上ここにいると死んでもらう」。仏週刊紙襲撃など一連の事件で、ユダヤ教徒向けスーパーに立てこもり射殺されたアメディ・クリバリ容疑者が少年時代に住んでいたフランスでも最貧困地区といわれるパリ南郊グリニ市を歩くと、住民から脅しや、嫌悪の視線をあびた。アラブ系や黒人などイスラム教徒ら約3万人が住む街には、社会からの偏見と貧困を背景に、若者の強烈な憎悪が渦巻いていた。クリバリ容疑者が育った同市ラグロンドボルヌ地区の市場に入るや、イスラム教徒とみられる4人の若い男に取り囲まれた。「この間も記者を袋だたきにした」。黒いマスクで顔を覆ったリーダー格の男が怒鳴るような口調で脅してきた。同行したフランス人助手が取材目的を説明しても、とりつくしまもない。憎しみに満ちたまなざしにぞっとして、言葉さえ出なかった。モスクの建設募金をしていたオマールさんの取りなしで、その場を何とか切り抜けた。しかし、若者らは記者が地区外に向かうバスに乗り込むまでの数十分間、遠巻きに見張り続けた。パリ中心部から南へ鉄道とバスを乗り継いで約1時間半。5階建てのアパートが無造作に並ぶ。レストランや商店は見当たらず、白人にも出会わない。パリ中心部から30キロも離れていないのに、まるで別世界だ。バスの運転手は「財布を手にした瞬間に強盗に襲われる。気をつけろ」と強くくぎをさしてきた。ピザ配達さえ入ることができない地区−−。仏フィガロ紙がこう表現した現状を、オマールさんは話してくれた。「行政から見捨てられている。急患対応の医者や郵便配達も、治安が悪いからと来てくれない。火事が起きた時だけ消防がやってくる」。若者の未来も「がんばって大学を卒業し、就職先を探しても、出身地を書いた履歴書はゴミ箱に行く。不公平だ」と嘆く。~街を歩いて、日常生活での孤立感や「テロの温床」との偏見を食い止めない限り、「第二、第三のクリバリ」は止められない気がした。(以下略)---フランスで、アルジェリア系移民などへの差別が存在することはもちろん知っていましたが、これほどまでの状況とは、絶句するしかありません。私は、南米でスラム街的な地域に足を踏み入れたことはありますが、もちろんそういうところには悪いやつ(スリ、かっぱらい)はいるにしても、割合ではあくまで少数派で、「珍しいやつが来た」という視線はあっても、憎悪の視線を多数受けた経験はありません。日本でも、スラムと言っても間違いではないところに足を踏み入れたことは多々ありますが、こういう意味での危険を感じたことはありません。人格面に問題を抱えた特定の個人に、危険を感じたことならありますけど。「行政から見捨てられている。急患対応の医者や郵便配達も、治安が悪いからと来てくれない。火事が起きた時だけ消防がやってくる」火事のときだけ消防車が来るというのは、日本語では「村八分」と言いますね。それを行政自らが行ってしまうのは、発展途上国ならいざ知らず、先進国の一員としてはどうなのか、ということになります。もっとも、現実問題として、行政サービスに従事する職員や、宅配ピザの配達員の安全を保障できないでしょうから、こういう対応にならざるを得ないのでしょう。まさしく負の連鎖です。※そう考えると、日本では、清川・日本堤だろうが百人町だろうが、寿町だろうが、釜ヶ崎だろうが、警察も救急も郵便も、税務署も保健所の保健師も介護のケアマネも、生活保護のケースワーカーも、おそらく宅急便もピザの宅配もすし屋の出前も、何の問題なく、一人でやってきます。日本ってすごいかも、と思わないでもありません。それにしても、この状況下で、貧困と差別に対して憎悪をたぎらせる若者に「報道の自由」「言論の自由」と言っても、さすがにむなしい。そんなものより生きる自由の方が先だ、ということにならざるを得ないでしょう。そして、テロ対策も何も、このような差別と貧困の温床を放置したままでは、お酒を飲みながらアルコール依存の治療をするようなもので、効果が望めるとは思えません。フランスという、世界有数の先進国の一角に、同じフランス人でありながらおよそ先進国の生活レベルとは隔絶した人たちが放置されている、多分こういう状況はフランスに限った話ではないですけど、国家を分断して治安を悪化させる、もっとも根源的で深刻な要因はそこにありそうです。
2015.01.20
コメント(6)
-
謝罪することなんかないと思うのだが・・・・・・
サザン桑田さんがお詫びと釈明 年越しライブ・紅白出演昨年紫綬褒章を受章した人気ロックバンド「サザンオールスターズ」のボーカル桑田佳祐さんと所属事務所のアミューズは15日、大みそかに横浜市内で開いたサザンの年越しライブで、桑田さんが観客に向けて受章の喜びを報告する際に配慮が足りない部分があったなどとして、お詫びのコメントを発表した。桑田さんはズボンのポケットから褒章を取り出して観客に披露し、オークションにかけるまねをした。ツイッターなどで一部批判の声が上がり、東京都内の事務所前で抗議する人も出た。コメントでは「ジョークを織り込み、紫綬褒章の取り扱いにも不備があったため、不快な思いをされた方もいらっしゃいました。深く反省すると共に、ここに謹んでお詫び申し上げます」などと記した。また、中継で出演したNHK紅白歌合戦で、演奏前にちょび髭をつけて登場した件にも触れ、「つけ髭は、お客様に楽しんで頂ければという意図であり、他意は全くございません」とした。紅白では「ピースとハイライト」などを歌い、歌の「解釈」を巡ってツイッターなどに賛否の投稿が相次いでいた。さらに2013年の全国ツアーで、ステージ上でデモなどのニュース映像を演出で流したことにも言及。「緊張が高まる世界の現状を憂い、平和を希望する意図で使用したものです」「特定の団体や思想等に賛同、反対、あるいは貶めるなどといった意図は全くございません」などと説明した。(以下略)---引用記事には触れられていませんが、一連の騒動には前段があって、12月28日に安倍首相がサザンオールスターズのコンサートを鑑賞した際、「爆笑アイランド」の中で「衆院解散なんてむちゃをいう」とアドリブで歌った、ということがあったそうです。もちろん、桑田は安倍が見に来ていることを知った上でこのアドリブをやったようです。私は、桑田佳祐はそんなに強い政治的主義主張を持っている人ではないのだろうと、あえて色分けすれば「真ん中からやや右」くらいの人だろうと、考えてみれば何の根拠もない勝手な思い込みですが、そんな印象を抱いていました。紫綬褒章を受章した、という報道も、そんな印象に拍車をかけましたが。いや、実際のところ、今だって桑田が左翼である、などとは思いませんけど、一連の騒動で、安部の政治姿勢に賛同する人ではないこと、平和を大事だと考えている人だ、ということは分かりました。いいじゃない、お詫びなんかする必要は全然ないよ、と思うのです。それこそ言論の自由というものです。「特定の団体や思想等に賛同、反対、あるいは貶めるなどといった意図は全くございません」とのことですが、そういう意図があったとしても、「特定の団体や思想等に賛同、反対」することは言論の自由というものです。やっていることも、ごくささやかで暗喩的な意思表示に過ぎないですし。こんなことで騒ぎ立てて、所属事務所の前で抗議デモなんかをやらかす連中が異常なだけです。桑田の主義主張に対する賛否は、当然あってよいですが、桑田が怪しからんからと、こういう威圧的行動に出るのは、異常な行為です。
2015.01.19
コメント(0)
-
もう終わっちゃったの?
「Windows 7」、メインストリームサポートが終了一部のユーザーにとっては悲しいことに、米国時間2015年1月13日が来た。「Windows 7」の無償サポートが終了する日だ。幸いにもそれは、コンピュータが自動的に壊れたり動作を停止したりするという意味ではない。しかし、Windows 7ソフトウェアで問題が今後生じた場合、Microsoftはもう無償で支援やサポートを提供してくれないことを意味する。また今後は、新機能が追加されることもなくなる。Windows 7がリリースされたのは2009年のことである。6カ月で1億本を売り上げた後、絶大な人気を維持し続けている。前世代の「Windows Vista」よりも安定しており、大幅刷新された後継版のWindows 8よりもなじみ深いことから、Windows 7は今でも世界中のPCの半数で稼働していると推定されている。13日でWindows 7は、すべてのユーザーに無償でサポートが提供されるメインストリームサポート期間を終了し、延長サポート期間に入る。つまり今後、同ソフトウェアのサポートは有償になる。2020年には延長サポートが終了し、その時点でWindows 7は永遠に廃止されることになる。セキュリティ面を懸念するユーザーもいるだろうが、Microsoftはセキュリティ問題に対するパッチの提供は継続する予定だ。したがって、Windows 7を使い続けていると、コンピュータが突然、同ソフトウェアをターゲットとするハッカーらに対して脆弱になるということはないはずである。---我が家のパソコンは、私のは2012年、相棒のパソコンは2013年にWindowsXPからWindows7に変えたばかりです。それからまだ2年経っていないのに、もうWindows7のメインストリームサポート終了だそうで。ただし、WindowsXPも同じだったけれど、メインストリームサポートが終わっても、延長サポートが続いている限りは、実用上は何の問題もありません。ところが、その延長サポートも2020年には終了すると。まだ5年ありますけど、昨年秋に組んだこの自作機が寿命を迎えるかどうが、というあたりでWindows7の寿命を迎えることになりそうです。マイクロソフトのOSは、1世代ごとに出来不出来が交互に繰り返す傾向があるようです。私が初めてパソコンを持ったのはWindows98の時代でした。いろいろと問題はあったOSですが、いくつかの注意事項に留意すれば、私にとっては使いやすいOSでした。しかし、その次のWindows meは、あまり評判の良いOSではなかった。そして、その次のWindowsXPは、今更言うまでもなく、不朽の名作です。私も、10年以上にわたって永く愛用しました。その次のWindows Vistaは、最悪。これは、私自身のパソコンにVistaをインストールしたことはありませんが、実家が使っていたことがあった。よく「あそこが不調、ここが不調」と言われて、振り回されました。その次のWindows7は、まずまず評判も良いし、私も使い勝手の良いOSだと思っています。しかし、その後継であるWindows8は、評判を聞く限りはあまりよくないらしい。タッチパネル対応なのはよいけれど、タブレットには使いやすいけどデスクトップパソコンには使い勝手がよくない、という話ですね。私はWindows8には一度たりとも触れたことがないので、評判として聞いているだけですけど。私自身は、Windows98→WindowsXP→Windows7と、まずまず評判のよいOSを使ってきたことになります。では、この3つのOSの中でどれが一番使いやすかったかというと、総合的に考えるとWindowsXPです。ただし、実は私はWindowsXPの画面は、3D効果などは一切オフにして、クラシックモードで使っていました。クラシックモードというのはWindows98と同じスタート画面です。つまり、ユーザーインターフェースとしては、私にとってはWindows98が一番使い勝手がよかった、ということになります。ただ、98は、いろんなウィンドウを広げておくと、すぐにシステムリソースが減って不安定になるので、適宜使わないウィンドウは閉じる必要がありました。そういう意味では、システム的な安定性はWindowsXPのほうが上手だし、私の好みであるWindows98のスタート画面もXPでそのまま再現出来るので、総合的にはXPが一番使いやすいOSだった、ということになります。(なお、Windows98のスタート画面と言っても、それ自体自分で使いやすいようにカスタマイズしていました)今使っているWindows7も悪くはありませんが、XP(98と同じスタート画面にした)と、どちらが使いやすいかといえば、正直言ってXPです。XPの限界は、32ビットOSなのでメモリが4GB弱までしか使えなかったことです(64ビット版もあるにはあったけど、一般的ではなかった)。でも、4GBのメモリが積めれば、動画編集だって音楽編集だって、一通りは何だってできましたから、それほど大きな制約でもありませんでした。今使っているパソコンがいいのは、起動がすごく速いこと。電源スイッチを入れてから25秒で立ち上がる。ただ、これはWindows7のおかげというよりマザーボードとCPUの仕様のおかげでしょう。昨年末まで使っていたパソコンは、Windows7に変えても起動速度はそれほど速くはなりませんでしたから。たらればを言っても仕方がないのですが、Windows7のスタート画面をクラシックモードでWindows98と同じ使い勝手にカストマイズできるなら、Windows7最強なんですけどね。または、WindowsXPの64ビット版。(存在はしたけど、あまり一般的ではなく、私も使ったことはありません)。いずれにしても、XPのサポートはすでに切れてしまっています。なんにしても、こうやってすぐにOSのサポートを打ち切るのは、次々と新しいOSを開発しては売りつけるためのテクニックなんだろうけど、使う側から言わせてもらえば、もっと長く使いたい。せめて発売開始から15年、できれば20年サポートしてほしいものです。
2015.01.18
コメント(0)
-
新型国際放送で、誤った日本の立場を宣伝したい人たち
新型「国際放送」で正しく日本の立場発信 慰安婦など歴史問題…「攻めの情報発信」 NHKと別、自民が創設検討へ自民党は14日、国際情報検討委員会(原田義昭委員長)などの合同会議を党本部で開き、慰安婦問題や南京事件などで史実と異なる情報が海外で広まっている現状を踏まえ、日本の立場を正確に発信する新型「国際放送」の創設を検討する方針を確認した。中国や韓国などの情報戦略を分析、在外公館による情報発信の拡充についても議論し、今年の通常国会会期内に結論を出すことにしている。会議で原田氏は「どういう形で相手国に情報が伝わるかにも目配りしながら、正しいことをきちんと発信していくことが大事だ」と述べ、「攻めの情報発信」の意義を訴えた。英語による海外への国際放送は現在、「NHKワールドTV」がある。しかし、検討委は「従来の枠内では報道の自由など基本的な制約が多いため、今日の事態に十分対応できない」として、新型「国際放送」の創設を挙げた。(以下略)---何というか、報道の自由が「制約」だという感覚って凄いなと思います。「政府が右と言っているのに左と言うわけにはいかない」などと言い放ったNHK会長もいましたが、それでも飽き足らず、完全に政府の意のままになる宣伝機関がほしい、というわけです。そこで何を放送するかというと慰安婦問題や南京事件などで史実と異なる情報が海外で広まっている現状を踏まえ、日本の立場を正確に発信するだそうですから、産経新聞をそのまま放送にのせたもの、なんでしょうね。いっそのこと、チャンネル桜を政府が買い取ったら?(もちろん、皮肉ですが)で、「慰安婦は捏造だ」とか「南京大虐殺はなかった」みたいな歴史修正主義を海外に向けて垂れ流そうというわけです。そういうことをやればやるほど、自称「日本の主張」(実際には、日本の右翼の主張)は世界に受け入れられる、のではなく、むしろ世界から批判の目で見られることになり、日本の立場を悪くします。何度も指摘したことですが、従軍慰安婦に関して米国下院で121号決議が上程されたとき、日本の右翼は、彼らの信じる慰安婦の「真実」なるものを世界に向けて発信しようと、ワシントンポストにでかでかと意見広告を掲載しましたが、それはむしろ米国の世論を硬化させ、決議案への賛同者を増やす結果となっています。それでもまだ、同じことを続けるつもりのようです。彼らは、本当に学ばない連中です。自分たちの主観で「正しい歴史」だと思っているものを開陳すれば、世界がそれに賛同してくれると、まだ思っているのでしょう。しかし、実際にはやればやるほど、日本の国際的立場を悪化させるだけとしか思えません。ワシントンポストの意見広告は、愚劣ではあっても、まだしもあれは右翼連中が自分たちのお金でやったことですが、今度はそれを公費でやろう、ということのようです。そんなことに税金を使うとは、冗談ではありません。
2015.01.17
コメント(27)
-
活動期に入った日本
「列島、活動期に入ったかも」…噴火予知連会長国の火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長が16日夜、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、「(日本列島が)火山の活動期に入ったかもしれない」と注意を呼びかけた。藤井会長は、御嶽山の噴火などを例に挙げ、火山活動が活発化していることを指摘。最近の桜島の火山活動について「大規模噴火の予兆とは言えないが、地下にマグマはたまっている。100年前と同じ大規模の噴火が起きる可能性はある」と話した。更に伊豆大島や三宅島でも「噴火の準備はできている」と説明。今の日本は「地震や噴火が相次いだ平安時代とよく似ている」と指摘した。---明日(日付上は今日)は、阪神淡路大震災から20年目の1.17です。あの時点では、日本では関東大震災以来の犠牲者を出した大地震でした。その間に起きた著名な大地震というと、1933年昭和三陸沖地震(死者約3000人)、1944年昭和東南海地震(死者約1200人)、1946年昭和南海地震(死者約1300人)、1948年福井地震(死者約3700人)、1983年日本海中部地震(死者約100人)、1993年南西沖地震(死者約200人)があります。それらのすべてより阪神淡路大震災のほうが犠牲者は多かったけど、しかしさらにその阪神淡路大震災より東日本大震災のほうがはるかに犠牲者が多かったわけです。ただし、地震の大きさと被害の規模は、必ずしも比例関係にあるわけではありません。どれほどの超巨大地震でも、無人の土地で起これば被害は皆無です。(遠方での津波被害は除いて)地震の規模、という意味で考えても、東日本大震災は桁違いの超巨大地震でしたが、阪神淡路大震災は必ずしもそうではありません。地震の規模を計るマグニチュードでは、東日本大震災の1000分の1以下でしたし、阪神淡路よりマグニチュードの大きな地震は戦後何回も起こっています。ただ、阪神淡路大震災は、巨大都市の至近距離で起こったために、被害規模では超巨大地震になったのです。同じことは火山の噴火についても言えます。御嶽山の噴火は、噴火の規模そのものはごくごく小規模なのです。それにもかかわらず多くの犠牲者が出たのは、噴火口の近くに多くの登山者がいたからです。その前に多くの犠牲者を出した1991年雲仙普賢岳の噴火も、これは御嶽山よりははるかに大規模な噴火ではあったものの、それでも他の主要な大噴火に比べれば、はるかに規模の小さな噴火だったのです。そういう意味では、御嶽山の噴火を根拠に「火山の活動期に入った」というのはどうだろうか、と思います。多分、あの程度の規模の噴火なら、桜島や阿蘇山ではごく頻繁に起こってたいるはずです。ただし、確かに他の火山でも噴火の予兆が観測されている山が多いこともまた事実です。東北の蔵王、吾妻山、九州の阿蘇山、桜島などが、火山性微動や火山性地震の増加、山体の膨張が伝えられています。また、日本の領海内ということで言えば、小笠原諸島の西ノ島は現在噴火継続中です。日本の本土からはかなり離れていますけどね。そういう意味では、「活動期に入ったかも」という問題提起は、もっともだなと思います。次に噴火するのはどの山になるんでしょうかね。
2015.01.16
コメント(0)
-

ワカン、スノーシュー、アイゼン
先日、谷川連峰の白毛門に登った際、ワカンを使用したことは、先の記事に書きました。通常、雪山に登るときは、登山靴にアイゼンを装着します。(厳密に言うと、登るときより下るときのほうがより必要性が高い)このアイゼンは、12本歯です。一方、↓のアイゼンは8本歯です。これより歯の数が少ない、4本歯、6本歯のアイゼンは、軽アイゼンと呼ばれ、傾斜のゆるい雪面や夏の雪渓歩きなどに使うものです。冬山で通常使うアイゼンは12本歯。8本歯というのは、最近は珍しいかも知れません。普通のアイゼンと軽アイゼンの中間的なもの、といえるでしょう。基本的に、雪山に登るときはアイゼンは必ず持って行きます。比較的雪の少ない山なら、登山靴にアイゼンがあれば充分なのです。ただし、雪の量が多くて、踏み跡が固まっていない山だと、アイゼンだけでは歯が立たない場合があります。足が雪の中にもぐってしまうからです。積雪が多い山だと、本当に膝より上までもぐってしまうことは多々あります。昨年2月の大雪の際の高尾山体重を1足の靴底の面積だけで支えようとすると、面積あたりの荷重が大きくなるので、足が雪の中にもぐってしまうわけです。それなら、面積あたりの荷重を下げればよいわけです。体重を減らすことはすぐには出来ないので、靴底の面積を増やせばいいわけです。雪山で靴底の面積を増やす道具は、3つあります。スキーとワカンとスノーシューです。スキーについては説明無用でしょう。実は、3つあげた中ではスキーが一番面積は大きく、従って雪面での浮力も一番大きい、はずです。しかし、その一方でスキー板とビンディングは重い。加えて、靴が特殊です。登山靴で装着できるスキーのビンディングは一般的ではないし、登山靴は足首の自由度が高いために、あまり滑りやすいものではないようです。一方、スキーブーツは歩きにくい。山スキーには、歩行にも考慮した兼用靴を使うそうですが、それでも登山靴ほど歩きやすくはない。結局、ある程度以上厳しい山だと、登山靴を履いてスキーブーツも持っていく、ということになり、荷物が重くなります。それでも、山スキーを楽しむ人はかなり増えています。が、これについてはとりあえず私はあまり語る資格がありません。何しろ、私はゲレンデスキーしかやったことがなくて、それも20年以上前に滑ったのが最後ですから。残る二つの道具、ワカンとスノーシューについての話です。ワカンと呼びますが、語源は輪かんじきです。名前から分かるように、日本が起源の雪上歩行具です。そしてスノーシューこちらは、「西洋かんじき」などという呼び方もあり、欧米起源のようです。私自身は、スノーシューは持っていません。ただ、ワカンとスノーシューを比較すると「床面積」はスノーシューのほうが広い。つまり、雪面での浮力はスノーシューのほうが大きいと思います。もっとも、フカフカの新雪では、スノーシューだってワカンだって、どうしたってもぐりますけど。一方、サイズはワカンのほうが小さいし重さも軽い。(サイズが小さいほうがザックにくくりつけて持ち歩きやすい)もっとも、登山用品店でスノーシューを手にした限りは、そんなに重いというほどのものでもありませんでしたけど。かさばるのは間違いありません。一方、斜面を歩くときの滑りにくさは、それぞれ一長一短があります。いずれもアイゼンのような歯がついているのですが、ワカンの歯は2本しかなく、しかも縦に付いているので、ブレーキ力はあまりない。一方スノーシューは、歯が横向きに付いているので、ワカンよりはブレーキ力がある。ただ、どちらにしてもアイゼンに比べればたかが知れています。そして、ワカンはアイゼンと重ねて装着することが出来ますが、スノーシューはアイゼンと併用は出来ません。だから単独で使うならスノーシューのほうがブレーキ力があるけど、現実にはアイゼンと併用すればワカンのほうがブレーキ力がはるかに大きい、ということになります。ただ、私自身はワカンとアイゼンの併用をしたことがないんですけどね。また、スノーシューは、雪面の斜度があまり大きいと、歩きにくいようです(かかとを上げて固定できるスノーシューもありますが、対応できる角度には限界がある)。あまりに急坂だと、ワカンだって歩きにくいですけどね。登りはともかく下りはね。結論として、先日の白毛門でも、山頂目指して登っている人は、私も含めて全員ワカンでした。ふもとの雪原でスノーウォーキングを楽しんでいる人たちはスノーシューでした。つまり、急斜面のある本格的な冬山登山に使うのは、ワカンのほうが有利、ということになるのだろうと思います。
2015.01.14
コメント(0)
-
言論の自由に反している、か?
元朝日記者提訴 言論の自由に反している元朝日新聞記者の植村隆氏が「慰安婦記事を捏造した」などの指摘で人権侵害を受けたとして、文芸春秋と東京基督教大学の西岡力教授に損害賠償と謝罪広告などを求める訴えを起こした。裁判を受ける権利はもちろん誰にでもある。だが、言論人同士の記事評価をめぐって司法判断を求めるのは異様ではないか。訴状によれば、植村氏は記事や論文などの指摘で社会的評価と信用を傷つけられ、ネット上の人格否定攻撃や家族への脅迫、勤務先大学への解雇要請などを招いた。こうした人権侵害から救済し保護するために司法手続きを通して「捏造記者」というレッテルを取り除くしかない-としている。植村氏の解雇を求めた大学への脅迫については、産経新聞も昨年10月2日付主張で「言論封じのテロを許すな」と題して、これを強く非難した。同時に文中では「言論にはあくまで言論で対峙すべきだ」とも記した。同じ文言を繰り返したい。自身や家族、大学に対する脅迫や中傷と、言論による批判を混同してはいないか。(中略)大学や家族への脅迫を、自らを批判する記事や論文が招いたとする訴訟理由には首をひねる。パリでは、イスラム教の預言者を登場させた風刺画などを掲載した週刊紙が襲撃され、編集長ら12人が殺害された。テロの誘発を記事に求めることが認められるなら、広義ではパリの惨事も報道が招いたことになる。そこに言論、報道の自由はあるのだろうか。---新聞・雑誌の報道に対して名誉毀損で損害賠償を求めることが「言論の自由に反している」というのなら、そもそも刑法から名誉毀損という罪を削除すべき、ということになります。裁判を受ける権利は誰にでもあり、また名誉毀損による損害賠償の前例も、掃いて捨てるほどある。それを「言論人同士の記事評価をめぐって司法判断を求めるのは異様」というのはいかがなものかと思います。それこそ、「裁判を受ける権利の侵害」でしょう。だいたい、他ならぬ産経新聞自身が、自らが原告になったわけではないけれど、百人斬り裁判、沖縄ノート裁判などで、本多勝一・朝日新聞・毎日新聞(百人斬り裁判)、大江健三郎・岩波書店(沖縄ノート裁判)を訴えた原告側を全面支援した前歴があります。まさか、自分たちの名誉毀損提訴は良い提訴、元朝日記者の名誉毀損提訴は悪い提訴、だなどとは言わないよね。(いや、言い出しかねないし、少なくとも腹の中ではそう思っていそうですけど)裁判に勝てるか否かは別の問題として(百人斬り裁判も沖縄ノート裁判も、産経が支援した原告側は前面敗訴したわけですが)、「裁判を起こすこと」自体を批判したってはじまらないのです。「テロの誘発を記事に求めることが認められるなら、広義ではパリの惨事も報道が招いたことになる。」という言い分も、まったくおかしいと言わざるをえません。パリで起こったテロは、シャルリー・エブドのメッドの風刺画に反発するイスラム過激派が、掲載元のシャルリー・エブドを襲撃した、というものです。植村隆氏の事例は、まったく逆です。この例に基づいて言えば、「シャルリー・エブドはけしからん、イスラムの敵だ」とイスラム過激派を煽った新聞か雑誌があったとして(実際に存在したかどうかは知りませんけど)それに対して事件の生存者か犠牲者の遺族が損害賠償を求めることが正しいか否か、というのに相当します。この事例に対して、産経新聞ならどういう態度を取るのかは、大いに興味ありです。やはりそれは「言論の自由に反する」というのでしょうかね。
2015.01.13
コメント(9)
-

水上温泉・白毛門
またまた山に登ってきました。と言っても、今回は半分は家族旅行です。ここ数年、この時期に水上温泉に旅行に行っており、その2日目に、私だけ別行動で山に登ってくるのです。去年は、谷川だけに登ってきました。今年は、谷川岳のとなりの、白毛門を目指すことにしました。そういえば、去年も成人の日の3連休に来たら、SLの運転がありましたが、今年も来ていたようです。時刻表に載っていなかったけどなあ、と思ったら、JTBの時刻表では本文ではなく、巻頭の黄色いページに別刷りになっていたようです。天気は雪。積雪量も、去年より断然多いようです。で、この日は、何年かお世話になっている某ホテルで夕飯を食べて寝るだけ。で、翌朝、つまり昨日なのですが、朝はどんよりした空から無情の雪が降ってきます。これは、単独で山を目指すのは、ちと厳しい天気だな、今回は山はあきらめて、一日相棒と子どもにくっついて歩こうか、と思い始めた矢先、8時半ころに急に天気が回復、やはり急転直下山に行くことにしました。目指す白毛門(しらがもんと読みます)は、海抜1720m、谷川岳のとなりに聳えており、谷川だけの展望台として知られています。時間的に、かなり出遅れたのでもう山頂までたどり着くのは無理そうでしたけどね。行きは、とりあえず水上駅からバスで登山口である土合橋まで向かいました。登山口がよく分からなくて、お店の人に聞きました。登山道は完全に雪に埋もれています。しかし、白毛門に向かって雪の上にはトレースが1本。これをたどればいいわけです、多分。もし違ったら、このトレースを頼りに引き返してくるしかありませんが。本日の武器はこれ。ワカン(輪かんじき)です。それにしても、我ながらアイゼン・ピッケルにワカンまで持ってくる家族旅行って・・・・・・笑。私の後ろからは、スノーシューの集団がいましたが、スノーシューで雪原歩き体験、みたいなツアーだったようで、奥のほうまでは入っていきませんでした。私はというと、トレースをたどってどんどん先に進み・・・・・・眼前に谷川岳の雄姿が。谷川岳も、海抜1977mしかない山なのですが、雪が多いだけに、山容に迫力があります。これは、先ほどの写真よりもう少し登ったところで撮りました。少し雲が増えてきたかな。さらに上り続けていくと・・・・・・あらら、先頭集団に追いついてしまいました。私がたどってきたトレースは、現在製造中のものだったわけです。ワカンをつけているからこの程度のもぐり方ですが、ツボ足(登山靴に何もつけないか、アイセンだけつけた状態)なら、腰くらいまでもぐりそうです。雪面にピッケルを刺してみたら、65cmある私のピッケルが全部もぐって、手ももぐって、まだ地面には付かなかったので、積雪1メートル以上は確実です。私が追いついたところで、先行していた皆さん(4人いました)は、小休止に入ったので、私は一人で先に進むことにしました。私の前にトレースなし。さて・・・・・・どうやって進もうか。でも、ルートは分かりやすいのです。だって山頂に向けて尾根をただ進むだけですから、迷いようがない。ただ、ワカンをつけてもなお膝までもぐる新雪の中を歩くのは、疲れます。登山口からそこまで、ずっとトレースを作ってきた、先行する4人の労力には頭が下がる限り。気がつけば時間は12時半過ぎになっており、昼食を食べ始めたのですが、ふと気がつくと・・・・・・さっきまで勇姿を見せていた谷川岳がガスの中に消えました。周囲はどんよりと暗く、激しい降雪がはじまりました。どの道、最初から山頂まで着けるとは思っていなかったし、時間的にも潮時、降雪でトレースが消えたりしたらえらいこっちゃ、と、下山することにしました。小休止していた4人の先行者も相次いで登ってきましたが、いずれも私が引き返した近辺で引き返しており、この日は山頂までたどり着いた人はいません。しかし、下ってみると結構な急斜面なのです。のぼりはワカンで登ってきたけど、下りはワカンじゃ厳しいところもあり(ワカンにも、一応申し訳程度に歯が付いてるんだけど、アイゼンほどの滑り止め効果はない)、一方、あれだけフカフカの新雪を掻き分けて登ったのに、たった4人が登って降りただけで、踏み固めなれた雪はかなり固まっているのです。下りの半分過ぎくらいで、ワカンをアイゼンに替えて下ったけど、もう足が潜るところはほとんどありませんでした。登山口付近まで戻ってくると、朝は一筋だけのトレースだったものが、その後スノーシューのハイキング組(私が目撃した以外にも何人もいたようです)がかなり歩き回ったようで、トレースが入り乱れています。もし登り始めの時点でこんなにトレースが入り乱れていたら、白毛門に向かうトレースをちゃんと判別できたかな?行きは土合橋までバスで来ましたが、帰りは、上越線の各駅停車で水上まで帰ることにしました。谷川岳ロープウェーから土合駅までを結ぶ道路です。土合駅まではたいした距離ではありません。除雪車が除雪しています。積雪量が分かりやすいですね。上越線の線路を横切ります。ここも、積雪量が分かりやすい。土合駅に着きました。何にもない雪原に、駅舎がポツンとある。ここでは、積雪量は完全に車の車高を超えていました。そして、車道から駅に向かうこの道、アイスバーン化していて、ツルツル。滑った滑った(転倒はしなかったけど)。路面には、12本歯のアイゼンの歯型が残っていた。こんな場所でアイゼンを使うとは、笑っちゃうけど、使いたくなる気持ちは分かります。(ただ、ちょっと注意すれば、アイスバーン化しておらず、滑らない場所を探し当てることも容易いのですが)土合駅は、通称「日本一のモグラ駅」下り線のホームは地下70m、駅舎からは462段の階段を下り、所要時間は10分だそうで。ただ、私が乗った水上行きの上り線ホームは地上にあります。話の種に下り線ホームに行ってこようかとおもったけど、戻ってくる前に電車が来ちゃったら悲しいので、やめました。私の足なら、標高差70mは往復15分もかからないとは思ったけど、さすがに疲れていましたから。もともとは単線だったところを後から複線化したため、上りと下りで大幅に位置が違う駅の配置になったようです。上越新幹線開業前は、特急「とき」をはじめ、1日に何十本もの列車がとおる大幹線(もっとも、その当時だって各駅停車はそう多くはなかっただろうけど)でしたが、今は定期列車は各駅停車のみ1日5往復という超ローカル線。(ただし、土日のみ運行、冬季のみ運行の季節列車、臨時列車を合わせると、この日は8往復あった模様)もちろん今は無人駅です。乗客も普段はかなり少ないようですが、この日は登山者が大勢いました。多くは谷川岳に向かった人でしょう。酒盛りをやっていたらしきグループもいました。かつての大幹線も現在は超ローカル線、そして無人駅ですが、ホームの除雪は完璧です。それにしても、このあたりは雪国である水上に比べても、一段と雪が多い。水上に戻ってきたら、一瞬「雪が少ない」と錯覚するくらいでした。で、宿に帰ったわけですが、夕飯を食べたら、(お酒を飲んだせいもありますが)午後8時過ぎにはダウン。山に登ったわけでもない相棒も同様で、子どもが一番遅くまで起きていました。実は、その前夜も同様で、普段の寝不足を解消するかのように、2日間とも、1日9時間くらい寝てしまった。その代わり、宿で読もうとおもっていた本も、書こうと思っていた当ブログ(笑)も、何も手を付けずに終わってしまいました。で、今朝なんですが・・・・・・2泊3日の旅行の中でも一番激しい降雪。この雪が昨日だったら、山登りなんてぜんぜんとんでもない、という感じです。幸い、今日はもう帰宅するだけですけど。宿から駅までは1kmあまり離れています。車で送ってくれるのですが、子どもが雪の中を歩きたがるし、駅までは雪の中を歩きます。これだけの激しい雪、1メートルをゆうに超える積雪でも、車道にはほとんど雪がない、その秘密がこの散水システムです。ただ、それほど寒くはない雪国だから通用するシステムかな、とも思います。まず、配管内の水が凍らない、そして、撒いた水も凍らない。これがもっと寒いところだと、配管の水が凍るから散水できない、散水できても、水がカチカチに凍るから、路面がスケートリンクになってしまうので、雪より始末が悪いことになりそうです。おそらく、北海道ではこのシステムは通用しないだろうと思います。この時間帯の水上の気温はマイナス2.5度。もちろん寒いし雪も降るんだけど、山の上の寒さとは、ちょっと違うことも確かです。水上駅。激しい降雪の中でも電車は問題なく走っています。昨晩あれだけ寝たのに、電車の中でまたまた寝てしまった。リバーサルフィルムでも写真を撮っていますので、完成したらそちらもアップする・・・・・・かも知れません。
2015.01.12
コメント(2)
-

西穂高岳独標、リバーサルフィルムの写真
年末に登った、西穂高岳独標の、フィルムカメラの写真がやっと完成しました。リバーサルフィルムは、ただでさえ時間がかかる上に、年末年始が挟まったため、29日に現像に出して、昨日プリントを受け取るまで、実に11日間もかかってしまった。こういうところは、デジカメに比べて圧倒的に不利ですね。初日、新穂高ロープウェイ終点から登ってきて、西穂高山荘のある稜線に出たところで撮った写真です。向こうは笠ヶ岳です。この時、ロープウェイ終点は吹雪でしたが、稜線は雲の上なので、このとおりでした。丸山付近から西穂高岳を撮影しました。時間は、おそらく四時頃だったと思います。最高の天気。 同じく西穂高岳、日没直前の夕焼けに染まる姿です。一番いいチャンスにシャッターを切れました。翌朝も、このとおりの快晴。風はそこそこにありますが、この時期の北アルプスとしては、まあそよ風と言って良いレベル。これで独標までくらい、登れないはずがない。すでに、頂上には何人も立っています。一昨年2月に登った赤岳に比べても、かなりあっさりと山頂に到着しました。以前に思っていたほどには困難ではありませんでした。独標は、西穂高岳の11個目、一番最初のピークです。眼前には、先に続く10個のピーク、さらにその先の奥穂高、前穂高まで一望できます。この先に行きたくなったけど、ちょっと進んで断念したのは、以前の記事に書いたとおりです。奥穂高から吊尾根を経て前穂高まで。雪が、天然の生クリームみたいです。独標の山頂に着いたら風が止んで、全く無風になりました。ただ、吊尾根の方は雪煙が上がっており、風は普通に強そうです。登ってきた稜線を振り返って。焼岳、その先に乗鞍岳が見えます。さらに先に御嶽山もあるのですが、乗鞍岳の陰になって、見えないようです。10月に乗鞍岳に登った時も噴煙が見えましたが、今回も噴煙が上がっているときがありました。ただ、常時上がりっぱなしではなかったですが。前穂高岳と岳沢。9月にはここを登ったのでした。考えてみると、3ヶ月で雪がまったくない山から雪に埋もれた山へ、環境激変です。これは、独標から下ってきて撮った写真です。こうやってみると、それなりに峻険です。夏場なら、ここまでは誰でも来られるところなのですが。新穂高ロープウェイ終点まで戻ってきて撮った写真です。この時は、新穂高ロープウェイも快晴でした。ここでは、iPadでは写真を撮るのを忘れてしまったので、フィルムカメラの写真しかありません。槍ヶ岳です。稜線上からは、槍ヶ岳は見えないので、ここからしか撮れません。同じく、新穂高ロープウェイ終点から西穂高岳を撮りました。独標は、写真からはみ出してしまった。なんにしても、手間も時間もかかるけど、フィルムカメラの写真はいいものです。ただ、11日もかかってしまう、スキャナに取り込みの手間、など考えると、デジタル一眼レフという想いも、最近チラチラと。山で使う関係上、あまり重くなく、しかしフィルムカメラ並みのファインダーの見易さ、フィルムカメラ並みの広角レンズ(使っているレンズは24-85mmですこれに匹敵する広角レンズをデジタル一眼レフでとなると、これまた重くてでかい)とか考えると、どうも候補が出てこないんですけどね。
2015.01.10
コメント(2)
-
乱射事件
風刺週刊紙で銃撃、12人死亡=大統領、テロと断定―イスラム過激派の犯行か・パリフランスの風刺週刊紙シャルリー・エブドのパリの本社に7日午前11時半ごろ、覆面をかぶった複数の武装犯が押し入り、職員らを銃撃した。仏メディアによると、警官2人と編集長、風刺漫画担当記者ら計12人が死亡、約20人が負傷した。現場に急行したオランド大統領は、記者団に「間違いなくテロだ」と断定。犯人は車で逃走しており、仏当局は最高レベルの厳戒態勢を敷いて行方を追っている。7日発売の同紙には、イスラム過激組織を挑発するようなイラストが掲載されていた。犯人が国際テロ組織アルカイダを名乗り、逃走する際に「ムハンマドへの侮辱に報復した」と叫んでいたとの目撃情報もあることから、イスラム過激組織による犯行の疑いが強まっている。オランド大統領は「どこまでも犯人を追い掛け、裁きを受けさせる」と強調した。同紙は過去にムハンマドを題材にした風刺画を掲載。2013年には「ムハンマドの生涯」と題した漫画を出版した。たびたびイスラム団体から批判を受け、11年には火炎瓶を投げ付けられて事務所が全焼している。同紙への脅迫はその後も続き、当局も警戒していただけに、警備態勢の不備を追及される可能性もある。現場はパリ中心部のバスティーユ駅から北に約400メートルの地域。事件当時は週1回の編集会議を開催中で、犯人が何らかの方法で内部情報を入手した可能性が高いとの見方もある。犯人は車で現場に到着。事件後に乗り捨て、別の車を奪って東方面に逃走したもようだ。---きわめて衝撃的な事件です。続報では、犯人の身元はすでに判明しているようです。アルジェリア系フランス人の34歳と32歳の兄弟だと報じられています。言論の自由に対するきわめて暴力的な攻撃であることは言うまでもありません。しかし、それに加えて、このような暴挙は、結果として他ならぬイスラム教徒、あるいはアルジェリア系の人々への差別や敵対心の拡大、という形で跳ね返ってくることになるのは確実です。また、イスラム教への風刺に対する批判だって、かなりやりにくくなるだろうと思われます。そういう意味では、確実に、イスラム社会(フランス国内の)の首を絞める結果となることは間違いありません。価値観の異なる他者に対する寛容な態度というのは、なかなか難しいものですが、それなしには、多様な価値観の存在するこの世界は、きわめて生きにくいものとなってしまいます。イスラム教を揶揄されたから自動小銃を乱射、というのはまさに非寛容の極地というものです。ただ、その一方で、イスラム過激派への批判はともかく、曲がりなりにも世界三大宗教のひとつであるイスラム教そのものに対する揶揄もまた、イスラム社会、イスラム教徒全体に対するある種の比寛容的な態度に通じるのではないか、という疑念も、なくはありません。いずれにしても、言論に対する不満は言論で対応するのが、寛容な社会のための最大のルールでしょう。言論に対して自動小銃で応じるのでは、どんな同情も吹き飛んでしまうというものです。
2015.01.08
コメント(16)
-

自衛隊太鼓持ち新聞
海自、新春の荒れる太平洋上で急患救出劇 「日本の守り神」豪華客船乗客から拍手年末年始を太平洋上で楽しむ乗客を乗せた豪華客船で2日、急患が発生し、救助要請を受けた海上自衛隊のヘリコプターによる救出劇が繰り広げられた。強い風と波に見舞われる中、救急搬送が必要な2人をヘリに引き上げるという難しい作業だったが、無事に成功。海自の高い救難技術に、乗客からは大きな拍手が湧いた。救出劇の舞台となったのは郵船クルーズが運航する客船「飛鳥II」。昨年12月26日に横浜港を出港し、グアムとサイパンに寄港後、横浜港に戻るところだった。飛鳥IIからの救助要請は2日昼ごろ、硫黄島の西約350キロ付近を航行中のことだった。防衛省によると、海上保安庁側から、ぜんそくの症状が出た乗客と、右足大腿骨を骨折した乗客の計2人について救助要請があり、海自73航空隊硫黄島航空分遣隊のヘリ「UH-60J」が出動した。飛鳥IIも硫黄島に向け針路を変更、午後4時15分ごろに硫黄島の西240キロ付近の海上で救助作業が始まった。しかし、付近の海上は風速9メートルに加え3~4メートルのうねりが続く天候不良。作業は容易ではなかった。(中略)船上から救助活動を見守り、救助の写真を産経新聞に送ってきた乗客の男性のメールには、こう書かれていた。「改めて自衛隊は、日本の守り神だと思った」---なんというか、歯が浮きそうなお世辞を並べ立てた記事、としか思えないんですけどね。これほどの規模の客船なら、船医が乗り組んでいるだろうし、ぜんそくの持病がある人なら、薬は持っているんじゃないかとか、大腿骨骨折は確かに重傷だけど、横浜に帰港するまで1日か2日も待てないほど緊急だったのか、とか(足の骨折で命の危険というのは、普通はあまり考えられません。ショック状態に陥って、ということならあり得るかもしれませんが)いろいろとよく分からないところがあるのですが、そのあたりは、まあいいとしましょう。私の知っている人に、元海上自衛隊のヘリパイロットがいます(どういう知り合いかは秘密です)。あるとき、突然視力が悪化する出来事があって、ヘリに乗れなくなったら、給料が激減して大変だったそうです(特殊技能ですから、自衛隊でもパイロットの飛行手当ては高額らしい)この方があるとき言っていたのは、同僚だったパイロットが何人も辞めて民間のヘリパイロットに移ったけど、その中から何人も死者が出た、という話です。海上自衛隊にいたときは、同僚が何人亡くなったのかは聞きませんでしたけど、ニュアンスとしては、海上自衛隊にいたときより、その後のほうが亡くなった(元)同僚はよほど多かったようです。電力会社の送電線の敷設工事で、ヘリに送電線を吊り下げて運ぶそうですが、その作業中に墜落して亡くなった仲間が何人かいるそうです。そういえば、私は送電線の敷設現場は目撃したことはありませんが、山では、かなり厳しい状況でヘリが飛んでくるのを目撃したことは何回もあります。だいたい、山というところは、何もなくても気流が乱れる場所です。そこに、山小屋への荷揚げや遭難救助のため、民間警察問わず、多くのヘリが飛びます。山小屋への荷揚げは、悪天候のときは飛ばないかもしれないけど、遭難救助のときは、そうとう悪天候でも飛びます。私が目撃した中では、20年くらい前でしたが、白馬大池で、ガスが湧いて視界が非常に悪い中を、けが人らしき人を収容するためにヘリが飛んできたときは、「こんな条件で、こんな山に囲まれた場所でもヘリは飛べるんだ」とびっくりした記憶があります。多分警察のヘリじゃないかとは思うのですが、シルエットしか分からないのではっきりしません。この写真だと、ただなだらかな草原に見えますけど、この一帯が少し平らなだけで、周囲は山に囲まれています。これとは別の機会、確か1998年に、やはり白馬岳近くの蓮華温泉で、登山道の橋の工事現場に通りかかったことがあります。雪崩で橋が流されたため、新しい橋の架けていたようです。屈指の豪雪地帯だから、また雪崩に流されるだろうし、登山道なんだから仮設橋でいいじゃん、と思ったのですが、それはともかくとして、です。工事現場にセメントを吊り下げたヘリが飛んできたのです。私は、川岸から十数メートル離れて岩陰で飯を食べていたのですが、ヘリの風圧に巻き上げられた水をかぶって、びしょ濡れになりました。そのくらい、ローターの巻き上げる風は強い。で、その川は、非常に深くて狭い峡谷、しかも両岸からは木々の枝がたくさん伸びています。ヘリは、その間を縫うようにして飛来して、工事の足場の上にセメントを落とすと、飛び去っていきました。ローターを木の枝に引っ掛けるんじゃないかと心配になるくらいのところです。それを、1日に何往復もするのでしょう。一瞬でも操作を間違えれば、ローターを機に引っ掛けて墜落は確実でしょう。橋の工事現場ですから、警察や消防、まして自衛隊のヘリであるはずがなく、民間のヘリのはずです。多分東邦航空じゃないかと思います。私が目撃したこれらの例は、飛行の難易度として、産経自衛隊御用新聞の持ち上げる例に、勝るとも劣らないものだろうと思います。実際、事故も起きている。自衛隊のヘリが危険な業務についていることは否定しませんが、それは別に自衛隊だけの専売特許ではないはずです。でも、産経としては、「改めて自衛隊は、日本の守り神だと思った」という結論のために、自衛隊のヘリだけを、せっせと持ち上げたいんでしょうねえ。岐阜県の防災ヘリコプター、若鮎IIです。このときは奥穂高山荘で、救助訓練をしていました。天気は晴天でしたけど、3000mの稜線上の鞍部ですから、一歩間違えれば墜落です。そして、実際に後年、同じ奥穂高のジャンダルム付近で、救助活動中に墜落してしまいました。
2015.01.07
コメント(2)
-
確かに守銭奴ではあるが・・・・・・
内部留保蓄積は「守銭奴」=麻生財務相が企業体質批判麻生太郎財務相が5日の信託協会の新年賀詞交歓会で行ったあいさつで、企業の内部留保蓄積が328兆円にまで膨らんでいることを指摘し、「まだカネをためたいなんて、ただの守銭奴にすぎない」と批判したことが6日明らかになった。守銭奴はカネに執着する人を指す。「守銭奴」発言は、企業に内部留保を賃上げや設備投資に回すよう求める中で出たもので、財務相は「ある程度カネを持ったら、そのカネを使って何をするかを考えるのが当たり前。今の企業は間違いなくおかしい」とも語った。この発言について麻生財務相は6日の記者会見で、「(内部留保積み上げは)デフレ不況と戦う中で好ましいとは思わない。利益が出れば賃上げ、配当、設備投資に回すことが望ましいということを説明する趣旨で申し上げた」と述べた。---麻生の舌禍は今に始まった話しではないし、麻生の主張に賛同することなどないのだけど、この発言だけに限定すれば、言わんとしていること自体については、そのとおりだと私も思います。内部留保と言ってもすべてをすぐに換金できる資産で持っているわけではないけれど、換金できる資産だけに限っても、相当の額の内部留保がある。それを抱え込んだまま、従業員にも社会にも還元しないのでは、何のためのお金だよと、私も思います。それはそうなんだけど、ただ、財務大臣という立場にある人間が、公開の場で企業に対して「守銭奴」という表現を使うのはどうなの?とも思うのです。もうちょっと、言い方というものがあるでしょうに。そこがやっぱり麻生クオリティーなのでしょう。言葉を選んで慎重に発言することが出来ない人なのだ、ということは、これまでの麻生の言動を見ていれば、明らかなことではありますけどね。
2015.01.06
コメント(0)
-
竹中平蔵も、「正社員」たる大学教授ですが
竹中平蔵氏の「正社員をなくせばいい」発言に賛否慶応大学教授で、安倍政権では日本経済再生本部の「産業競争力会議」の民間メンバーを務める竹中平蔵氏が1月1日、テレビ朝日の「朝まで生テレビ」に出演した際に「正社員をなくせばいい」と発言したことが話題になっている。この日の番組では、雇用や賃金に関する議論が行われ、正社員と非正規社員とでの処遇が異なることに話題が及んだ。竹中氏は正規社員が法律によって過剰に保護されていると指摘。非正規社員が増えているのは、1979年の最高裁の判例で整理解雇の四要件が示されたことが原因で、企業側が労働者を解雇した際の訴訟リスクを恐れて正社員を雇えなくなっているとした。一方で、訴訟リスクが低いと考える中小企業では、正規社員であっても簡単に解雇する現状があると述べた。さらに竹中氏は、同じ仕事をするのならば、非正規社員であっても正社員と同じ賃金や待遇を得られる「同一労働・同一賃金」の制度が必要だとして、そのためには正規の社員と非正規社員の垣根をなくす必要があり「(同一労働・同一賃金の実現を目指すなら)正社員をなくしましょうって、やっぱりね、言わなきゃいけない」と発言した。---本来で言えば、非正規雇用は、その不安定な立場がゆえに、正規雇用よりむしろ給料が上でなければならないと私などは思うし、ヨーロッパなどではそうなっている国が多いようにも聞きます。しかし、日本の場合は、人件費を下げるための方便として使われているのが現状です。で、竹中は正規社員が法律によって過剰に保護されていると指摘。非正規社員が増えているのは、1979年の最高裁の判例で整理解雇の四要件が示されたことが原因と言ったそうですが、法的な意味で正規社員が特別に保護されていることって、あるのでしょうか。整理解雇の四要件というのは、1 人員整理の必要性2 解雇回避努力義務の履行3 被解雇者選定の合理性4 手続の妥当性です。第一に、これが「過剰に保護」などというほどのものでしょうか。雇用という、人の生活におけるもっとも重大な条件を守るための、当然の保護規定だと思いますけど。第二に、竹中は明らかに勘違いをしている(あるいは、知っていながら頬かむりをして言っているだけか)のですが、整理解雇の四要件というのは、正規雇用だけに適用されているものではありません。アルバイトであろうがパートであろうが、建前上雇用期間の定めがあったとしても、それを何回も更新を繰り返して長期雇用となっている場合は、期間の定めのない雇用契約と同じとして、同じ保護の対象となります。判例もあります。ただ単に、雇っている側も雇われている側も、「非正規雇用とはそういうものだ」と思っているから、「辞めてくれ」「分かりました」みたいな形になっている例が多い、というだけの話です。そして、それは正規雇用でも似たようなものです。「辞めてくれ」と言われて、整理解雇の4要件は知っていても、争えば勝てるかも知れないとは思いつつも、拒否して居座るのも針の筵の上に座っているようなものだからと、辞めてしまう正社員だって、実際には少なくないでしょう。竹中が、整理解雇の四要件は「過剰な保護」だから、そんな条件は剥奪してしまえと考えていることだけは、よく分かりました。でも、それは経営者の胸先三寸で、気に入らない奴は好きにクビにしてしまえ、ということを合法化する、という話でもあります。そういうことが公然とまかり通ることになると、非正規雇用の労働者に何かいいことがあるのか。何もありません。実際、次の仕事探しの間充分生活できるだけの蓄えがあり、かつ転職先に関してある程度の自信があるとすれば、解雇無効を争うより、サッサと退職したほうが自分自身の精神衛生上も楽な場合もあるでしょう。だけど、たくわえもない、転職先の見通しもない、という状況だったらどうします。争うしかない。その道すら剥奪されたら、あとは福祉事務所に駆け込むくらいしか道がなくなってしまいます。だいたい、その竹中平蔵自身が、慶応大学の「教授」です。大学において、非正規雇用である非常勤講師と、正規雇用である専任講師以上との待遇差は非常に大きい。竹中の場合は、教授の地位をなげうって政界に打って出た、と思いきや、小泉首相が辞任したら、自身も任期途中で議員を辞職して、大学教授に復帰してしまった。最初から復帰できる約束をしていたとしか思えません。それこそ、百凡の正社員には及びも付かないくらいの手厚い保護です。「正社員をなくせばいい」のであれば、まずはご自身から実践したらどうですか、と言いたいところです。
2015.01.05
コメント(3)
-
少子化問題をめぐる視野狭窄
少子化問題 国民の機運高める年に 子供育てる喜びの再確認を年頭にあたり発表された厚生労働省の推計では、昨年の出生数は約100万1千人で戦後最少を更新する見込みだ。次世代が生まれてこなければ、日本の存亡に関わり国家は成り立たない。「国難」であるとの認識を共有する必要がある。安倍晋三政権は「2060年に1億人程度維持」との政府目標を掲げ、本格的な対策に乗り出した。≪国民の出産希望は強い≫年間出生数は低落が続いてきた。このペースで出生数が減り続ければ、社会の混乱は避けられない。地方の消滅や経済の縮小、社会保障の制度破綻、「若い力」を必要とする自衛隊や警察、消防といった職種にも多大な影響が生じる。農家は後継者不足に悩み、伝統や文化の継承も難しくなる。あらゆる面で国力の衰退を招く。希望はある。国民の多くが結婚し、子供が欲しいと考えていることだ。どうしたら、国民が望む「2人以上の子供が持てる社会」を実現できるのか。国民総がかりで知恵を絞り、子供を産み、育てやすい環境をつくることが求められている。安倍政権が人口減少対策に本腰を入れ始めたことは大きな前進だ。昨年末に政府がまとめた「長期ビジョン」では合計特殊出生率について2020年に1.6、2030年に1.8、2040年に人口が一定となる2.07との道筋を示した。政府目標の「1億人程度維持」実現に向けたシナリオを描いた意義は大きい。これまで少子化対策が効果を上げなかったのは、戦時中の「産めよ殖やせよ」への忌避感からか、政府が結婚・出産に関与することへの反発が強く、政府や地方自治体が及び腰になっていた弊害が大きい。その結果として、批判が出にくい、子育て支援策に比重が置かれてきた面がある。だが問われているのは、子供が生まれてこない現状の打開だ。日本では結婚による出産が圧倒的多数を占めている。結婚支援策が少子化に歯止めをかける最重要課題である。昨年の婚姻数は戦後最少の64万9千組。結婚を希望しているのに果たせずにいる人を減らすことから始めたい。≪萎縮せず大胆な政策を≫少子化の主要因は非婚・晩婚だ。男性の雇用や収入を安定させることが急務だ。企業や自治体には出会いの場や雰囲気づくりを求めたい。縁談を進める「世話焼き」の復活も望まれる。大都市圏では出生率が低迷している。地方へのUターン、Iターン促進と結婚・出産支援とを連携させるべき。結婚や出産は個人の選択であり、国民に心理的な圧力を与えてはならない。だが、数値目標のない政策は、実効性が上がらない。政府や自治体は萎縮することなく、大胆な政策を展開してほしい。少子化対策に魔法の杖があるわけではない。庭や子供を持つ喜びを再確認することこそ、真の解決につながる。(一部略)---ま、何というか例によって例のごとくの、産経新聞の社説です。少子化による人口減が大きな問題だ、というのは基本的には私も同意見です。が、しかし同時に、どうしようもない問題でもあります。「若い力」を必要とする自衛隊や警察、消防といった職種にも多大な影響が生じる。というあたりが、産経新聞がこの問題にこだわる最大の動機なのかな、という気がするのですが、これは実に本末転倒な話です。だって、防衛とか治安維持というのは、人口やそれに伴う国力に応じて必要とされるものです。人口100万人の国を防衛するのに、どうしても200万人の軍が必要だ、などということはあり得ないでしょう。その時々の人口と国力に応じて自衛隊や警察消防の規模を決めるしかないでしょう。幸いなことに、と言っていいのかどうか分かりませんが、産経が仮想敵として扱っているであろう中国は、日本をも上回る猛烈な勢いで少子化が進行しています。中国がこれまで表向き発表してきた合計特殊出生率は1.6前後でしたが、2012年に中国国家統計局が発表した数字は、何と1.18です。日本ですら、2005年に記録した1.26が底で、最近は1.4以上まで回復してきています。5年後はまだかもしれませんが、10年後には中国も人口減少社会に突入している可能性が高いのです。これまで少子化対策が効果を上げなかったのは、戦時中の「産めよ殖やせよ」への忌避感からか、政府が結婚・出産に関与することへの反発が強く、政府や地方自治体が及び腰になっていた弊害が大きい。という記述がありますが、結婚とか出産というのは、まさしく個人の選択の問題ですから、そこに国家が介入するのはおかしなことです。おかしなことであるばかりでなく、無駄なことでもあります。政府や地方自治体が及び腰、というのは、忌避感ということもあるでしょうが、そんなことやったって無駄と考えているからでもあるでしょう。過去の例を見ても、戦時中はまさしく、国を挙げて「産めよ殖やせよ」に取り組んだわけですが、それで出生数が増えたでしょうか?1944年から46年の間は、厚労省の出生に関する統計が欠落しており、この間の出生数に関しての正確な統計はありません。ただ、断片的なデータから、1945年と46年の出生数はそれ以前、それ以降と比べて急減していることは間違いありません。当たり前です。若い男はみんな兵隊にとられて、家庭にはいなかったんだから。そして、皮肉なことに政府が「埋めよ増やせよ」なんて言わなくなった敗戦後になって、団塊の世代の大量出生が始まりました。男たちが戦場から帰ってきたからです。戦時下という特殊な状況でさえ、国が「産めよ増やせよ」と号令をかけても、効き目はなかったのですから、まして平時に国が「産めよ増やせよ」と号令をかけて効果があるわけがない。希望はある。国民の多くが結婚し、子供が欲しいと考えていることだ。という記述もありますが、これは、どこかに根拠となる調査結果があるのでしょうか。おそらく、何らかの調査結果に基づいての記述なのでしょうけれど、単純に真に受けられるものかどうかは注意を要します。選挙の際の世論調査では、「必ず投票に行く」という回答の割合が、実際の投票率より常に何割も高い、という話を思い出してしまいました。「結婚したいか」「子どもはほしいか」と言われて、積極的に「結婚したくない」「子供はほしくない」と考える人は、確かに少数派だろうと思います。しかし、問題はそれが人生の中でどれほどの優先順位なのか、ということです。結婚したいかしたくないか、と聞かれれば結婚はしたいけど、そのために具体的な行動を取るかといわれれば「別に」という人が多いのではないか、という気がします。(これは私の推測)そして・・・・・・日本では結婚による出産が圧倒的多数を占めている。結婚支援策が少子化に歯止めをかける最重要課題である。という記述もあるのですが、ああ、やっぱり産経らしい枠の中の思考にとどまっているんだな、というのが実感です。「結婚による出産が圧倒的多数を占め」ていて少子化が進行しているなら、結婚を増やすことも考えるにしても、それだけではなく「結婚していない女性の出産も増やす」ことも考えないと、効果なんか望めないんじゃないでしょうか。積極的に誘導するべきとは思わないけど、「未婚の母」に対する差別を解消するさまざまな方策を講じる、くらいのことは考えてしかるべきと思うのですが、それは産経的イデオロギーの下では、おそらく排撃すべき思考なのでしょう。ならば、出生率増加なんて無理ですよ。男性の雇用や収入を安定させることが急務だ。企業や自治体には出会いの場や雰囲気づくりを求めたい。縁談を進める「世話焼き」の復活も望まれる。雇用や収入を安定させることが急務だ、というのは、まったくそのとおりだと私も思うのですが、なぜ「男性」だけなの?夫の収入のみで家計をまかなっている家庭は、おそらく少数派だと思われるので、女性だって雇用の見通しがなければ子どもをつくるのは躊躇するでしょう。時に、「子どもが出来たら退職して専業主婦になれ」みたいな圧力は、出生増加への妨げの最たるものと私は思いますけどね。企業や自治体には出会いの場や雰囲気づくりを求めたい、というのは、まあ何というか、間違ってはいないかもしれないけど、ちょっと現実離れしていると言わざるをえないような。「世話焼きの復活」も、何の寝言だよ、と思いますね。2020年に1.6程度、2030年に1.8程度、2040年に2.07という数値目標も(これは政府が決めたことですが)現実離れしていると思わざるをえません。「数値目標のない政策は、実効性が上がらない。」という記述もありましたが、現実性のない数値目標を掲げても、実効性は上がらないのではないかと思いますけどね。何にしても、少子化の進行具合を少しでも緩やかにすることは必要だと私も思いますが、少子化を完全に食い止めるなんてことは無理な相談です。少子化を少しでも引き伸ばしつつ、人口減少を前提とした社会の仕組みを作っていくしかないと私は思うんですけどね。
2015.01.04
コメント(2)
-
国家が嘘をつくとき
尖閣諸島「現状維持で合意」 82年に鈴木首相が発言沖縄県の尖閣諸島の領有権をめぐり、1982年に鈴木善幸首相が、来日したサッチャー英首相との首脳会談で、中国との間で問題を実質的に棚上げしている、という趣旨の説明をしていたことがわかった。両首脳のやりとりを記録した文書を、英公文書館が12月30日付で機密解除した。日英首脳会談は82年9月20日に首相官邸で行われた。文書によると、鈴木氏は尖閣問題について、「(中国のトウ小平氏と会談した際に、日中)両国政府は大きな共通利益に基づいて協力し、細部の違いは脇に置くべきだとの結論に容易に達した」と説明。「具体的に問題化することなしに現状維持で合意し、問題は実質的に棚上げされた」と語ったという。トウ氏の態度について鈴木氏は、「極めて協力的で、尖閣の将来は後世の決定にゆだねることができると述べた」と話し、「それ以来、中国が尖閣諸島に言及することはなくなった」と説明した。---以前に、棚上げ合意については記事を書いたことがあります。棚上げ合意はあった (追記あり)イギリスの外交文書を持ち出さなくとも、棚上げ合意があったことは明白なのです。ただ、この記事を書くにあたって、私も当初はその棚上げ合意が何か秘密協定のような類だと勘違いしていて、そのような趣旨で記事を書いてしまいました。(すぐに訂正したけれど)事実は、秘密協定でもなんでもない、日本の各マスコミは当時、尖閣諸島領有権をめぐる日中の対立は「棚上げ合意した」ということを大々的に報じていますし、日本政府、外務省当局は、それらの報道を否定するようなことはひとことも言っていません。日本側の公式な議事録によれば、首脳会談の場において、中国側が勝手に「棚上げ」を口にして、日本側はそれに対して返答しなかったことになっているそうです。それを根拠として、日本政府は「棚上げ合意はなかった」などと言っているのですが、相手国の首脳が勝手に独り言を言っていただけ、なんて話がとおる訳がないのです。その「独り言」に対して反対の意を明言しない時点で、同意とみなされるのは当然のことです。しかも、この件に関しての日本側の議事録は、後で操作されている疑いがあります。実際には中国側首脳の棚上げ発言に対して、日本側の首脳も賛同、同意の反応を示したと思われます。そうでないと、首脳会談のやり取りとして不自然だからです。いずれにせよ、日本側首脳のその後の国会答弁や述懐などからも、中国側の「独り言」に日本側も従っていたことは間違いありません。実際問題、棚上げというのはその時点の状況での現状固定ということだから、日本側にとってもかなり有利な話だったのです。つまり、領有権の主張は棚上げするとして、実効支配そのものは日本が行っていたから、引き続き日本が実効支配をする(ただし、うっすらと)ということになるわけです。実際、その後ずっとそのとおりに来たわけです。1978年といえば、私は小学校4年生だったのですが、まだそのような新聞報道に興味を持つような年齢ではなかったので、当時そんな報道があったことを、まったく記憶していませんでした。まして、1978年当時生まれていなかった人なら、知らなくても当然でしょう。それをいいことにして、かつては大々的に報じられていた棚上げ合意を、政府が公然と「合意はなかった」などと嘘をついているわけです。いや、政府だけではない。1978年10月26日の各新聞は、こぞって尖閣の棚上げ合意を報じているそうです。今になって、政府の尻馬に乗って「棚上げ合意なんてない」と主張している産経新聞は、当時「『尖閣』は棚上げ、解決、次世代に待つ」という見出しを掲げていたそうです。棚上げ合意なんてなかったと主張するならば、まずは自らが36年前の報道を誤報として撤回すべきなんじゃないだろうか、と思ってしまいます。ことほどさように、国家というものは自らの都合で平然と嘘をつくものだということです。もちろん、嘘をつくのは日本国だけではないですけどね。中国だって韓国だって、あるいは他のどこの国だって同じです。重要なことは、国家は無謬の存在ではない、ということ。まあ、国家といっても、その運営を行っているのは生身の人間の集合体なのですから、当たり前の話ですけどね。
2015.01.03
コメント(10)
-

冬山遭難・・・・・・
冬山、相次ぐ遭難…1人が死亡、2人が行方不明冬型の気圧配置が強まり寒波に見舞われた年末から年始にかけて、長野県の北アルプスなどで冬山登山の遭難が相次いだ。北アルプス・燕岳では女性1人が死亡し、山梨県の南アルプス市や栃木県日光市でも、連絡がとれない登山者の捜索が行われたが、悪天候で難航した。長野県警によると、燕岳では12月31日、1人で登山していた山梨県笛吹市無職(64)から携帯電話で家族に「道に迷った」と連絡があった。救助隊が標高約2600m付近で発見して山小屋に運んだが、心肺停止状態になった。~低体温症とみられる。12月30日から3泊4日の予定で入山したが、天候が悪化し道に迷ったとみられている。北アルプスでは、大遠見山でも1日、東京都調布市の男性(40)が遭難し、2日にヘリで救助された。男性は低体温症になったが命に別条はない。南アルプス市の北岳では12月31日、道に迷って遭難した男女2人から110番があった。男性は2日朝、頂上付近の避難小屋にいたところを救助されヘリで搬送されたが、手足に凍傷を負った。一緒に登山をしていた大阪府の40歳代女性は発見できず、山梨県警は3日も捜索を続ける。日光市では、女峰山から男体山にかけてのルートを1人で登山していたさいたま市会社員(47)が下山予定の12月31日に戻らず、登山仲間が1日、栃木県警日光署に届け出た。栃木県警は2日、ヘリで捜索したが悪天候で中断、3日は朝から捜索する予定。---引用した記事にはありませんが、このほかに槍ヶ岳で2人、奥穂高岳で4人が遭難と報じられましたが、こちらはその後無事に下山したようです。かく言う私も、27日かに28日にかけて西穂高岳独標に登ってきたわけですが、このときは天気は快晴、風も、それほど強くなく(この時期の北アルプスの稜線上としては、です)絶好の登山日和でした。ただ、その時点で、28日夜から天候は下り坂、という予報はありました。(なので、私は登るならこの日程しかないと踏んだわけですが)実際のところ、その後天気がどう推移したのか、Facebook内の「やさしい山のお天気教室」に、西穂高山荘付近の天気の概況が掲載されています。29~30日 吹雪、30日は稜線上で風速20~25mの暴風で、新穂高ロープウェーも30日午後は運休。31日 日中は風はそれほど強くないが終日降雪、夜間に低気圧通過によって風が強まり荒れる。1日 日中は降雪はあるものの風は弱く、標高の高いところでは視界が開ける時間帯もあった。降雪は、30日未明から午後3時までの間に吹き溜まりで50cm以上、31日日中は不明、夜間は事前予報よりは少なく30~40cm程度。山荘付近の累計積雪量は190cmくらい。というわけで、この間基本的にずっと天気が悪く、降雪も続いていたようですが、本格的に天気が悪かったのは30日だったようです。年越しの31日晩も荒れたものの、夜間なので、基本的には登山者は寝ている時間帯です。ただし、この間ずっと降雪はある。基本的に稜線上で行動するのはちょっと難しい天気だったものと思います。冬山で天気が荒れると、どのくらいすごいか、他ならぬ私自身が、一昨年の年末に同じ西穂高で経験しています。そのとき撮った動画です。(1年前にも紹介していますが)12月30日もかなり強烈な風ですが、このときはある程度は視界もあり、まだ序の口でした。本格的にやばかったのは12月31日で、風もいっそう強烈な上に、降雪でまったく視界が利かない、これが一番怖かったです。このときは、動画に写っている丸山というところから引き返しました。丸山というのは・・・・・・この写真に写っているのですが分かりにくいので一部を拡大すると写真左下に人と、標識が立っているところが丸山です。山小屋から独標までの1/3くらいの位置、距離的は山小屋から500mも離れていません。そんな場所で、早くもそれ以上先に進めなくなってしまったのです。動画に、吹雪の中、他の登山者が何人か写っていますが、彼らは先に進んでいきました。ところが、私は、彼らも引き返すのだと思い込んで、一瞬彼らについて歩き出してしまうくらい、視界が利かなかったのです。すぐ、間違いに気が付いて引き返しましてたが。他の登山者と離れて一人で引き返すことに、一瞬恐怖を感じました。めがねが曇ったまま凍りついており、この動画以上に、私自身の視界は悪かったと思います。ほとんど見えないめがねで丸山まで引き返して、指導標を発見するのが一苦労。そこからは、動画に写っている赤旗をつたって(それも、10メートル毎くらいに立っているにも関わらず、ぼんやりとしか見えなかった)山小屋まで無事に帰ったわけです。冬山のルート上に立つ赤旗、あれが実際に初めて役に立ちました。なお、先に進んでいったほかの登山者も、結局その後ほどなくして引き返してきました。しかし、そんなに荒れた天気でも、稜線から下って一歩樹林帯に入ると、雪は降っているものの風はほとんどなく、トレースもしっかりしているので、山小屋からロープウェー終点までは、何の問題もなく下ってきました。森は偉大だなと思いますよ。しかも、西穂高山荘は、北アルプスの中でも最南端に位置しています。冬型の気圧配置の際は、日本海に近ければ近いほど天気は荒れる。日本の気象というのは不思議なもので、日本海気候と太平洋気候の境目付近では、10キロの距離の差で積雪量や天候が大きく変わったりします。一人亡くなった燕岳は、北アルプスの中では南部ですが、西穂独標よりは10km以上北に位置しています。まして大遠見山は北アルプスの北部です。西穂高山荘付近より降雪はかなり多く、天気も西穂高よりさらに悪かったはずです。燕岳で亡くなった方は、3泊4日だそうで、ということは相当のベテラン登山者だったはずです。冬季、北アルプスで営業している山小屋は西穂高山荘と北部の八方尾根の八方池山荘の2つしかなく、燕岳には冬季営業する山小屋はありません。つまりテントか冬季避難小屋での宿泊を最初から前提にして、その装備と準備と覚悟で登っていたはずです。それでも、遭難してしまうくらいの天気だった、ということです。ヤバイ天気のときは、無理せず引き返せ、ということなのだと思います。一方、太平洋気候が卓越する八ヶ岳では、この間、天気はそれほど大崩れはしなかったはずです。(冬型が極度に強まると、八ヶ岳でも雪が降りますが、通常は冬型になれば八ヶ岳は晴れる)そのせいか、八ヶ岳ではこれまでのところこの年末年始では遭難は報じられていないようです。八ヶ岳は冬季営業している山小屋がたくさんあるので、登山者の絶対数は北アルプスより多いはずですけどね。ただ、天気は良かったでしょうが、風は強烈だったはずです。二人が遭難して一人だけ救助された北岳は、八ヶ岳以上に太平洋気候の下にあるので、やはりこの間に天気は大崩れしていないはずですが、何か特異な事情があったのでしょうか。一人は未発見だそうですが、冬山でテントでも避難小屋でもない屋外で一晩過ごしたら、残念ながら生存は厳しいだろうなあ・・・・・・。何とか無事でいてほしいですけどね。ちなみに、私は一昨年から山岳救助費用の保険に加入しています。遭難なんかしないのが一番だし、遭難するかもしれないような条件のときはサッサと引き返すことを信条にしていますけど、やっぱり万が一ということがあり得ますから。
2015.01.02
コメント(4)
-

明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。この1年は、どんな年になるのでしょうか。安倍政権は、早速法人税の減税を決めてしまったようです。私は、消費税のアップに関しては、一概に是非を決められないと思っているのですが(そのあたりが、かつてとは自分の考えが変わってしまった部分のひとつです)、それも日本が巨額の財政赤字を抱えているからです。財政再建のために消費税を上げる、というなら、これは仕方がないかな、という思いもあるのですが、現実には消費税を上げた分で法人税を下げるわけです。そういうことならば、私としてはやっぱり消費税の引き上げには断固として反対せざるをえません。だいたい、日本の法人税は高いとされていますけど、いろいろな抜け道があるので、企業が実際に負担している法人税率は、それよりだいぶ低いと言われます。ソフトバンクの払っている法人税はたった500万円に過ぎない、という話もあります。加えて、日本の企業は社会保険料負担が(先進諸国の中では)比較的低いといわれます。社会保険のある正社員を切って、非正規雇用に切り替えているせいでしょうか。だから、税金+社会保険料(雇用者負担分)を合計した企業の負担は、決して高いものではないとも言われています。これらのことを考え合わせると、「日本の法人税は高い(から、企業が海外に逃げる)」というのは、限りなくためにする論議のように思えます。もうひとつ、この1年で問題となりそうなのは原発の再稼動です。脱原発への道筋の中で一時的に原発を再稼動することにまでは、私は反対はしませんけど、現実には経産省は既存の老朽原発の建て替えを検討すると明言しています。つまり、今後も原発を維持し続ける気満々なのです。そのための第一歩として原発を再稼動しようというのですから、これについても断固として反対です。一方で、円安による値上げラッシュは、これからが本番だといわれます。特に食品や生活必需品関係の値上げがこれから始まりそうです。これらのことを考えると、どうも政治も社会もよい方向に向かっているようには思えないのですが、せめて、少しでもマシな社会、少なくとも戦争だけは縁のない社会であってほしいものです。・・・・・・と、思いつつ、今日はのんべんだらり寝正月しています。全国的に天気は大荒れのようで、山岳遭難も各地で発生しています。27~28日は、あんなにいい天気だったのに。これについては、明日行こう記事を書くかもしれません。お正月なので、富士山の写真でも。最近撮ったものではなく、2001年2月に、東京都の最高峰雲取山の山頂から撮影したものです。何はともあれ、今年もよろしくお願いします。
2015.01.01
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1