2025年05月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

佐久間象山(感想)
佐久間象山は、江戸時代後期の信州松代藩士で、兵学と朱子学に長けた思想家です。 ”佐久間象山”(2022年7月 吉川弘文館刊 源 了圓著)を読みました。 幕末に開国と海防を訴えて西欧の近代科学を積極的に受容すべきと説いた、時代の先覚者である佐久間象山の生涯を紹介しています。 通称は修理といい、諱は国忠、のちに啓、字は子迪、後に子明と称しました。 洋学、蘭学、砲術、造艦、天文、医術、あらゆる分野に最先端の深い知識をもっていました。 幕末の天才と呼ばれ、当時の日本最高の知識人と言われていました。 1811年に松代藩士の佐久間一学国善の長男として、信濃埴科郡松代字浦町で生まれました。 佐久間家は微禄でしたが、父は藩主の側右筆を務め卜伝流剣術の達人で藩からは重用されていました。 母は松代城下の東寺尾村に住む足軽の荒井六兵衛の娘で、国善の妾に当たります。 象山は、父が50歳母が31歳の時に生まれた男児でした。 1824年に、藩儒の竹内錫命に入門して詩文を学びました。 1826年に、佐藤一斎の門下生だった鎌原桐山に入門して経書を学びました。 1833年に、江戸に出て林家の塾頭の佐藤一斎の門下となりました。 林家は、林羅山を祖とする日本の儒学者・朱子学者の家系です。 のち帰郷しましたが、1839年に再び江戸に出て、神田お玉ヶ池付近に塾を開きました。 さらに、松代藩の江戸藩邸学問所頭取なども務めました。 このころ、松崎慊堂、藤田東湖、渡辺崋山などと交流しました。 源 了圓さんは1920年熊本県宇土市生まれ、第五高等学校を経て京都大学文学部哲学科に進みました。 1948年に同大学を卒業し、同大学大学院に進学しました。 京都学派の田辺元や西谷啓治に学び、梅原猛と親交を結びました。 日本女子大学文学部教授を経て、東北大学文学部教授に就任しました。 1981年に、学位論文を東北大学に提出し文学博士となりました。 1984年に東北大学を定年退官となり、名誉教授となりました。 その後は、国際基督教大学教授として教鞭をとりました。 2001年に、日本学士院会員に選出されました。 並行して、コロンビア大学・北京日本学センター・オックスフォード大学などで客員教授を務めました。 佐久間象山は、若い頃は朱子学を学んでいましたが、藩主・真田幸貫の命令により洋学研究の担当となりました。 1841年に松代藩主の真田幸貫が老中に抜擢されると、象山は海防顧問となり海防八策を提出しました。 アヘン戦争の報により対外的危機に目ざめ、1842年に江川太郎左衛門に入門して砲術を学びました。 大砲の鋳造をはじめカメラや地震予知機まで、洋書だけを頼りに自分で作り上げたという逸話も残っています。 続いてオランダ語学習をはじめ、砲術教授の塾を開きました。 そこで、勝海舟、吉田松陰、坂本竜馬、加藤弘之らを教えました。 蘭学・砲学を入り口に、西洋学問の第一人者となり日本初の指示電信機による電信を行いました。 ほかに、ガラスの製造や地震予知器の開発まで成功させました。 西洋技術の摂取による、産業開発と軍備充実を唱えました。 1854年に門人吉田松陰の海外密航の事件に連座して蟄居となり、洋書をむさぼり読びました。 ペリー来航時は攘夷論を主張していましたが、のちに和親開国論者に立場を変えました。 1863年に赦免となり、翌年幕命により上洛しました。 当時上洛していた徳川慶喜に、公武合体と開国の必要性を説くことになりました。 これにより、京都に潜伏していた尊王攘夷派に目をつけられることとなりました。 1864年に、幕末四大人斬りのひとりである河上彦斎らの手により暗殺されました。 7月11日の夕刻、路上を馬に乗って通りかかり、刺客に襲われて斬られ即死したといいます。 松代町の西南には象山生誕の地が残り、隣接して象山を祀った象山神社があります。 近代日本における西欧文明への対応には、二つの型がありました。 第一は、いかなる意味においても西欧文明を排撃しようとするものです。 第二は、日本の取るべき進路は積極的に西欧文明を受容することにあるとするものです。 アーノルド・トインビーに従うと、第一のタイプの人々はゼロット(熱狂的排外主義者)、第二のタイプの人々は耐え難きを耐えるヘロデ主義者とみなされるでしょう。 象山は、ヘロデ主義者の代表ともいうべき人でした。 西欧の科学技術文明を積極的に受容することによって、西欧諸国の圧力に抵抗して自国の独立を守ろうとしました。 したがって、象山は両義性をもつ日本の近代科学技術文明の型をつくった人と言ってよいといいます。 近代日本の優れた面もそこに潜む問題点も、自分の生涯に集約的に具現しました。 しかしその範囲だけでは、象山の歴史的個性や日本の西欧文明受容の個性は明確にはなりません。 大切なのは、象山がどんな仕方で西欧の科学技術文明を学び、それを受容しようとしたかです。 ここまで問題を深めてはじめて、歴史的意義も日本の近代化の特性も明らかになります。 本書の初版は、PHP研究所の歴史人物シリーズの一冊として刊行されました。 温厚篤実な人格者の著者が、変人奇人と評される象山を扱うのは意外かも知れません。 著者は江戸時代の実学思想史の研究において、幕末期を代表する重要人物として早くから象山に着眼していました。 それゆえ象山理解は本格的で、実学史研究のさまざまな作品の中に象山研究の成果が織り込まれています。 著者は、長年の実学思想史研究の中で得たエッセンスを、簡潔平易な文体をもって要約しています。 象山の地元史家の、長年に亘る地道な研究の産物です。 本書は、著者が象山になり代わって象山という人間の人と思想を簡潔に語った伝記と考えられます。 「序章」と、「象山の生い立ち」「儒者の時代」「兵学への開眼」「黒船来航」「聚遠楼の日々」「上洛とその死」の六章で構成されています。 さらに各章の中が五話前後に区分けされ、全体が「五〇話」で完結しています。 すなわち、五十面体の象山像を読みやすさ理解しやすさに配慮して書かれた象山の伝記です。 読み進めると、変人奇人と言われた象山の虚像が覆され、長短を併せ持つ個性豊かな象山の実像が浮かびます。 コメンテーターの坂本保富氏は、本書は象山の思想と行動の全体像を描写した、象山研究の啓蒙書といえるのではないかといいます。序章 佐久間象山への視覚/第1章 象山の生い立ち/第2章 儒者の時代/第3章 兵学への開眼/第4章 黒船来航/第5章 聚遠楼の日々/第6章 上洛とその死 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]【3980円以上送料無料】佐久間象山/源了圓/著佐久間象山に学ぶ大転換期の生き方 [ 田口佳史 ]
2025.05.24
コメント(0)
-

三浦義村(感想)
三浦義村は鎌倉時代初期の相模国の武将で、鎌倉幕府の有力御家人です。 ”三浦義村”(2023年10月 吉川弘文館刊 高橋 秀樹著)を読みました。 北条義時と政子の死後に執権泰時と協調して新体制を支えた、有力御家人であった三浦義村の生涯を紹介しています。 1168年ころ、桓武平氏良文流三浦氏の当主である三浦義澄の次男として生まれたとされます。 義村の母親は、伊東祐親の娘にあたります。 義村の時代は、源平の戦い、鎌倉幕府の成立、御家人らの権力闘争が行われた時期と重なります。 父親の義澄は相模の国の武将で、源頼朝の挙兵に初期から加わりました。 各地に転戦して鎌倉幕府の成立に尽力し、十三人の合議制の一人として選ばれました。 義村は、生年を始め幼少期についてあまり明らかにされていません。 義村が初めて史料に登場するのは、1182年の『吾妻鏡』です。 源頼朝正室政子の安産祈願のため、安房東条庤へ遣わされた使者として三浦平六の名前が見えます。 三浦平六は、義村の別名の通称です。 1184年と翌年の平氏追討や、1189年の奥州征伐に従い、父親とともに平氏追討に武功をあげました。 和田義盛の挙兵や承久の乱で北条氏を助けたことから信任され、評定衆にも選ばれました。 頼朝亡き後は北条氏と密接に結びつき、幕府内での政治的地位を高めました。 高橋秀樹さんは1964年神奈川県生まれ、1989年に学習院大学大学院人文科学研究科修士課程を修了しました。 1996年に同博士課程を修了し、”日本中世の家と親族”で博士(史学)となりました。 1992年に日本学術振興会特別研究員、1994年に放送大学非常勤講師となりました。 1995年に国立歴史民俗博物館非常勤研究員、1998年に東京大学史料編纂所研究員となりました。 2018年から國學院大學文学部史学科教授となり、現在に至っています。 1190年に頼朝が上洛したとき、義村は父親の功によって宮中の警備をする右兵衛尉に任じられました。 のちに左衛門尉に転じ、さらに駿河守となり正五位下に叙せられました。 1199年1月に源頼朝が没し、嫡男の源頼家が2代将軍となりました。 このころ鎌倉幕府内部では、御家人らの権力闘争が目立つようになりました。 義村は、そのなかでたびたび重要な役割を果たしました。 1199年12月の梶原景時の乱では、朋友の結城朝光を助け他の御家人たちの談合を画策しました。 義村は、御家人66名による梶原景時の糾弾状を作成し、梶原一族を退けました。 1202年には、娘を北条泰時に嫁がせ北条氏との関係を固め勢威を強めました。 1205年の畠山重忠の乱では、北条時政の命により義時とともに畠山重忠を討滅しました。 この事件は、牧の方が時政に讒訴したため畠山氏に叛意のなかったことが判明しました。 すると義村は、事件の関係者らを鎌倉の経師谷で討ちました。 同年7月には、将軍の実朝を廃して平賀朝雅を擁立しようとした牧の方の陰謀が発覚しました。 このとき義村は、北条政子と義時に協力して実朝の安全を守りました。 この事件がきっかけで、執権の時政は落飾して伊豆に隠退し義時が執権となりました。 義時の味方となったために、ときには一族と相対する立場に身を置くこともありました。 鎌倉幕府内部の権力闘争を、冷静かつ大胆に生き抜いたのです。 執権義時の亡き後は、幕府を左右する政治力を持つ存在となりました。 この頃、三浦一族の国司、守護、地頭職にあった地域は全国に及びました。 1213年に、一族の中で大きな勢力であった従兄弟の和田義盛と和田合戦で敵対しました。 将軍実朝と執権義時を廃して、故将軍頼家の遺子栄実を擁立しようとしました。 義村は、義盛に味方するという起請文を書きながら変心しました。 義時に義盛の挙兵を伝え、謀反人とされた義盛らは滅亡しました。 1219年1月27日に、将軍実朝が頼家の子の公暁に暗殺されました。 公暁は義村に幕府の準備を頼む書状を持った使いを出しましたが、義村は偽って討手を差し向けました。 公暁は、義村宅の塀を乗り越えようとしたところを殺害されました。 1221年の承久の乱では、弟の胤義から決起をうながす書状を受けとりましたたが、義村は使者を追い返し義時の元に向かい通報しました。 出戦が決まると、東海道方面軍の大将軍の一人として東海道を上り東寺で胤義と相対しました。 その後、胤義は子の胤連、兼義とともに現・京都市右京区太秦の木嶋坐天照御魂神社で自害しました。 乱終息後の戦後処理でも、義村は活躍しました。 1224年に北条義時が病死すると伊賀氏事件が起き、義村は伊賀の方一族を追放しました。 1225年夏に、大江広元・北条政子が相次いで死去しました。 執権北条泰時の下で評定衆が設置され、義村は宿老としてこれに就任しました。 幕府内の地位を示す椀飯の沙汰では、北条氏に次ぐ地位となりました。 1232年の御成敗式目の制定では、前駿河守平朝臣義村として署名しました。 4代将軍の藤原頼経には、義村は子の泰村と共に近しく仕えました。 そして1239年に亡くなり、死因は「頓死、大中風」だったといいます。 頓死とは急死、大中風とは脳卒中発作の後で現われる半身不随です。 ほとんどの日本人にとって、ごく最近まで三浦義村は未知の存在でした。 本人は、中学校歴史教科書や高等学校日本史教科書に登場しません。 子供の泰村は、1247年に起きた鎌倉幕府の内乱である宝治合戦で滅ぼされた存在として、多くの高校教科書に書かれています。 父親の義澄については、いわゆる十三人の合議制の一人として名を載せている教科書があります。 しかし、義村の名を記す教科書はないのです。 載っていないのは、北条氏に討たれなかったからです。 滅ぼされた梶原景時、比企能員、畠山重忠、和田義盛、三浦泰材は敗者として記述されています。 義村は北条氏の協力者かライバルとみられ、対象外でした。 義村像の再評価のきっかけをつくったのは、作家の永井路子氏でしょう。 1964年の直木賞受賞作『炎環』で、源実朝暗殺事件の黒幕として義村を描きました。 1978年の『執念の家譜』では、三浦一族の歴史をたどりました。 1979年のNHK大河ドラマ『草燃える』で、ダーティーな義村のイメージは一部に定着しました。 2022年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では、主人公の北条義時の生涯にわたる盟友として描かれました。 本書の主眼は、三浦義村の人生をたどることにあるといいます。はしがき/第1 義村の誕生/第2 若き日の義村/第3 宿老への道/第4 義村の八難六奇/第5 最期の輝き/第6 義村の妻子と所領・邸宅・所職、関係文化財/三浦氏略系図/略年譜/参考文献 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]三浦義村(321) (人物叢書) [ 高橋 秀樹 ]【中古】 三浦義村 / 暁 太郎 / KADOKAWA(新人物往来社) [単行本]【ネコポス発送】
2025.05.10
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- 楽天写真館
- 17 日 ( Monday ) の日記 流れ星…
- (2025-11-17 05:16:30)
-
-
-

- 政治について
- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…
- (2025-11-16 18:49:04)
-
-
-
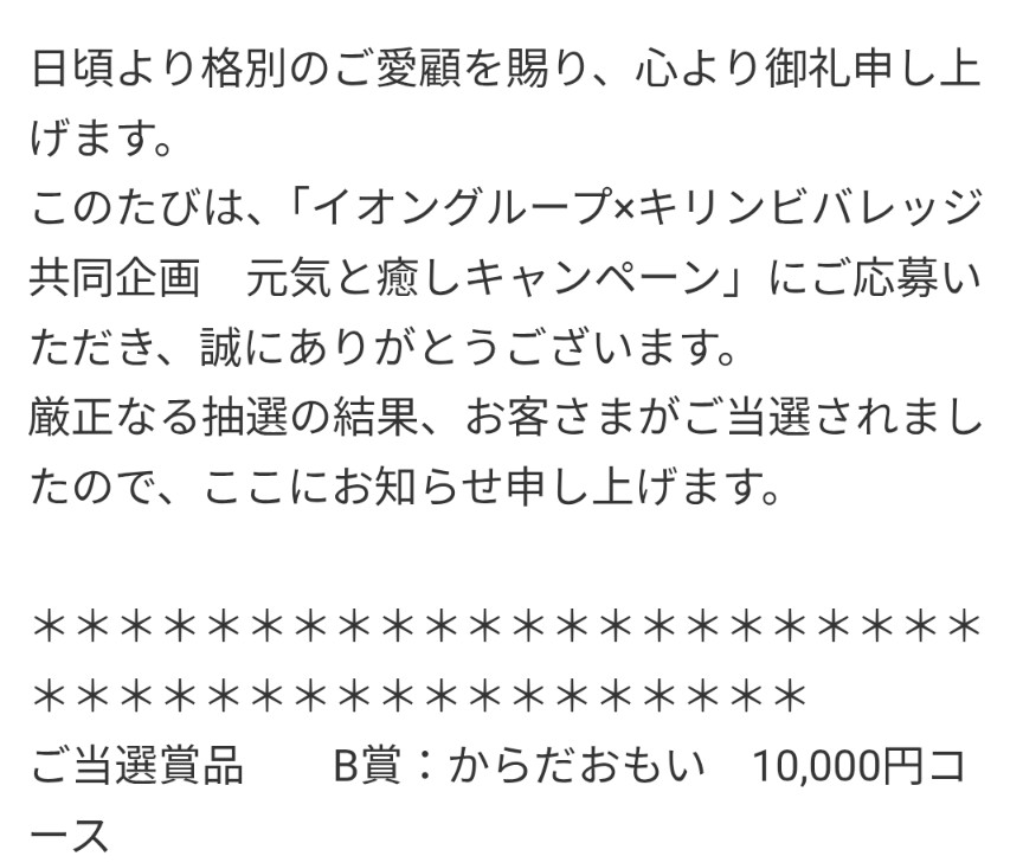
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-







