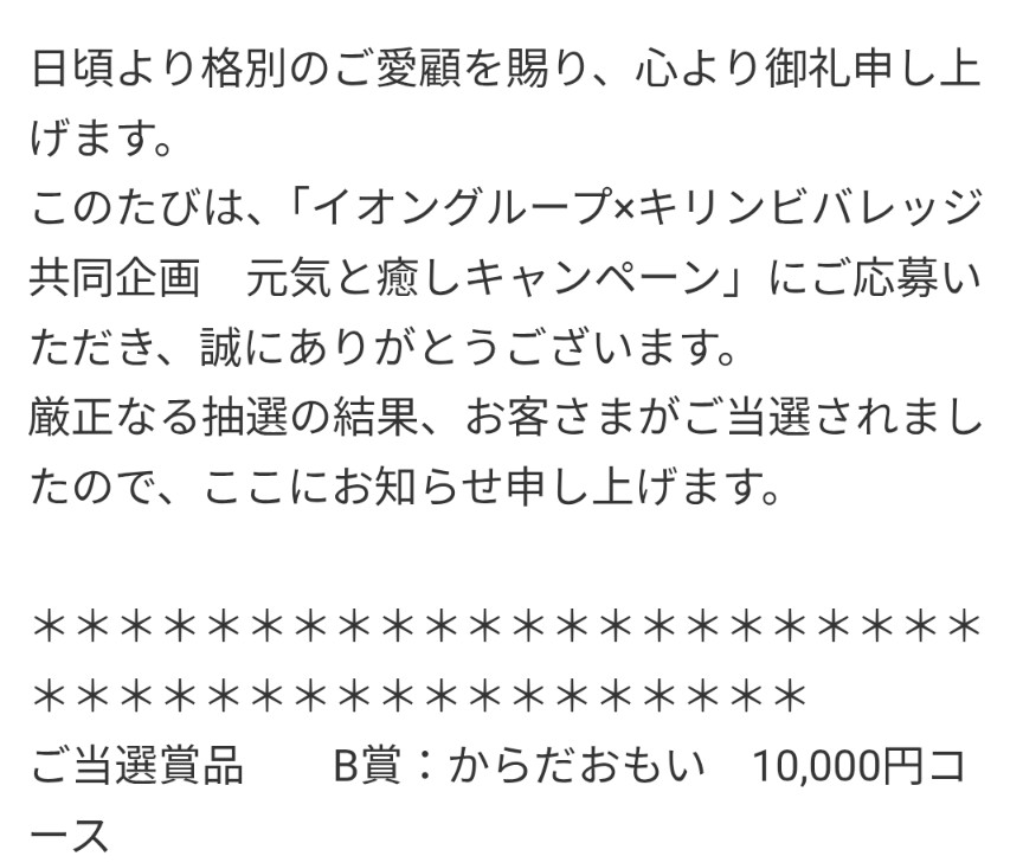2025年09月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

藤原広嗣(感想)
藤原広嗣は、生年不詳、奈良前期の政治家で式家宇合(うまかい)の第1子です。 母は蘇我石川麻呂の女で、弟に綱手・良継・田麻呂・百川らがいます。 ”藤原広嗣”(2023年12月 吉川弘文館刊 北 啓太著)を読みました。 藤原式家宇合の嫡男に生まれ出世街道を歩んでいましたが、突如左遷されました。 後に内乱の首謀者となって蜂起しましたが、敗死してしまった藤原広嗣の生涯を紹介しています。 宇合は藤原四子の一つで、藤原式家の開祖です。 藤原四子は、中臣鎌足の息子である藤原不比等の子供です。 四子はそれぞれ独自の家を起こして、当時隆盛を誇っていました。 武智麻呂は藤原南家、房前は藤原北家、宇合は藤原式家、麻呂は藤原京家の開祖です。 藤原家は、在位西暦724年~749年の第45代聖武天皇の時代に政治の中枢を担っていました。 広嗣は宇合の長男として生まれ、順調にいけば出世を約束されている地位にありました。 宇合は右大臣だった藤原不比等の三男で、官位は正三位・参議、勲等は勲二等です。 731年に参議となり、畿内副惣管となりました。 翌年に西海道節度使として九州に赴き、西国警備のための警固式を作成しました。 ところが、735年に大宰府管内において天然痘が襲い掛かかりました。 藤原四兄弟も次々と天然痘を発症し、737年に相次いで病没しました。 聖武天皇は緊急事態を打開すべく、橘諸兄に事態の収拾を任せました。 北 啓太さんは1953年北海道生まれ、1984年に東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学しました。 宮内庁書陵部編修課長、同庁正倉院事務所長、同庁京都事務所長を歴任し、2014年に定年退職しました。 藤原不比等政権の末期から、日本は新羅と安定した外交関係を築きました。 それを前提に、軍事を縮小して経済的に資するようにしました。 続いて長屋王もこの軍縮路線を継承しましたが、藤原四兄弟に討たれてしまいました。 藤原四兄弟は唐を支援する新羅に軍事的圧力をかけ、軍事拡張路線に転じたのです。 737年に藤原四兄弟が天然痘によって死去すると、代って政治を担ったのは橘諸兄でした。 諸兄は聖武天皇の皇后である光明子の異父兄で、臣籍降下して橘朝臣姓を名乗っていました。 諸兄は社会の疲弊を復興するため、新羅との緊張緩和と軍事力の縮小政策を取りました。 また、唐から帰国した吉備真備と玄昉を重用するようになりました。 この二人は、当時としては最先端の知識と学問を携えて帰国していたのです。 唐の最新文化を取り入れ国の威信を高めるために、当時の日本には適材適所でした。 これに対して、藤原氏の勢力は大きく後退し、広嗣は738年に大養徳守から大宰少弐に任じられました。 これは対新羅強硬論者だった広嗣を中央から遠ざけ、新羅使の迎接に当たらせる思惑がありました。 広嗣はこれを左遷と感じ、強い不満を抱いたとみられます。 藤原氏の地位低下に対し、日常的に周囲に不満をもらしていたといいます。 740年4月に新羅に派遣した遣新羅使が、追い返される形で8月下旬に帰国しました。 憤った広嗣は8月29日に政治を批判し、吉備真備と玄昉の更迭を求める上表を送りました。 同時に筑前国遠賀郡に本営を築き、烽火を発して太宰府管内諸国の兵を徴集しました。 朝廷はこの言動を謀反とし、広嗣逮捕の勅を出しました。 しかし広嗣はこれに従わず、9月3日に九州の兵を集めて反乱を蜂起しました。 藤原広嗣が反乱を起こしたとき、挙兵は大宰府管内諸国に及びました。 広嗣は、弟綱手に筑後・肥前などの軍兵5000人を率いて、豊後道より豊前国へ進ませました。 一隊は田河道に配し、自らは鞍手道を遠珂郡家に進み、ここに軍営を営みました。 烽火をあげて軍兵を徴発し、隼人を含めて大隅・薩摩・筑前・豊後などの軍兵5000人余を擁しました。 聖武天皇は大野東人を大将軍に任じて節刀を授け、副将軍には紀飯麻呂が任じられました。 東海・東山・山陰・山陽・南海五道の1万7000人を動員し、24人の隼人も従軍させました。 朝廷からは伊勢神宮へ幣帛が奉納され、諸国に戦勝を祈願するよう命じられました。 9月21日に東人は長門国へ到着し、渡海のために停泊中の新羅船の徴用の許可を求めました。 9月22日には、勅使・佐伯常人、阿倍虫麻呂が板櫃鎭に陣を構え、一帯を制圧しました。 これに伴い、広嗣勢の豊前国の京都鎮・登美鎮・板櫃鎮の三営は政府軍に抑えられました。 9月25日には、豊前国の諸郡司が500騎、80人、70人と率いて官軍に投降してきました。 10月初旬の板櫃川の対陣で、1万余の軍勢を擁しながら、広嗣勢は渡河を阻まれ隼人の降伏も続出しました。 中旬には船で敗走し、済州島付近に達しましたが、逆風で五島列島に吹き戻されました。 最後は9月23日に、宇久島で捕らえられ、11月1日に綱手とともに斬刑に処せられました。 反乱に対する処分は280人以上に及び、弟良継・田麻呂らも配流されました。 そして、広嗣の怨霊を鎮めるため、唐津に広嗣を祀る鏡神社が創建されました。 新薬師寺の西隣に鎮座する南都鏡神社は、その勧請を受けたものです。 藤原式家は一時衰退し、大宰府も742年から3年余り廃止されることになりました。 広嗣と言えば、一般的には、ほぽこの藤原広嗣の乱の一事のみで知られているのではないかといいます。 本書でも、それ以外に付け加えられる内容は多くないといいます。 乱関係を除くと、確かな史料が少ないからです。 五位以上にならないと、特別なことがないと正史には記載されません。 乱の時には五位になってわずか3年で、まだ20代だったと考えられます。 広嗣については、確かな史料に基づく事跡というものはあまり求められません。 そのため本書では、広嗣に関わる周囲の状況や歴史の流れをみていくといいます。 これにより、広嗣という人物を理解できるよう叙述を進める場合があるということです。はしがき/第1 家系、一族/第2 誕生、成長、出身/第3 五位貴族として/第4 藤原広嗣の乱の勃発/第5 乱の展開と終息/第6 乱後の世界/第7 伝承上の藤原広嗣/藤原広嗣関係系図/皇室略系図/略年譜 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]藤原広嗣/北啓太【3000円以上送料無料】聖武天皇 「天平の皇帝」とその時代 (法蔵館文庫) [ 瀧浪 貞子 ]
2025.09.27
コメント(0)
-

志筑忠雄(感想)
志筑忠雄は、1760年に長崎の資産家だった中野家三代用助の子として生まれました。 通称は忠次郎といい、名を盈長、忠雄といいました。 晩年には、飛卿、季飛と字を名乗り、柳圃と号しました。 ”志筑忠雄”(2025年1月 吉川弘文館刊 大島 明秀著)を読みました。 江戸後期に並外れたオランダ語力と数学的思考力で、天文学書の和訳に専念した志筑忠雄の生涯を紹介しています。 志筑は「しづき」と読まれてきましたが、現代の長崎では「しつき」と読む苗字もあるそうです。 生家は旧県庁舎にほど近い、現在の長崎市万才町の一画です。 中野家は、呉服商・三井越後屋の長崎での落札商人でした。 三井家との関係は、代理で貿易品の取引をした有力な家でした。 忠雄は幼時に長崎通詞の志筑家の養子となり、8代目を継いで1776年に稽古通詞となりました。 稽古通事は、長崎勤務の唐通事・オランダ通詞の職階で、見習いの通訳官です。 1777年に、18歳のとき病身のため辞職して中野家に出戻りました。 その後、本木良永について天文学、オランダ語学の研究に専心しました。 主著の『暦象新書』をはじめ、多くのオランダ書の訳述や著述に従いました。 主著は、イギリス人ジョン・ケールの著書のオランダ語訳書を解訳したものです。 このなかで地動説を述べ、地動説を肯定しながらも天動説を排除しない立場です。 付録の混沌分判図説では、星雲に関して独創的見解が述べられています。 ヨーロッパの自然科学説の紹介だけでなく、科学思想史的にも重要な意義をもちます。 大島明秀さんは1975年大阪府生まれ、1999年に関西学院大学文学部日本語日本文学科を卒業しました。 2003年に、九州大学大学院比較社会文化学府国際社会文化専攻修士課程を卒業しました。 2008年に、同大学院比較社会文化学府国際社会文化専攻博士後期課程を修了しました。 2008年に熊本県立大学 文学部講師、2010年に准教授、2022年に教授となりました。 博士(比較社会文化)で、研究分野は蘭学・洋学史、日欧交流史、日本近世史です。 志筑忠雄は、稽古通詞を遅くとも27歳までに辞め、その後は家にこもり蘭書の翻訳にふけったとされます。 志筑には4人の兄がいて、一人は養子に出され薬種目利という貿易の仕事に就いていました。 父用助は貿易関係情報入手のため、息子たちを能力に応じてそれぞれの職に就けたと思われます。 通詞を辞めた志筑を養ったのは、オランダ語ができる人間を置いておく利点がありました。 志筑は当時としては、飛び抜けたオランダ語の能力や国際的な感性を持っていたといいます。 23歳のとき、通詞は休職中でしたが、ジョン・キール蘭書訳出の唱矢である『天文管閥』(1782年)を訳出しました。 並行して、西洋のさまざまな事柄を記した雑記帳である、『万国管閥』を書き上げました。 1792年には、第一回ロシア遣日使節ラクスマンが来日しました。 1796年頃から、ロシア南下情報や西洋人の日本観などに関わる新分野の翻訳に取り組み始めました。 イギリス人ジョン・キールのニュートン力学解説書の蘭訳書を、『暦象新書』(1798年)で抄訳しました。 オランダ語で記された書籍を通して、日本で初めてニュートン物理学を紹介したのでした。 これは公儀、社会に対する貢献を目的として、公務ではなく私事として行いました。 また、ネイピアの法則を案内するなど、自然科学分野で稀代の才能を示しました。 ネイピアの法則は、直角球面三角形の辺と角に関する法則です。 その慧眼と能力は、国際関係分野においても発揮されました。 特筆すべきは、『鎖国論』(1801年)で鎖国という日本語を創出したことです。 また、ケンペル『日本誌』蘭語版の中から、日本の対外関係を論じた附録第六編(1802年)を訳出しました。 当時、ロシア南下の情報に動揺する社会情勢があったため、ヨーロッパの日本観を呈示しました。 絶筆となった『二国会盟録』(1806年)では、ネルチンスク条約締結の状況を訳出しました。 条約は、清朝とピョートル1世との間で結ばれた、境界線などを定めた条約です。 これは、約50年後の日露和親条約の交渉・締結の際に、勘定奉行と翻訳官が参考書としました。 これらの学問を支えた忠雄のオランダ語力は、同時代の水準を超越していました。 革命的な蘭文法書と蘭文和訳論は、西洋文法を踏まえてオランダ語を理解・説明していました。 これらは、蘭学者をはじめ19世紀日本人のオランダ語読解力を飛躍的に向上させました。 また、翻訳の際に使用した「引力」「重力」「弾力」「遠心力」「求心力」「真空」「分子」などは、後に自然科学分野の術語となりました。 「鎖国」「植民」など、国際関係あるいは政治にまつわる新しい言葉を創出しました。 このように、多岐にわたる仕事を成し遂げた、空前の才能と情熱の持ち主です。 しかし病弱で、後半生は人との交わりを絶ち、実家に螢居して蘭書翻訳に専念しました。 このように、著作は多数ありますが、意外に手紙や墓といった史料が残っていません。 そのため、業績のわりに活動の実態が分かっていないといいます。 忠雄の学問は、主に蘭書訳出を通してそれまでになかった新しい知識や視点、方法をもたらしました。 第一に、訳業を通して自身の言葉でオランダ語理解と蘭文和訳の要諦をまとめました。 第二に、『暦象新書』を代表として、天文学、弾道学、数学の新しい知識をもたらしました。 第三に、『万国管闚』などによる、地理誌、物産でも新しい知識をもたらしました。 第四に、『鎖国論』などによる、西洋に照準を合わせた国際情勢についての新しい所見をもたらしました。 これらは、それぞれの分野において、没後の近世後期社会にも一定の影響をもたらしました。 しかし、忠雄の社会的活動は短く、人生を跡付けられる一次史料がきわめて少ないです。 そのため、第二章以下の主要な史料は、目下25点確認されている生前の著述とならざるをえません。 近世後期の長崎を舞台に、謎と魅力に満ちた一学者の生涯を見ていくことになります。 仕事を手掛かりに、それぞれの時期における関心や活動を検討して見ていくといいます。はしがき/第一 生い立ちと通詞の辞職/第二 学問への熱情と献身/第三 学問の変容と再仕官の夢/第四 『暦象新書』の完成とその後/第五 オランダ語読解の革命/第六 晩年と没後の影響/中野家略系図/志筑家当主略系図/略年譜/生前(文化三年七月八日以前)の分野別著作・署名一覧/参考文献 [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし] 志筑忠雄 (人物叢書 325) [ 大島 明秀 ]【中古】 蘭学のフロンティア: 志筑忠雄の世界志筑忠雄没後200年記念国際シンポジウム報告書
2025.09.13
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1