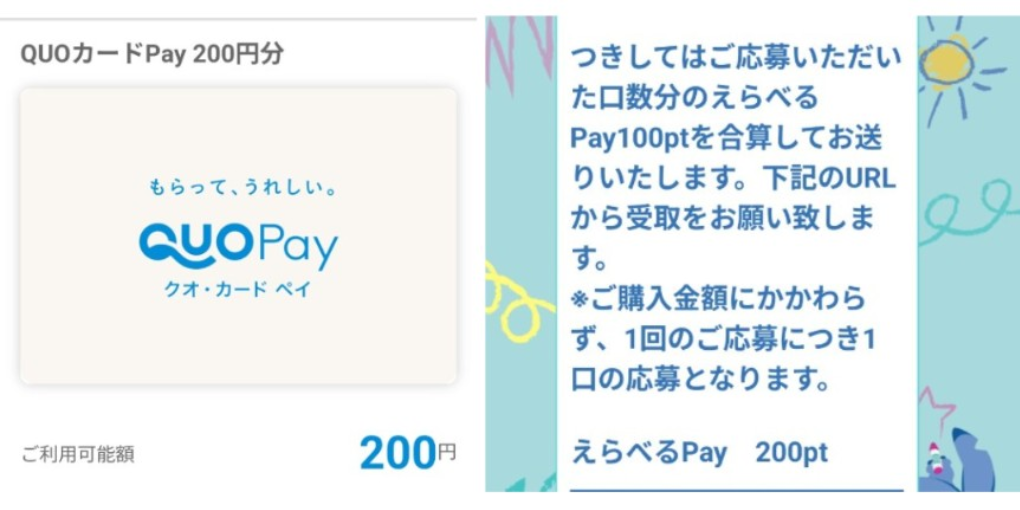2016年03月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

新作 『 入れ子 12面体 』 の公開!
2016年は当たり年とも言うべきか、一月初旬から数点の新作が生まれているのだが、自身のホームページ(下記に紹介)に公開できた作品は、今年になって今回が二作目となる。そこで上の画像は、今回が初めての公開となる新作『 入れ子12面体 』の晴れ姿を映したものだ。上に・・・今回が初めての公開・・・と記したのは、実はこの造形は十数年前に創作していたためで、この3月23日という春分に近い「満月」の月日に、満を持してこの『 入れ子12面体 』が公開できたことを嬉しく感じている。さて、作品の名称に「入れ子」を加えているのは、この造形が全体として、大小二つの「正12面体」の軸線構成が合体した二重の構造体になっているからである。つまり、内側にある「小さな12面体」の外側に、それを取り巻くように「大きな12面体」を組み上げた構成となっているので、例えば内から外へと拡大するマクロの方向、あるいは外から内へと縮小するミクロの方向・・・などと、イメージングを楽しみながら「入れ子」の関係にある大と小の12面体の相互関係を様々に類推することができる。おそらく想像力(創造力)の豊かな方は、この作品を通して変幻自在の想いを巡らせることができるだろう。
2016年03月23日
-

筑前「夫婦岩」からの夕映え
昨日の夕刻は、ほぼ真西の海に沈む夕陽を拝もうと、筑前 二見ヶ浦(ちくぜん ふたみがうら)にある「夫婦岩」(福岡県糸島市志摩桜井)を訪ねた。現地の撮影場所となる海岸に到着したのは落日の直前だったのだが、何とか間に合ってシャッターチャンスをものにした画像が上である。それにしても「春分の日」の翌日・・・玄界灘に沈む夕陽は、とても美しかった・・・。まるで扇を開いたかのように黄金色の光を放つ風情は、前回の日記(⇒リンク)等で何度も記してきた如く、日本列島の富士山を要として大地に刻印された、秘められし「扇(奥義)」を全開したかのようであった。この筑前二見ヶ浦の「夫婦岩」の夕日は、伊勢二見ヶ浦の「夫婦岩」の朝日とともに有名で、特に夏至の頃に夫婦岩の間に沈む夕陽の景観は、また格別とのことである。
2016年03月22日
-

春分の日を想う
年初の記事《「扇」が開く時》にも書いたように、私なりの感覚では明日の「春分の日」から「岩戸開き」に相応しい日取りとなる。その「扇」と「岩戸」を重ねて解説を試みてきたわけだが、そのどちらも「女性性」が共通項と言えよう。・・・となれば、その言わんとするところは日本の国母たる「イザナミ尊」の《よみがえり》であると同時に、「女性性の開放」と言えるのではなかろうか・・・。そして今朝になって気付いたのは、今月の23日が満月(旧暦2月15日)だということ・・・。その春分に近い「満月」こそが、年間の節目として相応しいと感じ始めた今日この頃である。◎関連記事・・・「扇(奥義)」の角度・・・⇒ リンク◎関連記事・・・「扇」を開く ⇒ リンク◎関連記事・・・「岩戸開き」に繋がる旅路・・・(1) ⇒ リンク
2016年03月19日
-

”光の道”のその先に・・・(3)
このシリーズでタイトルに掲げた”光の道”とは、宮地嶽神社からまっすぐ伸びた参道の延長線上に夕日が沈み、参道が夕日に照らされる状態のことをいう。季節によって徐々に夕日が沈む位置がずれるので、ピッタリの位置にくるタイミングは一年に二回ほどしかなく、その期間とは10月20日頃と2月20日頃のそれぞれ一週間とのことだ。実は今回、この神社の参道が10月20日頃、西海に沈む夕日の方向を示すことを知ったとき、直感的にかつて何度か訪れたことのある「金山巨石群」(上の画像)で確認された、一年の太陽運行における節目の月日に近いということを思い出したのだった。さもありなんということで、その「金山巨石群」に詳しいホームページ(以下に紹介)を開いてみると、上に記した一年に二回の日の頃が、一年間の周期を知る重要な節目の日として精確に観測されていたことが確認できると記されていたのである。☆【 金山巨石群と太陽暦 】⇒ リンクより、[ 冬至をはさんだ約120日間 ]をクリック◎関連記事・・・2013年 4月8日 「春」の旅日記(15)⇒ リンク◎関連記事・・・2013年10月23日 「秋」の旅日記(22)⇒ リンク一般的に一年間の節目といえば、夏至・冬至の二至、春分・秋分の二分を併せた「二至二分」が基本だが、「金山巨石群」ではその「二至二分」の観測よりも、むしろ上記の一年に二回の日(10月20日頃と2月20日頃)の観測の方が重要視されていた形跡がうかがえること、またその太古より伝わる太陽周期の観測の手法が、もしかすると宮地嶽神社の”光の道”たる参道に投影されているのかもしれないと思うと、おのずと感動が込み上げてくるのであった。ちなみに、上に紹介したホームページの金山巨石群(天体運行の観測装置)で古代人が観測してきたとされる、一年に二回の正確な月日とは《10月23日(二十四節気の「霜降」の日に相当)》と《2月19日(二十四節気の「雨水」に相当)》であり、その冬至をはさんだ約120日が磐座内に差し込む太陽光を連続して観測できる期間となっている。加えて「金山巨石群」の研究調査によれば、磐座に射込む光を「一年に二回の節目の日」に読み取ることによって、一年間の周期をかなり正確に知ることができる仕組みになっていることが判明していることから、太古よりこの「一年に二回の節目の日」が大切な日取りとされてきたことが推考できるというわけだ。さてこの画像は、「相島」の西海岸にある「龍王石」を、その全体が把握できるよう背後から撮影したもので、昔から漁を生業とする海の男の信仰を一身に集める御神体だったそうである。いつも引用させていただく書籍『 縄文の星と祀り 』の著者 堀田聰八郎氏の検証では、この「龍王石」が初めて祭祀された年は、紀元前2635年と明確に出たとのことで、縄文時代の中期頃には博多湾岸域の各地に意図的に形成された磐座や立岩等を繋ぐ、言わば「灯台ネットワーク」が形成されていたと推察できるとのことだ。今から4500年以上前より、「相島」には縄文系譜の祭祀場が形成されていた・・・それはおそらく上記の「金山巨石群」のように綿密な天体観測と地文測量に基づいて設置されたものであり、そのような歴史的背景を受け継ぐかたちで、宮地嶽神社と相島を結ぶ一直線の参道が成形されたのではないかと考える。最近のTVコマーシャルで見た”光の道”が、以上のように自分でも意外な展開をみせるとは・・・感慨無量である。
2016年03月02日
-

”光の道”のその先に・・・(2)
年に2回の2月20日頃と10月20日頃、宮地嶽神社の神前より西方の海に落ち行く夕陽は、参道の先に真っ直ぐ沈み、神社と海岸、そして「相島(あいのしま・あいしま)」が一直線で結ばれる。その年に2回の日取りに、当社では「夕陽の祭」が開催され・・・ご祖先様が坐(マ)します彼の世(あのよ)と この世が一直線に繋がる日・・・として大切にされてきたとのことだ。その祭日に神社と一直線に結ばれる「相島」は、福岡県糟屋郡新宮町の島(有人島)である。新宮漁港から北西約7.5キロメートル、町営渡船でわずか17分の玄界灘の海上に浮かぶ。島の形状は三日月型で東西に細長く、南に面して入り江になっており、夏季の台風接近や冬季の北西寄りの季節風等により玄界灘が荒れている場合も、対岸の九州本土に比べて船の出入りが可能であることが多く、昔から急な荒天の場合の船の避難場所となっていたそうだ。今回が初めてとなる「相島」に渡って訪れた東方の長井浜という場所に、国指定史跡の「相島積石塚群」があった。この積石塚は4世紀後半~6世紀のものとされ、約500m×50mの範囲に250基以上の積石塚群があり、円墳や方墳が中心だが、前方後方墳もある。冒頭の画像は、一帯の積石塚群の中央部にあって最大の「前方後方墳(相島大塚・120号墳)」を映したものだ。そして次の画像は、その解説版を撮影したものである。ある研究者によると、この「相島積石塚群」は海人族(安曇族)との関係がうかがえる貴重な遺跡で、宮地嶽神社の参道がピタリとこの古墳群に向けられており、神社境内地と古墳群は同時期に位置調整が行われたことがわかるそうである。・・・とのことから、冒頭に記した「夕陽の祭」の・・・ご祖先様が坐(マ)します彼の世(あのよ)・・・とは、まさしく神社の参道が指し示す先の「相島積石塚群」を意味していたことを、現地を訪れてみて実感したところである。平成13年に国指定史跡となった「相島積石塚群」の地域内は、現在は見学路が設けられ散策ができるようになっている。下の画像は、積石塚群で最大の前方後方墳の上から、画像では確認できないが対岸の中央部にある参道の、その先の高台に鎮座する「宮地嶽神社」の方面を撮影したものである。さてそこで、なぜ年に2回(2月20日頃・10月20日頃)の沈む夕日が示す方向を、神社の参道として定着させるほど重要視したのか・・・次回の日記ではその背景について考察してみたい。
2016年03月01日
全5件 (5件中 1-5件目)
1