2015年03月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

意外な翻訳者
今日は一日、ジョーゼフ・マーフィーの『眠りながら成功する』(上下、三笠書房)を読んでおりました。 まあ、内容的にはいつもの自己啓発系なのですが、潜在意識の効力を強調しているのが特徴。眠る直前など、潜在意識へのバリアが一番薄くなる頃合いを見計らって、その潜在意識に働きかけると、すべて物事は思い通りになると。 例えば、寝る前に「明日は7時に起きなきゃな」とか思いながら眠ると、不思議と6時59分とかに自然に目が覚めて、目覚まし時計が鳴る前に止めることがよくありますが、あれも結局はそういうことなんでしょうな。 ちなみにジョーゼフ・マーフィーは、ニューソート系ライターの中でも最も人気のあった人と言われていて、講演やら本やらで稼ぎまくった人。それだけに、この本もなかなか興味深いものでありました。 ところで私が一つ気になったのは、この本の翻訳者。大島淳一さんという人なんですが。 大島淳一って言ったって、誰それ? って感じですよね。 だけど、これは実はペンネームで、本名は渡部昇一。そう、上智大学名誉教授の。『知的生活の方法』というベストセラーで有名な人。右翼の論客。 そういう人が、なぜか名前を隠してこういう本を訳しているっていうのが面白いなと。 学者として名のある人が、こういう一歩間違えたら「トンデモ本」と言われそうな本を訳したり紹介したりするのが恥ずかしかったのかしら? ところで、自己啓発系のことを調べていて、面白いなと思うことは、この本も含め、意外な人がその紹介に携わっていることでありまして、たとえば物理学者の竹内均氏とか。この人も随分、自己啓発本の翻訳・紹介をしているんですよね。 物理学者が、何故? まあ竹内均氏は『ニュートン』を創刊した人で、「啓発」ということには昔から思い入れのある人だからかも知れませんが、論客とか、物理学者とか、理路整然たる思考能力のある人たちが、自己啓発にやられるというところが、私にすれば面白いなと。 ま、そんな自己啓発本をめぐるあれやこれやのことを楽しみながら、この種の本を読み進めている私なのであります。これこれ! ↓知的生きかた文庫マーフィー眠りながら成功する 上/J.マーフィー/大島淳一【後払いOK】【25...価格:555円(税込、送料別)
March 31, 2015
コメント(0)
-
二木の菓子
今日は春休み恒例、姉と家内と三人で東京散歩をしてきました。 先ず行ったのは、根津・東京大学農学部内にある「アブルボア」というレストラン。一般人も食べられる・・・というか、今日などほとんど一般人のおじさん、おばさんばっかりでしたが、とにかく皆さん情報通ばかりで、ここが穴場だというのは知れ渡っている模様。でも、結構安くて、9品の様々なおかずに白米か十穀米のごはん、それに何故か納豆がついて、さらにスープとサラダは食べ放題で880円! とくにサラダは、農学部内にあるレストランのせいか、すごく新鮮でおいしかったです。 それにしても、「東大」っていうと、何だかそれだけで気圧されるのか、近辺の道を行く白髪の老人が皆「博士」とか「教授」に見えるのは私だけだろうか? さて、ここでお腹を満たしてから、上野・不忍池の淵を回って御徒町方面へ。上野の公園内はサクラが満開で、陽気もいいし、ちょうどいい花見となりました。 ところで、何故に御徒町に向ったかと申しますと、「アメ横」に行くためなのでございます。東京でも西の方に実家があるもので、実は東京の東側ってあまり縁がなく、あの有名なアメ横なるところにワタクシは行ったことがなかったんですよね〜。 そして! ついに私は、アメ横で「二木の菓子」に入ってしまったのでありまーす。 昭和の爆笑王こと林家三平さんがCMをしていた「ニキ、ニキ、ニキ、ニキ、二木の菓子。ところはアメ横、菓子現金問屋二木の菓子。バンザーイ!! 安くてどうもすみません!」を、子供の頃に嫌になるほど見ていた、その二木の菓子に、ついに入っちゃったよ。子供の頃の夢が実現した! あと、「伊東へ行くならハトヤ、電話はヨ・イ・フ・ロ」に泊まったら、もう人生、思い残すことはないな。 そしてアメ横の雑踏を堪能し、大津屋というスパイス屋さんでカレー粉をゲットした後、もう少し南下して「2k540 AKI-OKA ARTISAN」というところに行ってみました。 ここはJRの高架下に、ものづくり系のお店がずらっと並んだしゃれおつなストリートでございまして、まあ、アメ横の雑踏とは大分趣の異なるところなのですけど、陶器、染め物、ガラス細工、木製細工、アクセサリーなどなど、一点もののグッズがそれぞれのお店で売られている。で、どの店もそれぞれ面白かったのですが、漆細工の「ミヤビカ」、樹脂製品の「トウメイ」、靴の「スピングルムーヴ」、傘の「トウキョウ ノーブル」、帆布の「日乃本帆布」あたりが面白かったかな。ちなみに、家内と姉は「スピングルムーヴ」でそれぞれお気に入りの靴を見つけて購入〜。っていうか、私が二人にプレゼントしたんですけどね。私は日乃本帆布でちょっとカッコいいバッグを見つけたのですが、それをどういう機会に使うか、想像が出来なかったので、今回はパス。 で、このストリートの一角にある「カフェ・アサン」というお店でちょっと一休みして、それから帰宅した次第。 帰宅後は買ってきたカレー粉で早速カレーを作ってもらいましたが、さすがこだわりのカレー粉だけあって、ちょっと辛かったけど、おいしかったです。 というわけで、今日は東大農学部内のレストランで食べるという裏ワザをしーの、上野公園のサクラを見ーの、アメ横行きーの、しゃれおつなショッピングをしーの、で、なかなか充実した春の一日となったのでした。今日も、いい日だ!
March 30, 2015
コメント(0)
-
身近に居た! ほんとに居るんだ、そんな人。
最近聞いた「ほんとに居るんだ、そんな人」という話題。 一つは、テレビで話題の「ライザップ」。姉の知り合いで、体重90キロ越えの人が居たのですが、最近、一念発起して60キロに瘦せたと。ライザップで。2ヵ月で。 ひゃー、ほんとに居るんだ、そんな人! で、掛かった費用が100万円と。 うーむ、それはまた痛い! でも、100万円というところがいいので、これが10万円とか20万円だったら、2ヵ月で30キロも落とせないですよね。100万円かけた以上、何が何でも瘦せなきゃ、という悲壮な決意がないと、そこまで出来ないんじゃないかな。 そこまで考えているなら、ライザップの料金設定って賢いかも。しかも、ちゃんと結果を出すわけだし。 あともう一つは、ロト6が当たったという話。 家内の友人の友人で、長年、自分のお気に入りの数字6つをずーーーっとロト6で賭け続けた結果、ついに当たりを出して6億円ゲットしたんですと。 ひゃー、ほんとに居るんだ、そんな人! で、その人は当たった後何をしたか? 会社を辞めて、沖縄に移住したのだそうで・・・。 やっぱりそうなんだ! 6億当たると、誰しも会社辞めて沖縄に行くんだ! ほんとに居るんだねえ、こういう人たちって。 さてさて、ライザップの方はいいとして、仕事辞めて沖縄の方はあやかりたいな、ワタクシも!! ま、ワタクシだったら沖縄じゃなくて、別なところかもしれないけどね!
March 29, 2015
コメント(0)
-
書評
本日発売号の『図書新聞』という書評紙に拙著の書評が出た模様、と知らせを受けたので、多摩センターの丸善まで買いに行ってきました。実際に見てみると、かなり長文の抜群に好意的な書評で、有り難い限り。 で、ついでに今日から発売された『CX−3のすべて』という雑誌も買っちゃった。マツダの新車の特集雑誌なんですけど、次の愛車候補なので、詳しく知りたいと。 その他、大型書店内を徘徊して、あれこれ本を立ち読みし、情報をたっぷり仕入れて帰宅。 そして後は、リラックスして雑誌を読んだり、家族と雑談をしたりの一日となりました。 とにかく、いい書評が出たというのがベースにあるので、今日は一日、何となく嬉しい一日でした。人間が出来てないせいかも知れませんが、いくつになっても、人に褒められるというのは嬉しいものですからね。だから私も、チャンスがあれば出来るかぎり沢山、人のことを褒めようって、あらためて思いました。自分がしてもらって嬉しいことは、人にもしてあげないとね!
March 28, 2015
コメント(0)
-
ホンダS660の屋根は正解か?
バブル時代の名車「ビート」の実質上の後継車となるホンダの新しい軽スポーツ「S660」が発表されました。ダイハツのコペンに対抗するものだけに、私も前から気にはなっておりまして。 で、全体的な形としては、まあ、許そう。ビートの面影もあるし、全体的にまとまりもある。 が! 「幌」とも言えない、布製のくるくる巻きみたいな変なものを屋根に広げるという、あの屋根の形はどうなんだ? コペンが電動ハードトップを、またジャンルは少し違いますが、マツダ・ロードスターが軽くて出来の良い手動式ソフトトップで武装してきたのに対して、あの安っぽいクルクル屋根はどうなんだ? あんなもので日本の豪雨や台風に耐えられるのか? 屋外駐車場に置いておけるのか? あの屋根を見た時点で、S660に興味を持っていた人の3分の2は、購入を断念すると思うな・・・。 このクルマの総責任者は26歳の若者だそうで、「若い連中にやりたいことをやらせました」的なことが売りなのでしょうけれども、そこは上の人が意見を言わなかったのだろうか。 まあ、好き好きですからご意見無用かもしれませんけれど、どうも最近のホンダはデザインの凡庸さも含め、エアバッグ問題/リコール問題も含め、迷走しているような感じがしますなあ。F1プロジェクトも、あまり上手く行ってないようだし。 さてさて、それはさておき、私は春休みの最後の一週間を実家で過すべく、今日から帰省しております。ということで、今日からしばらく東京からのお気楽日記。よろしくぅ!
March 27, 2015
コメント(0)
-
ネコは死に水を取れるか?
4月から新任として広島からはるばる赴任される若い先生が、準備のために大学に来たので、キャンパス内を案内したり、同僚を紹介したり、あれこれしてました。 その後、共同研究室でコーヒーを一緒に飲んでいたのですが、その時の茶飲み話で、今度新たに借りたというアパートの話などが出まして。 で、割と辺鄙なところにアパートを借りたというので、どうしてそこを選んだの? と尋ねたところ、「ペットOKのアパートが他になかったものですから」と。 え? ペット? ペットを連れて名古屋に来たんですか? ペットって何? そしたら、ネコです、とのこと。 ネコ・・・。じゃあ、ケージか何かにいれて新幹線で? と尋ねると、いえ、宅配で、と。 え!? ネコって宅配できるの!!?? クロネコだけに? そしたら、クロネコに限らず、動物の宅配をやってくれるところって結構あるんですってね。知らなかった・・・。しかし、動物を宅配って、うーん、その感覚がイマイチ分らんなあ。 それにしても、独身男がネコ連れで就職か・・・。さては結婚する気ないな。 女性目線でどうなんでしょう。ネコを飼っている独身男って。ネコって何となく女性的だから、独身男がネコ飼ってたら、「家に男の帰りを待っている女がいるな」って感じになりませんかね。 まあ、それは本人の勝手だからいいのですけど、話をしていて感じるのは、この先生自身、何となくネコっぽいなと。 つまり、一人でいることに自足していて、他人に対して自分から甘えて来ないというか。同僚に親しさを求めないというか。自分、ほっといてもらった方が良いです的な。 だけど、最近の若い同僚の先生方って、大抵そうですね。ネコタイプ。犬タイプの若い先生ってあまりいないです。 私は犬タイプというか、渡世人タイプなので、先輩同僚には忠誠を尽くし、立てる方なんですわ。だから、上の人たちとは親しいし、その人たちが還暦を迎えるとか、退職するとか、そういう時には積極的に動いて論文集を編纂したり、パーティを開いたり、そういう世話役を買ってでるし、またそういう先生が大学を辞めた後も、いつまでも親しく付き合うわけ。 だけど、私の下の先生方には、そういう感じの人がいないんだなあ・・・。私は先輩同僚の死に水はとるけれど、私の死に水をとってくれる後輩同僚がいないという。 犬は死に水取ってくれそうだけど、ネコはなあ・・・。 今度赴任したネコ先生は、私の死に水、とってくれるのかなあ・・・。
March 26, 2015
コメント(0)
-
面白い武術
八光流の参考になるのではと思い、暇な時など、よくYouTube などで「合気道」とか「大東流」とか、古武道系の動画を見たりするのですが、合気道はやたらにグルグル回るし、大東流は技を掛ける時にいちいち「エエイッ」と大声を出して、もう相手を倒す気迫が満々過ぎてちょっと引く、みたいなところがある。両者とも、八光流に似た技はありますが、どこかこう、根本的なところが違うような気がするんですわ。 で、なんか違うんだよなあ、とか思いながら、あれこれ検索しているうちに、ちょっと変わった、面白い武術を発見しました。「天心象水流」というものらしいのですが。 で、この動画を見ていると、動きがちょっと太極拳的というか、中国武術っぽいところがある。だけど、その一方で、全然気迫を漲らせないところとか、相手を振り回さないところなど、ちょっと八光流的なところもあって、見ていると、ああ、これは八光流でいう○○という技に近いな、とか、そんな風に思えるところも結構あるんですわ。 動画自体はちょっと古い感じがして、相当前に撮影されたものかと思いきや、実際には割と最近撮られたものらしく、技を掛けているのは、この流派の宗家とのこと。 ということで、相当面白い武術であるなあと、このところ、暇があれば象水流の一連の動画を見ているワタクシ。結構、参考になります。 まあ、武術がお好きな人ばかりではないと思いますが、この天心象水流、教授のおすすめ!と言っておきましょうかね。これこれ! ↓これが天心象水流だ!
March 25, 2015
コメント(0)
-
タリーズに響く高らかな音
昨夜、謝恩会がはねた後、教員四人でお茶でも飲んで行こうと言う話になり、タリーズでコーヒーを飲みながら雑談をしまして。 ま、それはそれでいいのですが、雑談の最中、ちょっと驚くことがありましてね。 というのは、我々が和やかに会話を楽しんでいた時に、突如、店内の片隅から相当大きな音で「ブ――――ッ!」という異音が発生したから。 我々四人を含めてほぼ満席の店内、ざわざわとした会話の雑音が一瞬途切れ、シーンとなったところでもう一発「ブーーーーーッ!」。 何かと思ったら、二十代後半くらいの妙齢の女性客(お一人様)が発した、鼻をかむ音だったんです。 あまりの大音声に、びっくり。店内の全員がその若い女性をおどろきの表情で見つめたことは言うまでもありませんが、当の女性はまったく動じることなく、イヤホンで音楽を聴きながら何かを読んでいる様子。 まあしかし、音源がハッキリ特定できたということで、また会話が始まり、店内は平常に戻ったわけ。 ところが。 およそ5分ほどたったところで、再びその女性が鼻をかんだのよ。「ブーーーーーーッ!!」と。再び、店内の客全員が「信じられない!!」という表情を浮かべながら女性を注視。いや、それどころか、店の店員さんも「何が起ったのか? テロか?」とばかり、二、三人飛び出してきた。そこへもってきて彼女は再び「ブーーーーーーッ!!」。 もうそれからは、いつ次の「ブーーーーーッ!」が飛び出してくるか気になって気になって。実際、それからもさらに二、三回あったのですが。 そしてしばらくして、その女性客が店を出たのですが、彼女が店を出た瞬間、残された店内の客全員が、異口同音に「今の人、何?」「どういうこと?!」「あんなの初めて!」と、それぞれの感想をまくし立てたのでした。彼女のおかげで、タリーズの店内では、サッカー・ワールド・カップのパブリック・ビューイングもかくや、と思われるほどの一体感が生じたという。 いやあ、豪傑な若い女性がいるもんですなあ・・・・。 さてさて、それはともかく、あの高らかなブーーーーッから一夜明けた今日は、我ら夫婦の結婚記念日。結婚まる17年で、明日から18年目が始まります。 ということで、今日はちょっと贅沢に外食することとし、最近めっぽうお気に入りの三好にある「シェ モン・アミ」へお洒落して出かけました。 注文したのは「シェフのおすすめコース」だったのですが、口取り、前菜、パスタ、魚料理、肉料理、デザート&コーヒーの構成のどれもが美味しかった! パスタは生うにのソースに春菊をあしらったもの、魚料理はホタテとさごしのソテーに白子のフリットの三品を新玉ねぎのバターソースでいただくというもの、肉料理は二種の牛肉料理で、片や牛ホホ肉の赤ワイン煮と、片や牛しんたまとフォアグラのソテーを酸味の効いたグリーン・マスタード・ソースでいただくという趣向。デザートも非常に凝ったもので、実に旨しでございます。 というわけで、美味なる記念日でございました。
March 24, 2015
コメント(0)
-
卒業式
今日は勤務先大学で卒業式がありました。 昨日までのポカポカ陽気はどこへやら、一転して冬のような寒さとなった今日ですが、まあ、それでも晴れましたから、卒業生たちの門出を祝うにはよかったかな。 しかし、毎年同じことを書きますが、卒業式の日の「華やかな淋しさ」というのは、私にはなかなか重苦しいもので、会うは別れの始まりとはいいながら、縁あって私の下で卒論を仕上げたゼミ生たちや、授業で教えた学生たちがキャンパスを去っていくというのは、仕方がないこととはいえ、やはり淋しいものでございます。 モノに執着する癖のある私は、結局、それ以上に人に執着するわけですよ。でもモノとは違って、人はいつまでも自分の手元に置けませんからね。 ただ、巣立っていく教え子たちが、それぞれ自分の人生を精一杯楽しんでくれることを祈って、淋しさを紛らわすことにいたしましょう。
March 23, 2015
コメント(0)
-
ウィキペディア活用・切り貼りアメリカ文学史
前にも書きましたが、来たる来年度のアメリカ文学史の授業で使う教材を作っておりまして。 私が考えているのは、『切り貼りアメリカ文学史』というもので、教科書自体はほぼ白紙、そこにウィキペディアからとってきた情報を文字通り切り貼りして、学生自身に教科書を作らせるという趣向。 で、今、その設計図を作るべく、自分でウィキペディアから切り貼りしてアメリカ文学史を自主編纂しているのですけど、これがね、結構面白いわけ。 で、教科書の冒頭はやはりお題目である「アメリカ文学」だろうと思い、ウィキペディアで「アメリカ文学」というワードで検索してみると、丁度いい分量の恰好の記事が出てくる。これはそのまま切り貼りしちまえば、完璧とは言わないまでもアメリカ文学を通観する上で必要十分な情報が盛り込まれているので、概説代わりにはなるでしょう。 で、それに続いて授業で取上げようと思っている作家それぞれについてウィキペディア検索させ、出てきた情報を選択しつつ切り貼りさせる、そんな「工作用台帳」を作れば、最終的には100頁ばかりの自作のアメリカ文学史が完成すると。ウィキペディアには、それぞれの作家の写真も豊富に入っているので、そういうのも切り貼りさせれば、自作の教科書も充実する、というわけ。もちろん、授業では私も独自の解説をするので、各作家の頁の最後には「メモ」がとれるようなスペースもつけておく。 もちろん、作家の情報だけでなく、「ロスト・ジェネレーション」とか「ビート・ジェネレーション」のような重要なタームの頁も作っておきましょう。 切り貼りする台帳は、大学出版会か知り合いの印刷所に「文具」として印刷してもらう。ウィキペディアから情報を得ているので、版権の問題もあり、教科書(=本)としては出版できませんからね。で、それを実費で学生に売ると。500円くらいで何とかなるんじゃないかな。 完璧じゃん! それにしても、ウィキペディアとかネット上の情報ってのは、大したもんだね。誰も頼んでないのに、勝手に情報がどんどん蓄積されていく。 大学の授業で学生にレポートを書かせると、学生がそういうものからコピペして、楽してレポートを仕上げようとするもので手を焼かされるのですけれども、私の『切り貼りアメリカ文学史』は、逆に教師の側が先手を打ってウィキペディアを積極的に使ってしまうというね。その攻守逆転の発想が、いかにも釈迦楽流というか。 ま、とにかく、春休みのうちに台帳の設計だけは終わらせてしまおうかなと、今、その切り貼りに夢中な私なのであります。
March 22, 2015
コメント(0)
-
山本茂久先生のこと
私には生涯、四人の恩師が居たのですが、その第一番目の恩師が小学校6年生の時の担任であった山本茂久先生。この先生のおかげで、私は真っ当な人間になれたようなものなのですが。 で、ふと、「そう言えば、山本先生のお書きになった本を私は一冊も所有していないな」と思い、ネット上の古書店を探したところ、『算数教育』という本が売られている事を発見。すかさず買ってみたと。 これは先生が小学校における算数教育について、具体的な問題から論を起し、最終的な理想論を語られている本でありまして、今の私の仕事には直接には関係してこないのですが、それでもパラパラとページを捲り、ところどころを読んでみると、先生の肉声というものが蘇ってくる。 そんな「ところどころ」のあるページに、こんなことが書いてあった。 例えば1リットルの容器があり、その中に水が入っている。これを500ミリリットルの容器二つに分けて、それぞれが一杯になれば、1リットルの容器には、500ミリリットルの容器の倍の水が入ることになる。 これを児童に実験させてみたと。 ところが子供のすることですから、少しこぼしてしまったりして、正確には1リットル=500ミリリットル×2にはならないわけ。 大人ならば、「誤差」で済ませてしまうのでしょうが、山本先生が観察していると、子供の心はそうは動かないというのですな。1リットルが自分たちの実験では500ミリリットル×2にはならないことを目敏く発見し、ため息をつき、当惑し、そして結論として、先生がどう言いくるめようとしても、頑として「1リットル=500ミリリットル×2」という公式を受け入れないと。 これを見ていた山本先生は、こうした子供の心を「尊い」と仰言る。この「正確さ」なるものへの厳密な信念がある限り、数学の嫌いな子供というのは、本当は存在しないはずだと。先生はそう結論づけられる。 こういう論を、人はどう見るのか、私には分りませんけれども、私はこのように書かれた山本先生の子供を見る目を思い出し、先生がその目でもって子供の時の私を見ていてくれたのだということに改めて感謝の気持を抱いたのであります。 山本先生は、教師というものが「聖職」という言葉で語られた、そういう時代の先生でありました。
March 21, 2015
コメント(0)
-
小さいクルマ
先日車検のために入庫していたシトロエンC4が戻ってきて、代車でもらっていたプジョー207を返却してきました。 で、乗り換えると、C4が随分大きなクルマに感じられてね。ああ、こんなに大きいクルマだったのかと。 やはり物の価値というのは相対的なもので、たとえ1週間でも一回り小さなクルマに乗っていると、今までは大きいとも思っていなかったC4が妙に大きく感じてしまう。 で、思ったのですが、年をとるにつれ、クルマは小さい方がいいなと。 若い頃は、5メートル近いクルマをいい気になって乗り回していたワタクシですが、もう、最近は軽自動車くらいの大きさのクルマで十分だな。軽自動車よりもう少し大きくてもいいけど、デミオとかポロとか、その辺の大きさで十分だ。 ただ、先日も書きましたが、207は乗り心地がすこしバタバタしちゃってね。小さい方がいいけど、安っぽいのはちょっとね。 C4はもともと、中継ぎ的な意味合いで買ったので、長く乗るつもりはないんです。だから、次の車検を通す気はない。 ということで、この先2年の内に次の愛車を決めるつもりなのですけど、何にしますかね。
March 20, 2015
コメント(0)
-
御木本真珠島
昨日のつづきですが、浦村で牡蠣を堪能してから、名古屋に戻りがてら御木本真珠島に行ったんですわ。鳥羽には前にも来たことがあるのですが、その時はここには寄らなかったもので。 で、真珠島に渡って、御木本幸吉記念館を訪れ、真珠養殖に世界で初めて成功した御木本翁の業績を学んだわけ。 で、やっぱり真珠に命を掛けた男ってのは、スゴイのよ。 もともとは地元で由緒あるうどん屋さんを営んでいて、幸吉翁もそのままいけばうどん屋の親父で終っていたわけなんですけど、そこはそれ、幼少の折りから外連味があるんだなあ。 例えば、たらいを足で回す「足芸」とか、そういうのを仕込んでおいて、外人さんの前でそれを披露し、「コイツ面白いな」と思わせておいて、うどんの他に、外国人の居留地に野菜を売り込む権利を得るとか。 で、商売に力を入れつつも、それだけじゃ終わらんとばかり、片道11日くらいかけて東京・横浜に出て都会の在り様を見に行くんですな。で、中華街とかで真珠が高値で取引されているのを見て、これは行けそうだと目星をつける。 で、そこから先は真珠一筋。それまで偶然の産物でしかなかった真珠の養殖を試みるわけ。 だけど、なかなかうまく行かない。効果的な方法も手探りなら、赤潮や台風の被害もあったりして、最初の内は失敗ばかり。 しかし、その失敗につぐ失敗にもめげず頑張り通した結果、ついに真珠の養殖に成功するわけ。 だけど単に養殖に成功したから満足、という人じゃないんだなあ。翁は「世界中の女の首を(真珠で)締めて見せる」と豪語し、海外への進出をためらわないんです。 そして、第二次大戦中は社員を兵隊にとられたりして、大打撃を受けるのですけど、戦地に赴く社員に「絶対に生きて帰れ。真珠は戦争しておらん」と命じるなど、非国民と非難されかねないようなことをしながら、戦争の後の世界のことまで見通していたんですと。その辺、国際人だなと。 で、思ったのですが、幸吉翁の生き方というのは、『マッサン』の次の朝ドラにならないかなと。幸吉さんには恋女房のうめさんというのがいて、この二人の愛情ドラマにもなるし。 『幸吉とうめ』でどう? え? 「ん」がつくタイトルにすると朝ドラが成功するんですと? じゃあ、「幸吉っつあん」でどう? NHKの方、このブログ読んでいたら、「幸吉っつあん」の脚本、釈迦楽にご用命を! さて、御木本翁の数奇な人生を学び、昭和な感じの「あまさんショー」などを見てから、さて名古屋に戻ろうと思ったのですけど、ちょっと小腹がすいたので、軽食でもと思って入ったのが、「たかま」というしぶーい喫茶店。 もう、ザ・昭和って感じの喫茶店だったのですが、これがまた奇跡の出会いで、ここの「たまごサンド」(600円)というのがものすごく旨かったのよ。こんなたまごサンド食べたことない、って感じ。教授の熱烈おすすめ!よ。 ということで、牡蠣は満喫するわ、二軒茶屋餅はうまいわ、御木本幸吉翁の人生には感動するわ、たかまのたまごサンドには驚かされるわで、大成功の伊勢・志摩旅行だったのでした。
March 19, 2015
コメント(0)
-
絶品・浦村の牡蠣
一日お休みをいただいて、伊勢・志摩方面にドライブし、浦村というところで牡蠣を食べてきました。 寡聞にして知らなかったのですが、伊勢と志摩の中間点ほどにある浦村というところは、牡蠣の養殖が盛んなところで、冬の時期、あちこちに「牡蠣小屋」が立つんですな。 で、数多ある牡蠣小屋は、牡蠣料理を供するところ、バーベQ方式で客に焼かせるところなどがあるのですが、私たちが訪れた「英治丸」というお店は、牡蠣を1個100円で店の方が焼いてくれるという、焼き牡蠣専門の店。焼き牡蠣しかありませんから、慣れた方は自分でおにぎりとかを持っていく人も。我々は初めてだったので、とにかく牡蠣を食べ続けました。 何しろ1個100円ですから、実に気楽。最初に10個頼んで家内と5個ずつ食べたのですが、あまりの美味しさにぺろりと食べてしまい、更に6個追加。これもペロッと食べてしまい、更に3個追加。結局私は10個、家内は9個を完食。それでも二人で1900円ですからね。 で、ここの牡蠣がすごくて、都会ではよほどの高級店でないとお目に掛かれないような大きくて身の肥ったプリプリの牡蠣でね。それを熟練の焼き手が絶妙の頃合いに焼き上げてくれるのですから、もう口いっぱいに牡蠣の旨味が広がるという。最高よ。 今回の経験で浦村牡蠣小屋の虜となった我らは、毎年シーズンに入ったらここに来ることに決定! 何十件と牡蠣小屋があるので、その都度行く店を変えてもいいし、楽しみは尽きません。牡蠣好きの方には、浦村の牡蠣、教授の絶賛おすすめ!です。これこれ! ↓浦村の牡蠣小屋マップ そして帰りがけ、たまたま目に留まった由緒ありげな和菓子屋さんに立ち寄り、「二軒茶屋餅」なるものを買って食べたところ、これがまためちゃくちゃ旨い。店の人に聞くと、四百年を超す歴史のあるお店とのこと。大昔、この辺りは葦の原だったのだけど、伊勢にお参りする人たちのために二軒だけ茶屋があった。そこで人呼んで「二軒茶屋餅」となった由ですが、実は知る人ぞ知る伊勢の銘菓なのだとか。何の知識もないのに、こういう隠れた名産を通りすがりに嗅ぎつけてしまう私の嗅覚もすごいねと自画自賛。 ところで、志摩方面をドライブしていて思ったのですが、ここのリアス式海岸というか、ミニ瀬戸内海的な風景というのは実に美しい。そして牡蠣やアオサ海苔など、海の恵みも非常に豊かなところなのですが、その割に、言っちゃ悪いですけど、閑散としているんですよね。 「志摩スペイン村」とか、「地中海村」とか、「合歓の郷」とか、バブル時代に一生懸命観光開発したんだな、という跡はあるのですけれども、いずれもバブルの波に乗って開発したはいいけれど、それがはじけてからは大苦戦、みたいな雰囲気がある。 で、同じくバブルの頃に建てられたと思しきリゾートマンションがあちこちに建っているのですが、人が利用している気配がない。家に戻ってから調べると、この辺りのリゾートマンション、大体250万円くらいで売っているんですな。250万円で別荘が買える。だけど、誰も買っていないという。 でまたさらに、志摩の道を走っていると、潰れた店というのがあちこちにあって、その廃墟がただよわせる「荒み感」が半端ない。 それこそ、日本のモナコとなっても不思議でないようなこの地が、こんな感じになっているのは、実にもったないないと。 日本って、そういう点、不思議ですよね。伊勢の「おかげ横丁」なんてのは、ものすごい賑わいなのに、こちらには誰もいないという。日本には「猛烈に混雑する観光地」と「閑散とした観光地」の二種類しかなくて、「適度に賑わっている観光地」というのがない気がする。そこがね・・・。 ま、判官びいきではないですけど、せめて天邪鬼の私としては「猛烈に混雑する観光地」に背を向けて、この閑散とした観光地を応援したいなと思うのであります。 あ、それから、帰りがけにもう一つ、鳥羽にも立ち寄ったので、その話はまた明日!
March 18, 2015
コメント(0)
-
ニューソート
昨日はニューソート関連の資料を読んでおりました。 ニューソートというのは、英語で書けば New Thought で、「新しい考え方」を意味する。では、何に対して「新しい」のかと言いますと、伝統的なキリスト教の考え方に対して、ということになります。 では、伝統的なキリスト教の考え方というのは何かと言いますと、まず人格を持った神がいる。で、その神が自分の子供であるイエスを地上に遣わしたと。そして、そのイエスが、人類の罪を背負って代理で死んでくれたために、人間は償われたと。 で、イエスは再臨することになっていて、その時、最後の審判が行われ、天国に行く連中と地獄に行く連中が分けられる。地獄に行ったら、業火に焼かれるのでとっても辛い。だから、天国に行けるように努力しなくっちゃと。 ま、大ざっぱに言えば、これが伝統的なキリスト教の考え方ですな。 ところが、ニューソートは、この考え方に異を唱えるわけ。 まず、彼等は人格神を否定します。神はエラそうなおっさんではなくて、創造のエネルギーそのもの、そして万物も基である。人格なんか持ってない。 で、万物はこの創造のエネルギーの、現実界での一時的な出現なので、人間であろうが山であろうが海であろうが獣であろうが、その意味では皆同じ、エネルギーの一部であると。 ただ、人間は万物の中で唯一、その道理が分る存在であるという意味で、一番上位の存在ではある。 で、仮にこの創造のエネルギーを「神」と呼ぶにしても、神には人格はないので、人間を懲らしめようとか思っていない。だから、イエスが人類の罪を背負って死んだとか、罪を犯すと地獄に落ちる、などということはないと考えます。 っていうか、そもそも万物はエネルギーの一部、神の一部なので、その神が罪を犯すはずがない以上、この世に罪というものはまったく存在しないと。だから、神と悪魔の二元論、善と悪の二元論なんてものは、ニューソートの世界にはない。 では、現実に存在する「罪」とか「悪」とか「病気」は何かと言いますと、あれは単に善がない状態、太陽が当っていない状態、だと。あるいは、気の迷いだと。 だから、この世に悪なんかない、病気もない、と信じれば、その瞬間から悪も病気も無くなります。 だから、人間は伝統的なキリスト教が押しつけてくるような「罪の意識」なんかに震えなくてもいい。 で、そういう風に病気の人に伝えると、実際に病気だった人が治るらしいんですな。それで、ニューソートの連中は、ホレ見たことか、やっぱり病気なんてものはないんだと言い切るわけ。 で、この考え方の流れがアメリカに行くと、例えばクリスチャン・サイエンス(ニューソートの考え方に基づくキリスト教解釈によって、人の病気を治す団体)になる。あるいは、ヨーロッパに行くと、形を変えてフロイト・ユングになる。フロイトは、深層心理にある滓をとり除けば、人は健康になる、と言っているわけですから。 そして、万物はエネルギーの表象であり、人が望めば、そのエネルギーが動き出して、その人の望み通りになる、という今日の自己啓発のアイディアは、このニューソートの末裔・・・というか、それそのものと言っても過言ではない。 そう言う意味で、今日の自己啓発本の原点は、ニューソートに、そしてそのニューソートの原点である思想家・スウェーデンボルグに行き着くと。 面白くない? 私にはめっちゃ面白いのですが。 ちなみに、日本というのは、実はニューソートのメッカで、その代表は谷口雅春氏、すなわち「生長の家」なんですって。知らなかった! というわけで、本を読むと、色々なことが判るなあと。 ま、こういう資料を読みながら、あれこれ自分の研究の道筋について考えていた今日のワタクシなのであります。
March 16, 2015
コメント(0)
-
車検
愛車シトロエンC4の車検が近づいてきたので、今日、ディーラーにクルマを預けてきました。 で、代車にもらったのがプジョー207。久々に乗るプジョー、しかもコレ、色がライトグリーン・マイカ、さらに屋根がガラスルーフじゃないですかっ!! いつも古い国産のクルマしか代車でもらえないのに、今日はラッキー! で、早速そのプジョー207に乗ってしばらくドライブしてみたのですが・・・ うーん、あまり良くないねえ・・・。 排気量が小さいのをカバーするためか、ちょっとアクセルを踏むとガバっと飛び出してしまうし、ブレーキを踏むとカックン・ブレーキ。だから走り出しには注意が必要な上、スムーズに運転しづらい。 じゃあ、ある程度スピードに乗ってきたらいいかというと、そうでもなくて、道路に吸い付くような猫足は感じられず。普通の国産の小さいクルマみたいに、ただ走るというだけで面白味がない。 306に乗っていた関係で、プジョー贔屓のワタクシではありますが、プジョーならどれでも乗り味がいいかというと、そうでもないね。我が愛する306のような絶妙の乗り味を味わうには、もう一つ上のクラスに乗らないとダメなのかも。シトロエンもC4は高級な乗り味だけど、C3は要注意だな。もし買うにしても、乗って確認しないと。 でも、上がガラスルーフというのは、やはり解放感があっていいなあ! 207に乗って、改めてC4は乗り心地がいいなあと再確認した次第。大枚はたいて車検も通すことだし、少なくともあと1年くらいは乗り続けようかな。
March 15, 2015
コメント(0)
-
大丈夫か、マクラーレン・ホンダ?
F1好きが待ちに待ったシーズン到来となりました! メルセデスが圧倒的に強かった昨シーズンと比べ、今年はフェラーリが巻き返すのではないか、古豪ウィリアムズがさらに肉迫するのではないか、レッドブルとて黙ってはいまいと期待は高まるばかり。 それにドライバーの交代も面白く、ベッテルはフェラーリで輝けるのか? アロンソはマクラーレンで復活するのか? というところもありますし、またフェルスタッペン&サインツ・ジュニアという、トロロッソの二世少年組は活躍できるのか? というのも興味深い。 つまり、昨年に比べ、見どころが一杯なわけよ。 そして、究極の見どころは「マクラーレン・ホンダ」の復活。かつて16戦15勝を挙げた栄光のタッグ復活が、メルセデス一強時代を崩せるのか? というのが、日本のF1ファンのみならず、世界のF1ファンからも注目されていたはず。 ところが・・・。 開幕戦となるオーストラリア・グランプリの公式予選で、マクラーレン・ホンダは何と驚きの最下位という・・・。それもダントツの最下位。 うーん、オフ中のテストでも故障続きでまともに走れなかったとはいえ、そこは几帳面な日本企業のこと、開幕までには間に合わせて、少なくとも予選Q1突破くらいのことはするだろうと思っていたのに・・・。 まあ、F1の世界も、過去の栄光が通用するほど甘くはないということですか。 でまた、不安になってくるのは、昨年以上のメルセデスの強さ。今年もまた、全戦でハミルトンかロスベルグのどちらかが優勝するのを見なくてはならない予感。 期待が大きかっただけに、「やっぱりそうなるのかあ」というところもありますけど、まあ、しかし、やはりF1シーズン開幕は、ファンにとっては大きなこと。 明日の本戦の展開に、今から期待することにいたしましょうかね。
March 14, 2015
コメント(0)
-

『本の逆襲』を読む
内沼晋太郎著『本の逆襲』という本を、教授会の内職で半分くらい読みましたが、そこそこ面白い本です。 内沼さんという人は、「ブック・コーディネーター」を名乗っておられるのですが、そもそもブック・コーディネーターというのは何かというと、一言で言えば「本と人とを結びつける仕事」となりますかね。 今、年間8万冊くらいの新刊本が出ていて、その意味では空前の出版ブームであるわけですけど、しかし、これらの新刊本は、日本の既存の本の流通システム(再版制度やら、取次の存在やら・・・)のために、話題の本以外は殆んど本屋の棚に収まることもなく版元に返本され、それこそ闇から闇へ消えてしまう。ゆえに、これだけ本が沢山出版されていながら、本と人が出会う機会なんて、ほんとに限られているというわけ。 もちろん、本と人をいかに出会わせるか、ということについては、今だって色々工夫されているわけですよ。書店員独自のポップを作るとかね。だけど、そういうのは、もともと本屋さんにやたらに出入りする本好きのためのものであって、本屋に来ない人にはその声は届かないと。 そこで、ブック・コーディネーターという仕事の出番がやってくる。 例えば内沼さんは、こんなアイディアを出しています。まず本にカバーをかけてしまい、中身が見えないようにする。で、そのカバーには、その本の中から選び出した飛び切りの一節を抜き書きしてあるんですな。そこで、その本が何の本かはわからないけれど、カバーに書かれた一節に惹かれた客が、その本を買い、普段だったら出会わなかったような本を手に入れる。 あるいは、同じく本にカバーをかけてしまい、カバーにはその本が出版された年だけを記すとか。誕生年と同じ年に作られたワインを買うように、自分と同い年の本を買ってみる、なんていうのも本と人の出会いとしては面白い、とかね。 あるいはまた、カフェと提携して、カフェのメニューに本を載せるとか。客は「カフェラテのホットと、この本」とか言って注文すると、コーヒーと本が出てくる。もちろん、本は持ち帰ることが出来る。これは「文庫本とケーキは同じくらいの値段だから。ケーキの代りに本が出て来てもいいじゃないか」という発想です。 内沼さんは、こんな風にあの手この手で、本と人を出会わせるアイディアを出していくわけ。 そんな内沼さんは、「今、本というのは定義できないものになっている」という基本的な考えをお持ちです。本=文字の書いてある紙の束、という認識は、もはや通用しないと。紙を使わない電子出版ももちろん本だし、また電子出版が本であるなら、ブログやツイッターだって、ネットから獲得できる情報の束という意味では立派な本ということもできる。また最近では書店でレトルトのカレーを売るところもあるくらいで、「書棚に乗っているものが本」だというのなら、レトルト・カレーだって本かもしれない。本の定義は、今、果てしなく拡張している。 だから、紙の束としての本は、流通制度のしがらみで衰えているかもしれないけれども、上に述べたような拡張した意味での本ならば、その可能性はまだまだあるのではないかと。 音楽のジャンルで、一枚聴くのに60分掛かるCDの売り上げは落ちたけれども、人は一曲ごとにダウンロードした音楽を目いっぱい楽しんでいる。それならば、本だって、例えば「一章分」ごとに売ったっていい。電子出版ならそれも可能だと。いや、一章分どころか、例えばビジネス書なんかだと「1アイディア」を単位に売ったっていい。 そんな風に考えていけば、本の未来は明るい。衰退しているどころか、今、本の逆襲が始まっているんだと。 まあ、これが本書『本の逆襲』の言わんとしているところですな。 なかなか面白いではないですか。 やっぱり、停滞している時こそ、大小様々、現実的なものから奇想天外なものまで、とにかくじゃんじゃんアイディアを出していかないと。そういう意味で、今まさにじゃんじゃんアイディアを出している内沼さんの本は、出版業界の人、本を書く人読む人だけでなく、他業種の人が読んでも参考になるんじゃないかな。 ということで、この本、ブレーンストーミングのためにも、教授のおすすめ、と言っておきましょう。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】本の逆襲 [ 内沼晋太郎 ]価格:1,015円(税込、送料込)
March 13, 2015
コメント(0)
-
送別会
国立大学後期二次試験があった今日、この3月で定年を迎える同僚のY先生の送別会がありました。 Y先生はフランス語・フランス文学の先生なので、専門が近いというわけではないのですが、私がこの大学に赴任した時に既におられた先生で、以来、22年間に亘って同僚として過ごしたわけですから、まあ、付き合いとしては長い。そういう先生が定年で大学を去られるというのは、感慨深いものでありまして。 Y先生が去られると、もう、うちの科で私より長く勤めておられるのはアニキことK教授のみ。ついに私も二番目の古株になってしまいました。自分ではまだ新人のつもりなのに、実際にはよっぽどの大年増ですわ。やんなっちゃうね。 さて、それはともかく、送別会の場では色々な昔話も出まして。 で、Y先生の思い出話を聞いていると、昔の大学ってところは、ほんとにのんびりしていたというか、ある意味、野蛮なまでに自由、かついい加減なところだったようで。 例えば、Y先生は野球がお好きで、大学職員野球部のメンバーでもあったのですが、そんなY先生が授業で学生にフランス語を教えていると、ガラッと教室のドアが開いて、同じ野球部の先生がユニフォーム姿で乱入して来るや、「おい、Y、今、野球やってんだけど、メンバーが足りないんだ。お前、授業なんか止めてすぐ来い」と言われたとか。これにはさすがのY先生も、それから授業を受けていた学生たちもびっくりしたのだそうで。 そんなウソみたいな話が日常だったなんて、昔の大学ってところは、いいところだったんでしょうなあ・・・。 それから、Y先生が赴任した当時の同僚の先生方の名簿をコピーしてきてくれたのですが、それを見ると懐かしい名前がずらっと並んでいて、ああ、あんな先生がいたなあ、こんな先生もいたなあと、皆で盛り上がりました。 それにしても、私よりも一世代、二世代上の先生方って個性的な人が多くて、自分の科の先生方だけでなく、他の科の先生方であっても、名前を見れば顔を思い出すことができる。今は、何だか誰も彼もが小粒になってしまったというか、強烈な個性で印象づけられるようなタマがいないよね、ってな話にもなりまして。 かつて小林秀雄が、「昔の日本人は、人間の形をしていた」というようなことをどこかに書いていましたが、確かにそういう感じがします。 というわけで、Y先生をダシにして、色々な話題が飛び出しましたけれども、同僚が一人、また一人といなくなるというのは、淋しいものでございます。Y先生には、健康に留意していただいて、たまには我々残された後輩に会いに、大学にも遊びに来てもらいたいですな。
March 12, 2015
コメント(0)
-
驚くべき進化
今日、夕食後のデザートとして「はるみ」ってのを食べましたよ。 「はるみ」って、御存知? まあ、ミカンの一種なのですが。とても甘くて、食べやすい。非常においしいものでありました。 しかし、ミカンも進化しましたよね。昔は温州ミカンを軸足にするとして、洋モノではオレンジ、ネーブル、グレープフルーツ。和モノでは夏みかん、甘夏、はっさく、ぶんたん、ぽんかん、伊予かん、それによくわけのわからないザボンとか、そんなものでしたよね、種類的に。 ところが、最近ではこれらに加えて、三宝柑とか、デコポンとか、清見タンゴールとか、はるかとか、せとかとか、紅まどんなとか、はるみとか、オロブランコとか、スウィーティ―とか、えらいことになってません? あんまり種類が増えすぎて、逆にネーブルとかオレンジとかを見かけなくなっちゃった。 でまた、昔の夏みかんとか、めちゃくちゃ酸っぱくて、食べるのが逆に罰ゲームみたいなところがありましたけれども、今、そういう酸っぱいミカンなんてないですからね。デコポンにしてもはるみにしても、基本、甘いからなあ。進化しとるねえ。 だけど、進化しすぎて、何も言われずに食べさせられたら、それがぽんかんなのか伊予かんなのかデコポンなのか、わからないな。それはいいことなんですかね? あと、全然ジャンルが違いますけど、最近の文房具もすごいね。 今日、たまたま糊を買ったのですが、これまで私は「スティック糊」が最も進化した糊だと思っていたのですけど、最近は「テープ糊」ってのがあって、修正テープみたいな感じでビーッとベタベタ状のものを引く奴があるのね。すごいね。 その他、「針を使わないホッチキス」とか、もう何が何だかわからない。文房具も進化し続けとるなあ。 そのうち「芯を使わないシャープペン」とか、「刃を使わないハサミ」とか、できるのかね。 まあ、ミカンも文房具も、昭和の男にはよく分からないものに進化しつつあるなあと。感心したり、戸惑わされたり、色々でございます。
March 11, 2015
コメント(0)
-
先輩同僚の本を編集する
何だか編集作業ばかりやっているようですが、今、私が編集しているのは、先輩同僚H先生のエッセイ集。これ、私が版下まで編集して、勤務先大学の出版会から出版しちまおうという計画なんです。 H先生は、私がこの大学に赴任した時の主任教授。すなわち、私を採用してくれたという意味でも、私にとっては大恩人。しかも、私が文学プロパーの研究からやや文化研究の方にシフトしたのも、この先生からの影響があったことは否定できない。 だから、私としては、H先生に対して何らかの形で「ワタクシ流」の御恩返しがしたかったんですわ。 で、何をしたら「ワタクシ流」になるかと考えた時、私は編集マニアなのだから、私が編集して先生の本を出してあげられないかと思った訳。 うちの科は、毎年卒業生に向けて「同窓会会報」というのを出していて、今年でもう22号が出るのですけど、この間、巻頭言はすべてH先生に書いていただいていたんですな。で、その巻頭言から選り抜きのものを12編ほど選び、これをエッセイ集としてまとめようと思い立った次第。編集作業は順調に進んで、第一稿の校正も済み、後は細かいところの打合わせのみ。 で、今日はH先生ご夫妻と名古屋駅周辺でお昼をご一緒させていただき、その打合わせをしてきたというわけ。 この前終了した紀要の編集とは異なり、今回は市販する本の編集ですから、ある意味、市場への訴求力も問われます。そっけない表紙じゃ、売れやしない。魅力ある装丁じゃなきゃ、出す意味がない。 ということで、紀要の編集以上に燃えております。 H先生に喜んでもらえるような本にすべく、今、あれこれ試行錯誤中。この試行錯誤している時が、めちゃくちゃ楽しいわけで、H先生のためと言い条、実は自分が一番楽しんでいるという・・・。とにかく、春休みののんびりしたひとときを編集作業に費やしながら、頭の中に描いた本の形を慈しんでいるワタクシなのであります。
March 10, 2015
コメント(0)
-

追悼・松谷みよ子
児童文学者の松谷みよ子氏が亡くなられました。享年89歳。 松谷みよ子と言えば、まずは『龍の子太郎』、なのかな? だけど私にとっては、まずは『ちいさいモモちゃん』なんだなあ。モモちゃんシリーズは、最初の三作くらいまで、よく読んだものでした。 特に私は途中から登場する黒猫のクー(プー)が好きで、モモちゃんがまだおしめを使っているのに、猫のクーは「ぼくなんて、おしっこシューってして、砂をパッパってかけるんだもんねー」とか言って、モモちゃんに自慢するシーンなど、今でもよく覚えております。たしかクーのその一言に発奮して、モモちゃんはおしめを卒業するんじゃなかったかな。 あと、「ガムガエル」も好きだった。本当は「ガマガエル」なんだけど、「さんざん噛んだガムみたい」とかいう理由で、モモちゃんが命名するのではなかったかしら。 このガムガエルの件もそうなんですけど、最初の二作品くらいまでは、モモちゃんという幼児の目を通して見た世界が実に生き生きと描かれていて実にいい。 ところが、シリーズの三作目で妹のアカネちゃんが生まれるあたりから私にとっては少しつまらなくなってくる。モモちゃんファンとしては、あくまでモモちゃん推しなのでありまして、そこに新人が絡んでくると、ちょっと面倒臭いなと。 だけど、さらに面倒臭くなってくるのはそこから先なんですよね。何しろ、モモちゃんのお母さんとお父さんが離婚する、っていう筋書きになっていって、それは松谷みよ子さんご自身の結婚生活の破綻が背景にあるのですけど、私も読んでいて、子供心に「これって、どうなの?」と。 コレ、ちょっと生臭すぎないか? 離婚するとかそういう話は、童話の外側でやってくれないかなあ・・・。小学生低学年ではありましたが、私はそういう感想を抱いて、モモちゃんシリーズとは決別したのでございます。 あと、モモちゃんシリーズ以外で印象に残っているのは『二人のイーダ』かな。これも、広島の原爆の話なので、子供の読者としては「ちょっときついな」と思いましたけれども、子供用の椅子が、かつて自分の上によく坐ってくれたイーダちゃんを探して歩き回るというシュールさ、さらに大人になっていたイーダちゃんに再会し、「(子供の)イーダちゃんを探し出す」という目的を失ってバラバラに自己崩壊するという展開は、なかなかいいじゃないかと。 だけど、ご自身の実体験に基づいた「大人の事情」をちょいちょいぶち込んでくる松谷童話の在り方に対して、子供時代のワタクシは、総じてちょっと批判的ではありましたね。童話ってのは、そういうんじゃないんじゃないかなと。そういう意味では、松谷みよ子さんよりお師匠さんの坪田譲二の方を、私は遥かに高く評価していたのであります。 しかし、そうは言っても、子供時代に親しんだ本の作者が亡くなったということで、私にも感慨があります。あの可愛い『ちいさいモモちゃん』の作者として、御冥福をお祈りしたいと思います。合掌。【楽天ブックスならいつでも送料無料】ちいさいモモちゃん [ 松谷みよ子 ]価格:1,188円(税込、送料込)
March 9, 2015
コメント(3)
-
『ダラス・バイヤーズクラブ』を観た
『ダラス・バイヤーズクラブ』を観ましたので、感想などを簡単に記しておきましょう。以下、ネタバレ注意ということで。 本作の背景となっているのは1980年代半ばのアメリカ。「エイズ」騒動が勃発して間もない頃で、不治の病として怖れられ、またゲイや麻薬中毒者がなる病気として偏見を抱かれ、しかも治療薬がまだあまりない状態。 そういう中、テキサスで電気技師を勤めながら、一方でロデオ賭博のようなこともしている女好きのロン・ウッドルーフ(マシュー・マコノヒー)は、その女好きのご乱交が祟って、HIVウィルスをうつされてしまうわけ。医者の見立てでは余命1ヵ月。 ロンは、典型的な南部の偏屈な男というのか、自分自身ゲイに対する烈しい偏見があり、自分がゲイの病気と思われていたエイズを発症したことに戸惑い、絶望に陥るんですな。しかも、彼をとりまく友人たちもそんな風ですから、彼は友人たちからも仲間外れにされてしまう。 で、ロンは生き延びるために必死になり、エイズの治療薬としてまだ未認可であったAZTというのがあることを知り、不正なルートでそれを手に入れて飲むのですけれども、副作用で死にかけてしまう。 で、更に調べると、アメリカでは認められていないけれども、海外ではAZT以外の治療薬もぼつぼつ出始めていることを知り、メキシコでエイズ患者の治療を試みている無資格医に接触して、そこでそういう薬をもらうんですな。 すると、少なくともAZTよりは、症状が回復するわけ。 そこでロンはこの無資格医と協力して、その薬をテキサスに密輸し、自分も服用するし、同じようにエイズにかかった人々にも薬を売って、自転車操業的に回していこうと計画するんですな。 で、その際、お金をとって薬を販売してしまったら、アメリカの薬事法にひっかかるので、「ダラス・バイヤーズクラブ」という会員制クラブを作り、そのクラブへの入会金として400ドルを受けとることにして、クラブ会員には無料で薬をサプリメント的なものとして配布すると、そういう仕組みを作るんです。 で、会員を募る過程で、どうしても協力者が必要になり、ロンは、見かけからしていかにもゲイのレイヨンと手を組むことにする。あれほどゲイ嫌いだったロンが、レイヨンと一緒にクラブを起ち上げるというところが、面白いところで。 エイズの恐怖にさらされていた患者が多かったため、ダラス・バイヤーズクラブは大繁盛します。その一方、正規の病院からはエイズ患者が消えてしまう。で、その状況に脅威を感じ始めた病院・医者側は、ダラス・バイヤーズクラブに対して、薬を没収したり、査察を入れたりと、色々と圧力をかけてくる。一方、ロンやレイヨンも、薬の入手先を変えたり、手を尽くして取締りを逃れようとする。 そしてその過程で、正規の医者で病院側の人間でありながら、生き延びるために必死なロンやレイヨンや彼らの顧客たちに共感するようになったイブという名の女医さんなんかも現われたりもすると。 で、ダラス・バイヤーズクラブは、エイズ患者自身の治療法選択の自由を求め、エイズ患者の治療を統括したい病院側(政府側)を裁判で訴えるというところまで行くのですが、さて、勝利はどちらの手に! ・・・というようなお話。 さて、この映画に対する私の評点はと言いますと・・・ 「73点」でーす。合格だけど、アカデミー主演男優賞と助演男優賞、特殊メイク賞などを受賞した作品にしては厳しいかな? まあね、アメリカらしい映画ではあるんですよ。一匹狼が自力で巨大な組織に立ち向かうとか、治療方法の選択は個人の自由であって、その自由を制限しようとするものは、たとえ政府であろうと許さんという姿勢とか、いかにも小さな政府を志向するアメリカ人の感性がよく描かれている。 減点の理由は、この映画が実話に基づいていること。最近多いんですよね、「実話に基づく」というアメリカ映画。『マネーボール』とか『それでも夜は明ける』とか『アメリカン・スナイパー』とか『ソウル・サーファー』とか『ゼロ・ダーク・サーティ』とかさあ、みんなそうじゃん。あと実在人物の伝記ものとか。それはつまり、実話を越える想像力と創造力が枯渇してしまったことの証左でありまして。 もちろん実話を元にしたっていいんですよ。だけど、この映画に関しては、その割に脚本がよくない。女医さんのイブがロンに共感していく過程にしたって、もう少し上手に描けそうなものなのに。 ただ、ロン役のマコノヒーの劇痩せ熱演と、ジャレッド・レトーのゲイ役が堂に入っていたことを評価しての73点。文句ないでしょ。 それにしても、『ゴッド・ファーザー』とか、『バック・トゥー・ザ・フューチャー』とか、細部の細部に至るまで完璧じゃん、と思えるようなオリジナル脚本の映画って、もう作れないもんですかね。そういう映画が観たいもんですなあ・・・。
March 8, 2015
コメント(0)
-

コーヒーミルの悩み
皆さんは、自宅でコーヒーを飲む時、どうしてます? 私を含め、まあ大半の方は粉に挽いたコーヒーを買ってきて、それをペーパーなりネルなりでドリップして、あるいはそれに類する方法で飲んでいらっしゃることでしょう。 ホールの豆を買ってきて、自分でミルで挽いて、その挽いた粉を使ってコーヒーを淹れている方はどのくらいの割合でいるのかしら。 職場で自分と同僚のためにコーヒーを淹れ続けて20年、もちろん自宅でも週末の時間のある時などには必ずインスタントでないコーヒーを飲む私ですが、なかなか自分で豆を挽いて、というところまでは凝っていなかった。 だけど、やっぱり粉で買うのと、豆で買って自分で挽くのでは、淹れたコーヒーの美味しさが違うというじゃないですか。 で、何年かに一度くらいの周期で「コーヒーミルを買ってみるか!」という気になるのですが、実は今、まさにその周期なんです。コーヒーミル、買ってみようかな・・・。 だけど、慎重なワタクシとしては、色々調べちゃうわけですよ。 すると、手動式のミルを買うことをためらわせるような情報が結構あることに気づく。 曰く、「安いのを買うと、なかなかうまく挽けないよ」とか。 「家庭用の手動式ミルだと、一回に20グラムくらいしか挽けないので、人数分挽くとなると結構大変よ」とか。 「挽いた粉を取り出す時に、粉が散って掃除が大変よ」とか。 中でも一番、私を恐れさせた一言がこれ:「最初は面白いからいいけど、8回目くらいで飽きて、物置の肥やしになるよ」。 やっぱり、簡便な電動ミルの方がいいのかなあ・・・。電動ミル、特に回転式ブレードの奴だと、熱が発生するので味が悪くなるとか、粗挽きと細挽きがごっちゃになるとか、色々言う人もいるようだけれども。 一方、「siroca STC-401」という製品は、機械に豆と水を入れたら、あとはスイッチ一つでコーヒーが出来るようで、こういうのもいいかなと。コンパクトだし、デザインもいいし。siroca シロカ STC-401 全自動コーヒーメーカー 全自動コーヒーマシン オートコーヒーメーカー ...価格:10,770円(税込、送料込) だけど、その種の製品であれば、他の家電メーカーも色々作っているわけで、そういう、「いかにも」なコーヒーメーカーを買うのもアレだよなあと。 うーん、結局、どうしよう。 で、堂々巡り。 一杯のコーヒーというのは、この世の至福の一つだと思いますが、悩みだすと悩みの種にもなるもんですな。皆さんはどうやってコーヒーを淹れておられるのでしょうか。これがいいよ、ってな情報がありましたら、ご教示下さい。
March 7, 2015
コメント(0)
-
紀要入稿! そして梅見!
私が版下まで作成するうちの科の紀要が完成し、今日午前中に出版社の人と会って入稿してきました。ああ、今年もこれでひと仕事終了だ~! ということで、今日は昼から梅見に行くことに。私は桜より梅派なんですよね~。知多半島の割と付け根の方に「佐布里」というところがありまして、ここが梅の名所なんです。 だけどその前にまずは腹ごしらえということで、今日は知多半島道路阿久比インターから5分のところにある「トラットリア ラ・ピアンタ」というところへ。古民家を改築したイタリアンでございます。 人気の店ということで、予約なしで大丈夫かな?と心配しましたけど、ラッキーなことにいきなりカウンター席に座ることができました。で、坐ってみると、ここが案外、特等席だったかも。というのは、シェフが料理をするのが直接見られるから。 この店のシェフは長髪オールバック・ポニーテールなんですが、この方がまた何と言いますか、「悠揚迫らぬ」というのか、まるでサメが水族館の大水槽をゆっくりと回遊するがごとくのしのしと歩かれていて、焦るとか慌てるとかそういう感じがまるでない。まるでないのだけれど、次から次へと入るオーダー(イタリア風に言えば「コマンダー」ですな)を難なくこなし、実に手際よく料理を仕上げていくわけ。それはもう、一見の価値ありよ。 で、今日注文したのは、1300円のランチコースで、前菜セットにパスタ、それに飲みものがつく。我々はこれに300円足して4種のデザートをつけたのですが、家内の注文した「タコとキャベツのパスタ」も、私が注文した「サーディンのプッタネスカ」も、実においしかったし、前菜もデザートもコーヒーもみんなおいしかった。これで1600円なら御の字だと思います。人気があるのも分かるね。 ちなみに私が注文した「プッタネスカ」ですが、注文する前に「プッタネスカってどんな感じのパスタでしたっけ?」と尋ねると、店員さん曰く「これはしょうふ風のパスタで・・・」と説明されたので、ん? 今なんて言ったの? と思い、もう一度「何風っておっしゃいました?」と再度尋ねると、「しょうふ風です」と。 しょうふ風? しょうふ風・・・。しょうふ・・・。 娼婦? 娼婦風? とりあえず、「じゃあ、それで」って言いましたけど、「娼婦風」って言われて、「ああ! 娼婦みたいなパスタね」って、なかなか納得できないですよね。要するに、サーディンに加え、ケイパーとかオリーブの実とかが入った、酸味の強いトマトソースだったのですが。でも、とにかくここの娼婦さんはとてもいいお味でした。ここ、ここ! ↓トラットリア ラ・ピアンタ で、いい具合にお腹いっぱいになった我らは、そのまま佐布里へと向かい、梅見へ。 今日の佐布里の梅は、まさに梅見にはどんぴしゃりのタイミングというのか、八部咲き~九分咲き。満開一歩手前のもっとも美しい状態でしたね。で、あの梅の爽やかな香りがねえ、もうえも言われぬところ。最高でしたよ。 だけど、佐布里も大分整備されちゃったというか、昔はもっと田舎風でのんびりしたところだったのですけど、梅見客の増加に伴って「梅の館」的な団体客もOKみたいな施設も作っちゃって、少しきれいになり過ぎましたね。植わっている梅の数も増えましたが、私はやっぱり昔の田舎っぽい風情が好きだったな。 さて、そんなことを言いつつ、しっかり売店で梅酒とかお団子とか買い求めつつ佐布里を後にし、ここまで来たのだからということで帰りがけにコストコショッピング。そしてさらについでにお隣の「めんたいパーク」に寄って明太子まで買ってしまったという。 とまあ、今日はひと仕事を終えた解放感から、あれこれと遊んでしまったワタクシなのでありました、とさ。今日も、いい日だ!
March 6, 2015
コメント(0)
-

小山薫堂氏の発想力
テレビ・プロデューサーの小山薫堂氏が書かれた『もったいない主義』という本を読んでいるのですが、これがまた面白くてね。 私は小山氏の『考えないヒント』という本を以前読んで、面白いことを考える人だなあと、その発想力の豊富さに舌を巻いたので、この本もきっと面白いのではないかと予想していたのですけど、やっぱり面白いです。 本書の冒頭、氏の経営する会社の受付嬢の話が書いてありまして。 まあ、受付嬢というのは、ある意味会社の顔みたいなところがあるので、ポストとしては非常に重要なポストであるという認識が小山氏にはある。だけど、ただ入口に坐って微笑んでいるだけでは「もったいない」。 そこで、小山氏は会社の入口にパン屋さんを作ってしまい、受付嬢にはパンも売ってもらったと。 で、会社への訪問客は、パンも売る受付嬢に案内され、店の奥に導かれる。その時点で、何だか秘密基地に招き入れられるような感じで、訪問客には好評だというのですな。で、社員たちも、会社の入口にパン屋があることで、世間と接しているような感じになるというのです。例えば、夏になればパンの売れ行きが落ちるのだそうですけど、そのことによって「ああ、夏って、そういうことなのね」という感覚が養われる。小山さんの会社に勤めるには、そういう世間の感覚を知ることも重要だというのです。 しかも、受付嬢の給料は、パン屋からの収益で賄われてしまうというのですから、一石二鳥にも三鳥にもなると。 小山さんの「もったいない」という感覚は、そういうものなんです。 で、小山さんはこの頃山形県にある某大学に招かれて教授をしているそうなのですが、そこでもプロデューサーならではの「もったいない」主義が発揮され、同大学にもとからある宿泊施設を改築し、一階をレストラン、二階をホテルにして、オーベルジュとして経営する、というアイディアを提案されているのですって。 大学の教員用の宿泊所として作られたその施設、温泉も引かれていて結構贅沢なものだったらしいのですが、それをただ内輪の宿泊所にしておいては「もったいない」というわけ。だったら、それをオーベルジュとしてもっと積極的に活用し、例えば学生に経営を任せるなどすれば、一つの施設を何重にも活用できるではないかと。何しろ小山さんは人脈がありますから、レストラン部門にはどこどこのシェフに入ってもらい、ホテル部門は日光金谷ホテルに指導してもらえばいい、と、すぐに算段が立ってしまうところも強味。 そうやって、「もったいない」という発想を膨らまして、色々な面白いことを企画してしまう。まさに小山薫堂さんの面目躍如といいましょうか。 うーむ、面白いねえ。 うちの大学、今、色々と「改革」の方向性を探ってはいるのですけど、大学の先生ってのはとにかく発想が貧困で、しかも世間知らずですから、愚にもつかないようなことばかりしか思いつかず、結局、文科省のいいなりにならざるを得ないというのが現状。 うちの大学も、小山さんみたいな人を連れてきて、改革の指導を仰ぐとか、した方がいいんじゃないかなあ。 とにかく本書を読み進むにつれ、小山さんの発想の驚くべき豊かさに驚かされたり、思わず膝を叩くことばかり。春休みのブレーンストーミングにはもってこいではないかと。 ということで、小山薫堂さんの『もったいない主義』、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】もったいない主義 [ 小山薫堂 ]価格:799円(税込、送料込)
March 5, 2015
コメント(0)
-

島田潤一郎著『あしたから出版社』を読む
島田潤一郎さんの『あしたから出版社』という本を読了しましたので、心覚えを書きつけておきましょう。 島田さんというのは、社員一人、本人だけという出版社、夏葉社を起した方。その島田さんが、なぜに一人で出版社を作ったかという、半自叙伝ですな。 島田さんは、大学は商学部を選んで公認会計士になるつもりだったのに、途中から文学に狂い、作家を志すわけ。だけど、プロにはなれず挫折。バイトをしたり、旅行をしたり、その時はそれなりに理由があって色々な事をするのですが、三十代になって、いざ就職しようとすると、「文学を志してました」とか「人より本を沢山読んでます」では何の履歴にもならず、どこの会社にも就職できないことが判明すると。 つまり、一旦脇道にそれた人間は、主流に戻れないということを身をもって体験するわけ。 そんな時、兄弟のようにして育った従兄弟が事故で亡くなるんです。で、その喪失感は島田さん自身にとっても大きかったのですが、従兄弟の両親、つまり島田さんの叔父さん、叔母さんにとっては破壊的で、それがまた島田さんには非常に辛かった。 悲嘆にくれる叔父・叔母を慰めることはできないかと考えているうちに、島田さんはある詩に出会う。それは、100年位前にとあるイギリス人が愛する者を失った時に慰めにしたという詩だったのですが。 で、島田さんはその詩を本にして、叔父さん、叔母さんに手渡したいと考えた。これが島田さんが三十代になって、しかも出版のことなどろくに知らずに、自分一人の出版社を起ち上げることになる動機だったと。 そこからの島田さんは割と行動的で、親父さんから資本金を借り、事務所を借り、出版業を営む知人から一つ一つ教わりながら出版の仕事に取り掛かるんですな。 で、もちろん出版社を起こす動機となった詩の出版に早速、取り掛かるのですけど、それと同時進行で、アメリカのユダヤ系作家、バーナード・マラマッドの『レンブラントの帽子』という短篇集が、ずいぶん昔に集英社から出た後、ずっと絶版になっていたのを何とか復刊したいと考え、マラマッドの遺族や訳者の小島信夫・浜本武雄・井上謙治各氏(またはその遺族)、さらには集英社からも了承をとりつけ、それから装丁にはどうしても和田誠さんのイラストが欲しいということで、見ず知らずの和田さんの事務所に手紙を書いたりするなど、素人ならではの熱意と無謀さでもって、最終的に出版まで漕ぎ着けるんです。 この辺の経緯が、出版というものに興味のある私にとっては非常に面白いところでして。 とにかく、この『レンブラントの帽子』の出版を通じ、島田さんは出版というもののイロハを学びつつ、また素人でも出版ってできるんだ! という手応えも掴んでいく。 とはいえ、出版するのと、それを売って黒字を出すのでは大違いでありまして、島田さんも日本全国を飛び回り、それこそ手売りのようにして売り歩くわけ。で、その苦労はすべて報われるわけではないのですが、それでもその過程でまた色々な人脈も出来てくる。 そんな人脈の中から生れたのが、良い本でありながらずっと絶版になっていた関口良雄の『昔日の客』の復刊の仕事。日に当たると退色するので、普通なら嫌われるクロース装をあえて採用するなど、オリジナルの『昔日の客』の雰囲気を再現することに務めるなど、素人ならでは、小出版社ならではの試みを、やはり島田さんは押し通すんですな。 そしてそして、ついに夏葉社誕生のきっかけとなった詩の本、『さよならのあとで』も完成する。ただ、この本は、まだ島田さんにとっても、完全に納得できるものにはならなかったとのこと。 でも、それも良かったんじゃないですかね。そこで納得してしまったら、夏葉社の使命が終ってしまって、島田さんのモチベーションもそこで終ってしまったかもしれないし。 そして、今なお、夏葉社ならではの企画に従った本が、ぽつりぽつりとながら世に出ていると。 ちなみに、私はこの本を読むまで意識してませんでしたが、私、『昔日の客』とか『早く家へ帰りたい』など、夏葉社の本の何冊かを既に買って読んでいたという。これらの本の背後に、こういうストーリーがあったのか、というのがわかって、私には大変面白い本でした。小出版社を成功させるには、本好きならではの企画もの(例えば『冬の本』とか『本屋図鑑』など)と、本好きが欲しがる、しかし、つい忘れられがちな隠れた名著を復刻させることを同時並行でやればいいんだな、ってことも分かりましたしね。 あ、それからこの本には、亡くなった従兄弟を偲ぶ痛切な思い出の記の他にも、島田さんの青春時代の思い出、特に島田さんにとって何となく忘れ難い友人たちの思い出話が色々綴ってあって、それもなかなか面白いです。そこは元作家志望というだけあって。 また、同時にこの本は、一度社会のレールから逸れてしまってからでも、やりようによっては、自力で自分の居場所を作ることができるよ、というメッセージにもなっていて、そういう状況に悩んでいる人にとっては、応援歌になるんじゃないでしょうか。 というわけで、小出版社・夏葉社社主、島田潤一郎氏のライフ・ストーリー、教授のおすすめ!と言っておきましょう。また、夏葉社を応援すべく、同社の出版物も宣伝しておきましょうかね。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】あしたから出版社 [ 島田潤一郎 ]価格:1,620円(税込、送料込)【楽天ブックスならいつでも送料無料】早く家へ帰りたい [ 高階杞一 ]価格:1,944円(税込、送料込)【楽天ブックスならいつでも送料無料】昔日の客 [ 関口良雄 ]価格:2,376円(税込、送料込)
March 4, 2015
コメント(0)
-
祝! ブログ開設10周年!
2005年3月初旬にこのブログを開設して、今日で3650日目。つまり、丸々10年が経過した、ということですね。その間、日記記入率94.7%だそうですから、「ほぼ毎日更新」と言ってもいいでしょう。 いや~、よく続いたもんだなあ! 我ながら、感心するわ。 このサイトの名前が「セレクトショップ」であることからも推測される通り、本来このサイトはアフィリエイト目的だったんです。モノを売ることを目的にしたサイトのつもりだった。 それで初期には結構頑張ってモノを売っていて、それはそれで面白い経験ではあったんです。 だけど、そのうち、ただサイトを開設しただけでは人は寄ってこないことに気づいた。何でもいいけれど、とにかく何か毎日コメント的なものをアップしないと、一向にアクセスが増えないことに気づいたんですな。それで、モノを売る一方で、毎日、何かを書き始めたわけ。それが「お気楽日記」の始まりです。 で、そのうちにいつしか、この「お気楽日記」の方が、つまり、ブログを続けることの方が、自分にとって重要になってきたと。 そのアフィリエイト中心からブログ中心へ。この変化の底には、しかし、もう一つ重要な側面がありまして 当時から私には、大学なんてさっさと辞めて、物書きになりたいという夢があったわけ。筆一本で立ちたいと。 しかし、それならもっと筆力を上げなければ、というところがある。年に1本か2本、論文書いて終り、というような大学の先生の生活じゃあ、プロの物書きになれるはずがない。どんなテーマであれ、とにかく素早く注文された原稿を書き上げること。この芸当ができなければ、話にもならないだろう。そう思ったわけ。 そこで、私はこのブログを利用することにしたんですな。千本ノックのように、毎日、ブログをつけ続けようと。たとえ「今日は書くことがないなあ」という日でも、なんとか文章をひねり出してきた。 そこから10年。まあ、曲がりなりにも、なんとか書き続けて参りました。その間、例えば、長年世話になった恩師が亡くなった時には、恩師の思い出を33日間に亘って書き続け、それがやがて本になり、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞することになる、なんてこともありました。 実際、この本を書き上げられたのは、それ以前に何年にも亘って毎日このブログをつけ続け、書くことへの体力が付いていたからだと、私は信じております。 先日、糸井重里さんの「ほぼ日」を読んでいたら、こんな要旨のことが書いてありました。 糸井さん曰く、なんであれ、毎日あることをやり続けて10年経てば、脳の形がそのことをすることに特化してくるものだ、と。 とにかく毎日書く、というその決意の10年の蓄積が、平凡に過ぎた一日の中からでも、何かしら書くことを見出す術を私にもたらしてくれたような気がします。 さて、今日で10周年、明日からはまた次の10年の始まりです。まだプロの物書きへの道は遠いですけど、もう10年続けたら、分かりませんよ。そのために、また明日から頑張ります。教授のお気楽日記、明日もお楽しみに!
March 3, 2015
コメント(2)
-

使い回しOK! 父探し映画
昨夜『ネブラスカ』という映画を観たので、心覚えを付けておきましょう。以下、ネタバレ注意です。 モンタナ州の田舎町に老夫婦が住んでいて、二人の息子も近くに住んでいる。兄はテレビキャスター、弟は音響製品の店の店長。 で、最近、親父さんが少しボケ気味で、やたらに家出をするようになるんですな。で、事情を聞くと、「百万ドルが当ったので、賞金を受けとりにネブラスカ州のリンカーンという町まで行く」と。 ところが、これはよくあるインチキ広告で、「あなたに百万ドルが当りました!」とか書いてあるけれども、よく読むと小さな文字で「番号が当っていれば」ってなことが書き添えてある。でも、親父さんはすっかりその気で、誰がそのことを指摘しても、断固として「賞金を受けとりに行く」と言って聞かないわけ。 で、奥さんを始め、誰もが手を焼いた結果、それならば実際にネブラスカ州まで連れて行って親父の気の済むようにしよう、そうすれば真実が本人にも納得できるだろうということになる。で、弟の方、デイビッドが会社から休暇をとって親父さんをクルマに乗せ、ネブラスカ州まで行くことにするんですな。 ところで、ネブラスカ州リンカーンの町から少し離れたホーソーンという町が、実はこの親父さん(と奥さん)の出身地。たまたま法事があり、結局、奥さんも兄もホーソーンまでは後から行くことになり、一旦ここで合流することに。 で、とりあえず親父さんとデイビッドは一足先にクルマでホーソーンまで行き、親戚と久しぶりに再会するわけですが、そこで親父さんは、つい自分が百万ドルに当ったことを漏らしてしまったために、小さなホーソーンの町は大騒ぎ。住民の一人がひと財産当てた、なんて話題は、この町では久しぶりの大ニュースですから、誰もがお祝いに来る。 だけど、お祝いだけならまだしも、「昔貸した金を返して欲しい」とか、そういう話が親戚・知人からどんどん舞い込んでくるわけ。で、デイビッドが「百万ドル当たったというのは、親父の妄想ですから」と言っても、「そんなことを言っても騙されるもんか」と、てんで本気にしてくれない。とうとう、それがもとで親戚・旧友とも仲たがい。 で、デイビッドの従兄弟のダメダメブラザースが、ついに思い余って親父さんを襲撃、百万ドルの当たりくじを強奪するという事件まで勃発。 しかし、奪ってみれば、確かにその当たりくじとやらが、下らないチラシに過ぎないことが判明するわけですよ。それで、期待が大きかっただけに、親父さんはホーソーンの町の笑いものになってしまうわけ。そして、親父さんを物笑いにしていた親父さんの「友人」を、デイビッドは殴ってしまう、というようなことまで起こる。 でも、親父さん本人はまだその気で、リンカーンに行くといって聞かないんですな。 で、デイビッドは、「人に笑われてまで、なぜ百万ドルを当てたいのか?」と親父さんを問い詰めるんです。すると、親父さん、「トラックが買いたい。それに、友人に盗られたコンプレッサーを買い直したい」と。 そこでデイビッドが、「だって、免許ももうないし、トラック買ってどうするの?」と言うのですが、「一度、トラックを自分のものにしたかった」と。 で、更にデイビッドが「トラックぐらい、百万ドルを当てなくても買えるでしょう?」というと、ここで親父さん、ついに本音を言うんですな。 「二人の息子たちに、多少なりとも財産を遺してやりたかった」と。 親父さんが百万ドルに固執した理由が、これだったんです。 で、デイビッドは結局、親父さんの気の済むように、もう一足伸ばして、親父さんをリンカーンまで連れて行きます。 そして、ついに親父さんは真実を知る。親父さんがゲットしたのは、あたりの百万ドルではなく、はずれの帽子一つだけ。がっかりした親父さんを連れて、デイビッドは帰路につく。 しかし、ここでデイビッドは、頑張るわけ。 途中、「寄るところがある」とか言って、中古車屋に立寄ると、今まで乗っていたスバルを売り、親父さんが欲しがっていたピックアップトラックを買うんですな。それも、親父さんの名義にして。 さらに、ホームセンターみたいなところにも寄って、親父さんが欲しがっていたコンプレッサーも買い、早速ピックアップトラックの荷台に積み込む。 そして、モンタナへの帰路、ホーソーンの町を通過する時、デイビッドはトラックのハンドルを親父さんに任せます。それで、親父さんのことを馬鹿にしたホーソーンの旧友たちの前を、親父さんは威風堂々、戦利品のピックアップトラックを運転して通り過ぎる。 そして、二人はモンタナへの帰路につきましたとさ。 ・・・ってな話。 この映画への私の採点は・・・ 「76」点でーす。合格。ま、いい話ですからね。 それにしてもこの映画、テーマ的には珍しくもない、というか、典型的な「父親探し系ロードムービー」でありまして、ちょっと疎遠になっていた父と息子が、否応なく父のルーツを辿る旅に巻き込まれることによって、息子が父の本当の姿を知るようになる、という奴。 このテーマはもう、永遠に使い回せるな。細部を変えれば、このテーマ、このプロットでいくらでも作れる。そういう意味で、ちょっと減点。見始めた途端に、いや、ほとんど見る前から、「ああ、あれね」って分っちゃうんだもの。 だけど『ネブラスカ』に関して言えば、全篇モノクロで撮っているというところが少し変わっていて、しかもこのモノクロが、アメリカ中西部の広大な、なーんにもない大地を美しく映像化することに貢献しているところがある。それに、脇役のお母さんが割といい味を出していて(アカデミー助演女優賞にノミネートされた由)、そこも見どころがあります。 ということで、「アメリカの田舎って、こんな感じなんだ、今でも」というのを知るためにも、一見の価値はあるんじゃないかな。そういう意味で、映画『ネブラスカ』、教授のおすすめ、と言っておきましょう。これこれ! ↓【楽天ブックスならいつでも送料無料】ネブラスカ ふたつの心をつなぐ旅【Blu-ray】 [ ブルース...価格:4,010円(税込、送料込)
March 2, 2015
コメント(0)
-
『ジャズ構造改革』を読む
後藤雅洋、(故・)中山康樹、村井康司の「熱血トリオ」の座談会を本にした『ジャズ構造改革』という本を読了したので、心覚えを。 この座談会の趣旨は、つまるところ、最近ジャズが面白くないと。で、その面白くないジャズをどうすべきか、ということを、評論家三人でしゃべるというところにあります。 で、三人の共通理解をかいつまんで言えば、ジャズというのは、ウィントン・マルサリスが出世して、大御所になってしまったところで基本的には終了したのだと。それ以後は、少なくともアメリカの(黒人の)ジャズは面白くなくなったし、その面白くないアメリカのジャズの停滞と比べると、ヨーロッパ系のジャズの評判が良いようではあるが、それはあくまでも相対的な話で、絶対的基準からすると、そっちもダメだと。 で、日本のジャズももちろんダメだと。日野皓正が一時ちょっとやるなと思ったけど、結局ダメだったし、ナベサダなんて昔から哀れなもんだと。今で言えば、綾戸智絵あたりがジャズだと思ってもらっちゃ困ると。 で、ジャズ雑誌も3つくらいあるけど、どれもダメだと。面白くないと。 書き手にしても、昔はそれぞれ個性的な書き手がいたし、今も寺島靖国みたいにまったくジャズが分ってないながら、ライターとしてはそれなりに工夫している奴がいるけれども、それ以外は小粒だと。菊池成孔とか、ちょっと気の利いたライターもいるけれども、書いていることに新味はないと。その一方、素人がネット上にあれこれ書いているけど、話にもならんと。 で、どっちを向いてもダメダメで、もうジャズは完全に終っていると。 じゃあ、これからどうすりゃいいのか? で、結論としては、昔のジャズは今聴いてもいいのだから、そういう昔の本物のジャズを、今時の若い人たちに聴かせるように、俺たちジャズ評論家が頑張って工夫して紹介していかなきゃだめだろうねと。 まあ、そういうような感じの座談会でした。 「構造改革」と言いながら、あまり建設的なことが述べられないし、まったくうんざりだ、というようなことがアマゾンのレビューにも書かれていますが、確かにジャズの現状はそうなのかも知れないけれども、あれもダメ、これもダメって、そんなことばっかりなもので、読んでいてそんなに楽しいものではなかったかな。本書の内容にはある程度同意するけど、本書に対するレビューにも同意、みたいな。 それにしても、私から見て「面白いなあ」というか、「不思議だなあ」と思うのは、ジャズ評論の世界の人って、どうしてこう、ジャズ全体に責任を持とうとするのかな、ってことですね。 この三人の座談会を読んでいると、今ジャズは全然ダメだ、の後に、俺たち、この状況を改善するためにどう骨を折ればいいんだろうっていう話が続く。今、ジャズがダメなのは、あなたがたの責任じゃないでしょうに。 これって、他の音楽ジャンルでもそうなのかしら? 最近、モーツァルトとかベートーベンみたいな大物が出ないけど、もうクラシックも終っちまったのかなあ、この先、一体どうすりゃいいんだろう? 俺たち評論家に出来ることはないだろうか? って、日本のクラシック評論家は、頭を悩ませるのかしら? 「今はダメ」って話であれば、アメリカ文学も同じよ。ジャズ評論家たちが、「マイルス・デイヴィスがいた頃は良かった」と嘆くのであれば、「ヘミングウェイやフォークナーがいた頃は良かったよね」ということになる。黒人文学も、トニ・モリスンがノーベル賞獲った時点で終りだよね、とか。昔は『英語青年』があったけど、今、アメリカ文学を広く論じる場すらないよね、とか。 だけど、このお三方が悩むようなスタンスで、「この状況を打破するために、俺たちアメリカ文学研究者はどうすればいいのだろう?」とかって、考えている奴いるのかな? いないような気がする。少なくとも、責任は感じてないんじゃないかな。 その辺、違うなあと。良く言えば、ジャズ評論家は今だに熱い、とも言えますが。逆に、我々アメリカ文学研究者が熱くなさ過ぎるのか。 かもね。 アメリカ文学も、ヘミングウェイ、フォークナーの時代の方が良かった、というのなら、今の若い人たちにこれら大御所を読ませる工夫を、我々がしなきゃいかん! とか思うべきなのかもね。 それにしても、ジャズは終っても、日本のジャズ文化はまだ終わってなくて、「いい耳を持っていて、しかもいい文章が書ける奴がいない」とか、「クラブのDJとか、ちょっとセンスがあっても、本格的に基本からジャズを聴きこんでない奴ばっかりだ」とか、そういう言説が普通に飛び交い、「素人は黙っとけ」みたいな雰囲気が残っているジャズ評論の世界って、なかなかこう、敷居が高いなと、思わされたのであります。
March 1, 2015
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- クマ対策に効果のあるものとは‼️⚠️
- (2025-11-27 10:47:26)
-
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 令和7年度宅建試験 合格発表 デー…
- (2025-11-26 23:43:33)
-
-
-
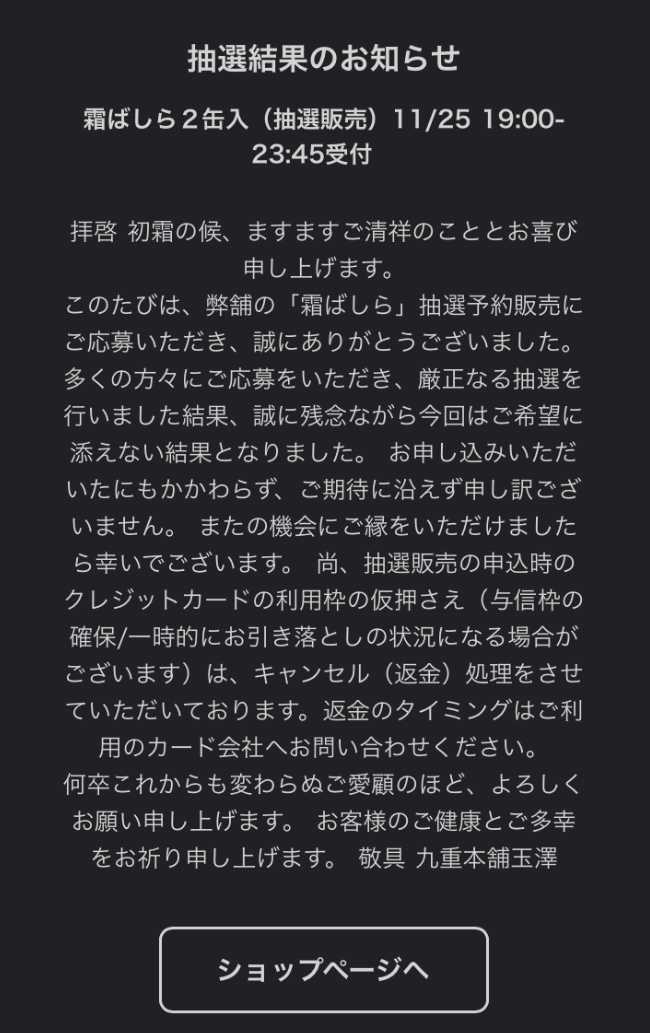
- 株式投資日記
- またまた上がってきた日経平均株価
- (2025-11-27 07:00:05)
-







