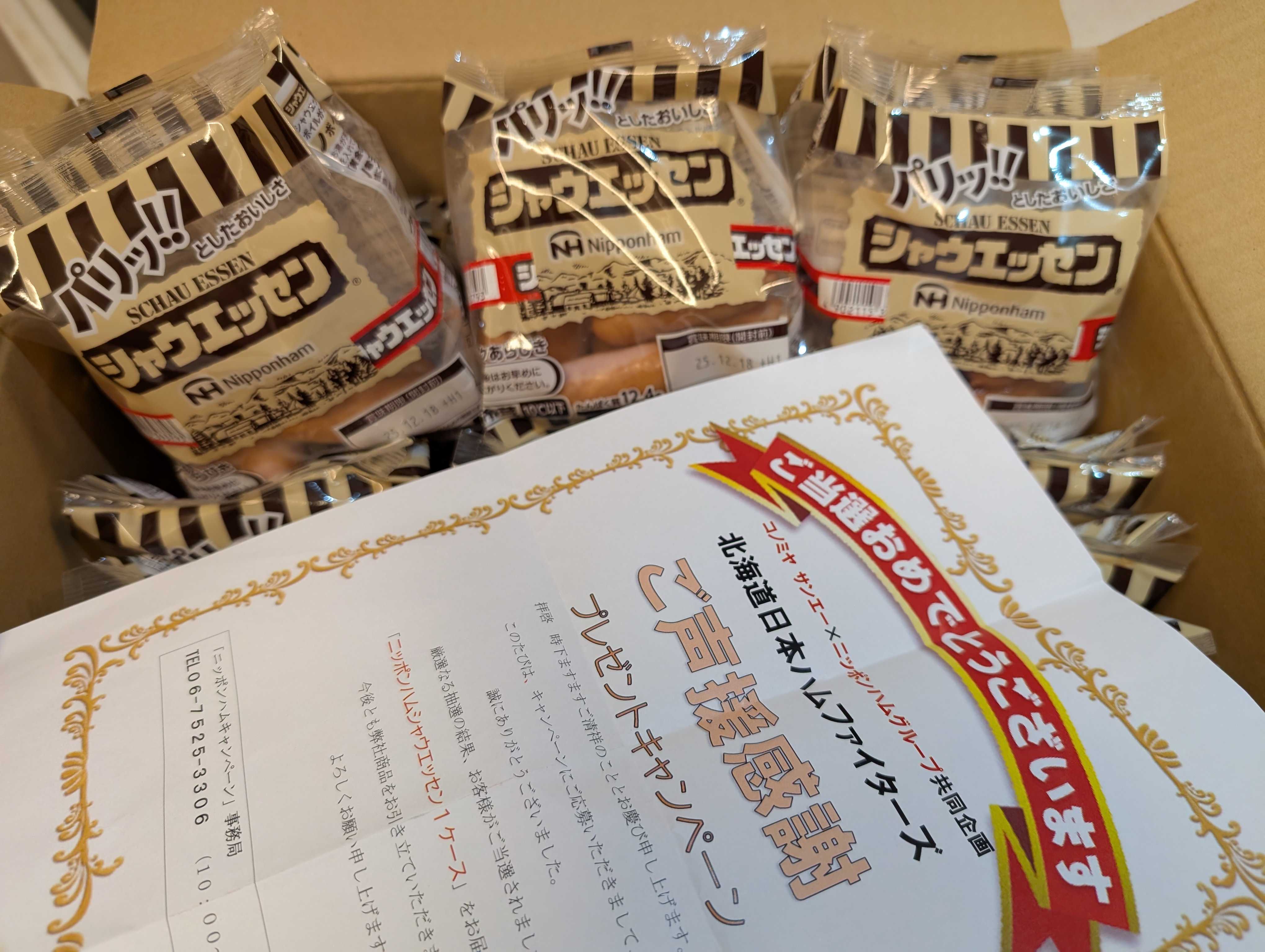2015年11月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
旅から戻る
先週の金曜日、お休みをいただいて、週末、ちょっと旅行に行っておりました~。9月、10月、11月と、結構仕事漬けの日々だったので、その憂さを一気に晴らしたろうかと。 で、向かった先は、このところ11月の旅の定番となりました北陸。今回は福井から富山まで縦断する形で。 まず名古屋から名神・北陸道と通って敦賀を目指します。北陸道を走行中、雪が降り出して、ノーマルタイヤのままの私をヒヤヒヤさせましたが、まあ、なんとか無事敦賀到着。この地で、蕎麦好きとして一度食べてみたかった「辛み大根のおろし蕎麦」を「千束」なるお店いただきます。相当辛いと噂に聞いてちょっとおっかなびっくりだったのですが、それほどでもなく、おいしくいただきました。 で、そこから日本海沿いの景色のいい道を越前岬を目指してひた走ることに。しかし、このあたり、押し寄せる波が凄い。逆巻くうねりとなった波が岩場にぶつかってドババーーン!と爆発するや、その波飛沫が道路にまで襲いかかるほど。後で聞いた話では、前日に強い北風が吹いて荒れたそうで、波というのは強風の当日ではなく、一日後に襲ってくるのですってね。勉強になります。また、このあたりでは台風で波が荒れることはあまりなく、あくまで冬の北風で荒れるのだとか。 越前岬では、名物の水仙が既にチラホラと咲きだしていて、近くにあったので立ち寄った水上勉なんかの文学館の管理人のおっちゃんに二、三本、摘んでいただいていただきましたけれども、何とも言えず清新な香りを楽しむことができました。 それから越前岬のちょっと先、「mare」という海沿いのカフェで一服。ここは目の前に海が見えて、この日のような波の荒れた日にはすごく迫力があっていい感じ。コーヒーもチーズケーキもおいしかったし、店員さんもみな感じがよくて、いい休憩になりました。 で、この日はさらに海沿いを北上し、芦原の辺りから山の方に向かって走って夕刻に山代温泉着。一昨年、山中温泉に泊まったので、今回は山代温泉をチョイス。 翌朝、山代温泉の温泉街を散策したのですが、このあたり、北大路魯山人が三十代の一時期滞在したことがあったそうで、その寓居跡を見ることができました。 で、地元の語り部みたいなおじちゃんから話を伺ったのですけれども、魯山人ってのは、もともと京都あたりの社家の出なんですってね。ただ二男だったもので、生まれて間もなく養子に出され、いわば親戚・知人の間をたらいまわしにされてしまった。だから、学校も尋常小学校の4年間しか通ったことがない。 だけど天性のものがあったのか、書をよくし、それが認められて書家となり、やがて各地のお大名さんたちの食客となって日本中を経巡ることになった。それで、山代にもしばらく滞在し、どうせ滞在しているんだったらということで、近所の旅館の看板なんかを書いたり篆刻したりしたらしい。 でまた、そんな感じで諸国漫遊しているうちに、京都で京料理の味を覚え、山代で九谷焼を学び、やがて飛びきりの料理を飛びきりの器で提供する「美食倶楽部」を設立するようになって、それがゆくゆくは星岡茶寮へと結びつくと。 しっかし、そんな魯山人の生涯を聞きながら思ったのですけれども、昔の日本のゆったりとした文化国家ぶりってすごいなと。 だって、今、小学校出ただけの、無名の、だけど書はうまい三十歳の男がいたとして、地方のそれなりのお金持ちが「そうか、定職もないのか。じゃあ、食客としてうちにしばらくいなさい。気が向いたら、このあたりの店やホテルの看板でも書いてやって」なんていう条件で何カ月も何年も受け入れることなんてある? 別にその男を育ててどうしようというのでもなく、ただ何となく才能だけはあるらしいから、こいつと書や器や料理の話がしてみたいという漠然とした理由で、どこの馬の骨か分からない奴を食客として家に置くなんてこと、今の世の中にある? で、結果的には魯山人は書や陶芸や料理道で名高くなるわけですけれども、ひょっとして魯山人のように有名にはならなかったけれども、地方地方で食客として扱ってもらった幾百人の魯山人もどきが沢山いたんだろうなと思うと、当時の日本の、その文化的な余裕、懐の深さというものに感慨を覚えずにはおられません。 だから私は声を大きくして日本政府に言いたい。大学の先生を「食客」として扱えと。何にもしなくていいよ、遊んでていいよ、気が向いたら、なんか面白いことでも考えてね、と、そういう風に扱えと。そうすることで、沢山居る大学の先生の中の何人かは、後世に残るすごい人になるよと。 ちなみに、ここまで書いてから言うのもなんですが、釈迦楽家ではね、魯山人なんて別に評価しないの。 私の母方の祖母は、「魯山人は下品」の一語で、その陶芸作品なんぞ歯牙にもかけませんでした。濱田庄司の作品ですら、濱田が是非にといって送ってくるから普通にご飯茶碗として使ったりはするけれども、それをぞんざいに扱って落として割ったりしても、別にどうとも思わない人でしたから、ましてや魯山人なんて商業主義の一語でバッサリ切って捨てる。その批評眼を、伝統芸として、孫である私も引き継いでいますので、魯山人なんて別にすごいとも思わない。 ちょっと有名だからって、後世の人全員に評価されるだろうなんて甘いこと考えるなよ、魯山人。わしはむしろ、お前を食客として遇した地方地方のお金持ちの篤志家の方を評価するんだからな。 さてその後、我らが向かったのは日本自動車博物館。こんなところにあるんですね、自動車好きの天国が。 日本製外国製問わず、昭和以後くらいの懐かしい自動車がずらりと保存してあり、私としてはめちゃくちゃ面白かったのですが、ここを訪れる人の中には私よりさらに年配のおじさんも多く、「ああ! このクルマ! これ初めて新車で買ったクルマだよ!」みたいな感慨がそこここで聞かれるという。で、それに対して嫌々ついてきているお子さん、お孫さんから、「このクルマが新車の時って・・・どんだけ年寄りなの・・・」などという罰当たりな言葉が漏れたり。 ちなみに自動車と何の関係があるのか分かりませんが、この自動車博物館の各階のトイレは、世界中から集めた便器が使われていて、お好みでフランス製の便器やドイツ製の便器で用が足せます。 さて、自動車博物館と世界のトイレを堪能した我らが次に向かったのは和倉温泉、なのですが、長くなりましたので、このあたりの話は、また明日にしましょうかね。
November 30, 2015
コメント(0)
-
おじさん枠
今日、職場で簡単な「一足早い忘年会」というのがあって、道場に行く前の腹ごしらえにちょうどいいかなと、ちらっと寄って立食を楽しんできました。 で、私がサンドイッチをつまんでいたところ、「釈迦楽先生はサンドイッチが似合うなあ・・・」と同僚に言われまして。 サンドイッチが似合う男・・・。何ソレ? 何でも、「釈迦楽先生は、おにぎりって感じじゃないんだなあ。やっぱりサンドイッチなんだなあ」だそうですけど、一応、いい方に解釈して、褒め言葉として承っておきましょう。 それはさておき。 今、来年度のゼミ決めをやっておりまして、学生に希望をとり、どの先生のゼミに入りたいか、決めさせているんです。 で、今年顕著だったのは、年輩の先生と若手に希望が集中し、中間層を遥かに陵駕したということ。私はもちろん、中間層に入るわけですが。 ま、若い先生に人気が集まるというのは分かる。だけど、年輩の先生(特にK先生とN先生)の所にそれ以上の人気が集まったというのは、ちょっと面白い現象かなと。 それで、学生を捕まえて、K先生とN先生の人気の原因を尋ねてみた。すると・・・ 「だって、二人共、可愛いんですもーーん」ですと。 ふーむ。学生にとって、年輩の教授は「可愛い」のか・・・。 ま、可愛いかどうかは別として、年輩の先生は概して穏やかな人が多く、めったに声を荒らげて怒ったりしないので、そういうところが今時の学生には受けるのかな。 以前は希望者が殺到した釈迦楽ゼミもこのところは人気も一段落。これを「えーーー! 俺は可愛くないのかぁ! サンドイッチは似合うのにぃぃ!」と悲しむべきか、それとも「まだまだ年輩と見なされてないわけね」と喜んでいいのか。 これもまた、一応、いい方に解釈しておきましょうかね。
November 26, 2015
コメント(0)
-
ここまで来たか、地方国立大の困窮
なんか、キナ臭くなってきましたなあ。トルコによるロシア機撃墜。パリのテロの余波も広がっているし。大丈夫? 第三次・・・とか、ないでしょうね! さすがに不安になってきたわ。 もっともキナ臭いのは外の世界だけじゃない。もっと身近なところ、地方国立大学の困窮もここまで来たのか、と思わされるような話を聞きまして。 なんかね、うちの大学、あまりにもお金がないので、準教授を教授に昇任させられないらしいんですな。教授になると、給料が少し上がるのですが、その分の差額が出せないと。 だから、一年間に4人しか昇任させられないと。 ひゃー! じゃ、あれだな。定年までに教授になれない人が沢山出るな。 よかった~、早いとこ教授になっておいて・・・っていう話ではなく。 国の教育行政として、どうなのこの事態? 真面目に務めて、普通に業績だしてる人たちに対し、お金がないから教授にしてあげられませんってんじゃ、めちゃくちゃモチベーション下がるじゃん。 企業と違って教育機関は、金を使いこそすれ金を生むものじゃない。そんなの最初から分かっていることなので、「だから、そんなものの存在は無駄だ」って話にしちゃいかんのじゃないの? 教育をここまで軽視する国、少なくとも先進国では他にないんじゃないかなあ。ドイツなんて、国が大学の面倒を見るので、大学生はほぼ100%、授業料なしなのに。 しっかし、それにしても、ほんとにそのレベルまで困窮しているんだ、うちの大学・・・。第三次の前に、うちの大学が潰れて、私自身が難民になる日も遠くないのかもね・・・。
November 25, 2015
コメント(0)
-
年賀状
喪中葉書がちらほらと届くようになり、ああ、また年賀状の季節だなと。 来週には師走にはいろうかというこの時期、教師稼業は猛烈に忙しくなるのですが、それに加えて年賀状をどうにかしなくてはならない、というのは結構な心の負担でありまして。 でもなあ、形式だけの印刷の年賀状は出したくないし・・・。一行でも手書きの文章を、それも出す相手によってすべて文面を変えた文章を添えたいという思いもある。 あと、年賀状のデザインをどうするか。これも悩むんだよな~。ネット上にテンプレートは山ほどあるけれど、そこから選ぶのが骨。 それはともかく、先ずは年賀状を買わないとね。 ところで今日、受け取った喪中葉書、親友H君からお父上様が亡くなられたという報せで、ちょっとガックリ。小学生の頃、彼の家に遊びに行った時にお会いした、ただその一回しか直接お目にかかったことはないけれど、優しそうな、いい感じのお父様だった。ナイスガイのH君が年を取ったらこうなるだろうな、と思われるような、いいお父様でした。 明日、H君になぐさめのメールを出そうかな。
November 24, 2015
コメント(0)
-
ますます混迷、パソコン選び
前に研究室のパソコン(Vista仕様)を新しいものに変えようと思っているものの、最近、どこのメーカーもいわゆるパソコンの開発に全然力が入ってなくて、選択肢がない、という話を書きました。 で、その件なんですけど、またまた面倒な情報が入って参りまして。 というのは、先日学会発表した際にお目にかかった先生とパソコン談義をしていたところ、今、売出し中の「ウィンドウズ10」に苦労しているという話を聞かされたんです。 N先生、この秋、お持ちのパソコンを「ウィンドウズ8.1」から「10」へと無償アップグレードをされたそうなのですが、そのおかげでパソコンが頻繁にフリーズするようになり、修理を繰り返した結果、2ヶ月を棒に振ってしまったと。 そして、それほど苦労して導入した「10」が、その甲斐あって優れていたかというと、そうでもなくて、むしろ「7」の方が良かったとのこと。不評の「8.1」を「7」に寄せて再開発したようなのですが、「7」の使い良さには遠く届いてないと。 うーーむ、そうなの~?! はあ・・・、そうなのか・・・・。じゃあ、ウィンドウズ10をプリインストールしたパソコンを20万円で買うより、今、在庫一掃中の「8.1」マシンを15万円で買った方がいいってこと? っていうか、むしろそれをさらにダウングレードして「7」を買う方がいいとか? 自宅で使っている「7」のマシンは、悪くないからなあ・・・。 もう、何だか分らなくなってきた! ま、そうは言っても「7」も寿命がいつまでか分からないし、「8.1」マシンを安く買う、その辺りでお茶を濁すか・・・。 ってなわけで、パソコン選びはますます混迷の度を高めているのでありました、とさ。
November 23, 2015
コメント(2)
-
学会発表終了
昨日、北の湖の追悼文をブログに書いたこともあり、その後でネット上にある「北の湖対輪島」の動画などを観たのですけど、これがね、実に面白い。千秋楽にそれぞれ1敗同士の東西横綱が結びの一番で雌雄を決する、的な場面で、北の湖と輪島が死力を尽くして戦う場面なんて、今見ても手に汗握ります。 でまた、そういう昔の動画を観ていると、解説が神風さんだったりするのよ。NHKで長く相撲放送の解説をやられた神風さん。これがまた懐かしくてね。今聴くと、実に味わい深い解説なんだ、これが。 その他、ネット上の動画を検索すれば、昔贔屓だった力士たちの熱戦がいつでも見られるんだ、ということが分かり、「大相撲ネット場所」として、しばし堪能しましたよ。これから、大相撲の場所が始まる度に、現在のモンゴル相撲は観ずに、ネットで古き良き昔の日本の大相撲を懐かしむようにしようかな。 さてさて、今日のことではなくて昨日のことなんですが、学会で研究発表をしてまいりました。久々に。 で、テーマは今やっている自己啓発本のことだったのですが、手ごたえは・・・うーーん、どうかな・・・。 アメリカ文学会の人たちって、基本、真面目なので、「宇宙に向って自分の願いを発信すれば、すべて叶います」みたいな、インチキ臭い自己啓発本の世界を紹介するのって、難しいんですよね。こちらの真意としては、このインチキ臭い世界の向こうに、実に面白い世界が広がっている、ということなのですけれども、そこまでちゃんと伝えられたかどうか・・・。 ま、いいけど。伝わらないなら伝わらないで。いずれこのテーマで本書いて、分かる人だけに読んでもらうもんね。 でも、とにかく一つ、宿題が終った。残る宿題はフォークナー論を書き上げること。年末までに。卒論・修論指導と重なる時期だけに、スケジュール的にはキツイですけど、まあ、頑張ります。
November 22, 2015
コメント(0)
-
追悼・北の湖
つい先日、白鵬の「ねこだまし」を「横綱らしからぬ」と批判されていた現・日本相撲協会理事長の北の湖さんが場所中に急逝され、いささかびっくりしております。 北の湖の全盛時代、こちとらは小学校高学年。当時から大相撲ファンだった私としては、ある意味、大鵬以上によく見知った横綱ではありました。当時は輪湖時代真っ只中でしたから。 が。 ファンではなかったですね。私としては、むしろ輪島の方が好きだった。 大体、北の湖は当時の力士の標準から言えば体格的に圧倒的に恵まれていて、そのでかい奴がカチ上げ気味にボーンとぶつかれば、まあ立ち会いで当たり負けするということはほとんどない。で、後はそのまま寄り切るか、右上手取って上手投げ。足が短いから足技とかはなし。で、勝つ。ただそれだけ。面白くもなんともない。でまた憎々しげな仏頂面に、愛嬌のかけらも無かったですし。 逆にたま~に負ける時の不様さもひどくて、手足の短いでぶっちょがあたふたして負けると、いかにもカッコ悪かった。 だから、輪湖時代、千秋楽に輪島と北の湖が激突する時には、輪島勝ってくれと願ったものでした。輪島と北の湖が対戦する時は、必ずといっていいほど立った瞬間に左四つになる(両力士とも左四つが得意なので)のですが、「黄金の左」と呼ばれた輪島の左下手投げも、北の湖の右上手投げと投げの打ち合いになると、どうしても分が悪く、私の願いも空しく、北の湖が勝つことが多かった。それが余計に、私を北の湖から遠ざけたわけですが。 輪島より前の世代、たとえば北の富士なんかと比べると、北の富士にはなんというか、大人の男の華があって、歌舞伎の花形役者が登場してくるような、そういう華やかさがあり、相撲そのものにも何と言うかこう、ドラマがあったものですけれども、北の湖となると、とっちゃん坊やというか、子供がそのまま大人になったような様子があって、相撲における歌舞伎的な華やかさを解さない奴が、ただ強いというだけで土俵に上がってるぞ、おい、みたいな感じがして、興醒めだなあという感じを、子供心にすら受けたものでありました。事実、長い北の湖の横綱時代、印象に残っているのは負けた時の相撲だけで、彼が勝った時の相撲で印象に残っているものがほとんどないという。 それだけに、長かった北の湖時代の終り頃、新しいスターとして千代の富士が出てきた時、ようやくまたドラマ性のある奴が出てきたという喜びがあったものでございます。それは北の富士のような大人の魅力ではなかったけれど、小さな身体という圧倒的な弱点を抱えた手負いの虎が、その弱点に付け込まれる危険を常に背負いながら戦うという、悲劇的なドラマを持っていましたから。 というわけで、北の湖の良いファンではなかった私ですが、あの人の相撲のつまらなさ、くそまじめさは、おそらく、理事長の重責を担うには適していたのでしょう。ひょっとすると、それが彼の寿命を短くしたのかもしれませんが。 しかし、ファンではなかったとはいえ、昭和の名横綱であったことは誰の目から見ても明らか。その北の湖さんが、あまりにも早い死を遂げたことに対し、私もファンの皆様と一緒に御冥福をお祈りしたいと思います。合掌。
November 21, 2015
コメント(0)
-
『コードネーム U.N.C.L.E.』を観た
スパイ映画の当たり年と言われる今年ですが、『007 スペクター』を後に控えて、もう一つの話題作である『コードネーム U.N.C.L.E.』を観てきました。ので、心覚えを。以下、ネタバレ注意ということで。 時は第二次大戦後、米ソが熾烈な冷戦状態に入り、互いに諜報活動を繰り広げていた時代。 そんな中、ナチスの残党がとある造船会社を隠れ蓑に著名な科学者を誘拐、原爆の製造に着手したという情報を得たアメリカとソ連は、何と共同でナチスの陰謀を阻止すべく、双方のピカイチのスパイを組ませてこの会社に忍び込ませ、核弾頭とその製造法を記した媒体を盗み出させるという作戦を案出する。そしてそのアメリカ側のスパイが元大泥棒にして腕を買われてCIAエージェントに転じたプレイボーイ、ナポレオン・ソロであり、ソ連側のスパイがKGBの腕利き、くそまじめにしてコンプレックスの塊たるイリヤ・クリアキンだったと。 で、ソロとクリヤキンのでこぼこコンビは、ナチスに利用された科学者の姪ギャビーを使って相手側に忍び込もうとするのですが、実はこのギャビーには別の顔があって一筋縄ではいかないと。 さて、男二人に女一人の、訳ありトリオは、無事、使命を果たせるのでしょうか?! というようなお話。 で、この映画に対する私の評価はと言いますと・・・ 「70点」! 合格・・・だけど、辛うじて、というところですな。 ガイ・リッチー監督ということで、色々などんでん返しが忍ばせてあるのだろうと期待して行ったのですけど、観ているうちに勘付く程度のどんでん返ししかなく、ちょっと退屈。すぐ喧嘩するでこぼこコンビというのも、まあ、ある意味、ありきたりではあるし。 ま、強いて言えば、これが1960年代くらいを想定しているスパイ映画ということで、例えば最新のスパイグッズが登場する『ミッション・インポッシブル』シリーズとは異なり、盗聴器にしても何にしても古いわけよ。その今となってはお笑い草のスパイグッズであれこれスパイ活動をする、その揶揄的な面白さが、この映画の一つの売りなのかなと。 それも想定内だけどね。 もっとも製作者サイドは続篇を作る気満々、というか、今回のこの作品自体が、これから始まるスパイ映画シリーズの前振りという位置づけらしい。面白いのは続篇からですよ、ということですかね。 さて、12月に入るといよいよ『007』が封切られますし、来年1月にはジェシー・アイゼンバーグの『エージェント・ウルトラ』がやってくる。スパイ映画好きには、まだまだ楽しみが続く、という感じですね。
November 20, 2015
コメント(0)
-
白鵬「猫だまし」問題
先日の取組で白鵬が「猫だまし」を試みた問題で、北の湖理事長が「横綱にあるまじき」とか言って批判し、白鵬がまた全然反省する風も見せずに開き直っているところから、より一層、批判されているようでありますが。 この件についての私の意見としてはですね、まあ、猫だましをやるというのは、それが横綱だろうと誰だろうと、構わないと思うわけですよ。突進してくるタイプの対戦相手に対する、一つの対処法なわけですから。同じことは注文相撲についても言えるので、先場所、鶴竜が注文相撲をした時も、私は「したっていいじゃないか」と書いたはず。 だけど。 白鵬は、上位の力士が下位の力士に猫だましをして何が悪いと開き直っているわけですよね? つまり、相撲の技に上位・下位はないと。上位だけが使える技、下位だけが使える技などないと。 だったら、下位の力士が上位の力士に「張り手」をしても構わないわけだ。そのことを、白鵬には肝に銘じておいてもらいたい。 私は相撲の技の中で「張り手」が一番嫌いで、むしろ相手の顔を叩かない「猫だまし」の方がよっぽどいいと思っているわけ。 で、横綱が下位の力士に対して張り手をするのが、特に嫌いなわけ。 で、万が一、下位の力士が白鵬に張り手でもしようものなら、白鵬は激怒して報復するじゃないですか。生意気だ、的な。それが最悪に嫌い。 今回、白鵬は「技に上位・下位なし」と自分で宣言したんだから、それだったら、お前、下位力士の張り手を甘んじて受けろよと。 私はそう言いたい。 否、そうじゃなくて、本当に言いたいのは、「張り手」こそ全力士に対して禁じ手にしてもらいたい。 要は、「猫だまし」なんて、どうでもいいのよ。
November 19, 2015
コメント(0)
-
お笑い芸人の演技力
たまたまテレビをつけたら、昼ドラでお笑いコンビ・ピースの綾部さんが主役を演じているのをチラッと見かけまして。 チラッと見ただけですけれども、まあ、様になってないこともないなと。いや、結構いい線行っているのではないかと。 ピースといえば、相方の又吉さんが芥川賞で一躍時の人となって、綾部さんとしては自分の心の整理も含め、対処が難しかっただろうと思うのですが、綾部さんはそれを上手にこなしたのではないでしょうかね。受賞直後は「又吉先生」と持ち上げ、まるで秘書のように振る舞いながら、コンビ格差を面白おかしくネタにしながら、取材しにくる取材陣にもうまいこと対応していたようですし。 そしてこの度の昼ドラ主役。お笑い芸人としての仕事をしながら、俳優業にも一歩踏み出した感があり、これはこれで又吉さんの文筆業進出同様、末永くキャリアを積んで行けるものを掴んだとも言える。 そういう意味で、又吉ブーム以降の綾部さんの一連の動きは、評価に値すると、私は見ておるのでございます。 ところで、「お笑い芸人の中には、演技の上手い人がいるよね」という話を家内としておりまして。 特にコントをやる人たち。そりゃ、コントというのは一回一回が短いシチュエーション・コメディでありまして、奇抜な設定の中でリアリティをもって何かを演じなければならないのですから、演技力が求められるのは当然。自然、演技力も磨かれるというもので。 で、管見によれば、その中でも特に演技が上手いなと私が思うのは、インパルスの板倉俊之さん。それからアンジャッシュの小嶋一哉さん。ハライチの澤部佑さん。ドランクドラゴンの鈴木拓さん。パッと思いつくのはそんなところですかね。 また家内に言わせると、北陽の虻川美穂子さんが演技派なのだそうで。なるほど。あと、これはお笑い芸人ではありませんが、元フジテレビアナウンサーの八木亜希子さんが女優としていい線行っているのだそうで。 ま、芸能界に残っている人というのは、いずれにせよ、才能あるよね。大したもんだ。
November 18, 2015
コメント(0)
-
『スミス都へ行く』
アメリカ映画史の授業で、1930年代のいわゆる「ポピュリズム映画の流行」の例として、『スミス都へ行く』を学生に見せたのですけれども、この映画、何度見てもいいねえ・・・。ポピュリズムと言ってしまえばそれまでだけれど、ジミー・スチュアート演じるジェファソン・スミス青年の一途さというのは、ほんとに素晴らしいし、彼を取り巻く様々なレベルの悪がまた素晴らしくて、これが人間ってもんだよな、と思わされます。ほんと、無駄なシーンがまったくないという意味では、『ゴッドファーザー』に匹敵するんじゃない? ってなわけで、学生に見せるという大義名分の下、自分の好きな映画を「授業」の一環として観てしまうこの心地よい背徳感。いいです。 それにしても、こんなにいい映画が391円って、どういうこと?
November 17, 2015
コメント(0)
-
幽霊の熟成
このところ、ホラー小説論を書いているゼミ生から教わることが多いのですけれども、今日のゼミの時間にも、一つ面白い話を聞きました。 アメリカのホラー小説を読んでいると、インディアン(本当はネイティヴ・アメリカンとか言わないといけないのだけど、面倒臭いのでこのまま)のことがしばしば出てくると。 つまりですね、インディアンの聖地を汚したために、たたりに遭って、えらいことになるとか、そういうことらしいのですが。 で、それは一体何故か? という話だったのですけれども、私にはもちろん即答できるはずもなし。 ですけれど、色々話しているうちに、やっぱりそれは、アメリカ合衆国自体に歴史がないからだろうということになりまして。 アメリカの歴史って、1776年の独立から数えると、せいぜい240年くらいなもの。これでは、幽霊が熟成するには時間が足りない。だから、先住民の幽霊を借りてくるしかなかったのではないかと。 そう言えば、アメリカのホラーものによく出てくるゾンビだって、あれ、元はと言えば、カリブ・ブードゥー系のものでしょ。 やっぱり、ある程度歴史の蓄積がないところには幽霊も出にくいと思う訳ですよ。日本だって、京都にお化けが出るといえば信憑性があるけれども、北海道の十勝平野の広大なジャガイモ畑に出たといっても、「ホントかよ?」という感じが先に立って、あんまり怖い感じがしないし。 っつーわけで、それが正しいかどうかは別として、「幽霊には熟成期間が必要で、アメリカにはそれがないから、先住民から熟した幽霊を借りてきたんだろう」という推論で押していくことになったのでした。 だから、これから幽霊のことを考える時は、「この幽霊、十分に熟れているかな?」っていう視点が新たに加わった私なのであります。
November 16, 2015
コメント(0)
-
高齢者町内会問題
週末、実家に電話して達者でいるか確認したところ、今週は町内会の問題で大変だったのだとか。 順番から言うと、来年、私の実家が町内会の役員になるそうなのですが、なにせ私の母も既に八十路。とても会長役は務まりそうもない。 ということで、「植栽係」とか、軽微な役職に立候補したようなのですが、それがなかなか受け入れられなかったと。 というのは、来季8人の役員のうち、母も含めた4人が後期高齢者で、この4人とも会長役を拒んだわけですな。 ところが若い方の4人は既に会長役経験者だったと。それで、「町内会規約」によれば、会長役は、まだその役を担当したことのない世帯から出すことになっているのだそうで、その若い方の4人も、規約に基づいて会長役を拒んだと。 つまり、誰もなり手がないわけよ。そりゃそうだよね。この先、市議会議員とか区長とかに立候補するつもりでもあるなら別、誰が好き好んで町内会の会長なんか引き受けるもんですか。 それで、その時の町内会は揉めに揉めて、大変だったと。 で、思うのですけど、高齢化と過疎化の進む日本において、これとまったく同じ状況が、日本各地で起っているのではないかと。 これは聞いた話ですが、高齢とか病気といった理由では町内会の仕事を回避できないというので、思い切って町内会を脱会したら、家の前の街灯を消されたり、ゴミの集積を拒否された、なんてことも、日本のあちこち起っているらしい。 だから、これは前にも書いたことですが、町内会なんてものは、無くす方向で地方行政は検討を始めないといかんのではないかと。 実際、無理ですよ。後期高齢者で、余生をゆったり暮したいと思っている人たちに、町内会の仕事を押し付けるのは。 最近の町内会は、議事録とかもきちんとワープロで作るみたいですけれども、後期高齢者の誰もがパソコンに堪能とは限らないでしょ。そういうことからして、無理なんだって。 今のように、親と子が同居しない世帯が増えている日本で、しかも高齢化社会が進む日本で、町内会の維持は無理。その、無理ということを前提に、新しい地域行政を組み立てないといかんのじゃないかなあ。 明日、市役所に就職することになったゼミ生に会うので、そういうことを伝えてやろうっと。
November 15, 2015
コメント(0)
-
イエロー・パンプキン
野暮用で外出した折、イエロー・パンプキンというお店によって、一番人気のカボチャプリンを買っちゃった。 これこれ! ↓ で、家に帰ってから食べてみると、うーん、まあおいしい。特にプリンは濃厚で、カラメルソースともよく合って美味。 ただ、これ、器になっているカボチャごと食べるのですけど、カボチャの部分が結構大きいので、食べているとお腹が一杯になっちゃうというね。それも、お菓子を食べてお腹いっぱいというより、カボチャの煮物を食べすぎてお腹一杯という感じ。 ま、でも、カボチャ系のお菓子好きにはいいんじゃないでしょうか。 ところで、このお店、私が20年くらい前に非常勤講師として通ったことのある大学の近くにありまして。まだ大学の先生になったばかりで、名古屋に引っ越してきたばかりだし、別にすることもないので、あちこちの大学に非常勤に行っていた時代のことなんですけど、その頃のことを思い出して、何だか懐かしくなっちゃった。 あの頃は、まだ独身だったし、授業をすることもまだ新鮮で、あちこちの大学に通うことに何のためらいもなかったどころか、結構楽しんでいたよな・・・。 甘苦いカラメルのかかったカボチャプリンを食べながら、自らの若き日のことを甘苦く思い出していた今日の私なのであります。
November 14, 2015
コメント(0)
-
当世鉛筆事情
先日同僚たちと話していたのですが、最近、「HBの鉛筆」ってのが使われなくなってしまったんですってね。 HBの鉛筆って、私の世代からすると、大スタンダードっていうか、「鉛筆って言ったら、HBでしょ」的な位置づけだったんですが、昨今の小学校あたりでは、HBの鉛筆を生徒に使わせないんですと。使わせるのはBか2Bなのだそうで。 Bはまだわかるとして、2Bって・・・。私からすると、2Bの鉛筆なんて、そろそろ「デッサン用」に入りかけているという感覚なのですが。「字を書く用」というよりは、「片目をつぶって縦にした鉛筆越しに石膏のダビデ像を睨む時用」みたいな。 ちなみに、なんでBか2Bか、と言いますと、最近の子供の筆圧が弱すぎて、HBの鉛筆では字が薄くなりすぎ、読めないからだとか。 いやあ、これは「HBの鉛筆、使用禁止」とかって言っている前に、まず生徒の筆圧アップ対策でしょ。っていうか、HBの鉛筆もまともに使えない筆圧って、何? 日本人の体力に、何が起こっているんだ?って話じゃないかと。 つまり、世も末だな。 それはさておき、鉛筆。色々な思いがあります。 私が小学生の頃、HBを通り越して、Hとか2Hとかを使う同級生の女の子とかいてさ。 で、そういう子に限って、そこそこ成績が良かったりして。そこから、何となく「頭のいい子はHの鉛筆を使う」的な伝説が生まれたり。 でも、Hの鉛筆を使う女の子って、なんかこう、鉛筆の芯同様、ちょっとお堅くて、プライド高くて、冷たくて、色が薄い感じがして、友達になりにくいなあ、みたいな。 逆に、バカっぽい男子生徒が、先の丸くなったBとかの鉛筆で、大きく下手な力強い字でノートにバカっぽいことを書いたりするのよ。 そのコントラスト。だからこそ、その中間点たるHBが、永遠のスタンダードだったわけで。 その一方、謎の鉛筆「F」というのがあってさ。これが謎。 「B」は、なんとなく「ブラック」とか、そんな言葉の略かなと。そして「H」は、「ハード」とかの略かなと。正確には分りませんが、何となくそんな理解をしている。 そうなると、じゃ、「F」は何の略なのさって話になるわけで。「ブラック」とか「ハード」とかの範疇を越えた何かではあるはずですが、ならばFはBと比べてどうなのか、Hと比べてどうなのか、ってのが全然想像できない。 いずれにせよ、BグループやHグループに混ざる気ないな、って感じがプンプンと。血液型で言うと、「Rhマイナス・AB」型みたいな。混ぜたら危険、みたいな。 それだけに、天邪鬼な私にはちょっと魅力のあるカテゴリーなので、1、2回は使ってみたこともありますが、続かなかったところを見ると、天邪鬼な私をすら拒む何か、腹に一物ある鉛筆だったのではないかと。 どうでもいいけどね。 でも、これも先日、ゼミに遊びに来たOBのM君(市役所勤務)が言っていましたけれど、市役所で備品を買う時に、「Fの鉛筆を買ってくれ」というリクエストがあったりするそうで、その意味では、世間のどこかに「F」ファンがいるんだよな・・・。 会ってみたい、敢えてFを注文する人に。 そして聞いてみたい。Fの魅力を。
November 13, 2015
コメント(2)
-
「パソコン」や、いずこ?
今研究室で使っているパソコン、富士通の「FMV FA-50」っていう機種なんですけど、これが実に実に名機でね。起動も作動もサックサク。スタイルはモニター一体型の走りで、シンプルながらすごくスタイリッシュ。強いて欠点を挙げれば、モニタが横長16インチで、今の基準からいうとかなり小さいことだけど、まあ、そこはね。 で、数年これを愛用してきて何の不満もなかったのだけど、さすがに最近、重くなってきた。 なんとなれば、こいつのOSは「ウィンドウズVista」なのでありまーす! 今時、まだこれを使っていたとは・・・。 ということで、そろそろ買い替えの時期かなあと思っているのですけれども、ここで困ったことが一つ。 代替機種で欲しいのがない。 っていうかね、今、各メーカー共に、パソコンなんかろくに力入れて作ってないのよ。 昔はさあ、富士通、NEC、東芝、ソニー、パナソニック、その他、春と秋にモデルチェンジして、何機種も新型を投入してたじゃない? だけど、今、モバイルとかスマホで用が済むので、メーカーはそちらに力を入れているのか、パソコンの新型モデルなんて、ぜんぜん力が入ってない。 だもので、選択肢がほとんどないのさ! それが時代の流れと言えばそうなんだけど、ついに「パソコン」も過去の遺物かあと思って。何だかちょっと、淋しいね。 とはいえ、こちとら、これが商売道具。少なくとも3年4年は酷使するものだけに、なるべく気の合う相棒を選びたい。 うーむ、何を買えばいいのか・・・。お勧めのメーカー、機種等ありましたら、ご推薦下さい。今まで東芝のパソコンを使ったことがないので、今回はその辺行ってみようかな、と、ちょっと思ってはいるのですけどね。
November 12, 2015
コメント(2)
-
アリス・マンローに見る女性の感性
大学院の授業でカナダのノーベル賞作家アリス・マンローの「夜」という短篇小説を読んでいる(=訳している)のですが、まだ途中ではあるものの、何だか気味の悪い話でね・・・。 14歳の少女が主人公なんですが、この子が盲腸炎になるわけ。で手術をする。 ところがお腹を開けてみると、盲腸もさることながら、腫瘍が見つかって、それも摘出することになったんですな。ただ、その腫瘍が良性だったか悪性だったかは不問に付されたまま。でも今も生きているので、多分、良性ではあったのでしょう。 で、そんなことがあったために、その年の夏、彼女は学校もしばらく休み、家族からも特別扱いされるような日々が続くわけ。皆がそれとなく気遣っているようで、そのため返って彼女は軽い疎外感を感じてしまうところもある。 ところで、彼女には9歳になる妹がいるんです。その妹というのは、どうやら彼女よりも美人なようで、気質も妹の方が家庭的、そして子どもらしい性格なんですな。 で、そんなこともあってか、この姉妹の関係はいつもどことなくギクシャクしている。例えばある時など妹の顔にお母さんの化粧品を塗りたくり、蝋人形のような不気味なメーキャップにしてしまったこともあったとか。意識的にか無意識的にか、遊びにかこつけて妹の顔を台無しにしておきながら「とっても綺麗になったわ」とか言っておだてるとかね。それから、二段ベッドで寝ていて、下の妹の顔に唾を吐きかけるふりをしていじめたりもしたのだとか。とにかく、二人の仲は決定的に悪いわけではないのだけれど、姉は妹に対してちょっとこう、いじめてやりたいという思いを抱いているようなんです。 そういう背景を踏まえての話ですが、結構大きな腫瘍があったという不安もあって、この年の夏、彼女は不眠症に陥るんですな。で、彼女は「眠れない夜の苦しみ」を生れて初めて味わうわけ。 そしてそんな中、彼女はある奇妙な思いにとりつかれ出す。 どんな思いだと思います? なんと、妹を絞め殺してみたい、という思いにとりつかれるのよ! 先にも言った通り、彼女としては別に妹が特に嫌いだとか、憎いというわけでもなく、ただ、妹の首を締めたらどうなるかなあっていう思いにとりつかれてしまったというのですな。 ま、今読んでいるのはそのあたりなので、この先どうなるか、本当に実行に移すかどうかは分かりませんが(もちろん、実行には移さないのでしょう)。 で、この話を院生たちと読んでいて、私は思うわけですよ。何なんだ、これは? と。 既に読み終わったマンローの作品も概してそうなんですけれども、女の子が思春期くらいの時に考えたこと、体験したことを、後になってから回想する、という体裁になっているのが多くて、なるほど、これがその時期の女の子の思いなのか、というのは確かに伝わってくる。 でも、そうだとすると、その年頃の女の子なら誰でも、誰かに嫌な仕打ちを受け、そいつがめちゃくちゃ憎くなって殺してやりたい~と思ったとかいうホットで健全な殺意ではなく、これといった理由のない、静かな、興味本位の破壊衝動を、一度くらいは持ったことがあるっつーことなのか? その辺が、男にはイマイチ分からないのですけれども、ひょっとしたらそうかもしれないいやきっとそうだそうなんだおっそろしいなめちゃくちゃおっそろしいなあ、的な、うすら恐ろしい思いを抱かされるところなんだなあ。 そういえばさ、日本でも『妊娠カレンダー』だっけ? 結婚して身重になったお姉さんに妹がちょっとずつ毒飲ましちゃう小説がありましたよね? 読んだことないけど。で、その世にもおっそろしい行為を静謐な文章で美しく綴っちゃうという小川洋子的世界がある。 マンローの小説も、なんかそれと似たアレがあるんじゃないかなと。 だとすると、ワタクシ的には苦手かな! 英語で読んでいるから、まだ我慢が出来るけれども、これ、日本人が日本語で書いた小説だったとしたら、読まないかも。そういう女性的(と言っていいのか?)感性、男の私には面倒臭すぎる。仮に男に破壊衝動があるとしたら、おそらくそれはもっと理屈っぽいんじゃないの? 三島の『金閣寺』みたいに。それなら、まあ、私にも理解できるし、共感すらできるけれども、マンロー的/小川洋子的「理由なき破壊衝動」は、はっきり言って鬱陶しいわ! 私は、人間、額面通りに生きて欲しいわけ。怒っているなら怒っている、憎いなら憎い顔をしていてもらいたい。それなら、こちらにも相手が自分のことどう思っているか分かるから。そうじゃなくて、素知らぬ顔して、普通に付き合いながら、内面では「こいつの首、締めたらどうなるかな」とか、「ちょっとずつ毒飲ましてみようかな」とか考えていてもらいたくないのよ。 とにかく、マンローの短編読んでると、女ってのは怖いなと。つくづく思います。
November 11, 2015
コメント(0)
-
洋モノホラーは冬の風物詩
うちのゼミにホラー小説で卒論書いている奴がいるんですが、そいつと話をしていて、またまた面白いことを聞きました。 「日本の怪談」というと、一般に夏の風物詩ということになっていて、夏の暑い時にゾッとして涼を得る、的なところがあるわけですけれども、イギリスやアメリカのホラーとなると、これがまたまったく逆で、一般に冬の風物詩だというのですな。 うーむ。そうなのか。そう言えば映画『シャイニング』は、冬場、営業停止しているホテルが舞台だったな。 まあ、良く考えれば、冬の方が夜が長い、すなわち闇の時間が長いわけですし、クリスマスを例に挙げるまでもなく冬至とは「太陽の死」を意味する。光が死んで、闇が世界を領するわけですな。草木も枯れるし、人間も室内に閉じ込められる。逃げ場がないわけだ。そこへコワイ奴がやってきたら・・・。 だから、ある意味、冬がホラーの季節というのは、言われてみれば納得でございます。 むしろ、逆に、何で日本では夏がホラーの季節なの?っちゅうー話でありまして。 で、そいつ曰く、歌舞伎に関係があるのではないかと。 江戸時代、歌舞伎の中心役者は江戸を離れて地方巡業に行っちゃったらしいんですな。やっぱり、忠臣蔵とか、主たる演目は冬が中心なので。だから、夏場に江戸に残っているのは、若手の、まだ演技力が未熟な役者しか残ってない。 で、この未熟な連中で出し物をやるとすると、怪談のように、ストーリーの怖さと音響効果でごまかせる演目の方がいいと。そこで江戸の夏の歌舞伎は怪談をやるのが定番となっっていった。もちろん、それプラス、日本の場合は「お盆」があって、何となく先祖の霊とかが夏場にはふわふわ漂っている的なイメージがあるので、お化けが夏に出るというのは、リアリティがあったんでしょうな。 ふうむ。なるほどね。あんまり意識したことがなかったけれども、日本以外では冬がホラーの季節、という知識は、頭の中に仕込んでおきましょう。 いやあ、勉強になるなあ。負うた子に教わるとはこのことか。
November 10, 2015
コメント(0)
-
流行
バブル期を体験したバブル世代としては、1980年代のけったいなファッション、すなわち男は長大な肩パッドの入った(時としてダブルの)上着に、これまたぶっといズボンを組み合わせたダブダブのスーツ、女物で言ってもブラウスの独特の襟の形、肩パッドの入った逆三角形みたいなスーツ、そしてあの前髪を立てたワンレンの髪型等など、今見ると噴飯もののファッションの数々に赤面せざるを得ないのですが、なんか最近の女性ファッションも、それにやや近いような傾向はありませんこと? ガウチョパンツに端を発する幅広ユルユルズボン系。そしてズートスーツのごとき長い裾のコート。なんかね、私は若干胡散臭いような気がするんだよね。あと男物だと、チェスターコート。あれも怪しい。 今から二年後位には、「もう恥ずかしくて着れない系」になって、箪笥の肥やしになるんじゃないの?? 思うんだけど、細めの服ってのは、割と流行のレンジが長いし、後から見てもそんな変な感じがしない。例えば、デビュー当時のビートルズのモッズ系の服装なんて、今見ても「まだ行けるんじゃね」ってな感じでしょ。ツイギーのミニスカートだって全然OKだし。それに比べて、太め・ゆるめのファッションは危ないと思う。 だからねえ、世の女性は、あんまり今のファッション雑誌にあおられない方がいいと思うんだよね。そこはさ、フランス女性みたいに、自分に合ったファッションを一生、ほとんど変えずに着続けるくらいの気概を持った方がいいんじゃないかと。 と、たまたま家にあったファッション誌をパラパラ読みながら思った私なのであります。 ちなみに、そのファッション誌では、大久保佳代子さんのコラムが面白い。本人が書いているのか、聞き書きかはアレですけど、もし本人が書いているなら文才あるね。逆に面白くないのは・・・言わない方がいいか・・・。自分でハンサムだと思っているのか、やたらに虚空を見つめたような自分の写真を前面に出しながら、よく分からないエッセイを書く東大名誉教授。女性ファッション誌に、何でこの人が登場するのか、分からないなあ。この人の文章、読んでいる人、いるの?
November 9, 2015
コメント(0)
-
名誉教授宅へ
今日は生憎の雨模様でしたけれども、2年程前に定年で勤務先大学を辞められた先生のご自宅にお呼ばれして、同僚数名と歓談してきました。 A先生のご専門は地理学で、私とはまったく接点がないのですが、なんとなく気が合うというのか、昔からキャンパスでお会いすれば雑談を交わすようなお付き合いがずっと続いていたんです。それで先生が退職される時には、個人的に送別会を開いたりもしたのですが、そういう昔からの流れがあって、今日はお招きにあずかったという次第。 A先生は、開けっぴろげというか、党派性の一切ない、来る者拒まずの懐の広いところがあるので、私もそばにいてちっとも堅苦しくない。今日初めてお目にかかった奥様も実に陽気で気さくな方で、一緒に歓談に加わられて座を盛り上げていらっしゃいました。なんか、全体として親戚の集まりみたいな感じでしたね。 男は外に出ると七人の敵がいると言い、実際、大学では色々面倒な事情もありますが、それでもそういう中から、今日のような利害関係のまったくない、楽しい会合が持てるような人間関係が築ける部分もあるわけですから、やっぱり社会生活というのは、人生の重要な側面でありますな。 というわけで、今日はA先生ご夫妻のおかげで、くったくのない、いい時間が過ごせました。先生の居間には掘りごたつがあって、今日はまだ畳で覆われていましたけれども、もう少し寒くなってこたつが出たら、また遊びにおいでと誘われましたので、それを真に受けて、いずれまた遊びに行くことにいたしましょうかね。今日はありがとうございました。
November 8, 2015
コメント(0)
-
白霧島
先日、同僚たちとお酒の話をしていたら、私以外の人たちは大体蒸留酒ファンなんですな。ウイスキーとか、焼酎とか。ワインとか日本酒が好きというのは案外少なくて、マッコリに至っては「飲んだことがない」という人ばかり。え、そうなの? で、彼らに言わせると、概して蒸留酒の方が残らないと。度数はもちろん高いけれども、後はスッキリしている。一番残るのは日本酒ではないかと。 ふーむ、そうなんですかねえ。アルコールに強くない、だけどお酒そのものの味は嫌いではない私は、どちらかというと醸造酒に向いがちなのですが・・・。 で、蒸留酒のことが頭に残っていた私、先日、つい「白霧島」を買ってしまったという。 前に友人から九州土産で「黒霧島」をもらって飲んだ時、焼酎にしては割と甘味があって美味しかった、という記憶があったので、それの別バージョンである白はどうなのか、ちょっと興味があったもので。 そして今日、夕食の時にちらっと飲んじゃった。すると・・・ なるほど、黒と比べてどうこうとは言えませんが、これはこれでスッキリとした甘味があって、いいんじゃないの? ということで、日本酒より残らないという同僚たちの言を信じて、久しぶりに芋焼酎をたしなんでしまった私。 まだ若干風邪の感じが残っているのですけれども、焼酎パワーで体を温めて、完全に抜けてくれるといいんだけどな。
November 7, 2015
コメント(2)
-
中村天風を知る
『中村天風の生きる手本』という本を読了したので、心覚えを。これ、天風が述し、作家の宇野千代が編集したものらしいですが。 天風は、日露戦争時に日本の軍事探偵、つまりスパイとして大陸をうろうろしていた人(その時には、機密書類を奪うために随分人を殺めたそうですが・・・)で、まあ相当肉体的にも元気な人だったのですが、その後急性の結核に罹り、体調を崩すと。 兄弟に医者が居たので、診てもらうのですが、どうなるもんでもない。これじゃ埒が明かない、自分の身は自分で治すしかないってんで、アメリカに行ってみた。それも、結核の身ではビザが出ないので、中国人のふりをして。で、アメリカでは中国人の大金持ちのボンボンの代理でコロンビア大学の医学部で学位をとるのですが、一向に体調は良くならない。 それで、どうせ死ぬなら富士山の下、桜の花の下、日本で死のうってんで海路日本に向かったら、途中で何だかよく分からないけどインドの偉い人に気に入られ、お前、俺に付いて来たら治してやると言われたので、ついその気になってヒマラヤの麓まで、三ヵ月もかけて付いていってしまった。 ところが、向かったのはカースト制のあるインド。当のその人(ヨガの聖人だったのですが)は神の地位であるブラマンなんだけど、天風は一番下の位なので奴隷扱い、犬・猫より位は下で、ご飯も家畜の後回し。 しかも、そのヨガの聖人さん、全然何も教えてくれない。毎日、遠巻きに姿は見えるのだけど、ブラマンと奴隷では対等に口が利けるはずもなし。ただただ犬・猫以下の扱いを受けながら無為に過ごしていたと。 で、こんなはずじゃあなかったと、遂に天風も堪忍袋の緒が切れて、ある時、聖人が通りかかった時に、無礼も顧みずに「一体いつになったら教えてくれるんじゃ!」と言ったんですな。そしたら、聖人曰く「いや、俺はお前が教わりたいっていうから連れてきたんで、一体いつになったら教わる気になるんだろうと、毎日待っておったのじゃ」と。 つまりね、聖人の目から見たら、天風はまだ彼から教えを受ける準備ができていなかったんですな。 天風は仮にもコロンビア大学の医学部を主席で卒業して、自分ではいっぱし医学の知識もある知識人だと思っている。そこへインドの聖人が教えを与えても、「ふーん、そういう考え方もあるのか」程度にしか認識しないだろうと。それでは本当の教えは与えられない。教えを受けるつもりがあるなら、それまで蓄積した、と自分では思っている知識なり、先入観なりを、全部捨て去って、空っぽの頭になって、師に向わなければならない。聖人は、天風の気持の中が本当に空っぽになって、素直になるまで、待っていたと。 で、ようやく学びの準備が出来た天風に、聖人がヨガの知恵を授け、それで彼は癒されていく。そしてそこから天風の第二の人生が始まり、以来40年に亘って彼は日本で「心身統一法」なるものを説く説教者となるわけ。 で、その心身統一法ですけれども、この本自体の中にはそれほど詳しくは説かれていない。でも、天風の語りの端々から伺うに、やはりそれはヨガの知恵を加えた形での、ニューソート系ポジティヴ・シンキングだろうと思います。 というのは、彼もまた神仏というものは適当にあがめておけばいい程度に脇にのけておいて、実質のところ宇宙の原理はガス状のエーテル(あるいはプランク・コンスタント)で、この宇宙エネルギーから人間はデル・ナツール・ヘリトリープ、すなわち自然治癒力を得ている。だから、その力を十全に受け、それを十全に発揮させれば、人間は病にかかることなく、死ぬまで健康に生き切って、この世での幸福を得られると。 で、そのためには、身体を鍛えるように、心も鍛えなくてはならない。じゃあ、心を鍛えるにはどうするか。 まず、たとえ身体の具合が悪くても、心が健康である以上、その心の健康を維持せよと。あそこが悪い、ここが痛いなどと愚痴を言わず、いつもハッピーでいろと。もし人に「調子はどう?」と聞かれたら、たとえ嘘でも、ニッコリ笑って、「絶好調!」と言えと。 そして、夜寝る時には、昼間のことを一切考えず、寝ることに専念しろと。寝る時までしなければならないほどの考え事なんか、あるはずがないと。 そうやっていれば、寿命のことはいざ知らず、生きているうちは楽しく生きられるよ、ってのが、天風先生の教えですな。 もう、ばっちりニューソートじゃん! でも、そのニューソートの教えを天風節で教えるというところがミソで、実際、天風のべしゃりはめちゃくちゃ面白い。天性の講演家でしょう。それに、スパイをやっていたり、アメリカに密航したり、中国人のふりをして、別人になりすまして医学の学位をとったり、フランスでは女優のサラ・ベルナールの世話になっていたり、インドでヨガの修行をしたりと、まあその人生がカラフルですから、そういうとっておきのエピソードを混ぜながら話せば、そりゃあ、人気は出るでしょうよ。 というわけで、この本、天風なる人物の語りの魅力に一端に触れるにはちょうどいいものではないかと。かなり面白いですよ。一応、おすすめ、と言っておきましょう。かの宇野千代女だって、天風に接したおかげで、十数年のブランクから解放され、再び名作を書き上げられるようになった、っつってるんですから。
November 6, 2015
コメント(0)
-
流浪の民
23年間に亘って所属してきた科が、例の人文学軽視の文科省の方針でお取り潰しとなることが決まったため、私も身の振り方を考えなくてはならなくなりまして。 と言っても、あまり選択肢はなくて、既存の別の科に移籍するか、新規に語学センターみたいなのを作ってそこに所属するか。前者は、移籍した時点で外様ですから、居心地も良くはなかろうなと。かといって、後者の語学センターで単に英語を教えるだけでは私の専門を活かせるはずもなし。 はあ・・・。 国を失ったユダヤ人か、ロマみたい。流浪の民か・・・。 どちらにしても、今より良い状態になるわけもないことが明らかである以上、会議をしていてもつまらなくてね。 あー、いかんいかん、愚痴を言うと愚痴を引き寄せてしまう! 楽しいこと、ワクワクすることを引き寄せねば! そういう時、気分転換には道場で汗を流すに限ります。 今日は三段技を中心に稽古。三段技のポイントは「肘」で、相手の肘をいかに制するかが重要。ちょっとした手首の極めを一つ入れるだけで、相手の肘が上がり、自在に動かすことが出来るようになるというね。その辺のコツを、同じ三段のO田さんに教わりながら、充実した稽古となりました。 職場で嫌なことがあっても、もう一つ道場という居場所があるってのは、いいもんですな。
November 5, 2015
コメント(0)
-
『おにいちゃん 回想の澁澤龍彦』を読む
矢川澄子さんの『おにいちゃん 回想の澁澤龍彦』を読了しましたので、心覚えを。 矢川さんは、澁澤の最初の奥さんだった人。で、それだけ身近にいた人だから、そういう人の書いた澁澤龍彦伝はきっと面白いに違いないと思って読んでみたのですけれども・・・ うーーーん。どうかな。期待したほどではなかったかな。 まず興醒めだったのは、回想の中で自分のこと(?)を「I」というイニシャル(あるいは一人称のI?)で語ることで、その他、時折出てくる人名もイニシャルだったりして、とりあえず面倒臭い。これは気取りなのか、「私」と名乗ることが怖いのか。 そのこともそうなんですけど、なんかね、メルヘンチックなのよ、書き方が。それでいて書いている内容は、澁澤に何度も中絶させられた、というような生々しいことだったりして。だったら「こいつ、ひでえ奴だったんですよ」ってな感じでズバッと言えばいいのに。離婚した後、澁澤から二つにぶった切った2ショット写真を送りつけられたとか、そんなことも書いてあるわけだし。 結局、矢川さんという人は離婚してもやっぱり澁澤が好きで、彼との思いでが大事で、それを宝物のようにしていたんでしょうな。だから、それを人に見せて自慢したいけれど、素のまま見せるのはちょっと嫌で、それで宝石箱に入れたまま、遠目にしか見せてくれないようなところがある。だから、何度も中絶させられたり、離婚後にまで嫌なことをされたりしたことまでも、飛び切りの美しい箱で飾るように提示したんでしょうな。 だから、それを読まされる方としては、どういう気分でそれを受けとりゃーいいのか、さっぱり分らないわけよ。そこが、すごく読後感を気持悪いものにしている。 矢川さんだって、大した文人なのだから、もっとギリギリと澁澤の人間性(悪魔性)に迫るなり、いっそ開き直ってそれでもなお余りある彼の魅力を語るなりすればいいのに。彼との生活の一瞬一瞬を慈しむように、目の中にお星さまキラキラで「こんなひどいことされました」って、うっとり語られる中途半端な感じは、ちょっとたまらないな。 というわけで、今回は教授のおすすめ! はなーしーよ。でも、興味のある方は別に引きとめませんけど。
November 4, 2015
コメント(0)
-
記念日
今日は我ら夫婦の16回目の結婚(式)記念日! で、正装して外食! の予定だったのですが・・・。 私の風邪を受け継いでしまった家内の具合がよろしくなかったので、ここで無理してもいかんだろうということになり、外食の予定はキャンセル・・・。で、一日静かにしていることにしました。残念。 でも、せめてお祝いはしようと、私がひとっ走り、近所のケーキ屋さんでおいしいケーキを買ってきておやつに食べ、そして夕食は私が腕を振るって(といっても簡単なんですけど)おでんを作り、デザートには(病気の時しか買ってあげない)ハーゲンダッツのアイスクリームを食べました。 それから、少しでも気分をあげようと、お花も買ってきちゃった。風邪を吹き飛ばすヒマワリの花。家内は8月生れですから、夏の花はいいでしょう。 ま、こういう時もありますわ。 ということで、私の体調も今一つであることもありまして、お祝いの外食は「祝い延ばし」ということで先送りし、ひっそりと休日を過ごしていた我らなのでしたとさ。
November 3, 2015
コメント(0)
-
日本語とホラー、ホラーの日本語
私の今年のゼミ生に、日米ホラー小説について卒論を書いている奴がいるのですが、今日のゼミの時間、こいつから面白い質問を受けまして。 彼曰く、日本のホラー小説の場合、字の使い分けによってホラー感を高めることがあるけれども、英語で書かれたホラー小説で、そういうケースというのはありますか?と。 つまりね、日本語の場合、漢字で書くか、ひらがなで書くか、カタカナで書くかによって、趣を変えることが出来るので、例えば、○お前を呪ってやる と○おまえをのろってやる と○オマエ ヲ ノロッテ ヤル とでは、それぞれ趣が違うので、作家はケース・バイ・ケースでこれを使い分けていると。英語でもそれに類する工夫はありますか? という質問なんですな。 うーーん、どうかねえ。ホラー小説、そんなに詳しくないし。 まあ、勿論、英語だってフォントを変えるとか、書体を変えてイタリックにするとか、ピリオドなどを無くすとか、その程度のアレはあると思いますけれども、さすがに漢字・ひらがな・カタカナを縦横に使い分ける日本語ほどのインパクトのある「趣変え」は無いんじゃないかなあ、どうなんだろう? あとね、彼がもう一つ言っていたのは、日本語の場合、縦書きになるので、短い文で切ったりすると、その下に広大な余白が残って、それが余韻になることがある。だから、作家はその余白を活用することがあるけれども、英語だと、横書きなので、短い文で切っても、その右側に大した余白が残らない。その辺に、日本語ホラーならではの特質があるのではないかと。 うーーん、これもこのジャンルに詳しくない私には何とも言えないけれども、言われてみればそうかもね。確かに、縦書きならではの視覚的効果というのは、あるかもしれないし、作家がそれを意識的に使っているとしたら、それはそれでスゴイことだと思う。 ふうむ、なるほどね。日本語ホラー、ホラーの日本語というのは、英語のそれと比較することによって、面白い観点になるかも知れませんな。 ということで、今日はゼミ生から結構教わることがありましたよ。
November 2, 2015
コメント(2)
-
『ザ・マスター・キー』を読む
10月は科研費やらその他の申請書を作成する必要があったり、学会があったり、アレがあったりコレがあったりで結局、何の勉強も出来なかったのですが、11月下旬には学会発表もあるし、そろそろちゃんと勉強しないといかんだろうという焦りもあって、今日は例によって自己啓発研究の一端として、チャールズ・F・ハアネルの『ザ・マスター・キー』という本を読んでおりました。 ハアネルというのは、1866年生れ、1949年に亡くなったニューソート・ライターですが、彼が『ザ・マスター・キー』を発表したのは1917年のこと。めちゃくちゃ売れたものの、教会がニューソート思想を危険視したため発禁となってしまった。 で、それが再注目されるようになったのが、ビル・ゲイツ伝説。ハーバード大学在学中に図書館でこの本に出会ったビル・ゲイツが大いに感銘を受け、かつ発奮して、その後の彼の成功につながったとか、つながらなかったとか。 で、さらに近年の自己啓発ブームの火付け役たるロンダ・バーンが、ハアネルのこの本とウォレス・ワトルズの本に啓発されて『ザ・シークレット』というドキュメンタリー、及び本を制作したおかげで、またまた再・再注目されるようになって今日に至る、的な。 で、その内容ですが、これは思想書というよりは訓練マニュアルでして、今日の自己啓発家と同じく、ハアネルも講演とかセミナーで儲けていたらしいんですな。で、そのセミナーの内容を活字にしたのがこの本なので、この本も「成功のための24週レッスン」になっていて、読者には「一度に全部読むんじゃなくて、毎週1章(=1レッスン)の指示内容をこなす形で、24週の訓練だと思って読みなさい」と断っている。 じゃあ、毎週のレッスンというのはどういうのかと言いますと、最初に「今週の訓話」的なお話があり、その次に箇条書き的に(=箴言的に)「教え」めいたものが30前後並んでいて、その次に具体的な、行動としてのレッスンの指示がある、という構成になっている。 で、そのレッスンですが、最初の方のレッスンはごく簡単で、例えば「1日15分、自分一人で静かな部屋に閉じこもり、目をつぶって心を無にしなさい」的なことなんですな。 で、次の週にはもう少し難しいレッスン、例えば「何でもいいけど、空想上で何か明確なイメージを心に描いてごらんなさい。細部まで明確に」とか、そういうことが指示される。 で、ふーん、この調子で行くと、最後の24週目辺りには、「空中浮遊してご覧なさい」とか、そういう辺りまで行くのかなと思いきや、そうでもなくて、「この世界が素晴らしいところで、あなたが輝かしい存在であることを肝に銘じて下さい」とか、そんな感じで終る。まあ、もちろん、24週間でこの世界が素晴らしいところで、自分がその中にあって輝かしい存在であることを肝に銘じられるようになれば、そりゃあそれで、大した成長というか、大いなる意識改革だとは思いますが。 で、ここまで辿り着く過程で書いてあることは、よくある引き寄せ系の自己啓発本と同じ・・・というのは逆で、ここにそれが書いてあったから、今日の引き寄せ系の自己啓発本がそれを繰り返しているわけですが。つまり、この宇宙はエーテルで、人間の思考がそれに形を与えて引き寄せる、ということなのですが。 で、そういう「うっそ~!」みたいなことを書く一方で、それを出来るだけ科学的裏付けをもって語ろうとするところも近年の自己啓発本と同じで、たとえば薔薇の木にアブラムシがたかっていると。で、その薔薇の木に水もやらずに日向に出しておくと、当然枯れる。するとどうなるか。 アブラムシに突如羽が生え始め、一斉に飛び立つのが観察される。つまり、「ここに居たんじゃ死んじまうから、羽を生やしてどっかへ行こう!」ということになったわけですな。 で、ハアネル曰く、アブラムシほど下等な虫ですら、必要に応じて体の仕組みさえ変え、飛べなかったものが飛べるようになる。それは実験で立証されている。いわんや、人間をや! と。 なるほど、説得力あるねえ! (あるか?!) ま、とにかくこんな調子なんですけれども、この本読んでいてちょっと感じるのは、「注意力」とか「集中力」の重要さへの言及(及び訓練)が多いな、ということ。 その一つの要因は、ハアネルという人が、ヨガ系のニューソートライターだからですな。つまり、呼吸法とか、そういう体の制御によって、心を制御しようとする発想が見られると。 実際、この人は同時代のヨガ系ニューソート・ライター、ウィリアム・アトキンソンの影響を受けているらしく、アトキンソンへの言及もあるし、またアトキンソンがアメリカに導入した「プラーナ」という呼吸法への言及もある。 ヨガねえ・・・。これに手を出すと、また面倒臭いことになりそうだなあ。 あと、これはこの本を読んでいて出てきたことじゃないですけど、最近、「フロー」っていう概念のことを知りまして。これ、「成功体験に基づく熱中体験」みたいなものらしくて、これもポジティヴ・シンキングの一端らしいんですな。今、特に教育学系の人たちが、勉強効果を高めるための手段としてフローに注目しているらしい。 もう、ヨガだ、フローだって、ポジティヴ哲学は果てしがないね。それらを追ってくのも疲れるわ。 とにかく、自己啓発本の元祖の一つであるチャールズ・ハアネルのこの本、興味のある方は是非!
November 1, 2015
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1