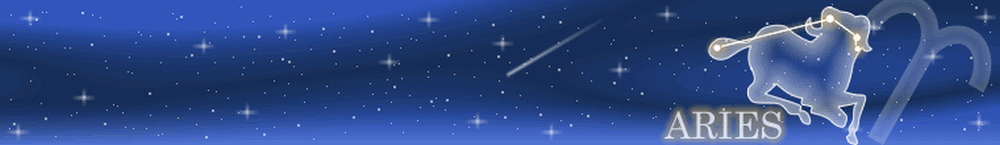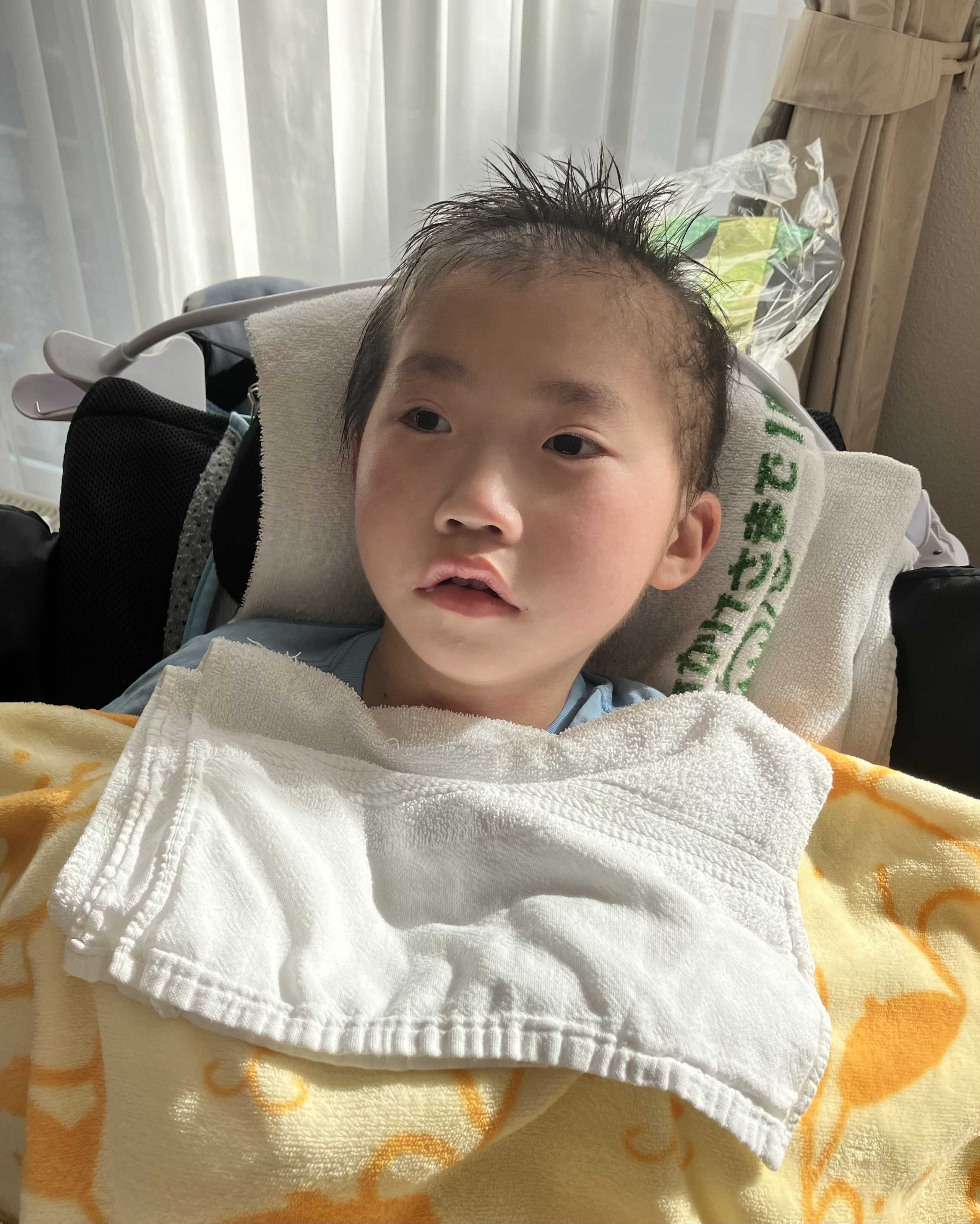2008年05月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

2008年6月1日 年間第9主日
わたしの言葉を聞いて行う者は、……(マタイ7・24より)岩の上の家と砂の上の家 手彩色紙版画 アルベルト・カルペンティール(ドミニコ会 日本)「岩の上の家」と「砂の上の家」のたとえを絵画化した例は初めて見る。たとえとの対応関係は明らかだろう。鑑賞しながら、たとえそのものの味わいも深めたい。一つのポイントは「岩」と「砂」との対比にある。岩は神、キリストあるいは神の言葉のたとえである。「どこまでも主に信頼せよ、主こそはとこしえの岩」(イザヤ26・4)、「この岩こそキリストだった」(1コリント10・4、出エジプト記17・6も参照)などの箇所があげられる。また、キリストの復活に関連づけられる「家を建てる者の退けた石が 隅の親石となった」(詩編118・22、使徒言行録4・11も参照)も思い起こされる。家々を襲った嵐の描写に関してはノアの洪水の記憶が根底に働いているといわれる。最後の裁きの暗示である。砂の上に建てられた家の倒れ方が「ひどかった」という表現には、救われなかったという最終決定の意味合いが響く。 ところで、「砂」は、ここではもろいことのたとえのように思われるが、聖書中の「砂」の用例をみると「海辺の砂」という語句が非常に多い。数が多いことのたとえである。そのうちアブラハムへの子孫の増加の約束(創世記22・17参照)、イスラエルの民は海の砂のごとく多いが救われるのは残りの者だという預言(イザヤ10・22参照)やその引用(ローマ9・27)などを併せて考えていくと、このたとえの含蓄はさらに広がっていきそうである。(『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)マザー・テレサ愛と祈りのことば
2008.05.31
コメント(0)
-

ゴーヤのツルがでた!
我家のゴーヤくんのツルが出てきました。棒を立ててグリーンカーテンを作る準備をしなければなりません。網を張ろうと思うのですが、その網を吐出窓の外側にうまく固定する方法を探さなければなりません。網がはれましたらまた報告します。園芸ネット 1.8×1.8m
2008.05.30
コメント(0)
-

ゴーヤの葉っぱを守る!
グリーンカーテンにするために植えたゴーヤの葉を何者かが食べている!犯人はまだわからないが、子供の話によると葉っぱの上にてんとう虫がいたことがあるそうだ。また、別の場所の花も食べられていて、こちらには「ヌル」っとした何かが付いていたそうだ。そこで、急遽網をかぶせることにした。いずれにしても、まずは犯人を特定せねば、効果的な対策はうてない。ゴーヤ 沖縄中長
2008.05.19
コメント(0)
-

国際協力の日
今日は「国際協力の日」のイベントである。大阪司教区座のある玉造教会でミサを受け、その後、となりの越中公園で開かれたイベントに参加した。ミサは聖堂から信者がはみ出るほどの盛況でその後のイベントももりあがった。イベントではペルー、ブラジル、フィリピン料理の屋台や、韓国、ペルー、そして司教様たちによるバンド演奏などが披露された。国際色豊かな休日を過ごすことができた。玉造教会ビショップ松浦とブラザーズボリビアの踊りペールの音楽
2008.05.18
コメント(0)
-

三位一体の主日
神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された(ヨハネ3・16より)十字架のキリスト 彩色木彫 スペイン バルセロナ カタルーニャ美術館 12世紀このようなキリストの姿を伴う単独の十字架像はクルチフィクスス(Crucifixus) という。11世紀以降、祭壇に十字架を置くことが慣例化してから数多く造られる。この作品はスペイン北東部、バルセロナを中心とするカタルーニャ地方で造られたもので、同地では「マイェスターデス」(majestades 荘厳) と呼ばれて特に親しまれたらしい。キリストは帯を結んだ長い式服をまとい、目を開けた生きている主、威光を帯びる神として尊厳をもって表現されている。すなわち、十字架の上に表されているのは復活の主、死に勝利した主、神の右におられる大祭司としてのキリストなのである。十字架に磔(はりつけ)にされたキリストを描く初期の作品と同様の考え方である。なお、この作品では足が失われているが、他の作例からもわかるとおり(下2図参照)、本来は両足が真下に下がる形になっており、釘づけられてはいない。ドイツのブランシュヴァイク(12世紀末)の作品(下図左)ではキリストの姿勢はまっすぐで、顔も真正面を向いているのに対して、この作品では頭が少し傾き、13世紀初めのルッカ(イタリア)の作品(下図右)ではさらに傾きが強くなっている。この後、13世紀を通じて十字架のキリストは苦しみ死せる姿で描かれるようになり、「磔刑像」として受け取られるようになる。(『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)愛とゆるしと祈りと
2008.05.17
コメント(0)
-

2008年5月11日 聖霊降臨の主日
五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると……(使徒言行録2・1より)聖霊降臨 フィテロのシトー会修道院ミサ典礼書 スペイン パンプローナ議事堂 12世紀シトー会のミサ典礼書の聖霊降臨の主日の欄に、祈願文の頭文字装飾として描かれた絵である。ちょうど右側の赤文字の下にあるDeusのDの文字を飾っている。聖霊降臨は、マリアを中心とする使徒たち(ここでは6人)の上に鳩の形で表された聖霊が降ってくるところとして描かれている。多くの場合描かれる「炎のような舌」は描かれていない。 このミサ典礼書の前のページには主の昇天の欄があり、そこにもほとんど同じ構図で昇天の図が掲載されており、マリアを中心とした使徒たちの上に、キリストの足(2008年5月4日、表紙絵解説参照)が描かれている (下図参照) 。 よく見ると両脇の6人の使徒たちは、どちらの絵でも赤い本をもっているが、主の昇天のマリアは何ももっていないのに対して聖霊降臨の図では、赤い色の本をもっている。ちなみに、一般に聖霊降臨の図でマリアが必ず中心に描かれるようになるのは、この作品が作られた12世紀半ばからである。明らかにマリア崇敬の高まりを示している。マリアが教会そのものの象徴となっていくとすると、ここで、マリアが抱えている赤い本は、聖霊降臨をとおして教会が、告げ知らせるべき神のことば、福音を本当に託されたということを意味するのかもしれない。フィテロはスペイン北部、ピレネー山脈のふもとのナバラ州に属する人口2000~3000人程度の町。州都パンプローナの南104kmに位置する。(『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)よくわかるカトリック
2008.05.10
コメント(0)
-

英作文のトレーニング 実戦編 例題47
伝統的社会においては、家庭はあらゆる役割を果たす場でした。家庭は、消費だけでなく生産においても主要な単位だったのです。しかし、現代産業社会においては、家庭は以前ほど総合的な役割を果たしていません。専門化した機関が、かっては家庭が行っていたことの大半を担っています。分解する1. 伝統的社会においては、家庭はあらゆる役割を果たす場でした。→ 「家庭はすべての事柄において重要な役割を演じた」、「家庭はあらゆる活動の中心だった」「家庭」:family、home2. 家庭は、消費だけでなく生産においても主要な単位だった。not only of~ but also of・・・「消費」:consumption「生産」:production3. 現代産業社会においては、家庭は以前ほど総合的な役割を果たしていません。→「家庭は総合的な役割を果たしていない」+「それが以前果たした」「現代産業社会」:modern industrial society「総合的な」:integral、comprehensive4. 専門化した機関が、かっては家庭が行っていたことの大半を担っています。→「専門化した機関が仕事のほとんどを引き継いでいる」で始め、「仕事のほとんど」+「かって家庭の中で行われていた」と続ける。「専門化した機関」:specilized organ「引き継ぐ」:take over「機能」:function「果たす」:performまとめる1、2、3、4はそれぞれ独立させる。3はhoweverを文頭に置くか、あるいは挿入句として補う。模範解答In traditional society the home was the setting for all activity. The home was an important unit of production as well as comsuption. However, in our modern industrialized society the home dosen't play the integral role it once did. Specilist bodies now perform most of the function once carried out in the home.In traditional society the family played an important role in all matters. The family was a primary unit both of consumption and of production. In morden industrial society, however, the family dosen't play the comprehensive role it used to play. Most of the functions it onece had are now performed by specilized organs.引用:英作文のトレーニング 実戦編 増進会出版社どんどん話すための瞬間英作文トレーニング
2008.05.07
コメント(0)
-

ゴーヤのグリーンカーテン
4月上旬に種をまいたゴーヤが芽を出し、本葉がでるまで成長しました。ゴーヤは東南アジア原産で発芽には平均地温が25度程度になる必要があり、発芽までに3週間程度ようしました。最近の陽気に誘われてすくすく成長中です。夏の日差しを遮るグリーンカーテンに成長してくれることを期待しています。ネットでゴーヤについて調べたところ、種の殻が固く発芽しにくいので、爪きりで殻の端を切り、水に下してからまくと発芽しやすいそうです。来年実践してみようと思います。
2008.05.06
コメント(0)
-

主の昇天
天に上げられたイエスは、……またおいでになる(使徒言行録1・11より)主の昇天 手彩色紙版画 アルベルト・カルペンティール(ドミニコ会 日本)きょうの第1朗読、使徒言行録1・10に登場する天使(聖書では「白い服を着た二人」、ここでは衣も彩色されている)がこの絵の中では大きく描かれている。上に天に昇るイエスの両足、下にイエスをほとんど真上に見上げるマリアと弟子たちの姿がある。「またおいでになる」という再臨の約束が強く響いてくる。 歴史的に見ると主の昇天の絵は400年頃から見られるが、それには、(1) イエスが天使によって天に運ばれる図、(2) イエスが山を登るように、天に向かって歩いて昇っていく図(この場合、上から伸ばされた神の手を握るものものある)、(3) キリストがマリアや弟子たちの上に祝福のしぐさをしながら天に昇っていく図などがある。この場合、天使たちは、上を見ているものもあれば、マリアと弟子たちに語りかけているものもある。 この作品のように、キリストの姿が画面から消え、下半身か両足だけを描く図が現れるのは1000年頃からである。見えない天の次元に入っていったことを表す工夫である。マリアと使徒たちは一心に天を見上げている。ゴシック時代に標準となった、このある種ユーモラスな表現法は、カルペンティール師の絵の温かい雰囲気ともよく溶け合っている。(『聖書と典礼』編集長 石井祥裕)マザー・テレサ愛と祈りのことば
2008.05.04
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1