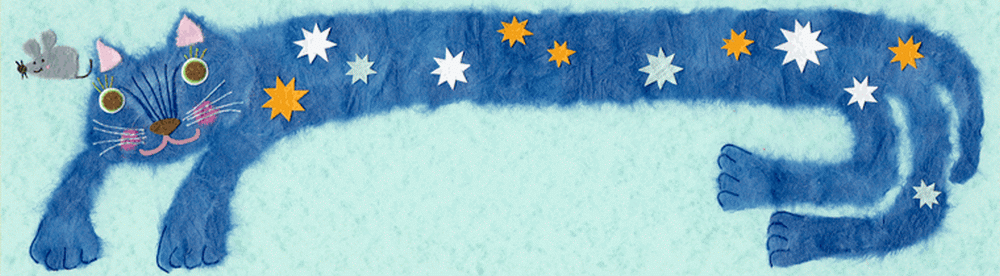2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年11月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

台湾パイナップルケーキ
誰の土産だろう? 「台湾パイナップルケーキ」がキッチンに置いてあったので早速食べてみた。 大きさは3x4cm位の四角い形。包装紙にはパイナップルの絵が書かれてある下に商品名なのだろうか「鳳梨酥」と書いてあるが読めない。「ほうりんそ?」 包みを開けるとパイナップルの甘い香りがほのかに漂う。 小麦粉で焼かれた一口ケーキのようだ。 ただ、口に入れるとケーキ部分はボロボロと口の中にこぼれる。しっとり系でなくてボソボソ・モソモソ系。 甘味は抑えられている。中心部にパイナップル餅(?)が入っている。餅というより、餅と餡の中間の硬さでやはり甘味は抑え目。 ネットで見るとパイナップルケーキは漢の時代から伝わる昔からの御菓子だそうだ。そう言えば何だか懐かしい味がする。
2004年11月30日
コメント(8)
-

タイラ貝のヒモ
タイラ貝(タイラギ)は確か九州有明が特産だったと思う。有明海は水門の問題で海が死ぬ寸前になり、海苔だけでなくタイラ貝(タイラギ)の収穫も極端に落ちているという。採れても身がないそうだ。 最近ようやく水門を再び開けるという事が決まったそうだが何故こんな訳のわからない事をやるんだろうか。プンプン!! タイラ貝は寿司屋で見かける。大きな貝柱で見た目は帆立と変わらないが、食感と味はぜんぜん違う。 コリコリシャキシャキですっきりとした甘味が美味しい。 寿司屋で「貝柱」といえばタイラ貝を差すらしい。 ただ帆立が全盛の時代に高いタイラ貝は食べられているのだろうか・・・? そんな時貝が好きな人との食事があってタイラ貝を食べた。 貝殻は黒く両手を広げた位の大きさで貝柱がでかい。 寿司ネタだと薄く切られるが刺身だったので厚く切ってくれて甘味とシャキシャキを堪能した。 それ以上に美味しかったのはヒモ。 赤貝や帆立などのどのヒモよりも海の味がして爽やかで美味い。赤貝のヒモほどコリコリしておらず帆立よりしっかりしているが何よりも貝自体が大きいので貝柱も大きいがヒモも大きく長い。 山葵を少しのせ、醤油につけて口に運ぶ。濃い海の味が山葵の香りと混じりあい、シャキコリの歯ざわりが口の中で反響する。 久し振りに幸せな気分に浸った。 ダ店長さんに怒られるかもしれないがやはり新鮮な貝は美味い。
2004年11月29日
コメント(4)
-
海老の湯葉巻揚げ
そろそろ年末。家庭で開くパーティ用にちょっと贅沢をした海老料理を紹介。 海老は刺身で食べられるぐらい新鮮な海老を用意してください。細巻きか車海老、ボタン海老になると思います。甘エビは小さいので避けてください。家では細巻きか車海老でやっています。 新鮮な海老は生よりちょっと火を入れた方が甘味が増して美味しくなります。 完全に火を入れると、生の食感のプリプリが無くなってしまい勿体無いので加減に注意。 ■ 海老のミディアムレア 山葵添え ■ 殻つきのまま沸騰したお湯に30-40秒入れてすぐ氷水で冷し殻をむき水気を取って山葵で食す。 レアからメディアムレアぐらいの状態になっているので、プリプリの生の食感+茹でた甘味が味わえます。 ■ 海老の湯葉巻揚げ ■1. 海老の頭と尻尾を残して身の部分だけ殻をむきます。2. 生湯葉を海老の頭と尻尾が外に出るようにして巻いていきます。(湯葉の巻く厚さによって食感と揚げる時間が変わってきます)3. 160度位で湯葉が狐色になるまで揚げてください。 (中身は半生になるようにしてください)4. 軽くレモンを絞って山椒塩か抹茶塩で食べてください。 ※ 1本そのまま出しても半分に切ってもOKです。※ 築地の場外で活海老が150円/本~売っていたと思います。
2004年11月25日
コメント(4)
-
洋風牡蠣の土手鍋
牡蠣の美味しいシーズンがやってきている。これからもっともっと牡蠣が美味しくなってくる。 冬の牡蠣は夏の岩牡蠣と違って作り方を変えれば毎日のように食べられる優れもの。 食べ方を生→加熱の順で書いてみると1. 生食:生牡蠣、酢牡蠣、牡蠣のキムチ(?)2. 準生食:焼牡蠣、しゃぶしゃぶ(常夜鍋風に日本酒たっぷりで)3. 加熱1(和食):土手鍋、寄せ鍋、釜飯4. 加熱2(洋食):牡蠣フライ、グラタン、ピラフといろいろメニューがある。(まだまだあるよね) 古くから営んでいるレストラン「レバンテ」は牡蠣料理が有名で、有楽町の駅前にあった頃(今は国際フォーラムに移転)は冬になると良く通った。牡蠣のメニューだけで7-8種類はあったのではないだろうか? 生牡蠣は的矢産を出している。殻が塞がった状態で出されるので店の人から貝柱の在りかとナイフを使っての外し方を教わって食べた。牡蠣フライは当然としても、殻にパン粉と何かいれてオーブンで焼く「xxx尼僧院風」とか美味しく食べていた。 今は国際フォーラムに移ってしまったので足を伸ばす機会がなかなかない。 我が家で作る(といっても自分が作る)牡蠣料理を紹介。■ 洋風牡蠣の土手鍋 ■1. 西京味噌をコンソメスープと白ワインで硬めに伸ばし火にかける。2. 鍋に生クリームを足して3-4分弱火で煮立てる。 ※味のバランスは味噌を抑え目にしてください。3. 一人用の土鍋にコンソメでぬらした昆布を敷きます。4. 2の味噌スープを鍋に入れぐつぐつ煮ます。5. 鍋に牡蠣をいれ、身が膨らんだら食べ頃です。 ※ 野菜は葱等を入れてもよし、ブロッコリーにこの味噌ソースをつけて食べても旨いです。 ※ 帆立やミル貝を加えて食すと「洋風海鮮土手鍋」になりまた違った味で美味しく頂けます。※ 味のイメージは和風グラタンです。 ※ これに白ワインを加えて伸ばし、チーズを入れていくと味噌チーズフォンデュになります。
2004年11月24日
コメント(2)
-
鶏のグリル「林檎・プルーンソース」
鶏肉はモモ肉が美味しいので、そのモモ肉の美味しい食べ方を紹介。 昨夜の主菜でした。 ■ 鶏のグリル林檎・プルーンソース ■1. モモ肉塊を塩胡椒し、フライパンで両面焦げ目をつける。2. オーブンを180度に温める。3. オーブン用プレートにクッキンシートを敷いて、皮のまま輪切りにしたメークイン(じゃが芋)と林檎の薄切り、ニンニク5片(皮付き)並べオリーブ油を軽くかける。4. ローズマリーを結構多めにかけ、鶏肉を並べる。5. 鶏肉の上にもローズマリーをかけ、プルーン各2個ずつ位肉の上におく。6. オーブンで180度、35分焼く。7. その間にフライパンに刻んだプルーン、林檎を炒め、コンソメ、赤ワインをいれ煮詰める。8. バターを入れてコクを出す。9. 皿にじゃが芋、ニンニク、林檎をのせる。9. 焼きあがった肉を切り、皿に盛り、上からプルーン・林檎ソースをかけて出来上がり。※ フライパンで肉を焼く時にしっかり皮に焦げ目をつけてください。※ すった林檎や液体のプルーンでやってもソースを美味しく作れます。※ ソースには茸を加えても美味しいと思います。
2004年11月22日
コメント(6)
-
酉の市の見世物小屋
11月は酉の市。今年は26日が三の酉。 色々な神社で酉の市が開かれるが、新宿の花園神社には他所にない名物目玉がある。 それは見世物小屋。 昔は見世物をやる興行屋さんがいくつか在ったそうだが今は大寅興行ひとつしかないと言う。 最近は見に行っていないが(前を素通りするぐらい)、自分の子供にも見世物小屋の文化を教えたくて数年前には酉の市になると何回か通った。その当時はまだ興行屋が3つぐらいあって花園神社の酉の市を年交代で小屋をかけていたような気がする。 大寅興行の目玉は「蛇娘」。 他の小屋で見たのでは「河童太郎」。有名な見世物では「人間ポンプ」がある。人間ポンプの人は昔テレビにも何回か出演したが、確か2-3年前に他界した。 「河童太郎」はあの小さい小屋に本当に出没するんだから驚く。どこに水槽や水があるのか不思議なくらいだ。 でも子供は大人が笑う見世物小屋でも怖いらしい。 そりゃ未体験ゾーンなのだから仕方ない。 入り口の大きな看板からしておどろおどろしい。 昔の看板画のタッチで美女が大蛇にからまれている画や、蛇を食べている画でっかく飾れている。 ほの暗い入り口には蛇が入っている水槽に手をかけて低い声で口上を言っている毛むくじゃらの男。 けたたましいベルの音が余計に猥雑さをかき立てる。入ろうと思ってもお金の払い方が判らない。 口上で「御代は見てからの頂戴する。」と言われても幾等なのかがわからない。自分が子供の頃は「見世物小屋に子供だけで入ると連れて行かれる。」と言われていたのが余計に不気味さを感じさせていた。 蛇娘は蛇を食べたり、鼻から喉に通したり、大蛇を巻きつけたりと結構おどろおどろした部分もあるが、最後に財布のお守りと言って大蛇の脱皮あとの鱗を分けてくれているのがうれしい。 今も財布に大切に入っている。
2004年11月20日
コメント(4)
-

酉の市の食べ物
11月、東京は酉の市で各地が賑わう。今年は三の酉まであるので火事が多いらしいから気をつけよう。 自分がよく行く神社は浅草鷲神社か新宿花園神社。 あと目黒の大鳥神社、深川八幡が有名。 酉の市と聞くと稲穂、熊手、八つ頭(芋)が有名らしいのだが、八つ頭は見かけた記憶があまりない。 お酉様の屋台で売られている食べものといえば大体お祭りの露天商で売られているものとかわらないけど、冬で年末が近いということでそれなりに特長がある。 おでんや焼鳥は勿論だがよく見かけるのはべったら漬け。 あちこちで売られている。だけど卸元が同じせいか値段は一緒。あと切山椒が売られているをよく見る。 珍しいのではのしイカが売られている。 昔はあんなのしイカ製造機械を屋台で見たことがなかった。いつからなんだろう? 注文を受けると七輪でするめイカを軽く炙り、のす(伸す)為のローラーに入れてグィーングィーンさせると20秒ほどで1m近いのしイカがゆっくり出てきて出来上がる。炙ってあるので暖かく美味しい。そういえば昔、小学校の時の遠足のおやつに甘いのしイカを必ず持っていったけ・・・。 茹で豆の屋台も並んでいる。えんどう豆、大豆・・・。
2004年11月19日
コメント(4)
-
簡単ドレッシング !!
家で作るサラダのドレッシングの基本です。 フレンチドレッシングでヴィネグレットソースとも呼ばれているもので非常に簡単できて応用もききます。 一度試してみてください。■ 用意するもの ■ マスタード、塩、酢、油、胡椒■ 作り方と注意 ■1. ボウルの水っけをペーパータオルか何かで取りのぞく。2. 一つまみの塩、マスタードを入れる。(塩は酢で味が引き立つので控えめに)3. 酢を入れよく混ぜる。4. 油を少しずつ入れ攪拌していって胡椒を加え出来上がり。5. ボウルに野菜を入れよく混ぜて皿に盛ってサラダの出来上がり。※ ドレッシングは少なめでも野菜と良く合えれば美味しく出来ます。 この基本に覚えるとなんにでも応用が利きます。 例えば油をピーナツ油や胡麻油にするだけで中華風になるし、酢をバルサミコにしたりするとカルパッチョのソースになったりします。 ハーブを加えれば香りも味も引き立ってきます。■ ハーブ ■ ローストビーフ、鶏やハム等の肉系を加える時はローズマリーやタイムを入れると美味しくなります。 バジリコは何にでも合いますがさっぱり系の時が良いかと思います。■ 和風 1 ■ 塩とマスタードの代わりに柚子胡椒にして醤油を少し加えてやると和風になる。■ 和風 2 ■ マスタードを山葵、醤油にして大葉、茗荷を加えローストビーフ、茹で豚薄切りと野菜(水菜など)と合えると旨いです。■ シーフード ■ 帆立や海老などを入れたシーフードの時は少し重めにしたほうが美味しいのでマヨネーズと生クリームを加えます。マスタードは多めに。 最後にどんなサラダを作るときでもドレッシングに野菜や食材を加えた時から野菜の水が出始めますので、合えるのはテーブルに出す直前にしょましょう。
2004年11月16日
コメント(0)
-

うどんすきに「昆布つゆ白だし」
昨日は寒かったのでうどんすきにしました。 うどんは手打ちで精魂傾けうち、つゆは関西風にしたいと思ったのですが、しかしながら関西風味付け作るの面倒(自前で作っても中々味を近づけられない)なので市販のつゆを借りてアレンジしました。 使ったのは「昆布つゆ白だし」。 指定の割合(1:7)でのばし、そこに干し椎茸をいれ、コクをつけます。 2-3時間後に火をつけ沸騰させそこに追い鰹をして出来上がり。かなりの旨さになりました。 「うどんすき」なので最後にうどんを食べますからつゆは多めにつくっておきます。■ うどんすき ■食材は食べたいものを何でも入れれば良いと思いますが昨日我が家では1. 鍋につゆをはり、鶏手羽を入れる。 煮込みながら出汁を取る。2. 真鱈の切り身をいれる。暫く煮て3. 牡蠣を入れる。4. 牡蠣を食べ始める。5. 鶏手羽、鱈を食べ始める。6. 豆腐を入れる。7. 黒豚もも肉、肩ロースを入れる。8. 野菜(せり、白菜、)を入れる。こんな感じで食べていきます。仕上げは手打ちうどん。茹でたてを少しだけ(2玉分位)釜玉うどんで食べて、残りのうどんと葱、刻み油揚げを鍋に入れて少し煮立てて食べる。昨日も手打ちうどんは腰があってつるつるで美味しかったな。うどんを作った感想でポイントは、1. 捏ねは荒捏ねと本捏ねの2回に分ける。2. 足で踏む必要なまったく無いけど手で丁寧に捏ねたほうが 好い。(自分は2回の捏ねを合わせて1時間)3. 数時間寝かすと好い。4. 茹であとの水洗いがうどんを引き締めてくれる。5. 釜玉の卵は黄身だけが旨い。
2004年11月15日
コメント(4)
-

ターキー(七面鳥)味のソーダ ?!
11月、アメリカの感謝祭(Thanksgiving day)の日に必ず食べられる七面鳥=ターキー。昔アメリカが新大陸と呼ばれていた時代に必死意に働いて切り開いてくれてくれた先祖達に感謝する日を設けてターキーやとうもろこしを食べて祝っていた。日本の正月みたいに家族が集まるらしい。(http://www.americaseikatsu.net/thanksgiving.html 日本ではちょうど勤労感謝の日に当り、USAではこのサンクスギビングが終わってクリスマスになる。 日本の七五三が終わってクリスマス商戦を展開しているデパート達やハロウィンが終わってすぐにクリスマス商戦をしているスーパー(伊藤xx堂)なんかもあるが、もっと季節や祭事に気を使う気持ちを持ってて欲しい。 サンクスギビングの日に食べるローストターキーは、その家の長=男性が切り分ける慣わしだそうだ。 以前LAでサンクスギビングに招かれてある家に伺うとテーブルの上にドンとターキーが置かれていた。それ以外に料理は2-3品ぐらい。 お父さんは亡くなっていたので息子が切り始めるのだが手にした大型ナイフは電動ナイフ。 「さすがアメリカ !!」ウィーンウィーンと音をたてながらターキーを切っていく様子に思わず笑ってしまった。 彼らは良くターキーを食べる。ファーストフードのメニューにものっている。ハムもあるし、冷凍の塊もスーパーで売っている。どうやらターキーは脂肪分が少なくダイエットに良いという理由だけではないらしい。 昔は食べるものがなく、野生のターキーを捕まえてはお祝いの時に食べていたらしい。その遺伝子が伝わっているのではないだろうか? だから11月の感謝祭にターキー=七面鳥。 12月のクリスマスにターキー=七面鳥。 春4月のイースターにターキー七面鳥。 大きい祭事には必ず出てくるターキー。 ある日、友人が、 「君らアメリカ人は感謝祭にターキー、クリスマスにターキー、イースターにターキーって何かというとターキーを食べるけど何か理由があるのかい?」 と聞くと、答えはシンプルに 「他に食べるものがないんだよ。」だった。 昔から引き継がれている食べ物といえばカボチャ、とうもろこし、ターキーだというのが歴史のないアメリカらしい。 そういえばハロウィンはカボチャだったな。 そんなターキーの味はと言えば「ボソボソの肉」というのが自分の感想。 ダイエットに良いといっても油で揚げてれば変わらないし、量を食べれば同じだよね。 面白い記事がのっていて、アメリカでターキーを食べる風習が少なくなってきたのに注目した清涼飲料メーカーのジョーンズ・ソーダ社は、感謝祭を何とかしたいと思い去年発売したのが「肉汁ソースかけ七面鳥風味ソーダ」。 これが爆発的にヒットしてインターネットオークションで$100の値がついたらしい。 で今年も発売するとのこと。 今年はターキーの他に付け合せやデザート味のソーダも販売するそうでセット価格で$16だそうだ。 セット内容は、「サヤインゲンのキャセロール味」「マッシュドポテト味」「フルーツケーキ味」「クランベリー味」に「肉汁ソースかけ七面鳥風味ソーダ」。 ) さすがアメリカらしいやね。誰か買って送ってくれ~!! 飲みてえ~!! ちなみにターキーってトルコですよね。七面鳥をターキーって言いはじめたのは、ヨーロッパにほろほろ鳥を持ち込んだのがトルコ人でほろほろ鳥をターキーコックと言って七面鳥と混同していたのが始まりだそうだ。
2004年11月12日
コメント(9)
-
アゴ=飛魚
ここ2週間で飛魚=アゴを何回か口にした。 生では刺身、塩焼き。干物だとくさや、丸干し。加工品になれば野焼き。焼アゴを使っての吸い物・・・。 飛魚は加工も結構されている。 ネットで調べたら飛魚の運動量は他の魚よりかなり多いため脂が少なく淡白な味と書いてあった。 そりゃそうだろう。 あんなに海の上を飛んでばっかしいるんだから。最高300m以上飛ぶという。といっても実際にはまだ見たことがない。 先日食べた飛魚の刺身は伊豆大島産。大きさは30cm位でかなり大きい。 ネットで書かれている通り味は淡白で青魚特有の臭みはない。青魚特有の脂臭さがないのがちょっと残念。鯵、鰯、秋刀魚みたいな脂ののりも全くない。生姜醤油で食べると生姜が勝ってしまう。 ちょっと拍子抜けといったところが正直なところ。 伊豆七島のくさやといえば鯵、それもムロ鯵が有名だが飛魚のくさやも負けてはいない。飛魚のほうが鯵より硬めでむしろ噛み応えがある。 先週食べたのはアゴ=飛魚の丸干。 出汁用の焼アゴは小さいし、食用の丸干といっても12-3cm位しかないが、食べたのは20cm位の大きなもの。 干物にすると淡白な味が逆に功を奏して臭味がなく噛むほどに旨みが広がってくる。これは鰯などにはない味わい。 その上、ワタの部分が甘くて美味しい。 普通苦いと感じるワタが甘いとこれは旨みに繋がり、焼酎が進む。 店の人曰く 「東京に普通入ってくるのは小さいアゴで美味しくない。だから実家の長崎から直接送ってもらっている。」とのこと。 イヤー美味いものを堪能するにはみんな苦労しているんだあ・・・。 大分前に、「アゴの野焼き」を食べた。当時アゴが飛魚と言うことは知っていたが「アゴの野焼き」は知らず、きっと飛魚を藁か何かで焼いたものを軽く干したのだろうって勝手に解釈していて、手にした時に驚いた。 「でっかい?! 」 口にいれてまた驚いた。 「普通のかまぼこじゃない?!」
2004年11月11日
コメント(4)
-
上海蟹が食べたい !!
もうすぐ秋が終わりる。秋の味覚をあまり楽しめなかったうちに冬が近づいて来ているので早くしないと・・・。 楽しめなかったものに松茸がある。今年はコンビニの松茸弁当を食べたぐらいで土瓶蒸しも焼き松茸も食べなかった。 鱧と松茸の食い合わせもしなかった。 そういえばお店で水炊きを食べる時に店員から「松茸入れますか?」と言われて、欲しくて頼もうとしたら「要らない。」と上の人間に言われ諦めたっけ。 秋刀魚、栗、葡萄、梨、天然舞茸は食べたと。モンブランもSワイル(本郷に新装開店)のを食べた。柿、ラフランスはこれから食べる。 松茸だけが気にかかるが仕方ない。 そうなると秋と冬の間の食べ物「上海蟹」は絶対食べなくては・・・。 上海蟹は味もさることながら香りが良い。雌と雄では味も香りも違う。どう違うかって昨年の事で忘れているので今年食べた時に改めて報告します。 去年、カミサンを連れて食べに出かけたがカミサンは毛蟹のほうが好きだと言う。全然別物なのになあ・・・。 雌蟹の老酒漬け:卵の甘味と肝臓(?)の甘味がなんとも言えない。 蒸し蟹:雌と雄とでは何で違うのだろう?どちらも美味しい。 自分は老酒漬、雄雌それぞれの蒸し蟹を食べればスープや炒め物はなくても平気。 ああ早く上海蟹を食べたい!! 誰か誘ってくれ~っ!!
2004年11月09日
コメント(8)
-
ソースの二度づけ禁止 !!
関西風の串揚げ屋さんは東京には少ない(と思う)。 きちんとした(座って食べさせる)店では「○の坊」が有名で都内各地にあるし、京都風と言えば銀座に「柊」がある。 わが亀戸でも2軒あるが立ち食いで串揚げを食べさせる店は少ないのではないだろうか? 立ち食い串揚げ屋は北千住にある店しか知らなかったが、3年位前に神田のガード下にも立ち食いを見つけた。1階が立ち食いで2階がテーブルのやや変則だが、他に東京で立ち食いはあるのだろうか? そうだ浅草に新しい(?)立ち食いの串揚やが出来ていた。馬車道通り横の道で、構えからするとまだ新しい感じがした。前を通っただけなので入った事はまだない。 関西の立ち食い串揚げを現地で食べたことがないので北千住の店「天七」(この店は20年位前から通っている)の話をしてみたい。 店は大きくカウンターがコの字型になっていて、揚げ場はコの字の中央にひとつあるだけ。カウンターには3-40人位入れる。 空いている時は正面を向いて食べているが混んで来ると斜めになり人が多く入れるようにする。 カウンターにはステンレスの箱にソースの入ったものとザク切りのキャベツ(無料で食べ放題)が入ったものが置かれており、上に「ソースの二度づけ禁止」の張り紙がある。 キャベツでも揚げ物のでもソースには一回しかつけてはいけないのだ。一度口に入れ噛んだものを何回も共有のソースにつけては衛生上問題があるために禁止されている。 昔は1串80円からあったので生ビール大2杯、串を結構食べても1500円あればお腹いっぱいになった。 確か値段は串の長さによって決まっていたと思う。鳥のチューリップ揚げの時は空(から)の串が皿に置かれたと思う。 今は多少値上がりしているがまだまだ安い。 ただ、注文が1種類2串からなので、種類を食べたい時は友人なり連れを誘わなければすぐにお腹いっぱいになってしまう。(すし屋と一緒だがなんとか1個ずつ頼めないだろうか?) 先日ネットで調べたらこの店も支店を出したらしい。そこは客の要望が多かったのか椅子に腰掛けて食べられるとのこと。 昨日久し振りに「串揚げを食べに行こう。」と家族を誘ったらカミサン以外「北千住の串揚げ!?」と声を揃えた。「イや、亀戸だよ。」と答えると「え~っ、北千住が良いなあ。」と不満げ。 大人に混じって立って好きなものを頼む雰囲気が好きらしい。 こいつら将来親ににて飲べえになるなあ・・・。続く
2004年11月08日
コメント(6)
-
昨夜のご飯
豚の日記を書いたら豚を食べたくなってしまい厚切り豚を食べさせる店へ行ってしまいました。 昨日食べて飲んだもの。1. ビール:エーデルピルスナー2. 短角牛のタルタルステーキ3. 白ワイン:シャルドネ4. 前菜盛合せ:芽キャベツフリット、豚パテ、秋刀魚燻製、生ハムイチジク他5. 赤ワイン:xxx種 コクがあって甘いベリー系の味。美味しい。6. フォアグラ洋ナシ添え7. 無菌豚のグリル8. カルバトス9. デザート:梨、林檎シャーベット食べ過ぎたあ~。深酒しすぎたあ~。
2004年11月06日
コメント(7)
-
豚は厚く切って焼け!!
豚肉の美味しいのは本当に旨い。脂が甘くて美味しい。脂を嫌がる人がいるけど、脂身が身体に良くないのは牛。 豚の脂身はビタミンがいっぱい含まれている。 問題は美味しい豚をどうやって食べると旨いかだ。 焼く時に大切なのは肉の厚さだ。 精肉店やスーパーでも肉はパックに入っており既に切り身になっている。 豚カツ、ステーキだと1cm前後の厚みだろうか。生姜焼きなどは薄切りになっている。 煮物用としてブロックでバラや肩ロースが売っている。 でもロースのブロックは売っていない。しかしロースは厚切りが絶対に旨い。 切り身3枚分の3cm以上だと肉の旨み、ジューシーさを十分に味わえる。 焼くのは中まで火を通すのに注意を払って焼く必要があるが、周りに焼き色をつけてあとはオーブントースターでアルミをのせながら焼くか、オーブンで焼けば中まで火が通る。 問題はどうやって入手するかだけどお店の人に「厚く3-4cm位のを切ってください。」って頼めば喜んでやってくれるよ。以前にも書きましたが、3-4cm位の豚肉の両面に焼き色をつけてからじゃが芋、ニンニクを敷いたプレートに肉をのせ、ローズマリーを3-4本のせて1時間ぐらい焼くと旨いローストポークができる。じゃが芋はニンニクと豚の油を吸って美味しいポテトに変身している。 先日、よく行く飲み屋で「もち豚のグリル」を通常の2.5倍の厚さで焼いてもらったら噛み応えとジューシーさが全く違いました。 後日談: この日記を書いていて豚を食べたくなってしまい厚切り豚を食べさせる店へ行ってしまいました。 そこで豚以外のものも頼んだので豚を半分にしてくれないか?と頼んだところ 「厚さを半分にしてしまうとジューシーさがなくなって美味しくないですよ。」と怒られてしまった。 自分は厚さはそのままにして半分と思ったのですが、考えてみると残り半分を頼む人はいないですね。
2004年11月05日
コメント(4)
-

美味しいみかん見つけたよ!!
冬の蜜柑といえば1-2箱の箱買いをして、一度に蜜柑を15.6個入れたかごをコタツの上にドンッとのせ、腰までコタツにつかりながら指の爪が黄色くなるまで蜜柑を食べていたのはいつの頃までだろう? 最近は蜜柑の出る時期が早くなったのだろうか? 我が家では先月からテーブルの上で見かけるようになった。 やさしい甘酸っぱさはオレンジともネーブルとも違う蜜柑独特の甘さ。 そんな蜜柑を当たりはずれがなく毎回美味しいみかんを買うことができないだろうか? 最近感じていることは「美味しいものは信用出来るところで買う」こと。 お店でも、スーパーでも確実に美味しいものを提供してくれているという信用があれば良いのだけれど、今のスーパーなどで安さや手軽さはあっても「美味しさの信用」はしていない。 一番信用できる人は美味しい蜜柑を作っている生産者と知り合うこと。 最近果物を通販とか産直で買うことが増えてきた。輸送料がかかるから割高なんだけど「美味しい果物」を食べる喜びには勝てない。 冬の沖縄のたんかん、たんかんジュース、マンゴー、桃(これは今年)、生雲丹、塩雲丹みんな通販だ。 枇杷、西瓜、骨付きハム、岩牡蠣、シラスなどは直接生産者へ出向き買っていた。 昨日届いた蜜柑も産直で頼んだが初めての注文だったので心配したが成功したみたい。 カミサン曰く 「美味しい蜜柑って皮が薄いのよね。」熊本不知火の山川さんの甘早生みかん。ここのみかんは小粒ですが優しい甘さが口中に広がり幸せにさせてくれます。 良く考えてみると一品一品自分で確かめなくてはいけない時代になったのだろうか? それとも直接買うショッピングの楽しさなのだろうか? 楽しさでやっている分には良いけれど、激安とディスカウントの量販に犯されている自分が反対側にいるのも事実。
2004年11月04日
コメント(0)
-

大笑い !! きなこもちチョコ
きなこ餅が美味しい!! チロルチョコの商品「きなこもち」美味しい。 大笑いするほど美味しい。 チョコレートなのにチョコレートの味がしない。今までのチロルチョコってフレーバーやジャムが入っていてチョコレートと判るのにこれは判らない。 きな粉色のチョコレートには当然きな粉が含まれていると思う。 その中心部に平べったくもち粉を使ったお餅グミが入っている。グミというより餅の感触。しかもそのグミの周りを黄な粉が覆っている。 口に入れると 「うん? 黄色いチョコか・・・。あまりチョコレートの感じがしないなあ。」 食べ進んでいくと中のお餅グミに遭遇する。 「あれ、お餅だ・・・。えっ!? 黄な粉がいっぱい。」 「あれれ!? 黄な粉餅だよこれ!!」と言う風に進んでいき、チョコレートを食べているつもりがいつのまにか「黄な粉餅」そのものを食べている錯覚に陥って笑ってしまう。 久々のチロルチョコのヒットだと思います。 チロルチョコのHPはこちら↓http://www.tirol-choco.com/info.html去年のチロルチョコのヒットは「抹茶あずき」だったと思います。
2004年11月02日
コメント(4)
-
鮫の心臓(ハツ)
人は食べる事に貪欲である。食べる事に執着し続けている。だから動物の中で大きな勢力を保っていられるのだろうか? その貪欲さの中に「珍味」というものがある。 珍しい食べ物。 要はあまり人が食べないものだけど食べたら不思議な味で美味しかったよ。と言う事だと思う。 人間は口に入るものは何でも食べようとするのだから生きる執着はそうとう強いのだろう。 別の見方をすれば本来捨てられてしまう物や見向きもされない物を手を変えて食べられるようにするということだから、リサイクルや、環境を考えていると言えなくもない。 例えば蚕のさなぎ。絹糸の採取として蚕からさなぎにさせられ、絹糸でくるまれたまま茹でられ糸を取られていく。 用を終え残されたさなぎ。そのさなぎを捨てないで味をつけて食べる地方があるという。 その行為は余すなく使うと言う精神でフカヒレ採りよっぽど良い。 高級食材のフカヒレは、採る為に背ビレだけ鮫から切り取ってそまま海に放すという。背ビレをなくした鮫は再びヒレは生えてこないのだから生き続けられるのだろうか? ここまで書いたのも先日鮫の心臓の刺身を食べたからだ。 鮫と聞いてアンモニア臭くないだろうかと一瞬躊躇したが、そう滅多に口に出来るものではないので、トライをした。 内臓の心臓、肝臓といえば牛や豚、鶏などが多く、白子や卵巣と言えば海の魚たちが多いような時に、鮫の心臓の刺身を食べるとは思わなかった。 色は赤銅色。牛や豚のレバーと全く同じ色。味は動物系の臭みは全くなく、馬の心臓(ハツ)のようにさっぱりしている。 しかしハツの持つコリコリ感はなくレバーのようなしっとりとした軟らかさの内臓だ。 生姜醤油で食べたが多分言われなければ誰もこれが鮫の心臓だとは思わないだろう。 普通のさっぱりとしたレバー刺しですね。 多分 「あ、このレバー刺し、臭くな~い。」って感じでしょうか?
2004年11月01日
コメント(6)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- スイーツ♪スイーツ♪
- 数量限定♪2025冬季 ARABIA ムーミン …
- (2025-11-25 09:32:29)
-
-
-

- 簡単レシピ
- いつもの卵焼きに「ちょい足し」アレ…
- (2025-11-22 17:00:05)
-
-
-

- 変なおっちゃんの食事とその日の体調
- 良品#018
- (2023-04-20 09:54:01)
-