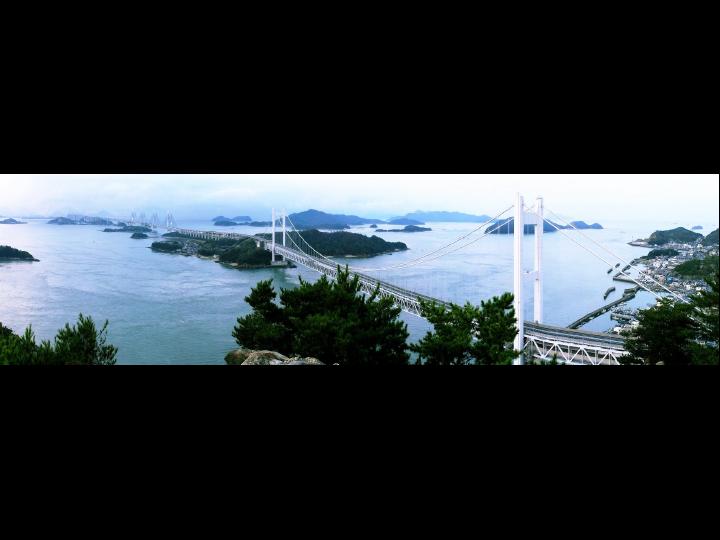PR
フリーページ
小説 堀河の局
戯曲 貞心尼の花 ・・・芸文館公演

貞心尼の動画 テレビ放映
戯曲 天野の里の露
小説 天使の赤褌 1

小説 天使の赤褌 2
大風呂敷の中の小石 毎日新聞連載
童話 ハッパ文文

児童文学 俺は天使か 1

児童文学 俺は天使か 2

児童文学 鬼の反乱 1

児童文学 鬼の反乱 2

児童文学 鬼の反乱 3
yuuの紹介

友に出した手紙

公演は倉敷演劇研究会、劇団滑稽座のもの

公演の後始末
滑稽座新聞
随筆 一週間の闘病生活
童話 星の光

見上げてごらん夜の星をの劇中詩
戯曲 紫しだれ櫻・・・芸文館公演

小説 紫枝垂れ櫻

朗読劇 麻生アヤ女史による。テレビ放映
戯曲 不覚文覚荒法師・・・芸文館公演

有線テレビで放映
戯曲 花時雨西行・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「花時雨西行」「紫しだれ桜」「堀河の局」
戯曲 小町うたびと六歌仙(連載中)

「小町」創作ノート
小説 となり

となり 続編 遠いい声

逢澤雄吉の幸福な災難

となり 続編 鳴き声 執筆中
月に吠える少年・市民会館大ホール公演

倉敷水島文化センターで公演

倉敷玉島文化センターで公演

倉敷本町公民館で公演
戯曲 花筵・・・芸文館公演

戯曲 花ござの里・目黒公会堂公演

新 「花筵」 国文祭芸文館公演

岡山市山陽町会館で公演

倉敷公民館大ホール公演

創作秘話 「花筵」
小説 遠いい声
小説 くらしき草子

朗読劇として 芸文館公演

倉敷公民館大ホール公演
戯曲 桜散るとき・・・
児童劇 さざんがく・・・芸文館公演

倉敷水島サロンにて公演
戯曲 西行のゆくへ(連載中)
戯曲 となり・・・芸文館公演
戯曲 風博士・・・和楽座公演

坂口安吾の「風博士」脚色して公演
小説 『今拓く華』 海の華 (1)

海の華 (2)
小説 冬の華
小説 春の華
小説 夏の華
小説 秋の華
小説 『今拓く路』 冬の路

小説 春の路

小説 夏の路

小説 秋の路
小説 『今拓く空』 冬の空 1

小説 冬の空 2

小説 冬の空 3

小説 春の空 1

小説 春の空 2

小説 春の空 3

小説 春の空 4

小説 春の空 5

小説 夏の空 1

小説 夏の空 2

小説 秋の空 1

「今拓く華と路と空」のあとがきとして…。

今拓く華と路と空と風 1

今拓く華と路と空と風 2

今拓く華と路と空と風 3

今拓く華と路と空と風 4

今拓く華と路と空と風 5

今拓く華と路と空と風6

今拓く華と路と空と風7

今拓く華と路と空と風8

今拓く華と路と空と風9

今拓く華と路と空と風10 執筆中
時代小説 倉子城物語朗読劇芸文館公演

味噌蔵

格子戸

中橋

藺草

太鼓橋

群雀

滑子壁

夕凪

銀杏

通り雨 1

通り雨 2

通り雨 3

冷や飯

藤戸饅頭

波倉

常夜石灯

今橋

創作秘話 「倉子城草紙」として出版のあとがき
小説 めぐり来るときに(新連載開始)
一人芝居 花時雨西行・・・芸文館公演

和楽座公演
yuu独り言

あの頃の、チャップリンの「独裁者」の言葉に心震わせて
yuuの創作メモ2も合わせて読んでください

作家が小説作法を書くと終わっている事、2
小説 九太郎がいく・・・

小説 九太郎がいく 2
劇団劇団滑稽座公演写真
yuuの仕事部屋(ヤフーHP)

劇空間 劇団滑稽座

yuuの環境問題

yuuの夢物語
小説 瀬戸の夕立

この小説は入選する 立石孫一郎伝

創作秘話 「瀬戸の夕立」立石孫一郎伝
戯曲 天領倉敷代官所炎上・・・芸文館公演

天領倉敷代官所炎上の動画

有線テレビで放映
戯曲 あの瞳の輝き永遠に・・・芸文館公演

シナリオあの瞳の輝き永遠に

児童劇 手のひらに太陽を・・・芸文館公演

あの瞳の輝きとわに 冊子として出版

倉敷市民会館大ホールにて2回再公演

母の女教師の会 岡山市大元小学校公演

あの瞳の輝きとわに、は三部作です。

有線テレビで放映

創作秘話「あの瞳の輝きとわに」
戯曲 ふたたび瞳の輝きは・・・芸文館公演

ふたたび瞳の輝きはの動画

この作品は「あの瞳の輝きとわに」の第二部

有線テレビで放映

創作秘話 「ふたたび瞳の輝きは」
戯曲 三太郎の記紀・・・芸文館公演

新 三太郎の記紀・・・芸文館公演

倉敷公民館大ホール公演

有線テレビで放映

創作秘話 「三太郎の記紀」
戯曲 心に華を草枕・・・芸文館公演

倉敷市民会館公演3回

倉敷水島文化センター公演

なぜ私が「瞽女さ」に魅かれ書いたのか…。

有線テレビで放映
戯曲 見上げてごらん夜の星を・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「見上げてごらん夜の星を」
戯曲 上を向いて歩こう・・・芸文館公演

旧 上を向いて歩こう

有線テレビで放映

創作秘話 「上を向いて歩こう」
戯曲 更け待ち藤戸・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「更け待ち藤戸」
小説 一合半庵異聞・・・芸文館公演

玉野市公民館公演
小説 冬の流れ 連載中
小説 子作り戦争
戯曲 現代水軍伝・・・芸文館公演

有線テレビで放映

創作秘話 「現代水軍伝」
異聞良寛乾いて候可・・・芸文館2回公演

良寛乾いて候可の動画

有線テレビで放映

創作秘話 「良寛乾いて候可」
一人芝居 堀河西山庵草紙
戯曲 汐入川
戯曲 倉敷物語
青年劇 干潮(ひきしお)・目黒公会堂公演

干潮 この作品は「倉子城草紙」にて出版

倉敷市市民会館大ホールで公演

総社市民会館で公演

倉敷水島文化センターで公演

この作品で脚本賞を頂く。

創作秘話 「干潮 祭りの夜」
青年劇 秋桜・・・公民館公演

倉敷水島文化センターで公演

岡山県久米南町で公演

和楽座公演
戯曲 天使達のララバイ 連載中
小説 冬蛾 連載中
小説 十七歳の海の華・・・1

小説 十七歳の海の華・・・2

創作秘話 「17歳の 海の華」
小説 待賢門院堀河
随筆 風立つ頃に 1

随筆 風立つ頃に 2
戯曲 海へ帰る・・・公民館公演

和楽座公演

倉敷公民館大ホール公演
戯曲 巡りくる春のために・目黒公会堂公演

岡山県矢掛福祉会館で公演
随筆 記憶の薄れいく中で
随筆 風の路 1

随筆 風の路 2

随筆 風の路 3

随筆 風の路 4

随筆 風の路 5

随筆 風の路 6

随筆 風の路 7

文化の意味を問う
戯曲 入れ歯のできる日まで 港区福祉会館

入歯の出来る日まで 冊子として出版

倉敷市公民館で公演
おはなし 星に願いを 1

星に願いを 2

星に願いを 3

星に願いを 4

星に願いを 5

この作品は 倉子城草紙に収録
戯曲 はちすの露1 倉敷市芸文館公演25年

戯曲 はちすの露 2

戯曲 はちすの露 3
あしあとひとつあしおとふたつ 芸文館公演

あしあとひとつあしおとふたつ 2

創作秘話 あしあとひとつ あしおとふたつ
小説 水島灘物語 連載中
小説 冬蛾 連載中 1
立石孫一郎についての考察

立石孫一郎についての考察 2
三っの石橋架かる町 冊子として出版

倉敷市民会館大ホールにて公演。

倉敷本町公民館にて公演
偉大な愚か人達 冊子として出版

この作品は 東京都町田会館にて公演

新見市民会館にて公演

倉敷本町公民館にて公演
ここに書いている小説は雑誌に掲載
波倉の町 倉敷市民会館大ホール公演

冊子として出版

戯曲 波倉の町 連載開始
蔵のある町 倉敷市民会館大ホール公演
戯曲 あの瞳に支えられ桜散る時・・・

この作品は「あの瞳の輝きとわに」の第三部
倉子城物語 波倉の村から 連載中
恨の藤戸は流れ星 倉敷公民館ホール公演
瀬戸の花嫁恋愛論 青年祭岡山福祉会館公演
戯曲 老いの桜
小説 蓮の露 1

小説 蓮の露 破 執筆中
劇団滑稽座 公演記録
作品の発表 公演は年代の順ではありません
会話小説 雨の夜の男と女 連載中
随筆 今思う明日 1

随筆 今思う明日 2

随筆 今思う明日 3

随筆 今思う明日 4
フェイスブックのコメント 1

フェイスブックのコメント 2

フェイスブックのコメント 3

フェイスブックのコメント 4

フェイスブックのコメント 5

フェイスブックのコメント 6
一人芝居 武蔵五輪書巌流島 執筆中
喜劇 平成縄文時代 執筆開始
勝新さんを忍んで 座頭市の旅の終わりに
推理小説 倉敷小町殺人事件 執筆中
小説 立石孫一郎 (現在の目で書く) 開始
吉馴悠と今田東の創作のあゆみ
小説 海の漁火
小説 母の痣1 新連載
小説 風化 書き始めます
文学を精神の主軸にする愚かしさ…。我が人生を振り返って…。つづく
戯曲 銀杏繁れる木の下で

戯曲 「銀杏繁れる木の下で」を書いた後の心残り
小説 惜春鳥 連載開始
小説 秋冬
篠田正浩監督作品に参加して 体験記
私と出会った温かい人たち 連載開始
勝新太郎さんと日本映画を振り替える…
昨日、不思議な夢を見た…。1-40

昨日、不思議な夢を見た…。41
小説 麗老
小説 銀杏繁れる木の下で
小説 砂漠の燈台 1

小説 砂漠の燈台 2

小説 砂漠の燈台 3

小説 砂漠の燈台 4
いつか何処かで・・・。1-28

いつか何処かで・・・。29
明日は今日より素晴らしい・・・。1

いつか何処かで…。 30
倉敷は空に雲がかかり晴れない一日であった。
風もなくよどんでいた。工場の煙突からいつもより多くの煤煙が吹きあげられていた。書いていると雨の足音がだんだんと激しくなっている。
今日は少し良寛さんのことを書いてみたいと思う。
良寛は出雲崎の大庄屋、橘屋の跡取り息子山本栄蔵として生まれた。平らに時が過ぎていれば山本栄蔵として何不自由もなく人生を全うしていたことだろう。
だが、ひとの定めとは時に悪戯をする。父親の左門泰雄は商いに向いてなく五七五に魅せられ惹かれ以南と号を持つ程の歌うたい。だんだんとお日様が当たらなくなって家督を栄蔵に譲ってしまった。
栄蔵は十七歳で庄屋見習いになった。
代官所と村人の仲を取り持ち、佐渡の金山から送られてくる金を荷揚げすることになる。
その頃、飢饉が続き百姓一揆が起こりその斬首に立ち会い胃のなかのものを吐き卒倒した。栄蔵は名主の重圧を受け止めることができなかった。栄蔵は女に酒にと溺れる日々が多くなって行った。そして、何もかも放りだして光照寺へと逃げ込んだのであった。
そこで寺男のような生活をしてのんびりと本ばかり読んで暮した。
以南はそんな栄蔵に見切りをつけて弟の由之が後を継いだ。
実家から仕送りを受けながら四年間過ごしたことになる。
二十二歳のときに大忍國仙和尚が越後に来られ得度し剃髪をして仏門に入った。
國仙和尚は栄蔵の顔をじっと見て「大愚良寛」と名付けられた。
良寛は國仙和尚に連れられて備中玉島の円通寺にやってきて、そこで十三年間修業をすることになった。
良寛はその修業の中で縋るように仏の道を修めた。が、知れば知るほど、縋ればすがるほど身を縛られる事を感じた。
良寛は円通寺の庭に出て遠く瀬戸の海を眺めることが多くなっていった。小波に操られながら漁をする舟を眺めながら人間の道もまだ同じなのだと思った。
同輩の仙桂が田地を耕して作物を育て汗をかいているのを見ても何も感じなかった。道元の教えの「只管多坐」のなかには「一日作さざれば一日喰わず」という教えがあるがその言葉の真意を理解しようとせず、経典の中に救いを求め生き死にの導きに縋ろうとしていた。
そんな日々の中に良寛はいてもなにもすることなく日向ぼっこをしながら内海の波が返すまたたきを見つめるだけだった。この当時にはうたの心も持ち合わせてはいなかった。
そんな日々で良寛の心に芽生えたのは虚無であったのか、師の國仙和尚が示寂された後良寛は円通じをさった。手には國仙和尚から下された「印可の下」、どこの寺の和尚になってもいいと言うお許しの言葉が書きつけられたものを持っていた。
良寛のそこ後の足取りは良寛しか知らない。
この数年間の行方は分からない。その後に国上の五合庵、乙子神社の境内で30年間ほど暮らすことになる。
俗説に良寛は子供たちと毬遊びをし、商家の屋号を書いたり、祝いの言葉を書いたりして、酒台を貰っていたというのがある。高名な寺の住職にと声がかかったというがこれは怪しい。良寛は越後に帰って自由に生きていたので声がかかるとは思えない。
「愛語,戒語」書いているがそれは若かったころのものとして笑っていた。
人に戒めなどいらないというのが良寛の精神であった。むしろ戒律の中で生きる方が楽なことは知ってそれを否定している。
自由に生きることは自分を律しなくてはならないからこれは苦行である。それをなぜ選んだのか、生き方の上で考えるという事を彼は望んだ。教えられて学ぶのではなく、自分で考えて学ぶ事の大切さを、「何事も教えられて学んではならない、自分で作るのじゃ」と良寛は語っている。
70歳のころ30歳の貞心尼と巡り合う、この出会いは良寛を人間として完成させることになる。
今までのすべてを棄て、なくなる4年間に良寛の心に芽生えたものは老いらくの恋であった。
「貞心さん、この世は総て夢、夢に生き、夢に遊び、この良寛、貴方のお陰で好い夢が見られた」
形見とてむ何か残さむ春の花
夏ほととぎす秋は紅葉 ( 良寛 )
生き死にの界はなれて住む身にも
避けぬ別れのあるぞかなしい ( 貞心 )
生きることは自らが作る、道を開くのだという事を私は感じた…。
カレンダー
 New!
ひじゅにさん
New!
ひじゅにさん「冬用タイヤに交換…
 New!
ツヨシ8さん
New!
ツヨシ8さん今日のバラ~クード…
 New!
萌芽月さん
New!
萌芽月さんあいち県民の日 New! ありんこbatanさん
2025年のコスモス行… リュウちゃん6796さん
散歩で出会ったお花…
 蘭ちゃん1026さん
蘭ちゃん1026さんウクライナ、東部要… 徒然2020さん
このページは「k.t15… k.t1579さん
山口小夜の不思議遊戯 小夜子姉貴さん
春夏秋冬 きままな… お局ちゃんさん
コメント新着
キーワードサーチ
・2025年10月
・2025年09月
・2025年07月
カテゴリ