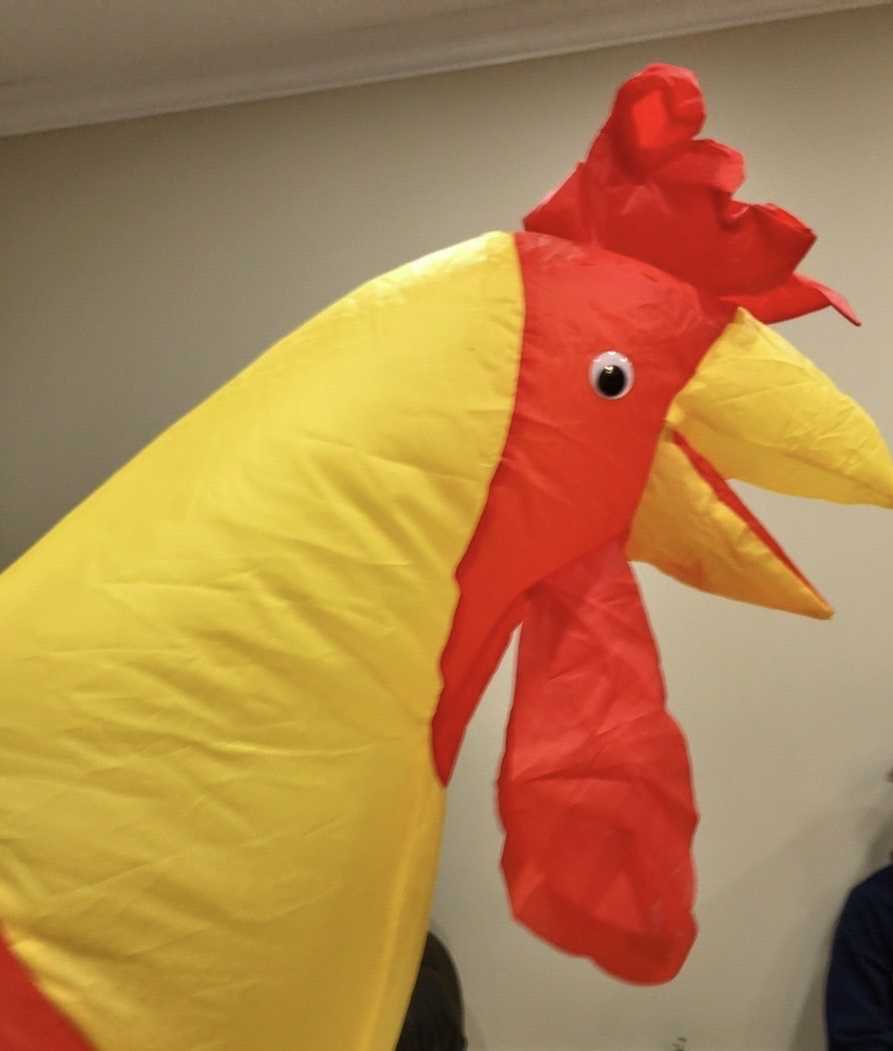2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2016年04月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

STOP!『競争・テスト漬け』に思う
昨日、大阪教育文化センターの第26回共同研究集会に、縁があって参加させていただきました。まずは、連休初めの日に、こどもたちの教育のために集まった方々と、本研究集会を準備・運営された方々にたいしまして、ここに心からの敬意と感謝を表明させていただきます。 当日は、その後に予定があり、感想文は提出できませんでしたので、簡単に記しておきます。パネリストやフロア発言など、貴重なお話を拝聴して、ほんとうにためになり感謝しているのですが、ただ参加者が、現役および退職の教職員、教育研究者、教職員組合幹部などがほとんどで、私のような一市民や保護者の参加がほとんどなかったのが、集会内容が良いだけに非常に残念でした。 このことが、当集会参加者の献身的なご努力・ご奮闘にも拘わらず、少なくとも大阪では、「競争・テスト漬け」の状態が大きくは改善していないことに表れているのではないでしょうか。当然ながら、そのことにより、いまだ多くのこどもたちが「競争・テスト漬け」の犠牲を強いられております。もちろん、この「競争・テスト漬け」をSTOPさせることは、現状では直ぐにでも解決できる課題ではないでしょう。 だから、報告・発言にもありましたように、そうした現状でも、こどもたちに寄り添って手を差し伸べる活動が必要ですし、その活動も広がりつつあります。しかし、まだ極めて不十分なのが現状だと思います。それは、こうした活動が、気付いた一部の教職員のみなさん方中心の活動になっているからではないでしょうか。たとえ、その活動が全教職員に広がったとしても、おそらくこどもたちはその数では圧倒しているので、やはり難しい課題です。 「競争・テスト漬け」STOPを実現するには、せめてこどもたちの保護者の、この活動への広範な参加が必要だと思います。そして、保護者だけでなく、広範な市民・国民の運動として発展すれば、「競争・テスト漬け」はSTOPさせることができるでしょう。そのためにも、本研究集会が、教職員・研究者中心から、ひろく市民が参加する研究集会へと進化することを期待するものです。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.30
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/10
長方形の紙(チラシなど)で折る雛 来月は「ひなまつり」、その時に活用していただきたい、「折り雛」を紹介します。チラシやノートなどの長方形の紙で作る立体的な「お雛様」です。 この折り方は伝承的な折り方で、私がこどもの頃(1950年代)に覚えたものです。比較的簡単に折れますので、お試し下さい。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2006-02-09)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.30
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/9
ある小さな作品展から 今日、2ヶ月に一度、ユニット折り紙を教えに行っている女性団体の作品展があった。と言っても、個人宅で開かれたもので、画像はそのユニット折り紙作品だが、他にも刺繍・ビーズ細工・油絵など様々なジャンルの作品が展示されていた。 この女性のサークル的活動は40年以上の歴史があるそうだが、全般的にこの様な文化活動は、女性の方が活発なように思われる。最近では、熟年の男性のピアノや絵画などの余暇や趣味の活動も増えてきているようだが、まだ女性の活発さには及ばないようだ。 こうした趣味の創造的活動は、脳を活性化しストレスをも軽減すると言われているが、平均的な寿命の長さでは女性に及ばない男性のみなさんも、もっと旺盛にこうした活動をして欲しいし、私もまたそうしていきたいと思っている。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2005-11-23)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.29
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/8
折り鶴と原爆忌(8月9日/長崎):本日の一句鶴折る子 見て胸ジンと 長崎忌 風ほうせん 一折り一折りに平和の願い込めて折り鶴を折り、慰霊碑に捧げる折り鶴。もはや日本の素晴らしい伝統ともなった平和の折り鶴をこども達が折っている。 このこども達の為に平和をつくり守るのは、おとなの役目なのだと、自分に言い聞かせる。早く、核兵器廃絶記念の折り鶴が折れるその日が来る事を願い、私もまた折り鶴を折る。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2005-08-09)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.28
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/7
折り紙と物理学:より大きく、より小さく 普通に折り紙を折っていれば、この地球の大自然の原理を感じ認識することなく時を過ごす。だが、極めて大きな作品や極めて小さな作品を折ろうとすると。この大自然の原理が大きく姿を現す。 例えば、ユニット折り紙をやっていて、普通は多くて数十枚(ユニット)程度の作品を作っている。しかし、ユニット数が100を越えるようになると、状況ががらっと変わってくる。 それは、何と地球の重力がその偉大な力をあらわすのだ。普通の大きさ(15cm角)と厚さの折り紙で、100ユニットを越える作品を組み上げてみると、何と!あの軽い紙の重さがものを言うようになり、形が歪んでくるのだ。 宇宙空間にあるスペースシャトル内の無重力の下では、何百ユニットの作品も形はまったく歪まない。地上で形が歪むのは、まさに、紙に地球の重力が働くたまものだ。この紙と地球の取り合わせが面白い現象だ。 ところで、このユニット折り紙もそうだが、作品が組み上げられるのも、そもそも考えれば摩擦力という自然の原理があるおかげだ。摩擦がなければ、せっかく組み上げた多くのユニット折り紙作品は、自然崩壊するだろう。 こうしたわけで、大きな作品より小さな作品を作ることに、私の折り紙は方向転換するようになる。しかし、ここにも普段気にしていなかった事が、にわかにクローズアップされ大変気になる存在になってくるのだ。 それは、紙には厚さがあると言うことだ。普通の15cmサイズの折り紙では厚さは、作る作品に大きな影響を与えるものは少ない。しかし、これが一辺が1cmぐらいになってくると、紙の厚さがきいてくる。(右図:30ユニット) この厚さが作品を折っていく上で邪魔になってくるのだ。それもそのはずだ、同じ比率で考えると同じ厚さの紙なら15cmの折り紙に対して、1cmの折り紙の厚さは15倍になる計算だ。 そして、この何倍にもなった厚さが、見かけ上の紙の硬さを増加させるのだ。だから、厚さと折り曲げにくさが相乗的に働き、ミニ折り紙は困難さを増す。 だから、極小の折り紙作品を作る場合、極めて薄手の折り紙を使用する場合が多い。しかし、そうした折り紙は市販されていないし、また他の紙を転用するのもやっかいだ。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2004-10-28)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.27
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/6
ユニット折り紙の私的ルーツとしての『重ね箱』 折り紙には、単独でも完成品となるものばかりでなく、ユニット折り紙や折り紙細工のように、ひとつでは作品となり得ず幾つかを組み合わせてひとつの作品を完成させるものがある。 その両方の性質を兼ね備える中間的な存在が、「重ね箱」と呼ばれる伝統的な折り紙だ。これは、単独でも箱として立派な作品ではあるが、サイズの違う物をもう一つ作って蓋付の箱の作品としても楽しめる。 さらに、どんどんサイズが小さい物を数多く作り、ロシア人形のマトリョーシカのように入れ子にして楽しむことが出来る。開けても開けても次から次へと箱が出てくるものだ。 私は、こどもの頃に数十個も作り、友達などに自慢して見せびらかせたことがある。この時は、市販されている奇麗な折り紙では勿体ない(貧乏じみてはいるが、それが普通の時代だった。)ので、藁(わら)半紙を切って作った。 これは、前に日記にも書いた「ハレとケ」の折り紙で言えば、生まれはハレで育ちはケと言った折り紙と言える物だ。長方形の紙をわざわざ正方形に切って作る、かえって面倒な作り方をして作る。 今、思い返してみてもおかしなくらいだが、こどもは思い立ったら先を考えずに一途に突き進む。これは、ある意味ではこどもの素晴らしくもあり、向こう見ずな行動でもあるのだ。 ともあれ、好きとは言え、こどもの頃では同じ物をひたすら折る事に苦痛を感じずいられることは、こどものひとつの能力だろう。そして、現在の私のユニット折り紙にはまりこむ素地がこのころ作られたのだろう。私のユニット折り紙のルーツでもあるのがこの「重ね箱」だ。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2004-09-15)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.26
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/5
多面体の美しさ(合同の多重集合美):ユニット折り紙の魅力 ユニット折り紙が「多面体の折り紙」と呼ばれるように、ユニット折り紙の魅力が多面体の美しさにあることは、前にも書いた。その多面体の美しさについての思いを綴っていく。 多面体の代表格は正多面体だが、それはインフォシークのネット辞書:大辞林(国語辞典)によると、「面がすべて合同な正多角形でできており、どの頂点に集まる面の数も等しく、どの頂点における立体角も等しい多面体。(カッコ内引用)」となる。 ここに、正多面体がかもし出す美しさが凝集されていると言って良い。「面がすべて合同な正多角形でできて」いる。たとえば、正三角形なら正三角形だけで覆い尽くされているのだ。 このように、全く同じ形で埋め尽くされている美しさは、自然界ではミツバチの巣・魚の鱗・トウモロコシなど、人工物ではタイル壁・連子格子・瓦葺きの屋根・千枚田などに感じる美しさと共通だ。 整然と同じ形が続く美しさに、人は太古の昔からひかれてきたことは、土器や青銅器などの文様にも少なからず現れていることにもうかがえる。合同形の集合美は時代を超えた普遍的な美なのだ。 さらに、正多面体は「どの頂点に集まる面の数も等しく、どの頂点における立体角も等しい」と言う性質で、その同じ形の連続に同じ配置の仕方という二重構造で一層その美しさを強調しているのだ。 このユニット折り紙の重層構造は、元の正多角形がのすべての辺や内角がそれぞれすべて同じ(合同)と言うことを考えれば、ユニット折り紙は合同の多重集合体とも言える。そして、そこに神秘的とまでも言えるユニット折り紙の美しさの秘密があるのではないだろうか。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2004-06-22)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.25
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/4
折り紙と算数:幾何学的認識のひとつのバックグランドとしてのあそび 小学校としてはピカピカの第1学年から図形の学習が始まる。今まであそびをはじめとする生活の中で親しんできた丸・三角・四角という「形」を幾何学として体系的に学び始めるのだ。 まだ、低学年のうちはいいものの、高学年になって半径・直径・平行・垂直などのまだ幾何学では初歩であるが、難しい?幾何学的概念が出てくると、そろそろ「図形の学習」が嫌いになってくるこどもが出始める。 ましてや、これが中学校・高等学校へと学習の水準が本格的幾何学のレベルに達すると、急激に幾何学大嫌いという子ども達が続出する。それは、それまでの体系的な学習の積み立て?をあざ笑うかのようでもある。 そうした一方で、幾何学の神秘的とも言える不思議さ・美しさに魅了され、幾何学が好きで好きでたまらないこども達も存在することも、周知の事実だ。 では、この両極端の分かれ目は何だろうかと言うことだ。ひとつは、ごく当たり前の事になるが図形というものに興味を示し得たかどうかだ。それは、はじめて「図形」と言う概念で教えられる小学校教育なかでも低学年での教育での関わりが重要と考えるが、それについては別の機会にゆずることにする。 つぎに、こども達が日常の生活の中でどれだけ図形に親しんでいるかどうかが、図形・幾何学の好き嫌いを導きうる要素(バックグランド)の一つとなると考えている。 こどもの生活の中ではあそびが効果的で、図形を意識して活動をするのが、タングラム・ジグソーなどのパズル類、組み立てブロックあそび、お絵かきあそびなどいろいろある。そんなあそびのなかで、日本において歴史と伝統のある折り紙あそびに論点をしぼる。 折り紙は紙を折ると言っても、周知のようにでたらめに折っていくのではなく、規則正しい折り方に則(のっと)って折っていく。そのひとつ一つが幾何学の重要で基本的な法則・定理などに依拠しているのだ。 例えば、折り紙を真半分に折るには二通りの方法があって、対角線(角の2等分線)で折って三角形にするか、辺の2等分線で折って長方形にするかのどちらかだ。また、特殊な折り方として頂点を辺の中点と重ねるような折り方もある。 この様に、その意味は全く知らなくても自然に2等分線や頂点・中点などのイメージ形成が培われているのだ。こうした、幾何学における基本要素の慣れ度合いは、将来や進行中の幾何学学習の大切なバックグランドになり得る。 さらに、折りあげる過程や結果に出現する様々な形、ユニット折り紙など立体的な形を見た経験の効果は、決して小さくはないと考えている。 この様に、折り紙は幾何学学習を助けるひとつのバックグランドをつくるが、これはあくまでバックグランドであって幾何学的知識は学校等での幾何学教育が無くては成立し得ないことは言うまでもない。 そして、折り紙が苦手な子のみならず、一般に折り紙は押しつけても、折り紙そのものを一層嫌いにしてしまい、効果はほとんど期待できない。親が、折り紙の楽しさを十分に味わうことが、一見回り道のように見えて実は近道なのだ。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2004-06-11)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.24
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/3
ユニット折り紙事始め:折り紙随想 私は、折り紙なかでもユニット折り紙に大きな魅力を感じ、創作を含めいろんな作品を折り続けてきた。そのきっかけとなったのは、ユニット折り紙の古典ともなった>薗部式ユニットに出会った時だ。 まずその美しさに惹かれた。同じ形がお互いに対称的な位置関係を持って、整然と組み合わされ立体を形成する美しさだ。これは、正多面体が持っている美しさに起因している分けだが、それに折り紙(色紙:いろがみ)の色彩が加わって美しさを倍加している。 そして、ユニット折り紙の素晴らしさは、同じ形に折った部品(ユニット)を組んでいく事によって一つの作品を作るのだが、その組み上げる過程のパズル的面白さが、これまた魅力を増す要素ともなっている。パズル好きの私が、ユニット折り紙にのめり込んだ一番の理由だ。 さらに、あれこれ苦労したうえに完成させて時の、充実感は折った者でしか味わえない喜びをもたらしてくれる。この様に、ユニット折り紙は折り紙の機能的な特性をいかんなく発揮した優れものだと思う。 もちろん、私自身の独自な性格や感性があって、これらのユニット折り紙の魅力を感じ取れたかも知れないが、学童保育所のこども達(高学年)の様に夢中になってくれた子も多かった。もし、暇をもてあますような状況になられたら、ぜひ試していただきたいものだ。 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2004-06-08)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.23
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/2
折り紙の晴れと褻(ハレとケ) 折り紙には、使う紙の形で大きく二つに分ける事が出来る。正方形とそれ以外の紙だ。それ以外の紙で大半を占めるのが、長方形それも辺の比率が1対ルート2のB5やA5などの定型の長方形の紙だ。ノート・ザラ半紙・新聞紙・チラシなどの紙だ。 この長方形の紙は、日常普段の生活の中で極めて簡単に手に入る紙でもある、反対に正方形の紙はある意味では特殊なわざわざ買い求めなければならない紙なのだ。 だから、普段するような折り紙あそびには長方形の紙が向いており、折り紙飛行機などはその代表格だ。今も昔も新聞の折り込みチラシを使って紙飛行機が折られているように、長方形折り紙はポピュラーな折り紙なのだ。 一方、奇麗な色の着いた折り紙(一般には色紙と呼ばれていた。)を使って折られたものは、それであそぶことよりどちらかと言えば飾り・作品として飾っておかれる場合が多い。長方形折り紙を褻(ケ)の折り紙と見なすと、正方形折り紙は晴れ(ハレ)の折り紙と言える。 かつてこども達は、「ハレとケ」をごく自然に使い分けていた。言い換えれば、「ケ」の時に長方形折り紙をあそび楽しみながら、「ハレ」の時の正方形折り紙の作品を作る腕を磨いていたとも言える。さて、今の子はどうだろうか・・・・・ 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2003-12-12)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.22
コメント(0)
-

折り紙ブログアーカイブ/1
ユニット折り紙をどうぞ! 趣味のひとつとして、ユニット折り紙(創作)をやっています。多面体折り紙・くす玉折り紙とも言われています。 同じもの(ユニット)を沢山折るので、手先・指先を使うので老化防止にも役立つとか、にわかに注目されつつあるようです。お奨めの熟年の「遊び」のひとつです。時間をもてあましている時にでもどうぞ。http://yuuyuu-sya.a.la9.jp/select/uni-ori-menu.html 本記事は、このブログの過去記事の再掲載です。(2003-09-28)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクト遊邑舎あそび館FC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.21
コメント(0)
-
哀悼!エクアドル地震
地球の裏側でも、大地震があった。この度の、エクアドル地震で、犠牲になられたみなさんに哀悼の誠を捧げ、まだ見つかっていない方々のご無事を祈り、被災されたみなさん方に対しまして、心からお見舞い申し上げます。
2016.04.20
コメント(0)
-

余震?前震?本震?関連無?関連有?
(前回からの続き、引用記事は再掲)【16日に起きた阿蘇山の小規模噴火について、気象庁は「一連の地震活動とは直接関連がない」との見解を明らかにした。だが揺れによって誘発された可能性もあり、今後の推移を注意深く監視する必要がありそうだ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース検索/産経ニュース:2016/04/16) また、今回の熊本地震のケースのように、本震と断定すれば、次に起こる「正しい」本震を、予想の圏外に置いてしまう危険性があり、実際にも、そうなってしまいました。そのことにより、「新たな」本震に対する備えや気構えを、過小に押さえ込み、その結果として、多大な犠牲が出たのかも知れません。 もちろん、地球内部の状況や、地震該当の活断層の正確な状況の、把握が難しい現状を考えれば、上記のことに関しての気象庁の見解を、批判するつもりはありません。しかし、やはり「余震」と言う語は、「余った」地震と言うような誤解を与えかねないので、今後の使用は止めるべきではないでしょうか。 なお、今回の熊本・大分地震が、中央構造線沿いに拡大するかどうかは、その時期を断定・予想することは難しいのは当然ですが、少なくとも、中央構造線上の他の地域に対して、確実に何らかの影響を与えたことは間違いがありません。 また、その波及する該当地域の状態、たとえば歪みの蓄積具合に比べ、今回の地震による新たな歪みが極めて小さければ、当面の影響は無いと考えられますが、その歪みの状況が、正確に把握できていないので、それも断定ができないのは言うもでもありません。エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.19
コメント(0)
-

余震?前震?本震?関連無?関連有?
【16日に起きた阿蘇山の小規模噴火について、気象庁は「一連の地震活動とは直接関連がない」との見解を明らかにした。だが揺れによって誘発された可能性もあり、今後の推移を注意深く監視する必要がありそうだ。】(【】内は記事から一部引用、Google ニュース検索/産経ニュース:2016/04/16) この度の、熊本・大分地震で、お亡くなりになられた方々に、哀悼の誠を捧げますとともに、被災された皆様方に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。 記事にあるように、熊本地震と阿蘇噴火の関連の有無には、専門家でも意見が分かれています。また、余震が前震に変わったことも気象庁から発表されています。さらに、今回の地震が、いわゆる中央構造線に沿った場所で起きていることから、その構造線に沿って、地震が東に拡がることにも、専門家の意見が分かれています。 このように、地震発生や火山噴火、すなわち地球内部の変動に関しては、予想が難しいのが現状です。その意味では、起きた地震が、本震であるか余震であるの断定も、地震と噴火の関連の有無の断定も、科学的ではないと考えていいでしょう。 大学在籍時に、地質学のごく一端に、関わっただけの素人に近い私ではありますが、このことに関して、若干の思い付き的私見を綴ります。まず、地震と噴火との関連性ですが、二つの事象は、同じマントル対流が引き起こす現象であり、その意味で、確実に関連が有ります。 それが、地球の反対側の遠く離れた場所であっても、そのそれぞれが及ぼす影響は有ると、考えるべきです。ただ、その影響は、当然ながら無視できるほど小さいものもあります。しかし、それとて、その回数(積み重ね)や規模などの、別の量的変化により、影響も無視できないレベルにも達するものもあることは、間違いがないでしょう。 起こった地震が前震か余震かの問題も、時間のスパンをどれだけ見積もるかや、対象とする個々の地震の選び方などにも、大きく左右されます。だから、科学的には、前震・本震・余震という現象は、ある個別地震を対象として、適応すべきものではないと言えます。(続く)エッセイは、次のページでいろいろ掲載しています。遊邑エッセイFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.18
コメント(0)
-
熊本地震お見舞い
この度の熊本地震で、お亡くなりになられた方々に、哀悼の意を表し、被災されたみなさま方には、心からのお見舞いを申し上げます。 黙祷
2016.04.17
コメント(0)
-
熊本地震お見舞い
熊本地震でお亡くなりになられた方に黙祷。
2016.04.16
コメント(0)
-
熊本地震お見舞い
この度の熊本地震で、お亡くなりになられた方々に、哀悼の意を表し、被災されたみなさま方には、心からのお見舞いを申し上げます。 黙祷
2016.04.15
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その7
新しい情報を取得し、さらに脳内において整理整頓する「学習」を行えば楽しくなる仕組みが生まれます。脳内物質の分泌は、少なくともその仕組みの一つです。だから、本来学ぶことは、楽しさや喜びをもたらせる活動なのです。そして、この楽しい、能動的・積極的な「学習」活動の一つとして、「遊び」が出現するのです。 おそらく、幾つかの動物において、この楽しい「学習」活動としての「遊び」は、幼体だけでなく成体の動物にも見られますが、やはり親による「子育て」により、その「学習」の時間を保障された幼体、すなわち子どもたちほど、「遊び」に有利な条件は持っていません。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.14
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その6
動物が、この「学習」能力を獲得して間もない頃は、この「学習」は、基本的に、外界から受身的に情報を取得するだけでした。これでは、外界から得られる情報は、偶然性に依拠した情報で、下界のより良い情報把握には、不充分です。 だから、受身的な情報取得だけでなく、もっと外界に働きかけたり、積極的あるいは主体的に情報獲得に邁進できる仕組みが必要となります。それが、「学習」することを、食事・生殖などの活動と同じように、好んで(積極的に)行うようになる必要があります。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.13
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その5
さらに、その情報と行動の制御は、大脳さらに大脳皮質の発達により、合理的・効果的に大きく発展します。このことは、その動物にとって、生存競争に極めて有利な条件となります。 ほぼ、DNAによる生得的な情動と行動だけに頼るよりも、生まれて以降の「学習」活動は、動物たちの生存能力を飛躍的に高めることになります。だからこそ、進化の一つの必然的方向として、脳の発達と「学習」能力の獲得が、進行したのです。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.12
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その4
「遊びたい」と言う動機付けが、DNAに刻まれていると、前回記しましたが、そのことの理由を、次に考察していきます。「遊び」以外の、食を求める索餌(さくじ)活動、食する食事活動、子を残す生殖活動なども、DNAに依存しており、それらの活動だけで、基本的に生命活動が全うできる動物も数多くいます。 にも拘らず、それ以上に「遊び」と言う活動まで、DNAに刻む必要があったのでしょうか。それを考えるには、まず「学習」と言う活動を考察していく必要があります。それは、脳と言う中枢神経系の獲得と、その発展を考えることと同じです。 中枢神経系を獲得した動物は、植物と違って、外界の状況を感覚器官を通じて得た情報を、中枢神経系で保持し、それを索餌行動やその他の生命活動に生かしています。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.11
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その3
では、どうして進んで「遊ぶ」のでしょうか。それは、一言で簡単に言えば、「本能」の成せる業だと言えます。もっとも、現在では「本能」も誤解を生む言葉として使われなくなっているそうですが、少なくとも、生まれながらにして「遊び」たいと言う情動があるのは間違いがないでしょう。 そのことを言い換えれば、「遊び」は遺伝する行動、すなわちDNAに刻まれ、必然的に、引き起こされる行動となります。まさに、人間は、「遊ぶ人(ホモ‐ルーデンス)」であり、こどもたちは「遊びをせんとや生れけむ」なのです。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.10
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その2
その「遊び」は、「遊び学」徒然でも指摘したように、狩りや採集などの労働や、敵から身を護る活動から、解放された自由時間の存在が生み出したのです。とりわけ動物のこどもたちは、その親たちが、一定期間「子育て」に専念してくれるおかげで、親よりも「遊び」に使える自由時間が多く持てているのです。 しかし、自由時間がタップリあったとしても、それが「遊び」と言う行動に結び付くわけではありません。下手をすれば、その時間ずっと、何もしないか眠っている状況にもなりかねません。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.09
コメント(0)
-

生物学的遊び論/その1
オランダの歴史家ホイジンガが提唱した「ホモ‐ルーデンス(遊ぶ人)」と言い、日本の平安時代に編まれた「梁塵秘抄(りょうじんひしょう)」にある「遊びをせんとや生れけむ」と言い、人間(人類/ヒト)と「遊び」の切っても切れない関係は、古くから論じられているように、間違いのない事実です。 それどころか、この間の動物学の進展に伴って、少なくない動物においても、「遊び」が、動物の成長・発達にとって重要な活動だと認識されるようになっています。ただ全ての動物が「遊ぶ」わけではありません。動物進化の途中で「遊び」が生まれたのです。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.08
コメント(0)
-

生物学的遊び論/事始め
昨日まで、この間に私が講演した「遊び学」の内容について、綴ってきましたが、そこでも触れた「遊び」の生命史における位置付けを、もう少しだけ突っこんで考察していくこととします。 ただ、一凡人に過ぎない私が、専門外の生物学から「遊び」を論じるには、いたらない点が多々あり、専門家諸氏からの手厳しい批判を受けるだろうと思いますが、その事を覚悟したうえで、私見を綴っていくこととします。(続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.07
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その26
・仲間さえいればあそべるあそびと、仲間がいなければあそべないあそびを!(講演会レジュメより再掲) そのためには、親たちをはじめとした、おとな同士が協力し合って、こどもたちに共有できる自由な時間を確保して、その回数と継続時間を増やす努力をしていくことが大切です。あとは、国・自治体・企業など、社会的に大きな責任を担っているおとなたちが、こどもたちの自由時間を、今より大幅に増やす決断をするだけです。 「遊び」は、こどもたちを立派なおとなにしてくれる、自然塾なのです。その意味で、あそびはこどもの仕事(やらなければならない活動)でもあるのです。こどもたちのあそぶ笑顔は、人類の明るい未来を切り開く偉大な仕事なのです。(完)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.06
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その25
・仲間さえいればあそべるあそびと、仲間がいなければあそべないあそびを!(講演会レジュメより再掲) 一人あそびにもなる、けん玉・コマ回し・お手玉なども、対戦形式ではなくて、それぞれが個々に遊んでいたとしても、友達のいるところで遊べば、さらに、同じ一人遊びではなく、それぞれが別の遊びをしていても、同じ時間帯に同じ空間で遊べば、こどもたち同士は結構、影響し合ったり、交流もします。 集団で同じ遊ぶをすることが難しいのなら、次善の方策として、上記の「遊び」も、こどもたちの「遊び」の改革には、効果が期待できます。こどもたちが一緒に時間と場所を共有すれば、こどもたちは、お互いに切磋琢磨するのです。その結果として、「集団あそび」に発展することも大いにあり得ます。 ようするに、こどもたちに、他の仲間と共有する時間さえあれば、こどもたちの「遊び」を本来の姿に戻し、やがてこどもたちの「三つの異変」は、楽しい時間の経過とともに大きく改善することでしょう。「遊び」には、そうした極めて大きな働きも、持っているのです。(その26に続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.05
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その24
・仲間さえいればあそべるあそびと、仲間がいなければあそべないあそびを!(講演会レジュメより再掲) 今のこどもたちの「遊び」を変革する、もう一つの「遊び」は「仲間がいなければあそべないあそび」です。これは、前記の「仲間さえいればあそべるあそび」と重複しますが、大きな違いは、それら重複する「遊び」の他に、トランプ・将棋などの玩具や、ボールや長縄(大縄)などの遊具を使った「遊び」が含まれます。 もちろん、対戦形式などの、遊び相手を必須とする「遊び」となりますし、対戦形式あるいは競争形式の「遊び」は、基本的には遊び相手を必要とします。ただ、ゲーム機やゲームソフトなどを使った「遊び」は、対戦形式ではあっても、対戦相手が機械やソフトでは、当然ながら、遊び相手を必要としない「遊び」となります。 このように、今のこどもたちの「遊び」の状況を改善するには、「仲間さえいればあそべるあそびと、仲間がいなければあそべないあそび」が大切なのです。これらの「遊び」は、こどもたちに仲間と共通できる「遊び時間」が十分に確保できれば、おとなが関わらなくても、こどもたちだけで、始めることができますし、多くのケースでは、ゲーム機やゲームソフトであそぶよりも、楽しくあそべるのも厳然たる事実です。(その25に続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.04
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その23
・仲間さえいればあそべるあそびと、仲間がいなければあそべないあそびを!(講演会レジュメより再掲) こどもたちだけのの「遊び」は、昔の「遊び」や、新しく生み出された「遊び」の中に多くありますが、そんな中でも、今のこどもたちの「遊び」を変革する上では、やはり仲間同士で、出来れば屋外で身体を使ってあそぶことが特に大切です。 そんな「遊び」として、「仲間さえいればあそべるあそび」と「仲間がいなければあそべないあそび」をお奨めします。まず、「仲間さえいればあそべるあそび」は、基本的に玩具や遊具などを一切必要としないか、必要だったとしても、木切れや小石など、ほとんどお金をかけず簡単に手に入るもので楽しめる「遊び」です。 実は、それは「外あそび」に多いのです。「鬼ごっこ」「かくれんぼ」「Sケン」「ドロケイ(探偵ごっこ)」「石けり」「ケンパ」など、数多くあります。そして、そのほとんどが、比較的ルールも簡単で、2・3回遊べば覚えることもできる「遊び」なのです。 ルールが単純・簡単だとは言っても、そのゲーム内容は、場所・時間帯・季節などで変化し、同年齢や異年齢などの遊び仲間の状況でも大きく変化します。さらに、全く条件が同じでも、あそぶ度にゲーム進行が変化することも良くあります。こどもたちは、その遊びの変化に応じて、自分で考え自分で行動するのです。(その24に続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.03
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その22
三.こどもたちを、あそばせるには・多くのこどもたちに、共通したあそび時間を、持続的に長く確保する。(講演会レジュメより再掲) こどもたちの遊びの変革は、「多くのこどもたちに、共通したあそび時間を、持続的に長く確保する。」ことを目指しながら、たとえ少人数ではあっても、共通したあそび時間を持った仲間同士で、あるいはその反対に、仲間同士が共有できる時間帯に、こどもたちだけで自由に遊ぶことを、日々、それが無理なら、日をおいてでも繰り返し、積み重ねていけばいいのです。 ただ、「遊び」を重視した、教育や保育が行われていますが、その多くは、徹頭徹尾かそれに近い、おとなが関与する『遊び』(「あそび的課業」)となっているケースもあります。それも、大切な取組みではあるのですが、「遊び」の持っている特長(意義)を、如何なく発揮するには、やはりこどもたちだけでの自由な「遊び」が大切です。(その23に続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.02
コメント(0)
-

『遊び学』徒然/その21
三.こどもたちを、あそばせるには・多くのこどもたちに、共通したあそび時間を、持続的に長く確保する。(講演会レジュメより再掲) こどもたちの遊びの変化が、こどもたちの三つの異変に大きく関わっているなら、その遊びの現状を、高度経済成長期以前に戻せば、異変は解消される可能性が高くなるでしょう。少なくとも、こどもたちの異変を、大きく改善することは、確実だと言えます。 しかし、実際に「遊び」を昔の状況に戻すには、かなりの困難が伴います。個人的に解決できる問題ではないのです。こどもたちは、学校5日制や授業時間数の増加などの学校教育全般の問題、熟や習い事の増加と低年齢化などの、子育て観の問題、子どもの遊びの異常な商業化など、ほぼ社会全般の問題、それはおとなが関与しているのですが、その大問題に、こどもたちは翻弄されているのです。 ただ、こどもたちの異変を短期間に大きく改善することは難しいにしても、できる範囲のところからでも、改善し始めることはできます。一人から二人へ、二人から集団へと、それに取り組むおとなの輪を、広げていくことは、今すぐにでもできることです。(その22に続く)「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。あそびセレクトFC2ブログランキングにも登録しています。↓よろしければ、ご支援のクリックを↓多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。
2016.04.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1