2025年07月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

良好な人間関係作り その4
今日のテーマは「自己肯定感」を育てるということです。アドラーは「承認欲求の否定」と言われています。人間は誰でも人から認められたい、褒められたい、評価されたいという欲求があります。アドラーもこの欲求を否定しているわけではありません。アドラーが言いたいのは、他人から承認を得ることが唯一最大の目標になってはいけないということです。他者からの承認や評価を自分の行動原則にはしないということなのです。アドラーは他者の評価に振り回されない勇気を持ちましょうと言っています。自分の価値を他者の評価に依存させないということです。他者に嫌われることを怖れて、自分の意見を言えなかったり、やりたいことを諦めたりする生き方から解放される道を目指しましょうということです。では、どうすれば他者承認に振り回されない生き方ができるのか。アドラーは自分で自分の価値を認めること、つまり「自己承認」に焦点を当てるべきだと考えました。そして「自己承認」を得るための最も健全な方法は「他者貢献」であると述べています。アドラーは、「他者承認」「他者評価」という受け身の姿勢ではなく、「他者貢献」という積極的、能動的な道を選択することで、自分の価値を大いに高めていきましょうと言っているのです。この考え方は石原加受子氏の「自分中心心理学」につながる考え方です。「自分中心心理学」では、「自分はどうしたいか、どう考えているのか」をすべての行動の基準にするという考え方です。これは、他者の評価や期待、あるいは社会の「かくあるべし」といった規範ではなく、自分の感情や欲求や意思を優先する生き方のことです。さて、アドラーは「嫌われる勇気」を持ちましょうとも言っています。他人の気持ちや考えを忖度しすぎるのではなく、自分の意志や感情や考えを相手にきちんと伝える努力をしましょうということです。いつも相手の言いなりになっていると、相手は自分のことを格下とみなして、部下や家来のような扱い方をしてきます。これはタテの人間関係に繋がります。支配・被支配の関係になって、人間関係は対立してきます。まず相手の話をよく聞き、次に自分の正直な気持ちを伝えることが肝心です。そこには容易に埋められない大きな溝が横たわっていることがよくあります。その時は暴言や暴力に訴えるのではなく、合意を目指して話し合うという態度が欠かせません。譲ったり譲られたりの人間関係作りを目指すことが肝心です。
2025.07.31
コメント(0)
-

良好な人間関係作り その3
アドラーは人間関係の悩みや不安は、「共同体感覚」が欠けているから生じると説明されています。この問題を解決するのは「他者貢献」であると述べています。自分の行動が誰かの役に立っていると感じることです。これによって、自分の価値を実感し、自己肯定感を育むことにもなります。アドラーは「人の為に尽くす」と「人の為に役に立ち、人に喜んでもらうこと」の違いについて説明しています。多くの人は仕事や役割を漠然とした義務感や責任感でこなそうとします。しかしこの状態では自分の意思が置き去りにされてしまいます。「人の為に尽くす」という目的の多くは、上司、組織、顧客といった「他者の目的」です。その目的を達成するために、自分の役割をこなすのですが、そこには自分の意思や喜びが伴いにくく、義務感やノルマ感から「やらされている」感覚に陥りやすくなります。これではモチベーションが長続きしません。「人の為に役に立ち、人に喜んでもらうこと」という目的は、他者の喜びや感動といったポジティブな反応を自分の行動の目標とすることになります。単に仕事や役割をこなすだけではなく、「どうすれば相手が笑顔になるか」「どうすれば感動してもらえるか」というクリエイティブな思考が生まれます。「人の為に尽くす」は、他者の要求に応えるという消極的な姿勢です。一方、「人の役に立ち、人に喜んでもらう」というのは、積極的、能動的な姿勢です。自分の意志で目標を設定し、それがさらなる行動の原動力となります。さて、アドラー心理学に「目的論」というのがあります。全ての行動の背後には目的があり、その目的を達成するために、人間は無意志のうちに行動を選択しているという考え方です。例えば、「私は過去のトラウマで社交的になれない」と考えるのは原因論です。これに対して、アドラーの目的論では「社交的になりたくない」という目的を達成するために、「過去のトラウマ」という理由を後付けしていると考えているのです。アドラーはネガティブな目的ばかりではなく、ポジティブな目的を持つことが大切だと力説しています。ネガティブな目的は、「人から承認を得る」「自分の利益の最大化を目指す」「自己顕示欲や名誉欲」などを追い求めることです。ポジティブな目的とは、「より良く生きること」「幸福になること」「共同体感覚を育むこと」など建設的で成長を促す方向性を持つものです。「共同体感覚を育む」ためには、「貢献したい」「協力したい」「幸せになりたい」という目的を持つことです。自分さえよくなればよいというのではなく、共同体に所属している自分が、人の為に役に立つことを実行して、「人を喜ばせたい」「人を感動させたい」という目的を持って行動することが肝心だということです。
2025.07.30
コメント(0)
-

良好な人間関係作り その2
アドラーは他者との信頼関係を高めることを重視しています。アドラーは、人間関係は「タテの人間関係」ではなく、「ヨコの人間関係」を築くことが大事であると言いました。「タテの人間関係」は、支配・被支配の人間関係に陥りやすく、支配されるものは、人間としての存在価値、プライド、財産、生命を粗末に扱われることになります。支配する者は、憎しみや対立の矢面に立たされ、不安と恐怖の世界に生きることになり、安心して人生を謳歌することができなくなります。「タテの人間関係」は森田でいうと、自分の「かくあるべし」を相手に押し付けることです。相手の気持ちや考えや欲求に耳を傾けないで、自分の気持ちや考えや欲求を一方的に相手に押し付けることです。人間関係がぎくしゃくして、神経症発生の原因につながるといいます。「ヨコの人間関係」は対等性、相互理解、相互信頼に基づいています。お互いの違いを認め、尊敬し、協力し合う関係です。意見の食い違いは話し合いによって解決を目指します。職場の同僚、仕事で付き合いのある人、配偶者、家族、友人関係、趣味の仲間、隣近所の人など、お互いを一個人として尊重し、協力し合う関係です。自他ともに活かす人間関係です。「ヨコの人間関係」は争いもなくなり、穏やかな理想の人間関係ですが、実際実現することはとても難しい。アドラーは、「ヨコの人間関係」を作り上げるためには、「課題の分離」が必要だと説明しています。これは相手が抱えている課題や問題点は相手が解決すべきものであり、他人が相手の領域に土足で踏み込むようなことはしてはならないということです。例えば、子供が勉強するかしないか、その結果を最終的に引き受けるのは子供自身です。親は勉強することの重要性を伝え、環境を整備することはできますが、最終的に勉強するかどうかは子供自身の課題です。親が勉強を押し付ければ、子どもは反発しやる気をなくします。子供に限らず大人の場合も、過保護、過干渉のかかわり方は、相手の自尊心を奪い、依存体質を強め、相手の反発を招きます。ただしこれは相手を突き放して見捨てることではありません。アドラーは「課題の分離」を明確にしたうえで、「勇気づけ」が必要だと言いました。相手の近くにいて「見守り」「寄り添う」ということです。森田では相手が抱えている解決困難な問題に対して、性急にとってつけたようなアドバイスをするよりも、「どうしたもんだろうか」と相手の話に耳を傾けて「見守り」「寄り添う」という態度を重視します。時間の経過に任せるということですが、そのうち相手は自分なりに折り合いをつけてくると聞いております。自分はなんの助けにもならないからと言って相手を見放してしまうのは考えものです。相手との信頼関係を築くために、「怒り」や「憎しみ」の感情の取り扱い方が重要になると思われます。私たちはネガティブ感情をためると精神錯乱状態になり、その苦しみから抜け出すことができなくなると考えます。ここで躓いては、他人と信頼関係を深めるどころの話ではありません。この点は森田理論の感情の法則を活用・応用していきたいものです。森田理論ではどんなに激しい「怒り」や「憎しみ」の感情も時間の経過とともに、薄まるか消えてなくなるといいます。それなら、収まるまで「我慢する」か「耐えること」が必要になります。決して「スズメバチの巣」をつつきまわすようなことをしてはいけない。あるいは、一見して反社会勢力の人と思われるような人を挑発してはいけないということです。これらは誰でもよく分かっているのに、「怒り」や「憎しみ」の感情はすぐにつつきまわして大変な事態を招いている人がいます。
2025.07.29
コメント(0)
-

良好な人間関係作り その1
今日から4回にわたりアドラー心理学から「良好な人間関係作り」を考えてみたい。アドラーは人間は社会的な存在である。すべての悩みは人間関係の悩みであるであると言っています。アドラー心理学を基にして4つの視点から人間関係の改善の方法を考えてみました。①所属集団での居場所を確保する。②他者を無条件に信頼する。③他者への貢献を考える。④自己肯定感を高める。今日のテーマは①です。アドラーは自分が所属しているところで居場所を確保することが大事だといいます。仲間として自分が所属している家族、仲間、会社、組織、国などから、暖かく受け入れられていることです。当たり前のことですが、人間関係で問題を抱えている人はこの段階で問題を抱えていることがあります。アドラーの議論をする前に、まず安心して安らげる自分の居場所を確保することが欠かせません。そのために、普段から心がけること、避けなければいけないことがあります。避けなればいけないこと・あいさつを軽視している。相手を無視する。・相手のことをからかう。仲間外れにする。・与えられた仕事や役割の義務と責任を果たさない。・相手の話を他のことをしながら上の空で聞く。・自分のしゃべりたいことばかり話す。・「あなたメッセージ」の会話ばかりをする。・怒りのままに暴言や暴力を振るう。・相手を非難、否定、叱責、拒否、脅迫、強制する。実行した方がよいこと・いつも笑顔で挨拶を心がける。・傾聴、共感、受容、許容を心がける。・相手の話に同意できなくても、相手の話に耳を傾ける。・「ありがとうございます」「助かります」「おかげさまです」という感謝の言葉を使う。・「私メッセージ」の会話を心がける。・強制するのではなく、複数の提案の中から相手に選んでもらう。・余裕があればおすそ分けをする。・親切にしてもらったらお返しをする。・相手が困っているときは相談相手になってあげる。・相手の長所や能力、努力しているところを評価する。集団の中でやってはいけないことをしたり、やらなければいけないことをすると集団から排除されてしまいます。良好な人間関係を作るために必要なことばかりですが、これが逆になっていることが多い。そういう場合は、普段から忘備録を見て、自分の行動をチェックすることが必要になります。
2025.07.28
コメント(0)
-

神経症が治るとはどういうことか
神経症が治るということは人によっていろいろな解釈があります。その一つの方法は次のようなものです。症状に陥ったときは、頭の中が100%症状のことで埋め尽くされています。私は症状が治るというのは、その割合が徐々に減少することだと考えています。そのためには、注意や意識を外向きにしていくことが必要になります。森田でいえば物事本位に目の前のことに手を出していくのです。日常生活、仕事、世話活動などに取り組んでいくのです。すると、症状のことを考えている割合が90%、80%、70%・・・と下がってきます。私は50%ぐらいまで下がれば、神経症を克服したと宣言してもよいと考えています。完全に治す必要もないし、それを目指すと神経質性格のよさを潰してしまいます。この考え方は森田関係の本に図入りで説明されていましたので、間違いないと思っています。今日はそれ以外の見分け方をご紹介いたします。①神経症で苦しんでいるときは、不安や症状を目の敵にしてなんとかして取り除こうとしています。取り除くほどのエネルギーのない人は、ひたすら逃げ回っています。その一方でしなければならない最低限の日常茶飯事、仕事、良好な人間関係作り、世話活動、子育てなどは眼中にありません。ほとんど親、配偶者、同僚などに肩代わりしてもらっている。この2つのどちらも当てはまる人が、神経症で苦しんでいる人の姿です。②神経症から解放された方は、不安や症状を天気と同じ自然現象として、ある程度は受け入れることができるようになります。森田理論学習によって、どうにもならないことは、受け入れていくしかないという考え方を持っている。不安や症状を抱えたまま、最低限の日常茶飯事、仕事、良好な人間関係作り、世話活動、子育てなどに取り組んでいる。自分の心身の状態に応じてボチボチと手足を動かしている。不安や症状に振り回されているときは、超低空飛行しかできませんが、墜落しないことだけを考えてそれでもゆっくりと前進している。こういう方は、普通の人と見分けがつきません。つまり神経症から解放されている人です。ここで①状態を0%として、②の状態は100%としましょう。自分の場合は、どの程度の段階にあるのか分析してみるという手法です。30%くらいなら希望が持てます。さらに森田理論の深耕と応用実践に力を入れていけば、神経症から解放されて、普通の人と同じような生活を楽しむことができるようになります。
2025.07.27
コメント(0)
-

見切り発車で行動するという考え方
何か新しいことに挑戦する時に次の2つの方法が考えられます。①完璧な設計図を頭で作り上げてから、満を持して取り組むという方法があります。最初の設計の段階で様々なシミュレーションを行います。②大まかな構想ができたら早速行動を開始するという方法があります。問題点は、必ず出てくるだろうが、その都度対処すればよいという考え方です。森田先生の考えは②の方法だと思います。森田先生曰く。「修養とは、理屈を捨てて、実行を先にするようにしなければならない」「教育の弊は人をして実際を離れて徒に抽象的ならしむるにあり」(森田全集 第5巻 614ページ 森田全集第5巻の最初のページ)普通は、頭の中で試行錯誤を繰り返して、ある程度の成功の見通しが立って満を持して取り組みたいと考えます。森田先生は行動を伴わない思考だけの場合は、ともすれば空回りし、より混乱するだけだと言われています。例えば畳の上でいくらクロールの練習を繰り返しても、プールに入ってすぐに泳ぐことはできません。実際にプールに入り、身体の浮かせ方、息継ぎのやり方、手足の動作などを練習しなければなりません。このように行動しないと見えてこないもの、身につかないものはたくさんあります。行動して難しいと思っていたことが意外と簡単にできたり、簡単だと思っていたことに難儀することは日常茶飯事です。また行動することで、不具合や問題点、ミスや失敗がたくさん出てきます。これらはある意味で宝の山です。これに基づいて、改良や改善をくり返すとより成功に近づくことができます。完璧な設計図づくりで満足している人は、さまざまな問題点をすべて頭の中で解決しようとします。成功確率が高いかどうか、評価されるかどうか、コストパフォーマンスが高いかどうか、経費や労力や時間の無駄にはならないかどうか等々。納得できる設計図ができたとしても、頭の中でシミュレーションしただけなので確信は持てません。満を持して行動に移しても、想定通りに進行することは殆どありません。想定外のことが起きると、すぐにパニックに陥って大慌てするのはこういう人です。乗り越えられない壁が立ちはだかると、早々に撤退することを考えるようになります。以後それがトラウマとなって、二度と立ち向かう意欲は湧いてきません。無計画に突っ走るのは論外でが、森田先生はネガティブ思考の悪循環に陥って、全く行動しないで現状維持に甘んじるというのは、本来の人間の姿ではないと言われています。完全・完璧というのは、観念の世界にのみあり得ることです。現実の世界は混とんとして想定外の予測不可能なことが次々に起こります。森田理論に、不安や恐怖を取り除こうと格闘するよりも、新しい行動を開始すれば、今まで苦しんでいた不安や恐怖は軽減されたり、気にならなくなるといいます。行動することで、不快な感情や気分が変化してくるのです。神経症で苦しんでいる方は、生の欲望の発揮に注力するようにすればよいということです。行動するにあたっては、大まかな予想を立てて、問題が出てくれば、その都度修正しながら目的に向かう方法が理にかなっていると思われます。このことを、時間切れを宣言して、見切り発車するといいます。
2025.07.26
コメント(0)
-

「即」という言葉を深耕する
森田先生は「即」という言葉を好んで使われている。「不安定即安心」「不安即安心」「煩悩即解脱」「煩悩即涅槃」「煩悩即菩提」「雑念即夢想」などがある。これ以外にも、帚木蓬生氏の「生きる力 森田正馬の15の提言」(朝日新聞出版)では、「幸即不幸」「不幸即高」「あわてふためき即平常心」「立腹即平常心」「ハラハラドキドキ即平常心」「恐怖即平常心」「苦即楽」「楽即苦」「善即悪」「富即貧」「貧即富」「矛盾即統一」「諸行無常即安心立命」「耳鳴り即無声」「病気即未病」「健康即不健康」などという言葉が出てくる。「即」という言葉は、「ただちに、すぐに」という意味があります。即日、即死、即決、即刻、即答などという使われ方をします。もう一つ「即」には、「近づく、至る」という意味もあります。天皇陛下が即位されるというような使いたかがあります。ただちに、近づくから転じて、「とりもなおさず」「つまり」「換言すると」という意味を持つようになりました。これら2つの言葉は、相反するように見えますが、これはコインの裏腹のような関係にあるということです。つまりこの2つの言葉は数学でいう同記号(=)になるというのです。どういう意味なのか。森田先生の説明を見てみよう。「不安定即安心」ということについては、不安定とは客観的な日常の事実であり、安心は主観的事実である。風や寒さや絶えず変化することが日常の不安定の事実であり、これをその事実ありのままに見るときに安心があり、いやなこと苦しいことをも、ことさらにこれをいやと思わず苦しいと感じないようにしようとするところに心の葛藤が起こり、私のいわゆる思想の矛盾が起こり、強迫観念が起こり不安が起こる。すなわち私はただ「事実唯真」という。(森田全集 第5巻 26ページ)強迫観念の療法は、その精神の葛藤・煩悶を否定したり回避したりするのではない。そのまま苦悩煩悶を忍受しなければならぬ。これを忍受しきったときに、そのまま煩悶・苦悩が消滅する。すなわち煩悶即菩提である。雑念即夢想・不安心即安心である。(森田全集 第5巻 388ページ)相反する2つの言葉は実は同じことを説明しているのですが、そうなるためには条件があると言われているのです。①不安な気持ちを排除しようとしないで、その不安をそのまま受け入れ、不安そのものになりきることで、自然にそこに安心が生まれる。不安心即安心という境地になる。②煩悶している状態を、苦しいもの、取り除くべきものとして敵対しないで、あるがままに受け入れることで、その煩悶の中に涅槃(安らかな境地)が宿っている。煩悶を排除しようとすればするほど、かえって煩悶にとらわれますが、煩悶している自分を否定しないでそのまま許容することで煩悶から解放されて自由になれる。「煩悶即涅槃」となる。
2025.07.25
コメント(0)
-

理屈よりも実行を優先するということ
森田先生のお話です。修養には、理屈を捨てて、実行を先にするようにならなければいけない。なんでも実行が先で、尻軽く手を出すことが早くならなければなりません。(森田全集 第5巻 614ページ)ちなみに「修養」というのは、神経症が治るということ、あるいは事実唯真が自分の体験を通して分かることだと言われています。決して頭で納得することではありません。ここで言われている理屈は「思考」、実行は「事実」という言葉に置き換えてみると分かりやすいと思います。観念を優先して思考をくり返して、事実を捻じ曲げることは厳に慎まなければならない。不快な感情の事実、受け入れることができない不都合な出来事に対して、きちんと向き合う態度を最優先させる必要がある。事実を自分の都合のよいように解釈して(先入観、決めつけ、思い込み、早合点)、事実を捏造することは百害あって一利なしです。どういうことでしょうか。具体的な例で考えてみましょう。仕事でミスをして、相手に不利益を与えてしまいました。最初は「穴があったら入りたい」くらいの恥ずかしい感情が湧いてきます。頭が真っ白になって放心状態になるかもしれません。このとき、事実唯真の立場に立つと、素直にミスを認めます。その事実をすぐに関係各所に連絡して謝罪します。そして被害を最小限に食い止めるために、できる限りのことに取り組みます。自分一人の力ではどうにもならないときは、仲間の応援を頼みます。すぐに対処すれば、その後益々信頼関係が強まることが考えられます。事実を無視して頭の中で処理しようとすると問題が出てきます。こんな時、得意先、上司、同僚、お客様など関係各所から非難される、叱責される、始末書を出さねばならないなど、ネガティブな感情が湧き上がってきます。それらを恐れて、ミスを隠す、ごまかす、言い訳をする、責任転嫁をする、逃げ回る、報告を遅らせる、全く報告をしない、事後処理を他人に肩代わりしてもらう。やりくりをするとその時はホッと安堵しますが、それは問題を先送りにしているだけです。時間が経過すれば問題は益々こじれてきます。ミスの発覚を恐れて夜も寝られなくなるでしょう。その小さな失敗が自分の一生を左右するかのような大きな問題に膨れ上がるのです。そして、次の当てがないのに、この仕事は自分に向いていないので退職して転職したいなどと考えるようになります。残念ながら、こういう人はたとえ次の会社に転職できたとしても、同じことをくり返すことになるでしょう。時間が経ってら事の顛末が白日の下にさらされた時は、もはや手遅れでこじれにこじれています。そのまま会社に残ったとしても、小さなミスがトラウマとなって、その後の仕事に積極的には手が出せなくなります。その結果、消極的な仕事ぶりに終始して、しだいに社内の信頼感を失ってしまいます。問題が起きたとき、頭の中でやりくりをくり返すよりも、不快な感情の事実、不都合な出来事にきちんと向き合い、板の鯉になったつもりで、すべてを白日の下にさらした方が得策であることがよく分かります。
2025.07.24
コメント(0)
-

自己中心、自分中心の違いについて
一般的に「自己中心」というのは、自分勝手で他人への配慮がなりない人のことを言います。こんなことを言ってはいけない、こんなことをしてはいけないという自制心が働かない人です。自己中心的な人は、他人に反撃されるようになります。仲間内から敬遠されるようになります。他人が完全に無視するようになると、所属している集団に居場所がなくなります。仕事がなくなる、会話する人がいなくなると孤立してしまいます。仲間内から排除されると、かろうじて生きて行くことはできますが、生きづらさを抱えることになります。神経質性格者も、自分勝手な言動で他人から顰蹙を買うことは多いように思います。自制心は幼児の時に親からしつけられますが、身につけることができなかった人は、苦難の人生が待っています。森田理論でいう「自己中心」というのは、それとは別の意味でも使われています。注意や意識が自分の内面に過剰に向けられて、自己内省的になりすぎる状態を指します。過剰に自己内省をするようになると、次のようなことが起きます。・自分の内面の不快な感覚や思考に意識がとらわれて、そこから抜け出すことができなくなる。・自分の理想像と現実の自分との間にギャップを感じ、それを埋め合わせようと観念的に葛藤して苦しむようになります。・不安感情や気分や症状に振り回されるようになります。「不安だから行動できない」「なる気が起きないので何もしない」「症状があるから何も手につかない」というように、自分の不快感情や気分、症状が行動を制限するようになります。森田では、不快感情、不快な気分、症状を持ったまま、「なすべきこと」に注意を向けて、実践行動することを推奨しています。物事本位の態度のことです。すると、注意や意識が自分の内面から外の世界や具体的な行動・実践へと移り、結果的に症状が軽減したり、気にならなくなったりすると考えられています。「自己中心」に似た言葉で、石原加受子氏が「自分中心」という事を言われています。石原加受子氏の「自分中心主義」は、現代社会において多くの人が陥りがちな「他人軸で思考し、行動する」「他人を忖度して自分の気持ちを抑圧する」という問題提起から生まれています。石原加受子氏の「自分中心主義」は、他人への過剰な配慮や依存から脱却して、自己信頼感や自己肯定感を高めて、自分らしい生き方を取り戻すための考え方です。具体的には、・自分の感情や感覚を大切にすること。他者の評価や期待、世間の常識にとらわれずに、自分の「こうしたい」「こう感じる」という気持ちや意思を最大限に尊重するる・他人に振り回されたり、過剰に気を遣いすぎたりするのではなく、自分自身の心身の健康や幸福を第一に考える。・自分の価値観や判断を信頼して、他人と比較したり、自分を卑下したりしない。
2025.07.23
コメント(0)
-

自覚を育てるために大切なこと
森田先生は自覚について次のように説明されている。自分の心の事実をありのままに・虚偽なしに正しく認識することのできるのを自覚と言います。(森田全集 第5巻 619ページ)自覚とは、自分は果たして、いかなるものを好み、何を人生の欲望とし目的とするかという事を、正しくかつ確かに認識することである。(同書 541ページ)自覚とは、自分の考え方の間違いや認識の間違いに気づいていくことです。自分で気づくことができない場合は、信頼できる第三者に指摘してもらうことが有効です。カウンセリングは、カウンセラーとの会話の中から、自分の誤った考え方に自ら気づいていくことだと言われています。自分一人で気づいていくためには、正しいとされる考え方や見方が分かっていることが必要です。正しい考え方・見方を身に着けるためにどうすればよいのかを考えてみました。まず基礎的な森田理論学習をすることが有効です。神経症の成り立ち、神経質性格の特徴、感情の法則、認識の誤り、不安の役割、不安と欲望の関係、治るとはどういうことか等を学習していると自分の考え間違いに気づきやすくなります。その他精神療法も役に立ちます。認知療法や内観療法などがあります。1週間の集中内観を受けた人によると、自然に感謝の気持ちが高まってきて、涙が止まらなくなるそうです。感謝の気持ちが大事だと力説するよりも、集中内観で感謝の気持ちを体験することができます。但しその後も内観を継続しないと元に戻ってしまうということでした。認知行動療法に暴露療法があります。これは不安をいくつかの階層に分けて、不安の薄いものから不安にならしていくという療法です。特急電車に乗れないという人は、最初は付き添ってもらって家を出て駅に向かうというところから始めます。段階をクリアーするごとに不安がなくなり自分一人でできるようになるというものです。自分一人でできるようになると、「何だ、そんなに心配することはなかった」という気づきを得ることができるようになります。多くの精神療法では、自分の感情や思考パターン、行動の背景にある無意識の要因などを頭で理解することを通じて「気づき」を得ることを重視します。これに対して森田療法における「自覚」は、単なる知識や理論の理解を越えた、身体的・感情的な「腑落ち」のようなものを重視しています。何かを体験して、その結果として「そういうことだったのか!」心底納得する感覚に近いと言えます。神経症の人は、頭では正しいと分かっていても、感情がそれに伴わないという状態に陥りがちです。不安を頭で打ち消そうとしても、感情としての不安は消えず、かえってそれにとらわれてしまいます。森田療法は、この「観念と感情の乖離」を埋めるために、実践・行動を重視しています。集談会で卒倒恐怖の方がいました。以前意識を失って救急搬送されたことがあったからです。医者の見立ては器質的な疾患はないということでした。でも、その方は会社や通勤電車の中で突然失神して倒れてしまうことをとても心配していました。ある日自分は卒倒することを怖れて生活したのですが、それ以降一度も失神して倒れたこともない。それがまぎれもない事実だということに気づいて、とても楽になったと言われていました。私の場合、アルトサックスで老人ホームの慰問活動をしているのですが、最初に吹き始める前はとても緊張します。手が金縛りにあったような状態になります。仲間からの助言してもらいました。「あなたは課題曲を一通り吹けるようになったときに気を抜いているのではないか。一通り吹けるようになってからが勝負だ。ひたすら100回の練習を繰り返してから本番に臨みなさい」私はその助言を受け入れて、ひたすら練習に打ち込みました。そして分かったことは、本番では練習のように完璧の出来という訳にはいかないが、ある程度の成果は出せることに気が付きました。心のゆとりが生まれて、演奏に行くのが怖いという気持ちは無くなりました。小さい時に犬に追いかけられて噛まれたことがある人は、大人になっても犬が怖い。小さい犬はかわいいものだと言われても納得できないのです。こういう人はペットショップに行って生まれた子犬に触れさせることで、「かわいい犬もいるのだ」という気づきを得ることができます。飛行機嫌いの人は墜落事故のニュースをテレビで見るたびにパニックになります。しかしこれでは海外旅行はおろか、海外出張もできなくなります。航空機事故は2018年から2022年のデータでは1370万回に1回だったそうです。自動車事故の死者数に比べるとはるかに低い数値です。そういう事実を冷静に見ることができれば、飛行機には乗らないという選択肢は考えものだという事が分かります。それよりも早く目的地に着くことのメリットの方が大きい。自分が体験することによって得られる自覚(気づき)は本物だと思います。今年は夏野菜が豊作でした。ミニトマト、シシトウ、ピーマン、カボチャ、ナスです。食費の節約に一役買っています。おすそ分けをして人間関係も良好です。
2025.07.22
コメント(0)
-

碁を打つときの心構えについて
森田先生のお話です。兼好法師の「徒然草」の110段に、「碁を打つに、勝たんと打つべからず、負けじと打つべし」と書いてあるが、私からいえば、どちらもいけない。ただ勝敗を超越し度外視して、その時々の現在になって、一挙手・一投足をゆるがせにしないようにしさえすればよいのである。(森田全集 第5巻 607ページ)吉田兼好は囲碁をするとき、勝とうという気持ちが強すぎると思わぬ不覚をとることがあるので、守りのほうに力点を置いて対局することが大事になると言われている。森田先生は勝とうという気持ち一辺倒になっても、守り一辺倒に偏ってもいけないと言われています。たまには形勢が勝ちに傾いたときは一気呵成に攻めていく。形勢が悪い時は専守防衛に心掛けることがあってもよい。しかし基本的には、攻め方のことを5分考えたら、守りのことも5分考える。その両者のバランスが大事だと言われています。森田先生は、勝とうとするのも、負けまいとするのも、どちらも「とらわれ」であり、不自然な心の状態であると考えられています。これは、単なる「攻める」「守る」といった二元論を越え、常に状況を客観的に判断し、最も効果的な行動を選ぶ柔軟性を意味します。野球に例えれば、打者が打席に立つ際、「ヒットを打とう」と意気込むあまり力んだり、「三振だけは避けよう」と萎縮したりするのではなく、ピッチャーの球筋やカウント、ランナーの状況などを冷静に判断し、その場で「今何をすべきか」を目的本位で選択する姿勢に通じます。この考え方をさらに深めるためには、森田理論の「両面観」「精神拮抗作用」「不即不離」「主観的事実と客観的事実」などのキーワードを深耕することが有効です。これらは全ての物事には相対立する2つの側面が存在している。片方に偏ることなく、相対立する2つの側面を熟慮して、その時その場で適切な対応方法を選択するように心がけることが欠かせないということになります。森田理論はサーカスの綱渡りのように長い釣り竿のようなものを持って、絶えずバランスを意識することが欠かせません。
2025.07.21
コメント(0)
-

ラクダの生き残り戦略
稲垣栄洋氏のお話です。ラクダは砂漠という過酷な環境に適応している。森林や草原に比べて、砂漠には、天敵となる肉食動物が少ない。「らくだ」というほど、砂漠に暮らすことは楽ではないが、その環境さえ克服することができれば、天敵がいない楽園なのである。同じラクダ科の動物にはラマやアルパカがいる。ラマやアルパカは、酸素の少ない高山に適応して進化している。高山も天敵となる肉食獣が少ない環境である。このようにラクダ科の仲間は、天敵やライバルがいない場所を選ぶという戦略を徹底しているのである。もちろん、ただずらせばよいという単純なものではない。ラクダ科は厳しい環境に適応するために、さまざまな能力を発達させているのだ。ラクダはコブが特徴的である。何日間も水を飲まなくても大丈夫なので、昔はあのコブには水瓶のように水が入っていると信じられていた。しかし実際には、コブは脂肪でできていて、栄養分を蓄えているのである。それでは水はどうするのであろうか。じつはラクダは血液の中に大量の水を蓄えている。砂漠に生きるため工夫は、それだけではない。砂ぼこりから目を守るために、長いまつ毛を持っている。また鼻の穴は閉じるようになっている。さらに、砂に足が埋まらないように、足の裏の面積が広く平らである。こうしてさまざまな工夫をして砂漠で生きているのである。(弱者の戦略 稲垣栄洋 新潮社 62ページ)天敵やライバルがいないということは生存には有利である。天敵に捕食されたり、ライバルとの生存競争に明け暮れてエネルギーを消耗すると生き長らえることは困難である。そこでラクダはあえて砂漠で生きていくことを選択した。砂漠は砂嵐が舞う。木が一歩も生えていない不毛の土地である。食べ物もない。水もない。高温である。想像を絶するほど過酷である。それだけ他の捕食者が入り込めないほどの厳しく棲みにくい環境であるということだ。ラクダは、その過酷な環境に適応するために、自己改造に取り組まなければならなかった。ラクダから学ぶことは何か。天敵やライバルから身体を守り通さないとすぐに捕食されかねない。だから彼らから安全・安心できる場所の確保が必要になった。それが砂漠という不毛の場所だったのだ。ラクダは自分たちが生き残ることができるニッチの世界を見つけたのだ。見つけたということが凄いことだ。しかし、そこに移り住んで暮らせば即安心という訳ではなかった。過酷でとても楽に生きていけるような場所ではなかった。砂漠で生きていけるように、過去の自分と決別して、自己改造を必要とした。自分の肉体改造に取り組まざるを得なかったのだ。幸いにもラクダは自然に適応し、変化に対応することができた。次々に待ち構える難題を解決して今のラクダがある。ラクダには変化対応力あったので生き延びることができたということは人間が学ぶべきところである。森田理論は変化を予測して、その変化に上手に乗っていく理論となっています。変化することを拒み現状維持に胡坐をかいていると、時代にとり残され、延命することが極めて難しくなります。
2025.07.20
コメント(0)
-

規則正しい生活習慣を作り上げることに異議あり
このブログでは規則正しい生活習慣の話をたびたび取り上げています。この考え方に反対している人の話も聞いてみる必要がありそうです、五木寛之氏・・・夜中の1時か2時に寝て午前9時くらいに起きるという生活を続けております。ただ、そういうのもあまり規則正しくやるとよくないと思うんですよ。ところどころ変拍子というか、バリエーションを加えたほうがいい。たまに徹夜をするとか、ご飯を食べない日をつくるとか、そういう変化をほどよく入れることも大事です。人間というのはあまり規則に縛られてしまうと、そこから外れた時に寝込んでしまいますから。そもそも生きるってことは、規則通りにはいかないじゃないですか。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 8月号 14ページ)五木寛之氏は毎日変化のない生活をくり返すよりは、時々カンフル剤的な刺激をとり入れたほうがよいと言われています。規則通りに生活することが「かくあるべし」になっては、それが崩れたときに自分を否定することになるとも言われています。水墨画家の篠田桃紅氏・・・私はこれまでスケジュールもなく生きてきました。一切、スケジュールを立てません。予定とか目標とかいうものを、あまり好まないからです。自然のなりゆきにまかせて、生きています。自分に規律というものは課さないし、外からも課せられないようにしてきました。縛られたくないから目標も立てません。なにか目標を決めると、それに向かってやみくもに一生懸命になってしまいます。そうすると、ほかが見えなくなります。私は、ほかにすごくいいものがあっても、目標のために見逃してしまうことがいやなのです。人生は、道ばたで休みたいと思えば休めばいいし、わき見をしたければわき見をすればいいと思っています。今日中にあそこまで行かなければいけないと決めるやり方より、自然のなりゆきに身をまかせるほうが、無理がありません。その方が私の性に合っています。規則正しい生活が性に合う人もいるでしょう。しかし、あまりがんじがらめになるとなにかを見過ごしたり、見失ってもそのことに気がつきません。(103歳になってわかったこと 篠田桃紅 幻冬舎 80ページ)篠田さんは、興に乗ると時間が経つのを忘れて朝まで墨絵を描いていることもあるそうです。途中で中断して身体を休めるという発想はないと言われています。規則正しい生活は、自由で創造的な生活を阻害するという考え方をお持ちのようです。篠田さんはこの考え方、生き方で107歳の天寿を全うされました。見事というほかありません。私は森田理論学習の中で、規則正しい生活習慣を作ると、次に何をしようかと考えなくても、体が自然に動いてくるということを教えてもらいました。早速取り組みました。3か月くらいでものになりました。もう15年くらいは起床時間は6時20分に固定しています。起床後8時まではブログに関わっていますが、生活にリズムが生まれました。観念的で行動力に問題を抱えていた私にとっては、これは救いの神となりました。また、平凡な生活の中に、問題点や課題、改善点や改良点が見つかると、行動に弾みがついて生活の質が上がることを日々実感しております。どちらの考え方を採用するかは人それぞれだと思います。さて、あなたはどちらの考え方を支持されますか。
2025.07.19
コメント(0)
-
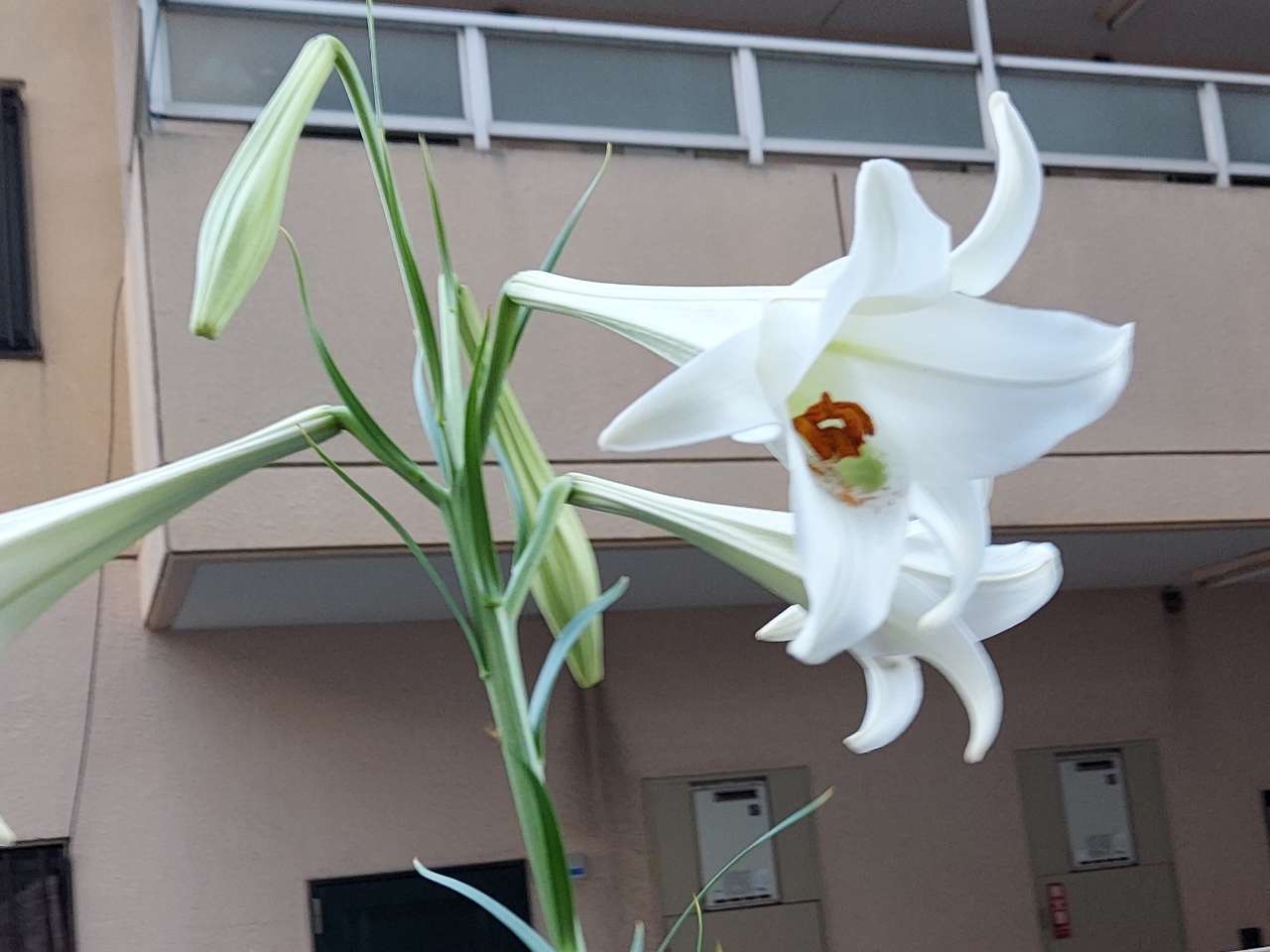
☆「ニーバーの祈り」を考える
アメリカの神学者であるラインホールド・ニーバーは、「ニーバーの祈り」という言葉を残しています。「神よ、変えることのできないものを受け入れる心の落ち着きを私にお与えください。変えることのできるものを変える勇気を私にお与えください。そして、変えることのできるものとできないものを見分ける賢さをお与えください」この祈りは、森田理論の核心をついていると思います。森田理論では変えることができないものはあるがままに認めて受け入れることだといいます。ネガティブな感情や気分、不安や恐怖や症状などは、天気などと同じ自然現象なので、自由自在にコントロールすることはできません。それらを取り去ろうと考えて行動すれば、実現不可能なことに取り組んでいるわけですから、エネルギーを消耗するだけです。恐れをなして逃げ回ることも同じことです。不安や症状などは、風船を膨らませるようにどんどん増悪してしまいます。坂道を転がる雪だるまの如しです。そして神経症のアリ地獄に落ちてしまうと、容易に地上に這い出ることは不可能となります。不安が不安を呼び寄せる。恐怖が恐怖を呼び寄せる。症状がさらに大きな症状に膨れ上がります。ニーバーの言うように、行動することによってよい結果が生まれるものと、行動すればますます窮地に追い込まれるものを明確に区別しておく必要があります。不快な感情や気分、相手に対する怒り、不平不満が湧き上がってきたとき、それらに振り回されて、衝動的・短絡的・反射的・反抗的な言動を取ることは、行動することによってますます事態を悪化させるものです。私はそんな間違いを犯さないために、自分に次のように言い聞かせています。不快な感情や怒りなどに振り回されて、売り言葉に買い言葉的な言動をとっているというのは、スズメバチの巣をつつきまわしているのと同じようなものだ。すぐに大量のスズメバチが体のあちこちに毒針をさしてくる。下手をすると再起不能に陥るか、死ぬことになってしまう。スズメバチの巣をつつきまわしてはいけないのは、誰でもわかります。しかし感情や気分、相手への怒りや腹立ちについては適切な行動がとれていない。あるいは一見して反社会的勢力と思われる人を挑発するようなものだ。即座に反撃される。暴力的行為を受ける。組事務所に連れていかれる。法外な損害賠償を要求される。家族にも被害が及ぶ。しまったと思ってもあとの祭りです。修復は不可能と考えた方がよい。不快な感情に対しては、冷静になって後から考えると、ひとつも得になることがないにもかかわらず、暴挙に出てしまう。これは人間として未熟と言わざるを得ない。まるで幼児並の行動です。やがて仲間内から排除されて、孤立して無為の人生を送ることになります。つい暴挙に出そうになったとき、これらの言葉が頭に浮かぶようになれば、なんとか我慢することができる。耐えることができるように思います。感情の制御ができなくて困っている人は、自分が納得できる言葉を見つけて、即実行することをお勧めします。次にニーバーは変えることができるものは変える勇気を持ちなさいと言っています。これは感情の暴発に耐えることができたとき、相手の為に何か役に立つことはないかと考えて実行することだと思います。相手も無理難題の発言を後悔しているときに、相手を許し、相手を思いやる言葉をかけることができれば、人間関係はとても良好となります。例えば、配偶者の料理がまずいと非難するよりも、自分が相手に代わって料理をすることができれば、夫婦関係はとても良好となります。
2025.07.18
コメント(0)
-

0か100、白か黒かの二分法的な考え方の問題点
0か100、白か黒、善か悪か、正しいか間違いか、良いか悪いか、強いか弱いか、美しいか醜いか、プラスかマイナスか、ポジティブかネガティブかという二分法的な思考方法をとる人は一旦こうだと決めたら、たとえ間違っていたとしても修正しようとしません。頑固で融通が効きません。当然人間関係は悪化します。周りの人は煙たがっているのですが、本人は開き直ってしまうので始末が悪い。事実に基づいて自分の信念を曲げないのならよいのですが、事実誤認による先入観、決めつけ、思い込み、早合点は犬も食わない代物となります。物事や相手の一面だけを見て、すべてを判断すると間違いだらけとなります。人間は誰でも清濁併せ持っているのが現実です。誤解に基づいた片寄った言動は問題行動となります。両者の関係性が悪くなり、益々対立的になります。他人が恐ろしいという対人恐怖症、社交不安障害の人はそのうち孤立してゆきます。この問題に対して森田理論は様々な面から解決策を提案しています。まず、森田には両面観という考え方があります。その他、精神拮抗作用、主観的事実と客観的事実、不即不離などという考え方もあります。すべて二分法的な考え方の取り扱いを説明しています。「迷いの内の是非は是非ともに非なり」という言葉も、二分法的な考え方からの脱却方法について説明しています。物事や相手は、必ず相対立する2つの側面を兼ね備えている考え方が基本になっています。森田先生は宇宙の法則から相対性原理の説明をされています。両方を過不足なく見て調整していかなければ、物事や相手を見誤ることになるという考えです。ある考え方や感情が湧き上がってきたら、「ちょっと待て、別の考え方もあるはずだ。両面観で考えてみたのか」と問いかけてみることが必要です。一方的な考え方に固執してしまうと、ブレーキが壊れた車を運転しているようなものです。いずれ生死にかかわる事故を起こすことになります。自分ではよく分からなかったら信頼できる人に聞いてみるが必要です。田原総一朗氏の「朝までテレビ」では、両極端な考え方の人を呼んできて喧々諤々の議論をしていました。両者の主張を聞いていると、視聴している人も客観的な立場に立って、自分なりの考えがまとまってきます。自分は欠点や弱点ばかりだと思ったら、森田の神経質性格のプラス面を思い出して、神経質性格の再評価をすることが大切です。そして神経質のプラスの面を前面に押し出して生活していくことが大事になります。心臓神経症で緊急搬送された人は、専門医が心臓に器質的な問題は見つからないと診断すれば、不安がなくならなくても、なすべきことを続けていくしかありません。卒倒恐怖の人は、突然失神して転倒して死んでしまうかもしれないと恐れていますが、今まで一度も倒れたことがないという事実に従わなければなりません。酒が好きな人は懇親会で飲み過ぎて前後不覚になることがあります。そういう人は、水と酒を交互に飲んだり、飲むスビートを押さえるなどの対応策を取らなければなりません。ある感情にとらわれると、その感情のネガティブな側面ばかりが強調され、ポジティブな側面や、その感情がもたらす意味合いを見失ってしまいます。人間関係においても、相手の良いところばかりを見ようとしたり、逆に悪いところばかりに焦点を当てたりすると、全体を捉えられず、バランスを崩してしまいます。二分法的な考え方は、サーカスの綱渡りをイメージして対応するとうまく収まります。物干し竿のようなものを持って、墜落しないように慎重にバランスを取ることに全神経を集中しています。しかも目の前の目的地に向かって前進している。
2025.07.17
コメント(0)
-

☆不快な感情や気分の取り扱い方
森田理論では不快な感情や気分は自然現象なので人間の意志で自由にコントロールできないと言われています。感情は私たちの意志とは関係なく勝手に湧き上がり、勝手に変化し、そして消えていく特徴を持っているのです。その日の天気は、私たちの意志ではどうする事もできないように、喜びや、悲しみ、怒り、不安、恐怖、気分などの感情も自由にコントロールすることはできません。感情は、扁桃体や海馬などの感情中枢が関与しており、外部・内部刺激によって瞬時に反応するようにできています。これは、危険を察知して身を守るための本能的な仕組みであり、意識のコントロール下にはありません。感情は、天気、気候、地震、台風、土砂災害、火山の噴火などと同じ自然現象です。自然現象に対しては、ある程度の備えはできますが、基本的にはあるがままに受け入れるしかありません。誰でも天気などに対しては自然に服従していますが、不快な感情が湧き起こったとき、あるいは相手から理不尽な扱いを受けたとき、つい相手に対して反射的に反抗的な態度を取ってしまうことがあります。売り言葉に買い言葉的な対応をしないと、相手に思うままにコントロールされて、不安やストレスだらけになってしまうと考えてしまうのだと思います。不快な感情に引きずられて衝動的・反射的・反抗的な行動をとれば、人間関係が崩れて孤立してしまうことはよく分かっていますが、つい問題行動をとってしまうのです。この問題に対して、どうすればよいのでしょうか。基本的には、不快な感情を「戦う相手」として捉えるのではなく、「今ここにあるもの」として認識する必要があると思います。不快な感情を無理にコントロールしようとするのではなく、その存在を受け入れて、自然に通り過ぎるのを待つしかありません。そのための方法として、不快な感情を台風のように眺めてみるのは如何でしょうか。台風には、1日で急速に通り過ぎるもの、何日も居すわるもの、その大きさも小、中、大型台風などいろんなタイプがあります。私たちは台風に対しては無力なので、あるがままに受け入れたうえで、その程度に応じてできる限りの様々な対策を立てて実行しています。天気予報で大きさや進路を逐次確認して情報をつかんでいます。基本的に外出はしないように心がけています。強風で物が飛ばないように固定するか家の中に入れています。甚大な被害が想定される大型台風の場合は、避難所へ退避することになります。不快な感情に対しても、台風と同様な対応を取るようにするのです。不快な感情に引きずられて衝動的・反射的・反抗的な行動を取ることは止めることです。感情の法則にあるように、「どんな感情も、そのままに放任し、またはその自然発動のままに従えば、その経過は山形の曲線をなし、ひと昇りひと降りして、ついに消失する」ようになっています。感情に引きずられて、売り言葉に買い言葉的な、衝動的・反射的・反抗的な行動をとることのメリットは全くありません。反射的・反抗的な行動は絶対に避けるという覚悟をしっかりと持って、しばらく我慢する、耐えることが必要になります。不安を無理に取り消そうとしないで、あたかも客人を迎えるように、一時的な感情としてそこに存在することを許すのです。感情は刺激しないでそのままにしておくと、自然に変化し、消えてなくなるということをしっかり意識することです。森田では不快な感情をそのままにして、その時、その場で、必要な行動をとれれば新しい感情が発生するといいます。ネガティブな感情はそのままにしておいて、積極的、生産的、建設的、創造的な行動を手掛けるようにするのです。意志や理性を活用して「自分は何をすべきか」「どうすれば建設的か」という「目的や義務」を果たしていくようにするのです。さまざまなネガティブな感情を持ちながらも、その感情に振りまわされることなく、自分の目的や周囲との調和のために適切な行動を選択できるようになりたいものです。せっかく森田理論で「感情と行動の分離」を学習したのですから、活用しないと宝の持ち腐れとなります。
2025.07.16
コメント(0)
-

後悔や罪悪感で苦しんでいる人へ
過去の不祥事や人間関係で苦しんだことが夢に出てくるので夜が怖いという人がいます。そういう人は自分嫌悪、自己否定することが習慣になっているのではないでしょうか。ミスや失敗や不祥事を犯すと、まわりの人、会社の人、社会から非難されます。要注意人物のレッテルを貼られて、自由な行動が制限されます。そんなとき、みんなと一緒になって、自己嫌悪、自己否定するというのは如何なものでしょうか。人間の最大の使命は、与えられた命を大切に取り扱い、できるだけ延命を図ることです。自己嫌悪、自己否定するということは、自分の存在と命を粗末にとり扱っていることになります。この心理は、自分の命は自分のものだから、自由に取り扱っても構わないという思い込みがあります。この考え方に真っ向から反対されていたのは樹木希林さんです。樹木希林さんは自分の命は神様からの預かりものという考え方をされていました。一時的に預かっているのだから、決して粗末に取り扱ってはいけないと言われているのです。自分の命を市民菜園を借りているようなものだと考えると、丁寧に取り扱うようになります。輪作体系を考えて、堆肥を入れて土を肥やすことを考えるようになります。ひとつの作物を作り続けたり、化学肥料や農薬をやりすぎで土地が荒れていくようなことは避けるようになります。後悔や罪悪感で苦しんでいる人は、自分の性格、容姿、能力、境遇、運命を呪い、親の育て方が悪かったなどといって絶えず不平不満、グチを言っているようなものです。他人から非難されたとき、みんなと一緒になって自分を否定するのは問題だと思います。どんな状況に置かれても、自分に寄り添い、自分を励まし、自分をどこまでも守り抜く必要があります。最後の砦の自分に見放されたら、自信を失って生きていく力が衰えてしまいます。車で交通事故を起こした場合、外国人は自分の非を認めることはありません。第三者から見て、どう考えても自分に非があるような状況でも、車から出て来ると相手の非を責め立てます。彼らには自己否定するという習慣はありません。そんな時に下手にでて「すみませんでした」などと言うと、自分の非を認めたことになり、相手の思うつぼとなります。大きな会社ではお客様からのクレームを受け付ける「お客様相談室」があります。お客様のクレームに対して、最初から下手に出て、あたかも自社の商品に不備があったという対応をとってはいません。まずお客様の怒りを十分に吐きだたせます。どんなに叱責されても「このたびはご心配とご迷惑をお掛けしております」と対応します。相手が落ち着いてきたのを見計らって、「内容の詳細をもう少し話していただけますか」というのです。クレームの内容を事細かに確認するという姿勢で対応しているのです。弊社の商品や会社の姿勢に問題があるという前提に立って、穏便にクレームを収束させようとすると相手を益々怒らせてしまいます。またクレームはお客様の取り扱い方にあるという先入観で対応するのも問題です。クレームは千差万別ですので、正確に事実確認することが問題解決につながるというスタンスを持ち続けることが肝心です。悪夢で夜中に目が覚めて苦しんでいる人は、不祥事の責任を全部自分が引き受けているのではありませんか。営業マンとしての教育やマネージャとしての教育を十分に受けない状態で、営業やマネージャーの仕事を押し付けられても上手にできるわけがありません。全責任を自分のせいにする必要はありません。してはいけません。どんなに窮地に陥っても、一方的に自分を否定することは避ける必要があります。自分は自分の最大の味方になることが大事になると思います。死んで不祥事の責任をとるという考え方は、責任の取り方としては問題だと思います。
2025.07.15
コメント(0)
-

メタ認知とは何か
ジョン・フラベルは「メタ認知」という言葉を使っています。森田理論にも関係のある話ですので取り上げてみました。この言葉は、自分の思考や感情を客観的に捉えて理解する能力のことを言います。この言葉は、心理学でいう「脱同一化」、認知療法でいう「脱中心化」、マインドフルネスでいう「観察する自己」と内容的にはほぼ同じ意味です。森田理論では、「感情と事実の分離」ということを言います。あるいは「感情と行動の分離」とも言います。症状で苦しんでいるときは不安感情や不快気分に振り回されています。注意や意識を一点に集中させて観念上、実生活面の悪循環が起きています。先入観、決めつけ、思い込み、早合点で自分勝手な考え方で判断して行動します。その時真実、事実、物事は見えていません。森田療法では、感情や症状を無理にコントロールしようとするのではなく、「あるがまま」に受け入れていくことを重視します。「あるがまま」に受け入れるためには、主観的な感情や気分に飲み込まれないである程度線引きを行い、それを客観的に観察するという側面があります。ここでのポイントは、ネガティブ感情や気分で右往左往している自分とは別に、そこから一歩距離をとって現実の自分の感情などを眺めることができるもう一人の自分を作っておくことです。客観的な自分、第三者的な自分、相棒、アナウンサーの実況中継のようなものです。私は専属アナウンサーと呼んでいます。現場に急行させて、自分が今感じているネガティブ思考や感情について、あたかもその時の様子をありありと実況するように心がけているのです。これは森田先生によると自覚を深めると言われています。ネガティブな自分の思考や感情に気づくということです。気づくためには森田理論の学習をしておく必要があります。症状と格闘しているときは次のような特徴があります。①考えることが無茶で大げさであり、論理的に飛躍しすぎている。②マイナス思考、ネガティブ思考一辺倒である。そして自己嫌悪、自己否定に陥っている。③事実を無視して、先入観、決めつけ、思い込み、早合点が多い。④完全主義、完璧主義、「かくあるべし」思考に陥っている。こういう側面に気づくようになればしめたものです。客観的な立場に立って自分の思考や感情を眺めると、売り言葉に買い言葉的な言動がなくなります。これが大きいと思っています。自分では客観的な立場に立つことができないと思っている人は、信頼できる人からアドバイスを受けるという方法も有効です。発見会の先輩会員でも、尊敬している先生、カウンセラーのような人でもOKです。その時は、5W1Hの手法で具体的に話すことが必要です。耳の痛いことを言われても、自分を客観的に眺めることができるようになります。
2025.07.14
コメント(0)
-

具体的に話すということ
森田先生は会話するときは、具体的であるということが大事になると言われている。例えば小児に、電車通りで「気をつけよ」とかいえば、小児は、どうしてよいかわからないで、てんてこ舞いをする。しかるに「前を見よ」とか、「こっちを向け」とかいえば、小児は電車なり・自動車なりに、目をとめて、自然に注意が緊張するようになる。(森田全集 第5巻 585ページ)具体的な指示が役に立つのは雷が近づいた時です。伊丹仁朗先生はヨーロッパ最高峰モンブランに登られたときに、雷が横に走っていて、とても怖い思いをされたそうです。私たちも大きな公園にいる時、海で釣りをしている時、ハイキングに出かけている時、大きな雷が鳴ると生きた心地がしなくなり、右往左往します。そんな時に雷に気をつけろというアドバイスは何の役にも立ちません。その時次のような具体的で明確な指示があるとすぐに行動することができます。・すぐに建物や車の中に避難しなさい。・避難場所がない時、姿勢を低くしてしゃがみなさい。・山では、窪地を見つけて身を寄せなさい。・釣竿や傘のようなものは自分の手もからできるだけ離して寝かせなさい。・大きな木に寄り添うのは危ないから離れなさい。・室内では窓際から離れなさい。具体的という点では、三重野悌次郎氏が1995年2月号の生活の発見誌で次のように説明されています。私はいつも失敗するという人に、「では最近の失敗がいつ、どのようなことがあったのか」と聞くとたいてい思い出せない。事実は、何日か何か月前に一度仕事上の失敗があった。その前にもいくつか失敗をしている。ということであって、その後は仕事の失敗も家庭での失敗もない。でも本人は「私はいつも失敗をする」と信じている。一般に「いつも」とか「みんな」とか、「絶対に」とかいうときは、「果たしてそうか」と自問する必要がある。ある人は「みんな」の名人であった。「みんなそういっている」というのが口癖だった。そこで誰が言ったのか聞くと、親戚の女の人が一人言っただけで、それに自分も賛成だと、みんなが言っていることになるのである。具体的に話さないと話の内容と事実が乖離するということになるのです。具体的に話すということでは次の話が参考になります。我々大人だと「新聞に水が滲みた」というところを、5歳の子どもはこんなふうに表現する。「新聞に水が(1滴)たれたら、小さな水のお山ができて、(そこに写った)字が大きくなった。だんだん水のお山が小さくなってきたら、今度は横に拡がっちゃった。そうしたら、別(裏)の字も見えてきた」(状況が人を動かす 藤田英夫 毎日新聞社 218ページ)このように説明されると、その時の状況がありありとイメージされます。集談会の自己紹介では、自分の悩みを具体的に話せば、聞いている人も自分のことのように親身になって聞いてくれます。具体的に話すというのは、心がけ次第で誰でもできるようになります。
2025.07.13
コメント(0)
-

稽古をくり返すことは問題なのか
森田先生のお話です。ここで一定日数入院修養中では、すべて稽古という心持がいけない。何事でも、その境遇における必要な事に、直接ぶつかるようにする。ここでは夜業に、板に文字を彫刻する事があるが、これも決して小刀を使う稽古をするのではなく、直接にぶつかると、初めから、随分上等の物ができる。患者の日記に、時々「飯炊きを見学した」とかいう事があるが、私はこの「見学」という字を消して、「見た」と直す。平均わずか40日の入院で、飯炊きや習字や、稽古などしていて、本当に我々の精神自然発動の体験ができるはずがない。(森田全集 第5巻 584ページ)森田先生は稽古や練習は神経症の克服には何の役にも立たないと言われています。本当にそうなのかという疑問が湧いてきます。剣道などの武芸では稽古を積み重ねて技術や能力の向上を図ります。楽器演奏でも本番に向けて暗譜で演奏できるまで何回も練習を重ねます。野球、体操、シンクロナイズドスイミング、フィギュアスケートの選手たちも練習に余念がありません。繰り返し練習しなければ、本番では高い確率で失敗します。森田先生が言われている稽古や練習の真意はどういうものでしょうか。森田先生は、神経症を克服するための行動を否定されています。「生活に実際に役立つ行動」「生活するうえで必要な行動」「目の前の目的を遂行するための行動」を勧められています。つまり、目的にかなった行動、ものごとに即した「目的本位」「物事本位」の行動を勧めておられます。神経症に陥ると、不安・恐怖していることに注意や意識を向けています。そのままにしておくと精神交互作用でどんどん症状は悪化してきます。神経症の苦しみから逃れるために、注意や意識を外に向けて動き回るというという方法があります。確かに注意が症状から離れると楽になります。私の体験では症状で苦しい時はそれで構わないと思います。但しいつまでもそれを続けていると、むしろ神経症は悪化の一途をたどるように思います。一時的には効果がありますが、そのうち効き目がなくなり症状は悪化していくのです。森田先生は、神経症を治すための行動ではなく、必要なときに、必要なことを、必要なだけするのが修養であると言われています。「症状から気を紛らわせる行動」「神経症を治す」ことを目的としている行動は、「ハツカネズミが糸車を回す」ようなことになります。エネルギーを使い果たして疲れるだけです。不快な感情や気分は、自分の意思とは無関係に湧き上がってくる自然現象です。それを自由にコントロールするのではなく、不快な感情や気分はあるがままに受け入れて、実際の行動はそれとは切り離して目の前のなすべきことに手を出していく。森田理論学習の要点の行動の原則に、「感情と行動は別物」というのがあります。これは「感情と行動を分離する」ということです。感情を主観的事実とすれば、行動する時は客観的事実を考慮する必要があります。主観的事実と客観的事実のバランスをとるように心がけると問題行動が少なくなります。バランスをとるためには、客観的事実を優先するようにすればうまく収まります。
2025.07.12
コメント(0)
-
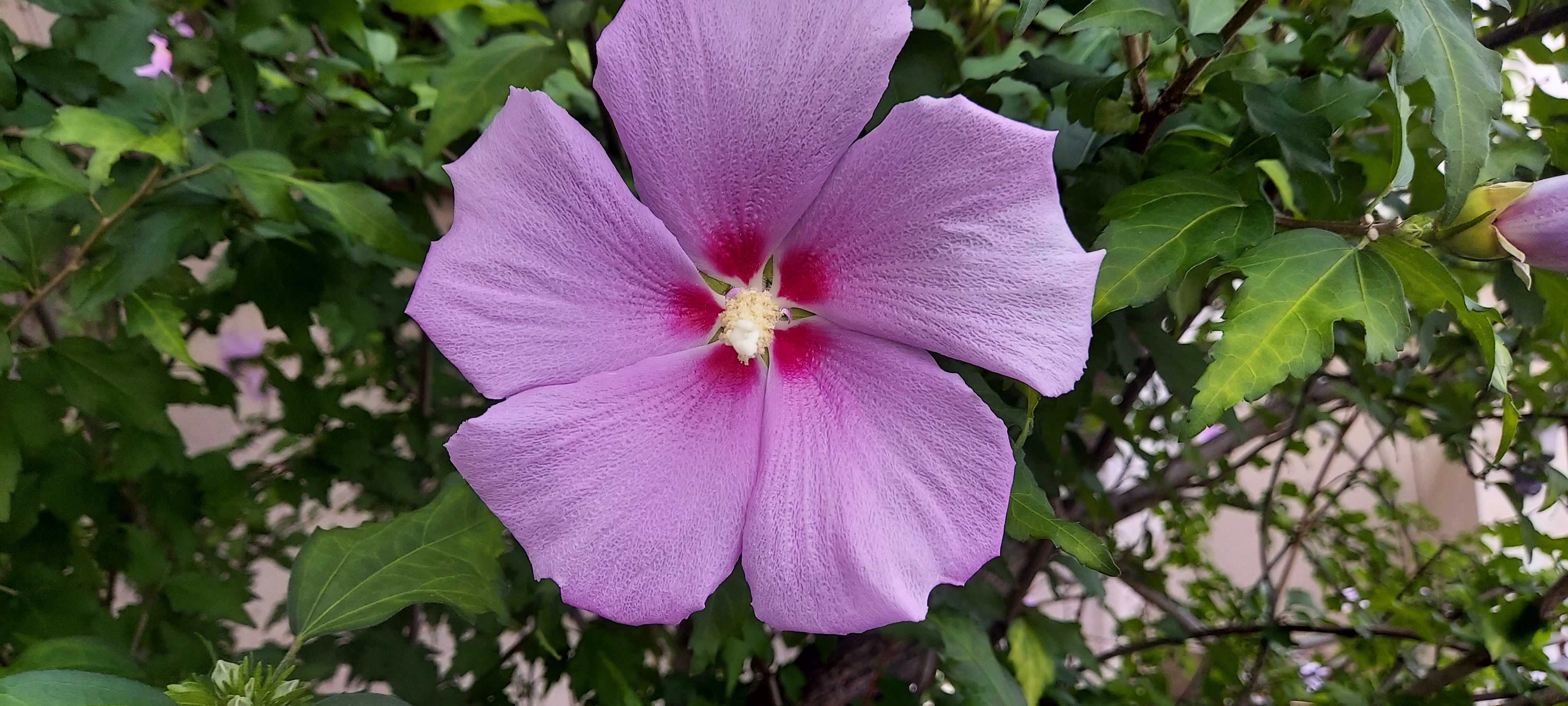
適度なストレスや不安は必要不可欠なものです
ストレスは嫌なものですが、ストレスが全くない状態はもっと悪い。アメリカの心理学者が行った興味深い実験がある。温度も一定で音も光もにおいもない特殊な部屋に実験協力者に入ってもらい、身体や心の反応を調べました。人間が、感覚刺激の全くない環境で過ごすと、どういう状態になるかを実験したのです。実験の報告書によると、おおむね90時間経過すると、実験協力者は性別や年齢を問わず、心や身体に新たな刺激を与えても、身体の反応が極めて鈍くなった。室内の気温が変化しても、汗を出したり鳥肌を立てて体温を調整する能力が著しく低下した。これは、外界からの刺激がないために、刺激に対応する能力が急速に低下したものと考えられる。また、周囲への警戒感が全くなくなり、非常に暗示にかかりやすい状態になっていた。外から何かを指示されると、間違った指示でも疑いもなくそれに従い、「もう立っていられない」と言われると、言葉通りの足の力が抜けてしまうようにまでなった。幻覚や妄想といった精神異常現象を口にする協力者も多かった。(図解解説ストレス 渡辺由貴子。渡辺覚 ナツメ社 192ページ)ストレスがなくなった渡り鳥の話は怖い。野生の渡り鳥に人間が餌付けをして見せものにすると、鳥は餌を求めて飛び立つことを止めてしまいます。そのうちブクブクと太り、飛び立つこともできなくなる。渡り鳥はシベリヤに戻ることを放棄してしまう。卵を産もうとしなくなる。温めようともしない。つまり子孫繁栄には興味がなくなってしまうのです。子育ては面倒なもの、自分たちの楽しい生活を維持するための足かせになるものだと考えるようになる。今だけ、自分たちだけが満ち足りた生活を満喫できれば、後がどうなろうとかまわないと思うようになる。ストレスがない状態に慣れてしまうと、たくましく生きる力を失い、最後には鳥たちは命を絶たれてしまう。これは鳥たちだけではありません。人間も同じことが言えます。ストレスと同様に不安もなくてはならないものです。不安はリスク管理に役立っています。森田で「不安は安心のための用心である」と言います。現実的な不安が湧き上がってきたら喜ぶべきことです。すぐに対応できることはすぐに手を付ける。命にかかわる危険や危機を察知したら一目散に逃げる。今すぐにできないことは、メモして後日対応する。自分一人で対応できそうになければ協力者に相談する。現実的な不安は放置していると、命を危険にさらします。次に神経症的な不安は、どんな欲望を持っているかを考えてくれる。その欲望を向上発展させていくことで生きがいを感じることができる。対応不可能な不安に振り回されていると、精神交互作用によって増悪していくというからくりは森田理論が教えてくれている通りです。そして、一旦アリ地獄に落ちてしまうと、生活の悪循環、観念上の悪循環が繰り返されて、無為の人生が口を開けて待っています。欲望の暴走に待ったをかけてくれているのが不安や恐れです。不安や恐れは欲望の暴走を制御するという大きな役割を果しています。欲望は際限なく追い求めてもよいというものではありません。欲望は主観的事実で大切なものですが、その裏には客観的事実があります。主観的事実を尊重しつつも、行動するにあたっては客観的事実との調和を図ることが欠かせないのです。
2025.07.11
コメント(0)
-

☆勝敗の8割は試合前に決まる
西田文郎氏のお話です。「勝敗は、試合前に80%決まる」これは長年、多くの選手やチームを見てきた私の結論です。試合前のコメントや直前の様子を観察できれば、どんなスポーツでも80%の確率で勝敗予想が的中します。なぜなら選手の言葉や動作、表情には、そのときのメンタル状態が明らかにあらわれるからです。言い換えれば、これから試合にのぞむ選手のメンタル状態は、その場のテクニックでどうにかなるものでものではなく、前の試合が終わった時点から、次の試合直前までにどんな時間を過ごしてきたかで決まるということです。(No.1メンタルトレーニング 西田文郎 現代書林 200ページ)練習段階では問題ないのに、本番の試合になると、「あせり」「力み」「ガチガチ」「頭の中が真っ白」「カッカして何が何だか分からなくなる」という人がいます。極度に緊張して、身体が金縛りになったような状態です。前頭前野がしゃしゃり出てきて「おまえ、本当に勝てるのか。最高のパフォーマンスをだすことができるのか」と問い詰めてきます。練習不足の場合、絶対的な自信がないので、益々不安になります。できればそこから逃げてしまいたい気持ちになる。そして予想通り失敗をして自己嫌悪、自己否定で苦しむことになります。本番前に「よし、やるってやる」「一心不乱になれる」「体が思い通り動く」「ワクワクしている」「たくさんの拍手がもらえるぞ」といったポジティブな心境になるためにはどうすればよいのでしょうか。そのためには徹底的な練習が必要だと思います。その練習量は無謀とも思えるような「数値目標」を掲げることがポイントです。明確な「数値目標」がないと、途中で自分に妥協してしまうからです。たとえば459回の練習を積み重ねると決めたら、数を正確にカウントしながら、たんたんと練習を積み重ねていくことです。ちなみに459回の練習を積み重ねると成功確率は99%になるそうです。詳しいことは2025年6月6日の投稿記事をご覧ください。練習を繰り返すことになんの意味があるのかと思っても途中で止めてはいけません。すると「徹底的に練習を積み重ねて自分を追い込んだのだから絶対に大丈夫」という気持ちになれるのです。また練習を重ねていると、微かな不安が湧いてくることがあります。小さな気づきや発見、問題点や課題、改善点や改良点が湧き上がってくることもあります。これらは神様が与えてくれた宝物です。練習がある程度進んでこないとこれらに気づくことは難しいです。それらを随時解消することでまた一歩成功に近づいていくのです。スビートスケートの小平奈緒さんが言われるように120%の練習を積み重ねて、本番では80%のパフォーマンでも勝てるという状態に仕上げると、本番では落ちついで演技することが可能になります。仲間に誘われてウクレレ教室に参加しました。見るのとやるのは大違いでした。とりあえず1つの曲を459回練習することにしました。
2025.07.10
コメント(0)
-

どんな書類でも30秒以内に取り出す整理術
私はブログを書く時にテーマが決まったら、自分の学習ノートや森田関係書籍の中から参考文献を取り出して思索・検討するようにしています。たとえば「純な心」について投稿しようと思ったとき、自分の考えだけでは心もとない。多くの人の考え方を比較検討して膨らませたほうが真実により近づくことができます。そのときすぐに「純な心」に該当する参考文献をいかに多く取り出せるかどうかは、時間を効率的に使うという面から見てとても重要になります。現在の私の実践例をご紹介します。「現代に生きる森田正馬の言葉①、②」(生活の発見会編 白揚社)があります。この本はテーマ別に森田正馬の言葉を整理してあります。5巻からの引用記事が飛び抜けて多い。この本は大いに活用できます。この本から森田全集5巻の引用箇所にすべてマーカーで印をつけています。その時どういうテーマに分類されているかを書いておきます。ちなみに5巻は分厚い表紙がついています。これでは手軽に持ち歩くことできません。私は断腸の思いで3冊に分割しました。俄然使い勝手がよくなりました。次に、目的の記事をすぐに探せるように、キーワード毎に整理しました。例えば「596ページ 純な心」と記載しておくと、すぐに目的の記事を見ることができます。インデックスとしては、「実践・行動」「無所住心」「変化への対応」「リズム・緊張と弛緩」「精神拮抗作用・不即不離・両面観」「生の欲望」「物の性を尽くす」「純な心」「認識の誤り」「事実唯真」などに分けています。自分が使いやすいように分類して整理しておくことが肝心です。気がついたらその都度補充をしていくとよいと思います。このブログは投稿件数が5300件を超えました。過去の記事をリニューアルして再度取り上げたいときがあります。その時に役立つのは、14項目に分類・整理しているファイルが役に立っています。その日の投稿記事は全て14項目のどれかに振り分けています。重要度、投稿日、簡単な投稿内容等を記載しています。ちなみに次の14項目です。①事実唯真、あるがまま②「かくあるべし」について③感情の法則、純な心④行動のポイント、今ここ、変化対応、リズム⑤子どものしつけ、教育⑥治るとはどういうことか、心身の健康問題⑦趣味、家庭菜園、川柳、ユーモア小話⑧神経質性格の活かし方⑨人間関係、不即不離⑩生の欲望の発揮、人生観⑪認識の誤り⑫脳神経の仕組み⑬不安と欲望の関係、精神拮抗作用、両面観、主観的事実と客観的事実⑭物、己、他人、お金、時間の性を尽くすこれらは森田理論の核心部分だと思っています。その他ブログにはキーワード検索があります。これも重宝しています。以前は発見誌もインデックスをつけて整理していました。何年何月号 ページ数、記事の内容などです。簡単なメモです。特に内容がよいものは永久保存版として切り離して、項目別に整理していました。不要なものは焼却処分しました。何しろ40年近く発見誌をとっているのですから、すべてを保管しておくのは大変です。どんな書類も30秒以内に取り出すという挑戦は、分類やインデックスをどのようにつけるかというのがポイントになると思います。大分類、中分類、小分類に分けて、インデックスをつけていくのは手間がかかりますが、一旦作ってしまえばあとはファイルするだけですから意外と簡単です。もう一つの注意点としては、分類したものは定期的に、棚卸と称して時々内容確認をすれば、意外な宝物が見つかることがあります。
2025.07.09
コメント(0)
-

試合の後で「してはいけないこと」「しなければいけないこと」
スポーツや勝負事に挑戦すると勝ったり負けたりします。終わった後「してはならないこと」と「しなければいけないこと」があります。西田文郎先生の話をもとにして整理してみました。【負けた時にしてはならないこと】・敗因を作った自分を否定をする。後悔や罪悪感で苦しむ。・敗因を作った監督やコーチや仲間を誹謗中傷する。・敗因について仲間と意見交換や議論し合うこと。・口に出したり態度に出してしまう。・これをやると次の試合に悪影響がある。「次の試合には絶対勝たなければ」という気負いが生まれて過緊張を招きやすい。・負けた試合をいつまでもネガティブに振り返らないようにする。・否定することは百害あって一利なし。【負けた時にしなければならないこと】・悔しい気持ちが湧き上がってきたら、その気持ちをごまかさないで一旦きちんと味わう。そうしないとストレスとして残り次に進めなくなる。「悔しい」「悲しい」「もう一歩だった」「力不足だった」などの気持ちです。ネガティブな気持ちを出し切り、心が空っぽになると、次の目標への意欲がやってくるのです。・気分転換を図りすぐに忘れるようにする。・課題や問題点、改善点や改良点、修正点をきちんと分析して共有化する。・次につながる建設的、創造的な反省は大いにする。【勝ったときにしてはならないこと】・勝った瞬間に喜びを表すのは構わない。できれば控えめにする方が顰蹙を買わない。・またいつまで勝利の余韻・美酒に浸っていてはいけない。・いつまでも勝った時のビデオを見て、ニヤニヤ悦に入ってはいけない。いつまでも余韻に浸っていると精神はすぐ緊張状態から弛緩状態に変化してくる。逆に弛緩状態から緊張状態に切り替えるには時間がかかる。【勝ったときにしなければならないこと】・勝った瞬間は嬉しさを体いっぱいで味わう。できれば仲間とともに喜び合う。・一区切りついたら、次の試合予定に合わせて、着々と準備を積み重ねていく。・試合に臨む前から、次に目指すべき目標をいくつか持っておくことが大事になる。・つまり精神が弛緩状態に陥らないように細心の注意を払うようにする。・緊張状態と弛緩状態の波をできるだけ少なくする。(No.1メンタルトレーニング 西田文郎 現代書林 202から206ページ参照)
2025.07.08
コメント(0)
-

劣等感や優越感をどう取り扱うか
誰でも人と比較して劣等感や優越感を抱きます。劣等感は自分と他人を比較して、自分が劣っていると感じることです。そして、自己卑下、嫉妬心、妬み、他者攻撃、孤立感等で苦しみます。つまり自己嫌悪、自己否定している状態です。一旦劣っていると判断すると、その部分を隠すようになります。あるいは、取り繕うようになります。必死に隠しても他人には見えていることが多い。夜中に部屋内から外は見えませんが、外から明かりのついた部屋内のことはよく見えるようなものです。隠すことで信頼感を失っているのですが、自分の欠点や弱点を目立たないようにしないと、仲間として受け入れてもらえないと潜在意識で思っています。人に好かれている人は、自分の欠点や弱点を認めて、あるがままに公開していることが多い。優越感は自分と他人を比較して他人を上から下目線で眺めている状態です。他人を心の中では軽蔑している。他人を否定している。他人を自分の意のままにコントロールすることにつながります。傾聴、共感、受容、許容する気持ちにはなりません。それどころか、逆に欠点や弱点を指摘して修正するよう迫っています。自己顕示欲が強く、プライドが高く、鼻持ちならない人として敬遠されるようになります。この状態はアドラーのいうタテの人間関係であり、勝つか負けるかをかけて戦うモードに突入します。助け合う、許し合うというヨコの人間関係もあるということは考えつかなくなります。劣等感と優越感はコインの裏表の関係にあります。劣等感の強い人は優越感の強い人でもあります。特徴としては、いずれも根底には現実、現状を嫌悪して否定しています。劣等感は自分を否定し、優越感では他人を否定しているわけです。この感情は自然現象ですからどうすることもできません。感情の取り扱い方は、森田理論学習で理解されていることと思います。自然に反旗を翻している限り私たちに勝ち目はありません。それなのに巨大な人間と見間違って、水車に飛び込んでいったドン・キホーテと同じようなことをしています。では具体的にどうすればよいのでしょうか。森田ではどんな不快な感情も自然服従の立場です。台風がきたときに立ち向かっていく人はいません。ただ通り過ぎるのを家の中にいておとなしく待っているだけです。逃げたり、格闘しないであるがままに受け入れていくだけです。間違っても外出してはいけません。「自分は人と比べて能力的に劣っている」「人をまとめる力がない」「学力面で劣っている」「容姿面ではかなり見劣りがする」「人前でオドオドしてなさけない」などという感情が湧き上がってきたとき、そんなことを感じてしまう自分と少し距離を置いて客観的に眺めることです。ネガティブな感情が湧き上がってきたことを価値批判しないで認めることです。森田ではこのことを自覚を深める(気づく)と言います。他人を見て、「彼は能力的に劣るな」「優柔不断で自分の意見を持っていないな」「頭が悪いな」「ガンや血管障害のある家系だな」「三枚目だな、美人とは言えないな」「消極的でやる気が感じられないな」と感じても自然現象なので何も問題はありません。感じてしまう自分を否定しないで、第三者の立場に立って、今の自分は他人のことをネガティブに感じているのだなと眺めることができれば上出来です。あとは森田理論や認知療法などを使って気づきや自己洞察を深めるようにすれば万全です。
2025.07.07
コメント(0)
-

潜在意識が思考や行動を支配している
ブルース・リプトン博士のお話です。イヌを訓練して、ベルの音を聞けば出すようにしたパブロフの古典的な実験のことを考えてみよう。パブロフはまず、ベルの音いう刺激と食物という報酬を組み合わせてイヌを訓練した。その後、食物を与えずにベルの音を聞かせた。イヌは訓練により、ベルが鳴った時は食物をもらえるというふうにプログラムされ、食物もないのに反射的に唾液を分泌するようになる。これは明らかに「潜在意識」で学習した反射的な行動である。(思考のすごい力 ブルース・リプトン PHP 212ページ)ブルース・リプトン博士曰く。人間は学習する能力はたいへん進んでいる。私たちは他人の思考や行動パターンから知覚の仕方を教わることがある。ひとたび他人の知覚を受け入れ、それが真実だと思ってしまうと、他人の知覚が自分の脳内の回路として固定してしまい、自分の「真実」となってしまう。もし親や養育者の思考や行動パターンが誤っていたらどうなるか。その場合、脳は誤った知覚をダウンロードし、潜在意識は刺激に対する反応を繰り返すことになる。潜在意識にプログラムされた誤知覚は、分析・検討されることなく習慣として存続し、私たちは、不適切でしかも制限された行動に縛られていることになる。ブルース・リプトン博士は、次のような興味深い説明をされている。人間の潜在意識の形成は母親の胎内にいるときから始まっている。生後7歳までの両親、養育者、幼少期の経験、周囲の環境によって形成される。私たちの行動の95%は潜在意識によってコントロールされている。そのうち70%は悲観的、否定的、ネガティブなものである。親や養育者などから、自己否定感を高める育て方をされた。悲観的、否定的、消極的、現状維持に甘んじるものの見方を植え付けられた。社交不安障害、無責任、無関心、無作法、自己中心的、本能の暴走、感情や気分にとらわれる。これらが幼少期に潜在意識に刷り込まれた場合、その人はその後生きづらさを抱えて苦難の人生が待ち構えていることは容易に想像できる。一旦形成された潜在意識は書き換えることは困難であるが、決して不可能というわけではない。ブルース・リプトン博士は、潜在意識に蓄積されたネガティブな信念や思考パターンをポジティブなものに置き換えることで人生をより良く生きることを目指します。このことを潜在意識の「再プログラミング」と言います。具体的には、自己肯定感を高めて自信を高める。成長思考を高める手法をとります。実際にはアファメーション、マインドフルネス、ビジュアライゼーションなどがあります。潜在意識が多少なりともポジティブなものに置き換われば楽な生き方に変わってきます。7歳までに形成された潜在意識によって、誤った思考(顕在意識)が生まれ、ネガティブな感情が発生しているという事実は大いに検証してみる価値があると考えています。
2025.07.06
コメント(0)
-

意欲的になれないことにどう取り組むか
森田先生のお話です。理屈で考えると、いやいやながらする事には間違いが多く、いやな心を取り直しておいて、朗らかにやればよくできると思うけれども、実際においては「思想の矛盾」となり、その結果は必ず間違いだらけになるのであります。(森田全集 第5巻 554ページ一部分引用)気が進まない・やる気が起きないけれどもしぶしぶでもやらなければいけないことはいくらでもあります。意欲がわかないというのは、扁桃体で「嫌い・不快」と判定された情報が、青斑核に送られ神経伝達物質ノルアドレナリンが脳全体に拡散されています。つまり防衛系神経回路が盛んに活動している状態です。モチュベーションが上がらないのは当然です。それは肝心の脳が行動の抑制をしているからです。この時、やる気が出ないので、逃げてしまう、あるいはその気持ちを朗らかに変えようと考えるのは、森田先生が指摘されているように無理があります。良識のある大人は最低限の日常茶飯事や与えられた仕事や勉強などに取り組むことが欠かせません。でも気がすすまないと思いながら行動すると、ミスや失敗をすることが多くなる。行動しないで静観していたほうがよかったということになるのではないかと考える。そう考えると、手も足も出なくなるのです。では、やる気が出ないときどうすればよいのでしょうか。またこの時に立ち上がった、「嫌い・不快」という感情にはどう対応すればよいのでしょうか。普通に考えると、一旦「嫌い・不快」と判定された感情が、「好き・快」という好ましい感情に変わることはないはずだと決めつけているのではないでしょうか。一旦「嫌い・不快」と判定されたものが、途中で「好き・快」に変わる場合もあり得るということが分かっていたら話は違います。皆さんに次のような経験はありませんか。最初は自分には無理だと思っていたが、実際にやってみたら意外と簡単にできた。あるいは、こんな簡単なことは誰でもできると思っていたが、次々に問題がでてきて、これは意外と難しいということが分かった。親や先生やコーチから無理やり押し付けられたことを渋々やっているうちに、面白くなって我を忘れて熱中していた。仕事に対して無気力でやる気が起きなかったが、自分のミスでお客様に損害を与えて、それを挽回しようとしていたら我を忘れて仕事に没頭していた。これらは最初人から言われたことを渋々やっていたとしても、その後の経過のなかで自分の目標を見つけることができれば、意欲ややる気に点火されるということだと思います。最初のとっかかりはイヤイヤ・シブシブでも一向に構わないのです。しかしその状態がいつまでも続くと精神的には辛くてストレスだらけになります。精神も身体も疲弊してきます。渋々と取り組む中で、気づきや発見、問題点や課題、改善点や改良点がないかなと思いながら取り組むと、「嫌い・不快」が「好き・快」に変わる可能性があるということになります。「好き・快」という情報が扁桃体から腹側被蓋野に送られると神経伝達物質ドーパミンによって、報酬系神経回路が脳内を駆け巡ります。特にやる気の司令塔である側坐核、帯状回、前頭前野など(A10神経群)が一挙に活性化されます。このからくりが分かっていれば、気がすすまないことにもなんとか手が出せるようになるのではないでしょうか。
2025.07.05
コメント(0)
-

☆主観的事実と客観的事実の調和
森田先生のお話です。「宇宙の現象は、すべてただ、発動力と制止力とが、常に平衡状態にあるときにのみ、調和が保たれている。天体にも物質にも、引力と斥力あって、その構造が保たれ、心臓や消化器にも、亢進神経と制止神経とが、相対峙し、筋肉には、拮抗筋の相対力が作用して、はじめてそこに、適切な行動が行われている。我々の精神現象も、けっしてこの法則から離れることはできない、私は特にこれを精神の拮抗作用と名づけている。欲望の衝動に対しては、常にこれに対する恐怖・警戒という抑制作用が相対している。欲望の衝動ばかりが強くて、抑制の力が乏しければ、無恥・悪徳者・ならず者となり、欲望が乏しくて、抑制ばかりが強ければ、無為無能・酔生夢死の人間として終わる。この衝動と抑制が、よく調和を保つときに、はじめてその人は、善良な人格者であり、その衝動が強烈で、したがってその抑制の剛健な人が、ますます大なる人格者である。(現代に生きる森田正馬の言葉② 白揚社 261ページ)森田先生は精神拮抗作用は自然現象であって、誰にも起こる普通の心理であると言われている。これを理解して普段の生活に活用・応用しなければならないと言われています。私はこの言葉を理解するにあたり、「主観的事実と客観的事実の調和」と捉えている。精神拮抗作用という言葉よりも、こちらの言葉の方が実感としてぴったりする。例えば、私はアルコールが好きである。集談会に参加している一つの楽しみは居酒屋での懇親会があるからである。その居酒屋には90分飲み放題のコースがある。主観的事実としては、思う存分お酒を飲むことができると思うとテンションが上がる。しかし今まで勢いにまかせて、飲み過ぎて失敗を繰り返してきた。意識がなくなり、鞄を紛失したことがあった。ケガをしたこともある。ベンチでそのまま寝ていたこともあった。二日酔いになって、酒がそのまま残ってしまった。翌日の大事な仕事などができなくなった。などなど。多くの失敗体験をしていたにもかかわらず、主観的事実だけで酒を飲んでいたのである。森田で「主観的事実と客観的事実の調和」を学習したとき、私は「客観的事実」が眼中になかったことがよく分かった。「主観的事実」の片肺飛行をしていたのである。「客観的事実」は理性・理知のことだと思う。森田先生も理知で調整しなさいと言われている。二日酔いにならないためにはどうするかを考えて実行すればよいのだ。自分でよい考えを思いつかなければ人に教えてもらえばよい。次のような対策を立てた。①一気飲みは止める。②最初の一杯目はおおむねみんなが飲み終わった後に飲み干す。③ビールを飲む時は同じ量のお冷を飲む。これは酒豪と言われる女性に教えてもらった。大きな効果がありました。まさに目からうろこです。④飲む前におにぎりを1個食べておく。⑤最初は飲むよりも、海鮮サラダなどを食べる。⑥二次会に誘われても、「明日大事な仕事が控えているので」と言って帰宅する。これで「主観的事実と客観的事実の調和」ができるようになった。森田理論を応用・活用できるようになることは、ひとつの能力を身に着けたようなもので嬉しい限りです。
2025.07.04
コメント(0)
-

スマートフォンの長時間の使用は脳を劣化させる
東北大学の川島隆太教授のお話です。スマホなどでインターネットを利用する時間が長い子供ほど、利用頻度が低い子どもに比べて、脳の発達が阻害されるというデータが出ています。言葉を司る前頭葉と側頭葉の発達が右脳も左脳も止まり、白質という情報伝達の役割を果す部分も、大脳全体にわたって発達が止まっていました。川島教授は学習用タブレット端末の使用時間と学力の関係を調査している。(毎日3時間以上学習する、小学3年生から中学3年生13001人を調査)これによると1時間以内の利用者は偏差値が55に伸びている。しかしその後使用時間が増えるにしたがって偏差値が減少している。3時間以上使用している人では45になっていた。東北大学の学生の中にも依存症のようにずーとスマホをいじっている人達がいますが、彼ら彼女らの脳を調べると、明らかな白質の変化が見られました。つまり若くして脳の老化が始まっているということです。さらに心理学の専門家に調査に入ってもらったところ、スマホに触れる時間が長い学生は、自尊心、自己肯定感や共感性が低かったり、感情の抑制ができなかったり、神経症状が出ていることも分かりました。原因として、デジタル端末の長時間の操作が特定の遺伝子に影響を与えて、脳の発達を抑制しているのではないかということがある程度分かってきました。お茶の水女子大教授の内田伸子教授は、アメリカのペンシルベニア州で健康で生まれた1800人の子どたちのその後の6年間の追跡調査を紹介されている。そのうち、約300名(6人に一人)に言語や認知の機能の明らかな遅れが見られました。その子どもたちは生後6か月以降、1歳まで早期教育ビデオを一日一時間以上見せられていたことが分かりました。生後6か月頃の赤ちゃんはほとんど寝ていますから、起きている時間は、ずっと光と音の騒がしい映像の中で生活していたということになります。それでファンクショナルMRIで子どもたちの脳を分析すると、言語を理解する脳のウェルニッケ野のネットワークが作られていなかった。これでは他人の声が雑音のようにしか聞こえなくなります。また落ち着きのないなどの行動特性も見られました。幼児期に映像を見せっぱなしにしていたことで、特別なサポートが必要な問題児にさせられてしまったのです。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 6月号 27ページ)スマートフォンの長時間使用は、電磁気の悪影響も指摘されています。幼児期のテレビや映像の長時間の視聴は深刻な精神障害をもたらしていることは驚きました。それよりは絵本の読み聞かせを続けていると子どもの脳は大いに鍛えられるようです。
2025.07.03
コメント(0)
-

☆マインドフルネスの「観察する自己」と「脱同一化」の関連性
マインドフルネスに「観察する自己」という考え方があります。マインドフルネスにおける「観察する自己」とは、自分の思考、感情、身体感覚などを、まるで空に浮かぶ雲を眺めるように、評価したり判断することなく、ただありのままに気付いている意識のことです。普段、私たちは思考や感情に巻き込まれやすく、「嫌な気分だ」と感じたらその感情にとらわれ、「こんなことを考えてしまう自分はダメだ」などと自己批判に陥りがちです。「観察する自己」では、これらのネガティブな思考や感情と同一化しないで、一歩引いた場所から客観的に捉えます。イメージとしては、映画館で映画を見ている時のことを想像してみて下さい。スクリーンに映像(ネガティブな思考や感情)は常に変化しますが、見ている自分(観察する自己)は、第三者の立場から冷静にその変化を見守っています。感動するシーンはいくつもありますが、スクリーンのなかの役者と完全に同一化しているわけではありません。この考え方は心理学でいう「脱同一化」の考え方に似ています。脱同一化とは、自分の思考、感情、感覚、信念、役割など、通常「自分自身」だと捉えているものから、心理的な距離を置くプロセスのことです。これらの要素は、あくまでも一時的な現象や概念であり、本質的な「私」そのものではないという認識を持つことを指します。マインドフルネスでいう「観察する自己」とは、この脱同一化を実践するための心の働きと言えます。ネガティブな思考や感情が湧き上がってきたとき、それに巻き込まれて同一化するのではなく、「ああ、今、私はこういうネガティブな思考をしているな」「今、私はこういう不快感や不平不満を感じているな」と、客観的に観察することで、ネガティブな思考や感情との間に距離を作り出すことができるのです。「観察する自己」も「脱同一化」も、いきなりネガティブな思考や感情に振りまわされるのではなく、その思考や感情を客観的に観察するということです。自分の中にもう一人の自分を作って、もう一人の自分が生身の自分がネガティブに考えていることや感情について自覚する、気づいていくということです。自分一人で無理ならば、せめて信頼できる第三者の客観的な考え方を聞いてみる。注意点が一つあります。湧きあがってきたネガティブな思考や感情に対して、「良い」「悪い」「正しい」「間違い」などといった判断を加えないようにすることです。あくまでも事実本位に徹することです。なお「脱同一化」については、2016年10月13日にも投稿しています。
2025.07.02
コメント(0)
-

「不即不離」の応用は人間関係だけに留まらない
森田先生の「不即不離」という考え方を人間関係の面からとらえられている人が多いと思います。人間関係はそのときの状況によって引っ付いたり離れたりしています。つまり臨機応変に適度な距離感を保ちながら付き合っているわけです。このバランスが崩れると、一方ではベタベタした依存関係に陥ります。他方では、天涯孤独な人生を送ることになります。ひっつきすぎず、離れすぎずの人間関係が無難です。必要に応じて付き合ったり、離れたりするのが人間関係の極意でしょう。さて距離感を意識するという意味では、人間関係以外にもあります。感情との関係・・・不安や恐怖といった感情にとらわれ過ぎず(即)、かといって無視したり抑圧したりするのではなく(離)、それらの感情を「あるがまま」に受け入れつつ、「なすべきこと」に手を出していくということです。自然に服従し、境遇に柔順が森田の考え方です。生の欲望との関係・・・所有欲、支配欲、食欲、飲酒などの欲望を際限なく求め続ける(即)のではなく、かといってすべての欲望を抑圧(離)するのでもない。基本は生の欲望の充足に邁進する。しかし「我唯足知」の言葉のように欲望の暴走には歯止めをかけることが大切です。対象との関係・・・仕事や趣味などに熱中しすぎる(即)のではなく、適度な距離を保ち、心身の健康、人間関係など他の事とのバランスをとる(離)ことが重要です。このように「不即不離」とは、あらゆる対象とのかかわりにおいて、固執せず、かといって切り離さず、主体的に適切な距離感を保つという、より普遍的なあり方のことを言います。森田理論の中に、精神拮抗作用、両面観、主観的事実と客観的事実、迷いの内の是非は是非ともに非なりという言葉がありますが、これ等の言葉が意味するところは、すべてのものごとには相反する2つの面があり、そのバランスを意識して調和を図るという事になります。6月29日(日曜日)ジャガイモの収穫をしました。ちょっと小ぶりですが家で食べる分には支障はありません。ミニトマト、ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャがすくすくと育っています。田舎へ帰り自家用野菜の手入れをするのがとても楽しみです。また、農作業で汗をかいた後のビールが格別です。
2025.07.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










