2025年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
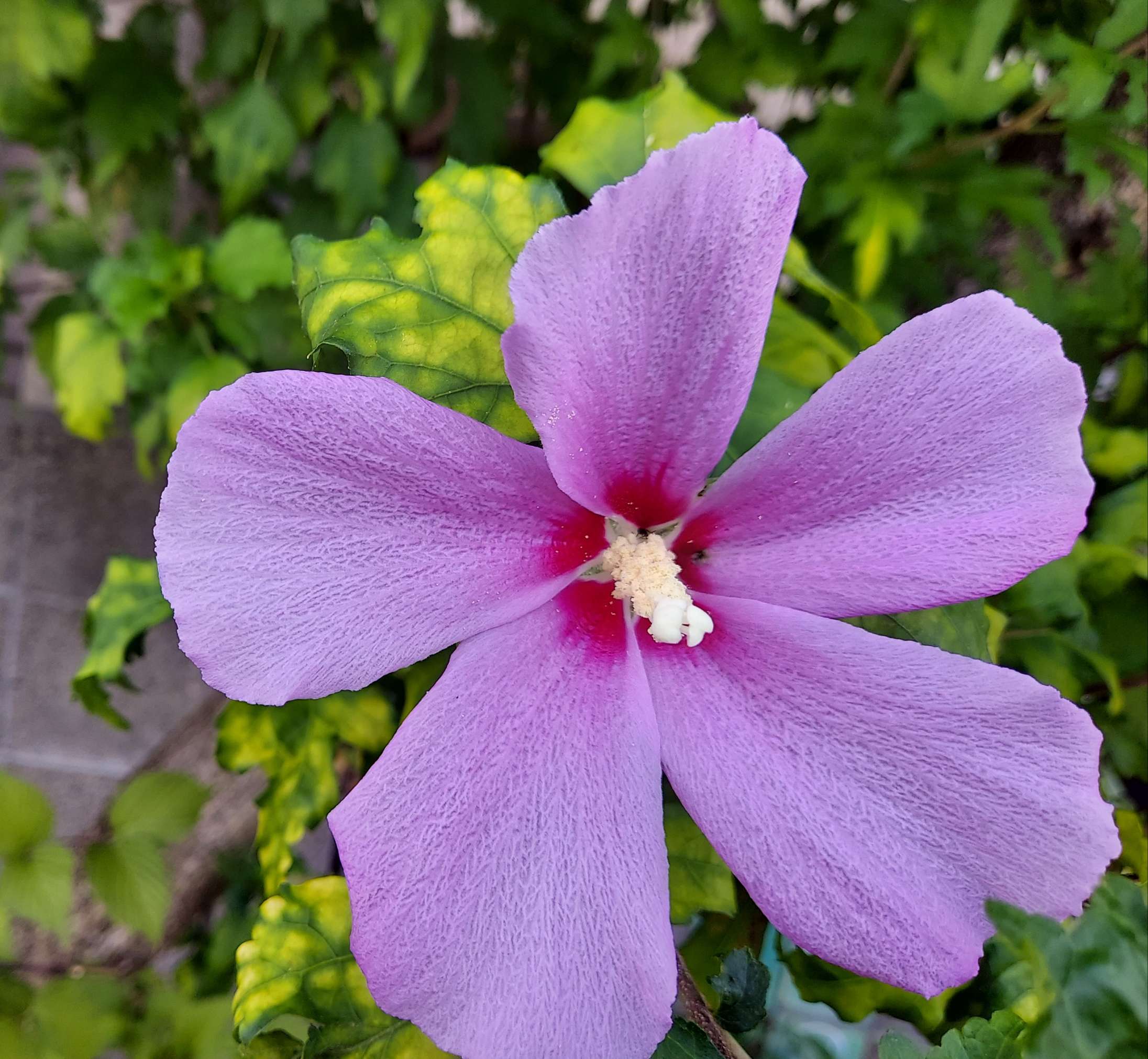
ユーモアスピーチのお勧め
伊丹仁朗先生の生きがい療法では、「ユーモアスピーチ」をとり入れておられます。実例をあげると次のような作品があります。この夏孫のケン太と街を歩いていましたら、ケン太がソワソワして言うんです。「おじいちゃん、撲うにが食べたいよ」驚いて「うに?なんでそんなものが食べたいんだい?」と尋ねると、ケン太は角の店の軒先を指して、「だってほら、あそこにうにって、ぶら下がっているじゃない。シンちゃんもミナちゃんも、あそこでうにをたべたんだよ・・・」ケン太の指先をたどると、そこにあったのは「氷」(うに)と染めぬかれた垂れ幕だったのです。(納得)ユーモアスピーチは、ともすれば内向きでネガティブなことを考えることが多い神経質者を外向きで楽しい気持ちに変えてくれます。まず題材を求めて、注意や意識を外向きに変える必要があります。伊丹先生は、目の付け処として、失敗ネタ、子どもネタ、動物ネタ、旅行ネタ、外国ネタ、外人ネタ、下ネタ、食欲ネタ、趣味ネタ、スポーツネタ、職業ネタ、方言ネタ、名前ネタ、病院ネタ、物真似ネタ、コマーシャルネタ、警察ネタ、ブラックユーモアをあげておられます。ネタが見つかったら、面白い話になるように工夫・脚色します。家族の前などで予行演習を行い、みんなの前で披露します。みんなを笑いの渦に巻き込みましょう。ちなみに私は伊丹先生から刺激を受けて、ユーモア小話、川柳の作成と収集に力を入れている。最後に私の収集作品から、おひとつご紹介しましょう。敬老会で女性司会者が100歳を超えた長寿者にインタビューしました。「元気で長生きするためのコツは何でしょうか」女性に囲まれて上機嫌の男性の長寿者曰く。「しいて言えば、キョウヨウとキョウイクです」「おじいちゃん、なかなか味のあることを言いますね。私もおじいちゃんを見習って、教養と教育を心がけたいと思います」「おいおい、変なこと言うなよ。教養じゃなくて、きょうなにか用事がある。教育じゃなくて、きょう行くところがあることだよ」「おじいちゃん、座布団3枚」「座布団より日本酒にしてくれ」チャン、チャン
2025.09.30
コメント(0)
-

劣等感と優越感の取り扱い
他人と比較して劣っていると思えば劣等感を抱き、優れていると思えば優越感を抱くことがあります。劣等感は他人と比べて自分が劣っていると感じる状態です。劣等コンプレックスとは、劣等感を向上心の原動力にするのではなく、自己嫌悪、自己否定するようになることです。優越感は他人と比べて自分が優れていると感じる状態です。優越コンプレックスとは、自分の優位性を誇示することで、他人を否定して見下すようになります。神経質者の場合は、劣等感的差別観を抱きやすいと言われています。これは、誰でも持っているような自分の小さな欠点や弱点をことさら過大に評価して、これがあっては自分の将来に禍根を残すことになるので、人並みに引き上げようと考えることです。自分で自分自身を全否定してしまうような極端なものの見方・考え方と言われています。劣等感や優越感は自然に湧き上がってくるものでコントロールすることはできません。もともとコントロールできない感情を無理やり操作しようとしているので苦悩や葛藤が生まれるのです。アドラーもこれを否定してはいません。とくに劣等感については、すべての人が持つ、より良い自分になりたいという向上心の原動力になるものであると述べています。つまり劣等感は神様が与えてくれた自分への贈りものと考えていたのです。優越感については、周りの人に感謝の気持ちを伝えるようにすると人間関係が好転します。アドラーは劣等感や優越感を乗り越えるために次の3つのステップを説明しています。1、自己受容 (違いを認めて、受け入れる)良いとか悪いとか評価することをやめて、不完全な自分をあるがままに認めることです。相手と自分の違いを正直に認めることです。2、他者信頼 (他者を仲間だと信じる)たとえ、裏切られる可能性があったとしても、まずは信じることです。相手を信じることで、競争相手ではなく、協力し合える存在としてみることです。相手の行動を「私を攻撃しようとしている」と考えるのではなく、「何らかの目的のために行動している」と理解し、対話の姿勢をとることが大切です。3、他者貢献 (他者に役に立つことをして喜びや感動を分かち合う)自己受容と他者信頼を経て、他者に貢献することで、劣等感から解放されます。他者貢献とは、「人の為に尽くす」といった建前上の目的ではなく、「人の役に立ちたい」「人を笑顔にさせたい」「人に感動を与えたい」という自分の欲求に基づいた目的を設定することが大事になります。そのうえで、「理想の自分との比較」をすることを勧めています。昨日の自分より今日の自分が少しでも前に進んでいれば、それは成長であり、価値があるという考え方です。劣等感や優越感の追及は、他者と自分を比較することから始まります。アドラーは、その比較から一歩踏み出し、他者との「違い」を認めて、互いに「貢献」し合う関係へと意識を転換することで、真の幸福と対等な人間関係を築けると説明しています。
2025.09.29
コメント(0)
-

アドラーの「承認欲求の否定」について
対人関係に問題を抱えている人は、他人の思惑ばかり気にして、自分を窮地に追いやっている場合があります。そんな人はアドラーの「承認欲求の否定」という考えはとても参考になります。人間は誰でも他人から認められたい、褒められたいという欲求があります。その欲求が強くなりすぎると、自分の気持ちや考えや欲求が置き去りになり、他人の言動に振り回されて他人の人生を生きているような状態になります。アドラー心理学では、他人からの承認を一切認めないということではありません。他人からの承認を人生の目標や行動原理にしてはいけませんと言っているのです。例えば、アドラー心理学では「賞罰教育」否定します。賞罰教育とは、良いことをすれば褒美をもらえ、悪いことをすれば罰を与えられるということです。褒美(承認)を求めて行動すると、その行動は「褒められること」が目的になります。褒められなければ、その行動に意味を見出すことができなくなり、やる気を失ってしまいます。逆に罰(非難)を恐れて行動すると、その行動は「罰を回避すること」が目的になります。いずれにしても、他人の言動に振り回されてしまいます。他人からの承認を人生の最大の目的や行動原則としないためにどうすればよいのか。アドラーは「承認欲求」は相手からの評価に一喜一憂するということです。相手が自分をどう評価するかは相手にゆだねられており、コントロールすることはできません。つまり他人の承認を得るということは「受け身」の行動です、他人の顔色をうかがい、嫌われないように振る舞うことに全エネルギーを投入してもよい結果は得られません。アドラーは「共同体感覚」の中で、「他者信頼」「他者貢献」という考え方を提唱しています。相手から仲間として受け入れられ、仲間内の中で自己存在感を高めるためには、「他者に貢献する」ことが欠かせないと言っています。「他者貢献」は、自分の意思によって行う「能動的」な行為です。他者からの反応がなくても、自分が貢献しようとすること自体が、自分の価値を高めることにつながります。アドラーの「承認欲求の否定」とは、他人の評価という「とらわれ」から解放され、「他者貢献」を通じて自己の価値を能動的に実感することで、より自由に、より幸福になるための指針であると言われています。「他者貢献」と言えば、森田理論学習の中で「人の為に尽くす」ということが盛んに言われます。この考え方についてアドラーは警鐘を鳴らしています。仕事や与えられた仕事や役割について、私たちは義務感や責任感でこなそうとします。「人の為に尽くす」というときの目的は、上司や組織、顧客といった「他者の目的」です。他者の目的を達成するために自分の役割をこなすのですが、そこには自分の意思や喜びが伴いにくく、義務感やノルマに縛られた「やらされている」感覚に陥りやすくなります。この状態ではモチベーションは長続きしません。行動の目的を「人に喜んでもらう」「どうすれば相手が笑顔になれるか」「どうすれば感動してもらえるか」という視点から見直す必要があると言っています。他者に喜びや感動を与えるという目的に付け替えると、「受け身」から「能動的」な行動に代わり積極的、建設的、生産的、創造的な行動に変わってきます。集団に受け入れられ、自分の存在価値を発揮して高めることができるようになります。
2025.09.28
コメント(0)
-
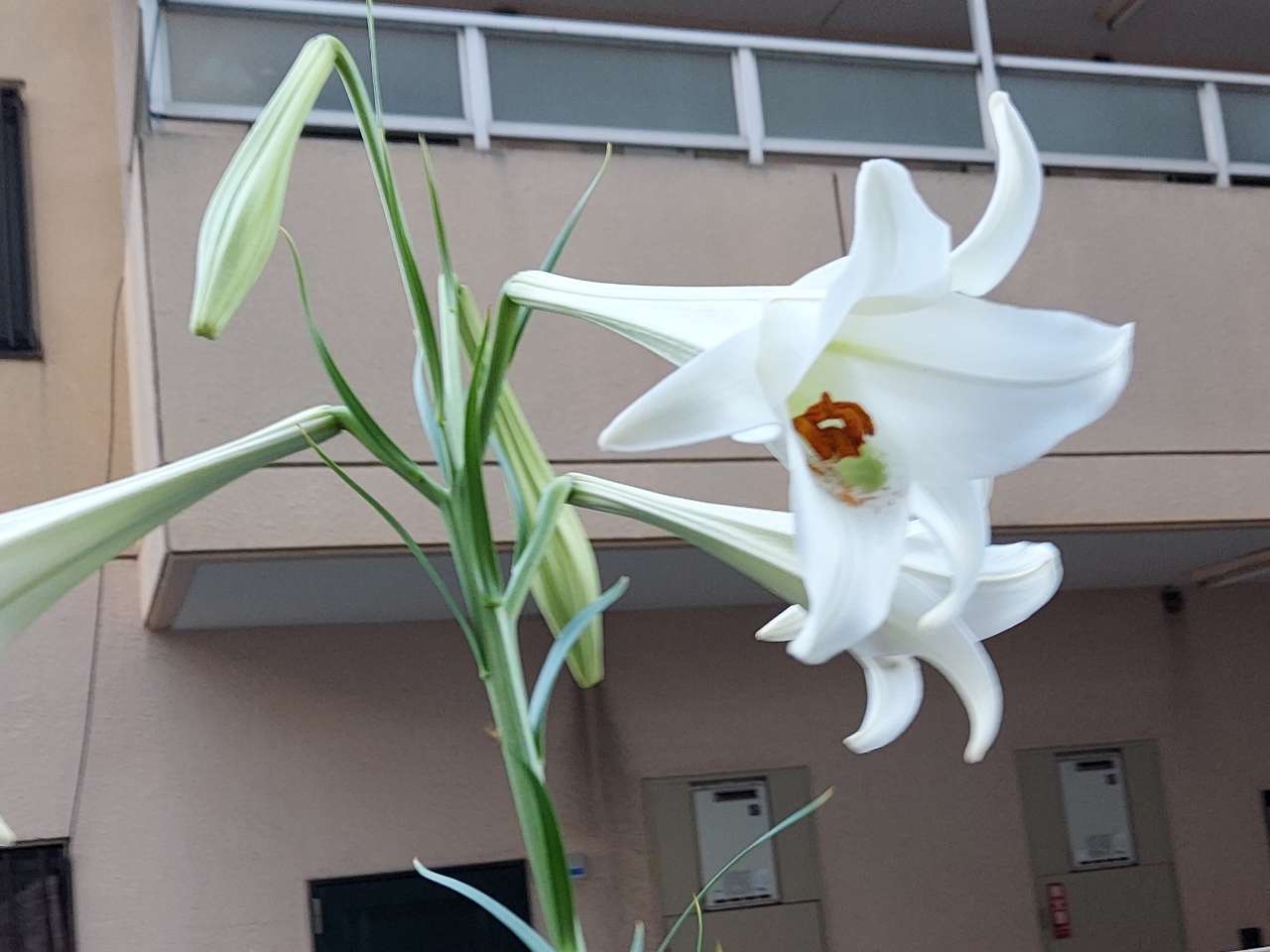
死の恐怖と生の欲望の関係について
森田先生のお話です。我々も昔は、随分長い間、「死を恐れない」という修養に浮身をやつしたのであります。その後ようやくにして、その努力の不可能であるという事を知ると同時に、ただひたむきに、生の欲望に対して突進するという事によって、初めて死の恐怖の影が消滅するということを知ったのである。仕事に対する心のあせりも同様で、そのあせりを取ろうとしては、不可能であるが、ただそのあせるがままに、仕事の能率をあげる工夫にのみ熱中しさえすれば、その間おのずから、あせるという不快の気分を、いつの間にか、忘れてしまっているのである。(森田全集 第5巻 625ページ)死が怖い(肉体的な死だけではなく、社会的な死も含む)という裏には、生の欲望があると言われている。「死の恐怖」と「生の欲望」は、コインの裏表の関係にあるということになります。ですから、「死の恐怖」ばかりを見つめて、なんとかこの苦悩から逃れようとすることは、片手落ちということになります。飛行機でいえば、片方のエンジンが故障して片肺飛行をしているようなものです。2つの側面を過不足なく見ることによって、パニックに陥ることを避けることができます。森田理論の中に両面観、精神拮抗作用、主観的事実と客観的事実の見方・考え方などがありますが、バランスや調和をとることをさまざまな角度から説明されているのです。2つの関係は正比例しています。「生の欲望」が強くなると、当然「死の恐怖」もそれなりに大きくなります。「生の欲望」が小さい場合は、「死の恐怖」も小さくなります。神経質者の場合、「生の欲望」が普通の人と比べて少し強めです。またその範囲も広いと言われています。神経質性格者は、不安や恐怖、違和感、不快感を感じやすいのが特徴です。「死の恐怖」をより強く感じるのは当然なことです。肝心なことは「死の恐怖」と「生の欲望」のバランスをとることです。神経症に陥ると、「死の恐怖」を取り除くことに注力して、「生の欲望」の発揮が蚊帳の外になってしまうことがあります。この方法は「死の恐怖」が無くならないばかりか、益々強くなりより事態が悪化します。森田では「目的本位」を重視します。「死の恐怖」という感情にとらわれるのではなく、いかにしてより良い生活を送り、自己実現していくかという「目的」に意識を向けることです。この「目的」に向かって努力していくことが「生の欲望」に他なりません。「死の恐怖」には手を付けないで、「生の欲望」に力点を置くほうがよいということになります。不安や恐怖、違和感、不快感などの対応も同様です。
2025.09.27
コメント(0)
-

アドラー心理学と森田理論が重なるところ
アドラー心理学では、「人間は社会的存在であり、すべての悩みは人間関係の悩みである」と指摘している。人間関係は「タテ」ではなく「ヨコ」の人間関係に持っていくことが不可欠であると言っています。「タテ」の人間関係は上下の人間関係です。上の人が下の人を支配、指導、評価、命令、非難、否定、叱責、拒否、脅迫、強制するような関係となります。下の人は自分の気持ちや意思を聞いてもらえないので、ストレスがたまり自己嫌悪感が強まります。エネルギーのある人は絶えず反発をくり返すようになりますので人間関係は悪化の一途をたどります。アドラーのいう「ヨコ」の人間関係は、対等性、相互尊敬、相互信頼に基づく関係を指します。お互いの違いを認め、尊重し、協力し合う関係です。生活の発見会の集談会では、先生もいなければ生徒もいないといいます。傾聴、受容、共感、許容の態度で話し合っています。分からないことや困ったことがあれば、みんなで助け合って解決していきましょうという考え方です。そして、お互いに乗せ合い、ほめ合い、たたえ合うようなアットホームな人間関係を目指しています。アドラー心理学に「課題の分離」というのがあります。人はそれぞれ解決すべき問題や課題を抱えています。他人のかかえている問題や課題はその人が解決すべき問題であり、そこに土足で愛り込むようなことをしてはいけないという考え方です。過保護、過干渉、ネグレクト、共依存の関係は厳に戒めています。このアドラーの人間関係の考え方は、森田では自分の「かくあるべし」を他人に押し付けないということになります。その人にはその人の事情があり、自分とは別の考え方を持っているという前提に立って、その溝を埋めるために調整や話し合いをしていくという考え方です。森田には「物の性を尽くす」という考え方があります。これは、物が持っている本来の機能や特性を最大限に引き出して、命つきるまで徹底的に活用するという考え方です。この考え方を敷衍すると、「他人の性を尽くす」ということになります。人間はだれでも優れたところもあれば劣るところもあります。それぞれ自分の長所や得意を活かして居場所を見つけ、その能力に磨きをかけて社会の役に立つ仕事をすることで自己肯定感や生きがいを見つけることができるということです。
2025.09.26
コメント(0)
-

老後を楽しく過ごす方法
老後の有効な時間の使い方がよく分からないという人がいます。暇を持て余し人生を楽しめない人です。次のような特徴があります。①もう歳だから新たなことを手掛ける体力も気力もないと思っている人。今更趣味を見つけることなんか無理だし、無謀なことだと思っている人。②やってみたいことが思い浮かばない。行ってみたいところが思い浮かばない。食べてみたいものが思い浮かばない。欲しいものが思い浮かばないという人。③異性への関心はほとんどなくなったと思っている人。④お金を使う楽しみが思い浮かばない。老後の自己破産に備えて貯えを増やすことに専念しているような人。⑤やろうと思えばできるかもしれないが、「しんどい、疲れる、面倒だ、やる気が出ない」が口癖になっていている人。⑥食料品や生活必需品の買い出しは宅配業者に頼んでいる。食事も自分では作らない。外食、宅配弁当、レトルト食品に頼っている人。⑦持病があり、足が不自由になったので、家に閉じこもっている。杖をついて歩くのが辛いので外出は控えているという人。これに対して、老後は楽しい、仕事から解放され、人生最大の至福のひとときだと思っている人がいます。①とにかく好奇心旺盛。興味や関心の幅が広い。お金をかけない楽しみをいくつも持っている。②60代からウォーキング、階段上り、ストレッチ、体操、ヨガなどを続けており、身体や足がよく動く。ふくらはぎの筋肉がよくついている。④脳トレと称して音読や書き取りを続けている。新聞の7つの間違い探しに興味を示す。④朝晩仏壇の前に座り、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えている。⑤高齢にもかかわらず、軽い仕事をしている。収入は少ないが、心のゆとりが生まれている。⑥趣味を共にする仲間を持っている。軽いスポーツ、カラオケ、囲碁・将棋、絵画、朗読ボランティア、楽器演奏、踊り、料理、花卉園芸、自家用野菜、居酒屋での懇親会、歩こう会、小旅行など。⑦シニア割引サービスの情報をたくさん持っている。自分で利用するだけでなく、人に教えてあげている。市町村やスーパーや家電量販店が行っているポイントサービス、外食、映画館、植物園、美術館、博物館、水族館などのシニア割引サービスなど。⑧地域のイベント、食の祭典、無料の演奏会、図書館などにたびたび足を運んでいる。⑨自分の体験を川柳やユーモア小話に換えて楽しむ能力を持っている。例えば川柳。「先に寝る 安らかにねと 妻が言う」「あちこちで 骨が鳴るなり 古希(こき)古希(こき)と」⑩顰蹙を買いながらも、ちょっとしたダジャレを絶えず披露している。⑪ボランティア活動が好きで、労力の提供、自分の特技を人に教えてあげることに興味がある。私は瀬戸内支部主催の「ボケずに元気で101歳まで生きよう会」に参加することにしました。互いに刺激を与えあい、老後の人生を大いに楽しみたいものです。
2025.09.25
コメント(0)
-

治った人は普段の生活態度を見ればすぐに分かります
森田先生のお話です。森田理論の説明はできなくても、治るということが、第一に必要なことです。私の話はよくわかり、説明がよくできても、実行ができずよく治らない人が時々あるので困ります。しかし治って説明ができれば「鬼に金棒」です。日常生活の万事に応用できます。強迫観念で、さまざまな疑問が多く、煩悶が強くて、これが解決にあこがれ努力した人は、治ったという体験と同時に、その解決と説明ができて、「大義ありて大悟あり」という風に、悟りの境涯になるという事は面白いことです。(森田全集 第5巻 635ページ)私たちは森田理論の理解から入ります。入院森田のやり方とは違います。森田先生は最初から理論を叩き込むというというやり方ではありません。入院患者は机に座り、テキストを開いて学校の授業を受けるような座学はなかったということです。臥褥期間が終わると、軽作業に取り組みました。掃除、洗濯、飯炊き、風呂炊き、小動物の世話などです。これに対して、本人はここまで落ちぶれてしまったかと涙を流すこともあったそうです。また家人が尋ねてきて、憤慨して連れ戻すようなこともありました。それでも、森田先生は納得できないと疑いながらも、私のいう通りにしていると、神経症は治るといわれました。これは何ごとも頭で納得しなければ行動に移らないという人にとって、とてもハードルが高かったのです。森田先生は有無を言わせず無理やり追い込むことをされました。森田先生は、入院患者は観念が先行し、実行力・行動力が乏しいとみておられたようです。行動する時は、頭で十分に納得してから初めて恐る恐る重い腰を上げる。それを逆転させて、理論や理屈はわからなくても、ともかく身軽に身体が動くような体質に変えてしまおうとされていたのです。無謀ともいえるやり方ですが効果てきめんでした。形外会というのは、森田理論の整理・体系化の役割がありました。昭和4年から昭和12年まで66回開かれています。これは主として元入院生たちが、自分たちの今までの行動や考え方の間違いなどを後付けで検証するという意味がありました。ここで初めて森田先生によって理論の裏付けができたのです。体験や体得が先で、後付けで森田理論の整理・体系化が行われていたということになります。ここでは神経症を治すだけではなく、神経質性格者の人生観の確立が問題にされています。理論から入ると効率的で無駄がないように見えます。理論を自分に引き寄せて、生活の中にすぐに取り入れるという人は良いかも知れません。しかし、森田理論を深耕して知識自慢に余念がないという人の場合は、神経症からの解放は遠のくばかりだと思います。ましてや神経質者の人生観の確立は夢のまた夢となります。森田理論を現代に生かすためには、どんなことを心がけたらよいのでしょうか。まず集談会で実践課題の進行状況を話し合うことが必要になると思います。次に先輩会員の中には、森田理論を活用・応用して魅力的な人生を送っている人がいます。その人たちの行動実践を自分の生活の中に取り入れるようにする。また、規則正しい生活習慣を作り上げると、何も考えなくても身体が自然に動いてくるようになります。そのなかで、問題点や課題に気づくようになるとしめたものです。集談会では理論的に詳しい人がいますが、肝心なことは理論と行動の車輪が同じ大きさで前に進んでいるかどうかです。理論の車輪が小さい時は、行動の車輪も小さい。両方の車輪のバランスがとれていることが肝心なのです。それを徐々に大きな車輪に付け替えていけばよいのです。理論的には完璧だが、実践面ではほとんど見るべきところがないというのは、残念なことですが、宝の持ち腐されとなっているのです。
2025.09.24
コメント(0)
-

はからいをやめるために取り組むこと
森田理論は不安な感情、怖い感情、怠惰な気持ち、本能的な欲望、神経症的なとらわれに対しての行動指針を示してくれています。どんな感情が湧き上がってきても、天気と同じ自然現象なので意志の力でコントロールすることはできません。我々ができることは、敵意を持って対抗するのではなく、自分の中の一部だと受け入れ、すべてをあるがままに認めて受け入れることだと学びました。森田先生は「感情の法則」の中で、どんなに不都合な感情でも、拒否・抵抗・はからいをしなければ、時間の経過とともにいずれ消失していくと言われています。これは何度も森田理論学習で学習してきました。耳にタコができるまで分かっているつもりなのに、実際にはそのように行動することはできない。これは、感情はコントロールすることはできないということと、感情はそのうち薄まっていくか消えてなくなるということが言葉の理解だけで終わっているからだと思います。ではどうすればよいのでしょうか。まず感情と行動を別物として取り扱うという覚悟を固めることだと思います。絶体絶命の窮地に立たされると、後がないわけですからそうせざるを得ないことになりますが、そういう状況に身を置くことは現実的には難しい。嫌な感情は人間の習性として、それらを取り除いてすっきりしたいという気持ちを誰でも持っています。昭和天皇が終戦宣言の中で、「堪え難きを耐え、忍び難きを忍ぶ」と言われました。この気持ちを持って対応することです。悔しい思いもある。つらい思いもある。イライラしている。しんどい。それらを打ち捨ててすべてを受け入れることは断腸の思いであることを認める。ひたすら耐える、ひたすら我慢するという覚悟を固める。そうすれば、時間が味方についてくれて、感情が薄まり楽になっていく。その逆の場合も考えておくことです。不快な感情をそのままにしておくことはつらいので、対抗措置を講じるとどうなるのか。スズメバチをつつきまわすと、すぐに反撃されて身体中に毒針を刺される。気に入らないことをされたといって、反社会勢力の人を挑発するとどうなるか。財産を失うだけではなく、命も奪われることになりかねない。どんなに理不尽なことがあっても、怒りや腹立ちで腹の中が煮えくり返っても、売り言葉に買い言葉的な対応は大きな禍根を残すことを肝に銘じておく。北野武氏は、「人間関係には間が必要だ。今の世の中、間抜けな人が多い」と言いました。阿部亨先生は、「人間関係では十分な車間距離を保つことが肝心だ」と言われました。感情はコントロール不能な自然現象なので、手出し無用な代物なのです。怒りの感情は、6秒から10秒で一山登ると言われます。一山登った後は自然に下って行きます。そのために深呼吸をしたり、一時的に席を外してかわすことは意識すれば誰でもできます。それが幼児並の人間と大人として常識のある人間の境目となります。森田理論で感情と行動の分離、気分と行動の分離は是非とも身につけたい項目です。
2025.09.23
コメント(0)
-

「強迫観念」とはどういう意味か
あなたは「強迫観念」とは何ですかと聞かれたとき、どう説明していますか。改めて聞かれると、即座に返答することはすこし難しい。神経症で苦しんでいる人の場合は、暗黙の了解がありますからなんとなく分かります。世間一般の人に説明するのはハードルが高くなります。ここで改めて、整理しておきましょう。強迫観念とは、自分の意思に反して、頭の中に繰り返し浮かんでくるネガティブな感情、恐怖、気分、思考、衝動的な欲望などのことです。別の言葉で言えば、不安を取り除こうとはからい行為をしている時に発生する精神的葛藤のことです。不安、怯え、心配事、悲観的、憂うつ、恥ずかしさ、孤独感、怒り、腹立たしさ、イライラ、不平不満、欲求不満、劣等感、後悔、罪悪感、猜疑心、自己嫌悪、自己否定、無力感、嫉妬心など多岐にわたります。それらが浮かんできただけでは強迫観念で苦しむことはありません。普通の人は、「イヤだけど仕方ないよね」「そのうちなんとかなるだろう」といつまでも深刻に考えていないのです。それよりも目の前の懸案事項を片づけることが優先事項だと思っている。強迫観念で苦しむような人は、目の前のことには手を付けないで、自分に不利益をもたらしているネガティブな感情を何とかしようと考えて行動している。そうしないといつまでもすっきりしない。不快感で身動きが取れなくなってくると考えています。本来の目的を忘れて、手段の自己目的化が起きているのです。本人としては、ばかばかしいことを考えているという自覚があります。しかしその不快な感情などに対してそのままにしておくことができないのです。自分にとって余計なもの、不純物、敵対物、放っておくと将来害を及ぼすものと考えている。そんなものが自分の体に取りついていることは到底容認できない。だからすぐに取り除かなければならないものと考えている。仮に取り除くことができなければ、逃げ回るしかない。本人は意志の力で不快な感情や思考は、自由自在に取り消すことができると信じて疑わない。しかし現実は最初は小さなとらわれだったものが、どんどん大きくなって自分の力では対応できないような化け物のようなものに変わってきている。観念上の悪循環、実生活上の悪循環、人間関係の悪化で窮地に立たされている。このパターンに陥らないためにどうするか。薬物療法、認知行動療法、森田療法があります。不安対する考え方はそれぞれ大きく違います。薬物療法、認知行動療法は直接不安を軽減させる療法です。短期的には大変有効です。しかし対症療法ですからしばしば再発します。森田療法は考え方、生き方を変えて、不安に振り回されない人生観の獲得を目指します。どれを選ぶかはよく比較検討してください。神経症のアリ地獄から地上に這い出すのは、薬物療法、認知行動療法、森田療法、その他の精神療法などなどなんでもありだと思います。神経症の軽快後の生き方を身につけるためには、自助組織生活の発見会で仲間と共に森田理論を学習するのがよいと思います。
2025.09.22
コメント(0)
-

神経症はどのようにして治すのか
三重野悌次郎氏は、「神経症は治す方法がないが、治る方法がある」と言われている。すぐに理解できる言葉ではない。もう少し深耕してみたい。神経症は自分を苦しめている不安を取り除こうして悪戦苦闘しているうちに、精神交互作用でアリ地獄の底に落ちてしまったようなものだと思います。もがけばもがくほど深みに落ちていきます。アリ地獄に落ちると、観念的な悪循環、実生活の悪循環で仕事も日常生活も停滞してきます。とりあえずアリ地獄から地上に這い出すことが欠かせません。こういう困難な状況を改善するのが、薬物療法、カウンセリング、森田療法、認知行動療法をはじめとしたさまざまな精神療法です。神経症は、これらに取り組むことによって改善できます。つまり治す方法があるのです。しかしこれが神経症治療の全てだと判断するのは早計です。曲がりなりにも仕事はできるようになった、日常生活はなんとかできるようになったといっても、生きづらさ、社会への適応困難さはそのまま先送りされています。人間関係や子育て、仕事への向き合い方、社会適応の仕方、神経質者としての人生観の確立などは皆目目途が立たないような状態です。これらを薬物療法、カウンセリング、森田療法、認知行動療法に求めるのは無理があります。ではどうすればよいのか。森田理論学習を続けて神経質者としての人生観を確立することが大切になります。森田には医療としての森田療法と人生観確立のための森田理論学習があります。これらは明確に分けて考えたほうがよいと思います。私たちは、不安にとらわれやすい神経質性格を持っている。神経症予備軍としての状態は依然として続いている。不安や症状にとらわれやすい。困難から逃げてきたために成功体験の蓄積がない。社会体験が不足していて、対人折衝能力が育っていない。人間関係でやってはいけないこととやらなければいけないことが分からない。多くの人を敵に回して、孤立して苦しんでいる。自己否定感が強く、自信が持てない、自己肯定感が乏しい。観念中心で物事を判断し、事実を否定する傾向が強い。過去を後悔し、将来のことに取り越し苦労ばかりする。不快感や気分本位のまま行動することが多い。そもそも行動することに苦痛を感じる。たった一度のミスや失敗を受け入れることができない。子育ての基本が全く分からない。これらの課題は、仲間と共に森田理論学習を継続することによって解決するできるものばかりです。特に生活の発見会の先輩会員の中には、神経症を克服して、森田理論を実生活の中で大いに活用している方がいらっしゃいます。お手本が目の前にあるわけですから、神経質者としての人生観を確立することはできるはずです。神経症の治癒は、アリ地獄から地上に這い出るのが第一段階ですが、そこで留まってしまうのは実にもったいないと思います。せっかく神さまが、「あなたは神経質性格者として、どのように生きて行くのですか」という課題を与えてくださったのですから、自分なりの回答を出して、悔いのない人生を送ろうではありませんか。
2025.09.21
コメント(0)
-

「主観的事実」と「客観的事実」の統合について
森田先生は心身同一論という立場です。精神的なストレスは身体面に影響を及ぼしますし、身体面の病気は精神状態に影響を与えます。胃潰瘍になったとき、薬を飲んで一時的に改善しても、心の悩みやストレスへの対応を怠ればすぐに再発します。根本的な治療としては、身体と心の両方面から対応しなければなりません。森田先生の心身同一論は、「両面観」「精神拮抗作用」「主観的事実と客観的事実」の考え方につながっています。神経症で悩んでいる人は「主観的事実」にとらわれている状態と言えます。例えば、「失敗するかもしれないから挑戦しない」「ミスが怖いから積極的に行動できない」「不安だから行動できない」「完璧にできないならやらない」「やる気が起きないから何もしない」「身体がだるいので何もしない」などというのは、主観的事実だけを見つめています。森田では「主観的事実」に対して、「客観的事実」というものがあります。「客観的事実」は、実際に目の前で起こっていること、測定可能なデータ、他者から見て明らかな事実など、自己の内面とは切り離された外部の状況や結果を指します。「主観的事実」は天気と同じ自然現象です。どんな感情が湧き上がってきたとしても、コントロールすることはできません。コントロールできるのは「客観的事実」の方です。「客観的事実」を無視した行動は、片肺飛行をしているようなものです。例えば線状降水帯が発生して、避難指示が出ているにもかかわらず、いま眠くて動くのがいやだから、避難所に行きたくないと避難を拒否するとどうなるか。警戒区域に指定されているところでは、山が崩れて大規模な土砂災害で命を落とす人が毎年何人もいます。気分がいくら行動することを拒否しても、主観的事実だけに頼って行動することは問題です。森田理論では神経症の人が主観的事実にとらわれ、それに基づいて行動を制限したり、回避することによって、かえって症状が悪化すると考えます。不安や恐怖といった感情は、主観的には非常にリアルで強いものですが、それを「客観的事実」としてとらえ直すことで、感情に振りまわされない行動が可能になります。
2025.09.20
コメント(0)
-

森田先生の言う「三重奏」を考える
森田先生のお話です。最近、朝日新聞に五重奏ということが出ていた。それは本を読みながら、会話し、字を書き、計算をするとか、同時に5種類の事をするということです。聖徳太子は一度に8人の訴えを聴かれたとのこと、すなわち8重奏である。私共も平常、2つや3つの仕事は同時にやっている。例えば病院などでも、患者の家人に面会しながら机上の雑誌を読み、一方には看護婦に用事を命令するとかいうようなものである。三重奏である。我々の日常は、誰でも同時にいくつもの方面のことを考えているのが普通のことである。強迫観念でも、苦しみながらなんでもできるものである。神経質の人の考え方の特徴として、それを自分でできない事と考え、理論的に独断してしまうのである。(森田全集 第5巻 99ページ)私は以前は一つのことをきちんと終わらせてから次の課題に取り掛かったほうがよいのではないかと考えていました。なぜなら、「二兎を追うものは一兎も得ず」ということわざがあるように、どちらも中途半端になって、成果を上げることができないと思っていたのです。森田先生の真意は何なのでしょうか。森田理論では、ひとつのことにとらわれ続けると、「注意や意識の流動性」が失われて、「特定の不安や懸案事項に注意や意識が集中・固定されてしまう」と言われています。そして精神交互作用が働き、アリ地獄の底に落ちてしまうことになります。山の谷間の小川を流れる水のように、感情は絶え間なく流れ続けているというのが大事になります。お城の水のように、感情が流れないということになると、水が濁り雑菌だらけになります。私は森田先生の話を次のように理解しました。気になることに一旦注意を向けることは必要な事です。次にその不安の中身を把握することが大事になると思います。そのまま放置しておくと問題が大きくなるものは対策を考えて実行する。神経症的な不安は欲望の裏返しとして湧き上がっているのでそのままにしておく。不安を活用しながら、生の欲望の発揮に取り組む。車の運転をしている時は、注意や意識が気になるところに次々に移っています。予想される危険を回避するために絶え間なく確認行為を行っています。仮に、ここは危険が潜んでいると判断すれば、しばらく注意や意識はそこに留まります。危険が解消されれば、注意や意識はすぐに次の不安案件に移ります。確認行為で特段問題がないと判断すれば、注意や意識はそこからすぐに離れて、次の不安案件に移動していきます。つまり、注意や意識が一ヵ所にそのまま居すわってしまうことはありません。特定の不安や懸案事項に注意や意識が固定されてしまうのが、神経症発生原因の一つとなります。一旦気になって注意や意識を向けるが、問題が解決すれば、すぐに次の案件に移るという緊張感を持った生活が大事になります。
2025.09.19
コメント(0)
-
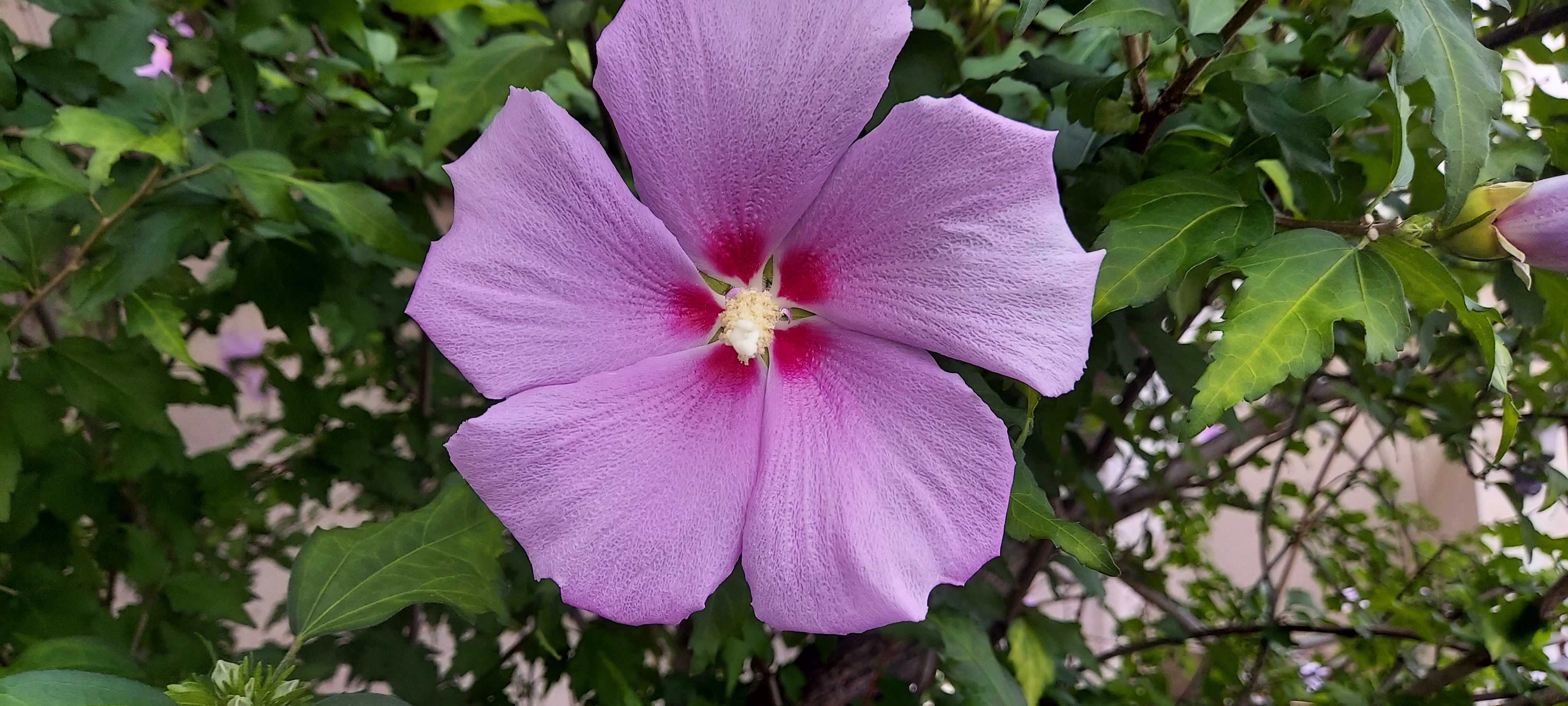
子育てで大切なこと
ダナ・サスキンド博士に「3000万語の格差・・・赤ちゃんの脳を作る、親と保育者の話しかけ」いう本があります。この本は、生まれた瞬間から最初の数年間(特に3歳まで)に、親や保育者が子どもとどれだけ「話したか」が、その後の子どもの学力、粘り強さ、自己制御力、思いやりといった様々な能力に大きな影響を与えていることを、科学的な裏付けと著者自身の具体的な実践に基づいて示しています。その中に3つのTというのがあります。T une In(チューン・イン)・・・子どもの興味や関心に注意を向け、体と心を子どもに向けること、子どもが何に夢中になっているのか、何を伝えようとしているのかを察し、それに寄り添う姿勢です。例えば、子どもがおもちゃで遊んでいるとき、そのおもちゃに目を向けて、「わあ、それ面白いね!」「どんな音がするの?」などと声をかける。T aik More(トーク・モア)・・・子どもにたくさん話しかけること。子どもの行動や身の回りのことについて、具体的に、そして豊かな言葉で説明したり、問いかけたりすることです。例えば、公園で遊んでいるときに、「きれいな花が咲いているね。赤くて、小さいお花だよ」「ブランコに乗ると、風邪が気持ちいいね!」などと、五感を使いながら描写する。T ake Turns(テイク・ターンズ)・・・会話のやり取りをすることです。子どもと交互に対話すること、子どもが発する声やしぐさ、言葉に対して、親や保育者が応答し、会話のラリーを続ける。具体例としては、赤ちゃんが「あー」とクーイングしたら、「あー、そうなんだね」と返したり、子どもが何か言ったら、「それはどういうこと?」と問い返したりして、会話のキャッチボールを意識する。これらはむずかしいことではありませんが、一般的にはつい自分のことを優先して、子どもから目を離してしまう傾向があります。特に神経症と格闘している状態では、自分のことで精一杯で、子どもとの付き合いが希薄になりがちです。3歳までの赤ちゃんがいる家庭では、神経症のことはなるべく横において、子どもの世話をすることが大切になります。その際、子どもを非難、説教、命令、指示、禁止、叱責、怒鳴るなどは、子どもと対立し、子どもの興味や主体性を削いでしまうことになりますので注意が必要です。危険な行為を止めるなどの「しつけ」は必要ですが、その際にも一方的な高圧的な態度を取るのではなく、その理由を説明するように心がけたいものです。過保護や過干渉は、親が先回りして何でもしてしまうため、子どもが自分で考えたり、試行錯誤したりする機会が奪われます。親が子どもを突き放したり、放任状態に置くと子どもは人間不信に陥ってしまいます。集談会では、相手の存在を認めて、「ほめ合い、たたえ合い、のせ合う」人間関係がよいと言われますが、子育ても同じことが言えます。
2025.09.18
コメント(0)
-

「修養」と「自覚」について
森田先生は「修養」「自覚」という言葉を大切にされています。「修養」とは、行動・実践を通して、これまでとは異なる「事実」を積み重ね、それが最終的には自分の「体験」となり、症状に支配されない生き方を身につけていくことです。頭で理解するだけではなく、実際に体を動かし、感情を伴って経験することで、本当の意味で変化が起こります。入院森田では、積極的に家事の体験をしてもらいました。ご飯炊き、風呂を沸かす、動植物の世話、エサ集め、下肥の処理、掃除、整理整頓など多岐にわたります。最初はおっかなびっくりの取り組みでしたが、弾みがついてドンドン積極的に取り組むようになりました。さまざまな日常茶飯事に丁寧に取り組み、ささやかな成功を積み重ねて自信をつけて自己肯定感を高めることが可能になったのです。神経質者は観念的に考える傾向が強いのですが、行動・実践・体験なくして悟りなしということになります。他人が怖い、犬が怖い、高いところが怖い、飛行機に乗るのが怖いと思っているときに、ハードルの低いところから行動してみると、特に問題になるようなことは何も起きなかったという体験ができます。不安や恐怖を取り除くために、頭の中でどんなに考え抜いてもどうにもなりません。行動することで、認識が変わり、感情の変化が起きて、行動の悪循環から抜け出すことができます。そういう体験を積み重ねることで修養が進み人間的に一回り大きな自分に成長できます。森田では、神経症的な苦しみの背景には「思想の矛盾」があると考えます。観念と事実の間に横たわっている溝のことです。例えば、「○○であるべきだ」「○○でなければならない」といったとらわれや、「こうなったらどうしよう」という未来への過度な取り越し苦労などがあげられます。森田理論を学び、ネガティブな思考の癖や、感情や気分や症状をコントロールしようとする努力が逆に苦しみを増幅させていることに気づくことを自覚と言います。森田理論では、神経症の成り立ち、神経質の性格特徴、感情の法則、認識の誤り、生の欲望、不安の役割、不安と欲望の関係、事実本位などを学習します。これらの学習が自覚を深めるために大いに役立ちます。「修養」と「自覚」は同時並行で取り組むことが有効です。「自覚」によって認識の間違いに気づき、「修養」(行動や実践)によって新たな成功体験を積み重ねていく。その繰り返しが生涯森田で目指すところとなります。敬老会真っ盛りです。私はチンドン演奏、傘踊り、マジック、獅子舞、どじょう掬いなどであちこちから引っ張りだこです。
2025.09.17
コメント(0)
-
物の性を尽くす
人間の最大のミッションは、この命をできるだけ延命する事だと思います。そして、この命を子孫代々途切れることなく引き継ぐことではないでしょうか。しかし延命するためには、他の動植物の命を強制的に収奪して自分の食べ物としなければなりません。人間が延命を図るという目的を達成するためには、他の動植物の犠牲の上に、初めて成立していることなのです。命を突然収奪されるその動植物もできるだけ延命し子孫繁栄を願っているはずです。生きとし生けるものは、同じミッションを持って生きています。人間が強制的にそのミッションを終了させているのです。人間の圧倒的な力を前にしてなすべきもありませんが、目的達成の途中で命を絶たれるわけですから、さぞかし無念だろうと思われます。これが人同士の場合は、報復攻撃を考えて実行することになります。そのため人間社会では紛争や戦争が絶えることがありません。そういう関係性の中で、人間と動植物はどう共生して生きていけばよいのでしょうか。人間が生きていくために最低限の命を頂くことは許容されていると思います。しかし、無制限に乱獲してしまうこと決して許されることではないと思います。人間の場合でいえば、欲望を無制限に追い求めるあまり、他の大勢の人を支配しようとしてはいけないということです。欲望の暴走は自重自戒しなければなりません。森田理論に「物の性を尽くす」というのがあります。これは、己の性を尽くす、人の性を尽くす。自然の性を尽くす、時間の性を尽くす。お金の性を尽くすことにもつながります。これは生きとし生けるものは、それぞれ能力などに違いはあるが、すべての生きものは独自の存在価値を持っているというものです。その能力や強みに応じてそれぞれに居場所与え、持てる能力を思う存分に発揮し、お互いにリスペクトする関係を築いていくことが欠かせないと考えます。
2025.09.16
コメント(0)
-

「鐘と撞木の間が鳴る」という意味
形外先生言行録(62ページ)に開業医の御津磯夫氏の話がある。鐘が鳴るかや 撞木が鳴るか 鐘と撞木の間が鳴る慈恵医大で私の精神科講義の森田教授の第一声がこれであった。黒の詰襟の洋服で、明治時代の小学教員か小使さんと思われるばかりのお姿であった。そして無表情で教室にはいってこられて、教壇の上の椅子に腰を下ろされ、何の挨拶もなく、ただちにこの禅語めいた言葉を吐かれたのであった。私は面食らって一瞬茫然としたが、この最初の一言が私の一生を支配した・・・。撞木は鐘を打つ道具である。鐘は撞木によって打たれるものである。私たちは普通「鐘が鳴った」と認識していますが、正確には撞木が鐘に当たることによって初めて音が鳴っています。つまり鐘が鳴るというのは、鐘と撞木の相互作用によってはじめて起きた現象です。鐘だけ、撞木だけでは音はでません。2つがぶつかり合うという「相互作用」や「関係性」の中にこそ、音が鳴るという現象の本質があります。これは、物事が孤立して存在しているのではなく、常に他の要素との関係性の中ですべての現象は生まれているという考え方なのです。ですから、私たちが普段見聞きしている現象や出来事を理解するうえで、表面的な部分や一部の要素だけを取り上げて論じるのは間違いのもとになるということです。その背後にある複数の要素間の相互作用や、全体としての関係性に目を向けることがとても大事になるということになります。森田理論の中に「両面観」「精神拮抗作用」「不即不離」「主観的事実と客観的事実」などというキーワードがありますが、これらは同じような意味合いがあります。つまり、物事には対立する2つの側面があり、それが相互に関係し作用しあって、目に見える現象を作り出しているということです。決して一方の側面から問題が生まれているわけではありません。森田では自分の主観的な思考、感情や気分、感覚などに対して、客観的事実があるといいます。誰が見ても客観的で妥当性のある考え方が存在している。私たちは客観的事実を、常に主観的なフィルターを通して解釈しています。森田では主観的事実にとらわれると客観的事実が見えなくなり、不適切な行動につながるといいます。客観的事実が主観に影響を与え、また主観が客観的な行動に影響を与えるという、絶え間ない相互作用の中で私たちは生きています。森田では、この相互作用や関係性を正しく認識し、主観的事実と客観的事実の調和を図ることを目指しているということになります。サーカスの綱渡りでは長いい棒のようなものを持ってバランスをとっています。片方を主観的事実、もう片方を客観的事実と見立てて、絶えずバランスをとりながら、しかも慎重に目的地に向かって前進している。これが森田理論がイメージしている本来の人間の生きる姿だと言えます。
2025.09.15
コメント(0)
-

自分の感情や思考を客観的に見る
能楽師の世阿弥は、演者が良い演技をするためには、「我見」(演者が主観的に自分の演技を見ること)だけでは不十分だと述べています。「離見」(観客の視点から客観的に自分の演技を見ること)の意識を持って、自分の欠点や観客にどう映っているかを認識する。また観客が何を求めているか、何に感動するかを理解し、その期待に応えられるように努力する。これは自分の演技を鏡で見て確認しているようなものです。世阿弥は、自分の感情や思考を主観的に見るだけではなく、客観的に眺めることが必要不可欠だと言っています。森田理論では、主観的事実と客観的事実の調和を図ることが欠かせないといいます。このことを言われているのだと思われます。思考や物事には相対立するものが相互に強く作用している。どちらかに自分の立場を固執してしまうと、まとまるものもまとまらなくなり、混乱を招きます。例えば、懇親会で酒を浴びるほど飲みたいと思っても、二日酔いになると次の日が台無しになります。そういう過去の失敗体験に学び、二日酔いにならない飲み方を考えて実行しなければなりません。酒が飲みたいという考え方だけではなく、飲み過ぎた場合の弊害も併せて考えて調和を図ることが肝心です。客観的に見るということができない人は、自分のネガティブな思考や不安を告白して、信頼できる人からアドバイスしてもらうことが有効です。集談会は自分の偏った認識を修正して客観的に眺めるために貴重な学習会となります。客観化するためにはほかにも方法があります。自分の不安や思考について、もし森田先生が生きておられたらどういう風に考えて、どの様なアドバイスされるだろうかと考えてみるのです。水谷啓二先生なら、高良武久先生なら、長谷川洋三先生ならどんな風に考えられるだろう。信頼できる森田の先輩がおられたら、その先輩ならどんなアドバイスをされるだろうと考えてみることです。困難な状況に陥った時、全盲のピアニストの辻井伸行さんはどう考えられるだろう。私は苦境に立ったとき、瀬戸大橋の現場監督で5000人の部下を束ねて、瀬戸大橋を完成させた杉田秀夫氏のDVDを視聴します。工事のさなか、ガンで妻を亡くされました。激務を続けながら、3人の娘さんを懸命に育てられました。一番の功労者であるにもかかわらず、瀬戸大橋開通の記念式典には杉田秀夫氏の姿はなかったという。まさに男のなかの男のような人です。
2025.09.14
コメント(0)
-

相手を受け入れるということ
未来食堂を経営されている小林せかい氏のお話です。この方は東京工業大学理学部を卒業し、日本IBM、クックパッドでシステムエンジニアとして働いていたという異色の経歴を持っている。この食堂では、50分間店の手伝いをすると一食無料になる「まかない」をとり入れている。また、過去に来店した方が使わなかった「まかない」の権利で食事をする「ただめし」もある。「まかない」の真の狙いは、金銭的に苦しい人を応援するという意味があります。その小林氏が次のような葛藤で苦しんでいたという。ある時期「ただめし券」を毎日使うお客様がいらっしゃいました。過去にお手伝いをした方が善意で譲った「ただめし券」を使われているだけなのでお店が損をすることはありません。ただ、どうしてもそれを単純に受け流せない自分がいました。どんな人でも使ってほしいという思いとは裏腹に、「また使っている」「あなたが使うべきじゃない」と感じる嫌な自分が顔を出したんです。本来の思いからすると、金銭的に困っていない人には使ってほしくない。けれどもある時から、本当に困っていない人が毎日使ってもいいのではないか、と考えるようになりました。困っているか、困っていないかを問うことが本質ではないと気づいたからです。それは、「私はあなたを助けます」というメッセージを送り続けることです。助けたいと思っても「困っている人しか使えません」と限定してしまうと、本当に困っている人が使いづらくなるかもしれません。仮に困っていない人が使い続けたとしても「あなたを助けます」というメッセージを送り続けていれば、もしかしたら明日、本当に困っている人が訪れてくれるかもしれない。だから「あなたは困っている」「あなたは困っていない」とふるいにかけるのではなく、ただただ来た人を受け入れる。それこそが、人を助けようとする者に求められている覚悟だと学んだのです。「ただめし券」は誰もが使える設計にしています。たとえ99回踏みにじられても、たった1回が誰かの支えになればいい。「ただめし券」使う人をすべてあるがままに受け入れることで、いつか本当に困った人を助けることができる。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 8月号 あるがままを受け入れる 88ページ)集談会にはいろんな人がやってきます。神経症で苦しんでいる人。生きづらさを抱えている人。森田を活用して楽しい人生を築きたい人。森田的な人生観を作り上げたい人。人とつながりを求めている人。話し相手を求めている人。集談会後の懇親会を楽しみたい人。結婚相手を見つけたい人。ただ暇つぶしをしたい人。など。集談会やってくる人は、森田理論を深めて、神経症を克服し、神経質性格を活かした人生観を確立することに限定して、目的外の人を排除してしまうのは考えものです。それは建前としては立派だが現実的ではない。趣旨に反する人は一切受け入れないということになると、参加者はどんどん減少してしまうと思います。自分で自分の首を絞めてしまうことになる。「来るものは拒まず、去るものは追わず」「森田に合う人、合わない人でもすべて受け入れる」「森田理論を学習するという目的を持っていない人でも受け入れる」「森田の活用や応用に関心がない人もすべて受け入れる」「1年に1回か2回しか参加しない人でも温かく受け入れる」許容、抱擁、寛容の気持ちですべてを受け入れていくという気持ちを持って、集談会を継続していると、本当に森田を必要としている人に出会うことができる。殺気ばった発言がなくなる。アットホームな雰囲気が生まれてくる。その気持ちを忘れてしまうと、森田を本当に必要としている人を見逃してしまう。100人に一人の対象者を見逃してしまうのは実にもったいない。その時のために、私たちは、絶えず森田を深耕し、森田理論の応用・活用を心がけて生活したいものです。
2025.09.13
コメント(0)
-

「得意淡然失意泰然」の心掛け
東京オリンピック女子マラソン日本代表の鈴木亜由子さんの座右の銘は「得意淡然失意泰然」だそうです。この言葉は、中国明時代の儒学者である崔後渠(さいこうきょ)の「六然訓」という処世術の一つとされています。この四字熟語の意味は以下の通りです。得意淡然・・・物事が自分の思い通りに進み、うまくいっている時でも、決して驕り高ぶらず、淡々とした態度でいること、喜びを露わにしないで、謙虚さを保つ姿勢を指します。失意泰然・・・物事がうまくいかず、落ち込んでいる時でも、慌てたり取り乱したりしないで落ち着いた態度でいること。焦らず、泰然自若とした心持を保つ姿勢を指します。普通は、うまくいったときは自分一人の力で成し遂げたことだと自分の力を過大に評価します。得意満面で、自分の思いどおりになんでもできると思いがちです。他人に相談することなく、自分一人の考えを押し通そうとするようになります。他人に無理難題を押し付けて、他人の力を利用しようとします。危機意識やリスク管理が希薄になってしまいます。そういう人は、一旦うまくいかなくなったとき、修正が効かなくなります。落ちるところまで落ちてしまい、再起を図ることができなくなる場合があります。逆に何をやっても、自分の思い通りにならないという人は、自己嫌悪、自己否定で苦しんでいます。自己信頼感、自己効力感、自己肯定感が持てないので、行動は消極的、回避的になります。そしてストレスや不安がたまるばかりです。それらを払拭して楽になるために、ギャンブル、アルコール、ネットゲーム、買い物、風俗などにはまることになります。この言葉を生活の中に活かす方法を考えてみました。得意淡然・・・うまくいっているときは「感謝」の気持ちを持つ。今の成功は、親や祖父母、周りの人のおかげだという気持ちを持つことです。あいさつを忘れない。お礼の言葉をかける。お返しをする。仏壇に手を合わせ、日記に「きょうの感謝」の言葉を書くことです。失意泰然・・・逆境や失意の時は、神様が自分にくれたギフトと考える。困難な状況に直面したとき、ただ落ち込むだけではなく、それを学びや成長できるチャンスととらえるようにする。自分が一回りも二回りも大きな人間に成長するためには、問題点や課題、目標や目的が必要になります。神さまから心の養う食べ物が与えられたと感謝の気持ちが持てれば、モチベーションが高まり、生きがいにつながるのではないでしょうか。
2025.09.12
コメント(0)
-

失明を乗り越えた人の話
歌手の大嶋潤子さんのお話です。1992年、32歳のときに、私は思いもかけず失明という運命を与えられました。急性緑内障と網膜剥離という病気でした。ある日、目を覚ますと目の前には色のない世界が広がっていました。それから2年間家に引きこもる生活が続きました。転機となったのは、実家に戻った後、34歳で息子を出産したことです。夫とは妊娠中に離婚することになりました。息子を一人で育てなくてはいけないという思いが心に火を灯したのです。普通の親ができることは何もできません。しかし盲目であっても、必ず立ち上がる母の生きざまを見せることができるのではないか。それこそが私の使命だと気づいたのです。使命に目覚めた私は、障害者手帳を取得し、中途失明者のための訓練施設に通い、掃除、洗濯などの家の中でできること少しずつ始めていきました。時間はかかりますが身の回りのことが少しずつできるようになりました。心のモチベーションを高めるために役だったのは、「この子を何としても一人前に育てる」という強い信念でした。私の人生で何よりうれしいのは、そんな母の生きざまが伝わったのか、息子は医師になって私のもとから巣立っていったことです。私は失明によって光を失いましたが、一方で初めて見えてきたものがたくさんあり、その最たるものが感謝の心です。失明していなければ、増上慢で、地位・名誉・財産がすべてだというような生き方をしていたかもしれません。けれども失明によって、社会的に弱い立場にある方、苦労している方の気持ちを知ることができました。そういう意味で、失明という困難は、私に感謝を教えるためのきっかけだったのではないかと思うのです。その後ひょんなことから音楽教室に通い、そこで才能を認められて54歳のときに歌手としてデビューしました。今の私には歌しかありません。だからこそ毎日無我夢中で練習をしています。現在は週に一度、東京都内を中心に高齢者・介護施設を訪問し、講演兼コンサートを行っています。どんな困難に直面しても必ず立ち上がる、その生きざまを、ステージを通して表現し、共感していただくことが私の生きがいになっています。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 8月号 78ページ参照)この方の生き方は私たちに勇気を与えます。森田に「運命は耐え忍ぶのではなく切り開いていくのだ」というのがありますが、大嶋潤子さんの生きざまはまさにその実例です。
2025.09.11
コメント(0)
-

思いついたことは48時間以内に取り掛かる
作家でエッセイストの浅見帆帆子氏のお話です。私が日常で大切にしていることの一つに、「思いついたら48時間以内に行動する」というのがあります。例えば、誰かと話している時に、突然どこかの場所が浮かんだとするじゃないですか。でも普通は48時間以内に行けないですよね。その場合は、その場所について調べるとか人に話すとか、裾野のことでいいので48時間以内に手をつけると、それがどんどん展開していくんですよ。これは何度も実験済みで、なぜか2日を過ぎてしまうと、そこで動いてもあまり面白い展開や引き寄せが起こらないんですよね。(人間学を学ぶ月刊誌 致知8月号 62ページ)浅見氏は、楽しい事やよいことを思いついたら、経済的、時間的に許される範囲で、すぐに行動してみることを勧めておられます。好奇心や興味や関心が湧いてきたら、すぐにその感情に沿って行動することが肝心です。一旦行動に移すと、それが呼び水となって、行動に弾みがついてくる。そして新しい発見や気づき、問題点や課題、改善点や改良点、新たなアイデアなどが生まれてきます。楽しみや感動に溢れた生活に変わっていきます。精神状態も弛緩状態から緊張状態に変わり、積極的、生産的、建設的、創造的な生活に変化してきます。普通は今すぐは無理だから、それをメモして置き、いずれお金が貯まり、時間的な余裕が生まれた時に取り掛かろうと考えることが多い。すると時間の経過とともに、その時にいくら素晴らしいことを思いついても、一山もふた山も越えているうちに感情の劣化現象が起きて来たのだと考えられます。市営プールで最初にプールに入る時、こんな冷たい水温で泳ぐのは耐えられないと思っても、しばらくすればすぐに慣れてしまい、最初の感覚は感じなくなってしまいます。いくら妙案を思いついても、その時、その場での意欲や関心に基づいた行動ではないために、やる気や意欲がでてこないということだと思います。感情は生鮮食品と同じ「生もの」だと思います。「生もの」賞味期間内に食べないと、処分することになります。時間の経過とともに、感情が劣化して使い物にならなくなる場合もあることを頭の片隅に入れておきたいものです。バナナのたたき売りイベントに行ってきました。運よくひと房100円でゲットしました。
2025.09.10
コメント(0)
-

心的外傷後成長モデルについて
今日は心理学で説明されている「ポスト・トラウマティック・グロウス・モデル」(心的外傷後成長モデル)を取り上げてみました。これは、非常に困難な、あるいは心的外傷となるような出来事を経験した後に、個人が経験するポジティブな心理的変化を指します。単に「立ち直る」というだけではなく、トラウマを経験するよりも、より高いレベルの心理的機能や意味のある変化を経験することを言います。つまり、辛い経験を乗り越える過程で、以前にはなかった新しい強さや洞察、価値観などを獲得するという考え方です。「雨降って地固まる」という言葉がありますが、困難や試練を乗り越えることで、新しい能力を獲得して、一回り大きな自分に成長していくということです。テレビ番組で「逆転人生」というのがありましたが、一旦どん底に落ちた人が、奇跡の急回復を遂げるというイメージです。これは神経症のアリ地獄に落ちた人や生きづらさを抱えた人が、森田理論学習と学習仲間に支えられて、神経症を克服し、その段階にとどまらず、神経質性格を活かした人生観を確立することと言い換えることができます。森田理論学習は生活の発見会が出している「森田理論学習の要点」に従って学習すればよいでしょう。その他森田の書籍は様々ありますから、自分に合う本を1~2冊くらい読めば概要が分かります。それを現状の自分の場合はどうなのだろうかとあてはめて学習されることをお勧めします。自助グループに参加する意味は、認識の誤りは自分では分かりませんが、他の参加者の話を聞いていると分かるようになります。また学習を深耕することができます。それと治った人の話を聞いたり、森田理論を生活の中に活用・応用している人の話が参考になります。森田のよさは「するめ」のようなもので、噛めば噛むほど味が出てくるものです。ですから最低1年、できれば3年間続けることをお勧めしています。ともすれば孤立しがちな人にとっては、人間関係を広げることにもなります。一つ注意点があります。どん底に落ちたときにその事実や現状を正しく認識するということです。ともすれば、自分の運命を呪い、親や他人のせいにしてしまいます。現実逃避、自暴自棄、他責の念、自己憐憫といった感情や思考のサイクルによって、精神的、物理的な行動力がさらに削がれていくことになります。そんなことをすれば、どん底の下にさらに二番底、三番底が口を開けて待っていたということになります。泥沼にはまってしまうと身動きできなくなります。事実や現状を否定しないで、素直に認めて受け入れることが大前提となります。むずかしいことですが、事実に反発していると逆転人生の展望が開けてくることはありません。
2025.09.09
コメント(0)
-

論語の「知好楽」という言葉の応用について
論語に「知好楽」という言葉あるそうです。物事を知識として知っているだけの者は、それを好んで行っている者には及ばない。さらに、それを好んで行っている者は、心から楽しんでそれと一体になっている者には及ばない。この言葉は、何かを学んだり取り組む上で、単に知識として知っているだけの段階から、それを好きになり、最終的には心から楽しむ境地に至ることの重要性を説いています。これを森田理論にあてはめて考えてみました。①森田理論を知る段階・・・森田理論の概念や内容を理解する段階です。この段階を通過しないと次の段階には進めません。「森田理論学習の要点」や森田関連の単行本などが役に立ちます。さらに生活の発見会の集談会などに参加して、仲間と学習することが有効です。森田理論にめぐりあったことに感謝して、最低でも1年は頑張って、森田理論の基礎編の学習をすることをおすすします。②好きになる段階。森田理論に沿って実践・行動してみようという段階・・・森田理論には活用や応用方法がふんだんに用意されています。森田理論を自分の仕事、日常生活、人間関係、子育て、趣味、習い事などに活かしてみようという段階です。森田理論は役に立つものなのかどうか、自ら実践・行動することでその真偽のほどを確かめる段階です。その際、自助組織に参加していれば、学習仲間が強力にアシストしてくれます。ここで成功体験が積み重なっていくと、次の森田を楽しむ段階に進むことが可能になります。③森田的生活を楽しむ・・・この段階では、意識的な森田の「活用・応用」というよりも、生活そのものが森田的になっていて迷いがなくなっている段階です。時々生活の発見会の人の中に「あの人の放つオーラは半端ではない」という人がいます。「この道より我を活かす道なし。この道を愚直に歩んで、最終ゴールを目指す」という心境に至っているような人です。森田理論がさらに深まり、周りの人を優しく穏やかに包み込んでいる。少しでもそばにいてその薫陶を受けたいと思わせるような人です。但しそういう人は飄々として普通に見ていただけではすごい人だとは気づかない。とりえのない、ただの平凡などこにもいるような人に見えてしまう。宝石の原石を見て、これが実は光輝く宝石になるのだとは皆目見当がつかないようなものです。目の前に目指すべき人がいるというのはとても励みになります。「森田の達人」レベルの人は、自分の今後の人生を左右する存在として光り輝いています。
2025.09.08
コメント(0)
-

人の役に立つ人間を目指す
アンパンマンというマンガの生みの親は、やなせたかし氏です。アンパンマンは、困っている人達に自分の顔(あんぱん)をちぎって食べさせる正義のヒーローでした。やなせたかし氏に「ひとつぶの水滴」という詩があります。雲の中でひとつぶの水滴が生まれた地上めがけて落ちていった無数の水滴はあつまって川になり海へ流れていった僕は何かの役に立ったのだろうかひとつぶの水滴はそうおもったひとつぶの水滴がなければ川もなく海もない地球は完全に乾いてしまう(人間学を学ぶ月刊誌 致知 10月号 115ページ)やなせたかし氏は、この世に生まれてきて、他人や社会のために、何か記憶に残るような貢献しただろうかと自問自答しているのである。こういう発想をすることができる人は滅多にいない。普通の人は、自分のやりたかったことを思う存分楽しむことができたかどうかを問題にする。欲しいものが何でも手に入れることができたかどうかを問題にする。子孫のためにひと財産を残したか、名誉や名声を得たかどうかを問題にする。つまり他人のために自分の存在が何か役に立ったかどうかは眼中にないのである。森田先生は人に良く思われるようなことに精力を使うよりも、人を気軽く便利に、幸せにするためには、自分が少々悪く思われ、間抜けと見下げられても、そんなことは、どうでもよいというふうに、大胆になれば、はじめて人からも愛され、善人ともなるのであると言われています。(森田全集 第5巻 205ページ)この考え方は、仕事を面白くするためのコツになると思われます。仕事をする第一の目的は、給料を得て自分と家族の生活を維持していくことにあります。しかしそれだけが唯一最大の目的になってしまうと仕事は苦痛になってきます。仕事が必要悪になるからです。本音と建前が乖離すると生きていくことは辛くなります。その時に、仕事をして他人や社会の役に立ちたい、喜んでもらいたい、感動を与えたいという目標や課題を持つことができた人は仕事が楽しくなります。それは人から与えられた課題をこなすということから、自分で見つけた目標や課題に取り組むことになるからです。目の付け所を少し変えるだけで、人生の三分の一を占めると言われる仕事が楽しくなると、人生の意義は全く変わってきます。
2025.09.07
コメント(0)
-

幸せな人生を送るために心掛けること
大山泰弘氏が住職さんから聞いた「4つの人間の幸せ」について紹介されている。1、人から愛されること。2、人からほめられること。3、人の役に立つこと。4、人に必要とされること。(1日1話、読めば心が熱くなる365人の生き方の教科書 藤尾秀昭監修 致知出版社 219ページ)1については、まずは両親から愛されることが欠かせません。特に愛着の形成期の生まれてから1年6ヶ月の間は親は子どもに付きっきりで面倒を見る必要があります。これは主としてお母さんの役割となります。その後はお父さんが外に連れ出して、できるだけ多く雑多な体験の機会を提供する。モンテッソーリ教育によると、子どもは何かに興味をもち、同じことを繰り返す時期(これを敏感期という)があると言われています。その敏感期(11項目あります)をスルーしてしまうと、後から取り戻そうとしても難しいそうです。子どもの敏感期を学習し、敏感期に応じた能力開発を心がければ子育ては楽しいものとなります。2については、他人から評価されるとやる気に火がつきます。特に親、先生、尊敬する人などです。私はそのためにトライアスロンに挑戦しました。また難関の国家資格にいくつも挑戦しました。いずれも目的は果たしましたが、人からほめられることはありませんでした。会社ではそんなエネルギーがあるのならば、仕事で大きな成果を出してほしいと言われました。今考えると順序が逆だったと思います。本業を疎かにして、本業以外のところで大きな成果をあげても、かえって軽蔑されるようになります。自分に与えられた仕事で最低限の責任と義務を果たすことが前提となります。そのうえで自分のやりたいことに取り組めば、おおいに尊敬されるようになます。水谷啓二先生は、我々神経質者は風雲に乗じて大きな成果を上げるよりも、凡事徹底で10年20年と努力を積み重ねた方がよいと言われていました。陸上でいえば短距離で勝負するよりも、マラソンのような持久力で勝負するのが性に合っているように思っています。3については、例えばシェフの場合でいえば、対価に見合った料理を提供するのは当たり前のことだと思います。そこを目標にしていると、お客様の期待値以下の料理を出すことになりかねません。人に役に立つこととは、相手の期待値にプラスアルファを積み上げていくことだと思います。相手から感謝される。感動の涙を流してくれる。何かお返しをしたくなる。期待値プラスアルファを目指していると、本人もやる気が出てきますし、相手も喜んでくれますし、感謝してくれるようになります。4についてですが、人類の祖先は東アフリカにルーツがあるそうです。その当時平原で肉食獣と命をかけて戦っていました。その戦いに勝利して人類が生き延びることができたのは、仲間と協力して闘うことを身に着けたからです。社会を作り分業制を確立し文明を発展させてきた。人間一人だけでは大きな成果を上げることはほぼ不可能です。自分の可能性や能力を見極めて、早めに自分の得意分野を見つけて、そこに磨きをかけて、社会貢献することが人間に課せられている宿命ではないでしょうか。自分の能力を開発して他の人や社会貢献をすることで、自分の居場所や活躍の場が確保されます。
2025.09.06
コメント(0)
-

否定的な気持ちになったとき、心がけていること
私はつい「イヤだ」「ダメだ」「できるわけがない」「腹が立つ」という言葉を口ずさんでいます。こんな言葉を使っていると惨めな気持ちになるばかりです。それは、思考回路も湧き出てくる感情もネガティブなものばかりになるからです。自己嫌悪、自己否定の繰り返しばかりになります。このマイナスの悪循環を止めようと思いますが、長年の癖はなかなか変えることができません。今取り組んでいることをご紹介します。・否定語は「忘備録」を取り出してすぐに肯定語に置き換える。「面白い」「愉快だ」「楽しい」「わくわくする」「いいぞ」「大丈夫」「いい調子だ」「最高だ」「たいしたものだ」「なんとかなるよ」「きっとできるよ」「すべて順調だ」「絶好調だ」そして深呼吸をする。・本番の楽器演奏でネガティブな気持ちになったとき、それは練習不足のせいかもしれないと考える。ひたすら練習を100回繰り返せば成功確率は64%になるという法則がある。200回で74%。300回で84%。400回で94%。459回繰り返せば99%の成功確率になるという。数値目標を明確にして、確率を信じて熱心に練習に取り組めば自信が育ってくる。本番で金縛りになることは予防できる。・相手の短所や欠点が気になったら、両面観で相手の長所や強みを考える。短所や欠点ばかりを口にしていると犬猿の仲になる。「ありがとう」「おかげさま」「助かります」という感謝の言葉を積極的に使う。・これから取り組むべき課題は何だったのか自問自答して、注意や意識を行動面に移す。・「感情や気分と行動」はできるだけ分離する。感情や気分に振り回されそうになったとき、すぐにその場から離れて「間」や「車間距離」をとる。いくら腹が立っても、スズメバチの巣をつつきまわすようなことはしない。よほど注意しないと、取り返しのつかない惨事に見舞われる。なんの根拠があってそう思えるのだと言われればお手上げです。そんな気持ちになれなくても、とにかく形から入っているのです。靴が揃えば、心が揃うのと同じことです。これらの言葉は、希望が持てます。ネガティブな思考回路を遮断してくれます。それ以上にマイナス感情が増幅するのを防いでくれます。気分本位の行動に耐える力を与えてくれます。森田ではどんな感情も自然服従と言います。使う言葉を変えると、新しい感情が生まれてくるように思います。
2025.09.05
コメント(0)
-

感謝や好奇心が人生を豊かにする
女優の小山明子さんは今年満90歳を迎えられたそうだ。小山さんが61歳のときに夫で映画監督の大島渚さんが脳出血で倒れました。仕事を休業して、17年間にわたり献身的な介護を続けてこられました。一人暮らしになってからの生活ぶりが参考になりますので今回取り上げました、小山さんは規則正しい生活を心がけておられます。朝は7時半に起きて昼間はお庭のお花の手入れをしたり、本を読んだり、友人と一緒に活動したり、夜はドラマやニュースを見て、だいたい12時か1時には休むことにしています。朝昼晩と三食きちんといただくことも大切な習慣ですね。私、この年になってもスケジュール帳がぎっしりなんです。水泳やコーラス、それに麻雀の女子会、一口馬主もやっています。特に若い人たちと会うのはいいですね。何よりも気持ちが若返る。いまは年を取って昔ほど参加できなくなりましたが、海岸清掃やお花見、上映会、防災訓練といった町内会の活動にも積極的に関わってきました。小山明子さんはいろんな好きな言葉を持っておられます。・「ありがとう」は魔法の言葉です。・人と比べないということ。人と比べることはかえって自分を精神的に追い込むことになるんです。・五木寛之氏の「諦めるということは実は前向きなこと」という言葉も好きです。・作家の柳田邦男さんの「人間は落差に弱い」けれど「人は、不幸を受け付けながら幸せになる」という言葉にも大きな力をもらいました。いろいろな壁にぶつかっても「神はその人が越えられない試練を与えない」と思えば、自然に力が湧いてくるんです。・好きな言葉は、カキクケコの法則。「カ」は感謝と感動、「キ」は興味、「ク」は工夫、「ケ」は健康、「コ」は好奇心と転ばないこと。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 8月号 18ページ参照)認知症を予防し、自分の足で歩いて、経済的に自立して、自分が喜ぶことをして100歳以上まで長生きることを目指している私にとって、参考になる事ばかりです。
2025.09.04
コメント(0)
-

相手の長所だけと付き合っていく
山崎房一氏のお話です。鯛を買ってきた。きれいに洗ってから刺身を作る。内臓だけを見て、「この鯛は汚い」と、ケチをつけて捨てる人はいない。内臓はそっと捨てるもの。人の欠点も同じこと。他人とのつき合い方も、相手の長所とだけつき合えばよいのである。相手の欠点、短所に、お互いに触れなければ、相手を嫌ったり傷つけてしまうことはないのである。相手が傷付きやすい子どもであればなおさらのこと。子どもは、欠点を指摘されると冬の荒野に放り出されたような気持になってしまう。家庭とは、暖かいところである。温かい家庭とは、欠点を優しくカバーしあえる場所のことである。欠点は、カバーされると、スッと消えていく。自分にとって、かけがえのない妻の欠点は見ずに長所だけを発見しその長所を言葉で妻に伝えることにしよう自分にとって、かけがいのない夫の欠点は見ずに長所だけを発見しその長所を言葉で夫に伝えることにしよう自分にとって、かけがえのない子どもの欠点は見ずに長所だけを発見しその長所を言葉で子どもに伝えることにしようどんなことがあっても、家族はお互いに、そのままを認め合うこと。すべてを受け入れ、味方になりきること。温かい家庭、仲のよい夫婦、笑顔のある家庭からは、けっして横道にそれる子どもは出ないものである。(心がやすらぐ本 山崎房一 PHP研究所 204ページ)時々「あの人はいつも一言多い」と言われる人がいます。私もその一人です。思いついたことを、なんでもすぐに口にしてしまう人のことです。「言っていいこと」と「言ってはいけないこと」の区別がつかない人です。たとえ区別がついても、「言ってはいけないこと」を心の内に納めることができない人です。目の前の人の弱点や欠点、ミスや失敗などを気が付いたまま、感じたままを口にするのですから、相手にとってはたまったものではありません。より良い人間関係を築かなくても楽しい人生を送ることができると思っている人は、このことをひたすら繰り返せば目的は達成できます。しかし自分一人で孤立気味の人生を歩んでいくことは寂しいものです。あとで「言わなければよかった」と後悔してもあとの祭りになります。「いつも一言多い発言」が気になる人は、森田理論の「感情と行動は別」を深耕することが役に立ちます。北野武氏の言う人間関係に「間」作る。人間関係に車間距離を作るという考え方を深耕し、1つでも2つでも、一言多い発言を少なくするように心がけたいものです。
2025.09.03
コメント(0)
-

活用なき森田理論は無学に等しい
福沢諭吉は、「人、学ばざれば智なし、智なきものは愚人なり」「活用なき学問は無学に等しい」という言葉を残している。これは森田理論学習に取り組んでいる人に対しても、同じことが言えると思われます。不安、恐怖、ネガティブな気分にとらわれやすい人は、森田理論学習に取り組むと今後の人生の羅針盤を得ることができます。ただし、森田理論を理解しただけでは宝の持ち腐れとなります。実際の生活の中で、森田理論を応用・活用していくことが欠かせません。活用なき森田理論は無学に等しい。この言葉を戒めにして、心してかかることが大事になります。森田では理論学習と実践・行動は車の両輪であるといいます。車の両輪は同じ大きさでないと前進することはできません。仮に理論の車輪が実践・行動の車輪と較べて大きいと、行動の車輪の周りを理論の車輪が空回りすることになります。症状が治ることはありません。理論と行動の車輪が小さいときは小さいなりにバランスがとれていればよいのです。理論の車輪が大きくなれば、行動の車輪は当然大きな車輪に付け替えなければなりません。例えば感情の法則3に「感情は同一の感覚に慣れるにしたがって、にぶくなり不感となる」とあります。私たち神経質者は細かいことによく気が付くわけですが、その気づきをすぐに書き留めておかないと、その素晴らしい気づきはすぐに忘却の彼方へと飛び去り、後から思い出そうとしても思い出せなくなります。気づきを書き留めておく習慣はとても大事です。この理論を生活の中で実践している人は、生活の好循環が始まります。これはほんの一例ですが、森田理論には星の数ほどの活用ポイントがあります。森田理論を一通り学習した人は、次に森田理論の活用や応用の事例を研究し、参加者全員で共有化することが欠かせません。森田理論学習がその方向に向かうと、お互いに刺激を与えあうことになります。逆に言うと理論学習にばかりに力を入れていると、マンネリ化を招き、学習会に参加する意義は薄くなってしまいます。バランスをとるためには、学習が3割、行動・実践が7割くらいの気持ちで取り組むことをお勧めいたします。
2025.09.02
コメント(0)
-

「ともかくも出を出す」とはどういうことか
森田正馬全集第5巻にこんな話があります。水谷氏・・・私はこのごろ学校の書物は読まず、カルタやトランプをやっても面白くなく、困った心理状態になっています。歩いていても、息苦しくなる事もある。こんな気持ちで、余興をやったら、かえって人に気まずい感じを与えはしないかと、様々に迷ったが、先生が常に私に「ともかくも手を出せ」といわれますので、手をつけた事ではあり、苦しい苦しいと思いながら、稽古をしたのであった。やってみると案外よくできました。これは、「ともかくも、手を出した」ことになるのでしょうか。森田先生・・・それは「手を出す」ことにならない。意味の違う事である。もし君が学校の書物を読めば、それが手を出す事に相当する。君が読まないのは、苦しくて興に乗らないからである。その苦しいながらも読む事を、「ともかくも」というのである。読書と滑稽劇やトランプなどと比較すると、ツイツイその楽な方へ手を出す事になる。そして「手を出せ」という標語にかこつけて、わずかに自分を欺いて、強いて我と我が心を慰めている。実は実際において、「ともかくも手を出す」べき事には、少しも手を出していないから、稽古もなかなか苦しいのである。歩いて息苦しくなる原因はここにある。決して鬱憂症などの突発性のものではない。それは自欺の罪の罰を科せられたと同じ価値の者である。もしこれを逆に、ともかくも、読書の方に手を出しているならば、自ら心も快活になって、勉強のできる上に、その余暇に、滑稽劇でもカルタでも、みな面白く元気よくできる。それは心に拮抗作用の強い抵抗がなくて、自然に能率が上がる事が面白くなるからであります。(森田全集 第5巻 301ページ)森田では不安や恐怖、ネガティブな気分などはあるがままに認めて受け入れ、目的に沿って必要なときに必要な事を必要な範囲でこなしていくようにと説明されています。水谷氏のお話では、読書をする気が起きないので読書は避けている。読書するのはおっくうだ、やる気が起きないという感情を認めていない。すると息苦しくなるばかりなので、いまの自分に興が乗りやすい滑稽劇の稽古に取り組んでいる。一見すると目的本位に行動しているように見えます。これは、不安や恐怖、ネガティブな気分などから目をそらし、別の行動に逃げて心の安定を得ようとしていることになります。森田の「自然に服従して、境遇に柔順」という方向からずれています。こういう方向に向かうと、神経症はこじれて増悪していきます。
2025.09.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 癌
- 悲しきかな…。末期癌は、大変ですね…
- (2025-11-18 21:46:27)
-
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- ジャパンラグビー、やっと勝ったな
- (2025-11-24 12:22:26)
-
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- スーパーテクニック・シリーズ29.0(…
- (2025-11-23 13:36:34)
-







