2020年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

ヒラズがきたっ。
ヒラズがきたっ。多発するとハウス栽培のピーマンやキュウリなどの果実の品質、とくに見た目に大きな被害を与えるアザミウマ類。そんなアザミウマの生息数が極端に増えていたのが、ここ宮崎県です。その生息数ですが・・・11月末に県が発表した発生予察注意報によれば、過去10年間で最も多い 10花当たり25.8頭! 平年の生育数は10花当たり6.1頭 といいますから、ざっと考えても現在のところ4倍以上の頭数が存在していることになります。 “10個の花に対して1頭が寄生したしても防除が必要となる“というアザミウマ類ですから、その被害たるやもう大変といってもよい状態。 発生予察第5号 → そんなアザミウマの大発生の原因ですが、やはりなんといっても一番の原因、それは気温が高すぎること。例年よりも平均気温で0.92度も高いとなれば、ハウス外の虫の死亡率は低下するでしょうし、さらにハウス内に侵入してきた虫の生存率はあがっていきますものね。そしてもうひとつ。今回のアザミウマ大発生の原因は、アザミウマの種類が異なっていたことがあげられます。気温が高いという条件のもと[天敵のスワルスキーカブリダニで防除ができる]ミナミキイロアザミウマだけではなく、ミナミキイロアザミウマよりも身体が大きいヒラズハナアザミウマ もまた生き残り、生息数を増やしていたのです。こうなると大変ですよ。例年なら天敵を使うことでミナミキイロアザミウマを中心に防除すればよかったものが、そうもいかなくなる。またアザミウマ対策として天敵を導入しているハウスでは、天敵類の健康を考えて薬剤を散布する回数も減らし・散布できる農薬の種類も限定して使用しているわけですから、そのあたりの管理状況もまた ヒラズハナアザミウマに有利にはたらいた。結果として「天敵を導入しているハウスほどヒラズハナアザミウマの発生が多い」という状況になっているといいますから、ヒラズハナアザミウマとしては してやったり。例年どおりのスリップス対策を実施していることで安心していた農家さんたちの裏をかいて大発生した・・・といえる状態になってしまったわけです。さて、そこでそのように難敵のヒラズハナアザミウマ対策です。主として花の内部で生活する[より薬剤がかかりにくいですよね]ヒラズハナアザミウマですから、 ここはひとつ花の数が少ないときを狙って防除すること、これが防除のコツになります。加えてよく薬が効くように展着剤も入れたいところですよね。また花に潜り込みやすいという性質ですから、開花する花の多い生長点付近に、青色粘着トラップなどを集中して仕掛けることなどもよい方法だと思われます。予察のでた12月はじめから依然として気温の高い状況がつづいている南九州ですから、ここはしっかりと対策していきたいところですねよ。ということで今回は、[同じアザミウマといえども種類がちがえば対策も変わってくるのですから]天敵のあるなしにかかわらず、現場の観察をよくおこなって虫の種類をよくよく確認し、そのうえで対策を練っていくことが肝要である というお話でした。それにしても、そもそもの原因はなんといっても予測できない高温です。簡単にコントロールできる代物ではないので、これからもいろいろな現象を引き起こしていくのだろうと思うと、かんがえるだけで頭が痛くなってしまいます。。ちなみに関連記事として、イチゴのタンソ病ににた症状をひきおこす虫、温暖化が引き起こす意外な虫の害についてのはなしはこちら。 アザミウマ類の名まえの呼び方ですが、 当地ではミナミ キイロアザミウマを スリップス。ヒラズハナアザミウマ は ヒラズ 。 と呼ぶ方が 多いです。 ちなみに虫の 名まえについてのはなしは こちら。よろしかったら。。「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」
2020.01.31
-

ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。
ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。Hやっぱり暖冬なのかなとおもっていたなかでの寒波襲来。そんなせっかくの寒波を防除にしっかり利用しようというおはなしです。おそらくはもっとも寒い節気。やるなら いま だなと。 ↓『ジャンボタニシや草の防除には“田起こし”が有効。』壁一面に産み付けられた ショッキングピンクの卵・たまご・卵 !!悲しいかな、いまやこれは日本の日常になりつつある光景なのです。この卵から孵ってくるのは、ジャンボタニシ こと スクミリンゴガイ。昭和56年頃に海外から食用として日本に持ち込まれて野生化し、関東以西の水稲やレンコンに大きな被害を及ぼしている貝になります。画像は こちら 。 このスクミリンゴガイは繁殖力が極めて旺盛、汚水にも強く、用排水路やクリークで増殖しながら移動分散し続けています。この急速な増加に伴い、「昨年までは見なかったけれど、今年になってからの増殖ぶりには驚いた」などと農家さんがおっしゃるのは日常温茶飯事のこととなった感が大いにありますよ〔地区の一斉防除で数十キロとれたり〕。さて、そして。そんなスクミリンゴガイの防除に最適な時期、それが 彼らが眠りつく いま、 トラクターで田を起こすこと なのです。そう、収穫の終わった水田の土の中、5センチ程度の深さで休眠を図る彼ら地中の貝の貝殻を回転するトラクターの爪で破壊、もしくは地表にかき出して凍死させる・・・。この機械的な防除は けっこう効果があるんです。効果を高めるにはコツとしては・・・ ■ ロータリーの回転数を上げる こと ■ そして 低速で耕うんする ことが挙げられますよ。この処置を施した水田においては、じつに 90パーセント以上の駆除率があった とする試験結果もありますので、心当りのある地区では、ぜひ この防除法もお試しくださいね。そしてもちろん、雑草防除にも田起こしは有効[宿根草の地下部を破壊したり、地表に出すことによる寒さによる防除]です。 もちろんジャンボタニシのはなしも取り上げて↓ ます。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.01.27
-

温暖化で増えるといえば、意外な虫の害。
イチゴ栽培において28度前後の温度が高い時期に、株のクラウン部に発病するのが、 ↓ イチゴの炭疽病[たんそびょう]です。 まずイチゴ葉の外縁が黄化・褐変し、そのあと外葉が枯死する株がみられ、最終的に上記の写真のような株そのものの褐変から枯死に至るというふうに病状がすすみます。とはいったものの長年にわたってイチゴ栽培を手がけておられる農家さんたちにとっては、さして恐ろしい病気といったものではなく、季節がすすんで次第に高温期が過ぎたり、病斑を確認する初期の段階での適切な薬剤散布をおこなったり、かん水の量を少なくして加湿を避けることなどによる適切な処置で防げる病気のはずなのですが・・・本作にかぎっては 宮崎のイチゴ農家さんにとって勝手が違いました。いつものように 適切な炭そ苗対策をおこなっても効果がないのです。新芽がのびず、展開した葉の葉柄が赤味を帯びてきて、葉の縁が黄化や褐変し、症状が重くなると、株や根までもがが枯死してしまう。これは大変ということになり、県外のイチゴのにたような事例を調べてその原因がわかったのは、11月もおわるころになってのこと。。じつはこの症状は虫の害。ハエの仲間であるチバクロバネキノコバエ[チビクロバネキノコバエとも]の幼虫による食害だったのです。イチゴに寄生するこのハエの幼虫は透明といってもよい体色をしており、大きさも最終的な段階でも四ミリほど。成虫は透明ではなく頭が黒で身体は褐色ではあるものの体長が約2ミリ前後しかないのですから、これではなかなか見つけられなかったのも いまとなってはよくわかります。ちなみにこのハエの生活史は ❝未熟な有機物に誘引された親が産卵、卵から成虫になるまでの時間が25度Cの気温条件で2週間ほど❞といいますから、今作のような気温の高い気象条件であれば 順調に世代交代しながらその生育数を増やし、結果的にイチゴの地下部や地際部をも食害・加害していった ということなのでしょう。さてそこで、このハエに対する防除方法です。ハウスイチゴ栽培においては、交配にミツバチを使っているケースが多いので、なるべく薬剤に頼らない方法をとるということになれば ● ハウスの開口部[入口や換気部分]に1ミリ目あいのネット展張 ● 圃場の周辺にある雑草の処理や作物の残さの片づけ ● 圃場の周りにある場合には、たい肥舎などの消毒などといった対策に加えて、なんといっても ● 未熟な有機物を圃場に大量に使わないことこれが 大切なポイントとなります。 炭疽病とおもって対策を実施して効果がなかったはず だなと、原因が分かってしまった現在ならおもえるの ですけれど・・・まさか原因が虫だったとは。。という ことで 農業はプロファイリング の回は こちら。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
2020.01.20
-
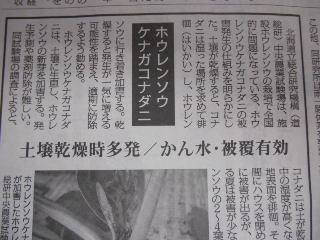
いつのまにやら害虫に。
いつのまにやら害虫に。過去分ですが、次回分参考として。よろしかったら。↓『いつのまにやら害虫に。』芽だったころのホウレンソウの葉が、縮れたり、こぶ状の小突起ができたりといった症状になり、ひどいときには芯どまりになって成長しない・・そんな経験はありませんか。じつはこれ、新芽部に寄生する体長約0.6mm前後の小さな虫、ホウレンソウケナガコナダニの仕業であることが多いんですよ。 こちら 。この虫がホウレンソウの芯の部分に寄生し食害することにより、商品価値を低下させ、特に春作と秋作では収量低下の大きな原因となります。またこの虫が土壌中にもっとたくさんいるときは発芽することさえままならない場合もあるということなので、注意が必要です。問題になりはじめたのは2005年以降。2008年には、2度にわたって日本農業新聞が、このホウレンソウケナガコナダニの被害が全国に広がっていることをトップ記事で報じて話題になりました。記事の内容はつぎのようになります。2008年6月13日分トップ記事。↓『ホウレンソウを食害するホウレンソウケナガコナダニによる被害が、全 国39都道府県に広がっていることが12日、本紙の調査で分かった。 環境保全型農業の拡大とともに、同ダニの餌になる未熟堆肥(たいひ) や有機質肥料の利用が進んだことが要因。関係者は「国を挙げて試験 研究に取り組んでもらいたい」と訴える。』と、いうことでした。つまり・・・これは環境保全型農業、いわゆる有機栽培における〔生の有機物使用の〕弊害が出た顕著な例のひとつなのです。本来土壌中に生息する有機物分解者であったはずのホウレンソウケナガコダニが、環境の変化によって害虫とされてしまった。 ホラーですね。そして、どれだけたくさんの未熟有機物が全国の耕地で施用されているのかと、心配させられる話でもあります〔土壌に保持できなくなった分は水に乗って環境中に放出されるわけですからヒトにとってもホラーです〕。ということですから・・有機物の耕地への施用に関する、質と量そして回数の規制がない現状としては、「ホウレンソウケナガコダニの被害がでるほ場では、未熟有機物の使用を控えてもらえませんか」と、いまのところは農業者の良心におねがいするしか方法がないわけです。 ということで、本年2016年8月18日の農業新聞↑にも載っている被害の実態の記事をお知らせして、人為的に生態が変えられてしまったダニのはなしはおしまいです。 『現代農業』誌の推奨された農法、「土ごと発酵」が盛んになって から確実に被害が増えた気がしますね、この虫の被害は。 「土の状態を見て入れるものをかえるのが農法」の回は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
2020.01.16
-

菜園では要注意なタネバエ。
菜園では要注意なタネバエ。2014年分ですが、次回参考としてよろしかったら。 ↓『菜園では要注意なタネバエ。』ダイズなどの豆類 や、きゅうりなどのウリ類 など、いろいろな作物を食害する小さなウジ虫が出て困られたことはありませんか。 それは タネバエ です。 こんな姿 。 ちょうど全国的にみて、寒さの和らぐ春先から梅雨時期が発生の適期に当たるんです。 鶏フン・豚プン・牛ふんといった動物質のふんや、植物質の作物の残さや生のコメヌカなどといった未分解有機物の腐敗臭 に誘われて成虫がやってきます。 雌成虫は、1個体だけでも700-1000個もの卵を産むっていいますから、いちど出ちゃったら、たとえ薬剤で対処しようとしてもきりがありません。 ださないことが肝心です。対策ですが、薬剤を使用しない対策として ● 有機物をどうしても使いたい場合は完熟させてから使用 ● ピートモスで土づくり して、無機質のミネラル肥料を使用 というような方法があります。 タネバエ被害に苦労されている方には、お薦めの方法です。 ちなみに ミネラルとは無機質の鉱物のこと。有機質ではありません。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
2020.01.15
-
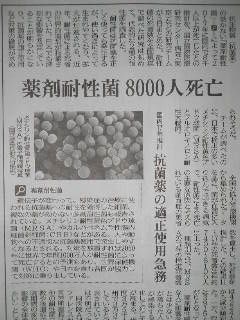
薬剤耐性菌で国内で8000人の死者だというのに。
薬剤耐性菌で国内で8000人の死者だというのに。術後の方や高齢者、免疫が落ちた方などが感染すると、重症化して死亡するリスクが高まる薬剤耐性菌。 米国では年間3万5000人以上、欧州では3万3000人が死亡しているとの推計が発表されているほどの、ある意味人類にとっての重要な課題であるともいえる この薬剤耐性菌問題の日本での死亡推計数なのですが・・・これが ずっと不明のままでした。その不明であった死亡感染者数が、国立国際医療研究センター病院(東京)などの研究チームによって[代表的な2種類の耐性菌について]全国規模ではじめて調べられ、その結果が昨年12月05日に公表されました。その死亡者数ですが、これがなんと・・・ 2017年には日本国内で8千人以上が死亡というもの。1年で、 2017年の1年間だけで8000人! というショッキングな数字です[代表的な2種以外もあると思われるので現実にはもっと大きな数字になるかと]。この事実を知って、個人的に死者数の多さに驚かされたのですが、それ以上にもっと驚かされたのが・・・この事実に対しての いわゆるマスコミの取り上げ方の熱のなさ。たとえばこの発表に関する新聞記事は第3面に掲載されているという 文字通りの三面記事扱いなんですもの。 宮崎県版の新聞記事 → こういったニュースを扱う マスコミの方々の身内のご家族やご親戚にも、いわゆる院内感染にかかった人も多いはずだと思うのですけれど、ねえ。[この記事の扱われ方には]なんとも信じられない思いで いっぱいです。さらに今回の、この記事には特徴があります。それは人間の抗菌薬の話がほとんどで、以前から問題視されている家畜への抗菌薬使用の話が、全く語られていないこと。・・・ヒトの医療研究センターチームによってまとめられた調査ですので、マスコミの方々としては 今回はヒトのはなしを中心に報道されたというかんじなのかもしれませんけれど、せめてネットニュースなどでは扱ってほしかったなと個人的には思ってしまいました。その傾向、無関心とも思われるようなこのニュースの扱いは、新聞発表された6日以降においても、地方版でも全国版でも、そしてネットニュースなどでも、同じなのです。 そこで・・ 注意を喚起するかんじで、わかりやすいこの図を使った、家畜も含めた抗菌薬の適正使用の話の回は、こちら。ということで今回は、現実に国内で年間8000人の死者を出しているというニュースに合わせる形で、「2020年までに抗菌薬の使用量を2013年の3分の2にまで減らす」としている政府のつくった行動計画の達成予定の年も もう来年に迫っていますよね、安心していてだいじょうぶなんですよね、というおはなしでした。 さらメシ・農家メシ・世界のオベントに天野君と天野君に負けじ と女子アナがたべる番組などなど、まるでなにかに憑かれたかの ように、平日のお昼の時間に 食の番組ばかりを放送しまくる NHK。ときどきでいいですから、たまには 家畜への抗菌剤の 話とか、家畜の飼育場所から発生する排水問題なんかも取り上げ てほしいとおもうんですけれど。N国さん、なんとかなりません かね。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
2020.01.07
全6件 (6件中 1-6件目)
1










