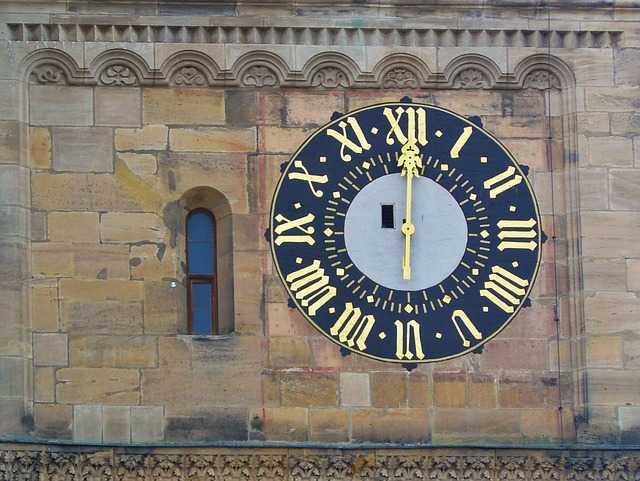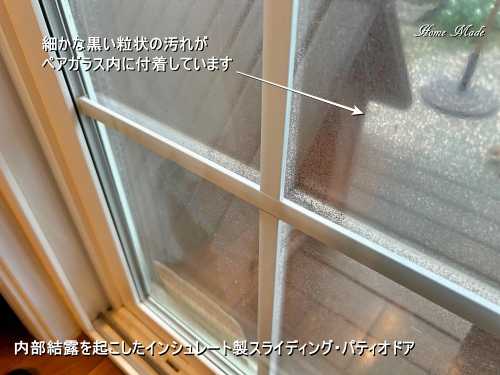2016年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

唐突すぎる寒波と積雪の到来で思い出したのは。
唐突すぎる寒波と積雪の到来で思い出したのは。 南九州での24日から25日にかけての最低気温がマイナス4度にもなり山沿いには積雪も・・・というニュースを聞いたのは 23日の土曜日。よりによって海辺を離れて山間部!にいたときのことでした。そして体験したのです。いきなりの積雪で道路が不通になり、寒さで水道管被害が発生して断水がおこってしまったことを。こんな天候の急変ぶりのなかでに思い出されたのは・・・そう『雪女』の物語でした。とくに舞台となった場所のお話しなどもからめて、よろしかったら。 ↓ 『武蔵の国のある村に、茂作と巳之吉という2人の樵が住んでいた。茂作は すでに老いていたが、巳之吉の方はまだ若く、見習いだった。 ある冬の日のこと、吹雪の中帰れなくなった二人は、近くの小屋で寒さ をしのいで寝ることにする。その夜、顔に吹き付ける雪に巳之吉が目を 覚ますと、恐ろしい目をした白ずくめの美しい女がいた。巳之吉の隣り に寝ていた茂作に女が白い息を吹きかけると、茂作は凍って死んでしま う。 女は巳之吉にも息を吹きかけようと巳之吉に覆いかぶさるが、しばらく 巳之吉を見つめた後、笑みを浮かべてこう囁く。「おまえもあの老人( =茂作)のように殺してやろうと思ったが、おまえは若くきれいだから、 助けてやることにした。 だが、おまえは今夜のことを誰にも言ってはいけない。誰かに言ったら 命はないと思え」 それから数年して、巳之吉は「お雪」という、ほっそりとした美しい女 性と出会う。二人は恋に落ちて結婚し、10人の子供をもうける。お雪は とてもよくできた妻であったが、不思議なことに、何年経ってもお雪は 全く老いることがなかった。 ある夜、子供達を寝かしつけたお雪に、巳之吉がいう。「こうしておま えを見ていると、十八歳の頃にあった不思議な出来事を思い出す。あの 日、おまえにそっくりな美しい女に出会ったんだ。恐ろしい出来事だっ たが、あれは夢だったのか、それとも雪女だったのか……」 巳之吉がそういうと、お雪は突然立ち上り、言った。「そのときおまえ が見たのは私だ。私はあのときおまえに、もしこの出来事があったこと を人にしゃべったら殺す、と言った。だが、ここで寝ている子供達を見 てると、どうしておまえのことを殺せようか。どうか子供達の面倒をよ く見ておくれ……」 そういうと、お雪の体はみるみる溶けて白い霧になり、煙だしから消え ていった。それ以来、お雪の姿を見たものは無かった。』 このお話しは、皆さまよくご存知の、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『怪談(Kwaidan)』で紹介されている「雪女」です。美しいけれど、しかしほんとうは怖ろしいという雪の世界を象徴するお話だなと思います。 そしてお気づきになりましたか、この物語は、じつは豪雪地帯が舞台ではなく、しかも2人の木こりも雪に慣れていなかったことに。 そう、物語の情景から、ついつい豪雪地帯の山岳部における木こりの遭難の話しだと勘違いしやすいのですが、じつはこの物語は 多摩川べりの船頭小屋が舞台となっており、しかも茂作と巳之吉という2人の木こりは、雪というものに対してあまりに知識もなく無防備なんです。 船頭小屋って こんなかんじ ですもの。 持ち運びもできたというこんな簡単な小屋に、大雪のなか避難したら、それはむしろ遭難しない方がおかしいですよ。 小泉八雲が東京都西多摩郡調布村出身の親子から採録したというこの物語は、じつは あまり雪が降らない地方における“突然の大雪”に対する警告的な教訓談 であったのかもしれません。 普段は豪雪地帯ではない地方 で降雪に遭われている皆さま。 寒さ対策は万全になされてくださいね。 → ビニールハウスが積雪に弱い話は こちら 。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2016.01.29
-

伝説はこうやって守られる。
伝説はこうやって守られる。本年の初日の出は、沖あいに2つの岩礁が浮かぶ美々津の浜で見た。 さえぎるものなどなにもない広大な日向灘から昇る太陽を見るには絶好のポイントであるこの浜では、初日の出用に紅白の幕まであり元日の朝にはけっこう人出があるのだ。そんな元日の朝、初日の出を待っている時間に海をみていて、この浜にはひとつの言い伝えがあるのを思い出した。それは左側の写真の沖あいに写っている2つの岩礁にまつわるもので、“この2つの岩礁の間を通ってさらに沖に出るとかえってこられなくなる”というもの。真実かどうかはわからないし、現代の美々津港からでる船がいまでもこの戒めを必ず守っているのかどうかもわからない。しかし、この地をふるさととして育ったものであれば、一度はきいたことがある言い伝えではあるのだ。そしてこの言い伝えには、理由がある。それは神武東征。この美々津から出港した神武天皇の船軍は、沖の2つの岩礁である一ツ礁と七ツ礁の間を通っていった。この船軍は再び国に帰ることはなかったので、それゆえにこの言い伝えがうまれたらしいのだ。そのような伝承だけではない。この美々津というところでは、船軍が旅立った日といわれる旧暦8月1日の未明には、町内の住人たちの住む住宅の木戸を“起きよ、起きよ”と激しく叩いて起こす奇祭である「おきよ祭り」が伝わっている。これは1日の昼に出港するはずだった予定が早まったことを伝えたものとされている。また、この祭りの日に食べる“つきいれ”とよばれる食べ物があるのだが、これは[出港が早まったために]船軍に提供する団子をつくる時間がたりなくなかったために、小豆と餅を搗き混ぜて差し上げのが起源といわれているのだ。さらには地区名。美々津のみなと周辺を“立縫/たちぬい”というのだが、これは貴人の衣のほころびを急いでてたために衣を立ったまま縫わせた故事に由来する。そのような毎年毎年の祭りや食の体験や、先達たちからの訓示/笑。こんな美々津の港の環境で育った船乗りであるならば・・・おそらくはいまでも言い伝えは守るだろうと思うのだ。ちなみに[立縫地区出身の]わたくし。いくどか釣り好きの船持ちの美々津出身ではない釣り人と、この海の沖の岩礁である一ツ礁と七ツ礁付近で釣りをしたのだが、 一ツ礁と七ツ礁のあいだだけは通るな・行くのなら周回しろと、なんどもいってしまってました/笑。そんな伝説に満ち満ちた[美しい湊が語源とされる]美々津を紹介したページは こちら。ということで、今回は 丸太のような巨大魚もいる美々津にまつわる伝説のおはなしでした。 七夕の行事がない美々津。ササ竹は、おきよ祭り時に 住民をおこすのに使用します。ササ竹で住宅の木戸や 雨戸を激しく叩くのです。笹とはいえど大人数でやる ので、これがまた寝てられぬほどのけっこうな物音!「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2016.01.17
-

アカメも育つ・・・「海のゆりかご」アマモ場。
アカメも育つ・・・「海のゆりかご」アマモ場。前回の 丸太のようにでかい魚 のつづきとなります。 ↓ 海で誕生した植物である海藻類の一部は陸上に進出し、やがて花を咲かせて増殖する被子植物へと進化していきました。その被子植物の一部のうち、再び海にもどってきた植物があるのですが、そのような植物のひとつにアマモがあります。 このアマモは穏やかな浅い海底の砂泥に根を張り、地下茎伸ばすと共に、花を咲かせてできた種でも増え、やがてアマモ場とよばれる群落を形成していきます。かつて日本各地の沿岸に広範囲に分布し広がるアマモ場はこうやって形成されていったのですね。 根があります → このアマモ場の作り出す酸素に富んだ空間は、さまざまな魚介類の生 活の場となるとともに、特に産卵のための場所や幼稚魚の時代の保育・成育場として重要な役割をはたしていることから、「海のゆりかご」とよばれていますよ。ちなみに前回ご紹介した巨大魚であるアカメも幼魚の時代にはこのアマモ場で過していることが、確認されています。 アカメの 成長の様子 → 「リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ/竜宮の乙姫の元結の切り外し」という別名を持つアマモ〔乙姫さまが髪を結ぶのに使っているという意味〕。この日本でいちばん長い植物名を持つアマモを育み、アマモ場を復活させていくことが、日本の自然環境再生の大事な足掛かりであることは、間違いのないことのようです。つづく。 アマモ場保全にかんするニュースは こちら 。 40年ほど前は駆除するほどに生息していたというアカメ。 そんなアカメも、アマモの群落の減少とともにその生息数を 減らしていったといいます。ん~、残念っ。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2016.01.09
-

まるで丸太のようにでかい魚。
まるで丸太のようにでかい魚。最大で、体長2メータ、重量40キロに成長する・・と、いわれている気水域に生息する魚です。そんな日本の魚の存在をご存知ですか? 『体は側扁し、銀灰色を呈する。頭部背縁は目の上方でくぼむ。背びれ はまるい。前鰓蓋骨の後縁には鋸歯がある。また、前鰓蓋骨の下縁に は強い4棘がある。鱗は大きい。側線は尾びれの後縁まで達する。 瞳はルビー色。』 といった形状をしたその魚の名前は・・『アカメ』。水中でルビー色に光る瞳の色が名前の由来といわれています。 そんなアカメの画像は、こちら。 日本での生息域は、主として宮崎県と高知県の河口となっており・・・。 大きいものの記録としては、高知県・四万十川での記録で、137センチ・30キログラム、そして 宮崎県美々津町河口の耳川で釣られたものは・・・体長150センチ・35キログラムといわれています。 わたくし美々津にすんでいたこともあるので、耳川のアカメが釣り上がった様子は、昔からいろいろな釣り人におききしているのですが、とくに印象的な話として・・・ ルアーで釣れる全長1メートル弱程度は、アカメとしては、 まだ小物。ルアーにかかった魚に 喰らいつくのが、大物と、そんな話が記憶に残っております。 とくに大きな個体を釣られた方は、河口に釣り用和舟をだしておられたのですが、釣ったアカメを船上に上げることはかなわなかったため、和舟の脇にアカメを引き寄せてなんとか岸までたどりつかれた・・などとまるでヘミングウェイの「老人と海」みたいな話もありました。 ちなみに、このアカメという呼び名は 全国共通の名前。宮崎県でのアカメ は、マルカとよばれますが、これっておそらくは丸太/マルタが変化したにちがいない[と、実際にアカメ/マルカを見た時に思いました]。つづく。 そのような水辺の生き物が暮らす環境、守っていきたいもの ですよね。ちなみに延岡市須美江町須美江ファミリー水族館 には体長110・体高50センチ・重量25キロの剝製が、 そして 宮崎市の大淀川学習館には生きた個体がいます。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2016.01.09
-

“さつま白波”てきな風景。
“さつま白波”てきな風景。鹿児島県の薩摩半島にある指宿からお茶の産地として有名な頴娃[えい]を通過して枕崎方面に向かう。その道すじで、左手にみえはじめるのが、みごとな円錐形をした開聞岳[かいもんだけ]。 晴れ間がみえるとおもっていると、いきなり小雨がふりだり、 雨になるのかとおもっていると やおら晴れたりという不安定な天候を表すかのようにそんな笠雲をかぶった開聞岳の姿を みつけ車中からシャッターを切る。あるときは 牧草地のむこうに。あるときは ビニールハウスの向こうに。あるときは 芝生畑のむこうに。あるときは 岬の向こうに。あるときは キャベツ畑の向こうに。あるときは エンドウ畑の向こうに。という具合に[まわりに山がないために]どこから見てもその美しい稜線を確認できる開聞岳。さすがに薩摩富士といわれることはあるな と、再認識していたところ・・・いやいやそうではなく いちばんの絶景は、いまでいうところの番所鼻自然公園からだといった男がいたのを思い出しました。そしてそんな番所鼻自然公園からみた 開聞岳のお姿がこちら 。ののののの 旅程の都合からお山が逆光になってしまったのですが、それはそれととして、やはりここからの光景はとても美しかったです[個人的には枕崎にあるさつま白波のラベルをおもいだしたりもして/笑]。ちなみにここからの風景をして「天下の絶景なり」と賞賛した人物は伊能忠敬。日本地図作成のために立ち寄った折にいった言葉とされています。ということで今回は、薩摩半島にある美しいおやま のご紹介でした。 サーフブランドのクイックシルバーの商標にも似てます よね、この風景。 そして航海時の目印にもなっていたのだろうなと山川港 の仲覚兵衛さんを思い出したり。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2016.01.04
全5件 (5件中 1-5件目)
1