2020年10月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

ペットだといえなくもない小さなアシタカ。
ペットだといえなくもない小さなアシタカ。昨日分[こちら]にひきつづき次回関連で再掲載です。 ↓座敷の神棚のお花のしたを定位置とし居住いを正して静かに“いる”小さなアシタカ。おそらくは、数日に一回の割合で定期的に取り替えるサカキについている虫をたべてくれているのだろう。またときどきは部屋に出没するゴキブり、窓から侵入するドクガなどの害虫を食してくれているのだと思う〔ひょっとしてナンキンムシなどもだったり〕。のの こういった部屋のいわゆる“警備”業務だけでも感謝に値するのだが、それにもまして、いつも控えに構えているその姿には好感をおぼえずにはおられない。そんな小さなアシタカの様子がちがったのは、今日。神さまのお花のお水をとりかえていたとき。どうにも姿勢が落ち着かない。 おもいあたるといえば、本日の急な寒さ。ここ2・3日の季節はずれの夏日のあとの急激な寒さで、なんだか弱っているようなのだ。そこで庭に出る扉を開けた。そう、いまやペットといえなくもない小さなアシタカのエサを探しにいくつもりで。するとそのとき。一匹のアオバハゴロモが、いずこから飛びきて着ているトレーナーに止まった。不思議なこともあるものだと、そのまま神棚の前まで引き返し正座しハゴロモを触るつもりで、トレーナーの左腕についたハゴロモに指を伸ばしたその瞬間・・・ 飛び立ったハゴロモは畳のうえに舞い降り、すぐさま小さなアシタカのエサとなった。それはまるで、祀られているお方が〔毎日お花を警備してくれるアシタカのために〕餌をお与えになったかのような、そんなできごとにみえた。それにしもアシタカグモ。ツルツルすべすべした身体をしているハゴロモを、なんなく捕らえた。それは、おなじくハゴロモを食する爬虫類のカナヘビなどよりもよほど上手で〔瞬殺でした〕、その器用な食事ぶりには改めて驚かされました。ということで今回は、この秋にペットだといえなくもないほどに親しくなった小さなアシタカクモのご紹介でした。 せっかく仲良しになったのだから、なんとかこの冬を乗り切って ほしい。しかしそうなったら、この個体も来年には 大人の手 の平ほどの標準サイズになるのかしらん。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.31
-

電子機器内に潜む〔ひそむ〕カメムシ!?
電子機器内に潜む〔ひそむ〕カメムシ!?H2013年09月分ですが、次回関連ということでよろしかったら。 ↓『電子機器内に潜む〔ひそむ〕カメムシ!?』海外に煩雑に出かける友人と会話しているときのこと。虫に刺されたという足元を痒がるので患部をみてみると、そこにはたんに虫に刺されたではすまないほどの〔掻きくずした〕傷と刺された跡があった。 この患部のようすはたしか・・・と、わたしが思い当たったのはカメムシの仲間である吸血性の昆虫・トコジラミによる被害。いわゆるナンキンムシによる刺し傷である。“病院にいかずとも治る”と言い張る友人に紹介したのは ■ 2009年の4月・米国ワシントンから配信された このニュース ■ 2012年の7月の NHKの 特集番組のサイト ■ 2013年9月・米国ニューヨークから配信された このニュースでした。これらのニュースや、自分で検索したトコジラミ被害の情報を得た友人。いまは治療してもらいにいった病院で処方された薬の効果で傷は快方に向かっています。それにしても“電子機器内で繁殖することもある”というのは脅威です。ちなみに 月いちのわりで出張にでかけるわたくしの場合ですが、帰宅したらとりあえずバックをひろげて、部屋の中をかってに徘徊している/笑 ハエトリグモ や アシタカグモ に パトロールしてもらっております。そして余談ですが・・・このまま世界の気温があがっていって、トコジラミの生息域が拡大し続けていくとするならば、そのうち 機械の本体を自らの機能で 〔防除の目的で〕加熱したり・冷却したりできる 抗トコジラミ携帯や、対ナンキンムシ〔蒸しですね〕パソコンなどといった機能がついた製品の開発が熱望されるようになったりして。 温度と生物の生息域関連の話ということで、コメにひろ がるカメムシ被害は こちら 。 そして別荘をもった ナメクジの話は こちら です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.30
-

帰ってきた?なぞ?の下草。
帰ってきた?なぞ?の下草。日当たりがわるくなったわけでもなく、寒くなったわけではなく、まして虫がついたわけでもなく、病気になったわけでもなく、水はけがわるくなったわけでもないのにお彼岸まえの時期にすーっと消えてしまった馬酔木/あせびの根元で目隠し的なかんじに植えてあった植物。元気に繁茂していたときは、まじまじと見ることもなかった、そんな根本の目隠しに植えてあった植物を思いだそうとしても、 たしかリュウノヒゲを大きくしたような いやいや ヒヤシンスのような 野生のランのような まてよ、スイセンのような葉っぱのようだったかなあと、正確には その葉の形状をおもいだせなかった植物。そんな自分にとっての謎の植物が、 お彼岸明けになって庭に帰ってきましたよ♡ といっても、もちろん走ってかえってきたなんてわけではなく、ただ同じ場所から芽だってきたわけなのですがそんな芽だちがこちら。 いやはや これで バランスがとれる。ほっとしました。というわけで 前回[こちら]分を見ていただいた方にご報告できるかたちにもなって安堵した次第。それにしても夏場になんの跡形もなく消えちゃうヒガンバナって、なんとも妖しいお花なんですね~。ちなみに同じ場所で、葉が消えて&お花が咲いているお彼岸のじぶんの映像がこちら。となります。 ということで、今回も 葉見ず花見ず のヒガンバナのおはなしでした。 お彼岸自分には視界一面に咲き誇っていた山間部に あるヒガンバナの群生地も、ドライブがてら再度訪問 してみたのですが[たとえばこちら]、お花は一斉に消 えていました。この場合は、❝お花が逝く❞なんて形容 してもよさそうですよね、お彼岸の時分に咲くだけに。。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.22
-

消えた下草ミステリー。
消えた下草ミステリー。10年ほど前になくなった祖母が管理していた庭。そんな家の庭を 私/自分が管理しはじめて2年ほどたちました。樹木の伸びた枝の剪定に、下草刈りなどやっているうちにだんだんと庭に愛着がではじめ、庭の植栽や配置もわかってきた気になってきて、最近では あの樹をこちらに移し、こちらにはこんなお花を植え てみようか、ヤツデなんか植えても 映えるかもねなんて庭の改造までかんがえはじめてきたのですが・・・ 夏になって、↑の写真の玄関先から駐車場の映像をみたときに、ひとつの疑念が頭をよぎりました。それは自然木の門柱の、写真でみると右手にある馬酔木/あしびの木。その馬酔木の木の根元に生えていたはずの草が すっかり刈り取られた・・というか根ごと堀たてられてたかのように なくなってしまっていたこと。そう、馬酔木の根元が いつのまにやらまる見えというか、スカスカというかいわゆる裸地になっていたのです。前回の庭の剪定&草取りをしたときには、たしかにあった下草。管理時に草刈をしたわけでもなく、まして除草剤をまいたわけでもないのに忽然と消えてしまっている下草。いくども頭の中で記憶を思い返してみましたが、たしかにあったはずの、あの下草がないのです。名前は知らないけれど、ちょうどいい塩梅で存在したあの下草・・・そこで おかしいなあとは思いつつ しようがない、もう少し涼しくなってきたら、似た ような雰囲気のリュウノヒゲとか、いやいやもっと 葉の長い水仙とか、そんな植物を植えようかななどと考え始めていたのです。さてそして、そんな庭仕事の計画をあたためながら迎えた9月下旬。暑さもいくぶん峠をこしたところでまずは剪定からかかろうかなと、ひと月ぶりに実家の庭にやってきて、いつものように駐車場に車を停めて、ガーデニングの道具や衣装やらを玄関に運び込んだちょうどそのとき・・・玄関の内側から、馬酔木の木を見た瞬間に くだんの下草がなくなった理由が分かりました!そこに生えていたのは ヒガンバナ。馬酔木の根元、その場所には“葉見ず、花見ず” と形容されるヒガンバナ[こちらも]が咲いていたのです。 ※茎が伸んで花が咲くあいだは葉がなく、花が終わるころになって葉は伸びてくるので、花と葉はお互いを見ることが出来ないということです※ぁあ、あの下草は ヒガンバナだったのかぁ・・とおもわずクチにだしてつぶやいた自分。 一週間ほど前の9月の中旬には、わざわざ 山手のほうに出向いてヒガンバナの群生も見にいっているというのに! まるで気づけなかったんです。。そう、それは有名マジシャンのマジックにかけられたようなそんなこころもち・・といったところ。そして祖母の植栽って味があるなぁと、おもいましたね。ということで今回は、ガーデニングによって故人とのコミュニュケーションが成り立ったというおはなし[こちら]でした。お彼岸の季節の、ヒガンバナのはなしですから 余計に コミュニケーションもとりやすかったりして。 さて今週末。祖母の庭にいった折には、お花は 終わって、葉がではじめていることでしょうね、 お庭のヒガンバナ。♪ニルヴァーナを聞きながら 車で再度の剪定に向かいます。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.15
-

タヌキが腹鼓をうつ音なのかなと思ったら。
タヌキが腹鼓をうつ音なのかなと思ったら。郊外にある事務所。まだそこかしこに田んぼがあるかんじの住宅地の一画。そんな事務所に泊まることになったある夜。昼間の何気ない物音がしなくなった夜更け。酷暑をやり過ごして鳴き始めた秋の虫たちの声のコーラスにまじって、どこからともなく聞こえてくる異音。深夜になってはじまる、20分おきくらいの周期をもって聞こえる 1回だけ聞こえる ポンっ という音。その怪音の ぬし、その音を立てている何者かを頭の中で想像してみれば・・・ それはたとえば お月さまを愛でる八百八タヌキの腹鼓[20分に一回だけ] のような怪異なものが出す音・・にもおもえたのです。そんな深夜になると聞こえ始める不思議・不可思議な音に興味をもった3日目の夜。どうにも音の主の正体を知りたくなって、再度事務所に泊まることとし、片手に懐中電灯腰にガーデニング用の蚊取り線香をぶら下げて午前2時すぎの事務所外に出て、昼間用意していた座椅子に腰掛け、怪音が聞こえるのを待ってみたのです。手を伸ばせば届きそうな星空のした、ほどなく聞こえてきたのは、ポンっという音。さっそくにおいでなすったか と、音のした方角にある電信柱の方向にライトを向けるが、なにもいない。念のために電信柱の裏側も確認したのだか、ここでもない。ままよ と、そのまま しばらくまってみたところ、またまた聞こえるポンっ。という音。方角は同じ。ただ今度は案外高いところから聞こえてきたのを確認した。そして 20分。そのままいても、こんどは音がしなくなったので、電信柱の裏手にある空き地まで足をのばしたちょうどそのとき。まさに その瞬間に、ふたたびのポンっ。そして、みたのです。その音と同時に、誰もいないはずのブロック塀越しに見えている無人のはずの事務所の勝手口とシャワー室の電灯が消えていったのを!!!すわっ騙された、怪異は屋内だったかっ・・と、踵を返し事務所へ急ぐ。鍵を回して開錠しドアをあけて屋内に入り、暗くなっている室内の電気をまずはつけようとスイッチを押す。だが点かない。懐中電灯で室内を照らすが誰もいない。電気をつけていた別の部屋を確認する。誰もいない。そこで再度入口にいき、何者かに切られたはずの勝手口の電灯の点灯スイッチ部分を手に持った懐中電灯で照らしてみれば・・なんとスイッチはオンのまま。あわててスイッチを触る。パチパチパチやってみる。つかない!勝手口から部屋に入って、もういちどスイッチをいれるが、やはりだめ。壁のエアコンを見あげる。つけておいたはずなのに、動いていない。。そうだ、ブレーカーだと閃いて、戸口付近のブレーカーのフタを開けて、懐中電灯でてらしてみれば、部屋ごとのブレーカーは、すべて異常なしで、落ちてはいない。そんな状況にもかかわらず、奥まった部屋からの灯りは点いている。。。まさに不思議な状態です。化かされてるのか・・とおもいましたね/笑。けれど 身体は無事だし、頭もクリア。 ひらきなおって室内の椅子に座り、こころを静め、各部屋の電気や電化製品の稼働状況を確認します。室内の電気が使えないのはひと部屋だけ。あとはシャワー室に、エアコンに冷蔵庫、トイレの電気などなど。それに加えて、さきほど外から消えるのを見た勝手口の灯りだということがわかりました。それ以外の部屋の電灯や電気を使うのには支障はない。ここにきてやっと、これは単に家屋内の一部が停電しているだけの状態であることが頭で理解できました。そして音の原因に推測がつきましたよ。そう、 ポンッという定期的に聞こえていた音の正体は、塩の害による電線のショート音。 これは台風10号の塩害のもたらす被害であったのです。 なるほどそれなら、時間をおいて発生することも、部分的な停電も[修理の時点で3本ある電柱からのびている引き込み線のうちの1本のみのショートであるとわかりました]合点がいく。昼間の喧騒がなくなり、静かになる深夜の時間帯に音が聞こえ、そのうち次第に被害が徐々に、しかし確実に顕在化していき、台風通過後の5日から7日後にかけて完全にショートしてしまう。たまたま今宵がその日 だったのです。ということで今回は、台風被害がたいしたことがなくてよかったとほっとしている頃に、塩害が時間差でやってきたという おはなしでした。雨の少ない台風に見舞われる場合には、こんな被害も起きるんだなあ と思いましたね。台風銀座なんてよばれたこともある宮崎に長年住んでいますが、台風通過後の塩害による停電に見舞われたのは 初。台風はいろいろなことをおこすものだなあと、あらためて思い知らされた次第です。・・・腹鼓を打つタヌキを見損なったことは、ちょっと残念でもありましけれど/笑。 怪現象よりももっと怖かったこと。それは・・・ 今回の状況を電力会社に問い合わせたら『ただいま そういった状況の問い合わせが昨日くらいから殺到 していまして、状況確認が何日後になるのかも、 いまのところ不明なんです、順番でやってますので お待ちください』と、いわれてゾゾゾッとしたこと。 トイレもシャワーも冷蔵庫も、つかえなのにぃぃぃ。 → 植物の塩害については こちら と こちら。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」
2020.10.12
-

お花版のスローフードみたいな・・・そんなお話。
お花版のスローフードみたいな・・・そんなお話。 次回関連で、2009年分再掲載です。 ↓『お花版のスローフードみたいな・・・。』仏壇のない家がふえているようですね。それに伴って仏壇に飾る お花の 種類も変化してきました。以前、仏花といえば菊。菊でなければいけないといった風潮さえあった時代が夢のようです。 いいことだと思うんです。仏壇はないけれど、故人の好きだった花や自分のすきな花を、写真のそばに活けてみる。たとえば「おばあちゃんの好きだったユリやバラをかざってあげたい」なんて想う心が、なんだかとてもほほえましい。 都市部のお花やさんで売れる仏花はとくにこの傾向が強いのだとか。ヒマワリやガーベラ、バラにデンフェレなどのリクエストも多いといいます。品種に詳しくないお客さんも「明るい花束を」、「ピンク系に仕立ててください」と、注文をされるのだそうです。 ガーデナーとしたら、その傾向をもう一歩すすめたいですね。自分の庭やプランターで作ったお花を飾りたい。リビングや床の間、お気に入りの家具の上においた大切な人の写真の横を自作のお花で彩りたい。 それに加えてこんな楽しみもあるんですよ。それは バラ作りを通じて、同じようにバラを栽培していた故人の体験を、あなたも追体験することができること。 「こんな生育状態のとき、おばあちゃんなら どうしてたんだろ?」とか、 「わたしもピンクのパラが好き、いっしょなんだなあ」なんてかんじで、 バラ作りを通じて時間と空間を越えた故人との会話が可能 になる。 それって、あなたの身体のなかに確かに存在するおばあさんの遺伝子を確認する行為でもありますよね。・・・なんだか いいなあ。さらによくよく考えてみれば、こういったガーデニングによる仏花の手作りは、経済が発達する以前の「自然な供養」の姿ではなかったのかなとも思います。そうであるなら、この『手作りのお花で供養』運動は、業者の手にわたっていた供養という行為と「供養花」を自らの手にとりもどす行為ということにもなりますね、きっと。 これって、つまりは お花版の地産地消、お花版スローフード。っていうか 『スローフラワー運動』 ですね。ふふふ。 そうやって、太古の昔からの先人達の努力の積み重ね でガーデニングや農業は発展してきたのではないのか とも思うのです。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.08
-

かわいいなと思ったお花は意外にも。
かわいいなと思ったお花は意外にも。宮崎県でも、鹿児島県よりの小林市をドライブ中に9月22日前後に 沿道でみつけた 植え込みのしたから顔を覗かせている お花の花茎。たとえば クロッカスとか、そんなかんじに見受けられてどんな葉しているのかな と思って、植えこみのしたを探しても ただ 花茎があるのみ。もっと成長のはやい個体はないかな・・・とおもって、日当たりのよい 別の場所を探したらありました・ありました。その正体は花のある時期に葉はなく、葉のある時期には花がないという ヒガンバナでした。植え込みの下からでてきている&開花したあとのお花のイメージや咲いている場所が[自分のなかでは]強烈すぎるので、連想できなかったのですがなかなかにかわいいお花でもあるのだなと 再認識。。 有毒ということで、田んぼの畦に植えられたり お墓のそばに植えられたりしているイメージの ヒガンバナ。食べるとしんじゃう/彼岸にいく こともあるということから、こういう名前が付 けられているという説もあるのですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」
2020.10.05
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-
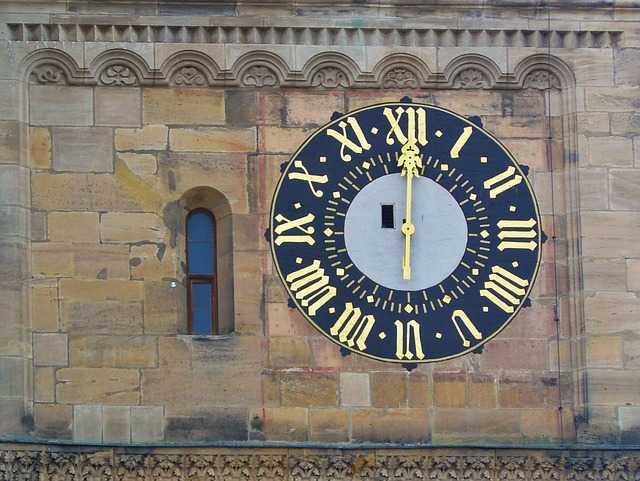
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- 日常の生活を・・
- 本日もドタバタ!洗濯機壊れてテンヤ…
- (2025-11-06 20:13:53)
-
-
-

- 地球に優しいショッピング
- ☆洗たくマグちゃん プラス☆
- (2025-09-04 23:16:08)
-







