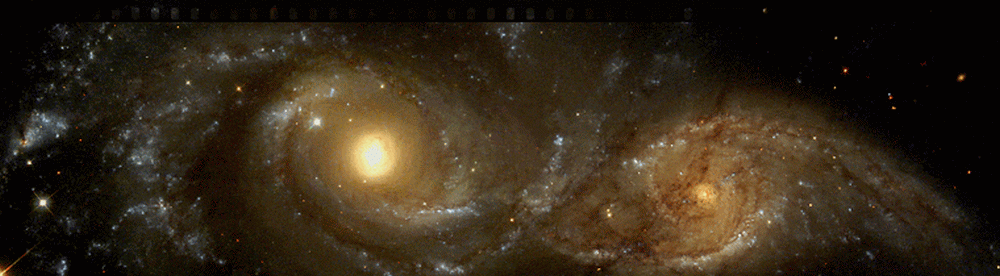2025年04月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-

玉電(たまでん)渋谷駅 1968年
写真は、1968年3月と8月に玉電渋谷駅で撮影したものです。 当時の玉電渋谷駅は、東急東横店から井の頭線の方向に向かって設置されていました。現在の渋谷マークシティー連絡通路辺りにありました。 玉電は、東京急行電鉄の軌道路線で、玉川線(通称玉電)と呼ばれていました。1907年(明治40年)に開業、1969年(昭和44年)に下高井戸線(現・世田谷線)を除いて廃止されました。 写真の車両は、デハ70形、デハ80形、デハ200形(2車体連接構造流線型電車)です。カラーの写真は、電車とバスの博物館に展示されているデハ200形です。【Bon appétit !】 Type DeHa 200 was launched in 1955. It is an articulated two-car tram. A total of 6 sets were manufactured by Tokyu Sharyo Company. One of the prominent features of this electric car is its low floor. The height of the floor is only 59 cm above the railway track. It was nothing less than epoch-making at the time. The single axle articulated truck was also quite unique.(https://tokyorailwaylabyrinth.blogspot.com/2012/05/electric-car-type-deha-200-in-tokyu.html)
2025.04.30
コメント(4)
-

暖房車マヌ34 2120形蒸気機関車
2枚の写真は、1968年4月に立川駅で見かけたマヌ34 13と、マヌ3413に流用されたボイラーの提供元となった2171と同形の2120形蒸気機関車の写真です。 マヌ34は、暖房車です。暖房車は、蒸気暖房用の蒸気を発生させるためのボイラーを積んだ車両のことです。車両表記「ヌ」は、「ぬくめる」や「ぬくもり」が由来という説があります。 マヌ34は、1949年から1950年にかけて29両が制作され、東海道本線で使用されました。その後、中央本線や北陸本線に転属し、1972年(昭和47年)まで稼働していました。 蒸気機関車が牽引する列車の場合は、蒸気機関車が発生した蒸気の一部を配管を通じて客車に流すことが出来ましたので暖房車の必要はありませんでしたが、無煙化が進み、蒸気を発生する装置が付いていない電気機関車やディーゼル機関車の登場に伴い暖房車が必要となってきました。 当時日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部は、暖房車の新製を認めなかったので、改造名義で既存車の資材を流用して暖房車を作ることとなりました。 マヌ3413は、当時休車中だった2120形蒸気機関車の2171(1903年ノース・ブリティッシュ・ロコモティブ社グラスゴー工場製)のボイラーや無蓋車の台枠や連結器等を流用して1950年に制作されました。1971年に廃車となっています。 なお、暖房車は、燃料に石炭を使っていますので、電化路線でもトンネル通過の際に窓を開けていると、暖房車から出る煤が入ってくる事がありました。
2025.04.27
コメント(4)
-

クモエ21000救援車 1968年
写真は、1968年3月に撮ったものです。どこで撮影したのか不明ですが、おそらく田町電車区だと思います。 写っている電車は、クモエ21000と呼ばれる救援車で、車体長17m級の半鋼製事業用制御電動車です。救援車とは、鉄道事業者が使う事業用鉄道車両の一種で、災害、鉄道事故や除雪現場などの際に出動し、枕木等の応急復旧資材や工作機械の保管・運搬や作業員の休憩所に用いられます。 クモエ21000は、片運転台の制御電動車クモハ11 114を救援車用に改造したものです。車体中央部に幅広の扉を設け、両運転台に改造されています。 調べると、クモエ21000は、当初は片運転台制御電動車デハ73200形として製造され、1928年の称号改正でモハ30 012に改称された車両で、1953年の称号改正によりモハ11 004に改番となり、その後修繕されモハ11 114に改番され、1963年に両運転台に改造されてクモエ21000になりました。 1963年から1967年にかけて、クモハ11形5両がクモエ21形救援車に改造され、1986年までに全車が廃車されました。
2025.04.26
コメント(0)
-

日光形電車、近郊形電車、パンタグラフ台付き付随車 1968年
3枚の写真は、1968年3月に東京駅で撮ったものです。 急行伊豆のヘッドマークを掲げている電車は、157系です。157系は、最初に投入された列車名から「日光形電車」とも呼ばれています。東海道新幹線開業による1964年10月のダイヤ改正では東海道本線の昼行特急が全廃となり、それまで特急で使用されていた157系が、1964年11月にデビューした東京~伊豆急下田・修善寺を結ぶ急行伊豆に使用されることとなりました。その後、1969年4月に東京~伊豆急下田を結ぶ特急あまぎに157系が使用されたため、急行伊豆は153系電車を使った普通の急行列車になってしまいました。 153系の急行東海と並んでいる両開き片側3ドアの近郊形電車は、113系です。1962年に湘南電車、横須賀線で営業運転が開始されました。113系は大都市圏のほか、房総地区や東海道・山陽地区のローカル輸送など、主に本州内の平坦で温暖な地域の路線で広く普通列車から快速列車に用いられました。 中間車両の写真は、サハ100-205です。この車両は、モーターも運転台もない付随車であるにもかかわらず、パンタグラフを置くための台が屋根に取り付けられています。パンタグラフ台が付いている理由は、車体と機器類は将来の電動車化を考慮した構造としたからです。101系は、全車両をモーター付きの電動車として編成全体の出力を高め、高加減速運転を行う方針の下で進められましたが、変電所容量やコスト面から困難となり、将来の電動化を考慮した付随車が製造されることとなりました。なお、写真のサハ100-205は、付随車ながら電動発電機と空気圧縮機が付いています。
2025.04.25
コメント(2)
-

クモハ73 クハ79 1968年
3枚の写真は、1968年3月に、日本車輛蕨工場をバックに撮ったものです。 日本車輛蕨工場は、新幹線の試作車や量産車0系が製造されたことで有名です。 写真に向かって左向きに走っている南行電車は、クハ79 366です。前面窓傾斜タイプとなっています。前照灯はまだ埋め込み式になっていません。 運転席側にパンタグラフがついていて、前照灯が埋め込まれていない電車は、クモハ73 126です。クモハ73の初期の標準的な形です。 115系電車に並んでいて側面に汚れがある電車は、クモハ73です。前照灯が埋め込まれ側面窓が従来の3段窓から2段式アルミサッシ窓になっています。
2025.04.24
コメント(0)
-

まだ桜が楽しめました 多摩森林科学園
2025年4月19日、高尾駅を降りて、八王子城址へ向かいました。途中、多摩森林科学園がありましたので、寄ってみました。ソメイヨシノなどは葉桜になっていましたが、まだまだこれから満開を迎える品種の桜もありました。ここには日本全国の主要な桜が1,800本植えられているとのことです。 I visited Tama Forest Science Garden on April 19,2025 where 1,800 cherry trees from all over Japan are planted. You can enjoy the various trees in bloom one after another even in late April. 【Bon appétit !】 The Cherry Tree Preservation Forest at Tama Forest Science Garden is one of the largest collections of famous cherry trees and their varieties, and it serves as a valuable genetic resource. There is a lot of confusion regarding traditional cherry trees varieties, which date back to the Edo period, due to issues such as some trees of the same variety having the different names and some trees of different varieties having the same name. As such, the Science Garden is working to establish methods for the accurate identification of these trees, involving morphological(形態学の)surveys, literature surveys, gene analysis, and so on. The Science Garden is also examining accurate management methods and moving ahead with research aimed at the conservation and future utilization of cherry trees.(https://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/en/visit/japanese-flowering-cherries.html)
2025.04.22
コメント(4)
-

東京駅のEF65、70系、101系 1968年
3枚の写真は、1968年3月に東京駅で撮ったものです。 電気機関車は、東京駅の9番ホームに入線してきたEF65 527です。後ろに20系客車の特急「あさかぜ」を牽引しています。EF65形電気機関車は、1965年 (昭和40年)に開発された直流用電気機関車です。1979年(昭和54年)までに国鉄電気機関車史上最多である308両が製造されました。写真のEF65 527は、高速旅客列車牽引用として、1965年から1966年に製造された17両のうちの一つです。 湘南型の電車は、70系電車です。「スカ色(横須賀色)」と呼ばれるクリーム色と青色に塗分けられています。70系は、3扉セミクロスシートの電車で、1951年から1958年にかけて導入されました。当初横須賀線に導入されていましたが、1962年以降111系や113系が投入されたため、1968年1月までに全車転出しています。この写真を撮った時期は、1968年3月ですので、何故東京駅にいたのか、ネットで調べてみましたがわかりませんでした。もしかしたら、1月以降も東海道線で使われていたことがあったのかもしれません。写真の先頭車はクハ76014です。1977年に廃車されています。 通勤電車は、101系電車です。写真の中央線特別快速は、1967年7月に登場しました。運行開始当初は前面窓の内側に「特別快速」の小型表示版が掲げられていましたが、9月には大型のヘッドマークに変更されています。写真にあるように、ヘッドマークには「特」と「快」の文字が大きく書かれていますので、「特快」の呼称が定着したと言われています。101系は、1957年(昭和32年)に登場した直流通勤形電車で、当初モハ90系電車と称されていましたが、1959年の称号改正に伴い、101系と改称されました。旧来の吊り掛け駆動方式から脱却し、カルダン駆動方式などの近代的メカニズムを搭載し、いわゆる「新性能電車」のはしりとなった系列です。【Bon appétit !】 The Class EF65 is a 6-axle (Bo-Bo-Bo wheel arrangement) DC electric locomotive type operated on passenger and freight services in Japan since 1965. A total of 308 locomotives were built between 1965 and 1979. The EF65-500 subclass consisted of a total of 42 locomotives, including newly built locomotives and locomotives (EF65 535 - 542) modified from the earlier EF65-0 subclass (EF65 77 - 84) for use on overnight sleeping car services and express freight services.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_EF65)
2025.04.19
コメント(0)
-

京成電車 1968年
写真は、1968年3月に日暮里駅で撮ったものです。 貫通幌がある車両は、京成500形クハ502だと思います。 両開きドアになっている車両は、京成3200形3224だと思います。
2025.04.18
コメント(0)
-

今朝の富士山、浅間山
写真は2025年4月16日に荒川左岸の道満公園-大宮健保グラウンド間から撮ったものです。富士山の左上には満月から3日ほど過ぎた月が見えていましたが、太陽が昇るにつれて見えなくなっていきました。水を引き入れた田んぼが現れ始めました。もうすぐ代掻きが始まり、5月の連休には田植えが始まることでしょう。 北の方角には浅間山が見えていました。富士山同様、雪をかぶって真っ白です。 I took pictures of Mt. Fuji and Mt. Asama covered with snow from a river bank of the Arakawa in Saitama City on April 16, 2025.
2025.04.16
コメント(0)
-

両国駅のキユニ11、蕨-南浦和間を走るキハ58系 1968年
写真は、1968年3月に、両国駅及び蕨-南浦和間で撮ったものです。 両国駅に停車中の気動車は、郵便荷物気動車のキユニ11です。両国駅は、千葉に向かう優等列車の出発駅となっていました。キユニ11は、千葉方面へ新聞を運んでいました。キユニ11は、1965年から両運転台気動車のキハ11を改造して、全部で3両製造され、2両が千葉に来ていました。ました。その後、房総地区各線の電化により千葉から岡山及び豊岡に転属し、1980年に廃車となっています。走行中の気動車は、蕨-南浦和間を上野方面に向かっています。キハ58系気動車です。かなり長編成の急行ですので、想像するに、「いいで+ざおう」のように、複数の急行が併合したものだと思います。キハ58系気動車は、1961年から1969年まで大量に増備され、1960年代から1980年代にかけて幹線・ローカル線を問わず、日本全国で急行列車を中心に運用されました。
2025.04.15
コメント(0)
-

浦和電車区の72系・73系電車 1968年
写真は、浦和電車区に停車中の72系電車等で、1968年3月に撮ったものです。 真正面から写した写真は、茶色のクモヤ90 009とスカイブルーのクハ103です。クモヤ90は、モハ72形を改造した事業用電車で、車両基地内での入換や回送時の牽引車に充当されていました。京浜東北線には、103系は1965年から導入されていましたが、72系・73系は、1971年まで走っていました。 斜めから撮った2編成が並んでいる写真は、向かって左側先頭がクモヤ90 009で、右側先頭がクモハ73 126です。 車止めの前に停まっている編成の先頭車はクハ79 344です。全面窓や運行番号表示窓がHゴム(断面がH型の帯状のゴム)支持となっています。また、前面窓のうち向かって左側のものは2段で、運転室への通風のため下部の窓は上昇可能となっています。本線を走っているのは115系です。
2025.04.14
コメント(0)
-

見沼の桜 ピークは過ぎましたが、まだまだ見ごろの桜もあります
写真は、2025年4月12日の見沼代用水東縁付近の様子です。 Photos show the cherry blossoms in Minuma area, Saitama City on April 25, 2025. 桜の写真3枚は、ソメイヨシノです。見沼代用水東縁、西縁に沿って総延長20kmを超えて2,000本ほどのソメイヨシノが延々と連なり花を咲かせます。桜の下を散策できる日本一の桜回廊です。道路には、桜の花びらが敷き詰められ、葉桜になっている桜もありますが、まだ満開の桜もあります。 真っ赤な花の写真は、見た目、西洋つつじのような気がしますが、正体はわかりません。今度見かけたらよく見てみようと思います。 黄色い花の写真は、芝川河岸の菜の花です。延々と続いていました。【Bon appétit !】 The longest walking path under cherry blossom trees is in Saitama city. There are many beautiful cherry blossom spots throughout the country, but this is the only place where you can walk under cherry blossoms for over 20 kilometers. The cherry blossom trees were planted in the 18th century when the canal of Minuma was developed. There are many kinds of cherry blossom trees in the region, so you can enjoy the bloom for longer period of time as compared with other spots.(https://newurawafilm.com/cherryblossom/)
2025.04.13
コメント(2)
-

雪の大宮駅のC11、大宮操車場のキューロク 1968年
写真は、1968年2月頃、大宮駅構内のC11と大宮操車場で入替するキューロクを撮ったものです。【Bon appétit !】 The Class C11 is a type of 2-6-4T steam locomotive built by the Japanese Government Railways and the Japanese National Railways from 1932 to 1947. A total of 381 Class C11 locomotives were built and designed by Hideo Shima.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_C11)
2025.04.12
コメント(0)
-

EF56 EF57 蕨-南浦和間
写真は、1968年(昭和43年)2-3月に、蕨-南浦和間で撮ったものです。 EF56は、1937年(昭和12年)から製造された直流用電気機関車です。パンタグラフが中央寄りに設置された独特の形態をしています。EF56は、暖房用の蒸気発生装置を追加して冬季の暖房車の連結を不要とした画期的な形式です。写真のEF56は、EF56形最後の12号機です。13号機として製作されていた車両は、電動機の出力を増強し、EF57形(EF57 1)とされました。写真のEF5612を含む5両は、1969年(昭和44年)にEF59に改造され、山陽本線急勾配区間「瀬野八」補機として活躍しました。残りの車両はEF58形の転入に伴い、1975年(昭和50年)に全車廃車されました。 EF57は、1941年(昭和16年)に2号機が登場し、1号機を含めて15両が製造されました。1949年(昭和24年)の東海道本線静岡地区の電化の際に、2号機以降はパンタグラフが車体端から極端に突き出した独特の形態となりました。【Bon appétit !】 The Class EF57 of 2-C+C-2 wheel arrangement DC electric locomotives was a development of the previous JNR Class EF56. 15 Class EF57s were built between 1939 and 1943. Introduced on Tokaido Line passenger services, they were seen at the head of expresses such as the Tsubame, complete with train headboard mounted precariously on the front of the cab decks. With the introduction of the newer semi-streamlined Class EF58s on Tokaido Line services, the EF57s were transferred to the Tohoku Main Line. At the same time, their steam-heating boilers were removed and replaced by electric-heating generators. The class remained in use on long-distance express trains on the Tohoku Main Line until the 1970s.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_EF57)
2025.04.11
コメント(2)
-

日本車輛の入替用SL 蕨駅付近のDL、貨車移動機 1968年
写真は、1968年2月頃に撮ったものです。 蒸気機関車は、日本車輛蕨工場の入れ替え用に使われていたものです。この写真を撮った時は既に廃車となっていました。ネットで調べると、蕨工場には国鉄105形蒸気機関車が1951年から導入されていたとのことですが、1960年に解体されたと言われています。写真の蒸気機関車は1968年に撮影したものですので、105形蒸気機関車は解体されていなかったということでしょうか?あるいは、違う蒸気機関車なのかもしれません。 B-B(2軸駆動×2セット)サイドロッド式(車輪外側面に取り付けられた棒を通じて駆動する方式)ディーゼル機関車は、住友セメントのD301 です。蕨駅には、住友セメント専用線があり、セメントを積んだホッパー車の入れ替え用に使用されていました。 貨車移動機と思われる車両は、蕨駅構内で貨車の入れ替えを行っていました。貨車移動機とは聞きなれない言葉ですが、駅構内の貨物側線などで貨車を動かす作業をするための機械のことです。従来は人や馬が行っていたことを代替して行います。形式名は無いようです。【Bon appétit !】 Nippon Sharyo Ltd., has been manufacturing railroad vehicles for more than 120 years. In addition to extensive penetration in the domestic Japanese market, Nippon Sharyo cars are currently running in Asia, the Middle East and North and South America. This group is an innovator in the famous “Shinkansen” bullet train, maglev(磁気浮上)motive technology, new materials, and improvements in safety, passenger comfort and ease of maintenance.(https://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo_e/2000history_e.html)
2025.04.08
コメント(0)
-

見沼田んぼの桜は満開でした
写真は、2025年4月7日の見沼代用水の桜の様子です。 満開です。もう何日か経つと、道路の上に花弁が敷き詰められることでしょう。 見沼代用水東縁(ひがしべり)から富士山が見えました。赤い橋は、氷川女體神社の前、見沼代用水西縁にかかる橋です。 I visited Minuma Tambo area in Saitama City on April 7, 2025. 【Bon appétit !】 In the vicinity of Minuma Tambo, there are three old Jinja (Shinto shrines): the Hikawa Shrine in Omiya Ward, the Hikawa Nyotai Shrine in Midori Ward, and the Nakayama Shrine in Minuma Ward. Among them, Hikawa Shrine is regarded as the head shrine of many other Hikawa Shrines found in different districts, mainly in the former Musashi-no-kuni area (present-day Tokyo, Saitama and Kanagawa).(https://www.minumatanbo-saitama.jp/english/culture.htm)
2025.04.07
コメント(2)
-

E491系(East i-E)が走ってきました
昨日2025年4月5日(土)、赤羽駅で電車を待っていると、見慣れない電車が走ってきました。East i-E(イーストアイ・ダッシュイー)の愛称を持つE491系電車です。初めて見ました。先頭車はクモヤE491 と思われます。 E491系は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の交直流事業用電車で、信号・通信・電力・軌道の検測を行います。 I encountered the E491 series electric multiple unit at Akabane railway station on April 5, 2025. It is operated for inspection of track and overhead line.【Bon appétit !】 The E491 series, branded the East i-E, is a Japanese non-revenue dual-voltage electric multiple unit operated by the East Japan Railway Company since March 2002 for track and overhead line inspection.(https://locomotive.fandom.com/wiki/E491_series)
2025.04.06
コメント(0)
-

霧の中の桜 満開まではまだ数日
写真は、今朝の見沼代用水西縁(みぬまだいようすいにしべり)のソメイヨシノです。 まだ開いていないつぼみが3-4割あり、まだまだ桜が楽しめそうです。場所によっては、花弁が散り始めています。 今朝は、太陽が昇り始めると、霧がどんどん濃くなってきて、すぐ先も見えないような状況になってしまいました。 I visited Minuma area in Saitama City early in the morning on April 4. Photos show the cherry blossoms in the fog. As they have not been in full bloom yet, you can enjoy viewing flowers for more several days.【Bon appétit !】 Minuma is the wetlands area spreading through the center of Saitama City, and is a prosperous rice production area of the Kanto region (tambo means rice field). Cherry blossoms often come up in talks about Japan’s unique nature, and it just so happens that the Minuma area has the single longest walkable stretch of cherry blossom trees in all of Japan. If you find yourself here during the blooming season, plop down and have some snacks and drinks under a tree.(https://www.stib.jp/saitamacity-visitorsguide/spots/minuma/)
2025.04.04
コメント(0)
-

大宮操車場のキューロク 1968年
写真は、入れ替え作業中のキューロクで、1968年2月頃、大宮操車場南端にある与野駅の北側にある大原橋付近から撮ったものです。79658、29680,59654が確認できます。 小学生の頃、しばしば大宮操車場で入れ替え作業をする蒸気機関車を日がな一日見ていました。与野駅で降りて、大宮駅方面に向かって歩いたところにある跨線橋大原橋の辺りが気に入っていました。大宮操車場の南端にあり、入れ替え作業中の蒸気機関車のほとんどを見ることが出来ます。 現在のさいたま新都心は、大宮操車場跡地に造られました。大宮操車場は、東京における貨物輸送の北の玄関口として機能し、1928年に開業し、1984年に操車場機能を停止しました。東北本線の操車場として一部が現存しています。【Bon appétit !】 The JNR Class 9600 is a 2-8-0 Consolidation-type superheated steam locomotive operated by the Japanese National Railways from 1913 to March 1976. The 9600s were used mainly as freight locomotives and could be considered to be the quintessential(典型的な)Japanese steam locomotive of the time, matching performance with Japanese ingenuity(創意工夫能力). The locomotives were retired in 1976, and were among the longest serving steam locomotives in Japan. Six more locomotives were built for use on private railways around Japan, with 39 more manufactured for use by the Taiwan Railways Administration as the Class DT580 and 9 more as the Class 80 for the Sakhalin Railway.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_9600)
2025.04.03
コメント(0)
-

181系、キハ81系 上野駅1968年
写真は、1968年2月に上野駅で撮ったものです。 特急「あさま」の写真は、181系電車です。181系は、151系「こだま形」の形状を踏襲しています。「こだま」は、国鉄初の電車特急で、東京-大阪間の日帰り出張を可能にした画期的車両です。その151系が1964年の東海道新幹線開業後は東海道本線を追われ、山陽本線系統の特急に転用されたほか、一部車両が性能向上工事を施したうえで上越線特急「とき」へ転用されることとなり、161系を経て1964年に181系へ改称されました。最後まで残った151系車両のサロ151-6・サロ150-2も1969年までに「あさま」増発用として181系に改造され、151系は形式消滅しました。特急「あさま」は、1966年から運転が開始され、田町電車区の181系が充当されました。 特急「はつかり」の写真は、キハ81系です。 キハ81系は、「はつかり形」とも呼ばれ、1960年に9両編成2本と予備8両の合計26両が製造された日本初の特急形気動車です。基本構造は、既に大きな成功を収めていた151系電車を全面的に踏襲していますが、先頭車の形状は、発電セット搭載とタブレット授受の観点から低く抑えた運転台となり、裾絞りを小さくし幅を広くしたため、151系電車の形状からはほど遠く、他に例のない独特のボンネット形デザインとなりました。特急「はつかり」は、1958年に上野駅 - 青森駅間で運転を開始しました。当初は常磐線経由で、C61形またはC62形蒸気機関車牽引の43系客車が使用され、1960年からキハ81系気動車に切り替えられました。この写真を撮った年の秋には583系電車が導入され、東北本線経由となります。【Bon appétit !】 The Hatsukari was first introduced on 1 October 1958 as a long-distance steam-hauled limited express service operating between Ueno in Tokyo and Aomori via the Jōban Line. From 1960, new KiHa 81 series diesel multiple units were introduced on the service, reducing the journey time to 10 hours 25 minutes. From 1 October 1968, the train was amended via the more direct Tōhoku Main Line using 583 series electric multiple units.(https://en.wikipedia.org/wiki/Hatsukari)
2025.04.02
コメント(0)
-

20系客車 カニ21、カニ22 1968年
「はくつる」の列車名を掲げている車両は、20系客車の荷物・電源車のカニ21で、1968年2月に上野駅で撮ったものです。 カニ21は、20系客車へ電源を供給します。電源車の登場により、列車を牽引する機関車に電源供給を依存する必要がなくなり、電化か非電化を問わず車両を運用することが出来るようになりました。20系客車のデザインは、建築限界いっぱいまで拡張された丸い屋根と流麗な曲線基調になっています。後方展望に配慮して曲面ガラスを利用しているナハネフ22に対して一般乗客が立ち入ることのないカニ21の場合は、平面ガラス3枚となっていますが、中央部の窓ガラスを大きくとって曲線基調のデザインが維持されています 「あさかぜ」の列車名を掲げている車両は、カニ2252で、1968年3月に東京駅で撮ったものです。 写真のカニ22は20系でありながら、パンタグラフを搭載した為に丸い屋根と曲面基調のデザインから離れてしまい、残念に思いました。カニ22は、カニ21形同様のディーゼル発電機2基のほか、山陽本線全線電化(1964年)による直流電化区間での架線電力有効利用のために電動発電機と屋根上にパンタグラフ2基を搭載しています。結果、軸重が最大16 tとなり、線路規格の高い区間でしか最高速度で運転できないという制約を受けることになりました。このため、順次、電動発電機とパンタグラフの撤去が行われました。写真のカニ22は、1965年に「さくら」運用での佐世保線入線に備えて電動発電機とパンタグラフが撤去されたものです。
2025.04.01
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1