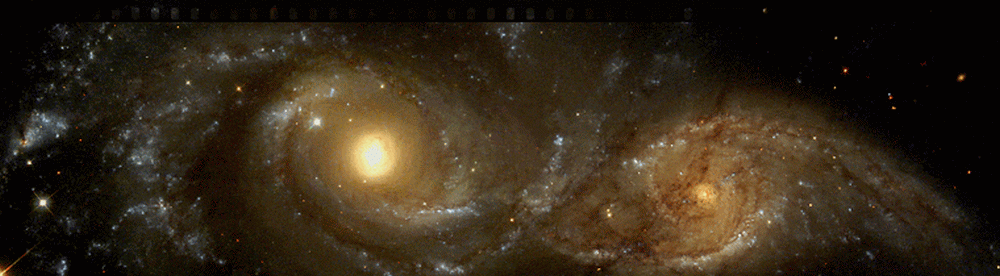2025年07月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

車両性能試験車 マヤ38形 1969年
写真は、1969年1月7日に、品川客車区で撮った車両性能試験車のマヤ381です。 この車両は、1934年に発生した東海道線瀬田川鉄橋急行列車脱線転覆事故で大破したマイネフ37200形のマイネフ37200を修理の上で改造した車両です。マイネフ37200形は、1928年に登場した初の鋼製一等寝台緩急車で、車両性能試験車に改造後も、高さの小さい側窓、魚腹台枠、3軸ボギーのTR71台車など一等寝台客車の特徴を残していましたが、丸屋根でありながら片側のガーランドベンチレーターが取付けられ、妻面には監視窓が、出入台下の3箇所には階段が設けられ、この形式独特の外観となっています。 マヤ38 1は交流機関車・ディーゼル機関車の性能試験に用いられ、1967年に新しい車両性能試験車マヤ10形が登場した後も使用され、1975年に廃車となりました。
2025.07.28
コメント(0)
-

オヤ31形 おいらん車?? 1969年
写真は、1969年1月7日に、品川客車区で撮ったものです。 写真の車輛の形式は不明ですが、見た目が「おいらん車」のように見えますので、おそらくオヤ31ではないかと思いますが、実際のところはわかりません。 「おいらん車」とは、建築限界測定用試験車のことを言います。矢羽根を広げている様子が花魁(おいらん)が沢山のかんざしを挿しているように見えることからその名が付いたと言われています。 建築限界試験とは、駅舎などの建造物が建築限界(線路を走行する車両に障害物が触れないようにするため、周囲の建造物が越えてはならない限界線)内に収まっているか測定する試験のことを言います。車両側面から矢羽根を広げ、建築限界からはみ出した建造物に矢羽根が触れて倒れるとケーブルまたは電気信号により伝達表示される仕組みになっています。
2025.07.27
コメント(0)
-

EF60形501号機 EF58形1号機 1968-1969年
EF60の写真は、1968年12月に新鶴見機関区で撮ったEF60形501号機です。EF60形500番台は それまで20系寝台特急を牽引してきたEF58形を置換えるため1963~64年に製造されました。外部塗色は20系客車に合わせて、地色は青色で前面窓まわりと側面の帯をクリーム色としました。華々しいデビューでしたが、1年後の1965年には20系客車牽引はEF65形500番台P形にバトンタッチしてしまいました。1964年に新幹線が登場し、夜行列車にもスピードアップが要求されたのですが、実は、EF60形500番代は、時速110kmには対応していなかったのです。結局、EF60形は、貨物輸送でその能力を発揮することになりました。 EF58の写真は、1969年1月に東京機関区で撮ったEF58形1号機です。EF58形は、1950年代から1970年代にかけ、東海道・山陽本線や高崎・上越線、そして東北本線黒磯以南といった主要幹線において、旅客列車牽引の主力として用いられました。EF58形1号機となっていますが、最初に落成された機関車は1946年の21号機で、1号機は、1947年に製造され、1948年までに1号機から31号機がそろいました。デザインは、戦前からの伝統に則った「前後デッキ付の箱形車体」でした。EF58形は、半流線型車体へ改造され、EF581は1955年に改造され、古い箱型車体はEF13形23号機に機器ごと転用されました。
2025.07.25
コメント(2)
-

クモル24形クモル24000 1968年
写真は、蕨-南浦和間で1968年12月に見かけた京浜東北線の電車です。 先頭車両は、配給車両で、車体長17m級の片運転台式事業用制御電動車のクモル24形のクモル24000です。後ろに72系旧型電車が続きます。 配給車は、主に車両工場と車両基地との間で、車両などの保守部品を配送するために使用される事業用車両のことを言います。車両記号は「ル」で、クバルの「ル」から来ています。 クモル24000は、1958年にモハ11形のクモハ11134を改造して製作されたものです。運転台直後の車体の3分の1は小物部品の運搬のため有蓋構造になっていて、車体の後半部は大型部品の運搬の便を図るため、無蓋構造になっています。
2025.07.24
コメント(0)
-

近所の田んぼと田町から見た東京タワー Rice field area and Heat island area
2枚の写真は、2025年7月20日に撮った自然の景色と人工の景色です。 案山子の写真は、朝食前に自転車で近所を回っているときに見かけた田んぼの景色です。稲も順調に生育していました。 奥のほうに東京タワーが写っている写真は、田町界隈から見かけた都会の景色です。人工の冷たさはありますが、実際はエアコンのせいでものすごく熱いのだろうと思います。緑地をもっと増やして、地表面の温度上昇を抑制し、蒸発散量を増やしてほしいものです。また、建物配置や街路設計を工夫して、風通しが良い熱がこもりにくい都市空間を形成してほしいものです。 I visited Minuma rice field area in the morning on July 25, 2025. On the same day I took a picture of Tokyo tower from Tamachi area. 【Bon appétit !】 Urban areas usually experience the urban heat island (UHI) effect; that is, they are significantly warmer than surrounding rural areas. The temperature difference is usually larger at night than during the day, and is most apparent when winds are weak, under block conditions, noticeably during the summer and winter. The main cause of the UHI effect is from the modification of land surfaces, while waste heat generated by energy usage is a secondary contributor.(https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island)
2025.07.23
コメント(2)
-

大宮機関区の9684 1968年
3枚の写真は、1968年12月に大宮機関区で撮った9600形蒸気機関車の9684です。 機関区を訪問した時、ちょうど、9684の煙室の扉が開いていて、煙室内の清掃をしていました。チリが舞い上がって清掃する人が霞んで見えます。煙室には、石炭の燃えカスが大量に貯まりますので、それを取り出しています。 煙室と火室は、ボイラ内にあるパイプ(煙管)を通じてつながっています。また一方で、シリンダーから排出された蒸気は、煙室内に入り、煙突に向かって勢いよく排出され外に出る仕組みになっています。蒸気が排出される時の通風で、石炭を燃やして熱くなった火室の燃焼ガスが強制的に煙管を通って煙室内に引き込まれる仕組みです。この時、煙室には石炭の燃えカスも引き込まれ、貯まります。
2025.07.22
コメント(0)
-

水運車ミム100形 大宮機関区 1968年
写真は、1968年12月に大宮機関区で撮った水運車ミム100形のミム182です。 水運車とは、水を運搬するための貨車です。水質の悪い地域にある機関区へはこの水運車を使って、蒸気機関車に使用するための不純物のない水を輸送しました。水の中に溶けているカルシウム、マグネシウム、塩化ナトリウム、シリカ、鉄、アルミニウムなどは、湯垢になって伝熱を妨げたり、ボイラ各部の目詰まりや腐食、水が蒸気に伴って出てゆくプライミングを起こします。機関区によって水質が違いますので、実際、ボイラの痛み方は、機関区ごとに差がありました。 水運車のほとんどは、用途廃止(廃車)となった蒸気機関車の炭水車を最小限の改造で済ませて転用していましたが、ミム100形は他車からの改造ではなく、新規製作車として誕生した形式で、タンク車と似たような形状になっています。 1968年10月の国鉄ダイヤ改正(ヨンサントオ)以降は速度制限運用車に指定され、側面に最高速度65 km/h以下を示す黄色の帯が入った他、記号番号標記は特殊標記符号「ロ」を前置し「ロミム」と標記されました。蒸気機関車の全廃後は用途を失い、1986年に形式消滅しました。なお、「ミ」は、水(ミズ)の「ミ」です。
2025.07.20
コメント(0)
-

新製配置DE10形 試作機DD90形 大宮機関区 1968年
3枚の写真は、1968年12月に、大宮機関区で撮ったものです。 凸型の機関車は、DE10形ディーゼル機関車527号機です。丁度、大宮機関区に新製配置されたDE10形ディーゼル機関車の1両です。DE10は、1966~1978年にかけて708両が製造され動力近代化を促進しました。動軸を5軸として13 t級の軽軸重を実現し、3軸+2軸の台車配置・前後非対称の車体構造など、9600形やC58形の代替機として広汎に使用可能とするための設計が随所に盛り込まれました。 見慣れない形の機関車2枚の写真は、DD90形ディーゼル機関車の1号機の前姿と後ろ姿です。戦後、国鉄がディーゼル機関車の開発を模索していたころ、日本国内の車両メーカーは、独自の機関車を設計・試作していました。DD901は、1954年にアメリカのゼネラル・エレクトリックとの提携で東芝が製造した試作品です。大宮機関区に配置され、入換に使用され、1958年に国鉄が購入しDD90形とされました。その後も大宮操車場で入換作業に従事していましたが、輸入部品ばかりで保守に難があり、1971年に廃車となりました。【Bon appétit !】 A single locomotive was built by Toshiba in 1954 and used as a switcher locomotive, initially numbered DD12 1 (not to be confused with the JNR Class DD12, another type of switcher locomotive); the locomotive was built in a technical partnership with General Electric. Deployed at the Ōmiya Rolling Stock Center and reclassified as the Class DD41, the locomotive was used to perform switching duties and other light duties; in 1958 the locomotive was reclassified as the Class DD90 and renumbered DD90 1. As many of the locomotive's parts had to be imported to allow for maintenance DD90 1 was not used often and was withdrawn in March 1971 and scrapped.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_DD41)
2025.07.19
コメント(0)
-

D51とキューロク 赤羽―大宮界隈 1968年
4枚の写真は、1968年12月に撮ったものです。 前向きの蒸気機関車はD51で、川口から赤羽方面に向かって走っています。大宮・板橋間のセメントを輸送していました。当時は、最後尾に車掌車が連結されていて、車掌(普通車掌)が乗務して運行中の車両検査や事故時における列車防護措置を行っていました。 バック運転している蒸気機関車はD51で、蕨から南浦和方面へ向かって走っています。 デフなし蒸気機関車は、9600形です。おそらく29680で、大宮駅付近で撮ったものです。川越線の貨物列車を牽引しているものと思いますが、もしかしたら、入れ替え作業中だったかもしれません。
2025.07.17
コメント(0)
-

キューロク、東武東上線の荷物電車 川越駅 1968年
2枚の写真は、1968年11月に川越駅で撮ったものです。 蒸気機関車はキューロクの愛称で知られる9600形の59669です。川越線の貨物列車を牽引しています。 「荷」のヘッドマークを付けている車輛は、東武東上線の荷物電車です。当時、荷物専用の車輛が荷物電車として運用されていたはずですが、この写真の車輛は、一般車両を流用して荷物専用車両として走らせているようです。このようなことが一般的にあったのかどうか、調べてみましたが、わかりませんでした。
2025.07.16
コメント(1)
-

東武鉄道ED4000形電気機関車、ヨ101形緩急車 1968年11月
2枚の写真は、1968年11月に東武鉄道川越駅で撮影したものです。 電気機関車は、ED4000形ED4001です。1955年までは、ED10形ED101と呼ばれていた機関車です。ED101は、1928年にイギリス・イングリッシュ・エレクトリック(E.E.)社で新製された、「デッカー形電機」です。デッキは台車側に設置されていて、板台枠台車と一体構造となっています。1930年に導入し、東武鉄道初の電気機関車となりました。1972年に近江鉄道へ譲渡されています。 貨車は、事業用貨車(車掌車)の東武ヨ101形のヨ122で、貨物列車の最後尾に連結されました。1960年から、無蓋車を改造して42両が投入されました。薄緑色の塗装で目立ちました。
2025.07.15
コメント(0)
-

関東鉄道鉾田線のDC35形1号機 1968年
写真は、1968年11月に撮ったものです。 何をどこで撮ったか不明ですが、おそらく、常磐線上り電車に乗って石岡駅付近で、車窓越しに撮ったものだと思います。写っているのは関東鉄道鉾田線のDC35形ディーゼル機関車の1号機だと思います。1952年に三菱で製造された液体式ディーゼル機関車で、 ロッド式の足回りが特徴的です。 関東鉄道は、今でも気動車が活躍していて、電化されていませんが、これは、石岡市に気象庁地磁気観測所があることによります。この施設では、地球の磁気を観測することで、地球の環境変化や火山活動の分析などに活用していますが、地磁気観測にとって、鉄道の直流電化は、観測に悪影響を及ぼしてしまうためです。【Bon appétit !】 A geomagnetic sensing station is a facility that monitors and measures the Earth's magnetic field. These stations are equipped with sensitive instruments, called magnetometers(磁力計), that detect variations in the magnetic field caused by various factors, including solar activity and internal Earth processes. The data collected at these stations helps scientists understand the Earth's magnetic field, its behavior, and its interactions with space weather.
2025.07.14
コメント(0)
-

ED75形2号機、キハユニ15形 水戸機関区 1968年
2枚の写真は、1968年11月に水戸機関区で撮ったものです。 電気機関車は、ED75形2号機です。1963年に製造された試作車2両のうちの1両です。試作車2両は勝田電車区に配置され、1964年以降水戸 - 平間で各種性能試験が行われ、量産機の車体構造、タップ切替器の駆動方式、機器配置等が決定されました。 湘南型の正面の車輛は、キハユニ15形キハユニ158です。キハユニ15形は、電気式気動車キハ09形(=キハ44000形)を1957-1958年に液体式気動車に改造し、併せて、郵便・荷物合造車に改造したものです。
2025.07.13
コメント(2)
-

水戸機関区のハチロク 1968年
2枚の写真は、1968年11月に、水戸機関区で撮った8620形蒸気機関車58632です。 58632は、構内入れ替え用に使用されていて、本線を走ることはなくなっていました。 この写真を撮った1年後に、47年の生涯を終え、廃車になりました。 【Bon appétit !】 The 8620s were used mainly as passenger locomotives and were the first domestically produced steam locomotives that were produced in volume. The locomotives were retired in 1975 after sixty-one years of service. The locomotives are popularly known as Hachiroku (eight six in Japanese) among railfans. The Class 8620 was depicted as the Mugen Train(無限列車) (lit. "unlimited train") in the film Demon Slayer(鬼滅の刃: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train. Both operational 8620 locomotives, 8630 and 58654, were given aesthetic changes to resemble the train as seen in the movie.(https://locomotive.fandom.com/wiki/JNR_Class_8620)
2025.07.12
コメント(0)
-

水戸機関区のC12形蒸気機関車、暖房車 1968年
写真は、1968年11月に水戸機関区で撮ったものです。 蒸気機関車は、C12形187号機です。入れ替え専用機として使用されていました。 暖房車は、ホヌ30形のホヌ304です。2軸ボギー車でありながら車体長6,680mmしかないことが何となくユーモラスです。室内にボイラーと水槽があり、車体後部に炭水庫があります。暖房車とは、列車に暖房用スチームを供給するための車輛です。蒸気機関車には蒸気発生装置があるので暖房車の必要はありません。初期の電気機関車やディーゼル機関車が牽引する列車用に、鋼製暖房車ホヌ20200形が1926年から製造されました。ホヌ20200形は、1949年に、ホヌ30形に名称変更されています。写真のホヌ304は、水郡線で使われていたものです。これは、8620形蒸気機関車が、蒸気発生装置を搭載しないDD13形ディーゼル機関車に置き換えられた1960年から運用されました。1972年に蒸気発生装置を搭載したDE10形ディーゼル機関車が配属されたことにより、ホヌ30 4は廃車となりました。
2025.07.11
コメント(0)
-

EF57、EF58、キハ81系「つばさ」 1968年
3枚の写真は、蕨駅付近で1968年11月に撮ったものです。 デッキ付き電気機関車は、EF57です。 流線型を取り入れた車体デザインの電気機関車は、EF58です。 「つばさ」のヘッドマークを掲げた気動車は、はつかり形キハ81系です。「つばさ」は、上野駅発着で宇都宮駅、福島駅を経由する初の昼行特急列車として、1961年に上野駅 - 秋田駅間でデビューしました。1970年にキハ181系にバトンタッチするまでキハ82系気動車で運用されていました。この写真は、81系で、キハ82系ではありませんので、不思議に思っていました。調べてみたら、1968年10月の東北本線青森電化で「はつかり」運用だったキハ81が583系にリストラされ、1年間だけ「つばさ」に転用されていたということでした。
2025.07.09
コメント(0)
-

日本車輛蕨工場付近を走るD51、EF15、EF65 1968年
3枚の写真は、1968年10-11月に、日本車輛蕨工場付近で撮ったものです。 蒸気機関車はD51、デッキ付きの電気機関車はEF15、箱型の電気機関車はEF65です。
2025.07.08
コメント(0)
-

事業用控車 ヒ600形 1968年
写真は、1968年11月に大宮工場付近で撮ったものです。 写真の貨車は、1968年10月のダイヤ改正(ヨンサントオ)で廃車となった事業用貨車ヒ600形ヒ641で、側面に白い文字で廃車と書かれています。 この貨車は、鉄道連絡船へ航送車輛を積み下ろしする際に、機関車と客車や貨車との間に連結して、可動渡り橋に重量の重い機関車が乗らずに済むようにするための「控車」と呼ばれる事業用車両です。 この車両は、既存の貨車の改造車で、機種周りを撤去して手摺と小屋(詰所)を設置したものです。 貨車記号「ヒ」は、ヒカエのヒから来ています。
2025.07.07
コメント(2)
-

3軸貨車 チ500形 1968年 大宮工場付近
写真は、1968年11月に大宮工場付近の線路上で見かけた3軸貨車のチ500形のチ718号車です。 現在では3軸貨車を目にする機会はありませんが、歴史を俯瞰してみれば少数というわけではなく、1968年頃に廃止されるまでに、国鉄線上に12,000両が足跡を残しました。2軸車よりも多くの積載量とすることができる一方で、ボギー車ほど構造が複雑でないというところに狙いがありました。 チ500形は、最初から遊車(ゆうしゃ)用に製作されたため、荷摺木や柵柱はなく、床面はフラットです。遊車とは、長物車、大物車等に車長をはみ出す積み荷がある貨物を1車または2車跨ぎで積載する場合、その前後あるいは中間に連結される空車の長物車のことを言います。貨車記号「チ」は、「Timber」(木材)に由来し、長物車を意味します。
2025.07.05
コメント(2)
-

大宮機関区界隈の蒸気機関車 1968年
写真は、1968年11月に大宮機関区及び大宮駅付近で撮った川越線の風景です。 9600形、D51形蒸気機関車が機関庫の前で休憩していました。 4桁ナンバーのキューロク9687号機が構内にいました。 川越線の貨物列車を牽引してキューロクが出発していきました。
2025.07.04
コメント(2)
-

蓄電池機関車AB10形を改造したEB10形電気機関車 田端機関区1968年
写真は、1968年10月に田端機関区で撮影した EB10形2号機です。 EB10形電気機関車は、国鉄唯一の蓄電池機関車であるAB10形を改造したものです。 AB10形は1927年に2両製造されました。王子 - 須賀間2.5 km、および王子 - 下十条(後の北王子)間1.2 kmで使用するために製造されました。須賀線は全線が東京市王子区(現在の東京都北区)にあり、須賀駅で大日本人造肥料(後の日産化学工業)と接続していました。また、途中には陸軍の火薬製造工場がありました。 1931年、須賀線の電化にともない、AB10形蓄電池機関車は、架線から集電する電気機関車に改造され、EB10形に改められました。1971年に須賀線が廃止になると用途がなくなり、1972年(昭和47年)に廃車されました。
2025.07.03
コメント(0)
-

消える運命 C58305 C588 38671 佐倉機関区 1968年
3枚の写真は、1968年10月に佐倉駅付近で撮ったものです。 客車列車を牽引している機関車は、C58形305号機です。佐倉機関区で最後までいた機関車のうちの1輛で、この写真を撮った翌年の1969年12月に廃車となりました。 貨物列車を牽引している機関車は、C58形8号機です。1969年3月に廃車となりました。 貨物列車を従えて出発を待っている機関車は、8620形38671です。1969年10月に佐倉機関区から水戸機関区に転属して、その翌年1970年4月に廃車となりました。
2025.07.01
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- ディズニーリゾート大好っき!
- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート
- (2025-11-15 13:34:40)
-
-
-

- 旅の写真
- 中国、北京に行って来た!【6】
- (2025-10-27 23:49:58)
-
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- 羽田第3ターミナル デルタ航空 ス…
- (2025-11-18 08:13:24)
-