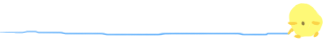2013年11月の記事
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-

オオヒカゲ越冬幼虫
昨日、クロミドリシジミの卵探しに行ったついでに、近くの小さな湿地にオオヒカゲ幼虫の確認に行きました。食痕のあるカサスゲ(豊田市) posted by (C)ドクターTまず食痕のあるカサスゲを探して、・・・。オオヒカゲ幼虫(豊田市)-001 posted by (C)ドクターT若い葉の根元付近を探すと、見つかりました。10月24日に来た時と比べて、あまり大きさは変わっていませんでしたが、10匹ほど見つかりました。
2013年11月30日
コメント(2)
-

落葉の季節、木から降りて来る。
今日は、豊田の森へクロミドリシジミの卵探しに行きました。場所は、6月頃に薄暗い梢をクロミドリシジミが群舞していた場所です。残念ながらクロミドリシジミの卵を見ることは出来ませんでした。クロミドリシジミはクヌギかアベマキが食樹です。卵は大木の梢付近に産み付けられます。産み付けられそうな大木はたくさんありますが、脚立と高枝バサミで届くような高さではありませんでした。降りてきたら、美味しそうなエノキの木がありました。そこで、急遽ゴマダラチョウの幼虫探しに変更しました。ゴマダラチョウ幼虫(豊田市)-003 posted by (C)ドクターTすぐに根本付近の枯れ葉の上から5匹の幼虫が見つかりました。ゴマダラチョウ幼虫-001 posted by (C)ドクターTあまりにもひょうきんで可愛いので、お持ち帰りしてしまいました。家の近くにはエノキの木もあるし、ゴマダラチョウも夏には飛んでいますので、・・・。
2013年11月29日
コメント(0)
-

ベニモンカラスシジミの卵探し
本州であと2種類の蝶が未撮影で残っています。ヒョウモンモドキとベニモンカラスシジミです。ヒョウモンモドキはいる場所が限局していますが、保護されていますので、その時期にそこへ行けば会えるでしょう。しかし、ベニモンカラスシジミは3カ所ほど生息地は知られていますが、なかなか会うことが出来ません。そこで、冬の間に食草を確認して出来れば、卵が確認出来ると会える確率が高まると思い、生息地のひとつに探索に行きました。6月に行ってヒルに血を吸われて逃げ帰って来たところです。クロウメモドキ posted by (C)ドクターT生息地は河川改修工事で随分木が伐られてしまっていました。なかなか食草のクロウメモドキが見つかりませんでしたが、ようやく1本だけ見つけることが出来ました。?(クロウメモドキ、南信濃町) posted by (C)ドクターT上から下まで探して、細枝の分枝部に1個だけ卵がついていましたが、何の卵なのか判りません。?(クロウメモドキ、南信濃町)-001 posted by (C)ドクターTファーブルセットで撮りなおして大きくして見ると、残念ながらベニモンカラスシジミでもミヤマカラスシジミの卵でもないようです。沢添いの傾斜地(南信濃町) posted by (C)ドクターT岩のゴツゴツした川沿いの傾斜地を登ったり降りたりしてクロウメモドキを探しましたが他に見つかりません。ミズイロオナガシジミの卵(コナラ、南信濃町) posted by (C)ドクターT川に降りて来たところにコナラの大木があり、枝が垂れ下がっていたので、何か着いてないかと探して見たら、・・・。ややや、これは、・・・ミズイロオナガシジミの卵(コナラ、南信濃町)-001 posted by (C)ドクターT細枝の分枝部にやや楕円形の金平糖のような卵がありました。初めて見るミズイロオナガシジミの卵でした。何処にでもいる蝶ですが、ミドリシジミのように集団で産んでなくて、産み付ける場所も一定しませんので、なかなか眼にすることがありませんでした。これを土産に探索は終了しました。三遠南信道が新城市名郷まで伸びましたので、151号線経由で入りましたが、蒲郡から2時間15分くらいで行くことが出来ました。
2013年11月28日
コメント(0)
-

ウォーリーを探せ!
ヒシクイ(琵琶湖) posted by (C)ドクターT琵琶湖に珍しいサカツラガンがヒシクイに混じって1羽だけ来ているそうです。何百羽と来ているヒシクイの中からよく似た少しだけ違うサカツラガンを探すのはウォーリーを探せ状態です。DSC_0222 posted by (C)ドクターT見~つけたサカツラガン(琵琶湖)-009 posted by (C)ドクターT首の前面が白いのと、嘴基部に白い部分がありますヒントは湖北水鳥ステーションの前の浮島の一番左端の方にいますよ。
2013年11月27日
コメント(2)
-

ナメコ採りの帰りに琵琶湖でオオワシを見る。
今日は、午前中坂内村でナメコ採り。ナメコ(坂内村)-001 posted by (C)ドクターT新兵器も活躍し、約1.5Kgの収穫でした。オオワシ(琵琶湖) posted by (C)ドクターT帰りに、木ノ本を回って、オオワシを見て来ました。10時半頃に一度飛んだと言う話でしたが、ねぐらでじっとしていました。
2013年11月26日
コメント(2)
-

シギは難しい
今日は、午前中常滑のH公園へカワセミを見に行こうと思っていたら、久し振りに蒲郡警察署から検案依頼がありました。仕事が終わって、午後の競艇場の仕事まで2時間ほど時間がありましたので、近場へ鳥見に行きました。ムナグロ冬羽(一色町) posted by (C)ドクターTイソシギ(一色町) posted by (C)ドクターT周りに大きさが比較できる既知のシギがいないと、なかなかシギの判別は難しいです。上は最初ダイゼンかと思いましたが、羽に黄色味があるので、ムナグロ冬羽だと思います。下は最初、肩の切れ込みがはっきりしないので、クサシギかと思いましたが、見る角度の問題だったようです。
2013年11月25日
コメント(0)
-

ジョウビタキ♂のミラー攻撃
冬鳥のジョウビタキが来ています。ジョウビタキ♂-003 posted by (C)ドクターT豊橋のI湿原にも来ていました。ジョウビタキ♂ posted by (C)ドクターTウラゴマダラシジミの卵探しをして車のところに戻ると、ミラーのところに停まって覗き込んでいました。時々ミラーに映る自分の姿を見て攻撃をしかけます。ミラーの手前の窓枠に鳥の糞があったらそれはジョウビタキ♂の仕業です。
2013年11月24日
コメント(2)
-

ウラゴマダラシジミの卵探し
豊橋へアサギマダラの幼虫の餌(キジョラン)を採りに行ったついでにI湿原に寄って、今年4番目のゼフィルスの卵探しをしました。いつもはくちもとですぐに見つかるのですが、今年は中々無くて、30分ほど探しました。ウラゴマダラシジミの卵(豊橋市) posted by (C)ドクターT少し奥に入ったところで、ようやく見つかりました。200mmマクロの手持ち撮影です。ウラゴマダラシジミの卵(豊橋市)-002 posted by (C)ドクターTこれも手持ち撮影ですが、60mmマクロに2倍のクローズアップレンズをつけて撮っています。ウラゴマダラシジミの卵は本当にユニークな形をしていますね
2013年11月24日
コメント(2)
-

ペリットを吐き出すカワセミ
久し振りに常滑のH公園へカワセミを見に行きました。常連のよしじいさんにも久し振りに会いました。カワセミ♂(常滑市)-014 posted by (C)ドクターT綺麗な若♂が来ていました。30分ほどゆっくり餌採りを見せてもらいました。ペリットを吐き出すカワセミ-002 posted by (C)ドクターTこの石の上に停まって何かもぞもぞしだしたと思ったら、ペリットを吐き出しました。ペリットを吐き出すカワセミ-003 posted by (C)ドクターTどうやらこの石の上はペリットを吐き出す場所にしているようです。魚ばかりを食べていると白いペリットが多いのですが、ここはエビも多いのでこんな色になるようです。
2013年11月23日
コメント(2)
-

まだまだ変化は続きます。
アサギマダラ前蛹 posted by (C)ドクターT11月18日前蛹となり、アサギマダラ蛹 posted by (C)ドクターT翌日(11月19日)、脱皮して蛹となりましたが、まだこれで終わりではありませんでした。アサギマダラ蛹完成(家) posted by (C)ドクターT今日見たらこんな綺麗な模様が現れました中でどんな変化が起こっているのか判りませんが、外側の変化も見事です。
2013年11月22日
コメント(0)
-

越冬するアサギマダラ─その2─
アサギマダラは渡りをする蝶の代表とされています。秋には南下の旅をし、春には北上の旅をします。もちろん、寿命は5か月~長くても7か月ですので、その間に世代交代が起こります。一方で愛知県でもアサギマダラは越冬をしています。豊橋には食草のひとつ、キジョランが冬でも枯れずにあり、そこでは全てのステージを見ることが出来ます。アサギマダラの卵(豊橋市) posted by (C)ドクターTアサギマダラ1齢幼虫 (4) posted by (C)ドクターTアサギマダラ2齢幼虫-001 posted by (C)ドクターTアサギマダラ3齢幼虫 posted by (C)ドクターTアサギマダラ終齢幼虫 posted by (C)ドクターTアサギマダラ前蛹 posted by (C)ドクターTアサギマダラ蛹 posted by (C)ドクターTこれらは、今の時期、愛知県でも見ることが出来ます。ならば、何故渡りをする必要があるのでしょうか?それはやはり温度に敏感なためと、食草の量であると思われます。アサギマダラの活動に適した気温は22℃から26℃と言われています。特に、暑さには弱いようです。活動は出来なくなりますが、冬の低温には比較的強く、雪が積もらないところでは越冬することが出来ます。食草はガガイモ科のつる性植物で、ガガイモ、イケマ、オオカモメヅル、キジョラン、サクララン、ツルモウリンカなどで南西諸島ではツルモウリンカが主な食草となっており、本州では高原地帯に多いイケマが主な食草と考えられますがこれも冬には枯れてしまいます。そして、愛知県ではガガイモが食草になりますが、それほど多くはなく、冬は枯れてしまいます。キジョランは常緑で冬でも枯れませんので、冬の間の食草とすることが出来ますが、そんなに多くはなく、私は愛知県では2か所しか自生地を知りません。南西諸島では秋に北から渡ってきた個体と春に発生した新鮮個体が多くなりますが、気温が30℃を超える日が続く夏には激減し、北へ渡って行くようです。その時期には、食草のツルモウリンカもアフリカマイマイやモンクロキシタアツバと言う蛾の幼虫の食害で少なくなってしまいます。渡りをする動機はやはり、気温と食草の量であろうと思いますが、それでは愛知県で越冬しているのは渡りをしないアサギマダラなのでしょうか私はアサギマダラに渡りをするグループと渡りをしないグループがいると考えるよりも、渡りをするという性質はアサギマダラに共通の性質と考える方が自然だと思います。と言うことは、愛知県で越冬するアサギマダラはもっと北の東北や北海道で生まれた個体が南下して愛知県に来たところで、食草のキジョランを見つけてそこに産卵したものではないかと思います。そのことを実証するには、マーキング調査をする必要があると思います。すなわち、春に羽化した個体にマーキングをして放して、それが東北や北海道で再捕獲されれば、愛知県で越冬したアサギマダラも同じように渡りをしているということになります。
2013年11月22日
コメント(0)
-

三重県で卵探し
昨日は、三重県の方で卵探しをしました。最初行った場所は、ハンノキとナラガシワが隣り合わせで生えている場所でしたので、まずミドリシジミの卵探しで眼を馴らします。ミドリシジミの卵(三重県)-003 posted by (C)ドクターTミドリシジミの卵(三重県)-004 posted by (C)ドクターTミドリシジミの卵(三重県)-002 posted by (C)ドクターTミドリシジミの卵(三重県)-001 posted by (C)ドクターTミドリシジミの卵(三重県) posted by (C)ドクターTすぐにたくさんの卵が見つかりました。眼の高さに集団で産み付けてありますので、判りやすいです。ウラジロミドリシジミの卵(三重県) posted by (C)ドクターTその勢いで隣のナラガシワに移りましたが、なかなか見つかりませんでした。30分ほど探してようやく1か所に3卵産んであるところを見つけました。60mmマクロに2倍のクローズアップレンズを付けて。ウラジロミドリシジミの卵(三重県)-002 posted by (C)ドクターTNIKONのファーブルセットで撮ってみました。
2013年11月21日
コメント(0)
-

ムキタケの処理について
一昨日採ってきたキノコはナメコ1kg、ムキタケ2.5kgほどありました。11月18日収穫 (2) posted by (C)ドクターT手前がムキタケ、奥がナメコです。処理後 posted by (C)ドクターT処理後はこれです。ナメコはそんなに量が変わりませんが、ムキタケは1kgほどに減ってしまいます。それは虫が入っている、ものが多いからです。5mm~1cmくらいの蛆虫が入っています。それはキノコ蠅の幼虫です。それではムキタケの処理の仕方を書いておきます。ムキタケ処理 (2) posted by (C)ドクターTまずゴミのついたまま大きな鍋で茹でこぼします。ムキタケ処理 (1) posted by (C)ドクターTその後、ひとつずつ、石付の部分を切り落として、断面を見て虫が入っていたら全て捨てます。そして、表面のヌルヌルした薄皮を歯ブラシでこすって落とします。そこにゴミがついているのと、その部分が消化が悪いと言われているからです。そして大きなものは食べる大きさに切り分けます。終わると2番目の写真のように、白っぽくなります。ムキタケは鍋や味噌汁、うどんなどに入れて食べます。癖のないキノコですが、人によっては少し埃くさいと言う人もいます。その処理が
2013年11月20日
コメント(8)
-

アサギマダラ、前蛹となる。
豊橋の山で採ってきたアサギマダラの幼虫が飼育箱の天井で前蛹となりました。アサギマダラ前蛹 posted by (C)ドクターTこれから脱皮して蛹になるところが見られるかも知れません。アサギマダラ蛹 posted by (C)ドクターT脱皮して蛹になるところの変化を写真に撮ろうと思っていたら、ちょっと眼を離した隙に終わってました。しかし、綺麗な蛹ですね
2013年11月19日
コメント(0)
-

晩秋のキノコ狩りを楽しむ
昨日は、岐阜県の方で晩秋のキノコ狩りを楽しみました。紅葉の中でムキタケを採る posted by (C)ドクターT天気も良く、紅葉もピークで気持ちの良い一日でした。雲の上のキノコ会(富士山をフィールドとするキノコブログ仲間の会)からも5名の方が参加しました。立ち枯れになった木に出ていますので、それぞれが自分でいろいろな道具を工夫して持ってきていました。ナメコ(坂内村) (4) posted by (C)ドクターTムキタケ(坂内村) (1) posted by (C)ドクターT主に、ナメコとムキタケが採れます。他にクリタケ、チャナメツムタケ、シイタケなどが採れました。一番採りたいのはやはりナメコなのですが、土・日にだいぶん人が入って採られていたようで、少なかったようです。11月18日収穫 (2) posted by (C)ドクターT私はナメコ1kg、ムキタケ2.5kgほど採ってきました。11月18日収穫 (1) posted by (C)ドクターT午後は別の沢へ入って、ワサビの葉を少し採ってきました。
2013年11月18日
コメント(4)
-

カンムリカイツブリ〇、サカツラガン〇、イヌワシ×
ナメコ狩りの下見が早く済んだので、木ノ本へ回って、鳥見をして帰りました。カンムリカイツブリ(余呉湖) (3) posted by (C)ドクターTまず最初に余呉湖へ行き、カンムリカイツブリを見て来ました。50羽ほど渡って来てました。1羽だけ岸近くに寄ってくれました。ヒシクイ(湖北水鳥ステーション) (1) posted by (C)ドクターT次に、湖北水鳥ステーションに寄りました。ヒシクイがたくさん来ていました。ステーションの人がサカツラガンが来ているというので、探しました。サカツラガン(湖北水鳥ステーション) (2) posted by (C)ドクターTこの辺りにいるのですが、距離100mくらいで、ロクヨンでもこれくらいにしか撮れません。しかも逆光です。サカツラガン(湖北水鳥ステーション) (5) posted by (C)ドクターT何枚か撮った写真をトリミングしてようやく見つけました。切り株の左に座っているのがそうです。ヒシクイと似ていますが、首が白っぽく、嘴基部に白い部分があるのが判ります。伊吹山スカイラインにて (1) posted by (C)ドクターTその勢いで伊吹山のイヌワシを狙ってみました。通行料¥3,000円の伊吹山スカイラインのあちらこちらに大砲を構えた人たちがいました。数えてみたら全部で35人いました。伊吹山スカイラインにて (2) posted by (C)ドクターT朝から来ているという4人の方がいるポイントで降りて、1時間ほど待ちましたが、出ませんでした。午前中に2回飛んだとのことでした。イヌワシはまた暇な時にリベンジに来ましょう。
2013年11月17日
コメント(0)
-

ナメコ狩り、下見報告
土曜日にナメコ狩りの下見に行って来ました。ナメコ(坂内村) (2) posted by (C)ドクターTムキタケとナメコ (2) posted by (C)ドクターTナメコ(坂内村) (1) posted by (C)ドクターT8時半頃に現地に到着したら、もういつも入るポイントには車が停まっていました。仕方ないので、あまり人が見ない河原の倒木を中心に探しました。2か所でたくさん出ていました。新兵器を使う(坂内村) posted by (C)ドクターT実際には使う必要はなかったのですが、新兵器も試して見ました。なかなか調子よさそうです。さて、明日が本番です。平日ですし、30分早く着く予定ですので、予定のポイントでナメコ狩りが出来そうです。
2013年11月17日
コメント(4)
-

今年は穴が開いていませんでした。
昨日は雨の中、鈴鹿の方へ卵探しに行って来ました。キリシマミドリシジミの卵(三重県員弁郡) posted by (C)ドクターT100本ほどのアカガシの木の芽を見て回り、ようやく1個だけ見つけました。昨年は穴が開いていましたが、今年は綺麗でした。コツは林の中の緑色の芽が着いた幼木または彦生えを探すことです。
2013年11月16日
コメント(2)
-

越冬するアサギマダラ─その1─
フジバカマ(蒲郡市) posted by (C)ドクターT昨日、さがらの森へ行って見ると、もうアサギマダラは1頭も飛んでいませんでした。朝の冷え込みは厳しかったですからね。多分南の方へ、もう渡ってしまったのでしょう。キジョランの花(豊橋市) posted by (C)ドクターTそれで、豊橋の山の方へ、アサギマダラの食草探しに行ってきました。ガガイモ科でもガガイモやイケマやカモメヅルは冬に地上部が枯れてしまいますが、キジョランは常緑ですから、冬でも青々としています。キジョランの食痕(豊橋市) posted by (C)ドクターTキジョランの葉には、アサギマダラの若齢幼虫が食べる時に開ける食痕が見られます。その付近をよく探して見ると、・・・。アサギマダラの卵(豊橋市) posted by (C)ドクターTアサギマダラ2齢幼虫-001 posted by (C)ドクターTアサギマダラ終齢幼虫 posted by (C)ドクターTアサギマダラの蛹(豊橋市) posted by (C)ドクターT全てのステージを見つけることが出来ます。すなわち、常緑の食草があるところでは、愛知県でも越冬が出来るということです。それでは、何故渡りをするのでしょうこれについてはもう少し検討が必要ですので、何回かに分けて考察します。
2013年11月15日
コメント(4)
-

温室を作りました。
2日間かけて、家に小さな温室を造りました。温室(家) (1) posted by (C)ドクターT隠居と前の畑の間に少しスペースを作り、まず基礎工事。温室(家) (2) posted by (C)ドクターTそこへカーマで買ってきた簡易組み立て式の温室を造りました。温室(家) (3) posted by (C)ドクターT毎年冬越しさせるのが大変なイペーとハイビスカスを入れました。温室(家) (4) posted by (C)ドクターTあとは私の下心です。
2013年11月14日
コメント(2)
-

仕事のついでに蝶探し
ムラサキツバメ♀(碧南市) (3) posted by (C)ドクターT11月から仕事をまた始めました。今日は碧南市医師会検診センターで検診の仕事に行きました。40人ほど問診・診察をしました。ほとんど異常のない人たちの中で、異常のある人を見逃さないようにしなければいけません。今日は幸い特に異常のある人はいませんでした。碧南へ行ったついでに終わってから近くの公園でムラサキツバメを探しました。この公園は遊歩道に沿って、マテバシイが植えられています。12時の気温が12~13℃でした。3頭ほど見つかりました。♀の開翅を見るのは今年初めてですね。これから時々碧南での仕事がありますので、天気がよければ帰りに寄ることにしましょう。
2013年11月13日
コメント(0)
-

今年の新兵器
新しい道具の材料 posted by (C)ドクターTホームセンターでこのような道具を買って来ました。全部で2,500円ほどです。それを使って、今年のキノコ狩り用の道具を創りました。IMGP1109 posted by (C)ドクターTじゃ~ん、これです。柄の部分は高所掃除用の箒の柄を使いました。4mほどに伸ばせます。それにキノコ鎌(上にも刃がついていてスクレーバーとしても使えます。それにキノコを受けるための網をつけました。柄の部分と上の鎌の部分はネジで取り外し出来ます。加工で苦労したのは、網を小さくするところと、ステンレスのパイプを短くカットするところです。
2013年11月12日
コメント(0)
-

プロファイルNo.218 分布の空白
ウラギンシジミ♀ posted by (C)ドクターT今頃何処にでもいるウラギンシジミですが、この写真は2012年5月7日石垣島で撮りました。この蝶は成虫越冬をし、秋には食草のクズが繁茂しますので、数が増えるようです。南東北以南に広く分布する蝶ですが、何故か南西諸島では沖縄諸島から宮古諸島の間に分布の空白地帯があります。宮古島には30年近く行っていますが、そう言えばこの蝶を見たことがありません。分布の空白と言うとついつい探したくなりますね。
2013年11月11日
コメント(0)
-

プロファイルNo.217 たかがヤマト、されどヤマト
ヤマトシジミ♀(阿久比町) posted by (C)ドクターT日本の蝶の中で、最普通種といえばやはりこれでしょう。よく似たシルビアシジミが絶滅危惧種となったのに対して、何処にでも年中生えているカタバミを食草としたために、春先から11月末まで何処でも見ることができます。成虫越冬でない蝶の中では、最も遅くまで飛んでいますが、春先や今頃(低温期)の♀は高温期に比べると青色鱗がよくのって、朝方の開翅タイムに見るとはっと息を呑むことがあります。
2013年11月10日
コメント(0)
-

カバマダラその後
10月24日に蒲郡で見つかったカバマダラの産卵していたフウセントウワタを見に行って来ました。カバマダラ幼虫 posted by (C)ドクターT幼虫が2匹いました。1匹は4cmくらいありました。3齢くらいでしょうかちょっと待って下さい。計算が合いませんね。10月24日の産卵で16日後に3齢は早すぎますね。24日に産卵していたところを見ると、まだ卵のまま残っているものがあります。これは24日以前にも産卵が行われていたと考えざるを得ませんね今後、24日に産卵した卵がどうなるのかそして大きくなった幼虫の運命はしばらく継続して観察してみます。
2013年11月09日
コメント(2)
-

誰が♂は地味だと、・・・?
今日は地元の公園で蝶探し。ムラサキシジミ♀(知多市) posted by (C)ドクターTムラサキシジミ♀(知多市) posted by (C)ドクターTまずは、ムラサキシジミ、これは知多市内、私の家の庭を含めて、何処にでもいます。しかし、開翅写真を撮るには今の時期が一番よいでしょうムラサキツバメ♂(知多市) posted by (C)ドクターTしかし、ムラサキツバメとなると、何処にでもいる訳ではありません。年によって、発生状況も変わるようです。ムラサキツバメ♂(知多市)-001 posted by (C)ドクターT開翅してくれたら、♂でしたが、♂が地味だなんて、誰が言ったんでしょうかそう言えば、昔私が言ったかも知れません。訂正します。♂でも光の当たり具合によってやはり紫に輝くのです
2013年11月08日
コメント(0)
-

ハイイロチュウヒ到着
今日は、篠島へ蒲郡から海上タクシーで行き、チャリティ釣り大会をしてきました。竿頭は獲れませんでしたが、真鯛4枚、カサゴ1匹で2番目でした。帰りに、一昨日ハゲノヤセウマさんがハイイロチュウヒが来ましたとのことでしたので、ちょっと寄ってみました。ハイイロチュウヒ♂(一色町) (1) posted by (C)ドクターT4時15分くらいになって、草原の上を飛び出しました。ハイイロチュウヒの♂はやはり綺麗ですね。
2013年11月07日
コメント(6)
-

森の王者、クマタカ!
クマタカ(古座川) posted by (C)ドクターTルーミスを撮りに行った、古座川の奥、熊も出る辺鄙な場所ですが、ルーミスを待っていると、上空をクマタカが旋回していました。トビよりも大きく流石は森の王者と呼ぶに相応しい貫禄でした。丁度ロクヨンを構えていましたので、すぐに撮ることが出来ました。
2013年11月06日
コメント(2)
-

世界遺産で出会った蝶
イシガケチョウ(花の窟) posted by (C)ドクターT沖縄では嫌と言うほど飛んでいる蝶ですが、本州でいざ見ようと思うとなかなか出会えない蝶です。南紀まで行くと結構飛んでいて、成虫越冬ですから、冬でも暖かい日には見ることが出来ます。昨日も5回ほど目撃しましたが、なかなか停まってくれない蝶です。花の窟へ行ったら、ナワシログミに吸蜜中でゆっくり撮らせてもらえました。イシガケチョウ(古座川) posted by (C)ドクターT昔、図鑑で初めて見た時には随分変わった模様の蝶がいるものだと思いました。
2013年11月06日
コメント(0)
-

今季のルーミス撮り納め
ルーミスの開翅が撮りたくて、もう一度遠征しました。ルーミスシジミ♀(古座川) posted by (C)ドクターTルーミスシジミ♀(古座川)-001 posted by (C)ドクターTこんなところで、今年の撮り納めとしましょう。
2013年11月05日
コメント(0)
-

今年もいませんでした。
一昨年、田原でクロマダラソテツシジミが発生したことがありました。でも1年だけでいなくなりました。採集者が押しかけて採り尽くしてしまったとも言われますが、もともと南の方では越冬態を持たずに、周年発生を繰り返すタイプの蝶ですので、愛知県では越冬できないのかも知れません。今年はどうなっているのか、確認に行きました。IMGP0937 posted by (C)ドクターT食痕のある蘇鉄は1本だけありましたが、クマソは飛んでいませんでした。ヤクシマルリシジミ♀(田原市)-003 posted by (C)ドクターTヤクシマルリシジミの♀が1頭飛んでいました。他には、ヤマトシジミ、ベニシジミ、ウラナミシジミ、モンシロチョウ、キタキチョウがいました。
2013年11月04日
コメント(0)
-

フユノハナワラビ巻き
今朝は秘密の場所で、フユノハナワラビを採ってきました。フユノハナワラビアク抜き posted by (C)ドクターTアク抜きをして、・・・。フユノハナワラビ巻き posted by (C)ドクターT小松でハナワラビ巻きを握ってもらいました。ワラビのようなぬめりはありませんが、食べられます。
2013年11月03日
コメント(6)
-

越冬場所発見!
ツマグロキチョウ点描俳句 posted by (C)ドクターT一昨年、夏型を見た、名古屋市守山区の新興住宅地へ秋型が見たくて2度行きましたが、空振りに終わりました。まだ結構カワラケツメイの生えている場所はあるのですが、・・・。それで、これは発生場所と越冬場所が違うかも知れないと思い捜索範囲を拡げました。広い雑木林の残る場所の南向きの風の当たらない林縁で、ようやくツマグロキチョウが集まっている場所を見つけました。狭い範囲でしたが、叩いたら10頭近いツマグロキチョウが出てきました。そこは、カワラケツメイがたくさんある場所から3kmほど離れており、その付近にはカワラケツメイもアレチケツメイも見当たりませんでした。
2013年11月02日
コメント(0)
-

フユノハナワラビ
フユノハナワラビ点描俳句 posted by (C)ドクターT山菜の中でもワラビが一番長期間にわたって採れ、3月中ごろから10月中ごろまで7か月間も採り、採ったワラビはアク抜きして蒲郡の小松(寿司屋)へ納めていました。今の時期流石にワラビは採れませんが替りになるものがあります。フユノハナワラビ(常滑市) posted by (C)ドクターT昨日、群生している場所を見つけてしまいました。そう言えばこれもワラビと同じように食べられるのでした。よし小松でフユノハナワラビ巻きを創ってもらおう
2013年11月02日
コメント(2)
-

チュウヒ到着
チュウヒ♂(一色町) posted by (C)ドクターTチュウヒ♀(一色町) posted by (C)ドクターT一色町の葦原にチュウヒがやってきました。今年はハイイロチュウヒはまだのようです。
2013年11月01日
コメント(2)
全35件 (35件中 1-35件目)
1