2012年05月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
新藤兼人監督を悼む
新藤兼人監督が昨29日、老衰のため亡くなられた。享年100。先月22日が100歳の誕生日だった。それからちょうど1ヶ月と1週間後の逝去である。映画作家として現役世界最高齢、昨年99歳の監督作品『一枚のハガキ』が遺作となった。 私は子供の頃から随分その作品を見てきた。監督第一作の『愛妻物語』(1951)を見たのは後年になってからだが、第2作目の『原爆の子』(1952)は、リアルタイムで見ている。その後も、『縮図』(1953)、 『どぶ』(1954)、『銀心中』(1956)、『第五福竜丸』(1959)と見、『裸の島』(1960)、『人間』(1962)、『鬼婆』(1962) と、旺盛な製作活動を追ってきた。 大学1年のときだったと記憶するが、学園祭で『人間』を上映し、監督自身が来校して講演をされた。広島訛のある言葉とともに、「ようしに(要するに)」を連発されたのが、50年近く経った今でも耳に残っている。言葉癖だったのだろう。 新藤作品の追いかけは、『薮の中の黒猫』(1968)あたりから滅きり少なくなった。多分、私の関心が外国映画の単館上映作品のようなものに傾いていったためだろう。また、仕事をするようになって、急に多忙となり、映画館で見ることを信条としてきた私としては、なかなか足を運べなくなったのだった。 じつは遺作となった『一枚のハガキ』を、先夜、TVで見た。 私の記憶には、新藤作品の忘れられない映像が、たくさん詰まっている。ご冥福をお祈りいたします。
May 30, 2012
コメント(0)
-
庭の茱萸(グミ)に異変
我が家の小庭に2本の茱萸(ぐみ)の木がある。丈は3メートルを超える。毎年、5月半ばを過ぎると真っ赤に熟した実がたわわになり、小さな祭提灯のようだ。三つ四つ口に入れることはあっても、収穫して食べるというわけでもない。甘酸っぱく美味しいことは美味しい。 その茱萸が、今年はなんだかヘンだ。実はなっても一様にヒネコビタように形がおかしい。色も冴えない。のみならず、熟さないうちにポタポタ落ちてしまう。実の数が非常に少ない。葉叢を探るように見ないと、みつからないほどである。かつてこんなことはなかった。冷たい雨が降りつづいたためであろうか。原因がわからないまま、いささか当惑気味である。
May 30, 2012
コメント(0)
-
晴天の霹靂クワバラクワバラ
午前中の好天が、夕方から雨になり、21時半、轟音とともに落雷。我が家の近所と思われる。たまたま私の膝の上に座っていた猫がびっくりして跳びあがった。昨日の関東地方の落雷で死者が出たと報じられていたが、避けて避けられるものでもない。青天の霹靂とはこのことだ。 落雷を避けるために「桑原桑原」と唱える人は、現代ではいないと思うが、この呪文のいわれは何か。 諸説あるが、ひとつは流刑死した菅原道真が怨霊と化し雷となって京の都を荒れ狂った。ところが道真公の旧領桑原にはまったく落雷がなかったことから、「桑原桑原」が避雷の呪文になった、と。 あるいはまた、とある農家の井戸に雷神が落ちた。その家の百姓が急いで井戸に蓋をして雷神をとじこめてしまった。雷は天に帰してもらうことと引き換えに、自分は桑の木が嫌いだから「桑原桑原」と言えば其処には落ちないと教えた、と。 避雷のマジナイは他にも、蚊帳を吊ってその中に入るとか、臍(へそ)を押さえるとか、いろいろある。 平安時代の人々は、現実として怨霊に恐れおののいていた。心性が怨霊に完全に支配されていた。政治もその支配のなかに組み込まれており、呪殺・謀殺・意趣討ち、はたまたそれに対する意趣返しが日常的に横行し、怨霊はいたるところに存在した。その怨霊鎮めをする役目を担った陰陽師は、国家のれっきとした高級官僚だったのである。 こういう社会というのは、興味深いことに、必ず醒めている人間がいて恐怖を利用して生きる。陰陽師もそうである。陰陽道は元来、古代中国では科学的なものであったが、日本に入って来て性格が変わった。非科学的な巫術の側面が突出した。怨霊の恐怖に支配されていた平安時代人の心性が巫術を要求したのであろう。そしてこのような社会は、一大破滅的なカタルシスによってしか覚醒しないものである。 アンダーグラウンド・カルチャー(サブ・カルチャー)から現代日本の表社会に出て来た「占いブーム』も、実のところ平安時代社会と共通するところがある。霊感商法しかり、信仰宗教しかり。信仰宗教ばかりではない。あらゆる宗教の布教の根底に、恐怖心あおりが、システマライズされている。潜在意識に恐怖を植え付ければ一丁できあがり。飯の種、金づるに事欠かないということになる。 さて、現代のカタルシス、晴天の霹靂は、いつ、どんな形で起るか。オウム真理教の場合はサリン散布による無差別殺人だったが。クワバラ、クワバラ。
May 29, 2012
コメント(0)
-
突然の嵐
午後3時少し前、東京西部の我が家のあたりに突然の嵐が襲った。激しい雨風が叩き付けた。猫達がパニックになり、鳴きながら二階の私のもとにやってきて大騒ぎとなった。ひとりひとり頭を撫で、「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と言いながら宥めた。こういう猫の行動はめったにあることではない。大地震のときでさへ、キッと身構え不安そうに私のそばに来たが、泣叫びはしなかった。この突然の嵐、その雨音の凄さは、よほどびっくりしたのだろう。キッチンの換気扇が電気が入っていないのに、グルグル回転していた。ものの数分で嘘のようにおさまったが、近頃の気象はなんだか異常に思われる。どうだろう?
May 28, 2012
コメント(0)
-
女子バレー五輪キップ確定
日本女子バレーボール・チーム、最終戦の対セルビアは、2セットを取れば五輪出場が決まるのだったが、やりました、キップをもぎとった。試合はまだ続行中。この試合そのものの勝敗が決定したわけではないが、よしんば2-3で敗れても得点1が加算されるので、ただいま日本チームの出場がきまった。昨日いささか不調だった江畑が、調子をとりもどして活躍中。 (続報) 試合は結局フルセットまでもつれこんだが、2-3で日本チームは敗れた。勝ったセルビアは総合順位3位を堅守して五輪出場権を獲得。 バレーボールの世界試合の出場権獲得戦績はちょっとわかりづらい。勝ち得点は、3-0の場合、勝者のみが3点。3-1の場合も勝者のみが3点。フルセットまで行っての3-2は、勝者が2点、敗者が1点を与えられる。これに総得点とセット勝率が加味されて総合順位が決まる。また、大会全体のなかでアジア出場枠があり、今大会で日本女子チームが出場権を獲得できたのは、アジア枠の中に入ったからである。すなわちアジア勢は総合2位の韓国があるが、総合4位以下のアジア最上位1カ国がアジア枠として出場権を与えられる。今日の試合で1点追加獲得した日本が、その条件をみたした。 サッカーも同様の決め方をしているが、バレーボールよりわかりやすい。バレーボールの場合、セット率というのが加味されるからで、これはよほどメモでもとっていないとTV観戦者は忘れてしまいがちだ。 しかし、まあ、女子日本チーム苦戦を強いられながらよく頑張った。江畑が通算個人得点91をあげているのはすばらしい。 さあ、もう2ヶ月もすればロンドン・オリンピックが開催する。頑張れニッポン。
May 27, 2012
コメント(0)
-
音楽評論家・吉田秀和氏を悼む
音楽評論家の吉田秀和氏が22日に逝去されたという。享年98。お年から言えば、天寿をまっとうされたと言っても失礼には当たるまい。 ただ残念なのは、あの明晰な文章を、もう読むことができないこと。 知的なすばらしい文章だった。音楽という目に見えない感覚世界を、みごとに論理的に、説得的に言語構築された。日本語というきわめて情緒的な、曖昧に陥りやすい、それだけに、油断するとだらしなくもなってしまう言語を使って。 ドイツ留学に拠る、ドイツ語に通じるような、きびきびとした、ときに切り捨てるような語尾の強い話言葉で話されたが、その文章もまた内部に激しい意志の強さをひそめるものだった。そう、私は思い、その文章を愛して来た。なんと言ったらよいか、「信用できる日本語文章」と言っておこう。このような日本語文章を書く人は、浅学を恥らわずに言うが、あまり多くはないのである。何より、そのようなきわめて論理的な文章から、吉田氏の肉声が「音」として聞える。みごとなものだ。 TVで最後の姿(私にとっては、たまたまそれが最後ということだが)を見たのは、水戸芸術劇場の館長としてプロデュースされた小沢征爾氏指揮の演奏会においてであった。 演奏途中で小澤氏の体調が突然悪化された。演奏会は中断してしまった。小澤氏はかねて闘病中であったのだが、この演奏会の指揮は是非と出演された。会場は騒然となった。小澤氏の薫陶を受けて練習を重ねて来た楽団員たちは、指揮者無しで小澤氏の音楽理念を実現したい、つまりこのまま演奏を続行したい意向をしめした。観客のなかにはそれを拒否する人たちもいた。その人たちの心情もわからないわけではない。音楽そのもを聴きたいには違いないが、世界的なスター・コンダクター小沢征爾が出演するのでやって来た人たちも多いはずだった。 会場は無言の苛立がたちこめた。ステージのオーケストラも当惑していた。 そのとき、観客席にいた吉田氏が立ち上がった。楽団員の意志を尊重してこのまま小澤氏抜きで演奏を続行してもらうけれど、聴いてやろうという人はこのまま残ってください。しかし、それは嫌だという人はここでお帰りください。料金はお返しいたします。これでいかがでしょう?・・・・このように吉田秀和氏は言った。会場に拍手が起った。 TVはこの一部始終を放映したのである。 私はこのときの吉田氏に、毅然として事態をさばく説得力とともに、誰をも非難しようとはしないで個人の意志にまかせる戸口をつくる人間的な優しさを感じた。こういうとき、人は、大勢のさまざまな感情がうずまく圧倒的な気配に押されて、言葉はつまずき、あるいは感情が露出して、説得までに時間を要するものだ。しかし、吉田氏は、ものの1,2分で会場をおさめてしまった。 ・・・これが、私が氏の姿をTVで見た最後である。私はかつて音楽会会場で直に吉田氏を見かけたこともあるが、このTVでの姿と、その文章を、私は忘れることはないだろう。吉田秀和氏のご冥福をお祈りする。
May 27, 2012
コメント(0)
-
女子バレー、ロシアに敗れる
惜敗と言いたいところだが、ストレート負けでは惨敗と言わなければなるまい。 点差はいずれのセットにおいても3点ほどだから、善戦なのだ。しかしその差に追いつき追い越すことはついに出来ずにおわった。この大会で、点差がいずれもビハインドだったというのは、この対ロシア戦が初めてのこと。 相手が強豪中の強豪と言ってしまえば、それで終ってしまう。たしかに高さがあり、高いところから鋭角の強烈なスパイクを打ってくる。守備に穴がない。ブロックが決まる。 ・・・それがロシア・チームだとすると、日本チームのレシーブはすばらしかった。何が問題かというと、昨日の対キューバ戦と比べて、スパイクがきまらない。サーブ・ミスが出る。ブロック・ポイントが出ない。 昨日活躍した江畑が不調で、ミスを連発。昨日勝利の立役者である迫田を、真鍋監督なぜかスターティング・メンバーからはずし、投入したのがようやく3セットになってから。 なぜこんな采配をしたのか分からないが、いかにも遅すぎた。フルセットに持ち込めば、敗れても得点1をもらうことができると考えたか。得点1を加算できれば五輪出場が決まる。まさかとは思うが、もしそう考えたとしたら、あまりにもイジマしい。フルセットにもつれ込む前に、ストレート負けしてしまった。得点1さへ手に入れることができなかった。 したがって、勝敗順位は第4位。3位のセルビアとはセット率で優っていたのだが、きょうの試合を落としたため、3,4位同得点となり、セルビア対タイの戦績いかんでは、日本チームが自力でロンドン行きを決めるためには、明日の対セルビア戦に勝利するしかない。 希望はあるが、引くことならぬ崖っぷち。頑張れ日本チーム。粘れ日本チーム。
May 26, 2012
コメント(0)
-
激戦女子バレー、キューバを制す
女子バレーボール、オリンピック出場を懸けた最終予選世界大会。出場権を得られるのは上位3チーム。真鍋監督率いる日本チームはこれまで3勝1敗。1位のロシアに付けての2位。しかしながら獲得点数において、まったく予断をゆるさない状況。きょうの対キューバ戦を逃すと、残る2試合がロシアとセルビア、いずれも強豪、是非キューバ戦を制さなければならない。 そのキューバ、華やかな桂冠チームではあるが、この大会では現在6位。きょうの試合に敗れるとオリンピック出場をのがすことになる。 というわけで、両チームともに必死である。 さて、試合運びは、観ているほうも手に汗握る激戦につぐ激戦。 第1セットはキューバが圧倒し、23対16と、日本チーム大差をつけられた。しかし、日本はここから目のさめるような力を発揮した。連続ポイントで、なんとひっくりかえしてこのセットを取ってしまった。 つづく第2Sセット、またもや大量得点差で、しかしこんどはキューバがセットを取る。 かくしてはらはらどきどきのシーソー・ゲームが展開し、ついに日本チームとしては大会初めてのフル・セットにもつれこんだ。 第5セットは15点先取で勝敗を決する。点差がつくと挽回が難しい。・・・両チームともに1点を取られると1点を取り返すという展開。マッチ・ポイント3度。ついに日本チームがキューバを制した。キューバはロンドンへの夢を断たれ、日本は大手をかけた。 日本チームが勝ったから言うわけじゃないが、それにしても面白い試合だった。 明日は対ロシア戦。明後日は対セルビア戦が待っている。
May 25, 2012
コメント(0)
-
きょうの老化予防
今日はほとんど終日、英語で短編小説を書いていた。このところたてつづけに、”Death Mask(死面)” “That Man(その男)” と書いてきたが、また新しいのを書いている。タイトルは、“The Infancy Lover's Suicide(幼年心中)”としようかと思う。一週間くらいかかるかもしれない。英語の勉強のつもり。老化予防だ。絵はほったらかし。6月に入ったら描きつづけよう。
May 24, 2012
コメント(0)
-
きょうの英語俳句(Today's three Haikus)
きょうの英語俳句。A continuous early summer rainerases the sound of the temple's bellIf it could do grief!Rolling sounds of distant thunderI feel still oppressed in the chestMemories of old love lostA flash of lightning suddenlyirradiated the inside of my old heartMy smoldered love just desert
May 23, 2012
コメント(2)
-
終日の雨寒く
一日中、雨が降っている。気温がぐっと下がって、薄着をしているといささか寒い。 雨音を聞きながら、頭の中の抽出をあれこれ開けて、何を考えるというのでもないが、次にやろうとすることを探っていた。寒いので、猫達が次々やってきて、机に向かっている膝に跳びのってくる。「待って待って」といいながら、かわりばんこに抱く。 山の中腹にある寺から、午後6時の鐘の音が聞える。朝夕二度、いずれも6時に鳴るのだ。 雨はしだいに激しく、鐘の音を掻き消す。 ・・・そういえば、亡母の生家の寺の梵鐘は、戦時中に、供出ということで持ち去られてしまった。だから、私は見たことがない。母は、鐘の音を聞くと、昔の寺の梵鐘を思い出すようだった。 五月雨や夕べの鐘を消しにけり 青穹
May 22, 2012
コメント(0)
-
次は6月6日の天体ショー
東京(関東一円)では173年ぶりという金環日食を観て、次の機会は300年後。東京在住者としては千載一遇のチャンスだったわけだ。しかもまさにゴールド・リングが完成したときに雲が晴れた。 朝、登校する子供たちが、「金環食、金環食」と言いながら通りを走ってゆくのが聞えていた。学校で観察することになっていたのかもしれない。いつもより登校時間が早かった。子供を送り出した母親たちが、そのまま通りで立ち話しながら日食を待っていたようだ。いざ金環食になったとたん,2,3の違った場所から母親たちの歓声が聞えた。「見える見える。すごいすごい」 食は9時2分に終った。 ところで、ひきつづき6月6日の朝方、こんどは金星が太陽面を通過するのが見られる。黒い芥子粒のような点が、太陽の左上部から右斜め下にむかって通過して行くはずだ。太陽と金星と地球が一直線上にならぶのである。 2012年6月6日のこの天体ショーを、遥か昔、マヤの天文学者たちが予測していた。彼らの天文学、おそるべし。地球滅亡などという愚言も呈するが、そういう人心攪乱の(政治的)予言を別にすれば、マヤ文明の真摯な観察を積み重ねたうえでの天文知識の高度さ正確さは、現代のそれに匹敵するほどである。 日本の天照大神の天の岩戸隠れの神話は、私見によれば日食、それも金環食の解釈である。すなわち太陽信仰のなかの一つのエピソードである。 日食メガネは捨てずに取っておき、6月6日の天体ショーに使うことにしよう。 閑話休題。 八百屋の店先に、小振りの朝掘り筍が、3本くらいずつまとめてパックして売っていた。今年最後の朝掘りだという。買って来て、筍御飯をつくり、仏前にそなえた。父の位牌のそばに母の位牌がならんだ。法名はそれぞれ、「蓮生院釋顕月」「光徳院釋尼恵心」という。
May 21, 2012
コメント(0)
-
見えた! 金環日食
欠けはじめて20分後、ふたたび雲におおわれてしまったが、なんとラッキー、金環食直前に太陽の周囲だけ穴が開いたようにポッカリ雲が晴れた。見えた! 金環食である。 街路から、「見える、見える」という声があがった。「すごいね、すごいね」 およそ10分間、金環食の間だけ晴れていた雲が、ふたたび太陽をおおった。
May 21, 2012
コメント(0)
-
金環日食にむけて進行中
ただいま日食が進行中。東京の我が家の上空は、午前6時19分の開始時には雲におおわれてい、太陽のあたりはまだら雲。だめかと思いながら、窓際で本を読んでいると、ベランダにサーッと陽が射した。それっと、出てみると、雲がとぎれている。観察用メガネをかける。オオッ、右上部がすでに欠けはじめている!(続報はのちほど)
May 21, 2012
コメント(0)
-
男の頭髪(ハゲとカツラ)
きょう末弟に会った。どこかレストランで一緒に昼食を摂ろうかと誘ったが、ほかに約束があるからと、30分ほどで別れた。 先に立って歩いてゆくその後ろ姿を見ると、頭髪に白いものが目立った。総白髪にはまだまだ遠いが、四分の一白髪というところか。私とは9歳違う。67歳の私はまだ黒々としている。鬢のあたりやところどころに白いものが混じってはいるが、額の生え際が後退するでもなく、頭頂が薄くなっているわけでもない。ずいぶん以前、ある友人に鬘ではないかと疑われてグイッと引っぱられたことがある。それ以来、疑わしそうな目に出逢うと、自分で髪を引っぱってみせることにした。そうではあるが、実のところ、私は頭髪などまったくもって気にしたことがない。ヘア・ドライヤーなど使ったこともない。第一、そんなものを持っていない。 自分の髪が黒く豊だからではないが、私は、ハゲを気にする人の気がしれないのだ。そんなもの、薄くなるときはなる。なったからといって人格に支障を来すわけでもあるまい。 例にもちだして申し訳ないが、随分以前、歌手の佐川ミツオさんがこんなことを言っていた。それまでは人に知られないようにカツラを着用していたのだが、あるとき、セックスの最中に、夢中になった女が佐川さんの髪をグイッと握って引っぱった。カツラがポロリ。見たこともないハゲ頭が目に飛び込んできた女は、凍りついてしまった。・・・それ以来、カツラとはおさらばすることにした、と。 カツラをとった佐川さんのお顔はとても素敵な味があると、私は思った。たぶん、そう思ったのは私だけではないはず。その後、TVドラマだったか、ハゲ頭のまま、喫茶店のマスター役をやっておられたのを見たが、とてもいい感じだったことを思い出す。 カツラの文化は、もちろんヨーロッパにも古くからある。ハイドンやバッハやモーツルァトなどはおなじみだ。映画『アマデウス』のなかで、モーツアルトが様々な色やスタイルのカツラを前にして、声をあげて大喜び。どれもこれも欲しくて迷いに迷うというシーンがあった。イギリスの法廷では、現在でも裁判官はカツラをかぶる。美容のためではなく、権威の象徴としての帽子のようなものと考えてよかろう。 かたや日本はというと、どうやら現在のカツラ技術は世界でも群を抜いているようだ。その繊細さは日ごとに進歩していると見受けられる。だが、映画演劇以外では、すくなくとも美容としての男性用カツラは、むしろ日本独特なのではあるまいか。どうなのだろう。 つまりハゲを異常に気にする。恥入ったり、憂鬱になったり、自信喪失したり。そんな心理的なマイナス状態が、カツラくらいで解消できるのなら、それにこしたことはない。 しかし、そのような一種の精神文化といってもよい現象は、分析研究すると比較文化としては意外に面白いかもしれない。私のような頭髪のことなど一向に無頓着な人間にとって、日本男性のありようが頭髪問題に反映しているのではないかと思われるのだ。 私は野球のアメリカン・メジャー・リーグの試合をよく見るのだが、彼ら20代30代の選手に幾人ものハゲ頭をみかける。アスリートにはカツラは不都合なのかもしれないが、選手ばかりではなく一般の人たちにもいわゆる若ハゲは大勢見かける。こういう光景を見ていると、どうも日本以外の国ではあまりハゲを気にしてはいないのではあるまいかと思えてくるのである。
May 20, 2012
コメント(0)
-
蝶と霊魂
かつてもこのブログに書いたことだが、蝶が霊魂(プシュケー;the psyche =ザ・サイキ)の象徴であるとは、日本のみならずギリシャやヨーロッパ文化圏に見られる。あるいは自由の象徴ともなっている。フランクリン・J・シャフナー監督作品、スティーブ・マックイーン、ダスティン・ホフマン主演の映画『パピヨン』は、主人公の胸の蝶(パピヨン)の刺青から来た題名にはちがいないが、蝶が自由の象徴であることが暗に下敷きになっている。絶海の孤島サン・ジョセフ刑務所に送られた無期懲役囚が脱獄に挑戦しつづける、実話にもとづいた物語。たしか、映画の最後に字幕が出て、脱獄に成功したパピヨンが「その後南米に流れ着き、自由人として余生を送った」とあった。霊魂もまた、考えようによっては、この世の軛(くびき)から自由になって、此岸彼岸を往来している。 昨日は亡母の四十九日。日本の仏教全般において、死んだ人の霊魂は四十九日間は此の世にとどまっているとする。その日を服喪の一応のくぎりとしているようだ。数字にかこつけた、すなわち四(死)と九(苦)からの離脱という、まあ、プリミティブな信仰である。要するにいつまでも陰鬱に喪に服していては社会生活者としては具合が悪い。かといって、あまり早々と喪をきりあげるのも死者への礼を欠く。そうした程度を勘案したところに創出された「四十九日」であろう。理由付けが、いくらでも枝葉を付けたり幹らしきものを太くしたりしても、万人を納得させる方便が一種の冗談というのはいい。 ところで、四十九日をすませた今日、散歩に出た私の目の前を、黒いアゲハチョウがどこからともなく現れて、ひらりひらりと舞った。夏型のクロアゲハとしては、やや小型。羽化したばかりなのかもしれない。 小さなクロアゲハは、やがてまた何処かへ飛び去っていったのだが、私は、母の霊魂という幻想を、しばし楽しんだのだった。
May 19, 2012
コメント(0)
-
四十九日
風まじりの雷雨が降ったり止んだりしていると思ったら、次にはかなりの揺れの地震である。仕事場にいたのだが、急いで居間に行き、あっそうだ、母はもういないのだと思った。亡くなってしばらくは、それまで介護用電動ベッドがあった周囲をうっかりぶつかったりしないように歩いたり、ドアをそっと開けてのぞきこむような動作が、無意識のうちに出ていた。長い間にしみこんでしまった身体の反応である。そんな身体反応がようやくなくなったと思っていたのだが、すは地震と、考える間もなく母が寝ていた部屋にとびこんで行った。 実は、今日は、いわゆる四十九日である。 法要は、弟たちの都合を考えて、他日にした。といっても、儀式的にとりつくろう考えは、私にはまったくない。 四年の看護の間に、他人が良かれと思って言って下さることと、私の思いとの間に、どうしても埋めることができない齟齬を感じて来た。他人は、たとえば医師にしろ看護師にしろ、介護保険のケアマネージャーにしろ民生委員にしろ、92歳という死をひかえた老人よりは生きている私たち家族を心配する。なんとありがたいことではある。が、私にしてみれば、私の心配など必要ないのだ。私がもちあわせていない専門知識で、とことん老母を生かす努力をしてほしいのだった。 死ぬことなど誰よりも私が一番良く承知していた。一日24時間、つききりで看護し、一日の休みなく4年間やってきたのだから、母が日ごとにどのように変化し、衰えて行っているか、私ははっきり冷静に観てきた。医者もそうであったろう。看護師もそうであったろう。理学療法士もそうであったろう。しかし、「あきらめない」という点では、彼等と私とでは断然ちがっていた。 それはそうだ。同じであることなど望んではいなかった。それだからこそだ、死んでしまったのだから、もう、家族以外をタッチさせるつもりはない。僧侶さへもだ。宗教などというところへ逃れて生きて来た人間に、私に語る何があるというのだ。 私の内部にある激しさをオブラートに包んで、せめてもの見える部分で、父の法名も母の法名もすでに20年も前に今は亡い僧侶の伯父につけておいてもらった。そのときに墓に名を刻んでおいた。父も母も、自分の名が刻まれた墓を生前に見知っていたのだ。何も心配せずに、死ぬまで精一杯生きなさい、と。 そして、それを、私は手伝った。・・・そう思っているのである。 父が逝き、母が逝き、私はまったく悲しんではいない。 今日は母が逝って、四十九日である。
May 18, 2012
コメント(0)
-
デスマスク
Death Maskby Tadami Yamada There is the short novel entitled "The Death Mask" that was written by Yasunari Kawabata who was a Nobel prize winner. ------In front of a woman's death mask, two rival men in love clasped hands each other. Reason why every one of death mask is difficult to distinguish regard of sex. This is the gist of the short novel. But I guess that is a rhetoric of the Kawabata's way. Death mask that I really saw, and that is generally well known in Japan, is of a novelist Soseki Natsume. And I suppose that either a poet Hakusyu Kitahara's or a general Maresuke Nogi's are well known. Of course, Ludwig van Beethoven's or Aleksei K. Tolstoi's too. We can see not only these great men, but also, for example, rarely devilish homicide's death mask in the Black Museum of Scotland Yard. Neither, I don't think them womanish or sexless death mask. In Japan, although there are some death masks of great man, but generally Japanese, if anything, wouldn't make death mask to smear dead face with plaster. Making death mask comes from an essential part of European culture, that is to say, that their spirituality would have made efforts to approach to immortality under the pretext of materialization. On the other side, Japanese would have tried to resolve both body and soul, both the glory and the misery, all memories of dead parson into "qui"---elements. With resolving into "qui", they gain their immortality. "------When they made the death mask, they smeared oil on face of my master who didn't move an inch and press on with plaster . I heard later. A man who was seeing things said to me that was a painful even to look at when they took plaster off face as master's mustache was twitched. With only this I thought I couldn't forget thing ever heard.------" A novelist Hyakken Uchida wrote in his "An Account of Master Soseki's Dying". Making death mask, it was an affair that was done a modern intellectual person in Japan. Soseki Natsume was one of a few person who touched the essential of Europe in the Meiji era. Anyway, there was one another death mask I really saw in addition to above mentioned. That is----- My friend, a painter, who had studied in Paris returned home since seven years. And he set up his new studio. One evening he invited me, I visited his new studio taking a bottle of sake---rice wine. The studio that the ceiling, the floor and four walls, everywhere were painted in white, so that it was unaccountable strange. The wall looked like a sickroom, a young girl's mask made of plaster was hung on. It was an unusually realistic style, considering that was decorative art, and also odd for an interior. He said it was the death mask. It was a girl who killed herself, who threw herself into the Seine. And he said that the death mask was selling as a souvenir. I guessed it was possible the end of disappointed love. The story about the young girl seemed to be well known that place, my friend said. I could infer her beauty from her death mask. But it was not as if sculpture possesses beauty. The death mask of the beautiful young girl was dogged by something cruelty of fate. He said the girl was beautiful, but it sounded strange for the souvenir of the death mask. Thinking that things, I went on drinking sake with him. And also I remembered an unsavory reputation of him in Paris. Smirking he had said that study abroad won't do these days though, and he had started for Paris to resolve permanent residence. However, for some reason his study had came to a standstill for a while, ----six months. After that, he indulged in wine and woman. I heard he had a risky love affair with some twins. It seemed as if he was a ropedancer. It is about one hundred fifty years from Soseki Natsume's time till nowadays. In former times, speaking France disease, it meant venereal diseases. But nowadays it seems to mean a depressive psychosis, because although they could go abroad the longed-for place, they would get depression. We can go to Paris for about fifteen hours today. However, for my friend, Paris might be a far metropolis. He went on drinking leaning on the wall. Above his top the young girl's death mask lowered her eyes. The liquor had begun suddenly to take effect on me. I was startled to look at my friend. His eyes were crooked oddly.
May 17, 2012
コメント(0)
-
聞きそびれたこと
東京は、昨日のやや肌寒ささえ感じる雨があがったと思ったら、一転、今日は夏のような暑さだ。 午後、来客があるので、午前中にちょっと用足しに外出した。帰途、我が家への坂道をあがってくると、舗装路のわきに水たまりができていて、雀が水浴びしたり飲んだりしている。その様子がいかにも無邪気で可愛らしい。それにしても、昨日の雨でできた水たまりではなさそうだが、と、なおも坂をのぼりながら角を曲がった。するとご近所の年配のご主人が、重装備で高圧洗浄機を操りながら石塀を洗っていた。その水が、雀たちの水浴場をつくっていたのだった。 「こんにちは」と挨拶すると、老主人は、 「きょうはいい塩梅な天気になりましたね」と、にこにこ笑いながら言った。 「これから暑くなるようですよ」 「おや、そうなんですか」 意外だという顔をした。 老主人の重装備はといえば、帽子に厚手の長袖シャツ、軍手をはめ、防水加工をしてあるらしい作業ズボンにゴム長靴。もうすでに日は中天に近く、私の額は汗ばんでいたが、老主人にはその気配さへもない。 なるほど、と私は胸の内に思った。お年が暑さをあまり感じさせなくなっているのだな、と。それから、熱中症に気をつけられるといいが、と。 私は、いままで毎年つづいた老母の看護のうえでの熱中症対策を思い出した。しかもそれについて、この3月の初めに主治医とも話し合っていたのだった。まさか同月30日未明に死亡するとは、少なくとも私自身は思っていなかったので、「5月に入ったら一応その対策の準備はしておいてください」と言う医師の言葉にうなづいていた。 午後、母が亡くなって以後、はじめての客を迎えた。と言っても、母の仏前に詣りに来てくださったのだが。 1時間ばかり思い出話をして、私は、ふと、母に聞きそびれたことがあるのを思い出した。それは、母のほかには、もう知る人もないことだった。特に重要なことではまったくないけれども、なんだか私自身の記憶に、ぽつりぽつりと穴ぼこが開いたままになるのだと思った。ちょうど一昔前のテレックス(telegraph exchange)の、穴の開いた紙テープのように。・・・もっとも、母は、ちょうど一年前から、一言もしゃべれなくなっていたけれども。 客は帰り際に玄関先で深々とおじぎをした。頭上に夏茱萸(ナツグミ)のいまだ青い小さな実がたわわに垂れ下がっていた。まもなく祭提灯のような真っ赤な実となるだろう。
May 16, 2012
コメント(0)
-
終日、書き物
きのう今日と、終日机に向かって書き物。ただいま21時、これからまた0時まで机に向かう。
May 14, 2012
コメント(0)
-
亀治郎さん襲名興行『ヤマトタケル』
市川亀治郎さんが四代目猿之助を、香川照之さんが九代目中車を、照之さんの長男・政明さん(8)が五代目団子を、そして澤潟屋一族の御大・猿之助さんが二代目猿翁を襲名する。その襲名御披露目の御練りが、きょう午前、浅草浅草寺でおこなわれたと、新聞が報じていた。 襲名興行は六、七月と新橋演舞場でスーパーカブキ、梅原猛・三代目市川猿之助作『ヤマトタケル』。もちろん現亀治郎の四代目猿之助が主演する。 この芸能ニュースに私が気をとめたのは、三代目猿之助による『ヤマトタケル』の初演を、小屋も同じ新橋演舞場で観ているからだ。亡母を連れて行ったのである。 母は歌舞伎が好きで、しかし右目が不自由になってからは一人で外出させるのも心配だったから、私が同行した。その後も、中村歌右衛門丈や坂東玉三郎丈など、二度ほど連れて行った。私が忙しくて同行できないときは、弟の嫁の母親を招いて一緒に観劇してもらった。 そんなわけで、『ヤマトタケル』は、母の嬉しそうな面影と結びついて思い出すのである。このたびの澤潟屋一門の襲名興行、もしも母が元気だったらと考えるのは、たとえ生きていたとしても無理なのだが、もういちど連れて行ってやりたかった。 亡くなった翌日、弟と相談して、棺のなかに遺体をおおうほど沢山の写真を私がコンピューターで複製して入れた。その写真を選んでいるとき、弟がアルバムに記された母の文章を見つけた。それは、弟が伊豆へのドライヴに母を連れていったときのもので、「維史は締め切りが迫って忙しくて行けない」と書いてあった。 私は仕事が忙しくて、36時間休憩なしに描きつづけ、1時間ほど睡眠を取る。そしてまた36時間描きつづけるという日々だったから、ほとんど死人のような顔をしていて、家族の行楽につきあってはいられなかったのだった。『ヤマトタケル』や、歌衛門丈や玉三郎丈を観に連れていったのは、そんなスケジュールの日々のたまさかの空き時間だった。 四代目猿之助(亀治郎)さんの『ヤマトタケル』、いいだろうなぁ。朝日新聞「澤瀉屋!」 猿之助襲名披露でお練り 浅草寺 2012年5月11日17時27分
May 11, 2012
コメント(0)
-
日食眼鏡を買う
来る21日の金環日食を見ようと、日食眼鏡を家族分購入した。このまま東京に住みつづけるとしても、次の金環日食まで300年。どう頑張っても生きられない。 さて、準備はととのったが、当日の天候はいかがであろう。きょうは、さきほどまで、東京西部は雷雨だった。このところ気象の変化がはげしい。茨城、千葉、栃木一帯の竜巻被害のTV映像がすさまじい。
May 9, 2012
コメント(0)
-
英語俳句(Three Haikus)
英語俳句。To be still in mourningbut I take off my long-sleeves shirtIt's the beginning of summerSweet the flowers of deutzia!Behind the hedge, each of children duckedto play hide and seekGreen plums drop down androll over and over on the lanein a continuous early summer rain
May 8, 2012
コメント(16)
-
七日の俳句
卯の花や垣に身を伏すかくれんぼ 青穹 柿わかば隣家の窓をたたくほど 青梅の落ちてころがる霖雨かな
May 7, 2012
コメント(0)
-
東京スカイツリー!?
見知らぬおばあさんが、 「あすこに見えるのは、東京スカイツリーですか?」 「エッ? どれですか?」 ここは東京西郊の多摩地区である。 「あの、高い塔です」 なるほど、ビルの重なりの上に、ひときわ高い、ちょっと風変わりな電波塔が屹立してのぞいている。 「いえ、あれは東京スカイツリーではありません。スカイツリーはこのあたりからは見えないんです」 「富士山から見えると聞いたから、それじゃあ、ここからも見えると思ったんだけど・・・」 「残念ですけど、見えないんです」 「ありゃー」 おばあさん、見たかったんでしょうね、東京スカイツリーを。ビルの上の風変わりな電波塔をしばらく見つめていました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【注目ニュース】msn産経ニュース 「レアアースの新鉱物発見 東大など、松山市の山地」 2012.5.6 01:36「この鉱物はレアアースのイットリウムとレアメタルのタンタル、ニオブの酸化物。褐色の板状または放射状の結晶で、大きさは数ミリから1センチ。松山市北部の高縄山(標高986メートル)の花崗岩から発見した。3月に国際鉱物学連合から新鉱物と認定され、「高縄石」(学名・タカナワアイト)と命名した。」
May 6, 2012
コメント(0)
-
ただただ読書三昧
このブログの管理データによれば、きょう5月5日、ブログ開設2500日目なのだそうだ。まもなく7年を過ぎるということか・・・。 たしか2300日のときにも書いたと覚えているが、我ながらよくもまあ続けてきたものだ。気随気侭に、まったく私的な日記、と考えを定めたからかもしれない。そしてもちろん、読んで下さる方がいらっしゃるからだ。ありがとうございます、と心から申し上げます。 さて、昨日までのドシャブリの雨がカラリとあがった休日。しかし我が家は、亡母の49日が過ぎるまでは、一応、殊勝に喪に服しているので、おとなしく家で過ごし、まるで何事も無い。アート・フェアのための韓国行きも遠慮させてもらった。ただただ読書三昧である。 そろそろ作品製作にとりかかろうと思い、描きかけのまま長らく手つかずにしていた作品もあるので、まずはそれらを完成させて気合を入れ直そう。とはいえ、4年間におよんだ24時間体勢の看護生活・・・一日の休暇もなかった状況が、パタリと終熄してみると、どこか奇妙なところへブッ飛んでゆく絵画製作の精神状況を再び日常的にするには、いささかの時間が必要かもしれない。それを、あらためて今、如実に感じているところだ。
May 5, 2012
コメント(0)
-
言葉の57年後の真相
会津の人たちが、現在も、この言葉を、日常的に使っているかどうか、私は知らない。「はいっとう」という言葉。 以前、「八総鉱山回想私記』を書いた。そのなかで、「荒海小学校通学のころ」として、私はこの言葉との出会いを次のように記した。昭和28,9年の思い出である。 「荒海小学校の(八総鉱山社員の子弟のための)スクールバスの停留所は、通用門脇に一軒あった商店の前、駅からまっすぐ30メートルほどの道が本通りにぶつかるところにあった。木のベンチが一脚置いてあり、まるい筒型の鋳物製のポストが立っていたように思う。(略)ベンチに座っていると、当然、商店にやってくるお客さんを見かけるのだが、みな「ハイットー」と言いながら入る。私は当初、意味がわからなかった。帰宅してから両親にきいたが、両親もわからなかった。何かを(配達)しているのだろうか?・・・おしえてくれたのが誰であったか忘れたが、「ごめんください、こんにちは」という意味だった。といっても、道ですれちがって「ハイットウ」と挨拶するわけではない。あくまでも訪問の挨拶だ。」 この言葉については、八総鉱山社員で東京などから転勤して来た方が興味をもったようだ。今も私の記憶にあるのは、父が編集に携わり、エッセーなどを掲載していたタブロイド版の社内新聞『八総』に、お向かいの塩澤さんが「ハイットウ」というエッセーを書いていた。塩澤さんは、「優しい言葉」と捉えていた。 あまりにも個人的な思い出なので、このブログを読んでくださっている方にはまことに申し訳ないのだが、記憶にあるうちにと、私自身の備忘録として実名も書いた。 ところで、きょう、亡母が残した本のなかから皆川博子『会津恋い鷹』を読んでいた。幕末の会津藩の鷹匠に嫁いだ肝煎(庄屋)の娘をめぐる物語。小説中の会津の地名、なかんずく若松の町名は、読みながら町から町への道筋さへたどれるので、ことのほか懐かしかった。 そこに、いきなりのように、「ハイットウ」という言葉が出てきたのだ。 私にとって、57,8年ぶりのめぐりあいである。 「おッ!」と、びっくりし、そして、その言葉の由来というか「真の姿」を知ったのだ。 小説は、こう書いていた。 「・・・下駄をぬぎ、小竹がはねのあがった素足を拭っているとき、「入(はえ)っと」と野太い声と共に、のっそり男が入ってきた。・・・・」 「ハイットウ」は、「入っと」だったのだ。すなわち「入りますよ」・・・「ごめんください、こんにちは」というわけ。 この言葉を耳に親しんでから、半世紀以上たって、ようやく真相にたどりついた。そして、冒頭に述べた荒海小学校付近の景色も甦って来た次第。 「ハイットウ」についてはこれぐらいにして、ついでに連想したもっと私的な思い出を書いておく。 ****** 上述の八総鉱山社内新聞『八総』を印刷していたのは、会津若松市の佐島屋印刷で、当時の社長は南雲さんとおっしゃった。私は小学校卒業と同時に親元を離れて、単身で会津若松市に在住し同市の中学校に通うようになり、さらに会津高校に進んでから、市内の、大人が子供のために演じる児童劇団『童劇プーポ』の同人になった。初舞台が同劇団の第10回記念公演、木下順二作『おんよろ盛衰記』。そのパンフレットや、その他劇団関係のチラシなどを印刷していたのが佐島屋印刷。 『おんにょろ盛衰記』パンフレットには出演俳優のプロフィール写真や自己紹介ふうな短文が掲載され、私の写真も載っていた。 今、記憶があやふやなのだが、どうやら私は演劇活動を始めたことを両親には告げていなかったようだ。というのは、佐島屋の南雲社長が、刷りあがった『おんにょろ盛衰記』のパンフレットを父に贈ったのである。「お宅の息子さんが出演していますよ」と。これで両親は私の演劇活動を知ることになった。 演劇活動について両親がとやかく言ったのではないが、実は、現在私が手元に保存している『おんにょろ盛衰記』のパンフレットは、「兄ちゃんの写真を見たよ」と父から手渡されたものなのだ。 佐島屋印刷は、社長は代替わりしたが、現在も、会津若松市の目抜き通りで営業している。童劇プーポの印刷物も手がけられている。5年前、私は同劇団の50周年記念パンフレットの表紙画とデザインをさせてもらった。印刷の打ち合わせで現社長と電話でお話しさせてもらった。事務的なことに終始し、南雲さんや八総鉱山のこと亡父のことは、あえて話さなかったけれども。
May 4, 2012
コメント(0)
-
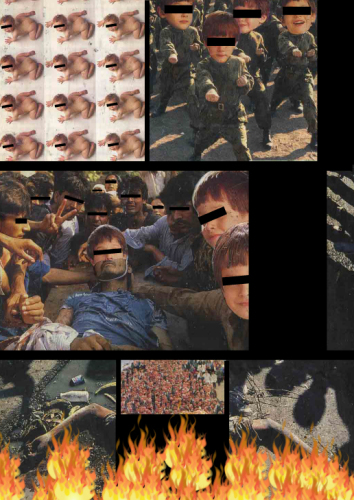
深く密かにファシズムは進む
憲法記念日に山田維史『深く密かにファシズムは進む』コラージュ 2012年5月3日Tadami Yamada《Fascism Going Profoundly and Stealthily》Collage, 3 May, 2012山田維史『230万の死せる日本兵士に捧げる』フォト・コラージュ 1991年5月Tadami Yamada "An Offering to 2,300,000 Japanese Soldiers Who Died in The Second World War" Photo collage, May 1991: An illustration for a book.
May 3, 2012
コメント(0)
-
豪雨予報が出ているが
夏立ちぬアガパンサスの紫に 青穹 降りつづく寒さ恨むや衣がへ 降る音の激しくなりて柿若葉
May 2, 2012
コメント(2)
全29件 (29件中 1-29件目)
1










