2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年01月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
名物に、旨いもの・・・??
カード会社から毎月送られてくる会員向けの冊子に、「読者が選んだランキング」という企画ページがあります。今月のテーマが「おすすめの地方銘菓」という、甘党&旅好きには興味津々のもので、発表されていたアンケート結果も面白かったのでご紹介しようと思います。 ◎読者が選んだ都道府県別人気銘菓はコレ!◎ 北海道 マルセイバターサンド(六花亭) 青森県 気になるリンゴ (ラグノオ) 岩手県 かもめの玉子 (さいとう製菓) 宮城県 萩の月 (菓匠三全) 秋田県 金萬 (金萬) 山形県 乃し梅 (乃し梅本舗佐藤屋) 福島県 ままどおる (三万石) 茨城県 水戸なっとうスナック (メーコウ) 栃木県 源太饅頭 (源太楼) 群馬県 旅がらす (旅がらす本舗 清月堂) 埼玉県 源兵衛せんべい(豊納源兵衛商店) 千葉県 鯛せんべい (亀屋本店) 東京都 東京ばな奈 (グレープストーン) 神奈川県 鳩サブレー (鎌倉 豊島屋) 新潟県 笹だんご (江口だんご本店) 富山県 甘金丹 (リブラン) 石川県 あんころ (円八) 福井県 五月ケ瀬 (五月ヶ瀬) 山梨県 桔梗信玄餅 (桔梗屋) 長野県 雷鳥の里 (田中屋) 岐阜県 栗きんとん (すや) 静岡県 うなぎパイ (春華堂) 愛知県 ゆかり (坂角総本舗) 三重県 へんば餅 (へんばや商店) 滋賀県 うばがもち (うばがもちや) 京都府 阿闍梨餅 (阿闍梨餅本舗満月) 大阪府 みたらし小餅 (菓匠千鳥屋) 兵庫県 ゴーフル (神戸風月堂) 奈良県 柿ようかん (石井物産) 和歌山県 かげろう (福菱) 鳥取県 ふろしきまんじゅう (山本おたふく堂) 島根県 利休饅頭 (仲屋) 岡山県 むらすずめ (橘香堂) 広島県 もみじ饅頭 (にしき堂) 山口県 豆子郎 (豆子郎) 徳島県 金長まんじゅう (ハレルヤ製菓) 香川県 名物かまど (名物かまど) 愛媛県 一六タルト (一六本舗) 高知県 かんざし (浜幸) 福岡県 博多通りもん (明月堂) 佐賀県 丸芳露 (北島) 長崎県 カステラ (福砂屋) 熊本県 誉の陣太鼓 (お菓子の香梅) 大分県 ざびえる (ざびえる本舗) 宮崎県 なんじゃこら大福 (お菓子の日高) 鹿児島県 唐芋レアケーキ (フェスティバロ) 沖縄県 ちんすこう (新垣ちんすこう本舗) (「JCB GOLD」2008年2月号より)・・・ここまで読んでくださった方、お疲れ様です(笑)ちなみに、47都道府県の銘菓のうち、私がいただいたことがあるお菓子は20品でした。名前だけでは、どんなお菓子なのかまったく想像もつかないような未知の品もあり。中には、ちょっと意外な結果も?三重県で選ばれたのが○福ではないのは、時節柄・・・ということでしょうか・・・。他にも、お菓子の名前を見ているだけで、旅の記憶が甦ったり、帰省の度にお土産としてそれを買ってきてくれた、かつての同僚の顔を思い出したり。異論反論含め、一覧を読んでいるだけでしばらく楽しめたランキングでした。その土地の銘菓、と一口に言っても、地元に暮す人と、旅人として訪れる人とでは、買いたくなる・食べたくなる名物も微妙に違うのかもしれませんね。(あ、ちなみに私は神奈川県出身ですが、“鳩サブレー”選出には納得!です)今の気持ちを一言で言うなら・・・“あぁ、饅頭こわい!(お茶もこわい!)”(笑)そして気がつけばもうこんな季節。月日の経つのはあっという間です。
2008.01.29
コメント(8)
-

甘く危険な香り
お客さまに、素敵な手土産をいただきました。一目見て、歓声を上げずにはいられない・・・ピエール・エルメのマカロン!カラフルで、ころんとした形が愛らしいこと。食べちゃうのがもったいなーい、なんて言いながら、食べちゃうのだ。食べずにいられるわけがない(笑)それにしても、洋菓子の包装を解いた瞬間に立ちのぼる、何ともいえない香りの、なんて素敵で、なんて罪作りなことでしょう。マカロンって結構カロリー高いのよね、とか、お正月太りは解消できたんだっけ?とか、そういう理性や理屈、すべて吹き飛ばされてしまいます。口に運んでしまえば、味わいの楽しみはほんの一時。そう思うと、目で、鼻で、ワクワクとさせられる時間も、お菓子をいただく喜びの一種として、決しておろそかには出来ないと思うのでした。【月替わりのマカロンコレクションは、イクスピアリのオンラインショップで】[ピエール・エルメ]イクスピアリ限定セレクト 1月のマカロン
2008.01.25
コメント(6)
-
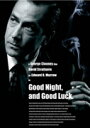
「グッドナイト&グッドラック」を観た。
モノクロの画面に映し出される、正装した人々が談笑するパーティー。和やかな列席者の表情を次々に映し出しながら、静かに映画が始まる。やがて、賞賛のスピーチに迎えられて壇上に立つ一人の男・・・大好きなジョージ・クルーニーの監督作、なかなか機会に恵まれず、やっと観ることが出来ました。1950年代アメリカ。東西冷戦の緊張が高まり、国民はマッカーシー上院議員による“赤狩り”の恐怖に怯えながら暮らしていた。全米が萎縮するなか、敢然と立ち上がった国民的キャスター、エド・マローと若き記者たちの闘いの行方は・・・。国家の方針にそぐわない“危険分子”を排除しようとするのは、何も旧社会主義国家の秘密警察に限ったことではないわけで。人々がお互いを監視しあい、裏切りや疑心暗鬼がはびこる状況。その張り詰めた緊張感が、ニューススタジオやオフィスの中にも否応なく漂っていることが、モノクロの画面を通して、ひしひしと伝わってきます。スーツと、ネクタイと、タバコの煙に満ちみちた映画。およそ半世紀前の、働く男たちのスタイルは、なんと“大人っぽかった”ことか・・・ということを、再認識させられました。全編をとおして、ダイアン・リーブスの歌うジャズの名曲が挿入歌として贅沢に盛り込まれます。ただ、この映画、いわゆる“劇伴”(物語の演出効果を盛りあげるための音楽)は一切使っていません。あくまで、大人の映画なのであります。その端正で硬質なつくりが、とても気に入りました。もちろん、マスメディアの中で報道に携わる者としての「良心」を貫こうとする人々の姿が、静かな感動をもたらすのは、言うまでもありません。自らの信ずる、良心の声に従うこと。それが、きれいごとだけでは済まされないことも描かれています。モローと志を同じにするスタッフの一人が、夜、ベッドの中でつぶやく「僕らのついているのが、間違った方だったら??」という自問の言葉は、深い。テレビが、娯楽や逃避のためにしかないのだとしたら、そんなものは初めから要らないものだ・・・劇中に登場するこの言葉。もはや、メディアの主軸がテレビという“マス”から、ネットの細分化された世界に移ろうとしている今の時代にも、十分に重みを持っていると思います。そして、「テレビ」の部分を「映画」に置き換えることも出来るのではないでしょうか。多くの人にお奨めしたい、噛み応えのある作品でした。ニュースキャスターだった父を持つ、ジョージ・クルーニーの熱い思い入れが伝わってきます。国連平和大使に任命されたという彼の、今後の活躍からますます目が離せません。【劇中で歌われるジャズの数々。楽天ダウンロードのサイトで無料視聴も出来ます。】「グッドナイト&グッドラック」-オリジナル・サウンドトラック-/サントラ[CD]ちなみに、私のお気に入りはこの一曲。Dianne Reeves『ハウ・ハイ・ザ・ムーン』
2008.01.22
コメント(6)
-

着付けお稽古はじめ
今年最初となる、着付けのお稽古へ行って来ました。教室となっている先生のご自宅に伺い、部屋に入った途端“わぁ・・・♪”と歓声を上げてしまいました。襖を開けた瞬間に目に飛び込んできた、華やかに着付けられた三体のボディ。先週の成人式の際に、先生や古参の生徒さんはお仕事で振袖の着付けをされたので、事前の準備としてずっと、いろいろな帯結びを研究されていたそうです。それを、私たちのクラスでも教材として披露してくださいました。左側の赤い着物は、女の子の十三参り用。中央は、先生のお若い頃の中振袖ということで、ため息が出るような総刺繍がしてありました。その後は、初稽古ということで、皆で着物を着てお茶会をしました。先生のご近所の方のご好意で、そのお宅のお茶室をお借りしての一席でした。正式な初釜とは違い、皆、お稽古用のカジュアル着物でしたが、炭の炎と温かい一服で、エアコンの暖房とは一味違う温もりが身体を包んでくれることを実感。静かな空気の中で、色々と教わりながら楽しく勉強し、いい一年のスタートがきれたと大満足でした。
2008.01.21
コメント(2)
-

玉三郎という女形
お正月のスペシャルゲストはイチロー、その次の回は小野二郎(“すきやばし次郎”鮨職人)、そして、今年3人目に取り上げられたのが、坂東玉三郎・・・ゲストの名前が、まるで数合わせのようにきれいに並んだNHKの人気番組“プロフェッショナル 仕事の流儀”。いつもは、9時のニュースからの流れで何となく見たり、見なかったり・・・という程度なのですが、敬愛してやまない玉三郎さんを拡大版で取り上げる!となれば、気合いの入りようが違います。火曜の夜は、テレビの前で正座して画面を見つめました。私の場合、祖母がとにかく玉三郎びいきで、テレビでお芝居がかかると「足が悪いのにねぇ、スッと立ち上がるのも大変だろう」「背が高いからねぇ、ほらあんなに背中丸めて、足かがめて、かわいそうに」・・・という具合で、解説つきで一緒に観ておりました。ポリオによる足の障害、長身という女形にとってのハンデ(その当時の相手役は、今の看板俳優たちの先代にあたる方たちだったから、その身長差は確かに相当のものだった)といった、乗り越えなければならなかった重荷は、そんな風に昔からよく知られていることだと思います。天性の美貌のほかに、もう一つ“努力できる”という才能を授かった人。型を守り、受け継ぐ伝統芸能の世界で、こんなにも突出した、オンリーワンの存在で居続けること。「妥協なき日々に、美は宿る」と題された番組を見て、しみじみ、この役者と同時代に生き、この人の道成寺を、鷺娘を、お染の七役を、ほかにも数々の舞台を目にすることが出来たわが身の幸運を感謝しました。かつて、「次に生まれ変わるときは、人間にはなりたくない」と答えたインタビュー記事を読んだことがあります。「あんたはもう世界一の、日本の、歌舞伎に残る名女形になるよ」と言った淀川長治に対して、「私、齢取ってまで女形になるのいやだよ」・・・と答えた、という若い日のエピソードもあります。遠くを見ない、明日のことだけ考えて生きる・・・内面の厳しさがにじみ出る“孤高の人”であり、どこか刹那的な、いつ消えてしまうかもわからないような緊張感をはらんだ美しさの持ち主。歌舞伎を心底愛し、亡くなった歌右衛門を崇拝していた淀川センセイは、先ほどの話を紹介した後で「これが今の時代なのね。もう歌舞伎を守る気はないんだね。(中略)もしも玉三郎がじっと歌舞伎をつかんでおったら、あの人は後光が射す女形になるだろう。けれども、あの人はあんまりきれいすぎて、野心がありすぎて、四方八方から褒められて、褒められて・・・」と、著書の中で苦言を呈しました。十年前にお亡くなりになった淀川センセイに、今、57歳になった玉三郎さんの歌舞伎を見せてあげたい気がします。でも、きっと天から舞台を観ていることでしょう。玉三郎さん本人も、そんな多くの、異界からの視線を感じつつ、一日一日の真剣勝負をつないでいるのだということを感じた番組でした。この次、また、彼の舞台の観客になれる幸せを味わう時が、今から楽しみです。齢を重ね、人生を重ねた玉三郎さんに演じてほしい役柄は、いくつもあるのですから!※番組中で行われた女形の所作指導は、着物の立ち居振る舞いにも応用できそうで・・・ 番組内容はNHKプロフェッショナル公式サイトで。 ちなみに、再放送は21日(月)深夜です。【ファン歴ン十年。歌舞伎以外のお仕事にも、私は魅了されました。】※ジュリーと玉三郎(男性役スーツ姿)の共演が嬉しすぎる、鈴木清順作品※夢二 デラックス版※こちらは映画監督としてのデビュー作。鏡花×小百合×玉三郎のコラボ※外科室 デラックス版(DVD)
2008.01.17
コメント(4)
-

「earth」を観た。
NHKとBBCが共同制作した自然ドキュメンタリー、「プラネットアース」。昨年放映されたこのシリーズ、毎回夢中になって観ておりました。この番組をもとに、劇場用に新たに編集された映画が本作。映画は、冬眠から目覚めたホッキョクグマの親子の姿に始まり、水を求めるゾウや、餌を探して長旅をするザトウクジラなどを追いながら、子午線に沿って南下していきます。たくさんの動物たちはもちろんのこと、砂漠や森や山や草原・・・圧倒的な大自然のランドスケープが随所に盛り込まれ、まさに“地球規模”の映像美に浸ることが出来ます。水の分子が、湧きあがる雲、なだれ落ちる滝、広大な海・・・と様々に形を変え、その中で生命を育む様子。その、有機的な連なりを見ていると、そもそも地球という惑星そのものが“生きている”のだと思えてきました。TVシリーズの視聴者にとっては、あぁこれ見た見た・・・というシーンも多く出てきますが、やっぱり大きなスクリーンとドルビーサラウンドの音響で体感すると、迫力は倍増!夜の闇の中で、360℃からライオンの群れに唸られる。そんなステキな疑似体験も出来ます(笑)野生動物の表情に迫ったどアップもすごい。けれど、広い広い海や雪原にポツンと生きているホッキョクグマ、すさまじい数のトナカイや鳥の群れ・・・そんな、どこまでもどこまでもカメラを引いていくロングショットには、ひれ伏したくなるような畏怖の念を抱かされました。どこまでも高みに上っていくカメラの視点。遥か下に生きもの達を見下ろして、それはまるで、神の目線に成り代わったような錯覚を起こさせる。でも、それはあくまでも錯覚、人間は造物主ではないということを忘れるわけにはいかないのです。見たことのないものを見たい、そういう基本的な好奇心を満足させてくれる映画。同時に、人の姿の見えない自然の極限の世界にも、人間がもたらした温暖化や環境破壊の影響が及んでいるという事実についても、考えさせられます。居心地のよい映画館で、外の寒さを気にすることもなく、座ったままで地球を一周できてしまう私たちの生活。文明が生み出したものと壊していくもの・・・立ち止まること、あるいは後戻りをすることは、人間の選択肢にあるのでしょうか。自分が生きているうちに、野生のホッキョクグマの絶滅をニュースで知ることになるのかもしれない・・・その事実はあまりにも重く、映画の余韻と共に胸に残りました。【TVシリーズ、私のナンバーワンはやはりこの回。】プラネットアース episode 8 極地 氷の世界【ニュルンベルク動物園の白熊の仔がニュースになっています。こちらは先輩格(?)ベルリンのクヌートのぬいぐるみ】クヌート■シュタイフ社テディベア
2008.01.15
コメント(2)
-

初釜の着物
通っている市民講座の茶道教室で、先生に初釜のご案内をいただき、出かけてきました。会場は、市内で茶道具を扱っているお店の二階にある茶室。いわゆる“大寄せの茶会”の形式で、昨年に引き続き二度目の参加になります。前回は、着ていくものがない・・・という理由で、ワンピースを着て出かけましたが、今年こそは!誂えた色無地を張り切って着ていくことにしました。帯は、色無地を購入した同じ時、一目惚れしてどうしても欲しくなり、ちょっと分不相応な買い物をして手に入れてしまった、袋帯をデビューさせることに。・・・ただ、直前になって、「これで、初釜の席に本当にふさわしいのか?」と、頭によぎる不安・・・綾織の、遠目には縞に見える帯。ちょっとファッション性が強すぎるかな?と。心配になって、本やネットで情報を集めてみても、実は着物の決まりごとというのは、大枠は決まっていても、細かい○×になると、人それぞれ言うことが違う・・・ということが多いのですよね。でも、一般的に「初釜にふさわしい」とされる吉祥文様や有職文様の帯など持っていないし、色無地もこれ1枚きり、無い袖は振れないのです。悩んだ末、「着物は一つ紋入り、半襟は白、金糸の入った袋帯と帯締め、結び方は二重太鼓」・・・と、これだけの要素がクリアできているなら、許容範囲じゃないか??そう考えて、当初考えたとおりのコーディネートで出かけました。着物は、洋服以上にTPOに重みがあるというか、見る人の心持ちまで考えておしゃれをすることが前提になるところがあって・・・だからこそ楽しみもあり、だからこそ悩みも尽きぬ・・・と、いうわけですね。実際に会場へ行ってみたら、集まった方々のお着物姿はバラエティに富んでいて、正客になられたお偉い先生(らしい方)は源氏香の散らし模様の小紋をお召しでしたし、色無地に名古屋帯を合わせた方もいらっしゃいました。約束ごとを守り、かつ踏み外さない程度に楽しむ。難しいところです。経験を積んでいくのが一番なのでしょうね。(左・待合にて、参加者の皆さん。右・並べられたお道具の箱書き。軸は“梅に鶯”)小さなねずみがついた香合、豪華な蒔絵が美しい平棗、“えくぼ”という名のお菓子。新春を寿ぐ様々な演出に、五感でおめでたい気分を満喫!実は、着物でお茶会へ行くのは今回が初めてだったのです。お茶と着付けのお稽古を初めて3年目、やっと“憧れ”に手が届いた、今日はそんなうれしい一日でした。【お稽古仲間の皆さんと、記念写真】※私は裏千家の先生に習っていますが、山口智子さんをゲストに先週から始まったこの番組、とても興味深く拝見しています。※武者小路千家 初釜を楽しむ
2008.01.13
コメント(10)
-

広島へ行ってきました
お正月の連休に合わせて、ぜひ・・・と、友人のご実家にお招きをいただき、フラリと広島へ遊びに行ってきました。友人の帰省にちゃっかり便乗する形になりましたが、二泊三日の旅で、牡蠣もお好み焼きも穴子めしももみじ饅頭も!堪能しました。以前のブログにもご登場いただいたことがある、心やさしい友人母には、自慢のお料理の腕をふるっていただいて(あぁ~、人に作ってもらう食事はなんて美味しいんだろう・・・)と、夜毎の幸せに目を細めていた私。本当に10年主婦をやってきたのだろうか(笑)【広島市内の移動は市電がダントツに便利。新旧色々な車体がありました】 実質、観光に使える時間は1日半しかなかったこともあり、今回はフェリーで宮島に行き、翌日は市内観光で時間切れ、という感じだったのですが、仕事で数時間滞在したことしかなかった街なので、ゆっくりと歩くことが出来てうれしかったです。【厳島神社の大鳥居。干潮のときに下をくぐると、その高さは大迫力らしい】 【宮島にも鹿がいました。奈良公園の鹿より小さく、おとなしかった・・・】 【宮島から帰るフェリーで見た、瀬戸内海の夕景。飛行機雲が光っていた】 翌日は、朝から平和記念公園へ。休日でしたから、早い時間から観光客がたくさんいて当然なのですが、資料館や公園内にいた人々のうち、二十代~三十代とおもわれる若い人の割合がとても多かったのが印象的でした。【冬空の下の原爆ドーム。手前の石碑には大きく“慰霊”の二文字。】 これは、広島平和記念資料館の窓から撮った光景です。 「安らかに眠って下さい 過ちは 繰返しませぬから」・・・という碑文で知られる原爆死没者慰霊碑に手を合わせて拝み、頭を上げると、アーチ型の碑のちょうど中心に、原爆ドームが見える・・・という設計になっています。原爆ドームのさらに向こうに、広島市民球場が見えました。世界のどの国も経験していない地獄を知り、語り継ぐその歴史のすぐそばに、平和と繁栄に支えられたごく普通の日常がある。そんな、広島をヒロシマたらしめている現実を、考えさせられました。でも、その時胸によぎった様々な思いは、安易に言葉に出来るようなものでなく、逆に、きれいな言葉になどせずに、ずっと持ち続けていたいのです。口に出せたのは、ここに来られてよかった。・・・その一言だけでした。今回は時間がありませんでしたが、尾道や、少し足を伸ばして錦帯橋など、まだまだご案内できるところはたくさんあるから・・・と、友人からはうれしい申し出があり、またぜひ訪れたいと思いました。
2008.01.09
コメント(4)
-

お正月は落語三昧
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお付き合いください。さて、「落語がちょっとしたビーム、いやブーム」なんてことを聞くようになってから、実はもう何年も経っているような気もしますが、私と夫の間で確実に“落語熱”が発火したのは昨年のことでした。地の利の関係で、寄席にはなかなか気軽に足を運べません。・・・が、その気になってアンテナを張ってみると、結構テレビでも落語観賞は楽しめるものだということも、わかってきました。(いやいや、やっぱり高座は生で聞かなきゃ・・・と、おっしゃりたくなる向きもあるかもしれませんが、そこは物理的に叶わぬ夢もあるので・・・)年末年始のテレビ欄で、目についた落語関係の番組を手当たりしだいに見たり、録ったりしていたら、気がついたら「ちりとてちん」などは3回も聞いておりました。お豆腐、腐りすぎですね(笑)同じ噺でも、味つけや工夫、そして噺家さんご本人の持ち味によって、その魅力がどんどん違う色合いを持っていくのだということが、よくわかりました。中でも楽しかったのが、関西地方で昨年放映された番組(NHK)の再放送、「南光・文珍のわがまま演芸会」です。桂南光・文珍両師匠が、若手の落語家を招いてその芸を楽しむ、という趣向のこの番組。笑福亭三喬さんの「花色木綿」は、袷、羽二重、紋・・・と、着物の仕立てに関する言葉がふんだんに出てくるのが、着物好きにはうれしい噺でした。もう一人のゲストが、ドラマ・ちりとてちんの“草原兄さん”こと桂吉弥さん。こちらは、歌舞伎芝居を題材にとった「七段目」を熱演され、これまた歌舞伎ファンの端くれとしては楽しかったです。型をなぞり、守りながら、受け継ぐ者たちがそれぞれの輝きを放つ。伝統芸能ならではの、奥深い楽しさですね。ビギナーの私にとっては、耳にする噺のほとんどが初めて聞くものばかりなのですが、立川談志師匠の言葉だったか、「落語は、人間の業を肯定する」というのは、その通りだなぁ・・・とうなづかされるのでした。「笑う門には福来る」という言葉があります。今年はたくさん笑ったお正月、福をたくさん呼び込めているかな??と、願っております・・・
2008.01.07
コメント(6)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- コストコ行こうよ~♪
- コストコで初購入品のレポと無料のも…
- (2025-11-10 08:40:41)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- [送料無料] ダーツ & はんこ & …
- (2025-11-13 21:04:35)
-
-
-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇
- 【ウエルシア・ウエル活】WAON POINT…
- (2025-11-16 06:00:05)
-







