2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年03月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

着物でランチとお買い物
着付け教室の先生と、同じクラスの生徒有志で、一緒にランチを楽しむことになりました。会合の主旨その1は、「着物で出かける機会を作る」こと。という訳で、今日の私の装いはこんな感じにしました。【飛び柄の小紋に袋帯。絞りの帯揚げを入り組にし、存在感のある帯〆を合わせました】もう一つの主旨というか、楽しみにしていた食後のイベントが「先生の後ろにくっついて、呉服屋さんを見て歩く」というもの。そもそも、この日は近隣の呉服店が合同で行う展示会があり、その案内をもらった先生から、展示会で目の保養をして、美味しいものでも食べましょうか、と提案していただいたのです。ちょうど先生、注文の品が出来上がってきたそうで、それなら展示会の後は、先生懇意の呉服屋さんも見てまわって・・・ということになった次第です。【ランチの後、お店の前で集合写真を撮ってみました。】ちなみに。本来なら、先生はご自分がお店に足を運ばなくても、「番頭の○○さんがいつもうちに来てくれる」・・・と、そういうお買い物をされているVIP顧客。そういう訳で、展示会でも、お店でも、下にも置かぬ厚遇でしたし、私たちが着付けを習っていることを聞くと、並んでいる商品の産地、職人さんの技、江戸時代から伝わる柄のこと・・・様々なお話を、社長さん自ら熱心に教えてくださり、本当に楽しい時間でした。私、以前デパートに入っている呉服店でとても怖い思いをしたことがあり(過去ブログ“恐怖の呉服屋”参照)、どうも呉服屋さんというものに対して構えてしまうのですが、プロフェッショナルの方に着物について熱く語っていただくことは、こんなに面白いことなんだ!!と、開眼しました。これも先生のおかげ・・・あ、そうそう、ここでは先生のお買い物が主目的でしたね・・・と、店の奥で番頭さんと話し込んでいる先生のところへ行くと、出来上がりの品は脇に置かれ、次から次へ、素敵な江戸小紋の反物が広がっています。どうやら先生、大小あられのシックな反物に一目ぼれしてしまった模様。(もしかして、私たちの存在は半分頭から消えていたかも・・・笑)その光景を見た社長さん、そういえば江戸小紋なら、この前仕入れたあれが・・・とブツブツ言いながら、棚からいくつかの箱を取り出しました。中から現れたのは、いずれもシックな色合いの、毛万筋や角通しの反物。(1ミリ以下の極少の模様が並んだ、遠めには無地にしか見えない江戸小紋の代表格です)それね、色々ありまして、お値段は・・・と、社長さんの言葉を聞いた瞬間、私ともう一人が先生の後ろから「欲しい!!」と同時に口に出していました(!)着物を自分で着るようになって3年になりますが、私、正絹の着物は今回着た小紋のほかに、この色無地とこの紬、後は色留袖を持っているきり。そんなに着物で出かける頻度は高くないので、困らないといえば困らないのですが、やっぱり本音は(あれも欲しい、これも欲しい)の“物欲ざかり”(苦笑)。中でも「欲しいものリスト」の筆頭が江戸小紋だったのです。着尺に八掛がついて3万円台というお値段を聞いたとき、まさに「キターーーッ!!」と心の中で叫んだ私。先生は、最初は思わぬ展開に驚かれたようですが、確かにお買い得には違いない、と、どの色柄が合うか一緒に選んでくださいました。後で、「何だか、私が呉服屋さんと結託して買わせちゃった感じじゃない?私に遠慮して無理して買い物したんじゃないの?」と心配されていたので、感謝こそすれ、そんな風に思うわけないじゃないですかー!とこちらも必死で打ち消したのでした。(私は先生のこういう素直なところ、好きです)反物から呉服屋さんで選んで着物を誂えるのは、初めての経験です。虎の威を借る狐のような具合で、予定外の買い物なれど心の中は大満足!の、着物で過ごした休日でした。【桜の蕾はまだ固いですが、自宅の近くでは雪柳が満開です】
2008.03.30
コメント(6)
-

ときめく“おまけ”
いつの頃からでしょうか、コンビニ等に並ぶペットボトル飲料の首に、ビニール袋に入った“オマケ”がぶら下がるようになったのは。ハンドタオルとかボトルカバーとかアクセサリーとか、結構充実しているのね、と思いつつも(オマケはいらないから、その分安くしてくれたらいいのに)・・・と考えていることに気づいた瞬間、自分がオバサンになったことを深く自覚しました(泣)そんな訳で、オマケを主目的に買い物をすることは基本的にないのです。…が、珍しく「これは欲しい!」と目を輝かせてしまったのが、こちらです。リプトンリモーネ(500cc)についていたのは、「PIERRE HERME アクセサリーコレクション」と書かれた袋。ピエール・エルメのお菓子を模したアクセサリーチャームなんです。マカロンのほかにチョコレートなどもあって、全8種類。最初にコンビニで見つけた瞬間に、ハートをわしづかみにされてしまいました。でも、私はペットボトルのレモンティーは甘すぎてちょっと苦手。いい歳をして、オマケにつられて好きでもないものを買うのはいかがなものか?な~んて、自分を戒めて一度はスルーしたのですが、その後、愛読しているLaura27さんのブログで紹介されているのを見て、陥落しました…結局は、大喜びで携帯につけてます。とてもリアルな外見、アクセサリーとわかっていても、見るたび「美味しそう」と思ってしまうのでした。ちなみに、本物のマカロンの写真はこちらから…。【ちなみに、携帯の待ち受け画面は今、こんな感じです(笑)】はい、ドラマ「ちりとてちん」の徒然亭『蜩紋』です♪ちなみに着メロは「ピタゴラスイッチ」のテーマ(栗コーダーカルテット)です。どんだけNHK好きなんだ~?って感じですね、ハハハ…
2008.03.27
コメント(8)
-

はちみつマスタードのソース
花粉症に端を発して、例年、この時期になるとどうも身体の調子を落としてしまいます。他の方はどうか知りませんが、私の場合、元気のない時に真っ先にやる気を失くす家事は、料理です。・・・と言っても、掃除だって洗濯だって基本的にやりたくないんですけど(苦笑)台所に立つ仕事は意外と頭も使うもの。ボーっとしていると、もう何から手をつけていいやらウンザリ、となってしまうのでした。夫のお弁当も、冷凍食品の割合が日々増えているような気が・・・という訳で、手抜き お手軽レシピが大活躍している今日この頃です。これは、野菜も美味しくいただけて、サっと作れるうれしい一皿。ちゃんとした蒸し器がない我が家では、鍋と足付きのステンレスのザルを使います。【蒸し鶏と野菜のはちみつマスタードソースがけ】材料: 鶏胸肉 (脂身を除いたもも肉でも) ブロッコリー、ニンジン等、野菜適宜 塩、こしょう はちみつ、粒マスタード、しょうゆ<レシピ>鶏肉と一口大に切った野菜をザルに並べて鍋に入れ、鍋底に少量の湯を入れてフタをし、強火で15分ほど蒸す(空焚きに注意)。鶏肉に火が通ったら薄切りにし、野菜と一緒に皿に並べ、ソースを回しかける。ソース・・・はちみつと粒マスタード(各大さじ1強くらい)にしょうゆ(小さじ2くらい)をよく混ぜ合わせる。工房アイザワ 厨房小物 リング付丸ザル20cm厚焼きのバタートーストと一緒に食べても美味しいし、白いご飯にも結構合います。(ただ、肉料理に甘い味付けは許せない!という方にはオススメしません・・・)旬のブロッコリーや、芽キャベツなどがもりもり食べられるのもうれしいです。
2008.03.25
コメント(7)
-
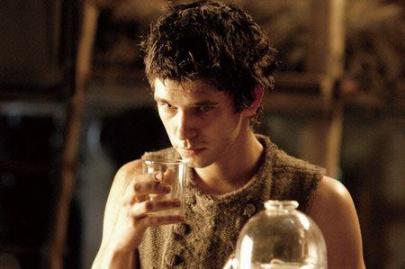
「パフューム」を観た。
*「ポリリズム」を歌っているカワイイ3人組のことではありません(笑) タイトルは、正しくは「パフューム ~ある人殺しの物語」。牢に繋がれた香水調合師の男が、民衆の怒号が渦巻く広場に引きずり出される場面から、映画が始まります。公衆の面前で、彼に言い渡される刑は、十字架に磔とし、鉄の棒で体中の骨を折ってから絞首刑にするという、残酷なもの…それほどまでに重い、彼の犯した罪とは、一体どのようなものだったのか?そして、なぜ彼はそうせざるを得なかったのか…一転、物語は時を遡り、主人公の男が魚市場の片隅で産み落とされる場面に切り替わります。それから映し出される、人間離れした嗅覚を持った彼、ジャン=バティストが歩む数奇な人生…トム・ティクヴァ(「ラン・ローラ・ラン」や「「ヘヴン」の監督)は、独特の『間合い』を持った美しい映像・演出を見事に織りなし、ベルフィン・フィルが奏でる荘重な音楽がぴたりと嵌まって、この“怪人”の一代記、ぐわわーっとのめりこんで観てしまいました。原作からして、すでに世界的ベストセラーな訳ですが、この映画も本当に面白かったです。ジャン=バティストが求め続けたものは、一貫して変わらない。それなのに(だからこそ?)彼自身は、腕利きの調合師から殺人者へと変容してしまう。絢爛豪華な味わいの中に、猟奇的なムードが漂い、何ともいえぬ倒錯的なイメージがあって…美女が次々と狙われ、殺人の餌食になっていくにつれ、この感じは何だか既視感がある、この物語のテイストを私はすでに知っている…と、考えていてハッと思いつきました。そうだ、江戸川乱歩だ!!と。常人にはとても理解の及ばぬ、歪んだ論理で犯罪にその身を捧げる主人公に、いつしか屋根裏の散歩者や、悪女黒蜥蜴をだぶらせて観てしまいました。この映画で描かれる犯罪の全容、今は亡き乱歩先生も、きっとこの着想はお気に召したはずと思うのですが。18世紀の、悪臭に満ちたパリの描写。香水産業の要地として、花々と自然に囲まれたグラースの美しさなど、文章とはまた違う、映像ならではの表現が堪能できる、という点でも見事です。闇の中から影が滲み出てくるように、主人公が姿を現すシーン…その不気味で、かつ美しいこと!(ちなみにそれは、映画の中で明かされる彼の特異な体質を表現するものでもあります)そしてそして、この映画を語る上では外せない、処刑台で起こる驚天動地(←実は、某映画評論家がこのくだりを思いっきりネタバレしていたのだけれど、知ってて見てもびっくり仰天しました)のクライマックスから、呆気にとられるほど哀しいラストまで…つくりごと、絵空事の面白さ、愉しさを満喫できた作品でした。うーん、映画館で観なかったのが悔やまれます…パフューム ある人殺しの物語 スタンダード・エディション (主人公に香水の調合を教える雇い主役に、ダスティン・ホフマン。好演でしたが、やっぱりこれ、鼻の大きさがキャスティングの決め手だったのだろうか・笑)
2008.03.24
コメント(7)
-

「木曜組曲」を読んだ。
昨日は冷たい雨が降り続く休日となり、結局、ずっと家の中で過ごしました。熱々のミルクティーや玄米茶をとっかえひっかえ、たまにお茶菓子をつまみながら…たまたま、図書館で借りてきていたこの本があったので、一気に読んで、あっという間に時間が経ってしまいました。こういう、「午後いっぱい」くらいがちょうどよい分量の、読み応えがあって余韻も心地良い小説があると、雨の日も何ともいえず贅沢な過ごし方ができますね。木曜組曲耽美派小説の巨匠、重松時子が薬物死を遂げてから4年。彼女が遺した家「うぐいす館」に、今年も時子に縁の深い女たちが集まった。それぞれ、文章を書くことに関わって生きている、5人の女性。時子を偲ぶ宴が進む中、彼女たちの会話は思わぬ方向へと発展していく。重松時子の死は自殺なのか、他殺だったのか??「うぐいす館」に集まり、思いもよらぬ謎解きゲームに巻き込まれていく女性たちのキャラクター描写が鮮やかで、年齢も性格も異なる、それぞれの人間の色合いが見事なコントラストを描いています。そして『描写の妙』といえばもう一つ。この小説、とにかく食べるもの、飲むものに関する記述が次々と出てきて、それが読んでいて本当に楽しい。タイトルのとおり、とある木曜日を挟んだ三日間の物語なのですが、その間、うぐいす館で彼女たちが囲む食卓のおいしそうなこと!ほうれん草のキッシュ、ブロッコリーと木綿豆腐のあんかけ、鯛すき鍋、夜中のおつまみにするポトフ、朝食のパンケーキ…食事以外にも、朝から紅茶が続いたから日本茶を淹れよう、という場面。そしてお茶菓子にするのは「しろたえ」のチーズケーキ、とか。何気ない描写だけど、一つひとつがとても“その場の空気”にはまっていて。読んでいて、現実にも、こんな細やかな心配りでもてなしたい、もてなされたい…と思わずにはいられません。恩田さん自身、料理がお得意なのかは知りませんが(笑)他人に台所を任せて、与えられるものをそのまま口に入れているような人には、逆立ちしてもこういう文章は書けまい、と思うのです。ちなみにこの作品は5年前に映画化されていて、私は公開時に観ました。その時、映画館で買ったパンフレットには、小説に忠実に再現されたお料理のレシピが載っていて、うれしかったです。(ちゃんと、実際に作ったかどうかは…内緒!)映画館を出たあと、友達と「お腹すいた、お腹すいた」と言いながら有楽町の街を歩いたものでした。登場人物それぞれが、胸に秘めていた告白や記憶の澱をさらけ出していく3日間。物語の終盤、まるでサイコロの面がバタンバタンと転がるように、次々と明らかになる事の真相。その展開の面白さは、映画でストーリーを知っていた私にも十二分に味わうことができました。書物を題材にしたミステリーとしては、著者には「三月は深き紅の淵を」という名作がありますが、こちらは「書く人」の方にスポットを当てて、その思いの強さがそのまま、ミステリの鍵になっているという…ちなみに、時子の死の真実。実は、映画と原作では少し異なるストーリーとなっているのですが、私には映画版の方が好みでした。それはおそらく、重松時子という女性を演じた浅丘ルリ子さんの存在感が、映画で描かれた顛末に説得力を持たせていたからかな?と、思います。【空腹時にはおすすめ出来ない映画です(笑)うぐいす館の佇まいも素敵!】木曜組曲
2008.03.21
コメント(2)
-

夢見るミモザ
しばらく会っていなかった友人と約束をして、馴染みのカフェで長話に花を咲かせました。彼女が、よかったらこれ・・・と差し出してくれたのは、無造作に新聞紙にくるんだ、たっぷりのミモザの花束。思わず歓声をあげてしまいました。一日経って、今日は朝から雨模様のぐずつくお天気でしたが、部屋の一隅はミモザの黄色のおかげで、光がこぼれているかのようです。 何度か遊びに行った彼女の家。庭のシンボルツリーとして、それはそれは立派な、見上げるようなミモザの木が立っていたのを思い出しました。どうせ枝をはらうんだから、ミモザの花をもらってくれる人は大歓迎!と、毎年周囲の人々に大盤振る舞いをしてくれるありがたさ。花を愛でるのは大好きですが、私はガーデニングというもの自体にはあまり興味がなくて、せいぜい、気が向いた年にベランダで朝顔を咲かせてみるのが関の山・・・そんな訳で、庭のある家に住みたいという願望も無いのですが、この季節に限っては、「自分だけのミモザの木を持つ」、そんな贅沢に憧れてしまうのでした。
2008.03.19
コメント(4)
-

弥生のお茶会
私が、市民講座で茶道を教わっている先生が、市内の某茶室で月釜を受け持たれるとご案内いただき、出かけてきました。お待合の掛け軸は、早蕨と黄色い蝶。香合は隅田川、棗はみる貝の蒔絵が見事な平棗。水指やお茶碗などは花尽くしという印象で、ちょうどポカポカ陽気の休日だったこともあり、春を実感した次第です。【茶花に使われた、黒い猫柳がシックで素敵でした】前日の夜。軽い気持ちで夫に「そんなに堅苦しくない集まりだって言われたけど、一緒に行く?」と尋ねたら、意外にも(?)「行こうかな」という返事。これまでも何度か、市民茶会のような場所には二人で出かけていて、不調法な彼も、それなりに毎回楽しんでいるようなのです。が・・・当日。客の側とはいえ、粗相をして先生に失礼があっては!と緊張気味の私を尻目に、扇子を持つや「え~、毎度バカバカしいお噺を・・・ズルズル(←ソバをすする真似)」・・・と“落語家ごっこ”を始める夫。席入りした後でそれやったら、殴るよっ!と一喝して、会場に向かった次第です。私の目はおそらく、狐のように釣り上がっていたことでしょう(苦笑)本日の着物です。洋服で来る人も多い席だから構えずに、という先生のお言葉を受けて、クリーム色の小紋に名古屋帯を合わせました(・・・確かに、洋服の方が半数近くでしたが、着物の方は色無地に袋帯という組み合わせが多かったので、このコーディネートは軽かったかな?とも思ったのですが・・・)。先月まで、お稽古では冬のお点前として、冷めにくい筒茶碗でお稽古をしていたのに。わずかな日数で季節がぐるっと移り変わったことを感じた一日でありました。【帰り道、通りかかった公園できれいな梅の花を観賞しました】
2008.03.17
コメント(12)
-

DEAN&DELUCAの和菓子
友達にDEAN&DELUCAの包みをもらいました。こちらから差し上げた、ちょっとした贈り物のお返し・・・ということで。クッキーかチョコレートかな?と思いつつ開けてみましたら、箱の中に入っていたのは「DEAN&DELUCA WAGASHI」と書かれたリーフレット。いただいたお品の中身は、金沢の村上さんの干菓子と、諸江屋さんの葛湯でした。さすがは、食の高級セレクトショップ!中でも、このセレクションに、友人のセンスの良さを感じた次第です。いそいそと、抹茶を点てる用意をしたくなりました。【「わり氷」。一見キャンディのような、カラフルなお菓子】※舌の上で、表面を覆った砂糖の固まりが溶けると、やわらかい寒天が表れます※【花咲か爺さんの絵柄が楽しい、マッチ箱サイズの「オトギクヅユ」】※袋の中にはお餅の入った葛粉が入っていて、熱湯を注げば葛湯の出来上がり※昨日はホワイトデーでした。唯一チョコレートを送った夫が、お返しに買ってくれたのがこちら。伊藤久右衛門さんのつぶつぶ苺抹茶ロールケーキです。ついに夫も、楽天のお取り寄せスイーツにはまる日が来たかも??(笑)苺たっぷりで、程よい甘さがちょうど良く、とっても美味しかったです。ブランチ代わりに危うく、二人で一気に完食するところでした・・・◎Shop info◎DEAN&DELUCA
2008.03.15
コメント(6)
-

“ちりとてちん”の着物
春は出会いと別れの季節。しかし、あと半月で、夫婦で熱中しているNHKドラマ「ちりとてちん」が終わってしまうというのは何とも寂しくて、発売が決まった完全版 DVD-BOXの購入を真剣に検討しています(苦笑)。東京周辺に住む友人・知人の間でも、このドラマは大好評で、「地獄八景亡者戯」をはじめ、上方落語のCDやDVDを買い漁る人まで出てきました。皆で、にわか磯七さん気取りで、米朝が、枝雀が・・・なんて話題で盛り上がっています。他愛無いのぉ~、フフフ。草原兄さん役の桂吉弥さんの高座は、チケットが争奪戦ですごいことになっているようだし、気のせいかNHKをはじめ、落語をテレビで見られる機会も増えてきたような・・・ここ数年じわじわと盛り上がっていた落語ブームに、本格的に火がついたというか、世間が落語を“見つけた”という感じですね。このドラマの素晴らしさは、まずはキャラクター設定を含めて練り上げられた脚本にあると思うのですが、他にも適材適所の俳優陣、凝りまくった小道具など見所は尽きません。そして、私にとっては、女流落語家である主人公・徒然亭若狭の着物姿を見るのも大きな楽しみ。主演の貫地谷しほりさんが、とても和服の似合う女の子だということもあるし、とにかく毎回(誰がコーディネートしてるのだろう??)と知りたくなるほど素敵なのです。 若狭の祖母は元芸者という設定で、この写真で主人公が着ているのは、その小梅おばあちゃんから譲られたもの。アップになると、万筋の小紋のようにみえます。着物も若々しくてかわいらしいけれど、組み合わせている河童の刺繍の帯やレモンイエローの帯揚げがまた、上級者のコーディネートという感じで、いいのですよね~。粋筋の人が着ていた、というニュアンスが伝わってきます。ドラマの中では、主人公が年齢を重ねるにつれて、高座で着る着物も変化しているのですが、どれも素敵で、思わず画面に目を近づけて隅々を見たくなってしまい。先日も、「ちりとてちんの落語をきこう」というNHKの特番で、貫地谷さんがドラマの衣装でインタビューに答えていました。ちょっと老けづくりのようなメークだったので、恐らくこれから登場するシーンの撮影中だったと思うのですが、玉子色のやさしい柄の小紋で、ああ、今の私の年代で着たい・・・と憧れてしまいました。ただでさえ、サントラを買ったりノベライズやガイド本を買ったり、あれこれ「ちりとて散財」をしているのに(蜩紋のTシャツだってほしい)、最近の私は楽天市場にアクセスするたび、「ゆかた屋さん」の江戸小紋の商品ページをチェックしてため息をついています(笑)。ああ、いっそ小次郎おじちゃんのように、宝くじを買いに行こうかなぁ・・・江戸小紋・名古屋帯、帯締め・帯揚げが揃います!【着物と帯のお仕立て代込み】きちんと着物はじめ【この公式ホームページともあと2ケ月でお別れです。哀しい・・・(涙)】http://www3.nhk.or.jp/asadora/関連ブログはこちら
2008.03.13
コメント(8)
-

「ペルセポリス」を観た。
小学生の頃、ニュースで見たイランのイスラム革命。私は、ゲジゲジ眉毛のホメイニ師の顔がとにかく怖くて、直感的に(この人は悪い人に違いない)と、革命の背景も知らずに思い込んだものでした。その後のイラン・イラク戦争については、新聞の「イラ・イラ戦争」という見出しが何だか冗談みたいだったと、そんなおぼろげな記憶があるだけ。一応、今のイランの大統領の名前は言えるし、キアロスタミの映画は大好きだけれど、じゃあイランという国について何を知っているのか?と問われたら・・・バブル期に上野あたりに群れていた出稼ぎのイラン人とか、ダエイとかマハダビキアとかアジジとか(←サッカー選手です)、わりと最近ではダルビッシュ君??そんな断片的なイメージしか、思い浮かびません。この作品は、イラン出身で現在はフランス在住のマルジャン・サトラピ女史が、自らの幼少期から、15年以上にわたる前半生を描いたアニメ映画。こちらの、自伝的グラフィックノベルが原作となっています。 ※楽天ブックスの商品紹介で、数ページ中身が紹介されています※これ以上簡略化できないというくらい、シンプルな線で描かれる人物の表情。それが、繊細な感情をとてもヴィヴィッドに伝えてくることに、冒頭から驚かされました。アニメーションを映画館で観るのは、「ハウルの動く城」以来か?という感じでしたが、本当に、この表現方法でなければ出来ないことがあるんだ、ということを実感しました。1978年の反王制勢力による革命、長期にわたって続いたイラン・イラク戦争の影響。急激に自由が奪われ、「言いたいことの言えない社会」が作りあげられていく過程がテンポ良く描かれて、すうっと少女マルジの日常に入り込み、彼女の喜怒哀楽に同調してしまいました。アイアン・メイデンを大音量で聞き、ブルース・リーに夢中になり、おばあちゃんと一緒に映画館で「ゴジラ」を観る・・・そんな女の子の日常が、親しい人々の投獄や処刑、言論統制や空襲と隣り合わせになっている。マルジが成長していく過程で、周囲の年長者たちが与える、深みのある言葉の数々がとても印象的です。中でも、主人公に最も大きな影響力を持っていたのはおばあさんなのですが、自由と安全を求めて国外留学をするマルジに言う「これから、お前の人生にたくさんの試練が待ってる。でも、バカなやつらに傷つけられても相手が愚かだと思えばいい。そうすれば仕返しをせずに済む」・・・このセリフには本当に、色々なことを考えさせられてしまって・・・胸にズーンと響きました。神経をすり減らす厳しい日常の中でも、楽しみを追わずにいられない“名もなき庶民のたくましさ”も、随所にユーモアを交えて描かれています。これが、悪の枢軸、と超大国に名指しされた国家の下、現実に生きている人々の姿なのだと思うと・・・マルジの人生に絡みつくイランの現代史。その出来事を追いつつ、あぁ、ニュースを追っていれば世界がわかるなんてことは、ないんだな。必要なのは、ニュース映像のさらに奥へ、裏へ、想像力をふくらませる力なんだ・・・ということ、改めて思い知らされました。映画は、オルリー空港でテヘラン行きの便の掲示を見上げる、大人になったマルジャンの姿から始まります。豊かな黒髪を、周囲の好奇の目にさらされながらヴェールで包み、“イスラムの女”となって、待合室のソファに座る彼女。ラストシーン、再び場面はオルリー空港に移り、そこで主人公のとった行動は切なく、エトランゼの悲哀を感じずにはいられません。ちなみに原作・監督のマルジャンは1969生、私と同年の生まれでした。それを知ったとき、何とも言えない苦さが私の胸のうちに広がり、生まれ合わせた歴史に翻弄されずにはいられない人間の運命を思ったのです。【「ペルセポリス」公式サイトはこちら。】 http://persepolis-movie.jp/この映画、アニメなので当然声優が演じるのですが、これがマルジャンとその母をキアラ・マストロヤンニとカトリーヌ・ドヌーヴの親子競演、という豪華ラインナップ!しかも、おばあちゃん役の声優はダニエル・ダリュー、「ロシュフォールの恋人たち」や「八人の女たち」でドヌーヴの母を演じたあの女優さんです。フランス語はわからないけど、でも三者三様、すばらしかったです。映画を観る事で世界を広げたい、そんな思いを抱いている方には超絶オススメの一本です。
2008.03.10
コメント(4)
-

欲望を解き放つ日
・・・一見、近頃横行している迷惑コメントのようなタイトルになってしまいましたが、要するにケーキバイキングに行って食べまくってきました、という話です。【この光景を見ると、まるで自分がアントワネット様になった気分・・・】 【こんな感じで、何枚プレートをお代りしたかは内緒です】食べることが何より好き!と、グルメ情報に精通している友人からお誘いを受けて出かけてきました。友人と私たち夫婦の4人でテーブルを囲み、「これ美味しいよ」「じゃあ次、挑戦する!」とワイワイ楽しいひと時でした。こういう時にちまちまとカロリー計算したり、ガマンをするのは野暮というもの。でも、苦しくなって味の記憶が台無しになってしまっては元も子もないので、美味しくいただけるギリギリのところで自制いたしました(笑)※今回、ドライブがてら出かけてきたのはこちらのホテルです。プライムリゾート賢島こちらは、神戸・北野ホテルの山口支配人がレストランのプロデュースをしていて、以前に宿泊した時のお食事も、とても満足のいく内容でした。今回いただいたスイーツ類も、神戸のイグレックプリュスの美味しさに通じるものがあり、堪能いたしました!(明日からはしばらく、粗食で過ごすことを誓います・・・)
2008.03.09
コメント(2)
-

「カラマーゾフの兄弟」を読んだ。
ある日、夫宛に某ネット書店から大きな包みが届きました。帰宅した彼がダンボールの中から取り出したのはなんと、光文社古典新訳文庫の「カラマーゾフの兄弟」全5巻。読みやすくなったと評判の新訳で、古典作品には珍しいほどのベストセラーになった、話題の書でした。巷の「カラマーゾフ」ブームは広がりを見せ、’69年作のソ連映画まで、DVDがよく売れているのだとか・・・パラパラと手にとってみると、なるほど平易な文章だし、5巻すべてに訳者の亀山郁夫氏による「読書ガイド」が付され、挟まれた栞にも登場人物一覧が印刷されているという“親切ぶり”。それぞれの本に巻かれた帯のコピーも、読む気を煽る言葉が並んでいて、世間の評判につられて本を注文した夫より先に、つい読み始めてしまったのです。そして、勢い止まらず一気に読破してしまいました。「何よりもわたしは、グローバル化と呼ばれる時代に、最後まで一気に読みきることのできる『カラマーゾフの兄弟』の翻訳をめざしたかった。勢いが、はずみがつけば、どんなに長くても読み通すことができる、そんな確信があった」これは、訳者あとがきに書かれた一文ですが、まさにその通りで、第一巻の冒頭から、登場人物それぞれの“キャラクター”の濃さにぐいぐいと引き込まれました。誰も彼も、強烈に際立つ個性を持っていて、みんな痛々しいほどバランスが悪い。それゆえに、誰もが大いなる葛藤を飼いながら生きている。ミーチャ、イワン、アリョーシャの三兄弟とその父フョードル。カラマーゾフの一族はもちろん、脇役の一人ひとりに至るまで、存在そのものがドラマチックなのですから、その彼ら、彼女らが絡まりあう人間関係が、面白くならない訳がない、という感じでした。長い小説の中で、“出来事”が“人の心”に及ぼす作用、そして、“人の心”によって生み出される“出来事”・・・この、ニワトリと卵の連鎖が形づくる“人生”というものの重みを、深く考えさせられる瞬間が何度もありました。本の世界へ踏み込む上で、キリスト教、中でもロシア正教の宗教観についての理解は基礎知識として必要だと思われます。また、私が特に新鮮に感じたのは、ドストエフスキーがこの小説に込めた“ロシアの大地”への思いの強さでした。子どもの頃に覚えた世界地図のおかげか、私の中では未だに「ロシア=ソ連」というイメージが拭いきれません。ドストエフスキーが生きた時代の「ロシア」を、しっかりと掴み直さなければ、彼の小説の魅力を捉えきれないのだな、と実感しました。ただ、この2点については、巻末の読書ガイドや、第5巻の付録である訳者の解題を読むことで、読者に濃密な情報提供がされています。そういう点でも、かゆいところに手が届く仕事がされているのでした。大まかなあらすじは知識として知っていましたが、それでもなお兄弟の「父殺し」とその顛末は、ミステリーとして十分に読み応えがあります。犯人探しの顛末はもちろん、後半の法廷劇も、そのストンと幕を下ろす結末にいたるまで、本当に面白かった!でも最大のミステリーは、人殺しという出来事そのものよりも、やはり人間という存在の、それぞれの心の内側にあるのだなぁと思い知らされる。ドストエフスキーの、圧倒的な作家としての力量が、この歳になってやっと理解できたような気がしました。美しい描写と言葉に満ちたエピローグ。アリョーシャが叫ぶ、「そう、かわいい子どもたち、かわいい友人たち、どうか人生を恐れないで!なにか良いことや、正しいことをしたとき、人生ってほんとうにすばらしいって、思えるんです!」という感激に満ちた言葉を読む頃には、思わず目頭が熱くなっていたのでした。この大部の小説は、解説によれば本来は二部作として構想されたものの第一部で、ドストエフスキーは自叙伝の要素もあるこの小説を未完のまま遺したのだそうです。でも、兄弟たちの物語の続きが書かれなかったことは、今となっては、読者の感銘をより深くしているようにも思えます。繰り返し読む度に新たな発見があることと思われ、「名作、恐るべし」と唸らされたのでありました。(でも、当の夫は一向に手に取る気配がないのですが・・・)
2008.03.07
コメント(6)
-

「それでもボクはやってない」を観た。
基本的に映画は映画館で観たい、と思う。たとえそれが叶わなくても「ノーカット、字幕、CMなし」で観たいので、私は民放各局の映画番組はチェックしません。だから、ずっと見逃していたこの映画が「地上波初登場!!」と、新聞のテレビ欄に載っているのを読んでも、最初は迷っていたのです。ところが、最初の5分を観たらもう、テレビを切ることはおろか、チャンネルを変えることすら出来ませんでした。観ていて切なく、苦しいのに、途中では止められない映画。そう、この作品は観ていて“おもしろい”のですね。主人公のたどり着く先がどうなっていくのか、追わずにはいられないという点で。(以下、若干の“ネタバレ”を含みます)映画の冒頭、まったく身に覚えのない痴漢事件の犯人として捕らえられ、警察署で主人公(加瀬亮くん、すばらしい演技!)が取調を受けるシーンがあります。大森南朋演じる刑事が、「私は○○いたしました。私は××だったのです。」・・・と、主人公が言ってもいない言葉をスラスラと並べ立てて調書を作ろうとする場面が出てきます。実は、これとよく似たシチュエーションを、私は昨年体験しました。夜道で、背後からひったくり狙いの何者かに襲われるという経験をして、110番通報して警察署に行ったときのことです。つまり、私は映画とは逆に、事件の被害者として調書を作成したわけで、警察の方々はとてもやさしく、パニック状態の私をなだめ続けてくれました。こちらはもう、年甲斐もなく嗚咽が止まらない状態に陥っていて、言葉も途切れ途切れだったのですが、その時も女性の警察官が「私は○○へ出かけた帰り、××電車で午後5時30分に□□駅に着きました」「私はその時大変な恐怖を感じ、犯人の姿をしっかり見ることさえ出来なかったのです」「私は何も悪いことをしておらず、ただいつもの道を帰ろうとしていただけなのに、こんな思いをさせた犯人を許すことは出来ません」・・・と、それはもうスラスラと、ジグソーパズルのように私の断片的な言葉を美しい口語に編み上げてくれたのです。映画のシーンを観ていて、立場は真逆なのに「おんなじだ。あの時と同じだ」と、思いました。結局私の事件は、犯人も失ったものの行方もわかりませんが、当時の警察の方々の対応には、心から感謝をしています。でも、あのよどみなく調書が作成されていく手際が、毎日毎日、似た様な事件と向き合っている人ゆえの「手馴れた仕事ぶり」だったことが、冷静になった今はわかるのです。その「慣れ」は、物事に対する予断に通じ、手抜きに通じ、判断を鈍らせることに通じていくかもしれない。もちろん、仕事で経験を積んでいくということには、少なからずそういう側面が含まれるものだと思います。・・・でも、それが、人を人が裁く場で、絶対的な権力を持つ側の人々にはびこっているとしたら??そう考えて、背筋がゾーっと冷たくなるようなシチュエーションが、いくつもこの映画には出てきます。でも、だからこそこの映画の先が観たい。結末が知りたい。観る側をのめりこませ、テンポ良く1年間の物語を進めていく脚本・演出の妙に、すっかりハマりました。正直、「シコふんじゃった。」の、そして「Shall We ダンス?」の周防監督ですからね。判決前夜のシーン、私の思いは、もたいまさこ扮する主人公の母が発する一言のセリフと、まったく同じものだったのです、が・・・この物語の結末が描いたものは“絶望”ではありません。でも、映画の冒頭とラストシーンに、序文とエピローグのように映し出される短い文章は、映画を観終わった後も本当に重く、胸に残ります。神のような完全無欠の存在ではあり得ない・・・それが、人間の本質というものなら、人が人の罪を量り、裁くということはどういうことなのか?面白い映画を観たなぁーという満足感の中に、何か、真剣な宿題を突きつけられたような思いが残る、力のある映画でした。観てよかったです。ぜひ、DVDで完全ノーカット版を見直してみたいと思います。
2008.03.04
コメント(4)
-

私の“着物1枚、帯3枚”
昨年末に初めて袖を通した色無地の着物。よく考えたら、このところ「着物でお出かけ」といえばそれしか着ていない!という事実に気づきました。「着物一枚、帯三枚」とは、和装の着まわしの幅広い楽しみ方を示すものとして、よく耳にする言葉です。(地域によっては「着物三枚、帯一枚」というところもあるようですが、意味するニュアンスは同様では?)帯や、合わせる小物によって、TPOへの対応も目に映る印象もガラリと変えられる。それが、着物という衣裳の魅力の一つであることは確かです。私の場合は、手持ちの着物の選択肢が狭いゆえの「苦肉の策」でもありますが(笑)気づかぬうちに実践していた「帯三枚」の着まわし。自分の参考のためにも、それぞれの写真を並べてみようと思います。 画面左から、*金糸銀糸の入った綾織りの袋帯と金糸の帯締め*ピンク系の刺繍半襟と西陣の刺繍入り袋帯*芥子色の半襟にターコイズブルーの帯揚げ+黒地に刺繍の名古屋帯・・・と、それぞれコーディネートしました。(着付けのマズさはお目こぼしください!)(ちなみに、各々の着物を着た日のブログは下記のとおりです)初釜の着物色無地デビュー着付け教室 春の集いこの色無地、戸外と室内、また照明の当たり方によって、写真に映る色合いが本当に様々なのですが・・・見た目の印象は、ブルーよりもグレーの方にずっと近くて、中央の写真の色目が実物に一番近いです。懐具合や、収納場所のことを考えると、今後も次から次へと着物を増やしていくことは難しいと思います。だからこそ、センスとアイディアを活かして、着まわしの幅を広げながら賢く、おしゃれを楽しんでいきたいものです。物欲にはキリがないですけれど・・・それとの闘いもまた面白し、ですものね。とはいえ、こちらとかこちらとか、もう「ポチっと」したくなる誘惑を何日しりぞけていることか・・・(苦笑)※永らく更新しないままでいた、着物関連のフリーページを編集、着物の写真は増えてきたので別ページにまとめ直しました。よろしければご覧ください。
2008.03.02
コメント(4)
-

着付け教室 春の集い
3年前から着付けを教えていただいている先生は、ご自宅で教室を開いていらっしゃるので、同じ曜日のクラスでお稽古する人数は6人が限度。でも、せっかく志を同じにして着物について学んでいるのだから、いつもは顔を合わせない生徒さん同士も出会える場を設けたい、という先生のご意向で、毎年この季節に教室主催のパーティーが開かれます。今年も、近郊のホテルを会場に、80人以上の出席者を集めて着物の集いが開催されました。着物姿の人が一堂に会すると本当に華やかで、コーディネートや着姿を見ているだけでも勉強になります。(あの帯、素敵)(あの半襟、かわいい)(襟の抜き方、上手だなぁ・・・)なんて、気がつくと無遠慮なほどの視線を送っていて、我に返って慌てたり。ただ、今年は会場の受付や進行の手伝いを先生に頼まれていたため、今日は朝早くからとても忙しい一日でした。6時起きで着付けをして、2時間前から準備をして・・・楽しかったけど正直、くたびれました(笑)あまり写真を撮りあう余裕もなかったのですが、本日のコーディネート。初釜の時にも着た色無地に、黒地に刺繍の水玉模様が散った名古屋帯を合わせました。帯揚げと帯〆は、ずっと前にキモノ 仙臺屋さんで半襦袢を購入したとき、送料無料にしたいがために(!)何となく選んで買ったものです。やっと登場させられました。なお、半襟は、大好きなドラマ「ちりとてちん」の公式サイトで、主人公の若狭ちゃんが着ているものを見て(あ!似てるの持ってる!)と出してきたもの。数千円で買える小物類だと、ちょこちょこ散財してしまいますが、こんな風にコーディネートが完成すると、うれしくなってしまいます。 着物を着て外出するとき、私の場合着付けをがんばらなければいけないのはもちろんですが、ヘアスタイルをどうするか?というのも毎度、大問題です。以前、楽天のリトルムーンで購入した夜会巻きコームが、髪を切ってからうまく使えず困っていたのですが、別のお店でアージュコームを購入し、悩みが解決しました。ラインストーンがついたものは華やかな印象が強いので、ふだん着にも使えるシンプルなバージョンを入手。色々な方がブログでおすすめされているのを読みましたが、これ、本当に使いやすいんですね!今日は、蝶の形のヘアクリップをワンポイントであしらいました。写真に映りにくいのですが、色無地と帯、それぞれの地模様はこんな感じです。
2008.03.01
コメント(8)
全15件 (15件中 1-15件目)
1










