2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年05月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

「マリー・アントワネット」を観た。
お昼に、再放送で大河ドラマ「篤姫」を観ていました。大奥の寝所で、お殿様から子作りを拒絶される篤姫さまの苦悩ぶり…それがまだ記憶に新しかったので、WOWOWで放映されていたこの映画を観ながら、(東西で時代を超えて、お姫様は同じようなご苦労をされていたのねぇ…)と、ため息をついてしまいました(笑)アントワネットも篤姫も、合理性とかけ離れた宮中や大奥の儀式ばった風習には、驚きと戸惑いを禁じえない訳ですが。お世継ぎの誕生ということが、国家的プロジェクトだった時代。夫婦の睦みごとも公式行事のようなもので、そこには「個人としての尊厳」は存在しないも同然。(それほどまでしないと、血筋をつなげていくシステムは本来成り立たないのか…なんて、わが国でも現在進行形の“お世継ぎ問題”を思い、複雑な心境になりますが)ウィーンの宮殿からフランスの王太子妃として嫁ぎ、その結婚を「完全なもの」にし、世継ぎを産むことを至上命令とされた少女。その彼女が、思い通りにいかない夫との関係や、外国人ゆえに受ける偏見に傷つきながらも、期待に応えようと努力し、悩み、やがて心の隙間を、刹那的な贅沢で埋めていく姿。フランス革命という、歴史上の強烈なトピックをモチーフにしながら、この映画、完全にマリー・アントワネットの視点だけで描かれています。歴史の重層的な捉え方という点では、「ベルサイユのばら」の足元にも及ばない、という印象でした。監督のソフィア・コッポラには、歴史映画ではなく、あくまでも「ある女の子の成長物語」を描くという狙いがはっきりとあったのでしょう。宮中での日々は、絵巻物のようなゴージャス感をもって描写され“こりゃホントに「大奥・ブルボン朝バージョン」だわ”と、観ているこちらもノって楽しませていただきました。結末はわかっているのに、つい(がんばれ!)とエールを送ってしまったのは、それだけ、マリーのキャラクター造型に、観る側(特に女性)の共感を誘うものがあったからでしょう。女の子なら絶対こういうの好きよ、とか、女ならこれは辛いわ、とか、ジェンダーフリーの視点からは怒られちゃいそうな、そんなコメントが脳内にぐるぐるしました(笑)「心象風景のBGM」としての映画音楽、という意味では、仮面舞踏会や郊外を馬車が走るシーンに、ロックやポップスが流れるのも(確かに、こういうのもありか)と思いました。映像の一つひとつは本当に、キレイ、カワイイ、カラフルの“3K”で素晴らしいし。Various Artist『マリー・アントワネット』(サントラ)それはいいとして、マリーがやっと王女を出産し、プチ・トリアノンで自然に囲まれ“ほっこりさん”の子育てライフを謳歌しはじめるあたりから、突然、物語のテンポとバランスが崩れ始めたのは、ちょっと残念…そう思ったのは、私だけでしょうか?手に取るように伝わってきた彼女の心境が、突然見えなくなってしまった感じがしたのです。どうせなら、尺が3時間になったとしても、もっとマリーの晩年の日々にもフォーカスしてほしかったと…(あと「ベルばら」ファンとしては、フェルゼンのあのキャラクターとキャスティングは、ちょっと受け入れ難いものがありました)オープニングでちらりと出てくる彼女(冒頭の写真のシーン)が、傍らのケーキのクリームを指でひょいと掬って舐めるように、時代の、歴史の、苦味や渋味をあえて無視して、甘い表面を掬い取って作ったような映画。マリー・アントワネットとはいえ、ラストシーンの頃には、私はすっかり映画の中のマリーが好きになっていましたから、観客としては見事に、監督の術中にはまったのかもしれませんね。
2008.05.31
コメント(2)
-

そら豆のスープ
お茶のお稽古に行ったら、そら豆の形を模した、かわいいお菓子を出していただきました。薄緑色のお饅頭の皮には、焼きごてでつけたのでしょうか?そら豆独特の、あの黒い筋もちゃんとついていて、口に入れてしまうのがもったいない、と思ってしまうほど。そもそもわが家は、夫婦そろってそら豆が大好き。出回る季節になると、野菜売り場を通りかかるたびに買わずにいられません(笑)料理法は特に手間をかけず、さやごとグリルで焼いて、ホクホクのところを食べたり タコと一緒にオリーブオイルでさっと炒めて、イタリアン風の一皿にしたり… でも、たまには気分を変えてみようと、今日はbamixの料理本(バーミックス 基本のクッキング)のレシピを参考に、グリンピースをそら豆に変えてアレンジし、ポタージュ風のスープを作りました。 材料: そら豆 (サヤから出し、軽く下茹でして薄皮もむく) 玉ねぎ 1/2 コンソメスープの素、塩、こしょう、EXバージンオリーブオイル<レシピ>薄切りにした玉ねぎを鍋で7~8分炒め、透明になったらそら豆を加えて、ひたひたの水とコンソメスープの素を入れて煮る。豆がやわらかくなったらバーミックス(ブレンダー、ミキサーでも)で混ぜてポタージュ状にし、塩こしょうで味を調える。いただくときに、オリーブオイル少々をたらす。豆の香りと、オリーブオイルの風味がぴったり合って、我ながら美味しく出来ました。きぬさやにグリンピースにスナップえんどう…緑の豆類が豊富に出回っているこの時期。そういえば、豆をさやから出したり、えんどうの筋を取ったりするのって、子どもの頃最初に覚えた料理のお手伝いだった気がします。どこかノスタルジックな気分になるのは、そのせいでしょうか?
2008.05.29
コメント(8)
-

ローズガーデン
家庭や自分のことで何かと忙しく、次から次へと細かい用事をこなしているうちに一週間が終わり、週末がやって来るという今日この頃。(ブログの更新も滞りがちで、コメントのお返事が遅れたり、おなじみの方々のブログも“読み逃げ”でコメントを残せない状態が続いております。この場を借りて失礼をお詫びいたします!)休日にはあれもしよう、これもしようと思っているのに、いざ週末がやってくると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。忙しくしていることは、余計なことを考えないで済む分、気が楽…と、そんな風にずっと思って来ました。でも、寄る年波のせい?(笑)“くたびれる”ということの重荷がずっしりとのしかかるのが実感されるようにも思うのです。体はホッと一息つけても、心の疲れは解消できないまま、澱のように溜まっていくような…そんな時、自然の姿かたちの美しさというものは、本当にホッと、一息つかせてくれるパワーを与えてくれるものだと思いました。家の近くにある公園の一角に、数種の薔薇を植えた花壇があって、今がまさに見ごろです。あいにくのお天気で、花びらはしっとりと雨露に濡れていましたが、それもまた何ともいえず綺麗で。傘を差しながらの鑑賞となりましたが、ついついじっと足を止めずにはいられないほど。あたりに漂う甘い香りも楽しめて、心をほどいてくれたひとときでした。そういえば、十年ほども前のこと、当時の同僚がモロッコへ旅したお土産といって、ローズウォーターのボトルをくれたことがありました。モロッコといえばダマスクローズが有名ですが、素朴なボトルに入ったローズウォーターはさすがに、素晴らしい香りでした。薔薇の咲き誇るシーズン、お風呂上りにパシャパシャと、甘い香りに包まれるゴージャスな体験もまた、いいかも…と、思い出した次第です。朝摘みばら水
2008.05.26
コメント(6)
-

カレー日和!
「五月晴れ」という表現では収まりきらないほどの、日差しが強く照りつける日が続いています。ついこの間まで、朝晩は肌寒いような陽気だったのに…と、移り変わる季節の速さに驚きながら、買い物に行って帰ってきただけでもう、汗だく。こういう暑い日に食べたくなるメニュー、冷やし中華やざるうどんなど数々ありますが…寝不足でちょっとたるんでいる(理由は、UEFAチャンピオンズリーグの決勝戦を生中継で観るため3時半起きしたから・笑)自分に喝を入れるため、インド風の、スパイシーなカレーを作ることに決定!【発芽玄米を加えたご飯と一緒にいただきます。】クミンシードをたっぷりのオリーブオイルで炒めて香りを出し、みじん切りの玉ねぎをじっくり炒めているだけで、もう美味しそうな香りがキッチン中に漂い、食欲が増してきます。鶏肉とカットトマトの缶詰を加え、水とガラムマサラ、ペパーミントを入れて、30分ほど煮込めば、本格的なチキンカレーの出来上がり。…と、さも料理自慢のように書いておりますが、実はレシピもそれぞれのスパイスも、この「無印良品」のキットに入っているものなのでした!スミマセン…(汗)暑い日の料理はスピーディに仕上げるのが一番なのですよね。なんて、言い訳がましい??
2008.05.22
コメント(10)
-
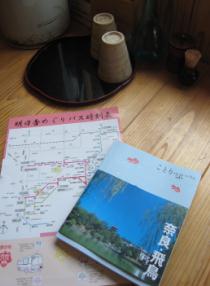
ことりっぷ
週末に奈良まで出かけた際、「ことりっぷ」というガイドブックを携えていきました。この頃、大きな書店の旅行ガイドの売り場に、平積みのコーナーが作られているのをよく目にするこのシリーズ。和風のイラストで色違いの表紙がずらっと並んでいるところが、何ともキュートで、旅の予定がなくても、何だかパラパラと立ち読みしたくなってしまいます。文字どおり、週末に出かける「小さな旅」のためのガイド、というコンセプト。あらゆる観光情報が網羅されているわけではないけれど、コンパクトにまとめられた誌面は見やすいし、バッグに入れて重くならない手ごろな大きさ、薄さが何といってもうれしい。そうそう、ちょっとしたお出かけならこれで十分なのよねぇ…という「ちょうど良さ加減」が気に入っています。タイトルにちなんだ小鳥のイラストが随所にあしらわれていたり、その土地固有の歴史や文化についてのひとくちメモが添えられていたり、読み物としても楽しめるのがうれしいところで、これからも色々なところへ出かけたいと、旅情を誘われています。私は、旅が終わっても、記憶が詰まったガイドブックを捨てられない性質なので、本棚に並べても美しいこのシリーズの登場は、とてもうれしいのでした。
2008.05.21
コメント(2)
-

キトラを見たら ~明日香村への旅
奈良へ、日帰りのドライブ旅行をして来ました。目的は、明日香村にある「飛鳥資料館」で開催中の、キトラ古墳壁画の特別公開を見学することです。…その前に、飛鳥時代の文化に触れるべく、資料館近くの石舞台古墳に立ち寄ることに。【古墳のそばにある“明日香の夢市茶屋”にて、古代米御膳のランチ】※葛豆腐や、地元産のお野菜をたっぷり使った素朴なおかずも美味しかった!※石舞台古墳は、蘇我馬子の墓という説が有力なのだそうです。日本史が大好きだったという夫は、飛鳥時代の年表を脳裏に広げて目をキラキラさせ、その横で私は、漫画「日出処の天子」の馬子登場シーンの数々を思い浮かべておりました…【元々は土に覆われた墳墓でした。39個もの巨石が積み上がっているとはビックリ】【石室の中にも入って見学することが出来ます。中はひんやり涼しかったです】この日はちょうど、隣接する公園で子ども用のイベントが行われていて、ミニSLは走るわはしご車体験コーナーはあるわピエロはいるわ…と、大変にぎやかでした。正直、古代のロマンに浸るにはちょっとキビシイ雰囲気だったのですが(笑)そもそも、明日香村全体がお祭り騒ぎのような大賑わい。その原因は、やはり17日間の限定で公開されるキトラ古墳壁画にあったようで、会期中に様々な催しが企画されていたようです。古墳から壁画が取り外されて以来、今年が3回目の一般公開。今回は、石室の四方の壁に描かれていた、獣頭人身の「十二支」のうち、子・丑・寅の3点が公開されました。会場の資料館に着いた私たちを待っていたのは、「ただいま175分待ち」という目を疑うような表示。(早い時間に来れば整理券の配布があったのを知らなかったのです…失敗!)資料館の中には数十分で入れたのですが、後は行列に並んで、内部の展示をゆーーーーーっくり見学しながら、ひたすら壁画の展示室にたどり着くのを待つ、というシステム。まぁ実際には、2時間ちょっとで壁画と対面出来ましたし、飛鳥文化やキトラ古墳についての予習がお腹いっぱい出来たことはよかったです。【見学を終えて外に出たら、もう日が暮れて月が昇っていました。】壁画そのものは本当に小さなものなのですが、1300年もの時を越えて、様々な経緯を経て、こうしてガラス1枚隔てた近さで対面することが出来たのだ、と思うと興奮しました。会場内では、壁画が古墳から外される瞬間の様子が、VTRで流れていました。不勉強な私は、壁そのものをバーナーか何かで切り取ったのかと思っていたのですが、そうではなくて、壁面から絵の描かれた漆喰の部分だけを剥ぎ取っているのですね(そりゃそうか、石室そのものが貴重な文化遺産なわけで…恥!)。防護服に身を包んだ作業員の人々。手袋の先からのぞいた指が華奢で、あれ?と思ってよく見たら、ほとんどが女性でした。高松塚古墳もそうですが、壁画の取り外しに至った事態には、批判的な意見も数多くあることと思います。が、実際にこの「絶対に失敗できない」プロジェクトに取り組んだ、現場の人たちの緊張や重責を思うと、賛否を超えたところで素直に(ご苦労さまでした)と頭を下げたい気持ちになります…短い時間でしたが、聖徳太子が生き、渡来の文化を吸収しながらこの国の基盤が作られていった時代の息吹に触れ、美しい緑もたくさん目にして、心身ともにリフレッシュ出来ました。この島国の歴史は本当に長いから、私などつい簡単に口にしてしまう「日本の伝統」とか「和の心」なんてものも、掘り下げてみればいくつもの源流があって、一筋縄では捕らえきれない深さがあるのだなぁ、ということも、考えさせられました。こんな歳になってから、あぁ、もっともっと勉強しなきゃなぁ…と痛感している自分が、ちょっと滑稽にも思えますが、いくつになっても「気づき」に遅すぎることはない、と信じたいものです。久々に、修学旅行気分を味わった小さなお出かけでした。壁画公開は25日(日)までとのことです。※おまけ※【お隣の天理市まで足を伸ばし、夕食は“彩華ラーメン”で。】お友達に教えてもらったラーメン屋さん。関西圏には多く支店が出ているそうですが、「天理ラーメン」なるジャンルがあるのを私は知りませんでした。醤油ベースでにんにくたっぷり、シャキシャキの白菜が美味しく、駐車場に県外ナンバーの車がズラリと並ぶのも納得、のお味でした。また食べたいな。
2008.05.18
コメント(12)
-

「いつか眠りにつく前に」を観た。
「人生の最期を迎えたとき、誰の名前を呼びますか?」死の床にある老いた女性。薄れていく意識の中で、過去の恋の思い出が、抑えようもなく立ち上ってくる…実際には巻き戻すことが許されない時間を、彼女の魂は自由に行き来します。過去と現在を、現実と幻想を、蝶のように軽やかに往還する。体はベッドに横たわったままでも。ある事情で封印せざるを得なかった、若き日の恋の顛末が、美しく丹念に描かれるのですが、私は、時折差し挟まれる、この女性の“その後の人生”の断片、その短い描写の方に、胸を揺さぶられました。日々を生きていくための悪戦苦闘。様々な瞬間に、彼女の心の奥底で沸いていたに違いない(あの時、あの恋を貫いていれば)という思い。しかし、現実には、そうはならなかった。そうすることは出来なかった。【原題は「EVENING」。冒頭とラストの黄昏の海辺は本当にきれい】自らの歩いてきた道を、最後に彼女がどのような思いでふり返るか。それは、これから映画をご覧になる方のために伏せますが、その結論は、彼女の娘たちの物語とあいまって、静かな感動の余韻となって私の心を満たしました。ひとつの人生が放った確かな輝きが、打ち寄せる波のように胸に迫ってくる作品だと思います。生きていくことは、思い通りにいかないことの連続。それでもやっぱり、すばらしいことなのだと思わせてくれる。そういう映画に出会った時は、本当にうれしくなります。トニ・コレットの出る映画にハズレなし、という、私の持論をまた一つ、裏付けてくれた映画でもありました。メリル・ストリープの若い頃を実の娘(メイミー・ガマー)が演じ、その母をグレン・クローズが演じるという、「顔面相似形」の配役の妙を楽しめる側面も(笑)いつか眠りにつく前に
2008.05.14
コメント(2)
-

茶の道は侘び?
ゴールデンウィークの終わり頃の話で、もう一週間前のことなのですが、近郊のお祭りに合わせて開催されたお茶会に出かけてきました。日差しは初夏を思わせるような、快晴のイベント日和。会場となる公園の一角に、古くから伝わる木造の建物があり、今は休憩所となっています。その中の和室を使って、大寄せの茶会が行われていたのでした。200円のお茶券で、観光客の方も気軽に参加できる席でしたが、きちんと着物をお召しになっていらしたお客様もちらほら。もちろん、係の方々は言うまでもなく…暑さに負けて、夫ともども“平服”で行ってしまった私は、まだまだ精進が足りないわ~と思い知らされました(笑)お茶碗は菖蒲の柄が描かれたものが多く使われていて、お菓子は青い楓の形の練り切り、さわやかな風味の甘さで、とっても美味しかったです。まさに「目に青葉」…の季節を味わいながら過ごす、ひとときとなりました。【竹筒に挿してある花は“夏臘梅(なつろうばい)”とのこと】【今月からお点前は風炉に。これは“蛤卓”?水指はぼんぼりの形】正客となられた方が、亭主とのやり取りの中で、本当に感慨深げにおっしゃっていた「客にならせていただくことは本当に幸せなことです、ひたすらもてなしていただくことを楽しんでいればいいのですから」という感謝の言葉が、とても印象的でした。立場が変われば、お客様を迎えるためにどれほどの準備や労力が必要か。それを十分に理解されているからこそ、出てくる思いなのだと思います。「侘び」とか「寂び」とか、そんな言葉の意味のかけらもつかめていない私ですが、未熟ながら茶道の世界の端っこを覗いてみて、つくづく思わされること。それは「行間を読む」能力を育てなければ、堪能できない世界がここにあるんだなぁ、ということです。小さなヒントをつなぎ合わせたり、ふくらませたりして、大きな世界を描き出していく…たった十七文字で様々な思いや風景を描写する、俳句の世界にも通じるものがあるかもしれません。この、“推して知るべし”が前提となった、「余白」を良しとする私たちの民族性は、欧米の価値観が基本となったグローバリゼーションの時代には、ともすれば悪しきもの、競争の邪魔になるものとみなされてきました。が、それもよく考えたらもったいない話だなぁ、とボンヤリ考えている、この頃の私なのです。【そんなわけで、今読んでいる本。司馬遼太郎×ドナルド・キーンの対談です】日本人と日本文化
2008.05.12
コメント(8)
-

「みそか寄席」を聴きに
ゴールデンウィークの真ん中、4月30日に、伊勢神宮のお膝元まで出かけてきました。でも、この日の目的は参拝ではなく、落語を聴くことでした。【到着後、五十鈴川を見下ろす“五十鈴茶屋”にてティーブレイク。】~きれいな紫のきんとんは、穀雨の節気菓子の一つ“藤浪”です~古い町並みを再現した「おはらい町」は、赤福の本店を含め観光名所として知られています。その中の、“すし久”という料理屋さんの広間を使って、一月に一度行われる「みそか寄席」を聴きに行ってきました。【提灯の灯りって風情がありますね。“すし久”の店先で記念写真】 【開演前に、別室の座敷でお菓子をいただくことも出来ます(また食べてる!)】 ~こちらで出るお菓子も“五十鈴茶屋”の節気菓子。名前は“神馬”~「みそか寄席」は二部制の公演で、あらかじめポスター等で、翌月の出し物が告知されます。この日、私たちは、21時過ぎから行われる第二部に行きました。ドラマ“ちりとてちん”で取上げられていた“はてなの茶碗”がかかる予定だったからです。3名の落語家さんが出演され、前座の桂しん吉さんが「桃太郎」、桂米平さんが「はてなの茶碗」。トリを務める桂文我さんは、最近ではあまりかからなくなった古い噺です、という前置きで「網船」(あみぶね)という噺をかけられました。私にとってのメインイベントだった「はてなの茶碗」、演じる米平さんは、米朝さんのお弟子さんです。へえ~と思ったのは、噺そのものだけではなく、マクラの部分まで、以前NHKで見た米朝さんの高座と同じだったこと。師匠の芸を受け継ぐ、って、こういうことなんですね。あれ?どこかでこんな話聴いたな~、と思いつつ笑ってしまいましたが。お三方とも、一部がよほど盛り上がったのか、ちょっとお疲れ気味かも?という雰囲気もあったのですが、やっぱり目の前で熱演してくれる落語というのは、伝わってくるものが違いますね。茶道で「一期一会」という心得をよく耳にしますが、落語家さんと観客の、寄席での出会いもまさに「同じ時は二度とない」ものなのだと思います。これからも、寄席のライブ感を色々な場所で体験したいと思ったのでした。・・・さてこの日は、“着物で寄席見物”という、ン年越し?の夢を実現させることが出来ました。 初夏のような陽気で暑かったこともあり、着物の下は身頃がさらしで出来た半襦袢。半幅帯に足元は下駄、と、カジュアルなコーディネートにしてみました。帯は、以前のブログで書いた、江戸小紋を購入した同じ時にお店の片隅で見つけた博多織のもの。在庫セールということで、14,000円の値札が4,980円になっておりました♪博多織の軽やかな締めやすさ、これから重宝しそうです。座布団に座りっぱなし(休憩なし)の2時間弱、大丈夫かな?と思いましたが、こまめに座り直したせいか、皺がクッキリ・・・ということもありませんでした。(以前はお茶会で、立ち上がった瞬間着物の裾が皺だらけ、ということもあったのです)しびれも防止できたし、一石二鳥だったかも(笑)?
2008.05.07
コメント(12)
全9件 (9件中 1-9件目)
1










