2019年11月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
11月30日(土)…
11月30日(土)、晴れです。本日も良い天気です。7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。リーガロイヤルのチョコレートと共に。美味い!!10時頃に支援戦闘機にスタッドレスタイヤを積み込んでBS系のタイヤショップへ。各地で道路工事(水道管の取り替え)をしています。先客1名で2番目でした。スタッフ曰く…このスタッドレス、今シーズン限りですよ…!帰宅すると居間にホットカーペットが敷かれて、ロマネちゃんが潜り込んで大喜びです。1USドル=109.51円。1AUドル=74.07円。昨夜のNYダウ終値=28051.41(-112.59)ドル。円安・株安ですね…。(ブルームバーグ)【NY外為】ドル指数、月間ベースで7月以来の大幅上昇 29日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が月間ベースで7月以来の大幅上昇。12月入りを目前に、米中の貿易合意について情報がもっと明らかになるとの期待が広がっている。ポンドはこの日の取引で上昇。ロンドンでテロ事件が起きた。市場の関心は来月の総選挙に向けられている。 ブルームバーグ・ドル指数は0.1%未満の下げ。朝方には0.1%上昇し、10月11日以来の高水準となっていた。11月全体では過去4カ月で最大の1.1%上昇となる見通し 米国は12月15日に中国製品への追加関税を発動する予定。トランプ大統領が香港人権法案に署名したことを受け、中国外務省は報復措置を警告したが、具体的な措置は明らかにしていない 主要10通貨のうち、上昇率が最も大きいのはポンド。一方で大きく下げたのはノルウェー・クローネ ポンドは1ポンド=1.29ドル前後で堅調。来月の総選挙に関連したリスクが引き続き警戒されている ニューヨーク時間午後4時30分頃、ドルは対円で0.1%未満安い1ドル=109円46銭。一時は5月30日以来の高値となる109円67銭を付けた。月間では9月以降最大の1.3%上昇 28日安値の109円33銭が支持線 ユーロは対ドルで0.1%高い1.1018ドル。一時は0.3%下げて10月10日以来の安値、1.0981ドルを付けた。週間ではほぼ変わらず。月間では7月以降最大の1.2%安 11月のレンジは1999年以降で2番目に狭い。最も狭かったのは2011年5月だとソシエテジェネラルのキット・ジャックス氏がリポートで指摘 ポンドは対ドルで0.2%上昇の1.2938ドル。週間では0.8%の値上がり。2週間のインプライド・ボラティリティーがこの日急伸。12月12日の総選挙が期間内に入った【米国株・国債・商品】株が過去最高値から下落、原油は大幅続落 29日の米株式相場は反落。欧州とアジアの株式が下げた流れを引き継ぎ、米主要株価指数は過去最高値を離れた。月間ベースではS&P500種株価指数が3カ月連続の上昇となった。米国債は高安まちまち。 米国株は反落、エネルギーや一般消費財の下げ目立つ 米国債はまちまち、10年債利回りは1.78%に上昇 NY原油は大幅続落、産油国から減産拡大に否定的姿勢 NY金先物は反発、月間では3%近い下げ 感謝祭の祝日明けの米株式市場は、ニューヨーク時間午後2時までの短縮取引。出来高は30日平均を約16%下回った。下落が目立ったのは、エネルギーや一般消費財関連の銘柄だった。 S&P500種株価指数は前営業日比0.4%安の3140.98。ダウ工業株30種平均は112.59ドル(0.4%)安の28051.41ドル。ナスダック総合指数は0.5%低下。米国債市場では10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.78%。 ユニジェスチョンのシニアポートフォリオマネジャー、ディディエ・アンサマテン氏は米国の感謝祭翌日とあってトレーダーの多くが市場に参加しておらず、「流動性が非常に低い」と指摘した。 ニューヨーク原油先物相場は大幅続落。石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟産油国は一段の減産に動かない可能性が示唆された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は2.94ドル(5.1%)安の1バレル=55.17ドルで終了。週間ベースでは4.5%安と、10月初旬以来の大幅安となった。ロンドンICEの北海ブレント1月限は、1.44ドル安の62.43ドル。1月限はこの日が最終取引日となった。 ニューヨーク金先物相場は反発。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.8%高の1オンス=1472.40ドルで終了。月間ベースでは3%近い下げとなった。【日本株週間展望】小幅高、堅調な米経済と為替安定-米中協議は警戒 12月1週(2ー6日)の日本株は小幅上昇が予想される。年末商戦に向けて消費拡大期待が膨らむ中、安定したドル円相場に支えられて買いが先行する。ただ、米中貿易協議が合意に向けて順調とも言えず積極的な展開にもなりにくい。 米国では11月の経済指標が相次ぐ。2日に供給管理協会(ISM)製造業景況指数、4日にISM非製造業景況指数、6日に雇用統計が発表される。市場予想はISM製造業が49.5(前回48.3)、非製造業は54.5(同54.7)、非農業部門雇用者数は19万人増(同12万8000人増)の見通し。製造業の改善に加えて年末商戦に楽観的な見方が広がれば、日本株にも追い風となりそう。 米国の香港人権法成立による米中対立は警戒されるが、部分合意を目指して貿易協議は継続しており、対中追加関税の発動期限に向けた進展が引き続き材料になる。このほか、5日の石油輸出国機構(OPEC)総会と6日のOPECプラス会合も注目。減産継続なら原油価格は安定し、世界景気への懸念が後退する。11月4週のTOPIXは週間で0.5%高の1699.36と3週ぶりに反発。 ≪市場関係者の見方≫ SMBC信託銀行の山口真弘シニアマーケットアナリスト 「底堅い展開を予想。材料になるのは海外経済指標。米国で耐久財受注の増加が見られたが、これに続いてISM製造業指数が改善すれば景気回復への期待感が高まる。米国は雇用と所得が良好な上、株高の資産効果から年末商戦で消費拡大が見込まれる。香港人権法の成立で米中関係は警戒されるが、中国は外交問題より通商協議に集中するとみられ部分合意への期待が続く。日経平均で心理的節目の2万3500円付近では上値が重くなる」 野村証券投資情報部の伊藤高志エクイティ・マーケット・ストラテジスト 「小幅続伸を予想。市場は、米中協議が部分合意で着地する可能性が高いとみる。香港問題に関連して中国がどんな手を打つかわからないが、通商摩擦の悪影響が米国より大きいことを考慮すれば、対立をエスカレートさせることはしないだろう。また、米国が実務レベルで決定したことをひっくり返す事態もないだろう。ブラックフライデーから始まった年末商戦で、米国の強い個人消費が確認されれば、景気に敏感な日本株にもポジティブ。ただ、日本株のバリュエーションに割安感がなく、大きな上値トライは考えにくい」(ロイター)米国株は下落、米中通商懸念で軟調地合い 小売株さえず[29日 ロイター] - 米国株式市場は下落して取引を終えた。米中通商協議を巡る懸念に加え、年末商戦の幕開けとなる感謝祭明けの「ブラックフライデー」での店舗の集客が例年よりも少なかったことで小売株が売られた。 中国共産党機関紙・人民日報傘下の有力国際情報紙、環球時報の胡錫進編集長は28日、ツイッターで、中国が香港の反政府デモを支援する米国の法案を起草した人物を中国本土および香港、マカオへの入国を禁止するリストに載せることを検討していると明らかにした。 またロイターは29日、関係筋の話として、米政府は米国の技術が用いられている海外製品の中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)への販売制限を強化する可能性があると報じた。 S&P総合500種はこの日の安値をやや上回る水準で引けたが、ファーウェイに関する報道を受け、取引終盤は売りが強まった。 通商面の影響を受けやすいフィラデルフィア半導体(SOX)指数.SOXは1.1%安となった。 リフィニティブのデータによると、月次ではS&Pが3.4%高。ダウ工業株30種とナスダック総合はそれぞれ3.7%、4.5%上昇した。月間上昇率は主要3株価指数いずれも6月以来の大きさだった。 ナティクシス・インベストメント・マネジャーズ・ソリューションズのポートフォリオマネジャー兼ストラテジスト、ジャック・ジャナシーウィックツ氏は、米中関連のニュースが29日の市場の「やや弱い地合い」につながったと述べた。 この日は感謝祭の休場明けで市場参加者が少なかった上、ジャナシーウィックツ氏によると、来週には雇用統計などの経済指標が発表されるほか、ブラックフライデーの売上高を確認したいとの見方もあり、手控えムードだったという。 ブラックフライデーを巡っては、店舗に行列をつくる人の姿が例年より少なく、セール前倒しやオンラインショッピング拡大の影響が出ているとみられている。 S&P小売指数.SPXRTが0.8%安。コールズ(KSS.N)が2.7%安、ギャップ(GPS.N)が1.8%安となった。ウォルマート(WMT.N)は0.3%上昇した一方、コストコ(COST.O)は0.3%下落。ベスト・バイ(BBY.N)も値下がりした。 個別銘柄ではテック・データ(TECD.O)が12.3%急伸。アポロ・グローバル・マネジメント(APO.N)が同社に対する買収額を51億4000万ドルに引き上げた。 ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.86対1の比率で上回った。ナスダックでも1.35対1で値下がり銘柄数が多かった。 29日は短縮取引で、米取引所の合算出来高は35億5000万株。直近20営業日の平均は68億6000万株。 ドル小幅安、米中交渉巡り警戒 感謝祭明けで動意薄=NY市場[ニューヨーク 29日 ロイター] - ニューヨーク外為市場ではドルが主要通貨に対して当初値上がりしていたものの、その後は買いが続かず下げに転じた。米中通商協議を巡って警戒感が根強いほか、感謝祭明けの週末で動意薄となった。 主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.12%安の98.253。一時98.544と10月15日以来の高値を付ける場面も見られた。週間ではほぼ横ばい。月間では0.9%上昇と、7月以来の高い伸びとなった。 米中協議を巡っては、トランプ大統領が27日、香港の反政府デモを支援する「香港人権・民主主義法案」に署名し、同法が成立。これに対し、中国政府が「断固とした報復措置」を取ると反発するなど、にわかに不透明感が増している。 クラリティーFX(サンフランシスコ)のディレクター、アーモ・サホタ氏は、さえない市場心理が相場の重しになったと指摘した。 ユーロ/ドルEUR=は0.09%上昇。11月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)速報値は前年比1.0%上昇と、10月の0.7%から加速し、ロイターがまとめたエコノミスト予想を上回った。ただ2%未満でその近辺とする欧州中央銀行(ECB)の目標からは程遠い水準にとどまった。 ポンド/ドルGBP= GBP=D3 GBPX1=は1.29ドル近辺で推移。政治絡みのニュースには反応薄だった。ジョンソン首相は29日、トランプ大統領が来週、北大西洋条約機構(NATO)首脳会議のためにロンドンを訪れる際、12月12日の英総選挙に関与しないことが「最善」と述べた。 (株探ニュース)【市況】今週の【早わかり株式市況】3週ぶり反発、米株高・米中協議進展期待も後半伸び悩む■今週の相場ポイント 1.日経平均は週半ばまで4日続伸、週間ベースでは3週ぶりの上昇に 2.NYダウが連日の最高値更新、日経平均も一時ザラ場の年初来高値更新 3.「香港人権法」の成立で地合いは一変、米中協議に警戒感台頭で様子見に 4.ソニーや富士通、日立など中核のハイテク銘柄の上昇相場は継続 5.東証マザーズ指数や日経ジャスダック平均は6日続伸と強調展開■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比181円(0.78%)高の2万3293円と3週ぶりに上昇した。 今週の前半はNYダウが連日の最高値更新に沸き、日経平均もザラ場での年初来高値を更新した。しかし28日早朝に米国で「香港人権法」が成立。中国は強い反発を示し、米中通商協議への不透明感が台頭。東京市場も高値警戒感が強まり上値が抑えられた。 週明け25日(月)は、米中協議に関して交渉進展への期待が先行。香港ハンセン指数や上海総合指数も堅調に推移するなか、日経平均は前週末比179円高と上昇した。26日(火)はNYダウなど主要3指数が揃って最高値を更新。中国が知的財産権の保護強化を発表したことで、米中協議の前進期待が膨らんだ。日経平均は80円高となり一時、ザラ場の年初来高値を更新した。27日(水)はNYダウが連日の最高値更新。東京市場では機関投資家の配当再投資の買いも取り沙汰され、日経平均は64円高と4日続伸した。28日(木)は日本時間の早朝に「香港人権法」が成立。米中協議の先行き不透明感が強まり、日経平均は28円安と5日ぶりに反落した。29日(金)は日経平均が115円安と続落。前日の米国市場は感謝祭で休場だったため薄商いだったが、米中協議への警戒感から売りが先行した。ただ、東証マザーズや日経ジャスダック平均は6日続伸と小型株は堅調。週間を通じてソニー や富士通 、日立製作所 のような中核のハイテク株は堅調な値動きとなっている。■来週のポイント 今週後半に米中関係の先行き懸念が強まっただけに、来週も米中の動向に揺れる展開が続きそうだ。 重要イベントとしては、国内では2日朝に発表される7-9月期法人企業統計調査や6日発表の10月景気動向指数が注目される。海外では2日発表の米国11月ISM製造業景況指数や5日発表の米国10月貿易収支、6日発表の米国11月雇用統計のほか、5日-6日に開催されるOPEC総会に注視が必要だろう。■日々の動き(11月25日~11月29日)【↑】 11月25日(月)―― 続伸、米株高や香港株高を好感し買い優勢 日経平均 23292.81( +179.93) 売買高10億1101万株 売買代金 1兆6991億円【↑】 11月26日(火)―― 米株最高値・米中協議進展期待で買い優勢 日経平均 23373.32( +80.51) 売買高16億2299万株 売買代金 3兆1584億円【↑】 11月27日(水)―― 4日続伸、配当再投資の買い優勢も後半伸び悩む 日経平均 23437.77( +64.45) 売買高10億7787万株 売買代金 1兆8960億円【↓】 11月28日(木)―― 5日ぶり反落、米中協議の不透明感で上値の重い展開 日経平均 23409.14( -28.63) 売買高 9億2501万株 売買代金 1兆5982億円【↓】 11月29日(金)―― 続落、米中協議の先行き警戒感で売り優勢 日経平均 23293.91( -115.23) 売買高 9億9450万株 売買代金 1兆7571億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、23業種が上昇 (2)国際石開帝石 など鉱業、コスモHD など石油株は反発 (3)住友電 など非鉄、JFE など鉄鋼、川崎汽 など海運といった景気敏感株に買い戻し (4)金融株は野村 など証券、第一生命HD など保険、三菱UFJ など銀行が堅調も オリコ などその他金融株はさえない (5)輸出株はソニー など電機、日立建機 など機械が高いも トヨタ など自動車株は低調 (6)JR東日本 など陸運、セブン&アイ など小売り、日清粉G など食品といった内需株は軟調■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(1) 5G ── “IoT社会の進化系”と融合へ 2(3) セルロースナノファイバー(CNF) ── 自動車軽量化で注目 3(6) 人工知能(AI) 4(2) クラウドコンピューティング 5(8) 量子コンピューター ※カッコは前週の順位(msn)(フォーブス・ジャパン)米国株が3日連続最高値でも消えない「大崩壊」への恐怖米国の株式相場は11月27日も続伸し、連日の最高値更新となった。背景には今年第3四半期の米国経済の伸びと個人消費の力強さがあり、米中の貿易交渉の先行きに楽観ムードが漂うなかで、景気後退への懸念が吹き飛んだ形だ。27日のS&P 500種株価指数とダウ工業株30種平均は、3日連続で最高値を更新した。株式市場は予想を上回る経済指標に後押しされ、第4四半期も適度な拡大が続くとの見通しが高まった。直近の統計で第3四半期の米実質国内総生産(GDP)改定値は前期比2.1%となり、速報値の1.9%から上方修正された。一方で、速報値で3%減とされた企業設備投資も2.7%減にとどまった。10月の個人消費の伸びや失業率の低下が示される中で、景気見通しは改善し、短期間でリセッション入りする懸念は遠のいた。さらに26日にはトランプ大統領が、米中の交渉が最初の重要な合意にむけての最終段階に入ったとコメントしたことで、貿易交渉の先行きにも楽観ムードが高まった。それに加え、相場を後押ししたのが第3四半期の企業収益の好調さだ。S&P 500銘柄に含まれる484社のうち、75%の企業の業績は予想を上回り、予想に届かなかった企業は18%だった。これまでの平均的な四半期においては、予測を上回る企業は65%に過ぎなかったとされる。今年に入り、S&P 500は約25%の上昇となり、ダウ平均も21%近い伸びとなった。S&P 500は過去1カ月で12回以上、最高値を更新している。米国の大手金融ブローカーのコモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークの投資主任、Brad McMillanは直近の顧客向けレポートで「現在の株式市場には楽観ムードが漂い、需要は力強い。このトレンドはしばらく続く」と述べた。リセッション入りの懸念は当面の間は後退し、米国株の上昇は2020年まで続くとの見方もあるが、ロイターの直近の調査では、伸び幅は今年よりは縮小する見通しだ。アナリスト投票では、今後の市場の成長を後押しするのは世界経済の安定的な発展や、各国政府による金融緩和、米国企業の収益の改善とされた。一方で、2020年の最大のリスク要因といえるのは大統領選挙にからむ不確定要素や、米中の経済対立が世界経済にダメージを与えることだ。米中の交渉の先行きが楽観視される一方で、民主化デモが吹き荒れる香港では予断を許さない状況が続いている。(msn)(GIZMODE)Amazonの野望「全世界アレクサ化計画」 すべての家電がユーザーの個人情報を吸い上げる恐怖。Amazon(アマゾン)の音声アシスタントAlexaが、充分な機能に組み込まれていないと思っていた人のために、AmazonはAI内蔵の音声アシスタントを安くて賢くないものにも追加する新しい方法を、シレっと発表しました。この新技術を使うと、もっとも基本的なプロセッサーと1MB未満のメモリーでAlexaを動かすことができるようになります。つまるところ、電灯のスイッチやトースター、歯ブラシまでもが、主人の命令を聞き始めるかもしれないのです。小さくともハイテクな精密機器このニュースは驚くことではありません。Amazonは9月に開催されたハードウェア・イベントにて、Alexaデバイスを安く簡単に、家庭内だけでなく身体にもインストールできるようにする思惑があることを明らかにしていました。AmazonのデバイスにはAlexa対応の小さなスピーカー・Echo Flexがあり、壁のコンセントに電灯のように挿し込みます。Alexaは、イヤホンのEcho Buds、スマートリングのEcho Loop、およびスマートグラスのEcho Framesの中心となる技術です。しかし、大局的に見れば、これらはどれもが相当に洗練された電子機器なのです。低スペック機器にも搭載可能新たなAlexaの技術は、AVSに統合されたAWS IoT Coreと呼ばれており、シンプルで低電力のマイクロコントローラー、そして最小限のRAMを搭載したガジェット上でAlexaを実行できることを意味します。Amazonは開発者ブログにて、以前のAlexa内蔵製品には「LinuxまたはAndroidで動作する50MB以上のメモリーを搭載した高価なアプリケーション・プロセッサーをベースにしたデバイス」が必要だった、と説明していますが、聞いていると今では理論的にコーヒーカップでもAlexaを動かすことができるようになったように思えてきます。副社長のコメントAWS IoTのダーク・ダイダスカルー副社長が、TechCrunchにこう話しています我々は今、ほとんどすべてをクラウドに移しています。なので機器類はとてつもなくおバカになりかねません。デバイスが必要な機能は唯一、ウェイクワード検知です。それはまだデバイスに内蔵されていないといけないのですダイダスカルー副社長からは、ほかにも終末的未来についていくつかコメントがありました。それは、私たちが真の環境知能と、環境コンピューティング空間と呼ぶものを開くだけです。なぜなら今では、ハブがどこにあるのかを特定する必要はありません。ただ周囲の環境に話しかければ、あなたの環境との対話が可能になります。これはAlexaによる「環境知能(ambient intelligence)」への非常に大きな一歩だと思います言い換えると、Alexaはアっという間に家庭に浸透し、どのデバイスと話しているのかさえわからなくなってしまう、ということです。ウェイクワードにまつわる問題いくつかのデバイスは、ウェイクワードしか理解できないほど愚かなものもあります。でもこれは実際、音声アシスタントにとって非常に重要なタスクです。結局のところ、デバイスがユーザーの指示をどの時点から記録し始めるかを理解するくらい優秀でなければ、誤ってユーザーの言動を記録する可能性が高くなってしまいます。これはよく知られた問題でもあり、AlexaやGoogle Assistantのような技術にとっては、正直いってかなり深刻な問題です。かつてはAmazon Echo Dotが夫婦の会話を録音し、Alexaがその録音をユーザーの同意なしに知人に送ったという話がありました。あれは、内蔵コンピューターがウェイクワードとコマンドを聞いたと勘違いした単純な例です。ユーザーは、ほとんどの音声アシスタントが1日に何度もこの間違いをすることに気付いていないかもしれません。確認するには、設定画面を開いてAlexaやGoogle Assistant、またはSiriが聞いてはいけないあなたの人生の断片を記録していないかとうかを調べることになります(そうした記録を削除する方法はコチラ)。 音声アシスタントとクラウドを連携させたくない人たちウェイクワード問題に加えて、一部の企業が音声アシスタントによるクラウド使用を避けたいと考える大きな理由として、プライバシーの改善が挙げられます。Sonosは最近フランスのSnipsという会社を買収し、デバイス上ですべての処理を行うAI音声プラットフォームを開発しています。これは、Sonosスピーカーを、録音した記録をクラウドに上げずに音声コントロールができる、ということを意味しているのかもしれません。同様にAppleは、Siriのすべての機能がクラウドにデータを送信する必要があるわけではない、といっています。プライバシーはどうでも良いAmazonどうやらAmazonは、ユーザーにすべてのデータをクラウドへ送信することを望んでいるようです。この会社は最近「ウェイクワード前に発生する可能性のある発話コマンドの部分を捕捉して処理するシステム」の特許を取ったのと同じ会社です。そんなのはAlexaがすべてのものにインストールされ、常に耳を傾けていれば、もっとうまく動作するはずです。プライバシーは後付けですが、いずれにせよAmazonはプライバシーのことなんて気にしていないようです。(日刊ゲンダイ)“本当の賞金女王”は渋野日向子で決まっている…女子プロの戦意削ぐ制度の欠陥 今季の女子プロ最終戦は賞金女王争いが話題になっている。現在のランキング1位は鈴木愛(25)。2位申ジエ(31)、3位渋野日向子(21)と続いている。 2日目(29日)の渋野は3バーディー、1ボギーの70で通算4アンダー。首位のテレサ・ルー(32)に3打差3位タイにつけている。鈴木、申は通算1オーバーの17位タイだ。 注目の渋野の逆転女王は単独2位以上が最低条件と報じられているが、「実際のところ賞金女王はすでに決まっている」との声がある。 ゴルフライターの吉川英三郎氏が言う。「国内の男子プロと違い、女子プロの賞金ランキングは海外メジャーの賞金は加算されない。それはおかしな話です。この決まりがあるために、海外メジャーの出場資格がありながら、これを欠場する選手がいる。日本の試合に出なければ獲得賞金ランキングが下がり、翌年のシード権(ランキング50位以内)確保などに関わるからです。海外メジャーへの挑戦意欲をそぐ制度と言わざるを得ず、日本の賞金ランキングは適正とはいえない。仮に海外メジャーの賞金を加算すれば、渋野の現在の獲得額は2億円を超えている(別表参照)。鈴木は全米女子オープン22位の賞金を加え、さらに今大会に優勝(賞金3000万円)しても2億円に届かない。ANAインスピレーションで21位の申ジエもしかりです」 さらに吉川氏は続ける。「渋野は日本勢では42年ぶりにメジャー優勝の快挙を成し遂げ人気選手になった。レベルの低い国内ツアーの賞金だけでランクを決めることに違和感のあるファンは多いはずです。賞金女王が渋野で決定なら、今大会はまったく盛り上がらないことになるが、国内ツアーの話題づくりにはなっても、それによって海外メジャーを目指す選手が減るのは、世界で活躍する選手を育てなければならない使命がある女子プロ協会としては本末転倒です」 ホールアウトした渋野は「苦しいゴルフでしたが(今日は)2アンダーで回れてよかった。明日は気負わず自然体でいきたい」と語り、その後はグリーンで鈴木とともにパターの練習を繰り返した。 もっとも、最終戦で“逆転女王”になれば、本人が一番すっきりするだろう。(GDO)国内男子 カシオワールドオープン 3日目小林伸太郎は2打差2位で最終日へ 首位にクウェイル2打差2位から出たアンソニー・クウェイル(オーストラリア)が終盤に5連続バーディを奪い、この日ベストスコアの「65」でプレー。通算15アンダーで単独首位に浮上した。2018年シーズンから日本ツアーに本格参戦する25歳がツアー初優勝へ好位置につけた。首位から出た33歳の小林伸太郎は4バーディ、1ボギーの「69」で回り、通算13アンダー2位。通算12アンダー3位にキム・キョンテ(韓国)と17年大会覇者スンス・ハン(米国)が並んだ。通算11アンダー5位に宮本勝昌、小田孔明の2人が続いた。賞金ランキング5位の石川遼は終盤に4連続バーディを含む8バーディ、1ボギー1ダブルボギーの「67」でプレー。川村昌弘、浅地洋佑、重永亜斗夢、同ランキング2位ショーン・ノリス(南アフリカ)と並んで通算10アンダー7位とした。賞金ランキング1位の今平周吾は59位で最終日を迎える。<上位成績>1/-15/アンソニー・クウェイル2/-13/小林伸太郎3T/-12/キム・キョンテ、スンス・ハン5T/-11/小田孔明、宮本勝昌7T/-10/浅地洋佑、重永亜斗夢、石川遼、川村昌弘、ショーン・ノリス国内女子メジャー第4戦 LPGAツアー選手権リコーカップ 3日目イ・ボミが単独首位 渋野日向子は2打差3位で最終日へ首位に3打差から出たイ・ボミ(韓国)が7バーディ、4ボギーの「69」とし、通算7アンダーの単独首位に浮上した。後続に1打差をつけ、2017年8月「CATレディース」以来のタイトルに前進して最終日を迎える。通算6アンダーの2位にペ・ソンウ(韓国)。後半に2つ伸ばして「71」とし、スタート前と同じポジションをキープした。通算5アンダーの3位に、賞金ランキング3位の渋野日向子。イと同組で3打差を追い、上がり2ホールを連続ボギーで落とすなど5バーディ、4ボギーの「71」。逆転女王には単独2位以上が最低条件となる。通算4アンダーの4位に古江彩佳、首位から出て「75」と落としたテレサ・ルー(台湾)が続いた。17位から出た鈴木は4バーディ、2ボギーの「70」とし、通算1アンダーの12位に浮上。同ランク2位の申ジエ(韓国)は通算イーブンパーの17位。申は通算1オーバー以内で大会を終えれば、ツアー史上初となる平均ストローク60台の偉業達成となる。<上位の成績>1/-7/イ・ボミ2/-6ペ・ソンウ3/-5渋野日向子4T/-4/古江彩佳、テレサ・ルー(goo)(AERAdot.)アルコール業界の“希望の星” 国産とは違う「日本ワイン」が空前の量産体制へ 日本ワインをご存じだろうか。国産ワインとは違うことも。いま国内だけでなく世界からも注目され、各社が増産計画を打ち出す。AERA 2019年12月2日号の記事を紹介する。 「ウイスキーは世界で認められたことで広がった。同じことが日本ワインでもできると確信している。令和の時代を振り返ったとき、日本ワインが世界に羽ばたいているように」 ここはワイン大手メーカー「メルシャン」が9月にオープンさせた「シャトー・メルシャン 椀子(まりこ)ワイナリー」(長野県上田市)。その内覧会で、同社の長林道生社長は、熱く語った。 同社は他にも、桔梗(ききょう)ケ原(同県塩尻市、2018年9月)と勝沼(山梨県甲州市、19年8月に新セラー開業)の2ワイナリーを持つ。3番目となる椀子は、ぶどう畑「椀子ヴィンヤード」をオープンして以来10年以上をかけて開業を準備し、満を持してのオープンとなった。 長林社長が語った「日本ワイン」は、いわゆる「国産ワイン」とは意味合いが違う。18年に施行された国税庁の「果実酒等の製法品質表示基準」、いわゆる「ワイン法」によって、「日本で醸造され、日本産のぶどうを100%使ったワイン」だけが「日本ワイン」と明確に定義されたのだ。国産ワインの中には、海外のぶどう果汁を日本で醸造する物もある。日本ワインは、限られた国産ワインだけが名乗れるブランドだ。 その日本ワインはいま、人気が急上昇している。国税庁の調査では、14年に162万ケースだった出荷量が17年には173万ケースに。さらに、ワイナリーの数は18年3月末時点で303場にもなった。 こうした人気を受けて、大手ワインメーカー各社も、日本ワインを絶賛増産中だ。メルシャンは、18年時点の日本ワインの販売数4.4万ケースを「26年には6万〜7万ケースまで伸ばす」(同社を傘下に持つキリンホールディングス広報)という、強気の目標を設定。 またサントリーも、110年の歴史がある登美の丘ワイナリー(山梨県甲斐市)を含む自社のぶどう畑を「26年までに約2倍の広さにする」(同社広報部)という目標を掲げる。 サッポロビールは年間3万ケース(18年)の販売数を、「26年までに10万ケースまで伸ばす」(同社広報室)。アサヒビールも、子会社を合わせた販売数を25年までに現在の約3倍にあたる2万ケースに増やす計画を掲げており、主要メーカーがこぞって、この先6〜7年で販売数を2〜3倍に伸ばす計画を打ち出しているのだ。 空前の増産体制には、国内のアルコール離れが進むなか、ワインは消費が拡大している貴重なジャンルという背景がある。日本ワインというブランドが確立されたことで、国内だけでなく海外からの注目度も年々上がり、アルコール業界の“希望の星”となっている。 そして何と言っても、日本ワインが格段においしくなったことが、日本ワインの販売量を増加させている。 「10年ほど前、久しぶりに味わった日本ワインのおいしさに衝撃を受けました。その後もすばらしい栽培家や醸造家がつぎつぎ登場して、日本ワインの質は今も進化していると思います」 日本ワインに魅了され、4年前に四谷・荒木町で専門のバーを始めた「日本ワイン中村」のオーナー中村雅美さんはそう話す。 かつては日本ワインというと、「味が薄い」「水っぽい」などというネガティブな評価が多かった。「湿気が多い日本は、おいしいワイン造りには向いていない」などといった身も蓋もない風評が、まことしやかに語られていたこともある。 それがいまは、例えば白なら「上品」「繊細」などといった評価が目立つように。国際コンクールでの受賞も相次ぎ、日本ワインは、世界中のワイン通から熱い視線を送られるブランドに成長しつつある。(ライター・福光恵、編集部・福井しほ)※AERA 2019年12月2日号より抜粋(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)NY市場概況-3指数がそろって反落 月間では大幅高 29日のNY株式相場は反落。感謝祭の翌日で午後1時までの短縮取引となるなか、トランプ米大統領が前日に、「香港人権法・民主主義法」に署名し、法案が成立したことで米中関係を見極めたいとして様子見姿勢が強まった。12月15日の対中関税引き上げまでに米中が「第1段階」の合意文書への署名に至るかが焦点となるが、ウォールストリート・ジャーナルが中国サイドは合意の条件から香港問題を切り離すとの観測を報じたことなどで、過度な悲観は避けられた。ブラックフライデーの好調な消費が伝えられ、ウォルマートなどが上昇したものの、週末、月末の取引で、月初から大きく上昇した銘柄には利益確定売りも強まった。主要3指数は、ダウ平均が112.59ドル安(-0.40%)、S&P500が0.40%安、ナスダック総合が0.46%安となり、そろって5営業日ぶりに反落した。 週間では、ダウ平均が0.63%高、S&P500が0.99%高、ナスダック総合が1.71%高とそろって反発。月間ではダウ平均が3.72%高、S&P500が3.40%高、ナスダック総合が4.50%高とそろって3カ月続伸。年初来では、ダウ平均が20.25%高、S&P500が25.30%高、ナスダック総合が30.60%高となった。(yahoo)(フィスコ)NY株式:下落、米中協議の先行き懸念が相場の重しに 米国株式相場は下落。ダウ平均は112.59ドル安の28051.41、ナスダックは39.70ポイント安の8665.47で取引を終了した。株価上昇を受けた利益確定の動きから売りが先行。午後1時までの短縮取引となる中、米国での香港人権・民主主義法案の成立で米中協議の先行き懸念から、終日軟調推移となった。セクター別では家庭用品・パーソナル用品を除いて全面安となり、特にエネルギーや半導体・半導体製造装置の下落が目立った。 米中協議への先行き懸念から半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)やクアルコム(QCOM)が下落。原油相場の下落で、エネルギー会社のチェサピーク・エナジー(CHK)や深海油田開発のトランスオーシャン(RIG)などエネルギー銘柄が軟調推移。一方で、IT関連製品の卸売を手がけるテック・データ(TECD)は、投資会社のアポロ・グローバル・マネジメントへの身売りで合意し、大幅上昇となった。 週明けの月曜日はサイバーマンデーと呼ばれ、オンラインでの売上が急増する日と言われている。アドビ・システムズの調査によると、今年のサイバーマンデーの売上高は、過去最高となる前年比18.9%増の94億ドルを達成すると予想されている。(Horiko Capital Management LLC)国内株式市場見通し:日経平均は米中協議睨みつつ上値を意識■日経平均は3週ぶり反発、香港情勢が懸念材料前週の日経平均は3週間ぶりに反発した。米中貿易協議の第一弾合意への期待が週前半高に寄与した一方、週後半は香港情勢が相場に影を落とす形となった。米中首脳の貿易協議を巡る前向きな発言を好感して22日のNYダウは4日ぶりに109ドル高と反発した。これを受けた週明け25日の日経平均は続伸した。香港株高なども支援材料となり、前引けにかけて前週末比234.30円高まで上昇する場面があったが、後場に入ると伸び悩んだ。売買代金は1兆6991億円と10月21日以来、およそ1カ月ぶりの低水準となった。中国が知的財産権を巡る問題で譲歩と報じられ、25日のNYダウは続伸。この流れを引き継いだ26日の日経平均も3日続伸となった。個別では、アナリストによる目標株価引き上げの動きが相次いでいる村田製作所の上昇が目立った。26日のNYダウが3日続伸し史上最高値を更新し、27日の日経平均も4日続伸。ただ、日中の上下の値幅は90円弱に留まり、こう着感の強い展開となった。28日朝方にトランプ米大統領が「香港人権・民主主義法」に署名したことが伝わると米中協議への警戒感が生まれ、日経平均は5日ぶりに反落した。為替相場やアジア株式市場の反応が限定的で下げ幅は小幅に留まったものの、米国市場が感謝祭による休場を控えていることから積極的な売買は敬遠されて東証1部の出来高は10月21日以来となる10億株割れに沈んだ。個別では、半導体事業からの撤退が報じられたパナソニックが大幅高となった。日経平均が一服した一方で、東証2部指数、マザーズ指数、ジャスダック平均は5日続伸し、物色の流れは中小型株に向かった。29日の日経平均は、手掛かり難のなかで小幅続落した。押し目買いが先行して始まったが、週末とあって買いが続かず日経平均はマイナスに転じた。なお、月間で見た日経平均は3カ月連続高となった。■日経平均は堅調さ維持へ今週の日経平均は、模様眺めムードが継続しつつも堅調な展開を維持しそうだ。トランプ大統領が「香港人権・民主主義法」に署名したことを受けて、米中貿易協議への悪影響が懸念されているものの、米中ともに過激な対応は出ていない。相場への影響が大きい米中の通商交渉に関してのニュースには、引き続き神経質な展開を強いられることになる。8日に香港民主派が大規模抗議集会を計画していることも気掛かりだ。米中通商協議フェーズ1の合意が不透明で、米国による12月15日の対中追加関税発動期限も接近しているが、米中交渉の進展期待が相場の下支えとして働いていることも事実だ。一方、29日朝方の寄り付き前に経済産業省が発表した国内10月の鉱工業生産は、事前の市場予想を下回る一方、ユーロ圏景況感指数は改善が伝えられて、内外の経済指標は強弱感が交錯している。6日の米11月雇用統計は日本時間同日夜の発表であり、株式市場への影響は翌週となる。こうしたなか、米ブラックフライデーの出足が低調過ぎる事態にでもならない限り、相場基調は崩れずに週明けを迎えることが出来そうだ。12月2日のサイバーマンデーへの期待も根強く、本格化入りする米クリスマス商戦の話題が日経平均をサポートしてこよう。1ドル=109円台半ばで安定的に推移している為替相場が、一段の円安になれば、下値抵抗を強めている日経平均は上値を一気に慕うこともありそうだ。限られた動きとなっていた海外勢のフローも翌週末13日のメジャーSQに向けて、動意を強める可能性がある。■物色の関心は中小型株と新興市場に物色的には、半導体関連を始めとする優良株と内需関連株に買い一巡感が漂い、大型株は一服ムードが継続しやすい。ただ、相対的な日本株の出遅れ感は意識されており売りも限られてこよう。こうしたなか、個人主体の中小型株・材料株物色に関心が一段と高まる方向にある。なかでも、12月のIPO(新規上場)ラッシュに加えて、季節性からマザーズやジャスダックなど新興市場銘柄の活躍期待が膨らんでいる。マザーズ指数、ジャスダック平均は29日に掛けて6日続伸と助走を開始している。このほか、米アップルが2日(日本時間3日早朝)にメディア向けイベントを開催する。新製品の発表はなく、今年人気のアプリとゲームを表彰の観測があるが、手掛かり材料となる期待もある。また、2日から6日にかけて開催されるNATO(北大西洋条約機構)が主催するサイバー防衛演習「サイバー・コアリション2019」に、日本の防衛省が公式に初参加する。サイバーセキュリティ関連に関心が向く可能性があるほか、ファーストリテの11月国内ユニクロ売上高が3日に発表され、消費関連株にもスポットが当たるだろう。■サイバーマンデー、米雇用統計、中国貿易統計主な国内経済関連スケジュールとして、2日は7-9月期法人企業統計、11月自動車販売台数、3日は11月マネタリーベース、6日は10月毎月勤労統計調査、10月家計調査、10月の景気動向指数の発表が予定されている。一方、米国など海外主要スケジュールとしては、2日に米11月ISM製造業景況指数、米サイバーマンデー、4日に米11月ADP雇用統計、5日に米10月貿易収支、米10月製造業受注、ユーロ圏7-9月期GDP確定値、6日に米11月雇用統計、8日に中国11月貿易統計が予定されている。来週の相場で注目すべき3つのポイント:米サイバーマンデー、11月国内ユニクロ売上高、米11月雇用統計■株式相場見通し予想レンジ:上限23700-下限23000円来週の日経平均は、模様眺めムードが継続しつつも堅調な展開を維持しそうだ。トランプ氏が「香港人権・民主主義法」に署名したことを受けて、米中貿易協議への悪影響が懸念されているものの、米中ともに過激な対応は出ていない。相場への影響が大きい米中の通商交渉に関してのニュースには、引き続き神経質な展開を強いられることになる。8日に香港民主派が大規模抗議集会を計画していることも気掛かりだ。米中通商協議フェーズ1の合意が不透明で、米国による12月15日の対中追加関税発動期限も接近しているが、米中交渉の進展期待が相場の下支えとして働いていることも事実だ。一方、29日朝方に経済産業省が発表した10月の国内鉱工業生産は、事前の市場予想を下回る一方、ユーロ圏景況感指数は改善が伝わり、内外の経済指標は強弱感が交錯している。6日の米11月雇用統計は日本時間同日夜の発表であり、株式市場への影響は翌週となる。こうしたなか、米ブラックフライデーの出足が低調過ぎる事態にでもならない限り、相場基調は崩れずに週明けを迎えることができそうだ。12月2日のサイバーマンデーへの期待も根強く、本格化する米クリスマス商戦の話題が日経平均をサポートしてこよう。1ドル=109円台半ばで安定的に推移している為替相場が一段の円安になれば、下値抵抗を強めている日経平均は上値を窺うこともありそうだ。限られた動きとなっていた海外勢のフローも翌週末13日のメジャーSQに向けて、動意を強める可能性がある。物色的には、半導体関連を始めとする優良株と内需関連株に買い一巡感が漂い、大型株は一服ムードが継続しやすい。ただ、相対的な日本株の出遅れ感は意識されており、売りも限られてこよう。こうしたなか、個人主体の中小型株・材料株物色に関心が一段と高まる方向にある。12月のIPO(新規上場)ラッシュに加え、季節性からマザーズやジャスダックなど新興市場銘柄の活躍期待が膨らんでいる。マザーズ指数、日経ジャスダック平均は29日にかけて6日続伸と助走を開始している。このほか、米アップルが2日(日本時間3日早朝)にメディア向けイベントを開催する。新製品の発表はなく、今年人気のアプリとゲームを表彰との観測があるが、手掛かり材料となる期待もある。また、2日から6日にかけて開催されるNATO(北大西洋条約機構)主催のサイバー防衛演習「サイバー・コアリション2019」に、日本の防衛省が公式に初参加する。サイバーセキュリティ関連に関心が向く可能性があるほか、ファーストリテイリングの11月国内ユニクロ売上高が3日に発表され、消費関連株にもスポットが当たるだろう。主な国内経済関連スケジュールとして、2日は7-9月期法人企業統計、11月自動車販売台数、3日は11月マネタリーベース、6日は10月毎月勤労統計調査、10月家計調査、10月の景気動向指数の発表が予定されている。一方、米国など海外主要スケジュールとしては、2日に米11月ISM製造業景況指数、米サイバーマンデー、4日に米11月ADP雇用統計、5日に米10月貿易収支、米10月製造業受注、ユーロ圏7-9月期GDP確定値、6日に米11月雇用統計、8日に中国11月貿易統計が予定されている。■為替市場見通し来週のドル・円はもみ合いか。米主要経済指標の改善を受けて景気底入れが意識され、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ打ち止め観測が広がっている。ただ、米中通商協議の先行きは不透明であり、ドルを下押しする場面もあろう。発表される11月ISM製造業景況指数や11月雇用統計など、金融政策に大きな影響を与える経済指標が予想を上回った場合、利下げ打ち止め観測はより強まる可能性がある。株式市場ではNYダウなど主要株価指数が最高値を更新し、ドル買いを支援する見通し。ただ、香港人権・民主主義法の成立を受け、中国政府の反応を慎重に見極める必要はあるだろう。中国政府は声明で「重大な内政干渉」と反発しており、今後報復措置を発動する構えをみせる。米中両国は第1段階の合意に向け調整を進めているとみられているが、市場関係者の間からは、「香港人権法は超党派で圧倒的支持を受けて可決されており、通商協議への影響が全くないとは思えない」との見方も出ている。米中通商協議は12月中に進展するとの期待は残されているが、この問題に対して中国側の態度がすみやかに軟化することは期待できないことから、目先的にリスク選好的なドル買いは抑制される可能性がある。■来週の注目スケジュール12月2日(月):日・設備投資、中・財新製造業PMI、トルコ・GDP、ユーロ圏製造業PMI、米・ISM製造業景況指数、米・建設支出、ラガルドECB総裁が欧州議会で証言など12月3日(火):オーストラリア中銀が政策金利発表、スイス・消費者物価指数、南ア・GDP、ブ・GDP、NATO首脳会議、韓・GDP、米自動車販売など12月4日(水):サービス業PMI、豪・GDP、中・財新サービス業PMI、ユーロ圏サービス業PMI、ブ・サービス業PMI、米・ISM非製造業総合景況指数、ユーロ圏財務相会合など12月5日(木):対外・対内証券投資、豪・貿易収支、インド中銀が政策金利発表、ユーロ圏GDP確報値、米・貿易収支、OPEC総会、など12月6日(金):独・鉱工業生産指数、米雇用統計など12月7日(土):中・外貨準備高12月8日(日):中・貿易収支(yahoo)(モーニングスター)株式週間展望=米国頼み続くも個別物色旺盛―指数は割安是正一巡、中・小型株へのシフト一段と 年初来高値更新を目前に足踏みをし、上値の重さが意識された今週(11月25-29日)の日経平均株価。それでも、頑強な米国市場を頼りに底堅さを維持している。ただ、マクロベースの独自手掛かりを欠く中、米中貿易協議の先行きに暗雲が漂う点は警戒が必要だ。師走相場に突入する来週(12月2-6日)は指数を追わず、中・小型株への物色傾向が一段と強まりそうだ。 米国では11月29日のブラックフライデーで年末商戦が幕開けし、12月2日にはネット通販セールのサイバーマンデーを迎える。この週は商戦を刺激に為替が円安・ドル高にフレやすい特性を持つが、好調な米国経済を踏まえると今回も例年通りの動きを示す下地がある。 円安は日本株にとって基本的に追い風だが、より強く影響するのは米国株だ。このため、トランプ米大統領の署名によって同国で中国の一国二制度の機能を監視する「香港人権・民主主義法」が成立し、閣僚級で進められてきた米中貿易協議は年内の合意に黄信号がともった点には警戒が必要。米国株が息切れすれば、日本株の支える力も弱まるだろう。 今年の上昇率はNYダウ(11月28日時点)の20.7%に対し、日経平均(同29日時点)も16.4%と極端な出遅れ感はなく、ドルベースでは約18%とよりNYダウに迫っている。予想PER(円ベース)も14倍を上回るレベルに達し、割安是正は一巡した可能性がある。今週は取引時間中に今年の最高値を上抜く場面があったが、引け値では2万3500円に押し返された。 高い期待をさらに上回る米年末商戦の速報や、米中協議の電撃合意といった好材料が浮上した場合は、米株高に伴い日経平均も再び騰勢を強める公算。しかし、その点は見通しにくい。一方、外国人投資家が徐々に休暇に入り始め、売買代金が縮小しつつある東京株式市場では、テーマや材料を重視した個別株の物色が引き続き際立ちそうだ。東証マザーズ指数の今週の上昇率は2.9%と前週に続いて日経平均を凌駕(りょうが)した。 来週は米国で2日の11月ISM(米サプライマネジメント協会)製造業景況指数、4日に11月ADP(オートマチック・データ・プロセッシング)雇用統計と同ISM非製造業景況指数、5日に10月貿易収支、そして6日に11月雇用統計が発表される。決算は3日のセールスフォース・ドットコムに注目。日本は2日に7-9月期法人企業統計。日経平均の予想レンジは2万3000-2万3600円。週初は配当再投資の買いへの期待もあって好発進が見込まれる。(市場動向取材班)昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の7銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。
2019.11.30
コメント(0)
-
11月29日(金)…
11月29日(金)、晴れです。良い天気ですね。まさに行楽日和。そんな本日は7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。美味い!!10時45分頃に家を出る。印鑑屋さんへ…住所印の作り直しです。JAの直売所へ…野菜の調達です。昼食は関市の「そばがきの助六」さんへ…がっかりな休業です…不定休ですから…。肉製品の調達に「メツゲライ・トキワ」さんへ…体調不良で作業が出来なくて商品があまりありません…。夕食はスキヤキと決まったので、昼食は関市の「マーゴ」の中の「丸亀製麺」で済ませる。「ユニクロ」でヒートテックのソックスを調達。帰宅途中で燃料の残量警告が点灯したので、いつものGSで愛車に燃料を補給。燃費は軽く10を超えていますね。総平均で9.6km/lとなりましたね。それではしばらく休憩です。そろそろ支援戦闘機のスタッドレスへのタイヤ交換も考えなくては…ですね。1USドル=109.45円。1AUドル=74.16円。現在の日経平均=23345.06(-64.08)円。金相場:1g=5685(+4)円。プラチナ相場:1g=3558(-17)円。(ブルームバーグ)UBSも富裕層の下位グループに照準、クレディSに追随 スイスの銀行大手UBSグループは同業のクレディ・スイス・グループに追随し、富裕層下位グループ向けビジネスを見直し規模縮小したサービスをより多くの富裕層に提供する計画だ。 欧州・中東・アフリカ担当ウェルスマネジメント責任者クリスティーヌ・ノバコビッチ氏は従業員宛て文書で、預かり資産が50万ドル(約5477万円)から500万ドルのスイス国内顧客は来年早々から、テクノロジーの利用を増やし人とのやり取りを減らす新しいカバレッジモデルに分類されると説明した。従来は、200万ドル以上の顧客は自動的にパーソナルアドバイザーが担当する別の層に分類されていた。 ノバコビッチ氏はブルームバーグが確認した同文書で、最高500万ドルの資産を持つ顧客を「当社の最も重要な顧客グループの1つ」と位置付け、「顧客のデータと調査では、資産が500万ドルを超えると、顧客ニーズは変化し始める」と指摘した。 こうした動きは、超富裕層とはまだ呼べない顧客層を一層重視して収益性向上を図る取り組みの表れだ。スイスのプライベートバンキング事業でUBSに次ぎ2位のクレディ・スイスはこうした顧客向けビジネスが超富裕層向けよりも銀行にとって収益性が高くなる可能性があると見込み、国際的な富裕層ビジネスで富裕層下位グループ向けの特別部門を設立した。 ウェルスマネジメント事業の利益率は激しい競争の脅威にさらされているため、こうした顧客グループは自動化とコスト削減の主要なターゲットとなる。富裕層上位グループは企業オーナーなどが含まれ、カスタムメイドのサービスを必要とするケースが多いが、富裕層下位グループは比較的複雑でない金融商品を求めることが一般的だ。 事情に詳しい複数の関係者によると、クレディ・スイスではインターナショナル・ウェルスマネジメント部門を率いるフィリップ・ウェーレ氏が、資産2000万スイス・フラン(約22億円)前後かそれ以下の顧客を新しく設立した「プライベート・バンキング・インターナショナル」という部門に移すことを検討するようリレーションシップマネージャーらに要請し始めている。同部門は資産管理のデジタルツールとより迅速な口座開設で収益拡大を目指すという。米国、貿易戦争で中国より優位に-少なくとも金融市場で 米国は、少なくとも金融市場においては対中貿易戦争で中国より優位に立ちつつある。 米国債は今年の上昇を維持しており、ドルは3回の利下げにもかかわらず引き続き堅調。米株は最高値を更新している。一方、中国株や人民元、中国債はこのところ勢いを失っている。 金融市場での米国の優位性はこの数カ月、特に際立っており、S&P500種株価指数の上海総合指数に対する比率は過去最高水準にある。 こうした違いは、両国の金融市場のセンチメントをけん引する力の相違点を浮き彫りにしている。米経済が予想以上の好調を保つ中、米金融当局のこの1年のハト派への傾きは米国のリスクセンチメントを下支えしてきた。一方、中国人民銀行(中央銀行)は、予想を下回る経済指標が続く中、刺激策への穏健なアプローチを堅持している。中国経済は少なくとも1990年代前半以来の低成長となっている。 申万宏源集団の国際ビジネス部門ディレクター、ジェリー・アルフォンソ氏は、「米株式市場は実に好調だが、中国株に年初見られた勢いはやや失速した」と指摘。「貿易問題を巡る状況よりも、中国経済の減速が投資家心理にはるかに影響している」と説明した。(ロイター)日経平均は続落、米中対立に新要素 3日連続で売買代金2兆円割れ[東京 29日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は続落。前日の米国株式市場は感謝祭に伴い休場だったことから手掛かり材料に欠ける中、円安を好感して高値圏で寄り付いた。その後は為替相場に連動しながら前日終値付近で一進一退していたものの、アジア株が下落したことが嫌気された。香港ハンセン指数.HSIは2%超安となり、投資家心理を圧迫、日経平均は下げ幅を拡大した。商いは細り、東証1部の売買代金は3日連続の2兆円割れとなった。 トランプ米大統領が「香港人権・民主主義法案」に署名し、同法が成立したことを受け、米中対立に「人権カード」という新しい要素が加わった。両国が進める通商協議が難航することも予想され、香港ハンセン指数や上海総合指数.SSECをはじめとするアジア株が下落。為替のドル/円は109円台半ばで円安基調となっていたものの、積極的に買い上げていく材料に乏しく、上値は伸びなかった。 TOPIXも続落。東証33業種では、ガラス・土石製品、輸送用機器、金属製品などが値下がり率上位。一方、鉱業、証券業、パルプ・紙の3業種は買われた。 市場からは「需給が弱いが、週末なのでこの辺が居心地のいい水準。100円安程度であれば許容範囲」(国内証券)との声が出ていた。 個別銘柄では、ぐるなび(2440.T)と「食べログ」を運営するカカクコム(2371.T)が売られた。公正取引委員会が飲食店情報サイトを対象に実態調査を進めているとの報道が嫌気された。報道によると、公正取引委員会は、飲食店情報サイトによる一部レストランなどでの予約座席の囲い込みを問題視しているという。 東証1部の騰落数は、値上がり856銘柄に対し、値下がりが1184銘柄、変わらずが117銘柄だった。 (株探ニュース)【市況】後場に注目すべき3つのポイント~新規材料難のなか薄商いで狭いレンジ推移29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続落、新規材料難のなか薄商いで狭いレンジ推移・ドル・円は上げ渋り、日本株などの軟調で・値下がり寄与トップはリクルートHD、同2位はTDK■日経平均は小幅続落、新規材料難のなか薄商いで狭いレンジ推移日経平均は小幅に続落。31.55円安の23377.59円(出来高概算4億1689万株)で前場の取引を終えた。前日の米国市場は感謝祭の祝日で休場。米中貿易協議に関する新しいヘッドラインも見当たらない中、1ドル=109円50銭台後半と円安基調に弱含んだ為替を材料に日経平均は反発して始まった。ただ、その後再び1ドル=109円台前半に戻したことから下げに転じ、結局、日経平均は前日比マイナスで折り返している。前日の日経平均は、取引開始直前にトランプ米大統領による「香港人権・民主主義法案」の署名報道が伝わったことで市場センチメントが後退し、5日ぶりに反落した。上述の法案署名による米国株式市場への影響を見極めたいとの思惑もあり、本日の日経平均はほぼ対ドルでの為替の動きと連動する展開となった。セクターでは、鉱業、証券業、非鉄、パルプ、電機などがプラスで推移する一方、サービス業、精密業、建設業、卸売業、不動産業などがマイナス推移。売買代金上位では、半導体事業の売却発表から収益力向上の期待が高まっているパナソニックや、先日国内証券による目標株価の引き上げがあったレーザーテクが大きく上昇している。その他、ソニー、村田製作所、ファナックなど、取引前半の円安を背景に半導体関連を中心とした電気機器や機械といった景気敏感株が強含んで推移した。日経平均は引き続き23500円前後の水準での値固めとなっている。昨日にも説明したように、24000円を窺うようなもう一段の上値を追う動きは米中貿易協議に具体的な動きが見られない限りは難しいだろう。ただ、こうしたもどかしい中でも、日々下値が堅いことが確認されることはセンチメントを明るくさせよう。昨日発表された投資主体別売買動向によれば、7週連続で買い越してきていた海外投資家が8週ぶりに売り越しに転じた一方で、6週連続で売り越していた個人投資家が逆に買い越しへと転じてきており、10月以降の上昇相場に乗り遅れていた個人の押し目買い需要の強さが確認される形となった。こうした事に加え、9月末配当の再投資や買い余力を依然残している日銀のETF買いなどの思惑も下支えとして意識され、日経平均は引き続き底堅さを保つことが予想される。東証1部市場の大型株の細かい動向を確認してみると、上昇相場の前半にけん引役となっていた半導体関連の代表格である東エレクが10月末の終値から昨日まででみて2.5%程度の上昇であるのに対し、東証業種別で機械株の時価総額上位にあるSMCは7%近い上昇を見せており、物色の矛先が半導体から機械など景気敏感業種の中で広がっていることが分かる。その他、11月に入ってJASDAQ平均が引き続き年初来高値を更新し続ける中、出遅れていたマザーズ指数も52週移動平均線を上抜いてくるなど、物色が大型株から中小型株へと転じてきていることからも、買いの対象が幅広く巡っていることが分かる。こうした背景からも市場環境の良好さが窺えよう。29日の米国市場が短縮取引であることや11月最終週末であることなどから、後場の東京市場は引き続き薄商いとなることが予想される。そのため、昨日同様、この先も幕間つなぎ的なかたちでマザーズ市場を中心とした中小型物色が中心となることが予想される。■ドル・円は上げ渋り、日本株などの軟調で29日午前の東京市場でドル・円は上げ渋り。国内勢の買いが先行したが、日本株などの軟調地合いが嫌気されドルは失速した。ドル・円は、朝方から月末に伴う国内勢の買いが先行し、109円60銭まで値を上げた。ただ、日経平均株価が下げに転じると国内勢の買いは一巡し、ドルは109円40銭台に失速している。ランチタイムの日経平均先物はマイナス圏で推移しており、日本株安継続を警戒した円買いに振れやすいようだ。上海総合指数やハンセン指数も軟調地合いが続き、今晩の株安が警戒されているもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円48銭から109円60銭、ユーロ・円は120円50銭から120円66銭、ユーロ・ドルは1.1008ドルから1.1013ドルで推移した。■後場のチェック銘柄・ブティックス、阿波製紙など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値下がり寄与トップはリクルートHD、同2位はTDK■経済指標・要人発言【要人発言】・黒田日銀総裁「物価が持続的に下がる意味でのデフレではない」【経済指標】・日・10月有効求人倍率:1.57倍(予想:1.56倍、9月:1.57倍)・日・10月失業率:2.4%(予想:2.4%、9月:2.4%)・日・11月東京都区部消費者物価指数(生鮮品除く):前年比+0.6%(予想:+0.6%、10月:+0.5%)・日・10月鉱工業生産速報値:前月比-4.2%(予想:-2.0%、9月:+1.7%)<国内>・黒田日銀総裁講演(パリ・ユーロプラス主催フォーラム)<海外>・16:00 独・10月小売売上高(前月比予想:+0.2%、9月:0.0%←+0.1%)(GDO)国内女子メジャー第4戦 LPGAツアー選手権リコーカップ 2日目今季優勝者ら32人によるシーズン最終戦は、大会2勝のテレサ・ルー(台湾)が3バーディ、1ボギーの「70」でプレーし、通算7アンダーで単独首位をキープして折り返した。「68」としたペ・ソンウ(韓国)が通算5アンダー2位。逆転での賞金女王へ単独2位以上が最低条件となる賞金ランキング3位の渋野日向子は4番でボギー先行も、3バーディを取り返して連日の「70」をマーク。イ・ボミ(韓国)とともに、通算4アンダー3位タイの好位置につけて残り36ホールに臨む。賞金ランキング1位の鈴木愛と同2位の申ジエ(韓国)は、通算1オーバー17位タイで並んだ。鈴木は1バーディ、2ボギーの「73」とスコアを落とした一方、初日26位と出遅れた申は4バーディ、2ボギーの「70」と伸ばして週末に弾みをつけた。<上位成績>1/―7/テレサ・ルー2/-5/ペ・ソンウ3T/-4/渋野日向子、イ・ボミ5/-3/古江彩佳国内男子 カシオワールドオープン 2日目ツアー初優勝を目指す33歳の小林伸太郎が7バーディ、2ボギーの「67」でプレー。通算10アンダーで2位から単独首位に浮上した。通算8アンダー2位に「65」でプレーしたアンソニー・クウェイル(オーストラリア)。首位から出た宮本勝昌は「71」とし、松原大輔、香妻陣一朗、小田孔明、額賀辰徳と並んで通算7アンダー3位に後退した。賞金ランキング2位のショーン・ノリス(南アフリカ)は通算6アンダー8位。同ランキング5位の石川遼は「70」でプレーして、通算5アンダー12位につけた。2年連続の賞金王を目指す同ランキング1位の今平周吾は通算1アンダー48位で決勝へ進んだ。前年覇者のチェ・ホソン(韓国)が通算3オーバー89位で予選落ちを喫した。賞金ランキング上位65人を争う来季シード争いは、圏外で決勝ラウンドに進めなかったプラヤド・マークセン(70位)、上井邦裕(75位)、竹安俊也(76位)、セン世昌(77位)、谷口徹(99位)、大堀裕次郎(111位)らの賞金シード喪失が決まった。谷口は2018年「日本プロ」優勝により23年までシードを有しているが、連続賞金シードは22年で途切れた。<上位成績>1/-10/小林伸太郎2/-8/アンソニー・クウェイル3T/-7/宮本勝昌、松原大輔、香妻陣一朗、小田孔明、額賀辰徳8T/-6/中西直人、キム・キョンテ、スンス・ハン、ショーン・ノリス(msn)(日経スタイル)売られる別荘地軽井沢、買い手なく 創業者ら遠のき… 日本を代表するリゾート、長野県軽井沢(長野県軽井沢町)の別荘地で異変が起きている。政財界の著名人の別荘なども建ち軽井沢のなかで最も地価が高いとされる旧軽井沢やその隣接地域の超一等地でも売り物件が目立ち、なかなか買い手がつかないという。高級別荘地の代名詞、軽井沢でいま何が起きているのか。■700坪余りの土地が3.8億円で売りに11月上旬の土日ともなると旧軽井沢銀座通りは紅葉狩りとお土産目当ての訪日外国人でにぎわう。ここから徒歩圏にある別荘地に向かうと、「売物件」と書かれた看板が点在する。地元の不動産会社の店長は「最近は旧軽井沢エリアなどの超一等地でも売り物件が目立ってきた」と語る。売り物件の中には看板を立てずに売られているものもある。「700坪(1坪=3.3平方メートル)余りの土地が3億8000万円で売りに出されている」(不動産会社の営業担当者)。前出の不動産会社の店長によると、旧軽井沢で信託銀行系列の不動産会社の紹介で坪単価70万円、総額5億円にのぼる別荘地が売りに出された。■1部上場の創業家や旧財閥系、内々で売れず売りに出ている超一等地の坪単価は60万~70万円程度だ。別荘地の動向に詳しい不動産会社の社長は「一等地の言い値とはいえ軽井沢で70万円もの坪単価は高い。実勢価格は半額程度ではないか」と指摘する。超一等地の売り手は、「東証1部上場企業の創業家や、日本を代表する旧財閥の家筋」(地元の不動産会社の営業担当者)という。東京・田園調布の一等地と同様に相続や世代交代の影響が大きいようだ。従来なら、超一等地の売り手は名前とともに物件情報が表に出ることを嫌い、内々で買い手を探して売却してきた。ところが、3億、5億円といったまとまった資金を用意できる買い手が不在となり、内々では売れず、売り物件として表に出るようになったとみられる。■軽井沢のブランド力も低下別荘はお金がかかる。古い建物がある場合、解体したり再利用したりする違いはあっても、敷地内を整備して調度品などをそろえると、別荘地の購入費の2倍はかかるといわれる。5億円で買えば10億円必要だ。これだけの資金力のある買い手はいるのか。2000年のIT(情報技術)バブルのころ、新規株式公開(IPO)で莫大な利益を手にした創業者のなかには軽井沢に別荘地を購入したり、検討するケースは多かったという。最近のIPOは小粒になったうえ、「軽井沢のブランド力低下もあって創業者による別荘地の需要は以前に比べ激減している」(大手不動産会社の社長)のが現状だ。以前から軽井沢で別荘を求める中心層は医師だ。「建物が築5年、古くても10年以内で、土地と合わせて7000万円程度、高くても1億円まで」(地元の不動産会社の店長)というニーズが多い状況では、3億~5億円の物件は手が届かない。■海外からの引き合いも少なく地元の不動産会社に海外投資家からの引き合いについて水を向けると、「リーマン・ショックの後ほど目立たない。不良債権処理の一環で複数の物件をまとめて売るバルクセールの中に軽井沢の別荘地が入っていて取引される程度」と語る。超一等地の物件は果たして売れるのか。どの不動産会社に聞いても「売り手は倒産したりお金に困ったりしているわけではないので、言い値を下げない。現状の値段では売れないだろう」と話す。バブルのころは旧軽井沢近辺で坪当たり200万円台、旧軽井沢では同300万円台で取引が成立した物件もあるという。その後の景気悪化に伴い軽井沢の別荘地の値段は一気に下落した。「値段の底は2004年ごろ。最高値の10分の1にあたる坪25万円程度で成約(取引が成立)した。当時は競売でも物件が落ちないこともあった」と地元の不動産会社の店長は振り返る。超一等地が売りに出るのは、「さらなる地価上昇は見込めないという売り手の相場観を反映するため、不動産市況で価格がピークから下落に転じる転換点を示唆している」(外国証券の不動産アナリスト)といわれる。東京・銀座やその周辺の商業地では海外の不動産ファンドが大型商業ビルの売り時を探っているという話が聞こえてくる。軽井沢の別荘地も例外ではなく、潮目の変化を示している。〔日経QUICKニュース(NQN) 齋藤敏之〕(goo)(読売新聞)オービス画像「被告と断定できず」…高検上告せず、逆転無罪確定 速度違反自動監視装置(オービス)の画像に写ったドライバーが被告本人か、友人かが争われた裁判で、「被告が犯人と断定できない」として逆転無罪を言い渡した福岡高裁判決について、福岡高検は上告期限の28日までに上告せず、無罪が確定した。高検は「適切な上告理由を見いだすことは困難と判断した」としている。1審・福岡地裁判決は被告が運転したと判断し、求刑通り罰金5万円としたが、高裁判決は破棄していた。(goo)(西日本新聞)速度違反に逆転無罪 「オービス画像不鮮明」 福岡高裁 福岡県福津市の国道でスピード違反をしたとして道交法違反の罪に問われた同県内の女性被告(25)の控訴審判決で、福岡高裁は14日、求刑通り罰金5万円とした一審福岡地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。野島秀夫裁判長は、速度違反取り締まり装置(オービス)と女性の顔を比較し、同一人物である可能性を示した鑑定結果について「一審判決は評価を誤っており、不合理だ」と述べた。 女性は2015年1月、福津市の国道で、制限速度を35キロ上回る時速95キロで自動車を運転したとして在宅起訴された。一審の公判では、証人として出廷した女性の友人が「運転したのは私」と名乗り出て、誰が運転していたのかが争点となっていた。 判決理由で野島裁判長は、一審判決が有罪の根拠とした鑑定結果について「オービスの画像は不鮮明な上、顔の部位の位置関係が全て合致しているわけでもない」と指摘。「鑑定のみに依拠して犯人と被告の同一性を認めた一審判決は是認できない」とした。 さらに運転に至る経緯などを踏まえると、自分が運転したと主張する友人の証言は、信用性が全くないとは言い切れないと判断。「被告か友人、それ以外の人物が運転した可能性は排除できない」と結論付けた。 福岡高検は「判決内容を精査、検討し適切に対処したい」としている。 (鶴善行)今日は11月29日=良い肉の日ですね。奥がいい肉をキロ単位で買い込んできました。夕食はスキヤキです…ワインと共に楽しみましょう。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-続落でも週間では上昇、来週は楽観ムードが優勢か 29日の日経平均は続落。終値は115円安の23293円。米国株が休場で手がかりが少ない中、上昇して始まったもののほぼ寄り付き天井。じわじわと値を消し、前場のうちに下げに転じた。後場は香港株の下げが大きくなったことが嫌気されて、売りの勢いが一段と強まった。米株先物も弱く、他のアジア株も連れ安するなどリスク回避の流れとなり、下げ幅を3桁に拡大。23300円を割り込み、ほぼ安値圏で取引を終えた。一方、マザーズ指数とジャスダック平均はプラスを保っており、新興市場の堅調さが光った。東証1部の売買代金は概算で1兆7500億円。業種別では鉱業、証券・商品先物、パルプ・紙が上昇しており、プラスはこの3業種のみ。一方、ガラス・土石、輸送用機器、金属製品などの下げが大きかった。技術戦略説明会の内容が好感された東芝が大幅高。半面、上期の最終赤字幅が拡大したユー・エム・シー・エレクトロニクスが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり856/値下がり1184。半導体事業の譲渡を正式発表したパナソニックが大幅上昇。上方修正を発表した土屋HDや集英社との業務提携を発表したLink-Uがストップ高となるなど、地合いが悪い中でも好材料のあった銘柄には資金が殺到した。大真空や昭和真空が個別に賑わい、新興市場優位の中でワークマンが買いを集めた。一方、トヨタや日立が軟調。リクルートHDやKDDIなど、内需の一角も弱い動きとなった。飲食店情報サイトによる予約席の囲い込みを公正取引委員会が問題視していると報じられたことを受けて、ぐるなびやカカクコムが大幅安。直近で買いを集めていたカイオムやDWTIなど創薬ベンチャー株が売りに押された。 日経平均は後場に入って下げ幅を拡大。終値(23293円)では5日線(23361円、29日時点、以下同じ)を割り込んだ。来週は下に控えた25日線(23198円)辺りまでで下げ止まり、早々に5日線上を回復できるかが注目点となる。12月に入り、小売などを中心に、11月の月次が多く出てくる。10月は増税実施月で各社需要の落ち込みを防ぐ対応に力を入れていたであろうから、そういった影響が一段落した11月の数字は、先行きを占う上でも要注目だ。増税が痛手となったところ、企業努力で克服したところ、また、消費者の節約志向を追い風にできているところなど各社さまざまであろうから、結果を踏まえた個別の選別が進むと考える。また、悪影響がそれほど大きくなかった場合には、全体市場への好影響が期待できる。この場合、クリスマスや年末にかけては消費者の財布の紐が緩む展開が期待できるという点から、小売株を見直す動きが強まると考える。【来週の見通し】 堅調か。米中交渉関連のニュースに一喜一憂する地合いは続くだろうが、米国の年末商戦に関するニュースも多く出てくると予想される中、楽観ムードが優勢になると予想する。直近で発表された米国の7-9月期GDP改定値や10月耐久財受注などは良好な内容となり、米国株高やドル高(円安)を促した。来週も米国では11月ISM製造業および非製造業の景気指数、10月製造業受注など注目の指標発表が多い。これらが安心感のある内容となれば、米国株の上昇にも寄与すると見込まれる。悪かった場合でも、金融緩和継続期待が高まることから、大きく崩れる展開にはなりづらいと考える。【今週を振り返る】 総じて堅調となった。米中通商合意期待の高まりを受けて日経平均は週初から水準を切り上げると、26日には取引時間中の年初来高値を更新した。高値警戒感が強まったことからその後の上値は重くなった。また、トランプ大統領が香港人権法案に署名したことで米中交渉への楽観的な見方が後退してからは、売りに押される場面も増えた。しかし、為替市場で円安が進んだことが下支えとなり、週間では上昇を達成した。米国株が感謝祭休場を挟む週であったため、商いは低調となった。また、出遅れ感のあったマザーズ指数に関しては、強含む動きが見られた。日経平均は週間では約181円の上昇。週足ではほぼ横ばいに近いものの、3週ぶりに陽線を形成した。【来週の予定】 国内では、7-9月期法人企業統計、11月新車販売台数(12/2)、10月毎月勤労統計、10月家計調査(12/6)がある。 企業決算では、伊藤園、ロックフィール、ザッパラス、ゼネパッカー、ピープル(12/2)、アインHD(12/3)、オリバー、モロゾフ、ティーライフ、Link-U、不二電機、楽天地(12/4)、ファーマフーズ、ラクーンHD、アルチザ、スバル興(12/5)、積水ハウス、日駐、ケア21、鳥貴族、ポールHD、エイチーム、ソフトウェアサー、アイル、gumi、ユークス、HEROZ、日本スキー、巴工業、インスペック、トミタ電機、エイケン工業、トップカルチャ、光・彩、カナモト、精養軒、丹青社(12/6)などが発表を予定している。 海外では、中国11月製造業PMI(11/30)、米11月ISM製造業景気指数、米10月建設支出、米サイバーマンデー(12/2)、米11月ADP全米雇用リポート、米11月ISM非製造業指数(12/4)、米10月貿易収支、米10月製造業受注、OPEC定例総会(12/5)、米11月雇用統計、米10月消費者信用残高、非加盟国を含めたOPECプラス会合(12/6)などがある。 米企業決算では、セールスフォース・ドットコム(12/3)、ティファニー、ダラーゼネラル(12/5)などが発表を予定している。NY為替見通し=ブラック・フライデーで閑散取引の中、米中関連の報道に要警戒か 本日のNY為替市場のドル円は、ニューヨーク市場が感謝祭翌日のブラック・フライデーで閑散取引の中、引き続き米中通商関連の報道に警戒する展開が予想される。 本日のニューヨーク市場は、債券・株式・商品市場は短縮取引となる。 月末のロンドンフィキシング(30日午前1時)では、ポートフォリオ・リバランスのドル売りが警戒されており、要警戒となる。 ドル円は、2日のNYカットオプションが109.50円と109.52円、本日のNYカットオプションが109.35円に控えており、値動きを抑制することが予想される。上値には、109.60-80円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買い、下値には、109.30円にドル買いオーダー、割り込むとストップロス売りが控えており、サプライズ的な発言や報道には要警戒か。 中国政府はトランプ米政権が「香港人権・民主主義法案」を成立させたことで報復措置を示唆しており、香港に干渉していると見なす米企業や個人をリスト化し、中国市場から締め出すことを検討している、と報じられている。 楽観的な見方としては、12月15日の対中制裁関税第4弾の発動を控えて、通商合意を優先させて報復措置を控える場合となる。 悲観的な見方としては、報復措置を発動することで、米中通商協議が決裂した場合となる。・想定レンジ上限 ドル円の上値の目処(めど)は、ダブル・トップのネック・ラインの109.71円。・想定レンジ下限 ドル円の下値の目処(めど)は、日足一目均衡表・転換線の108.95円。NY株見通し-底堅い展開か 午後1時までの短縮取引 今晩のNY市場は底堅い展開か。感謝祭の休日前の27日は強い経済指標が好感され主要3指数がそろって4日続伸し、史上最高値の更新が続いた。休場の27日にトランプ米大統領が「香港人権法・民主主義法」に署名し、法案が成立したことで米中通商合意の行方が懸念されるものの、感謝祭のオンライン販売が前年同期比20%近い伸びとなったとの報道もあり、ブラックフライデー、サイバーマンデーの消費も好調が見込まれる。今晩は、午後1時までの短縮取引で市場参加者も少ないと思われるが、クリスマス商戦への期待などを背景に底堅い展開が期待できそうだ。 今晩は主要な経済指標や決算発表はなし。 (yahoo)(モーニングスター)今晩のNY株の読み筋=手じまい売り優勢か きょうの米国株式市場は、ブラックフライデーで短縮取引となる。きのうの感謝祭の祝日に絡み連休をとる市場関係者も多く、薄商いが見込まれる。 一方、きのうの米国株式市場休場の流れを受けて始まった日本株式市場は買い先行で始まったものの、米国での香港人権法の成立を契機とした米中関係の先行き不透明感が強まり、結局、日経平均株価は続落して引けた。中国では上海総合指数、香港ハンセン指数ともに売られた。 香港人権法を成立させた米国に対し中国が報復措置を慎重に検討している最中、休日前に主要3指数が史上最高値を付けた米国株は上値追いとはなりにくい。少ない市場参加者がポジションを手じまう流れが強まりそうだ。<主な米経済指標・イベント>米ブラックフライデー(株式・債券市場短縮取引)(日付は現地時間)来週の日本株の読み筋=米中協議などにらみ神経質な展開か 来週(12月2-6日)の東京株式市場は、神経質な展開か。米国での「香港人権・民主主義法」の成立を契機に米中関係に不透明感が漂っており、米中貿易協議の行方をにらみつつ、投資家心理が揺れる可能性がある。 日経平均株価は予想PER14倍で割安是正は一巡したとの見方が出ている。市場では、「次に良い話が出てくるまでは、しばらくは日柄調整か」(中堅証券)、「26日に上ヒゲ陰線を引いた後、陰線が続いており、上値の重さが意識される」(準大手証券)などの声が聞かれた。 ただ、米国では11月29日のブラックフライデーで年末商戦が幕開けし、12月2日にはネット通販のサイバーマンデーを迎える。この週は米商戦を刺激に円安・ドル高に傾きやすい特性があり、好調な米経済を踏まえると例年通りの動きを示す下地があり、サポート要因になり得る。師走相場に突入し、中・小型株への物色傾向が一段と強まることも想定される。 スケジュール面では、国内で12月2日に7-9月期法人企業統計が発表される。海外では2日に米11月ISM製造業景況指数、4日に米11月ADP雇用統計、米11月ISM非製造業景況指数、5日に米10月貿易収支、6日に米11月雇用統計などが予定されている。 11月29日の日経平均株価は続落し、2万3293円(前日比115円安)引け。朝方は、為替相場の落ち着きを支えに買いが先行し、寄り付き直後に90円近く上昇したが、一巡後は米中協議への警戒感もあり、利益確定売りに傾き、下げに転じた。香港ハンセン指数や中国・上海総合指数が下げ基調となり、時間外取引の米株価指数先物安も重しとなり、後場終盤には下げ幅が130円を超えた。(yahoo)(時事通信)〔ロンドン外為〕円、109円台半ば(29日午前9時) 【ロンドン時事】週末29日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、薄商いの中を1ドル=109円台半ばで推移した。午前9時現在は109円50~60銭と、前日午後4時(109円50~60銭)比変わらず。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1000~1010ドル(1.1000~1010ドル)。対円では同120円55~65銭(120円50~60銭)。(了) 〔NY外為〕円、109円台半ば(29日朝) 【ニューヨーク時事】休日明け29日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、1ドル=109円台半ばで小動きとなっている。午前8時45分現在は109円55~65銭と、前営業日午後5時(109円51~61銭)比04銭の円安・ドル高。 28日の感謝祭休日に伴い週末にかけて連休を取る市場参加者が多く、薄商いとなっている。この日は米主要経済指標の発表がなく、売り買いのきっかけとなる材料にも乏しい。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.0985~0995ドル(前営業日午後5時は1.0994~1004ドル)、対円では同120円45~55銭(同120円42~52銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、ナスダックともに反落(29日朝) 【ニューヨーク時事】休日明け29日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の行方に不透明感が強まり、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前営業日(27日)終値比84.91ドル安の2万8079.09ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は21.33ポイント安の8683.85。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の27銘柄が値を下げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を下げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の5銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では1銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.29
コメント(0)
-
11月28日(木)…
11月28日(木)、曇りです。6時25分に起床しましたが、まだ日の出前です…。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時30分頃には家を出る。ゴルフではありません…、久しぶりのアルバイト業務です。本日は8:30~15:30とのこと。定刻にスタートすると、なかなかにハードです…。11時45分頃に人波が切れた…と思ったら、スタッフから午後の予定の人もほとんど午前中に来ちゃいました…とのこと…。どうなってるの…。忙しいはずだわ…。午後の分はもうわずかなのでこちらで処理するから帰ってもいいですよ…とのこと…。ありがたく帰らせていただきます。帰宅して、昼食にラーメンを食べて一休み…。1USドル=109.44円。1AUドル=74.02円。昨夜のNYダウ終値=28164.00(+42.32)ドル。現在の日経平均=23412.40(-25.37)円。金相場:1g=5681(-3)円。プラチナ相場:1g=3575(-34)円。(ブルームバーグ)日本株は機械や商社安い、電機や医薬品高い-株価指数は方向感乏しい 28日の東京株式相場は下落。米中通商協議に関する不透明感が高まったことから機械や商社が安いほか、陸運や建設、サービスなど内需も下げている。半面、米景気指標の底堅さから電機や精密機器、鉄鋼は買われ、医薬品も高い。 TOPIXは前日比0.43ポイント(0.03%)安の1710.55 日経平均株価は16円19銭(0.07%)高の2万3453円96銭 〈きょうのポイント〉 米大統領は香港人権法案に署名とホワイトハウスが発表 きょうのドル・円相場は1ドル=109円40銭近辺、昨日は一時109円60銭台まで円安が進展 7-9月の米実質国内総生産(GDP)改定値は2.1%増に上方修正、在庫が寄与 10月の米耐久財受注はコア資本財が予想外の増加-1月以来の大幅増 しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹運用部長は「本来もう少し堅調かと予想していたが、香港人権法案成立で若干懸念材料が広がったことと株価上昇で値幅が出たため利益確定も出ている」と述べた。 続伸して始まった株価指数は、米国株先物が軟調に推移する中で下落に転じる場面もみられるなど方向感が出にくくなっている。米大統領の香港人権法案署名後、中国は報復をあらためて警告したが詳細は示さなかった。きょうの中国上海総合指数は前日終値を挟んでもみ合いとなっている。 野村証券投資情報部の若生寿一エクイティ・マーケット・ストラテジストは、GDPや耐久財受注などきのう発表の米指標について「米金融当局が経済の下振れリスクは限定的として金融政策を様子見できるとした流れに沿った内容。マーケットとしては一定の安心感が出る内容だ」と評価。香港人権法案については「中国政府が通商協議にリンクさせるのかを確認しなければならない」とも話していた。 東証33業種では陸運や電気・ガス、機械、卸売、鉱業、建設、サービスが下落 鉄鋼や石油・石炭製品、保険、精密機器、医薬品、電機、証券・商品先物取引は上昇金価格は約3倍も、NY市場で行使価格4000ドルのオプション大口取引 金オプション市場では27日、金相場が1年以上先に過去最高値を超えて3倍近くに急騰することに賭ける175万ドル(約1億9200万円)相当のブロック取引が見られた。 ニューヨーク市場では27日正午ごろ、2021年6月に1オンス当たり4000ドルで買う権利を保有者に与える金オプションが5000ロット売買された。このオプションは1オンス当たり3.50ドルで売却された。 BMOキャピタル・マーケッツの金属デリバティブ(金融派生商品)取引責任者、タイ・ウォン氏は電子メールで「1年半の定期生命保険のようだ。金価格が4000ドルを付ければ世界はどうなるだろう」と述べ、このコールオプションを購入した人は「急激な動きを期待している」と指摘した。 金先物は2011年に1オンス=1923.70ドルの最高値を付けた。今年は14%上昇したが、依然として史上最高値を24%下回っている。パナソニックが半導体事業から撤退へ、台湾の新唐科技に売却-報道 パナソニックは、半導体の開発・製造・販売を手掛ける全額出資子会社パナソニックセミコンダクターソリューションズを台湾の新唐科技(ヌヴォトン・テクノロジー)に売却する。日本経済新聞が情報源を明らかにせずに報じた。 同紙によれば、パナソニックセミコンダクターソリューションズとイスラエルの半導体企業タワーセミコンダクターとの合弁会社パナソニック・タワージャズセミコンダクターの3つの半導体生産施設も手放す。 新唐科技は、台湾の半導体メーカー、華邦電子(ウィンボンド・エレクトロニクス) が過半数の株式を保有し、傘下に置く。 パナソニックの広報担当、渡辺やよい氏は「事業改革についてさまざまな可能性を検討していることは事実」と、ブルームバーグニュースの取材に対して発言。「開示すべき事実が発生した場合、速やかに公表する」と述べた。東証業種別で「奇妙な同居」-電機と医薬品の高値は気迷い示唆か 東京株市場で景気敏感の代表である電機とディフェンシブの代表である医薬品の上昇が同時に進行している。一見奇妙なこの現象は上値追いに慎重になる兆しとの見方が市場関係者の間から出ている。 東証33業種で27日に年初来高値を更新したのは電機や精密機器、医薬品、情報・通信、証券・商品先物取引、サービスの6業種。市場全体の値動きを示すTOPIXがことし高値を更新する中で、高値業種では電機と医薬品が並んだ。きょう午前終値時点でも両業種はともに上昇している。 野村証券投資情報部の若生寿一エクイティ・マーケット・ストラテジストは、輸出関連の中でも輸送用機器や機械が直近高値を上回っていないなど、景気敏感業種の裾野に広がりが見られないと指摘。一方で医薬品が高値を付けたことは「マーケットが景気の先行きに両にらみであることを示している。来期以降の企業業績に気迷いが残っていることの表れ」と述べた。 若生氏によると、同証予想の日経平均の12カ月先1株利益は約1700円。2016年以降のPERが12-14倍で推移していたことから、上限に評価して2万3800円。きのう終値は2万3437円と上限に接近しており、「新規に買うには来期業績回復の確度が高まるなどもう少し理由が欲しい。長期的な視点からは、上がれば売っていく方が適している可能性がある」と、若生氏は話していた。(ロイター)ドル109円半ば、米中対立に再度警戒[東京 28日 ロイター] - 正午のドルは前日NY市場終盤から小幅安の109円半ば。トランプ米大統領が現地時間27日夜、香港の反政府デモを支援する「香港人権・民主主義法案」に署名したことで、米中対立への警戒感が強まった。ドルは一時109.33円まで下落した。 市場では「中国の出方によっては、再び市場でリスクオフムードが高まり、円が買われる可能性がある」(外銀)との声が出ていた。 中国政府は28日、「断固とした報復措置」を取ると表明した。アングル:来年の株式市場、投資家は米国外に注目か[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米株式市場は過去最高値を更新し続け、S&P総合500種指数は年初から25%近く上昇している。ただ投資家は来年、より魅力的なバリュエーションを求めて米国外の株式に目を向ける可能性が高い。 米投資信託協会(ICI)によると、9月初旬から資金流出超が続いていた世界の株式ファンドには過去2週間で82億ドルが流入した。一方、米株式ファンドからはここ2週間で100億ドル以上が流出した。 欧州の一部地域やアジアで経済ファンダメンタルズに改善の兆しが見られる一方で、米経済成長は鈍化しつつあるもようで、米国外の株式市場へ資金シフトがシフトしている。 世界の株式を対象とする代表的な株価指数MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)は既に、2018年1月に記録した過去最高値に迫っている。 だが、過去10年のほとんどの期間において米国株の上げに追いついていなかったため、米国以外の株式市場は、そのバリュエーションの低さから今後1年、米国株をアウトパフォームする機会があると運用担当者やアナリストは見込んでいる。 エバーモア・グローバル・アドバイザーズのデービッド・マーカス最高投資責任者(CIO)は「バリュエーションがリターンのけん引役になりつつある」と述べ、ベルギーに拠点を置く医療検査機器メーカーのファグロン(FAGRO.BR)やフランスのメディア大手ボロール(BOLL.PA)など、欧州株に資金をシフトしていると説明した。 リフィニティブのデータによると、STOXX欧州600種指数の予想株価収益率は15.4倍。一方、S&P総合500の19.3倍。 Federated International Small-Mid Companyファンドのポートフォリオ・マネジャー、トーマス・バンクス氏は「これまでの米国株の高いバリュエーションの一部は、米経済成長率が(他国よりも)ずっと速いペースだったことに正当化されている。ただ、今後貿易協定が発表されたり、友好的なブレグジット解決策が出たりすれば、成長率の差は収束に向かう可能性がある」と述べた。 同氏は、 ロンドン証券取引所(LSE)グループ(LSE.L)や、スウェーデンに拠点を置くカジノゲーム運営会社、エボリューション・ゲーミング・グループAB(EVOG.ST)に対して引き続き強気という。両社は年初から50%上昇している。 米商務省が発表した第3・四半期の実質国内総生産(GDP)改定値(季節調整済み)は年率換算で前期比2.1%増と、速報値の1.9%増から上方改定された。成長率は昨年の2.9%から確実に鈍化している。第2・四半期の伸びは2%止まりだったほか、今年前半も2.6%と、トランプ政権が目標に掲げる3%に届いていない。[nL4N2873QM] 一方、欧州連合(EU)の欧州委員会は、ユーロ圏成長率について、2018年の4年ぶり低水準から引き続き低下するとの市場の見方に反して、2020年にわたり年率1.2%成長すると予想している。 Davis Internationalファンドのポートフォリオ・マネジャー、ダントン・ゴエイ氏は、バリュエーションがより魅力的なことから、インドや中国の内需の恩恵を受けることが見込まれるアジアの株式や多国籍企業に積極的に投資していると説明した。 ネットサービス大手騰訊控股(テンセント・ホールディングス)(0700.HK)など収益を貿易にさほど依存していない中国企業や、利益追求型の教育関連企業、ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ(EDU.N)などに対して強気だとしている。 「これらの企業への貿易戦争の影響は非常に限定的だが、マクロ面での懸念からバリュエーションは大きく下がっている。非常に堅調な事業があり、バリュエーションがそれと無関係な理由で下がっているとしたら、恐らく良い買い機会だ」述べた。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米国が連日最高値、堅調な経済指標でダウは42ドル高の2万8164ドル[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米国株式市場は続伸し、主要株価指数が連日で最高値で引けた。経済指標で国内景気の底堅さが示されたほか、米中通商協議に対する慎重ながらも楽観的な見方が、引き続き投資家心理を支えた。感謝祭の祝日を前に、商いは薄かった。米商務省が発表した第3・四半期の実質国内総生産(GDP)改定値は年率換算で前期比2.1%増と、速報値の1.9%増から上方改定され、前期から伸びが加速した。また、10月の個人消費支出は前月比0.3%増となり、第4・四半期も緩やかな経済成長が続くことを示唆する内容となった。USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア・インベストメント・ディレクター、ビル・ノーシー氏はこれについて「マクロ面から言えば、成長しつつも引き続き減速という状況に合致している」と指摘。「ここ3カ月間、単なる減速ではないとの懸念がくすぶっていたが、そうした不安がある程度和らいだ」と話した。一般消費財株は0.83%高で上げを主導した。10月の耐久財受注統計でも、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財(非国防資本財から航空機を除く)の受注が9カ月ぶりの大幅な伸びとなった。個別銘柄ではボーイングが1.48%下落。米連邦航空局(FAA)は26日、同社の737MAX機について、今後はFAAのみが耐空証明を発行すると同社に通知した。過去には同社と共同で発行していた。来年の利益減少を警告した農業機械メーカーのディアも4.3%安となった。ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.76対1の比率で上回った。ナスダックでも1.98対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は55億7000万株。直近20営業日の平均は70億6000万株。28日は感謝祭で休場、29日は短縮取引となる。日経平均は5日ぶり反落、香港人権法案を嫌気 米感謝祭控え薄商い終値は28円安の2万3409円[東京 28日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は小幅に5日ぶり反落。米国株高と円安基調が支援材料となり買い優勢で始まったものの、トランプ米大統領が香港人権法案に署名したことが投資家心理を圧迫した。28日の米国株式市場は感謝祭に伴い休場のため、商いは細り、東証1部の売買代金は連日の2兆割れとなった。27日の米国株式市場は、経済指標で国内景気の底堅さが示され、感謝祭の祝日を前に商いは薄いながらも主要3指数は連日の最高値更新。外為市場ではドル/円が109円台半ばまで円安に振れるなど、日本株に追い風が吹く格好となった。トランプ大統領が香港のデモ隊を支援する法案に署名したことに、中国側の反発が懸念され、利益確定売りを急ぐ動きが広がった。前場は前日終値を挟んでもみあい、後場はマイナス圏でじりじり下げ幅を拡大した。市場からは「前日まで4日続伸し高値警戒感が出ていたため、売りが出やすい状況だった。そこに、香港人権法案の成立というネガティブな材料が加わったため、下落した」(国内証券)との声が出ていた。「米国市場への影響を見極めたい投資家が手控えていて、大きく売られているわけではない。ただ、米国市場は28日休場なので、影響は来週以降となる」(同)との指摘もあった。TOPIXも反落。東証33業種では、金属製品、陸運業、鉱業などが値下がり率上位。一方、医薬品、空運業、鉄鋼などは買われた。個別銘柄では、ファルテックは連日の年初来高値更新。東証1部値上がり率も同じく連日のトップとなった。政府が国内で販売される新車に衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)の取り付けを義務づける方針を固めたとの27日の報道が引き続き材料視された。同社は自社開発したミリ波レーダーカバーを商品化している。東証1部の騰落数は、値上がり628銘柄に対し、値下がりが1416銘柄、変わらずが108銘柄だった。(会社四季報オンライン)アルフレッサHDなど医薬品卸4社が続落、大口の見切り売りも アルフレッサホールディングス(2784)やメディパルホールディングス(7459)、スズケン(9987)、東邦ホールディングス(8129)の医薬品卸の大手4社がそろって続落。業界トップのアルフレッサを傘下に持つアルフレッサHDは午後1時23分現在で前日比79円(3.27%)安の2340円で推移している。 27日の取引時間中だった午後2時すぎに、独立行政法人「地域医療機能推進機構」(JCHO)発注の医薬品の納入を巡り談合を行っていた疑いが強まったとして、公正取引委員会が4社の本社に独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で強制調査に入ったと報じられ、各社の株価は引けにかけて下落していた。ただ、大引けまでの時間が短かく、詳細を十分に織り込んでいなかった面もあり、本日は外国人を含む大口投資家からの見切り売りも増えてさらに株価を押し下げているようだ。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】後場に注目すべき3つのポイント~香港人権・民主主義法署名で利食い売りの動きも28日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅に5日続伸、香港人権・民主主義法署名で利食い売りの動きも・ドル・円は下げ渋り、香港人権法案の成立で先行き不透明感も・値上がり寄与トップは京セラ、同2位は信越化学工業■日経平均は小幅に5日続伸、香港人権・民主主義法署名で利食い売りの動きも日経平均は5日続伸。16.19円高の23453.96円(出来高概算4億7502万株)で前場の取引を終えた。前日の米国市場では、トランプ米大統領が米中交渉について「最重要の貿易協議は、生みの苦しみの最終段階にある」などと述べたことで、両国の合意への期待が高まるなか、市場予想を上回る米経済指標が相次ぎ、NYダウは3日連続で最高値を更新した。これを受けて円相場は日本時間で早朝頃までは1ドル=109円台後半の円安水準に弱含んでいたが、取引開始直前に、トランプ米大統領が香港人権・民主主義法に署名したことが伝わり、再び1ドル=109円台前半に押し戻される展開に。こうした流れから、日経平均は結局小幅高で前場取引を終えた。セクターでは鉄鋼業が1%高となったのを筆頭に石油、保険業、医薬品、空運業などがプラス推移した一方で、陸運業や金属、ガス、機械など下落。売買代金上位では、保有する日立化成株を昭和電工に売却する方針が伝えられている日立製作所が2%近い上昇となったほか、ソフトバンクG、任天堂、トヨタ自動車、東エレクなどが小幅高。他方、ソニー、ファーストリテ、村田製作所などが小安い。日経平均が終値で明確に23500円を上抜いて24000円が次の高値目標となってくるためには、米中貿易協議についてもう一段階の進展がない限りは難しいだろう。ただ、上値が重い一方で引き続き下値は堅いとみられる。足元の需給動向としては、投資家別売買動向で見た際の海外投資家が10月以降から11月第2週まで7週連続で買い越してきていることに加えて、9月末配当の再投資の思惑が下支え要因として働いている。その他、各国の経済指標の改善傾向も世界経済の底入れ機運を強め、市場の支えとなっていると考えられる。米国では、先週発表されたフィラデルフィア連銀景況指数(11月)や昨日発表された耐久財受注額(10月)などが市場予想を上回ったほか、7-9月期GDPが上方修正された。また、米国以外では、ドイツのIfo景況感指数(11月)が前回結果を上回り、輸出比率の高い同国経済の底打ち感が強まったことで、世界経済の回復機運に対する期待感も改めて強まってきた。日経平均は、テクニカル的には5日移動平均線が再び上向きに転じてきているほか、ローソク足で見た場合には、一時400円超下落した21日に25日線にワンタッチして反発しており、同移動平均線のサポートラインとしての有効性も増してきている。米中貿易協議の第一段階が合意に至らないなど突発的な外部ショックがない限りは、当面は底堅い押し目買い需要のもと、安定した株価推移となりそうだ。米国株式相場は、28日は感謝祭で休場、翌29日も午後1時までの短縮取引となるため、本日から明日にかけては引き続き薄商いとなりそうだが、この間は、ここのところ騰勢を強めているマザーズ指数を中心とした新興市場の中小型株が幕間つなぎ的なかたちで引き続き買いの対象となりそうである。■ドル・円は下げ渋り、香港人権法案の成立で先行き不透明感も28日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。米国で成立した香港人権法案をめぐり米中貿易協議への先行きを懸念した円買いが強まり。やや警戒感が広がった。トランプ米大統領は27日、米国議会で先に成立した香港人権法案に署名し、同法案は成立した。目先は中国政府の反発が予想され、米中協議は第1段階の合意に至らないとの懸念から円買いが強まる場面もあった。ランチタイムの日経平均先物はマイナス圏で推移し、上海総合指数に続き日経平均株価も下げに転じる可能性があろう。ただ、中国政府の対応を見極める状況だが、米10年債利回りは下げ渋りドル売りを抑制しているもよう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円33銭から109円58銭、ユーロ・円は120円33銭から120円59銭、ユーロ・ドルは1.0999ドルから1.1011ドルで推移した。■後場のチェック銘柄・ファルテック、大真空など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値上がり寄与トップは京セラ、同2位は信越化学工業■経済指標・要人発言【要人発言】・香港政府「トランプ米大統領の署名に強く反対。香港と米国の関係を著しく損なわせる」<国内>・黒田日銀総裁講演(パリ・ユーロプラス主催フォーラム)<海外>・米国休場(感謝祭)・15:45 スイス・7-9月期GDP(前年比予想:+0.8%、4-6月期:+0.2%)【市況】明日の株式相場戦略=米中間に不協和音、中小型株へのシフト鮮明に 28日の東京株式市場で日経平均は5日ぶりに小反落した。前日のNYダウは4日続伸し最高値を更新しており、この日は日経平均も年初来高値(2万3520円)の更新が期待された。しかし、この楽観論を打ち破ったのが米国の「香港人権法」成立だ。 同法の成立を受け、中国政府は「重大な内政干渉」とコメントを発表し米国への報復の姿勢を示した。この日の上海総合指数や香港ハンセン指数も小幅安にとどまった。ただし、きょうは米国が感謝祭による休場となり市場参加者は限定的だ。明日も薄商いは続くとみられる。このため、東京を含むアジア市場が、米中間の不協和音を吟味し織り込むのは来週の週明けからとなることが予想される。 「香港人権法の成立に中国は反発する姿勢を見せる必要がある。このため、12月15日の対中第4次関税引き上げ期限のギリギリまで駆け引きが続く可能性が出てきた」(市場関係者)とも指摘されている。米中の歩み寄りを前提に高値を買い上がってきた、日米の株価は当面、上値を抑えられる状況となることもあり得る。 こうしたなか、相場の物色の流れは中小型株に向かうことが見込まれている。全般軟調地合いが続いたこの日も、東証マザーズ指数と日経ジャスダック指数はともに5日続伸した。特に、東証マザーズ指数は1月の年初来高値から6%強下落した水準にあり、出遅れ感は強い。中小型株アナリストからは、中核銘柄としてSansanやUUUM、弁護士ドットコムを挙げる声が出ている。Sansanは大手証券の格上げが材料視されたが、この3銘柄はともに業績面の伸びが評価されている。 直近IPOでは、21日に東証マザーズに上場したトゥエンティーフォーセブンが相場の牽引役となっているようだ。同社はパーソナルトレーニング事業などを行っている。ギフティやカオナビなども注目されている。また、カルナバイオサイエンスやセルソースのようなバイオ株からも目が離せない。(岡里英幸)(GDO)国内男子 カシオワールドオープン 初日47歳の宮本勝昌が単独首位 石川遼14位 今平周吾は出遅れ47歳の宮本勝昌が7バーディ、1ボギーの「66」でプレー。5月「中日クラウンズ」に続く今季2勝目へ6アンダーで単独首位発進を決めた。今季は欧州ツアーを主戦場としてきた川村昌弘が6バーディ、1ボギーの「67」で回り、香妻陣一朗、堀川未来夢、小林伸太郎と並んで5アンダー2位とした。4アンダー6位に片山晋呉、武藤俊憲、キム・ヒョンソン(韓国)、アマチュアの杉原大河(東北福祉大)、藤田寛之ら8人が並んだ。賞金ランキング5位でホストプロの石川遼は3バーディ、ノーボギーの「69」でプレー。同ランキング2位のショーン・ノリス(南アフリカ)、塩見好輝、浅地洋佑らと並んで3アンダー14位とした。前年覇者のチェ・ホソン(韓国)が1オーバー72位。2年連続の賞金王を目指す賞金ランキング1位の今平周吾は2オーバー84位と出遅れた。<上位成績>1/-6/宮本勝昌2T/-5/小林伸太郎、堀川未来夢、川村昌弘、香妻陣一朗6T/-4/片山晋呉、武藤俊憲、杉原大河、藤田寛之、中西直人 ほか国内女子メジャー第4戦 LPGAツアー選手権リコーカップ 初日渋野日向子が3打差3位発進 鈴木愛10位 申ジエは出遅れ今季優勝者ら32人によるシーズン最終戦が開幕。大会2勝のテレサ・ルー(台湾)が5バーディ、ボギーなしの「67」でプレーし、5アンダーとして首位で発進した。古江彩佳が3アンダーの2位で追う。ルーは「すべてが良かったですね。少しのミスはあったけど、大きなミスがなかった」と笑顔で好プレーを振り返った。特に「アプローチ、パターに助けてもらいました」とショートゲームが冴え、6番で5m、8番(パー3)で6mを沈めるなど高麗グリーンを攻略した。今季未勝利だが「(ここで)勝ったらかっこいいなー!でも、賞金女王と関係のない人が勝ってもいいの?(笑)」とおどけた。プロになり4戦目となる古江は「緊張感は若干ありましたけど、楽しくできました」と大会初出場も貫禄たっぷりに語った。1番で10mを沈め波に乗ると、その後も4ホールのパー5のうち、3ホールでバーディを奪うなど、落ち着いたプレーでスコアをつくった。10月「富士通レディース」に続く今季2勝目に向け、「1日1日何が起こるか分からないので、集中してプレーしたい」と意気込んだ。賞金女王の可能性が残るのはランキング1位の鈴木愛、2位の申ジエ(韓国)、3位の渋野日向子の3人。渋野は1イーグル1バーディ、1ボギーの「70」とし、2アンダー3位タイで、単独2位以上が最低条件となる逆転女王に向けて好スタートを切った。鈴木は上がり4ホールで3ボギーを喫して「72」とし、イーブンパーの10位。申は「75」をたたき、3オーバーの26位と大きく出遅れた。<初日の上位成績>1/―5/テレサ・ルー2/-3/古江彩佳3T/-2/渋野日向子、柏原明日架5T/-1/ペ・ソンウ、イ・ミニョン、イ・ボミ、比嘉真美子、岡山絵里(京都新聞)金塊3億円超、市に寄付 88歳医師「使い道はお任せ」 京都府綾部市は26日、市内の産婦人科医から「地域振興に使ってほしい」と金塊の寄付を受けたと発表した。金塊は110個計60キロで3億3600万円相当。市は金塊を現金化する議案を市議会12月定例会に提案し、使途を今後検討する。 寄付したのは市内の産婦人科医の男性(88)。市には2016、17両年にも紫水ケ丘公園に河津桜と維持管理費を寄付している。 金塊は10月に市が受領した。男性は「米寿の記念にと思い、市に寄付しました。使途は市にお任せします」と話している。 市は昨年7月の西日本豪雨被災で財政難に陥っており、山崎善也市長は「ふるさとを思う気持ちに感激している。感謝し、大切に使いたい」と話している。(msn)(マネーポストWEB)年下妻を持つ夫 年金受給額は4つのパターンでこんなに変わる 夫婦で第2の人生のライフプランを考えるとき、重要な要素となるのが夫婦の年齢差だ。現在の年金制度は、「夫の厚生年金」が老後の夫婦の生活基盤となることを前提に組み立てられている。「妻が年下」の夫婦であれば、夫が先に65歳を迎えて年金受給が始まる。この場合、妻が年金をもらえるまでの期間、原則として夫の年金額に“配偶者手当”にあたる「加給年金」(年額約39万円)が上乗せして支給される。月額にして約3万2500円の加算は大きい。 夫婦の働き方は多様化し、妻が3号被保険者か、妻も厚生年金加入の共稼ぎかなどで夫婦の年金額や「得する受給方法」の考え方のポイントが違ってくる。ここでは年下妻を持つ夫のケースを見てみよう。年下妻がもらえる「加給年金」と「特別支給」 妻が年下で3号主婦(厚生年金加入歴なし)の場合、夫の年金に「加給年金」は上乗せされるが、妻は国民年金の満額をもらえないケースが多い(パターンA)。夫婦の年金は月額22万7000円で、年金だけで生活するにはギリギリの金額で人生プランにも余裕が持てない。 そこで夫婦の年金をさらに増やすには2つの方法がある。 1つは妻が60歳以降も厚生年金に加入して働く方法だ。すでにパート勤めをしている3号被保険者(サラリーマンの夫に扶養されている)の妻なら、60歳で3号から外れた後、年金加入期間が40年になるまでの期間を会社の厚生年金に入るのが有効だ。月給10万円でも、5年間働くと65歳から妻に厚生年金が上乗せされ、受給額がアップする(パターンB)。「基礎年金繰り下げ」でさらに増額 さらに年金アップの効果が高いのが、夫が年金受給しながら働き、「基礎年金」だけ70歳まで繰り下げるというやり方だ(パターンC)。 年下の妻を持つ夫が年金を全部繰り下げるのは、配偶者手当にあたる「加給年金」まで停止されるから損失が大きい。しかし、基礎年金だけの繰り下げであれば、加給年金は停止されない。 この方法を取れば、65歳から70歳までの間、夫の年金額は月額17万円から10万円ほどに減るものの、加給年金(月額約3.2万円)が上乗せされるうえ、給料収入もあるから生活の心配なく繰り下げできるはずだ。 そして70歳からは、繰り下げによる割増しなどで夫の年金額は月額3万1000円もアップする。老後資金を趣味などに使える余裕が出てくる。 妻が年下の「共稼ぎ夫婦」の年金は、妻の厚生年金加入期間が20年を超えるかどうかが加給年金支給の境界になる。「妻は独身時代は会社員で、結婚後も子供が生まれるまで共稼ぎだった」というケースで、妻のトータルの厚生年金加入期間が20年未満であれば、夫の年金に「加給年金」が加算される。 妻の年金加入期間15年(平均月給20万円の場合)の夫婦が前述の「夫の基礎年金繰り下げ」を選んだ場合、夫70歳、妻65歳になった時の夫婦の年金月額は28万2000円まで上がる。“たまには夫婦で年金旅行”もできそうだ。 同じ共稼ぎでも、夫婦とも定年まで厚生年金に加入して働くケースは、妻が年下であっても「加給年金」はもらえない。そのかわり、厚生年金をダブルで受給できるから夫婦の年金額は最も高くなる(パターンD)。 とくに妻が現在54歳以上の「得する年金」世代なら、夫が65歳で年金受給が始まった後、妻も65歳になる前に厚生年金の特別支給が始まる。60代の年金ダブル受給で、老後は無理して働かなくても“悠々自適”の年金生活に入ることができそうだ。(msn)(AERAdot.)手数料値上げは「アベノミクス」のしわ寄せ? 苦境に立つ銀行 あなたの大切なお金。預金しても金利はほとんどつかないのに、振り込みなどの手数料は高まる。さらに、口座を持っているだけで維持費をとられる時代がやってくる。「日本でも口座維持手数料をとるようになります。銀行に勤めていたときに、行内で検討していました。米国の銀行では何十年も前からとっている。ほかの銀行がどうするのか横目で見ていて、どこかが始めると一斉に追随すると思います」 こう話すのは最近までメガバンクに勤め、メーカーに転職した男性だ。銀行は稼ぐ力が弱まっていて、口座維持のコストを利用者に押しつけようとしている。お金を預けていると、知らないうちに維持費をとられ、残高がゼロになるかもしれないのだ。 地方銀行出身で、いまは静岡県富士市の産業支援センター「f-Biz」の責任者として中小企業支援に取り組む小出宗昭さんも、こう話す。「口座維持手数料は間違いなく導入されます。金融機関は積極的な営業で預金口座を増やしてきましたが、優良な貸付先はなくなり、従来のビジネスモデルに限界が見えてきました。口座維持には、マネーロンダリング(資金洗浄)のチェックなど、昔に比べコストがかかっています。手数料は、もはや、いつ導入するかの問題でしょう」 金融機関の経営に詳しいコンサルティング会社マリブジャパンの高橋克英代表も、導入は避けられないという。『銀行ゼロ時代』(朝日新書)の著書があり、銀行経営は厳しさを増していると指摘する。「銀行の収益力は落ちています。どこも早く導入したいでしょうが、顧客の反発が予想されます。三菱UFJや三井住友、みずほなど、まずメインプレーヤーが始めるのではないでしょうか」 こうした見方を裏付けるように、全国銀行協会会長の高島誠・三井住友銀行頭取は9月の会見で、口座維持手数料についてこう述べた。「口座を維持・管理するために一定のコストが発生しています。昨今、そのコストが高まっていることも事実です。一般論として、付加価値の高いサービスを提供し、お客さまのご理解を得たうえで必要な手数料をいただいていくことが、引き続き基本的な考え方でしょう」 口座維持手数料を明示しているところはまだ少ないが、一部の銀行では始まっている。 三井住友銀行の子会社のSMBC信託銀行は、旧シティバンク銀行の個人顧客向け事業を買収。SMBC信託銀行プレスティアのブランドで富裕層向けサービスを展開し、口座維持手数料として月額2千円(税別)を設定している。月間平均総取引残高が50万円相当額以上などの条件を満たせば、手数料はかからない。 実質的に同じようなことをしているところもある。 りそなホールディングス傘下のりそな銀行と埼玉りそな銀行は、預金残高が1万円未満で出し入れが2年以上ないと、「未利用口座」と認定。管理手数料として1200円(税別)を年1回引き落とす。残高が手数料に足りなくなると自動的に口座を解約する。残高が5千円の口座では、計算上4年目で足りなくなる。 事前に顧客の住所に文書を送り注意を促すというが、引っ越しなどで届かなかったとしても、「通常到達すべき時に到達したものとみなす」。手数料の返却や解約した口座の再利用には応じない。 顧客が住所変更をしないまま残高が1万円未満の口座を放っておくと、知らないうちに全て手数料としてとられてしまう。 りそな側は、「休眠口座にならないよう顧客に利用再開を促すためのものだ」としている。 コンビニエンスストアのローソンが子会社を通じて運営するローソン銀行も、「未使用口座管理手数料」として、りそなと同じような仕組みがある。 こうした仕組みは顧客からすれば納得しにくいが、銀行側にも言い分はある。 どこでも、紙の通帳1冊につき毎年200円の印紙税を銀行側が負担している。口座管理のシステムや人件費もかさむ。残高にかかわらず、一つの口座あたり年間数千円の維持費がかかるとされる。残高が少なく取引もない口座は、銀行側にとってはコストだけかかる“お荷物”なのだ。 10年以上出し入れがない口座の預金は「休眠預金」として、公益活動の資金にまわす国の制度も始まっている。銀行側が独自に未使用口座管理手数料などを設定すれば、年間数百億円生まれるとされる休眠預金が減り、結果的に公益活動に資金がまわらなくなる可能性もある。 振り込みや両替などの手数料の値上げも相次ぐ。 みずほ銀行は、来年3月からATMでの振込手数料を値上げすると10月に発表した。キャッシュカードを使って同じ店舗の口座に振り込む場合、これまでは無料だったが220円かかる。3万円未満を別の店舗の口座に振り込む場合、110円から220円に、他行あては220円から330円に上がる。インターネットバンキングの手数料は据え置く。 電話で担当者が顧客に対応するテレホンバンキングのサービスも、来年4月から順次廃止する。 ATMの維持や電話担当者の確保にはコストがかかるため、ネットサービスのほうに誘導する狙いだ。 三菱UFJ銀行や三井住友銀行でも、両替や海外送金などにかかる手数料が値上げされている。 地方銀行でも値上げの動きは広がる。 京都銀行は10月から手数料を一部値上げした。ATMにおいて現金で3万円未満を別の店舗の口座に振り込む場合、108円から220円になった。 ネットサービスは逆に値下げしている。3万円未満を別の店舗の口座に振り込む場合、108円から無料になった。窓口やATMでの取引を減らし、ネットに誘導するのは、金融業界全体のトレンドだ。 ネットを使いにくい高齢者にとっては、こうした動きは痛手。あるメガバンク銀行幹部もこう認める。「窓口やATMの取引には人手や維持費がかかる。ネットサービスは人手がかからず、振り込みが手軽にできるなど顧客にとっても便利。これまでは高齢者らの反発が予想され、手数料の見直しには慎重でしたが、銀行も余裕がなくなっている。コストの一部を負担してもらうしかないのです」 金融機関の余裕がない背景には、政府が主導する異例の政策がある。「アベノミクス」の一環として日本銀行は、2016年からマイナス金利政策を実施している。超低金利になり、預金してももらえる金利はほぼゼロ。企業などへの貸出金利も大幅に下がり、銀行は利ざやで稼げなくなっている。 大手行や地方銀行など118行が加盟する全国銀行協会によると、18年度の全国銀行の決算(単体ベース)は、純利益が前年度に比べ27.1%減の2兆2131億円だった。 銀行の稼ぐ力を示す「総資金利ざや」は年々低下している。融資や資金運用の利回りから、預金など資金調達にかかる金利などを差し引いたものだ。貸出金利が下がったことに加え、国債の金利も下がっており、総資金利ざやは減少傾向だ。 経営環境は地方を中心にますます厳しくなる。東京商工リサーチ情報本部の原田三寛・情報部長はこう話す。「貸し倒れのコストが上昇しています。地方の金融機関は競争が激しく、集まりすぎた預金を地域を超えて『越境融資』しているところもあります。越境した地域については企業に関する情報が乏しいので、審査が不十分になりがちです」 地方経済は疲弊(ひへい)しており、経営に行き詰まる中小企業が目立つ。「以前は借金を返済してから休廃業していました。最近は借金を返さないまま、休廃業するところも多い。休廃業の件数は18年に過去最高となり、これからも増えるでしょう。地方の金融機関にとって、経営環境は一段と厳しくなりそうです」(原田さん) 地方の金融機関の競争が激しいのは、地方経済が縮小しているのに銀行が過剰な、「オーバーバンキング」が続いていることもある。 地銀は銀行同士だけでなく、信用金庫や信用組合などとも貸し出し競争をしている。(本誌・浅井秀樹、池田正史、多田敏男)(yahoo)(産経新聞)社名を「ENEOSホールディングス」に変更 JXTGホールディングス 石油元売り最大手のJXTGホールディングスは28日、来年6月開催予定の定時株主総会で、社名を「ENEOSホールディングス」に変更すると発表した。中核子会社の「JXTGエネルギー」も「ENEOS」に変更する。 JXTGホールディングスは平成29年4月に、JXホールディングスと東燃ゼネラルが経営統合し、社名を変更した。 主力事業のガソリンなどの石油製品事業では、「ENEOS」や「ゼネラル」「Mobil」など複数あったサービスステーションのブランドについて、今年7月に「ENEOS」に統一したことなどから、認知度の高いブランド名を社名にすることを決めた。 同時に、ENEOSホールディングスとENEOSでは、役員を極力兼任させるなど、意思決定機関を集約することなどによって、実質的な一体経営を図っていく。 一方で、傘下のJX石油開発、JX金属は社名は変更しないとしている。(yahoo)(時事通信)富裕層の申告漏れ763億円 過去最多を更新 国税庁 全国の国税局が6月までの1年間に実施した所得税の税務調査で、高額な資産などを持つ富裕層に対し、総額763億円の所得の申告漏れを指摘したことが28日、国税庁のまとめで分かった。 前年比13.9パーセント増で、現在の統計方法となった2009年以降、最多を更新した。 同庁によると、富裕層に対する調査は5313件実施し、うち4517件で申告漏れを指摘。追徴税額は同14.7パーセント増の203億円、1件当たり383万円で、海外投資をしている人ほど高額だった。 (goo)(時事通信)Bウイルス感染、国内初=サル由来「拡大の恐れなし」―鹿児島市 鹿児島市は28日、市内の研究施設で動物実験に携わる技術員1人が、脳炎などを引き起こす「Bウイルス」に感染したと発表した。市によると、Bウイルスはアカゲザルなど一部のサルに引っかかれるなどして感染するが、国内での確認は初めて。市は「施設が適切な対策を行っており、感染拡大の恐れはない」としている。 市によると、Bウイルスは脳炎や接触部位のまひなどを引き起こす恐れがあり、世界で約50例が確認されている。 感染したのは医薬品開発受託・研究会社「新日本科学」の市内にある研究施設の技術員で、2月に頭痛や発熱を訴えて医療機関を受診。11月上旬にBウイルスの感染が確認された。技術員は動物実験を補助していたが、サルに引っかかれるなどした記憶はないという。 新日本科学によると、技術員は防護服を着て実験に当たっていたといい、「防護対策や管理体制をさらに強化する」とコメントした。 (yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-楽観ムード修正で5日ぶり反落、あすは方向感に欠ける展開か 28日の日経平均は5日ぶり反落。終値は28円安の23409円。米国株は上昇したものの、朝方にトランプ米大統領が香港人権法案に署名したと伝わったことから、ポジティブな反応は限定的となった。上昇スタートも買いが続かず下げに転じた後は、前日終値近辺でもみ合いながらも前引けではプラスを確保。しかし、後場は今晩の米国市場が休場で手がかり難の中、マイナス圏での時間帯が長かった。取引終盤まではじり安基調が続いたが、引け間際には値を戻す動きも見られ、小幅な下落で取引を終えた。東証1部の売買代金は概算で1兆5900億円。業種別では騰落率上位は空運、医薬品、鉄鋼、下位は金属製品、陸運、鉱業となった。ソフトバンクユーザー向けに迷惑メッセージ自動振り分け機能の提供を開始すると発表したトビラシステムズが急騰。半面、ゲームアプリ2タイトルのリリース延期を発表したenishが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり628/値下がり1416。証券会社が投資判断を引き上げた東芝が大幅上昇。パナソニックは半導体事業からの撤退観測が報じられたが、リストラ進展を好感した買いが入った。中外製薬やエーザイ、参天製薬など薬品株の一角が上昇。上方修正を発表したサイボウズが急伸した。株式分割と優待導入を発表した共栄タンカーは買いが殺到してストップ高比例配分となった。一方、アドバンテストやディスコなど半導体株のほか、安川電機やキーエンスなどFA関連株が売りに押される展開。過年度決算でも元従業員による不適切な会計処理があったと発表したJDIが大幅安となった。日本一ソフトウェアはゲームアプリのサービス再開を発表したものの好感されず、12%超の下落。北海道がIR誘致を断念するとの報道が失望材料となったフジタコーポレーションはストップ安をつける場面もあるなど急落した。 日経平均は米国株高や円安進行を受けて年初来高値が期待されたものの、朝方に出てきたネガティブニュースを受けて楽観ムードが急速に冷え込んだ。アジア株も弱かったがパニック売りを誘うような下げではなく、ドル円も円安は一服したが109円台より上で推移しており、外部環境がそこまでリスクオフであったわけではない。にもかかわらず、23500円すら上回れず、後場に入って売り圧力が強まった。今晩の米国市場は感謝祭で休場。きょうが警戒ムードが強かった分、追加の悪材料が出てこなければ、休場明け後の米国株高を期待した買いが入る展開は期待できる。ただ、市場参加者も少ないと予想される中、全体的には方向感に乏しい地合いになるだろう。今週はザラ場の年初来高値を更新するなど強い動きも見られただけに、週初の23292円を上回り、週足で陽線を形成できるかに注目したい。(yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=週末と月末が重なり、米感謝祭の休場などもあり、弱含みの展開か 29日の東京株式市場は、弱含みの展開か。週末と月末が重なるうえ、現地28日の米国株式市場が感謝祭の祝日で休場で、翌29日は短縮取引取引となることから、模様眺めムードが広がりそうだ。トランプ米大統領の署名待ちだった「香港人権・民主主義法」が成立し、時間外取引の米株価指数先物が下落したが、市場では「同法案の成立は想定内で、影響は限られるとみられるが、米株価の上昇持続には米中貿易交渉の以外の材料もほしいところ」(中堅証券)と言う。また、米国の「ブラックフライデー」や「サイバーマンデー」は好調な消費が期待されているだけに「サプライズが無いと反応が限られる場面もありそう」(同)との声も聞かれた。 28日の東京株式は、前日比28円63銭安の2万3409円14銭と5日ぶりに反落して取引を終えた。東京証券取引所が28日引け後に発表した、11月第3週(18-22日)の投資部門別の株式売買状況によると、海外投資家は金額ベースで160億円の売り越しで、8週ぶり売り越しとなった。一方、個人投資家は124億円の買い越しと、7週ぶりで買い越した。(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕5日ぶり小反落=米中関係見守る(28日)☆差替 【第1部】日経平均株価は前日比28円63銭安の2万3409円14銭、東証株価指数(TOPIX)は2.92ポイント安の1708.06と、ともに5営業日ぶり小反落。米国で香港人権・民主主義法が成立したことに対する中国の反応など、米中の通商問題を見守る状態になり、終日方向感を欠いた。 銘柄の66%が下落し、29%が上昇。出来高は9億2501万株、売買代金は1兆5982億円。 業種別株価指数(33業種)は、金属製品、陸運業、鉱業、機械などが下落。上昇は医薬品、空運業など。 ファーストリテが小幅に続落し、武田がさえず、リクルートHD、ZOZOは軟調だった。JR東海が売られ、三井住友は小幅安。国際帝石が甘く、住友鉱は値を下げた。SUMCOが値を消し、ソニー、東エレク、コマツも下落した。半面、トヨタが堅調で、日立、パナソニックは値を上げた。任天堂はしっかり。ソフトバンクGが小高く、JALが続伸し、日本新薬は大幅反発。 【第2部】5日続伸。東芝、サイバーSが堅調。那須鉄、FRACTALEはさえない。出来高9994万株。 ▽海外勢は休暇入りか 27日の米主要株価指数はそろって上昇したが、日本時間の朝方にトランプ米大統領が「香港人権・民主主義法案」に署名して同法が成立したと伝わると、中国による報復措置への警戒感が出て、日経平均株価は前日終値近辺で上下するはっきりしない動きになった。28日の米市場が感謝祭で休場のため「海外投資家が休暇体制に入り、積極的な売買が見られなかった」(国内証券)との指摘もあった。 この日の取引時間中は、香港人権法案に対して中国政府からは「極度の遺憾の意」とする抗議声明が出ただけで、具体的な報復措置は示されなかった。海外勢が本格的に取引に市場に戻るのは12月2日に米国市場の取引が再開された後となるため、「中国が貿易協議を停滞させる反応をするか見守りつつもみ合う状況が、来週初めまで続くかもしれない」(銀行系証券)という。 225先物12月きりは軟調。香港人権法の成立による米中貿易協議の停滞などへの警戒感出る中で、利益確定や手じまいの売りがやや優勢になった。225オプションはプットが値を上げ、コールは下落。(了) 昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の11銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。今晩のNY株式市況に関するニュース等は感謝祭(サンクスギビング・デー)による祝日で休場のため、休信となります。
2019.11.28
コメント(0)
-

11月26日(火)~27日(水)…
11月26日(火)、曇りです。7時45分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、10時頃に家を出る。天候がイマイチですが、行楽の秋ですから今週は…Go To NARA!です。奈良…、久しぶりなんですよね。小学校の修学旅行以来…。東海環状~東海北陸~名神と走って、多賀SAで少し早目のランチタイムストップ。多賀SA内のちゃんぽん亭でランチです。熱々で体が熱くなって汗が出てきます…。名神~京滋自動車道~京奈和道と走って奈良市の郊外へ。右に大きな古墳が見えてきます…、さすが奈良!以外に近いんですね。210km程度。14時前にはホテルに到着。チェックインは15時からですが、フロントがすぐに部屋を用意してくれて、ロビーでお茶していると入室出来ました。お世話になるのは、スモールラグジュアリーな登大路ホテル奈良です。フロントで鹿せんべいをいただいて、外へ出ます。ホテルが興福寺のすぐ隣に立っていますから奈良公園周辺の観光には最高です。興福寺…インバウンドと修学旅行ですごい人です。阿修羅像…少しゆっくり眺めることができました。興福寺から東大寺へ向かう途中でおやつタイム…。吉野葛の黒川本店で葛三昧や葛ぜんざいをいただく。更に歩いて東大寺へ…。南大門で仁王像を眺めて、中へ進むと大仏殿が見えてきます。こちらも、インバウンドと修学旅行がすごい…。ミュージアムを拝見すると17時を過ぎました…。ホテルへ戻ると、歩き回ったのでヘロヘロです。ベットでバタンキューです。18時を過ぎた頃に起きて、身支度。こちらのホテルはガストロノミーも売りです。19時からレストランへ…、13室のホテルですが先客もほぼ同年代のようですね。僕たちのメニューはこんな感じで。後はお料理に合わせたワインを楽しむ。後半はほぼ貸し切りになりましたね。満足して部屋へ引き上げると21時30分頃。夕食の途中から雨が降り出したようですが…、明日はどうなるのか…。こうして奈良の夜は更けていくのでした…。11月27日(水)、ほぼ曇り…。6時45分頃に起きると外は濡れていますが、雨は降っていません。8時から朝食をいただく。朝食も美味しく、お腹いっぱいです…。9時30分頃に身支度を終えてチェックアウト。車で春日大社へ向かうとパーキングは満車と表示されているが、数台並んだだけでスムーズに入場できました。春日大社も観光バスでインバウンドがバンバンやって来ます。インバウンドとのトラブル…わかります。祇園のお店の人がここには観光客に来ないでもらいたい…と言うのがわかります。次いでならまちエリアの元興寺へ。こうした小さなお寺は静かでいいですね。国宝の小さな五重塔を拝見。次いでならまちエリアの趣味が高じた吉野葛のお店へ…。葛餅ぜんざいをいただく。体が温まります。奈良市の中心部を離れて唐招提寺へ向かう。こちらも綺麗なお寺です。やはり郊外になるせいかインバウンドも少なく良い環境です。次いで学園エリアの松柏美術館へ。たどり着いたら…、門が閉まっています…。展示物の入れ替えのための臨時休館とのこと…。アイヤ~!ここで帰宅決定。来た時と同じコースを逆にたどって、多賀SAで休憩して、16時頃には帰宅。それではしばらく休憩です。1USドル=109.14円。1AUドル=74.02円。昨夜のNYダウ終値=28121.68(+55.21)ドル。本日の日経平均終値=23437.77(+64.45)円。金相場:1g=5684(+28)円。プラチナ相場:1g=3609(+45)円。(会社四季報オンライン)(ロイター)米国株式市場は3指数が最高値、米中協議巡る大統領発言でダウは55ドル高の2万8121ドル[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米国株式市場は小幅続伸し、主要3指数がともに最高値を更新した。一部の経済指標が予想より軟調だったものの、米中通商協議を巡るトランプ大統領の前向きなコメントが相場を支援した。トランプ大統領は26日、米中通商協議について、「第1段階」の合意が近いとの見方を示した。米政府として香港の抗議デモを支持する立場も強調した。ホライズン・インベストメンツの最高投資責任者スコット・ラドナー氏は「(通商協議を巡る)状況は良好と評されており、それを材料にやや上昇している。ただ、合意に至るまで完了とは言えない」とし、「現時点では様子見が適切だろう」との見方を示した。年末商戦期の消費動向が注目される中、コンファレンス・ボード(CB)がこの日発表した11月の消費者信頼感指数は4カ月連続で低下した。ただ、安定した消費の下支えに必要な水準は維持した。これとは別に、米商務省が発表した10月の新築一戸建て住宅販売戸数(季節調整済)は、年率換算で前月比0.7%減となった。ただ、9月分は上方改定され、約12年ぶりの高水準となった。ウォルト・ディズニーは1.3%高。動画配信サービスの新規契約者が1日平均100万人近くに達していると報じられた。ベストバイは9.86%急伸。年末商戦にかかる10─12月期の利益見通しが市場予想を上回った。一方、ダラー・ツリーは15.24%急落。10─12月期の利益見通しが市場予想を下回り、貿易摩擦が影響している可能性を示唆した。このほか、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)は8.48%安。第4・四半期(10月31日終了)の売上高がアナリスト予想に届かなかった。米取引所の合算出来高は79億6000万株。直近20営業日の平均は71億2000万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.34対1の比率で上回った。ナスダックでも1.01対1で値上がり銘柄数が多かった。日経平均は4日続伸、上値重い 売買代金は2兆割れ大引けは前日比64円45銭高の2万3437円77銭[東京 27日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は4日続伸。米国株高や為替の円安基調などを好感し、朝方から買いが先行した。高値を付けた後は上げ幅を縮小し、一進一退の展開となった。東証1部の売買代金は節目の2兆円を割り込み、薄商いだった。 26日の米国株式市場では、米中通商協議を巡るトランプ大統領の前向きなコメントが相場を支援し、主要3指数が最高値を更新した。為替のドル/円が109円前半に固めたことも追い風となり、日経平均は続伸スタート。午前9時29分に高値の2万3507円82銭を付けたあとは、高値警戒感から利益確定売りに押され、上げ幅を縮小した。その後は高値圏での一進一退となり、小幅高で取引を終えた。 市場からは「相変わらず材料には乏しいが、需給は締まっている。今週と来週は、機関投資家が11月末に支払われる9月期末の中間配当を再投資に回す可能性もあるので、買われやすい」(国内証券)との声も出ていた。 TOPIXも4日続伸。東証33業種では、鉱業、非鉄金属、電気・ガス業などが値上がり率上位。一方、その他金融製品、保険業、陸運業などは売られた。 個別銘柄では東芝が続伸、4%超高となった。東京証券取引所が2020年にも2部市場から1部市場への移行基準を緩和するとの26日付日本経済新聞電子版の報道が材料視された。新基準の導入により、2部上場の東芝が1部に復帰できる可能性が高いという。東証2部指数における東芝の指数ウエートは高いため、東証2部総合指数を大幅に押し上げ、同指数は1.51%高となった。 そのほか個別銘柄では、富士通、TDK、キーエンスなど情報、電子部品、センサーなどの主力銘柄で年初来高値を更新するものが目立った。 東証1部の騰落数は、値上がり1436銘柄に対し、値下がりが637銘柄、変わらずが82銘柄だった。(会社四季報オンライン)セルソースが一時S高、脂肪由来幹細胞を住商系に分譲 再生医療のプラットフォームとして法規対応支援・新治療の開発等を手がける東証マザーズのセルソース(4880)が続騰した。午後1時10分現在、前日比1320円(15.26%)高の9970円で推移している。一時は制限値幅上限の同1500円高の1万0150円ストップ高まで上伸した。 26日に、自社で培養・加工するヒト脂肪組織由来間葉系幹細胞の分譲に関して住友商事(8053)子会社の住商ファーマインターナショナル(SPI・東京都千代田区)と契約したと発表し、買い材料視された。SPIはセルソースから分譲された幹細胞をまず研究用途として国内外の大学などの研究機関や企業に対して順次提供していく。患者自身の脂肪由来幹細胞を用いた再生医療については整形外科や形成外科を中心に臨床応用が広がっている。(取材協力:株式会社ストックボイス)あすか製薬が大幅続伸、子宮筋腫治療剤が第3相試験で良好結果 婦人科系や泌尿器科系の治療薬に強みを持つあすか製薬(4514)が大幅続伸した。一時は1418円まで上伸し、3月4日の年初来高値1384円まで上伸した。午後1時26分現在、前日比43円(3.32%)高の1338円で推移している。 26日に開発中の経口子宮筋腫治療剤「ウリプリスタル酢酸エステル」の第3相比較試験で主要評価項目を達成したと発表し、買い材料視された。比較対象の「リュープロレリン」よりも非劣性や早期の症状改善、良好な忍容性が確認されたとしている。現在、当社は過多月経を伴う子宮筋腫患者を対象に「ウリプリスタル」の長期使用の際の有効性、安全性を評価するための第3相長期投与試験を実施中としている。(取材協力:株式会社ストックボイス)カイオムバイオ大幅続伸、がん治療用抗体でマイルストーン受領 独自の抗体作製技術を持つ理研発の創薬ベンチャーで東証マザーズ上場のカイオム・バイオサイエンス(4583)が大幅に5日続伸した。午後1時37分現在、前日比17円(8.54%)高の216円で推移している。一時は230円まで上伸した。 26日に当社がスイスのADCT社にライセンスアウトしたがん治療用抗体「ADCT-701」についてIND(新薬臨床試験開始届)申請準備に必要な毒性試験が終了したことによる25万ドル(約2700万円)のマイルストーンを受領すると発表し、好感された。2019年12月期第4四半期(10~12月)に事業収益として計上する。また、「TROP-2」を標的にした光免疫療法が、予後不良で治療法の選択肢が少ないすい臓がんや胆道がんの新たな治療法となりうる可能性を示す論文が米誌に掲載されたことも買い材料視された。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】明日の株式相場戦略=日米ともに中小型株のキャッチアップ相場 きょう(27日)の東京株式市場では日経平均株価が4日続伸。終値は64円高の2万3437円だった。この水準で売り物を吸収して下値を切り上げているという現実に対し、上値が重いというのも贅沢な話。心理的なフシ目となっている2万3500円どころを、どこで明確に突破してくるのか、具体的には終値で抜き去ってくるタイミングが注目される。 組み入れ比率を維持するための機関投資家による配当再投資の買いなども取り沙汰されており下値抵抗力は強そうだが、2万3500円ラインは鬼門という見方も一部にある。日経平均リンク債の設定が1兆5000~1兆7000億円あることが観測されており、指定日に2万3500円にノックインした場合、先物の売りを誘発して大きな下方圧力が働く理屈となる。したがって、米中協議の行方だけでなく、株式需給面からも波乱要素があることは念頭に置いておく必要がある。 過去をさかのぼって、2017年の6月から8月にかけて2万円近辺でもみ合った後、9月初旬にかけ下値を試す展開となった時も同様に2万円で設定されたリンク債の存在が言われていた。もっとも、この後の年末から18年年始にかけての日経平均の鮮烈な上昇の方が投資家の記憶に強く刻まれているはず。今回も2万3500円超えで乱気流が発生したら、そこは願ってもない買い場提供場面という前向きな視点で臨むところかもしれない。 また、日経平均だけを見ていても今の相場の体感温度を知ることはできない。個人投資家の土俵である中小型株は好調を極めている。米国株市場でもNYダウやナスダック総合指数の最高値更新の陰で、中小型株指数のラッセル2000がこれらに急速にキャッチアップしており、あとわずかで最高値奪回という水準に漕ぎつけている。遅ればせながら日本株もこの流れをなぞらえる状況にある。 個別では前週から上げ足を強め、目先上昇一服となっているハイパーに着目してみたい。法人向けを中心にパソコン販売を手掛けるが業績は成長加速局面にあり、19年12月期は前期比2ケタ増収で営業利益は45%増益予想と大幅な伸びを見込む。20年度から小学校でプログラミング教育が必修化されることで、小中高校におけるパソコンやタブレットなど学習用コンピューター不足を解消することが喫緊の課題となっている。同社の収益機会が高まることは必然の流れで、成長期待は来期以降一段と強まりそうだ。 バイオ関連にも強い銘柄が目立つ。これはマザーズ指数の上昇基調にも反映されるものだが、10月28日にマザーズに新規上場した再生医療関連のセルソースが再び上値指向をみせていることもムードを良くしている。そのなか、同関連では11月13日をターニングポイントにヒタヒタと下値を切り上げてきたリボミックに目が行く。同社は東大発の創薬ベンチャーでリボ核酸(RNA)を使ったアプタマー薬(分子ターゲット薬)の開発を手掛けており、そのなか、加齢黄斑変性治療薬「RBM-007」の開発に対するマーケットの期待が大きい。RBM-007については、今月に入り欧州特許庁に出願していた物質特許が成立したことを開示、これに伴い日米欧3極で物質特許を成立させたことになり、今後の展開力に厚みが加わることになる。 このほかでは、販促支援業務を手掛け業績絶好調のサニーサイドアップや、自動車部品の受託生産を手掛け電気自動車(EV)用2次電池関連商品も手掛けるサンコーのほか、以前にも複数回取り上げた光ビジネスフォームなども改めてマークしておきたい。 日程面では、あすは10月の商業動態統計、10月の建機出荷額などが発表される。このほか2年物国債の入札も予定される。海外では11月の独CPI(消費者物価指数)速報値。なお、感謝祭の祝日に伴い米国株市場は休場。(中村潤一)(msn)(ブルームバーグ)ソニーとトヨタ、輸出両雄の株価大台迫る-大型株に海外資金流入 (ブルームバーグ): 日本株市場でソニーとトヨタ自動車が数年ぶりの株価大台に接近している。輸出関連の代表で株価指数ウエートが高い両社の再評価は、海外勢による日本株現物への資金流入を象徴している。 TOPIXの指数ウエートでトヨタは1位。ソニーはソフトバンクグループに替わって夏場から2位だ。今月に入ってトヨタは7949円まで上げて2015年8月以来の8000円台に接近。ソニーは一時6958円と、2007年6月以来の7000円台に迫る。 楽天投信投資顧問第二運用部の平川康彦部長は「海外投資家は景気敏感としての日本株を組み入れる際、『時間を買う』ためにまず先物を買い、長期投資家などは次に個別銘柄を現物でピックアップする傾向がある」と指摘。その中で「ソニーとトヨタは高い流動性と圧倒的な競争力が共通点」と評価する。 日本取引所グループ(JPX)によると、外国人投資家は8月3週に先物(ミニを含めたTOPIXと日経平均株価)を買い越した後はほぼ買い越し基調。現物株は10月1週から買い越しに転じ、11月2週時点で2年ぶりの7週連続買い越しとなっている。 海外勢の売買動向では投機筋の短期トレードに使われやすい先物に対し、現物株は投資期間が長い機関投資家の動向が表れるとされる。大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジストは「世界景気が底入れから反転へと向かう中、海外投資家はアンダーウエートとしてきた日本株の比率を上げざるを得なくなっている」と話し、その過程では「大型株中心に現物株が買われやすい。足元ではTOPIXコア30指数の動きが強くなっている」との見方を示す。 楽天投信の平川氏はソニーについて「画像のCMOSセンサーはスマホだけでなく、自動運転など車向けのニーズも見えている」と分析。トヨタは「世界の自動車需要が減少する中でも販売を伸ばす力があり、来年以降の欧州の環境規制への対応も考えると、世界ナンバーワンの競争力」と言う。「グローバルで選ばれる企業であることが、両銘柄がアウトパフォームを続けている要因」と述べた。 一方、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンの寺尾和之最高投資責任者(CIO)は「日本株は常に海外勢の買いで上がる傾向がある」とした上で、「日経平均が2万3000円を上回る水準からは海外勢の新規の買いが入りづらい」と話していた。(msn)(ロイター)武蔵精密、イスラエルのベンチャーと新型エンジン開発へ[テルアビブ 26日 ロイター] - イスラエルのベンチャー企業、アクエリアス・エンジンズは武蔵精密工業と新型エンジンの共同開発で合意したと発表した。武蔵精密はアクエリアス・エンジンに出資したが、その規模は明らかにしていない。アクエリアスはこれまでに重量10キログラム、1気筒の小型エンジン(排気量0.8リットル)を開発した。自動車用エンジンとしても発電システムとしても使用できる。武蔵精密の大塚浩史社長によると、両社はまずアクエリアスの発電システムを次世代通信規格「5G」の基地局向けに共同開発し、順次他の市場にも拡大していく方針。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-動意薄でも4日続伸、休場前の米国株にもう一伸びはあるか 27日の日経平均は4日続伸。終値は64円高の23437円。米国株高を好感して上昇スタート。ただ、場中は手がかり難の中でこう着感が強まった。23500円近辺では上値が重くなった一方、地合いの良さから大きく崩れることもなく、23400円台で値動きが落ち着いた。後場も動意は薄かったが、終盤にかけてはやや伸び悩み、大引けが後場の安値となった。東証1部の売買代金は概算で1兆8900億円。業種別では騰落率上位は鉱業、非鉄金属、電気・ガス、下位は保険、その他金融、陸運となった。女川原発2号機に関して、原子力規制委員会が新規制の基準に「適合」したと判断したことが伝わったことを受けて、東北電力が後場に入って上げ幅拡大。半面、医薬品卸大手4社が談合を行っていたとの報道を受けて、アルフレッサ、メディパルHD、スズケン、東邦HDが後場に入って急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1436/値下がり637。東証1部への移行基準が緩和されるとの報道を材料に東芝が4%超の大幅上昇。新型車に自動ブレーキが義務化されるとの報道を受けてファルテックやタツミがストップ高まで買われた。証券会社の新規カバレッジが入ったSansanがストップ高となり、ブロードリーフやSCREEN、住友電工などもリポートを手がかりに大幅高となった。一方、政府が海外住宅投資の節税を認めない方針とするとの報道を受けて、海外事業が伸びていたオープンハウスが12%超の大幅下落。ZHDが大きめの下げとなったほか、コロプラやenish、ミクシィなどゲーム株の一角が弱かった。シスメックスは証券会社の投資判断引き下げが嫌気されて大幅安。直近で急伸していたトミタ電機やウチダエスコが手じまい売りに押された。 日経平均は4日続伸。場中に市場を揺さぶるような材料はなく、凪(なぎ)のような地合いが続いた。引け間際に失速はしたものの、一日の安値は前場の早い時間につけており、崩れたという印象はない。良くも悪くも相場の急変がないとの見方が強まる中で、マザーズ指数やジャスダック平均は後場に上げ幅を広げている。今晩の米国市場では、10月耐久財受注や7-9月期GDP改定値など注目度の高い指標の発表が多い。そして、翌28日は感謝祭で休場。そのため、今晩の米国株の動向が、週後半の日本株の動向を大きく左右しやすい。米国株が休場前に上昇一服となるようなら、日経平均が今週23500円を超えることは厳しいであろうから、軽めの調整が入ると考える。一方、年末商戦期待などから米国株の上昇が続くようなら、楽観ムードが支配的となり、23500円突破から一段高の展開を予想する。NY株見通し-底堅い展開か 7-9月期GDP改定値など経済指標が多数発表 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は米中通商合意への期待が続くなか、好決算を発表したベストバイの大幅高も追い風に主要3指数がそろって史上最高値の更新を続けた。今晩は、翌日が感謝祭の祝日で休場、翌々日が短縮取引となることで様子見姿勢が強まることが予想されるものの、米中合意への期待や感謝祭明けからスタートする年末商戦への期待などを背景に底堅い展開となりそうだ。7-9月期GDP改定値など注目度の高い経済指標の発表も多い。 今晩の米経済指標は10月耐久財受注、7-9月期GDP改定値、同コアPCE価格改定値、新規失業保険申請件数、10月個人所得・個人消費支出、10月中古住宅販売仮契約指数、地区連銀経済報告(ベージュブック)など。企業決算は寄り前にデイアが発表予定。(執筆:11月27日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)今晩のNY株の読み筋=休暇前のポジション調整に注意 28日の米国は感謝祭で全市場が休場となる。26日は米経済指標が強弱入り混じるなかでも米中貿易協議に対する楽観的な見方からリスク選考の動きが優勢となったが、貿易問題は正式に合意できるまで予断は許さず、また、米中関係は香港デモをめぐる対応でも対立している。主要3指数は高値圏を維持しているものの不安材料は少なくない。27日も多くの重要経済指標が発表されるが、弱い結果が相次げば休暇前の手じまい売りが強まる恐れがある。<主な米経済指標・イベント>米10月耐久財受注、米7-9月期GDP(国内総生産)改定値、米10月個人所得・個人消費支出(PCE)、米10月仮契約住宅指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、109円台前半(27日朝) 【ニューヨーク時事】27日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、良好な米経済指標の発表を受け、1ドル=109円台前半で弱含みに推移している。午前8時45分現在は109円20~30銭と、前日午後5時(109円01~11銭)比19銭の円安・ドル高。 米感謝祭休場を翌28日に控え、27日朝は米経済指標の発表が目白押し。商務省が発表した2019年7~9月期の実質GDP(国内総生産)改定値は、季節調整済み年率換算で前期比2.1%増となり、速報値(1.9%増)から上方修正された。また、10月の耐久財受注は前月比0.6%増と2カ月ぶりにプラスに転換。週間新規失業保険申請件数は21万3000件と前週から1万5000件減少し、いずれも市場予想に比べて良好な結果となった。これを受けてドル買いがやや加速し、円相場は若干下げ幅を拡大している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.0995~1005ドル(前日午後5時は1.1013~1023ドル)、対円では同120円15~25銭(同120円17~27銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、もみ合い=一時最高値更新(27日朝) 【ニューヨーク時事】27日のニューヨーク株式相場は、良好な米経済指標を受け、優良株で構成するダウ工業株30種平均は取引時間中の史上最高値を更新して始まった。その後はもみ合いに転じ、午前9時35分現在は前日終値比12.93ドル安の2万8108.75ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数も最高値を付け、同時刻現在は22.51ポイント高の8670.44。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の21銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の14銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では3銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.27
コメント(2)
-
11月25日(月)…
11月25日(月)、晴れです。これまた良い天気ですね。そんな本日は7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機ですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。美味い!!1USドル=108.71円。1AUドル=73.85円。現在の日経平均=23287.25(+174.37)円。金相場:1g=5665(-2)円。プラチナ相場:1g=3546(-75)円。(ブルームバーグ)【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース 世界で最も裕福な100人の総資産が、3兆ドルに届きそうです。パウエル議長率いる米金融政策当局では、これまで尻込みしていた格差拡大という問題に踏み込もうとする動きが出てきました。ハト派で知られるミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、富の再配分において当局は役割を担えると主張しています。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。争点の一つ中国は知的財産権の侵害に対する罰則を強化すると発表した。刑罰を科すボーダーラインの引き下げも検討する。措置の詳細は明らかにしていない。同国は2022年までに知的財産権の侵害を減らすことを目指すとし、侵害を受けた被害者が賠償を得やすい環境にする計画だ。遅れて参戦ブルームバーグ前ニューヨーク市長は、米大統領選挙の民主党候補者指名争いに出馬すると正式に表明。ビジネスや政治、慈善活動での実績に基づいた、独自の中道派の政策スタンスでトランプ大統領の打倒を狙う。「無鉄砲で倫理観を欠いた行動がさらに4年続くことに、米国は耐えられない」との声明を発表した。激動期の民意香港の区議会議員選挙では、民主派が躍進したもようだと現地メディアで報じられている。当初は選挙の実施自体が危ぶまれていたが、支障なく予定通りに行われた。投票率は71%と高く、投票総数は過去最高を記録した。開票結果は25日早朝に明らかになると予想されている。富裕層市場フランスの高級ブランド、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは米ティファニーの買収で近く合意がまとまりそうだと、関係者が述べた。買収額は160億ドル(約1兆7400億円)を超える。両社とも取締役会を24日に開いて、最新の買収案を承認する是非を話し合い、早ければ25日に結果を発表する可能性があるという。私が消えたらトランプ氏の個人弁護士であるジュリアーニ元ニューヨーク市長は、自分の消息が不明になるといった事態が起きれば、バイデン氏とその家族に不利になる情報が公表されることになっているとツイッターに投稿。先のFOXニュースとのインタビューで述べた「保険」について、説明した。その他の注目ニュース米金融当局は格差拡大と闘える、ミネアポリス連銀総裁が布陣強化テスラ「サイバートラック」、すでに注文14万6000台-マスク氏韓国が日本に抗議、GSOMIA関連の合意発表をゆがめたと非難ティファニー買収で近く合意の見通し、LVMHが買収額再引き上げ フランスの高級ブランド、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは米ティファニーの買収で近く合意がまとまる見通しだ。提示された買収額は160億ドル(約1兆7400億円)を超え、LVMHのベルナール・アルノー会長にとって過去最大の買収となる。 事情に詳しい複数の関係者によれば、LVMHはティファニー買収案を1株当たり135ドルに修正した。最初の提示額120ドルから12.5%の引き上げとなる。両社とも取締役会を24日に開いて、最新の買収案を承認する是非を話し合い、早ければ25日にも結果を発表する可能性があるという。関係者らは詳細が非公開だとして、匿名で話した。 関係者によれば、LVMHはつい数日前にティファニー買収案を1株130ドルに引き上げたばかり。欧州随一の富豪であるアルノー氏は、ティファニーを取り込むことで米国の高級品購入層へのアクセスを狙う。一部のアナリストはティファニー買収額はもっと引き上げられる可能性があると見ており、クレディ・スイスは140ドル、カウエンは160ドルをめどとしている。(株探ニュース)【市況】前場に注目すべき3つのポイント~全般こう着の中でマザーズ銘柄の出遅れ修正に関心25日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し: 全般こう着の中でマザーズ銘柄の出遅れ修正に関心■前場の注目材料:豊田合、20/3期業績予想を下方修正、子会社譲渡で事業整理損失を計上■テクノスマート、滋賀工場に25億円投資、リチウム電池用フィルム増産■全般こう着の中でマザーズ銘柄の出遅れ修正に関心25日の日本株市場は、引き続きこう着感の強い相場展開が続きそうである。22日の米国市場ではNYダウが100ドルを超える上昇となった。米中協議を巡り、習近平国家主席やトランプ大統領が協議進展に前向きな発言を行ったことが材料視されている。しかし、米連邦通信委員会(FCC)が米企業に対してファーウェイやZTEの製品に連邦補助金を使用することを禁じたことから上値は限られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円高の23165円。円相場は1ドル108円60銭台で推移している。先週の日経平均は米中協議を巡る報道等に翻弄される格好となったが、結局はチャート上に長い下ヒゲを残して23000円を回復している。今週も米中協議に関連する報道等に振らされやすいだろうが、この下ヒゲを残している局面ではセンチメントは悪化しないだろう。23000円処での底堅さが意識される局面においては、買い戻しの流れが意識されやすいだろう。先週の急落後の戻りの速さについては、短期筋のショートカバーのみではなく、大幅調整局面において依然として買い戻したい需給が存在していることが挙げられよう。ポジションは依然として大きくロングに傾いている訳ではないとみられ、また、個人の需給状況についても売り越し基調となるなど、10月以降の上昇局面によって、利益確定を進めている格好である。キャッシュポジションの高さから、押し目買い意欲は強そうである。さらに、足元でマザーズ指数が出直りをみせてきており、中小型株物色が徐々に活気づいてきていることも、センチメントを明るくさせてきているとみられる。昨年の中小型株の急落によるトラウマから慎重姿勢は崩せないところだったこともあり、それ故にセンチメントが改善することによって、次第に年末高への意識も高まってきそうである。また。今週は米国では感謝祭の祝日明けから、クリスマス商戦に入る。ブラックフライデー、翌週のサイバーマンデーなどにおいて好調な売上が示されるようだと、良好な米個人消費を手掛かりにセンチメントを明るくさせるだろう。物色の流れとしては、米国の感謝祭を控えて海外勢のフローは次第に減っていく中、個人を主体に引き続き出遅れが顕著であるマザーズ銘柄への物色も続くだろう。■豊田合、20/3期業績予想を下方修正、子会社譲渡で事業整理損失を計上豊田合は22日、2020年3月期の業績予想を下方修正した。連結子会社の株式譲渡および事業整理損失計上によるもので、営業利益は従来の410億円から210億円、当期純利益を250億円から120億円に修正している。合理化の一環で、ドイツ子会社を株式譲渡し追加費用が生じる。■前場の注目材料・日経平均は上昇(23112.88、+74.30)・NYダウは上昇(27875.62、+109.33)・ナスダック総合指数は上昇(8519.89、+13.67)・シカゴ日経225先物は上昇(23165、大阪比+35)・1ドル108円70-80銭・VIX指数は低下(12.34、-0.79)・米長期金利は低下・日銀のETF購入・株安局面での自社株買い・トヨタ「レクサス」EV投入、まず中国・欧州から・豊田合欧事業を再編、生産子会社の全株式譲渡・テクノスマート滋賀工場に25億円投資、リチウム電池用フィルム増産・フェローテク中国に8インチウエハー工場、月産10万枚・パナソニック21年度までに「赤字撲滅」、トップダウンで改革・テルモ米アオルティカ買収、個別化医療を推進☆前場のイベントスケジュール<国内>・日中外相会談・ローマ教皇訪日(26日まで)<海外>・特になし【市況】後場に注目すべき3つのポイント~出遅れ感が目立っている中小型株に注視25日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、出遅れ感が目立っている中小型株に注視・ドル・円は小じっかり、株高を背景に円売り先行・値上がり寄与トップはファナック、同2位は東エレク■日経平均は大幅続伸、出遅れ感が目立っている中小型株に注視日経平均は大幅に続伸。213.73円高の23326.61円(出来高概算5億1000万株)で前場の取引を終えた。先週末の米国市場の上昇というよりも、香港で24日投票が行われた区議会議員選挙で、民主派が圧勝する見通しとなったと伝えられたことが材料視された。民主派は区議選をデモの賛否を問う「住民投票」と位置づけられていたこともあり、民主派圧勝によってデモの鎮静化につながるとの期待が高まったようである。日経225先物はシカゴ先物清算値(23165円)を大きく上回り、23280円で寄り付くと、その後は23340円まで上げ幅を広げる局面もみられた。日経平均についても、前引け間際には23347.18円まで上げ幅を広げている。東証1部の騰落銘柄は値上がり数が1600を超えており、全体の7割を占めている。セクターでは精密機器を除いた32業種が上昇しており、鉱業、鉄鋼、海運の上昇率が2%を超えたほか、非鉄金属、パルプ紙、石油石炭、保険、証券、機械の強さが目立つ。指数インパクトの大きいところでは、東エレク、TDK、ソフトバンクG、ファナック、ファーストリテ、オムロンが堅調。一方で、バンナムHD、オリンパス、コムシスHDが小安かった。日経平均は200円を超える上昇となったが、日中値幅としては50円程度であるほか、出来高も低水準であるため、日経平均の上昇ほど積極的な参加はしづらいところであろう。香港の区議会議員選挙では、デモ支持の民意が示されたが、区議会は地域にかかわる政策を政府に提言する機関で実質的な権限は大きくないため、様々な政府見解の撤廃などが進んでいくのかを見極めたいところであろう。初動反応としてはショートカバーを誘う格好となったが、さらに上値を買い上がる状況につながるかは見極めが必要なところである。そのほか、米国では週後半に感謝祭の祝日を控えていることもあり、週を通じて商いは膨らみづらいところである。しかし、小幅ながらも日経平均は底堅い値動きが続いていることで、センチメントを明るくさせるだろう。そのため、ニュースフロー等で先物に振らされやすい需給状況ではあるが、物色としては相対的に出遅れ感が目立っている中小型株に、個人主体の資金が向かいやすいだろう。■ドル・円は小じっかり、株高を背景に円売り先行25日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。日本株などの堅調地合いで円売りが先行し、ドルは108円後半の高値圏で推移した。週明け25日の東京市場で、日経平均株価が前週末比200円超高となり円売りが先行。また、香港の区議会選で民主派圧勝を受けたハンセン指数の大幅高も円売りを支援。ドルは108円後半で小幅に値を上げた。ランチタイムの日経平均先物は引き続き堅調で、日本株高継続への期待感から円売りに振れやすいようだ。また、上海総合指数や欧米株式先物もプラス圏で推移し、午後の取引も株価にらみの展開で円売りを誘発しやすい見通し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円64銭から108円80銭、ユーロ・円は119円67銭から119円93銭、ユーロ・ドルは1.1017ドルから1.1024ドルで推移した。■後場のチェック銘柄・リブワーク、柿安本店など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値上がり寄与トップは東エレク、同2位はソフトバンクG■経済指標・要人発言【要人発言】・トランプ米大統領「香港と立場を共にするが、貿易合意も望んでいる」「香港に部隊派遣しないよう、習主席に警告した」「米中通商合意が非常に近い可能性がある」「米中交渉成立の判断はまだしていない」・習近平中国国家主席「中国と米国、誤った判断を避けるため戦略的な問題で対話を強化すべき」「中国と米国、両国関係を正しい方向へ発展させるべき」【経済指標】米・11月製造業PMI速報値:52.2(予想:51.4、10月:51.3)米・11月サービス業PMI速報値:51.6(予想:51.0、10月:51.0←50.6)米・11月総合PMI速報値:51.9(10月:50.9)米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値:96.8(予想:95.7、速報値:95.7)米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値:2.5%(速報値:2.5%)<国内>・日中外相会談・ローマ教皇訪日(26日まで)<海外>特になし(GDO)米国男子 ザ・RSMクラシック 最終日タイラー・ダンカンが初優勝 小平智は74位通算19アンダーで首位に並んだタイラー・ダンカンとウェブ・シンプソンのプレーオフとなり、これを制したダンカンがツアー初優勝を飾った。5位から出たダンカンはバックナインで4バーディを奪い、この日のベストスコアに並ぶ「65」で首位を捕らえる。18番の繰り返しで行われた1ホール目をパーで分け合い、迎えた2ホール目。ダンカンは7.5mのバーディパットを沈めて決着をつけた。通算18アンダーの3位にセバスチャン・ムニョス(コロンビア)。通算16アンダーの4位にブレンドン・トッドが続いた。トッドは首位スタートから「72」と落とし、3連勝はならなかった。74位から出た小平智は2バーディ、2ボギー1ダブルボギーの「72」。通算イーブンパーの74位で今年の米国ツアー最終戦を終えた。12時少し前に知人のクリニックへ…。過日に実施した健診の結果説明です…。まっ、血液検査の一部がわずかに基準を超えた程度で生活改善のお話のみ…。生検された部分は問題なしでした…。連休明けで混雑していましたが、うまく処理していただけて助かりました。帰り道のコンビニでサンドイッチを購入して、いつものGSで愛車に燃料補給と洗車をして、帰宅後にコーヒーで昼食タイム。(msn)(時事通信)ティファニー買収で基本合意=LVMH、総額1.7兆円―米報道 【ニューヨーク時事】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(電子版)などは24日、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」を抱える仏LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)による米高級宝飾ブランド、ティファニーの買収が基本合意に達したと報じた。 LVMHがティファニーの株式を1株当たり135ドル、総額約163億ドル(約1兆7700億円)で買い取ることで合意。両社とも24日に役員会を開いて最終合意案を協議しており、25日にも買収が正式発表される見込みという。 がん、血液1滴から検出=東芝が検査装置開発―精度99%、来年実証 東芝は東京医科大などと共同で、1滴の血液から13種類のがんを発見できる検査装置を開発した。がん細胞が血液中に放出する核酸分子の濃度を検出する仕組みで、がん患者と健常者を99%の精度で識別することに成功。数年以内の実用化に向け、2020年から実証試験を行う。 検査結果は、血液採取から2時間以内で判明。装置は持ち運び可能な小型タイプで、検査価格は2万円以下を想定している。 東芝は血液中にあり、遺伝子やタンパク質を制御する核酸分子「マイクロRNA」に着目。マイクロRNAは、がんのタイプにより放出する量や種類が異なることが分かっている。同社はこの核酸分子の濃度を測定する装置を開発した。 研究開発レベルで、大腸がん、胃がん、肺がんなど日本人がかかることの多い13種類のがんと健常者の血液中のマイクロRNAの濃度を測定し、99%の精度でがんの種類などを識別できた。「ステージ0」と呼ばれるごく初期のがんも検出できたという。 東芝によると、血液によるがん検査装置は他にもあるが、結果判明までの時間が長く、精度も低いという。同社は「定期健診や人間ドックなどで活用できる可能性がある」(研究開発センター)と期待している。 (msn)(東洋経済オンライン)マイナンバー「25%還元」は大化けするか マイナポイントが所得格差是正のツールに 来年度予算編成と新たな大型経済対策の議論が進む中、2020年9月以降に、マイナンバーカードを持つ人に25%のポイント還元を行うことが検討されている。 予算規模は2500億円という。2020年の東京オリンピック後に景気の落ち込みが心配されることから、その対策として今年10月に始まったキャッシュレス決済のポイント還元事業を継続するかどうか、その検討の中で出てきた案である。ポイント還元事業は2020年6月に終わることになっている。キャッシュレス決済するとマイナポイントを付与 ポイント還元事業を単純に延長するのではなく、利用が低迷するマイナンバーカードの普及も狙い、マイナンバーカードを活用した消費活性化策が浮上した。カードを持っている人が、キャッシュレス決済を用いて一定額を前払いなどすると、国が「マイナポイント」を付与する形でポイント還元を行う。 マイナポイントとは、マイナンバーカードにひもづけられたポイント制度だ。事前に登録などをすることによって、自分がよく使う電子マネーやQRコードなどのキャッシュレス決済に使うことができる。 今浮上している案では、一定額前払いなどをした額に対して、還元率25%でポイントを付与し、その上限額は1人当たり最大5000円とするという。つまり、最大で2万円を支払えば、国から5000円分のポイントが付与されて買い物などに使うことができる。 ただし、このポイントを受け取るには、まずマイナンバーカードを持たなければならない。その上で、マイナポイントを使えるようにするために、マイナンバーにひもづく「マイキーID」を作成しなければならない。 ポイントを還元してもらうのにわざわざそこまでしなければならないのか、と面倒に思う人も多いだろう。「マイキーID」や「マイナポイント」といった初めて聞く言葉が飛び出し、仕組みはややこしく聞こえる。 ただ、まだマイナンバーカードを持っていない人は、住んでいる自治体で発行手続きをすれば、マイナンバーカードを受け取る窓口でマイキーIDを作成できる体制が今後整えられることになっている。子どものマイキーIDは親が代理で作成できるようにするという。 そして、スマホなどで自分のキャッシュレス決済口座にマイキーIDをひもづける操作をすれば、マイナンバーカードを常時携帯する必要はない。マイナンバー普及で広がる政策余地 とはいえ、東京オリンピック後の景気対策として、キャッシュレス決済へのポイント還元をするぐらいなら、所得税を減税したほうがよほど簡単だと思う人もいるだろう。マイナンバーカードが普及していない現状からすればそうかもしれないが、所得税の減税で恩恵を受けるのは所得税を払っている人である。所得税を課税されないほどに低所得の人は、所得税減税の恩恵は受けられない。 他方、低所得者向けに限定して給付金を出す政策も、給付する窓口を市町村に担ってもらわなければならず、事務コストも馬鹿にならない。 そう考えると、マイナンバーカードとマイナポイントがもっと普及すれば、政策も工夫の余地が広がっていくと考えられる。今や、所得税を源泉徴収される場合などでは、所得を受け取る人が支払う側にマイナンバーを提供しなければならず、誰がいくら所得を稼いでいるかについて、以前よりも正確に把握できるようになっている。マイナンバーを使うとプライバシーが守れなくなると言おうにも、所得税関係ではすでにマイナンバーがかなり網羅的に付されている。 ただ、それは有効に活用されていない。つまり、所得税や住民税の課税額を計算する際に使われているが、それを他の用途には使っていない。今後、所得格差の是正策として、低所得者にはきちんと給付し、高所得者には給付しないというメリハリをつけたいなら、マイナンバーを用いて捕捉した所得の情報を活用する必要がある。 他方、これまでの給付は現金で渡すか、手続きをとって銀行振込みするしかなかった。それでは給付に多大なコストがかかる。銀行口座にマイナンバーを付番することが法律上認められているが、その体制が整っていない。銀行業界も、口座へのマイナンバー付番に積極的とは言えない。ベーシックインカムの発想も実現可能に しかし、マイナポイントがこのほど新設されることになった。多くの人がマイナポイントを使えるようになれば、国から個人に直接給付できるようになる。しかも、銀行口座にマイナンバーが付番されていなくてよい(もちろん、仕組みを今後整えてマイナポイントと銀行口座を個人でひもづけられるようにすることもできよう)。加えて、市町村の窓口に給付業務を委ねる必要はないから、行政の事務コストはかなり減る。 マイナンバーを用いて捕捉した所得情報と、マイナポイントを使った給付という組み合わせなら、所得の多寡に応じてきめ細かく給付する政策もできる。ベーシックインカムの発想も取り入れられるかもしれない。 2020年9月から2021年3月までの7カ月間に、マイナンバーカードを持つ人には25%のポイント還元を行う政策は、残念ながらまだそこまでの体制が整っていない。その結果、高所得者にも最大5000円のポイント還元が行われてしまう。 しかし、この政策を契機に、政策手段のインフラとしてマイナンバーカードとマイナポイントが普及すれば、今後「大化け」するかもしれない。世界的にもベーシックインカムが議論されながら具体化できていないが、行政のICT化後進国といわれた日本で、諸外国に先駆けてそうした政策が実現できる日が来るかもしれない。(msn)(ロイター)スイス製薬大手ノバルティス、米メディシンズを97億ドルで買収へ [チューリッヒ 24日 ロイター] - スイス製薬大手ノバルティスは24日、米バイオ医薬品メディシンズを約97億ドルで買収すると発表した。心血管疾病治療薬の強化が狙い。 ノバルティスはメディシンズ株1株当たり現金85ドルを支払う。これは同社株22日の終値に約24%上乗せした水準。ノバルティスは、買収は既に取締役会の承認を得ており、取得資金は手元資金と短長期の借り入れで賄うと説明した。ノバルティスは、メディシンズ買収により開発段階にあるコレステロール降下剤「インクリシラン」を入手する。同薬はノバルティスの心不全薬「エントレスト」を補完し、特許切れを迎える一連の医薬品によって脅かされる成長を補い、米アムジェンの「レパーサ」や仏サノフィと米リジェネロン・ファーマシューティカルズの「プラルエント」などの競合薬に対抗する。 ノバルティスによると、買収手続きは2020年第1・四半期に完了する見通しで、インクリシランは21年から売上高に貢献し始めるとみられ、将来的に売上高で最大規模の医薬品の1つに成長する可能性がある。ノバルティスは従来、心血管疾病の医薬品は得意分野だったが、かつて年間売上高60億ドルを誇った「ディオバン」が12年に特許切れを迎え、それに直ちに続く医薬品が無かったことが打撃となった。ノバルティスのナラシムハン最高経営責任者(CEO)は既存のビジネスモデルを新製品やテクノロジーで補完・強化する最大100億ドル規模のボルトオン型の買収に焦点を当てており、メディシンズの買収はこれに当てはまる。(yahoo)(ブルームバーグ)旭化成:米製薬会社ベロキシスを1432億円で買収、米事業基盤確立(ブルームバーグ): 旭化成は25日、米製薬会社のベロキシス・ファーマシューティカルズ(ノースカロライナ州)を約1432億円で買収することを決めたと発表した。旭化成の発表資料によると、ベロキシスの株式100%を保有するデンマークの会社から旭化成のデンマーク子会社が12月中に株式公開買い付け(TOB)を開始する。価格は 1 株当たり6デンマーククローネ(約 97 円)で公開買付けに要する資金は総額約89億デンマーククローネ。買収には保有する手元資金や新規のブリッジローンを充て、その後、最適な財務構成実現に向けた資金調達を検討する。ベロキシスは独自のドラッグデリバリー技術を活用して腎移植後に用いられる免疫抑制剤を販売し、高い成長が見込まれている。旭化成は買収を通じてこの技術の取り込みを図るほか、米国の医薬品市場での事業基盤を確立して日本やアジア事業に強みを持つ旭化成との相乗効果を創出する。ドラッグデリバリーは、薬物の効果を最大限に発揮させるため体内で必要最小限の量を患部に届ける技術。副作用を抑えることができることからがん治療などへの応用が有望視されており、国内では富士フイルムホールディングスも研究開発に注力している。ベロキシスの2018年12月期の売上高は3900万ドル(約42億円)。19年12月期は7500万ドルから8200万ドルを予想している。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-日経平均とマザーズのチャートが好転、「閑散に売りなし」相場に突入か 25日の日経平均は続伸。終値は179円高の23292円。米中通商合意期待から先週末の米国株が上昇した流れを受けて買いが優勢の展開。ただ、180円程度上昇して始まった後は、こう着相場が続いた。前場はじり高、後場は上げ幅を縮めたものの終盤にかけて盛り返し、終値(23292.81円)は始値(23292.85円)とほぼ同水準となった。東証1部の売買代金は概算で1兆6900億円と低水準。業種別では全33業種中、31業種が上昇しており、騰落率上位は鉱業、鉄鋼、海運、下位は精密機器、ゴム製品、繊維となった。証券会社がレーティングを引き上げたワークマンが大幅高。半面、架空発注により東京国税局から所得隠しを指摘されたと報じられた安藤ハザマが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1555/値下がり508。アリババの香港上場をあすに控えたソフトバンクGが大幅上昇。国際帝石やJFEHD、コスモエネルギーなど市況関連銘柄に非常に強い動きが見られた。がん検査キットの開発観測を材料に東芝が3%超の上昇。TATERUが新経営方針の発表を手がかりに急騰し、スルガ銀行やレオパレス21など投資用マンション絡みで売り込まれた銘柄に資金が向かった。東証1部への市場変更が好感された柿安本店はストップ高まで買われる場面があるなど値を飛ばした。一方、パナソニックや富士通、NECなど総合電機の一角が軟調。決済トラブルが発生したと報じられた楽天が売りに押された。日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)の失効回避で軍事リスクが低下したことを受けて細谷火工や石川製作所など防衛関連銘柄が大幅安。公募・売り出しが嫌気されたアーバネットコーポレーションが急落した。 日経平均は続伸。場中の値動きは乏しく、売買代金も低水準と物足りなさはある。ただし、先週後半に23000円を割り込んだ後、盛り返して買いが続いたことで、底打ち感が強まってきた。チャートを見ると25日線を割り込んだところで買いが入り、きょうの上昇で5日線を上回っている。この先は11月8日高値の23591円を試しに行く動きが見られるかが注目される。また、出遅れていたマザーズ指数も、きょうの上昇(終値:894.36p)で9月26日の戻り高値894.05pや52週線(893.05p、25日時点)を上回ってきた。テクニカル面からは、ここから主力株と新興株が歩調を合わせて上昇する展開も期待できる。週後半には米国株の休場を控えているため、今週は商い増加はあまり期待できないが、目先は「閑散に売りなし」相場が続く可能性がある。NY株見通し-今週は米中通商合意の行方を睨み神経質な展開か 今週のNY市場はもみ合いか。先週は米中通商合意への不透明感が強まったことで主要3指数がそろって反落したものの、先週前半につけた史上最高値(終値ベース)からは、ダウ平均が0.57%安、S&P500が0.38%安、ナスダック総合が0.59%安にとどまった。今週も高値警戒感が強いなか、米中関連報道を睨んだ神経質な展開が予想されるものの、いずれ何らかの形で米中が通商合意に至るとの期待が強いほか、緩和的金融政策の長期化見通しや、経済指標の改善傾向も相場の支援となりそうだ。今週の経済指標は11月コンファレンス・ボード消費者信頼感指数、10月新築住宅販売件数、7-9月期実質GDP改定値、10月個人消費支出(PCE)、同PCEコア・デフレーター、地区連銀経済報告(ベージュブック)など。決算発表はPVH、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、アナログ・デバイセズ、ダラー・ツリー、ベストバイ、HPなどに注目。 今晩の米経済指標・イベントは10月シカゴ連銀全米活動指数など。企業決算は寄り前にジェイコブズ・エンジニアリング、引け後にPVH、ヒューレット・パッカード・エンターなどが発表予定。(執筆:11月25日、14:00) (yahoo)(時事通信)〔東京株式〕続伸=香港株高で買い先行(25日) 【第1部】米中貿易協議への進展期待に加え、香港などアジア株高が材料となり、買い先行の展開だった。日経平均株価は前営業日比179円93銭高の2万3292円81銭、東証株価指数(TOPIX)は11.62ポイント高の1702.96と、ともに続伸した。 銘柄の72%が値上がりし、下落は24%だった。出来高は10億1101万株、売買代金は1兆6991億円。 業種別株価指数(33業種)は鉱業、鉄鋼、海運業が上昇し、下落は精密機器、ゴム製品のみ。 個別銘柄では、東エレク、キーエンス、村田製が買われ、SUMCO、ソニーは値を上げた。資生堂、エーザイは堅調で、任天堂もしっかり。三菱UFJ、三井住友、みずほFGが強含み、ソフトバンクG、ファーストリテは締まった。半面、トヨタ、日野自が売られ、日本電産、パナソニック、オリンパスは値を下げた。楽天は軟調で、ブリヂストン、横浜ゴムも緩んだ。 【第2部】続伸。東芝がにぎわい、サイバーSは急伸した。半面、音通は売られた。出来高1億1121万株。 ▽個人投資家が主役の相場 前週末の米国株式市場は、米中両首脳が協議に前向きな姿勢を示したことが報じられたことで投資家心理が改善し、主要指数は上昇した。この流れを受け、日経平均も約200円上昇して始まった。香港区議選で民主派が圧勝したことを受けてアジア株高となったことも、電子部品など中国関連銘柄への買いを強めた。ただ、午後に入ると利益確定売りに押され、上げ幅をやや縮小した。 売買代金は週明けということもあり、大きく膨らまなかった。「今週28日の感謝祭を前に、休暇モードに入った米国投資家が取引を控えている」(銀行系証券)という。一方、相場の主役となったのは個人投資家で「10月からの上げ相場で投資余力はまだあり、値動きのある銘柄を個別物色する動きが日本株を支えている」(大手証券)との指摘も出ていた。 225先物12月きりは、上昇した。終日2万3300円を挟んで高値圏でのもみ合いが続いた。(了) 〔東京外為〕ドル、108円台後半=終盤伸び悩む(25日午後5時) 25日の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は終盤伸び悩み、1ドル=108円台後半で推移した。午後5時現在は108円84~88銭と前週末(午後5時、108円60~60銭)比24銭のドル高・円安。 ドル円は前週末の海外市場で、トランプ米大統領が米中貿易協議の合意が近いと述べたことで108円70銭前後に上昇。東京時間の早朝も海外の流れを引き継ぎ、同水準で推移した。午前9時以降は五・十日要因の実需買いにより108円80銭近くまで上昇した。午後は中国メディアから米中協議が合意に近づいているとの報道があり、108円80銭台まで上伸。終盤は戻り売りに小緩んだ。 市場では「テーマとなる材料は変わらない」(FX会社)といい、引き続き米中協議に注目が集まっている。こうした中、香港区議会選挙で民主派が圧勝したが、「中国がどう出るか、現時点では判断できない」(同)ため、あまり材料視されていないようだ。 ただ、「米経済指標も良く、ドルを買うしかない状況ではある」(大手邦銀)と見る向きが広がっている。また、「市場にはマグマがたまっており、少し上抜けしたら、ドルは110円台後半まですぐに上がる可能性もある」(同)との声が聞かれた。 ユーロは終盤、対円、対ドルでもみ合い。午後5時現在は1ユーロ=120円05~06銭(前週末午後5時、120円16~17銭)、対ドルで1.1029~1030ドル(同1.1064~1064ドル)。(了) 〔NY外為〕円、108円台後半(25日朝) 【ニューヨーク時事】週明け25日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米中貿易協議の年内合意への期待などを手掛かりに売りが優勢となり、1ドル=108円台後半に下落している。午前9時現在は108円85~95銭と、前週末午後5時(108円61~71銭)比24銭の円安・ドル高。 ロイター通信によると、オブライエン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は23日、年末までに中国と「第1段階」の最終合意に達する可能性は依然としてあるとの認識を表明。また、中国共産党機関紙・人民日報系の環球時報も「第1段階」の合意は極めて近いと報じたという。これを受け、海外市場ではじりじりと円売り・ドル買いが進行した。 ニューヨーク市場入り後は、米経済指標の発表などの材料に乏しく、108円台後半で小動き。この日夜にパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が行う予定の講演にも注目が集まっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1010~1020ドル(前週末午後5時は1.1016~1026ドル)、対円では同119円90銭~120円00銭(同119円67~77銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも続伸(25日朝) 【ニューヨーク時事】週明け25日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の進展への根強い期待を背景に続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前週末終値比88.64ドル高の2万7964.26ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は60.48ポイント高の8580.37。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の26銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の16銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げてスタートしましたね。
2019.11.25
コメント(0)
-

11月24日(日)…2019ラウンド88…
11月24日(日)、雨~曇り…。予報とは裏腹に起床時は雨…、その後も明るい日差しはほとんど見られず…。そんな本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の研修競技に参加させていただきました。競技内コンペもあり。8時52分スタートとのことですから6時15分に起床。雨でテンションが低いです。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時30分頃に家を出る。8時頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…イマイチ…。本日の競技は西コースのブルーティー:6613ヤードです。ご一緒するのはいつものH君(10)、U君(15)、M君(15)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:1.1.2.0.2.1.1.2.1=47(17パット)1パット:2回、3パット:1回、パーオン:0回。1打目のミスが4回、2打目のミスが3回、アプローチのミス:2回、パットのミス:1回…、7番ショートまでしか記録ないです…。ひどい…、本当にひどい…、やることなすことすべてがミス…。もう途中で捨てましたから…。スルーでINへ。IN:1.1.0.2.0.0.1.1.1=43(16パット)1パット:2回、3パット:0回、パーオン:1回。もう切れていますから…。47・43=90(9)=81の33パット…。何の期待も持てません…、握りも負け…。スコアカードを提出して、握りの清算を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.4kg,体脂肪率20.5%,BMI21.9,肥満度-0.3%…でした。14時20分頃には帰宅。コーヒーとジンジャーケーキでおやつタイム。奥は落語へ出かけていきました。それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には57人が参加して、トップは72(4)=68とのこと。H君が84(10)=74で12位。E氏が92(16)=76で19位。I君が83(7)=76で21位。M君が92(15)=77で31位。僕が90(9)=81で42位。U君が103(15)=88で54位。お疲れ様でした…。<11月のゴルフの総括>11月は8ラウンド(77~91)して…1ラウンド平均ストローク:83.91ラウンド平均パット数:31.01ラウンド平均バーディー数:1.01ラウンド平均OB数:0.1握り:4勝2敗0分<2019年のゴルフの総括>2019年はここまでに88ラウンドしてそれぞれ…84.031.30.60.325勝15敗8分12月は今のところ7ラウンドが予定されています。年とともに成績は下り坂ですね…。(GDO)米国男子 ザ・RSMクラシック 3日目ブレンドン・トッドが3連勝に前進 小平智は74位シーサイドコースのみで行われる決勝ラウンドに7位で進んだブレンドン・トッドが8バーディ、ボギーなしの「62」をマークし、通算18アンダーの単独首位に浮上した。2連勝で迎えた今週も優勝争いに絡み、2017年のダスティン・ジョンソン以来となる3連勝に王手をかけた。通算16アンダーの2位にウェブ・シンプソンとセバスチャン・ムニョス(コロンビア)。通算15アンダーの4位にD.J.トレイハン。通算14アンダーの5位にイ・キョンフン(韓国)、リッキー・バーンズ、首位から後退したタイラー・ダンカンが並んだ。2週連続で決勝ラウンドに進んだ小平智は59位からスタートし、1バーディ、3ボギーの「72」。通算2アンダーの74位に後退した。国内男子 ダンロップフェニックストーナメント 最終日最終ラウンドは悪天候のため中止 今平周吾が今季2勝目雷の影響で2時間遅れの午前9時40分にスタートしたが、再び雷雲の接近により同10時16分に中断。その後は強い雨にも見舞われ、再開できないまま同10時45分に最終ラウンドの中止が決まった。前日までの成績を受けて、第3ラウンドを終えて通算10アンダーの単独首位にいた今平周吾が今季2勝目を飾った。54ホール短縮のため、賞金加算は75%。賞金ランキングトップの今平周吾は優勝賞金3000万円を加算して今季獲得賞金を1億5716万9312円とし、今大会を腹痛で棄権した2位のショーン・ノリス(南アフリカ)との差を約3720万円差に広げた。通算8アンダーの2位にハン・ジュンゴン(韓国)。3年連続の出場となった松山英樹は首位に5打差のまま、通算5アンダーの8位で大会を終えた。<最終成績>優勝/―10/今平周吾2/―8/ハン・ジュンゴン3T/-7/出水田大二郎、S.ビンセント5T/―6/S.ハン、M.ホマ、C.モリカワ8T/―5/松山英樹、B.ケネディ、キャメロン・チャンプ、木下稜介、池田勇太ZOZOを見た後のこうした展開にはちょっとしらけますね…。国内女子 大王製紙エリエールレディスオープン 最終日渋野日向子が涙の大逆転V 賞金女王決着は最終戦へ「全英」覇者の渋野日向子が逆転でツアー4勝目を挙げ、賞金女王戴冠へ望みをつないだ。首位と2打差の7位から、賞金ランキング1位の鈴木愛と同組でチャージをかけた。前半で3つ伸ばして鈴木と1打差の2位で折り返すと、10番から2連続バーディで首位に浮上。15番でもバーディを奪い、ボギーなしの「66」。通算19アンダーでライバルを振り切って優勝を決めると、涙を流した。前週「伊藤園レディス」で国内26試合ぶりに予選落ちを喫し、賞金レースで鈴木と約2430万円差で迎えた今大会。鈴木がツアー史上初の4連勝を決めればタイトルの望みが絶たれる状況で、自らの手でストップをかけた。ルーキーイヤーながら4勝目を積み上げ、優勝賞金1800万円を加算。鈴木、申ジエ(韓国)との三つ巴の争いは最終戦「LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」で決着する。<上位の最終成績>優勝/-19/渋野日向子2/-18/鈴木愛3/-17/イ・ミニョン4T/-16/古江彩佳、森田遥6/-15/高橋彩華7T/-14/ペ・ソンウ、勝みなみ9T/-13/藤田さいき、菊地絵理香(msn)(東洋経済オンライン)キーエンス、「40代半ばで新社長」の最強法則 9年ぶり社長交代、株式分割に伴い実質増配も トヨタ自動車、NTT、NTTドコモ、キーエンス、ソフトバンクグループ、ソニー、三菱UFJ――。 日本の株式市場の時価総額トップ企業を並べたとき、1社だけ消費者にあまりなじみのない企業がある。平均年収2100万円の高給で知られるキーエンスだ。 11月5日に株価は7万7470円をつけて年初来高値を更新。11月22日現在、時価総額は9兆円を超え、トヨタ自動車やNTT、NTTドコモに次いで日本で4位だ。株式分割で流動性を高める キーエンスはFA(ファクトリーオートメーション)に関わるセンサーや画像処理システムを手がける企業だ。FAとは工場の生産工程を自動化するために導入するシステムのことだ。2020年3月期上半期(4~9月期)こそ、米中摩擦などで世界的に設備投資需要が減退し、営業利益が前年同期比14%減少した。ただ、工場の自動化需要が旺盛なこともあり、同社の業績は今後も堅調に推移するとみられる。 経済産業省の企業活動基本調査によると、製造業の売上高営業利益率は5.5%(2017年度実績)。それに対し、キーエンスの2020年3月期上期の決算は売上高2769億円、営業利益1388億円で、営業利益率は実に50%にのぼる。 高い収益力が評価され、これまでも高い水準で株価が推移していたが、11月に入ってからは一段高となっている。市場が大きく反応したのが10月31日に第2四半期決算とともに発表した1株を2株にする株式分割だ。 キーエンスは機関投資家などの大口投資家の保有比率が高く、1単元以上50単元未満の株主の保有割合を示す「浮動株比率」は2.3%に過ぎない(2019年3月)。今回の株式分割により、流動性が高まることが期待される。 キーエンス株の最低売買単位は100株なので、投資するには最低でも700万円近くの資金が必要だったが、株式分割によってその半額で済む。 さらに市場が評価しているのが実質増配だ。株式分割を行うと普通は配当も分割した割合に合わせて減少するが、今回の株式分割では1株あたり年200円の配当を継続し、実質的に400円の増配となる。 キーエンスは2017年1月に1株を2株にする分割を実施した際には実質的な配当額を据え置いたが、今回は実質増配に踏み切った。 キーエンスの経営情報室長である木村圭一取締役は「これまでも決して株主を軽視していたわけではなく、引き続き株主の利益を重視していく」と話す。最近は株主還元を強化 多くの投資家はこれまで、「キーエンスは株主還元に積極的ではない」と捉えてきた。株主総会では毎回、社長や創業者である滝崎武光名誉会長の取締役選任議案に約3割程度の反対があり、株主総会での賛成率9割強が一般的な日本企業にあって、株主の不満が高い会社だといえる。 ただ、配当額は2018年3月期に年間100円、2019年3月期は年間200円、今回の株式分割で2020年3月期は実質400円と最近は株主還元を強化していた。 さらに、今年10月にアナリストや機関投資家向けの電話会議を初めて開いた。これまでアナリストや機関投資家からの問い合わせは個別に回答していた。10月発表の決算補足説明資料では、決算短信に記載されていない地域別売上高や状況、国内の業種別売上を記載している。 「開示内容の範囲はこれまでの個別の問い合わせでの回答と大きな差はない」(電話会議に出席したアナリスト)。地域別の状況についても決算後にアナリストがレポート等で投資家らに示していたため、市場で出回る情報量に大きな変化はないが、「会社側が自ら資料を作成し、説明会を行う態度に意義がある」(都内の機関投資家)と印象は悪くないようだ。 木村氏は「個別での対応だと回答するまで待ってもらうことでタイムラグが発生していた」と話し、個別対応にもこれまでどおり応じていくと説明している。 決算発表と同じ日にキーエンスはもう1つ重大な発表を行った。9年ぶりの社長交代だ。山本晃則・現社長が12月21日付で代表権のない取締役特別顧問に就き、事業推進部長で6月に取締役となった中田有氏が社長となる。中田氏は45歳で、現在9人いる取締役(監査役を除く)の中で2番目に若い。社長業における「キーエンスウェイ」 現社長の山本氏は2009年に取締役事業推進部長となり、翌2010年に45歳で社長に就任した。前社長の佐々木道夫氏は1999年に取締役事業推進部長となり、翌年に43歳で社長に就任した。その前任は創業者の滝崎武光氏だが、55歳で社長を佐々木氏に譲っている。 滝崎氏を除く歴代社長は、事業推進部長を経て40代半ばで社長となり、社長として約10年間職務を担っている。キーエンスは「事業の発展のために最適な人事を行っている」とするのみだが、「何かしらのキーエンスウェイなるものがあるのだろう」(外資系証券会社のアナリスト)との見方もある。 1988年2月13日号の「週刊東洋経済」で取材に応じた滝崎氏(当時は社長)は「私個人はそんなに好かれる人間ではないし、泥臭く個性で引っ張る経営は中小企業止まり。大企業はどこでも理念主導、オーソドックスでしょう」と語っており、個性的なトップに依拠する経営には否定的な考えを示していた。 もちろん、キーエンスが社長は誰でもいいと思って選んでいるわけではないだろうが、1人のカリスマに依存しない経営を築き上げているのなら、それは強みといえる。創業者の滝崎氏を含め、上司でも「さん」付けで呼び合い、論理的であれば新人の意見にも耳を傾けるフラットな組織文化がある。「技術開発力と自社の商品をしっかり説明できる直販営業体制という2つの強みがある以上、社長交代で経営に問題が起きることはない」(前出外資系アナリスト)。 ただ、現在のキーエンスを生み出した滝崎氏は、自身の資産管理会社を含めてキーエンスの株式の2割以上を握るとされる事実上の筆頭株主で、取締役名誉会長として経営にも携わっている。 キーエンスが本当にカリスマに依存していないのか。それは滝崎氏が経営を退いた時に真価が問われることになりそうだ。本日の夕食は、ビーフシチュー、野菜サラダ、パンでした。一緒に楽しんだのは…マルゴーの破格のガレージワイン:2007マロジャリアでした。美味しくいただきました。口福・口福!!
2019.11.24
コメント(0)
-
11月23日(土・勤労感謝の日)…2019ラウンド87…
11月23日(土・勤労感謝の日)、晴れです。起床時は日の出時ですから東の空が赤い…。本日はホーム1:GSCCの東コースで開催の勤労感謝の日杯に参加させていただきました。8時52分スタートとのことですから、6時15分頃に起床。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時20分頃に家を出る。7時50分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…マアマア…。本日の競技は東コースのホワイトティー:6512ヤードです。本日の競技は7本競技なので選択したクラブは、1W,5W,U24,7I,9I,SW,Ptです。ご一緒するのは、いつものU君(15)と、Sさん(4)、Hさん(18)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:1.0.1.1.1.0.0.0.1=41(18パット)1パット:0回、3パット:0回、パーオン:4回。パーオン4回のうちの2回はバーディーチャンスですが決まりません…。アプローチを寄せてのパーパットも決まらず、常に2パット…。1打目のミスが4回、2打目のミスが1回、3打目のミスが1回、パットのミスが3回…。スルーでINへ。IN:1.1.1.0.1.1.1.0.0=42(14パット)0パット:1回、1パット:2回、3パット:0回、パーオン:1回。1打目のミスが1回、2打目のミスが4回、3打目のミスが3回、パットのミスが1回…。3打目のトップが多くなりました…。18番ミドルも3打目をトップしてグリーン奥の斜面へ…、そこからの4打目がチップインパー…。41・42=83(9)=74の32パット。上位は望めませんね。ホールアウトの時点でNET:69,70がいますから…。スコアカードを提出して、握りの清算(勝ちました)を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.2kg,体脂肪率19.9%,BMI21.9,肥満度-0.6%…でした。帰宅すると14時00分頃。TVで国内男子ツアーを観戦しながら、コーヒーとカステラとシュークリームで少し早目のおやつタイム。ムービングサタデイですね!本日の競技の成績速報も出ていますね。本日の競技には75人が参加して、トップは85(16)=69とのこと。E氏ですね!I君が79(7)=72で10位。僕が83(9)=74で18位。U君が90815)=75で23位。T君が87(8)=79で53位。A君が91(10)=81で60位。O君が109(16)=93で74位。お疲れさまでした。(ブルームバーグ)【米国株・国債・商品】株上昇、貿易合意「非常に近い」とトランプ氏 22日の米国株相場は上昇。中国との貿易合意とりまとめは「非常に近い」とのトランプ大統領の発言が好感された。トランプ氏は一方で、貿易合意は自分よりも中国側の方が強く望んでいるとも述べた。 米国株は上昇、貿易協議巡るトランプ大統領の発言を好感 米国債はほぼ変わらず-10年債利回り1.77% NY原油は反落-週間では3週続伸 NY金変わらず、経済指標やトランプ氏発言で上げを消す FOXニュースが報じたトランプ大統領の発言に反応し、貿易協議の動向に特に敏感な自動車株が上昇をけん引。週間ベースでのS&P500種株価指数は、10月上旬以降で初の下落となった。原油先物はこの日下げ、米国債利回りはほぼ変わらず。 今週は米中貿易交渉の行方を巡り、楽観と悲観が交錯。相場のボラティリティーは抑制され、主要株価指数は小幅なレンジでの推移となった。 FTSEラッセルの世界市場調査担当マネジングディレクター、アレック・ヤング氏は「短期的な株式相場の方向性は、いまだに全て貿易協議次第だ」と指摘。「このところ実質的な進展がほとんど見られないことを考えると、相場が狭いレンジを抜けず、ボラティリティーが数カ月ぶりの低さにあるのは意外ではない」と述べた。 S&P500種は0.2%高の3110.29。ダウ工業株30種平均は109.33ドル(0.4%)上げて27875.62ドル。ナスダック総合指数は0.2%上昇。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時38分現在、10年債利回りがほぼ変わらずの1.77%。 ニューヨーク原油先物相場は反落。トランプ氏は中国との貿易合意が「非常に近い」としつつ、自分より中国側の方が合意を強く望んでいると述べた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は81セント(1.4%)安い1バレル=57.77ドル。週間では0.1%高となり、これで3週続伸。ロンドンICEの北海ブレント1月限はこの日58セント下落し63.39ドル。 ニューヨーク金先物相場は変わらず。朝方早い段階では上昇していたが、堅調な米経済指標や米中貿易協議を巡るトランプ氏の前向きな発言に反応し、逃避需要が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は前日比変わらずの1オンス=1470.50ドル。【NY外為】ドルが上昇、米経済指標が堅調-ポンドは安い 22日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対し上昇。一方、スイス・フランやユーロ、ポンドは対ドルでの下げが比較的大きかった。米国の製造業購買担当者指数(PMI)や消費者マインド指数が予想を上回ったうえ、英国や一部欧州諸国で発表された同様の指標がそれほど良くなかった。 ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。週間ベースでは0.4%上昇 同指数は55日、100日、200日の移動平均線を全て上回り、11月14日につけた直近の高値に近づいた カナダ・ドルは同国小売売上高が予想ほど減少しなかったことに反応して上げた後、原油相場の下落に沿って下げに転じた トランプ米大統領は中国との貿易合意が近いとの見方を再び表明。「香港を支持し、自由を支持する」一方、貿易合意の成立も希望していると語った この日発表された経済指標では、マークイット・エコノミクスの11月米製造業PMIが予想を上回り、前月から上昇。11月のミシガン大学消費者マインド指数(確定値)もエコノミスト予想を上回った ニューヨーク時間午後3時46分現在、ポンドはドルに対し0.6%安の1ポンド=1.2835ドル 11月13日以来の安値をつける場面があった 英野党・労働党のコービン党首は、総選挙で勝利し首相になった場合、公約通りEU離脱を巡る国民投票で中立姿勢を保つと表明 ユーロはドルに対して0.3%安の1ユーロ=1.1022ドル ニューヨーク時間遅くに下げ幅を拡大、1週間ぶりの安値となった 欧州には新しいポリシーミックスが必要だと、ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁は講演で述べた ドルは対円でほぼ変わらずの1ドル=108円64銭 ドルは一時、108円73銭まで上昇 米ドルはカナダ・ドルに対し0.1%高の1米ドル=1.3295加ドル WTI原油が下げる中、米ドルは週間ベースの上昇幅を拡大(ロイター)米国株109ドル高、米中協議巡る発言好感 テスラさえず[ニューヨーク 22日 ロイター] - 米国株式市場は上昇。ダウ平均株価.DJIは109ドル値上がりした。米中通商協議を巡る双方の発言が好感されたほか、底堅い経済指標も買い材料となった。 トランプ大統領は米中合意が「非常に近い可能性がある」と表明。ただ最終的な取りまとめを望むかどうかはまだ判断していないと述べた。中国の習近平国家主席も通商合意の取りまとめに意欲を示した。 ジャニー・モンゴメリー・スコット(フィラデルフィア)の主任投資ストラテジスト、マーク・ルスキーニ氏は、市場は米中交渉の行方に慎重だとした上で「合意が間近だという話は前から聞いている。どの程度間近なのかが問題なのであって、それが分からないために市場は様子見を迫られている」と述べた。 トランプ氏が香港人権法案への署名を明言しなかったことも相場を後押ししたという。 経済指標では、11月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が52.2と、10月の51.3から上昇し、4月以来7カ月ぶりの高水準を付けた。市場予想は51.5だった。 業種別ではS&P500の主要11業種中、7業種が値上がりした。 個別銘柄では、高級百貨店のノードストローム(JWN.N)が10.6%急騰。2019年の利益見通し引き上げや、予想を上回る第3・四半期(11月2日まで)の利益が好感された。低価格で商品を提供するオフプライス事業の売り上げ増や、在庫抑制などが寄与した。 一方、電気自動車(EV)メーカーのテスラ(TSLA.O)は6%安。同社初のピックアップトラック型電気自動車を発表したが、斬新な外観を巡って異論の声が上がったほか、窓ガラスの強度を証明する公開実演で窓が破損する事態にも見舞われた。 ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.50対1の比率で上回った。ナスダックでも1.40対1で値上がり銘柄数が多かった。 米取引所の合算出来高は59億6000万株。直近20営業日の平均は70億3000万株。 ドル上昇、好調な米経済指標受け=NY市場[ニューヨーク 22日 ロイター] - ニューヨーク外為市場では、ドルが当初軟調だったものの、11月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)が7カ月ぶりの高水準を付けたことを受け、上昇に転じた。 IHSマークイットが発表した11月の米製造業PMI速報値は52.2と、10月の51.3から上昇し、4月以来の高水準を付けた。市場予想は51.5だった。サービス部門PMIも51.6と、10月の50.6から上昇し、市場予想の51.0を上回った。 これに対しユーロ圏では、IHSマークイット発表の11月総合PMI速報値が50.3と、前月の50.6から低下し、景況拡大と悪化の分かれ目となる50に一段と迫った。 主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.24%高の98.23。一方、ユーロは対ドルで0.28%下落した。UBS(ニューヨーク)の外為ストラテジスト、ワシーリー・セレブリアコフ氏は、米PMIが好調だった一方、ユーロ圏PMIが軟調だったことでドルがやや押し上げられたと述べた。 ドル指数は週初からは0.24%上昇。来週に感謝祭の祝日を控える中、今週は米中通商協議を巡り相反するニュースが出てきたことで、積極的な取引が手控えられる展開となった。 米中通商協議を巡っては、中国の習近平国家主席がこの日、米国と「第1段階」の通商合意をまとめたい考えで、貿易戦争を起こさないよう取り組んでいると表明。ただ同時に、必要なら報復措置を講じることを恐れていないと述べた。トランプ米大統領もこの日、米中通商交渉は非常に順調に進んでいると表明。ただ最終的な取りまとめを望むかどうかはまだ判断していないと述べた。 外為市場におけるボラティリティーはこのところ低下しており、ドイツ銀行外為ボラティリティー指数.DBCVIXは5.86と、7月中旬以来の低水準を付けた。ただセレブリアコフ氏は「PMI統計、および通商問題を巡る一連のニュースは、ともに強弱材料がまだ入り混じっている」としている。 英ポンドは0.6%安の1.2836ドル。IHSマークイット/CIPSが発表した11月の英国のPMI速報値は、製造業とサービス部門を合わせた総合PMIが48.5と、10月の50.0から低下し2016年7月以来の低水準となった。EU、5G供給業者の厳格な選定で合意 ファーウェイに打撃[ブリュッセル 22日 ロイター] - 欧州連合(EU)は22日、ブリュッセルで大使級会合を開き、第5世代移動通信システム(5G)の機器供給業者を選定する際に厳しい基準を採用する案に支持を示した。中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)[HWT.UL]に対する打撃となる。 ロイターが入手した草案文書は、供給業者が第3国で従う必要のある法的、政治的な枠組みなどの技術以外の要因をEU加盟国は検証する必要があると指摘。EU加盟国は供給業者の多様化を図り、1社に依存してはならないとも提言した。 EUは来月の閣僚会議でこうした方針を承認するとみられている。 ファーウェイを巡っては米連邦通信委員会(FCC)がこの日、中国の中興通訊(ZTE)(000063.SZ)とともに、安全保障上の脅威に指定した。 (会社四季報オンライン)米国株上昇は結局、どうして続いているのか企業の利益は伸び悩んでいるが… 世界的な景気への懸念や様々なイベントリスクの中で世界の株式市場は堅調を保っているが、それを支えているのは、言うまでもなく米国株の好調さである。 しかしながら、米国株はなぜこんなにも上がるのか、そしてそれはまだ続くと見るべきなのか。 米国株の1949年末以降の株価(S&P500)の推移を示したものが図1である(1949年末を1として表示)。 長い目で見れば米国の株価は、一見急激に上昇し続けていることが分かる。パッと見た感じでは、危険なほど上がりすぎているようにも見えるが、それは単なる見た目のマジックであり、価格の絶対値ではなく上昇率で見てみると、実はそれほど不自然なものではない。昔も今も上がり続けている米国株 それを見るために先ほどのグラフを対数グラフというものに変換すると(図2)、米国株は、短期的な浮き沈みはもちろんあるものの、ならしてみるとほぼ一定の率で上昇し続けてきたことが分かる。 ちなみに、この70年間の年平均上昇率は8%弱である。ここには配当の受け取りが含まれていないので、それを含めれば年当たりの平均収益率は10%を軽く超える。投資対象としては大変魅力的だ。 この間、様々な出来事があり、米国覇権の終わりだとか米国衰退の始まりだとか、様々なことが言われてきたが、結局米国株は、相変わらず強い経済を背景に、昔も今も変わらずコンスタントにリターンを生み続けているのである。ある意味で、現在の米国株式相場は、今まで通りに上がり続けているだけに過ぎず、とくに異常な事態が生じているわけではないと見ることが可能だ。 さらに、株価上昇の長期的トレンドライン(図2の点線)との比較で言えば、50~60年代のアウト・パフォーマンス、70~80年代前半までのアンダー・パフォーマンス、2000年ごろまでのアウト・パフォーマンス、その後のアンダー・パフォーマンスを経て、現在再びアウト・パフォーマンスの領域に入ったばかりであり、単純に考えれば、まだ伸びしろはかなりあると見て取れるのである。 だが一方で、1990年代ごろから、米国の経済成長率は、名目ベースで見ても実質ベースで見ても、趨勢的に低下傾向にある。このことと、以前と変わらぬペースで株価が上がり続けることの間には矛盾はないのだろうか。 この20~30年ほどの間、GDPに占める被雇用者報酬の割合を示す労働分配率が大きく低下し、企業利益の比率が高まっている。それが、経済成長率が低下しても株価の上昇が衰えない一因であるとも考えられる。ただし、それだけでは説明は難しいだろう。 実際に企業利益の推移と株価推移を比べてみたものが図3だ(対数グラフ)。 これを見ると、2012年ごろ以降、企業利益は明らかに伸び悩んでいるにも関わらず、株価は上昇を続けていることがわかる。その結果、企業利益の水準と比較した株価には明らかに割高感が漂っているのだ。その一方で、過去においても同程度以上の割高さだった時期は見られる。とくに金利低下局面では企業利益の水準に比して株価が高くなりがちである。「超低金利時代」であることは、どう影響しているか さらに言えば、1990年代以降は、リーマンショック期を除いて株価水準が割高な状況がいわば常態化しつつあるようにも見える。その背景には、世界的な金余りを背景とした超低金利時代の到来があると考えるべきだろう。 フローとしての経済成長が停滞しても、ストックとしてのお金は積みあがっていく。そして、今や世界中であり余ったお金が超低金利環境の中で行き場を失い、割高であったとしても株(とくに米国の大型株)に流れ込まざるを得ないのだ。割高な米国株は、そうした意味ではニュー・ノーマル(新たな常態)とも言えるかもしれない。 もちろん、企業利益がこのまま停滞を続けるならば、株価だけがいつまでも上昇を続けることは難しくなるだろう。しかし、だからといって、単に割高だからということが株価の大幅下落を引き起こすとも考えにくい。株を売っても、ほかに持っていき場のないお金が大量にある以上は、なにかよほどの理由がなければ株式市場から資金が逃げていかないし、イベントリスクで一時的に逃げたとしても、結局また戻ってこざるを得ないからだ。 こうした見方は、あくまでも長期的な観点から見たざっくりとした話である。短期的にはもっといろいろなことが起こりうる。ただし、理解しておかなければならないのは、米国株が割高であることは明らかだとしても、超のつく金余りの環境では、相当な理由がなければ株は大きくは売られないということである。 その“相当な理由”になりそうなものについては、また機会をあらためて考えてみたい。(株探ニュース)【市況】国内株式市場見通し:日経平均は3週ぶりの反発を試す■米中通商協議を警戒し日経平均は2週続落前週の日経平均は下落した。週間ベースでは2週連続での下げとなった。週初18日の日経平均は、小幅高で寄り付いた後、マイナスへ転じる場面があるなど、その前の週末のNY株高の影響は限定的だった。しかし、香港ハンセン指数の上昇を受けて日経平均は続伸した。19日の日経平均は3日ぶり反落し、終日マイナスゾーンで推移した。NYダウは続伸で最高値を更新したものの、米メディアが米中貿易協議を巡り「中国側は悲観的なムード」などと報じ、先行き不透明感から円相場が1ドル=108円台半ばまでの円高となったことが嫌気された。19日のNYダウは複数の主要小売企業の決算が嫌気されて3営業日ぶりに反落し、20日の日経平均も続落した。朝方にかけて米議会上院が「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決し、米中対立が激化するとの懸念が浮上したが、後場は10月9日以来となる日銀によるETF(上場投資信託)買いがあり下げ渋った。米中通商協議が年内に第一段階の合意もできない可能性が報じられ、21日の日経平均は3日続落となり、11月1日以来となる約2週間半ぶりに節目の23000円を一時割り込んだ。トランプ米大統領が香港人権法案に署名する見通しが報じられ、米中対立懸念の高まりが警戒されて前場の日経平均の下げ幅は一時400円を超えた。しかし、中国の劉鶴副首相が米中第1段階合意に前向きな発言をしたことが伝わったことで、後場にかけて下げ幅を縮小し、日経平均は終値で23000円をキープ。米中協議の難航が懸念された21日のNYダウは3日続落となった。これを受けて22日の日経平均は軟調な寄り付きだったが、直近3日間で400円近く下げていたことから押し目買いが強まり4日ぶりに反発。後場は週末とあって模様眺めムードから伸び悩み、日経平均は74.30円高の23112.88円で大引けた。物色的には、中国通信機器最大手の華為技術(ファーウェイ)が日本企業からの部品調達額を拡大する見通しを示したことで電子部品関連に関心が向かったことが特徴となった。■中間配当金の再投資が下支え今週の日経平均は23000円を挟んだ往来相場が想定されるなか、3週間ぶりの反発を試す展開になりそうだ。年内の第一段階合意という米中通商協議に不透明感が台頭してきたが、中国の劉鶴副首相がライトハイザー米通商代表部(USTR)代表に対して、協議のために月内に訪中するよう招請したことが伝えられて、過度な警戒感は後退。いずれにせよ、NYダウ、日経平均ともに米中貿易協議と香港情勢のニュースフローに振り回される展開は続きそうだ。こうしたなか、27日にはMSCI新興国市場指数が、中国A株の比率引き上げを開始する。中国株にとって需給面でのプラス材料として働くことは東京市場にも間接的な支援材料だ。ちなみに、25日には日経平均先物が中南米で初、海外ではシンガポール、米シカゴに続いて3例目となるブラジル市場B3(サンパウロ)に上場する。一方、25日の10月シカゴ連銀全米活動指数を皮切りに12月第1週(2-5日)まで。米国で各種経済指標の発表が集中する。その内容に神経質な展開を強いられることも予想される。感謝祭のため26日に米国市場が休場、翌27日は半日の短縮取引となることから、週後半は手控えムードも強まりやすい。ただ、21日現在の東証1部騰落レシオが116.69%と直近ピークだった12日の142.34%から低下して割高感が後退する一方、日経平均23000円割れ局面では押し目買い意欲の強さも確認できている。全般は先物主導のインデックス売買の影響の強さが継続しそうだが、需給的には市場推定で約4兆3000億円規模とされる3月期決算企業の9月中間配当金の再投資が12月中旬まで期待されて、相場の下支えとして働いてくる。2000年以降、11月最終週と12月第1週の日経平均は上昇確率が高いというジンクスもある。■ブラックフライデーが刺激材料物色的には半導体関連などハイテク株に利益確定売りが先行する中で、相対的に出遅れていた医薬・食品のディフェンシブ株や資源・エネルギー関連株に買いの輪が広がってくるかが焦点となる。相対的にバリュー株(割安株)のパフォーマンスが注目されてきたが、26日にMSCIリバランスが予定されていることから、26日の大引けに掛けて個別株の動きは注意が必要となる。また、29日の米ブラックフライデーに絡んだニュースも個別の株価を刺激しそうで、消費関連、ネットショッピング関連銘柄にも関心が向かいそうだ。ブラックフライデーの売上速報は、例年通りならば12月1日か2日に出てくることになる。ブラックフライデーの前日となる28日はファーストリテイリングの株主総会で、小売り・消費関連は注目されやすい。■黒田日銀総裁講演や米感謝祭など主な国内経済関連スケジュールとして、26日は10月企業向けサービス価格指数、28日はパリ・ユーロフィナンシャルフォーラムで黒田日銀総裁講演(12時30分から14時頃)、10月商業動態統計、29日は10月失業率・有効求人倍率、10月鉱工業生産、11月消費動向調査が予定されている。一方、海外主要スケジュールとして、25日はパウエルFRB議長講演、26日は中国アリババ集団が香港市場に上場、27日は米7-9月期GDP改定値、米10月耐久財受注、28日は感謝祭で米国市場休場などが予定されている。(GDO)米国男子 ザ・RSMクラシック2日目2コースを2日間で回る予選ラウンドが終了し、シーサイドコースをプレーしたタイラー・ダンカンが自己ベストの「61」をマーク。前半8番では105ydの2打目をカップに沈めてイーグルを奪ったほか、7バーディを量産し、通算14アンダーの単独首位に浮上した。通算12アンダーの2位に、シーサイドコースを回ったセバスチャン・ムニョス(コロンビア)とライン・ギブソン(オーストラリア)、プランテーションコースを回ったD.J.トレイハンの3人が並んだ。3週連続優勝がかかるブレンドン・トッドはプランテーションコースで連日の「66」とし、通算10アンダーの7位で決勝ラウンドへ向かった。43位から出た小平智はプランテーションコースを3バーディ、1ボギーの「70」でプレー。通算4アンダーの59位とし、前週「マヤコバクラシック」から2週連続の予選通過を決めた。決勝ラウンド2日間はシーサイドコースのみを使用する。国内男子 ダンロップフェニックストーナメント3日目2年連続賞金王へ今平周吾が単独首位 松山英樹は5打差8位トップタイから出た賞金ランキング1位の今平周吾が7バーディ、2ボギーの「66」をマークし、通算10アンダーで単独首位に立った。2年連続賞金王へ、10月「ブリヂストンオープン」以来となる今季2勝目を狙う。2打差2位にハン・ジュンゴン(韓国)。8バーディ、1ボギーでこの日ベストスコアとなる「64」で回った出水田大二郎が通算7アンダーとし、スコット・ビンセント(ジンバブエ)とともに3位タイにつけた。松山英樹は6バーディ、2ボギーの「67」。ブラッド・ケネディ(オーストラリア)、キャメロン・チャンプ(米国)、池田勇太、木下稜介と並ぶ通算5アンダー8位タイ。逆転で5年ぶりの大会制覇を目指す。松山と同組で回った、6月の海外メジャー「全米オープン」覇者ゲーリー・ウッドランド(米国)は「70」と伸ばしきれず、通算2アンダー20位タイ。石川遼は4バーディ、ボギーなしの「67」で回り、通算1オーバー34位タイで最終日を迎える。<主な成績>1/-10/今平周吾2/-8/ハン・ジュンゴン3T/-7/出水田大二郎、スコット・ビンセント5T/-6/マックス・ホマ、スンス・ハン、コリン・モリカワ8T/-5/松山英樹、ブラッド・ケネディ、キャメロン・チャンプ、木下稜介、池田勇太国内女子 大王製紙エリエールレディスオープン3日目森田遥が単独首位 申ジエ1打差、鈴木と渋野が2打差で追う2位から出た森田遥が1イーグル6バーディ、3ボギーの「67」で回り、通算15アンダーの単独首位で最終日へ。2017年「北海道meijiカップ」以来となるツアー2勝目に向けて前進した。通算14アンダーの2位に、前年覇者の勝みなみ、賞金ランキング2位の申ジエ(韓国)、イ・ミニョン(同)、ペ・ソンウ(同)、高橋彩華の5人。勝は1イーグル、8バーディ、1ボギー1ダブルボギーと出入りの激しい内容ながら「65」をマークし、大会連覇と今季3勝目を狙える位置につけた。通算13アンダーの7位に、賞金ランク1位の鈴木愛と、同3位の渋野日向子が並んだ。渋野は9位スタートから6バーディ、ボギーなしの「66」と伸ばし、首位に2打差に迫った。10月「富士通レディース」のアマ優勝からプロ3戦目の古江彩佳は通算12アンダーの9位。カットライン上の50位で決勝ラウンドに進んだ菊地絵理香が、この日のベストスコア「63」をマークし、通算10アンダーの11位にジャンプアップした。<上位の成績>1/-15/森田遥2T/-14/勝みなみ、申ジエ、イ・ミニョン、ペ・ソンウ、高橋彩華7T/-13/渋野日向子、鈴木愛9T/-12/岡山絵里、古江彩佳(msn)(マネーの達人)「年金」ほど優遇された金融商品はない! 「年金」「生命保険」「傷害保険」の範囲で一生涯保障 老後のマネープランを構築するにあたり、社会保険制度を理解しておくことは重要です。特に・ 年金・ 医療・ 介護この3つの制度なくしてライフプランは語れません。制度を勉強するほど時間はない社会保険制度を正しく理解していないと、不利益を被ることもあります。重要だからといって制度の詳細にわたり、入門書などで学習するといった時間の使い方はおすすめできません。社会保険制度は常に改正や変更を繰り返し、また制度の細部にまで入ると非常に複雑な構造になっています。日常生活に追われる日々を送っている一般の方が勉強して追いつく時間はありません。そこで社会保険制度の仕組みについての理解は、大まかな形を捉えて、大きなキーワードだけ押さえておくといったスタンスで十分です。あとは必要なときが来たら、検索したり必要な知識を持っている専門家に丸投げすることが、最も合理的な考え方です。今や制度の細かな仕組みやルールは、ネットを介して無料で入手できる時代ですし、対応の良し悪しを度外視すれば、各自治体や年金事務所などに問い合わせることで、そこに待機している知識を持つ人たちの力を借りることが賢明です。年金制度によってカバーされている範囲日本の年金制度が多くの問題を抱えていることは周知の事実ですが、ここでは、日本の年金制度がカバーしている範囲についてだけ触れておきます。一般的に年金というと、リタイア世代が受け取る年金(老齢年金)を指します。つまり生きている限り無期限で受給できる終身年金です。しかし、年金によってカバーされているのは、こうした長生きへのリスクだけではありません。年金は「生命保険」としての役割も果たすこれを「遺族年金」といいますが、夫が亡くなった後でも一定額妻に支給されます。また、大きなケガを負ったときには、「障害年金」が支給されます。これは民間でいうところの「傷害保険」のようなものです。このような終身年金、生命保険、傷害保険を民間の保険会社で補おうとすると、相当高額な掛け金を覚悟しなければなりません。そもそも年金制度には税金が半分も入っているため、民間の保険会社とは比較にならないほど加入者にとって有利な仕組みで設計できる ことは当たり前なのです。また、年金の保険料は所得控除され、年金を受け取るときも公的年金等控除の適用を受けられるため、税金に関しても明らかに優遇されています。これほど有利な金融商品を見逃す手はない年金の未納、未加入の状態の方を時々見かけますが、いくら日本の年金制度に欠陥があるからといって、この有利な金融商品を放棄してしまう選択は極めて軽率な判断といわざるを得ないのです。なお、経済的な事情等がある場合には、保険料の免除制度といった、これまたおもいっきり優遇された制度があるので検討されてみることをおすすめします。(執筆者:長崎 寛人)(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)NY市場概況-3指数がそろって反発 週間ではS&P500が7週ぶりに反落 22日のNY株式相場は反発。米中両首脳の発言を受けて通商合意期待が再び高まったほか、良好な経済指標や好決算を受けた百貨店株の上昇なども投資家心理の改善につながった。ダウ平均は132ドル高まで上昇し、109.33ドル高(+0.39%)と4日ぶりに反発して終了。ファイザー、3M、ボーイング、ナイキなどが1%超上昇した。S&P500も0.22%高と4日ぶりに反発。不動産、エネルギーなど4セクターが下落したものの、金融、一般消費財、資本財、ヘルスケアなど7セクターが上昇した。ハイテク株主体のナスダック総合も0.16%高と3日ぶりに反発した。 週間では、ダウ平均が0.46%安と5週ぶりに反落し、S&P500は0.33%安と7週ぶりに反落。ナスダック総合も0.25%安と8週ぶりに反落した。 トランプ米大統領が「中国との合意は非常に近い」と発言したほか、中国の習主席も米国との通商交渉について前向きな姿勢を維持するとしたことで通商合意への期待が高まった。米経済指標では11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値が前月の95.5から96.8に上昇したほか、11月マークイット製造業PMIと同非製造業PMIも前月や市場予想を上回った。決算発表銘柄は、予想を上回る8-10月期決算や見通し引き上げが好感された百貨店のノードストロームが10.58%高と急伸したほか、アパレルのギャップも4.44%高となった。(yahoo)(フィスコ)国内株式市場見通し:日経平均は3週ぶりの反発を試す■米中通商協議を警戒し日経平均は2週続落前週の日経平均は下落した。週間ベースでは2週連続での下げとなった。週初18日の日経平均は、小幅高で寄り付いた後、マイナスへ転じる場面があるなど、その前の週末のNY株高の影響は限定的だった。しかし、香港ハンセン指数の上昇を受けて日経平均は続伸した。19日の日経平均は3日ぶり反落し、終日マイナスゾーンで推移した。NYダウは続伸で最高値を更新したものの、米メディアが米中貿易協議を巡り「中国側は悲観的なムード」などと報じ、先行き不透明感から円相場が1ドル=108円台半ばまでの円高となったことが嫌気された。19日のNYダウは複数の主要小売企業の決算が嫌気されて3営業日ぶりに反落し、20日の日経平均も続落した。朝方にかけて米議会上院が「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決し、米中対立が激化するとの懸念が浮上したが、後場は10月9日以来となる日銀によるETF(上場投資信託)買いがあり下げ渋った。米中通商協議が年内に第一段階の合意もできない可能性が報じられ、21日の日経平均は3日続落となり、11月1日以来となる約2週間半ぶりに節目の23000円を一時割り込んだ。トランプ米大統領が香港人権法案に署名する見通しが報じられ、米中対立懸念の高まりが警戒されて前場の日経平均の下げ幅は一時400円を超えた。しかし、中国の劉鶴副首相が米中第1段階合意に前向きな発言をしたことが伝わったことで、後場にかけて下げ幅を縮小し、日経平均は終値で23000円をキープ。米中協議の難航が懸念された21日のNYダウは3日続落となった。これを受けて22日の日経平均は軟調な寄り付きだったが、直近3日間で400円近く下げていたことから押し目買いが強まり4日ぶりに反発。後場は週末とあって模様眺めムードから伸び悩み、日経平均は74.30円高の23112.88円で大引けた。物色的には、中国通信機器最大手の華為技術(ファーウェイ)が日本企業からの部品調達額を拡大する見通しを示したことで電子部品関連に関心が向かったことが特徴となった。■中間配当金の再投資が下支え今週の日経平均は23000円を挟んだ往来相場が想定されるなか、3週間ぶりの反発を試す展開になりそうだ。年内の第一段階合意という米中通商協議に不透明感が台頭してきたが、中国の劉鶴副首相がライトハイザー米通商代表部(USTR)代表に対して、協議のために月内に訪中するよう招請したことが伝えられて、過度な警戒感は後退。いずれにせよ、NYダウ、日経平均ともに米中貿易協議と香港情勢のニュースフローに振り回される展開は続きそうだ。こうしたなか、27日にはMSCI新興国市場指数が、中国A株の比率引き上げを開始する。中国株にとって需給面でのプラス材料として働くことは東京市場にも間接的な支援材料だ。ちなみに、25日には日経平均先物が中南米で初、海外ではシンガポール、米シカゴに続いて3例目となるブラジル市場B3(サンパウロ)に上場する。一方、25日の10月シカゴ連銀全米活動指数を皮切りに12月第1週まで米国で各種経済指標の発表が集中する。その内容に神経質な展開を強いられることも予想される。感謝祭のため26日に米国市場が休場、翌27日は半日の短縮取引となることから、週後半は手控えムードも強まりやすい。ただ、22日現在の東証1部騰落レシオが113.01%と直近ピークだった12日の142.34%から低下して割高感が後退する一方、日経平均23000円割れ局面では押し目買い意欲の強さも確認できている。全般は先物主導のインデックス売買の影響の強さが継続しそうだが、需給的には市場推定で約4兆3000億円規模とされる3月期決算企業の9月中間配当金の再投資が12月中旬まで期待されて、相場の下支えとして働いてくる。2000年以降、11月最終週と12月第1週の日経平均は上昇確率が高いというジンクスもある。■ブラックフライデーが刺激材料物色的には半導体関連などハイテク株に利益確定売りが先行する中で、相対的に出遅れていた医薬・食品のディフェンシブ株や資源・エネルギー関連株に買いの輪が広がってくるかが焦点となる。相対的にバリュー株(割安株)のパフォーマンスが注目されてきたが、26日にMSCIリバランスが予定されていることから、26日の大引けに掛けて個別株の動きは注意が必要となる。また、29日の米ブラックフライデーに絡んだニュースも個別の株価を刺激しそうで、消費関連、ネットショッピング関連銘柄にも関心が向かいそうだ。ブラックフライデーの売上速報は、例年通りならば12月1日か2日に出てくることになる。ブラックフライデーの前日となる28日はファーストリテイリングの株主総会で、小売り・消費関連は注目されやすい。■黒田日銀総裁講演や米感謝祭など主な国内経済関連スケジュールとして、26日は10月企業向けサービス価格指数、28日はパリ・ユーロフィナンシャルフォーラムで黒田日銀総裁講演(12時30分から14時頃)、10月商業動態統計、29日は10月失業率・有効求人倍率、10月鉱工業生産、11月消費動向調査が予定されている。一方、海外主要スケジュールとして、25日はパウエルFRB議長講演、26日は中国アリババ集団が香港市場に上場、27日は米7-9月期GDP改定値、米10月耐久財受注、28日は感謝祭で米国市場休場などが予定されている。《FA》来週の相場で注目すべき3つのポイント:ブラックフライデー、米パウエルFRB議長講演、米中絡みのヘッドライン■株式相場見通し予想レンジ:上限23600-下限22800円来週の日経平均は23000円を挟んだ往来相場が想定されるなか、3週間ぶりの反発を試す展開になりそうだ。米中貿易協議で年内の第1段階合意に不透明感が増してきたが、中国の劉鶴副首相がライトハイザー米通商代表部(USTR)代表に対し、協議のために月内に訪中するよう招請したことが伝えられ、過度な警戒感は後退。いずれにせよ、NYダウ、日経平均ともに米中貿易協議と香港情勢のニュースに振り回される展開は続きそうだ。こうしたなか、27日にはMSCI新興国市場指数が、中国A株の比率引き上げを開始する。中国株にとって需給面でのプラス材料として働き、東京市場にも間接的な支援材料となる。ちなみに、25日には日経平均先物が中南米で初、海外ではシンガポール、米シカゴに続いて3例目となるブラジル市場B3(サンパウロ)に上場する。一方、25日の10月シカゴ連銀全米活動指数を皮切りに、12月第1週まで米国で各種経済指標の発表が集中する。その内容に神経質な展開を強いられることも予想される。米国市場は感謝祭のため26日に休場、翌27日に半日の短縮取引となることから、週後半は手控えムードも強まりやすい。ただ、22日現在の東証1部騰落レシオが113.01%と直近ピークだった12日の142.34%から低下して過熱感が後退する一方、日経平均の23000円割れ局面では押し目買い意欲の強さも確認できている。全般には先物主導のインデックス売買の影響の強さが継続しそうだが、需給的には市場推定で約4兆3000億円規模とされる3月期決算企業の9月中間配当の再投資が12月中旬まで見込まれ、その期待感が相場の下支えとして働いてこよう。2000年以降、11月最終週と12月第1週の日経平均は上昇確率が高いというジンクスもある。物色的には、半導体関連などハイテク株に利益確定売りが先行するなかで、相対的に出遅れていた医薬品・食品といったディフェンシブ株や資源・エネルギー関連株に買いが広がってくるかが焦点となる。相対的にバリュー株(割安株)のパフォーマンスが注目されてきたが、26日にMSCIリバランスが予定されていることから、26日の大引けにかけて個別株の動きは注意が必要となる。また、29日の米ブラックフライデーに絡んだニュースも個別物色を刺激しそうで、消費関連、ネットショッピング関連銘柄に関心が向かいそうだ。ブラックフライデーの売上速報は、例年どおりなら12月1日か2日に出てくることになる。ブラックフライデーの前日となる28日はファーストリテイリングの株主総会で、小売・消費関連株は注目されやすい。主な国内経済関連スケジュールとして、26日は10月企業向けサービス価格指数、28日はパリ・ユーロフィナンシャルフォーラムで黒田日銀総裁講演(12時30分から14時頃)、10月商業動態統計、29日は10月失業率・有効求人倍率、10月鉱工業生産、11月消費動向調査が予定されている。一方、海外主要スケジュールとして、25日はパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長講演、26日は中国アリババ集団が香港市場に上場、27日は米7-9月期国内総生産(GDP)改定値、米10月耐久財受注、28日は感謝祭で米国市場休場などが予定されている。■為替市場見通し来週のドル・円はもみ合いか。第1段階の合意に向けた米中通商協議の行方や米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策を巡る思惑が交錯し、方向感の乏しい相場展開となりそうだ。ただ、ドル安・円高に振れる局面ではドルの押し目買いが増える可能性があるとの見方が多いことから、引き続きドル・円は底堅い値動きが予想される。米上下両院で可決した「香港人権・民主主義法案」をめぐる両国の関係悪化への懸念から、米中協議のすみやかな進展への期待はやや低下している。また、通商協議における「第1段階」の署名に関して、来年にずれ込むとの観測も浮上している。米中通商協議の先行きは依然として不透明であることから、ドル・円は狭いレンジ内での値動きが続くとみられる。20日に公表された連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨では、目先は政策金利据え置きで一致したことが明らかになった。12月10-11日に開催されるFOMC会合での追加利下げ観測は後退したが、18日にパウエルFRB議長はトランプ大統領と会談しており、追加利下げを要請された可能性は否定できず、追加利下げを巡る市場の思惑が大きく後退する可能性は低いとみられる。■来週の注目スケジュール11月25日(月):国際通貨基金(IMF)が対日4条協議(経済審査)で記者会見、独IFO企業景況感指数、米パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が講演、ASEAN特別首脳会議など11月26日(火):企業向けサービス価格指数、米・卸売在庫・新築住宅販売件数・消費者信頼感指数、アリババが香港上場など11月27日(水):中・工業企業利益、米GDP改定値(7-9月)、米耐久財受注、米個人所得、米地区連銀経済報告(ベージュブック)など11月28日(木):日・小売売上高、黒田日銀総裁がパリ・ユーロプラス主催のフォーラムで講演、スイス・GDP(7-9月)、独・消費者物価指数、米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)など11月29日(金):日・有効求人倍率・住宅着工件数・消費者態度指数・鉱工業生産指数、台湾・GDP(7-9月)、独・失業率、韓・中央銀行が政策金利発表、印・GDP(7-9月)など《SK》(yahoo)(モーニングスター)株式週間展望=小型・個別株に資金シフト、指数底堅さ維持も薄商い備え―海外勢「店じまい」 米中対立の激化懸念を背景に今週(18-22日)は勢いが一服した日本株相場だが、押し目を待つ向きは多く、底堅さも示した。クリスマスシーズンが迫り、商いは徐々に閑散化する可能性がある一方、中・小型株や個別のテーマ株に関しては餅(もち)つき相場入りも想定される。香港をめぐる米中の緊張関係は予断を許さないものの、過度に弱気になる必要はない。<クリスマス商戦期待が株価下支え> 今週は日経平均株価が21日に前日比で一時420円超下落し、2万3000円を大きく割り込む場面があった。米上下院で香港での人権尊重や民主主義を支援する「香港人権法案」が可決され、中国側はこれを内政干渉ととらえ強く反発。折からの米中貿易協議の合意にも暗雲が立ち込めたことで、市場のリスク許容度低下を招いた。 ただ、前週の当欄で指摘した通り、日経平均は切り上がる25日移動平均線が一定の下支えとして機能している。21日も取引時間中に下回った同線を終値では奪回。押し目買いの意欲を映す下ヒゲを引いた上、図らずも今月初旬にあけた上げのマド(2万2852-2万3090円)が埋まるなど、需給面の安定感を取り戻したように見える。 香港人権法案についてはトランプ大統領による最終的な署名が焦点となり、依然として火種がくすぶる。また、学生らによる抗議活動が続く香港では24日に迫る区議会議員選挙の実施も危ぶまれる状況(22日午後3時現在)。リスクオフが進むことへの警戒は怠れない半面、好調な米国経済を背景に、クリスマス商戦への期待が株価の支援材料になりそうだ。 もっとも、これまで相場に乗ってきた海外勢はそろそろ休暇に入る時期。このため指数の影響を受けやすい主力株は、停滞感を強める可能性がある。今週はNYダウ(21日時点)やドル・円が狭いレンジにとどまったことからも、年間パフォーマンスが良好な投資家が「店じまい」を早めている様子がうかがえる。 今週は前週比で0.8%下落した日経平均とは対照的に、東証マザーズ指数は4.1%高と躍動した。年末特有の中・小型株へのシフトの兆しとも考えられ、来週(25-29日)も同じ傾向に備えたい。薄商いの中で、意外高を演じる銘柄も増えそうだ。日経平均の予想レンジは2万2700-2万3500円とする。 主な経済指標は国内で29日に10月鉱工業生産や同有効求人倍率、11月都区部消費者物価指数。海外では米国で26日に10月新築住宅販売件数と11月CB消費者信頼感指数、27日に10月耐久財受注と同中古住宅販売成約指数、欧州で25日に独IFO景況指数、29日にユーロ圏消費者物価指数の発表が予定されている。 このほか25日にパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が講演し、29日は米年末商戦のブラックフライデー。決算は26日の5G(次世代高速通信システム)関連企業の米キーサイト・テクノロジーズに注目したい。(市場動向取材班)昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の11銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。
2019.11.23
コメント(0)
-

11月22日(金)…
11月22日(金)、曇りです。朝は薄日もさしていましたが、午後になると雨もパラパラと…。そんな本日は7時20分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分頃には家を出る。ゴルフではありません…、今週の唯一のアルバイト業務です。インフルエンザ業務をスタッフがある程度を代行してくれたので午前のお仕事は少し早くに完了。お弁当を用意して近くの道の駅へGo!前回の訪問時より山並みの色が赤みを帯びましたね。お弁当を食べ終えたところで時間があるのでもう少し奥まで…小さな温泉郷がいくつかありますが、立派な日帰り温泉施設もありました。源泉が飲用できると書いてありますが、硫黄分を含んでいますね。職場の近くの観光施設の辺りでは雨が降り始めました…書類の作成などを終えて帰宅すると奥は不在です…。コーヒーとカステラとニキータ2号作成のジンジャーケーキで遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.61円。1AUドル=73.76円。昨夜のNYダウ終値=27766.29(-54.80)ドル。本日の日経平均終値=23112.88(+74.30)円。金相場:1g=5667(-26)円。プラチナ相場:1g=3621(-2)円。(ブルームバーグ)【日本株週間展望】足場固め、米中交渉期待根強い-香港情勢に警戒 11月4週(25ー29日)の日本株は足場固めが予想される。対中追加関税の発動期限を控えて米中交渉が進展するとの期待が根強いほか、米経済の堅調も評価されそう。半面、香港情勢は警戒される。 1600億ドル(約17兆3600億円)相当の中国製品への上乗せ関税を発動する12月15日が近づく中で、株式市場では米中間交渉に一層注目が集まる。関係者によると、劉鶴副首相はライトハイザー米通商代表部(USTR)代表に協議のための訪中を招請した。また、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)は、合意がなくても関税発動を米国が遅らせる公算と報道した。 一方、懸念されるのは香港情勢を巡る米中関係。米国で香港人権法案が成立すれば報復を中国が明言しており両国の考えは対立している。24日には香港で区議会議員選挙が予定されるが、通商交渉に影響を与えるきっかけになるかもしれず注意が必要だ。3週のTOPIXは週間で0.3%安の1691.34と続落。 経済指標では、米国で25日に10月シカゴ製造業景況指数、27日に10月新築住宅販売件数や11月消費者信頼感指数、10月耐久財受注が発表される。新築住宅販売は前月比0.8%増(前回0.7%減)、消費者信頼感指数126.8(同125.9)、耐久財受注は前月比0.5%減(1.2%減)とそれぞれ改善する見込み。≪市場関係者の見方≫ 三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之シニアストラテジスト 「日経平均2万3000円で値を固める動きを予想。関税発動期限を考えると間もなく両国で何らかの動きが出る可能性が高い。部分合意か実質的にはそれに近い形の妥協で、15日の関税実施は先送りとみる。実質的な合意となれば、米中摩擦は悪化するだけではないとの認識が初めて広がりそうだ。香港区議会選挙は香港市民の民意を確認する機会として注目される。日本の第2四半期決算では設備投資関連の下方修正が目立った。米中部分合意で設備投資が動き出せば企業業績とマクロ景気に対する見通しが改善し、もう一度買い直されるだろう」 三菱UFJ国際投信戦略運用部の石金淳チーフストラテジスト 「上昇を予想。米中交渉は第1段階の合意で経済への悪影響回避を目指す動機が双方にあり、決裂はなさそう。中国側が米高官を中国に招請しており、停滞気味だった協議が進展するとの期待が高まる。香港問題で米中関係が悪化する懸念はあるが、武力介入などがない限りすぐに中国を制裁するとは思えない。過熱感の強かった日本株は利益確定売りが出尽くした感じ。日経平均は25日移動平均線を支持線に下値は固い。予想レンジは2万3000円から2万3500円」【債券週間展望】上値の重い展開、一部に景気楽観論やオペ減額に警戒 11月第4週(25-29日)の債券市場は、買い戻しの動きが一巡し上値の重い展開が予想されている。一部に景気楽観論が浮上していることや、日本銀行の買い入れ減額への警戒感も重しになるとみられている。 市場参加者の見方◎SMBC日興証券の森田長太郎チーフ金利ストラテジスト金利の低下局面はひとまず終わり、方向としては反転上昇かマイナス金利深掘り観測が再浮上する理由は当面はない米中貿易交渉も少しずつ前進している感じがあり、株価にプラス材料と受け止められれば金利は上方向に動きやすい長期金利の予想レンジはマイナス0.11%~マイナス0.04%◎岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト良好な需給環境に支えられ底堅く推移しようが、一部に景気の底打ち見通しも広がっており、上値追いには慎重な投資家が多いだろう来年度の国債発行計画に向けた財務省の方針が注目超長期国債は投資家の根強い需要が続こうが、日銀オペ減額も警戒先行き不透明感は強くしばらくこう着状態となろう長期金利の予想レンジはマイナス0.11%~マイナス0.06%(会社四季報オンライン)(ロイター)米国株市場は小幅続落、米中通商協議巡る情報交錯で様子見ダウは54ドル安の2万7766ドル[21日 ロイター] - 米国株式市場は小幅続落して取引を終えた。米中通商協議が進展している明確な兆候がない中、情報が交錯し様子見の展開となった。米下院は20日、香港の民主化デモを支持する2つの法案を可決し、人権を巡る警告を中国に発した。これに中国は反発している。しかし、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が21日、関係筋の話として報じたところによると、中国政府は米政府に対し、新たな対面通商協議を提案したという。前日には米中通商協議の「第1段階」の合意が来年にずれ込む可能性があるとの報道が、市場の重しとなっていた。米株市場は過去最高値付近にあり、情報が交錯する中、様子見ムードが広がった。CFRAリサーチの最高投資ストラテジスト、サム・ストバル氏は「市場の一進一退の動きは、第1段階の米中通商合意への期待が軸となっている。投資家は『今年に起きる、起きない』と花びらをちぎって花占いをするように思案している」と指摘した。また、市場は基本的に可能な限り上昇しているとし、「予想PER(株価収益率)は18.5倍と20年平均の16.5倍を上回り、バリュエーションは割高になっているようだ」と述べた。この日は経済指標もまちまちの内容となった。新規失業保険申請件数は前週から横ばいで5カ月ぶりの高水準となり、労働市場がやや弱含んでいることを示唆。一方、10月の米中古住宅販売戸数は市場予想以上に増加。価格上昇率は前年比で約2年ぶりの大きさとなった。クレセット・キャピタル・マネジメントのジャック・アブリン最高投資責任者(CIO)は、経済指標には市場の値動きを大きく左右するほどのサプライズはなかったと語った。S&P総合500種の主要11セクターでは3セクターが上昇。エネルギーセクターは1.6%高と上昇率が最も大きかった。石油輸出国機構(OPEC)など産油国が協調減産を来年半ばまで延長するとの期待から原油価格が上昇したことが背景。不動産セクターは1.4%安で、下落率が最大だった。情報技術セクターは0.5%下落し、S&P総合500種を押し下げた。個別銘柄では、オンライン証券のTDアメリトレード・ホールディングが16.9%急伸。同業チャールズ・シュワブが、TDアメリトレードを買収する方向で協議しているとCNBCが報じたことが背景。チャールズ・シュワブは7.3%上昇した。宝飾品大手ティファニーは約2.6%高。仏高級ブランドLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)がティファニーに対する買収提示額を引き上げ、ティファニーがLVMHからのデューデリジェンス(対外秘の資産などの査定)の要請を受け入れたとのロイターの報道が好感された。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.55対1の比率で上回った。ナスダックでも1.37対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は68億3000万株。直近20営業日の平均は70億5000万株。日経平均は4日ぶり反発、後半伸び悩み売買代金は2兆円割れ終値は74円高の2万3112円[東京 22日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発した。米中通商協議に対する不安が若干後退したほか、外為市場でドル/円が落ち着いて推移したことを好感、さらに前日の引け味が良かったことから買い優勢で始まった。調整に一巡感が台頭したものの、週末とあって次第に見送りムードが強まり、後半は伸び悩んだ。東証1部の売買代金は2兆円を割り込んでいる。中国の劉鶴副首相が21日に米国との第1段階合意について「慎重ながらも楽観」と述べたことが引き続き注目された一方、中国がさらなる通商協議を行うため米交渉担当者を北京に招くという一部報道も材料視された。米中関係のポジティブなニュースは相場に安心感を与え、上海総合指数や香港ハンセン指数などアジアの主要株指数も上昇した。ただ「今夜発表される米国マークイット11月製造業購買担当者景気指数(PMI)や、24日に香港で行われる可能性のある区議会(地方議会)選挙を見極めたい投資家も多い」(国内証券)との声もあり、週末という事情も重なって後場に入り模様眺めとなり、急速に商いが細った。TOPIXは0.12%高で終了。東証33業種では証券業、パルプ・紙、ガラス・土石製品などの上昇が目立ち、その他製品、電気・ガス業が値下がり率上位に入った。東証1部の売買代金は1兆9031億7600万円と2兆円を下回った。個別では、トヨタ自動車、ソニーなど主力輸出関連株に高い銘柄が目立つほか、東京エレクトロン、アドバンテストなど半導体関連株も高い。半面、三菱地所、東京電力ホールディングスなど内需系銘柄の一角が軟化し、任天堂もさえない。東証1部の騰落数は、値上がりが1079銘柄に対し、値下がりが952銘柄、変わらずが123銘柄だった。(株探ニュース)【市況】来週の株式相場戦略=米中協議巡り「神経戦」続く、短期調整には一巡期待も 来週の株式市場は、依然、米中協議をにらんだ神経質な展開が予想される。日経平均株価の予想レンジは2万2800~2万3600円。 今週の日経平均株価は2週連続の下落となった。米議会が可決した「香港人権法案」に対し、中国が猛反発したことから米中協議の先行きに警戒感が台頭した。米国と中国関連の報道に一喜一憂する状況が続くが、来週もこれといったイベントはないなか、米中動向に株式市場は左右される展開が続きそうだ。 年内の米中動向が関心を集めているが、市場では「12月15日に予定されている第4弾関税引き上げは実施されず先送りとなり、米中協議も越年となる」(アナリスト)との観測が浮上している。しかし、これに対して「万が一、米中が決裂し関税が引き上げられるようならNYダウは1000ドル安も」(市場関係者)との見方がある。逆に、「米中交渉が予想通り前進する兆しが強まれば、NYダウは最高値更新基調を強める」(同)とみられている。米中協議の行方次第で全く違う状況が生まれるだけに、当面は手が出しにくい状態が予想される。 ただ、一時過熱感が指摘されていた日経平均株価は、調整を経てだいぶ落ち着いてきた。10月安値から11月高値までの上昇幅の3分の1押しは達成したほか、一時140%を超えた騰落レシオも110%台に低下してきた。米中情勢に大きな波乱がなければ、なお一進一退が続くというのが来週のメインシナリオだが、再上昇への準備は整いつつある。 来週は26日にパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演が予定されているほか、同日に米11月消費者信頼感指数、27日に米7~9月期GDP改定値が発表される。また26日には、5G関連の有力企業である米キーサイト・テクノロジーが決算を発表する。国内では29日に10月鉱工業生産と10月失業率などが発表される。 個別銘柄では、日経平均株価のもみ合いが続く場合は、富士通やリクルートホールディングスのようなグロース系の情報通信関連株、全体相場が上昇基調を強める場合は、安川電機や東京エレクトロンのような景気敏感の機械や半導体株が物色されそうだ。(岡里英幸)(GDO)米国男子 ザ・RSMクラシック初日ワグナーがツアー最多3度目のアルバトロス達成 小平智は43位2日間で2つのコースを回る予選ラウンド。プランテーションコース(パー72)で「65」をマークしたウェブ・シンプソンが今季2試合目の出場で、単独首位でスタートした。6アンダーの2位に同じプランテーションコースを回ったライン・ギブソン(オーストラリア)のほか、シーサイドコース(パー70)でプレーしたキャメロン・トリンガーリ、イ・キョンフン(韓国)がつけた。3アンダーの31位タイのジョンソン・ワグナーが、シーサイドコースの後半15番(パー5)で、残り255ydの第2打でアルバトロスを達成した。ツアーで自身3度目は、記録の残る1983年以降、ティム・ペトロビッチに並ぶ最多となった。小平智はシーサイドコースで2バーディ、ボギーなしの「68」で回り、2アンダー。前年王者のチャールズ・ハウエルIII、大会ホストのデービス・ラブIIIと同じ43位タイで滑り出した。国内男子 ダンロップフェニックストーナメント2日目今平周吾と池田勇太が首位並走 松山英樹は「9」で13位後退2年連続の賞金王を目指す賞金ランキング1位の今平周吾と2010年大会覇者の池田勇太が通算5アンダーの首位で並び、大会を折り返した。1打差2位から出た今平は3バーディ、4ボギーの「72」とスコアを落としながら、今季2勝目へ絶好の位置に浮上。池田は3バーディ、2ボギーの「70」でプレーした。ハン・ジュンゴン(韓国)と米ツアーから参戦のコリン・モリカワ(米国)が通算4アンダー3位タイ。通算3アンダー5位タイで昨年大会優勝の市原弘大、プラヤド・マークセン(タイ)、初日首位のジャン・ドンキュ(韓国)、木下稜介が続いた。米ツアー屈指の飛ばし屋キャメロン・チャンプ(米国)が星野陸也、スコット・ビンセント(ジンバブエ)、スンス・ハン(米国)とともに通算2アンダー9位タイにつけた。初日3位の松山英樹はスタートホールの1番で「9」をたたくなど「75」で通算1アンダー。6月の海外メジャー「全米オープン」優勝のゲーリー・ウッドランド(米国)らと並ぶ13位タイに後退した。石川遼は通算5オーバー49位タイで3試合ぶりに予選を通過。賞金ランキングで2位につけるショーン・ノリス(南アフリカ)はスタート前に腹痛で棄権した。<主な成績>1T/-5/池田勇太、今平周吾3T/-4/ハン・ジュンゴン、コリン・モリカワ5T/-3/プラヤド・マークセン、市原弘大、ジャン・ドンキュ、木下稜介9T/-2/キャメロン・チャンプ、星野陸也、スコット・ビンセント、スンス・ハン国内女子 大王製紙エリエールレディスオープン2日目ペ・ソンウ首位 鈴木愛5位、渋野日向子9位 藤本麻子らシード喪失首位と2打差の2位から出たペ・ソンウ(韓国)が6バーディ、ノーボギーの「66」でプレー。通算11アンダーとして首位に立った。首位で出た森田遥は「69」として通算10アンダー2位に後退し、21歳の高橋彩華と並んだ。通算9アンダー4位に、この日のベストスコア「65」をマークしたイ・ミニョン(韓国)がつけた。賞金ランキングトップで4週連続優勝が懸かる鈴木愛も「65」をマークし、通算8アンダー5位に浮上。同2位の申ジエ(韓国)、10月「富士通レディース」でツアー史上7人目のアマチュア優勝を飾った古江彩佳、岡山絵里と並んだ。賞金ランキング3位の渋野日向子は5バーディ、3ボギーの「70」でプレー。通算7アンダー9位で、前年大会覇者の勝みなみ、来季は米ツアーに挑戦する河本結ら5人と並んだ。今大会をもってツアー撤退を表明している一ノ瀬優希は通算6アンダー15位で決勝へ。佐伯三貴は通算4オーバー81位、諸見里しのぶは通算11オーバー91位で予選落ちした。今週が最後となる賞金ランキング50位までを巡る来季シード争いでは、圏外で予選落ちしたカリス・デイビッドソン(オーストラリア/53位)、藤本麻子(64位)、フェービー・ヤオ(台湾/67位)、佐伯(69位)、木戸愛(73位)、木村彩子(75位)、大江香織(78位)、ささきしょうこ(88位)、香妻琴乃(102位)らの賞金シード喪失が決まった。<上位の成績>1/-11/ペ・ソンウ2T/-10/森田遥、高橋彩華4/-9/イ・ミニョン5T/-8/鈴木愛、申ジエ、古江彩佳、岡山絵里9T/-7/渋野日向子、勝みなみ、河本結、テレサ・ルー、福田真未、蛭田みな美(msn)(ブルームバーグ)アップルがソフトのテスト方法見直し、iOS13で不具合続出-関係者 (ブルームバーグ): 米アップルは、「iPhone(アイフォーン)」と「iPad(アイパッド)」向け最新基本ソフト(OS)「iOS 13」で不具合が相次いだことを受け、ソフトウエアのテスト方法を見直している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。 ソフトウエア責任者クレイグ・フェデリギ氏やステイシー・リシック氏ら幹部は、ソフト開発者との最近の社内「キックオフ」ミーティングで今回の方針転換を発表した。 アップルの開発チームは新たな方法の下では、今後のソフトウエアアップデートのテストバージョンについて、未完成だったり不具合がある機能をデフォルトで無効にすることができる。テスト担当者は新たな社内プロセスや設定メニューを通じ、これらの機能を選択的に有効化するオプションを持ち、個々の機能追加によるシステムへの影響を限定することが可能になる。 今年9月の「アイフォーン11」発売と同時に「iOS 13」の配信が開始された時、アイフォーン所有者とアプリ開発者は、アプリの強制終了や起動の遅さなど、数々のソフト関連の不具合に見舞われた。 アップルの広報担当トルーディー・ミュラー氏はコメントを控えた。 新たな戦略は既に、来年公開予定の「iOS 14」の開発に取り入れられている。アップルは安定性重視の取り組みにより時間をかけるため、一部のiOS 14の機能を2021年まで先送りすることも検討している。 iOS 13の初期バージョンには不具合が多かったため、アップルは急いで修正パッチを用意しなければならなかった。iOS 13配信開始後の最初の2カ月で、8回のアップデートが提供された。これはフェデリギ氏がアップルのiOSソフトウエアエンジニアリンググループを引き継いだ2012年以降で最多となる。(msn)(ロイター)焦点:年金改革、将来不安は解消遠く 変わらぬ高齢者偏重 [東京 22日 ロイター] - 政府が年内に見直しをとりまとめる予定の年金制度の方向性が社会保障審議会で明らかになりつつあるが、2000万円問題を契機として高まった現役世代の不安解消期待は望めそうにない。急増する高齢者への給付財源を確保するため、パートなど年金の支え手を増やし働く高齢者を厚遇するが、一方で肝心の給付抑制には踏み込めず、4400万人の現役世代の給付改善への配慮は限定的だ。<「将来の安心」へシフト要望相次ぐ>21日に首相官邸で開催された第3回全世代型社会保障検討会議で、日本商工会議所の三村明夫会頭は安倍晋三首相に、政策の軸足を足元の安心から「将来の安心」へシフトすべきと提言した。高所得の高齢者の負担を増やし、事業主や子育て世代にかかる負担の抑制などの改革を早急に進めるべきという視点だ。 第2回の会議でも、学生企業家から「従来の高齢者偏重の社会保障制度から、どの世代も合理的に社会保障制度の便益を享受できる仕組みを作ってほしい」(株式会社GNEX代表取締役CEO、三上洋一郎氏)との意見が出ている。こうした現役世代が抱える不安の背景にあるのは、いびつな人口構成だ。年金保険料を支払う側の労働力人口は、現在7400万人が20年後には1400万人減少する一方、給付を受ける65歳以上は300万人増加する。今夏、厚生労働省が出した年金財政試算では、将来世代への年金支給率(現役男子手取りに対する年金額)は、今の高齢者の受給率61.7%に比べて、40%台にとどまるというシナリオも示されている。<働く高齢者の厚遇、将来給付には逆効果>しかし、5年に1度行われる今回の改革でも、年金の支え手を増やすために、高い収入があっても満額受給できる人を従来より増やす方向で見直しが進んでいる。現状の「在職老齢年金」という制度では、65歳以上で月47万円以上の収入のある人を対象に給付を減額しているが、高齢者の働く意欲を削ぐとして社会保障審議会では廃止も視野に議論されている。13日の審議会では、収入上限を51万円に引き上げる方向性が打ち出された。 「就労高齢者増加に合った年金制度に変える」(厚労省幹部)ことを大義名分に、高齢者にはなるべく長く働いてもらい、年金の支え手であり続けてもらうことが狙いだ。日本総合研究所・主席研究員の西沢和彦氏は「現役世代の将来の所得代替率は減少することなり、将来世代の不安解消には逆行するものだ」と指摘している。<本丸の給付抑制策、経済情勢頼みに限界> その一方で、政府の議論は、高額の年金をもらう高齢者への給付を抑制するところまでは踏み込んでいない。現状の年金制度は、物価や賃金が上昇した際に給付の上昇分を抑制する「マクロスライド」を用いており、経済・物価上昇した際にまとめて減額することになっているが、物価や賃金が上がりにくい局面においては全く機能しない。 日本総研の西沢氏は「経済情勢に依存する制度では不安定。人為的に毎年抑制していくべき」と指摘。高齢者にとっても「物価が上がった時だけ年金が減額されるのは、逆に生活が苦しくなる」(ニッセイ基礎研究所・主任研究員の中嶋邦夫氏)との見方もあり、現役世代、高齢者のいずれにとっても好ましい政策とは言い難いものになっている。<パートも厚生年金加入へ、125万人担い手拡大狙う>現役世代に対しては、支え手となる厚生年金加入者を増やして保険料徴取を拡大する方針だ。厚労省は、従来加入対象でなかった中小企業のパート労働者にも厚生年金の適用を拡大する方針で、厚生年金への加入者を「現状の4400万人から125万人程度の増加を目指す」(別の厚労省幹部)としている。今後、フリーワーカーや個人事業所の雇用者にも幅広く加入してもらうことを目指す議論も出ている。ニッセイ基礎研の中嶋氏は「時短勤務で働く人にとっては、厚生年金加入により将来の受給額増のメリットがある」とみている。ただ、現役世代の中には「年金の支え手が増えても、将来の給付が確実に受け取れる安心感が持てない。保険料拡大を図りたい政府に都合の良い改正」(50代男性)との声もある。今後、年金に続いて医療改革の議論も本格化する。しかし、厚労省の幹部の1人は「医療費削減も含め、今回論点に上がっている社会保障改革を全て実現できたとしても、40年後の給付金は改革前とそれほど変わりないとの試算がある」と本音を漏らす。中嶋氏は「少子化を食い止めなければ、問題は抜本的には解決しない。政府はもう少しその点に力を入れるべき」と指摘している。「負担と給付の見直し」だけでなく、より長期的視点で少子化対策による世代構成のゆがみを是正すべく、根本的な取り組みが求められている。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-下げ渋り後の反発で底打ち期待が高まる、来週は新興市場に注目 22日の日経平均は4日ぶり反発。終値は74円高の23112円。米国株の下落を受けて小幅に下げて始まったが、寄り付きを安値に早々にプラス圏に浮上。前日に売られた半導体株などに見直し買いが入ったことで投資家心理が改善し、上げ幅を3桁に広げた。ただ、23200円台に乗せたところでは買い一巡感から上値が重くなった。後場は週末で様子見ムードが強まる中で伸び悩んだが、プラス圏で落ち着いた動きが続いた。東証1部の売買代金は概算で1兆9000億円。業種別では騰落率上位は証券・商品先物、パルプ・紙、ガラス・土石、下位はその他製品、電気・ガス、空運となった。1:2の株式分割を発表したgooddaysホールディングスがストップ高。半面、証券会社が投資評価を引き下げたテレビ朝日ホールディングスが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1079/値下がり952。証券会社が目標株価を引き上げた村田製作所が大幅上昇。アドバンテストや太陽誘電などハイテク株に買いが入り、日本電産が年初来高値を更新した。直近で動意づいた後に調整を入れていた銘柄が見直されており、ZHDが4%近い上昇。前日大幅安の木村化工機が急伸した。きのう新規上場して好発進となった247は商いを伴って10%超の上昇と上値を伸ばした。一方、証券会社が投資判断を引き下げた任天堂が3%超の下落。資生堂やコーセーなど化粧品株が売りに押された。好地合いでディフェンシブ系が敬遠されたことから関西電や東電HDなど電力株が総じて軟調。公募・売り出しが嫌気された第一精工が大幅安となった。 日経平均は4日ぶり反発。終盤は萎んだが、外部要因からは買い材料に乏しかったにもかかわらず、比較的強い動きとなった。きのう大きく売られた半導体株などにも買いが入っており、目先の底打ち期待を高める上昇であったと言える。週間では日経平均が0.8%安、TOPIXが0.3%安であったのに対して、マザーズ指数が4.1%高と、逆行高かつ大幅な上昇となった。週末値(888p)で26週線(876p、22日時点、以下同じ)を上回っており、すぐ上に52週線(894p)が控えている。今年はまだ52週線を上回ったことはなく、ブレークできれば上昇に弾みがつく展開が期待できる。日経ジャスダック平均も今週は週間上昇で、きょう年初来高値を更新している。来週は新興市場の動向に注目しておきたい。【来週の見通し】 堅調か。引き続き米中関連のニュースには振り回されるだろう。ただ、日経平均は今週、下を試して切り返しており、押し目があれば買いが入ると考える。月末週で経済指標の発表が多く、中でも米7-9月期GDP改定値や米10月耐久財受注などが注目される。これらは相場のかく乱材料となりうるが、現状では指標が悪くても金融緩和長期化期待が高まりやすく、マーケットにネガティブに作用する可能性は低いと考える。28日の米国市場は感謝祭により休場で、年末商戦が意識されるタイミング。今年は米株高と利下げ効果で好調が見込まれることから、商戦活況期待が楽観ムードを高めやすい。神経質な地合いは続くとみるが、弱材料には一定の耐性を示し、戻りを試す展開を予想する。【今週を振り返る】 軟調となった。序盤は米国株高を好感した買いが入った。しかし、中国が米中合意に悲観的との報道や、米中合意が来年にずれ込むとの報道が流れたことで、米中通商協議に対する楽観的な見方が後退。交渉進展を示唆する報道も出てきたが、錯綜する情報にリスク回避ムードが強まり、次第に売りが優勢となった。天井感が強まり、日経平均は節目の23000円を割り込む場面もあった。しかし、そこでは押し目買いが入って急速に値を戻したことから、終盤にかけては持ち直した。日経平均は週間では約190円下落し、週足では2週連続で陰線を形成した。【来週の予定】 国内では、10月企業サービス価格指数(11/26)、10月商業動態統計(11/28)、10月失業率、10月有効求人倍率、11月都区部消費者物価指数、10月鉱工業生産、10月住宅着工統計(11/29)がある。 海外では、独11月Ifo景況感指数、米10月シカゴ連銀活動指数(11/25)、米9月FHFA住宅価格指数、米9月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米10月新築住宅販売件数、米11月消費者信頼感指数(11/26)、米7-9月期GDP改定値、米10月耐久財受注、米10月個人消費支出・個人所得、米10月NAR仮契約住宅販売指数、ベージュブック(11/27)などがある。 なお、11/28の米国市場は感謝祭のため休場となる。NY株見通し-底堅い展開か 米経済指標は製造業PMI、ミシガン大消費者信頼感指数確報値など 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は米中通商交渉を巡る先行き不透明感から積極的な買いは控えられ、主要3指数がそろって続落した。ただ、週前半に付けた史上最高値からの下落率はダウ平均が0.96%、S&P500が0.59%、ナスダック総合が0.75%と、そろって1%未満の下落にとどまった。年初からの上昇率はダウ平均が19.03%、S&P500が23.80%、ナスダック総合が28.20%となっており、高値警戒感や不透明感が強いなかでの堅調推移となっている。今晩は週末の取引で持ち高整理の動きが警戒されるほか、米中関連ニュースを睨んだ神経質な動きが予想されるものの、緩和的な金融政策の長期化見通しなどを背景に引き続き底堅い展開が期待できそうだ。 今晩の米経済指標は11月マークイット総合PMI、同製造業PMI、同サービス部門PMI、11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値など。企業決算は寄り前にJMスマッカーなどが発表予定。(執筆:11月22日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)来週の日本株の読み筋=米中問題注視も押し目買いニーズ根強い 来週(25-29日)の東京株式市場は、香港をめぐる米中の緊張関係は予断を許さないものの、押し目買いニーズは依然根強いとみられる。 米上下両院で香港人権法案が可決され、中国側はこれを内政干渉として強く反発。トランプ米大統領による最終的な同法案への署名が焦点になり、火種がくすぶっている。また、抗議活動が続く香港では、24日に迫る区議会議員選挙の実施も危ぶまれ、リスクオフへの警戒感は怠れない。 一方、米議会の香港人権法案可決で、21日の日経平均株価は一時420円超の下落を演じたが、売り一巡後は急速に下げ渋り、前日比109円安にとどめた。押し目待ちの投資家は多く、日銀のETF(上場投資信託)買い期待とともに需給面でのサポート役として意識される。当日は、下ヒゲの長い日足を形成し、直近の「マド」(1日高値2万2852円-3連休明け5日安値2万3090円)埋めを達成。終値で25日移動平均線をキープし、目先調整一巡との見方も出ている。市場では、「米中の話で揺れる可能性はあるが、下への耐性ができたようだ」(中堅証券)との声が聞かれた。加えて、好調な米経済を背景にクリスマス商戦への期待が株価の支援材料になる可能性もある。 スケジュール面では、国内で29日に10月失業率・有効求人倍率、10月鉱工業生産が発表される。海外では25日に独11月Ifo景況感指数、26日に米10月新築住宅販売件数、米11月CB消費者信頼感指数、27日に米7-9月期GDP改定値などが予定されている。 22日の日経平均株価は4日ぶりに反発し、2万3112円(前日比74円高)引け。朝方は、21日の米国株安を受け、小安く始まったが、すかさず切り返した。きのうの3日続落で短期的な過熱感が後退するとともに円弱含みもあって買い優勢に転じ、上げ幅は一時180円に達した。一巡後は、昼休みの時間帯に中国・上海総合指数が下げに転じ、香港ハンセン指数が上げ幅を縮めたこともあり、後場中盤に向けて伸び悩んだ。とりあえず下ブレを回避したが、市場では「まずは下向きの5日線を早期に回復できるかが注目される」(準大手証券)との読みがあった。今晩のNY株の読み筋=米中関係の動向にらみ神経質な展開か 22日の米国株式市場も、米中関係の動向をにらみながら神経質な展開とみる。連日安の反動も期待したいところだが、NYダウは依然として高値圏にあって過熱感が残る。米中貿易協議や香港情勢に進展や落ち着きがみられればポジティブだが、現時点でその兆しはみられていないため、買いが優勢となっても懸念が払しょくされない間は上値の限られた展開が予想される。また、香港では24日に区議会(地方議会)選挙が予定されており、これが様子見の材料にもなりそうだ。<主な米経済指標・イベント>11月製造業PMI、11月非製造業PMI、11月ミシガン大学消費者態度指数(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕4日ぶり反発=中国株高や円安好感(22日)☆差替 【第1部】中国株の値上がりや小幅な円安を好感し、買いが優勢となった。日経平均株価は前日比74円30銭高の2万3112円88銭、東証株価指数(TOPIX)は1.96ポイント高の1691.34と、ともに4日ぶりに反発した。 銘柄の50%が値上がりし、44%が値下がりした。出来高は11億1711万株、売買代金は1兆9031億円。 業種別株価指数(全33業種)は情報・通信業、小売業、電気機器が上昇し、その他製品、医薬品、空運業は下落した。 個別では、ソフトバンクGがにぎわい、ファーストリテは強含み。トヨタの買いが厚く、ソニー、東エレクも値上がりした。キーエンス、ファナックはしっかり。木村化は個別に買われ、急伸した。半面、任天堂は大量の売りを浴び、大幅に下落した。SUMCOが甘く、SMCも下押した。武田が売られ、資生堂、コーセーは軟調だった。JR東日本が下げ、ANAは緩んだ。 【第2部】小反発。アルデプロが高く、技研HDも堅調。半面、東芝、那須鉄がさえない。出来高1億0319万株。▽一時180円高 22日の東京株式市場は、中国・香港や上海株の値上がりと小幅な円安を受け、前場中盤にかけて買いが先行した。ただ、株価が上昇するにつれて売り注文が厚みを増し、午後の取引で伸び悩む銘柄が多かった。日経平均株価は前日比180円93銭高の2万3219円51銭まで上昇した後、上げ幅を縮小した。 海外投資ファンドが休日を前に株価指数先物をいったん買い戻し、現物株の値上がりにつながったとみられる。ただ、「新規の資金流入は少なかった」(銀行系証券)とみられ、取引は盛り上がりを欠いた。「米国と中国の貿易交渉の先行きが不透明なため、上値追いには慎重な投資家が多かった」(中堅証券)との指摘があった。 225先物は2万3030~2万3210円で推移した。上値では買いが細り、下値では売りが止まるボックス相場となった。(了) 〔ロンドン外為〕円、108円台後半(22日午前9時) 【ロンドン時事】週末22日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難から動意に乏しく、1ドル=108円台後半での小動きとなっている。午前9時現在は108円55~65銭と、前日午後4時(108円45~55銭)比10銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=120円20~30銭(前日午後4時は120円15~25銭)で、05銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1065~1075ドル(1.1070~1080ドル)。(了) 〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも反発(22日朝) 【ニューヨーク時事】週末22日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議をめぐり楽観的な見方がやや強まり、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比51.86ドル高の2万7818.15ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は22.99ポイント高の8529.20。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の20銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の13銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げてスタートしましたね。
2019.11.22
コメント(0)
-

11月21日(木)…
11月21日(木)、晴れです。本当に良い天気が続きますね。本日は休養日ですね。でも、8時頃には起床…。ニキータ2号はまだ寝ていますが…。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。ゴディバのチョコレートと共に。美味い!!1USドル=108.44円。1AUドル=73.70円。昨夜のNYダウ終値=27821.09(-112.93)ドル。現在の日経平均=23022.57(-126.00)円。金相場:1g=5693(+1)円。プラチナ相場:1g=3623(+34)円。(ブルームバーグ)米国株が下落、米中合意の成立時期巡り懸念 20日の米株式市場では、S&P500種株価指数が1カ月ぶりの大幅安。米中貿易合意の第1段階が年内にまとまる可能性は低いとの報道が響いた。 米国株は下落、通信や自動車の下げ目立つ 米国債は上昇、10年債利回り1.74% NY原油先物は反発、クッシング在庫が3カ月ぶり大幅減 NY金先物はほぼ変わらず、12月限は1474.20ドル 通信と自動車銘柄を中心にS&P500種は下落。米中貿易協議で第1段階の合意がまとまるのは、来年以降になる可能性があると、ロイター通信は報じた。その後、協議は進展しているとの報道も流れ、同株価指数は下げ幅を縮小した。米上院本会議は前日、香港人権法案を全会一致で可決。デモ参加者らを支援する同法案可決を受け、中国は反発する声明を出していた。米下院はこの日、この法案を採決する。 S&P500種は0.4%下げて3108.46。ダウ工業株30種平均は112.93ドル(0.4%)安い27821.09ドル。ナスダック総合指数は0.5%下落。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時32分現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.74%。 18日に最高値を更新したS&P500種とダウ平均は2日連続で下落。貿易の見通しを巡り懸念が広がった。投資家は景気に関するニュースに敏感ながらも、米中の緊張が和らぐとの見方に支えられ、今年の株式相場は上昇。このままいけば、2013年以来の大幅高となる。 ネッド・デービス・リサーチの米国担当チーフストラテジスト、エド・クリソルド氏は「市場は今年の大半にわたって貿易を材料に取引してきた。貿易に関する期待と不安だ」と指摘。「過去数週間には何らかの合意が成立するとの期待があった。現実の状況が明らかになりつつある」と述べた。 ニューヨーク原油先物相場は反発し、月初来の大幅高。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計では、米石油受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫が8月以来の大幅な減少となった。全米での原油在庫は前日の米石油協会(API)発表より小幅な増加にとどまった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は1.90ドル(3.4%)高の1バレル=57.11ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は1.49ドル上げて62.40ドル。 ニューヨーク金先物相場はほぼ変わらず。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は10セント安い1オンス=1474.20ドルで終了。ニューヨーク時間午後2時20分現在、金スポットも0.1%未満の下落。米中貿易協議で緊張が高まっている兆しを背景に、金連動型上場投資信託(ETF)の保有高は拡大した。【NY外為】ドル指数が続伸、米中貿易巡る懸念で安全逃避の動き 20日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。米中貿易協議への懸念が高まり、リスク選好の動きが後退した。米金融当局がこの日公表した連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨によれば、今年3回の利下げ後は金利を維持することに当局者の大半が賛同した。主要10通貨の中ではユーロと円が比較的しっかり。 ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇で続伸 先進国通貨の大半は対ドルで小幅な値動きに終始 ドルは前日遅くから上昇。米上院が香港人権法案を可決し、中国の反発を招いたことが手掛かり 円とスイス・フランは、米中貿易協議で第1段階の合意が年内にまとまらない可能性があるとのロイター報道を受けて値上がり 米国株と国債利回りはいずれも下げ ニューヨーク時間午後4時48分現在、ドルは対円で0.1%高の1ドル=108円63銭 ポンドはドルに対し0.1%未満安い1ポンド=1.2923ドル 英総選挙を控えて行われた党首討論では、ジョンソン首相とコービン労働党党首がほぼ互角だったとの世論調査結果が出た ユーロはドルに対して0.1%安の1ユーロ=1.1072ドル 欧州中央銀行(ECB)は緩和的な金融政策がもたらす副作用のリスクを警告 米ドルはカナダ・ドルに対して0.3%高。原油相場の上昇にもかかわらず、米ドルは10月10日以来の高値をつけたLVMHがティファニーへの買収案で条件引き上げ、協議入り 仏高級ブランド、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは米ティファニーへの買収提案で条件を引き上げ、両社は協議に入っている。事情に詳しい関係者が明らかにした。部外秘であることを理由に匿名で語った。 同関係者によると、LVMHはティファニーの買収額を1株130ドル前後としている。最終的な決定は下されておらず、協議は物別れとなる可能性もある。 LVMHは10月にティファニーに同120ドルでの買収を提案していた。(ロイター)米国株式市場は下落、米中の「第1段階」合意が越年も[20日 ロイター] - 米国株式市場は、主要株価3指数がいずれも下落して取引を終えた。米中通商協議の「第1段階」の合意が来年にずれ込む可能性があるとの報道を受けて懸念が高まった。米連邦準備理事会(FRB)が20日公表した10月29─30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨も市場の支援材料にはならなかった。 FRBは議事要旨で、今後の見通し変更につながる要因についてほとんど示唆しなかった。10月のFOMCでは今年3度目の利下げを決定。今後利下げを休止する可能性があることを示唆していた。[nL3N28042S][nL3N27F4UG] 米上院は19日、中国が香港に高度の自治を保障する「一国二制度」を守っているかどうか米政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決した。[nL3N27Z5K5] これを受け、米中間の緊張が高まることへの懸念から米株市場は下落して始まった。その後、ロイターが専門家やホワイトハウスに近い関係者の話として、米中通商協議の「第1段階」の合意が来年にずれ込む可能性があると報じたことから、3指数は下げ幅を拡大。午後の早い時間に日中安値を付けた。[nL3N280458] ホライズン・インベストメンツのスコット・ラドナー最高投資責任者(CIO)は「トランプ米大統領は12月15日に対中追加関税の発動を予定している。市場は第1段階の合意がこの日までに成立することを期待してきた」と指摘した。 LPLフィナンシャルのシニア市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は、S&P総合500種.SPXが20日まで、過去30営業日において2日続落していなかったことに言及。市場はとっくに下落しても不思議はなかったと話した。 その上で、香港を巡る米中間の緊張が通商協議の進展に大きな影響を及ぼす可能性に懸念を示した。 この日は幅広い銘柄に売りが出た。S&P総合500種.SPXの主要11セクターでは8セクターが下落。上昇したのは公益事業.SPLRCU、不動産.SPLRCR、エネルギー.SPNYだけだった。 貿易動向に敏感な情報技術セクター.SPLRCTは0.7%安。フィラデルフィア半導体指数.SOXは1.2%下落した。 素材セクター.SPLRCMは1.2%安と下落率が8セクター中最大だった。金利動向に敏感な金融セクター.SPSYは日中安値からやや持ち直したものの、0.5%安で終了。安全資産とされる国債が買われ、米10年債利回りがさらに低下したことに圧迫された。 個別銘柄では、小売大手ターゲット(TGT.N)が14%急伸。ホームセンター大手ロウズ(LOW.N)も3.9%上昇した。両社とも通期の利益見通しを引き上げたことが好感された。[nL3N2803NI][nL3N2803RL] 一方、アパレル小売チェーンのアーバン・アウトフィッターズ(URBN.O)は15.2%急落。四半期の売上高が市場予想を下回った。 ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.36対1の比率で上回った。ナスダックでも1.70対1で値下がり銘柄数が多かった。 米取引所の合算出来高は78億7000万株。直近20営業日の平均は70億3000万株。(株探ニュース) 【市況】前場に注目すべき3つのポイント~前日の日銀ETF買い入れで23000円処での底堅さ意識21日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し: 前日の日銀ETF買い入れで23000円処での底堅さ意識■前場の注目材料:ケア21、19/10期上方修正 営業利益10億円←8億円■住友電、中国から水処理膜モジュール受注、来年度47%増強■前日の日銀ETF買い入れで23000円処での底堅さ意識21日の日本株市場は、米株安の流れもあり、こう着感の強い相場展開になりそうだ。20日の米国市場はNYダウが連日で100ドル超の下落となった。米中通商協議が年内に第一段階の合意もできない可能性が報じられ、売りが先行。米上院が可決した香港人権法案に対して中国が反発していることから先行き不透明感が強まり、軟調推移となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比5円安の23135円。円相場は1ドル108円50銭台で推移している。米株安の流れから利益確定の流れが優勢になりやすいところであろう。一方で、前日には10月9日以来となる日銀のETF買い入れが観測されている。日経平均の23000円接近で買い入れが行われたことにより、短期筋の売り仕掛け的な動きも抑制されることになり、23000円処での底堅さが意識されやすいだろう。米中通商協議に向けた期待感が後退していることからリバウンド力は強くないだろうが、米上院が可決した香港人権法案に対しての中国の反応などは前日の下落などで織り込まれており、リバランス中心ながらも底堅さが意識されそうだ。セクターでは原油相場は大きく反発していることもあり、このところ調整基調が続いていたエネルギー株へは買い戻しが意識される。また、住友鉱には外資系証券による強気観測が相次いでいることもあり、非鉄金属セクターへの動向も見極めたいところ。その他、本日はマザーズ市場にトゥエンティーフォーセブンが上場する。パーソナルトレーニング事業を展開しており、RIZAPグループの経緯から神経質なところではあろうが、足元の中小型株物色への回帰などもあり、センチメントが改善傾向にある中で、人気化しやすいだろう。マザーズ指数は4営業日続伸で直近の戻り高値水準を捉えてきている。長期的な調整トレンドの中で、上値抵抗として意識されていた26週線も僅かに突破してきている。もう一段の上昇で明確に抵抗線を突破してくるようだと、より中小型株への修正リバウンドが意識されてくる可能性もある。日経平均がこう着感を強める中で、中小型株の活躍に期待したいところであろう。■ケア21、19/10期上方修正 営業利益10億円←8億円ケア21は2019年10月期業績予想の修正を発表。営業利益は従来の8億円から10億円に上方修正している。新規出店を含めより高い効果が見込める施策へのシフトによって、投資効率の改善を進めた。■前場の注目材料・1ドル108円60-70銭・米原油先物は上昇(57.11、+1.90)・VIX指数は低下(12.78、-0.08)・米長期金利は低下・日銀のETF購入・株安局面での自社株買い・住友電中国から水処理膜モジュール受注、来年度47%増強・キリンHD米クラフトビール会社買収、ノウハウ共有・NTTトヨタにAI技術提供、車載アシスタント向け・豊田合米3工場増強、内外装部品の売上高1.3倍・島津製健康寿命延伸、明治HD・帝人・オリエンタル酵母と企業連合・富士フイルム米で抗がん剤の臨床開始、卵巣がんなど適応☆前場のイベントスケジュール<国内>・特になし<海外>・特になし円高・株安傾向が進行していますね…。(msn)(ダイヤモンド・オンライン)三菱ケミカルの「野望」、田辺三菱製薬に5000億円の大枚をはたく理由 化学国内首位の三菱ケミカルホールディングスが、約5000億円の大枚をはたいて田辺三菱製薬を完全子会社化する。田辺三菱を巡っては一時、売却の可能性までうわさされたのに、だ。狙いはどこにあるのか。(ダイヤモンド編集部 新井美江子、土本匡孝)化学業界にうずまく長年の疑問がようやく解決した 11月18日、化学国内首位の三菱ケミカルホールディングス(HD)は、化学業界に長らく渦巻いていた同社への疑問の答えをようやく明確にした。 疑問とは、56.4%を出資する田辺三菱製薬の“処遇”についてである。製薬会社は対売上高研究開発費比率が20%前後とただでさえ高い上、日本では2018年の薬価(医療用医薬品の公定価格)の抜本改革によってますます強まった薬価の引き下げ圧力で、利益も出にくくなる一方なのだ。 コングロマリットディスカウント(さまざまな事業を展開する複合企業<コングロマリット>の価値が、事業をそれぞれ個別に展開して足し合わせた価値より劣っている状態)を回避し、化学事業に集中するためには売却することが得策なのではないか――。 かつて筆者は、越智仁・三菱ケミカルホールディングス社長本人にこの疑問をしつこくぶつけたことがある。だが、「コングロマリット企業として事業同士リスクヘッジしながら、一定規模を保つことが重要」と、可能性さえ微塵も匂わせることなく交わされた。 果たして、越智社長が出した答えは、売却どころかむしろ完全子会社化の道を選ぶことだった。11月15日の終値に53.08%のプレミアムを乗せ、なんと約5000億円の大枚をはたいて田辺三菱の株式を買い付けるというのである。 確かに、田辺三菱にとっては、いまや三菱ケミカルHDの完全子会社になること以外に激動の製薬業界を生き延びる選択肢は残されていなかった。 足元では、スイス製薬大手ノバルティスからのロイヤリティ収入を巡って係争が勃発し、仲裁手続きが進行中。そのため、一部のロイヤリティ収入を売上収益に計上することができず、19年3月期、20年3月期上半期と減収減益が続く。 おまけに特許が切れた新薬(いわゆる長期収載品)の割合が高く、「革新的な新薬のみ評価する」傾向を強める薬価制度下では、今後も引き下げ影響をまともに食らう可能性が高い。かといって海外の自社展開が他社に比べて進んでいるわけでもなく、先行きにも暗雲が立ち込めていた。 一方で、将来の飯のタネを確保するには新薬開発の手を緩めるわけにいかない。実際に、研究開発費比率は年々高まって20年3月期は22.7%(予想)と、高水準を保たざるを得ない状況が続いている。 この持ち出しばかりが増える事態に、短期的な利益還元を望む少数株主の不満をぬぐうことができず、田辺三菱は頭を抱えていた。 もっとも、いくら困っていたからといって、これが田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併した2007年当時であれば、製薬会社として世界で2番目に古い“名門田辺”が、三菱への完全軍門入りを許さなかったかもしれない。 ただ、14年には三菱化成工業(現三菱ケミカル)出身の三津家正之氏が社長に就き、17年には三津家社長就任と同時に会長職に就いた土屋裕弘氏が相談役に退いていた。社内取締役の数のバランスは「旧田辺出身者:三菱グループ出身者=3人:3人」を維持したものの、経営陣の“三菱色”は確実に強まっていた。 事業面でも、低分子化合物で稼げる時代はとうの昔に終わり、事業拡大には新たな知見とさらなる資金が必要になっていた。 2000年代ならば規模や有望な開発品を求めて、さらなる競合との合併があり得た。だが現在、国内同士の合併は「統合作業の苦労など経営停滞のデメリットを超える統合効果が得られないことが、2000年代に皆よく分かったので考えにくい」(某アナリスト)。 海外大手との合併も、2000年代とは異なり日本販路を開拓済みの海外大手にメリットがない。はたまた武田薬品工業のように有望他社を買収しようにも、M&A(企業の買収・合併)市場の“出物”の相場は高騰の一途を辿っている。中堅に過ぎない田辺三菱が、現在の局面をドラスティックに変えられるほどの買収に成功するとは考えにくい。着々と進めていた1.4万人分の健康データ分析 三菱ケミカルHDの完全子会社となることで、田辺三菱は業績低迷期にあっても、市場関係者などに文句を言われることなく、存分に研究開発費を投じられるようになる。三菱ケミカルHDが持つ海外人材やITを活用した新たな開発技術、海外ベンチャーへのパイプなどを使うことで、創薬と海外展開のスピードアップも図れるようになる。 では、翻って三菱ケミカルHDのうま味は何なのか。どうやら越智社長には、“野望”があるようだ。 ずばり、ヘルスケアサービス事業の確立である。病気予防を促す個人向けのアプリや、医療を後押しする医師向けのサービスの展開で、新たな収益源を手にする思惑があるのだ。 前触れはあった。三菱ケミカルHDは17年、「i² Healthcare(アイツー ヘルスケア)」なるプラットフォームを独自に開発。従業員にウエアラブル端末を配布し、取得した歩数や睡眠、心拍数のデータと、健康診断のデータや残業時間といった働き方のデータなどを連携させ、従業員の健康をモニタリングしている。 実はこれ、「健康経営」を達成するための社内的な試みである半面、次のビジネスの壮大な実験でもあった。ウエアラブル端末のデータは、従業員からビッグデータとして活用していいとの許可を得ており、着々と分析が進んでいるのだ。ちなみに、端末は経営陣を含め1.4万人に配布済み。まずまずのサンプル数が集まっている。 こうした健康データの解析の精度を上げるとともに、将来的には薬の服用データなども加え、個人の健康促進のみならず、患者の生活習慣に合った有効な投薬を後押しするような医師向けのサービスの展開にもつなげたい考えがある。つまり、三菱ケミカルHDが構築したプラットフォームが、新たに田辺三菱の知見とノウハウが乗っかる形で、“大化け”するかもしれないのだ。 田辺三菱には医療従事者とのネットワークがあり、三菱ケミカルHDの新たなサービスも展開しやすい。薬に関するこれまでの膨大なデータや、各国の審査当局に安全や有効性の「お墨付き」をもらうための交渉ノウハウもある。 ただし、ITベンチャーを含め、ヘルスケアサービスを医療の現場に広げようと鼻息の荒い企業は多い。三菱ケミカルHDが5000億円のリターンを得ることができるかどうかは、じっくり事に臨みがちな化学企業らしからぬ、ハイスピードな開発体制を確保できるかどうかにかかっている。午後になって外出すると、またしてもタイヤ空気圧の警告灯が点灯…。ディーラーを訪問すると、やはりというか…右後ろのタイヤに異物が刺さっていました…。修理時間は約30分…。来春に新しいタイヤに交換の予定で帰宅。(ロイター)日経平均は3日続落、米中協議に不透明感 日銀ETF買い観測は支え[東京 21日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均株価は3日続落した。米中通商協議の「第1段階」の合意が来年まで持ち越される可能性が出てきたことで株高の前提に疑念が生じた。トランプ米大統領が米議会が可決した香港人権法案に署名する見通しと伝わったことも米中対立の激化を想起させ、東京市場では朝方から幅広い業種で売りが先行。下げ幅を一時400円超に拡大した。その後、中国の劉鶴副首相の発言が安心感を誘ったほか、後場、日銀のETF(上場投資信託)買いの観測などもあり下げ幅を縮小。節目の2万3000円を回復して取引を終えた。 20日の米国株式市場は主要3指数がいずれも下落。ロイターが専門家やホワイトハウスに近い関係者の話として、米中通商協議の「第1段階」の合意が来年にずれ込む可能性があると報じ、不安ムードが急速に広がった。 東京市場は続落でスタートするとじりじり下げ幅を拡大。午前9時半過ぎに節目の2万3000円を割り込み、下げの勢いを強めた。25日移動平均線を下回ったことで調整が長引くとの懸念も生じた。市場からは「今週に入って外国人投資家が売り越しに転じた可能性もあり、これも不安要因となっている」(大和証券・チーフテクニカルアナリストの木野内栄治氏)との指摘も出ていた。 外為市場でドル/円の円高が進行し、為替に連動する先物売りも出た。下げ幅は一時400円を超えたが、前引け付近に中国の劉鶴副首相が米国との第1段階合意について「慎重ながらも楽観」と述べたとの報道があり、安値圏から反発した。 午後は日銀のETF買い入れが確実視され、下げ幅を縮小。前場に割り込んだ2万3000円を回復したことで先物を買い戻す動きもあった。「2万3000円を上回って取引を終えたら上場トレンドは維持とみる向きもいた」(東海東京調査センターのシニアストラテジスト、中村貴司氏)という。 東証33業種では海運、非鉄金属、パルプ・紙などが値下がり率上位に入った。半面、電気・ガス、不動産、ゴム製品などが値上がりした。個別では、東京エレクトロン(8035.T)、SCREENホールディングス(7735.T)、アドバンテスト(6857.T)など半導体関連株の下げが目立った。 東証1部の騰落数は、値上がりが1009銘柄に対し、値下がりが1031銘柄、変わらずが114銘柄だった。 米中協議に不透明感で株価続落:識者はこうみる[東京 21日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均株価は3日続落した。米中通商協議の「第1段階」の合意が来年まで持ち越される可能性が出てきたことで株高の前提に疑念が生じた。トランプ米大統領が米議会が可決した香港人権法案に署名する見通しと伝わったことも米中対立の激化を想起させ、東京市場では朝方から幅広い業種で売りが先行。下げ幅を一時400円超に拡大した。その後、中国の劉鶴副首相の発言が安心感を誘ったほか、後場、日銀のETF(上場投資信託)買いの観測などもあり下げ幅を縮小。節目の2万3000円を回復して取引を終えた。 市場関係者のコメントは以下の通り。 <SMBC日興証券 チーフエコノミスト 牧野潤一氏> 米議会での「香港人権・民主主義法案」可決の後に注目されるのは、中国の対抗措置だ。トランプ米大統領が来年の大統領選で再選するには、貿易州であるテキサスでの勝利が鍵となる。同州の共和党支持率と中国向け輸出は連動しているため、もし中国が米国の農産品の購入を停止すると、再選は危うくなる。しかし、中国国内における農産品のインフレ状況を踏まえると、この種の対抗措置はあまり現実的ではない。米中対立の激化が警戒されているものの、極端な方向に向かう可能性は低いと考える。 株価の下げも限定的だろう。米中対立の激化はボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)を高めても、世界経済に与える影響は少ないからだ。世界情勢の不透明感が高まり、株価が下がっても、米連邦準備理事会(FRB)はリスクに対しての保険として利下げに動くだろう。これは逆にアップサイドリスクととらえることもできる。 <楽天証券 チーフ・ストラテジスト 窪田真之氏> 市場では米中通商協議の「第1段階」の合意が近いという期待が高まっていたが、来年にずれ込む可能性が出てきたと報じられている。香港情勢の深刻化に伴う人権問題も絡まり、「この部分をこうすれば合意できる」という条件が複雑になってしまった。多くの人は、米中は一時休戦し、米大統領選が終わった頃から再び対立が激化するという流れをメーンシナリオとみていたと思うが、一時休戦は簡単ではないというリスクが、きょうは意識されている。 センチメントは一日で変わるものなので何とも言えないが、この先、次世代通信規格(5G)に関連する投資が盛り上がっていくことはかなりみえている。米中対立が過激にエスカレートすることがないということが前提となるものの、5G関連や半導体関連への投資の盛り上がりが下支えとなり、日経平均は年末2万3000円のレベルを維持するとみている。仮に、米中が部分合意し、12月15日に予定される対中追加関税が先延ばしになった場合は2万5000円も視野に入る。 <大和証券 チーフテクニカルアナリスト 木野内栄治氏> 下げの要因として、環境面では米中対立の激化懸念、需給面では外国人投資家の買い一巡と大きく2点が考えられる。 人民元がやや元安に設定されたことで、これは米中対立において中国側が再びファイティングポーズを示すサインとして受け止めることができ、今後、米中対立が激化するとの懸念が一段と大きくなった。ここまでの株価上昇の要因が米中通商協議の進展期待にあっただけに、不安を増幅させる格好となっている。 需給面では、外国人投資家の動向だ。しばらく外国人投資家が大幅に日本株を買い越していたが、朝方発表された財務省の統計によると買い越し幅はこれまでの5000億円規模から1000億円台まで急減。今週に入って売り越しに転じた可能性もあり、これも気にされたようだ。 ただ、株価の下げは限定的になるとみている。ここから先は、配当金の再投資による買いが入るとみられる一方、米国の消費が好調と想定されるためだ。きょうの急落にはマーケット関係者は不安を抱いたものの、夏以降の上昇を踏まえれば、許容範囲の下げとみることもできよう。 (会社四季報オンライン)テルモがプラス転換 米社買収を発表 上昇トレンド続く テルモ(4543)が強含み。午前10時48分には前日比64円(1.7%)安の3700円まで売られたが、午後13時時点では25円(0.6%)高の3789円付近とプラス圏で推移。前日に米国企業の買収を発表しており、一定のポジティブ感も意識されているようだ。 同社が買収するのは、医療技術スタートアップのアオルティカ社。同社は大動脈瘤治療のサポート業務が主業で、大動脈から分岐した細い血管に留置する「カバードステント」と呼ばれる製品や関連ソフトウェアを開発している。テルモは年内に買収手続きを完了させるという。買収額は非公表だが、テルモの業績や財務に与える影響は軽微という。 テルモ株は11月8日に年初来高値4045円を付け、その後はやや調整色の強い動き。ただ、チャート上では上向きの25日移動平均線(3643円)から上方に乖離して株価が推移しており、上昇トレンドそのものは維持されている。(取材協力:株式会社ストックボイス)(GDO)国内男子 ダンロップフェニックストーナメント 初日ジャン・ドンキュ首位発進 今平周吾1打差2位 松山英樹3位上がりを大会記録に並ぶ6連続バーディで締めたジャン・ドンキュ(韓国)が1イーグル8バーディ、3ボギーの「64」をマークし、7アンダーで単独首位発進した。賞金ランキング1位の今平周吾が6アンダー2位。5年ぶりの大会制覇を目指す松山英樹が堀川未来夢と並んで5アンダー3位の好位置で滑り出した。池田勇太が4アンダー5位。6月以来の国内ツアーとなる谷原秀人は昨年大会優勝の市原弘大らと並んで3アンダー6位につけた。「全米オープン」覇者のゲーリー・ウッドランド(米国)は1アンダー17位。米ツアーから参戦の飛ばし屋キャメロン・チャンプ(米国)は2オーバー40位で初日を終えた。直近2週連続予選落ちの石川遼は3オーバー53位。今平を約720万円差で追う賞金ランク2位のショーン・ノリス(南アフリカ)は「81」をたたき、10オーバー82位と大きく出遅れた。尾崎将司は12ホールを終えたところで途中棄権し、自身のシーズンを終えた。ジャンボは参加を取りやめて、ジャンボ用のシード席1つを若手のために開放するべきだろう!!見苦しい!!国内女子 大王製紙エリエールレディスオープン 初日森田遥が首位 渋野日向子2打差2位、鈴木愛36位2017年「北海道meijiカップ」以来のツアー2勝目を目指す23歳の森田遥が7バーディ、ノーボギーの「65」をマーク。7アンダーで単独首位発進を切った。5アンダー2位に賞金ランキング3位の渋野日向子、同2位の申ジエ、ペ・ソンウ(ともに韓国)、高橋彩華の4人がつけた。4アンダー6位グループに前年大会覇者の勝みなみ、来季は米ツアーに拠点を移す河本結、10月「富士通レディース」でツアー史上7人目のアマチュア優勝を飾った古江彩佳ら9人が入った。4週連続優勝が懸かる、賞金ランクトップの鈴木愛は5バーディ、4ボギーの「71」でプレーし、首位と6打差の1アンダー36位とした。今大会をもってツアー撤退を表明している一ノ瀬優希は3アンダー15位、佐伯三貴は1アンダー36位、諸見里しのぶは3オーバー77位で初日を終えた。<主な成績>1/-7/森田遥2T/-5/渋野日向子、申ジエ、ペ・ソンウ、高橋彩華6T/-4/河本結、古江彩佳、勝みなみ、権藤可恋、比嘉真美子、大出瑞月、ペ・ヒギョン、エイミー・コガ、蛭田みな美(msn)(ロイター)アップルとインテル、ソフトバンクG傘下のフォートレスを提訴 [サンフランシスコ 20日 ロイター] - 米国のアップルとインテルは20日、ソフトバンクグループ傘下の米投資会社フォートレス・インベストメント・グループが特許権を買い集め、ハイテク企業を次々に訴えている行為は反トラスト法(独占禁止法)に違反するとして、カリフォルニア州北部地区連邦地裁に提訴した。 インテルは先月、同様の訴訟を起こしていたが、20日に同訴訟を取り下げ、アップルとともに新たな訴訟を起こした。アップルは訴状で「当社は訴訟コストに加え、イノベーションではなく一連の不愉快な訴訟への対応にリソースを割かなければならないという形で、経済的な損害を受けている」と表明した。ソフトバンクグループとフォートレスのコメントは現時点で取れていない。インテルが先月、同様の訴訟を起こした際、フォートレスは「当社のビジネス慣行や法的見解に自信を持っており、今回の訴訟に価値はないと考えている」とコメントしていた。アップルによると、フォートレスと関連のある複数の企業は、アップルに対し、少なくとも25の訴訟を起こしており、26億─51億ドルの損害賠償を求めている。インテルは訴状の内容以外のコメントはできないとしている。アップルのコメントはとれていない。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-下げは続くも節目はキープ、上昇再開か下落加速かの分岐点 21日の日経平均は3日続落。終値は109円安の23038円。米中交渉に関するニュースに一喜一憂が続く中、米国株安を嫌気して下落スタート。その後、節目の23000円を割り込んだことでセンチメントが一気に弱気に傾き、前場のうちに下げ幅を400円超に広げた。一方、前引け間際に切り返す動きが見られると、後場に入ってからは下げ幅を縮める展開。為替市場で円高に一服感が出てきたこともあり、上昇に転じる銘柄も増加した。終盤にかけてはリバウンドを期待した買いも入り、23000円を上回って取引を終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆3400億円。業種別では騰落率上位は電気・ガス、不動産、ゴム製品、下位は海運、非鉄金属、パルプ・紙となった。前場でもプラスを維持していたコロプラが後場に入って上げ幅を広げて6%超の大幅上昇。半面、シェアハウス絡みの債権を放棄するとの観測が報じられたスルガ銀行が、業績懸念から大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1009/値下がり1031。前場ではほぼ全面安であったが、終わってみれば値上がり・値下がりが均衡した。主力どころでは日本電産やKDDI、SMCなどが上昇。トヨタやファストリなどにもしっかりとした動きが見られた。自己株取得を発表したエフティGやカカクコムが大幅上昇。イワキは優待導入が好感されて買いを集めた。移植用「軟骨再生シート」の米国特許を取得したと発表したセルシードが急伸した。一方、東京エレクトロンやアドバンテスト、SCREENなど半導体株が軒並み大幅安。ソフトバンクGや安川電機、武田なども軟調となった。証券会社が投資判断を引き下げたコナミが下落。地合いの変調が意識される中、澤藤電機やWASHハウスなど直近でにぎわっていた銘柄が利益確定売りに押された。 日経平均は取引時間中には23000円を割り込んで下げが拡大したが、終値(23038円)では23000円を上回った。長い下ヒゲをつけて5日線(23015円、21日時点、以下同じ)も上回っており、押し目での買い意欲が確認できた。こういった動きが出た後にポジティブな材料が出てくれば買いに勢いがつきやすく、短期調整完了で上昇再開が見込まれる。ただ、上値の重さが強く意識されていたからこそ、前場には大きく下げたわけで、もう一段の下げがあった場合には、逆に見切り売りが加速するとみておいた方が良い。その場合、13週線(22225円)や26週線(21674円)が下値のメドとなる。今週から来週にかけては、きょうの安値22726円を下回ることなく推移できるかが注目される。NY株見通し-底堅い展開か 米経済指標は10月中古住宅販売件数、10月景気先行指数など 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は米中通商合意の先送り報道が嫌気され主要3指数がそろって下落した。ただ、ダウ平均が258ドル安まで下落後に112.93ドル安まで下落幅を縮小するなど底堅い動きをみせ、主要3指数はそろって史上最高値から0.4-0.8%安の水準にとどまった。今晩も米中通商合意の行方を睨んだ神経質な展開が予想されるものの、緩和的な金融政策の長期化見通しなどを背景に底堅い展開が期待できそうだ。 今晩の米経済指標は新規失業保険申請件数、11月フィラデルフィア連銀業況指数、10月中古住宅販売件数、10月景気先行指数など。メスター米クリーブランド連銀総裁、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁の講演も予定されている。企業決算は寄り前にメーシーズ、引け後にノードストローム、ギャップなどが発表予定。(執筆:11月21日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=方向感の出づらい展開か 22日の東京株式市場は、方向感の出づらい展開になりそう。21日の日経平均株価は3日続落となったが、一時400円超の下げから109円安まで引き戻して終えており、下値での買い需要もうかがえる。ただ、米中貿易交渉の進展がみられないなか、目先的にはポジション調整の売りが優勢となることも想定される。市場では「一時2万2700円台を付け、先高期待の過熱感が冷やされた格好となったが、終値ベースで25日移動平均線(2万3015円)維持したことから、堅調な展開も期待される」(中堅証券)との声も聞かれた。 21日の東京株式は、前日比109円99銭安の2万3038円58銭と3日続落して取引を終えた。前場には一時420円を超える場面がみられた。その後、下げ幅を縮小する動きに転換し、引けにかけ心理的なフシ目の2万3000円を回復した。東京証券取引所が21日引け後に発表した、11月第2週(11-15日)の投資部門別の株式売買状況によると、海外投資家は金額ベースで2045億円の買い越しで、7週連続の買い越しとなった。今晩のNY株の読み筋=相次ぐ小売企業決算に注目 きょうの米国株式市場は、方向感が出にくそうだが、ギャップ、メーシーズなど小売企業の決算が手掛かりになる可能性がある。 前日の米国株式市場は、米下院が上院で可決した香港人民・民主主義法案に同意したことや、米中通商協議の第1弾合意が来年にズレ込むとの観測が広がったことなど受け、主要3指数が揃って反落。この流れを受け継ぎ、きょう東京株式市場も日経平均株価が売り先行となった。ただ、中国の劉鶴副首相が米中通商協議の第1弾合意について「慎重ながらも楽観的」と伝わると、日経平均は次第に下げ渋った。米中通商協議をめぐるニュースヘッドラインに振られやすい地合いはまだまだ続きそうだ。 一方、前週のウォルマートを皮切りに立て続いている小売企業決算は、まちまちながらも20日はターゲット、ロウズが好決算を発表し、いずれも大幅高となった。きょう決算発表のギャップの時価は市場コンセンサスに近い水準で上値が重くなる可能性もありそうだが、メーシーズは市場コンセンサスに対して割安だ。年末商戦の見通しにも注目したい。<主な米経済指標・イベント>11月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数、10月CB景気先行総合指数、10月中古住宅販売件数、10年物価連動国債入札ギャップ、メーシーズ、ノードストロームなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕3日続落=香港めぐる米中対立を嫌気(21日)☆差替 【第1部】香港人権法案をめぐる米中対立が嫌気され、幅広い銘柄に売りが広がった。日経平均株価は前日比109円99銭安の2万3038円58銭、東証株価指数(TOPIX)は1.73ポイント安の1689.38と、ともに3日続落となった。 銘柄の48%は値下がりし、上昇は47%だった。出来高は13億4257万株、売買代金は2兆3406億円。 業種別株価指数(33業種)は海運業、非鉄金属、パルプ・紙が下落し、上昇は電気・ガス業、不動産業、ゴム製品など。 個別銘柄では東エレク、村田製、アドバンテスが売られ、SUMCO、太陽誘電、ファナックが値を下げた。武田、資生堂は軟調で、ソフトバンクGはさえなかった。商船三井、川崎船は弱含み、三菱UFJは緩んだ。半面、ファーストリテは買われ、リクルートHDは値を上げた。九州電、関西電は堅調で、菱地所、三井不はしっかり。トヨタは強含み、ブリヂストンは締まった。 【第2部】3日続落。東芝が売られ、千代化工は軟調。半面、那須鉄は急伸した。出来高8143万株。 ▽アジア株安が下押し 米国の上下院で香港人権法案が通過し、米中貿易協議が難航するとの懸念が高まっている。20日の米国市場で主要指数が下落した流れを受け、日経平均も軟調で寄り付いた。朝方にトランプ大統領が法案に署名するとの見方が伝わると先物主導の売りが強まり、一時400円超安と下げ幅を拡大。香港などアジア株安も日経平均の下落に拍車を掛けた。その後、昼ごろに中国の劉鶴副首相が20日夜に米中協議の第1段階が合意に達することを「慎重ながらも楽観している」と述べたことが報じられ、下げ幅は縮小。心理的節目の2万3000円台を回復して取引を終えた。 米中協議に新たな進展がみられない中、日経平均は高値圏を維持しており、利益確定売りが出やすい状況にある。市場からは「米中協議のネガティブな報道で株価が急落しやすくなっている」(ネット証券)との指摘も出ていた。 225先物12月きりは、下落した。取引開始直後に2万2700円に向かって急速に値を下げた後、昼前に買い戻しが入り、下げ幅を縮小していった。(了) 〔ロンドン外為〕円、108円台半ば(21日午前9時) 【ロンドン時事】21日朝のロンドン外国為替市場では、米中貿易協議をめぐってもみ合いとなり、円相場は1ドル=108円台半ばで推移している。午前9時現在は108円50~60銭と、前日午後4時(108円60~70銭)比10銭の円高・ドル安。 対ユーロは、1ユーロ=120円25~35銭(前日午後4時は120円15~25銭)で、10銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1080~1090ドル(1.1060~1070ドル)。(了) 〔米株式〕NYダウ、続落=ナスダックも安い(21日朝) 【ニューヨーク時事】21日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の行方をめぐり思惑が交錯する中、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比36.48ドル安の2万7784.61ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は12.84ポイント安の8513.89。(了) 本日の夕食はおでんでした。一緒に楽しんだのは…美味しくいただきました。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の12銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の8銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では1銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.21
コメント(0)
-

11月19日(火)~20日(水)…
11月19日(水)、晴れですね。良い天気です。7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、10時頃には家を出る。Go To East!!東海環状に乗り、豊田のジャンクションから新東名へ入る。トラックが多いですね…、混雑していて120km/h区間も役に立たず…。浜松SAのはまきた食堂で少し早目のランチタイムです。芝えびのかき揚げうどんをいただく。アジア系のお客さんが多いです…。しばらく走ると見えてきました…富士山がきれいに見えます。この辺りからだと三峯ですね。御殿場で高速を降りると、箱根のお山へ…。途中のふじみ茶屋からもキレイに富士山が見えます。お団子を食べようと思いましたが、販売されていなかったのでタイ焼きをいただく。仙石原を経由して…ポーラ美術館で絵画鑑賞です。藤田の猫がなかなかいいですね。ティールームでお茶をいただいて本日のお宿へ…。本日のお宿は最近の箱根の定宿…ザ・ヒラマツ・ホテル&リゾーツ仙石原です。残念なことに、先日の水害の影響で温泉がまだ復旧していません。宿泊客も少なく、部屋はアップグレードされていました。やはりこちらのお楽しみは食事ですから…こんなメニューでした。お食事のシステムもレジデンス棟がオープンしたことで少し変更されています。スタートの一品。締めの一品です。そして箱根の夜は更けていきました。11月20日(水)、晴れです。6時30分頃に起床。今朝も富士山がきれいです。朝風呂して、新聞に目を通し、身支度して8時から朝食です。朝から大変に美味しいお食事を堪能!!荷造りをしたりして、10時頃にチェックアウト。御殿場へ下りると、途中で愛車の警告灯が点灯…。タイヤの空気圧が低下とのこと…。右の後輪だけ空気圧が低いです…。GSでタイヤの空気圧を調整して、警告モニターを初期化して、しばらくそうこうしても変化はなさそうですね。御殿場のプレミアム・アウトレットへ…。朝はまだ空いていましたが、お昼頃からは混雑してきました。やはりこちらもアジア系のお客さんが多いですね…。中にはアジア色に染められたお店もあってちょっと入れません…。空がきれいです。僕は靴を一足ゲットでしたが、奥はいろいろとゲットできたようで…。御殿場のインターに入るまでに、周辺のお店に2軒立ち寄り…。高速に乗ると、おやつ休憩、トイレ休憩、夕食の食材調達と3度のSAストップをして19時前には帰宅。遊びに来た、ニキータ2号と3人で夕食を済ませて、休憩です。1USドル=108.47円。1AUドル=73.92円。昨夜のNYダウ終値=27934.02(-102.20)ドル。本日の日経平均終値=23148.57(-144.08)円。金相場:1g=5692(-6)円。プラチナ相場:1g=3589(+51)円。(会社四季報オンライン)(ロイター)米国株市場はダウとS&Pが下落、小売企業の業績見通しさえずダウは102ドル安の2万7934ドル[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米国株式市場はダウ工業株30種とS&P総合500種が最高値から下落して取引を終えた。ホームセンター大手ホーム・デポや百貨店コールズのさえない業績見通しを受け、消費支出への懸念が高まった。米中貿易摩擦も引き続き重しとなった。トランプ米大統領は19日、米政府が中国と通商問題で合意できなければ、対中関税を一段と引き上げると述べた。ホーム・デポは5.4%値下がりし、S&Pとダウを押し下げた。同社は2019年の通期売上高見通しを引き下げた。今年2回目の下方修正となった。コールズは19.5%急落。同社は通期利益見通しを下方修正。第3・四半期の既存店売上高や利益も市場予想を下回った。米株市場は、米中通商合意への期待や、おおむね市場予想を上回っている第3・四半期企業決算を背景にここ数週間上昇してきた。ナスダック総合はこの日、0.24%上昇し、最高値を更新した。コモンウェルス・フィナンシャル・ネットワークのブラッド・マクミラン最高投資責任者(CIO)は「市場は上値を追いたいが、障害が多過ぎる」と指摘。米経済のけん引役として投資家が注目する消費支出に関する第4・四半期の見通しについて、数週間前よりも楽観度合いが弱まったの見方を示した。トランプ大統領のウクライナ疑惑を巡る弾劾調査の公聴会も、市場を圧迫した。国家安全保障会議(NSC)でウクライナ問題を担当するビンドマン陸軍中佐は19日、下院情報特別委員会の公聴会で、米大統領が選挙戦での対立候補の捜査を外国に要請したことは「不適切」だったとの認識を示した。マクミラン氏は「大統領に不利なニュースが続いており、市場の観点からするとマイナス要因だ」と語った。S&Pの主要11セクターでは7セクターが下落。一般消費財は0.97%安。小売指数は1.24%安。エネルギーセクターは1.5%安と下落率が最大だった。原油価格の下落が背景。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.04対1の比率で上回った。ナスダックでは1.46対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は67億株。直近20営業日の平均は69億4000万株。今週はロウズ、ターゲット、ノードストロームなど他の小売企業も決算を発表する。米連邦準備理事会(FRB)が今年3回目の利下げを実施した10月の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨も注目される。日経平均は続落、米中対立への懸念から弱気が支配終値は144円安の2万3148円東京株式市場で日経平均は続落した。米上院が香港人権法案を可決したことに中国が強く反発し、米中対立悪化に対する懸念の高まりから市場は弱気ムードに支配された。ただ、売りが一巡した後は下げ渋り、後半は小幅なレンジで推移。東証1部の売買代金は2兆1572億2000万円と3営業日ぶりに2兆円台を回復した。日本時間の朝方、中国が香港に高度の自治を保障する「一国二制度」を守っているか米政府に毎年検証を求める「香港人権・民主主義法案」を米上院は全会一致で可決。下院では既に可決されており、今後上下両院の調整を経た上で、トランプ大統領に送付される。[nL3N27Z5K5]中国外務省は、米議会の動きを強く非難。米中通商協議の先行きに懸念が広がっているタイミングだけに、リスク回避ムードを誘っている。ファナック、コマツ、日立建機など中国関連株が売り優勢となった。ただ、日経平均は心理的な下値の目安である2万3000円にトライすることなく下げ渋った。外為市場ではドル/円が108円台で落ち着いて推移しているうえ、売り崩すだけの材料が見当たらない。需給面では「先行き配当金の再投資に伴う資金が流入するとみられ、ここから軟調となっても下げ幅は限定的になるのではないか」(岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏)と指摘され、これも下げ渋りの背景にあるようだ。TOPIXも続落。東証33業種では、海運業、石油・石炭製品、水産・農林業、銀行業、鉱業などの値下がりが目立つ。個別では、ソニー、トヨタ自動車など主力輸出株が軟調に推移し、Zホールディングスも続落。半面、田辺三菱製薬が大幅上昇となった。東証1部の騰落数は、値上がりが680銘柄に対し、値下がりが1388銘柄、変わらずが86銘柄だった。あすか製薬が急騰、子宮筋腫治療剤の実験進展をハヤす あすか製薬(4514)が急騰。11時10分時点では前日比135円(11.6%)高の1295円まで買われている。前日に、国内で開発中の子宮筋腫治療剤についての試験結果を学会で発表したとリリースしており、これをハヤす買いが集まっているようだ。 今月7~8日に開催された日本生殖医学会学術講演会で、子宮筋腫治療剤「CDB-2914」(一般名:ウリプリスタル酢酸エステル)についての第2相試験の結果を発表した。日本人の子宮筋腫患者121人に1日1回12週間投与し、有効性と安全性を確認したという。投与による有害事象も、軽度な便秘や鼻咽頭炎にとどまった。同剤は海外ですでに80万人以上の子宮筋腫患者が使用しており、国内の実験進展による早期実用化が期待され、今日の資金流入につながっているようだ。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】明日の株式相場戦略=5G・ゲームなど“材料株繚乱”の流れに乗る きょう(20日)の東京株式市場は、米議会上院で「香港人権・民主主義法案」を全会一致で可決したのに対し、中国外務省がこれを非難する声明を発表したことで、またぞろ「米中対立」の構図が取り沙汰され、株価は下値を試す展開を強いられた。きょうは香港ハンセン指数や中国上海株総合指数も安く、この下げ圧力はアジア株市場全般に広がった。日経平均も9月、10月の怒涛の上昇局面を経て、少なからず売り圧力を感じる地合いとなってきた。“相場は生き物”というが、さすがに呼吸を整える段階に来たということだろうか。 しかし、基本的には米国株が崩れない限り、リスクオフの歯車が本格的に回り始めることはない。大臣の辞任を巡り安倍首相と菅官房長官の間に不協和音が生じ、国内政局を不安視する声も聞かれるが、「政局不安を嫌う外国人投資家の日本株離れ」というお決まりのシナリオに結びつけるのは早計に失する。 材料株物色は年末ラリーを前に百花繚乱の気配をみせている。日経平均は2日間で260円あまり下げたが、これが投資家マインドを悪化させている感触はない。マザーズ指数はといえば4日続伸。日経ジャスダック平均は4日ぶりに反落となったが下落率はわずかに0.02%で横ばいに等しく、個人投資家のファイティングエリアは健在であることがうかがえる。 個別では前日紹介したレイが上放れ鮮明で、目先テクニカル的にもほぼ5日・25日移動平均線のゴールデンクロスを達成し、弾みがつくところ。映像制作関連では東北新社の700円近辺のもみ合いも上値思惑を漂わせる。 ここ休養十分の5G関連株も動意づく銘柄が散見されるようになってきた。そのなか、急速に立ち上がった日本アンテナなどの押し目は狙い目となりそうだ。通信アンテナの研究開発で業界を先駆、既に次のジェネレーションである6G時代をにらんだ開発に着手していることも伝わっている。業績面で安定感のあるイードなども上値追い余力が感じられる。同社は自動車やIT系ニュースサイトなどを運営するが、自動車業界と通信業界双方に太いパイプを持つ強みを生かし、5G分野で両業界の相互乗り入れを支援する「イード5Gモビリティ」を経営戦略として進めている。 更に、きょうは任天堂を筆頭に、バンダイナムコホールディングス、カプコン、スクウェア・エニックス・ホールディングス、コナミホールディングスなどゲーム関連株に頑強な値動きを示す銘柄が多かった。日米で年末商戦が意識されるなか、株価には浮揚力が働きやすい。特に米グーグルが、19日から鳴り物入りでクラウドゲーム のプラットフォーム「STADIA(スタディア)」の提供を開始、日本の大手ゲーム会社が有するIP(知的財産)が改めて注目される流れにある。高グラフィックなゲームを楽しむ際に、端末機側に専用機のような高い演算処理能力を要求しないクラウドゲームは、汎用PCやスマホ向けで巨大市場が創出される可能性が高く、ゲーム関連株はこの時期、単に季節性で買われるという従来のケースとは少し趣が異なっているようだ。 こうなると、ゲーム関連でも株価面で高いボラティリティを潜在させる銘柄におのずと目が行くことになる。enishやコロプラをはじめ、イマジニア、gumi、ブシロードといった銘柄に投資資金が向かう可能性を考慮しておきたい。 日程面では、あすは10月の全国スーパー売上高が発表される。また、IPOが1件予定されており、マザーズ市場にトゥエンティーフォーセブンが新規上場する。海外では米国で重要経済指標の発表が相次ぐ。11月の米フィラデルフィア連銀製造業景況感指数、10月の米景気先行総合指数、10月の米中古住宅販売件数などがある。このほか、インドネシア中銀が政策金利を発表する。(中村潤一)(msn)(AllAbout)2019年年末ジャンボ宝くじで一攫千金!いつ、どこで買うのがベスト? 2019年の年末ジャンボ宝くじの発売期間は、11月20日(水)から12月21日(土)までの32日間です。この期間でいつ、どこで買うと運を味方にできるのか、お伝えします! 買うならいつがベスト? 数秘&カラーで運気を見ていくと、2019年はみんなで楽しむこと。これはサマージャンボ宝くじのときと同じです。多くの人と一緒に楽しむとツキが回ってくる年ですので、1人で行くよりは2人、2人よりも3人と、みんなでイベントにしていくと、ツキが得られます。1人で行く場合には、並んでいる人に話しかけるのも手。その他、楽しい雰囲気で買うことも大切です。宝くじ売り場で並ぶときは、好きな音楽を聴きながら待つのもよいですね。今回の発売期間で金運に結びつく日は、11月21日(木)、30日(土)、12月2日(月)、11日(水)、20日(金)の5日間です。その他、最も金運に縁のある「寅(トラ)の日」といわれている吉日にあたるのが、11月25日(月)、12月7日(土)、19日(木)の3日間です。いつもは宝くじ発売期間で、金運に結びつく日と金運に縁のある「寅(トラ)の日」が一致する日があるのですが、2019年の年末ジャンボ宝くじの場合には、重なる日はありませんでした。これらの日を総合して考えるのではなく、自分の良い日や思い入れのある日を考慮して、購入日を選んでみてもよいですね。この中から強いて金運の良い日をあげるとすれば、今年の運気を最も反映している11月25日(月)がよいでしょう。11月と12月では、その月が持っている運気も違っています。2019年の11月はクリエイティブ力に優れ、自由にアクティブに動くことができる月です。また、一度失敗したことにもう一度チャレンジするのにもよい月ですので、「今年こそは当せんするぞ!」という人なら、11月中に購入するのがおすすめです。2019年の12月は、愛情がテーマの月です。宝くじが当たったら独り占めするよりも、家族でどう使うのかを考えている人にツキが回ってきます。12月は家族で買いにいくとよいですし、プレゼントされたモノにツキがあります。自分で買ってもよいですが、金融機関の宝くじ付き定期預金なども狙い目だったりします。ここまで複数の日をあげていますが、特定の日に購入する、複数回に分けて購入するというのもアリですよ。運気の良い場所は? 宝くじを買うならここ!運気の良い日に続いて、運気の良い場所についても押さえておきましょう。11月の運気が良い購入場所は、水にまつわる場所です。水辺とか川・河川の近くにあるお店で購入してもよいですし、地名や店名に「水」や「海」、「川」などの水にまつわる地名の店舗や、そのような名前の担当者から購入するのもよいですね。購入時間は、日中。晴れていても曇っていても大丈夫です。購入するときには、ターコイズのアクセサリーを身に着けていると、さらなるツキを呼び込めますよ。12月の運気の良い購入場所は、人が多く集まる場所にある人気の店舗がよいのですが、大型店よりはアットホームな雰囲気のこぢんまりとした店舗がおすすめです。可能であれば、夕方までに購入するとよいですね。購入するときには、ピンクやブルーのモノ、家族や大切な人からプレゼントされたモノを身に着けて行くと、運気がアップします。毎回お話ししていますが、購入するときには前回までに当せんしたお金を購入資金にあてると、運気はさらにアップ! ツキを呼び込むことを忘れてはなりません。とはいえ、狙い方は参考程度に!? くれぐれも買い過ぎに注意しながら、年末ジャンボを楽しんでください。みなさんに幸運が訪れますように!!(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-連日の3桁下落も後場は下げ渋る、23000円台を維持できるかに注目 20日の日経平均は続落。終値は144円安の23148円。ダウ平均が大きく下げたことや円高進行を嫌気して、寄り付きから3桁の下落。すぐに押し目買いが入って一気にプラス圏まで戻したものの、米上院で香港人権法案が可決されたことに対して、中国が強い反対の意を示したことから再び売られる展開となり、下げ幅を200円超に広げた。後場に入ると値動きは落ち着いたが、米中関係悪化懸念が意識される中では戻りは限定的。前場の安値や23000円は下回らなかったものの、23100円近辺でこう着感の強い地合いが続いた。一方、マザーズ指数はプラスで終えており、軟調相場の中で動きの様さが目立った。東証1部の売買代金は概算で2兆1500億円。業種別では騰落率上位は空運、その他製品、その他金融、下位は海運、石油・石炭、水産・農林となった。きのうストップ高の木村化工機に買いが殺到しており、場中では値がつかずストップ高比例配分。半面、きのうストップ高の日本通信は前場で上を試した後に急失速。後場に入ってマイナス圏に沈み大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり680/値下がり1388。自己株取得の発表が好感されたロームが大幅上昇。国内初の直営店「ニンテンドートウキョウ」のオープンを間近に控えた任天堂が強く、年初来高値を更新した。田辺三菱はTOB価格にサヤ寄せして22%超の上昇。東証1部への指定替えを発表した明豊ファシリティが急騰した。一方、米中対立懸念が再燃したことから、ディスコやアドバンテスト、東京精密など半導体関連が大幅安。日本郵船など海運大手が軒並み安となった。証券会社がレーティングを引き下げた製造業派遣大手の日総工産が5%超の下落。日経新聞で自動車メーカーが期間従業員の募集を停止すると報じたこともあり、UTグループやアウトソーシングなど他の人材関連にも売りが広がった。ほか、前期の決算発表再延期を発表したMTGが急落した。 日経平均は連日の3桁下落。ただ、後場に売り圧力が強まらなかった点は期待の持てる動き。東京時間で米中関係悪化を示唆する材料が出たため、今晩の米国株にはネガティブな影響が想定されるが、きょうの下げで一定程度は織り込んでいると思われる。米国株が急落してしまうと厳しいが、常識的な下げであれば、ここからの下げは限定的だろう。米国株が悪材料を吸収して上昇するようなら、直近の下げ分の大半を戻すような展開も期待できる。チャートを見ると、23000円の下に25日線(22982円、20日時点)が控えており、テクニカル要因もサポートとなりそうだ。ただし、同水準を明確に割り込んだ場合には、見切り売りが加速する展開も想定しておくべき局面。不安定な地合いが続くが、あすは23000円台を維持できるかが注目される。NY株見通し-米中問題を睨みもみ合いか 消費関連の決算やFOMC議事要旨に注目 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日はホーム・デポの下落が重しとなったダウ平均が3日ぶりに反落したものの、S&P500はほぼ変わらず、ナスダック総合は3日続伸となった。 取引時間中では主要3指数がそろって史上最高値を更新。米中通商協議の「第1段階」合意の署名を巡る不透明感が強いなかでの堅調な推移となった。 今晩は、米上院が香港人権・民主主義法案を可決したことで中国が反発している一方、ロス米商務長官からは米中合意についての楽観的な発言もあり、米中問題の行方を睨んで神経質な展開か。 寄り前に発表されるロウズ、ターゲットなどの消費関連の決算発表や午後に公表されるFOMC議事要旨にも注目か。 今晩の米経済指標・イベントはMBA住宅ローン申請指数、EIA週間原油在庫、FOMC議事要旨など。企業決算は寄り前にロウズ、ターゲット、引け後にLブランズなどが発表予定。(執筆:11月20日、14:00) (yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、108円台半ば(20日午前8時) 【ニューヨーク時事】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円42~52銭と前日午後5時(108円49~59銭)比07銭の円高・ドル安で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1052~1062ドル(前日午後5時は1.1073~1083ドル)、対円では同119円88~98銭(同120円19~29銭)。(了) NY株、続落 【ニューヨーク時事】20日のニューヨーク株式相場は、香港をめぐる問題が米中貿易協議に悪影響を及ぼすとの懸念が強まり、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比60.14ドル安の2万7873.88ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は20.65ポイント安の8550.01。 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の8銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を下げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の8銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.20
コメント(0)
-

11月19日(火)…
11月19日(火)です。
2019.11.19
コメント(0)
-

11月18日(月)…
11月18日(月)、晴れです。小春日和のような天気ですね。そんな本日は8時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機ですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。美味い!!本日の案件は、郵便局~銀行~GSと回れば終了かな。1USドル=108.74円。1AUドル=74.13円。現在の日経平均=23307.45(+4.13)円。金相場:1g=5693(+9)円。プラチナ相場:1g=3533(+46)円。(ブルームバーグ)【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース 「水の都」と呼ぶのが不謹慎にさえ思われるイタリアのベネチア。記録的な高潮で文化遺産や観光にばく大な被害が及んでいます。日本では台風19号の爪痕がまだ消えていません。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は先週の議会証言で、気候変動の問題は金融においてもリスクとなり得ると認めています。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。当初より控えめサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは新規株式公開(IPO)の目論見書を更新。同社の評価額は最大1兆7100億ドル(約186兆円)と暫定的に見積もっており、ムハンマド皇太子が目指していた2兆ドルに届かない。12月5日に最終発表する。米国とオーストラリア、カナダ、日本では募集しない。関係者によれば、サウジ中銀はアラムコ株を購入するリテール投資家について、銀行借り入れのレバレッジ限度を引き上げた。建設的な協議中国の劉鶴副首相がムニューシン米財務長官、ライトハイザー通商代表部(USTR)代表と電話会談した。中国商務省によると、電話会談は米国側の要請で行われ、貿易合意の「第1段階」を巡り双方が抱いている中心的な懸念について「建設的な協議」を行った。引き続き緊密に連絡を取り合うことで一致したという。数カ月早い検査トランプ米大統領はワシントンで年次の健康診断に関連した「簡易検査」を受けた。ホワイトハウス報道官の説明によれば、2020年が非常に忙しくなると予想して定期健康診断の一部を開始したのであり、体調不良を訴えたのではない。トランプ氏が前回に健康診断を受けたのは2月、その前は2018年1月だった。副作用FRBは最新の金融安定性報告で、低金利が長引けば米銀の収益を圧迫し、金融機関をリスクの高い行動に向かわせる可能性があるとし、金融システム安定を脅かしかねないとの認識を示した。銀行や保険会社が直面する利ざや縮小を強調。これがひいては融資基準を損ねる恐れがあると指摘した。急ぐ理由トランプ大統領は北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に対し、バイデン前米副大統領は北朝鮮の国営メディア朝鮮中央通信(KCNA)で最近言及されたような「狂犬」ではないとした上で、米国との核合意署名に向け「行動を急ぐよう」、ツイッターで促した。これより数時間前、北朝鮮は米国が「敵視政策」をやめない限り、非核化交渉には一切応じないと表明している。その他の注目ニュース米大統領選:ブティジェッジ氏躍進、民主党候補レースで首位浮上バイパス手術やステント不要か、投薬より高い効果望めず-研究報告イランで抗議拡大、ガソリン急騰に不満-当局は数百人を拘束HP、ゼロックス提示の買収案を拒否-協議の可能性は閉ざさず米HPの取締役会は米ゼロックス・ホールディングスから提示された買収案が「HPを著しく過小評価している」として、ゼロックスのジョン・ビセンティン最高経営責任者(CEO)に宛てた書簡で受け入れ拒否を表明した。 「ゼロックスと統合した場合にHP株主に価値が生じるかどうか、模索することは排除しない」 「答えを出すべき根本的な疑問」があるとし、2018年6月以降にゼロックスの売上高が減少したことを指摘。「ゼロックスの事業見通しと将来の展望について、著しい疑問を抱かせる」と説明 ZホールディングスとLINE、経営統合で合意-12月に最終契約 ソフトバンクグループ傘下で「ヤフー」を展開するZホールディングス(HD)とLINE(ライン)が経営統合する。両社が18日に発表した。 発表によると、最終契約の締結は12月を予定しており、統合完了は2020年10月を目指す。 ZHDの親会社であるソフトバンクとLINEの親会社である韓国ネイバーが50%ずつ保有する新会社を設立。ZHDの傘下にヤフーとLINEがぶら下がる形態になる。 新会社は、現在上場しているLINEにソフトバンクとネイバーが共同で株式公開買い付け(TOB)を実施し、設立する。現時点でTOB価格は1株5200円で提案するとしており、その場合、両社の負担額は1700億円ずつとなる。 ソフトバンクの財務アドバイザーはみずほ証券、ネイバーはドイツ証券がそれぞれ務める。ZHDの川辺健太郎社長とLINEの出沢剛社長はきょう午後5時に会見する。(ロイター)米HP、ゼロックスによる買収案拒否 逆買収による統合に含み[17日 ロイター] - 米パソコン大手HP(HPQ.N)は17日、米事務機器大手・ゼロックス(XRX.N)が提示した現金と株式交換の組み合わせによる335億ドルの買収案について、自社の価値を「著しく過小評価」しているとして拒否したことを明らかにした。その上で、ゼロックスに対する逆買収を模索する意向を示した。 ゼロックスは11月5日に買収提案を行った。同案についてHPは発表文書で、統合会社が「巨額の債務」を負うことになり、株主の最善の利益にならないと指摘した。 一方で、両社の統合は恩恵をもたらす可能性があるとの認識を示し、ゼロックスを買収する可能性に言及。「ゼロックス経営陣の深い関与と、ゼロックスの資産査定に関する情報へのアクセスがあれば、取引の利点を早期に評価できるだろう」とした。 ゼロックスに帳簿公開を求めた形だが、ゼロックスは買収ターゲットとしてHPと交渉するかどうかに関してコメント要請に応じていない。 ゼロックスの提案はHPの株主に対して、1株当たり22ドル(現金17ドルとゼロックス株0.137株)を支払う内容で、受け入れられた場合、HP株主が保有する統合後の新会社の株式比率は約48%になっていた。LINEとZHD、経営統合で基本合意 2020年10月完了目指す[東京 18日 ロイター] - SNSサービスのLINE(3938.T)とヤフーを傘下に持つZホールディングス(HD)(4689.T)は18日、経営統合について基本合意を締結することを決議したと発表した。 12月をめどに法的拘束力のある最終契約の締結に向けて協議・検討を進め、2020年10月の統合完了を目指す。 LINEとZHDは午後5時から会見する。(株探ニュース)【市況】前場に注目すべき3つのポイント~中小型株の出直りに期待18日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:中小型株の出直りに期待■前場の注目材料:日本アクア、19/12上方修正 営業利益18.07億円←14.22億円■メルカリ、世界100カ国以上で越境販売■中小型株の出直りに期待18日の日本株市場は、米株高の流れから買いが先行しようが、その後はこう着感の強い相場展開になりそうだ。15日の米国市場では、NYダウが222ドル高となり、28000ドルを突破した。米政権高官が米中交渉の進展を示唆したほか、10月小売売上高が予想を上振れたことも好感された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の23365円。円相場は1ドル108円70銭台で推移している。米株高は好感されそうだが、シカゴ先物の反応がみられず、方向感を掴みづらくさせそうである。円相場も1ドル108円70銭台と足元でやや円高に振れて推移していることも手掛けづらくさせる。引き続き米中交渉の進展を見極めたいほか、香港情勢の緊迫化なども不安要因である。また、ここにきて日銀のETF買い入れが見送られており、ステルステーパリング(政策変更を伴わない緩和縮小)に動き始めたのではないかとの見方も出てきている。そのため、戻りの鈍さが意識される局面において、短期筋の売り仕掛け的な動きも警戒されやすい。もっとも、10月半ば以降の上昇によって過熱感も警戒されていただけに、想定内の一服との見方であろう。先週は調整局面において23000円処が心理的な支持線として意識されている。そのため、こう着ながらも目先的には23000-23500円辺りでの底堅い相場展開を意識しておきたいところである。そのほか、今後12月上旬に向けては中間配当支払い開始に伴う再投資の買いが期待されるため、需給面での下支えとして意識されやすい。物色の流れとしては米中交渉の行方を睨みながらのスタンスは変わらないため、積極的な売買は期待しづらいところではある。ただし、決算発表が一巡したことで、機関投資家も動きやすくなるだろう。中小型株などは決算数値に過剰反応を見せた銘柄も多く、改めて決算内容を見直す動きが意識されやすい。日経平均が高値もち合いとなる中で、個人主体の材料株物色に向かうことが出来れば、次第に年末相場への期待感にもつながりそうだ。■日本アクア、19/12上方修正 営業利益18.07億円←14.22億円日本アクアは第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は従来の210億円から211.95億円、営業利益は14.22億円から18.07億円に上方修正している。消費税率引上げの影響が懸念されるものの、戸建住宅部門、建築物部門共に「アクアフォーム」の商品力を生かした営業展開が奏功し前回発表予想を上回る見込み。■前場の注目材料・日経平均は上昇(23303.32、+161.77)・NYダウは上昇(28004.89、+222.93)・ナスダック総合指数は上昇(8540.83、+61.81)・シカゴ日経225先物は上昇(23365、大阪比+25)・1ドル108円70-80銭・SOX指数は上昇(1742.93、+15.34)・VIX指数は低下(12.05、-1.00)・米原油先物は上昇(57.72、+0.95)・米長期金利は低下・日銀のETF購入・株安局面での自社株買い・パナソニックミリ波Wi?Fiで道路状況を可視化、日米で実証・コクヨぺんてるの連結子会社化目指す・マツダ生産ライン柔軟化、新世代車投入を機に拡大・メルカリ世界100カ国以上で越境販売・日立デジタル新会社が海外けん引、IoT基盤売上高比率3割へ・三井化学レンズ材増産、積極投資続ける☆前場のイベントスケジュール<国内>・特になし<海外>・特になし(GDO)米国男子 マヤコバゴルフクラシック 4日目決着は月曜日に持ち越し 小平智は通算3オーバーで終える第3ラウンドと最終ラウンドを行った。12人がホールアウトできずに日没となり、決着を月曜日に持ち越した。ボーン・テーラーとブレンドン・トッドが4ホールを残して、通算20アンダーの首位に並ぶ。地元メキシコのカルロス・オルティスが1ホールを残して通算19アンダーとし、14ホールを終えたハリス・イングリッシュと並んでいる。小平智は第3ラウンドを「74」とした後、最終ラウンドを4バーディ、3ボギー1ダブルボギーの「72」でプレーし、通算3オーバーで大会を終えた。(msn)(ビジネス・インサイダー・ジャパン)ヤフー・LINE「経営統合ショック」が業界にもたらす巨大インパクト Yahoo! JAPAN(ヤフー)とLINEが経営統合について協議していると報じられた。実現すれば日本国内で約1億人にリーチする巨大なネット企業が誕生する。仮にこの経営統合が実現した場合、どのようなことが起こり得るのだろうか。(注:関係者によると、一部報道のとおり、11月18日中に都内で経営統合の正式発表をする見込み) 両社の統合のメリットはスマホでの卓越した「起点」の獲得にあるヤフーの強みはインターネットにPCからアクセスすることが主流だった時代に、「起点」であるポータルサイトを押さえていたことだ。ブラウザーが立ち上がって最初に表示する「ホームページ」を、検索やニュースを提供する「ポータルサイト」が奪い合った。この「起点」を持つことの強みを熟知しているヤフーだからこそ、ネット利用の起点が検索やスマホのホーム画面、SNSのタイムラインに移ってからも、常にネットの「起点」を押さえようとしてきた。ヤフーは各サービスで数多くのアプリを出し、アクセス数ベースでPCをスマホが抜く水準まで持っていったものの、個々のアプリでトップの座につくことはできなかった。ニュースではSmartNews、地図ではGoogleマップなど、各カテゴリーでヤフーよりも強いアプリがある。LINEはメッセージング分野で最も強いアプリであると同時に、他カテゴリーに対しても入口となる「スーパーアプリ」となる。日本においてスマホアプリの最高の起点であるLINEと、ヤフーが持っている数々のサービスを連携させれば、日本国内で最強の「スーパーアプリ」として、スマホでの起点を押さえることができる。 メルカリ、楽天、ドコモ、KDDIなどは戦略の練り直し必至スマホ決済では、300億円超の投資を行ったPayPayがアプリの利用者数・加盟店数ともに独走し、LINE Payが追う展開となっている。LINE Payはメルカリのメルペイ、NTTドコモのd払い、KDDIのauペイと連携して加盟店の相互乗り入れを行うことを発表していたが、ヤフーと経営統合すれば、株主であるソフトバンクの推し進めるPayPayとの関係を強めるのではないか。そうすることでPayPayは個人間送金で最強のソーシャルグラフ(友達関係)を手にして、LINE Payは泥沼の加盟店開拓・ポイント還元競争から脱却できる。逆にいえば、LINE Payを核に連携を考えていたメルカリ、NTTドコモ、KDDI、加えて楽天、Origamiなどのスマホ決済業者は、加盟店や利用者の獲得について戦略を練り直す必要に迫られる。 懸案のEC強化へ向けた飛び道具にヤフーは川邊健太郎社長の就任以降、アスクルの経営権獲得やZOZOTOWN(株式会社ZOZO)の買収、PayPayフリマ、PayPayモールを矢継ぎ早に投入するなど、ここ数年ECのテコ入れに力を入れている。LINEを通じてスマホでの起点と利用者とのタッチポイントを獲得すれば、アマゾン・楽天を追撃する上での大きな武器となる。まだまだEC分野ではアマゾン・楽天に水を開けられているが、PayPayでスマホ決済を押さえ、アスクルの経営権取得でアマゾンに負けない物流拠点を持ち、LINEを通じてスマホでのユーザー接点でアマゾン・楽天を圧倒できれば、EC領域の成長へ向けて足がかりをつくることができる。LINEにとっても、ソフトバンクの携帯電話販売店やPayPayの加盟店開拓部隊の営業力を活かした地上戦を展開できるようになる。 アジア戦略の足掛かりになるヤフーは旧米Yahoo! Inc.との契約で、ヤフーブランドでの事業展開を日本国内に制限されてきた。一方でLINEは世界各国でサービスを展開し、タイやインドネシアでも数字を持っている。(ヤフー陣営は)LINEブランドでサービスを拡充することによって、人口減で市場の縮小が見込まれる日本を飛び出して、成長著しい東南アジア市場での展開も容易になる。アジアではソフトバンク・ビジョンファンドがさまざまなサービスを展開しており、これらを日本を含めたLINEの普及している国々で展開することも考えられる。 一方で統合へ向けた課題は山積11月14日付 日本経済新聞の報道によると、今回の経営統合ではソフトバンクと韓国ネイバーで共同持株会社を設立してZHDの株式を7割近くを保有し、その下にヤフーとLINEが並存するかたちが検討されているという。いきなり合併せず持株会社を介した兄弟会社として存続することは、事業レベルでの統合プロセスにおいて、着地点を見出すべきさまざまな課題があることも示唆している。 重なり合うユーザー層とサービスいずれも日本を代表するネット企業であるヤフーとLINEは、重複するサービスも数多くある。ゲームのようなコンテンツであれば共存できるが、ニュース、スマホ決済はじめ数多くの重複するサービスが多い。またYahoo! JAPAN IDとLINE IDは、いずれも国内最大規模の利用者数を擁している。金融分野でもヤフーがジャパンネット銀行を持っているのに対して、LINEはみずほ銀行と組んでLINE銀行を設立しようとしている。IDをはじめとしたサービス基盤を統合し、事業のポートフォリオを整理するには、かなりの豪腕を要するだろう。一方でヤフーとLINEともにリーチできていない利用者層も日本国内にいる。検索にグーグル、ソーシャルメディアにTwitterやFacebook、買い物にAmazonを使っていて、ヤフーもLINEも楽天も使っていないユーザー層である。日本国内で圧倒的な利用者数を抱えているヤフーとLINEだが、苦手としているセグメントもやや似ている。LINEは日本国外でもタイ、台湾、インドネシアで比較的高いシェアを持つが、両社とも日本市場を主たる収益源として、日本市場で高いシェアを持っており、重複した利用者も多いのではないか。LINEが公表している紹介資料(上図:2019年10-12月版)によると、普段スマートフォンで利用しているサービスとしてLINEを挙げている人は81.3%、ヤフーを挙げている人が51.6%おり、そのうちLINEのみを使っている人が19.1%、Yahoo! JAPANのみ使っている人が4.1%いるとしている。LINEからみるとヤフーの利用者はかなりの部分がかぶっているが、ヤフーからみると、LINEとの連携で新たに獲得できるリーチが2割近くあることが分かる。両社を足すと85.4%の利用者がスマホで普段から使っている計算となり、まさに国民的サービスといえる。 利用者は「スーパーアプリ」を求めているのか?LINEには既に多くのサービスが統合されており、関連アプリへの導線は複雑になりつつある。LINE Payで決済した店舗からのプッシュ通知が煩わしいという不満も聞かれる。事業上のシナジー(相乗効果)を出すにはLINEから各サービスへの誘導を増やす必要があるが、それ自体がLINEの競争力を損なうリスクがある。その上、単にLINEアプリから呼び出せるというだけでは、各セグメントでトップを獲ることは難しい。例えばLINEは「LINE NEWS」という単体のニュースアプリを出したが、SmartNewsやGunosyといった専業ニュースアプリと比べて存在感は薄い。LINEアプリ自体でニュースを配信するようになってリーチは拡大したが、LINEから他アプリへの誘導には必ずしも成功していない。単にYahoo!ショッピングやZOZOTOWNといったECアプリをLINEアプリから呼び出せるようにしただけでは、顧客を思うように誘導できるとは限らない。ユーザー不在の企業戦略でLINEに様々な機能を盛り込もうとし過ぎれば、LINE自体からのユーザー離れを招いてしまう危険性もある。ソーシャルメディア疲れという言葉にも見られるように、コミュニケーションツールの移り変わりは早い。今は日本市場でLINEが圧倒的なプレゼンスを誇るが、経営統合で機能改善のスピードが遅くなったり、事業上のシナジーを優先して、UIが複雑になったり、動作が重くなったり、通知を送り過ぎるなどして利用者からの支持を失うことがあれば、大きなリスクとなり得る。 社風と競争軸の違いを克服して新たな文化を創造できるかが鍵ヤフーは長らくソフトバンクグループでありながら経営の自律性を保ってきたところ、ここ数年はソフトバンクの影響が増していた。LINEは韓国ネイバーが資本を持ち、全く異なる企業文化を持つ。ライバル視する企業も、ヤフーであれば楽天、リクルートといった国内大手であるのに対して、LINEの競争相手はWeChatやWhatsAppなど海外のメッセンジャーアプリで、対象とする市場も日本に留まらない。経営と開発のカルチャーやスピード感、戦略の優先順位にも違いがありそうだ。事業統合プロセスがうまく行けば、新グループは日本国内での圧倒的なプレゼンスを持ってスマホのスーパーアプリを提供してマネタイズしつつ、東南アジアを中心にソフトバンク・ビジョンファンドの投資先ポートフォリオを、LINEが比較的強いタイ、台湾、インドネシアなどの国々に展開することも考えられる。一方でグループでの意思決定プロセスが複雑化したり、サービスの統廃合に手間取って足を引っ張り合うことがあれば、互いの事業資産を磨耗して時間を空費してしまうシナリオもあり得る。とはいえ楽天、メルカリなどの国内ネット各社、NTTドコモ、KDDIなどの国内キャリア各社は、敵失を期待するよりも前に新たなグループとの競争をにらんだ戦略の練り直しを迫られることになる。(yahoo)(モーニングスター)NTTドコモがプラス転換、SMBC日興証は目標株価3500円に引き上げ NTTドコモ が安寄り後にプラス圏に転じ、前週末比0.4%高の2988.5円を付けた。SMBC日興証券が15日付で、目標株価を3000円から3500円に引き上げた。 同証券はリポートで、NTTドコモについて通信収入が底堅く推移し、21年3月期以降の利益回復の確度も高まってきたと指摘。投資判断は3段階中最上位の「1」を継続した。21年3月期の営業利益を9200億円(20年3月期会社計画は8300億円)と予想している。ヴィンクスが急騰、米セールスフォースとの協業伝わる ヴィンクス が急騰した。顧客情報管理の大手の米セールスフォース・ドットコムとの協業が報じられ、買い手掛かりとなった。 セールスフォースの流通企業向け顧客管理情報サービスに、ヴィンクスが在庫管理などの機能を開発し提案すると伝わっている。ヴィンクスの株価は前週末比15.3%高の1283円まで買われた。新日科学が急騰、インフル用「経鼻ワクチン」で思惑か 新日本科学 が急伸し前週末比4.8%高の814円を付けた。一般財団法人阪大微生物病研究会が、鼻にスプレーするインフルエンザワクチンを開発したと伝わったことに絡み、同様の研究に取り組む新日科学にも思惑が向かっているようだ。 阪大微生物病研は、国産としては初めてとなるインフルエンザの経鼻ワクチンを、近く国へ承認申請するという。一方、臨床試験受託の新日科学も、独自技術の経鼻投与デバイスを開発している。ZHDとLINEに買い先行、経営統合を正式発表 Zホールディングス とLINE に買いが先行した。両社は18日朝に、経営統合に関する基本合意書を締結すると正式発表している。 メッセンジャーアプリのLINEと、ネットサービス「ヤフー」を展開するZHDは、年内をめどに最終的な資本提携契約の締結を目指す。ZHD、LINEのそれぞれ親会社であるソフトバンク と韓国ネイバーは、LINE株の非公開化を目的にTOB(株式公開買い付け)を実施。ZHDを株式交換完全親会社とし、交換比率はZHD1株に対しLINE承継会社を11.75とする。 LINEとZHDの売上高の合計は前年度実績で約1兆1600億円。利用者1億人を超える巨大インターネットサービス企業が誕生する方向だ。株価はZHDが一時前日比5.0%高の438円、LINEが3.2%高の5200円を付けた。日経平均は113円高と続伸、買い一巡後に伸び悩む場面も引けにかけ締まる=18日後場 18日後場の日経平均株価は前週末比113円44銭高の2万3416円76銭と続伸。朝方は、買い物がちで始まった。前週末15日に米中貿易協議の進展を示唆する米高官発言が相次いで報じられ、米主要3株価指数がそろって最高値を更新し、支えとなった。ただ、年初来高値圏で利益確定売りが出やすく、直後に下げに転じた。しばらく前週末終値を挟んでもみ合ったが、その後は、円安・ドル高歩調や香港ハンセン指数の上昇もあって、前場終盤には2万3420円62銭(前週末比117円30銭高)まで値を上げた。一巡後は、いったん伸び悩んだが、買い気は根強く、大引けにかけて引き締まった。 東証1部の出来高は12億2347万株、売買代金は1兆9051億円。騰落銘柄数は値上がり1090銘柄、値下がり973銘柄、変わらず90銘柄。 市場からは「米中協議合意への期待は根強いが、まだ決着していない。上値では利益確定売りが出るが、売り崩すようなものではなく、逆に下げを待ち構えている買い手もおり、極端に強気にも弱気にもなれない」(準大手証券)との声が聞かれた。 業種別では、エーザイ 、小野薬 などの医薬品株が上昇。任天堂 、バンナムHD などのその他製品株や、ソフバンG 、ZHD などの情報通信株も堅調。HOYA 、東精密 などの精密株や、リクルートH 、エムスリー などのサービス株も高い。東エレク 、アドバンテスト などの電機株も買われた。 半面、東レ 、帝人 などの繊維製品株や、JXTG 、出光興産 などの石油石炭製品株が軟調。日水 、マルハニチロ などの水産農林株も安い。 個別では、日本アクア が一時ストップ高となり、ファインD 、パスコ 、レオパレス 、オープンハウス などの上げも目立った。半面、LIXIビバ 、チャームケア 、ネクシィーズ 、三桜工 、CARTAH などの下げが目立った。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、20業種が下落した。昼食を済ませて、午後からは…郵便局~いつものGS~銀行と回ってきました。途中で喫茶店に立ち寄って週刊誌を拝読…。途中で雨が降り始めました…。予報通りですね…。明日の朝までは雨ですか…。(yahoo)(時事通信)〔東京外為〕ドル、108円台後半=買い一巡後は小動き(18日午後3時) 週明け18日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米中貿易協議の進展期待を受けた買いが一巡した後は1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午後3時現在は108円82~82銭と前週末(午後5時、108円54~54銭)比28銭のドル高・円安。 ドル円は早朝、108円70銭台で取引された。午前9時前にはやや緩む場面もあったが、その後は実需筋の買いが入り、仲値後は108円80銭台に浮上。同水準では上値が重く、午後に入ってからは同水準で小動きが続いている。 前週末の海外市場では米中協議の進展期待で「リスクオンの円売りが優勢になった」(FX業者)ものの、週明けの東京市場は「進展期待はドル円の支援要因ながらも、上値を追うほどの買い材料が見当たらない」(為替ブローカー)ため、全般は様子見ムードが強い。 チャート的には「なお109円前後が重い印象」(大手邦銀)とされ、上値を切り上げるには「米中貿易の進展を期待させる新たな材料が必要」(先のブローカー)という。 ユーロも午後は対円、対ドルで小動き。午後3時現在、1ユーロ=120円37~37銭(前週末午後5時、119円58~59銭)、対ドルでは1ユーロ=1.1061~1061ドル(同1.1017~1017ドル)。(了) 〔東京株式〕続伸=米中協議期待も上値重く(18日)☆差替 【第1部】日経平均株価は前営業日比113円44銭高の2万3416円76銭と続伸。米中貿易協議の進展期待が株価の下支えとなったが、一段と買い上がる材料はなく、上値は重かった。東証株価指数(TOPIX)は4.05ポイント高の1700.72と小幅高。 51%の銘柄が上昇、45%が下落。出来高は12億2347万株、売買代金は1兆9051億円。 業種別株価指数(33業種)は、医薬品、その他製品などが上昇。繊維製品、石油・石炭製品、水産・農林業、保険業などは下落した。 ソニー、東エレクが値を上げ、アドバンテスは大幅高。トヨタが小高く、HOYAは続伸した。ソフトバンクG、ZHD、LINEが買われ、任天堂は反発。武田、ファーストリテが堅調で、リクルートHDは年初来高値。半面、ZOZOが値を下げ、三菱UFJが甘く、第一生命は売られた。日水は反落。出光興産、東レは安かった。コマツがさえず、SUBARU、日立も下落。 【第2部】小反発。アルチザ、那須鉄が値を上げた。半面、東芝、千代化建は軟調。出来高1億2706万株。 ▽2兆円割れ 日経平均は横ばい圏で始まった後、香港株の上昇などを眺めて小幅に水準を上げた。ただ、最近の株価上昇の原動力となっていた米中貿易協議の進展期待については、「両国の交渉は続いているとされるものの、具体的に何か決まったという話は出ていない」(銀行系証券)といい、この日は上値追いには材料不足だった。月曜日のため欧米投資家の影も薄く、東証1部の売買代金は2兆円を割るなど取引は盛り上がらなかった。 プラスで終わった日経平均も、構成銘柄の騰落バランスを見ると下落が上昇の数を大きく上回っている。米半導体関連企業の好決算など個別に材料が出た一部の業種を選んで買う動きが日経平均を押し上げたが、相場全体の雰囲気は前週末の終値近辺で一日中もたついていたTOPIXにより正確に表れていたと言えるかもしれない。 225先物12月きりは小幅高。小安く始まった後、香港株や米株先物の時間外取引での底堅さなどを眺めてプラスに転じた。ただ、上値追いの材料がなく、上げ幅は広がらなかった。225オプションはプットが売られ、コールも全般に弱含み。下値不安は小さいが、一段高への期待感もあまり膨らんでいないようだ。(了) 〔NY外為〕円、108円台後半(18日朝) 【ニューヨーク時事】週明け18日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米中貿易協議の先行きに不透明感が広がる中、1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午前8時50分現在は108円70~80銭と、前週末午後5時(108円72~82銭)比02銭の円高・ドル安。 円相場は109円付近でニューヨーク市場入り。ただ、米CNBCが朝方に、政府筋の話として、米中貿易協議の成果文書の取りまとめをめぐり中国側のムードは悲観的だとの見方を伝えた。これをきっかけに協議の行方に懐疑的な見方が広がり、米長期金利が急低下。安全資産としての円が買われ、円は下げ幅を急速に圧縮した。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1055~1065ドル(前週末午後5時は1.1047~1057ドル)、対円では同120円25~35銭(同120円20~30銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、一時最高値更新=ナスダックは反落(18日朝) 【ニューヨーク時事】週明け18日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の行方に引き続き注目が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は寄り付き直後に一時史上最高値を更新し、午前9時35分現在は前週末終値比4.74ドル高の2万8009.63ドルとなった。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は22.19ポイント安の8518.64と反落している。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の11銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の6銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄ではすべてが値を下げてスタートしましたね。(ブルームバーグ)三菱ケミH:田辺三菱をTOBで完全子会社化へ-総額4918億円 三菱ケミカルホールディングスは18日、子会社の田辺三菱製薬を公開買い付け(TOB)によって完全子会社化を目指すと発表した。研究開発費が今後も増加するとの見通しの下、経営の効率化を図る。 買い付け価格は1株2010円で同日の田辺三菱の株価終値を50%上回る。買い付け総額は約4918億円で、買い付け期間は19日から2020年1月7日までとしている。TOB成立後に田辺三菱株は上場廃止となる見込み。田辺三菱は同日、TOBへの賛同意見を表明した。 応募株数が買い付け予定数の下限(5767万731株)に満たない場合はTOBを行わないとしている。田辺三菱は07年に田辺製薬と三菱ウェルファーマの合併により発足。三菱ケミHが56.39%の株式を保有している。 三菱ケミHは買い付け代金の全てを三菱UFJ銀行からの借り入れで賄うとしている。また田辺三菱は、TOBが成立することを条件に従来1株当たり28円としていた今期(20年3月期)の期末配当予想を撤回して無配とすることも発表した。同社は9月末に28円の中間配当を実施している。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-3桁上昇で23400円台を回復、マザーズも動意づきリスクオンの流れが強まる 18日の日経平均は続伸。終値は113円高の23416円。先週末の米国株はダウ平均が28000ドル台に乗せるなど強い動き。ただ、東京市場では好材料を先取りして先週上昇していたことから、スタートはほぼ横ばいとなった。しかし、大型株が強く徐々に買いの勢いが強まった。23400円より上では心理的節目の23500円を前に伸び悩んだものの、後場に入っても概ね高値圏を維持。終盤にかけて買いが入り、終値で23400円を上回った。東証1部の売買代金は概算で1兆9000億円。業種別では騰落率上位は医薬品やその他製品、情報・通信、下位は繊維、石油・石炭、水産・農林となった。1棟499万円から購入できる投資用戸建賃貸住宅の販売を開始したと発表したフィットが後場に入ってストップ高まで買われた。半面、15日にストップ安となった東京ボード工業は売りが止まらず連日の大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1090/値下がり973。アドバンテストやレーザーテックなど半導体関連が大幅上昇。エーザイや小野薬品など薬品株の一角にも買いが入った。「ドラゴンクエストウォーク」のダウンロード数が1000万を突破したことを好感して、コロプラとスクエニHDがそろって大幅高。経営統合を正式発表したZHDとLINEが買いを集めた。足元のモメンタムが強い銘柄には短期資金が殺到しており、WASHハウスやレアジョブが連日のストップ高となった。一方、先週後半から売りが続いているZOZOが大幅安。高速取引に関する日経新聞のコラム記事を材料にSBIHDが後場に入って下げ足を強めた。先週、決算を受けて急伸したLIXILビバは一転して売りに押される展開。ファイナンスが嫌気されたメドレックスやチャームケアが急落した。 日経平均は続伸。場中はやや気迷いムードも見られたが、大引け間際に強い買いが入り、ほぼ高値圏で取引を終えた。東証1部の売買代金が2兆円を割り込むなど、商いが細っている点は警戒材料ではある。ただし、米国株の高値更新基調が続く中では売りは出しづらく、引き続き好地合いが続くと期待できる。きょうの上昇で5日線(23340円、18日時点)を上回っており、節目の23500円や8日の高値23591円も射程圏内に入ってきた。ここまで戻してきた以上は上述の水準を一気に超えておきたいところだ。きょうはマザーズ指数が1.8%高と動きの良さが目立った。ここまで出遅れ感が強かったが、リスクオンの流れが維持される中、そろそろ反転が見られるかに注目したい。このタイミングでマザーズ銘柄の動きが良くなれば、全体の商い活況にも一役買う可能性が高く、日本株のブル基調に勢いがつく可能性がある。NY株見通し- 今週は米中通商合意期待を背景にリスクオン継続か 今週のNY市場は堅調持続か。先週末にクドロー米国家経済会議(NEC)委員長やロス米商務長官が米中通商合意について楽観的な見通しを示したことで米中通商合意期待が引き続き相場の支援材料となりそうだ。ただ、主要3指数がそろって史上最高値の更新を続け、過熱感を示すテクニカル指標も増えており、通商問題への不透明感が高まった場合は、高値警戒感から利益確定売りが強まることも予想される。また、今週はホーム・デポ、ターゲットなど小売り関連銘柄の決算発表が多く、決算発表を受けた消費関連株の動向も焦点か、経済指標・イベントでは10月住宅着工件数、MBA住宅ローン申請指数、10月中古住宅販売件数などの住宅関連指標や10月景気先行指標総合指数に注目が集まる。 今晩の米経済指標・イベントは9月企業在庫、11月NAHB 住宅市場指数、メスター米クリーブランド連銀総裁講演など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:11月18日、14:00) (yahoo)(フィスコ)日経平均は続伸、香港株高で安心感、コロプラなどに買い/相場概況 日経平均は続伸。15日の米国市場でNYダウは222ドル高と反発し、初めて28000ドルを上回った。政府高官が相次いで米中貿易協議の進展を示唆し、10月小売売上高の予想上振れも好感された。しかし、週明けの東京市場では利益確定の売りも出て、日経平均は小幅高からスタートすると、朝方にはマイナスへ転じる場面があった。前場中ごからは香港株の上昇などが安心感につながって強含み、一時23420.62円(前週末比17.30円高)まで上昇。後場に入り伸び悩む場面もあったが、この日の高値圏で取引を終えた。 大引けの日経平均は前週末比113.44円高の23416.76円となった。東証1部の売買高は12億2347万株、売買代金は1兆9051億円だった。売買代金は3週間ぶりの2兆円割れ。業種別では、医薬品、その他製品、情報・通信業が上昇率上位だった。一方、繊維製品、石油・石炭製品、水産・農林業が下落昇率上位だった。東証1部の値上がり銘柄は全体の51%、対して値下がり銘柄は45%となった。 個別では、売買代金トップのソフトバンクGや任天堂、武田薬、ソニー、東エレクなどが堅調。経営統合で基本合意したZHDとLINEも揃って上昇した。スマートフォンゲーム「ドラゴンクエストウォーク」の1000万ダウンロード突破でコロプラは5%超の上昇。業績下方修正のヤーマンは悪材料出尽くし感から買い優勢となった。また、業績上方修正と増配を発表した日本アクアなどが東証1部上昇率上位に顔を出した。 一方、ZOZOが3%安で3日続落。三菱UFJや資生堂は小安い。公募増資実施を発表したチャームケアは急落し、LIXILビバなどとともに東証1部下落率上位に顔を出した。《HK》
2019.11.18
コメント(0)
-
11月17日(日)…2019ラウンド86…
11月17日(日)、晴れです。起床時は日の出時でしたが…。本日はホーム1:GSCCの西コースで開催のダブルス競技に参加させていただきました。チーム2人のネットの合計スコアで競うだけですが…。8時52分スタートとのことですから、6時15分に起床。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時20分頃に家を出る。7時50分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、11/13のプロアマ研修会で入賞の賞品をいただいて、12/15のエントリーを済ませて、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…ショット…マアマア…、パット…マアマア…DERA-MAX04…いい仕事してくれそうです。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはいつものU君(14)です。もう1組はT君(12)とK君(16)です。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:1.0.1.0.0.0.1.-1.1=39(12パット)0パット:1回、1パット:4回、3パット:0回、パーオン:2回。1打目のミスが2回、2打目のミスが2回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが3回…。出だしはバタバタでしたが、5番ミドル~6番ミドルのバーディーチャンスを逃した後の8番ロングの4打目がチップインバーディーになって救われました。スルーでINへ…。IN:0.2.-1.-1.0.0.1.0.1=38(15パット)1パット:4回、3パット:1回、パーオン:5回。1打目のミスが1回、2打目のミスが1回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが2回、パットのミスが1回…。11番ミドルの1打目を右プッシュしてお隣りへ…、そこからトラブルが続いて素ダボでしたが、続く12番ロング~13番ミドルをバーディーとしてイーブンにできたのは大きかった。16番ロングで3パットボギーとして勢いがなくなったが…。39・38=77(8)=69の27パット。ただ、僕が調子よくてもダブルス戦で相方の成績もよくないと…。本日は残念な結果でした…。スコアカードを提出して、靴を磨いて、握りの清算を済ませて、知人たちとしばしの立ち話(知人たちの間でのBB4の使用率が上がっています!)のあとにお風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,62.8kg,体脂肪率21.1%,BMI21.7,肥満度-1.2%…でした。帰宅すると14時30分頃。ロマネちゃんに猫おやつをあげて、僕はプリンとどら焼きとコーヒーでおやつタイム。国内男子ツアーをTV観戦していると奥が帰宅。金谷アマの18番の2打目~イーグルパット…いいものを見せていただきました!!続いて国内女子ツアーをTV観戦…。鈴木Pの18番の2打目は明らかにミスなんだろうけれど柔らかいグリーンのおかげでいいところに止まった!そこからのバーディーパットは見事にど真ん中から…!持っている人は違いますね!それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には56人(28チーム)が参加して…トップは-8とのこと。A君が75(10)=65+E氏が87(12)=72の137で2位。I君が78(6)=72+T君が81(7)=74の146で着外。僕が77(8)=69+U君が92(14)=78の147で着外。個人戦なら4位だが…。(GDO)米国男子 マヤコバゴルフクラシック 3日目イングリッシュが首位 小平智は63位で予選通過8位で出たハリス・イングリッシュが7バーディ、ボギーなしの「64」をマークし、通算13アンダーとして単独首位に立った。悪天候で進行が遅れた大会は17日(日)に決勝ラウンド36ホールを行う考えだ。ボーン・テーラーが通算12アンダーの2位、ブレンドン・トッドが通算11アンダーの3位で追う。首位発進としたダニー・リーは通算4アンダーの4位タイに後退した。小平智は3バーディ、3ボギーの「71」でプレー。カットライン上の通算1アンダー63位で予選を通過した。国内男子 三井住友VISA太平洋マスターズ 最終日金谷拓実が史上4人目のアマ優勝 松山以来8年ぶり単独首位で出たアマチュア世界ランキング1位の金谷拓実(東北福祉大3年)が1イーグル6バーディ、3ボギーの「65」をマークし、通算13アンダーで逃げ切り優勝した。2011年大会の松山英樹以来となるツアー史上4人目のアマチュア優勝を飾った。アマ優勝は1980年の倉本昌弘(中四国オープン)、2007年の石川遼(マンシングウェアオープンKSBカップ)、11年の松山(三井住友VISA太平洋マスターズ)に次ぐ。同じ最終組のショーン・ノリス(南アフリカ)と通算11アンダーで並んだ最終18番(パー5)で、2オンに成功。7mのスライスラインをねじ込んでイーグルを奪い、バーディとしたノリスを1打差で振り切った。優勝インタビューで「(東北福祉大OBの)松山選手から『プロのトーナメントで勝て』と言われていた。松山選手は世界トップレベル。早く同じステージで戦えるよう頑張りたい」と語った。金谷は広島県出身の21歳。広島国際学院高在学中の2015年に「日本アマチュア選手権」を史上最年少の17歳51日で制覇。東北福祉大に進学して、18年の「アジアパシフィックアマチュア選手権」で優勝し、19年の「マスターズ」に出場した。2位にノリス。通算8アンダーの3位にY.E.ヤン(韓国)が入った。国内女子 伊藤園レディス 最終日鈴木愛が3連勝 12年ぶり2人目の快挙1打差の3位で出た鈴木愛が5バーディ、ボギーなしの「67」で回り、通算14アンダーで逆転。今季7勝目を挙げた。最終18番で2mのバーディパットを決め、拳を握った。2週前の「樋口久子 三菱電機レディス」からのツアー3連勝は、2007年の全美貞(韓国)以来になる史上2人目の快挙。2年ぶり2回目の賞金女王に向け、賞金ランキングは申ジエ(韓国)を抜いて1位に上がった。通算13アンダー2位に大山志保、通算12アンダー3位にペ・ソンウ(韓国)。通算11アンダー4位に勝みなみ、福田真未ら4人が並んだ。首位から出た申ジエは「72」と伸ばせず、通算10アンダー8位に終わった。今大会でツアーから退くことを表明している大江香織は2バーディ、3ボギーの「73」でプレーし、通算9アンダーで9位。前年覇者の黄アルム(韓国)は通算8アンダー14位で終えた。<上位成績>優勝/-14/鈴木愛2/-13/大山志保3/-12/ペ・ソンウ4T/-11/岡山絵里、ユン・チェヨン、福田真未、勝みなみ8/-10/申ジエ9T/-9/大江香織、上田桃子、森田遥、比嘉真美子、稲見萌寧(goo)(時事通信)増える「粉飾倒産」=低収益で甘い銀行審査 粉飾決算で財務内容をごまかしていた中小企業の倒産がじわりと増えている。日銀の超低金利政策の影響で収益の低迷が続く中、甘い審査でこうした取引先に資金を貸し出し、痛手を被る金融機関も目立つ。 「各金融機関、顔を合わせれば(融資先の)粉飾という言葉が出てくる」。西日本シティ銀行と長崎銀行を傘下に置く西日本フィナンシャルホールディングスの谷川浩道社長は6日の記者会見でこう嘆いた。 信用調査会社の東京商工リサーチによると、2019年1〜10月の企業倒産件数のうち、粉飾決算を理由とする倒産は16件。前年同期の2倍に増えた。「経営不振で長らく粉飾を続け、隠し切れなくなった企業が多い」(担当者)という。 横浜銀行などを抱えるコンコルディア・フィナンシャルグループの川村健一社長は「結構いい調子に見える会社が実は粉飾で、倒産している」と指摘する。多くの銀行が警戒感を強め、倒産に備えた引当金の積み増しに動いている。 粉飾が増えた理由はさまざまだ。景気の影響より経営者の順法意識など「個別の話」(全国地方銀行協会の笹島律夫会長)との声が多い。ただ、プロである銀行が見抜けなかったのは、低金利と地元の融資先減少に苦しむ地方銀行などが「地の利がない地域で融資した」(笹島氏)事例が増えたことも一因のようだ。 金融当局筋は「都道府県境を越えた融資の審査が緩くなっている。危ない融資先が(他地域から来た)新参者に押し付けられている」と不安視する。粉飾倒産の「地雷」を踏む銀行が一段と増える恐れもありそうだ。
2019.11.17
コメント(0)
-
11月16日(土)…
11月16日(土)、晴れです。朝から爽やかな青空が広がり、気持ちいい~!そんな本日は7時45分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階のモップかけですか…。ハイハイ。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。ロッテのチョコレートと共に…。美味い!!1USドル=108.73円。1AUドル=74.14円。昨夜のNYダウ終値=28004.89(+222.93)ドル。やや円安・ドル高に戻してきましたね。昨夜の日経+10の解説だと中間配当が始まって、海外投資家への支払いで円をドルに換えるのでこの時期はドル高傾向になりやすいとのこと。合わせて12月の第1週頃までは株価も高くなりやすいとのこと。(ブルームバーグ)【米国株・国債・商品】株価指数は最高値、国債下落-貿易合意を楽観 15日の米株式市場ではS&P500種株価指数が再び終値ベースの最高値を更新。米国債は小幅安となった。中国との第1段階の貿易合意に近いと米当局者が示唆し、楽観が広がった。 米国株は主要株価指数が最高値更新、米中貿易合意を楽観 米国債は小幅安、10年債利回りは1.83%に上昇 NY原油先物は反発、貿易合意への楽観で2カ月ぶり高値 NY金は反落、1オンス=1468.50ドルで終了-週間では上昇 S&P500種は週間ベースでも上げて6週連続上昇と、ここ2年で最長の連続高。クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は米中貿易協議の第1段階の合意に関して、「われわれは取りまとめに近づいている」と話した。ダウ工業株30種平均は初めて2万8000ドルを突破、ナスダック総合指数も最高値を更新した。 S&P500種は前日比0.8%高の3120.46。ダウ平均は222.93ドル(0.8%)高の28004.89ドル。ナスダック総合は0.7%上昇。ニューヨーク時間午後4時7分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.83%。 株はヘルスケアや、貿易動向に敏感なハイテク銘柄の上昇が目立った。半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズは市場予想を上回る売上高見通しを示し、株価は急伸。 アドバイザーズ・アセット・マネジメントの最高投資ストラテジスト、マット・ロイド氏は電話取材に対し、「『貿易戦争だ』とか、『関税は撤回だ』といった話を聞くたびに、ある程度はそういう動きに反応して情勢は揺れ動くが、もう重要ではない」と指摘。オオカミ少年の物語と同じだと語った。 ニューヨーク原油先物相場は反発。米中が第1段階の貿易合意取りまとめに近づいているとのクドローNEC委員長の発言を受け、約2カ月ぶりの高値に達した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は95セント(1.7%)高の1バレル=57.72ドルで終了。週間ベースでは0.8%高となった。ロンドンICEの北海ブレント1月限は1.02ドル高の63.30ドル。 ニューヨーク金先物相場は反落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.3%安の1オンス=1468.50ドルで終了。週間ベースでは0.4%上昇した。【NY外為】ドル下落、米鉱工業生産が低調-リスク選好で円も安い 15日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが下落。週間ベースでも値下がりした。米小売売上高が市場予想を上回った一方、米製造業の活動は落ち込んだ。リスクセンチメント改善で株価が最高値を更新したのに伴い、安全逃避通貨は下落した。 ニューヨーク時間午後4時11分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%下落。週間でも0.2%下げた。前日には10月16日以来の高水準を付けていた。主要10通貨ではこの日、円とスイス・フランの下げが目立った 10月の米鉱工業生産指数のうち、製造業生産は6カ月ぶりの大幅なマイナス。ゼネラル・モーターズ(GM)のストライキが響いた。11月のニューヨーク連銀製造業景況指数も低下10月の小売売上高は前月比0.3%増と、予想(0.2%増)を上回る伸び。消費者の支出意欲は年初に比べてペースは落ちているものの、継続していることが示唆された カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース(CIBC)のストラテジスト、ジェレミー・ストレッチ氏: 米国には「減速」リスクがあるが、想定していたほどの「ドル安は見られない」。貿易戦争による圧迫は引き続きユーロ圏など他地域の方が強い ドルは来年いっぱい、徐々に下落するとストレッチ氏は予想 来週は20日に米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が公表される。利下げ決定に関する一段の詳細に市場の注目が集まる この日はリスクテーク意欲が強まる中、円とフランが下落。クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は、米中が貿易協議「第1段階」の合意取りまとめに近いと述べた 米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.83%。週間では11bp低下 ドルは対ユーロで0.3%下げて1ユーロ=1.1053ドル。対円では0.3%高の1ドル=108円78銭米小売売上高、予想上回る増加率-家具など一部に消費減速の兆候 米商務省が発表した10月の小売売上高は、予想を上回る伸びだった。自動車ディーラーやガソリンスタンドが好調だった一方、衣類や家具は振るわなかった。 キーポイント 10月の小売売上高は前月比0.3%増 前月は0.3%の減少、速報値から修正されず ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は、10月に0.2%の増加 飲食店と自動車ディーラー、建材店、ガソリンスタンドを除いたベースのコア売上高は0.3%増、予想と一致 消費者の支出意欲は年初に比べてペースは落ちているものの、好調な雇用市場と賃金の伸びを背景に継続していることが示唆された。個人消費はこの数四半期の経済成長をけん引してきたが、このトレンドが10-12月(第4四半期)も続く可能性をこの日のデータは浮き彫りにした。 一方で10月の小売売上高では主要13項目のうち7項目が減少し、個人消費が勢いを失いつつある兆候も出てきた。家具は0.9%減少し、今年最大の落ち込み。レストラン、バーも減少した。 この3カ月のコア売上高は年率で4%増。7-9月の6.3%増から減速した。 オンラインショッピングを含む無店舗小売りは、前月比0.9%増。前年同月比では14.3%増加し、主要グループで最も伸びた。 ガソリンスタンドは前月比1.1%増。自動車ディーラーは0.5%増加。前月は1.3%の減少だった。(ロイター)米株最高値、米中協議への楽観で ヘルスケア株高い[15日 ロイター] - 米国株式市場は主要3株価指数が最高値を更新。米中通商合意を巡る楽観論が追い風になったほか、ヘルスケア株の大幅上昇が寄与した。 S&P総合500種は6週連続で上昇。週間の連続上昇記録としては約2年ぶりの長さだった。ダウ工業株30種平均は初めて2万8000ドル台に乗せた。 カドロー米国家経済会議委員長は14日、中国との通商協議について、両国が電話で緊密に連絡を取り合っていると明らかにするとともに、協議は極めて建設的で合意は近いとの認識を示した。 グレンミードのジェイソン・プライド最高投資責任者(CIO)は、米中通商関係を巡る不透明感が「かなり長期にわたって市場や株式の大きな変動源であったことは明らかだ。それが何らかの形で解決すれば、多くの投資家や経営陣の心の中にある不確実性が取り除かれ株高につながる」と述べた。 セクター別では11業種中10業種が上昇。ヘルスケア株.SPXHCが上昇をけん引し、2.2%高と1日の上昇率としては1月以来の大きさとなった。医療保険最大手ユナイテッドヘルス・グループ(UNH.N)が5.3%、製薬大手ファイザー(PFE.N)が2.0%上昇した。 トランプ政権がこの日、医療価格の透明性に関して発表したことがヘルスケア株の買い材料となった。グリーンウッド・キャピタルのウォルター・トッドCIOは、規制や選挙を巡るリスクがヘルスケアセクターの2019年のアンダーパフォームにつながっており、この日の上昇はその巻き戻しとの見方を示した。 半導体・ディスプレー製造装置の米アプライド・マテリアル(AMAT.O)は9.0%高。第1・四半期の売上高および利益見通しが市場予想を上回った。 フィラデルフィア半導体(SOX)指数.SOXは0.9%上昇し、最高値を更新。ただ、米半導体大手エヌビディア(NVDA.O)が決算を受けて2.7%下落し、SOX指数の上値を抑えた。 米商務省が15日発表した10月の小売売上高は前月比0.3%増と、前月の落ち込みから持ち直した。ただ衣料や高額の家庭用品の売り上げは減り、好調な年末商戦への期待が後退する可能性がある。市場予想は0.2%増だった。[nL4N27V434] ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.84対1の比率で上回った。ナスダックでは1.50対1で値下がり銘柄数が多かった。 米取引所の合算出来高は約65億株。直近20営業日の平均は69億株。 ドルが対ユーロで下落、通商協議巡る楽観論で=NY市場[ニューヨーク 15日 ロイター] - 終盤のニューヨーク外為市場ではドルが下落した。米中通商協議を巡る楽観的な見方を背景に、ユーロやポンドなど貿易関連の材料で変動しやすい通貨が上昇した。 ロス米商務長官はFOXビジネス・ネットワークとのインタビューで、「第1段階」の米中通商合意が最終決定される可能性は非常に高いと指摘。ただ、対中関税が発動される12月15日までにまとまるかどうかには言及しなかった。 ドルは対ユーロEUR=で0.28%安の1.105ドル、対ポンドGBP=で0.18%安の1.290ドルだった。一方、対円JPY=では0.4%上昇し、終盤は108.81円。今週は香港デモの激化や通商面の不確実性を背景にリスク選好が後退し、安全通貨が上昇していた。スイスフランも対ドルCHF=で0.21%安となった。 テンパスのシニア外為トレーダー兼ストラテジスト、ジュアン・ペレス氏は「米国の経済指標はほとんど伸びていないが、中国は減速しており、経済的な影響力はおそらく米国側に傾いている。中国は何があっても署名するだろう」と述べた。 米商務省が15日発表した10月の小売売上高は回復したものの、衣料や高額の家庭用品の売り上げは減少し、米経済を支える堅調な消費に対して懸念が広がった。[nL4N27V434] ペレス氏は「欧州と英国の第2・四半期の経済指標は非常に気掛かりな内容だったが、第3・四半期はやや改善し、そのペースは予想以上だった。一方で米国は実質的に鈍化している。ドルはこの日、これらの指標に反応し、米経済の成長ペースがそれほど良好ではないことを示した」と語った。 ドル/円 NY終値 108.73/108.76 コラム:米金利上昇を阻む「ドル化した世界」=唐鎌大輔氏[東京 15日] - 米株が断続的に史上最高値を付け、米金利も上昇基調にある中、今後1年間のドル高相場をメインシナリオとする向きも増えてきそうである。 実際、米供給管理協会(ISM)景気指数の底打ち機運などを見ると、そのようなシナリオも検討に値する。また、製造業購買担当者景気指数(PMI)を見ても、米国や中国については持ち直しの兆しも感じられる。昨年来、これほど製造業のセンチメントが悪化し、米金利も過去1年で半分以下(2018年10月の3.2%から2019年9月には1.4%まで低下)の水準となったにもかかわらず、ドル/円JPY=EBS相場はその過程で104円台までしか下がらなかった。 世界経済の減速、これに応じた米連邦公開市場委員会(FOMC)のハト派傾斜、その結果としての米金利低下は、いずれも筆者は予想してきたメインシナリオだったが、ドル/円相場の異常な底堅さだけは誤算であったとしか言うほかない。 <アップサイドリスクの広がるドル円相場> その理由は判然としないが、本邦の対外純資産構成の変化(対外証券投資の相対的な減少、対外直接投資の相対的増加)は、ほぼ確実に寄与しているだろう。リスク許容度の毀損を受けて保有している海外の有価証券を売却する(円買い・外貨売りする)投資家はいても、買収した海外企業を売却する企業はいない クロスボーダーM&Aの隆盛は本邦企業部門による円の売り切りを意味し、容易には巻き戻されない根雪のような外貨になっていると推測される。ドル/円相場が底堅くなった理由は他にもあるだろう。米金利は確かに大幅に下がったが、先進各国の金利が水没する中では依然として高金利だったことも事実である ゆえにドル売りがはやらなかった側面はあろう。また、昨年来の世界経済減速をもたらしている震源地が中国やユーロ圏であって、米国の傷はそもそも浅かったというのも、ドル売りが進まなかった理由かもしれない。 いずれにせよ、企業部門の大幅なセンチメント悪化とこれに伴う米金利の急低下をもってしても、ドル/円相場が下値を攻め切れなかったことの意味は小さくない。既に、センチメントの底打ちを期待する向きも出てきており、2020年年以降のドル/円相場に関し、リスクがアップサイドに拡がっていることはある程度認めなければならない。 <「円高が進まなかった」のではなく「ドル安が進まなかった」> しかし、アップサイドリスクの存在を認めつつも、ドル/円相場が110円台を回復し、定着、上値追いとなる展開も難しいように感じられる。そもそも2019年は「円高が進まなかった」わけではなく、「ドル安が進まなかった」というのが正確な理解だ。 実質実効為替相場(REER)を見ると、円は年初来で+2.4%、前年比では+5.0%と相応に上昇している。実効ベースで見れば、今年が「円高の年」であったことは間違いない。だが一方、ドルのREERも年初来でプラス2.8%、前年比ではプラス2.5%と上昇している。 「円も買われるが、ドルも買われる」という状況下、ドル/円相場が大きく下がるのは難しかったという話であって、「円が全く買われなくなった」わけではないことは留意したい。円買い圧力は相応に残っており、ドル/円相場の上値を重くする力はありそうである。 ちなみに、ユーロのREERを見ると年初来でー0.6%、前年比ではー4.4%とはっきり下落している。日米欧三極で最弱のファンダメンタルズがはっきり出ていると言える。REERの動きは2通貨間のペアよりも素直に各国の経済・金融情勢の相対的な位置関係を映し出している。 <とはいえ、「ドル化した世界」は健在> では、米景気がこのまま再拡大の局面に入り、米金利の上昇に追随してドル/円相場が続伸するという展開があり得るのか。それもまた、難易度が高いシナリオだろう。繰り返し言われているように、金融市場にとって最大のリスクである米中貿易戦争はもはや通商問題の枠を超えた覇権争いの様相を呈しており、早期解決を期待するものではない。 トランプ大統領の一挙手一投足で明暗が目まぐるしく切り替わる状況は何も変わっておらず、現状は「明」の方に偏っているだけとも考えられる。既報の通り、トランプ米大統領は米中貿易交渉に関して予断を許さない発言を繰り返しており、状況はいつでも「暗」の方に転び得ると構えておくべきだ。 また、確かに10月FOMCを経て米連邦準備理事会(FRB)は「利下げ休止」を示唆しているが、だからといって「利上げ転換」に至る見通しが立っているわけではない。まして欧州中央銀行(ECB)や日銀が正常化に目を向けることも全く考えられない。こうした現状を踏まえれば、各国金利の上昇を前提に見通しを作ることも危ういというのが筆者の基本認識である。 なお、米金利の行方を考える上では「ドル化した世界」という論点を忘れてはならない。金融危機後の10年間で新興国(とりわけその企業部門)はドル建て債務を積み上げてきたという経緯がある。国際決済銀行の与信統計を見れば一目瞭然だが、国内総生産(GDP)比で見てもかなり大きな幅を持って積み上がっている2017─2018年でもしばしば見られたが、「ドル化した世界」では米金利が上がれば新興国・地域を中心に資本流出が促され、国際金融市場が揺らぐことになる。 より具体的な話をすれば、米金利が上がった場合、新興国・地域は資本流出を抑えるための自衛的な利上げに追い込まれ、結果として当該国・地域の消費・投資意欲が毀損する展開が懸念される。2018年後半以降の世界経済減速にはそのような側面もあったと考えられる。米金利やドルが上昇すれば外貨としてドルを借り入れている国の負担感が増すのは当然であり、今後、米金利が上昇してくれば、同様の問題が浮上するだろう。 もちろん、2018年に何度も目にしたが、米金利の上昇は米株式市場の動揺も誘う。その転換点は米10年金利で3.0%前後であったというのが当時の経験則だ。株価下落は逆資産効果を通じて米国経済の消費・投資意欲を削ぐというのが当時、最も懸念された経路である。結局FRBがハト派に急旋回し、株価が持ち直したのでそのような展開は回避されたが、こうした株式市場の動揺は今後も課題となるだろう。 要するに、フェデラルファンド(FF)金利は世界の資本コストであり、FRBは世界の中央銀行であるという理解と共に米金利や世界経済を展望する必要があるということだ。米国が如何に好調であろうと、米金利の上昇は緩やかにしか進まないという大局的な視点が相場見通しの策定に求められるのである。 <2020年もレンジ相場か> また、大統領選挙を控えた政権を尻目に利上げ軌道に復帰するという政治的な難しさも残る。再選に意欲を見せるトランプ大統領は激しい口調になるだろうし、かつてのように更迭というフレーズが飛び交う恐れもある。国内外の経済・金融情勢に加え、そうした国内政治情勢も勘案すれば、2020年のFRBの政策運営は「現状維持」を1つの目標とするのではないか。市場参加者としては非常に苦痛な状況(実体経済にとっては非常に好ましい状況)だが、米金利の方向感が出ない以上、2020年のドル/円相場もレンジ相場に収束する可能性が高まっているように感じられる。 しかし、「金利を低位安定させることで株価を維持する」という政策運営は、いつまでも続けられるものではない。FRBは「mid-cycle adjustment」(サイクル半ばでの政策調整)と呼んだ今次利下げ局面で75bpsののりしろを使わされたが、このような局面を繰り返し、政策金利がゼロに接近してくれば株価の下支えもいずれ難しくなるだろう。そのことが意識された時に株価を筆頭とする資産価格が大崩れすることは考えられる。それが大統領選の年に起きる可能性は高く無さそうではあるが、十分警戒に値するシナリオである。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の16銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。(GDO)米国男子 マヤコバゴルフクラシック 2日目ダニー・リーが首位発進 小平智は62位大雨の影響により順延となった第1ラウンドが1日遅れではじまり、「62」をマークしたダニー・リー(ニュージーランド)が9アンダー単独首位で発進した。リーは前半アウトの「29」で加速をつけ、惜敗した前年大会の雪辱に向けて最高のスタートを切った。8アンダーの2位にブレンドン・トッドとアダム・ロング。7アンダーの4位にザック・ジョンソン、ボーン・テーラー、マーク・ハバード、クリス・ベーカーの4人が続いた。自身の今季初戦をディフェンディング大会で迎えたマット・クーチャーは、2つのダブルボギーを叩きながらも「69」とし、2アンダーの44位でスタートした。小平智は3バーディ、2ボギーの「70」とし、1アンダーの62位で終えた。国内女子 伊藤園レディス 2日目引退表明の大江香織が首位タイで最終日へ 渋野は予選落ち今大会を最後に引退を表明している大江香織と、賞金ランキングトップを走る申ジエ(韓国)が通算10アンダーで首位に並んだ。6位から出た大江は「66」とチャージ。有終の美となるツアー4勝目をかけて最終日に臨む。申は15位から7バーディ、ノーボギーとし、この日のベストスコアに並ぶ「65」をマークした。通算9アンダーの3位に賞金ランク2位で3週連続優勝がかかる鈴木愛、「65」でジャンプアップした臼井麗香、今季2勝の勝みなみが続いた。通算8アンダーの6位にイ・ボミ(韓国)、大山志保、稲見萌寧、菊地絵理香、福田真未の5人が並んだ。36位から出た渋野日向子は4バーディ、2ボギー1ダブルボギーの「72」と伸ばせず、カットラインに1打差の通算1アンダー51位で決勝ラウンド進出を逃した。予選落ちは3月末の「アクサレディス」以来で、今季3回目となる。<上位の成績>1T/-10/申ジエ、大江香織3T/-9/鈴木愛、臼井麗香、勝みなみ6T/-8/イ・ボミ、大山志保、稲見萌寧、菊地絵理香、福田真未<こちらの会場のグレートアイランドは好きなコースの一つですね!>国内男子 三井住友VISA太平洋マスターズ 3日目アマチュアの金谷拓実が単独首位 2打差4位に池田勇太16位から出たアマチュアの金谷拓実(東北福祉大3年)が8バーディ、1ボギーの「63」とチャージをかけ、通算8アンダーの単独首位に浮上した。後半インに5バーディを集中させ、2011年大会を制した松山英樹以来となる8年ぶりのアマチュア優勝に前進した。通算7アンダーの2位に、首位スタートから一歩後退したY.E.ヤン(韓国)とショーン・ノリス(南アフリカ)。通算6アンダーの4位に、「66」をマークした池田勇太が浮上した。通算5アンダーの5位に、大会2勝の片山晋呉、時松隆光、首位から出た正岡竜二の3人が続いた。賞金ランキングトップを走る今平周吾は「71」とし、通算5オーバーの46位とした。<上位の成績>1/-8/金谷拓実2T/-7/Y.E.ヤン、ショーン・ノリス4/-6/池田勇太5T/-5/片山晋呉、時松隆光、正岡竜二8T/-4/出水田大二郎、ブレンダン・ジョーンズ(yahoo)(共同通信)鼻に噴射、痛くないインフル予防 国産ワクチン開発、承認申請へ 鼻にスプレーするだけで、インフルエンザの感染を防ぐ国産の経鼻ワクチンを大阪府吹田市の阪大微生物病研究会が16日までに開発した。人に予防接種して安全性と有効性を調べる治験が今年7月に終わり、近く国へ承認申請する方針。従来の注射に比べて高い効果が期待できるという。 経鼻ワクチンは既に米国で広く使われているが、国産品は初。承認されれば、数年後に痛みを伴う注射をしなくても、インフルエンザを予防できる時代が来るかもしれない。 申請するのは、病原性をなくしたウイルスを利用した不活化ワクチン。細いスプレー容器に入ったワクチンを鼻に差し込んで噴射する。(yahoo)(フィスコ)国内株式市場見通し:日経平均は24000円睨みの展開入りへ■日経平均は6週ぶりに反落前週の日経平均は下落した。週間では6週ぶりの反落となった。週初11日の日経平均は5営業日ぶりに下げた。8日のNYダウが小幅続伸し、日経平均も堅調なスタートだったものの、トランプ米大統領が対中関税の段階的撤廃について現時点での合意を否定したことに加え、香港のデモ激化からアジア株が総じて軟調となったことを受けてマイナスに転じた。12日の日経平均は反発。朝方の寄り付き直後にマイナス場面もあったが、後場中ごろから日米で長期金利が一段と上昇するとともに株価指数先物に買いが入り、日経平均は一時前日比213.86円高と上げ幅を広げた。13日の日経平均は200.14円安の23319.87円と反落した。米中協議をめぐる関税撤回についてトランプ米大統領が明確に発言しなかったことに加えて、パウエルFRB議長の議会証言を控えて積極的な買いが限られる中、香港ハンセン指数の軟調な動きから利食い売りが優勢となった。注目されたパウエルFRB議長の議会証言では、当面の金利据え置きが示唆された。しかし、米中交渉が農産物購入を巡って難航していることが伝わり13日の米国市場はNYダウが上昇する一方、ナスダック指数は反落とまちまちの展開になった。14日の日経平均は、1ドル=109円を割り込む円高を警戒し続落した。香港情勢の緊迫化に伴う中国株価指数の軟調な展開や、10月の中国経済指標が弱含んだことが警戒された。個別では、経営統合で最終調整に入ったと報じられたLINEがストップ高比例配分、Zホールディングスも16%高となったことが話題となった。14日のNYダウは米中合意への楽観的な見方が後退するなか、同値引け1日を挟んで6営業日ぶりの小反落となった。15日の日経平均は朝方寄り付き直後にマイナス場面があったものの、米政府高官による米中協議の合意について前進との報道を受け、日経平均は先物主導で上げ幅を広げた。後場は小幅なレンジでのもみ合いとなり、大引けの日経平均は161.77円高の23303.32円と3日ぶりに反発した。■11月のSQ値23637.93円超えが焦点今週の日経平均は、心理的な節目として働いている23000円を下値ラインとしての強調展開が見込まれるなか、きっかけ次第では日経平均24000円台を臨む位置まで浮上しそうだ。クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長が記者団に対して、「米中貿易協議は終了していないものの、取りまとめに近づいている」と発言したことを受けて、15日の日経平均は先物から引き戻す展開となった。米中協議を巡ってはポジティブ、ネガティブなニュースが交錯しているが、米中両国が何らかの合意に至るとの期待は根強く残っている。14日に掛けての続落で日経平均は約378円の調整幅を見て、短期的な高値警戒感は和らいだことから、この米中協議で具体的なポジティブ材料が浮上すれば、上値トライの期待が膨らんでくる。現状で「幻のSQ値」となっている11月8日の23637.93円を超えてくると上げに弾みが付く可能性がある。ただし、先物の売買などで日経平均が大きく振らされる場面が目立ち始め、株価変動率(ボラティリティー)がやや高まってきていることは気掛かり要因だ。香港情勢の緊迫化に伴い、香港ハンセン指数や上海総合指数の影響を受けて、日経平均は神経質な展開を見せているが、24日に香港区議会(地方議会)選挙を控えている点も懸念材料だ。このほか今週は、日米中ともに大きな金融政策イベントや経済指標の発表は予定されていないが、翌週は27日に米国経済指標(ベージュブックと10月個人消費支出)の発表を控えているのに加えて、28日は感謝祭で米国市場が休場となることから、手控えムードが出てくる可能性もあろう。■中小型の個別株物色にも広がり一方、3月期第2四半期を中心とする決算発表が一巡したことを受け、個別株物色が高まってくることが見込まれる。東京証券取引所が集計、発表する投資部門別株式売買状況(2市場、1部・2部合算)によると、海外投資家の現物株と先物を合計した買い越しは11月8日時点で6週連続の買い越しとなっていることから、引き続き大型株、バリュー株(割安株)優位の展開が見込まれる。ただ、15日は週末ながらも一時を含めた東証上場(マザーズ・ジャスダック含む)銘柄のストップ高は17銘柄と14日の9銘柄から急増し、物色動向にうねりが生じ始めており、中小型物色にも広がりが出てくることが予想される。■10月訪日外客数、米10月住宅着工件数、FOMC議事録主な国内経済関連スケジュールは、20日に10月訪日外客数、10月貿易統計、21日に9月全産業活動指数、22日に10月消費者物価が発表予定にある。一方、米国など海外主要スケジュールでは、19日に米10月住宅着工件数、20日に10月29日・30日開催のFOMC議事録などが予定されている。このほか、18日は米政府による中国通信機メーカー大手ファーウェイへの制裁措置の一部猶予期限、22日はG20外相会合(23日まで、名古屋)、日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)失効期限が予定されている。(yahoo)(モーニングスター)株式週間展望=強調展開に陰りなし―腰の入った買いに需給良好、2万4000円台視野 上げ一服となった今週(11-15日)の日経平均株価は、前週比で88円安の2万3303円で終えた。週次のマイナスは6週間ぶり。もっとも、大きく調整する気配はなく、前日比161円高となった週末15日は力強い陽線を引いている。海外勢の買いには腰が入っており、強調展開に陰りはない。来週(18-22日)は再び2万4000円台が視野に入りそうだ。 合意文書への署名が待たれる米中貿易協議をめぐっては今週、段階的な双方の関税撤廃への期待感を背景に株式市場に勢いが付いたが、その後は米国側から慎重な発言もあり週半ばにかけては日経平均が伸び悩んだ。12日の取引時間中高値2万3545円に対する下げ幅は最大で480円強に達したが、2万3000円台を割ることなく切り返した。 東証の投資部門別売買状況(2市場)によれば、外国人投資家の現物株と先物を合わせた買い越しは11月第1週(5-8日)まで6週連続となった。特にこのところは現物株の買い越し幅が大きい(第1週は約4600億円)。市場では、「単なる買い戻しにとどまらない長期の買い手」(大手証券)の存在がささやかれる。 世界的に債券から株式への資金の移動が加速している可能性があり、日本株もその恩恵を受けている。直近出そろった7-9月決算の内容は各社の事業環境の厳しさを映し出したものの、マネーフローに支えられる高時価総額銘柄を中心に、値動きは堅調そのものだ。 日経平均は8月の安値(2万110円)を底に上昇基調が鮮明となり、上向きの25日移動平均線がサポートラインとして意識される。米中協議や香港情勢、欧州景気の不透明感など外部環境に懸念材料は残るものの、それらを上回る買い意欲に突き動かされている。また、高値警戒感からくる根強い逆張りが、結果的に相場上昇の一翼を担う構図も変わらない。 来週はまず18日に、米政府による中国通信機器大手ファーウェイへの制裁の一部例外措置の猶予期限を迎える。期限が再延長されれば、一段と買い安心感が高まりそうだ。20日には10月29、30日分のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録が公表されるものの、市場は年内の追加利下げを想定していないため大きなリスクにはならないとみられる。 経済指標は19日に米10月住宅着工件数、21日に10月中古住宅販売件数と11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、22日にユーロ圏11月製造業PMI(購買担当者指数)がそれぞれ発表される。日本では20日に10月貿易統計。21日の10月工作機械受注(確報値)は、速報が底割れしているだけにその詳細が注目される。 このほか、19日に米グーグルのクラウドゲームサービスがスタート。22日には映画「アナと雪の女王」続編が日米で同時に公開される。来週の日経平均の想定レンジは2万3000-2万3800円とする。(市場動向取材班)(yahoo)(株探ニュース)今週の【早わかり株式市況】6週ぶり小反落、米中協議・香港情勢で不安定も底堅い展開■今週の相場ポイント 1.日経平均は6週ぶりに反落、米中協議先行きに思惑が錯綜し不安定な動き 2.香港では政情不安を背景にハンセン指数が大きく売られ、市場心理が悪化 3.トランプ大統領の講演を受け、米中貿易交渉に対する楽観ムードがしぼむ 4.今週木曜日は中国経済指標が嫌気され、日経平均は約1ヵ月半ぶりの続落 5.週末は米中協議における部分合意への期待が再燃し、先物主導で切り返す■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比88円(0.38%)安の2万3303円と6週ぶりに小幅ながら反落した。 今週の相場を左右したのは、主に米中協議の先行きに対する思惑、香港情勢、そして中国経済への警戒感の3つ。前週に日経平均は4営業日すべて高く、大幅に水準を切り上げていたこともあって、その反動が出たともいえる。 週明けの11日(月)は5日ぶりに日経平均が反落。香港の政情不安が取り沙汰されるなか、香港ハンセン指数の大幅下落などが嫌気され利益確定売りを促した。ただ、下値は固かった。12日(火)は大きく反発した。香港ハンセン指数がいったん下げ止まり、海外ヘッジファンドの先物への買いが現物株市場も浮揚させる形となった。13日(水)は久しぶりに200円超の下げをみせた。トランプ米大統領の講演を受けて米中協議に対する過度な進展期待が剥落したほか、香港ハンセン指数が再び下値を探る展開となり、アジア株が総じて軟調だったことが重荷に。為替の円高も逆風材料となり、日経平均は一時250円近い下げをみせた。14日(木)は続落し、日経平均は一時2万3000円近辺まで水準を切り下げる場面があった。続落したのは約1ヵ月半ぶりのこと。取引時間中に発表された中国の経済指標が事前予測を下回り、市場心理を悪化させた。しかし、週末の15日(金)はヘッジファンドの先物買い戻しで切り返す展開に。米中交渉における第1段階での部分合意が接近しているとの観測や、香港株が下げ止まったことが、リスクオフに傾きかけた市場にストップをかけた。■来週のポイント 来週も米中貿易協議や香港情勢を巡り不安定な相場展開が続きそうだ。ただ、下値には海外勢を中心に買いが入るとみられることから下げは限定的になりそうだ。 重要イベントとしては、国内では20日朝に発表される10月貿易統計や22日朝に発表される10月全国消費者物価指数が注目される。海外では19日に発表される米国10月住宅着工件数のほか、引き続き米中貿易協議に注視が必要だろう。■日々の動き(11月11日~11月15日)【↓】 11月11日(月)―― 5日ぶり反落、アジア株安受け利益確定売り優勢 日経平均 23331.84( -60.03) 売買高12億4128万株 売買代金 2兆1814億円【↑】 11月12日(火)―― 反発、先物主導で上げ幅を拡大し年初来高値更新 日経平均 23520.01( +188.17) 売買高12億5976万株 売買代金 2兆2015億円【↓】 11月13日(水)―― 反落、米中協議の過度な期待剥落し売り優勢 日経平均 23319.87( -200.14) 売買高12億1532万株 売買代金 2兆1558億円【↓】 11月14日(木)―― 続落、米中交渉先行き不透明感で売り優勢 日経平均 23141.55( -178.32) 売買高14億0040万株 売買代金 2兆2436億円【↑】 11月15日(金)―― 3日ぶり反発、米中協議の前進期待で買い優勢 日経平均 23303.32( +161.77) 売買高13億6514万株 売買代金 2兆2269億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、21業種が下落 (2)出光興産 など石油、国際石開帝石 など鉱業株が大幅反落 (3)住友鉱 など非鉄、神戸鋼 など鉄鋼、クボタ など機械といった景気敏感株が売られた (4)日産自 など自動車、日立 など電機といった輸出株は総じて軟調 (5)金融株はまちまち 第一生命HD など保険、三菱UFJ など銀行は低調も 野村 など証券、オリックス などその他金融は堅調 (6)日水 など水産・農林、三菱倉 など倉庫、SB など情報・通信といった内需株の一角は上昇■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(1) 5G 2(2) 全固体電池 3(5) 人工知能(AI) 4(9) 量子コンピューター ── 注目度高い、テラスカイなど新たに頭角現す 5(3) 半導体 ※カッコは前週の順位株探ニュース(minkabu PRESS)午後にはいつものゴルフショップまで…。やたらとクラブにうんちくのオジサンが先客でいます。会話の合間に僕のクラブを渡して作業の依頼。(1):シャフト=DERA MAX04 52D(S)にBB4用のスリーブの取り付け。(2):ウエッヂ2本のグリップ交換…PALMAXのオレンジに。1時間ほどで作業が終わり帰宅。試打クラブコーナーに新しいRYOMAのドライバーとRAVE TOXIC-R460にアサルト・アタックを組んだドライバーが2本置いてあります。まだ、おNewですね。12~1月のお遊びラウンド時に借りていって打ってみましょう。帰宅して、どら焼きとお茶でおやつタイム。国内男子ツアーのTV中継を観戦。金谷アマが首位ですね。岐阜関での日本オープンのリベンジなるか…?!?!
2019.11.16
コメント(0)
-

11月15日(金・七五三)…
11月15日(金)、晴れです。良い天気ですね。そんな本日は7時20分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分頃には家を出る。ゴルフではありません…、アルバイト業務です。途中の山並みはこんな感じであまり紅葉が見られません…。本日は10:00~16:00です。昼食インターバルは1:00ですね。インフルエンザ予防接種があったのでバタバタです…。昼食時にはお蕎麦屋さんを訪問しましたが、どこも混雑…。2軒目に何とか座席確保で天ざるをいただく。午後のお仕事を終えて、お土産に飛騨牛カレーパンを購入しようとしたのですが、昨日に続いて売り切れ…。人生…、こんなものですか…???帰宅して「大黒屋」のお饅頭とコーヒーで遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.50円。1AUドル=73.70円。昨夜のNYダウ終値=27781.96(-1.63)ドル。本日の日経平均終値=23303.32(+161.77)円。金相場:1g=5684(+1)円。プラチナ相場:1g=3487(+14)円。円高・株安ですか…。(ブルームバーグ)【日本株週間展望】一進一退、高値警戒と先高期待交錯-好業績を物色 11月3週(18日-22日)の日本株は一進一退となりそうだ。国内企業の業績回復を見込んだ先高期待と高値警戒感が交錯する中、来期以降の収益拡大が期待される5G関連などの個別銘柄を物色する動きが活発化する。 日経平均株価が12日終値で年初来高値を付け、目先の過熱感が意識されるようになった。14日の日経平均の株価収益率予想(PER)は約14倍と、アベノミクス以降の平均に近づいてきたため割安感が薄れつつあるという。 米中関係への関心は引き続き高い。クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は14日、米中貿易協議の第1段階が合意に「近い」と記者団に語り、協議の先行きへの警戒感が後退した。一方、中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)に対する禁輸措置の一部猶予が18日に期限を迎えることで、米政府の対応が注目される。猶予の再延長が認められなければ米中協議に悪影響を及ぼす可能性があり、株式相場のマイナス要因になりかねない。 19日には、米国の10月住宅着工件数が発表される。市場予想は前月比4.9%増(前月9.4%減)と好転する見込み。21日の中古住宅販売件数は同2.1%増(同2.2%減)、11月のフィラデルフィア連銀製造業景況感指数は6.5(前回5.6)とそれぞれ改善が予想されている。一方、国内では20日に公表される10月貿易収支が注目。市場予想は2831億円の黒字。 11月2週のTOPIXは週間で0.4%安の1696.67と6週ぶりに反落。《市場関係者の見方》ニッセイ基礎研究所の井出真吾チーフ株式ストラテジスト 「昨年2月の急落以降、日経平均株価の株価収益率(PER)は、久しぶりに14倍近辺まで回復しており高値警戒感は出ている。一方で、来期以降、業績回復するのであれば今の水準はまだ割安という見方もできる。両者の思惑が交錯しつつ、2万3000円ー2万3500円のレンジ相場を予想する」三木証券の北沢淳投資情報課長 「堅調を予想する。米中貿易協議にかかる第1段階合意への期待が続き、株価が大きく崩れることはないだろう。対立激化で株安を招くような対応を取りにくいトランプ米大統領と、12月の追加関税を避けたい中国の利害関係は一致する。ゴルディロックス(適温相場)的な状況の中で米国株が上昇すれば日本株にもプラスだ。とはいえ、心理的な壁となる日経平均2万3500円を抜けるには、米中首脳会談の設定など、確実な協議の進展を必要とする」債券は下落、米中協議の合意期待で売り圧力-超長期債オペ結果も重し 債券相場は下落。米中貿易協議を巡る楽観的見方を背景に株高となるなどリスク選好の動きが強まり、債券には売り圧力がかかった。日本銀行が実施した国債買い入れオペで超長期ゾーンの需給緩和が示されたことも相場の重しとなった。 新発10年債利回りは一時前日比0.5ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.07%まで上昇。朝方はマイナス0.095%に低下 新発20年債利回りは一時1bp高い0.305%、新発30年債利回りは一時1.5bp高い0.46%まで上昇 長期国債先物12月物の終値は7銭安の153円05銭。午前には19銭高の153円31銭まで上昇する場面もあったが、午後に入って下げに転じ、一時152円99銭まで下落 市場関係者の見方岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト 米中貿易問題の決定打がない中で、まだ市場が振らされる展開が継続 ここからの米長期金利低下余地は限定的とみられ、さらに円債の上値を追う動きにはなりにくい 超長期債オペは買い入れ額が据え置かれたものの、日銀の利回り曲線スティープ(傾斜)化姿勢には警戒感が残る 日銀オペ 対象は残存期間10年超。買い入れ額は前回から据え置き 応札倍率は残存10ー25年が4.92倍、25年超が3.56倍と、ともに前回から上昇 パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長 新発30年物64回債が対象になるとの期待があったが、今回も除外された。ただ、25年超は買い入れ額が少ないため影響は限定的 オペ結果ではあらためて需給の緩さを確認。月内には20年と40年の入札が続くこともあり、持ち高を落とす動きもあったようだ 背景 クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は14日、米中貿易協議の第1段階の合意に関して「米国側は現在毎日彼らと連絡を取っている」と記者団に語った これを受けて、米株価指数先物が上昇。東京株式相場も反発し、日経平均株価は0.7%高の2万3303円32銭で終了ドル・円小幅高、米中部分合意への期待でリスク選好-108円台半ば 東京外国為替市場のドル・円相場は小幅に上昇。米中貿易協議の第1段階の合意に関して取りまとめに近づいているとのクドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長の発言が好感され、リスク選好の円売りがやや優勢になった。 ハイライト ドル・円は午後3時現在、前日比0.2%高の1ドル=108円58銭。ここまで108円38銭を安値に一時108円63銭まで上昇 ユーロ・ドルは前日比ほぼ変わらずの1ユーロ=1.1022ドル。ユーロ・円は0.2%高の1ユーロ=119円68銭 市場関係者の見方モルガン・スタンレーMUFG証券債券統括本部の加藤昭エグゼクティブディレクター 米中交渉が難航してるとの見方から期待が後退していたが、クドローNEC委員長をはじめ進展を強調する声もあり期待は維持されている きょうのドル・円はクドローNEC委員長の発言や五・十日仲値でのドル需要への期待から買いが優勢に ただ、週末の香港情勢への警戒などもあり、調整色が強い相場が続くとみられ、ドル・円の戻りは108円70銭あたりが重くなりそう三菱UFJモルガン・スタンレー証券の植野大作チーフ為替ストラテジスト 米中の交渉が難航しても決裂でなければ、ドル・円の下値は限定的ということを確認した 最終的な合意を見るまでは、ニュースに一喜一憂し、短期的に反応はしてもポジションを長持ちできない状況が続きそう 市場の関心は米中がメーンで、前日も米経済指標や連銀高官の発言を全く材料にしなかった 海外時間には米小売売上高や鉱工業生産が予定されているが、予想から多少振れても影響は限定的になりそう 背景 クドローNEC委員長は14日、米中貿易協議の第1段階の合意に関して「われわれは取りまとめに近づいている」と述べた 米中貿易交渉では、中国が年間で最大500億ドル(約5兆4300億円)相当の米国産農産物を購入する目標を達成する方法が「第1段階」の合意に向けた争点に(ロイター)来週の日本株は材料難、米中協議関連のニュースに振れやすい[東京 15日 ロイター] - 来週の東京株式市場は、米中通商協議の動向をにらみながら方向感を探るとみられている。国内外で相場を動かすような重要経済指標がなく、国内企業の決算発表も一巡している。米中協議に絡むヘッドラインで上下に振れる展開となりそうだ。 日経平均の予想レンジは2万3000円─2万3700円。 国内では3月期決算企業の第2・四半期(4─9月期)決算の結果がほぼ出そろった。SMBC日興証券の集計によると、11月14日までに東証1部(金融除く)の99.9%が開示し、経常利益は前年同期比10.9%減となった。米中貿易摩擦に伴う世界経済減速を受け、製造業が同21.4%減と急激に悪化したことが影響した。 来週は、日本で貿易統計、消費者物価、米国で住宅着工件数、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨、コンファレンス・ボード米景気先行指数などが発表されるが、いずれも相場の方向を決定する材料にはなりにくい。そのため「基本は米中協議の動向や香港情勢など政治問題がテーマになる」(みずほ証券の投資情報部部長、倉持靖彦氏)との見方が多い。 18日には、米国によるファーウェイへの制裁について一部猶予措置の期限を迎える。この猶予が延長されるとの観測がある一方、米国のバー米司法長官が米連邦通信委員会に充てた書簡で、ファーウェイとZTEは「信用できない」とし、両社は安全保障上の脅威との見方を示すなど予断はできない。 カドロー米国家経済会議委員長は14日、中国との通商協議について、極めて建設的で合意は近い、との認識を示したものの、協定署名の日時や開催地など詳細が明らかになるまでは投資家の疑心暗鬼も続きそうだ。 香港情勢の悪化も懸念される。デモは通常、週末に行われていたが、今週は平日にも抗議活動が行われ混乱が拡大した。学校が休校となっているほか、一部の主要道路は封鎖。大学には学生がバリケードを築いて立てこもっている。「中国が本格的に介入すると米中通商協議にも影響を与えかねない」(国内証券)との声も出ていた。 水準的に2万3000円付近は底堅いとみる向きは多いものの、「2万3500円の上を狙うには材料不足。どちらかというと、下値警戒のほうが優勢」(SMBC信託銀行のシニアマーケットアナリスト、山口真弘氏)との見方もあった。 コラム:4兆円弱の大手行保有「ベア型」投信、相場変動の激化要因に[東京 15日 ロイター] - 国内の大手銀が保有する4兆円弱の「ベア型投資信託」が、株価や長期金利の変動を増幅させる変動要因として、市場の一部で意識され出した。株価下落ヘッジ用のベア型は、想定を超えた株価急騰時の対応が難しい。今月5日の日経平均.N225の大幅上昇と6日の長期金利JP10YTN=JBTC上昇には、このベア型が影響したとされる。 今後、電撃的な米中の通商合意などがあった場合、予想外の株高と長期金利上昇の「誘因」になりかねないパワーを秘めている。 日銀が10月24日に公表した金融システムリポートは、地域金融機関に経費節減や非金利収入の拡大を促したことなどに注目が集まったが、市場関係者の多くが見逃した一節に、実は大きな意味があった。 金融機関の有価証券投資について言及した同リポートの23ページに「大手行では、引き続き株式投資信託に関して厚めの残高を維持しつつも、債券や政策保有株式等の評価損益を管理するための『ベア型』の投資信託を積み増す先がみられ、足元の残高増加のかなりの部分を『ベア型』が占めているとみられる」と記された。 そのうえで脚注には「投資残高ベースでは、『ベア型』は大手行の投資信託残高の約5割を占める」との説明が付いた。 日銀によると、2019年8月末の大手行の投信残高は約7.5兆円。ベア型は3兆円台後半で推移していたとみられている。 「ベア型」投信は、株価の下落局面でリターンを得る可能性が高まるように組成されている。日銀によると、19年8月末の大手行の株式保有残高は約6.4兆円。 多くは企業との取引関係を重視して保有する「政策保有株式」とみられ、その損失リスクを抑制するために保有したのが、「ベア型」投信だったとみられる。 昨年から米中貿易摩擦が激化し、株価下落リスクの高まりが意識され、そのことも「ベア型」の保有に大手行が傾いた要因だったようだ。 この「ベア型」が、東京市場で株価押し上げに一役買ったのが今月5日だった。米中通商交渉の部分合意観測が高まり、4日の米株が大幅高となり、5日朝から日経平均は足取り軽く上昇。午後になって一段と上げ、401円高で引けた。 複数の市場関係者によると、その背後に大手銀によるベア型投信解約による「上げ効果」が加わっていたという。 その余波は、翌6日にも続く。今度は円債市場で長期金利が一時、マイナス0.075%まで急上昇した。 この金利上昇の背景にも、短期的な株価の大幅上昇を受け、リスク量の調整を余儀なくされた大手銀などが、長期ゾーンの国債を売却したことが影響したという。 つまり、「ベア型」投信への対応を起点に、株高と長期金利上昇の幅がかさ上げされた構図になったということだ。 株価下落に備えた「ベア型」投信の保有だったが、11月上旬のような急激な株高時には、かえって株と債券の両方で損失リスクが拡大してしまった。 理想的には、政策保有株の残高を今後、一段と減少させつつ、「ベア型」投信の残高も減らすことが、大手行のリスクを減少させる近道となる。だが、規模が大きいだけに急激な残高削減は難しいだろう。 そうなると、次に大幅な株価上昇が短期間に実現した場合、今回と同じような展開になることが予想される。では、どういうときに想定されるのか──。 最も考え得るのは、足元で膠着(こうちゃく)している米中通商交渉で期待された「部分合意」が成立し、米国の関税撤廃の範囲が予想を超えるケースだろう。 そのほか想定外の出来事でリスクオン相場が急進展した場合、「ベア型」投信のまとまった解約が発生するのではないか。 しばらくの間、「ベア型」投信解約の破壊力を注視する必要があると考える。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米S&Pが最高値更新、ウォルマートの好決算が支援ダウは1ドル安の2万7781ドル[14日 ロイター] - 米国株式市場はS&P総合500種が小幅に上昇し、最高値を更新して取引を終えた。ネットワーク機器大手シスコシステムズのさえない業績見通しに圧迫された一方、小売大手ウォルマートの好決算に支援された。前日に最高値を更新していたダウ工業株30種は小幅安で終了。ナスダック総合も小幅安で引けた。シスコシステムズは7.3%急落。世界経済の先行き不透明感が一段と高まり、ルーターやスイッチなどネットワーク機器需要が低迷する中、第2・四半期の収益が予想に届かないとの見通しを示したことが嫌気された。[nL4N27U0AW]シスコ株の下げは3指数の最大の重しとなったほか、S&P情報技術セクターを圧迫。同セクターは0.1%下落した。ウォルマートは、通期利益見通しを上方修正。第3・四半期(8─10月)の利益や米既存店売上高が予想を上回った。[nL4N27U4C2]同社株は一時、過去最高値に上昇。終値は0.3%安だった。ただ、同社の決算を受け、S&Pの小売株指数と一般消費財株指数は上昇した。ユニオンバンクのシニア・ポートフォリオマネジャーは「米経済にとって重要な年末商戦期の前に消費者セクターが底堅さを見せ、健全なペースを維持している」と指摘。その上で、米中貿易摩擦や世界経済情勢が引き続き圧迫要因となっているようだとの見方を示した。米株市場はこのところ、米連邦準備理事会(FRB)の利下げや、市場予想を上回る企業決算、景気底入れの兆候に支援され、最高値を更新してきた。リフィニティブによると、S&P総合500種採用企業の第3・四半期決算は、発表シーズンが終盤に近付く中、約4分の3が市場予想を上回っているものの、全体では0.4%の減益になる見通しだ。FRBのパウエル議長は14日、下院予算委員会で証言し、過去最長の拡大局面にある米経済に過熱の兆候は見られず、急激な景気後退に陥るリスクは極めて低いとの見解を示した。[nL4N27U4MT]15日に発表される10月の小売統計が注目される。S&Pの主要セクターでは不動産が0.8%高と最大の上昇率を記録。一方、エネルギーと主要消費財は、情報技術セクターと同様に軟調となった。百貨店のディラーズは決算が好感され、14.2%急伸した。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.34対1の比率で上回った。ナスダックでは1.21対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は約63億株。直近20営業日の平均は69億株。日経平均は3日ぶり反発、高値警戒感和らぎショートカバー15日終値は161円高の2万33303円[東京 15日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は3日ぶり反発。直近の下げで高値警戒感が和らぎ、買い戻しや押し目買いが入った。ドル安/円高に振れていた為替相場が落ち着いたことや、香港ハンセン指数がプラス圏で推移したことも安心感を誘った。日経平均は8日に直近高値をつけてから14日までに2%超下落し、過度な高値警戒感が後退したことで、朝方から買いが先行した。14日の米国株市場でS&P総合500種が最高値を更新して取引を終えたことも好感された。週末を前にショートカバーを急ぐ動きも観測された。日経平均はドル/円のじり高に歩調を合わて上げ幅を拡大し、後場寄りにきょうの高値2万3340円77銭を付けたが、その後は手掛かり材料難で動きが乏しくなった。このところ弱含んでいた香港ハンセン指数がプラス圏で推移したことも好材料だった。市場からは「米中協議の行方が懸念されているが、いったんトランプ米大統領がポジティブなコメントを出せば地合いが一変する可能性もあり、売り込みにくい」(キャピタル・パートナーズ証券チーフマーケットアナリストの倉持宏朗氏)との声が出ていた。TOPIXも3日ぶり反発。東証33業種では、石油・石炭製品、鉱業以外の31業種が買われた。水産・農林、パルプ・紙、海運などが値上がり率上位となった。個別では東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体関連銘柄が堅調。米半導体製造装置のアプライド・マテリアルズが14日の米市場の時間外取引で大幅に上昇したことが材料視された。同社は取引終了後に決算を発表、売上高と見通しともに市場予想を大幅に上回った。東証1部の騰落数は、値上がり1711銘柄に対し、値下がりが370銘柄、変わらずが73銘柄だった。(株探ニュース)【市況】来週の株式相場戦略=2万3500円前後が抵抗線、中間配当再投資で需給良好 来週の株式市場は、依然高値圏でのもみ合い相場が予想される。日経平均株価の想定レンジは2万3000~2万3600円。 今週の日経平均株価は6週ぶりに反落した。10月初旬から急ピッチの上昇が続き、チャート面からの過熱感も指摘されていた。日経平均株価の25日移動平均線との乖離は今月5日には5%弱に達したが、足もとでは2%前後に落ち着いてきた。ただ、騰落レシオは120%台と依然として高水準で「もう少し調整が必要」(アナリスト)との声は少なくない。当面の日経平均株価は2万3500円前後が上値抵抗線となりそうだ。 ただ、需給は良好で下値不安は小さいとみられる。特に、来週から12月初旬にかけては、3月決算企業の中間配当の支払いが始まり、その再投資資金が株式市場に流入するとの観測が出ている。中間配当の支払い金が現物株買いに回れば、全体相場は底堅い展開が見込める。 日銀のETF買いが今週の下落場面で入らなかったことが話題を呼んでいるが、「ETFの買いが入らなくても堅調な相場は続くとみて買いを見送ったのでは」(市場関係者)との声もある。一部ヘッジファンドは日銀ETFの不在を材料に売りを仕掛けたとの観測もあるが、「状況を見たうえで日銀のETF買いは再開されるだろう」(同)との見方が出ている。 来週は目立ったイベントはなく19日の米10月住宅着工件数や21日の米10月景気先行総合指数、それに20日に10月開催分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が公表される程度。決算発表も今週で一巡することから、手掛かり材料難となることが予想される。なお、21日にトゥエンティーフォーセブンが東証マザーズに新規上場(IPO)する。 最大のポイントは依然、米中協議の行方だ。米国による第4弾の対中関税引き上げの実施が12月15日に迫る中、見直しのタイムリミットは迫っている。来週にかけて米中協議に関わるニュースは一段と注目されそうだ。また、米アプライド・マテリアルズの決算は堅調だったことから、半導体関連株の強気相場はなお続くとみられている。ZホールディングスとLINEの経営統合報道の余波で、ネット関連株物色の流れも続くとみられる。(岡里英幸)昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の14銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の24銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-好材料に素直に反応して3桁上昇、来週は底堅い展開か 15日の日経平均は3日ぶり反発。終値は161円高の23303円。小動きの米国株を受けて、序盤は前日終値近辺での一進一退。しかし、クドロー米国家経済会議(NEC)委員長が中国との貿易協議が合意に近づいていると表明したことが伝わったことから、買いの勢いが強まった。幅広い銘柄に買いが入り、指数は上げ幅を3桁に拡大。23300円台に乗せた後は、週末を前に値動きが落ち着いたが、後場に入っても強い基調が崩れることはなく、高値圏を維持した。東証1部の売買代金は概算で2兆2200億円。業種別では全33業種中、31業種が上昇。騰落率上位は水産・農林、パルプ・紙、海運、下位は石油・石炭、鉱業、その他製品となった。中国市場への進出を発表したWASHハウスが後場急騰してストップ高。半面、今期が大幅な減益計画となったスプリックスが急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1711/値下がり370。東京エレクトロンや太陽誘電、SCREENなどハイテク株が大幅上昇。上期の最終増益が好感された日本郵政が商いを伴って5%超上昇した。上方修正を発表したスルガ銀行やKADOKAWAが急伸し、三桜工業やレアジョブはストップ高。アドベンチャーは1Qは営業減益も大幅な増収が好感されてストップ高まで買われた。一方、ZOZOが連日の大幅安。きのう統合観測を受けて急騰したLINEとZHDがともに大きく売られた。下方修正を発表した奥村組やペッパーフードが急落。前期計画未達のキャリアや、9月決算の発表が遅れていると報じられたMTGはストップ安まで売られる場面があった。 日経平均は3日ぶり反発。きのうまでの弱い流れや昨晩の海外動向からはさえない展開が想定されたものの、場中に出てきた好材料に素直に反応して強い動きを見せた。週末値は23303円と、今週は23500円より上の買いづらさが意識された割には比較的値を保った。5日線(23323円、15日時点)には若干届いておらず、来週は早々に同水準を上回ることができるかが注目される。業種別の週間騰落を見ると、上位は上から水産・農林、証券・商品先物、倉庫・運輸、精密機器、情報・通信で、下位は下から石油・石炭、ゴム製品、鉱業、非鉄金属、電気・ガスとなっている。総じて内需が強く、市況関連が売られている。米中交渉に関して、少し前に話が出てきたように関税撤廃の方向で進むのであれば、下位業種の巻き返しがあるだろう。しかし、合意でも条件付きなどの内容であったり、そもそも進展がないようであれば、目先は内需の相対優位性が高まると予想する。【来週の見通し】 底堅い展開か。決算発表が一巡し、日米ともあまり材料は多くない。10月開催のFOMC議事録公表(20日)が注目イベントではあるが、今週、パウエルFRB議長の議会証言を無難に消化していることから、新たな材料にはなりづらい。米中交渉関連のニュースには引き続き神経質な反応を示すと考える。ただ、日本株は今週、交渉難航の可能性なども織り込みつつクールダウンしている。日経平均の23000円より下では押し目を待っている投資家も多いと想定されるだけに、交渉決裂などのネガティブシナリオとならない限りは、大崩れはないだろう。3月決算企業の中間配当支払いによる再投資期待も高まりやすく、下値は堅く、好材料が出てくれば上を試しやすい地合いが続くと予想する。【今週を振り返る】 軟調となった。週前半に年初来高値を更新したものの、急ピッチの上昇に高値警戒感も強まる展開。米中交渉が難航しているとの報道や、香港情勢の緊迫化、中国の経済指標の悪化、円高進行などが楽観ムードを冷やした。指数は直近高値から500円以上下落し、調整色が強まった。しかし後半にかけては、米中交渉に関する好材料も出てきたことから値を戻した。物色では企業再編や提携に関するニュースが多く出ており、LINEやZHD、西芝電機、福島銀行などが大賑わいとなった。日経平均は週間では約88円下落し、週足では陰線を形成した。【来週の予定】 国内では、10月首都圏マンション販売(11/18)、10月貿易収支(11/20)、9月全産業活動指数(11/21)、10月全国消費者物価指数、G20外相会合(名古屋、~11/23)(11/22)がある。 企業決算では、東京海上、SOMPOHD、MS&AD(11/19)がある。 海外では、米11月NAHB住宅市場指数、米9月対米証券投資(11/18)、米10月住宅着工件数(11/19)、FOMC議事録(10/29~10/30開催分)(11/20)、米11月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、10月景気先行総合指数、10月中古住宅販売(11/21)などがある。 米企業決算では、ホームデポ(11/19)、ターゲット、ロウズ・カンパニーズ、エル・ブランズ(11/20)、メ―シーズ、ギャップ(11/21)が発表を予定している。NY株見通し- 堅調か 米経済指標は10月小売売上高など 今晩のNY市場は堅調か。昨日はダウ平均とナスダック総合がわずかにマイナス圏で終了したものの、S&P500は小幅に続伸し、終値での最高値更新を続けた。 引け後の決算発表では半導体製造装置最大手のアプライド・マテリアルズが予想を上回る10-12月期決算や強い1-3月期の見通しが好感され時間外で約4%高となった。 また、米中通商問題では引け後にクドロー米国家経済会議(NEC)委員長の「中国との貿易協議は合意に近づいている」との発言も伝わった。 今晩は、週末の取引で、高値警戒感から利益確定売り圧力が高まることも予想されるものの、米中合意への期待やアプライド・マテリアルズの好決算が支援材料となるほか、10月小売売上高などの経済が良好な結果となれば、主要3指数の上値追い期待される。 今晩の米経済指標・イベントは10月小売売上高のぽか、11月NY連銀製造業業況指数、10月輸入物、10月鉱工業生産など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:11月15日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)来週の日本株の読み筋=強調展開維持か、米中合意への期待感根強く好需給も支え 来週(18-22日)の東京株式市場は、強調展開を維持か。クドローNEC(米国家経済会議)委員長は14日、米中貿易協議の第1段階の合意について「近づいている」と発言したと伝わった。合意に向けた期待感は根強く、足元の好需給も支えとして意識される。 東証の投資部門別売買状況(2市場)によれば、外国人投資家の現物・先物合計の買い越しは11月第1週(5-8日)まで6週連続となった。特に直近は現物株の買い越し額(第1週で約4600億円)が大きく、中・長期マネーの流入が観測されている。買い戻しとともに、株価上昇を後押しする要因として注目される。 18日に、米政府による中国通信機器大手ファーウェイへの制裁の一部例外措置の猶予期限を迎えるが、期限が再延長されれば、買い安心感が一段と広がる可能性がある。20日には、10月29-30日開催のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録が公表されるが、13日にパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が米議会証言で利下げを当面停止する方針を表明済みであり、新たなリスクにはなりにくい。 スケジュール面では上記以外に、国内で20日に10月貿易統計、22日に10月消費者物価、G20外相会合(23日まで)などがある。海外では、19日に米10月住宅着工件数、21日に米11月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数、米10月CB景気先行総合指数、米10月中古住宅販売件数などの発表が予定されている。 15日の日経平均株価は3日ぶりに反発し、2万3303円(前日比161円高)引け。朝方に強含んで始まったあと、下げに転じる場面もあったが、下値は堅く、その後はプラス圏に浮上した。クドロー発言や、時間外取引での米株価指数先物の上昇を支えに、先物主導で買われ、上げ幅は一時200円近くに達した。市場では、「決算も終わり、一段高には支援材料が欲しいが、海外投資家が現物株買いに動いており、上昇基調は変わらないとみている」(中堅証券)との声が聞かれた。今晩のNY株の読み筋=米中協議の懸念後退なら経済指標に関心高まるか 15日の米国株式市場では、注目度の高い経済指標の発表が多い。11月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米10月小売売上高、10月鉱工業生産指数など。東京時間にクドローNEC(米国家経済会議)委員長が米中協議の合意が近いとの認識を示したと報じられ、投資家マインドが改善。懸念後退により経済指標にも反応しやすい。 市場予想の平均値はNY連銀製造業景気指数がプラス6.0、小売売上高が前月比0.2%増、鉱工業生産が同0.4%減となっている。NY連銀指数と小売売上高は前月から改善する見通し。目先の利下げ打ち止めが示唆されているだけに、強い経済指標には素直な反応が期待される。<主な米経済指標・イベント>経済指標=11月ニューヨーク連銀製造業景気指数、10月小売売上高、10月鉱工業生産指数要人発言=パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が下院で証言、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕3日ぶり反発=米政権幹部発言を好感(15日)☆差替 【第1部】米政権幹部が中国との貿易協議について「合意に近づいている」との見方を示したことが好感され、幅広い銘柄に買いが入った。日経平均株価は前日比161円77銭高の2万3303円32銭、東証株価指数(TOPIX)は12.27ポイント高の1696.67と、いずれも3日ぶりに反発した。 銘柄の79%が値上がりし、値下がりは17%だった。出来高は13億6514万株、売買代金は2兆2269億円。 業種別株価指数(全33業種)では、水産・農林業、パルプ・紙、海運業の上昇が目立った。下落は石油・石炭製品、鉱業の2業種だった。 個別銘柄では、東エレク、アドバンテス、HOYAがしっかり。武田、日水、三菱紙も値を上げた。トヨタ、ソニーは小幅高。三桜工が買われた。日本郵政が上伸。三菱UFJは強含み。川崎船が堅調。半面、ZHD、LINE、ZOZOが大幅安。ソフトバンクGは反落。任天堂、キーエンス、日産自がさえない。国際帝石、出光興産も軟調。 【第2部】3日続落。東芝が下げ、那須鉄は急落した。半面、技研HDは大幅高。出来高9918万株。 ▽食品、医薬品株に買い 15日の東京株式市場は、米中貿易協議の進展期待で買いが優勢だった。 取引開始直前に、クドロー米国家経済会議(NEC)委員長が「中国との貿易協議が建設的に進んでいる」と発言したと伝わった。前日の海外市場では貿易協議の先行きを警戒する見方が優勢で、クドロー氏の発言で投資家心理が一転した。日経平均株価は先物主導で上昇した。 後場の寄り付きには前日終値からの上げ幅が約200円に広がった。また、「香港情勢について目立ったニュースがなかった」(大手証券)ことも、市場の安心感につながったとの指摘もあった。 食品や医薬品など、業績が景気の動きに左右されにくい銘柄に買いが目立った。「海外勢の資金が流入している」(同)との見方が出ていた。 225先物12月きりは堅調。クドローNEC委員長の発言を手掛かりに買い優勢で始まり、現物市場の昼休みの間に2万3400円まで上昇した。225オプション12月きりは、プットがさえず、コールはしっかり。(了)〔ロンドン外為〕円、108円台半ば(15日午前9時) 【ロンドン時事】週末15日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の中を1ドル=108円台半ばで推移した。午前9時現在は108円50~60銭と、前日午後4時(108円50~60銭)比変わらず。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1020~1030ドル(1.0995~1005ドル)。対円では同119円60~70銭(119円40~50銭)。(了)〔NY外為〕円、108円台後半(15日朝) 【ニューヨーク時事】週末15日午前のニューヨーク外国為替市場では、米中貿易協議の進展期待を背景にリスク選好姿勢が強まり、1ドル=108円台後半に軟化している。午前9時現在は108円65~75銭と、前日午後5時(108円35~45銭)比30銭の円安・ドル高。 ロス米商務長官は15日、米FOXビジネスのインタビューで、米中両国が電話による貿易協議を同日行う見通しと発言。「第1段階」合意の署名に向け調整がかなり進んでおり、署名する可能性は「非常の高い」と述べた。これを受けて、米中貿易摩擦の先行きに対する悲観的な見方は後退。安全資産としての円は売られやすくなっている。 朝方に発表された一連の米経済指標は強弱まちまちとなり、市場への影響は限定的。米商務省が朝方発表した10月の小売売上高は前月比0.3%増と2カ月ぶりのプラスで、市場予想の0.2%増を上回った。一方、10月の輸入物価指数は前月比0.5%低下(予想は0.2%低下)。11月のニューヨーク州製造業景況指数は2.9と、前月(4.0)、市場予想(5.0)のいずれも下回った。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1035~1045ドル(前日午後5時は1.1017~1027ドル)、対円では同119円95銭~120円05銭(同119円43~53銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも史上最高値更新(15日朝) 【ニューヨーク時事】週末15日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の進展期待が再び高まり、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は寄り付き直後に史上最高値を2日ぶりに更新。午前9時35分現在は、前日終値比96.61ドル高の2万7878.57ドルで推移している。ハイテク株中心のナスダック総合指数も一時史上最高値を更新。同時刻現在は33.68ポイント高の8512.70。(了) 今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の13銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.15
コメント(0)
-

11月14日(木)…
11月14日(木)、雨~晴れ…でした。6時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、7時20分頃に家を出る。ゴルフではありません…、アルバイト業務です。本日は8:30~16:15です。昼食インターバルが約2:00。お仕事はハードでほぼ時間通り…。インターバルはのんびり雑誌を読んでいられるコメダ珈琲店へ。食事を済ませてこちらのお店へ移動…名産の栗製品を購入しようとしたのですが、午前中で売り切れ…。トホホ・・・です…。午後のお仕事もほぼ時間通り…。17時過ぎに帰宅して、御座候とお茶で遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.68円。1AUドル=73.86円。昨夜のNYダウ終値=27783.59(+92.10)ドル。本日の日経平均終値=23141.55(-178.32)円。金相場:1g=5683(+10)円。プラチナ相場:1g=3473(+4)円。(ブルームバーグ)グローバル株1年でさらに20%高も、資金が流入に転じれば-シティ グローバル株式市場の騰勢への逆風が向きを変える兆しが表れており、その場合には株価がさらに押し上げられる可能性があるとシティグループが指摘した。 グローバル株の指標が年初来で20%上昇する中で、投資家は株式を2300億ドル(約25兆円)相当売り越したとロバート・バックランド氏らストラテジストが13日のリポートで指摘。そのような現象は過去に2回しか起きたことがなく、トレンドが反転した段階で、資金流入により株価はその後1年でさらに20%上昇したという。 シティのチームは「11月はこのままいけば、新興国・先進国市場の株式ファンドに2年ぶりに資金が流入する月となる。それが続けば、上昇にさらに勢いが加わることもあり得る」と分析した。 「同じような株価と資金フローのデカップリングは2012年と16年にも起きた。いずれも資金流出が流入に転じたことに伴い、グローバル株式はその後12カ月でさらに20%上昇した」とストラテジストらは指摘した。ドル・円は小幅安、米中楽観の後退や中国景気懸念が重し-豪ドル下落 東京外国為替市場のドル・円相場は小幅下落。米中通商協議への楽観後退や低調な中国経済指標を背景にリスク回避ムードが広がった。オーストラリアドルは豪雇用統計が市場予想を下回ったことが嫌気され、対ドルで約1カ月ぶり安値を付けた。 午後3時21分現在のドル・円は前日比0.1%安の1ドル=108円71銭。一時108円63銭まで下落 豪ドル・ドルは0.5%安の1豪ドル=0.6801ドル。中国景気に対する懸念も重しとなり、一時0.6796ドルと10月17日以来の豪ドル安水準 市場関係者の見方大和投資信託調査部の亀岡裕次チーフエコノミスト トランプ大統領が米中合意を否定してみたり、その後も市場が好感するような材料が出てきていないので徐々に不安が高まりつつある 中国では米中貿易摩擦の影響が企業サイドや個人にも出てきている。中国やオーストラリアの指標が弱かっただけに、この後発表のドイツの7-9月のGDP(国内総生産)が2四半期連続でマイナス成長になるとユーロ・円を通じて円高要因になり得る 背景 中国の投資減速、98年以降で最低の伸び-工業生産と小売売上高も低調 日経平均株価は前日比178円安。米中通商協議が難航しているとの観測や中国景気懸念から米株先物も下落 米長期金利は時間外取引で2ベーシスポイント(bp)低下し1.86%台 10月の豪雇用統計は雇用者数が予想外の減少、失業率も横ばい予想に反して上昇 ドイツの7-9月期GDPの予想中央値は前期比0.1%減-4-6月期と同じいつまで続くか、日本株への海外資金流入-買い戻しなら5合目 海外投資家は6週連続で現物株を買い越した。TOPIX(東証株価指数)は8日の取引時間中に昨年10月以来の高値を付けたが、海外からの資金流入が支えた格好だ。市場では、年初から持ち高を外していた外国人投資家の買いとの見方があるが、継続性については見方が分かれる。 東京証券取引所が14日に発表した投資部門別売買動向(東証、名証1・2部等合計)によると、11月1週(5ー8日)の買越額は4602億円。先物を含めると5801億円で5週連続の買い越しとなる。年初から9月27日までに現物株を約3兆円売り越した海外勢は、その後の6週間の買越額が約1.6兆円となった。半分ほど買い戻した計算になる。 大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジストは、海外勢の買い余力はまだ十分あるとみる。石黒氏は現物株1兆円の買い越しの感応度は日経平均で2.5%の押し上げ効果として換算できると試算し、「年末に向けて18年10月2日の日中高値2万4448円近くまで上昇する可能性がある」と数字をはじく。 もっとも14日のTOPIXは続落した。12日まで6営業日連続で上昇したが、息切れ感も出ている。みずほ証券エクイティ調査部の三浦豊シニアテクニカルアナリストは米中貿易協議の難航や香港情勢の緊迫化から海外勢も慎重になっているため、月内は日経平均株価2万2500円までのスピード調整があると話した。 東海東京調査センターの関邦仁ストラテジストも「もはや割安とは言えない」と指摘する。TOPIXの株価収益率(PER)が13年のアベノミクス以降の平均を上回ってきており、「米中貿易合意が確実に署名されるまで、株価の大幅な上昇は見込めない」という。海外勢の買い戻しが続くかは、世界経済に悪影響を与えた通商問題の決着に向かう流れが強まるかどうかにかかっている。(ロイター)コラム:孫氏が本領発揮、ヤフー・LINE統合に大きなうまみ[ロンドン 13日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 検索サービスのヤフーを展開するZホールディングス(4689.T)と無料通信アプリを手掛けるLINEが、経営統合に向けて検討に入った。高齢者の5人に4人が買い物の支払いを現金で行っている日本で、出遅れていたデジタル決済サービスが拡大のチャンスを迎えた。Zホールディングスの親会社・ソフトバンクグループ(9984.T)を率いる孫正義氏が、本領を発揮した形だ。ソフトバンクグループ傘下の通信会社・ソフトバンク(9434.T)は、Zホールディングス(旧ヤフー、時価総額170億ドル)株式の45%を保有している。LINE(時価総額100億ドル)は韓国のネイバー(035420.KS)が73%の株式を保有し、LINEの日本人ユーザー数は8200万人に上る。 ロイターの13日の報道によると、統合計画には孫氏とネイバーのハン・ソンスク最高経営責任者(CEO)が関与した可能性がある。両陣営は折半出資してヤフーとLINEの支配権を持つ新会社を設立する。12日の株価に基づく新会社の企業価値は、約150億ドルだ。 今回の計画は、日本のモバイル決済市場で大規模な提携関係を生み出す点に大きなうまみがある。安倍晋三首相は、デジタル決済の比率を2025年までに現在の2倍の40%に高める目標を掲げている。 LINEのキャッシュレス決済サービス「LINEペイ」の登録者数は約3700万人。今年1─9月の同サービスを使った決済額は80億ドル弱だが、それでも巨大な顧客基盤だ。 ヤフーのスマホ決済サービス「ペイペイ」は、ソフトバンクとインドの決済フィンテック企業Paytm(ペイティーエム)との共同事業で、利用者数は1200万人余り。 LINEペイとペイペイを合わせると、電子商取引最大手の楽天を抜く。統合報道を受けて米市場に上場しているLINEの米預託証券(ADR)は、25%以上も急騰した。 孫氏にとっても実入りは大きい。折半出資の新会社設立によりソフトバンクは事実上、保有するZホールディングス株の半分をLINE株式の36%と交換することになる。アナリストによると、LINEの売上高は今後5年間に、ほぼ3倍に膨らむ見通しだ。 孫氏は、LINEの若年ユーザー層へのアクセスも拡大できる。こうしたユーザーによるLINEでの「スタンプ」送信は昨年、1日平均で約4億回に達した。 何よりもすばらしいのは、LINEのフリーキャッシュフローが、21年にはプラスになり始めるとアナリストが予想していることだ。 共有オフィス「ウィーワーク」への巨額出資で大きな損失を被った孫氏だが、風向きが「追い風」に変わるかもしれない。 ●背景となるニュース *ロイターは13日、関係者2人の話として、検索サービスのヤフーを傘下に持つZホールディングス(HD)と無料通信アプリを手掛けるLINEが、経営統合に向けて調整に入ったと報じた。ZホールディングスLINEはそれぞれ14日、「協議を行っていることは事実」とするコメントを発表した。 *計画によると、Zホールディングスの親会社ソフトバンクとLINEの親会社ネイバーが、折半出資の新会社を設立する。新会社はZホールディングスを傘下に収め、ZホールディングスがLINEとヤフーを運営する。通信大手のソフトバンクはソフトバンクグループの中核会社。 *ヤフーとLINEの経営統合報道を受けて、13日のニューヨーク市場でLINEの米預託証券が25%余り値上がりした。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米ダウ・S&P最高値更新、米中協議巡る懸念なお重しダウは92ドル高の2万7783ドル米中協議が農産物購入を巡り「暗礁に乗り上げた」との米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の報道が懸念材料となった。3指数はいずれも一時、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の発言を受けて上昇していた。パウエル議長はこの日、上下両院合同経済委員会で証言し、米経済の「持続的な拡大」を予想しているとの見解を示した。FRBの利下げや、予想を上回る第3・四半期企業決算、景気底入れの兆候に支援され、米株市場は過去最高値圏にあるが、米中の「第1段階」の通商合意の行方が引き続き、主要な不確定要因となっている。チェリー・レーン・インベストメンツのパートナー、リック・メックラー氏は「中国が引き続きテーマだ。投資家は合意が署名にこぎ着けるかどうか見極めようとしている」と指摘した。市場はまた、トランプ米大統領のウクライナ疑惑を巡る弾劾調査に関連して行われた議会証言や、民主化デモが続く香港情勢など地政学リスクにも注目している。S&P総合500種のセクターでは、公益事業、不動産、主要消費財といったディフェンシブ銘柄が大きく上昇。一方、金融、エネルギー、素材などシクリカル銘柄は下落した。ディズニーは7.3%急伸。12日に開始した動画配信サービス「ディズニー・プラス」の加入者が1000万人を突破した。競合のネットフリックスは3.0%安。歯列矯正製品を扱うスマイルダイレクトクラブは20.3%の大幅安となった。第3・四半期の赤字が拡大したことが嫌気された。リフィニティブのデータによると、S&P総合500種採用企業の第3・四半期決算は、約4分の3が市場予想を上回っているものの、全体では0.5%の減益になる見通し。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.17対1の比率で上回った。ナスダックでも1.35対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は約68億株で、直近20営業日の平均とほぼ一致する水準。日経平均は続落、複数の売り材料 先行きに不透明感日経平均終値は178円安の2万3141円東京株式市場で日経平均は続落。ドル/円の円高基調、中国経済指標の予想下振れ、連日の香港ハンセン指数の下落などが投資家心理を圧迫した。前場はプラス圏に浮上する場面はあったものの、後場には下落し、下げ幅は一時250円を超えた。前日の米国株市場では、ダウ工業株30種とS&P総合500種が最高値を更新した一方で、ナスダック総合が下落した。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が米経済の「持続的な拡大」を予想しているとの見解を示したことは好材料だったが、米中協議が農産物購入を巡り「暗礁に乗り上げた」と米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じたことが嫌気された。朝方に発表された日本の7─9月期実質国内総生産(GDP)は市場予想を下回った。中国の10月鉱工業生産や小売売上高なども予想を下回った。また、香港情勢の悪化に伴い、香港ハンセン指数は連日のマイナス圏。円高以外にもさえない経済指標やアジア株がネガティブ材料となり、日経平均は利益確定の売りが強まった。市場では「午後1時頃に利益確定売りがピークに達して日経平均は急落した。株式市場は不透明感を嫌う。香港情勢は悪化する一方で、もしここから中国が本格的に介入するとなると、米中通商協議にも影響を与えかねない。しばらくは売られるのではないか」(銀行系証券)との声が出ていた。TOPIXも続落。東証33業種では、情報・通信業、水産・農林業以外の31業種が売られた。パルプ・紙、繊維業、ゴム製品などが値下がり率上位となった。個別銘柄では、Zホールディングス(HD)とLINEが買われた。経営統合に向けて調整に入ったことが材料視された。Zホールディングスを傘下に持つソフトバンクグループもしっかり。「ソフトバンクグループは経営統合の中の中核企業。ネガティブな材料が続いた後のグループを強化する好材料が出現したことで、見直し機運が高まりそう。もともと人気株だけに、市場全体にも好影響を与えそうだ」(国内証券)との指摘があった。東証1部の騰落数は、値上がり371銘柄に対し、値下がりが1726銘柄、変わらずが57銘柄だった。メドピアが4連騰、会員数増加で20年9月期営業益は4割増予想 医師向け情報サイトを運営している東証マザーズのメドピア(6095)が4連騰した。前引けは前日比237円(18.3%)高の1530円となった。一時は1559円まで上伸した。 13日の引け後に前2019年9月期連結決算と今20年9月期業績予想を発表した。19年9月期の営業利益は前の期に比べ51.8%増の5億5800万円で着地した。20年9月期の営業利益は8億円(前期比43.4%増)と連続最高益更新を見込む。医療情報コンテンツで会員の裾野を拡大すると同時に、優良なコンテンツを拡充する。法人向けオンライン健康相談や特定保健指導の導入件数を伸ばす。また、東証本則市場への市場変更申請に向けて準備を開始することも明らかにした。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】明日の株式相場戦略=ZHDとLINE統合で変わる業界地図 10月中旬以降、押し目待ちに押し目なしという強い相場だったが、前日の200円安に続き、きょう(14日)も下値を探る展開となった。日経平均株価は5日移動平均線を陰線で下回り、売り煽りが入りやすいタイミングではある。3連休前の今月1日にも日経平均は5日移動平均線を下回ったが、この時は陽線で引けており連休明け後に待っていたのは日経平均の急騰劇(終値段階で401円高)だった。今回は陰線だった点が異なるが、日経平均は後場後半に下げ渋る動きをみせており、果たしてどうなるか。深押しがあっても25日移動平均線が位置する2万2700円どころを下値メドと見ておきたい。 外部環境からのアプローチでは、日替わりで変わる米中協議の進展に対する思惑はあまり意味がないし、中国の経済指標発表を受けた同国経済に対する不安心理も、当の上海株市場はプラス圏を維持しており、これも下げの理由として妥当ではない。香港の政情不安は今の相場にとってはアキレス腱だが、この地政学リスクが日本株に与える影響については、東京市場単独ではなく、あくまでアジア株全面安の状況のなかで取り沙汰されるべきもの。注意は必要だが、今の段階では大勢トレンドを揺るがす材料には至っていない。 それよりも、前場にマーケットが軟化しても「日銀のETF砲不発が投資家の疑心暗鬼を誘っている」(国内証券ストラテジスト)という見方は一理ある。年内まだ2兆円の買い余力を残しながら、ETF買いを温存していることにステルステーパリングを指摘する声もある。日銀の真意を測りかねるというムードが市場関係者の間に漂っていることは否定できない。 個別株をみると、きょうは、ZホールディングスとLINEによる協奏曲が株式市場に響き渡った。両社が経営統合に向けて最終調整に入ったとの報道が投資マネーの集中買いを誘い、ZHDは東証1部売買代金トップで17%高、LINEにおいてはストップ高水準のまま寄る気配もなく、大引けに買い物を残す強烈人気となった。きょう午前中の段階で、両社は協議入りしたことを認めている。両社合併に伴う売上高合計が楽天を上回るということが、今回のストーリーの骨子であり、ソフトバンクグループの孫社長によるネット市場“日本列島総取り”に向けた野望を、株式市場は強く感じ取った形だ。ネット業界の地図が大きく変わるとすれば、それに付随した投資テーマも新たに生じる可能性が高い。 このほか、中小型材料株に対する個人の投資意欲は旺盛。旭化学工業の株価に火がついた格好となった。通常はあまり目立たない銘柄だが、こうした株はいったん確変モードとなれば、圧倒的な割安感を寄りどころに水準訂正の動きが長続きするケースも多い。同社の場合、業績がここ数期にわたって急拡大途上にあることがポイント。「国内だけでみれば前期まで長く営業赤字が続いていたが20年8月期は8期ぶり黒字化することがほぼ確実」(会社側)という。2%の配当利回りを有しながら1株純資産1200円に対し500円前後の株価は合理的なポジションとはいえない。自動車軽量化の流れも追い風に中期的には大幅な水準訂正があって不思議はない。 前日取り上げた建設機材のタカミヤも全体下げ相場のなかで強い足。国土強靱化や東京五輪、大阪万博関連の有力株として綺麗な日足チャートが描かれている。同社独自の「次世代足場」への需要が急増傾向にあり、これが成長ドライバーの役割を担うとなれば、株価の居どころを変えるだけの十分なインパクトがある。 また、英和もチャートだけをみると、怖い位置に見えるがPERやPBRからはむしろ割安感が強い。光通信が大株主の銘柄に変身株が多いというのは、ひとつのアノマリーとしても、売り物薄のなかで継続的な買いが入っていることは見逃せない。 このほか、半導体関連ではダイトーケミックスが急騰後の調整一巡でいい位置にいる。また、顔認証関連では1000円トビ台で売り物をこなしているソリトンシステムズなどが魅力的に映る。 日程面では、あすは9月の鉱工業生産確報値が経済産業省から開示される。海外では、10月の米鉱工業生産、米小売売上高、米輸出入物価など。また、11月のニューヨーク連銀製造業景況感指数も発表される。(中村潤一)昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の9銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の1銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を下げて終了しましたね。円高・株安と悪い傾向になってきました…。(オートカー・デジタル)フェラーリ新型ローマ ポルトフィーノの固定ルーフ版 620ps 内装/スペック(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-連日の3桁下落でセンチメントは悪化、あすは上値の重い展開か 14日の日経平均は続落。終値は178円安の23141円。前日終値近辺からスタートすると、前場では強弱感が入り交じりプラス圏とマイナス圏を行き来した。ダウ平均やS&P500の最高値更新は支援材料となった一方、円高進行は警戒材料となった。11時発表の中国指標が弱く、前引けは55円の下落(23263円)。しかし、昼休みに先物にまとまった売りが出てきたことから、後場はスタートから大きく水準を切り下げる展開。警戒ムードが強まり、250円近く下げる場面もあった。23100円を下回ったところでは押し目買いが入ったものの戻りは緩慢で、引けまでさえない動きが続いた。東証1部の売買代金は概算で2兆2400億円。業種別では情報・通信と水産・農林の2業種が上昇しており、医薬品が小幅の下げにとどまった。一方、パルプ・紙や繊維、ゴム製品が大幅安となっている。証券会社が目標株価を引き上げた東映が急騰。半面、アドバンテストが特段の材料が観測されないなかで、後場に入って急落している。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり371/値下がり1726。経営統合観測が流れたLINEとZHDが大賑わいとなり、LINEはストップ高比例配分、ZHDは17%近い上昇となり、全市場の売買代金トップ(ETFを除く)となった。これに関連してSBやソフトバンクGも上昇した。上期大幅増益のトリドールHDや上方修正を発表したシンクレイヤが急伸。マツオカコーポレーションは下方修正を発表したものの、悪材料出尽くしの見方から、株価は強い買い反応となった。ヤマハ発動機は3Qは2桁の営業減益であったものの、為替影響を除けば実質増益との会社リリースを好感して大幅高となった。一方、LINEとZHDの統合が警戒材料となった楽天が5%超の下落。ZOZOや日産自、OLCが大きく売られた。地合いが悪いなかで決算失望銘柄はたたき売られており、LIFULLやアルファクスFSはストップ安。下方修正を発表したJMCはストップ安比例配分となった。 日経平均は連日の3桁下落。両日とも場中の動きが悪く、5日線(23341円、14日時点、14日終値23141円)も明確に割り込んだ。23500円台に乗せてわかりやすく上値が重くなった後、円高を伴っての失速となっただけに、上昇一服感が強く意識される。週末のあすは外部環境に相当ポジティブな材料がない限りは上値は重いだろう。ただし、23000円より下には25日線(22711円)も走っており、もう一段の下げがあれば押し目を待っていた投資家からの買いが入ると考える。きょうはアドバンテストが後場に急落しているが、欠点の少ないいわゆる「勝ち組」銘柄に関しては、目先は利食い売りに押されやすくなるかもしれない。今回の決算では内容が悪くても悪材料出尽くしで買われる銘柄が多くあった。また、足元では再編に関するニュースが多く出てきており、それまで市場の評価が高くなかった銘柄が急伸している。これらの点から市場では、変わる要素のある「負け組」探しの流れが強まる可能性がある。跳ねる銘柄をピンポイントで見つけることは難しいが、今回の決算を受けて底打ち感が出てきた銘柄など、過熱感のあまりないところにシフトする戦略が有効と考える。NY株見通し- 底堅い展開か 決算発表はウォルマートなど 今晩のNY市場は底堅い展開か。 主要3指数がそろって史上最高値圏で推移を続け、テクニカル指標にも買われ過ぎを示すものが増えているものの、債券から株式への資金シフトが続いていることや、昨日のパウエルFRB議長の議会証言で緩和的金融政策の長期化見通しが確認されたことで底堅い展開が続きそうだ。 今晩は、昨日引け後に弱い10-12月期見通しを発表し、時間外で5%下落したシスコ・システムズがハイテク株の重しとなることが予想されるほか、米中通商関係のヘッドライン・ニュースや寄り前に発表されるウォルマートの決算が注目される。 今晩の米経済指標・イベントは新規失業保険申請件数、10月生産者物価指数、パウエルFRB議長議会証言のほか、クラリダFRB副議長、エバンズ米シカゴ連銀総裁、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、ブラード米セントルイス連銀総裁、カプラン米ダラス連銀総裁の講演など。 企業決算は、寄り前にウォルマート、バイアコム、引け後にエヌビディア、アプライド・マテリアルズなどが発表予定。(執筆:11月14日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=弱含みの展開か 15日の東京株式市場は、弱含みの展開となりそう。14日の日経平均株価は続落したが、日経平均株価が続落するのは10月2-3日以来、約1カ月半ぶり。それだけ強い足取りを続けてきただけに、ある程度の調整は致し方ないところか。米中貿易交渉の進展がみられないなか、政府への抗議活動が過激化している香港情勢もあり、目先的には利益確定売りが優勢となることも想定される。市場では「今月1日の高値(2万2852円)と5日の安値(2万3090円)の間に空けたマドが、下値として意識されそう」(中堅証券)との声も聞かれた。 14日の東京株式は、前日比178円32銭安の2万3141円55銭と続落して取引を終えた。後場に入り下げ幅を拡大し、一時、同257円71銭安の2万3062円16銭を付け、心理的なフシ目の2万3000円に接近する場面もみられた。東京証券取引所が14日引け後に発表した、11月第1週(5-8日)の投資部門別売買状況によると、海外投資家は金額ベースで6週連続となる4602億円の買い越しだっだ。今晩のNY株の読み筋=ウォルマートの決算に注目 きょうの米国株式市場では、ウォルマートの決算に注目したい。同社の株価は年初来市場で約30%上昇するなど堅調だが、現値は市場コンセンサスより若干割安で買い戻し余地が残されている。好決算や年末商戦に向けた明るい材料が示されれば、今後発表が目白押しとなる小売企業決算への期待も膨らみそうだ。 また、引け後には半導体大手のエヌビディア、アプライド・マテリアルズの決算も控えている。米中貿易交渉をめぐる動向と合わせて注目したい。<主な米経済指標・イベント>10月PPI(生産者物価指数)、米通商拡大法232条による自動車関税の発動期限ウォルマート、エヌビディア、アプライド・マテリアルズなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(株探ニュース)出遅れ「バイオ株」に復活機運、国際規格制定で再生医療関連に脚光 <株探トップ特集>―iPS細胞の活用に期待膨らむ、株価低位に位置しテクニカル的な投資妙味も― 日経平均株価は10月以降、年初来高値を更新し上昇基調を強めている。景気敏感株を中心に相場は上昇しているが、出遅れが目立つのがバイオ関連株だ。人工多能性幹(iPS)細胞関連株は低位で投資妙味が膨らんでいる。そのなかiPS細胞などを使った「再生医療」には新たな進展がみられ始めている。再生医療の現状を探った。●iPS細胞による心臓病治療など期待、「再生医療実現プロジェクト」に注目 再生医療とは、胚性幹(ES)細胞、iPS細胞や体性幹細胞などの様々な細胞を用いて、病気や事故によって失われた体の組織を再生することを目指して提案された医療技術。2014年9月に世界で初めてiPS細胞を用いた移植手術が行われると、18年5月には、大阪大学が申請していたiPS細胞を使った心臓病の臨床研究計画を厚生労働省が条件付きで了承している。心臓の疾病にiPS細胞の再生治療を行うのは世界初となる。 これまで有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるなど、再生医療に対する期待は高い一方、新しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要がある。国が定める「医療分野研究開発推進計画」では医薬品創出プロジェクト、医療機器開発プロジェクト、革新的医療技術創出拠点プロジェクトなど、9つの総合プロジェクトが掲げられており、その一つに再生医療実現プロジェクトがある。 再生医療実現プロジェクトでは、iPS細胞などを用いた再生医療の迅速な実現に向けて、基礎から臨床段階まで切れ目なく一貫した支援を行う。また、再生医療関連事業のための基盤整備並びに、iPS細胞などの創薬支援ツールとしての活用に向けた支援を進め、新薬開発の効率性の向上を図るプロジェクトとしている。●ISOから世界初の国際規格が発行、再生医療の「共通言語」も規定 この再生医療に関して昨年末に大きな進展がみられた。国際標準化機構(ISO)から細胞製造に関する世界初の国際規格が発行されたのである。これは、経済産業省の委託を受けて再生医療分野の国際標準開発活動を行っている再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)が中心となり、ISO/TC 276(国際標準化機構専門委員会 276)に提案し開発を進めていた。第1部「一般要求事項」、第2部「補助材料のサプライヤーのためのベストプラクティスガイダンス」、第3部「補助材料のユーザーのためのベストプラクティスガイダンス」からなり、FIRMは第1部を起草するとともに、日本・米国・英国・ドイツなどの専門家による検討・開発作業をとりまとめ、3部作の同時発行を達成している。 日本は第1部の「一般要求事項」を担当したが、これは用語とその定義、および誰が何をしなければならないかを規定している。つまり、再生医療の「共通言語」となるものとされている。再生医療の実用化、産業化には多くの関係者(企業)が関わるだけに、同じ目線で議論を重ね共通理解を促進、あるいは保証するための「言語」が不可欠とされている。今回の国際標準が発行されたことで、培地に代表される原材料の規格から、研究・開発・製造・物流・医療・規制など関連するステークホルダー間の「共通言語」として使われることになり、再生医療の一層の進展に対する貢献が期待される。更に、今後も再生医療分野の国際標準化が推進されることで、同事業に関連する企業の成長期待も高まることになりそうだ。●セルソースやヘリオス、セルシードなどに注目 再生医療の関連銘柄となると、製薬企業やバイオ企業が多く挙げられるだろうが、10月28日に上場したセルソース [東証M]は、変形性膝関節症の再生医療のため、患者自身の脂肪から幹細胞を培養している。同関節症の患者は国内3000万人弱とされている。株価は上場後に2倍に上昇し、足もとでは過熱感も警戒されるが、押し目買い意欲は強そうである。 ヘリオス [東証M]は、理化学研究所より独占的ライセンスを受け、iPS細胞由来の網膜色素上皮細胞をiPSC再生医薬品として移植することによる加齢黄斑変性の治療法の開発を行っているほか、大日本住友製薬 は日本国内における共同開発パートナーである。 また、10月には「再生医療JAPAN2019」が開催され、そこで注目されていたのが、セルシード [JQG]の細胞を1枚のシート状にして患部に移植するための技術「細胞シート工学」や独自に開発した細胞培養器材。富士フイルムホールディングス は、創薬支援の製品を展示しており、ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング [JQG]と連携して提供する。 その他、日立製作所 はiPS細胞の自動培養装置、ニコン は細胞の育成状況の画像反転システム、ソニー は細胞の動きを定量的に測定する装置などを出展しており、製薬企業にとどまらず、iPS細胞の利活用に向けた動きが広がりをみせている。(yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、108円台後半(14日朝)【ニューヨーク時事】14日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下などを背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は1ドル=108円台後半で強含んでいる。午前9時現在は108円55~65銭と、前日午後5時(108円76~86銭)比21銭の円高・ドル安。 米中貿易協議の進展をめぐる不透明感などを背景にこの日はアジア、欧州株式相場が総じて下落。投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産としての円が買われている。 米労働省が発表した10月の卸売物価指数(PPI)は全体が前月比0.4%上昇、エネルギーと食料品を除いたコア指数は0.3%の上昇だった。同時に発表された米新規失業保険も前週比1万4000件増の22万5000件。いずれもほぼ市場予想通りと見なされ、相場の反応は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.0995~1005ドル(前日午後5時は1.1001~1011ドル)、対円では同119円40~50銭(同119円73~83銭)。(了)〔米株式〕NYダウ、もみ合い=ナスダックは続落(14日朝) 【ニューヨーク時事】14日のニューヨーク株式相場は、強弱材料が入り交じる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比10.69ドル高の2万7794.28ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は15.62ポイント安の8466.48。(了) 今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の7銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では2銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.14
コメント(0)
-
11月13日(水)…2019ラウンド85…
11月13日(水)、晴れ~曇り…。そんな本日は7時頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時30分頃には家を出る。本日はホーム1:GSCCの西コースで開催のプロアマ研修会に参加させていただきました。10時20分スタートとのことですからゆっくりです。9時頃にはコースに到着。フロントで記帳して、来月のプロアマのエントリーを済ませて、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…イマイチ…。本日の競技は西コースのブルーティー:6613ヤードです。ご一緒するのは、S君(10)とOさん(20)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:3.0.2.1.0.1.0.0.0=43(14パット)1パット:4回、3パット:0回、パーオン:1回。1番ロングの1打目をシャンクして右斜面へ…、2打目は斜面の木に当たって木の根っこへ…、3打目は出しただけ…、4打目でフェアウェイへ…、5打目でグリーン40ヤード地点へ…、6打目でグリーンオンして、2パットの素トリ…。もう何のチェックをする気力も起きません…。ダラダラゴルフです…。10番のスタートハウスでおでんをいただく。IN:1.1.0.1.2.0.0.0.1=42(17パット)1パット:3回、3パット:2回、パーオン:2回。13番ミドルの1打目は頭を叩いてボールは前の谷へ…。14番ショートの1打目はへなちょこボールでグリーン右手前へ…、2打目アプローチはグリーンに乗っただけ…、そこから3パットの素ダボ…。18番ミドルは2オンしてピン右5mのバーディートライ…からの3パット・ボギー…。ひどいです!43・42=85(9)=76の31パット…。スコアカードを提出して、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.6kg,体脂肪率19.2%,BMI22.0,肥満度0.0%…でした。御座候のお茶でおやつタイム。夕方からはいつもの美容室でのヘアカットですね。それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には13人が参加して、トップは80(16)=64とのこと。僕は85(9)=76で5位。皆さん…叩いたようですね…。1USドル=108.90円。1AUドル=74.31円。昨夜のNYダウ終値=27691.49(0)ドル。本日の日経平均終値=23319.87(-200.14)円。金相場:1g=5673(+2)円。プラチナ相場:1g=3469(-19)円。(ブルームバーグ)伊フェラガモ、7ー9月の売上高が45%減ー香港の抗議活動の影響で イタリアのファッションブランド、サルバトーレ・フェラガモの香港での7-9月(第3四半期)売上高は前年同期比45%減となった。香港で数カ月にわたり続いている抗議活動の影響で、観光客や地元住民の支出が抑えられた。 同社の売り上げ減は、他の有名高級ブランドへの影響を上回った。「ルイ・ヴィトン」や「ジバンシー」のブランドを持つフランスのLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは香港での7-9月の売上高が25%減、グッチを抱えるケリングは35%減との概算を発表していた。 フェラガモの12日の発表資料によると、中国での1-9月の売上高は為替変動の影響を除いて15%増となり、中国本土での力強い成長が香港での売り上げ減を相殺した格好だ。付加価値税の引き下げにより、中国の消費者は既に、香港などの観光地へ旅行に行き買い物をするよりも、高級品をより多く国内で購入するようになっていた。日本株は反落、米中貿易合意の期待がやや後退-素材や石油安い 13日の東京株式相場は反落。トランプ米大統領が米中貿易の部分合意がなければ対中関税を引き上げると述べ、協議の先行きに対する楽観的な見方が後退した。貿易摩擦による世界景気への影響が懸念され、石油関連や鉄鋼など素材中心に幅広い業種が下げた。 TOPIXの終値は前日比9.34ポイント(0.5%)安の1700.33-7営業日ぶりに反落 日経平均株価は同200円14銭(0.9%)安の2万3319円87銭 <きょうのポイント> 中国との包括的貿易合意の第1段階がまとまらなければ対中関税を引き上げ-トランプ大統領 米中首脳会談の日程などには言及せず 合意が近く実現する可能性はある 香港金融街に再びデモ参加者-保安局長は「想像もできない」結果警告 香港ハンセン指数が大幅下落、抗議活動拡大で 三井住友信託銀行の瀬良礼子マーケット・ストラテジストは、トランプ大統領のスピーチは「注目されていた割にいつもの発言だった」と総括。マーケットは次の手掛かりになるような内容が出るかとみていたとし、「最近大きく上昇した反動で下落している」と述べた。 小安く取引を開始した株価指数は徐々に下げ幅を広げた。混乱が続く香港のハンセン指数が一時2.2%安となりアジア株は軒並み下落。為替市場ではドル・円相場が一時1ドル=108円87銭と円高で推移し、リスク資産への投資が手控えられた。 東証1部33業種は鉄鋼、石油・石炭製品、鉱業、保険、食料品、サービスが下落率上位 繊維製品や証券・商品先物取引は上昇(会社四季報オンライン)(ロイター)米S&Pとナスダック小幅高、トランプ氏通商問題で詳細語らずダウは前日比横ばいの2万7691ドル[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米国株式市場は、S&P総合500種とナスダック総合が取引時間中に過去最高値を更新した後、小幅高で終了した。トランプ米大統領はこの日の講演で米中の「第1段階」の通商合意署名は間近だと表明したものの、通商交渉の詳細については明らかにしなかった。ダウ工業株30種は変わらず。トランプ大統領は12日、ニューヨークのエコノミック・クラブで行った講演で、中国の貿易慣行への批判も繰り返した。ホライズン・インベストメント・サービシズのチャック・カールソン最高経営責任者(CEO)は「市場は貿易に関してもう少し明確な手掛かりを期待していたが、得られなかったようだ」と指摘。その上で「市場は、貿易に関するトランプ氏の発言に過剰反応を示さないように若干なり始めている」との見方を示した。この日はS&P総合500種を構成する大半のセクターが上昇。ヘルスケアセクターの上昇率が最も高かった。不動産セクターは0.8%安で最大の下げとなった。娯楽大手ウォルト・ディズニーは1.3%上昇。この日開始した新動画配信サービス「ディズニー・プラス」に強い需要がみられていると明らかにしたことが好感された。同市場を主導するネットフリックスは0.7%下落した。産業用自動制御システムを手掛けるロックウェル・オートメーションは10.5%急伸。四半期決算と2020年の利益見通しが市場予想を上回った。メディア大手CBSは3.6%安。四半期売上高が市場予想を下回った。CBSと統合予定のバイアコムも3.8%下落した。リフィニティブによると、S&P総合500種採用企業の第3・四半期決算は決算シーズンが終盤に近付く中、約4分の3が市場予想を上回っているものの、全体では0.5%の減益になる見通しだ。今週は、ウォルマート、エヌビディア、シスコシステムズなど主要企業の決算や、一連の経済指標が発表される。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.04対1の比率で上回った。ナスダックではほぼ同数だった。米取引所の合算出来高は約66億株。直近20営業日の平均は68億株。日経平均は反落、香港情勢を嫌気 後半は下げ渋る日経平均終値は前日比200円14銭安の2万3319円87銭[東京 13日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は反落した。前日の上昇の反動などで売りが先行して始まった後、混乱する香港情勢を嫌気して香港ハンセン指数や上海総合指数が軟調に推移すると、日経平均も一時250円近くまで下げ幅を拡大した。ただ、外為市場でドル/円が109円台で推移するなど、売り崩すだけの材料は見当たらず、後半は下げ渋った。 香港では12日、警察が金融街の中環(セントラル)や2大学の構内で催涙ガスを噴射するなど、警察とデモ隊の衝突による混乱が続いている。 テクニカル面では、前日までの上昇によって過熱感が生じていたため、「これまで目立った押しがなかったので、リズム的にみると、ここでの押しは歓迎できる」(国内証券)との声さえあり、悲観する雰囲気は感じられない。 市場では「懸念される香港情勢も大ごとにはならないとの見方が多いようだ。ただ、商いが細っていることが気がかり。目先は調整局面となりそうだ」(SBI証券・投資調査部長の鈴木英之氏)との指摘もある。 TOPIXは7日ぶり反落で、前日比0.55%安。東証33業種では、繊維業、証券業を除き31業種が値下がりした。東証1部の売買代金は2兆1558億7300万円。 個別では、指数寄与度が大きいファーストリテイリングが軟調。主力の輸出関連株に安い銘柄が目立つ中で、アドバンテスト、いすゞ自動車が散発高した。 東証1部の騰落数は、値上がり479銘柄に対し、値下がりが1606銘柄、変わらずが68銘柄だった。(株探ニュース)【市況】明日の株式相場戦略=全般上昇一服も材料株は花盛り ようやくというべきか、ここまで超強調展開を続けていた相場がブレーキを踏んだ。米中協議に対する不透明感や香港の政情不安、中国経済を取り巻く思惑など背景はいくつかあるが、それらを後付け講釈にして、実際のところはこれまで走り続けてきた相場が“いったん足を止めて深呼吸”というのが本質に近い。 トランプ米大統領の講演内容については、もしその後に相場がリスクオンに傾いた場合は、「第1弾の部分合意の署名が間近であると強調した」ことを好感したという解釈に変わっていたはず。首脳会談の具体的なスケジュールに言及しなかったからマーケットが失望したというのは、当を得ているとは思えない。香港の政情不安についても分析は難しく、要はハンセン指数の動向を注視しておくということに尽きる。ハンセン指数は75日移動平均線上に位置しており、まだ現段階では何ともいえない部分がある。 きょう(13日)の東京株式市場は、日経平均株価が先物主導で一時250円近い下げをみせ、後場は今月に入って初となる日銀のETF買いの思惑から下げ渋ったが、戻りは限定的だった。大引けは200円安。日経平均寄与度の高い内需系値がさ株が先物絡みで売られた関係もあって、TOPIX と比べても日経平均の下げの方が大分深かった。ざっくり言えば、前日の先物市場でのアルゴの歯車がそのまま逆回転したという構図だ。 ちなみに、今回の強力な上昇波形成は10月中旬からスタートしているが、日銀はその出発地点の押し目形成時、10月9日に704億円の買いを入れた後はETF砲をこれまでに一度も轟かせていない。つまり、1カ月以上ご無沙汰の状態だった。きょうは、通常であれば前引け時点でTOPIXが0.5%下げているので買いを入れるところだが、(本稿執筆時には確認できないが)見送られた可能性がある。間断なくETF買いを入れるような地合いは困るが、その存在すら忘れさせるような地合いもある意味変調ともいえる。上昇相場継続には屈伸運動でいうところの屈む局面も必要となる。とりあえずは、日本時間深夜、午前1時頃に行われるパウエルFRB議長の米議会(上下両院の経済合同委員会)での証言にマーケットの関心が高いようだが、これが相場の波紋を変えるとは考えにくい。押し目があれば粛々と買い向かうというスタンスでよいのではないか。 個別では、前日の繰り返しになるがクラウド関連株周辺に強い株価の動きを示すものが多い。景気停滞への警戒感が強いなかも、今回の四半期決算でもソフト開発やシステムの提供などクラウドサービスに絡むビジネスを展開する企業の業績数値が総じて好調であることが改めて確認されている。量子コンピューター関連で異彩の連騰を続けるテラスカイは2月決算企業だが、同社も米セールスフォースのクラウド導入支援・開発に特化した企業であり、株価評価の根元には会社側の想定を上回る収益拡大がベースにあることはいうまでもない。 民間だけではなく、各省庁もクラウド導入を一斉に進める構えにあり、来秋をメドに基幹システムのクラウド化を本格化させる算段だ。同テーマではセールスフォースのクラウド基盤を活用した保険事業者向け業務システム構築を展開するネオスなども既に人気化している。同社はクラウド型電子マネー管理システムなども手掛けており、投資マネーの琴線に触れたようだ。 このほか、個別材料株の物色テーマには事欠かない状況で花盛りといっても過言ではない。例えばリチウムイオン電池関連では電子計測機器の専門商社の英和が穴株としてここ一気に浮上、実質青空圏で足が軽い。同銘柄は大株主に光通信が入っていることからも思惑を呼びやすい。また、応用技術などの物色人気化で、国策テーマである国土強靱化にもスポットライトが当たっている。そのなか、“次世代足場”が本格的に軌道に乗ってきたタカミヤなどにも妙味が感じられ、ここでの押し目形成場面は注目しておく価値ありとみる。 日程面では、あすは取引開始前に内閣府から発表される7~9月のGDP(速報値)が注目される。また、5年物国債の入札も予定されている。海外では中国の重要経済指標が相次ぎ、10月の工業生産、10月の小売売上高、10月の都市部固定資産投資などが足もとの中国景気実勢を知るうえで重視される。このほかでは、10月の米卸売物価指数(PPI)や、7~9月の独GDPなども発表される。(中村潤一)本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の3銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を下げましたね。(msn)(ブルームバーグ)日産株一時4.5%安、3カ月ぶり下落率-営業益下方修正し配当も減額(ブルームバーグ): 日産自動車の株価は13日、一時前日比4.5%安の682.7円と8月5日以来の日中下落率となった。前日に今期(2020年3月期)の業績見通しの下方修正したほか、中間配当の大幅減額や年間配当予想を撤回したことなどが嫌気された。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の杉本浩一シニアアナリストは12日付のリポートで、中間期の減配や配当計画の取り下げは「当面ネガティブ視される可能性が高い」と指摘。 SBI証券の遠藤功治シニアアナリストは12日の取材に7ー9月期の自動車部門は赤字であるものの赤字額は縮小しており、下期(10-3月期)の営業利益はわずかながら前期より増益予想で、「大底は打ったとの印象」はあると述べた。 マッコーリー証券のジャネット・ルイスアナリストらは英文リポートで次期最高経営責任者(CEO)昇格が決まっている内田誠常務執行役員ら若い世代の経営陣が経営立て直しにつながる事業改革を実行することに期待しているとしながら、それには数年という時間が必要だろうとの見方を示した。 日産は12日、今期(2020年3月期)の営業利益見通しを従来の2300億円から1500億円に下方修正。売上高と純利益の見通しも引き下げた。中間配当を昨年より18.5円引き下げ1株あたり10円とし、従来40円としていた年間配当予想を取り下げて未定とした。業績予想修正の要因として為替レートの円高傾向や今後の自動車需要の低迷傾向が継続すると想定されることなどを挙げていた。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-前日の上昇を打ち消す大幅下落、パウエルFRB議長発言に要注目 13日の日経平均は反落。終値は200円安の23319円。米国株は小動きであったが、寄り付きから80円程度の下落と弱めのスタートとなり、その後も売りに押される展開。前日に急伸した反動か、前場のうちに下げ幅を200円超に広げた。後場は売り圧力が和らぎ下値は限定的となったものの、低空飛行が継続。取引終盤には戻りを試す動きも見られたが、引けにかけては売り直された。全般的に売り優勢ではあったが、ジャスダック平均はプラスで終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆1500億円。業種別では上昇は繊維と証券・商品先物の2業種のみで、ほか、化学の下げが限定的。一方、鉄鋼や石油・石炭、鉱業など市況関連セクターが大きく売られた。日経新聞電子版で東芝による完全子会社化観測が報じられたことを受けて、西芝電機とニューフレアテクノロジーがストップ高。東芝プラントシステムが急騰した。半面、1Qが減収減益となったロジザードが後場下げに転じて大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり479/値下がり1606。通期の純利益見通しを引き上げた富士フイルムが6%超の上昇。決算が好感されたGMOインターネットや協和エクシオ、トーヨーカネツが大幅高となった。曙ブレーキは継続疑義の注記解消を受けて急伸。筆頭株主の兼松によるTOBに賛同の意を示したカネヨウはストップ高比例配分となった。また、アドバンテストや東京精密、レーザーテックなど、半導体株の一角に強い動きが見られた。一方、下方修正を発表したパーソルHDやニチイ学館、じげんが大幅安。そーせいGは3Q累計で営業黒字を達成したものの、市場の反応は強い売りとなった。ユーザベースは3Qの営業赤字転落に加えて第三者割当による新株発行が嫌気されて急落。オプトランは証券会社のリポートが売り材料となり大きく値を崩した。 日経平均はきのうが188円高できょうは200円安。両日とも明確な要因がはっきりせず、高値圏で乱高下した格好となった。基調は強いが高値警戒感もくすぶっており、強弱感が交錯している。今晩米国ではパウエルFRB議長の議会証言が注目されるが、タイミング的にはこれを材料に、上か下かに大きな動きが出てくる可能性がある。米中の対決色が強まらない限りは、足元の上昇トレンドに変化はないであろうから、下に振れた場合でも調整は短期にとどまると考える。節目の23000円がサポートになると期待できるが、深押しした場合には25日線(22641円、13日時点)あたりまでの下げはみておいた方が良い。一方、上に振れた場合は、短期的な過熱感を内包しながらも24000円を目指す展開になると考える。その場合、為替が株高を後押しする可能性が高く、半導体や自動車関連など、大型の外需が上昇のけん引役になると予想する。NY株見通し- 米10月CPI、パウエルFRB議長議会証言に注目 今晩のNY市場では金融政策の先行き見通しが焦点か。10月29-30日のFOMCで利下げの打ち止めが示唆されたものの、利上げについてはパウエルFRB議長がハードルが高いとしたことで、緩和的な金融政策の長期化見通しが強まった。 今晩は、寄り前に発表される米10月消費者物価指数(CPI)が市場予想並みにとどまり、午後のパウエルFRB議長の議会証言もハト派的な内容となれば、安心感が広がりそうだ。米中通商合意の行方を巡り関連報道にも引き続き要警戒か。 今晩の米経済指標・イベントは10月CPI、パウエルFRB議長議会証言のほか、MBA住宅ローン申請指数、10月月次財政収支など。企業決算は、寄り前にアプライド・マテリアルズ、引け後にシスコ・システムズなどが発表予定。(執筆:11月13日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)今晩のNY株の読み筋=パウエルFRB議長の議会証言に注目 きょうの米国株式市場は、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の議会証言をにらんだ動きが想定される。 10月FOMC(米連邦公開市場委員会)では、声明文で予防的な利下げの停止が示唆された一方、直後にパウエル議長が会見し当面の利上げ再開の可能性を否定した。年内の政策金利観測は政策決定に幅を持たせた状態といえる。一方、きょうの議会証言の前には米10月CPI(消費者物価指数)の発表もあり、インフレ鈍化を示す結果となれば、利下げ観測が再燃する可能性もある。トランプ米大統領がきのうの講演でFRBの利下げは遅すぎると非難したことも利下げ期待を促すかもしれない。第1弾合意が間近と伝えられる米中貿易交渉もいまだ不透明なままだ。 こうした中、パウエル議長の現時点での発言が10月FOMCからどう変化するかに注目が集まる。<主な米経済指標・イベント>10月CPI、10月財政収支、パウエルFRB議長が米議会で証言シスコシステムズ、ネットアップなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、108円台後半(13日朝) 【ニューヨーク時事】13日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言などを前に様子見ムードが広がり、1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は108円75~85銭と、前日午後5時(108円97銭~109円07銭)比22銭の円高・ドル安。 円ドル相場は12日夜以降、109円付近でもみ合っていたが、13日未明からは日欧株安や米長期金利の低下などを背景に円高・ドル安方向に振れ、ニューヨーク市場は108円84銭で取引を開始した。 米労働省が早朝に発表した10月の消費者物価指数(CPI)は、季節調整後で前月から0.4%上昇。変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコア指数は0.2%上昇した。市場予想(ロイター通信調べ、中央値)は全体が0.3%上昇、コアが0.2%上昇で、ほぼ想定内の結果。また、この日はパウエルFRB議長の議会証言をはじめ、FRB高官による講演が相次ぐこともあり、動きづらい地合いとなっているもようだ。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1000~1010ドル(前日午後5時は1.1004~1014ドル)、対円では同119円70~80銭(同119円93銭~120円03銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、下落=ナスダックは反落(13日朝) 【ニューヨーク時事】13日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言を控え、下落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比24.04ドル安の2万7667.45ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は22.68ポイント安の8463.41。(了) (yahoo)(ロイター)ヤフーとLINE、経営統合で調整=関係筋[東京 13日 ロイター] - ヤフーを傘下に持つZホールディングス(HD)<4689.T>とSNSサービスのLINEが、経営統合に向けて調整に入った。関係筋が13日、明らかにした。月内にも基本合意する方向。Zホールディングスを傘下に収めるソフトバンク<9434.T>と、LINEの親会社である韓国ネイバー<035420.KS>を含めた交渉をしている。ソフトバンクとネイバーが折半出資する共同出資会社を設立し、ZHDの筆頭株主になる統合案などが検討されている。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の6銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では2銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.13
コメント(0)
-
11月12日(火)…
11月12日(火)、晴れです。朝は濃い霧が立ち込めていましたが、やがては青空が広がりました。そんな本日は7時頃に起床。昨日は本当に良く眠りました…。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時15分頃には家を出る。本日のアルバイト先も近いです。助かります。拘束は8:45~11:45とのこと。午前勤務です。時間通りに仕事を終えて、帰宅して、関市の「助六」さんへGo!いつも通りのざると田舎を1枚ずついただく。美味しいです!!帰宅して、雑務処理して、しばらく休憩です。1USドル=109.11円。1AUドル=74.70円。昨夜のNYダウ終値=27691.49(+10.25)ドル。現在の日経平均=23420.80(+88.96)円。金相場:1g=5671(-19)円。プラチナ相場:1g=3488(-51)円。(ブルームバーグ)債券バブル破裂が次の米リセッションの引き金となる公算大-BofA 2020年代に米経済がリセッション(景気後退)に陥る場合、その引き金として最も可能性が高いのは債券市場バブルの巻き戻しだと、バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストらが予想した。 トミー・リケッツ 、マイケル・ハートネット両氏を含むストラテジストらは11日のリポートで、11兆ドル(約1200兆円)余りのマイナス利回り債券の存在や約1%のオーストリア100年債利回り、記録的低水準になお近い世界の債券利回りを指摘。 今後数年には、中央銀行が「ひもを押す」という「政策の無能」に陥ることが金利ボラティリティーの急上昇を招き、「最低の金利と最大の利益」という10年にわたる強気の組み合わせを終わらせると共に「資産価格のピーク」を示すだろうとストラテジストらは分析。さらに、当局が現代貨幣理論を実践しインフレ上昇を招くまで国債を発行するなどの政策ミスを犯すことも要因になると指摘した。 「利回りの無秩序な上昇は、ウォール街がレバレッジを減らす際に大きな痛みを引き起こす可能性が高く」、必然的にその直後に、経済にさらなる痛みをもたらすだろうと続けた。債券市場のバブルは向こう10年の間に巻き戻すとの見通しの下で、債券バブル破裂のシナリオに対して、金融資産に代わり金や米財務省短期証券(Tビル)、実物資産を介してヘッジすることを勧めた。ソフトバンクG出資のオンライン銀行、ゴールドマンが「売り」判断 ゴールドマン・サックスはブラジルのオンライン銀行バンコ・インターの投資判断を、「売り」で開始した。モルガン・スタンレーに続き弱気見解を示した格好だ。第3四半期決算が予想を下回ったことで、顧客ベースの急拡大を収益につなげる計画に疑念が生じている。バンコ・インターは、ソフトバンクグループが一部株式を保有する。 ゴールドマンのアナリスト、ティト・ラバルタ氏は「バンコ・インターの成長見通しについて当行は前向きだが、現在の株価バリュエーションを正当化するには顧客ベースを効果的に収益化することが課題になるだろう」とリポートで指摘。優先株の目標株価は11レアルとし、現水準から約27%の下げ余地があることを示唆した。 11日のサンパウロ市場でバンコ・インター株は一時、前週末比3.6%安となった。先週は週間ベースで9%余り下落した。クオンツファンド主導か、2013年以来の規模の日本国債売り 2013年以来の規模の日本国債売りの背景に、クオンツヘッジファンドの存在があるようだ。 未決済ポジションやファンドフロー、利回りの状況は、トレンド追随のクオンツ戦略ファンドである「コモディティー・トレーディング・アドバイザーズ(CTA)」が10年物日本国債先物で持っていた大きなロング(買い持ち)ポジションを縮小した可能性を示唆している。 モルガン・スタンレーMUFG証券の杉崎弘一債券ストラテジストは、最近の日本国債の一斉売りはCTAが日本国債先物を大量に売却したことが要因のようだと述べた。 日本の10年債利回りは先週、12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)急上昇し、6年余りで最大の上昇となった。クオンツの関与を示すデータが以下にある。 先物主導 CTAファンドが好む先物の原資産である7年物国債の利回りは先週12bp上昇し、さまざまな年限の中で最も売られた債券だった。 ロングポジション 2013年までさかのぼってブルームバーグがまとめたデータによれば、日本国債先物とヘッジファンド・リサーチのマクロ・CTA指数との90日ローリング相関は9月に過去最高に達した。この相関の高さからは、ファンドが最近の売りの前に大きなロングポジションを組んでいたことがうかがわれる。 外国勢フローデータ 日本取引所グループの週次データによると、外国ファンドは6月と8月の大量購入後、11月1日終了週には6カ月で最大の売りを出した。 未決済ポジションの減少 過去1カ月に日本国債相場が下落するとともに未決済の先物ポジションが1万枚余り減少した。先物でロングポジションを保持していた投資家が売っていたことが示唆される。 杉崎氏によると、未決済ポジションが減り続けている状況はCTAがまだロングを完全に解消していないことを示唆している。テクニカル指標次第ではバリュエーションにかかわらず1段の先物売りの可能性があるという。(ロイター)米グーグル、ヘルスケア情報に関するクラウドで医療会社と提携[11日 ロイター] - 米アルファベット傘下のグーグル(GOOGL.O)は、ヘルスケアに関する情報のクラウドコンピューティングで米医療サービス会社アセンションと提携する。アセンションが11日発表した。 アセンションはグーグルのクラウド事業では医療部門で最大の顧客となる。 米ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は先に、グーグルがアセンションと組み、米21州で多数の米国人の医療に関する個人情報の収集に乗り出すと報じていた。 アセンションの声明によると、グーグルとの提携では患者の安全性向上と治療効率改善のため、人工知能(AI)や機械学習の活用も検討する。グーグルとしては、高収益の可能性を秘めたAIツールの強化に役立つ可能性がある。 グーグル・クラウドのトーマス・クリアン最高経営責任者(CEO)は就任1年目の優先事項として、ヘルスケア部門を含む6業種の最大手級企業からのビジネス獲得を挙げていた。 グーグルはここ数年、MRI(磁気共鳴画像)装置などから患者の個人情報を自動的に分析するためのAI開発を進めてきた。 アセンションは米国内で150件の病院と50件余りの高齢者向け施設を運営している。 グーグルは11日、ブログで「(患者のデータを)グーグルの消費者データと統合することは不可能であり、統合はしない」と表明。 グーグル・クラウドの幹部は 「(アセンションは)データの管理者であり、当社はアセンションに代わってサービスを提供する」と説明した。 アセンションは声明で、今回の提携が、医療情報を保護する「医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律(HIPAA)」を順守していると表明した。 米S&Pとナスダック反落、貿易巡る懸念で ダウは横ばい[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米国株式市場はS&P総合500種.SPXとナスダック総合.IXICが下落して取引を終えた。トランプ米大統領の発言を受け、米中通商協議を巡る懸念が再燃した。ダウ工業株30種.DJIは、ボーイング株(BA.N)の上昇に支援され、ほぼ変わらずだった。 主要株価3指数は前週末8日にそろって最高値を更新していた。 市場ではこのところ、米中の「第1段階」の通商合意への期待が主な支援要因となってきたが、トランプ大統領は9日、中国との協議は望んでいたよりもゆっくりとしたペースで進んできたと指摘し、米国にとり適切な内容である場合のみ合意を受け入れるとの考えを示した。[nL3N27Q0IV] 香港でのデモ隊と警察の衝突も、市場のセンチメントを圧迫した。[nL3N27R0A2] ベアードの投資ストラテジスト、ウィリー・デルウィッチ氏は「ネガティブなニュースのヘッドラインが5週続伸した後の値固め要因になった」と指摘。「最大のリスクは過剰な楽観で、数日の値固めを通じてそれがある程度緩和すれば、市場全般にとって健全な展開となる」との見方を示した。 S&P総合500種は前週まで5週連続で値上がりしていた。 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの首席投資ストラテジスト、マイケル・アローン氏は「株式市場には多くのポジティブなニュースが織り込まれている」と指摘。米連邦準備理事会(FRB)の利下げや、比較的低い期待を上回っている第3・四半期決算、景気底入れを示唆する経済指標、貿易摩擦解消の可能性への期待などに言及した。 ボーイングは4.5%高。墜落事故で運航が停止されている737MAX機について、今後数週間に米航空規制当局から運航再開の承認が得られる見込みで、来年1月には運航を再開できるとの見通しを示したことが好感された。[nL4N27R3O5] ボーイングはダウ工業株30種の構成銘柄でウエートが最大で、同社株の上昇に支援され、ダウは最高値を更新した。 ドラッグストアチェーン大手、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス(WBA.O)は5.1%高。ブルームバーグの報道によると、プライベートエクイティ(PE)企業のKKR(KKR.N)が同社のレバレッジドバイアウトに向け、正式なアプローチを行った。過去最大のレバレッジドバイアウトになる可能性があるという。 この日はS&P総合500種の大半のセクターが下落。公益事業.SPLRCU、エネルギー.SPNY、ヘルスケア.SPXHCの下げがきつかった。 ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.36対1の比率で上回った。ナスダックでも1.17対1で値下がり銘柄数が多かった。 米取引所の合算出来高は約55億万株。直近20営業日の平均は68億万株。 市場の焦点は週内に予定される経済指標発表や、パウエルFRB議長の証言にシフトする見通し。ウォルマート(WMT.N)、シスコシステムズ(CSCO.O)、エヌビディア(NVDA.O)など一部の主要企業も決算を発表する。 日経平均は反発、売り材料見当たらず 終値で年初来高値更新[東京 12日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は反発した。前日の米国株市場はさえない動きとなったものの、日経平均は目立った売り材料が見当たらず小反発で始まった。その後、次の材料を待ちながら2万3300円台半ばから後半を中心にもみあいが続いたが、後場、大引けにかけて上げ幅を拡大。終値ベースで2万3500円台を回復し年初来高値を更新した。 終値では2018年10月5日以来の高値となった。大引けにかけての上昇局面でも特段のニュースはなく、市場からは「皆が納得できる材料がない。あえて言えば香港のハンセン指数がしっかりした動きになってきたくらい」(国内証券)との声や、「前場はTOPIXがマイナスで引けている。日銀のETF買いが入っているのではないか」(ネット系証券)との観測が出ていた。 テクニカル分析ではオシレーター系指標が短期的な過熱感を示唆しているものの「今のように海外の中長期の投資家の買いが入ってきているような時は、短期的な過熱感も無視される」(ストラテジスト)との声もあった。 TOPIXは6日続伸。東証33業種では、建設、石油・石炭、証券が値上がり率上位に入った。半面、ゴム製品、非鉄金属、電気・ガスなどが値下がりした。 個別銘柄では、東芝プラントシステム(1983.T)が急伸し年初来高値を更新したほか、東証2部上場の西芝電機(6591.T)がストップ高比例配分となった。東芝(6502.T)が上場子会社の完全子会社化を検討していることも材料視された。 一方、三井金属鉱業(5706.T)は大幅続落。11日、2020年3月期の連結営業利益予想を従来の260億円から165億円(前年比9.4%減)に下方修正すると発表したことが嫌気された。 東証1部の騰落数は、値上がり1270銘柄に対し、値下がりが787銘柄、変わらずが96銘柄だった。 (会社四季報)米国企業の決算はアナリスト予想上回り堅調『米国会社四季報』で見るGAFA決算 米国株式市場は第3四半期の決算発表がほぼ一巡した。S&Pグローバルの調べによると、10月末までにS&P500銘柄のうち約8割が決算を発表。業種別では「ヘルスケア」「金融」「資本財」「消費財」が前年比で小幅増益だった。一方で「エネルギー」「素材」「ハイテク」が大幅減益だった。全体では平均1.5%の減益となった。ただ業績はアナリスト予想を7.2%上回り、予想より悪くなかった。さらに米中貿易摩擦の懸念後退で年末高の期待が高まっている。 『米国会社四季報』編集部は、ハイテク巨人のGAFAを改めて紹介する。今回の決算ではGAFAが強さを示した。アップルは主力のiPhoneが減少したが、サービス部門の成長で補った。アマゾンは年末商戦でプライム会員の翌日配送に対応するため費用がかさんだが、Eコマースは世界中で利用増が続いた。アルファベットとフェイスブックも主力の広告が増収だった。ただいずれも成長継続にコストが膨らんでいる。割高感には引き続き注意が必要だ。 本記事の掲載内容は『米国会社四季報2019秋冬号』の企業概況を編集したものに加え、直近の決算コメントを追加した。また、米国では四半期決算と予想との乖離が意識されるため、直近5四半期決算の推移と予想数値を並べて示した。予想は11月8日時点のS&Pグローバルのコンセンサス予想。1株利益(EPS)は調整後1株利益を用いた。(出所)S&Pグローバルアップル(AAPL)【企業概況】デジタル機器の開拓者。商品開発力に強みがあり、iPhoneが稼ぎ頭。Mac、iPad、アップルウォッチ、アップルペイなど商品・サービス群を構築。バフェット銘柄の代表格。動画配信参入などサービスに活路。19年9月、カメラ強化のiPhone11を発売。【直近決算コメント】10月30日、4Q決算発表。売上高は前年比2%増(予想+1.53%)、調整後1株益は3.03ドル(予想+6.69%)。主力のiPhoneが前年比9%減。ただサービスが18%増と成長加速。iPadとウェアラブルも貢献。1Q売上高見通しは前年比1~6%増。アマゾン(AMZN)【企業概況】世界最大のネット小売り。書籍、CD・DVD、ゲーム、家電、日用品まで幅広い品ぞろえ。在庫リスク負う仕入れ販売が強み。クラウドサービスAWSが収益柱に成長。ドローン配送、自動音声アレクサ、無人店アマゾン・ゴーなど先端技術に積極投資。【直近決算コメント】10月24日、3Q決算発表。売上高は前年比24%増(予想+1.83%)、調整後1株益は4.23ドル(予想-5.79%)。AWSが35%増と牽引。柱の北米は24%増、海外は18%増と改善。ただ年末商戦に向け投資重荷。4Q売上見通しは前年比11~20%増。アルファベット(GOOG.L)【企業概況】インターネット検索の世界首位。独自の検索エンジンで起業。グーグルマップ、Gmail、買収した動画配信YouTubeなど無料サービスを投入し、利用者を獲得。広告収入が柱。モバイルOSのAndroidを提供。EUが独禁法に関連し巨額制裁金。【直近決算コメント】10月28日、3Q決算発表。アルファベットが3Q決算発表。売上高は前年比20%増(予想+0.83%)、調整後1株益は10.77ドル(予想-15.26%)。柱の広告が前年比17%増。有料クリック数は18%増。費用かさんだが「クラウド、機械学習に投資継続」。フェイスブック(FB)【企業概況】SNS世界首位。月間利用は24億ninn超。実名登録によるネットで交流するサービスに特徴。収益柱は広告。画像共有アプリのインスタグラムなどM&Aで成長加速。ただ偽ニュース、個人情報規制など課題。仮想通貨リブラ計画発表、当局は難色。【直近決算コメント】10月30日、3Q決算発表。売上高は前年比29%増(予想+1.74%)、調整後1株益は2.12ドル(予想+12.77%)。月間利用者は前四半期比35百万増。主力の広告が前年比28%増。ザッカーバーグCEOは「コミュニティと事業は成長を続けている」。急落REITに替わるバリュー株投資日経平均は当面2万3500円水準が上値か 日経平均株価は2万3000円を超えても堅調な地合いが続き、利益確定売りを吸収しているように映る。芳しくない決算を発表しても買い直される銘柄があり、売られすぎ銘柄の修正高もあって総じて堅調となっている。カラ売りの買い戻しで上げている面も大きいが、今回の上昇局面での特徴の一つが、ここまで売られてきた銀行株などが買われていることだろう。 銀行株だけでなく建設株や不動産株、そして食品株も含めてPER(株価収益率)が一桁の銘柄が軒並み買われている。結局は割安感があるからで、単純に低PER、低PBR(株価純資産倍率)銘柄が買い直されている。割安感が強い銘柄に関しては、いま一つの決算を発表しても、しっかり買い直され、業績の回復を待たずに株価が回復している銘柄が多い。 地銀株のように業界再編を取り沙汰されて買い直されるセクターもある。「自己株買い」ならぬ「他社株買い」の要素から、割安感が強い地銀株の見直しが行われている。その一方で、REIT(不動産投資信託)がここにきて大きく売られている。 REITが売られ地方銀行や「バリュー株」が買われる状況をどう考えるべきか。資金の流れの変化も含めて検証してみると、REITが買われる場合は「金利が低下する過程」で、不動産価格の上昇が見込まれる、あるいは不動産の賃貸収入を考えた利回り上昇に期待できる局面だろう。 つまり、現状、利回りの低下が懸念されていることになる。分配金が減少して利回りが低下するとの意味ではない。REIT価格の上昇が利回り低下の要因であり、これ以上高い価格でREITは買い難いということだ。株式を配当利回りで買うことを以前述べたが、株式の利回りとREITの利回りを比較して、より高利回りのものに資金がシフトされたということだろう。 株式の利回りを考える際には、前回も述べた「益回り」という考え方がフィットすると思われる。これはREITにも合う。益回りはPERの逆数であり、株価の何%の利益を年間に上げているか、だ。PER10倍は、企業の利益の10倍の株価なので、換言すれば、その株価の10分の1=年間10%の利益を出していることになる。 もし仮に企業の利益をすべて株主に還元すれば、株主とすれば、10年間で資金が倍になる。仮に、年利1%の国債を持っていれば、100年間で資金が倍になる。もちろん株式にリスクはあるが、リターンが10倍違うと(実際にはもっと違うのだが)さすがにそのリスクを取れることになるのだろう。 足元の低金利下では地価が急落するリスクが小さく、オフィス空室率も空前の低さが続いている――、こうした側面が強調され、これまでREITが買われてきた面が大きい。しかし、米国では利下げに打ち止め感があり、金利低下がピークを越えたと判断されれば、上昇を続けてきたREITから、より割安となっている地銀株などに乗り換える手が浮上してくる。 地銀株だけでなく、いわゆるバリュー株であれば、商社株の一角なども含め、PER10倍割れやPBR1倍割れの銘柄が少なくない。配当利回りもREITと遜色ない銘柄も多く、格好の乗り換えの対象となろう。 もちろん、REITとバリュー株ではリスクが異なるが、上昇し続けたREITとここまで下落したバリュー株ならば、下落リスクを考慮した場合、乗り換えメリットが優る。また、バリュー株の業績の落ち込み懸念が薄れてくれば、さらに割安感が際立ってくるだろう。 米国での利下げ打ち止め感が出ている一方で、世界的な金利低下が進み、リスクに対する許容度が上昇したことも、相対的に割高感が出ているREITや債券からバリュー株へのシフトを促していると思われる。 注目される銘柄としては、引き続き指数の上値が限られるシナリオでも、2万4000円台まで上昇するシナリオでも、やはりPERやPBRが低い銘柄、先週同様にまだ三菱商事(8058)などの商社株の一角や森永乳業(2264)などの食品株、日本水産(1332)などの水産株があげられる。地方銀行株やメガバンク株も注目だが、目先的な過熱感が冷めたところで注目したい。 日経平均は当面2万3500円水準が上値となるのではないかと思われ、カラ売りの買い戻しが一巡となると、一気に2万2000円台までの調整もありそうだ。逆にカラ売りがさらに積み上がるようならば、いったん11月中に下押した後、12月にかけて戻すシナリオが有力になる。(株探ニュース)【決算】富士フイルム、今期最終を5%上方修正・最高益予想を上乗せ 富士フイルムホールディングス が11月12日大引け後(15:00)に決算(米国会計基準)を発表。20年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比6.6%減の611億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1550億円→1620億円(前期は1381億円)に4.5%上方修正し、増益率が12.2%増→17.3%増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比38.9%増の1008億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比25.1%増の464億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の7.7%→9.2%に改善した。(msn)(産経新聞)【ビジネス解読】消費税増税で際立つ国の税収増 閉じる「ワニの口」 10月1日に消費税の税率が10%に引き上げられる中、国の税収の好調ぶりが際立っている。財務省によると、消費税増税を受けた令和元年度の税収は前年度に続き過去最高を更新する見込み。慢性的な財政赤字の大きさが少しずつ縮小してきているともみられる。ただし、税収の着実な増加は国民負担の重みが増していることの裏返しでもある。働く世代の間では社会保障のために払う費用の上積みなどもあって負担感はさらに大きくなっており、国の税収増を喜んでばかりもいられなさそうだ。 「ワニの口が徐々に閉じてきている」 クレディ・アグリコル証券の森田京平チーフエコノミストはリーマン・ショック後の税収の推移についてこう分析している。 ワニの口とは財政赤字の拡大傾向が続いてきたことの例えだ。国の一般会計での支出と税収の推移を折れ線グラフで示した場合、支出が税収を上回り続け、あたかもワニがパックリと口を開けたような形になる。ところがこのところ下アゴにあたる税収のグラフが上向き、横ばい傾向にある支出のグラフとの差が縮まってきている。 財務省によると、平成30年度の税収は2年度以来28年ぶりに過去最高を更新。消費税増税の効果が加わる令和元年度の税収は記録をさらに塗り替え、約62兆5000億円に達する見込みだ。 税収の増加は最近だけの傾向ではない。税収の直近の底はリーマン・ショック直後の平成21年度(約38兆7000億円)で、その後はほぼ一貫して上昇。令和元年度までの10年で約1・6倍に膨らむ計算だ。◇ ここまで税収が増え続けてきた要因は消費税率引き上げと所得税の伸びにある。 平成26年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、消費税による税収はそれまでの10兆円程度から17兆円程度に大幅アップした。またリーマン・ショック後の堅調な企業業績の回復や人手不足を背景に、働き手が多くなってきたことが所得税収の増加をもたらした。さらに株価上昇で運用利益が生じやすくなっていることも所得税の増加につながっているとみられている。 今回の消費税増税を受けて、消費税による税収はまもなく所得税による税収を上回るとみられる。森田氏は「国際的な水準からみれば日本は税収全体に占める消費税の割合は小さい」と指摘。消費税による税収は景気変動に左右されにくく、今後も継続的に増えていく社会保障費を賄うのに適しているという特徴があるとして、「消費税増税は避けられない選択だった」とみている。◇ 一方、納税者の視点に立てば、国の税収が増えることを喜んでばかりもいられない。 個人や企業など国民全体の所得の規模を示す国民所得に対する一般会計税収の比率は令和元年度で約15%の見通し。これに地方税と社会保障負担も考慮した国民負担率は約43%にもなる。国民負担率は平成に入ってから30%台後半で推移してきたが、消費税増税があった26年度を境に40%台前半で推移するようになった。 日本の国民負担率は、50%を超える国も多い欧州の水準と比べると決して高いわけではない。ただ、少子高齢化で公的年金の財政健全性が損なわれることや、医療費の増加を背景とした医療保険の危機などが指摘されるなか、負担だけが増えていけば国民の不安が高まることは確実だ。 大和総研は昨年秋のリポートで、平成23年から令和2年にかけての10年間で、4人家族で年収1000万円の共働き世帯の可処分所得は45万円以上減ることになると試算した。このうち今回の消費税率引き上げによる可処分所得の押し下げ効果は7万5700円。このほかにも子供手当ての支給額の減少や厚生年金保険料の引き上げなど、消費者生活に影響を与える施策が行われてきたことが影響したという。 リーマン・ショック後、企業業績はおおむね好調だったが、このところは米中貿易摩擦などの不安材料が積み重なっている。国際通貨基金(IMF)は10月の世界経済見通しで「世界経済の活動のペースは引き続き弱い」と分析しており、今後、日本企業の業績や賃金が弱含めば、国民の消費生活にかかる税や社会保障の負担が重みを増すことは間違いない。(経済本部 小雲規生)(msn)(ブルームバーグ)大塚HD、アルツハイマー認知症薬の開発継続へ-株価は大幅上昇 (ブルームバーグ): 大塚ホールディングス(HD)の100%子会社である大塚製薬と米国子会社アバニアが、いったん終了していた「AVP-786」 のアルツハイマー型認知症に伴う行動障害(アジテーション)に関する開発プログラムを継続すると発表した。 現在進行中の3本目のフェーズ3試験については試験を継続し、2020年度から追加のフェーズ3試験の開始を予定しているという。同社はこれまでの試験結果の詳細な解析を進めていた。 大塚HDの株価は午後に急伸し、一時前日比7.3%高の4820円へ上昇、17年1月10日以来の日中上昇率となった。 大塚製薬は今年9月、「AVPー786」の2本目のフェーズ3試験結果速報で、統計学的に有意な改善は見られなかったと発表、大塚HDの株価は一時的に大きく下げていた。世界の富裕層投資家、大規模な株売りに備える-UBSウェルス調査(ブルームバーグ): 世界の富裕層は2020年に混乱が起こるかもしれないと考え、事態に備えている。UBSグローバル・ウェルス・マネジメント(GWM)の調査で分かった。 富裕層投資家を対象に行った調査によると、3400人を超える回答者の過半数が来年末までに大幅な相場下落を予測しており、平均資産の25%相当を現在現金で保有している。米中貿易摩擦を最大の地政学的な懸念事項と受け止めているほか、来年の米大統領選挙も資産ポートフォリオへの重大な脅威とみている。 GWMの顧客戦略オフィサー、ポーラ・ポリト氏は「急速に変化する地政学的環境が世界の投資家にとって最大の懸念となっている」と述べ、「世界規模での相互接続性や変化に伴う反響が、これまでのような企業のファンダメンタルズ以上に資産ポートフォリオに影響を及ぼすとみられている。過去と比べて顕著な変化だ」と指摘した。 リポートによれば、回答者の5分の4近くはボラティリティーが上昇する可能性は高いとみており、55%は2020年末までに大規模な売り浴びせがあると考えている。調査は8-10月に、投資可能な資産100万ドル(約1億900万円)以上を持つ投資家を対象に行われた。 回答者の60%は手持ちの現金をさらに増やすことを検討しており、62%は資産クラスのさらなる多様化を計画している。 ただ富裕層投資家の警戒は短期的な見通しに限られており、回答者の約70%は今後10年間の投資リターンについては楽観的だ。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-後場騰勢を強めて年初来高値を更新、楽観ムードが強まるか 12日の日経平均は反発。終値は188円高の23520円。米国株はまちまちで、寄り付きは小幅高。序盤は下げに転じる場面もあり、前場では小動きかつ、方向感に乏しい地合いが続いた。一方、後場は一転して強含む展開。前場では壁となった23400円を突破すると上昇に勢いがつき、上げ幅を3桁に拡大。心理的節目の23500円も上回り、ほぼ高値圏で取引を終えた。終値で年初来高値を更新している。ただ、日経平均の強さが目立っており、TOPIXは小幅高。マザーズ指数は下落で終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆2000億円。業種別では騰落率上位は建設、石油・石炭、証券・商品先物、下位はゴム製品、非鉄金属、電気・ガスとなった。決算を発表した大手ゼネコンの鹿島と清水建設がそろって後場に大幅高。半面、前期が大幅な営業減益となった日本農薬が後場に入って下げ幅を広げた。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1270/値下がり787。東芝が完全子会社化を検討していると報じられた西芝電機とニューフレアテクノロジーがストップ高比例配分。東芝プラントシステムも急騰し、東芝は3%超上昇した。アドバンテストやダイフク、伊藤忠などが大幅上昇。決算を材料にツクイやTOWA、クルーズなどが値を飛ばした。SBIHDとの提携を好感した買いが続いた福島銀行はストップ高。決算発表時にSBIHDとの具体的な提携内容をリリースした島根銀行が急伸した。一方、下方修正を発表した三井金属が13%超の下落。Vテクノロジーやソースネクスト、堀場製作所なども決算失望で大きく売られた。オルトプラスはゲームアプリの配信延期を嫌気した売りが止まらず連日の大幅安。マザーズ市場の相対的な弱さが目立つなか、直近上場のセルソースが大きく値を崩し、全市場の下落率トップとなった。 日経平均は反発。前場は模様眺めムードの強い地合いが続いたが、後場はかなり強い動きとなった。先週末の8日に23500円台に乗せた後に急失速したが、深押しすることなく早々に23500円台を回復してきたことは先高期待を高める。こういった動きを見せられると買い方は勢いづき、売り方は手じまいを余儀なくされる。あすはパウエルFRB議長の議会証言(13日~14日)を前にして動きづらい局面ではあるが、きょうの上昇を受けて、楽観ムードが強まると予想する。そもそも直近で利下げを決定したパウエル議長の発言が、急にタカ派的となることは想定しづらい。日経平均は8日の高値23591円を上回ってくれば、一気に24000円どころを試しに行く可能性が高い。NY株見通し-もみ合いか 米長期金利や欧州市場にも注目 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日は米中通商合意の先行き不透明感や香港での市民デモの激化などが意識され、S&P500とナスダック総合が小幅に反落したが、ダウ平均はボーイング株の上昇に支援され、小幅ながら史上最高値を更新して終了した。 今晩も米中通商合意の行方や香港情勢の米中関係への影響などが懸念材料となるほか、取引が再開される債券市場が注目される。米債利回りの上昇トレンドが続けば株高の支援となるが、利回りが低下に転じた場合は株価の重しとなりそうだ。 このほか、景気後退期入りが懸念されるドイツでは11月ZEW景況感指数の発表があり、指標結果を受けた欧州市場の動向にも要警戒か。 今晩の米経済指標は10月NFIB中小企業楽観度指数など。このほか、トランプ米大統領、クラリダFRB副議長、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁の講演なども予定されている。 企業決算は、寄り前にCBS、D.R.ホートン、タイソン・フーズ、引け後にスカイワークス・ソリューションズなどが発表予定。(執筆:11月12日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=強弱感対立か、「下げの特異日」に警戒も あす13日の東京株式市場は、強弱感が対立か。12日の日経平均株価は大幅反発、TOPIX(東証株価指数)は6営業日続伸し、ともに年初来高値水準にあり、改めて基調の強さを印象付けた。相場の落ち着きとともに買い戻しを誘いやすい状況に変わりはない。もっとも、外部環境に変調を来せば、利益確定売りが出やすい面もある。香港の政情不安が続き、米中貿易交渉の先行きも明確には見通せず、不透明感は尾を引いている。 市場では、「急ピッチな上昇を演じただけに、積極的に上値は買えず、上がれば戻り待ちの売りが出てくる」(銀行系証券)、「ここから買ってどれだけ取れるかを考えるとなかなか踏み出せないのではないか」(準大手証券)といった声が聞かれる。短期的な反動を見据え、調整待ちの見方も増えつつある。ちなみに、2000年から2018年までの11月13日の日経平均株価の騰落を追うと、13営業日中で2勝11敗。いわば、「下げの特異日」に映り、警戒する向きもある。 12日の日経平均株価は2万3520円(前日比188円高)引けとなり、終値で昨年10月10日以来1年1カ月ぶりに2万3500円を回復した。11日のNYダウの最高値更新を受け、強含んで始まったが、香港情勢の不透明感もあって下げに転じる場面もあった。ただ、下値は限定的で、円安・ドル高歩調を支えに持ち直した。その後やや上値が重くなったが、後場に入り、株価指数先物買いに戻りを試し、上げ幅は一時210円を超えた。香港ハンセン指数が午後に切り返し、支えとして意識されたとの見方も出ていた。今晩のNY株の読み筋=トランプ米大統領の講演に注目 12日の米国株式市場では、ニューヨークのエコノミッククラブにおけるトランプ米大統領の講演が注目となる。最近のトランプ大統領は発言機会があるたびに米中貿易問題に言及している。前週8日には中国の関税撤廃を否定したが、9日には協議が「良好に進展している」と述べた。さすがに11日の退役軍人らによる式典でのあいさつでは目立った発言もなかったが、この日は米国務省が香港情勢について「重大な関心」を持っているとの声明を発表しており、米中関係は必ずしも良好とはいえない。トランプ大統領はきょうの講演で中国との協議について何かしら発言する恐れがあると市場は警戒しており、注目しておきたい。<主な米経済指標・イベント>トランプ米大統領、クラリダFRB(米連邦準備制度理事会)副議長、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が講演(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京外為〕ドル、109円台前半=米大統領の講演待ち(12日午後3時) 12日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、日本時間13日未明のトランプ米大統領の講演を待ちたいとして様子見気分が広がり、1ドル=109円10銭台の狭い値幅で推移している。午後3時現在、109円20~20銭と前日(午後5時、108円95~96銭)比25銭のドル高・円安。 東京市場は109円00銭台で始まった後、日経平均株価の上昇を好感したドル買い・円売りや輸入企業の決済資金調達などで109円20銭付近まで上昇した後は、もみ合う展開になった。午後に入って日経平均は上げ幅を拡大したものの、「米長期金利がそれほど上がっておらず、ドルを買い進む状況ではない」(邦銀)との見方から、ドルはやや上値が重かった。 市場参加者はトランプ大統領の講演について、米中貿易協議の行方を占う上で「注目すべき材料」(同)と位置付けている。内容は予断を許さないが、「ネガティブなことは話さないのではないか」(FX会社)との観測も出ている。肯定的な発言が飛び出せば、リスク選好の姿勢が強まりそうだ。 ユーロは対円で午後はじり高、対ドルは小幅高。午後3時現在、1ユーロ=120円50~51銭(前日午後5時、120円18~18銭)、対ドルは1ユーロ=1.1033~1037ドル(同、1.1030~1030ドル)。(了) 〔東京株式〕年初来高値=主力株に買い(12日) 【第1部】日経平均株価は前日比188円17銭高の2万3520円01銭と反発し、終値で年初来高値を更新した。東証株価指数(TOPIX)は5.64ポイント高の1709.67と続伸した。海外市場が落ち着き、主力株を中心に買い戻しが入った。一段と買い上がる材料に乏しく、利益確定売りに押される銘柄もあり、TOPIXの上げ幅は小さかった。出来高は12億5976万株。 【第2部】4営業日続伸。東芝が買われ、那須鉄は急伸した。半面、大日本コンは軟調。出来高2億1035万株。 ▽過熱感くすぶる 前日の海外市場に目立った動きがなく、日本株は手掛かり難の状態だった。日経平均株価はファーストリテなど指数寄与度の大きい値がさ株に買いが入り、前場から強含みの展開。東証株価指数(TOPIX)は後場中盤までマイナス圏で推移するなど、相場全体は上値の重さが目立った。「前週までの急速な株価上昇に伴う過熱感がくすぶっていた」(大手証券)といい、売りも出やすかったとみられる。 とはいえ、利益確定の動きを急ぐ様子はなく、日経平均、TOPIXともに取引終了にかけて強含んだ。米主要株価指数が過去最高水準となり、「株高自体が投資家心理を上向かせている」(投資助言会社)という。前日急落した香港株もこの日はしっかりした値動きとなるなど、特に悪材料がなかったこともあり、底堅さの目立つ一日となった。 225先物12月きりは反発。中国株の上昇などを眺めて後場にかけて買いが強まった。225オプションはプットが売られ、コールは値上がりした。(了) 〔NY外為〕円、109円台前半(12日朝) 【ニューヨーク時事】連休明け12日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、トランプ米大統領の講演に注目が集まる中、1ドル=109円台前半で小動きとなっている。午前9時現在は109円05~15銭と、前週末午後5時(109円21~31銭)比16銭の円高・ドル安。 トランプ大統領は12日、ニューヨークで通商政策と経済政策について講演する。市場では、安全保障を理由とした自動車・同部品の輸入制限措置について、追加関税などの是非を判断する期限をさらに6カ月延長すると表明するのではないかとの観測が広がっている。米中貿易協議に関する発言も注目されている。講演内容を見極めたいとの思惑が強まり、円相場は海外市場を通じて小幅なレンジでの商いが続いている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1015~1025ドル(前週末午後5時は1.1015~1025ドル)、対円では同120円25~35銭(同120円33~43銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ小幅続伸、ナスダックは史上最高値更新(12日朝) 【ニューヨーク時事】12日のニューヨーク株式相場は、トランプ米大統領の通商・経済政策に関する講演を控え、小幅続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時41分現在、前日終値比13.25ドル高の2万7704.74ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は3営業日ぶりに取引時間中の史上最高値を更新。同時刻現在は20.05ポイント高の8484.33。(了) 昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の10銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。
2019.11.12
コメント(0)
-

11月11日(月)…
11月11日(月)、曇り~雷雨~晴れ…。目まぐるしく天候が変化する日であります。そんな本日は7時30分頃に起床。身支度をすると、奥の運転で知人のクリニックへ搬送…。本日は自身の健診&インフル予防接種です。一般的な諸検査と予防接種を済ませて、最後は胃カメラです。こちらでは精神安定剤を使用するので検査中の記憶が全くございません…。10時頃には検査も終わり、起こされて、車いすで個室へ移動して休憩です。目を閉じるとすぐに眠りに落ちます…。12時前にだいぶしっかりしてきたのでお迎えを依頼して帰宅。昼食にお粥を食べて、午睡に突入です…。15時30分頃に目が醒める。帰宅時は雷雨でしたが、今は青空が広がっています。ホットハニーミルクでおやつタイム。本日は休養日ですね…。1USドル=108.96円。1AUドル=74.67円。本日の日経平均終値=23331.84(-60.03)円。金相場:1g=5690(-23)円。プラチナ相場:1g=3539(-66)円。若干の円高・株安方向ですか…。(ブルームバーグ)米国民の上位1%、超富裕層の富が中流階級の合計資産上回る寸前 米国の歴史的な景気拡大は上位1%の超富裕層の富を膨らませ、彼らの資産はミドル層とアッパーミドル層の人々の合計資産額を上回ろうとしている。 米国の上位1%の家計は過去10年間に株式相場上昇から大きな恩恵を受け、米連邦準備制度理事会(FRB)のデータによると、現在では米国の公開企業と民間企業の株式の半分以上をこの層が保有している。 この株式保有のおかげで、米国民の中で超富裕層が握る富の部分は増え続けている。 1%の超富裕層が持つ資産は4-6月(第2四半期)に約35兆4000億ドル(約3860兆円)となり、米国民の50パーセンタイルから90パーセンタイルを構成するミドルおよびアッパーミドル層の合計36兆9000億ドルに迫っている。 富裕層向け投資サービスのレイクビュー・キャピタル・パートナーズのチーフマーケットストラテジスト、スティーブン・コラビト氏は、低金利を背景に富裕層が株式に投資せざるを得なかった状況が株式相場全体を支え、これによってさらに豊かになった富裕層がヘッジファンドやプライベートエクイティ(PE、未公開株)に投資できるようになったと説明。「金持ちになればなるほど、さらに資産を増やす機会が増える」と語った。 上位1%の家計資産は2019年第2四半期に6500億ドル増えたが、50パーセンタイルから90パーセンタイルの米国民の資産増加は2100億ドルにとどまった。上位1%がミドルおよびアッパーミドル層を上回るのは遠くなさそうだ。 ちなみに、90-99パーセンタイルの米国民は「超富裕層」ではなく普通の富裕層だが、合計資産はこのグループが最も多く42兆6000億ドル。投資の巨人ボンダーマン氏、ウォーレン氏支持-「富裕税」実現しない 2020年米大統領選の民主党の公認指名を争うエリザベス・ウォーレン上院議員は、プライベートエクイティ(PE、未公開株)投資会社を批判する急先鋒(せんぽう)だが、投資業界の巨人が支持しない理由にはならないようだ。 TPGキャピタルの共同創業者で資産家のデービッド・ボンダーマン氏は、既存のリストに掲載されている候補者の方が、トランプ大統領よりもうまくやるだろうと述べ、トランプ氏よりもウォーレン議員を選ぶ意向を示した。 ボンダーマン氏は9日午後、ロサンゼルスで開かれた会議でブルームバーグの質問に対し、「トランプ氏かウォーレン氏かという選択になれば、どちらを選ぶかは明白だと思う」と語った。 ボンダーマン氏は、ウォーレン氏が賢いとしながらも、提案の多くを実行できるとは考えていない。同氏は「そうは言っても、彼女は多くの点で魅力的な候補だ。ウォール街の同業者は2%の富裕税に関心を向けていない。いずれにせよ実現しないだろう」と発言した。(ロイター)アングル:米小型株、バリュー株人気で上昇へ 指標次第で急落も[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米国の小型株は、バリュー株人気で大幅な上昇が見込まれる一方、景気低迷で急速に上値が消える可能性も指摘されている。 小型株の指標であるラッセル2000指数は、今年の大半はS&P500.SPXを下回るパフォーマンスとなっており、昨年12月に確認された弱気相場を抜け出せていない。 それでも第4・四半期に入りラッセル指数は4.6%上昇し、S&P500指数の3.6%を上回る伸びとなっている。ラッセル指数の好調ぶりは、S&P500バリュー指数.IVXの5.2%上昇と連動。同時期のS&P500グロース指数.IGXの上昇率は2.3%にとどまっている。 景気に対するセンチメントの改善で、投資家の間ではバリュー株と小型株の割安銘柄を見直す動きが広がっている。バリュー株は金融やエネルギーなど景気に敏感なセクターに多い。小型株は大型株より国内重視の銘柄が多く、米経済に対する投資家の見通しを反映する傾向が強い。 景気改善見通しで米国債10年物の利回りUS10YT=RRは9月の低水準から上昇し、3カ月物US3MT=RRと10年物のイールドカーブはスティープ化した。その結果一部の投資家の間では、小型株の上昇を予想する声が広がっている。 特に金融株のパフォーマンスは向上著しく、小型株の押し上げにつながる公算が大きい。金融株はラッセル2000の20%を占めており、S&P500の13%より比率が大きい。 ホッジズ・キャピタル・マネジメントのシニア・バイス・プレジデント兼ポートフォリオマネジャーのゲリー・ブラッドショー氏は「金利上昇は景気上向きを意味する。大型株に比べ出遅れ感のあった小型株のキャッチアップは確実だ」と述べた。 同氏によると、ホッジズは過去数カ月で石油・天然ガスのマタドール・リソーシズ(MTDR.N)、パースリー・エナジー(PE.N)、チリのレストランを保有するブリンカー・インターナショナル(EAT.N)のポジションを積み増した。 大型のバリュー株が今後も相場の主導権を握ることに懐疑的な見方がある一方、小型株は業績改善を足掛かりに株価押し上げが見込まれている。 RBCキャピタル・マーケッツの米株戦略部門の責任者、ロリ・カルバシナ氏によると、今年は通常と異なり小型株の利益の伸びが大型株に遅れる時期があった。ただその後は小型株の利益の伸びは改善している。 同氏は「長期的に利益の伸びが大きいとの見方で小型株が好まれている。年初の状況では当てはまらないが、今は通常のパターンが戻りつつある」と指摘した。 依然として小型株の見通しは経済指標に大きく左右される状況にあるが、現在示唆しているのは景気減速だ。10月の米供給管理協会(ISM)の製造業指数は景気拡大・縮小の節目となる50を3カ月連続で下回った。米中通商合意は製造業の統計押し上げに寄与する見込みだが、依然として部分的だ。 ジェフリーズの株式ストラテジスト、スティーブン・デサンクティス氏は「通商協議で合意できなければ、景気減速を示す兆候が増えれば小型株は急落するだろうが、景気は持ちこたえるとみている」と述べた。 日経平均は5日ぶり反落、高値警戒 米中協議にも不透明感[東京 11日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均株価は5日ぶり反落した。前週末の米国株が上昇した流れを引き継いで続伸スタートとなったが、米中通商協議を巡る不透明感や連騰後の高値警戒感などもあり、買い一巡後は利益確定売りに押された。香港で警官とデモ隊が衝突し混乱が広がっていることも、投資家心理を冷ます要因となった。 先週は米中通商協議が進展するとの期待がリスクオンムードを醸成したが、トランプ米大統領が対中関税の撤回で合意していないと明らかにしたことで協議の先行きに不透明感が生じた。日経平均は前日まで4日続伸し年初来高値を更新していたこともあり、「利食い売りの材料にされた」(国内証券)という。 香港での混乱が嫌気され、11日の香港ハンセン指数.HSIは一時2%超下落。外為市場でもドル/円が朝方の水準からやや円高方向に振れた。米中協議や香港の動向をにらんで、ファナック(6954.T)、村田製作所(6981.T)、TDK(6762.T)、日立建機(6305.T)など中国関連銘柄の一角が軟調に推移した。 一方、TOPIXは続伸。東証33業種では、倉庫・運輸関連、その他金融、繊維などが値上がり率上位に入った。半面、建設、石油・石炭、非鉄金属は軟調だった。東証1部の騰落数は、値上がり1294銘柄に対し、値下がりが787銘柄、変わらずが72銘柄だった。 前場の市場では「これまで動きが出ていなかった新興株市場も堅調で、個人投資家が少し買いで入ってきているようだ」(内藤証券の投資調査部長、田部井美彦氏)との声が出ていた。日経ジャスダック平均は0.40%高、東証マザーズ指数は1.15%高できょうの取引を終えた。 このほか個別では、福島銀行(8562.T)が一時ストップ高となった。SBIホールディングス(8473.T)との資本・業務提携に関する報道が好感された。SBIは午後に資本・業務提携を正式発表、福島銀行と共同の店舗を作りSBIグループの金融商品を顧客に提供するほか、新規技術の導入による顧客利便性の向上や運用資産受託を通じた収益力の強化を図るという。 (msn)(マネーの達人)銀行の「口座維持手数料」導入が現実味を帯びてきた 欧米を例に導入後を検証 最近、「銀行の普通預金口座における口座維持手数料が導入されるかもしれない」というニュースをよく耳にしないでしょうか?実は、これについては数年前から大手銀行を中心に検討されており、現在その可能性が非常に高くなっています。一方で、欧米では口座維持手数料は当たり前で、ほとんどの銀行で導入されていると言われていますが本当なのでしょうか。 今回は、報道された内容などをもとに日本の銀行での口座維持手数料導入の可能性について議論をし、欧米での口座維持手数料について解説します。欧米での状況をみれば、それを参考にして日本の銀行がどのように導入するのか大体予測できると思います。発端は日銀のマイナス金利政策2017年12月、産経ニュースは、・ 三菱UFJ銀行・ 三井住友銀行・ みずほ銀行の3つのメガバンクが口座維持手数料の導入の検討を始めたことを報じました。2016年に日銀は、民間の銀行の貸し出しを増やすために、民間銀行が日銀に預けている預金金利をマイナス(−1%)にしたことがその背景にありました。このマイナス金利政策により、民間銀行の経営が苦しくなったのです。特に、地方銀行が大きな影響を受けたようです。現時点でも、口座維持手数料の導入はまだ検討段階ではあるようです。しかし、三井住友信託銀行の橋本社長は、2019年9月における産経新聞との単独会見において、口座維持手数料導入ついてもう少し踏み込んだ発言をしました。「マイナス金利が拡大されるなら三井住友信託銀行としても検討する」 と述べたのです。三井住友信託銀行は大手銀行のひとつであるため、この発言は重いですし、他の銀行もこのように考えているとみて良いでしょう。 その後、2019年10月31日、日銀の黒田総裁は必要があればマイナス金利をさらに引き下げる可能性を示唆したことが多くのメディアで報じられました。以上のことから、口座維持手数料の導入はほぼ行われると覚悟しておいた方がよさそうです。欧米での口座維持手数料は必ずしも当たり前ではない日本のメディアなどでは、欧米において口座維持手数料はほとんど全ての銀行に導入されていると言われているのですが、本当なのでしょうか?アメリカでのケース例えば、US bankという銀行におけるEasy checking口座では月に6.95ドル(約760円)徴収されます。ただし、合計で1,000ドル(約10万9,000円)以上が毎月入金されれば無料になります。つまり、給料支払いをこの銀行口座に指定していれば手数料は取られません。他の銀行を見てみると、多くの銀行は口座維持手数料を取っています。場合によっては、月に30ドル(約3,200円)取られますが、多くの場合US bankと同様に条件付きで無料になるようです。ヨーロッパ(イギリスとスペイン)でのケースイギリスでは、スペインのメガバンクであるSantander(サンタンデル)を除いた主要な銀行では口座維持手数料は取っていません。主要な銀行として、他にはHSBCやRBSがあります。Santanderでの代表的な銀行口座では月に口座維持手数料として5ポンド(約700円)取られますが、1.5%(変動)の利息で相殺できます。一方、口座維持費を取らないベーシックアカウントもありますが、利息は0%です。スペインのほとんどの銀行では、口座維持手数料が取られます。しかし、同様に利息で手数料を相殺できますし、もしくは給与が毎月振り込まれていれば無料になるケースがほとんどです。以上のことから、欧米では口座維持手数料は必ずしも当たり前ではなく、またあったとしても何とか無料にできるケースが多いです。日本の口座維持手数料を予想日本の銀行で口座維持手数料導入される場合、同様に条件付きで手数料をとるのではないでしょうか。日本の場合、金利が低すぎて利息で手数料を相殺させるのは困難なので、一定以上の金額が入金されれば手数料は免除されるということになればよいのですが。欧米の例を参考にすると、口座維持手数料の金額は月に数百円から数千円くらいになることが予測されます。ただし、銀行業界(特に地方銀行)は預金者の反発に対する警戒感が強い上にほとんどの日本人は経験したことがないため、最初に導入される手数料はかなり低いか限定的である可能性があります。その後、他の手数料と同様に少しずつ口座維持手数料は上がっていくかもしれません。一方で、消費税が上がった後に口座維持手数料が導入されるとなると、消費者心理に悪影響を与え、消費動向指数が低下するのではないかと考えられます。これは日本経済をさらに悪化させるので、むしろこれが一番大きな問題になるかもしれません。口座維持手数料に対する対策口座維持手数料は月ごとで見るとそれほど高くはないのですが、年単位で見ると結構な値段で無視できません。したがって、口座維持手数料が導入された場合、使っていない銀行口座を閉じるなどの対策をするべきでしょう。もしくは今から準備しておいても良いかもしれません。(執筆者:小田 茂和)(msn)(ブルームバーグ)債券市場に警告シグナル、タームプレミアムが急上昇-売り続く兆候か(ブルームバーグ): 債券市場のある指標が突然、赤信号を発した。前回に赤が灯った時には世界金融危機後の時期以来で最大の債券売りにつながっていた。 その指標とはタームプレミアムで、米国債とドイツ国債の両方について前四半期の記録的低水準から反転上昇している。米国債タームプレミアムの3カ月での上昇は2016年後半以来の最大に向かっている。 8月までの安定した上昇から一転し、世界の債券相場は最近数週間に下落した。貿易紛争の緩和が世界経済への懸念を和らげたことが背景にある。タームプレミアムの反発は債券売りがさらに続くことを示唆する。短期債をロールオーバーする代わりに長期債を保有する投資家が求めるプレミアムの上昇トレンドは、始まったばかりだと投資家やストラテジストが指摘する。 10年物米国債利回りは7日に3カ月ぶり高水準となり、ドイツ国債利回りも7月半ば以来の高さとなった。フランスとベルギーではゼロを上回った。8日の日本国債利回りは5月以来の最高に達した。 景気悪化懸念の後退に伴い、安全資産からリスク資産への資金の流れが見込まれる中で投資家は長期債保有について不安を深めている。こうした傾向はすでに利回りを押し上げ、米連邦準備制度が利下げ停止を示唆していることと相まって、タームプレミアムが上昇。欧州でも緩和的な金融政策の中でインフレ見通しが上向きタームプレミアムへの上昇圧力になっている。 コーナーストーン・マクロのパートナー、ロベルト・ペルリ氏は、貿易問題や英国の欧州連合(EU)離脱を巡るリスクが和らいだため、「タームプレミアムは50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)程度上昇する余地がある。米金融当局は金利を据え置いており利上げの可能性はゼロなので投資家がリスクを取るインセンティブは大きい」と話した。 ニューヨーク連銀のモデルによると、10年物米国債のタームプレミアムは8月末から約42bp上昇し、3カ月で16年以来最大の上昇に向かっている。8月はマイナス1.29%という記録的な低さだったが、先週にはマイナス0.84%まで回復した。(msn)(AllAbout)ポイントはたった1つ!超おいしい高配当株の見分け方誰でもお得な高配当株を見分けられる?配当といえば、不労所得の代名詞です。株式投資では、投資先企業から配当(お金)をもらえます。とはいえ、投資先を間違えると、「3000円の配当金を受け取るために、3万円も損してしまった!」ということにもなりかねません。そこで、配当金をもらえるだけでなく、株価上昇も期待できる「超おいしい高配当株」を見分けるたった1つのポイントを解説します。僕自身も利用しているテクニックなので、ぜひご活用ください。高配当株の目安は、利回り4%以上手始めに、高配当株を探しましょう。投資家のジェームズ・オショーネシーによると、高配当株はその他の株と比べて株価が上がりやすいのだとか。 ですから、配当金を受け取ることもそうですが、「株価が上がりそうな株を買いたい!」と考えている方にとっても、高配当の株は有利です。現在、日本には3700社ほどの上場企業があり、そのうち約3200社が配当金を分配しています。配当利回りの中央値は「約2%」ほどです。たっぷり配当金をもらいたい場合は、平均値よりも配当利回りの高い会社を選ぶとよいでしょう。目安としては、配当利回りが「4%」を超える会社がオススメ。日本の上場企業の中でも、この条件で上位1割の高配当株を抽出できます。ポイントは、借金の少ない会社を選ぶことここからがミソです。高配当株の中でも、「借金の少ない企業」の高配当株を探しましょう。単に配当利回りが高いだけでなく、借金が少ない会社の株式は、株価が上がりやすい傾向が確認されています。一部の研究では、「高配当かつ借金が少ない会社の株を買うだけで、年率18%を達成できたぞ!」というデータさえあります。借金の少ない会社を探すときには、「自己資本比率」という指標を確認するのが有効です。目安としては、「自己資本比率が50%を超えると借金が少なく、財務が健全」と考えるとよいでしょう。ちなみに、配当利回りが4%を超える高配当株のうち、過半数は自己資本比率が50%を切っています。つまり、高配当株の半分以上は「借金まみれ」といえます。借金まみれの企業の株を買うと、たとえ配当をもらえたとしても、株価が景気に左右されやすく、リスクが大きい可能性があります。安全に配当を受け取るためにも、借金の大きな会社の株は避けるのが無難でしょう。ポイントを押さえ、賢くお金を増やそう!「配当はお得だ!」というイメージが広まっていますが、それはあくまで「株価が下がらない」場合に限っての話です。本当においしい高配当株は、配当利回りが高いだけでなく、株価の値上がりも期待できます。配当を受け取りつつ、値上がりを狙う場合は、「借金の少ない企業」を買うのがオススメです。賢くお金を増やし、上手に配当を受け取るためにも、本記事でご紹介したポイントを覚えておきましょう。高配当ランキング: TOPIX大型株 (Core30)1 2914 日本たばこ産業 6.31% 東証一部2 7751 キヤノン 5.32% 東証一部3 8058 三菱商事 4.59% 東証一部4 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.48% 東証一部5 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.36% 東証一部6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.23% 東証一部7 8031 三井物産 4.15% 東証一部8 4502 武田薬品工業 4.11% 東証一部TOPIX大型株 (Core30+Large70)1 2914 日本たばこ産業 6.31% 東証一部2 8604 野村ホールディングス 5.77% 東証一部3 9434 ソフトバンク 5.71% 東証一部4 7201 日産自動車 5.63% 東証一部5 7751 キヤノン 5.32% 東証一部6 8053 住友商事 4.78% 東証一部7 7270 SUBARU 4.76% 東証一部8 8058 三菱商事 4.59% 東証一部9 4188 三菱ケミカルホールディングス 4.55% 東証一部10 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.48% 東証一部11 8591 オリックス 4.38% 東証一部12 8002 丸紅 4.37% 東証一部13 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.36% 東証一部14 1878 大東建託 4.34% 東証一部15 8308 りそなホールディングス 4.34% 東証一部16 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.23% 東証一部17 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.22% 東証一部18 5020 JXTGホールディングス 4.19% 東証一部19 8031 三井物産 4.15% 東証一部20 4502 武田薬品工業 4.11% 東証一部21 6301 小松製作所 4.11% 東証一部さて、こうした発想で株式を選別していくと…2914 JT 6.31%7751 キャノン 5.32%8219 青山商事 5.13%4544 みらかHD 4.85%7270 SUBARU 4.76%が上位に来ますね。この5社の平均利回りは、5.15%となります。退職金の1000万円をこの5社株に均等に振り分けたとすると、年間の配当金は515000円となります。税金を引かれての手取りは約412000円となりますね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-アジア株軟調を受けて5日ぶり反落、売買代金急減は警戒材料 11日の日経平均は5日ぶり反落。終値は60円安の23331円。先週末の米国株の上昇を受けて小高く始まったものの、上値の重い展開。開始早々に高値をつけた後は失速し、10時過ぎには下げに転じた。香港株が大幅安となり、他のアジア市場も連れ安したことが警戒材料となった。後場は小動きが続き、下押し圧力は和らいだ。しかし、値を戻す動きはほとんど見られず、取引終盤にかけては売り直された。一方でTOPIXや新興指数は上昇で終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆1800億円。業種別では騰落率上位は倉庫・運輸、その他金融、繊維、下位は建設、石油・石炭、非鉄金属となった。上期が大幅増益となったイーレックスが後場プラス転換から上げ幅拡大。半面、前通期見通しの下方修正と期末配当予想の取り下げを発表した阪和興業が後場に入って急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1294/値下がり787。自己株取得の発表が好感されたホンダが4%超の上昇。好決算の島津製作所やセコムが大幅高となった。直近で急落していたEduLabは今期の見通しが安心材料となってストップ高比例配分。SBIホールディングスとの提携観測が報じられた福島銀行が急騰し、山形銀行や岩手銀行など他の地銀株にも買いが波及した。一方、3Q減益のユニ・チャームが7%超の下落。大和ハウスも決算を嫌気した売りが止まらず大幅安となった。下方修正を発表したNISSHAやラウンドワンが急落。公募・売り出しが嫌気されたユーザーローカルはストップ安をつける場面もあるなど大きく値を崩した。期待が高まっていたゲームアプリの配信延期を発表したにはオルトプラスには売りが殺到し、ストップ安比例配分となった。 日経平均は5日ぶりに反落。ただ、アジア市場の弱さを受けても大きく崩れることはなかった。ローソク足では連日で陰線となったが、終値(23331円)では5日線(23321円)を上回っており、弱いながらもテクニカルの節目では下げ渋った。TOPIXはプラスで終えており、リスクオンの地合いは維持されていると言える。一方、東証1部の売買代金が低水準となっている点にはやや警戒が必要。8日の3.12兆円からきょうは2.18兆円と大きく減少した。8日の多さはSQが影響しているが、決算発表は今週で一段落するなか、早くも2兆円割れに突入しそうな雰囲気もある。商いが細ると上に行くエネルギーが低下してピークをつけることも多い。実際、きょうの高値は23471円までで、23500円には届かなかった。あすも強弱感は交錯しそうではあるが、そのなかで売買代金が増加してくるかを注視しておきたい。NY株見通し-今週は米中通商協議の進展期待を背景にリスクオン継続か 今週のNY市場は堅調持続か。 主要3指数がそろって史上最高値の更新を続け、過熱感を示すテクニカル指標も増えており、高値警戒感から利益確定売りが強まることが予想される一方、米中通商合意への期待などを背景に、安全資産とされる米国債や金を売る流れが続くなど、リスク資産への選好が強まっており、今週も景気敏感株を中心に堅調な相場が期待できそうだ。 経済指標や決算発表が良好な結果となれば、主要指数の最高値更新が続きそうだ。経済指標・イベントでは10月消費者物価指数(CPI)、パウエルFRB議長議会証言(以上13日)、10月生産者物価指数(PPI)(14日)、10月小売売上高(15日)などに注目。 終盤戦を迎えた企業の7-9月期決算はCBS、アプライド・マテリアルズ、シスコ・システムズ、ウォルマート、エヌビディアなどS&P500の15銘柄が発表予定。 今晩の米国市場はベテランズデーで債券市場が休場。為替・株式市場は通常取引。米経済指標はなし。企業決算は、引け後にDXCテクノロジーなどが発表予定。(執筆:11月11日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=もみ合い商状か、高値警戒感くすぶるも押し目買いニーズ根強い あす12日の東京株式市場は、もみ合い商状か。高値警戒感がくすぶり、利益確定売りが出やすいものの、押し目買いニーズも根強い。週明け11日の日経平均株価は5営業日ぶりに反落した一方、TOPIX(東証株価指数)は5営業日連続の続伸となり、連日で年初来高値を更新し、全体感では「なかなか粘り強い」(中堅証券)との声が聞かれた。20年3月期第2四半期(19年4-9月)の決算発表が続くなか、企業業績は上期底入れ、下期回復の読みから売り込みにくい面もある。 ただ、トランプ米大統領が8日、中国が相互に行っている追加関税を段階的に撤回することで一致したと発表したことに関し、現時点では「何も決まっていない」と発言。9日には中国との通商協議は「とてもうまく進んでいる」と述べるなど、依然として不透明感が残り、米中貿易交渉の第一段階の合意への道筋を見極めたいとの空気もある。 11日の日経平均株価は5日営業ぶり反落し、2万3331円(前週末比60円安)引けとなった。朝方は、前週末のNYダウ、ナスダック総合指数がともに最高値を更新した流れを受け、前場早々に上げ幅が80円近くとなった。一巡後は、直近連続上昇への警戒感もあり、利益確定売りに下げに転じた。香港情勢の悪化懸念でハンセン指数が大幅安となり、上海総合指数も下落するなど中国株安が重しとして意識され、後場後半には下げ幅が70円近くとなった。(yahoo)(産経新聞)NTTが電力網整備に6千億円 蓄電池や配電網で電力最適制御 災害時にも NTTが来年度から6千億円程度を投じ、独自の電力網整備に乗り出すことが11日、分かった。全国に約7300カ所ある電話局に設置した蓄電池やグループ会社のグリーン電力発電などのさまざまな電力の供給源を束ね、電力需給に応じてオフィスや工場、病院などに供給できるようにする。災害時などのバックアップ電源として活用することなども見込む。 独自の電力網構築に向け来年度から令和7(2025)年度にかけ毎年1千億円程度の設備投資を計画する。電力関連事業の売上高は現在3千億円程度だが、7年度には6千億円に倍増させる方針。 電話局では固定電話の利用減で生じたスペースにリチウムイオン電池を配備するほか、非常用蓄電池も鉛蓄電池から繰り返し充放電できるリチウム電池に切り替える。また、1万台程度の社用車を12年度にはすべて電気自動車(EV)に変え、蓄電池としても使えるようにする。 電話局の周辺などにはグループ会社を通じて太陽光発電を設置するほか、風力やバイオマスなどのグリーン電力発電による電源を外部から調達も含めて整備する。 電話局の周辺の施設には配電網を構築し、電力のロスが少ない交流の配電網を使って、効率良く送配電する。災害時には病院などに電力を供給し、停電リスクを分散する。また、蓄電池やEVなど分散する電力の供給源を束ねて一つの仮想的な発電所として機能させ、電力需給を最適制御するビジネスも手がける。 NTTが電力事業を強化するのは、主力の携帯電話事業で値下げ競争などが進み、これまでのような高成長が難しくなる中、新たな収益源を確保するのが狙いだ。6月には電力事業の司令塔となる新会社を設立し、グループ会社ごとに分かれている事業の連携を強化する体制を整えた。(yahoo)(時事通信)〔ロンドン外為〕円、109円近辺(11日正午) 【ロンドン時事】週明け11日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、薄商いの中を1ドル=109円近辺で推移した。正午現在は108円90銭~109円00銭と、前週末午後4時(109円10~20銭)比20銭の円高・ドル安。 東京市場で米中貿易協議をめぐる楽観論が後退し、円は109円台前半から108円台後半に上昇。午前のロンドンでは材料難の中を109円近辺でこう着状態となり、方向感のない時間帯が続いた。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1020~1030ドル(1.1015~1025ドル)。対円では同120円10~20銭(120円25~35銭)。 ポンドは1ポンド=1.2825~2835ドル(1.2790~2800ドル)。7~9月期の英GDPは前期比0.3%増となり、景気後退入りは回避したが、市場予想の0.4%増は下回った。ただ、ポンドへの影響は限定的に終わり、その後はポンド買いが優勢になると、一時1.2830ドル近辺に上昇した。 このほか、スイス・フランは1ドル=0.9945~9955フラン(0.9960~9970フラン)。(了)〔米株式〕NYダウ、ナスダックともに反落(11日朝) 【ニューヨーク時事】週明け11日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の進展をめぐる不透明感から、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前週末終値比129.91ドル安の2万7551.33ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は45.12ポイント安の8430.19。(了) 今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の4銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では1銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.11
コメント(0)
-
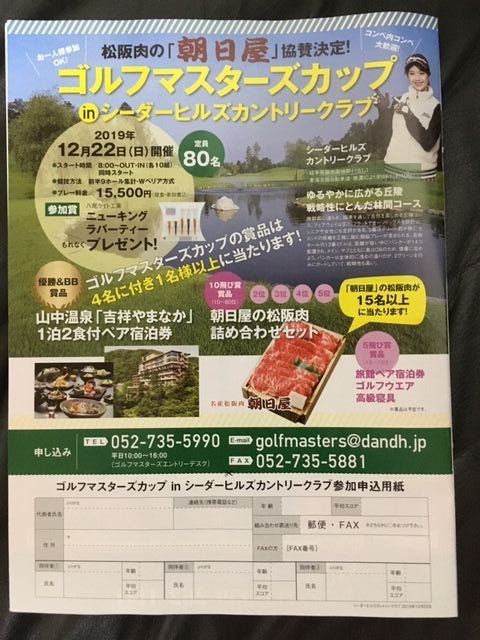
11月10日(日)…2019ラウンド84…
11月10日(日)、晴れです。本日はホーム1:GSCCの月例杯・西コースの部に参加させていただきました。8時52分スタートとのことですから、6時15分に起床。ちょうど日の出時です。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時20分頃に家を出る。7時50分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、12/8のエントリーを済ませて、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…練習できず…。本日の競技は西コースのブルーティー:6613ヤードです。ご一緒するのはいつものU君(14)、M君(14)、お久しぶりのT君(12)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:0.-1.1.1.1.0.0.2.0=40(14パット)0パット:1回、1パット:4回、3パット:2回、パーオン:3回。1打目のミスが2回、2打目のミスが3回、アプローチのミスが1回、パットのミスが2回…。バーディートライを入れに行くと痛い目に遭いますかね…。スルーでINへ。IN:0.1.0.1.3.1.1.1.0=44(15パット)1パット:4回、3パット:1回、パーオン:1回。1打目のミスが4回(OBあり)、2打目のミスが2回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが1回、パットのミスが1回…。11番ミドルの1打目…、ティーグラウンドでのドライバーはヒールにこすって前のくぼみへ…。14番ショートの1打目…、大きくダフッてボルはティーグラウンドの前へ転がって…OB…。参りました…。40・44=84(9)=75の29パット…。何の期待もできませんが、握りに勝ったから良しとしましょう…。スコアカードを提出して、握りの清算を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.6kg,体脂肪率20.3%,BMI22.0,肥満度0.0%…でした。帰宅すると14時30分頃。国内女子ツアーは鈴木Pが3打のリードで最終ホール…、しかし…ここで陛下のパレードの実況に…。「エス・コヤマ」のバームクーヘンと紅茶でおやつタイム。それではしばらく休憩です。(ロイター)コラム:不安増すマイナス金利、「懲罰」はどこまで広がるのか 大槻奈那 マネックス証券 執行役員チーフ・アナリスト[東京 8日] - 米国が10月31日、今年3回目の利下げに踏み切り、日本もマイナス金利の深掘りこそなかったものの、フォワードガイダンスを修正して利下げの可能性を示した。今年は世界の金融政策が正常化から遠のき、一気に緩和モードに逆戻りした。 これを受けて株価が堅調に推移する一方で、マイナス金利に対する不安も広がりつつある。欧州中央銀行(ECB)がマイナス金利を深掘りするドイツでは、預金金利をマイナスにする金融機関が急増、その数は10月末時点で135行にも上っている。 マイナス金利を「懲罰的金利(Strafzins)」と称し、これから逃れるための「タンス預金」ならぬ「マットレス預金」の増加が話題となっている。貯金箱が水没する挿絵とともに、貸金庫の料金をその中に保管できる札束の数で割った額を預金金利と比較し、どちらが割安かなどと論じるマネーの専門誌もある。 <景気回復に大きな効果> もちろん、マイナス金利はこれまでの景気回復に貢献している。2012年にマイナスに転じたユーロ圏の成長率は、14年のマイナス金利導入後はプラスとなり、失業率も着実に減少し始めた。 これを支えたのが銀行貸出の増加である。減少傾向にあったユーロ圏の貸出は、マイナス金利導入後は見事に増加に転じた。今日までの貸出伸び率は累積で8%に上る。 とりわけ増加が著しいのは住宅ローンで、マイナス金利導入後の約5年で17%と大きく伸長した。政策金利がマイナス0.75%とユーロ圏よりさらに低いデンマークではこの8月、ついにマイナス金利の住宅ローンが登場し、7─9月期の住宅ローン実行額は前年比で2.7倍に膨れ上がった。 金利がマイナスになっているからと言って、住宅ローンの場合は元本返済があるので、キャッシュが個人口座に振り込まれるわけではない。それでも、月々の支払いは都市部の平均家賃よりも少なくて済むため、個人の住宅取得意欲を高めるには十分なインセンティブになる。 住宅ローン増加の恩恵で、デンマークの一部大手行は10月、今年度の収益予想を引き上げた。ローンの借り換え手数料収益が増加した上、預金金利のマイナス幅の深掘りが貸出金利の低下をカバーしている。こうした好調な決算を受け、その他の銀行もマイナス金利の住宅ローンに追随する可能性がある。 <様々な歪みも表面化> 一方、マイナス金利が生む様々な歪みを指摘する声もこれまで以上に強まっている。 マイナス金利の元では預金が減っていくことになるため、人々はますます預金を増やさねばならないという思いに駆られる。ECBがマイナス金利を導入した時点で年3.4%だった預金の伸び率は、マイナス金利深掘り後の19年9月末も前年比5.0%と高止まりしている。欧州の消費者センチメント指数も、今は「貯蓄すべき時だ」と答える人の割合が「買い物をすべき時だ」と答える人を上回り、この2年で大きく増加している。 日本でも、マネックス証券が行っている日本の個人向けサーベイでは「今は貯金を殖やすべき時だ」と答える人の割合が過去2年間増加トレンドにある。これらを踏まえると、マイナス金利の消費刺激効果は限定的と考えざるを得ない。 また、マイナス金利が適用される預金の範囲にも問題がある。欧州では、マイナス金利は基本的に10万ユーロ以上の大口預金にのみ適用されている。これは預金保険のカバー対象と一致している。これ以下の預金は生活資金なので「懲罰金利」は適用しないという考え方だ。このため、金融機関からすると、小口預金は預金保険料が取られる上、マイナス金利も転嫁できないため、利益を出せない預金ということになる。長期的には、小口預金を拒むインセンティブが金融機関に働きかねない。 銀行がさらに過度なリスクテイクに走るのではないか、という指摘は多い。米国では債券発行額が過去最高レベルで推移しているが、その中で財務制限条項などが緩い債券の割合が過半を占めるまでに増加している。普通なら借りられない人に対するNon-QMと呼ばれる非適格住宅ローン(non-qualified mortgage)を裏付けとする社債も、前年比44%の急増ぶりなどと聞くと、かつてのサブプライム問題をほうふつさせる既視感がある。 しかも、消費者に恩恵を与えるはずの住宅ローンにも課題が見え隠れする。ドイツやデンマークなどの低金利の国では、住宅ローンの総額が大きく増加しているにも関わらず、国民の持ち家比率にはあまり変化は見られない。住宅ローンの増加は、物件価格の上昇によるものであり、個人の持ち家普及に貢献していない可能性がある。 <顧客への転嫁、邦銀に難題> 預金へのマイナス金利適用は、欧州では大手行にも広がりつつある。第3四半期決算後、ドイツ銀行やコメルツ銀行、イタリアのウニクレディトなども適用の可能性に言及している。環境の苦しさは日本の銀行も同じで、いよいよマイナス金利を顧客に転嫁する可能性も排除できないだろう。 仮に、欧州と同様に、預金保険上限である1000万円を超える預金にのみ0.1%のマイナス金利を転嫁した場合、国内銀行で年間合計1700億円の収益が見込める。これは、全銀行の業務純益合計の6%程度に相当する。悪くない収益源にはなるが、これによる弊害も考えざるを得ない。 2018年にオリコンが実施した利用者アンケートでは、約4割が預金金利がマイナスになったら口座を解約すると回答している。そうなると、おそらく1000万円に達しない範囲で預金を複数の銀行に分散しようというモチベーションが働く。各行は金融資産を自行に集約させ、富裕層ビジネスの強化を狙っているが、そうした戦略にはそぐわない結果を生んでしまう。 また、銀行同士の合併手続きも煩雑になるかもしれない。合併行の両方に口座を持つ預金者が、合併後に図らずも1000万円以上の残高になってしまう場合はどうするのか。その告知が必要になる上、預金が他行に逃げるという懸念もある。 これらのリスクを考えると、たとえ収益的にはプラスでも、地元密着で今後他行との統合の可能性も高い地方銀行が預金にマイナス金利を適用するのは得策ではないかもしれない。 <マイナス金利脱却にはなお時間> 各国の中央銀行も、当然のことながら、マイナス金利がもたらす様々な弊害は理解している。ならば、金利はいつ正常化できるのか。 スウェーデンのリクスバンク(中央銀行)は10月23日の金融政策決定会合で、12月の会合でマイナス金利から脱却することを示唆した。スウェーデンの民間債務の増加は著しく、国内総生産(GDP)比で280%に上り、住宅価格の上昇率も2010年から55%と先進国中有数のペースとなっている。 しかし、他の多くの先進国では経済成長に疑問符が付いており、物価の伸びも鈍い。このため、スウェーデンの利上げに追随しそうな国は現局面でみられない。現在、次回の政策会合で金利の引き上げが予想されているのは世界中でスウェーデンとメキシコのみ、との報道もある。 随所に広がる歪みを残したまま、マネーはどこまで膨らんでいくのだろうか。株高に活気づく金融市場の裏側で、マイナス金利という史上初の試みが世界経済の行く末に不安の影を落としている。 コラム:中国の「富裕化・肥満化・老化」で稼ぐ世界的製薬企業[ニューヨーク 4日 ロイター BREAKINGVIEWS] - お金持ちになるのは嬉しいが、肥満と老化は避けたいものだ。しかし世界的な製薬企業にとっては3つそろうのが好ましく、急速に人口動態が変化する中国で順調に売り上げを伸ばしている。例えば米メルク(MRK.N)は第3・四半期の中国での売上高が前年同期比84%も伸びた。3つの要因に加え、製薬企業におおむね好意的な中国政府の政策方針も追い風となっており、少なくとも中国国内のライバル企業が台頭してくるまでこの潮流は続きそうだ。 米アムジェン(AMGN.O)が10月31日、中国のバイオテクノロジー企業、百済神州(ベイジーン)(6160.HK)の株式を27億ドルで取得すると発表したことは、中国市場における商機の大きさを浮き彫りにした。百済神州はアムジェンのバイオ医薬品を中国で商品化する。英アストラゼネカ(AZN.L)の中国の売上高は40%増えた。ファイザー(PFE.N)の新薬もほぼ同程度、売り上げを伸ばしている。スイスのノバルティス(NOVN.S)は2023年までに中国で50種類の新薬を認可申請する計画だ。 しかも現在、中国市場の拡大は著しい。調査会社IQVIAによると、昨年の医薬品販売高は1370億ドルで、米国に次ぎ世界第2位の市場だ。メルクの売上高の7%、アストラゼネカの20%を占めている。 人口動態でビジネスのすべてが決まるわけではないが、製薬業界にとって好影響はある。中国は急速に裕福になり、高齢化も進んでいる。2002年には65歳以上の人口が全体の7%にとどまっていたが、世界銀行の推計では2050年には26%を占める見通しだ。中国人は健康状態も悪化している。米医学雑誌アナルズ・オブ・インターナル・メディシンの調査によると、過去10年間で肥満の人の比率は3倍の14%に高まった。この結果、循環器系の疾患や糖尿病、がんの患者が増えた。 中国政府はグローバルな製薬企業に概して好意的だ。デロイトによると、多国籍企業が昨年得た新薬の認可は40件と、2016年の3件から増えた。これは売り上げ増につながる。 一部には陰りもある。中国の消費者は伝統的に国内製のジェネリック医薬品を敬遠してきたが、国内製品の質向上に向けた取り締まりなどにより、一部グローバル企業の古い医薬品の利益率は圧縮された。仏サノフィ(SASY.PA)は心臓疾患治療に使われる「プラビックス」と高血圧症薬「アプロベル」の売上高が来年50%減少する可能性があるとしている。とはいえ、より高価な処方薬は堅調だ。 中国は科学者を多数輩出しており、規制によって国内企業の研究・開発支出を後押ししている。国内の巨大製薬企業が確固とした地位を築くには長年を要しそうだ。しかし主要産業で国内企業を育成してきた中国政府の実績を考えれば、グローバル企業は今のうちにわが世の春をおう歌するべきだろう。 ●背景となるニュース *アムジェンは10月31日、中国のバイオテクノロジー企業、百済神州(ベイジーン)の株式20.5%を27億ドルで取得し、中国での事業を拡大すると発表した。 *百済神州はアムジェンの抗がん剤3種類を中国で商品化することで合意した。アムジェンの抗がん剤開発にも協力する。 *サノフィは10月31日、中国での売上高が前年同期比14%増えたと発表した。医薬品とワクチンがけん引役となった。メルクは同29日、中国での売上高が前年同期比84%増加したと発表した。 (GDO)国内男子 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 最終日チェ・ホソンが今季初勝利 今平周吾とのマッチレース制す単独首位から出たチェ・ホソン(韓国)が4バーディ「67」で回り、通算14アンダーとして今季初優勝を飾った。昨年11月「カシオワールドオープン」以来の日本ツアー通算3勝目。同じ最終組で1打差2位から出た今平周吾とのマッチレースの様相を呈した。チェは前半8番(パー3)までに一時トップの座を明け渡したが、首位タイで迎えた後半17番でバーディを奪取。賞金ランキング1位の今平は同ホールでボギーをたたき、通算12アンダーの2位に終わった。通算11アンダーの3位にショーン・ノリス(南アフリカ)、ディラン・ペリー(オーストラリア)が入った。<上位成績>優勝/-14/チェ・ホソン2/-12/今平周吾3T/-11/ショーン・ノリス、ディラン・ペリー5T/-10/ブラッド・ケネディ、スコット・ビンセント7/-9/リチャード・ジョン8/-8/時松隆光9T/-7/アンジェロ・キュー、キム・ソンヒョン、トッド・ペク日米女子ツアー共催 TOTOジャパンクラシック 最終日鈴木愛が逃げ切りで米ツアー初優勝 渋野日向子は13位単独首位から出た鈴木愛が、国内ツアー今季6勝目(通算15勝目)で自身初の米ツアー大会制覇を遂げた。5バーディ「67」で回り、通算17アンダー。前年大会の畑岡奈紗に続く日本人チャンピオンが誕生した。2週連続で初日から首位を守る完全優勝を果たした。鈴木は前日2日目までに築いた3打のリードをハーフターンまでに5打にひろげた。バックナインはパーを並べ、独走のままノーボギーで最終18番(パー5)をバーディで締めた。鈴木と3打差の通算14アンダー2位にキム・ヒョージュ(韓国)。ミンジー・リー(オーストラリア)が11アンダーの3位に入った。6アンダー7位から出た渋野日向子は5バーディ、4ボギーの「71」で、通算7アンダーの13位タイ。前週Qシリーズを戦い、来季の米ツアー出場権を手にした河本結が「68」で回り6アンダー16位タイで終えた。〈上位陣の成績〉優勝/-17/鈴木愛2/-14/キム・ヒョージュ3/-11/ミンジー・リー4T/-10/ジェニファー・カップチョ、ヤン・ジン6T/-9/小祝さくら、菊地絵理香、フォン・シャンシャン、ギャビー・ロペス10T/-8/アサハラ・ムニョス、モーガン・プレッセル、ハンナ・グリーン本日の競技の成績速報が出ていますね。月例杯・西コースの部には70人が参加して、トップは85(17)=68とのこと。T君が86(12)=74で12位。E氏が91(16)=75で18位。僕が84(9)=75で19位。O君が91(16)=75で20位。M君が93(14)=79で41位。I君が87(7)=80で43位。U君が97(14)=83で56位。月例杯・東コースの部には72人が参加して、トップは81(16)=65とのこと。H君が79(11)=68で3位。お疲れ様でした。12月22日(日):シーダーヒルズCC ゴルフマスターズ杯参加してみますか…?
2019.11.10
コメント(0)
-

11月9日(土)…
11月9日(土)、晴れです。本当に好天が続いていますね。気持ちいい~!そんな本日は7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは…、1階・2階のモップかけ…、ベッドパッド干しですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで。美味い!!1USドル=109.27円。1AUドル=74.95円。昨夜のNYダウ終値=27681.24(+6.44)ドル。(ブルームバーグ)【米国株・国債・商品】株が続伸、最高値更新-米中の次の展開に期待 8日の米株式相場は続伸。関税を巡りさまざまなニュースが流れた1週間を最高値で終えた。米中貿易戦争での次の展開への期待も広がった。米10年債利回りは上昇。 米国株は続伸、最高値更新-ハイテクやヘルスケア高い 米国債は下落、10年債利回り1.94% NY原油先物は続伸、トランプ氏発言は材料視せず NY金先物は小幅続落、トランプ氏発言で一時は上昇 S&P500種株価指数は終値ベースの最高値を更新した。週間ベースでは5週連続高。世界的な成長を巡る問題が消えつつあるとの楽観から、買いが入った。テクノロジーとヘルスケア銘柄が上昇をけん引。一方、エネルギーと公益は下落した。ダウ工業株30種平均は小幅高で終了したものの、S&P500種とナスダック総合指数とともに最高値を更新した。 S&P500種は前日比0.3%上げて3093.08。ダウ平均は6.44ドル高い27681.24ドル。ナスダック総合指数は0.5%上昇。ニューヨーク時間午後4時50分現在、米国債市場では10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.94%。 暫定的な貿易合意への進展を巡り矛盾する内容の報道が相次ぐ中、投資家はここ2日間一喜一憂してきた。前日は米中両国の当局者が第1段階の貿易合意について、関税の段階的巻き戻しが盛り込まれると述べたが、トランプ大統領はこの日、米国は中国に対する関税の完全撤回に同意していないと発言。暫定的な貿易合意が近く結ばれるとの期待が後退した。 ベンシニョール・グループ創業者で、モルガン・スタンレーのストラテジストを務めた経歴を持つリック・ベンシニョール氏は、「投資家は概して、何かがやり遂げられると判断している。何らかの貿易合意が今後数カ月、恐らく年末までにあり得ると考えている」と指摘。「2つの国が一体となって何かをやり遂げられることを示す前向きな一歩だ」と述べた。 ニューヨーク原油先物相場は続伸。米国は対中関税を完全撤回することに同意していないとするトランプ氏発言を材料視しなかった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は9セント(0.2%)高い1バレル=57.24ドルで終了。週間では1.9%上昇。ロンドンICEの北海ブレント1月限は前日比22セント高の62.51ドル。 ニューヨーク金先物相場は小幅続落。米中貿易合意の進展を巡る相反する報道を背景に、日中は荒い値動きとなった。関税に関するトランプ氏の発言を受けて、第1段階の貿易合意の進展を巡る楽観が後退、金は一時上昇する場面もあった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%安い1オンス=1462.90ドルで終了。週間では3.2%下落。【NY外為】ドルと円が上昇、貿易巡るセンチメント悪化 8日のニューヨーク外国為替市場ではドルと円が上昇。一方、高リスク通貨はさえないパフォーマンスとなった。米中貿易交渉に対する市場のセンチメントが悪化した。 ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇、3週間ぶりの高水準 週間ベースでは0.9%上昇。今週は米中が部分的な貿易合意に向けて進展していると伝わり、米国株が上昇、10年債利回りは約3カ月ぶりの高水準に達した 中国に対する関税を完全に撤回することに米国は同意していないとトランプ大統領が述べた後、リスク選好ムードが後退。円が買いを集めた ニューヨーク時間午後4時22分現在、ポンドは0.2%安の1ポンド=1.2787ドル手掛かり材料が乏しい中、3週間ぶり安値をつけた 英総選挙に関する最新情報が待たれている。ユーガブの最新世論調査では、与党保守党のリードが2ポイント縮小 週明け11日の米祝日を控え、出来高は少なかった-欧州拠点のトレーダー ドルは対円で0.1%安の1ドル=109円22銭 ニューヨーク時間の序盤に109円48銭まで上昇-前日の日中高値をごくわずかに下回る水準 米10年債利回りは一時1.95%に上昇 ユーロはドルに対して0.3%安の1ユーロ=1.1022ドル 一時は1.1017ドルに下げる場面があった 週間ベースでは1.3%安トランプ大統領、関税撤回での米中合意を否定-期待に水を差す トランプ米大統領は中国に対する関税を完全に撤回することに、米国は同意していないと述べた。米中貿易合意をまとめるために米国が関税で譲歩するとの期待は、この発言で薄れた。 大統領は8日、記者団に対し「中国は撤回を望むだろうが、私は何にも同意していない」と説明し、「中国は関税の撤回を望むだろうが、完全な撤回ではない。私がそれには応じないことを中国は知っているからだ」と述べた。 トランプ大統領の発言を受け、米国債は上昇、米国株は下落した。高まっていた米中合意への楽観が後退した。 クドロー米国家経済会議(NEC)委員長は前日、米中両国が「第1段階の合意に至れば、関税の合意・譲許もあるだろう」と語った。 大統領はこの日、米国がまだ合意に達していないことを明確にした上で、関税を全面撤回することはないと強調した。人気の高い消費財を対象とした関税が12月15日に発動する予定だが、第1段階の貿易合意の一環として見送られるとの期待がある。 米中貿易合意の署名場所についてトランプ氏は、「実現するまで話したくないが、仮に合意がまとまったとして、署名する場所はアイオワ州などの農業地帯になるだろう」と述べ、米国内だと話した。(ロイター)世界の億万長者資産、18年は3年ぶり減 中国の落ち込み目立つ[8日 ロイター] - スイス金融大手UBSと大手会計事務所プライスウォーターハウスクーパース(PwC)が8日発表した報告書によると、世界の億万長者(ビリオネア)の総資産は昨年時点で8兆5000億ドルとなり、前年比4.3%減少した。減少は2015年以来3年ぶり。 地域別では、米国の総資産が0.1%微増の3兆6000億ドル。億万長者の数は19人増の89人。 アジア太平洋(APAC)の総資産は8%減の2兆5000億ドル。中国の景気減速や米金利上昇の煽りを受けた。億万長者の数は60人減の754人。 中国の総資産は12.3%縮小して9824億ドル。人民元CNY= CNY=CFXS CNY=SAECが対ドルで約6%下落したほか、MSCI中国株指数(MCHI.O)は約20%値下がりし、2011年以降でもっと大幅な落ち込みを記録した。 ただ、過去5年間で見ると中国の総資産は約3倍に拡大。18年末時点で世界の億万長者資産の約8分の1を占めている。 欧州・中東・アフリカ(EMEA)の総資産は6.8%減の2兆4000億ドル。億万長者の数は31人減の598人。 UBSの幹部は今年の見通しについて、再び増加が見込まれるものの伸びは控えめになる見通しだと語った。ドル指数上昇、米中関税撤廃巡る不透明感で安全買い=NY市場[ニューヨーク 8日 ロイター] - ニューヨーク外為市場では、ドル指数が3週間ぶりの高水準を付けた。米中追加関税撤廃を巡る不透明感が高まる中でリスク選好度が低下し、安全資産とされるドルに買いが入った。同様に安全資産と見なされる円も買われた。 米中は7日、「第1段階」の通商合意の一環として、双方が貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に撤廃することで合意。ただ、追加関税の段階的撤廃にはホワイトハウス内外から強い反発の声が出ていることも明らかになった。 この日はトランプ米大統領が対中関税の撤回には合意していないと表明。開始からすでに1年4カ月が経過している米中貿易戦争がいつ終結するのか、疑念が再燃した。 ナットウエスト・マーケッツ(コネチカット州)のG10外為戦略部門責任者、ブライアン・ダインジャーフィールド氏は「関税撤廃を巡る不透明感が根底に存在していることが相場を動かす大きな要因となっている」と指摘。ただ、通商合意に向けた取り組みが続いていることでリスク資産に対する市場心理は当面下支えされるとみられ、「追加関税措置の撤廃に向け何らかの協議が行われていることは歓迎すべきことだ」と述べた。 主要6通貨に対するドル指数.DXYは主にドルの対ユーロでの上昇に押し上げられ、一時は3週間ぶりの水準に上昇。終盤の取引では0.2%高の98.362となっている。 キャピタル・エコノミクス(ロンドン)のシニア市場エコノミスト、ジョナス・ゴルターマン氏は、通商を巡る緊張が高まっている間はドルは底堅く推移すると予想。「金利差が短期的にドルの大きな押し上げ要因になるとは予想していない」とし、「貿易加重ベースでドルはすでに2000年代初頭以来の高値に近づいているにもかかわらず、通商問題と世界的な景気減速が根強く継続していることが要因となり、ドルは2020年は一段と上昇するだろう」と述べた。 ユーロ/ドルEUR=は0.3%安の1.1020ドル。ドル/円JPY=は0.1%安の109.17円。 カナダドルCAD=D3は対米ドルで下落。10月の雇用統計で雇用者数が予想に反して減少したことで売られ、終盤の取引で対米ドルで0.4%安の1.3228カナダドルとなった。 ケンブリッジ・グローバルペイメンツの市場ストラテジスト、ドン・カレン氏は、この日の雇用統計を受けカナダ銀行(中央銀行)は向こう数カ月で利下げに踏み切る可能性があるとの見方を示した。 ドル/円 NY終値 109.27/109.30 米主要株価指数が最高値更新、ウォルト・ディズニー高い[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米国株式市場は上昇し、主要株価指数が揃って最高値を更新。S&P総合500種指数.SPXが週間で5週連続で値上がりした。 米中通商協議を巡っては、トランプ大統領が8日、対中関税の撤回で合意していないと明らかにした上で、中国が自身に関税撤回を望んでいるとの認識を示した。米中が貿易戦争を終結させる時期を巡って疑念が再燃した。 中国共産党系メディア「環球時報」の胡錫進編集長はツイッターで、トランプ氏の発言は市場で予想されていなかったと指摘。トランプ氏は全面的に否定したわけではないとした上で「関税撤廃がなければ、第1段階の合意はないだろう」と述べた。 インバーネス・カウンセル(ニューヨーク)の主任投資ストラテジスト、ティム・グリスキー氏は、トランプ氏発言で相場は振れが大きくなったものの、その後は買いが戻ったと指摘。「部分合意にせよ年末までには何らかの合意が得られるという期待がある」と述べた。 株式投資家の不安心理の度合いを示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数).VIXは12.07と、7月24日以来の低水準で引けた。 個別銘柄では娯楽大手のウォルト・ディズニー(DIS.N)が3.8%高。第4・四半期(7─9月)決算は、利益が市場予想を上回った。好調なテーマパーク事業や、実写版「ライオン・キング」など映画の興行収入が寄与した。動画配信サービスに絡んだコストも、自社予想ほど拡大しなかった。 マイクロソフト(MSFT.O)は1.2%高。一方、衣料品大手ギャップ(GPS.N)は7.6%安。アート・ペック最高経営責任者(CEO)の退任を発表し、通年の利益予想を下方修正した。 ニューヨーク証券取引所では、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.07対1の比率で上回った。ナスダックでは1.13対1で値上がり銘柄数が多かった。 米取引所の合算出来高は65億9000万株。直近20営業日の平均は67億9000万株。 (yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)NY市場概況-ダウ6ドル高と小幅続伸 3指数がそろって最高値を更新 8日のNY株式相場は続伸。トランプ米大統領が、中国側が発表した「関税撤廃で合意」を否定したことで朝方は軟調に推移したものの、何らかの合意に達するとの期待も強く、引けにかけて主要3指数がそろってプラス圏を回復した。ダウ平均は午前中に95ドル安まで下落したが、6.44ドル高(+0.02%)で終了し、わずかながら2日続伸。前日に続いて終値での史上最高値を更新した。ボーイングが1.77%安となり1銘柄でダウ平均を43ドル近く押し下げたものの、好決算を発表したウォルト・ディズニーが3.76%高となったほか、ジョンソン・エンド・ジョンソン、マイクロソフトも1%超上昇し、3銘柄でダウ平均を56ドル押し上げた。S&P500も0.26%高と3日続伸し、最高値を更新。エネルギー、公益、不動産が下落したものの、ヘルスケア、ITの上昇が指数を支えた。ハイテク株主体のナスダック総合も0.48%高と2日続伸し、最高値を更新した。 週間では、ダウ平均が1.22%高と3週続伸、S&P500が0.85%高と5週続伸、ナスダック総合は1.06%高と6週続伸。年初来ではダウ平均が18.66%高、S&P500が23.39%高、ナスダック総合が27.73%高となった。 寄り後に発表された10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値は95.7と市場予想の95.9を下回るやや弱い結果となったが、債券売り・株買いの流れが続いた。前日に一時1.973%まで上昇した米10年債利回りは0.023%上昇し、1.945%で終了。週間では利回りが0.217%上昇した。株式市場でもディフェンシブ株に売りが続いた。S&P500の公益指数は週間で3.72%安、不動産指数も3.67%安となった一方、利ざや縮小による収益悪化懸念が後退した金融指数は2.43%高となった。(yahoo)(フィスコ)NY株式:上昇、米中協議を見極めたいとの思惑が強まる米国株式相場は上昇。ダウ平均は6.44ドル高の27681.24、ナスダックは40.80ポイント高の8475.31で取引を終了した。トランプ大統領が中国との段階的な関税措置の撤廃には以前合意していないと述べ、売りが先行。米政権内部で中国への追加関税撤廃に反対する見方もあり、米中協議の楽観的な見方が後退した。主要株価は最高値圏で推移しており、利益確定の動きも広がり、小動きとなった。セクター別では、医薬品・バイオテクノロジーや自動車・自動車部品が上昇する一方で電気通信サービスやエネルギーが下落した。アパレルのギャップ(GPS)は、通期の利益見通しが予想を下振れたほか、ペックCEOの退任を発表し、下落。エネルギー会社のデューク・エナジー(DUK)は、売上高が予想を下振れ、軟調推移。一方で、不動産情報のジロー・グループ(Z)は、決算内容が好感され、大幅上昇。エンターテイメントのウォルト・ディズニー(DIS)は、決算内容が予想を上振れ、堅調推移となった。ナバロ米大統領補佐官は、12月15日に発動予定の対中関税を先送りする可能性を示唆した。(Horiko Capital Management LLC)《TN》国内株式市場見通し:目先調整もバブル崩壊後の最高値を意識へ■日経平均は5週連続高、連日の高値更新前週の日経平均は上昇した。5週連続高を見て週間では541円の上昇幅となった。3連休明けとなった週初5日の日経平均は、前週末比401.22円高の23251.99円と大幅高し、終値としても10月29日の年初来高値を更新した。日本の3連休中、NYダウは大幅続伸し、約3カ月半ぶりに最高値を更新した。10月雇用統計で雇用者数の伸びが市場予想を上回ったほか、トランプ大統領が米中貿易協議の合意「第1弾」の署名場所について言及したことが好感された。東京市場では、日経平均が23328.52円(前週末比477.75円高)まで上昇する場面があるなか、米中摩擦の懸念後退から、コマツが5%超上昇するなど景気敏感株が大きく買われたほか、富士フイルムが富士ゼロックスを巡る報道を受け急伸した。5日のNYダウ、ナスダック指数がともに連日で最高値を更新し、6日の日経平均も小幅続伸し年初来高値を更新した。短期的な過熱感から利益確定売りに下げに転じる場面もあったが、為替の円安・ドル高も支えとなって大引けにかけて持ち直した。米中首脳会談の開催時期が12月にずれ込む見込みと報じられ、7日の東京市場は朝方から利食い売りが先行して始まったものの、日経平均は大引けに掛けてプラス圏に引き戻して3日続伸し、終値ベースで連日の年初来高値更新。ファンド事業の損失計上で7-9月期が大幅赤字になったソフトバンクグループが朝安後は下げ渋りに転じる一方、決算が好感されたオリンパスが一段高、後場の取引時間中の決算発表後に買い優勢となったトヨタの上昇が好地合いを継続させた。7日の米国市場は、米中両国が段階的な関税措置の撤廃で合意と伝わったことに加えて、長期金利の上昇を受けて金融セクターを中心に買いが広がり、NYダウとS&P500指数はともに最高値を更新した。この流れを受けて8日の日経平均も4日続伸で連日の年初来高値更新。一時260.77円高の23591.09円まで上げたが、米中貿易協議を巡り、米大統領補佐官による現時点での合意を否定した発言が報じられ、前引け間際にマイナス圏に入る場面もあった。ただ、その後は持ち直し61.55円高の23391.87円で大引けた。■日経平均は23000円台で日柄調整今週の日経平均は、23000円台での日柄調整に転じてきそうだ。追加関税における段階的な撤廃で合意など米中協議の進展と米国株高、為替の円安を背景に、今週の日経平均の上げ幅は541円強、5週連続高となったこの間の上げ幅は1981円超に達している。7日の時点で25日騰落レシオが134%台となるなど高値警戒感は高まっており、上値追いに慎重になるのは自然な流れでもある。8日の日経平均が、SQ値23637.93円を前にして失速したことで、目先はこのSQ値が一つの上値メドとして意識されてくることにもなりそうだ。引き続き、米中貿易協議の進展に向けたニュースに敏感に反応する地合いが継続することにもなるだろう。また、13日に予定されるパウエルFRB議長による米議会の上下両院合同経済委員会の公聴会における議会証言と、14日に集中している10月小売売上高などの中国経済指標も気掛かり材料だ。15日に予定されている10月小売売上高など米国の経済指標については、いずれも、東京市場の大引け後の発表時間であり、週末にかけての手控え要因として働きやすい。しかし、全般が調整に転じたとしても、大きな崩れを引き出す悪材料も見当たらないなか、日経平均は23000円台の高値圏でのもち合い推移を維持することが見込まれる。ここからは、昨年10月2日に付けたバブル崩壊後の最高値24448.07円に向けた波動に入る準備局面入りと見ることができる。■決算発表は14日で一巡こうしたなか、今シーズンの決算発表は14日で一巡する。主要銘柄では、11日に大林組、12日に富士フイルム、日産自動車、13日にリクルートHD、三菱UFJ、14日に日本郵政、みずほFGが予定している。決算悪が警戒されたソフトバンクグループの株価が持ち直し、事前予想を上回った決算のトヨタが堅調に推移していることで業績に対する警戒感は後退している。今週は半導体関連人気が一巡して、紙パルプ、海運などにも物色の矛先が向いたが、引き続き、相場的に出遅れた業種・銘柄での循環物色が続きそうだ。■10月工作機械受注、FRB議長の議会証言、中国10月小売売上高主な国内経済関連スケジュールは、11日に10月景気ウォッチャー調査、9月機械受注、10月30日・31日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、12日に10月マネーストック、10月工作機械受注、13日に10月国内企業物価指数、14日に7-9月期GDPの発表がそれぞれ予定されている。一方、米国など海外主要スケジュールでは、13日に米10月消費者物価、米10月財政収支、パウエルFRB議長の議会証言、14日に中国10月小売売上高、米10月生産者物価、15日に米10月小売売上高、米10月輸出入物価が予定されている。このほか、11日は中国光棍節(独身者の日)、13日はBRICS首脳会議(14日まで、ブラジル)が予定されている。(yahoo)(モーニングスター)株式週間展望=一段高意識も警戒含み―「パウエル発言」注目、金融政策方向性占う 調整知らずの日経平均株価は今週(5-8日)、早々に終値でも2万3000円台を回復するとその後も上げ幅を拡大した。TOPIX(東証株価指数)も終値ではほぼ1年ぶりに1700ポイントに乗せた。米中貿易協議をめぐる懸念後退や、米国景気の底堅さを背景にリスクオンムードが保たれている。ただ、一方では高値警戒感が根強く、来週(11-15日)はもう一段高を意識しつつも「パウエル発言」に注意したい。 今週の日経平均は全4営業日で上昇し、8日は2万3391円(前週比541円高)で引けた。一時は2万3500円台まで上伸し、年初来高値の更新が続く。年末高を視野に、バブル崩壊後の最高値(昨年10月の2万4448円)奪回は日々現実味を増している。 ただ、ここ1カ月の日経平均の上昇幅は2000円を優に超え、過熱感を指摘する声も少なくない。実際8日は、最大260円あった前日比の上げ幅を完全に失い、マイナス圏に突っ込む場面もみられた。米中協議について、追加関税の撤廃へ向けた段階的な引き下げで合意したとする中国当局の発表を、その後にナバロ米大統領補佐官が打ち消す発言が伝わったことがきっかけだ。 また、米国の金融政策に関しても、来週は市場心理を左右しかねないイベントが控える。それが、現地13、14日に予定されているパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長による議会証言だ。 直近10月29、30日のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、3会合連続の政策金利の引き下げが打ち出された。一方で米国の経済指標は堅調だ。パウエル議長は経済見通しを示すとみられるが、その内容は今後の政策の方向性を決める1つの要素となる。 オプション取引の値動きを基に米シカゴ・オプション取引所が算出するVIX指数が低位で推移していることから分かる通り、投資家の持つ先行き不透明感が薄い状況にある。半面、需給面ではVIX指数先物の売り残が歴史的高水準となっており、一つのきっかけで抑制されてきた不安が噴出しかねない下地ができている。 来週は、引き続き米中協議の成り行きをにらみ、パウエル発言にも備える局面となる。経済指標は国内で11日に9月機械受注と10月景気ウオッチャー調査、12日に10月工作機械受注の速報値、14日に7-9月期GDP(国内総生産)の一次速報が出る。海外は13日に米10月消費者物価指数、14日に中国10月鉱工業生産や同小売売上高など。15日には、米10月小売売上高や11月ニューヨーク連銀製造業景況指数が発表される。 残り少ない決算は11日の大林組 や13日のリクルートホールディングス 、三菱UFJフィナンシャル・グループ 、14日のみずほフィナンシャルグループ 、日本郵政 など。海外は14日のアプライド・マテリアルズやエヌビディアに注目したい。 日経平均の想定レンジは2万2800-2万3700円とする。(市場動向取材班)(yahoo)(株探ニュース)今週の【早わかり株式市況】5週間で2000円近く上昇、米中交渉の進展期待で上げ加速■今週の相場ポイント 1.日経平均は大幅高で5週連続の上昇、押し目待ちに押し目なしの超強調展開続く 2.米中貿易交渉の進展期待を背景にリスクオン相場が加速、米株高に追随する展開 3.ハイテクなど世界景気敏感株を中心に買われ、為替市場の円安進行も追い風材料 4.ソフトバンクGは決算悪も下げ幅限定的、トヨタは好決算背景に年初来高値更新 5.週末も利益確定の売り圧力をこなし日経平均は上昇波継続、新値街道を走る展開■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比541円(2.37%)高の2万3391円と5週連続で上昇した。5週間の上げ幅は1981円に達した。 今週は米中貿易交渉の進展に対する期待を背景に、上昇相場が加速。最高値圏を急ピッチで駆け上がる米国株市場を横目にリスク選好の流れが一気に強まり、日経平均は週初の急騰を皮切りに連日で新値圏を進む展開となった。 3連休明けとなった5日(火)は、米国株市場が前週末金曜日と東京市場が休場だった週明け月曜日に大きく水準を切り上げたことを受け、リスクを取る動きが加速した。貿易協議の部分合意が接近しているとの思惑から米中対立への警戒感が緩み、ハイテクなど世界景気敏感株を中心に買われ、日経平均は一時470円強の上昇。大引けも401円高で2万3000円台を上回り年初来高値を更新、リスクオン相場の様相を極めた。6日(水)は外国為替市場で円安が進んだことなどを追い風に続伸。更に7日(木)も利益確定の売り圧力をこなし小幅ながら高く引けた。前日に7-9月期最終損益7000億円の赤字決算を発表したソフトバンクグループ の下げ幅が限定的だったことや、この日の取引時間中に好決算を発表したトヨタ自動車 が新高値に買われるなど、総じて強い地合いを印象付けた。週末の8日(金)も米中貿易協議の進展期待を背景とした好調な米国株の後を追う形で買い優勢で始まったものの、米中交渉への不透明感が再燃したことで一時マイナス圏に沈む場面もあった。ただ、物色意欲が強く大引けにかけて買い戻されプラス圏で着地し、4日続伸となった。■来週のポイント 超強調相場が続いているだけに、来週は年末に向けて2万4000円を目指す展開が期待される。ただ、米中貿易協議を巡って不透明感が再燃すれば調整する場面もありそうだ。 重要イベントとしては、国内では11日朝に発表される9月機械受注統計や14日朝に発表される7-9月期GDPが注目される。海外では14日に発表される中国10月の小売売上高と鉱工業生産や、15日に発表される米国10月の小売売上高と鉱工業生産に注視が必要だろう。なお、独身の日である11日は中国でアリババなどが大規模なネット通販セールを実施する。■日々の動き(11月5日~11月8日)【↑】 11月 5日(火)―― 大幅反発、リスクオン一色で新高値更新 日経平均 23251.99( +401.22) 売買高16億6076万株 売買代金 3兆0554億円【↑】 11月 6日(水)―― 続伸、米株高や円安で利食いを吸収し連日の新高値 日経平均 23303.82( +51.83) 売買高13億8852万株 売買代金 2兆4823億円【↑】 11月 7日(木)―― 3日続伸、朝安も引け際に買われ年初来高値を更新 日経平均 23330.32( +26.50) 売買高12億6775万株 売買代金 2兆3894億円【↑】 11月 8日(金)―― 4日続伸、連日の高値更新も朝高後は上昇幅縮小 日経平均 23391.87( +61.55) 売買高16億2680万株 売買代金 3兆1255億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、31業種が上昇 (2)国際石開帝石 など鉱業、JXTG など石油株が大幅反発 (3)DOWA など非鉄、日本製鉄 など鉄鋼、川崎汽 など海運といった景気敏感株が買われた (4)野村 など証券、第一生命HD など保険、三菱UFJ など銀行といった金融株は高い (5)オリンパス など精密、トヨタ など自動車といった輸出株も堅調 (6)内需株はセブン&アイ など小売り、日通 など陸運は上昇も 菱地所 など不動産、中部電 など電力・ガスは低調■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(2) 5G ────── 米「クアルコム」決算を受け再注目も 2(3) 全固体電池 3(1) 半導体 4(4) 半導体製造装置 5(7) 人工知能(AI) ※カッコは前週の順位株探ニュース(minkabu PRESS) 昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の12銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。そうこうしているうちにこんなモノが届きました…DERA-MAX 04 52D(S)ですね。活躍してくれるでしょうか?(GDO)国内男子 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 3日目チェ・ホソンが首位浮上 今平周吾が1打差3打差の3位で出たチェ・ホソン(韓国)が6バーディ、3ボギーの「68」でプレーし、通算10アンダーとして首位に立った。2018年11月「カシオワールドオープン」以来のツアー通算3勝目に向け、1打差で最終日を迎える。通算9アンダーの2位に賞金ランキングトップの今平周吾がつけた。リチャード・ジョン(カナダ)とスコット・ビンセント(ジンバブエ)が通算7アンダーの3位で続いた。2位から出た宮本勝昌は通算4アンダーで池田勇太らと並んで8位となった。<上位成績>1/-10/チェ・ホソン2/-9/今平周吾3T/-7/R.ジョン、S.ビンセント、5T/-6/D.ペリー、B.ケネディ7T/-5/S.ノリス8T/-4/R.ワナスリチャン、木下稜介、キム・ソンヒョン、T.ペク、池田勇太、宮本勝昌日米女子ツアー共催 TOTOジャパンクラシック 2日目逆転賞金女王へ向けて今季6勝目を狙う賞金ランキング3位の鈴木愛が、首位タイから出て7バーディ、ボギーなしの「65」をマーク。通算12アンダーで単独首位に立った。2週連続優勝を目指し、後続に3打リードで最終日を迎える。通算9アンダー2位にギャビー・ロペス(メキシコ)がつけた。通算8アンダー3位に今季海外メジャー覇者のハンナ・グリーン(オーストラリア)、キム・ヒョージュ(韓国)の2人。通算7アンダー5位にミンジー・リー(オーストラリア)、フォン・シャンシャン(中国)が並んだ。9位から出た渋野日向子は2日連続の「69」で通算6アンダーとし、菊地絵理香、黄アルム、チェ・チェラ(ともに韓国)、ジェニファー・カップチョ、ヤン・ジン(中国)と並んで7位につけた。昨年大会覇者の畑岡奈紗は「76」で通算3オーバー63位に沈んだ。1/-12/鈴木愛2/-9/ギャビー・ロペス3T/-8/ハンナ・グリーン、キム・ヒョージュ5T/-7/ミンジー・リー、フォン・シャンシャン7T/-6/渋野日向子、菊地絵理香、ジェニファー・カップチョ、チェ・チェラ、ヤン・ジン、黄アルム
2019.11.09
コメント(0)
-

11月8日(金)…
11月8日(金)、晴れです。気持ちの良い天気が続きますね。ブラボ―!!そんな本日は7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分頃には家を出る。ゴルフではありません…、アルバイト業務です。ついでに奥は名古屋へお出かけのご様子…。本日は10:00~16:00の勤務予定。昼食インターバルは1:00ですね。各地で道路工事をしていて到着は少し遅れる…。お昼にはサンドイッチとドリンクを用意して職場の近くをドライブ…。目的地の道の駅:はなもも街道へ。まだ紅葉は見られませんね…。中にはこんな樹も見られますが…。川べりのベンチで昼食を済ませる。良い気分で食事できました!!職場に戻って午後の部を済ませる。帰宅するとまだ奥は戻っていません。奥の自家製アップルパイですが…、ちょっと焼き過ぎました…。遅めのおやつタイムはちょっと失敗…。1USドル=109.25円。1AUドル=75.19円。昨夜のNYダウ終値=27674.80(+182.24)ドル。本日の日経平均終値=23391.87(+61.55)円。金相場:1g=5713(-64)円。プラチナ相場:1g=3605(-53)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の14銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の20銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。(ブルームバーグ)日本株は小幅続伸、米中楽観や金利上昇-自動車や金融高く不動産安い 8日の東京株式相場は小幅に4日続伸。米中の貿易合意が楽観視される中、自動車など輸出関連や商社など景気敏感、銀行など金融株が上げた。半面、金利上昇デメリット業種の不動産や建設、電気・ガスは安く、決算失望の資生堂も売られた。 TOPIXの終値は前日比4.64ポイント(0.3%)高の1702.77 日経平均株価は61円55銭(0.3%)高の2万3391円87銭 〈きょうのポイント〉 米中は相互の製品に賦課している関税を段階的に撤回することで合意 7日の米10年債利回りは1.92%、9ベーシスポイント上昇 きょうのドル・円相場は1ドル=109円10-40銭台、前日の日本株終値時点は108円76銭 営業利益予想を引き下げた資生堂がTOPIX下落寄与度1位 三菱UFJ国際投信の向吉善秀シニアエコノミストは「米大統領選挙が本格化してくる中で、トランプ氏は選挙にマイナスとなることを実行しにくくなっているイメージがある」と語る。米中摩擦の影響で足元の決算は厳しいものの、「今年度が業績のボトムとの見方が市場で固まってきている。来期決算への期待から日本株は来週も上値を試しそうだ」とみている。 景気や業績の先行き期待が継続し、TOPIXは終値で昨年10月以来の1700ポイント台を回復した。みずほ証券の倉持靖彦投資情報部長は「米株式市場では金融や資本財、素材に物色の矛先が向かい、商品市場では金から銅へと資金がシフトするなど、投資対象がシクリカルバリューとなっている。米長期金利の上昇が背景」と指摘。チャート分析からは米長期金利が2.15%、ドル・円相場は1ドル=111円台後半まで円安に振れてもおかしくなく、「景気敏感の日本株は上がりやすい」と言う。 ただ、日経平均が一時マイナス圏に転落するなど上値は重かった。倉持氏はテクニカル的な過熱感から「加速的に上値を追っていくのは難しい」と話した。日経平均に短期過熱警戒の記事はこちらをご覧ください 東証33業種では精密機器や鉄鋼、輸送用機器、卸売、ガラス・土石製品、食料品、銀行、石油・石炭製品が上昇 化学のほか、不動産、電気・ガス、建設、陸運など金利上昇デメリット業種は安く、東証REIT指数は大幅安安全資産が軒並み下落、金も国債も円も-「世界の終わり」取引が崩壊 投資家は今年の大半、貿易戦争と成長減速が最終的には世界経済をリセッション(景気後退)に陥れると考え、金や国債などの安全資産に逃避してきたが、「世界の終わり」を見込むこうした取引が7日、逆噴射に見舞われた。 金は一時、1オンス当たり30ドル下落、米国債は夏以降で最大の値下がり、ディフェンシブ株も売られた。米中貿易休戦の兆候がこの動きのきっかけになった。 ビスポーク・インベストメント・グループのマクロストラテジスト、ジョージ・ピアクス氏は「夏の終わりごろには債券やイールドカーブがリセッションまっしぐらを示唆していた」が突然、「リセッションにならないばかりか成長が上向くとの見方になった」と指摘した。 米中「第1段階」合意、関税巻き戻し盛り込むと米国 国債は世界で下落し、10年物米国債利回りは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。フランスとベルギーの10年債利回りは数カ月ぶりにプラス圏を回復。世界のマイナス利回り債券残高は約12兆5000億ドル(約1365兆円)に減少した。金相場は7日に1.5%下落。 フランスの10年国債利回りがプラス圏回復、米国債利回りも上昇 円も下げ1ドル=109円台となった。週初来ではドルに対して約1%下落。アジア太平洋地域の債券も8日に値下がりし、日本の10年国債利回りは週間ベースで6年以上で最大の上昇に向かっている。東証REIT指数急落、金利低下圧力和らぎ調整売りとの声-チャート 8日の東証REIT指数は一時2.9%安の2168.94まで下げた。下落率は2018年2月6日以来の大きさ。三菱UFJ国際投信の向吉善秀シニアエコノミストは「(株式のPBRにあたる)NAVレシオのバリュエーション面から見てやや割高感が出てきたところに金利上昇が加わったため、金利変動を調整する格好で利益確定売りが出ている」と指摘した。REIT相場は年明けから右肩上がりの相場が続き、高値警戒感が出やすい。向吉氏はスピード調整的な側面が強く落ち着けば再び投資資金が入るとの見方も示し、「大きく崩れるイメージにはない」とみていた。(ロイター)来週はドル110円を試すか、米中交渉を巡る思惑と金利動向が鍵[東京 8日 ロイター] - 来週の外為市場では、米中通商交渉に対する楽観的な見方を背景とする株高や米長期金利高の持続可能性が鍵を握りそうだ。期待先行の楽観論が維持されれば、金利面で優位に立つドルは110円台を試すとみられる。 予想レンジはドルが108.00━110.30円、ユーロが1.0950―1.1150ドル。 米中は7日、通商協議の「第1段階」の合意の一環として、双方が貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に撤廃することで合意した。 ただ、追加関税の段階的撤廃には米政権内に強い反対論があるとのロイターの報道を受け、米主要株価指数は上げ幅を縮小した。[nL3N27N4UC] 来週の相場について市場では「ドル高地合いが続けば110円台ワンタッチもあり得るとみているが、米中協議は期待先行の部分も大きく、思惑通りに協議が進まなければドル高/円安の巻き戻しもあり得る」と上田東短フォレックスの営業推進室長、阪井勇蔵氏はいう。日米株価の過熱感や実体経済の実力にそぐわない米長期金利の過度な上昇もリスク要因だという。 米政府高官は6日、米中の第1段階の合意の署名が12月にずれ込む可能性があるとロイターに明らかにした。 署名の場所を巡っては、トランプ大統領はこれまでに米国内有数の穀倉地帯とされるアイオワ州で署名する可能性を示していたが、その可能性は排除されたもよう。また、中国からは「一帯一路」政策の西の拠点となるギリシャ案が出されたが、米政府筋はその可能性を否定した。 金利差では「ドル優位」が続きそうだ。 米10年国債利回りUS10YT=RRは7日に1.9730%と3カ月ぶり高水準に達した。同利回りは10月29―30日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の後に1.6700%まで低下していた。 「日本、ユーロ圏、英国と金融緩和の方向性が明確な一方で、米国は12月に追加緩和を見送るとみている。年末に向かってドル需給が逼迫しやすいという季節性もあり、ドルは110円台を目指すだろう」とFXプライムbyGMO、常務取締役の上田眞理人氏は予想する。さらに、米中交渉で極端に悪い材料が出てこないという前提で「ドルが110円に乗せたとしても、達成感から売られるリスクは限定的」(同)だという。 足元のドル高にはユーロ圏経済の一段の減速も寄与している。 国際通貨基金(IMF)は6日、ユーロ圏19カ国の今年の成長率見通しを1.2%とし、4月予測の1.3%から下方修正した。ドイツは0.5%と昨年実績の1.5%から大幅に低下する見込みだ。 来週の日本株は堅調、高値警戒感を「買わざるリスク」が打ち消す[東京 8日 ロイター] - 来週の東京株式市場は、堅調な展開が想定されている。最大の懸念材料だった米中通商協議で、双方が歩み寄りをみせ、環境面の重しが取れた格好となった。買わざるリスクが台頭しており、これまでの上昇で生じている高値警戒感を良好な需給が打ち消す可能性もある。ただ、過去の経緯から、トランプ米大統領が対立解消に向けた交渉を台無しにする可能性もあり、そうなった場合の波乱を警戒する関係者も少なくない。 日経平均の予想レンジは、2万3200円─2万3700円 行方が注目されていた米中通商協議は、貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に撤廃する方向となり、世界的な景気悪化懸念が後退。これまで、米中対立が世界的に景気を悪化させる要因になるとみられていたため、相場を取り巻く環境は著しく好転した。 市場では「投資の前提が覆った。今後はこれまでと反対に景気の上向きを買うような動きになる」(東洋証券・ストラテジストの大塚竜太氏)との声が出ており、決算発表シーズンが終盤を迎える中で、好決算銘柄に見直し買いが入る可能性もある。 需給面については「ほとんどの投資家が安いところで買えていない。弱気でみていた人がこれから上昇を織り込みに行く」(東海東京調査センター・チーフエクイティマーケットアナリストの鈴木誠一氏)との声が出ていた。環境の変化から、上げに耐えていた売り方の踏み上げを読む関係者もいる。 さらに、海外勢が買い姿勢を強めていることも見逃せない。財務省が8日に発表した10月27日─11月2日の対外及び対内証券売買契約等の状況 (指定報告機関ベース)によると、対内株式投資は4209億円の買い越しだった。「このところの外国人投資家の買いは、IMFが経済見通しで主要国で日本のみ上方修正したことが背景にある。アンダーウエートにしたまま日本株が上昇すれば、言い訳ができないので、今後もこの流れは続きそうだ」(大和証券・チーフテクニカルアナリストの木野内栄治氏)という。 一方、リスク要因としては「トランプ米大統領は合意の直前になって脅しをかける傾向がある。今までの交渉戦術を振り返ると、楽観視はできない」(岡三アセットマネジメント・ シニアストラテジストの前野達志氏)との声が聞かれた。このほか、テクニカル面ではオシレーター系指標の過熱感が強い。上値では年金などの利益確定売りも警戒されるため、基調の強さを維持しながらも、目先的な調整を入れる可能性もある。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米ダウ・S&P最高値、米中関税撤廃の期待でダウは182ドル高の2万7674ドル[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米国株式市場は上昇し、ダウとS&P500が終値で最高値を更新した。米中が発動済みの追加関税を段階的に撤廃する方針で一致したと伝わり、安心感が広がった。ただ、その後の報道で合意に不透明感が生じ、上値は抑制された。中国商務省の高峰報道官は7日の会見で、中国と米国がここ2週間の間に、双方が貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に撤廃することで合意したと明らかにした。また、中国国営の新華社は、中国政府が鶏肉の輸入制限解除を検討していると報じた。ただ、その後に追加関税の段階的撤廃には、ホワイトハウス内や外部の顧問から反対論が出ており、最終決定は下されていないとのロイターの報道を受け、主要株価指数は午後の取引で上げ幅を削った。アラン・B・ランツ・アンド・アソシエーツのプレジデント、アラン・ランツ氏は「相場が最高値にある状況で少しでも不透明感が浮上すれば、利食い売りが出やすい」と話した。企業決算も一定の支援材料となった。今四半期の利益見通しが市場予想を上回ったクアルコムが6.3%高となり、S&P情報技術指数は0.7%上昇。中国へのエクスポージャーが大きい他の半導体銘柄も買われ、フィラデルフィア半導体指数は0.7%高となった。貿易に敏感な工業株も0.2%上昇した。アパレル大手ラルフ・ローレンは14.7%急伸。コスト管理の強化に加え、中国や欧州の好調な需要が寄与し、四半期利益が市場予想を上回った。一方、旅行予約サイト大手のエクスペディア・グループは27.4%急落。四半期利益が予想に届かなかった。ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.06対1の比率で上回った。ナスダックでは1.09対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は79億2000万株。直近20営業日の平均は68億3000万株。日経平均株価は4日続伸、連日の年初来高値 米中対立の緩和期待終値は61円高の2万3391円[東京 8日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均株価は4日続伸。前日の米国株市場で主要指数が強含んだ流れを引き継ぎ、買い先行で始まった。寄り付きでザラ場ベースの年初来高値を更新し、一時2万3591円09銭まで上値を伸ばしたが、これまでの上昇による高値警戒感も強く、利益確定売りが出て伸び悩んだ。午後はしばらく手控えムードとなったものの、為替の円安基調が下支え。大引け直前に買いも入り、終値でも連日の年初来高値を更新した。前日の米国株市場は、米中が貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に撤廃することで合意したと伝わり、ダウとS&P500が終値で最高値を更新した。日経平均はオプションSQ(特別清算指数)算出に絡む買い注文も加わり、大きく上昇してスタートしたが、高値では利益確定売りに押された。後場は為替が109円前半で安定的に推移したことなどが安心感を誘った。目先、売り材料は見当たらないとの見方があった一方、「トランプ米大統領は合意の直前になって脅しをかける傾向がある。今までの交渉戦術を振り返ると、楽観視はできない」(岡三アセットマネジメントのシニアストラテジスト、前野達志氏)との声も聞かれた。TOPIXは小幅に4日続伸。東証33業種では、精密機器、鉄鋼、輸送用機器などが値上がり率上位に並んだ。半面、化学工業、金属製品、不動産などは値下がりした。個別銘柄では、テルモが急伸し年初来高値。7日発表した2019年4─9月期の連結当期利益(IFRS)が前年同期比32.7%増の457億円と、足元の業績が好調だった。20年3月期の通期当期利益見通しに対する進捗率は56.4%。心臓血管カンパニーなど各セグメントで売り上げが伸びた。一方、資生堂は大幅反落。7日に2019年12月期の連結業績予想を下方修正したことが嫌気された。東証1部の騰落数は、値上がり1028銘柄に対し、値下がりが1022銘柄、変わらずが103銘柄だった。テルモは大幅高で3日ぶり上場来高値、上振れの2Q決算を好感 医療機器大手のテルモ(4543)がまとまった買い注文を集めて大幅高。株式分割を考慮した実質で3日ぶりに上場来高値を更新しており、時価総額は初めて3兆円を超えてきた。午前11時22分時点で前日比464円(13.1%)高の4006円となっている。 7日の引け後に発表した今2020年3月期の第2四半期累計(19年4~9月期)連結決算(IFRS)が好調で予想から上振れたことを好感した買い注文が朝方から増加した。売上高は3072億7800万円(前年同期比7.8%増)、純利益が457億1100万円(同32.7%増)となり、同利益は当社が公表していた385億円という従来予想を大きく超過達成した。カテーテルを中心に主力の心臓血管が2ケタ増収となり、収益拡大を牽引した。売上高6350億円(前期比5.9%増)、当期純利益810億円(同1.9%増)などの通期予想は変えていないが、同利益の進捗率は約56%と高く、今後の上方修正を期待する投資家も増えているようだ。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】来週の株式相場戦略=米中協議の行方注視、銀行株など水準訂正も 日経平均株価の上昇基調は強く、週間ベースでは5週連続の上昇。10月に入ってから日経平均は1600円強、7%強の値上がりとなっている。来週は高値一服も予想される一方、米中絡みの動向次第でなお一段高の可能性もある。日経平均株価の予想レンジは2万3000~2万3600円。 強調相場の背景にあるのは、米中通商協議の進展と業績底打ちへの期待だ。11月中旬に予定されていたチリでのAPECが中止されたことから、米中首脳会談の日程が定まらない状況となった。12月15日の米国の第4弾追加関税引き上げまでに両国は何らかの合意に漕ぎつけるとの期待は強い。市場では「12月初旬にロンドンで開かれる北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で米中首脳会談が開かれる可能性」(アナリスト)も指摘されている。 米中首脳会談が追加関税削減へ前向きな形で開催される格好となれば、日経平均は2万3000円台後半への上昇も期待できる。ただ、「万が一決裂すれば2万1000円台への急落も」(同)との見方も囁かれる。 決算発表は来週にはほぼ一巡するが、足もとでは減額修正も目立つ。しかし「7~9月期あるいは10~12月期が業績の底」(市場関係者)との見方から株価は押し目買いが優勢だ。 来週は12日のSMCや日産自動車、13日の三菱UFJフィナンシャル・グループ、14日の日本郵政などが注目される。海外では、14日に半導体関連の米アプライド・マテリアルズやエヌビディアが決算を行う。 また、経済指標では14日の10月中国鉱工業生産など、15日の米10月小売売上高など。国内では11日の9月機械受注や14日の7~9月期実質国内総生産(GDP)への関心が高い。 注目を集めているのが、長期金利の上昇だ。米国10年債利回りは1.9%台に乗せてきた。これを受け、8日の東京市場ではREIT指数が大幅安となった。この流れが続くようなら、三菱UFJなど銀行株への出遅れ株物色が強まることも予想される。(岡里英幸)(GDO)国内男子 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2日目S.ビンセント首位 今平周吾「64」猛追 石川遼は今季初予選落ちツアー初優勝を狙うスコット・ビンセント(ジンバブエ)が1イーグル4バーディ、ボギーなしの「65」でプレーして単独首位に立った。初日首位の宮本勝昌が通算8アンダー2位。賞金ランキング1位の今平周吾が上がり5連続を含む8バーディを奪い、この日のベストスコア「64」でプレーして通算7アンダー。チェ・ホソン(韓国)、ブラッド・ケネディ(オーストラリア)と並んで3位に浮上した。賞金ランク2位のチャン・キム(米国)はスコアを伸ばせず通算1オーバー42位で大会を折り返した。故郷沖縄で今シーズン国内初戦となる宮里優作は通算3オーバー70位で決勝ラウンドに進めなかった。同ランク3位の石川遼は2日連続スタートホールでダブルボギーをたたくなどスコアを落とし、通算5オーバー84位。この大会では3年連続となる今季初の予選落ちを喫した。<上位の成績>1/-10/スコット・ビンセント2/-8/宮本勝昌3T/-7/チェ・ホソン、ブラッド・ケネディ、今平周吾6/-6/久保谷健一7T/-5/ディラン・ペリー、スンス・ハン、阿久津未来也10T/-4/池田勇太、ショーン・ノリス、藤田寛之、木下稜介、キム・ソンヒョン日米女子ツアー共催 TOTOジャパンクラシック 初日鈴木愛が首位発進 渋野日向子は2打差9位前週の「樋口久子 三菱電機レディス」で今季5勝目を飾った鈴木愛が6バーディ、1ボギーの「67」でプレー。6月「全米女子プロ選手権」覇者のハンナ・グリーン(オーストラリア)と並び、5アンダー首位で発進した。1打差の3位に、ジェニファー・カップチョ、ギャビー・ロペス(メキシコ)、テレサ・ルー(台湾)、キム・ヒョージュ(韓国)、リディア・コー(ニュージーランド)、ミンジー・リー(オーストラリア)の6人がつけた。3アンダー9位グループに大会初出場の渋野日向子、9番(パー3)でホールインワンを達成した松田鈴英、勝みなみ、三ヶ島かな、リウ・ユ、ヤン・ジン(ともに中国)、ジェニー・シン、ペ・ソンウ(ともに韓国)、エンジェル・インの9人が並んだ。前年覇者の畑岡奈紗はイーブンパー39位で初日を終えた。<上位の成績>1T/-5/鈴木愛、ハンナ・グリーン3T/-4/ジェニファー・カップチョ、ギャビー・ロペス、テレサ・ルー、キム・ヒョージュ、リディア・コー、ミンジー・リー9T/-3/渋野日向子、松田鈴英、勝みなみ、三ヶ島かな、リウ・ユ、ジェニー・シン、ペ・ソンウ、エンジェル・イン、ヤン・ジン国内女子 最終プロテスト 最終日21人の新人誕生 安田祐香、吉田優利、アン・シネらが合格/女子プロテスト女子ゴルフの最終プロテストは最終ラウンドが行われ、18位タイまでの21人が合格した。28歳のイ・ソルラ(韓国)が通算9アンダーでトップ通過を果たした。韓国・ソウル市出身のイは今季レギュラーツアーに30試合出場。4月「KKT杯バンテリンレディス」の8位が最上位だった。1打差の8アンダー2位タイに山路晶、西村優菜が入った。注目のアマチュア安田祐香は4打差の4位、吉田優利は6打差の12位、アン・シネは8打差の15位で合格を果たした。3日目を終えて通算8オーバー78位だった三浦桃香は最終ラウンドを前に体調不良で棄権した。<プロテスト通過者>1/-9/イ・ソルラ2T/-8/山路晶、西村優菜4T/-5/安田祐香、劉依一6T/-4/山下美夢有、澁澤莉絵留8T/-3/セキ・ユウティン、中西絵里奈、プリンセス・スペラル、石川怜奈12T/-2/吉田優利、ハン・スンジ、常文恵15T/-1/アン・シネ、河野杏奈17/E/田中瑞希18T/+1/西郷真央、笹生優花(ユウカ・サソウ)、宮田成華、石井理緒(msn)(ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル)EVの次なるフロンティア:地下深いトンネル 【シドニー】電気自動車(EV)のブームが次に訪れるのは、世界中の鉱山で活躍する大型車両かもしれない。 カナダの地方部やオーストラリア内陸部などで鉱山を運営する企業の間で、ディーゼルエンジン式の掘削機やホイールローダーなどの動力源をリチウムイオン電池に切り替える動きが活発だ。地下坑道の空気を汚染し、作業員の健康を危険にさらす排ガスを減らすのが目的だ。 カナダのオンタリオ州シャプロー近郊にあるボーデン鉱山では、鉱石を掘り出すためや、作業員を敷地内の各所に運ぶために約35台のEVが稼働している。鉱山を所有する産金世界最大手ニューモント・ゴールドコープは100%の電動化を目指している。電動掘削ドリルは年明けに納品される予定で、ディーゼル式トラックは段階的に廃止する見込みだと広報担当者は話す。 「究極の目標は大型ダンプカーだ」。時価総額で世界最大の鉱業会社BHPで低排出技術を統括するカーステン・ローズ氏はこう話す。 高馬力のダンプカーは地下坑道の底から何トンもの鉱石を運び出す。ディーゼルエンジンの馬力に匹敵するためには、現在の技術では巨大なバッテリーパックが必要になる。 BHPは豪州最大の地下鉱山オリンピックダムに1年前から小型EVを試験的に導入している。今月中にもう1台増やす予定で、豪州各地の鉱山にも拡大する考えだ。カナダで計画中のBHPの炭酸カリウム鉱山ジャンセンでは、何台のEVが配備可能かを検討している。 ローズ氏によると、いずれ鉱山から一切のディーゼルエンジン機械をなくしたいという。 より小規模な企業も環境への配慮を強化している。例えば、ヌーボー・モンド・グラファイトはカナダのケベック州に100%電動化した露天掘り黒鉛(グラファイト)鉱山を作る計画だ。 世界有数の鉄鉱石産出量を誇る豪フォーテスキュー・メタルズ・グループのエリザベス・ゲインズ最高経営責任者(CEO)は「ディーゼルから切り替えるチャンスがあればいつでも大歓迎だ」と述べた。だが「この技術、つまりバッテリー駆動時間がわれわれの事業に見合う水準に達していない」 技術の発達は急ペースで進むが、だからこそ別の課題も持ち上がる。「ノートパソコンと同じだ。あなたが家に持ち帰るともう旧式になっている」。オリンピックダム鉱山でのEV実験を指揮するドリュー・オサリバン氏はこう話す。 さらなるハードルは価格だ。専門家によると鉱山用EVはディーゼル車に比べて40%から時に3倍も値段が高いからだ。 だがEV推進派はランニングコストが安いと反論する。ボーデン鉱山の年間エネルギー支出は、従来の鉱山より約900万ドル安くなり、場合によってはそれ以上の違いがあるとニューモントの広報担当者は話す。その一因は、トンネルから汚染物質を除去する巨大換気システムを動かすのに地下鉱山のエネルギーコストの最大40%を費やしていることだ。 顧客や投資家は、世界の資源企業が行いを正すことに期待を寄せる。投資の社会的影響力への関心が高まる中、プロジェクトに融資する銀行だけでなく、大手年金基金や資産運用会社の多くが、二酸化炭素排出量を公表し、削減に取り組むよう資源会社に求めている。ディーゼルはいま旬のターゲットだ。BHPの場合、事業活動に伴う直接排出量の3割以上をディーゼルが占めているとローズ氏は言う。 間もなく規制当局もこれに同調するかもしれない。西オーストラリア州の鉱山局は7月、地下迷宮で1日最大12時間も重機を操作する作業員の健康状態に改めて懸念を示した。 「ディーゼルエンジンの排ガスは鉱山事業の危険要因として知られる。特に地下鉱山ではそうだ」。同局の鉱山安全責任者アンドリュー・チャップリン氏は言う。政府の委員会は同国の資源担当相に対する勧告を作成中だという。 もっとも、発電方法を化石燃料から再生可能エネルギーに移行しない限り、採掘機械や車両を電動化するだけでは排出量削減に大きな効果は期待できない。 一部の鉱山会社はその方向に努力している。フォーテスキューは先月、豪電力会社アリンタ・エナジーと契約を結び、鉄鉱石生産拠点チチェスターの電力を太陽光発電でまかなうことにした。年間およそ1億リットルのディーゼル燃料に取って代わるという。(goo)(読売新聞)光技術で次世代半導体…NTTとソニー、インテル連携へ NTTとソニー、米半導体大手のインテルが、光技術を使って高速処理を可能にする新たな半導体の開発に向けて連携する。3社はまず、来春にもほかの通信事業者やメーカーなども交えた新たな民間団体を設立し、共通の規格の策定に向けた技術や知見の共有を進める考えだ。 半導体は現在、スマートフォンなどの通信機器やサーバーに不可欠な重要部品となっている。NTTは、半導体を電気信号ではなく、より速い光信号で動かす研究を進めている。2030年ごろの実用化を目指しており、共通規格の策定で取り組みを加速させ、主導権を握りたい考えだ。 NTTによると、光を用いた半導体では、理論上、2時間の映画5000本を1秒でダウンロードできるほか、消費電力が少ないため、スマートフォンは1年間、充電が必要なくなるという。5Gよりも安定した自動運転や遠隔医療の実現にもつながるとの期待がある。 NTTは光技術による新しいネットワーク構想「IOWN(アイオン)」を今年6月に発表しており、今回の連携もその一環となる。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-後場盛り返して今週は全勝、来週も好地合いが継続か 8日の日経平均は4日続伸。終値は61円高の23391円。中国商務省の発表を受けて米中の追加関税撤廃期待が高まったことから、スタートは大幅高。200円超の上昇で23500円台に乗せた。しかし、買い一巡後は急失速。東京市場で円安にブレーキがかかったこともあり、前場では下げに転じる場面もあった。後場は売り圧力が和らぎ、値動きが落ち着いた。小幅高でのもみ合いが長く続いたが、取引終盤にかけては上げ幅を広げた。一方、長期金利上昇を受けてREIT指数が大きめの下げとなったほか、マザーズ指数やジャスダック平均など新興指数は軟調となった。東証1部の売買代金は概算で3兆1200億円。業種別では騰落率上位は精密機器、鉄鋼、輸送用機器、下位は化学、金属製品、不動産となった。上期が大幅増益となり、自己株取得も発表した三越伊勢丹ホールディングスが急騰。半面、前19.9期が大幅な最終赤字となったコナカが後場マイナス転換から下げ幅を広げた。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1028/値下がり1022。主力どころではトヨタやソフトバンクG、武田が強い動き。金利上昇を受けて三菱UFJや三井住友など銀行株に買いが入った。上期が大幅増益となったテルモは商いを伴って13%超の上昇。自己株取得が好感されたキリンや、上期上振れ着地のカシオなども大幅高となった。NISSHAは証券会社のリポートを材料に急伸。上期の営業黒字転換見通しを発表した第一商品はストップ高比例配分となった。一方、太陽誘電やSUMCOなどハイテク株が軟調。安川電機やキーエンスなどロボット・FA関連も弱い動きとなった。下方修正を発表した資生堂が8%超の下落。3Qが最終赤字となった楽天や、修正した今期見通しが失望を誘ったKLabが大幅安となった。1Qが大幅な営業赤字となったメルカリはストップ安まで売られる場面があるなど大きく値を崩した。 日経平均は大幅高スタートから下げに転じたものの、売りが加速することもなく終盤に盛り返した。結局4日続伸で今週は全勝。直近の上昇ペースが速かっただけに、今週はいったんブレーキがかかる可能性もあるとみていたが、一気に23500円台まで駆け上がった。23000円をアッサリ超えてきたことで、来週は同水準が一定のサポートになると期待できる。米中に関しては、つい最近まで終わりの見えない関税引き上げ合戦を繰り広げていたのが、足元では関税を撤廃するかもしれないという話になっている。双方に立場はあり、この先も出てきた話が覆るといったことは出てくるだろう。そして、引き続きそういったニュースに翻弄され続けるだろう。ただし、追加関税撤廃の方向に向かうのであれば、間違いなく企業活動にはポジティブな影響が見込まれる。交渉がスムースに進めば、多くの企業の業績が今期でボトムを打つ可能性はある。一本調子の上昇が続いていたREIT指数が今週崩れており、安全資産から株式への資金シフトが進みそうな雰囲気もある。押し目があれば買い場とみて、強気で臨みたい局面だ。【来週の見通し】 堅調か。今週、長期金利の上昇を受けてREITが売りに押されたことから、ハイテクを中心にグロース株には上値が重くなるものも出てきそう。しかし、金融やエネルギーなど出遅れ感のあるセクターには見直し余地があり、物色のシフトが進むことで、全体としての強い基調は維持されると予想する。13~14日にはパウエルFRB議長の議会証言が予定されている。直近10月のFOMCでは、同氏の会見が株高に勢いをつけただけに、発言内容が大きく注目される。決算発表は来週で一巡するが、ここまでの地合いが良かったこと、今回は好決算でも売られた銘柄が少なくないことなどから、引き続きアナリストレポートなどを材料に個別の活況は続くと考える。急ピッチの上昇に高値警戒感も意識されるが、下げ局面では上昇に乗り遅れた投資家の押し目買いが入る可能性が高く、下値は堅く、好材料により反応しやすい地合いが続くと予想する。【今週を振り返る】 堅調となった。良好な10月雇用統計などを好感して米国株が騰勢を強めたことから、三連休明け5日の日経平均は400円を超える大幅上昇。その後は上値追いには慎重姿勢が見られたものの、23000円を明確に突破してきたことで楽観ムードが強まり、高値圏を維持した。週後半には米中が追加関税を段階的に撤廃する方向と伝わったことを受けて、23500円台に乗せる場面もあった。一方、マザーズ指数は週間では下落し、REIT指数は大幅安となるなど、物色には濃淡がついた。日経平均は週間では約541円上昇し、週足では陽線を形成した。【来週の予定】 国内では、9月機械受注、10月景気ウォッチャー調査、日銀金融政策決定会合の主な意見(10/30~10/31開催分)(11/11)、10月工作機械受注(11/12)、10月企業物価指数(11/13)、7-9月期GDP(11/14)がある。 企業決算では東急、博報堂DY、大林組、三井E&S、安藤ハザマ、熊谷組、クレハ、みらかHD、東和薬品、Dガレージ、日製鋼、三井金、栗田工、堀場製、ホトニクス、太陽誘電、めぶきFG、コンコルディア、凸版印、アイフル、スターツ、ユー・エス・エス、ふくおか、TKC(11/11)、日産自、日揮HD、鹿島、清水建、クラレ、日医工、大塚HD、浜ゴム、ヤクルト、タクマ、メニコン、クレセゾン、協エクシオ、パーソルHD、GMOPG、ユーザベース、そーせい、ペプチド、富士フイルム、タカラバイオ、太平洋セメ、JFEHD、DOWA、SMC、ハーモニック、NOK、タカラトミー、大日印、セイコーHD、ソニーFH、住友不、近鉄エクス、GMO、ニチイ学館、宝HD、カネカ、ユニバーサル(11/12)、三菱UFJ、三井住友、東芝、洋エンジ、光通信、前田建、近鉄GHD、東映、マツモトキヨシ、FFRI、応化工、アミューズ、ロート、サイボウズ、ノーリツ、リクルートHD、荏原、THK、新生銀、京急、トリドールHD、PKSHA、ヤマハ発(11/13)、みずほ、日本郵政、ゆうちょ、かんぽ、京都銀、すかいHD、オープンハウス、ガンホー、電通、出光興産、フリークアウト、ブランジスタ、日機装、ワタミ、サイバダイン、MTG、KADOKAWA、奥村組、あおぞら、第一生命、夢真HD(11/14)などが発表を予定している。 海外では、英7-9月期GDP(11/11)、独11月ZEW景況感指数(11/12)、米10月消費者物価指数、米10月財政収支、パウエルFRB議長による米議会の上下両院合同経済委員会の公聴会での議会証言(11/13)、中国10月固定資産投資、中国10月鉱工業生産、中国10月小売売上高 、独7-9月期GDP、米10月生産者物価指数(11/14)、米10月輸出入物価指数、米11月NY連銀景気指数、米10月小売売上高、米10月鉱工業生産(11/15)などがある。 米企業決算では、シスコシステムズ(11/13)、エヌビディア、ウォルマート(11/14)が発表を予定している。NY株見通し-米中通商関連報道を睨んだ神経質な展開か 今晩のNY市場は神経質な展開か。昨日は米中双方が第1段階の通商合意のために既存の関税を段階的に撤廃するとの報道が好感され主要3指数がそろって史上最高値を更新した。しかし、NY引け後に、通商担当のナバロ米大統領補佐官は「現時点で合意はない」と、関税取り下げ合意を否定した。今晩は、昨日引け後に好決算を発表したウォルト・ディズニーの上昇が予想されるものの、暫定合意文書への署名に向けて米中の駆け引きが続いており、通商関連報道を睨んだ神経質な展開となりそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは、11月ミシガン大消費者信頼感指数速報値、9月卸売在庫、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁の講演など。企業決算は、寄り前にデューク・エナジー、アメレンなどが発表予定。(執筆:11月8日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)来週の日本株の読み筋=強弱感対立の可能性、「パウエル発言」に注目 来週(11-15日)の東京株式市場では、連日の年初来高値更新をにらみ、先高期待が根強いものの、過熱感を指摘する向きも少なくなく、強弱感が対する可能性がある。特に注目されるが、現地13、14日に予定されているパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長による議会証言。米経済見通しを示すとみられるが、その内容は今後の政策の方向性を決める要素となるだけに、市場の受け止め方次第では相場変調につながるとの読みも出ている。 一方、米シカゴ・オプション取引所が算出するVIX指数が低位で推移していることから、投資家にとっては先行き不透明感が薄い状況にある。半面、需給面ではVIX指数先物の売り残が歴史的な高水準となっており、きっかけがあれば不安心理が噴出しかねない下地ができており、その動向を注視する必要がある。 スケジュール面では、国内で11日に9月機械受注、10月景気ウォッチャー調査、10月30-31日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、14日に7-9月期DPなど。海外では13日に米10月消費者物価、14日に中国10月の工業生産、小売売上高、都市部固定資産投資、米10月生産者物価、米通商拡大法232条による自動車関税の発動期限、15日に米10月の小売売上高、鉱工業生産・設備稼働率などが予定されている。 8日の日経平均株価は2万3391円(前日比61円高)引けと4日続伸し、連日で年初来高値を更新した。中国商務省は7日、米中の貿易交渉に関し「追加関税の段階的な引き下げで合意している」と発表し、NYダウが最高値を更新した流れを受け、朝方は買い優勢で始まり、上げ幅は一時260円に達した。その後、ナバロ米大統領補佐官が「現時点で合意はない」と述べたと報じられ、懐疑的な見方から株価指数先物に売りが出て前場終盤には下げに転じる場面もあった。その後、持ち直したが、戻りは限定された。この日算出の日経平均先物ミニ・オプション11月限のSQ(特別清算指数)値は2万3637円となり、日経平均が一度もタッチしない幻のSQに終わったが、「早期にこのラインをクリアできないと上値抵抗線として意識されることになる」(準大手証券)との声が聞かれた。今晩のNY株の読み筋=米中貿易交渉の動向にらみ手じまう流れか きょうの米国株式市場は、いったんポジションを手じまう動きが出る可能性がありそうだ。 米中貿易交渉をめぐる動向は、7日に中国側が双方による段階的な追加関税撤廃で合意と発表したことを受け、同日の米国株は主要3指数が揃って史上最高値を更新した。その余勢はきょう東京株式市場にも引き継がれ、日経平均株価は買い先行となったが、ナバロ米大統領補佐官が「現時点で第1段階合意の条件として、関税撤廃を含めることに合意していない」と発言したことを受け、日経平均は一時マイナス転換した。その後、匿名の米政府高官発言として、段階的な関税撤廃で合意していると伝わり、日経平均はプラス転換して引けた。 米中貿易交渉は追加関税の撤廃を足掛かりに前向きに進むとの観測は持続しそうだが、米政府関係者の発言に足並みが揃わないこともあり、きょうのところは一段のリスクオンムードは望みにくい。加えて、週明け11日はベテランズデー(退役軍人の日)の祝日。株式市場は通常営業だが、例年祝賀ムードで薄商いになりやすい。週明けの米中貿易交渉をめぐる動きや米10月CPI(消費者物価指数)など米経済指標を見据えつつ、いったんポジションを手じまう動きも出そうだ。<主な米経済指標・イベント>米11月ミシガン大学消費者マインド指数・速報値デューク・エナジー、マジソン・スクエア・ガーデンなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕4日続伸=利食いで上げ幅縮小(8日) 【第1部】米中貿易協議の進展期待と円安進行を材料に買いが先行したが、利益確定売りも出て上げ幅を縮小した。日経平均株価は前日比61円55銭高の2万3391円87銭、東証株価指数(TOPIX)は4.64ポイント高の1702.77といずれも4日続伸。 銘柄の48%が値上がりし、下落は47%だった。出来高は16億2680万株、売買代金は3兆1255億円。 業種別株価指数(33業種)は精密機器、鉄鋼、輸送用機器が上昇し、下落は化学、金属製品、不動産業など。 個別銘柄ではテルモ、オリンパスが買われ、トヨタ、日産自、ホンダは値を上げた。ソニー、カシオは堅調で、ソフトバンクGは締まった。三菱UFJ、三井住友が強含み、リクルートHDはしっかり。半面、資生堂は売られ、キーエンス、東エレク、SUMCOは値を下げた。三桜工は軟調で、ファーストリテは緩んだ。OLCが弱含み、楽天、KDDIもさえなかった。 【第2部】小幅続伸。ユーピーアールが堅調。東芝は小幅高。半面、アイスタディ、プロスペクトが値を下げた。出来高1億4137万株。 ▽連騰続きで調整局面入りか 前日に中国商務省の報道官が、米中両国で制裁関税の段階的な撤回で一致したと会見で述べたことが協議進展への期待を高めた。投資家心理が上向く中、東京市場も上昇してスタート。日経平均は朝方2万3600円近くまで値を上げた。その後、2019年9月中間決算がヤマ場を迎える中、テルモなど好業績銘柄への個別物色の動きが相場を下支えしたが、連騰の反動もあり、利益確定売りに押された。週末の手じまい売りも加わった。 強気の投資家心理で上昇が続いてきた日本株だが、市場では「そろそろ調整局面に入ってきた」(中堅証券)との指摘も出始めた。「米中協議で首脳会談の日程が決まるといった具体的進展がない限り、2万3500円以上の水準では上値が重くなる」(銀行系証券)とみられている。 225先物12月きりは、横ばい。堅調で寄り付き、朝方に2万3600円まで上昇した後は利益確定売りの動きに押され、前日終値付近での小動きに終始した。(了)(yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、109円台前半(8日朝) 【ニューヨーク時事】週末8日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米中貿易協議の行方をにらみ、1ドル=109円台前半で小動きとなっている。午前9時現在は109円30~40銭と、前日午後5時(109円24~34銭)比06銭の円安・ドル高。 円相場は海外市場を通じ、109円台前半のレンジで方向感なく推移した。中国商務省の高峰報道官は7日、「第1段階」合意に向け、米中両国が「協議の進み具合に合わせ、追加関税を段階的に撤廃することに同意した」と説明。しかし、米政府は発動済みの関税引き下げを協議している事実はあるものの、「決定していない」(米当局者)と否定的な見解を示したため、交渉の行方は依然として予断を許さないとの警戒感が台頭し、8日朝は様子見ムードが広がっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1025~1035ドル(前日午後5時は1.1045~1055ドル)、対円では同120円55~65銭(同120円74~84銭)。(了) NY株、もみ合い 【ニューヨーク時事】週末8日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の行方に引き続き注目が集まる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比27.11ドル安の2万7647.69ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は14.39ポイント安の8420.13。 今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の8銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では2銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.08
コメント(0)
-

11月7日(木)…
11月7日(木)、晴れです。気持ちの良い天気ですね。車の窓を開け放って走りたい…!そんな本日は7時頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時15分頃には家を出る。ゴルフではありません…、アルバイト業務です。本日は近場で助かります。8:45~16:30です。ランチタイムはほぼ2:00なので帰宅して昼食ですね。朝の職場での光景です…戦時対応ですか…?お昼に帰宅するとロマネちゃんが寛いでいます。昼食を済ませ、少しお昼寝をしてから職場に向かう途中でミニパトが違反車両の軽を捕まえていました…。アルバイトを終えて、近くのパンの名店でパンを購入しての帰り道…暗くなるのが早くなりましたね。帰宅して、奥の自家製アップルパイとコーヒーで遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.92円。1AUドル=75.10円。昨夜のNYダウ終値=27492.56(-0.07)ドル。本日の日経平均終値=23330.32(+26.50)円。金相場:1g=5777(+10)円。プラチナ相場:1g=3658(-9)円。(ブルームバーグ)米中が段階的な関税撤回に合意、協議進展に合わせ-中国商務省 中国商務省は7日、米中両国が貿易合意に向けて取り組む中、相互の製品に賦課している関税を段階的に互いに比例する形で撤回することで合意したと発表した。 商務省の高峰報道官は「この2週間、交渉担当トップが真剣かつ建設的な協議を行い、合意を巡り進展するに合わせ追加関税を段階的に撤回することで合意した」と述べた。 「米中が第1段階の合意に達した場合、両国は合意内容に基づき同時に同じ割合で既存の追加関税を撤回すべきであり、合意に至るには重要な条件だ」と語った。 米国側もこの事実を確認すれば、世界経済に影を落としてきた貿易戦争の緩和に向けた工程表が浮上することになる。 高報道官は、米中両国は第1段階の合意を署名する場所と時期について交渉を続けると述べた。 オーバーシー・チャイニーズ銀行の謝棟銘エコノミストは、「現時点での問題は米中両国が実際に何について合意したのかだ。市場では関税に関する中国のコメントに米国が今後どのように反応するのかに関心が向かっている」と指摘。「投資家はまだ慎重で、人民元の上昇はなお限定的。米国が関税解除に関するニュースを確認することになれば、1ドル=6.9元へと元が上昇する可能性がある」と話した。日本株は小幅続伸、好決算の精密や小売高い-米中協議不透明は重し 7日の東京株式相場は小幅に3日続伸。米中通商協議に対する不透明感が高まり投資家が様子見姿勢となる中、決算が評価されたオリンパスなど精密機器、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスなどの小売、医薬品が上昇。ソフトバンクグループやSUMCO、味の素といった決算失望銘柄が売られ、上値を抑制した。 TOPIXの終値は前日比3.68ポイント(0.2%)高の1698.13 日経平均株価は同26円50銭(0.1%)高の2万3330円32銭 〈きょうのポイント〉 米中の部分的貿易合意の署名、12月になる可能性 オリンパスは第2四半期決算が市場予想上回る、パンパシIは営業利益予想を上方修正 トヨタの7-9月期営業益14%増、北米回復-為替も追い風 ソフトBGは第2四半期営業損失、SUMCOの第4四半期営業利益予想は市場予想下回る、前日午後決算の味の素は下げ止まらず 東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストは米中貿易交渉について、「トランプ米大統領がいつどう変化するかわからない。中国が求めている関税撤回でどこまで譲歩するのかなど、マイナス面もプラス面も織り込み切れていない部分が多い」と述べた。 新規の手がかり材料に乏しく、株価指数は前日終値を挟んだ動きとなった。主要企業の決算発表が相次ぎ、個別色の強い展開だった。午後に上期決算を発表したトヨタ自動車は買われ、52週高値を更新した。 野村証券投資情報部の若生寿一エクイティ・マーケット・ストラテジストは、足元の株価上昇で同証予想の日本株のPERは13倍に上昇し、「2016年以降の基本レンジ12-14倍の真ん中に戻した」と指摘。国内決算は全体に下方修正の加速感がなくなり株価を押し上げているとし、今後は「来期の増益回帰に確信が持てるかが焦点」とみていた。 東証33業種では精密機器、その他金融、非鉄金属、小売、医薬品、電機が上昇 海運や鉄鋼、ゴム製品、銀行は下落(ロイター)5G、米中日韓で普及へ 欧州は出遅れ=調査[ベルリン 7日 ロイター] - GSMAインテリジェンスの調査によると、第5世代(5G)モバイル通信規格は中国、米国、日本、韓国で普及が進み、2025年までには4カ国のユーザーが世界全体の半分以上を占める見通し。 欧州は5G網の敷設が遅れており、一般消費者への普及が遅れる見通しだが、「スマート工場」などビジネス分野では5Gの利用拡大が見込まれている。 韓国では、モバイル通信の66%が2025年までに5Gとなる見通し。米国は50%、日本は49%と予想されている。 ユーザー数では中国の5G利用者が6億人と、世界首位になる見通し。 世界全体では15億7000万人が2025年までに5Gを利用するとみられる。これはモバイル通信の利用者全体の18%に相当する。 インターネット・オブ・シングス(IoT)市場の規模は2025年には1兆ドルに達する見通し。これは昨年のモバイル業界全体の収入にほぼ匹敵するという。 ただ接続料金は全体の5%にすぎず、通信会社はコンサルティング会社やアマゾン(AMZN.O)、マイクロソフト(MSFT.O)など米ハイテク大手との競合を迫られるとみられる。 途上国では4Gの普及が進む見通し。2025年の世界全体のモバイル通信の59%は4Gになるとみられている。 米と追加関税の段階的撤廃で合意、中国商務省が表明[北京 7日 ロイター] - 中国商務省の高峰報道官は7日の会見で、中国と米国がここ2週間の間に、双方が貿易戦争の過程で発動した追加関税を段階的に廃止することで合意したと明らかにした。 高報道官は、「第1段階」の通商合意が成立するためには、両国が互いに発動している追加関税を同時に撤廃しなければならないとし、撤廃は、合意を成立させるための重要な条件と表明。 撤廃する追加関税の割合は同じでなければならず、撤廃する対象品目数は交渉可能とした。 「貿易戦争は関税で始まっており、関税撤廃で終わらせるべきだ」と述べた。具体的な予定などは示さなかった。 通商協議の中国交渉団に近い筋によると、中国は米国側に「すべての追加関税をできるだけ早く撤回」するよう要求している。 「第1段階」の通商合意の署名はトランプ米大統領と習近平中国国家主席がするとされるが、その時期も場所も情報が錯綜している。 高報道官は、署名の時期や場所についてコメントを差し控えた。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米国株式市場は横ばい、米中協議巡る懸念が重し ヘルスケア好調ダウの終値は2万7492ドル[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米国株式市場は、ほぼ横ばいで取引を終えた。米中の「第1段階」の通商合意の署名が12月にずれ込む可能性があるとの報道が重しとなった。その一方、ヘルスケアセクターが好調で株価を下支えした。ナスダックは前日まで3日連続で終値での最高値を更新したが、この日はストップがかかった。前日まで2日連続で最高値となったダウも、わずかに下落して引けた。トランプ政権高官は6日、ロイターの取材に対し、第1段階の通商合意は条件や開催地を巡る協議がなお続いており、署名は12月にずれ込む可能性があると明らかにした。これを受け、貿易戦争が続く可能性を巡り不安が再燃した。ジョーンズトレーディングのチーフマーケットストラテジスト、マイケル・オルーク氏は、報道を受けて売りが出たものの、目立った下げではなかったと指摘。「市場は最高値を付け、それを突破して行けるかどうか様子見の展開だ」と話した。トランプ政権高官は、第1段階の合意に達しない可能性もまだ残されているとしつつ、合意する確率の方がより高いと述べた。医療保険のヒューマナは3.5%高。四半期利益が市場予想を上回ったことを好感した。ドラッグストアチェーン大手のCVSヘルスも好決算で5.4%上昇。S&Pヘルスケア指数は0.6%高となった。ヘルスケア以外では、金融指数が続伸した一方、エネルギー指数は原油安を受けて2.3%下落した。ニューヨーク証券取引所では、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.21対1の比率で上回った。ナスダックでも1.76対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は79億3000万株。直近20営業日の平均は67億4000万株。日経平均は3日続伸、終値で連日年初来高値更新終値は26円高の2万3330円[東京 7日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は3日続伸し、終値で年初来高値更新。オーバーナイトの米国株主要指数が横ばいで決め手となる材料が不足する中、早朝からドル/円がやや円高方向に振れたことが上値を重くした。前日のソフトバンクグループ決算を受けたネガティブショックは広がらず、オリンパスやトヨタ自動車の好決算が投資家心理を支え、大幅下落には至らなかった。TOPIXも3日続伸。東証33業種では、精密機器、その他金融業、非鉄金属などが値上がり率上位に入った。一方、海運業、鉄鋼、石油・石炭製品などは売られた。個別銘柄ではソフトバンクGが反落し2.22%安。同社が6日に発表した2019年4─9月期決算(国際会計基準)は、営業損益が155億円の赤字となり、前年同期の1兆4207億円の黒字から大幅に悪化したことが嫌気された。市場からは「ウィーワークの公正価格の減少については、事前に報道されていたし、ソフトバンクGの株価は既に下がっていた。今回の決算では細かい数字が確認された程度。日経平均への影響は限定的で、ショックまでには至らなかった」(国内証券)との声が出ていた。オリンパスは急騰し年初来高値を更新した。6日に発表した20年3月期の連結業績予想(国際会計基準)では当期利益を前年比7.7倍の630億円と据え置いたものの、同日発表した新たな経営戦略が評価された。そのほか、本日午後1時25分に決算発表を発表したトヨタ自動車は後場上昇し連日の年初来高値を更新。2019年7―9月期連結決算(米国会計基準)では、営業利益が前年同期比14.4%増の6623億円となった。また、同時期に自社株買いも発表したことから、需給改善を期待した買いも入った。東証1部の騰落数は、値上がり984銘柄に対し、値下がりが1070銘柄、変わらずが99銘柄だった。トヨタは決算を受け新値追い、2Q営業益2ケタ増で自己株買いも トヨタ自動車(7203)は午後の決算発表を受けて上げ幅を拡大。前日に続いて年初来高値を更新して2018年1月下旬以来およそ1年10カ月ぶりの高値をつけており、午後1時52分現在では前日比85円(1.1%)高の7734円で取引されている。 午後1時25分に当社が発表した今2020年3月期の第2四半期累計(19年4~9月期)連結決算(米国基準)は売上高が15兆2855億円(前期比4.2%増)、営業利益が1兆4043億円(同11.3%増)だった。直近の四半期である第2四半期(19年7~9月期)の同利益も6623億円(前年同期比14.4%増)と2ケタ増益だったことが好感されている。同時に発行済株式総数の1.19%にあたる3400万株、金額で2000億円を上限に自己株式の取得枠を設定したことも明らかにしており、これも買い材料視されている。通期業績予想は微修正したが、売上高29兆5000億円(前期比2.4%減)、営業利益2兆4000億円(同2.7%減)などは据え置いた。 また、当社株は直近の信用残高が売り残184万株に対して買い残は78万株にとどまり、信用倍率は0.42倍と大幅な売り残超過の状況。5日に日証金ベースでは15銭の逆日歩がついており、苦しくなった売り方が損失確定のために買い戻す動きもあるとみられる。(取材協力:株式会社ストックボイス)(株探ニュース)【市況】明日の株式相場戦略=SBG、トヨタの値運びが映しだす相場の実態 全体相場はリスクオンの潮流に変化がみられず、このまま調整らしい調整もなく年末相場に突入するような気配すら感じさせる。きょう(7日)の東京株式市場は利益確定売りのタイミングと思われたが、押し目では買い板が厚く容易に下がらない。その挙句、大引けを目前にしてプログラム的な売買が流入し全体指数を押し上げ、小幅ながら日経平均は3日続伸となり、年初来高値を更新して着地した。 きょうのマーケットは寄り前に利食いを誘導するようなムードがあり、その背景には米中首脳会談が11月にはできない可能性、つまり事前に報道されていた部分合意について、その署名が12月にずれ込む可能性が伝わった。しかし、これにどれほどの意味があるのか。そう言わんばかりの値動きを株価は示した。 確かに、12月15日に対中追加関税の第4弾の期限が来ることで、「そこに署名が間に合わなければ、今度こそ発動されてしまう。だから大変だ」という理屈も分からないではないが、だから保有株は売りというほどのインパクトはない。そもそも部分合意についても現段階では観測の域を出ていない。オオカミ少年並みに流動的で確度の低いメディアの情報でも、今の市場はヘッドラインに反射的に対応するAI売買が相場をかき回す構図となっている。“人間サイド”としては、これを考慮したうえで振り回されないような心構えが必要となる。 東京市場で言えば、8月初旬の急落や9月上旬の急速な切り返し、そして10月中旬以降の急騰相場において、この間にグローバル経済及び政治面からのアプローチで大きな変化はみられなかった。思惑に振り回され続けた。米中交渉については「進展期待」を放置したまま、先送りの連打で、そのたびに周りが騒がしくなり、それに投資マインドが揺さぶられることの繰り返し。結局、8月初旬の急落時の残像が強すぎて、その後の戻り相場が見えなくなるというトラップに多くの市場関係者が陥った。 醸成された先入観や感情が邪魔をするのが人間の弱さであり、その弱い部分を真逆の現実で株式市場は見事なまでに体現する。投資家にとって敢えてバックミラーを見ない、過去の軌跡にとらわれず、すべて白紙の段階に思考を戻すこと。簡単にできることではないが、これは難局打開のひとつの技術といってもよい。 きょうの相場を振り返ればポイントとなったのは、売買代金ランキングの1位と2位を占めた2つの“主力株”だ。ソフトバンクグループは7~9月期に7000億円の最終赤字となり、孫会長いわく「ぼろぼろ」の決算内容となったが、株価はぼろぼろとはならなかった。寄り前は4000円大台を巡っての攻防になっておかしくないと個人的には見ていたが、実際は4200円台で寄り付き、その後はあわよくばプラス圏に浮上するかという水準まで切り返す強さをみせた。 そして、きょうの午後取引時間中に発表したトヨタ自動車の決算は4~9月期の営業利益が11.3%増と2ケタ増益を確保、同時に自社株買いも発表し、これを素直に好感する形で連日の新高値に買われた。とにかく、今の相場は強いとしかいいようがない。この2銘柄をみても流動性相場の真骨頂というべき株価の値動きを示している。 個人投資家の信用余力の回復で中小型株も出番待ちの銘柄が列をなしている印象だ。今週5日にマドを開けて買われた平河ヒューテックの上昇一服場面はマークしてみたい。5Gとの融合で市場拡大余地が意識される4K・8K関連。決算発表は既に通過している。また、1日に940円台で戻り高値形成後押し目を形成しているアイティフォーもちょうど25日移動平均線との上方カイ離を埋めたところで、好調な業績を考慮してもここは買いに分がありそうだ。 日程面では、あすは9月の景気動向指数(速報値)が後場取引時間中に内閣府から発表される。このほか9月の毎月勤労統計、7~9月の家計調査、10月上中旬の貿易統計など。海外では10月の中国貿易収支、11月の米消費者態度指数(ミシガン大学調べ)などが注目される。(中村潤一)(GDO)国内男子 HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 初日宮本勝昌が首位タイ発進 石川遼は出遅れ95位5月の「中日クラウンズ」以来の今季2勝目を狙う宮本勝昌が5バーディ、ボギーなしの「66」で回り、5アンダーとしてスンス・ハン(米国)、アンジェロ・キュー(フィリピン)、ブラッド・ケネディ(オーストラリア)と並んで首位発進した。今シーズン下部のAbemaTVツアーを主戦場としている平塚哲二が池田勇太、重永亜斗夢、木下稜介らと並んで1打差の4アンダー5位タイにつけた。賞金ランキング1位の今平周吾はイーブンパー47位、ランク2位のチャン・キム(米国)は前週優勝のハン・ジュンゴン(韓国)らと並ぶ1オーバー60位。故郷沖縄で今シーズン国内初戦となる宮里優作は2オーバー74位。賞金ランク3位の石川遼はスタートの10番でダブルボギーを喫するなど「75」で、4オーバー95位と出遅れた。〈上位陣の成績〉1T/-5/スンス・ハン、宮本勝昌、アンジェロ・キュー、ブラッド・ケネディ5T/-4/スコット・ビンセント、重永亜斗夢、木下稜介、池田勇太、トッド・ペク、ディラン・ペリー、ガン・チャルングン、平塚哲二国内シニア 富士フイルム選手権 初日ツアールーキーの深堀圭一郎が単独首位発進51歳の深堀圭一郎が、5アンダーの単独首位で発進した。使用パターを「(通常の)1.5倍くらい重たいのにして、ストロークが自然に動きやすくするように試している」と話す深堀は、最終ホール18番で下りラインの4mを外してイーグルを逃し、6バーディ、1ボギーの「67」でプレーした。深堀はことし4月「ノジマチャンピオンカップ 箱根シニア」でツアーデビューを飾り、今大会で11試合目の出場となる。レギュラーツアーでは8勝しており、同ツアーでの初優勝に期待が懸かるが「今年はいろんなことにチャレンジして、どういうシニアライフになれるかっていうことを探しながら」と気長に構える姿勢だ。1打差の4アンダー2位に今季獲得賞金ランキング2位のタワン・ウィラチャン(タイ)がつけたほか、グレゴリー・マイヤー(米国)、キム・ジョンドク(韓国)が続いた。大会2連覇を狙うバリー・レーン(イングランド)は、尾崎直道、篠崎紀夫らと並んで3アンダー5位で滑り出した。<主な上位成績者>1/-5/深堀圭一郎2T/-4/タワン・ウィラチャン、グレゴリー・マイヤー、キム・ジョンドク5T/-3/バリー・レーン、尾崎直道、篠崎紀夫8T/-2プラヤド・マークセン、鈴木亨、倉本昌弘、日下部光隆、川岸良兼、岡茂洋雄、ソク・ジョンユル国内女子 最終プロテスト 3日目安田祐香は4位で最終日へ アン・シネ17位、三浦桃香78位2打差の6位で出たイ・ソルラ(韓国)が5バーディ、ボギーなしの「67」で回り、通算9アンダーの単独トップに上がった。岡山・作陽高OGで渋野日向子の一学年後輩の石川怜奈、劉依一(中国)が通算7アンダーの2位。安田祐香は「71」と3日間アンダーパーを並べ、通算6アンダーの4位につけた。「スコアは積み重ねていけているので、順調かなとは思う。今日の(3パットボギーだった)1番みたいなミスをしないことを目標に、(合格圏内の)20位以内に入れるようにプレー出来たらと思う」と述べた。常文恵、澁澤莉絵留、石井理緒、プリンセス・スペラル(フィリピン)が5アンダー5位、中西絵里奈が4アンダー9位。吉田優利、セキ・ユウティン(中国)らが2アンダー12位。首位で出たアン・シネ(韓国)は「77」と崩れ、通算1アンダーの17位に後退した。三浦桃香は通算8オーバーの78位で最終日を迎える。大会は4日間72ホールで争われ、20位タイまでに入れば合格となる。<主な成績>1/-9/イ・ソルラ2T/-7/石川怜奈、劉依一4/-6/安田祐香5T/-5/常文恵、澁澤莉絵留、石井理緒、プリンセス・スペラル9/-4/中西絵里奈10T/-3/ハン・スンジ、西村優菜(朝日新聞)製薬謝金:製薬謝金2000万円超7人 16年度、医学部教授ら 文部科学省は6日、2016年度に製薬会社から受け取った講師謝金などの合計額が、2000万円以上に上る大学医学部教授らが7人いたことを明らかにした。同日の衆議院厚生労働委員会で答えた。文科省は、学外の仕事で診療や教育に影響が出ないよう、各大学の兼業規定などについて見直しを求める考えを示した。 製薬各社は医師らに提供した講演料などの講師謝金の金額を毎年公表しており、NGO「ワセダクロニクル」などがこれを集計し、ウェブサイトで公表している。文科省はこれを基に、16年度に全国の大学医学部の教員らが受け取った謝金やコンサルティング業務委託費を調べた。 7人は国立と私立の大学の教授や特任教授ら。糖尿病や認知症、感染症などが専門だった。最多だったのは西日本の私大の特任教授で、20社から153件の謝金など計2899万円を受領した。文科省は、7人の兼業の状況や診療の受け持ちなどを調査している。1000万円以上受け取っていたのは教授など80人(国立27人、公立6人、私立47人)だった。 国民民主党の岡本充功氏への答弁で、佐々木さやか文科政務官は「大学病院で教育、研究、医療の使命を果たし、社会的信頼を損なわないことが重要だ」と述べた。【熊谷豪】(msn)(東洋経済オンライン)キヤノン、ミラーレス不振で3度目修正の深刻度 ソニーが大きく伸長、揺らぐ絶対王者の地位 「結局、また下方修正だったね」 キヤノンが10月28日に開催した投資家やアナリスト向けの説明会の参加者からはあきらめに近い感想が漏れた。 キヤノンは同日、2019年12月期(米国会計基準)の業績について、売上高は3兆6250億円(前期比8.3%減)、営業利益は1880億円(同45.2%減)と、減収減益を見込むとした。7月の中間決算時点での予想から売上高を1200億円、営業利益は270億円引き下げ、業績予想の下方修正は今期3回目となる。米中貿易摩擦の長期化が影響 業績悪化の背景についてキヤノンは、為替が円高に推移していることや米中貿易摩擦の長期化による世界経済の減速を挙げた。「カメラメーカー」のイメージの強いキヤノンだが、プリンターやオフィス向け複合機、半導体露光装置など、法人を主要顧客とするBtoB事業を幅広く手がけている。 度重なる下方修正には、ヨーロッパでのプリンター関連の減収や、半導体露光装置と有機EL蒸着装置など産業機器関連で顧客の設備投資が鈍化したことなどが含まれている。 ただ、プリンターを含むオフィス事業の売り上げは前期(2018年12月期)比で6%減にとどまる見通しだ。産業機器事業の売り上げも前期比11.3%減収するとみられるが、半導体市況の回復や有機ELパネルの需要増が今後見込まれることから先行きは暗くない。 それでもキヤノンが3回目の下方修正を迫られたのはなぜか。それは主力事業であるカメラ事業が不振だからだ。 キヤノンは7月の中間決算時に300億円の構造改革費用を計上した。その中にはカメラの生産・販売体制の見直しが含まれている。 ほかの事業と比較してもカメラ事業に明るい未来は見えない。10月の決算時に公表された最新見通しによると、2019年12月期のカメラ事業の売上高は前期比20.2%減の4747億円を見込んでいる。 苦戦する理由の1つは、スマートフォンの普及などで写真を撮影するためにカメラが必要とされなくなっていることだ。カメラ映像機器工業会によれば、日本のデジタルカメラの出荷台数は2010年の1億2146万台をピークに急減。2018年には1942万台となり、ピーク時の約10分の1になった。ミラーレスカメラの伸びが想定以下に さらにキヤノンを苦しめているのが、ミラーレスカメラの販売台数が当初の想定よりも伸びていないことだ。キヤノンがこれまで強みとしてきた一眼レフカメラと異なり、ミラーレスカメラには本体内部にレンズがとらえた光をファインダーに反射させる「ミラー」がない。そのため、一眼レフよりも小型化・軽量化が可能となり、消費者の支持を集めている。 カメラ市場全体が縮小している中でもミラーレス市場は成長を続けている。2018年の世界出荷台数は一眼レフが前年比約16%減の622万台と減少傾向にあるのに対し、ミラーレスは同約3%増の428万台と増加を保っている(テクノ・システム・リサーチ調べ)。 キヤノンは2018年9月、高級機種であるフルサイズミラーレスとして「EOS R」シリーズを発表。従来は入門機のみでしか扱っていなかったミラーレスに本腰を入れ始め、「ミラーレスカメラでもシェアナンバー1を奪うのは当たり前」(キヤノン開発部門幹部)と意気込んでいた。 【2019年11月7日17時34分追記】写真説明で真栄田雅也社長の社名が誤っていました。上記のように修正いたします。 しかし、キヤノンに立ちはだかったのがソニーだ。ソニーは2013年にフルサイズミラーレスを発売。2018年のミラーレスのシェアは42.5%と圧倒的強さを誇っている(テクノ・システム・リサーチ調べ)。キヤノンにミラーレスカメラ部品を供給している部品メーカーの幹部は「フルサイズミラーレスが投入されて(キヤノンの)売り上げが増えると思ったが、当初の計画にまったく及ばない水準で推移しており、経営計画を変更するしかない」と明かす。 一眼レフカメラの王者だったキヤノンがミラーレスカメラで苦戦するのはソニーの技術力の高さも背景にある。ミラーレスカメラの肝となるのはイメージセンサーの技術力だが、ソニーはCMOSイメージセンサーで世界シェアの過半を占めている。 ミラーレスは、センサーに当たった光を信号処理して電子ファインダーに表示するため、一眼レフと比べて撮影に若干の遅れが出てしまう。ピントを自動で合わせるオートフォーカス(AF)の速度も遅く、スポーツ競技など一瞬をとらえたり、連写が必要な撮影では不利だとされていた。 ところがソニーはその欠点を克服。2017年に「ミラーレス一眼の歴史的な転換点」(同社デジタルイメージング本部の大島正昭担当部長)となった「α9」を発売した。メモリーを内蔵した積層構造のCMOSセンサーを世界で初めて導入。膨大な信号をメモリーに一時保管することで高速処理が可能になり、一眼レフと同等以上の性能を実現した。ソニーがミラーレスカメラのリード役に デジカメ市場に詳しいテクノ・システム・リサーチの大森鉄男シニアアナリストは「ソニーのα9が一眼レフにはない撮影体験を実現したことで、カメラ市場の構造が変わり、ソニーがリーディングカンパニーになった」と話す。 商品のラインナップも、フルサイズミラーレスで20万~40万円弱の商品を主力にするソニーに対し、キヤノンは10万円台後半から20万円強が中心と平均単価に差が出ている。交換レンズ本数もソニーが30本以上あるのに対し、キヤノンは年内にようやく10本そろえた段階だ。 国内市場では、キヤノンのミラーレスカメラでエントリー機種に位置づけられる「EOS Kiss M」が、ミラーレス一眼レフ分野の台数シェアで2018年に1位になっており、「王者」の反撃はようやく始まりつつある。しかし、世界市場でソニーを追撃できるのか、カメラの王者は正念場を迎えている。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-引けではしっかりプラスを確保、決算発表期間中はブル基調が継続か 7日の日経平均は3日続伸。終値は26円高の23330円。米国株が小動きで手がかりに乏しいなか、スタートは小幅安。前場では強弱感が入り交じり、プラス圏とマイナス圏を行き来した。前場を8円安で終えると、後場はこう着感が強まる展開。トヨタが決算発表後にプラス転換しても連れ高することはなかったが、ソフトバンクGが売り直されても連れ安はせず、狭いレンジでのもみ合いが続いた。ただ、終盤にかけて強めの買いが入ってプラス圏に浮上すると、そのまま上昇を保って取引を終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆3800億円。業種別では騰落率上位は精密機器、その他金融、非鉄金属、下位は海運、鉄鋼、石油・石炭となった。上期の増益着地が好感された森永乳業が後場プラス転換から上げ幅を拡大。半面、3Qの減収減益が失望となったノムラシステムコーポレーションが後場に入って急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり984/値下がり1070。上期が大幅増益となったオリンパスが15%超の上昇となり、市場の注目を大きく集めた。下方修正発表で悪材料出尽くし感が強まったシスメックスや、上期最高益更新観測が報じられたゼンショーHDが大幅高。下方修正発表のヤマシンフィルタは売りが先行したものの、切り返して6%超上昇した。直近で派手に動いた銘柄を蒸し返すような動きが見られ、三桜工業が大商いとなってストップ高。霞ヶ関キャピタルもストップ高まで買われた。一方、上期営業赤字のソフトバンクGが下落。売り気配スタートから4%超下げた後、値を戻す場面もあったが、戻りは鈍く引けでは2.2%安となった。通期の見通しが失望を誘ったSUMCOや、下方修正を発表した東海カーボンが大幅安。今期が大幅減益見込みとなったリンクバルはストップ安比例配分と売りが殺到した。ペプチドリームは空売り投資家の売り対象となっていると伝わったことから、大きく売られる展開となった。 日経平均は3日続伸。プラスの時間帯は短かったが、下げても売り崩すような動きがほとんど見られず、終日落ち着いた地合いとなった。ソフトバンクGやトヨタの決算反応が注目されたが、良くも悪くもこれらの値動きに指数が翻弄されることはほとんどなかった。あすは週末となるが、来週以降も決算発表がまだ控えていることを鑑みると、売りが急がれることもないだろう。テクニカル面をみると、今週はここまで5日線(23132円、7日時点)より上での推移が続いており、海外要因で売られたとしても、同水準がサポートになると期待できる。引き続き好地合いが見込まれるなか、週末一段高で23500円どころを目指す動きが見られるかに注目したい。NY株見通し-もみ合いか継続か 決算発表は引け後にウォルト・ディズニー 今晩のNY市場はもみ合い継続か。昨日は米中通商合意署名のための米中首脳会談の先送り報道を受けて一時下落する場面もあったが、ダウ平均とS&P500はほぼ変わらずで終了し、ナスダック総合も小幅な下落にとどまった。主要3指数がそろって史上最高値圏にあることや、過熱感を示すテクニカル指標も増えており、利益確定売り圧力が強まるなかでの底堅い展開だった。今晩は、昨日引け後に好決算を発表したクアルコムが半導体株の上昇をけん引することが期待されるものの、米中通商交渉関連報道などをにらみ引き続き神経質な展開となりそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは、新規失業保険申請件数、9月消費者信用残高、カプラン米ダラス連銀総裁の講演など。企業決算は、寄り前にラルフローレン、エアープロダクツ、引け後にウォルト・ディズニー、ブッキング・ホールディングスなどが発表予定。(執筆:11月7日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=堅調な動きが続きそう 8日の東京株式市場は、底堅い動きが継続し、堅調な動きとなりそう。市場では「東証1部の売買代金が2兆円をキープするなか、戻り待ちの売りを吸収しているようだ。現在の水準を上抜けると2万4000円近い水準までは、急落した反動で戻り待ちの売りは少ないとみられ、キッカケ次第で上値を試しに行く可能性もある」(中堅証券)との見方も聞かれた。ただ、週末要因から手じまい売りに押されることに注意が必要のほか、11月限株価指数先物・オプションのSQ(特別清算指数)値の市場速報値が意識される場面もありそうだ。 7日の東京株式は、前日比26円50銭高の2万3330円32銭と3日続伸し、連日で年初来高値を更新して取引を終えた。後場に入り一時下値を試す場面がみられたものの、午後2時50分すぎ、株価指数先物に断続的な買いが入ったことから、上昇に転じた。今晩のNY株の読み筋=米中首脳会談開催をめぐる動向に注意 きょうの米国株式市場は、底堅い展開か。 前日は米中首脳会談の開催が12月にずれ込む可能性があると報じられたことが株価の重しとなり、NYダウは5日に付けた史上最高値から小反落した。ただ、好決算を受け買われたCVSヘルス、ダビータなどヘルスケア関連が相場をサポートするなど、地合いは損なわれていない。 きょうの米国株式市場は、寄り前にヘルスケア関連のゾエティス、高級衣料品のラルフローレンなどの決算発表がある。いずれも株価は市場コンセンサスより割安で、好決算には買いで反応する可能性がある。そうなれば、引け後に決算発表を予定するウォルト・ディズニー、ドロップボックスなどにも期待が集まりそうだ。 一方、米中首脳会談の開催調整が難航するようだとリスク回避姿勢が意識され、利益確定売りが出やすくなる点には注意したい。<主な米経済指標・イベント>9月消費者信用残高、30年国債入札センターポイント・エナジー、カーディナルヘルス、ノーブル・エナジー、ニールセン・ホールディングス、ゾエティス、ディスカバリー、ラルフローレン、ゴープロ、ウォルト・ディズニー、ドロップボックスなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔NY外為〕円、109円台前半(7日朝) 【ニューヨーク時事】7日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米中貿易協議の進展期待が高まる中、1ドル=109円台前半で弱含みに推移している。午前9時現在は109円10~20銭と、前日午後5時(108円94銭~109円04銭)比16銭の円安・ドル高。 中国商務省の高峰報道官はこの日の記者会見で、米中両国が「協議の進み具合に合わせ、追加関税を段階的に撤廃することに同意した」と説明。これを受け、貿易協議の「第1段階」合意文書の署名実現へ向けた条件が整いつつあるとの期待感が台頭した。 円相場は7日未明に、108円70銭付近から40銭ほど下落。ニューヨーク市場は109円12銭で取引を開始し、米経済指標などの手掛かりに乏しい中で小動きとなっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1060~1070ドル(前日午後5時は1.1016~1026ドル)、対円では同120円75~85銭(同120円56~66銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも史上最高値更新(7日朝) 【ニューヨーク時事】7日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の進展期待が広がり、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は2日ぶりに取引時間中の史上最高値を更新し、午前9時40分現在は前日終値比185.56ドル高の2万7678.12ドルとなった。ハイテク株中心のナスダック総合指数も史上最高値を更新し、同時刻現在は57.31ポイント高の8467.94。(了) (yahoo)(みん株FX)クアルコムが好決算で上昇 5Gへの期待を強調=米国株個別 クアルコムが上昇。7-9月期決算を発表しており、1株利益、売上高とも予想を上回った。同社はスマホ市場について、2019年に最低17億台に減少した後、来年は回復すると予想。2020年の出荷台数が最高18.5億台に上り、そのうち5G端末は最高2.25億台に達するとの見通しを示した。 モレンコフCEOはインタビューで、「売上高は減収となっているものの、懸念されていた状況より好調で、来年の早い時期に5Gの急速な浸透から恩恵を受ける見込みだ。5Gで多くの動きが見られている」と述べた。また、「四半期決算と見通しは5Gが来年に転換点を迎えるとのわれわれの確信の表れだ」とも述べた。クアルコム製チップ搭載の5Gモデルが現在230種と、3ヵ月前の150種から増えていることも明らかにした。 同社の半導体部門の責任者トップアモン氏はアナリスト説明会で、5Gを巡る予想は保守的で、消費者がスマホの買い替えを活発に行えば、この数字は増える可能性がある」と語った。(7-9月・第4四半期)・1株利益(調整後):0.78ドル(予想:0.71ドル)・売上高:48億ドル(予想:47.1億ドル)・MSMチップ出荷量:1.52億個(予想:1.5億個)(10-12月・第1四半期見通し)・1株利益(調整後):0.80~0.90ドル(予想:0.77ドル)・売上高:44~52億ドル(予想:47.8億ドル)・MSMチップ出荷量:1.45~1.65億個(予想:1.5億個)(NY時間09:43)クアルコム 90.67(+6.04 +7.14%)本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の16銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の19銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げてスタートしましたね。
2019.11.07
コメント(0)
-
11月6日(水)…2019ラウンド83…
11月6日、晴れです。今日も良い天気です。そんな本日は、ホーム1:GSCCの西コースで開催の水曜杯に参加させていただきました。9時40分スタートですから7時頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時10分頃に家を出る。8時40分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…マアマア…。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはいつもの、M君(12)、T君(18)です。O君はお仕事でお休みです。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:-1.0.2.0.0.1.0.1.2=41(18パット)1パット:2回、3パット:2回、パーオン:4回。1打目のミスが2回、2打目のミスが3回、アプローチのミスが1回、パットのミスが4回…。前半の素ダボ2発でほぼ切れてしまいました…。10番のスタートハウスで稲荷寿司をいただく。IN:0.2.0.1.1.0.1.0.1=42(16パット)1パット:3回、3パット:1回、パーオン:1回。1打目のミスが5回、2打目のミスが4回、アプローチのミスが1回、パットのミスが2回…。ままならないゴルフにイライラが募ります…。41・42=83(8)=75の34パット…。何の期待もできませんね…。握りも大敗…。スコアカードを提出して、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.6kg,体脂肪率21.0%,BMI22.0,肥満度0.0%…でした。帰宅すると15時10分頃。奥の自家製アップルパイと紅茶でおやつタイム。それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には49人が参加して、トップは79(14)=65とのこと。M君が80(12)=68で3位。僕が83(8)=75で25位。T君が96(18)=78で35位。お疲れ様でした。1USドル=108.96円。1AUドル=75.10円。昨夜のNYダウ終値=27492.63(+30.52)ドル。本日の日経平均=23303.82(+51.83)円。金相場:1g=5767(-61)円。プラチナ相場:1g=3667(-12)円。(ブルームバーグ)世界経済、最悪期を脱した可能性-利下げや米中合意期待で安定の兆し ここ10年で最も大きく減速していた世界経済は、最悪期を脱した可能性がある。 最近落ち込んでいた主要経済指標が安定化の兆しを示す中、米金融当局を含む世界各国・地域の中央銀行の相次ぐ利下げや、米中通商合意への期待の高まりで、金融市場の信頼感が押し上げられている。 堅調な回復はまだ先の話かもしれないが、相対的な改善を受け、ほんの数週間前に浮上していた世界経済がリセッション(景気後退)に向かいつつあるという懸念に終止符が打たれる可能性がある。こうした状況は、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長ら金融当局者が金融緩和の休止を決定するのに当面十分であるように見受けられる。 スタンダードチャータードのチーフエコノミスト、デービッド・マン氏(シンガポール在勤)は「2020年の世界経済の成長が19年と比較して安定化する多くの理由が確かに見られる」と指摘し、国際通貨基金(IMF)と同様、来年に世界経済の成長が加速すると予測している。 市場の信頼感の一因となっているのが、JPモルガン・チェースの世界製造業指数だ。同指数は10月に6カ月連続で活動縮小を示す50割れとなったものの、生産と受注は共に底堅く、活動拡大の領域に若干近づいた。 ただ、ソフトランディングのシナリオが確定的となったわけではない。5月にも同様の期待が高まっていたが、トランプ米大統領の対中関税を巡る発表を受けて米中間の緊張が高まった。米中は「第1段階」の貿易合意に近づきつつあると示唆しているが、通商協議が包括的合意に向けて継続するかは不明だ。 ベレンベルク銀行のチーフエコノミスト、ホルガー・シュミーディング氏は、「米中貿易摩擦が再びエスカレートしたり、米国が欧州連合(EU)に対して新たな貿易戦争を仕掛けたりした場合、依然として事態は悪化しかねない」と指摘。「しかし、そうした新たな政治的ショックがない限り、世界経済の低迷は20年の早い時期に終了し、その後は緩やかに回復していく可能性がある」と述べた。米住宅ローン市場に流動性リスク、影の銀行成長で ムニューシン米財務長官が議長を務め、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長も参加する金融安定監視評議会 (FSOC)は、11兆ドル(約1200兆円)規模の住宅ローン市場で経済に打撃を与えかねない流動性の逼迫(ひっぱく)が発生するリスクがあるとスタッフから報告を受けた。 高リスク分野を中心とする住宅ローンの組成および債権回収業務でシャドーバンキング(影の銀行)が急成長している状況が、米金融規制・監督機関で構成するFSOCに最近示された懸念の背景にある。 「住宅ローン市場における流動性の危機」と題する2018年の論文の共同執筆者であるカリフォルニア大学バークリー校のナンシー・ウォレス教授は「現実の脆弱(ぜいじゃく)性がここに存在する。これらの業者の多くが資金的に不安定だ」と指摘した。 これらの金融業者は、金融ストレスが発生すれば取り下げられるであろう短期の銀行与信に依存しており、住宅ローン業務を縮小せざるを得なくなれば、住宅市場と経済全般に最終的に打撃になりかねないと懸念されるという。債券は大幅続落、10年入札弱めで先物売りー長期金利5カ月ぶり高水準 債券相場は大幅続落。長期金利は約5カ月ぶりの水準に上昇した。リスク選好の流れで前日に米長期金利が上昇したことに加え、この日に実施された10年国債入札の結果を受けて先物の売りが強まった。 新発10年国債利回りは一時、前日比6.5ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.075%、新発5年国債利回りは7.5bp高のマイナス0.195%と、いずれも5月以来の高水準を付けた 長期国債先物12月物の終値は66銭安の153円23銭。一時は153円00銭と、中心限月の日中取引ベースで5月30日以来の安値 市場関係者の見方 野村証券の中島武信シニア金利ストラテジスト10年入札結果の発表後に先物主導で下げ幅を拡大しており、海外勢の先物売りが続いている可能性米中貿易協議の進展期待で株式相場が堅調な中、利下げ期待の後退で米長期金利が上昇している10年金利はかなり上昇したが、結局は海外勢が買うかどうか。米10年金利はもっと上昇しており、ドル建て10年債の妙味が低下。中期債も同様だ みずほ証券の松崎涼祐マーケットアナリストここまで売られるとポジションを落としたい動きが出るが、現物だけではさばけず、先物にヘッジ売りが集中しやすい中期債は利下げがないと正当化しづらい水準だった上、10年入札も付利のマイナス0.1%を上回り、利下げに懐疑的な見方がある海外金利上昇がドライバーになる中、円金利スワップでも海外勢の受けが減っているかアンワインドかで勢いが弱まっている 10年債入札 最低落札価格101円94銭と、ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値101円95銭をやや下回る 応札倍率は3.62倍と前回3.42倍をやや上回る。テール(最低と平均落札価格の差)は5銭と前回29銭から縮小 パインブリッジ・インベストメンツ債券運用部の松川忠部長 やや弱めの結果でヘッジ売りが先行。それほど大きな需要はなかった感がある 日銀のサポートが消え、10年以下はマイナス金利深掘り期待のポジションが解消されているようだ 背景 米ISM非製造業総合景況指数:10月は上昇、市場予想も上回る 5日の米10年国債利回りは一時1.87%と、約1カ月半ぶりの高水準 米主要株価指数が過去最高付近で推移する中、この日の日経平均株価は0.2%高の2万3303円82銭。円相場は1ドル=109円台で推移日本株は小幅続伸、米景気堅調と円安-商社など景気敏感や金融高い 6日の東京株式相場は小幅続伸。堅調な米国の経済指標や為替相場の円安、米金利上昇が追い風となり、商社や素材など景気敏感業種や銀行が高い。NTTやアサヒグループホールディングスなどの決算失望が加わった内需ディフェンシブ関連の一角は安い。 TOPIXの終値は前日比0.29ポイント(0.02%)高の1694.45 日経平均株価は51円83銭(0.2%)高の2万3303円82銭〈きょうのポイント〉 10月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合景況指数は54.7に上昇、市場予想53.5 5日の米10年債利回りは8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.86%-9月以来の高水準 NTTの4-9月期営業利益は市場予想を下回る、アサヒGHは営業利益予想を下方修正 三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩シニアストラテジストは「米中協議の進展、雇用統計そしてISM非製造業指数と、底堅い米経済を受けて投資家の目は景気敏感に向かいやすい」と述べた。きのう大きく上げた反動が警戒されたものの、「先行きの景況感改善や企業業績の底打ち期待から大きくは崩れない」とみる。 海外景況感の改善を背景としてTOPIXは取引開始時に昨年10月以来となる1700ポイントを一時回復した。いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は「米中摩擦で米国の製造業は悪いが、雇用は良く消費や住宅市場は悪くないなど非製造業は落ち込んでいない。景気後退(リセッション)を予想していた債券市場は間違いだった」と指摘した。 買い戻しの勢いがやや欠ける中で株価指数の上げ幅は限定的だった。いちよしAMの秋野氏は「市場関係者の間では日本株は一本調子で上がってきたとの感覚があるため、いったんスピード調整になりやすい」と話していた。空売り比率40%割れの記事はこちらをご覧ください 東証33業種では鉄鋼や海運、非鉄金属、鉱業、卸売、証券・商品先物取引、銀行が上昇 食料品や情報・通信、サービス、精密機器は下落(ロイター)米ゼロックス、米パソコン大手HPの買収を検討=WSJ[6日 ロイター] - 米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は5日、米事務機器大手ゼロックス(XRX.N)が米パソコン大手HP(HPQ.N)の買収を検討していると報じた。現金と株式交換を組み合わせ、HPの時価総額である270億ドルを上回る価格での買収が検討されているという。 報道によると、ゼロックスは5日に取締役会を開き、HP買収の可能性について話し合った。 ただ、ゼロックスが実際に買収を提案すると確定したわけではなく、提案した場合も成功する確証はないとWSJは伝えている。 ゼロックスは、ある大手銀行から非公式に資金調達の了解を得ているという。 HPはロイターに対し、うわさや観測にはコメントしないと述べた。 ロイターはゼロックスにコメントを求めたが、これまでのところ応じていない。 ゼロックスは5日、富士フイルムホールディングス(4901.T)との合弁会社、富士ゼロックスの株式25%を23億ドルで売却すると発表した。 HPはプリンター部門が低迷。第3・四半期の同部門の収入は前年比で5%減少した。 同社は10月、コスト削減の一環で最大9000人を削減する計画を発表した。 コラム:巨額債務のソフトバンク、資産下落時に逆回転リスク[ロンドン 5日 ロイター Breakingviews] - 孫正義氏が会長兼社長として率いるソフトバンクグループ(9984.T)は、ハイテク分野の巨大投資マシーンであり、気前よく重ねた借金が潤滑油の役割を果たしている。同社が抱える資産の価値が高まっていた局面では、借り入れによる経営がうまく機能した。しかし、今後は資産価値が下がって、借金が問題になりかねない。 孫氏が好んで用いる指標に基づくと、ソフトバンクグループの債務負担は、やり繰りが可能に思われる。同氏は、借入金を総資産価値の25%未満にとどめたい考えだ。この総資産には、中国電子商取引最大手アリババ(BABA.N)の株式や、携帯電話2社、半導体メーカーのArm(アーム)、1000億ドル規模の巨額ファンド「ビジョン・ファンド」が含まれる。 これらの資産価値は、上場株の時価やソフトバンクによる未上場資産の評価を踏まえると2600億ドルに上る。6月末の純債務は450億ドルで、この17%に収まる。手元の現金は少なくとも2年間の社債返済資金をカバーしており、キャッシュフローは6月までの1年間の利払い額の2倍を超える。 だが、こうした指標で全ての状況が説明されたわけではない。まず初めに、傘下の携帯電話会社である米スプリント(S.N)と日本のソフトバンク(9434.T)は、合計で約900億ドルを借り入れている。 法的に考えると、両社の債務は返済原資が限定されるノンリコース型なので、ソフトバンクグループは万が一の場合、債権者の追及を免れることができる。とはいえ、孫氏がスプリントとすっぱり手を切るとは想像しがたい。そんなことをすれば、ソフトバンクグループの資産価値の10%強が一気に消滅し、他の子会社による将来の借り入れがより難しくなる。 実際に孫氏は最近、ソフトバンクグループの資産価値を利用して、経営難に陥っている共有オフィス「ウィーワーク」を運営する米ウィーカンパニーの支援策を打ち出した。債権者は、資金繰りに窮している出資先企業への救済措置は、いわゆる「偶発債務(将来何らかの形で返済義務が生じる債務)」ではないかとみなす傾向にある。 ビジョン・ファンドは、配車サービスの米ウーバー・テクノロジーズ(UBER.N)など赤字企業の株式を保有しているという面で、別の重荷も背負っている。 同ファンドの資本のうち約400億ドルは優先株の形になっており、サウジアラビアのパブリック・インベストメント・ファンドといった出資者に年間7%の配当を支払っている。優先株は厳密には債務ではないが、孫氏はソフトバンクグループの株主への利益還元よりも、優先株の配当をきっちりと行わなければならない。 また、ビジョン・ファンドは、一部投資案件について最大41億ドルを銀行から借り入れることができる契約に調印し、優先株の配当にも活用されている。その点でも資産価値が急落すれば、事態悪化に拍車が掛かる。 最後に、孫氏自身の問題がある。ブルームバーグの報道によると、同氏は個人的な借り入れの担保として、保有しているソフトバンク株180億ドル相当の38%を差し入れている。ビジョン・ファンドへの投資資金としてソフトバンクの幹部・社員に提供された総額50億ドルの融資のほとんども、孫氏向けだ。つまり孫氏とソフトバンクグループはともに、ビジョン・ファンドのパフォーマンスに命運が左右される側面が強まっている。 孫氏が定義する狭義の純債務で判断しても、ソフトバンクグループの借り入れ負担は、見た目よりも重い。公式に発表している総資産有利子負債比率(LTV)は、かさ上げされた資産が前提になっているのだ。 例えば、アリババの持ち分26%について、処分すれば最大で30%の税率が課せられてもおかしくないにもかかわらず、時価の1200億ドルのままで評価している、とバーンスタインのアナリストチームはみている。 株式市場の投資家は適切に、より懐疑的な見方をしており、ソフトバンクグループの時価総額は、債務を差し引いた後の総資産価値の38%程度に過ぎない。 ソフトバンクグループの今後の利払い能力も、見かけほど堅固ではない。6月までの1年間に傘下企業から受け取った現金は45億ドル前後で、約21億ドルの債務返済費用を十分に賄えた。 ただ、現金の出所は2つだけだ。1つ目はビジョン・ファンドからの資産管理手数料と半導体企業・エヌビディア(NVDA.O)などの株式売却益の20億ドル。2つ目は携帯電話子会社・ソフトバンクが配当金として支払った25億ドルだ。 ウィーワークの上場中止でハイテク企業の新規株式公開(IPO)に対する需要が冷え込んだことから、ビジョン・ファンドからの現金納付はもはやほとんど当てにできない。 そこで孫氏が携帯電話子会社からの配当金だけに依存するようになれば、余裕は乏しくなる。6月までの1年間のソフトバンクグループの利払い費は、携帯電話子会社から受け取った配当金の82%に達するからだ。リフィニティブのデータに基づくと、ソフトバンクグループは、向こう3年間で債務返済予定額が140億ドルに急増するという逆風にも見舞われる。 では、孫氏は現金が必要になった場合、何ができるのか。良いニュースは、流動性のある資産に不自由はしないことだ。保有するアリババ株の4%を現在の価格で売れば、税率30%と仮定しても、来年から2022年までに満期が到来するソフトバンクグループの全社債の返済資金が確保できる。2016年に320億ドルで買ったアームなどの未上場資産を手放す方法もある。 悪いニュースは、やむを得ない形の資産売却が、売り手にとって満足のいく価格になるケースがほとんどないことだろう。ソフトバンクグループはアリババの圧倒的な大株主なので、売却に動けばアリババ株の需給自体を崩してしまう。 一方、資産価値が下落するのに伴って、借り入れによって投資を拡大するという孫氏の戦略が裏目に出てくるだろう。ソフトバンクグループの純債務は、企業価値のほぼ5分の2に上る。したがって保有資産の価値が20%目減りすれば、株価は33%程度下がるはずだ。その時点で、孫氏の巨大な投資マシーンは逆回転し始める。 ●背景となるニュース *ソフトバンクグループは6日に7─9月期決算を発表する。ブルームバーグは10月24日、ソフトバンクが傘下のビジョン・ファンドのウィーカンパニーやウーバー・テクノロジーズなどへの出資に絡んで最低50億ドルの評価損を計上する方針だと報じた。 *ソフトバンクグループの広報担当者はBreakingviewsに対して、総資産有利子負債比率(LTV)を安全な水準に保ち、適切なキャッシュポジションを維持し、子会社からの安定的な配当収入を確保して自社の財務上の安全性をしっかりと継続していくとの考えを示した。 (会社四季報オンライン)(ロイター)S&P小幅安、米中協議への期待受けた買い一服ダウは30ドル高の2万7492ドル[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米国株式市場はS&P500が小幅安で取引を終えた。米中通商協議進展への期待から前日は主要3指数がいずれも最高値を更新したが、この日は買いが一服した。米中通商協議を巡っては楽観的な見方が強まっているが、投資家の間では慎重な姿勢も見られ、ここ数日は割安株が成長株をアウトパフォームしている。ラッセル1000バリュー指数が過去3営業日で2%近く上昇したのに対し、ラッセル1000グロース指数は0.8%上昇にとどまっている。関係筋によると、中国は米国との通商協議における「第1段階」の合意の一環として、9月に発動した対中関税を撤回するよう求めている。インバーネス・カウンセルの最高投資責任者ティム・グリスキー氏は「株価は過去最高値水準にあり、投資家は通商協議を巡りやや神経質になっている」と指摘。「間違いなく割安株へのシフトが見られるが、むしろ金利上昇を受けた金融株へのシフトや商品価格上昇に伴うエネルギー株へのシフトだ。両セクターは大きく売り込まれてきたため、割安になっている」と語った。金融株は、米10年債利回りが6週間ぶり高水準を付けたことを受けて0.42%上昇。原油価格が1%超値上がりし、エネルギー株も買われた。一方、金利に敏感な不動産株は1.76%安となった。米中通商協議への期待感に加え、第3・四半期の企業決算がおおむね予想を上回っていることや、米連邦準備理事会(FRB)による前週の利下げ、堅調な経済指標もこのところ株価の下支え要因となっている。米供給管理協会(ISM)が5日発表した10月の非製造業総合指数(NMI)は54.7と、市場予想を上回り、製造業の減速が他部門に波及しているとの懸念が和らいだ。個別銘柄ではボーイングが2.05%高。同社のカルホーン会長は5日、墜落事故を起こした「737MAX」機の問題を巡り、取締役会はデニス・ミューレンバーグ最高経営責任者(CEO)が「すべて適切に対応した」と確信していると述べた。アドビは2020年度通期の見通しなどを好感して4.25%上昇した。一方、ウーバー・テクノロジーズは9.85%急落。前日発表した第3・四半期決算で赤字が拡大したことを嫌気した。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.13対1の比率で上回った。ナスダックでは1.10対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は78億9000万株。直近20営業日の平均は66億1000万株。日経平均は小幅続伸、連日年初来高値更新 外部環境が安心感誘う日経平均終値は51円83銭高の2万3303円82銭[東京 6日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は小幅に続伸し連日年初来高値を更新。オーバーナイトで米国株が堅調推移し、為替も1ドル109円台で安定的に推移したことが好感され、朝方から買いが先行した。寄り付きで年初来高値を付けた後は利益確定の売りに押され、小動きとなった。 前日の米国株市場では、ダウ工業平均とナスダック総合が終値で過去最高を更新。S&P総合500種は小幅安で取引を終えた。米中通商協議の進展期待や前週の米連邦準備理事会(FRB)の利下げに加え、10月の米ISM非製造業総合指数が市場予想を上回ったことが安心感を誘った。 東京市場は良好な外部環境を背景に続伸でスタートし、年初来高値を付けた後は利益確定売りが上値を重くした。米国株先物をにらみ一時マイナス転換する場面もあったものの、大引けではプラス圏を確保した。 市場からは「米中の『第1段階』の通商合意に対する期待から先高観が維持されている。日経平均は前日に400円上昇したことを踏まえれば、堅調に推移しているといえる」(三木証券・投資情報課長の北澤淳氏)との声が出ていた。 そうした中で、「米株が過去最高値を更新するなか、CTA(商品投資顧問業者)やリスク・パリティ・ファンドが債券先物を売って、株式先物に乗り換えている可能性がある」(アライアンス・バーンスタイン・債券運用調査部長の駱正彦氏)との指摘もあった。 TOPIXも続伸。東証33業種ではパルプ・紙、鉄鋼、海運業などが値上がり率上位。一方、食料品、情報・通信業、精密機器などは売られた。 個別では、アサヒグループホールディングスが大幅反落。2019年12月期の連結業績予想(国際会計基準)を下方修正したことや、配当予想の減額を発表したことが嫌気された。取引時間中に同じく下方修正を発表したSUBARUや味の素も売られた。 そのほか、ファーストリテイリングは小幅高。5日、10月の国内ユニクロ既存店売上高が前年比1.9%減少したと発表したが、ネガティブな見方は広がらなかった。シャープは4日続伸で年初来高値更新した。 東証1部の騰落数は、値上がり1009銘柄に対し、値下がりが1039銘柄、変わらずが106銘柄だった。医薬品開発で次世代の主役「核酸医薬」とは何か日本新薬など国内企業も急ピッチで開発 2019年のノーベル生理学・医学賞は「細胞の低酸素応答の仕組み」が対象となりました。昨年はがん治療向けの抗体医薬品開発に寄与した京都大学高等研究院特別教授の本庶佑(たすく)博士らが受賞。生理学・医学賞は基礎研究と応用研究が交互に受賞するとの指摘もあり、次回は創薬分野での受賞も期待されます。抗体医薬品はたんぱく質の一種であり、現在の世界の創薬ビジネスをリードしています。 次期の医薬品開発のメインテーマは何か。現在、最も期待される分野が「核酸医薬」です。 たんぱく質はアミノ酸を結合させたものであり、核酸はヌクレオチドから構成されています。核酸は遺伝情報の本体であり、アミノ酸の結合を誘導することでたんぱく質合成を司っています。核酸が抗体をコントロールしているという議論も誤りとは言えないと思われます。 DNAはデオキシリボ核酸、RNAがリボ核酸であり、ともに核酸。核酸医薬は遺伝情報を操る物質を医薬品に応用するという試みです。遺伝子本体を薬品化すれば、遺伝病などにとっての福音になるという発想は、古くからありましたが、核酸はコントロールが難しく、毒性などの問題も抱えています。このため、抗体医薬品の方が開発で先行し現在は全盛期を迎えています。 しかし、ここにきて核酸医薬への期待は高まっています。背景には、抗体の研究開発が進み創薬としての限界が見え始めたことや、核酸医薬の利便性が再認識されたことも無視できません。 一般に化学合成で製造された医薬品は低分子医薬品。低分子医薬品とは文字どおり分子量が小さいという意味です。合成が比較的容易であり、薬剤の作用メカニズムもシンプル。逆に、高分子医薬品は分子量が大きく作用も複雑です。抗体医薬品は代表的な高分子医薬品です。作用機構は複雑で低分子にはない薬効も期待されますが、他方で合成コストが高く、高薬価が社会問題となっています。 このため、開発現場ではより低分子の医薬品ができないかという問題意識が出てきて、これが核酸やペプチドなどの中分子医薬品開発に直結しました。しかし、ペプチドはたんぱく質を分解した物質で次期の柱と考えるには荷が重すぎるとの見方が一般的です。このため、核酸医薬が次世代の主役として期待が高まってきたという訳です。 現在、世界の抗体医薬品の市場は欧米企業に独占されています。小野薬品工業の「オプジーボ」は、その例外的な存在といえるでしょう。次世代のホープと期待される核酸医薬も欧米企業が開発をリードしているのが実情です。ただし、世界的に開発が順調に進んでいるとは言いがたい状況にあります。このため、日本企業にもチャンスはあります。 世界で最初に登場した核酸医薬はスイスのノバルティス社などが開発したエイズ患者向けCMV性網膜炎治療薬。同薬はすでに販売中止に追い込まれており、同薬を除くと現在世界で販売されている核酸医薬は8品目です。8品目はすべて、米国のバイオベンチャー企業などが手がけています。 核酸医薬は作用システムにより多岐に分類されます。代表的なものはアンチセンス、アプタマー、SiRNA、など。前述のCMV性網膜炎治療薬はアンチセンス治療薬です。同薬はRNAなどの相補性を利用して遺伝子発現を抑制します。アプタマーは特異的に結合する核酸分子の性質を応用するものであり、SiRNAは原理的にアンチセンスに近く、干渉作用を用いて遺伝子発現を抑制する薬剤です。 わが国でもこの代表的な3分野での開発が急ピッチで進んでいます。日本新薬(4516)はアンチセンスの治療薬「NS―065」を米国で承認申請中。同薬のターゲットはデュシェンヌ型筋ジストロフィーであり、国内でも現在臨床中期レベルにあります。この他、武田薬品工業(4502)や第一三共(4568)なども同分野の開発を推進中。SiRNA分野ではテープの技術系譜を背景に事業展開する日東電工(6988)やベンチャー企業のリボミック(4591)なども開発で先行しています。この他、バイオベンチャーのアンジェス(4563)も米国で核酸医薬の臨床を進めるなど積極的な開発により注目が高まっています。(共同通信)器物損壊疑いで医師逮捕 「玉打つことが快感」 ゴムでパチンコ玉などを飛ばす道具「スリングショット」を使って他人の家の雨戸をへこませたとして、警視庁富坂署は6日までに、器物損壊の疑いで、東京都文京区、医師安藤寛(あんどう・ひろし)容疑者(59)を逮捕した。 富坂署によると、安藤容疑者の自宅周辺では、家の窓ガラスが割られたといった被害の申し出が8件あり、同署が関与を調べている。安藤容疑者は「ゴムを解き放って玉を打つことが快感だった。一戸建てを狙い、昨年9月からやった」と供述している。 逮捕容疑は3日午前2時半ごろ、自宅マンションの廊下から、近くの60代男性宅の雨戸に複数回金属製の玉を発射し、雨戸を壊した疑い。(goo)(共同通信)従業員が顧客の個人情報持ち出し トレンドマイクロの海外拠点 情報セキュリティー企業のトレンドマイクロは6日、海外拠点の従業員が顧客情報を不正に持ち出し、第三者に売却していたと発表した。同社は、情報流出があったのは米国、英国、ドイツなど8カ国の最大12万人に上るが、日本の製品利用者に被害はないと説明している。 今年8月に顧客から、サポート窓口を装った詐欺被害を訴える連絡が同社にあり発覚した。捜査機関に通報するとともに内部調査を続けていたが、従業員が持ち出しに関与していたことが判明した。従業員はすでに解雇したという。 同社は海外拠点の場所や詐欺被害があった国を明らかにしていない。(goo)(文春オンライン)河井前法相の大幅スピード違反を広島県警が見逃していた!「週刊文春」(10月31日発売号)が報じた妻・案里氏の参院選における公選法違反疑惑を受けて、同日、法務大臣を辞任した河井克行衆院議員(56)。法相在任中に、悪質なスピード違反を秘書にさせていたことが新たに判明した。 事件が起きたのは10月5日。河井氏は、正午から北広島町で始まるイベントのため、急いで広島県内を移動していた。その際、河井大臣(当時)が急ぐように求め、80キロ制限の高速道路を、60キロオーバーの140キロで走行したという。 50キロ以上の超過は本来、一発免停で、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となる。ところが、警護についていた広島県警の後続車両は、140キロで走る河井氏の車を追いかけつつ、事務所に注意を促す電話を入れたのみで、違反を検挙しなかったというのだ。 その決定的な証拠を「週刊文春」は新たに入手した。克行氏と事務所スタッフらとのLINE上のやり取りだ。そこには、10月5日の12時に〈県警より、「現在140キロで飛ばされていますが、このようなことをされたら、こちらとしてはかばいきれません。時間に余裕を持って、時間割を組んでください」とお電話がありました〉と記されていた。 広島県警に聞くと、「個別の事案については回答を差し控えます。ただ、一般論として警護対象者が乗っている車が一時的に法定速度を上回る速度超過が疑われるような事があった場合は、秘書等を通じて是正を促すこともあります」と回答した。 河井氏の事務所に一連の行為について聞いたが回答はなかった。 今年3月には、麹町署の巡査が、警察官の交通違反を見逃したとして、犯人隠避容疑で書類送検されている。一般市民の違反については厳しく取り締まる一方、政治家の違反は見逃していたとすれば、警察への信頼を失墜させることになりそうだ。 11月7日発売の「週刊文春」では、“あおり運転”を指示されたという河井氏の元運転手の詳細な証言や、公選法違反に絡み、二転三転するウグイス嬢の証言などを詳報している。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-日経平均の強さが際立つ、あすはソフトバンクGやトヨタの動向に注目 6日の日経平均は続伸。終値は51円高の23303円。米国株はまちまちとなったが、ドル円の109円台乗せを好感して、90円近く上昇して始まった。しかし、買いが続かず失速。TOPIXや新興指数が早々に下げに転じるなか、瞬間的にマイナス圏に沈む場面もあった、ただ、押し目では買いが入ったことから下げ渋り、その後は小幅高でのもみ合いとなった。後場も小動きが続いたが、下げることなく推移したことから、終盤にかけては上げ幅を拡大。23300円台に乗せて取引を終えた。マイナス圏での時間帯が長かったTOPIXも、引けでは小幅にプラスを確保した。東証1部の売買代金は概算で2兆4800億円。業種別では騰落率上位はパルプ・紙、鉄鋼、海運、下位は食料品、情報・通信、精密機器となった。通期の利益見通しを引き下げたものの、増配が評価された三菱商事が後場に入って大幅高。半面、下方修正を発表した味の素が後場に大きく値を崩した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1009/値下がり1039。アドバンテストやSUMCOなど半導体株の一角が買いを集めた。証券会社が投資判断を引き上げたシャープは13%超の上昇。航空電子もリポートを手がかりに急伸した。決算を材料に個別の選別が進み、UACJやセーレン、グンゼ、ベネッセなどが大幅高となった。一方、下方修正を発表したアサヒや、上期大幅営業減益のスズキが大幅安。ワークマンは上期大幅増益も利益確定売りが優勢。上期減益のNTTは株式分割が下支えとはならず3%超の下落となった。日本光電工業やハウスドゥ、オリコンなどが決算を材料に急落。通期見通しを大幅に引き下げ、大幅な減配を発表したヘリオステクノはストップ安ストップ安比例配分となった。 日経平均は続伸。TOPIXや新興指数が早々に下落に転じたことで、前場ではそれにつられて売り圧力が強まりそうな雰囲気も漂ったが、後場は非常にしっかりとした動きが続いた。日経平均の強さに引っ張られるかのように、TOPIXはプラス圏まで戻して終えている。過熱感がやや削がれながらも日経平均は上昇が続くという、非常に良い流れとなっている。為替にらみの状況は続くが、ドル円が108円台半ばより上での推移が続くのであれば、日本株は引き続き堅調な地合いが続くと予想する。あすも決算を材料に個別の物色が活況となるだろう。引け後にソフトバンクGが決算を発表しているが、上期は営業赤字に転落した。業績悪化懸念から直近まで下げ基調が続いていたが、悪材料出尽くしとなるかが注目される。また、あすはトヨタが取引時間中に決算を発表予定。きょうも年初来高値を更新しているが、決算を受けて一段高となるようなら、大型株優位の様相が一段と強まると考える。NY為替見通し=ドル円、109円近辺で新規の手がかり待ちか ドル円は109円を挟んで小幅の上下にとどまっている。米中貿易交渉の進展期待で引き続き底堅い動きも、109円前半では上値の重さも確認され、一段の上昇には新規の手がかりが必要になりそうだ。 本日のNYタイムでは注目の経済指標の発表は予定されておらず、米中協議のヘッドラインに注目する動きが見込まれる。昨日に史上最高値を更新したダウ平均もスピート調整の売りが入りやすく、ドル円の上値を圧迫する要因になり得る。米中協議への楽観ムードが続いているものの、米中首脳会談の日程は決まっておらず、両国の駆け引きは続いているもよう。米中首脳会談の日程がなかなか決まらなければ、米中協議への懸念が再燃し、ドル円に売り圧力が強まる可能性はあるか。・想定レンジ上限 ドル円は10月30日の高値109.29円が上値めど。・想定レンジ下限 ドル円は昨日の安値(同21日移動平均線)の108.56円近辺が下値めど。NY株見通し-もみ合いか スピード調整にも要警戒か 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日は米中通商合意への期待や、米10月ISM非製造業PMIが強い結果となったことでダウ平均とナスダック総合が史上最高値更新を続けたが、S&P500は小幅ながら3日ぶりに反落した。今晩も米中通商合意期待や米景気減速懸念の後退を受けてリスクオンの流れが継続することが期待される一方、主要3指数が史上最高値圏での推移を続け高値警戒感が強まるなか、S&P500のRSI(14日)が75を超えるなど、テクニカル指標にも過熱感を示すものが増えてきた。些細な悪材料に反応したスピード調整にも注意が必要か。 今晩の米経済指標はMBA住宅ローン申請指数、EIA週間原油在庫など。エバンズ米シカゴ連銀総裁、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁の講演や発言も予定されている。企業決算は、寄り前にヒューマナ、CVSケアマーク、引け後にクアルコム、EOGリソーシズなどが発表予定。(執筆:11月6日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)今晩のNY株の読み筋=要人発言に注目 6日の米国株式市場では、要人発言が注目となる。エバンス米シカゴ連銀総裁が講演するほか、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁やハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が討議に参加する予定。ニューヨーク連銀総裁はFOMC(米連邦公開市場委員会)の常任理事で常に投票権を持ち、シカゴ連銀総裁は今年の投票権を、フィラデルフィア連銀総裁は来年の投票権を有する。特にフィラデルフィア連銀のハーカー総裁は利下げ不要との立場を示している。同氏の発言機会は日本時間の午前5時すぎと取引時間の終盤ではあるものの、来年のFOMCの方向性にも深くかかわるため、注目しておきたい。<主な米経済指標・イベント>経済指標=米7-9月期労働生産性指数要人発言=エバンズ米シカゴ連銀総裁が講演、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁やハーカー米フィラデルフィア連銀総裁が討議に参加決算発表=スクエア、クアルコム(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕続伸=円安を好感、値がさ株に買い(6日)☆訂正 【第1部】米ダウ工業株30種平均が最高値を更新し、為替が円安に進んだことで安心感が広がり、値がさ株や割安感のある株が買われた。日経平均株価は前日比51円83銭高の2万3303円82銭と続伸し、年初来高値を2日連続で更新。東証株価指数(TOPIX)も0.29ポイント高の1694.45と続伸した。 銘柄の47%が値上がりし、値下がりは48%だった。出来高は13億8852万株、売買代金は2兆4823億円。 業種別株価指数(33業種)では、パルプ・紙、鉄鋼、海運業の上昇が目立った。一方、食料品、情報・通信業、精密機器などが下落した。 個別銘柄では、三菱商が値を上げ、三菱UFJも堅調。ソフトバンクG、ファーストリテがしっかり。川崎船は上伸。シャープが大幅高。村田製、日立も買われた。SUMCO、王子HD、神戸鋼も高い。半面、NTT、ZHDが値を下げた。任天堂、キーエンス、HOYAが軟調。ソニーもさえない。スズキが安い。富士フイルム、アサヒが売られた。 【第2部】反落。東芝が売られ、フライト、ダイトケミクスは値を下げた。千代化建は買われた。出来高1億1888万株。 ▽利益確定売りが重し 日経平均株価は年初来高値を更新したが、前日に急騰した反動で利益確定売りが出て伸び悩んだ。 為替が1ドル=109円台まで円安が進み、5日の米ダウ工業株30種平均が史上最高値を更新したことが好感され、買い先行で始まった。日経平均は取引開始直後に前日比100円高まで上昇幅を広げた。 ただ、前日までに上昇した銘柄には、売りに押されるものも目立った。値がさ株は堅調な銘柄が多かったため日経平均はプラス圏で推移したが、実際は「売り買い交錯のもみ合い相場」(銀行系証券)と指摘されている。 「高配当など割安感のある銘柄に買いが集まった」(中堅証券)といい、業種別ではパルプ・紙や鉄鋼など出遅れていた素材株の上昇が目立った。 225先物12月きりはもみ合い。午前は、シカゴ市場の清算値にさや寄せして小高く始まった後、戻り売りに押された。午後は小口買いが支えとなり、下げ渋った。225オプション11月きりは、プット、コールともにおおむね軟調。【注】リードの「は小反落した」を「と続伸した」に訂正。4パラ目の「東エレク」を削除。(了)〔NY外為〕円、109円近辺(6日朝) 【ニューヨーク時事】6日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル=109円近辺で小動きとなっている。午前9時現在は108円90銭~109円00銭と、前日午後5時(109円12~22銭)比22銭の円高・ドル安。 米中貿易協議の進展期待などを背景に前日は円売り・ドル買いが進行。この日はその流れが一巡し、米中の貿易摩擦緩和に向けた動きに注目が集まる中、海外市場を通じて小幅なレンジでの取引が続いている。 前週末の米雇用統計や5日に発表された米サプライ管理協会(ISM)の非製造業景況指数など予想を上回る指標を受けて、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融緩和観測が後退していることが、ドルの下値を支えているもようだ。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1080~1090ドル(前日午後5時は1.1069~1079ドル)、対円では同120円75~85銭(同120円83~93銭)。(了) 本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の24銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。
2019.11.06
コメント(0)
-

11月5日(火)…
11月5日(火)、晴れです。予報通りに朝の気温は低いですね…。そんな本日は6時45分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、ゴミ出しをして、家を出る。奥は僕より早くに岐阜へGo!です。僕もゴルフではありません…、アルバイト業務です。本日は、8:30~11:30の午前勤務。時間通りでした…。帰り道のカフェでパスタランチをいただく。帰宅してしばしの休養…ソファでお昼寝…。奥が帰宅して、御座候とお茶でおやつタイム。1USドル=108.76円。1AUドル=75.06円。昨夜のNYダウ終値=27462.11(+114.75)ドル。本日の日経平均=23251.99(+401.22)円。金相場:1g=5828(+20)円。プラチナ相場:1g=3679(+38)円。(ブルームバーグ)米10年債利回りは今後半年で急騰か、95年再現の可能性-JPモルガン 米連邦公開市場委員会(FOMC)が3会合連続の利下げを決定したことで、向こう6カ月に株価がじりじりと上昇する一方、米10年債利回りは急騰する可能性があると、JPモルガン・チェースが予測した。 JPモルガンのストラテジストによると、FOMCが「保険」として実施した利下げに対する市場の反応は、これまでのところ1990年代半ばの展開に極めてよく似ている。 ニコラオス・パニギリツオグル氏ら同行ストラテジストは1日付のリポートで、「市場が1995年のサイクル半ばに起きた展開と同じ道をたどり続けるのであれば、向こう6カ月に株価は5%程度の小幅上昇となるだろうが、米10年債利回りは100ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と大幅に上昇し、利回り曲線はスティープ化すると示唆される。ドルやクレジットのスプレッドはほぼ変わらないだろう」と述べた。 ただ、この予測にはいくつか大きな条件があるという。 JPモルガンによると、雇用や消費者景況感の底堅さ、製造業の回復などサイクル半ばの動きに米マクロ経済が全体として外れずにいることが前提となる。異例な高水準にある個人投資家の債券ファンド買い・株式ファンド売りの流れが反転することなども必要になる。ゴールドマン、米国株は独り勝ちだとリスク志向の富裕層顧客に助言 米国株はS&P500種株価指数が最高値付近にあってもなお、投資資産の中で独り勝ちの状況だとゴールドマン・サックス・グループは富裕層顧客に助言している。 ゴールドマン・サックス・プライベート・ウェルス・マネジメントの投資戦略グループでマネジングディレクターを務めるシルビア・ アルダーニャ氏は、「リターンは依然として、主に米国株をオーバーウエートにすることで得られるというのが当社の見解だ」とロンドンでのインタビューで述べた。「世界の中で米国は傑出している」と続けた。 ゴールドマンの同部門(運用資産約5000億ドル=約54兆3000億円)によると、理由は単純だ。世界経済の成長が減速し、ドイツが狭義のリセッション(景気後退)に陥る可能性がある中、米景気は中期的に他国よりも堅調に見受けられる。1日に発表された10月の米雇用統計では、雇用者数の伸びが予想外に強く、米金融当局が発信した利下げ休止シグナルの正当性が実証された。 米中貿易協議で進展が見られることを背景に、富裕層の顧客は資産を有効に運用したいとの意欲を強めていると、アルダーニャ氏は説明。これを裏付けるかのように、10月30日までの1週間に61億ドルの資金が世界の株式ファンドに流入。リスク資産の人気上昇を浮き彫りにした。 元ハーバード大学准教授のアルダーニャ氏は、「米中の貿易摩擦が和らいだことをきっかけに、投資家はこれまで悲観的過ぎたのではないか、前向きなサプライズが起こるのではないかという疑問が生じた」と説明。「経済指標が改善し、製造業が安定化するとともにサービス業の堅調が持続すれば、この上昇局面は明らかに続く可能性がある」と話した。日経平均上げ400円超、米中楽観や米雇用堅調-景気敏感など広く買い 5日の東京株式相場は午後一段高となり、日経平均の上げ幅は400円を超えた。米中通商交渉に対する楽観や米国の堅調な雇用情勢、為替の円高一服から業績懸念が後退している。機械や素材、海運など海外景気敏感業種を中心に広く買われている。 TOPIXは前営業日比28.35ポイント(1.7%)高の1694.85-午後1時4分現在 日経平均株価は451円47銭(2%)高の2万3302円24銭〈きょうのポイント〉 米中は第1段階の貿易合意に向けさらなる進展を示唆 ロス米商務長官は華為技術(ファーウェイ)への米企業による部品販売のライセンス付与が「近く」行われると言明 米国は中国製品1120億ドル(約12兆2000億円)相当への関税を撤回するか議論-英紙フィナンシャル・タイムズ 10月の米非農業部門雇用者数は12万8000人増、市場予想(8万5000人増)上回る ドル・円相場は一時1ドル=108円80銭台、前週末の日本株終値時点は107円98銭 JPモルガン・アセット・マネジメントの前川将吾グローバル・マーケット・ストラテジストは「雇用統計で想定以上に景気が強い、耐えているという中で米中貿易も改善するということなら、景気後退という懸念を若干低下させるような形で動いている」と述べた。 株価指数はことし高値を更新。米S&P500種株価指数のEミニ先物や中国上海総合指数が上昇する中、日経平均は需給面の追い風もあり上昇率が2%を超えた。 大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジストは米中通商問題について、「これまでは米国と中国の発言内容が違っていたことが多かったが、今回はそろっており合意は近い。日本株は業績先行き期待から上がりやすい」とみていた。 東証33業種は鉱業や石油・石炭製品、ガラス・土石、機械、保険、証券・商品先物取引、海運が上昇率上位(ロイター)米ゼロックス、富士ゼロックスの株式25%を富士フイルムに売却へ 合弁解消=WSJ[5日 ロイター] - ウォール・ストリート・ジャーナルは5日、関係筋の話として、米事務機器大手ゼロックス(XRX.N)が富士フイルムホールディングス(4901.T)に富士ゼロックスの株式25%を売却し、合弁を解消することで合意したと伝えた。売却額は22億ドルという。アングル:自動運転で揺れる車の整備市場、純正品以外は保証なしか[30日 ロイター] - 衝突回避技術の急速な発達に伴い、自動車メーカーとカー用品店の間で修理の安全性をめぐる新たな衝突が生じるようになっている。自動車の整備や修理を行うアフターマーケットの規模はおよそ8000億ドル。メーカーと用品店のあつれきは、この巨大市場の主導権をめぐる争いにもなっている。 車線維持支援、自動ブレーキ、死角監視などのシステムが空前の進化を遂げていることを踏まえて、多くの自動車メーカーは、純正パーツや自社系列ディーラーによる修理でなければ安全性は確保できないと主張している。 これに対して、現在ではアフターマーケットで優位に立っている独立系のカー用品店やサプライヤーは強く反発。純正品・サービスの数分の1のコストでパーツの製造や自動車の修理ができる自分たちが締め出されるのはおかしい、という言い分だ。 たとえばスバルの場合、顧客に対して、「アイサイト」システムに関してサードパーティの交換部品を用いて何か問題が生じても保証の対象外であると告げている。「100%スバル純正品で、あなた自身とあなたの投資を守りましょう」。 スバルだけではない。ロイターが先進運転支援システム(ADAS)の修理・調整に関する自動車メーカーの姿勢を検証したところ、日産とその高級車ブランドであるインフィニティ、それにボルボは、やはり認可ディーラー以外によるパーツ及び修理は保証に影響するとしていた。 一方、ゼネラルモーターズ(GM)やホンダは、安全性を確保するためには純正パーツと系列ディーラーによる装着・修理が重要であるとしながらも、保証に影響するとの警告には至っていなかった。 <米では政府や議会の介入も> アフターマーケットに関する議論が沸騰しているのは米国である。独立系のカー用品店やパーツメーカーは、消費者保護を担当する政府機関である連邦通商委員会(FTC)と連邦議会に介入を求めている。 彼らが求めているのは、自動車メーカーが純正のADASパーツやサービスの利用を保証の条件とすることを禁止し、この新技術についても従来の自動車部品に関するルールに合わせることである。また彼らは、最新の診断データを車載ソフトウェアから取得することも望んでいる。 独立系のサプライヤーをまとめる米国自動車部品工業会(MEMA)のポール・マッカーシー会長は、「自動車産業は、安全性と修理可能性は二律背反であるかのような誤った論法を生み出している」と言う。だが自動車産業の側では、新技術の先進性のレベルゆえに、アフターマーケットの状況は変わった、と主張する。 自動車メーカーを代弁する米国の業界団体であるオート・アライアンスは、自動車メーカー側では必要な訓練と情報を提供できるが、独立系の店には、そうしたリソースや専門能力が不足している場合が多い、と話している。 「テクノロジーは安全性という点で偉大な進歩を可能にしている。だから、技術者は最新の情報に精通していなければならない」と同団体の広報担当者は言う。 FTCは修理問題に関して業界の見解とパブリックコメントの募集を続けているが、コメントは拒否している。 どちらに理があるかはさておき、運転支援ソフトウェアの発達は自動車セクターを変貌させつつあり、争うべきパイは大きい。業界団体とアナリストによれば、米国の自動車アフターマーケット・修理産業は年間3900億ドル規模であり、世界全体ではその2倍以上である。 この争いに勝利すれば、予想される自動運転革命から利益を得る最も有利な立場を占めることになろう。ADASの機能は、そうした革命の先触れと見なされている。 <複雑で高コスト> 米国の路上を走る自動車のうち、ADAS搭載車は現在では10%にすぎないが、自動車メーカー各社は2020年までに、前方衝突アラームや市中速度自動緊急ブレーキをほぼすべての新車に装備すると公約しており、その数は急速に伸びると予想されている。 アフターマーケットの囲い込みは、このところ売上高の低迷に悩んでいる自動車メーカーにとってはカンフル剤になる。だがそれは潜在的に、米国における修理の大半を担い、数百万人の雇用に結びついている小規模経営の独立系カー用品店のネットワークを荒廃させてしまいかねない。 新たなシステムは、バンパーやフェンダー、ミラー、フロントガラスのなかにカメラやレーダー、超音波センサーを仕込んであり、単にミラーをこすった程度でも、これまでより修理が複雑・高額になる。 自動車車体部品協会のエグゼクティブ・ディレクターを務めるエドワード・サラミー氏は、独立系のサプライヤーは、ADASのパーツをメーカー純正価格の25~50%で製造できると話している。 米国道路安全保険協会(IIHS)のデータと、米国内の整備ショップ11社のオーナーらにロイターがインタビューしたところでは、アフターマーケットにおけるフロントガラスの平均価格は、純正品に比べ約420ドル安くなっている。 だが、一部の自動車メーカーは、低価格のパーツには安全性の点でリスクがありうると警告している。センサー類にはキャリブレーション(較正)を行わなければならない。スペースと水平な地面、特殊な照明、ソフトウェアにアクセスするための純正スキャンツールを必要とする、コストの掛かるプロセスである。 業界の専門家は、消費者は不適切な修理に伴うリスクにほとんど気づいていないと話している。 調査会社JDパワーの保険事業調査担当マネージングディレクター、カイル・シュミット氏によると、過去2年間のあいだにADASを装備した車の修理を受けた消費者500人を対象とする調査では、15%が先進的な安全装備がうまく機能しない、あるいは修理前と動作が異なるなど、修理が適切でなかったと回答していた。 修理に関して把握されている問題の件数は、独立系カー用品店ではディーラーの4倍に達している。 一例としては、IIHSが行ったテストにおいて、メーカー認定のないフロントガラスは、センサーの正常な動作を妨げる場合があった。 <データをめぐる対立> アフターマーケット業界団体は、この対立を安全性の問題としても提示している。彼らの主張によれば、ドライバーたちは必要な修理であっても費用がかさむとなれば先送りしてしまう可能性があり、メーカー系列のディーラーには、増え続けるADAS搭載車に対応するほどの余裕がないという。 4月、MEMAはFTC宛ての書簡のなかで、米国の路上を走る車のうち少なくとも3000万台が、メーカーがアフターマーケット企業による修理を妨害しているせいで、ADAS関連の修理を制限されている、と述べている。 整備ショップ11社のオーナーによれば、メーカー純正のスキャンツールがなければ、カー用品店ではADASが出力するエラーコードの20─30%を解読・解決できず、ディーラーにその車を移送せざるをえなくなるという。 だが、こうしたツールを入手し、修理に必要なデータにアクセスするためには、最大10万ドルもかかる。用品店のオーナーらによれば、これは多くの店にとってとても手が出ない金額だ。この金額については、自動車メーカーの側からも特に否定する声はない。 米国自動車保険大手のオールステートは、こうした懸念の一部に同意する。 オールステートのテックコア研究・衝突修理センターでシニアマネジャーを務めるリチャード・ベックウィズ氏は、自動車メーカーはADASに関して十分なデータを提供していないと話す。同氏は自動車産業に対し、小規模な用品店でももっと容易にデータを入手できるようにすることを要求している。 <見えてきたチャンス> 自動車分野を専門とする弁護士4人がロイターに語ったところでは、ADASに関する責任問題もほぼグレーな領域にあるという。テクノロジーが法律分野における前例を追い越してしまい、これまでのところ、修理後のADASの動作不良をめぐる明白な訴訟例がないからだ。 キング&スポルディングのパートナーとしてワシントンを中心に活動するジャッキー・グラスマン弁護士は、「理屈の上では、修理指針を明らかにしていれば、メーカー側としては合理的な抗弁が可能だ。だが現状ではケースバイケースということになるだろうし、多くのシナリオが生じてくる可能性がある」と語る。 ビジネスチャンスを窺っている企業もある。 スマートエクスプレスやアズテックといった新規参入企業は、メーカー純正のスキャン・較正ツールに投資し、ハイテク満載のバンに社員を乗せて国内の用品店に派遣するという移動サービスを提供している。 スマートエクスプレスのジェフ・エバンソン最高業務責任者は、かつてテスラでグローバル投資家対応(IR)担当バイスプレジデントを務めていた。同氏は、ますます自動運転志向を強める自動車産業においては、アフターマーケットのツールや部品では安全上の要件を満たせないだろうと話す。 さらにエバンソン氏は、「自動車産業では、自ら生み出した問題について十分に考えていないが、こうしたシステムの複雑性やハッキングを受けるリスクを考えると、車両の安全性・セキュリティを確保するために、自動車メーカーは修理情報を封印しておくべきだということになる」と言う。(会社四季報オンライン)(ロイター) 米国株式市場は主要3指数が最高値、米中通商合意に期待ダウは114ドル高の2万7462ドル[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米国株式市場は続伸。米中通商協議を巡る期待感などを背景に、主要株価3指数が終値で過去最高値を付けた。終値での最高値更新は、S&P500とナスダックが2営業日連続。ダウは7月以来となった。米当局者は1日、中国との第1段階の通商合意に月内に署名する可能性があるとの見方を示した。また、ロス米商務長官は3日、米国企業に中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)への部品販売を認めるライセンスをまもなく付与するとの見通しを示した。通商問題に最も敏感とされるセクターが買われ、S&P情報技術指数は約0.6%上昇。フィラデルフィア半導体指数は過去最高値を付け、S&P工業指数は1.2%高となった。米中通商協議への期待感に加え、米連邦準備理事会(FRB)による前週の利下げや、10月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を上回ったことも株価を下支えしている。ウェドブッシュ証券の株式トレーディング担当マネジングディレクター、マイケル・ジェームズ氏は、1日の株高の後に米中協議の進展に期待が高まったことで、投資家は買いを継続しやすくなったと指摘した。原油の値上がりを受けてS&Pエネルギー指数は3.2%の大幅高となった。S&P金融指数は0.9%高。著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイの四半期決算で営業利益が市場予想を上回ったことなどが指数を押し上げた。一方、ファストフード大手のマクドナルドは2.7%安。スティーブ・イースターブルック最高経営責任者(CEO)が、社員との合意に基づく関係を巡って解任された。スポーツ用品のアンダーアーマーは18.9%急落。通年の売上高見通しを引き下げたほか、会計処理を巡り連邦当局の調査に協力していると認めたことが重しとなった。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.69対1の比率で上回った。ナスダックでも1.62対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は75億3000万株。直近20営業日の平均は65億5000万株。シンバイオがS高気配、抗悪性腫瘍剤の第3相試験で良好結果 がんや血液領域を軸に希少疾患薬に特化しているジャスダックのシンバイオ製薬(4582)が11連騰した。朝方から値付かずの展開となる中、午後0時58分現在、制限値幅上限の前営業日比100円(14.47%)高の791円ストップ高買い気配で推移している。 本日午前8時30分に、抗悪性腫瘍剤「トレアキシン」の第3相試験で、主要評価項目の期待奏効率を上回る良好な結果を得たと発表し、買い材料視された。対象となる疾患は、再発・難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫で、大型で悪性のB型細胞性リンパ球がリンパ節や様々な臓器で増殖して悪性腫瘍を形成する。悪性リンパ腫の中では最も頻度が高いといわれ、発症年齢のピークは60~70歳。高齢化の進展とともに、患者数が増加傾向にあると推計されている。 当社は10月25日には、抗がん剤「リゴセルチブ」の今後の臨床計画を発表しており、相次ぐ材料発表となった。(取材協力:株式会社ストックボイス)日経平均は大幅反発、401円高 年初来高値を更新日経平均株価、5日の終値は2万3251円99銭[東京 5日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は大幅反発し年初来高値を更新した。前日の米国株主要3指数が過去最高値で取引を終えたことに加え、上海総合指数や米国株式先物などが堅調に推移したことが支えとなった。終値ベースでは2018年10月10日以来となる2万3000円台を回復した。 TOPIXは反発。東証33業種全てが値上がりし、鉱業、パルプ・紙、金属製品などが値上がり率上位となった。 前日の米国株式市場は、中国との第1段階の通商合意に月内に署名する可能性があることや、米国企業に中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)への部品販売を認めるライセンスがまもなく付与されるとの見通しが好感され、主要3指数が過去最高値で取引を終えた。 東京市場も朝方から買いが先行し、寄り付きでザラ場ベースの年初来高値を更新。後場に入って一段高となった。中国人民銀行が1年物中期貸出ファシリティー(MLF)を引き下げ、上海総合指数が上昇したことなどが材料視された。 市場からは「国内投資家が重い腰を上げ始めたようだ。2万3000円をしっかり超えてきたところをみて、先物を売ってヘッジをかけていた人が買い戻したり、買い遅れていた人がおそるおそる買いを入れ始めたりしている」(マーケットアナリスト)との声が出ていた。 今後の日経平均について、三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之シニアストラテジストは「これまで互いにかけた報復関税を元に戻すのは簡単ではなさそうだが、米国が12月15日に発動する計画の対中追加関税を取り下げれば、さらに投資家心理は好転するだろう」との見解を述べた。 個別銘柄では、Zホールディングスが急反発し年初来高値を更新。1日に発表した2019年7─9月期連結営業利益が前年同期比11.2%増の394億円と、2桁のペースで伸びたことなどが好感された。 東証1部の騰落数は、値上がり1743銘柄に対し、値下がりが356銘柄、変わらずが55銘柄だった。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-23000円台を回復し年初来高値を更新、商い増加で一段高への期待が高まる 5日の日経平均は大幅反発。終値は401円高の23251円。東京市場が休場の間の海外市場にはポジティブな材料が多く、米国では主要3指数がそろって史上最高値を更新。為替市場でも円安が進んだことから、スタートから大きく水準を切り上げた。開始早々には上げ幅を300円超に拡大。地合いが一段と改善するなか、その後も高値圏を維持した。後場は先物主導で買いが入り、上げ幅を400円超に拡大。23300円台に乗せる場面もあるなど騰勢を強め、終値で年初来高値を更新した。東証1部の売買代金は概算で3兆0500億円と3兆円台に到達。業種別では全業種が上昇しており、騰落率上位は鉱業、パルプ・紙、金属製品、下位は電気・ガス、空運、不動産となった。上期で営業増益を確保した王子ホールディングスが後場急騰。半面、アシックスは3Q累計で通期の営業利益計画を超過したものの、見通し据え置きで材料出尽くし感が強まり、大きく売られる展開となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1743/値下がり356。TDKやSUMCOなどハイテク株が軒並み大幅高。建機のコマツと日立建機がそろって5%超上昇した。決算ではZHDが16%超上昇し、市場の注目を集めた。自己株取得を発表したヤマハや上方修正を発表した三井倉庫が急伸。通期見通しを引き上げた不二硝子やフライトHDはストップ高比例配分と買いが殺到した。富士フイルムはゼロックスによる富士ゼロックス株の売却観測が伝わり、取引終盤に買いを集めた。一方、今期営業赤字に転落する見込みとなった三井海洋開発と三井E&Sが急落。三井海洋はストップ安で終え、三井E&Sもストップ安をつける場面があった。下方修正を発表したコニカミノルタは10%超の下落。EduLabは大学共通テストの民間活用見送りを嫌気した売りが止まらず、ストップ安となった。 日経平均は大幅反発。外部環境が良好で高く始まることは予想されたものの、寄った後も上げ幅を大きく広げたことは特筆される。22500円を上回ってからは、高く始まってもそこから上値を伸ばすことが少なかっただけに、きょうの上げ方には意外感がある。物色を見ても、先週に決算で売られたアドバンテストやコマツなどが大幅高となった一方、先週に決算で買われた武田なども一段高となるなど、決算の良し悪しはいったん脇に置いたような動きが見られた。東証1部の売買代金は3兆円を超えている。今週は高値警戒感から上昇一服の展開を予想していたが、きょうの値動きやボリュームを見ると、ここから上昇が本格化しそうな雰囲気すらある。週初から非常に強い動きが見られたことで、あすは下げづらく上げやすい地合いを予想する。きょうは終値で23000円を大きく上回ってきたが、ここから24000円までは抵抗が少ない。海外で悪材料が出てこなければ、心理的節目の23500円はあっさり超えても不思議ではない。NY株見通し-堅調持続か 経済指標は10月ISM非製造業総合指数に注目 今晩のNY市場は堅調か。昨日は経済指標の改善や米中通商合意への期待などを背景に先週末の堅調な流れが続き、ダウ平均が3カ月半ぶりに史上最高値を更新し、S&P500とナスダック総合も先週に続いて最高値を更新した。米国が発動済みの対中制裁関税の一部解除を検討などの報道もあり、今晩も米中通商合意への期待が引き続き支援材料となりそうだ。米経済指標では、寄り後に発表される10月ISM非製造業総合指数が注目される。前月分は52.6と、前月の56.4、市場予想の55.0を下回り、2016年8月の51.8以来の水準に悪化したが、非製造業の景況感悪化が一服となれば、センチメントが一段と改善しそうだ。 今晩の米経済指標は10月ISM非製造業総合指数のほか、9月貿易収支、10月マークイット総合PMI、同サービス部門PMIなど。バーキン米リッチモンド連銀総裁、カプラン米ダラス連銀総裁の講演も予定されている。企業決算は、寄り前にタペストリー、マイラン、リジェネロン・ファーマ、引け後にデボン・エナジー、ダヴィータなどが発表予定。(執筆:11月5日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)明日の日本株の読み筋=底堅い展開か、投資家心理好転でリスクマネー流入継続の可能性 あす6日の東京株式市場で、主要株価指数は底堅い展開か。米中貿易交渉の進展とともに投資家心理が好転している。米中協議をめぐっては、トランプ米大統領が1日、部分合意について米アイオワ州で署名する可能性を示したと報じらた。一方、中国商務省は2日、米中両国が貿易交渉において「原則合意」に達したと声明で発表。両国の歩み寄りが世界景気の先行き懸念の後退につながり、リスクマネーが継続して流入する可能性がある。市場では、「日本は世界経済の先行指標であり、上昇基調は続くとみている」(中堅証券)、「(過熱感から)いずれは調整するだろうが、買い戻しが終わるまでは止まらない」(準大手証券)などの声が聞かれた。 5日の日経平均株価は大幅反発し、2万3251円(前週末比401円高)引け。4営業日ぶりに年初来高値を更新した。米中交渉の進展期待で米主要3株価指数がそろって最高値を更新し、円安・ドル高も支えとなり、買い優勢の展開となった。昼休みの時間帯に中国・上海総合指数が持ち直して上げ基調を強めたこともあり、後場は一段高となり、上げ幅は一時470円を超えた。チャート上では、昨年10月10日以来ほぼ1年1カ月ぶりに心理的なフシ目となる2万3000円を回復したことで、とりあえず目前の「マド」(10月10日安値2万3373円-翌11日高値2万3051円)埋めや、2万3500円が意識される。(yahoo)(時事通信)〔東京外為〕ドル、108円台後半=上げ一服後は高値もみ合い(5日午後3時) 連休明け5日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、上げ一服後は1ドル=108円台後半の高値圏でもみ合っている。午後3時現在は108円77~77銭と前週末(午後5時、107円96~96銭)比81銭のドル高・円安。 ドル円は早朝、108円50銭台で取引された。午前9時前から株高を期待した買いが優勢となった後、仲値に向けては実需筋の買いも入り、108円80銭近くに上伸。いったん緩んだが、正午前後は108円70銭台に強含んだ。午後は買い一服となったが、正午とほぼ同水準を維持している。 引き続き米中貿易交渉の進展期待が根強く、「日経平均株価の大幅高がドル円を支援している」(為替ブローカー)という。もっとも、「やはり109円近くは売りが厚い」(大手邦銀)とされ、109円手前で足踏みとなっている。午後に入って黒田日銀総裁の会見内容が伝えられたが、目立った反応は見られていない。 ユーロも午後は対円、対ドルで小動き。午後3時現在、1ユーロ=121円03~04銭(前週末午後5時、120円52~52銭)、対ドルでは1ユーロ=1.1127~1127ドル(同1.1163~1163ドル)。(了) 〔東京株式〕年初来高値更新=米中交渉期待、急反発(5日)☆差替 【第1部】日経平均株価は前営業日比401円22銭高の2万3251円99銭、東証株価指数(TOPIX)は27.66ポイント高の1694.16とともに急反発し、年初来高値を更新して取引を終えた。米国と中国の貿易協議の進展に対する期待を背景に全面高となった。 81%の銘柄が値上がりし、値下がりは17%。出来高は16億6076万株、売買代金は3兆0554億円。 業種別株価指数は情報・通信業、電気機器、輸送用機器、銀行業など全33業種が上昇した。 個別では、任天堂が買いを集め、ソニーも上伸した。村田製が値上がりし、トヨタも高く、キーエンス、ファナックはしっかり。ソフトバンクGが3営業日続伸し、ファーストリテは堅調だった。三菱UFJ、三井住友が締まり、東京海上は大幅高で引けた。ZHDは個別に買われて急騰した。半面、東エレクが緩み、日立は軟調。アステラス薬が甘く、第一三共も値下がりした。 【第2部】反発。原弘産が大幅高。千代化建は小じっかり。半面、サイバーSが安い。東芝は小幅安。出来高1億2914万株。 ▽1年1カ月ぶり高水準 3連休明け5日の東京株式市場では、米国と中国の貿易交渉の進展に対する期待感の高まりから幅広い銘柄が買われた。日経平均株価は10月29日に付けた年初来高値を更新し、2018年10月10日以来約1年1カ月ぶりの水準で取引を終えた。 米ダウ工業株30種平均が前日に史上最高値を更新したことや1ドル=108円台後半の円安・ドル高が、トランプ政権が対中制裁関税の一部撤廃を検討していると報じられたことも株価上昇を後押しし、電子部品や情報通信、銀行といった主力業種の株式が活発に取引された。中国・上海総合指数や時間外取引の米株先物の堅調も好感された。市場関係者からは「海外投資家が買いを入れてきた」(銀行系証券)との見方が出ていた。 225先物は2万3130~2万3330円で推移した。時折大口買いが入り、現物株を基準とした配当込み理論値を上回って買われた。(了) 〔NY外為〕円、108円台後半(5日朝) 【ニューヨーク時事】5日午前のニューヨーク外国為替市場では、米中貿易協議の進展期待を背景に円売りが優勢となり、円相場は1ドル=108円台後半で弱含んでいる。午前9時現在は108円85~95銭と前日午後5時(108円53~63銭)比32銭の円安・ドル高。 米中貿易協議で「第1段階」合意の署名が月内にも実現するとの期待など、楽観ムードが広がり、安全資産の円を売ってドルを買う流れが継続している。ニューヨーク市場では、円は108円86銭で取引を開始。米長期金利の上昇基調もドル買いを後押ししている。 米商務省が朝方発表した9月の貿易統計(国際収支ベース、季節調整済み)によると、モノとサービスを合わせた貿易赤字は前月比4.7%減の525億ドル。米中摩擦の長期化に伴い世界経済が減速し、輸出入ともに鈍化したが、市場への影響が限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1095~1105ドル(前日午後5時は1.1124~1134ドル)、対円では同120円85~95銭(同120円77~87銭)。(了) 〔米株式〕NYダウ続伸、再び最高値更新=ナスダックも高い(5日朝) 【ニューヨーク時事】5日のニューヨーク株式相場は、米中貿易協議の進展期待を背景に続伸して始まり、優良株で構成するダウ工業株30種平均は取引時間中の史上最高値を再び更新した。午前9時35分現在は、前日終値比34.41ドル高の2万7496.52ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は11.43ポイント高の8444.63。(了) 昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の8銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の26銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。少しもふもふ感が出てきたロマネちゃんです。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の8銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄では2銘柄が値を上げてスタートしましたね。
2019.11.05
コメント(0)
-

11月4日(月・振替休日)…2019ラウンド82…
11月4日(月・振替休日)、晴れです。少し風がありましたが、気持ちの良い青空が広がり、世間でいうところの行楽日和な3連休でしたね。365連休の身には何ということもありませんが…。そんな本日は、ホーム1:GSCCの西コースで開催の霜月杯に参加させていただきました。昨日の「91」のリベンジマッチですね…。9時16分スタートとのことですから6時30分頃に起床。ロマネちゃんのお世話をして、新聞に目を通し、朝食を済ませる。身支度をして、7時45分頃には家を出る。やはり祝祭日は日曜日ほどには空いていないですね…。8時15分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、コーヒーブレイクして、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…マアマア…。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはいつものU君(14)、K君(16)と、お初のYさん(17)です。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:0.1.2.0.1.-1.-1.0.1=39(14パット)0パット:1回、1パット:3回、3パット:1回、パーオン:3回。1打目のミスが2回、2打目のミスが2回、3打目のミスが2回、アプローチのミスが2回、パットのミスが2回…。1番ロングは2打目・3打目をミスしましたが無難にパーで切り抜ける。2番ミドルで2オンからの3パットで雲行きが怪しくなる…。3番ミドルでまたも2打目・3打目をミスして4オン2パットの素ダボ…。5番ミドルも1打目が気の後ろについて3オン2パット…。5番で+4で気分は最悪…。ここからの立て直しが良く出来たと感心します…!!スルーでINへ。IN:1.1.-1.2.0.0.0.0.0=39(14パット)1パット:6回、3パット:2回、パーオン:3回。10番ミドルで2オンからの3パット…。11番ミドルで2打目を左の谷に落としての4オン1パット…。12番ロングでバーディーを取ったと思ったら、13番ミドルで3オン3パットの素ダボ…。ここからよく我慢できました…!!39・39=78(8)=70の28パット。スコアカード提出の時点では3位ですが…。スコアカードを提出して、握りの清算を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です…。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.5kg,体脂肪率20.7%,BMI22.0,肥満度-0.1%…でした。帰宅すると14時30分頃。栗のタルトとコーヒーでおやつタイム。シルバーのスタッフが庭の芝刈りと除草に来てくれています。それではしばらく休憩ですね。1USドル=108.22円。1AUドル=74.91円。(ロイター)コラム:変貌する巨大企業の「市場支配」、求められる新規制[ロンドン 30日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 「最も重要なことは、城主が誠実で、広く頑丈な堀を巡らせて素晴らしい城を守っている企業を探し出すことだ」──。 巨大投資会社バークシャー・ハザウェイ(BRKa.N)を率いるウォーレン・バフェット氏が1995年にこう助言した時、念頭にあったのは株主リターンのことだけだった。企業を囲う堀が増え、ますます強固になった今、政治家や規制当局、エコノミストは別の教訓を引き出すかもしれない。 企業が高い利益を稼ぐために独占や寡占状態、市場での支配的地位を築こうとするのは、今に始まった話ではない。しかし、最近は競争を阻む堀がさらに深くなった上、容易にその堀を拡張できるようになっている。 第1に、情報の収集、分析、配信コストが急低下した。安くなる一方の情報を集め、売っているのはグーグルの親会社アルファベット(GOOGL.O)やフェイスブック(FB.O)といった企業だ。 こうした企業の持つ豊富な情報は「ネットワーク効果(利用者数の増加によって製品やサービスの価値が高まること)」を生み出すのに役立つ。グーグルでの検索数が増えれば増えるほど、同社はユーザーをどんぴしゃりの広告に案内しやすくなる。フェイスブックは、利用者数が増えるほどプラットフォームの価値が高まる。 データの豊富さは、グローバルな企業を運営する上でも鍵を握り、巨大グループはしばしば中小企業よりも優位に立つ。巨大企業はデータ処理の高い専門性によって、在庫の最小化、製品設計、顧客サービス、「最適な慣行」、課税逃れなど多くの分野で先んじることができるかもしれない。 他方、「規模の経済」も変化した。グローバル化により、スケールメリットを確保するコストは上昇した。世界規模で展開していなければ、本当に効率的な事業運営はできないからだ。世界展開のメリットは巨大だ。多国籍企業は新製品・技術開発のコストをより多くの顧客に分散して転嫁できる。規制当局の基準設定に影響を及ぼす上でも、有利な立場に立つことが多い。 多くの産業分野で、純粋に国内展開している企業は規模が小さ過ぎて生き残れなくなっている。例えば、次世代通信規格「5G」対応のスマートフォン・インフラ設置を巡る競争は、完全にグローバル企業同士の戦いになった。中国通信機器最大手・ファーウェイ(華為技術)[HWT.UL]にとっては、人口14億人の中国市場でさえおそらく小さ過ぎる。安全保障上の懸念から同社の世界市場でのシェアが狭まるなら、収益力に打撃が及ぶだろう。 もちろん小回りの利く企業は、少なくとも一定期間は大規模な企業を出し抜くことができる。掃除機のダイソンのように、賢い発明によって大企業を打ち負かす例もある。新興のバイオ技術企業が素晴らしい製品を1つ開発したり、小規模な動画プロダクションが1つ2つのヒットを飛ばすこともあるだろう。 しかし、世界的な配信・物流ネットワークを築くコストは、小規模な企業には手が届かないほど巨額だ。理にかなった戦略はあきらめて、既存のグローバル企業に身売りすることになる。買収価格は一見高いが、買い手はワニを堀に閉じ込めてしまうことができる。 こうした買収には批判が高まっている。エコノミストであトーマス・フィリッポン、マット・ストラー両氏は近著で、米国の反トラスト法執行が手ぬるくなったことで、業界首位の企業が、過大な力を持つようになったと指摘している。 この指摘は、必ずしも間違っていない。一般的な規制緩和の潮流が、特に米国でM&Aを後押ししているし、大企業同士が暗黙のうちに談合することは、おそらく容易になった。 しかし、こうした批判は重要な点を見逃している。現在の企業を囲う堀の多くは、19世紀末に生まれ、20世紀初頭に解体されたスタンダード・オイルやUSスチールのような巨大独占企業のそれと、かなり様相が異なっているということだ。 第1に、現在の巨大企業は往々にして顧客に優しい。フェイスブックやアルファベットを解体したり、多くの企業に競合他社のスマホや自動運転技術を開発するよう義務付けたりすれば、顧客は得るものより失うものの方が多いだろう。 同様に、消費者は高くて品質管理の劣る地元企業の商品よりも、ユニリーバ(UNA.AS)(ULVR.L)やネスレ(NESN.S)の製品を買う方がしばしば得だ。 とはいえ、当世の巨大企業が持つ権力が、必ずしも無害だというわけではない。バフェットの言う「城主」が誠実であったとしても、万人の利益を追求しているとは限らない。 しかも、誠実とは限らない。反トラスト法の執行が機能しないなら、企業が支配的な地位を利用して適法とは言えない優位性を得ることがないよう、新たなスタイルの規制が必要になる。 実際には、全く新しいスタイルというわけではない。公益、航空、その他の自ずと独占状態になりやすい業種については、複雑で詳細な規制が設けられていることが多い。監督当局は、価格支配や株主資本利益率(ROE)だけでなく、顧客サービスや排出ガスについても一定の水準を義務付けることがある。この種の規制を、理想としては世界規模で導入することが現在、最適な道であるように見受けられる。 課題と最適な解決策は、企業と業界ごとに異なる。例えば、フェイスブック(FB.O)には、ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)と幹部らが、顧客データから密かに不公正な優位性を得ないよう監視する、同社専門の監督機関が必要かもしれない。 こうした新たな規制当局は、企業の収益性を狙い撃ちにして低下させる必要は必ずしもない。それよりも不適切な価格設定に集中する方が良いだろう。例えば、米国ではしばしば、製薬企業が独占状態を利用して、開発・製造コストの低さとは無関係に、顧客が払える限りの価格を設定することが可能になっている。 昨今の企業の堀は昔よりも幅と深さを増し、渡りにくくなっている。それでも規制当局は、橋を渡すための設備を手に入れることが可能だ。 マクドナルドCEO解任、社員との関係を規定違反と判定[3日 ロイター] - 米ファストフード大手マクドナルド(MCD.N)は3日、スティーブ・イースターブルック最高経営責任者(CEO)が、社員との合意に基づく関係を巡って解任されたと発表した。 取締役会は、イースターブルック氏が社員と関係を持ったことは、同氏の「おそまつな判断を象徴」するとし、会社規定に違反すると判定した。イースターブルック氏は取締役からも退いた。 イースターブルック氏は3日の社員宛ての電子メールで、社員との関係は「誤りだった」とし「企業の価値を考え、去るべき時であるとの見解で取締役会と一致した」と述べた。 後任には、米国マクドナルドの社長を務めていたクリス・ケンプチンスキー氏が指名された。 職場でのセクシャルハラスメントをソーシャルメディアなどで訴える動きを受けて、企業幹部と社員の関係については厳しい目が向けられるようになった。2018年6月にはインテル(INTC.O)のトップが、社員との関係が問題となり辞任している。(msn)(共同通信)海外資産隠し・税逃れ対策を強化 富裕層に、預金記録の保管要請 政府は3日、海外に保有する財産が5千万円を超える富裕層らの税逃れを防ぐ仕組みを強化する方針を固めた。国外にある銀行預金の入出金記録などの保管を新たに納税者側に要請することで、資産隠しをさせないようにする。税務調査で申告漏れなどが発覚した場合、記録の提示があれば加算税を軽減する措置を2020年度税制改正で導入し、自主的な保管を促す。対象となる個人や企業は1万を超えるとみており、対応を厳格化する。 富裕層による租税回避地への資産隠しや、海外の取引法人を利用した税逃れ行為は後を絶たない。海外取引の調査は難しく、情報開示を促す仕組みづくりが課題だった。(goo)(弁護士ドットコム)深刻な「職場いじめ」退職する人も…仕事を教えず「聞こえるように悪口」悲痛な声神戸市立東須磨小学校で、教員4人が同僚をいじめていた問題が波紋を広げています。弁護士ドットコムのLINE公式アカウントで「職場のいじめ」の経験を募ったところ、「いじめが理由でうつ病に」「退職を余儀なくされた」など、たくさんの悲痛な声が寄せられました。その一人からは、いじめではなく「職場内の優位性を悪用したパワハラです」との指摘もありました。●根も葉もない噂を広められ「うつ病」に 具体的な事例をみていきます。職場いじめが原因で、うつ病を発症した方からも自身の経験が寄せられました。「仕事を教えてもらえない、無視をされる、聞こえるように悪口を言われる等、毎日そのような態度を取られていました」(女性・会社員)「パートで入社し3年くらいはいい職場だと思っていたのに、女性パート1名の一言から突然いじめが始まりました。最初のうちは2、3人で陰口を言うくらいでしたが、最後はまったく根も葉もない噂を会社以外にまで広められました。結局1年近くその状態が続き、ウツ病を発症しました。今は転職をして病気も治りましたが、その会社では今も別の人が入れ替わりでいじめられているそうです」(30代女性・パート従業員)●仕事を教えてもらえず、「私のする仕事を全て否定」 今回、寄せられた声で、もっとも多かった業界は、医療・介護職でした。一体、何が起こっているのかーー。寄せられた声を読み、編集部員も驚くほかありませんでした。「仕事は教えてもらえず、私だけを省いて、3時間も4時間もミーティングを行う。私のする仕事を全て否定する」(30代女性・ソーシャルワーカー)様々な職種がかかわるためか、中には立場の違いを悪用する医療者もいます。「独身時代は、院長先生に腰に手をまわされたり、勉強会のあとの飲み会と称して夜の11時付近まで付き合わないといけなかったり、それで何度か彼氏と別れる原因に」(30代女性・歯科衛生士)●なぜ医療職でいじめはなくならないのか? どうして、医療職でいじめがなくならないのか。その背景の1つに、医療現場の深刻な「人手不足」があげられるのかもしれません。「不倫のアリバイにつかわれたり、誹謗中傷を言いふらされたり、無視は当たり前。業務時間外のラインでの嫌がらせもありました。人格否定等。上司もいじめる側につき、ハラスメント委員会に相談するも、どんな対応がなされたかわからず。最終的にハラスメント委員会からもごめんなさいみたいなことを言われたあげく、上司からはどうしようもないんですよーの一言でした」(女性)「保育園へ預けてから出社するママナースの仕事は手伝わない、なぜなら定時出勤するから。あたし達は40分以上早く来てるのに、という理由からです。他には、教えない。ミスを見つけて騒ぐ。ミスにもならない事柄をあたかもミスをしたかのようにしていく。自分がしでかしたインシデントを弱い立場や誠実なナースに押し付けてインシデント報告書を書かせる。気に入らないナースがいると退職へ追い込もうとする、そのナースが辞めないならあたしが辞めます、と管理職を脅す」(50歳代、女性、関東地域在住、介護福祉士)●「会社は助けてくれない。自分の命は自分でしか守れない」 厳密には「社内」ではありませんが、「親会社」からのパワハラ に悩まされた方からの声をご紹介します。「中小零細企業は、大会社や親会社から常にパワハラ受けてます。“じゃあ取引止めるぞ”という恐怖の一言で、何でもやらされます。利益がないことがわかっていながらさらなる値引き要求をしてきたり、ありえない納期要求、女性営業に肉体関係を求めてきたり、日常茶飯事です。それでも、自分の販売目標が達成できなくなるので、泣き寝入りするか会社を辞めるかしかありません」(50代男性・会社員)証拠など条件が揃えば、法的な手続きを進めることもできます。ある方は、職場いじめを苦にして退職を決意。弁護士に相談した上で、労働審判をし、和解後に退職したそうです。自分と同様の経験をする方に対して、次のように指摘しました。「和解したから、全てが終わったわけでも、私の傷が消えたわけでも、家族が救われるわけでもありません。でも、(弁護士の)先生方に支えられ、あの和解を得られないければ、今の私にはありません。今私は、治療をしながら、自分を取り戻しながら、新しい資格・ステップアップの為の資格の勉強をしています。悩んでるいる人・苦しんでいる人に伝えたいです。会社は助けてくれません。自分の命は自分でしか守れない。でも、生きていればきっと。命だけは、大切にして欲しい。誰かに助けを求めて欲しい。逃げたっていいって伝えたい。自分が苦しんだ分、今心からそう思っています」(30代女性・神奈川県在住・ソーシャルワーカー)本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には85人が参加して、トップは81(18)=63とのこと。I君が71(6)=65で3位。・・・立派!!僕が78(8)=70で9位。U君が84(14)=70で10位。E氏が88(15)=73で24位。A君が84(10)=74で33位。M君が86(9)=77で54位。O君が93(16)=77で55位。K君が94(15)=79で68位。お疲れ様でした。本日の夕食は…国産黒毛和牛の2種食べ比べ、スイートポテトのポタージュ、野菜サラダ、パンでした。一緒に楽しんだのは…2005シャトー・コス・デストゥルネルでした。美味しくいただきました。口福・口福!!(msn)(東洋経済オンライン)エーザイが開発中止の「認知症薬」復活のわけ 株価急騰、世界初の治療薬に高まる期待 異例の逆転劇となるのか――。 製薬大手のエーザイは10月30日、2019年度第2四半期の決算を発表した。同時に通期予想も修正。2020年3月期通期の売上高は前期比6%増の6800億円、営業利益は70億円上方修正して同28%増の1100億円とした。自社開発の抗がん剤「レンビマ」の販売が想定以上に伸びていることを反映させた。開発中止した薬を承認申請する「異例」 目下、エーザイの業績はがん領域が牽引して絶好調といえる。だが、中間決算会見の場で同社の内藤晴夫CEOが説明に多くの時間を割き、記者やアナリストの質問が集中したのは、開発中のアルツハイマー病(AD)治療薬についてだった。 それは、エーザイが10月22日に、アメリカの製薬大手・バイオジェンと共同開発していたAD治療薬の「アデュカヌマブ」を、2020年初めにもアメリカ規制当局に新薬として承認申請すると発表していたからだ。承認されれば、世界初のAD根治薬が世に出ることになる。 エーザイは今年3月、臨床試験(治験)第3フェーズでアデュカヌマブの開発中止を発表していた。「一度中止になった開発品目が申請に至るというのは、異例中の異例の出来事」と業界関係者は驚きを隠さない。何しろ、内藤CEOですら「中止になったときと今回とで、驚きで2度も死ぬ思いをした」ほどなのだ。 そうしたサプライズもあり、エーザイの株価は10月23~24日にかけ2日連続でストップ高となった。11月1日の終値は前日比261円安の7887円で、承認申請発表前に比べ50%近く値上がりした水準で推移している。 認知症の患者は現在、世界で5000万人と推計されている。2030年には8000万人に増えると見込まれ、介護などを含めた周辺コストは200兆円を超えると言われる。ただ、現在販売されている認知症薬は症状を一時的に緩和するだけで、病気そのものを改善させるアデュカヌマブのような根治薬は存在しない。開発に成功すればエーザイは莫大な収益を手にすることになる。 それだけに、アメリカのファイザーやイーライリリー、スイスのロシュなど世界の巨大製薬企業がAD根治薬の開発に巨額の資金を投じてきた。が、開発はことごとく失敗。業界内からは「エーザイの開発も残念ながら絶望的だろう」という声も聞こえてくる状況だった。エーザイはなぜ中止薬剤の申請をしたのか そんな状況の中で今回、エーザイが一度開発を中止した薬剤を一転、申請することになったのはなぜか。 経緯はこうだ。アデュカヌマブの治験では、遺伝子の型や症状の進行度合いなどの被験者の条件、投与用量などがまったく同じ試験が2本行われていた。試験のスタート時期はそれぞれ2015年8月と同年9月で、1カ月の差がある。 そして、2018年12月時点で、決められた一定期間の投与が完了した被験者のデータを分析。その結果、2019年3月に「成功する確率は低い」と第三者機関から判断され、中止に至る。この時の分析で対象になった患者は、全参加者の約半数、1748人だった。 一方、今回は3285人の被験者全員を対象に分析し、決められた一定の投与期間に満たなかった被験者も、統計学の手法で効果を予測することで分析対象のデータに組み入れた。 分析対象となる人数が増えただけで異なる結果が出たのは、「期間の途中で治験内容を変更し、高用量を投与する患者が増えたこと」(エーザイ)だと考えられている。 当初は副作用の大きさから、特定の遺伝子を持つ患者への投与量は少なめに抑えられていた。だが、副作用のコントロールがある程度できるようになったことで、2017年3月から特定の遺伝子を持つ患者への投与量を増加させた。治験終盤には高用量を投与された患者の割合が増えており、最終解析の成績がよくなったというわけだ。アデュカヌマブ申請が承認されない懸念も 今後の焦点は、当局に申請が受理され、承認にこぎ着けることができるかだ。アデュカヌマブは一度中止になった後の申請という異例の展開をしているだけに、承認を得られない懸念がある。 実は2つの試験のうち、1カ月先に始まった試験では、偽薬を投与する「プラセボ群」よりアデュカヌマブを投与した患者のほうが症状が悪化するという結果が出ている。 そういった点を含めアメリカの当局が認める可能性について、内藤CEOは「治験は2つとも高用量では奏功しているという点で一貫している。そこを評価してもらえるのではないか」と話すものの、見通しはまだ不透明だ。 アデュカヌマブの治験結果の詳細は、12月に開催される学会で発表される予定だ。ここでの発表に注目が集まる。(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)NY株見通し-今週はテクニカル、センチメント改善で堅調か ダウ最高値更新に期待 今週のNY市場は堅調か。市場予想通り政策金利が0.25%引き下げられたFOMCでは、利下げの打ち止めが示唆されたものの、パウエルFRB議長が利上げのハードルは高いとしたことで緩和的金融政策の長期化見通しが強まった。10月雇用統計では非農業部門雇用者数が大幅に予想を上回ったほか、過去2カ分も上方修正されたことで、米景気後退懸念も和らいだ。これまで発表された7-9月期決算は約75%の銘柄で利益が市場予想を上回り、決算発表終盤戦への期待も続いた。S&P500が7月と9月の上値抵抗線を明確に上抜けるなどテクニカルも大きく改善しており、今週は史上最高値まであとわずかに迫ったダウ平均の高値更新が期待される。リスク要因では、米中貿易問題を巡る関連報道や、6日に発表される10月ISM非製造業景気指数などに注目。終盤戦を迎えた企業の7-9月期決算はタペストリー、クアルコム、トリップ・アドバイザー、ラルフローレン、ウォルト・ディズニーなどが注目される。 今晩の米経済指標は10月雇用傾向指数、9月耐久財受注改定値、9月製造業新規受注など。企業決算は寄り前にアンダー・アーマー、バークシャー・ハサウェイ、引け後にマリオットインターナショナルなどが発表予定。(執筆:11月4日、9:00) (yahoo)(フィスコ)欧州為替:ドル・円は108円29銭から108円47銭まで上昇 4日のロンドン外為市場では、ドル・円は108円29銭から108円47銭まで上昇した。米国経済の減速懸念後退や米中貿易協議の部分合意への期待感から、欧州株全面高、米10年債利回り上昇を受けてドル買い、円売りが優勢になった。 ユーロ・ドルは1.1172ドルから1.1149ドルまで下落。ユーロ・円は120円86銭まで下落後、121円08銭まで上昇した。 ポンド・ドルは1.2941ドルから1.2910ドルまで下落。ドル・スイスフランは0.9857フランから0.9889フランまで上昇した。(yahoo)(時事通信)〔ロンドン外為〕円、108円台前半(4日正午) 【ロンドン時事】週明け4日午前のロンドン外国為替市場では、株高などを背景に円は売りが先行し、円相場は1ドル=108円台前半で弱含みで推移した。正午現在は108円35~45銭と、前週末午後4時(108円10~20銭)に比べ25銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=121円00~10銭(前週末午後4時は120円75~85銭)で、25銭の円安・ユーロ高。 円の対ドル相場は薄商い。東京市場が祝日で休場で、新規の手掛かり材料にも乏しく、相場は動意を欠いた。堅調な株価を眺めながら、安全資産とされる円がやや売られる展開となった。ただ、前週末に発表された米雇用統計が底堅い内容だったとはいえ、「なぜ全体的にリスク選好になっているのかはよく分からない」(邦銀筋)との声が出ている。 ユーロも小動き。朝方発表されたIHSマークイットの製造業PMIで、ドイツやフランス、ユーロ圏の景況感が市場予想をわずかに上回った。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1160~1170ドル(1.1165~1175ドル)。 ポンドは1ポンド=1.2920~2930ドル(1.2945~2955ドル)。 スイス・フランは1ドル=0.9875~9885フラン(0.9850~9860フラン)。(了)
2019.11.04
コメント(0)
-

11月3日(日・文化の日)…2019ラウンド81…
11月3日(日・文化の日)、曇り~晴れです。天気予報では曇りでしたが、現場は晴れて暖かく(暑く)なりました。そんな本日は、ホーム1:GSCCの西コースで開催の菊花杯に参加させていただきました。同業者コンペもあり。10時20分スタートとのことですが、6時50分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時頃には家を出る。奥はニキータ2号と一緒に名古屋のホテル催事に招待だそうです…。8時30分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、12/1のエントリーを確認して、着替えて、コーヒーブレイク(A君としばしの歓談)して、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…マアマア…。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。本日の僕のハンディは(8)とのこと。久しぶりにシングルプレーヤーに復帰です。OUT:0.0.2.0.1.0.1.2.2=44(16パット)1パット:3回、3パット:1回、パーオン:2回。1打目のミスが3回、2打目のミスが4回、3打目のミスが2回、アプローチのミスが2回、バンカーのミスが1回、パットのミスが4回…。ミスショットが多いです…。バーディートライを50cmほどオーバーしてのパーパットをお先にで外します…。しかも2~3回…。切れますよね~!10番のスタートハウスでおでんをいただく。IN:0.2.0.3.2.1.2.0.1=47(18パット)1パット:3回、3パット:3回、パーオン:2回。ミスが多いのでミスのチェックができません…。切れていますから…。44・47=91(8)=83の34パット…。いいとこなしです…。スコアカードを提出して、靴を磨いて、お風呂に入って、パーティー会場へ…。Wペリア戦での7位だけですね…。本日のフィジカルチェック…170.0cm,64.0kg,体脂肪率20.2%,BMI22.1,肥満度+0.7%…でした。早々に会計を済ませて、16時頃には退散です。16時30分頃には帰宅。奥も食事は普通、ワインはまずかった…とのことで早々に帰宅していました。(GDO)世界選手権シリーズ WGC HSBCチャンピオンズ 最終日マキロイが今季初勝利 シャウフェレとのPO制す 松山英樹は11位ロリー・マキロイ(北アイルランド)が早くも今季初勝利を挙げた。単独首位から「68」で回り、通算19アンダー。「66」をマークしてトップで並んだ前年覇者のザンダー・シャウフェレをプレーオフ1ホール目で破った。昨季最終戦の「ツアー選手権」以来となるツアー通算18勝目は、10月に開幕した2019-20年シーズンの初タイトル。世界選手権シリーズは3勝目ルイ・ウーストハイゼン(南アフリカ)が通算17アンダーの3位に入った。松山英樹は4連続を含む7バーディ、1ダブルボギーの「67」とし、通算11アンダーの11位タイで終えた。川村昌弘は通算7アンダーの22位。浅地洋佑はこの日のフィールドベストスコア「65」を記録して通算2アンダーの38位。堀川未来夢は1オーバーの49位、石川遼は7オーバーの67位となった。国内男子 マイナビABC選手権 最終日ハン・ジュンゴンが4年ぶり4勝目 今平周吾は1打及ばず首位に1打差の2位から出たハン・ジュンゴン(韓国)が1イーグル3バーディの「67」でプレーし、通算19アンダーで逆転優勝を果たした。2015年11月「カシオワールドオープン」以来、4年ぶりのツアー通算4勝目。賞金ランキング2位の今平周吾は単独首位から出て、1イーグル4バーディ、3ボギーの「69」で、1打差の2位に終わった。米ツアーが主戦場の小平智が通算16アンダーの3位。岩田寛、藤田寛之、リチャード・ジョン(カナダ)が通算14アンダーで4位に入った。通算13アンダー7位にイ・サンヒ(韓国)、トッド・ペクら6人が並んだ。6位タイから出た阿久津未来也は「74」と崩れ、25位に終わった。<上位成績>優勝/-19/ハン・ジュンゴン2/-18/今平周吾3/-16/小平智4T/-14/R.ジョン、岩田寛、藤田寛之6T/-13/イ・サンヒ、B.ジョーンズ、パク・サンヒョン、カン・キョンナム、G.チャルングン、T.ペク国内女子 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 最終日1打差の首位から出た賞金ランキング4位の鈴木愛が5バーディ、1ボギーの「68」でプレー。通算14アンダーで逃げ切って、9月「ニトリレディス」以来となる今季5勝目を挙げた。ツアー通算14勝目。1打差2位に賞金ランキングトップの申ジエ(韓国)。通算12アンダー3位に小祝さくら、通算11アンダー4位に岡山絵里がつけた。通算9アンダー5位にペ・ソンウ(韓国)。通算8アンダー6位に勝みなみ、高橋彩華が並んだ。前週「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」を制した柏原明日架は通算1アンダー27位。前年覇者ささきしょうこは通算4オーバー50位に終わった。<上位成績>優勝/-14/鈴木愛2/-13/申ジエ3/-12/小祝さくら4/-11/岡山絵里5/-9/ペ・ソンウ6T/-8/勝みなみ、高橋彩華8T/-6/新垣比菜、葭葉ルミ(ブルームバーグ)バフェット氏のバークシャー、利益と手元現金が過去最高 著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる米保険・投資会社バークシャー・ハサウェイの7-9月(第3四半期)は、多くの意味で新たなピークを迎えた。 まず、営業利益が過去最高を更新した。バフェット氏が過去最大の買収で傘下とした鉄道会社BNSFの業績が過去最高となり、バークシャーの利益を押し上げた。また、バフェット氏の株式投資利益も寄与してバークシャーの純利益は520億ドル(約5兆6300億円)に達し、同社は世界で最も利益を上げている上場企業となった。 さらに、手元現金は1280億ドルとこれも過去最高。ただ、バークシャーのクラスA株の年初来上昇率は今月1日までで5.7%と、S&P500種株価指数の22%を下回っている。 CFRAリサーチのアナリスト、キャシー・サイファート氏はインタビューでバークシャーについて、「手元現金を使いたくてたまらなくなるかもしれない中、慎重になるのは賢明だ。だが、いずれかの時点で重荷のようになり、全体のリターンに響くほどになるだろう」と述べた。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技は年代別ですね。翁組には15人が参加して、トップは83(17)=66とのこと。寿組には16人が参加して、トップは86(14)=72とのこと。松組には46人が参加して、トップは78(13)=65とのこと。僕は91(8)=83で41位ですね。竹組は18人が参加して、トップは75(7)=68とのこと。梅組は11人が参加して、トップは82(11)=71とのこと。お疲れ様でした。我が家の鎹:ロマネちゃん4態。
2019.11.03
コメント(0)
-

11月2日(土)…
11月2日(土)、晴れです。気持ちの良い秋晴れですね。そんな本日は7時40分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、奥を近くのJRステーションまで送る。奥は京都でのアイスショーにご招待だそうです…。帰宅して、まずは1階の掃除…。途中でこんなモノが届きました…京都・伏見の藤岡酒造の「蒼空」の純米吟醸ですね。後日に楽しみます。1階の掃除が終わると、洗濯のスタート…。洗濯機が動いている間に2階の掃除です…。2階の掃除が終わると洗濯物を干す…。本当に働き物ですね!!コーヒーブレイクはネスプレッソでエチオピアを…。美味い!!1USドル=108.17円。1AUドル=74.78円。昨夜のNYダウ終値=27347.36(+301.13)ドル。(ブルームバーグ)【米国株・国債・商品】株が反発、強気相場盛り返す-雇用統計が好調 1日の米株式相場は反発。金融危機後に始まった息の長い強気相場があらためて勢いを盛り返した。S&P500種株価指数は年初来上昇率が22%を超え、週間ベースでは4連騰。米国債は反落。 米国株は反発、S&Pが4週連騰-雇用統計、米中動向が追い風 米国債は反落、10年債利回り1.71% NY原油は反発、経済指標良好で6週間ぶりの大幅上昇 NY金先物は反落、好調な米雇用統計と米中協議の進展が重し 10月の米雇用統計では雇用者数の伸びが市場予想を上回り、個人消費のけん引で過去最長の景気拡大がなおも継続する可能性が示された。これを受け、S&P500種は終値ベースの過去最高値を更新。米中貿易協議で米中が「原則コンセンサス」に達したとの認識を中国商務省が示した後、短時間ながら株上昇の勢いが強まった。 S&P500種株価指数は前日比1%高の3066.91。週間ベースでは1.5%高となった。ダウ工業株30種平均は301.13ドル(1.1%)高の27347.36ドル。ナスダック総合指数は1.1%上昇。ニューヨーク時間午後4時19分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.71%。 連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長はブルームバーグとのインタビューで、金融政策は「良好な状況」にあり、消費者動向は堅調だとの見方を示した。 FTSEラッセルの世界市場調査担当マネジングディレクター、アレック・ヤング氏は雇用統計について、消費者や雇用、低金利などの恩恵を受けて米経済がしっかりと成長し「よく持ちこたえているとの見方を裏付けるものだ」と指摘した。 ニューヨーク原油先物相場は大幅反発。良好な米雇用統計や中国の製造業指標を手掛かりに、6週間ぶりの大幅上昇となった。週間ベースでは依然、世界経済の成長減速や米在庫積み上がり、貿易交渉への不安で下げた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は2.02ドル(3.7%)高の1バレル=56.20ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は、2.07ドル高の61.69ドル。 ニューヨーク金先物相場は小反落。3カ月連続の米製造活動縮小を示す指標が出たが、米雇用統計が予想より強かったことの方が材料視された。米中貿易協議が「原則コンセンサス」に達したと中国商務省が説明した後、金は下げ幅を拡大した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%安の1オンス=1511.40ドルで終了。【NY外為】ドル指数が5日続落、円は米中交渉の進展で下落 1日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数が5日連続で低下。米経済統計が強弱まちまちの内容となる中、ドル売りが優勢になった。円は主要10通貨に対して軟調。中国商務省は通商交渉で米中が「原則コンセンサス」に達したと説明した。 ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%低下。供給管理協会(ISM)の製造業総合景況指数を嫌気して、この日の安値水準に下げた。週間では0.4%低下し、ここ5週間で4週目の下げISM製造業総合景況指数は48.3に上昇。予想中央値の48.9を下回った。前月は10年ぶり低水準の47.8だった。10月の米雇用統計では非農業部門雇用者数が12万8000人増となり、市場予想(8万5000人増)を上回った。前月は上方修正された 経済指標がまだら模様となる中、金利先物市場が織り込む0.25ポイント利下げの時期は2020年7月と、前日に比べ2カ月ほど先送りされた クラリダFRB副議長らの発言は、政策金利の据え置きを金融政策当局が示唆したとの見方を裏付けた 円は中国商務省の声明後に下げ幅を拡大した 米中両国は協議が「建設的」だったと評価 ニューヨーク時間午後4時49分現在、ドルは対円で0.1%上げて1ドル=108円16銭。対ユーロでは0.1%安の1ユーロ=1.1164ドル。(ロイター)S&Pとナスダック最高値更新、雇用統計好調[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米国株式市場は、米雇用統計が好調だったことで株価が押し上げられ、S&P総合500種とナスダック総合が終値ベースで過去最高値を更新した。 労働省が発表した10月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月から12万8000人増加した。自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)のストライキの影響で伸びは前月から鈍化したものの、予想の8万9000人増を上回った。8、9月の雇用者数も計9万5000人上方改定された。 USバンク・ウエルスマネジメント(フェニックス)の地域投資ストラテジスト、ジェフ・クラベッツ氏は雇用統計について、「景気サイクルの終りにこれほど近い時期になっても経済に耐性があることが示された。これにより市場でリスク選好度が高まっている」と述べた。 このほか、財新/マークイットが発表した10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)が51.7と、約2年半ぶりの高水準となったことも市場心理の支援要因となった。 この日は米政権高官らが米中通商協議が順調に進展しており、米国は「第1段階」の通商合意の月内署名を目指しているなどと表明。米中協議を巡る動きも株式市場の支援要因となった。 米供給管理協会(ISM)が発表した10月の製造業景気指数は48.3と、景気拡大・縮小の節目となる50を3カ月連続で下回ったものの、雇用統計が好調だったことで大きく意識されなかった。 週間ベースではダウ工業株30種が1.44%、S&P総合500種が1.47%、ナスダック総合が1.74%、それぞれ上昇。S&Pの上昇は4週間連続で、2月以来最長となった。ナスダックの上昇は5週間連続。また、ダウは過去最高値まであと12ポイントの水準に迫っている。 個別銘柄では、石油大手エクソンモービル(XOM.N)が3.00%高。第3・四半期決算で利益が予想を上回ったことで買いが入った。 アップル(AAPL.O)に半導体を供給するコルボ(QRVO.O)は20.23%高。10億ドルの自社株買い戻しの発表のほか、第3・四半期の売上高が予想を上回ったことが好感された。 一方、画像共有サイトの米ピンタレスト(PINS.N)は17.02%安。四半期売上高が予想を下回ったことで売られた。 ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.81対1の比率で上回った。ナスダックでは2.86対1で値上がり銘柄数が多かった。 ドル下落、まちまちの指標や米中協議巡る期待で=NY市場[ニューヨーク 1日 ロイター] - ニューヨーク外為市場ではドルが下落。強弱まちまちの経済指標が相場の重しとなったほか、米中通商協議を巡る期待からドルに対する質への逃避買いが後退した。 10月の米雇用統計が予想を上回ったことでドルは当初値上がりした。非農業部門の雇用者数は前月から12万8000人増加。自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)のストライキの影響で、伸びは前月から鈍化したものの、市場予想の8万9000人増を上回った。一方、10月の米供給管理協会(ISM)製造業景気指数は3カ月連続で節目を割り込み、ドル買いが続かなったという。 スコシアバンク(トロント)の主任外為ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は雇用統計について、GMのストの影響でもっと悪い数字が予想されていたので、実際の内容はかなり良かったと指摘。同時に「米経済の減速に対する懸念がドルを圧迫し始めている」とした。 主要6通貨に対するドル指数.DXYは0.12%安の97.24。一時97.45まで値上がりした。 金融当局者発言では、連邦準備理事会(FRB)のクラリダ副議長が、FRBによるこれまで3回の利下げはその最大効果をまだ発揮していないものの、米経済を「かなり支援」していると述べた。 米中通商協議については、通商代表部(USTR)が、部分貿易協定を巡りライトハイザー代表とムニューシン米財務長官、および中国の劉鶴副首相が電話協議を行い、様々な分野で進展があったと明らかにした。 ドル/円 NY終値 108.17/108.20 (yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)NY市場概況-ダウ301ドル高 S&Pとナスダックが史上最高値更新 1日のNY株式相場は大幅反発。強い雇用統計を受けて投資家心理が大きく改善したほか、米中貿易問題への過度な警戒感が和らいだことや、半導体のコルボやエネルギーのエクソン・モービルなど好決算銘柄の上昇も相場を押し上げた。寄り前に発表された米10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が12.8万人増と、市場予想の8.9万人増を大きく上回り、9月分と8月分も上方修正された。ダウ平均は301.13ドル高と大幅に反発し、過去最高値に接近。S&P500は0.97%高の3066.91ポイントで終了し、2日ぶりに最高値を更新。ハイテク株主体のナスダック総合も1.13%高と反発し、3カ月ぶりに史上最高値を更新。時価総額最大のアップルは2.84%高と続伸し、4日ぶりに上場来高値を更新した。週間では、ダウ平均が1.44%高と2週続伸し、S&P500が1.47%高と4週続伸、ナスダック総合は1.74%高と5週続伸となった。 寄り前に発表された米10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が12.8万人増と、市場予想の8.9万人増を大きく上回ったほか、9月分が13.6万人増から18.0万人増に、8月分も16.8万人増21.9万人増に上方修正された。もう一つの注目の10月ISM製造業PMIは48.3と市場予想の48.9を下回り、3カ月連続で好不況の分かれ目の50を下回ったものの、10年ぶりの低水準となった前月の47.8を上回ったことで製造業景況感の一段の悪化は回避された。9月建設支出は前月比+0.5%となり、前月の+0.1%、市場予想の+0.2%を上回った。(yahoo)(フィスコ)NY株式:上昇、雇用統計を好感米国株式相場は上昇。ダウ平均は301.13ドル高の27347.36、ナスダックは94.04ポイント高の8386.40で取引を終了した。10月雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を上振れ、米景気拡大への期待感から買いが先行。投資家心理の改善から終日堅調推移となった。S&P500やナスダック総合指数が最高値を更新した。セクター別では、運輸や自動車・自動車部品が上昇する一方で家庭用品・パーソナル用品や消費者・サービスが下落した。フィットネス関連機器のフィットビット(FIT)は、検索大手アルファベット(GOOGL)と21億ドルで身売り合意し、大幅上昇。石油メジャーのエクソン・モービル(XOM)と製薬アッヴィ(ABBV)は、決算内容が好感され、堅調推移。原油相場の上昇で、エネルギー会社のチェサピーク・エナジー(CHK)や深海油田開発のトランスオーシャン(RIG)などエネルギー銘柄が上昇。一方で、食肉メーカーのタイソンフーズ(TSN)は、業績見通しを引き下げ、下落した。世界貿易機関(WTO)は、中国が申し立てていた米国の反ダンピング措置の一部について違法性を認め、米国製品36億ドル相当に報復措置を実施することを認めた。米中協議に何らかの影響を与える恐れがあり、今後の展開を注視したい。(Horiko Capital Management LLC)NY為替:ドル108.19円、米雇用統計でFOMCの年内政策金利の据え置き思惑11月1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、107円92銭から108円32銭まで上昇して108円19銭で引けた。米10月雇用統計で非農業部門雇用者数が予想外に10万人台の伸びを維持、過去2カ月間の雇用も大幅に上方修正されたほか、貿易を巡り米中閣僚が電話会談を実施し、協議に一段の進展が見られたため景気見通しが改善。米連邦公開市場委員会(FOMC)が年内政策金利を据え置くとの思惑が一段と強まりドル買いに拍車がかかった。その後、米10月ISM製造業景況指数が予想を下回り、3カ月連続で50割れ、活動の縮小が示されたことが嫌気され、ドルの上値を抑えた。ユーロ・ドルは、1.1128ドルまで下落後、1.1172ドルまで反発して1.1166ドルで引けた。ユーロ・円は、120円36銭から120円94銭まで上昇。ポンド・ドルは、1.2970ドルから1.2927ドルまで下落した。ドル・スイスは、0.9895フランまで上昇後、0.9851フランまで下落した。国内株式市場見通し:日経平均は騰勢一服、決算発表は佳境へ■日経平均4週連続高前週の日経平均は小幅ながら4週連続高となった。なお、10月月間では2カ月連続の上昇で、4月を上回り今年最大の上げ幅を記録した。米中の通商合意「第1段階」成立が最終段階に入ったと伝わり25日のNYダウが反発した流れを受けて、週明け28日の日経平均も上昇のスタートとなった。高値警戒感や日米の金融政策、企業決算などを見極めたいとの思惑から上値追いの動きは鈍かったものの、東京エレクトロンが3%近く上昇するなど半導体、電子部品関連が上げた。欧州連合(EU)が英国のEU離脱期限の延長を認めたことを好感し、29日も日経平均は7日続伸となった。1ドル=109円近辺まで円安が進んだことも追い風となって取引時間中としては昨年10月以来、およそ1年ぶりに23000円台を回復する場面があり、終値としては7日連続で年初来高値を更新した。30日の日経平均は8日ぶりに反落。前日に23000円台を一時回復したことで短期的な達成感が台頭して利益確定売りが先行したほか、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの思惑から、控え持ち高調整の売りが優勢となった。こうしたなか、通期業績予想を上方修正した富士通が大幅高、経営統合観測が報じられたケーヒンなどホンダ系部品3社のストップ高が話題になった。大方の予想通りFOMCで政策金利が引き下げられて、30日のNYダウは反発。この米国株高を受けて31日の日経平均も上昇した。日銀の金融政策決定会合で金融政策は現状維持となり、フォワードガイダンスの修正が決定。イベント通過によるアク抜け感から日経平均は堅調となったものの、節目の23000円を前に上値の重さが意識された。個別では、第2四半期業績が想定を上振れたソニーが4%高となった。米中貿易協議に不透明感が台頭するとともに一部の経済指標を嫌気された米国市場の流れを受け、3連休控えとなった11月1日の日経平均にも売りが先行。一時1ドル=107円台まで円高が進んだことも悪材料視されたものの、先物の買い戻しなどから朝方の売り一巡後に下げ幅を縮小し、76.27円安の22850.77円で大引けとなった。個別では、上期決算が市場予想を上回った任天堂の上昇が目立った。■日経平均はもみあいに転換か今週の日経平均は、次の展開を探るもみ合いが見込まれる。前週までで日経平均は4週連続高となるなか、心理的な節目である23000円に突っ掛けた目標達成感も生まれて、連騰後の一服感が生じやすいタイミングだ。10月31日発表の米シカゴ購買部協会景気指数が3年10カ月ぶりの低水準まで下げたことで、米国の景況感に対して警戒感が生じてきた。11月5日発表の米10月ISM非製造業景況指数や8日の米11月ミシガン大学消費者マインド指数などで弱い数字が表面化すると、東京市場にも下振れ作用として働いてこよう。また、米長期金利の低下とともに為替相場が円高方向に振れる場面が前週あった。米連邦準備制度理事会(FRB)による政策金利の引き下げ打ち止め観測が広がると、ドル安・円高を誘いやすくなり、日経平均の調整幅が大きくなる可能性もあり、為替動向も気掛かり材料だ。一方、中国メディアの財新が1日に発表した10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は51.7と9月と比較して上昇し、約2年半ぶりの高水準となった。これを受けて、中国の景況感に対する過度な懸念は足元で後退している。中国最大の小売りイベント「独身の日」を翌週の11日に控えて消費を刺激するニュースも出やすいことが予想される。また、10月の雇用統計の内容を好感して1日のNYダウは今年7月19日に記録した最高値27398.68ドルに迫った。S&P500、ナスダック指数に続いて史上最高値をNYダウも更新してくると「リスクオン」の強気ムードが東京市場にも生まれてこよう。いずれにせよ、全体では強弱感が交錯することにもなり、下値不安が少ないながらも方向感が掴みにくい展開となりそうだ。■トヨタの決算は7日、5G関連イベントもこのため、市場の関心は引き続き個別の企業業績に集まることになるだろう。主力銘柄では5日にNTT、6日にソフトバンクグループ、SUMCO、7日にトヨタ、8日にホンダ、ブリヂストンがそれぞれ決算発表を予定している。8月の第1四半期決算発表時に減収減益の通期予想を下方修正しているトヨタの決算内容が関心を集めることになるだろう。また、NTTやKDDIなど通信会社のトップが一堂に顔を揃えて出席する次世代通信規格「5G」に向けた「TOKYO Data Highwayサミット」が8日に東京都庁で開催されることから、物色テーマとして「5G」関連が注目される可能性がある。5G基地局の測定電子計測器を手掛けるアンリツを中核に、アルチザネットワークスやエコモットなど中小型株にも人気が拡大するかが焦点となる。■9月景気動向指数やオプションSQなど主な国内経済関連スケジュールとして、4日は文化の日の振替休日で東京市場休場、5日に10月マネタリーベース、6日に9月18・19日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨、7日に10月都心オフィス空室率、8日に9月景気動向指数、9月毎月勤労統計調査、オプションSQがそれぞれ予定されている。(yahoo)(モーニングスター)株式週間展望=堅調な展開維持:米中合意文書調印をにらむ―2万3000円台固めるか、下値は25日線支持 決算発表シーズンたけなわを迎えた日本株相場は、相変わらず堅調なムードをキープしている。日経平均株価は今週(10月28日-11月1日)、1年ぶりに2万3000円台を回復。その後はやや上値が重いものの、下値は上昇中の25日移動平均線が足場として意識される。また、市場は米中貿易協議の合意をにらむ形になりそうだ。 日米の金融当局の会合を通過した今週、日経平均は2万2850円で引け、前週比では50円の小幅高となった。10月29日には2万3008円を付けたが、その後は頭を押さえられている。もっとも、高値までに7連騰するなど、急激な上昇を踏まえれば反動を問題なくこなしたと言える。 FOMC(米連邦公開市場委員会)では3会合連続の政策金利の引き下げが決まり、日銀は金融政策における金利のフォワードガイダンス(指針)に将来的なマイナス金利拡大の可能性を盛り込んだ。いずれも事前の観測に沿った結果となり、マーケットは無難にイベントを乗り越えた。また、企業の決算に対しても、ネガティブな株価反応は限られている。 一方、米中貿易摩擦をめぐっては、両首脳が会談するはずだったAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が、開催地のチリでの反政府デモ激化により中止に追い込まれた。ただ、トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席と別の場所で会い、予定通り貿易協議の合意文書に調印する考えを示している。 欧州では英国のEU(欧州連合)離脱問題がひとまず先送りされるなど、政治リスクは後退したように見える。そうした中、年終盤にかけて上昇しやすい季節性も相まって、日経平均は改めて2万3000円台での値固めをうかがう情勢だ。昨年10月に2万4448円のバブル崩壊後高値からの下落過程であけたマド(2万3051-2万3373円)を、埋め戻せるかが注目される。 本稿は締め切り時間の都合で、日本時間1日夜に発表される米国の10月雇用統計や同ISM(米サプライマネジメント協会)製造業景況指数の内容を確認していない。また、政治リスクの沈静化は既に織り込み済みの材料とも考えられるため、ここからは出尽くしになりやすい地合いも視野に入れる必要がある。 もっとも、着実に下値を切り上げる日経平均は、調整しても2万2000円台を駆け上がる25日線(1日は2万2186円)に接近するあたりが足場として意識される。このため来週(5-8日)の想定レンジは2万2400-2万3200円とする。 企業決算の後半戦は7日のトヨタ自動車 を筆頭に、5日のソフトバンク 、6日のソフトバンクグループ 、8日(オプションSQ<特別清算指数>算出日)のホンダ などに注目が集まる。海外は、メモリー市況を占う米クアルコムが最重要だ。 このほか、日本では8日に9月景気動向指数、米国で5日に9月貿易収支と10月ISM非製造業景況指数、8日に中国10月貿易収支、土曜日の9日には中国10月消費者物価と生産者物価が出る。(市場動向取材班)昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の14銘柄が値を上げて終了しましたね。重点5銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。(GDO)世界選手権シリーズ WGC HSBCチャンピオンズ 3日目マキロイが首位浮上 松山英樹は15位で最終日へロリー・マキロイ(北アイルランド)が5バーディ、ボギーなしの「67」でプレーし、通算15アンダーとして単独首位に浮上した。ルイ・ウーストハイゼン(南アフリカ)が1打差の2位。前年覇者のザンダー・シャウフェレ、マシュー・フィッツパトリック(イングランド)が通算13アンダーの3位で続いた。松山英樹は1イーグル5バーディ、1ボギー1ダブルボギーの「68」とし、通算6アンダーの15位から最終日に臨む。川村昌弘が「66」をマークし、通算4アンダーの22位に浮上した。堀川未来夢は通算3オーバーの59位、浅地洋佑は5オーバーの63位、石川遼は6オーバーの67位で3日目を終えた。国内男子 マイナビABC選手権 3日目今平周吾が今季2勝目へ単独首位浮上 2打差に小平智首位と3打差の5位から出た今平周吾が、無傷の1イーグル6バーディの「64」をマーク。通算15アンダーとして、単独首位に躍り出た。現在、賞金ランキング2位につける今平。あす最終日は10月「ブリヂストンオープン」以来の今季2勝目を狙う。通算14 アンダー2位にハン・ジュンゴン(韓国)。通算13アンダー3位に「62」でプレーした小平智が続いた。首位で出た岩田寛は「70」とし、藤田寛之と並び通算12アンダー4位に後退した。通算11アンダー6位に阿久津未来也、トッド・ペク(米国)、ガン・チャルングン(タイ)、チョ・ミンギュ(韓国)の4人が並んだ。前年覇者の木下裕太は「74」とし、通算2オーバー60位で3日目を終えた。<上位陣の成績>1/-15/今平周吾2/-14/ハン・ジュンゴン3/-13/小平智4T/-12/岩田寛、藤田寛之6T/-11/阿久津未来也、トッド・ペク、ガン・チャルングン、チョ・ミンギュ国内女子 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 2日目鈴木愛が単独首位 プロデビュー戦の古江彩佳は予選落ち今季4勝で賞金ランキング4位の鈴木愛が4バーディ、ノーボギーの「68」でプレー。通算10アンダーで首位を守った。同ランキング1位の申ジエ(韓国)は「66」でプレー。小祝さくら、岡山絵里と並んで通算9アンダー2位。通算7アンダー5位にキム・ハヌル、ペ・ソンウ(ともに韓国)、大江香織の3人がつけた。前週「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」を制した柏原明日架は通算1オーバー41位。前年覇者ささきしょうこは通算2オーバー47位で最終日に臨む。2週前の「富士通レディース」で史上7人目のアマチュア優勝を果たし、プロ転向したばかりの19歳・古江彩佳は予選落ちとなる通算3オーバー56位。ほろ苦いプロデビュー戦となった。<上位成績>1/-10/鈴木愛2T/-9/小祝さくら、申ジエ、岡山絵里5T/-7/ペ・ソンウ、大江香織、キム・ハヌル8T/-6/勝みなみ、高橋彩華
2019.11.02
コメント(0)
-
11月1日(金)…
11月1日(金)、晴れです。とうとう11月に突入ですね。今年も終盤です。そんな本日は7時35分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分頃に家を出る。ゴルフではありません…、アルバイト業務です。本日は恒例の10:00~16:00です。昼食インターバルは1:00ですね。午前のお仕事はジャスト…。お昼は天ざるをいただく。午後のお仕事は少し早くに終わったので、帰り道でいつものGSによって、愛車に洗車・タイヤ空気圧調整、燃料補給を済ませる。カステラとコーヒーで遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=107.97円。1AUドル=74.57円。昨夜のNYダウ終値=27046.23(-140.46)ドル。本日の日経平均=22850.77(-76.27)円。金相場:1g=5808(+25)円。プラチナ相場:1g=3641(+4)円。(ブルームバーグ)日本株は小反落、米中協議の不透明感と米景気不安-素材安く電機高い 1日の東京株式相場は小幅に反落。米中通商協議に対する中国の慎重な見方が伝わる中、米経済指標が予想を下回った上、為替相場が円高に振れたことから非鉄金属や鉄鋼など素材関連、機械や精密機器など輸出関連の一角が下落。株式分割を発表したキーエンスや営業利益計画を上方修正した村田製作所などの電機は高い。 TOPIXの終値は前日比0.51ポイント(0.03%)安の1666.50 日経平均株価は同76円27銭(0.3%)安の2万2850円77銭〈きょうのポイント〉 中国、トランプ大統領との長期的貿易合意の実現性に疑念-関係者 10月の米シカゴ製造業景況指数は43.2、前月の47.1から予想外に低下ー市場予想48 米個人消費は予想下回る、失業保険申請件数は増加 ドル・円相場は1ドル=108円近辺、前日の日本株終値時点は108円69銭 米10年債利回りは8ベーシスポイント低下し1.69% 10月の米供給管理協会(ISM)製造業景況指数や雇用統計、今晩発表 みずほ証券の倉持靖彦投資情報部長は米中協議について、「中国側から疑念が示され、11月の合意署名があるのかを見極める必要が出てきた」と述べた。米経済指標も悪化して米債券相場が金利を押し上げる方向に向かず、為替市場で円高が進んでいることが「景気敏感株中心に日本株を下げる要因」と指摘した。 米中通商問題に対する楽観的な見方が薄れて前日の米国株が下げた流れを引き継ぎ、TOPIX、日経平均とも下落して始まった。日経平均の下げ幅は一時200円を超えた。 午前半ばに公表された中国の10月財新製造業購買担当者指数(PMI)が予想外に上昇し、為替市場で円高が一服。中国株を含めてアジア株が総じて値を上げたため、日本株も下げ幅を縮めた。 米景気の現状を見極める上で、今晩発表されるISM製造業景況指数への注目度が高い。インベスコ・アセット・マネジメントの木下智夫グローバル・マーケット・ストラテジストは、実質国内総生産(GDP)が弱く「設備投資は戻っていないため、製造業景況指数も弱く出て景気不透明感が広がるとみて日本株が売られている」と話した。 ただ「連動性の高いニューヨーク連銀製造業景気指数の改善から若干改善との見方もある」ため、大きな下げにはなっていないとも同氏は指摘した。 東証33業種は卸売や医薬品、機械、化学、精密機器、保険、非鉄金属、鉄鋼が下落。前日に四半期決算を発表した任天堂のほか、キーエンスやパナソニック、村田製作所といった電機株が指数を支えた。【日本株週間展望】反落、手がかり材料難で短期過熱を懸念-決算注視 11月1週(5ー8日)の日本株は5週ぶり反落の見込み。主要な株価指数が前週に年初来高値を更新したため、短期的には反動が出やすい。米金融政策決定などを通過し新たな重要イベントが乏しく、個別企業の決算内容を見極めたいとのムードも強まりそうだ。 10月のTOPIXは月間で5%上げた。米S&P500種株価指数の2%高や中国上海総合指数の0.8%高などと比べ上昇率の高さが目立つ。TOPIXが1650、日経平均株価2万3000円と心理的な節目を回復した後でもあり、いったん戻り売りが出やすい。 市場の目は東証1部社数ベースで8日に後半戦のピークを迎える企業決算へと引き続き目が向かいそうだ。大和証券の集計(発表率39%、10月30日時点)によると、主要企業ベースで上期経常利益は前年同期比7%減益。7-9月期では製造業が15%減益だが、非製造業はITシステムや建設などの寄与から11%増益と内外需まちまち。全体での低調な決算は株価に織り込んではいるものの、先行きの回復期待は同じ業種内でも濃淡が分かれているとあって、決算が市場全体を押し上げるには力不足だ。 米経済指標では5日の10月供給管理協会(ISM)非製造業景況指数や9月の貿易統計が予定される。非製造業指数は前回の52.6から53.4へ改善が予想され、世界経済をけん引する米景気は消費中心に堅調との評価は変わらないとみられる。 もっともこれら以外に目立った指標やイベントは少ない。チリでのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議は中止されたものの、米中通商協議をめぐって両国首脳の話し合いが進展するようなら、株価を下支えしそうだ。10月5週のTOPIXは週間で1.1%高の1666.50と4週続伸。≪市場関係者の見方≫ピクテ投信投資顧問の松元浩常務 「スピード調整の週となりそうだ。短期的にはやや利益確定売りが出て、日経平均は2万2000円台前半まで緩やかに下落する可能性がある。米中通商協議は継続し、英国の欧州連合(EU)離脱は1月まで延期となるなど外部投資環境は改善。ピクテ投信試算の景気先行指数は悪化モメンタムの底打ちが見え始め、株式をアンダーウエートにし過ぎた投資家は中立に戻そうとする動きが出ている。それでも業績はまだ下向きで、上期がボトムだったと言い切れるまでの自信はまだ持ちきれない。割安を拾う動きはあっても、PERが拡大して日経平均で2万4000円まで上がるような力には乏しい」三木証券の北沢淳投資情報課長 「上値の重い展開が予想される。足元で急ピッチに上昇してきた日経平均は心理的節目の2万3000円付近では利益確定売りが出やすい。明確に同水準を抜けて上昇するには、米中貿易摩擦の緩和と来期の企業業績が増益転換するとの確度の高まりが必要だ。最近はトランプ大統領の米中協議に関する発言が前向きで部分合意への期待は続くだろうが、実際に米中首脳会談を開催して署名するまでは警戒感は残る。米国でISM非製造業指数が市場予想通りに改善し米国株高となれば支援材料にはなる」GPIFは資産構成比公表を一時停止、ポートフォリオ決定まで市場配慮 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は国内外の債券や株式などの保有額や運用資産に占める割合の公表を一時的に取りやめる。運用目標値を定めた基本ポートフォリオを見直す作業に入っており、市場への影響を配慮した。 GPIFが1日公表した8月27日開催の第27回経営委員会の議事概要によると、新たなポートフォリオを策定・公表するまで、四半期ごとの資産別の保有額や年金積立金全体に占める構成割合、収益額は公表しないことを決めた。ただ、可能な範囲で情報開示を徹底していく観点から資産別の収益率は公表を続けるとしている。 GPIFは政府による5年ごとの年金財政検証や、厚生労働省の社会保障審議会での議論を踏まえながら、基本ポートフォリオの見直し作業を進めている。きょう午後には7-9月期の運用成績を公表する予定だ。 GPIFの運用資産は6月末時点で159.2兆円、年金特別会計の資金を合わせた年金積立金は160.7兆円に上る。資産構成の目標値のわずかな変更でも数兆円単位の増減に相当するため、市場の波乱要因となる可能性がある。前回2014年10月末にリスク性資産の目標値を大幅に引き上げた後は日本株が上昇し、円安・ドル高が進むなど市場の波乱要因となった。 6月末の構成割合は国内債券26.93%、国内株式23.50%、外国債券18.05%、外国株式26.43%、短期資産5.09%。目標値はそれぞれ35%、25%、15%、25%で、上下に乖離許容幅が設けられている。GPIF:運用収益1.8兆円、4資産収益率そろってプラス-7~9月 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の2019年度第2四半期(7-9月期)の収益額は、海外金利の大幅な低下を背景に1兆8058億円増となり、運用資産額は過去3番目の高水準を記録した。 GPIFが1日公表した運用状況によると、運用収益率はプラス1.14%。9月末の運用資産額は161兆7622億円だった。国内外の債券・株式の4資産の収益率は、2四半期ぶりにそろってプラスとなった。米欧の中央銀行による金融緩和への期待が株と債券投資の追い風となった。 一方、内外債券・株式別の保有額や構成比、四半期ごとの収益額については、基本ポートフォリオの見直しが終わるまで公表を一時停止した。 高橋則広GPIF理事長は公表資料のコメントで、7-9月期の運用環境について、米国やユーロ圏が世界経済の減速懸念への対応として利下げなどの金融緩和を行ったことなどから世界的に金利は低下し、株価は上昇したと説明した。 運用状況データの一部公表停止については、基本ポートフォリオの見直しに向けた議論を進める中、「経営委員会における議論を踏まえ、今年度中は資産別資産額と構成割合および資産別収益額を開示しない。これらの情報は来年度に公表する2019年度の業務概況書に記載する」とした。 ピクテ投信投資顧問の松元浩常務は、GPIFの今後の展開について、「これだけ世の中の金利が下がってしまった後なので、GPIFがどういう債券運用を設定するのか注目したい。為替ヘッジ付き外債の比率もどうするのかが気になる」と語った。(ロイター)日経平均は小反落、押し目買いで後半下げ渋る[東京 1日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は小反落。前日の米国株主要3指数が下落したことや、為替のドル/円が円高基調で推移していたことなどを嫌気し、朝方から売りが先行。下げ幅は一時約200円まで拡大したが、その後は押し目買いが入って縮小した。 前日の米国株式市場では米中通商合意を巡って相反する情報が飛び交い、投資家に警戒感を与えた。東京市場もその流れを引き継いだものの、影響は限定的だった。市場からは「米中通商協議の先行き不透明感も生じたが、この手の話には慣れてきた印象。米中が『第1段階』の貿易協定の署名に向けて新たな開催地を近く公表する、とトランプ大統領が述べたことも悲観を和らげた」(東洋証券のストラテジスト、大塚竜太氏)との見方が聞かれた。 TOPIXは反落。東証33業種では、鉱業、非鉄金属、精密機器などが値下がり率上位。一方、その他製品、電気機器、陸運業などは買われた。 市場では3連休や米ISM製造業景況指数と雇用統計の発表を控えていることから、様子見ムードが強まり薄商いになるとの予測もあったが、好決算銘柄中心に押し目買いが入り、商いは細らず、東証1部の売買代金は2兆円を超えた。 個別銘柄では、任天堂(7974.T)が大幅続伸。家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」のハードとソフトの販売が好調で、4─9月期の連結営業利益が10年ぶりの高水準になったことなどが好感された。村田製作所(6981.T)も大幅反発。連結営業利益予想を上方修正したことが材料視された。 そのほか、 個別銘柄ではキーエンス(6861.T)が急騰し年初来高値を更新。前日に発表した2020年3月期上半期の決算は営業利益が14%減とマイナスで着地したものの、株式分割を同時に発表したことが好感された。 東証1部の騰落数は、値上がり801銘柄に対し、値下がりが1283銘柄、変わらずが70銘柄だった。 米アムジェン、中国バイオ企業に27億ドル出資[ロサンゼルス 31日 ロイター] - 米医薬品大手アムジェン(AMGN.O)は31日、中国のバイオテクノロジー会社、百済神州(ベイジーン)(6160.HK)の株式20.5%を現金約27億ドルで取得すると発表した。 世界2位の医薬品市場である中国で事業を拡大する。 ベイジーンの米国預託証券(ADS)1単位当たりの取得価格は174.85ドル。 ベイジーンは、アムジェンの抗がん剤3種類を中国で商品化するほか、アムジェンの抗がん剤開発にも協力する。 ジェフリーズのアナリスト、マイケル・イー氏は「中国には大きな商機があり、新たな収入源になる」と指摘。「アムジェンは中国で多くの製品を商品化しており、早期に事業を構築するのは非常に合理的だ」と述べた。 ベイジーンADSは時間外取引で25%上昇し173.10ドル。アムジェン株は213.25ドルで横ばい。来週の日本株は底堅いか、米経済指標や企業決算見極め[東京 1日 ロイター] - 来週の東京株式市場は、米経済指標や企業決算の内容を見極めつつ、底堅い展開となりそうだ。今晩米国で発表されるISM製造業景気指数と雇用統計が注目されるが、日本は4日が休日で、すぐには株価に織り込めない。連休明けに米国市場の反応を含めて消化することになる。国内では引き続き企業決算が相次ぐ。6日のソフトバンクグループ(9984.T)、7日のトヨタ自動車(7203.T)などが注目される。 日経平均の予想レンジは2万2400円─2万3200円。 1日の日経平均は朝方から売りが先行し、一時下げ幅を200円超に拡大したが、その後はじりじり値を戻し、前営業日比76円27銭安で取引を終えた。前日海外時間に広がった米中通商協議の先行き不透明感によるリスク回避は強まらず、押し目買いが下値を支える形となった。 今晩、米国で10月のISM製造業景気指数と米雇用統計が発表されるが、市場からは「前回のISMの悪化は行き過ぎで、今回反発するだろう。雇用統計も市場予想をよほど下回らない限り、景気認識が変わることはない」(第一生命経済研究所の主任エコノミスト、藤代宏一氏)との声が出ている。 両者が市場予想の範囲内と受け止められ、米国市場で株価や為替の動きが大荒れにならなければ、来週の東京株式市場もある程度は底堅い展開が見込めそうだ。 テクニカル面では、下値サポートして意識されていた5日移動平均線を下抜けて調整色を強めた格好だが、一目均衡表の転換線(2万2733円16銭=1日現在)をキープしたことで、調整は短期間で済むことが想定される。オシレーター系指標に生じていた過熱感が和らぐのを待ち、再び2万3000円にトライする可能性もある。 国内では、企業の決算発表が後半戦に入る。前半は今後の業績への強い期待感から、業績悪化銘柄が上昇し、好業績銘柄が売られる傾向が見られたが、好悪材料に素直に反応する動きも見受けられるようになった。市場からは「決算も後半に差し掛かると良くない内容が増えてくるかもしれない」(証券ジャパンの調査情報部長、大谷正之氏)と警戒する声も出ている。 個別では、ソフトバンクグループの決算が注目される。このところ下げ止まっているものの、米ウィーカンパニーへの支援に対して懐疑的な投資家が多いほか、ソフトバンク傘下の投資会社がインテル(INTC.O)に提訴されるなど、周囲にネガティブな材料も多い。決算にどのような反応を示すのか関心が高い。 ドル107円後半、ドル安の流れ続き一時3週間ぶり安値[東京 1日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点から若干ドル安/円高の107円後半。実需のドル売りや株安などを受けドルは107.89円まで下落し3週間ぶりの安値をつけた。30日に終了した米連邦公開市場委員会(FOMC)後のドル安の流れはこの日も続いたが、3連休を控えて積極的にポジションを取る向きは少なく、107円台のドル売りは勢いづかなかった。 ドルは仲値にかけて108.05円まで上昇したものの、仲値後には107.89円まで下落し、10月11日以来3週間ぶりの安値をつけた。値動きの背景には実需の売買があるとみられる。 東京市場では、FOMCや日銀金融政策決定会合の結果の消化などで「前日からの疲労が残っている」(証券会社)ことや、3連休を控えた様子見ムードが広がり、実需の動き以外のフローは低迷した。 一方、FOMC後のドル安のドライバー(推進役)となっている米長期金利は持ち直したものの、FOMC前の水準には戻っていない。 午後3時時点の米10年国債利回りUS10YT=RRは1.6998%付近。前日ニューヨーク市場終盤は1.6910%だった。FOMCの1日目に当たる29日には1.860%を付けていた。 財新マークイットによる10月の中国製造業PMIは51.7と2017年2月に並ぶ高水準となった。9月は51.4だった。 中国PMIを受け、豪ドル/円は74円の前半からじわじわと上値を伸ばし、74.64円まで上昇した。豪ドルの対円での上昇はユーロ/円にも波及し、ユーロは午前の安値120.41円から120.63円まで小幅に上昇した。 今夜は10月の米雇用統計やISM製造業景気指数などの重要指標が発表されるほか、複数の米連邦準備理事会(FRB)高官の発言機会がある。 9月雇用統計では失業率が3.5%と50年ぶりの低水準となった一方で、時間当たりの平均賃金は前年同月比で2.9%増と昨年9月以来の低水準となった。平均賃金の伸び率は今年1月―8月は3.1―3.4%のレンジ内で推移していた。 商務省が31日発表した9月の個人消費支出(季節調整済み)は、前月比0.2%増と小幅に伸びた。 「雇用統計が遅行指数であることを踏まえれば、米景気は既にピークアウトしている」(金融アナリスト)との意見も聞かれた。 (会社四季報オンライン)(ロイター)米株反落、通商合意巡る不透明感で アップル・FBは高いダウは140ドル安の2万7046ドル[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米国株式市場は反落。アップルやフェイスブックが前日発表した四半期決算は好調な内容だったが、米中通商合意を巡る不透明感が重しとなった。通商合意を巡り相反する情報が飛び交う中、市場では警戒感が高まった。ブルームバーグは、中国がトランプ米大統領と長期的で包括的な通商合意を結べるか疑問視していると報じた。トランプ大統領はその後、米中が「第一段階」の貿易協定の署名に向け、新たな開催地を近く公表すると述べた。過去3営業日で2回、終値で最高値を更新していたS&P総合500もこの日は反落。しかし、下落は過去7営業日で2日目と、なお底堅い動きとなっている。スレートストーン・ウエルスのシニア市場ストラテジスト、ケン・ポルカリ氏は「この日の下げは懸念すべき動きではない。ここ2週間ほどの上昇を受けた一服症状と考えられる」と述べた。通商問題に敏感なS&P工業株は1.14%安。中国へのエクスポージャーが大きい半導体も売られ、フィラデルフィア半導体株は0.62%安。一方、アップルは2.26%高で終了。年末商戦にかかる第1・四半期(10─12月)の売上高見通しが市場予想を上回ったことが好感された。フェイスブックも1.81%高。第3・四半期決算は売上高が3四半期連続増となったほか、ユーザー数も増加した。そのほか、食品クラフト・ハインツは13%超急伸。四半期利益が予想を上回ったことを受け、来年はコアブランドへの投資を拡大する方針を示した。化粧品大手エスティローダーは3.62%安。通期利益見通しの下方修正を受け売りが優勢となった。米指標では、9月の個人消費支出が小幅な伸びとなり、個人消費が経済を支え続けられるかどうか疑問を投げ掛けた。11月1日に発表される10月の米雇用統計が注目される。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.66対1の比率で上回った。ナスダックでも1.67対1で値下がり銘柄数が多かった。(ロイター)米アップル、7─9月期は中国減収抑制 幸運長続きせずとアナリスト[上海 31日 ロイター] - 米アップル(AAPL.O)の第4・四半期(7─9月)は、最新機種「iPhone11」の発売時期などの幸運が重なり、中国市場における一段の減収は食い止められたが、アナリストはこうした幸運は長続きしない可能性があると警告している。 アップルが30日発表した7─9月決算は、売上高は640億4000万ドルで、1株利益は3.03ドル。リフィニティブのアナリスト予想である629億9000万ドルと2.84ドルをそれぞれ上回った。 地域別では、中華圏の売上高が2.4%減の111億3000万ドルと、減収率は4─6月期の27%減から大きく縮小した。アナリストは、この背景には価格を抑えたiPhone11の投入などのさまざまな要因があったと指摘。カウンターポイント・リサーチのジェームズ・ヤン氏は「アップルが中国で進めている低価格戦略の影響は極めて大きい」と述べた。 ただ、アップルが次世代モバイル通信規格「5G」対応機種を投入するのは来年。中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)[HWT.UL]が6月に5G対応機種をすでに発売していることを踏まえ、アナリストの間で懸念が出ている。 7─9月期は、中国当局がこれまで禁止していたゲームの解禁を継続したことでアプリ配信サービス「アップストア」のゲームのダウンロード数が増加し、アップルが成長の柱の1つとして位置付けているサービス収入が2桁台の伸びを示した。 中国のスマホ市場に詳しいカナリスのニコール・ペン氏は、サービス収入の増加は中国のユーザーの間で有料のオンラインコンテンツの利用が一段と広まっていることを示していると指摘。新機種の買い替え時に古い機種の下取りを行うトレードインサービスをアップルが中国でアピールしていることにも言及し、再販業者の取り組みにより他社端末への乗り換えが防がれる中で「アップルがトレードインサービスの利用を勧める機は熟していた」と述べた。(株探ニュース)【市況】来週の株式相場戦略=2万3000円視野に下値固めも、決算発表はピークに 来週の東京株式市場は、日経平均株価の2万3000円乗せを意識しながら下値を固める展開となりそうだ。日経平均の予想レンジは2万2500~2万3100円。 今週は、米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策決定会合などビッグイベントが相次いだ。今晩の米雇用統計やISM製造業景況感指数の結果が気になるところだが、これまでのところはほぼ無難にイベントをこなした格好だ。 日経平均は10月29日、約1年ぶりに一時2万3000円台に乗せた。しかし、その後は利益確定売りにも押され、市場には「いったん目標達成感が台頭した」(アナリスト)との見方も出ている。週後半にかけては米中貿易協議に対する不透明感も強まった。先月29日まで7連騰したこともあり、やや過熱感も出ている。こうしたなか、来週にかけて日経平均は高値圏でのもみ合いとなることも予想される。 来週の注目ポイントは決算発表がピークを迎えることだ。特に8日には約560社が業績を公表する。なかでも、6日のソフトバンクグループと7日のトヨタ自動車は市場の関心を集めそうだ。この2社以外では、6日にはダイキン工業や三菱商事、7日には東レや楽天、三井不動産、8日にはブリヂストンや住友金属鉱山、ホンダなどが決算を発表する。なお、4日は文化の日の振り替え休日となる。 経済指標では、5日に米9月貿易収支、米10月ISM非製造業景況感指数、8日に中国10月貿易収支いが発表される。国内では8日に9月景気動向指数が公表される。(岡里英幸)(GDO)選手権シリーズ WGC HSBCチャンピオンズ 2日目松山英樹が32位に浮上 首位にフィッツパトリック3位で出たマシュー・フィッツパトリック(イングランド)が5バーディ、ボギーなしの「67」でプレーし、通算11アンダーとして単独首位に立った。ロリー・マキロイ(北アイルランド)が1打差の通算10アンダー2位。アダム・スコット(オーストラリア)、ザンダー・シャウフェレ、イム・ソンジェ(韓国)の3人が通算9アンダーの3位で追う。松山英樹は6バーディ、1ボギーの「67」で通算2アンダーとし、初日の70位から32位に浮上。堀川未来夢らと並んだ。浅地洋佑は通算1オーバーの56位、川村昌弘は通算2オーバーの61位。石川遼は「79」と大きく崩れ、通算4オーバーの67位に沈んだ。国内男子 マイナビABC選手権 2日目岩田寛が首位キープ 後続に2打差2015年「長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ」以来となるツアー3勝目を目指す岩田寛が4バーディ、1ボギーの「69」でプレー。通算10アンダーとし、「65」をマークしたチョ・ミンギュ(韓国)と並び首位をキープして大会を折り返した。2打差の通算8アンダー3位にハン・ジュンゴン(韓国)デービッド・ブランスドン(オーストラリア)が続いた。通算7アンダー5位に賞金ランキング2位の今平周吾、竹谷佳孝、出水田大二郎、阿久津未来也ら6人が並んだ。小平智は通算3アンダーの33位。前年覇者の木下裕太はスコアを落とし、通算イーブンパー52位とカットライン上で決勝ラウンドに進んだ。谷口徹は通算1オーバー61位、池田勇太は通算3オーバー76位で予選落ちとなった。<上位陣の成績>1T/-10/チョ・ミンギュ、岩田寛3T/-8/ハン・ジュンゴン、デービッド・ブランスドン5T/-7/ジャン・ドンキュ、阿久津未来也、出水田大二郎、カン・キョンナム、竹谷佳孝、今平周吾国内女子 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 初日鈴木愛と蛭田みな美が首位発進 プロデビュー戦の古江彩佳43位今季4勝で賞金ランキング4位の鈴木愛が7バーディ、1ボギーの「66」でプレー。ツアー初優勝を目指す22歳の蛭田みな美と並んで6アンダー首位で発進した。1打差3位に今季2勝の勝みなみ、岡山絵里、吉川桃。4アンダー6位に大江香織、ペ・ソンウ(韓国)、小祝さくらが並んだ。3アンダー9位に賞金ランキング1位の申ジエ(韓国)、キム・ハヌル(同)、金田久美子、原英莉花、大山志保、葭葉ルミらがつけた。前年覇者ささきしょうこは2アンダー19位とした。元賞金女王の森田理香子をキャディに起用した一ノ瀬優希は1アンダー31位、2週前の「富士通レディース」で史上7人目のアマチュア優勝を果たし、プロ転向したばかりの19歳・古江彩佳はイーブンパー43位で初日を終えた。2週連続優勝を目指す柏原明日架は1オーバー49位と出遅れた。<上位成績>1T/-6/鈴木愛、蛭田みな美3T/-5/勝みなみ、岡山絵里、吉川桃6T/-4/大江香織、ペ・ソンウ、小祝さくら9T/-3/申ジエ、大山志保、葭葉ルミ、キム・ハヌル、金田久美子、原英莉花 ほか(yahoo)(トレーダーズ・ウェブ)明日の戦略-反落も下げ渋り週間上昇、来週は決算にらみも円高進行を警戒か 11月に入り1日の日経平均は反落。終値は76円安の22850円。米中の通商合意に関する不透明感が強まったことなどから米国株は下落し、為替市場では円高が進行。これを嫌気して200円近く下落して始まった。しかし、開始早々に安値をつけた後は下げ渋って値を戻し、下げ幅を2桁に縮めて前場を終えた。後場は三連休を前に小動きが続いたが、終盤にかけて押し目買いが入り、下落ではあったものの、ほぼ高値圏で取引を終えた。東証1部の売買代金は概算で2兆3800億円。業種別ではその他製品や電気機器、陸運どが上昇した一方、鉱業や非鉄金属、精密機器などが下落した。通期の利益見通しを引き下げたものの、自己株取得や増配発表が好感されたダイセルが後場プラス転換から上げ幅拡大。半面、通期見通しの引き下げと減配を発表した住友商事が後場に急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり801/値下がり1283。株式分割と実質増配を発表したキーエンスが8%超の上昇、上期大幅増益の任天堂が7%超の上昇と、2大値がさ銘柄の急騰が市場の注目を大きく集めた。前期大幅増益で株式分割も発表したM&Aキャピタル、増税影響も踏まえた通期見通しの引き下げ幅が小幅にとどまったセリア、2Q期間(7-9月)の利益の伸びが好感された元気寿司などが大幅上昇。大幅上方修正を発表したクリナップがストップ高比例配分となった。一方、上期減益のコーセーや、下方修正を発表したフジクラ、ロイヤルHD、九州電力などが大幅安。3Q大幅減益のJIAはストップ安比例配分と売りが殺到した。大学共通テストの英語民間試験実施見送りを受けてEduLabがストップ安。きょうマザーズに新規上場したダブルエーは公開価格割れのスタートから下値模索が続いた。 為替市場では円高が進み、ドル円は108円を割り込んだ。FRBは今年3回目の利下げを実施したが、過去2回の利下げ実施局面(1回目7/31、2回目9/18)では、その直後にはドル安・円高が進んでいる。今回も同様の動きとなりそうな雰囲気が出てきており、来週のドル円の動向には注意が必要だ。ただし、ドル安は米国株にとっては支援材料となる。仮に円高に振れたとしても動きがマイルドであれば、ある程度のところで再びドル高・円安の流れに回帰すると考える。7月の利下げ局面では、8月に入ってすぐに米中の対決色が強まったため、円高・株安が加速した。一方、9月の利下げ後は、その前に急速に進んだ円安を修正するといった程度の動きにとどまり、その後のドル円は円安に振れ、株高基調が強まった。今回は9月のケースに近い動きになるとみている。10月初旬の106円50銭近辺までで円高が止まるかどうかがポイントになると考える。【来週の見通し】 横ばいもしくはやや弱含みを予想する。東京市場は4日立ち合い。海外は材料難となるなかで、国内は決算発表ラッシュとなる。6日のソフトバンクGや7日のトヨタの決算などが注目される。マクロ面では米中の通商合意に関して、期待を後退させるようなニュースも出てきたことから、やや不安定な地合いが続くだろう。また、FRBの利下げ実施で短期的には円安があまり期待できない点が、日本株にとっては上値を抑える要因になると考える。騰勢を強めていたアドバンテストが上方修正を発表したにもかかわらず急落したほか、決算で好材料を出してきた銘柄が売りに押されるケースがいくつか散見されており、高値警戒感も意識されそう。一方、今回の決算では弱い決算でも悪材料出尽くしの見方から買われる銘柄も多く見られる。個別の活況が引き続き期待できる点は下支え材料になることから、大きく売られることも考えづらい。23000円乗せでひと休みといった局面を想定している。【今週を振り返る】 高値圏で強弱感が入り交じる展開となった。週前半はS&P500の史上最高値更新や円安進行を好感して、日経平均も23000円台に乗せるなど上値追いの展開が続いた。ただ、一定の到達感も出てきたことから、その後は伸び悩む動きも見られた。FOMCでは大方予想通り利下げは実施され、パウエル議長の会見も市場に安心感をもたらした。一方、米中通商合意に対する不透明感が強まったことや、米国の経済指標が弱かったことなどから、後半にかけてはリスク回避の売りにも押された。日経平均は週間では約50円の上昇。週足ではほぼ十字に近い形ではあるが、4週ぶりに陰線を形成した。【来週の予定】 国内では、10月マネタリーベース(11/5)、日銀金融政策決定会合議事要旨(9/18~9/19開催分)(11/6)、10月都心オフィス空室率(11/7)、9月家計調査、9月毎月勤労統計、9月景気動向指数(11/8)がある。 企業決算では、NTT、ソフトバンク、スズキ、アサヒ、サントリーBF、丸紅、日水、王子HD、三菱ガス、持田薬、日軽金HD、マルハニチロ、寿スピリッツ、ニチレイ、グンゼ、古河電、三浦工、ユニオンツール、オイレス工、ブラザー、日信号、タムラ製、横河電、日光電、ニチコン、ワークマン、アコム、東建物、テーオーシー、京王、JR九州、ベネッセHD、ユニプレス、千代建、タカラスタン(11/5)、ソフトバンクG、ダイキン、三菱商、オリンパス、SUBARU、国際帝石、旭化成、西松建、日触媒、科研薬、東急建設、DeNA、アルフレッサHD、アルペン、SUMCO、コロプラ、昭電工、ムラ、アース製薬、東海カ、神戸鋼、シスメックス、Uアローズ、コロワイド、日ユニシス、富士急、住友ゴム、GSユアサ、三菱自(11/6)、トヨタ、三井不、菱地所、資生堂、テルモ、クボタ、キリン、楽天、東レ、リンナイ、DMG森精、東洋紡、日精機、森永乳、住阪セメ、ニプロ、ミツコシイセタン、メルカリ、フジHD、ノエビアHD、三菱マ、アマダHD、SANKYO、グローリー、ミネベアミツミ、ルネサス、カシオ、ゼンショーHD、ニコン、丸井G、日テレHD、ジャストシステ、西鉄、コスモエネHD、スクエニHD(11/7)、ホンダ、大和ハウス、ブリヂストン、ユニチャーム、セコム、住友鉱、雪印メグ、デンカ、セブン銀行、石油資源、大成建、長谷工、五洋建、ショーボンド、コムシスHD、NIPPO、ミクシィ、マクドナルド、日産化、ケネディクス、沢井製薬、ラウンドワン、いすゞ、島津製、ナカニシ、東京精、ケーズHD、共立メンテ、東急不HD、飯田GHD、ダイフク、りそなHD(11/8)などが発表を予定している。 海外では、米9月製造業受注(11/4)、米9月貿易収支、米10月ISM非製造業指数(11/5)、米9月消費者信用残高(11/7)、中国10月貿易収支(11/8)などがある。NY株見通し-米10月雇用統計と米10月ISM製造業PMIに注目 今晩のNY市場では米10月雇用統計と米10月ISM製造業PMIに注目が集まる。昨日は米中通商合意への先行き不透明感が高まったことや米10月シカゴPMIが大きく悪化したことで主要3指数がそろって反落した。今晩は寄り前に発表される米10月雇用統計と寄り後発表の米10月ISM製造業PMIに注目が集まる。昨日の米10月シカゴPMIは2カ月連続で好不況の分かれ目の50を下回り、約4年ぶりの水準まで低下した。前月に10年ぶりの水準に悪化した10月ISM製造業PMI(予想48.9、前回47.8)も下振れとなれば再び米景気後退の可能性が強く意識されそうだ。雇用統計の市場予想は、非農業部門雇用者数が8.9万人増(前回+13.6万人増)、失業率が3.6%(3.5%)、平均賃金が前月比+0.3%(0.0%)。 今晩の米経済指標は、10月雇用統計、10月ISM製造業PMIのほか、10月マークイット製造業PMI、9月建設支出など。クラリダFRB副議長、カプラン米ダラス連銀総裁、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁の講演も予定されている。企業決算は、寄り前にエクソン・モービル、AIG、アッヴィ、シェブロンなどが発表予定。(執筆:11月1日、14:00) (yahoo)(モーニングスター)来週の日本株の読み筋=底堅い展開か、決算相次ぐなか今後の業績回復期待が支えに 来週(5-8日)の東京株式市場で、主要株価指数は底堅い展開か。注目された日米金融当局の会合は無難に通過した。決算発表が相次ぐなか、ネガティブな反応は限られ、業績悪への織り込みが進むとともに今後の業績回復への期待感が相場を支えていくとみられる。日経平均株価は10月29日に一時2万3000円を回復し、短期的な過熱感もあって調整を入れたが、この間の急激な上昇を踏まえれば、反動は浅く下値抵抗力の強さを指摘する向きは多い。 一方、米中貿易摩擦をめぐって、両国は「第1段階」の貿易協定調印に近づいているが、中国は最重要問題で譲歩する意向はないなどと報じられた(10月31日付のブルームバーグ通信)。両首脳が会談するはずだったAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が、開催地のチリでの反政府デモ激化により中止に追い込まれたことも先行きの不透明感を意識させた。ただし、トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席と別の場所で会い、予定通り貿易協議の合意文書に調印する見通しを示しており、米中対立緩和へ向けて前進する可能性がある。 スケジュール面では、国内で決算ラッシュとなり、8日に9月景気動向指数が発表される。海外では5日に米9月貿易収支、10月ISM(米サプライマネジメント協会)非製造業景況指数、8日に中国貿易収支などが予定されている。 1日の日経平均株価は反落し、2万2850円(前日比76円安)引け。米中交渉への不透明感を背景にした10月31日の米国株安や円高・ドル安を受け、売り優勢で始まり、下げ幅は一時220円を超えた。一巡後は株価指数先物買いを交えて下げ渋りの流れとなった。中国・上海総合指数が堅調に推移し、支えとなった面もある。市場では、「材料次第で需給は揺れるが、根本的には金融相場なのだろう」(準大手証券)との見方が出ていた。今晩のNY株の読み筋=雇用統計、ISM製造業景況指数に注目 きょうの米国株式市場は、米10月雇用統計の結果が市場ムードに大きく影響を与えそうだ。雇用統計はゼネラル・モーターズのストの影響で非農業部門の雇用者数の伸びが9月から弱含むとの見方が根強い。10月末のFOMCを通過後、マーケットでは年内利下げ観測が後退したが、雇用統計がさえない結果となれば利下げ観測が再燃し、株式市場の支援材料となる可能性がある。また、足元で米中貿易交渉に対する悲観的な見方が強まっているが、10月ISM(米サプライマネジメント協会)製造業景況指数が好結果となれば、米中貿易交渉への悲観的な見方が後退するとみられる。<主な米経済指標・イベント>10月雇用統計、10月ISM(米サプライマネジメント協会)製造業景況指数、9月建設支出アッヴィ、シェブロン、AIG、ドミニオン・エナジー、エクソンモービル、バークシャー・ハサウェイなどが決算発表予定(日付は現地時間)(yahoo)(時事通信)〔東京株式〕反落=景気悪化懸念で利益確定売り(1日)☆差替 【第1部】世界的な景気悪化懸念を背景にした円高などを嫌気し、日経平均株価は前日比76円27銭安の2万2850円77銭と反落した。米雇用統計の発表や3連休を控えて利益を確保する手じまい売りがかさみ、東証株価指数(TOPIX)は0.51ポイント安の1666.50と軟化した。 銘柄の60%が値下がりし、値上がりは37%。出来高は12億5612万株、売買代金が2兆3870億円。 業種別株価指数(33業種)は、鉱業、非鉄金属、精密機器の下落が目立ち、その他製品、電気機器、陸運業などは上昇した。 個別銘柄では、石油資源が値を下げ、古河電は下押した。HOYAが安く、ソニー、SUMCO、TDKも売り物がち。三菱UFJ、野村は弱含んだ。エーザイが大幅安で、三桜工は続落。半面、任天堂が値を飛ばし、キーエンス、村田製、アドバンテス、パナソニックは大幅高で、東エレクも締まった。武田が高く、ファーストリテは小じっかり。東武も上伸した。 【第2部】3日続落。東芝が売られ、田岡化は小幅安。サイバーS、ショクブンは急伸し、千代化建は買われた、出来高8294万株。 ▽押し目は拾え? 1日の東京株式市場で日経平均株価は反落したが、相場の雰囲気は悪くない。市場関係者からは、「押し目は拾い場」(大手証券)と前向きな声も上がっていた。 前日発表の米国と中国の経済統計が悪化し、世界的な景気動向に警戒感が強まった。米中貿易交渉の行方も不透明な中、最近の上昇相場による過熱感が残っている東京市場では「利益確定売りが広がりやすい」(銀行系証券)のが現状だ。 しかし、日経平均は取引開始直後に下げ幅を前日比200円超に広げた後は下げ渋った。業績予想を上方修正した村田製が大幅高となるなど、投資意欲そのものは冷え込んだわけではない。11月は2012年から7年連続で上昇している株高の特異月となっているため、強気派にとっては絶好の買い場になったようだ。 225先物12月きりも、軟調な値動き。株価指数オプション取引は、原指数の下落を受けてプットが締まり、コールは下落した。(了) 〔NY外為〕円、108円台前半(1日朝) 【ニューヨーク時事】週末1日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、予想より堅調な米雇用統計の発表を受け、1ドル=108円台前半に下落している。午前9時5分現在は108円10~20銭と、前日午後5時(107円97銭~108円07銭)比13銭の円安・ドル高。 米労働省が朝方発表した10月の雇用統計によると、景気動向を示す非農業部門の就業者数は前月から12万8000人増加し、市場予想(ロイター通信調べ)の8万9000人増加を上回った。また、9月と8月も上方改定があり、労働市場は依然として底堅さを保っているとの見方が台頭。ドル買いが活発化する中、円は一時108円27銭近辺に下落した。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1130~1140ドル(前日午後5時は1.1146~1156ドル)、対円では同120円35~45銭(同120円37~47銭)で推移している。(了) 〔米株式〕NYダウ、反発=ナスダックは3カ月ぶり史上最高値更新(1日朝) 【ニューヨーク時事】週末1日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計の堅調な内容を受け、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比163.09ドル高の2万7209.32ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は一時8342.15と取引時間中の史上最高値を約3カ月ぶりに更新、同時刻現在は38.31ポイント高の8330.67となっている。(了) 午前中はまたしても円高ドル安傾向になってきましたね…。夜間には若干の円安方向に振れてきていますが…。(ブルームバーグ)米雇用統計:10月の雇用者数12.8万人増―予想上回る伸び 米国の10月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比12万8000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は8万5000人増だった。前月は18万人増(速報値13万6000人増)に上方修正された。 家計調査に基づく10月の失業率3.6%で、前月(3.5%)から上昇。平均時給は前年同月比3%増で、伸びは市場予想と一致した。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の8銘柄が値を上げて終了しましたね。配当・優待期待4銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の17銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点5銘柄ではすべてが値を上げてスタートしましたね。
2019.11.01
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- F1ニュース・レース
- Mclaren MP4/5B GP Car story 50
- (2024-12-15 20:31:43)
-
-
-

- 愛車!新車!
- ナミBOXJOY 1,700km超
- (2025-08-05 07:05:33)
-
-
-
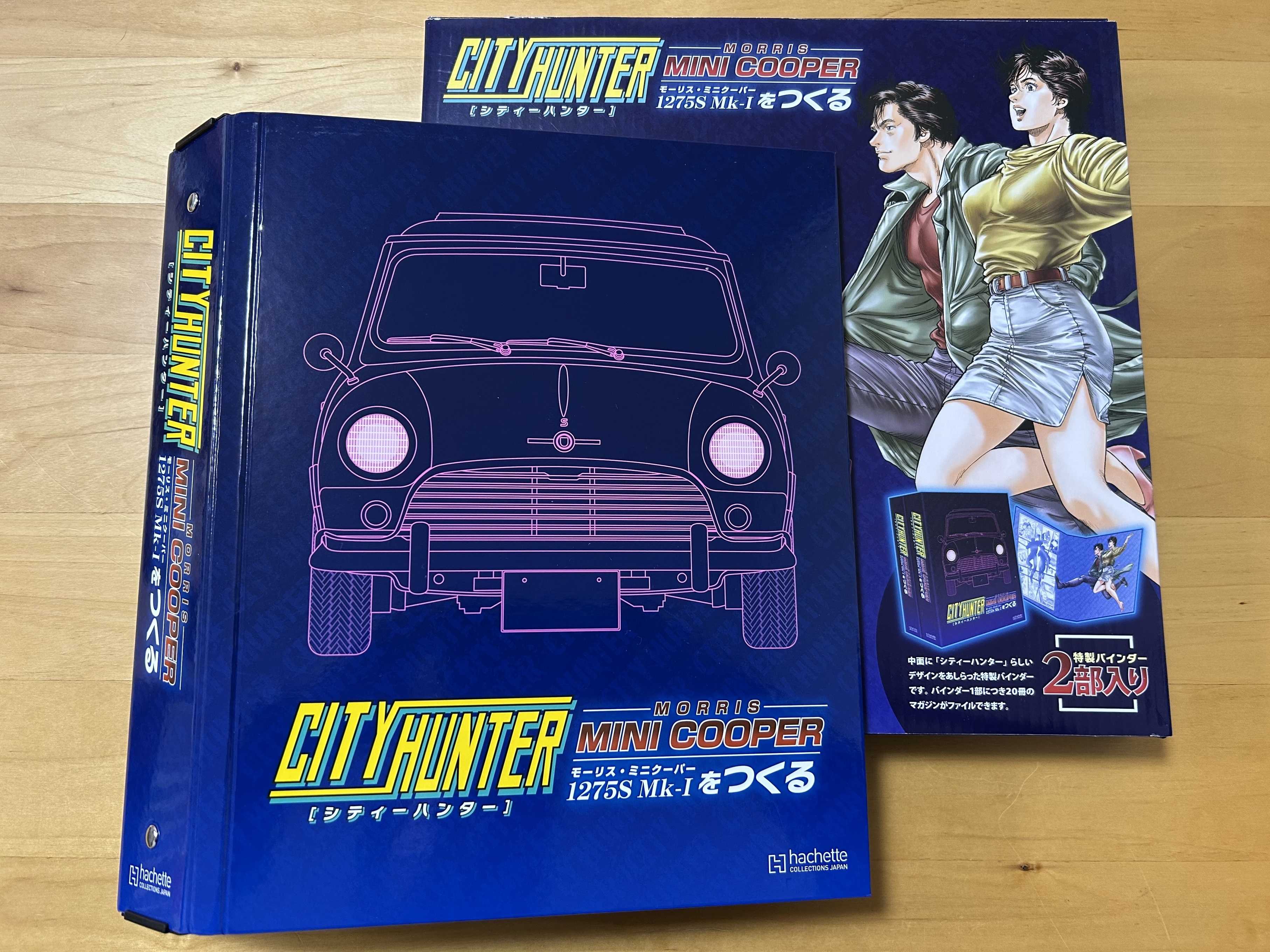
- MINIのある生活(^o^)
- 次の休暇こそ、絶対、きっと、多分!…
- (2025-11-14 10:45:14)
-







