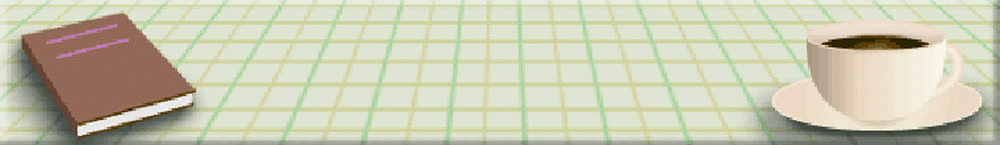2011年12月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
ありがとうございました。
ドラマ「坂の上の雲」が終わってしまったので、 このブログの書き込みも、これで終わりにしたいと思います。 これまで、アクセスして頂いた皆さん、 どうもありがとうございました。
2011年12月28日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(大往生)
秋山真之の臨終の地は、小田原にある友人「山下亀三郎」の別荘でした。 大正7年2月4日、 真之の腹は異様に膨れ上がり、 黒い血を幾度となく吐き、いよいよ危篤に陥ったのです。 午前3時ごろ、邸内に待機していた見舞客を病室に招きいれて、最後の挨拶を行いました。 『皆さん、いろいろお世話になりました。』 『これから独りでいきますから』 この後、真之の遺言が始まりました。 苦しそうに息を継ぎながら、それでも激しい口調であったそうです。 『今日の状態のままに推移したならば、わが国の前途は実に深憂すべき事態に陥るであろう。 総ての点において行き詰まりを生じる恐るべき国難に遭遇せねばならないであろう。 俺はもう死ぬるが、俺に代わって誰が今後の日本を救うか』 遺言が終り、しばらくして、 『辞世というほどのものではないが』 と、いって、 『不生不滅明けて烏の三羽かな』 最後の「かな」は、聞き取れなかったようですが、恐らく「かな」であったろうとのことです。 そして、13歳になった長男には「宗教をしろ」と、 11歳の三男には「軍人になれ」と、はっきり言い切ったのです。 しかし、12歳の次男は、養子に出していたので、わざと遺言は与えなかったそうです。 そして、親友の山下との会話が真之の最後の言葉となったようです。 『今まで君に何もたのんだことはなかったなあ』 『うん何も頼まれたことはなかった』 『○○を頼む』 『よし、子供のことは引き受けた』 この、○○というのは、多分、二女の名前であったのでしょう。 いくら死を覚悟しているとはいえ、3歳になったばかりの末っ子の娘のことを想うと、 後ろ髪をひかれたのではないでしょうか。 相模湾に太陽がようやく登ろうとして、水平線上がわずかに紅く染まった時、 真之は、逝ってしまいました。 夜明け烏がどこかで、カァカァと鳴いているのを聞いた真之は、「やっとお迎えが来てくれたなあ」と思ったのかもしれません。 迎えにきた烏は、いったい誰だったのか。 「正岡子規」だったのかもしれませんし、「広瀬武夫」だったのかもしれません。 しかし、迎えに来たのは、やはり父烏と母烏だったのではないかという気がします。 両親に導かれた子烏は、夜明け前の空に飛び去ってしまいました。 『不生不滅明けて烏の三羽かな』
2011年12月27日
コメント(0)
-
ドラマ「坂の上の雲」第13回「日本海海戦」
ドラマ「坂の上の雲」で一番見たかったのが、日本海海戦のシーンで、 これまで、この海戦シーンは「円谷プロ」でしか見たことが無かったので、 それに比べれば、当然のことかもしれませんが、とても良く出来ていると思いました。 ロシアの戦艦が沈没するシーンは、不謹慎な言い方なのでしょうけど、 絵画のように美しかったです。 ただ、日本海海戦の最も重要なシーンである「敵前回頭」は、 波濤の処理がしょぼく、三笠がおもちゃのように見えたのは残念でした。 以下は、原作にはないオリジナルのシーンの感想です。 海戦が終了し、戦艦「三笠」の病室で、 加藤友三郎参謀長が東郷平八郎長官に「だいぶ怪我人を出してしまいました」と言って、 東郷が加藤を見ながら「もっと怪我人が出ると思っていた」と返答し、 秋山真之参謀と眼が合うというシーンがありました。 真之は、多分「三笠」の惨状を見て驚愕し、深く沈みこんでいたのだと思います。 それで、東郷は「お前のおかげで怪我人を多く出さずにすんだ」と真之を慰労しているわけで、 慰労の仕方が回りくどいと言えば回りくどいのですが、 東郷らしいというか、渡さんらしいという気がして、 このシーンはオリジナルの中では珍しく良かったのではないでしょうか。 そういえば、敵弾が三笠を直撃した時の、渡さんのシーンはしびれるぐらいにカッコ良かったです。 戦争が終わって、児玉源太郎満州軍総参謀長が、乃木希典第3軍司令官に、 「これからどうなるのかのう」と聞いて、乃木が「何も変わらん」と答えるシーンがありました。 「明治」が終わると同時に死を選ぶという乃木の将来を暗示しようとしたのかもしれません。 それから、兄好古が弟真之に「これからどうなるのかのう」と聞いて、 真之は「急がんとひと雨来る」と答えるシーンがありました。 「ひと雨」とは何を暗示しているのでしょう。 それから、「急ぐ」とは何を急ぐ必要があるというのでしょうか。 まさか、「アメリカとの戦争に備えよ」と言ってるわけではないでしょうから、 何か気になるシーンではありました。 この3年間におよぶ長いドラマのラストは、 これまでおざなりに扱われてきた「好古」の臨終シーンでした。 これは、多分、阿部さんというより松さんに配慮したのかもしれません。 しかし、「あなた、馬から落ちてはいけませんよ。」では、泣くに泣けないのです。 たぶんというか、まちがいなく、これから逝こうとする夫に対して、 妻が「馬から落ちるな」という発想をするわけがありません。 これは、やっぱり、「貴様と俺とは同期の桜」であって、 もう70歳を過ぎた陸軍仕官学校同期の爺さんが見舞いにやって来て 「あきやまあー、うまからおちるなあー」 と叫んでくれないと、さまにならないわけです。 このラストシーンの「がっかり感」みたいなものが、ドラマ全体を支配していたような気がします。
2011年12月26日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(晩年、真之病む)
大正5年12月1日、秋山真之(49歳)は「第2水雷戦隊司令官」に補せられました。 年が明けて、真之は勤務中に突然腹痛を起こし帰宅したそうです。 真之は、息子たちを厳しく育てていたようで、 冬でも、足袋を履いたり、炬燵に入ったりすることを禁じていました。 どうやら、兄好古から受けた教育方法を、 そのまま自分の息子達に適用していたようです。 この時、炬燵に入って寝そべっている父親を見つけた10歳になる三男が、 『男が炬燵に入ってはいけません』 と、逆襲したのですが、 真之は、脂汗を流しながら、激痛をこらえていて、 苦笑することも、怒ることもできなかったようです。 真之は、虫垂炎でした。 この当時、虫垂炎の治療といえば、手術しか無かったようですが、 真之は、 『必ず自己の心霊の力によって直してみせる』 と言って、これを拒否したのです。 この「自己の心霊の力」というのは、 当時真之が入信していた「大本教」の教えによるものなのかもしれません。 真之が、「大本教」に入信した時期、理由は明らかにされていないようですが、 手術を回避したいという願いが、入信の一因であったような気がします。 大本教は、奇跡を実演することができて、 真之も教祖から「手かざし」を受けると、 さしもの激痛がうそのように引いたとそうです。 しかし、疾病の根源を断つことはできなかったようで、 日増しに症状は悪くなるばかりでした。 大正6年7月16日、「第2水雷戦隊司令官」を免じられ、 「海軍将官会議議員」に補せられした。 「海軍将官会議議員」は閑職ですから、 これは海軍から真之に与えられた初めての休暇のようなものでした。 同年12月1日、真之は「海軍中将」に任じられますが、 既に通常の勤務をこなすことはできなくなっていたようで、「待命」になっています。
2011年12月25日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(晩年、第2水雷戦隊司令官)
大正5年2月、秋山真之(49歳)は海軍省軍務局長の職を解かれて、 軍令部出仕と同時に、欧米各国への長期出張を命じられています。 第1次世界大戦が勃発してから2年近く経過したのに、 この戦争は収束の気配さえ見えず、長期化の様相を呈していました。 海軍としても、これをつぶさに観察し、 来たるべき海戦に備えようと考えたのでしょう。 そのための観察者を海軍の中から抽出するのであれば、 なるほど真之ほどの適任者は外に居なかったのかもしれません。 それにしても、この人事はあまりにも唐突すぎていて、 軍務局長という重要なポストの後任者は4ヶ月近く決まらず、 その間、海軍次官「鈴木貫太郎」少将が兼任したのです。 真之を海軍省から追い出したい勢力が、 何とか理由を付けて、外見的にはスムーズに事を運んだという気がしないでもありません。 この出張は8ヶ月にもおよび、真之に同行した軍令部参謀「山梨勝之進」中佐によれば、 『将軍(真之のこと)この御旅行中は、 大変健啖(食欲旺盛)にして健康もすこぶる良好で実に愉快そうにみえた。』 と、語っています。 真之は既に4年以上陸に上がっていたわけで、帰国してほどなく、 「第2水雷戦隊司令官」に補されて海に戻っています。 ただ、この役職は、陽のあたる場所だけを歩いてきた真之にとっては、 とても相応しいとは思えず、 真之自身も相当ショックを受けて、自らの将来を悲観したという話もあるようです。 真之が大佐になった時、初めは3,000トン級の艦長で、 その後、少しずつ排水量の大きい艦船の艦長となっていますので、 4年以上陸に上がっていた事が考慮されて、 最初は負担の少ないポストが与えられたのではないかという気もします。 いずれにしても、この後海軍が真之をどのように処遇するつもりであったのかは、 永遠の謎になってしまったのです。
2011年12月24日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(晩年、横綱と小結)
海軍大臣「八代六郎」中将は、大ナタを振るってシーメンス事件を処理してしまうと、 さっさとその職を「加藤友三郎」中将に譲って、現場に復帰したのですが、 「秋山真之」少将は海軍省で軍務局長としての業務を継続しました。 日本海海戦では、絶妙の連携をみせた加藤と真之ですが、 軍政方面ではうまくいかなかったようです。 加藤が、 『秋山もいいけれど、もう少し俺をたててくれないと困るよ』 と愚痴ったという話は、多分この時期のことであったのでしょう。 当時、真之は、 『日本の海軍のことはもうこれで宜しい。 これからは支那問題、大亜細亜洲の問題だ。』 と、語ったとされていて、 これは、文字通り捉えることもできるのですが、 「日本海海戦以上の功績を挙げることは、軍令系統では(今が平時であるから)できないから、 軍政系統に活路を見出したい。」 という、日露戦争後の苦悩の中で、 やっと見出すことができた方向性であったのかもしれません。 同じ松山人で、俳人の「河東碧梧桐」(カワヒガシ、ヘキゴトウ)は、 本当は「小結」程度の実力しかないのに、 「横綱」になってしまった「力士」の苦悩を「真之」に当てはめていて、 真之が軍務局長の職を引き受けたのもこの苦悩ゆえだと考えていたようです。 碧梧桐は、次のように述べています。 『軍務局長のごとき吏務は、 もしこの人(真之のこと)が徹底していたならば、 容易に承諾すべき地位ではないからだ。 果然、そのために、「頓挫」というほどではなくても、 多少の暗影をその智嚢の上に投げられてしまった。』 真之の苦悩は、軍務局長を勤めることによりさらに深まってしまったようですが、 それを解決しようにも、真之の時間は、あと2年しか残っていなかったのです。
2011年12月24日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(晩年、海軍省軍務局長)
第1艦隊参謀長を約1年8ヶ月務めた後、大正元年12月(45歳)、 秋山真之は陸に上がり、軍令部の参謀(海軍大学校教官兼務)になります。 翌年、海軍大学校同期のトップをきって、海軍少将に昇格するのですから、 真之は海でも陸でも陽のあたる道を歩いているという感じであったでしょう。 この頃、海軍始まって以来の大疑獄といわれる「シーメンス事件」が発生し、 真之のキャリアにも大きく影響を及ぼすことになります。 政府は、シーメンス事件を早急に後始末する必要に迫られ、 次期海軍大臣のポストには、派閥に無縁で名利に潔癖であるとされる「八代六郎」中将に白羽の矢が立ったのです。 八代は、次官に「鈴木貫太郎」少将、軍務局長に真之を指名して、 この難局を乗り切ろうしたのですが、 鈴木は次官の就任を躊躇したようです。 事件の処理方法を誤れば、次官の職を解かれるだけでなく、 海軍まで辞めねばならないからです。 鈴木は、最終的に次官への就任を承諾するのですが、 当時のことを次のように回想しています。 『秋山君が八代さんから頼まれて、 私に是非海軍次官にということをいって来られた。 私は「行政上のことは嫌いだから断る」といって最初は断った。 むしろ秋山が適任だから「君がやったらどうか」といった。 しかし秋山君は「僕には敵が多いから君がやれ」といったが、 「いやだ」と断ると電話を切ってしまった。』 真之は、八代とは肝胆相照らす仲であったこともあり、 進んでこの難局に飛び込んだようです(大正3年4月、真之47歳)。
2011年12月23日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(晩年、第1艦隊参謀長)
日露戦争が終り、連合艦隊も平時編成に戻されることになり、 明治38年12月21日に解散式が行われています。 この時、「秋山真之」が起草したと言われる訓示が読み上げられています。 真之は連合艦隊の参謀職を解かれ、再び海軍大学校の教官になりました。 この頃、国会では日露戦争の報告会が行われています。 陸軍の報告演説は、満州軍の高級参謀であった松川敏胤(トシタネ)少将が担当し、 海軍は真之が担当したのです。 中佐という低い位で海軍を代表して演説を行ったのですから、 やはり目立ったでしょうし、 「舷舷相摩す」に代表される海軍の公報が真之の筆であるという風聞と相まって、 一般にその名を知られるようになったようです。 俳人で松山人の高浜虚子が他県人から 「ご同郷人に秋山参謀をお持ちになるのはお国の方のご名誉です」 と言われのもこの頃でしょう。 次に、真之は海の勤務となり、明治41年には大佐になっています。 大佐になると艦長になれるわけで、艦長は一国一城の主ですから、海軍士官の一つの目標であったそうです。 真之も、 巡洋艦「音羽」(3,000トン)、 巡洋艦「橋立」(約4,000トン)、 装甲巡洋艦「出雲」(約10,000トン)、 巡洋戦艦「伊吹」(約15,000トン) の艦長を歴任しました。 そして、明治44年3月、真之は第1艦隊参謀長になり、約1年8ヶ月の間、この職にあったのです。 しかし、真之の大佐時代の勤務ぶりについては、真之の伝記にも一切記述が無く、 どうも、暗闇の中に姿を消してしまっていたと言われても仕方が無いようです。
2011年12月22日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、最悪のシナリオ)
単縦陣は、先頭艦(通常、旗艦になります)の跡を、 後続艦が金魚の糞のように追いかける陣形で、 単純明快ですから、艦隊のコントロールが容易であるという長所があります。 しかし、先頭艦が砲撃を受けて撃沈されたり航行不能になると、 艦隊そのものが崩壊する可能性が高いという短所も持ち合わせていました。 そこで、単縦陣同士の砲撃戦になると、 互いの先頭艦(旗艦)が狙われたのです。 日本海海戦でも連合艦隊旗艦「三笠」がバルチック艦隊からの砲撃を最も受けており、 「三笠」の砲術長であった「安保清種」は、次のように証言しています。 『東郷長官直卒の戦艦6隻(第1戦隊、実際は戦艦4隻、装甲巡洋艦2隻)、 上村長官隷下の出雲級6隻(第2戦隊)、合計12隻の主力艦が、 この日本海海戦で被った6インチ以上の敵弾は、合計103発を算するのでありますから、 この命中弾の4分の1が三笠一艦に命中しているわけであり、 しかも三笠のこの32発のうち25発、 即ち命中弾の約4分の3というものは 実に戦いが始まってから僅かに3分の間に命中したものであって 海戦の初期において三笠がいかに苦戦を致したかは これによってみても判るのであります。』 昨日書いたように、当時連合艦隊先任参謀であった「秋山真之」は、 明治37年8月10日の黄海海戦のデータなどを分析して、 この程度の被弾は予想していたことでしょう。 そして、「東郷ターン」の最悪のシナリオについても、思い描いていたはずです。 それは、第1戦隊が「東郷ターン」から「丁字戦法」へ移行する間に、 敵弾が旗艦「三笠」の露天艦橋を直撃し、 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将とその幕僚を吹き飛ばしてしまい、 これにより、第1戦隊は混乱の中で烏合と化し、 バルチック艦隊を取り逃がしてしまうというものです。 黄海海戦の「怪弾」の例もあるのですから、 連合艦隊参謀長「加藤友三郎」少将と真之の間で、 事前にその対応策の協議が行われていたはずです。 「東郷ターン」という歴史的瞬間に、 その発案者であろう真之が「三笠」の露天艦橋からその姿を消したのは、 リスク分散の為の加藤の指示であったのではないでしょうか。 その日、真之は「三笠」の露天艦橋に陣取り、 「敵前大回頭」を行える位置に「三笠」をコントロールしたのです。 この目的を達成したのは、明治38年5月27日14時2分で、 「東郷ターン」が開始される3分前でした。 自らの役割を終えた真之は、勝利への確信に満ち溢れていたはずで、 そして、静かに露天艦橋から立ち去ったのだと思います。
2011年12月21日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、大勝利)
日本海海戦は、緒戦の30分で、その大勢が決したとはいえ、この戦いが終結したのは、 翌日の明治38年5月28日になっていました。 バルチック艦隊は、戦艦8隻のうち、6隻が撃沈、2隻が捕獲され ウラジオストックにたどり着いたのは、巡洋艦1隻を含めてわずか4隻でした。 日本側の損害は水雷艇3隻のみという、まさに空前絶後の大勝利だったのです。 そして、その最大勝因は、 やはり第1戦隊による敵前大回頭(東郷ターン)であったでしょう。 戦後、日本海海戦時に連合艦隊先任参謀であった秋山真之は、次のように語っています。 『敵前における逐次回頭は、 假令(ケリョウ、たとえば)一時我が艦隊を不利の情勢に陥らしむるも、 数分時の難局をだに凌がば、 いわゆる丁字戦法の理法により先頭を圧迫し、 その教導艦(先頭の旗艦のこと)に我が全砲火を集中し得て、 逐次、その後続艦を撃破し、 最も有利に最も迅速にかつ最も決勝的に敵を圧服し得るべし。 かの敵と反航して戦機を逸し、容易にこれを回復し得ざりし苦き経験は、 我れこれを8月10日の海戦(黄海海戦のこと)において嘗めたり。 したがって、いかなる場合ありても断じて反航戦を避けざるべからず。 區々(クク、取るに足らない)たる一時の不利のごときは、また顧みるところに非ざるなり。』 真之は、明治37年8月10日の黄海海戦のデータなどを分析して、 敵前8,000mでの大回頭によりある程度の被弾はしても、 三笠が絶対に沈むことは無いという確信があったのだと思います。 しかし、この真之の戦策は、致命的な欠陥を秘めていたのです。
2011年12月20日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、緒戦の30分で勝敗は決定した)
第1戦隊が左に回頭を開始した時、 後続する第2戦隊の先頭艦「出雲」(第2艦隊旗艦)に乗艦していた 上村彦之丞司令長官の幕僚たちはさぞかし驚いたことでしょう。 第2艦隊先任参謀「佐藤鐡太郎」中佐は、 戦術家というよりむしろ戦史家であったとされていて、 その戦術は堅実で、受動的であったそうですから、 実戦的な戦術家の連合艦隊先任参謀「秋山真之」中佐の戦術などは、 理解できなかったというより、理解したくもなかったのかもしれません。 戦後、日本海海戦の大勝利の原因は何であったかと聞かれた佐藤は、 「6分が運で、残りの4分は人による運(バルチック艦隊よりも連合艦隊の方が砲撃が正確であったなど)」と答えていて、 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将の幕僚達の功績については、 これを認めるつもりは無かったようです。 次々に左に回頭していく第1戦隊の艦艇を目前にして、 「なんと、乱暴な事をする」そう思ったのは佐藤だけでは無かったでしょうが、 とりあえず、第2戦隊を第1戦隊に続いて左に回頭させるのか、 それとも直進してバルチック艦隊をやり過ごした後に、 その後を追うかを決めなければならなかった筈です。 この時、上村の幕僚たちは、「露探艦隊」と罵倒された忌まわしい過去を引きずっていたかもしれず、 直進して「逃げた」と言われたくはなかったでしょうから、 左に回頭する選択肢しか無かったのかもしれません。 14時15分、東郷の旗艦「三笠」の左回頭から10分遅れて、 上村の旗艦「出雲」も左への回頭を開始したのです。 戦艦「三笠」が砲撃を開始したのは14時10分で、 順次、後続の回頭を終了した艦艇がこれに続きました。 連合艦隊は、左に回頭している間は、 砲撃することもできず、非常に不利な状態でしたが、 回頭終了後は、最も有利な陣形(丁字戦法)で砲撃戦を行うことができたのです。 連合艦隊の砲火は、第1戦艦隊旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」と第2戦艦隊旗艦「オスリャービャ」に集中され、 約30分の砲撃戦で、この2艦は戦闘能力を喪失してしまいましたので、 日本海海戦の勝敗は、この30分間で決定したといわれています。(第2戦隊の装甲巡洋艦「浅間」が遅れているのは、舵機が被弾したためです。)
2011年12月19日
コメント(0)
-
ドラマ「坂の上の雲」第12回「敵艦見ゆ」
どうもこのドラマの視聴率が良く無いようです。 第1部の平均が17%、 第2部が13%、 今年になって、第3部の第10回が12.7%、前回は11%ですから、 一ケタ台は目前です。 どうして、視聴率が低いのかというと、面白くないからというのは明白でしょうし、 何故、面白くないかというと、いろいろな理由があるのでしょうけど、 今回の放送を見て思ったのは、時間が足りずに描き切れていないからではないかという気がしました。 前半の陸軍は、はしょってはしょりまくっているので、 原作を読んでいない人は、何がなんやら判らないでしょうし、 原作を読んでいる人は、あれも描かれていない、これも描かれていない、あそこがおかしい、ここがおかしい、ということになって、 フラストレーションがたまってしまうのではないでしょうか。 その点、海軍は、それなりの時間をかけて描かれていましたから、 あそこがおかしい、ここがおかしいという点があるかもしれませんが、 それなりに面白いと思いながら見ることができました。 90分の13回では無くて、大河ドラマのように45分の47回ぐらいで放送してもらった方が視聴率も稼げたのではないかと思うし、 見る方も幸せになれたのではないかという気がします。 ところで、バルチック艦隊が対馬を通るのか、津軽を通るのかは、 バルチック艦隊の航路を予想した地図を販売する出版会社もあったそうですから、 国民的な関心事であったわけです。 第2戦隊司令官「島村速雄」少将から 「長官は、バルチック艦隊がどの海峡を通って来るとお思いですか」 と聞かれて、連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将は、 「それは対馬海峡よ」 と言ったとされているわけです。 それで、司馬遼太郎は、 『世界の戦史に不動の位置を占めるにいたるのはこの一言によってであるかもしれない。』 と、書くのですけど、この言葉にはそのような価値は無かったように思います。 というのは、ドラマでも東郷が言っていたように、 東郷の幕僚である参謀長「加藤友三郎」少将と先任参謀「秋山真之」による計画に何ら変更は与えなかったからです。 東郷が世界の戦史に不動の位置を占めるに至ったのは、 やはり、戦時における自らの幕僚人事の断行であって、 島村を更迭して加藤を迎え入れたことに尽きるような気がします。 それほどまでに日本海海戦における加藤の役割は多分大きかったのだろうと思うのです。 「ミイラのようなしかもミイラほどの愛想のない」と評せられた加藤ですが、 内閣総理大臣の椅子に座るほどの才能と人望を持ちあわせていて、そのような加藤だからこそ、 天才参謀秋山真之の能力を最大限活用できたのではないでしょうか。
2011年12月18日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、第2艦隊)
これまで書いてきたように、 バルチック艦隊との距離が8,000mになった時に取舵にするという「東郷ターン」を知っていたのは、 戦艦「三笠」の乗員の中では、 「東郷平八郎」司令長官と「加藤友三郎」参謀長、 そして「秋山真之」先任参謀の3人であったと考えられます。 つまり、真之が脚本を書き、 加藤が演出し、 東郷が見事に演じきった訳で、 3人の絶妙な連携であったと言えるでしょう。 第1戦隊の先頭艦は、連合艦隊司令長官の旗艦「三笠」であり、 この戦艦の露天艦橋での緊迫した状況は、 「安保清種」砲術長という正直な証言者のおかげで、 何となく想像することができました。 それでは、第1戦隊の後に続く第2戦隊は、 いわゆる「東郷ターン」が行われていた時に、 どのような状況判断のもとに行動したのでしょうか。 第2戦隊の先頭艦は、 第2艦隊司令長官「上村彦之丞」中将の旗艦、装甲巡洋艦「出雲」でした。 この出雲には、上村の幕僚である参謀長「藤井較一(コウイチ)」大佐や 先任参謀「佐藤鐡太郎」中佐などが乗艦していたのです。 「東郷ターン」は、加藤と真之以外の東郷の幕僚にさえ知らされていなかったのですから、 上村の幕僚には誰一人知らされていなかったのだろうと思われます。 なぜなら、これまで書いたように、連合艦隊の戦策が藤井により少なくとも2回潰されていて、 もしも、「東郷ターン」を事前に知らせていたなら、 上村の幕僚は猛反対しただろうことは十分に想像されるからです。 12月13日に書いたように、 当時最新式の鋼板が使用され最も装甲が固いとされた戦艦「三笠」の艦長でさえ、 左への正面変換を反対したのです。 装甲巡洋艦とはいえ、しょせん巡洋艦です。 戦艦の装甲の厚さにはかなうはずもなく、 敵前での回頭時に、戦艦が敵の砲撃に耐えられたとしても、 装甲巡洋艦がこれに耐えれるとは限りません。 藤井に反対されることを危惧した加藤は、 これを秘匿して、 あたかも偶然行われたように装うとしたのではないでしょうか。 日本海海戦の30年後に座談会で、安保は、次のように回想を締めくくっているのです。 『この変換(東郷ターン)は、計画的に行われたものではなく、 今述べた如く、 混雑のうちに演ぜられた一つの偶然からの結果であることを申して置く次第である。』 第1戦隊の左回頭(取舵)を開始したのが、14時5分。 14時8分には、 バルチック艦隊旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」より最初の一弾が三笠に向けて発せられ、 バルチック艦隊の砲撃が、着弾による水柱のために、 三笠の艦影が消えるほど凄まじいものであったとき、 第2戦隊は、右に変針して、第1戦隊と距離を取ったのです。 これは、例えば、車を運転していたら、前の車が左折して事故を起こしたのを見て、 これを避けるために瞬時にハンドルを右に切った様なものであったのかもしれません。
2011年12月16日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、戦闘開始)
「東郷平八郎」司令長官の旗艦「三笠」が左に回頭を開始したのは、 14時5分とされています。 その後に続く第1戦隊の各艦(戦艦「敷島」、「富士」、「朝日」、装甲巡洋艦「春日」、「日進」)は、 三笠の行動にさぞかし驚いたことでしょう。 三笠の露天艦橋ですら、この回頭に対して、 若干の争議(「伊地知彦次郎」艦長の反問)があったくらいですから。 しかし、12時38分に「三笠」より第1戦隊に、 『旗艦の通跡を進め』 という信号旗が掲げられていましたから、 敷島以下の第1戦隊は、三笠の航跡に従ったのです。 三笠を先頭とした第1戦隊が、バルチック艦隊の前を無防備に横切っていた時、 司令長官「ロジェストヴェンスキー」中将旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」のセーラー達は、 色めきたったといいます。 「トーゴーは、気でも狂ったのか。 すぐに、敵艦隊を叩き潰してやる。」 どうやら、ロジェストヴェンスキーも同じ考えであったようで、 これを好機の到来と確信して、全艦隊に戦闘開始を命じたのです。 14時8分、「クニャージ・スヴォーロフ」より最初の一弾が三笠に向けて発せられ、 以下の艦船も砲撃を開始し、 その砲撃は、着弾による水柱のために、三笠の艦影が消えるほど凄まじいものであったといいます。 このようにして、「秋山真之」先任参謀の描いたシナリオ通りに 日本海海戦が開始されたのです。
2011年12月15日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、え、取舵になさるのですか?)
連合艦隊参謀長「加藤友三郎」少将が、三笠艦長「伊地知彦次郎」大佐に 『艦長、取舵一杯に』 と伝達したとき、 伊地知は、瞬時に 『え、取舵になさるのですか?』 と、反問したのです。 伊地知は、海軍兵学校は加藤と同期で、 切羽詰まったときにでも加藤に敬語を使うとは、 よほど律義な男であったのでしょう。 常備艦隊の参謀長職も歴任していますので、参謀職の大変さも良く理解していたでしょうし、 東郷の幕僚たちへの信頼もあったはずです。 だからこそ、先ほどまで、先任参謀「秋山真之」中佐に、 三笠のコントロールを任せきっていたのです。 しかし、バルチック艦隊との距離が、 8,000mをきったところでの取舵には、反対せざるを得ません。 なぜなら、三笠は取舵を取っている間、 無防備となり、バルチック艦隊に袋叩きにあう可能性があり、 最悪の場合、沈没してしまうかもしれないと思ったからです。 連合艦隊の旗艦の沈没は、この戦いの敗北であり、 その責任は一人、戦艦「三笠」の艦長が負わねばならないのです。 伊地知は激昂し、「それは、末代までの恥だ」と思ったとしたなら、 この奇策を考案したであろう真之に飛び掛かろうとしたかもしれません。 しかし、この露天艦橋から真之は消えていたのです。 それでも、伊地知は、加藤に対して、 このまま直進して、反航戦を仕掛けるべきだと訴えたのですが、 加藤は、冷酷にもそれを無視したのです。 三笠が取舵の動作を行っていないにもかかわらず、 『長官、取舵に致しました。』 と、「過去形」で復命し 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将は、その復命に対し静かにうなずいたのです。 それを見た伊地知は、もう腹をくくるしかありません。 東郷の旗艦「三笠」の艦首は左に向けて大角度変換を開始したのです。 戦後、伊地知は、 『いやああれは私は恥ずかしいような気がする。 あれは一遍やり過ごして、そうして、陣形を整えてやらんと負けるとおもったから、 一遍反航することを主張したが、 もし自分の意見が通ったら、恥ずかしい事になったのだ。』 と、語ったそうです。 それを聞いた当時第2艦隊先任参謀「佐藤鐡太郎」中佐は、 『私は武人としての名誉等のことを繕うという考えのない、 非常に高潔な偉いことだと思いました。』 と語っていて、 佐藤もたまには良いことを言うようです。
2011年12月13日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、東郷ターン)
明治38年5月27日、14時5分、 連合艦隊は、バルチック艦隊と反航する陣形になったのです。 このような状況を、戦艦「三笠」砲術長「安保清種」少佐が満足したのかというと、 決してそうではありませんでした。 安保は、4月12日の戦策、すなわち 『第1戦隊は、敵の第2順にある部隊の先頭を斜めに圧迫する如く敵の向首する方向に折れ、 勉めて併航戦を開始し、爾後戦闘を持続』する陣形で、 砲撃戦を行うことを想定していたからです。 したがって、安保は、「とりかじにしてくれ、とりかじにしてくれ」と念じていたのですが、 何時まで経っても取舵の号令が行われないのです。 もっとも、「何時まで経っても」といっても、1分か2分のことで、 それでも安保にしてみれば無限の時間が経過したように思えたのでしょう。 「いったい秋山(真之、先任参謀、中佐)は何を考えているのか」そう思って詰め寄ろうとした時、 この「三笠」をコントロールして居るはずの真之が露天艦橋から忽然と姿を消していることを知ったのです。 愕然としていると、距離測定儀を操作している「長谷川清」少尉が、 彼我艦隊の距離を8,500mであると報告しました。 しかし、その報告に東郷平八郎司令長官以下誰も反応しないのです。 安保は、やけになって 『もう8,500でありますが』 と、叫んだのです。 加藤友三郎参謀長は、 先ほどからちょこまかとうるさい安保を少し落ち着かせようと思ったのでしょうか。 『砲術長、君一つスワロフを測ってくれたまへ』 と言ったのです。 先程は、真之に「宜候」の号令をかけさせられ、今度は長谷川の代わりに距離測定をさせられるわけで、 こうなったら何でもやってやると、安保は距離測定儀を使って、 バルチック艦隊司令長官「ロジェストヴェンスキー」中将旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」との距離を測定し、 次のように大声で報告しました。 『もはや8,000になりました。』 そして、更に大きな声で 『どちらの側で戦をなさるのですか』 と叫んだのです。 これが正に砲術長としての切実なる疑問であったのでしょう。 その時、東郷はゆっくりと右手を挙げて、それを左に降ろしたのです。 この東郷の動作を後々まではっきりと覚えていたのは、 その時、ちょうど東郷の後ろにいた「今村信次郎」少尉候補生でした。 東郷の合図を確認した加藤は、いつもよりさらに甲高い声で、 『艦長、取舵一杯に』 と伝達したのです。 これが、後に世に言う「東郷ターン」の始まりでした。
2011年12月12日
コメント(0)
-
ドラマ「坂の上の雲」第11回「二〇三高地」
主役であるはずの秋山真之は、 相変わらず恰好が悪かったです。 上司に叱られるだけでなく、 部下にまでたしなめられるのですから。 次回第12回「敵艦見ゆ」の予告編では、 日本海海戦は、作戦参謀秋山真之の双肩にかかっていると言っていましたので、 次回からはカッコ良く描いてくれるのでしょうか。 なんとなく望み薄のような気がするのですけど。 第3軍参謀長「伊地知幸介」少将については、 原作の小説「坂の上の雲」で、 可哀そうなぐらいひどく描かれていましたが、 ドラマではそれほどでもなく、不愉快な気分にならなくてすみました。 二○三高地を奪取した翌日、乃木がここを巡視するのですが、 乃木の万感の想いとでもいうのでしょうか、 それが映像から伝わってくるような気がしました。 それにしても「二○三」を「爾霊山」とは、乃木もよく言ったものだと思います。 児玉源太郎は、相変わらず桃太郎侍でした。 二○三高地が堕ちて、ここと司令部を電話線で繋いだ時、 児玉が、「そこから旅順港は見えるか」と叫ぶと、 「見えます。まる見えであります。」という返事がかえってきました。 児玉は引き続き、 「直ちに旅順港内の敵艦を射撃し、これをことごとく撃沈せよ」 と命令するのです。 まあ、この場面が、11回の最大の見せ場だと思います。 しかし、どうも実際は二○三高地を奪取する前に、 旅順港内の艦隊のほとんどは大破、沈没していたらしいのです。 そうすると、児玉が「そこから旅順港は見えるか」と聞くと、 「見えます。ほとんどの艦が大破、着底しています。」と答えが帰ってきた筈で、 児玉は愕然として、ヒザから崩れ落ちたのではないでしょうか。
2011年12月11日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、おい秋山)
明治38年5月27日、13時55分、 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将の旗艦「三笠」から、 隷下の艦隊に向けて、次の信号旗が掲げられました。 『皇国の興廃はこの一戦にあり。 各員一層奮励努力せよ。』 ただ、各艦艇で働くセーラーたちにしてみれば、 「コウコクノコウハイ」と言われても何のことかも判りませんので、 士官たちが「この戦いに負けたら国が滅びる。とにかく一所懸命働け」 と意訳して伝えたそうです。 Z旗が掲げられると同時に、 先任参謀「秋山真之」中佐は、三笠の針路を西に変針することを命じました。 このままでは、連合艦隊は、バルチック艦隊から遠ざかってしまうだけでなく、 敵艦隊は連合艦隊の左舷を通り過ぎてしまうかも知れません。 砲術長「安保清種」少佐は、もうよほど切羽詰まって居たのでしょう。 ついに黙って居ることができなくなって、真之に声をかけたのです。 『おい、秋山』 安保は、海軍兵学校18期で、真之とは1期後輩となります。 また、この時点で安保は少佐ですから真之より位が低いのです。 それでも真之のことを呼び捨てにしたのですから、 怒り心頭であったのかもしれません。 『おい、秋山、どこまで、艦を廻そうというのだい。』 真之は振り返りながら、安保を見て、 『その辺で宜候(直進する)にしてくれ』 と指示したのです。 三笠艦長「伊地知彦次郎」大佐や航海長「布目満造」中佐の了承も得ずに、 砲術長が転舵の指示を出すなどあってはならないとの思いが一瞬安保の頭をよぎったのですが、 精神的に余裕を失っていたであろう安保は、 コンパスの側方に付いている「ラッパ管」に口を付けて、 『戻せヨーソロー、今の処』 とどなったのです。 いくら真之の指示とはいえ、安保自らの号令により、 連合艦隊は、南西方向に針路をとったのですから、 どうも不安で仕方がありません。 安保は真之に「今少しもとにもどさんでもよいか」とたずねたのですが、 真之は「いや、その辺で、まあ、よかろう」と答えたそうです。 これにより、連合艦隊のの航路はバルチック艦隊の航路と逆進、平行となったわけで、 真之は、通信担当の参謀「飯田久恒(ヒサツネ)」少佐のミスを、 約20分間で帳消しにすることに成功したのです。
2011年12月10日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、皇国の興廃はこの一戦にあり)
明治38年5月27日13時39分、 連合艦隊は、南西方向にバルチック艦隊を発見しました。 海面の濛気(モウキ、もうもうと立ちこめる霧やもや)は少し減って、 15km程度先まで目視で確認できるようになっていました。 露天艦橋から、最初に敵艦隊を確認したのは、 最新式の12倍双眼鏡を首に掛けていた東郷平八郎司令長官であったでしょう。 「ヘンナカタチダネ」 と、つぶやいたそうです。 バルチック艦隊は、雑然とした陣形で向ってきていて、 これから戦闘を開始しようとする艦隊とはとても思えなかったのでしょう。 しかし、東郷は、 「ヘンナイチダネ」 と、つぶやいたのかもしれません。 秋山真之先任参謀の戦策で示された彼我艦隊の位置関係と実際の位置関係にズレを認めて、 東郷はそのズレを気にしたのではないでしょうか。 プロの棋士は、他人の将棋でも、その盤面を一瞬見ただけで、 数十手先を読むことができるといいます。 この時の真之も、バルチック艦隊の出現位置を確認した瞬間に、 戦策とのズレに対する対応策(連合艦隊が進むべき航路)を見出していたのではないかという気がします。 13時40分、三笠は北西微北に変針しますが、 ラッパ管に向って「おもかじ」の号令をかけたのは、 真之であったのではないでしょうか。 この「三笠」の露天艦橋にあって、 極度の緊張に震えていたのは砲術長の「安保清種」少佐であったでしょう。 これまでの砲撃戦は、それぞれの砲の指揮官が、照準を合わせて砲撃していたのですが、 この戦いでは、砲術長が艦橋から一元的に砲を指揮するという「射撃指揮法」が導入されていたからです。 三笠がどれほどの功績を挙げることができるのかは、 安保の射撃指揮に委ねられていたと言えます。 真之の戦策を知っているのは、東郷と加藤友三郎参謀長だけのはずです。 安保は、真之の戦策を知らされていないのです。 この「おもかじ」の意味を必死で探ろうとしても理解できず、 なにより、ラインの長でも無いスタッフの真之が、 連合艦隊をコントロールしている事の不思議。 露天艦橋を見渡すと、 東郷は、身動きもせず敵艦隊を凝視したままです。 加藤と伊地知彦次郎艦長は何かしきりに話をしています。 布目満造航海長は、航海士と共に彼我艦隊の位置を海図に入れるのに熱中しているようです。 どうやら、真之の「おもかじ」の号令をとがめる者は、誰一人いないのです。 その時、真之は東郷に近づき、 『先刻の信号(Z旗のこと)整えり。直ちに掲揚すべきか。』 と許可を願い、 東郷は静かにうなずいたのです。 13時55分、東郷は、隷下の艦隊に次の信号を発令しました。 『皇国の興廃はこの一戦にあり。 各員一層奮励努力せよ。』
2011年12月09日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、東郷は老人じゃ)
バルチック艦隊の位置を予測して(この予測は間違っていたのですが)、 針路を変更したのが13時31分(明治38年5月27日)で、 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将の旗艦「三笠」が バルチック艦隊を発見したのは13時39分でした。 この8分間は、 東郷の司令部もそれまでの喧騒がうそのように、 静かな時間が流れていたのではないでしょうか。 この時、「三笠」の露天艦橋では、東郷と参謀長「加藤友三郎」少将との間で、 次のようなやり取りがあったようです。 『司令塔の中にお入り願いたい。 今日は最も大事な戦いでありますから、 ぜひとも司令塔の中から指揮されるように願いたい。』 『東郷は老人じゃ。 今日はこの位置を離れない。 貴方がた若い者こそ将来ご奉公の前途が大切じゃから、貴方がたはお入りなさい。』 明治37年8月10日の黄海海戦では、 旅順艦隊(ロシア太平洋艦隊)旗艦「ツェザレーヴィチ」の艦橋に連合艦隊が放った砲弾が爆中し、 司令長官「ヴィトゲフト」少将とその幕僚を吹き飛ばしてしまったのです。 指揮官を失った旅順艦隊は迷走し、 戦略目的である「旅順艦隊のウラジオストックへの回航」を達成することができませんでした。 これを教訓とするなら、 砲撃戦を行うにあたり、司令長官が露天艦橋に立って指揮をするなど、どうしても避けたいところですが、 東郷はすでに老人で頑固であったでしょうから、 加藤も東郷を司令塔に入れることを早々と諦めたようです。 その後の加藤の指示について、当時の連合艦隊参謀「飯田久恒(ヒサツネ)」少佐は、 後に次のように回想しています。 『最上艦橋には、長官と自分と秋山(真之、先任参謀、中佐)といるから、 副官の永田(泰次郎、中佐)と飯田と清河(純一、大尉)参謀はその次の甲板におれ。 一弾のために怪我をしてはならぬから、 なるべく分かれ分かれにして働け。』 この飯田の回想は、当時戦艦「三笠」の砲術長「安保清種」少佐の回想とは少し食い違いがあるのです。 『結局、三笠の最上艦橋には東郷司令長官と加藤参謀長がおられ、 それ以外の幕僚は戦闘中は司令塔や、上甲板以下の防御部内に別々に位置を占め、 時々戦況に応じて艦橋に顔を出すというわけでした。』 飯田は、真之は露天艦橋に居たと言っているし、安保は居なかったと言っているわけで、 何故、このような食い違いが生じたのかということについては、 また次の機会に書きたいと思います。
2011年12月08日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、つまりどこだ)
明治38年5月27日13時過ぎ、 連合艦隊は、西に針路を取り航行していました。 連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将の旗艦「三笠」は、 まだバルチック艦隊を目視で確認できていません。 12月6日に書いたように、 連合艦隊は、下図のような位置関係で、バルチック艦隊と対峙する必要があって、 そのためには、敵艦隊の位置を正確に知る必要があったのです。 バルチック艦隊の情報は、味方艦から次々と入ってきており、 北東に針路を取って直進して向ってきている筈でした。 情報の発信源は、 第3艦隊司令長官「片岡七郎」中将旗艦「厳島」、 第1艦隊第1戦隊司令官「出羽重遠」中将旗艦「笠直(カサギ)」 第3艦隊第6戦隊所属の防護巡洋艦「和泉」 の3艦でした。 しかし、情報は錯そうし、バルチック艦隊の予想ルートに食い違いが生じてしまい、 3つの予想ルート(厳島ルート、笠置ルート、和泉ルート)が存在してしまったのです。 連合艦隊とバルチック艦隊の距離は、刻一刻と短くなっていて、 今すぐにでもこれら3つのルートからより正しいルートを選択し、 それに合わせて、連合艦隊の針路を修正しなければなりません。 この時、連合艦隊の司令部は極度の緊張状態にあったでしょう。 参謀長の加藤友三郎少将や、先任参謀の秋山真之中佐から、 『つまり(バルチック艦隊は)どこだ』 と、問い詰められ、舞い上がってしまったのは、 無線担当の参謀「飯田久恒(ヒサツネ)」少佐でした。 飯田は、正解の和泉ルートでは無く、厳島ルートを選択してしまったのです。 その理由は、情報源である3艦の中では、厳島に最も位の高い将官が乗艦していたからというものでした。 13時31分、戦艦「三笠」は、南南西に針路を変更しました。 その8分後、三笠はバルチック艦隊を発見することになります。
2011年12月07日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、どこまでも科学的組織的な作戦)
連合艦隊先任参謀「秋山真之」中佐の対バルチック艦隊用の戦策は、 11月25日に書いたように、 『先頭を斜めに圧迫する如く敵の向首する方向に折れ、 勉めて併航戦を開始し、爾後戦闘を持続』 することでした。 11月13日と14日に書いたように、 この陣形に持ち込むことができれば、連合艦隊は圧倒的に有利になるのです。 (図のB艦隊が連合艦隊、A艦隊がバルチック艦隊) しかし、バルチック艦隊は、 連合艦隊と雌雄を決するために日本海に乗り込んでくるのではなくて、 取りあえずウラジオストックへの回航を望んでいることでしょう。 旅順艦隊(ロシア太平洋艦隊)との海戦(黄海海戦)を経験した真之は、 この事を当然予想していました。 したがって、なまなかな方法では、 この陣形に持ち込むことができないことも、判っていた筈です。 そこで、真之は、その前段として、 下図のような陣形に持ち込むことを考えたのでしょう。 この場合、もし、連合艦隊が直進したとしたなら、 バルチック艦隊も直進した筈です。 なぜなら、反航戦になりますから、 砲撃可能な時間は限られてしまうからです。 バルチック艦隊は、ある程度の損害は生じるでしょうが、 ひたすらウラジオストックへ針路を取ればよい事になります。 距離Aが10,000mを超えたところで、 連合艦隊が左に転舵した場合、 この距離では、砲撃してもまず当たることはありません。 バルチック艦隊は、 連合艦隊が同航戦に持ち込もうとしていることを察知して、 例えば、左に回頭してこれを避けるかもしれません。 しかし、この距離Aが8,000mであったらどうでしょう。 既に砲撃可能な距離になっています。 連合艦隊は、回頭している間、 速度は出ませんし、砲撃もできず、ほとんど無防備なのです。 バルチック艦隊は、針路をそのままにして、 回頭している連合艦隊の艦艇に砲火を集中する筈です。 ただ、当時、この距離での艦砲射撃は当てることはできても、 当たる確率は極めて低かったのです。 つまり、連合艦隊は相当な打撃を被るでしょうが、 反撃する余力を残したまま回頭を完了し、 最初の図の陣形、つまり丁字戦法に持ち込むことができるのす。 日本海海戦の完璧な勝利の要因として、あまりにも有名な「東郷ターン」を評して、 当時連合艦隊参謀「飯田久恒(ヒサツネ)」少佐は、後に、 『あの場合、ああいうこと(東郷ターン、または大回頭、または大角度の正面変換)をされたことは、 東郷長官の直感というより外はないだろうと思います。』 と、語っているのですが、少しの説得力があるはずもありません。 真之の伝記の言葉を借りれば 『将軍(真之のこと)の作戦についてのみいえば、 それは決して投機的でなく、どこまでも科学的組織的であったのだ。』 ということなのだと思うのです。 話を元に戻すと、 連合艦隊は、二番目の図のような陣形で、 バルチック艦隊と相まみえれば良かったのですが、 この重要な局面で、 通信担当の飯田参謀が致命的なミスを犯してしまうのです。
2011年12月06日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、奇襲隊列を解く)
明治38年5月27日。 この日は天気は晴朗でしたが、 海面に濛気(モウキ、もうもうと立ちこめる霧やもや)があって、 10km先が目視で何とか確認できる程度でした。 風力は5から7(8mから17m/秒)。 波濤は砕けて白い泡が風に吹き流されていたことでしょう。 8時50分、連合艦隊旗艦「三笠」のマストに、 水雷艇隊に向けて次の内容を示す信号旗が掲げられました。 『航海に困難ならば三浦湾に避け、時機を見て艦隊に合すべし』 この波濤の激しさから、 100トンほどの小船に過ぎない水雷艇隊の航海は困難と判断されたための処置でした。 しかし、秋山真之先任参謀の考案した秘密兵器「連繋水雷」作戦を実行する 「奇襲隊」(装甲巡洋艦「浅間」(9,700トン)、第1駆逐隊(300トンクラス)、第9水雷艇隊(100トンクラス))は、 第1戦隊(三笠以下、連合艦隊の主力)の後方に位置しており、 大波に翻弄されながらもなんとか本隊に付いて航行していたのです。 この「奇襲隊」の戦策が発令されたのは、 10日前の5月17日のことでした。 この時、第2艦隊参謀長藤井較一(コウイチ)大佐は、 連合艦隊参謀長加藤友三郎少将にこの戦策の撤回を求めたのです。 第2艦隊の主力である6隻の装甲巡洋艦の内の1隻を奇襲作戦に引き抜かれるので、 第2艦隊の戦力が低下してしまうことを懸念したのです。 第2艦隊単独で戦った蔚山沖(ウルサンオキ)海戦(明治37年8月14日)では、 装甲巡洋艦6隻のうち2隻を引き抜かれており、 藤井は、それが原因でウラジオストック艦隊を全滅できなかったと考えていたのかもしれません。 藤井は、4月21日に発令された戦策も撤回要求し、 加藤はこれを認めていたのです。 多分、第1艦隊と第2艦隊は抜き差しならない状況になっていて、 その融和に努める加藤は、 藤井からの撤回要求を認めざるを得なかったのだと思います。 5月17日の戦策撤回要求について、 加藤は藤井に次のように語ったと伝えられています。 「4月21日の戦策撤回についても東郷司令長官の許可をもらうのにさんざん苦労した。 5月17日の戦策まで東郷司令長官に撤回を願い出るのはいささか困難である。 そこで、この戦策は実行しないと約束するので、それで引き下がってもらいたい。」 藤井は、海軍兵学校の同期生であり、 自らの前任者(前第2艦隊参謀長)でもある加藤をこれ以上追い込むことを嫌ったのか、 加藤との黙約を信じて引き下がったそうです。 「いかに紛糾、錯雑せる案件に処するも、熱せず、惑わず、 著々措弁(ソベン、物事をうまく取りはからい、処置すること)し去ること あたかも節々、刃を迎えて断つがごとし」 と評されるほど明晰、冷酷な頭脳の持ち主であった加藤は、 この奇襲作戦を大局的な見地から実行するべきであると決意していたにちがいないと思うのです。 戦策の考案者である真之と真之の良き理解者である浅間艦長「八代六郎」大佐以外には、 実行の決意を秘匿して、加藤はバルチック艦隊との決戦に臨んだものと思われます。 しかし、波濤は時がたつにつれ更に強くなり、これ以上の水雷艇隊の帯同も、 連繋水雷の敷設も困難であると判断されたようです。 10時5分、「三笠」より奇襲隊に向けて次の無線電信が発せられました。 『奇襲隊列を解く、所属隊に帰り列に入る。』 八代は地団駄を踏んで悔しがり、 藤井はこの処置を黙約通りと冷静に受け止めたことでしょう。 加藤と真之といえば、これを悔しがる暇は無かったはずです。 バルチック艦隊は目前に迫っており、最後の秘策を実行する時が、刻一刻と迫っていたからです。
2011年12月05日
コメント(1)
-
ドラマ「坂の上の雲」第10回「旅順総攻撃」
ついに第3部が始まりました。 もう一度見ると、感想も変わるのかもしれませんが、 ファーストインプレッションを書いておきます。 36歳になって既におじさんの域に達した真之が、 三笠艦上でセーラー達の見ている前で、背負い投げされたのですから、 痛々しいというか、真之の描き方が可哀そう過ぎるんじゃないかと思いました。 不謹慎かもしれませんが、ドラマ「坂の上の雲」に一番期待しているのは、艦隊戦の映像です。 しかし、今回は、マカロフの爆死、戦艦「初瀬」、「八島」の触雷、沈没のシーンは全く描かれず、 日露海戦前半戦の最大の山場である「黄海海戦」の映像も全く無かったのですから、 やっぱり残念としか言いようがありません。 この回あたりの主役は、どうしても児玉源太郎(満州軍総参謀長)になるのでしょうが、 大山巌(イワオ、満州軍総司令官)も乃木希典(第3軍司令官)も伊地知幸介(第3軍参謀長)もいい感じなのに、 児玉源太郎だけはどうしても児玉に見えません。 児玉が怒りだすシーンでは、頭の中でいくら振り払っても 「桃太郎侍」 が出てきて困りました。 戦争のシーンばかりで、 いくらやっても旅順は落ちないし、兵士が死んでいくシーンがどうしても多くなり、 1時間半を通して殺伐とした雰囲気の中で、 秋山家の団らんのシーンだけが一息つけるところです。 このシーンで使われた「秋山好古」の手紙を、 少し長いですが書きだしておきます。 『別に用もないから鉛筆で面白い話しを始めましょうね。 お祖母さんの心意気 戦さなどやめて 平和に暮らしたい (1)戦さは平和の為にせよ お母さんの心配 さよふけてもはや 大酒はお身の毒 (2)酒を慎み身を大切に 伯父さん(真之のこと)の気楽 世を捨てて日露戦争 何処にやら (3)虚心平気で進むべし よし子(長女)の優しさ 父さんの戦さがへりが 待ち遠しい (4)早く帰りを待ち居れど 賢子(次女)の落付(オチツキ) 遅くても勝って下さい お父さん (5)必ず勝って帰らんせ 信好(長男)の健気さ 父さんが負けたら わしが仇うち (6)負けてもかまわぬ何処までも 勝子の無心 この戦さきっと勝子と 楽しめり (7)勝子の名をば懐に おっと忘れた季子(真之の妻)に豊子 戦場は若い士官の懲役場 女狂いの心配もなし 婆やの苦労 正岡が居るから 内は大丈夫』
2011年12月04日
コメント(1)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、本日天気晴朗なれども浪高し)
明治38年5月27日早朝、 連合艦隊の主力は、朝鮮半島の南端、加徳水道に碇泊していました。 5時5分、第3艦隊からの電報「敵艦隊出現」を受け、 第2艦隊司令長官上村彦之丞中将は、 加徳水道に碇泊している総艦艇に「出港用意、総缶点火」を命じました。 この時、連合艦隊司令長官「東郷平八郎」大将の旗艦「三笠」は、 独り鎮海湾に停泊していました。 それは、大本営との通信の便宜のためであったのでしょうが、 大日本帝国の存亡をかけた決戦の前に、独り静かに佇む「三笠」の情景は、 ロマン性を感じざるをえません。 三笠は大本営(軍令部)に対し、次の電文を打電し出港しました。 『敵艦見ゆとの警報に接し、 連合艦隊は直ちに出動し之を撃滅せんとす、 本日天気晴朗なれども浪高し』 この電文こそは、連合艦隊先任参謀「秋山真之」中佐の名を広く世に知らしめ、 秋山文学とさえ称賛されたのですが、 実は暗号であったとする説もあるようです。 つまり、対バルチック艦隊の秘策は、 11月19日と20日に書いた連繋水雷作戦であって、 「波高し」の電文により作戦の中止の可能性を軍令部に伝えたというのです。 波が高く海が荒れると、 これを敷設する水雷艇は100トン程度の小船であったため、目的地に回航することは困難ですし、 連繋水雷自体も本来の機能を発揮することが困難だからです。 しかし、この暗号説は、ちょっと無いのではないかと思うのです。 というのは、 東京中央気象台からの「本日天気晴朗なるも浪高かるべし」という天気予報の電文を見て、 真之が「本日天気晴朗なれども浪高し」を付けくわえたとされているからです。 つまり、東京中央気象台の天気予報は、 当然の如く軍令部にも届けられていたでしょうから、 連合艦隊からの電文を待つまでもなく、 軍令部の参謀たちは当日波が高くなることを知っていたと考えるられるからです。 それでは、真之は何故この文章を付けくわえたのでしょうか。 真之の伊予松山藩から受け継がれた文学的素養に関係している様にも思いますし、 その時の真之の心情が、その日の天気予報の電文とシンクロして、 決戦前の荒ぶる気性が、それを付けくわえさせたのではないかという気がします。 6時34分、連合艦隊旗艦「三笠」は、連合艦隊艦艇と合流し、総艦艇に 「序列に従い各隊揚錨出港せよ、通常速力15節(15ノット、28km/時)となせ」 と命令し、艦隊の先頭に占位したのです。
2011年12月03日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、敵第2艦隊見ゆ)
明治38年5月26日の明け方、 軍令部次長「伊集院五郎」中将より連合艦隊に 「5月25日14時30分、呉淞(ウースン、上海の外港)に、 ロシア帝国義勇艦隊4隻、運送船3隻が入港したとの報告が上海より入電した」 との、電報が入りました。 この情報により、バルチック艦隊はまだ南方にあり、 そこで輸送船を切り離したということは、 最短距離の対馬ルートを選択した可能性が高いことが明らかとなったのです。 連合艦隊は、26日正午に予定していた密封命令の開封を延期し、 新たな情報が得られるまで、朝鮮半島南岸付近に留まることとしました。 そして運命の5月27日。 4時50分、仮装巡洋艦「信濃丸」より、 「203地点、敵第2艦隊見ゆ」 との電文が発せられたのです。 当時の状況を、安保清種(アボ、キヨカズ、当時「三笠」砲術長、少佐)は次のように回想しています。 『敵の艦隊が北廻りして津軽海峡に現れるのか、 それとも、そのまま朝鮮海峡に現れるのか判らぬので、 我が連合艦隊は、これを迎え撃つべく、 いずれの方に待ちかまえておったが良いかについて、 東郷長官はじめ非常に思い悩んだものであって、 この一両日は正にその心配の絶頂にあったのである。 ところが今、敵艦隊がこの朝鮮海峡に現れ、 確実に、ここで、彼我艦隊の決戦が試み得られるというのであるから、 喜びに耐えないのも無理は無いのである。 ことに、秋山参謀の如きは、その点でもっとも心配された一人であり、実際、喜色満面 「占めた、占めた」 と言って、三笠の後甲板で、こ踊りして居られたほどであった。』
2011年12月02日
コメント(0)
-
秋山真之伝記(日本海海戦、訛傳)
バルチック艦隊が対馬海峡から来るのか、津軽海峡から来るのかという問題は、 日本の存亡にもかかわる大問題でしたから、 連合艦隊司令部も大本営(軍令部)の意向を重視、尊重したはずです。 したがって、明治38年5月23日(24日と書いてある本もあります)に、 連合艦隊司令長官東郷平八郎大将は、軍令部長伊東祐亨(スケユキ)大将宛て、 『相当の時機まで敵を見ないときは、北海方面に迂回したものと判断し、連合艦隊も津軽方面に移動す』 と、打電したのです(第1電)。 これは、とりあえず連合艦隊司令部の方針を示しておけば、軍令部のほうに異論があれば、 何か言って来るだろうという判断であったでしょう。 (ちなみに、この電報の発信を、東郷本人が知らなかったという話が、まことしやかに伝わっていて、 それでは、誰がこんな電報を勝手に打ったのだということになって、 それは、先任参謀の秋山真之だろうというのは、 あまりに出来の悪い作り話ではないでしょうか。) 5月25日、戦艦「三笠」艦上に、第2艦隊司令長官以下各司令官が集めて、 連合艦隊の方針が示されようとする時になっても、軍令部からの返電は無かったのです。 そこで、連合艦隊の最終方針を軍令部宛てに、 『明日正午まで、当方面に敵影を見ざれば、当隊は明夕刻より北海方面に移動す』 と、打電しました。 この後、伊東軍令部長より東郷長官宛てに、第1電の返信がやっと届いたのです。 『艦隊の移動については特に慎重を希望す』 軍令部は、1日も2日もかけて、いったい何をやっていたのか、 結局のところ、全ての責任を現場に押し付けたと言われても仕方のない返信でした。 まあ、本店と支店の関係は、何時の時代もどのような社会でも同じようなものかもしれません。 ところで、連合艦隊の司令部は、25日中に津軽に向けて出発するつもりであったのに、 第2艦隊参謀長藤井較一(コウイチ)大佐と第2戦隊司令官島村速雄少将が、 バルチック艦隊の対馬通過説を強く主張し、出発が26日に延期されたという説があるのですが、 それは、ちょっと無いのではないかという気がします。 というのは、連合艦隊司令部は、軍令部の意向を尊重していた筈ですから、 最終方針を軍令部に示してから実行するまでに、 1日程度の猶予時間(連合艦隊の方針を軍令部が反対であるなら、その旨を連合艦隊に伝えるために要する時間) を予め見込んでいただろうと思うからです。 電波は直ぐに飛んだとしても、当時は電報を打つ、受けるに時間を要したでしょうし、 軍令部からの返電には、最低でも伊東軍令部長の決裁と山本権兵衛海軍大臣の合議が必要であったでしょうし、 返信するのにそれなりの時間を要することは、 加藤友三郎参謀長も真之も織り込み済みであったことでしょう。 つまり、東郷の司令部が25日に最終電を打って、 当日出発を予め計画していたというのは考えにくく、 やはり、最初から25日に最終電を打ち、 26日に出発することを計画していた考えるほうが自然だと思うのです。 水野広徳は、日露戦争後、戦史編纂部にいたので、 日本海海戦のことを何でもかんでも知っていた筈であり、 真之の伝記に、この問題について、次のように書いています。 『世間では往往この万一の場合に処する二段の備えを立てた点を誤解して、 連合艦隊司令部は敵は津軽に来るものと判断したと決めてしまい、 これを、かれこれ言う説が無いでもない。 はなはだしいのは、司令部の計画を止める提案をした人があるなどの話も聞くが、これらは全て誤聞であって、 戦略研究がその度を超え、詮議し過ぎて、却って訛傳(カデン、誤伝)となったのである。』 水野は、誤伝の生じた理由を「戦略研究が度を超えて詮議し過ぎたため」と書いていますが、 さすがに発禁処分になっても困るので正直なところが書けなかったのではないでしょうか。 全ての功績を東郷に帰そうとする動き、 露探艦隊と言われた第2艦隊の名誉回復への動き、 東郷の司令部、特に秋山真之の輝かしい功績に対する妬み、 などが、ごちゃ混ぜになって、このような誤伝が生まれたのではないかという気がします。
2011年12月01日
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…
- (2024-10-04 21:52:45)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【くびの痛み・頸椎症の長年の痛…
- (2025-03-07 00:00:46)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- チェンマイに佇む男達 寺本悠介の場…
- (2025-03-02 12:39:36)
-