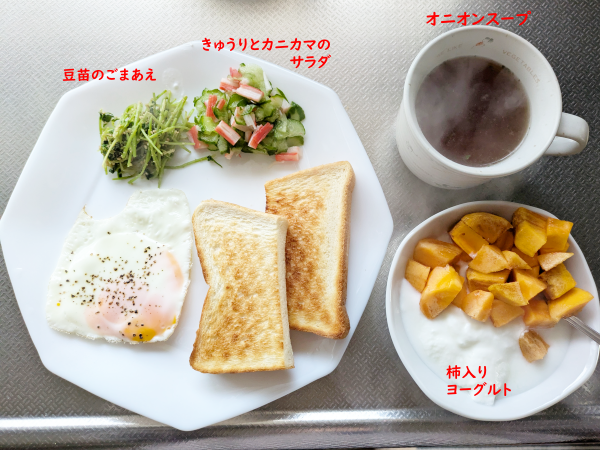2005年11月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
「関東煮き」
「かんとうだき」とは何でしょう。厚揚げ、こんにゃく、ねり製品(竹輪や、魚のすり身を揚げたもの=てんぷら)、大根、じゃがいもなどを、醤油味で煮込んだものを言います。「関東風のおでん」ですが、発祥は関東ではなく、かつての貿易港であった大阪の堺で、中国人が食べていた海鮮煮込みが広東煮き(カントンだき)と呼ばれ、「カントだき」と呼ばれているうちに「関東」と書かれるようになったという説があります。「おでん」は田楽のことで、関西では茹でたり焼いたりした豆腐やこんにゃくに味噌を塗ったものを指します。関東煮きに限らず鍋物一般に、具材のハーモニーが重要だと言えます。わが家の関東煮きは、調味料は醤油と酒だけで、だしは使いません。ねり製品は必ず使うので、それを煮込んでいるうちにいいだしが出てくるのです。野菜の中では大根が“名役者”です。厚揚げ、てんぷら(牛蒡天、平天、三色天など)、それに昔よく使っていたコロ(鯨の脂身)など、油ものも必要です。昆布巻きや結び昆布も、あればいいでしょう。これらに比べれば、茹で卵、こんにゃく、(煮崩れる前の)じゃがいもなどは、煮汁に助けられている感がありますね。うちの子たちは餅入り巾着がお気に入りで、わたしはヒロウス(ヒリョーズ=飛竜頭、がんもどき。ポルトガル語のフィリョス<油で揚げた食品>が語源)です。餅キンはあまり長く煮込むと溶け出してしまいますが、他のものは何度も煮き直したほうが、よく味がしみますね。なお、鍋いっぱい食べ尽くして、煮汁が残ったら、じゃがいもの煮崩れを取り除いた上澄みを、肉じゃがの煮汁にでも転用してみてください。予期せぬサカナ系のだしが出ていますから。
2005年11月23日
コメント(22)
-
「まんばのけんちゃん」
万葉というのは高菜のような葉物野菜、「けんちゃん」は巻繊(けんちん)で豆腐を使った油炒め、という意味の、香川県の郷土料理です。巻繊はもともと、細切りにした根菜類を春巻のように包んだものだそうですが、それが「けんちん汁」といったように(豆腐を使った)精進料理の代名詞のように使われ、さらに現代の「けんちん汁」には肉類や魚のダシも入るようです。「けんちゃん」でもいりこダシを使うそうですが、精進の巻繊でないからいいのかな(^_^;)?高菜のような「万葉」が手に入らなくても、タアサイなどで作ってみましょう。材料:タアサイ2~3把、もめん豆腐半丁、油、醤油(、ちりめんじゃこ)。手順:1)豆腐はラップをせずに電子レンジに2~3分かける(水切り)。 2)タアサイは水洗いして葉と軸に分け、軸は3cmほどに切って、まず 油で炒める。3)続いて葉と、ダシ代わりのちりめんじゃこ少量を加え、 炒める。4)そこへ豆腐を加えて崩しながら炒め、醤油で味付けする。 5)水気を少し飛ばして仕上げる。お好みでこしょう少々を振ってもよい。豆腐と一緒に炒めるというのですぐに思いついたのは、沖縄のチャンプルーです。チャンプルーにもかつお節やツナが入ることがあります。でも油と豆腐という組み合わせですから、きっとダシ無しでも美味しいと思います。湯がいたほうれん草や菊菜(春菊)でもできそうですが、タアサイだとアク抜きの手間が要りません。醤油を入れた段階で、どうしても水気が多く出てしまいますが、なるべくシンプルに仕上げるのがこの料理の持ち味なので、水溶きかたくり粉などは入れないほうがいいでしょう。入れても、別の料理としてはOKですが。
2005年11月07日
コメント(4)
-
「しみコンニャク」
豆腐を凍らせて、戻したものを高野豆腐といいます。高野山の僧坊にちなんだ精進料理なのかもしれませんが、別名凍り豆腐、凍み豆腐(しみどうふ)とも呼びます。で、しみコンニャクです。高野豆腐と同様、元のこんにゃくとは少し違った食感のものになります。例えて言えば、戻す前の寒天というか、目の粗いスポンジというか……。そんなですから、薄切りまたは細切りにして使うのがいいでしょう。醤油等の味しみも今ひとつで、食感を楽しむ食材です。こんにゃく1丁は、薄切りにして水に放し、引き上げて軽く水気を切ります。これを冷凍庫に入る大きさの皿に(できれば重ならないように)広げて並べ、5~10分置きます。その後、皿を傾けて、出てきた水を捨て、凍らせます。真っ白に凍ればOK。短冊状の「しみこんにゃく」ができました。薄く切って作ると繊細な味わいになりますが、分厚いと噛むのが大変かもしれません。自然解凍または水で戻したうえで、三度豆と細切りの平天(薩摩揚げ)と一緒に煮付けてもいいですし、小さな色紙に切って煮豆にまぜてもいいでしょう。細く切って、にんじんと薄揚げのきんぴらにも。とはいえ、しみこんにゃくにしてから切るよりも、はじめから使い方を決めて、その形に切ってから凍らせたほうが効率的です。わが家はハプニングから生まれ、その後何回か人為的に作りましたが、いい料理法を思いつきましたら教えてくだされば幸いです。
2005年11月04日
コメント(2)
全3件 (3件中 1-3件目)
1