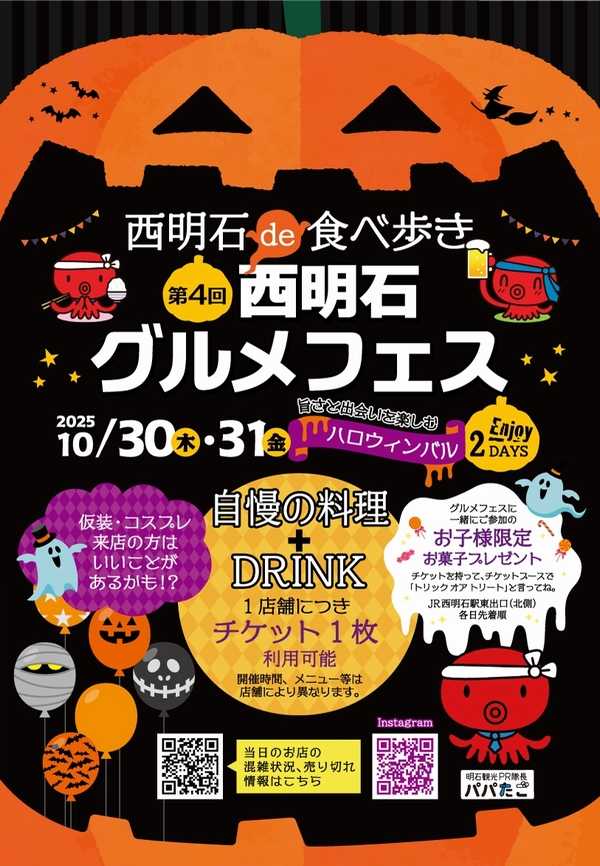2013年01月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
「犬めし」
わたしが小さい頃、すき焼きの残りの汁で父が作って食べていたものです。いや、作るのは母ですが、できあがりにソースを掛けて、父だけが美味しそうに食べていたのを、わたしは羨ましそうに見ていました。そしてついに、実現です(^o^!)。…昔は、すき焼きの汁や若干の具が残ると、すき焼き鍋のままひと晩おいておき、翌日の昼に温め直して食べました。今よりも冬は寒く、しかも台所は石敷きの土間でしたから、冷蔵庫に入れる必要もなかったのでしょう。すき焼きの具は、牛肉のほかは長ねぎ、糸ごんにゃく、麸ぐらいなものです。そのうち、犬めしには麸は余分だったらしく、温め直したものを時々おかずにもらっていました。それ以外の具と汁に、冷やごはん2膳分を入れ、しばらく煮込んで、できあがり。甘辛い味付き飯ですが、父はソースを掛けて味を引き締めていたようです。残り物ながら、肉とねぎのエキスが凝縮されており、さぞ美味しかったでしょう。犬めしという命名は、きっと父の照れ隠しですね。きょう、わたしも作って食べました。実は、ゆうべのすき焼きは、あまり残らなかったのですが、それでも一部を汁ごと卵でとじて弁当(500ccタッパーに入れたすき焼き弁当)に。残りが犬めし用でした。この犬めしを食べていて、そうそう、昔は、すき焼きなど味の濃いものを食べたあとは、父はよく砂糖湯(さとゆ)を飲んでいたなあ、と思い出しました。しゃっくりに効くという砂糖水ではなく、砂糖湯です。甘いコーヒーなどでないあたりが、時代ですね。
2013年01月28日
コメント(4)
-
「続・すき焼き」
先日の初湯豆腐鍋につづき、きょうはわが家での、食卓に置いたガスコンロでいただく初すき焼きでした。実はきのう、和牛もも切り落としの半額のパックが2つも出ており(計340g)、きょうも半額ではないものの、薄切り200gのパックを購入、さらに冷凍庫に使い残しの薄切り牛が80g程度あったので、4人家族でそこそこ満足できる量の肉が確保できたのが最大の理由です。加えて言うならば、月曜に下の子が私立中学に合格した、ということもありました。大きな鍋に油を熱し(ごま油も少々加え)、強火のまま牛肉を1枚ずつ広げて入れ、炒めていきます。今回は2/3ほどの肉を炒め(残り1/3は追加用にとっておき)、砂糖と醤油を多めに加えて絡め、しっかり味をつけました。そこへ長ねぎの斜め切り3本分と、捌いたしめじ1株を加え、砂糖、醤油、お湯200ccを加えて、ねぎがしんなりするまで煮込みます。そしてやおら食卓へ。残りの肉、ねぎ、湯がいた糸ごんにゃく、戻した麸、捌いたえのきだけも運びます。あとは火加減に注意しながら、ぐつぐつ煮込まれた肉や野菜を、溶き卵につけて食べていきます。鍋の中身が減れば、次々と具を加えて煮込んでいき、最後はねぎときのこが少し残っただけでした。よく食べました。こんにゃくは(使いませんでしたが豆腐も同様)、肉を硬くする成分が入っているので、あとのほうで加えました。わたしが小さいころは、しめじもえのきだけも、今のように普通にはありませんでしたが、ほかは昔ながらのわが家のすき焼きでした。
2013年01月27日
コメント(0)
-
「干し大根入りオムレツ」
会社の近くに「台湾小皿料理」のお店があり、母を連れて先日食べに行ってきました。それぞれはたいした量ではないけれど、何品も注文して分けて食べると、そこそこ満足しました。値段も手頃で嬉しかったです。中でも気に入ったのが台湾風オムレツ。戻した干し大根が入った、卵の平焼きです。やさしい味つけでしたし、これなら家でもできそう!…というわけで、切り干し大根でもよかったのですが、少し太そうな長崎県産「ゆがき大根」を買ってきました。干し大根は、水かぬるま湯で戻しすぎない程度に戻します。フライパンの大きさに合わせて、卵を2~3個溶き、長ねぎの小口切りと塩少々を混ぜておきます。フライパンに油を熱し、戻した干し大根を炒めます。火が通ったら、卵を流し込み、ふたをして中弱火で両面を焼いて、できあがり。卵に胡椒を混ぜておいたり、油はごま油を使ったりしてもOK。干し大根は、刻まずに長いままで大丈夫です。最初に炒めずに、全部を混ぜてから焼く方法もあるようです。いただく時は、包丁で切り分けるか、大皿からめいめいが自分の分を箸で取ればよいでしょう。干し野菜の甘みが感じられる一品です。台湾の干し大根は、保存のためか塩をしてあることがあり、その場合は戻したあとで塩分の濃さを確かめて味付けする必要がありますが、日本の干し大根なら、あとで加える塩分だけが味付けになります。醤油や砂糖は入れないほうが、素朴な味を味わえるでしょう。干したせん切りにんじんを少し入れれば、彩りも鮮やかですね。
2013年01月26日
コメント(0)
-
「生ハム」
スペイン語でハモン(フランス語でジャンボン)というのは太もものことで、特に豚のもも肉の塩漬け、いわゆる英語で言うハムを指します。ハムのうち、塩漬けしたまま乾燥させるだけで、いぶしたり茹でたりしないものが生ハムです。薄切りにすると透明感があって、柔らかく、適度な塩味と豚肉のうまみが味わえる食材です。どちらかというと、普通のハムよりも高級で、レストランなどでは、これもまた高級食材のメロンに上に、ぴらっと乗って出てきます。生ハムとメロンは相性が良いのでしょうか。生ハムの塩気とメロンの甘みが、どちらもほど良いのと、赤と緑という見た目の鮮やかさで、オードブルの定番になっているように思います。これがメロンではなく、パイナップルやキウイだったら、蛋白分解酵素のせいで、生ハムがどろどろに溶かされていたことでしょう。いちごや柿なら構いませんが、色合いではやはり、メロンの勝ちですね。もっとも、マスクメロンのような緑色のメロンである必要がありますが。きょうはパックの生ハムが、日切れが近いのか、半額のものがあったので、これは「買い!」とばかりに購入しました。そして、きゅうり1本の皮を皮引き器できれいにむき、乱切りにして皿に離して置き、その上に生ハムを1枚ずつ掛けました。ハムの上からは下の緑色の実が見えています。メロンかと思って喜んで食べた者もいましたが、いや何、きゅうりで全く美味しいです。無理にはちみつなぞを掛けたりせずとも、生ハムの美味しさは充分に味わえました。
2013年01月20日
コメント(2)
-
「湯豆腐鍋」
前回、湯豆腐を書いてから、ずいぶん年月が過ぎました。きょう、わが家で初めて鍋料理をしてから丸1年にして、初めての湯豆腐鍋です! 近所で豆腐が安く出ていたので、喜んで8パック買いました(4人分)! 具は長ねぎ、菊菜、えのきだけのみ(他におかずも作りましたが)。大きな鍋に水を半分ぐらい入れ、だし昆布を2枚敷いて1時間ほど置き、捌いたえのきだけ1パックを入れて、沸騰寸前まで加熱します。火を弱めて、えのきだけを取り出します。6つに切った豆腐3パック分と、斜め切りのねぎを入れて、また沸騰寸前まで沸かします。そしていよいよ食卓のガスコンロへ! とろ火を保ったまま、薄めた醤油、またはぽん酢でいただきました。薬味は大根おろしと青ねぎの小口切り。昆布のいいだしが出ています。豆腐を大半食べたら、残りの豆腐やえのきだけ、ねぎ、菊菜を追加。火力を調節して、沸き立たないようにしながら食べました。量が少し多かったのか、豆腐1パック分と若干の具が残りました。わたしは湯豆腐鍋は、豆腐主体と言うより、ほとんど豆腐だけを食べるものと心得ていますので、これでも具が多かったかな、と思っています。子たちにも正しい「湯豆腐鍋」が伝わりますように! なお、豆腐はほとんどが水分なので、満腹したと言っても、体に負担になるほどではなく、満足感は残ります。さて、鍋の底に敷いていただし昆布ですが、勿論、あとで引き上げてごく細く切り、かつおだしと醤油と砂糖それぞれ少しで、さっと煮付けてありますよ。
2013年01月14日
コメント(2)
-

「ばってら」
晩に外出する予定のあった日、何か夕食を作り置いてやろうと考えましたが、大きな片身のきずし(〆鯖)が出ていたので、これで寿司を作ろうと思いました。鯖の棒ずしを「ばってら」と呼びます。ポルトガル語でボートを意味するバテイラから来ているそうです(フランス語ならバトーです)。魚の身が舟の形に思えたのでしょうか。本来なら鯖の上には白昆布を張り付けるところですが、上等な昆布は高いので、おぼろ昆布で昆布の風味を出すことにしました。わが家には棒ずしの枠が無いので、20cm×14cmの大ぶりな保存容器で代用です。米3合を、水を少なめに炊き、すし酢を少し掛け回して、多少冷まします。容器にラップを(2枚が重なるように)敷き、おぼろ昆布をふんだんに、しかも重ならないように敷きつめ、薄くそぎ切りにしたきずしを並べます。この上に、ある程度冷めたすしめしを乗せて、上からラップをし、均等な厚みになるように、押します。フライ返しやマッシャーを使うと便利だと思います。よく押したら、ラップの余白で全体をしっかり包み、まな板に逆さに取り出します(写真)。これをラップごと、長く3本に切り、そしてラップを取ってから、さらに1口サイズに切りました。くれぐれもよく切れる包丁をお使いください。わたしは崩れた2切れだけ食べて外出しましたが、残りは家族3人で完売!だったそうです。鯖ずしは、〆鯖が全体の厚みの半分ほどもある、分厚い松前ずしが豪華ですが、わたしは薄い身を並べたばってらのほうが好きです。
2013年01月12日
コメント(0)
-
「厚揚げのケチャップ煮」
みなさん、明けましておめでとうございます。お正月から何これ?、と言われそうですが、元日の晩に食べましたので紹介します。わたしが小さいころ、わが家では毎月1日・16日・午(うま)の日は肉を食べないことになっていました。熱心な仏教徒だったのでしょうか。このため新年元日に肉料理が出ることはありませんでしたが、今回のメニューはそれとは全く関係がありません。単に厚揚げをメインに、どんな料理を作ろうかと考えて、ふと思いつきました。厚揚げ1人あたり2~3枚を、広い鍋に敷き詰めるようにして並べます。ここへひたひたになるようにだしを注ぎ、風味づけに醤油を加えたら、火にかけます。煮立ったら、ケチャップ適量を加えて、鍋を揺するなどして全体に溶かします。そうして弱火で5分ほど煮込むか、または水溶きかたくり粉で、薄くとろみをつけます。汁ごとめいめいの小鉢によそって、できあがり。煮込む際に揚げの上に、えのきだけやしめじなどのきのこ類を乗せても美味しいですね。ケチャップ味(トマト味)の煮込み料理は、ケチャップが多すぎると味が濃くなりすぎて、くどくなりますが、かと言って使う量が少ないと、しゃぶしゃぶで物足りません。ほどほどの量を使いながら、薄くとろみをつけることで、具材との絡みが良くなります。厚揚げは、いつも醤油味の煮付けではつまらないので、たまにはこんな洋風仕立てはいかがでしょうか。お好みなら、厚揚げとこんにゃくを使った精進カレーに挑戦してみても、面白いと思います(^o^!)。
2013年01月01日
コメント(6)
全7件 (7件中 1-7件目)
1