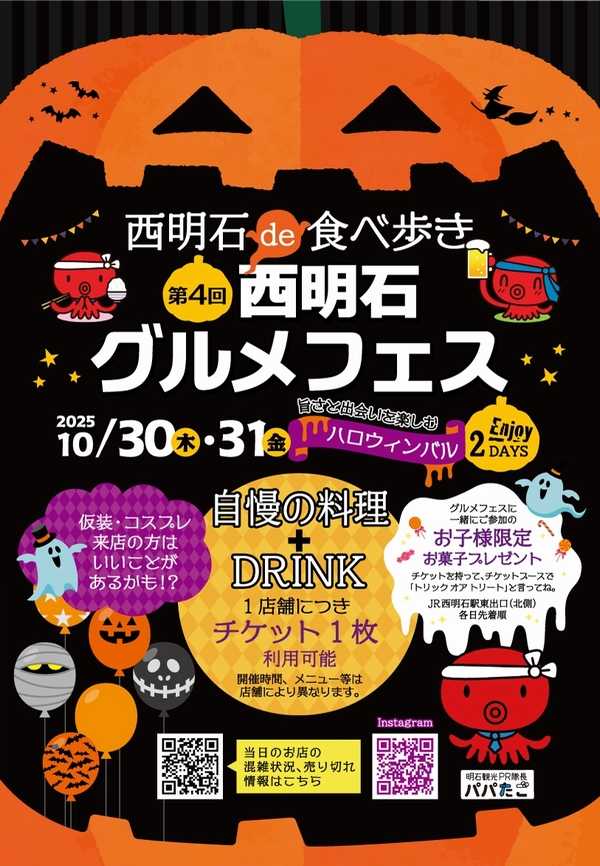2021年01月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

「続・焼いた餅にお湯を掛けたん」
台所をリフォームしてから、こんろのすべての口に温度センサーが付いたために、餅をこんろで焼くことができなくなり、鉄板式のグリルで焼くことになりました。たしかにふんわりと焼けて、よく膨らみもしますが、昔人間にとっては「餅に焦げがない」というのが物足りないです。今回は、小腹が減ったときにちょうどいい“虫養い”になる「焼いた餅にお湯を掛けたん」ですが、焦げも味、とも言えるため、ほんのりきつね色の焼け具合では頼りなかったです。食べたい量だけの餅を用意します。餅は切り餅(50g)や小餅(33g)のサイズのままでもいいですが、今回は小さめのサイコロに切って焼きました。膨らんだところをお椀に入れ、少ししょうゆを垂らして熱々のお湯を掛けます。焼けて硬くなった所がふやけて軟らかくなり、汁となじみます。餅に焦げがあれば、しょうゆでなく塩だけのほうが、風味があったのですが。お茶漬けの素を使っても、粉末の即席スープに焼いた餅を浮かせても、美味しいでしょうね。
2021年01月31日
コメント(2)
-

「ナポリタンうどん」
茹でたスパゲティーを炒めて、ケチャップかトマトソースで味付けしたものがスパゲッティ・ナポリタンです。イタリア本国にはなく、日本生まれの調理法だと言われますが、応用上手な日本人は、スパゲティーだけでなく中華麺でもうどんでも、何でもナポリタンにできます。今回は「うどんdeナポリタン」。ピーマン、たまねぎ、しめじ、焼き豚を具にしてうどん玉を炒め、ケチャップで味付けをして仕上げに粉チーズを振りました。“なんちゃってイタリアン”ですが、食材は間違いのないものを使っているため、美味しくいただけます。
2021年01月30日
コメント(2)
-

「続・寒餅」
小寒から立春の間の「寒」の時期に搗く、もしくは売り出される寒餅。7年前に紹介した4種類詰め合わせの10枚パックはここ数年出なくなりましたが、寒餅ファンの家内もいることから、今年はえび、黒豆、よもぎ、黒糖の4種類の10枚入りパックをすべて買って、いろいろと食べています。台所のリフォーム以来、ガス火の網で餅を焼くことができなくなり、鉄板式のグリルで焼いていますが、これがそこそこ便利です。写真はおふざけで、切った寒餅を数種類並べて焼いたものですが、それほど味が混ざらずに、美味しくいただけました。
2021年01月29日
コメント(2)
-

「ボルシチ」
ロシア料理の代表のように言われるボルシチは、赤紫色の根菜「ビーツ」を使った煮込み料理です。ロシア語の発音は「ボルシ」に近く、しかも元はウクライナ料理なのだそうです。近郊農家が育てているのか、小ぶりなじゃがいもほどの大きさのビーツが売っていたので、一度ボルシチを作ってみようと思って買ってみました。皮をむいて縦に細切りにしましたが、まな板も手も赤紫色になります。色みは、過マンガン酸カリウム水溶液の色が近いかもしれません。薄切りの牛肉に塩とこしょうを振り、鍋で炒めます。ここに水を加え、一口大に切ったにん・たま・じゃがを加えて煮ます。これだけだとカレーのようですが、キャベツを必ず使うのがボルシチの特徴です。今回はかぶも加え(茎は刻んで最後に飾りとして散らしましたが)、コンソメ顆粒、塩、ケチャップ大さじ2杯と、やや反則ですがハヤシライスのルー1山で調味しました。この時点ではビーツを入れておらず、全体がオレンジ色の煮込み料理になっています。煮えたらしばらく置いておきます。ビーツは長く煮ると色が悪くなるそうなので、煮るのは10分と決め、食べる直前に鍋を沸かし、沸いたらビーツを加えて10分間で火を止めました。ビーツを加えて混ぜることで、鍋全体が赤紫色になります。これを各自によそい分け、青みとしてかぶの茎を散らします。本来ならスメタナクリームというのを中央にあしらうのですが、ないので、プレーンヨーグルトを乗せました。やさしい味わいの一品で美味しくいただけました。
2021年01月27日
コメント(2)
-

「雑穀米カレー」
雑穀米とは、麦や粟、黍などを米に混ぜ込んで炊いたものです。「白米のほうが絶対にうまい」と言う友人がいますが、たまには雑穀米も味わいがあっていいものです。今回、キャンペーンで39種類の雑穀が入った袋が当たり、それを米に混ぜて炊いてみました。黒米などが混じっているのか、ほんのり紫色ですが、大豆や小豆など粒の大きいものは米と同じぐらいに砕かれて入っているので、目をつぶって食べると食感はさほど白米と変わらない感じのものでした。このあたりは好みもあるでしょうが、わたしには物足りなく感じました。この雑穀米を夕食に炊き、余った分を丸めて取っておきましたが、これをある日の朝食のときに、レトルトカレーとともに食べてみました。雑穀米もカレーも、いずれも電子レンジで温めたものを合わせます。薬膳カレーというほどのものではありませんが、きっといろいろな栄養が入っていると思います。福神漬けを添えて食べましたが、味は特段変わらず、まあ普段どおりのカレーでした。米以外のものを混ぜると言えば、節分に食べる麦めしがあります。今年は珍しく立春が2月3日なので、節分は2日になるようですが、ほとんどが在宅勤務のわたしは、たまたま節分が出社の日に当たりました。わが家の節分の日の夕食は「麦めしと塩いわし」ですが、子たちが食べたがっている巻きずしの丸かぶりにするかどうかも含めて、家内に任せます。ただ、数え年+1個の福豆だけは、夜にわたしが神社へ奉納に行こうと思って準備をしておくつもりです。
2021年01月24日
コメント(2)
-

「カレーうどん」
カレーうどんには2種類あって、わたしが好きなのは、湯がいたうどんに、カレーライスとして食べるような濃いカレーをそのまま掛けたものです。これをうどんと絡めて食べます。もう一方のカレーうどんは、かけうどんのつゆがカレー味になっている、というものです。うどん屋のカレー、とでも申せましょうか。今回は後者を作りました。それはなぜか。家内が使い残したのか、カレーのルーが1山だけ冷凍庫に残してあって、どうにも半端に思えたからです。今回のカレーうどんのつゆは、しょうゆとみりんで作ったつゆ3.5人分に、160ccのお湯で溶いたカレールー1山を加え、4人前としました。「しょうゆ、みりん各40cc、水720cc、粉末かつおだしの素多め」がつゆ部分、「水160cc、カレールー1山」がカレー部分です。このうち、カレールー以外を煮立て、薄切りの牛肉を1枚ずつしゃぶしゃぶして加えてから、長ねぎと薄揚げを加えて少し煮ます。ここへカレールーを溶かして、風味ととろみを付けます。あとは湯がいたうどんを鉢に取り、カレー味のつゆと具を掛けて、かまぼこを飾れば、できあがり。カレーの辛さにもよりますが、お好みで唐辛子またはこしょうを振って、いただきます。カレールーを使ったので軽いとろみが付いていますが、このような汁気の多いカレーうどんでは、ふつうにカレーを掛けるときのような、きついとろみはなくていいように思います。カレーラーメンでも、このような飲めるスープになっているものが多いのではないでしょうか。
2021年01月23日
コメント(2)
-

「かつおのたたきと大根おろし」
「夏大根は辛い」と言います。辛いものが苦手な子たち用には、夏に大根おろしを作るときは、電子レンジで軽く加熱して辛みを抜いています。先日買った大根は、おろすと甘みさえ感じるようなものでした。そこで、すき焼きの日のおかずとして、よく買う「かつおのたたきのあら」に大根おろしを合わせてみました。輪切りのきゅうりは飾りで、極端に薄くしませんでした。箸休め、または、すき焼きが「焼き」から「煮る」に移る場面で、食べてもらいました。
2021年01月22日
コメント(0)
-

「続^5・すき焼き」
先日の日曜日に「すき焼き」をしました。子たち2人も夕食の定刻に揃っているし、寒いし、何か鍋にしようと思って肉と魚の売り場を見て回ったところ、魚を煮る鍋にも惹かれましたが、結局牛肉を買いました。100g328円(税込み354円)の国産牛の切り落とし肉を約400g買って4人分にしただけですから、自慢できるような量ではありませんが、家で久しぶりに食べる、肉がメインの鍋料理です。食卓にガスこんろを置き、大阪の標準的な作り方で作りました。【左上】まず平たい鍋を火にかけて牛脂を溶かし、牛肉を鍋いっぱいに広げて入れて、砂糖としょうゆで炒りつけます。これだけを溶き卵で食べても美味しいです。【右上】長ねぎを加えて牛肉と一緒に焼きつけます。ねぎに火が通れば、まずこの段階で肉とねぎをいただきます。肉とねぎは追加して焼きます。【左下】頃合いを見て焼き豆腐、水で戻した麩、糸ごんにゃく、菊菜を加え、水1カップ程度としょうゆ適量を加えて、煮ながら肉とともにいただきます。麩は圧搾麩を使いました。砂糖は最初に使っただけです。長ねぎは4人で4本でした。ほかにも、さわらの味噌漬け、かつおのたたきと大根おろし、白菜の味噌汁を用意し、いつもより長く、夕食に30分以上かかりましたが、すき焼きは最後にはほとんど汁も残らず食べてしまいました=右下。これではすき焼きの翌日のお楽しみ、残った汁にごはんを入れて温めた“犬めし”も作れませんが、仕方がありません。味が濃すぎず、家族みんなに好評のすき焼きでした。
2021年01月20日
コメント(2)
-

「続・むかご」
この正月は新型コロナ感染症の影響を懸念して、家族揃って大阪市内のわたしの母を訪ねるのはやめ、その代わりにお正月用の届け物を、わたし1人が年末に、勤務の合間に持って行きました。その帰り際、子たちへのお年玉とともにもらったのが零余子(むかご)です。もう30年以上も前に、食べ残した長芋から芽が出てしまったのを庭に植えてみると、つるが出て、毎年むかごを付けるようになりました。今でも毎年収穫できているというのはすごいことですね。今回は炒っていただきました。温めたフライパンに薄くごま油を引き、中弱火でむかごを気長に炒ります。香ばしくなってきたら塩を振り掛け、もうしばらく炒って、できあがり。ホクホクした素朴なおやつです。酒のアテにもいいですね。長芋なのでアクは少ないですが、皮は多少ほろ苦く、これが風味になっています。なお、中でも大きめの粒のむかごを、わが家の庭にも数粒蒔きました。ぶじに芽が出て育ち、むかごを付けてくれるようになれば嬉しいですが。
2021年01月18日
コメント(2)
-

「続^4・すき焼き」
「すき焼きとは何か」と問われたら、元は熱した鋤の上で肉を焼いて食べた料理、としか言いようがないでしょう。一度も焼かずに最初から煮る調理法までが「すき焼き」と呼ばれるようになると、混乱するばかりです。今回作ったのは、フライパンで牛肉を焼き付けて砂糖としょうゆで調味し、その前にごま油で焼いておいた長ねぎを加えて、炒め合わせたものです。これを「すき焼き」と呼ばずして、何と呼びましょう。大阪のすき焼きよりもさらに原型に近いように思いますが、あえて呼び分けるなら「焼きねぎのすき焼き」でしょうか。いや、名前はともかく、ねぎが香ばしくてしかも甘くて、美味しかったです。
2021年01月17日
コメント(0)
-

「アールグレイ」
正月の屠蘇に使う屠蘇延命散の袋を使ったスパイスティーを紹介したときに、今回と同じような写真を載せました。紅茶の淹れ方で標準的なのは、大きめのティーポットをお湯で温めておき、お湯を捨ててから、茶さじ「人数+1」杯分の茶葉を入れ、そこへ沸きたてのお湯を注いでふたをし、葉が開くまで3~5分待つ、というものです。このとき、必ずくみたての水道水を使い、お湯の表面に10円玉大の泡が出てくるまで沸騰させたものを使う、とされています。わたしは小鍋でお湯を沸かしたら、そこへ茶葉を投入し、火を止めてからふたをして3~5分待つ、という方法を採っています。どちらのやり方も理にかなっています。充分に沸騰させつつも、沸騰水に含まれる空気が抜けきらないうちに茶葉を入れ、葉が水分を吸って膨らみ、開くまでに、重くなって沈んだり空気の泡が付いて浮いたり、というのを繰り返すこと(ジャンピング)によって、対流が生まれてお茶の成分が均質に抽出される、ということになります。写真は沸騰させたお湯に茶葉を投入した直後で、今回のお茶はアールグレイです。ダージリンやアッサムは葉の産地による名称ですが、アールグレイはベルガモットという柑橘類の花を混ぜて茶葉にその香りを移した、着香茶の一種です。紅茶は、葉が沈んでから注ぎ分けて飲みますが、葉が沈みきる時間は葉の大きさによります。この「待つ時間を楽しむ」のも紅茶のいいところです。わたしは小鍋を使うので玉杓子と茶こしで紅茶を注ぎ、2煎目まで楽しみます。
2021年01月16日
コメント(2)
-

「続^5・小豆粥」
15日は小正月。3が日のお祝い(雑煮と煮〆)、4日に鏡餅を下げて切り分けるのに続いて、この日の小豆粥で正月の行事はおしまいです。邪気を払うとされる赤い色の小豆を入れた餅入りの粥は、行事以外で食べても美味しいかと思いますが、小豆を用意するのが面倒なこともあって、2007年以来、ちゃんとしたものは作っていません。今年はコロナ禍で在宅勤務という特別な年であることもあり、ゆで小豆の小さなパックを買ってきて14年ぶりに作ってみました。これまでは黒豆の残りや煮汁を使って作ったりしていたので、必然的にやや甘くなっていましたが、本来は米と小豆で粥を炊き、薄い塩味にして、焼いた餅を加えます。今回も甘い味のゆで小豆だったので、小豆の粒だけを取り出し、ちょっと水ですすいでから、塩味の粥に加えて少し煮ました。それでも豆はやや甘かったですが。なお、3が日と小正月、節分は祝い箸を使うのが本来ですが、それは省略しました。小豆粥から始めた当ブログも満16年になりました。 (↓近所の神社で「とんと」。橙を外したわが家のお飾りも右端あたりで焼かれています)
2021年01月15日
コメント(2)
-

「橙」
新年を迎えてから2週間、大阪では14日までが門松を飾る期間=松の内です。14日の夕方になると、門松と〆縄を外します。これらは15日の小正月に、近所の神社での「とんと」に持っていき、焼いてしまいます。とんと(とんど)は左義長とも呼び、昔はその火で餅をあぶって食べると風邪をひかないと言われたそうです。最近はダイオキシン発生に留意し、燃えにくいものは燃やさないよう徹底されていて、焼く前に〆縄の橙(だいだい)も外されてしまいます。ここは食べ物に関したことを記すおリョオリブログですから、橙に言寄せて、門松と〆縄について書いておこうと思います。門松は年神さまが訪ねてくるときの目印で、わが家では外から家に向かって左側に雄松、右側に雌松を飾ります。〆縄は藁を横長に綯(な)い、片方を細くしたゴンボ(ごぼう)と呼ばれる形で、鏡餅と同じく橙を飾ります。とんとでは、どうせ橙が外されてしまうので、ここ数年はあらかじめ橙を外してから、持っていくようになりました。さて、外した橙はどうするか。昔は〆縄の橙は焼きましたが、鏡餅の橙は残るので、父が「たきたき」のときのぽん酢として使っていました。橙を横半分に切り、かぶとのような形のレモン搾り器で汁を取り、各自の手元の器に移します。これを、しょうゆと「たきたき」の煮汁で割り、大根おろしや刻みねぎを加えたうえで、白菜や肉などを浸して食べます。かなり酸っぱいですが、橙さえも余さないという、食べ物を大切にする精神の表れなのだろうと思います。
2021年01月14日
コメント(0)
-

「続^3・屠蘇」
つい先日、「正月の屠蘇は日本酒をベースとしたハーブ酒だ」と書きました。家にあった屠蘇延命散(屠蘇白散)のパックは使ってしまいましたが、ハーブ酒だと書いた以上、やってみるわけです(^-^!)。ハマボウフウなど、漢方薬にしか使わないような材料は家にはありませんが、幸い各種スパイスは常備しています。写真でいうと、左端から時計回りに桂皮(シナモン)、丁字(クローブ)、山椒、八角(大ウイキョウ=スターアニス)、陳皮(ゆずの皮)です。粉のものはほんの耳かき1杯程度ずつですが、これらを左の茶袋(紙パック)に入れ、120ccの日本酒に浸けました。そうしたらどうでしょう。2~3分するうちに、酒がほんのわずか茶色くなってくるのです。エキスが出すぎてはいけないと思い、これをグラスに注いで飲んでみると、屠蘇と同じ味わいの酒ができています。計量カップにはまた120ccの酒を足し、しばらくして2杯目を楽しみました。これでいいなら、もういつでも屠蘇が飲めることになります!今回はゆずを使いましたが、陳皮はほんとうは干したみかんの皮です。もちろん、屠蘇というのは楽しみに飲むだけでなく、正月の年迎えの行事ですから、ちゃんと意味のあるものです。ただし、雑煮だって、正月を離れてふだんの食事に食べても美味しいのですから、屠蘇だって例外ではないでしょう。行事としていただく時にはその意味をかみしめ、でもそれ以外の時期にも楽しむ。こうすることにより、食べたり飲んだりすることの幅が広がるように思います。
2021年01月12日
コメント(2)
-

「続^3・味噌煮込みうどん」
白菜を買ったので、味噌煮込みうどんです。いや正確には、白菜の外葉を無駄なく使うために、味噌煮込みうどんの具にした次第です。外葉なので、少し茶色くなった所は惜しみなく捨てても「勿体ない」と感じませんが、濃い緑色の葉も含め、食べられる所は余さず使うのが「始末」というものです。ちょうど期限が近く値引きのうどん玉が売っていたので、味噌煮込みうどんにしましたが、うどん玉が高ければ、皿うどんなど別のメニューを考えるところでした。栄養を考えて、深めのフライパンに水を浅く入れて沸かし、ポーチドエッグを作っておきます。お湯が沸いたら割っておいた卵をそっと入れ、ふたをして強火で20秒加熱して、沸きかけたら火を切り、5分放置して、できあがりです。別の中華鍋を熱して油少々をなじませ、白菜の外葉、にんじん、舞茸、チンゲンサイ、ちくわを炒め、1人あたり300~350ccの水を加えて煮ます。ここに乾燥わかめ、粉末かつおだしの素を加え、味噌を溶かして味噌汁を作ります。食べる際には味噌汁に人数分のうどん玉を加えて、うどんが少し膨らむまで煮ます。各自の丼鉢にうどんを分け、ポーチドエッグを乗せたら、具と汁を掛けて、できあがり。お好みで七味とうがらしやゆずこしょうをお使いください。ポーチドエッグが半熟に仕上がっていると、少し黄身が崩れて流れても、美味しいです。煮込み汁は味噌汁ですし、ふだんの味噌汁程度の濃さであれば、飲み干しても罪悪感はありません。白菜の外葉を食べきった満足感もあります。
2021年01月11日
コメント(2)
-

「スパイスティー」
ふだん、わたしが家にいる日の「3時のおやつ」は、いつも紅茶を飲みます。家にはダージリン、アッサム、ヌワラエリヤ、アールグレイの4種類の茶葉を決まったお店で買って常備しており、そのまま飲む以外に、ペパーミントの葉を使ったハーブティーや、シナモンやクローブを使ったスパイスティーなども楽しみます。今回のスパイスティーは、シナモンや山椒、陳皮(みかんの皮)などが入ったスパイスミックスを使って作った、特別なスパイスティーです。実はこれ、お正月のお屠蘇で使った屠蘇白散の袋を置いておき、紅茶に転用したものです。酒(アルコール)に浸して充分に成分を抽出したあとですが、熱を加えれば残っている成分がもう少し出るだろうと思ってのことです。そもそも、屠蘇散はホットワイン(バンショー)を作るときのスパイスミックスに似ているところがあり、煮出すなら屠蘇の使い残しでも行けるだろうと思っていました。4杯分の紅茶に屠蘇散1袋ですから、そんなにくどくないはずです。子たちもいる日に作ってみました。アッサム茶さじ1杯とヌワラエリヤ2杯の茶葉をブレンドした紅茶に、屠蘇散の袋を浸して3分ほど待ちます。わたしと家内はストレートのホットティーで飲み、子たちはミルクティーにするのですが、「言われてみれば、お屠蘇の風味かな」というぐらいで、違和感もなく、子たちも普通に飲んでいました。わざわざ屠蘇散を使わずに置いておき、スパイスティーにする必要はありませんが、これもアリかな、という試みでした。
2021年01月10日
コメント(2)
-

「続・七草がゆ」
七草なずな、菜っ切り包丁まな板、唐土の鳥が、日本の国に、渡らぬ先に、叩いてバッタバタ(3-211222-|222212216-|2-23222-||2-223222-|2-223222-|2-2112222-|)…という囃し言葉とともに、春の七草を刻み、おかゆに仕立てるのが「七草がゆ」です。明治末期以降、大阪の町なかに暮らしてきたわが家には七草がゆの風習はなく、父は「田舎で、しかも旧暦でないと、とても無理な行事」と言っていました。本来は春の七草をおかゆの具にします。今回わたしが作ったのは、雑煮大根の残り(すずしろ)、壬生菜、ねぎの3草がゆです。もともと七草(七種)とは種類の多いことを指す言葉かもしれませんが、たとえ3草がゆであっても、この冬の時期に青物でビタミンを摂ろうというには充分ではないでしょうか。他にもキャベツ、白菜、ブロッコリーなどが冷蔵庫にありましたが、どうせ破格のものを作るなら、この程度にしたろやないかい、と思った次第です(^o^;)。まず、丸餅を4つに切って、こんがりと焼きます。鍋に水180~200ccと冷やごはん半膳を入れ、粉末かつおだしの素、塩、うすくちしょうゆ少々で調味しておかゆを作ります。適当なところで野菜類を加え、大根が軟らかくなったら餅を加えて、餅が軟らかくなるまで煮れば、できあがり。7日の七草(人日=じんじつ)当日ではなく、しかもわたしだけのわずか1膳分ですが、まずまずのものができたように思います。わが家の行事の例外として紹介いたします。
2021年01月09日
コメント(2)
-

「水菜の煮浸し」
わが家は正月2日に水菜の澄まし雑煮を食べますが、その水菜はいつも年末の悩みどころです。多く買って余らせても、いつ使うのか、ということになりますし、あまりに小さな束を買うと、雑煮自体が貧相になってしまいます。ちょうど使い切れるか、または少し余るぐらいの量の束を買うことが重要です。今回は税込み115円の水菜(前年は118円、19年正月は141円、18年正月は180円)を買ったので、雑煮に大半を使い、株元のほうだけが残る格好になりました。これを使った正月明けの一品です。食べやすい長さに切った水菜の軸以外は、薄揚げでもよかったんですが、今回はちくわの細切りです。鍋に180~200ccの水を沸かし、ちくわ、粉末かつおだしの素少々、しょうゆ、酒各10ccを加えて煮立てます。煮立ったら、水菜を入れ、すぐに火を止めて、できあがりです。水菜はしゃきしゃきとした食感が持ち味ですから、くたっとならないようにします。淡い味付けですが、だしの素とちくわからのうまみが出ています。
2021年01月08日
コメント(2)
-

「続^2・屠蘇」
わたしが幼い頃とほとんど変わらない(変えていない)お正月の食事ですが、大きく変わったのは屠蘇です。屠蘇というのは日本酒をベースとしたハーブ酒で、シナモンやオレンジピールなどを調合した屠蘇延命散(奈良の春日大社のものは屠蘇白散)を清酒かみりんに浸して、そのエキスを抽出した酒をいただきます。これには好き嫌いがあって、父などは「日本酒のほうがうまい」と言い、屠蘇延命散を使わずに普通の酒を「お屠蘇」と呼んで、飲んでいました。それに加えて、近年の飲酒運転厳罰化です。どうしても家族揃って、大阪市内のわたしの母と芦屋市内の家内の両親を年始に訪ねるものですから、車を運転します。そこで、朝のお祝いの席ではお屠蘇を飲まない、ということが定着していました。ところが今回はコロナ禍。高齢の親を訪ねるのをやめたため、車を運転せずお正月を過ごしました。また、去年9月に下の子が20歳になり、家族全員がお酒が飲める年齢になったのです。家には幸い屠蘇白散もあります。…ということで、今年のお正月のトピックスとして、全員でお屠蘇を飲んでみました。お試しですので、お祝いをおおぶく茶でしたあと、全員が比較のために日本酒を少し飲み、そのあとで屠蘇白散を浸した日本酒(お屠蘇)を飲み比べました。家内はもともと日本酒が好みではなく、長男はアルコール自体があまり好きではないようですが、長女はそこそこ興味を示していました。そこで1袋の屠蘇白散のパックを3日間使い回して、お屠蘇をいただいた次第です。
2021年01月06日
コメント(2)
-

「続^2・鏡餅」
わたしが子供の頃のお正月は、玄関と2階の床の間に飾る3升の鏡餅、そのほかに神棚の4柱分と三宝さん用の3つ重ねの餅、さらに餅箱いっぱいの丸い小餅を、それぞれ近所の餅屋(和菓子屋)に注文していました。合計1斗ほどもあったかと思います。これを多いときで7人の家族が食べ、2月中旬ごろにようやくなくなる、というのが通例でした。今のように冷凍して保存することのなかった当時は、1月下旬ごろからは青かびとの戦いでもありました(^_^;)。今のわが家は4人家族ですが、300gのパックの鏡餅と小餅が1kgあれば、お正月の行事はまかなえます。小餅も個包装になっていて、かびが来ません。鏡餅はかなりダウンサイズしましたが、基本は変えていません。三方の上に裏白を敷き、その上に餅を重ねます。餅の上には白昆布を左右に垂らし、串柿と葉付きみかんを飾ります。串柿は、本来は干し柿を10個連ねたものですが、鏡餅が小さいので2個にしています。葉付きみかんは、本来飾る橙の代わりです。鏡餅は11日に鏡開きをする所が多いでしょうが、わが家では4日の朝に下ろして切り分けてしまいます。飾っているのが3が日だけとはいえ、昔の3升の鏡餅は相当硬くなっており、餅箱のふたを台にして両方に柄のある包丁で大人が体重をかけて切らないと、歯が立たない代物でした。祖父と父がシャツ1枚で汗まみれになって、家じゅうの餅を切り分けていたのを覚えています。小さな鏡餅に飾った葉付きみかんと硬くなった串柿は、子供のおやつになりました。 (*11年と18年のブログで「1升の鏡餅」と書きましたが、いずれも「3升の鏡餅」に訂正します)
2021年01月05日
コメント(2)
-

「続・2種類の雑煮」
関西では一般に、雑煮は白味噌で丸餅と言われます。それはわが家も例外ではないのですが、元日・3日と違って、2日は澄まし雑煮です。2種類の雑煮を作る家は珍しいと言われますが、わたしが生まれた60年前はすでにそうでしたから、これもずっとわが家で続いている伝統の風習かと思います。白味噌雑煮は宮中で食べられていた白一色の雑煮になぞらえたもの、水菜だけを具にした澄まし雑煮は河内・大和の田舎の風習かもしれない、と父は言っていました。白味噌雑煮には、焼かない丸餅、小芋、輪切りの雑煮大根と、これだけは四角い具ですが焼き豆腐が入ります。現在は豆腐も日もちするようになったので、焼き豆腐にせず、丸い豆腐にすれば、すべてが白くて丸い具になりますが、わたしの代ではそこまでするつもりはありません。餅以外の具は事前に茹でて火を通しておき、元日と3日の朝に白味噌の味噌汁を作って、最後に餅を加え、餅が浮いてくるぐらい加熱すれば、できあがりです。まったりとした味です。澄まし雑煮には、焼いた丸餅が入ります。膨らませなくても後で煮るので、強火で焦げ目を付けます。澄まし汁を作って餅を加え、餅に火が通ったら、食べやすい長さに刻んだ水菜をたっぷり加えます。水菜がしゃきしゃきしているうちに火を止めて、できあがり。食べるときは水菜を高く掲げて「名ァ(菜)が上がりますように」と唱えていただきます。立身出世を願った頃の縁起食でしょうか。食べ物の観点からは、あっさりしていて、家族にも評判の一品です。
2021年01月03日
コメント(2)
-

「続^2・おおぶく茶」
お正月は、食卓に煮〆と雑煮とめいめいの祝い箸が並べられ、家族全員が着席すると、家長が「お祝い!」と言っておおぶく茶を飲むことから始まります。おおぶく茶(皇服茶または大福茶)は「おおぶくの梅」と白昆布を入れたお茶で、父は「おんぶくのお茶」と言っていました。梅はカリカリした小粒の梅干しを使います。白昆布は鏡餅に飾るものと同じなので、わが家では鏡餅を飾る前に、白昆布の端を4人分×3が日=12枚切って拝借し、用意しておきます。湯飲みに梅干しと細い白昆布を入れ、熱い煎茶を注ぐと、できあがり。梅昆布茶というのがありますが、それの煎茶ベースといった感じで、さっぱりとした口当たりです。食事開始の「お祝い!」のときに全部飲んでしまわなくても良く、煮〆を食べながら口直しに飲んでもかまいません。本来は「行事」で、正月の祝い肴とともに心していただくものだったのでしょう。気分が引き締まるひとときです。なお、写真の湯飲みの家紋は、わが家の「丸に違い矢」です。
2021年01月02日
コメント(2)
-

「わが家のおせち(煮〆)2021」
2021年かのとうし年、あけましておめでとうございます。昨年はコロナ禍で在宅勤務が増えたことから、生存確認のつもりで、このブログを精力的に書いてきました。今年は従来のペースに戻して、ちょこちょこと書き記していこうと思っています。わが家は今年も家族揃って、おだやかにお正月を迎えました。いかにも晴れの特異日らしく、いいお天気の元日でした。今年もいつもどおりの、わたしが子供の頃から食べてきた御節料理(煮〆)の紹介から始めます。今は重箱ではなく、冷蔵庫での保存に適したタッパーに煮〆を詰めています。右上のタッパーから時計回りに、かまぼこ・厚焼き/高野豆腐・くわい・たけのこ/れんこん・金時にんじん・ごぼう/鱈のうま煮・こんにゃく・ごまめ、と入っています。上は左から、黒豆/栗の甘露煮/かずのこです。かまぼこは赤と焼きの2色。れんこんやごぼうは酢の物にせず、煮いてしまいます。棒鱈の代わりの鱈のうま煮は、今年は市販品を買いました。こんにゃくはよく見ると右側が緑色で2色になっています。黒豆のみ大量に作ったものの一部です。小さい頃からお正月はこのメニューを食べてきましたので、大きく言えば「今年も伝統を受け継いだ」ということになりますが、息子や娘が覚えていてくれれば、いやこのブログを参照してくれれば、この先も伝統が続いていくことになります。わたし亡き後は好きにしてもらってかまわないと思うものの、わたしなりに「お正月らしい」と思える食卓の風景を、書き残しておく次第です。
2021年01月01日
コメント(2)
全23件 (23件中 1-23件目)
1