2010年04月の記事
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
ハクセキレイ
GW前半の平日の4月30日。仕事を休んで朝は多賀城の歌枕を巡ってきた。良い天気だ。4月になっても雪が降ったり、震えるほど寒かったり、記録的なエイプリルだったが、月の晦日になって初夏を思わせる陽気になった。異常気象のお陰か、まだ咲いている野山の桜を見て、小鳥たちも驚いているに違いない。昼にふと庭を見たら、ハクレキレイが来た。秋に見かけると灰色っぽいが、もう夏の服に着替えたようで、白黒のコントラストがくっきりだ。そんなわけで、公開アルバムに1枚加えておく。
2010.04.30
コメント(0)
-
末の松山・沖の石
芭蕉が訪れた歌枕。多賀城駅のやや南、今では宅地に囲まれた中に残されて、歴史と風情を今に伝えている。看板書きを転記してみる。----------末の松山(平成11年12月10日多賀城市教育委員会) 「末の松山」は、「君をおきてあだし心をわがもたばすゑの松山浪もこえなむ」(古今和歌集 東歌)「ちぎりきなかたみにそでをしぼりつつすゑのまつ山なみこさじとは」(後拾遺和歌集 清原元輔)の歌で著名ですが、源信明、源重之、橘為仲など多賀城を訪れた官人〈陸奥守 その他〉ともゆかりが深く、多くの歌人たちに親しまれた、みちのくの代表的な歌枕です。 「末の松山」の所在地については諸説がありますが、この多賀城市八幡説が最も有力です。 元禄2年5月8日(1689年 陽暦6月24日)松尾芭蕉は、塩竈到着(仙台から)ののち、「野田の玉川」「浮島」を経て、「末の松山」を訪れています。「おくのほそ道」には、 「末の松山は、寺を造て末松山といふ。松のあひあひ皆墓はらにて、はねをかわし枝をつらぬる契の末も、終はかくのごときと、悲しさも増りて、...」と「末の松山」に接しての感動をしるしています。「寺」とは末松山宝国寺のことを指しています。 芭蕉の感動は、「末の松山」のもつ歴史の重みを無視しては考えられませんが、同時に「おくのほそ道」のこの行文は、「末の松山」の歴史に、新しい一ページを加えてといえます。 「おくのほそ道」ののちも、芭蕉の足跡を慕って、多くの文人たちが、この歌枕を訪れており、その風潮は現在にも引き継がれています。市指定文化財 沖の井(沖の石)(平成11年12月10日多賀城市教育委員会)おきのゐて 身をやくよりも かなしきは 宮こしまべの わかれなりけり 古今和歌集 小野 小町わが袖は しほひにみえぬ おきの石の 人こそしらね かわくまぞなき 千載和歌集 二条院讃岐 沖の井(沖の石)は、古来歌に詠まれた歌枕であり、今もって池の中の奇岩は磊磊とした姿をとどめており、古の情景を伝えています。 江戸時代の元禄2年5月8日「おくのほそ道」の旅の途上、松尾芭蕉と同行者の曽良は、この地を訪れました。 また、四代藩主伊達綱村の時代には、仙台藩により名所整備が行われ、手厚い保護を受けていたことが知られています。----------4月も末日にまで桜が咲いている今年だが、もう鯉のぼりもちらほら目にする。やっと来ましたとばかり、初夏らしい朝の陽ざしが、やわらかく降り注いでいた。
2010.04.30
コメント(0)
-
米沢と石巻
米沢市観光物産協会のサイト(上杉の城下町米沢)を眺めていたら、関連団体リンクとして、「(社)石巻観光協会(姉妹観光協会)」と出ていた。リンク先は、ロマン海遊21である。ちなみに、同サイトのリンク集の観光関連(団体)でも真っ先に米沢観光物産協会が姉妹協会として掲げられている。互いに他の都市の協会は記載がないから、1対1の姉妹提携のようだ。だが、どういう経緯なのか、すぐには調べられなかった。
2010.04.29
コメント(0)
-
イーグルスと監督を考える
3連勝の余勢を駆って、と思ったら2連敗。昨日の大敗はそれとして、1か月以上が過ぎたブラウン・イーグルスの底が見えてしまったような気がして、大変淋しい。野村監督の存在や采配には、是非の両論があった。わかりにくい面もあったけれども、チーム全体で勝つために戦うという姿勢が、昨季にはあったように思う。選手起用や戦術にも、1つ1つに意味があったように思う。今季はどうだろう。クルクルと変わる打順。変わってはいるが、新しい面子といえば、聖沢と辛島、それに去年十分休んだ中村ノリくらいだ。鳴り物入り(とまでは言えないか)の新戦力アンディは既に無く、モリーヨはどこよ。もっと深刻なのは、従来の戦力の低下だ。山崎は好機をほとんどつぶし、渡辺直人も活きが悪い。草野と鉄平も、コンスタントに打撃成績を上げられないのは、守備や打順をいじられているからではないかと勘ぐってしまう。それに、福盛、青山も姿を消した。要するに、前向きな要素がほとんどないのだ。監督業とは、せいぜい毎日打順をいじっているだけなのか、と言いたくなる。それも、ポリシーのない変更に思えてならない。昨日は山崎を初めてスタメンからはずした。休養のためという。はずすことは別に構わない。だが、なぜ今なのか。山崎が主砲の役割を果たしていれば間違いなく勝てた試合は、この1か月で5試合くらいはあった。結果を客観的に評すれば、チーム不調の最大の原因は(選手では)山崎だ。1点差で負けた試合の多さとも関係している。だったら、監督の役割の重要な1として打線をいじるというのなら、どうしてもっとはやく動かなかったのか。結局、ブラウン監督のオーダーは、いじるために打線をいじる、というような気がしてならない。持ち駒の中で、明日はどうしようか、だれか若いやつも試してみようか、と。或いは、監督の裁量とはそのくらいしかない、とでも割り切っているのだろうか。応援している方は、大変辛い。ワンプレー毎に意図と気迫をもったプロの戦いを展開して欲しい。選手はどう思っているのかわからないが、毎日変えられるオーダーに戸惑っているのではないか。もちろん、プレーの結果が反映されるのは当然としても、変更の意味や監督の意図が伝わっているのだろうか。そして、持ち駒が足りないというのなら、新戦力を持ってくる、2軍から引き上げる、を断行すべきだ。もっとも、今の時期に言う話ではないけれども。こう考えていくと、昨秋のブラウン起用のニュースの際に囁かれていたことが、思い出される。会社側は、個性が強くなく、自己主張の少ない、ついでに年俸も少ない監督を望んだ、だからブラウンなのだ、と。選手の強化や勝利には目もくれず、そこそこ勝ってそこそこ負けて、営業を続けられればいい、と。私は、興行主としての会社の方針はわからないし、評論する立場でもない。したくもない。監督の個性も二の次だ。ただただ、熱気にあふれ、選手が連携した多彩な戦略をからめた、最上質で本気のプロのプレーを見たいと思うのだ。そして、できれば勝利して欲しい。そのための基本条件が欠けているような気がする。スタジアムに足を向けるとき、またラジオのスイッチをひねるときの、ワクワクした夢が、消えかかっている。
2010.04.29
コメント(0)
-
駅の駅?
最初は、新しい道の駅のオープンかと思った。違う。「駅の駅」だ。JR青森駅舎の一角に、農産加工品などの販売施設が28日に開業したというのだ。東北新幹線全線開業(今年12月)に合わせて、JR関連会社が運営し、県産の野菜や果物、海産物などをPRする。それにしても何故「駅の駅」なのか。意味も意図も分からない。報道したNHKが命名しただけなのだろうか。JRや青森県のサイトには、ズバリは見あたらないようなのだが。
2010.04.28
コメント(0)
-
なまはげと東北人の記憶を考える
読売新聞の企画連載は大変素晴らしい、と思う。海の民、山の民と題したシリーズで、今後の展開が楽しみだ。現在の地図で眺めるような東北の地理にとらわれず、海の視点や世界の交流史における東北について、伝承や記録に基づく地域の記憶の視点から考える。そういう企画だと思われるが、これは大変良い企画だと思う。第1回の4月11日は、なまはげ。遠い昔に海の向こうからやって来た異邦人が原形だったのではないか、と示唆する。男鹿半島には今でも大柄で肌の白い女性がいる。シベリアの白人の漂着民ではないか。男鹿市のナマハゲは有名だが、他にも、能代市のナゴメハギ、にかほ市のアマノハギ、山形県遊佐町のアマハゲ、岩手県大船渡市のスネカ。間違いなく東北と外界の交流を反映していると、私も思う。読売の企画の着眼に敬意を表したい。
2010.04.27
コメント(0)
-
来たかっ!
と思ってしまう。揺れが来ると反射的にそう感じるのだ。昨日のイーグルスの素晴らしい勝利を河北新報で味わった直後の、先ほどの地震。大した揺れではなく、妻などは気づかなかったようだが、TVでは、宮城県北部で震度3と出た。とりあえずホッとする。
2010.04.26
コメント(0)
-
見事な3連勝!
初夏の陽気の中、Kスタに子ども達と応援に行きました。田中と武田久の投手戦かと思われましたが、3回に嶋の気迫のヘッドスライディング内野安打を足がかりに、2連続犠打できっちり得点。しかし、4回表にまずい守備もあって1点を許す。それでも、田中が安定してくれれば逃げ切れるかと思ったのですが、6回に突如制球に苦しみ出して、3-2と逆転を許す。大崩れしなかったのが幸いとホッとしていた矢先、見事だったのはそのウラの反撃。草野の四球の後に、嶋の見事な2点適時打。7回はスパッと辛島にスイッチして零封。9回も川岸がピシャリ。9回表にはレフト牧田が、レフト線側の内野席、「かもめちくわ」の壁にジャンプして好捕。これはレフトスタンド大盛り上がりでした。こんなわけで、再逆転でガッチリ勝利。辛島と川岸が素晴らしいが、田中が要所をゴロや小フライで仕留めていたのも、結果的に大きかったと思います。子ども達は、中村紀洋のノリ弁当を食べて応援。その甲斐がありました。
2010.04.25
コメント(2)
-
ノヴェンバー・ステップス
新聞の訃報で横山勝也さんの名前を見た。反射的に連想するのは、鶴田錦史、武満徹の名だ。大学生の時分にノヴェンバー・ステップスをFM放送からカセットテープに録音した記憶がある。念のため昔のリストを開いてみたら、岩城宏之のN響で1984年の演奏だ。武満徹の代表作で、また、鶴田の琵琶と横山の尺八という不動のコンビによる国内外の演奏実績を踏まえて現代日本音楽の名品と位置づけられていると思われるのが、この「ノヴェンバー・ステップス」で、1967年の作品だ。今日の午前中、このテープを再生してみた。保存状態が悪くなかったようで、ちゃんと聴けた。私はノヴェンバー・ステップスを聴いたのは、この1984年のエア・チェックの時が初めてだったと思う。だが、作品名や武満徹のことは、高校時代からある独特のイメージを伴って知っていた。もう30年も前の頃だ。たぶん武満には、音楽ではなく文章で最初は接したと思う。試験の題材だったのかも知れない。そして、偉い音楽家でノヴェンバー・ステップスという代表作がある、というのを、知識として知ることになった。ところで、はじめは、全く根拠のないイメージとして、中央アジアあたりの乾いた青空の下、晩秋の草原が広がり、蒼白でうら淋しいのではあるが、何となく伸びやかで未来を予感させるような、そんな風景を勝手に頭に描いていた。11月の草原(steppe)だと思ったのだ。その後、標題音楽ではなく琵琶と尺八を用いた現代曲だと、これも知識として知ったが、実際に曲を聴いたときには、実はとりたてて感想は持たなかった。午前に聴いた約20分の間、私は大きな驚きに包まれてしまった。異様なまでに立体的で、幽玄で、尺八の調べと琵琶の響きが、何物かを変転させながらスーッと消える。我々が住むユークリッド空間は3次元だが、これに、時代、色彩、無と有、さまざまな次元の軸が響き合ってくるような、いや、的確な言葉を探せないが、とにかくこんな音楽だったのか、と。考えてみれば、現代曲に限らず、音楽を主体的に集中して聴く、ということ自体が、実は久しぶりなのだ。ポップスやTV主題歌は、どんな相手にも同一のデジタル情報で勝手に頭に入ってくるものであって、音楽鑑賞とは原理的に違う営みだ。音楽鑑賞は、鑑賞する主体の存在が重要だ。主体が異なれば聴き方も違う。同じ主体でも時代が変われば、変わるのだろう。主体が、何かを探して見つけようとして聴く。決してデジタル情報ではない。だから演奏者の違いも重要で意義を有する。中年オヤジであるからこそ、そんな時間を、もう少し持つべきか。日常の現実に縛られずに、広がりを志向せよ、と。
2010.04.24
コメント(0)
-
寒天の下で快勝!
小雨の中の試合決行、しかもラズナー先発で(失礼)不安を抱える観戦でしたが、実に素晴らしい試合展開。打っては効率的な攻め。守ってはラズナーが快調。特に、2回と3回の連打は見事。これで試合を決めました。結局は早めのテンポの試合で11-2で快勝。ラズナーが、何と何と余裕の完投。この勝利は大きい。カード3連勝を予告する価値ある勝利、と言いたい。我らがイーグルス応援団も、久々の内野席。雨天の中必死に応援した甲斐がありました。ところで試合に先立つKスタ前のイベントで、キーナートGMと握手ができました。今シーズンは、今からですよね。と言うと、キーナートさんは、まだ80%残っているからね、と笑顔で話しておられました。会話できたのも、大変光栄です。
2010.04.23
コメント(0)
-
春満開 あとは...
仙台も桜に彩られ、遅い春が満開。今日からまた天気が崩れそうですが、これ以上崩れて欲しくないのが、わがイーグルス。ドームの主催ゲームで4万人を集めた首位ロッテ戦は見事だったが、郡山、仙台と移動しながらの変則日程3連勝は、とりあえず成らず。こうなれば、金曜は岩隈で絶対取らねばならないが、今日(木曜)からホーム4連戦は、投打の噛み合った試合展開を期待したい。4連勝がもちろんベストだが、大事なことは、一丸となったチームの勝とうとする意識。長いシーズンを戦いきれる展望をファンに与えて欲しい。ホームで、その奮起を見せて欲しい。4連戦の頭。今日の試合が大事だ。ラズナー頑張れ。打線も、頭と体と運気と、すべて駆使してKスタを春満開にして欲しい。
2010.04.22
コメント(0)
-
日本三大うどんと稲庭うどん
JTBパブリッシング『楽楽東北1』(2009年2月)のご当地の麺のコーナーを眺めていた。冷麺、冷やし中華、わんこそば、喜多方ラーメン、板そば。東北の麺はすばらしい。このページにはないが、最近では、やきそばも豊富な顔ぶれが出揃いつつある。さて、稲庭うどんも当然登場しているのだが、機械を使わず掌で何度も練り続け、のど越しと上品な味わい、と説明。そして、四国の讃岐うどん、名古屋のきしめんと並ぶ「日本の三大うどんのひとつ」とある。稲庭が三大うどんの一角を占めるのは東北人の誇りだし、当然とも思う。我が国の三大うどんなる言い方は初めて接すると思うのだが、讃岐はなるほど。ただ、名古屋のきしめんは、確かに名物ではあるし、消費量も膨大だろうが、そんなものか。ネットで見ると、群馬県伊香保の水沢うどんが数えられることも多いようだが。
2010.04.21
コメント(0)
-
へそくりのミステリー
私事だが、ヘソクリ金を机にしまってある。毎月の小遣いを有効に使うがために、全部財布に入れず幾らか分け取っておく趣旨だから、ヘソクリとも言えない僅かで、すぐカラになる。それでも少々溜まると、休日の小旅行で子ども達と各地のラーメンなど食べる楽しみに使ったりする。さて、月曜の朝のこと。ヘソクリ封筒から財布に札を1枚移そうとした時、アレレと気がついた。封筒に誰かが落書きしていた。誰かといっても当然子ども達に決まっている。最近10歳になった2番目の娘の作だな、と直感したが、本人は真顔で否定している。では、3歳上の中学生の姉のイタズラか。引出しに封筒があることは子ども達も知っているし、封筒にお父さんのへそくりと大書しているから、秘密でも何でもなく、誰が書いたとしても全く構わないのだが、お姉ちゃんの作にしては、ちょいと筆致が弱い感じがする。或いは、3年くらい前にでも書いたのだろうか。薄い鉛筆書きで気がつかなかったか。いやいや、気がつかないはずもない。よく見ると、意外とセンスがあるようにも思えてくる...絵文字2つで、封筒の中身を表現したのは言うまでもないが、後ろの栗はともかく、最初の絵の方は、意外と苦労したのではないか。
2010.04.20
コメント(0)
-
大崎市長選は伊藤氏再選
選管最終は、いずれも無所属で1 伊藤康志 34,4042 本間俊太郎25,9243 佐藤仁一 14,656合計74,984票。投票率は市選管のサイトに出ていないが、報道によると、69.30%だった。現職の圧勝に終わったが、3者が約1万票差の形。本間氏と佐藤氏の票を合わせると4万票を超える。朝日新聞によると、本間氏は、病院移転反対の立場で2人出馬したことで、票差がついてしまったと述べたという。
2010.04.19
コメント(0)
-
大崎市長選挙を考える
17時現在の市選管公表では、48.59%とされている。前回73.5%の投票率だが、今回はどこまで伸びるか。事前のマスコミ報道では、70%前後というあたりか。現職の伊藤市長は、前回選挙の公約でもあった市民病院の現在地立替の方針を、昨年変更した。市議会の賛成を得た形にはなったが、これを軸として、合併前の旧町首長などの支持勢力が離れたとされる。その半面で、地元知名度が高い対立候補の2新人が立候補したことが、反現職の票を分け合う懸念も指摘されている。前回は伊藤氏と本間元知事の戦いで、約2400票差で伊藤氏が勝利。河北新報の数日前の予想では、伊藤氏やや優勢とされる。大崎市の人に聞くと、市民病院移転問題は、たしかに関心は高いが選挙の争点という程ではないとの実感だそうだ。なるほど、旧古川市街地の人ならば、2キロ離れた地に移るという拠点病院に対して、行ってくれるな、或いは来てもらえば歓迎、という心理はあって当然だろう。しかし、無くなる訳ではないし、現在地では狭いという課題もあった。さらに、現職の公約違反という政治の争いの道具にされすぎた面もあるのではないか。私自身は、誰が市長に相応しいかの論は控えたい。そもそも、政策の違いがあまり明確でない気もする。いずれにしても、市民病院自体が象徴しているように、県北部地域の生活の拠点として都市機能や魅力を高めて欲しい都市だ。開票は9時30分からだそうだ。今夜の大勢判明を待ちたい。
2010.04.18
コメント(0)
-
四月の雪を考える
私の住んでいる辺りはやっと雪も止んだ。東京では1969年以来41年ぶりに、最も遅い降雪日の記録に並んだという。横浜や千葉では史上最も遅い記録を更新した。さて、ならば東北はどうか。東京が4月17日なら、東北の晩雪はもっと遅いだろう。■雪の終日(平年値) 盛岡 4月16日 青森 4月13日 宮古 4月12日 八戸 4月11日 山形 4月10日 若松 4月9日 仙台 4月8日 大船渡 4月7日 深浦 4月7日 秋田 4月7日 福島 4月5日 酒田 4月4日 小名浜 3月21日(気象台のデータから)小名浜はやはり春が早い。気象台のデータを拾える範囲では、盛岡がもっとも雪が遅いようだ。今日は仙台でも積雪を記録した。13日に気象台が桜の開花を宣言したばかり。昨日は市内の公園でもきれいな桜を見ることができた。河北新報によると、史上3番目に遅い積雪という。仙台の積雪の最晩記録は4月23日(1947年)。積雪記録ではなく降雪の最晩記録だと、仙台は5月3日(1991年)となるようだ。画像は我が家の近く、紅白の梅が雪に囲まれている里の風景。
2010.04.17
コメント(0)
-
花と雪
何と雪降りです。咲きかけた桜に雪がかかる風景を撮りに出かけましたが、身近には良い場所が得られず、結局ご近所のお宅の庭です。美しい梅の花ですが、庭一面が冬に逆戻り。我が家では片づけてしまったのですが、このお宅のコタツに招かれて、しばし冬のひとときを過ごして参りました。
2010.04.17
コメント(0)
-
秋田の高校生就職決定率は例年並み
ABS秋田放送のニュースによると、今春卒業の秋田県内の高校生就職決定率は97.4%で、例年並みの水準に達した。就職希望2709人のうち先月末までに2638人が就職を決定。去年を0.4ポイント下回ったものの例年並みの水準に達した。県教育庁では、各高校の教職員が求人掘り起こしに積極的に取り組んだことが主な要因と分析しているという。この数字も、このコメントも、わが宮城県では耳にすることはないだろう。さて、今春の就職決定状況を機会を見て整理したい。
2010.04.16
コメント(0)
-
食べてみたい米麺ラーメン in 摺沢
岩手日報の記事が気になっている。14日の記事で、一関市大東町摺沢で、地元産の米粉を使ったラーメンを、中華レストラン「バンバン」さんで提供しているそうだ。メニューは2品あるが、5月23日までは特別に500円で提供。一関市の東部(旧東磐井郡)は、気仙沼に行く際などに通ることは何度かあったが、最近はあまり訪れたことがない。摺沢なら、あの芦東山先生記念館も訪れたい。先日記事に書いた千厩の小角食堂の「あんかけかつ丼」も頭に残っているので、是非一関市東部に足を伸ばしたい。
2010.04.15
コメント(0)
-
打ち勝てず 守りきれず
そんな試合が2つ続きました。悔しいですね。夜フロに入っていたら、特別秘書がしとやかにノックして扉を開け、編集長、イーグルスは小山が救援登板しております、と報告してきた。(正確には、下の娘が心配そうにドアを開け、トーチャン、パソコン見ていたら小山が出てきたよ...)3連続カード勝ち越しどころか、借金がかさんでいます。がんばれ、イーグルス。明日は、ラズナー。きびしいナー。
2010.04.14
コメント(2)
-
大井沢の大栗
山形県西川町の大井沢地区を訪ねたことがある。5年前の秋だ。日曜日(11日)の河北新報に、大井沢の地域医療に生涯を捧げた志田周子の顕彰活動の記事があった。寒河江川上流の山あいの寒村で、志田は病人をそりに乗せて25キロも先の町の病院まで歩いたなど、地域の恩人だった。5年前の旅は、鶴岡に向かう途中で、秋の風景を求めて国道から一路大井沢に入り、湯ったり館という温泉施設を訪れ、また、小さな看板を頼りに日本一という栗の木を探訪し、眺めてきた。画像はその時の大栗の写真。走っている姿は5年前の我が子で、栗の木の大きさがわかる。幹周が8メートルもある。旅情あふれる秋の大井沢を思い出し、かの地の昔に思いを馳せている。
2010.04.13
コメント(0)
-
がんばれ!!気仙沼フェア
画像は近くのセブンイレブンです。外から写させてもらいました。気仙沼の食材大集合!! ということで、南米チリ大地震で発生した津波被害を受けた気仙沼を元気にするため、県内の全店で商品を発売。気仙沼港水揚げのカジキステーキ弁当550円です。あたりまえですが、産地に偽装はないでしょう。その他にも、気仙沼加工ふかひれ入り中華春雨スープ398円、気仙沼港水揚げまぐろのひとくちカツ398円などなど。気仙沼市の観光キャラクター 海の子ホヤぼーや もちゃんと登場しています。
2010.04.12
コメント(0)
-
体で覚える富谷の歴史と地名
大亀山森林公園のフィールドアスレチックに挑戦してきました。この公園には、かなり以前にすべり台をしに来たことはあるのですが、そんなことも覚えていない下の娘と2人、人影もない日曜の林を散策しながら、アスレチックを楽しみました。面白いと思ったのは、遊具それぞれに、富谷の地名をもじった名前が付いており、看板には地名の由来などが記されていることです。例えば、画像の遊具は、「明石の朝日のぼり」という名だそうですが、お日様が力強く昇ってくるように、元気に登らなければ成りません。結構難しかったです。娘は軽々と2度もやって見せていましたが。合計20個弱の遊具が配備されていますが、残念なのは、丸太につかまってケーブルをスライドして移動するものや、網の中をくぐって行くものなど、数点は使用禁止になっていることです。さて、看板に書いてあった地名の由来について、いくつか以下に転記しておきます。明石(台) 昔、この地方には里神の明石神社の床石の神に、開運を祈るため、人々が登った台地がありました。この伝説にちなんで新たに明石台という名前がつけられました。明石 平安時代、坂上田村麿(ママ)の子どもが、七北田の洞雲寺に勉学に通う途中、いつも岩下明神の石の上で夜が明けたことから、夜の明ける石と呼ばれ、それが明石になったと伝えられています。西成田 西成田は昔、成田という地名でした。天正年間(1951)まで熊野城主成田源兵衛の居城があったことから、成田という地名が生まれたといわれています。この地方の人は「なんだ」と発音しています。黒川郡内には成田という地名が2ケ所あってまぎわらしいので、明治3年以降は、それぞれ西と東をつけて区別しました。大童 黒川安芸守の家臣、大童豊後は天正年間(1753)以前、この地に住んでいたと伝えられています。明治維新後、村社八幡神社の別当をつとめた大童氏の祖先もこの地に住んでいました。大童の地名は、この二人のいずれかにあやかったものと言われています。一ノ関、二ノ関、三ノ関 宮床側と竹林川流域には古くから広大な田園地帯が広がっていました。この田園に「かんがい」を行うために三つの堰(関)が設けられました。これらの堰は上流から順番に一の堰、二の堰、三の堰と呼ばれておりました。現在の地名はこれらの堰に由来すると思われます。富谷 昔、富谷に「おまさ」という村一番の美人がいました。紫太夫という美男に化けた大蛇が、娘を見染めて毎夜くどきました。密かに男の正体を知った娘は、中国から渡ってきた「こうのとり」の卵をとってくれば従うと約束しました。しかし、大蛇は「こうのとり」の親鳥に反撃され死んでしまったのです。里人はこれをあわれんで死体を十の数に分けてまつったことから、この地を十宮(トミヤ)と呼び、後に富谷と書かれるようになったということです。あけの平 あけの平団地は、平沢及び明坂という地名から文字(もじ)ったもので、新しく移り住む人々が互いに手をたずさえて明るく生きることと、運が開ける(開運)の願いを込めて新たにつけられたまちの名前です。団地内にある「あけの平近隣公園」はいこいの場です。そこからは団地の全景が一望できます。
2010.04.11
コメント(0)
-
ゴルフのスイングで火事?
びっくりさせるニュースだった。我が家の子どもも不思議に受け取っている。そんなことがあるのなら、今までもっと報道されたり、対策が取られているはず。10日午後、ミヤヒル36ゴルフクラブ(大和町)で、50代の男性客がコース内でボールを打った際に引火し、コース内の芝900平方メートルを焼いた。けが人はなし。警察によると、付近にタバコの吸殻などはない。ゴルフ場では、スイングで火花が出ることはあるが、引火した例は初めてとのこと。(TBCニュースから)3人でプレーしていた客が、ラフから出そうとしたところ地面付近から火花が出た。スイングした客が踏み消そうとしたが火の勢いが強く、119番通報したところ、消防車5台が駆けつけ、現場は一時騒然となった。火は20分後に消し止められた。(産経ニュース)今朝の河北新報では、詳しく出ている。17番ホールのフェアウェイで、第2打を5番アイアンで打った際に出火した。クラブによると、芝は新芽が出たばかりで枯れ草も多かった。ベテラン従業員は、スイングで火花が飛ぶことはあるが、焼けたのは初めて、という。まさかのミステリー(今は昔の番組ですが)に出てきそうな話だ。科学的に、いつくかの条件が偶然的に重なって、発生した現象だろう。乾燥注意報が出ていたことも関連しそうだ。それにしても、アイアンのヘッドと枯れ草の摩擦だけで燃え広がるのだろうか。何か小石のようなものがあったのだろうか。もし事件が学校や福祉施設なら、すぐさま対策と称して、あれこれ規制がはめられ行政の手厚い指導があるだろう。ゴルフ場は大人の娯楽いやスポーツの場で、施設も野外だから、規制もなかろう。それでも、もし頻発の恐れがあるならば、客離れを防ぐ意味で業界側が安全対策をアピールするのかも知れない。プレー中は消火器を携帯すること、そしてその消火器はゴルフ場側がプレゼントしますよ、とか。ありえないが。
2010.04.11
コメント(0)
-
丸森ファンねっと会員になりましょう
自然豊かな丸森の魅力を満喫できるファンクラブ。皆さん、登録しましょう。私も案内をいただきました。そのうち入会しようかと思っております。丸森ファンネットワーク運営協議会(町役場)の募集パンフのとおりで、レギュラー会員(3000円)、ゴールド会員(10000円)、プレミア会員(20000円)があり、それぞれ特典として特産品が送られるそうです。このほか、情報会員(1000円)もあります。考えてみると、宮城県民の私ですが、丸森町を訪れたのは、4回か5回しかありません。ここを通過してどこかに向かうということが、基本的にないことから、丸森に用事があって行くのでないと、この町には行かないことになります。斎理屋敷、不動尊公園などに行ったことはあります。また、通過は基本的にないと書きましたが、実は梁川に抜ける際に丸森町を通過したこともあります。それでも、4回か5回しかありません。旗巻古戦場、筆甫地区、阿武隈川ラインなど、まだまだ知らない魅力がたくさん待っているのです。皆さんも、登録しましょう。がんばれ丸森。
2010.04.10
コメント(0)
-
仙台のエスカレーター作法を考える
今日(9日)の読売新聞に出ていた。エスカレーターに乗るときに、急ぐ人に道を空けるのが通例だが、普通の人は東京では左に立ち(急ぐ人は右)、大阪では右に立つ。仙台の場合は、一定に定まっていない、という。デパートでの実際の写真が出ていて、たしかに混乱がみられるようだ。私の感覚では、10年くらい前までは、仙台でも大抵は右に立っていた(急ぐ人は左)ように思う。とにかく、東京と仙台で違う、と記憶していた。しかし、今ではJR仙台駅の朝の時間帯は、左に立っている。仙台駅だけのルールかとも思われるが、最近できた青葉通りからペデストリアンデッキに登るエスカレーターでも、みんな左側に立っているので、仙台でも、左に立つのが定着したと言えるのではないだろうか。東京人の影響か、それとも、地域性などもとより関係なくて、たまたま先頭の人に合わせたのが定着したのか。日本の西と東の固有の文化論があるが、おそらくそこまでは及ばない偶然の所産だと思われるが、一応気になることだ。
2010.04.09
コメント(0)
-
塩竈寿司めぐり
みやぎ寿司海道 塩竈寿司めぐり という名の小さなパンフレットがある。みやぎ寿司海道塩竈地域推進協議会(塩竈市観光物産協会加盟寿司店)が発行と書いている。アンケートハガキが綴じ込まれており、今回ご利用頂いた寿司店はどこか、と14の寿司屋さんを並べてマルを付けさせるようになっている。なるほど、このパンフは加盟店に常備しておくもののようだ。特典としては、アンケートに答えると、抽選で20名に食事券や地酒などが当たる。また、ハガキの下を切り取ると、お店自慢の一品をサービスしてもらえるクーポン券。これは、気仙沼や石巻の寿司海道参加店でも利用できるそうだ。いろいろ考えていますね。このパンフによると、塩竈は、1平方キロあたりの寿司屋の数が日本一と言われているという。ちなみに、アンケートのハガキに列記された店は、一森、大入、亀喜、しらはた、寿司仙、すし哲、すし徳、魚作、鮨のしおがま、山孝、大黒、仁王、はま勢、丸長の14店舗だ。行ったことのあるのは、4つくらいか。
2010.04.08
コメント(0)
-
打ち子募集を装う振り込め詐欺
福島県で発生しているという新手の詐欺のようだ。パチンコ台の玉がよく出るように見せかけるサクラの役で、1日1万7千円の報酬だが、登録料20万円を指定口座に振り込め、というのだ。被害男性は、事前研修などの名目で、合計1600万円も振り込んだという。正直に言って、被害に遭った人の対応も常識はずれだと思うが、もちろん騙した方が悪いに決まっている。警察には摘発をお願いしたい。
2010.04.07
コメント(0)
-
青森県の所得 六ケ所村がダントツ
青森県の平成19年度市町村民経済計算が発表された。1人当たり市町村民所得では、六ケ所村がトップの1520万円。しかし、前年より698万円も減少している。2位が東通村の292万円なので、いかに六ケ所が突出しているかが分かる。3位以下は、八戸市、青森市、おいらせ町と続く。(毎日新聞による)青森県の公式サイトのファイル(人口1人当たり市町村民所得)にあるとおり、六ケ所村は、文字通り桁違いだ。そもそも、18年度の2219万円が異常値であり、前年の17年度が321万円である(それでも県内トップ)のに比較して、驚異的な伸びだ。もちろん、村民1人の実際の所得が向上したのではなく、再処理工場の建設関係のようだ。統計上は人口で割って見せるから、こうなるのだろう。陸奥新報では、中泊町が148万円で県内最下位であること、また、前年比マイナスの市町村が多かったことについて、コメ産出額の減少や公共工事の削減、小売・卸業の不振が影響した、と説明している。
2010.04.06
コメント(0)
-
千厩の「あんかけかつ丼」
一関市千厩の小角食堂の「あんかけかつ丼」は今や全国区の知名度だそうだ。大正14年創業の老舗であるこの店で60年も親しまれているメニューで、マスコミにも取り上げられ、県外からも多くの人が訪れる。こっかど食堂、と読むようだ。ご飯の上に、千切りキャベツと揚げたてのカツ。その上から甘酸っぱい濃厚なあんをたっぷりかけたものだそうだ。豚肉は、藤沢町の館ヶ森アーク牧場のものを使うという素材のこだわりも。FOMAP2010春号(NTTドコモのフリーペーパー)の一ページに、東北のカツ丼を紹介するコーナーがあり、小角食堂とおいしそうな「あんかけかつ丼」が紹介されていた。800円です。ところで東北でカツ丼と言えば、やっぱり会津。このページには、会津若松の「伝統会津ソースカツ丼の会」や白孔雀食堂が紹介され、また、山形県河北町の一寸亭本店のソースかつ丼も紹介されている。(「カツ丼」「かつ丼」の表記は上記パンフの記事に従った。)■関連する過去の記事 ソースかつどんの会津(08年9月9日)
2010.04.05
コメント(0)
-
がんばれ!イーグルス
この記事実は1週間後の11日に書いています。4日のSB戦は我が家の今季初観戦でした。田中の力投報われず、中軸の不振極まった感がありました。しかし、その後、ノリや山崎が当たりだし、直人も復調。そして、好調ヒジリの活躍が継続し、草野も先発定着の雰囲気です。強いイーグルスの無形の力が甦ったようです。画像は、3日の土曜日に張った順番待ちのシート。いつも子ども達が作ってくれます。岩隈が崩れてワンサイドの長い負けゲーム。終了まで待った行列も、寒かった。今、そのことを思い出しています。昨日は岩隈初勝利。今日(11日)の田中もスイスイ、打線もお祭りを期待しております。
2010.04.04
コメント(0)
-
3月の久慈市長選挙を考える
宮城県では大崎と気仙沼の市長選挙が注目されている。先月のことになるが、久慈市長選挙は、大変な僅差だったので印象に残っている。もちろん、票差の絶対値は制度上意味が無く、勝ち負けだけがモノを言うし、候補擁立や争点を巡る地元の政治状況をよく知らないで数字だけを見て受け取る感覚に過ぎないのではあるが、それにしても53票差とは、本当に僅かの票差だ。久慈市長選挙(3月14日) 当 10562 山内隆文(58)無現 10509 遠藤譲一(56)無新 582 宮古邦彦(70)無新投票率70.61%(前回58.30)山内氏は、県議会議長を経験した自民党の要人。底堅い支持基盤の山内氏を遠藤氏が猛追するという構図だったようだ(岩手日報)。現職の山内氏に対して、前の県南広域振興局北上総合支局長である遠藤氏が、民主と社民の推薦を得て、市政革新を訴えた。岩手県では、県の職員が首長に就任するケースが多いが、同日に行われた奥州市長選挙でも、現職の元県職員が1万票以上の差で敗退している。遠藤氏の場合も、思ったより浸透しなかった(毎日)ようだ。遠藤氏には、かつて山内氏との間で市長選挙を戦った旧市市長だった久慈義昭氏が支援に回ったという。達増知事や畑代議士など、民主党の総力を挙げて追撃を図ったが、わずかに及ばなかったようだ。ところで、再選された山内隆文氏の父親、山内堯文氏はかつて6期連続で市長を務めた大物だ。そして、1979年、県議から出馬した久慈義巳氏に敗れる。翌年春、義巳氏病死後の市長選挙で、長男で30代前半の義昭氏が当選している。そして、2003年には、7選を狙った久慈義昭氏を、県議5期の山内隆文氏が破ったのである。両家を軸にした地元政治の構図、か。なお、宮古氏は新聞発行業だそうだ。久慈市職員を経て、1985年にミニコミ紙・東亜新報社社長に就任(岩手日報)。かつて久慈市では久慈さんが市長を務めており、宮古さんが仮に市長になれば話題だと思ったが、果たせなかった。この方、旧市時代から6回連続で立候補しているそうだ(デーリー東北)。
2010.04.04
コメント(0)
-
イースタン利府球場の開幕戦
娘と2人、車で出かけてみました。イースタンリーグの対ジャイアンツ公式戦で、利府町野球場のホーム開幕戦です。
2010.04.03
コメント(2)
-
がんばれイーグルスの絵
家に帰ったら、壁に貼っていました。我が家の応援団長、娘の絵です。よく見ると、EAGESで、1文字足りませんが。さあ、今5-4でリード。ホーム3連勝目指して、頑張れイーグルス!
2010.04.02
コメント(0)
-
石巻で食べずに帰る客が4割も
豊かな海の幸を誇る石巻で、わざわざ食事をしないで帰る客が4割もいるそうだ。石巻かほくの記事だ。石巻専修大学の調査チームが調べた。すしや刺身など、食べたいと思っても、実際には期待に合致する食事を提供する施設がない、などと厳しい指摘だ。厳しい。けど、分かるような気もする。工夫の余地は、それこそ豊かにありそうだ。
2010.04.01
コメント(0)
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天お買い物マラソンで目が疲れて限…
- (2025-11-15 20:30:04)
-
-
-
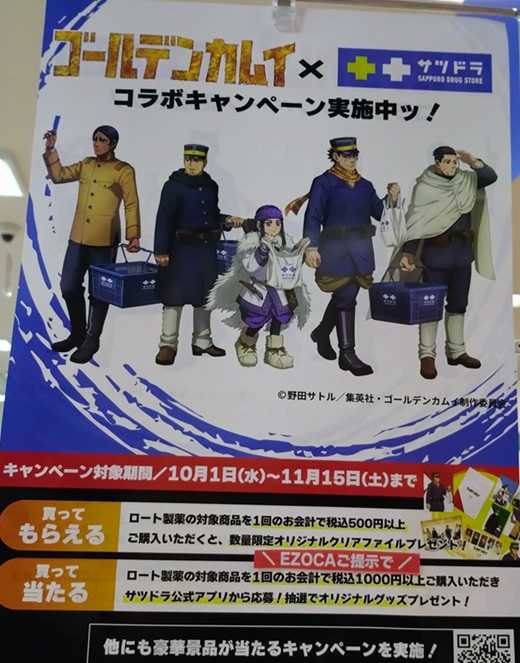
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-







