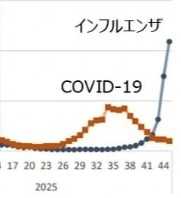2010年11月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
仙台のロータリー(その5)ひより台
旧286号からひより台を目指して道を登る。上野山小学校入口、月ヶ丘を過ぎて坂を上がっていくと、ひより台団地に出る(仙台市サイトの地図)。最初に出会ったのは、小さい方のロータリー。画像では見にくいが、杉の木が植えられていたように思う。もう一つはバス通りの真ん中に堂々としたロータリー。車もバスも、周回していた。■関連する過去の記事(仙台のロータリー) 仙台のロータリー(その4)東仙台5丁目(2010年11月26日) 仙台のロータリー(その3)永和台(2010年11月22日) 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)■関連する過去の記事(ひより団地の周辺道路など) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日)
2010.11.27
コメント(0)
-
仙台のロータリー(その4)東仙台5丁目
またまたロータリーの話題。東仙台5丁目の案内公民館付近です。造成時期からすると、仙台で一番古いのではないでしょうか(未確認)。県道仙台松島線を、松岡町の信号から案内公園側に登っていくと程なく到達します(地図)。■関連する過去の記事(仙台のロータリー) 仙台のロータリー(その3)永和台(2010年11月22日) 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)■関連する過去の記事(案内公園) 仙台百景画像散歩(その3 東仙台案内踏切)(06年3月22日)(06年当時は、案内の名の付くものを2つしか探せなかった。今なら、堂々と「ねすと案内集会所」を挙げます。)
2010.11.26
コメント(0)
-
茂庭のトンネル
太白トンネルの続きで、秋保電鉄の遺構。茂庭浄水場の下をくぐっている「さかのしたトンネル」です。往時は、この付近(西側に出た辺り)に萩ノ台駅があったそうだ。■以前の記事 山田自由ヶ丘のバス専用道(2010年11月24日) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 23)(2010年10月23日)■参考(秋保電鉄関係) 秋保電鉄 宮城の旅 秋保電鉄 廃線探索-秋保電気鉄道(いずれも素晴らしいレポートで敬服いたします。) 秋保電鉄と沿線の歴史を探る(仙台市教育委員会教材映像アーカイブ)
2010.11.25
コメント(0)
-
山田自由ヶ丘のバス専用道
珍百景にも出そうな道路の真ん中の電柱。外側はバス専用の車道になっている。山田自由ヶ丘の宮城交通バス車庫付近の光景です。■関連する過去の記事 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日)■参考(秋保電鉄関係) 秋保電鉄 宮城の旅 秋保電鉄(いずれも素晴らしいレポートで敬服いたします。) 秋保電鉄と沿線の歴史を探る(仙台市教育委員会教材映像アーカイブ)
2010.11.24
コメント(0)
-
太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)
旧秋保電鉄の太白トンネル(旗立トンネル)である。勤労感謝の休日、編集長と公設第二秘書(2番目の娘)は探険に出かけた。以前から聞いていたが実際に見たことはない、あのトンネルを訪ねて。本降りとは言えないまでも、冷たい雨は気持ちまで湿らすようだ。太白山も息苦しいように煙っていた。山田自由ヶ丘の宮城交通バス車庫の手前。ちょうど東北自動車道をくぐるところだ。ここに登ってくるまでの旧秋保電鉄の軌道は、現在の旧国道286号の山田市民センター付近交差点からこの団地に向かう通り(この日記では山田自由ヶ丘・太白団地線とします)に沿っていたようだ。思うに、この山田自由ヶ丘団地に向かう道(山田自由ヶ丘・太白団地線)(おそらく旧電鉄軌道)が旧286と交差している所から、ほんの数軒ほど旧286を長町寄りに行くと、今度は西多賀病院や上野山団地・ひより台団地に登る別の道(この日記ではひより台線とします)が分岐している交差点がある。これらの2筋の登り道は、並行して走っているような関係にある。たぶん、開発史的に言えば、主要車道としてはひより台線が先行し、その後に太白団地(宮城県住宅供給公社だと思う)の開発などと併せて、旧電鉄路線沿いの山田自由ヶ丘・太白団地線が開かれたのではないか、と推察する。違うかも知れないが。全然関係ないのだが、今日太白団地を久々に訪れた。もう30年近くも前だが私の自動車教習コースだったはずだ。大きなスーパーがあったのは記憶にあるが、今はかなり古びていた。あのときのコースは、旧286から山田自由ヶ丘・太白団地線に折れて、途中から同線を別れて太白団地に向かう道路に入る。団地の中で、たぶんこのスーパーを見ながら周回して元の道をもどって旧286に戻り、今度は新道(286バイパス)に出たようなルートだったと思う。今回はひより台線をのぼって、ひより台・太白団地から山田自由ヶ丘に出て、冒頭のトンネル地点にたどり着いた。旧286から山田自由ヶ丘・太白団地線を登ってくれば、さらに昔の記憶を掘り起こせるのかも知れない。話を戻して、旧電鉄のトンネルだ。山田自由ヶ丘の太白トンネル入口に立ちつくした編集長と秘書だが、やはり中に入る勇気は、なかった。一応反対側も見たいと思い、来た道路(旧電鉄の路盤がバス専用道路になっている珍しい区間)を引き返し、今度は人来田(仙台南ニュータウン)から団地西側を降りて高速道をくぐり抜けて茂庭浄水場の側に出る。高速道沿いにしばらく北に行くと、林道でこれ以上立入禁止という看板がある辺りに、おそらく太白トンネルの出口から続いて東北道の西側に出ていると思われる小径があった(冒頭の画像)。旧秋保電鉄の路盤なのだろう。■参考(秋保電鉄関係) 秋保電鉄 宮城の旅 秋保電鉄(いずれも素晴らしいレポートで敬服いたします。) 秋保電鉄と沿線の歴史を探る(仙台市教育委員会教材映像アーカイブ)■シリーズ仙台百景 以前の記事です。こんな企画で100枚まで続けるのが目標です。 ○富士宮やきそば(シリーズ仙台百景 31)(2010年10月17日) ○フェンスのメッセージ(シリーズ仙台百景 30)(2010年2月28日) ○宮城刑務所(シリーズ仙台百景 29)(08年10月12日) ○松森焔硝蔵跡(シリーズ仙台百景 28)(08年8月31日) ○十一面観音堂(シリーズ仙台百景 27)(07年10月23日) ○陸奥国分寺薬師堂(シリーズ仙台百景 26)(07年10月17日) ○県民の森 鶴ケ丘口(シリーズ仙台百景 25)(07年8月26日) ○一時停止だ!三時はお茶だ!(シリーズ仙台百景 24)(07年8月20日) ○風の環(シリーズ仙台百景 23)(07年7月7日) ○冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日) ○県民の森(シリーズ仙台百景 21)(07年4月8日) ○数字の練習ボード?(シリーズ仙台百景 20)(07年3月25日) ○半田屋一番町に進出!(シリーズ仙台百景 19)(07年3月1日) ○仙台百景画像散歩(その18 撮影成功!霊気のトンネル)(07年2月6日) ○仙台百景画像散歩(その17 変な漢字の看板)(07年1月28日) ○仙台百景画像散歩(その16 駅前東宝ビル)(07年1月13日) ○仙台百景画像散歩(その15 空から見た仙台)(06年12月29日) ○仙台百景画像散歩(その14 光のページェント)(06年12月13日) ○仙台百景画像散歩(その13 東京スター銀行)(06年11月30日) ○仙台百景画像散歩(その12 建設ラッシュ再来?)(06年11月10日) ○仙台百景画像散歩(その11 E721系電車)(06年7月25日) ○仙台百景画像散歩(その10 ワンコイン端末)(06年7月7日) ○仙台百景画像散歩(その9 ヤギさんの看板)(06年6月19日) ○仙台百景画像散歩(その8 キック治療?)(06年6月18日) ○仙台百景画像散歩(その7 ホテルモントレ)(06年6月4日) ○仙台百景画像散歩(その6 佐々重ビル)(06年5月24日) ○仙台百景画像散歩(その5 車止めポール)(06年4月29日) ○仙台百景画像散歩(その4 オロナミンC)(06年4月4日) ○仙台百景画像散歩(その3 東仙台案内踏切)(06年3月22日) ○仙台百景画像散歩(その2 はんだや)(06年3月18日) ○仙台ミステリー?風景(06年3月4日)
2010.11.23
コメント(0)
-
仙台のロータリー(その3)永和台
すっかりロータリー好きになった訳ではないのですが、今日も近くを通ったので寄ってみました。永和台団地の小さなロータリー。県道仙台三本木線を国道4号バイパスから少し進んでいくと、東北学院大学を過ぎてすぐに、永和台入口の信号のある交差点がある。これが団地の入り口。これを登っていくと、このロータリーを通ることになります。県道側に降りてゆく斜面に設けられているため、北と西には木々が豊かに色づき、南には学院大学の建物が見えました。このロータリーをさらに東に登っていくと松陵団地に出る。県道仙台三本木線から松陵団地に出たことは何度かありますが、実はいつも永和台入口より1つ先の信号(山の寺3)から登っていたはずです。向陽台中学校を右手にしながら登るこの方が、道も広く傾斜も緩やか。したがって、わたしは今日初めてこのロータリーに出会ったのだと思います。ところで、県道を挟んだ北西側の丘陵には、あの向陽台の大ロータリーがあります。前回撮影したもの以外にも、やや西側にやはり大きなロータリーがある(向陽台保育所付近)。また、富谷町分の東向陽台団地には鉄塔を囲むサークルの形のものが2つほどある。高圧電線の鉄塔があった事情が大きいとは思いますが、まるでミステリーサークルのようにボコボコと多数あります。おそらく仙台では随一でしょう。そして、ミステリーゾーンを降りて向かいの永和台団地には、この小さいながらも美しいロータリー。赤い花が印象的。この交差点を南に向かうと、松森団地(歩坂町)に出て、市名坂のヤマダ電機の辺りに降りるようです。かなり交通量もありました。(地図)■関連する過去の記事 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)
2010.11.22
コメント(0)
-
仙台のロータリー(続)
地図を眺めて探した。桜ヶ丘、向陽台、永和台、日本平のほかには...やっと見つけたのは、中山吉成の団地内に2か所。よくヨーロッパの大都市などで、自動車がグルグル回っている巨大なラウンドアバウトがみられる。日本では、他の都市は知らないが仙台に関して言えば、比較的早期の団地開発で、団地内の交通結節点に、シンボル的な意味も添えて設けられているように感じる。現在ならば、直交にして信号を設けるのが好まれるのだろうが。あとでまた探してみます。■関連する過去の記事 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)
2010.11.22
コメント(2)
-
仙台のロータリー交差点を考える
地図を眺めていた。向陽台団地のロータリー。不思議だが、なぜか懐かしい感慨におそわれる。国道4号から坂を登って団地に入り、セブンイレブン(たぶん30年近く続いていると思う)の角を折れて平らで大きな道路に出る。ずっと進むとロータリーがある。たしか送電線の鉄塔があったようにも記憶している。よく見たら、地図ではこのロータリーが、ミッキーマウスの耳のように、ギリギリで富谷町(東向陽台)の領分となっている。ところで、交差点をロータリーにするのは、おそらく交通計画上の検討を経て決めているのだろうけれど、最近の団地には少ないような気がする。思いつくのでは、向陽台の外には、桜ヶ丘団地のど真ん中にある。また、太白区の日本平にも、かなり小振りだがロータリーがあったと思う。泉区の地図(ゼンリンのmi-ru-to)を眺め渡すと、向陽台の近く、永和台団地の入口から登ったところにもそれらしいものが見える。追記。この画像は今日の午後に撮影したので埋め込んだ。地図を見て向陽台のロータリーを思い出したのは朝のことで、その後昼の仕事がたまたま付近だったので、ちょいと寄り道して久々に「再会」を果たした。傾きかけた夕陽を浴びながら、何も言わず(当たり前です)、ゆっくりと周回する車たちの渦の中にがんばって存在していた。
2010.11.21
コメント(0)
-
宮城県の高校の進学実績を考える
学校要覧やホームページなどから拾って整理したもの。現役合格だけを拾っている。もちろん、仙台二や仙台一の場合は特に、これ以外に浪人合格が多数あるのだが、現役での進路達成を高校の重要な務めとする立場から、あえて現役だけに絞った。 高校名現役・国公立うち東北大備考仙台第一11328仙台第二13768仙台第三16022宮城第一10621仙台二華9710仙台三桜100泉876仙台向山9411泉松陵30泉館山11810仙台南1004富谷380宮城野596市立仙台200白石263旧白石分のみ古川725石巻1038気仙沼470仙台育英6113秀光中等教育191古川学園6111東北10前後0東北学院3816(※)※過卒含む山形東13152医?東12米沢興譲館12914酒田東13016盛岡第一17044医?東8花巻北15514一関第一12315医?東1会津15514安積17626秋田18050医14東10青森18224医17東0八戸15333医11東2高校の力を評価する場合に、国公立で測ること、東北大学を目安にすることについても様々な意見があるだろう。また、私学の場合は推薦制が多様に存在するメリットなどもあるし、一概にこれだけの指標で議論できないことは当然だ。しかし、もしシンプルに尺度を示すなら、やはり「現役」での国公立合格実績、そして東北大学合格者数の比率を併せ見るのが、さしあたり一番わかりやすいと思う。詳しい分析は後回しなのだが、共学化で白石、古川、気仙沼あたりは今後とも進学実績を伸ばすであろう。仙台二高はいまだに現役合格数が極めて少ないが、東北大学の比率は、山形東と並んで抜きん出ている。合格者のちょうど半数が東北大なのである。おそらく二高は名実ともに東北のトップ高の地位を不動にするだろう。もっとも、現役進路達成の実力と雰囲気を着実に備えて欲しいのだが。後ほど評論を整備したい。
2010.11.20
コメント(0)
-
仙台二華中・高校
宮城県第二女子高校を前身に今年からスタートした。かねてから当ジャーナルで指摘してきた仙台・宮城の高校教育の沈滞を打ち破るリーダーとなって欲しい。今月上旬の秋晴れの休日に、荒町や連坊を散策した。二女高というと連坊小路で仙台一高の近くという思いこみのイメージがあったが、歩いてみたら新寺通りにもすぐ出られ、仙台駅にも歩いて10分足らずだろう。お寺がたたずむ文化の香り高いエリアに、関東以北の高校で例がないという7階建ての校舎。県立初の仙台での中高一貫でもある。恵まれた教育環境を得て、大きく踏み出す、その第一歩が今なのだ。しばらく宮城の教育関係の論評から遠ざかっていた。そろそろ再開しなければならないのだが。
2010.11.19
コメント(0)
-
急に肩が凝る
なぜか帰宅する頃になって急に右肩が重くなった。回した左腕で揉んでみたりしたが、逆に違和感を増したような気もする。とにかく、辛い。原因としては、いや関係ないかも知れないが、最近朝晩寒いのでコートのポケットに手を突っこんで上半身を前に倒したようにして、銀杏の葉っぱなどを踏みながらスタスタ歩いている。(昔友人Fはサザエさん歩きと命名した。)このとき、勢い肩も丸めてしまうのではないだろうか。どうでも良いのだが、まずは背筋を伸ばして早めに寝ることとしよう。
2010.11.18
コメント(0)
-
栽松院の白樫
真新しい仙台二華中高の校舎のお隣に、静かに佇んでいる。推定樹齢千年の白樫だ。仙台の保存樹木(仙台市サイト説明)。栽松院は伊達政宗の祖母(久保姫)の位牌寺。お墓は根白石の白石城にある(仙台市サイト白石城跡 根白石 白石城と栽松院)。政宗を守り育て、政宗もまた深く敬愛した。昭和62年のあの大河ドラマでは誰が演じたのだろうか。調べてみたら、谷口香さんだったとのことだ。
2010.11.17
コメント(0)
-
泰心院の山門(藩校養賢堂正門)
ピンボケだが、荒町通り(旧奥州街道)からちょっと入った泰心院さんの山門だ。伊達の藩校養賢堂の正門を移築した。仙台市有形文化財(解説)。ところで、久々にこの辺りに来て驚いたのだが、仙台箪笥伝承館付近で荒町通りに交差する幅の広い道路を工事している。連坊小路から東北本線を跨いで(新幹線高架下を)つながってくるようだ。とすると、国道45号からここまでストンと南北の直結路ができるのだろう。この都市計画道路は、荒町通りを横切り更に南下して、舟丁橋まで届くようだ。そして、舟丁橋の辺りで、国道286号根岸交差点から広瀬川を渡って(宮沢橋に新橋を架ける)若林区役所やウルスラの南に既に出来ている幅の広い道路まで、ちょうど七郷堀沿いに東西に通るであろう街路と交差するのだ。(仙台市の都市計画インターネット情報が便利)仙台の街も変わるんだべな。
2010.11.16
コメント(0)
-
飛び地の多い上谷刈
一番町の金港堂さんで、100周年記念のブックフェアをやっている。すばらしい企画で早速今月初めに足を運んだのだが、本を買ってカレンダーをもらった。もう年末なのかとビックリしたが、開いてみると仙台の地図になっていて、眺めていたらあることに気が付いた。七北田川の付近で、大字の上谷刈、野村、古内が、七北田川の流域沿いで複雑に絡み合っている。特に、上谷刈の飛び地が野村や古内の中に何か所も入り込んでいるのだ。大字別に色を分けているからハッキリわかる。今まで気が付かなかった。それにしても、随分と複雑だ。気になったので、最近泉区内に全戸配布したゼンリンの地図情報マガジンmi-ru-to(泉区)で確認した。この冊子は、さすがゼンリンだけあって、ベースとなる地図情報も非常によく出来ていて、地図好きには持ってこいだ。大字も色分けされているし、小字も点線でエリアを表示している。上谷刈は七北田川の以南だと漠然と思っていたが、例えば、野村小学校の南側に、野村に囲まれた形で飛び地で存在し、また、パークタウン入口交差点(古内大橋の北)周辺は、野村と上谷刈が実に複雑に入り組んでいる。総じて言えば、野村は七北田川の北岸だが、上谷刈が野村の中に虫食いで随所に入っているという感じだ。念のため、我が研究所の仙台地図ライブラリー(3つしかないのですが)の1991年版を開いてみる。大字の色分けはあるが、最新のmi-ru-toとは様相が違う。91年の地図が大字を精確に色分けしていないのかも知れないのだが、それだけではない。線引きがまったく異なる場所もあるのだ。例を上げると、北河原公園のあるエリアは、現在は上谷刈だが、91年の地図では野村としてカラーリングされている。また、加茂団地(町名表示は加茂2丁目)に隣接する北側は、長命橋を越えて七北田川の反対岸(野村小学校近く)までが、91年地図では古内とされているのだが、現在は、七北田川以南は上谷刈、さらには川の北側も上記のように野村小学校南に飛び地の上谷刈が存在する。こんな風に文章で書いても、わかりにくい。一体何でこんなに複雑になっているのか。また、ここ10年や20年で様相が変わるのか。考えられるのは、昔なら区域外の人のための神社や耕作地などだろうか。それにしても、近時複雑に変動するのはなぜか。研究課題とします。
2010.11.15
コメント(0)
-
船で脇谷閘門を通過する
貴重な体験だった。登米船着場から北上川を下り、旧北上川への分流地点である脇谷閘門を船で渡った。新北上川(放水路)と旧北上川に85%対15%の割合で流れを配分しているが、本流と旧北上川では1.5mの水位差があるため、パナマ運河と同様の方法で、船体を前後のゲートで閉じられた区画に入れて、徐々に水位を下げてから旧北上川に出るのだ。待ち時間は20分くらいだったか。ちょっと解説を加える。北上川は壮大な改修の歴史を持つが、前世紀前半に本川を分流させる大工事を行った。すなわち、1911年(明治44年)から1934年(昭和9年)までに柳津と飯野川の間に河道を開削、追波川を利用して新北上川を放水路として追波湾に導いた。旧北上川は1920年(大正9年)から1932年(昭和7年)までに改修を行い、分流堰として鴇波洗堰、脇谷洗堰が建設され、舟運確保のため脇谷閘門も併設された。完成した分流施設は、二本の澪筋が大きな中洲を囲む形で、それぞれの澪筋に堰(脇谷洗堰、鴇波洗堰)が設けられている。2つの洗堰は、下部にオリフィス構造を有し、平時は一定流量を旧川に分配し、大半の水は本川(放水路)に導く。大規模な出水時には堰体を越流してある程度は旧川にも洪水を流すという仕組みだ。しかし、河川計画上は洪水時の旧北上川への分派はゼロとしているため、越流する構造を改めて、洪水時の旧川への流れを阻止する改築が必要とされた。そして、文化的価値の高い既存施設を残しつつ、新たに2つの水門を設置することとし、1996年に建設に着手。こうして120億円をかけた「旧北上川分流施設」は08年3月に完成。内陸地震の影響で1年遅れて09年に落成式を登米市津山町柳津の現地で開いた。新設された2つの水門は、脇谷水門と鴇波水門。脇谷水門は、本体26m、ゲート高12.8mで、板状のゲートをワイヤウインチで上下させて開閉する。鴇波水門は本体20m、ゲート高3.5mでドラム缶を縦に切ったような特殊な形のゲートを回転させて開閉する。私たちの乗った船は、新しい脇谷水門の黄色いゲートをくぐって、歴史的価値のある閘門施設で水位調整を受けた。旧北上川に出てからは、中洲を回り込む形で鴇波洗堰の方にも船を寄せた。遡上するサケを網でつかまえる光景が見られた。■参照 北上川脇谷閘門「クルーズ船通る」-Wind of TOME-NO.6 (まさに我々の乗船したクルーズの動画のようです!) 新・旧北上川の分流地点 (大変わかりやすいので引用させていただきました。Mr.Kappaさんの北上川ガイド) 北上川の河川改修の歴史(河川事務所) 旧北上川分流施設の竣工式の記事(登米市資料) 分流施設の解説(国土交通省の資料)■関連する過去の記事 宮城県の渡船を考える(2010年6月5日)(鴇波・柳津の渡しの廃止) 北上川改修の歴史と流路の変遷(08年2月17日) (リンクしていた流路変遷図が切れています。上記の河川事務所サイトを参照下さい。) 北上川流域の「水山」(08年2月11日)
2010.11.14
コメント(0)
-
愛宕堰、七郷堀
仙台開府以来、まちを潤し産業を支えた七郷堀・六郷堀の起点、愛宕堰周辺を散策した。(県政だより11月号の表紙にも出ていたが。)広瀬川の越路側の河岸は、歩道が整備されているが、土樋側は切り立った崖の上に、鬱蒼とした森の雰囲気だ。愛宕橋のたもと、真福寺向かいの墓地脇を人ひとりがやっと通れる通路を進んでいくと、民家やアパートの中の路地につながる。しばらく歩いて、静寂の世界から一旦国道4号に出てしまったが、石垣町の信号のある交差点から再び広瀬川をめざして横丁に入る。すると、ほどなくして左手に変電所施設を見ながら、道は下りながら、広瀬川から別れてきたばかりの七郷堀を渡る小さな橋につながるのだ。橋を渡り、右方向に少しだけ歩くと、広瀬川本流から堀に流れ入る樋門の案内標識がある。ここは、本流と堀にはさまれた地点で、再び静寂の世界から、広瀬川を望んで急に空間が開けた感じだ。堀はここから、分岐しながらの城下を潤す水の旅に出て行くのだ。引き返して今度は七郷堀沿いに歩を進めていくと、急患センター付近で国道4号をクロスし、舟丁、南材木町、南染師町と続いていく。水の流れと歴史の流れを感じながらの散策だった。
2010.11.13
コメント(0)
-
華足寺
登米市東和町の国道346号から分かれて、鱒渕(ホタルの里)方面に向かうと、集落の先の小高い山に華足寺がある。山門は寛政11年(1799)伊達9代藩主周宗公の祈願によって建てられた。見事な建築だ。開山は古く、坂上田村麻呂の霊を弔うため、大同2年(807)建立されたという。ご本尊が鱒渕馬頭観音大菩薩で、田村麻呂の乗った馬の骨が納められているとか。全国の馬や牛などを扱う人びとから信仰され、一時は競馬関係者で賑わったという。山あいの里に、静かに佇む偉容だ。■関連する過去の記事 海無沢の三経塚(2010年11月11日) カトリック米川教会(2010年11月9日)
2010.11.12
コメント(0)
-
海無沢の三経塚
登米市米川の町を、小学校のあたりで西郡街道から国道456号に分かれて、やや北に向かうと、綱木地区に出る。道脇に綱木農村公園(綱木親和会館)があり、小高い山に登ると、海無沢の三経塚がある。1720年頃処刑された殉教者の亡骸は、経文とともに3か所に埋葬され、松を植えたと伝えられている。海無沢、朴の沢、老の沢の3か所で、老の沢経塚は訪れる人もない。海無沢の小高い山上では毎年6月第一日曜日にキリシタンの里祭りが行われ、多くの信者が山上青空ミサに集い、殉教者の心に思いを巡らせる。また、この殉教地の下にある広場では地元の芸能や市が奉納される。(カトリック米川教会のパンフレットから)綱木沢の海無沢、朴の沢、老の沢(経の森)に鉱山があって、大籠、保呂羽方面から多くのキリシタン並びに類族達が来て働いていた。享保年間のキリシタン弾圧の時召しとらえ、はりつけにされ処刑された。その遺体が、40人ずつお経と共に三か所に埋められた。これが、三経塚と呼ばれていたが、朴の沢、老の沢の松は切られ、塚は掘られ、原形をとどめているのは、この海無沢の塚一つとなっている。1639年から40年、近くの大籠(岩手県藤沢町)で約300名が殉教する。大籠は仙台藩の製鉄の場で、備中から信者の千松兄弟を招いて技術指導をさせていたために、地区にキリシタンが広まっていた。その80年後に綱木地区の狼河原で120名が殉教する。密告によるものだったという。弾圧の史実は1952年に米川の旧家で古文書により判明したものである。■関連する過去の記事 カトリック米川教会(2010年11月9日)
2010.11.11
コメント(0)
-
憲史トライアウトに臨む
新聞に出ていた。一番の思い出は、05年ロッテとの開幕戦。3番で先発してチーム史上初打点。あのパンチ力は群を抜いている。まだまだ活躍できるはず。頑張れ川口憲史。
2010.11.11
コメント(0)
-
宮出ヤクルトへ
良かったと思います。イーグルスでもっと活躍して欲しかったのですが、結局は古巣へ。まだまだ実力は発揮できるでしょう。頑張れ宮出。
2010.11.10
コメント(0)
-
カトリック米川教会
登米市米川。国道346号西郡街道からちょっと入ったところ。丘の上に佇む。信徒会の会長さんが説明してくれた。米川が殉教の地であることを知り、1954年小林有方司教が布教に入る。1955年には集団洗礼で311人が受洗。体育館を貸してくれた中学校も偉かったし、受洗を許した大慈寺の和尚さんも偉かった、と会長さんは語った。寄附により建てられたこの教会は1957年の落成。集団洗礼を受けた人たちは、やがて就職して出て行った人が多い。今でも何人か当時の方がミサに集まる。また、フィリピンから来たお嫁さん達が子どもと一緒に訪れるのだという。皆さん、踏み絵を迫られたらどうしますか。生きることを選ぶでしょうか。自分は殉教しても妻子は改宗して生き残れ、と思うでしょうか。でも当時の人たちは喜んで死を選んだのです。自分は何度か信徒をやめようとも思ったが、ここまで信徒でやってきたんですよ、と明るく話してくれた会長さんだった。歴史を積み重ねて、その町がある。国道を走り過ぎたことは何度もあるが、降り立ったことはなかった。ここにはここの大事な歴史がある。秋の山あいの里は美しかった。
2010.11.09
コメント(0)
-
みのり
仙台駅ホームで見かけたので、一枚撮らせてもらった。陸羽東線を経由して新庄行きである。東北本線部分は、仙台から小牛田の間は松島駅だけ。3時間をかけて新庄まで結ぶ。キハ48系気動車の3両編成だ。私以外にも、オジサンと若者がカメラを向けていた。いつの時代にも、列車は旅情を誘う。ところで、「みのり」とは良い言葉だ。実を結ぶ。豊かで美しい。かと思えば、首を垂れる稲穂のように、あくまで控えめで調和的だ。子どもに名付けようとも思ったのだが、世界に出たときに minority と揶揄されるような気がしてやめた。でも、良い名前だと思う。日本語として語感も良い。列車にローマ字が振ってあるので、そんなことを思い出した。
2010.11.09
コメント(0)
-
子どもの夢
家に帰ったら机に置いてありました。まだまだ幼いですね。そう言えば今年行ったときは、ハニーハントでたしか1時間半以上並んだのでした。夕方になっても暑い夏の日でした。それでも、やっぱり子どもにとっては夢の世界なのでしょう。
2010.11.08
コメント(0)
-
車の右側面のテキストは左右どちら向きに書くか
子供の頃から気になっている。最近でも、仙台市営バスの場合、「ノンステップバス」という白文字が車体の右の場合で、左から書く(通常の表記)のと、右から書く(車の進行方向)の2通りを発見した。何年か前には、会社名の英文表記を、右から書いているのを見つけてビックリしたことがある(下記の日記)。出だしが .OC と始まるので、一体どこの言語かと面食らってしまった。落ち着いて右から読めば良いのだが、もちろんアラビア語ではない。アルファベットを右から書いているだけなのだ。さて、きょうは登米市でたまたま並んでいる車を「発見」したので、ご紹介してみる。これも最初はびっくりした。一瞬、うぐいすの町として売り出したのか、と思ったくらい。■関連する過去の記事 車体右側の「社名」をどう書くか(07年5月24日)
2010.11.07
コメント(0)
-
きょう宮城刑務所から出てきました
収監されていたのではなく、矯正展を訪れてきました。チョイと散歩がてらに出かけてみたのですが、秋晴れの若林城は人の波で賑わっていました。出店や音楽などで、まさしくお祭りです。人気の刑務所の食事の試食コーナーに並んで、頂きました。実際のメニューの一部を味わう体験で、麦ご飯に漬け物、汁物という感じです。素朴ですが美味しいと思いました。我が子も完食。妻は、出店で食べ物や花をおみやげに買っていました。受刑者の作ったタンスやバッグなどの展示コーナーも人気。北海道や東北などの各刑務所毎のブースになっています。所内の見学コースもあったのですが、時間の関係もあり今回は断念しました。塀の中を見たことはないし、中に入る予定のも今のところないものですから、来年は見学ツアーに入って見たいと思います。■関連する過去の記事 宮城刑務所(シリーズ仙台百景 29)(08年10月12日)
2010.11.06
コメント(0)
-
東北学院発祥の地
南町通りを歩いていて、あれこんな石碑があっただろうか。思わず写真を撮った。彫った感じが真新しいし、据え付けた歩道のブロックも新鮮だ。そしたら、翌日(4日)の朝刊に偶然その碑が写真で出ていたのでまた驚いた。10月28日に除幕式をしたという。一番町二丁目の仙建ビルの敷地だ。記事によると、かつて学院中高のあった一番町一丁目にも今年度中に碑を建てるという。明治19年(1886年)木町通と北六番丁の角に仙台神学校が誕生。明治24年(1891年)には南町通に面した当地に、赤煉瓦造り、方形5層の塔と円錐屋根のゴシック風の典雅な校舎が完成。名を東北学院と改称した。碑の台座に近い部分には、「地の塩・世の光」とあり、月浦利雄の名がある。戦後に中学校高校の校長をされた先生とのことだ。思い出したのだが、荒町通り(旧奥州街道)を散歩していて、この姓の表札のお宅に気づいたことがある。あまり多いお名前ではないと思うが、ゆかりの方の邸宅なのだろうか。■関連する過去の記事 東北学院大学の明日(08年3月3日)
2010.11.05
コメント(0)
-
がんばれロッテ!
仙台駅東口のロッテのビル(ロッテ商事東北支店、新寺一丁目)。休日で閉まっているが、小さいながらちゃんと出ていた。皆様のご声援をお願いします、と。今季のロッテは終盤の猛追はすばらしかった。勢いを駆って日本シリーズ進出。昨夜は惜しくも延長で敗れたが、パシフィックの意地を示してくれ。頑張れロッテ。
2010.11.04
コメント(0)
-
街の中の変電所
仙台の市街地のど真ん中。五橋交差点に接し、市立病院のあるブロックの東七番丁側にある。東北電力株式会社五ッ橋変電所(門のプレートの表記)。変電所とはいっても、でかいトランスがぼこぼこ見えているのではない。おそらく地下化している部分もあると思うが、地上部分はきれいにキューブ状に覆われていて、それ以外はすべて契約制駐車場にしているようだ。連絡先は太白区郡山と書かれているから、施設は無人で管理されているようだ。変電所を挟んだ東七番丁の東側には、仙台電気工事組合会館。また変電所から東七番丁の同じ西側を数軒南に歩くと福與電気株式会社。この一帯は昔から電気にゆかりがあるようだ。
2010.11.03
コメント(0)
-
築館小校長の飲酒運転逮捕を考える
私は本当に怒っている。本当に情けない。教育を担う人間、しかも地域の拠点校の校長職ではないか。この不祥事続発の緊急時に、なんの緊張感も持たないどころか、指導的立場をよそに自分はコソコソ飲酒運転。これはどこの世界の出来事かと言いたくなる。築館小の校長が10月31日に酒気帯び運転容疑で逮捕された。校長は30日午後5時10分頃、栗原市栗駒中野の市道上で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑い。道路縁石に乗り上げる事故を起こして発覚。校長は30日昼から自宅近くの催し会場など数カ所で酒を飲み、歩いて帰宅。その後に運転したとみられる。(読売新聞、河北新報による)一応言っておくが、私は行きすぎた公務員バッシングを問題視するバランス感覚も持ち合わせているつもりではある。たまたま事件が重なったからといって教員や公務員の不祥事を殊更に喧伝するマスコミの姿勢にも、一歩距離を置いている(他方で、公務に対する批判的姿勢は有る意味で社会の健全なバランス感覚だとも思っている)。さらに言えば、確定判決までは容疑者は推定無罪に扱うべきと純朴に考えている立場だ。しかし、どう考えても、この一件はどうにも救いようがないと思うし、宮城の教育界を考えてもどうしようもない気持ちに襲われてしまう。つまり、こういうことだ。最近教員の不祥事が続き、県教委では各学校の宣誓書を促すなど、従来にない姿勢で現場の意識を喚起していた。その折りも折り、しかも拠点校の校長だ。本当に言いたくないのだけれど、この人の行動は、つまるところ、酒を飲んで帰って、その意識は十分ある前提で、たぶん「自分は大丈夫だろう、捕まりはしない」との軽信でハンドルを握った。その神経が、私は許せない。多いに非難に値する。自動車の前面が破損した映像もTVで見た。言い逃れはできない。平時にも許せるものではないが、今は県教委を挙げて信頼回復に努めているときだ。そんな時に、なんでそんな、わざわざ事を起こすのか。悪く言えば、この校長は普段からこうなのだろう。世間に向けては小綺麗なことを言って、それで立派に校長も務まってきた。表面的には。飲酒運転も実際に何度もやったのでないか(思い込みで言うのは控えるべきだが、今回だけはどうしても言いたい)。少なくとも、教育界が騒然としているときに、仮にこの人間が普段は飲酒運転をしていたとしても(失礼)、こんな時ばかりは(せめて)、形だけでも(それも哀しいが)、範を示すべきだ。そんな最低限のことも履践できなかったのだ。どう考えても、故意に行った酒飲み運転なのだ。どこに弁護の余地があろうか。そう考えるから、私は本当に残念で、悔しくて、怒っているのだ。月曜日や火曜日に、意外とこうした視点の報道ぶりはなかったが、私は重大なことだと思っている。仮にマスコミが、自分たちも飲酒運転をしているから過度な報道を控えているとしても、そんな問題ではない。とにかく、教育者の反社会的行為なのだ。極言かも知れないが、教育界や他の多くの善良な教育者を、冒涜しているのだ。一般には「上がりポスト」と見なされている拠点校の校長。この人も早くから見込まれた人材なのだろう。(たかが)酒飲み運転で教育者の評価を歪めるのは妥当でない、というもっともらしい反批判が、一昔前ならあったかも知れない。しかし、私は確信を持って言う。現在の情勢を踏まえるならば、最優先にコンプライアンスを自ら発信すべきだ。それができないなら如何なる意味でも教育者と言えない、と。哀しい出来事だ。教育界は歴史に残したくないだろう。しかし、こういう出来事こそ、歴史に刻むべきなのだ。その良識が、県教委には備わっていると思いたい。絶対にかくあってはならない、と後世に教えるために。
2010.11.02
コメント(2)
-
多賀城碑、壺の碑、日本中央碑について
まずは多賀城碑の簡潔明瞭な解説。多賀城市の観光案内(2009.9)から。------------(p.4)高さ196cm最大幅92cmの古碑は、江戸時代初期に土中から発見され、仙台藩が歌枕の「壺碑」として名所にしたことから脚光を浴びる。碑文には平城京や各国境からの距離と、多賀城の創建修造に関する記事など141文字が刻まれていますが、歌枕「壺碑」との関連性がないことから、明治以降に真贋論争が起こる。しかし、近年、宮城県多賀城跡調査研究所の調査により奈良時代に建立された真碑であることが確認され、平成10年に国の重要文化財に指定された。碑文は史実であり、名実ともに日本三古碑(那須国造碑、多胡碑)となった。(p.7壺の碑の説明)「むつのくの おくゆかしくそ おもほゆる つほのいしふみ そとのはまかせ」山家集・西行法師多賀城碑が奈良時代に建立された真碑であることは確認されたが、「つぼ」については不明のままで、「いしぶみ」を「文」の意味で引用した歌も多く歌われています。(p.7コラム)歌枕は古代のみならず近代詩にも生かされている。明治期文部省に作られた小学唱歌、中学唱歌には、土井晩翠作詞、瀧廉太郎作曲で知られる「荒城の月」などとともに、坂正臣作詞、栗本清夫作曲と考えられる「壺の碑」の歌が収められている。作詞の坂正臣は華族女学校(現在の学習院女子部)教授を勤めた人。「海は田となり 田は海と うつりかはりし 世の中を ひとり静かに みちのくの つぼのいしぶみ 苔深し」(p.9コラム)壺の碑の北西脇にある「つほのいしふみ」道標は、芭蕉が訪れた40年後に建てられたもので「つほのいしふみ 是より二丁四十間(約290m)すくみちあり」の道案内と、「和州南都(奈良県)古梅園」との寄進者の名が刻まれている。道標だからもとは別の場所にあった(旧街道追分の石あたりと思われる)のだが、この碑には逸話がある。「古梅園」は今も奈良にある墨屋で、そこには二つに割れ、全く同じ文面の道標が残されている。一度送られた道標が多賀城に着いたときには割れていて、再び同じものを作って運んだという。270年前のことだから、その熱意に心を動かされる。------------さて、多賀城碑の真贋論争は決着したが、「つぼ」の方はどうなのだろうか。また、青森にあるという「壺(坪)の碑」との関係はどうなのだろうか。そもそも仙台藩が掘り起こして、これぞ本物の「壺のいしぶみ」です、と宣伝したのだから、それまで、壺の碑についてある程度の共通理解があって、なおかつ、それがどこにあるか今ではわからない、という点も認識が共有されていたはずだ。まず、古来人々に東北の果てにあるものと認識された壺の碑の由来だ。歌枕となった経緯は不明だが、文治年間の藤原顕昭「袖中抄」に、次のような趣旨が説明されている。東の果てに「つぼのいしぶみ」があり、坂上田村麻呂が弓のはず(両端の弦をかけるところ)で彫った日本中央の文字があり、その場所を「つぼ」という、とのことだ。それでは、青森の壺(坪)の碑なる日本中央の碑(南部碑)について。青森県東北町の坪と呼ばれる集落のそばに千曳神社がある。昭和24年、川村種吉氏によって千曳集落と石文(いしぶみ)集落の間の赤川支流の湿地帯から巨石が偶然発見され、これをひっくり返してみると、日本中央の文字が発見されたというものである。千曳神社には、千人の人が石碑をひっぱて埋めたとの伝説(千曳の由来)が残っている。明治初年の天皇巡幸の際も政府の名で付近を発掘したという。現在、日本中央の碑保存館に所蔵されている(日本中央の碑歴史公園)が、本物かどうかはわからない。■関連する過去の記事 多賀城 壺の碑(08年9月15日) 船形山神社の仏像と多賀城(07年8月30日) 加瀬沼から多賀城六月坂地区へ(07年4月16日) 多賀城跡の風景(07年2月19日) 多賀城の基礎知識(後編)(06年8月8日) 多賀城の基礎知識(前編)(06年8月7日) 岩切の寺社をめぐる(06年1月3日) 平泉への道(06年1月11日) 芭蕉が感激した「おくのほそ道」岩切・多賀城(06年1月25日) 古代東北の理解(06年5月31日)
2010.11.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1