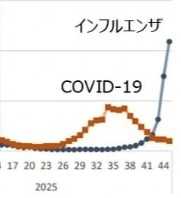2010年12月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
ホテルにおせち料理を取りに行く
完全に仕事もナシ。家人の命を受けて一っ走り行ってきました。市内の某ホテル。正月料理を予約していたので、取りに行ったというわけです。酒とカレンダーが付いてきました。大荒れの年越しと言われていますが、今のところ天気は悪くない。陽ざしも出ています。市内はなぜか県外ナンバーの車が多かった。水戸、八戸、岩手、福島、などなど。愛媛ナンバーも見かけた。この入れ物の中にはさぞかし素晴らしい料理がつまって居るのでしょう。貧しい農家だった我が少年時代には取り立てて正月料理の記憶とか、家庭ならではの味とか、思い当たることはあまりありません。餅だけは随分出たように思いますが。明日の元日に開けてみれば、テレビや雑誌で見聞きするような、色とりどりの料理があるのでしょう。ありがたいことです。ついでに新年の福もつまっているか。皆さん、本年もつまらぬ我がジャーナルをお読み頂いて、ありがとうございました。編集長 小田島樹成 敬白
2010.12.31
コメント(0)
-
職人を目指す問合せ先と東北
職人になるためのガイド本で、問い合わせ先として東北地方の連絡先が記されたものをピックアップしてみた。(山中伊知郎『職人になるガイド』新講社、2010年)■こけしみやぎ蔵王こけし館■つる細工つる工芸の会(掲載の電話番号から検索したら、小国町観光協会でした。■鉄器職人岩手県南部鉄器協同組合連合会■鞠(まり)由利本荘市民工芸技能協会むかしの貴族が遊んだ蹴鞠は鹿革だが、室町以降、公家や武士階級の女性が絹糸を巻いた鞠(御殿鞠、ごてんまり)を作り、そこから手鞠の伝統が始まった。加賀や本荘が名産地となった。
2010.12.30
コメント(0)
-
2010東北の十大ニュース(その2)
河北新報で東北の十大ニュースを掲載した。1 東北新幹線全線開業2 参院選民主大敗3 仙台地裁裁判員裁判で被告少年に全国初の死刑判決4 記録的猛暑5 チリ地震津波被害6 個別所得補償制度の導入7 トヨタ系工場など自動車産業の集積8 仙台銀、きらやか銀の経営統合方針9 プルサーマルの動きと六ヶ所村再処理工場試運転延期10 岩手・宮城内陸地震で被災の国道398号開通福島県。まずは福島民報による。1 異常気象2 合唱王国3 クマ出没4 聖光学院甲子園8強5 玄葉氏入閣6 公務員不祥事7 プルサーマル始動8 佐藤知事再選9 駅伝で柏原が活躍10 凶悪事件相次ぐ福島民友新聞。1 記録的猛暑2 クマの目撃や被害3 合唱コンクール「合唱王国ふくしま」の実力発揮4 夏の甲子園で聖光学院が強豪撃破しベスト85 天候不順の春。低温、日照不足が続き季節はずれの大雪も6 いわき市で生きていれば102歳の女性が自宅から白骨遺体で発見7 佐藤雄平知事が東京電力福島第1原発3号機のプルサーマル計画受け入れ。県内初のプルサーマル発電が開始8 県内でも子ども手当支給開始9 知事選で無所属現職の佐藤雄平氏が再選10 急激な円高の進行で県内製造業の業績に影響
2010.12.29
コメント(0)
-
秋田の人口減を考える
今年実施した国勢調査の速報で、秋田県では全市町村で人口が減少。減少率も5.2%と戦後最大という衝撃的な内容だ(河北新報記事(広域)、同(秋田版))。県の人口は1,085,845人で戦後初めて110万人を割り込んだ。藤里、上小阿仁、小坂の3町では10%以上の減少である。世帯数は7市町村で増加したものの、県全体では初の減少に転じている。宮城県以外は速報が報告されているようなので、まずは各県の状況をざっと見てみよう。■青森県(資料)県人口は1,373,200人で、前回比4.4%の減。減少幅は過去最大。前回より人口が増えたのは、原発建設中の大間町(2.1%)とおいらせ町(0.1%)の2町のみ。5年間の人口減少率の高い市町村は、今別町(15.7%)、佐井村(14.8%)、外ケ浜町(13.7%)、深浦町(11.2%)、田子町(10.3%)など。世帯数は2,574の増加。■岩手県(資料)全県で54,511人の減となり、総人口は1,330,530人。市町村別では、滝沢村(293)、矢巾町(177)以外の市町村は減少。減少割合の最大は西和賀町で10.5%である。世帯数は全県で45の微増。盛岡市は人口は減少(-2,174)だが、世帯数が3,181の増で県内最大の伸びを示した。■山形県(資料)県人口は1,168,789人で、減少率は3.90%だった。4地域別では最上のマイナス7.07%が最高。県人口が120万人台を割り込むのは戦後初。市町村別人口では東根市(+578)のみが増加。前回は4市1町がプラスだった。減少の34市町村では、減少数が大きいのは酒田市(-6,407)、鶴岡市(-5,757)、米沢市(-3,786)、上山市(-2,170)、山形市(-1,928)など。減少率では大蔵、鮭川、戸沢の3村がいずれもマイナス10%を上回る。世帯数は38万8670世帯で前回より1942世帯の増加。■福島県県人口は2,028,752人で、減少率3.0%である。世帯数は720,587で、前回から10,943世帯増。------------やはり、秋田県の全市町村で人口減、県全体で世帯数も減、というのは特筆されると思う。全市町村での人口減という結果には、市町村合併が進んだ側面もあるだろう。青森県では半島部で15%もの激減もみられるが、それでも人口増の町があるにはある。その意味でも、秋田の全市町村マイナスは、やはり象徴的である。さて手許に明治初年の各県と主要都市の人口データがある。青森県 44万人 弘前 3.3万人岩手県 56 盛岡 2.5宮城県 56 仙台 5.2福島県 73 若松 2.1秋田県 58 秋田 3.3山形県 64 米沢 3.4今思えば、福島と山形の人口は多かったのだ。ちなみに、よく言われるように新潟県は全国一で144万人。これはダントツで、兵庫県131万人、愛知県122万人、広島県113万人、東京都109万人などを従えている。都市別に見ると、仙台の5.2万人はたしかに雄藩仙台の名残をとどめているが、他を見ると、東京の83.1万人は別格で、大阪27.2と京都22.6も格が違うとしても、それに次ぐのは、金沢11.0万人、名古屋11.0万人、鹿児島8.9万人、広島6.7万人が後に続く。やはり大藩の城下町が人口が多いのがわかる。秋田は当時で3.3万人。東北ではかなりの集積だ。私自身も小学校の頃は、50万都市の仙台と、大同合併の30万都市いわき市を別とすれば、秋田市が、青森市、郡山市あたりと並んで東北の中心都市というイメージだった。盛岡市、福島市、山形市あたりは20万人プラプラで集積が薄という感覚だったのが実情だ。改めてデータを確認する。秋田市は人口32万人で、それだけを見れば青森市30万人、盛岡市29万人、山形市25万人などを上回るが、今回の国勢調査をみても、勢いが感じられないように思う。秋田市 人口323,363人 前回比2.9%減(-9,746人)青森市 299,429人 3.8%減盛岡市 298,572人 0.7%減山形市 254,084人 0.75%減という具合だ。青森市も元気がないけれど。
2010.12.28
コメント(2)
-
2010東北の十大ニュース(その1)
青森県の十大ニュース。東奥日報は読者が選ぶ形式です。やっぱり第1位はコレでした。1 東北新幹線全線開業(八戸-七戸十和田-新青森81.8キロが12月4日開業)2 連日の真夏日「スーパー猛暑」3 陸奥湾ホタテ大量へい死4 「はやぶさ」帰還(プロジェクトマネージャー川口淳一郎教授が弘前市出身)5 サッカー山田高準優勝6 「わさお」フィーバー、映画化も(鰺ヶ沢町のイカ焼き店)7 大鰐町長選くじ決着8 「土俵の鬼」逝く(元横綱初代若乃花の花田勝治さんは弘前市出身)9 リンゴ産地混在10 青森市官製談合当ジャーナルでは、大鰐町長選のくじ引きが印象に残ります。青森署の脱走事件はランクインしなかったようです。■過去の記事大鰐町長選挙は得票同数で抽選(10年6月30日)青森警察署の事件を再び考える(10年8月24日)警察署留置施設の脱走事件を考える(10年8月23日)岩手県は、岩手日報の10大ニュース。これも読者の応募です。1 記録的猛暑 熱中症死者も2 チリ大地震で18億円津波被害3 地元衝撃 小沢氏強制起訴へ4 民主代表選 小沢氏敗れる5 参院選 県内勝利も民主大敗6 県内も裁判員裁判スタート7 中学生スポーツ県内V続々8 景気足踏み 回復実感遠く9 10年産コメ概算金大幅値下げ10 アジア大会 県勢3人「金」岩泉線の脱線事故は、13位でした。タロちゃんも懐かしいですね。■過去の記事岩泉線を考える(10年8月1日)タロちゃんは元気か(10年3月4日)タロちゃんのその後(10年2月5日)タロちゃん、タロウちゃん、そして「たろちゃん」(10年1月25日)タロちゃん?タロウちゃん?(10年1月20日)松島のタロちゃんを考える(10年1月19日)松島のタロちゃんを考える(10年1月19日)(宮古市のタロちゃん松島へ)秋田魁新報も読者選定。1 秋田市の弁護士殺害事件2 暑い夏3 bjリーグに秋田NH参入4 全国学力テスト 4年連続トップ級5 参院選で石井、寺田両氏が初当選6 コメ不作7 100周年の 大曲の花火8 「IRIS」人気9 イトーヨーカドー閉店(秋田駅前)10 季節性インフルで8人死亡(北秋田市鷹巣病院)
2010.12.27
コメント(0)
-
今朝の雪だるま
朝から下の子が何やらせっせと雪の造形作業をしていました。数センチは積もりましたから。■昨日の雪だるま君 25日の日記
2010.12.26
コメント(0)
-
耀け!!ベガルタ仙台(シリーズ仙台百景 33)
散歩していたら10歳の子が指摘。あれなんて読むの。耀け!!ベガルタ仙台。「かがやけ」だろうけど、当て字みたいだね。普通の 輝け! ではないぞ。あれは、コクヨウセキのヨウだ、いや違うか、などと親も不安。おなじみ、泉中央駅からユアスタに至る道。泉図書館の向かいです。■シリーズ 仙台百景(こんな企画で100まで続くでしょうか) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日) 富士宮やきそば(シリーズ仙台百景 31)(2010年10月17日) フェンスのメッセージ(シリーズ仙台百景 30)(2010年2月28日) 宮城刑務所(シリーズ仙台百景 29)(08年10月12日) 松森焔硝蔵跡(シリーズ仙台百景 28)(08年8月31日) 十一面観音堂(シリーズ仙台百景 27)(07年10月23日) 陸奥国分寺薬師堂(シリーズ仙台百景 26)(07年10月17日) 県民の森 鶴ケ丘口(シリーズ仙台百景 25)(07年8月26日) 一時停止だ!三時はお茶だ!(シリーズ仙台百景 24)(07年8月20日) 風の環(シリーズ仙台百景 23)(07年7月7日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日) 県民の森(シリーズ仙台百景 21)(07年4月8日) 数字の練習ボード?(シリーズ仙台百景 20)(07年3月25日) 半田屋一番町に進出!(シリーズ仙台百景 19)(07年3月1日) 仙台百景画像散歩(その18 撮影成功!霊気のトンネル)(07年2月6日) 仙台百景画像散歩(その17 変な漢字の看板)(07年1月28日) 仙台百景画像散歩(その16 駅前東宝ビル)(07年1月13日) 仙台百景画像散歩(その15 空から見た仙台)(06年12月29日) 仙台百景画像散歩(その14 光のページェント)(06年12月13日) 仙台百景画像散歩(その13 東京スター銀行)(06年11月30日) 仙台百景画像散歩(その12 建設ラッシュ再来?)(06年11月10日) 仙台百景画像散歩(その11 E721系電車)(06年7月25日) 仙台百景画像散歩(その10 ワンコイン端末)(06年7月7日) 仙台百景画像散歩(その9 ヤギさんの看板)(06年6月19日) 仙台百景画像散歩(その8 キック治療?)(06年6月18日) 仙台百景画像散歩(その7 ホテルモントレ)(06年6月4日) 仙台百景画像散歩(その6 佐々重ビル)(06年5月24日) 仙台百景画像散歩(その5 車止めポール)(06年4月29日) 仙台百景画像散歩(その4 オロナミンC)(06年4月4日) 仙台百景画像散歩(その3 東仙台案内踏切)(06年3月22日) 仙台百景画像散歩(その2 はんだや)(06年3月18日) 仙台ミステリー?風景(06年3月4日)
2010.12.26
コメント(0)
-
雪だるま
子ども達が作りました。雪の一日です。
2010.12.25
コメント(0)
-
海の民、山の民
読売新聞東北総局による企画連載だ(海の民、山の民)。今年4月にスタート以来、大変楽しみにしている。東北のあちこちに根付く風習や考え方に、遠い先祖たちの生活、交流、思想が深く刻まれているではいか。新幹線もインターネットもない古い昔から、わが先人は遠く海外と交易し、研ぎ澄まされた知恵で道を切り開き、地域を守り、子孫を育ててきた。今の時代、ともすれば見過ごしてしまう民俗の扉を開き、東北とは何かを探る、そんな企画でないかと思う。オムニバス形式だが、なぜかどの話題も、普遍的に我々東北に生きる心に浸み入ってくるように思う。タイムリーなニュースバリューとは異質だろうが、いや、それだけに、息長く続いて欲しい。実は私は読売を自宅で購読していないのだが、ネットで読めるのは大変ありがたい。今朝はじっくり読ませて頂いた。来年も期待したい。
2010.12.25
コメント(0)
-
東北福祉大の鉄道交流ステーション
先日NHKのTVニュースでも取り上げていたのだが、河北ウイークリーにも出ていた。鉄道旅行の楽しみである駅弁にスポットを当てた企画展「シリーズ・旅の脇役たちno.1 駅弁の今昔」と題して、東北福祉大駅そばステーションキャンパスにある鉄道交流ステーションで展示されている。入場無料。なかなか面白そう。ところで、何で福祉大で鉄道交流ステーションなのか。興味深いホームページもあります。企画展はこれで12回目という。企画運営の体制がしっかりとしているようです。
2010.12.24
コメント(0)
-
秋田美人を考える
わが東北には、日本三大美人に数えられる秋田もあれば、その逆の三大名産地と言われる某政令指定都市もある。美人の方の3つの地域とは、京都、秋田、博多、金沢など諸説ありそうだが、秋田美人の名声は昔から全国区だろう。私が知っている秋田出身の女性は、いずれももちろん美人だが、考え方が開明的で自己確立度の高い人が多いように感じる。たまたまそうなのだろうが、岩手や山形とは、私の印象ではハッキリ違うように思うのだ。ところで、俗説では佐竹の殿様が水戸から美人を連れてきたことになっているが、秋田県観光ガイドによれば、肌の色の白さが指摘されている。年間日照時間が日本一少ない(1453時間。最長は山梨県で2249時間)という。また、秋田は人口あたり美容室・理容室の数が日本一で、これも関係有るかも知れないという。
2010.12.23
コメント(0)
-
12月の雨
というと荒井由実の詞だが、東北人としてはNSP風に、冬だから雨は似合わないと感じる。もちろん東北でも冬の雨はあるけれど、あんなに真夏のような雷鳴と横殴りの雨は、めずらしい。昨日は、仕事で出かけていたのだが、一番町アーケードを歩いていてさえ、歯が抜けたようなビルの間から降り注ぐ雨に濡れてしまう。タクシーに飛び乗るその瞬間だけでも、十分濡れまくってしまうのだった。河北新報の今朝の見出しが言い表している。「暴風烈雨、冬至襲う/仙台で12月最多42ミリ/東北」と。仙台では時間雨量42ミリは12月として最多だという。降り始めからの雨量128.5ミリも、平年の5か月分の降水量だというから、すごい。加えて強風だ。風は今日も強く、朝に自転車で出かけてきたら、向かい風で漕いでも進まないほどだった。今は家に戻って、陽ざしも出てきた窓の外を眺めている。雨も風も自然の営為で、さらされる立場こそ人間の自然の姿だが、とは言え、家の中にいるのが、良い。夕方にまた、たぶん自転車で出かけるのだが。
2010.12.23
コメント(0)
-
歩行者は左右どちらを通行するか 仙台のエスカレータ再論
現在道路交通は車は左、人は右と規定される。歩行者を車と対面させて双方に注意を促す趣旨だろうが、実はこれは昭和35年(1960)の道路交通法によるもので、それ以前の我が国は明治以来、車馬も人も左、だったという。もっとも、駅構内や地下街、歩行者専用の商店街などの場合はどうだろうか。JRの駅によっては、構内通路の左側通行を案内しているそうだ。仙台駅ではたぶん明確な表示やアナウンスはないと思うのだが、各駅によっては改札口と券売機の配置の関係によってそう案内することがあるそうだ。ある実験(加藤孝義氏)によると、人間は壁が右側にあると歩きにくく、左に壁を見て歩く方が安定する感じがするのだそうだ。右利きの手の側を自由にしておくという心理が働くのかも知れない。車の乗り入れがない歩行者専用の商店街の場合は、6:4または7:3で概ね左側通行だそうだ。仙台、京都、大坂、鹿児島など、アーケード街はどこも同じだという。また、八重洲、JR大阪駅前、天神などの地下街もやはり左側。さて、エスカレータの立ち位置はどうか。よく東西の差が取り上げられる話題であり、大阪は右立ち、東京は左立ちとされる。その理由として大阪人は右手に風呂敷を持つから、とも言われるが、昭和45年の大阪万博で阪急電鉄梅田駅が混雑回避のために、パリやロンドンを参考に、エスカレータの左空けを案内したのが始まりとするのが有力説である。東京は大阪から遅れて90年代に左立ちが定着した。風呂敷の大阪人に対抗してか武士の習慣という俗説もあるが、上述のように駅の構内が左側通行であることの自然な延長と見られている。世界標準ともいうべき右立ちは、実は日本では大阪など少数派。京都は、市営地下鉄は左立ちが多いが、地下鉄京都駅やJR京都駅は左右混在だそうだ。都道府県庁所在地で左空け(右立ち)に統一されているのは、大阪、神戸、奈良、和歌山の4か所だけだという(横田耕治氏)。とすると、東京をはじめ東日本はすべて左立ちとなりそうだが、なんと仙台では市営地下鉄の駅が右立ちだ。仙台市交通局によると、交通局が右立ちを案内したことは開業以来一切ない。多くの客が自然に右に立っている、とのことで、その理由は交通局でもわからないそうだ。■小沢康甫『暮らしのなかの左右学』東京堂出版、2009年 を参考とした仙台のエスカレータは、JRは左立ち、地下鉄は右立ち、デパート等の建物はたぶん右が多い、ような気がする。統一されないのも不思議だが、駅の場合は、エスカレータを終えてから向かう方向とも関係しているのかも知れない。エスパルやロフトなど仙台駅周辺では左に立ち、藤崎や三越では右に立つ、と解説してくれる人もいる。そこまで割り切れているとは思えないが。■関連する過去の記事 仙台のエスカレーター作法を考える(2010年4月9日)
2010.12.21
コメント(0)
-
左沢(あてらざわ)を考える
山形県の左沢(大江町)は難読地名だが、鉄道の路線名でもあり、難読ゆえに逆に有名なのではないだろうか。この不思議な地名について詳しく論じている本があった。■小沢康甫『暮らしのなかの左右学』東京堂出版、2009年柳田国男は昭和11年『地名の研究』で、アテは陰地、ラは名詞を確定する語尾であり、他県でもアテラ地名として、阿寺沢、安寺沢などを挙げている。昭和26年東條操編『全国方言辞典』では、アテの第一義を樹木の日が当たらない側として、東京都西多摩郡檜原、和歌山県日高郡、徳島県祖谷でその意味で使うという。ではなぜ「左」の字を当てるのか。丹羽基二『日本の苗字読み解き事典』によると、木こりはアテ(日陰に当たる木の部分)にまず斧を入れ、日向のほうから鋸で切っていく。このため、木こりから見るとアテは必ず左側になる、という。山形県大江町の左沢に関しては、この日陰由来説以外にも、諸説がある。1 最上川上流から見て右(こちら)に対して、左(あちら)の沢2 寒河江城主大江氏が長岡山から西方の山谷を指して、「あちの沢」と呼んだので左の字を当てた3 アイヌ語のアッチャケ(対岸)で、最上川の対岸の位置ところで、左沢の地名は山形県内に10か所あるという(山中襄太)。左岸の左沢に対して、右岸の右沢は、コチラサワ、カテラサワと読むそうだ。しかし、大江町史編さん事務局によると、最上川の右岸にも左沢はみられ(山形市青野左沢、尾花沢市玉野左沢)、反対に左岸でも右沢がある(朝日町大谷右沢(かてらさわ)など)。とすると最上川の流れの視点では説明しきれない。大江町の左沢は南面で日当たりも良く、日陰の意味も当てはまらない。ヒバ(アスナロ)をアテと呼ぶ地方があるので、アテの育つ沢という見方もある、ということだ。
2010.12.20
コメント(0)
-
紅葉の名所と東北
紅葉の名所を解説する最新の本では、東北のどこが紹介されているだろうか。■主婦の友社『見直したい日本の美 日本 紅葉の名所100選』(2010年、主婦の友社ベストBOOKS)白神山地(青森県西目屋村)奥入瀬渓流(十和田市)八幡平(八幡平市)鳴子峡(大崎市)田沢湖抱返り県立自然公園(抱返り渓谷)(仙北市)蔵王連峰(山形市)磐梯吾妻スカイライン(福島市)久慈渓谷(久慈市)秋の宮温泉郷/鬼首エコロード(湯沢市)赤芝峡(山形県小国町)ブナ平(福島県檜枝岐村)いずれも美しい写真で紹介されている。
2010.12.19
コメント(0)
-
光のページェントを考える
仙台の冬の風物詩、光のページェントは、今、火事のため中止となっている。今夜も定禅寺通りを歩いてみたが、やっぱり冬の風景としては物足りない。実行委員会では20日から再開するというが、点検作業の遅れは快勝されていないという報道だ。楽しみにしている市民にとっては、残念ではあるが、しかし、こんな時こそ考えてみても良い。ページェントの無かった25年前の仙台を。木々の枝に揺らめく明かりは、確かに美しく賑やかだが、それがなくても仙台は明るい町だったではないか。光のページェントは全国にも誇って良い市民の財産だと思う。しかし、やっぱり器械であり、電気だ。故障もして当然だ。たまには休みたいのかも知れない。良いではないか。大目に見てやればいい。光が消えても、人々の心に幸せを灯そうとした人々の善意の輝きが、失せることはないだろう。
2010.12.17
コメント(0)
-
花巻の満にらラーメン
仙台駅前で配っていたNTTドコモのフリーマガジンを読んでいたら、何とも美味しそうなラーメンが紹介されていました。花巻で「満州にらラーメン」を出す「さかえや本店」さんです。創業者の菅野さんが戦時中に行っていた満州をイメージした渾身の一杯だそうです。オーダーしてから目の前に3分で運ばれる素早さも魅力、とか。530円の値段設定も嬉しいです。是非一度行きたいです。ホームページのアドレスがmanniraというのも、面白いです。また、駐車場50台、というのは、かなりスゴイと思います。
2010.12.16
コメント(2)
-
ジンギスカンと遠野
ある本でジンギスカンについて読んだ。北海道では盆・暮れ・正月・花見にジンギスカンと言われるほど親しまれている。由来は、政府が1918年(大正7年)に初めた綿羊百万頭計画で、軍隊や警官の制服を作るためだが、同時に肉を食用とすることを考え、満州で出会った中国料理「?羊肉(カオヤンロウ)」という羊料理を日本人好みにアレンジしたのがジンギスカン。命名は、満鉄調査部長で後の満州国国務長官の駒井徳三とされる。モンゴルの広大な牧羊地帯をイメージしたが、モンゴル料理とは関係がない。ところでジンギスカンをよく食べる地域は、北海道のほか、遠野市、成田市、長野県信州新町、高知市など。これらは昔から羊の飼育が盛ん。羊肉は独特の臭みを持つが、これは格安の老廃羊肉が食されていたことにある。生後一年未満がラム、それ以外がマトンだが、マトンは時間が経過するほど臭みが強くなりやすい。つまり、昔から羊の飼育が盛んだった地域では、臭みのない新鮮な羊肉を食べたため、ポピュラーな食材として根付いた。■はてな委員会『日本のはてな(はてなシリーズVol4)』講談社、2009年さて、遠野についてだ。遠野では、焼肉といえばジンギスカン、というほど根付いているらしい。北海道道民一人あたりの羊肉消費量が2.4kgのところ、遠野市では2.1kgだそうで、かなりの羊肉好きだ。(東京ジンギスカン倶楽部による)
2010.12.14
コメント(0)
-
新郷村とキリスト伝説を考える
泉保也『ムーミステリー大事典』(学習研究社、1999年)から。なお、同書では、イスラエル10支族が日本に来ていたという日ユ同祖論のコーナーで、エルサレムのヘロデ門の上部に菊の紋章があり、また伊勢神宮の内宮に至る賛同の石灯籠にダビデの星に似た模様が刻まれていることを紹介した後に、青森県戸来村のキリスト伝説が記されて、日本とユダヤの結びつきがクローズアップされている。その後には、再び失われた10支族の謎を提起し、東に向かい日本に至った可能性を指摘。具体的に、渡来人とされる秦氏がユダヤ人とする学説と、三種の神器である八咫鏡の裏面に古代ヘブライ語でヤハウェの言葉が記されているとされていることを指摘する。------------十来塚はキリストの墓とされる。竹内巨麿が、自家に代々伝わる文書に根拠があるとして、昭和10年8月に戸来村を訪れる。村中は騒然となり、佐々木伝次郎村長も立ち会い、墓探しが始まる。やがて、沢口家の墓地のある小高い笹藪の中に土饅頭を発見。ここがキリストの墓とされた。処刑されたのは身代わりとなった弟のイスキリで、本人は秘かに日本に逃れて戸来村に住み、106歳の天寿を全うした、と古文書に書かれているという。竹内巨麿(1874-1955)は古神道家で、正月元旦に生まれ19歳で京都の鞍馬山に入山、天狗の磐座で修行して神霊の示現を得る。自家に伝わる竹内文献をもとに太古日本が世界文明の中心だったとする独特の神代秘史論を説いた。後に皇祖皇太神天津教を興し、数十万の信者を集めたが、国体の秘密に関わる神体神骨論争に巻き込まれ身柄を拘束される。裁判では無罪を勝ち取った。竹内文献とは、越中(富山県)負婦郡神明村の赤池大明神の神主家、竹内一族に伝承された数々の古文献、系図、神代文字が刻まれた神剣、神鏡、超古代天皇の骨を砕いて固めたと言われる神体神骨など、数千店に上る文書や器物など。中には、キリストの遺書、遺骨、モーセの十戒石板、ムー大陸時代の超古代地図など常識からかけ離れたものも含まれる。ところで当地には不思議が多い。まず、言葉である。地名(へらい)はヘブライ(古代ユダヤ)に通じる。また、かつて父親をアヤ、アダ、ダダ、母親をアバ、アパ、エバと呼んだが、アダムとイブを連想させる。また、子供が生まれると額に墨で十字を書き入れるなど、十字が魔除けのシンボルとして使用されてきたという。さらに、十来塚を代々守ってきた沢口家にはソロモンの星に似た五芒星の紋章を打ち付けた戸袋が残されている。ナニャドヤラという盆踊りが戸来村をはじめ、青森県や岩手県の一部に古くから唱われているが由来はわからない。ナニャドヤーラ、ナニャドヤーラ、ナニャドナサレータ、ナニャドヤーレャ、と単調な歌詞を何度も繰り返すが、歌う村人にも意味はとうの昔から分からなくなっており、江戸時代にはサンスクリット語説も出たほどである。ところが今から50年(ママ)ほど前、シアトルに住んでいた日本人神学者川守田英二博士が古代ヘブライ語で解釈できることを発見した。それによると、「民の先頭にヤハウェ進み給え、汝の聖名をほめたたえん」となるという。この解読は国際的にも注目され、現在ではヘブライ大学でも研究されているという。------------■新郷村ホームページ(キリストの墓などの解説有り)
2010.12.12
コメント(0)
-
日本の音風景100選と東北
石巻市の観光ガイドブックを読んで、昨日(かおり風景100選と東北)は金華山のことを書いたが、別のページ(河北・北上編)に、日本一の葦の群生地である北上川河口のヨシ原が、日本の音風景百選と解説されている。では東北ではどこが選ばれているか。環境省サイト(残したい日本の音風景100選)によると、こうだ。■青森県(鳥)八戸港・蕪島のウミネコ/八戸市(鳥)小川原湖畔の野鳥/三沢市(渓流)奥入瀬の渓流/十和田湖町(祭)ねぶた祭,ねぷたまつり/青森市・弘前市■岩手県(波)碁石海岸・雷岩/大船渡市(風鈴)水沢駅の南部風鈴/水沢市(祭)チヤグチヤグ馬コの鈴の音/滝沢村■宮城県(虫)宮城野のスズムシ/仙台市(蛙・鳥)広瀬川のカジカガエルと野鳥/仙台市(草風)北上川河口のヨシ原/北上町(鳥)伊豆沼・内沼のマガン/築館町・若柳町・迫町■秋田県(松籟)風の松原/能代市■山形県(虫)山寺の蝉/山形市(祭)松の勧進の法螺貝/鶴岡市(鳥)最上川河口の白鳥/酒田市■福島県(鳥)福島市小鳥の森/福島市(用水)大内宿の自然用水/下郷町(機織)からむし織のはた音/昭和村
2010.12.11
コメント(0)
-
かおり風景100選と東北
石巻市の観光ガイドブックを眺めていたら、金華山は東奥三大霊場(出羽三山、恐山)として知られるが、「かおり風景100選」にも選ばれ、「潮風にのった草木のかおり」が自然の息づかいを感じさせる、という。(石巻観光ガイドブック から 金華山)さて、かおり風景とは東北で他にどこが選定されているのか。環境省のサイト(かおり風景100選)によると、東北関係分は、■青森県 平川市 尾上サワラの生け垣 南部町 南部町長谷ぼたん園■岩手県 宮古市 浄土ヶ浜の潮のかおり 盛岡市 盛岡の南部煎べい■宮城県 栗原市 南くりこま一迫のゆり 石巻市 金華山原生林と鹿■秋田県 能代市 風の松原 小坂町 小坂町明治百年通りのアカシア■山形県 鶴岡市 羽黒山南谷の蘚苔と杉並木 大石田町 大石田そばの里 村山氏 東沢バラ公園■福島県 須賀川市 須賀川牡丹園の牡丹焚火 郡山市 郡山高柴デコ屋敷
2010.12.10
コメント(0)
-
祖父江孝男の指摘する東北の県民性
先日ふとしたことから、祖父江孝男『県民性』(中公新書、1971年)を久々に開いた。不朽の名著である。東北各県はたとえばこんな風に解説されている。(同書後半の各論的部分)■青森 シラフでは恥ずかしがり屋だが、酒を飲むと疾風怒濤のような接待で愛情表現。もっともこれは津軽の特徴で、津軽と南部は互いに仲が悪い。南部は津軽を不倶戴天の仇敵とし、津軽は、もともと津軽の土地を取り返しただけだ、という。南部地域はほとんど岩手日報をとっている。■岩手 不平があっても口に出さない。県南は旧伊達の大藩意識で、県北より団結が強いようだ。県北は雪に閉ざされているから思索的で学者や芸術家を輩出。■秋田 秋田犬に似て、決断が遅いがいったん重い腰を上げると粘り抜く。仲間意識が非常に強く封鎖的。県人会が二つに分裂して、エリートだけのグループ「十人会」がある。■山形 多数の藩や幕領が交錯していたので、青森や岩手のような激しい地域対立はないが、庄内は個性の強い思想家が出、米沢は藩学の伝統で学者や軍人が多く出る。■福島 多くの藩や代官領であったため、地域差もハッキリしないが、会津は未だに歴史の怨念が残る。■宮城 ユッタリズムとダンディスム。ノンビリ性、独立心、我が道を行く気位の高さ。仙台が二高、第二師団が置かれた関係で東北でも一段格上とのプライドが県民性に影響している。
2010.12.09
コメント(0)
-
河北新報の誤字を考える
特に珍しくもなく、今さら大騒ぎはしないが、やはり残念だ。たまたま私も6日の記事(潜在看護師さんて、いったい誰ですか)に書いていた山形大学医学部の医師看護師確保に関するニュースを、今朝の河北新報で取り上げていたが、見出しに、堂々と「看護婦」。思い切りやってしまった。その記事「医師・看護婦を確保へ 山形大医学部が県と連携協定」(早晩リンクも切れるでしょう。)どういう校閲体制になっているのか。あるいは、そもそも社員の資質や常識の問題か。それにしても間違いは誰にでもあるとして、訂正や自己省察の姿勢があまり見られないのも河北新報の特徴だと、私は以前から指摘してきた。もともと新聞には、権力の批判、社会の木鐸として十全に機能を果たしてもらえば良いのであって、新聞社や記者が人格円満だったり一般人の前にへりくだることは全く必要ない、と私は思っている。記者が人間として尊敬できなくても、記事を通じた新聞の果たす社会的役割は別だ、と。しかし、記事の誤りや偏向は、少なくとも自分が認めるのならできるだけ訂正をしっかりと報じて欲しい。どうでも良い小さな事をつまみ上げてわざわざ大げさに書きたてて居るようだが、若い自分に何度か質問をして、返事ももらえなかった新聞社なので、どうしても私は敏感に反応してしまうのだ。東北をどこよりも深く考えている、と自認する新聞社であるだけに、できれば一段と素晴らしい新聞であって欲しいと、応援しているのだ。民主主義を支え社会の鏡となる新聞。その存立基盤は、政治や行政に拠るのではなく、健全な市民の賛同的あるいは批判的な意識にあるべきだ。しかし、このことは同時に、特定の新聞社の存立を保障するものではなく、本来はそれこそフリーマーケット論に基づいて、言論主体も新陳代謝していいはずなのだ。存立自体にこだわったり、あるいは永続を前提に物事を考えることは、市民の期待することではない。やはり競合者の不存在がよどみを作るのか。仙台の気風そのものを象徴しているのか。私はいつか「河北新報論」を定式化して発表するのではないだろうか、と我ながら思っている。
2010.12.08
コメント(0)
-
出羽三山
出羽三山は、月山(1984m)、湯殿山(1500m)、羽黒山(419m)を総称するが、はじめは湯殿山ではなくて、寒河江市北西の葉山(1462m)を加えて三山と称したことがある。いずれも山の神として別々に信仰されていたが、紀伊熊野の熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)が修験信仰の霊山として知られると、中世以後、出羽三山も修験道行者の聖地となり、江戸以降一般民衆の参詣者や登山者が増えた。山の神の発祥地は羽黒山で、平安時代に出羽(いでは)神社が鎮座し、出羽の国の鎮守の神であった。羽黒は、は(端)くら(鞍)の意で、山尾根の端にある山をいう。月山は山頂に月読命(月を数える神)を祀る月山神社に由来する名。湯殿山は、社殿のない湯殿山神社によるが、御神体は水酸化鉄を混ぜた滝の湯で、これを湯殿と尊称したことによる。なお、葉山は、端山の意味で、山尾根の端に盛り上がった山。■吉田茂樹『図解雑学 日本の地名』ナツメ社、2005年 から
2010.12.07
コメント(0)
-
木村頑張れ!自分を見失わずに
今季は背番号を92から15に変更し、一軍定着と一層の活躍を期待されていた。しかし、故障で結局二軍マウンドにも立てず。先月の新人沢村が背番号15と発表されたのに対して、木村は自由契約の上、改めて育成契約を結び背番号は011だそうだ。何とも浮沈の激しさだが、なに、気にすることはない。自分を見失わず、背伸びもせず萎縮もせず、思う道をただただ突き進むだけだ。昨季の一軍での活躍は、間違いなくその右腕で実力で手繰り寄せたもの。なにが通用する力なのか、また或いは自分の弱点も、フィジカルもメンタルも確かな手応えを得たはずだ。揺るがない財産だ。雄伏に徹すべき時もあろう。それを知ることも大きな前進だ。それがバネになって飛躍の時が今度はやってくる。行け行け木村。東北人みんなが応援している。あなたが野球に対する情熱を燃やし続ける限り、いつまでも。
2010.12.07
コメント(0)
-
潜在看護師さんて、いったい誰ですか
山形のニュース。山形大学医学部附属病院で今日(6日)、子育てなどで現場を離れた「潜在看護師」に給与を支払いながら研修を受けてもらう精度の第一号として、辞令の交付式が行われたそうだ。県内だけでも看護師は1000人不足している(NHKによる。SAYでは900人不足)とのことで、こうした「潜在看護師」が現状打開の鍵になるということだ。(NHKニュース、SAYスーパーニュースから)うん、なるほど。それにしても、「潜在」看護師とはネーミングとしていかがなものか。魔術師や忍者じゃあるまいし、ひっそり息を潜めているものではなかろう。もっとも、資格がありながら第一線を離れている看護師さん、どこにいるのか。そしてどうしたら復職してもらえるのか。戻って欲しいと呼びかける側にとっては、その存在も復帰の手法も闇の中。ならば、やっぱり潜伏と言いたくなるのか。わからんではないが、もっと配慮があっていいのでないか。厚生労働省用語なのだろうが、そのまま使う山形大学も、どうだろう。復職研修制度の対象者として報道された方(もちろん固有名詞で報道)は、私が潜在看護師です、ということになるのだが。紙の上の役所用語で住むなら良いが、これではこの方や、本当に復職しようとしている見えない方々に、ちょっと申し訳ないように思うのは、私だけか。
2010.12.06
コメント(0)
-
海の魚の内陸地名、首の地名
青森県の鰺ヶ沢は、魚のアジではなく、葦が沢が転化。福島県の鮫川は、冷たい地下水にちなんで、冷め川の意味。吉田茂樹『図解雑学 日本の地名』ナツメ社、2005年 からところで、同書によると、「首」の地名が東北に多い。○大崎市(旧鳴子町)鬼首 坂上田村麻呂が蝦夷の首領の首を切って落としたところとの説話が残る。実際は、11世紀中頃、蝦夷の囚人を従えた安倍頼時の反乱軍が朝廷の征討軍を打ち破った所という。これに由来して鬼切部とされたのが、後に転化。○奥州市(旧江刺市)人首(ひとかべ) 坂上田村麻呂が悪路王の息子、人首丸の首を切って落としたと言われ、人こうべ村から、ひとかべ村に変化したという。○秋田県大仙市(旧西仙北町)強首(こわくび) もともと、近くの大巻に対して小巻(こまき)と呼ばれていたが、これが「こわまき」に音が変化し、後に強首になったようだ。大巻・小巻とは、雄物川が曲がって流れる地形に由来するから、巻が首に変化したのは、曲がる意味で共通するのだろう。
2010.12.05
コメント(0)
-
仙台のロータリー(その8)名取市相互台東(桜坂)
前回の相互台に続いて、そのお隣で、相互台東(桜坂)団地です。ロータリーは比較的早期の住宅団地に多くて最近は好まれないような気がすると、前に書きましたが、そうでもないですね。ここは最近の開発です。■関連する過去の記事(仙台のロータリー) 仙台のロータリー(その7)名取市相互台(2010年12月3日) 仙台のロータリー(その6)日本平(2010年12月2日) 仙台のロータリー(その5)ひより台(2010年11月27日) 仙台のロータリー(その4)東仙台5丁目(2010年11月26日) 仙台のロータリー(その3)永和台(2010年11月22日) 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)■調査成果を地図に落としてみました
2010.12.04
コメント(0)
-
仙台のロータリー(その7)名取市相互台
地図で見つけたので行ってみました。ところが、後でガックリ。よく地図を見るともう1つロータリーがあったのでした。画像の2つのほかに、さらに北にもう1つです。団地内の直線のメイン道路に串だんごのように。R286から相互台に上がった地点から、メイン道路の南側部分だけを往復してしまったのでした。反省。そして残念。とりあえず、2つを画像でご紹介します。■関連する過去の記事(仙台のロータリー) 仙台のロータリー(その6)日本平(2010年12月2日) 仙台のロータリー(その5)ひより台(2010年11月27日) 仙台のロータリー(その4)東仙台5丁目(2010年11月26日) 仙台のロータリー(その3)永和台(2010年11月22日) 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)
2010.12.03
コメント(0)
-
仙台のロータリー(その6)日本平
今度はこちら。近くに宅配ピザ屋さんがあって、店舗に戻る配達用バイクが、ロータリーをぐるりとUターンする光景を、子どもと一緒に眺めました。■関連する過去の記事(仙台のロータリー) 仙台のロータリー(その5)ひより台(2010年11月27日) 仙台のロータリー(その4)東仙台5丁目(2010年11月26日) 仙台のロータリー(その3)永和台(2010年11月22日) 仙台のロータリー(続)(2010年11月22日) 仙台のロータリー交差点を考える(2010年11月21日)(向陽台ロータリー)
2010.12.02
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1