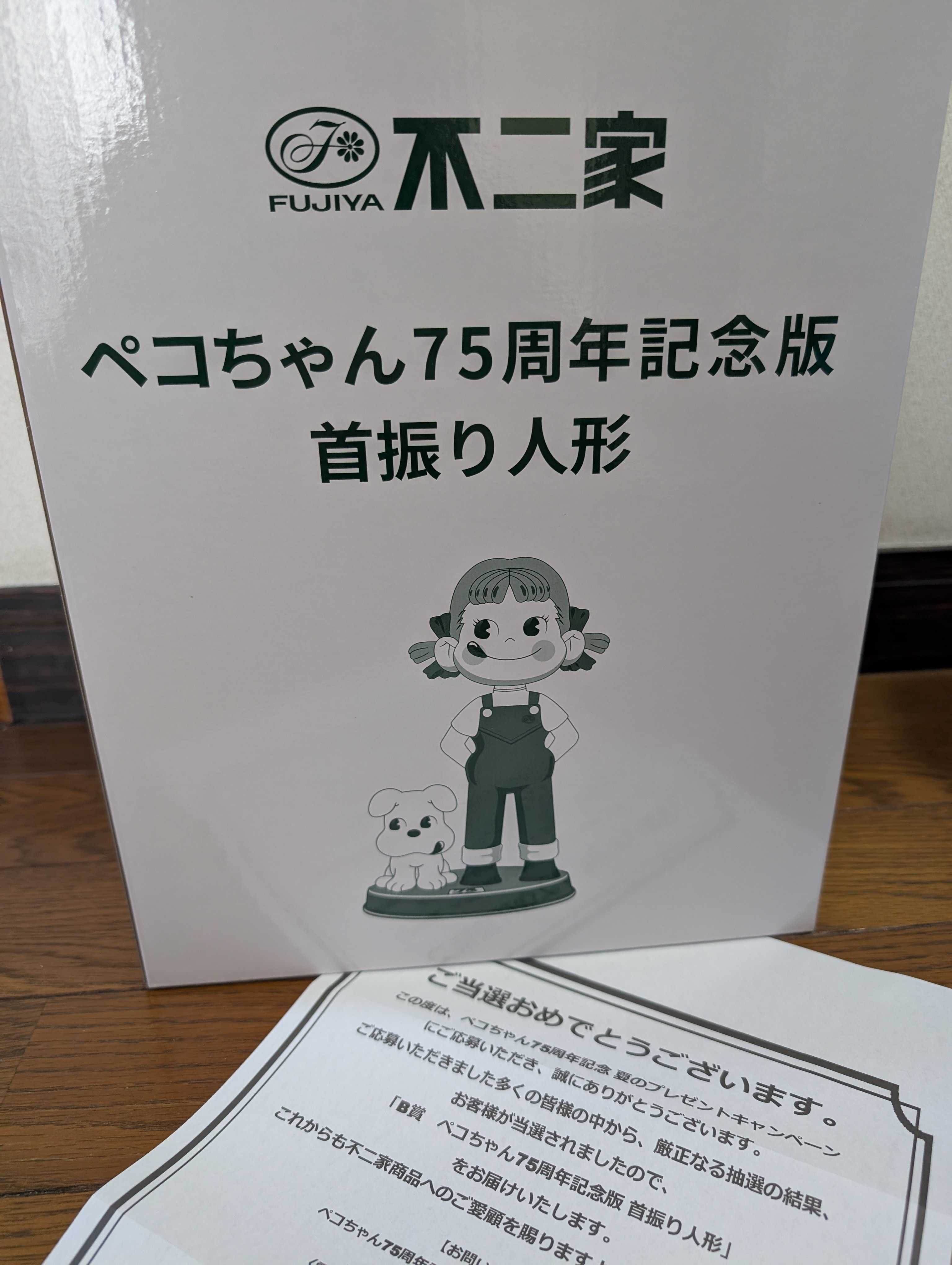2015年04月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
ドローンと法規制論議を考える
政府与党はドローンの法規制の検討に入ったという。まず、官邸や国会周辺の上空を飛行禁止とする議員立法を、いまの定例会に提出。次いで、購入の際の登録義務づけなどの規制を、次の臨時国会に提案するという方針と報道されている。そんな中、大阪市は市内981の全ての公園でドローン飛行を禁じる方針を打ち出した。条例の制定や改正を行うのではなく、「他人に危害を及ぼす恐れのある行為」という現在の条項の運用で対処するのだとか。一網打尽にドローンの操作を禁止するのは広汎に過ぎないか、との懸念は一応感じる。もちろん、社会情勢の変化に応じた法(条例)解釈の多少の幅はあって当然ではあるが。運用上にしても立法論としても、届出制にするとか、構築物の周辺に限定するなどの、より制限的な規制方法は考えられるだろう。おそらく、保守派の首長のことだから、いま国に先んじて厳しい印象を与える行動そのものに意義を感じているのだろう。この動きが上滑り的な時流にのって全国に広まってしまうかも知れない。ところで、総務省総合通信基盤局が28日に、小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起、というものをリリースしている。読んでみると、ドローンは「普段人の目が届かない民家やマンションの部屋の中などを空から撮影することが可能です」から始まって、撮影した画像をインターネットで公開することは、プライバシーや肖像権を侵害するおそれがあるということを述べている。政府の方針に沿ってまずは注意喚起ということだろうが、おかしいと感じるのは私だけであるまい。そもそも、飛行物体を承諾なく他人の家の上に飛ばすこと自体が、所有権を侵しているのであり、(民事上)違法と評価されるべきことである。「...が可能です」と言える役人の感覚がおかしいのだ。インターネット通信を所管する立場で言えること(だけ)を精一杯国民に伝えたということだろうが、まさに縦割りの典型だ。そもそも、ドローンなる新手の飛び道具が登場したとはいえ、ドローン問題の本体は、勝手にのぞき見してはいけないよという点と、これに加えて勝手に人家の敷地内に飛ばしてはいけない、という点。何のことはなくて、違法ではあるが、本来的に社会生活におけるマナーに属すると言っても良い程度の話だ。そんなこと言ったって、やっぱり危険だろう、という国民の方々もおられるだろう。しかし、ドローン自体に危険があるのではなく、危険物を装填して落下させるとか、機密やプライバシーを覗かれることについて、危険や危機を感じるのではないか。とすれば、それはドローンなる道具を極めて特殊な用途に活用した場合なのであって、当該の行為そのものを規制(強い処罰)することが本筋だ。銃について、道具じたいが危険であることから規制を行っている(登録制など)こととは、本質的に異なるのだ。また、官邸などの危機管理は当然のことで、警備や情報管理をしっかりして守るべきを守ることにつきる。今回は、黒く塗って悪質だとか、福島の放射能を含む砂を入れた点からテロに悪用されるだとか、警備の不備を押し隠そうと躍起になる故か、無理をして危険性を誇張しようとしているようにさえ見える。何だか余計なところで大騒ぎ。
2015.04.30
コメント(0)
-
人口推計でみる東北(その1 新潟と宮城)
ちょっと前に、総務省統計局の推計人口(平成26年10月現在)統計をながめて、自然増と社会増の関係で都道府県を類別し、宮城がやや特異な地位にあることなどを記した。■データ出典及び参考:「人口推計(平成26年10月1日現在)」総務省統計局■関連する過去の記事 人口増減の偏り(2015年4月24日)転入転出も大事だが、年齢階層、つまり少子高齢化も重要な視点だ。いくつかポイントを挙げれば...○ 全国で総人口は4年連続で減少○ 戦後生まれは80.3%(初めて8割台)○ 自然減は8年連続で減少。減少幅拡大○ 65歳以上人口が初めて年少(14歳以下)人口の2倍を上回る○ 75歳以上人口は12.5%となり(8人に1人)、過去最低となった年少人口割合(12.8%)に迫るなどが、一定の衝撃感をもって報道もされたとおりである。ところで、全国の数値で対前年(平成25年10月)の減少215千人のうち、自然減は251千人、社会増が36千人である。全国値での社会増だから、国外から移住または帰国する日本人と外国人ということ(正確に言えば出国者から入国者を引いた数値)になる。社会増36千人は近年では多い方で、内訳は日本人がマイナス23千人、外国人がプラス60千人とある。つまり、日本人は出る方が多く、外国人の移入が国全体の社会増を支えている。純増減マイナス215千人に対して社会増36千人なので、寄与率は高くないとも言えるが、今後の世界経済情勢や外国人労働力論議などの行方によっては重要な点になる可能性がある。さて、ふたたび都道府県別の数値に目を移して、ややじっくりと検討したい。(これから何点かに分けて検討していきます。)その1 宮城が新潟を抜いて14位にあまり宮城では報道されなかったように思うが、新潟が14位の座を宮城に譲っている。新潟日報では、この点を見出しにして、4月18日に報じている(web版で確認)。新潟は自然減、社会減が同時に進むが、宮城では自然減は進むものの社会増であることを、比較として示している。新潟は明治は日本で最も人口が多い県だったはずだ。宮城に越されたことがまさにニュースになるのだろう。明治初年の新潟県は人口144万人で飛び抜けて全国一だった。続くのは兵庫県131万人、愛知県122万人、広島県113万人、東京都109万人。■関連する過去の記事 秋田の人口減を考える(2010年12月28日)今では、人口総数よりも、高齢化や社会増減など、また地域間格差という構造分析が重要とされるが、総数の意味も小さくはないだろう。
2015.04.29
コメント(0)
-
涌谷町の地名 産仮小屋
かつては出産期の女性は穢れと結びつけられ、家族や産婦を見舞った者は、たとえば神社に行くことや神事を控えた。産婦や月事の女性が、家の裏口だけで出入りしたり、家族と別の小屋で生活するなどの習俗もあった。こうした小屋や月事そのものを、産屋、ヒマヤ(信州)、ヒゴヤ(火小屋)(三河)、カド(三宅島)、カリヤ(仮屋)(三河)、タヤ、オリタヤ(降り田屋)(諏訪)、ベツヤ(別屋)(隠岐)、ツリヤ(讃岐)、不浄小屋(大隅半島)、汚れ屋(伊豆)、アサゴヤ(敦賀)などと称した。敦賀のばあい、月々の忌みでアサゴヤに入るのは明治まで続き、その後は家にはいるが、戸口の敷居に腰を掛けて食べ、食後は水か湯で浄める。出産はアサゴヤとは別にコヤと謂い、産後3日から男児23日、女児24日間いる。産小屋の習俗は重視され、かなり後にまで続いた。産屋の習俗は昭和40年代まで、敦賀市あたりでは残っていた。東京の世田谷区の以前の大字のうち8つに、山谷の小地名があったが、産屋に由来するらしい。涌谷町にある「のの岳字産仮小屋」は間違いない。■参考 柳田国男『禁忌習俗事典 タブーの民俗学手帳』河出書房新社、2014年 同書は、柳田国男『葬送習俗語彙』(岩波書店、1937年)を改題したもの。 巻末の筒井功氏による解題も参考にした(上記の昭和40年代の記述以降の部分)。
2015.04.25
コメント(0)
-
人口増減の偏り
総務省統計局の人口推計(昨年10月1日現在)が先週発表された。対前年で総人口は減少するなか、都道府県別では増加が7都県。しかも東京、埼玉、神奈川などは増加率が前回よりも増えている。減少率は、秋田、青森、高知の順に高い。宮城は増加から減少に転じた。人口増減の要因別に都道府県を類別してみると、下のとおり。(1)人口増加(1a)自然増・社会増 東京、神奈川、愛知、沖縄(1b)自然減・社会増 埼玉、千葉、福岡(2)人口減少(2a)自然増・社会減 滋賀(2b)自然減・社会増 宮城(3b)自然減・社会減 その他増減の結果を捨象して類別すると、a 自然増・社会増 東京、神奈川、愛知、沖縄(前回は同4県プラス滋賀)b 自然増・社会減 滋賀 (前回はなし)c 自然減・社会増 埼玉、千葉、福岡、宮城 (前回は宮城、埼玉、福岡、千葉、大阪)d 自然減・社会減 その他38道府県 (前回は37道府県。今回は大阪が加わる)である。自然増が若い世代のいる東京や神奈川など、地域的に限定されているということ。しかもこれら地域では、社会増の率も上昇している。
2015.04.24
コメント(0)
-
「衆議院」売り上げで福島県に寄付
こんな話題が配信されている。今日(23日)は、4県の知事が来年度以降の後期5年間の復興事業財源の要望に官邸や各省に行っているはずだが、内堀知事は、「衆議院」の名の日本酒の売り上げの一部を福島県に寄付する贈呈式に臨んだという。これは、昨年3月11日から国会内で販売されているもので、純米吟醸酒。福島県の蔵元が作った酒だそうだ。売り上げの3パーセントにあたる35万円あまり。なるほど、復興に向けた福島と国会の熱い想いだ。別の記事では、伊吹元議長の発案とある。
2015.04.23
コメント(0)
-
季節が変わったと思うわけ
電車の乗客でコート姿がめっきり減ったこと。来ているのは仙台からちょっと離れて早起きの人。通勤経路にある家のシーリングファンが止まっている。大きな吹き抜けがあるようで、窓からいつもファンが見えるのだが、今までは常に回っていた。我が家にもあるのだが、そろそろ止めるか、それとも夏向きに回すか(暖房使用時の冬とは逆の回転)気にしていたところだ。4月下旬、来週は連休。田んぼに水が張られるだろうか。本州最北、青森の桜は例年になく早いようだ。
2015.04.23
コメント(0)
-
空き家率、持ち家率ともに減少する被災地
平成25年住宅・土地統計調査の確報集計が2月に公表されている(総務省)。空き家の増加が問題となっており、昨年には特別措置法も制定されたところだが、空き家率は13.5%(前回平成20年13.1)である。都道府県別では山梨県がトップで22.0%、長野、和歌山、四国4県などが続く。逆に、空き家率の低いのは、宮城がトップで9.4%(前回平成20年は13.7)、第2位は沖縄10.4(前回10.3)だ。以下、山形、埼玉、神奈川、東京、福島11.7(13.0)と続く。世代間同居の多い沖縄や山形は前回から高く、人口再集中がすすむ首都圏も依然空き家は少ない。これに対して、宮城と福島は明らかに震災の影響で、空き家が増える傾向にある全国に対して、空き家が顕著に少なくなっている。(おだずま注)発表資料では別荘等の二次的住宅を除いた数値で都道府県別の空家率を出しているものがある。実際上の意味があるのだろうが、上記は、全住宅の数値で統一した。持ち家率は、全国で61.7%で前回(61.1)より上昇。富山79.4、秋田78.1、山形76.7などが高く、低いのは東京45.8、沖縄、福岡、大阪、北海道の順。宮城は58.0で前回60.8から大きく後退。岩手68.9(前回71.9)、福島66.5(68.8)ともに、全国の上昇傾向に逆行して大きく減少したのが特徴だ。(おだずま注)上記数値は正確には「持ち家住宅率」というもの。ベースが住宅か世帯かで数値もことなるようだ。このように、住居の状況は被災地は全国とまったく逆行しているわけだ。
2015.04.22
コメント(0)
-
伊能嘉矩
明治元年に岩手県下閉伊郡遠野町の南部藩の学者の家に生まれ、のち東京に出て坪井正五郎博士に人類学を学ぶ。28歳で台湾に渡る。晩年は郷土につくして大正14年、58歳で死去。(いのうよしのり)日清戦争で台湾を領土としたものの、野蛮人の巣のように思われた当地の特に奥地については全くわかっていなかった。伊能は、ひとり台湾にわたり探検と研究に10年を費やして、50年にわたる台湾統治で暮らしやすさと日本の発展の足がかりのきっかけをつくった。明治38年遠野に帰り、台湾で書き留めたものの整理をしながら『上閉伊郡誌』、『遠野方言誌』などを書き、郷土史研究の方法を明らかにした。生涯を捧げて書いた『台湾文化志』は死後に出版されたが、いまでも台湾を知る最も大事な資料とされている。■宮本常一『辺境を歩いた人々』(河出書房新社、2005年)から当ジャーナル整理■関連する過去の記事 笹森儀助(2015年4月19日)
2015.04.20
コメント(1)
-
笹森儀助
弘前藩御目付役の子に生まれ、のちに千島、沖縄、奄美、台湾や朝鮮などを歩き回り、晩年は請われて青森市第2代市長(1902-03)を務めた。廃藩置県後の県庁役人として中津軽郡郡長まで務めたが、37歳で辞職し、明治14年、かつて藩の牧場があった常盤野に農牧社を興す。東京まで28日かけて出て行き、政府から金を借り入れ、牛馬をひいて戻ったという。明治24年には国内を旅行。25年には千島探険を実施、日本にとって非常に重要な千島の開発と守りについて意見をまとめる。儀助の出版した『千島探験』は書記長官井上毅の斡旋で明治天皇もご覧になる。同書を読み感銘した井上馨内務大臣は、国内の砂糖生産をあげる方策を考えるため、南の島々の実情を調査する必要を感じていたことから、儀助に南島探検を依頼した。明治26年、49歳の儀助はマラリヤやハブの危険がある南西の旅に、決死の覚悟で弘前を旅立つ。東京では、沖縄探検を先行した田代安定に話を聞き、6月那覇に着く。本島、宮古島、石垣島、西表島、与那国島、戻って奄美大島などをつぶさに歩いた。マラリヤと食糧難で極貧の生活。役人や士族の搾取を含めて、物産、金融、商業、風俗、気候、地理などをひろく見て歩いた。大島では、製糖業の実態を調べ、鹿児島の商人が利益をしぼりとって島民が借金に苦しんでいる姿には、儀助も驚いた。決死の旅で調べたことは『南島探験』に著し、人々に感銘を与え、日本人は沖縄をもっと大事にしなければならないことを示した。明治27年から31年まで、大島島司となる。むかし薩摩藩が総買上制により島民の売買を禁じることで莫大な利益を得ていたが、維新後も県は鹿児島商人と結んで大島商社をつくり、砂糖代と差し引きに日用品を高く売りつけるなど、島民を苦しめてきた。明治11年に自由取引が認められると、各地の砂糖商人が買い付けに集まったが、島民の気を引くため品物を高利で掛け売りにしたため、島民には借金を作って財産をなくすものが続出した。儀助が島司になったときはこの有様で、島の状況は党派がいがみあい、鹿児島派が人民派を圧迫していた。また、島の役所でさえ小さい島々を調査していないことに気がつき、薩南十島の生活の様子を調べ『拾島状況録』を書いている。島司として、儀助は産業開発に力を注いだが、31年突然辞職。結局、鹿児島派と意見が合わなかったようである。東京に帰った儀助は、陸羯南の推薦で東亜同文会の嘱託として日本語学校開校のため、明治32年、55歳で朝鮮にわたる。その間数度にわたり、国境地帯やシベリアも視察している。明治34年日本に戻るが、青森市の初代市長工藤卓爾が後任として儀助を推薦した。県の中心である青森市が他と渡り合うには外交の腕前が必要。また自分や一部の利益ではなく、公平で熱心に働く人が必要だ、というのが推薦の理由であった。市長としては、まず財政の整理に務めた。税金の未納が2万4千円余りあった。儀助の苦心により、市長を辞めるときには未納はわずか660円余りに減っていた。そのほか、水道を引くことの糸口をつけた。市立商業補習学校(のちの県立商業学校)も儀助の努力の結果である。大正4年(1915)9月に71歳で亡くなる。■宮本常一『辺境を歩いた人々』(河出書房新社、2005年)から当ジャーナル整理■関連する過去の記事 陸羯南(2007年7月23日)
2015.04.19
コメント(0)
-
宮城県進学トップ高校の今はどうか(続)
某週刊誌による。国公立大医学部医学科の合格実績でみる高校ランキング。大都市圏や西日本が強い。医学部定員の西高東低とも関係していよう。宮城県では仙台第二が全国30位。公立高校だけでみれば、全国5位になるようだ。■公立高校だけを抜き出した場合(国公立医学部医学科合格者数)順位高校名卒業数合格者数東大京大理系合格数12札幌南31854717熊本397411124藤島(福井)340361624高松321361130仙台第二312331830旭丘(愛知)3193324■北海道・東北の状況1 札幌南 (合格者数)542 仙台第二 333 秋田 234 弘前 226 山形東 217 旭川東8 盛岡第一、県立福島10 札幌北11 八戸12 安積13 仙台第一 12仙台第二は前年は合格者数45で、札幌南(44)を越えて第1位であった。(ここ4年間の仙台第二の推移は、43人→44→45→33 で今春はやや減らしている。)関東以北の公立高校を牽引する進学高に成長したと評していいだろう。この週刊誌は、国公立医学科合格の水準と比較させて、東大京大の理系合格者数を並べているのだが、医学科は女子も志望が多いことなどもあり、共学化のひとつの効果と言えるようにも思われる。■関連する過去の記事 宮城県進学トップ高校の今はどうか(2015年4月13日) 宮城県進学トップ高校の状況は変わったか(2012年9月8日) 今春の各高校の大学合格実績 概略(2012年5月29日) 宮城県の高校の進学実績を考える(2010年11月20日) 宮城の県立高校の「現役」進路実現力を考える(09年8月25日) 宮城県の県立高校の進路実現力を考える(09年8月21日) 共学化の方針を堅持(09年2月5日) 県立高校共学化論議を考える(08年12月18日) 梅原市長の高校男女別学の主張を考える(08年11月13日) 高校の進学状況 福島県のデータ(08年8月3日) 宮城県の伝統校の進学力を考える 青森県との比較(08年8月1日) 改めて宮城県の伝統校の進学実績を考える(08年7月31日) 公立高校の学区撤廃を考える(08年7月30日)(宮城県の方針) 宮城県立高校の男女共学化を考える(4)真に学校を思うなら(05年12月11日) 宮城県立高校の男女共学化を考える(3)妙案登場!?(05年12月7日) 仙台市梅原市長の「仙台一高・仙台二高別学維持」発言に思う(05年11月30日) 宮城県内の公立高校の男女共学化論議を考える(2)歴史(05年11月28日) 宮城県立高校の男女共学化を考える(1)序論(05年10月28日) 宮城の進学率と公立高校を考える(05年9月6日)
2015.04.18
コメント(0)
-

send i(シリーズ仙台百景 37)
市内の専門学校の建物。道路に面したガラスに Send i School of ... とある。朝の陽光に輝いているのが目にとまった。iが存在感を発揮しているからだ。愛を送信するという主義のもとの何とか学部(school)か、虚数の i か、はたまた、iPOD や iPS細胞のようにあえて小文字のiを使って何か世界に発信しようというのか。いや、単に sendai の a が、シールが剥がれただけのようだ。ちなみにここはペット専門学校で、ガラスの表記も、of Total Pets と続く。ペットたちの学校(メダカの学校みたい)、ペットたち総体の群れ? あるいは、完全な力をもつ(時代の)寵児を養成する学校と深読みされるかも。おそらく、school of(for) pet care とか、school of comprehensive(total) pet keeping とか言葉を補った方が良いように感じた。学校の教えている内容がわからないのだが。send i に話を戻すが、かなり以前に(1990年代か)、藤崎が、sendaiをもじって、send ai(愛を贈る)みたいなことで、ギフトのキャンペーンかロゴマークかをやっていたような気がする。面白い着眼をした人が居たのだなと感心したものだ。■シリーズ 仙台百景(こんな企画で100まで続くでしょうか) 何と4年ぶりに追加いたしました。ふと目にとまった不思議や、何かを象徴する光景などを探してまいりましたが(ほとんどくだらないものばかり)、100に達するのはいつやら。 飲酒運転に、喝!(シリーズ仙台百景 36)(2011年9月24日) みんなのよい食プロジェクト(シリーズ仙台百景 35)(2011年5月14日) 彩雲?でしょうか(シリーズ仙台百景 34)(2011年5月3日) 耀け!!ベガルタ仙台(シリーズ仙台百景 33)(2010年12月26日) 太白トンネル(シリーズ仙台百景 32)(2010年11月23日) 富士宮やきそば(シリーズ仙台百景 31)(2010年10月17日) フェンスのメッセージ(シリーズ仙台百景 30)(2010年2月28日) 宮城刑務所(シリーズ仙台百景 29)(08年10月12日) 松森焔硝蔵跡(シリーズ仙台百景 28)(08年8月31日) 十一面観音堂(シリーズ仙台百景 27)(07年10月23日) 陸奥国分寺薬師堂(シリーズ仙台百景 26)(07年10月17日) 県民の森 鶴ケ丘口(シリーズ仙台百景 25)(07年8月26日) 一時停止だ!三時はお茶だ!(シリーズ仙台百景 24)(07年8月20日) 風の環(シリーズ仙台百景 23)(07年7月7日) 冷やし中華の龍亭(シリーズ仙台百景 22)(07年6月29日) 県民の森(シリーズ仙台百景 21)(07年4月8日) 数字の練習ボード?(シリーズ仙台百景 20)(07年3月25日) 半田屋一番町に進出!(シリーズ仙台百景 19)(07年3月1日) 仙台百景画像散歩(その18 撮影成功!霊気のトンネル)(07年2月6日) 仙台百景画像散歩(その17 変な漢字の看板)(07年1月28日) 仙台百景画像散歩(その16 駅前東宝ビル)(07年1月13日) 仙台百景画像散歩(その15 空から見た仙台)(06年12月29日) 仙台百景画像散歩(その14 光のページェント)(06年12月13日) 仙台百景画像散歩(その13 東京スター銀行)(06年11月30日) 仙台百景画像散歩(その12 建設ラッシュ再来?)(06年11月10日) 仙台百景画像散歩(その11 E721系電車)(06年7月25日) 仙台百景画像散歩(その10 ワンコイン端末)(06年7月7日) 仙台百景画像散歩(その9 ヤギさんの看板)(06年6月19日) 仙台百景画像散歩(その8 キック治療?)(06年6月18日) 仙台百景画像散歩(その7 ホテルモントレ)(06年6月4日) 仙台百景画像散歩(その6 佐々重ビル)(06年5月24日) 仙台百景画像散歩(その5 車止めポール)(06年4月29日) 仙台百景画像散歩(その4 オロナミンC)(06年4月4日) 仙台百景画像散歩(その3 東仙台案内踏切)(06年3月22日) 仙台百景画像散歩(その2 はんだや)(06年3月18日) 仙台ミステリー?風景(06年3月4日)
2015.04.18
コメント(0)
-
石巻こけし
河北新報朝刊に載っていた。林屋呉服店の若旦那が考案して、隣接の空き店舗にこけし販売店を開設。商店街の再生と、新たな名物を目指す。海をイメージした青色が基調。林さんは、東北の11系統の伝統こけしに類似しないよう注意もはらい、12番目の伝統こけしにしたいとのこと。■関連する過去の記事 木地業とこけしの歴史を考える(その2)(2014年8月10日) 木地業とこけしの歴史を考える(その1)(2014年8月8日) 木地師と東北を考える(2014年7月12日) 黒石の純金こけし(07年12月22日)
2015.04.17
コメント(0)
-
ゆとり~と小牛田
販促の回し者ではないのですが、考え方一つでここは便利なまち。JR小牛田駅に隣接なので仙台にも快適に通勤通学。休みにはふらっと野でも山でも足を伸ばせる。もちろん、小牛田駅前で引っ掛けて帰ってもよし。宮城県住宅供給公社のパンフレットに空撮写真がある。駅、小中学校、役場などが集まっていて、周囲には田園も。158区画。先着順だそうです。坪7万円台。■関連する過去の記事 小牛田駅前 20時(08年5月10日)
2015.04.15
コメント(0)
-
庄内と秋田の新幹線延伸構想
14日に新庄駅で「陸羽東西線利用推進協議会」が開かれ、陸羽西線を活用した山形新幹線の酒田延伸が話題となったが、協議会長の山尾新庄市長は、長年秋田県側といっしょに大曲延伸に取り組んできた経緯があることから、両にらみはできないと、延伸を望む酒田市とは共同歩調を取らない姿勢を示した、という報道があった。つまり、山形新幹線をさらに奥羽本線を使って、湯沢、横手、大曲とのばす構想があること。そして、酒田には陸羽西線を使って新庄から酒田に新幹線を延伸する構想があること。これらのことがわかる。庄内への延伸は、酒田市が力を入れているが、本間市長の公約とのこと。現在、酒田と山形市は、鉄道で2時間半もかかる。実現すれば、1時間15分程度と、通勤も可能となるのだという。宮城県人の感覚でいうと、仙台と気仙沼の関係だろうか。新庄と酒田の間55.2kmのミニ新幹線化の概算事業費は350億円。フル規格の20分の1で、高速道路の10分の1の費用。酒田市は、工期は3年で開業できると説明している。(1999年新庄までの延伸の事業費は343億円だった。)ところで、庄内でも鶴岡市は羽越新幹線や羽越線高速化に力を入れる。羽越と奥羽の2本の新幹線は、1973年の全国新幹線鉄道整備法の基本計画線であり、山形県も、フル規格での奥羽新幹線と羽越新幹線の実現を掲げている(同県のサイト。東京酒田が2時間40分と謳われている。)酒田市とて県や鶴岡市の羽越新幹線実現には賛成だが、何十年も先の話より現実的なミニの可能性に賭けているようだ。最初のニュースに出ていた大曲延伸については、湯沢市や横手市で熱意も見えるようではあるが、当の秋田県の議会答弁などでは費用負担を想定してか、だいぶ引き気味の姿勢だ。■関連する過去の記事 山形の鉄道建設熱を考える(続)(07年1月3日) 山形の鉄道建設熱を考える(07年1月2日)
2015.04.14
コメント(0)
-
宮城県進学トップ高校の今はどうか
仙台第二高校の今春(平成27年春)の進路実績が同校サイトに出ている。宮城県の進学トップ校の充実をねがって記事にしたのが、もう3年前のこと。当時の記事のテーブルに併せて、今春の実績を記してみる。仙台第二高校 大学合格状況 種別平27年3月うち現役平24年3月現役23年3月現役22年3月現役国立大学232127218137221129233125公立大学207201116102012私立43590397131374103東北大学1066810675894812568東京大学1710126127126医学科国公立35124416医学科総数68135518いま時間がないので、平成26や25を省略してしまっているのだが、仙台二高は安定的に東北地域でぬきんでた実績を確立しつつあるといって良いだろう。週刊誌では例によって主要高校の大学進学状況が出ているが、関東以北では随一だ。東京大学進学者数でみても、県立高校としては全国的にも有数になるだろう。ただ、切磋琢磨の校風が上昇志向を生みすぎるのか、現役の進路達成状況は相変わらずだ。ここは評価が分かれるかも知れないが、本県の大きな特徴であることは間違いない。(週刊誌でみると、他県はずいぶん浪人は減っているように感じられる。)以前はひとりきり論じたが、もう、共学の是非や学区制論議は落ち着いただろう。(もちろん検証はされるべきだが。)時間をみつけて、当ジャーナル流の分析を行いたい。(ところが、仙台一高、三高など、まだデータが出ていないのですよ。)■関連する過去の記事 宮城県進学トップ高校の状況は変わったか(2012年9月8日) 今春の各高校の大学合格実績 概略(2012年5月29日) 宮城県の高校の進学実績を考える(2010年11月20日) 宮城の県立高校の「現役」進路実現力を考える(09年8月25日) 宮城県の県立高校の進路実現力を考える(09年8月21日) 共学化の方針を堅持(09年2月5日) 県立高校共学化論議を考える(08年12月18日) 梅原市長の高校男女別学の主張を考える(08年11月13日) 高校の進学状況 福島県のデータ(08年8月3日) 宮城県の伝統校の進学力を考える 青森県との比較(08年8月1日) 改めて宮城県の伝統校の進学実績を考える(08年7月31日) 公立高校の学区撤廃を考える(08年7月30日)(宮城県の方針) 宮城県立高校の男女共学化を考える(4)真に学校を思うなら(05年12月11日) 宮城県立高校の男女共学化を考える(3)妙案登場!?(05年12月7日) 仙台市梅原市長の「仙台一高・仙台二高別学維持」発言に思う(05年11月30日) 宮城県内の公立高校の男女共学化論議を考える(2)歴史(05年11月28日) 宮城県立高校の男女共学化を考える(1)序論(05年10月28日) 宮城の進学率と公立高校を考える(05年9月6日)
2015.04.13
コメント(0)
-

八峰町 漁火の館
昨日につづき、八峰の旅の一画像を。岩館地区農林漁業体験交流施設、漁火の館と表記されています。昨日の記事では、八峰町を訪問したルートと施設を全部覚えているなどと豪語しましたが、写真を振り返るとこの一枚が。書き漏らしていたものがあったのです。あきた白神駅・御所の台地区からチゴキ岬にむかって大間越街道(R101)を走る途中、岩館駅のあたりで、海岸方面に降りてみようと思い立って、小道に分け入ってみました。五能線の海側、とは言っても海から見ればかなり高台に、旧街道のような道沿いに家並みがあり、その中にあったのが、この施設。比較的新しいもののようでした。岩館地区は、漁港を抱え、海水浴場や民宿などもある町のようです。車ですっ飛ばす主街道ではわからない地域の良さが、あるはずでしょう。■関連する過去の記事(八峰町) 八峰町を思い出す(2015年4月11日) 五能線の駅たち(2013年6月1日) チゴキ灯台、お殿水(八峰町)(2013年5月17日) ハタハタ館(八峰町)(2013年5月16日) 鹿の浦展望所(八峰町)(2013年5月15日) 手這坂を訪ねた(2013年5月11日) 秋田の桃源郷 手這坂(2013年2月3日)
2015.04.12
コメント(0)
-

八峰町を思い出す
朝仕事の車のラジオ。真打ち競演は秋田県八峰町からだった。先週もそうだったのだが、収録は一度にやっているのだろう。先週土曜日は、堺すすむさんが出ていて、同乗していた子どもにナンデカを聴かせた。子らが小さい頃は、風邪を引いたオッさんと盲腸(牛と蝶々)のネタをクイズにして出しては喜ばれたのだが、御本家を聴いてどう思ったか。(■関連する過去の記事 堺すすむと仙山線(12年9月23日))その堺さんは、盲腸のネタも出していたし、気(木)が変わった、などの定番ネタも披露。また地元に引っ掛けて、ハッポウ美人などとやっていた。いや名人芸ですね。さて、八峰町というと、2年前の一人旅で訪れた。旅のひとコマを引っ張り出してみました。手這坂のあと大きな農道まで戻り、北上するときに、手間を悠々と走るバイクがあって、やむを得ず追い越したのだが、新しい役場庁舎が目に入って、車を停めて写真を撮った。冒頭の画像です。このバイクが映っている。このあと、また追い越しをさせていただくのだった。思い出します。道の駅みねはま、ポンポコ山公園、手這坂集落、新しい町庁舎、鹿の浦展望所、ハタハタ館と白神体験センター、いさりび温泉、あきた白神駅と連絡跨線橋、チゴキ灯台、御殿水、など。今でも巡った順番やルートはよく覚えている。初夏の沿線のさわやかな緑、穏やかな日本海と青い空。■関連する過去の記事 五能線の駅たち(2013年6月1日) チゴキ灯台、お殿水(八峰町)(2013年5月17日) ハタハタ館(八峰町)(2013年5月16日) 鹿の浦展望所(八峰町)(2013年5月15日) 手這坂を訪ねた(2013年5月11日) 秋田の桃源郷 手這坂(2013年2月3日)
2015.04.11
コメント(0)
-
女性社長の多い青森と岩手
朝日新聞の記事(データでみる東北経済)に、女性社長の比率は青森が全国一とあった。2014年の女性社長の比率は、全国が7.5%(04年比の増加幅は1.5ポイント)。これは、帝国データバンクが全国150万社の情報を初めて都道府県別に集計したものだという。東北6県では7.6%で、青森10.1%は全国最高で、かつ唯一10%を超えている。04年比での伸び率でも最高だ。青森 全国1位 10.1%(04年比増加幅1.8ポイント)岩手 15位 8.l(1.4)宮城 28位 7.3(1.5)秋田 35位 7.0(1.4)山形 40位 6.4(1.7)福島 38位 6.7(1.5)東北6県 7.6(1.6)全国 7.5(1.5)これだけみると、何だ、青森や岩手は女性の社会進出が進んでいるじゃないか... とは言えない。後継者難が深刻で、男性社長の死亡後に妻がやむなく後を継ぐケースが多いのだという。帝国データバンクのサイトにあるレポートを読んでみた。第1位は朝日の記事のとおり、青森(10.14%)で、以下、2 沖縄 9.95%3 徳島 9.78%4 佐賀 9.64%5 奈良 9.42%などと続く。青森以外ずーっと西日本の独占が続き、15位岩手、16位東京、17位茨城でやっと青森以外の東日本が登場する。女性社長比率の上昇ランキングも出ている。前回2004年との比較だ。1位が沖縄で4.89ポイントも上昇。2位佐賀、3位鳥取が3ポイント以上。4位以下は、山梨、高知、島根、福井など。青森は1.78で18位。全国平均は1.47ポイントだ。ちなみに、前回の比率は第1位徳島8.51%、第2位青森8.36%で、以下、奈良7.75%、東京7.24%が7%以上。つまり、青森は今回たしかに第1位だが、この10年間での伸びは他県より高いわけではなく、今回上位に来た沖縄、佐賀などの「急追」で、前回の飛び抜けた高水準(前回は第2位だったものの、首位徳島とともに他を引き離していた)に比べれば、ランクは1位でも、水準の顕著さは薄れているとも言えそうだ。むしろ、順位よりも内容だろう。朝日が指摘しているように、高齢化と後継者難だとすれば、統計データの解析や解釈の恰好のモデル事例ともいうべきで、非常に興味深い。イメージとして、第1変数は女性の積極的な進出で、サービス産業のチャンスの大きい大都市地域や、地場産業の発達した地域、飲食や観光業などの女性がリードしやすい地域などが寄与する。第2変数は、高齢化、人口減少などの類のファクターで、係数がマイナスである。クロスセクションで観察すれば、西日本が圧倒し、時系列では第2変数より第1変数の影響が高い、という感じか。などとインスタントに想像してみたが、いやしかし、静岡、愛知、岐阜などが下位にひしめいていて伸びも鈍いなど、謎も多い。■関連する過去の記事 社長輩出率トップの山形県(2012年11月24日)
2015.04.09
コメント(0)
-
錦ヶ丘小学校
仙台市に127番目の小学校が開校。児童1400人とマンモス化した愛子小学校の学区を分ける形で、児童数は新1年生を入れて961人と、市内4番目とか。地域の方々には待ちに待った開校だろう。さて、重箱の隅をつついた話題で恐縮だが、かつて「ヶ」と「ケ」にこだわり、また、旭丘小、鶴谷小など仙台市の学校命名法を論じた当ジャーナルとしては、今日の報道で各メディアが「錦ケ丘小学校」と記していることに注意が及んだ。市教委のリリース通りなのだろうが、敢えてこれまでの慣例を離れてこうしたのは、団地名と合わせようという地域の声だったのだろうか。■関連する過去の記事(ほかにも何度か取り上げたような気がしますが...) 七ヶ浜のボッケ祭に行きました(09年11月8日)(全国市町村の「ケ」と「ヶ」について) 金ケ崎町は大きな「ケ」で決まり(07年9月29日) 旭ヶ丘などの表記「ケ」を考える(07年8月3日) 宮城・悩みの地名あれこれ(07年6月9日) やっぱりウ「オ」ークなのね(06年9月28日)
2015.04.06
コメント(0)
-
宮城県の民謡界
渡辺波光『宮城県民謡誌』(萬葉堂出版、1978年)は、民謡の宝庫であるわが宮城県の民謡について整理し、また、変遷する民謡界の大概を把握しようとする力作であると思う。これによると、20年ほど前(つまり1960年頃)は、桃水会、木兆会、大西会の3つだけが県内の民謡会だったが、いまでは小党分立。師匠の許でみっちり仕込まれて独立旗揚げを許されたものや、そうではないものなどもあるが、百花繚乱の状態という。著者がアンケートを集めて、40数件の会の概要が記されている。民謡にはまったく詳しくない私だが、何人か聞いたことのある御名前や、白鳥ビルも登場している。会の中には会員数が1万を超えるものもあり、脈々と地域に根付いた民謡の力に圧倒される。私の祖父はよくTVの民謡番組を見ていた。明治後年生まれの祖父の世代では、歌というと、長持唄やさんさ時雨などのような謡曲や民謡がなじんでいたのだと思う。歌謡曲系ではやはり演歌が好きだったようで、日常を話し言葉で方縷々ようなフォークソング系の楽曲に対しては「歌ではない」と断言していた。収穫や漁労、あるいは子守歌や望郷の念、新作の民謡などもあるようだ。庶民の生活にねざして、暮らしや心を唄い綴ってきた民謡について、勉強してみたい。
2015.04.05
コメント(1)
-
自転車を修理してもらう
一昨日の夜のこと。帰宅すると、自転車空気抜けてたようだと家族の声。上の子が日中の用事で使ったのだが、夕方に自動車学校に行く際には使えずに、そのため車で迎えに行ってくれとのこと。迎えは良いのだが、自転車は早速直しておかないと明日以降困ることになりかねない。さっそく自転車を確かめると、たしかに前輪がペチャンコ。前日にしっかり空気入れてやったのだが。パンクだろうか。もう夜7時も過ぎたし、どうしようか。よく行くDIYに電話で聞くと、外注になるのですぐには直せないと。それでは、と自転車を車に積んで、やや離れたところの自転車屋さんに直行してみたら、シャッター締まっている。次にショッピングモールに行った。自転車屋さんがあったはずだと。自転車屋さんが開いていて、受け付けてくれた。夜9時前に取りに来てくれと言われる。どこかの親子が、やはり故障したのだろう、マウンテンバイクを持ち込んでいた。ホッとして、その足で上の子を迎えに行き帰宅。ゆっくり風呂にも入ってから、再度ショッピングモールに行って、自転車を回収。あの親子もマウンテンバイクもって店を出るところだった。虫ゴムの交換で、500円程度。(こっちが古い感覚だったのかもしれないが)遅い時間でも対応してもらって、本当に良かった。
2015.04.04
コメント(0)
-
山村宏樹さんの見たイーグルスと仙台・東北
山村宏樹さんといえば、阪神ドラフト1位で入団、後に近鉄に移り、分配ドラフトで新生イーグルスに入る。創生期のわがイーグルスを支えてくれた貴重な戦力だ。今では仙台のメディアで解説をしてくれる。山村さんの本を読んでみた。(『楽天イーグルス 優勝への3251日』角川SSC新書、2013年)結構、優等生的なことを書いているのかなというのが率直な感想だが、それでも、時に鋭い叙述がある。たとえば、誰もが手探りだった球団創生。また、大震災の後のチームの意識。おそらく御仁の人柄を反映してのことで、やさしい文章でくるまれているが、山村さんや当時の選手たちの思いがわかるような気がする。また、仙台に残る決意を書いたくだりがある。失礼ながら、決して順風満帆ばかりではなかったプロ野球人生の中で、一からの球団づくり、野村監督や星野監督との出会い、そして震災など、さまざまなことがあって、それでもまだまだ本当は現役を続行できる可能性もあるのに、この仙台で引退して仙台に残るという決意をされた。このような人がいることに、ありがたい気持ちになります。球界のハプニングで生まれたわが楽天イーグルス。それでも、そこに集まった選手やスタッフが居て、それを応援する東北の人々が居て、いつしか人々は選手に励まされて、地域に根ざしてきていると言えるのではないか。今日は雨で中止になった。実は、球団とともに成長した我が家の子どもたちが、春休みで行く予定だった。残念だが、我々はこれからいつでも応援できる。山村さんとともに今年のイーグルスを応援していきたい。
2015.04.01
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1