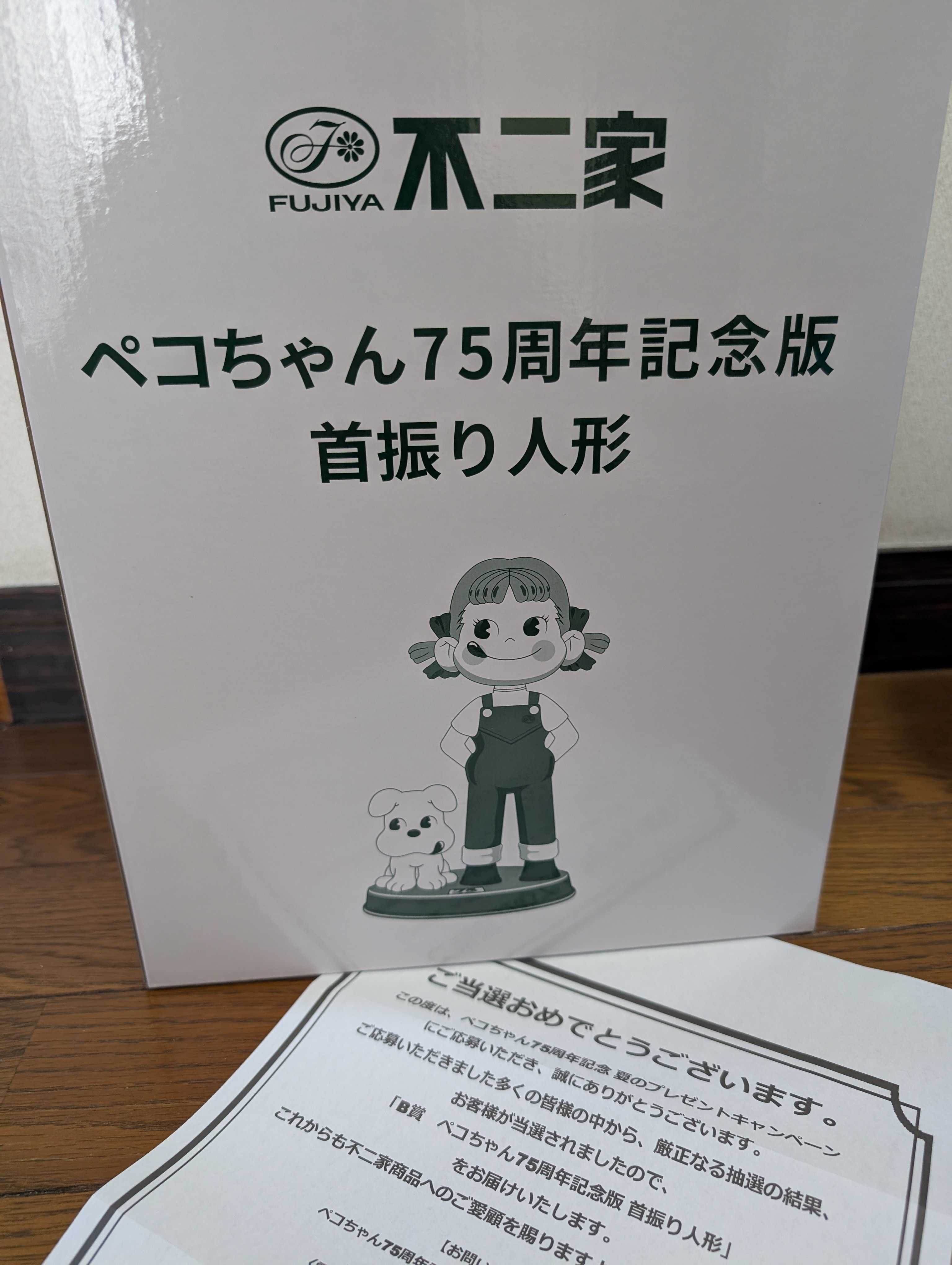2015年02月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

平田五郎の力試し石 画像です
先日、利府の延慶の碑について書きました。■関連する過去の記事 平田五郎の力試し石(2015年2月23日)県道利府バイパス(いわゆる利府街道です)を走って仙台市と利府町の境を過ぎると、ちょっとした坂道になります(化粧坂)。坂を上って吉野家の先。グランディ21に曲がる大きな交差点の手前。道路沿いに所狭しとばかりに、板碑と説明の看板がありました。看板には、狐の伝説が書かれています。碑の前には、藁に御幣、また茶碗に水が供えられていました。地元の方なのか、あるいは原町小学校隣にあるという平田神社でお世話しているのでしょうか。たまたま通る機会があったので、写真を撮りました。毎日車でここを走っているとしても、おそらく気がつかないのではないでしょうか。三原先生の著作をもとに先日書いた記事では、板碑は2つ並んでいて、「ア」ではなく「アン」の方が力試し石だ、とされています。現地には碑は一つだけ。梵字は「ア」です(との説明書き)。すると、ちょっと食い違うようにも思われますが。おそらく、最近まで別の場所に2基並んでいたものが、利府バイパスの工事の際に、用地の提供に伴う建物の建て直しなどの事情で、石碑を移す必要が生じて、1基だけを路傍のこの場所に移したのではないだろうか。残る1つは、もとの場所にひっそり残っているのか、あるいは残っていないのかもしれません。そして、もとの場所とは、浜街道(利府街道の旧道)沿いだったのではないだろうか。旧道は、この地点の付近では、利府バイパスと平行してすぐ西側を走っています。三原先生の文章では、平田五郎と狐の話で、神谷沢(利府町)の浜街道で神谷川にかかる土橋、という言い方が出てきて、今も平田橋がある、と書いています。五郎のいた藩政時代には、この付近で浜街道に土橋があって、そのそばに石碑2つがあったのでしょう。平田橋も神谷川も碑のまわりにはないのですが、いつか旧街道を歩いて探してみましょう。石碑に刻まれた延慶の時代は、鎌倉時代の後半の頃ですが、すでに浜街道(利府街道の旧道)は成立していたのでしょう。何かの供養か、旅が無事であるよう御加護を願ったのか。はるか中世の人々の思いが刻まれた碑が、いまは車で飛ばすせっかちな現代人を見守っています。
2015.02.27
コメント(0)
-
秋田県でTDKが2工場新設
TDKが発表したというニュース。由利本荘市とにかほ市に、2工場を建設。業績回復で250億円の投資をするという。既存敷設の増強なので、すぐに雇用の増はないということだが、地域経済にとって明るい話題ではないか。誘致企業に関しては、地元との産業連関が薄いとか、誘致にお金掛けてもすぐ撤退や雇用整理やらで実効性がないとか、いろいろに言われるが、それでも地域にとって目に見える「きざし」に違いない。人口減少社会において、人もそうだし、事業所だって来てくれることは、何はさて置いてもありがたいことだ。TDKといえばカセットテープのイメージが強く(古くてスミマセン)、完全に経済の時流や産業の今に乗り遅れている私だが、新工場ではスマートフォンの電子部品を作るのだそうだ。円安を踏まえて国内拠点に回帰、というような解説をする報道もあった。秋田は一大拠点だ。地域の視点からみた産業立地政策をめぐる環境も、見つめ直す転機かもしれない。
2015.02.26
コメント(0)
-
仙台の行人塚を考える
三原良吉氏の説明で仙台には行人塚が2つあるとされている、ということを書いた。■関連する過去の記事 秋保の木食知足上人(2015年2月20日) 行人塚の地名の由来(2008年9月12日) ガソリンカーと仙台(2012年11月5日)ところで、三原先生の同じ御著のなかに、川内のエノキ塚の話があって、「仙台市内に4箇所ある」行人塚の1つである、と書いている。う~ん、2か所ではなく、4か所もあるのか。古城神社(行人塚踏切)のほか、あと2つはどこになるのだろう。エノキ塚についての三原先生の解説は概ね次のとおり。仙台商業の扇坂プール前の筋違橋の北から、山屋敷に通じる坂道を登り詰めると右側に高台があって、綱村公の御茶屋の跡。その南向かいに行者塚と伝えられるエノキ塚がある。榎の老木があったのでそう称する。下は二之丸裏下馬から続く千貫沢である。二之丸がわの谷の斜面は今も大木の密林で昔は狐狸の類が多く、昔は仙台城の化け物話の中心だった。このような説明である。(三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』宝文堂、1982年)ここでエノキ塚とされているのは、東北大の川内キャンパスの西側の外縁あたりになるだろうか。千貫沢とされるのは植物園のあたりのことか。それとも教養部設置前の付近一帯を指しているのだろうか。さて、行人塚のほかの場所。他の文献で探してみたい。
2015.02.25
コメント(2)
-
無灯火運転の危険を考える
最近多く見かけるようになった気がするのだが、夜に無灯火のまま道路を走行する車。非常に危険である。たとえば、仙台駅前や東二番丁通り辺りなら、街路灯と周囲の建物の明かりで、何とか車の存在が認識されるだろうが(だから良いという訳では勿論ない)、普通の道路上でこのまま50kmで走られたのでは、たまったものではない。当のドライバーは(通常の感覚で)前後左右を注視して運転しているのだが、対向車や歩行者はそうはいかない。もし何気なく車道に歩き出す人がいて、眼前に停車していた車の背後から無灯火の車が飛び出してきたり...あるいは、交差点で右折しようとしたら、前から無灯火車が平然と直進してきたり...などなど、考えるとゾッとする。考え過ぎかもしれないが、交通安全には考えすぎも必要かと。無灯火車をみつけたら、皆さんどうしますか。どうしようもない。それも一理。しかし、私は、いちおうできるだけのことはする。パッシング、手振り、クラクション、など。私が歩行者のときだったら、大きいジェスチャーで教えようとする。ちょっとまえに、逆送自動車について書いた。■自動車の逆送を考える(1月27日)ひょっとすると、無灯火もお年寄りが多いのかも。いや、前に目撃したのは若いor準若い女性だったような気がする。とにかく、皆さん気をつけよう。防げる事故は防ぎましょう。当然、かくいう自分も戒めます。交通ルール 守るあなたが 守られるこれは本当に名言。いい標語だと思います。時たま、「交通ルール」を他に置き換えますが、結構通じます。お互いを尊びあい、励まし合い、学び合って過ごしていくのが世の中。だから、当たり前ながらも深みのあるいい言葉で、いつまでも残る至言なのです。ところでこの標語、宮城県警察のオリジナルだったのでしょうか。宮城県の人にはすっかり定着していますね。他県の人に今度聴いてみよう。いいぞ、宮城県警。
2015.02.24
コメント(0)
-
平田五郎の力試し石
力試し石と伝えられるものが各地にあるが、利府町の神谷沢にも有名な力試し石がある。664年前(原文ママ。おだずま注)の板碑で、2基がある。1つは高さ5尺幅3尺余りの安山岩で梵字は「ア」、紀年は延慶3年2月27日とあるが、これではない。もう1つが、高さ6尺幅2尺余りの砂岩で種子(しゅじ)は「アン」、紀年延慶3年8月26日、銘文が摩滅しているが、これが力試し石である。舟山万年「塩松勝譜」(文政6)にも、高六尺許、横之ニ半ス、記文剥落ス、延慶三年僅ニ読ムベシ、之ヲ土人試力石ト云フ、とあって持ち上げたのは平田五郎と書いてある。平田五郎は、会津四宿老の平田土佐守実範の次子周防の子で、政宗公に仕え、利府本郷で2百石を領した。身長7尺、豪勇で知られ、一回に2、3升の飯を食いだめして何日も食わない腹芸があった。ある夕方に神谷沢の浜街道にかかる神谷川の土橋を通ると、干上がった川に狐の群れが海老ざっこをむさぼり食って五郎に気づかない。五郎がおもしろ半分に大喝すると狐は逃散したが、見事に光る玉を落としていったので五郎は持ち帰ったところ、夜更けに玄関をたたく者がある。見ると若い女がしょんぼり立って、あの時の狐で逃げるときに大切な玉を置いてきた、あの玉がないと仲間入りできない、何とぞ返し願いたい、ご恩に怪力を身につけて進ぜる、と涙を流して歎願するので、もぞこくなり玉を返してやった。翌日、神谷沢に行って試しに延慶の碑を持ち上げると、軽いこと藁束のようで、狐の約束どおり。時は文禄4年7月14日、伏見城大広間。関白秀次が高野山で切腹に処せられた直後で、政宗公は秀次に党与した容疑で至急太閤から上洛を命ぜられた。世上の取沙汰は政宗公の切腹で持ち切りの土壇場。この日、片倉景綱が政宗公の刀を捧げ平田五郎は草履取りとして従った。太閤が政宗詮議の最中に地震のような屋鳴り振動を感じ、数人の侍臣が遠侍の玄関に出ると、柱と土間の間に草履が挟んである。そこへ雲突く巨漢の五郎があらわれ、閑所(トイレ)に行く間はさみ申した、どうれ、と片手で柱を持ち上げ片手で草履を取り出したから、一同舌を巻いた。太閤の耳にも入って、政宗佳士を得たり、と賞め公の疑いも晴れた。五郎から4代目の長右衛門茂直は2代藩主忠宗の恩遇厚く、万治元年忠宗他界の時殉死。子孫代々虎乃間番士。370石。神谷沢の東浜街道には、今も平田橋がある。原町二丁目、原ノ町小学校となりの平田神社は五郎が慶長8年に勧請した稲荷の社である。■三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』宝文堂、1982年 を参考にさせていただきました。■利府町観光協会のサイトに延慶の碑と平田五郎が解説されています。
2015.02.23
コメント(0)
-
仙台城跡と青葉城址
仙台城跡の石垣の修復が完了して、見学会が開かれた。そのニュースがNHKでやっていた。仙台城「あと」と読んでいたので、昔は青葉城址(じょうし)と良く呼んだと思うが、国史跡上の名称は「せんだいじょうあと」なのだろうな、などと感心して聴いていた。しかし、そのうち、「4年前の震災の地震で石垣が崩れる被害を受け...」という。あれ、震災の地震、か。ちょっとおかしい気がする。震災は大地震と津波を含む全体を示すから、その部分である地震による被害、と丁寧に説明しているのだろうか。でも、やっぱりおかしい。「震災で被害を」か「震災の揺れで被害を」あたりで。震災の地震の件は、まあどうでも良いことですが。とりあえず、青葉城址と仙台城跡の関係を思い出したので。■関連する過去の記事(青葉城址、仙台城跡の呼び方、バス停の名称) 岩手公園の愛称が決定(06年9月17日)
2015.02.22
コメント(0)
-
関山街道
国道48号関山峠は今年も大雪で通行止めに。山形と仙台をむすぶ大動脈だけに、両県側で防災対策を国に求めている。ところで、関山街道の歴史は古く、陸奥出羽の交通は平安時代に始まる。近世には京都方面の物資は酒田から最上川をのぼって、関山越えに仙台に運ばれた。仙台藩では、今の仙山線作並駅の西北方、旧道沿いの作並の宿場に境目番所を置き、峠直下の坂ノ下に出先の関門を立て2人の足軽並み百姓を定置して交通を取り締まった。山形県の初代県令三島通庸は、山岳に囲まれた袋状の盆地で産業も文化も孤立無援である同県には、何をさておいても東京と直結する交通路が急務であると考え、道路の鬼となる。その第一が、米沢福島間の栗子街道と、仙台山形間の関山街道である。関山街道は、三島が県令となる2年前の明治7年に岩崎弥太郎の三菱汽船が石巻市の荻ノ浜に発着したので、塩竈を中継地とする関山街道に魅力を感じたのだろう。福島に来た内務卿伊藤博文に現地を視察してもらい、国庫から5万2千円の支出を即決してくれた。三島の計画は、関山の直下標高600メートルに幅員14尺、長さ69間のトンネルを抜き、併せて延長4400間の新道に改修するもので、工費6万円で明治13年6月着工。1か月後の7月21日には、坂ノ下の番所跡で、トンネル掘削用の爆薬を運搬していた40人余りのの労働者が休息していたところ、煙草火から引火して死者22人の大惨事にあう。東京から仙台に着いた爆薬の運搬で、多くは東根の住民。中には秋保や愛子、作並の者もいた。当時はダイナマイトのような安全性の高い爆薬はなく、打ち上げ花火につかう引火しやすい危険な黒色の粉火薬で、煙草は厳禁されていたのだが、一人が点火した煙草の灰が、包装が不完全で箱の隙間から地面に落ちていた火薬粉に引火して、40箱の爆薬全部が、山谷をゆるがす大爆音もろとも40人を宙に吹き飛ばした。爆死者の供養碑は、山形側の東根大滝の路傍と遭難現場の坂ノ下路傍の2か所に立っている。大きな犠牲を払って、関山新道は15年11月3日落成。その5年後の明治20年には東北線が仙台まで開通。このころが関山街道の全盛時代で、関山部落に20軒の宿場が建ったという。明治24年奥羽線開通後しばらく衰微したが、昭和43年10月、旧トンネルの北700メートルの地に全長890メートルの新トンネルができ、毎日2000台が走っている。■三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』宝文堂、1982年 を参考にいたしました。■関連する過去の記事 仙山鉄道 3つのルート(2015年2月13日) 幻の鉄道計画 改正鉄道敷設法の予定線(その2)(2013年4月20日) 堺すすむと仙山線(2012年9月23日) 山形の鉄道建設熱を考える(続)(07年1月3日) 山形の鉄道建設熱を考える(07年1月2日) 仙台・宮城と山形を結ぶ街道に思う(2005年11月29日)
2015.02.21
コメント(0)
-
秋保の木食知足上人
仙台市長の岡崎栄松さんは戦後はじめての公選市長だ。栄松さんの父も祖父も秋保の佐藤家の出身。二口街道の宿場だった馬場部落を過ぎて、上ノ原から名取川の渓谷を対岸に越えて坂路を上ったところを深野といい、すぐ目の前に以前は茅葺き重層の大きな農家があった。ここが佐藤家で、秋保大滝不動堂の中興開山知足上人の生家である。知足上人は天明8年佐藤家の三代太兵衛の長男太作として生まれ、子どもの頃から親孝行。ある時、母親が眼病にかかった。深野から1キロばかりの秋保大滝に慈覚大師が貞観年中に不動明王をまつったところであるが、太作は大滝不動にこもって祈願を続け、この孝子の念力で母は失明を免れた。これが衆生済度に一生を掛ける動機となる。太作は家督を弟の太吉につがせ、馬場の大滝不動別当真言宗の西光寺住職順昌法印に決意をうちあけ、文化2年18歳の時、仙台城か八幡町の竜宝寺39世実阿上人について得度して、名を岳蓮(ママ。他では岳運とされる。おだずま注。)と改める。大滝の東南の沢股山の大岩で三七日断食修行を行い、さらに羽黒山の荒沢で千日の穀類断食を修すること2回、引き続き苦行14年、ついに木食となり、知足と号した。上人の脚力は当時有名で、秋保では空中を飛行したと言い伝え、石巻まで日帰りで往復したという。いつも通過した八幡町では、風のように早く足が地面に着かなかったと伝えている。石巻には帰依者が多かったと見え、寿福寺境内に碑が建っている。上人の宿願は大滝の道場たる不動堂の再興であった。この脚力で東北くまなく行脚して浄財をつのり、文政8年に地方まれに見る不動堂が成り、翌9年に本尊を安置したのが現存の大滝不動堂である。近世秋保奥地の観光開発に生涯をかけた別当大滝周名氏によって堂は完全に修理され、その傍らに知足上人の木像を安置する開山堂と講舎が建てられている。本尊の不動明王は銅造坐像で像高12尺、東北第一の巨像。作者は仙台城下北目町の大出屋八代四郎右衛門(津田甚四郎と同一か。おだずま注)。近くの滝ノ原、野尻、馬場には今も上人の話を語り伝えている。深野坂で上人の集めた浄財をねらった数人の山賊を、上人は呪文で金縛りにかけたという。また、上人は高徳をもって村民を感化し、加持祈祷で多くの人を救った。しかし修験道の究極は自ら現世の命を絶って魂と化し衆生を済度するを目的とし、その手段は多くの場合生き埋めであった。これを全国的に行人塚と称し、仙台市内にも2か所ある。知足上人は、文政11年9月5日、直下56メートルの秋保大滝の日天月天と称する瀑口の絶壁から身をおどらして飛びこみ示寂した。41歳。山や畑で働いていた人たちは、大滝の方向にただならぬ大きな音を聞いて、思わずその方角を見ると、不動堂の杉林の中空高く知足上人の姿をはっきり見たという。共同幻覚であろう。堂から滝見台に行く道の右側に五輪の墓がある。生家の佐藤氏宅に自作の上人木像がある。故岡崎市長は顔が木像そっくりであった。■以上は、三原良吉『郷土史仙臺耳ぶくろ』(宝文堂、1982年)によっています。知足上人と岡崎栄松市長について、秋保・里センターのサイト秋保の歴史的人物にあります。■関連する過去の記事 昭和30年仙台市長選挙の無効事件(2009年12月05日) 仙台市長選挙の無効判決とやり直し(2009年11月21日) 仙台と競馬の歴史(2006年10月1日)(ところで、岡崎さんが市長の地位を失う契機となった選挙無効事件。上記の記事に書きましたが、仙台市選管の対応ぶり、今回の衆院選の不手際と重ね合わせてしまいます。あまり言いたくないことですが。)また、文中で仙台市内に2か所あるという「行人塚」ですが、1つは若林区の行人塚踏切に名を残す古城神社がその場所でしょう。■関連する過去の記事 行人塚の地名の由来(2008年9月12日) ガソリンカーと仙台(2012年11月5日)すると、もう1か所とはどこなのでしょうか。
2015.02.20
コメント(2)
-
磐梯町と地方創生
昨日のことだが、早めに帰宅して所さんのTV見ていたら、ダーツの旅で福島県の磐梯町をやっていた。意外だったのが、人口3千人台ということ。国道49号の会津街道沿いだし、もっと集積があるというイメージだった。しかし、後で地図を見たのだが、町域に磐越西線は走るが(磐梯町駅)、猪苗代湖に面しておらず、R49は実は通っていないのだ。磐梯という町の名前にも引きずられて、私のいい加減な感覚が形成されていたようだ。最近のある雑誌で、磐梯町は小中の連携や英語教育など教育に力を入れている。小学校2校、中学1校だけで高校もない町で、ひとづくりを何より大事に考えている、という町長さんの談を拝読した。地方創生のモデル例という位置づけだ。顔の見える小振りな町ならではの、良さがあるはずだ。ダーツの旅は、地域の良さと人の温かさをクローズアップしてくれる。期せずして、地方創生のヒントを何か教えてくれているような気もする。安倍総理や石破大臣が言い出したからでは、決してないのだが、地方の崩壊や再生は以前から課題だ。気負わず、焦らず、等身大で、しかしながら本気で考える。マスコミが喧伝する「優良事例」には眉唾も多いが、かといって、よその事例を知ることが大切であることに変わりはない。そこに住み続けたいという人たちがいる事実を重んじながら、謙虚で大胆に考えていきたい。
2015.02.19
コメント(0)
-
東日本大震災の余震 いまだに
昨日の東北は2度揺られた。8時6分頃に最大震度4があった。岩手県沖で深さ10kmM6.9という。今朝の新聞で図をみると、日本海溝のあたりか。私はすでに仕事場にいたが、ユッサユッサと横に揺られる感じだった。岩手県沿岸に津波注意報。午後1時46分には青森県で最大震度5強。M5.7で深さ50kmだが、震央が海岸線付近のようで、津波なし。ともに、東北太平洋沖地震(東日本大震災)の余震という。ここ1週間は震度5弱程度の地震の可能性がある、ということだ。来月で満4年になるのだが、地球活動のうごきは人間たちの社会の尺度などお構いなしだ。忘れたいとしても、忘れてはならないことだが、それにしても、さまざまの意味で揺さぶられてしまう。
2015.02.18
コメント(0)
-
東北七州とは何か
東北七州ということがある。土井晩翠の二高校歌にも出てくる。明治初年のことだから、北海道も含めて観念していたのか。あるいは新潟県を含む7県のことか、などと漠然としたままでいた。明治14年に、河野広中らにより東北七州自由党が結成されたが、旧奥羽の諸国、すなわち、概ね福島県域に磐城、岩代の2国を含む7つの「旧国」を示している。東北6県と同じ地理範囲だ。奥羽や陸羽という古い用語を用いず、また、県の範囲は曲折があるものの6県全体では範囲は固定していたこと、県や国の語ではなく州を用いて一体感や主体性を訴えようとしたこと、などが指摘されているようだ。この経緯からも、旧7国を指すという理解のようだが、異論もあるかもしれない。
2015.02.17
コメント(0)
-
仙台ハクサイと沼倉吉兵衛
結球が良く締まり味も良い「結球ハクサイ」が、大正11年から「仙台ハクサイ」の名で、大量安価に全国出荷されるようになった。作り育てたのは沼倉吉兵衛。登米町の生まれで明治13年に東京の駒場農学校に入り、18年に宮城農学校(現宮城県農業高校)の教師。ハクサイとの出会いは、28年に日清戦争から凱旋した第二師団参謀長が、芝罘(チーフー)ハクサイの種子を同校に寄贈したのが最初。二年継続の試作では結球をつけたのは半分以下。採取方法の不完全が原因と判断した沼倉は、伊達伯爵の養種園(現在の若林区役所の地)の技師に転じたのを幸いに、再び結球ハクサイの栽培、採取の研究に取り組んだ。球形が整わず商品としての市場性が低かったが、渡辺顕二(ママ。ODAZUMA注:渡辺採取場のサイトでは渡邉穎二と表記。)(小牛田町の渡辺採取場創立者)の協力で研究を進めた。大正3年、宮城県農会が養種園を借り受けた際に、園内温室を原種採取室に改造。;また、松島湾内の馬放島と扇谷を県から借り受け採取場を設けるなど、沼倉の努力で、仙台ハクサイが生み出された。なお、日本のハクサイ栽培は明治8年愛知県植物栽培所に始まり、28年、愛知の野崎特四郎により中国の山東ハクサイに劣らぬ結球ハクサイが生まれ、明治天皇が賞味されたという。当時は高級とされたこの野崎ハクサイをしのいで、仙台ハクサイが大量生産されて全国に愛されるようになったのは、沼倉のお陰である。■逸見英夫『仙台はじめて物語』創童舎、1995年 をもとにしました。■関連する過去の記事 日本の白菜を育てた宮城県(2011年5月11日)
2015.02.16
コメント(0)
-
警視庁重大事件と東北
警視庁は2014年1月15日に創立140年を迎えたのを機に、特別展を開催するとともに、「みんなで選ぶ警視庁140年の十大事件」として来館者等によるアンケートを実施した。下記の本には、警視庁全職員と一般の投票によるランキングとともに、重大事件が解説されている。第1位はオウム真理教事件。第2位に東日本大震災。以下、あさま山荘事件、3億円事件、と続く。当然ながら東京の事件ではあるのだが、政治経済の中心でもあり、中にはわが東北に関係するものもあるだろう。そこで、同書から、東北に深く関わる事件を拾ってみた。■佐々淳行監修『警視庁重大事件100-警察官の闘いと誇りの軌跡-』学研パブリッシング、2014年東日本大震災(第2位)警視庁から派遣された職員はのべ23万人におよぶ。大喪の礼、即位の礼、大嘗祭(第5位)一般のアンケートでは順位は高くないが(19位)、長期間にわたり大規模に対応した警察組織の観点から高い順位となったようだ。全国の警察の応援を得て警備を完遂したという一大出来事だろう。ところで、日程表の1990年9月28日に「斎田抜穂の儀(悠紀田)」とあり、前日27日には「斎田抜穂前一日大祓(悠紀田:秋田県五城目町)」と記されている。大嘗祭で天照大神に供える稲穂を作る斎田として、東に悠紀田(ゆきでん)、西に主基田(すきでん)が設けられる。今上陛下の即位に際しては、同年2月の斎田点定の儀により、秋田県が選ばれたもので、五城目町のあきたこまちが献上された。秋葉原無差別殺傷事件(第8位)2008年犯人の元自動車工場派遣社員加藤は、青森県出身。岐阜の短大を卒業後、各地を転々、仙台にも在住していたようだ。犯行当時は静岡県の大手自動車工場に派遣されていた。非正規雇用問題など現代の若者の抱える社会病理も指摘された事件だった。また、ネット掲示板で予告したことも話題を集めた。西南の役(第9位)征韓論をめぐる分裂から帰郷した西郷を盟主に、九州の士族が武力反乱。警視庁初代大警視の川路は9500人からなる警視隊を派遣した。各地で白兵戦が行われたが、警視隊には士族出身者も多く、元会津藩士の佐川官兵衛や元新撰組三番組長の齋藤一らが参加していた。特に剣豪を選抜した警視庁抜刀隊は鎮圧に多大な貢献をした。陸軍の後方支援が役割だったが、徴兵された農民が中心の帝国陸軍に対して実際には同等以上の戦力を示した。二・二六事件(第18位)1936年昭和維新を掲げる陸軍皇道派が、岡田啓介首相、鈴木貫太郎侍従長、斎藤実内大臣、高橋是清蔵相らを襲撃。高橋蔵相は殺害される。斎藤実は水沢出身で、五・一五事件のあと首相に就いた。■関連する過去の記事 高橋是清と仙台(2009年10月17日)吉展ちゃん誘拐殺人事件(第20位)1963年報道協定や公開捜査などの警察捜査の転換点となり、また、刑法の営利誘拐に身代金目的略取という加重類型が設けられることとなった。戦後最大の誘拐事件と注目された。犯人が指定した場所に母親が身代金50万円を持参したが警察は犯人を取り逃す。2年が経過したが、元時計職人の小原が全面自供。平塚八兵衛刑事の驚異の粘りで、事件当時に郷里の福島県内に帰省していたとのアリバイが崩れたのである。宮城刑務所で死刑が執行された。原首相暗殺(第49位)1921年憲政史上初の現職首相の暗殺事件。東京駅で平民宰相原敬を殺害した中岡は、政治方針に不満を持つ鉄道省大塚駅職員だった。耐震構造計算書偽装事件(第66位)2005年一級建築士の姉歯がマンションなど21棟の構造計算書を偽造したことが発覚。その後、名義貸し(建築士法違反)も発覚して懲役5年の刑に処せられた。■関連する過去の記事 耐震強度偽装問題に新たな視点(2005年12月22日)さて、上掲書の最後のページにある佐々さんの「あとがき」を読んで、驚いたことがある。西南戦争の抜刀隊が百大事件に入ったことに触れて、警視庁の飯を食った者にしかわからない戊辰戦争のフュード(確執)の現れと解説する。上記に西南戦争の項でも記したように、そのそも警視庁は川路大警視が薩摩藩士を率いて上京してつくった武力組織であって、昔から「薩摩警部と茨城巡査」と呼ばれたように藩閥が強かった。抜刀隊は9000人以上が編成され、奮戦の末900余名が戦死したと言われる。(なお、田原坂を守って官軍に大損害を与えたのは、佐々氏の祖父佐々友房率いる小隊だった。西南戦争の話が警視庁内で出ると、板挟みで困ったと書いている。)抜刀隊が強かったのは、戊辰の官軍、特に薩摩軍の無法非道、狼藉ぶりに怒り復讐の念に燃えた東北諸藩の士族、とくに会津藩の士族たちだった。会津藩士の薩摩に対する復讐心は今でも残っており、警視庁現職の警察官には、会津藩士の子孫たちが多い。会津出身者が首都の治安を守っている。戊辰戦争のフュードか。警視庁が140年にわたり関わった大事件とともに、歴史が今を導いている重みについて考えさせられる。
2015.02.15
コメント(0)
-
わが子の自動車学校
3つ違いの娘たちが受験生なのだが、高3の上の子は過日入学先が決まった。自分の描いた職業に一歩近づいたことになるが、今後は与えられる勉強だけでなく、広い視野で物事を考え、常に人や世の中を考えながら地域に尽くす自分の進路を歩んでほしい。と格好いいことをいっているが、子の行く末の第一段階が来たという実感は、親としてはない。今週、銀行で払い込みや郵便局で書類の郵送などやってあげたが、この間郵送したばかりの2次試験の前期や後期を、受けなくて良くなったのだなという目先の感覚ばかりが強い。なんだかんだ言って、推薦で早めに決まったことにホッとしたのが先に来る。もっと実感がないのが、御本人。普段したくてもできなかった読書でも何でも思い切りやってはどうか、などと諭すが、突如解放された空虚感のようなものに包まれているようだ。さて、そこで、進学までに自動車の免許を取得してもらおうかと考え、本人もそのつもりでいるので、近くの自動車学校に行った。さっそく今日、入校式と学科の勉強。空きがあれば技能もやるという。今頃ハンドルを握っているかもしれない。入校手続までそばで見ていたが、教習の仕方もずいぶん昔とは違っている。私の頃は4段階制だった。第3段階の最後が修了検定で、仮免取って第4段階で路上。今は、2段階制で、しかも、各段階の中で一定の順番を踏んで実技や学科を受けなければならないものもあるそうで、安全運転のために工夫がされているのだろう。ところで、我が子は誕生日が3月で、免許を取得できる年齢の18歳に達するには、またひと月以上ある。松森の免許センターに行く日が誕生日以降なら良いのだろうと思っていたのだが、そうではなくて、仮免許が誕生日以降ということだった。すなわち、誕生日までにできるのは第一段階までになる。ちょっと早すぎたかとも思ったが、2月3月はかなり混むのでやっぱり正解のようだ。技能の時間もかなり埋まるらしい。ともあれ、我が子も人生の歩みを進めているということか。
2015.02.14
コメント(0)
-
仙山鉄道 3つのルート
仙台と山形を結ぶ鉄道の路線のプランは3つあった。すなわち、仙台-愛子-作並-関山の案。仙台-秋保-二口-山寺(秋保電気鉄道の延長)。塩釜-七北田-関山の案。沿線では利害関係も絡み、代議士などを巻き込んで激しく論争された。結局昭和元年、現在の路線が決定し、昭和4年に仙台-愛子間が開通。翌年に作並に延長される。一方山形側では昭和8年に羽前千歳-山寺間が開業。しかし、作並-山寺間は面白山に阻まれて東西に路線が分かれたままだった。これが物資の交流を妨げ、軍事的にも不都合なことから、昭和10年春に隧道工事に着手、翌11年9月貫通し、12年11月に営業運転が行われている。5361メートルの面白山隧道は、当時、清水、丹那トンネルに次ぐ日本第3位の長大トンネルであった。標高1224メートル。■吉岡一男監修『新・仙台の散策 -歴史と風土をたずねて-』宝文堂、1990年 より■関連する過去の記事 幻の鉄道計画 改正鉄道敷設法の予定線(その2)(2013年4月20日) 堺すすむと仙山線(2012年9月23日) 山形の鉄道建設熱を考える(続)(07年1月3日) 山形の鉄道建設熱を考える(07年1月2日) 仙台・宮城と山形を結ぶ街道に思う(2005年11月29日)
2015.02.13
コメント(0)
-
長町の蛸薬師堂
さきほどOH!バンデスで長町のお菓子屋さん「蛸屋」の蛸さんが出演しておられた。お名前も蛸さんである。屋号がそのまま名字になったと話しておられた。先日も書いたが田村昭さんの文章にも、仙台の蛸さんが出ている。田村さんは直接会って話を聞くなどされているようだが、おそらく、長町の蛸屋さんのことではないだろうか。■ 東北の変わった苗字(2015年2月9日)蛸屋さんは「全勝餅」で有名で、TVでも映していた。ただ、お名前やその元となったという屋号が何に由来するかは、知り得なかった(私が画面をチラ見しただけなので前後で説明があったかも)。長町駅前だと、近くに蛸薬師堂がある。これに関係があるのだろうか。■関連する過去の記事 蛸薬師(長町4丁目)とイボのこと(2013年2月10日)奥州街道と笹谷街道の分岐点、長町三丁目の川熊商店前には笹谷道の道標が建っている。ここから100m入って小道を右折し50mのところに、舞台八幡神社と蛸薬師堂が並んで建っている。八幡神社は天喜年中に源頼義父子が安倍頼時と戦ったときに河内国平岡(東大阪市)から遷祀されたと伝えられている。その後荒廃したのを永禄中、北目城主粟野大膳が再興したという。明治5年、平岡村社となった。江戸に向かう一番目の宿駅であった旧長町宿は、根岸村の北長町宿と平岡村の南長町宿で一宿をなしていた。根岸村は経ケ峯、大年寺山、越路山などを含む広大な村域で、気候温和で百代の里といわれ、近世より茶園があった。南長町宿分は藩政時代平岡村に属し、明治7年、根岸村と平岡村が合併し宿名を取って長町村となった。明治11年郡制の編成により名取郡が成立し郡役所を長町村に設置。明治22年市町村制施行で、長町村と郡山村が合併し茂ヶ崎村が成立(長町と郡山は大字に)。村役場は長町南町に置いた。大正4年に茂ヶ崎村は町制施行、改称して長町に。昭和3年仙台市に編入された。舞台八幡神社の右隣に、蛸薬師といわれる二間四面の堂。由緒不詳だが、伝承では、昔津波によって町裏渕上に漂着した薬師如来像を祀ったもので、渕上薬師瑠璃光如来または蛸薬師と称し、村民から篤く信仰された。次のような伝説がある。長町南町で味噌醤油屋を営んでいる川熊の家の裏に池がある。いつの頃か、この辺一帯に洪水があって水が引いたあとを見ると、池の中島に薬師さんの像が蛸に吸い付かれて流れ着いていた。洪水のあったところから池まで、新しく堀ができていた。今もこれを薬師堀といっている。それ以来、中島に生えていた蘆はみな片葉になった。これを煎じて飲ます、またはこの布団の下に片葉の蘆を入れると、子どもの夜泣きは止まるという。その後川村家では薬師を池の西に堂を建てて祀った。これを蛸薬師といった。(仙台民俗誌)■以上は、木村孝文『太白の散歩手帖』(宝文堂、2001年)から全国的にも類を見ない蛸薬師は珍しい。味噌醤油醸造の川熊は長町の旧家の一つだが、いつのころからかこの一帯が洪水にあった水がひいたあと、家の裏の池の中の中島に薬師様の像が蛸に吸いついて流れ着いていた。(以下、薬師堀のこと、子ども夜泣きのことなど、上記と同趣旨。)川村家では薬師蔵を屋敷内に安置し祀り、赤飯をはじめ供物を供え、町内の守護神となっている。店頭歩道に秋保街道の道しるべが、人目に触れぬようひっそりと置かれているのが痛ましい。■以上は、吉岡一男監修『新・仙台の散策』(宝文堂、1990年)から
2015.02.11
コメント(0)
-
吉村十七夜月署長
今回も、田村昭『東北お国ぶり』(宝文堂、1970年)に説明されている東北の変わったお名前に関して。大正年代の仙台警察所長に、吉村十七夜月という名の方がおられた。苗字はともかく、十七夜月を「かなぶ」とは、誰も尋常には読めそうにありません。こんな趣旨の文章がありました。まさしく風格のあるお名前ですが、読み方は、まったく想像もつかないですね。子孫の方が宮城県におられるのでしょうか。私自身も、吉村さんは知人に何人かおりますが、こんど尋ねてみようか。失礼ながら4代か5代前くらいの立派なご先祖様に、おられませんか...■関連する過去の記事(田村昭さんの解説される苗字に関して) 変わった名前で珍問答(2015年2月10日) 東北の変わった苗字(2015年2月9日) 尻屋の共産部落(2015年2月6日)
2015.02.11
コメント(2)
-
変わった名前で珍問答
さいきん、田村昭『東北お国ぶり』(宝文堂、1970年)を読みながら何件か記事を書いた。珍しい苗字として、留守(るす)さんが紹介されている。鎌倉時代に奥州の留守職となった伊沢左近将監家景は留守を名乗るようになった。現在もこの姓はある。電話で「留守さんを(お願いします)」と言われて、「(ハイ)留守です」と答えると、相手は留守と思ってガチャリと切るなど、困ってしまう。また、生江(なまえ)さんが同じ職場にいて、「名前は?」と問われて「生江です」と返事をしても素直に受け取られなかった。むかしの仙台逓信局での実話だそうだ。田村さんのご勤務された経験から綴られているのだろうが、氏のウィットの利いた文章とともに、心あたたまる話だ。(当のご本人様方は、さぞかし苦労だったでしょう。)
2015.02.10
コメント(0)
-
東北の変わった苗字
今回も、田村昭『東北お国ぶり』(宝文堂、1970年)の中から題材を拾って、記させて頂く。県別に特徴的な苗字として、次のようにあげられる。青森県 神(じん)、夏堀、工藤、福士、三上、今、葛西岩手県 八重樫、千田、及川、小野寺、村上、菊池宮城県 菅原、千葉、庄子、石垣、中鉢、蜂谷、早坂秋田県 越前屋・加賀谷・能登屋のように屋・谷のつくもの、照井、八柳山形県 富樫、本間、神保、奥山、安孫子、志鎌、鏡、土屋福島県 菅家、菅野、星、丹治、渡辺、五十嵐、宗形なるほど。私なども、そう言われると、知人や有名人や政治家などで、出身がこのとおりの方を思いつく。田村さんが書いているように、これをもって即断は危険にしても、ご先祖が出身であるなど、目安がつく場合が多いように思う。東北地方の珍奇な苗字として、紹介されているものとして、仙台の八月朔日(ほずみ)さん、加美郡の川童(かっぱ)さん、仙台市の蛸(たこ)さんなどがあげられるという。また、次の苗字は解説がくわしい。鉄炮(てっぽう):下北半島の尻屋部落には昔からよく難破船が漂着した。この先祖は難破船から上陸する際に、できるだけの品物をもってあがったが、その持ち物が鉄砲だった。槍を持った人は、槍を苗字としたという。我慢(がまん):津軽藩に住んでいた先祖が同僚たちと戦禍を逃れて旅に出たが、途中で具合が悪く行動を共にできなくなったとき、仲間からここで我慢して永住してはどうか、と話が出たから。猿賀(さるが):宮城県では1軒だけ。青森県尾上町の猿賀神社に関わりがあるらしく、この起源を見ると、津軽地方では谷地の下部から出る泥炭層を「さるけ」と読んでいるが、秋田県鹿角郡の辺りから流出してきたため、川を去るの意味で「去河」という地名が起こり、さらに猿賀に転化したという。鬼(おに):仙台、青森に。幸福(こうふく):酒田市に実在。山寺の末寺、幸福寺の寺侍だった先祖がつけたという。などなど。
2015.02.09
コメント(0)
-
尻屋の共産部落
田村昭『東北お国ぶり』(宝文堂、1970年)で、恐山や下北半島について記した項目の中に、学術的にも研究の対象となった尻屋のいわゆる共産部落、という記述があった。貧しい漁村であったことから、皆が平等に分配される共同体が形成されていたということらしく、また、他の子を貰いうけて育てることも行われ、民俗学、法社会学などの観点から取り上げられたようだ。ざっとネットで見てみただけなのですが。田村氏の書には、尻屋33軒の旧家には、鉄炮、槍などの苗字もあって、かつて難破船からかろうじて脱出して上陸した際の持ち物を名付けたと伝承される、とある。あるサイトでは、強い偏東風の吹く尻屋は難破船の名所で人々は漂着物を拾って生計の助けとした貧しいところだけに、素朴な原始共産制が生まれたのだろう、と記されている。■関連する過去の記事 尻屋崎の寒立馬(東通村)(2013年6月22日)
2015.02.06
コメント(0)
-
旧日本軍とは
朝のNHKニュースで、市民10万人が犠牲になったとされるマニラ市街戦から70年が経ち、体験者が語るなどの催しがマニラ市内で開催されたという報道があった。10万という数字にも異論があるだろうし、これだけの一般人が犠牲になった原因や背景をどう考えるかについては、さまざまな見方があるだろう。今朝の報道は、連合国側と日本のいずれにも責任を負わせるような言い方はしていないようだったが、大事なことは市街戦で多数の市民が亡くなり、都市が壊滅した事実の存在と、それを伝えていくことの重要さだろう。ところで、本題をほとんど逸れるのだが、このニュースでは、「旧日本軍とアメリカ軍が」市街戦を演じたなどと説明していた。なぜ、日本だけは「旧日本軍」というのか。確かに、「旧日本軍」という言葉は一般に定着している気はするのだが、字幕にまで出たのを改めてみると、なぜアメリカはそのままで日本は「旧」なのか、と思ったのだ。おそらく、日本には現在は軍隊はないという前提で、あるいは、日本の陸軍と海軍は終戦をもって組織がなくなったのだから、過去の存在であることから「旧」としているのだと一応は考えられる。しかし、過去の存在に何も「旧」を付していない事例だって多いだろう。たとえば、「昭和60年にA氏は大蔵省に採用された。」「昭和60年に泉市内であった殺人事件を今思い出す。」などの文章を考えよう。その組織名や地名が現在は存在しないことを敢えてハッキリさせたいのならば、たぶん、「当時の大蔵省に入り」や「当時の泉市内であった」とするか、「大蔵省(現財務省)」「泉市(現仙台市泉区)内で」「仙台市泉区(当時は泉市)内で」などとやるのが通常ではないだろうか。もちろん、「昭和60年に旧大蔵省に採用された」「昭和60年に旧泉市内であった殺人事件」でも、解らなくはないが、昭和60年時点では「旧大蔵省」なる存在はないから、時制の一致の関係でちょっと違和感もなしとしない。とすると、「70年前に旧日本軍とアメリカ軍が戦った」と表現する場合には、現在から見て「今はない昔の組織であるところの旧日本軍」という意図を込めて表現しているということになるのだろう。ここには、戦前と戦後の断絶をことさら意識し、また戦争や戦力を忌避してきた戦後の国民感情を背景に、「あの時代のもの」という戻ることのない過去に押し込められたイメージをまといながら、単語として独り立ちした「旧日本軍」の存在がうかがえると思う。たんに言葉の感覚の問題として。
2015.02.04
コメント(0)
-
ハンコタンナと覆面風俗
由利地方から庄内にかけてみられる風俗に、ハンコタンナと呼ばれるかぶりものがある。野外で働く女性が顔を覆う布で、目だけを露出した姿。藩政時代から続くという。現在もなお使われる理由として、夏は汗どめに、また、稲刈りなどの時顔を葉で傷つけないように、虫除けや日焼けを防ぎ、さらには防寒用などと、多彩にわたって実用的な原因が説明される。俗説として巷間伝えられるには、色好みの殿様に顔を見られるのを防ぐためというのがあるが、付会にほかならない。でなければとうの昔に廃れたはずだ。なぜ、ハンコタンナという名か。タンナは一般的に帯の類を指す呼称といわれる。例として、・タナ(タンナ)---(1)子供を負う帯(鹿角郡、津軽地方、新潟県北部)、(2)帯または腰帯(庄内地方)、(3)男の褌(青森県の一部、宮崎県)、(4)女の腰巻(宮崎県)・コビタンナ、コビタナ---子供を負う帯(庄内地方、伊豆大島の一部)・ツイダンナ---越中褌(九州薩摩地方)(『定本柳田国男集』から)などを挙げることができる。長い年代の経過でタナが手拭いに変わった地方もあるようで、秋田県仙北地方ではタナが手拭い、由利地方では幅の広い手拭いがヒロタナとなり、5尺2寸ほどの長いものはナガタナ(長手拭い)と呼ばれ、ナガタナは秋田を中心とした被り物として知られていたが、生活様式の変化で姿を見る機会は少なくなった。これらの長いタナを半分くらいの長さ、つまりハンコにして使われるのが、ハンコタンナということになる。よく物事を中途でやめることをハントでやめるなどということがある。ハンコと短いタンナの関わりが推察されるがどうか。先日も酒田の波止場で若い女性がハンコタンナで顔を覆っていた。女性が黒い覆面をしていれば、よそ者には全くどこの誰か判別がつかなくなってしまう。若い男性には大きな不満もあるだろう。生活テンポの早いこの時代に、何も好んで顔を包んでおくことを真剣に続けていこうなどと考えている人も少ないだろう。長い伝統あるハンコタンナも近い将来姿を消してしまいそうである。------------以上は、田村昭『東北お国ぶり』(宝文堂、1970年)の一説である。(当ジャーナルで若干要約)初出が昭和41年(電気通信共済会ニュース)の文章なので、昭和40年頃にはまだ酒田で若い女性が着用していた事実が知られる。私は初めて聞く言葉だ。東北の覆面風俗という項名にハッとして、ナマハゲなどの結社意識など民俗の基底意識との関連があるのか、などと思ってしまった。しかし、祭祀との関連もないようなので、非日常の世界ではなく、まさに日常そのもの、あくまで戸外作業をする際の実用性から生じたものなのだろう。■関連する過去の記事 秘密結社とナマハゲ(2011年6月4日) 奇祭 鶴岡化けもの祭(2011年1月3日) 秋田ナマハゲは秘密結社か 再論(2010年5月20日) なまはげと東北人の記憶を考える(2010年4月27日) なまはげ事件を考える(08年1月13日) 秋田なまはげは秘密結社か(07年8月13日)
2015.02.01
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1