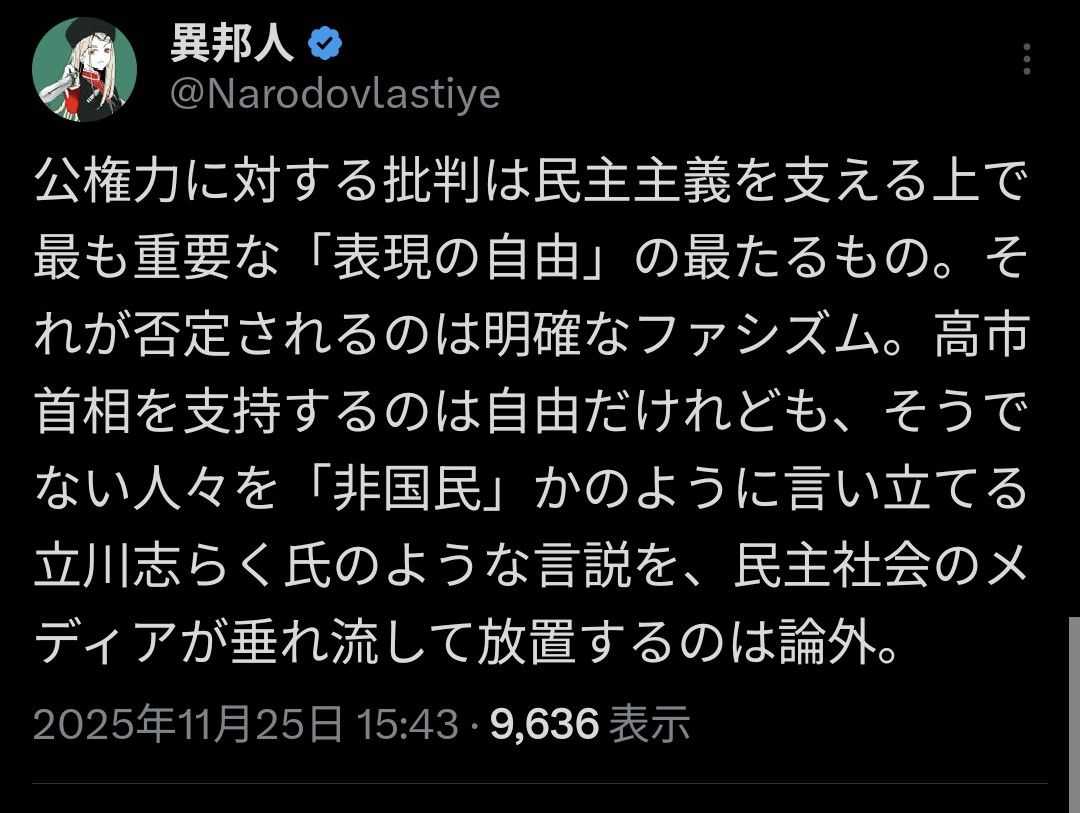2025年08月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

未発表?「出湯の女」
〇昔作った曲の歌詞を綴っておきます。1)純で素直で 可愛い娘(コ)だと そっと両手で 包んでくれた 歳は離れて いるけれど 深い優しさ 持った人 もう一度会いたい 大人の私 2)君は真面目な 男に惚れろ そっと諭して 目を見つめてた あとは黙って 肩たたく 渋い魅力を 持った人 今なら抱いてよ 大人の私 3)酒も煙草も 覚えた私 きっと会わぬが 良いとは思う だけどあげたい 捧げたい 惚れる情けを 知ったから 出湯に根づいた 大人の私譜面が残っていないので、なす術もありませんが、ギター伴奏曲。ぼんやりイメージが残っています。作品としては製作年度が新しい部類で、平成11年頃でしょうか。
2025.08.31
コメント(0)
-

京町家の魅力
〇京の町家で生まれた私ですが、町家の暮らしを知りません。余りにも幼かったので記憶にないのです。しかし、父方の祖父・祖母に会いに行く時は、京都銀行本店真裏にある借家まで出向き、春休み、夏休み、冬休みには寝泊りしました。借家は心なしか右側に傾いているように見えましたが、造りそのものは頑丈に出来ていてビクともしません。道路に面する部屋は”店”と言って、木綿製品や見本帳を並べたり、客の応対をする場所でしたが、戦時中に廃業していましたので、今は祖父夫婦の居間でした。奥には二階へ上る階段、食事をする居間があって、その正面は台所で井戸もあれば水甕もありました。階段の下は富山の薬箪笥のような物容れになっていました。その又奥の部屋は寝室兼仏間で日中は暗い部屋でした。縁側の向こうには小庭と厠(便所)などがありました。台所が比較的明るいのは天窓があったからでしょう。布袋さんが並んだ荒神棚もありました。店の真上に当たる二階は屋根裏部屋で、殆ど物置き場になっていましたが、後年、叔母の手で綺麗な部屋になっていました。犬矢来、虫籠窓、紅殻格子、ばったん床几等ある懐かしい造りでしたが、今はありません。 近頃はこの京風の町家がリフォームされ、画廊や喫茶店や和装小物の店などに再利用されていることは喜ばしいことですが、出来るだけ”本物”の京ものを販売して欲しいなぁと思っています。光の明暗がくっきり浮かぶのは空気の澄んだ秋。入日どきは風情があるし、ほんのり橙色の灯火の入った町家も心を落ち着かせることでしょう。
2025.08.30
コメント(0)
-

出前ガイドの効能。
〇発足23年目の「大山崎ふるさとガイドの会」は数年前では4つの班、60数名の会員が在籍し、ファックスにて頂戴した指定日に、資料館当番週の班から適宜数名のガイドがご案内しています。 初夏と秋の「天王山ウォーキング」の他、早春の「写経」や3月の「水辺の散策」というイベント。また掲題「出前ガイド」も年々依頼が増えて来つつあります。燈明守の娘、天王山のカエル、飛び倉、閻魔さまと極楽・地獄、山崎の合戦、大山崎油神人、行基さんと山崎橋、大山崎町の史跡案内、大山崎の野鳥、大山崎山荘の花木、聖天さんとどろぼう、十七烈士と新選組、きつねの渡しと淀川の三渡し、鬼くすべ1、鬼くすべ2、大将とマッサンの16演目。私達の手になった脚本、造形芸術大さんの画のスクリーン画面に声優としての演技を行うのです。ガイドを引退した近年は、カラオケ曲のセリフの言い回しに役立っています。
2025.08.29
コメント(0)
-

出兵兵士用の手帖
〇数年前に見つけた「陣中日記」。縦12.5センチ、横8.5センチ、厚み2センチ足らずの掌中サイズ。装丁はしっかりとした絹地だから丈夫そうです。頁数は本文224.但し各月あたり10頁の白地日記欄付き。付録には、事変一年史、簡易東洋史年表、簡易支那地理、支那地名の読方、歌謡索引、年数早見表、氏名録、備忘録が31頁ほど。出征兵士に配られたこの陣中日記は昭和14年製なので処々に載せられている歌謡は、敗戦色の濃い時代とは大いに異なり、艶っぽいものも多々。陣中に詠まれた短歌や、古来の俳句・川柳や詩吟もある中に、以下のような都々逸も。恋にこがれて鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が身をこがす留めてよかつたあのまま帰しや 何処かで濡れてる通り雨星の数ほど男はあれど 月と見るのは主ばかり (抜粋)或いは、 お声はすれども姿が見えぬ ぬしは草葉のきりぎりす山で伐る木は数多けれど 思ひきる木は更にない (抜粋)歌謡には最上洋の「忘れちやいやよ」など、結構軟弱な内容の歌詞さえ掲載されていますが、富士山、子供たち、女優、芸者さんなどの写真もあってこころの慰みになったことでしょう。
2025.08.28
コメント(0)
-

藤沢周平作品
〇家屋や物置小屋の容量が決まっているので本などは貯める一方では済ませません。だから図書館に寄付したり、古本屋に売却したり、果ては古新聞と同格の処理をせざるを得ません。しかしどうしても手放せない好みの作家も居られ、その一人が藤沢周平さんです。彼の作品の全編に流れる”人への優しい慈愛の風”。お人好しというものではなく、自分というものがしっかり成り立っている人が、不幸な人達に寄せる優しさが感じられます。また藤沢作品の特徴は歴史的に有名な人をモデルに選ぶ訳でもなく、市井に埋もれた男女、武家なら下級武士の男女、そして江戸の香りがぷんぷん匂う町民の男女や生活、風俗を描いておられるところです。平凡な人物を採り上げながら、その個性を数行の文章で描き、春夏秋冬の季節と織り交ぜ物語にまとめている手腕には、参ってしまいます。
2025.08.27
コメント(0)
-

持病は歯痛の藤原定家
〇堀田善衛著『定家明月記私抄続編』(新潮社)の頁を繰っていると、彼も歯の治療を受けていた事に親近感が増して来ました。 ”歯取りの老嫗を喚(ヨ)び、歯を取らしむ” 建暦2(1212)年、51歳になると彼にも老いの様相が出てきます。元日の宴から退出した折、階段でよろめき刀を損じた事が後鳥羽院にも伝わり哄笑を買ってしまった事や、1月21日には弱くなった足腰ながら有馬温泉まで湯治に出かけたものの効果なく、2月に脚気、咳、きつい腹痛(膀胱結石?)など惨憺たる日々が続いていたようです。 神経痛や腹痛に対し漢方薬「大黄」や「鹿の角」などを服したり、身体の7ケ所に灸をすえたり・・・。そしていよいよ8月22日には上記の抜歯の記述に至ります。 当時は歯科医など居なく、歯取り専門の老婆が居たらしく、その手法は18年後の日記(寛喜2年4月4日)に、”苧(カラムシ)を付け、少年嬰児の如くに引落し了(ヲハ)んぬ”苧(イラクサ科の多年草つまり麻の一種)の頑丈な皮で作った糸で歯を抜き取ったようです。麻だから麻酔効果があったのかも知れませんし、巻きつけて置き自然に抜けるのを待つ方法だったのかも知れません。
2025.08.26
コメント(0)
-

紫蘇ジュースクレオパトラに招かれてby星子
〇庭の各所にこぼれ育ちしていた赤紫蘇、その種を集め、プランターに播いていたものが生育し、可憐な小花を並べて咲いています。今もうお亡くなりになったと思われますが、句会の場所取りに貢献された桐壺さん。その方から2、3度紫蘇ジュースを頂いたことがあります。佐賀市に2年在住、小学生の頃に憧れていたお客様用ワイン色のシロップジュースにそっくり。豪華な色合いと清涼味は大好きな飲み物の1つ。そこで詠んだ句は 紫蘇ジュースクレオパトラに招かれて 星子 話題を紫蘇の花に戻せば、その可憐な花茎は、料亭のさしみの盛り合わせに見かける、ちょっと乙なもの。今日の夕餉の鉢に添えられ、家族の目を楽しませてくれることでしょう。
2025.08.25
コメント(1)
-

奥琵琶湖に沈む白蝋死体。
〇連歌の大家・高城修三氏の『関西こころの旅路』というエッセイ集。その中の”湖北の隠れ里を訪ねて”の一文。 <・・・竹生島のあたりは琵琶湖でも最も深いところで、湖底の水温も四度くらいしかないため、難破した水死人はここに吸い込まれると腐敗することなく蝋人形のような姿でいつまでも水底に漂っているという。・・中略・・菅浦が早くから奥琵琶湖の要港として栄えていたことは『万葉集』に採られた次の歌からも知られよう。 高島の安曇のみなとを漕ぎ過ぎて 塩津菅浦今か漕ぐらん・・・(菅浦は)いつ来ても、自然に荘厳された湖がある。そこに歴史が深い色調をかもしだす。そうした風景に我が身をひたし、日がな一日、湖と山をながめて過ごしたい気がする。ここには日本人の忘れたものがある。> 実は例として挙げた部分よりもほかの場所が美文なのですが・・・。琵琶湖は嵯峨野同様、我が俳句の師、鈴鹿野風呂も愛した場所です。どこを訪っても何らかの発見があり、飽きの来ない風光明媚な”まほらの地”ですね。
2025.08.24
コメント(0)
-

暫し見入る花押のかずかず♪
〇花押には草名体、二合体、一字体、別用体、明朝体の種類があって、能書家と言われた藤原行成のような柔らかな書体や王と義を組合せた二合体、実名の一字だけから成る平忠盛の花押のほか、時代と共に複雑化したものまであるようです。足利一門は、三十四代・義輝、その次の義昭の二人を除けば、初代の尊氏の花押からそれほど変わらないものを踏襲。信長を翻弄した義昭公は五度も書体を変更、一方疑り深くならざるを得なかった信長公は七種類の花押を残し、のちは天下布武の印に。信長公から一字貰った長政(旧賢政)は「長」の字を右に倒した花押を作りました。勝海舟公の花押は信長公五度目の花押にそっくりな花押にして居たり、三好某の花押はまるで水鳥そっくり、徳川歴代将軍は慶喜公を除けば、家康公の書体を忠実に守っています。また明治から昭和に至る政治家や文豪、画家なども花押を愛した人たちでした。
2025.08.23
コメント(0)
-

白秋の詩集
〇縦15センチ余り、横11センチ、厚味3センチほどの紙のケース(表にはトランプのダイヤのQ、箱の裏面は柳川、沖ノ端の風景写真)に容れられた北原白秋の抒情詩集。これは明治44年6月5日、東雲堂書店から90銭で発刊されたものを彼をこよなく誇りに思う野田宇太郎氏が昭和53年2月15日東京堂筑後柳川版として復刊されたもので、<この書物は故郷柳河を生涯愛した詩人北原白秋を永久に記念するため、日本郷土文芸叢書の趣旨により柳川市に於てのみ発売するものである。>という但書きが付されています。頒価1500円。 白秋自身がカット絵を施した、実に洒落た詩集です。亦<この小さき抒情小曲集をそのかみのあえかなりしわが母上と、愛弟Tinka Johnに贈る。>とTonka Johnのサインをしています。Tinka(ちんか)=小さい、 Tonka(とんか)=大きい、John(じよん)=坊ちゃんという意味の筑後全般の方言のようです。序のページ数はローマ数字で表記、9頁の<わが生ひたち>に始まって、序詩からはアラビア数字表記に変えています。骨牌(カルタ・トランプ)の女王・・・11編断章・・・・61編過ぎし日・・・20編おもひで・・・19編生の芽生・・・36編TONKA JOHNの悲哀・・・19編柳河風俗詩・・・4編酒の黴・・・・・25編其の他18編など2百編以上網羅されています。大切にしたい贅沢な詩集です。
2025.08.21
コメント(0)
-

台風の季節
〇出足の遅かった日本への台風、いよいよその季節がやって来ました。折りしも亡父の詠んだ台風の句があったので紹介いたします。以下は2003年に綴ったもの。 台風に姿あるごと予報聞く 吉田すばる 沖縄、九州を襲った台風は今夜半関西に到達するという。二百十日の頃、日本人は大なり小なり、この招かざる客が、逸れると言えば一喜、襲うと聞けば一憂する。 そして頼りにするのは天気予報。受信料支払いに多少の不満はあるものの、この時ばかりは、NHKさまさま。ラジオで聞いてもテレビで見ても、台風という姿、形ある生きもの、魔物のように擬人化して捉えてしまう。風神に非ず、昇竜にも非ず、漠然とした中にまるで意思を持った生きもののように錯覚する。・・・被害の出ないことを只管祈るのみ。
2025.08.20
コメント(0)
-

夜空の星の命名者
〇秋気を感じるこの季の季語には、星月夜、星明り、秋の星や天の川、銀河・銀漢とか流星、夜這い星、流れ星、星飛ぶ、星流るなどのロマンチックなものがあります。 流星の使ひきれざる空の丈 鷹羽 狩行 ところで、倉敷出身の御年79才、佐治天文台に関わりの深い香西洋樹氏は、永年、国立天文台にて天体観測に携われ、50個ほどの小惑星の発見と(今は行方不明になっていますが)彗星一つを発見しておられ、吉備、難波、瀬戸内など40個もの小惑星命名者でもある方なのです。 小惑星とは太陽系が出来た折、惑星に成り損ねた、言わば星屑のことですが、1999年の時点で、世界中に登録されているその数は10257個、うち2030個が日本人の登録、つまり約2割を発見した日本は世界1の<星持ち国>なんだとか。しかも直径1キロ級の小惑星の内、発見されているのは僅か5%ですから、あなたが<お星持ち>になれる可能性は十分なんです。また、他の国では天文台に勤める職員がほとんどですが、日本の場合はほぼアマチュアというのが特徴なんです。 発見してから命名までの段取りは以下のようです。1)新小惑星の発見 → 国際天文学連合へ連絡、仮符号を付与して貰う。2)公の場で、この小惑星の軌道を観測、計算の上確定まで数年を要し、許可が降りる。3)名前はアルファベットにて16文字以内、政治家や軍人は死後百年以上経過が条件です。 シェクスピア、ピカソ、バッハ、ジョン・レノン、ソクラテス・・・・地名、人名、文学者、画家、音楽家など。面白いことに、日本の人物名を利用したものは、平清盛、源義経、坂本竜馬、夏目漱石、手塚治虫、坂本九など。 日本を含む北半球では、秋から冬にかけてが観測に向いているとか。あなたも<お星持ち>にチャレンジなさいませんか?
2025.08.19
コメント(1)
-

稀代の戦国武将・信長公
〇稀代の戦国武将・信長公は時代の先取りのできる逸材でした。元来、戦国時代の兵は9割が領内の農民兵で占められていたので、武田信玄や上杉謙信と謂えど農繁期には兵力を本国に戻す必要性がありました。ならば年がら年じゅう戦のできるよう専門の兵隊を作れば良いという風に信長は考えたようです。長篠の合戦では千梃もの鉄砲を使ったとされていますが、1梃5万石とすれば、5千石、5千人を1年間養え得る価額と言えます。 楽市・楽座を推奨、商人に稼がせた売上金を一旦回収し、再分配するという方法を採りました。 国会議員の条件には「地盤、看板、カバン」と言われていますが、まさにその通り。信長には尾張という地盤があり、再興させた将軍(足利義昭)という看板、商業で吸い上げた金というカバンがあったのでした。農業生産を基準にしていない信長は、本拠地の尾張から、美濃、近江と経済基盤を拡大していったのです。
2025.08.18
コメント(0)
-

茗荷に寄せて
〇東の隣家との境には酔芙蓉や白夾竹桃、時計草などが一角を占めていますが、その陰に抜きんでいる十本ほどの茗荷、先日家内が折よく見つけ、かそけき花の咲いているのを一つ摘んで来、昨夜の薬味として味わいました。高橋治著『くさぐさの花』の「茗荷」からそっくり引用すると<どこかで、柿と茗荷は仲が良いという文章を読んだ。拙宅に毎年休まず実をつける柿の木があって、勤勉さに感嘆していたのだが、どうも茗荷の側面援助らしい。・・略・・そもそも庭に植えたのは、韮、大蒜、辣韭、匂いのするもの一切御法度の父が、茗荷だけは大好物だったからだ。父が出張に出かけると、それっと、母が韮の味噌を作ってくれる。母子で賞味して首をすくめている。・・・略。 * 茗荷掘る市井の寸土愉しめり 西島麦南 人しれぬ花いとなめる茗荷かな 日野草城迂生食うばかりに精出して、とても花を楽しむ大悟には程遠い。> ショウガ科の多年草、日影を好む。春の若芽を茗荷竹、晩夏に根元から出るタケノコ状の花穂を「茗荷の子」と言って、共に食用。ランに似た淡黄色の花。
2025.08.17
コメント(0)
-

『大山崎史叢考』という名著
〇他所から大山崎に引越してまで大山崎の歴史を研究された吉川一郎先生。その著『大山崎史叢考』は氏の真面目な探究心がひしひしと読者に伝わってくる名著で、数年ぶりに読み、感動を新たにしました。宝積寺蔵として掲載されている「山崎架橋図」はこれまで心に留めていませんでしたが、本尊の十一面観音像が「橋架け観音」と称された伝説を意識して天安3年(859)に描かれたもの。一方「観音寺日譜」によれば娯楽と興行物として、元旦、節句、端午、七夕、盂蘭盆会、八朔、重陽、玄猪、節分はもとより、春の土筆摘みには狐浜や外島へ、蕨取りには天王山に登ったことなどが記されています。盂蘭盆の経木流しには淀の本流に流すのですが、その帰途には必ず西観音寺(現サントリー蒸留所)の閻魔堂に参詣していたようです。盆の放生会の頃には、離宮八幡では相撲が神事として行われていたことが記されています。観音寺山主と聞法寺住職が仲良く観ていたようです。
2025.08.16
コメント(0)
-

読経→オクターブ上の女声も聞こえる。
〇〇〇〇「懺悔偈(サンゲゲ)」 我昔所造諸悪業(ガシャクショゾウショアクゴウ) 皆由無始貧瞋痴(カイユムシトンジンチ) 従身語意之所生(ジュウシンゴイシショショウ) 一切我今皆懺悔(イッサイガコンカイサンゲ) 私たちが長い間犯してきた罪過(ツミトガ)は昔から心の中にもっているむさぼり、いかり、愚痴といった迷いが私たちの身体と言葉と意(ココロ)を通して現れたものです。いまみ仏のみ前に心から懺悔いたします。 この本にはこの他、香偈、三宝礼、四奉請、歎仏偈、三尊礼、開経偈、無量寿経四請偈、本請偈などのお経のほかに、年中行事、仏事の基礎知識が、懇切丁寧に書かれています。日本人である限り、お寺やお経と無縁で居られる道理もありませんので、偶には、お経や仏教に触れてみるのも良いと思うのです。 読経には多少時間を要する経典もあって、意味不明では退屈するのが人情。でも、耳を澄ませば、1オクターブ上、2オクターブ上の女声が美しく聞こえます。是非、お試しあれ。
2025.08.15
コメント(0)
-

篠塚流
〇某年某月、午後1時に家を出て大山崎町役場の施設にて「大山崎ふるさとガイドの会」の春・秋のイベント”天王山ウォーキング”への準備委員会に同席、その足で京都市内まで。この楽天で親しくさせていただいている柳居子翁がこよなく愛される姉小路一帯の地蔵盆の行事、「姉小路行灯会」の様子を見学させて貰いました。1口200円也の豪華賞品の当る宝くじも楽しみの一つです。随分前、この近辺に高層マンション建設の動きがあった折、有志が反対行動を興したのがきっかけで「姉小路界隈を考える会」が発足し、町内の安全と京都の美観や伝統を守ろうという趣旨のもと地蔵盆には、姉小路の東は鳩居堂近くの寺町から西は烏丸に至るまでの700mの道路の両端に紙で拵えた行灯をずらり並べるという試みが始められて、今年で13回目。寺町から富小路までは今年85歳の藤井のおばあさんの描かれた優雅な絵柄、向日葵を初め色んな花の行灯が、富小路から数筋西は御池中学生の絵、耐・愛・夢・美・静・麺・魂などのカラフルな字、私の名:陸が絵柄で書いてあったのが嬉しい。これより西数筋は園児の描いた行灯・・・と将来へのバトンまで工夫されていました。御池中学生によるブラスバンドが演奏しながら姉小路通りを反復練り歩き、詰め所で数曲ご披露。ご多忙な門川京都市長が挨拶なさったところをみると、この「姉小路界隈を考える会」は行政の中枢にも通じておられることが推察されました。 今年は「京おどり」でお馴染みの宮川町に根付いていた篠塚流。少し解説するなら1804年~30年は初代次郎左衛門・喜左衛門・歌桐・宗之と続き一時中断するも文三郎・・・5代目文三郎<梅扇>5代目梅扇翁のお嬢さん篠塚瑞穂氏のお弟子さん達の舞を見せて戴きました。道路に床几が幾つも道路に並べられやや暗い詰所を舞台として下は3歳ぐらいの女の子、上は人生の甘辛を知り尽くされたご年齢のお弟子さんまでの舞披露。この模様は本日正午より”京都テレビ”で放映される予定。京都を代表する推理小説家・山村美沙さんのお嬢さん・紅葉さんにそっくりの方の舞が一番優れているなとファンになりました。この直観は大正解、現篠塚流宗匠・瑞桜さんです。
2025.08.14
コメント(0)
-

人間が思いつく生活品の籠。
〇大昔から日本人の暮しの中には籠がありました。子供の頃、母に代わって市場への買い物には買物籠を提げて行った記憶があります。山仕事に携わる人々には背負い籠が無くては生活が成り立たないでしょう。蔦などの植物の蔓で編んだ籠は雨に濡れても重くはならないし、乾きも早い。その上、籠に弾力があるので身体に馴染み易く、入れたものも傷みません。或る写真集にはアケビの実が詰めてあるものや蕨などが入った籠が写っています。海浜に於いては魚を、畑にあってはピーマンや南瓜など・・・。整然と並んだ編み目の美しさ。ぎっしり編まれた籠にはいろんな模様さえ組み込まれています。子供の頃には、竹を編んだ大きな籠に鶏を入れて育てていた光景もありました。そう言えば、祇園祭鶏鉾の浴衣の柄は竹籠の模様でしたね。
2025.08.13
コメント(0)
-

松榮堂広報室編『香りの本』
〇亡父は最晩年、香道にも足を踏み入れました。叔母(妹)と一緒に月一度、十数人の仲間と楽しんでいました。香老舗松榮堂広報室編『香りの本』の頁を繰るだけで、日本特有の「雅」の世界のアリスになってしまいます。先ず螺鈿を施された道具類の奥ゆかしさ、香を嗅ぐ姿の優美さ、そしてお出かけの身だしなみとしての香袋。 目次にある<香りの文化は天地創造と同時に始まった>とか<イエスに贈られた乳香とねつ薬>或いは<シバの女王の国は香料の産地><暴君ネロは妻の葬儀に十年分の香料を使った>ずっと時代を下って、<元禄時代の”伽羅の油”><徳川家康が収集した伽羅は二十七貫><においの正体は何><人間の嗅覚は百億分の一の濃度を感じ取る><花の五パーセントは悪臭>と言った具合に、百三十を超える話題を解り易く記述してあります。
2025.08.12
コメント(0)
-

下から読んでも「山本山」
〇いろんなトイレで用を足す時、「いつも綺麗にみんなのトイレ」という標語がタイルに張り付けてあるのを見て、文字の置き換えにチャレンジする癖があります。例えば、「例の時遂に未練も無い」などとついつい置き換え等をする性分なんです。 桑原茂夫さんの『ことばの遊び百科』には<酢豚つくりモリモリ食ったブス>とか<軽い機敏な仔猫何匹いるか>とか<力士手で塩舐め直し、出て仕切り>などの回文を紹介したりノサ言葉の例として、<きのさようぼのさくのうのさちでねのさこがねのさずみをつのさかまえようとしてやのさかんはひのさっくりかえすわ、たのさたみはよのさごすわ、おのさおさわぎ>を挙げたり、<つびきびのぼさばくぶをぼはばるぶばばるぶとぼたばびびのぼらばくぶだばばがいびきびばましびたば>バ行をいれると唱歌も歌いづらくなります。
2025.08.11
コメント(0)
-

花合わせ(花札)の魅力
〇月や夏休み期間、わが家には親戚が集まり、大人も子供も興じるものは花札。用意するものは花札2組(茶色地、黒地)、金物製の点棒入れ、麻雀の点棒や土で拵えたカラフルな達磨さん(小指の爪より小さい)、記録簿、手役出来役一覧表。 + + + 3人で行い、一月から十二月までの12回でひと括りになるのですが、3人を超える場合は、配られた手札と相談にらめっこの上、親から順に降りることが出来ます。降りる(ゲームからリタイヤ)場合は、親が罰金10円、親の隣は20円と順に増えて行きます。 + + +例えばのっけから5人で花札を開始した場合、7枚づつ5人に札を配られますが、この状態で手役という役(並札ばかり6枚に10点札が1枚とか、くっつきと言って麻雀のニコニコみたいな、その他沢山の役があります)があって、親もその隣も、そのまた隣もゲームに参加する意思を表示したら、残り二人は止む無くゲーム不参加になるのですが、この時、手役があれば、面前で公開して、手役の点数を他の者から貰うことが出来ます。ゲームを進行して、その途中で作った出来役、20点札4枚の四光、5枚の五光、そして赤い短冊を3つ(松、櫻、梅)、或いは青い短冊(牡丹、菊、紅葉)を3つ揃えたら出来役としての点数を他の二人から徴求できます。手役は配札による運の如何ですが、出来役は、それが完成するのを他の二人が協力したり、或いは裏切ったりしながら阻止する訳です。シンプルなルールゆえ、返って頭脳ゲームとしての面白さがあるのです。ゲームに興じながら、相手のキャラを冗談でディスったり・・・などで、洋間は賑やかな話声と笑いに包まれていました。これらの思い出は、わが実家の歴史に例えれば、青春時代のような華やかな時代でした。
2025.08.10
コメント(0)
-

歴史上の人物の不思議、ふしぎ。
〇京に在る官幣大社には上賀茂・下賀茂、岩清水八幡、松尾、平野、稲荷、平安、八坂神社の八つがあります。官幣中社には梅宮、貴船、大原野、吉田、北野の五つ。別格官幣社には、和気清麿を祀る護王神社、信長の建勲神社、秀吉の豊国神社、三條実美の梨木神社など。古代から戦国までの関所一覧には、大山崎・山崎の山崎関(関戸明神)、大江関、木幡関が載っていました。系図で興味を惹いたのは、孝元天皇の後裔に「紀」や「蘇我」があって、紀貫之と蘇我入鹿が遠い親戚。敏達天皇の後裔に小野妹子、小野道風、小野小町がいること。天武天皇の系統に清原深養父、清少納言、菅原系統に紫式部が絡んできます。お茶では、千利休の弟子として信長、秀吉、高山右近、毛利輝元、茶屋四郎次郎の名前などが載ってきて面白いこと。何かの折に役立つだろうと可なりの頁を複写しました。
2025.08.09
コメント(0)
-

女学生の義祖母
〇某年某月、家内の実家を訪った折、納戸に置かれた小さめの段ボール箱を物色。是非貰い受けたい祖母の高女時代の作品などが見つかりましたので持ち帰りました。1)郵便はがきに描かれた風景その他の手書き作品。明治二十年前後は国力も旺盛、簡単に外国へはがきを送れたもよう。何故なら<内国行ニハ壹錢五厘、外國行ニハ四錢>と切手貼付欄に書かれて居、祖母は墨で四年ろ河合と書いたものもあります。富士山の景や広い公園での花見の景、琵琶湖畔らしき墨絵、愛らしい乙女の後ろ姿など。 2)日本橋高女の校歌、裏面には十条にわたる十則が凛々しく唱えられています。この他、近畿を中心に下関~東京・北海道を描いた地図、裏面には、大正十五年三月二十日~五月卅一日会期の<電氣大博覧會内容一斑>や各社の広告が時代を物語っています。
2025.08.08
コメント(0)
-

暑さに負けない頭脳訓練
〇クイズ番組大流行の日々ですが、<マジカル頭脳>から。例によって 左側があるもの 右がないもの1)は今までと違って 右にもご注意 漢字 かな 京都 奈良 母 乳母ヒントをプラスしますと 背中 腹 しょうゆ 酢 おの かまえっ? まだ解らないって?右の列には何かことばを足せば・・・タバコ吸う?吸わない? カラオケ 歌 秘密 胃 ギャク わら2) トランプ 水晶玉 炭 灯油 煙 空気本問も右側に注意 雲 雨 紙テープ セロハンテープ 牛乳 水おまけしますよ アルミホイル ラップ 板 ガラス ピンクレディー 透明人間ね お解りですよね。色がない?
2025.08.07
コメント(0)
-

涼味あふれるガラスの器
〇こう毎日毎日猛暑が続くのなら、目を休ませたくなりませんか?それには打って付けのグッズがあります。掲題のびいどろ・ぎやまんと称される江戸期のガラス器。びいどろはポルトガル語のVidroから出た呼称だし、ぎやまんはダイヤモンドを意味するポルトガル語のDiamanteディアマンテ或いはオランダ語のディアマントに由来しているようです。上質のヨーロッパ製の輸入ガラスや16世紀末から始まった日本製の上質ガラスや無色透明の厚味のあるガラス器の呼称でもあります。 難しい説明は兎も角、岡 泰正著・加藤成文写真の「びいどろ・ぎやまん図譜」から抜き出してみましょう。逆円錐型に底をつけたむらさき色の盃や無色の浅い皿に笹や鯛・鮃模様を施したもの、むらさきいろの瓢箪形徳利や黄色の徳利、角を丸くした御所車絵の角瓶、涙粒のような形に扇を描いた緑色徳利。安永・文政年間の緑色フラスコ形のガラス徳利、花びら形の盃は上が紫、軸や底は黄色。かぶらの形をした徳利は深い紫色地に金いろの藤模様、鯛紋や桜吹雪紋の入った薄黄色の盃。まるで上下ともラッパ型の鼓のような盃の軸は捩ってある藍色ねじり脚付ガラス杯。これらの作品はこげ茶色に変色した桐箱に入っているようです。濃むらさきのやかん状のちろり。型吹き淡青色草花文六角ガラス四段重、黄土色・白・緑色の六角三段重箱には唐草文様が。型吹き蘭文丸形ガラス三段重、十字紋の緑色丸形二段重、得も言われぬ黄土色のガラス向付。中には、ビーズ飾り蓋付菓子器やビーズ飾りガラス絵中国人物文菓子器やグラヴユール松に楼閣文吊り行燈なども。限がないので最後にしますが、ビーズ飾り手拭掛も粋の極みです。
2025.08.06
コメント(0)
-

ウグイス笛の吹き下手
〇比叡山の名物、緑の渓間をささやきかわすうぐいすの声が近ごろめっきり悪くなり、その上他の小鳥類までが山奥まで逃げ込んでしまい問題化している。原因は山頂の売店で盛んに売っている人工うぐいす笛の音に本物が真似て声が悪くなり、他の小鳥たちも気味悪がって山奥へと逃げ込んでしまったとのこと。調査にあたった川村氏から京都府社寺課にうぐいす笛の販売禁止の申し出があった。社寺課では比叡山の鳥類は天然記念物に指定されている関係から、ことの重大性に驚き、滋賀県と相談の上、うぐいす笛の販売は認めるが、この地で吹くことはいっさい禁止するとの制札を山の数箇所に設置することになった。 (参考文献・昭和5年6月18日:大阪毎日新聞)
2025.08.05
コメント(0)
-

死語・流行り語・造語
〇週刊誌やテレビ番組の表題でも一目で人々を惹きつける言葉には頭が下がりますね。所謂コピー・ライターという範疇のものです。難しくする必要性もなく、いつも使っている言葉もしくは新たに創造した「造語」も含めて・・・。私に星子という雅号をつけて下さった野風呂翁は、実に端的な表現に秀でた俳人でした。 新しく生まれた「造語」は作者の手元を離れて生き生きと呼吸を始めます。高浜虚子の「炎昼」なども季語に入っていますね。過去、こうして生まれた語彙も少なくないように思います。 若者によって造語・新語・略語がどんどん作られる反面、表現力は年々低下して行く傾向にますね。超○○とか、ヤバイとか・・・ 一方、俳句に携わっていると今まで知らなかった言葉がわんさと出て来ます。句会の席では電子辞書を引いたりしながら句帳に控える等して順次覚えるようにしています。 言葉を沢山知っておくといろんなおしゃべりの時、当意即妙に合いの手を入れることが出来たり、アドリブの効いた会話で場を愉しい雰囲気に演出することも出来ますね。
2025.08.04
コメント(0)
-

江國滋さんエッセイより。
江國滋著『にっちもさっちも 』の愚痴エッセイには、「名人だらけ」という章で、生まれてこの方、自動車運転に興味もなく、免許証を得もせず、車を持たず、専ら他人の車に乗せて貰う人生を選択された人で、主に5人の知人に助けて貰ったそうな。職業、年齢、地位、収入が違うように、車の種類、性能も違うのだけれど、5人が5人、「ほかのことはともかく、運転だけは誰にもヒケは取らない。タクシー運転手になってもトップクラス」と異口同音に唱えるから面白い。そして共通事項は警笛は鳴らさない。方向指示器は直前にオン。他の車が自分の前に走るのを許せない。車間距離をむやみに詰めたがる。だって。
2025.08.03
コメント(0)
-

「主婦の友」表紙の女性達♪
〇「主婦の友」の創刊号(大正6年3月号)の表紙は石井滴水画伯の、丸髷に赤い手絡の若夫人の顔に内裏びなをあしらったものでした。彼を手始めに、馴染み深い月間誌の表紙には、各時代の第一級の画家の息吹が感じとれるのです。森田ひさし、武田比左、島成園、尾形奈美子、山岸元子、岡田三郎助、長谷川昇、・・・藤島武二・・・と経て昭和に入り、岡吉枝、・・松田富喬・・・宮本廉三郎・・・そして風間完、富永岳彦へと。 武田比左の婦人には哀愁が感じられ、島成園は女性の個性を浮き彫りにしているし、岡吉枝は健康的な女性を謳歌させ、その後の昭和12年から暫らくはモデルさんの表情も明るい。ところが18年になると戦時下という時代背景があってか、憂いに満ちた表情に変わります。戦争に敗れはしたものの、明日への希望があるのか、21年以降の表紙はみんな笑っています。やがて昭和40年頃からは画筆をやめて八千草薫、浅丘ルリ子、吉永早百合といった女優さんの写真になりました。流行歌も雑誌の表紙もコマーシャルもすべてその時代の申し子と言っても過言ではありませんね。
2025.08.02
コメント(0)
-

福助「邦楽まはり舞台」より
〇今から凡そ300年前、享保5年に近松門左衛門が書き下ろした「心中天網島」のほかに特に初代都一中の為に素浄瑠璃として作られたものと言われている名作の一節。 黒髪の 乱れて今の憂き思い 眼には泣かねど 気に痞(ツカ)え 胸に涙の玉櫛笥(タマグシゲ) 向かう鏡はくもらねど 映す顔さえ水櫛や 思えばすまぬことばかり 所詮この世は仮り髷の 恋に憂き身を投島田 覚悟極めし心をば 主に何とぞ黄楊の櫛 合わせ鏡と泣く涙 落ちて流れて鬢水の 哀れ果敢なき花の露 消ゆる間近き風情なり・・・・・・・ 胸に涙の玉 玉櫛笥。 映す顔さえ水櫛 見ず櫛。 憂き身を投げ 投島田。 何と黄楊 告げ。合わせ鏡 逢わせ。というように、昔は言葉掛けをしながら名文でリズミカルに綴っています。掛け言葉が卑しくない程度に選ばれていますね。
2025.08.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1