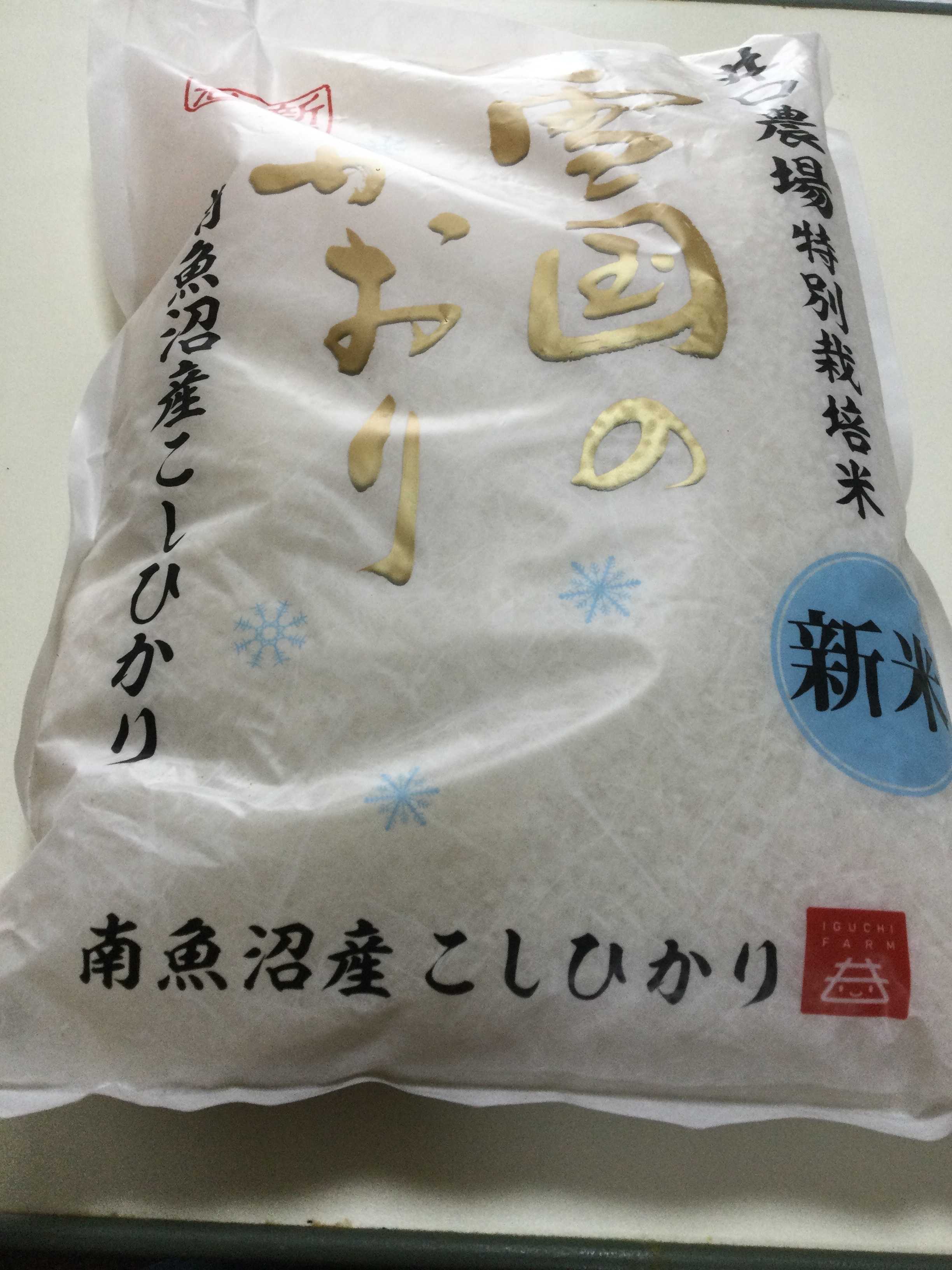2018年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

手相診断あんなこと、こんなこと♪
〇母胎からおぎゃ~と生まれて来たとき、しっかり握り締めている手。爾来、わたし達の手相は刻々と変化しているそうな。 * 浅野八郎著「手相診断」を流し読みしていると、指紋や爪の形にまで及んでいます。 * 四角い爪・・・忍耐強く執念深い。敵に回さない。アーチ型の爪・・・平和で温厚、闘争心は秘める。長方形の爪・・・落ち着き。潔癖すぎる。 *アーモンド型の爪・・・素直・誠実・礼儀正しい。剣型の爪・・・意志強固、強引。幅広型の爪・・・あっさり。熱しやすく冷め易い。ンだって。 * また指紋は渦巻き・蹄状・弓状の3種類があって、その組み合わせで人格や仕事ぶりに現われるンだとか。 *本論の4大線の生命線・頭脳線・感情線・運命線ぐらいは誰もが知っていますが、太陽線・結婚線は兎も角、障害線・影響線・財運線・健康線・金星環・土星環・上昇線・ヴィアラシビア・旅行線・情愛線まだまだあるぞ * 反抗線・ソロモンの環・不動産線・直感線・神秘十字・テンプル・奉仕十字・ラシェット・メディカルライン・スタミナ線・ファミリーリング・スポーツ線など、聞いたこともないようなものも。 *このほか、線の姿・状態やマークからいろんなことを読み取るンだそうです。
2018.01.31
コメント(0)
-

好きになる前に、分かっておいてね♪
○歌詞:「マリーの言葉」・・・20世紀末ごろだろうか、スナック嬢へ捧げた詩。軽快なメロディです。 好きになる前に 分かっておいてね 私の性格 好みを 自慢できるのは ウジウジしないこと 好き嫌いが はっきりしてるから 付き合いやすいと 思うよ 愛してくれただけ 愛してあげるわ あらゆる出来事に いろんな男に 興味が尽きない 浮気症 自慢できるのは 尻込みしないこと 振り振られて 全然平気なの 兎に角退屈 させない 愛してくれただけ 愛してあげるわ もしも傷ついて 落ち込んでいても 知らない顔して おいてね 自慢できるのは 七転八起人 嘘じゃないよ しっかりしてるから いつでも相手に なるわよ 愛してくれただけ 愛してあげるわ 歌詞:「みれん雪」・・・この曲がちょうど110曲目辺りかな? 貴方が残した 胸乳の痕(あと)が ミドラミレファラミ トレドシラシドシ 出湯の中で 見え隠れ ミファミラシラシドミ シミミドシラ 今夜別れの 今夜別れの みれん雪 シラファシラファミシラファミドドシラドシ ミシミドシラシラ 追いかけましょうか 諦めましょうか 運命(さだめ)の糸よ ほつれ髪 窓に冷たい 窓に冷たい みれん雪 貴方に添えない 淋しい夜は 心の中で 泣いている 明日も続くか 明日も続くか みれん雪
2018.01.30
コメント(0)
-

野風呂先師の序文集♪
〇わが心の師:鈴鹿野風呂翁の「野風呂序文集」は京鹿子五十周年記念に上梓されたものですが、その中に亡父の「春燈」に添えて戴いた序文があります。 * <・・・すばる兄みたいに(最初の)来訪記念日をよつく覚え、而も年々歳々欠かさずに親しくとひ、遠くにあつても消息を怠らぬあたゝかい心の持主は稀である。 * すばる兄は私と同じく純粋の京都つ子である。而も兄は中京の鉾町生れである。京都人と云へばどこかヾ冷かなところがあるとやゝもすれば噂せらるゝ、けれどもすばる兄の如くあたゝかく正しき好漢も居る。 昨年祇園会の一つの鉾が損傷した。復旧に骨が折れる。 この記事のある京の新聞(佐賀に居る間、父は叔母をして郵送して貰っていました)を佐賀で読んだ兄は金若干をイの一番に喜捨した。やがてこの事が京の新聞、ラジオが報じた。 * あたかも私がスイツチをひねると電波にのつて胸に迫るではないか。放送の終りも敢へず筆をとつて知らせた。之によりその鉾町の人々乃至京の人等を刺激し、立派に復興した。> * 野風呂先師を敬愛する所以の一つはこの文章からも汲み取ることが出来ましょう。
2018.01.29
コメント(0)
-

名刺によせて♪
○万延元年(1860)に渡米した木村摂津守が日本人として最初に名刺を作った人物で、 *「アドミラル キムラ セットノカミ」とローマ字表記したもので木村大将、木村提督という意味のようでした。 * 3年後、渡仏した池田筑後守は紋章入りで日本語とローマ字を併記されていたようです。 * 明治の治世になると大臣や高官、下級官吏までが名刺を使用、明治22年の大阪の県会議員選挙から積極的に名刺が重宝されるに至りました。 * その仕組みは印紙の真ん中に丸形に自分の肖像を印刷したものを名刺に貼り付けたもので12枚単位で1円80銭。 * タバコ商で有名な岩谷松平なる人物は、明治36年の衆議院選挙に際して純金入りの名刺を有権者に配ったそうな。 * 5年後には日露戦争の成金たちが、金無垢の台紙にダイアモンドで姓名を嵌め込んだ代物で、1枚あたり35000円という史上最高値の豪華さ。 * 名刺の人気は衰えず、大正末期から昭和初期には小学生までが名刺づくりに熱中したとは驚きですね。 *<参考図書:紀田順一郎著「近代事物起源事典」>
2018.01.28
コメント(0)
-

奥村寛純氏の集めた郷土玩具♪
〇今から12年前に書いた日記の一部をそのまま掲載しますので、現在の事実とは異なっています。 * <亡父が郷土玩具をかなり遺していますので、水無瀬の自宅の庭に増築した会館で伏見人形などの展示して居られる奥村さんを、予約もなしに訪れましたが、奥様が快く入れて下さいました。 *奥村さんは中学校で教鞭をとるかたわら、ひたすら伏見人形をメインとした郷土玩具の蒐集に明け暮れして居られたようで、その品数(数万点)は全国一でしょう。また地元島本地区や近隣の大山崎などに関する著作も精度の高い秀逸ものです。 * 奥様も先生だったようで、趣味の詩吟は師範格でいらっしゃいます。家の中が郷土玩具でいっぱいになる状態を”忍”の一字で堪え、ご主人を支えて来られた奥様の努力も報われ、平成14年と同16年度の二度に渡って叙勲を受けられ、ご夫婦で天皇に拝謁されておられます。奥様のご心中は、わが亡き母と同じ想いであったことでしょう。 * なお、この「伏偶舎 郷土玩具資料館」には亡父も一度訪れていました。さぞかし奥村先生と話が弾んだことだったろうと思います(奥村さんは外出中で逢えませんでした)。> *ここからが今の著実になります。 *この膨大な品々は、高槻市の「しろあと歴史館に寄贈されました。また、京都の東寺の傍にも郷土玩具を並べている店があります。
2018.01.27
コメント(0)
-

雅び仕掛けの「起こし文」♪
〇以前図書館から借りた書籍の1つに山岡進著:和の仕掛け絵手紙「起こし文」という綺麗な本があります。 パラパラを頁を繰った時には、小さな屏風と思い込んでいましたが、実はこれは手のこんだ手紙なのです。山岡進さんの文章をそのまま載せると、 * <電話やメールでは伝えられない心を手紙は伝えてくれます。 送られてきた封筒を開けるときのあのわくわくした感じは格別のものです。 * その手紙をもっと風流なものにしてみては、と思い、作りはじめたのが、「起こし文」です。 * もらった人が広げると、四季に沿って紙の持つ素朴な味わいを活かした「和」の世界が出現します。 * 文章は、直接書き込んだり、好みの紙に書いて添えたり、 ときには自分で好きな詩を書いてみたりと、さまざまに書きつけられます。 読んだあとは、飾って楽しむこともできます。> *子供の飛び出す絵本の大人版、絵手紙版と言えばご理解いただけることでしょう。 * (春の文)には、梅、竹、3段飾りのお雛さま、出産祝いに桃太郎・かぐや姫、つくしとねじり花など。 * (夏の文)では、睡蓮、下駄、暑中見舞いの朝顔、あじさい、扇、かたつむり、縁側など。 * (秋の文)お月見、秋虫、秋の七草、うさぎ、下地窓、行灯など。 *(冬の文)では、書院、茶室、床の間、鐘、暖簾はがき、鏡餅、のし袋など。 * 街並みはがきでは、まるで芝居の舞台のような黒塀に柳や打ち水の桶など、風呂屋、おもちゃ屋、せんべい屋なども愛らしい作品です。 * 本書には作り方もそれぞれ説明が附してあり、税抜きで1500円。貴女も1冊如何?
2018.01.26
コメント(0)
-

古歌の梅か、それとも桜か♪
〇古来、花と言えば梅を指していましたが、御所の紫宸殿の前に桜が植えられて以来、桜に人気が集まりました。で、梅か桜か比較検討してみようという趣向です。 * 先ず枝ぶりから比較すると、幹の光沢、風情から圧倒的に梅に軍配が上がります。桜の中には香りを放つ種も一部ありますが、梅の芳香は遠くからでも匂って来ます。 * 花芯はどうでしょう。これは好みの問題ですが、やや粗い感じの梅よりも桜の蕊の方が、なよなよとして居て優れているように思います。しかし桜と言えば、この人を抜きにして語れない佐野藤右衛門さんに言わせれば、我々が好む”染井吉野”よりも山桜こそ本物の桜と言うことから、素朴さが決め手になります。 * 松竹梅という言葉があるように、かの歌姫、鶯も梅の枝に停まります。ですから、ここんところは梅に花を持たせて、そろそろ耳にする寒梅を探しに歩き廻りませんか?
2018.01.25
コメント(0)
-

相撲界の危機を救った双葉山♪
〇当初、明治政府は鑑札制度を採り入れて居り、芸人は遊芸稼ぎ人という資格証(のちに技芸師)が必要でした。 * 相撲界も同じで、明治初期には裸とちょん髷は野蛮的だという風潮を流し、新規力士の鑑札を認めず、正業に就かせなさいという意見まで飛び交っていたようです。 * ところが明治11年、初代梅ケ谷藤太郎が大関になった頃には1月、5月の2場所制になったものの野天小屋ゆえ雨が降れば中止されるという始末でした。 * 明治42年に国技館が開かれ設立委員長の板垣退助が開館の挨拶を行ったとあります。それでも末期に活躍した太刀峯右衛門以降、目だった力士が出ず、昭和の初めには幕内力士の分離独立騒ぎもありました。 * この危機を救ったのが35代横綱双葉山で、昭和11年から14年にかけての69連勝、優勝決定戦の日は会社・官庁も休業状態だったということでした。 * 戦争で再び下火になりまつつも次第に昔日の隆盛に戻っていた矢先、昭和32年、国会で相撲協会の非公益性が問題視され、出羽海親方の切腹騒ぎもありました。 * この折、事態収拾に活躍したのが双葉山(時津風)で、思い切った改革を図り、協会の安泰に寄与、33年から6場所制を定着させました。 * こうして角界の歴史を振り返ってみると相撲協会はいろんな障害を乗り越えて来たのですね。
2018.01.24
コメント(0)
-

勘違い♪
〇昭和31年4月に発刊された『セクスタシイ』(高文社、150円、訳者:岩下肇)という粋な本から抽き出しました。 * <街から遠く離れた淋しい道路で車が急に動かなくなった。調べてみると、タンクにガソリンが1滴も残っていなかった。 * もう夜になっていた。男は少し離れた所に見えている明かりの方へと歩いて行った。ドアをノックすると美しい婦人が出て来た。 * 「恐縮です、マダム」と男は言った。「車が動かなくなってしまったんです。こちらで、1晩御厄介になれませんでしょうか?」 * 「結構ですわ」レディが答えた。「わたし独りなんですが、こんなこともあるかと思って、部屋が用意してありますの」 * 彼女は男を案内して、2階の小ぎれいな部屋に通した。 * 彼はベッドに入る仕度をしながらも、女主人のことが念頭から去らなかった。彼女の美しい姿態は薄い化粧着に包まれていた。 * 彼はとうとう諦めため息をつきながらベッドに入った。しかし横になっても独身マダムの幻は消えなかった。 *その時、ノックの音が、 * 「カム・イン」彼の声は弾んでいた。歓喜にあふえた声だった。ドアの隙間から彼女の美しい顔が覗いた。 * 彼女の顔は誘うような微笑に満ちていた。「一緒に寝る人が居ても構いませんこと?」彼女がやさしく尋ねた。 * 「構いませんとも!」男は叫んだ。「命をかけても大丈夫です。大歓迎ですとも!」 * 「良かったわ」レディが答えた。「もう1人、車を壊した男の方がいらして、泊めてくれっておっしゃるんですもの」
2018.01.23
コメント(0)
-

「洋酒天国 22号」♪
〇父の遺した「洋酒天国 22号」(昭和33年2月25日発行 当時頒価30円)には”酒飲みの文化史 No10”としてギリシア編が載せてあります。 *<大食と大酒>ギリシアではオリンピア祭などの運動競技に出る選手みは、大食が1つの資格だったので、競技の練習と並行して腹一杯に食べる練習が行われていた。そして付け足しとして大酒飲みも。 * ヘラクレスは2頭分の雄牛の胴体を真っ赤な石炭の上に積み、片っ端から肉を引き裂き、骨をへし折って全部平らげたとも。 * このほか、心が泣き悲しんでいる時も胃袋は飲食を要求すると述べたオデュッセウスという大酒大食漢。 * 西暦6世紀頃のレスリング6回優勝した怪力のミロンに至っては、1回の食事に20ポンドの肉、同量のパンそして甕3杯の葡萄酒を飲んだとか。 * 或いはヘロドラスは小男ながらミロンほどの大食漢で、彼が同時に吹く2個のラッパの轟音に軍隊は勢い勇んだ話。 * 女性のラッパ吹きのアガライスも大食にして大酒飲み、リティエルサスという王も大食・大飲の獰猛にして残酷な人物だった由。
2018.01.22
コメント(0)
-

中文表記の人物当ててみますか?
〇下に並べた人たちって、一体誰??? 1歴 山 2維 廉 3以利沙伯 4加利列窩 5坎 徳 6格侖児 7瓜 得 8哥白尼 9雑未耶 10施福多 11沙 翁 12瑣 子 正解と思われる人名を下の欄からお選びください。 aソクラテス bシェクスピア cシーボルト dザビエル eコペルニクス fゲーテ gクロムウェル hカント iガリレオ jエリザベス kウィリアム lアレキサンダー これは中国において、発音の似たものを充てたものと思われます。ご参考までに↓のサイト(weblio中国語翻訳)。 https://translate.weblio.jp/chinese/
2018.01.21
コメント(0)
-

寺の門のは引っ越し好き??
〇芸術新潮編集による「国宝」(国宝大百科)には興味をそそる記事が多々あります。ほぼ丸写しになってしまいそうですが・・・。 <「門」というのはいわば建物の「顔」であるわけだから、本体と一蓮托生かと思いきや、これまた平気で門だけが引っ越したりする。>から名文が流れ出すのですが、 * <お寺の門が売買されるというのは昔はとりたてて珍しいことではなかったようだ。 *国宝ではないが、現在南禅寺の塔頭・金地院にある明智門は、最初は大徳寺にあったのを明治22年に買い取ったものである。売った側の大徳寺はどうしたか、空いた門の場所に寺内の別な場所から門を移した。つまり自前で調達したわけだ。 *それが現在の国宝・大徳寺唐門である。一方、現在豊国神社に構えられた国宝・唐門も、実は”転校生”。 *かつて二条城にあったそれがまず金地院に移され(明智門とは別門)、さらには明治時代に豊国廟の再興にあたって豊国神社が建てられた際、金地院から移された。しかもこの門、 *もともとは伏見城の遺構だった可能性もあるというのだから、あるいは三度引っ越しているのかもしれない。> いつもなら、自分の文章でまとめるのですが、なかなかの名文、調べが似ていますので、ほぼ全文頂戴しました。
2018.01.20
コメント(0)
-

厳しい寒さの中にも芽吹きや下萌えが♪
〇正月から3月上旬にかけての田や畑には白菜や大根が稔る程度で、休耕期の野良の色合いは寂しい限りです。 *魔女の節くれだった指のような枯れ枝にはカラスが置物のように動きを止めています。 * 真冬に通勤していた時、列車の線路際には草木も見えず、その殺風景さに嫌気がして居たものですが、それでも着々と春への準備が進んでいるのでした。 *梅花祭の記事や菜の花の写真が新聞紙上に載せられる頃になると大好きな緑の季節が靴音高く近づいて来るのです。 *早朝の太陽の輝きも日増しに逞しく豊かになって行きます。奈良のお水取りの儀式が終わる頃には冬コートから薄物のコートに変り、街中には白い色、ピンク色が行き交うようになります。 * 黒土には二日三日で緑鮮やかな草が見る見る溢れ、鳥の囀りも勢いを増して来ます。 *緑がいっぱいになる頃、桜の季節、葉さくらの季節へと目まぐるしい変化の日々に突入します。 *もう、そこいらは若葉色、黄緑色で満ち溢れ、光・光・光の五月へと移ろい行くのです。
2018.01.19
コメント(0)
-

昭和25年当時の「新球団選手画報」♪
〇十年ひとむかし。京都銀行本店の真西にあった家を従姉妹が立て直す折に見つけだしたグッズは、父の書籍のほかに、 *野風呂先生の綺麗な葉書、可愛がって戴いた水野白川(男爵)さんの葉書などは葉書専用アルバムにきちんと挟んで保存されていました。 *また、高浜虚子から送られたハガキ数枚、次女の星野立子の年賀状もありました。 * それから夏の甲子園野球第10~12回の特集号や昭和25年5月発行の面白少年の付録でありながら立派な「新球団選手画報」が残っていて、 *それには巨人総監督が三原脩、監督が水原、別所投手、千葉茂、川上哲治、青田昇といった選手(写真付)。 * 阪神タイガースでは松木謙次郎監督、藤村富美男助監督、田宮謙次郎選手らが。 *毎日オリオンズに別当薫選手。近鉄パールズには関根潤三投手など。本誌共で定価80円の時代でした。 *京都の家には父の遺した書物が別誂えの大きな書棚2基にびっしりありましたので、 *処分費用などを鑑み、その他の値打ちものと一緒に上記の冊子は古書店に引き取って貰いました。
2018.01.18
コメント(0)
-

初夢、それは龍だった♪
○十数年前の二日の夜中から朝方にかけて見た初夢は”龍”でした。 *何でも、私は新しい家に移り住んで居て、二階の窓から三角形の大きな池を見下ろしていました。 *池の水はやや褐色を呈していましたが、前方に大振りな黒い蛇が泳いでいるのが見え、やがて水没して行きました。 * すると手前に見えていた、もう一匹の更に大きな蛇がうねりながらこちらに近づいて来ます。 *な、な、なんと、蛇と思ったのはぎょろ目、長い鬚を張らせた龍でした。 *京は御所近くの相国寺、その天井に這いつくばって居る顔つきそっくりの龍でした。 *私の傍を横切って龍は悠々と、夢の画面から消えて行きました。 *夢と謂えど、その画像の鮮明だったことは、昨日のように脳裏から離れないのでした。
2018.01.17
コメント(1)
-

あいうえお正月♪
○父すばるがワープロで打った1枚の句集、題して「あいうえ”お正月”」。 「あいうえ”お正月”」 あ 姉いもと番号つづく賀状くる い 威勢よく負けてくれたる戎笹 う 歌かるたいつも読み手の修道女 え 戎笹提げて南座見上げゐる お 親と子のかしは手揃う初詣で か 書き初めや筆の穂のぼる墨の筋 き 京極と背中合はせの初湯かな け 献燈のわが名に会ひぬ初詣 こ 紅梅町白梅町や羽根日和 さ 参宮の父に陰膳小豆粥 す 炭の香のけだかくもある二日かな た 大将と呼びかけられし初戎 つ つくばひの柄杓あたらし初明り な 撫で牛のてらてら光る初詣で ね 寝足りたる二日の妻の顔と会ふ は 初刷や余白ゆたかに選者吟 ひ 緋の舞妓女将ら連れて初戎 ふ 古女房きりりきらきらお元日 よ 吉田山詩吟の徒あり筆初め わ 腕白にして猫舌やなづな粥
2018.01.16
コメント(0)
-

角界の大改革案(8年前の日記)
○角界がニュースの焦点になっていますね。この日記は8年前に書いたものです。 * 相撲の魅力は武士道をベースにした国技的崇高なスポーツの一つであり、また肉弾戦、 *或いは技が決まった時の両者のスタイルの美しさに在ると思っています。 * わたし達がこどもの頃、テレビが一般家庭に普及し始めた頃の相撲は見ごたえがありました。 * 制限時間いっぱいになると館内の歓声が大きく谺(コダマ)しました。 *好取組の栃・若(栃錦・若の花)になると全国の人々が仕事の手を休めて魅入るほどの人気、緊迫感がありました。 * 今の相撲と根本的に違うのは”仕切り”での呼吸合わせです。 * 時間いっぱいになると両力士は塩を撒いた後の立ち振る舞いを相手に合わせる気使いをしていました。 * 今のように、相手を無視して先に土俵に両拳を着けるような無作法はしていませんでした。 * 最後の仕切りだけは、きちんと相手との間合いを合わせながら、そして迷う事なく、両者がぶつかっていました。 *昨今の立ち合いでは、某親方が声を荒げて注意をする光景を度々見ますが、あれは何の役にもたっていません。 * 武士道・騎士道にそった”正々堂々”の勝負を、もう一度、みっちり教え込むことです。 * それに従わない力士、明かに相手と呼吸を合わせない力士は相撲を取らせず、強制的にその一番を敗戦者にすること、 * 双方とも呼吸を合わせない場合の取組(一番)は、これも相撲をさせず、その一番は両者とも負け勘定にすること *このくらいの荒療治をしないと改革はできないと思われます。 * 仕切りがきちんとできれば、角界のいろんな負の問題は解消されるものと信じています。
2018.01.15
コメント(0)
-

発泡スチロール箱の効能♪
〇冬場の厨房道具に欠かせない、大活躍のグッズがスーパー等から無料で頂いた”発砲スチロール”の深めの箱なのです。 * やや大きめの鍋で炊き込んだ煮物は、まだグズグズ煮えたぎる音を出している鍋ごと、この容器にいれます。 * 鍋と容器の壁の隙間には、古新聞紙をぐしゃっと丸めて埋め込みます。 * このまま、数時間放置して蓋を開けても、まだまだちゅんちゅんに熱いんです。 * 冬の味覚と言えば、先ずは大根。今回は蕪に似た丸大根、油揚げ、鶏肉などと一緒に煮込んだものを * 夕飯時に再び温め直し、食卓の中央に、でんと据えます。その他のおかずと一緒に、この煮物を戴くのです。 * 暗くて寒い真冬は大嫌いですが、鍋物がほぼ毎日食卓を賑わせますので、耐え忍んで行けると言えないでもないですね。
2018.01.14
コメント(0)
-

流麗文のビタミン剤は何?
〇ここ数年間で文章力が落ちて来たなと感じているのですが、それは、そろそろ始まった呆けの前兆だと思い込んでいましたが、それだけではなく、他にも原因があったことに気づきました。 *それは美文、名文に接していないから、流麗な文章を読んでいないからに相違ありません。 *例えば京を愛した長田幹彦の一文なら *<・・・なかでも円山の夜桜は昔から天下の人口に膾炙してゐる。「春は花、いざ見にごんせ東山、色香争ふ夜桜や・・・」と、 *やさしい節調で艶曲、「京の四季」にも唄はれるとほり、名代の枝垂桜で賑はふ祇園の夜桜ほど艶かしいものは又とあるまい。 *今の時世でこそ祇園町にも電車の軋りが喧しく、紅提灯もあたら不風流な電燈にかはってしまったが、 *つひ七、八年前まではかがり火の美しく燃えたつ花見小路から円山までの道さへ既に一幅の画中の趣を呈してゐたのである。> *情景が瞼に浮かんで来、いつまでも引用したくなるほどの名文です。吉井勇の小説をいつぞや紹介したことがありますが、彼のは五七調で綴っていますので、猶更のことしみじみ文章に惚れ込んでしまいます
2018.01.13
コメント(0)
-

本能寺の乱♪
〇歴史書として著名な「信長公記」(人物往来社)桑田忠親<校注>から一部抜き出しました。 * <六月朔日、夜に入り、老の坂へ上り、・・・(略)。信長も、御小姓衆も、当座の喧嘩を下々の者ども仕出し候と・・・(略)、明智が者と見え申し候と、 *言上候へば、是非に及ばずと、上意候。(略)信長、初めには、御弓を取り合ひ、二、三つ遊ばし候へば、何れも時刻到来候て、御弓の絃切れ、其の後、 *御鎗にて御戦ひなされ、御肘に鎗疵を被り、引き退き、是まで御そばに女どもつきそひて居り申し候を、女はくるしからず、急ぎ罷り出でよと、 *仰せられ、追ひ出させられ、既に御殿に火を懸け、焼け来り候。・・・(略)> * 原本を解読するとなると大変ですが、後世の学者の注釈のお陰で、楽に読むことができますね。 *現在、日野草城と「京鹿子」を創刊したを野風呂翁の俳諧日誌(草書体)を活字に直していますが、 *実に大変な作業です。京の俳句の歴史や戦時中の生活が生生しく書かれています。 *なお、写真は足利義教公が赤松氏に滅ぼされる図ですが、江戸幕府の咎めを回避目的で描かれたもの。実は本能寺の変。 *大山崎歴史資料館に展示してあります。画像はインターネットから拝借。
2018.01.12
コメント(0)
-

「歌会始」と言えば「春」の折♪
〇明日はいよいよ「歌会始」。ひと昔「春」の折に一度だけも応募したことがありました。いろんな条件がありますが、誰にも漏らしていない未発表の作品に限ります。応募用紙は半紙に毛筆にて、〆切日までにお題の、例えば今年の「語」を右端に書きます。 *そして自分の歌を書き入れます。住所、年齢、職業など規定の項目をその半紙に認めて、宮内庁に郵送します。 *当時の拙作は「嵐峡は蒼きふところ桜餅春滔々と水の流るる」だったでしょうか? * 畏れ多くもかしこくも、ご皇族、選者、入選者等の御作品には触れませんが、毎年、この雅やかな行事は、わが国の誇りとすべき文化の粋だと思っています。 *今上天皇陛下には、学生時代に将棋の名手であらせられたこと、そして麻雀にも興じて居られたことは、元毎日新聞論説委員:藤田信勝氏の随筆にあります。 * 民間から妃を選ばれ、その後お二人の着実なるご尽力で天皇家と国民との距離が身近になりました。 *私たちはご理解ある現天皇様、皇后様に心から謝意を申し上げ、来年のご譲位の儀を謹んで見守りましょう。
2018.01.11
コメント(0)
-

竹久夢二の限定本♪
〇父は殊の外竹久夢二というロマン画家、詩人を好んでいたようで、夢二にまつわる書物は数え切れないほど残しています。今ここに龍星閣の「風のやうに」という書がありますが、 * 昭和37年の第2版もので、大阪桜橋の高尾書林という古本屋で購入しています。その本にハガキが二枚挟んであって、41.3.12の消印の新刊書案内で、 * 昭和8年創業の同社が2年がかりで出版に漕ぎ付けた背景が切々と記述され、「歌の絵草紙」普通版では予約価3800円、限定百部のものは10000円。 * 後者は朱染総皮表紙。天金。本金箔押装画。特織布函入。前者は本絹多色刷表紙。菊大型アート374頁。多色刷12図。写真版268図。英文解題。となっています。 * 翌年42.3.25付消印のハガキの文面には「歌の絵草紙」がびっくりするほどの注文で、発売日には影も形もなくなり、古本市場で高値になったとの苦情が後を絶たなかったと。 * <「思い出ぐさ」には夢二全盛時代の作品群、明治大正を目でみる情緒史とあって、夢二が明治末から大正にかけての10年間に「月刊夢二絵はがき」として描いた326図の収録もの。 * これら一つ一つには遠い日の思い出につながり、しかも風刺あり、諧謔あり、浪漫あり女人の美しさにただよう侘しさ、やるせなさは夢二ならではの「浮世絵」である。 * 夢二の絵は、いつも身ぢかなものの楽しさや愛しさで人をつつむ。人生は、つきることのない哀詩であることを記録する。特に肉筆原画から製版した60図は、夢二の線描の繊細さ、鋭さ、奔放さなど夢二の息づかいまでも伝えて、圧巻である。> *この夢二評はこの本の解説を請けた長田幹雄氏の文章なのでしょうか。こちらの特装版は250部の限定。 夢二の描くような和製美人は影を潜めてしまったのでしょうか?遠くなってしまった昭和時代と共に消滅したのでしょうか?
2018.01.10
コメント(0)
-

十二月の拙句記録帖♪
〇いよいよ数え日となって参りました。恥をしのんで ここに記録しておきます。〇吾も亦師走の貌の一つたり〇船宿の伊根の鰤しやぶ旅ごころ 舟屋群る伊根の浦曲waの鰤起し(注)鰤起し=鰤のよく獲れる時期になる雷 鰤漁や餌を撒くシャベル途切れざる 鰤漁やここを先途と餌を撒く〇隠し持つ短銃龍馬の懐手 文豪の群像ふたりは懐手◎深山なる銃声の帯猟解禁 肉弾のラガーの噴ける息白し〇菊炭の著shiruき裂け目や鄙住まひ〇幹太き冬木を父のごと抱idaく〇武専なる稽古納めの気迫かな新年度はまた、新たな気持ちで俳句を詠みます。
2018.01.09
コメント(0)
-

女流文学への橋渡し♪
〇『枕草子』や『源氏物語』など、女流文学発祥に貢献したとされる紀貫之の『土左日記』の以下の件りは *舟に依る長旅の不安な道中にようやく石清水八幡(男山)に差し掛かった時の感動の様が如実に綴られています。 *(注)土佐ではなく、土左日記が正しい。 * 大山崎歴史資料館にも日記のこの部分を展示しています。旧暦二月十一日の部分から載せてみます。 * <十一日、雨いさゝか降りてやみぬ。かくてさしのぼるに東のかたに山のよこをれるを見て人に問へば「八幡の宮」といふ。 * これを聞きてよろこびて人々をがみ奉る。山崎の橋見ゆ。嬉しきこと限りなし。 * こゝに相應寺のほとりに、しばし船をとゞめてとかく定むる事あり。(以下当日分略) * 十二日、山崎にとまれり。 * 十三日、なほ山崎に。 * 十四日、雨ふる。けふ車京へとりにやる。 * 十五日、今日車ゐてきたれり。船のむつかしさに船より人の家にうつる。この人の家よろこべるやうにてあるじしたり。このあるじの又あるじのよきを見るに、うたておもほゆ。いろいろにかへりごとす。家の人のいで入りにくげならずゐやゝかなり。 * 十六日、けふのようさりつかた京へのぼるついでに見れば、山崎の小櫃の繪もまがりのおほちの形もかはらざりけり。>(以下略) * この綴りから少なくとも大山崎に四泊している勘定になります。向日町の石塔寺のある島坂で饗応を受けていたことも分ります。
2018.01.08
コメント(0)
-

インフルエンザに寄せて♪
〇1890年(明治23)の2月にアメリカからインフルエンザが入って猛威をふるいました。 *16日の朝日新聞には流行性感冒という語訳が載っていたようです。 * しかし俗には「お染風」と呼ばれたのですが、伝染病の「染」から連想されたものらしく、 *やがて「久松留守」と書いた赤い張り紙が流行したようです。 *その心は、久松は居ないから来ても無駄だよの意味だったのでしょう。 * まだまだ迷信というものが浸透していた時代色豊かな話じゃありませんか。 * (注)参考資料:「明治・大正・昭和の新語・流行語辞典」米川明彦編集<三省堂>
2018.01.07
コメント(0)
-

七草粥によせて♪
〇正月(ムツキ)廿三日の子(ネ)の日に、左大将の北の方から若菜をお贈りになります。・・・(源氏物語:若菜上) * 玉かづら 若菜さす野べの小松を引きつれて もとの岩根を祈るけふかな * 源氏 小松原すゑの歳(ヨハヒ)に引かれてや のべの若菜も年を摘むべき * 万葉集巻頭を飾る雄略天皇の求婚の御歌から若菜を摘む慣習が始まったとされますが、宮中でも内膳司がその年の七種の新菜を羹(アツモノ)として献上しました。 * この行事は中国から伝えられ、万病を除くといわれ、不老長寿を祈念するものでした。七草粥の源となる慣いで、芹、なづな、すずな、すずしろ、仏の座、御行、はこべら。 * 我が家ではワン・セット二百五十円もするものは買わないで、専ら庭に生えているハコベや元日の雑煮に使った小さい大根、人参やセリ、白菜など七種類の菜の粥で済ませることになりそうです。
2018.01.06
コメント(0)
-

合点とけりについて♪
〇日常で、合点が行くとか、合点できないとか言いますが、 * 角川の国語中辞典(時折誠記・吉田精一共編)で調べると、1)承知・了解・承認すること とあり、2)和歌などの良いものに印として点をつけることとなっています。 *広辞苑の電子辞書では、上の2)が1番目に挙げられ、和歌などを批評して佳いものに点・丸・鉤などの印を付すこと2)回状などで承知の意を表すために、自分の名の肩に印を付すこと3)承知。承諾。うなずくこと。がてん。4)納得。得心。がてんとあります。 * また和歌や俳諧から出たことばに<けりをつける>もあります。 *<逢ひ見ての後の心に比ぶれば昔は物を思はざりけり>(権中納言敦忠)や *<磯千鳥足をぬらして遊びけり<>(蕪村)というように、助動詞<けり>で終わる * 和歌や俳句が多いことから、終わりにする、決着をつける意味で、<けりをつける。と言うようになった由。
2018.01.05
コメント(0)
-

出雲の阿国♪
〇慶長8(1603)年、出雲の巫女と称する妙な歌舞団が京に根付きました。男装凛々しい阿国の首にはクルスがかけられ、むせかえるような若さの律動に群集は虜になったと言われています。 * 阿国に関するものとして京都は南座の西側(川端通に面して)の石碑や、その斜め向い四条大橋の袂に阿国の像が立っています。 * 過去の習いを覆す新手の舞踊を観にくる観客の中には、近年の竹の子族、マハラジャ族とも言えそうな連中も多く居たものと思われます。 *傾(カブ)くという言葉は信長の居た時代にもあったようですが、阿国の一行からかぶき踊りが始まり、今日の歌舞伎の由来になっています。 * この熱狂的に人気のある踊りは、やがて女かぶきと言う形で遊女屋でも盛んに真似られ、また携帯電話のCMに登場する樋口可南子婆の恋人役のような * 前髪姿の若衆歌舞伎も同時代に流行り、風紀上よろしくないということで4、50年後には禁止され、前髪を切ったいわゆる野郎かぶきのみ公認されました。 * 中山幹雄編の「歌舞伎絵の世界」というA4サイズの本を開けると、歌舞伎の風俗絵巻を楽しむことができます。 * また歌舞伎絵を分類すれば、舞台姿、役者似顔絵、役者風俗絵、看板絵、劇場図絵、 * 番付絵、絵入狂言絵など多種あって、浮世絵師の流派には、主に鳥居派と歌川派など。いまさら深入りは出来ませんが、奥のある世界のようです。
2018.01.04
コメント(0)
-

栃錦か若乃花か、ひばりかチエミか♪
〇物心がつき、佐賀市内で初めて映画を観た頃には、美空ひばりと言えばれっきとした女優さんでした。 * こちらが長じ、あちらも大人になって行かれるうち、愛想の良い江利チエミさんのファンになり、つんと澄ましたようなひばりさんを姉弟揃って嫌っていたようです。 *亡くなる数年前から従来のひばり観を捨て、客観的に見る様になると、若干イメージも変ってきました。 *ここにある和田誠編「日本の名随筆」のひばりさんの芸談に触れると、 * 彼女が逆境を乗り越え、一流の女優、一流歌手として看板を張って来られた生き様や仕事に関する身の処し方に、深いものを感じるのです。 * ファンの為に時代の変化に機敏に合わせながらも、どっこい”ひばりイズム”を必ず織り交ぜることを忘れない彼女でした。 * <・・・とくにこのごろの歌には、顔をそむけたくなるような歌詞のものがありますが、ああしたものはうたえません。 * わたしは日本人の血が流れている女ですから、日本人らしい、日本の歌を、その心を生かした歌をうたいつづけていくつもりです。> * つんとしていたようでありながら、実際には敬虔な部分の多い大物歌手であったことが、これらのエッセイを通して理解できたのでした。
2018.01.03
コメント(0)
-

年賀状に寄せて♪
〇お年玉つき年賀はがきが売り出されたのは昭和24年12月1日からであったらしいです。 * 年賀郵便については当局も昔からいろいろ気を配り、明治39年12月29日には、年賀特別郵便規則を定め特別集配に着手したり、昭和10年12月1日からは、年賀郵便特別切手の発行を開始しています。 *戦後も23年から年賀郵便の特別扱いを再開し、このお年玉はがきは、当時2億円の増収を狙ってのアイディアでしたが、これがまんまと当たり、現在に至っているということです。 * 郵政省では、その賞品を賞品とはいわず、「お年玉物品」と称し、第一回目のお年玉物品は、特等がミシン、一等賞が純毛服地、二等賞:学童用グローブ、三等:学童用こうもり傘、さらに四等:ハガキ入れ。 *数年前まではこの四等止まりでした(現在は三等賞まで)が、その頃はさらに *五等:便箋と封筒組み合わせ、そして六等に切手シートという具合でサービス満点でした。
2018.01.02
コメント(0)
-

初鏡での女性の会話♪
明けましておめでとう御座います。 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 山口某さんの句に 言葉えらび褒め合って居る初鏡 新年会の集まりでトイレに行くと、仲間が数人居ます。 「〇〇さん、貴女ちっとも老けないわねエ、羨ましいわ」 「あらツ、△△さんこそ肌が綺麗で、昔と変わってへんやないの」 とか言い合っておられる様な光景が目に浮かびます。 男どもには理解し難い、女性同士のお付き合いの常識、 御苦労様ですと申し上げるほかありません。女の世界で 村八分になってしまったら、もうそれでおしまい。 取り返しがつかないのではと推察する次第です。
2018.01.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1