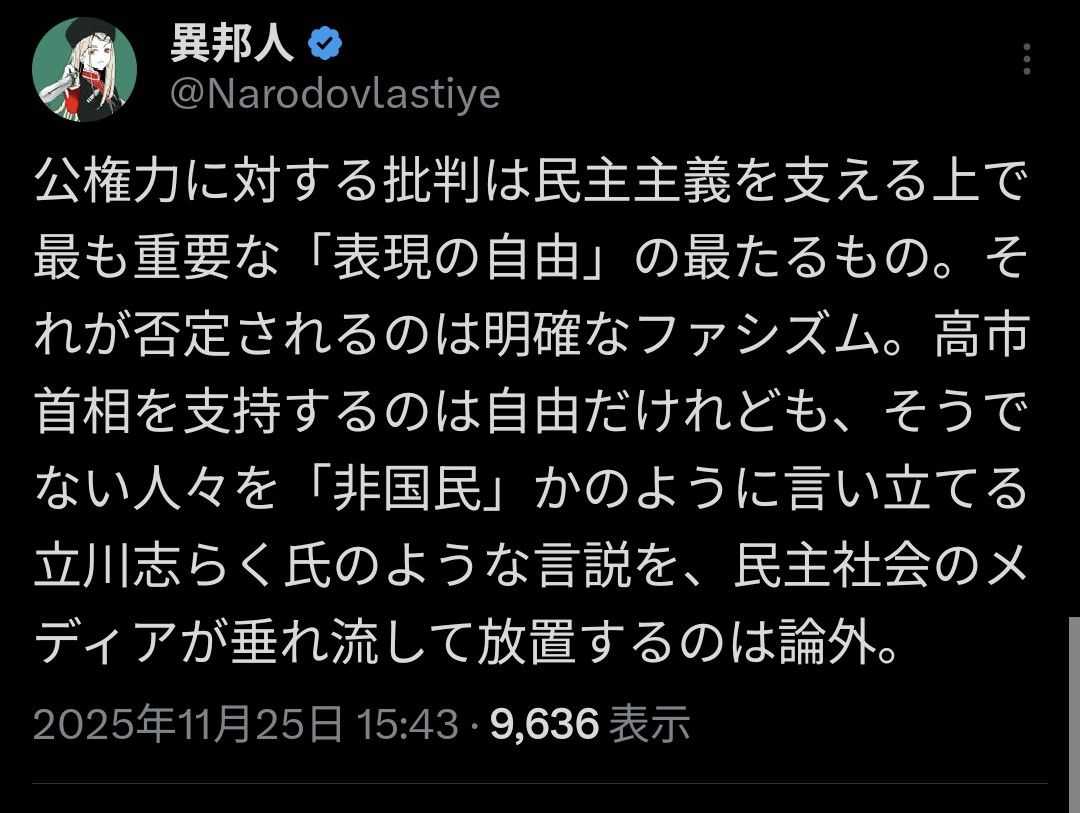2015年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
ストーンヘンジの巨石は語る♪
〇ジャクリーヌ・ド・ブルゴワンの「暦の歴史」を何気なく読んでいると、太陰暦が先にできたと書かれていて、ついその辺りの頁を読んでしまいます。<最初の暦は太陰暦だった>の見出し部分を要約すれば、メソポタミア、エジプト、ギリシア、中国ではまず太陰暦が発達。1朔望月=29.5だから、その12倍は354日、ほぼ太陽暦の1年に相当します。現代ではイスラム暦がこれに近いのですが、農耕での種まき時では矛盾がうまれるので、計画的に閏月を入れる太陰太陽暦も考えられました。 一方、太陽に基づいて暦を作ったのは後年のエジプト人やマヤ人だけではなく、イギリス南部にあるストーンヘンジの環状列石は、これを建てた人々が太陽の動きについて正確な知識を持っていた証左となっています。巨石の柱は同心円状に配置され、夏至には太陽が中央通路の、祭壇があったとされる石(ヒールストーン)の背後から昇ってくる様に工夫されていたことから、時を計測するための天文台として機能していたものと推測されています。ドイツ語のソンネンヴェンデは、太陽が向きを変える点という意味で、夏の行路の極点に達した太陽が、回れ右をすることを知っていたことを物語り、上記のストーンヘンジ時代の人々も、太陽の行路が変化する瞬間=夏至ととらえていたと思われるのです。
2015.01.31
コメント(2)
-
アレ何て言うの?
〇佐々木正孝著・篠崎晃一監修の「アレ何?大事典」(小学館、税抜き1300円)は雑学の書として面白いです。 わたし達が普段目にする物体・道具などの名称を探るという本です。例えば鍋料理で取り分け用の容器は”トンスイ”と言うんだそうです。本書では幾つかのジャンルに分類されて居て、街編、からだ・ファッション編、暮らし編、スポーツ・文化編の4つ。では今回は街で見かけるもの、1)道路工事の人のV字に光るチョッキの名は?2)同じく工事現場でチカチカしているロープ状 のものの名は?3)葬式の会場までを案内する指のマークは?4)タクシーの背中・てっぺんにある目印は?5)線路に落ちたものを拾うマジックハンドの名 は?6)自動改札機のハの字の扉の名は?7)コンビニのレジでバーコードを読む機械名は?8)つり銭を入れてくれる皿状のものは?9)コンサートで観客が振る蛍光色の棒は?10)抽選場でガラガラ廻す八角形のアレは?<回答編>1)夜光チョッキ 2)チューブライト 3)指差し4)社名表示灯 5)安全取得器 6)バーコード リーダー 8)カルトン 9)ケミカルライト 10)ガラポン
2015.01.30
コメント(0)
-
東京ローズのこと♪
〇先日NHKの歴史ヒストリアで詳しく採り上げていた掲題の女性。ウィキペディアで検索して戴ければそれで良いのですが・・・。戦争時、相手国兵士のやる気を損なうような放送や漫画等のビラを撒くようなことをプロパガンダと言いますが、日本の某局のジャズ・アワー時にそれに近い語り口でアナウンスしたことについて、終戦後、味方である筈のアメリカ本国から有罪判決を受け、つらい思いをした不運な日系人東京ローズの半生。終戦後、敗戦国日本の現状の偵察の為来日したマッカーサーと同行した新聞記者団は出征地やアメリカ本国に於いて絶大な人気を博した「東京ローズ」その人を捜すべく躍起になり、無理に探し出したのが、彼女(実際は純日本人の別人)。当初はこの役を拒んでいたものの、アメリカ兵士の心を慰めながら、勇気づけると信じて精一杯頑張ったのに、国家反逆者と罵られ、有罪とされた彼女の想いは如何程であったのでしょうや。
2015.01.29
コメント(2)
-
武士に三通りがあった?
〇大学教授陣の講義がその最たるものですが、各講演会や結婚スピーチにしても、話が脳に浸みこんで来る語り口と、これと正反対で講演やスピーチの内容を殆ど思い出せない、紋切型とがあるやに思います。「黄金の日本史」の執筆者・加藤廣さんの書き物は、変化球に富んでいて、話がどんどん面白い方へと逸れて行くものの、忘れずに、元の論旨に戻って来られ、挿入した部分が隠し味として見事な講演、スピーチへと仕上がっているのです。 例えば「武士のルーツに三派あり」に書かれているのは、 もののふ=武力をもって朝廷などの公に奉仕 する、いわば近衛兵。皇族から臣 籍に下った皇子に遡り、 源氏=清和・宇多・村上・花山帝の源流 平氏=桓武帝から二代の帝や皇子の源流 さぶらひ=貴族らの家財や身辺の警護を主と し、「畏まってさぶろふ」が返事 この言葉の末尾の変化→侍 つはもの=どんな紛争でも請け負い、合戦を 生業とする派遣武士解り易く言えば、東北の場合 もののふ(武士)=八幡太郎義家 さむらひ(侍)=彼に馳せ参じた中堅幹部ら つはもの(兵)=侍が率いた部下の兵力後年これらがごちゃ混ぜになって侍に集約化。 因みに武士の「武」=戈ホコ+足の下部分の表 意=武器を担いで土地を踏み荒 す奴であって、信長ほどの偉人すら思い込まされた 「武」=戈+止=戈を止める平和の勇士という政秀寺住持・沢彦の言とは大違い。 ね、こういう語り口で歴史を解り易く教えて下さる良書なのです。
2015.01.28
コメント(0)
-
拙作「恋と恋敵」♪
〇演歌系やポップスにしても私の場合、歌詞が先に有って、その詞に曲を作る手順が殆どですが、これは曲が先で、無理矢理歌詞をつけたものです。 1. 恋に恋する 時は とても眠れは できぬ 胸の鼓動が 鳴る ドキドキドキラ キキドキラ あの娘だけは 誰にも渡せ ないさ それを思う 時は 胸が高鳴 るのさ 恋に恋する 時は 居てもたっても 居れぬ これが恋の 病 誰も一度は 経験するのさ2. 恋の仇は 強敵 とても俺には 勝てぬ だけど命を 賭けて ヤルヤルヤルサ ヤルヤルサ あの娘決して 美人ではない けれど 気だての良さは 一番 色の白さも 抜群 恋の仇が どうした 俺の真ごころが いつか勝利を 掴む 誰も構うな 今度は ヤルのさミファミファミ♯レミ ドッドーミファミファミ♯レミ シッシー♯レミレミレ♯ドナチョレ ラッラードレドレドシラ シッシーミミミラという感じです。 ♭
2015.01.27
コメント(0)
-
今月2度目の5冊♪
〇月曜が図書館の休刊日になりますので、清水寺界隈での吟行句会から返る途中に図書館に寄りました。1)「黄金の日本史」加藤廣著(新潮社) 世界経済が不安定な時、信頼できる財と言えば金。ジバングと称された日本の金の歴史を辿ります。2)「渥美清」堀切直人著(晶文社) 映画館では1度も寅さんシリーズを見たことがないのですが、宝塚大劇場では間近に見た大物俳優の内部が知りたくて。3)「印刷・製版テクニック」安達史人著(美術 出版社) 目で愉しむも良し。4)「乙女の日本史」堀江宏樹・滝乃みわこ共著 (東京書籍) 現代の女学生向きに書かれた歴史書ですが、知って損をすることがないので、気楽に読もうかな。5)「日本の名匠」海音寺潮五郎著(中央公論社) 大文豪が書かれた歴史小説。何かヒントが得られそうに思います。閉館までの10分間で急いで選んだ5冊でした。只今から大山崎は宝積寺に出かけ、節分に撒く豆の袋詰めに行って来ます。
2015.01.26
コメント(0)
-
またまた珍本発見♪
〇物置から書斎の書棚に移した珍本があります。父すばるが可愛がって頂いた中田余瓶さん編による「虚子京遊句録」で、表紙は京洛図絵で清水寺や高台寺、西行庵、芭蕉堂(昨日鴨鍋を頂いた茶寮辺り)鴨川の下流では米俵を摘んだ牛車が川を渡っていたり、四条大橋を渡る人通りの多い素描画。富書店からの昭和23年発刊で定価弐百圓となっていて、要は高浜虚子の京洛での作品をまとめたもので、昭和22年11月12日付、鹿ケ谷桜谷町のミューラー初子邸滞在中に虚子が本書の序を書き残しているのも興味深いものがあります。ミューラー初子邸の桜谷町と言えば、父すばるの第二の職場、ノートルダム女学院のある場所だから。シスターキャーレンの案内で大木の桜を見学させて頂いたのが2001年の4月。 話を戻して床の間の前に執筆する虚子の写真や平八郎氏の串だんご(右は白3個茶1個、左は緑3個に白2個)、傘かりて八瀬の里へとしぐれけり 他1句の短冊なども添えてあり、鴨川・木屋町、三条大橋、南座、顔見世、祇園新地、都踊、東山、祇園会などから五百羅漢の石嶺寺、深草、山科、黄檗山、三室戸、宇治、木津、男山、羅城門、・・・という具合に有名な個所の句を余す所なく満載している良書と言えましょう。京都新聞本社近くの松栄堂での「虚子と余瓶展」で本展を開催された美しい方とお話する機会を得ましたが、この本お持ちなのでしょうか?本書はいずれ野風呂記念館に寄贈する予定です。
2015.01.25
コメント(0)
-
暦あれこれ♪
〇池上俊一監修、南條郁子訳、ジャクリーヌ・ド・ブルゴワン著の「暦の歴史」は、私たちが日常生活を円滑に過ごしていく上で切り離せない時間的なルールを知る上で、興味ある総合書です。 俳句を詠む側としては、季節を先取りする事が多いので、旧暦の方が便利に思う時もあります。航海や漁業に携わる人々には月の満ち欠けを基とする太陰暦が便利だし、種を蒔くタイミングが大事な農耕には太陽暦が不可欠となりそうです。 十進法が大勢を占める中、なぜ暦や時間は六十進法で考えられているのか、それには太陽暦だけでも太陰暦だけでも成り立たないギャップがあるように思われます。何故1年の始まりは冬でそして12カ月なのか?ひと月でも30日もあれば、31、28の日もあります。1日が24時間、1時間が60分、1分も60秒という刻みの中で生活しています。でもこの基本ルールをお互いに守らなくては1日たりとて円滑に生活できません。時折、時計の無い世界で暮らしたいと思う日も・・・。暦の理論は個々では避けますが、宇宙へ飛ばすロケットの時間調整は、ひょっとしたら四次元的な事も考慮されているのでしょうか。
2015.01.24
コメント(0)
-
先づは梅はありき♪
〇寒がりの身には、背を丸め、空中に白息を吐きながら観る二月の梅よりも、暖かくなり、光の照度も増す四月の桜の方が親しいのですが、古来、花と言えば梅を指していたのですから、その良否を検討してみたいなと思いました。先ず幹や枝ぶりから比較すると、光沢著き桜よりも盆栽的な幽玄風情の梅に軍配が上がります。桜の中には香りを放つ種も一部ありますが、梅の芳香は遠くからでも匂って来ます。花芯はどうでしょう。これは好みの問題ですが、やや粗い感じの梅よりも桜の蕊の方が、なよなよとして居て優れているように思います。しかし桜と言えば、この人を抜きにして語れない佐野藤右衛門さんに言わせれば、大衆的人気を攫う”染井吉野”よりも”山桜”こそ本物の桜と言うことから、素朴さが決め手になります。松竹梅という言葉があるように、古来、貴族は梅を愛でていましたが、御所の紫しん殿の前に桜が植えられて以来、桜に人気が集まりました。かの歌姫、鶯も梅の枝に停まります。ですから、ここんところは梅に花を持たせて、そろそろ耳にする寒梅を探し出かけませんか?
2015.01.23
コメント(0)
-
拙作「占い」♪
〇最近女性の結婚年齢は極端な20才未満か或いは30半ば以降と、年々晩婚化している傾向にあるので、10数年前に作った歌詞ほどの焦りは無いのかも知れませんが・・・。 「 占 い 」1) 占いを信じますか? 見料少々 高いけど やっぱり気になる 近頃の運勢 彼は真面目ですか 彼をゲットできますか 彼を旦那にできますか 自分じゃ分らない 手相の溝、溝2) 占いを信じますか? 今までお金に 縁がない やっぱり気になる 将来の金運 彼は金のなる木ですか 彼は出世できますか 部長夫人に なれますか あれこれ欲張っても 根も葉も無い、無い3) 占いを信じますか? チャンスに何度も 負けたけど やっぱり気になる この次の勝運 石田君を狙います 勝てる見込みありますか 後に退けない 本気です 心底祈ってる プライド捨て、捨てソラドドドミレ ドドドドドーソラレレレレレ ファミレレレードシドソ ラソミソー レミレソドラソミドーーーこんな出だしですが、テンポの速い曲で、半音ずつあげながら2番3番へとつないでいきます。
2015.01.22
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」最終章♪
〇創作落語「大坂の陣」最終章(Y男=義経)「そう言ってもみんな楽しそうに 大坂の陣に参加されているじゃーありませ んか。例え時代が古くっても参加させて下 さいよ」(マスター)「はい、分かりました。ほんなら義経さ んは大坂方という約束で、こっちの仲間に 入って貰います。いいえいな、今も聞いて の通り、こっちはもう分裂状態でっさかい に、 義経さんであろうがなかろうが、一人でも 多く仲間に入って貰て、何ですがな、今度 こそ狸親父の鼻あかしてやらんといけませ んなぁ。よろしゅう頼ンます」(石田)「もし、・・・もし、六三郎殿、我々は 皆武士で御座る。そなたの話しようは町人 のようで、軽軽しいですぞ。しかも戦の評 議で御座れば、もう少し重々しく話してい ただかねば困るで御座る」(マスター)「まこと、その通りで御座る。勘弁仕う まつる。淀君様、これは軍議で御座れば、 何事もそれがしにお任せ下さりませ」(田代)「爺がさほど申すなら、我慢しようぞ」てな具合で、波瀾に富んだ軍議が再開されました。(石田)「東方の軍容は如何ほどで御座るや?」(真田)「某が忍びに探らせた処、秀忠の率いる 部隊が未だ到着していないようで御座る」(石田)「それは好都合。幸村殿の言われる夜討 ちが最良の手だてと存ずる」(後藤)「いかにも、それが良策で御座ろう」(義経)「夜討ちとは何のことよ」(後藤)「義経公は夜討ちを御存知ないか?」(義経)「我等の時代は白昼堂々と名乗りを挙げ て、1対1で腕を競うのが常道なれば」マスター)「あのねぇ、義経はんの時代と違て、今や 鉄砲・大砲が戦の主力ですがな。時代錯誤 も甚だしいじゃありませんか」(石田)「これっ!六三郎殿、また平成の言葉を 使っておじゃる。時は慶長の御世なれば、 文語でお話しあれ」(マスター)「これは失礼仕った。どうも義経公は仲 間数には勘定出来かねまするな」(義経)「今一つこと問わん。鉄砲・大砲とは如 何なるものに候や?」(後藤)「軍議が横道に逸れては心もとのう御座 るによって、略して申せば飛び道具で御座 る」(義経)「さすれば何か、弓矢に代わって新しい 武器が発明されたと申すのじゃな?」後藤)「いかにも、十五間離れた所から敵を打ち 崩すことが出来まする」(義経)「なれば騎兵隊とは趣が違うようじゃな」(後藤)「ご納得が行けば、会議をとくと進める ことに致す。・・・夜討ちの人数じゃが・・・」 とまぁ、軍議の捗々しくないことったらありゃしません。一方、東軍は何事もスマートに運ぶようで、(福島)「西軍は毛利、島津、長曽我部の残党も 増えて、大軍になっていると聞き及ぶが、 各々方、如何致したものであろう」(藤堂)「大御所様の仰せになる通り事を運べば、 烏合の衆の西軍など問題では御座らん」(福島)「いかにも仰せの如く、大砲で天守閣を脅 かし、太閤の堀を逐一埋めて行けば、裸城 も同然。故太閤の常套手段、大がかりな土 木作業を併せて行うのが良策に相違あるま いて」(藤堂)「城方の慌てふためく様が見えるようじ ゃ、ワッハッハッハッ!」 時に家康公は若い時は信長公に義理立てされ、立派な武将であったンですが、太閤秀吉が「浪花のことは夢のまた夢」と辞世の歌を遺して亡くなってからは智謀の限りを尽くした為に、人気は陽気な太閤さんの足元にも及びませんな。血液型で言えば家康はA型、秀吉はO型の典型であったンじゃなかろうかと思います。でぇ~何で御座います。大坂方はいつまで経っても埒が行かないようで、(義経)「弓矢隊が必要とあらば、義経直属の部 隊を遣わせても苦しゅうない」(マスター)「義経はんは未だ理解できたはらへんよ うですな。アンタの時代と違て、世の中回 転が速おますンや。弓矢なンて、ぎゅーう と絞っている間に、ズダーンであの世行き ですがな。もおええ加減に時代について来 て貰わなどもならん!」(石田)「これっ!六三郎、控えぬか!」(マスター)「関西弁であろうとなかろうと、そんな ン気にしてられまへん。イライラしますが な」(石田)「静かに召されい。・・・時に義経の殿、 静御前は大層な美人だったと専らの噂で御 座るが、まことのことに候や?」(義経)「ふーむ。あれほど綺麗な女子は居らぬ わい」(石田)「色が抜けるように白かったンでしょう な?」(義経)「色が白い上に餅肌であった」(マスター)「ちょっちょっ一寸待って下さい。その 辺で何の話、しているンですか。大坂の陣 はどうなるのですか?」(後藤)「大坂の陣よりこっちの方が面白い。ねぇ 皆さんそうですな?」 もうこうなって来ると話がごちゃごちゃになってしまいます。源平なら源平、大坂の陣なら大坂の陣とどっちかに纏めなくては、にっちもさっちも行かなくなります。(後藤)「義経さん、貴方がジンギス汗だという 裏話もあるンですが、其処ン処はどっちで すか?」(義経)「はぁーて、そんな話になっていたンで すか。とんと身に覚えありませんが」(後藤)「なら、あの話は嘘ですね?」(義経)「嘘です。きっと天狗の仕業でしょう」 (後藤)「何でそんなに自信持って言われるンで すか?」(義経)「元はと言えば私ゃ~牛若丸、一緒に暮 らした天狗のしそうな事ぐらい分かります。」 この落語は20世紀の終焉近くに庶民的な語り口で、落語を我らに近づけた桂 枝雀師匠に語って貰ったらなとの思いで創作した現代落語です。
2015.01.21
コメント(2)
-
創作落語「大坂の陣」その5♪
〇創作落語「大坂の陣」その5(石田)「前回の戦では、淀の御方様が差しで口を 挟まれたゆえ、全軍を率いるそれがしも苦労 致した。今回は幸村、又兵衛両氏の戦法を第 一と致したい。各々方、異存は御座りますま いな」(後藤)「無論もろ手を挙げて賛成仕ります」(真田)「大坂城から秀頼様が一歩もお出ましなさ らなかったのが敗因で御座った。それにな、 今度は夜討ちを掛けたいと思うが如何で御座 ろう」(田代=淀)「出て行くは勝手じゃが、秀頼は放し ませぬぞ」(後藤)「これ淀君、また口をお出しになる。女子 供は評議には関わりの無いこと。お控え召さ れ」(田代=淀)「今度は必ず勝てると申すのじゃな。 秀頼を死なせることは無いと申すのじゃな?」(後藤)「じゃから男共にお任せあれと申して居る」(田代=淀)「随分横柄な態度じゃな。身分をわき まえよ」(後藤)「止ーめた。こんな評議は御免被る。いず れも様、退座致すで御座る」 一番目に怒ったのは後藤又兵衛。歴史は繰り返すとは本当の話ですな。(Y男=義経)「あいや待たれい!後藤殿」急に口を開いたのは、困りきっていたジャガー君です。(後藤)「待てとお止めなされしは、身共がことに 御座りまするか」(Y男=義経)「その台詞は白井権八では御座らぬ か。ちょっと不釣り合いで御座る」(後藤)「いや、失礼申した。で、そなたはどなた で御座る」(Y男=義経)「余は九郎判官義経なるぞ」(マスター)「ちょっと待って下さいよ。何でこんな処 に義経が出て来るンですか?変ですよ変!」 ここで東軍の連中が、どっと笑います。
2015.01.20
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」その4♪
〇創作落語「大坂の陣」その4(酒井)「片桐殿は、いよいよ間者の立場がばれ て、江戸城まで逃げ込まれたそうではない か」(藤堂)「ちょいと待て、お主らは東方の者か、 ここで席替えを提案する。マスター、一体 誰と誰が大坂方で、誰が東軍側か、はっき りさせてくれ」(マスター)「分かりました。挙手願います。田代淀 子さんを中心として、大坂方の方、手を挙 げて下さい。・・・あぁ判りました。真田 さんは文字通り、真田幸村で、れっきとし た大坂方ですなぁ。さっき石田と言うて居 られた石田さん、アンタは石田三成さんで すか、ハハ~なるほど。で、そこで手を挙 げてなさるアンタ、そうそう貴方ですが、 どちらさんですか?」(後藤)「後藤又兵衛で御座る」(マスター)「なるほどそれで後藤さんて誰か最前言 ってられたンですな。もう大坂方は居られ ませんか?・・・居られんようやな。では 大坂方は淀君に、真田、石田、後藤さん、 これだけですか?」(福島)「オィ マスターあんた最前六三郎とか 言っていたみたいだが・・・」(マスター)「あぁそうか、私は淀君の爺やだから大 坂方か」(藤堂)「東京もん、おや、江戸もん、これもお かしいな。東軍は残り全部ということにな る訳だよな」(酒井)「藤堂さんとやら、アンタが仕切ってど うするンや。こっちにはもっと偉い人が居 て下さるから、あまり出しゃばらん方がい いよ」(藤堂)「その偉い人ちゅうンはどなたですか?」(加藤)「加藤清正じゃ」(マスター)「へぇー、あの裏切り者の虎之助がアン タか、太閤殿下になり代わり、成敗してや る」(石田)「まぁーまぁー六三郎はん、慌てなさん な。これから歴史の塗り替えじゃ。皆でど うしたら東軍に勝てるか協議しよやないか」(後藤)「身共も賛成で御座る。のう幸村殿」(真田)「いや、まったく持って同感で御座る。 淀君様、それで宜しゅう御座いますな?」(田代)「良きに計ってくりゃれ。今度はわらわ も嘴入れる積もりは無い」 えらいことになって来ました。ちょっと東軍のメンバーを整理して申し上げますと、加藤清正、藤堂に、福島正則、それにもう一人、三河の英雄酒井家次とその家来、これまた錚々たる人が、たまたま集まったことになります。そこへ先程の二人が戻って来ました。(G女=お江)「忘れ物したの。ネッカチーフ ありませんでしたぁ?」(マスター)「今、取り込み中です。何でも好きな もん持って帰りなさい」(G女=お江)「あらっ!お姉様じゃないの、 私よ私」(田代=淀)「あぁ、お江かえ。なんで私ら姉 妹が西と東に別れて争わないかんの。女 は不幸やわ」(G女=お江)「姉さん、大坂城落城の目に遇 われて、お気の毒でしたねぇ。私みたい に上手に世渡りせんといかんよ!」(田代=淀)「放っといて、もっと自分に正直 に生きなあかへんやんか」(G女=お江)「姉さん、完全に関西弁になっ てるわよ」(田代=淀)「・・・心得ました。そなたと私 は敵味方、とっとと片隅に引っ込んでお りゃれ」(G女=お江)「いけずな人。フン!」 皆が皆、昔に戻れる訳ではないのです。ジャガーの兄さんは今度はそのままなンです。・・・これ困りますよ。東軍が一人増えたので、彼が西に就かないと不公平になります。それがどうしてもそうは行かないので西軍に分が悪くなりました。折角協議しなおして歴史を覆す意気込みでしたンですけど、大変ですわな。
2015.01.19
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」その3♪
〇創作落語「大坂の陣」その3(藤堂)「マスターいつものブランデー頼む」(マスター)「いらっしゃい。今日はお一人ですか? この間のお連れさん、えっと」(藤堂)「あぁ、真田君のことか」(マスター)「そうそう真田さんでした。苦味走った いい男でしたね」(藤堂)「そりゃーそうかも知れんが、俺はどう なんだ?」(マスター)「いえー、藤堂さんも何しろお歳より貫 禄があって、その辺の女が黙ってませんや ろ?」(藤堂)「そうだといいンだが、未だ独身て言う のは推して知るべしちゅう処かな?」(マスター)「大丈夫、大丈夫、何せ藤堂さんは仕事 の手際が良いと聞いていますから、別嬪さ んゲットされるに決まってます」(藤堂)「まぁそうして置くとして、俺が店に入 る前、何やワーワーと騒いでいたみたいだ けど?」(マスター)「えっ、そんなこと無いですよ、ねぇー」(Y男)「ええ、僕達は静かに飲んでいましたけ ど?」(藤堂)「そうですか、まるで喧嘩していたよう に聞こえたけど」(マスター)「この辺は最近カラオケばかり歌う客が 増えて来たので、うるさかったン違います か」 という訳で、この場は丸く収まりました。先程えらい剣幕で言い争っていた恋人同志も場所を変えるンですか、勘定払って出て行きました。ここから暫くは藤堂君とマスターが宝くじの話なンてぇくだらん話をしている処へ、グラマーな美人連れで真田君がやって参りました。(真田)「ヤぁー今晩は」(藤堂)「あれっ、真田、その人紹介しろよ」(真田)「君は知らなかったのか、一橋商事の受 付嬢:田代さん」(田代)「初めまして、田代です」(マスター)「真田さん、美人のお客さん連れて来て いただいたンで、ちょっとだけ割引させて 貰います」(真田)「マスター、そんなら今夜はタダか?」(マスター)「タダ言う訳には行きませんけど、割引 させて貰います。今後もどんどん連れて来 て下さい」(マスター)「このお嬢さん、何とおっしゃるンです か?真田さん」(真田)「田代さんって紹介したじゃーありませ んか」(マスター)「いえ、お名前の方です」(田代)「珍しい名なンです。淀子って父がつけ たンですよ」(マスター)「淀? 淀って淀君の淀ですか?」(田代)「ええ、変な名前でしょう、私困ってる の」(マスター)「淀君さまに御座りまするか、お懐かし ゅう御座います」(田代)「えっ」(マスター)「爺の六三郎に御座りまする」(藤堂)「おい、マスター急に何を言ってるン だ」(田代)「六三郎、そなたは大坂冬の陣の前に、 わらわを残して死んでしまったではないか」ねぇー、ここから四百年前に逆上がるンで御座います(マスター)「はい、無念で御座いました。もっと長 生きしたかったので御座いますが、運命に は逆らえぬものでして」(藤堂)「ウン?そちらは大坂方か?片桐は如何 致した。最近とんと城内の様子を知らせて 寄越さんが・・・」(真田)「オイ、藤堂、お前何言ってるンだ。そ れに田代さんも、マスターもさっぱり訳の 解らないことばかり言って・・・」(藤堂)「ムムー!貴様は音に聞こえた真田幸村 に似ているぞ。隠すな隠すな」(真田)「俺は何も隠しちゃーいないよ、マスタ ー助けてよ、皆変なンだよ」こうなってしまっては只一人、昔に戻らない真田君は大変です。捨てる神あれば拾う神ありで、運よく別のグループが入って来ましたンで、ちょっと中休みってぇ所です。しかし時は悪戯もんで、新しく入って来た客五人も、このけったいな大坂の陣に組み込まれてしまいます。
2015.01.18
コメント(0)
-
創作落語「大坂の陣」その2♪
創作落語「大坂の陣」その2 街にぁ色とりどりのネオンの花が咲き、宵闇迫った頃合の時間です。皆さんも昔を思い出して頂ければ、あの独身時代の逢引ーーーいや~済みません。今じゃ何と言うンですか、お茶するちゅーンですかね。男と女が時間を待ち合わせて、楽しいひと時を持つ訳で御座います。仕事を早めに切り上げたままの背広姿で、有名なビルの一角で彼女を待って居ります。其処へスカート翻し、ヒールの音も軽やかに彼女がやって来るンですな。まあ、こんな場合、女性は美人にしておかないと噺は盛り上がりません。へちゃむくれのぶさーいくな女でしたら、お客さんも耳をそば立てて聞く気にもなりませんから、この場合、超美人にしておかなくちゃならないンで御座います。(G女)「待った~?」(Y男)「いや、今来た処だよ」近頃は何だかんだ云っても女性上位時代です。この男、小一時間も待っていた癖に見栄を張っているンで御座います。(Y男)「今日は何にしようか?」(G女)「私は何でも・・・貴方と同じものでいい わ」 あのねぇ、こんなん言ってくれるのは最初の内だけですよ。世帯持って共働きしてご覧なさい。炊事、洗濯、掃除、買い物、諸々の家事は折半になりますよ。嫁はんが料理の番で、その辺のスーパーで買って来た出来合いものを出しよるンで、文句の一つでも言おうもンなら、「あ~ら、何か不服なの?人が忙しい中、折角買って来たのに、文句を言うの?」てな具合で、そこからチャンチャンバラバラの大喧嘩が始まるンで御座います。で、二人仲良く、ちょっと高級なレストラン、まあフランス料理でしょうか、優雅に夕食を楽しむンですな。また、話が横道に逸れてしまいますが、男っちゅう奴も何で御座いますね?一旦釣り上げた魚には餌を与えないって言うンですか、こんな高級なフランス料理なンてーものは世帯を持った途端、二度と連れて行かないものなンですね。会社のOLには鼻の下伸ばして奢ってやる癖に、嫁さんには勿体無いちゅうンですか、金をかけたがりませんなぁ。 きっと将来を嘱望された若手デザイン家の考えた処なンでしょう。そりゃームードのある、美しい、ビューティフルな場所なンですよ。天井には間接照明のコバルトブルーが綺麗な光を放っているし、ボトルの収納棚は真っ黒な上等な奴で、高級なボトルがずらり並んでいます。カウンターは真っ白で椅子も薔薇色のビロードか何かで、店内高級感に充ち溢れている処なンで御座います。(Y男)「今度いつ逢えるかな?」今逢ったばかりなのにこの男は、この女他人に取られては大変とばかり、次のデートの都合を聞きます。(G女)「明後日の日曜、空いているわ」(Y男)「よし! 僕のジャガーで湘南海岸へ行こ う」 私なんざー、車を持つには持っているンですが、ジャガーなンて高級車じゃありません。辛うじて動くという国産車なンですが、この男、ジャガーを武器にしているようです。不思議ですな。女ってぇのは高級車に弱いンですな。いっぱしの女にもなってないそこいらのギャルでも偉そうに、ジャガージャガーなンて申して居ります。・・・じゃが~芋みたいな顔して・・・・。(G女)「うわ~ ス テ キ !一度ジャガーに 乗って見たかったの」もう女はうっとりしています。場所が湘南海岸と聞いただけでも、ドラマのヒロインになったかのように悦に入って居ります。(Y男)「晩は中華街に寄って、レインボーブリッ ジから夜の海を眺めようか」 男はぐいぐい自分のペースに女を引き込みます。私なンざーこんな気の効いたこと言えませんでしたンで、今の嫁はんがええとこなンですよ。高倉健みたいに女の痺れるような台詞がポンポンと湧いて来てゐりゃーまともな美人の嫁はんをゲットできたンでしょうが、・・・もう後の祭り・・・・。(Y男)「昼は映画でいいかい?」(G女)「嬉しいわ、貴方とロマンチックな映画が 観れるなンて・・・。」(Y男)「今さ、タイタニックが凄い人気らしいじ ゃないか、あれを観ようか」(G女)「ええ、私も一度観たかったの」こんな調子の会話だけでしたら、もう落語じゃ御座いません。そろそろ落語へと進みまして皆さんを退屈させないように致します。初めに申しましたように、この盛り上がった処へ、前世の記憶が二人とも急に甦るンで御座います。(G女)「ちょうどあの時、私は幼い皇子ミコを抱い ていたわ」(Y男)「えっ、今何て言ったの?」(G女)「だから私は群がる源氏から逃れるように、 皇子を抱いて舟に乗ったのよ」(Y男)「皇子って誰のこと?」(G女)「私一度死んでしまったから、皇子の名前 は忘れたわ。・・・あぁ、思い出した。安徳 天皇よ、そうよ源氏への恨みは忘れはしない。 あんなに平和な平家の世だったのに・・・。」(Y男)「源氏やら平家って、一体何の話なンだ」(G女)「あらっ!貴方は義経! 我ら平家の者を 海へ沈めた憎い仇!」(Y男)「ちょっと待ってよ!今、平成の時代だよ。 平家源氏は鎌倉時代の話だよ・・・。」(G女)「そんなの関係無いわ。貴方は私達の仇、 九郎判官義経公ね。皆になり代わって貴方に 一矢報いてやる!マスター、其処のナイフ貸 して頂戴!」(マスター)「お嬢さん、此処はBAR、ダン・ノーラ ですよ。壇ノ浦ではありませんよ」(G女)「じゃかましい!取って呉れないンなら、 カウンターに上がるまでよ」(マスター)「えらいことになってしまった。お客さん、 早くこのけったいな人連れ出して下さい」(Y男)「そう言うお前は熊谷直実。余が命令じゃ。 この女を連れ出し、幼き皇子の所在を確かめ て参れ!」(マスター)「貴方まで何をおっしゃるンですか、困っ たなぁ、どうしよう」(G女)「まことそなたは熊谷ぞ。我らが勇士惟盛 殿を討ち取った男ぞな。もう許しゃせぬ。わ が身はどうなろうと、二人とも生かして置か ぬぞえ~!」(マスター)「一体、何が何やら、さっぱり訳が解らん。 ---まぁ、強いて言えば、近藤勇君は知っ ているけどなぁ」(Y男)「誰じゃい、近藤勇って」(G女)「誰なのよぅ、近藤って」(マスター)「へぇ~、あんたら知りませんか、あの有 名な近藤勇を。我々勤皇志士を目の仇にした 奴ですがな」(Y男、G女)「そんなン、知らん」(マスター)「そらそうですな。あんたらは源平合戦時 代のこと言うてなさるし、こっちはもっと時 代が下がって江戸幕府崩壊の頃ですからな」 ワーワ、ワーワ言うている中へ、別の客が入ってきました。不思議と言うかひょんなことと言うか、今までの会話が急に終わってしまいました。
2015.01.17
コメント(2)
-
創作落語「大坂の陣」その1”口上”♪
創作落語「大坂の陣」<口上> 誠にこの世は不思議で御座いますね。いつ如何なる理由があって、我々はこの世に生まれて来たンで御座いましょう。気がついて見れば、今の自分がある訳ですよネ。理屈じゃ簡単で、おとっつぁんとおかんが仲良くなってなにしたから、我々がこの世に生まれたことには間違いがありませんが、このことは此処にお越しになっている皆様がよ~く御存知の筈で御座いますが・・・。 さて、世間で言われるように、死んでもあの世があって永遠に魂が消えないンでしたら、あの世はこの世以上に人だらけで、交通事故も受験地獄ももっと凄いンじゃありませんでしょうか?死人だらけでしたら、幾ら広いあの世も、人また人で麻痺してしまうンじゃなかろうかと愚考するので御座います。 それに何で御座います。霊を呼び寄せる呪術師が現に何人か居られるようですが、もしあの方達が本当に亡くなった人の霊を呼び寄せることができるンでしたら、歴史なンぞ、正確に復元解明できる訳でして、歴史学者なンてぇ仕事は要らなくなっちゃいますし、リストラされてしまわれるハメになります。 (呪術師)「エエイ!ハンダラハミティソアカ、ナ ンジャラカンジャラ、ハッ! う~む」(霊)「熱い、熱い・・・・」(聞き手)「何方さまで御座いますか?」(霊)「信長じゃ」(聞き手)「あぁ、本能寺で光秀に討ち滅ぼされた 桃山時代の信長公さんですかい?」(霊)「いかにも、それがしは信長じゃ、首を渡す 訳にもゆかず、寺に火を点けさせたが、熱い のなんの。こんなことなら、火を点けさせる んじゃ無かったわい」(聞き手)「ちょっとお尋ねしても、よーござんす かい?」(霊)「何なりと聞くが良い」(聞き手)「中国の毛利に勝てる目前で、油断でも されたンでしょうか?」(霊)「まっこと、あれは一生の不覚であった」(聞き手)「それはお気の毒でしたネ。で何ですか い。貴方の後継ぎは太閤秀吉と読んで居られ ましたか?」(霊)「そのことじゃ、わしは柴田勝家の方が絶対 有利と思っとたンじゃが、あいつは昔から策 がのろい。運も秀吉に味方したンであろうよ」てな訳で、義経がジンギス汗かどうかも直ぐ解明できる筈なンで御座います。そこで、このお噺は、輪廻転生という考え方に立って、死んだ人の魂が別の人に生まれ変わってゆく立場にたってですな、但し、生前の記憶が完全に消しこみされない侭で新たに生まれ変わったら、一体どのようになるかというお噺なンで御座います。仮に我々が輪廻現象というンですか、転生っていうンですか、何度も生まれ変わるとして、過去の記憶装置を着けたまま、生まれ変わった場合を想定した噺なンで御座います。 そこン処をよ~~く覚えて貰いませんとこの噺はぶち壊しになっちゃいますンで、まあ、宜しくお願い致します。そしてその記憶が、或る時点で急に甦るって趣向で御座います。
2015.01.16
コメント(0)
-
虚子・草城らの葉書・短冊ぞくぞく♪
〇京都の書棚に残してあった葉書保存帖には、父の青年時代からの交友との葉書がきちんと保存されていました。全部で9冊。一番多いのは父すばるが尊敬してやまなかった鈴鹿野風呂先師。続いて学生時代に支えて下さった水野白川男爵。路葉子、十七星、余瓶、如是、一水など錚々たるメンバーですが、高浜虚子5通、日野草城、星野立子など第一線の俳人からも頂戴しています。また縦40×横30×厚み10センチほどの短冊保存帖1冊、これより幅の少ない短冊帖が2冊あって、その中には上記の野風呂、夫人の静子、余瓶、一水、十七星、白水、王城、素十、桃十、素逝の短冊に混じって、いはほ、日野草城、水原秋櫻子、山口誓子各1枚に、高浜虚子の短冊も沢山頂戴していました。 白牡丹といふといへども紅ほのか 虚子 船下りて桟橋ゆるゝ秋の雨 虚子 さて”すばる”の短冊より一句 生涯の山河こゝろにかるた読む すばる人との交友を大切に温めていた父だから、こうして遺されてあるのでしょう。
2015.01.15
コメント(2)
-
跳力を鍛えた忍術♪
〇時代劇では忍者が後ろ飛びに塀に乗るシーンを観ることがありますが、一旦塀の上から飛び降りる場面を撮影し、そのフィルムを逆順につなぎ合せば、そのシーンになると思いますが、忍者は本当にそれだけの高さを飛ぶことが出来たのでしょうか、若干無理としても、胡坐を組んだ姿勢のまま、天井に張り付いたり、歩いてくる人の頭上を跳び越したりしたのは資料から察すれば、可能だったようです。彼らは成長の速い麻や竹を毎日跳び越えてジャンプ力をつけたとされますが、実際には無理のようです。 実は秘密の鍛え方があって、地面を胴回りほどに掘り、その穴から地上に跳び出る訓練を日々重ねたようです。足首や膝の屈伸に頼らないで、身につけるもの、例えば鎖帷子カタビラなどをつけて足指の力を鍛えたのだとか。高い屋根や塀から飛び降りる時は、恐怖心があると身体のバランスが崩れ危険なので、目線を低く、しゃがんだ格好で飛び降り、猫のように両手・両足を同時に着地させて衝撃を分散させたようです。もっと高いところなら、傘や羽織・上着をパラシュートのように使って恐怖心を克服したとも記述されています。(参考図書・黒井宏光著「忍術教本」)
2015.01.14
コメント(0)
-
謙虚さがいちばん♪
〇京都は永い間、日本の都として政治・文化の中心にありました。明治維新後皇居が東京に移されると聞かされた都の人々の落胆ぶりは想像を絶するほどでした。そこで賑やかさを取り戻そうといろんなイベントが催されました。京都大博覧会、平安神宮を祀り、その時代祭の開催等がそれです。 京都と言えば古色豊かで、いかにも雅びの総本家のように称されますが、只単純に古い伝統だけを守り通して来ただけなのではありません。一見排他的に見える京都人の気質はプライドと謙虚さを巧く配合することに長けていて、新しい流行や文化を一旦謙虚に受け入れながら、その研ぎ澄まされた美的感覚で、都のあった処として相応しいものかどうかをプライドという秤(ハカリ)にかけながら良いもの選別し、その良いものを京都色にアレンジし都ブレンドとしながら残して来たのだと思います。京都人に謙虚さが無かったら、単に旧いものだけを守る”デッド・タウン”と化した京都でしかあり得なかったと思われます。京都は謙虚さを以って、新しいもの、新しい血を受け入れ、常に住みよい、心癒される町として悠久の歴史を伝えて来ているのだと思います。 わたし達もできるだけ謙虚な姿勢を忘れないで、ここに集まる仲間の斬新的なものの考え方や感覚の優れた部分、自分の琴線に合う部分を吸収し、更に自分という”原石”を磨いて参りましょう。
2015.01.13
コメント(0)
-
飛翔したいな♪
〇本日は成人の日、すでに成人式を終えた地地域も一部あるようです。何歳になっても大空へ飛び立ちたいという願望が薄れないし、成長・飛躍という意味合いの飛翔という字に憧れるものです。 ところで、わたし達は「とんでもない」と言う言葉を時々使いますが、一説には、獅子文六の「自由学校」に数箇所ある「とんでもハップン」のフレーズが流行語となり、始まったとされています。しかし乍らこのトンデモナイは良く調べてみると、近松の「用明天皇職人鑑」に、「はて風をつかまへるやうな、とでもない問ひやうかな」とあるように、昨今の言葉でも無さそうです。飛んでも及ばないの意を込めて飛んでもないと書きがちですが、それこそトンデモナイ当て字になります。トデモナイ(途でもない)を強めたもので、トはトカク・トモカク・トコウなどと言うときと同じ用法とも思われます。(参考図書:鈴木棠三著「日常語語源辞典」その他)
2015.01.12
コメント(0)
-
ちょっと怖い漢字のハナシ♪
〇森鴎外の「山椒太夫」は原書を読まなくてもおとぎ話として周知の通りです。 藤堂明保著「女へんの文字」にその話から漢字へと展開されていて、<古代の中国やエジプトに於いては、とても山椒太夫の比ではなく、奴隷は家畜以下の扱いで、逃亡を防ぐために、目を針で潰して全盲にするか、ひたいに大きな入墨を施した様です。人民の民という字は、その状態の目を表現していて、民=メクラ奴隷の意味。睡眠の眠は目の見えない状態即ち眠っていることを指すのだそうです。 時代が下って宋や明の時代でも罪人の額には真っ赤に焼いた銅印を押し当て、どこに逃げても一見して判るようにしていましたが、水滸伝に登場する豪傑の多くは、この烙印を押された連中だとか。 女奴隷も同様に針で目を突いたり入墨していた証が、辛(ハリを意味します)+女から出来た妾という字に、接合の接もその派生と言えるようです。
2015.01.11
コメント(2)
-
拙作「勝負」♪
〇近々当方では市長選挙が行われます。それに因むか否か、人生劇場を唄われた村田英夫さんの唱法をイメージして平成11年ごろ作詞、作曲しました。 「勝 負」1)夢に敗れて 野に下る 苦節十年 立ち上がる 男の錦は こころざし 人生 人生 勝負だよ2)惚れた女は 余所に嫁ユく 受けし傷心 訓として 男の錦は 思い遣り 人生 人生 勝負だよ3)心豊かに 日々処せば 期せず人の 集い来る 男の錦は 侠気魂ダマ 人生 人生 勝負だよミーラシ ドードシラ シーシラファ ミーーーミーシミ レーミファミ ミーミドシ ラーーーレーレレミ ファミファラファ レーレミファ ミーーーミファミ3連ラーー レミファ3連ミーードシドミー ドシラーーーーーこれでいいのかな?
2015.01.10
コメント(0)
-
新春に借出した5冊♪
〇このブログを永く続けるには、その内容について自分自身飽きの来ないようにすることが、読者目線だけでなく、自分を高めることにも繋がり、一挙両得と言えましょう。1)「忍術教本」黒井宏光著(新人物往来社) 第1部は<忍術の不思議>で、分身の術や 変装術、占術、歩法、走法など30項目。 2部は源流、3部は忍者伝説人物録まで。2)「話のおもしろい人、ヘタな人」立川談 四楼著(PHP) お蔭様で私は瞬時に初対面の人から様々な 情報を聞き出せます。昨日の資料館での当 番でも、大阪市庁の人たちを浮き彫りに、 生家が明石の近大生が中世の油のレポート を出す参考に立ち寄ったことなど。彼には 資料館から適宜、コピーや講演の資料を。3)「暦の歴史」ブルゴワン著(創元社) 陽暦と陰暦の差異は少々知ってはいますが 地球上での世界の暦の歴史などを目で追い たくて・・・。4)「妻の口一度貼りたいガムテープ」綾小 路きみまろ著(PHP) つい先日、なかなか芽の出なかった半生の 特番テレビがありました。一度底辺を知っ た人たちから多くが学べると。5)「民話で見直す日本人の心」鄭友治著 (ごま書房) 最近のテレビでは日本人の匠のワザや日本 人の気遣い、優しさを世界の人が評価して いることを特集しています。例のオ・モ・ テ・ナ・シですね。今回は若干変化球で脳の老化予防に?
2015.01.09
コメント(0)
-
手製の切抜き本♪
〇〇昭和十六年四月一日から五月二十七日まで 朝日新聞に連載された柳田國男作「こども風 土記」の切抜きノート、父手製の本が物置か ら見つかりました。 無地のノートに、毎日その切抜きを貼り付け もので、表紙の図柄は全身赤色の小悪魔たち がきのこの椅子に腰かけ、しゃぼん玉を膨ら ませています。 各ページには、絵筆によるカット絵、例えば 黒駒、土の鳩笛、土鈴、こけし人形、でんで ん太鼓などが今も色褪せずにノートの欄外 に貼り付けてあります。 また二つの新聞小説、川端康成の「古都」と 水上勉の「桜守」をそれぞれ切抜きとして まとめ、 <新聞小説は大てい単行本になりますが、挿 絵をすべて残すには新聞を切り抜いて保存す るほかありません。> と添え書きしています。本当にマメな人物で した。
2015.01.08
コメント(4)
-
空欄を埋める問題♪
〇清水義範さんの「日本語がもっと面白くなるパズルの本」に良い問題がありました。<紋切り型フレーズの穴埋め問題> 次は新聞記事やテレビのニュースでお馴染みの紋切り型フレーズである。空欄を埋めよ。1)犯人は朝食を〇〇〇と平らげ、〇〇〇た様 子も見せず、〇〇に取調べに応じている。2)夏休み〇〇の日曜とあって、湘南海岸には 〇〇〇家族連が繰り出し、〇〇〇〇〇〇〇〇 ほどの混雑でした。3)京都の葵祭が〇〇〇〇〇〇行なわれ、優雅 な〇〇〇〇に見物客の〇〇が漏れていました。4)乗鞍岳では、〇〇〇〇〇秋の訪れを告げる ナナカマドの紅葉が見頃となり・・・・・。さぁ一番ふさわしい言葉を当て嵌めて下さい。
2015.01.07
コメント(2)
-
年賀状に寄せて♪
〇編集責任者になって以来、秋から年末にかけては、結社の大祭や俳句連盟の吟行大会や小冊子作成、新年号の準備・校了、2月号の原稿持出しなどに加えて年賀状が毎年増え続け、私は印刷業者に頼む主義でなく、下手な毛筆ながら表も宛名も皆手書きを維持していますので大変多忙です。いつも思う事ですが、それほど親しくない人との賀状だけの縁。それを絶縁する勇気が無くて、とどの詰りは対応に大わらわ。どなたの句だったか もどかしや名なし賀状の友探しこれは心の中でもどかしいと何度も叫んでいるからで、詠嘆を上5に持ってこられた。律義な詠者は返信を欠かすような人物ではなく、是が非でも名無しの権兵衛さんの解明に困り果てておられる。平常時の葉書なら内容で誰だかすぐ判明しますが、集中的な年賀状は・・・。
2015.01.06
コメント(0)
-
昨年12月拙句の備忘録♪
〇去年12月中に詠んだ拙句の記録を忘れていました。昨年の句会納めは28日の吟行、年明け早々の昨日、本部での初句会でした。 白鳥やボリショイバレエ特等席 白鳥や京のへそ石太子堂◎プリマの座あの白鳥が狙ふらし 木枯しや末社の絵馬の鳴り止まず 式内の兵主神社や蔦紅葉 親日の鴨群れ来キタる兵主池◎冬虹や丁度半ばの砂時計〇京野菜わけて人参金時派(注)わけて=とりわけ△小蕪や妻は手品師一夜漬〇顔見世や女形オヤマいささか長躯なり〇停止線食み出す車年の暮◎断捨離の一歩が踏めず花八ツ手他にもありましたが・・・。木曜と金曜にも句会が控えております。今年は句作に気合・気迫を籠めて詠んで参りたい所存に御座候。
2015.01.05
コメント(2)
-
百八つの煩悩って?
〇皆さんの記憶に歳末の印象がが消え去らない内に、この話題を。寺ごとに百八つの鐘を鳴らせて新年を迎える風習は何と奈良時代から始まっていた様で、江戸期に増えたのは平和な時代になった故。第二次世界大戦の折、供出された為、一時は釣鐘も激減していましたが、今は和風総本家という番組でも取上げるように潤沢化。 百八つという数には諸説がありますが、仏教思想では、人間が悩み苦しむのは目、耳、鼻、舌、身、意の六根が原因であり、六根は良い、普通、悪い、楽しい、苦しい、何でもないの六通りの感覚。これで三十六の煩悩になりますが、それぞれ過去、現在、未来の三つがあるので合計百八つになるという次第です。日本古来の”霊振り”信仰が加味されて、鐘衝きのゴ~ンという響きで悪霊を追い出し、善霊の生命力を蘇えらせるのかも。
2015.01.04
コメント(2)
-
母の婚荷目録♪
〇正月を目前にして室内や物置の書物など整理していたら、「捨てられない手紙箱」があって、中には母方祖父母、叔父、叔母、父方の祖父母、姉妹や俳句にからむ方々の手紙、大阪市助役になる前の祖父の「中央卸売市場について」という論文や甥や姪、わが家の子たちの幼い手紙や絵、作品などに交じって、母結婚時の荷目録が出てきました。 紅白の水引きで綴じられた和紙の目録は母方の祖父の筆で父方の祖父宛になって居て、1.総桐羽織箪笥 一棹1.総桐衣装箪笥 一棹1.総桐手許箪笥 一棹1.総桐長持 一棹1.人形 三個1.帛紗箱 一個1.鏡台 一揃1.本箱机 一組1.火鉢 一対 以上右幾久敷御受納相成度候也昭和十四年一月吉日となっています。他にも婚荷は多々あったのですが、長持と鏡台、以外の箪笥などは今も残っています。婚前の荷のお披露目の時だけに婚荷にかけた大袱紗は可なり大きなもので横幅は1メートルを越える錦繍でどっしりと重く、この生地で日本人形が何体も造れそうな立派なものです。花嫁衣裳も当時の桐箪笥に保存してあります。
2015.01.03
コメント(2)
-
雑煮というのは何故?
〇おめでたい正月の正式料理を指して、何故雑煮などと言うのでしょうか?樋口清之監修の「雑学おもしろ歳時記」によれば、現在では正月三ガ日の食べ物とされていますが、もともとは大晦日に歳神様に供えた餅や食べ物を一つの鍋に混ぜて入れて煮たものを元日にみんなで分配して食べたから雑煮という次第。正月料理だから年男、つまり一家の主(男)が作るのが正式なやり方。丸餅か角餅かの分岐点は、富山県では富山と高岡の間、滋賀では彦根と近江八幡の間、三重県では四日市と松坂の間あたりで分れるようです。西日本は年神さまの新しい生命力(トシダマ)を入れて食べるから丸い形、東日本ではもともと戦に持っていく携行食だったので、武家作法の名残として角餅なのだそうです。
2015.01.02
コメント(2)
-
藤原定家の長所・短所♪
〇〇明けまして おめでとう御座います。〇正月と言えば、挙ってカルタ遊びなどに興じますね?小倉百人一首は小学高学年になると一部暗記させられるのではないでしょうか。あの百首を選んだのが藤原定家、この系統を継いでおられるのが冷泉家。 97番目の和歌来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに 焼くや藻塩の身もこがれつつ一一六二~一二四二、和歌の大先生・俊成卿の子で、母は、美福門院の女房・伯耆という人。<この卿若かりし時、文治元年、殿上にて源雅行と争論に及び、燭を以て雅行の頬を打たれ、勅勘を受けらる。>父俊成卿深く憂い、あしたづは雲居に迷ふ年暮れて 霞をさへや隔て果つべきと詠まれたのを帝が気の毒に思われ、あしたづは雲居をさして帰るなり 今日大空の晴るる気色にとご返歌遊ばれ、後日許されました。後鳥羽院は彼の才能を愛されましたが、やや高慢な性格もあって疎遠になられました。後鳥羽院が武家政治に嫌気さされ、謀反を起こされましたが、疎遠だったことが奏功。しかし矢張り後鳥羽院との蜜月を懐かしみ、百人一首には水無瀬から山崎辺りの景色が織込まれていると解する学者も・・・。
2015.01.01
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1