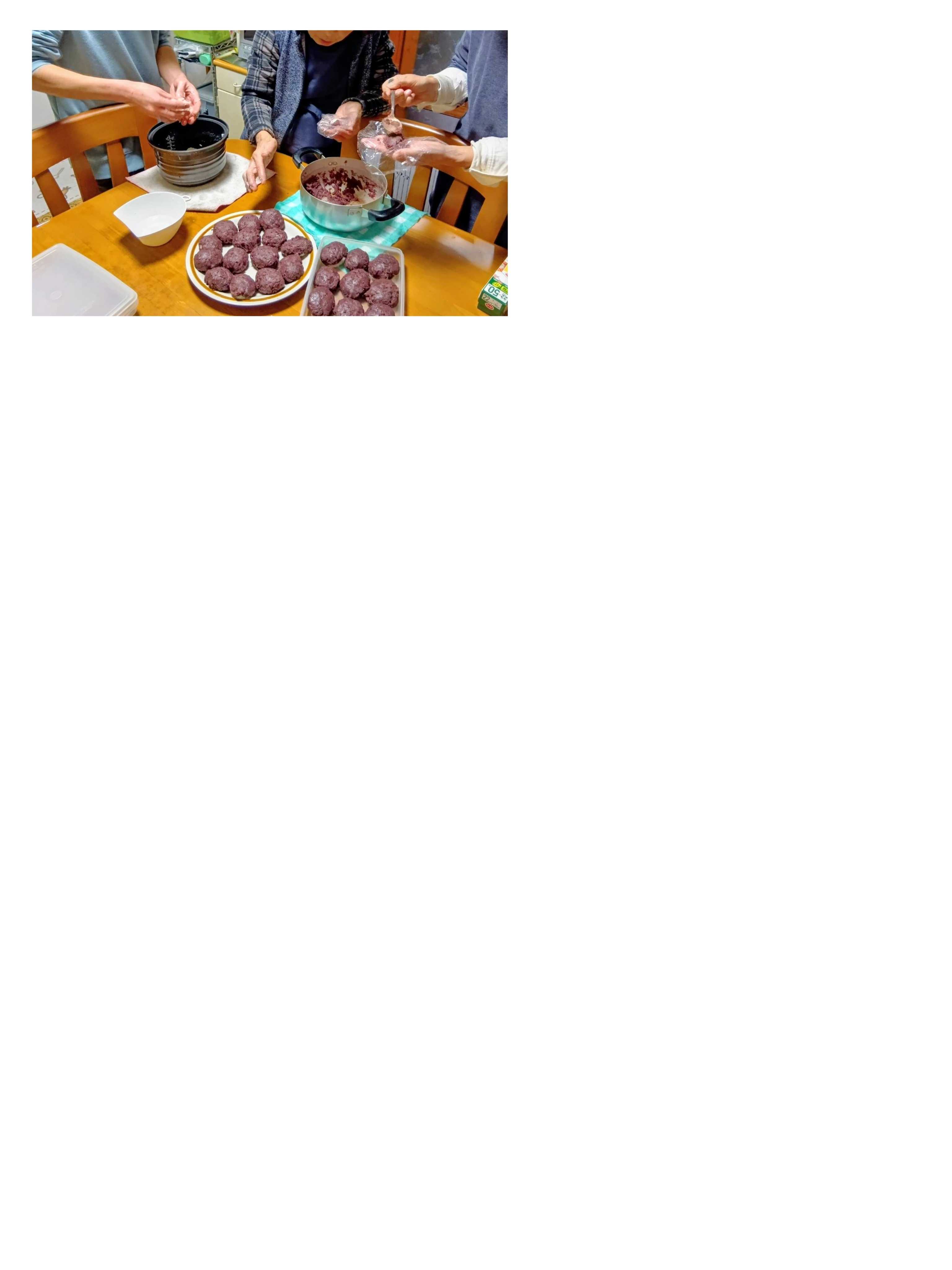2017年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
一姫二若三老人♪
○清水義範さんの「日本語がもっと面白くなるパズルの本」から拾ってみました。なお、文章は一部わたし風に変えています。 一富士二鷹三茄子は初夢のベストスリーですが、以下の「一~二~」は何に関してのベスト(ワースト)スリーでしょうか? 1)一金二押三男 2)一に運、二に腰、三拍子 3)一楽二萩三唐津 4)一に調子、二に振り、三男 5)一姫二若三老人 こたえ) 1)女性を口説くいて成功する秘訣。 2)相場師にとって大切なもの。二の腰=粘り、三拍子 =売買のタイミング。 3)これはほぼ常識ですね。焼き物の窯元の序列。 4)歌舞伎役者にとって大切なもの。調子=台詞の出来 具合。二の振り=仕草や舞踊。そして男っぷり。 5)危険なドライバーの順。昔は一姫二トラ三ダンプ。 5番目などは日常茶飯事になりつつあって、困りもんでですね。
2017.01.31
コメント(0)
-
天下分け目の天王山♪
〇10数年前の日記、まだボランティア・ガイドの講習生だった頃の日記がありました。 <寒がりやの私にとって、冬は余りにも酷。それでも家から図書館への道すがら、天神さまの池畔には蕾と幾つかの愛らしい花をつけた梅を見つけたよ。大山崎へ向う住宅街の一角で、大きな花弁をつけた黄色い薔薇の花も見つけたよ。 薔薇の花びらは、あんなにも薄いのに、幾重にあつまって木枯しに堪えているよ。 来月(注・’05.2)の9日は「四温句会」の日だけれど、国宝の”待庵”(妙喜庵)を拝観できるので、大山崎ふるさと案内人講座の実地案内の行事に参加することにしよう。茶道の父、千利休が茶の道は斯くあるべしと形で表わした、小ぶりな茶室。 本日の講座ではガイドとしての心得などを学びましたが、”歴史街道”にも参画している大山崎は、例えば大文字山よりも天王山の方が人気で勝っていたようです。 制服のサイズなど、いよいよ卒業まであと1カ月半あまり。私たち同期生十数名が加わって、当地の観光が更に活発化すれば嬉しい限りです。 哭く莫れこんな冬さえ薔薇は咲く 星子 >ボランティア・ガイドの会は21年目に突入。初心を忘れず、謙虚に技能を高めようと誓いました。
2017.01.30
コメント(0)
-
いちにち24時間は万民平等ですね♪
〇食料不足や医療設備の整わない国に生まれて来られた人々は本当にお気の毒なことだと思います。それに較べりゃ、少々の貧富の差こそあれ、低迷する日本であっても、起伏のある自然ときちんと守られる四つの季節、そして先人が残してくれた日本の文化の中で生かさせて貰える幸運を先ず、感謝したいものですね。 落語の「茶漬け閻魔」という話の中でお釈迦さまが述べられた言葉。「喜びというものは、過去のそれと現在との”差”のことで、昨日よりも今日、今日よりも明日、明日よりも明後日と、より大きな喜びを求めて行くことになる。言わば、際限の無い深みを追い求めること、これを無限地獄というのじゃ」 ・・・その意味をよく理解した上で、少しずつ進歩したいと思っています。人の役に立つよう心がけて居さえすれば、地獄という生々しい感覚から逃れられるかも知れませんね。 そんなことを踏まえた上で、もう一言付け加えさせて貰うなら、一日24時間は、生きている人間に共通した時間という宝物です。時間を如何に過ごすかという事で、その人の生涯は濃くも薄くもなることでしょうね。
2017.01.29
コメント(0)
-
天下分け目の天王山♪
〇10数年前の日記、まだボランティア・ガイドの講習生だった頃の日記がありました。 <寒がりやの私にとって、冬は余りにも酷。それでも家から図書館への道すがら、天神さまの池畔には蕾と幾つかの愛らしい花をつけた梅を見つけたよ。大山崎へ向う住宅街の一角で、大きな花弁をつけた黄色い薔薇の花も見つけたよ。 薔薇の花びらは、あんなにも薄いのに、幾重にあつまって木枯しに堪えているよ。 来月(注・’05.2)の9日は「四温句会」の日だけれど、国宝の”待庵”(妙喜庵)を拝観できるので、大山崎ふるさと案内人講座の実地案内の行事に参加することにしよう。茶道の父、千利休が茶の道は斯くあるべしと形で表わした、小ぶりな茶室。 本日の講座ではガイドとしての心得などを学びましたが、”歴史街道”にも参画している大山崎は、例えば大文字山よりも天王山の方が人気で勝っていたようです。 制服のサイズなど、いよいよ卒業まであと1カ月半あまり。私たち同期生十数名が加わって、当地の観光が更に活発化すれば嬉しい限りです。 哭く莫れこんな冬さえ薔薇は咲く 星子 >ボランティア・ガイドの会は21年目に突入。初心を忘れず、謙虚に技能を高めようと誓いました。
2017.01.28
コメント(0)
-
日記がわりの家計簿♪
〇身持ちの良い奥さんは、家計簿に金銭の出費などを記録し、備考欄に、ちょっとした出来事を記しています。親の代から、独立した子の代へと、その習慣は継がれ、言わば、或る家系史をつぶさに記録したものが、家計簿でもあります。 家計簿に女を綴る秋灯下 星子 という句を十年前に詠みましたが、正にわが母も克明に記した家計簿を残していました。 ’82年度の新年には正月から皆が集まる様子が日付毎に記されています。またこの年には3歳だった私の長女が風邪をこじらせ、脱水症状で入院した記録や、 妹の長女(姪)のお雛様の準備、亡父との月2、3回の宝塚歌劇の観劇や歯科医への通院。84年度には次姉にお雛様を買ってあげたことやご近所さんからの戴きものまで記録してあります。 バレンタイン・デーには必ず家内が、父あてにチョコレートを届けていたこと、その他、私達の家系にまつわる懐かしい記録が感情を入れず、単なる記録として残してありました。
2017.01.27
コメント(2)
-
黒焼けの手鍋♪
〇わが家の厨には、黒焼けのでこぼこした手鍋が、日々現役で使われています。鍋に穴など空いていませんが、ふと、鋳掛屋さんのことを想起しました。 まだ学校へ上る前だったろう、頭の片隅にあるのは鋳掛屋さん。 鍋・薬缶の漏れを直すのが本業ですが、それだけに留まらず、傘の修繕、鋏・包丁の研ぎ、鋸の目立てまで、何でもござれ。鍋の穴は白目という特殊な金属で上手に塞いで下さいます。 白目は白鑞とも書き、銅と亜鉛の合金で、シルクハットのような型をしていたような記憶があります。 鋳掛屋のおじさんは風采はあがりませんが、表情に独特の味わいがあって、修繕の手際の良さは天下一品。 いつまで見飽きず、その段取りの良さ、手捌きの良さに感心していました。 大正・昭和初期の日本人は、ドイツ同様、ものを大切に使っていたように思います。 昨近、テレビ番組でも日本職人の誠実な仕事ぶり、腕の確かなこと、仕事への誇りなどを、外国人を通して喧伝していますね。
2017.01.26
コメント(0)
-
面白い同音意義、笑える?
◎ストレスを貯めても利息はつかず、返って損するばかりです。そこで、アハハ!と笑うが勝ち。「大言海」の教訓編から抄出してみました。 〇あしたの滋養。 〇あたし 伝記になあれ! 〇足の向くまま、昨日むくんだまま 〇あ痛っ、口がふさがらない。 〇(歌)愛、あなたでふたり♪ 〇愛とは公開しにくいもの。 〇悪銭でもいいから身につけたい。 〇愛って絶えるものなのね。 〇浅き夢見し飽きもせず---宝くじ 〇穴があったら歯 痛い。 〇足に向って撃て!---威嚇射撃。 〇(歌)明かりをつけましょ ボンヤリと♪ーーー省エネ時代。 〇あかぬける娘 毛抜ける親父。 〇あがきのヤマも今宵限りーーー試験前夜。 〇あっしには何の×÷(カケワリ)もござんせんぜーーー+-(タシヒキ算) 〇あいつ同化してるぜーーーカメレオン。 本日はこの辺で~~~♪
2017.01.25
コメント(0)
-
暮れゆく空に雁の声♪
〇小説家佐藤愛子さんの異母兄で、童謡”ちいさい秋みつけた”や 歌謡曲”長崎の鐘””二人は若い””あゝそれなのに”、数え切れないほどの校歌など 多くの作品を残されたサトウ・ハチロー氏に掲題のような花柳界をテーマにした詩集があります。 「小唄と絵」(内外社、昭和6年)がそれで、清水三重三さんの挿絵があってつやっぽい本です。 おもひがかなつて おもひがかなつて 紅てがら ごはんじたくや 拭掃除 あぶない手つきの 針仕事 みやげを待てよと やさしくも 朝に出かけた そのあとも 気のやるせなさ もどかしさ 思ひのたけを あらはせて 半襟さへも 幅広に 出してゐたのは すぎし夢 いまはきつちり 襟あはせ ほそめにほんのり うすあづき 色さへじみな しとやかさ ひとり帰りを 待ちわびて いくどと立つ 門先の 暮れゆく空に 雁の声 最後のフレーズなどは俳句的技巧ですね。
2017.01.24
コメント(2)
-
名優たちの言の葉♪
〇和田誠編の「芸談」から一つ二つ拾ってみます。文章は原型を留めないほど変えています。 若山富三郎・・・長谷川一夫先生が侍姿の折、正座の右手がやや前に置かれている。いざと言う時に刀の柄に早く手が届くからと教わった。 江利チエミ・・・乙女時代に進駐軍で歌い終わると7、8時だから、11時過ぎに終わるバンドの人に送って貰う都合で傍で聞いていたの。それがテネシーワルツ。哀れな時に憶えたのよ。 勝新太郎・・・台本を貰ってから役づくりしていては遅い。日頃から自分の幅を広げておく、幾つかの抽斗から繋ぎあわせるようにする。 小沢昭一・・・一人芝居の或る日、舞台の真ん前に盲導犬が居て、驚かしていけないなどと考えながら芝居していると妙に上って、失敗をしたけれど、 その動転をよそに、大声を出す最後のシーンでは開き直って絶叫したところ、舞台監督から一番良い出来だったと褒められた。犬の御蔭で芸が進化した。
2017.01.23
コメント(0)
-
漱石の前任教師が、ラフカディオ・ハーン♪
〇大山崎町の観光ボランティア・ガイドの会に入って12年になりますが、 漱石と加賀正太郎の「大山崎山荘」、そしてその縁を取り持ったのが 祇園の女将磯田多佳までは今でも諳んじているのですが、 漱石が初めて教壇に立った時、「耳なし芳一」や「雪女」で有名なラフカディオ・ハーン つまり小泉八雲がその前任者だったとは、「漱石の書画美術」なる本を手にするまで、知りませんでした。
2017.01.22
コメント(0)
-
海の波や雷から電気を貯められない??
〇阪神大震災から22年。そして津波被害を伴った東北大震災など、狭い日本に原子力発電は本当に必要なのでしょうか?日本の森林の多くは経済性の無い理由から伐採されることもなく、原生林化、荒廃の一途を辿っているようです。此処に労働力を集められないのでしょうか。 海に囲まれた日本なら、絶え間なく海岸に押し寄せる波の力をエネルギーに替えられないものでしょうか?宇宙に飛び出る技術を持つ時代の今日、雷のエネルギーを貯め込むことが不可能なのでしょうか?行政の在り方次第では、太陽電池の驚異的な進歩も期待できそうです。 国支援の下、地方自治体ごとに大規模な農地を開墾し民営化し、其処へ溢れた労働力を集約できないものでしょうか?魚貝の養殖・漁業の体制にも目を注ぐ必要性もありましょう。 はるか律令時代から江戸幕府・明治初期の施政者たちは、将来を見据える大きな展望から政治を行ってきた事実があります。 ご苦労とは思いますが、国の施政を担う方々には、是非とも大きな構想から論じ合い、具体的にそれらを実現化して戴きたいと願っています。
2017.01.21
コメント(0)
-
梅開花だより♪
〇雅やかな平安時代、花と言えば”梅”を指していたのでが、さくらの花と梅とを比較してみましょう。先ず枝ぶりから比較すると、幹の光沢、風情から圧倒的に梅に軍配が上がります。桜の中には香りを放つ種も一部ありますが、梅の芳香は遠くからでも匂って来ます。 花芯はどうでしょう。これは好みの問題ですが、やや粗い感じの梅よりも桜の蕊の方が、なよなよとして居て優れているように思います。しかし桜と言えば、この人を抜きにして語れない佐野藤右衛門さんに言わせれ我々が好む”染井吉野”よりも山桜こそ本物の桜と言われますので、素朴さが決め手になります。松竹梅という言葉があるように、古来、貴族は梅を愛でていましたが、御所の紫しん殿の前に桜が植えられて以来、桜に人気が集まりました。けれども、かの歌姫、鶯も梅の枝に停まります。ですから、ここんところは梅に花を持たせて、そろそろ寒梅を探しに出歩き廻りませんか?
2017.01.20
コメント(0)
-
電気人間?磁気帯び人間?
〇旧訳聖書を読むとイエス様が手を差し延べると病気が治ったとか、極端な例では盲人の視力が一瞬にして回復したとか記述されていますが、 反論に糸目をつけない大学の教授陣は別室にて待機していただくとして、そう言った超常現象であっても、先入観さえ払拭すれば、有り得そうだなと思えなくもありません。 凡そ、天才とか麒麟児とか称せられた人々は神々から選ばれた特異な人物で、名曲を作ったり、前例のない建物を拵えたり、千年後にも伝わる物語を創作したり、不朽の絵画を残したり、英雄と崇められる戦さ上手だったり・・・。 しかしながら、数百年前の故人の魂に乗り移って宣託を伝えたり、数十年前の事故死の霊になって恨みつらみを述べたり、動物霊を駆除するなどと言う霊媒と自称する特殊技能者は信じることはできませんけれども、 特殊なパワーを発することが出来る人々は「有って然るべし」と幾何かの信頼を託すことは、ケースバイケースでは肯定出来そうにに思います。電気人間たら、磁石人間と称される人々は皮膚から地味にして強烈な磁力を発することの出来る人種なのでありましょう。 己を神格化しないで、ひたすら日々迷える人々の救済に勤しむ特殊技能を持つ人の存在は肯定できるように思うのです。
2017.01.19
コメント(0)
-
一線級俳人の短冊やはがき♪
〇京都市内の書棚に残してあった葉書保存帖には、父の青年時代からの交友者との葉書がきちんと保存されていました。全部8冊。 一番多いのは父すばるが尊敬してやまなかった鈴鹿野風呂翁。続いて学生時代に支えて下さった水野白川男爵。路葉子、十七星、余瓶、如是、一水など錚々たるメンバーですが、 高浜虚子7通、星野立子など第一線の俳人からも頂戴しています。 このほか縦40×横30×厚み10センチほどの短冊帖1冊、これより幅の少ない短冊帖が2冊あって、その中には野風呂、夫人の静子、余瓶、一水、十七星、白水、王城、素十、桃十、素逝の短冊に混じって、 いはほ、日野草城、水原秋櫻子、山口誓子各1枚に、高浜虚子の短冊も沢山頂戴していました。 白牡丹といふといへども紅ほのか 虚子 船下りて桟橋ゆるゝ秋の雨 虚子 さて”すばる”の短冊より一句 生涯の山河こゝろにかるた読む すばる 人との交友を大切に温めていた父だから、こうして遺されてあるのでしょう。
2017.01.18
コメント(0)
-
回転率の良い古書「南座」♪
〇昨年の京の顔見世興行は改装修理工事のため、他に場所を移して演じられましたが、物置の棚に堂本寒星著「南座」(文献書院)という分厚い書物があります。 古本屋さんでは知らない人は居ないというほど、著名な書物。昭和4年11月20日発行で、定価4円です。 表紙の装丁は金泥を付した布地の色刷りで豪華なものです。また、本書は京都は南座の歴史と歌舞伎の近世を記録しています。 現在の南座は凡そ30年ほど前に改装されたものですが、桂米朝師匠が博打・狸をサイコロに化けさせる内容の落語の枕で、 改築前の南座のエレベーターの秘話を披露。何でもあすこのエレベーター、人数オーバーのときは重量チェックの働きでブザーが鳴り、一人分を拒みますが、そぉっと再度乗れば、そのまま動いたのだとか。 本書にはまるで銭湯”松の湯”と呼んでもおかしくない風情の明治時代の南座の写真、 続いて、それよりもずうっと立派になり尖がったイメージの大正時代のもの、 そして3つ目には、唐門のような風情の昭和初期の写真が掲載されています。 南座の真向かいには、北座があって、1、2階は八ツ橋本舗、その上には歌舞伎関係の写真や資料が展示されています。
2017.01.17
コメント(0)
-
大阪弁、名古屋弁♪
〇昨日は娘の結婚式でした。女子駅伝は大変でしたが、こちらは無事、華やかに挙式できました。 番付表なるものは相撲に限らず食べ物などにもありますが、”浪花ことば大番付”というものを亡父が残していて、その中身を挙げると東方横綱 けったいな しぶちん 西方横綱 えげつない がしんたれ東方大関 あほだら しんきくさい西方大関 あかんたれ あほくさい東方関脇・小結 西方同じく いとさん ごりょんさん いけず ぼんち おえさん へんねしこの他列挙すれば すかたん あんじょう せんぐり いちびる ごんたetc 一方”なごやことば番付”から抜粋すれば、東西大関 なんだいも とろくさい関脇小結 だちかん えいわいも ちょろまかす いこぬとる(?) etc 最近”なまり”をテーマにしたテレビ番組もありますが、父郷や母の里など、田舎のある人は幸せかも知れませんね。
2017.01.16
コメント(2)
-
苗字あれこれ♪
〇家系を辿ることは、通常大変なことですね。字数の多い苗字では「勘解由小路かでのこうじ」、「八月一日宮ほずみや」、一方短い苗字は沢山あって、「井」、「紀」、「志」など。わが家の苗字も平凡だから、15代遡るなんて至難なことになりそうです。 韓国では金、李、朴、崔、鄭の五つの姓で過半数を占めることは韓国ドラマの配役を観るだけでも解ります。日本では佐藤、鈴木、高橋ほか上位五つでもそうはいきません。 丸山浩一著「家系のしらべ方」(金園社)によれば、阿部や犬養は古代からある苗字、無着、般若さんは明治に作られた名なんだそうです。また多気・吉田・石毛・小栗・谷田・馬場が一つの家臣団、畠山・豊島・小沢は秩父系、相馬・椎名・君島などは千葉系、村山・大井・金子・山口がグループ、三浦系には和田・杉本・岡崎・佐原・小林・土屋・品川などがあるようです。
2017.01.15
コメント(0)
-
全国都道府県対抗女子駅伝に寄せて♪
〇黒田正子著「京都の不思議」第二巻に、日本の駅伝発祥について記されたものがあります。<日本で初めての駅伝は、(丁度百年前・筆者変更)京都の三条大橋からスタートした。 大正六年(一九一七)の四月二十七日、第一回駅伝である「東海道駅伝徒歩競争」がはじまった。めざすゴールは、東京上野の不忍池。上野は当時、東京遷都五十周年記念博覧会の真っ最中。実は駅伝は、この博覧会にあわせて行われたのであった。>結果的には丸三日間走り、四日目の五月一日、東京上野に到着したようです。実にスケールの大きい駅伝でしたね。 二〇〇二年四月、三条大橋東詰に「駅伝の碑」が建てられ、その形は「襷」なんだそうです。面白いことに、この日に遅れること四日後に、東京・上野不忍池にも、同じ碑が建てられたとか。 私の、一年間で一番好きなテレビ番組が、都大路を走りぬける全国都道府県対抗女子駅伝です。新聞記事をいっぱい集め、予備知識を得ながら、応援かつ楽しんでいます。
2017.01.14
コメント(0)
-
本能寺の変♪
〇<六月朔日、夜に入り、老の坂へ上り、・・・(略)。信長も、御小姓衆も、当座の喧嘩を下々の者ども仕出し候と・・・(略)、明智が者と見え申し候と、言上候へば、是非に及ばずと、上意候。(略)信長、初めには、御弓を取り合ひ、二、三つ遊ばし候へば、何れも時刻到来候て、 御弓の絃切れ、其の後、御鎗にて御戦ひなされ、御肘に鎗疵を被り、引き退き、是まで御そばに女どもつきそひて居り申し候を、女はくるしからず、急ぎ罷り出でよと、仰せられ、追ひ出させられ、既に御殿に火を懸け、焼け来り候。・・・(略)> 歴史書として著名な「信長公記」(人物往来社)桑田忠親<校注>から一部抜き出しました。原本を解読するとなると大変ですが、後世の学者の注釈のお陰で、楽に読むことができます。本日借りた書物です。
2017.01.13
コメント(0)
-
にたり地蔵♪
〇昨年末は婚儀の準備や数え百二歳の叔母の容態などで多忙を極めていましたので、久しぶりの図書館詣。1)「にたり地蔵」澤田ふじ子著(幻冬社) いわゆる公事宿事件簿シリーズの一つで、笑いかけた 地蔵が忽然と消えなさった話題ほか五件。2)「ことばの切っ先」葛西聖司著(小学館) 本書は歌舞伎や浄瑠璃の中の、心にせまるセリフ集。 男のセリフでは、寺子屋のせまじきものは宮仕えなど 恋編では河庄の魂ぬけて、とぼとぼ、うかうか等。3)「昭和」永六輔著(朝日新聞社) 広い視野に立って、あまたの言葉を遺して去られた永 六輔さんの昭和のまとめ。4)「向田邦子全集十一」(文芸春秋) エッセイ七、男どき女どきエッセイの副題がついてい ます。気品があって、セリフも活きていて、文章も素 敵なエッセイ集。5)「乳のごとき故郷」藤沢周平著(文芸春秋) 藤沢さんの作品に触れていると、彼の温かい人柄が自 然に伝わってきます。幼年期のふるさとを中心に自由 な綴り集。
2017.01.12
コメント(0)
-
昭和初期の流行語♪
〇大正15年12月25日から昭和になって、たった1週間で昭和2年に変わったようです。 シャン→綺麗、恰好良いの意味でドイツ語のSCHOンN から来ています。応用編としてハットシャン(はっとするほど美人)バックシャン(後ろ姿にほだされ前へまわって、ああ、び っくり!) イミシン→A子がB男に送る視線、ちょっと意味深だわ。 昭和初期の女学生の隠語から流行り出しまし た。 三面記事(これは日活映画のタイトルから)。恐妻家(徳川夢声が提唱して恐妻組合ができたのだそう です)。世が世であれば(大利根月夜の歌詞から)。その後、戦争・軍事臭の強い言葉が流行り出し、敗戦の日を迎えることになりました。
2017.01.11
コメント(0)
-
時計に寄せて♪
〇離れ小島に独り生活する人は別として、現代人は一日に幾たび時計を見るのでしょう。二十歳過ぎ、銀行という職場で働いていた頃は、現在の数倍、いや数十倍もの頻度で時計を確認していたものと思われます。 映画「時を追いかける少女」とは逆の、時に追いかけられる生活は多くの職業にあります。主婦業然り、真昼時の飲食業、無数の人を安全に送り迎えする鉄道関係の職業、締め切りの迫った作家・・・それは数え切れないことでしょう。 銀行はシャッターを下ろした三時過ぎ以降が、まるで砂時計の世界。数秒、数分単位で時に追いかけられる仕事場でした。小切手類の持出し準備、税金等の持出し準備、窓口(キャッシャー)や出納元締の現金ご名算など。 それらの指針となるのが時計。子供の頃に見た大きな柱時計。数日に一度はネジを廻さないと止まってしまいますが、映画のシーンでも大きくクローズ・アップされ、待つ人の心理を描き出していました。 社会人になったお祝いに義兄から、過去に見たことのないような薄手の巻き腕時計を戴きました。羽のような軽さやワイシャツの袖口を傷めない利点や、四角い形をしたスマートさに愛着を感じる逸品ものでした。 間もなく腕を振ることによって自動的に巻くことの出来る自動巻き腕時計も市販されました。それが今じゃ殆ど電池によるデジタル腕時計。装飾三昧の高級時計。金持ち、成功者の証のように買い求められる高級品。 一般家庭の中に、昔懐かしいアナログ時計は残されているのでしょうか?おそらく鎖のある懐中時計が辛うじて手巻きとして残っている位に違いありません。 時計はその人にとって、人生の年表となる存在だと思っています。今刻んでいる時間は二度と戻ることもなく、セピア色化する自分史の一コマに過ぎないけれど、かけがえのない、大切なものに違いありませんね。
2017.01.10
コメント(0)
-
割に合わない貧乏巡査♪
〇維新直後世は混乱していて、東京府内では強盗が白昼でも横行していたようです。 総督府は藩兵を集め急場を凌ぎ、明治4年の”ら卒”を経て、巡査へと呼称が変りました。 食い詰めた書生や没落士族の彼らは腰に3尺棒をぶら提げて人民を脅す面もありましたが、それは余りにも酷い薄給に起因するもので、 どんなに倹約しても一人当たりの米代が3円かかる時代に4等巡査は4円、1等巡査は7円という有様、交番所(小屋)のない街角に終日吹き晒されるという惨めさでした。 戦中のMPに相当する監督検察官(オバケと称した)に、居眠り現場や、差し入れの小金を溜めて買った焼芋にかぶりつく現場をみつけられと、時には100分の3減俸など、苛められました。 制服・靴は現物支給か現金支給があるので2年ほどはごまかして貯金、検査には仲間の借り物で対処するほどの割りに合わない仕事だったようです。 ところが、こんな彼らにも余得があって、戸籍調べの折に美人に遭遇すると再調査と称して面会などし、覗き見もしていたそうな。 当時堕胎は大きな罪でしたから腹の大きい娘に目をつけ、堕胎を発見すると25円もの賞金にありつけたと言います。 <参考図書・「近代事物起源事典」紀田順一郎著(東京堂出版)>
2017.01.09
コメント(0)
-
美文に触れて置くが大事♪
〇文章力が加齢とともに低下するのか、しないのかということは不詳ながら、日ごろ美文に接しておくべきでしょうね。例えば京を愛した長田幹彦の一文なら <・・・なかでも円山の夜桜は昔から天下の人口に膾炙してゐる。「春は花、いざ見にごんせ東山、色香争ふ夜桜や・・・」と、やさしい節調で艶曲、「京の四季」にも唄はれるとほり、名代の枝垂桜で賑はふ祇園の夜桜ほど艶かしいものは又とあるまい。 今の時世でこそ祇園町にも電車の軋りが喧しく、紅提灯もあたら不風流な電燈にかはってしまったが、つひ七八年前まではかがり火の美しく燃えたつ花見小路から円山までの道さへ既に一幅の画中の趣を呈してゐたのである。> 情景が瞼に浮かんで来、いつまでも引用したくなるほどの名文です。この流れに似た作家には尾崎紅葉・泉鏡花たち、浪々たる綴りは谷崎潤一郎、読者をすぐ惹き込むのは夏目漱石や短文の志賀直哉、横光利一らでしょうか。吉井勇の小説をいつぞや紹介したことがありますが、彼は更に五七調で綴っていますので、そのリズムに惚れ込んでしまうことも。
2017.01.08
コメント(2)
-
笑ってもいいですか?
〇ビックリハウス版国語辞典(応募者数千人)の”せ”の部から抽出してみました。笑っとうくれやす♪ 先生政治=国会議員を先生などとおだて、自分の利益になるよ うに図る日本の政治体制。 染料役者=派手な化粧で演技の未熟さを誤魔化す役者。 ○潜入姦=夜這いのこと。 窃盗語=「おい、金出せ」などの言葉。 ○先客番台=一番最初に来た客は番台に座ることができる。早 い者勝ちのこと。 整容料理=容姿を整える為のダイエット食品。 宣誓政治=先ずは自分自身が公明正大であると誓ってから嘘をつきまくる政治。 千客万歳=千人もの客入りを喜ぶ興行主。 宣戦不告=宣戦を告げずに敵を襲撃すること。 ○是々非々=マラソンを走りきった後の息づかい。 雪喜時代=雪が降ったと無邪気に喜んで居られる幼稚園、小 学低学年期のこと。 ○専悶誌=エロ本。 成績不審=結果的にカンニングの疑いのある成績。 性態模写=春的な浮世絵。 ○染色体=ボディペインティング。 世界視=地球儀を眺めて世界旅行気分に浸ること。 ○銭望=お金持ちを羨むこと。 星人映画=SF映画。 と、まぁこんなところです。説明文句は若干私の手を入れたものも御座います。
2017.01.07
コメント(0)
-
七草(種)かゆ♪
〇早いもので明日は七種かゆをいただく日。城南宮さんさんの「七草粥」の行事は二月十一日(土)です。正月廿三日の子の日に、左大将の北の方から若菜をお贈りになります。・・・(源氏物語:若菜上) 玉かづら 若菜さす野べの小松を引きつれて もとの岩根を祈るけふかな 源氏 小松原すゑの歳(ヨハヒ)に引かれてや のべの若菜も年を摘むべき 万葉集巻頭を飾る雄略天皇の求婚の御歌から若菜を摘む慣習が始まったとされますが、宮中でも内膳司がその年の七種(ナナクサ)の新菜を羹(アツモノ)として献上しました。 この行事は中国から伝えられ、万病を除くといわれ、不老長寿を祈念するものでした。七草粥の源となる慣いで、芹、なづな、すずな、すずしろ、仏の座、御行、はこべら。 我が家ではスーパーなどの七草セット商品は買わないで、専ら庭に生えているハコベや元日の雑煮に使った小さい大根、人参や葱、白菜など七種類の菜の粥で済ませました。
2017.01.06
コメント(0)
-
どうです?小粋な都々逸の味は♪
〇「想い出にかわるまで」、「ひらり」、「都合のいい女」、「毛利元就」などの脚本で知られる内館牧子さんの「小粋な失恋」という本は絶妙なコメントの附された恋愛指南書です。未婚の女性には是非一読して戴きたい読み物です。 楽天サイトやほかのサイトでブログを更新するのは、ボケ防止、或いは編集の急な穴埋めに充当する類のもので、その出所を明らかにすると共に、著者の文章をそのまま拝借することを潔く思わないので、本日も彼女が抜粋した<古い都々逸>の一部を紹介するに留めます。 <あの人のどこがいいかと尋ねる人に どこが悪いと問い返す> <枕出せとはつれない言葉 そばにある膝知りながら> <思い切られぬ心が不思議 こんな不実にされながら> <惚れられようとは過ぎたる願い 嫌われまいとの この苦労> <私しゃロウソク芯から燃える ぬしはランプで口ばかり> <惚れた証拠にゃお前の癖が みんな私の癖になる> <唄もうたわずお酌もせずに 花をあびてる石地蔵> <あなた恋しと鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が身を焦がす> <思いなおして来る気はないか 鳥も枯れ木に二度止まる> <おろすわさびと恋路の意見 きけばきくほど涙出る> と、まぁ48もある中から適宜選んでみました。これらの作者の粋な表現の妙には感服するばかり。内館氏は、これらの一つ一つに女性ならではの解説や余談をエッセイ風に仕上げて居られます。正月気分の収まった今夜辺り、ゆず風呂にでも浸かりながら味わって欲しいと思います。
2017.01.05
コメント(0)
-
鹿の子絞り♪
〇源氏物語の”鈴虫の巻”に<花づくゑのおほひなど、をかしきめぞめもなつかしうきよらなるにほひそめつけられたる心ばえ、めなれぬさまなり>とあるように、 絞り染めは、舞妓さんの”割れしのぶ”で解るように実に愛らしいものです。昔NHK紅白歌合戦での都はるみさんの総絞りは見事でした。 鹿の子は文字通り、小鹿の背の斑模様に似ているところから言われ、「京鹿子娘道成寺」という演目は、その名だけでも華やかな舞踊が推測できます。絞染めの歴史は古く、インドから中国を経て伝えられ、平安時代には鹿の子絞が京の都で行われていたので”京鹿の子”と呼ばれたようです。 江戸時代には飛鹿子、匹田鹿子、黄返し藍鹿子、小太夫鹿の子などが大流行。総鹿子絞の着物は庶民には贅沢品として禁止されていました。 一方鹿子絞に似た花として6月に咲く”京鹿子草”があります。一旦枯れたので義兄から立派な京鹿子草を貰いましたが、リフォーム増築の折、再び枯らせて仕舞いました。 線香花火のような、かそけなく愛らしい鹿の子模様に咲く花は、俳句結社の名前になっています。
2017.01.04
コメント(0)
-
短編小説「五百羅漢」
〇稲荷山の中腹に××寺という古刹がある。此処には五百もの羅漢が仏道の悟りを求め、今日も空を睨んで居られる。しかし、これは表向きの話で いわゆる丑三つの頃になると、ぼそぼそ、そこいらで談話が始まる。中には、向うの草むらから歩いて来られ、その座に加わる羅漢も居られる。 折から山颪が来て、一斉に乾いた草木が泣き出す。俳句では虎落笛(もがりぶえ)と言う季語を使っている。寒さが厳しいから、星がよく光る。すばる星など鮮明に見える位である。 「ほほう、御坊が仏門に入られたのは、十九で御座ったか。」 「はい、忘れることができませぬ。」 先に相槌を打ったのは、福禄寿のように頭の長い羅漢であった。垂れんばかりの鷲鼻である。これから正に告白しようとするのは、凡人っぽい、それでいて若さの匂う羅漢であった。 羅漢は総じて眼玉が大きいが、この方のは、眼に顔があるといった見事な眼玉であった。 「すると、女人から逃れて参られたかの?」 鷲鼻の羅漢が覗くようにして尋ねられた。額の皺は六十の齢を見せつけるようであった。 「はい、高貴な御方に恋慕した訳で・・・・・」 恋慕と言う言葉が耳に入ったのか、八方の草陰から、ぞろぞろと来られるわ来られるわ。仏話を拝聴する信心者のように、忽ち円座が出来てしまった。 さすがに冷やかすような野暮なことはなさりはしない。只、にやけそうになる顔に神経を通わせ、静聴して居られる。若い羅漢は苦行を乗り越えただけあって、此処に至ってぐっと落ち着かれ、舌もよく回転し始めた。 「いかに高貴な御方とは言え、女人は女人と高を括って居った其の上、己を褒めるのもおこがましいが、容姿にも自信が御座りました。・・・若かったのですな。平井保昌宜しく、紅梅一枝を肩に挿して、寝所に忍んだので御座ります。」 「ふむ。」 鷲鼻の羅漢は味わうように、頭を上下させて聴き入ってられる。山颪も止んだらしい。 「偉い御方で御座りました。愚僧の参るのを知っておいでで、諭すように、こう申されたので御座ります。」 夥しい視線が若い羅漢の口許に凝集して、辺りの空気は、一瞬、止まった。 「あなた様のお志、有り難う御座りまするが、物盗りになるような子供は、産みとうは御座りませぬ。」 「それだけじゃったか?」 「はい、たったこの一言で御座りました。その方からこれ以上の言葉の出る隙の無いことは、血気盛んな愚僧にも感じ得たほど。・・・・考えあぐんだ末、仏門に入った訳で御座ります。」 福禄寿の羅漢が、静かに問われた。 「それで、答は出たかのう?」 「はい、今なおこうして考えて居りまする。」 円座の羅漢はそれぞれ尤もだと頷いて、それから首を傾げながら、八方草蕪に戻られた。鷲鼻の羅漢も腕組みして考え込まれた。當の羅漢は、また、きいっと星を睨み返して居られる。 辺りは、やはり凍てるような寒さが根を下ろし、草木はますます干乾びて泣き止まない。 <この短編は若冲が晩年に隠棲した「石峰寺」の五百羅漢を見て、二十四歳の頃に書いたものです。伏見稲荷のすぐ近所にある寺です。是非、訪い下さい。>
2017.01.03
コメント(0)
-
お正月今昔♪
〇太古の昔から人には進歩しようという意欲が具わっているため、毎年、正月を迎える都度今年こそと誓いを起てるのが人情。それが一週間もすればほかのことに気を奪われたり、日常の生活パターンに戻ってしまいますが、それはそれで安寧の世界、居心地の良い世界でもあります。平成も二十九年目の御世となりますが、私が少年であった昭和の頃を想い起こせば、正月の雰囲気がまるっきり異なっています。正月は下着から靴下、洋服、ズボンなど新調をおろす区切りの日でした。また近所の子供が集まってわいわいがやがや、正月にしかできない遊び、福笑い、凧揚げ、羽つき、独楽回し、トランプ、歌留多取りに興じる三が日でした。中学生の兄さん・姉さんから、数え年五つ六つの子が一堂に会して楽しんだ時代だったのでした。平成の御世にも引き継がれている慣習は、雑煮、初詣、お年玉・・・そんな処でしょうか。子供たちは家に引篭もらないで、ご近所同士で遊んで欲しいものですね。それが”ふるさと”なのかも知れないから。
2017.01.02
コメント(2)
-
鶏・鳥に因んで♪
〇明けましておめでとう御座います。本年もよろしくお願い申し上げます。 山と渓谷社の「鳥のことわざ うそほんと」(国松俊英著)のページをパラパラ捲ってみると、80もの諺のあることに驚いてしまいます。「雀百まで踊り忘れず」、「鳩に豆鉄砲」、「梅に鶯」、「目白押し」、「烏合の衆」、「烏の行水」、「鳶に油揚げ」 「掃き溜めに鶴」、「鶴の一声」、「おしどり夫婦」、「千鳥足」、「一富士、二鷹、三なすび」、「雉も鳴かずば撃たれまい」、「閑古鳥が鳴く」など。 ところで「鶴は千年、亀は万年」という言い伝えから、鶴は千年も生きるのかなと誰しも思いますよね。内田清之助の本「鳥」では、セグロカモメ:36年、ダイシャクシギ:31年、イヌワシ:25年、ガン:25年、カラス:14年、ハト:10年、スズメ:8年、そして鶴は30年~60年も生きるのだから、あながち諺は間違っているとは言えません。 地球の環境は年々悪化を辿っていますが、私たち人間は身近に目にすることのできる「鳥」たちとも仲良く暮らして行きたいものですね。
2017.01.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1