2025年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

大山崎町は利休に因み茶会
〇今から14年も前の記事。 元文化庁長官だった三浦朱門さんの提唱で1986年、東京から始まった国民文化祭。以降、熊本、兵庫、埼玉・・・と続き、昨年の岡山県から京都府へとバトンタッチされました。去年秋のこの日記にも記しましたように、昨年はプレ国民文化祭として、大山崎町ではお茶会、長岡京市ではバレエ、向日市は剪画をテーマとしてそれぞれ試験的に催し物を実施しました。図書館に置いてあったプレガイド・ブックはA4サイズ、全頁カラー印刷で50数頁あります。10月29日(土)11:00~13:00御池通での都大路オープニングパレードを皮切りに、国際会館でのフェスティバルから11月6日の閉会まで9日間、市内・府内の各市町村で賑々しく繰り広げられます。小倉百人一首かるた競技全国大会や食文化の祭典、暮しの文化展、大茶会、華道展、俳句・連歌・詩などの催し。合唱祭や吹奏楽の祭典、オーケストラの祭典、吟詠剣詩舞道祭、日舞祭、能楽祭など多岐に渡っていました。
2025.05.31
コメント(0)
-

ツーピース = 蟹
〇日々更新のこの日記。時々はビックリハウス版国語辞典『大語海”』に頼るのです。ツマヅク=妻らしくなる。ツキトバス=ロケットを打ち上げる。or運が逃 げてゆく。痛心母=問題児を抱える母。○ツーピース=蟹転移無法=ガン細胞のこと。転地無用=転勤などあり得ない零細企業の宣伝文 句。点下大変=成績・業績が下がって慌てること。亭主淡白=夜分元気のないご主人。天津乱饅=天津甘栗が売れすぎて隣の饅頭屋が困 ること。○臀電虫=ホタル。低額処分=バーゲンセール。テノール=文鳥愛好。臀波=おなら。電気スタンド=電気自動車の為の充電所。てぬきそば=かけそば。テニス=手の艶出しクリームのこと。では、ごきげんよう♪
2025.05.30
コメント(0)
-

難聴予備軍ぞくぞく生成。
〇小学生の頃には、広告の裏側やわら半紙に何度も何度も書きなぐって漢字を覚えました。暗記ものも教科書や参考書の該当箇所を定規などで隠し自問自答を繰り返して覚えたものです。 謄写版、カーボン紙による複写というアナログ方式から、複写機(コピー機)やワープロ、ノートパソコンの時代へ移り、仕事量の倍増、スピード処理が可能になりましたが、脳は画像だけの記憶を残すのみ。だから脳の海馬の機能が低下すると手作業による触覚の記憶とは異なるので、復元、呼び戻すことが出来なくなります。 また通勤の大半の人々がイヤーホーン、無線のイヤーホーンを耳に挟んで、音楽等を聴いておられますが、車内での騒音下、あれは将来恐ろしいことが待っているのでは無いでしょうか。そう、難聴。 現在以上に電車・バス内の老人の会話は姦しい状態になっていることでしょう。
2025.05.29
コメント(0)
-

御子左家→為相の冷泉家
〇冷泉家と言えば、藤原定家の後裔の家系だと大概の方々はご周知のことですが、そもそも「和歌の家」の象徴である御子左家・定家の子の為家が亡くなる時、遺言書に相当する「譲り状」を巡って、嫡流二条家の為氏及び京極家の為教と後添いの母・阿仏尼の子として生まれた為相の冷泉家という3つの家系が相続権を争ったのでした。幕府に嘆願する為、鎌倉へ下向した際に阿仏尼が書いた旅日記が有名な『十六夜日記』です。それから30年を経て、二条家、京極家の断絶の結果、御子左家の血筋を引く「冷泉家」として誕生しました。爾来、現在の25代目為人さんまで800年ほど続いています。余談ながら24代の為任さんが某年金基金の理事長をして居られた折、私は担当銀行員として面前に居たことも。 戦国の世は冷泉家にとって存亡の危機に見舞われた時代で、滋賀県の近江に疎開。6代目為広さんは駿河の今川氏や能登の畠山氏と親交を結びました。9代から12代は安土桃山、江戸初期にあたり、一時、大坂にも居を構えましたが秀吉の命により再び京に戻り、家康の庇護をも受けるようになりました。この間、日本国家の宝とも言うべき冷泉家の古文書は戦火を逃れ、幕府や皇室から手厚い保護を受けました。冷泉家の住宅と定家が書いた日記・国宝『明月記』の修理には8億~9億円もの費用がかかりましたが、75%は国・京都府・京都市の負担、残りの自己負担部分が高額でしたので、バブル崩壊期ながら1億3千万円を超える寄付金が集まったようです。(参・冷泉為人編『京都冷泉家の八百年』)
2025.05.28
コメント(0)
-

愛らしい京鹿子草
〇絞り染めは、舞妓さんの”割れしのぶ”で解るように実に愛らしいものです。鹿の子は文字通り、小鹿の背の斑模様に似ているところから言われ、「京鹿子娘道成寺」という演目は、その名だけでも華やかな舞踊が推測できます。絞染めの歴史は古く、インドから中国を経て伝えられ、平安時代には鹿の子絞が京の都で行われていたので”京鹿の子”と呼ばれたようです。江戸時代には飛鹿子、匹田鹿子、黄返し藍鹿子、小太夫鹿の子などが大流行。総鹿子絞の着物は庶民には贅沢品として禁止されていました。一方鹿子絞に似た花として京鹿子草があります。父の時代にはこの庭に咲いていました。線香花火のような、かそけなく愛らしい鹿の子模様に咲く花から、鈴鹿野風呂先師と日野草城が私たちの俳句結社の名として選び、百周年も数年前に迎える事ができました。
2025.05.27
コメント(0)
-

たかが扇一本、されど
〇酒宴の座興には<扇一本手にもつならば 舞を舞うか、踊りををどろか 絵か歌かかうか、七輪あふがうか 光秀討たうか、ながながの浪人で・・・>と最後は扇を開いて、その上にものを受けるポーズで止めて、拍手喝さい。扇ひとつで舞、踊りができるし、七輪あおいだり、蕎麦を啜ったり、槍や刀にもなります。それが証拠に寄席・演芸場へ行けば、不慣れな前座の落語から最後のトリまで、扇片手に見事な話芸で観客を満足させて帰します。王朝時代には笏の内側に読み上げる文章を書いた紙片を隠し持っなど、カンニング用のものが扇に代用され、或いは、他人の所作の重要なポイントを書きとどめたりされたようです。何せ折りたためる至便性は世界一、抜群ですね。
2025.05.26
コメント(0)
-

祇園祭に、山崎からも山鉾参加
〇室町期の公卿だった一条兼良が編んだ『尺素往来』には、<祇園御会、今年殊に結構。山崎の定鉾、大舎人の鵲鉾、処々跳鉾、家々笠鉾、風流の造山、八撥、曲舞、在地の所役、定めて神慮に叶う歟。晩頃、白河鉾入洛すべきの由、風聞に候。>とあります。山崎は荏胡麻(エゴマ)の販売権を独占することによって中世から江戸中期まで繁栄しました。自由都市としては明治維新前まで荘が存続したところでもあります。上記の資料で、その繁栄の一端が垣間見えます。ところで、この情報は吉岡幸雄著『京都町家 色と光と風のデザイン』という美しい書物からいただきました。
2025.05.25
コメント(0)
-

電報に恋情を
〇昭和25、6年、桂に住んで居た頃は、京都の家にも桂にも電話機などなく、翌年、父の転勤で佐賀市内の社宅に移って初めて、ギョロ目みたいな、ぐりぐり廻す柱電話があった遠い記憶。大阪住吉の社宅にもありましたが、電話に代わる急ぎの伝言法は、郵便局や国鉄(今のJR)の駅で電報文を依頼し、カタカナで局員が記入したそうな。 濁音は二文字扱いに計算されるので、清音で記入するのが一般的。そこで<かなしやくやしやちゆうべいがめいどへ>とある電文を悲しや悔しや忠兵衛が冥途へ。正しくは金杓子屋忠兵衛、亀戸へ・・・という笑い話(教科書にて学んだ)もありました。『暮しの昭和誌』の著者・林えり子さんは、好きな彼氏には恋愛電報を利用しておられた由。現在のEメールのように安直なものでなく、局員に笑われないほどの精度の高い文言を考えたようです。 短く推敲を重ねた電報を打った時の心の昂ぶり、或いは、受け取った時の全身の高潮感・・・。
2025.05.24
コメント(0)
-

孫ふたりとも大好きなつるつる
〇名古屋名物と言えば”きしめん”。新幹線のホームで寸暇に啜る”きしめん”の食感には捨て難いものがありますね。ではこの”きしめん”、どんな漢字で表現するのかご存知ですか?「棊子麺」と書き、棊=碁石で、昔は丸い碁石の形そっくりのまま食してしました。水で練った小麦粉を薄く板状に延ばしたものを竹の輪切りで刳り抜いたものを茹でて黄な粉を降りかけて食べたとか。それが鎌倉時代のことで、江戸期に入って細い麺に変ったのですが、名前の「棊子麺」がそのまま残った訳です。 一方、うどんは中国の「索餅サクベイ」が「唐菓子」或いは「麦索ムギナワ」と呼ばれ、奈良時代まで遡ることができます。切ってつくる麦索を”切麦”と呼び、熱いのを”熱麦”、冷たいのを”冷麦”と呼び、後者が現代まで使われています。うどんは奈良時代の唐菓子の「混沌コントン」が由来で、言わば小麦粉の団子。 <混沌は温麺にして熱麦>、混沌コントン→饂飩オントン→温飩オントン→饂飩オントン→ うどんと変化して来たようです。
2025.05.23
コメント(0)
-

夏の風物詩・浴衣
〇古くは内衣、明衣、湯帷子と書いてゆかたびらと称していましたが、後年にゆかたと言うようになりました。湯気を拭いとるのに用いた湯帷子が起源とされ、延喜式に「曝布湯帷二條、浴衣一領」などと載っていることから平安期には既に用いられていたと思われます。伊勢貞丈の記に「天子御湯を召すとき、上臈一人、典侍一人御湯めさするに、裳の衣の上に白き生絹の衣を着て御湯をあびせ奉る也、その白き生絹の衣を湯巻ともいまきともいふ也、これは湯の滴の飛びて衣を濡らすを防ぐための衣なり」とあります。 初期は文字通り湯上りに用いられたものであり、江戸時代の末ごろまで、婦女は浴衣での外出は勿論、店先でさえ禁じられていました。やがて真岡木綿地の浴衣が染め上がりもよく、お洒落な浴衣が流行りだしました。 好きな人すきな浴衣で逢ふ夜店 獣庵 振り向いた訳は浴衣が同じ柄 正澄 豊満な肉そのままに見る浴衣 和樽
2025.05.22
コメント(0)
-

熊川宿の鯖寿司・芋車
〇10数年前、四条大宮のバスターミナルからミニバスに20名が乗り込んで、67号線から303号線へと走り続けると滋賀から福井の県境。やがて熊川宿に着きました。街道筋独特の、対面して列を成し並ぶ住宅の前には水嵩も豊かな水が迅く流れ、鯖寿司だの大き目の小豆だの、焼さば寿司だの、へしこなど山海の産物を並べる店々を覗きこみながら牛歩の時間。水流を利用した芋洗い器は竹製の水車のようなものですが、歯車の内側の箱部分で芋を洗う道具で、俳句サークル向きに、地元のガイドさんが「芋水車」とか「芋ぐるま」とか五文字で教えて下さいました。後年、下記の句ができました。 澄む秋や丹波水路の芋車 by星子
2025.05.21
コメント(0)
-

叔父への手紙から、同じ野村銀行を。
〇今から5年ほど前では、新型コロナウイルスの疫災の為、9月入学などの改革案が論議され、新一年生や就職戦線にある学生達は大変だろうなと推測していました。 父が叔父の麻田駒之助(中央公論創始者、俳人椎花)に宛てた手紙を発見。その内容の偶然性、運命的なものに驚いています。というのも、昭和十一年十月八日付の五枚綴りの内容は、 <(略)就職戦線もいよいよ決戦期となりました。本日、東洋紡より封書来り、十月九日午前八時より京都ホテルにて面接試験を行う旨、通知がありました。 今となれば何事も天命に任せて、平静、当日に臨みませう。(略)勝てば萬歳、負けたとて悔いは残らぬ道理です。> 更に住友の学内詮衡が終わり、十月中旬面接試験。第一銀行の面接が二十日前後、さらに野村銀行の学内詮衡が東洋紡の面接と重複する故、学生課にかけあう意志を記し、その上、三菱銀行をも視野に入れていました。 父は結局住友生命へ入社。私は野村銀行に勤め、母の弟も野村銀行、次弟が東洋紡。私の長姉、次姉も野村銀行。甥が東京三菱銀行といった次第です。
2025.05.20
コメント(0)
-

墨塗女・芸能きわみ堂
〇高橋英樹氏と大久保佳代子さんの「芸能きわみ堂」は芸事の番組なので、時々観ています。掲題の演目は、西川扇代一の大名、若柳吉優の太郎冠者、花柳貴代人のお妾という役どころ。都まで出掛け、訴訟事を上手く解決し、良い地域への栄転も決まった大名が、それまで囲っていた女性に、先ずは訴訟解決の吉事を祝う舞を所望、美しい喜代一さんが、艶っぽく舞われ、機嫌の良い頃合いに、大名が別れ話を持ち出すと、女性は一変、驚愕すると次に悲嘆に暮れ、涙を流しますが、このお妾、なかなか強かな女性で、噓泣きである証拠に、水の入った浅い容器に指を突っ込み、目や頬に塗っていたのです。太郎冠者が目ざとく見つけ、花道まで主人を誘い、噓泣きだと進言しますが、お人好しの大名は信じません。そこで太郎冠者が妾が舞っている隙に、墨汁の入った容器にすり替えます。正月の羽根つきの罰のような墨塗の顔に。それに気づかず、妾は大名に顔を向けるものだから、大名もふき出してしまいます。そして大名と太郎冠者は、お妾に鏡を渡しますと、妾はびっくり仰天。墨たっぷりの筆を持って二人を追いかけ、最後の決めポーズが三者三様の墨の顔。
2025.05.19
コメント(0)
-

大学教授と印鑑老舗の競い合いも。
〇信じられないことですが、古代信仰では容易に名前を知られたくなかったらしく、故意に難解な文字を使った名前を考えた家系もあったようです。では、次なる苗字は何と読むのでしょうか? 1.小鳥遊 2.月見里 3.四月一日 4.八月一日5.栗花落 6.○さん 、さん (解説)1.小鳥遊 たかなし (理由)鷹が居ないので 小鳥が自由に飛び遊びできるから。2.月見里 やまなし (理由)山が無けりゃ月 がよく見えるから。3.四月一日 わたぬき (理由)旧暦4月は更 衣つまり衣替の季節、綿入れの着 物から袷に替えるから。四月朔日、 更衣、綿貫みんな同じです。4.八月一日 ほずみ (理由)旧暦八月一日に 稲穂を摘んで神様にお供えするから。 穂積。5.栗花落 つゆ ついり つゆり(理由)栗の 花が散る頃に梅雨が始まるから。6.○さん 、さん 前者:まる まどか 後者 :しるし しるす とどむ (理由)正式に は麻呂とか丸と書いていましたが ・・・。(参・『つい誰かに話したくなる 雑学の本』)
2025.05.18
コメント(0)
-

ホタルに寄せて
〇およそ10年ほど前、50年ぶりに佐賀を訪れましたが、実に水の豊かな市街でした。家のすぐ近くの川には蛍が無数に舞っていました。当時は農薬などを散布しなかったから、蛍と人は仲良く共生していました。佐賀に移る前、京都に居た時にも、広い桂川の川敷に蛍が舞っていました。浴衣地の布に丸い輪の枠を二つ嵌めこむだけの虫篭。笹を拾って来て、とっぷり暮れた河川に行くと、夥しい蛍が群れを成したり、別れたりしてまるで戦さの陣形のように変化するのでした。竹の笹で上から地面に降ろすと、笹の葉には何疋かの蛍がいました。それを籠に入れたり、掌に包んだりして、翠色の幻想を楽しむのでした。家に持ち帰ったら霧吹きで水を吹きかけると、蛍の点滅が活発になり、真っ暗な部屋の一部がぼうっと妖しく見えました。京都の「哲学の道」もそうですが、こちらの小泉川にも蛍が生息していて、蛍祭りも毎年開催されています。 蛍火の闇より零れて闇となる 蛍火の移れば闇も移ろひぬ by星子天の橋立などへの直通高速がわが家のすぐ近所を通るようになりました。果たして蛍の風物詩に出会えるのでしょうか?
2025.05.17
コメント(0)
-

角屋・輪違屋存続の危機
〇娼妓・芸妓側との貸借関係もパーにせよとのお達しで、島原の”角屋”が養鶏場に、”輪違屋”が糸屋に変ろうかという正に危うき土壇場に、年季奉公ではなく自発的な務めなら、芸妓にしても養女、親戚などの形なら元のままの鑑札を認めるという<骨抜き>の法令で元の鞘に納まりました。 これは芸妓を解放したなら、困窮している田舎の暮らしが立ち行かないので、返って心中・自殺者を増やすことこそ人道に反するという植村参事の意見が罷り明治5年と言えば、○東京大阪間電信開通、○僧侶の妻帯・肉食・蓄髪許可、○修験宗を天台・真言の2宗に帰属、○新橋・横浜間鉄道開業、○太陰暦から太陽暦に変更、○神武天皇即位の年を以って紀元元年(因みに、この年は紀元2532年)とした年ですが、 マリア・ルーズ号が奴隷を大勢積んで日本に立ち寄りました。これが国際問題となり、寄港地の日本が意見を求められ、「人道にもとる」と公言したら、「日本には廓という奴隷組織がある」と指摘され、止む無く発したのが”開放令”、つまり娼妓・芸妓は一切解放せよ」というお墨付きで、娼妓・芸妓側との貸借関係もパーにせよとのお達しで、島原の”角屋”が養鶏場に、”輪違屋”が糸屋に変ろうかという正に危うき土壇場に、年季奉公ではなく自発的な務めなら、芸妓にしても養女、親戚などの形なら元のままの鑑札を認めるという<骨抜き>の法令で元の鞘に納まりました。 これは芸妓を解放したなら、困窮している田舎の暮らしが立ち行かないので、返って心中・自殺者を増やすことこそ人道に反するという植村参事の意見が罷り通ったという次第。更に芸妓たちが後年手に職が持てるよう教育を施す趣旨から、養蚕・製茶・染色・裁縫・算術などの教練場、つまり明治7年には「祇園女紅場」ができました。<参考文献:「更訂国史研究年表」黒板勝美編(岩波書店)、「鴨川」毎日新聞社編>
2025.05.16
コメント(0)
-

「洋酒天国」通巻22号
〇父が遺した「洋酒天国」通巻22号(昭和33年2月)には、1958年全日本カクテル・コンクールのノーメル賞グラン・プリの模様が記載されています。 審査員19名には淡谷のり子、岡本太郎、徳川夢声、笠置シズ子、左幸子、横山隆一、サトウハチロー、と言った方々も。応募総数は前年より3倍の12772通。数回の予選を経て、最後に20通に絞り、産経国際ホールにて公開審査が開催された。当日の模様はKRT、OTVのネットによりテレビ放映された由。 グラン・プリ「赤玉パンチ」、金賞「福寿草」、金賞「マダム」、銀賞「ダーク・ムーン」、銀賞「ポニーテイル・カクテル」、銀賞「枯葉」ほか14の佳作が選ばれました。 受賞者の手にはカップや楯のほか、順に5万円、3万円、1万円、1千円の賞金も。
2025.05.15
コメント(0)
-

その人の筆跡による手紙こそ
〇某年某日の日記では、関西では8チャンネル、アンビリバボーの番組では5月23日を恋文の日として紹介し、その最たる例として宮崎の貴島テル子さん97歳の現役女医の純愛を報道していました。 文字が綺麗でないという理由、書き誤っても消しゴムも二条線も要らない便利さゆえに、最近は専らパソコンに頼る日々を過ごしていますが、心の中では自責の念が薄れません。やはり文章は書いた人物の筆跡を通して相手に伝わる度合いが高くなると思っていますので、ましてや恋文は・・・。ここからテル子さんの話です。<友人の兄と初めて出会い、双方ともに一目ぼれ状態。それが高じて主に文通によってふたりの信頼が深まっていました。彼からのプロポーズを快く受け入れましたが、戦闘機の軍人である彼をテル子さんの父親は認めようとはしませんでした。それでもふたりの根気が奏功し、めでたく結婚。しかし新婚生活も彼の戦地への赴任もあって、わずか75日。ふたりをつなぐものは手紙のみ。いよいよ米国との激戦が顕著になって来ると、彼からの手紙は死を覚悟した文面ばかり。やがてそれもぷっつり途絶えました。テル子さんの許に愛おしい彼の戦死の知らせが届き、1カ月ほどは泣き暮らしていたテル子さんは、婚前の彼とのデートの折、彼の姉のように、女性も職業をもって独立すべきと言っていたことを思い出し発心。彼の両親に一旦別れを告げ、必ず戻って来ると誓い、猛勉強の末、立派な女医として嫁ぎ先の名、貴島医院を開業され、現在も現役として子供たちの病気を治していらっしゃいます。>彼女の宝は150通もの亡夫の手紙。 メールが悪いとは言いませんが、やはり自筆の、そこそこ思いの伝わる手紙が、言葉として永遠に輝きを保つのではないでしょうか。
2025.05.14
コメント(0)
-

日帰り吟旅
〇先日の母の日、本来ならグリーOB会の練習に参加すべきところですが、学生時代から社会人になって数年と、父逝去翌年以来続けている俳句、その「京鹿子」社の恒例の吟旅の日が競合、先に参加届と参加費を支払い済の俳句を選択しました。従来の吟旅といえば、5月第2日曜からの1泊旅でしたが、コロナ禍での中止やいろいろあって3年ぶりの、日帰り方式を導入した訳で、来年は再度1泊制に戻り、翌年は日帰りという具合に繰り返す予定です。 さて、5月11日午前8時30分に新幹線乗車口に集合、9時にヤサカ観光バスにて出発。ベテランのガイドさんとのフィーリングもぴったり。しかし、途中から私たちは若葉、青葉の景色に目を遣りながら作句ないしは作句への境地への準備で、申し訳ないけれど、ガイドさんの説明には馬耳東風。画像のように近江八幡市のメンソレータムでお馴染み(現在はロート製薬)の帰化人・ヴォーリズ(一柳)記念館、ロープウエイにて山頂の古城跡からの眺望を楽しみ、日牟禮八幡宮に参拝して句作。ホテルにて昼食並びに句会、京都駅そばの都ホテルにて宴会、秋の京鹿子祭での再会を誓い合いました。拙句は 田水張る田の字田の字の米どころ 眺望は薫風渉(わた)る近江郷 日牟禮社の一枚巌滴れり 湖国守る日牟禮八幡若葉騒 湖畔の声てふ伝道誌聖五月 by星子
2025.05.13
コメント(0)
-

釜座町の鬼殿跡
〇茶道千家の十職の一つ釜師大西清右衛門宅のある釜座町には古くは“鬼殿跡”と呼ばれる伝説がありました。唯一の取り柄が笛の名手、他はどう仕様もない大飯喰らいの百貫デブ“三条の中納言”と称されたのは藤原朝成。 名にし負はば逢坂山のさねかづら 人に知られでくるよしもがなの和歌でお馴染みの貞信公・三条右大臣藤原実方の六男。その面相はまさしく赤鬼そっくり。藤原伊尹と蔵人頭の任官争いで負け、犬猿の仲となりました。その後、ライバル伊尹は摂政まで大出世。大納言に欠員ができた折、止む無く朝成は伊尹にその位を懇願しましたが却下され、恨みに恨みました。伊尹が四十九歳でぽっくり死ぬと、京童は「ありゃ、あの赤鬼はんにとり殺されたんどっせ」と口さがなく噂した由。その朝成も二年後には五十八歳で没しました。しかし世間の評は「あんなお人や、死んでも祟りまっせ」といった具合。 伊尹の子孫は勿論、京童たちも朝成の屋敷を「鬼殿」とか「悪所」と呼んで、誰も寄り付かなくなったと、大鏡や古事記、十訓抄にも記載されているという噺。諸説有。
2025.05.12
コメント(0)
-

浪速芸妓らのストライキ
〇大阪南地の芸妓らは、かねて搾取制度に反旗をひるがえし「南地芸妓組合」を作り、南地五花街遊郭事務所に対して、その承認をもとめ、交渉中であったが、昭和十二年正月二十五日に要求が一蹴されるに及んで山籠もりを敢行することになり、芸妓お琴、三吉をはじめ約六十名は信貴山玉蔵院に籠城し、そこで必勝祈願の裸足詣りや寒夜の水垢離を行うなど悲壮な闘争を続けていたが、府当局の調停によって新検番の設立その他の条件にて解決するに至り、ようやく籠城九日間にして下山し、女ばかりで南地新検番株式会社を創立したものである。 本当のことを芸者へ芸者言い 久坊 騙されてからは旦那の有難さ 汀柳 都合よく女涙を持ち合せ 薩城(参考図書・日置昌一著『ものしり事典』)
2025.05.11
コメント(0)
-

美空ひばりさんの悲しい酒
〇斉藤茂さんによれば「悲しい酒」は美空ひばり以前に北見沢淳という歌手がレコード化したもののヒットしないまま歌手を止めた経緯があったようです。この曲は「酒は涙か溜息か」の現代版との注文で、石本美由起氏も簡単に請け合ったのに、いざ書くとなると二行詩は結構難しくて、悶々と過ごされた由。石本氏いきつけのバーで偶然隣に座ったホステスから身の上話を聞かれた。彼女は夫と別れ、夜の勤めをしながら子供を育てている事からヒントを得、「ひとり酒場で 飲む酒は 別れ涙の 味がする」の一番そして「飲んで棄てたい 面影が 飲めばグラスに また浮かぶ」の二番、次々に六番まで出来上がったそうな。 この歌詞を見た古賀政男氏は四行詩に仕立てて、作曲し三番の歌にまとめられたので、一番には飲むが三か所、二番には酒が二か所、三番には泣くが二か所使われています。本来は巧い遣り方ではないのですが、曲想にぴったりする結果となって、ひばりの歌唱力と相まって、ヒットしたと言うことです。
2025.05.10
コメント(0)
-

神がかりな奇跡は起こり得る
〇旧約聖書を紐解けば、イエズス様が手を差し延べると病気が治ったとか、極端な例では盲人の視力が一瞬にして回復したとか記述されていますが、反論に糸目をつけない大学の教授陣は別室に待機いただくとして、そう言った超常現象であっても、先入観さえ払拭すれば、有り得そうだなと思えなくもありません。 凡そ天才とか麒麟児とか称せられた人々は神々から選ばれた特異な人物で、名曲を作ったり、前例のない建物を拵えたり、千年後にも伝わる物語を創作したり、不朽の絵画を残したり、英雄と崇められる戦さ上手だったり・・・。 一方では、数百年前の故人の魂に乗り移って宣託を伝えたり、数十年前の事故死の霊になって恨みつらみを述べたり、動物霊を駆除するなどと言う霊媒と自称する特殊技能者は信じることはできませんが、特殊なパワーを発することが出来る人々は「有って然るべし」と70%程度の信頼を託すこともケースバイケースでは肯定出来そうに思います。己を神格化しないで、ひたすら日々迷える人々の救済に勤しむ特殊技能を持つ人の存在は肯定できるように思います。
2025.05.09
コメント(0)
-

ほっこり絵てがみ
〇東京テレビ「和風総本家」で茶の間をほっこりさせて下さったのが今は亡き地井武男さん。或る時は「椎茸」の着ぐるみで喫茶へ、呼び出しが「しいたけお」さまとあるなど、親しみを醸し出すお人柄でした。彼にテレビ朝日から東京近郊の散歩の案内役のオファーがあった時、散歩の終りには必ず1枚の絵を描かせて貰うことを条件にされたようです。その集積が新日本出版社による『地井さんの絵手紙』として10数年前に出版されました。テレビ番組収録は200回を越え、その同じ数の作品が残っているのですが、その内の40枚が上梓された次第です。何とも言えない味わいのある絵は大評判で、伝統の職人技、古さと新しさが絶妙に調和する街風景などを纏めた第2~5(最終)集が発刊されています。
2025.05.08
コメント(0)
-

土御門天皇御陵ちかくの桐大樹
〇わが家の坂を真っ直ぐ下りたところのお宅には以前、ハンカチの木がありました。このお宅の奥にはには温室もあり、門前には大きなさくらんぼの木があったのが、今や15台おける貸しガレージとなってしまいました。。 このお宅に沿った道近くの田圃は今も健在、真向かいに有った無花果の栽培地も無くなりました。無花果ってまるで水稲みたいに畝に水が湛えられていました。他所より時期が遅く、8月のはじめ早朝から百姓家にご近所の買い手が並びました。 小泉川を渡って爪先上がりの道を行けば住宅地と田舎風の田畑が混在する山手になり、景色も長閑になっていきます。村の小さな祠に手をあわせ、田舎道を行けば土御門天皇御陵が祀られ、その手前の岐れ路を行けば野草がいっぱい咲いています。この村の墓群近くには数本の桐の木があり、それはそれは見事。野いちご、きんぽうげ、紫色の草花に混じって、淡いピンクの昼咲月見草も捨てがたい風情です。
2025.05.07
コメント(0)
-

九一のばあ
〇昭和43年頃、東京は西久保には「樽小屋」という名のアングラ酒場があったそうな。大きなビヤ樽を型どった壁面に入り口があって、階段を降りてゆく。店内もビヤ樽型で天井は弧を描き、壁面にはヒッピーのポスターが貼りついている。右側がカウンター、左側と奥にテーブルがあって、夕刻になるとすぐに若い男女で満杯になる。肩と肩がくっつきあいそうな混み具合で70人を収容するところ。ステレオが鳴り響き、わずか3畳分ぐらいしかないフロアーではミニスカートやヒッピー髭の若者たちがゴーゴーダンスを踊りまくっている。昭和の良き時代の風物詩。これと似た雰囲気の店が京都にもあって、その名「九一のばあ」。ほぼ夜通し飲み明かすこともできる庶民的な、カウンターと畳敷きのある店。いろんな職種の男女が転がり込んでくる穴場?
2025.05.06
コメント(0)
-

西郷どんの恋人
〇昔の祇園近辺の表通りには骨董屋が多く、早目に店じまいするので宵を過ぎると暗かったようです。 それでも都をどりが近づき、祇園だんごの紅提灯がお茶屋軒にぶら下がると、いかにも春めいた賑わいを見せていたそうな。幕末には、勤皇の志士達が祇園で一献酌みながら日本の将来を語っていたようで、銅像からも解る大男の西郷さんは得意の相撲甚句を唄ったり踊ったり、無邪気に遊んでいたようです。桂小五郎は三木本の幾松を、大久保利通は祇園一力の娘おゆうを、後藤象二郎は先斗町の小仲を贔屓にしていましたが、西郷さんは奈良富の仲居のお末さんにに気があったようです。しょっちゅう口説いては、あっさり諦めていたとのこと。もうひとり、心底好きだった仲居さんにお虎さんが居て、二人に共通する特徴は、二十貫以上もある大ぽっちゃり系なのでした。徳川征伐に西郷さんが出発する時は、お虎さんは隊列に連れ添い、大津まで見送るほど切ない別れだったようです。 昔も昔に私にが観た新作歌舞伎の演目に「西郷と豚姫」があって、西郷さんの人柄と豚姫さんであるお虎さんの一途な気持ちは、子供ごころ乍らも、それとなく記憶に残っているのです。
2025.05.05
コメント(0)
-

太眉毛の時代。
〇古くは『魏志倭人伝』に「朱丹をもって、その身体に塗る」とあるように、古墳の埴輪には男女ともに顔面には朱が塗りこめていました。 時代は下って、紫式部の作品に「若くきたなげなき女ども五、六十人ばかりに、裳袴というもの白く着せて、白き笠ども着せて、歯ぐろめ黒らかに、紅赤こう化粧させて続けたりとあって、平安時代の女性たちの化粧は、眉と歯がポイントだったように思われます。毛抜きでげじげじ眉の手入れを怠らず、平安末期から鎌倉時代には、額の生え際と目の間に、大きく眉を描くようになっていたようです。
2025.05.04
コメント(0)
-

6年前の記録帖
〇6年前、4月に詠んだ句について、この場を借りて控えて置こうと思います。◎春宵や石塀小路の黙明かり〇真贋を問ふ美人図や春の宵◎花篝ひと夜限りの恋つづり〇花万朶倖せすぎて怖いほど〇色帯を展げる畑やチューリップ〇揚雲雀えんぴつ削る肥後守 肥後守=ひごのかみ=小刀〇葉桜や水占ひの水のいろ うみ〇行春の湖に釣り人動かざる うみ おか〇湖の波陸にのぼれば青葉騒 湖面を走るさざ波、それが陸へのぼって来ると重なり合う葉桜の擦れる音になってしまう。〇残る鴨番もをれば孤に浮くも鴨の殆どは北国に帰っていきますが、日本に留まる鴨もいます。つがいになって残る者も居れば、恋に破れたショックで残留しながら独り波に揺れる者も。〇庭球の音長閑なり釣り日和
2025.05.03
コメント(0)
-

声量恐るべし。
〇イタリアに再々行かれていたオペラ界の権威・河原廣之さんはもう30数年も昔、マントバという町で居酒屋に立寄られた折、仕事を終えた男達が10人ほど、ワインを飲み、賭け事や話に興じていたところ、あご髯を生やした中年の恰幅の良い男が河原さにんに近づき、グラスにワインを少し入れるや、あ~~あ~~と力のこもった声を彼に浴びせ始めたのです。それは大声ではないけれど、紛れもなく芯のあるテノールの声でした。なおも男はグラスに向って叫び続けます。 と、突然、グラスはこなごなに砕けて床に飛び散りました。男の声帯から出る振動、波長にグラスが共鳴し始め、やがて極限に達して砕けたのです。イタリアの名テノールと言われたマリオ・デル・モナコがミラノのスカラ座で歌うと、大天井のシャンデリアが揺れて鳴り出したと言います。恐るべき声帯の持ち主なのでした。(参考図書:上前淳一郎著『読むクスリ』)
2025.05.02
コメント(0)
-
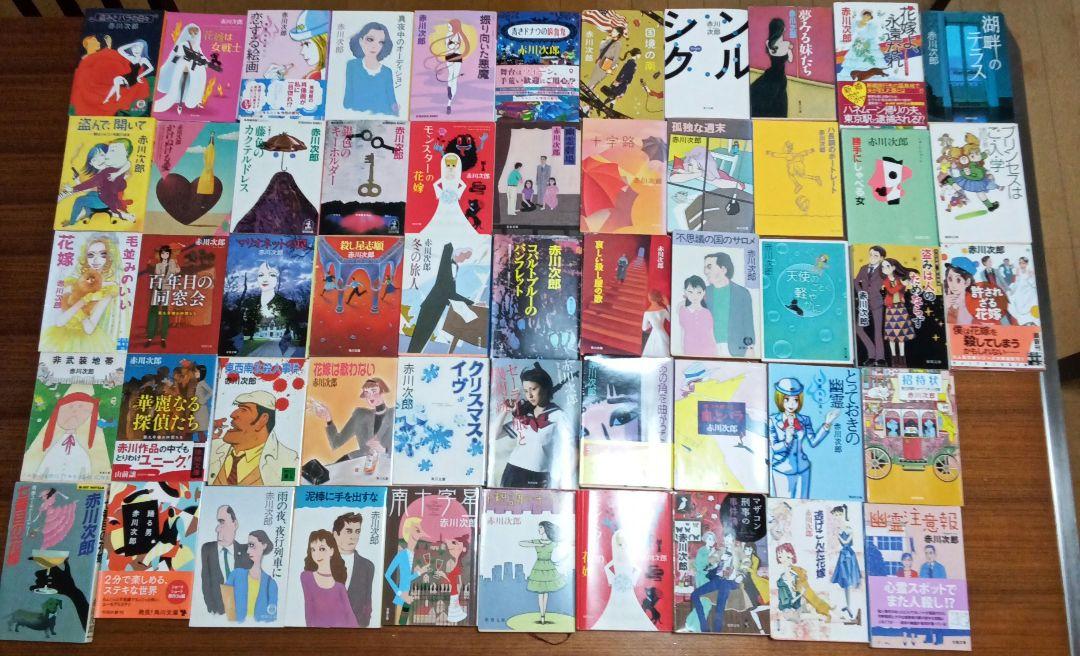
十二支と推理小説
〇十二支をテーマにした推理小説として「十二支殺人事件」(山前譲編、天山文庫)によれば、 *子・・・「ねずみ穴」泡坂妻夫丑・・・「牛に引かれてお礼まいり」赤川次郎寅・・・「人食い虎」遠藤周作 *卯・・・「うさぎさんは病気」仁木悦子辰・・・「切手収集事件」中町信巳・・・「蛇の環」高木彬光 *午・・・「幻の馬」皆川博子未・・・「二匹目の幸せな羊はいま」新羽精之申・・・「踊る手なが猿」島田荘司 *酉・・・「東宮鶏」日影丈吉戌・・・「白い騎士は歌う」宮部みゆき亥・・・「イノシシを買いに来た男」斎藤肇 *と言った作品が挙げられ、また、今西錦司著「自然と山」(筑摩書房)には、子ノ泊山(三重、907m)、牛松山(京都、627m)、虎子山(滋賀・岐阜、1181m)、赤兎山(福井・石川、1629m)、竜門ケ岳(奈良、904m)、蛇谷ケ峰(滋賀、901m)白馬山(和歌山、958m)、羊蹄山(北海道、1893m)、 *猿ケ山(富山、1448m)、鶏冠山(滋賀、491m)、犬伏山(広島、791m)、白猪山(三重、620m)など記されているとか。
2025.05.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










