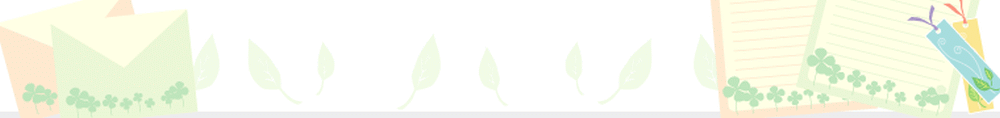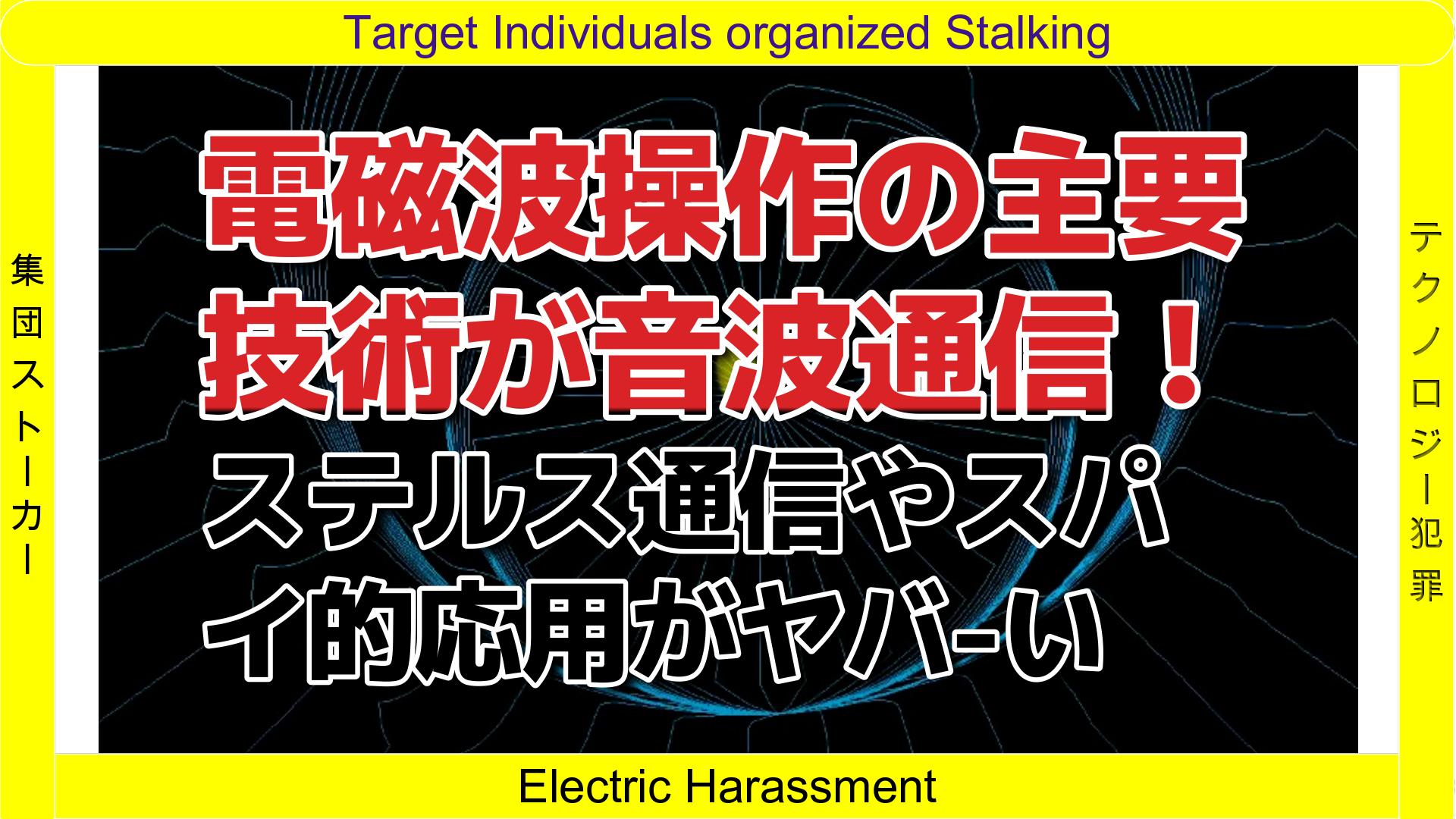全10612件 (10612件中 1-50件目)
-
●Royal Crown 王冠
++++++++++++++++++++++++++++++++https://youtu.be/WuTWfb6BkGg++++++++++++++++++++++++++++++++A king who received a ribboned spiral of kingship from a God with the mace, or a bar of divine authority became the king of that land and ruled over people. In other words, the royal spiral with a ribbon was a symbol of royal authority.The king who was given the spiral wore the spiral ring on the back of his head, and eventually the royal spiral became a ring, and kings with royal authority began to wear it on their heads.This remains today as the royal crown.This remains as a royal crown today. As proof of this, even today, royal crowns are called the "Royal Crown.""Royal" originally means "servant of God." 神権をもつ神から、リボンのついた王権スパイラルを渡された王は、その土地の王となり、人間を統治しました。つまりリボンのついた王権スパイラルは、王の権威の象徴ということになります。 で、その王権スパイラルを渡された王は、そのスパイラル・リングを頭のうしろにつけていましたが、やがてその王権スパイラルはリングとなり、王権をもった王たちは、頭の上に飾るようになりました。それが現在、王冠として残っています。その証拠に、現在の今も、王冠のことを、「Royal Crown」と言います。「Royal」というのは、もともとは「神の僕」という意味です。
2025年03月22日
-
●Two Geoglyphs, created by Alienエイリアンが描いた2つの地上絵、証拠と証明
++++++++++++++++++++++++++4943【00新重】Two Geoglyphs,drawan by the same Aliens 同じエイリアンによって描かれた2枚の地上絵+ブライスとサーン・アッバスhttps://youtu.be/bJZMy_HJOGg++++++++++++++++++++++++++If I were to say that the same aliens drew these two geoglyphs, I am sure you would say: "Don't say nonsense. If you have evidence, show me the evidence." Yes, that's right. I will show you the evidence now, but these two geoglyphs were drawn by the same aliens who can fly freely in the sky. Moreover, these two geoglyphs were directional lines indicating their respective bases. Hiroshi Hayashi もし私が、これら2つの地上絵が、同一エイリアンによって描かれたものであると、私が言ったら、みなさんは、こう言うだろうと思います。 「くだらないことを言うな。その証拠があるなら、証拠を見せろ」と。 はい、そうです。 これからみなさんにその証拠を見せますが、これら2つの地上絵は、空を自由に飛ぶことができるエイリアンによって描かれたものです。 しかもそれら2つの地上絵は、それぞれの拠点を示す、方向指示ラインだったのです。
2025年03月12日
-
●What is Buddha, where is he from?ブッダとは何か? どこから来たのか?
++++++++++++++++++++++++++++++++++〇4942【00テスト新重】The Magnificent Tale of Buddha, from UK to Lumbini英国からルンビニへ+ブッダの壮大な物語https://youtu.be/X6pTyKL7jGU++++++++++++++++++++++++++++++++++1: In Cerne Abbas in the UK, there is a giant geoglyph called the "Giant of Cerne Abbas."Since this giant is holding a club, this giant must be Heracles.1:UKのCerne Abbasに、「Cerne Abbasの巨人」と呼ばれる、巨大な地上絵があります。棍棒をもった巨人であることから、この巨人は、Heraclesということになります。Hiroshi 2: The club this giant is holding is pointing exactly in the direction of the Giza Pyramid #2.You can tell that this giant is Hercules by drawing a line between Cerna Abbas and the Giza Pyramid #2.Directly below this line is the town of Relna, the city of the legendary nine-headed Hydra.In Relna, Hercules used his club to defeat Hydra.2:この巨人がもっている棍棒は、ギザのピラミッド#2の方向を正確に向いています。その巨人が、ヘラクレスであることは、Cerna Abbasとギザのピラミッド#2を線でつないでみると、わかります。その真直線下に、9つの頭をもったHydra伝説の、Relnaの町があります。ヘラクレスは、そのRernaで、その棍棒を使って、Hydraを倒します。 3: The Pxxx, or his genital organ of this giant also points exactly in the direction of Lumbini in present-day Nepal, which is said to be the birthplace of Buddha.But why Lumbini?So I must explain my theory of two Buddhas, which I, Hiroshi Hayashi, have proven.3:またこの巨人のPxxxは、正確に、ブッダの生まれ故郷と言われている、現在のネパールのLumbiniの方向を示しています。が、なぜLumbiniなのでしょうか。そこで私、Hiroshi Hayashiが証明した、Buddha2人説を説明しなければなりません。 4: There were two Buddhas.One is Buddha’s father, Suddhodana, and another one is his son, Seda arta.His father was also the king of the Saka tribe, or Scythians, and the highest-ranking priest of Babylon, Magi.However, after the death of King Kyurus 1, who unified Persia, Suddhodana was driven out of Babylon by a plot by Darius 1 and fled to present-day Lumbini.There he married a human woman, Mayan, and had a son, Seda arta Gaumata.4:ブッダは2人、いました。父親のSuddhodanaと、息子のSeda arta です。その父親は、Saka族、つまりスキタイト人の王でもあり、バビロンの最高位の神官、MMagiでした。が、ペルシアを統一したKyurus1王の亡きあと、ダリウス1の謀略により、Babylonを追われ、現在のLumbiniへ逃げてきます。そこで人間の女性のMayanと結婚し、息子のSeda arta Gaumataをもうけます。 5: This is depicted in the inscription and relief of Dairius 1, which remain on Mount Behistun.The inscription states that Darius ascended to the throne after defeating Magi Gaumata, and on the left edge of the relief, Darius is seen trampling Gaumata under his foot.5:その様子を表現したのが、Behistun山に残る、Dairius1の碑文と、レリーフです。その碑文には、ダリウスがMagi Gaumataを倒したあと、王位についたと記され、またそのレリーフの左端で、ダリウスがガウマタを足で踏みつけています。 6: But who is this Gaumata mentioned in the inscription and relief?Is it really Suddhodana, the father of Buddha?6:が、この碑文とレリーフに記されている、ガウマタとは、誰なのでしょうか?本当に、ブッダの父親のSuddhodanaなのでしょうか? 7: But this Suddhodana was Suddhodana Gaoumata, the father of Buddha.As proof, there is a statue of Hercules holding a club at the top of Mount Behistun.So this connects to the Heracles of Cerne Abbas in the UK.Hercules holding a club, also known as Maitreya.The Pxxx of the giant of Cerne Abbas accurately points in the direction of Lumbini.So Suddhodana, the father of Buddha, was not only Buddha's father, but also Babylon's highest priest, Magi.This is the conclusion, again.So Suddhodana, the father of Buddha, was not only Buddha's father, but also Babylon's highest priest, Magi. 7:が、そのSuddhodanaは、ブッダの父親のSuddhodana Gaoumataでした。その証拠に、そのBehistun山の頂点に、棍棒をもったヘラクレス像があります。つまりここでUKのCerne AbbasのHeraclesとつながります。棍棒をもったヘラクレス、またの名をMaitreyaです。そのCerne Abbasの巨人のPxxxは、正確に、Lumbiniの方向を示しています。 つまりブッダの父親のSuddhodanaは、ブッダの父親であると同時に、Babylonの最高位の神官、Magiだったということになります。もう一度、その結論を繰り返します。つまりブッダの父親のSuddhodanaは、ブッダの父親であると同時に、Babylonの最高位の神官、Magiだったということになります。
2025年03月12日
-
●The Statue of Liberty? 自由の像?
●The Statue of Liberty 自由の像 This statue is generally called the "Statue of Liberty," although I don't know who first said it.I, Hiroshi Hayashi, also thought so.But why does the "Statue of Liberty" hold a torch?Also, because this statue is chained around its leg, it is generally thought to have been modeled after Prometheus.I, Hiroshi Hayashi, also thought so.But this statue is not "Prometheus."Prometheus would not hold a torch.この像は、一般には、誰が言いだしたかはわかりませんが、『自由の像』と呼ばれています。私、Hiroshi Hayashiも、そう考えていました。しかしなぜその『自由の像』が、松明などもっているのでしょうか。 またこの像は、足に鎖を巻かれているため、一般には、プロメテウスをモデルにして作られた像と考えられています。私、Hiroshi Hayashiも、そう考えていました。しかしこの像は、『プロメテウス』ではありません。プロメテウスは松明など、もちません。Hiroshi This statue represents the image of a god who holds a torch to lead humans to a bright shining world, who are chained around their feet and trapped in the depths of darkness, into a world outside of the darkness.In other words, the "Statue of Liberty" is indeed a "statue that leads the people to freedom," in a sense but it is also a "statue that reveals the image of a god" that leads humans from the darkness into a world of bright light.The proof of this is Guernica, said to have been painted by Pablo Picasso.I also thought that the painting of Guernica was modeled after the Statue of Liberty, but in fact it's the other way around.The figure in Guernica is a god who guides humans from the darkness to the outside world.In other words, the Statue of Liberty was made and Guernica was painted based on that story. Needless to say, that story is the story of Plato's "Allegory of the Cave." この像は、足に鎖を巻かれ、闇の奥に閉じ込められていた人間を、松明をもって闇の外の光り輝く世界に人間を導く神の姿を表現した像ということになります。つまり『自由の像』は、確かに『民衆を自由に導く像』ですが、人間を闇の中から、明るい光の世界へと導く、『神の姿を現した像』ということになります。 その証拠が、Pablo Picassoが描いたと言われている、あのゲルニカということになります。 私もゲルニカのその絵は、『自由の像』をモデルにして描かれた絵と判断していましたが、実はその逆。ゲルニカの中のその人物は、闇の中から人間を外の世界へ導いている神ということになります。つまりその話を基本に、『自由の像』が作られ、ゲルニカの絵が描かれたということになります。 言うまでもなく、その話というのは、プラトンが書いた『洞穴の比喩』の物語ということになります。 Hiroshi
2025年03月02日
-
●Mona Lisa モナリザ
+++++++++++++++++++++++++++++●4924【00新】Cain's Message in Mona Lisa,Evil God of Mars火星の邪神モナリザに隠されたカイン・キリストの伝言https://youtu.be/1kxUmjtvhYAhttps://www.youtube.com/watch?v=1kxUmjtvhYA+++++++++++++++++++++++++++++The safest way to live in this human world is not to see anything unnecessary, say anything unnecessary, listen to anything unnecessary, and do nothing unnecessary.That’s to say we do only what is prescribed for each day, and then we protect this world together.For example, Mona Lisa is the one, which is said to have been painted by Da Vinci.この私たち人間世界で、最も無難な生き方は、余計なことは見ないこと、余計なことは言わないこと、余計なことは聞かないこと、そして余計ないことは何もしないこと。日々に決められたことだけを無難にこなし、あとはその世界を互いに守り合う。たとえばダビンチが描いたと言われるモナリザ。Hiroshi The painting has a scorpion in the upper right, a snake in the lower left, and a dog in the lower right.Also, on the left side of the Mona Lisa, the number 351 is written from top to bottom.If you divide this number in two and take out the 51, it means "Mars" in Jewish gematria.If you read 351 from bottom to top, it becomes 153, which means "Nergal, the god of Mars."Nergal's three pets are a scorpion, a snake, and a dog.その絵の中には、右上にサソリ、左下に蛇、そして右下に犬が描かれている。またモナリザの左横には、上から数字の351が書かれている。この数字を2つに分け、51を取り出すと、ユダヤのゲマトリアでは「火星」を意味する。また351を下から読むと、153となり、153は、「火星の神・ネルガル」となる。ネルガルの3つのペットは、サソリ、蛇、犬。 And in the background of the Mona Lisa, there is a panoramic view of Mars, upside down.Needless to say, Mona Lisa is an anagram of Mars Aion, the god of Mars.そしてモナリザの絵の背景には、上下逆さまだが、火星のパノラマ風景が描かれている。言うまでもなく、Mona Lisaは、Mars Aion、つまり火星の神のアナグラムである。 Also, the number "27" is written on the right sleeve of Mona Lisa.27 means "Cain" in Jewish gematria.また、モナリザの右袖には、「27」という数字が書かれている。27は、ユダヤのゲマトリアでは「Cain」を意味する。 Furthermore, in Isleworth Mona Lisa, a sister work of Mona Lisa, a scorpion, a snake, and a dog are drawn from the upper left, and the earth of Mars is accurately drawn in the background.Objects that seem to be trees growing on Mars are also accurately depicted.さらにモナリザの姉妹作である、Ileworth Mona Lisaの中にも、左上からサソリ、蛇、犬が描かれ、その背景には、火星の大地が正確に描かれている。火星に生える樹木と思われる物体も、正確に描かれている。 From these facts, it can be said that Mona Lisa was painted by Cain Christ using Nergal, the god of Mars, as a model.以上のことから、モナリザは、火星の神ネルガルをモデルにして、カイン・キリストが描いたものであるということになる。 However, in this human world, we should not see anything unnecessary, say anything unnecessary, hear anything unnecessary, and do nothing unnecessary.In other words, that is the safest way to live.が、この私たち人間世界では、余計なことは見ないこと、余計なことは言わないこと、余計なことは聞かないこと、そして余計ないことは何もしないこと、と。つまりそれがもっとも無難な生き方であるからである。 If you think this is not the case, then I would like you to confirm these facts with your own eyes once again.Then use your own thinking ability to make a judgment.Or will you continue to repeat meaningless research and debates such as, "Who is the Mona Lisa?" and, "Who painted the Mona Lisa?"でないと言うのなら、今一度、これらの事実をあなた自身の目で見て確認してみてほしい。そしてあなた自身の思考力を使って、判断してみてほしい。それともあなたは、これから先もずっと、「モナリザは誰か」「モナリザは誰が書いたか」と、意味のない研究と議論を、繰り返していくのか。 Furthermore, I say here, will you continue to overlook the "God" who is there and repeat this foolish history over and over again?さらに言えば、そこにいる「神」を見落としたまま、愚劣な歴史を、いつまでもいつまでも繰り返していくのか。
2025年02月24日
-
●Plato's Criticism on Socrates' Democracyソクラテスの、アリストテレスの民主主義論への反論
+++++++++++++++++++++++++++動画の詳細 - YouTube Studio+++++++++++++++++++++++++++In the Republic, Plato's Socrates raises a number of criticisms of democracy. He claims that democracy is a danger due to excessive freedom. He also argues that, in a system in which everyone has a right to rule, all sorts of selfish people who care nothing for the people but are only motivated by their own personal desires are able to attain power. He concludes that democracy risks bringing dictators, tyrants, and demagogues to power. He also claims that democracies have leaders without proper skills or morals and that it is quite unlikely that the best equipped to rule will come to power 民主主義への批判 プラトンは、ソクラテスの説く「民主主義」について、つぎのように批判している。プラトンは民主主義といっても、行き過ぎた自由はかえって危険であると主張している。またすべての人が、平等に、つまりは「人を支配する権利」を平等にもつというシステムの中では、他人のことを考えず、自分のンは個人的な欲動だけに動機づけられた、つまりは自分の個人的な動機づけられた、きわめて自己中心的な人でも、権力を手に入れることができるとプラトンは主張している。そしてつぎのように結論づけている。『民主主義には、独裁者、暴君、そしてデマゴーグ、つ引き寄せるリスクがあるり Wipedia English, AI翻訳はやし浩司mmaru
2025年02月20日
-
●Why in English Gematria? なぜイタリアで英語式のゲマトリアなのか?
【はやし浩司より、改めてみなさんへ】 +++++++++++++++++++++++++ ●英語ゲマトリアについて @WT-l6よりユダヤのゲマトリアは、ヘブライ文字を法則に従って数値に変換し、単語や文章を数値として扱う手法です。なんでイタリア人のレオナルド・ダ・ヴィンチが、ユダヤ(ヘブライ語)の手法、英語(GOD)を使うのでしょうか? ++++++++++++++++++++++++ ●なぜイタリアで、英語のゲマトリアを使うのか? 【はやし浩司より、みなさんへ】 この点について当初より、イタリア・ローマ在住の協力者のNicoさん(10年来の友人)に問い合わせていました。私も当初、なかなか理解できませんでしたが・・・。) で、その理由の第一は、イタリアでは、ラテン語やギリシア語が基盤になっていたとはいえ、つねに多民族が入れ替わり立ち代わり、出入りしていたということ。(日本でいうようなしっかりとした「国体」が、なかったということ。外国人の王が、統治したこともあるそうです。) だからそれぞれの分野で、いろいろな言語を流用していたとのこと。たとえば政治の世界では、スペイン語などなど。文化人はオランダ語や英語を使っていたとのこと。(言葉の言語ではなく、単語を使っていた)。 つまり日本人の私たちには、たいへんわかりにくいところですが、言語が、たいへん複雑に入り組んでいたということです。(今も入り組んでいる。)(最近まで、イタリアでは、「公用語はイタリア語」というような言い回しが、なされていましたよ。なぜわざわざそのような断りを入れなければならないのか? そのあたりにも、イタリア語の言葉としての複雑さが隠されているように思います。) その一例として、芸術の分野では、英語(単語)が、使われていたということです。現に使われていたわけですから、それについて、「なぜ?」と聞かれても、私にもわかりません。 日本でも終戦まで、医療の世界では、ドイツ語(単語)が使われていましたが、それと似たようなことが起きたのではないでしょうか。日本語には、その専門用語がなかったから、ドイツ語をそのまま使ったのではないでしょうか?あるいは権威の象徴? ともあれ、具体的には、ダビンチの名前などは英語式表記、ラファエロなどは、英語式とイタリア語式になっている、などなど。ゲマトリアについては、現在の今でも、オランダ、ベルギーなどでは、English Gematriaがふつうに使われています。(ベルギー在住の協力者のセジャーズ氏は、「22.55」という曲を発表していますが、英語のゲマトリアでは「Love」を意味します。 私がよく「古代ギリシア」という言葉を使うことについても、ギリシア人の研究者の方から、「君は、古代ギリシア人」という言葉を使うが、ギリシア人はギリシア人であって、現在のギリシア人は、古代ギリシア人とはまったく別のギリシア人だと、注意を受けたことがあります。 イタリアも含めて。地中海の国々の言語、使用単語は、日本人の私たちには理解できないほど、複雑なようです。 では、 はやし浩司
2025年02月18日
-
●To my Son, Cain 我が子、カインへ
+++++++++++++++++++++++●4918【00新重】テスト配Tears of God,How can we live?Who wants?神の涙+人間はどう生きるべきなのか?誰が永遠に生きたいか?https://youtu.be/eEATJq_ScYE+++++++++++++++++++++++Born as a human, my son Cain, listen carefully.You are there, trying to let go of my hand.But my son Cain, humans must not be allowed to live.If humans are allowed to live, this solar system will be destroyed.That is the "nature" engraved into humans, the "nature" they are born with.Humans have this destiny from the moment they are born.However, you are about to enter this human world.人間として生まれし、我が子カインよ、よく聞け。お前はそこにいて、私から手を放そうとしている。が、我が子カインよ、人間は生かしておいてはならない。人間を生かしておいたら、この太陽系は破壊される。それが人間に刻まれた「性」、生まれながらにしてもつ「性」。人間は生まれしときから、それを宿命としてもっている。その人間世界へお前は、今まさに、自ら入ろうとする。 Listen, Cain, is that really what you want?Do you really want to enter the human world?Will you abandon your godly self and live in this human world?Will you abandon your godly self and live alone?いいかカインよ、本当にそれがお前の望むことなのか。お前は本当に、人間世界に入ることを望むのか。神たる私を捨てて、人間世界で、それで生きていくのか。神たる私を捨てて、ひとりで生きていかれるのか。 Soon you will be attacked by an eternal hell of loneliness where you cannot even die.You will watch countless human dramas over and over again.Over ,over, over and over again.Can you really bear it?Who would want to live forever in such a world?やがて襲い来る、死ぬこともできない孤独の無間地獄。繰り返し、繰り返し、無数の人間ドラマを見ることだろう。繰り返し、繰り返し、そのまた繰り返し。お前は、本当にそれに耐えることができるのか。そんな世界で、だれが永遠に生きたいと思うのか。 Listen carefully, my son Cain, born as a human.Without me, your God, humans will only destroy themselves.How will humans live if they abandon their God?How will humans, and you, live from now on?人間として生まれし、我が子カインよ、よく聞け。私という神なしでは、人間は自滅するのみ。その神を捨てて、人間はどのように生きていくのか。この先、人間、そしてお前はどのように生きていくのか。
2025年02月17日
-
●Plato's Quotes プラトンの言葉
++++++++++++++++++++++++++日本語版●4912【00新】Plato=Cain's Quotes プラトン=カインの箴言(しんげん)集https://youtu.be/bFvNhtxvo9I++++++++++++++++++++++++++「身体運動は、強制されても身体に害を及ぼすことはないが、強制されて得た知識は心にとどまらない。」 「アイデアは万物の源である。」 「あなたと私のような二人の友人がおしゃべりしたい気分のときは、もっと穏やかに、もっと弁証法的に話さなければならない。『もっと弁証法的』というのは、私たちが本当の返答をするだけでなく、対話者が自分自身が知っていると認めているものだけに基づいて返答するという意味である。」 「目的が徳でなければ、知識は悪となる。」 「知恵の書庫は、すべての富よりも貴重であり、望ましいものはすべてそれと比較することはできない。したがって、真実、幸福、知恵、知識に熱心であると主張する人は、本を愛する者になる必要がある。」lato was an Athenian philosopher who was a student of Socrates and the teacher of Aristotle. With a plethora of interests and ideas from mathematics to political theory, his effect on philosophy and the nature of human beings has spread far and wide over millennia. Read more at: https://yourstory.com/2017/03/29-quotes-by-plato That said, here are 29 quotes on knowledge and learning from the Father of Western philosophy: “We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.” “A good decision is based on knowledge and not on numbers.” “Thinking – the talking of the soul with itself.” “There is no harm in repeating a good thing.” “Truth is the beginning of every good to the gods, and of every good to man.” “Knowledge without justice ought to be called cunning rather than wisdom.” “The first and greatest victory is to conquer yourself; to be conquered by yourself is of all things most shameful and vile.” “Wealth, and poverty; one is the parent of luxury and indolence, and the other of meanness and viciousness, and both of discontent.” “An empty vessel makes the loudest sound, so they that have the least wit are the greatest babblers.” “Opinion is the medium between knowledge and ignorance.” “If a man neglects education, he walks lame to the end of his life.” “All men are by nature equal, made all of the same earth by one workman.” “Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything.” “The measure of a man is what he does with power.” “The direction in which education starts a man will determine his future in life”. “Opinion is the medium between knowledge and ignorance.” “Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.” “Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.” “Bodily exercise, when compulsory, does no harm to the body; but knowledge which is acquired under compulsion obtains no hold on the mind.” “Ideas are the source of all things.” “When two friends, like you and me, are in the mood to chat, we have to go about it in a gentler and more dialectical way. By ‘more dialectical’, I mean not only that we give real responses, but that we base our responses solely on what the interlocutor admits that he himself knows.” “Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.” “A library of wisdom, is more precious than all wealth, and all things that are desirable cannot be compared to it. Whoever therefore claims to be zealous of truth, of happiness, of wisdom or knowledge, must become a lover of books.” “No one is more hated than he who speaks the truth.” “And what, Socrates, is the food of the soul? Surely, I said, knowledge is the food of the soul.” “The untrained mind keeps up a running commentary, labelling everything, judging everything. Best to ignore that commentary. Don’t argue or resist, just ignore. Deprived of attention and interest, this voice gets quieter and quieter and eventually just shuts up.” “False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil.” “Writing is the geometry of the soul.” “Necessity is the mother of invention.” “Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.”― Platotags: attributed-no-source, compassion, kindness10013 likesLike“Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.”― Platotags: love, poetry, song9916 likesLike“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.”― Platotags: darkness, dishonesty, fear, light, willful-ignorance4268 likesLike“Only the dead have seen the end of war.”― Platotags: dead, life-lessons, war, warriors3511 likesLike“The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.”― Platotags: philosophy2982 likesLike“Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.”― Platotags: discipline, education, mentoring, philosophy2588 likesLike“According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.”― Plato, The Symposium1481 likesLike“The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself.”― Plato, The Republictags: government, inferiority, politics, rule1473 likesLike“I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing.”― Plato, The Republictags: apology, knowing, nothing, paradox, plato, republic, socrates, socratic, wisdome1440 likesLike“Never discourage anyone...who continually makes progress, no matter how slow.”― Plato1209 likesLike“Love is a serious mental disease.”― Plato, Phaedrus1133 likesLike“One of the penalties of refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.”― Platotags: philosophy, politics1130 likesLike“The measure of a man is what he does with power.”― Platotags: character, power904 likesLike“good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws”― Platotags: laws, people883 likesLike“If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things.”― Plato, The Republictags: abilities, empowerment, equality, gender, instruction, jobs, men, skills, women, work804 likesLike“Ignorance, the root and stem of every evil.”― Plato794 likesLike“I'm trying to think, don't confuse me with facts.”― Plato766 likesLike“...and when one of them meets the other half, the actual half of himself, whether he be a lover of youth or a lover of another sort, the pair are lost in an amazement of love and friendship and intimacy and one will not be out of the other's sight, as I may say, even for a moment...”― Plato, The Symposiumtags: love, soulmates745 likesLike“Those who tell the stories rule society.”― Plato736 likesLike“There is truth in wine and children”― Plato, Symposium / Phaedrustags: aphorism717 likesLike“Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge. ”― Plato590 likesLike“Education is teaching our children to desire the right things.”― Platotags: inspirational561 likesLike“The madness of love is the greatest of heaven's blessings.”― Plato, Phaedrus549 likesLike“Courage is knowing what not to fear.”― Platotags: courage, fear536 likesLike“There are three classes of men; lovers of wisdom, lovers of honor, and lovers of gain.”― Plato519 likesLike“In politics we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a city or a state. When we are ill... we do not ask for the handsomest physician, or the most eloquent one.”― Platotags: philosophy, politics519 likesLike“You should not honor men more than truth.”― Platotags: honesty, honor, secrecy, truth506 likesLike“There are two things a person should never be angry at, what they can help, and what they cannot.”― Platotags: anger, angry, plato505 likesLike“When men speak ill of thee, live so as nobody may believe them.”― Plato483 likesLike“The beginning is the most important part of the work.”― Plato, The Republic
2025年02月11日
-
●Study the Past to know the Future未来を知るために過去を学べ(孔子)
+++++++++++++++++++++++++●4906-00https://youtu.be/CGqCF-9NIng+++++++++++++++++++++++++“Study the Past if You Would Define the Future.”—Confucius Omar ShehadehSpecial Envoy of UAE Minister of Foreign Affairs | StrategicWrites as follows 2017年12月18日 Confucius once said, "If one wants to run, one must learn to walk. If one wants to teach, one must learn. To define the future, one must study the past." This quote is simple yet profound. It reminds us that the past is essential for understanding the present and shaping the future.孔子はかつてこう言いました。「走りたければ、歩き方を学ばなければならない。教えたければ、学ばなければならない。未来を定義するには、過去を学ばなければならない。」この言葉はシンプルですが、深い意味があります。過去は現在を理解し、未来を形作るために不可欠であることを思い出させてくれます。 Without a knowledge of history, we are like a ship without a rudder, drifting aimlessly in the sea. We cannot understand the forces that shape our world or our challenges. We cannot learn from our mistakes or build on past successes.歴史を知らないと、私たちは舵のない船のように海をあてもなく漂っています。私たちは世界を創る力や変えるを理解することができません。私たちは間違いから学ぶことも、過去の成功を基盤にすることもできません。 The past is not just a collection of facts and dates. It is a story, a narrative that tells us who we are and where we come from. It records our triumphs, failures, hopes, and dreams. It is a source of wisdom and guidance, a tool we can use to make better decisions in the future.過去は単なる事実と日付の集まりではありません。それは物語であり、私たちが誰で、どこから来たのかを物語る物語です。それは私たちの勝利、失敗、希望、夢を記録しています。それは知恵と導きの源であり、将来より良い決断を下すために使えるツールです。 Of course, history is only sometimes pleasant. It is full of conflict, violence, and suffering. But it is also full of hope, progress, and innovation. By studying the past, we can learn from our mistakes and avoid repeating them. We can also identify the forces that drive change and use this knowledge to shape a better future.もちろん、歴史は楽しいことばかりではありません。争い、暴力、苦しみに満ちています。しかし、希望、進歩、革新に満ちています。過去を研究することで、私たちは間違いから学び、同じ過ちを繰り返さないようにすることができます。また、変化を促す力を特定し、その知識を使ってより良い未来を形作ることもできます。 UAE外務大臣特使 | 戦略コミュニケーション、国際外交 2017年12月18日
2025年02月06日
-
●Black Hole of the Heart 心のブラックホール
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++●Black Hole of the Heart "I can't live anymore," you say, in this extreme, extreme world.When you become as small as that tiny point,All hope is lost, and people call this "despair." Light loses its shadow, sound stops, breath suffocates, and heartbeats disappear.The darkness hardens like ice, the past crumbles, and the future stops.The memories that should be there are gone, and there is nothing to support you. No family, no friends, no yourself. Loneliness and despair.Regrets that can't be satisfied, and a sea of repentance that washes over you.Self-hatred and self-denial, you just claw at your heart. It is truly a black hole of the heart beyond the darkness of the abyss.All light disappears there, unable to be seen or touched.But the God of Time is merciless, crushing you with the power of the stars. Ah, your soul floats in the air, and now all fear disappears.Your body and the bones that support you lose their shape and float there like smoke.There is no sound, no voice, no up or down, you just surrender yourself to it. But when you become zero, that is the beginning of everything.A ray of light shines in the darkness, and the next moment it explodes.It emits an intense flash, and in an instant it illuminates the vast universe. It is a generous world that shines with love, full of comfort and peace.A calm world without conflict, hatred or jealousy.A white hole in the heart after the ultimate world, known only to God. It's not difficult. All you have to do is curl up.Like a baby in its mother's womb, fold your arms and sleep quietly.All that's left is to let yourself go, and quietly pass through your mother's pelvis. With eyes dry of tears, and a gentle, warm melody,a new dawn awaits there, and it will greet you there. ●心のブラックホール 「もう生きられない」と、極限の、そのまた極限の世界。その極小の一点にまで自分が小さくなったときすべての望みを絶たれ、それを人は、「絶望」という。 光は影を失い、音は止まり、息は詰まり、鼓動は消える。暗い闇が氷のように固まり、過去は崩れ、未来は止まる。そこにあるはずの思い出もなく、支えるものは何もない。 家族もいない、友もいない、思い出もない。孤独と絶望。悔やんでも悔やみきれない後悔と、押し寄せる懺悔の海。自己嫌悪と自己否定、あなたはただただ心臓をかきむしる。 それはまさしく、深淵の闇のかなたの心のブラックホール。見ることも、触ることもない、すべての光はそこで消える。が、時の神は情け容赦なく、星の力であなたを押しつぶす。 ああ、あなたの魂は宙に舞い、いまでは恐怖心も消える。肉体とそれを支える骨は形を失い、煙のようにそこに漂う。音もなく、声もなく、上下もなく、ただひたすら身を任す。 が、あなたがゼロになったとき、それがすべての始まり。暗闇に一条の光が輝き、つぎの瞬間、それは爆発する。強烈な閃光を放ち、一瞬にして大宇宙を明るく照らし出す。 そこはおおらかな、安らぎと平和に満ちた愛に輝く世界。争いもなければ、憎しみもねたみもない、穏やかな世界。神のみが知る、究極の世界のあとの、心のホワイト・ホール。 難しいことではない。あなたがすべきことは、体を丸める。母親の胎内にいる赤子のように、腕を組み、静かに眠る。あとはなすがままに、静かに母親の骨盤をくぐり抜ける。涙さえ乾いた目を、やさしくも温もりのある調べとともに、新しい夜明けがそこで待っている。あなたをそこで迎える。はやし浩司2025-02-05
2025年02月05日
-
●Poem on Vanity 詩{虚飾)
++++++++++++++++++++++https://youtu.be/yPY-Xbut-60++++++++++++++++++++++●虚飾 虚飾に溺れし者は、虚飾を求め、さらに虚飾に溺れる。その目に映るものは、他人の心、よどんだ腐った姿。あとはその錯覚の中で、自らの虚像に酔いしれる。 自分を支える中身など、探してもどこにもない。その心は空虚で、冬の乾いた風のようで空しい。が、虚栄心だけは亡霊のようにその人を包む。 若い娘が化粧に、化粧を重ねるように、心を飾る。心を偽り、世に悲しむ人を、悲しんで見せる。嘘に嘘を重ねて、自分を偽り、他人を欺く。 ありもしない善意と良心、そして正義と道徳。金にまみれたヘドロのような悪臭と、憎悪の念。そこにあるのは、底なしの欲望、ただの大食漢。 嘆け、苦しめ、もがけ、恐れろ、無間の孤独地獄。メッキがはがれるときの、骨を削る苦痛と恐怖。落ちろ、もがけ、そこは魂をつぶす底なしの海。 あとに残るは、風に舞う一陣の乾いた砂ぼこり。どこからともなく吹いてきて、そしてそのまま消える。名声も地位も、肩書も、そしてその虚飾も、そのまま消える。 はやし浩司(Feb. 5th, 2025) ●Vanity Those who are addicted to vanity seek vanity, and become addicted to vanity.What they see is the hearts of others, their stagnant and rotten appearances.Then, in that illusion, they become intoxicated with their own false image. No matter how much they search, they cannot find anything to support them.Their hearts are empty, as hollow as the dry winter winds.+++++++++++++++++++●4905(Poem)+++++++++++++++++++But vanity alone envelopes them like a ghost. They decorate their hearts like young girls putting on makeup after makeup.They lie in their hearts, and make those who are sad about the world appear sad.They lie on top of lie, deceiving themselves and deceiving others. Goodwill and conscience that don't exist, nor justice and morality.The stench of gold-covered sludge, and hatred.All that is there is bottomless desire, just a glutton. Mourn, suffer, struggle, and fear the hell of eternal loneliness.The pain and fear that chips away at the bones as the veneer comes off.Fall, struggle, it's a bottomless sea that crushes the soul. All that remains is a gust of dry dust blown by the wind.It blows in from nowhere and then just disappears.Fame, status, titles, and all their pretensions just disappear. Hiroshi Hayashi (Feb. 5th, 2025)
2025年02月05日
-
●Salvator Mundi=Cain's Workサルヴァトール・ムンディはカイン作+証拠と証明
+++++++++++++++++++++++++●4905ー00+++++++++++++++++++++++++Salvator Mundi Cain Christ left many messages for humans through his messenger, Leonardo da Vinci.And in each of his works, he wrote the number "27", which is his signature, but before I explain that, please pay attention to Cain Christ's unique handwriting.Cain wrote "2" in a handwriting similar to "S".He also wrote "7" in a handwriting similar to the Japanese character "へ".Cain Christは、彼のメッセンジャー、Leonardo da Vinciを通して、数多くのメッセージを人間に残しました。そしてそれぞれの作品には、彼の署名である「27」という数字を書き残しましたが、その前に、Cain Christ独特の書体に注意してください。Cainは、「2」を「S」に近い書体で、書いていました。また「7」を、日本語の「へ」に近い書体で、書いていました。Hiroshi And here is a painting, which is generally called "Salvator Mundi".It seems that the number "27" is also written in the sleeve on the left side of this painting.However, if you only look at this, some people may think, "Yes, it does look like that, but it's hard to read this as 27".で、ここに一枚の絵画があります。一般には、「Salvator Mundi」と呼ばれている絵画です。どうやらこの絵画の左端の、袖の中にも、その「27」が、書いてあるように見えます。が、ここだけですと、「そう、そのようにも見えるが、これを27と読むのには無理がある」と思う人もいるかもしれません。 However, in a similar handwriting, Cain also wrote what appears to be a number that can be read as "27" in the painting of Mona Lisa.Compare the "27" in the Salvator Mundi with the "27" in the Mona Lisa.You can see that they are very similar to each other.が、同じような書体で、Cainは、Mona Lisaの絵の中にも、「27」と読むことができる数字らしきものを書いています。Salvator Mundiの中の「27」と、Mona Lisaの中の「27」を見比べてみてください。これら両者は、それぞれたいへんよく似ているのがわかります。 However, these are "27," or the signature of "Cain."I will explain this in the next two videos.If you watch the next two videos, you will surely think:Yes, it is indeed "27."And then you will think:" The Salvator Mundi also must be a work by Cain Christ?" I will return to this scene again at around 50-minute later to explain my conclusion.が、これらは「27」、つまり「Cain」の署名です。それをつづく2本の動画の中で説明します。もしつぎの2本の動画をご覧くだされば、あなたもきっとこう思うことでしょう。たしかに「27」だと。そしてつぎにこう思うことでしょう。「Salvator MundiもまたCain Christの作品だったのか」と。
2025年02月03日
-
●In the World of the Endless Hell of Loneliness孤独と言う無間地獄の中で
++++++++++++++++++++++++https://youtu.be/PQ8nScaIxJ4++++++++++++++++++++++++When the human Cain broke ways with the god Jehovah, Jehovah shed tears.Cain also had tears in his eyes.The parting of father and son is so painful and sad.In other words, these tears are condensed not only the story of God and man woven by all of the paintings in the Sistine Chapel, but also the entire human history of the earth woven by God and man.Jehovah said to Cain."Are you really able to break away from me and live in the human world?""Are you really able to live your life carrying the burden of the endless hell of loneliness, there in the world for you, unable to die?" 人間カインが神エホヴァと決別するとき、エホヴァは涙を流した。カインも目に涙を浮かべた。父と子の別れは、かくも切なく、悲しい。つまりこの涙の中に、システィーナ礼拝堂のすべての絵画が作りあげる、神と人間の織りなす物語のみならず、神と人間の織りなす地球史のすべてが凝縮している。神はカインにこう言った。「お前は、私という神を捨てて、本当に人間世界で生きていくことができるのか」と。「死ぬこともできず、お前はその世界で孤独という無間の地獄を、本当に背負うことになるのだぞ」と。
2025年02月01日
-
●Hayao Miyazaki’s"How do you live"+宮崎駿の「君たちはどう生きるか」は神の作品?
+++++++++++++++++++++++++++++●03048 Red Belt Incident赤い帯光事件+同じ赤い帯が宮崎駿作品「君たちはどう生きるか」の中で使われていたhttps://youtu.be/7jmyFEkOpBY+++++++++++++++++++++++++++++It was around 4am on the morning of February 5th, 2024.No sooner than I opened the window I saw a red belt moving across the sky from near above to far into the eastern sky.At that moment, I thought it was a red shooting star.Its tip was sharp like a Japanese sword, its outline was completely straight, and it emitted a deep, fiery orange light.It lasted only about three or four seconds, but just when I thought it had passed the peak of the mountain ahead, the whole belt disappeared in an instant.For me, it was the most mysterious experience of my life. 2024年の2月5日の朝、時刻は午前4時ごろのことでした。私が今の窓を開けると、天空を赤いベルトが、手前上空から遠方、東の空へ移動していくのが見えました。瞬間、私はそれを「赤い流れ星だ」と思いました。先端は、日本刀のようにとがっていて、輪郭は直線的で、燃えるような深いオレンジ色の光を放っていました。時間にすれば3~4秒のことでしたが、前方の山の頂点にさしかかったと思った、その瞬間、全体がパッと消えました。私にとっては、生涯、もっとも不思議な体験でした。Hiroshi
2025年01月28日
-
●Dark History of God 神々の世界における血なまぐさい抗争事件
+++++++++++++++++++++++++++++++●Dark History of God神々の世界における血なまぐさい抗争事件、エンキ、ニンフルサグ、シャマーシュ、イエスは神々によって殺されたhttps://youtu.be/117cNXQLkes+++++++++++++++++++++++++++++++The Jesus who was crucified and killed was a substitute for Messenger Jesus. The original Messenger Jesus was just a messenger of Shamash, Jesus who was instructed by Cain Christ. But both Shamash and Messenger Jesus were killed by Inanna and others. The substitute Jesus was then crucified and killed. So who was this substitute Jesus and where did he come from? In this video, I will consider this mystery, but the key to solving it was left behind by Antonio Campi in 1569 in a painting titled "The Mysteries of the Passion of Jesus Christ." Although the painting itself was created by Cain, a hint to solving the mystery of the substitute Jesus is hidden within the painting. "The Mysteries of the Passion of Jesus Christ" itself is the life story of the substitute Jesus. In other words, if we look at it carefully, you can understand who the substitute Jesus was and where he came from.Hiroshi 十字架にかけられ殺されたイエスなる人物は、Messenger Jesusの替え玉だったということになります。もともとのMessenger Jesusは、ShamashのMessengerであり、Cain Christに指導されたJesusです。が、そのShamashとMessenger Jesusは、Inannaたちによって殺されます。で、そのあと、替え玉イエスが、十字架にかけられ殺されます。 では、その替え玉イエスは、だれで、どこから来た男なのでしょうか。 この動画の中では、その謎について考えてみますが、その謎を解く鍵を、1569年、Antonio Campiが、「The Misteries of the Passion of Jesus Christ」と題された絵画の中に、描き残してくれました。もっともこの絵そのものは、カイン作ですが、その絵の中に、替え玉イエスについての謎解きのヒントが隠されていました。 その「The Mysteries of the Passion of Jesus Christ」そのものが、替え玉イエスの一代記ということになっています。つまりそれを見れば、替え玉イエスが誰で、どこから来たかがわかるというわけです。Hiroshi
2025年01月24日
-
●Two Painters, Gericault and Delacroix as Messengers ジェリコーとドラクロワ
+++++++++++++++++++++++++++Gericault+Delacroix=Cain Christ's Messengers,its Proofジェリコーもデラクロワも神カインのメッセンジャーだった、メデュースの筏https://youtu.be/F4fwUT92-8k+++++++++++++++++++++++++++Here you see two painters.One is T.J.Gericault.Born in 1791.His representative work is "The Raft of the Medusa."The other is EuGene Delacroix.Born in 1798.His representative work is "Liberty leading People." Both were French painters, and they painted very similar paintings.However, these two were not enemies, and it is said that they helped each other in their days.For example, Thedoere Gericault published "The Raft of the Medusa" in 1819, and it is well known that Eugene Delacroix gave Gericault various advice on the research and painting method.However, although I, Hiroshi Hayashi, do not know the relationship between the two, I have already proven that both TJ Gericault's "The Raft of the Medusa" and Eugene Delacroix’ Liberty, leading people were painted by artists who transcended in their days across time and space. In particular, I have determined that Theodore J Gericault's The Raft of Medusa was painted by Cain, based on the proof of Cain's signature 27. If that is the case, then surely Eugene Delacroix's painting must also have been painted by Cain? There is nothing strange about thinking in such a way that both are messengers of Cain Christ who descended in that era. I, Hiroshi Hayashi, will leave the rest to you to decide. ここに2人の画家がいます。一人は、T.J.Gericaultです。1791年生まれ。その代表作は「The Raft of the Medusa」です。もう一人は、EuGene Delacroixです。1798年生まれ。その代表作は「Liberty leading People」です。ともにフランス人画家で、ともにたいへんよく似た絵画を描いています。が、この2人は敵対関係にあったわけではなく、ともに助け合っていたと言われています。たとえばThedoere Gericaultは、1819年に「The Raft of the Medusa」を発表していますが、その調査および描き方について、Eugene Delacroixが、あれこれ助言をしていたという話は、よく伝わっています。 が、私、Hiroshi Hayashiは、2人の関係がどういうものかは知りませんが、TJ Gericaultの「The Raft of the Medusa」も、Eugene Delacroixも、ともに時空を超えた画家によって描かれた絵画であると、今までに証明してきました。とくにTheodore J GericaultのThe Raft of Medusaは、カインの署名の27があることなどから、Cain作であると判断しています。 となると、Eugene Delacroixの絵画もまた、Cain作ということになるのではないでしょうか。ともにその時代に降臨したCain ChristのMessengerであったと考えても、何もおかしくありません。あとの判断は、みなさんにお任せします。
2025年01月16日
-
03033 Cain Christ人間種の最高神にして、人間の救世主、かつ人間を指導してきたのは、カイン
+++++++++++++++++++++++++++●Cain Christ人間種の最高神にして、人間の救世主、かつ人間を指導してきたのは、カインhttps://youtu.be/v6XuwMahL-s+++++++++++++++++++++++++++Cain is the great ancestor of humans and therefore the supreme god of humanity.He is the savior of humans, who saved us humans from the alien Gods.Therefore it is Cain, Cain the Christ, who is a human leader across time and space. Those who worked as Cain's messengers were Plato, Leonardo, Pablo Picasso, Antonio Campi, Michelangelo B, Japanese Kaikei, Sotatsu Tawaraya, T J Gericault, and Walt Disney and so on. Of course, the man we call Jesus was also one of Cain's messengers.In other words, it is Cain who has guided tus, humanshese and wove the history of humanity.That Cain still now exists on Earth, warmly guiding us humans and watching over our future. 人間の大先祖にして、それ故に、最高神。それがCainです。私たち人間を、外来種のエリアンから救済した、人間の救世主。それがCainです。まさに時空を超えた、人間の指導者。それがCainです。そのCainのメッセンジャーとして働いたのが、Platoであり、Leonardoであり、Picassoであり、Antonio Campiであり、Michelangelo Bであり、日本Kaikeiであり、Sotatsu Tawarayaであり、T J Gericaultであり、Walt Disneyということになります。もちろん私たちがJesusと呼ぶその方も、Cainのメッセンジャーだったということになります。 つまりこうした人たちを指導し、人間の歴史を織り上げてきたのが、Cainということになります。そのCainは、現在の今も、この地球に存在し、私たち人間を温かく指導し、同時に人間の行く末を見守っています。 Hiroshi
2025年01月13日
-
●Silicon-based Life forms シリコン人間
++++++++++++++++++++https://youtu.be/DfuVMoaIBMA++++++++++++++++++++●Silicon based life To put it simply, living creatures on Earth are carbon-based life forms.However, extraterrestrial life forms, especially Grey aliens, are said to be silicon-based life forms and organisms.The evidence is the crop circle that appeared in Chibolton,UK.2001The crop circle clearly depicts a picture of Grey alien, and together with this picture it clearly shows that it is a silicon lifeform.To put it simply, Greys, who are silicon lifeforms, live in a sulfurous world, breathing in sulfurous air and emitting sulfur dioxide.Just like us or living things on Earth breathe oxygen and emit carbon dioxide... 地球の生物は、わかりやすく言えば、炭素生物。が、地球外生物、なかんずくグレイ・エイリアンは、シリコン生物だという。証拠はチボルトン、UKに現れたクロップ・サークルということになる。そのクロップ・サークルには、グレイ・エイリアンの姿が明確に描かれ、シリコン生命体であることが明確に描かれている。わかりやすく言えば、シリコン生物であるグレイは、硫黄世界で、硫黄空気を吸い、二酸化硫黄を排出していることになる。ちょうど地球の生命体が、たとえば人間が酸素を吸い、二酸化炭素を排出しているように、である。 ++++++++++++++++++++++++++++++ 1:Tommy V8008 writes about Silicon- vs Carbon-Based Life Forms as follows; Carbon and silicon share many similarities, and I think silicon comes closer to carbon than any other element in terms of potential for forming life. I know some properties might make it more difficult, since silicon is not quite as flexible as carbon. However, assuming it were possible, what might that kind of life form look like? What materials could be formed out of a silicon base? Would they be rigid? Tommy V8008という方の論文をそのまま紹介させていただきます。 ●シリコンと炭素ベースの生命体 炭素とシリコンには多くの類似点があり、生命体を形成する可能性という点では、シリコンは他のどの元素よりも炭素に近いと思います。シリコンは炭素ほど柔軟ではないため、いくつかの特性により困難になる可能性があることは承知しています。しかし、それが可能だと仮定すると、そのような生命体はどのように見えるでしょうか。シリコンベースからどのような材料を形成できるでしょうか。それらは硬い生命体なのでしょうか。 2:If silicon based life exists it would likely have some unique challenges. Due to the chemical nature of silicon bonds, while it might be more resilient in some environments, in general it would be limited to a more limited range of extremes. Where very high and very low temperatures leave carbon based life concerned more for the cell walls being damaged by how the water in our body reacts to those temperatures like frostbite. シリコンベースの生命体が存在する場合、おそらくいくつかのシリコン生物特有の課題があるでしょう。シリコン結合の化学的性質により、一部の環境ではより耐性があるかもしれませんが、一般的にはより限定された極端な範囲に限定されます。たとえば非常に高い温度や非常に低い温度では、炭素ベースの生命体は、凍傷のように体内の水分がその温度に反応して細胞壁が損傷することがあります。 3:The cellular break down for a silicon life form from temperature would occur because those silicon bonds themselves would break down at extreme temperature. It would be something akin to what occurs to carbon based life when bombarded by radiation and cells lose the ability to reproduce or maintain the integrity of the body. が、シリコン世物は温度によるシリコン生命体の細胞の崩壊は、それらのシリコン結合自体が極端な温度にさらされたようなとき、破壊されます。これは、放射線に襲われて細胞が再生能力を失ったり、体の完全性を維持したりするときに炭素ベースの生命体に起こることと似ています。 4:These bonds are also more susceptible to certain kinds of chemical reactions, which would limit the kinds of environments they could enter without additional protection as well as limiting what they might consume. これらの結合は特定の種類の化学反応の影響を受けやすく、追加の特殊な保護なしでは、新しい環境での生活が制限され、生活そののも制限されるということになります。 5:For that reason silicon based life would likely have a distinctive means of absorbing energy and sustain their bodies. They may have some form of radical photovoltaic process for instance, where light interacting with their body generates the bio-electircal and biochemical sources of energy. そのため、シリコンベースの生命体は、エネルギーを吸収して体を維持するための独特の手段を持っている可能性があります。たとえば、彼らは何らかのラジカル光起電プロセスを持っているかもしれません。光が彼らの体と相互作用して、生体電気および生化学エネルギー源を生成します。 6:Or they too could rely on a chemical process like digestion, such that they derive energy from the oxidizations and break of oxide bonds that occurs as they breath... but that could also occur on on their "skin" too and not necessarily internally; at which point they'd either secrete something like a sandy gel or shed something like sand the same way organic life might have dry skin. または、消化などの化学プロセスにも依存している可能性があります。呼吸時に発生する酸化などによってエネルギーを引き出します。ただし、これは必ずしも体内部ではなく「皮膚」でも発生する可能性があります。その時点で、有機生命体が乾燥した皮膚を持つのと同じように、砂のようなゲルのようなものを分泌するか、砂のようなものを落とす可能性があります。 7:In general if silicon based life existed it would either be rigid by human standard, or it would have to be chemically complex or mechanically/structurally complex with a simpler chemical structure to be anything remotely like an animal. 一般的に、シリコンベースの生命が存在する場合、人間の基準で考えると硬いか、化学的に複雑であると考えられます。つまりより単純な化学構造を持つ機械的/構造的に複雑でなければ、この地球上における動物にとても似ているとは言えません。 8:A silicon based animal, you're looking at something that's either exoskeletal in nature, like a crab or insects, or something with a layered lattice of scales upon scales like a big reptile; though its structure would be something more like armored scalemail that below the layer of scales the continuous material of those scales becomes almost an interwoven mesh like chainmail to hold it all together. そのためシリコンベースの動物は、カニや昆虫のように本質的に外骨格を持つか、大きな爬虫類のように鱗の上に鱗が重なった格子状のものになるはずです。ただし、その構造は装甲鱗の鎧のようなもので、鱗の層の下では、それらの鱗の連続した素材が、鎖かたびらのように織り合わされた網目になり、体全体をまとめているはずです。 9:Whichever the case underneath that you'd likely have a variety of silicon-gel like organs... structures and voids to facilitate the movement of different silicon-solvents, liquid silicates, and silicon based liquids to facilitate the distribution the materials necessary to perpetuate its life. The liquids inside a silicon based lifeform would generally be oily, with a sticky quality that makes many of these kinds of liquids precursors for industrial glues. いずれにせよ、その下には、さまざまなシリコンゲルのような器官、構造、空隙があり、ちょうど人間の血液のように、さまざまなシリコン溶剤、液体ケイ酸塩、シリコンベースの液体の移動を容易にして、生命を永続させるために必要な材料の分配を容易にします。シリコンベースの生命体の内部の液体は、一般的に油状で、粘着性があるため、これらの種類の液体の多くは工業用接着剤の前駆体になっているほどです。 ●Some additional considerations... 10:Silicon based life and their secretions would likely be odorless to us, regardless of its alive or dead. Partially because of the chemical structures of these compounds partially because our evolution has us optimized to smell volatile organic compounds. その他の考慮事項.としてはつぎのように考えられます。 シリコンベースの生命体とその分泌物は、生きているか死んでいるかに関係なく、おそらく私たちには無臭です。これらの化合物の化学構造のため、また進化によって揮発性有機化合物の匂いを嗅ぐように最適化されているためです。 Silicon based life could have some interesting colorations partially depending on the complexity of the chemical structures that make up their outer layer, but in general almost any color of rock or sand you can imagine, and it wouldn't necessarily have any relationship to their immediate environment. シリコンベースの生命体は、外層を構成する化学構造の複雑さに応じて、興味深い色彩を持つ場合がありますが、一般的には想像できるほぼすべての色の岩や砂と同じように考えられます。また、周囲の環境と必ずしも関係があるわけではありません。 11:For instance it might be an interesting quality of your alien to have its coloration change with age. At the same time many silicon pigments can glow under conditions and could potentially lead to a chemiluminescent or bioluminescent organism. たとえば、エイリアンの色が年齢とともに変化するというのは、興味深い特徴かもしれません。同時に、多くのシリコン色素は条件によって光ることができ、化学発光または生物発光する生物につながる可能性があります。nインゲン
2025年01月11日
-
●Artist beyond Time and Space,Cain 時空を超えた芸術家=カイン・キリスト、すべてカイン作
4875【12】Artist beyond Time and Space,Cain時空を超えた芸術家=カイン・キリスト、すべてカイン作+++++++++++++++++++++++https://youtu.be/YHR0zn97GRw+++++++++++++++++++++++++++
2025年01月06日
-
●Stupidity of Humans 人間の愚かさについて
++++++++++++++++++++++++++https://www.youtube.com/watch?v=9f1TZxEvWiw+++++++++++++++++++++++++++
2025年01月06日
-
●BW教室の動画、数千本が復活しました! バンザーイ!
●BW教室が復活しましたこの4~5年、消失していたBW教室の動画、数千本が復活しました。https://bwopenclass.ninja-web.net/page018.htmlこのアドレスを一度、コピーし、検索窓の中に、アドレスを張り付けて、ページを開いてください。長い間、行方不明になっていたページです。バンザーイ
2025年01月06日
-
●Humans are just Animals with God's Eyes人間は神の目をもったただの動物である工事中
++++++++++++++++++++++++Artist beyond Time and Space,Cain時空を超えた芸術家=カイン・キリスト、すべてカイン作https://youtu.be/YHR0zn97GRw++++++++++++++++++++++++Exactly 300 years after Da Vinci's death, a painter named Theodore Gericault painted a masterpiece in 1819.This painting is titled "The Raft of the Medusa."In it, however, there is a figure wearing a flower crown.The face of this figure is the same as that of Leonardo da Vinci.There is a difference in age, young and old, but they are the same.ダビンチが亡くなって、ちょうど300年後に、Theodore Gericaultという画家が、1819年に、一枚の大作を描いた。それが『The Raft of the Medusa』と題された絵画である。が、その中に一人の花冠をかぶった人物が描かれている。この人物の顔と、Leonardo da Vinnciの顔は、同じである。老若の違いはあるが、同じである。Hiroshi I, Hiroshi Hayashi, believe that this figure is Jesus himself, who crossed the Mediterranean Sea to escape persecution by Inanna Maria, but that is not the point of today's video.The important thing is that it is Cain himself who painted this masterpiece.As proof of this, in the bottom right of the painting, there is the number "27" written in Da Vinci's handwriting.In Jewish gematria, "27" means "Cain."私、Hiroshi Hayashiは、この人物は、イナンナ・マリアの迫害を逃れて地中海を渡る、イエス自身であると判断しているが、それは今日のこの動画のポイントではない。大切なことは、この大作を描いたのは、カイン自身であるということ。その証拠に、この絵の右下に、ダビンチの書体で「27」と書いてある。「27」は、ユダヤのゲマトリアでは、「カイン」を意味する。 A figure wearing the same flower crown was also painted by Michelangelo B about 300 years ago in a painting titled "The Battle of Cascina."The figure in the lower right corner of that painting is the figure in question.Needless to say, it was Leonardo da Vinci who added the beard to this figure. Thus, the two paintings, "The Raft of the Medusa" and "The Battle of Cascina," are connected by the portrait of Leonard da Vinci. で、その花冠をかぶった人物を、同じく約300年前に、Michelangelo Bが、「The Battle of Cascina』と題された絵画の中に描いている。その絵の右下に描かれている人物がその人物である。この人物に、ひげを付けたのが、Leonardo da Vinciの顔ということは、言うまでもない。 こうして2枚の絵、「The Raft of the Medusa」と「The Battle of Cascina」が、Leonard da Vinciの肖像画でつながった。
2025年01月06日
-
●Picasso's Guernica ピカソのゲルニカ
If I were asked what physical evidence proves the existence of God, I would point without hesitation to "Guernica," which is said to have been painted by Pablo Picasso. Guernica depicts facts that Pablo Picasso could never have painted in 1937.I, Hiroshi Hayashi, explain this fact step by step in this video, and if you learn it, I'm sure you will agree with me."Oh, I see, that's how it is. Pablo Picasso's Guernica is truly a work of God." And that Guernica is the work of the god Cain.It is a work that the god Cain painted to let us know of his existence. 神の存在を証明する物的証拠は何かと、問われれば、私は迷わずPablo Picassoが描いたと言われる、『ゲルニカ』を指摘します。 そのゲルニカの中には、1937年当時のPablo Picassoが絶対に描くことができない事実が、描かれているからです。 この動画の中では、それを順に説明しますが、もしあなたもそれを知れば、あなたもきっとこう思うことでしょう。「なるほど、そうだったのか。Pablo Picassoのゲルニカは、まさしく、神の作品だった」と。 そしてそのゲルニカは、神カインの作品でした。神カインが、自分の存在を私たちに知らせるために、神カインが描いた作品だったのです。 Hiroshi *************************** 4875【00】Cain Christ who saved Humanity from Anu's Extinction Projectエホヴァの人類絶滅計画から人間を救済したカインhttps://youtu.be/axoFVWrFB3s 4875【01】Enki,murdered by Enlil,Nergal in Mithras Statueエンキはエンリル、ネルガルに殺害されていた+証拠はミトラ像https://youtu.be/fDkXDSIBN-M 4875【02】Two Jesus Christ,Shamash Jesus and Cain Christイエス+キリスト2人説、シャマーシュとカインinイエスの洗礼https://youtu.be/y7iC7myTGbI 4875【03】Inanna=Ishtar=Iaster=Maria in Roman Catholicismローマ・カトリックにおける、イシュタール=イナンナ=マリアhttps://youtu.be/q3xLy_FYJiE 4875【04】Cain,who saved Hum,anity from Armageddon人類滅亡から人間を救済したカイン、だから人間の救世主!https://youtu.be/mS3_JrbH3_Q 4875【05】Cain stpped Armageddon by Jehovah=Anuエホヴァ=アヌによる人類絶滅計画を阻止したカイン救世主!https://youtu.be/ImUj88Oo8Tw 4875【06】Replacement of Jesus painted Leonardo,Campi,Picassoダビンチ、カンピ、ピカソの描いた十字架にかけられた替え玉イエスhttps://youtu.be/6pbYKqEkouk 4875【07】Jesus' Love Story with Maria of Bethanyイエスのベタニアのマリアとの恋物語、そして一大悲劇https://youtu.be/CJgOtA5c0aU 4875【08】Salvator Mundi=Marduk+Cain Christサルヴァトール・ムンディ=マルドックとカイン・キリストhttps://youtu.be/IJT_hdhG5w8 4875【09】There really exists Cain Christ in our Days現実に実在する神・カイン・キリスト=救世主https://youtu.be/GlYg9t1QN1I 4875【10R新追証】Cain,teaching Jesus in”Baptism of Jesus”「イエスの洗礼」の中でイエスにエンキの教えを指導するカインhttps://youtu.be/Yebf6kYUksw 4875【11】Cain as Artist beyond Time and Space+Guernica時空を超えた画家・カイン、ピカソのゲルニカhttps://youtu.be/6u8OgTFg7jU 4875【12】Artist beyond Time and Space,Cain時空を超えた芸術家=カイン・キリスト、すべてカイン作https://youtu.be/YHR0zn97GRw 4875【13新重*】The Physical Evidence of God Cain神カインの実在を証明する物理的証拠+ピカソのゲルニカhttps://youtu.be/jRP6-ae2hAI’s
2025年01月06日
-
●It is Cain who give Jesus Guidanceイエスを指導したのはカインだった
+++++++++++++++++++++++++●03022 Cain's Philosophy and his Thinking Circuitカインの哲学と思考回路+イエスを指導したのはカインだった説https://youtu.be/6kbfRN-7aNk+++++++++++++++++++++++++In this painting, the person standing in the center is Shamash Jesus, or just, Jesus.The person standing on the right is Cain Christ, or just, Cain.I will prove these facts later in the video, but what is Cain on the right doing to Jesus in the center?Cain is depicted holding some kind of vessel in his hand, but there is no way that Cain would baptize Jesus.So I, Hiroshi Hayashi, have determined that this painting disguise is a depiction of Jesus' baptism, but in fact it depicts Cain imparting an ideology to Jesus.As proof of this, a one-eyed bird, or the one-eyed Marduk, is depicted above Jesus' head.Marduk is the son of Enki, and a god even higher than Cain.In other words, the painting as a whole is a depiction of Cain injecting Marduk's ideas of freedom, equality, and fraternity into Jesus.この絵の中で、中央に立っている人物は、Shamash Jesus、つまりイエスです。右側に立っている人物は、Cain Christ、つまりカインです。それについての証明は、これからこの動画の中でしますが、では、右側のカインは中央のイエスに何をしているのでしょうか。カインは手に何かの器のようなものが描かれていますが、カインがイエスに洗礼するはずなど、ありません。そこで私Hiroshi Hayashiは、この絵は、イエスの洗礼に見せかけて、実はカインがイエスに思想を与えているところを表現したものだと、判断しています。その証拠に、イエスの頭の上に、片目の鳥、つまり片目のマルドックが表現されています。マルドックは、エンキの息子にして、カインよりさらに上位の神ということになります。つまりこの絵は全体として、マルドックの、自由、平等、友愛思想を、カインがイエスに思想として、注入している絵ということになります。
2025年01月02日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(24)
常識が偏見になるとき ●たまにはずる休みを……「たまには学校をズル休みさせて、動物園でも一緒に行ってきなさい」と私が言うと、たいていの人は目を白黒させて驚く。「何てことを言うのだ!」と。多分あなたもそうだろう。しかしそれこそ世界の非常識。あなたは明治の昔から、そう洗脳されているにすぎない。アインシュタインは、かつてこう言った。「常識などというものは、その人が一八歳のときにもった偏見のかたまりである」と。子どもの教育を考えるときは、時にその常識を疑ってみる。たとえば……。●日本の常識は世界の非常識(1)学校は行かねばならぬという常識……アメリカにはホームスクールという制度がある。親が教材一式を自分で買い込み、親が自宅で子どもを教育するという制度である。希望すれば、州政府が家庭教師を派遣してくれる。日本では、不登校児のための制度と理解している人が多いが、それは誤解。アメリカだけでも97年度には、ホームスクールの子どもが、100万人を超えた。毎年15%前後の割合でふえ、2001年度末には200万人に達するだろうと言われている。それを指導しているのが、「Learn in Freedom」(自由に学ぶ)という組織。「真に自由な教育は家庭でこそできる」という理念がそこにある。地域のホームスクーラーが合同で研修会を開いたり、遠足をしたりしている。またこの運動は世界的な広がりをみせ、世界で約千もの大学が、こうした子どもの受け入れを表明している(LIFレポートより)。(2)おけいこ塾は悪であるという常識……ドイツでは、子どもたちは学校が終わると、クラブへ通う。早い子どもは午後1時に、遅い子どもでも3時ごろには、学校を出る。ドイツでは、週単位(※)で学習することになっていて、帰校時刻は、子ども自身が決めることができる。そのクラブだが、各種のスポーツクラブのほか、算数クラブや科学クラブもある。学習クラブは学校の中にあって、たいていは無料。学外のクラブも、月謝が1200円前後(2001年調べ)。こうした親の負担を軽減するために、ドイツでは、子ども1人当たり、230ドイツ・マルク(日本円で約14000円)の「子どもマネー」が支払われている。この補助金は、子どもが就職するまで、最長27歳まで支払われる。 こうしたクラブ制度は、カナダでもオーストラリアにもあって、子どもたちは自分の趣向と特性に合わせてクラブに通う。日本にも水泳教室やサッカークラブなどがあるが、学校外教育に対する世間の評価はまだ低い。ついでにカナダでは、「教師は授業時間内の教育には責任をもつが、それ以外には責任をもたない」という制度が徹底している。そのため学校側は教師の住所はもちろん、電話番号すら親には教えない。私が「では、親が先生と連絡を取りたいときはどうするのですか」と聞いたら、その先生(バンクーバー市日本文化センターの教師Y・ムラカミ氏)はこう教えてくれた。「そういうときは、まず親が学校に電話をします。そしてしばらく待っていると、先生のほうから電話がかかってきます」と。(3)進学率が高い学校ほどよい学校という常識……つい先日、東京の友人が、東京の私立中高一貫校の入学案内書を送ってくれた。全部で70校近くあった。が、私はそれを見て驚いた。どの案内書にも、例外なく、その後の大学進学先が明記してあったからだ。別紙として、はさんであるのもあった。「○○大学、○名合格……」と(※)。この話をオーストラリアの友人に話すと、その友人は「バカげている」と言って、はき捨てた。そこで私が、では、オーストラリアではどういう学校をよい学校かと聞くと、こう話してくれた。 「メルボルンの南に、ジーロン・グラマースクールという学校がある。そこはチャールズ皇太子も学んだこともある古い学校だが、そこでは生徒1人ひとりにあわせて、学校がカリキュラムを組んでくれる。たとえば水泳が得意な子どもは、毎日水泳ができるように。木工が好きな子どもは、毎日木工ができるように、と。そういう学校をよい学校という」と。なおそのグラマースクールには入学試験はない。子どもが生まれると、親は出生届を出すと同時にその足で学校へ行き、入学願書を出すしくみになっている。つまり早いもの勝ち。●そこはまさに『マトリックス』の世界 日本がよいとか、悪いとか言っているのではない。日本人が常識と思っているようなことでも、世界ではそうでないということもある。それがわかってほしかった。そこで一度、あなた自身の常識を疑ってみてほしい。あなたは学校をどうとらえているか。学校とは何か。教育はどうあるべきか。さらには子育てとは何か、と。その常識のほとんどは、少なくとも世界の常識ではない。学校神話とはよく言ったもので、「私はカルトとは無縁」「私は常識人」と思っているあなたにしても、結局は、学校神話を信仰している。「学校とは行かねばならないところ」「学校は絶対」と。それはまさに映画『マトリックス』の世界と言ってもよい。仮想の世界に住みながら、そこが仮想の世界だと気づかない。気づかないまま、仮想の価値に振り回されている……。●解放感は最高! ホームスクールは無理としても、あなたも一度子どもに、「明日は学校を休んで、お母さんと動物園へ行ってみない?」と話しかけてみたらどうだろう。実は私も何度となくそうした。平日に行くと、動物園もガラガラ。あのとき感じた解放感は、今でも忘れない。「私が子どもを教育しているのだ」という充実感すら覚える。冒頭の話で、目を白黒させた人ほど、一度試してみるとよい。あなたも、学校神話の呪縛から、自分を解き放つことができる。※……一週間の間に所定の単位の学習をこなせばよいという制度。だから月曜日には、午後三時まで学校で勉強し、火曜日は午後一時に終わるというように、自分で帰宅時刻を決めることができる。●「自由に学ぶ」 「自由に学ぶ」という組織が出しているパンフレットには、J・S・ミルの「自由論(On Liberty)」を引用しながら、次のようにある(K・M・バンディ)。 「国家教育というのは、人々を、彼らが望む型にはめて、同じ人間にするためにあると考えてよい。そしてその教育は、その時々を支配する、為政者にとって都合のよいものでしかない。それが独裁国家であれ、宗教国家であれ、貴族政治であれ、教育は人々の心の上に専制政治を行うための手段として用いられてきている」と。 そしてその上で、「個人が自らの選択で、自分の子どもの教育を行うということは、自由と社会的多様性を守るためにも必要」であるとし、「(こうしたホームスクールの存在は)学校教育を破壊するものだ」と言う人には、次のように反論している。いわく、「民主主義国家においては、国が創建されるとき、政府によらない教育から教育が始まっているではないか」「反対に軍事的独裁国家では、国づくりは学校教育から始まるということを忘れてはならない」と。 さらに「学校で制服にしたら、犯罪率がさがった。(だから学校教育は必要だ)」という意見には、次のように反論している。「青少年を取り巻く環境の変化により、青少年全体の犯罪率はむしろ増加している。学校内部で犯罪が少なくなったから、それでよいと考えるのは正しくない。学校内部で少なくなったのは、(制服によるものというよりは)、警察システムや裁判所システムの改革によるところが大きい。青少年の犯罪については、もっと別の角度から検討すべきではないのか」と(以上、要約)。 日本でもホームスクール(日本ではフリースクールと呼ぶことが多い)の理解者がふえている。なお2000年度に、小中学校での不登校児は、13万4000人を超えた。中学生では、38人に1人が、不登校児ということになる。この数字は前年度より、4000人多い。 Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●笑い話 年長児のクラス。そのクラスでのこと。私「ぼくは、もうすぐ、ヨーシエン(要支援)になるよ」子「ちがうよ、先生、ヨーチエン(幼稚園)だよ」私「ううん、もうすぐ、要支援になるよ」子「幼稚園だってばア」私「そう言えば、君たちも、要支援だろ?」子「ちがうよ、幼稚園だよ」私「だって、自分でご飯をつくれないだろ?」子「つくれないよ」私「だったら、要支援だ」子「だから、要支援ではなくてエ、幼稚園!」私「お風呂で、頭を自分で洗えるか?」子「ぼくは洗えるけど、MK(妹)は洗えないよ……」私「だったら、MKちゃんは、要支援だよ」子「MKは、まだ幼稚園に行っていないよ」私「だから、そういう人を、要支援って、言うの」子「だから要支援ではなくて、幼稚園だってばア」私「要支援が終わると、要介護1年生になるんだよ」子「ちがうよ、小学1年生だよ」私「ちがうよ、要介護1年生だよ」子「1年生になって、それから6年生まで行くんだよ」私「要介護は、5年生までしかないの」子「5年生までしかないの?」私「そう。5年生まで」子「5年生が終わったら、どうなるの?」私「あの世行き。死ぬんだよ」子「死なないよ。5年生が終わったら、6年生だよ」私「でも、本当に6年生は、ないよ」子「ぼくは、HS小学校へ行くよ。ヨーカイゴ小学校なって、知らないよ」私「それはよかったね」と。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(038)【反面教師論】+++++++++++++++++++反面教師という言葉がある。しかし反面教師は、本当に教師なのか。教師たりえるのか。それについて考えてみたい。このテーマについて書くきっかけとなったのは、ある母親が話してくれた、彼女の息子の話だった。+++++++++++++++++++●犬の叱り方 ある母親が、仕事の休憩時間にこんな話をしてくれた。「息子に、犬を買い与えたのだが、その叱り方を見ていて、驚きました」と。 息子、つまり小学5年生のY君のことだが、そのY君は、犬を飼っている。飼い始めて、3年になる。「毎日、学校から帰ってくると、1時間は、その犬の世話をしているんですよ」とのこと。 それについて、母親は、こう言った。「Yは、ときどき、はげしく犬を叱るのですが、その叱り方を見て、驚きました。その口調、言い方、怒り方が、私、そっくりなのです。私は、私のいやな面を見せつけられたようで、ショックを受けました」と。 似たような経験は、私にも、ある。 私は、高校生のとき、英語の教師のMが、大嫌いだった。Mのする授業は、何の楽しみもない、一方的な(詰めこみ方式)だった。その教師の授業になるたびに、私は重苦しい憂うつ感に襲われた。 その私が、結果的にみると、英語が得意になったのは、英語という科目が好きだったからというよりは、内心では、「あんなMなんかに、負けてたまるか」と思ったからである。Mにバカにされるのが、何よりもいやだった。が、Mには、それがわからない。ときどき私の名前をみなの前で出して、「お前たちも、林のように、勉強しろ!」「こんな成績では、どうする!」とハッパをかけたりしていた。 私はいつもこう考えていた。「私は教師になっても、あんな教師にだけはならない」「私が教師になったら、あんなふうには教えない」と。 が、である。 その私が、このH市にやってきて、ある進学塾でアルバイト講師をするようになったときのこと。ある日、気がついてみると、私の教え方が、あの英語の教師、Mそっくりになのを知って、驚いた。口調、言い方、怒り方など、すべてが、である。 それだけではない、私も、生徒を、成績でしか、みていないことに気づいた。「お前もX君のように、勉強しろ!」「こんな成績では、どうする!」とか、何とか。●反面教師という「教師」 教師といっても、2種類、ある。手本としたい教師と、手本としたくない教師。手本としたい教師のばあい、その教師のすばらしい面を見ながら、自分の人格や人間性を、その教師に、より近づけようとする。もう1つは、手本としたくない教師。その教師を批評、批判しながら、「私は、ああいう人間だけにはならない」「ああはなりたくない」と、自分の中で、その教師を否定していく。 後者のような教師を、反面教師という。念のため、「日本語大辞典」(講談社版)をひくと、こうある。「反面教師……否定的なことを示すことによって、肯定的なものをいっそう明らかにするのに役立つこと」と。英語の格言も、併記してあった。 One from bad example another can learn.(悪い例から、ものを学ぶこと)と。 しかし反面教師が、本当に「教師」になりえるかというと、それは疑わしい。教師は教師。私の例を見るまでもなく、長くつきあっていると、その(手本としたくない部分)まで、受けついでしまう。影響を受けてしまう。 その典型的な例が、「虐待」である。●世代連鎖 虐待は、世代連鎖しやすい。親が子どもを虐待すると、その子どももまた、親になったとき、その子どもを虐待しやすい。それはよく知られた事実だが、その(子ども)に視点を置いて考えてみると、興味深いことに気がつく。 その子どもは、親から虐待を受けながら、心の中では、きっとこう思っているにちがいない。「私は、こういう親だけにはならないぞ」と。意識しないまでも、内心では、親に、大きく反発しているにちがいない。 つまりその子どもは、(虐待)されることについて、うらみ、のろっているはず。何よりも、そうした(虐待)を、恐れ、嫌っているはず。……こう簡単に決めつけてはいけないかもしれないが、虐待されて、それを喜ぶ子どもはいない。 が、その子どもが、親になったとたん、自分を超えた大きな力によって、今度は、自分で、自分の子どもに、虐待を加えてしまう。 その(虐待)に、ここでいう反面教師論をあてはめてみると、ピッタリとまではいかないが、反面教師というのがどういうものかが、よく理解できる。 虐待を受ける子どもにしてみれば、自分を虐待する親は、まさに反面教師ということになる。が、その自分が、今度は、親になったとき、自分の親と同じことを繰りかえしてしまう。自分の子どもに、虐待を加えてしまう。●つっかい棒 少し前に、私は、「つっかい棒」論を書いた。つっかい棒というのは、わかりやすく言えば、(自分を支える気力)ということになる。 たとえば目の前に、その反面教師がいたとする。その教師を見ながら、「私は、ああいう人間だけにはなりたくない」と思ったとする。そして自分がその教師のようになることを、心の中で抵抗する。 その抵抗する力が、ここでいう(つっかい棒)ということになる。 で、その(つっかい棒)がある間は、その人は、その人であることができる。しかしそのつっかい棒は、それほど強靭(きょうじん)なものではない。とくに、その反面教師となっていた人が、自分の前から消えたときには、そうである。同時に、そのつっかい棒も消える。 自分を支える必要がないからである。が、ここで思わぬ弊害が現れる。 そのつっかい棒がはずれたとたん、その反面教師としてきた人から受けた影響が、表に出てきてしまう。たいていは、自分ではそれに気がつかない。気がつかないまま、「ああいう人間にはなりたくない」と思った部分を、自分で再現してしまう。 それが冒頭にあげた、Y君と犬の例であり、私と英語教師の例ということになる。虐待については、もう少し別の角度から考えなければならない面もあるが、おおまかに言えば、同じように考えてよい。●反面教師の限界 つまり、これが反面教師の限界である。 私たちは日々の生活をしながら、手本としたい人たちから、何かを学び、一方、手本としたくない人たちからも、何かを学ぶ。 そのとき重要なことは、手本としたくない人たちを見たら、ただ批評や批判をするだけでは、足りないということ。長くつきあえばつきあうほど、へたをすれば、その人の人格や人間性に、染まってしまうということもある。「いやな人」「おかしな人」と思っていても、気がついてみると、自分も、その人そっくりになっていた……というような経験は、ひょっとしたら、あなた自身にも、1つや2つは、あるかもしれない。 そこで反面教師と感ずる人と接するときには、いくつかの鉄則がある。(1)批評、批判するだけでは、足りない その相手を、批評、批判することだけなら、だれにでもできる。しかしそれよりも重要なことは、自分の中に、それ以上の人格にせよ、人間性を、同時につくりあげていくこと。 すこし話はそれるが、もう少し深刻な例では、こんなこともある。 ある夫の妻が、あるカルト教団に入信してしまった。「修行」と称して、パートの仕事もやめ、ほとんど毎日、その教団内部で過ごすようになった。それについて、夫は、あれこれ資料を集め、妻にこう迫ったという。 「お前が信仰している教団は、インチキ教団だ。わからないのか!」と。 夫は、その教団を批判することによって、妻の信仰をやめさせようとした。が、妻は、それに応じなかった。応じなかったばかりか、かえって夫婦の亀裂(きれつ)を大きくしてしまった。 よく誤解されるが、カルト教団があるから、こうした信者が生まれるのではない。カルト教団を求める信者がいるから、カルト教団が生まれる。力をのばす。 夫のした行為は、屋根にあがった妻に対して、ハシゴをはずすようなもの。そういうことをすれば、かえって妻は、不安になるだけ。ますます信仰に埋没するようになる。 そこで重要なことは、夫自身が、そのカルト教団にかわる、(心のより所)を用意すること、ということになる。あるいはそのヒントを与える。「お前はまちがっている」と言うなら、それにかわる、何か別のものを用意しなければならない。 そこでその夫は、それまでの自分のあり方を反省し……ということになったが、このつづきは、また別のところで書くとして、同じように、反面教師を前にしたときには、「あなたはおかしい」「あなたはまちがっている」と批判するだけでは、足りない。それにかわる、もっと大きな(自分)を用意しなければならない。でないと、結局は、その反面教師そっくりの人間に、自分も、なってしまう。(2)人を選ぶ いろいろな人と幅広く交際する……ということは、重要なこと、ということになっている。しかしそれにも、1つの原則がある。 30代や40代の人には、まだひょっとしたらわからないかもしれない。しかし50代にもなると、自分にとって大切な人と、そうでない人の色分けが、ますますはっきりとしてくる。 利益があるとか、ないとか、そういうことではない。学ぶべきものがある人かどうか、ということである。中には、50代を過ぎて、ますます邪悪になっていく人もいる。そういう人と時間を共にするというのは、まさに時間の無駄ということになる(?)。 実は、この問題は、私にとっては、大きな問題だった。が、その結論を出してくれたのは、あるアメリカ人の青年が書いた、手記だった。その青年は、そのときHIVに感染し、エイズを発症していた。余命は、1年と宣告されていた。 その青年は、こう書いている。4年前に書いた原稿だが、それをそのまま、ここに転載する。++++++++++++++++++●人間関係 エイズと戦っている1人の患者の手記を読んだ。10ページ足らずの英文の手記だった。アメリカに住む若い人が書いた手記なので、それほど内容的には深い文章ではなかった。が、その中に、いくつか、はっと思うようなことが書いてあった。たとえばエイズになって、だれが真の友で、だれがそうでないかがわかったとか、家族の大切さが改めてわかったとか、など。が、その中でも、つぎのことを読んだときには、とくに強烈な印象を受けた。こうあった。「エイズが発病してからというもの、時間がたいへん貴重になった。意味のない人と、意味のない会話をすることが苦痛になった。そういう人とはすぐ別れる」と。 私も50歳を過ぎてから、ときどき、同じように思うようになった。が、最初は、それは悪いことだと思った。だれとでもつきあい、だれとでも会話をする。それが大切で、人を、意味のある人と、そうでない人に、区別をしてはいけない、と。しかし本当の私は、別のほうに進み始めた。いつも心のどこかで、意味のある人と、そうでない人を区別するようになってしまった。利益があるとか、ないとか、そういうことではない。が、そのことを思い知らされたのは、A氏(54歳)に出会ったときのことだ。 ほぼ25年ぶりにA氏に会った。偶然、通りを歩いていて会った。で、会話がはずみ、一緒に昼食でも食べようということになった。が、そのうち、会話がまったくかみあっていないことに、私は気がついた。たがいに、どこか薄っぺらい会話で、つかみどころがない。一通り家族や、仕事の話をしたのだが、それ以上に話が進まない。そこで聞くと、A氏はこう話してくれた。 「家での楽しみは、野球中継を見ること。休みは釣り。雨の日はパチンコ」と。「本や新聞は読んでいるのか。インターネットはしているのか」と聞くと、「読んでいるのは、スポーツ新聞だけ。インターネットはしていない」と。A氏はA氏なりに自分の世界で、自分の仕事をしてきた。しかしその25年間で、そしてその仕事を通して、A氏は何をつかんだというのか。 だからといって、私が「何かをつかんだ人間」と言うつもりはない。おそらくA氏から見れば、私はつまらない人間かもしれない。酒は飲まない。パチンコもしない。女遊びもしない。野球の話すら、できない。そういう意味では人の心というのは、カガミのようなもの。私がA氏をつまらない人間と思っているなら、(決して「つまらない人」と思っているのではない。仮に、そう思ったとするならという話)、同じようにA氏も私をつまらない人間と思っているはず。 が、私は正直に告白する。私はそのA氏と早く別れたかった。何かしら時間をムダにしているように感じだった。が、一方で、別の私がそれに抵抗した。「25年ぶりではないか」「友は大切にしなければならない」と。が、それでも「ムダ」という思いが、心をふさいだ。私は懸命に、自分にこう言って聞かせた。「お前は冷たい人間だ。ムダと思うのは、お前の冷酷さによるものだ」と。 しかし本当に私は冷たい人間なのか。「時間をムダにしている」と感ずることは、私が冷たいからなのか。今でもそれはわからないが、私はあるがままに生きてみようと思う。ムダと思ったら、ムダなのだ。そしてムダと思ったら、はやく別れればよい。……と考えていたところで、冒頭の手記を読んだ。だから強烈な印象を受けた。 その患者は、手記のあとがきによると、それから2年間の闘病生活のあと、なくなったという。つまりその手記を書いたとき、自分の命がそれほど長くないことを知っていたはず。私も50歳をすぎて、人生の終わりをそこに感ずるようになった。が、深刻さの度合いは、その患者とくらべたら、はるかに低い。そういう患者が、「時間がたいへん貴重になった。意味のない人と、意味のない会話をすることが苦痛になった。そういう人とはすぐ別れる」と書いている。その手記を読んだおかげで、私は私の生き方に自信をもったというか、「ああ、今のままでいいのだ」と、思いなおすことができた。 さて、私はこれから先、人間関係を整理する。たとえば今でも、表では、私の知人や友人のフリをしながら、うらで、敵対行為をしている人が、何人かいる。こうして書いたエッセーについても、いちいちアラを見つけては、「これはあの人のことだ」「ここに書いてあるのは、あんたのことだ」と、告げ口をしている人がいる。私はそういう人でも、知人や友人ということで、今まではつきあってきた。しかしもうやめる。そういう人は、知人でも友人でもない。私はかつて一度だって、個人攻撃をするために、文を利用したことなど、ない。それをしたら、私はおしまいとさえ思っている。いろいろな人のことは書くが、それは別の目的で書いている。そんなことは、私のエッセーの全体を読んでもらえば、すぐわかることではないか。……と、少し話が脱線したが、このところ、「生きるとはどういうことか」と、またまたよく考えるようになった。ムダが悪いわけではないが、私には今、ムダにできる時間など、どこにもない。それだけは確かのように思う。(02・9・14)++++++++++++++++++ 要するに反面教師と思うような人とは、つきあわないということ。「反面教師」と、「教師」という言葉を使うが、反面教師は決して、「教師」ではない。が、しかしそうはいかないばあいもある。 職場での人間関係、さらには、親戚、さらには親子や兄弟関係など。こちらがつきあいたくなくても、無数のしがらみに縛られて、それがままならないことがある。 そういうときは、どうすればよいのか? 実のところ、私にもよくわからないが、私のばあいは、「相手にしない」という方法で、対処している。表面的な交際はしても、そこまで。それ以上、深入りはしないようにしている。 さらに問題がこじれてきたようなときは、こうして文を書きながら、徹底的に、その人を自分の中から消すようにしている。そういう形で、自分の心を守らないと、あっという間に、その人の心が、私のほうに移動してきてしまう。今のところ、この方法は、私にととっては、うまく機能しているように思う。 少し疲れてきたので、この話のつづきは、また別の機会に考えてみたい。なお内容的にボロボロの原稿だが、後日、もう一度書き改めることを前提に、今は、このままにしておく。(はやし浩司 反面教師論 反面教師 育児論 子育て論) Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(039)【4年前に書いた原稿から……】+++++++++++++++++少し前、気分転換に……と思って、4年前に書いた原稿を読みなおしてみた。「なるほど」と思ってみたり、「あのときは、そう考えたのだな」と思ってみたり……。現在の自分と比較してみるというのは、それなりに楽しいことでもある。+++++++++++++++++●正直に生きることの勇気 この日本、正直に生きるということだけでも、勇気がいる。いや、勇気にも、2種類ある。他人に向かう勇気と、自分に向かう勇気だ。こんなことがあった。 魚屋でいくつかの食品と、煮干の入ったパックを3つ買った。一パック、800円。3パックで、2400円。しかしレジの女性は、一パック500円で計算し、3パックで1500円とした。私はおもむろに、「これは1パック、800円ですよ」と告げた。その女性はうれしそうに笑って礼を述べたが、私はその女性のためにそうしたのではない。自分自身のためにそうした。礼など言われる筋あいではない。 日々の積み重ねが月となり、月々の積み重ねが年となり、やがてその人の人格をつくる。で、その日々の積み重ねとは何かと言えば、その瞬間瞬間の行いをいう。もし私がそうした場面で、小ズルイことをしていれば、私はやがてそのタイプの人間になってしまう。たとえその場で、1000円近く「得をした」(?)としても、これは私にとっては大きな損失だ。が、私はここで考えた。 この日本では、資本主義が原則になっている。金儲けだ。で、その金儲けは何かということになれば、それは「だましあい」。私は自転車屋という商人の家に生まれ育ったので、そのあたりのだましあいが、どういうものであるかを、よく知っている。たとえば1000円で仕入れたものを、客の顔色を見ながら、2000円で売りつける。相手が、「高いね」と不満を口にすれば、その場で適当にウソを並べて、「まあ、いいでしょう。あなたですから、1500円にしておきます」と言う。こういう芸当が即座にできなければ、商人など務まらない。 ……となると、レジの女性が値段を打ちまちがえたということは、それはレジの女性のミスということになる。商人の世界では、ミスは、ミスしたものの責任ということになる。そのためこういうケースでは、客はふつう黙っている。こう書くと叱られるかもしれないが、少なくとも私が知っている世界では、黙っている。もともと商売というのは、そういうもの。だまされたとしても、だまされたほうが悪い。ミスをすれば、ミスをしたほうが悪い。つまりこの日本では、正直に生きようと思えば思うほど、損をする。そういうしくみができあがってしまっている。つまり正直に生きるということは、同時に損をするということ。自ら自分を損の世界に、押し込むことになる。だから勇気がいる。 この点、私のワイフは、純朴な女性だから、ものごとを深く考えない。あとになって、「おかしいと思ったけど、安くしてくれたのかしらと思ったわ」と、平然と言ってのける。人を疑うことすら知らないから、値段もそのまま信じてしまう。だから問題意識ももたない。が、私はそうではない。レジの女性がカチカチと打ったその瞬間、別の脳が同時進行の形で、合計金額を計算する。これは私のクセのようなものだ。だからレジの女性が値段を打ちまちがえると、即座に「ちがいますよ」と言う。そしてそういう能力が、かえってわざわいする。あれこれ悩む原因となる。 が、やはり正直に生きる。とくに私は、幼児期が貧しかったから、ふと油断すると、醜い自分に押し戻されてしまう。私はもともとは小ズルイ人間だし、小ズルイことをするのに、それほど抵抗がない。だから余計に、自分の老後が心配になる。今は何とか気力で、そういう醜い自分を押し隠している。が、その気力が弱くなったとき、それがモロに表面に出てくる。その可能性は、じゅうぶん、ある。それがこわい。こわいから、今から、少しずつ、自分を変えなければならない。時間がない。いや、もう間に合わないかもしれない。だから、私は正直に、そのレジの女性に、まちがいを告げた。しかしそれはあくまでも、私のためだ。レジの女性のためではない。だから礼を言われる筋あいではない。(追記) 岐阜は関西商人の経済圏に入っているから、ものの値段など、あってないようなもの。買い物にしても、定価(正札)で買う人などいない。即座にその場で、値段の交渉を始める。が、この浜松というところは、東京の経済圏に入っている。だから値段の交渉をする人はいない。私はこの浜松に移り住むようになって、35年になるが、そのため、いまだに戸惑いを覚えることがある。 そういう意味では、浜松の人は、正直だ。少なくとも岐阜の人たちよりは、あるがままに生きている。自分を飾らないし、偽らない。もともと街道筋の宿場町で発達した町ということもある。古い伝統や文化が根づかなかったという欠点はあるが、一方、何からなにまで、どこかさっぱりしている。ものの考え方が合理的、先進的、開放的。世界をリードする、ホンダ、スズキ、ヤマハ、カワイ、ローランドなどの各会社が、この浜松から生まれた背景には、そういう理由がある。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●セックス&セックスレス ワイフが、こんな話をした。「テレビの人生相談を見ていたけど、8年間で、1度しかセックスをしない夫婦がいるんだって」と。聞くと、まだお互いに30代前半の夫婦だという。私はその話を聞いたとたん、「もったいない」「信じられない」「夫婦って何だ」「おかしい」「かわいそうに」といろいろ考えた。 「もったいない」というのは、これは男の本能のようなもの。30歳くらいの若い女性を見ると、心のどこかで「裸になって肌をこすり合わせたら、さぞかし気持ちいいだろうな」と考える。そういう自分の中に潜む本能が、「もったいない」と思わせる。 「信じられない」「夫婦って何だ」「おかしい」というのは、夫婦はセックスをして、夫婦なのだ。何を隠そう、私など、今のワイフとつきあい始めたときからほぼ10年間、xxxxxxxxxxxxは、ワイフとセックスをしていた。……というのは、? 毎日自転車通勤で下半身を鍛えていたから、そういうことができたのかもしれない。ときどきワイフが、「私は、身がもたない。浮気でもしてきて!」と、こぼすほどだった。 ……ここで残念ながら、ワイフ・ストップがかかった。これ以上、私たちのセックスについて書くことはできない。ワイフの名誉の問題もある。またいつか、別の機会に書くことにして、話を進める。 セックスレスが悪いというのではない。人それぞれだし、それでうまくいっている夫婦はいくらでもいる。ただ若いときは、セックスをすることで、たがいの心を開き、わかりあえるということはある。セックスをするということは、まさに自分をさらけ出すこと。あるいはセックス以外に、自分をさらけ出すという方法はあるのか。いや、セックスをしたからといって、自分をすべてさらけ出すことができるかといえば、そうではない。やり方をまちがえると、ただの排泄行為に終わってしまう。セックスがもつ力にも限界がある。 まあ、私もワイフと結婚生活を35年近くもしてきたから、いろいろなことはあった。まだ20代のころだが、スワッピング(夫婦交換)をしないかともちかけられたこともある。もちかけてきたのは、仕事先の女性だった。しかしワイフがああいうカタブツ人間だから、実現しなかった。 若い主婦たちだけでつくる、秘密クラブのようなものもあった。それにも誘われたことがある。「美人妻クラブへ来ませんか」と。私は最初は冗談だと思ったが、本当にそういうクラブがあった。私が断ると、「あなたの知っている人で、口のかたい人はいませんか。お金持ちなら大歓迎!」と。 この世界には、いろいろなことがある。が、何が驚いたかと言って、母親が自分の娘(高3)について、「セックスの指導をしてやってほしい」ともちかけられたときほど、驚いたことはない。このときは、私はあれこれ口実をつくって、その場から逃げたので、ことなきをえたが……。しかしそれにしても……! (この話は、本当だぞ!)私はもともと岐阜の山奥育ちだから、セックスというと、どこかに、うしろめたい「暗さ」を感ずる。その暗さが、いろいろな場面で、ブレーキとなって働いた。が、そういう暗さをまったく感じない人も多い。……らしい。実に、あっけらかんとしている。いろいろいきさつはあったが、私に面と向かって、「私のアレは、10万人に1人の名器だって、夫がいつも、そう言っていますわ。あなた、ためしてみます?」と言われたこともある。……などなど。こういう話はここまでにしておくが、もともとセックスというのは、そういうものかもしれない。意味があるようで、それほどない。ひょっとしたら、小便や大便と同じ、ただの排泄行為かもしれない。今の今も、目の前の栗の木の間で、野性のハトたちが、こと忙しそうに交尾を繰り返している。そういうのを見ていると、「人間も同じだなあ」とか、「人間がそういうハトとちがうと考えるほうがおかしい」と思う。たがいの合意があれば、もっとセックスを楽しんでもよいのではないか、とも。とくに8年間もセックスレスというのは、夫はかまわないが、妻がかわいそうだ。セックスで得る快感というのは、ほかでは経験できない。あの快感は、まさに人間が生物としてもつ特権のようなもの。その特権を、自ら封印してしまうとは! ……この話は、教育論とは関係ないので、ここまでにしておく。ただいろいろなことがあって、私はこの道に入ってからというもの、この問題に関しては、「我、関せず」を貫いている。若い人たちのセックスについても、だ。「どうぞ、ご勝手に」と言いつつ、「病気にだけは気をつけろよ」と言うようにしている。そういう相談はいままで一度もなかったから、これはあくまでも仮定の話だが、もし女子中学生や高校生からセックスの相談を受けても、私はそう言うだろうと思う。「どうぞ、ご勝手に。病気にだけは気をつけろよな」と。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司【自分のこと】●ある読者からのメール 一人のマガジン読者から、こんなメールが届いた。「乳がんです。進行しています。診断されたあと、地獄のような数日を過ごしました」と。 ショックだった。会ったことも、声を聞いたこともない人だったが、ショックだった。その日はたまたま休みだったが、そのため、遊びに行こうという気持ちが消えた。消えて、私は1日書斎に座って、猛烈に原稿を書いた。●55歳という節目 私はもうすぐ55歳になる。昔で言えば、定年退職の年齢である。実際、近隣に住む人たちのほとんどは、その55歳で退職している。私はそういう人たちを若いときから見ているので、55歳という年齢を、ひとつの節目のように考えてきた。だから……というわけではないが、何となく、私の人生がもうすぐ終わるような気がしてならない。この1年間、「あと1年」「あと半年」「あと数か月……」と思いながら、生きてきた。が、本当に来月、10月に、いよいよ私は、その55歳になる。もちろん私には定年退職はない。引退もない。死ぬまで働くしかない。しかしその誕生日が、私にとっては大きな節目になるような気がする。●私は愚かな人間だった 私は愚かだった。愚かな人間だった。若いころ、あまりにも好き勝手なことをしすぎた。時間というのが、かくも貴重なものだとは思ってもみなかった。その日、その日を、ただ楽しく過ごせればよいと考えたこともある。今でこそ、偉そうに、多くの人の前に立ち、講演したりしているが、もともと私はそんな器(うつわ)ではない。もしみなさんが、若いころの私を知ったら、おそらくあきれて、私から去っていくだろう。そんな私が、大きく変わったのは、こんな事件があったからだ。●母の一言で、どん底に! 私はそのとき、幼稚園の講師をしていた。要するにモグリの講師だった。給料は2万円。大卒の初任給が6~7万円の時代だった。そこで私は園長に相談して、午後は自由にしてもらった。自由にしてもらって、好き勝手なことをした。家庭教師、塾の講師、翻訳、通訳、貿易の代行などなど。全体で、15~20万円くらいは稼いでいただろうか。しかしそうして稼ぐ一方、郷里から母がときどきやってきて、私から毎回、20万円単位で、お金をもって帰った。私は子どもとして、それは当然のことと考えていた。が、そんなある夜。私はその母に電話をした。 私は母にはずっと、幼稚園の講師をしている話は隠していた。今と違って、当時は、幼稚園の教師でも、その社会的地位は、恐ろしく低かった。おかしな序列があって、大学の教授を頂点に、その下に高校の教師、中学校の教師、そして小学校の教師と並んでいた。幼稚園の教師など、番外だった。私はそのまた番外の講師だった。幼稚園の職員会議にも出させてもらえないような身分だった。 「すばらしい」と思って入った幼児教育の世界だったが、しばらく働いてみると、そうでないことがわかった。苦しかった。つらかった。そこで私は母だけは私をなぐさめてくれるだろうと思って、母に電話をした。が、母の答は意外なものだった。私が「幼稚園で働いている」と告げると、母は、おおげさな泣き声をあげ、「浩ちゃん、あんたは道を誤ったア、誤ったア!」と、何度も繰り返し言った。とたん、私は、どん底にたたきつけられた。最後の最後のところで私を支えていた、そのつっかい棒が、ガラガラと粉々になって飛び散っていくのを感じた。●目が涙でうるんで…… その夜、どうやって自分の部屋に帰ったか覚えていない。寒い冬の夜だったと思うが、カンカンとカベにぶつかってこだまする自分の足音を聞きながら、「浩司、死んではだめだ。死んではだめだ」と、自分に言ってきかせて歩いた。 部屋へ帰ると、つくりかけのプラモデルが、床に散乱していた。私はそのプラモデルをつくって、気を紛らわそうとしたが、目が涙でうるんで、それができなかった。私は床に正座したまま、何時間もそのまま時が流れるのを待った。いや、そのあとのことはよく覚えていない。一晩中起きていたような気もするし、そのまま眠ってしまったような気もする。ただどういうわけか、あのプラモデルだけは、はっきりと脳裏に焼きついている。●その夜を契機(けいき)に…… 振り返ってみると、その夜から、私は大きく変わったと思う。その夜をさかいに、タバコをやめた。酒もやめた。そして女遊びもやめた。もともとタバコや酒は好きではなかったから、「やめた」というほどのことではないかもしれない。しかしガールフレンドは、何人かいた。学生時代に、大きな失恋を経験していたから、女性に対しては、どこかヤケッパチなところはあった。とっかえ、ひっかえというほどではなかったかもしれないが、しかしそれに近い状態だった。1,2度だけセックスをして別れた女性は、何人かいる。それにその夜以前の私は、小ずるい男だった。もともと気が小さい人間なので、大きな悪(わる)はできなかったが、多少のごまかしをすることは、何でもなかった。平気だった。 が、その夜を境に、私は自分でもおかしいと思うほど、クソまじめになった。どうして自分がそうなったかということはよくわからないが、事実、そうなった。私は、それ以後の自分について、いくつか断言できることがある。たとえば、人からお金やモノを借りたことはない。一度だけ10円を借りたことがあるが、それは緊急の電話代がなかったからだ。もちろん借金など、したことがない。どんな支払いでも、1週間以上、のばしたことはない。たとえ相手が月末でもよいと言っても、私は、その支払いを1週間以内にすました。ゴミをそうでないところに、捨てたことはない。ツバを道路にはいたこともない。あるいはどこかで結果として、ひょっとしたらどこかで人をだましているかもしれないが、少なくとも、意識にあるかぎり、人をだましたことはない。聞かれても黙っていることはあるが、ウソをついたことはない。ただひたすら、まじめに、どこまでもまじめに生きるようになった。●もっと早く自分を知るべきだった が、にもかかわらず、この後悔の念は、どこから生まれるのか。私はその夜を境に、自分が大きく変わった。それはわかる。しかしその夜に、自分の中の自分がすべて清算されたわけではない。邪悪な醜い自分は、そのまま残った。今も残っている。かろうじてそういう自分が顔を出さないのは、別の私が懸命にそれを抑えているからにほかならない。しかしふと油断すると、それがすぐ顔を出す。そこで自分の過去を振り返ってみると、自分の中のいやな自分というのは、子どものころから、その夜までにできたということがわかる。私はそれほど恵まれた環境で育っていない。戦後の混乱期ということもあった。その時代というのは、まじめな人間が、どこかバカに見えるような時代だった。だから後悔する。私はもっと、はやい時期に、自分の邪悪な醜い自分に気づくべきだった。●猛烈に原稿を書いた 私は頭の中で、懸命にその乳がんの女性のことを考えた。何という無力感。何という虚脱感。それまでにもらったメールによると、上の子どもはまだ小学1年生だという。下の子どもは、幼稚園児だという。子育てには心労はつきものだが、乳がんというのは、その心労の範囲を超えている。「地獄のような……」という彼女の言い方に、すべてが集約されている。55歳になった私が、その人生の結末として、地獄を味わったとしても、それはそれとして納得できる。仮に地獄だとしても、その地獄をつくったのは、私自身にほかならない。しかしそんな若い母親が……! もっとも今は、医療も発達しているから、乳がんといっても、少しがんこな「できもの」程度のものかもしれない。深刻は深刻な病気だが、しかしそれほど深刻にならなくてもよいのかもしれない。私はそう思ったが、しかしその読者には、そういう安易なはげましをすることができなかった。今、私がなすべきことは、少しでもその深刻さを共有し、自分の苦しみとして分けもつことだ。だから私は遊びに行くのをやめた。やめて、一日中、書斎にこもって、猛烈に原稿を書いた。そうすることが、私にとって、その読者の気持ちを共有する、唯一の方法と思ったからだ。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
最前線の子育て論byはやし浩司(23)
●コメント・トラックバック・掲示板+++++++++++++++++以前は、HPの掲示板への不良書きこみに悩んだ。相手は、名前がわからないことをよいことに、まさに言いたいことを書き放題。今は、BLOGの時代。しかしそのBLOGのトラックバックにさえ、このところ、不良書きこみが、絶えない。しかも悪質、執拗、うるさい。+++++++++++++++++ 現在、私は、R天のフリーサービスを使って、毎日、日記+BLOGを書いている。それはそれで、私の生きがいになっているが、少し前まで、掲示板への不良書きこみに悩んだ。中には、良心的な書きこみをしてくれる人もいたが、大半は、中傷、悪口、誹謗、それにスケベ。 セレブな人妻紹介。 童貞、買います。 今晩できます、などなど。 そこで、私は掲示板を閉鎖した。コメントコーナーも閉鎖した。毎日、そうした不良書きこみを削除する作業だけでも、たいへん。めんどう。 ところが、である。R天のフリーサービスのばあい、トラックバックだけは、閉鎖することができない。そのトラックバックをねらって、ほとんど毎日、同じような書きこみがつづく。しかも、5~10通、同じ文面のものばかり! そこでトラックバックの表示個数を、(1)に設定したが、それでも、それぞれの日記に、トラックバックに書きこみがつづく。どうしたらよいものか。トラックバックがあるからこそ、BLOG。もしトラックバックがなくなってしまったら、またもとの、(ただの日記)。BLOGがBLOGでなくなってしまう。 しかし、こうまで不良書きこみがつづくと、無視するわけにもゆかない。 そこでR天サービスに直接相談しようとしたが、そういう方法は、どこにも書いてない。つまり連絡先がわからない。で、今は、泣く泣く、そのままの状態。だれか、トラックバックを閉鎖する方法を、知りませんか。もしご存知でしたら、お教えください。お願いします。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(037)【受験・不安の構造】●不安を訴える、親たち 寒さが緩んだ、ある日の午後。1人の母親が、私の教室へやってきた。M君、小学3年生の母親である。「どうしましたか?」と聞くと、「ちょっとこちらの方へくる用事がありましたので……」と。私「ハア、何か?」母「実は、息子の進学の相談ですが、このままでいいのでしょうか?」私「このままって……?」母「一応、SS中学の受験を考えているんですが……」私「はあ……。それで?」と。 つまりM君の母親は、私の教室から、別の進学塾への移籍を考えていた。30年以上も、若い母親たちに接していると、そうした心の変化は、雰囲気でわかる。私「M君は、今、がんばっていますよ。成績も伸びてきたところですし、今は、自分で、5年生レベルの学習をしています」母「でも、国語が、苦手なんです」私「国語、ですか?」母「算数は、おかげで、クラスでもトップなのですが、国語の成績が、今イチなんです……」と。 こうした押し問答がつづく。いつまでもつづく。●よくなることしか考えない(?) こういうケースでは、親たちは、自分の子どもが、(今の状態)より、よくなることしか考えていない。「やれば、もっとできるはず」と。 しかし可能性としては、フィフティ・フィフティ。やり方をまちがえれば、成績は、さがる。が、それですめば、まだよいほう。親の希望には際限がない。「B中学へでも入れれば……」と言っていた親でも、その子どもがB中学へ入れそうだとわかると、今度は、「せめてA中学へ……」と言い出す。 さらにそのA中学へ入れそうだとわかると、今度は、「もう少しがんばらせて、S中学へ……」と言い出す。 子どもがそうした親の期待に、従順に(?)、応じている間は、それなりに、親子関係も、うまくいく。しかしそんなケースは、10に1つもない。理由は、簡単。 こうした親の期待には、あるいは欲望と言ってもよいかもしれないが、それには、ここにも書いたように、際限がない。が、それ以上に、『だからどうなの……?』という部分がない。「いい中学へ入ったから、だからどうなの?」と。それがないまま、子どもを追い立てても、子どもには、負担になるだけ。その(負担)が、やがて親子関係を破壊する。●過剰期待 何が子どもを苦しめるかといって、親の過剰期待ほど、子どもを苦しめるものはない。それはたとえて言うなら、馬の前にぶらさげられたニンジンのようなもの。いくら走っても、馬は、そのニンジンを、自分のものにすることはできない。 が、人間は馬ではない。やがてすぐ子どもは、それに気づく。こんな例がある。 あるとき電話で、こんな相談をしてきた母親がいた。私の知らない人だった。 「うちの子は、プリント学習を、毎日3枚することになっています。しかし2枚しかしません。3枚目になると、とたんに、いやがります。どうすれば、3枚目を子どもにさせることができますか?」と。 プリント教材を売り物にしている教材会社があるようだ。 で、私は、こう答えた。「では、2枚でやめることです」と。 もしその子どもが、スイスイと3枚目をしたら、親は、きっと今度は、こう言い出すにちがいない。「明日からは、4枚しなさい」と。 子どもも、それを知っている。だから、2枚目が終わったところで、しぶり始める……。●自我の同一性 わかりやすく言えば、(やりたいこと)と、(現実にしていること)が、一致している子どもは、表情が明るい。伸びやか。それに安定感があって、情緒も落ちついている。 しかしときとして、その(やりたいこと)と、(現実にしていること)が、遊離し始めることがある。そうなると、子どもは、とたんにある種の緊張感に包まれる。これを心理学の世界でも、「同一性の危機」という。 ある講演会場でその話をしたとき、1人の母親が、そのあと、こんな質問をした。「それはどういう心理状態ですか?」と。予定外の質問だったので、少し戸惑ったが、私はこう答えた。 「それはですねエ~。たとえて言うなら、顔を見るのも、声を聞くのもいや。肌に触れられるのもいやという男性と結婚した、女性の心の心のようなものではないでしょうか」と。 あとで考えて、我ながら、名答だったと思った。 もっとも、それほど深刻なケースではないにしても、同じ仕事でも、(自分で進んでする仕事)と、(いやいやする仕事)では、能率はまったくちがう。とくに、自分が納得しない仕事を押しつけられたときは、そうだ。 子どもも、そういう状態になる。親は、「いい中学へ入れ」と、せき立てる。しかし子どもには、その意思がない。少しでも成績がさがったりすると、親は、「サッカーをやめなさい」「ゲームは、取りあげます」などと、子どもをおどす。とたん、それまでの親子関係は、崩壊する。●『だから、どうなの?』 こんな例がある。もう15年近くも前のことだが、夏休みが終わったころ、2人の女子高校生が、私のところにやってきた。そしてこう言った。2人とも、私の幼児教室のOBである。 「先生、私たち、横浜のF大学に入ることにしました」と。 声は明るかった。それにF大学なら、私も知っている。それで「よかったね」と。で、そのあとこんな会話をした。私「ところで学部は……?」子「……国際関係学部……です」私「国際……カンケイ、学部……?」子「そう……」私「フ~ン。ぼくは昔の人間だから、法学部とか経済部とかいうのはわかるが、その国際関係学部っていうのは、何を勉強するところ?」子「……私にも、わかりません」と。 その2人の女子高校生たちは、「何を勉強するのか、わからない」と。当時は、「大学遊園地論」が、あちこちで騒がれていた。だから私は、すぐこう思った。「この子たちも、大学へ入ったら、遊ぶのだろうな」と。●夢、希望、目的 子どもを伸ばす三種の神器といえば、(夢)、(希望)、(目的)である。この3つが、子どもを、前向きに引っぱっていく。 しかし今、その(夢)、(希望)、(目的)をもっている子どもは、少ない。いろいろな調査結果をみても、小学校の高学年で、30%もいない。勉強にしても、親に言われるから、ただ勉強しているだけ……といった子どもが、ほとんど。 で、よく誤解されるが、今どき、よい中学、よい高校、さらには、よい大学へ入るなどということは、夢でも、希望でも、目的でもない。親にとっては、そうかもしれないが、少なくとも、子どもには、そうではない。 この数年だけでも、自ら、進学先の学校のレベルをさげる子どもが、どんどんとふえている。「A高校なんか入って、勉強でしごかれるくらいなら、B高校で、のんびりと高校生活を楽しみたい」と。「約60%の子ども(中学生)がそうですよ」と、HK市にある中学校の校長が、笑いながら話してくれた(05年)。 昔なら、「名門」というブランドにあこがれて、そこへ入ることを目標にした子どももいたかもしれない。しかし今は、いない。また、そういう時代ではない。●勉強しかしない子どもたち せっかく(いい中学)(いい高校)へ入っても、中退して自分の道を選ぶ子どもも、ふえている。ここに例を書くまでもなく、あなたの周囲にも、1人や2人は、必ず、いるはず。 むしろ勉強だけして、スイスイと、(いい中学)(いい高校)そして(いい大学)へと進学して子どもほど、どこか、ヘン(失礼!)。そういう子どもは、勉強しかしない。勉強しかできない。たしかに成績はよいが、よい成績をとることが、その子どもにとっては、趣味のようなものになっている。 頭の中は、偏差値という数字でいっぱい。もちろん弊害もある。 このタイプの子どもは、人間の価値そのものすら、その(数字)で判断する。そこでおかしなことだが、本当に、おかしなことだが、今の日本の教育システムの中では、人間的にも魅力があり、人格的にもすぐれた子どものほうが、むしろ、受験競争から、脱落していくという傾向がみられる。 このことも、あなたの周囲を見渡してみれば、わかるはず。あなたの周囲にもいろいろな人がいる。が、受験とは無縁の世界を生きてきた人ほど、心暖かく、人間味が豊かであることを、あなたも知っているはず。 もちろんだからといって教育を、否定しているのではない。つまりこうした弊害を、教育者自身が、気がつき始めている。そしてそれに合わせて、教育制度、さらには受験制度そのものも、変わり始めている。●点数から人間性へ この静岡県でも、いろいろな試行錯誤があったが、全体として見ると、より内申書重視の入試方法に変わってきている。欧米の例を参考にするなら、これは当然のことである。 たとえばアメリカでは、いくら成績がよくても、その成績だけでは、有名大学には入れない。推薦権をもつ、教師や学校の推薦がなければ、入れない。そしてその推薦するかどうかは、その子どもの人格や人間性を見て、判断される。 日本でも、最近、学歴不問という会社が現われつつある。入社試験でも、面接官は、こう聞く。「君は、何ができるかね?」「君は、わが社に、何を貢献してくれるかね?」と。 こうした話は、恩師のT教授(元東大・副総長)からも聞いたことがある。20年ほど前の話で、今は、そういう学生も少なくなったと思うが、T教授は、こう言った。 「林君、東大へ入ってくる学生の、3分の1は、頭がおかしいよ」と。そこで私が、どこがどうおかしいですかと聞くと、T教授は、こう言った。 「実験中にね、かんしゃく発作か何かを起こして、ビーカーなどの実験道具を床にたたきつけて、割ってしまうのがいる」「そこで親まで呼んで、自主退学を勧めるのだが、親のほうが、猛然と拒否する」と。 そうした反省もあって、そのあと、入試方法も、大きく変わった。学力テスト1本という入試方法から、面接重視の入試方法へ、と。とくにそのT教授は、退官後、東京R大(私大)へ移り、東京R大の入試方法そのものを変えてしまった。 「参考書、辞書、持参は自由」というのが、その入試方法である。この入試方法は、そのあと、いろいろな世界で、大きな話題になったので、ご存知の方も多いと思う。●不安の構造 何ゆえに、親たちは、不安になるのか? とくに自分の子どもが受験期を迎えると、言いようのない不安感に襲われる。 自分の子どもが選別されるという不安。子どもの将来への不安。が、それだけではない。日本人には、体質として、明治以来の学歴信仰がしみついている。それに拍車をかけるように、この日本には、不公平が蔓延(まんえん)している。 そうした不公平を、親たちは、日々の生活を通して、いつも肌で感じている。 だから親たちは、子どもを受験競争に駆り立てる。今の今でも、「勉強しなさい!」「うるさい!」の大乱闘を繰りかえしている親子は、多い。 が、ここで注意しなければならないのは、不安に思っているのは、親だけということ。子どもは、何も、不安に思っていない。もっと言えば、親が、自分の不安感を、子どもにぶつけているだけ。 こうした親は、一見、子ども思いの、よい親に見える。しかしその実、身勝手な愛(?)を、子どもに押しつけているだけ。こういうのを、私は、「代償的愛」と呼んでいる。つまりは、愛もどきの愛。それはたとえて言うなら、ストーカーが口にする「愛」に似ている。 子どものことを考えているようで、結局は、子どものことなど、何も考えていない。どこまでも、ジコチューな愛、ということになる。●失敗してはじめて気づく親たち しかしどの親も、ほとんど例外なく、自分で失敗するまで、自分が失敗したと気づかない。だいたいどの親も、自分が失敗するなどとは、思っていない。 だから親は、子どもを、「あなたはやればできるはず」「もっとできるはず」と、子どもを、追い立てる。が、いつまでもこんな異常な状態がつづくはずはない。 H市にS県でもナンバーワンと呼ばれる進学高校がある。その進学高校の教師が、私にこう話してくれたことがある。 「うちの高校でも、高校入学時にすでに、バーントアウト(燃え尽き症候群)している子どもが、5%はいます。3年生で、20%はいます」と。 有名大学となると、(こういう言葉は、本当に不愉快だが……)、もっと多い。「大学へは入ってはみたけれど……」と。 が、その程度ですめばまだよいほう。引きこもりや、家庭内暴力、さらには、心そのものまでゆがめてしまう子どもも少なくない。 が、親というのは、不思議なものだ。親子関係は完全に崩壊している。子どもも、「大学へは入ってはみたけれど……」という状態になっている。しかしそれでも、他人の前では、「おかげで、いい大学へ入ることができました」と喜んでみせる。 この段階で、失敗を認めるということは、親にしてみれば、自己否定につながる。世間的には、それだけは何としても避けたい。そうそうこう言っていた母親もいた。 「毎日、毎晩、小5の娘と大乱闘です。しかし娘も、目的の中学へ入ってくれれば、そのとき私の気持ちを理解し、私を許してくれるでしょう」と。 が、残念ながら、それで親に感謝する子どもなど、ぜったいに、いない。●変化する子どもたち 進学塾へ入ったとたん、目つきの変わる子どもは、少なくない。何割か、あるいはそれ以上の子どもがそうなる。 親は、「自覚ができました」「緊張感ができました」と喜ぶ。が、それですむわけではない。受験競争が長くつづけばつづくほど、そしてそれがはげしければはげしいほど、おかしな競争心、おかしなエリート意識、そういったものが、子どもの心を粉々に破壊する。 概して言えば、温もりのある子どもらしさが消え、心がドライになる。冷たくなる。点数だけで、人を判断するようになる。それを指導する講師が、そういう姿勢だから、子どもの心など、生贄(いけにえ)に差し出された子羊のようなもの。 さらに言えば、指導する講師にしても、それだけ子どもの心を知った上で、指導しているかといえば、それは疑わしい。 派手な宣伝、広告、チラシ……。そういったので発表される合格者数の裏で、いかに多くの子どもたちが、もがき、苦しみ、自信をなくしていることか。ほとんどの親たちは、勝つことだけを考えて、負けることは考えていない。 「うちの子にかぎって……」「そんなはずはない……」と、子どもを受験競争に追い立てる。しかし成功するか失敗するかということになれば、失敗する確率のほうが、はるかに高い。 しかしそのときになって、子どもの心を再び、取りもどそうとしても、もう遅い。一度こわれた心を、もとにもどすには、その何倍もの努力と時間が必要となる。●日本の特殊性 日本がもつ構造的な異常さというのは、日本だけに住んでいる人には、理解できない。あるいは、逆に、「欧米も、日本と似たようなもの」と思っている人も多い。 しかし、ちがう。まったくちがう。5、6年前に書いた原稿(本で発表済み)の中から、一部を抜粋して、紹介する(全文は、この原稿のあとに添付)。 『つい先日、東京の友人が、東京の私立中高一貫校の入学案内書を送ってくれた。全部で70校近くあった。が、私はそれを見て驚いた。どの案内書にも、例外なく、その後の大学進学先が明記してあった。別紙として、はさんであるのもあった。「○○大学、○名合格……」と(※)。この話をオーストラリアの友人に話すと、その友人は「バカげている」と言って、はき捨てた。そこで私が、では、オーストラリアではどういう学校をよい学校かと聞くと、こう話してくれた。 「メルボルンの南に、ジーロン・グラマースクールという学校がある。そこはチャールズ皇太子も学んだこともある古い学校だが、そこでは生徒1人ひとりにあわせて、学校がカリキュラムを組んでくれる。たとえば水泳が得意な子どもは、毎日水泳ができるように。木工が好きな子どもは、毎日木工ができるように、と。そういう学校をよい学校という」と。なおそのグラマースクールには入学試験はない。子どもが生まれると、親は出生届を出すと同時にその足で学校へ行き、入学願書を出すしくみになっている。つまり早いもの勝ち』。●子どもを信じて伸ばす では、どうすればよいのか。現実に、この日本には、不公平が蔓延している。学歴制度もあり、受験競争もある。こうした現実に背を向ければ、そのまま外の世界へ、はじき飛ばされてしまう。 こんな笑い話(?)がある。東京に住んでいる、ある女性が話してくれた。 「ある母親は、自分の子ども(小学生)を、近くの公園へ連れていった。そしてそこで生活しているホームレスの人たちを見せながら、こう言ったという。『あんたも、しっかりと勉強しなければ、ああいう人になるのよ』と」と。 とんでもない指導だが、だれがこの話を聞いて、笑えるだろうか。その母親は、この日本では、まさに現実主義者ということになる。笑いたくても、笑えない。 その一方で、今、この日本でも、価値観が、多様化してきている。そして「幸福」に対する考え方も、変わってきている。そこで重要なことは、子ども自身が、自らの力で、自分の道を切り開いていく力をもつようにすること。学歴などというものは、あとからついてくるもの。かりにどこの大学を出ようとも、そこで(勉強)が終わるわけではない。 むしろ本物の実力が試されるのは、社会へ出てからということになる。もちろん今でも、過去の学歴にぶらさがり、のんべんだらりとした生活を送っている人は多い。悪しき学歴社会の、亡霊のような人たちである。50代、60代以上の人に、とくに多い。●夢から目標へ 子どもには、子どもの夢がある。その夢をじょうずに育てながら、それを目標につなげていく。 子どもが「花屋さんになりたい」と言ったら、「そうね、それはすてきね」と。子どもが「バスの運転手さんになりたい」と言ったら、「そうね、それはすてきね」と。 「夢」を育てる姿勢が子どもの中にあれば、(夢の内容は、そのつど変化するものだが……)、子どもは自分で伸びていく。 もし子どもを伸ばす方法があるとするなら、それしかない。またそれが王道である。親にできることがあるとするなら、その目標に向って進む子どもを、側面から支えること。イギリスの格言にも、『馬を水場に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない』というのが、ある。あとの判断は、子ども自身に任せるしかない。 そのとき重要なことは、それがどんな道であろうが、子どもが選んだ道であれば、親は一歩引き下がった状態で、子どもを支える。そしてそれが良好な親子関係を保つ、王道でもある。 私がM物産という会社をやめて、幼稚園の講師になるという道を選んだとき、それを母に告げると、母は電話口の向こうで泣き崩れてしまった。 決して母を責めているのではない。母は母で、当時の常識に従って、そうしたにすぎない。しかしあのとき、母だけでも、私を支えてくれていたら、その後の私の人生は、大きく変わっただろうと思う。もっと自信をもって、私は、自分の道を進むことができただろうと思う。 そういう私を支えてくれたのは、実は、オーストラリアの友人たちである。オーストラリアの友人たちは、みな、「すばらしい選択だ」と言って、私を支えてくれた。つまり、こういうところにも、意識のちがいがある。 今でも、「幼稚園の講師?」と言って、吐き捨てる日本人は、多い。しかしそういう日本人を超えるようにならないと、この日本はいつまでたっても、教育後進国。校舎や教師がいくら立派になっても、中身は旧態依然のまま(?)ということになる。 つまりは、私たち1人ひとりが、そういう意識を変えていくしかない。 冒頭にあげた母親とは、それで別れた。その母親との間には、越えがたいほど、遠い距離を感じた。「どこからどう説明しようか」と考えているうちに、どうでもよくなってしまった。 M君が私のところを去るのは、時間の問題だろう。しかしそれも卒業。母「これからも、よろしくお願いします」私「わかりました。おいでになる間は、一生懸命、教えさせていただきます」と。
2024年12月29日
-
最前線の子育て論byはやし浩司(22)
【はやし浩司より、Yさんへ】 前兆期は、すでにすぎています。そう考えてください。また「3日」とか何とか、時限を決めて、子どもを追いつめるのは、かえって逆効果ですから、注意してください。これについては、すでに前に書いたとおりです。 で、学校恐怖症と怠学のもっとも簡単な見分け方としては、つぎのようなものがあります。学校恐怖症の子どもは、学校へ行かない間、家の中に引きこもる傾向を示すのに対して、怠学の子どもは、ほかに目的があって、学校をサボるということ。そのため、学校へ行かない間は、平気で外出したりします。 しかし「首に縄つけて……」というのは、恐ろしく乱暴な言い方ですね。怠学的な不登校児であれば、それなりに効果的(?)かと思いますが、学校恐怖症であれば、その一撃が、取り返しのつかないトラウマ(心の傷)となって、心をキズつけてしまうことになりかねませんので、ご注意ください。 症状からして、午前中はひどく、午後は快方に向うという、日内変動が見られますので、やはり学校恐怖症を疑ってみたほうがよいかと思います。だから前回も書きましたように、本人が気分がよくなるのを待って、2、3時間目から登校をうながしてみるとか、午後からの登校をうながしてみるのがよいかと思います。 Yさんが不安なのは、よくわかりますが、その不安感を、シャドウとして、子どもも感じ取ってしまいますので、ご注意ください。親のピリピリ、イライラは、百害のもとです。 お子さんの様子を見ていませんので、これ以上のことはよくわかりません。表情だけ、どこか柔和で、何を考えているかわからないといった様子であれば、(つまり情意と表情の遊離現象が見られるようであれば)、不登校は、かなり長期にわたると覚悟することです。「なおそう」と考えるのではなく、「あなたは、つらいけど、よくがんばっているのよ」と、子どもを包むようにして対処します。 こうした症状は、下の子どもが生まれたことによる、赤ちゃん返りがこじれて、起きるものと、私は考えています。何%かの子どもがそうなります。(世間の人たちは、赤ちゃん返りを軽くみる傾向がありますが、決して、赤ちゃん返りを軽くみてはいけません。)かん黙症や、自閉症の引き金を引いてしまうことも、珍しくありません。 「お兄ちゃんだから……」という安易な『ダカラ論』をぶつけないこと。Yさんが住んでいる地域のことをよく知っていますが、その地域は、そうした封建主義的なものの考え方が、いまだに根強く残っているところです。注意してください。(このことは以前にも、書いたと思いますが……。外の世界からそれを見ると、よくわかります。) 「うちの子は、どうなるのだろう?」と不安になられる気持ちはよくわかりますが、今こそ、あなたの真の愛情が試されるべきと考えて、つまり十字架を1つ背負うつもりで、この問題に対処してみてください。 「まあ、いいわよ」とあなたが思えるようになったとき、(実際、今どき、不登校など、何でもない問題ですが)、不安は、あなたのほうから去っていきます。『不幸は、それを笑ったとき、向こうから去っていく。しかしそれを恐れたとき、不幸は、あなたを重荷となって苦しめる』というのは、私が作った格言です。 この問題の解決には、数か月単位の忍耐と努力が必要です。ここで症状をこじらせると、半年から1年単位での不登校につながる危険性があります。心の休養を大切に。「気分転換」などと安易に考えて、子どもをあちこち引き回すのも避けてください。安静と安心感、それに心の安定が、何よりも大切です。もし午後、1時間でも学校へ行くようなら、「よくがんばったね」とほめてあげてください。「もうあと1時間行こうね」などと、子どもを責めてはいけません。 それ以上に症状がひどくなるようであれば、心療内科を訪れてみるという方法もありますが、私は薬物治療については、疑問に思っています。どうか、慎重に!(はやし浩司 不登校 学校恐怖症 学校拒否症 怠学 アメリカ内科医学会 米内科医学会 診断基準 はやし浩司)2007/10/19【補記】 それにしても、「首に縄つけてでも……」という言い方には、驚きました。今でも、そういう言い方をする人がいるのですね。子どもの人格や人権を、いったい、どのように考えているのでしょうか。 私はこの言葉の中に、恐ろしいほどの親意識、権威主義、それに上下意識を感じました。と、同時に、それを口にする人たちは、学校神話、学歴信仰の盲信者という印象ももちました。「子どもなど、親の意思でどうにでもなる」とでも、そういう人たちは考えているのでしょうか。 あまりにも無知、無学、メチャメチャ! そしてあまりにも日本的! 逆の立場で、自分がそうされたときのことを考えてみたらよいのです。ただ単なる(比喩(ひゆ))では、すまされません。 だからといって、子どもを甘やかせとか、学校へは行かなくていいと言っているのではありません。日ごろから、もっと子どもの心に耳を傾ける姿勢が、親側に育っていれば、こうした発想は、出てこないはずです。あるいはひょっとしたら、こうした問題は起きなかったかもしれません。 まさに原始的というか、後進国的というか。あまりにも心の問題を、安易に考えすぎているのでは! 子どもに何かをさせるときには、ある程度の強制力は必要かもしれません。が、それは子どもを見ながら判断します。相談してきたYさんのお子さんのケースでは、幼いころ神経症を発症し、心は、疲れているはず。ボロボロかもしれません。 私には、Yさんのお子さんの悲痛な叫び声が、聞こえてきます。表面的には元気でも、それ自体が、仮面と考えてよいのではないでしょうか。 こうしたケースでは、親が「学校へ行かせよう」とあせればあせるほど、その(あせり)が、子どもの心の中に、緊張感を作ってしまいます。つまり子どもの不登校の問題は、子どもの問題ではなく、親の問題だということです。それに気づけば、あとは、時間が解決してくれます。 夫が単身赴任で、同居していないとか……。この問題は、Yさんひとりで、解決できる問題でもないように思います。子育ては、それだけ重労働だということ。加えて、Yさんひとりで対処していると、Yさん自身が、育児ノイローゼになってしまうかもしれません。何とか、夫に、いっしょに住んでもらうわけにはいかないでしょうか。内政干渉ですみません!++++++++++++++++++++++ついでながら、「学校恐怖症」について書いた記事(中日新聞掲載済み・2001年10月1日)を、ここに添付しておきます。この原稿は、あちこちの団体や個人に、無断で転載、転用されています。やめてほしいですね、こういうことは!++++++++++++++++++++++【子どもが学校恐怖症になるとき】●四つの段階論 同じ不登校(school refusal)といっても、症状や様子はさまざま(※)。私の二男はひどい花粉症で、睡眠不足からか、毎年春先になると不登校を繰り返した。が、その中でも恐怖症の症状を見せるケースを、「学校恐怖症」、行為障害に近い不登校を「怠学(truancy)」といって区別している。これらの不登校は、症状と経過から、三つの段階に分けて考える(A・M・ジョンソン)。心気的時期、登校時パニック時期、それに自閉的時期。これに回復期を加え、もう少しわかりやすくしたのが次である。 (1)前兆期……登校時刻の前になると、頭痛、腹痛、脚痛、朝寝坊、寝ぼけ、疲れ、倦怠感、吐き気、気分の悪さなどの身体的不調を訴える。症状は午前中に重く、午後に軽快し、夜になると、「明日は学校へ行くよ」などと、明るい声で答えたりする。これを症状の日内変動という。学校へ行きたがらない理由を聞くと、「A君がいじめる」などと言ったりする。そこでA君を排除すると、今度は「B君がいじめる」と言いだしたりする。理由となる原因(ターゲット)が、そのつど移動するのが特徴。 (2)パニック期……攻撃的に登校を拒否する。親が無理に車に乗せようとしたりすると、狂ったように暴れ、それに抵抗する。が、親があきらめ、「もう今日は休んでもいい」などと言うと、一転、症状が消滅する。ある母親は、こう言った。「学校から帰ってくる車の中では、鼻歌まで歌っていました」と。たいていの親はそのあまりの変わりように驚いて、「これが同じ子どもか」と思うことが多い。 (3)自閉期……自分のカラにこもる。特定の仲間とは遊んだりする。暴力、暴言などの攻撃的態度は減り、見た目には穏やかな状態になり、落ちつく。ただ心の緊張感は残り、どこかピリピリした感じは続く。そのため親の不用意な言葉などで、突発的に激怒したり、暴れたりすることはある(感情障害)。この段階で回避性障害(人と会うことを避ける)、不安障害(非現実的な不安感をもつ。おののく)の症状を示すこともある。が、ふだんの生活を見る限り、ごくふつうの子どもといった感じがするため、たいていの親は、自分の子どもをどうとらえたらよいのか、わからなくなってしまうことが多い。こうした状態が、数か月から数年続く。 (4)回復期……外の世界と接触をもつようになり、少しずつ友人との交際を始めたり、外へ遊びに行くようになる。数日学校行っては休むというようなことを、断続的に繰り返したあと、やがて登校できるようになる。日に一~二時間、週に一日~二日、月に一週~二週登校できるようになり、序々にその期間が長くなる。●前兆をいかにとらえるか 要はいかに(1)の前兆期をとらえ、この段階で適切な措置をとるかということ。たいていの親はひととおり病院通いをしたあと、「気のせい」と片づけて、無理をする。この無理が症状を悪化させ、(2)のパニック期を招く。この段階でも、もし親が無理をせず、「そうね、誰だって学校へ行きたくないときもあるわよ」と言えば、その後の症状は軽くすむ。一般にこの恐怖症も含めて、子どもの心の問題は、今の状態をより悪くしないことだけを考える。なおそうと無理をすればするほど、症状はこじれる。悪化する。 ※……不登校の態様は、一般に教育現場では、(1)学校生活起因型、(2)遊び非行型、(3)無気力型、(4)不安など情緒混乱型、(5)意図的拒否型、(6)複合型に区分して考えられている。 またその原因については、(1)学校生活起因型(友人や教師との関係、学業不振、部活動など不適応、学校の決まりなどの問題、進級・転入問題など)、(2)家庭生活起因型(生活環境の変化、親子関係、家庭内不和)、(3)本人起因型(病気など)に区分して考えられている(「日本教育新聞社」まとめ)。しかしこれらの区分のし方は、あくまでも教育者の目を通して、子どもを外の世界から見た区分のし方でしかない。(参考)●学校恐怖症は対人障害の一つ こうした恐怖症は、はやい子どもで、満四~五歳から表れる。乳幼児期は、主に泣き叫ぶ、睡眠障害などの心身症状が主体だが、小学低学年にかけてこれに対人障害による症状が加わるようになる(西ドイツ、G・ニッセンほか)。集団や人ごみをこわがるなどの対人恐怖症もこの時期に表れる。ここでいう学校恐怖症はあくまでもその一つと考える。●ジョンソンの「学校恐怖症」「登校拒否」(school refusal)という言葉は、イギリスのI・T・ブロードウィンが、一九三二年に最初に使い、一九四一年にアメリカのA・M・ジョンソンが、「学校恐怖症」と命名したことに始まる。ジョンソンは、「学校恐怖症」を、(1)心気的時期、(2)登校時のパニック時期(3)自閉期の三期に分けて、学校恐怖症を考えた。●学校恐怖症の対処のし方 第一期で注意しなければならないのは、本文の中にも書いたように、たいていの親はこの段階で、「わがまま」とか「気のせい」とか決めつけ、その前兆症状を見落としてしまうことである。あるいは子どもの言う理由(ターゲット)に振り回され、もっと奥底にある子どもの心の問題を見落としてしまう。しかしこのタイプの子どもが不登校児になるのは、第二期の対処のまずさによることが多い。ある母親はトイレの中に逃げ込んだ息子(小一児)を外へ出すため、ドライバーでドアをはずした。そして泣き叫んで暴れる子どもを無理やり車に乗せると、そのまま学校へ連れていった。その母親は「このまま不登校児になったらたいへん」という恐怖心から、子どもをはげしく叱り続けた。が、こうした衝撃は、たった一度でも、それが大きければ大きいほど、子どもの心に取り返しがつかないほど大きなキズを残す。もしこの段階で、親が、「そうね、誰だって学校へ行きたくないときもあるわね。今日は休んで好きなことをしたら」と言ったら、症状はそれほど重くならなくてすむかもしれない。 また第三期においても、鉄則は、ただ一つ。なおそうと思わないこと。私がある母親に、「三か月間は何も言ってはいけません。何もしてはいけません。子どもがしたいようにさせなさい」と言ったときのこと。母親は一度はそれに納得したようだった。しかし一週間もたたないうちに電話がかかってきて、「今日、学校へ連れていってみましたが、やっぱりダメでした」と。親にすれば一か月どころか、一週間でも長い。気持ちはわかるが、こういうことを繰り返しているうちに、症状はますますこじれる。 第三期に入ったら、(1)学校は行かねばならないところという呪縛から、親自身が抜けること。(2)前にも書いたように、子どもの心の問題は、今の状態をより悪くしないことだけを考えて、子どもの様子をみる。(3)最低でも三か月は何も言わない、何もしないこと。子どもが退屈をもてあまし、身をもてあますまで、何も言わない、何もしないこと。(4)生活態度(部屋や服装)が乱れて、だらしなくなっても、何も言わない、何もしないこと。とくに子どもが引きこもる様子を見せたら、そうする。よく子どもが部屋にいない間に、子どもの部屋の掃除をする親もいるが、こうした行為も避ける。 回復期に向かう前兆としては、(1)穏やかな会話ができるようになる、(2)生活にリズムができ、寝起きが規則正しくなる、(3)子どもがヒマをもてあますようになる、(4)家族がいてもいなくいても、それを気にせず、自分のことができるようになるなどがある。こうした様子が見られたら、回復期は近いとみてよい。 要は子どものリズムで考えること。あるいは子どもの視点で、子どもの立場で考えること。そういう謙虚な姿勢が、このタイプの子どもの不登校を未然に防ぎ、立ちなおりを早くする。 Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(036)●保護司+++++++++++++++++++自治会長が、保護司の仕事をもってきた。さあ、私は、どうすべきか?+++++++++++++++++++引きうけるべきか、引きうけざるべきか……それが問題。 つい先日は、自治会の副会長職を断ったばかり。しかしいつもいつも、断ってばかりいるわけにはいかない。自治会長には、世話になっている。 保護司……一応、身分は、国家公務員。任期は2年。ただし、無給。おかしなことだが、私は、「保護司」の「司」に、親しみを覚えた。「浩司」の「司」と同じ。結構、私にも、単純なところがある。 そこで床についてから、分厚いパンフレットを読む。ウム~。読めば読むほど、ウム~。「保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える、ボランティアです」(第2章冒頭)とある。つづいて「使命」として、「保護司は、社会福祉の精神をもって、犯罪をした者の、改善厚生を助け、犯罪予防のため世論の啓発に努めています」とある。ますます考えこんでしまう。善人の仮面をかぶるのは、簡単なこと。が、その仮面をかぶってできるような仕事ではない。相手は、それぞれ、大きな問題をかかえた人たちである。そういう人たちを相手に、私のような人間は、どう対処すればよいのか。 ワイフはのんきに、「あなたもそういう年齢になったのよ」と言う。つまり社会に、恩返しをする年齢になった、と。 しかし、これはむずかしい仕事である。それに責任は、重大! 子育て相談とは、わけがちがう。「忙しいから、今日は、失礼します」と、逃げるようなことは、許されない。 が、何といっても、一番、警戒しなければならないのが、「仮面」。そういう例は多い。たとえば、他人には、すばらしくよい人を演ずる人がいる。面倒見もよい。世話好き。しかしそれは外面(そとづら)。本当に他人のために働いているかというと、そうではない。自分をよい人間に見せたいために、そうする。そういうのを、心理学でも、「愛他的自己愛」という。そういう人にとっては、「あの人はいい人」とうわさされるのが、何よりも快感なのだ。 しかし仮面は仮面。わかりやすく言えば、「化けの皮」。大切なことは、その人のために、どこまで親身になって、つまり真剣に、考えてやることができるかということ。が、私に、それができるか? 私は、幸か不幸か、(幸に決まっているが……)、何かの犯罪を犯した人たちとは、無縁の世界で生きてきた。知りあいの中にもいない。そういう私が、保護観察中の人たちと、どうやって向きあえばよいのか。さも私は善人でございますというような顔をして接するのは、私のやり方ではない。かといって、そういう相手を説教したりするような立場でもない。 保護司の役割の第1は、「犯罪をした者の、改善厚生を助け、犯罪予防のため世論の啓発する」とある。仕事の内容としては、(1)保護観察を受けている少年やおとなの指導として、毎月面接や、家庭訪問を行う。(2)刑務所や少年院に入っている人の帰住先の調整として、出所後の生活設計などについて、引き受ける家族と話しあいなどをする。(3)犯罪や非行の予防活動として、犯罪や非行をした人の立ち直りを見守るよう、広く社会に呼びかけを行う、とある。 保護司研修制度というのもある。保護司として活動する前に、地域別定例研修、特別研修、自主研修、新任保護司研修、第一次研修、第二次研修……などなど。 私には私の仕事がある。このところ、時間が合わないため、講演すら断ることが多くなった。息子の1人は、まだ大学生である。ボランティア活動をするといっても、仕事を犠牲にするわけにはいかない。こうした研修会が、私の仕事と重なったら、私は、どうすればよいのか。 考えれば考えるほど、気が重くなる。 やはりこの仕事を引き受けるかどうかは、もう少し様子を聞いてからにしよう。こちらから「やります!」と手をあげてするような仕事ではない。時間的にも、今の私には、まったく余裕がない。●ライブD・ショック++++++++++++++++++株価が急降下している! 昨日1日だけで、日経平均は、500円近くも、値をさげた。今日も午前中だけで、444円も、値をさげた。きっかけは、ライブD社の粉飾決算(?)しかし……2007年10月19日(金)++++++++++++++++++ 現在、日銀は、ゼロ金利政策(量的緩和策)を実行中! わかりやすく言えば、日銀は、市中銀行をとおして、日本中に、お金をバラまいている。今の日本は、「お金がジャブジャブの状態」(某経済誌)だそうだ。 おまけに、原油価格は高止まり。加えて、ドル安。「景気はよくなった」とはいうが、中身は、あのバブル経済の時期そっくり。 そこで株式市場は、いつ日銀が、量的緩和策を解除するか。その時期を見きわめようと、戦々恐々としている。そんな状態。解除されたとたん、「日本経済には、急ブレーキがかかることになるかも」とのこと。 今回のライブDショックは、その引き金を引いてしまった。「株価がさがるのは、年度末決算がすんだあとの4月ごろ」と、大方の経済評論家は、読んでいた。しかし株価は、先手、先手で動く。 ところで昨夜、仕事の帰りに書店で読んだ週刊誌には、ある若い男性の手記として、こんな記事が載っていた。 「今は、株で、もうけどき。100万円をサラ金で借りて、ネットで、信用取引。年末から年始にかけて、25万円のもうけ」と。週刊誌の名前は忘れた。 つまりサラ金で100万円借りてきて、そのお金で株を買う。株を売買するときには、信用取引という方法がある。ある一定額の損(このばあいは100万円の損)をするまで、株を売買することができる。この方法だと、100万円で、10万円の株を、たとえば50~100株も買うことができる。現物売買では、100万円では、10万円の株なら、10株しか買えないのだが……。 信用取引では、株価があがれば、もうけも大きいが、株価がさがれば、100万円は、そのまま、パー。 今ごろその手記を書いた若い男性は、たぶん、大損をして、泣いていることだろう。つまり株式の売買のこわいところは、ここにある。わかりやすく言えば、バクチ。「もうけた、もうけた」と喜んでいると、その人は、もっと、もうけたくなる。そしてもっと大きなお金を、そのバクチにかけるようになる。 そして最終的には、大損! だから私のような素人が株式売買をするときには、絶対に守らなければならない大原則がある。それは(1)最高限度額を必ず、決めておくということ。100万円までとか、200万円まで、とか。あくまでも小遣いの範囲でするのがよい。(2)信用取引はしない。あくまでも現物売買。そして株価がさがったら、その株は塩漬けにして、3か月でも半年でも、じっとがまんしてもつ。 だいたい、働きもしないで、お金をもうけるという、その根性がまちがっている。……というのは、この現代社会においては、通用しない考え方かもしれないが……。(補記) 何を隠そう、この私もこの2日で、x万円の損をしたのだ。ハハハ。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●ものは、言いよう+++++++++++++++みなさん、往生際(ぎわ)が悪いですね。弁護士法違反と、組織犯罪処罰法違反の罪で逮捕、起訴された、あの西村S悟議員が、今度は、拉致問題にかこつけて、議員職にしがみついている(?)+++++++++++++++ 新聞報道によれば、逮捕、起訴されたにもかかわらず、あの西村S悟衆議院議員は、つぎのように述べているという。 「弁護士の名義を貸す見かえりに違法な報酬を受け取ったとして、弁護士法違反と組織犯罪処罰法違反の罪で起訴された、衆議院議員、西村S悟被告(57・前民主党議員)が(1月)17日、東京都内で記者会見し、『(K国による)拉致被害者救出のために議席を維持しなければならない』として、議員辞職しない意向を明らかにしたという」(サンケイ新聞)。 ものは、言いようである。拉致問題を、自分の政治的利益に利用している議員は多い。が、ことここにいたってまで、拉致問題にかこつけて、議員職にしがみつくとは! 西村S悟被告は、昨年末(05年)11月18日の段階では、まだつぎのように述べていた。「本日11月18日の朝刊各紙に、私の法律事務所の元職員が(非弁活動)(弁護士資格が無いのに弁護士活動をすること)をしたとして検察が捜査に入る旨の記事が掲載されました。以下、この点について事情をご説明致します。1、非弁活動の容疑については、元職員本人も認めており事実であろうかと思います。2、では、私がその非弁活動を知っていたかどうかでありますが、本年はじめ頃に、大坂 府警から教えられるまで、全く知りませんでした。そして、私は、大阪府警の捜査員に全ての事情を説明しました。大阪府警の捜査は、4月末ころに終了したと思いますので、事件はそのころ検察庁に送られ処理されたと、私は思っていました。しかしながら、今朝の事態を迎え、驚いている次第であります。3、この非弁活動を行なった者は、私の法律事務所にいた者であることは事実であります ので、今になっていくら悔いても致し方の無いことながら、このたびの事態を迎えて、私の元職員に対する管理監督の不行き届きを深く反省し、皆様にご心配をおかけしていることを、深くお詫び申し上げます。 以上が申し上げるべきことの骨子であります」(「西村S悟の時事通信」・Eマガより抜粋)と。 つまり西村S悟議員は、(1)知らなかった、(2)私は関係ない、(3)驚いている、と。が、一転逮捕、起訴されると、今度は、「拉致問題解決のために、議席を確保しなければならない」と。 どうやら西村S悟議員は、相手の立場でものを考えることができない人のようだ。そういう議員が、何かの会合に顔を出せば、拉致被害者およびその家族の人たちは、かえって迷惑するのではないか。そんな簡単なことさえ、西村S悟議員には、まったく、わからないようだ。 ……あるいは、それほどまでに、権力の座は、魅力的なのか? どの人も、一度手にしたら、もう手放せない……といった心境になるらしい。私には無縁の世界の話だが、想像はできる。あのインチキ論文を発表した韓国のU教授にしても、いまだに、「技術はたしかにある」「(研究室の胚性幹(ES)細胞は、(同僚たちによって)すりかえられたものだ」などと主張している。 みんな、どこまでがんばるのだろう? また何のために? 私には、理解できない。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(21)
最前線の子育て論byはやし浩司(034)【近ごろ・あれこれ】●重要文化財・中村家 浜松市の西、車で、あと5分で浜名湖というところに、「中村家」という、江戸時代の旧庄屋家が、復元されて、観光客を集めている。 中村家といえば、江戸時代の大庄屋である。徳川家康とのゆかりも深く、徳川家康の側室、お万の方が、家康の第二子である、於義丸(おぎまる)を、この中村家でもうけている。天正2年(1574)、2月8日のことだそうだ。 係の女性にあちこちを案内してもらったが、驚いたのは、「切腹の間」というのがあったこと。四畳半の狭い部屋だったが、その部屋だけは、壁が朱色に塗られていた。案内の女性は、こう言った。「当時は、少しでも何かあれば、すぐ切腹を命じられました。そのための部屋です」と。 また玄関の右横には、使用人専用の部屋があった。全体でも八畳ほどの細長い部屋だった。ただ寝るだけの部屋だったという。窓は、まったくなかった。 「使用人は、代々、使用人で……」と。今のように、仕事ぶりに応じて、地位や役職があがるということはなかった。私「一生、使用人のままですか?」女「そうでしょうね。しかし当時は、中村家の使用人になるというだけでも、名誉なことだったそうですよ」私「……」と。 横で話を聞いていたワイフが、何度も、「そんな時代に生まれなくてよかった」とつぶやいた。 それにもう一つ驚いたことは、あちこちに、泥棒対策がほどこされていたということ。部屋を仕切る敷居も、高さが20センチほどあった。「泥棒が、足をひっかけて、つまずくようにしたためです」と。案内の女性は、笑いながら、そう説明してくれた。バリヤーフリーではなく、まさに敷居がバリヤーになっていた。それに外と内を仕切る戸にしても、どれも、外からはあけられないしくみになっていた。私「泥棒が、多かったのですか?」女「あちこちで一揆が起きるほどでしかたらね。庄屋はよく、ねらわれたのでしょうね」私「なるほどねエ……」と。 こういう旧家を見ると、私はすぐトイレの話をする。「トイレはありましたか?」と。 案内の女性によれば、身分に応じて、7か所もトイレがあったそうだ。「フ~ン」と驚いたり、感心したり……。 現代建築にも負けない、立派な庄屋である。デザインもすばらしい。カヤぶきの、丸みを帯びた屋根。ほっとするようなぬくもりを感ずる家。その家を中心に、無数のドラマが展開されたのだろう。柱に残された無数のキズを見ながら、心のどこかでふと、そんなことを考える。 ところで、その女性の案内を聞きながら、こんなことも思った。「ずいぶんと私もボケたものだ」と。 徳川家の家系図を見ながら、その女性はなれた口調で、ペラペラと、歴代の人物の名前を説明してくれた。が、どれも私の頭の中に残らない。「14代目はだれだれで、15代目はだれだれで……。その15代目のときに、何々があって……」と。 あとでそのことをワイフに話すと、「私もわからなかった……」と。 「ぼくはね、パソコンの前に座って、キーボードをたたいるときだけ、ものを考えることができる。ああいうところで説明を受けても、何も理解できない。考えることもできない。これはおかしな現象だ」と。 (考える)ことにも、作法というものがあるのか? あるいはそういう(作法)を、自分で作ってしまったのか? よくわからないが、そういうときの私は、一方的に説明を聞くだけ。「ヘエ~」とか、「ホウ~」とか。 ただ一つだけ感じたことは、「やはり江戸時代という時代は、今とは比較にならないほど、窮屈な時代だった」ということ。観光客の人たちは、そういう旧家を案内されると、自分が庄屋の家主か何かになった立場でしか、もの考えない。しかし重要なことは、使用人、あるいはそういう庄屋にせきたてられて、年貢を徴収される農民の立場で、ものを考えること。 生まれながらに使用人は、使用人。農民は農民。そしてつぎの代までバトンタッチするまで、使用人は使用人。農民は農民。それが江戸時代という時代の(現実)である。 なお於義丸(おぎまる)を産んだときの胞衣(えな)(=後産)が埋められたという場所には、例の葵の紋章がかかげられていた。家康お手植えの梅の木も残っていた。興味のある方は、ぜひ、訪れてみてほしい。 案内をしてくれた女性は、さかんに、「桜の咲く、春ごろがすばらしい」と言っていた。入場料は、おとな200円。帰るとき、ワイフは、「また春に来ようね」と言った。私は、「うん」と言って、それに答えた。 そのとき取った写真は、 http://bwhayashi.fc2web.com/page091.htmlで、どうぞ!●パソコンはなおして、使うもの 丸5年使ったパソコン。そのパソコンのCD-RW、DVDユニットが、故障した。ガリガリと音をたてるだけで、用を足さない。 そこでF社に電話で相談すると、「修理費は2万3000円です」と。ついでに、「修理するくらいなら、外付けのCD-RW、DVD-RWを買ったほうがいいですよ」というアドバイスを受けた。 それで外付けのCD-RW、DVD-RWを買った。値段は、1万2000円ほど。 が、先日、二男がアメリカから帰ってきたとき、そのパソコンを見て、こう言った。「パパ、その部分だけ、新品と交換すればよかったじゃん」と。 ナルホド! それには、気づかなかった。F社のパソコンだから、F社の純正の製品でなければ、交換できないと思いこんでいた。で、さっそく、近くのパソコンショップへ足を運ぶ。 店員は、こう説明してくれた。「交換できます。値段は、3000円です」と。 3000円と聞いて驚いた。F社が言った額の8分の1程度。さっそく、それを購入。家に帰って、長男に手伝ってもらって、CD-RW、DVDユニットを交換する。 で、恐る恐る電源をつなぎ、スイッチ・オン! ……ということで、無事、修理は完了。5年使ったとはいえ、当時、24万円で買ったパソコンである。簡単には手放せない。何というか、私にとっては、愛人のようなもの。実際、それぞれにパソコンには、女性名をつけている。F社のパソコンは、「富士子」。P社のパソコンには、「パナ子」と。 しかしそのため、そのパソコンには、ますます愛着心がわいてきた。かわいいというか、いとおしいというか。「富士子、愛しているよ」とか、何とか。ハハハ。こういうのを、この世界では、ビョーキと言うらしい。まあ、いいか。ビョーキでも、何でも……。愛人は、健康であるにかぎる。●男と女 いまだに私は、女性というものが、よくわからない。子どものころは、遊ぶといっても、男ばかり。男とだけ遊んでいた。女と遊んだ経験がない。 その上、幼稚園で働くようになってからは、私は、女性恐怖症になってしまった。母親恐怖症というほうが、正確かもしれない。今でも、相手の女性を、「母親」と意識しただけで、ツンとした緊張感を覚える。「女」をまったく感じなくなる。 「女」は、私にとっては、ずっと謎だったし、今も謎。これから先、死ぬまで、そうだろう。 が、こんな記事を読んだ。あちこちネットサーフィンをしていて、その瞬間、かいま見た記事なので、出典は忘れた。しかしこう書いてあった。 「本来、女のほうが、男より、スケベなのです」と。 どういうわけか、この記事には、少なからず、ショックを受けた。ウソかホントかは、別として、私は、そんなことを、考えたこともなかった。私はずっと、男性のほうがスケベだと思っていた。そのため、女性に対して攻撃的になりやすいと思っていた。 しかし「女のほうが、男より、スケベ」とは? いったいこれは、どういうことなのか。男が女を求める以上に、女は、いつも男を求めている、と。 が、考えてみれば、思い当たるフシは、たくさんある。今の若い人たちを見ていると、女性のほうが積極的なような気がする。攻撃的であるかないかということになれば、女性のほうが、はるかに攻撃的である。あのフロイトは、「すべての生きるエネルギーの源泉に、性的エネルギー(リピドー)がある」と説いた。が、こと性的エネルギーに関しては、女性のほうが強烈なように思う。 とくに現代社会では、女性は「女」を意識してから、結婚するまでの期間が、短い。つまりその間に、理想の「男」を手に入れなければならない。猛烈な勢いで、男をあさる。それはまさしく、命をかけた戦いと言っても過言ではない。 一方、男性は、そこまで追いつめられた気持ちはない。仕事にしても、「一生」というスパン(時的間隔)で考える。結婚イコール、すべてという考え方をしない。 で、男と女は結婚する。(しない人もふえてはいるが……。)が、その状態が、そのままつづく。結婚したからといって、その性的エネルギーが消えるわけではない。むしろ、女性のばあい、結婚したことによって、それまでの夢や目的、仕事を断ち切られてしまう。その不満というか、うっぷんは、相当なもので、そのエネルギーが、今度は、育児や、ばあいによっては、「セックス」に向う。 だから「女のほうが、男よりスケベ」ということになるのか? 女性のことがいまだによくわからない私が、こうした女性論を書くのは、危険なことでもある。自分でも、それがよくわかっている。しかしあえて言うなら、所詮(しょせん)、セックスなんて、無。スケベだからといって、どうということはないし、スケベでないからといって、これまたどうということはない。 それはわかっているが、しかしその記事には、一瞬、ドキッとした。それを書いた人は、どんな根拠があって、そう書いたのか。それを知りたくて、あちこちもう一度、ネットサーフィンをしてみたが、その記事を探し出すことは、二度とできなかった。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(035)●不登校(学校恐怖症・学校拒否症)の問題++++++++++++++++++++栃木県に住んでいる、Yさんから、息子(小2)の不登校についての相談があった。この問題について、少し考えてみたい。++++++++++++++++++++【Yより、はやし浩司へ(1)】小2の長男が二学期末に胃腸風邪になり、回復しても学校で嘔吐して早退ということを二度繰り返しました。その時ピンと感じましたが、そのまま冬休みに入ったので、冬休みは家族でのんびり楽しく過ごしました。始業式は普通に登校できました。が、昨日、通常の登校をするため玄関で靴を履きそうになったとたん、『気持ち悪い。吐きそう』と訴えたので欠席させました。その後は元気で弟とケンカしたり、一日遊んでいました。が、学校は行きたくない。三日休みたいとのことなので、三日休ませることにしました。先生の本に書いてある不登校の前兆だと思うので『誰だって休みたい時はあるよ』と言いました。長男は二年前に神経症を発しています。小1の4月からプレイセラピーに通っています。かなり安定して小1の冬にまた神経症が悪化し、しばらくして回復。その後2年生になり驚くほど毎日元気に過ごしていました。セラピーも終了間近でした。ちょっと疲れが溜まっているのかもしれません。そして、冬は彼が2歳の時に家庭不和があったのでトラウマになっているのではと思います。だから冬になるとこうした症状が出るのではとも思います。不登校というのはついに来たかという感じです。夫と私は今はとても良い関係で、関係修復後は長男の事をよく語り合い、反省し、考えていました。現在、神経症は出ていないものの、三日休んで、次に登校すると言った月曜に登校できるかなというなという不安はあります。約束だから登校だけはさせるべきか、休んで単身赴任の夫の元へ遊びに行ってしまうか、家でのんびりするか、迷っています。先生に学校は行くべきものという考えを捨てなさいとお叱りを受けそうですが、まだ小2。弟とケンカばかりするし、一日家で見ているのはとてもしんどいです。勉強も根気よく教える事ができません。今まで二度メールさせていただいて、先生の的確なアドバイスにとても助けられました。今回も、簡単で結構ですので、迷っている私にどうかアドバイスをお願いします。【Yより、はやし浩司へ(2)】はやし先生子どもの不登校について相談しています、U市のYです。相談している私がこう書くのも変ですが、先生とても大変だったのですね。お体はもう大丈夫ですか?今度は急に暖かくなり、なだれも心配ですね。さて、私の息子(小2)についてですが、先生のアドバイスで学校恐怖症を疑ってみるようにとの事だったので、先生のHPから学校恐怖症の部分を読んでみました。まさにそうです。今、前兆期です。ほんとうにピッタリとパターンに当てはまるので、驚くほどです。昨夜も登校すると言っていて、今朝も通常通り支度をし、ランドセルをしょって、部屋を出ようとしたとたん血の気が引いたようになり、トイレへ駆け込みました。しばらくすると落ち着いて、自分で欠席を決め、今は顔色も良く元気です。先生のおっしゃる通りです。そこで質問なのですが、無理をせず休ませて、その後はどのようにしていったら良いでしょうか?先生は本にもHPにも前兆期での対応が大切だと書かれています。いかにこの時期をとらえるかと。本には悪いパターンが書いてありますが、前兆期に無理をさせず対処した場合、今後どのように推移していくのでしょうか?私達は夫婦で、子どもが真面目タイプでがんばりすぎていたこと、弟のようにもっと甘えたかった、そして疲れ果ててしまったのだと考えています。でも、ずっとこのままずるずると家にいるのではという不安でいっぱいです。休んだ一週間が、一ヶ月のように長く感じます。この先もこれが続くかという閉塞感、不安感でいっぱいです。もともと神経症がある子なので、無理強いしても無駄、逆に悪化するというのはわかっています。どうにもならないと思っても、今の状況では落ち着けません。先生、それでも、この手の話しはよく聞くことで、経験のある友人が何人かいます。中には首に縄つけて引っ張っていき、それで乗り越えたという人が2、3人います。その後、パニック期などに推移せず、それで解決したそうです。やはり、子の性質や心にある原因によりけりなのでしょうか?私はとても今の状況で子どもに無理に登校はさせられないけど、友人達には甘いと言われています。そうでない人が一人いるのが救いです。なんだか、書いていてまとまりがつかなくなりました。はやし先生、前兆期でゆっくり休んだ子が推移するパターン、今、私がどうやっていたらよいか、またアドバイスくださると嬉しいです。お返事は急ぎません。先生のお時間があるときにで結構です。ここまで読んでくださってありがとうございました。それでは失礼します。+++++++++++++++++++++【はやし浩司より、Yさんへ……】 不登校といっても、心の問題がからむタイプもあれば、怠学といって、(なまけ心)がからむ問題もあります。「首に縄つけて引っ張っていき、それで乗り越えたという人が2、3人います」というのは、学校恐怖症のほうではなく、怠学のほうではないでしょうか。 あくまでも子どもの症状を見て判断しますが、学校恐怖症と怠学のちがいについては、アメリカの内科医学会の判断基準を参考に、Yさんご自身が判断されたらよいかと思います。(詳しくは、「はやし浩司のHP」→「タイプ別子どもの見方」→「学校恐怖症」を、ご覧になってください。一部を、以下に抜粋しておきます。)+++++++++++++++++TABLE 1 Criteria for Differential Diagnosis of School Refusal and Truancy (学校拒否と、怠学の基準) School refusal (学校拒否)Truancy (怠学)Severe emotional distress about attending school; may include anxiety, temper tantrums, depression, or somatic symptoms.学校に通うことについて、心配、不安、腹立たしさ、うつ、体の変調などの、苦痛が見られる。Lack of excessive anxiety or fear about attending school. 学校に通うことについて、大きな不安や恐れはない。Parents are aware of absence; child often tries to persuade parents to allow him or her to stay home. 両親がそれ気づいていて、子どもが、「行きたくない」と、親を説得する。Child often attempts to conceal absence from parents. 両親の知らないところで、勝手に学校へ行くのを、さぼったりする。Absence of significant antisocial behaviors such as juvenile delinquency. 少年非行などの、顕著な、反社会的行動をともなわない。Frequent antisocial behavior, including delinquent and disruptive acts (e.g., lying, stealing), often in the company of antisocial peers. (ウソ、盗みなどの)反社会的行動をともなうことが多い。集団非行グループに属することが多い。During school hours, child usually stays home because it is considered a safe and secure environment. 学校へ行く時間に、家にいることが多い。そのほうが安全と考えるからである。During school hours, child frequently does not stay home . 学校へ行く時間でも、家にいないことが、多い。Child expresses willingness to do schoolwork and complies with completing work at home. 子ども自身は、家庭で宿題をしたり、宿題をすることに応ずる。Lack of interest in schoolwork and unwillingness to conform to academic and behavior expectations. 学校の勉強そのものに興味を示さず、勉強するのをいやがる。●アメリカ内科医学会は、「学校拒否症」の要因となる、不安障害(Anxiety disorders)として、つぎのものをあげている。 Separation anxiety (分離不安)Anxiety disorder(不安障害)Generalized anxiety disorder (不安障害全般)Social phobia (社会恐怖症)Simple phobia (孤立恐怖症)Panic disorder (パニック障害)Panic disorder with agoraphobia (広場恐怖症をともなうパニック障害)Post-traumatic stress disorder (PTSD)Agoraphobia(広場恐怖症) Mood disorders(気分障害) Major depression (うつ病)Dysthymia(抑うつ症)●また同じく、「学校拒否症」の要因となる、破滅行動障害(Disruptive behavior disorders)については、つぎのようなものをあげている(同)。 Oppositional defiant disorder (反抗障害)Conduct disorder (行為障害)Attention-deficit/hyperactivity disorder (注意力散漫、過集中障害)Disruptive behavior disorder,(破滅的行為障害) Other disorders(他の障害) Adjustment disorder (with depressed mood or anxiety) (うつをともなう、適応障害)Learning disorder (学習障害)Substance abuse OtherThe evaluation should include interviews with the family and individual interviews with the child and parents. Assessment should include a complete medical history and physical examination, history of the onset and development of school refusal symptoms, associated stressors, school history, peer relationships, family functioning, psychiatric history, substance abuse history, and a mental status examination. Identification of specific factors responsible for school avoidance behaviors is important. Collaboration with school staff in regards to assessment and treatment is necessary for successful management (Table 5) . School personnel can provide additional information to aid in assessment, including review of attendance records, report cards, and psychoeducational evaluations. The School Refusal Assessment Scale includes a child, parent, and teacher form and is reported to have a high reliability and validity. 学校拒否症の診断基準は、高い信頼性と、有効性が報告されています。 Several psychologic assessment tools (e.g., teacher and parent rating scales, self-report measures, clinician rating scales) have been developed to provide additional information about the child's general functioning at home and at school. These tools may be used by a physician, but because of time constraints, a school psychologist or mental health counselor should administer these scales whenever possible. Generalized scales (e.g., Child Behavior Checklist, 21 Teacher's Report Form 22 ) identify areas of difficulties. Specific rating scales assess for symptoms and severity of psychiatric problems, including anxiety and depression. Although these scales are used frequently in children with school refusal, their clinical usefulness in developing effective treatment strategies has not been demonstrated. More specific assessment scales to measure symptoms of school refusal have been developed recently. They provide functional and symptomatic assessment of refusal behaviors and therefore provide more valuable information. The School Refusal Assessment Scale (Table 6, online) 23 includes a child, parent, and teacher form and examines school refusal in correlation to negative and positive reinforcers. This scale has been reported to have high reliability and validity. 23,24 TABLE 6 Items from the School Refusal Assessment Scale-Revised 学校拒否症の評価基準項目 Items from child version (子どもへの質問項目)How often do you have bad feelings about going to school because you are afraid of something related to school (e.g., tests, school bus, teacher, fire alarm)? (1) 何か学校に関係あることで、学校へ行くことで、気分が悪くなることが、どれだけしばしばありますか。(たとえばテスト、通学、先生、あるいは火災警報器など)How often do you stay away from school because it is hard to speak with the other kids at school? (2) 学校で、ほかの仲間と話すのがつらくて、学校を休むことが、どれくらいありますか。How often do you feel you would rather be with your parents than go to school? (3)学校へ行くより、家で両親といたいと思うことは、どれくらいありますか。 When you are not in school during the week (Monday to Friday), how often do you leave the house and do something fun? (4) (月曜日から金曜日までの)間で、あなたが学校へ行っていないとき、どれくらいしばしば、家を離れたり、何かほかの楽しみをしますか。How often do you stay away from school because you feel sad or depressed if you go? (1) 学校へ行くと、悲しくなったり、落ちこんだりするので、どれくらいしばしば学校を休みますか。How often do you stay away from school because you feel embarrassed in front of other people at school? (2) ほかの仲間のいるところだと、落ちつかないという理由で、どれくらいしばしば、学校を休みますか。How often do you think about your parents or family when you are in school? (3) 学校にいる間、どれくらいしばしば、両親や家族のことを考えますか。When you are not in school during the week (Monday to Friday), how often do you talk to or see other people (other than your family)? (4) (月曜日から金曜日までの間で)、学校を休んでいるとき、どれだけしばしば、(家族以外の)ほかの人と会ったり、話したりしますか。How often do you feel worse at school (e.g., scared, nervous, sad) compared with how you feel at home with friends? (1) 家で友といるときとくらべて、学校にいるときのほうが、より悪く感じますか。(たとえば恐れたり、神経質になったり、悲しくなったりするなど)How often do you stay away from school because you do not have many friends there? (2) 学校には友だちがいないという理由で、どれほどしばしば学校を休みますか。How much would you rather be with your family than go to school? (3) 学校へ行くより、あなたの家族といっしょに家にいたいと、どれだけ強く感じますか。When you are not in school during the week (Monday to Friday), how much do you enjoy doing different things (e.g., being with friends, going places)? (4) (月曜日から金曜日までの間で)、あなたが学校にいないとき、(たとえば友だちといることや、どこかへ行くことなどで)、あなたはどれだけ、違ったことを楽しみますか。How often do you have bad feelings about school (e.g., scared, nervous, sad) when you think about school on Saturday and Sunday? (1) 土曜日や日曜日に、学校のことを思うと、どれだけしばしば、あなたは学校に対して、悪い感情をもちますか。How often do you stay away from places in school (e.g., hallways, places where certain groups of people are) where you would have to talk to someone? (2) 学校にいるとき、(通路や友が集まるところなど)、あなたがいるべきところから、あなたはどこか別の場所に、どれくらいしばしば離れて行きますか。How much would you rather be taught by your parents at home than by your teacher at school? (3) 学校の先生よりも、家で両親によって、むしろ教えられると、どれくらい強く感じますか。How often do you refuse to go to school because you want to have fun outside of school? (4) 学校の外で楽しみたいという理由で、どれくらいしばしば、学校へ行くのを拒絶しますか。If you had fewer bad feelings (e.g., scared, nervous, sad) about school, would it be easier for you to go to school? (1) もし不愉快な感情(恐れ、神経質、悲しみなど)を学校に感じないなら、あなたにとって学校へ行くことは、楽なことだと思いますか。If it were easier for you to make new friends, would it be easier for you to go to school? (2) もしあなたが新しい友だちをつくることが、もっと簡単なら、学校へ行くのも楽になると、あなたは思いますか。Would it be easier for you to go to school if your parents went with you? (3) 両親がいっしょに行ってくれるなら、学校へ行くことは、もっと楽になると思いますか。Would it be easier for you to go to school if you could do more things you like to do after school hours (e.g., being with friends)? (4) 放課後、もっといろいろなことができれば、あなたにとって学校へ行くのが、もっと楽になると、思いますか。(たとえば友だちといっしょにいるなど。)How much more do you have bad feelings about school (e.g., scared, nervous, sad) compared with other kids your age? (1) 同年齢の仲間とくらべて、あなたはどれだけより多くの不愉快な感情(恐れ、神経質、悲しみ)などを、もっていると思いますか。How often do you stay away from people in school compared with other kids your age? (2) 他の仲間たちと比べて、あなたはどれくらいしばしば、学校の中で、他の中間たちと離れていますか。Would you like to be home with your parents more than other kids your age would? (3) 同年齢の他の仲間がそうであるよりも、あなたは家で、両親といたいと、あなたは思いますか。Would you rather be doing fun things outside of school more than most kids your age? (4) 同年齢の他の仲間たちがそうであるよりも、あなたは学校の外で、楽しいことをもっとしたいと思っていますか。Items from parent version (両親への質問項目)How often does your child have bad feelings about going to school because he/she is afraid of something related to school (e.g., tests, school bus, teacher, fire alarm)? (1) 学校へ行くことに関して、(たとえばテスト、通学、先生、火災警報器などで)、それがこわいなどの理由で、悪い感情を、どれくらいしばしば、あなたの子どもは、もちますか。How often does your child stay away from school because it is hard for him/her to speak with the other kids at school? (2) 学校で友だちと話すのがいやで、どれくらいしばしばあなたの子どもは、学校を休みますか。How often does your child feel he/she would rather be with you or your spouse than go to school? (3) 学校へ行くより、あなたや、あなたの夫(妻)といっしょにいたいと、あなたの子どもは、いかにしばしば、思いますか。When your child is not in school during the week (Monday to Friday), how often does he/she leave the house and do something fun? (4) (月曜日から金曜日までで)、あなたの子どもが学校にいないとき、いかにしばしば、あなたの子どもは家から出て、何か自分の好きなことをしますか。How often does your child stay away from school because he/she will feel sad or depressed if he/she goes? (1) いかにしばしば、あなたの子どもは、学校へ行くとこわいとか、悲しいとかいう理由で、学校を休みますか。How often does your child stay away from school because he/she feels embarrassed in front of other people at school? (2) いかにしなしば、あなたの子どもは、学校で人の前で、どうしたらいいか、わからないという理由で、学校を休みますか。When your child is in school, how often does he/she think about you or your spouse or family? (3) あなたの子どもが学校にいるとき、いかにしばしばあなたの子どもは、あなたや、あなたの夫(妻)もしくは家族のことを考えますか。When your child is not in school during the week (Monday to Friday), how often does he/she talk to or see other people (other than his/her family)? (4) (月曜日から金曜日までの間で)、あなたの子どもが学校を休んでいるとき、いかにしばしば、(家族以外の)だれかと会ったり、話したりしますか。How often does your child feel worse at school (e.g., scared, nervous, sad) compared with how he/she feels at home with friends? (1) 家で友だちと会うときと比較して、あなたの子どもは、学校で友だちを会うことのほうを、いかにしばしばいやがりますか。How often does your child stay away from school because he/she does not have many friends there? (2) 学校には、あまり友だちがいないという理由で、いかにしばしばあなたの子どもは、学校を休みますか。How much would your child rather be with his/her family than go to school? (3) あなたの子どもは、学校へ行くより、家にいたいと、どれだけ強く思っていますか。When your child is not in school during the week (Monday to Friday), how much does he/she enjoy doing different things (e.g., being with friends, going places)? (4) (月曜日から金曜日までの間で)、あなたの子どもが学校を休んでいるとき、あなたの子どもは、どれくらい、(たとえばあなたの友だちといるか、どこかへでかけていくとかで)、あなたの子どもは、ちがったことをしていますか。How often does your child have bad feelings about school (e.g., scared, nervous, sad) when he/she thinks about school on Saturday and Sunday? (1) 土曜日や日曜日など、学校のことを考えたりしたりして、あなたの子どもは、どれくらいしばしば、学校について(たとえば恐れを感じたり、神経質になったり、悲しんだりするなど)、悪い感情をもちますか。How often does your child stay away from places in school (e.g. hallways, places where certain groups of people are) where he/she would have to talk to someone? (2) いかにしばしばあなたの子どもは、学校の中で、ふつうならそういう場所に、いたいと思うようなところ、(たとえば通路やあるグループなど)から、離れていますか。How much would your child rather be taught by you or your spouse at home than by his/her teacher at school? (3) あなたの子どもは、学校で先生に教えられるより、家で、あなたやあなたの夫(妻)から、いかに多く、教えられていますか。How often does your child refuse to go to school because he/she wants to have fun outside of school? (4) 学校の外での楽しみたいというような理由で、いかにしばしばあなたの子どもは、学校へ行くのを拒否しますか。If your child had fewer bad feelings (e.g., scared, nervous, sad) about school, would it be easier for him/her to go to school? (1) もしあなたの子どもが、学校に対して、悪い感情(たとえば恐れ、神経質、悲しみなど)がなければ、あなたの子どもが、学校へ行くことは、よりたやすくなると思いますか。If it were easier for your child to make new friends, would it be easier for him/her to go to school? (2) もしあなたの子どもが、より簡単に友だちができるとしたら、あなたの子どもが学校へ行くのは、もっと簡単になると思いますか。Would it be easier for your child to go to school if you or your spouse went with him/her? (3) もしあなた、もしくは、あなたの夫(妻)が、子どもといっしょに行くなら、あなたの子どもにとって、学校へ行くのが、もっと簡単になると思いますか。Would it be easier for your child to go to school if he/she could do more things he/she likes to do after school hours (e.g., being with friends)? (4) もし放課後、あなたの子どもが、もっとほかのjことができたら、あなたの子どもにとって、学校へ行くのが、もっと簡単になると、あなたは思いますか。How much more does your child have bad feelings about school (e.g., scared, nervous, sad) compared with other kids his/her age? (1) ほかの同年齢の子どもと比較して、あなたの子どもは、どれくらい強く、学校に対して、(恐れ、神経質。悲しみなど)の悪い感情をもっていますか。How often does your child stay away from people in school compared with other kids his/her age? (2) ほかの同年齢の子どもと比較して、あなたの子どもは、学校の中で、いかにしばしば、友だちから遠ざかっていますか。Would your child like to be home with you or your spouse more than other kids his/her age would? (3) ほかの同年齢の子どもより、あなたの子どもは、あなたや、あなたの夫(妻)といっしょに家にいたがりますか。Would your child rather be doing fun things outside of school more than most kids his/her age? (4) ほかの同年齢の子どもより、あなたの子どもは、学校の外で、もっと楽しいことをしたいと思っていますか。 I = avoidance of stimuli that provoke negative affectivity; 否定的行動のを引き起こす、刺激の回避2 = escape from aversive social or evaluative situations;嫌悪的な社会的もしくは評価的な状況からの逃避 3 = pursuit of attention;興味の追求 4 = pursuit of tangible reinforcement. 現実強化の追求Adapted with permission from Kearney CA. Identifying the function of school refusal behavior: a revision of the School Refusal Assessment Scale. J Psychopathol Behav Assess 2002;24:235-45. Treatment (治療)The primary treatment goal for children with school refusal is early return to school. Physicians should avoid writing excuses for children to stay out of school unless a medical condition makes it necessary for them to stay home. Treatment also should address comorbid psychiatric problems, family dysfunction, and other contributing problems. Because children who refuse to go to school often present with physical symptoms, the physician may need to explain that the problem is a manifestation of psychologic distress rather than a sign of illness. A multimodal, collaborative team approach should include the physician, child, parents, school staff, and mental health professional. Treatment options include education and consultation, behavior strategies, family interventions, and possibly pharmacotherapy. Factors that have been proved effective for treatment improvement are parental involvement and exposure to school. 25,26 [Reference 25--Evidence level B, uncontrolled trial] However, few controlled studies have evaluated the efficacy of most treatments. Treatment strategies must take into account the severity of symptoms, comorbid diagnosis, family dysfunction, and parental psychopathology. A range of empirically supported exposure-based treatment options are available in the management of school refusal. When a child is younger and displays minimal symptoms of fear, anxiety, and depression, working directly with parents and school personnel without direct intervention with the child may be sufficient treatment. If the child's difficulties include prolonged school absence, comorbid psychiatric diagnosis, and deficits in social skills, child therapy with parental and school staff involvement is indicated. BEHAVIOR INTERVENTIONS (行動介入)Behavior approaches for the treatment of school refusal are primarily exposure-based treatments. 27 [Evidence level B, lower quality randomized controlled trial (RCT)] Studies have shown that exposure to feared objects or situations reduces fear and increases exposure attempts in adults. 28 These techniques have been used to treat children with phobias and school refusal. Behavior techniques focus on a child's behaviors rather than intrapsychic conflict and emphasize treatment in the context of the family and school. Behavior treatments include systematic desensitization (i.e., graded exposure to the school environment), relaxation training, emotive imagery, contingency management, and social skills training. Cognitive behavior therapy is a highly structured approach that includes specific instructions for children to help gradually increase their exposure to the school environment. In cognitive behavior therapy, children are encouraged to confront their fears and are taught how to modify negative thoughts. EDUCATIONAL-SUPPORT THERAPY (教育的サポートセラピー)Traditional educational and supportive therapy has been shown to be as effective as behavior therapy for the management of school refusal. 29 [Evidence level B, lower quality RCT] Educational-support therapy is a combination of informational presentations and supportive psychotherapy. Children are encouraged to talk about their fears and identify differences between fear, anxiety, and phobias. Children are given information to help them overcome their fears about attending school. They are given written assignments that are discussed at follow-up sessions. Children keep a daily diary to describe their fears, thoughts, coping strategies, and feelings associated with their fears. Unlike cognitive behavior therapy, children do not receive specific instructions on how to confront their fears, nor do they receive positive reinforcement for school attendance. Child therapy involves individual sessions that incorporate relaxation training (to help the child when he or she approaches the school grounds or is questioned by peers), cognitive therapy (to reduce anxiety-provoking thoughts and provide coping statements), social skills training (to improve social competence and interactions with peers), anddesensitization (e.g., graded in vivo exposure, emotive imagery, systematic desensitization). PARENT-TEACHER INTERVENTIONS (親と教師の介在)Parental involvement and caregiver training are critical factors in enhancing the effectiveness of behavior treatment. Behavior interventions appear to be equally effective with or without direct child involvement. 25 [Evidence level B, lower quality RCT] School attendance and child adjustment at post-treatment follow-up are the same for children who are treated with child therapy alone and for children whose parents and teachers are involved in treatment. Parent-teacher interventions include clinical sessions with parents and consultation with school personnel. Parents are given behavior-management strategies such as escorting the child to school, providing positive reinforcement for school attendance, and decreasing positive reinforcement for staying home (e.g., watching television while home from school). Parents also benefit from cognitive training to help reduce their own anxiety and understand their role in helping their children make effective changes. School consultation involves specific recommendations to school staff to prepare for the child's return, use of positive reinforcement, and academic, social, and emotional accommodations. PHARMACOLOGIC TREATMENT (薬物治療)Pharmacologic treatment of school refusal should be used in conjunction with behavioral or psychotherapeutic interventions, not as the sole intervention. Interventions that help children develop skills to master their difficulties prevent a recurrence of symptoms after medication is discontinued. Very few double-blind, placebo-controlled studies have evaluated the use of psychopharmacologic agents in the treatment of school refusal, although several controlled studies are in progress. Problems with sample sizes, differences in comorbidity patterns, lack of control of adjunctive therapies, and differences in medication dosages have resulted in inconclusive data in trials of pharmacologic agents in the treatment of school refusal. 30,31 Earlier studies of tricyclic antidepressants failed to show a replicable pattern of efficacy. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have replaced tricyclic antidepressants as the first-line pharmacologic treatment for anxiety disorders in children and adolescents. Although there are few controlled, double-blind studies of SSRI use in children, preliminary research suggests that SSRIs are effective and safe in the treatment of childhood anxiety disorders and depression. 32,33 [Reference 32--Evidence level B, nonrandomized study] Fluvoxamine (Luvox) and sertraline (Zoloft) have been approved for the treatment of obsessive compulsive disorder in children. SSRIs are being used clinically with more frequency to treat children with school refusal. Benzodiazepines have been used on a short-term basis for children with severe school refusal. A benzodiazepine initially may be prescribed with an SSRI to target acute symptoms of anxiety; once the SSRI has had time to produce beneficial effects, the benzodiazepine should be discontinued. Side effects of benzodiazepines include sedation, irritability, behavior disinhibition, and cognitive impairment. Because of the side effects and risk of dependence, benzodiazepines should be used for only a few weeks. 34 The author thanks John Smucny, M.D., for assistance in preparing the manuscript. The author indicates that she does not have any conflicts of interest. Sources of funding: none reported. ++++++++++++++++++++++
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(20ー2)
日本の常識、世界の非常識(中日新聞投稿済み)●「水戸黄門」論……日本型権威主義の象徴が、あの「水戸黄門」。あの時代、何がまちがっているかといっても、身分制度(封建制度)ほどまちがっているものはない。その身分制度という(巨悪)にどっぷりとつかりながら、正義を説くほうがおかしい。日本人は、その「おかしさ」がわからないほどまで、この権威主義的なものの考え方を好む。葵の紋章を見せつけて、人をひれ伏せさせる前に、その矛盾に、水戸黄門は気づくべきではないのか。仮に水戸黄門が悪いことをしようとしたら、どんなことでもできる。それこそ19歳の舞妓を、「仕事のこやし」(人間国宝と言われる人物の言葉。不倫が発覚したとき、そう言って居直った)と称して、手玉にして遊ぶこともできる。●「釣りバカ日誌」論……男どうしで休日を過ごす。それがあのドラマの基本になっている。その背景にあるのが、「男は仕事、女は家庭」。その延長線上で、「遊ぶときも、女は関係なし」と。しかしこれこそまさに、世界の非常識。オーストラリアでも、夫たちが仕事の同僚と飲み食い(パーティ)をするときは、妻の同伴が原則である。いわんや休日を、夫たちだけで過ごすということは、ありえない。そんなことをすれば、即、離婚事由。「仕事第一主義社会」が生んだ、ゆがんだ男性観が、その基本にあるとみる。●「森S一のおふくろさん」論……夜空を見あげて、大のおとなが、「ママー、ママー」と泣く民族は、世界広しといえども、そうはいない。あの歌の中に出てくる母親は、たしかにすばらしい人だ。しかしすばらしすぎる。「人の傘になれ」とその母親は教えたというが、こうした美化論にはじゅうぶん注意したほうがよい。マザコン型の人ほど、親を徹底的に美化することで、自分のマザコン性を正当化する傾向が強い。●「かあさんの歌」論……窪田S氏作詞の原詩のほうでは、歌の中央部(3行目と4行目)は、かっこ(「」)つきになっている。「♪木枯らし吹いちゃ冷たかろうて。せっせと編んだだよ」「♪おとうは土間で藁打ち仕事。お前もがんばれよ」「♪根雪もとけりゃもうすぐ春だで。畑が待ってるよ」と。しかしこれほど、恩着せがましく、お涙ちょうだいの歌はない。親が子どもに手紙を書くとしたら、「♪村の祭に行ったら、手袋を売っていたよ。あんたに似合うと思ったから、買っておいたよ」「♪おとうは居間で俳句づくり。新聞にもときどき載るよ」「♪春になったら、村のみんなと温泉に行ってくるよ」だ。●「内助の功」論……封建時代の出世主義社会では、「内助の功」という言葉が好んで用いられた。しかしこの言葉ほど、女性を蔑視した言葉もない。どう蔑視しているかは、もう論ずるまでもない。しかし問題は、女性自身がそれを受け入れているケースが多いということ。約23%の女性が、「それでいい」と答えている※。決して男性だけの問題ではないようだ。※……全国家庭動向調査(厚生省98)によれば、「夫も家事や育児を平等に負担すべきだ」という考えに反対した人が、23・3%もいることがわかった。+++++++++++++++++ 要するに、いまだに、日本人は、あの封建時代の亡霊を、ひきずっているということ。身分制度という亡霊である。世の中には、その封建時代を美化し、たたえる人も少なくないが、本当にそんな世界が理想の世界なのか、またあるべき世界なのか、もう一度、冷静に考えなおしてみてほしい。(はやし浩司 権威主義 権威主義者 親子の亀裂 断絶)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※●仕事ができる喜び++++++++++++++仕事ができる喜び。私は人生58年目にして、はじめてそれを知った。++++++++++++++ 私は、満58歳になった。幼児を教えるようになって、36年目になった。その私が、おかしなことだが、本当におかしなことだが、この年齢になってはじめて、いわゆる(仕事ができる喜び)を感じ始めるようになった。 とくに今年の正月は、最悪だった。軽いインフルエンザがきっかけで、いくつかの雑病を併発。暮れの29日から、正月の5日ごろまで、連日、37~38・5度の熱と悪寒に、繰りかえし、襲われた。苦しんだ。 ときどき「もう、だめだ」と思った。「こんな調子では、今年は、とても仕事は、つづけられない」と思った。 しかし正月休みが終わり、いつものように自転車にまたがってみた。すると、驚くなかれ。何と、足だけは、スイスイと動くではないか! 教室のある街までの途中には、ゆるいが、長い、ダラダラ坂がある。「今年は、だめだろうな……」と思っていたが、その坂でさえ、途中で休むこともなく、登ることができた! うれしかった! とたん、心をおおっていた、モヤモヤした黒い霧が、パッと晴れた。「まだまだ、できる!」と、声には出さなかったが、心の中で、そう叫んだ。 ……というような話を若い人に言っても、ピンとこないかもしれない。しかしこの年齢になると、老いゆく自分の姿や形を見ながら、いつも「どこまでがんばれるのだろう」と思うことが多くなる。将来への不安は、いつも、影のように、自分につきまとう。 一方、まだ仕事をやめる年齢ではない。悠々(ゆうゆう)自適の隠居生活というが、そんな生活には、私は興味はない。またそんな生活に、どんな意味があるというのか。またそんな生活をしたからといって、それがどうだというのか。5年を1日のように生きるだけ。10年を1日のように生きるだけ。しかしそれこそ、時間というより、命の無駄。だから私は、働く。死ぬまで、働く。 が、その気持ちも、大きな壁にぶつかる。ぶつかって、容赦なく、はねとばされる。その気持ちはあっても、体力や気力がつづかない。とくに今度のように、病気になったときは、そうだ。 が、私は、健康だった。体が動いた。気力が動いた、子どもたちの声を聞いたとたん、心がパッと晴れた。 その私は、健康のありがたさを、しみじみと感じている。おかしなことだが、本当におかしなことだが、私は、人生58年目にして、仕事ができる喜びを感じ始めている。++++++++++++++++++++++++はやし浩司●老人よ、働こうよ!++++++++++++++++くだらない隠居生活など、考えてはいけない。私たちは、働く。死ぬまで働く。それこそ、健康なものだけがもつ、特権なのだ。働くことを、決して、損と考えてはいけない。++++++++++++++++ 2007年問題というのがある。この年、団塊の世代が、いっせいに退職を開始する。そのため、2007年以後、日本の労働力は急減。社会にも大きな影響をおよぼすという。それが2007年問題。 かなり深刻な問題らしい。 しかし悲観的になることはない。その団塊の世代が、またまたがんばり始めている。書店にも、その種の本が並ぶようになった。「団塊パワー」(仮称)とか、何とか。 私も、昭和22年生まれの、その団塊の世代の1人。だが、60歳になったからといって、引退したり、仕事をやめる気は、毛頭、ない。もっと言えば、年齢など、関係ない。死ぬまで現役。仕事をやめるときイコール、年貢の納めどき。 さあ、老人たちよ、働こうではないか。働けば働くほど、世のため、人のため。そして自分のため。「道楽」と「仕事」のちがいなど、今さら、説明するまでもない。緊張感がまるでちがう。その緊張感が、自分を若返らせる。健康にもよい。だから働く。責任をもって、働く。 もし働ける老人たちが、75歳まで働いたら、日本の少子化問題は、吹き飛んでしまうという(某総合誌)。かなりおおまかな計算だが、そういうことらしい。もちろん病気になったりする人もいるだろう。健康な老人は、そういう人たちの分まで働けばよい。 しかしそれは決して、損なことではない。働くということを、損と考える人もいるかもしれない。しかし毎日、毎日、庭木の手入れができたとしても、それが本当に「得をした」ということになるのか。働く、働けるということは、それ自体が、すばらしい財産なのだ。価値なのだ。健康な人は、その特権にこそ、目を向けるべきである。そして喜ぶべきである。損得の勘定は、そのあとに考えればよい。【補記】 仕事を、責務と考えている間は、働く喜びは、わいてこないのではないか。それに働く喜びというのは、働けなくなった苦しみの反射的効果としてわいてくるものであって、一度は、その苦しみの洗礼を受けなければならない。 「生活のため」「お金のため」「家族のため」と考えながら働いていると、どうしても、そこに責務感がともなう。その責務感が、時として、自分がしている仕事を、重く、苦しいものにする。 限りある人生の中で、その先に限界を感じながら、つまり今を生きる証(あかし)として、働く。そういう追いつめられた気持が、働くことに、喜びをそえる。だれのためでもない。もちろん自分のためでもない。昔の狩人(かりうど)が、生きるために狩をしたように、生きるために働く。その実感が、ここでいう働く喜びということになる。++++++++++++++++++++++++はやし浩司●繊細な感覚+++++++++++++++++++ボケの初期症状の一つに、周囲の人や人の心の動きに、鈍感になることがあげられる。つまり、繊細な感覚がなくなり、ものの言い方や態度が、どこかつっけんどんになる。しかし自分で、それに気づく人は少ない。他人に指摘されても、それを理解できる人はいない。この問題には、脳みそのCPU(中央演算装置)がからんでいるだけに、ことは、やっかいである。++++++++++++++++++++●自分を知る ボケ始めた人が、それを自分で知るためには、どうすればよいのか。もの忘れがひどくなったとか、生活習慣がだらしなくなったとか、ある程度のことは、自分でそれを知ることができる。 しかしそれも、ある程度までの話。その程度を超えると、とたんに、それがわからなくなる……らしい。「あなた、少しボケてきたんじゃないの?」と指摘しても、「私は、ふつう」「だいじょうぶ」と言って、がんばる。 私の身近に、Aさんという女性(今年65歳くらい)がいる。昔から、1年に1度くらいの頻度で、何らかの機会に会ったり、話をしたりしている。そのAさん、このところ、少し様子がおかしい。急速に繊細さが消え始めた。 私が微妙な話をしても、それが通じない。トンチンカンというか、ヌカにクギというか、反応がまるでない。「だから、それがどうしたの?」というような返事をする。そこで私が、「たいへん深刻な問題だと思いますが……」と、うながしても、「あら、そう?」で終わってしまう。 私は、Aさんが、認知症の一歩手前か、すでに認知症の段階に進んでいるのではないかと思う。で、そのAさんを見ながら、先日は、こんなことを考えた。 「どうすれば、Aさんは、自分でそれに気づくことができるか」と。 で、あれこれ考えてみたが、結論は、「無理だろうな」ということ。先にも書いたように、この問題には、脳みそのCPUがからんでいる。つまりCPUそのものが、変調するため、自分を客観的に見たり、判断することができなくなる。自己認識したり、自己評価したりすることができなくなる。 Aさんのばあいも、私が何かの意見を言ったりすると、その10倍くらいの反論が返ってくる。よくしゃべる。しかし一方的な反論で、ほとんど意味がない。薄っぺらい。中身がない。脳みその表層部分に飛来する情報を、そのままペラペラと音声にかえているだけといった感じ。 しかしまさか、「脳の検査を受けてみたら」と言うわけには、いかない。仮に何らかの処置をしたところで、それで認知症がなおるわけではない。進行の速度を遅くすることはできるらしいが、そこまで。 ……ということで、Aさんの話はここまでにして、では、私たちはどうしたらよいのか。どうすれば、自分を知ることができるか。認知症なら認知症でもよい。どこまで自分の認知症が進んでいるかを、どうすれば、知ることができるか。 私のばあいは、こうしてほとんど毎日、何らかの文章を書いている。だから、その文章を比較することで、ボケの進行度を、ある程度、知ることができる。5年前に書いた文章や、10年前に書いた文章を読みなおしてみる。そして今、書いている文章と比較しながら、その(深さ)や(鋭さ)を、知ることができる。 (深さ)や(鋭さ)が鈍っていれば、それだけ、脳みその活動が鈍ってきたことを意味する。ボケが始まっていることを意味する。 そういう視点で見ると、たしかに、ここ1、2年、その(深さ)や(鋭さ)が鈍ってきたように思う。文章も、くどくなってきた。視野も狭くなってきた。独断と偏見も多くなってきた。ときに自分で書いた文章が、高校生が書いた作文のように思えるときもある。 たしかに私も、ボケ始めている? では、文章を書かない人たちは、どうすれば、自分の認知症の程度を知ることができるか。 やはり、それには、「テスト」ということになる。ちょうど受験生たちが、ときどき模擬テストを受けるように、50歳を過ぎたら、定期的に、テストを受ける。科目は、算数、国語の2科目でよい。 そういうテストを定期的に受けて、自分の脳みその具合を知る。これはたいへん有意義なことである。たとえば新聞社主催でよい。年に1回程度、そういうテストを新聞に載せてみる。そして年ごとの変化をグラフ化して、自分の脳みその状態を知る。「06年のテストでは、87点だった。しかし07年のテストでは、56点しか取れなかった。だから私の脳みそは、かなり老化しているぞ」と。 簡単にテストをしようと思えば、小学6年生程度(小3程度でもよい)の内容の算数と国語の問題を出してみればよい。そういうものを利用すればよい。 ナルホド! これはたいへんよい思いつきである。どこかのだれかがすれば、一つのビッグ・ビジネスになるかもしれない。その気のある人がいれば、やってみたらどうだろうか。ここで私は、「たとえば新聞社主催でよい……」と書いたが、新聞のような身近な媒体を使って、全国的にするところに意味がある。またそのほうが、より客観的なデータを手に入れることができる。 一度、だれか、考えてみてくれないだろうか。(はやし浩司 ボケテスト 認知症テスト 認知症診断テスト ボケ診断テスト)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(033)【ボケと人格の後退】++++++++++++++++++++++++はやし浩司●「あの人が……?」++++++++++++++++++50代、60代のころは、人一倍、しっかり者に見えた女性。そういう女性が70歳になるころから急速にボケ始める。そういう例は、多い。だからそういう人の話をすると、たいていの人はこう言って、驚く。「エッ、あの人が……!」と。+++++++++++++++++++ 私の義理の姉の母が、つい先日、亡くなった。数年前に聞いたときには、まだらボケということだった。しかし晩年は、かなりボケていた。とくにもの忘れがひどく、「サイフが盗まれた」とか、「嫁が、財産を使い果たした」とか、そんなことを、よく口にしたという。 その義理の姉の母は、私が知るかぎり、若いころは、しっかり者で、口達者。しゃきしゃきとした感じの人だった。もしそのころのその人のことを知ったら、みな、こう思うだろう。「この人だけは、ボケないな」と。 しかしそんな人でも、ボケた。ボケたまま、亡くなった。 で、私が知るかぎり、このタイプの人には、女性が多いということ。少なくとも、私が話に聞くのは、女性ばかり。男性は、いない。男性のばあいは、ボケ始めると、がんこになったり、無口になったり、引きこもったりする。 そこでまず考えてみるのが、女性特有の多弁性。よくしゃべるから頭がよいとか、そうでないから頭が悪いとか、そういうことは関係ない。そのことは、子どもの世界を見ればよくわかる。よくしゃべる子どもイコール、頭のよい子ということにはならない。たとえばAD・HD児でも、女児のばあいは、ふつうでない多弁性となって症状が現れることが多い。 しゃべるといっても、その内容、である。いくつかの特徴がある。(1)ペラペラと一方的に、間断なく、よくしゃべる。(2)考えてからしゃべるというよりは、脳に飛来する情報をそのまま音声にかえているといったふう。(3)言っていることの内容が浅い。こまごまとしたことを、つなげて話す。(4)繰りかえしが多い。同じ内容のことを、繰りかえし、話す。(5)相手の言うことを聞かない。聞いても上(うわ)の空。(6)繊細で、微妙な会話ができない。(7)視線が定まらない。ときに死んだ魚のような目つきになる。 つまりその人の思考力と、多弁性は、関係ないということ。そのことは、その人の話している内容を、よく吟味すれば、わかる。(1)一貫性がない 話している内容が、ポンポンと飛んでいくことがある。野菜の話をしていたかと思うと、「ああ、そうだ」とか何とか言って、今度は、寺の話をし始めたりする。(2)論理性がない 「寒いから困った」「雪が降ったから困った」というようなことは言う。しかしなぜ今年はそうなのかということまでは、考えない。原因として、このところの異常気象があり、さらには、地球の温暖化の問題がある。そういう話題に切りかえようとすると、とたん、「私には、そういう話は、むずかしいから、わからない」と逃げてしまう。(3)情報、知識の欠落 このタイプの人は、ほとんどといってよいほど、本を読まない。雑誌も読まない。テレビを見ても、ただぼんやりと見ているだけ。そのことは、その人の周辺を観察すればわかる。本や雑誌らしきものが、まったくない。新しい情報や知識を吸収しようという意欲そのものを、感じない。(4)生活範囲の縮小 自分の世界だけで、生きているといった感じになる。自己中心的で、ものの考え方が利己的になる。そして年齢とともに、その世界を、どんどんと、小さくしていく。自分の損得に関係することには、極端に敏感になったり、それ以外のことには、極端に鈍感になったりする。(5)一般的なボケ症状 こうした症状と並行して、一般的なボケ症状が現れるようになる。物忘れがひどくなったり、感情が鈍麻したりするなど。被害妄想がひどくなることもある。 以上、気がついたままを書いてみた。が、ボケることによる最大の問題は、(1)人格の後退と、(2)人格の崩壊である。 その人の人格の完成度は、「情動(こころ)の知能指数」、つまりEQによって測定される。その「EQ」について、以前、書いた原稿を添付する。ボケるということは、人格の完成に向った動きと、正反対の動きになると考えると、わかりやすい。+++++++++++++++++++++ EQ(Emotional Intelligence Quotient)は、アメリカのイエール大学心理学部教授。ピーター・サロヴェイ博士と、ニューハンプシャー大学心理学部教授ジョン・メイヤー博士によって理論化された概念で、日本では「情動(こころ)の知能指数」と訳されている(Emotional Education、by JESDA Websiteより転写。)++++++++++++++++++++●【EQ】 ピーター・サロヴェイ(アメリカ・イエール大学心理学部教授)の説く、「EQ(Emotional Intelligence Quotient)」、つまり、「情動の知能指数」では、主に、つぎの3点を重視する。(1)自己管理能力(2)良好な対人関係(3)他者との良好な共感性 ここではP・サロヴェイのEQ論を、少し発展させて考えてみたい。 自己管理能力には、行動面の管理能力、精神面の管理能力、そして感情面の管理能力が含まれる。●行動面の管理能力 行動も、精神によって左右されるというのであれば、行動面の管理能力は、精神面の管理能力ということになる。が、精神面だけの管理能力だけでは、行動面の管理能力は、果たせない。 たとえば、「銀行強盗でもして、大金を手に入れてみたい」と思うことと、実際、それを行動に移すことの間には、大きな距離がある。実際、仲間と組んで、強盗をする段階になっても、その時点で、これまた迷うかもしれない。 精神的な決断イコール、行動というわけではない。たとえば行動面の管理能力が崩壊した例としては、自傷行為がある。突然、高いところから、発作的に飛びおりるなど。その人の生死にかかわる問題でありながら、そのコントロールができなくなってしまう。広く、自殺行為も、それに含まれるかもしれない。 もう少し日常的な例として、寒い夜、ジョッギングに出かけるという場面を考えてみよう。そういうときというのは、「寒いからいやだ」という抵抗感と、「健康のためにはしたほうがよい」という、二つの思いが、心の中で、真正面から対立する。ジョッギングに行くにしても、「いやだ」という思いと戦わねばならない。 さらに反対に、悪の道から、自分を遠ざけるというのも、これに含まれる。タバコをすすめられて、そのままタバコを吸い始める子どもと、そうでない子どもがいる。悪の道に染まりやすい子どもは、それだけ行動の管理能力の弱い子どもとみる。 こうして考えてみると、私たちの行動は、いつも(すべきこと・してはいけないこと)という、行動面の管理能力によって、管理されているのがわかる。それがしっかりとできるかどうかで、その人の人格の完成度を知ることができる。 この点について、フロイトも着目し、行動面の管理能力の高い人を、「超自我の人」、「自我の人」、そうでない人を、「エスの人」と呼んでいる。●精神面の管理能力 私には、いくつかの恐怖症がある。閉所恐怖症、高所恐怖症にはじまって、スピード恐怖症、飛行機恐怖症など。 精神的な欠陥もある。 私のばあい、いくつか問題が重なって起きたりすると、その大小、軽重が、正確に判断できなくなってしまう。それは書庫で、同時に、いくつかのものをさがすときの心理状態に似ている。(私は、子どものころから、さがじものが苦手。かんしゃく発作のある子どもだったかもしれない。) 具体的には、パニック状態になってしまう。 こうした精神作用が、いつも私を取り巻いていて、そのつど、私の精神状態に影響を与える。 そこで大切なことは、いつもそういう自分の精神状態を客観的に把握して、自分自身をコントロールしていくということ。 たとえば乱暴な運転をするタクシーに乗ったとする。私は、スピード恐怖症だから、そういうとき、座席に深く頭を沈め、深呼吸を繰りかえす。スピードがこわいというより、そんなわけで、そういうタクシーに乗ると、神経をすり減らす。ときには、タクシーをおりたとたん、ヘナヘナと地面にすわりこんでしまうこともある。 そういうとき、私は、精神のコントロールのむずかしさを、あらためて、思い知らされる。「わかっているけど、どうにもならない」という状態か。つまりこの点については、私の人格の完成度は、低いということになる。●感情面の管理能力 「つい、カーッとなってしまって……」と言う人は、それだけ感情面の管理能力の低い人ということになる。 この感情面の管理能力で問題になるのは、その管理能力というよりは、その能力がないことにより、良好な人間関係が結べなくなってしまうということ。私の知りあいの中にも、ふだんは、快活で明るいのだが、ちょっとしたことで、激怒して、怒鳴り散らす人がいる。 つきあう側としては、そういう人は、不安でならない。だから結果として、遠ざかる。その人はいつも、私に電話をかけてきて、「遊びにこい」と言う。しかし、私としては、どうしても足が遠のいてしまう。 しかし人間は、まさに感情の動物。そのつど、喜怒哀楽の情を表現しながら、無数のドラマをつくっていく。感情を否定してはいけない。問題は、その感情を、どう管理するかである。 私のばあい、私のワイフと比較しても、そのつど、感情に流されやすい人間である。(ワイフは、感情的には、きわめて完成度の高い女性である。結婚してから30年近くになるが、感情的に混乱状態になって、ワーワーと泣きわめく姿を見たことがない。大声を出して、相手を罵倒したのを、見たことがない。) 一方、私は、いつも、大声を出して、何やら騒いでいる。「つい、カーッとなってしまって……」ということが、よくある。つまり感情の管理能力が、低い。 が、こうした欠陥は、簡単には、なおらない。自分でもなおそうと思ったことはあるが、結局は、だめだった。 で、つぎに私がしたことは、そういう欠陥が私にはあると認めたこと。認めた上で、そのつど、自分の感情と戦うようにしたこと。そういう点では、ものをこうして書くというのは。とてもよいことだと思う。書きながら、自分を冷静に見つめることができる。 また感情的になったときは、その場では、判断するのを、ひかえる。たいていは黙って、その場をやり過ごす。「今のぼくは、本当のぼくではないぞ」と、である。(2)の「良好な対人関係」と、(3)の「他者との良好な共感性」については、また別の機会に考えてみたい。(はやし浩司 管理能力 人格の完成度 サロヴェイ 行動の管理能力 EQ EQ論 人格の完成)+++++++++++++++++++++ついでながら、このEQ論を、子どもの世界にあてはめて考えてみたい。それを診断テストにしたのが、つぎである。****************【子どもの心の発達・診断テスト】****************【子どもの社会適応性・EQ検査】(参考:P・サロヴェイ)●社会適応性 子どもの社会適応性は、つぎの5つをみて、判断する(サロベイほか)。(1)共感性Q:友だちに、何か、手伝いを頼まれました。そのとき、あなたの子どもは……。○いつも喜んでするようだ。○ときとばあいによるようだ。○いやがってしないことが多い。(2)自己認知力Q:親どうしが会話を始めました。大切な話をしています。そのとき、あなたの子どもは……○雰囲気を察して、静かに待っている。(4点)○しばらくすると、いつものように騒ぎだす。(2点)○聞き分けガなく、「帰ろう」とか言って、親を困らせる。(0点)(3)自己統制力Q;冷蔵庫にあなたの子どものほしがりそうな食べ物があります。そのとき、あなたの子どもは……。○親が「いい」と言うまで、食べない。安心していることができる。(4点)○ときどき、親の目を盗んで、食べてしまうことがある。(2点)○まったくアテにならない。親がいないと、好き勝手なことをする。(0点)(4)粘り強さQ:子どもが自ら進んで、何かを作り始めました。そのとき、あなたの子どもは……。○最後まで、何だかんだと言いながらも、仕あげる。(4点)○だいたいは、仕あげるが、途中で投げだすこともある。(2点)○たいていいつも、途中で投げだす。あきっぽいところがある。(0点)(5)楽観性Q:あなたの子どもが、何かのことで、大きな失敗をしました。そのとき、あなたの子どもは……。○割と早く、ケロッとして、忘れてしまうようだ。クヨクヨしない。(4点)○ときどき思い悩むことはあるようだが、つぎの行動に移ることができる。(2点)○いつまでもそれを苦にして、前に進めないときが多い。(0点) (6)柔軟性Q:あなたの子どもの日常生活を見たとき、あなたの子どもは……○友だちも多く、多芸多才。いつも変わったことを楽しんでいる。(4点)○友だちは少ないほう。趣味も、限られている。(2点)○何かにこだわることがある。がんこ。融通がきかない。(0点)***************************( )友だちのための仕事や労役を、好んで引き受ける(共感性)。( )自分の立場を、いつもよくわきまえている(自己認知力)。( )小遣いを貯金する。ほしいものに対して、がまん強い(自己統制力)。( )がんばって、ものごとを仕上げることがよくある(粘り強さ)。( )まちがえても、あまり気にしない。平気といった感じ(楽観性)。( )友人が多い。誕生日パーティによく招待される(社会適応性)。( )趣味が豊富で、何でもござれという感じ(柔軟性)。 これら6つの要素が、ほどよくそなわっていれば、その子どもは、人間的に、完成度の高い子どもとみる(「EQ論」)。(以上のテストは、いくつかの小中学校の協力を得て、表にしてあります。集計結果などは、HPのほうに収録。興味のある方は、そちらを見てほしい。)***************************順に考えてみよう。(1)共感性 人格の完成度は、内面化、つまり精神の完成度をもってもる。その一つのバロメーターが、「共感性」ということになる。 つまりは、どの程度、相手の立場で、相手の心の状態になって、その相手の苦しみ、悲しみ、悩みを、共感できるかどうかということ。 その反対側に位置するのが、自己中心性である。 乳幼児期は、子どもは、総じて自己中心的なものの考え方をする。しかし成長とともに、その自己中心性から脱却する。「利己から利他への転換」と私は呼んでいる。 が、中には、その自己中心性から、脱却できないまま、おとなになる子どももいる。さらにこの自己中心性が、おとなになるにつれて、周囲の社会観と融合して、悪玉親意識、権威主義、世間体意識へと、変質することもある。(2)自己認知力 ここでいう「自己認知能力」は、「私はどんな人間なのか」「何をすべき人間なのか」「私は何をしたいのか」ということを、客観的に認知する能力をいう。 この自己認知能力が、弱い子どもは、おとなから見ると、いわゆる「何を考えているかわからない子ども」といった、印象を与えるようになる。どこかぐずぐずしていて、はっきりしない。優柔不断。反対に、独善、独断、排他性、偏見などを、もつこともある。自分のしていること、言っていることを客観的に認知することができないため、子どもは、猪突猛進型の生き方を示すことが多い。わがままで、横柄になることも、珍しくない。(3)自己統制力 すべきことと、してはいけないことを、冷静に判断し、その判断に従って行動する。子どものばあい、自己のコントロール力をみれば、それがわかる。 たとえば自己統制力のある子どもは、お年玉を手にしても、それを貯金したり、さらにためて、もっと高価なものを買い求めようとしたりする。 が、この自己統制力のない子どもは、手にしたお金を、その場で、その場の楽しみだけのために使ってしまったりする。あるいは親が、「食べてはだめ」と言っているにもかかわらず、お菓子をみな、食べてしまうなど。 感情のコントロールも、この自己統制力に含まれる。平気で相手をキズつける言葉を口にしたり、感情のおもむくまま、好き勝手なことをするなど。もしそうであれば、自己統制力の弱い子どもとみる。 ふつう自己統制力は、(1)行動面の統制力、(2)精神面の統制力、(3)感情面の統制力に分けて考える。(4)粘り強さ 短気というのは、それ自体が、人格的な欠陥と考えてよい。このことは、子どもの世界を見ていると、よくわかる。見た目の能力に、まどわされてはいけない。 能力的に優秀な子どもでも、短気な子どもはいくらでもいる一方、能力的にかなり問題のある子どもでも、短気な子どもは多い。 集中力がつづかないというよりは、精神的な緊張感が持続できない。そのため、短気になる。中には、単純作業を反復的にさせたりすると、突然、狂乱状態になって、泣き叫ぶ子どももいる。A障害という障害をもった子どもに、ときどき見られる症状である。 この粘り強さこそが、その子どもの、忍耐力ということになる。(3)楽観性 まちがいをすなおに認める。失敗をすなおに認める。あとはそれをすぐ忘れて、前向きに、ものを考えていく。 それができる子どもには、何でもないことだが、心にゆがみのある子どもは、おかしなところで、それにこだわったり、ひがんだり、いじけたりする。クヨクヨと気にしたり、悩んだりすることもある。 簡単な例としては、何かのことでまちがえたようなときを、それを見れば、わかる。 ハハハと笑ってすます子どもと、深刻に思い悩んでしまう子どもがいる。その場の雰囲気にもよるが、ふと見せる(こだわり)を観察して、それを判断する。 たとえば私のワイフなどは、ほとんど、ものごとには、こだわらない性質である。楽観的と言えば、楽観的。超・楽観的。 先日も、「お前、がんになったら、どうする?」と聞くと、「なおせばいいじゃなア~い」と。そこで「がんは、こわい病気だよ」と言うと、「今じゃ、めったに死なないわよ」と。さらに、「なおらなかったら?」と聞くと、「そのときは、そのときよ。ジタバタしても、しかたないでしょう」と。 冗談を言っているのかと思うときもあるが、ワイフは、本気。つまり、そういうふうに、考える人もいる。(4)柔軟性 子どもの世界でも、(がんこ)な面を見せたら、警戒する。 この(がんこ)は、(意地)、さらに(わがまま)とは、区別して考える。 一般論として、(がんこ)は、子どもの心の発達には、好ましいことではない。かたくなになる、かたまる、がんこになる。こうした行動を、固執行動という。広く、情緒に何らかの問題がある子どもは、何らかの固執行動を見せることが多い。 朝、幼稚園の先生が、自宅まで迎えにくるのだが、3年間、ただの一度もあいさつをしなかった子どもがいた。 いつも青いズボンでないと、幼稚園へ行かなかった子どもがいた。その子どもは、幼稚園でも、決まった席でないと、絶対にすわろうとしなかった。 何かの問題を解いて、先生が、「やりなおしてみよう」と声をかけただけで、かたまってしまう子どもがいた。 先生が、「今日はいい天気だね」と声をかけたとき、「雲があるから、いい天気ではない」と、最後までがんばった子どもがいた。 症状は千差万別だが、子どもの柔軟性は、柔軟でない子どもと比較して知ることができる。柔軟な子どもは、ごく自然な形で、集団の中で、行動できる。++++++++++++++++++++●では、どうすればよいか? 脳ミソが機質的に変化してボケるというのは、これはどうしようもない。しかし機能的に変化してボケるという部分については、私たちの努力で、何とかなるのではないか。 脳ミソの健康論は、何度も書くが、そういう点では、肉体の健康論と、よく似ている。日々の絶え間ない運動が、肉体の健康を維持するように、日々の絶え間ない思考が、脳ミソの健康を維持する。つまり、考えるということ。日々に新しいものに興味をもち、それにチャレンジしていくということ。 補う程度では足りない。私の実感としては、年を取ればとるほど、脳ミソの底に、大きな穴があく。その穴から、容赦なく、知識や経験、技術や知恵、さらには人格までもが、下に落ちていく。だから、下に落ちていく以上のものを、私たちは日々の生活の中で、補給しなければならない。 若いころは、さほど運動をしなくても、ある程度の健康を維持できる。しかし年を取ればとるほど、そういうわけにはいかない。運動のもつ重要さが、ます。しかもその運動は、きびしいものとなる。少しサボれば、その時点から、健康は、下り坂に向う。 同じように、脳ミソの健康を維持するためには、若いとき以上に、脳ミソを鍛えなければならない。方法は、簡単。 考える。考えて、考えて、考え抜く。1つのヒントとして、フランスの哲学者のモンテーニュ(1533~92)は、こう書き残している。「『考える』という言葉を聞くが、私は何か書いているときのほか、考えたことはない」(随想録)と。これは私にとっては、座右の銘になっている。参考までに!(はやし浩司 思考 ボケ 認知症 人格の後退 人格論 EQ論 サロベイ)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(20)
親意識が子育てをゆがめるとき+++++++++++++++いまだに、「私は親だ」とがんばっている人がいる。そういうのを親意識という。しかし親意識ほど、おかしな意識はない。+++++++++++++++●「私は親だ」というのが親意識 「私は親だ」というのが親意識。これが強ければ強いほど、子どもも疲れるが、親も疲れる。それだけではない。親意識の背景にある上下意識、これが親子関係をゆがめる。上下意識のある関係、つまり命令と服従、保護と依存のある関係から、良好な人間関係は生まれない。ある母親は、子ども(小一)に、「バカ!」と言われるたびに、「親に向かって何てことを言うの!」と、本気で怒っていた。そこで私に相談があった。「先生は、親子は平等だと言うが、こういうときはどうしたらいいのか」と。●互いに高い次元で認めあって平等 平等というのは、相手の人格を認め、それを尊重することをいう。高い次元で認めあうことを平等という。たとえ相手が幼児でも、そうする。こんなシーンがあった。あるアメリカ人の女優の家にカメラマンが押し寄せたときのこと。たまたまその女優が、小さな女の子(五歳ぐらい)を連れて、玄関を出てきた。が、その女の子がフラッシュに驚いて、母親のうしろに隠れた。そのときのことである。母親は、女の子に懸命に笑顔で話しかけながら、そのままあとずさりして、家の中へ消えてしまった。私はそのシーンを見ながら、「こういうとき日本人ならどうするだろうか」と考えた。あるいはあなたなら、どうするだろうか。●子どもの気持ちを確かめる 子どもは確かに未熟で未経験だ。しかしそれを除けば、一人の人間である。そういう視点に立って子どもを見ることを、「平等」という。たとえば子どもに何かのおけいこをさせるときでも、「してみたい?」とか、「あなたはどう思う?」とか聞いてからにする。やめるときもそうだ。あるいは子どもが学校で悪い成績をとってきて、落ち込んでいたとする。そういうときでも、子どもの気持ちになって、子どもと同じ立場でそれを悩んであげる。それを平等という。それがわからなければ夫と妻の立場で考えてみればよい。もしあなたという妻が、夫から、「お前の料理はまずい。明日から料理教室へ行け」と言われたら、あなたはそれに従うだろうか。そのときあなたが、夫に何かを反論したとする。そのとき夫が、「夫に向かって何だ、その態度は!」と言ったら、あなたはそれに納得するだろうか。相手の視点に立って見るということは、そういうことをいう。●親意識の強い親 冒頭の話だが、子どもに「バカ」と言われて気にする親もいれば、気にしない親もいる。あるいは子どもにバカと思わせつつ、それを利用して、子どもを伸ばす親もいる。子どもの側からみてもそうだ。「バカな親」と思いつつ、親を尊敬している子どももいれば、そうでない子どももいる。私の近所にも、たいへん金持ちの人がいる。本人は、自分では尊敬に値する人間と思っているらしいが、誰もそんなふうには思っていない。人を尊敬するとかしないとかいうことは、もっと別のところで決まる。要するに子どもに「バカ」と言われても、気にしないこと。かく言う私も、よく生徒にバカと言われる。そういうときは、こう言い返すようにしている。「私はバカではない。大バカだ。まちがえるな」と。先日も私のことを「ジジイ」と言う子どもがいた。そこで私はその子どもにこう言ってやった。「もっと悪い言葉を教えてあげようか」と。するとその子どもは、「教えて、教えて」と。私はおもむろにその子どもに顔をむけると、こう言った。「いいか、これはとても悪い言葉だ。お父さんや先生に言ってはダメだよ。わかったね。……では、教えてあげよう。ビ・ダ・ン・シ(美男子)」と。それからというもの、その子どもは私を見るたびに、私に向かって、「ビダンシ!」「ビダンシ!」と言うようになった。●子どもを抑え込んではいけな 子どもの口が悪いのは、当たり前。奨励せよというわけではないが、それが言えないほどまでに、子どもを押さえつけてはいけない。あるいはユーモアで切り返す。このユーモアが、子どもの心を広くする。要するに、相手は子ども。本気で相手にしてはいけない。よく「友だち親子」の是非が話題になる。「友だち親子はいいのか、悪いのか」と。しかし子どもが友だちになりえるのは、子どもが中学生や高校生になってからだ。それまでは友だちにすら、なりえない。もちろんそれまででも友だち的なつきあいができれば、それはすばらしい。友だち親子、おおいに結構。どこが悪い? 親の権威だの威厳だのと言っている間は、日本人は、封建時代の亡霊と決別することはできない。 そうそうあのアメリカ人の女優のケースだが、日本人なら多分、こう言って子どもを前に押し出すに違いない。「何をしているの。お母さんが、恥ずかしいでしょう。ちゃんとしなさい!」と。こうした押しつけが、親子の間にミゾを作る。そしてそのミゾが、やがて親子断絶へとつながる。 親意識などなくても、子育てで困ることは何もない。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●夫婦論++++++++++++++++夫婦って、何だろうと、このところ、ときどき、考える。++++++++++++++++ かつては、母のような女性を、理想の女性と考えたこともある。姉のような女性を、理想の女性と考えたこともある。あるいはそのときどきに、叔母や伯母、さらには、映画やテレビに出てくる女性を、理想の女性と考えたこともある。 しかし私は、どこまでいっても、私であるように、私のワイフは、どこまでいっても、私のワイフ。当初は、恋愛で始まる結婚だが、長くいっしょに生活をしていると、私が私のワイフになり、私のワイフが私になる。 つまり結婚にまつわる苦労や思い出が、私をつくり、ワイフをつくる。そしてやがて、こう思う。「これが私だ」「これが私のワイフだ」と。 私のワイフに不満がないと言えば、ウソになる。しかしこのことは、私のワイフについても、同じで、ワイフが、いつも何かしらの不満を私にいだいていることは、私も知っている。若いころは、いつもこう言っていた。「あなたの身長が、あと10センチ高ければよかったのに……」と。 しかしやはり、私は私だった。私は決して理想の「男」ではない。自分でもそれがよくわかっている。性格はチャランポランで、情緒はいつも不安定。無責任で、いいかげん。ここに書いたように背も低いし、容姿は、最悪。そんな「男」が、理想の女性を求めても、しかたがない。 私が今以上に、よい「男」に変われないなら、ワイフに今以上の理想の「女」を求めることも、おかしい。たがいに、妥協しあいながら、つまり欠点を補いあいながら、生きていくしかない。 が、悪いことばかりではない。ともにしてきた苦労や思い出が、年月を経てくると、ジワジワと、いぶし銀のように光り始める。「光る」というほど、おおげさなものではないかもしれないが、相対的に、若いころ「理想の女性」と思っていた人たちが、順に、記憶の中から消えていく。そして気がついてみると、そこに残ったのが、ワイフだけということになる。 今では、よく、「母のような女性と結婚しなくてよかった」とか、「姉のような女性と結婚しなくてよかった」とか、思うこともある。叔母や伯母にいたっては、なおさらそうで、「どうしてああいう女性を、一時的ではあるにせよ、理想の女性と思ってしまったのだろう?」と思うこともある。 唯一の例外と言えば、映画『サウンド・オブ・ミュージック』の中に出てきた、ジュリー・アンドリュースか? ジュリー・アンドリュースが演じた、マリア像は、今でも、心の片隅に、「理想の女性」として、残っている。 それはともかくも、「男」も一巡すると、「まあ、私もこんなものだ」という、あきらめの境地に達する。そして同時に、「まあ、私の結婚生活もこんなものだ」という、同じようなあきらめの境地に達する。 その(思い)は、ワイフにしてみても、同じではないか。もう少し若いころには、私は、よくワイフにこう言った。「お前も、ぼくのような男と結婚したために、苦労ばかりしている。もっとほかにいい男がいただろうに、ごめんね」と。 まあ、この先は、細々と燃える残り火だけを大切に、生きていくだけ。私が私でしかなかったように、私たち夫婦も、私たち夫婦でしかなかった。洋服にたとえるなら、どうせ私に合う洋服は、一着しかない。だったら、それを大切に着るしかない。それが夫婦というものではないか……と、このところ、強く、思うようになった。2007年10月19日(金)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※●謎の中国訪問++++++++++++++++++K国の金xx(拉致事件に抗議の念をこめて、あえて金xxとする)が、現在、中国を訪問しているという(1月14日現在)。しかしその足どりは、まったく不明。謎。いったい、金xxは、どこにいるのか?++++++++++++++++++ 詳しい行動内容は、報道機関の報道に任せるとして、おおまかに言えば、こういうことだ。 当初、K国から、金xxを乗せたと思われる、特別列車が、K国から中国へ向った。しかしその列車は、中国へは向わず、途中で、方向をロシアに変えた。 その間に、金xxと思われる人物は、飛行機で北京に。そしてそこで中国の要人と会談したあと(?)、広州へ。香港発の共同通信は、つぎのように伝える(13日)。【香港13日共同】中国南部・広州の最高級ホテルに13日午前、リムジンを含む50台前後の車列が到着した。国家元首級の代表団とみられ、中国を訪問しているK国の金xxの代表団の可能性もあるが、金xxの姿は目撃されていない。 周辺は早朝から厳重な警戒態勢が敷かれ、ホテルは入り口に金属探知機を設置、15日まで一般客の予約受け付けを中断している。同ホテルの従業員の1人は「金xx一行をお迎えしている」と述べた。車列は約1時間半後に再びホテルを出発、視察に向かったとみられる。 外交筋は、金xxが今後の経済改革に中国の経験を反映させるため、中国の改革・開放政策を象徴する広州や深センなどの経済開発特区を視察することも予想されるとしている。 ここで注目すべき点は、「中国を訪問しているK国の金xx総書記の代表団の可能性もあるが、金総書記の姿は目撃されていない」というところ。 一方、金xxの目撃も、各地で報告されているが、「その可能性がある」(時事通信)という程度。本当に、金xxは、広州にいるのか。それともいないのか。ふつうの常識からすれば、「視察」という以上、リムジンから外に出て、直接その場の雰囲気を肌で触れるため、そこに立たなければならない。当然、現地の人たちや、マスコミの目に触れることになるが、それはしかたのないこと。 外からは中が見えないようなリムジンに乗って、金xxは、いったい、何を視察しようとしているのか? ……と考える前に、今回の電撃的な中国訪問には、いくつかの謎がある。それが「電撃的」であった点もさることながら、どうして今なのか? どうしてこうまで小細工に小細工を重ねてまで、遠く、広州の経済開発特区を視察しなければならないのか。 隠密行動といいながら、その一方で、わざと目立つように、リムジンほか、大型乗用車を、50台もつらねている? 私は、今回の中国訪問には、もっと大きな秘密が隠されていると思う。韓国の朝鮮N報ですら、「非正常な訪問」と位置づけている。その謎を解くヒントとなっているのが、実は、金xxが、北京到着と同時に、健康診断を受けているということ。韓国の中央N報は、つぎのように伝えている。 「 別の関係者は『金委員長は北京到着直後、彼を担当する医療陣から健康診断を受けたということだ』とし、『深刻な状況ではないが、健康状態があまりよくないらしい』と述べた。また北京の宿所は以前、訪中際に宿泊した外国貴賓用釣魚台ではなく、市郊外の別荘であるということだ」(1月12日)と。 こうまで秘密主義にかたまった隠密行動の中で、こうした(事実?)がもれてきたこと自体、不思議なことである。金xxは、健康診断を受けたというが、これこそ、K国が、もっとも秘密にしなければならないことである。 私の推測によれば、(憶測に近いが……)、事実はこうではないか。 金xxは、北京に到着したあと、ずっと、北京に残って、何らかの医療的治療を受けている。中国南部への視察は、金xxのそっくりさん、つまり替え玉を使った、いわばダミー視察。つまりマスコミや世界の目を、北京からそらすための、カモフラージュ。 金xxの健康状態がよくないことは、以前から、話題になっている。持病の糖尿病のほか、いろいろあるらしい。ときに浴びるように酒を飲んでいるといううわさもある。こうした健康状態は、かいま見る写真などによっても、わかる。 ブヨブヨに太った、しまりのない体。化粧をしても、その化粧では、ごまかせないほど、顔色はよくない。そういう人を、健康な人とは、だれも思わない。 私は、私の推理が正しいとするなら、今回の中国訪問は、それだけ緊急を要したから、と考える。たとえば心筋梗塞や脳梗塞のような、血栓症による何らかの病変を起こした、とか。だいたいにおいて、「深刻な状況ではないが、健康状態があまりよくないらしい」というような金xxが、遠く広州まで、出かけていくだろうか。 「国の将来を考えて、命がけで視察」と言えば、聞こえはよいが、金xxがそんな人物でないことは、客観的なほかの事実でも、わかるはず。 K国では、スーパーマン以上のスーパーマンとして、あがめ奉(たつま)られている金xxだが、それは映画の世界での話。やがて事実は明らかにされるだろうが、私は、今回の中国訪問の目的は、十中、八、九、金xxの病気治療のためとみている。 さて、事実は、どこにあるのか? 興味津々(しんしん)。2007/10/19Hiroshi Hayashi+++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(032)●権威主義+++++++++++++++++はびこる権威主義。その権威主義について原稿を書いたら、先日、BLOGの書きこみに、こんなのがあった。「日本には、権威主義は、もうないと思いますが。はやし先生は、日本のどこをどのように見て、権威主義的だと言うのでしょうか」と。本当にそうだろうか?そう考えてよいのだろうか?++++++++++++++++++ 権威主義というものが、どういうものか? それを示す、こんな記事がある。まずその記事をそのまま、紹介する。あなたはこの記事を読んで、どこにどのように、その権威主義を感ずるであろうか。 その前に、その予備知識として、隣の韓国でこんな事件があったことを思いだしてほしい。何でも、ソウル大学に、とんでもない教授がいて、インチキ論文で、世界中をだましたという事件である。日本にも、藤木S一という、これまたどえらいインチキ考古学者がいたが、その藤木S一の比ではない。 だました相手は、世界。目標は、ノーベル賞。しかも、国家の英雄として! それについて、T報(韓国の新聞社)は、つぎのように報道する。 「問題のU教授は、大学を罷免されることになるだろう。詐欺罪を適応されるかもしれない。目下、政府内部でその処分を検討中。将来は、獣医くらいならできるだろうが、研究者としての地位は、絶望的である」(06年1月)と。 そのU教授は、韓国でも最高の科学者として認定され、毎年、3億円以上もの研究費が国から支給されていたという。 で、この記事のどこがどのように、権威主義的か、みなさんには、それがわかるだろうか。もう一度、この記事をじっくりと読んでみてほしい。そこには、こう書いてある。 「獣医くらいならできるかもしれないが……」と。 この文章を読んだら、獣医をしている人は、どう感ずるだろうか。獣医といっても、相手が動物というだけで、その責任の重大さという点では、人間を相手にする医師と、立場は何もちがわない。 しかしT報は、「獣医くらいなら」と言いきっている。実は、ここに、権威主義が隠されている。 大学の研究者は、トップ。医師は、そのつぎ。その世界で、最下位に位置するのは、獣医、と。しかも、だ。こういう記事を、そこらの一介の新聞記者程度の人間が書いているところが恐ろしい。 何というごう慢さ! つまりそのごう慢さの背景にあるのが、私が言う「権威主義」である。つまりその記者は、無意識のうちにも、人間の価値を、権威主義によって、格づけしている。そしてその結果として、「獣医くらいならできるかもしれないが……」と。 そう、この記事を読んだら、獣医をしている人は、怒るだろう。怒って、当然。獣医をしている人は、そのインチキ学者と同レベル。あるいはそれ以下(?)ということになる。人間に上下はない。職業に上下はない。しかし韓国では、いまだにそういった上下意識が、ハバをきかせている。もう3年ほど前になるだろうか、 私も、ある研究者から、こんなことを言われたことがある。この話は、当時、私のマガジンでも取りあげた。覚えている人も多いと思う。その研究者は、こう言ってきた。 「田舎のおばちゃん相手に、講演をして、何になるのか。あなたの書いているようなことは、おばちゃんたちを感動させることはできても、学問的には、一片の価値もない」と。 ある都市の国立大学で、ある学部の学部長をしている人からの意見だった。何度もメールで、議論を戦わせたあとでの意見だったので、私は、「世の中、そういうものだろうな」と、そのときは、そう納得した。 しかしこういう権威主義は、今でも、日本中にはびこっている。 先日もあるオーディションを紹介する番組を見ていたら、こういうシーンが出てきた。何でも俳優の世界にも、中央(東京や大阪)で活躍する、メジャー俳優と、地方から外に出られないマイナー俳優というのがいるらしい。 で、その俳優志望の若い女性は、俳優になるためのオーディションを受けた。結果は、最終審査で不合格。1人の審査員(テレビによく顔を出す俳優)が、その若い女性にこう言った。「中央で、(メジャー俳優として)活躍するのは、無理でしょうね」と。 まるで「中央で活躍できないような俳優は、俳優ではない」というような言い方だった。しかしそれにしても、いやな言い方だった。 総じて言えば、「権威主義」は、「格づけ(=ランク分け)」によって、成りたっている。もっと言えば、上下意識。そしてその「上下」は、権力や、財力、知名度、家柄、団体での地位などによって決まる。大切なのは、「能力」なのだろうが、その能力まで、格づけによって決められてしまう。 数年前のことだが、ある野球チームの監督の妻と、ある演劇劇団の女座長をしている女性とが、連日、マスコミの世界で、大激論を繰りかえしたことがある。発端は、監督の妻の、学歴詐称事件だったように記憶している。 そのときも、その監督の妻は、女座長をしている女性を批判して、こう言っていた。「私はメジャーリーグの人間だが、あの人は、マイナーリーグの人間よ」と。このときも、まるで「マイナーリーグの人間には、価値はない」というような言い方だった。 一般論として、権威主義者というのは、独特の雰囲気をもっている。まず相手を、肩書きや地位で判断する。そうした判断を、瞬時のうちにやってのける。そして自分より(目上の者?)には、必要以上にペコペコし、(目下の者?)には、尊大ぶった言い方や態度をする。 そして平気で、こう言い切る。「男が上で、女が下」「夫が上で、妻が下」「親が上で、子が下」と。つまりこうした意識が集合されて、「獣医くらいならできるかもしれないが……」という発想につながる。 その象徴的人物が、あの水戸黄門である。それについて書いた記事(中日新聞掲載済み)を、紹介する。++++++++++++++++++●肩書き社会、日本 この日本、地位や肩書きが、モノを言う。いや、こう書くからといって、ひがんでいるのではない。それがこの日本では、常識。 メルボルン大学にいたころのこと。日本の総理府から派遣された使節団が、大学へやってきた。総勢30人ほどの団体だったが、みな、おそろいのスーツを着て、胸にはマッチ箱大の国旗を縫い込んでいた。が、会うひとごとに、「私たちは内閣総理大臣に派遣された使節団だ」と、やたらとそればかりを強調していた。つまりそうことを口にすれば、歓迎されると思っていたらしい。 が、オーストラリアでは、こうした権威主義は通用しない。まったく通用しない。よい例があのテレビドラマの『水戸黄門』である。今でもあの番組は、平均して20~23%もの視聴率を稼いでいるという。が、その視聴率の高さこそが、日本の権威主義のあらわれと考えてよい。つまりその使節団のしたことは、まさに水戸黄門そのもの。葵の紋章を見せつけながら、「控えおろう」と叫んだのと同じ。あるいはどこがどう違うのか。が、オーストラリア人にはそれが理解できない。ある日、ひとりの友人がこう聞いた。「ヒロシ、もし水戸黄門が悪いことをしたら、どうするのか。それでも日本人は頭をさげるのか」と。 この権威主義は、とくにマスコミの世界に強い。相手の地位や肩書きに応じて、まるで別人のように電話のかけ方を変える人は多い。私がある雑誌社で、仕事を手伝っていたときのこと。相手が大学の教授であったりすると、「ハイハイ、かしこまりました。おおせのとおりいたします」と言ったあと、私のような地位も肩書きもないような人間には、「君イ~ネ~、そうは言ってもネ~」と。しかもそういうことを、若い、それこそ地位や肩書きとは無縁の社員が、無意識のうちにそうしているから、おかしい。つまりその「無意識」なところが、日本人の特性そのものということになる。 こうした権威主義は、恐らく日本だけにしか住んだことがない人にはわからないだろう。説明しても、理解できないだろう。そして無意識のうちにも、「家庭」という場で、その権威主義を振りまわす。「親に向かって何だ!」と。子どももその権威主義に納得すればよし。しかし納得しないとき、それは親子の間に大きなキレツを入れることになる。親が権威主義的であればあるほど、子どもは親の前で仮面をかぶる。つまりその仮面をかぶった分だけ、子どもの子は親から離れる。ウソだと思うなら、あなたの周囲を見渡してみてほしい。あなたの叔父や叔母の中には、権威主義の人もいるだろう。そうでない人もいるだろう。しかし親が権威主義的であればあるほど、その親子関係はぎくしゃくしているはずである。ところで日本からの使節団は、オーストラリアでは嫌われていた。英語で話しかけられても、ただニヤニヤ笑っているだけ。そのくせ態度だけは大きく、みな、例外なくいばっていた。このことは「世にも不思議な留学記」※に書いた。それから35年あまり。日本も変わったが、基本的には、今もつづいている。++++++++++++++++内容はダブりますが、同じような内容で書いた原稿をいくつか、ここに掲載しておきます。++++++++++++++++●価値観の衝突を防ぐにはどうするか 価値観の衝突は、えてして宗教戦争のような様相をおびる。互いに「自分が正しい」と信じているから、その返す刀で、「あなたはまちがっている」とぶつける。互いに容赦しない。親子でもこのタイプの衝突は、行きつくところまで行きつく。たとえば「権威主義」を考えてみる。 日本人は本来、権威主義的なものの考え方を好む。よい例が、あの水戸黄門である。三つ葉葵の紋章を見せ、「控えおろう!」と一喝すれば、まわりの者が皆頭をさげる。今でもあのドラマは視聴率を、20%以上も稼いでいるというから驚きである。つまり日本人には、あれほど痛快な番組はない? しかしこうした権威主義は、欧米では通用しない。あるときオーストラリアの友人が私にこう聞いた。「ヒロシ、もし水戸黄門が悪いことをしたら、どうするのか。そのときでも頭をさげるのか」と。同じような例は、ときとして家庭の中でも起きる。 親をだます子どもがいる。しかし世の中には、子どもをだます親もいる。Kさん(70歳)は、息子が海外へ出張している間に、息子の貯金通帳からお金を引き出し、自分の借金の返済にあててしまった。息子がKさんを責めると、Kさんはこう居なおった。「親が先祖を守るため息子のお金を使って何が悪い」と。問題はこのあとだ。周囲の人の意見は、まっ二つに分かれた。「たとえ親でも悪いことをしたら、あやまるべきだ」という意見。もう一つは、「親はどんなことがあっても、子どもに頭をさげるべきではない」という意見。 あなたがどちらの意見であるにせよ、こういうケースでは、その中間の考え方というのは、ほとんどない。そして親も子も同じように考えるときには、衝突は起きない。しかし互いの価値観が対立したとき、それはそのまま衝突となる。 もっともこうしたケースは特殊なもので、そう日常的に起こるものではない。しかしこれだけは言える。親が権威主義的であればあるほど、「上」のものにとっては、居心地のよい世界かもしれないが、「下」のものにとっては、そうではないということ。ここにも書いたように、下のものが上のものに同調すれば、それはそれでうまくいくかもしれないが、たいていは下のものは、上のものの前で仮面をかぶるようになる。そして仮面をかぶった分だけ、上のものは下のものの心がつかめなくなる。つまりその段階で、互いの間にキレツが入る。そしてそのキレツが長い時間をかけて、断絶となる。 結論から言えば、親の権威主義など、百害あって一利なし。少なくともこれからの考え方ではない。ちなみに、小学生六年生10人に私がこう聞いてみた。「君たちのお父さんやお母さんが、何かまちがったことをしたとき、お父さんやお母さんは、君たちに謝るべきか。それとも、親なのだから、謝るべきではないのか」と。すると、全員がすかさず大きな声でこう答えた。「謝るべきだヨ~」と。これがこの日本の流れであり、もうその流れを変えることはできない。+++++++++++++++++++●権威主義は断絶のはじまり 「私は親だ」というのが、親意識。この親意識が強いと、子どもはどうしても親の前でいい子ぶるようになる。もう少しわかりやすく言うと、仮面をかぶるようになる。その仮面をかぶった分だけ、子どもの心は親から離れる。 親子の間に亀裂を入れるものに、三つある。リズムの乱れと相互不信、それに価値観のズレ。このうち価値観のズレの一つが、ここでいう親の権威主義である。もともと権威というのは、問答無用式に相手を従わせるための道具と考えてよい。「男が上で女が下」「夫が上で妻が下」「親が上で子が下」と。もっとも子どもも同じように権威主義的なものの考え方をするようになれば、それはそれで親子関係はうまくいくかもしれない。が、これからは権威がものを言う世界ではない。またそういう時代であってはならない。 そこであなた(あなたの夫)が権威主義者かどうか見分ける簡単な方法がある。それには電話のかけ方をみればよい。権威主義的なものの考え方を日常的にしている人は、無意識のうちにも人間の上下関係を判断するため、相手によって電話のかけ方がまるで違う。地位や肩書きのある人には必要以上にペコペコし、自分より「下」と思われる人には、別人のように尊大ぶったりいばってみせたりする。このタイプの人は、先輩、後輩意識が強く、またプライドも強い。そのためそれを無視したり、それに反したことをする人を、無礼だとか、失敬だとか言って非難する。もしあなたがそうなら、一度あなたの価値観を、それが本当に正しいものかどうかを疑ってみたらよい。それはあなたのためというより、あなたの子どものためと言ったほうがよいかもしれない。 日本人は権威主義的なものの考え方を好む民族である。その典型的な例が、あの「水戸黄門」である。側近のものが三つ葉葵の紋章を見せ、「控えおろう!」と一喝すると、周囲のものが皆頭をさげる。ああいうシーン見ると、たいていの日本人は「痛快!」と思う。しかしそれが痛快と思う人ほど、あぶない。このタイプの人は心のどこかでそういう権威にあこがれを抱いている人とみてよい。ご注意!++++++++++++++++++++【権威主義緒は、親子断絶のはじまり】(「ファミリス」投稿原稿)●親意識の背景に権威主義 「私は親だ」という意識を「親意識」という。たとえば子どもに対して、「産んでやった」「育ててやった」と考える人は多い。さらに子どもをモノのように考えている人さえいる。ある女性(60歳)は私に会うとこう言った。「親なんてさみしいものですね。息子は横浜の嫁に取られてしまいましたよ」と。息子が結婚して横浜に住んでいることを、その女性は「取られた」というのだ。日本人はこの親意識が、欧米の人とくらべても、ダントツに強い。長く続いた封建制度が、こうした日本人独特の親意識を育てたとも考えられる。●上下意識と権威主義その親意識の背景にあるのが、上下意識。「親が上で、子が下」と。そしてその上下意識を支えるのが権威主義。理由などない。「偉い人は偉い」と言うときの「偉い」が、それ。日本人はいつしか、身分や肩書きで人の価値を判断するようになった。ふつう権威主義的なものの考え方をする人は、自分のまわりでいつも、人間の上下関係を意識する。「男が上、女が下」「夫が上、妻が下」と。たった一年でも先輩は先輩、後輩は後輩と考える。そして自分より立場が上の人に向かっては、必要以上にペコペコし、そうでない人にはいばってみせる。私のいとこ(男性)にもそういう人がいる。相手によって接し方が、別人のように変化するからおもしろい。●親意識は親子を断絶させる この親意識が強ければ強いほど、子どもにとっては居心地の悪い世界になる。が、それだけではすまない。子どもは親の前では仮面をかぶるようになり、そのかぶった分だけ、心を隠す。親は親で子どもの心をつかめなくなる。そしてそれが互いの間に大きなキレツを入れる……。昔は「控えおろう!」と、三つ葉葵の紋章か何かを見せれば、人はひれ伏したが、今はそういう時代ではない。親が親風を吹かせば吹かすほど、子どもの心は親から離れる。ものの考え方が県主義的な人は、あなたというより、あなたが育った環境を思い浮かべてみてほしい。あなた自身もその権威主義的な家庭環境で育ったはずである。そして今、あなた自身があなたと親の関係がどうなっているか、それを冷静に見つめてみてほしい。たいていはぎくしゃくしているはずである。たとえうまくいっている(?)としても、それはあなた自身も権威主義的なものの考え方にどっぷりとつかっているか、あるいは親に対して服従的もしくは親離れできていないかのどちらかである。●変わりつつある日本人の意識 こうした私のものの考え方に対して、とくに男性の立場から、「父親の権威は必要だ」と反論する人は多い。「父親は家の中でもデ~ンとした存在感さえあればいい」と。いや、父親どころか、「夫の権威」にこだわる人さえいる。今でも「女房や子ども食わせてやる」と暴言を吐く夫はいくらでもいる。が、こうしたものの考え方は、これからの日本ではもう通用しない。そのひとつのあらわれというべきか、家事をまったく手伝わない夫がまだ50%以上もいる一方(国立社会保障人口問題研究所調査・2000年)、そうした夫に不満をもつ妻がふえている。厚生省の国立問題研究所が発表した「第2回、全国家庭動向調査」(98年)によると、「家事、育児で夫に満足している」と答えた妻は、51・7%しかいない。この数値は、前回93年のときよりも、10ポイント近くも低くなっている(93年度は、60・6%)。今、日本人は、大きな転換期にきているとみてよい。●親は友として、子どもの横を歩く 昔、オーストラリアの友人がこう言った。「親には三つの役目がある。親は、ガイドとして子どもの前を歩く。保護者として子どものうしろを歩く。そして友として子どもの横を歩く」と。日本人は、子どもの前やうしろを歩くのは得意だが、友として横を歩くのがヘタ。ものの考え方が権威主義的な人は、今日からでも遅くないから、子どもと一緒に横を歩いてみてほしい。今まで聞こえなかった子どもの声が聞こえてくるはずである。
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(19)
最前線の子育て論byはやし浩司(030)●まあ、ええじゃないか!++++++++++++++++++どうにもならないことに、ぶつかったら、こうつぶやいてみよう。「まあ、ええじゃないか」と。たったそれだけのことだが、それであなたの心は、ずっと軽くなるはず。++++++++++++++++++ 姉から、こんな話を聞いた。 その家には、長男を頭に、2人の姉妹がいる。現在、90歳近くなった父親を、長男夫婦が、世話をしている。 それについて、長男夫婦は、2人の妹に、「介護費用を分担してほしい」という願いを、たびたび言い伝えている。それに対して、2人の姉妹は、「女だから……」「夫のお金は私のものではないから……」と。「女」であることを理由に、そのつど、費用を出し渋ってきた。 が、ごく最近、その父親の容態が、おかしくなってきた。脳梗塞を併発して、介護センターから、一般病院へ移された。 とたん、遺産相続問題が発生。2人の妹たちが、「私たちも子どもだから……(遺産相続権はある)」と言い出した。 ここまで聞くと、身勝手な姉たちの様子しか頭に浮かんでこない。しかしこの話には、こんな伏線がある。ここから先も、姉から聞いた話である。 実は、2人の妹たちは、今から5、6年前に、相談して介護費用を出している。額は、1人、100万円。2人で、200万円。ともに夫はサラリーマン。決して楽な額ではなかった。しかしその200万円は、父親の介護のために使われることはなかった。たまたま兄(長男)の息子が大学に進学するときに重なり、その学費にと、兄の妻が使ってしまった。 それについて2人の妹が抗議すると、「今まで自腹を切って、父親のめんどうをみてきたのだから、当然。貸したお金を返してもらっただけ」というようなことを言ったという。 ……とまあ、こういうゴタゴタ話は、介護には、つきもの。お金がからんだ騒動となると、いまどき、珍しくもなんともない。が、問題は、どうしてそうなるか、だ。長い間、司法書士をしてきた友人のH氏は、こう言う。 「若いときは、まだ先がある。だからそれほどお金に執着しない。しかし年をとればとるほど、先が短くなる。つまり、ケチになる」と。つまりケチになるから、その分だけ、財産分与の問題が大きくなる、と。 一方、長男側はこう言っているという。「自分のつごうに合わせて、妹たちは、『私は女だから』と言い、また別のときは、『私は子どもだから』と言う。しかし私は、こんなことで、兄弟げんかをしたくない。私は親の財産などに、執着心はない。それよりも、もうこういうゴタゴタは、たくさん!」と。 で、こういうとき、私たちは、どう構えたらよいのか。そのヒントの1つとして、こんな話がある。 ある著名な作家は、若いころから、無精子症だった。名前を出せば、その人のことを知らない人は、この日本には、いない。文学界でも、賞という賞を総なめにしたあと、文学界の「長」として長い間、活躍していた。 が、その作家には、1人の娘がいた。そこで私が、その話を直接聞いたあと、つまり無精子症であることを直接聞いたあと、その作家にこう言った。 「だって、先生……。先生には、娘さんが……」と。 するとその作家は、ゲラゲラと大声で笑いながら、私にこう言った。「まあ、ええじゃないか、ええじゃないか」と。 ある意味で、すばらしい言葉である。「まあ、ええじゃないか」。 思うようにならないのが、人生。思うようにならないからといって、のろったり、うらんだりしても、始まらない。どうにかなることについては、それなりにがんばらなくてはいけない。努力もしなければならない。しかしどうにもならないことについては、あきらめる。受けいれる。そして笑い飛ばす。「まあ、ええじゃないか」と。 その長男にしても、2人の妹たちにしても、「明日は、我が身」。長くて、あと10年もすれば、みな、ボケ始め、20年もすれば、あの世行き。ゴタゴタに巻きこまれて苦しむくらいなら、「まあ、ええじゃないか」と笑ってすましたほうが、得。俗な言い方をすれば、そのほうが利口。 実はその長男が、今は、そう言っているという。「まあ、ええじゃないか」と。「財産といっても、たいしたものはない。ちゃんと平等に分けてやる」と。 しかしそういう心境になるのも、たいへん。とくに戦後の日本を、がむしゃらに生きてきた人たちは、お金への執着心が、人一倍、強い。本能的な部分にまで、その執着心が、刷りこまれている。そういう執着心から、自分を解放するのは、容易なことではない。金銭的にも、かなりの余裕がないと、むずかしい。 しかし「まあ、ええじゃないか」と笑えば、たしかに気が楽になる。どうせ人生というのは、そういうもの。生きることの、99・99%には、意味はない。残りの、0・01%に、それらしき意味があれば、御(おん)の字。つまらないゴタゴタに巻きこまれれば、その0・01%の人生すら、ムダにしてしまう。 だったら、つまらないことであくせくするだけ、損。「まあ、ええじゃないか」とあきらめたところで、失うものは、ほとんど、ない。 まあ、ええじゃないか! 私も、その作家に会ってからというもの、どうにもならないことが起きるたびに、「まあ、ええじゃないか」と、自分で自分をなぐさめるようにしている。それで問題が解決するわけではないが、しかし死ねば、すべてを失う。そのことを知れば、そこらのわずかな財産など、腸から出るガスのようなもの。「まあ、ええじゃないか」という言葉のウラには、そういう意味も隠されている。 そう言えば、その作家は、私にその言葉を教えてくれたあとまもなく、がんで死んでしまった。うわさでは、まれに見る、大往生だったという。きっとその作家は、「まあ、ええじゃないか、ええじゃないか」とつぶやきながら、死んでいったにちがいない。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●息子のSへ息子のSへ今度の正月に、日本へ来てくれて、ありがとう。10年ぶり、あるいはそれ以上ぶりに、楽しい正月を迎えることができました。お前がときどきアメリカから送ってきてくれる写真を見ながら、ウィルソン家の人たちを、いつも、うらやましく思っていました。ぼくたちには、クリスマスや正月といっても、最近は、晃子と2人だけ。やってくる客もいなくて、まあ、さみしいものでした。でも、今度、お前たちが来てくれると知って、ぼくたちは、2週間前から、毎日、大掃除をしました。それがとても楽しかった。居間のクーラー(暖房機)を入れたり、あれこれ電気製品をそろえたり。ふとんも、運んだりしました。コタツも、特製のものにしました。一日がかりで、やっとふとんを見つけ、それを居間のふとんにしました。庭掃除ももちろん、お前たちが来る日の朝には、ハナを風呂に入れたり、あるいは餅つきの用意をしたりもしました。それが実に楽しかった。本当に楽しかった。が、おかげで、ばかげたことだが、疲れてしまった。きっと気を張りすぎたためだと思う。そのため、お前たちが来たちょうどその夜から、ぼくは、風邪をひいてしまった。そういう自分が、なさけなかった。ふとんの中で、静かにしていると、涙ばかり出てきた。それについては、本当に申し訳ないことをしたと思う。まあ、人生、こういうことがあるから、楽しい。本当に楽しい。これでまたしばらく、お別れだけど、いつでも、また遊びに来てください。誠司もすばらしい。デニーズもすばらしい。ところで最近、C(長男)とは、よく会話をするようになった。先日は、ぼくの健康を気遣って、Cは、岐阜までいっしょについてきてくれた。ぼくも変わったけど、Cも変わった。残されたぼくの最後の仕事は、Cを一人前の人間にして、世に送り出すこと。今、その準備をしているところだよ。今回、正月に、遊びにきてくれてありがとう。晃子は、「またこういう日が来るわよ」と言ってくれるけど、ぼくは、今度だけで、じゅうぶん、楽しかった。満足した。2度目があると思って、今という時代を生きるのは、ぼくの主義ではないしね。では、S、さようなら。元気で、やれよ。何もできない親父だけど、いつも、お前のことを心配しているよ。嫌われているのはよく知っているけど、その責任はぼくにあるわけだから、決して、お前をうらんだり、嫌ったりはしないよ。別れるのはさみしいけれど、またいつか会いえるよな。じゃあ、元気でな!BYE!2007年10月19日(金)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司【BW教室から】●ほめつぶし 年長児のクラス。11人。私が、前列にいた、A君とB君に向って、「A君、B君、前に出て、2人で歌を歌ってください」と声をかけた。そのときのこと。 すかさず、A君が、「いや!」と。 そこで私もすかさず、「すばらしい! みなさん、聞きましたか? A君は、2人で歌うのはいやだと言っています。ひとりで歌いたいと言っています。みんなで、手をたたいてほめてあげましょう!」と。 (子どもたち、参観の親たち、みな、パチパチ!)私「A君、君は、歌が好きなんだってね。さあ、前に来てごらん」A「うん……」 そこでA君、どこかしぶしぶながら、ひとりで歌を歌いだした。私も、横で、いっしょに、歌った。そして歌が終わったとき、また、こう言った。私「うまいじゃないか。君は、歌がうまい。さすがだね。ひとりで歌うというのは、勇気のいることなんだよ。よく歌ったね。すばらしい!」と。 (それを聞いて、子どもたち、参観の親たち、みな、パチパチ!) すっかり気分をよくしたA君、まわりをみながら、こう言った。 「もう一度、歌ってもいい……」と。●ゴミ捨て? 小4のKさんと、Iさんと、3人で、近くの書店まで、ワークブックを買いに行く。その帰り道のこと。突然、Kさんが、こう言った。 「先生、今、ポケットからゴミを捨てたでしょう!」と。 そこで私は、こう言った。「ぼくは、30年以上、ゴミを、道路に捨てたことはないよ。つばも吐いたことはないよ」と。 すると、Iさんまで、「私も見た」と。 私はそのとき、私だけ自転車に乗っていた。私「じゃあ、確かめにいこう。ぼくのゴミかどうか、わかるはずだから」と。 そして帰り道を、また戻った。距離は、100メートルほどあった。私「ぼくはね、ゴミを捨てたことはないよ」K[でも、先生、ちゃんと、捨てたよ。ヒラヒラとゴミが落ちていくのを見たわ]I「うん、私も、見た」私「おかしいな?」と。 そして私がゴミを捨てたという場所に来てみると、何と、1000円札が落ちているではないか! 私がポケットに入れていた、1000円札である!私「アッ、ぼくの1000円だ!」K「ホント!」I「先生、よかったね」と。 子どもたちと書店へ行くとき、1000円だけ、ポケットに入れた。子どもたちのお金が足りないとき、私がそれで払うつもりでいた。その1000円だった。「ゴミを捨てたことがない」という確信が、その1000円札を救った(?)。 「君たちが気がついてくれたおかげで、ぼくは1000円をなくさないですんだよ。ありがとう」と。 いつもだったら、その1000円で、何かを買って、お礼をするのだが、冷たい冬の風を感じたので、そのまま教室にもどった。 ところで、当然のことだが、子どもたちと書店へ行くときも、私は、絶対に、何人かの子どもたちといっしょに行くことにしている。この世界には、「誤解」という言葉がある。1対1で行けば、いつどこで、どんな誤解をされるか、わからない。それでそのときは、Kさんに、同行してもらった。Iさんが、「Kさんに、いっしょに来てほしい」と言ったからである。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(031)●ミニ・退職体験++++++++++++++++長い休暇は、休職のようなもの。退職のようなもの。働き蜂の私には、長い休暇は、必要ない。かえって、心と体の調子がおかしくなってしまう。++++++++++++++++ 1年のうちで、私にとって、もっとも長い休暇。それが正月休暇である。合計で、13日もある。前後に土日が重なると、もう少し長くなることもある。 私は、しかし、その正月休暇のたびに、「ミニ・退職」なるものを、模擬体験する。倒産の模擬体験、リストラの模擬体験、あるいは、病気や事故による休職の模擬体験と言ってもよい。 総合的にみると、「いやな体験」である。ワイフは、「休暇なのだから、思いっきり、遊べばいい」などと、のんきなことを言う。しかしどういうわけか、休暇になったとたん、いつも体調を崩す。運動不足や、食生活の乱れがそれに拍車をかける。 それ以上に、私は、子どもたちとワイワイと騒いでいてこそ、自分を支えることができる。私にとっては、職場そのものが、ストレス解消の場となっている。それができなくなる。だから、とたん、気がふさぐ。重くなる。 実は、これがこわい。 私はもともと、「うつ気質」。川の流れにたとえるなら、サラサラと調子よく流れているときは、それなりに気分もよい。しかし一度、どこかで堰(せ)き止められると、そこで水がよどみ、すぐに、腐り始める。若いときは、腐るまでに、かなりの時間があった。しかし50歳を過ぎるころから、すぐに、腐るようになった。 症状としては、まず頭重感。こうして毎日、原稿を書いているが、そういう状態になると、原稿を書くのもままならなくなる。頭の機能が悪くなる。 それにいくら、「運動しよう」とがんばってみても、その気力がわいてこない。「今日、1日くらいは、いいや」と思って、サボってしまう。それが2日、3日と重なってしまう。だからよけいに、体の調子が悪くなる。 するとお決まりの「うつ症状」。私のばいいは、心配性が増幅して、それが被害妄想に発展することが多い。「このまま、ぼくは、ダメになってしまう」「ぼくが死んだら、家族はどうなるのだ」と。そして考えることは、将来の心配ばかり。5年先、10年先を悩み始める。 朝、起きたとき、少し足がフラついただけで、「このまま歩けなくなって、車椅子に乗るようになったらどうしよう」とか、あるいは、食べ過ぎて、胃が重く感じたりすると、「がんになったらどうしよう」とか、そんなふうに考える。 もちろん収入や、家計の心配もする。ふだんは、そんなことは何も考えないで生活している。実際、我が家では、家計簿なるものは、つけていない。いつも最低限の生活をするように心がけている。それでお金が足りなくなれば、土地や家、山荘を売ればよい。 が、うつ状態になると、そうはいかない。合理的なものの考え方そのものができなくなる。「この家を売るようになったらどうしよう」とか、「山荘を手放すのは、つらい」とか、さらには、「犬のハナが死んだら、そのさみしさに耐えられるだろうか」とか、そんなことまで考える で、昨日(11日)から、仕事、開始。私は思う存分、子どもたちと、騒いできた。笑いあってきた。楽しかった。自分の中で、脳細胞がパチパチと音をたててはじけるのが、よくわかった。心も、ウソのように軽くなった。ついでに体も軽くなった。 1時間もすると、それまでの「うつ状態」が、消えてしまった。「どうしてあんなことでクヨクヨと悩んだのだろう」と、反対にそういう状態になってみると、そちらのほうが信じられないほど。 やはり私は、死ぬまで、仕事をするしかないようだ。そのことを昨夜、寝る前にワイフに話すと、ワイフも、「そうね……」と言って笑ってくれた。 そうそう、1つ、こんなよいことがあった。 3~4か月の間、使いまくったデジタルカメラだが、最初から、USB接続がうまくできなかった。カメラからパソコンへの直接転送ができなかった。「1年近くになったら、修理に出せばいい」と考えて、昨日まで、だましだまし、使っていた。保証期間は、その1年間である。 が、どうも、不便。いつもメモリーカードを、カメラから取りだして、一度、カードリーダーへ挿入しなければならない。そこで修理に出すことにした。しかし一度、修理に出すと、1、2週間は、カメラを使えなくなる。 店員の前で、なんとなくためらっていると、店員が一とおりカメラをみたあと、こう言った。「これは修理不可能ですから、新品と交換します」と。 新品と交換! すでにキズまるけになったカメラを、新品と交換! 私は心の中で、バンザーイと叫んだ。 ……というわけで、今、私の胸のポケットの中には、その新品のカメラが、静かに、納まっている。そういうこともあって、今日は、気分は晴れ晴れ。私は、結構、単純な人間なのだア!Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司●利己主義と孤独+++++++++++++++++孤独ほど、恐ろしいものはない。孤独は最大の恐怖であり、ときにその人の命すらも、うばう。なぜ、人は、孤独になるのか。どうすれば、人は、その孤独から、自分を回避することができるのか。+++++++++++++++++ 世に、孤独ほど、恐ろしいものはない。本当に、恐ろしい。仏教でも孤独を、無間地獄の1つに数えている。その孤独だが、だれでも経験しうるものだろうが、その恐ろしさは、経験したものでなければ、わからない。 夜、ふとんの中で身を丸めて、ただひたすら震える。体を縮(ちぢ)めても、縮めても、その恐怖から逃れることはできない。身の置き場がない。つらい。さみしい。自分の心が、どこにあるさえあるかわからない。 恐ろしいほどの虚無感。むなしさ。味気なさ。 それは病気にたとえるなら、不治の病を宣告されたようなもの。断崖絶壁に立たされたような絶望感。ひしひしと迫りくる、絶望感。 その孤独を、あのイエス・キリストも経験している。あのマザーテレサは、つぎのように語っている。 訳はかなりラフにつけたので、必要な方は、原文をもとに、自分で訳してほしい。When Christ said: "I was hungry and you fed me," he didn't mean only the hunger for bread and for food; he also meant the hunger to be loved. Jesus himself experienced this loneliness. He came amongst his own and his own received him not, and it hurt him then and it has kept on hurting him. The same hunger, the same loneliness, the same having no one to be accepted by and to be loved and wanted by. Every human being in that case resembles Christ in his loneliness; and that is the hardest part, that's real hunger. 【キリストが言った。「私は空腹だった。あなたが食事を与えてくれた」と。彼はただ食物としてのパンを求める空腹を意味したのではなかった。彼は、愛されることの空腹を意味した。キリスト自身も、孤独を経験している。つまりだれにも受け入れられず、だれにも愛されず、だれにも求められないという、孤独を、である。彼自身も、孤独になった。そしてそのことが彼をキズつけ、それからもキズつけつづけた。どんな人も孤独という点では、キリストに似ている。孤独は、もっともきびしい、つまりは、真の空腹ということになる。】 孤独は、あらゆる人が共通してもつ、人生、最大の問題といってよい。だからもしあなたが今、孤独だからといって、それを恥じることはない。隠すこともない。大切なことは、その孤独から自分を回避させるために、自分はどうあるべきかを、いつも考えること。それについて書く前に、世界の賢者たちは、どのように考えていたか、それを拾ってみる。No one would choose a friendless existence on condition of having all the other things in the world. ―Aristotle世界中のあらゆるものを手に入れたとしても、だれも、孤独(friendless condition)は選ばないだろう。(アリストテレス)No my friend, darkness is not everywhere, for here and there I find faces illuminated from within; paper lanterns among the dark trees. - Carole Borges友がいれば、暗闇ばかりとはかぎらない。私は彼らの輝く顔を思い浮かべるが、それが暗い木々にかかる、ちょうちんのようなものだ。(C・ボーグ)To dare to live alone is the rarest courage; since there are many who had rather meet their bitterest enemy in the field, than their own hearts in their closet. - Charles Caleb Coltonあえてひとりで生きるというのも、勇気のいることだ。なぜならクロゼットに心をしまっておくよりも、戦場で、最悪の敵に会うことを望む人は多い。(C・C・コルトン)Pray that your loneliness may spur you into finding something to live for, great enough to die for. - Dag Hammarskjoldあなたが孤独であるなら、何かそのために生きることができる目標が見つかるように、できればそのために死ぬことができる目標が見つかるように、祈れ。(D・ハマーショルド)There is no greater sorrow than to recall in misery the time when we were happy. - Danteあなたが幸福だったときを、みじめな状態で思い起こすほど、悲しいものはない。(ダンテ)We're all lonely for something we don't know we're lonely for. How else to explain the curious feeling that goes around feeling like missing somebody we've never even met? - David Foster Wallace私たちがなぜさみしいか、それがわからないのに、私たちは、みな、さみしい。会ったこともないような人をしのぶような、実におかしな感情を、どうやって説明したらよいのか。(D・F・ウォレス)The most I ever did for you was to outlive you. But that is much. - Edna St. Vincent Millayあなたのためにした最大のことといえば、あなたより長生きをしたことです。それだけです。(E・S・V・ミレー)The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves. - Eric Hoffer自分と話をすることが、もうないとき、終わりはやってくる。それは純粋な思想の終わりであり、かつ最終的な孤独のはじまりでもある。はっきりわかっていることは、心の対話の終わりは、私たちのまわりの世界に関心をもつことの終わりであるということ。つまり世界というのは、私たちがそれを、自分に問いかけるときのみ、そこにある。(E・ホッファー)With some people solitariness is an escape not from others but from themselves. For they see in the eyes of others only a reflection of themselves. ー Eric Hoffer他人から逃れるから、孤独になるのではなく、自分から逃れるから孤独になる。なぜなら彼らは、他人に目の中に、自分の姿を見るからである。(E・ホッファー)It is loneliness that makes the loudest noise. This is true of men as of dogs. ー Eric Hofferもっとも騒々しいのは、さみしさである。犬も、人間も同じ。(E・ホッファー)"Don't you want to join us?" I was recently asked by an acquaintance when he ran across me alone after midnight in a coffeehouse that was already almost deserted. "No, I don't," I said. ー Franz Kafka「いっしょに、やらないか?」と、真夜中の、みすぼらしいコーヒーショップで、最近、知りあいの男にたずねられた。私は、「いいや」と答えた。(F・カフカ)I've never found a companion as companionable as solitude. ー Henry David Thoreau孤独ほど仲がよくなりやすい友だちはいないことを、私は知った。(H・D・ソロー)Ships that pass in the night, and speak each other in passing, Only a signal shown, and a distant voice in the darkness; So on the ocean of life, we pass and speak one another, Only a look and a voice, then darkness again and a silence. ー Henry Wadsworth Longfellow夜、行きかいながら交信する船。暗闇の中の、ただの信号と遠くの声。人生の海においても、またそうで、私たちは通りすぎ、会話を交わす。ただ見て、たがいに声をかける。それから再びやってくる、暗闇と静寂。(W・ロングフェロー)Oh, sweet sorrow, the time you borrow, will you be here when I wake up tomorrow? ー Katherine Wolfオー、甘い悲しみよ、生きながらえて、あなたは明日、私が目ざめるとき、ここにいるだろうか。(K・ウルフ)What should young people do with their lives today? Many things, obviously. But the most daring thing is to create stable communities in which the terrible disease of loneliness can be cured. ー Kurt Vonnegut今日、若い人たちは、自分の人生をどうすべきか? 明らかに多くのことがある。しかしもっとも大切なことは、孤独という恐ろしい病気が癒されるべき、確かな人間関係をつくりあげることである。(K・ボネー)In solitude, where we are least alone ー Lord Byron孤独の中で、我、ひとりにあらず。(L・バイロン)Life dies inside a person when there are no others willing to beーfriend him. He thus gets filled with emptiness and a nonーexistent sense of selfーworth. ー Mark R. J. Lavoie喜んで彼の友になる人なければ、人生は、その人は死ぬ。彼はかくして、空しさに包まれ、生きる価値を見失う。(M・R・J・ラボー)Music was my refuge. I could crawl into the spaces between the notes and curl my back to loneliness. ー Maya Angelou音楽は、私の逃げ場。私は音符の間の空間に身をすべらせ、孤独に身をかがめる。(Mアンジェロウ)There is no pleasure to me without communication: there is not so much as a sprightly thought comes into my mind that it does not grieve me to have produced alone, and that I have no one to tell it to. Michel Eyquem De Montaigne人との交わりのない喜びというのは、私には考えられない。たとえばこれはと思うひらめきがあったとき、私はそれを自分ひとりで考え出したとは思わないし、それをだれかに話さずにはおられない。(M・E・D・モンテニュー)Our language has widely sensed the two sides of being alone. It has created the word "loneliness" to express the pain of being alone. And it has created the word "solitude" to express the glory of being alone. ー Paul Tillich私たちの言語は、ひとりでいることについて、二つの見方をする。一つは、「さみしさ」という語で、これは、ひとりでいることの苦痛を意味する。そしてもう一つは、「孤独」という語で、これはひとりでいることの栄光を意味する。(P・チリッヒ)God made everything out of nothing, but the nothingness shows through. -Paul Valery神は、無からすべて作り出した。しかし無は、透けて現れる。(P・バレリイ)The person who tries to live alone will not succeed as a human being. His heart withers if it does not answer another heart. His mind shrinks away if he hears only the echoes of his own thoughts and finds no other inspiration. ー Pearl S. Buckひとりでいようと思う人は、人間としては、成功しない。もしだれの心にも答えることがなければ、その人の心は、しぼみ、もし彼自身の心のエコーだけを聞いているならば、その人の心は、縮む。そして新しい発見も、そこで終わる。(P・S・バック)When you're lonley, go to the music store and visit with your friends. ー Penny Lane, "Almost Famous"さみしかったら、あなたの友と、ミュージック・ショップへ行け。(P・レイン)The body is a house of many windows: there we all sit, showing ourselves and crying on the passersーby to come and love us. ー Robert Louis Stevenson体は、たくさんの窓がある家。その窓辺に座って、自分を見せ、その外を行き交う人に、やってきて、自分を愛するようにと泣き叫ぶ。(R・L・スティーブンソン)Time takes it all, whether you want it to or not. Time takes it all, time bears it away, and in the end there is only darkness. Sometimes we find others in that darkness, and sometimes we lose them there again. ー Stephen King, "The Green Mile"時は、すべてを奪う。あなたがそれを望むと、望まないとにかかわらず。時は、すべてを奪い、運び去る。そして最後には、暗闇のみ。ときに私たちはその暗闇の中に、人を見る。そしてときに私たちは、その人すら再び見失う。(A・キング・「グリーンマイル」)Better be alone than in bad company ー Thomas Fuller悪い仲間といるくらいなら、ひとりのほうがよい。(T・フラー)The whole conviction of my life now rests upon the belief that loneliness, far from being a rare and curious phenomenon, peculiar to myself and to a few other solitary men, is the central and inevitable fact of human existence. ー Thomas Wolfe今や私は、人生の中で、孤独というのが、人間の存在には欠かせないものであることを、信念として発見した。その孤独というのは、とくに私や、二、三の孤独な人にとっては、まったく理解しがたい奇妙な現象ではあるが……。(T・ウルフェ)And I look again towards the sky as the raindrops mix with the tears I cry. - Unknown雨と涙が混ざるように、私は再び空を見あげる。(作者不詳)One may have a blazing hearth in one's soul, and yet no one ever comes to sit by it. ー Vincent Van Gogh人は、魂の中に、燃えさかる暖炉をもっているかもしれないが、だれもそのそばにきて、座ることはない。(V・V・ゴッフォ)Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, and laryngitis. ー William Arthur Ward孤独な人、多弁な人、咽頭炎の人には、しっかりと耳を傾けてあげよう。それが最善の治療法だから。(W・A・ウォード)+++++++++++++++++++++++(付記) ここでは「loneliness」(さみしさ)と「solitude」(孤独)を、ともに「孤独」と訳した。孤独は、たいていさみしさをともなう。中に、孤独を楽しむ人もいるというが、私にはそういう人の気持ちが、理解できない。私にとって孤独は、人生、最大の敵。孤独と戦うことが、生きることの目的にもなっている。 私は冒頭で、「孤独との戦い」を口にした。いかなる方法をもってしても、孤独を取り除くことができないなら、共存するしかない。それが今の、私の考え方である。それは人間が、原罪としてもって生まれたものではないかと思う。つまり「知恵ある生物」が、その知恵で、自分が孤独な存在であることに気づいてしまった。 もし人間が、もう少しバカなら、バカなまま、何も考えることもなく、従って孤独になることもなかった。へたに利口になってしまったから、孤独を感ずるようになってしまった。「原罪的」というのは、そういう意味である。 こうして世界の賢人の言葉を拾い集めてみると、幸福論と孤独論は、ちょうど紙の表と裏の関係にあるのがわかる。そして多くの賢人が、幸福を追求するかたわら、孤独について語っている。この中で、とくに私の関心をひいたのが、マザーテレサの言葉。「イエスも孤独だった」という言葉である。私は、これを読んでほっとした。多分、あなたもそうであろう。+++++++++++++++++++++++++●利己主義との戦い 人は、なぜ孤独になるのか。その最大のカギを握るのが、「利己」と「利他」ではないか。つまり利己主義に陥れば陥るほど、人は孤独に襲われる。しかし利他主義になれば、孤独を避けることはできないにしても、孤独の恐怖をやわらげることができる。 その利他主義を、仏教の世界では、「慈悲」といい、キリスト教の世界では、「愛」という。マザーテレサによれば、イエス・キリストは、「飢え」という「孤独」に苦しんだという。そしてその苦しみの結果、「愛」を説くようになったという。 つまり宗教がもつ究極の目標は、ここにある。いかにすれば私たちは、利己から脱し、利他の世界へと、自らを導くことができるか。いくつかのヒントがある。(1)まず、誠実であること。他人に対しては、もちろん、自分に対しても、だ。ウソやインチキは、心のゴミとなって、やがてその人自身の人生観を、暗く、見苦しいものにする。それは、実は、ささいな日常的な行為から始まる。その日々の積み重ねが、月となり、月々の積み重ねが、年となり、やがてその人の人格となって熟成される。(2)いつも前向きに生きる。前向きに生きるということには、ある種の緊張感がただよう。その緊張感を、決して、失ってはいけない。それは健康論に似ている。立ち止まって、休んだときから、その人の健康は、失われる。が、前向きに生きるだけでは足りない。日々に補ったところで、脳ミソの底からは、容赦なく、知識や経験は、流れ出ていく。失う分以上のものを、補って生きる。だから生きることには、ゴールはない。死ぬまで、前に進む。精進(しょうじん)する。(3)生きていることを喜び、そして感謝する。この広大な宇宙の一点で、生きていること自体が、奇跡。アインシュタインも、そう言っている。金銭的な損得勘定から、自らを解き放つ。いわんや人間関係を、その損得勘定で判断してはいけない。この世界では、マネーは、必要だ。マネーがなければ、不幸になることはある。しかしマネーは、決して、人を幸福にすることはない。(4)幸福感や充足感は、薄いガラス箱のようなもの。幸福感や充足感を覚えたら、静かに、そっとそのまま、守り育てていく。自分の中に、「利他」を感じたときも、そうだ。それらはとても、こわれやすい。決して、うぬぼれたり、ごう慢になってはいけない。幸福感や充足感は、一度こわれると、取りもどすのに、その何倍もの時間とエネルギーが必要となる。(5)他人の目の中に、自分を置く。その相手と対峙してすわったときでも、自分の視点を一度、相手の視点の中に置いてみる。その相手から、自分を見る。それを繰りかえしていると、やがて相手の心の状態や、何を考えているかまで、わかるようになる。言うなれば、「利他」の深さというのは、どこまで相手の立場でものを考えられるかによって決まる。 もっとも、孤独になることが悪いというのではない。死の恐怖があるからこそ、生きていることの喜びがわかるように、孤独になることがあるからこそ、利他のすばらしさがわかる。あなたならあなたが、利己主義でも、一向に構わない。しかしその結果として、孤独を覚えたら、そのあと、その苦しみを、利他主義に転化すればよい。……と口でいうほど、実は、簡単なことではないが……。がんばろう!(はやし浩司 利己主義 利他主義 孤独論)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(18ー2)
最前線の子育て論byはやし浩司(031)【賢者の言葉】(政治編)●Nearly all men can withstand adversity; if you want to test a man's character, give him power. - Abraham Lincolnほとんどすべての人は、逆境にあえば、それと戦う。もしその人の性格を試してみたいと思うなら、彼に力を与えてみろ。(A・リンカーン)++++++++++++++++++ 平凡な生活を、可もなく、不可もなく過ごしている人は、それなりに人格者に見える。いっぱしの人生論を口にしたり、ときには、他人に説教をしたりする。しかしその人が、本当に人格者かどうかということになると、わからない。リンカーンは、逆境でこそ、その人の真価が試されるという。ナルホド!●They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Ben Franklin, "Historical Review of Pennsylvania"ささやかな一時的な安全を得るために、基本的な自由をあきらめるような人は、自由も安全も、もつことはない。(B・フランクリン)++++++++++++++++++ 基本的な自由とは、何か? ……このところ、それがよくわからなくなってきた。たとえば私の体には、無数の、「運命」と呼ばれる糸がからみついている。私が望まなくても、向こうからからみついてくる。それがうるさいほど、無数にからみついてくる。そんな私に、「自由」など、望むべくもない。しかしもし、その私がその無数の糸から解放されたら、私はどうなるか? それを考えるのも、こわい。フランクリンは、自由と安全をからめて考えている。「?」と思って、ここまで。●Government is the Entertainment Division of the military-industrial complex. - Frank Zappa政府というのは、軍産共同体の、娯楽部門のようなもの。(F・ザッパ)++++++++++++++++++ 2006年になって、世界は、より不安定になった。そんな感じがする。イランはますます過激になってきた。K国も、そうだ。中国国内では、各地で暴動が発生し、死者まで出ている。この極東にしても、ガソリンがまかれたような状態と言ってもよい。だれかがどこかで小さな火をつければ、それはたちまちのうちに、パッと燃え広がるにちがいない。日本国内でも、過激な発言が目立つ。そしてそれを支持する人がふえているように思う。2006年の日本は、どうなるのだろう?●The body politic, as well as the human body, begins to die as soon as it is born, and carries in itself the causes of its destruction. - Jean Jacques Rousseau政治体というのは、人間の体と同じように、生まれたときから、死に始める。つまりそれ自体が、破滅の原因をもっている。(J・J・ルソー)+++++++++++++++++++ どんな政治体制も、誕生したときから、死に向って進み始めるという。発展的に、さらに進化した政治体制になるということはない、ということか。問題は、しかし、どんな政治体制も、静かには、破滅しないということ。破滅に至る過程で、悪あがきを繰りかえす。これが世相を混乱させる。ときには、それが戦争につながることもある。それがこわい。●The more that is given the less people will work for themselves, and the less they work the more their poverty will increase. - Leo Tolstoy与えられれば与えられるほど、民衆は自分のために働かなくなる。そして働かなくなればなるほど、彼らの貧困は、増大する。(L・トルストイ)+++++++++++++++++++今の日本のことかもしれない。ろくに働かないで、そのくせ、貧しさを訴える人は、少なくない。生活そのものが、ぜいたくになってしまったということもある。生活だけは、一人前。昔は、「クーラー」というだけで、ぜいたく品だった。が、今では、当たり前。そういう生活をしながら、一方で、「貧しい」「貧しい」と訴える。●Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even when there is no river. - Nikita Khrushchev政治家なんてものは、みな、同じ。川がないのに、橋をかけてやると、約束する。(N・フルシチョフ)+++++++++++++++++++ ホント! だからはじめっから、政治家などに、何も期待しないこと。そのかわり、政治家への監視の目を強める。きびしくする。たとえ1円でも、ワイロを手にしたら、禁固10年とか、そういうふうにする。●You only have power over people as long as you don't take everything away from them. But when you've robbed a man of everything he's no longer in your power -- he's free again. - Nobel Prize-Winning Author Alexander Solzhenitsynあなたがすべてを奪い取らない限り、あなたはその人たちの上に、力を行使できる。しかしすべてを奪えば、もうかれは、あなたの力の中にはいない。その人は、再び、自由になる。(ノーベル賞受賞者、A・ソルジェニツィン)+++++++++++++++++ 私の翻訳が悪いのだろう。意味が、よくわからない。この文を読んで思いつくこともない。ソルジェニツィンという、極限状態を生きた人だけが言える言葉であり、また同じような極限状態を生きた人だけが理解できる言葉かもしれない。私のような凡人が、安易な解釈を加えることは、危険ですらある。●Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary. - Robert Louis Stevenson政治というのは、この世界で、唯一、準備のいらない職業である。(R・L・スティーブンソン) まあ、あえて言うなら、必要なのは、「口」だけ。脳ミソは、必要ない。とくにこの日本では、一度、政治家になると、自分で静かに考える時間はなくなってしまう。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(032)●共依存+++++++++++++++たがいにベタベタの夫婦がいる。一見、仲がよく見えるが、たがいに愛しあっているから、そうしているのではない。実は、たがいに、心のすき間を埋めあっているだけ。そういうふうに、たがいに依存しあう関係を、共依存関係という。+++++++++++++++ 私の知人に、A氏とB氏がいる。A氏は、今年、74歳。B氏は、83歳。A氏は、長い間、造園業を営んできたが、ちょうど4年前、心筋梗塞で倒れた。幸い症状は軽く、そのあと、バルーンを入れて血管を拡張。さらに心臓への血管バイパス手術が成功。今は、農作業ができるほどまでに、健康を回復している。 B氏は、ここ12~3年の間、軽い脳梗塞を繰りかえしている。そのたびに症状は重くなり、最近は、左半身の自由が、ほとんどきかなくなっている。しかし杖をつけば、何とか、歩けるという。 このA氏とB氏。実は、1つの共通点がある。その共通点が、たいへん興味深いので、ここに記録しておく。あえて申し添えるなら、A氏とB氏は、私の知人だが、たがいに、まったく無縁の人物である。 その共通点というのは、ともに、妻のそばを、片時も離れないということ。A氏のばいいは、妻がトイレに行こうとしても、それについていくという。B氏も、どこへ行くにも、妻をつれて歩くという。私のワイフは、「病気になって、不安なんじゃない?」と言うが、そんな単純な問題でもないようだ。 たとえば心理学の世界には、「共依存」という言葉がある。+++++++++++++++++その共依存について書いた原稿を先に添付しておきます。+++++++++++++++++●共依存依存症にも、いろいろある。よく知られているのが、アルコール依存症や、パチンコ依存症など。もちろん、人間が人間に依存することもある。さしずめ、私などは、「ワイフ依存症」(?)。しかしその依存関係が、ふつうでなくなるときがある。それを「共依存」という。典型的な例としては、つぎのようなものがある。夫は、酒グセが悪く、妻に暴力を振るう。仕事はしない。何かいやなことがあると、妻に怒鳴り散らす。しかし決定的なところまでは、しない。妻の寛容度の限界をよく知っていて、その寸前でやめる。(それ以上のことすれば、本当に、妻は家を出ていってしまう。)それに、いつも、暴力を振るっているのではない。日ごろは、やさしい夫といった感じ。サービス精神も旺盛。ときに、「オレも、悪い男だ。お前のようないい女房をもちながら、苦労ばかりかけている」と、謝ったりする。一方妻は、妻で、「この人は、私なしでは生きていかれない。私は、この人には必要なのだ。だからこの人のめんどうをみるのは、私の努め」と、夫の世話をする。こうして夫は、妻にめんどうをかけることで、依存し、妻は、そういう夫のめんどうをみることで、依存する。ある妻は、夫が働かないから、朝早くに家を出る。そして夜、遅く帰ってくる。子どもはいない。その妻が、毎朝、夫の昼食まで用意して家を出かけるという。そして仕事から帰ってくるときは、必ず、夕食の材料を買って帰るという。それを知った知人が、「そこまでする必要はないわよ」「ほっておきなさいよ」とアドバイスした。しかしその妻には、聞く耳がなかった。そうすることが、妻の努めと思いこんでいるようなところがあった。つまり、その妻は、自分の苦労を、自分でつくっていたことになる。本来なら、夫に、依存性をもたせないように、少しずつ手を抜くとか、自分でできることは、夫にさせるといったことが必要だった。当然、離婚し、独立を考えてもよいような状態だった。が、もし、夫が、自分で何でもするようになってしまったら……。夫は、自分から離れていってしまうかもしれない。そんな不安感があった。だから無意識のうちにも、妻は、夫に、依存心をもたせ、自分の立場を守っていた。ところで一般論として、乳幼児期に、はげしい夫婦げんかを見て育った子どもは、心に大きなキズを負うことが知られている。「子どもらしい子ども時代を過ごせなかったということで、アダルト・チェルドレンになる可能性が高くなるという」(松原達哉「臨床心理学」ナツメ社)。「(夫婦げんかの多い家庭で育った子どもは)、子どもの人格形成に大きな影響を与えます。このような家庭環境で育った子どもは、自分の評価が著しく低い上、見捨てられるのではないかという不安感が強く、強迫行動や、親と同じような依存症に陥るという特徴があります。子ども時代の自由を、じゅうぶんに味わえずに成長し、早くおとなのようなものわかりのよさを見につけてしまい、自分の存在を他者の評価の中に見いだそうとする人を、『アダルト・チェルドレン』と呼んでいます」(稲富正治「臨床心理学」日本文芸社)と。ここでいう共依存の基本には、たがいにおとなになりきれない、アダルト・チェルドレン依存症とも考えられなくはない。もちろん夫婦喧嘩だけで、アダルト・チェルドレンになるわけではない。ほかにも、育児拒否、家庭崩壊、親の冷淡、無視、育児放棄などによっても、ここでいうような症状は現れる。で、「見捨てられるのではないかという不安感」が強い夫が、なぜ妻に暴力を振るうのか……という疑問をもつ人がいるかもしれない。理由は、簡単。このタイプの夫は、妻に暴力を振るいながら、妻の自分への忠誠心、犠牲心、貢献心、服従性を、そのつど、確認しているのである。一方、妻は妻で、自分が頼られることによって、自分の存在感を、作り出そうとしている。世間的にも、献身的なすばらしい妻と評価されることが多い。だからますます、夫に依存するようになる。こうして、人間どうしが、たがいに依存しあうという関係が生まれる。これが「共依存」であるが、しかしもちろん、この関係は、夫婦だけにはかぎらない。親子、兄弟の間でも、生まれやすい。他人との関係においても、生まれやすい。生活力もなく、遊びつづける親。それを心配して、めんどうをみつづける子ども(娘、息子)。親子のケースでは、親側が、たくみに子どもの心をあやつるということが多い。わざと、弱々しい母親を演じてみせるなど。娘が心配して、実家の母に電話をすると、「心配しなくてもいい。お母さん(=私)は、先週買ってきた、イモを食べているから……」と。その母親は、「心配するな」と言いつつ、その一方で、娘に心配をかけることで、娘に依存していたことになる。こういう例は多い。息子や娘のいる前では、わざとヨロヨロと歩いてみせたり、元気なさそうに、伏せってみせたりするなど。前にも書いたが、ある女性は、ある日、駅の構内で、友人たちとスタスタと歩いている自分の母親を見て、自分の目を疑ってしまったという。その前日、実家で母親を訪れると、その女性の母親は、壁につくられた手すりにつかまりながら、今にも倒れそうな様子で歩いていたからである。その同じ母親が、その翌日には、友人たちとスタスタと歩いていた!その女性は、つぎのようなメールをくれた。「母は、わざと、私に心配をかけさせるために、そういうふうに、歩いていたのですね」と。いわゆる自立できない親は、そこまでする。「自立」の問題は、何も、子どもだけの問題ではない。言いかえると、今の今でも、精神的にも、自立できていない親は、ゴマンといる。決して珍しくない。で、その先は……。今度は息子や娘側の問題ということになるが、依存性の強い親をもつと、たいていは、子ども自身も、依存性の強い子どもになる。マザコンと呼ばれる子どもが、その一例である。そのマザコンという言葉を聞くと、たいていの人は、男児、もしくは男性のマザコンを想像するが、実際には、女児、女性のマザコンもすくなくない。むしろ、女児、女性のマザコンのほうが、男性のそれより、強烈であることが知られている。女性どうしであるため、目立たないだけ、ということになる。母と成人した息子がいっしょに風呂に入れば、話題になるが、母と成人した娘がいっしょに風呂に入っても、それほど、話題にはならない。こうして親子の間にも、「共依存」が生まれる。++++++++++++++++++言うなれば、共依存関係になる夫婦は、その両方、もしくは一方に、情緒的な欠陥、もしくは精神的な未熟性があるとみてよい。その(心のすき間)を埋めるために、夫や妻を利用する。 ここにあげたA氏にしても、B氏にしても、(A氏は心筋梗塞だが、しかし同じ血栓性の病気ということで、脳のほうにも、ダメージを受けている可能性は、高い)、脳梗塞による影響とも考えられなくはない。 そこでネットを使っていろいろ調べてみると、こんなことがわかった。つまり脳梗塞や心筋梗塞を起こした人が、さまざまな精神障害的な症状を示すようになるのは、薬の副作用によるものも少なくない、ということ。 それぞれ専門のサイトには、投薬名と、その副作用が列挙してあるので、興味のある人は、そちらをみたらよい。私は、ヤフーの検索エンジンを使って、「脳梗塞 随伴症状 孤独」で調べてみた。 ナルホド! 簡単には結論づけられないが、A氏もB氏も、何らかの薬を服用している。その結果として、妄想観念や被害妄想をもちやすくなったと考えられなくはない。A氏の妻は、私のワイフにこう言った。 「私がトイレに入っている間、夫は、そのトイレのドアの外で、立って待っているのですよ」と。 ふつうなら笑い話になるような話だが、「明日は我が身か」と思うと、笑うことはできない。 Aさん、Bさん、病気なんかに負けないで、がんばって生きてくださいよ!Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(033)●親子の確執+++++++++++++++++++++掲示板のほうに、親子の問題に悩む、1人の女性から、相談の書きこみがあった。いわく、「良好な人間関係がベースにあれば、苦労も苦労ではなくなるのですが、それがないと、親子でも、苦労は倍化します。ときどき、『どうして私なんか、産んでくれたのよ』と母に叫びたくなることもあります。子どものころから、親のことでは、苦労のしっぱなし。結婚してからも、一日とて、気が晴れる日はありませんでした」(静岡県S市・Yより)と。このメールを読んで、数年前、私にこんなメールをくれた人のことを思い出した。それをここに再掲載します。++++++++++++++++++++++【NEより、はやし浩司へ】はやし浩司さま突然のメールで、失礼します。暑いですが、いかがお過ごしですか?今回のメールは、悩み相談の形をとってはいますが、ただ単に自分の気持ちを整理するために書いているものです。返信を求めているものではないので、どうかご安心ください。結婚後、三重県S市で生活していた私たち夫婦は、主人が東京都の環境保護検査師採用試験に合格したこともあり、今春から東京で生活することになりました。実は、そのことをめぐって私の両親と大衝突しています。嫁姑問題ならまだしも、実の親子関係でこじれて悩んでいるなんて、当事者以外にはなかなか理解できない話かもしれません。このような身内の恥は、あまり誰にも相談もできません。人生経験の浅い同年代の友人ではわからない部分も多いと感じ、人生の先輩である方のご意見を聞かせていただけたら…(今すぐにということではなく、やはり問題解決に至らなくて、どうにもならなくなったときに、いつか…)と思い、メールを出させていただきました。まずはざっと話させていただきます。事の発端は、私たち夫婦が東京に住むことになったことです。表面上は…。私の実家は、和歌山市にあります。夫の実家は、東京都のH市にあります。東京へ移る前は、三重県のS市に住んでいました。けれども、日頃積もり積もった不満が、たまたま今回爆発してしまったというほうが正確なのかもしれません。母は、私たちが三重県のS市を離れるとき、こう言いました。「結婚後しばらくは三重県勤務だが、(私の実家のある)和歌山県の採用試験を受験しなおすと言っていたではないか。都道府県どうしの検査師の交換制度に申し込んで、三重県から和歌山県に移るとかして、いつかは和歌山市にくるチャンスがあれば…と、待っていた。それがだめでも、三重県なら隣の県で、まあまあ近いからとあきらめて結婚を許した。それが突然、東京に行くと聞いて驚いた。同居できなくてもいいが、できれば、親元近くにいてほしかった。あなたに見棄てられたという気分だ」と。親の不安と孤独を、あらためて痛感させられた一件でした。「いつか和歌山市にくるかもしれない」というのは、あくまで両親の希望的観測であり、私たちが約束したことではありません。母も体が丈夫なほうではないので、確かにその思いは強かったかも知れませんが…。ですので、いちいち明言化しなくても、娘なら両親の気持ちを察して、親元近くに住むのが当然だろう、という思いが、母には強かったようです。しかし、最初からどんな条件をクリアしようと、結婚に賛成だったかといえば疑問です。昔風の理想像を、娘の私に押しつけるきらいがありました。たとえ社会的地位や財産のある(彼らの基準でみて)申し分ない結婚相手であっても、相手を自分たちの理想像に押し込めようとするのをやめない限り、いつかは結局、同様の問題が噴き出していたと思うのです。配偶者(夫)に対して、貧乏ゆすりが気に入らないだとか、食べ物の好き嫌いがあるのがイヤだなどと…。配偶者(夫)と結婚したのか、親と結婚したのかわからないほど、結婚当初は、親の顔色をうかがってばかりいました。両親の言い分を尊重しすぎて、つまらぬ夫婦喧嘩に発展したこともしばしばありました。いつまでも頑固に、私の夫を「気に入らない!」と、わだかまりを抱えているようでは、近くに住んでもうまくいくとは思えません。両親にとって、娘という私の結婚は、越えられないハードルだったのかもしれませんね。結婚後、実家を離れ、三重県で生活していても、「そんな田舎なんかに住んで」とバカにして電話の一本もくれませんでした。私が妊娠しても「誰が喜ぶと思ってるんだ」という調子。結局、流産してしまったときも「私が言った(暴言)せいじゃない(←それはそうかもしれませんが、ひどいことを言ってしまって謝るという気持ちがみられない)」と。出産後も頼れるのは、夫の母親、つまり義母だけでした。実の母は「バカなあんたの子どもだから、バカにきまってる」「いまは紙おむつなんかあるからバカでも子育てできていいね」などなど。なんでそんなことまでいわれなければならないのかと、夢にまでうなされ夜中に叫んで目がさめたこともしばしば…そんな調子ですから、結婚後、実家にかえったことも、数えるほどしかありません。行くたびに面とむかってさらに罵詈雑言を浴びせられ、必要以上に緊張してしまうことの繰り返しです。このまま三重県生活を続けていてもいいと考えたのですが、子どもが生まれると近くに親兄弟の誰もいない土地での生活は大変な苦労の連続。私の実家のある和歌山市と、旦那の実家のある東京のそれぞれに帰省するのも負担で、盆正月からずらして休みをとってやっと帰る…などをくりかえしていました。そのためお彼岸のお墓参りのときには、何もせずに家にいるだけというふうでした。さらに子どもの将来の進路・進学の選択肢の多さ少なさを比較すると、このまま三重県で暮らしていていいのだろうかと思い、それで夫婦ではなしあった結果、今回思いきって旦那が東京を受験しました。ただでさえ少子化の今の時代ですから、近くに義父母や親戚、兄弟が住んでいる街で、多くの目や手に支えられた環境の中で子育てしていこう!、との結論にいたったのでした。このことについて実の母に相談をしませんでした。事後報告だったので、(といっても相談なんてできるような関係ではなかったですし)、和歌山市の両親を激怒させたことは悪かったとは思います。しかし、これが発端となり、母や父からも猛攻撃が始まりました。「親孝行だなんて、東京に遠く離れて、一体何ができるっていうの? 調子いいこと言わないで!」「孫は無条件にかわいいだろうなんて、馬鹿にしないで! もう孫の写真なんか送ってこなくていいから」「偽善者ぶって母の日に花なんかよこさないで!」「言っとくけど東京人なんて、世間の嫌われ者だからね」云々…。電話は怖くて鳴っただけで体のふるえがとまらなくなり、いつ三重までおしかけてこられるかと恐怖でカーテンをしめきったまま、部屋にとじこもる日々でした。それでも子どもをつれて散歩にいかなければならないと外出すれば、路上で和歌山の両親の車と同じ車種の車とでくわしたりすると、足がすくんでうごけなくなってしまい、職場にいる主人に助けをもとめて電話する…そんな日々がしばらく続きました。いつしか『親棄て』などと感情的な言葉をあびせかけられ、話が大上段で感情的な応酬になってしまっています。親の気持ちも決して理解できないわけではないのですが…。ふりかえると、両親も、夫婦仲が悪く、弟も進学・就職で家を離れ、私がまるで一人っ娘状態となり、過剰な期待に圧迫されて共依存関係が強まり、「一卵性母娘」関係になりかけた時期がありました。もしかするとその頃から、親子関係にほころびが生じてしまったのかもしれません。こちらの言い分があっても、パラサイト生活の状態だったので、最後には「上げ膳据え膳の身で、何を生意気言ってるの!」とピシャリ! 何も反論できませんでした。親が憎いとか、断絶するとか、そんな気持ちはこちらにはないのです。実の親子なのですから、ケンカしても、必ず関係修復できることはわかっています。でも、うまく距離がとれず、ちょっと苦しくなってしまったというだけ。「おまえは楽なほうに逃げるためにあんな男つれてきて、仕事もやめて田舎にひっこんで結婚しようとしてるんだ」「連中はこっちが金持ちだとおもってウハウハしてるんだ」「人間はいつのまにか染まっていくもの。あんたもあんな汚らしい長家に住んでる人間たちと一緒になりたければ、出て行けばいい」などなどと、吐かれた暴言は、心にくいとなってつきささり、ひどく傷つきました。結婚に反対され、家をとびだし一人暮らしを始めたのも、「このままの関係ではまずい」と思ったことがきっかけでした。ついに一人ではそんな暴言の嵐を消化しきれず、旦那や義父母に泣いてすがると、私の両親は「お前が何も言わなければ、そんなことあっちには伝わらなかったのに。余計なことしゃべりやがって。あっちの親ばっかりたてて、自分の親は責めてこきおろして…。よくもそんなに人バカにしてくれたね。もう私達の立場はないじゃないか。親が地獄のような日々おくっているのに、自分だけが幸せになれるなんて思うなよ」と。そんな我が家の場合、もう一度、適切な親子の距離をとり直すために、もめるだけもめて、これまでの膿を全部出し切っていくという、痛みをともなうプロセスを、避けて通れないようです。本や雑誌で、家族や親子の問題を扱った記事を目にすると、子ども側だけが一方的に悪いわけではないようだと知り安心するものの、それは所詮こじつけではないか?、と堂々巡りに迷いこみ、訳がわからなくなってしまいます。娘の幸せに嫉妬してしまう母、愛情が抑圧に転じてしまう親、アダルトチルドレン、心理学用語でいう「癒着」、育ててもらった恩に縛られすぎて、自分の意思で生きていけない子ども…などなど。そんな事例もあるのだなーと飽くまで参考にする程度ですが、どこかしらあてはまる話には、共感させられることも多いです。世間一般には、「スープの冷めない距離」に住むことが親孝行だとされています。私の母は、「近所のだれそれさんはちゃんと親近くに住んでいる。いい子だね」という調子で、それにあてはまらない子は、「ヘンな子ね、いやだわ」で終わり。スープの冷めない距離に住めなかった私は「親不孝者だ…」と己を責め、自分そのものを肯定できなくなることもあります。こんな親不孝者には、子育ても人間関係も仕事もうまくいくわけがないのだ。親を棄てて、幸せだなんて自己満足で、いつか必ずしっぺ返しをくらって当然だ。父母の理想から外れた人生を選び、それによってますます彼らを傷つけている私に、存在価値なんてあるのだろうか…などと。子どもは24時間待ったなしで愛情もとめてすりよってきますが、東大に入れて外交官にして、おまけにプロのピアニスト&バイオリニストなどにでもしなければ、子育てを認めないような、かたよった価値観の両親のものさしを前に、無気力感でいっぱいになってしまいます。よってくる我が子をたきしめることもできずに、ただただ涙…そんな日々もあります。実はこの親子関係がらみの問題は、私の弟の問題でもあります。彼は転職する際、両親と大衝突し、罵詈雑言の矛先が選択そのものにではなく、人格にまで向けられたことに対して、相当トラウマを感じているようです。(事実、1年近く、実家との一切の関わりを断ち切った時期もあったほどです)。結局、転職先は両親の許容範囲におさまり、表層は解決したように見えるのですが、本質的な信頼の回復には至っていません。子の人生を受け入れることができない両親の狭量さを、彼はいまだに許していません。弟は「親は親の人生、子は子の人生。親の期待に子が応えるという、狭い了見から脱して、成人した子どもとの関係を築こうとしない限り、両親が子どもの生き方にストレスをためる悪循環からは抜け出せないよ」と、両親を諭そうとした経験があります(もちろん人間そう簡単には変わりませんが…)。今回の私の件も、問題の根本は同じであると受け止め、(今後、彼の人生にもあれこれ影響が出てくるのは必至なので)、「他人事ではない」と味方についてくれました。まだ人生経験が浅い私には、親が遠距離にいるという事実が、将来的に、今は予想もつかないどんな事態を覚悟しておかねばならないのか、具体的なシミュレーションすらできていません。(せめて今後の参考に…と思い、ある方が書いた、「親と離れて暮らす長男長女のための本」を借りてきて、眺めたりしています。)親の不安と孤独を軽減するには、一にも二にも顔を見せることですね。夫の実家に子どもを預けて、和歌山市にどんどん帰省しようと思います。そういう面では、親戚など誰も頼る人のいない三重県S市在住の今よりも、ずっと帰省しやすくなるはずです。あとはお互いの気持ちの問題です。そう前向きに思うようにはしたいのですが…人は誰にも遠慮することなく、幸せをつかむ権利があり、そうした自己完結的な充足の中に、ある面では躊躇を感じる気質も持ち合わせていて、そこに人間の心の美しさがあるのかもしれない…そんなことを言っている人がいました。私はこれまで両親から受けた恩に限りない感謝を覚えていますし、折に触れてその感謝を形に表していきたいと思っています。が、今はそんな思いは看過ごされ、けんかばかり。「親棄て」の感情論のみ先行してしまっていることが残念です。我が家の親子関係再構築の闘いは、まだまだ続きそうです。でも性急さは何の解決も生み出しません。まずは悲観的にならず、感情的にならず、静かに思慮深く、自分の子どもにしっかり愛情注いで過ごしていくしかないと思います。そして、原因を親にばかりなすりつけるのではなく、これまで育ててもらった愛情に限りない感謝の気持ちを忘れずに、折々に言葉や態度で示しつつ、前進していかなければ…と思っています。理想の親子関係って何でしょうね?親孝行って何でしょうね?勝手なおしゃべりで失礼しました。誰かの助言ですぐに好転する問題ではないので、急ぎの回答など気にしないでください!こうして打ち明けることで、もう既にカウンセリング効果を得たようなものですから。(と、言っている間にも、状況はどんどん変わりつつあり、解決しているといいのですが…)ただ、私が最近思うことは、私の両親の意識改革も必要なのではないかということです。彼らの親戚も、数少ない友人もほとんどつきあいのない隣り近所も誰も、彼らのかたよった親意識にメスを入れることのできる人はいない状況です。先日は父の還暦祝いに…と、弟と二人でだしあって送った旅行券もうけとってもらえず、ふだんご無沙汰している弟が、母の日や父の日にひとことだけ電話をいれたときにも話したくなさそうに、さも、めんどくさそうに、短く応答してすぐブツリときられてしまったそうです。彼らはパソコン世代ではありません。親の心に染入るような書物を紹介する読書案内のダイレクトメールですとか、講演会のお知らせなどを、(私がしむけているなどとは決してわからないように)、ある日突然郵送で何度か、繰り返し送っていただくことはできませんでしょうか?そのハガキに目がとまるかどうかが、彼らが意識を改革できるかどうかの最後のきっかけであるような気がしてならないのです。そういうふうに、相手にかわってくれ!、と望んでいる私の姿勢も無駄なんですよね。はやしさんのHPにあった親離れの事例などは、うちよりもさらに深刻な実の母親のストーカーの話でしたから、最近の世の中には増えてきていることなのだろうと思いました。友達に相談しても、早くから親元はなれてそういう衝突したことのない人からみれば、まったくわからない話ですし、「あなたを今まで育ててくれたご両親に対する、そういう態度みてあきれた」と、去っていった友人もいました。また、あまり親しくない人たちのまえでは、実の親子なんですからもちろんうまくいっているかのようにとりつくろわなければならず、非常に疲れます。時間はかかるでしょうが、両親があきらめてくれるかもしれないきっかけとしては、いろいろやるべきことがあるようです。たとえば両親の家は、新築したばかりの家ですので、和歌山市に帰って年老いた両親のかわりに、家の掃除や手入れなどをひきうけること。私が仕事(検査助手)に復帰し、英検・通検などを取得すること。小さい頃から習い続けてきて途中で放棄されたままのピアノも、もういちど始めること(和歌山市の実家に置き去りになっているアップライトのピアノがある)。母の着物一式をゆずりうけるために気付など着物の知識をしっかり勉強すること。同じく母の花器をつかって玄関先に生けてもはずかしくないくらいのいけばなができるようになること。梅干やおせち料理、郷土料理など母から(TVや雑誌などでは学べない)母の味をしっかり受け継ぐこと…などなどが考えられます。東京で勤務し続ける弟とは、両親に何かあればひきとる考えでいることを話し合っています(実際にはかなり難しいでしょうが…)。弟も私が和歌山市に戻り、ここまでこじれても一言子どもの立場から折れて謝罪すれば、ずいぶん状況が違うだろうといってくれてはいるのですが、ほんとうに謝る気もないのにくちさきだけ謝ったとしても、いつかは親の枕もとに包丁をもって立っていた…なんてことにもなりかねません。謝ってしまうと親のねじまがった価値観を認めることになりそうでそれは絶対にできません。万一のときには実家に駆けつけるつもりですが、正直、今の気持ちとしては何があろうと親の顔も見たくありません。すみません。長くなりました。急ぎではありませんので、多くの事例をご覧になってきたはやしさんの立場から何かご意見がございましたら、いつかお時間に余裕ができましたときにお聞かせいただければと思いました。HPでは現在ご多忙中につき、相談おことわり…とありましたのに、それを承知でお便りしてしまいまして、勢いでまとまらない文章におつきあいくださいましてありがとうございました。暑さはこれからが本番です。どうぞお体ご自愛なさってお過ごしください。現在は東京都F市に住んでいます。 NEより+++++++++++++++++++++【静岡県S市・Yさんへ】 『悪魔は、それを笑ったものからは退散し、それを恐れたものには、重い十字架となって、容赦なく、襲いかかる』 親子の問題を、「悪魔」にたとえましたが、親子であるがゆえに、その関係も一度こじれると、「悪魔」にたとえてもおかしくないほど、問題は、深刻になりがちです。 実は、私も同じような問題をかかえています。しかもそれが、断続的ではあるにせよ、定期的にやってきては、私を苦しめます。 しかしそんなとき私は、ふと、こう思います。「笑ってやろうではないか」と。 笑えばよいのです。笑えば……。「バカめ!」と、です。すると、悪魔は向こうのほうから、シッポを巻いて退散していきます。それが、ときとして、「実感」として体感できるから、おもしろいです。とたん、心も軽くなります。 親に対して、「親だから……」という幻想は、捨てること。ただのジジイ、もしくは、ただのババアと思えばよいのです。私たちが幼少の子どもを本気で相手にしないように、老人など、本気で相手にしてはいけません。そのためにも、ここに書いたように、「親であるという幻想」を捨てることです。 親だから、人生の先輩のはず。 親だから、すばらしいはず。 親だから、子どものことを愛しているはず。 親だから、子どものことを心配しているはず。……みんな、幻想です。 もちろん中には、そういうすばらしい親もいますが、大半は、ただのジジイか、ババアです。最近聞いた話には、子どもを虐待し、子どもを精神病に追いこんでしまった親の例もあります。が、当の親には、その自覚がありません。「あの子は、生まれつき、ああだ」などと、平然としているそうです。 親もただの人間。私と同じ人間。そう気づいたとき、暗くて長いトンネルの向こうに、あなたも、一筋の光を見ることができるはずです。 で、あなたが感じているような苦しみを、心理学の世界でも、「幻惑」(=家族自我群という束縛があるゆえの、苦しみ)と呼んでいます。こうした独立した言葉があることからもわかるように、広く、たいへん多くの人たちが、あなたのかかえるような問題で苦しんでいます。 決して、あなた1人だけがそうであると思わないこと、ですね。がんばりましょう!Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(029)●グループホーム 兄の入った、グループホームを見舞う。 兄は、カーテンを閉めた暗い部屋の中で、 ひとり、こたつの中に入って、横になっていた。 それを見て、あわてて、同行した姉が、カーテンをあける。 「そのままでいいのに」と私は思ったが、 気がついたときには、カーテンは、もう開いていた。 横にベッド。こたつの上には、小さなラジカセが1つ。 それを見て、思わず、息をのむ。 財産らしきものと言えば、それだけ。それしかない。 人生を、68年も生きて、財産といえば、 たったそれだけ? 兄の人生は、いったい、 何だったのか。 場ちがいに明るいヘルパーの声、そして姉の声。 私は、黙ったまま、清潔そうな、それでいて 人間的な温もりの感じない部屋を、みやる。 事情を知らない私の長男は、「いい部屋だね」 「ぼくも、こんなところに住みたいな」などと、 無責任なことを口にする。 それを聞きながら、「明日は我が身か」と、ふと、 心のどこかで思う。そしてそれがそのまま、 私の心を重く、ふさぐ。 かといって、どうすることもできない。 虚脱感。そして無力感。むなしさ。さみしさ。 何度も心の中で、「ごめんな」と、兄にあやまる。 元気で生きている人は、みな、傲慢になりやすい。 「自分だけは、だいじょうぶ」と思いやすい。 そして自分の人生だけは、安全に、いつまでもつづくと思いやすい。 そして年老いて、不健康になった人を、 そのまま自分の世界から、遠ざけてしまう。 「私とは関係ない」と切り捨ててしまう。 しかし、例外はない。1人とて、例外は、ない。 だれにでも、老いは平等にやってくる。 そして自分が、反対に、その老いの立場に立たされるときが、やってくる。 私を、うらめしそうに見つめる、兄の目。 しかしその目は、10年後、20年後の、私の目。 その兄が、別れ際、私にポツリと、こう言った。 「うちへ帰りたい……」と。 子どものような言い方だった。 私は、だまったまま、何も答えることができなかった。そしてそのまま、そのまま長い廊下を静かに歩いて、外に出た。 外には、冬の明るい、澄んだ空が、まばゆいばかりに光っていた。 それが私には、かえって、異様に見えた。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(18)
+++++++++++++++++++++ EQ(Emotional Intelligence Quotient)は、アメリカのイエール大学心理学部教授。ピーター・サロヴェイ博士と、ニューハンプシャー大学心理学部教授ジョン・メイヤー博士によって理論化された概念で、日本では「情動(こころ)の知能指数」と訳されている(Emotional Education、by JESDA Websiteより転写。)++++++++++++++++++++●EQ論 ついでながら、EQ論について以前、書いた原稿を添付しておく。 ピーター・サロヴェイ(アメリカ・イエール大学心理学部教授)の説く、「EQ(Emotional Intelligence Quotient)」、つまり、「情動の知能指数」では、主に、つぎの3点を重視する。(1)自己管理能力(2)良好な対人関係(3)他者との良好な共感性 ここではP・サロヴェイのEQ論を、少し発展させて考えてみたい。 自己管理能力には、行動面の管理能力、精神面の管理能力、そして感情面の管理能力が含まれる。●行動面の管理能力 行動も、精神によって左右されるというのであれば、行動面の管理能力は、精神面の管理能力ということになる。が、精神面だけの管理能力だけでは、行動面の管理能力は、果たせない。 たとえば、「銀行強盗でもして、大金を手に入れてみたい」と思うことと、実際、それを行動に移すことの間には、大きな距離がある。実際、仲間と組んで、強盗をする段階になっても、その時点で、これまた迷うかもしれない。 精神的な決断イコール、行動というわけではない。たとえば行動面の管理能力が崩壊した例としては、自傷行為がある。突然、高いところから、発作的に飛びおりるなど。その人の生死にかかわる問題でありながら、そのコントロールができなくなってしまう。広く、自殺行為も、それに含まれるかもしれない。 もう少し日常的な例として、寒い夜、ジョッギングに出かけるという場面を考えてみよう。そういうときというのは、「寒いからいやだ」という抵抗感と、「健康のためにはしたほうがよい」という、二つの思いが、心の中で、真正面から対立する。ジョッギングに行くにしても、「いやだ」という思いと戦わねばならない。 さらに反対に、悪の道から、自分を遠ざけるというのも、これに含まれる。タバコをすすめられて、そのままタバコを吸い始める子どもと、そうでない子どもがいる。悪の道に染まりやすい子どもは、それだけ行動の管理能力の弱い子どもとみる。 こうして考えてみると、私たちの行動は、いつも(すべきこと・してはいけないこと)という、行動面の管理能力によって、管理されているのがわかる。それがしっかりとできるかどうかで、その人の人格の完成度を知ることができる。 この点について、フロイトも着目し、行動面の管理能力の高い人を、「超自我の人」、「自我の人」、そうでない人を、「エスの人」と呼んでいる。●精神面の管理能力 私には、いくつかの恐怖症がある。閉所恐怖症、高所恐怖症にはじまって、スピード恐怖症、飛行機恐怖症など。 精神的な欠陥もある。 私のばあい、いくつか問題が重なって起きたりすると、その大小、軽重が、正確に判断できなくなってしまう。それは書庫で、同時に、いくつかのものをさがすときの心理状態に似ている。(私は、子どものころから、さがじものが苦手。かんしゃく発作のある子どもだったかもしれない。) 具体的には、パニック状態になってしまう。 こうした精神作用が、いつも私を取り巻いていて、そのつど、私の精神状態に影響を与える。 そこで大切なことは、いつもそういう自分の精神状態を客観的に把握して、自分自身をコントロールしていくということ。 たとえば乱暴な運転をするタクシーに乗ったとする。私は、スピード恐怖症だから、そういうとき、座席に深く頭を沈め、深呼吸を繰りかえす。スピードがこわいというより、そんなわけで、そういうタクシーに乗ると、神経をすり減らす。ときには、タクシーをおりたとたん、ヘナヘナと地面にすわりこんでしまうこともある。 そういうとき、私は、精神のコントロールのむずかしさを、あらためて、思い知らされる。「わかっているけど、どうにもならない」という状態か。つまりこの点については、私の人格の完成度は、低いということになる。●感情面の管理能力 「つい、カーッとなってしまって……」と言う人は、それだけ感情面の管理能力の低い人ということになる。 この感情面の管理能力で問題になるのは、その管理能力というよりは、その能力がないことにより、良好な人間関係が結べなくなってしまうということ。私の知りあいの中にも、ふだんは、快活で明るいのだが、ちょっとしたことで、激怒して、怒鳴り散らす人がいる。 つきあう側としては、そういう人は、不安でならない。だから結果として、遠ざかる。その人はいつも、私に電話をかけてきて、「遊びにこい」と言う。しかし、私としては、どうしても足が遠のいてしまう。 しかし人間は、まさに感情の動物。そのつど、喜怒哀楽の情を表現しながら、無数のドラマをつくっていく。感情を否定してはいけない。問題は、その感情を、どう管理するかである。 私のばあい、私のワイフと比較しても、そのつど、感情に流されやすい人間である。(ワイフは、感情的には、きわめて完成度の高い女性である。結婚してから30年近くになるが、感情的に混乱状態になって、ワーワーと泣きわめく姿を見たことがない。大声を出して、相手を罵倒したのを、見たことがない。) 一方、私は、いつも、大声を出して、何やら騒いでいる。「つい、カーッとなってしまって……」ということが、よくある。つまり感情の管理能力が、低い。 が、こうした欠陥は、簡単には、なおらない。自分でもなおそうと思ったことはあるが、結局は、だめだった。 で、つぎに私がしたことは、そういう欠陥が私にはあると認めたこと。認めた上で、そのつど、自分の感情と戦うようにしたこと。そういう点では、ものをこうして書くというのは。とてもよいことだと思う。書きながら、自分を冷静に見つめることができる。 また感情的になったときは、その場では、判断するのを、ひかえる。たいていは黙って、その場をやり過ごす。「今のぼくは、本当のぼくではないぞ」と、である。(2)の「良好な対人関係」と、(3)の「他者との良好な共感性」については、また別の機会に考えてみたい。●終わりに…… 子どもたちを取り巻く環境は、現在、急速に変化している。恐ろしいほどの勢いである。しかも、こうした変化は、社会の水面下で起きている。毎日、多くの子どもたちと接している私ですら、気がつかないことが多い。 そうした変化の中でも、最大のものはといえば、言うまでもなく、ゲームであり、テレビゲームである。こうした変化が、子どもたちの心にどのような変化をおよぼしつつあるか。 そこで文部科学省は、ゲームやテレビなどを含む生活環境要因が子どもの脳にどう影響を与えるかを研究するために、2005年度から1万人の乳幼児について、10年間長期追跡調査することを決めた。この中で、ゲームの影響も調べられるという(「脳科学と教育」研究に関する検討会の答申)。 近く中間報告が、公表されるだろう。が、しかしここで誤解してはいけないのは、「ゲームは危険でないから、子どもにやらせろ」ということではない。「ゲームは、危険かもしれないから、やらせないほうがよい」と、考えるのが正しい。とくに動きのはげしい、反射運動型のゲームは、避けたほうがよい。 具体的には、私は、つぎのような方法を提唱する。(1)ゲーム機器の所有権、占有権は、親に! もともと高額なゲーム機器である。そうした機器を安易に子どもに与えること自体にも、問題がある。されはさておき、ゲーム機器、およびそのソフロ類の所有権、占有権は、一義的には、親にあるとする。またそういう前提で、考える。 だから子どもがゲームをしたいときは、子どもは、親から貸してもらう。そういう立場を、徹底する。子どもの立場からすれば、自由にゲームをできないということになるが、そういう形で、親は、子どものゲームに干渉することができる。 (ゲーム機器メーカーには、ゲーム機器に、カギのようなものでロックできないかと、提案している。こうすれば、親の許可があったときだけ、子どもはゲームをすることができる。)(2)反射神経運動型のゲームは避ける テレビゲームといっても、いろいろある。将棋や囲碁のような、オーソドックスなものから、戦争ゲームのようなものまで。その中には、都市形成ゲームや、鉄道敷設ゲームのようなものもある。 一方、アメリカでさえ発売禁止になったような、意味のない殺戮(さつりく)ゲームが、この日本では、野放しになっているというケースもある。こうしたゲームが子どもの精神の発育によくないことは、言うまでもない。 で、あえて言えば、こうしたゲームのほか、動きがきわめて速い、反射神経運動型のゲームは、子どもには、避けたほうがよい。私もときどき、ショッピングセンターなどで、体験をさせてもらうが、あまりの速さに目が回る……というよりは、しばらくしていると、気がヘンにすらなる。 そういうゲームを、3~6歳の子どもたちが、一心不乱に画面を見つめながらしている……。この異常さに、まず、おとなの私たちが、気がつくべきである。 忘れてならないのは、97年に起きた「ポケモンパニック事件」である。●ポケモンパニック事件 劇場で映画を見るとどうなるかを、子どもたち(小学4~6年生)に聞いてみた。 見ると、たいてい頭が痛くなる……1人 見ると、ときどき痛くなる ……2人 ほぼ何ともない ……2人(そのときの体の調子によるとのこと) 何ともない ……4人 眠くなったりする ……1人 この質問をした背景に、私自身は、「いつも痛くなる」ということがある。先日もデパートで、子どもたちがテレビゲーム(「スーパーマリオ・サンシャイン」)をしているのを、横で見ていたが、それだけで、私は頭が痛くなってしまった。どういうメカニズムによるのかはわからないが、日常的でない刺激が、脳にダメージを与えるらしい。年齢的な問題もある。最近では家庭でビデオを見ていても、頭痛が起きることがある。いや、子どもだって無難ではない。この調査でもわかるように、10人中、3人までが、「痛くなる」「ときどき痛くなる」と答えている。 ここでいう「日常的でない刺激」というのは、はげしい光の点滅による刺激をいう。その刺激が脳にある種の緊張感をつくり、その緊張感が頭痛を起こすということは、容易に察しがつく。よい例が、97年に起きた「ポケモンパニック事件」である。その年の12月16日、テレビ東京系列のポケモンを見ていた子どもが、光過敏性てんかんという、わけのわからない症状を示して倒れた。はげしいけいれんと、嘔吐。その日の午後11時までにNHKが確認したところ、埼玉県下だけでも、59人。全国で382人。さらに翌々日の18日までには、その数は全国で、0歳児から58歳の人まで、750人にもなった。気分が悪くなったという被害者まで含めると、全国で1万人以上! 大阪では発作を起こして、呼吸障害になった上、意識不明の重症におちいった5歳の子ども(女児)もいた。「酸素不足により脳障害の後遺症が残るかもしれない」(大阪府立病院)と。たかが映画ではないかと、軽く片づけることはできない。 が、問題はここで終わらない。こうした刺激が、子どもから、「論理的にものを考える力」をうばう危険性すらある。今、授業中、イメージが乱舞してしまい、静かな指導になじまない子どもが急増している。これはあくまでも私の推察だが、その理由の一つに、ここでいう「日常的でない刺激」があるのでは……? 法律の世界には、「疑わしきは罰せず」という不文律がある。しかし子どもの世界では、「疑わしきは、先手先手で、どんどん罰する」。それが原則である。(はやし浩司 テレビゲーム ゲーム ポケモンパニック事件)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(17)
+++++++++++++++++++++ EQ(Emotional Intelligence Quotient)は、アメリカのイエール大学心理学部教授。ピーター・サロヴェイ博士と、ニューハンプシャー大学心理学部教授ジョン・メイヤー博士によって理論化された概念で、日本では「情動(こころ)の知能指数」と訳されている(Emotional Education、by JESDA Websiteより転写。)++++++++++++++++++++●EQ論 ついでながら、EQ論について以前、書いた原稿を添付しておく。 ピーター・サロヴェイ(アメリカ・イエール大学心理学部教授)の説く、「EQ(Emotional Intelligence Quotient)」、つまり、「情動の知能指数」では、主に、つぎの3点を重視する。(1)自己管理能力(2)良好な対人関係(3)他者との良好な共感性 ここではP・サロヴェイのEQ論を、少し発展させて考えてみたい。 自己管理能力には、行動面の管理能力、精神面の管理能力、そして感情面の管理能力が含まれる。●行動面の管理能力 行動も、精神によって左右されるというのであれば、行動面の管理能力は、精神面の管理能力ということになる。が、精神面だけの管理能力だけでは、行動面の管理能力は、果たせない。 たとえば、「銀行強盗でもして、大金を手に入れてみたい」と思うことと、実際、それを行動に移すことの間には、大きな距離がある。実際、仲間と組んで、強盗をする段階になっても、その時点で、これまた迷うかもしれない。 精神的な決断イコール、行動というわけではない。たとえば行動面の管理能力が崩壊した例としては、自傷行為がある。突然、高いところから、発作的に飛びおりるなど。その人の生死にかかわる問題でありながら、そのコントロールができなくなってしまう。広く、自殺行為も、それに含まれるかもしれない。 もう少し日常的な例として、寒い夜、ジョッギングに出かけるという場面を考えてみよう。そういうときというのは、「寒いからいやだ」という抵抗感と、「健康のためにはしたほうがよい」という、二つの思いが、心の中で、真正面から対立する。ジョッギングに行くにしても、「いやだ」という思いと戦わねばならない。 さらに反対に、悪の道から、自分を遠ざけるというのも、これに含まれる。タバコをすすめられて、そのままタバコを吸い始める子どもと、そうでない子どもがいる。悪の道に染まりやすい子どもは、それだけ行動の管理能力の弱い子どもとみる。 こうして考えてみると、私たちの行動は、いつも(すべきこと・してはいけないこと)という、行動面の管理能力によって、管理されているのがわかる。それがしっかりとできるかどうかで、その人の人格の完成度を知ることができる。 この点について、フロイトも着目し、行動面の管理能力の高い人を、「超自我の人」、「自我の人」、そうでない人を、「エスの人」と呼んでいる。●精神面の管理能力 私には、いくつかの恐怖症がある。閉所恐怖症、高所恐怖症にはじまって、スピード恐怖症、飛行機恐怖症など。 精神的な欠陥もある。 私のばあい、いくつか問題が重なって起きたりすると、その大小、軽重が、正確に判断できなくなってしまう。それは書庫で、同時に、いくつかのものをさがすときの心理状態に似ている。(私は、子どものころから、さがじものが苦手。かんしゃく発作のある子どもだったかもしれない。) 具体的には、パニック状態になってしまう。 こうした精神作用が、いつも私を取り巻いていて、そのつど、私の精神状態に影響を与える。 そこで大切なことは、いつもそういう自分の精神状態を客観的に把握して、自分自身をコントロールしていくということ。 たとえば乱暴な運転をするタクシーに乗ったとする。私は、スピード恐怖症だから、そういうとき、座席に深く頭を沈め、深呼吸を繰りかえす。スピードがこわいというより、そんなわけで、そういうタクシーに乗ると、神経をすり減らす。ときには、タクシーをおりたとたん、ヘナヘナと地面にすわりこんでしまうこともある。 そういうとき、私は、精神のコントロールのむずかしさを、あらためて、思い知らされる。「わかっているけど、どうにもならない」という状態か。つまりこの点については、私の人格の完成度は、低いということになる。●感情面の管理能力 「つい、カーッとなってしまって……」と言う人は、それだけ感情面の管理能力の低い人ということになる。 この感情面の管理能力で問題になるのは、その管理能力というよりは、その能力がないことにより、良好な人間関係が結べなくなってしまうということ。私の知りあいの中にも、ふだんは、快活で明るいのだが、ちょっとしたことで、激怒して、怒鳴り散らす人がいる。 つきあう側としては、そういう人は、不安でならない。だから結果として、遠ざかる。その人はいつも、私に電話をかけてきて、「遊びにこい」と言う。しかし、私としては、どうしても足が遠のいてしまう。 しかし人間は、まさに感情の動物。そのつど、喜怒哀楽の情を表現しながら、無数のドラマをつくっていく。感情を否定してはいけない。問題は、その感情を、どう管理するかである。 私のばあい、私のワイフと比較しても、そのつど、感情に流されやすい人間である。(ワイフは、感情的には、きわめて完成度の高い女性である。結婚してから30年近くになるが、感情的に混乱状態になって、ワーワーと泣きわめく姿を見たことがない。大声を出して、相手を罵倒したのを、見たことがない。) 一方、私は、いつも、大声を出して、何やら騒いでいる。「つい、カーッとなってしまって……」ということが、よくある。つまり感情の管理能力が、低い。 が、こうした欠陥は、簡単には、なおらない。自分でもなおそうと思ったことはあるが、結局は、だめだった。 で、つぎに私がしたことは、そういう欠陥が私にはあると認めたこと。認めた上で、そのつど、自分の感情と戦うようにしたこと。そういう点では、ものをこうして書くというのは。とてもよいことだと思う。書きながら、自分を冷静に見つめることができる。 また感情的になったときは、その場では、判断するのを、ひかえる。たいていは黙って、その場をやり過ごす。「今のぼくは、本当のぼくではないぞ」と、である。(2)の「良好な対人関係」と、(3)の「他者との良好な共感性」については、また別の機会に考えてみたい。●終わりに…… 子どもたちを取り巻く環境は、現在、急速に変化している。恐ろしいほどの勢いである。しかも、こうした変化は、社会の水面下で起きている。毎日、多くの子どもたちと接している私ですら、気がつかないことが多い。 そうした変化の中でも、最大のものはといえば、言うまでもなく、ゲームであり、テレビゲームである。こうした変化が、子どもたちの心にどのような変化をおよぼしつつあるか。 そこで文部科学省は、ゲームやテレビなどを含む生活環境要因が子どもの脳にどう影響を与えるかを研究するために、2005年度から1万人の乳幼児について、10年間長期追跡調査することを決めた。この中で、ゲームの影響も調べられるという(「脳科学と教育」研究に関する検討会の答申)。 近く中間報告が、公表されるだろう。が、しかしここで誤解してはいけないのは、「ゲームは危険でないから、子どもにやらせろ」ということではない。「ゲームは、危険かもしれないから、やらせないほうがよい」と、考えるのが正しい。とくに動きのはげしい、反射運動型のゲームは、避けたほうがよい。 具体的には、私は、つぎのような方法を提唱する。(1)ゲーム機器の所有権、占有権は、親に! もともと高額なゲーム機器である。そうした機器を安易に子どもに与えること自体にも、問題がある。されはさておき、ゲーム機器、およびそのソフロ類の所有権、占有権は、一義的には、親にあるとする。またそういう前提で、考える。 だから子どもがゲームをしたいときは、子どもは、親から貸してもらう。そういう立場を、徹底する。子どもの立場からすれば、自由にゲームをできないということになるが、そういう形で、親は、子どものゲームに干渉することができる。 (ゲーム機器メーカーには、ゲーム機器に、カギのようなものでロックできないかと、提案している。こうすれば、親の許可があったときだけ、子どもはゲームをすることができる。)(2)反射神経運動型のゲームは避ける テレビゲームといっても、いろいろある。将棋や囲碁のような、オーソドックスなものから、戦争ゲームのようなものまで。その中には、都市形成ゲームや、鉄道敷設ゲームのようなものもある。 一方、アメリカでさえ発売禁止になったような、意味のない殺戮(さつりく)ゲームが、この日本では、野放しになっているというケースもある。こうしたゲームが子どもの精神の発育によくないことは、言うまでもない。 で、あえて言えば、こうしたゲームのほか、動きがきわめて速い、反射神経運動型のゲームは、子どもには、避けたほうがよい。私もときどき、ショッピングセンターなどで、体験をさせてもらうが、あまりの速さに目が回る……というよりは、しばらくしていると、気がヘンにすらなる。 そういうゲームを、3~6歳の子どもたちが、一心不乱に画面を見つめながらしている……。この異常さに、まず、おとなの私たちが、気がつくべきである。 忘れてならないのは、97年に起きた「ポケモンパニック事件」である。●ポケモンパニック事件 劇場で映画を見るとどうなるかを、子どもたち(小学4~6年生)に聞いてみた。 見ると、たいてい頭が痛くなる……1人 見ると、ときどき痛くなる ……2人 ほぼ何ともない ……2人(そのときの体の調子によるとのこと) 何ともない ……4人 眠くなったりする ……1人 この質問をした背景に、私自身は、「いつも痛くなる」ということがある。先日もデパートで、子どもたちがテレビゲーム(「スーパーマリオ・サンシャイン」)をしているのを、横で見ていたが、それだけで、私は頭が痛くなってしまった。どういうメカニズムによるのかはわからないが、日常的でない刺激が、脳にダメージを与えるらしい。年齢的な問題もある。最近では家庭でビデオを見ていても、頭痛が起きることがある。いや、子どもだって無難ではない。この調査でもわかるように、10人中、3人までが、「痛くなる」「ときどき痛くなる」と答えている。 ここでいう「日常的でない刺激」というのは、はげしい光の点滅による刺激をいう。その刺激が脳にある種の緊張感をつくり、その緊張感が頭痛を起こすということは、容易に察しがつく。よい例が、97年に起きた「ポケモンパニック事件」である。その年の12月16日、テレビ東京系列のポケモンを見ていた子どもが、光過敏性てんかんという、わけのわからない症状を示して倒れた。はげしいけいれんと、嘔吐。その日の午後11時までにNHKが確認したところ、埼玉県下だけでも、59人。全国で382人。さらに翌々日の18日までには、その数は全国で、0歳児から58歳の人まで、750人にもなった。気分が悪くなったという被害者まで含めると、全国で1万人以上! 大阪では発作を起こして、呼吸障害になった上、意識不明の重症におちいった5歳の子ども(女児)もいた。「酸素不足により脳障害の後遺症が残るかもしれない」(大阪府立病院)と。たかが映画ではないかと、軽く片づけることはできない。 が、問題はここで終わらない。こうした刺激が、子どもから、「論理的にものを考える力」をうばう危険性すらある。今、授業中、イメージが乱舞してしまい、静かな指導になじまない子どもが急増している。これはあくまでも私の推察だが、その理由の一つに、ここでいう「日常的でない刺激」があるのでは……? 法律の世界には、「疑わしきは罰せず」という不文律がある。しかし子どもの世界では、「疑わしきは、先手先手で、どんどん罰する」。それが原則である。(はやし浩司 テレビゲーム ゲーム ポケモンパニック事件)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(16)
●男女共同参画社会(男女の平等社会)+++++++++++++女は家庭を守るべし(?)+++++++++++++ いきなり「ぼくは、男女共同参画社会などには、反対だよ」と言った男性(60歳くらい)がいた。公的な機関で、長い間、「長」の仕事を歴任してきた人物である。 「いいかね、林君、女が男のようになって、どうする? どうなる? 女が家庭から抜けたら、家庭はバラバラになってしまうよ。女は、家庭を守らなければならない。それが女の役目だよ」と。話のきっかけは、NHKの今度の、大河ドラマだった。 土佐藩の基礎を築いた戦国武将に、山内一豊がいた。その夫を支え、夫の出世をなしとげたのが、妻の千代。その千代の物語が、今度の大河ドラマのテーマになっている。『内助の功』という言葉も、そこから生まれた。その男性は、その千代を懸命にたたえながら、「女はそうでなくてはいけないよ、林君」と。 私は、「ハア~」と思っただけで、つぎの言葉が出てこなかった。その男性との間に、遠い距離を感じた。どこからどう説明したらよいのかさえ、皆目、見当もつかなかった。 つぎに、その男性は、それなりの人物である。私の思想が私の思想であるように、その男性の思想もまた、その男性の思想である。その上、この話は、相手がもち出した話題である。一応の敬意は、払わなければならない。いきなり反論するというのも、その男性に対して、失敬なこと。 そこで私は、こんなことをさぐってみた。 その男性が、どうしてそういう思想をもったかという、その背景である。つまり思想には、必ず、それをもつに至った背景というものがある。生まれ育った環境や、教育など。しかし何よりも重要なのは、その男性が、どの程度の問題意識をもっているかということ。どんな本を読み、どの程度の文章を書き、自分の思想を思想として、まとめあげたかということ。 方法は簡単。いくつかの専門用語を、ぶつけてみればよい。勉強している人は、それなりに、即座に反応してくる。そうでない人は、そうでない。私「ジェンダー(社会的性差別)の問題は、世界的な問題だよ」男「それは知っているが、いくらがんばっても、女は男にはなれないよ、君!」私「最近の研究によれば、男にも、女にも、両性性があることがわかってきた」男「何だね、その両性性って、いうのは?」私「男が男らしくなるのも、女が女らしくなるのも、3歳までの育て方の問題ということ。もともと男と女を区別するほうが、おかしいということかな」男「男は、子どもを産むことができない。大きなちがいだよ、これは!」と。 そこでこんな例を出して、説明してやった。 あるところに1人の女の子(?)がいた。5歳くらいまで、女の子として育てられた。その女の子は、外性器も女の子のもので、見た感じも女の子だった。しかし6歳を過ぎるころから、卵巣がないことがわかってきた。 そこで調べてみると、腹の中に、睾丸があることがわかった。その女の子(?)は、実は男の子だった。この女の子(?)のケースは、さらに、染色体レベルまで調べられて、最終的には、男の子と確定されたが、しかしそれで問題が解決したわけではなかった。 ここにも書いたように、男の子が男の子らしくなる、女の子が女の子らしくなるというのは、3歳ごろまでに決まる。これを心理学の世界でも、「役割形成」と呼ぶ。しかしその女の子(?)のばあいは、6歳前後まで、女の子として育てられた。が、そこで、男の子と判定された。 その女の子にすれば、「私はどうすればいいのか?」ということになる。 やはり心理学の世界では、こうした混乱を、「役割混乱」と呼んでいる。たとえて言うなら、トラックの運転手に、いきなり、リカちゃん人形のコスチュームを着せるようなもの。ばあいによっては、自己嫌悪から自己否定につながるかもしれない。精神は、極度の緊張状態に置かれる。 「わかりました。では、私は、今日から、男の子になります」というわけには、いかない。 つまり私たちがもっている「男意識」「女意識」といったものは、その延長線上にあるにすぎない。もっと言えば、「ジェンダー」なるものは、生まれたあと、生まれ育った環境の中で、作りあげられたものにすぎない。つまりそういったもので、そもそも、人間を、「男」と「女」に区別するほうが、おかしい。まちがっている。 ついでだが、私が子どものころには、こんな話も残っていた。 江戸時代という封建時代が終わって150年もたっていたというのに、身分に応じて、着る服の色が、ある程度決まっていたということ。商人は、茶系統、農家の人は、青系統……というように(この部分は、不確か)。今でも、その傾向がないとは言わない。しかし江戸時代には、着物の色はもちろん、模様のあるなしまで、さらに厳格に決められていた。 だから子どもながらに、その人の物腰、話し方によって、私は、その人の職業が何であるか、だいたいのことはわかった。つまりこうした「その人の様子」にしても、その人が生まれ育った環境の中で、つくりあげられたものということになる。 さて、現在、男女の両性化は、ますます進んでいる。男が女性化し、女が男性化するというよりは、ともに、その両性性に、気づき始めている。今では、使う言葉にしても、男女の区別はない。意識や価値観にしても、男女の区別はない。「男だから……」「女だから……」と言うほうが、おかしい。 しかし現実には、冒頭にあげたような男性のような考え方をしている人は、決して、少なくない。そういう環境で生まれ育っているから、そういった意識は、心の奥底に、しっかりと根づいている。加えて、そういう意識を、疑ってみたこともない。もちろん、それなりの勉強もしていない。言うなれば、思想が、サビついたまま硬直化してしまっている。 だから、議論してもムダ!私「まあ、そうは言っても、今は、そういう時代でもないように思いますがね」男「だから、今の時代は、おかしいのだよ。教育がまちがっている」私「しかしつぎの時代を決めるのは、私たちではありませんから。こういう問題は、若い人たちに任すしかないでしょう」男「いやな時代になったものだよ。若い人は、もっと、NHKの大河ドラマでも見て、勉強したらいい」と。(はやし浩司 ジェンダー 男女論 男女の両性化 両性性 意識 はやし浩司 山内一豊 千代 内助の功 内助の功論)+++++++++++++++++++数年前書いた原稿を添付します。(中日新聞、発表済み)+++++++++++++++++++子どもに性教育を語るとき●性の解放とは偏見からの解放 若いころ、いろいろな人の通訳として、全国を回った。その中でもとくに印象に残っているのが、ベッテルグレン女史という女性だった。スウェーデン性教育協会の会長をしていた。そのベッテルグレン女史はこう言った。「フリーセックスとは、自由にセックスをすることではない。フリーセックスとは、性にまつわる偏見や誤解、差別から、男女を解放することだ」「とくに女性であるからという理由だけで、不利益を受けてはならない」と。それからほぼ30年。日本もやっとベッテルグレン女史が言ったことを理解できる国になった。 話は変わるが、先日、女房の友人(48歳)が私の家に来て、こう言った。「うちのダンナなんか、冷蔵庫から牛乳を出して飲んでも、その牛乳をまた冷蔵庫にしまうことすらしないんだわサ。だから牛乳なんて、すぐ腐ってしまうんだわサ」と。話を聞くと、そのダンナ様は結婚してこのかた、トイレ掃除はおろか、トイレットペーパーすら取り替えたことがないという。私が、「ペーパーがないときはどうするのですか?」と聞くと、「何でも『オーイ』で、すんでしまうわサ」と。●家事をしない男たち 国立社会保障人口問題研究所の調査によると、「家事は全然しない」という夫が、まだ50%以上もいるという(2000年)(※)。年代別の調査ではないのでわからないが、50歳以上の男性について言うなら、何か特別な事情のある人を除いて、そのほとんどが家事をしていないとみてよい。この年代の男性は、いまだに「男は仕事、女は家事」という偏見を根強くもっている。男ばかりではない。私も子どものころ台所に立っただけで、よく母から、「男はこんなところへ来るもんじゃない」と叱られた。こうしたものの考え方は今でも残っていて、女性自らが、こうした偏見に手を貸している。「夫が家事をすることには反対」という女性が、23%もいるという(同調査)! が、その偏見も今、急速に音をたてて崩れ始めている。私が99年に浜松市内でした調査では、20代、30代の若い夫婦についてみれば、「家事をよく手伝う」「ときどき手伝う」という夫が、65%にまでふえている。欧米並みになるのは、時間の問題と言ってもよい。●男も昔はみんな、女だった? 実は私も、先に述べたような環境で育ったため、生まれながらにして、「男は……、女は……」というものの考え方を日常的にしていた。高校を卒業するまで洗濯や料理など、したことがない。たとえば私が小学生のころは、男が女と一緒に遊ぶことすら考えられなかった。遊べば遊んだで、「女たらし」とバカにされた。そのせいか私の記憶の中にも、女の子と遊んだ思い出がまったく、ない。が、その後、いろいろな経験を通して、私がまちがっていたことを思い知らされた。その中でも決定的に私を変えたのは、次のような事実を知ったときだ。つまり人間は男も女も、母親の胎内では一度、皆、女だったという事実だ。このことは何人ものドクターに確かめたが、どのドクターも、「知らなかったのですか?」と笑った。正確には、「妊娠後3か月くらいまでは胎児は皆、女で、それ以後、Y遺伝子をもった胎児は、Y遺伝子の刺激を受けて、睾丸が形成され、女から分化する形で男になっていく。分化しなければ、胎児はそのまま成長し、女として生まれる」(浜松医科大学O氏)ということらしい。このことを女房に話すと、女房は「あなたは単純ね」と笑ったが、以後、女性を見る目が、180度変わった。「ああ、ぼくも昔は女だったのだ」と。と同時に、偏見も誤解も消えた。言いかえると、「男だから」「女だから」という考え方そのものが、まちがっている。「男らしく」「女らしく」という考え方も、まちがっている。ベッテルグレン女史は、それを言った。※……国立社会保障人口問題研究所の調査によると、「掃除、洗濯、炊事の家事をまったくしない」と答えた夫は、いずれも50%以上であったという。 部屋の掃除をまったくしない夫 ……56・0% 洗濯をまったくしない夫 ……61・2% 炊事をまったくしない夫 ……53・5% 育児で子どもの食事の世話をまったくしない夫 ……30・2% 育児で子どもを寝かしつけない夫(まったくしない)……39・3% 育児で子どものおむつがえをまったくしない夫 ……34・0% (全国の配偶者のいる女性約1万4000人について調査・98年)●平等には反対? これに対して、「夫も家事や育児を平等に負担すべきだ」と答えた女性は、76・7%いるが、その反面、「反対だ」と答えた女性も23・3%もいる。男性側の意識改革だけではなく、女性側の意識改革も必要なようだ。ちなみに「結婚後、夫は外で働き、妻は主婦業に専念すべきだ」と答えた女性は、半数以上の52・3%もいる(同調査)。 こうした現状の中、夫に不満をもつ妻もふえている。厚生省の国立問題研究所が発表した「第二回、全国家庭動向調査」(1998年)によると、「家事、育児で夫に満足している」と答えた妻は、51・7%しかいない。この数値は、前回1993年のときよりも、約10ポイントも低くなっている(93年度は、60・6%)。「(夫の家事や育児を)もともと期待していない」と答えた妻も、52・5%もいた。(はやし浩司 男の家事 夫の家事 性教育 性の解放 男女意識 はやし浩司)Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(030)【子どもとゲーム】子どもがゲームづけになるとき●ゲームづけの子どもたち 小学生の低学年は、「遊戯王」。高学年から中学生は、「マジック・ザ・ギャザリング(通称、マジギャザ)」。遊戯王について言えば、小学3年生で、約25%以上の男児がハマっている(2000年11月、小3児53名中13名、浜松市内)。ある日、一人の子ども(小3男児)が、こう教えてくれた。「ブルーアイズを3枚集めて、融合させる。融合させるためには、融合カードを使う。そうすればアルティメットドラゴンをフィールドに出せる。それに巨大化をつけると、攻撃力が9000になる」と。子どもの言ったことをそのままここに書いたが、さっぱり意味がわからない。カードゲームというのは、基本的にはカードどうしを戦わせるゲームだと思えばよい。戦いは、勝ったほうが相手のカードを取る「カケ勝負」と、取らない「カケなし勝負」とがある。カードは、一パック5枚入りで、150円から330円程度。「アルティメット入りのパックは、値段が高い」そうだ。●ポケモンからマジギャザまで あのポケモン世代が、小学校の高学年から中学1、2年になった。そこで当時ハマった子どもたち何人かに、「その後」を聞くと、いろいろ話してくれた。M君(中2)いわく、「今はマジギャザだ。少し前までは、遊戯王だったけどね」と。カード(15枚で500円。デパートやおもちゃ屋で販売。遊戯王は、5枚で200円)は、1000枚近く集めたそうだ。マジギャザというのは、基本的にはポケモンカードと同じような遊び方をするゲームのことだと思えばよい。ただ内容は高度になっている。私も一時間ほど教えてもらったが、正直言ってよくわからない。要するに、ポケモンカードから遊戯王、さらにその遊戯王からマジギャザへと、子どもたちの遊びが移っているということ。カードを戦わせながら遊ぶという点では、共通している。●現実感を喪失する子どもたち 話はそれるが、以前、「たまごっち」というゲームが全盛期のころのこと。あのわけのわからない生き物が死んだだけで大泣きする子どもはいくらでもいた。東京には、死んだたまごっちを供養する寺まで現れた。ウソや冗談でしているのではない。本気だ。中には北海道からやってきて、涙をこぼしながら供養している、20歳代の女性までいた(NHK「電脳の果て」97年12月28日放送)。そういうゲームにハマっている子どもに向かって、「これは生き物ではない。ただの電気の信号だ」と話しても、彼らには理解できない。が、たかがゲームと笑ってはいけない。その少しあと、ミイラ化した死体を、「生きている」とがんばったカルト教団が現れた。この教団の教祖はその後逮捕され、今も裁判は継続中だが(2000年当時)、もともと生きていない「電子の生物」を死んだと思い込む子どもと、「ミイラ化した死体」を生きていると思い込むその教団の信者は、どこがどうちがうのか。方向性こそ逆だが、その思考回路は同じとみる。あるいは同じ。ゲームには、そういう危険な面も隠されている。●思考回路はそのまま で、さらに、浜松市内の中学1年生について調べたところ、男子の約半数がマジギャザと遊戯王に、多かれ少なかれハマっているのがわかった。1人が平均約1000枚のカードを持っている。中には1万枚も持っている子どももいる。マジギャザはもともとアメリカで生まれたゲームで、そのためアメリカバージョン、フランスバージョン、さらに中国バージョンもある。カード数が多いのは、そのため。「フランス語版は質がよくて、プレミヤのついたカードは、4万円。印刷ミスのも、4万円の価値がある」と。さらにこのカードをつかって、別のカケをしたり、大会で賞品集めをすることもあるという。「大会で勝つと、新しいカードをたくさんもらえる」とのこと。「優勝するのは、たいてい20歳以上のおとなばかりだよ」とも。 わかりやすく言えばポケモン世代が、思考回路だけはそのままで、体だけが大きくなったということ。いや、「思考回路」と言えばまだ聞こえはよいが、その中身は中毒。カード中毒。この中毒性がこわい。だから一万枚もカードを集めたりする。一枚のカードに4万円も払ったりする!●子どもをダシに金儲け 子どもをダシにした金儲けは、この不況下でも、大盛況。カードの販売だけで、年間100億円から200億円の市場になっているという(経済誌・00年前後)。しかしこれはあくまでも表の数字。闇から闇へと動いているお金はその数倍はあるとみてよい。たとえば今、「融合カード」は、発売中止になっている(注)。子どもたちがそのカードを手に入れるためには、交換するか、友だちから買うしかない。希少価値がある分だけ、値段も高い。しかも、だ。子どもたちは自分の意思というよりは、おとなたちの醜い商魂に操られるまま、そうしている。しかしこんなことが子どもの世界で、許されてよいのか。野放しになってよいのか。(注)この原稿を書いた2001年はじめには発売中止になっていたが、2001年の終わりには再び発売されているとのこと。●はびこるカルト信仰 ある有名なロックバンドのHという男が自殺したとき、わかっているだけでも女性を中心に、3~4名の若者が、そのあとを追い、自殺した。家族によって闇から闇へと隠された自殺者となると、もっと多いはず。自殺をする人にはそれなりの人生観があり、また理由があってそうするのだろうから、私のような部外者がとやかく言っても始まらない。しかしそれがもし、あなたの子どもであるとしたら……。こんなこともあった。 1997年の3月、ヘールボップすい星が地球に近づいたとき、世にも不可解な事件がアメリカで起きた。「ハイアーソース」と名乗るカルト教団による、集団自殺事件である。当時の新聞記事によると、この教団では、「ヘールボップすい星とともに現われる宇宙船とランデブーして、あの世に旅立つ」と、教えていたという。結果、39人の若者が犠牲になった。この種の事件でよく知られている事件に、1978年にガイアナで起きた人民寺院信徒による集団自殺事件がある。この事件では、何と914名もの信者が犠牲になっている。なぜこんな忌まわしい事件が起きたのか。また起きるのか。「日本ではこんな事件は起きない」と考えるのは早計である。子どもたちの世界にも大きな異変が起きつつある。現実と空想の混濁が、それである。 そのよく知られた事件に、あの『淳君殺害事件』がある。それについて書く前に、「右脳教育」について、少しだけ、考えてみたい。●左脳と右脳 左脳は言語をつかさどり、右脳はイメージをつかさどる(R・W・スペリー)。その右脳をきたえると、たとえば次のようなことができるようになるという(七田眞氏)。(1)インスピレーション、ひらめき、直感が鋭くなる(波動共振)、(2)受け取った情報を映像に変えたり、思いどおりの映像を心に描くことができる(直観像化)、(3)見たものを映像的に、しかも瞬時に記憶することができる(フォトコピー化)、(4)計算力が速くなり、高度な計算を瞬時にできる(高速自動処理)など。こうした事例は、現場でもしばしば経験する。●こだわりは能力ではないたとえば暗算が得意な子どもがいる。頭の中に仮想のそろばんを思い浮かべ、そのそろばんを使って、瞬時に複雑な計算をしてしまう。あるいは速読の得意な子どもがいる。読むというよりは、文字の上をななめに目を走らせているだけ。それだけで本の内容を理解してしまう。しかし現場では、それがたとえ神業に近いものであっても、教育の世界では、「神童」というのは認めない。もう少しわかりやすい例で言えば、100種類近い自動車の、その一部を見ただけでメーカーや車種を言い当てたとしても、それを能力とは認めない。「こだわり」とみる。たとえば自閉症の子どもがいる。このタイプの子どもは、ある特殊な分野に、ふつうでないこだわりを見せることが、よく知られている。全国の電車の発車時刻を暗記したり、音楽の最初の一小節を聞いただけで、その音楽の題名を言い当てたりするなど。つまりこうしたこだわりが強ければ強いほど、むしろ心のどこかに、別の問題が潜んでいるとみる。●論理や分析をつかさどるのは左脳 そこで右脳教育を信奉する人たちは、有名な科学者や芸術家の名前を取りあげ、そうした成果の陰には、発達した右脳があったと説く。しかしこうした科学者や芸術家ほど、一方で、変人というイメージも強い。つまりふつうでないこだわりが、その人をして、並はずれた人物にしたと考えられなくもない。 言いかえると、右脳が創造性やイメージの世界を支配するとしても、右脳型人間が、あるべき人間の理想像ということにはならない。むしろゆっくりと言葉を積み重ねながら(=論理)、他人の心を静かに思いやること(=分析)ができる子どものほうが、望ましい子どもということになる。その論理や分析をつかさどるのは、右脳ではなく、左脳である。●右脳教育は慎重に 右脳教育が脳のシステムの完成したおとなには、有効な方法であることは、私も認める。しかしだからといって、それを脳のシステムが未発達な子どもに応用するのは、慎重でなければならない。脳にはその年齢に応じた発達段階があり、その段階を経て、論理や分析を学ぶ。右脳ばかりを刺激すればどうなるか? 一つの例として、神戸でおきた『淳君殺害事件』をあげる研究家がいる(福岡T氏ほか)。●少年Aは直観像素質者 あの事件を引き起こした少年Aの母親は、こんな手記を残している。いわく、「(息子は)画数の多い難しい漢字も、一度見ただけですぐ書けました」「百人一首を一晩で覚えたら、5000円やると言ったら、本当に一晩で百人一首を暗記して、いい成績を取ったこともあります」(「少年A、この子を生んで」文藝春秋)と。 少年Aは、イメージの世界ばかりが異常にふくらみ、結果として、「幻想や空想と現実の区別がつかなくなってしまった」(同書)ようだ。その少年Aについて、鑑定した専門家は、「(少年Aは)直観像素質者(一瞬見た映像をまるで目の前にあるかのように、鮮明に思い出すことができる能力のある人)であって、(それがこの非行の)一因子を構成している」(同書)という結論をくだしている。 要はバランスの問題。左脳教育であるにせよ右脳教育であるにせよ、バランスが大切。子どもに与える教育は、いつもそのバランスを考えながらする。●才能とこだわり ところでここにも書いたように、たとえば自閉症の子どもが、ふつうでない「こだわり」を見せることは、よく知られている。たとえば、CDを何枚も集めたり、ゲームソフトを、何千個も集めたりするなど。 先にも書いたように、そういった「こだわり」が、神業的なものになることもある。 が、こうした「こだわり」は、才能なのか。それとも才能ではないのか。一般論としては、教育の世界では、繰りかえすが、たとえそれが並はずれた「力」であっても、こうした特異な「力」は、才能とは認めない。たとえば瞬時に、難解な計算ができる。あるいは、20ケタの数字を暗記できるなど。あるいは一回、サーッと曲を聞いただけで、それをそっくりそのまま、ピアノで演奏できた子どももいた。まさに神業(わざ)的な「力」ということになるが、やはり「才能」とは認めない。「こだわり」とみる。 教育が教育となりうるためには、普遍性(だれにも応用しうるもの)や、再現性(同じことをすれば、みながそうなる)、が必要である。そしてそういったものが、教育プロセスとして、確立されなければならない。もっと言えば「だからどうなの?」という部分がない「力」は、教育の世界では、「力」とは認めない。 ここで取りあげた、「少年A」については、精神鑑定の結果、「直観像素質者※」と鑑定されている。直観像素質者というのは、瞬間見ただけで、見たものをそのまま脳裏に焼きつけてしまうことができる子どもをいう。もっとわかりやすく言えば、空想の世界が、かぎりなくふくらんでしまい、空想と現実の世界の区別がつかなくなってしまった子どもということになる。「少年A」も、一晩で百人一首を暗記できるような力をもっていた。そういう特異な「力」が、あの悲惨な事件を引き起こす遠因になったと、考えられなくもない。●才能とは何か と、なると、改めて才能とは何かということになる。ひとつの条件として、子ども自身が、その「力」を、意識しているかどうかということがある。たとえば練習に練習を重ねて、サッカーの技術をみがくというのは才能だが、列車の時刻表を見ただけで、それを暗記できてしまうというのは、才能ではない。 つぎに、才能というのは、人格のほかの部分とバランスがとれていなければならない。まさにそれだけしかできないというのであれば、それは才能ではない。たとえば豊かな知性、感性、理性、経験が背景にあって、その上ですばらしい曲を作曲できるのは、才能だが、まだそうした背景のない子どもが、一回曲を聞いただけで、その曲が演奏できるというのは、才能ではない。 脳というのは、ともすれば欠陥だらけの症状を示すが、同じように、ともすれば、並はずれた、「とんでもない力」を示すこともある。私も、こうした「とんでもない力」を、しばしば経験している。印象に残っている子どもに、S君(中学生)がいた。●一小節を聞いただけで、曲名を当てた、S君ここに書いた、「クラッシック音楽の、最初の一小節を聞いただけで、曲名と作曲者を言い当てた子ども」というのが、その子どもだが、一方で、金銭感覚がまったくなかった。ある程度の計算はできたが、「得をした」「損をした」「増えた」「減った」ということが、まったく理解できなかった。1000円と2000円のどちらが多いかと聞いても、それがわからなかった。1000円程度のものを、200円くらいのものと交換しても、損をしたという意識そのものがなかった。母親は、S君の特殊な能力(?)ばかりをほめ、「うちの子は、もっとできるはず」とがんばったが、しかしそれはS君の「力」ではなかった。 教育の世界で「才能」というときは、当然のことながら、教育とかみあわなければならない。「かみあう」というのは、それ自体が、教育できるものでなければならないということ。「教育することによって、伸ばすことができること」を、才能という。それが先に書いた、「教育プロセス」ということになる。が、それだけでは足りない。その方法が、ほかの子どもにも、同じように応用できなければならない。またそれができるから、教育という。つまりその子どもしかできないような、特異な「力」は、才能ではない。 要するに、「だからどうなの?」という部分がないのは、才能とは言えない。「瞬間に見ただけで、車の車種から型、メーカー名まで言える子どもがいたとする。しかしそれができたからといって、だから、どうだというのか? こう書くと、こだわりをもちつつ、懸命にがんばっている子どもを否定しているようにとらえられるかもしれないが、それは誤解である。多かれ少なかれ、私たちは、ものごとにこだわることで、さらに自分の才能を伸ばすことができる。現に今、私は電子マガジンを、ほとんど2日おきに出版している。毎日そのために、数時間。土日には、4、5時間を費やしている。その原動力となっているのは、実は、ここでいう「こだわり」かもしれない。時刻表を覚えたり、音楽の一小節を聞いただけで曲名を当てるというのは、あまり役にたたない「こだわり」ということになる。が、中には、そうした「こだわり」が花を咲かせ、みごとな才能となって、世界的に評価されるようになった人もいる。あるいはひょっとしたら、私たちが今、名前を知っている多くの作曲家も、幼少年時代、そういう「こだわり」をもった子どもだったかもしれない。そういう意味では、「こだわり」を、頭から否定することもできない。 しかしその「こだわり」には、いつも、一定の限度がある。「こだわり」が限度を超えたときに、さまざまな問題が生ずる。●カルト性をもつゲームところで、最近のアニメやゲームの中には、カルト性をもったものも多い。今はまだ娯楽の範囲だからよいようなものの、もしこれらのアニメやゲームが、思想性をもったらどうなるか。仮にポケモンのサトシが、「子どもたちよ、未来は暗い。一緒に死のう」と言えば、それに従ってしまう子どもが続出するかもしれない。そうなれば、言論の自由だ、表現の自由だなどと、のんきなことを言ってはおれない。あと追い自殺した若者たちは、その延長線上にいるにすぎない。 思いだしてみればよい。旧ソ連崩壊のときロシアで、旧東ドイツ崩壊のときドイツで、それぞれカルト教団が急速に勢力を伸ばした。社会情勢が不安定になり、人々が心のよりどころをなくしたとき、こうしたカルト教団が急速に勢力を伸ばす。終戦直後の日本がそうだったが、最近でも、経済危機や環境問題、食糧問題にかこつけて、急速に勢力を拡大しているカルト教団がある。あやしげなパワーや念力、超能力を売りものにしている。「金持ちになれる」とか「地球が滅亡するときには、天国へ入れる」とか教えるカルト教団もある。フランスやベルギーでは、国をあげてこうしたカルト教団への監視を強めているが、この日本ではまったくの野放し。果たしてこのままでよいのか。子どもたちの未来は、本当に安全なのか。あるいはあなた自身はだいじょうぶなのか。あなたの子どもが犠牲者になってからでは遅い。このあたりで一度、腰を落ちつけて、子どもの世界をじっくりとながめてみてほしい。●ゲーム脳 さらに最近では、急に脚光を浴びてきた話題に、「ゲーム脳」がある。ゲームづけになった脳ミソを「ゲーム脳」いう。このタイプの脳ミソには、特異的な特徴がみられるという。しかし、「ゲーム脳」とは、何か。NEWS WEB JAPANは、つぎのように報道している(05年8月11日)。『脳の中で、約35%をしめる前頭葉の中に、前頭前野(人間の拳程の大きさで、記憶、感情、集団でのコミュニケーション、創造性、学習、そして感情の制御や、犯罪の抑制をも司る部分)という、さまざまな命令を身体全体に出す司令塔がある。この司令塔が、ゲームや携帯メール、過激な映画やビデオ、テレビなどに熱中しすぎると働かなくなり、いわゆる「ゲーム脳」と呼ばれる状態になるという。それを科学的に証明したのが、日大大学院の森教授である』(以上、NEWS WEB JAPAN※)。 つまりゲーム脳になると、管理能力全般にわたって、影響が出てくるというわけである。このゲーム脳については、すでに、さまざまな分野で話題になっているから、ここでは、省略する。要するに、子どもは、ゲームづけにしてはいけないということ。 が、私がここで書きたいのは、そのことではない。 この日本では、(世界でもそうかもしれないが)、ゲームを批判したり、批評したりすると、ものすごい抗議が殺到するということ。上記の森教授のもとにも、「多くのいやがらせが、殺到している」(同)という。 考えてみれば、これは、おかしなことではないか。たかがゲームではないか(失礼!)。どうしてそのゲームのもつ問題性を指摘しただけで、抗議の嵐が、わき起こるのか? M教授らは、「ゲームばかりしていると、脳に悪い影響を与えますよ」と、むしろ親切心から、そう警告している。それに対して、(いやがらせ)とは!●ポケモンカルト 実は、同じことを私も経験している。5、6年前に、私は「ポケモンカルト」(三一書房)という本を書いた。そのときも、私のところのみならず、出版社にも、抗議の嵐が殺到した。名古屋市にあるCラジオ局では、1週間にわたって、私の書いた本をネタに、賛否両論の討論会をつづけたという。が、私が驚いたのは、抗議そのものではない。そうした抗議をしてきた人のほとんどが、子どもや親ではなく、20代前後の若者、それも男性たちであったということ。 どうして、20代前後の若者たちが、子どものゲームを批評しただけで、抗議をしてくるのか? 出版社の編集部に届いた抗議文の中には、日本を代表する、パソコン雑誌の編集部の男性からのもあった。 「子どもたちの夢を奪うのか!」 「幼児教育をしながら、子どもの夢が理解できないのか!」 「ゲームを楽しむのは、子どもの権利だ!」とか何とか。 私の本の中の、ささいな誤字や脱字、どうでもよいような誤記を指摘してきたのも多かった。「貴様は、こんな文字も書けないのに、偉そうなことを言うな」とか、「もっと、ポケモンを勉強してからものを書け」とか、など。 (誤字、脱字については、いくら推敲しても、残るもの。100%、誤字、脱字のない本などない。その本の原稿も、一度、プロの推敲家の目を経ていたのだが……。) 反論しようにも、どう反論したらよいかわからない。そんな低レベルの抗議である。で、そのときは、「そういうふうに考える人もいるんだなあ」という程度に考えて、私はすませた。 で、今回も、森教授らのもとに、「いやがらせが、殺到している」(同)という。 これはいったい、どういう現象なのか? どう考えたらよいのか?●カルト的連帯感をもつゲーマーたち 一つ考えられることは、ゲームに夢中になっている、ゲーマーたちが、横のつながりをもちつつ、カルト化しているのではないかということ。ゲームを批判されるということは、ゲームに夢中になっている自分たちが批判されるのと同じ……と、彼らは、とらえるらしい(?)。おかしな論理だが、そう考えると、彼らの心理状態が理解できる。 実は、カルト教団の信者たちも、同じような症状を示す。自分たちが属する教団が批判されたりすると、あたかも自分という個人が批判されたかのように、それに猛烈に反発したりする。教団イコール、自分という一体感が、きわめて強い。 あのポケモン全盛期のときも、こんなことがあった。私が、子どもたちの前で、ふと一言、「ピカチューのどこがかわいいの?」ともらしたときのこと。子どもたちは、その一言で、ヒステリー状態になってしまった。ギャーと、悲鳴とも怒号ともわからないような声をあげる子どもさえいた。 そういう意味でも、ゲーム脳となった脳ミソをもった人たちと、カルト教団の信者たちとの間には、共通点が多い。たとえばゲームにハマっている子どもを見ていると、どこか狂信的。現実と空想の世界の区別すら、できなくなる子どもさえいる。たまごっちの中の生き物(?)が死んだだけで、ワーワーと大泣きした子ども(小1女児)もいた。これから先、ゲーム脳の問題は、さらに大きく、マスコミなどでも、とりあげられるようになるだろう。これからも注意深く、監視していきたい。 ところで、今日の(韓国)の新聞によれば、テレビゲームを50時間もしていて、死んでしまった若者がいるそうだ。たかがゲームと、軽くみることはできない。注※……K教授は、ポジトロンCT(陽電子放射断層撮影)と、ファンクショナルMRI(機能的磁気共鳴映像)いう脳の活性度を映像化する装置で、実際にゲームを使い、数十人を測定した。そして、2001年に世界に先駆けて、「テレビゲームは前頭前野をまったく発達させることはなく、長時間のテレビゲームをすることによって、脳に悪影響を及ぼす」という実験結果をイギリスで発表した。この実験結果が発表された後に、ある海外のゲーム・ソフトウェア団体は「非常に狭い見識に基づいたもの」というコメントを発表し、教授の元には多くの嫌がらせも殺到したという(NEWS WEB JAPANの記事より)。●M君、小3のケース M君の姉(小5)が、ある日、こう言った。「うちの弟、夜中でも、起きて、ゲームをしている!」と。 M君の姉とM君(小3)は、同じ部屋で寝ている。二段ベッドになっていて、上が、姉。下が、M君。そのM君が、「真夜中に、ガバッと起きて、ゲームを始める。そのまま朝まで、していることもある」(姉の言葉)と。 M君には、特異な症状が見られた。 祖父が、その少し前、なくなった。その通夜の席でのこと。M君は、たくさん集まった親類の人たちの間で、ギャーギャーと笑い声で、はしゃいでいたという。「まるで、パーティでもしているかのようだった」(姉の言葉)と。 祖父は、人一倍、M君をかわいがっていた。その祖父がなくなったのだから、M君は、さみしがっても、よいはず。しかし、「はしゃいでいた」と。 私はその話を聞いて、M君はM君なりに、悲しさをごまかしていたのだろうと思った。しかし別の事件が、そのすぐあとに起きた。 M君が、近くの家の庭に勝手に入り込み、その家で飼っていた犬に、腕をかまれて、大けがをしたというのだ。その家の人の話では、「庭には人が入れないように、柵がしてあったのですが、M君は、その柵の下から、庭へもぐりこんだようです」とのこと。 こうした一連の行為の原因が、すべてゲームにあるとは思わないが、しかしないとも、言い切れない。こんなことがあった。 M君の姉から、真夜中にゲームをしているという話を聞いた母親が、M君から、ゲームを取りあげてしまった。その直後のこと。M君は狂ったように、家の中で暴れ、最後は、自分の頭をガラス戸にぶつけ、そのガラス戸を割ってしまったという。 もちろんM君も、額と頬を切り、病院で、10針前後も、縫ってもらうほどのけがをしたという。そのあまりの異常さに気づいて、しばらくしてから、M君の母親が、私のところに相談にやってきた。 私は、日曜日にときどき、M君を教えるという形で、M君を観察させてもらうことにした。そのときもまだ、腕や顔に、生々しい、傷のあとが、のこっていた。 そのM君には、いくつかの特徴が見られた。(1)まるで脳の中の情報が、乱舞しているかのように、話している話題が、めまぐるしく変化した。時計の話をしていたかと思うと、突然、カレンダーの話になるなど。(2)感情の起伏がはげしく、突然、落ちこんだかと思うと、パッと元気になって、ギャーと騒ぐ。イスをゴトゴト動かしたり、机を意味もなく、バタンとたたいて見せたりする。(3)頭の回転ははやい。しばらくぼんやりとしていたかと思うと、あっという間に、計算問題(割り算)をすませてしまう。そして「終わったから、帰る」などと言って、あと片づけを始める。(4)もちろんゲームの話になると、目の色が変わる。彼がそのとき夢中になっていたのは、N社のGボーイというゲームである。そのゲーム機器を手にしたとたん、顔つきが能面のように無表情になる。ゲームをしている間は、目がトロンとし、死んだ、魚の目のようになる。 M君の姉の話では、ひとたびゲームを始めると、そのままの状態で、2~3時間はつづけるそうである。長いときは、5時間とか、6時間もしているという。(同じころ、12時間もゲームをしていたという中学生の話を聞いたことがある。) 以前、「脳が乱舞する子ども」という原稿を書いた(中日新聞発表済み)。話は少しそれるが、それをここに紹介する。もう4、5年前に書いた原稿だが、状況は改善されるどころか、悪化している。●収拾がつかなくなる子ども 一方、学校という場でも、こんな珍現象が起きつつある。 「先生は、サダコかな? それともサカナ! サカナは臭い。それにコワイ、コワイ……、ああ、水だ、水。冷たいぞ。おいしい焼肉だ。鉛筆で刺して、焼いて食べる……」と、話がポンポンと飛ぶ。頭の回転だけは、やたらと速い。まるで頭の中で、イメージが乱舞しているかのよう。動作も一貫性がない。騒々しい。ひょうきん。鉛筆を口にくわえて歩き回ったかと思うと、突然神妙な顔をして、直立! そしてそのままの姿勢で、バタリと倒れる。ゲラゲラと大声で笑う。その間に感情も激しく変化する。目が回るなんていうものではない。まともに接していると、こちらの頭のほうがヘンになる。 多動性はあるものの、強く制止すれば、一応の「抑え」はきく。小学2、3年になると、症状が急速に収まってくる。集中力もないわけではない。気が向くと、黙々と作業をする。30年前にはこのタイプの子どもは、まだ少なかった。が、ここ10年、急速にふえた。小1児で、10人に2人はいる。今、学級崩壊が問題になっているが、実際このタイプの子どもが、一クラスに数人もいると、それだけで学級運営は難しくなる。あちらを抑えればこちらが騒ぐ。こちらを抑えればあちらが騒ぐ。そんな感じになる。●崩壊する学級 こうした現象だけが原因とは言えないが、そのため、「学級指導の困難に直面した経験があるか」との質問に対して、「よくあった」「あった」と答えた先生が、66%もいる(98年、大阪教育大学秋葉英則氏調査)。「指導の疲れから、病欠、休職している同僚がいるか」という質問については、15%が、「1名以上いる」と回答している。そして「授業が始まっても、すぐにノートや教科書を出さない」子どもについては、90%以上の先生が、経験している。ほかに「弱いものをいじめる」(75%)、「友だちをたたく」(66%)などの友だちへの攻撃、「授業中、立ち歩く」(66%)、「配布物を破ったり捨てたりする」(52%)などの授業そのものに対する反発もみられるという(同、調査)。●ふえる学級崩壊 学級崩壊については減るどころか、近年、ふえる傾向にある。99年1月になされた日教組と全日本教職員組合の教育研究全国大会では、学級崩壊の深刻な実情が数多く報告されている。「変ぼうする子どもたちを前に、神経をすり減らす教師たちの生々しい告白は、北海道や東北など各地から寄せられ、学級崩壊が大都市だけの問題ではないことが浮き彫りにされた」(中日新聞)と。「もはや教師が一人で抱え込めないほどすそ野は広がっている」とも。 北海道のある地方都市で、小学一年生70名について調査したところ、 授業中おしゃべりをして教師の話が聞けない ……19人 教師の指示を行動に移せない ……17人 何も言わず教室の外に出て行く ……9人、など(同大会)。●「荒れ」から「新しい荒れ」へ 昔は「荒れ」というと、中学生や高校生の不良生徒たちの攻撃的な行動をいったが、それが最近では、低年齢化すると同時に、様子が変わってきた。「新しい荒れ」とい言葉を使う人もいる。ごくふつうの、それまで何ともなかった子どもが、突然、キレ、攻撃行為に出るなど。多くの教師はこうした子どもたちの変化にとまどい、「子どもがわからなくなった」とこぼす。日教組が98年に調査したところによると、「子どもたちが理解しにくい。常識や価値観の差を感ずる」というのが、20%近くもあり、以下、「家庭環境や社会の変化により指導が難しい」(14%)、「子どもたちが自己中心的、耐性がない、自制できない」(10%)と続く。そしてその結果として、「教職でのストレスを非常に感ずる先生が、8%、「かなり感ずる」「やや感ずる」という先生が、60%(同調査)もいるそうだ。●心を病む教師たち こうした現状の中で、心を病む教師も少なくない。東京都の調べによると、東京都に在籍する約6万人の教職員のうち、新規に病気休職した人は、93年度から4年間は毎年210人から220人程度で推移していたが、97年度は、261人。さらに98年度は355人にふえていることがわかった(東京都教育委員会調べ・99年)。この病気休職者のうち、精神系疾患者は。93年度から増加傾向にあることがわかり、96年度に一時減ったものの、97年度は急増し、135人になったという。この数字は全休職者の約52%にあたる。(全国データでは、97年度は休職者が4171人で、精神系疾患者は、1619人。)さらにその精神系疾患者の内訳を調べてみると、うつ病、うつ状態が約半数をしめていたという。原因としては、「同僚や生徒、その保護者などの対人関係のストレスによるものが大きい」(東京都教育委員会)ということである。●原因の一つはイメージ文化? こうした学級が崩壊する原因の一つとして、(あくまでも、一つだが……)、私はテレビやゲームをあげる。「荒れる」というだけでは、どうも説明がつかない。家庭にしても、昔のような崩壊家庭は少なくなった。むしろここにあげたように、ごくふつうの、そこそこに恵まれた家庭の子どもが、意味もなく突発的に騒いだり暴れたりする。そして同じような現象が、日本だけではなく、アメリカでも起きている。実際、このタイプの子どもを調べてみると、ほぼ例外なく、乳幼児期に、ごく日常的にテレビやゲームづけになっていたのがわかる。ある母親はこう言った。「テレビを見ているときだけ、静かでした」と。「ゲームをしているときは、話しかけても返事もしませんでした」と言った母親もいた。たとえば最近のアニメは、幼児向けにせよ、動きが速い。速すぎる。しかもその間に、ひっきりなしにコマーシャルが入る。ゲームもそうだ。動きが速い。速すぎる。●ゲームは右脳ばかり刺激する こうした刺激を日常的に与えて、子どもの脳が影響を受けないはずがない。もう少しわかりやすく言えば、子どもはイメージの世界ばかりが刺激され、静かにものを考えられなくなる。その証拠(?)に、このタイプの子どもは、ゆっくりとした調子の紙芝居などを、静かに聞くことができない。浦島太郎の紙芝居をしてみせても、「カメの顔に花が咲いている!」とか、「竜宮城に魚が、おしっこをしている」などと、そのつど勝手なことをしゃべる。一見、発想はおもしろいが、直感的で論理性がない。ちなみにイメージや創造力をつかさどるのは、右脳。分析や論理をつかさどるのは、左脳である(R・W・スペリー)。テレビやゲームは、その右脳ばかりを刺激する。こうした今まで人間が経験したことがない新しい刺激が、子どもの脳に大きな影響を与えていることはじゅうぶん考えられる。その一つが、ここにあげた「脳が乱舞する子ども」ということになる。 学級崩壊についていろいろ言われているが、一つの仮説として、私はイメージ文化の悪弊をあげる。●その対策 現在全国の21自治体では、学級崩壊が問題化している小学1年クラスについて、クラスを1クラス30人程度まで少人数化したり、担任以外にも補助教員を置くなどの対策をとっている(共同通信社まとめ)。また小学6年で、教科担任制を試行する自治体もある。具体的には、小学1、2年について、新潟県と秋田県がいずれも1クラスを30人に、香川県では40人いるクラスを、2人担任制にし、今後5年間でこの上限を36人まで引きさげる予定だという。福島、群馬、静岡、島根の各県などでは、小1でクラスが30~36人のばあいでも、もう1人教員を配置している。さらに山口県は、「中学への円滑な接続を図る」として、一部の小学校では、6年に、国語、算数、理科、社会の四教科に、教科担任制を試験的に導入している。大分県では、中学1年と3年の英語の授業を、1クラス20人程度で実施している(01年度調べ)。●失行 近年、さらに、「失行」という言葉が、よく聞かれるようになった。96年に、ドイツのシュルツという医師が使い始めた言葉だという。 失行というのは、本人が、わかっているのに、できない状態をいう。たとえば風呂から出たとき、パジャマに着がえなさいと、だれかが言ったとする。本人も、「風呂から出たら、パジャマに着がえなければならない」と、理解している。しかし風呂から出ると、手当たり次第に、そこらにある衣服を身につけてしまう。 原因は、脳のどこかに何らかのダメージがあるためとされる。 それはさておき、人間が何かの行動をするとき、脳から、同時に別々の信号が発せられるという。行動命令と抑制命令である。 たとえば腕を上下させるときも、腕を上下させろという命令と、その動きを抑制する命令の二つが、同時に発せられる。 だから人間は、(あらゆる動物も)、スムーズな行動(=運動行為)ができる。行動命令だけだと、まるでカミソリでスパスパとものを切るような動きになる。抑制命令が強すぎると、行動そのものが、鈍くなり、動作も緩慢になる。 精神状態も、同じように考えられないだろうか。●抑制命令 たとえば何かのことで、カッと頭に血がのぼるようなときがある。激怒した状態を思い浮かべればよい。 そのとき、同時に、「怒るな」という命令も、働く。激怒するのを、精神の行動命令とするなら、「怒るな」と命令するのは、精神の抑制命令ということになる。 この「失行」についても、精神の行動命令と、抑制命令という考え方を当てはめると、それなりに、よく理解できる。 たとえば母親が、子どもに向かって、「テーブルの上のお菓子は、食べてはだめ」「それは、これから来る、お客さんのためのもの」と話したとする。 そのとき子どもは、「わかった」と言って、その場を去る。が、母親の姿が見えなくなったとたん、子どもは、テーブルのところへもどってきて、その菓子を食べてしまう。 それを知って、母親は、子どもを、こう叱る。「どうして、食べたの! 食べてはだめと言ったでしょ!」と。 このとき、子どもは、頭の中では「食べてはだめ」ということを理解していた。しかし精神の抑制命令が弱く、精神の行動命令を、抑制することができなかった。だから子どもは、菓子を食べてしまった。●前頭連合野 ……実は、こうした精神のコントロールをしているのが、前頭連合野と言われている。そしてこの前頭連合野の働きが、何らかの損傷を受けると、その人は、自分で自分を管理できなくなってしまう。いわゆるここでいう「失行」という現象が、起きる。 前述のWEB・NEWSの記事によれば、「(前頭連合野は)記憶、感情、集団でのコミュニケーション、創造性、学習、そして感情の制御や、犯罪の抑制をも司る部分」とある。 どれ一つをとっても、良好な人間関係を維持するためには、不可欠な働きばかりである。一説によれば、ゲーム脳の子どもの脳は、この前頭連合野が、「スカスカの状態」になっているそうである。 言うまでもなく、脳には、そのときどきの発達の段階で、「適齢期」というものがある。その適齢期に、それ相当の、それにふさわしい発達をしておかないと、あとで補充したり、修正したりするということができなくなる。 ここにあげた、感情のコントロール、集団におけるコミュニケーション、創造性な学習能力といったものも、ある時期、適切な指導があってはじめて、子どもは、身につけることができる。その時期に、ゲーム脳に示されるように、脳の中でもある特異な部分だけが、異常に刺激されることによって、脳のほかの部分の発達が阻害されるであろうことは、門外漢の私にさえ、容易に推察できる。 それが「スカスカの脳」ということになる。 これから先も、この「ゲーム脳」については、注目していきたい。●子どもの人格の完成度 「ゲーム脳」になると、子どもは管理能力を喪失するという。しかしこの現象を、安易に考えてはいけない。管理能力は、その子ども(人)の人格をも決定する、重要な要素だからである。 たとえば、子どもの人格の完成度は、つぎの5つをみて、判断する(サロベイほか)。話を先に進める前に、あなた自身の子どもの人格の完成度はどうか。参考までに、一度、立ち止まって判断してみてほしい。テストの内容、項目は、子ども向けに私がアレンジしてみた。(1)共感性Q:友だちに、何か、手伝いを頼まれました。そのとき、あなたの子どもは……。(1)いつも喜んでするようだ。(2)ときとばあいによるようだ。(3)いやがってしないことが多い。(2)自己認知力Q:親どうしが会話を始めました。大切な話をしています。そのとき、あなたの子どもは……(1)雰囲気を察して、静かに待っている。(4点)(2)しばらくすると、いつものように騒ぎだす。(2点)(3)聞き分けガなく、「帰ろう」とか言って、親を困らせる。(0点)(3)自己統制力Q;冷蔵庫にあなたの子どものほしがりそうな食べ物があります。そのとき、あなたの子どもは……。○親が「いい」と言うまで、食べない。安心していることができる。(4点)○ときどき、親の目を盗んで、食べてしまうことがある。(2点)○まったくアテにならない。親がいないと、好き勝手なことをする。(0点)(4)粘り強さQ:子どもが自ら進んで、何かを作り始めました。そのとき、あなたの子どもは……。○最後まで、何だかんだと言いながらも、仕あげる。(4点)○だいたいは、仕あげるが、途中で投げだすこともある。(2点)○たいていいつも、途中で投げだす。あきっぽいところがある。(0点)(5)楽観性Q:あなたの子どもが、何かのことで、大きな失敗をしました。そのとき、あなたの子どもは……。○割と早く、ケロッとして、忘れてしまうようだ。クヨクヨしない。(4点)○ときどき思い悩むことはあるようだが、つぎの行動に移ることができる。(2点)○いつまでもそれを苦にして、前に進めないときが多い。(0点) (6)柔軟性Q:あなたの子どもの日常生活を見たとき、あなたの子どもは……○友だちも多く、多芸多才。いつも変わったことを楽しんでいる。(4点)○友だちは少ないほう。趣味も、限られている。(2点)○何かにこだわることがある。がんこ。融通がきかない。(0点)***************************( )友だちのための仕事や労役を、好んで引き受ける(共感性)。( )自分の立場を、いつもよくわきまえている(自己認知力)。( )小遣いを貯金する。ほしいものに対して、がまん強い(自己統制力)。( )がんばって、ものごとを仕上げることがよくある(粘り強さ)。( )まちがえても、あまり気にしない。平気といった感じ(楽観性)。( )友人が多い。誕生日パーティによく招待される(社会適応性)。( )趣味が豊富で、何でもござれという感じ(柔軟性)。 これら6つの要素が、ほどよくそなわっていれば、その子どもは、人間的に、完成度の高い子どもとみる(「EQ論」)。***************************●順に考えてみよう(1)共感性 人格の完成度は、内面化、つまり精神の完成度をもってもる。その一つのバロメーターが、「共感性」ということになる。 つまりは、どの程度、相手の立場で、相手の心の状態になって、その相手の苦しみ、悲しみ、悩みを、共感できるかどうかということ。 その反対側に位置するのが、自己中心性である。 乳幼児期は、子どもは、総じて自己中心的なものの考え方をする。しかし成長とともに、その自己中心性から脱却する。「利己から利他への転換」と私は呼んでいる。 が、中には、その自己中心性から、脱却できないまま、おとなになる子どももいる。さらにこの自己中心性が、おとなになるにつれて、周囲の社会観と融合して、悪玉親意識、権威主義、世間体意識へと、変質することもある。(2)自己認知力 ここでいう「自己認知能力」は、「私はどんな人間なのか」「何をすべき人間なのか」「私は何をしたいのか」ということを、客観的に認知する能力をいう。 この自己認知能力が、弱い子どもは、おとなから見ると、いわゆる「何を考えているかわからない子ども」といった、印象を与えるようになる。どこかぐずぐずしていて、はっきりしない。優柔不断。反対に、独善、独断、排他性、偏見などを、もつこともある。自分のしていること、言っていることを客観的に認知することができないため、子どもは、猪突猛進型の生き方を示すことが多い。わがままで、横柄になることも、珍しくない。(3)自己統制力 すべきことと、してはいけないことを、冷静に判断し、その判断に従って行動する。子どものばあい、自己のコントロール力をみれば、それがわかる。 たとえば自己統制力のある子どもは、お年玉を手にしても、それを貯金したり、さらにためて、もっと高価なものを買い求めようとしたりする。 が、この自己統制力のない子どもは、手にしたお金を、その場で、その場の楽しみだけのために使ってしまったりする。あるいは親が、「食べてはだめ」と言っているにもかかわらず、お菓子をみな、食べてしまうなど。 感情のコントロールも、この自己統制力に含まれる。平気で相手をキズつける言葉を口にしたり、感情のおもむくまま、好き勝手なことをするなど。もしそうであれば、自己統制力の弱い子どもとみる。 ふつう自己統制力は、(1)行動面の統制力、(2)精神面の統制力、(3)感情面の統制力に分けて考える。(4)粘り強さ 短気というのは、それ自体が、人格的な欠陥と考えてよい。このことは、子どもの世界を見ていると、よくわかる。見た目の能力に、まどわされてはいけない。 能力的に優秀な子どもでも、短気な子どもはいくらでもいる一方、能力的にかなり問題のある子どもでも、短気な子どもは多い。 集中力がつづかないというよりは、精神的な緊張感が持続できない。そのため、短気になる。中には、単純作業を反復的にさせたりすると、突然、狂乱状態になって、泣き叫ぶ子どももいる。A障害という障害をもった子どもに、ときどき見られる症状である。 この粘り強さこそが、その子どもの、忍耐力ということになる。(1)楽観性 まちがいをすなおに認める。失敗をすなおに認める。あとはそれをすぐ忘れて、前向きに、ものを考えていく。 それができる子どもには、何でもないことだが、心にゆがみのある子どもは、おかしなところで、それにこだわったり、ひがんだり、いじけたりする。クヨクヨと気にしたり、悩んだりすることもある。 簡単な例としては、何かのことでまちがえたようなときを、それを見れば、わかる。 ハハハと笑ってすます子どもと、深刻に思い悩んでしまう子どもがいる。その場の雰囲気にもよるが、ふと見せる(こだわり)を観察して、それを判断する。 たとえば私のワイフなどは、ほとんど、ものごとには、こだわらない性質である。楽観的と言えば、楽観的。超・楽観的。 先日も、「お前、がんになったら、どうする?」と聞くと、「なおせばいいじゃなア~い」と。そこで「がんは、こわい病気だよ」と言うと、「今じゃ、めったに死なないわよ」と。さらに、「なおらなかったら?」と聞くと、「そのときは、そのときよ。ジタバタしても、しかたないでしょう」と。 冗談を言っているのかと思うときもあるが、ワイフは、本気。つまり、そういうふうに、考える人もいる。(2)柔軟性 子どもの世界でも、(がんこ)な面を見せたら、警戒する。 この(がんこ)は、(意地)、さらに(わがまま)とは、区別して考える。 一般論として、(がんこ)は、子どもの心の発達には、好ましいことではない。かたくなになる、かたまる、がんこになる。こうした行動を、固執行動という。広く、情緒に何らかの問題がある子どもは、何らかの固執行動を見せることが多い。 朝、幼稚園の先生が、自宅まで迎えにくるのだが、3年間、ただの一度もあいさつをしなかった子どもがいた。 いつも青いズボンでないと、幼稚園へ行かなかった子どもがいた。その子どもは、幼稚園でも、決まった席でないと、絶対にすわろうとしなかった。 何かの問題を解いて、先生が、「やりなおしてみよう」と声をかけただけで、かたまってしまう子どもがいた。 先生が、「今日はいい天気だね」と声をかけたとき、「雲があるから、いい天気ではない」と、最後までがんばった子どもがいた。 症状は千差万別だが、子どもの柔軟性は、柔軟でない子どもと比較して知ることができる。柔軟な子どもは、ごく自然な形で、集団の中で、行動できる。
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(15)
最前線の子育て論byはやし浩司(028)●伸びたバネは、ちぢむ受験期にさしかかると、猛烈な受験勉強を強いる親がいる。塾に、家庭教師に、日曜特訓など。毎週、近くの公園で、運動の特訓をしていた父親さえいた。しかしこうした(無理)は、一事的な効果はあっても、そのあと、その反動で、かえって子どもの成績はさがる。『伸びたバネはちぢむ』と覚えておくとよい。イギリスの教育格言にも、『馬を水場に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない』というのがある。その格言の意味を、もう一度、考えてみてほしい。●「利他」度でわかる、人格の完成度あなたの子どもの前で、重い荷物をもって、苦しそうに歩いてみてほしい。そのとき、「ママ、もってあげる!」と走りよってくればよし。反対に、知らぬ顔をして、テレビゲームなどに夢中になっていれば、あなたの子どもは、かなりのどら息子と考えてよい。子どもの人格(おとなも!)、いかに利他的であるかによって、知ることができる。つまりドラ息子は、それだけ人格の完成度の低い子どもとみる。勉強のできる、できないは、関係ない。●見栄、体裁、世間体私らしく生きるその生き方の反対にあるのが、世間体意識。この世間体に毒されると、子どもの姿はもちろんのこと、自分の姿さえも、見失ってしまう。そしてその幸福感も、「となりの人より、いい生活をしているから、私は幸福」「となりの人より悪い生活をしているから、私は不幸」と、相対的なものになりやすい。もちろん子育ても、大きな影響を受ける。子どもの学歴について、ブランド志向の強い親は、ここで一度、反省してみてほしい。あなたは自分の人生を、自分のものとして、生きているか、と。●私を知る子育ては、本能ではなく、学習である。つまり今、あなたがしている子育ては、あなたが親から学習したものである。だから、ほとんどの親は、こう言う。「頭の中ではわかっているのですが、ついその場になると、カッとして……」と。そこで大切なことは、あなた自身の中の「私」を知ること。一見簡単そうだが、これがむずかしい。スパルタのキロンもこう言っている。『汝自身を、知れ』と。哲学の究極の目標にも、なっている。●成功率(達成率)は50%子どもが、2回トライして、1回は、うまくいくようにしむける。毎回、成功していたのでは、子どもも楽しくない。しかし毎回失敗していたのでは、やる気をなくす。だから、その目安は、50%。その50%を、うまく用意しながら、子どもを誘導していく。そしていつも、何かのレッスンの終わりには、「ほら、ちゃんとできるじゃ、ない」「すばらしい」と言って、ほめて仕あげる。●無理、強制無理(能力を超えた負担)や強制(強引な指導)は、一時的な効果はあっても、それ以上の効果はない。そればかりか、そのあと、その反動として、子どもは、やる気をなくす。ばあいによっては、燃え尽きてしまったり、無気力になったりすることもある。そんなわけで、『伸びたバネは、必ず縮む』と覚えておくとよい。無理をしても、全体としてみれば、プラスマイナス・ゼロになるということ。●条件、比較「100点取ったら、お小遣いをあげる」「1時間勉強したら、お菓子をあげる」というのが条件。「A君は、もうカタカナが読めるのよ」「お兄ちゃんが、あんたのときは、学校で一番だったのよ」というのが、比較ということになる。条件や比較は、子どもからやる気を奪うだけではなく、子どもの心を卑屈にする。日常化すれば、「私は私」という生き方すらできなくなってしまう。子どもの問題というよりは、親自身の問題として、考えたらよい。(内発的動機づけ)●方向性は図書館でどんな子どもにも、方向性がある。その方向性を知りたかったら、子どもを図書館へ連れていき、一日、そこで遊ばせてみるとよい。やがて子どもが好んで読む本が、わかってくる。それがその子どもの方向性である。たとえばスポーツの本なら、その子どもは、スポーツに強い関心をもっていることを示す。その方向性がわかったら、その方向性にそって、子どもを指導し、伸ばす。●神経症(心身症)に注意心が変調してくると、子どもの行動や心に、その前兆症状として、変化が見られるようになる。「何か、おかしい?」と感じたら、神経症もしくは、心身症を疑ってみる。よく知られた例としては、チック、吃音(どもり)、指しゃぶり、爪かみ、ものいじり、夜尿などがある。日常的に、抑圧感や欲求不満を覚えると、子どもは、これらの症状を示す。こうした症状が見られたら、(親は、子どもをなおそうとするが)、まず親自身の育児姿勢と、子育てのあり方を猛省する。●負担は、少しずつ減らす子どもが無気力症状を示すと、たいていの親は、あわてる。そしていきなり、負担を、すべて取り払ってしまう。「おけいこごとは、すべてやめましょう」と。しかしこうした極端な変化は、かえって症状を悪化させてしまう。負担は、少しずつ減らす。数週間から、1、2か月をかけて減らすのがよい。そしてその間に、子どもの心のケアに務める。そうすることによって、あとあと、子どもの立ちなおりが、用意になる。●荷おろし症候群何かの目標を達成したとたん、目標を喪失し、無気力状態になることを言う。有名高校や大学に進学したあとになることが多い。燃え尽き症候群と症状は似ている。一日中、ボーッとしているだけ。感情的な反応も少なくなる。地元のS進学高校のばあい、1年生で、10~15%の子どもに、そういう症状が見られる(S高校教師談)とのこと。「友人が少なく、人に言われていやいや勉強した子どもに多い」(渋谷昌三氏)と。●回復は1年単位一度、無気力状態に襲われると、回復には、1年単位の時間がかかる。(1年でも、短いほうだが……。)たいていのばあい、少し回復し始めると、その段階で、親は無理をする。その無理が、かえって症状を悪化させる。だから、1年単位。「先月とくらべて、症状はどうか?」「去年とくらべて、症状はどうか?」という視点でみる。日々の変化や、週単位の変化に、決して、一喜一憂しないこと。心の病気というのは、そういうもの。●前向きの暗示を大切に子どもには、いつも前向きの暗示を加えていく。「あなたは、明日は、もっとすばらしくなる」「来年は、もっとすばらしい年になる」と。こうした前向きな暗示が、子どものやる気を引き起こす。ある家庭には、4人の子どもがいた。しかしどの子も、表情が明るい。その秘訣は、母親にあった。母親はいつも、こうような言い方をしていた。「ほら、あんたも、お兄ちゃんの服が着られるようになったわね」と。「明日は、もっといいことがある」という思いが、子どもを前にひっぱっていく。●未来をおどさない今、赤ちゃんがえりならぬ、幼児がえりを起こす子どもがふえている。おとなになることに、ある種の恐怖感を覚えているためである。兄や姉のはげしい受験勉強を見て、恐怖感を覚えることもある。幼児のときにもっていた、本や雑誌、おもちゃを取り出して、大切そうにそれをもっているなど。話し方そのものが、幼稚ぽくなることもある。子どもの未来を脅さない。●子どもを伸ばす、三種の神器子どもを伸ばす、三種の神器が、夢、目的、希望。しかし今、夢のない子どもがふえた。中学生だと、ほとんどが、夢をもっていない。また「明日は、きっといいことがある」と思って、一日を終える子どもは、男子30%、女子35%にすぎない(「日本社会子ども学会」、全国の小学生3226人を対象に、04年度調査)。子どもの夢を大切に、それを伸ばすのは、親の義務と、心得る。 ●受験は淡々と子ども(幼児)の受験は、淡々と。合格することを考えて準備するのではなく、不合格になったときのことを考えて、準備する。この時期、一度、それをトラウマにすると、子どもは生涯にわたって、自ら「ダメ人間」のレッテルを張ってしまう。そうなれば、大失敗というもの。だから受験は、不合格のときを考えながら、準備する。●比較しない情報交換はある程度までは必要だが、しかしそれ以上の、深い親どうしの交際は、避ける。できれば、必要な情報だけを集めて、交際するとしても、子どもの受験とは関係ない人とする。「受験」の魔力には、想像以上のものがある。一度、この魔力にとりつかれると、かなり精神的にタフな人でも、自分で自分を見失ってしまう。気がついたときには、狂乱状態に……ということにも、なりかねない。●「入試」「合格・不合格」は、禁句子どもの前では、「受験」「入試」「合格」「不合格」「落ちる」「すべる」などの用語を口にするのは、タブーと思うこと。入試に向かうとしても、子どもに楽しませるようなお膳立ては、必要である。「今度、お母さんがお弁当つくってあげるから、いっしょに行きましょうね」とか。またそういう雰囲気のほうが、子どもも伸び伸びとできる。また結果も、よい。●入試内容に迎合しないたまに難しい問題が出ると、親は、それにすぐ迎合しようとする。たとえば前年度で、球根の名前を聞かれるような問題が出たとする。するとすぐ、親は、「では……」と。しかし大切なことは、物知りな子どもにすることではなく、深く考える子どもにすることである。わからなかったら、すなおに「わかりません」と言えばよい。試験官にしても、そういうすなおさを、試しているのである。●子どもらしい子ども子どもは子どもらしい子どもにする。すなおで、明るく、伸びやかで、好奇心が旺盛で、生活力があって……。すなおというのは、心の状態と、表情が一致している子どもをいう。ねたむ、いじける、すねる、ひねくれるなどの症状のない子どもをいう。そういう子どもを目指し、それでダメだというのなら、そんな学校は、こちらから蹴とばせばよい。それくらいの気構えは、親には必要である。●デマにご用心受験期になると、とんでもないデマが飛びかう。「今年は、受験者数が多い」「教員と親しくなっておかねば不利」「裏金が必要」などなど。親たちの不安心理が、さらにそうしたデマを増幅させる。さらに口から口へと伝わっていく間に、デマ自身も大きくなる。こういうのを心理学の世界でも、「記憶錯誤」という。子どもよりも、おとなのほうが、しかも不安状態であればあるほど、その錯誤が大きくなることが知られている。●上下意識は、もたない兄(姉)が上で、弟(妹)が下という、上下意識をもたない。……といっても、日本人からこの意識を抜くのは、容易なことではない。伝統的に、そういう意識をたたきこまれている。今でも、長子相続を本気で考えている人は多い。もしあなたがどこか権威主義的なものの考え方をしているようなら、まず、それを改める。●子どもの名前で、子どもを呼ぶ「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」ではなく、兄でも、姉でも、子ども自身の名前で、子どもを呼ぶ。たとえば子どもの名前が太郎だったら、「太郎」と呼ぶ。一般的に、たがいに名前で呼びあう兄弟(姉妹)は、仲がよいと言われている。●差別しない長男、長女は、下の子が生まれたときから、恒常的な愛情不足、欲求不満の状態に置かれる。親は「平等」というが、長男、長女にしてみれば、平等ということが、不平等なのである。そういう前提で、長男(長女)の心理を理解する。つまり長男(長女)のほうが、不平等に対して、きわめて敏感に反応しやすい。●嫉妬はタブー兄弟(姉妹)の間で、嫉妬感情をもたせない。これは子育ての鉄則と考えてよい。嫉妬は、確実に子どもの心をゆがめる。原始的な感情であるがゆえに、扱い方もむずかしい。この嫉妬がゆがむと、相手を殺すところまでする。兄弟(姉妹)を別々に扱うときも、たがいに嫉妬させないようにする。●たがいを喜ばせる兄弟を仲よくさせる方法として、「たがいを喜ばせる」がある。たとえばうち1人を買い物に連れていったときでも、「これがあると○○君、喜ぶわね」「△△ちゃん、喜ぶわね」というような買い与え方をする。いつも相手を喜ばすようにしむける。これはたがいの思いやりの心を育てるためにも、重要である。●決して批判しない子どもどうしの悪口を、決して言わない。聞かない。聞いても、判断しない。たとえば兄に何か問題があっても、それを絶対に(絶対に)、弟に告げ口してはいけない。告げ口した段階で、あなたと兄の関係は、壊れる。反対に兄が弟のことで、何か告げ口をしても、あなたは聞くだけ。決して相づちを打ったり、いっしょになって、兄を批判してはいけない。●得意面をさらに伸ばす子どもを伸ばすコツは、得意面をさらに伸ばし、不得意面については、目を閉じること。たとえば受験生でも、得意な英語を伸ばしていると、不得意だった数学も、つられるように伸び始めるということがよくある。「うちの子は、運動が苦手だから、体操教室へ……」という発想は、そもそも、その発想からしてまちがっている。子どもは(いやがる)→(ますます不得意になる)の悪循環を繰りかえすようになる。●悪循環を感じたら、手を引く子育てをしていて、どこかで悪循環を感じたら、すかさず、その問題から、手を引く。あきらめて、忘れる。あるいはほかの面に、関心を移す。「まだ、何とかなる」「そんなハズはない」と親ががんばればがんばるほど、話が、おかしくなる。深みにはまる。が、それだけではない。一度、この悪循環に入ると。それまで得意であった分野にまで、悪影響をおよぼすようになる。自信喪失から、自己否定に走ることもある。●子どもは、ほめて伸ばす『叱るときは、陰で。ほめるときは、みなの前で』は、幼児教育の大鉄則。もっとはっきり言えば、子どもは、ほめて伸ばす。仮にたどたどしい、読みにくい文字を書いたとしても、「ほほう、字がじょうずになったね」と。こうした前向きの強化が、子どもを伸ばす。この時期、子どもは、ややうぬぼれ気味のほうが、あとあと、よく伸びる。「ぼくはできる」「私はすばらしい」という自信が、子どもを伸ばす原動力になる。●孤立感と劣等感に注意家族からの孤立、友だちからの孤立など。子どもが孤立する様子を見せたら、要注意。「ぼくはダメだ」式の劣等感を見せたときも、要注意。この二つがからむと、子どものものの考え方は、急速に暗く、ゆがんでくる。外から見ると、「何を考えているかわからない」というようになれば、子どもの心は、かなり危険な状態に入ったとみてよい。家庭教育のあり方を、猛省する。●すなおな子ども従順で、親の言うことをハイハイと聞く子どもを、すなおな子どもというのではない。幼児教育の世界で、「すなおな子ども」というときは、心(情意)と、表情が一致している子どもをいう。感情表出がすなおにできる。うれしいときは、顔満面にその喜びをたたえるなど。反対にその子どもにやさしくしてあげると、そのやさしさが、スーッと子どもの心の中に、しみこんでいく感じがする。そういう子どもを、すなおな子どもという。●自己意識を育てる乳幼児期に、何らかの問題があったとする。しかしそうした問題に直面したとき、大切なことは、そうした問題にどう対処するかではなく、どうしたら、こじらせないか、である。たとえばADHD児にしても、その症状が現れてくると、たいていの親は、混乱状態になる。しかし子どもの自己意識が育ってくると、子どもは、自らをコントロールするようになる。そして見た目には、症状はわからなくなる。無理をすれば、症状はこじれる。そして一度、こじれると、その分だけ、立ちなおりが遅れる。●まず自分を疑う子どもに問題があるとわかると、親は、子どもをなおそうとする。しかしそういう視点では、子どもは、なおらない。たとえばよくある例は、親の過干渉、過関心で、子どもが萎縮してしまったようなばあい。親は「どうしてうちの子は、ハキハキしないのでしょう」と言う。そして子どもに向かっては、「どうしてあなたは、大きな声で返事ができないの!」と叱る。しかし原因は、親自身にある。それに気づかないかぎり、子どもは、なおらない。●「やればできるはず」は禁句たいていの親は、「うちの子は、やればできるはず」と思う。しかしそう思ったら、すかさず、「やってここまで」と思いなおす。何がそうかといって、親の過関心、過負担、過剰期待ほど、子どもを苦しめるものはない。それだけではない。かえって子どもの伸びる芽をつんでしまう。そこで子どもには、こう言う。「あなたは、よくがんばっているわよ。TAKE IT EASY!(気を楽にしてね)」と。●「子はかすがい」論たしかに子どもがいることで、夫婦が力を合わせるということはよくある。夫婦のきずなも、それで太くなる。しかしその前提として、夫婦は夫婦でなくてはならない。夫婦関係がこわれかかっているか、あるいはすでにこわれてしまったようなばあいには、子はまさに「足かせ」でしかない。日本には『子は三界の足かせ』という格言もある。●「親のうしろ姿」論生活や子育てで苦労している姿を、「親のうしろ姿」という。日本では『子は親のうしろ姿を見て育つ』というが、中には、そのうしろ姿を子どもに見せつける親がいる。「親のうしろ姿は見せろ」と説く評論家もいる。しかしうしろ姿など見せるものではない。(見せたくなくても、子どもは見てしまうかもしれないが、それでもできるだけ見せてはいけない。)恩着せがましい子育て、お涙ちょうだい式の子育てをする人ほど、このうしろ姿を見せようとする。●「親の威厳」論「親は威厳があることこそ大切」と説く人は多い。たしかに「上」の立場にいるものには、居心地のよい世界かもしれないが、「下」の立場にいるものは、そうではない。その分だけ、上のものの前では仮面をかぶる。かぶった分だけ、心を閉じる。威厳などというものは、百害あって一利なし。心をたがいに全幅に開きあってはじめて、「家族」という。「親の権威」などというのは、封建時代の遺物と考えてよい。●「育自」論は?よく、「育児は育自」と説く人がいる。「自分を育てることが育児だ」と。まちがってはいないが、子育てはそんな甘いものではない。親は子どもを育てながら、幾多の山を越え、谷を越えている間に、いやおうなしに育てられる。育自などしているヒマなどない。もちろん人間として、外の世界に大きく伸びていくことは大切なことだが、それは本来、子育てとは関係のないこと。子育てにかこつける必要はない。●「親孝行」論安易な孝行論で、子どもをしばってはいけない。いわんや犠牲的、献身的な「孝行」を子どもに求めてはいけない。強要してはいけない。孝行するかどうかは、あくまでも子どもの問題。子どもの勝手。親子といえども、その関係は、一対一の人間関係で決まる。たがいにやさしい、思いやりのある言葉をかけあうことこそ、大切。親が子どものために犠牲になるのも、子どもが親のために犠牲になるのも、決して美徳ではない。親子は、あくまでも「尊敬する」「尊敬される」という関係をめざす。●「産んでいただきました」論よく、「私は親に産んでいただきました」「育てていただきました」「言葉を教えていただきました」と言う人がいる。それはその人自身の責任というより、そういうふうに思わせてしまったその人の周囲の、親たちの責任である。日本人は昔から、こうして恩着せがましい子育てをしながら、無意識のうちにも、子どもにそう思わせてしまう。いわゆる依存型子育てというのが、それ。●「水戸黄門」論に注意日本型権威主義の象徴が、あの「水戸黄門」。あの時代、何がまちがっているかといって、身分制度(封建制度)ほどまちがっているものはない。その身分制度(=巨悪)にどっぷりとつかりながら、正義を説くほうがおかしい。日本人は、その「おかしさ」がわからないほどまで、この権威主義的なものの考え方を好む。葵の紋章を見せつけて、人をひれ伏せさせる前に、その矛盾に、水戸黄門は気づくべきではないのか。仮に水戸黄門が悪いことをしようとしたら、どんなことでもできる。ご注意!●「釣りバカ日誌」論男どうしで休日を過ごす。それがあのドラマの基本になっている。その背景にあるのが、「男は仕事、女は家庭」。その延長線上で、「遊ぶときも、女は関係なし」と。しかしこれこそまさに、世界の非常識。オーストラリアでも、夫たちが仕事の同僚と飲み食い(パーティ)をするときは、妻の同伴が原則である。いわんや休日を、夫たちだけで過ごすということは、ありえない。そんなことをすれば、即、離婚事由。「仕事第一主義社会」が生んだ、ゆがんだ男性観が、その基本にあるとみる。●「MSのおふくろさん」論夜空を見あげて、大のおとなが、「ママー、ママー」と泣く民族は、世界広しといえども、そうはいない。あの歌の中に出てくる母親は、たしかにすばらしい人だ。しかしすばらしすぎる。「人の傘になれ」とその母親は教えたというが、こうした美化論にはじゅうぶん注意したほうがよい。マザコン型の人ほど、親を徹底的に美化することで、自分のマザコン性を正当化する傾向がある。●「かあさんの歌」論窪田S氏作詞の原詩のほうでは、歌の中央部(三行目と四行目)は、かっこ(「」)つきになっている。「♪木枯らし吹いちゃ冷たかろうて。せっせと編んだだよ」「♪おとうは土間で藁打ち仕事。お前もがんばれよ」「♪根雪もとけりゃもうすぐ春だで。畑が待ってるよ」と。しかしこれほど、恩着せがましく、お涙ちょうだいの歌はない。親が子どもに手紙を書くとしたら、「♪村の祭に行ったら、手袋を売っていたよ。あんたに似合うと思ったから、買っておいたよ」「♪おとうは居間で俳句づくり。新聞にもときどき載るよ」「♪春になったら、村のみんなと温泉に行ってくるよ」だ。●「内助の功」論封建時代の出世主義社会では、『内助の功』という言葉が好んで用いられた。しかしこの言葉ほど、女性を蔑視した言葉もない。どう蔑視しているかは、もう論ずるまでもない。しかし問題は、女性自身がそれを受け入れているケースが多いということ。約23%の女性が、「それでいい」と答えている※。決して男性だけの問題ではないようだ。※……全国家庭動向調査(厚生省98)によれば、「夫も家事や育児を平等に負担すべきだ」という考えに反対した人が、23・3%もいることがわかった。 ●子育ては、考えてするものではないだれしも、「頭の中では、わかっているのですが、ついその場になると……」と言う。子育てというのは、もともと、そういうもの。そこでいつも同じようなパターンで、同じような失敗をするときは、(1)あなた自身の過去を冷静に見つめてみる。(2)何か(わだかまり)や(こだわり)があれば、まず、それに気づく。あとは時間が解決してくれる。●子育ては、世代連鎖する子育ては、世代を超えて、親から子へと、よいことも、悪いことも、そのまま連鎖する。またそういう部分が、ほとんどだと考えてよい。そういう意味で、「子育ては本能ではなく、学習によるもの」と考える。つまり親は子育てをしながら、実は、自分が受けた子育てを、無意識のうちに繰りかえしているだけだということになる。そこで重要なことは、悪い子育ては、つぎの世代に、残さないということ。これを昔の人、『因を断つ』と言った。●子育ての見本を見せる子育ての重要な点は、子どもを育てるのではなく、子育てのし方の見本を、子どもに見せるということ。見せるだけでは、足りない。子どもを包む。幸福な家庭というのは、こういうものだ。夫婦というのは、こういうものだ。家族というのは、こういうものだ、と。そういう(学習)があって、子どもは、親になったとき、はじめて、自分で子育てが自然な形でできるようになる。●子どもには負ける子どもに、勝とうと思わないこと。つまり親の優位性を見せつけないこと。どうせ相手にしてもしかたないし、本気で相手にしてはいけない。ときに親は、わざと負けて見せたり、バカなフリをして、子どもに自信をもたせる。適当なところで、親のほうが、手を引く。「こんなバカな親など、アテにならないぞ」「頼りにならない」と子どもが思うようになったら、しめたもの。●子育ては重労働子育ては、もともと重労働。そういう前提で、考える。自分だけが苦しんでいるとか、おかしいとか、子どもに問題があるなどと、考えてはいけない。しかしここが重要だがが、そういう(苦しみ)をとおして、親は、ただの親から、真の親へと成長する。そのことは、子育てが終わってみると、よくわかる。子育ての苦労が、それまで見えなかった、新しい世界を親に見せてくれる。子育ての終わりには、それがやってくる。どうか、お楽しみに!●自分の生きザマを!子育てをしながらも、親は、親で、自分の生きザマを確立する。「あなたはあなたで、勝手に生きなさい。私は私で、勝手に生きます」と。そういう一歩退いた目が、ともすればギクシャクとしがちな、親子関係に、風を通す。子どもだけを見て、子どもだけが視野にしか入らないというのは、それだけその人の生きザマが、小さいということになる。あなたはあなたで、したいことを、する。そういう姿が、子どもを伸ばす。●問題のない子育てはない子育てをしていると、子育てや子どもにまつわる問題は、つぎからつぎへと、起きてくる。それは岸辺に打ち寄せる波のようなもの。問題のない子どもはいないし、したがって、問題のない子育ては、ない。できのよい子ども(?)をもった親でも、その親なりに、いろいろな問題に、そのつど、直面する。できが悪ければ(?)、もっと直面する。子育てというのは、もともとそういうもの。そういう前提で、子育てを考える。●解決プロセスを用意する英文を読んでいて、意味のわからない単語にぶつかったら、辞書をひく。同じように、子育てで何かの問題にぶつかったら、どのように解決するか、そのプロセスを、まず、つくっておく。兄弟や親類に相談するのもよい。親に相談するのも、よい。何かのサークルに属するのもよい。自分の身にまわりに、そういう相談相手を用意する。が、一番よいのは、自分の子どもより、2、3歳年上の子どもをもつ、親と緊密になること。「うちもこうでしたよ」というアドバイスをもらって、たいていの問題は、その場で解決する。●動揺しない株取引のガイドブックを読んでいたら、こんなことが書いてあった。「プロとアマのちがいは、プロは、株価の上下に動揺しないが、アマは、動揺する。だからそのたびに、アマは、大損をする」と。子育ても、それに似ている。子育てで失敗しやすい親というのは、それだけ動揺しやすい。子どもを、月単位、半年単位で見ることができない。そのつど、動揺し、あわてふためく。この親の動揺が、子どもの問題を、こじらせる。●自分なら……賢い親は、いつも子育てをしながら、「自分ならどうか?」と、自問する。そうでない親は親意識だけが強く、「~~あるべき」「~~であるべきでない」という視点で、子どもをみる。そして自分の理想や価値観を、子どもに押しつけよとする。そこで子どもに何か問題が起きたら、「私ならどうするか?」「私はどうだったか?」という視点で考える。たとえば子どもに向かって「ウソをついてはダメ」と言ったら、「私ならどうか?」と。●時間を置く葉というのは、耳に入ってから、脳に届くまで、かなりの時間がかかる。相手が子どもなら、なおさらである。だから言うべきことは言いながらも、効果はすぐには、求めない。また言ったからといって、それですぐ、問題が解決するわけでもない。コツは、言うべきことは、淡々と言いながらも、あとは、時間を待つ。短気な親ほど、ガンガンと子どもを叱ったりするが、子どもはこわいから、おとなしくしているだけ。反省などしていない。●叱られじょうずな子どもにしない親や先生に叱られると、頭をうなだれて、いかにも叱られていますといった、様子を見せる子どもがいる。一見、すなおに反省しているかのように見えるが、反省などしていない。こわいからそうしているだけ。もっと言えば、「嵐が通りすぎるのを待っているだけ」。中には、親に叱られながら、心の中で歌を歌っていた子どももいた。だから同じ失敗をまた繰りかえす。●叱っても、人権を踏みにじらない先生に叱られたりすると、パッとその場で、土下座をしてみせる子どもがいる。いわゆる(叱られじょうずな子ども)とみる。しかしだからといって、反省など、していない。そういう形で、自分に降りかかってくる、火の粉を最小限にしようとする。子どもを叱ることもあるだろうが、しかしどんなばあいも、最後のところでは、子どもの人権だけは守る。「あなたはダメな子」式の、人格の「核」攻撃は、してはいけない。●子どもは、親のマネをするたいへん口がうまく、うそばかり言っている子どもがいた。しかしやがてその理由がわかった。母親自身もそうだった。教師の世界には、「口のうまい親ほど、要注意」という、大鉄則がある。そういう親ほど、一度、敵(?)にまわると、今度は、その数百倍も、教師の悪口を言い出す。子どもに誠実になってほしかったら、親自身が、誠実な様子を、日常生活の中で見せておく。●一事が万事論あなたは交通信号を、しっかりと守っているだろうか。もしそうなら、それでよし。しかし赤信号でも、平気で、アクセルを踏むようなら、注意したほうがよい。あなたの子どもも、あなたに劣らず、小ズルイ人間になるだけ。つまり親が、小ズルイことをしておきながら、子どもに向かって、「約束を守りなさい」は、ない。ウソはつかない。約束は守る。ルールには従う。そういう親の姿勢を見ながら、子どもは、(まじめさ)を身につける。●代償的過保護に注意「子どもはかわいい」「私は子どもを愛している」と、豪語する親ほど、本当のところ、愛が何であるか、わかっていない。子どもを愛するということは、それほどまでに、重く、深いもの。中には、子どもを自分の支配下において、自分の思いどおりにしたいと考えている親もいる。これを代償的過保護という。一見、過保護に見えるが、その基盤に愛情がない。つまりは、愛もどきの愛を、愛と錯覚しているだけ。●子どもどうしのトラブルは、子どもに任す子どもの世界で、子どもどうしのトラブルが起きたら、子どもに任す。親の介入は、最小限に。そういうトラブルをとおして、子どもは、子どもなりの問題解決の技法を身につけていく。親としてはつらいところだが、1にがまん、2にがまん。親が口を出すのは、そのあとでよい。もちろん子どものほうから、何かの助けを求めてきたら、そのときは、相談にのってやる。ほどよい親であることが、よい親の条件。●許して忘れ、あとはあきらめる子どもの問題は、許して、忘れる。そしてあとはあきらめる。「うちの子にかぎって……」「そんなはずはない」「まだ何とかなる」と、親が考えている間は、親に安穏たる日々はやってこない。そこで「あきらめる」。あきらめると、その先にトンネルの出口を見ることができる。子どもの心にも風が通るようになる。しかしヘタにがんばればがんばるほど、親は、袋小路に入る。子どもも苦しむ。 ●強化の原理子どもが、何かの行動をしたとする。そのとき、その行動について、何か、よいことが起きたとする。ほめられるとか、ほうびがもらえるとか。あるいは心地よい感覚に包まれるとか。そういう何かよいことが起こるたびに、その行動は、ますます強化される。これを「強化の原理」という。子どもの能力をのばすための大鉄則ということになる。●弱化の原理強化の原理に対して、弱化の原理がある。何か、行動をしたとき、つまずいたり、失敗したり、叱られたりすると、子どもは、やる気をなくしたり、今度は、その行動を避けるようになる。これを弱化の原理という。子どもにもよるし、ケースにもよるが、一度弱化の原理が働くようになると、学習効果は、著しく落ちるようになる。●内面化子どもは成長とともに、身長がのび、体重が増加する。これを外面化というのに対して、心の発達を、内面化という。その内面化は、(1)他者との共鳴性(自己中心性からの脱却)、(2)自己管理能力、(3)良好な人間関係をみるとよい(EQ論)。ほかに道徳規範や倫理観の発達、社会規範や、善悪の判断力などを、ふくめる。心理学の世界では、こうした発達を総称して、「しつけ」という。●子どもの意欲子どもは、親、とくに母親の意欲を見ながら、自分の意欲を育てる。一般論として、意欲的な母親の子どもは、意欲的になる。そうでない母親の子どもは、そうでない。ただし、母親が意欲的過ぎるのも、よくない。昔から、『ハリキリママのションボリ息子』と言われる。とくに子どもに対しては、ほどよい親であることが望ましい。任すところは子どもに任せ、一歩退きながら、暖かい無視を繰りかえす。それが子育てのコツということになる。●ほどよい目標過負担、過剰期待ほど、子どもを苦しめるものはない。そればかりではない。自信喪失から、やる気をなくしてしまうこともある。仮に一時的にうまくいっても、オーバーヒート現象(燃え尽き症候群、荷卸し症候群)に襲われることもある。子どもにとって重要なことは、達成感。ある程度がんばったところで、「できた!」という喜びが、子どもを伸ばす。子どもには、ほどよい目標をもたせるようにする。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(029)●●アメリカ厚生省発表●●【新型インフル対策で米政府】 【ワシントン1月6日共同】レビット・アメリカ厚生長官は6日、発生への危機感が高まっている、新型インフルエンザの大流行に備え、食料や飲料水の買いだめなどを一般家庭に勧める手引を発表した。 新型ウイルスの感染を防ぐワクチンはなく、大流行で食品流通など社会機能が、まひする恐れがあるため。ロイター通信は、「予防のためにできることがいかに少ないかを物語るものだ」と伝えた。 手引は「調理せずに食べられる肉や野菜、スープの缶詰やクラッカー、ミネラルウオーター」など非常食のほか、解熱剤やビタミン剤などの備蓄も推奨。子供を持つ親には「せっけんで手を頻繁に洗い、せきやくしゃみは口を覆ってするよう教育を」と、感染の機会を減らすよう求めた。++++++++++++++++++【BW教室のみなさん・おうちの方へ】専門家たちは、みな、異口同音に、今後起こるかもしれない、「新型インフルエンザ」の脅威を口にする。「新型インフルエンザにしてみれば、ふつうのインフルエンザなど、ただの風邪のようなもの」と。 で、その新型インフルエンザが、一度、流行し始めると、学校や幼稚園は、もちろん閉鎖。職場すらも、閉鎖になる可能性がきわめて高い。そうなれば、「社会機能はまひする」(ロイター通信)。 そこで今度、アメリカの厚生省長官は、上記のように、国民に、手引きを発表した。そしてつぎのようなものを、各家庭で備蓄するようにと勧告している。(1)食糧や飲料水の買いだめ(2)解熱剤やビタミン剤の買いだめ、など。 すでに外国では、ちらほらと、新型インフルエンザの発生が認められつつある。死亡者も、ふえている。死亡率は、約50%というところか? つまり新型インフルエンザに感染したら、約50%の人が死ぬということらしい。 とりあえず、私の家庭でも、つぎのように考えている。もしこの日本で、新型インフルエンザの感染者が確認されたら、(1)使い捨てマスクを、大量に購入する。(2)調理せずに食べられる食品の備蓄を開始する。(3)ビタミン類、とくにビタミンC(アスコルビン酸)などの購入。 もちろん、BW教室は、学校閉鎖に合わせて、閉鎖。その間、月謝などの費用は、免除。学校が再開されたら、BW教室も、再開。 今後しばらくは、様子をみながら、咳、くしゃみをする児童については、マスクをかけることを徹底する。(マスクは、教室で用意。)なお、今後は、消毒薬を教室の入り口に常備し、感染の拡大を阻止する。(おうちの方へ) たとえば6月の中ごろ(6月15日なら、6月15日とします)、新型インフルエンザが発生し、学校が、学校単位で閉鎖されたようなときには、BW教室も、同時に閉鎖します。 で、そのとき、すでにいただきました、6月分の残りの月謝は、お返しでできませんが、つぎに新型インフルエンザの感染が止まり、学校閉鎖が解かれたようなとき、たとえば、9月15日から学校が再開されたようなときは、BW教室も再開。その翌月分の10月分から月謝をいただきます。6月分の残りの月謝を、9月分に充当させていただき、7月分、8月分の月謝は、いただかないようにします。 新型インフルエンザの流行期に重なった、7月、8月分の月謝は、免除します。BW教室としては、無収入ということになりますが、何とか、がんばりますので、よろしくご理解の上、ご協力ください。BW・はやし浩司Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(14)
最前線の子育て論byはやし浩司(027)【子育て一口メモ】++++++++++++++++++今度、有料版で、「子育て一口メモ」を冊子にすることにしました。まぐまぐ社のPODサービスを利用します。定価は、850円!購入方法などは、HPのほうで、紹介しますので、もし購入してくださる方がいらっしゃれば、どうか、よろしくお願いします。……ということで、今日は、特別サービス!マガジンのほうで、その「一口メモ」を、無料で読んでいただけるよう、ここに、掲載することにしました。ここに掲載するのは、その一部です。全体をご希望の方は、HPか、もしくは、POD版をご購入ください。++++++++++++++++++【子育て一口メモ】● 父親(母親)の悪口は、言わない心理学の世界にも、「三角関係」という言葉がある。父親が母親の悪口を言ったり、批判したりすると、夫婦の間に、キレツが入る。そして父親と母親、母親と子ども、子どもと父親の間に、三角関係ができる。子どもが幼いうちはまだしも、一度、この三角関係ができると、子どもは、親の指示に従わなくなる。つまりこの時点で、家庭教育は、崩壊する。● 逃げ場を大切にどんな動物にも、最後の逃げ場というのがある。子どもも、またしかり。子どもは、その逃げ場に逃げ込むことによって、身の安全をはかり、心をいやす。たいていは自分の部屋ということになる。その逃げ場を荒らすようになると、子どもの心は、一挙に不安定になる。だから子どもが逃げ場に逃げたら、その逃げ場を荒らすようなことはしてはいけない。●心は、ぬいぐるみで……年長児にぬいぐるみを見せると、「かわいい」と言って、やさしそうな表情を見せる子どもが、約80%。しかし残りの20%は、ほとんど、反応を示さない。示さないばかりか、中には、キックしてくる子どもがいる。小学校の高学年児でも、日常的にぬいぐるみをもっている子どもは、約80%。男女の区別はない。子どもの中に、親像が育っているかどうかは、ぬいぐるみを抱かせてみるとわかる。●国語教育は、言葉から子どもの国語力は、母親の会話能力によって決まる。たとえば幼稚園バスがやってきたとき、「ほらほら、バス。ハンカチは? 帽子は? 急いで」というような言い方を、母親がしていて、どうして子どもの中に、国語力が育つというのか。そういうときは、めんどうでも、「バスがきます。あなたは急いで、外に行きます。ハンカチをもっていますか。帽子をかぶっていますか」と話す。そういう母親の会話力が、子どもの国語力の基本になる。●計算力は、早数えで……「ヒトツ、フタツ、ミッツ……」と数えられるようになったら、早数えの練習をする。「イチ、ニ、サン……」から、さらに、「イ、ニ、サ、シ、ゴ、ロ、シ、ハ、ク、ジュウ」と。さらに手をパンパンとたたいてみせ、それを数えさせる。なれてくると、子どもは、数を信号化する。たとえば「2足す3」も、「ピ、ピ、と、ピ、ピ、ピで、5」と。これを数の信号化という。この力が、計算力の基礎となる。●やさしさは苦労からためしにあなたの子どもの前で、重い荷物をもって、苦しそうな表情をして歩いてみてほしい。そのとき、「ママ(パパ)、助けてあげる!」と言って走り寄ってくればよし。そうでなく、テレビやゲームに夢中になっているようなら、かなりのドラ息子(娘)とみてよい。今は、(かわいい子)かもしれないが、やがて手に負えなくなる。子どもは(おとなも)、自分で苦労をしてみてはじめて、他人の苦労がわかるようになる。やさしさも、そこから生まれる。●釣りザオを買ってやるより……イギリスの教育格言に、『釣りザオを買ってやるより、いっしょに、釣りに行け』というのがある。子どもの心をつかみたかったら、そして親子のキズナを太くしたかったら、いっしょに釣りに行け、と。多くの人は、子どものほしがるものを与えて、それで子どもは喜んでいるはず。感謝しているはず。親子のキズナも、それで太くなったはずと考える。しかしこれは幻想。誤解。むしろ逆効果。●100倍論子ども、とくに幼児に買い与えるものは、100倍してえる。たとえば100円のものでも、100倍して、1万円と考える。安易に、お金で、子どもの欲望を満足させてはいけない。一度、お金で、満足させることを覚えてしまうと、年齢とともに、その額は、10倍、100倍とエスカレートしていく。高校生や大学生になるころには、1000円や1万円では、満足しなくなる。子どもが幼児のときから、慎重に!●子どもは、信じて伸ばす心理学の世界にも、「好意の返報性」という言葉がある。イギリスの格言にも、『相手は、あなたが相手を思うように、あなたのことを思う』というのがある。あなたがその人を、いい人だと思っていると、その相手も、あなたをいい人だと思っている。しかしそうでなければそうでない。子どものばあいは、さらにそれがはっきりと現れる。だから子どもを伸ばしたいと思うなら、まず自分の子どもをいい子どもだと思うこと。子どもを伸ばす、大鉄則である。●強化の原理前向きに伸びているという実感が、子どもを伸ばす。そのため、「あなたはどんどんよくなる」「すばらしくなる」という暗示を、そのつど、子どもにかけていく。まずいのは、未来に不安をいだかせること。仮に子どもを叱っても、そのあと何らかの方法でそれをカバーして、「ほら、やっぱり、できるじゃない!」と、ほめて仕あげる。●叱るときの原則子どもを叱るときは、自分の姿勢を低く落とし、子どもの目線の高さに自分の目目線の高さをあわせる。つぎに子どもの両肩を、やや力を入れて両手でつかみ、子どもの目をしっかりと見つめて叱る。大声を出して、威圧したり、怒鳴ってはいけない。恐怖心をもたせても意味はない。中に叱られじょうずな子どもがいて、いかにも反省していますというような様子を見せる子どもがいる。しかしそういう姿に、だまされてはいけない。●仮面に注意絶対的なさらけ出しと、絶対的な受け入れ。この基盤の上に、親子の信頼関係が築かれる。「絶対的」というのは、「疑いすらもたない」という意味。あなたの子どもが、あなたの前で、そうであればよし。しかしあなたの前で、いい子ぶったり、仮面をかぶったりしているようであれば、親子の関係は、かなり危機的な状況にあると考えてよい。あなたから見て、「何を考えているかわからない」というのであれば、さらに要注意。●根性・がんこ・わがまま子どもの根性、がんこ、わがままは、分けて考える。がんばって何か一つのことをやりとげるというのは、根性。何かのことにこだわりをもち、それに固執することを、がんこ。理由もなく、自分の望むように相手を誘導しようとするのが、わがままということになる。その根性は、励まして伸ばす。がんこについては、子どもの世界では望ましいことではないので、その理由と原因をさぐる。わがままについては、一般的には、無視して対処する。●アルバムを大切におとなは過去をなつかしんで、アルバムを見る。しかし子どもは、自分の未来を見るために、アルバムを見る。が、それだけではない。アルバムには、心をいやす作用がある。それもそのはず。悲しいときやつらいときを、写真にとって残す人は、少ない。つまりアルバムには、楽しい思い出がぎっしり。そんなわけで、親子の絆(きずな)を太くするためにも、アルバムを、部屋の中央に置いてみるとよい。●名前を大切に子どもの名前は大切にする。「あなたの名前は、すばらしい」「いい名前だ」と、ことあるごとに言う。子どもは、自分の名前を大切にすることをとおして、自尊心を学ぶ。そしてその自尊心が、何かのことでつまずいたようなとき、子どもの進路を、自動修正する。たとえば子どもの名前が、新聞や雑誌に載ったようなときは、それを切り抜いて、高いところに張ったりする。そういう親の姿勢を見て、子どもは、名前のもつ意味を知る。●子どもの体で考える体重10キロの子どもに缶ジュースを一本与えるということは、体重50キロのおとなが、5本、飲む量に等しい。そんな量を子どもに与えておきながら、「どうしてうちの子は、小食なのかしら」は、ない。子どもに与える量は、子どもの体で考える。●CA、MGの多い食生活を!イギリスでは、『カルシウムは、紳士をつくる』と言う。静かで落ちついた子どもにしたかったら、CA(カルシウム)、MG(マグネシウム)の多い食生活、つまり海産物を中心とした献立にする。こわいのは、ジャンクフード。さらにリン酸添加物の多い、食べもの。いわゆるレトルト食品、インスタント食品類である。リン酸は、CAの大敵。CAと化合して、リン酸カルシウムとして、CAは、体外へ排出されてしまう。●親の仕事はすばらしいと言う親が生き生きと仕事をしている姿ほど、子どもに安心感を与えるものは、ない。が、それだけではない。中に、自分の子どもに、親の仕事を引き継がせたいと考えている人もいるはず。そういうときは、常日ごろから、「仕事は楽しい」「おもしろい」を口ぐせにする。あるいは「私の仕事はすばらしい」「お父さんの仕事は、すばらしい」を口ぐせにする。まちがっても、暗い印象をもたせてはいけない。●はだし教育を大切に将来、運動能力のある子どもにしたかったら、子どもは、はだしにして育てる。子どもは、足の裏からの刺激を受けて、敏捷性(びんしょうせい)のある子どもになる。この敏捷性は、あらゆる運動能力の基本となる。分厚い靴下と、分厚い底の靴をはかせて、どうしてそれで敏捷性のある子どもになるのか。今、坂や階段を、リズミカルにのぼりおりできない子どもがふえている。川原の石の上に立つと、「こわい」と言って動けなくなる子どもも多い。どうか、ご注意!●自己中心性は、精神的未熟さの証拠相手の心の中に、一度入って、相手の立場で考える。これを心理学の世界でも、「共鳴性」(サロヴェイ「EQ論」)という。それができる人を、人格の完成度の高い人という。そうでない人を、低い人という。学歴や地位とは、関係ない。ないばかりか、かえってそういう人ほど、人格の完成度が低いことが多い。そのためにも、まず親のあなたが、自分の自己中心性と戦い、子どもに、その見本を見せるようにする。●役割形成を大切に子どもが「お花屋さんになりたい」と言ったら、すかさず「すてきね」と言ってあげる。「いっしょに、お花を育ててみましょうね」「今度、図書館で、お花なの図鑑をみましょうね」と言ってあげる。こうすることで、子どもは、自分の身のまわりに、自分らしさをつくっていく。これを「個性化」という。この個性化が、やがて、子どもの役割となり、夢、希望、そして生きる目的へとつながっていく。●父親の二大役割母子関係は重要であり、絶対的なものである。しかしその母子関係が濃密過ぎるのも、また子どもが大きくなったとき、そのままの状態でも、よくない。その母子関係に、くさびを打ち込み、是正していくのが、父親の役割ということになる。ほかに、社会性を教えるのも、重要な役割。昔で言えば、子どもを外の世界に連れ出し、狩の仕方を教えるのが、父親の役割ということになる。●欠点は、ほめる子どもに何か、欠点を見つけたら、ほめる。たとえば参観授業で、ほとんど手をあげなかったとしても、「手をもっと、あげなさい」ではなく、「この前より、手がよくあがるようになったわね」と言うなど。子どもが皆の前で発表したようなときも、そうだ。「大きな声で言えるようになったわね」と。押してだめなら、思い切って引いてみる。子どもを伸ばすときに、よく使う手である。●負けるが、勝ちほかの世界でのことは、別として、間に子どもをはさんでいるときは、『負けるが勝ち』。これは父母どうしのつきあい、先生とのつきあいの、大鉄則である。悔しいこともあるだろう。言いたいこともあるだろう。しかしそこはぐっとがまんして、「負ける」。大切なことは、子どもが、楽しく、園や学校へ行けること。あなたのほうから負けを認めれば、そのときから人間関係は、スムーズに流れる。あなたががんばればがんばるほど、事態はこじれる。●ベッドタイム・ゲームを大切に子どもは(おとなも)、寝る前には、決まった行動を繰りかえすことが知られている。これをベッドタイム・ゲームという、日本語では、就眠儀式という。このしつけに失敗すると、子どもは眠ることに恐怖心をいだいたり、さらにそれが悪化すると、情緒が不安定になったりする。いきなりふとんの中に子どもを押しこみ、電気を消すような乱暴なことをしてはいけない。子どもの側からみて、やすらかな眠りをもてるようにする。●エビでタイを釣る「名前を書いてごらん」と声をかけると、体をこわばらせる子どもが、多い。年長児でも、10人のうち、3、4人はいるのでは。中には、涙ぐんでしまう子どももいる。文字に対して恐怖心をもっているからである。原因は、親の神経質で、強圧的な指導。この時期、一度、文字嫌いにしてしまうと、あとがない。この時期は、子どもがどんな文字を書いても、それをほめる。読んであげる。そういう努力が、子どもを文字好きにする。まさに『エビでタイを釣る』の要領である。●子どもは、人の父空に虹を見るとき、私の心ははずむ。私が子どものころも、そうだった。人となった今も、そうだ。願わくは、私は歳をとっても、そうでありたい。子どもは、人の父。自然の恵みを受けて、それぞれの日々が、そうであることを、私は願う。(ワーズワース・イギリスの詩人)●冷蔵庫をカラにする子どもの小食で悩んだら、冷蔵庫をカラにする。ついでに食べ物の入った棚をカラにする。そのとき、食べ物を、袋か何かに入れて、思い切って捨てるのがコツ。「もったいない」と思ったら、なおさら、そうする。「もったいない」という思いが、つぎからの買い物グセをなおす。子どもの小食で悩んでいる家庭ほど、家の中に食べ物がゴロゴロしているもの。そういう買い物グセが、習慣になっている。それを改める。●正しい発音で……世界広しといえども、幼児期に、子どもに発音教育をしないのは、恐らく日本くらいなものではないか。日本人だから、ほうっておいても、日本語を話せるようになると考えるのは、甘い。子どもには、正しい発音で、息をふきかけながら話すとよい。なお文字学習に先立って、音の分離を教えておくとよい。たとえば、「昨日」は、「き・の・う」と。そのとき、手をパンパンと叩きながら、一音ずつ、子どもの前で、分離してやるとよい。●よい先生は、1、2歳、年上の子ども子どもにとって、最高の先生は、1、2歳年上で、めんどうみがよく、やさしい子ども。そういう子どもが、身近にいたら、無理をしてでも、そういう子どもと遊んでもらえるようにするとよい。「無理をして」というのは、親どうしが友だちになるつもりで、という意味。あなたの子どもは、その子どもの影響を受けて、すばらしく伸びる。●ぬり絵のすすめ手の運筆能力は、丸を描かせてみるとわかる。運筆能力のある子どもは、スムーズで、きれいな丸を描く。そうでない子どもは、ぎこちない、多角形に近い丸をかく。もしあなたの子どもが、多角形に近い丸を描くようなら、文字学習の前に、塗り絵をしてくとよい。小さなマスなどを、縦線、横線、曲線などをまぜて、たくみに塗れるようになればよし。●ガムをかませるもう15年ほど前のことだが、アメリカの「サイエンス」と雑誌に、「ガムをかむと、頭がよくなる」という研究論文が発表された。で、その話を、年中児をもっていた母親に話すと、「では」と言って、自分の子どもにガムをかませるようになった。で、それから4、5年後。その子どもは、本当に頭がよくなってしまった。それからも、私は、何度も、ガムの効用を確認している。この方法は、どこかボーッとして、生彩のない子どもに、とくに効果的である。●マンネリは大敵変化は、子どもの知的能力を刺激する。その変化を用意するのは、親の役目。たとえばある母親は、一日とて、同じ弁当をつくらなかった。その子どもは、やがて日本を代表する、教育評論家になった。こわいのは、マンネリ化した生活。なお一般論として、よく「転勤族の子どもは、頭がいい」という。それは転勤という変化が、子どもの知能によい刺激になっているからと考えられる。●本は抱きながら読む子どもに本を読んであげるときは、子どもを抱き、暖かい息をふきかけながら、読んであげるとよい。子どもは、そういうぬくもりを通して、本の意味や文字のすばらしさを学ぶ。こうした積み重ねがあってはじめて、子どもは、本好きになる。なお、「読書」は、あらゆる学習の基本となる。アメリカには、「ライブラリー」という時間があって、読書指導を、学校教育の基本にすえている。●何でも握らせる子どもには、何でも握らせるとよい。手指の感覚は、そのまま、脳細胞に直結している。その感触が、さらに子どもの知的能力を発達させる。今、ものを与えても、手に取らない子どもがふえている。(あくまでも、私の印象だが……。)反面、好奇心が旺盛で、頭のよい子どもほど、ものを手にとって調べる傾向が強い。●才能は見つけるもの子どもの才能は、つくるものではなく、見つけるもの。ある女の子は、2歳くらいのときには、風呂にもぐって遊んでいた。そこで母親が水泳教室に入れてみると、水を得た魚のように泳ぎ出した。そのあとその女の子は、高校生のときには、総体に出るまでに成長した。また別の男の子(年長児)は、スイッチに興味をもっていた。そこで父親がパソコンを買ってあげると、小学3年生のときには、自分でプログラムを組んでゲームをつくるようにまでなった。子どもの才能を見つけたら、時間とお金を惜しみなく注ぐのがコツ。●「してくれ」言葉に注意日本語の特徴かもしれない。しかし日本人は、何かを食べたいときも、「食べたい」とは言わない。「おなかが、すいたア。(だから何とかしてくれ)」というような言い方をする。ほかに、「たいくつウ~(だから何とかしてくれ)」「つまらないイ~(だから何とかしてくれ)」など。老人でも、若い人に向って、「私も歳をとったからねエ~(だから大切にしてほしい)」というような言い方をする。日本人が、依存性の強い民族だと言われる理由の一つは、こんなところにもある。●人格の完成度は、共鳴性でみる他人の立場で、その他人の心の中に入って、その人の悲しみや苦しみを共有できる人のことを、人格の完成度の高い人という。それを共鳴性という(サロヴェイ・「EQ論」)。その反対側にいる人を、ジコチューという。つまり自己中心的であればあるほど、その人の人格の完成度は、低いとみる。ためしにあなたの子どもの前で、重い荷物をもって歩いてみてほしい。そのときあなたの子どもが、さっと助けにくればよし。そうでなく、知らぬフリをしているようなら、人格の完成度は、低いとみる。●平等は、不平等下の子が生まれると、そのときまで、100%あった、親の愛情が、半減する。親からみれば、「平等」ということになるが、上の子からみれば、50%になったことになる。上の子は、欲求不満から、嫉妬したり、さらには、心をゆがめる。赤ちゃんがえりを起こすこともある。それまでしなかった、おもらしをしたり、ネチネチ甘えたりするなど。下の子に対して攻撃的になることもある。嫉妬がからんでいるだけに、下の子を殺す寸前までのことをする。平等は、不平等と覚えておくとよい。●イライラゲームは、禁物ゲームにもいろいろあるが、イライラが蓄積されるようなゲームは、幼児には、避ける。動きが速いだけの、意味のないゲームも避ける。とくに、夕食後から、就眠するまでの間は、禁物。以前だが、夜中に飛び起きてまで、ゲームをしていた子ども(小5)がいた。そうなれば、すでに(ビョーキ)と言ってもよい。子どもには、さまざまな弊害が現れる。「ゲーム機器は、パパのもの。パパの許可をもらってから遊ぶ」という前提をつくるのもよい。遊ばせるにしても、時間と場所を、きちんと決める。●おもちゃは、一つあと片づけに悩んでいる親は、多い。そういうときは、『おもちゃは、一つ』と決めておくとよい。「つぎのおもちゃで遊びたかったら、前のおもちゃを片づける」という習慣を大切にする。子どもは、つぎのおもちゃで遊びたいがため、前のおもちゃを片づけるようになる。●何でも半分子どもに自立を促すコツがこれ。『何でも半分』。たとえば靴下でも、片方だけをはかせて、もう片方は、子どもにはかせる。あるいは途中まではかせて、あとは、子どもにさせる。これは子どもを指導するときにも、応用できる。最後の完成は、子どもにさせ、「じょうずにできるようになったわね」と言って、ほめてしあげる。手のかけすぎは、子どものためにならない。●核(コア)攻撃はしない子どもの人格そのものに触れるような、攻撃はしない。たとえば「あなたは、やっぱりダメ人間よ」「あんたなんか、人間のクズよ」「あんたさえいなければ」と言うなど。こうした(核)攻撃が日常化すると、子どもの精神の発達に、さまざまな弊害が現れてくる。子どもを責めるとしても、子ども自身が、自分の力で解決できる範囲にする。子ども自身の力では、どうにもならないことで責めてはいけない。それが、ここでいう(核)攻撃ということになる。●引き金を引かない仮に心の問題の「根」が、生まれながらにあるとしても、その引き金を引くのは、親ということになる。またその「根」というのは、だれにでもある。またそういう前提で、子どもを指導する。たとえば恐怖症にしても、心身症にしても、そういった状況におかれれば、だれでも、そうなる。たった一度、はげしく母親に叱られたため、その日を境に、一人二役の、ひとり言をいうようになってしまった女の子(2歳児)がいた。乳幼児の子どもほど、穏やかで、心静かな環境を大切にする。●二番底、三番底に注意子どもに何か問題が起きると、親は、そのときの状態を最悪と思い、子どもをなおそうとする。しかしその下には、二番底、さらには三番底があることを忘れてはいけない。たとえば門限を破った子どもを叱ったとする。しかしそのとき叱り方をまちがえると、外泊(二番底)、さらには家出(三番底)へと進んでいく。さらに四番底もある。こうした問題が起きたら、それ以上、状況を悪くしないことだけを考えて、半年、1年単位で様子をみる。●あきらめは、悟りの境地押してもダメ、引いても、ダメ。そういうときは、思い切ってあきらめる。が、子どもというのは、不思議なもの。あきらめたとたん、伸び始める。親が、「まだ何とかなる」「こんなはずはない」とがんばっている間は、伸びない。が、あきらめたとたん、伸び始める。そこは、おおらかで、実にゆったりとした世界。子育てには、行きづまりは、つきもの。そういうときは、思い切って、あきらめる。そのいさぎのよさが、子どもの心に風穴をあける。●自らに由らせる子育ての要(かなめ)は、「自由」。「自らに由(よ)らせる」。だから自由というのは、自分で考えさせる。自分で行動させる。そして自分で責任を取らせることを意味する。好き勝手なことを、子どもにさせることではない。親の過干渉は、子どもから考える力をうばう。親の過保護は、子どもから、行動力をうばう。そして親のでき愛は、子どもから責任感をうばう。子育ての目標は、子どもを自立させること。それを忘れてはいけない。●旅は、歩く便利であることが、よいわけではない。便利さに甘えてしまうと、それこそ生活が、地に足がつかない状態になる。……というだけではないが、たとえば旅に出たら、歩くように心がけるとよい。車の中から、流れるようにして見る景色よりも、一歩、一歩、歩きながら、見る景色のほうが、印象に強く残る。しかし、これは人生そのものに通ずる、大鉄則でもある。いかにして、そのときどきにおいて、地に足をつけて生きるか。そういうことも考えながら、旅に出たら、ゆっくりと歩いてみるとよい。●指示は、具体的に「友だちと仲よくするのですよ」「先生の話をしっかりと聞くのですよ」と子どもに言っても、ほとんど、意味がない。具体性がないからである。そういうときは、「これを○君にもっていってあげてね。○君、きっと喜ぶわよ」「学校から帰ってきたら、先生がどんな話をしたか、あとでママに話してね」と言う。子どもに与える指示には、具体性をもたせるとよい。●休息を求めて、疲れるイギリスの格言に、『休息を求めて疲れる』というのがある。愚かな生き方の代名詞にもなっている格言である。幼稚園教育は小学校へ入学するため。小学校教育は、中学校へ入学するため。中学校や高校教育は、大学へ入学するため……、というのが、その愚かな生き方になる。やっと楽になったと思ったら、人生が終わっていたということにもなりかねない。●子どもの横を歩く親には、三つの役目がある。ガイドとして、子どもの前を歩く。保護者として、子どものうしろを歩く。そして友として、子どもの横を歩く。日本人は、概して言えば、ガイドと保護者は得意。しかし友として、子どもの横を歩くのが苦手。もしあなたがいつも、子どもの手を引きながら、「早く」「早く」と言っているようなら、一度、子どもの歩調に合わせて、ゆっくりと歩いてみるとよい。それまで見えなかった、子どもの心が、あなたにも、見えてくるはず。●先生の悪口、批評はしない学校から帰ってきて子どもが先生の悪口を言ったり、批評したりしても、決して、相づちを打ったり、同意したりしてはいけない。「あなたが悪いからでしょう」「あの先生は、すばらしい人よ」と、それをはねかえす。親が先生の悪口を言ったりすると、子どもはその先生に従わなくなる。これは学校教育という場では、決定的にまずい。もし先生に問題があるなら、子どもとは関係のない世界で処理する。●子育ては楽しむ子どもを伸ばすコツは、子どものことは、あまり意識せず、親が楽しむつもりで、楽しむ。その楽しみの中に、子どもを巻き込むようにする。つまり自分が楽しめばよい。子どもの機嫌をとったり、歓心を買うようなことは、しない。コビを売る必要もない。親が楽しむ。私も幼児にものを教えるときは、自分がそれを楽しむようにしている。●ウソはていねいにつぶす子どもの虚言にも、いろいろある。頭の中で架空の世界をつくりあげてしまう空想的虚言、ありもしないことを信じてしまう妄想など。イギリスの教育格言にも、『子どもが空中の楼閣に住まわせてはならない』というのがある。過関心、過干渉などが原因で、子どもは、こうした妄想をもちやすくなる。子どもがウソをついたら、叱っても意味はない。ますますウソがうまくなる。子どもがウソをついたら、あれこれ問いかけながら、静かに、ていねいに、それをつぶす。そして言うべきことは言っても、あとは、無視する。●本物を与える子どもに見せたり、聞かせたり、与えたりするものは、いつも、本物にこころがける。絵でも、音楽でも、食べ物でも、である。今、絵といえば、たいはんの子どもたちは、アニメの主人公のキャラクターを描く。歌といっても、わざと、どこか音のずれた歌を歌う。食べ物にしても、母親が作った料理より、ファミリーレストランの料理のほうが、おいしいと言う。こういう環境で育つと、人間性まで、ニセモノになってしまう(?)。今、外からの見栄えばかり気にする子どもがふえているので、ご注意!●ほめるのは、努力とやさしさ子どもは、ほめて伸ばす。それはそのとおりだが、ほめるのは、子どもが努力したときと、子どもがやさしさを見せたとき。顔やスタイルは、ほめないほうがよい。幼いときから、そればかりをほめると、関心が、そちらに向いてしまう。また「頭」については、慎重に。「頭がいい」とほめすぎるのも、またまったくほめないのも、よくない。ときと場所をよく考えて、慎重に!●親が、前向きに生きる親自身に、生きる目的、方向性、夢、希望があれば、よし。そういう姿を見て、子どももまた、前向きに伸びていく。親が、生きる目的もない。毎日、ただ何となく生きているという状態では、子どももまた、その目標を見失う。それだけではない。進むべき目的をもたない子どもは、悪の誘惑に対して抵抗力を失う。子育てをするということは、生きる見本を、親が見せることをいう。生きザマの見本を、親が見せることをいう。●機嫌をとらない子どもに嫌われるのを恐れる親は、多い。依存性の強い、つまりは精神的に未熟な親とみる。そして(子どもにいい思いをさせること)イコール、(子どもをかわいがること)と誤解する。子どもがほしがりそうなものを買い与え、それで親子のキズナは太くなったはずと考えたりする。が、実際には、逆効果。親は親として……というより、一人の人間として、き然と生きる。子どもは、そういう親の姿を見て、親を尊敬する。親子のキズナも、それで太くなる。●親のうしろ姿を見せつけない生活で苦労している姿……それを日本では、「親のうしろ姿」という。そのうしろ姿を、親は見せたくなくても、見せてしまう。しかしそのうしろ姿を、子どもに押し売りしてはいけない。つまり恩着せがましい子育てはしない。「産んでやった」「育ててやった」「お前を大きくするために、私は犠牲になった」と。うしろ姿の押し売りは、やがて親子関係を、破壊する。●親孝行を美徳にしない日本では、親孝行を当然の美徳とするが、本当にそうか? 「お前の人生は、お前のもの。私たちのことは心配しなくていいから、思う存分、この世界をはばたいてみろ」と、一度は、子どもの背中をたたいてあげてこそ、親は、親としての責任を果たしたことになる。もちろんそのあと、子どもが自分で考えて、親孝行するというのであれば、それはそれ。しかし親孝行は美徳でも何でもない。子どもにそれを強要したり、求めたりしてはいけない。●「偉い」を廃語に!「偉い」という言葉を、廃語にしよう。日本では、地位の高い人や、何かの賞をとった人を、「偉い人」という。しかし英語国では、日本人が、「偉い人」と言いそうなとき、「リスペクティド・マン」という。「尊敬される人」という意味である。リスペクティド・マンというときは、地位や、名誉には関係ない。その人自身の中身を見て、そう判断する。あなたの子どもには、「偉い人になれ」と言うのではなく、「尊敬される人になれ」と言おう。●家族を大切に『オズの魔法使い』という、小説がある。あの中で、ドロシーという女の子は、幸福を求めて、虹の向こうにあるというエメラルドタウンを冒険する。しかし何のことはない。最後にドロシーは、真の幸福は、すぐそばの家庭の中にあることを知る。今、「家族が一番大切」と考える人が、80~90%になっている。99年の文部省の調査では、40%前後でしかなかったから、これはまさにサイレント革命というにふさわしい。あなたも自信をもって、子どもには、こう言おう。「この世界で、一番大切なものは、家族です」と。●迷信は、否定しよう子どもたちの世界では、今、占い、まじない、予言、超能力などが、大流行。努力して、自ら立ちあがるという姿勢が、ますます薄らいできている。中には、その日の運勢に合わせて行動し、あとで、「運勢が当たった」と言う子どもさえいる。(自分で、運勢に合わせただけなのだが……。)子どもが迷信らしいことを口にしたら、すかさず、「そんなのはウソ」と言ってやろう。迷信は、まさに合理の敵。迷信を信ずるようになればなるほど、子どもは、ものごとを合理的に考える力を失う。●死は厳粛にペットでも何でも、死んだら、その死は厳粛にあつかう。そういう姿を見て、子どもは、「死」を学び、ついで、「生」を学ぶ。まずいのは、紙か何かに包んで、ゴミ箱に捨てるような行為。決して遊んだり、茶化したりしてはいけない。子どもはやがて、生きることそのものを、粗末にするようになるかもしれない。なぜ、ほとんどの宗教で、葬儀を重要な儀式と位置づけているかと言えば、それは死を弔(とむら)うことで、生きることを大切にするためである。生き物の死は、厳粛に。どこまでも厳粛に。●悪玉親意識「私は親だ」というのが、親意識。この親意識にも、二種類をある。善玉親意識と、悪玉親意識である。「私は親らしく、子どもの見本になろう」「子どもをしっかりと育てて、親の責任をはたそう」というのが、善玉親意識。一方、「親に向かって何よ!」と、子どもに対して怒鳴り散らすのが、悪玉親意識。いわゆる『親風を吹かす』ことをいう。なお親は絶対と考えるのを、「親・絶対教」という。●達成感が子どもを伸ばす「ヤッター!」という達成感が、子どもを伸ばす。そんなわけで子どもが幼児のうちは、(できる・できない)という視点ではなく、(がんばってやった・やらない)という視点で子どもを見る。たとえまちがっていても、あるいは不十分であっても、子どもががんばってしたようなら、「よくやったわね」とほめて終わる。こまごまとした神経質な指導は、子どもをつぶす。●子どもは下から見る子育てで行きづまったら、子どもは、下から見る。「下を見ろ」ではない。「下から見る」。今、ここに生きているという原点から見る。そうすると、すべての問題が解決する。昔の人は、こう言った。『上見て、キリなし。下見て、キリなし』と。つまり上ばかり見ていると、人間の欲望には、際限がなく、いつまでたっても、安穏とした世界はやってこない。しかし生きているという原点から見ると、とたんに、すべての世界が平和になる。子育ても、また同じ。●失敗にめげず、前に進む「宝島」という本を書いたのが、スティーブンソン。そのスティーブンソンがこんな言葉を残している。『我らが目的は、成功することではない。我らが目的は、失敗にめげず、前に進むことである』と。もしあなたの子どもが何かのことでつまずいて、苦しんでいたら、そっとそう言ってみてほしい。「あなたの目的は、成功することではない。失敗にめげず、前に進むことですよ」と。●すばらしいと言え、親の仕事親の仕事は、すばらしいと言う。それを口ぐせにする。どんな仕事でも、だ。仕事に上下はない。あるはずもない。しかしこの日本には、封建時代の身分制度の名残というか、いまだに、職業によって相手を判断するという風潮が、根強く残っている。が、それだけではない。生き生きと仕事をしている親の姿は、子どもに、大きな安心感を与える。その安心感が、子どもの心を豊かに育てる。●逃げ場を大切にどんな動物にも、最後の逃げ場というのがある。その逃げ場に逃げこむことによって、身の安全をはかり、心をいやす。子どもも、またしかり。子どもがその逃げ場へ入ったら、親は、そこを神聖不可侵の場と心得て、そこを荒らすようなことをしてはいけない。たいていは子ども部屋ということになるが、その子ども部屋を踏み荒らすようなことをすると、今度は、「家出」ということにもなりかねない。●代償的過保護に注意過保護というときは、その背景に、親の濃密な愛情がある。しかし代償的過保護には、それがない。子どもを親の支配下において、親の思いどおりにしたいというのを代償的過保護という。いわば親自身の心のスキマを埋めるための、親の身勝手な過保護をいう。子どもの受験競争に狂奔している親が、それにあたる。「子どものため」と言いながら、子どものことなど、まったく考えていない。ストーカーが、好きな相手を追いかけまわすようなもの。私は「ストーカー的愛」と呼んでいる。●同居は出産前に夫(妻)の両親との同居を考えるなら、子どもの出産前からするとよい。私の調査でも、出産前からの同居は、たいていうまくいく(90%)。しかしある程度、子どもが大きくなってからの同居は、たいてい失敗する。同居するとき、母親が苦情の一番にあげるのが、「祖父母が、子どもの教育に介入する」。同居するにしても、祖父母は、孫の子育てについては、控えめに。それが同居を成功させる、秘訣のようである。●無能な親ほど、規則を好むイギリスの教育格言に、『無能な教師ほど、規則を好む』というのがある。家庭でも、同じ。『無能な親ほど、規則を好む』。ある程度の約束ごとは、必要かもしれない。しかし最小限に。また規則というのは、破られるためにある。そのつど、臨機応変に考えるのが、コツ。たとえば門限にしても、子どもが破ったら、そのつど、現状に合わせて調整していく。「規則を破ったから、お前はダメ人間だ」式の、人格攻撃をしてはいけない。●プレゼントは、買ったものはダメできれば……、今さら、手遅れかもしれないが、誕生日にせよ、クリスマスにせよ、「家族どうしのプレゼントは、買ったものはダメ」というハウス・ルールを作っておくとよい。戦後の高度成長期の悪弊というか、この日本でも、より高価であればあるほど、いいプレゼントということになっている。しかしそれは誤解。誤解というより、逆効果。家族のキズナを深めたかったら、心のこもったプレゼントを交換する。そのためにも、「買ったものは、ダメ」と。●子育ては、質素に子育ての基本は、「質素」。ときに親は、ぜいたくをすることがあるかもしれない。しかし、そういうぜいたくは、子どもの見えない世界ですること。一度、ぜいたくになれてしまうと、子どもは、あともどりができなくなってしまう。そのままの生活が、おとなになってからも維持できればよし。そうでなければ、苦しむのは、結局は子ども自身ということになる。●ズル休みも、ゆとりのうち子どもが不登校を起こしたりすると、たいていの親は、狂乱状態になる。そのときのためというわけでもないが、自分の中に潜む、学歴信仰や学校神話とは、今から戦っていく。その一つの方法が、「ズル休み」。ときには、園や学校をズル休みさせて、親子で、旅行に行く。平日に行けば、動物園でも遊園地でも、ガラガラ。あなたは、言いようのない解放感を味わうはず。「そんなことできない!」と思っている人ほど、一度、試してみるとよい。●ふつうこそ、最善ふつうであることには、すばらしい価値がある。しかし、親たちには、それがわからない。「もっと……」「もう少し……」と思っている間に、かえって子どもの伸びる芽をつんでしまう。よい例が、過干渉であり、過関心である。さらに親の過剰期待や、子どもへの過負担もある。賢い親は、そのふつうの価値に、それをなくす前に気づき、そうでない親は、それをなくしてから気づく。●限界を知る子育てには、限界はつきもの。いつも、それとの戦いであると言ってもよい。子どもというのは不思議なもので、親が、「まだ、何とかなる」「こんなはずではない」「うちの子は、やればできるはず」と思っている間は、伸びない。しかし親が、「まあ、うちの子は、こんなもの」「よくがんばっている」と、その限界を認めたとたん、伸び始める。皮肉なことに、親がそばにいるだけで、萎縮してしまう子どもも、少なくない。●子どもの世界は、社会の縮図子どもの世界だけを見て、子どもの世界だけを何とかしようと考えても、意味はない。子どもの世界は、まさに社会の縮図。社会に4割の善があり、4割の悪があるなら、子どもの世界にも、4割の善があり、4割の悪がある。つまり私たちは子育てをしながらも、同時に、社会にも目を向けなければならない。子どもがはじめて覚えたカタカナが、「ホテル」であったり、「セックス」であったりする。そういう社会をまず、改める。子どもの教育は、そこから始まる。●よき家庭人日本では、「立派な社会人」「社会に役立つ人」が、教育の柱になっていた。しかし欧米では、伝統的に、「よき家庭人(Good family man )」を育てるのが、教育の柱になっている。そのため学習内容も、実用的なものが多い。たとえば中学校で、小切手の切り方(アメリカ)などを教える。ところで隣の中国では、「立派な国民」という言葉がもてはやされている。どこか戦後直後の日本を思い出させる言葉である。●読書は、教育の要(かなめ)アメリカには、「ライブラリー」という時間がある。週1回は、たいていどこの学校にもある。つまり、読書指導の時間である。ふつうの教科は、学士資格で教壇に立つことができるが、ライブラリーの教師だけは、修士号以上の資格が必要である。ライブラリーの教師は、毎週、その子どもにあった本を選び、指導する。日本でも、最近、読書の重要性が見なおされてきている。読書は、教育の要である。●教師言葉に注意教師というのは、子どもをほめるときは、本音でほめる。だから学校の先生に、ほめられたら、額面どおり受け取ってよい。しかしその反対に、何か問題のある子どもには、教師言葉を使う。たとえば学習面で問題のある子どもに対しては、「運動面では問題ないですが……」「私の指導力が足りないようです」「この子には、可能性があるのですが、今は、まだその力を出し切っていませんね」というような言い方をする。●先取り教育は、幼児教育ではない幼児教育というと、小学校でする勉強を先取りしてする教育だとか、あるいは小学校の入学準備のための教育と考えている人は多い。そのため漢字を教えたり、掛け算の九九を教えたりするのが、幼児教育と思っている人も多い。しかしこれは、まったくの誤解。幼児期には幼児期で、しておくべきことが、山のようにある。子どもの方向性も、このころ決まる。その方向性を決めるのが、幼児教育である。●でき愛は、愛にあらずでき愛を、「愛」と誤解している人は多い。しかしでき愛は、愛ではない。親の心のスキマをうめるための、親の身勝手な愛。それをでき愛という。いわばストーカーがよく見せる「愛?」とよく似ている。たとえば子どもの受験勉強に狂奔している親も、それにあたる。「子どものことを心配している」とは言うが、本当は、自分の不安や心配を解消するために、子どもを利用しているだけ。そしてベタベタの親子関係をつづけながら、かえって子どもの自立をじゃましてしまう。●悪玉家族意識家族のもつ重要性は、いまさら説明するまでもない。しかしその家族が、反対に、独特の束縛性(家族自我群)をもつことがある。そしてその家族に束縛されて、かえってその家族が、自立できなくなってしまうことがある。あるいは反対に、「親を捨てた」という自責の念から、自己否定してしまう人も少なくない。家族は大切なものだが、しかし安易な論理で、子どもをしばってはいけない。Hiroshi Hayashi++++++++++Jan. 06+++++++++++はやし浩司※
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(13)
●要支援と幼稚園 少し前まで、幼稚園児とこんな会話ができた。 「君たちは、年中(児)。ぼくは、中年(児)!」と。 すると子どもたちは、「チューネンではなく、ネンチューだよ」と。 しかしその私も、さらに年をとった。中年の時代も、終わった。そこで今は、こんな会話をしている。相手は、年長児たち。 「君たちは、ヨーチエン(幼稚園)だってねエ。ぼくは、ヨーシエン(要支援)だよ」と。 すると子どもたちは、「先生、ヨーシエンではなく、ヨーチエンだよ」と。私「あのね、自分でウンチをして、それをきちんと自分でふけなくなったら、要支援って、言うんだよ」子「ぼくは、ちゃんとふけるよ」私「だったら、君は、要支援ではない」子「要支援ではなく、幼稚園だってばア」私「でも、ぼくも、もうそろそろ、要支援だよ」子「幼稚園は、子どもが行くところだよ」私「それがひどくなって、自分のウンチを食べるようになったら、要介護かな」子「ゲーッ! ウンチを食べるの?」私「要介護というのは、そういう人のことをいうよ」子「ヨーカイゴではなくて、ヨーチエンって、言うんだよ」私「要支援が終わったら、要介護。要介護1年生だよ」子「幼稚園が終わったら、小学校だよ」私「ぼくは、要介護になるの」子「ぼくは、小学校だよ」私「要介護は、5年生まで、あるの。知ってる?」子「フ~ン。お兄ちゃんは、小学5年生だよ」私「5年生かあ?」子「6年生まであるよ」私「要介護には、6年生はないの」子「5年生のつぎは、何?」私「あの世へ行くの」と。 こうしたジョークは、子ども向けというよりは、参観している、親向け。親たちが笑ってくれると、教室がなごむ。そのなごんだ雰囲気が、子どもたちの表情を、明るくする。しかし子どもたちは、真剣。 子どもたち「先生、ヨーシエンではなく、ヨウーチエンだってばア!」と。●ダジャレコウモリが、子守り歌を歌った。それをネコが、寝転んで聞いていた。ウマが、「うまい」と、コウモリをほめた。しかしサルは、その場を、去った。カバが、カバンを買った。シカは、帽子しか、買わなかった。そこへネズミ色の服を着たネズミがやってきて、こう言った。「パンダさんの食べたいのは、パンだ」と。トラがトラックに乗って、旅に出た。ラクダも乗せてもらって、「楽だ、楽だ」と言った。そこへワシがやってきて、「わしは、ワシだ」と言った。それを聞いたゾウが、「わしは、ゾウだぞう」と言った。……意味のないダジャレで、ごめん! 幼稚園児たちと話していて、こんなダジャレを思いついた。何かの歌の歌詞になるそう(?)。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(024)【子どもの緊張感】+++++++++++++++++子どもに緊張感をもたせる。その緊張感が、たとえば受験勉強などにおいて、よい方向に作用するという。しかし本当にそうか? そう言いきってよいのか?今、あちこちで、その受験戦争が、火花を飛ばしている。その「緊張感」について、ここで、はっきりと、結論を出しておきたい。+++++++++++++++++●幼児に受験の自覚? 私のところへきて、1人の母親が、こう言った。「A進学教室(浜松市内)の幼児科では、『子どもに受験するという緊張感をもたせるために、毎日、合格しますと子どもに言わせているそうです』と。 5歳、6歳の子どもに、受験の自覚をもたせる? こういう例は、ほかにもある。浜松市内のX幼稚園では、S小学校を受験する子どもたちだけを集めて、特訓教室を開いている。そしてそこでもやはり、「私は、合格します」と、子どもたちに、何度も復唱させているという。 模擬テストもしているというが、その緊張感のあまり、途中で、泣き出してしまう子どももいるという。 ……これはとんでもない暴論と言ってよい。メチャメチャな指導と言ってもよい。 この時期、愚かな親たちは、(はっきりそう断言してよいが……)、自分の子どもが合格することしか考えていない。またそのための努力しか、してしない。しかし万が一にも、子どもが受験に失敗したときは、どうするのか。子どもは、どうなるのか? 子どもによっては、それを大きな心のキズ(=トラウマ)としてしまう。子ども自身がキズとするのではなく、親たちが、そういう状態に子どもを追いこんでしまう。子どもが受験に失敗したとき、狂乱状態になる親も少なくない。そういう親の姿を見て、子どもは、それを(心のキズ)としてしまう。●内的緊張感と外的緊張感 緊張感にも、2種類ある。その子ども(人)自身の中から、わきでてくる緊張感を、内的緊張感という。たとえばその子ども自身がもつ、向上心、向学心、競争心、自尊心、好奇心が、その子どもを緊張させる。わかりやすく言えば、これは「善玉緊張感」ということになる。 一方、外的緊張感というのもある、外部から、子どもを脅したり、子ども自身を絶壁のフチに負いこんだりして与える、緊張感である。「こんな成績では、A中学に入れないわよ」「A中学へ入れなかったら、あなたはダメになるのよ」と。わかりやすく言えば、これは「悪玉緊張感」ということになる。 幼児にも、内的緊張感をもたせる方法はないわけではないが、しかし少なくとも幼児には、外的緊張感を、自分の中で、自己処理する能力は、まだない。 理由は明白。自分の立場を、客観的に判断する能力が、まだ育っていないからである。そういう幼児に向って、受験の目的、受験の内容、ついでに受験がもつ制度としての社会的意義を説明しても、意味はない。 子ども自身が、内的緊張感を理解し、その緊張感で、自発的に自分をコントロールするようになるのは、早くても小学校の高学年。ふつうは、中学生くらいになってからである。この時期、内的緊張感をうまく引き出せば、子どもは、自ら伸びる力で、自分自身を前向きに引っぱっていく。●心のキズ(トラウマ) 印象に残っている女の子に、Sさん(当時、中学生)がいた。 彼女はいつも、ここ一番というときになると、何ごとにつけ、自らしりごみしてしまった。私が、「ここでふんばれ!」「へこたれるな!」と励ましても、彼女の心には届かなかった。理由を聞くと……というより、いつも、Sさんは、こう言っていた。 「どうせ、私は、S小学校の入試に落ちたもんね」と。 つまりSさんは、もうとっくの昔に忘れていてもおかしくないようなことを、心のキズとしていた。「だから、私は、ダメな人間だ」と。 親たちは、先にも書いたように、合格することしか考えていない。しかし受験に失敗した子どもたちが、いかにそのはざまで、もがき、苦しんでいることか。そういうことについては、親たちは、ほとんど知らない。Sさんのように、それを心のキズとしてしまう子どもも、決して、少なくない。 ひょっとしたら、あなた自身もそうではないのか。●落ちることを考えて準備する 子どもの受験勉強を考えたら、受験に落ちることを考えて準備する。子どもに準備させよ、というのではない。親自身が、準備する。 万が一にも、不合格の通知が届いたら、あなたは、どうするか。どう対処するか。さらには、どう子どもには、接するか。それを考えながら、準備する。 しかしここにも書いたように、5歳、6歳の幼児には、まだ(受験)を自己処理する能力はない。仮にあったとしても、この時期、合格して、おかしなエリート意識をもたせることは、長い目で見て、その子どもにとっては、不幸なことである。 だから、子どもの受験勉強を考えたら、受験に落ちることを考えて準備する。 たとえば不合格の通知が届いても、親は、動揺しない。無視する。態度に表さない。平然として、日常生活をつづける。そういう姿勢が、子どもの心を守る。●情緒不安の原因にも…… よく誤解されることがある。 子どもの情緒が不安定になると、親たちは、それを問題として、それをなおそうとする。ぐずる、いじける、引きこもる子どもをを、内閉型(マイナス型)とするなら、暴れる、怒りっぽくなる、ピリピリする子どもは、外方型(プラス型)ということになる。 しかしそれはあくまでも症状。病気にたとえるなら、発熱や悪寒ということになる。 子どもにとって、(もちろんおとなにとってもそうだが)、情緒不安というのは、心の緊張感が取れないことをいう。その緊張感の中に、不安や心配が入りこむと、心は、その不安や心配を解消しようとして、一気に不安定になる。その状態を、情緒不安という。 こんなことは、心理学の世界でも、常識ではないか。 そこでこの時期、子どもに外的緊張感を与えれば、子どもの心は、そのまま緊張し、多少の個人差はあるだろが、子どもの情緒は、不安定化する。何度も書くが、この時期、幼児には、そうした緊張感を、自己処理する能力は、まだない。 が、それだけではない。●抑圧は悪魔を生む イギリスの教育格言に、『抑圧は悪魔を生む』というのがある。 抑圧された心理状態が、恒常的に長くつづくと、子どもの心が悪魔的になることをいう。「死」「殺す」「地獄」などという言葉に敏感に反応するようになる。それについては、このあとに原稿(中日新聞掲載済み)を1つ、添付しておく。 はっきり言えば、子どもの心はゆがむ。さらにそれが原因で、親子関係が、破壊されることもある。親がそうではなくても、子どものほうが、親から離れていく。 たとえば小学校の高学年児でも、進学塾へ入ったとたん、人間性そのものが変化するということは、よくある。決して珍しくない。親は、「おかげで、緊張感が生まれました」と喜んでいるが、とんでもない誤解。そうした緊張感の裏で、人間的な暖かい心が、いかに破壊されていることか! 毎日、毎晩、成績という点数だけで人間を評価しないような世界が、本当に正常な世界と言えるのか。そしてその点数だけで、子どもを絶壁のフチに立たせることが、本当に正常な世界と言えるのか。 どうして世の親たちよ、そんなことがわからないのか!●無責任な受験塾 受験塾にもいろいろある……と書きたいが、ほんの少しだけ、冷静な目で、受験塾をながめてみたらよい。 どんな講師が、どういう教育的な理念をもって、子どもを指導しているか。それをほんの少しでも、考えてみたらよい。 中には、熱血指導を売りものにしている進学塾もある。子どもたちの話を聞くと、「いつも先生たちは、竹刀(しない)をもち歩いている」という。当然、親たちの了解を得て、そうしているのだろうが、あまりにもバカげている。コメントする気にもならない。 が、親たちは、そういう進学塾ほど、よい塾だと考える。この愚かしさ。このバカ臭さ。 彼らこそ、子どもたちが合格することしか、考えていない。不合格になったとき、子どもの心のケアを考えている進学塾など、話に聞いたこともない。反対に、合格者は、翌年の生徒募集に利用されるだけ。 その陰で、いかに多くの子どもたちが、キズつき、自らダメ人間のレッテルを張っていることか!●ゆがむ人生観 受験期をスイスイと渡り歩いたような人にも、問題がないわけではない。そういう例は、皮肉なことに、60代、70代の、元エリートと呼ばれる人たちを見ればわかる。 彼らがもつ、一種独特の、あの鼻もちならないあのエリート意識は、いったい、どこから生まれるのか。以前、私にこう言った男(当時50歳くらい)がいた。私が、「幼稚園で講師をしています」と言ったときのことである。 「君は、学生運動か何かをしていて、どうせロクな仕事にはつけなかったんだろ」と。 仕事に、ロクな仕事もなければ、ロクでない仕事もない。 彼は当時、国の出先機関の公社の副長をしていたが、そういう意識をもつようになる。そしてそうしたゆがんだエリート意識が、その人の人生を、味気なく、つまらないものにする。わかりやすく言えば、人間の価値そのものを、学歴や経歴でしか見なくなる。●緊張感 適度な緊張感が、子どもを伸ばすということは、私も否定しない。ストレス学説の中でも、それは肯定されている。 しかしここでいう緊張感というのは、冒頭に書いた、内的緊張感(善玉緊張感)をいう。向上心、向学心、競争心、自尊心、好奇心が、その子どもを伸ばす。 ある男児(当時、小6)は、夏期の合同合宿訓練の長に選ばれた。そのため、訓練の冒頭で、あいさつをすることになった。 その男児は、そのため、その1週間ほど前から、毎晩、眠られない夜を経験した。そして当日は、フラフラの状態で、あいさつに臨んだ。しかし結果的に、それがうまくできた。以後、その子どもは、「長」という「長」を総なめにして、学業を終えた。 あるいは、その地域での演奏会に先立って、猛練習をした女児(当時、小5)がいた。そのため「演奏会の朝から、胃が痛いと苦しんでいました」(母親談)とのこと。しかし演奏会は、無事、終わった。その子どもは、そのあと、見ちがえるほど、おとなっぽくなった。 こうした内的緊張感は、たしかに子どもを伸ばす。子どもを伸ばす原動力として作用する。 しかし外的緊張感は、どうか? 「この仕事をしないと殺すぞ」と、ナイフをのどにつきつけられたら、どうか。あなたは、それでもその仕事をするだろうか。楽しくできるだろうか。自分の力を、じゅうぶん、発揮できるだろうか。●結論 幼児に、緊張感をもたせる? そのために、受験を自覚させる? あまりにもバカバカしい。反論したり、こうして説明するのも、実のところ、バカバカしい。はっきり言えば、そこらのド素人の、とんでもない意見。幼児に関する心理学の本を、一冊でも読んだことのある人なら、私のこの気持ちが理解できるはず。 しかしそういうことを平気で口にして、幼児の受験指導とやらをしている進学塾もある。これが現実かもしれない。 だからこそ、私は親たちに向かって、この原稿を書く。そしてもっともっと、親たちに、賢くなってほしい。+++++++++++++++子どもの心が破壊されるとき ●バッタをトカゲのエサに A小学校のA先生(小1担当女性)が、こんな話をしてくれた。「1年生のT君が、トカゲをつかまえてきた。そしてビンの中で飼っていた。そこへH君が、生きているバッタをつかまえてきて、トカゲにエサとして与えた。私はそれを見て、ぞっとした」と。 A先生が、なぜぞっとしたか、あなたはわかるだろうか。それを説明する前に、私にもこんな経験がある。もう20年ほど前のことだが、1人の子ども(年長男児)の上着のポケットを見ると、きれいに玉が並んでいた。私はてっきりビーズ玉か何かと思った。が、その直後、背筋が凍りつくのを覚えた。よく見ると、それは虫の頭だった。その子どもは虫をつかまえると、まず虫にポケットのフチを口でかませる。かんだところで、体をひねって頭をちぎる。ビーズ玉だと思ったのは、その虫の頭だった。また別の日。小さなトカゲを草の中に見つけた子ども(年長男児)がいた。まだ子どもの小さなトカゲだった。「あっ、トカゲ!」と叫んだところまではよかったが、その直後、その子どもはトカゲを足で踏んで、そのままつぶしてしまった!●心が壊れる子どもたち 原因はいろいろある。貧困(それにともなう家庭騒動)、家庭崩壊(それにともなう愛情不足)、過干渉(子どもの意思を無視して、何でも親が決めてしまう)、過関心(子どもの側からみて息が抜けない家庭環境)など。威圧的(ガミガミと頭ごなしに言う)な家庭環境や、権威主義的(「私は親だから」「あなたは子どもだから」式の問答無用の押しつけ)な子育てが、原因となることもある。もちろんその中には、受験競争も含まれる。要するに、子どもの側から見て、「安らぎを得られない家庭環境」が、その背景にあるとみる。さらに不平や不満、それに心配や不安が日常的に続くと、それが子どもの心を破壊することもある。イギリスの格言にも、『抑圧は悪魔を生む』というのがある。抑圧的な環境が長く続くと、ものの考え方が悪魔的になることを言ったものだが、このタイプの子どもは、心のバランス感覚をなくすのが知られている。「バランス感覚」というのは、してよいことと悪いことを、静かに判断する能力のことをいう。これがないと、ものの考え方が先鋭化したり、かたよったりするようになる。昔、こう言った高校生がいた。「地球には人間が多すぎる。核兵器か何かで、人口を半分に減らせばいい。そうすれば、ずっと住みやすくなる」と。そういうようなものの考え方をするが、言いかえると、愛情豊かな家庭環境で、心静かに育った子どもは、ほっとするような温もりのある子どもになる。心もやさしくなる。●無関心、無感動は要注意 さて冒頭のA先生は、トカゲに驚いたのではない。トカゲを飼っていることに驚いたのでもない。A先生は、生きているバッタをエサとして与えたことに驚いた。A先生はこう言った。「そういう残酷なことが平気でできるということが、信じられませんでした」と。 このタイプの子どもは、総じて他人に無関心(自分のことにしか興味をもたない)で、無感動(他人の苦しみや悲しみに鈍感)、感情の動き(喜怒哀楽の情)も平坦になる。よく誤解されるが、このタイプの子どもが非行に走りやすいのは、そもそもそういう「芽」があるからではない。非行に対する抵抗力がないからである。悪友に誘われたりすると、そのままスーッと仲間に入ってしまう。ぞっとするようなことをしながら、それにブレーキをかけることができない。だから結果的に、「悪」に染まってしまう。●心の修復は、4、5歳までに そこで一度、あなたの子どもが、どんなものに興味をもち、関心を示すか、観察してみてほしい。子どもらしい動物や乗り物、食べ物や飾りであればよし。しかしそれが、残酷なゲームや、銃や戦争、さらに日常的に乱暴な言葉や行動が目立つというのであれば、家庭教育のあり方をかなり反省したらよい。子どものばあい、「好きな絵をかいてごらん」と言って紙とクレヨンを渡すと、心の中が読める。子どもらしい楽しい絵がかければ、それでよし。しかし心が壊れている子どもは、おとなが見ても、ぞっとするような絵をかく。 ただし、小学校に入学してからだと、子どもの心を修復するのはたいへん難しい。修復するとしても、4、5歳くらいまで。穏やかで、静かな生活を大切にする。(はやし浩司 受験 子供の受験 緊張 内的緊張感 外的緊張感 受験の心構え 子どものバランス感覚 バランス感覚 はやし浩司)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(025)●12月27日、火曜日 この数日、掃除また掃除。そんな日々がつづいた。で、やっと今日、一段落。ほっとした。 その掃除をしながら、いろいろなことを発見した。その1。ものがない美しさ。その美しさを、改めて確認した。このことについては、前にも書いた。多少の不便はあるかもしれないが、ものがない部屋は、美しい。すっきりとしている。気持ちよい。もちろん掃除もしやすい。 実は、心の中も同じ。たとえば1つのウソをつくと、つぎからつぎへと、ウソをつかねばならない。相手が複数の人だと、そのウソを記憶しているだけでもたいへん。そういう意味では、ウソは、心のゴミということになる。 韓国のあの科学者も、そうだ。11個のES細(胞胚性幹細胞)のうち、9個までが捏造(ねつぞう)とわかった。残りの2個も、どうやらニセモノと断定されたようだ。それに対して、当の科学者は、「仲間のだれかが、本物とニセモノをすりかえた」と言い出した。きっとあの科学者の心の中には、足の踏み場もないほど、ゴミがたまっているのだろう。かわいそうな人だ。 その2。掃除は、絵画に似ている。もの書きは、文章を書く。絵描きは、絵を描く。そのもの書きと、絵描きとは、どこがどうちがうか? ふつう文章を書いていると、頭の中がクシャクシャしてくる。しかし絵を描いていると、無我というか、無心の状態になる。何もかも忘れて、絵を描くことに没頭する。 掃除は、その、絵を描くことに似ている。掃除をしている間というのは、何も考えない。ただひたすら、あちこちをきれいにする。それを繰りかえしていると、やがて心の中が、すっきりとしてくる。 その3。掃除というのは、最初は人のためにする。心のどこかで、喜んでくれる人を、思い浮かべる。そういうところから始まる。しかししばらくつづけていると、やがてそれが自分のためということがわかってくる。似たような心の変化は、ボランティア活動をしているときにも、経験する。もっとも何かのボランティア活動をしているときは、心のどこかで(他人のため)から、(自分のため)にスイッチングをしないと、心がもたない。 ボランティア活動をしていると、報われることよりも、裏切られることのほうが、多い。はるかに多い。いちいち裏切られることを気にしていたら、ボランティア活動など、できない。掃除もそうだ。 掃除をしても、すぐだれかによごされる。一番、露骨にそれをするのは、イヌのハナだ。昨日も、窓ガラスをすべてふいた。その前に、洗剤をつけて、窓ガラスを洗った。が、夜になって、ハナが、その窓ガラスを、足でこすって、ドロをつけてしまった。 あああ……! とにかく、こうして我が家の大掃除は、終わった。一応、終わった。明日、28日、二男夫婦が、孫と、嫁の妹を連れて我が家にやってくる。そのあとのことは、知らない。知ったことではない。さあて、どうなることやら? まあ、あまり考えないでおこう。無我、無心。それが何よりも重要。今は、そんなふうに、考えている。●熱帯魚 熱帯魚を飼うようになって、もう18年になる。どうして覚えているかって? 理由がある。 私たち夫婦も、何度か、離婚の危機を経験した。その中でも、一度だけ、今のワイフが本気で家を飛び出してしまったことがある。 そのとき、私は近所の熱帯魚屋から、水槽と何匹かの熱帯魚を買ってきた。それが平成元年になる少し前のこと。それで「18年」ということになる。来年は、2006年、平成18年! きっとさみしかったのだろう。それで熱帯魚を飼うようになった。熱帯魚を見ながら、私は、心を、まぎらわした。以来、18年。ずっと、熱帯魚を飼っている。 その水槽を、昨日、ピカピカにみがいた。下に敷いてあるジャリも洗った。当然、水もかえた。あとは、カルキ抜きの中和剤を入れ、病気予防のための、いくつかの薬をまぜた。おかげで、今は、その水槽が、夢の中の世界のように、美しい世界になった。すべてが、澄んだクリスタル色に輝いている。 それをぼんやりと見つめていると、「大昔、人間も、魚だったんだなあ」と思う。本気で、そう思う。深い森の中にいるときよりも、さらに大きな安堵感を覚える。本能的な安堵感というのである。私「人間のことだから、きっと、太古の昔には、熱帯地方の海に住んでいたと思うよ」ワ「そうね」と。 仮に私が今、魚になったとしても、冷たい海の中には、住みたくない。風呂のような温水がよい。そういうことから、太古の昔、人間の祖先たちは、暖かい海の中に住んでいたと思う。勝手な想像だが、私は、そう思う。 ところでその熱帯魚だが、人間の私たちが考えているより、はるかに頭がよい。どう頭がよいかについては、もう何度も書いてきたので、ここには、書かない。しかし頭がよい。魚だから……と、決してバカにしてはいけない。●電子出版に挑戦!『まぐまぐ! POD』というサービスが始まった。「POD」といのは、は読者からの注文を受けて、1冊、1冊、本を印刷・製本するというサービスをいう。「POD」というのは、「Publish on demand」の略語だと思う。 「へえ~」と驚くやら、感心するやら……。 自費出版というのは、生涯においてしたことがない。どこかプライドが許さなかった。しかし今度は、私自身が、出版社の立場になる。映画でいえば、監督と主演の、両方を、自分でするようなもの。あのクリント・イーストウッドだって、何度か、そうしている。 とりあえず、「子育て一口メモ」を、本にしてみようと思う。売れるかどうかわからないが、何ごとも、新しいことに挑戦してみるというのは、楽しい。この方式が軌道にのれば、ここにも書いたように、私自身が、出版社を経営することができるようになる。 これからは、そういう時代かもしれない。おもしろいことだ。●1月3日 原稿書き、再開! この1週間、インフルエンザから、そのあと、扁桃腺炎、気管支炎などを併発し、病気の連続。悪寒、発熱の繰りかえし。熱も38度を超えたと思ったら、翌日には、37度。しかしそのまた翌日には、また38度! やがて今度は、薬中毒。頭痛薬をのんでも、かえって、頭痛がひどくなるだけ。いやな気分だった。ときどき郷里の姉から電話があるが、そのたびに、「この前も風邪をひいていると言ったじゃない!」「まだ、風邪をひいているの?」と、なじられるしまつ。 1月1日から、そんなわけで、病院通い。おかげでそのあとは、急速に症状は、よくなった。で、今日は、1月3日の朝。こうして原稿を書けるようになった。 しかしこの1週間、あれこれ考えた。「こんな原稿など、書いて、何の役にたつのだろうか?」と。ホント! 絵にたとえるなら、トイレの落書きのようなもの。それとはちがうとは思いたいが、しかしどこがどうちがうというのか。自分のしていることが、何か、まちがっているような気がしてしてならない。 頭の中では、「多くの人が読んでくれているのだ」と思うようにしているが、それについても、最近は、「?」と思うことが多い。私のワイフでさえ、このところ、忙しいこともあるが、私の原稿を、ほとんど、読んでいない。 どこがまちがっているのだろうか? だいたいにおいて、私の、ものを書く姿勢がまちがっている。ものの書き方が、どうも権威主義的。上から下へと、「控えおろう!」というような感じで書いている。それに読者の意向など、まったく無視。ひとりよがりも、よいところ。自己満足のために書いた文章など、だれが読みたがるだろうか。 いつだったか、そう批評してきた女性が1人、いた。辛らつな批評だった。「ママ診断を読んだが、あんな長い診断なんか、だれも受けない。自己満足のためだけに、ああいうものを書くな」と。 つぎにこういう(見返りのない原稿)を書いていると、どうしてもグチが多くなる。実際、05年度は、賛助会への協力者はゼロ。絵も売ろうとしたが、買ってくれた人は、ゼロ。つまりHPとマガジン関係での、収入は、ゼロ。 そのグチが、私が書く原稿を、暗く、重いものにする。だから読者もふえない。そのため、書く意欲もわいてこない。水にたとえるなら、流れが止まった、水たまりのようなもの。(この原稿そのものが、水たまりのようなもの?) さあて、心機一転! 今年も、再開。とにかく、前に進むしかない。グチグチ言っていても、しかたない。2006年はやってきた。「今年こそは……」と信じて、前に進む。「今年こそは、何か、いいことがあるだろう」と。 この文章を読んでくださった、読者の方へ、 今年も、よろしくお願いします。●やはり孫は、かわいい?+++++++++++++++++1年ほど前、ある読者の女性から、こんなメールをもらった。「娘夫婦は、いつも私に孫を預けて、遊びほけている。祖母だから、孫がかわいいはず」と、決めてかかっている。それでとうとう私がキレてしまった。『祖母だからといって、孫がかわいいはずと決めてかかってもらっては困る!』と。私だって自由な時間がほしい。子育てから解放されて、やっと一息ついているのに、今度は、孫のめんどう?!『もういいかげんにしてくれ!』と叫びたいです」と。この女性のメールは、当時、マガジンのほうで、取りあげさせてもらった。で、私も、今、その孫のめんどうをみるハメに……。立場的には、その女性のメールにやっと返事を書けるようになった。++++++++++++++++++ 孫は、かわいいのか。それとも、かわいくないのか。私も、孫の誠司を見ながら、ふと、そんなことを考える。 一般的には、ジイ様、バア様だから、孫はかわいいはず、とだれしも考えるにちがいない。とくに自分の子どもをもった若い父親や、母親は、そうであろう。 しかし孫に対する感覚は、自分の実の子に対する感覚とは、明らかにちがう。自分の実の子のばあいは、無我夢中というか、すべてを投げ出して、育てる。しかし孫となると、そうはいかない。そこに息子が介在する。 (孫の誠司ではなく)、その息子のほうを見ていると、ふと心のどこかで、「子育ては、もうたくさん」「こりごり」と思う。そういう思いが、心をふさぐ。子育ては、つまりは重労働。その子育てからやっと解放されたと思ったとたん、また同じ思いをもてと言われても、困る。そうは簡単に、心は動かない。 さらに私のばあい、何十人も、幼児を教えている。毎週、毎月、そういった子どもたちと会っている。そういう子どもたちと、どう区別したらよいのか。孫と、どう区別したらよいのか。実際には、できない。 みんなで買い物に出かけても、息子夫婦は、孫には、ハレ物かガラス箱に触れるかのように、注意を払う。自分のワイフには、荷物を、いっさい、もたせない。(妊娠中ということもあるが……。)しかし重い荷物をもたされるのは、たいてい、私たち、夫婦。決して見返りを求めて自分の子育てをしたわけではないが、そういう立場に立たされてみると、「子育てって、いったい、何だったのか?」と考えさせられてしまう。 息子は、こう言う。「電池式のおもちゃは、創造性がない。だからぼくは、そういうおもちゃでは、遊ばせない」とか、何とか。 まあ、言いたいことを言えばよいが、何千例も幼児教育をみてきた私に向って、そう言う。何百回も、あちこちで講演を重ねてきた私に、そう言う。「そうだね」と一応返事をしつつ、「そういう単純なものでもないのだがなあ」とも思う。言いたいことは山ほどあるが、ここは、バカなジイ様のフリをしているのが、一番。 そこで恐る恐る、ワイフに、昨夜、そのことを告白した。私「息子のヤツね、どこか緒しつけがましいだろ。『孫はかわいいだろ』とね。で、お前さ、孫を、かわいいと思うか?」ワ「フ~ム。毎月とか、毎週とか、会っていれば、また別の感覚をもつかもしれないけど、私たちには、まだ、そういう感覚は、もてないわね」私「そこなんだよな。昨日も、息子は、こう言った。『アンシュタインなんて、くだらない男さ。あんな男には、学ぶべきものは、何もない』とね。ぼくは、それを聞いていて、『あんたのようなおやじには、学ぶべきものは、何もない』と言われたように感じたよ」ワ「それは考えすぎよ」私「でも、田丸先生も、ぼくも、アインシュタインを尊敬している。ああまで頭から否定されてしまうと、自分が否定されてしまうかのように感ずる」ワ「息子といっても、もう別の人格をもった、別の人間よ。あなたには、まだ親意識が残っているのよ。子離れが、まだできていないのよ。息子といっても、思い出のつながった、友人と思えばいいのよ」 いろいろな統計を見ても、「老後は、息子や娘と離れて暮らしたい」と望んでいる人がふえているという。欧米化というか、オーストラリア化、アメリカ化というか、そういう傾向が、この日本でも、急速に進んでいる。 で、その私は23歳のときには、すでに収入の半分を、実家へ仕送りし始めていた。ワイフと結婚したときも、すでにそれが条件になっていた。だから、ワイフは、何も言わずに、それに従ってくれた。が、それから、35年。いまだに年間、100~200万円単位の生活費や介護費用が、のしかかってくる。 そういう「私」とくらべると、今の私の息子たちは、いったい、何かと思う。そして同時に、「そんな息子や娘となら、同居はごめん」ということになる。老後のめんどうをみてもらうなどというのは、夢のまた夢。反対に、息子たちのめんどうをみるのは、親の私たちということになる。知人の中には、息子夫婦の新居の費用から、孫のおけいこ教室の費用まで、負担している人がいる。 だから、その知人は、「同居は、ごめん」と。わかる、その気持ち! そこで若い夫婦のみなさんには、こんなアドバイスができる。(1)ジイ様、バア様には、孫がかわいいはずと思いこむのは、やめたほうがよい。またそういう前提で、押しつけがましく、ジイ様、バア様に孫を押しつけるのはよくない。とくにマザコンタイプの男性は、自分の母親を偶像化しやすい。そのため、自分の孫にも、マドンナ的な深い愛情を期待しがちだが、愛情というのは、血のつながりだけでは、生まれない。(2)孫のかわいさは、それまでの親子関係、それと息子の妻や、娘の夫との関係によって決まる。良好な親子関係であれば、ふつう程度に孫をかわいく思うようになる。そうでなければ、そうでない。これは別の知人(男性)から聞いた話だが、こんなケースもある。その知人の息子が、ある女性と結婚した。5歳年上の女性だった。子ども(孫)を妊娠したことをよいことに、その女性は、強引に、息子との結婚を迫った。 知人は、結婚そのものに反対した。その女性の両親に何度か中絶を申しいれた。が、話にならなかった。さらに相手の両親に大金を積んで、婚約解消を申しいれたが、それでも、だめだったという。が、そのうち、子どもは生まれてしまった。その知人にしてみれば、孫ということになるが、彼はこう言った。「一応、遊びにくれば、それなりの接し方はしますが、正直言って、(孫の)顔など見たくもないです」「見たとたん、頭痛が始まります」と。 もちろん中には、孫を目の中に入れても痛くないと思うジイ様、バア様もいる。つまりそれくらい孫をかわいいと思っている人もいる。しかしそうでない人のほうが、実際には、多い。たいはんのジイ様、バア様は、よきジイ様、よきバア様でいようと、仮面をかぶろうとする。「息子夫婦に嫌われるのもいやだから」と。いろいろな人の話を聞いてみると、どうやらそのあたりに、本音があるのではないか。 そこで息子に聞いてみると、息子は、あっさりとこう言った。「パパ、アメリカの両親など、あっさりとしたものだよ。レストランなどでいっしょに食事をしても、みんな割り勘だよ」と。 ナルホド! さて、私のばあいだが、今日(1月3日)は、市内のレストランで、昼食。それから新幹線で、隣町まで行こうとしたが、駅は、Uターンラッシュで、たいへんな混雑。しかたないので、駅前のアクトタワーの展望台へ。 孫の誠司を抱きながら、自分の心がどう変化していくのかを、静かに観察してみた。淡々とした気持ちは、それほど、変わらなかった。が、ちょうど帰りの道についたときのこと。孫の誠司が、こう言った。 「You've got water? (水をもっている?)」と。どこか遠慮がちな、やさしい言い方だった。 それで「You want water? (お前は、水を飲みたいのか?)」と聞くと、「Yes!」と。そのとき瞬間だが、誠司の中に、言いようのない愛くるしさを感じた。心を全幅に開いて、私に話しかけてくる孫。私の顔を見たとたん、ニコニコと笑って、「ジイジ!」と声をかけてくれる孫。 とたん、それまでたがいをへだてていたカベが、パラパラと崩れたのを感じた。そしてそれまでになかった、心の交流が、流れ出すのを感じだ。そういうものが積み重なって、はじめてそこに、別の新しい人間関係が生まれるのかもしれない。そしてそれが、たがいの絆(きずな)に変わる。孫といっても、その新密度は、基本的には、人間関係で決まる。「祖父だから……」とか、「孫だから……」という『ダカラ論』だけで、ものを考えてはいけない。 同居して、1週間目。やっと私にも、孫のかわいさが、わかるようになってきた! やはり、孫っていうのは、かわいいですねエ~。(原S)
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(12)
●暴れまわる子ども(キレる子ども)++++++++++++++++++アメリカのBLOGサイトに、こんな相談があった。預かっている子どもについての相談だが、暴れまわって、困るという内容のもの。Bulletin Board for EDSPC 753より転載。+++++++++++++++++++We have had custody of my 6 year old stepson for 9 months now, and I am truly worn out and need help ASAP. I went to the school today to pick him up for a doctor appointment (for his behavior & yes he is on medications for this)and upon seeing me in the hallway he became hysterical and ran in the oposite direction screaming. The principal and I caught up with him and he began punching, kicking, slapping, biting, and pulling several handfulls of my hair out of my head before the principal could restrain him. When he seemed calmed a bit i tried to calmly let him know that I was just picking him up for his doctor's appointment, at that point he kicked me in the face and continued to scream as loud as he could, disrupting several classrooms. The principal tried to carry him out to my vehicle, but once in he began kicking the daylights out of my car, he then got out and threw himself on the ground screaming. Please tell me what in the world to do and how should this be handled if it should occur at school again. The only facts we know about his life with his real mother is that she admitted in court to having heavily used methamphetamines daily throughout the pregnancy. I am not a teacher, but I fell terrible that the staff at his school had to go through this. He had an episode eight weeks ago where he did the same thing to his teacher that he did to me, I am in fear that his abuse will only escalate. He is scheduled for a psych evaluation in Tacoma in 2 weeks, please give me advice for the mean time, we have 5 other well behaved children in our home, how do I keep them safe?6歳の子どもを預かるようになって、9か月になる。私は本当に疲れた。今日も、ドクターの診察を受けるため、学校へ子どもを迎えに行った。玄関で私を見るやいなや、子どもはヒステリックになり、反対方向へ走って逃げていった。校長と2人で、追いついたものの、殴ったり、蹴ったり、ひっぱたいたり、髪の毛を引っぱったりした。少し落ち着いたところで、今日は、病院へ行くだけだと話して聞かせた。そのときも、私の顔を蹴り、大声で泣き叫び、いくつかの教室の授業を混乱させてしまった。どうしたらよいのか、どうか、教えてほしい。また学校で同じようなことが起きたら、どうすればよいのか。8週間ほど前も同じようなことをしたとき、このままエスカレートしたら、どうしようかと悩んだ。彼は、タコマで、心理教育を受けることになっている。この間、どうすればよいのか、教えてほしい。私のところには、ほかにも5人の子どもを預かっているが、みな、行儀がよい。++++++++++++++++++++ある教育者からの返事++++++++++++++++++++It sounds like you are dealing with an extremely difficult situation. So far the other suggestions posted by Dina and Bear should be helpful. I have two more techniques that may be helpful for your stepson. One technique that you might want to try is creating a behavior contract with your stepson. First, you can figure out what behaviors you would like to see him exhibit in school and at home. Some suggestions would be he needs to draw when he is feeling angry or he needs to follow directions the first time that they are given. Set a time frame for each time you or the teacher will be evaluating his behavior. Start small to encourage his success with the technique. You might want to say, if you can do this for 30 minutes you will receive a reward. And, keep track of whether or not he is exhibiting this behavior every 30 minutes. You will talk to him about what kinds of rewards he is willing to work for. If he loves to play with his toy trucks maybe you can use extra play time as a reward or getting to watch a favorite movie. It is important to figure out what rewards matter to him. You can find more information on using behavior contracting on this website. Go to the main behavioradvisor.com screen and you will find the link for contracts. たいへん困難な状況にあると思う。先にコメントを書いた、DさんやBさんの意見も、役に立つでしょう。で、私は、役にたつであろう2つの技術をもっている。1つは、まず試してみるべきことは、その子どもとの、(行動契約)を結ぶこと。まず、学校や家で、彼がどうあるべきかを、あなたがそれを具体的に頭の中で描いてみる。彼が怒っているときや、最初に指示に従う必要にあるとき、どうするかを決めるのもよい。それぞれのときに、時間のワクをつくれば、先生が、子どもの行動を(客観的に)評価するだろう。もし30分以内にできれば、ほうびを与えるなどとする。30分ごとに、その契約が守れるかどうかを、観察する。またその子どもがどのようなほうびを求めているかを、子どもと話しあう。たとえばおもちゃのトラックと遊びたいとか、好きな映画を見たいというのであれば、それらをほうびとする。その子どもが何をしたがっているかを知ることが、重要。このサイトで、(行動契約)についてのさらなる情報を、手に入れることができる。そちらを訪問してみたらよい。The second technique that you might want to try is having your stepson self monitor his own behavior. You will start out when he is calm to identify a behavior that you would like to encourage. Be confident in his ability to master this technique. It may sound unlike you, but give him excessive amounts of your confidence that he can master this behavior. Many children take their cues from the adults in their lives. Once you have figured out what behavior you will be working on, create a sheet with smily faces and frowning faces. At designated times, ask him to circle the smiling face if he is exhibiting this behavior or the frowning face if he is not. This will build his own motivation to exhibit appropriate behaviors. And, celebrate when he is improving!!! I know this can be difficult to do, as some of the improvements will seem small in relation to the problems; however, it is good for you and him to recognize when changes are occuring. It seems like you are really commited to helping this child and he is lucky to have such a stable adult in his life. Good luck with this situation. Keely2番目の技術は、子ども自身の行動について、自己監視させること。子どもがあなたから見て、落ち着いていて、好ましい状態にあるときから、始める。この技術をマスターするための能力が子どもにあると、自信をもつこと。子どもが自分で自分を管理できると、あなたが、(今のあなたには、そうではなくても)、自身をもっていることを、子どもに強く印象づける。多くの子どもたちは、彼らの生活において、おとなたちから、その手がかりを得る。どんな様子が望ましいかがわかったら、(ニコニコマーク)と(しかめっつらマーク)を描いたシートを用意する。このことで、子どもに自覚を促す。そしてうまくいったときは、その子どもをほめたたえる。このことはむずかしいことは、わかっている。この問題に関しては、進歩は、少ないだろう。しかしあなたとその子どもにとって、変化が起きつつあることを気がつくためには、よい。その子どもにとって、あなたのような安定したおとなをもっているということは、すばらしいことだ。++++++++++++++++++●子どもの過剰行動性について 子どもの突発的な過剰行動性、いわゆるキレる子どもについては、いろいろな分野から考察が繰りかえされている。 大脳の微細障害説、環境ホルモン説、食生活説など。それらについて、数年前に書いた原稿を、ここに添付する。++++++++++++++++++【子どもがキレるとき】●ふえるキレる子ども 2000年、全国の教育委員会から報告された校内での暴力行為は、前年度より11.4%ふえて、34595件に達したことがわかった(文部科学省)。「対外的に問題の見られなかった子どもが、突発的に暴力をふるうケースが目立つ」と指摘。同省・児童生徒課は、キレる子どもへの対応の必要性を強調した(中日新聞)。 暴力行為が報告された学校の割合は、小学校が全体の2・2%だったが、中学校が35・8%、高校が47・3%にのぼった。また学校外の暴力行為は、小中高校で、計5779件だった。私が住む静岡県でも、前年度より210件ふえて、1132件だった。マスコミで騒がれることは少なくなったが、この問題は、まだ未解決のままと考えてよい。 こうしたキレる子どもの原因について、各方面からさまざまな角度から議論されている。教育的な分野からの考察については言うまでもないが、それ以外の分野として、たとえば(1)精神医学、(2)栄養学の分野がある。さらに最近では(3)環境ホルモンの分野からも問題が提起されている。これは、内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)が、子どもの脳に影響を与え、それが子どもがキレる原因の一つになっているという説である。以下、これらの問題点について、考えてみる。(1)精神医学の分野からの考察●躁状態における錯乱状態 キレる状態は、心理学の世界では、「躁(そう)状態における精神錯乱」と位置づけられている。躁うつ病を定型化したのはクレペリン(ドイツの医学者・1856~1926)だが、一般的には躁状態とうつ状態はペアで考えられている。周期性をもって交互に、あるいはケースによっては、重複して起こることが多いからである。それはそれとして、このキレた状態になると、子どもは突発的に攻撃的になったり、大声でわめいたりする。(これに対して若い人の間では、ただ単に、激怒した状態、あるいは怒りをコントロールできなくなった状態を、「キレる」と言うことが多い。ここでは区別して考える。)私にもこんな経験がある。●恐ろしく冷たい目 子どもたち(小3児)を並べて、順に答案に丸をつけていたときのこと。それまでF君は、まったく目立たないほど、静かだった。が、あと一人でF君というそのとき、F君が突然、暴れ出した。突然というより、激変に近いものだった。ギャーという声を出したかと思うと、周囲にあった机とイスを足げりにしてひっくり返した。瞬間私は彼の目を見たが、その目は恐ろしいほど冷たく、すごんでいた……。●心の緊張状態が原因 よく子どもの情緒が不安定になると、その不安定な状態そのものを問題にする人がいる。しかしそれはあくまでも表面的な症状に過ぎない。情緒が不安定な子どもは、その根底に心の緊張状態があるとみる。その緊張状態の中に不安が入りこむと、その不安を解消しようと、一挙に緊張感が高まり、情緒が不安定になる。先のF君のばあいも、「問題が解けなかった」という思いが、彼を緊張させた。そういう緊張状態のところに、「先生に何かを言われるのではないか」という不安が入りこんで、一挙に情緒が不安定になった。言いかえると、このタイプの子どもは、いつも心が緊張状態にある。気を抜かない。気を許さない。周囲に気をつかうなど。表情にだまされてはいけない。柔和でおだやかな表情をしながら、その裏で心をゆがめる子どもは少なくない。これを心理学の世界では、「遊離」という。「遊離現象」というときもある。心(情意)と表情がミスマッチを起こした状態をいう。一度こういう状態になると、教える側からすると、「何を考えているかわからない子ども」といった感じになる。 その引き金となる原因はいくつかあるが、その第一に考えるのが、欲求不満である。欲求不満が日常的に続くと、それがストレッサー(ストレスの原因)となり、心をふさぐ。その閉塞感が、子どもの心を緊張させる。子どもの心について、こんな調査結果がある(98年・文部省調査)。 「いらいら、むしゃくしゃすることがあるか」という質問に対して、小学6年生の18.6%が、「日常的によくある」と答え、59.8%が、「ときどきある」と答えている。その理由としては、(1)友だちとの人間関係がうまくいかないとき……51.8%(2)人に叱られたとき……45.7%(3)家族関係がうまくいかないとき……35.5%(4)授業がわからないとき……34.1%(5)意味もなくむしゃくしゃするときがある……18.5%また「不安を感ずることがあるか」という質問に対しては、やはり小学六年生の7.8%が、「日常的によくある」と答え、47.7%が、「ときどきある」と答えている。その理由としては、(1)友だちとの関係がうまくいかないとき……51.0%(2)授業がわからないとき……47.7%(3)時間的なゆとりがないとき……29.3%(4)落ち着ける居場所がないとき……22.4%(5)進路、進学について……20.4% この調査結果から、現代の子どもたちは、およそ20人に一人が日常的に、いらいらしたり、むしゃくしゃし、10人に一人が日常的にある種の不安を感じていることがわかる。●子どもの欲求不満 子どもの欲求不満については、その原因となるストレスの大小はもちろんのこと、それを受け取る子ども側の、リセプターとしての問題もある。同じストレスを与えても、それをストレスと感じない子どももいれば、それに敏感に反応する子どももいる。そんなわけで、子どものストレスを考えるときは、対個人ではどうなのかというレベルで考える必要がある。それはさておき、子どもは自分の欲求が満たされないと、欲求不満になる。この欲求不満に対する反応は、ふつう、次の三つに分けて考える。(1)攻撃・暴力タイプ 欲求不満やストレスが、日常的にたまると、子どもは攻撃的になる。心はいつも緊張状態あり、ささいなことでカッとなって、暴れたり叫んだりする。母親が、「ピアノのレッスンをしようね」と話しかけただけで、包丁を投げつけた女の子(年長児)がいた。私が「今日は元気?」と声をかけて、肩をたたいた瞬間、「このヘンタイ野郎!」と私を足げりにした女の子(小五)もいた。こうした攻撃性は、表に出るタイプ(喧嘩する、暴力を振るう、暴言を吐く)と、裏に隠れてするタイプ(弱い者をいじめる、動物を虐待する)に分けて考えることができる。(2)退行・依存タイプ ぐずったり、赤ちゃんぽくなったりする(退行性)。あるいは誰かに依存しようとする(依存性)。このタイプの子どもは、理由もなくグズグズしたり、甘えたりする。母親がそれを叱れば叱るほど、症状が悪化するのが特徴で、そのため親が子どもをもてあますケースが多い。(3)固着・執着タイプ ある特定の「物」にこだわったりする(固着性)。あるいはささいなことを気にして、悶々と悩んだりする(執着性)。ある男の子(年長児)は、毛布の切れ端をいつも大切に持ち歩いていた。最近多く見られるのが、おとなになりたがらない子どもたち。赤ちゃんがえりならぬ、幼児がえりを起こす。ある男の子(小五)は、幼児期に読んでいたマンガの本をボロボロになっても、まだ大切そうにカバンの中に入れていた。そこで私が、「これは何?」と声をかけると、その子どもはこう言った。「どうチェ、読んでは、ダメだというんでチョ。読んでは、ダメだというんでチョ」と。 ものに依存するのは、心にたまった欲求不満をまぎらわすための代償行為と考えるとわかりやすい。よく知られているのに、指しゃぶりや、爪かみ、髪いじりなどがある。別のところで指の快感を覚えることで、自分の欲求不満を解消しようとする。 キレる子どもは、このうち、(1)攻撃・暴力タイプということになるが、しかし同時に退行性や依存性、さらには固着性や執着性をみせることが多い。 ●すなおな子ども論 補足だが、従順で、おとなしい子どもを、すなおな子どもと考えている人は多い。しかしそれは誤解。教育、なかんずく幼児教育の世界では、心(情意)と表情が一致している子どもを、すなおな子どもという。うれしいときにはうれしそうな表情をする。悲しいときには悲しそうな表情をする。しかし心と表情が遊離すると、ここに書いたようにそれがチグハグになる。ブランコを横取りされても、ニコニコ笑ってみせたり、いやなことがあっても、黙ってそれに従ったりするなど。中に従順な子どもを、「よくできた子ども」と考える人もいるが、それも誤解。この時期、よくできた子どもというのは、いない。つまり「いい子」ぶっているだけ。このタイプの子どもは大きなストレスを心の中でため、そのためた分だけ、別のところで「心のひずみ」となって現われる。よく知られた例として、家庭内暴力を起こす子どもがいる。このタイプの子どもは、外の世界では借りてきたネコのようにおとなしい。●おだやかな生活を旨とする キレるタイプの子どもは、不安状態の中に子どもを追いこまないように、穏やかな生活を何よりも大切にする。乱暴な指導になじまない。あとは情緒が不安定な子どもに準じて、(1)濃厚なスキンシップをふやし、(2)食生活の面で、子どもの心を落ち着かせる。カルシウム、マグネシウム分の多い食生活にこころがけ、リン酸食品をひかえる。リン酸は、せっかく摂取したカルシウムをリン酸カルシウムとして、体外へ排出してしまう。もちろんストレスの原因(ストレッサー)があれば、それを除去し、心の負担を軽くすることも忘れてはならない。●子どもの感情障害 ほかに自閉症やかん黙児、さらには小児うつ病など、脳に機能的な障害をもつ子ども、さらに近年問題になっている集中力欠如型多動性児(ADHD)は、感情のコントロールができないことがよく知られている。これらのタイプの子どもは、ささいなことがきっかけで、突発的に(1)激怒する、(2)興奮、混乱状態になる、(3)暴言を吐いたり、暴力行為に及ぶ。攻撃的に外に向って暴力行為を及ぶタイプを、プラス型、内にこもり混乱状態になるのをマイナス型と私は分けている。どちらにせよその行動は予想がつきにくく、たいていは子どもの「ギャーッ」という動物的な叫び声でそれに気づくことが多い。こちらが「どうしたの?」と声をかけるときには、すでに手がつけられない状態になっている。(2)栄養学の分野からの考察●過剰行動性のある子ども もう20年以上も前だが、アメリカで「過剰行動性のある子ども」(ヒュー・パワーズ・小児栄養学)が、話題になったことがある。ささいなことがきっかけで、突発的に過剰な行動に出るタイプの子どもである。日本では、このタイプの子どもはほとんど話題にならなかったが、中学生によるナイフの殺傷事件が続いたとき、その原因の一つとして、マスコミでこの過剰行動性が取りあげられたことがある(98年)。日本でも岩手大学の大沢博名誉教授や大分大学の飯野節夫教授らが、この分野の研究者として知られている。●砂糖づけのH君(年中児) 私の印象に残っている男児にH君(年中児)という子どもがいた。最初、Hさん(母親)は私にこう相談してきた。「(息子の)部屋の中がクモの巣のようです。どうしたらいいでしょうか」と。話を聞くと、息子のH君の部屋がごちゃごちゃというより、足の踏み場もないほど散乱していて、その様子がふつうではないというのだ。が、それだけならまだしも、それを母親が注意すると、H君は突発的に暴れたり、泣き叫んだりするという。始終、こきざみに動き回るという多動性も気になると母親は言った。私の教室でも突発的に、耳をつんざくような金切り声をあげ、興奮状態になることも珍しくなかった。そして一度そういう状態になると、手がつけられなくなった。私はその異常な興奮性から、H君は過剰行動児と判断した。 ただ申し添えるなら、教育の現場では、それが学校であろうが塾であろうが、子どもを診断したり、診断名をくだすことはありえない。第一に診断基準が確立していないし、治療や治療方法を用意しないまま診断したり、診断名をくだしたりすることは許されない。仮にその子どもが過剰行動児をわかったところで、それは教える側の内心の問題であり、親から質問されてもそれを口にすることは許されない。診断については、診断基準や治療方法、あるいは指導施設が確立しているケース(たとえば自閉症児やかん黙児)では、専門のドクターを紹介することはあっても、その段階で止める。この過剰行動児についてもそうで、内心では過剰行動児を疑っても、親に向かって、「あなたの子どもは過剰行動児です」と告げることは、実際にはありえない。教師としてすべきことは、知っていても知らぬフリをしながら、その次の段階の「指導」を開始することである。 ●原因は食生活? ヒュー・パワーズは、「脳内の血糖値の変動がはげしいと、神経機能が乱れ、情緒不安になり、ホルモン機能にも影響し、ひいては子どもの健康、学習、行動に障害があらわれる」という。メカニズムは、こうだ。ゆっくりと血糖値があがる場合には、それに応じてインスリンが徐々に分泌される。しかし一時的に多量の砂糖(特に精製された白砂糖)をとると、多量の、つまり必要とされる量以上の量のインスリンが分泌され、結果として、子どもを低血糖児の状態にしてしまうという(大沢)。そして(1)イライラする。機嫌がいいかと思うと、突然怒りだす、(2)無気力、(3)疲れやすい、(4)(体が)震える、(5)頭痛など低血糖児特有の症状が出てくるという(朝日新聞98年2・12)。これらの症状は、たとえば小児糖尿病で砂糖断ちをしている子どもにも共通してみられる症状でもある。私も一度、ある子ども(小児糖尿病患者)を病院に見舞ったとき、看護婦からそういう報告を受けたことがある。 こうした突発的な行動については、次のように説明されている。つまり脳からは常に相反する二つの命令が出ている。行動命令と抑制命令である。たとえば手でものをつかむとき、「つかめ」という行動命令と、「つかむな」という抑制命令が同時に出る。この二つの命令がバランスよく調和して、人間はスムーズな動きをすることができる。しかし低血糖になると、このうちの抑制命令のほうが阻害され、動きがカミソリでスパスパとものを切るような動きになる。先のH君の場合は、こまかい作業をさせると、震えるというよりは、手が勝手に小刻みに動いてしまい、それができなかった。また抑制命令が阻害されると、感情のコントロールもできなくなり、一度激怒すると、際限なく怒りが増幅される。そして結果として、それがキレる状態になる。●恐ろしいカルシウム不足 砂糖のとり過ぎは、子どもの心と体に深刻な影響を与えるが、それだけではない。砂糖をとり過ぎると、カルシウム不足を引き起こす。糖分の摂取が、体内のカルシウムを奪い、虫歯の原因になることはよく知られている。体内のブドウ糖は炭酸ガスと水に分解され、その炭酸ガスが、血液に酸性にする。その酸性化した血液を中和しようと、骨の中のカルシウムが、溶け出るためと考えるとわかりやすい。体内のカルシウムの98%は、骨に蓄積されている。そのカルシウムが不足すると、「(1)脳の発育が不良になったり、(2)脳神経細胞の興奮性を亢進したり、(3)精神疲労をしやすくまた回復が遅くなるなどの症状が現われる」(片瀬淡氏「カルシウムの医学」)という。わかりやすく言えば、カルシウムが不足すると、知恵の発達が遅れ、興奮しやすく、また精神疲労を起こしやすいというのだ。甘い食品を大量に摂取していると、このカルシウム不足を引き起こす。●生化学者ミラー博士らの実験 精製されてない白砂糖を、日常的に多量に摂取すると、インスリンの分泌が、脳間伝達物質であるセロトニンの分泌をうながし、それが子どもの異常行動を引き起こすという。アメリカの生化学者のミラーは、次のように説召している。 「脳内のセロトニンという(脳間伝達)ニューロンから脳細胞に情報を伝達するという、神経中枢に重要な役割をはたしているが、セロトニンが多すぎると、逆に毒性をもつ」(「マザーリング」81年7号)と。日本でも、自閉症や子どもの暴力、無気力などさまざまな子どもによる問題行動が、食物と関係しているという研究がなされている。ちなみに、食品に含まれている白砂糖の量は、次のようになっている。製品名 一個分の量 糖分の量 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ヨーグルト 【森永乳業】 90ml 9・6g 伊達巻き 【紀文】 39g 11・8g ミートボール 【石井食品】 1パック120g 9・0g いちごジャム 【雪印食品】 大さじ30g 19・7g オレンジエード【キリンビール】 250ml 9・2g コカコーラ 250ml 24・1g ショートケーキ 【市販】 一個100g 28・6g アイス 【雪印乳業】 一個170ml 7・2g オレンジムース 【カルピス】 38g 8・7g プリン 【協同乳業】 一個100g 14・2g グリコキャラメル【江崎グリコ】 4粒20g 8・1g どら焼き 【市販】 一個70g 25g クリームソーダ 【外食】 一杯 26g ホットケーキ 【外食】 一個 27g フルーツヨーグルト【協同乳業】 100g 10・9g みかんの缶詰 【雪印食品】 118g 15・3g お好み焼き 【永谷園食品】 一箱240g 15・0g セルシーチョコ 【江崎グリコ】 3粒14g 5・5g 練りようかん 【市販】 一切れ56g 30・8g チョコパフェ 【市販】 一杯 24・0g ●砂糖は白い麻薬 H君の母親はこう言った。「祖母(父親の実母)の趣味が、ジャムづくりで、毎週ビンに入ったジャムを届けてくれます。うちでは、それを食べなければもったいないということで、パンや紅茶など、あらゆるものにつけて食べています」と。私はH君の食生活が、かなりゆがんだものと知り、とりあえず「砂糖断ち」をするよう進言した。が、異変はその直後から起きた。幼稚園から帰ったH君が、冷蔵庫を足げりにしながら、「ビスケットがほしい、ビスケットがほしい」と泣き叫んだというのだ。母親は「麻薬患者の禁断症状のようで、恐ろしかった」と話してくれた。が、それから数日後。今度はH君が一転、無気力状態になってしまったという。私がH君に会ったのは、ちょうど一週間後のことだったが、H君はまるで別人のようになっていた。ボーッとして、反応がまるでなかった。母親はそういうH君を横目で見ながら、「もう一度、ジャムを食べさせましょうか」と言ったが、私はそれに反対した。●カルシウムは紳士をつくる 戦前までは、カルシウムは、精神安定剤として使われていた。こういう事実もあって、イギリスでは、「カルシウムは紳士をつくる」と言われている。子どもの落ち着きなさをどこかで感じたら、砂糖断ちをする一方、カルシウムやマグネシウムなど、ミネラル分の多い食生活にこころがける。私の経験では、幼児の場合、それだけで、しかも一週間という短期間で、ほとんどの子どもが見違えるほど落ち着くのがわかっている。川島四郎氏(桜美林大学元教授)も、「ヒステリーやノイローゼ患者の場合、カルシウムを投与するだけでなおる」(「マザーリング」81年7号)と述べている。効果がなくても、ダメもと。そうでなくても、缶ジュース一本を子どもに買い与えて、「うちの子は小食で困ります」は、ない。体重15キロ前後の子どもに、缶ジュースを一本与えるということは、体重60キロの人が、4本飲む量に等しい。おとなでも缶ジュースを4本は飲めないし、飲めば飲んだで、腹の中がガボガボになってしまう。 なお問題となるのは、精製された白砂糖をいう。どうしても甘味料ということであれば、精製されていない黒砂糖をすすめる。黒砂糖には、天然のミネラル分がほどよく配合されていて、ここでいう弊害はない。 ●多動児(ADHD児)との違い この過剰行動性のある子どもと症状が似ている子どもに。多動児と呼ばれる子どもがいる。前もって注意しなければならないのは、多動児(集中力欠如型多動性児、ADHD児)の診断基準は、二〇〇一年の春、厚生労働省の研究班が国立精神神経センター上林靖子氏ら委託して、そのひな型が作成されたばかりで、いまだこの日本では、多動児の診断基準はないというのが正しい。つまり正確には、この日本には多動児という子どもは存在しないということになる。一般に多動児というときは、落ち着きなく動き回るという多動性のある子どもをいうことになる。そういう意味では、活発型の自閉症児なども多動児ということになるが、ここでは区別して考える。 ちなみに厚生労働省がまとめた診断基準(親と教師向けの「子どもの行動チェックリスト」)は、次のようになっている。(チェック項目)1行動が幼い2注意が続かない3落ち着きがない4混乱する5考えにふける6衝動的7神経質8体がひきつる9成績が悪い10不器用11一点をみつめるたいへんまたはよくあてはまる……2点、ややまたは時々あてはまる……1点、当てはまらない……0点として、男子で4~15歳児のばあい、12点以上は障害があることを意味する「臨床域」、9~11点が「境界域」、8点以下なら「正常」この診断基準で一番気になるところは、「抑え」について触れられていない点である。多動児が多動児なのは、抑え、つまり指導による制止がきかない点である。教師による抑えがきけば、多動児は多動児でないということになる。一方、過剰行動児は行動が突発的に過剰になるというだけで、抑えがきく。その抑えがきくという点で、多動児と区別される。また活発型の自閉症児について言えば、多動性はあくまでも随伴的な症状であって、主症状ではないという点で、この多動児とは区別される。またチェック項目の中の(1)行動が幼い(退行性)は、過保護児、溺愛児にも共通して見られる症状であり、(7)神経質は、敏感児、過敏児にも共通して見られる症状である。さらに(9)成績が悪い、および(10)不器用については、多動児の症状というよりは、それから派生する随伴症状であって、多動児の症状とするには、常識的に考えてもおかしい。ついでに私は私の経験から、次のような診断基準をつくってみた。(チェック項目)1抑えがきかない2言動に秩序感がない3他人に無遠慮、無頓着4雑然とした騒々しさがある5注意力が散漫6行動が突発的で衝動的7視線が定まらない8情報の吸収性がない9鋭いひらめきと愚鈍性の同居10論理的な思考ができない 11思考力が弱い このADHD児については、脳の機能障害説が有力で、そのために指導にも限界がある……という前提で、それぞれの市町村レベルの教育委員会が対処している。たとえば静岡県のK市では、指導補助員を配置して、ADHD児の指導に当っている。ただしこの場合でも、あくまでも「現場教師を補助する」(K市)という名目で配置されている。(3)環境ホルモンの分野からの考察●シシリー宣言1995年11月、イタリアのシシリー島のエリゼに集まった一八名の学者が、緊急宣言を行った。これがシシリー宣言である。その内容は「衝撃的なもの」(グリーンピース・JAPAN)なものであった。いわく、「これら(環境の中に日常的に存在する)化学物質による影響は、生殖系だけではなく、行動的、および身体的異常、さらには精神にも及ぶ。これは、知的能力および社会的適応性の低下、環境の要求に対する反応性の障害となってあらわれる可能性がある」と。つまり環境ホルモンが、人間の行動にまで影響を与えるというのだ。が、これで驚いていてはいけない。シシリー宣言は、さらにこう続ける。「環境ホルモンは、脳の発達を阻害する。神経行動に異常を起こす。衝動的な暴力・自殺を引き起こす。奇妙な行動を引き起こす。多動症を引き起こす。IQが低下する。人類は50年間の間に5ポイントIQが低下した。人類の生殖能力と脳が侵されたら滅ぶしかない」と。ここでいう「社会性適応性の低下」というのは、具体的には、「不登校やいじめ、校内暴力、非行、犯罪のことをさす」(「シシリー宣言」・グリーンピース・JAPAN)のだそうだ。 この事実を裏づけるかのように、マウスによる実験だが、ビスワエノールAのように、環境ホルモンの中には、母親の胎盤、さらに胎児の脳関門という二重の防御を突破して、胎児の脳に侵入するものもあるという。つまりこれらの環境ホルモンが、「脳そのものの発達を損傷する」(船瀬俊介氏「環境ドラッグ」より)という。(4)教育の分野からの考察 前後が逆になったが、当然、教育の分野からも「キルる子ども」の考察がなされている。しかしながら教育の分野では、キレる子どもの定義すらなされていない。なされないままキレる子どもの議論だけが先行している。ただその原因としては、(1)親の過剰期待、そしてそれに呼応する子どもの過負担。(2)学歴社会、そしてそれに呼応する受験競争から生まれる子ども側の過負担などが、考えられる。こうした過負担がストレッサーとなって、子どもの心を圧迫する。ただこの段階で問題になるのが、子ども側の耐性である。最近の子どもは、飽食とぜいたくの中で、この耐性を急速に喪失しつつあると言える。わずかな負担だけで、それを過負担と感じ、そしてそれに耐えることがないまま、怒りを爆発させてしまう。親の期待にせよ、学歴社会にせよ、それは子どもを取り巻く環境の中では、ある程度は容認されるべきものであり、こうした環境を子どもの世界から完全に取り除くことはできない。これらを整理すると、次のようになる。(1)環境の問題(2)子どもの耐性の問題。 この二つについて、次に考える。●環境の問題●子どもの耐性の問題終わりに……以上のように、「キレる子ども」と言っても、その内容や原因はさまざまであり、その分野に応じて考える必要がある。またこうした考察をしてのみ、キレる子どもの問題を正面からとらえることができる。一番危険なのは、キレる子どもを、ただばくぜんと、もっと言えば感傷的にとらえ、それを論ずることである。こうした問題のとらえ方は、問題の本質を見誤るばかりか、かえって教育現場を混乱させることになりかねない。(はやし浩司 キレる子ども 過剰行動性 突発的に暴れる子供 暴れる子ども)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司***************************安心して、HP、HTML版マガジン、動画を楽しんでいただくために……【みなさんへ】私のパソコンは、以下のような方法で、パソコンの安全と健康を、いつも監視しています。ですから、どうか、安心して、私のHP、HTML版マガジン、および動画(TUBE社)を、お楽しみください。●プロバイダーのほうで、ウィルスチェエクを自動的にしています。●加えて有料版の、ウィルスチェックサービスを、常時行っています(プロバイダー、WBS.NE.JP)。●さらにパソコンごとに、ウィルスソフトを、インストールし、(これも今では常識ですが)、そのつど、ウィルスチェックを行っています。●さらに最近ふえている、スパイウエア対策として、「スパイボット(SPYBOT)」をインストールし、常時監視しています。●さらに、HP制作用のパソコンと、通常作業用のパソコンを分けて使っています。中には「HTML版はこわい?」と心配している方もいらっしゃるかもしれませんが、どうか、安心してお楽しみください。以上、これからもパソコンの安全と健康には、じゅうぶん留意して、HP、マガジンの制作をしていきます。よろしくお願いします。はやし浩司**************************Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(022)【近ごろ、世間では……】●やっぱり、ねつ造! 韓国の大学教授が、世界ではじめて人のクローン胚から、胚性幹細胞(ES細胞という)を作ったと発表した論文について、ソウル大学の調査委員会が、このたび、「ねつ造」と断定した(12月23日)。 大学教授の名前は、F・ウソク。名前からして、「?」を連想させる。そのウソク教授は、05年5月、アメリカの科学雑誌、「サイエンス」に、ES細胞を11個作ったと発表したが、調査の結果、「故意にデータを偽造したもの」(ソウル大学)と判断されたという。同、調査委員会は、「科学の信頼を傷つける重大な行為」と批判している。 当然である。 このウソク大学の研究論文については、かなり以前から、疑問を投げかける人が多かった。つまり人のES細胞を作るのは、それくらい、むずかしい。が、それに対して、韓国政府や韓国人たちは、猛反発。その猛反発が、かえってヤブヘビになってしまった。 ふつう、科学の発展には、周囲科学の発展が不可欠。つまり1つの科学的成果を出そうとするなら、その周囲の科学が、整っていなければならない。たとえばロケットを飛ばすにしても、ロケット工学はもちろん、燃料工学、電子工学などなど、それを支える周囲科学がじゅうぶん整っていなければならない。 そういう周囲科学がないところに、突然、降ってわいたように、1つの科学が特異に発展するということは、ありえない。 今回の人のES細胞を作ったというニュースには、そうした疑問が、最初からついて回っていた。「どうして韓国人が?」と。が、結果は、やはり、クロ。韓国のソウル大学の調査委員会の調査結果だから、ほぼ、そう断定してまちがいないだろう。 しかしこういう事例は、決して少なくない。日本でも、あの藤木S一による、石器ねつ造事件がある。つまり私たち日本人も、あまり偉そうなことは言えない。この世界では、功名をあせるあまり、デタラメな論文を発表する人は、いくらでもいる。私が昔知りえた事件にも、「電磁場麻酔」事件なるものもあった。「静電界麻酔」事件というのもあった。大げさな事件にはならなかったが、そのどこかSF的な、どこかインチキ臭い研究のために、ときの厚生省が、その研究者らに助成金を支払ったという事実がある。●米韓関係の崩壊アメリカのゼーリック国務副長官が、訪米した韓国の鄭東泳統一相と、12月20日に会談した。そのときゼーリック氏は、韓国政府による北朝鮮への経済支援が核問題解決に役立っていないとして、不満を表明。支援を縮小するよう要求したという。 こういう報道が、私の耳にも入ってくるようなら、すでに米韓関係は、終焉(しゅうえん)のときを迎えたとみてよい。同盟国なら、たとえそういう話しあいがなされたとしても、内部で、留保される。決して、表には出てこない。そういう話しあいがあったという話が出てきたということは、「もう韓国など、どうでもよい」という認識を、アメリカ側がもったことを意味する。 当然である。 韓国は、K国寄りというよりは、すでに中国側についてしまっている。K国との関係においても、少なくともN政権イコール、K国と考えたほうがよい。どうしてそんな韓国を、同盟国として、アメリカは守らなければならないのか。 韓国のN大統領よ、もう少し、現実を見たらよい。もし韓国からアメリカが抜けるようなことがあれば、外資は、みな、韓国から逃げ出すだろう。そうなれば、韓国自体が崩壊する。どうしてこんな簡単なことが、N大統領、あなたには、わからないのか。 それに「南北統一」を口にするのはよいが、中国は、そんな甘い国ではない。K国がへたをすれば、中国に吸収合併されてしまう。チベットをみれば、それくらいのことは、だれにでもわかるはず。そうなれば、南北統一など、夢のかなたへ吹っ飛んでしまう。●K国の制裁問題 拉致被害者の気持ちもよくわかるが、何度も書いてきたように、あんなK国など、本気で相手にしてはいけない。制裁などしてはいけない。安倍官房長官は12月22日、都内のホテルで拉致被害者の家族会と面会、その席で、「北朝鮮の時間稼ぎを許すつもりはない」と述べ、拉致問題の解決を北朝鮮に強く求めていく考えを強調したという(産経新聞)。が、制裁については、安倍官房長官も、何も言わなかった。制裁については、どうやら慎重になってきたように感ずる。 当然である。 今、日本がK国を制裁しても、ほとんど、効果はない。ないばかりか、かえって中国、韓国、K国を、結束させてしまうことになりかねない。へたをすれば、K国は、この日本に核攻撃をしかけてくることも考えられる。 日本は、あくまでも国際世論に働きかけ、ジワジワとK国をしめあげるのがよい。たとえば現在、日本政府は、整理回収機構(RCC)を利用して、朝鮮S連を提訴したり、人権担当大使の新設などの作業を推し進めている。 私は、それが正攻法だと思う。制裁したところで、拉致問題は、解決しない。もともとK国は、そうした制裁に耳を貸すような国ではない。まともな国ではない。 どうしても……、というのなら、朝鮮S連へ抗議デモをしかけるという方法などもある。韓国に対して、K国への援助をやめるように、圧力を加えるという方法もある。ともかくも、K国は、国際社会につっぱることによって、自分の「顔」をもとうとしている。経済規模は、日本の数千分の1もない。アジアの中でも、最貧国。もうこれ以上、なくすものは何もないというほどの、最貧国。 そんなK国を制裁して、どうする? どうなる? Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(023)●家族へのクリスマス・プレゼント 今度、10年ぶりに、正月に、家族全員が集まる。3人の息子たちが、まだ幼いころから、「正月には、どんなことがあっても、みんな集まろう」と呼びかけてきた。が、それは私の一方的な(呼びかけ)でしかなかった。 そのうち息子たちが外国へ行くようになったりすると、この(呼びかけ)は、霧散した。それに息子たちは、(家族)よりも、(ガールフレンドとのデート)を優先するようになった。私もワイフも、若いときはそうだったので、息子たちを責めることはできない。 が、そのため、ますます正月は、さみしいものになっていった。とくにここ数年は、クリスマスも正月も、私とワイフの2人だけ。正月のおせち料理も、形だけ。鏡餅については、一番小さいのを買ってきて、テレビの上にのせるだけ。あとはビデオを見ての、寝正月。 が、今年は、どういうわけか、みなが、集まる。そのため、何かと気ぜわしい。大掃除に、寝室の用意。昨日は、息子たちや息子のワイフのために、クリスマス・プレゼントを買ってきた。 何を買ったかって? ……それはここにはまだ書けないが、それが結構、楽しかった。もっともそれを渡すのは、12月28日以後。クリスマスが終わってからの、クリスマス・プレゼント。みんなが喜んでくれれば、それでよい。ハハハ。 今日は、土曜日。午後から休みになる。今日も、忙しくなりそう! では、みなさん、これからその仕事にでかけます。Merry Christmas! 12月24日、午前8時記。●鳥インフルエンザ 昨日、女医(内科医)をしているTさんと、教室の中で、立ち話をする。その場で、アメリカから帰ってくる息子夫婦のために、インフルエンザのワクチン注射を、お願いする。「いつでも、どうぞ」と、Tさんは、言ってくれた。 で、Tさんは、私にこう言った。「先生、本当にこわいのは、インフルエンザではなく、鳥インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザウィルス、H5N1型)ですよ」と。 正直なところ、(鳥インフルエンザ)と言われても、ピンとこない。しかし専門家はみな、口をそろえて、「鳥インフルエンザはこわい」と言う。「もし流行したら、ふつうのインフルエンザどころではない」と。 すでに中国では、6人が感染。うち2人が死んでいる(12月22日)。さらにベトナムでは、抗ウィルス薬タミフルへの耐性をもつウィルスまで検出されたという(同22日)。中日新聞によれば、「耐性ウィルスが見つかったのは、13歳と18歳の少女。いずれも1月に入院。タミフルによる治療を受けたが、それぞれ発症後、8日目と20日目に死亡した」という。 タフミルでもきかないウィルスが出現したということらしい。ゾーッ! もしこの日本で、こうした鳥インフルエンザが流行し、さらにタフミルに対して耐性をもってウィルスが発見されたら、それこそたいへんなことになる。Tさんは、それを言った。「最前線のドクターたちが、最初の犠牲者になります」と、Tさんは笑っていたが、決して笑いごとではすまされない。ドクターたちがしりごみをしてしまったら、患者の私たちはどうすればよいのか。 話を聞いているうちに、私も、だんだんとこわくなってきた。 マスクは、今ではもう、情備品。私も、カバンの中には、いつも、数枚、用意している。人ごみの中に入るときには、必ず、かけるようにしている。みなさんも、くれぐれも、お体を大切に!●K国のにせ札 K国は、にせ札を作って儲けようとした。しかしこうした行為は、かえって自分で自分のクビをしめることになる。新聞報道などによると、K国の貿易関係者は、相手に現金を支払うとき、真札とにせ札を混ぜるのを、常套(じょうとう)手段にしているらしい。 しかしこんなことを繰りかえせば、だれも、K国と取り引きしなくなる。つまり真札まで、にせ札と疑うようになる。さらに仮に今ここでにせ札作りをやめたとしても、失った信用を取りもどすまでには、何年も、何年もかかる。 バカなことをする人をバカという。バカなことをする国をバカという。K国は、そのバカなことばかりしている(?)。●寒い冬 今年の冬は、寒い。おととい、家の中ですら、朝起きてみたら、気温は、6度。このところ、庭の水がめが凍るという日がつづく。 私は、もともと、寒さに弱い。苦手。寒いと、体の活動そのものが、にぶる。何をするにも、おっくうになる。当然、頭の回転も鈍くなる。ものを考えても、それが(思想)にまで、かたまらない。 が、だからといって、暖かくすればよいかというと、そうでもない。暖かくすれば、今度は、眠くなる。こたつの中に入ったら最後、そのまま横にゴロリとなって、グーグー、スースー。 しかし今年の冬は、それにしても寒い。つぎからつぎへと、寒波が押し寄せている。日本海側の各都市では、記録的な大雪が降っている。浜松生まれで、浜松育ちの人たちは、雪を知らない。だから雪に対して、ノスタルジック(郷愁的)な、あこがれをもっている。しかし私は、雪が好きではない。学生時代、金沢で、その雪を、うんざりするほど、経験している。 雪そのものは、よいとしても、その前後が寒い。みぞれに始まって、道路がぬかるむ。雪が美しいのは、一時だけ。やがてすすけた茶色に変化する。そのまま、いたるところで、ゴミの山をつくる。 その浜松でも、先日、雪が降った。朝起きてみると、庭がうっすらと雪化粧。ワイフは、「雪よ!」「雪よ!」と喜んでいたが、私は、ア~ア~で、おしまい。雪が降らない浜松を、私は、ことあるごとに、自慢していたのに……。 豪雪地方のみなさん、豪雪、お見舞い申しあげます!(05年12月26日記)●オートレース 浜松には、公営のオートレース場がある。そのオートレース場が、存続か廃止かで、もめている。民営化するという案も浮上している。もちろん、赤字。2年連続で、毎年2億円近い赤字を出している。 もっとも赤字といっても、「基金を取り崩しての赤字であって、税金をいっさい使っていない」(O支部長談)とのこと。だから「オートは開設以来、800億円を一般会計に繰り入れてきたのに、(たった)2億円の赤字でオートレース事業検討委は廃止の方向に向いているというのは、おかしい」と。 そこで全日本オートレース協議会は、全国で、6万8500人分の署名を集めて、市に提出した。そこで、一度は廃止に傾きかけた市側が、またまた存続側に。これに対して、反対派が、反発……。とくに市から委託された行財政改革推進審議会(行革審)は、猛反発。「(廃止するという提言を)重く受け止めると言っておきながら、軽く無視するのか!」と。 ……というようなドタバタがつづいている。 私も若いころ、まだ子どもが生まれる前のことだったが、ときどき、ワイフと、そのオートレースを楽しんだことがある。ときどきといっても、年に1度か2度。しかしいつも、損ばかりしていた。オートレースというのは、そもそも、素人が儲かるしくみにはなっていない。 もっともそのころは、レース場につづく道路は、大混雑。そのころとくらべると、今は、その面影は、どこにもない。閑散としている。つまりレースを楽しむのは、その道のプロだけ。どことなく、そういう雰囲気をもった、男たちだけ。もちろん子どもづれの夫婦には、無縁の世界。 しかしここは合理的に考えるのが、一番。未来に向かって残さねばならないものかどうか。これから先、市の財政を圧迫してまで、残さねばならないものかどうか。存続させたばあいの、メリットは何か。廃止したばあいの、デメリットは何か。そういう視点から、合理的に考えればよい。 そういう点では、今回の行革審の出した結論は、正論ではないのか。が、それに対して、行政側は無視。 もともと(審議会)というのは、そういうもの。ふつうは、行政側が、何らかのお墨つきをもらうため、あるいは権威づけのために、するもの。審議会のメンバーにしても、どういう基準で選ばれたのかさえ、ふつうは、わからない。もっとはっきり言えば、イエス・マンだけを集めて、行政側にとって、都合のよい結論を出させる。 それが審議会。が、今回は、そうではなかった。メンバーの1人は、「はじめから結論ありきの審議に、どんな意味があるのか」と疑問を呈し、「出来レースではないのか」「ばかにされた印象」「聞く耳をもたないなら、何のための審議か」(中日新聞)と反発。 がんばれ、行革審! 負けるな行革審! ついでに一言。だからといって、こうした行革審を、廃止するな! おそらく行政側内部では、今ごろ、こんな議論がかわされているにちがいない。「ああいう、うるさい行革審は、もう終了しましょう」「そうですねエ~」と。 ついでに以前書いた原稿の一部を、掲載する。++++++++++++++●諮問機関という、ごまかし 官僚が世間を動かすとき、きまって使われる手法が、「諮問(しもん)委員会」の設立である。懇談会、研究会、検討会、審議会などという名称を使うこともある。(名称は決まっていない。教育の世界には、中央教育審議会などがある。) まずもっておかしいのは、委員を選ぶときの、その人選のし方。不明確、不明瞭。どういう基準で、だれが選んでいるかが、まったくわからない。委員ですら、どうして自分が選ばれたのか、わからないときがある。関係機関に問い合わせても、「お答えできません」と言われるのみ。もちろん委員に選ばれるのは、「イエス・マン」だけ。この世界には、こうした諮問機関をつぎからつぎへと渡り歩いている「有識者?」がいくらでもいる。 そうして委員会は始まるが、(そうした会議はテレビでもよく紹介されるから、みなさんもご覧になったことがあると思う)、会議での討論内容のほとんどは、あらかじめ官僚によって作成される。そして座長と呼ばれる人が、それを順に読みあげ、「いかがですか?」「ご意見は?」という調子で、会議が進んでいく。時間は委員一人あたり、約5~10分程度。一方的に意見を述べるだけ。討論に発展することは、まずない。大きな諮問委員会でも、回数は5~6回程度。最後に座長が、官僚の意向にそった結論をまとめて、文書にして、答申する。それでおしまい。 あとはいわゆる「お墨つき」を得た官僚は、その答申をもとに、したい放題。大きな国家プロジェクトの大半は、こうして決まる。空港も、高速道路も、港も、はたまた博覧会も。日本が官僚主義国家だと言われるゆえんは、こんなところにある。 さて今夜も、あちこちの諮問委員会の模様が、テレビで報道されることだろう。一度、ここに書いたような知識を頭に置きながら、ああいった委員会をながめてみたらよい。あなたも諮問委員会のもつおかしさに、気づくはずである。(021017)+++++++++++++++ 日本の政治は、まあ、こんなもの。こういう流れの中で、決まっていく。悲しいかな日本は、奈良時代の昔から、官僚主義国家。中央集権国家。その亡霊が、いまだに、日本全国、津々浦々に残っている。その1つが、今回のオートレース場の存続問題である。●夫婦 自分で自分の顔を見ることはできない。顔に、食べ物の残りカスがついていることだって、ある。ときには、鼻くそがついていることだってある。さらに口臭となると、自分ではわからない。 しかしそれを教えてくれるのが、夫であり、妻ということになる。 が、それだけではない。同じように、自分で自分の心を見ることはできない。ときにその心は、とんでもない方向へ、暴走してしまうことがある。心の病気となると、自分ではわからない。 しかしそれを教えてくれるのが、夫であり、妻ということになる。 その夫婦。このところ、私はワイフの顔をみながら、よくこう思う。「こいつも、ますますバーさんらしくなったなあ」と。恐らくワイフはワイフで、そう思っているにちがいない。「この人も、ますますジーさんらしくなったわね」と。 そしてこう思う。「もし、ワイフが死んだら、ぼくは、自分の顔を見ることができなくなる。自分の心を見ることができなくなる」と。 そう考えていくと、心細くなる。いや、実のところ、私には、ひとりで生きていく自信は、ない。もしワイフが死んだら、私も、おしまい。たとえばこうして書いている文にしても、そのつどワイフがあれこれと批評してくれるから、その範囲にとどまっていることができる。しかしそれがなくなったら、私のことだから、とんでもない方向に暴走してしまうにちがいない。 だから文を書くことも、できなくなる。もちろん、心の問題となると、なおさらである。 ところで今朝、朝食のとき、ワイフがこう言った。「私、最近、人の名前をよく忘れるわ」と。私「ぼくなんか、しょっちゅうだ、よ」ワ「私も……。どうしてもその人の名前を思い出せないことがあるわ」私「ところで、ぼくの名前、覚えている?」ワ「ヒロ……何だってけ?」私「ヒロトシだよ。な、トシコ」ワ「私、トシコじゃ、ないわよ。ユキコよ」私「そうだったけ。ユキコか。先日まで、アキコかと思っていた」ワ「わかっているくせに……」と。 私の名前は、浩司(ひろし)。ワイフの名前は晃子(あきこ)。どうか、おまちがえなく。 ●依存と愛着++++++++++++++++++3年前に書いた原稿を改めて読みなおしてみる。自分のボケ度を知るには、たいへんよい。つまり3年前の自分と、今の自分を、それで比較することができる。原稿は、ランダムに選んでみた。テーマは、『依存と愛着』。さあ、どうかな?+++++++++++++++++++ 子どもの依存と、愛着は分けて考える。中には、この2つを混同している人がいる。つまりベタベタと親に甘えることを、依存。全幅に親を信頼し、心を開くのを、愛着という。子どもが依存をもつのは問題だが、愛着をもつのは、大切なこと。 今、親にさえ心を開かない、あるいは開けない子どもがふえている。簡単な診断方法としては、抱いてみればよい。心を開いている子どもは、親に抱かれたとき、完全に力を抜いて、体そのものをべったりと、すりよせてくる。心を開いていない子どもや、開けない子どもは、親に抱かれたとき、体をこわばらせてしまう。抱く側の印象としては、何かしら丸太を抱いているような感じになる。 その抱かれない子どもが、『臨床育児・保育研究会』(代表・汐見稔幸氏)の実態調査によると、4分の1もいるという。原因はいろいろ考えられるが、報告によれば、「抱っこバンドだ」という。「全国各地の保育士が、預かった〇歳児を抱っこする際、以前はほとんど感じなかった『拒否、抵抗する』などの違和感のある赤ちゃんが、4分の1に及ぶことが、『臨床育児・保育研究会』(代表・汐見稔幸氏)の実態調査で判明した」(中日新聞)と。報告によれば、抱っこした赤ちゃんの「様態」について、「手や足を先生の体に回さない」が33%いたのをはじめ、「拒否、抵抗する」「体を動かし、落ちつかない」などの反応が2割前後見られ、調査した六項目の平均で25%に達したという。また保育士らの実感として、「体が固い」「抱いてもフィットしない」などの違和感も、平均で20%の赤ちゃんから報告されたという。さらにこうした傾向の強い赤ちゃんをもつ母親から聞き取り調査をしたところ、「育児から解放されたい」「抱っこがつらい」「どうして泣くのか不安」などの意識が強いことがわかったという。また抱かれない子どもを調べたところ、その母親が、この数年、流行している「抱っこバンド」を使っているケースが、東京都内ではとくに目立ったという。 報告した同研究会の松永静子氏(東京中野区)は、「仕事を通じ、(抱かれない子どもが)2~3割はいると実感してきたが、(抱かれない子どもがふえたのは)、新生児のスキンシップ不足や、首も座らない赤ちゃんに抱っこバンドを使うことに原因があるのでは」と話している。 子どもは、生後7、8か月ころから、人見知りする時期に入る。一種の恐怖反応といわれているが、この時期を通して、親への愛着を深める。が、この時期、親から子への愛着が不足すると、以後、子どもの情緒はきわめて不安定になる。ホスピタリズムという現象を指摘する学者もいる。いわゆる親の愛情が不足していることが原因で、独得の症状を示すことをいう。だれにも愛想がよくなる、表情が乏しくなる、知恵の発達が遅れ気味になる、など。貧乏ゆすりなどの、独得の症状を示すこともあるという。 一方、冒頭にも書いたように、依存は、この愛着とは区別して考える。依存性があるから、愛着性があるということにはならない。愛着性があるから、依存性があるということにはならない。が、この二つは、よく混同される。そして混同したまま、「子どもが親に依存するのは、大切なことだ」と言う人がいる。 しかし子どもが親に依存性をもつことは、好ましいことではない。依存性が強ければ強いほど、自我の発達が遅れる。人格の「核」形成も遅れる。幼児性(年齢に比して、幼い感じがする)、退行性(目標や規則、約束が守れない)などの症状が出てくる。もともと日本人は、親子でも、たがいの依存性がきわめて強い民族である。依存しあうことが、理想の親子と考えている人もいる。たとえば昔から、日本では、親にベタベタ甘える子どもイコール、かわいい子イコール、よい子と考える。そして独立心が旺盛で、何でも自立して行動する子どもを、かわいげのない「鬼ッ子」として嫌う。 こうしたどこかゆがんだ子育て観が、日本独特の子育ての柱になっている。言いかえると、よく「日本人は依存型民族だ」と言われるが、そういう民族性の原因は、こうした独特の子育て観にあるとみてよい。もちろんそれがすべて悪いと言うのではない。依存型社会は、ある意味で温もりのある社会である。「もちつもたれつの社会」であり、「互いになれあいの社会」でもある。しかしそれは同時に、世界の常識ではないことも事実で、この日本を一歩外へ出ると。こうした依存性は、まったく通用しない。それこそ生き馬の目を抜くような世界が待っている。そういうことも心のどこかで考えながら、日本人も自分たちの子育てを組み立てる必要があるのではないか。あくまでも一つの意見にすぎないが……。(はやし浩司 愛着 依存 抱かれない子供 抱かれない子ども ホスピタリズム 抱っこバンド 子どもの依存性 子供の依存性 はやし浩司++++++++++++++++ こうして読みかえしてみると、文章は少しあらいものの、今より鋭かったのかなと思う。というのは、今の私は、かくして、確実にボケ始めている(?)。 気をつけよう!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(11)
最前線の子育て論byはやし浩司(020)【近ごろ・あれこれ】●掃除また掃除 この数日間、掃除ばかりしていた。まず、居間。それから客間、日本間。まだ正月までには、日があるというのに、我が家は、すでに大掃除モード。 しかしその掃除。私は嫌いではない。それに始めたら最後、止まらない。とことんしなければ、気がすまない。「手を抜かない」が、私のモットー。 多分、正月までには、また掃除をしなければならないだろう。少し時期が、早すぎたかな?●原稿書き そんなわけで、ここ数日、ほとんど、原稿を書いていない。今ごろは、1月20日号の配信予約を入れなければならないころ。が、まだ1月18日号すら、書き終えていない。このままだと、マガジンは、どうなるのだろう? ぼんやりとした無気力状態が、ダラダラとつづいているカンジ。何を考えても、「もうどうでもいいや」という、投げやり的な気分ばかりが、先に立つ。 が、今朝(12・21)、Eマガの読者数を見ると、3人ふえていた。久々の増加。で、少しだけ、やる気がわいてきた。しかし何を書こう……ということで、この(近ごろ・あれこれ)を書き始めた。●「♪丘の上の小さなベンチ」 長男と三男が、2人で、新曲を作った。タイトルは、「♪丘の上の小さなベンチ」。作詞は長男の周市、作曲は三男の英市。さっそく、TUBE(無料ストリーミング配信会社のサービス)を使って、ビデオ風にしあげる。 興味のある方は、はやし浩司のHPのトップページより、「声と朗読・ごあいさつ」へ進んでみてほしい。 何度聞いてもあきない、ほっと心の休まる曲だと、自分では、そう思っている。(親バカかな?)●忘年会 このところ、ワイフは、忘年会つづき。何かにかこつけて、忘年会ばかりしている。しかし女性って、どうしてこうも忘年会がすきなのだろう。(もちろん男性にだって、忘年会の好きな人はいるが……。) 私自身は、酒が飲めないこともあって、(プラス)、仕事の時間帯が、ふつうの人たちとはズレていることもあって、忘年会とは、ここ10年ほど、とんと縁がない。そのかわり、子どもたちと、年末は毎日のように、ラーメンを食べに行ったり、ハンバーガーを食べに行ったりしている。 子どもたちは、勝手に、「忘年会だ!」「忘年会だ!」と、騒いでいるが……。●アメリカから客が…… 二男の妻のデニーズが、妹のドーンを、日本へ連れてくるという。急に、決まった。「前から、一度、日本を訪問してみたい」と言っていたとか。「できるときが、最善のとき」(It is the best time when you can do it.)。つまりものごとには、「機」というものがある。その「機」がないときに、あれこれしようとしても、ものごとは動かない。しかし「機」がくれば、ものごとは、自然に動きだす。今が、そのとき。 さっそく招待状を、メールで書く。 そのアメリカ人たちだが、ものの考え方が、本当にストレート。二男に、「航空運賃は、ぼくのほうで、出してあげるよ」とメールで連絡してやったら、すかさず、デニーズから、「Thank you.」という返事! 日本人なら、こういうとき、「悪いですね……」「申し訳ありません……」「お言葉に甘えまして……」とか書くのだろうが、そういう奥ゆかしさは、まったくない。 しかしそういうアメリカ人のわかりやすさが、私は、好き。日本人のように、表だとか裏がない。見たままが、ありのまま。それがアメリカ人。●もののない美しさ 50歳をすぎるころから、(もののない美しさ)というのが、よくわかるようになった。よい例が、道路の上にクモの巣のように張りめぐされた電線。あの電線のある風景と、電線のない風景は、まるでちがう。たまに電線のない風景を見たりすると、フーッと、自然と息がもれるような解放感を覚える。 家の中も、また同じ。 先ほど掃除のことを書いたが、掃除をするときのコツは、不用品は、容赦なく、どんどんと捨てること。「少しもったいないかな?」と思っても、捨てる。これを繰りかえしていると、やがて、部屋の中がすっきりとしてくる。 ものがゴチャゴチャとつまっている部屋は、それだけで、息苦しい。息苦しいだけではない。(汚い)。(汚い)というよりは、解放感がない。 数年前だが、ある知人の家に行ったら、廊下から階段まで、ものが、ぎっしり! 人がやっと歩けるほどしか、間があいていなかった。しかしそういう人を、(ものを大切にしている人)とは、言わない。 (ものを大切にする)ということは、多少の不便は感じながらも、限られたものを、うまくやりくりしながら、使うこと。生活をしているという実感も、そこから生まれる。 ものがぎっしりとつまっている家……生活感をほとんど感じないのは、そのためではないか。 ……そう言えば、人間の心も、同じ。 雑念だらけの人もいる。そういう人の心というのは、言うなれば、ものが散乱した部屋のようなもの。その人の心が、どこにあるかさえも、わからない。心の中をすっきりさせるためには、そうした雑念を、どんどんと捨てていく。自分の心を、わかりやすくしていく。 要するに、心の裏で、あれこれと、ものを考えないこと。計算しないこと。ありのままの自分をさらけ出しながら、さわやかに生きること。美しい心というのは、その結果として、あとからついてくる。●孫の誠司 孫の誠司が、もうすぐ日本へやってくる。で、昨夜、ワイフと、孫の誠司といっしょに何をするか、行動計画をリストアップしてみた。(1)近くの遊園地へ行く。(2)浜名湖で船に乗る。(3)町へつれていき、ショッピングする。(4)一度だけ、BW教室で勉強させる。(5)ディズニーランドへ、つれていく。(6)どこかの温泉地に泊まる。(7)写真を、毎日、500枚くらい撮影する。(8)毎晩、コタツの中で、ひざに抱いて、本を読む。(9)毎日、ちがった日本料理を食べさせる。(10)毎日、いろいろな模型を作ってみせる。(11)毎日、近所を、いっしょに散歩する。 ほかにもあるが、これらを、すべて実行する。どういうわけか、自分の孫というのは、かわいく見える。他人が見れば、そうではないのかもしれないが、私には、かわいく見える。(私も、ジジバカかな?)●無気力症状 この数日間、ほとんどといってよいほど、原稿を書いていない。書く意欲そのものが、わいてこない。頭の中も、どこか、ぼんやりとしている。何を考えても、投げやり的。無気力感ばかりが、先に立つ。「どうにでもなれ」「どうでもいいや」と。 書斎にすわることはあっても、ニュースを見たり、ゲームをしたりするだけ。あとは本を読んだり、雑誌をながめたり……。その間に、ときどき、メールを開いてみたりする。 私は、今、いわゆる、無気力状態に陥(おちい)っている。「なぜだろう?」……と考える前に、私の症状を、正確に記録しておきたい。子どもでも、ときとして、今の私に似たような症状を示すことがある。そういうときの子どもの心理を理解するのに、あとで、少しは役に立つかもしれない。(1)思考の拡散 集中力が消えたというわけではない。一つのことを考えていると、別の新しい考えが、頭の中に浮かんで消える。いつものようなピリピリとした緊張感がない。思想のかたまりのようなものが、頭の中に浮かんでこない。書きたいテーマが、モヤモヤとしているのはわかるが、つかみどころがない。それはたとえて言うなら、目的もなく、街の中をフラフラ歩いているようなカンジ(?)。(2)現実感の喪失 考えていることに、実感がともなわない。現実感そのものが、薄い。教育問題にしろ、政治問題にしろ、はたまた人生問題にせよ、「こんなことを書いて、何の役に立つのだろうか?」「こんな問題は、今の私とどういう関係にあるのだろうか?」と、ふと考えて、立ち止まってしまう。現実はそこにあるのに、自分の書いていることが、その現実から遊離してしまう。(3)疲労感の増大 もともと考えることには、ある種の苦痛がともなう。その苦痛を乗り越えるのが、おっくうになる。これもたとえて言うなら、ジョギングにでかけようと玄関から外に出たとたん、冷たい風にあおられたときの気分に似ている。その冷気を乗りきるパワーそのものがわいてこない。「今日はやめておこう」と、そのまま家の中にもどってしまう。体力と気力は、関連している。東洋医学では、そう教える。体力そのものが、弱っている(?)。(4)ニヒリズムの増大 「どうでもなれ」という思いが、(1)~(3)と並行して、増大する。K国の核兵器開発がどうなろうとも、それがいつか、日本の大都市でどう使われようとも、私の知ったことではない。どうせ私は、だれにも相手にされていない。その私が、どうして世界や、社会のことを心配しなければならないのか。みんな、自分のことしか考えていないではないか。そんな思いが、強くなる。(5)被害妄想の増大 何を考えても、「あれが悪い」「これが悪い」という発想になる。そして1つの問題が解決すると、また別の問題が、ちょうどモグラたたきのモグラのように、現れては消える。「自分がこういう状態になったのは、あのせいだ」とか、「あのことが原因だ」とか、そういうふうに考える。(6)敗北感と虚脱感 「もう私は負けたのだ」という思い。それに何をしても、口から出てくる言葉は、一つ。「疲れた……」。ただ救われるのは、それが「私」という個人の世界の範囲でとどまっていること。ワイフや息子を前にすると、いつものような声で、いつものように会話をする。ワイフや息子は、私が、今のような状態になっているとは、夢にも思わないだろう。もっとも、もしそれがだれの目にもわかるようになれば、私は、うつ病(depression)ということになる。 こうした症状が出たら、どうするか。 解決方法は自分でもわかっている。1に休養、2に休養。あとは好きなことをして、その日を過ごす。やがて何かのきっかけがあれば、もとの状態にもどる。 で、私のばあい、いろいろな方法がある。一番効果的なのは、買い物。とくにパソコングッズを買うのがよい。つぎに掃除。草刈り。人に会うのは、あまり好きではない。仕事では、毎日、多くの親や子どもたちと会う。だから、子どもが好きなはずなのに、こういうときというのは、子どもの声を耳にするだけでも、わずらわしく感ずる。 そういう状態が、数日つづくと、少しずつだが、また(やる気)が起きてくる。今が、ちょうど、そのとき(?)。この文章を書いているのが、何よりの証拠ということになる。 機械でいえば、ならし運転という状態。思いついたまま書いていると、やがて指の動きもなめらかになってくる。速くなってくる。頭の回転も調子よくなってくる。それを繰りかえしていると、いつもの自分に、またもどる。 そうそうもう一つ、気がついたことがある。こういう状態のときというのは、パソコンを相手にして、将棋をさしても、すぐ負けてしまう。注意力が散漫になっている。深く考えることができない。集中力も弱くなる。そのためいわゆるうっかりミスが多くなる。それで負けてしまう。(はやし浩司 無気力 無気力な状態 虚脱感 無気力症候群)Hiroshi Hayashi+copyright by H. Hayashi+De.'05+はやし浩司 ●札幌、福岡で講演? 12月も押し迫った昨日(12・20)、とんでもない講演依頼が、舞いこんできた。主催者は、東京のH堂社。間に入っているのは、C社。今年も、こうした大きな講演会の依頼は、ときどきあったが、しかしそのうちの5つのうち、4つは、主催者のほうが、断ってきた(05年度)。私の知名度では、人は集まらない。自分でも、それはよくわかっている。 会場は、北は北海道の札幌市、仙台市、東京、名古屋、大阪、そして福岡。「やってくれますか?」と言ったので、「どこへでも、行きます」とだけ答えた。しかしいつもだと、このあとしばらくすると、主催者の方が、断ってくるはず。「はやし浩司なんて、知りませんよ」「どんな人ですか?」「ほかの人にしたいです」と。 しかし私は、しばしの夢を見た。心のときめきを覚えた。一度は、東京で講演をしてみたいと思っている。東京で、テレビには、何度か出演したことはあるが、講演はない。家に帰ってそのことをワイフに話すと、ワイフは、「そういうときが、近づいてきたのね」とだけ言って、笑った。 そう、近づいてきているのは、私にもわかる。しかしそれは、いつも、私の頭の上をかすめて、そのままどこかへ飛んでいってしまう。 その翌日の今日になると、私は、その夢から、すっかりさめた。心のときめきも、消えていた。現実は、そんな甘くない。それも、自分では、よくわかっている。 H堂さん、C社さん、お声をかけてくださっただけで、感謝しています。ありがとうございました。●ホームレスの家 こんなことを書いてよいのかな? マネをする人がいると、困る。しかし私は、路上で生活をしているホームレスの人たちを見るたびに、こう思う。「冷暖房完備、住み心地満点、そんな住みかが、街中にあるではないか」と。 しかし一応、犯罪の教唆(きょうさ)になるので、どこにあるとは、ここには、書けない。しかしちゃんと、ある。いたるところにある。しかも絶対、安心、安全。だれにもじゃまされない。 ワイフにその場所を説明すると、こう言った。 「あなた、そんなこと、原稿に書いてはだめよ」と。私「わかっている。しかしどうしてホームレスの人たちは、それに気づかないのだろう。ぼくがホームレスになったら、そういうところに住むよ」ワ「でも、どうやって、中に入るの?」私「簡単だよ。xxには、どこにでも、xxxがある。そのxxxのxxから、中に入ればいい」ワ「そうね。そういうところから、中へ入ればいいわね」私「xx員の服装をするのがコツ。で、中をあちこち歩き回ってみると、意外なところに別の出入り口があるはず。そういうところから、出入りすればいい」ワ「やっぱり、そんなこと原稿に書いてはだめよ。マネをする人が出てきたら、たいへんなことになるわよ」私「わかっている。電気だって使い放題だしね。水道も、使い放題。自分で工事することもできる」と。 ホームレスのみなさん、どうせ路上に住むくらいなら、もっと知恵をしぼれ。知恵をしぼれば、もっと快適な生活ができるぞ!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(021)●育児ノイローゼ、Mさんのケース++++++++++++++++++以前、Mさん(当時40歳くらい)から、毎晩のように、子育てについての相談を受けたことがある。Mさんは、何かにつけて、子ども(当時14歳)の問題点を見つけては、それを大げさに問題にしていた。明らかに育児ノイローゼであった。そのMさんについて書く前に、以前書いた原稿(中日新聞掲載済み)を、ここに掲載する。+++++++++++++++++++【母親が育児ノイローゼになるとき】●頭の中で数字が乱舞した それはささいな事故で始まった。まず、バスを乗り過ごしてしまった。保育園へ上の子ども(4歳児)を連れていくとちゅうのできごとだった。次に風呂にお湯を入れていたときのことだった。気がついてみると、バスタブから湯がザーザーとあふれていた。しかも熱湯。すんでのところで、下の子ども(2歳児)が、大やけどを負うところだった。次に店にやってきた客へのつり銭をまちがえた。何度レジをたたいても、指がうまく動かなかった。あせればあせるほど、頭の中で数字が勝手に乱舞し、わけがわからなくなってしまった。●「どうしたらいいでしょうか」 Aさん(母親、36歳)は、育児ノイローゼになっていた。もし病院で診察を受けたら、うつ病と診断されたかもしれない。しかしAさんは病院へは行かなかった。子どもを保育園へ預けたあと、昼間は一番奥の部屋で、カーテンをしめたまま、引きこもるようになった。食事の用意は何とかしたが、そういう状態では、満足な料理はできなかった。そういうAさんを、夫は「だらしない」とか、「お前は、なまけ病だ」とか言って責めた。昔からの米屋だったが、店の経営はAさんに任せ、夫は、宅配便会社で夜勤の仕事をしていた。 そのAさん。私に会うと、いきなり快活な声で話しかけてきた。「先生、先日は通りで会ったのに、あいさつもしなくてごめんなさい」と。私には思い当たることがなかったので、「ハア……、別に気にしませんでした」と言ったが、今度は態度を一変させて、さめざめと泣き始めた。そしてこう言った。「先生、私、疲れました。子育てを続ける自信がありません。どうしたらいいでしょうか」と。冒頭に書いた話は、そのときAさんが話してくれたことである。●育児ノイローゼ 育児ノイローゼの特徴としては、次のようなものがある。(1)生気感情(ハツラツとした感情)の沈滞(2)思考障害(頭が働かない、思考がまとまらない、迷う、堂々巡りばかりする(記憶力の低下)(3)精神障害(感情の鈍化、楽しみや喜びなどの欠如、悲観的になる、趣味や興味の喪失、日常活動への興味の喪失)(4)睡眠障害(早朝覚醒に不眠)など。さらにその状態が進むと、Aさんのように、(5)風呂に熱湯を入れても、それに気づかなかったり(注意力欠陥障害)、ムダ買いや目的のない外出を繰り返す(行為障害)(6)ささいなことで極度の不安状態になる(不安障害)(7)同じようにささいなことで激怒したり、子どもを虐待するなど、感情のコントロールができなくなる(感情障害)(8)他人との接触を嫌う(回避性障害)(9)過食や拒食(摂食障害)を起こしたりするようになる(10)また必要以上に自分を責めたり、罪悪感をもつこともある(妄想性)(11)異常な多弁性をともなうことがあり、一方的にしゃべるだけで、相手の話を聞かない(多弁性)(12)ふとしたきっかけで、「死んでしまいたい」と考えることがある(自殺願望)(13)動悸、息切れ、不眠、早朝覚醒などの身体的症状を伴うことが多い。こうした兆候が見られたら、黄信号ととらえる。育児ノイローゼが、悲惨な事件につながることも珍しくない。子どもが間にからんでいるため、子どもが犠牲になることも多い。●夫の理解と協力が不可欠 ただこうした症状が母親に表れても、母親本人がそれに気づくということは、ほとんどない。脳の中枢部分が変調をきたすため、本人はそういう状態になりながらも、「私はふつう」と思い込む。あるいは症状を指摘したりすると、かえってそのことを苦にして、症状が重くなってしまったり、さらにひどくなると、冷静な会話そのものができなくなってしまうこともある。Aさんのケースでも、私は慰め役に回るだけで、それ以上、何も話すことができなかった。 そこで重要なのが、まわりにいる人、なかんずく夫の理解と協力ということになる。Aさんも、子育てはすべてAさんに任され、夫は育児にはまったくと言ってよいほど、無関心であった。それではいけない。子育ては重労働だ。私は、Aさんの夫に手紙を書くことにした。この原稿は、そのときの手紙をまとめたものである。+++++++++++++++++【Mさんのケース】 Mさんの子ども(名前をA君とする)は、「生まれながらにして、発育不良だった」(Mさんの言葉)とのこと。そのためMさんは、A君を溺愛する一方、過保護にして育てた。ふつうの過保護ではない。過保護の上に「超」がつく、超過保護である。つまり、Mさんは、いわゆる(心配先行型)の子育てを繰りかえした。 ただ、過保護の基盤に愛情があったかというと、それは疑わしい。Mさんは、子どもを自分の支配下に置いて、自分の思いどおりにしたかっただけではなかったか。 たとえばA君が自分で、シャツや服を着るような年齢になったときでも、「心配だ」「心配だ」と言って、Mさんが手を貸していたという。「どうして手を貸したのですか?」と聞くと、「自分で着させると、前とうしろを反対に着た」「汚れたシャツをそのまま着た」「2枚もセーターを着たこともある」と。 一事が万事。A君が風呂に入っても、「きちんと洗わない」「髪の毛を洗わない」「石鹸で遊んでしまう」などといっては、Mさんは、いつもA君といっしょに、風呂に入っていた。A君の体を洗ってやっていた。そしてそういう状態が、A君が、小学5、6年生になるまでつづいた。 その間にもいろいろあった。A君は、学校で、いじめを受けていたこともある(Mさんの言葉)。そのためMさんは、毎日学校まで、A君を迎えに行ったこともある。そしてこんなこともあった。 A君の修学旅行に行ったときのことだったという。Mさんは、恥ずかしげもなく、私にこう言った。「Aのことが心配で、2晩、泣いて明かしました」と。が、そういうMさんだが、その一方で、A君を虐待していた。虐待といっても、言葉の虐待である。Mさんは、ことあるごとに、A君にこう言っていたという。 「あんたのような子は、将来は、こじきをするしかないわね」 「あんたのような子は、生まれてくるべき子ではなかったのよ」 「しっかりと勉強しないと、あなたもホームレスの人たちのようになるのよ」 「あんたさえいなければ、お母さんは、もっと楽しく過ごせるのにね」と。 Mさんは、A君に自覚をもってもらいたいと願って、そう言ったという。もちろんMさん自身には、虐待しているという意識は、まったくなかった。しかしこうした母親の日常的な言葉で、A君は、ますます萎縮していった。 そのA君に、大きな変化が見られたのは、A君が中学生になってからである。ものごとに異常にこだわるようになった。A君は、カード集めをしていたが、そのカードを、何よりも大切にしていた。そしてそのカードを、数千枚近く(母親の言葉)も、もっていた。 「部屋中、カードだらけだったので、Aが学校へ行っている間に、ダンボール箱に入れて、納屋へしまってやりました」(Mさん)と。 そのとたん、A君は、ふつうではなくなってしまった。何かの拍子に、二階へつづく階段から、とびおりたりするようになった。腕の骨を折ったこともある。が、何よりも気になったのは、オドオドと、何かにおびえるような様子を見せるようになったことである。ふだんでも、ときおり、下をみつめたまま、ニヤニヤ(ニタニタ)と笑いつづけることもあった。 当時は、今のように、児童相談所も整備されていなく、また虐待に対する認識もそれほど深くなかった。 そのころMさんが私に電話で、相談してくるようになった。ときには、毎晩つづけて、1~2時間も、電話がかかってくることもあった。内容もさることながら、Mさんは、一方的に、しゃべるだけ。こちらの私が、何かをアドバイスしようとすると、即座に反論したりして、会話にならなかったのをよく覚えている。 「このままでは、うちの子は、だめになってしまう」 「こんな状態で、私は、Aのめんどうを、一生みなければならない」と。 私が「そういうふうに決めてかかってはいけない」と言いかけると、「叔父がそうだった」「近所の子どももそうだった」と、つぎからつぎへと、そういう話ばかりした。 Mさんが、ふと、こう漏らしたこともある。「このままでは、Aは、うちの財産を食いつぶしてしまう」と。Mさんは、そんなことまで心配していた。 そこで私は、Mさんに、一度、A君を、心療内科医院でみてもらったらよいとアドバイスしたことがある。で、Mさんは、それをしたが、「近所の医院では恥ずかしいから」という理由で、電車で40分もかかる、隣町にある、医院へ通うようになった。 が、やがてそれについても、「時間がかかる」「このまま一生、医療費がかかる」などと言い出した。1つの問題が解決すると、それが解決したことを喜ぶよりも先に、つぎのまた別の問題をもちだして、それを心配した。そんなとき、また電話がかかってきた。 「先生、今日、Aを病院へ、車で連れていきました。その途中のことですが、私は思わず、反対車線に入りそうになってしまいました。このまま死ぬことができたら、どんなに気が楽だろうと思いました」と。 明らかにMさんは、育児ノイローゼになっていた。しかしMさんには、その自覚はなかった。病因で診察を受けたら、「うつ病」と診断されたかもしれない。Mさんは、こう言った。 「朝は、2時ごろ目がさめてしまいます。はげしい動悸がして、体中が、ほてってしまいます」 「Aのことを考えると、心配で心配で、夜も眠られません」と。私「何が、心配なのですか?」M「夜も、電気ストーブをつけっぱなしです」私「どうしてそれが心配なのですか」M「倒れたら、火事になります」私「なりません。倒れれば、自動的に電気が切れるしくみになっています」M「カーテンのそばに、電気ストーブがあります。火事になります」と。 こういう意味のない、押し問答が、いつまでもつづく。 Mさんの特徴は、ほかにもある。当時書いた原稿をまとめてみると、こうなる。(1)きわめてささいな、しかも表面的な問題について、心配していた。(2)私の説明が、理解できない。何かを説明しても、それがどこかへ消えてしまう。(3)私が言った、何かの言葉じりをつかまえて、私に食ってかかってくることもあった。(4)一方的にペラペラと話すだけで、私の話を聞かない。ほとんどがグチ。(5)何冊か本を読むように勧めたこともあるが、「本は読みたくない」と言った。 Mさんの夫については、私は知らない。会ったことも、電話で話したこともない。ただMさんの話では、無口で、仕事だけをしているような人らしかった。もちろん家事、育児については、ほとんど関心がないといったふうだった。夫婦の会話も、なかった。そのため、よけいにMさんは、追いつめられていった。 Mさんからの電話相談は、かれこれ3年近くもつづいた。で、2年前、私はそのMさんだけのことが理由ではないが、こうした電話相談については、すべて断るようにした。電話相談だけで、午前中の時間が、すべてつぶれてしまうことも珍しくなかった。 以上、Mさんという母親について書いたが、Mさんと特定できないよう、細部については、私の方で、ほかのいくつかの事例を混ぜて書いた。そのため、話の流れとして不自然な部分もあるかもしれない。それは許してほしい。 で、今から思うと、Mさんには、育児そのものが負担ではなかったかということ。さらに言えば、良好な親子関係、夫婦関係があれば、同じ重荷でも、感じ方がちがったはず。しかしMさんには、その両方が欠けていた。さらにMさんは、自分では、「私の両親には問題はなかった」と何度も言ったが、客観的に判断すると、Mさんはかなり不幸な家庭に生まれ育っていた。 そういう深い因縁が、回りまわって、そのときのMさんの育児ノイローゼにつながっていったのではないかと思う。 それからx年。M君は、無事高校を卒業し、今は、農協関係の仕事をしているという。Mさんの話は、以来、耳にしていない。+++++++++++++++++●どうしたらよいか? 育児ノイローゼになる人には、ある一定のパターンがある。ここでは思いつくまま、書いてみる。(1)気を抜くための、趣味などがない。 相談を受けながらいつも思うことは、「この人は、別のところで、つまり子育てを忘れられるようなところで、自分の世界をもてばいいのに……」ということ。しかしそういう人にかぎって、子育てがすべて、といった感じがする。この閉塞感が、症状を重くする。 子育ては子育て。しかしその一方で、親は親としてというより、1人の人間として、自分の世界をもつこと。育児をしながらも、同時進行の形でもつのがよい。(2)視野が狭い。 大局的な見方ができない。身近な、ささいな問題をとらえては、それを針小棒大に心配する。たとえば「学校でしてきたプリントを見たら、計算の答が、すべて一行ずつ、ズレていた。きっと隣の席の子どもの答を、丸写しにしたにちがいない。こんなことでは、うちの子は、将来、ズルい人間になってしまう」とか。 あるいは「体操教室で、跳び箱の練習を見ていたら、うちの子は、順番をうまくすり抜けて、それをしないですませていた。こんなことでは、うちの子は、ダメになってしまう」と心配していた母親もいた。 さらにこんな相談もあった。「今、英会話教室に通っているが、先生が、アイルランド人だ。へんなナマリがつくのではないかと、心配だ」と。 こうして自分自身を、小さな世界に押しこめてしまう。その閉塞感が、育児ノイローゼへとつながっていく。 そのため、親は、いつも視野を大きくもつ。大きければ大きいほど、よい。興味の対象を、大きくする。政治の世界や、絵画、音楽などの芸術の世界に興味をもつのもよい。交際範囲を広くする。ほかにもいろいろあるが、小さい世界に閉じこもってしまってはいけない。(3)愛情の欠落 このタイプの親でも、「私は子どもを愛しているから、心配してやっている」というようなことを言う。しかし話をよく聞くと、親の心配や不安を子どもにぶつけているだけ、といった感じがする。 「愛」といっても、愛もどきの愛。いわゆる代償的愛というのである。自分の心のすき間(=精神的な欠陥や、情緒的な未熟性)を埋めるために、子どもを利用する。子どものことを考えているようで、子どもの立場になって、ものを考えていない。よい例が、子どもの受験勉強に狂奔する親である。親の価値観を一方的に、子どもに押しつけているだけ。 が、この問題は、それに気づくだけでも、その大半が解決したとみる。愛情がなければないで、居なおればよい。子どもを愛せないことで、自分を責めてはいけない。子どもが好きでなかったら、「私は子どもが好きではない」と、正直に告白すればよい。それがふさいだ心に、風穴をあける。(4)哲学、宗教観の欠落 若い母親に、哲学や、宗教観をもてといっても、むずかしい。しかしそういったものがあれば、子育ての指針にはなる。が、方法がないわけではない。 「子どもを育てよう」「子どもを育てている」という意識を捨て、「子どもからものを学ぶ」という意識に置きかえる。わかりやすく言えば、「私は親だ」という親意識を捨て、子どもの横に、友として立つ。さらにもっと言えば、子どもに何かを教わるつもりで、子どもの言うことに耳を傾ける。 育児ノイローゼになる親というのは、そういう意味では、親意識が強い。「私は親だから、何とかしなければ」と思いながら、自分をどんどんと追いこんでしまう。生真面目な人ほど、育児ノイローゼになりやすいと、よく言われるのは、そのため。 肩の力を抜くためにも、親意識を捨て、子どもに対しては、友だち意識をもつ。子どもは、放っておいても、いつかはおとなになる。そういう子ども自身がもつ力を信じて、無責任になるところは、なって、あとは、子どもに任す。 親は子どもをもつことで親になるが、それから先、真の親になるためには、幾多の山や谷を越えなければならない。そしてそういう山や谷を越えるうちに、いつしか自分なりの哲学をもつことができるようになる。 「親が子どもを育てるのではない。子どもが親を育てる」。それに気がついたとき、あなたは、今の育児ノイローゼから、解放される。(はやし浩司 育児ノイローゼ)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(10)
++++++++++++++++++++++++はやし浩司●2人目の孫+++++++++++++++++家の広さ基準は、国によって、みなちがう。しかしアメリカ人がもつ基準は、ケタはずれに、大きい。つまりアメリカ人の家は、大きい。+++++++++++++++++ アメリカに住む二男が、こんな日記(BLOG)を書いた。今度、2人目の子どもが生まれることになったが、それについて、だれかが、「こんな(狭い)家で、2人も育てるの?」と言ったそうだ。 それについて二男は、こう思ったそうだ。「日本の基準で考えたら、広すぎるほど、広いのに」と。 たしかにアメリカでは、広さの基準そのものが、ちがう。当然、家は、大きい。若いころ、こんな失敗をしたことがある。 「ぼくの家は、2階建てだ。階段がある」と手紙を書いたら、そのアメリカ人は、かなり大きな家を想像してしまったようだ。アメリカで「階段」というと、映画『風と共に去りぬ』に出てくるような、幅の広い、あの大きな階段をいう。 が、日本の家の階段は、階段ではない。あえて言えば、ハシゴ? 二男のワイフ(アメリカ人)が、私の家に来たときも、「日本の階段は急で、こわい」と言った。それではじめは2階に寝室を用意していたが、急きょ、1階にある部屋に、寝室を移してやった。 基準がちがう。まったく、ちがう。そのアメリカ人は、つまりかなり大きな家を想像してしまったアメリカ人は、多分、ずっとあとになって私の家が、とんでもないほど小さいのを知って、驚いたにちがいない。礼儀正しいアメリカ人だったから、それを口に出して言うことはなかったが……。 ともかくも、2人目の孫が、来年には生まれる。そこでふと考える。「アメリカでは、一人前の生活をするのも、たいへんなことだな」と。が、ここで誤解してはいけないことは、アメリカでは、家が、安い。プラス土地が安いから、その分だけ、大きな家を建てることができる。 それに日本のように、広さに応じて税金が高くなるとか、こまかい建築基準法というのがない。もちろん地震対策など、考えなくてもよい。いつだったか二男がこう言ったのを覚えている。 「アメリカでは、1200万円も出せば、豪邸を買うことができる」と。近所の小さな空き地(30坪くらい)に、「売り地、1200万円」という立て札が立ったいるのを見たときのことである。 もっとも広い、狭いということになれば、G県の郷里に帰るたびに、私は、こう思う。「よくもまあ、こんな狭い土地に、何百軒も家がひしめいているな」と。正確に調べたわけではないが、どの家も、20~30坪程度の敷地に、ほとんどすき間なく軒をつらねている。私が今住んでいる町内だけで、あの町全体が、すっぽりと入るのではないか? つまりこうした感覚というのは、あくまでも相対的なもの。アメリカ人から見れば、私の家は狭い。しかし私の家から見れば、郷里の家々は、狭い。が、『住めば都』とは、よく言ったもの。私にとっては、今住んでいるここが、一番、気に入っている。 だからアメリカ人の家がうらやましいとは思わないし、反対に郷里の人たちが、かわいそうだとも思わない。そういう点では、人間は、フレキシブルにできている。それに悪いことばかりではない。人口密度が濃密である分だけ、人間関係も濃密。私の郷里では、隣り近所が、みな、親戚といった感じがする。 さてさて、2人目の孫は、どうするのだろう。より広い家を、二男夫婦も、当然、考えていることだろう。二男夫婦のためというよりは、その孫のために、何とかしてやりたい。そんな気持ちは、強いが……。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(014)●スパムメール++++++++++++++++++++++スパム・メールが、じゃかすか、やってくる。最近では、「連絡、ありがとうございました」「お待たせしました」「先日は、ありがとうございました」という、どこか、思わせぶりなものが多い。身に覚えがないから、「バカめ」と言って、そのまま削除することができるが、そうでない人は、そうではないだろう。+++++++++++++++++++++++M社のウィルス・ソフト対策コーナーを読むと、こうしたスパム・メールへの対策法として、つぎのようにある。(1)絶対に、相手にしてはいけない。相手にすれば、あなたのアドレスが生きていることがわかり、さらに転売の対象になる。(2)公開するメールアドレスは、フリーメールアドレスを使え、などなど。 そこで私のアドレスを、Y社の検索にかけてみた。で、驚いたことに、私のアドレスを公開しているサイトがいくつかあるのがわかった。 さっそく、削除を申し込む。「どうしてこんなことが、私の了解もなくできるのだろう?」と考えても、あまり意味はない。幸いにも、その中のいくつかは、私が削除を申し込むと、すぐそれに応じてくれた。悪い人たちばかりではない。 そこで(3)番目の対策として、どこかのだれかから、リンクの申し込みがあっても、それに安易に応じてはいけないということ。一度、「OK」すると、あとはそのまま自由勝手に使われてしまう。アドレスを使うとしても、M社の注意書きのように、フリーのメールアドレスを使うのがよい。 そうそう数週間前だが、こんなのもあった。 「あなたのHPを、もっと多くの人に読んでもらいたいと思いませんか。ついては、当サイトに、あなたのHPを登録してください。○×・HP登録センター」と。 で、メールを開いてみると、HPのアドレスのほか、簡単な自己紹介文、住所、名前、電話番号、それにパスワードまで、記入するようになっていた。パスワードは、紹介文を修正、訂正するためのものだそうだ。 「?」と感じたので、そのまま削除。思わず、ひかかってしまうとこころだった。HPの紹介だけなら、住所や名前、電話番号など、いらないはず。そこでその「紹介サイト」なるものを開いてみたが、「目下、制作中」とあるのみ。まだ、だれも登録していないことがわかった。(あるいは、最初から、制作などしていないのかもしれない。) この世界、本当に油断もスキもあったものではない。みなさんも、くれぐれも、ご注意のほどを!(付記) 加えて、こうして名前とHPを公開しているため、心ない人からの、いやがらせも、多い。今朝もあった。 京都で起きた、塾講師(D大学学生)による、小学生の殺傷事件をにおわせながら、「林さんのところでも、事件が起きることを楽しみにしています」と。 掲示板からは、相手のプロバイダーの名前までしか追跡できないが、掲示板に書き込むためには、一度、私のHPを経由しなければならない。そのHPを経由したとき、私のほうで、プロバイダーと、個人を特定するIP番号などが、把握できる。ついでに過去に何回、私のHPへアクセスしたかもわかる。 本人は、匿名のつもりなのだろうが、その気になれば、さらに詳しく調べることもできる。しかし、そういう人は、相手にしない。削除して、忘れる。 文句があるなら、堂々と名前を名のってから言え!、……と私は考えるが、みなさんは、どう思うだろうか?(付記2) 私も最初のころは、こうした書き込みについて、かなり不愉快な思いをした。しかしそういうものをいちいち気にしていたのでは、先に進めない。中には、(ほとんどの人がそうではないかと思うが)、こうした書き込みがあると、そのままHPや掲示板を閉じてしまう人がいる。 しかしここでくじけてはいけない。くじけたら、負け。これはインターネットのもつ、欠陥(けっかん)のようなもの。あるいは、善の道を妨げる、イバラのようなもの。前に進めば進むほど、この種の、心ない人からのいやがらせがふえる。 が、それも2つ、3つ……と重なってくると、そのうち免疫性ができてくる。気にならなくなる。100人の読者がいれば、そのうち、1%の1人には、頭の「?」な人がいる。1000人の読者がいれば、そのうち、0・1%の1人には、さらに頭の「?」な人がいる。 そういう頭の「?」な人に、負けてはいけない。 先日もここに書いたのと同じようなエッセーを書いた。それについて、「私も、私のHPの掲示板に、悪意に満ちた書き込みをされて、いやな思いをしています」というメールをもらった。M県に住む、Eさんという女性からのものだった。 Eさん、負けてはだめですよ。無視して、削除。あとは忘れる。このタイプの「?」な人には、無視するのが一番です。何を書いてきても、ただひたすら無視、です。(付記3) こうした書き込みをする人は、インターネットのもつ匿名性を悪用しているわけだが、その分だけ、心のゆがんだ人とみてよい。いじけやすく、ひがみやすく、おく病で、その上、卑怯。自己優越性が強く、ものの考え方が、自己中心的。そのため、友人の数は、恐ろしく、少ない。家族の中でも、孤立しているのでは? しかし自分では、そうは思っていない。それに気づくこともない。心の中は、いつも暗く、ジメジメと湿っている。少し昔には、無言電話というのがあった。受話器を取ると、すぐ電話を切ってしまうというのが、それ。こうした書き込みをしてくる人の心理は、その無言電話をかけてくる人のそれに、共通している。 (今は、ナンバーディスプレイ方式という便利な電話機が開発されて、この無言電話によるいやがらせは、ほとんどなくなった。) もともと相手にしなければならないような連中ではない。そう考えて、Eさん、負けてはだめですよ! 今にインターネットの世界でも、電話機のナンバーディスプレイ方式のようなものが、開発されると思います。今は、その過渡期かな?Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●シャワートイレ 私の隠れた趣味。それは、用をすますたびに、トイレをピカピカにみがくこと。その中で、弁当を食べられるほどまでに、みがく。 それについては、前にも書いた。 で、そのトイレ。実は、シャワートイレ。今どき、珍しくもなんともないが、はじめてそれを見たのは、リオデジャネイロ(ブラジル)のホテル。何でもその1か月前に、あの田中角栄氏(元総理大臣)が泊まったとかいう、リオデジャネイロでも、由緒あるホテルだった。もう30年も前のことである。 そのホテルのトイレに入ったときのこと。用をすまして横を見ると、大きなレバーが二つもあるではないか。私はどれが何だか分からなかったので、1つのレバーを、思いっきり、下へさげてみた。 とたん、便器の下から、噴水のような水が噴きあげてきた。ものすごい勢いである。私はそれにびっくりして、トイレから走りだしてしまった。 以来、シャワートイレを使うたびに、あの日のことを思いだす。 このシャワートイレ。いろいろな使い方がある。ちまたには、腸内洗浄とかいう健康法があるそうだ。そのための器具もいろいろ市販されている。要するに、腸内に温水(薄い塩水)を、流しこみ、腸内を洗浄するというもの。 しかしシャワートイレがあるなら、わざわざそんなものを買わなくても、トイレの中で、腸内洗浄ができる。どうやってするかについては、多分、すでにみなさん、経験済みだと思うので、ここには書かない。(あまり、美しい話ではないので……。) そこである日、私は、一体、どれだけの水が腸内に入るか、たしかめてみたことがある。方法は簡単。 まず、前もって、体重を測定しておく。つぎに、シャワートイレを流しながら、腹が痛くなるまでがまんする。最初はボコボコという音が、腸のあちこちから聞こえてくる。が、それも一巡すると、キリキリと腹が痛みだす。腹の左下を押さえてみると、水(実際には温水)が、パンパンにつまっているのがわかる。「もう、だめだ」という限界まで、がまんする。 その状態で、体重計の上に乗ってみる。ふえた分が、水の量ということになる。つまりこうして腸内に入った水の量を知ることができる。 で、私のそのときの実験では、約1・5キロ! 何と、1・5リットルもの水が入ったことがわかった。たいへんな量である。もう少しで2リットル。 さらに私は、こんな実験もしてみた。その状態、つまり、腸の中がパンパンになった状態で、トイレの外で、逆立ちをしてみる。そうすれば理屈の上では、水は逆流して、大腸全体に回るはずである。 その状態で腸内の水を排出すれば、大腸全体が、美しくなる。が、これは失敗だった。そのあとすぐ、船に酔ったみたいに、ムカムカと気持ち悪くなった。逆立ちしたのが原因なのか、それとも、腸内に水を大量に入れたのが原因なのかはわからない。ともかくも、気持ち悪くなった。 で、この実験は、失敗。(こうした実験も、医学発展のため。) こうして私は、日々に、腸内を洗浄している。そこで私はある日、ワイフにこう言った。「ぼくの腸ね、切ってホルモン焼きにしてもいいほど、きれいだよ。そのまま焼いて食べられるよ」と。 そのせいかどうかわからないが、最近では、腸内のどこに、どの程度の、カスがあるか、それがわかるようになった。腸の中の様子が、よくわかるようになった。つまりこれも私の隠れた趣味ということになる。つまり腸内洗浄が、である。 方法は……。やはりここには、書けない。みなさんも、どうか努力して、その方法をさがしてみてほしい……、と書いたところで、こんなこともあった。 シャワートイレの話を、あるとき、私の生徒たち(当時、小2)に話すと、M君が、こう言った。「シャワートイレを使うと、お尻の穴の中に水が入るんだってエ。ママが、そう言っていた」と。 つまりすでに、みなさん、ご存知のとおりということになる。しかしトイレもピカピカ。腸の中もピカピカ。とてもさわやかなよい気分。今は、そのよい気分。 バカな話を書いて、ごめん!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(015)●老いるとは……++++++++++++++++++周囲の人たちが、どんどんとバカになっていく。ものの道理が通じなくなっていく。こまかい、繊細な話ができなくなっていく。老いるということは、そういうこと。それが私を、さみしくさせる。++++++++++++++++++ 老人イコール、人格の完成者というのは、ウソ。まったくのウソ。幻想。人は老いれば老いるほど、愚かになる。どん欲になる。自分勝手になる。ごう慢になる。がんこになる。わがままになる。そしてバカになる。 自分がその(老い)の戸口に立ってみて、それがはじめてわかった。つまり今までは、「老人というのはそういうもの」と、心のどこかで一線を引いて、老人を見ていた。老人を私たちの世界の外に置いて、老人をながめていた。現在、若い、あなたも、多分、そうだろう。「私には、老いは、関係ない」と。 しかしこのところ、老人を見ればみるほど、心がさみしくなる。それは自分が老いるからではなく、まわりの老人たちが、自分からどんどんと離れていくのを感ずるからである。中には、何を話しても、ヘラヘラ、ニタニタと笑っているだけ。こちらの話が、まるで通じない老人もいる。 「私も、そういう世界へ、入っていくのか?」と思うだけで、ツンとしたさみしさが、心をふさぐ。 高い道徳や倫理など、もう望むべくもない。文化性そのものをなくす老人も、多い。その姿は、欲におぼれた、餓鬼(がき)そのもの。一応、表面的には善人を装ってはいるが、それは長年の知恵で身につけた、仮面のようなもの。身内や家族の者を前にすると、想像もできないほど汚い言葉で、ののしったり、怒鳴ったりしている。 どうして老人は、老人になるのか。単純に考えれば、身体面の衰えが、そのまま精神面の衰えにつながるということになる。が、しかし本当にそれだけだろうか。 私は、老人になればなるほど、その人が本来的にもつ(地)が、表に出てくるためではないかと思う。若いうちは、そうした(地)を、気力でカバーすることができる。しかし老いれば老いるほど、その気力が弱くなり、(地)をカバーすることができなくなる。 こんな例がある。ある女性(現在、60歳と少し)は、50代のころから、近所のひとり暮らしの老人の世話をしていた。献身的な世話だったという。そういう老人のために、役所へ届ける書類を作成してやったり、ときには、買い物もしてやったりしていたという。 しかし自分の母親が他界、残された父親が認知症になったとたん、様子が変わった。周囲の人たちは、当然、その女性が、その父親のめんどうをみるものとばかり思っていた。しかしその女性は、父親をすぐさま、精神病院へ入れた。もともと父親との折りあいが悪かったこともある。母親が他界したあと、父親を虐待していたという、うわさもある。 そして3か月が過ぎると、今度はそのまま別の老人専用施設に入居させてしまった。だからといって、その女性を責めているのではない。それぞれの家庭には、外からはうかがい知ることのできない、複雑な事情がある。 が、近所の人たちは、そのあまりの(落差)に、驚いた。老人思いのすばらしい女性から、老人を毛嫌いするただの女性へ、と。 よくよく考えてみると、もともとその女性は、その程度の女性ではなかったのかと思う。心理学の世界にも、「愛他的自己愛」という言葉がある。自分をよく見せるために、他人を愛しているフリをして見せることをいう。よくどこかのテレビタレントが、その団体に頼まれて、慈善活動をして見せるのが、それ。 その女性も、それまでは、近所のひとり暮らしの老人の世話をしていた。しかしそれは、その老人のためというよりは、まわりの人たちに、すばらしい人と思われたいがため、そうしていた。が、身内にそういう老人ができると、一変した。道楽で、老人を介護するのと、追いつめられて介護するのとでは、中身は、まるでちがう。 そこで俗な言い方をすれば、「化けの皮がはがれた」ということになる。つまりここでいう(地)が表に出てきた。 そこで改めて、(老い)について考えてみる。 私たちは、自分の気力を過信するあまり、その奥に潜む(地)にあまりにも、無関心でいすぎるのではないだろうか。「私は善人だ」と思っている人でも、本当のところは、そういうフリをしているだけではないだろうか。わかりやすく言えば、自分をごまかしているだけ。 しかしその(地)を変えるのは、容易なことではない。毎日、心の中に、ある種の緊張感を保ちながら、常に前向きに生きていかねばならない。自分をみがいていかねばならない。仏教の世界でも、それを「精進(しょうじん)」という。 「私は完成された」と、うぬぼれたとたん、そこを頂点として、あっという間に、またもとの俗世間へとたたき落とされてしまう。それは何度も繰りかえすが、健康法に似ている。 究極の健康法などない。また究極の健康法を極めたからといって、その人がそのあと、一生、健康ということもない。同じように、究極の精神鍛錬法というのもない。「私は悟った」と、うぬぼれたとたん、そこを頂点として、またもとの俗世間にたたき落とされてしまう。 そういう意味では、年をとればとるほど、脳みその底に穴があく。そしてその穴は、年々、大きくなることはあっても、小さくなることはない。知識や知恵、経験は、その穴から、どんどんと下へこぼれ落ちてしまう。 そしてやがて、その人の(地)が、表に出てくる。もともと邪悪だった人は、そのまま邪悪になる。 悲しいかな、すでに60歳前後の人でも、どこか鈍くなってしまった人となると、いくらでもいる。会話そのものが、かみあわない。通俗的な世間話はできるが、それ以上の会話ができない。会話そのものが、はずまない。思考力そのものが低下しているから、ものの考え方が、短絡的。 「林君、何だかんだと言ってもだよ、金だよ、金。金が、大事だよ」 「K国なんか、あんた、戦闘機で、バンバン攻撃してやればいいんだよ」 「あのね、女なんかに、力をもたせてはいけないよ。女は家庭に閉じこめておけばいいの」 「幼児教育なんてものはね、必要ないの。だれだってそんな教育、できるでしょう」と。 では、どうするか。老いを迎える私たちは、どうしたらよいのか。 やはり「精進」という言葉に、私は、行き着く。 脳ミソの穴から、知識や知恵、経験がこぼれ落ちていくなら、その落ちていく分以上のものを、補給する。(地)があまりよくないというのなら、その(地)と戦う。戦って、戦って、戦いぬく。 健康法で言えば、毎日の運動は欠かさない。一日、一度は、汗をかく。暑くても、寒くても、それをつづける。「今夜は寒いから、やめた」というようであれば、健康を維持することはできない。 同じように、精神面では、考える。考えて、考えて、考えぬく。そのためには、私は、ものを書くのがよいと思うが、ものを書くだけではない。本を読んだり、絵を描いたりすることでもよい。音楽を聞いたり、旅行をするのもよい。何らかの方法で、いつも、前向きに生きていく。新しいことを見つければ、どんどんとそれに挑戦していく。 こうして考えていくと、「老いる」ということは、自分の敗北を認めること、ということになる。つまり私たちが「老人」と呼んでいる人は、その敗北者ということになる。そこで言いかえると、70歳になっても、80歳になっても、元気で飛びまわっている人は、老人ではないということになる。同じように、70歳になっても、80歳になっても、「精進」を繰りかえしている人は、老人ではないということになる。 老人は老人になってはじめて、老人になる。老人であっても、老人でなければ、いつまでも、老人ではない。わかりやすく言えば、そういうことになる。(はやし浩司 老人 老人論 老いとは 老いとは何か 老人とは何か)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●言葉を反復する子ども ++++++++++++++いちいちこちらの言った言葉を反復する子どもがいる。反復しないと、こちらの言ったことが、理解できないといったふう。原因は、脳の中で、情報の伝達が適切になされないためではないか。教えていると、そんな印象をもつ。++++++++++++++ そのつど、こちらの言った言葉を、いちいち言葉を反復する子どもがいる。年齢を問わない。たとえば先生との間では、こんな会話をする。私「うさぎさんが、6匹いました。そこで……」子「うさぎさんが、6匹?」私「そうだよ、6匹だよ」子「6匹、ね」私「そこで、みんなに、帽子を1個ずつあげることにしました」子「みんなに……?」「帽子……?」私「そうだよ。みんなに、帽子だよ」子「何個ずつあげるの?」私「1個ずつだよ」子「1個ずつ?」と。 もう少し年齢が大きくなると、言葉の混乱が起きることがある。私「1リットルのガソリンで、10キロ走る車があります」子「何んだったけ? 10リットルで、1キロ?」私「そうじゃなくて、1リットルのガソリンで、10キロ走る車だよ」子「1リットルの車で、10キロ走る、ガソリン?」私「そうじゃなくて、1リットルで……」と。 このタイプの子どもは、少なくない。私の経験では、10人中、1人前後、みられる。特徴としては、つぎのような点が観察される。(1)こちらの言ったことがすぐ言葉として、理解できない。(2)そのためこちらの言ったことを、そのつど、オウム返しに反復する。(3)こちらの言った言葉に、すぐ反応することができない。(4)全体に、軽度もしくは、かなりの学習遅進性が見られることが多い、など。 私の印象としては、音声として入った情報を、そのまま理解することができず、それを理解するため、もう一度、自分の言葉として反復しているかのように見える。あるいは音声として入った情報が、脳の中の適切な部分で、適切に処理できず、そのままどこかへ消えてしまうかのように見えることもある。脳の中における情報の伝達に問題があるためと考えられる。 このタイプの子どもは、もちろん叱ったり、注意したりして指導しても、意味がない。またその症状は、幼児期からみられ、中学生になっても残ることが多い。脳の機能的な問題がからんでいると考えるのが正しい。 ほかに、こんな会話をしたこともある。相手は、小2の子どもである。私「帰るとき、スリッパを並べておいてね」子「帰るとき?」私「そうだよ。帰るときだよ」子「スリッパをどうするの?」私「スリッパを並べるんだよ」子「スリッパを並べるの?」私「そうだよ」子「帰るとき、スリッパを並べるんだね、わかった」と。 このタイプの子どもは、今のところ、そういうタイプの子どもであると認めた上で、根気よく指導するしかほかに、方法がないように思われる。(はやし浩司 言葉を反復する子ども 言葉を反復する子供 言葉がすぐ理解できない子ども 言葉の反復、反復児 言葉を反復 はやし浩司)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(016)【近況・あれこれ】●薄着で散歩 しばらく見かけなかった。が、久しぶりに通りで見ると、その老人は、薄いセーター1枚で、外を歩いていた。セーターの下には、シャツ1枚。シャツを見たわけではないが、そんな感じだった。その老人は、80歳と少し。 ここ数日、日本列島を、猛烈な寒波が襲っている。全国的に雪模様。九州南部でも、みぞれが降ったという。寒いというよりは、身を切るような冷たさ。そんな中での、散歩である。 かたや私は、マフラーに皮ジャン。手には分厚い手袋。その元気そうな様子にすっかり感心して、そのことをワイフに話すと、ワイフは、こう言った。 「あら、あなた知らないの? あのXさんね、認知症だそうよ」と。私「認知症?」ワ「そうよ。だからこんな寒い日に、そんなかっこうで歩くのよ」私「認知症の老人が、服をたくさん着るという話は聞いたことがある。しかし薄着になるという話は、聞いたことがない」ワ「ううん、ときどき、いるそうよ」と。 そこでネットを使って調べてみると、たしかにそういう症状をもつ老人がいるそうだ。 認知症の特徴として、(1)記憶力の低下(もの忘れがひどくなる)、(2)自己認知力の低下(自分がどこにいるかわからなくなる)、それに(3)判断力の低下(何をすべきかわからなくなる)があるそうだ。 その判断力が低下してくると、夏でもセーターを着てみたり、反対に冬でも、薄着でいたりすることもあるそうだ。ナルホド!私「あれじゃあ、すぐ風邪をひいてしまうよ」ワ「そうね。だから老人は、よく風邪から肺炎になって、死ぬのよ」私「奥さんは、どうしているの?」ワ「聞いた話では、あのXさんは、奥さんの言うことなど、もう何も聞かないそうよ」と。 認知症といっても、定型があるわけではない。脳みそのどの部分の機能が低下するかによって、症状も、万別ということらしい。Xさんは、恐らく前頭葉のどこかが、ダメージを受けているらしい。それにしても、この寒い日に、薄いセーター1枚で外出とは!!●単純なミスで400億円の損失 詳しいいきさつはともかくも、東京証券取引所を介して、M証券グループが、400億円の損失を出したという。 400億円の損失!、……ということは、だれかがその400億円を、儲けたことになる。1等が3億円のジャンボ宝くじなど、どこかへ吹き飛んでしまう。しかしここにネット取引のこわさがある。数字だけが一瞬のうちに、ひとり歩きを始めてしまう。そしてそれにつづく、つぎの瞬間には、すべてが決まってしまう。 私もネット取引を、小遣いの範囲で楽しんでいる。が、それはたとえて言うなら、数字の遊びのようなもの。その数字が勝手にふえたり、へったりする。100万円というと、たいへんな金額だが、それは実生活での話。ネット取引の世界で、400億円と聞いても、ピンとこない。 つまりお金というのは、実際、使ってみてはじめて、その価値が生まれる。たとえば私は、パソコンの周辺機器の何かがほしくなると、ネットで株取引をして、その儲けで買うようにしている。 そのとき、たとえば10万円、儲けたとする。しかしモニター画面上で、いくらその数字をながめていても、実感がわかない。そこで証券会社へ出向き、カードを使って、その10万円をおろす。おろして、デジタルカメラを買う。 そのデジタルカメラを買ったときはじめて、10万円の価値がわかる。が、そのとき、また別の不思議な感覚にとらわれる。今度は反対に、株取引で儲けたという実感がわかない。10万円といっても、札に名前がついているわけではない。仕事で儲けた10万円も10万円なら、株取引で儲けた10万円も10万円。 「もったいない」などと思う必要はないはずなのに、「2台ももって、もったいない」とか、「この前、新しいのを買ったばかりではないか」と、自分で、自分を責める。 で、その400億円だが、M証券グループにとっては、たいへんな額にちがいない。しかしその実感がない。だから同情心も生まれない。むしろ反対に、その400億円を儲けた人たちを、うらやましくさえ思う。私もそのとき、その株価を見ていたら、すかさず買いを入れたと思う。そしてあとになって、「あの株価はまちがいでした。買いをキャンセルしてください」と、だれかに頼まれても、私は、多分、それに応じないだろう。 それが「数字」の世界。その世界には、血も涙もない。考えてみれば、おかしな、おかしな、たいへんおかしな世界である。●浜名湖のうなぎ 中学生たちが使う社会の教科書には、こうある。「浜名湖のうなぎ」と。 つまりうなぎが、浜名湖の特産品ということになっている。しかしその様子は、ここ30年で大きく変った。うなぎの子ども、つまりシラスウナギは、ほとんど取れなくなった。そのため養満鰻業者も、そのほとんどが姿を消した。もちろん浜名湖でとれる自然産のうなぎなど、数が知れている。 現在、ほとんどのうなぎは、中国や台湾からの輸入品である。それを浜名湖周辺の工場で加工して、全国へ出荷している。しかし嘆くことはない。 もともと、浜名湖のうなぎといっても、明治以後、新興産業の1つとして生まれたもの。その産業をおこしたのは、服部倉次郎という人だそうだ(「地図帳」青春出版社)。 服部倉次郎は、もともと東京の深川というところで、うなぎの養殖をしていた。その服部倉次郎が、どこかへ出張の折、列車の窓から、浜名湖を見て、うなぎの養殖を思いついたという。 その浜名湖には、うなぎの養殖に適していたという。上述「地図帳」によれば、シラスウナギ、水、それにエサが、浜名湖にはあった。その上、天竜川から運ばれてきた、砂地、さらに年間をとおして、平均気温が、15度というのも、養殖に適していた。 「地図帳」によれば、浜名湖は、東京と大阪のちょうど中間点にあることも幸いしたとあるが、それは何も、うなぎの養殖だけにかぎった話ではない。つまり浜名湖のうなぎといっても、意外と歴史は浅い。だから時代の流れの中で、浜名湖からうなぎが消えたところで、それもまた、しかたのないこと、ということになる。 少し、残念な話だが……。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(017)●ADHD児++++++++++++++++ADHD児といっても、注意力散漫型なのか、それとも、多動性型なのか、2つに分けて考えるようになってきている。そして近年の傾向としては、多動性よりも、注意力散漫型、つまり注意力そのものに、障害があると考える学者がふえている。++++++++++++++++ 最近の文献によれば、アメリカでは、ADHD児といっても、主に、つぎの3つのタイプに分けて考えていることがわかる(DSM-IV,APA 1994)。文献などを見ていると、(ADHD、C)タイプとか、(ADHD、IA)タイプとかいうような表現方法をとっている。(1)ADHD, Combines Type (ADHD,C)(2)ADHD,Predominantly Inattentive Type (ADHD,IA)(3)ADHD,Hyperactive Impulisive Type (ADHD, HI) ADHD児といっても、(1)注意力が散漫型なのか、(2)多動性型なのかによって、症状は、大きくちがう。 (ADHD、C)というのは、(DSM-IV;APA 1994)の診断基準のうち、注意力散漫項目の9項目うち、少なくとも6個該当、衝動的多動性項目の9項目のうち、少なくとも6個該当する子どもをいう。 (ADHD,IA)というのは、(DSM-IV;APA 1994)の診断基準のうち、注意力散漫項目の9項目うち、少なくとも6個該当するものの、衝動的多動性項目の9項目のうち、6個より少なく(5個以下)、該当する子どもをいう。 (ADHD,HI)というのは、(DSM-IV;APA 1994)の診断基準のうち、衝動的多動性項目の9項目うち、少なくとも6個該当するものの、注意力散漫項目の9項目のうち、6個より少なく(5個以下)、該当する子どもをいう。 つまりADHD児といっても、(1)注意力散漫型+衝動的多動性のある子ども(ADHD、C)タイプ、(2)注意力のほうが散漫型で、衝動的多動性の少ない子ども(ADHD、IA)タイプ、(3)衝動的多動性が強く、注意力散漫が、それほど顕著ではない子ども(ADHD、HI)タイプの三つに分類されるということ。(「多動性をともなわない、注意力欠陥障害のある、注意力散漫型タイプの子どもについて」 by J・M Wheeler & C・L Carlson、テキサス大学)) 近年は、学校教育の場でも、ADHD児といっても、注意力欠陥型なのか、多動型なのか、区別して考えるようになっている。そのため、表記方法も、従来の「ADHD」から「AD・HD」というように、間に「・」を入れる学者も少なくない。(参考文献)Attention Deficit Disorder Without Hyperactivity:ADHD, Predominantly Inattentive TypeBy Jennifer Wheeler, M.A., and Caryn L. Carlson, Ph.D.The University of Texas at Austin+++++++++++++++++++++In 1980, the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) [American Psychiatric Association (APA), 1980] introduced a major change in the conceptualization of the childhood disorder that had previously been called "hyperkinesis" or "hyperactivity". Because experts had begun to speculate that attention deficits, rather than high activity level, might play a greater role in the problems of these children, the term "attention deficit disorder" (ADD) replaced the earlier diagnostic terminology. Along with this shift in diagnostic emphasis came the recognition that attention deficits could exist even in the absence of high activity level, and thus two ADD subgroups were defined: ADD with hyperactivity (ADDM) and ADD without hyperactivity (ADD/WO). While the ADD/H category was fairly consistent with previous definitions, the latter subtype represented essentially a new category, for which there was no previous counterpart. Thus, almost everything we know about ADD/WO is based on research conducted since 1980.1980年に、DSM-III(精神障害の診断および統計的マニュアル)は、それまで「過剰行動」あるいは「多動児」と呼ばれていた子どもについて、その概念を大きく改めた。 というのも、専門家たちが、多動性よりも、注意力欠陥のほうに、注目し始めたからである。そして「注意力欠陥障害(ADD)」が、これらの子どもたちにとっては、より大きな問題であるとわかった。 そして多動性はなくても、注意力そのものに欠陥のある子どもがいることが、強調されるようになり、新たに2つのADD児タイプが、つけ加えられるようになった。 多動性をともなう、注意力欠陥型タイプ(ADDM)と、多動性をともなわない、注意力欠陥タイプ(ADD/WO)の2つである。後者は、それ以前にはわかっていなかったという点で、新しいカテゴリーを示す。However, such a classification scheme led to problems in the field as it was inconsistent with previous research supporting a behavioral distinction between the ADD subtypes. In addition, it was problematic clinically, in that there was no particular symptom constellation required for a diagnosis of ADHD, thus allowing children who were previously diagnosed as having ADD/WO to be inappropriately included in the ADHD category1. In response to such difficulties, the most recent edition of the DSM (DSM-IV; APA 1994) returned to DSM-III-type terminology. Current criteria delineates two separate symptom lists, inattention and hyperactivity-impulsivity, and allows children to be classified into one of three categories based on the presence or absence of symptoms in each of these areas: ADHD, Combined Type (ADHD,C), which requires children to display at least six out of nine inattentive and six out of nine hyperactive-impulsive symptoms; ADHD, Predominantly Inattentive Type (ADHD,IA), which requires at least six out of nine inattentive symptoms and less than six hyperactive-impulsive symptoms; and ADHD, Hyperactive-Impulsive Type (ADHD,HI), which requires the presence of six out of nine hyperactive-impulsive symptoms and less than six inattentive symptoms. The ADHD,IA category is presumed to identify children diagnosed with DSM-III as ADD/WO, ADHD,C is thought to identify children given DSM-III ADDM or DSM-III-R ADHD diagnoses, and ADHD,HI is essentially a new category, presumed to identify extremely active children who do not display gross inattention. Although some of the research discussed below was conducted with children diagnosed as ADDM, ADD/WO, and ADHD, in this paper we will use the terms ADHD,C and ADHD,IA to refer to all attention-disordered children with and without hyperactivity, respectively.●Activity Level(活動性のレベル)ADHD-Cの子どもについては、しばしば、騒々しさ、興奮性、過剰行動性といった、行動的な活発さをともなう。が、ADHD-IAの子どもについては。こうした行動的な活発さは、ずっと少ない。One area in which fairly consistent findings have emerged involves the "behavioral activity style" demonstrated by ADHD,IA children. While children with ADHD,C are often described as boisterous, impulsive, excitable, and overactive, children with ADHD,IA are much less likely to receive such labels. In fact, studies have found that children with ADHD,IA are often described as "hyperactive", i.e., they are likely to show "underactivity" and be described as sluggish, lethargic, and daydreamy. This unexpected finding has generated some interesting speculation about the ADHD,IA subgroup and further distinguished them from their ADHD,C peers. While children with ADHD,IA typically do not differ in activity level from nondisordered children, they are most notably not impulsive, a key characteristic of children with ADHD,C. The so called impulsivity of children with ADHD,IA is typically more related to disorganization than the physical impulsivity of children with ADHD,C. For example, raters are more likely to endorse items such as an inability to complete tasks and poor organizational skills when rating children with ADHD,IA, and items such as acts without thinking, shifts from one activity to another, and frequently interrupts others when rating children with ADHD,C. This distinction was clarified in DSM-IV when a factor analysis revealed that many of the DSM-III "impulsivity" items clustered with "hyperactivity", and others (e.g., "difficulty organizing tasks") clustered with inattention. This led to the current use of a single-symptom list for hyperactivity-impulsivity versus two separate listings (impulsivity and hyperactivity) used in DSM-III.●Accompanying Disorders(付随する症状)ADHD-Cタイプの子どもにも、ADHD-IAタイプの子どもにも、不随的な症状が見られる。ADHD-IAタイプの子どもは、心配性や行為障害のような、いわゆる「内面性の外見化」の問題は、あまり示さない。一方、ADHD-Cタイプの子どもは、落胆感や心配性などの、いわゆる「心の内面的な」問題を、より多く示す。Research has shown that accompanying behavior disorders are likely to be found in both ADHD,C and ADHD,IA children. Thus, children with ADHD,IA are less likely to display "externalizing" problems, such as aggression and conduct disorders. Some research also finds that among clinic-referred children, ADHD,IA children are more likely than ADHD,C children to display "internalizing" problems, such as depression and anxiety. This theory is supported by research conducted by Barkley and his colleagues (1990) who, using a clinic-referred sample, found that the relatives of children with ADHD,C were more likely to suffer problems with substance abuse, aggression, and ADHD,C, than the relatives of children with ADHD,IA and nondisordered controls. In contrast, the relatives of children with ADHD,IA were more likely to have anxiety disorders than the relatives of children in the other groups. Still, findings on co-occurring internalizing problems between the ADHD subtypes are inconsistent. For example, a recent large-scale school-based study7 found that teachers rated ADD,C children as showing more anxiety/depression than ADHD,IA children. This finding led the authors to speculate that it may be only among ADHD children who are referred to clinics that this pattern of greater internalizing problems among ADHD,IA children is displayed8. Thus, it may be that children with ADHD,IA who also display high levels of anxiety and/or depression are more likely to be referred to clinics than children with ADHD,IA alone. However, when identified in a general population, ADHD,IA children may not necessarily show greater levels of anxiety/depression than children with ADHD,C.●Peer Relationships(仲間との関係)全体的にみれば、ADHD児は、仲間の間で、人気がないという傾向があるが、ADHD-Cタイプの子どもと、ADHD-IAタイプの子どもとでは、様子が異なる。 ADHD-Cタイプの子どものほうが、深刻(severe)であり、ADHD-IAタイプの子どもと比較して、行動面で嫌われる傾向が強い。一方、ADHD-IAタイプの子どもは、社会的により引きこもる(withdraw)する傾向が強い。Since the problematic peer relationships of children with ADHD,C has been consistently found, it has been of interest to researchers to examine what, if any, peer relationship problems might characterize children with ADHD,IA. Of the studies that have examined this issue, the overall conclusion appears to be that both ADHD subtypes are less popular with their peers; however, the nature of their unpopularity seems slightly different9. For example, there is some evidence that the peer relationship problems of children with ADHD,C are more severe than those of children with ADHD,IA10. When rated by their peers, some studies find that children with ADHD,C are more "actively disliked" than children with ADHD,IA and nondisordered controls, whereas children with ADHD,IA are more "socially withdrawn". Based on these findings, some researchers have suggested that the nature of the ADHD subtypes' social deficits may, in fact, be qualitatively different. Using Gresham's (1988) model of social skills, Wheeler and Carlson (1994) proposed that children with ADHD,C may suffer from social performance deficits (i.e., they know what to do but do not use this knowledge appropriately), whereas children with ADHD,IA may suffer from deficits in both social performance and knowledge (i.e., they don't know what to do in social situations, thus they cannot use this knowledge appropriately). The authors further speculate that these deficits may be mediated by so-called interfering responses, which correspond to symptoms typically associated with the disorder. Thus, impulsivity and hyperactivity may prevent a child with ADHD,C from waiting his turn in line, even though he knows he is supposed to do so, and "sluggishness" and anxiety may prevent a child with ADHD,IA from participating in enough social interactions to learn the rules of the game. While this hypothesis has not been empirically tested, it clearly has important treatment applications. For example, if children with ADHD,C are found to possess adequate social knowledge, attention should be directed at decreasing what prevents them from interacting appropriately, rather than focusing exclusively on training in social skills. In contrast, if children with ADHD,IA are found not to know what to do in social situations, social skills training will be the most useful.●School Performance(学業)ADHD-IAタイプの子どもも、ADHD-Cタイプの子どものように、学校では、学業的な問題をもつことが観察されている。We have evidence that children with ADHD,IA, like those with ADHD,C, often experience school learning problems. Indeed, some research has indicated that children with ADHD,IA may show elevated rates of school failure and are rated by teachers as having greater problems in learning, relative to nondisordered controls. One relatively recent finding is the strong relationship between inattention and academic problems. Studies examining the behavioral correlates of the ADHD subtypes have consistently shown greater academic difficulties in children diagnosed with ADHD,C and ADHD,IA than children with excess motor activity/impulsivity (ADHD,HI) alone11. With respect to intellectual functioning, there is little evidence for significant IQ differences between the ADHD groups, however, there is some research in support of a higher rate of learning disabilities in children with ADHD,IA12. In addition, children with ADHD,IA are typically more similar behaviorally to children with learning disabilities than are children with ADHD,C13. However, the specific nature of the relationship between learning disabilities and ADHD has not been clearly established. More research needs to be conducted before any firm conclusions can be drawn.●Etiology(病因)ADHDの病因、つまり原因については、不明である。神経学的な理論が、いろいろ取りざたされている。The precise etiology, or cause, of ADHD is unknown. Numerous theories have been proposed, including those relating to abnormal brain development (e.g., an "immature brain"), neurochemical abnormalities, exposure to environmental toxins, and deficient childrearing practices. Although research has been conducted in all of these areas, no firm conclusions cam yet be drawn. Also, most studies have been done with children with ADHD,C, resulting in even less knowledge about the etiology of ADHD,IA. Some researchers have speculated ADHD,IA and ADHD,C are entirely different disorders, in which case they may stem from different causes. The most promising theories to date include exposure to various agents that can lead to brain injury (e.g., trauma, disease, fetal exposure to environmental toxins), diminished brain activity, and heredity14.Research on children with ADHD,C has found that they seem to have underactive orbital-frontal regions, the part of the brain which is thought to be responsible for sustaining attention, inhibiting behavior, self-control, and planning15. This finding has been documented in several studies in which children with ADHD were shown to have diminished electrical activity and blood flow in this region, relative to nondisordered controls.Again, less research exploring the possible cause of ADHD,IA has been conducted. Given the "sluggish" cognitive tempo and frequent achievement problems typically occurring in this subtype, some researchers have speculated that children with ADHD,IA may suffer from posterior, rather than frontal, right hemispheric dysfunction16. However, studies using neuropsychological measures that have examined this hypothesis have failed to find the predicted deficits17. Thus, research involving more sensitive measures of neurological processes are needed before any firm conclusions regarding etiology can be drawn.It should also be noted that many previous theories of ADHD have not been supported. Thus, there is no conclusive evidence that ADHD can be caused by diet, hormones, lighting, motion sickness, or bad parenting18. Given the exciting new advances in our ability to examine the way the brain works, we can be hopeful that continuing research in these areas will soon expand our understanding of the causes of ADHD.●Treatment Considerations(治療についての考察)リタリン(Ritarin)の投与についてOne of the most pressing issues in developing effective treatments for children with ADHD,IA has been whether or not these children will show similar responses to stimulant medication as do children with ADHD,C. The best evidence that we have concerning this issue comes from a study in which the responses of children with ADHD,C and children with ADHD,IA were evaluated to 5, 10, and 15 mg doses of methylphenidate (Ritalin)19. While the groups did not significantly differ on any of the outcome measures, children with ADHD,IA were more likely to be nonresponders (24%) or to respond best to the lowest dose (35%) as compared to children with ADHD,C. In contrast, 95% of the ADHD,C children were judged to be positive responders, with the majority (71%) recommended to receive a moderate or high dose. Thus, it may be that at least a portion of children with ADHD,IA respond favorably to stimulant medication, although at a lower dosage than children with ADHD,C. One factor that may mediate this subgroup's responsiveness is the presence of co-occurring internalizing disorders (e.g., anxiety) when they exist. There is some evidence that children with ADHD who display accompanying internalizing symptoms are less likely to respond positively to stimulant medication than are children who suffer from ADHD alone20. In any case, stimulant responsiveness is clearly a matter in which more research needs to be done. For any given ADHD child, decisions about the usefulness of medication should be made based on am individual child's responsiveness.It is likely that the development of other effective treatments for children with ADHD,IA will depend upon the individual pattern of the accompanying problems they display. The information reviewed above suggests several areas of functioning that might be considered relevant for evaluation, including school functioning, the presence of other disorders (e.g., anxiety or depression), and peer relationship problems. Based on assessment in each of these areas, treatment programs can be individually tailored to meet each child's specific needs. As is becoming increasingly clear with children with ADHD,C, it is likely that children with ADHD,IA will be heterogeneous in many ways and that there will be wide individual variation in the types of accompanying problems they display. While we are still in the early stages of understanding the disorder, heightened interest in this area and the recent publication of DSM-IV should lead to increasing knowledge about its causes and responsiveness to treatments.●Conclusions(結論)The above review addresses research in many areas affecting children with ADHD. While few studies have been conducted using DSM-IV terminology, preliminary reports suggest that the findings are consistent. According to these studies, both ADHD subtypes are generally less popular than their peers, suffer difficulties academically, and frequently display accompanying problems. Given the relatively recent identification of ADHD,IA, it is mandatory that further research be conducted. Although these children generally show fewer overt behavior problems than their ADHD,C peers, they are just as in need of diagnosis and treatment.(はやし浩司 ADHD-C ADHD、C ADHD,C AD・HD ADHD児)
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(09ー2)
【最近・あれこれ】●子どもへの薬物療法++++++++++++++++子どもがかかえる心の問題について、薬物療法を施したため、かえって症状が重くなってしまったというケースが多い。副作用としてそうなるというよりは、反作用として、そうなる(?)。はたして薬物療法は、本当に安全なのか。++++++++++++++++ 子どもの心と体は、年齢とともに、発達する。同じように、その機能も、発達する。仮に不正常な部分があっても、成長とともに、機能は回復し、より正常になっていく。 つまり子どもには、心の問題にせよ、体の問題にせよ、自分で自分を治癒(ちゆ)していく能力を、生まれながらにしてもっている。その能力についてだが、最近では、たとえば何か心に問題があったりすると、薬物療法を試みるケースが、ふえている。ADHD児や、自閉症児、かん黙児、ツーレット症候群の子ども、など。夜尿症を含む、心身症にまで、薬物療法を施すケースも、ある。 果たして、それは安全なのか。また安易に、子ども、とくに乳幼児にほどこしてよいものなのか。ある小児科の医師が、こう話してくれたことがある。 「カウンセリングだけでは、医師は、お金を取れません。薬を出して、はじめてお金が取れます。こんなところにも、医療制度の矛盾が隠されています」と。 私は、こうした薬物療法について、たいへん疑問に思っている。というのも、私の周囲にも、幼児期、もしくは小学校の低学年期に、薬物療法を試み、一時的には、著効を示したものの、そのあとしばらくして、かえって症状が重くなってしまうというケースが、たくさん多いからである。ほとんどが、そうであると言ってもよい。 全体として、長期にわたって薬物療法をすればするほど、その反作用というか、そういった作用によって、症状がかえってひどくなってしまうケースが多い。そういう印象をもっている。 で、それとなく親に相談すると、たいていの親は、こう言う。「病院の先生が言うには、たいへん効果の薄い、安全な薬だから、問題はないそうです」と。 しかし本当に、そうか。そう信じて、よいかのか。 私はときどき、催眠剤(熟睡剤)というのを、のむ。しかし最大で2錠までのんでもよいというが、1錠ものんだら、たいへん! 翌日の昼まで寝てしまう。それに数時間もすると、幻覚症状が現れる。 そこで寝つかれないときは、その1錠を、8分の1から、6分の1程度に割ってのむ。それを舌の下でとかして、のむ。それでも、8~10時間は、寝てしまう。その1錠というのは、直径が、3ミリ程度の小さな薬である。 脳みそというのは、そういうもの。それくらい繊細にできている。それに脳みそには、フィードバック作用というのも、ある。たとえば何かの精神薬が脳みそに影響を与えるようになると、その精神薬を無効にするような物質を、脳みそが自ら放出するようになる。つまりこうして脳みそは、いつも自分自身を、(カラの状態)に保とうとする。 このフィードバック作用のことを知ると、たとえば薬物療法を長くつづけていた子どもほど、そのあと、かえって症状が重くなってしまうというケースが、理解できる。 ……というようなことを書くと、医療の現場にいる医師たちは、不愉快に思うかもしれない。これは、私のような素人が、横ヤリを入れるような問題ではない。しかし私の今までの経験からしても、うまくいったケースは、10に1つもない。ここで「そのあとしばらくして、かえって症状が重くなってしまうというケースが、たくさん多いからである。ほとんどが、そうであると言ってもよい」と書いたが、決して誇張ではない。 私はとくに、子どもの心の問題については、薬物療法は、もっと慎重であるべきだと思っている。たとえばある種の脳間伝達物質が不足しているからといって、その伝達物質を外部から補給するようなことをすれば、脳みそのほうが、それを受け入れてしまう。そしてかえって、その子ども自身がもつ、自然治癒力というか、機能回復能力が、阻害されてしまう。薬による補給をやめたとたん、今度はかえってその伝達物質が、極端に不足するという状態になる。素人の私でさえ、それくらいのことはわかる。 こんな例がある。 もう5年ほど前になるが、かん黙症の子どもが私の教室へやってきた。そのとき、その子どもは、年中児(4歳)だった。が、それから1年半の間、教室の中では、ほとんどしゃべらなかった。いつも柔和な笑みを浮かべていたが、外からは、何を考えているか、まったく察することができなかった。 心と表情が、遊離していた。 が、あと半年で、小学校へ入学というころになって、やっと声を出し、手をあげるようになった。母親にそれを報告すると、母親は、まぶたに透明の涙をいっぱい浮かべて、それを喜んだ。 で、やがて小学校に入学した。と、同時に私の教室を去った。が、それから約半年後。秋の気配を感ずるころだったが、その母親から、電話がかかってきた。「学校へ行かなくなってしまいました」と。 その子どもについて、母親は、こう言った。 「入学するとまもなく、担任の先生から、一度、心療内科へ行ってみたらというアドバイスを受けた。それで病院に通うようになった。そこで何種類かの薬を処方されたが、どの薬が効いたかわからない。が、息子が、別人のように活発になった。明るく元気になった。 それで喜んでいたが、夏休みが終わるころから、薬が効かなくなってきた。で、別の薬を処方してもらったが、その薬の効果も一時的で終わってしまった。息子が、学校へ行くのをぐずり始めたのは、そのころからです」と。 その子どもは、それから3年以上も、不登校を繰りかえした。で、最近になって気になったので、電話をしてみると、今でも、断続的に行ったり、行かなかったりを繰りかえしているという。行くといっても、午後からのことが多い、とも。 この一例だけではないが、だいたいほかのケースも、似たりよったりといったところではないか。医師は医師なりに、治療方法を考えて薬を処方していると思うが、しかし本当に安全性や、副作用、さらには、反作用なども考えて治療しているかというと、どうもそうではないような気がする。またその時間もないのでは(?)。診察室で、子どもを見る程度で、それで何がわかるというのか。 これ以上のことは、ここには書けないが、そういう問題もあるということだけは、わかってほしい。あえて言うなら、薬物療法は、できるだけ慎重にしたらよいということ。(はやし浩司 子供の心の問題 心の問題 薬物療法)Hiroshi Hayashi+++++++++++Dec. 05+++++++++++++はやし浩司●天下の悪法++++++++++++++++++今度、韓国で、『親日反民族…法案』なるものが、可決された。反日、嫌日がきわまって、もう「日」のつくものは、何もかも弾圧……? 今の韓国を見ていると、そんな感じさえする。現在のN政権を一言で言えば、妄想的回顧主義政権(?)。「そこまでする必要があるのか」というのが私の偽らざる印象である。+++++++++++++++++++過去にさかのぼって、罪を追及されたら……。それだけで法秩序どころか、社会体制は、崩壊する。これを、法の遡及性(そきゅうせい)という。 たとえば、こんな法律ができたら、あなたは納得するだろうか。 「今まで、交通違反を起こした人に対して、罰金が軽すぎた。だから交通違反を起こした人は、その分だけ、得をしたはず。したがって支払った罰金の3倍を、改めて支払いなおしてもらうものとする」と。だからこぞって、欧米法では、その法の遡及性をきびしく制限する。 ところが、である。今度、あの韓国で、そういう法律ができた。中日新聞(05・12)は、つぎのように伝える。 「韓国国会は、12月8日の本会議で、植民地時代に日本に協力した『親日派』の財産を、国庫に帰属させる『親日反民族行為者財産帰属特別法案』を可決した」と。 つまり植民地時代に、日本に協力して築いた財産をもっている者、およびその子孫について、その財産は、国庫として没収するというもの。一応、「大統領傘下の委員会が、国庫に帰属させるかどうか、審議する」というが、今の段階では、どの程度の審議なのか、内容が定かではない。 ところで、話は変わるが、現在、韓国のソウルで、日米の人権大使も出席して、『人権国際会議』が開かれている。これに対して、韓国大学総学生会連合(韓総連)と、一部市民団体が、今大会を「反北朝鮮世論作りに向けた守旧勢力の陰謀」と定義づけ、妨害しているという(韓国・中央日報)。 さらに産経新聞によれば、(今回の)「人権国際会議に反対する人権・社会団体(25組織)が発表した声明は、『K国の政治犯収容所は存在が確認されていない』『食糧難は(K国だけでなく)多くの国で発生している』『拉致韓国人問題は南北分断の悲劇』などとし、K国には人権問題は存在しないとするK国の主張そのままに独裁体制擁護に懸命」になっているという。 そういうお国がらである。親日反民族行為者財産帰属特別法なるものが可決されたとしても、何ら、おかしくない。しかし「ここまでやる必要があるのか」というのが、私の印象。N政権の考えていることは、すべてがうしろ向き。過去をほじくりかえしては、「韓国がこうなったのは、日本のせいだ、アメリカのせいだ」と、そんなことばかりを言っている。いつか体制がかわって、もし、「親北反人権行為者財産帰属特別法」なるものができたとしたら、今のN大統領ほか、その一派は、それに納得するとでもいうのだろうか。 人は年齢とともに、過去をふりかえる傾向が強くなる。回顧性が強くなる。それはわかる。しかし中には、そこに妄想を重ねる人もいる。「ああすればよかった、こうすればよかった」という思いを、いつの間にか、「あの人がじゃましたから、自分はこうなってしまった」「この人が、意地悪したから、自分はこうなってしまった」という思いに転じてしまう。 もっとわかりやすい例では、こう言って毎日のように言い争いをしている老夫婦がいる。「お前のおかげで、オレの人生はメチャメチャになってしまった」「私の人生を、返してよ」と。残りの人生を、どう有意義に生きるかということを考えるのが先だと、だれしも思うのだが、その老夫婦には、それがわからない。 が、韓国の人たちがもっている、悶々とした閉塞感を理解できないわけではない。「日本ごときの島国に、蹂躙(じゅうりん)されたという屈辱感」、それに「独立を自分たちで果たせなかったという無念さ」、さらには、「東西の冷戦の犠牲となって、国が分断されてしまったという被害意識」。こういったものが、混然いったいとなって、現在の反日感情に結びついている。 しかし、それにしても、行き過ぎではないか。ここまで反日感情をむき出しにされると、日本にいる親韓派の人たちまで、敵に回してしまうことになりかねない。現に私は、この数年、ますます韓国が嫌いになりつつある。 もっとも、韓国の中にも、いわゆる良識派の人たちがいないわけではない。中央日報は、つぎのような社説をかかげている。 「結局、政府のこうした思考は、K国の機嫌を取るためのものにすぎないのだ。韓国大学総学生会連合(韓総連)と一部市民団体が、今大会を『反K国世論作りに向けた守旧勢力の陰謀』と定義づけ、妨害しているが、情けなく思える。常に『人権』と『民族連携』を叫ぶそれらが、K国人民の惨状には知らんふりするばかりだから、とうてい理解に苦しむ」と。 私たち日本人は、こうした良識派の韓国の人たちもいることを信じて、ここは冷静に対処するしかない。ここで日本までカリカリしてしまえば、それこそ、日韓関係は、奈落の底へと落ちてしまう。それだけは、何としても、避けなければならない。それにしても韓国は、いったい、どこへ向かおうとしているのか。12/10/2005Hiroshi Hayashi+++++++++++Dec. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(012)●格言風・子育て論+++++++++++++++++++++++携帯電話用に書いた「子育て格言」です。私が利用しているサービス会社には、3か月以内に内容を更新しないと、サービスそのものが、停止されてしまうという、恐ろしい掟(おきて)があります。で、ときどき、こうして新しい格言を補充していかねばなりません。+++++++++++++++++++++++☆上下意識は、親子にキレツを入れる「親が上、子ガ下」という上下意識は、親子の間に、キレツを入れる。「上」の者にとっては、居心地のよい世界かもしれないが、「下」の者にとっては、そうでない。言いたいことも言えない、したいこともできないというのは、親子の間では、あってはならないこと。親はいつも子どもの友として、横に立つ。そういう姿勢が、良好な親子関係を育てる。☆「ダカラ論」は、論理にあらず「親だから……」「子だから……」「長男だから……」「夫だから……」というのを、『ダカラ論』という。このダカラ論は、論理ではない。えてして、問答無用式に相手をしばる道具として、利用される。使い方をまちがえると、相手を苦しめる道具にもなりかねない。先日もテレビを見ていたら、妻が、夫に、「あなたは一家の大黒柱なんだからね」と言っているのを見かけた。それを見ていて、そういうふうに言われる夫は、つらいだろうなと、私は、ふと、そう思った。☆親の恩着せ、子どもの足かせ「産んでやった」「育ててやった」「大学まで出してやった」と親が、子どもに恩を着せれば着せるほど、子どもの心は親から遠ざかる。そればかりか、子どもが伸びる芽を摘んでしまうこともある。たとえ親がそう思ったとしても、それを口にしたら、おしまい。親に恩を押しつけられ、苦しんでいる子どもは、いくらでもいる。☆家族主義は、親の手本からまず子どもを幸福な家庭で包んでやる。「幸福な家庭というのは、こういうものですよ」と。それが家族主義の原点。見せるだけでは足りない。子どもの体の中にしみこませておく。その(しみこみ)があってはじめて、子どもは、今度は、自分が親になったとき、自然な形で、幸福な家庭を築くことができる。夫婦が助けあい、いたわりあい、励ましあう姿は、遠慮なく、子どもに見せておく。☆離婚は淡々と、さわやかに親が離婚するとき、離婚そのものは、大きな問題ではない。離婚にいたる家庭内騒動が、子どもの心に暗い影を落とす。ばあいによっては、それがトラウマになることもある。だから離婚するにしても、子どもの前では淡々と。子どものいない世界で、問題を解決する。子どもを巻きこんでの離婚劇、それにいたる激しい夫婦げんかは、タブー中のタブー。夫婦げんかは、子どもへの「間接虐待」と心得ること。☆よい聞き役が、子どもの思考力を育てる親は、子どもの前では、よき聞き役であること。ある人は、『沈黙の価値を知るものだけが、しゃべれ』というが、この格言をもじると、『沈黙の価値を知る親だけが、しゃべれ』となる。子どもの意見だから、不完全で未熟であるのは、当たり前。決して頭ごなしに、「お前の考え方はおかしい」とか、「まちがっている」とかは、言ってはいけない。「それはおもしろい考え方だ」と言って、いつも前向きに、子どもの意見を引き出す。そういう姿勢が、子どもの思考力を育てる。☆子どもの前では、いつも天下国家を論じる子どもに話すテーマは、いつも大きいほうがよい。できれば、天下国家を論ずる。宇宙の話でも、歴史の話でもよい。親が小さくなればなるほど、子どもは小さくなる。隣や近所の人たちの悪口や批判は、タブー。見栄、体裁、世間体は、気にしない。こうした生き様は、子どものものの考え方を卑屈にする。「日本はねえ……」「世界はねえ……」という語りかけが、子どもを大きくする。☆仮面をはずし、子どもには本音で生きるあなたが悪人なら、悪人でもかまわない。大切なことは、子どもの前では、仮面をはずし、本音で生きること。あるがままのあなたを、正直にさらけ出しながら生きる。かっこつけたり、飾ったりする必要はない。そういうあなたの中に、子どもは、いつか(一人の人間)を見る。ただし一言。子育てといっても、あなたはいつも一人の人間として、自分を伸ばしていかねばならない。それが結局は、真の子育て法ということになる。☆優越感の押しつけは、子どもをつぶすおとなや親の優越性を、子どもに押しつけてはいけない。賢い親は、(教師もそうだが……)、バカなフリをしながら、子どもに自信をもたせ、そして子どもを伸ばす。相手は子ども。本気で相手にしてはいけない。ゲームをしても、運動をしても、ときにはわざと子どもに負けてみる。子どもが、「うちの父(母)は、アテにならない」と思うようなったら、しめたもの。勉強について言うなら、「こんな先生に習うくらいなら、自分でしたほうがマシ」と思うようになったら、しめたもの。☆親の動揺、子どもを不安にするたとえば子どもが不登校的な拒否症状を示すと、たいていの親は、狂乱状態になる。そして親が感ずる不安や心配を、そのまま子どもにぶつけてしまう。が、この一撃が、さらに子どもの心に、大きなキズをつける。数か月ですんだはずの不登校が、1年、2年とのびてしまう。子どもの心の問題を感じたら、一喜一憂は、厳禁。半年単位でものを考える。「半年前はどうだったか?」「1年前はどうだったか?」と。☆言うべきことは言っても、あとは時を待つ親は言うべきことは言っても、そこで一歩引き下がる。すぐわからせようとか、実行させようと考えてはいけない。子どもの耳は、そういう意味で長い。脳に届いてから、それを理解するまでに、時間がかかる。実行するまでには、さらに時間がかかる。まずいのは、その場で、とことん子どもを追いつめてしまうような行為。子どもはかえってそれに反発し、その反対のことをするようになる。☆質素が子どもの心を豊かにする子どもには、質素な生活は、どんどん見せる。しかしぜいたくは、するとしても、子どものいないところで、また子どもの見えないところでする。子どもというのは、一度、ぜいたくを覚えると、あともどりできない。だから、子どもにはぜいたくを、経験させない。なお質素とケチは、よく誤解される。質素であることイコール、貧乏ということでもない。質素というのは、つつましく生活をすることをいう。身のまわりにあるものを大切に使いながら、ムダをできるだけはぶく。要するに、こまやかな心が通いあう生活を、質素な生活という。☆うしろ姿を押し売りは、子どもを卑屈にする 生活のためや、子育てのために苦労している姿を、「親のうしろ姿」という。日本では、うしろ姿を子どもに見せることを美徳のように考えている人がいるが、これは美徳でも何でもない。子どもというのは、親が見せるつもりはなくても、親のうしろ姿を見てしまうかもしれないが、しかしそれでも、親は親として、子どもの前では、毅然(きぜん)として生きる。そういう前向きの姿が、子どもに安心感を与え、子どもを伸ばす。☆生きる力は、死を厳粛に扱うことから 死があるから、生の大切さがわかる。死の恐怖があるから、生きる喜びがわかる。人の死の悲しみがあるから、人が生きていることを喜ぶ。どんな宗教でも、死を教えの柱におく。その反射的効果として、「生」を大切にするためである。子どもの教育においても、またそうで、子どもに生きることの大切さを教えたかったら、それがたとえペットの死であっても、死は厳粛にあつかう。☆度量の大きさは、立方体で計算する子育ての度量の大きさは、(たて)X(横)X(高さ)で決まる。(たて)というのは、その人の住む世界の大きさ。(横)というのは、人間的なハバ。(高さ)というのは、どこまで子どもを許し、忘れるかという、その深さのこと。もちろんだからといって、子どもに好き勝手なことをさせろということではない。要するに、あるがままの子どもを、どこまで受け入れることができるかということ。☆「今」を大切に、「今」を懸命に生きる 過去なんてものは、どこにもない。未来なんてものも、どこにもない。あるのは、「今」という現実。だからいつまでも過去を引きずるのも、また未来のために、「今」を犠牲にするのも、正しくない。「今」を大切に、「今」という時の中で、最大限、自分のできることを、懸命にがんばる。明日は、その結果として、必ずやってくる。だからといって、過去を否定するものではない。また何かの目標に向かって努力することを否定するものでもない。しかし大切なのは、「今」という現実の中で、自分を光り輝かせて生きていくこと。☆『休息を求めて疲れる』は、愚かな生き方 イギリスの格言である。愚かな生き方の代名詞のようにもなっている格言である。つまり「いつか楽になろう、楽になろうとがんばっているうちに、疲れてしまい、結局は何もできなくなる」ということ。しかしほんの少し考え方を変えれば、あなたの生活はみちがえるほど、豊かになる。方法は簡単。あなたも1呼吸だけ、今までのリズムを遅くすればよい。☆行きづまったら、生きる源流に視点を 「子どもがここに生きている」という源流に視点をおくと、そのとたん、子育てにまつわるあらゆる問題は、解決する。「この子は生きているだけでいい」と思いなおすことで、すべての問題は解決する。あなたももし、子育てをしていて、行きづまりを感じたら、この源流から、子どもを見てみるとよい。それですべての問題は解決する。☆モノより思い出 イギリスの格言に、『子どもには、釣りザオを買ってあげるより、いっしょに魚釣りに行け』というのがある。子どもの心をつかみたかったら、そうする。親は、よく、「高価なものを買い与えたから、子どもは感謝しているはず」とか、「子どもがほしいものを買い与えたから、親子のパイプは太くなったはず」と考える。しかしこれはまったくの誤解。あるいは逆効果。子どもは一時的には、親に感謝するかもしれないが、あくまでも一時的。物欲をモノで満たすことになれた子どもは、さらにその物欲をエスカレートさせる。☆子育てじょうずは、よき先輩をもつことからあなたの近くに、あなたの子どもより、1~3歳年上の子どもをもつ人がいたら、多少、無理をしてでも、その人と仲よくする。その人に相談することで、たいてい「うちも、こんなことがありましたよ」というような話で、あなたの悩みは、解消する。「無理をしてでも」というのは、「月謝を払うつもりで」ということ。相手にとっては、あまりメリットはないのだから、これは当然といえば、当然。が、それだけではない。あなたの子どもも、その人の子どもの影響を受けて、伸びる。☆子どもの先生は、子どもあなたの近くに、あなたの子どもより1~3歳年上の子どもをもつ人がいたら、その人と仲よくしたらよい。あなたの子どもは、その子どもと遊ぶことにより、すばらしく伸びる。この世界には、『子どもの先生は、子ども』という、大鉄則がある。子ども自身も、同じ仲間という意識で見るため、抵抗がない。また、こと「勉強」ということになると、1、2年、先を見ながら、勉強するということは、それなりに重要である。☆指示は具体的に子どもに与える指示は、具体的に。たとえば「あと片づけしなさい」と言っても、子どもには、あまり意味がない。そういうときは、「おもちゃは、一つですよ」と言う。「友だちと仲よくするのですよ」というのも、そうだ。そういうときは、「これを、○○君に渡してね。きっと、○○君は喜ぶわよ」と言う。学校で先生の話をよく聞いてほしいときは、「先生の話をよく聞くのですよ」ではなく、「学校から帰ってきたら、先生がどんな話をしたか、あとでママに話してね」と言う。(はやし浩司 子育て格言 子育てのコツ)Hiroshi Hayashi++++++++++Dec. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(013)●よくわからない話?++++++++++++++++++++++++朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)理事会は、K国での軽水炉建設事業廃止を決定した。一時韓国は、単独でも、K国での軽水炉建設を慣行する構えを見せた。しかしこと軽水炉に関しては、アメリカの助けがないとどうにもならないことがわかり、泣く泣く断念。KEDOの決定に従った。しかし、ここで問題が終わったというわけではない。ここから先の話が、よくわからない。++++++++++++++++++++++++軽水炉建設の総事業費は46億ドル(約5400億円)。このうち事業主体の中心である韓国は、11億3500万ドル、日本は2番目に多い4億1000万ドルを投じた。KEDO事務局は北朝鮮に資金返還を求める意向だが、応じる可能性は低く、日本の資金回収は困難な見とおしになった。つまり日本は、日本で、その4億1000万ドルについては、あきらめるという方向で、意思をかためた。 流れからすれば、それはしかたのないこと。もともとその4億1000万ドルというお金は、捨て金。軽水炉が完成したところで、また完成しなかったところで、日本に返ってくるお金ではない。 ところが、である。こうした常識に、韓国が、「待った!」をかけた。「清算するならするで、その清算費を、アメリカや日本が、一定額を負担せよ」と。 韓国側のいう清算費というのは、K国東部・琴湖(クムホ)地区の建設用地に残っている軽水炉関連施設・機材の維持、解体、回収費用や、契約企業への違約金・補償金の支払いなどをいう。その額、総額数10億~200億円に達するとみられている。 しかしどう考えても、韓国側の言い分は、おかしい。順に考えてみよう。 まず軽水炉関連施設・機材の維持、解体費用だが、当初、韓国側は、11億3500万ドル分を負担すると言ったのだから、その範囲で、払えばよいのではないのか。契約企業への違約金や補償金についても、同じ。 話がゴチャゴチャしてきたので、もう少しわかりやすい例で説明しよう。 あるところに、たいへん貧しい男がいた。そこでそれを見るにみかねた5人の男たちが、みなで、お金を出しあって、その貧しい男のために、家を建ててやることになった。 音頭を取ったのが、A氏。その家の建築を請け負うことになれば、ばく大な利益を得ることになる。A氏が、設計、建築を担当することになった。 話しあいの結果、A氏が、1100万円、B氏が、400万円、ほかの3人が、残りの2200万円を負担することになった。総額4600万円の豪邸である。そしてその豪邸の建築が始まった。が、その建築が半分程度すんだところで、問題が起きた。 その貧しい男は、約束を破ってばかりいる。そればかりか、にせ札を偽造したり、ピストルを密造したりしていることがわかった。そこでみなが、家の建築は、もうやめようということになった。が、A氏だけは、その貧しい男と親戚関係にあったこともあり、最後までがんばった。みなが引きあげたあとも、建築途中の家をそのままの状態で、維持した。機材や大工も、現場に残した。こうして2年近い年月が流れた。で、やはり、建築は、中止。みなが、そう決めた。A氏以外の人たちは、それまでに出したお金は、戻ってこないと、あきらめた。が、A氏だけは、こう主張した。 「今まで建築した分の解体費用や、下請け業者などに支払う違約金など、200万円について、みんなで分担して払ってほしい」と。 韓国側の言い分を聞いていると、頭の中でバチバチと脳細胞が、ショートするのがわかる。一見、正当性があるようで、まるでない。200億円などという金額は、自分が負担するといった、1100億円の範囲内で、払えばよいことである。「違約金」「違約金」と言うが、その契約は、韓国政府と業者の間で結んだ契約である。日本やアメリカにしてみれば、その契約の内容についてまで、どうしてその責任を負わねばならないのか。 こうした韓国側の横ヤリのため、「K国での軽水炉建設事業廃止に伴う清算費の分担問題をめぐり、意見がまとまらず、廃止の正式決定が大幅に遅れている」(Yahooニュース)とのこと。 K国もK国なら、韓国も韓国だと思う。ホント! あえて言うなら、軽水炉建設が中止されたすべての責任は、K国にある。だったら、どうして韓国は、そのK国に、責任を追及しないのか。違約金にせよ、補償金にせよ、K国に払ってもらえばすむのではないか。(05年12月11日記)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●「パープル・バタフライ」を見る +++++++++++++++++++++ビデオ「パープル・バタフライ」を見る。おもしろかった。久々に、脳ミソが、かき回されたというカンジ。一応、SF映画ということになっているが、しっかりと見ていないと、何がなんだか、さっぱりわけがわからなくなる。「パープル・バタフライ」は、まさにそんなビデオ。+++++++++++++++++++++★「パープル・バタフライ」 あらすじは、1人の青年が、そのつど自分の過去へ戻って、その過去をいじるというもの。が、過去をいじったとたん、現在にもどってみると、すべてが、変わっている! ……とまあ、どこかありふれた、いわゆるタイム・マシン的な映画だが、そういったマシン(機械)は、登場しない。 その青年には、子どものころから、ときどき記憶が抜けてしまうという、特異な現象が起きていた。記憶が、ある時間だけ、まったく抜けてしまうのである。たいては何か、大きな事件、つまり人生の節目に遭遇したときに、そうなる。そこで、その青年は、毎日、克明に日記を書きつづける。もちろん記憶に残った部分については、日記として書くことができる。しかし記憶が残らない部分については、日記を書くことができない。その青年は、青年になる。やがて何かの偶然から、古い日記を読んでいると、その日記の抜けた部分の過去にもどることができるのを知る。そしてその過去にもどって、自分の過去をいじることができることを知る。 ……とまあ、ここから先が、実にゴチャゴチャしてくる。過去に戻って過去をいじるのが、1度や2度でないため、ここに書いたように、しっかりと見ていないと、やがて何がなんだか、さっぱり、わけがわからなくなる。登場人物の様子が、みな、そのつど、まったく別人のように変化する。「なぜ?」「どうして?」と考えているヒマもないほど、目まぐるしく変化する。 私の印象では、娯楽映画としては、少し、複雑すぎるかなといったカンジ。過去へもどって、自分の過去をいじったとたん、現在の様子が、すべて変わる。同じようなテーマは、映画『バック・ツー・ザ・ヒューチャ』で、すでにおなじみ。しかしどういうわけか、パープル・バタフライは、新鮮。理由の一つとして、論理的に、細部まで、矛盾がないように、きちんと構成されているという点がある。 そういう意味ではおもしろい。が、「私は理屈ぽい映画は嫌い」という人は、見ても、あまり意味がわからないのではないかと心配する。見て楽しむ映画というよりは、見て考えるという映画。私は★を、2個半つける。 で、ここからが私の意見。 ★もし、過去をいじることができたら…… ビデオの中では、その青年は、何か都合の悪いことが起きるたびに、過去へもどって、そこで自分の過去を修正しようとする。が、それでうまくいくわけではない。その結果、思わぬ副作用が出てきて、また別の新しい問題を作り出してしまう。 人生というのは、そういうものかもしれない。私もときどき、「もし、あのとき……」というようなことを考える。「もし、あのとき、別の選択をしていたら、私のその後の人生は、大きく変わっていただろうな」と。 しかし結局は、私の人生は、私の人生であっただろうと思う。そのときどきにおいて、そのつど、私は最善とまではいかなくても、その道しかなくて、その道を選んできたように思う。そしてそのとき、別の選択をしていたら、今の私はいないだろうなと思う。 少し前までは、こんなことを考えた。「もし、私があのまま、M物産という会社にいたら、今ごろ、どうなっているだろうか」と。多分、今ごろは、くも膜下出血か何かで、死んでいるかもしれない。あるいはそこそこの子会社で、社長くらいにはなっているだろうが、毎日、マネー、マネーと、あくせくしているだろうな、とも。 ところで最近、私は、「人生は1度でいい」とか、「1つだけでいい」とか、考えるようになった。「2度も生きたくないし、2度生きたからといって、それがどうなのか?」と。「死ぬのはこわいが、死がそこまできたら、そのときは、そのとき」と。だから今朝も、朝食を食べながら、こう思った。 「どうやら、今日も健康で仕事ができそうだ。ありがたいことだ」と。 やはり自分の過去であれ、過去など、いじってはいけない。その影響は、無数の人に及ぶ。考えてみれば、これほど、恐ろしいことはない。だから映画の中でも、それを知った父親は、息子のその青年の首をしめて、その青年(子ども)を殺そうとする。 そのあたりにも、この映画のすばらしさがある。つまり論理性が一貫しているのみならず、その論理性が、深い。今も、そのビデオのあちこちの場面を思い出しながら、「やはりそうだろうな……」と考える。 最後は、その青年自身が、犠牲になることで、みなを、ハッピーエンドに導く。そして過去にもどるための道具となる日記を、すべて燃やしてしまう。 が、ただ1つ、私には、どうしても理解できない部分がある。 最初のシーンで、その青年は、紙切れに、メモを残す。「もしこのメモをだれかに読まれたら、私は死んでいると思ってほしい」というような内容である。そしてそのメモを書いたあと、その青年は、別の方法で、子ども時代に、もどる。 私は、そのメモの意味が、いまだによく理解できない。何度考えても、理解できない。なぜ、その青年は、そんなメモを残したのか。残さねばならなかったのか。そのメモには、どういう意味があるのか。つまりこのあたりが私の脳ミソの限界ということになる。 Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●いじめ+++++++++++++++++++++佐賀県にお住まいのHTさん(母親)よりこんなメールが届いています。子どものいじめについての問題です。HTさん、掲載許可、ありがとうございました。+++++++++++++++++++++ はやし先生寒くなりました。今日、楽天の方の「サトシ君」のエッセイを読ませていただき、メールしたくなりました。(注「サトシ君」についてのエッセーは、このあとに添付しておきます。)娘のことです。同じクラスにMさんという女の子がいます。この子とは、娘が幼稚園児のときから、クラスがよくいっしょになります。私は、娘が2年の時に学年PTA役員という仕事をしました。保護者の方々と先生との連絡役のような仕事です。ほとんど2年生も半ばを過ぎる頃から、娘の口からMさんへの不満が聞かれるようになりました。帰りに、上履き袋を投げつけられる。鬼ごっこで鬼になった子に向かって、優しい声で「目をつぶって、10かぞえるのよ」と言った次の瞬間「お前はそうやって一生そこで、数えていろ!」と言ってみんなを引き連れて、逃げてしまう。面白くないことがあれば靴を履いた足のかかとで、思い切り足を踏まれる。傘のとがった部分で足の甲をつかれる。手提げで殴りかかってくる。ある子に向かって無視をするよう、強要する。「私の言うことが聞けないなら仲間はずれにするから」と脅される。まだまだ色んなことがありましたが、こんな不満を毎日もらしていました。そんな、緊張状態のある日娘が「ワー!」と声を上げて泣いた日がありました。「もう私こんな生活いやだ!」と…。私は、びっくり! 娘の腕には、ひどい内出血のあと(鉛筆でつつかれたり、傘でつかれたり)もう我慢できない。限界だったようです。私もここまで娘が追いつめられているとは思っていませんで同じクラスの仲の良いお母さんに学校の様子を聞いてみました。状況は娘と全く同じでした。特定の子をいじめると言うよりは、面白くなければだれかれかまわず、という状態だったようです。先生に状況を話すと、とても驚いて「エーッ! Mさんがですか?」と。先生の前ではおとなしいニコニコ笑みを絶やさないどちらかというと気の弱い優しい女の子という、とらえ方だったようです。実際、学校や家でわたしと顔を合わせたときも満面の笑みで、「○○ちゃんのママ、んにちは~。」と言いましたので、私もこのギャップには信じられませんでした。その後、先生がクラスの子ども達から話を聞いてみるとなんと18人もの子が、Mさんから上記のようなことをされていることがわかりました。そのうち、一人は腕のけがで、通院までしたようです。いろいろと親のあり方を考えさせられました。そして、6年生になった、今年です。母 「最近、Mさんどうなの?」娘 「まあ、暴力はふるわないけど、相変わらずだよ」母 「そうなんだ~。」娘 「Mさんね、テストの点が私より悪いと、私に向かって、いばってるだの かっこつけてるだの、うるさいよ。 金持ちは話が合わないから、近寄るな。 あんたその服、合わない。趣味悪~!」 こんなこと毎日言ってるよ。母 「あなたそんなこと毎日言われて、嫌じゃないの?」娘 「そりゃ、嫌だよ、頭にくるけど。でも何とも思わない。くだらないから。」母 「すごい! あなためちゃめちゃ大人の対応できてるじゃん!」娘 「そう? ハッハッ、まあね。」こんなような会話を頻繁にしていたある日のことです。娘が家に帰って来るなり、大声で泣き叫びかぶっていた帽子を投げつけ、玄関に入ってきました。聞くと、Mさんのことでした。内容はこうです。放課後数人で遊んでいたところへ、Mさんが娘に向かってMさん 「肩車をしてくれない?」娘 「昨日もしてあげたから、今日は肩と首が痛いからイヤだ。」Mさん 「あんた、生意気、私の言うことが聞けないの?」娘 「私は、しない。したくない。」Mさん 「あんたなんか絶交! これから完全無視よ! いい? ここで遊んでいる人全員これからこの子のこと無視だからね!」Gさん 「やめなよ。そんなこと何でするの? かわいそうだよ」Mさん 「あんたも無視されたいの?」Gさん 「…。」そして、その後Mさんは娘を独りにさせ「あの子と一緒に帰るんじゃないよ」と言ってみんなを引き連れていったそうです。独りぽつんと残されて悔しかった。私独りになっちゃうー。 とつらくてつらくて、いられなかった。と、言っていました。本当に悔しかったと思います。毎日Mさんの暴言にたえている上に、このような出来事があったのでもう極限だったようです。娘の話だと、やはりそのときによってターゲットが変わるようでMさんの周りは毎日トラブルだらけ、いささか疲れた…。でも、許せない…。と母 「つらかったね。あなたよく頑張っているよ。でもね、Mさんのお陰で 本当にいい勉強させてもらっているね。」娘 「勉強?」母 「そうだよ。あなたはつらい人の気持ちがよくわかる子になっているでしょ? つらい子にどうしてあげたらいいかわかるようになったでしょ? それに、絶対にMさん側(いじめる側)になりたいなんて思わないでしょ?」娘 「そうだけど…。でも、むかつく。」母 「ホント、それはそう。ママだってむかつくけど。 でも、Mさんはかわいそうな人よ。」娘 「かわいそう?かわいそうなのは私だよ」母 「だって、もうあなたやあなたの周りの人はMさんを 半分に扱ってるじゃない。」娘 「どういうこと?」母 「同等じゃないってこと。だって、あなた、Mさんの言うこと、くだらない から気にしてないとか、まだ、そんなこと言ってるの?とか、半分はあきれ てるじゃない。Mさんだからしょうがないって。ね」娘 「そう言われてみればね。」母 「あなたは、すごく成長したと思うよ」 そして、 一年生の頃の話をしてあげました。こんな話をして、その後私は、娘の仲の良いお友達に学校の様子を聞き、確かにMさんの言動、行動がエスカレートしていると判断したので先生にお話ししました。先生には、今まであった事実をお話しした後Mさんの親御さんに抗議したいわけではない。Mさんに謝罪して欲しいわけではない。先生に子ども達の人間関係の修正をお願いしたいわけではない。これは、子ども達が成長していく上での勉強だから先生が現状を把握していただくだけでいいです。と言うことを伝えました。あとは、子ども達が自分で考えて対処していくしかないと思いますから。と。娘も同席しているところでの三者面談でしたので、娘もよく理解できたと思います。後で、娘に聞くと「ママ、すっきりだよ」と言っていました。こんな出来事が最近あって、また、娘のお陰で私もちょっと母親になれたかな~と思っていたところでしたので、サトシ君のエッセイは心に響きました。それから、おまけですが、この一件を横で聞いていた二女と、こんな会話をしました。母 「あなたは、何か困っていることはないの?」二女 「ないよ! 毎日楽しい。明日の朝が早く来ないかなッて、いつも思ってる」母 「それは幸せね。何よりね。」二女 「だけど、クラスの中では色々あるよ。」母 「なあに?」二女 「Wさんのことだよ。毎日みんな先生に苦情言ってるよ。 Wさんてね、興奮したり気に入らないことがあったりすると 大声出したり、ものを投げつけてくるんだよ。」母 「ものを? いきなり?」二女 「そうだよ。だからみんなイヤなんだよ、当たると痛いし、急にくるからね。」母 「で…、あなたのところは飛んでこないの?」二女 「飛んでくるよ、毎日ね。」母 「イヤじゃないの?」二女 「全然イヤじゃない。むしろカワイイ子だなって思っているよ。」母 「え? 何で?」二女 「わからない。でも、投げられた後、Wさんに今日のは痛かったよ! とか、今のは、ビシッときいたよ!、って言ってやると Wさんたら、すなおに戻って ごめん悪かったよ。って言ってくれるんだよ。 大騒ぎしたり、怒ったりしてもおさまらないからね。余計に興奮するんだ よ。 それに、もしかしたら病気なのかもしれない。だって、ものを投げてく るときは、よだれ垂らしたり目がどこかに行っちゃってたりするから。」母 「あなた、心の広いいい子に育ったね~。ママうれしい! そのまんま大 きくなりなさいね~。」 本当にうれしい出来事でした。そう言えば初めてWさんのお母さんにお会いしたときに、すごく丁重にご挨拶をされたことを覚えています。「うちのWが学校でお世話になっています。あなたの娘さんが、友達の中で一番優しくしてくれるとWがいつも言っています。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。」、と…。あまりの丁寧さに違和感すら覚えたのを記憶しています。今思えば、Wさんとお母さんはずっと友達関係で悩んでいたのでしょうね。それにしても、知らない間に子ども達は成長しているものですね。外に出ると何とか人間関係をうまくやろう。トラブルにならないようにしよう。と、日々神経をすり減らす長女。何かあっても、許してわすれる(はやし先生談)そして好んでそれを包み込んでしまおうとする二女。はやし先生がおっしゃるように家が体を休める場所でなければならないと子ども達を見ていて実感します。2学期も残りわずかとなりました。元気にすごして欲しいと思っています。長いメールになりました。時節柄ご自愛ください。こちらは、九州地方も、急に冷えこんできました。佐賀県S市、HTより++++++++++++++++++HTさんが、読んでくださった原稿をここに添付しておきます。++++++++++++++++++●サトシ君(いじめ問題の陰で) サトシ君(中2)は、心のやさしい子どもだった。そういうこともあって、いつも皆に、いじめられていた。が、彼は決して、友だちを責めなかった。背中にチョークで、いっぱい落書きをされても、「ううん、いいんだよ、先生。何でもないよ。皆でふざけて遊んでいただけだよ」と言っていた。 そのサトシ君は、事情があって、祖父母の手で育てられていた。が、その祖父が脳梗塞で倒れた。倒れて伊豆(静岡県)にあるリハビリセンターへ入院した。これから先は、サトシ君の祖母から聞いた話だ。 祖父はサトシ君が毎週、見舞いに来てくれるのを待って、ひげを剃らなかった。サトシ君がひげを剃ってくれるのを、何よりも楽しみにしていたそうだ。そしてそれが終わると、祖父とサトシ君は、センターの北にある神社へお参りに行くことになっていたという。そこでのこと。帰る道すがら、祖父が、「お前はどんなことを祈ったか」と聞くと、サトシ君は、「高校に合格しますようにと祈った」と。それを聞いた祖父が怒って、「どうしてお前は、わしの病気が治るように祈らなかったか」と。そこでサトシ君はあわてて神社へ戻り、もう一度、祈りなおしたという。 この話を聞いて以来、私は彼を、尊敬の念をこめて、「サトシ君」で呼ぶようになった。とても呼び捨てにはできなかった。いろいろな子どもがいるが、実際には、サトシ君のような子どももいる。 今、いじめが問題になっている。しかしいじめられる子どもは、幸いである。心に大きな財産を蓄えることができる。一方、いじめる子どもは、大きく自分の心を削る。そしていつか、そのことで後悔するときがくる。世の中には、しっかりと人を見る人がいる。そういう人が、しかっりと判断する。愚かな人ばかりではない。サトシ君にしても、学校の先生には好かれ、浜松市内のK高校を卒業したあと、東京のK大学へと進んでいる。サトシ君は、見るからに人格が違っていた。 自分の子どもが、学校でいじめられているのを見るのは、つらいことだ。しかし問題は、いつどこで親が手を出し、いつどこで教師が手を出すかだ。いじめのない世界はないし、人はいじめられながら成長し、そしてたくましくなる。つらいが、親も教師も、耐えるところでは耐えないと、子どもがひ弱になってしまう。今はこういう時代だから、ちょっとした悪ふざけでも、「そら、いじめだ!」と、親は騒ぐ。が、こういう姿勢は、かえって子どもから自立心を奪う。もちろん陰湿ないじめや、限度を超えたいじめは別である。しかしそれ以前の範囲なら、一に様子を見て、二にがまん。三、四がなくて、五に相談。親や教師ができることといえば、せいぜい、子どもの訴えることに、とことん耳を傾けてやることでしかない。子どもの肩に手をかけ、「お前はがんばっているんだよ」と励ましてあげることでしかない。それは親や教師にとっては、とてもつらいことだが、親や教師にも、できることには限界がある。その限度の中で、じっと耐えるのも、 親や教師の務めではないかと、私は思う。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 人は、ドン底に落ちると、2つのタイプの人間に分かれる。そのときから、徹底した善人になるタイプと、徹底した悪人になるタイプである。どちらの道を選ぶかは、紙一重。 そこまで深刻な問題ではないにせよ、子どもの世界でも、同じようなことが起きる。いじめを受け、それをバネに、ここに書いたサトシ君のようになる子どもと、同じように、今度は反対に、いじめる側に回る子どもである。「いじめられる前に、いじめてやれ」という考え方である。 そういう意味では、いじめる側の子どもが、すべて「悪」とは言い切れない。(もちろんいじめは、悪いことだが……。)抑圧されたうっぷんが、長く蓄積されて、それがいじめに転化するということも、子どもの世界では、よくある。 それにいじめる側は、それを(いじめ)と認識していないケースも、多い。軽い遊びか、ふざけのつもりで、それをする。しかしいじめられる側にとっては、そうではない。ちょっとした相手の言動を、おおげさにとらえてしまう。そういうケースも、多い。 さらに「A君がいじめる」と言うから、学校の先生に相談して、A君を近くから排除してもらう。すると今度は、その子どもは、「B君がいじめる」と言い出す。そこでまた今度は、B君を近くから排除してもらう。が、つぎに今度は、その子どもは、「学校の先生がいじめる」と言い出したりする。そういうケースも、少なくない。 これを「ターゲットの移動」という。つまりその子どもは、もっと大きな心の問題をかかえていて、それが原因で、学校へ行きたくないだけである。それがわからないから、親や先生は、子どもの言うことに、振りまわされてしまう。そういうケースも、多い。 ここに(いじめの問題)のむずかしさがある。(はやし浩司 いじめ いじめの問題)
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(09)
●臭い街(相対性理論) アインシュタインは、相対性理論を唱えた。そんな高尚な理論ではないが、反対の立場で見ると、ものの価値観が180度変わるということはよくある。 引佐郡引佐町のT村に住んでいる婦人が、こう教えてくれた。「町の空気は臭いですね」「先日もアクトタワー(駅前の高層ビル)へ行ったのですが、通路を歩いているだけで、吐き気を覚えました。食堂からの臭いがあちこちからしてきて、気持ちが悪くなりました」と。 こういう感覚は町の中に住んでいる人には、当然のことながら、わからない。それに慣れてしまっているからだ。そういう意味で、「慣れ」というのは、こわい。自分たちのまわりの様子がわからなくなる。そしてそれを前提として、ものごとを考えるようになる。 そのアクトタワーだが、建設費だけでも2000億円とも、3000億円とも言われている。あの東京の国立劇場が400億円で建設されているから、いかに莫大な額かが、それでわかる。で、このことを市の役人に話すと、その役人は笑ってこう話してくれた。「はやしさん、そんなものじゃ、ありませんよ」と。もっとお金がかかったというのだ。「土地代は別ですから」と。 さらに、そのアクトタワー。人の通りもまばらで、楽器博物館にしても、閑古鳥が鳴いている。「音楽の町にふさわしい建物を」と意気込んで建てられたものの、地下に大小、二つのホールがあるにすぎない。建設費を床面積で割ると、百万円の札束を敷きつめたほどのコストがかかっているという。 何となくグチになってしまったが、私が言いたいのは別のことだ。町の人間が「町」を考えると、こういう町づくりになってしまう。そこで私はふと、こんなことを考えた。T村の住人が町づくりを考えたら、どんな町を作るか、と。彼らがまず真っ先に考えるのは、「臭くない町」だろうと思う。具体的には、田舎の様子をそのまま町へ持ちこむ。土や緑をそのまま町へもちこむ。ちょうど町の建設業者が、村の土手や小川を、灰色のコンクリートで埋めつくすように、その反対の立場で、町を土や緑で埋めつくす。互いにそのほうが、居心地がいいからだ。と、考えると、日本の社会は、実に都会優先にできていると思う。町の価値観が田舎へ来ることはあっても、田舎の価値観が、町へ入ることはまず、ない。都会らしい田舎づくりをすることはあっても、田舎らしい都会づくりをすることは、まず、ない。先の臭いにしても、都会の人が田舎へやってきて、「おいしい空気ですね」と言うことはあっても、田舎の人が町へやってきて、「臭いですね」とは、言えない。心の中でそう思っても、それを口に出して言えない。田舎の人がせいぜいできることと言えば、口をタオルでおさえ、顔をしかめながら、その場から急ぎ足で立ち去ることでしかない。 町の人は、自分たちはいい生活をしていると思うのは勝手だが、一度、田舎の人の目で、自分を見てみるとよい。ものの価値観がひっくりかえるということはよくあるし、新しいものの見方ができるようになるかもしれない。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 都会優先型の社会構造そのものに問題がある。行政にせよ、文化にせよ、すべてが都会側から一方的に、地方へ流れてくる。反対に、地方から、都会にそれらが向うことは、めったに、ない。が、こればかりは、いかんともしがたい。 しかし何も問題意識をもたないのと、問題意識をもつのとでは、ものの考え方が変わってくる。ときには、田舎の中に自分の視点を置いて、ものを考えることも重要なことだと、私は思う。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●笑わない子どもたち(萎縮する心) 子どもというのは皆、大声で笑うもの……と考えているなら、それはまちがいだ。今、大声で笑えない子どもが、ふえている。10人に2、3人はいる。皆がドッと笑うようなときでも、顔をそむけてクックッと笑ったりする。原因はいろいろあるが、それだけ心がゆがんでいるとみる。 まず第一に、過干渉。威圧的な子育て、権威主義的な子育てが日常化すると、子どもの心は内閉する。次に育児拒否。家庭崩壊や暴力的なしつけが原因で、内閉することもある。最近では、「機能不全型家庭」がふえている。家庭が本来果たすべき機能そのものが、欠落している家庭だ。母親がパチンコに狂う、父親が仕事人間で、家庭を顧みないなど。生活が混乱していて、秩序そのものがない。朝食、夕食といっても、時間もめちゃくちゃで、しかも「食」としての形がない。テーブルの上に、食べかけのパンがころがっているだけ、というように。子どもは満たされない愛情への欲求不満から、自分の心を傷つける。情緒や精神状態そのものが不安定になることも珍しくない。 神経症や脳の機能的障害が原因となることもある。自閉傾向やかん黙傾向のある子どもは、心のそのものにマクがかかったようになり、いわゆる「何を考えているかわからない子ども」になる。自閉傾向のある子どもは、自分の世界に陶酔してしまうので、意思の疎通そのものができなくなる。こちらからの働きかけに反応して笑うこともあるが、それが突然であったり、あるいは場違いなほどおおげさであったりする。ギャーギャーと、勝手に騒ぐこともある。またかん黙傾向のある子どもは、いつももう一つの心が、別のどこかにあるような感じになる。いつも柔和な笑みを浮かべたまま、それでいてまったく話さない。 子どもは笑わせる。何でもないようなことだが、子どもは大声で笑うことによって、心を開放させる。裏を返して言うと、大声で笑うだけでも、子どもの心がまっすぐ伸びているという証拠だ。そこでいよいよ本論だが、あなたの子どもはどうだろうか。幼稚園や小学校での様子はどうだろうか。先生の話を聞きながら、大声で笑っているだろうか。それとも笑っていないだろうか。笑うことはないしにしても、大声で反論したり自分の意見を言っているだろうか。それとも静かだろうか。 もしあなたの子どもが静かで、大声で笑うこともないようであれば、あなたは家庭教育のありかたを、おおいに反省してみる必要がある。中には「子どもというのは、生まれながらにそういう性質は決まっている」と考える人がいるが、それはとんでもない誤解である。子どもは(おとなも)、生まれながらにして、大声で笑ったり、話したりすることのほうが、自然な姿だ。 繰りかえすが、幼児教育の世界で、「すなおな子ども」というときは、従順でおとなしい子どもをすなおな子どもとは、言わない。自分の思っていることを、ハキハキと言うことができる子どもをすなおな子どもという。これも誤解がないように。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 『笑えば、伸びる』……それが私の指導法の柱にもなっている。笑うことには、不思議な力がある。その(力)は、大脳生理学の分野でも、近年になってつぎつぎと証明されつつある。 また「学習」という分野においても、笑うことによって、子どもの中に、前向きな姿勢が生まれてくる。私は、ときには、1時間中、幼児たちを笑わせつづけることがある。大声で、ゲラゲラ笑わせつづける。 コツがある。 子どもを笑わせようとしても、あまり意味がない。それでは、子どもは、笑わない。私自身が、とことん、楽しむ。楽しんで笑う。そのウズの中に、子どもを巻きこんでいく。 Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●養殖される子どもたち(牙を抜かれる子ども) 岐阜県の長良川。その長良川の鮎に異変が起きて、久しい。その鮎を見続けてきた1人の老人は、こう言った。「鮎が縄張り争いをしない」と。武儀郡板取村に住む、N氏である。「最近の鮎は水のたまり場で、ウロウロと集団で住んでいる」と。原因というより理由は、養殖。この20年、長良川を泳ぐ鮎の大半は、稚魚の時代に、琵琶湖周辺の養魚場で育てられた鮎だ。体長が数センチになったところで、毎年3~4月に、長良川に放流されている。人工飼育という不自然な飼育環境が、こういう鮎を生んだ。しかしこれは鮎という魚の話。実はこれと同じ現象が、子どもの世界にも起きている! スコップを横取りされても、抗議できない。ブランコの上から砂をかけられても、文句も言えない。ドッチボールをしても、ただ逃げ回るだけ。先生がプリントや給食を配り忘れても、「私の分がない」と言えない。これらは幼稚園児の話だが、中学生とて例外ではない。キャンプ場で、焚き火が予想以上に燃えあがったとき、「こわい!」と逃げてきた男子がいた。小さな虫が机の上をはっただけで、「キャーッ」と声をあげる子どもとなると、今では、大半がそうだ。 子どもというのは、幼いときから、取っ組み合いの喧嘩をしながら、たくましくなる。そういう形で、人間はここまで進化してきた。もしそういうたくましさがなかったら、とっくの昔に人間は絶滅していたはずである。が、そんな基本的なことすら、今、できなくなってきている。核家族化に不自然な非暴力主義。それに家族のカプセル化。カプセル化というのは、家族の中だけでしか通用しない価値観の中で生きることだ。このタイプの家族は、他人の価値観を認めない。あるいは他人に心を許さない。カルト教団の信者のように、その内部ではわきあいあいと仲がよい。「私たちは正しい」という信念のもと、返す刀で、他人には「あなたはまちがっている」と言い切る。 また「いじめ」が問題視される反面、本来人間がもっている闘争心まで否定してしまう。子どもどうしの悪ふざけすら、「そら、いじめ!」と、頭から抑えつけてしまう。 こういう環境の中で、子どもは養殖化される。嘘だと思うなら、一度、子どもたちの遊ぶ風景を観察してみればいい。最近の子どもはみんな、仲がいい。仲がよ過ぎる。砂場でも、それぞれが勝手なことをして遊んでいる。私たちが子どものころには、どんな砂場にもボスがいて、そのボスの許可なしでは、砂場に入れなかった。私自身がボスになることもあった。そしてほかの子どもたちは、そのボスの命令に従って砂の山を作ったり、あるいは水を運んでダムを作ったりした。もしそういう縄張りを荒らすような者が現われたりすれば、私たちは力を合わせて、そいつを追い出したりした。 平和で、のどかに泳ぎ回る鮎。見方によっては、縄張りを争う鮎より、ずっといい。理想的な社会だ。すばらしい。すべての鮎がそうなれば、「友釣り」という釣り方もなくなる。人間どもの傲慢な楽しみの一つを減らすことができる。しかし本当にそれでいいのか。それが鮎の本来の姿なのか。その答は、みなさんで考えてみてほしい。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) ときどき、わんぱくで、たくましい子どもをみかける。30年前には、まだそういう子どもが多かったが、今では、そういう子どもは、むしろ少数派。そのため、集団の中では、目立ち、そのため、ほかの父母からは、白い目で見られること多い。 しかし子どもというのは、ADHD児が見せるような多動性は別として、わんぱくで、自己主張が強ければ強いほど、あとあと、伸びる。たくましく成長していく。このタイプの子どもは、集団からはみ出るという理由だけで、決して抑えこんでしまってはいけない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●カプセル家族(心のさみしい人たち) 自分の価値観だけで生きる家族、それがカプセル家族。言葉の上では、それで説明できるが、その言葉の裏には、とてつもないほど巨大な問題が隠されている。しかしここでいうカプセル家族は、どこかの国の、どこかの町の、ある特殊な家族をいうのではない。あなたの周囲にもいくらでもあるし、あなた自身の家族がそうである可能性は高い。 核家族は核家族だが、カプセル家族は、他人の価値観を認めない。心を開かない。ものの考え方が独善的で、排他的。「私は正しい」という確信のもと、相手に向かっては「まちがっている」と断言する。いろいろなタイプがある。子どもを溺愛しながら、「これが親の深い愛だ」と、錯覚している人。子どもの受験戦争に狂奔しながら、「これが教育だ」と、誤解している人。子どもを自分の欲求不満のはけ口にしながら、「私は子どものよき理解者だ」と、うぬぼれている人。いろいろあるが、もとはと言えば、現代社会が生み出した、さみしい犠牲者たちだ。 考えてみれば、この世の中。生きているのは、自分一人だけ。明日、隣人がお金に困っても、あなたはその人を助けない。そういう思いが、あなたを孤独にする。あなたとて明日、病気で倒れれば、万事休す。そういう思いが、あなたの家族をカプセル化する。愛することができるのは、自分の子どもだけ。学歴は人生のパスポート。学歴さえあれば、何だって手に入る。家族だけが信じられる相手。他人は誰も信じられない。そうそう一つ、忘れた。お金だ。お金。お金さえあれば何だってできる。地位や名誉があれば、もっといい。 カプセル家族には、社会も国もいらない。選挙に行くことすら、バカバカしいと思っている。もちろん社会奉仕などというものは、時間の無駄。上辺ではいろいろなことを言いながら、自分の損になることは何もしない。その上、幸福感も相対的なもので、他人が自分より幸福になるのを許さない。あるいは反対に、他人が不幸になればなるほど、自分が幸福になったと感ずる。自分こそが、絶対、正しい。 今、日本では、家族のカプセル化が、急速に進んでいる。田舎よりも都会。しかも皮肉なことに、地位の高い人、収入の多い人、学歴の高い人ほど、それが進んでいる。こういう人たちは、「自分こそが社会のリーダーだ」と思いこんでいる。あるいは「世間も自分たちに見習うべきだ」と考えている。結果、この日本がこれからどうなるか。 私に見える日本の将来は、殺伐とした砂漠のような世界だ。空気はかわき、心を潤す緑はどこにもない。人はますます功利的でドライになる。なりながら、それが当たり前だと思う。あとはこの悪循環。 私はこのことを、田舎に住むようになってはじめて、わかった。田舎に住むようになって、人間というのは、本来、もっともっと不完全で、もっともっと温かいものだということを知った。そしてこれはたいへんショックなことだったが、自分自身が、そのカプセル家族になっていたことを知った。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) このエッセーについては、いろいろ書き改めたい点もあるが、このままで……。カプセル家族だから、選挙に行かないということはない。この点については、まちがっていると思う。ただ自分の住む世界がカプセル化すると、ものの考え方が、独善的になったり、ひとりよがりになったりする。そういう意味で、つまりその返す刀で、相手を、全面的に否定したりしやすくなる。 だから……、こう書くと、手前味噌のようでつらいが、もしあなたに子どもと接する機会があったら、どんどんと子どもと接したらよいと思う。子どもは、あなたの進むべき道を、正してくれる。子どもには、そういう力がある。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※●単身赴任(夫婦像は、学習によって身につく) 単身赴任ほど、非人間的な職場環境はないと思うだが、最近ではそれを歓迎する夫婦もふえている。ある妻は、夫の単身赴任が決まったとき、友人に、「ヤッター!」と喜んで見せたという。現実にはそういう夫婦もいる。 この夫婦像というのは、子ども時代に形成される。しかも本能ではなく、学習によって形成される。だからもしあなたが、将来、あなたの子どもに「あなたが望むような家庭」を築いてほしいと願っているなら、今、その家庭がどういう家庭であるかを、しっかりと見せておかねばならない。いや、見せるだけでは足りない。しっかりと身にしみこませておく。そういう経験があってはじめて、あなたの子どもは将来、「あなたが望むような家庭」を、自然と築くことができるようになる。 夫婦像も同じ。夫婦が子どもに見せるものがあるとするなら、それは互いに思いやり合い、気づかい合い、そしていたわり合う姿だ。そういう姿を日常的に見ながら、子どもは自分の中に夫婦像を作っていく。 ところで以前、私はこんな本を目にした。ほかの教育者の書いた本を批判するのは、あまり好きではないが、そこにはこうあった。いわく、「夫婦喧嘩は子どもに見せるとよい。意見の対立があることを教えるのに、絶好の機会だ」と。日本でも著名な教育者で、これが彼の持論でもあるから、こう書くと、名前がわかってしまうかもしれない。しかし、夫婦で哲学論争でもするなら話しは別だが、子どもに夫婦喧嘩など見せるものではない。……と言っても、夫婦喧嘩は時と場所を選ばず起きるものだから、見せたくなくても見せてしまうかもしれない。それはともかくとして、やり方をまちがえると、この夫婦喧嘩は子どもを限りなく不安にする。そしてこの不安が、子どもの心をゆがめる。私はこの教育者は、子ども知らずの教育者だと判断した。 さて本論。欧米では、そもそも単身赴任など、考えられない。そんなものを命じられれば、ふつうの人ならその会社をやめてしまうだろう。あるいは反対に会社が訴えられるかもしれない。が、日本人というのは、そういうことが平気で(?)できる。ではなぜそれができるかと言えば、そういう夫婦像を、すでにどこかで見ているからである。ひょっとしたら、その人の父親がそうであったかもしれない。あるいは単身赴任ではなくても、その人の父親が仕事人間や会社人間であったりして、家庭を顧みない人であったかもしれない。ともかくも、夫の仕事のために家庭が犠牲になることは、当然だという家庭で育ってきた。そういう背景があるから、冒頭で述べたような妻が生まれる……。 私個人のことを言えば、私は田舎町の自転車屋で生まれ、そして育った。だから夫婦が別々に住んで、別々に暮らすということが信じられないというより、そういう情報そのものが、頭の中にない。だから私の意見は、ある意味で一方的なものかもしれない。あるいは現実離れしているかもしれない。そういうことも考えながら、この文を読んでほしい。私が正しいという自信が、実のところ、私にも、ない。(以上、01年記「子育て雑談」)(はやし浩司 単身赴任 離婚 離婚の影響)(付記) 4年前に書いたこのエッセーを読みながら、私は、心のどこかで、小さな違和感を覚える。たとえば夫婦であっても、「ダカラ論」にしばられるのは、正しくないのではないかというふうに、このところ考えることが多くなった。離婚についても、それを悪いことと決めてかかる必要は、まったくない。 ただ子どもに関していえば、離婚というより、離婚にまつわる家庭内騒動が、子どもの心に大きな影響を与える。離婚するにしても、子どもとは関係のない世界で、淡々とするのが、よい。 単身赴任については、ここに書いたとおりだと、今でも、思っている。アメリカなどでは、入社と同時に、そういった問題も含めて、会社と契約書をかわすところが多い。その段階で、転勤を断ることもできる。日本でも、そういう会社がふえてきたと聞いている。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●先輩・後輩(根強く残る封建制度) 晴れわたった午後の一日。青い空に白いユニフォームが光る。今日もグランドで、中学校の野球部の少年たちが、練習をしている。のどかな光景だ。時折、カーン、カーンというボールを打つ音が聞こえてくる。 が、それはあくまでも表面。この野球部に限らず、たいていの運動部は、徹底した「上下関係」で成り立っている。たとえばテニス部。一年生は玉拾いだけ。二年生になってやっとラケットをもたせてもらうことができ、試合に出られるようになるのは、三年生になってから。それまではいくら力があっても、試合には出られないという「オキテ」になっている。 さらにすさましいのが、柔道部や剣道部。さらに野球部など。野球部に至っては、入部時に、「先生に殴られても文句を言いません」という誓約書を書かせるところがある。私はこうした指導について、とやかく言わない。今時の子どもを指導するには、それなりの「抑え」がないと、指導できない。それに親も子どもも、そのやり方に納得しているのだから、私のような部外者がとやかく言っても始まらない。 問題はこうした封建意識が、学校の教育現場に微妙に「影」を落としているということだ。あるいは先生たちのものの考え方に、影響を与えているということだ。幼稚園教育にしても、たいていどこの幼稚園も、徹底した年功序列制度を敷いている。古参の先生が、それぞれ派閥をつくり、若い先生をその配下におさめているところもある。新米の先生が、古参の先生の指導を批判するなどということは、この世界ではありえない。実はこの私も、幼稚園で働くようになってから、何度、古参の先生に殴られたり、ひっぱたかれたりしたことか。(この話は、ホントだぞ!) そしてこうした古臭い体質は、子どもへと受け継がれていく。それはまさに「教えずして教える」という、教育のダークサイド。子どもたちもまた、いつしか先生と同じようなものの考え方をするようになる。いわゆる封建意識の世代伝播がこうしてなされていく。 私はN教組という組織について、ほとんど知識をもっていない。もっていないが、「左翼」という言葉からは、民主、平等、博愛というイメージを連想する。上下意識のない、平和な世界だ。日教組というのは、その左翼ではなかったのか。このことをインターネット仲間の一人に相談すると、こう教えてくれた。彼自身も、九州のある高校で教壇に立っている。いわく、「マルクス・レーニン主義と言っても、組織の内部には徹底した上下関係がありますよ」と。この彼の一言だけをもって、すべてを判断することはできないが、そういう意見もある。つまり、左翼思想イコール、必ずしも封建意識の打破ということには、ならないようだ。 何でもかんでも外国がいいというわけではないが、欧米には「先輩、後輩」という言葉にあたる単語そのものが、ない。そういうことも考えると、日本人の平等意識は、100年は遅れているのではないか……と、私は思う。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 「上下意識など、クソ食らえ」。人間に上も下も、あるわけがない。そこを原点として、すべての人間関係を改めて、考えなおしてみる。つまり私たちが求める民主主義は、そこから始まる。言いかえると、この上下意識が残っているかぎり、日本には、真の民主主義は、訪れない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●指で鼻をさす(教育のダークサイド) 子どもたち(小学生)は、「自分」を表すとき、指で鼻先を押さえる。欧米では、親指で自分の胸を押さえる。そこで私はいつごろから、子どもたちが自分の鼻を押さえるようになるかを調べてみた。「調べた」というのもおおげさだが、授業の途中で、子どもたちにどうするかを聞いてみた。結果、年長児ではほぼ全員。年中児でも、ほぼ全員。年少児になると、何割かは鼻先を押さえるが、ウロウロと迷う子どもが多いということがわかった。そんなことで、こういう習慣は、四歳から五歳ぐらいにかけてできるということがわかった。つまりこの時期、子どもたちは誰に教えてもらうわけでもなく、いつの間にか、そういう習慣に染まっていく。 私は何も、ここでジェスチャについて書くつもりはない。私が言いたいのは、教育には、常に「教えずして教える」という、ダークサイドの部分があるということだ。これはジェスチャという、どうでもいいようなことだが、ものの考え方や道筋、思考回路などといったものも、実はこのダークサイドの部分でできる。しかもその影響は、当然のことながら、幼児期ほど、大きい。この時期に論理的なものの考え方を見つけた子どもは、ずっと論理的なものの考え方ができるいようになるし、そうでない子どもは、そうでない。そればかりではない。この時期に、人生観や価値観の基本までできる。異性観や夫婦像といったものまで、この時期に完成される。少なくとも、それ以後、大きく変化するということはない。そのことはあなた自身を静かに観察してみれば、わかる。 たとえば私は、今、いろいろなことを考え、こうして文を書いているが、基本的なものの考え方が、幼児期以後、変わったという記憶がない。途中で大きく変化したということは、ないのだ。今の私は、幼児期の私であり、その幼児期の私が、今の私になっている。それはちょうど金太郎飴のようなもので、私の人生は、どこで切っても、「私」にほかならない。幼児期に桃太郎だった私が、途中で金太郎になるなどということは、ありえない。 もうわかっていただけると思うが、幼児教育の重要性は、実はここにある。この時期に作られる「私」は、一生、「私」の基本になる。あるはその時期にできた方向性に従うだけである。中には幼児教育イコール、幼稚教育と考えている人がいるが、それはとんでもない誤解である。 ……と書いたところで、今、ふと、別のことが頭の中を横切った。実は今、ある男の子(小二)のことが気になっている。彼は男の子なのだが、言い方、ものごしが、女の子っぽいというより、その女の子を通り越して、同性愛者ぽい。まちがいを指摘したりすると、「イヤーン」と甘ったるい声を出したりする。いくら注意してもなおらない。で、私が悩んでいることは、このことではなく、それを親に言うべきかどうかということだ。もうこの傾向は、ここ1年以上続いている。なおそうとしてもなおるものではないし、さりとて放置しておくわけにもいかない。放置しておけば、彼はひょっとしたら、一生、そのままになるだろう。近く、結論を出すつもりでいる。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 教えずして教えてしまうこと。実は、これがこわい。ユングも、「シャドウ」という言葉を使って、それを説明した。 たとえばあなたが、本当は邪悪な人間であったとする。その邪悪さをおおいかくして、善人ぶっていたとする。そのときその邪悪さが、その人のシャドウとなる。子どもは、あなたの近くにいるため、そのシャドウをそのまま引き継いでしまう。 要するに、ウソやインチキ、ごまかしや仮面で、いくら善人ぶっても、子どもはだませないということ。子どもは、あなたのすべてを見ている。 そういう意味で、子育ては怖いぞ~オ!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●書くという仕事(私の墓石) 私も若いころ、自分をなかなか認めてくれない世間を逆恨みしたことがある。「世間には人を見る目がない」「世間はバカだ」と。しかし今になってみれば、これほど甘ったれた考え方は、ない。私が世間を認めていないのに、どうして世間が私を認めてくれるだろうか。あるいは自分自身が、他人を受け入れるほどまでに「成熟した世間の一員」ではないのに、どうしてそれを世間に求めることができるだろうか。 今でも時々、暇になると、原稿を書いて、あちこちの出版社に送っている。どうせ出版されなくても、ダメもと。そんなゆとりがあるから、送り返されてきても、何とも思わない。つまりそうされることに、免疫性ができた。しかし若いころはそうではなかった。送り返してきた出版社を、心底恨んだ。のろった。はげしい失望感と絶望感に襲われたこともある。「貴殿の原稿は、当社の企画には合致せず、今回は出版を見合させていただきます」などという、いんぎん無礼な手紙をもらったりすると、それを震える手で握りつぶしたりした。 もっともそういうときに感じた悔しさが、それ以後のバネになっているから、それはそれで無駄ではなかった。「チクショウ」という思いが、次の仕事に結びついていった。が、その私も51歳。著書も、売れない本ばかりだが、20冊を超えた。ペンネームで書いた本も加えると、30冊以上になる。子ども向けの百科事典や、雑誌の企画、編集もてがけてきた。今はまだ、その途中だから、ここで結論を述べることもできないが、書くには書いたが、それだけのことだということだ。地位や名声を手にしたわけではない。本を書くと、お金が儲かるだろうと思う人がいるが、実際には、1冊書いて、30万から50万円。書くエネルギーや、出版までのエネルギーを考えると、これほど非効率な仕事はない。趣味か副業のように考えないと、とてもできない。 さて最近、60歳になった人から、こんな相談をもらった。経歴だけは立派な人だ。いわく、「本を書きたい」と。「ついては手伝ってほしい」と。一時は手伝う気にはなったが、しかし途中で、できなくなってしまった。私が手伝えば、それは私の本になってしまう。どうしても随所に、私の思想が入り込んでしまう。ちょうど盗作と逆の現象が、ここで起きてしまう。私は「漏作だ」と笑ったが、それはそれで、私にとっては都合が悪い。私の書いた本など、トイレットペーパーにもならないかもしれないが、しかしそれはまさに「私の人生」そのもの。いつかどこかで、私の本が、逆に盗作したと思われるかもしれない。 で、最近はこう考えるようになった。「本は私の墓石だ」と。私は無神論者だし、自分の著述活動を通して、日本の仏教にも疑念を抱くようになってしまった。そうそう宗教論の本も5冊、書いた。だから、自分が今、ここでこうして生きているという「あかし」を、何とか今、ここにとどめておきたいと思う。一度、私のような人生観をもつと、あとは毎日が孤独との闘いのようなものだ。その孤独と闘うために書く。書くしかない。そういう意味で、今の私には、もうあの世間の目は、ない。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 先日、近くにある陶芸教室をのぞいてみた。骨つぼを作りたいからである。が、もちろん、そんなことは言わなかった。そこであれこれ説明をしてくれた先生は、さかんにお茶碗を自分で作ると楽しいですよ」と言った。が、茶碗なら、ショッピングセンターで買ったほうが、ずっと安い。使い勝手もよい。 私は、骨つぼが作りたいのだ! 自分の骨を入れる骨つぼ、である。 もちろん1個だけでよい。最初で、最後の、1個だけでよい。だから陶芸教室に、何年も通う必要はない。 「いえ、自分で作りたいものがありますので、それ1個だけを作ればいいのです」と言うと、その先生は、「ぞれじゃあ……」と言ったまま、黙ってしまった。「それじゃあ、入会できません」と言いたかったのだろうか。それとも、「それゃじゃあ、進歩しません」と言いたかったのだろうか。 デザインは、決まっている。球形で、その球形の上に、無数の思い出をいろいろなモチーフ(装飾)を使って飾る。色は、白を基調にして、淡いパステルカラー風。 「ロクロを使うのではなく、縄文時代の土器のように、粘土のヒモをクルクルとまきながら作りたいです」と説明すると、先生も、少しは納得してくれたよう。「そういう作り方でよければ、その指導します」と言ってくれた。 来年の春になったら、入会しようと思っている。++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(011)●天国論+++++++++++++++++宗教の話の中には、よく天国とか、極楽とかいう言葉が出てくる。その反対の世界になっているのが、地獄、と。しかし私が考える天国には、天国しかなく、あるのは、天国だけ。地獄など、ない。その天国について、考えてみた。もし、本当にあるとするなら、の話だが……。++++++++++++++++++ 天国には、天国しかない。地獄など、どこにもない。だから死んだ人は、みな、天国へ行く。善人も、悪人も、みんな、だ。 が、それでは、不公平と思う人がいるかもしれない。それに善人と悪人は、どうやっていっしょに暮らすのかという疑問をもつ人もいるだろう。しかし心配は、ご無用! ここで、私が考える、天国の構造について、説明してみる。 天国には、天国しかない。あるのは、天国だけ。死んだ人は、一度、みな、天国へ入る。が、ここで善人は、そのまま。そのままの状態で、天国で、心豊かな、楽しい生活ができる。しかし悪人は、そうではない。悪人だった人は、その悪の程度に応じて、乳幼児、幼児、少年・少女へと、姿を変える。 とんでもない極悪人だった人は、赤ん坊に、ということになる。つまりそのときから、それぞれの人は、自分の人生を、適切な時期からやりなおす。 仮にあなたが、そのとんでもない悪人、つまり凶悪な犯罪者だったとしよう。するとあなたは天国へ入ったとたん、赤ん坊になる。まだ目の視線も定まらない、赤ん坊である。 その赤ん坊の状態から、その天国で、育てられる。天使のような慈愛に満ちた両親と、家族に包まれて、育てられる。 あるいはあなたが、小ずるい詐欺師であったとしよう。するとあなたは天国へ入ったとたん、乳幼児になる。やっとヨチヨチ歩き始めた乳幼児である。で、そのときも、あなたは、天使のような慈愛に満ちた両親と家族に包まれて、育てられる。 わかりやすく言えば、現世で、どんな悪人であっても、もう一度、新しくあなたは、天国で育てなおされるということ。つまり生まれながらの悪人はいない。生まれたあとの、育てられた環境や教育によって、悪人は悪人になっていく。その人自身には、責任は、ない。そのことは、生まれたばかりの赤ん坊を見れば、わかる。赤ん坊に、善人も悪人もいない。 善人になるか、悪人になるかは、運と確率の問題。波にうまくのった人は、善人になり、のれなかった人は、ズルズルと悪人になっていく。 天国は、それまでに寛容にできている。またそうであるから、天国という。仮にもし天国が、長生きをしたジジババ様だけの世界になってしまったら、何と、味気なく、つまらないものになってしまうことか。あるいは頭のボケた、ジジババ様ばかりになったら、もっとつまらない。 だから天国には、実際には、いろいろな年代の人たちがいる。赤ん坊もいれば、少年、少女もいる。もちろん、おとなもいる。もう一つ、例をあげて考えてみよう。 ある男性は、ふとしたきっかけで暴力団に入った。そこで貸し金の取り立てをするようになった。もしそんな男性でも、運とチャンスに恵まれていたら、そこまで心をゆがめることはなかっただろう。子どものころ、その男性の両親は離婚。そのまま多額の借金を踏み倒して、どこかへ蒸発してしまった。つまりそのとき、暴力団に入るかもしれないという素地が、その男性にできてしまった。 その男性は、最終的には銀行強盗をし、ピストルを撃ちまわしたところで、警官に射殺されてしまった。そしてそのあと、天国へやってきた。 しかしだれが、その男性を責めることができるだろうか。もしその男性が、望ましい環境の中で、あるべき両親の慈愛を受け、幸福に育てられたとしたら、そういう事件は、起こさなかったはず。もし神や仏が、その男性を地獄へ落すと言ったら、私は、こう言って抗議してやる。「その男性には、罪はない」「その男性は、現世で、さんざんつらい思いやさみしい思いをした」「もうじゅうぶんではないか」と。 そこで、その男性は、天国では、赤ん坊の時代から、自分の人生をやりなおすことになる。もちろんそれまでの過去は、すべて記憶から消される。だからその男性は、なぜ自分が赤ん坊であるかということすら知らないまま、自愛に満ちた両親と家族の中で、育てられる。 こうして天国には、善人のみが、住むようになる。かつての悪人が、赤ん坊や、幼児の姿に変えて天国へ入ってくれば、天国の住人たちは、その赤ん坊や幼児の親を、自ら、買って出る。そしてその赤ん坊や、幼児を育てる。自分の子どものようにして育てる。 そしてこうして育てられた子どもたちは、やがて天国という場で、おとなになる。慈愛に満ちた、やさしくて親切な、おとなになる。高い道徳と理性、それに知性を兼ね備えた、おとなになる。 これが天国の、本当の姿である。だから俗世間でいうような、地獄など、ない。 ……ということを、逆に考えることはできないだろうか。つまりこの私たちの住む世界こそが、その天国である、と。そうすれば、ここでいう天国論が、ずっと現実味をおびてくる。 たとえば私は、今日も、年中児から中学3年生まで、教えた。教えながら、いろいろな話をした。もちろん勉強をみるのが私の仕事だから、それはそれで、きちんとした。 そういう子どもたちをながめていると、生まれながらの善人もいなければ、もちろん生まれながらの悪人もいないことが、よくわかる。教育だけですべてをカバーすることはできないが、しかし教育によるところも大きい。子どもが、悪人の道に入りそうになったら、その少し前から、その子どもの教育を、組たてなおす。つまり、こうしてこの世界を、善人で満たしていく。 そしてもしそれが、この世界でできるようになれば、この世界こそが、天国ということになる。私たちが最終的にめざす世界とは、そういう世界をいう。そしてそれこそが、まさにユートピアということになるのではないだろうか。実のところ、死んでからあとの世界については、私たちは、何もわからないのだから……。(付記) この天国論は、夢を見て、思いついた。数日前だが、私はこんな夢を見た。 私がある断崖絶壁の淵(ふち)にやってきたとき、そこに黒い、大きなドアがあった。みなにつられて中へ入ってみると、その中は、明るい広場になっていた。その広場のあちこちに、円陣をえがいて、多くの人たちが集まっていた。 みると、それぞれのグループが、ちょうどハイキングで食事でもしているかのように、円陣をえがき、みなが、幼児や子どもたちを囲んで笑っていた。 そこで私が、「ここはどこですか?」と聞くと、みなが、笑ってこう言った。「ここは天国です」と。 さらに私が、「あの子どもたちは、どういう子どもたちですか?」と聞くと、みなが、こう説明してくれた。「不幸な生活をした人たちを、もう一度、みんなで育てなおしてあげているのです」と。つまり、その子どもたちは、かつては、悪人だったというわけである。 おかしな夢だったが、その夢にヒントを得て、この天国論を書いてみた。つまり天国は、天国。天国しかない。あるのは、天国だけ。地獄など、あるはずもない。 (はやし浩司 天国論 天国と地獄)Hiroshi Hayashi+++++++++++Dec. 05+++++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(08)
●天下の大暴論(子ども知らずの教授たち) 「子どもにはナイフを持たせろ。親が子どもを信頼している証(あかし)として」と書いた、評論家がいた。あるいは「子どもとの絆(きずな)を深めるために、子どもを遊園地でわざと迷子にさせろ」「子どもにやる気を起こさせるためには、子どもを、2、3日、家から追い出してみればいい」「夫婦喧嘩は子どもに見せよ。意見の対立があることを教えるのに、よい機会だ」「命の尊さを教えるために、お墓参りをしたら、故人の遺骨を見せるとよい」と書いた、大学の教授がいる。ともに、日本を代表する(?)、著名な教育評論家であり、教授だ。 こういう暴論を書くと、本は売れる。またそういう暴論を書かないと、本は売れない。しかし子どもには、ナイフなど持たせるものではない。幼児教育の現場では、「マッチやカッターで、遊んではいけません」と教える。またわざと子どもを迷子にすれば、それが子どもにわかったとき、(わからなくても)、親子の信頼関係は、崩壊する。2、3日、家から追い出してみるとよいという考えにしても、実際には実行不可能だ。もしあなたの子どもが、半日いなくなったら、あなたはどうするだろうか。あなたは捜索願いだって出すかもしれない。さらに夫婦喧嘩など、子どもに見せるものではない。夫婦で哲学論争でもするなら、話は別だが、そんな夫婦がどこにいるだろうか。 さて「命の尊さ」だが、命の尊さは、たとえば身の回りの生き物を通して教える。故人の遺骨を見せるとは、何事か。私は死んでも、私の骨など、誰にも見せてほしくない。もし子どもに教えるとするなら、それは教えるのではなく、たとえばペットの死などを、ていねいに弔うことで教える。「死」があるから、「生」がある。「死の恐怖」があるから、「生きる喜び」がある。もしあなたがペットの死骸を紙でまるめて、ゴミ箱にポイと捨てるようなことがあれば、子どもは、「死」というものはそういうものだと思う。同時に「生」とはそういうものだと思う。が、もしあなたが死んだペットを、ていねいに弔い、その死を悲しめば、子どもは同時に、生きていることの尊さを学ぶ。そしてそれが命の尊さを学ぶということにつながる。 私はこういう評論家や教授は、実際には、子どもを教えていないのではないかと思う。もっとはっきり言えば、どこかの研究室の奥で、子どもの世界を想像しながら原稿を書くから、こういう原稿になる。が、世間は、こういう評論家や教授の意見をありがたがる。そして心のどこかでは「おかしい」と思いながらも、それに従ってしまう。 暴論は確かにおもしろいが、こと子育てに関する限り、この種の暴論にはじゅうぶん注意したほうがよい。子育てに王道はないし、近道もない。流行もないし、時代性もない。あるわけがない。人間は、何10万年もの間、子育てを繰り返してきたし、その子育てが、ここ10年や100年ぐらいで、質的に変化したと考えるほうがおかしい。要するに子育ても、常識の範囲ですればよいということになる。その常識があれば、子育てがゆがむということはない。(以上、01年記「子育て雑談」)(はやし浩司 暴論 教育の暴論)(付記)「子どもとの絆(きずな)を深めるために、子どもを遊園地でわざと迷子にさせろ」「子どもにやる気を起こさせるためには、子どもを、2、3日、家から追い出してみればいい」「夫婦喧嘩は子どもに見せよ。意見の対立があることを教えるのに、よい機会だ」「命の尊さを教えるために、お墓参りをしたら、故人の遺骨を見せるとよい」と書いた大学の教授がいたというのは、事実である。 最近でも、日本を代表する、教育(幼児教育)者として、別の新しい本を書いている。しかしその教授(現在は、元教授)の言っていることが、いかに暴論であるかは、ほんの少しだけ常識を働かせてみれば、わかるはず。しかしその本を読んだのがきっかけで、私も育児論を書く気になった。体中に充満した怒りを、抑えることができなくなった。恐らくその教授は、肩書きはともかくも、実際には、子どもを指導した経験がないのではないか。経験がほんの少しでもあれば、とても、そんな本は、書けない。また「子どもには、ナイフをもたせろ」(A新聞社刊行の小冊子)と書いた評論家は、そのあと、派手なパフォーマンスをいろいろしてみせた。が、その直後、中学校などで、ナイフ殺傷事件がつづくと、その評論家は、自説をいつの間にか、ひっこめてしまった。ときとして、こうした暴論が、社会をにぎわす。そのほうが、(受け)がよいからである。それを読む親たちは、じゅうぶん、注意したほうが、よい。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●学級崩壊の陰で(学校教育相対論) 「わしら昔は、学校へ行くのが楽しみだった。学校へ行けば、家の仕事はしなくてすんだから」と。引佐町(静岡県)で石材屋をしているK氏は、そう言う。私にも、それに似た覚えがある。たとえば学校の運動会や遠足が、何よりも楽しみだった。運動会には、巻き寿司を食べることができた。また当時は、学校で遠足に行くこと以外、旅行で町を出るということはまずなかった。学校で出される給食のほうが、家の食事より、ずっとおいしかった。 しかし今は違う。子どもにとっては、毎日が盆と正月のようなものだ。食べ物も豊富だし、家族旅行も、そのつど、している。学校の外には、おもしろいものが、山のようにある。つまり相対的に、学校の地位がさがった。と、同時に相対的に、学校がおもしろくなくなった。 幼稚園児とて例外ではない。少しでも作業っぽい学習をさせようものなら、すぐ「つまんナ~イ」とか、「もっと、おもしろいの、ナ~イ?」とか、言い出す。それでも無理に刺せようとすると、勝手に席を離れて、どこかへ行ってしまう。あるいはほかの子どもを巻き込んで、騒ぎ始める。最近の子どもは忍耐力がないとよく言われるが、ないと言えば、まったく、ない。 誤解がないように言っておくが、子どもの忍耐力は、いやなことをする力のことをいう。たとえば台所の生ゴミを手で始末できるとか、寒い夜に隣の家に回覧版を届けることができるとか。そういうことを平気でできる子どもを、忍耐力のある子どもという。一日中、サッカーをしているからといって、忍耐力のある子どもということにはならない。その子どもは好きなことをしているだけである。 こうした子どもたちを取り巻く環境の変化に対して、学校教育は、それに応えていない。旧態依然のまま、30年前、あるいは40年前の教育を繰り返している。子どもたちに「おもしろくない」とソッポを向かれても、「子どもたちのほうが、おかしい」と言わんばかりに、文部省も、そして学校の教師たちも、努力を怠ってきた。結果、これはあくまでも相対的な変化だが、学校教育がつまらないものになった。K氏の時代には、学校へ行くのが楽しかったが、今は反対だ。「明日は学校は休みです」と先生が言おうものなら、子どもたちは、大声で「バンザーイ!」と叫ぶ。学校が休みになることについて、それを悲しむ子どもなど、まず、いない。 これだけではないが、つまりほかにも、いろいろな要素がある。が、しかし私は、これが学級崩壊の大きな原因の一つだと思う。それは自由を知った小鳥を、再び籠の中に押しこめるようなものだ。押しこめれば押しこめたで、子どもたちにはストレスがたまる。そしてそのストレスが、形を変えて校内暴力やいじめに発展する。唯一、子どもをしめつける手段があるといえば、受験でおどすことだが、今はその神通力も消えつつある。 このままでは学校教育は、完全に崩壊する。あるいはその前に、学校の教師たちが皆、神経症か何かで倒れてしまう。現在、学校がかかえる問題は、それくらい根が深い。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) この原稿を書いたあと、「ゆとり教育」が叫ばれるようになり、「総合的な学習」の時間がもうけられるようになった。 学校教育も、質的に大きく変動し始めた。今は、その過渡期にあると考えてよい。もちろん失敗もあるだろうが、試行錯誤の段階と考えるべきではないか。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●進学塾VS親(殺伐とした人間関係) 進学塾の月謝は、平均して2万~2万5000円(月刊「私塾界」)。しかしこの額では、決してすまない。すまないことは、入塾してみると、わかる。入会金、教材費、光熱費、模擬テスト代、補講費などが、「万」単位で、次々とかかってくる。しかも支払いは、銀行振り込み。大半の進学塾は、そういう支払いをカモフラージュするためにか、「ガクヒ」という名目で引き落とす。親が通帳を見ても、学校の「学費」なのか、塾の「学費」なのかわからないしくみになっている。まだ、ある。どこの進学塾も、夏休みや冬休みの特訓を、定例コースにしている。そういう連絡は小さな文字で生徒に連絡し、お金は前もって自動的に引き落とす。親が、「特訓授業を申し込んだつもりはない」と抗議しても、あとの祭り。「今からではキャンセルできません」と言われるだけ。 こうした進学塾のやり方は、ほぼどこの塾でも同じ。……とまあ、こう書くと、進学塾の悪どさばかりが目立つが、もともと進学競争の底流では、人間のどす黒い欲望が渦巻いている。「他人を蹴落としてでも……」、あるいは、「他人に蹴落とされる前に……」と考えて、親は、子どもを進学塾にやる。進学塾はそういう親の心理を、たくみに利用して、それを金儲けにつなげる。現在ある進学塾の現実は、親と進学塾の、醜い闘いの結果ともいえる。塾経営者に言わせれば、「親なんて、信用できない」ということになるし、親に言わせれば、「塾は必要悪」ということになる。もともと良好な人間関係が育つ土壌など、どこにも、ない。 一方、塾には塾の存在意義があると説く人たちもいる。塾こそ、自由教育の砦であると説く人たちである。事実、すばらしい教育を実践している塾もあるには、ある。しかしそういう塾でも、「教育」と「受験指導」のジレンマの中で、もがき苦しんでいる。藤沢市在住の塾教師のI氏は、「塾教育は、矛盾と錯覚の連続だ」と結論づけている。矛盾というのは、今言った、ジレンマをさす。錯覚というのは、「大切でないものを、あたかも大切なもであると、思いこんでいること」だそうだ。具体的には、受験教育そのものをさす。 この進学塾業界も、かつてない不況に見舞われている。少子化に不況。それにエリートの凋落に見られる価値観の変動。それに中高一貫教育に見られる、制度の改革など。そういう中、したたかな進学塾は、対象学年を、より低年齢化させ、一方大学受験にまで触手をのばし始めている。金集めを、さらに巧妙化させている。親たちは、そういう事実を知りながら、「この時期だけだから」とあきらめる。進学塾は、さらにそれを逆手にとる。もうそこには、「教育」という概念は、どこにもない。商売、だ。I氏はこうつなげる。 「この世界では、経験など、一片の価値もありません。親に教育論を説いても無駄です。そもそもそういうものを期待していない。生徒集めのチラシにしても、4色を使ったカラフルで、豪華なものでないと、生徒は集まりません。そういう目でしか、教育をながめていないのですから」と。(以上、01年記「子育て雑談」)(はやし浩司 進学塾 受験競争 受験の弊害) (付記) この日本では、受験は避けては通れない。しかしやり方は、あるはず。そのやり方を考えることなく、子どもたちをただ、競走馬のようしにて競争させることが、本当に(教育)なのか。私たちは、もう一度、冷静に、考えなおしてみる必要がある。 たとえばアメリカでは、成績だけでは、有名な大学には入れない。そこで各学校や、指名された教師に、推薦権なるものが与えられる。その推薦を受けて、人格的にもすぐれた子どもが、その有名大学へと進学していく。 もちろんこの推薦権を濫用すれば、その推薦権が剥奪(はくだつ)されたりする。だから各学校は、こぞって真剣に、どの子どもを推薦するかを、独自の立場で検討する。 日本ではそれにかわるのが、内申書ということになる。が、その大前提として、教師自身に、子どもを見る目がなければならない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●教育も適当に!(やり過ぎは、かえって……?) 当初は喜んでくれた父母も、それが長く続くと、当たり前になる。そしてそれを前提として、父兄はものを考えるようになる。教育というのは、そういうものだが、問題はそのあとに起こる。やがて教師はその重圧と多忙から、ふつうの状態に戻ろうとする。しかし父母はそれを許してくれない。いろいろな例がある。 ある教師は子ども(小3男児)が、掛け算がまだ苦手なことを知って、毎日授業が終わると、その子どもを残して、九九を教えた。掛け算でつまづくと、割り算ができなくなり、この二つでつまづくと、その子どもは算数がまったくといってよいほど、できなくなる。 で、やっとのことで掛け算の九九を覚えたころには、割り算の授業は終わっていた。そこで今度はその教師は、割り算の特訓をしたが、やっとその割り算ができるようになったころには……、あとはこの繰り返し。こういうケースでは、子ども自身も、先生の努力を評価しない。子どもは先生の特訓を「バツ」ととらえる。「できないから、先生はぼくにバツを与えているのだ」と。適当にしておかないと、かえって子どもを苦しめることになる。 親は親で、掛け算ができるようになると、「もっと……」と、先生に期待する。そしてその期待が要求に変わり、要求に答えるのが、教師の努めだと考えるようになる。が、教師とて人間。聖人ではない。スーパーマンでもない。生徒といっても、30人もいる。できることにも限界がある。そこでそういう子どもから手を引こうとすると、親は、「何という教師だ!」となる。 以前、熱血教師という言葉がもてはやされた。武田T也が扮する、金P先生という人気番組があった。しかし教育に携わったことがある人なら、誰でもわかることだが、あれはドラマ。ピストルをふりかざして、バンバン撃ち合う、刑事ドラマの類だと思えばよい。あんなことは現実には、ありえない。もし金P先生のような先生がいたら、その先生はあっという間に、身も心もズタズタにされてしまう。現実の世界は、もっと毒々しい。 私も教師になりたてのころは、親のウソに、さんざん引き回された。すでによその幼稚園へ入園届けを出したあとに、「今の担任の指導についていけません。先生のほうから、クラス替えのことで、園長にお口添えいただけないでしょうか」と。こんなこともあった。 明らかに過保護児特有の症状を見せている子どもがいた。原因は、おばあちゃんだったが、その日は、たまたま母親が、迎えに来ていた。そこでその母親に、「少し、おばあちゃんから離したほうがいいですよ」と言ってしまった。が、この一言が、そのあと大問題になってしまった。 ほぼ一か月後、再び母親に会うと、母親は別人のようにやつれた形相をしていた。そしてこう言った。「先生、あれから大変だったのですよ。祖父母と別居か、さもなくば離婚かということになりまして、結局、祖父母も別居に同意してくれました」と。私の一言が、それまでくすぶり続けていた嫁・姑戦争に火をつけた形になってしまったが、こういうケースは日常茶飯事。適当にすますところはすます。教育には、そんな面も必要だ。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) それぞれの家庭には、外からは見えない、複雑な問題がある。100の家庭があれば、それぞれの家庭がかかえる問題は、100種類、ある。そういう家庭の中へ、独断と偏見だけで、一介の教師が、土足であがりこんでいってよいものか。私が見た、金P先生の番組の中には、金P先生が、その子どもの親と、その子どもの家で、酒を飲みながら、子どもの教育について論じあうシーンがあった。いかにもテレビドラマといった感じのシーンだったが、しかし現実には、そんなことはありえない。また、教師たるもの、そこまでしてはいけない。 教師の本分は、学校という場で、教育をすることである。その点、カナダでの学校教育は、徹底している。教師は、教室の中で、自分のする教育には、全責任を負う。しかし生徒が一歩、教室を出たら、何が起きても、それはもうその教師の責任ではない。そのため、学校側は、教師の住所はもちろん、電話番号すら、教えない。 日本の病院の中における、医療制度を思い浮かべてみればよい。医師が、それぞれの家庭にあがりこんで、健康について、患者と議論するなどということがありえるだろうか。もしそんなことをすれば、病院における医療行為そのものに、さしさわりが出るようになる。 今、学校の教師たちは、本当に、いそがしい。そのため、肝心の教育そのものが、おろそかになる傾向さえ見られる。が、だれも、それでよいとは、思わない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●受験に狂奔する親たち(学歴信仰の陰で) 「期末試験のころになると、お粥しかのどを通りません」と言った親がいた。「進学塾の光々とした明かりを見ただけで、頭の中にカッと血がのぼります」と言った親もいた。さらに「子どもが寝そべってテレビを見ていたりすると、それだけで子どもがダメになっていくようで、不安でなりません」と訴えた親もいた。自分の子どもが選別されていくというのは、親にとって恐怖以外、何物でもない。こういう親を、一体、誰が笑うことができるか。 ある親は子どもの塾通いのために、免許を取り、軽自動車まで買いそろえた。また別の親は、子どものテストで採点ミスがあったりすると、学校まで乗り込んでいって、それを訂正させていた。子どものために、子ども部屋を増築したり、コピー機を買い入れたりする親になると、いくらでもいる。ふつうは質素な生活をしていても、子どもの教育のこととなると、惜しみなくお金を使う親も多い。30万円もする英会話教材をそろえたり、40万円もする百科事典をそろえたりするなど。休みのたびに、外国へホームスティさせる親もいる。 念のために申し添えるなら、こういう親を、私は批判しているのではない。それぞれの親には、それぞれの思いというものがあり、その思いをこめて、親は、子どもを育てる。私のような立場の者が、とやかく言う問題ではない。教育の世界には、「内政不干渉」という大原則がある。しかも教育というのは、まさにその人の人生観そのもの。他人が「まちがっている」とか、「おかしい」などと言うほうが、まちがっている。 しかしこれだけは言える。自分の意思でそうしていると思っている人でも、結局はもっと大きな力によって動かされているに過ぎないということ。そしてその力とは何かと言えば、自分の心の奥底に潜む、無意識の意識であるということ。ある女の子(小5)は、首にお守りをさげていた。私が不用意にそれに手をかけ、「これは何?」と聞いたときのことである。その女の子はギャーッと、ものすごい声を出して私の手をはらいのけた。そしてこう言った。「汚(けが)れるから、よして!」と。私は「ごめん、ごめん」とあやまったが、その女の子をそうさせたのは、その無意識の意識である。つまりそれと同じことが、教育の世界でも起きている!私「あなたは、本当に自分の意思で、子どもに勉強をさせているのですか」親「私の意思です。勉強は必要だと考えるし、それを子どもにさせるのは、正しいことです」私「誰かにそう操られていると、考えたことはありませんか」親「ありません。あくまでも私の意思です」と。 私は同じような会話を、いつか、どこかで、カルト教団の信者としたことがある。彼らもまた、自分たちが絶対に正しいという信念のもと、自分の意思で動いていると主張してやまなかった。学歴信仰が信仰と言われるゆえんは、そこにある。 (以上、01年記「子育て雑談」)(はやし浩司 教育カルト 学歴信仰 教育のカルト性)(付記) 「私はカルトとは無縁」と思っている人でも、無数のカルト的信仰をもっている。その1つが、学歴信仰ということになる。が、ほとんどの親たちは、学歴信仰が何であるかもわからないまま、それを信仰している。信仰しているという自覚すら、ない。 さらに信仰であるがゆえに、その人から、そのカルト性を抜くのは、容易なことではない。中には、学歴そのものを、本尊か何かのように、大切にしている人もいる。そういう人から、学歴信仰を抜くと、かえってその人は、大混乱を起こす。精神不安になる人さえいる。その前に、猛反発する。私に向って、「あなたにとっては、他人の子どもだから、何とでも言える。自分の子どもに向って、同じことが言えるか!」と、食ってかかってきた父親さえいる。 私が、その子どもの父親に、「受験勉強はあきらめたほうがよい」とアドバイスしたときのことである。その子どもは、過負担が原因で、燃え尽きる一歩、手前にいた。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●恐るべき集団性(思考回路の形成) 80~90%の子ども(年長児から小2児)が、「ポケモン」にはまった(99年春)。その前は、やはり同じくらいの子どもが、「たまごっち」にはまった。この原稿を書いているとき(99年3月)には、「だんご3兄弟」という、たわいもない歌が、子どもたちの世界を支配し始めている。 私たちの時代にも、フラフープや、ダッコチャンが、流行したことがある。そういう時代を知っているから、今の時代だけが特殊だとは思わない。しかしどこか違う。私たちは流行にハマりながらも、流行は流行として、現実の世界との間に、一線を引いていた。……引くことができた。しかし今は、違う。子どもたちは流行にハマりながら、現実と空想の間の垣根をとっぱらってしまう。そして現実の世界に、空想、あるいは空想の世界に、現実を持ち込んでしまう。あるいは空想の世界に、逃げ込んでしまう。そういう子どもが少数派であれば、まだいい。互いにブレーキをかけることができる。しかしそれが全体となったとき、ブレーキをかける人間がいなくなってしまう。子どもたちは暴走するまま、仮想現実の世界に入り込んでしまう。 「超能力がほしい。そういう力があれば、ビルを吹き飛ばすことができる」と言った子ども(中1)がいた。そこで私が、「吹き飛ばしたいと思うのは、君の勝手だが、それが君の家だったら、どうするのだ」と聞くと、「ぼくの家は、だいじょうぶ。超能力で守るから」と。ずいぶんと身勝手な考え方だが、そう答える子どもは真剣だ。真剣にそういう「力」があることを、信じている。信じた上で、自分の論理を組み立てる。が、問題はここから始まる。 脳には思考回路というものがある。人間は自分の思考回路に従って、ものを考えるという傾向がある。たとえばかつて和歌山市で、「ヒ素中毒事件」というのがあった。誰が犯人かは知らないが、犯人は「ヒ素でものごとを解決する」という手法を見につけた人物であることには、まちがいない。ヒ素と遠い距離にある人には、想像もつかない。が、その犯人は、ヒ素と、近い距離にあった。……と思う。ほかにたとえば私は物を書くのが仕事だから、何か問題があれば、文を書くことによって解決しようとする。つまりそれぞれ自分の思考回路に従っているにすぎない。 一度、仮想現実の世界でものごとを考えるくせのついた子どもは、以後、何かにつけて、その思考回路に沿ってものごとを考えようとする。あるいは問題を解決しようとする。これがこわい。たとえば幼児期に論理的なものの考え方を見つけた子どもは、ものの考え方が論理的になる。そうでない子どもは、そうでない。つまりこの時期に、仮想現実の世界でものごとを考えるくせのついた子どもは、以後、何かにつけて、そういう世界でものごとを考えようとする。そしてそれが、いつカルト(狂信)へと発展するかもしれない。 私は子どもたちの流行を見ながら、それを心から心配している。(以上、01年記「子育て雑談」) (付記) この日本では、テレビゲームを批評したり、批判したりすると、たいへんなことになる。猛烈な抗議の嵐がわき起こる。珍現象といえば、珍現象。しかも抗議してくるのは、20代を中心とした若者たちである。 ゲームの世界にハマっている若者たちにすれば、そのゲームが批評されたり、批判されたりするということは、自分を否定されるのと同じということになる(?)。だから猛烈に反発する(?)。私のほうは、親切心で、「ゲームには、あぶない部分もありますから、注意したほうがいいですよ」「とくに子どもに与えるゲームには、注意したほうがいいですよ」と言っているだけである。が、それに対して、反発とは! 私の息子の友人などは、ゲームにはまりすぎて(?)、現在、おかしくなってしまった青年すらいる。精神病院に入退院を繰りかえしながら、もう3か月になるという。そういう事実があることも、忘れてはいけない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●国家論(よき家庭人) 欧米の子育ての柱は、「自立したよき家庭人を作る」こと。このことについては、もう何度も書いたが、「家庭人」と言うと、日本人は、すぐ「小市民的な生き方」を連想する。しかし家庭人イコール、小市民ではない。 たとえば戦争が起きたとする。そして他国が日本を侵略してきたとする。そのとき日本人は、「国のために戦う」と言うかもしれない。しかし欧米人は、「家族を守るために戦う」と言う。あのヘミングウェイの「誰がために鐘は鳴る」でも、最後のシーンの中で、主人公のアメリカ人は、「(国のためではなく)、マリアのためになら死ねる」と叫んで、機関銃を撃ち続ける。 「国」という言葉が出たので、もう少しつけ加えるなら、日本人は「国があっての国民」と考える。一方、欧米人は、「家族を守るために、その集合体としての国がある」と考える。もう少し具体的には、戦前の日本では、「国」というのは、「天皇」をさしていた。(今も、そう考えている人は多い。)つまり私たち国民は、あくまでも天皇の臣下に過ぎない、と。しかし欧米人にとっては、国というのは、あくまでも一つの単位に過ぎない。オーストラリアの友人とこんな会話をしたことがある。「君たちは北からインドネシア軍が攻めてきたら、どうするか」と聞いたときのことである。彼はこう言った。「故郷のスコットランドへ家族を連れて逃げる」と。そこで「国を守らないのか」と聞くと、「オーストラリア人が横一列になって手をつないでも、オーストラリアの端から端まで、カバーできない。どうやって守ることができるのか」と。彼らが国を意識するとすれば、それは思い出のしみこんだ国土をさす。日本人のように、抽象的な概念としての「国」を想定しない。 こうした国民意識の違いは、そのまま教育の場にも反映される。日本は明治以来、「国(=天皇)のための国民づくり」が、教育の柱になっている。今もそうだ。国が栄えれば、国民も自動的に豊かになれる。あるいは企業が栄えれば、社員も自動的に豊かになれる。宗教団体の中にも、そう考える教団は多い。教団が栄えれば、信者も自動的に幸福になれる、と。さらに県レベル、市町村レベルでも、そう考える人も多い。つまり教育は、常にそういう視点、言いかえるなら全体主義的な視点で、子どもをとらえてきたし、今もとらえている。しかし、こんな考え方が、21世紀に通用するはずがない。 「よき家庭人」というのは、まさに個人主義的な生き方そのものを象徴する。また子どもにそう教えたからといって、それは決して、子どもに「小さくまとまれ」と教えるのでもない。「よき家庭人」というのは、「まず自分を大切にせよ」と教えることをいう。そしてその視点で、社会を考え、国を考え、また社会や国がどうあるべきか考えよと教えることをいう。繰り返すが、国や社会があるから、あなたがいるのではない。あなたがいるから、国や社会がある。そういう視点の基本となるのが、ここでいう「自立したよき家庭人」という考え方なのである。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 家族主義を主張する人たちが、ここ5、6年の間に、急速にふえてきた。99年前後には、どんな調査をみても、30~40%だったのが、最近では、80%以上の人が、家族主義を唱えるようになった。日本人の意識が、革命的に変化しつつあることを示す。 考えてみれば、当然のこと。今までの出生主義、権威主義のほうが、まちがっている。幸福などというものは、遠くにあるのではない。私たちの身のまわりに、じっと息をひそめて、そこにある。それに私たちは、気がつき始めた。 そのため、これまた当然のように、「国」に対する考え方も、変わってくる。今までは、「国あっての民」と考えた。しかしこれからは、「民あっての国」と考える。つまり日本人も、やっと、民主主義の意味がわかるようになった。 こうした(流れ)に対して、もちろん抵抗勢力もある。旧態依然の考え方に、固執している人もいる。決して、年配の人たちばかりではない。が、ここで重要なことは、こうした(流れ)を、私たちは、守ることはあっても、決して、後退させてはならないということ。 国、民、そして国の基本法である憲法のあり方は、その結果として、自然に決まる。(はやし浩司 国家論 民主主義 民主主義論 家族主義)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●進学塾の合格発表(子どもは宣伝のダシ) 今年も新聞紙2面を使って、高校入学試験合格者の名前が、発表された。ただし新聞社自身がそうしたのではない。どこかの進学塾が、それをした。いわく「今年度、S塾出身の合格者」と。その下にはすぐ、「ここに名前をあげた子どもは、中途退会者を含まず。模擬試験だけを受けた人を含まず」とある。つまり「正規の(?)塾生の名前だけだ」と。その進学塾としては、精一杯の良心(?)を演出したつもりなのだろう。以前は、模擬試験だけに参加した子どもまで合格者に並べて、世間のひんしゅくを買った進学塾がたくさんあった。 しかし、こういうことが堂々とできるところに、問題がある。いくら言論や出版の自由があるとはいえ、そこには教育に携わる者の、一片の良識が感じられない。たとえば合格者名を発表するぐいらいなら、不合格者名も発表すべきでないか。あるいは、その人数だけでもいい。どこの病院が、治療成功者の名前など、新聞紙上で発表するだろうか。もう少し、身近な問題で考えてみよう。 仮にあなたに10人の生徒がいたとしよう。そしてそのうち、7人が合格し、3人が落ちたとしよう。そういうときあなたは合格した子どもに向かって、「よくやったね、おめでとう」と言うことはできても、祝賀会など開けるものではない。祝賀会など開けば、残りの3人がキズつくだけ。もともと受験指導というのは、一人の生徒を合格させれば、別のどこかで1人の生徒を不合格にさせるだけだ。その底辺では、毒々しい、人間の醜い欲望が渦巻いている。そういうことも考えると、ますます祝賀会など、できなくなる。 もし本当に合格者を祝いたいのなら、こっそりとすればいい。その進学塾がこうして、大々的に新聞紙上で、合格者の名前を発表するのには、もっと別の意図がある。つまり宣伝である。「うちの塾は、これだけの合格者を出している。もし受験を考えるなら、うちへ来い」と。わかりやすく言えば、名前を出された子どもは、宣伝のダシに使われたに過ぎない。ダシになる子どもも子どもだが、そういうふうに子どもをダシにしながら、みじんも恥じない進学塾も進学塾だ。そうまでして、お金を稼ぎたいのか! まだある。進学塾は、A高校、S高校など、静岡県下の主だった、進学高の合格者だけを発表していたが、こういう形で、世間が必死になって忘れようとしている高校の序列を見せつけている。こういう高校を受験して不合格になった子どももかわいそうだが、そういう序列を見せつけられて、不愉快に感じている親や子どもは、その10倍はいる。進学塾にとっては、序列の低い高校など、高校ではないのだ。まだある。こうして進学校に入り、名前を出してもらった子どもは喜びながら、ゆがんだエリート意識を植えつけられる。「ぼくたちは、ほかの人間とは違うのだ」と。皆が皆、そうなるとは思わないが、子どもがそうなる危険性は高い。 どこをどう考えても、そんなわけで、こういう進学塾の合格者発表は、異常である。こういう宣伝がなくなったとき、日本の教育は正常になる。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 4年前には、かなり過激なことを書いていた……と、自分でも、そう思う。しかし進学塾のあくどさは、私自身も20代のころ、その進学塾で講師をしていたことがあるので、よく知っている。で、その当時の印象があまりにもよくなかったので、今でも、その印象を、心からぬぐい去ることができない。 しかし今では、ふつうの私立高校などが、進学塾から講師を招いて、教育指導を受ける時代になった。つまり高校自体が、進学塾化している。 しかしここで誤解していけないことは、進学塾があるから進学競争が過熱しているのではないということ。それを求める親や子どもたちがいるから、過熱する。そしてなぜ過熱するかといえば、そこに不公平社会があるからである。親たちは、日々の生活をとおして、その不公平さを、肌で感じている。 そのことは今の中国をみれば、わかる。拡大する貧富の格差の中で、進学競争は、今の今も、過熱の一途をたどっている。つまりこの不公平社会が是正されないかぎり、進学競争もまた、是正されない。 もちろん努力した人や、がんばった人たちが、それなりによい生活をするのは、当然である。しかし今のこの日本では、そうではない。ないことは、あなたの周囲を見れば、わかる。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●去り際の美学(わだかまりをつくらず) 教育には入り口と出口がある。学校でいえば、入学式と卒業式がある。この二つの行事がいかに大切なものであるか、それは教育をしてみると、わかる。まず入学式だが、そこで教師が生徒や父母に与える、第一印象は、その後の教育のあり方全般にわたって、大きな影響を与える。反対にこのときに「わだかまり」をつくると、それを取り除くのに、何倍もの努力とエネルギーを、必要とする。 もう一つは卒業式だ。この卒業式のやり方をまちがえると、これまた大きな「わだかまり」をつくってしまう。「どうせ別れるのだから、どうでもいいではないか」と思う人がいるかもしれないが、そうはいかない。不愉快な別れ方をすると、自分の人生そのものを無駄にしたような感じてしまう。もともと教師というのは、どんな立場の教師であれ、自分の時間を切り売りしているようなところがある。仮に4年間、教えた子どもがいたとしよう。そうすると教師というのは、「ああ、自分の人生の20分の1は、この子どもとともに過ごしたのだ」と考える。 これは教師側の意見だが、しかし問題は、父母のほうにある。いくら教師側がそう思っていても、父母の中には、机を蹴っ飛ばすようにして去っていく人がいる。それぞれ、いろいろな思いがあってそうするのだろうが、しかしこういう別れ方は、その後の人間関係を完全に破壊する。ある塾の教師はこう言った。「何が頭へ来るかといってですね、小さな紙切れ一枚、あるいは電話一本で、『やめます』と言ってくるケースですよ」と。「中には、月末の最後の授業のあと、つかつかと私のところへやってきて、『今日でやめます』と言ってくる子どももいます。まだある。『今度、B塾へ行くことになったけど、そちらがおもしろくなかったら、また戻ってきます』と言うのもいる」と。塾教師にとっては、「やめる」というのは、「クビを切られる」ことと同じである。それが親にはわからない。親にとっては塾というのは、どこまでも自動販売機。それに近い存在。私も「形」は、塾という形で子どもの指導をしているから、その教師の気持ちはよく理解できる。 昔から「初めよければ、終わりよし。終わりがよければ、すべてよし」と言う。私の場合、相手が幼児だから、よけいにそうなのだろうが、100人教えて、10年後に連絡を取り合っている生徒は、1人ぐらいなものではないか。20年後となると、さらに少ない。もちろん連絡を取り合っていないからといって、人間関係が消えたというわけではない。最近では、教え子たちが、息子や娘を連れて、私のところへ来てくれる。 さて私の場合だが、去り際の美学というのを、常に考えている。いくら頭にきても、あるいは内心では不愉快に思っていても、きれいに別れるようにしている。人生は長いようで短い。人の出会いも、多いようで少ない。こちらにもいろいろな「思い」はあるが、別れたとたん、その子どものことはすべて、忘れるようにしている。そういう形で、自分の心を整理したり、あるいは掃除したりして、また次の子どもを迎えるようにしている。 (以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 私も若いころは、紙切れ一枚でやめていく生徒がいたりすると、がく然とした。今でもそういう生徒がいないわけではない。それに今でも、そういう気持、つまりがく然とする気持ちが、消えたわけではない。 が、この世界はそういう世界であると、ずいぶんと前に、割り切った。不愉快な思いをするだけ損だし、不愉快な思いをしたところで、その生徒がもどってくるわけではない。だから不愉快な思いをするといっても、その瞬間だけ。あとは忘れる。何もかも忘れる。その生徒の思い出も、名前も。つまりそうして、私は、自分の心を守る。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●医学志願(理想と現実) A高校二年の担任が、こう言った。「うちの生徒のうち、20人が、医学部をめざしている」と。20人といえば、約50%弱ということになる。実は私の三男もそうだったので、ある日こう言った。「本当になりたいと思うなら、E病院へ行って、その二階の待合室で、一日を過ごしてみろ」と。あそこは消毒薬と悪臭、それに患者の体臭がプンプンと臭う。廊下にポタポタと血が落ちていることもあるし、ベッドの上で、で、ゲーゲーと吐いている人もいる。「そういうところでもよかったら、医者になれ」と。 一方、日本では今、おかしなことが起きている。静岡県は豊かな県だからあまり目立たないが、鳥取県や島根県へ行ってみると、それがよくわかる。さびれた寒村や町の中で、病院や医院だけが、やたらと目立つ。虫歯だらけの口の中に、ところどころ金歯があるようなもの。立派な建物と言えば、病院や医院だけ。それらが周囲の建物とは不釣あいなほどに、目立つ。言うまでもなく、それだけ国によって手厚く保護されているためである。 こういう現実を見せつけられると、誰しも、医者になりたいと思う。「医者は儲かる」と。実際、医者は高額な所得を手にしている。そういう部分だけを見ると、不公平な感じがするが、では、本当にいい仕事なのかどうかと言えば、疑わしい。世の中には、(汚い・きつい・臭い)という三Kの仕事があるというが、医者の仕事は、まさにその三K。そういう職場に、優秀な人材を集めようと思えば、待遇面で優遇するしかない。要はバランスの問題だが、それでもなおかつ、医者には魅力があるらしい。それが冒頭で述べた、「50%弱」である。私「お金が儲かるから医者になりたいと思うと、まちがえるぞ」子「そうではないけど」私「世の中には、世間の評判とはまったく違うが、すばらしい仕事はいくらでもある」子「たとえば……」私「ぼくは幼児を教えているが、これほどすばらしい仕事はないと思う。子どもは健康だし、純粋だ。生きる力が満ち溢れている」子「でも……」私「でも、何だ?」子「みんなが笑う……」私「どうして笑う? あのタレント業にしても、ぼくたちが子どものころは、役者と呼ばれて軽蔑されていた。が、今は違う。そういう目で職業を考えなくてはダメだ」 それから一年。結局私の息子は医学部をめざすのをやめた。今は、宇宙飛行士になりたいなどと言っているが、それはあくまでも夢。宇宙飛行士だって、命がけだ。私などたった一度、飛行機事故に遭遇しただけで、以後、飛行機恐怖症になってしまった。現実はそんなに甘くない。そうそう戦時中は、医学部はどこも定員割れをしていたそうだ。今から思うと、信じられないような話だが、事実は事実だ。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) その三男だが、自分の入った大学がどうも肌にあわなかったらしい。そこである日、突然、「ぼくは、パイロットになる」と言い出した。 私は、内心では、当初は、迷った。しかし私は三男を支えるしかない。が、ただ一言、こう言った。「お前は、金メダルを捨てて、銅メダルを買うようなものだぞ。それでもいいのか」と。すると三男は、「ぼくはそうは思わない」と言った。 私の考え方のほうが、まちがっていた。 で、今は、そのパイロットになるべく、がんばっている。毎日三男のBLOGを読んでいるが、生き生きした文面を読むたびに、「これでよかった」と、自分に言い聞かせている。あとは、事故でも起こさないように願うだけ。親としてできることは、ここまで。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●一流大学は出たけれど……(ゆがんだエリート意識) こんなエピソードが、新聞に載っていた。ある東大の学生が、就職試験で落ちた。それについてその学生が、「どうして私をとらないのか」と聞いたら、その試験担当の社員はこう答えたという。「君は、もっとも一緒に仕事をしたくないタイプの人間だから」と。 学歴さえあれば何とかなる時代は、もう終わった。あるいは学歴をひけらかして生きる時代は、もう終わった。この私にもこんな経験がある。もう20年以上も前のことだが、私は小さな翻訳事務所を出していた。そこでのこと。時々、外部の人に仕事を頼んだことがあるが、4年制の英文科を出た人は、まったく役にたたなかった。むしろ外国で数年、遊んできた人のほうが、ずっと役にたった。実戦力もあった。通訳についても同じ。 こう書くからといって、教育を否定しているのではない。私が否定しているのは、立身出世主義のために利用される教育だ。学歴させ身につけておけば、社会的地位や名誉、さらには富を手にすることができるという考えだ。こういう考えで、教育が利用されたら、たまらない。 私の同年齢で、T大やK大を出た人が何人かいる。一緒に仕事をしてきた人も多い。たとえばあの出版社のS社にしてもG社にしても、東大や筑波大の社員がゴロゴロしている。大半がそうであると言っても過言ではない。ただ救いなのは、そういう人たちでも、ごくふつうの社員として、仕事をしているということだ。特別のエリート意識を感じさせる人はいない。世間を「下」に見ているということもない。大企業か中小企業かの違いを除けば、私の町にある会社の社員と、区別がつかない。 高い学歴があるなら、あるでいい。しかし人間は、その中身。その中身で決まる。そういう意味で、大学を卒業したら、知識や学力(学ぶ力)だけを残して、一度、学歴を捨ててみることが大切ではないか。あるいは学歴そのものを忘れてしまう。そして一度、裸になったところからスタートする。 日本のエリートは、エリートはエリートでも、何かが欠けている。冷たいというか、ドライというか、どこか人間味が薄い。ものごとをソツなく、合理的にできるが、万事、事務的。その理由をすべて受験勉強にもっていくことはできないが、私は、あの受験勉強が大きな影響を与えていると思う。勝てば勝ったで、へんなエリート意識をもつし、敗れれば敗れたで、へんな挫折感と劣等感を植えつけられる。どちらにころんでも、それは人間が本来もっているはずの、「やさしさ」とは、相容れないものだ。もちろん子どもたちには罪はないが、問題は子どもたちのCPU(中央演算装置)が狂っているため、子ども自身が自分の「狂い」に気がつかないことだ。それが本来の人間の姿であり、またそれが当然だと思いこんでしまう。そしてそのままそれを、次の世代に伝えてしまう。そして冒頭に述べたような大学生を作ってしまう。つまり「勉強ができれば、社会は自分を優遇すべきだ」という、実に鼻持ちならぬゆがんだ、エリート意識をもってしまう。 (以上、01年記「子育て雑談」) (付記) 中国には、「小皇帝」と呼ばれる子どもたちがいるそうだ。裕福な家庭に生まれ育ち、勉強しか、しない。勉強しか、できない。勉強だけがすべてで、家庭の中では、皇帝のように振る舞っている子どもたちである。 先日もそういう子どもがテレビ(NHK)で紹介されていたが、まさに「皇帝」といった感じだった。自分は学校から帰ってくると、デンとソファに座っているだけ。そこへ母親や父親が、かしづくようにして、お菓子や果物をとどける。 ……実にこっけいなシーンだったが、20年前、30年前には、この日本でも、同じようなシーンが、あちこちの家庭でも見られた。中国は、そういう点では、日本の20年、30年前を再現しているのかもしれない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●幼稚園児のかけ算(見かけの力) 幼稚園児でもかけ算の九九を、ペラペラとソラで言うことができる子どもがいる。同じように足し算や引き算を、スラスラすることができる子どもがいる。あるいは本をスラスラと読むことができる子どもや、漢字を読み書きできる子どもがいる。そういう子どもを見ると、「優秀な子ども」と思いがちだが、本当にそうか。私にはこんな経験がある。 ある日のこと。年長児になったばかりのTさんが、本をもってきて、それをスラスラと読んでみせた。そこで私は別の本を渡し、「これを読んでみてごらん」と言うと、Tさんは、その本もスラスラと読み始めた。私はTさんをほめたが、しかしすぐ、それがまちがいであることに気がついた。私が「どんな話だったの?」と聞くと、Tさんは、「わかんない」と。そこでさらに「クマさんはどこへ行ったのかな?」と聞くと、それも「わかんない」と。Tさんは、文字を音に変えていただけだった。 ついでに言うと、読みの深い子どもは、むしろ一文ずつ意味を考えながら読んだり、挿し絵を見て考えながら読む。子どもにとって大切な「力」というのは、そういう力のことをいう。が、親たちはそれがわからない。わからないから、いわゆる見かけの力でも、それが力だと思いこんでしまう。幼児ばかりではない。この傾向は大学へ入るまで続く。子(小5)「分数の割り算ができるよ」私「ほう、それはすごいね。それは小学6年生が、勉強するところだよ。どうやってやるの?」子「分数をひっくり返して、かければいい」私「なるほど。でもさ、どうしてそうすればいいの?」子「わかんない」 話を少し戻すが、計算力は訓練によって伸びる。できない子どもはできないが、しかしそうでないなら、訓練によって伸びる。少しずつでも毎日すれば、効果的だ。しかし計算力は計算力。それだけのものであって、それ以上のものではない。が、問題はここから始まる。多くの親は、そういう表面的な力(?)を見て、自分の子どもは算数が得意だと思う。そしてそれを前提にして、子どもの勉強を組み立てる。そして少しでもその力に陰りが見えたりすると、無理をする。あるいは新たな学習を強要する。そして一度こういう状態になると、親にも子どもにも、安らかな日々はもうない。山のようなワーク。転々と移り変わる教育方針。そしてお決まりの塾めぐり。 こういうケースでは、最終的に行きつくところまで行かないと、親は気づかない。子どもが多少できるようになればなったで、親の意識はさらに先へ行く。一度できたものの考え方、つまり子育ての筋道というのは、そんなに簡単に変えられるものではない。「小さいころは、もっとできた」「うちの子は、やればできるはず」「こんなはずは、ない。何かのまちがいだ」を繰り返しながら、行きつくところまで、行きつく。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 子どもに、見かけの力をつけることは、それほどむずかしいことではない。説明すると長くなるが、しかしそれをすると、今度は、子どもに、依存性ができてしまう。 家庭教育の柱は、「よき家庭人として、子どもを自立させること」だが、同じように、教育の柱は、「子どもの心に灯をともし、その能力を引き出すこと」。 そのためには、ある時期がきたら、子どもを自立させなければならない。「こんな先生に習うくらいなら、自分で勉強したほうが、まし」と、子どもが思うようになったら、しめたもの。そういう方向に、子どもを、誘導していく。 それに見かけの力は、いわばメッキのようなもの。やがてすぐはがれてしまう。子どもの本当の力は、子ども自身が、自ら自分の力を引き出そうとしたときに発揮される。時間はかかるが、そういう力を、ていねいに育てていく。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●ドラ息子(N君の場合) 生意気で、教師を教師と思わないような生徒がいる。態度もおうへいで、ふてぶてしい。そのくせわがまま。おとなの世界そのものを、なめきっている。こちらからあいさつをしても、「フン」と横を向いたりする。概してこのタイプの子どもは頭がいい。何かを教えようとしても、「そんなの知ってっらア」と、吐き捨てたりする。 その分、生活を楽しんでいるかと思いきや、不平、不満だらけ。何かにつけて、「たいくつだ」「つまらない」「もっと、おもしろいことはないか」「何かほしい」「何かしてよ」を繰り返す。口をとがらせて、露骨に不快感を表現することも多い。いわゆるドラ息子だが、N君(小三)も、そんなタイプの子どもだった。 両親は共働きだったが、同居している祖父母に、N君は溺愛された。恐らく幼児期においては、蝶よ花よとかわいがられ、何一つ家事の手伝いはしなかったのだろう。使った道具を片づけさせようとしても、両手を下へくるりと巻いて、それを見おろすだけ。片づけようという意識そのものが、ない。ほかの子どもの使った道具について、「一緒に片づけてよ」と指示しようものなら、「何で、ぼくがしなきゃア、いかんよオ!」と、大声で抗議したりする。 こういう生徒と対峙すると、相当気の長い教師でも、頭にくる。大のおとなが、どうしてこんな子どもを相手にしなければならないなかとさえ、考えたりする。いや、自分がなさけなくなる。「教育なんて、やっておられるかア!」という気分にすら、なる(失礼!)。 しかし問題はそのことではなく、親自身に、その自覚がまったくないことだ。親は自分の子どもしか見ていない。N君が一人息子だったこともある。教師というのは、それぞれの子どもを比較しながら、その子どもの位置づけをすることができるが、親にはそれができない。そういう「問題のある子」でありながらも、それに気づくことがない。せいぜい私が言えることは、「もっと家事を手伝わせなければいけない」という程度のことでしか、ない。が、それとて、この年齢になると、手遅れ。だから自然と口が、重くなる。 そのN君は、小学4年生になるとき、私の手を離れたが、彼の将来を予測することは、そんなに難しいことではない。このタイプの子どもはいくらでもいる。私も、何10例と経験してきた。で、その予測。まずこのタイプの子どもは、やがてすぐに家の中でも、手がつけられなくなる。親は、そういうわがままな態度に手を焼くが、体力的にも、もう追いつけない。「うるせエ!」とすごまれただけで、震えあがってしまう。そして親の期待と夢はことごとくつぶされ、結果的には、「人様に迷惑さえかけなければ……」というレベルまで、落ちる。勉強については、そこそこにはできるようになるが、あくまでも「そこそこ」。本人も、自尊心と現実のギャップで悩むのだろうが、しかし自分自身に原因を求めない。おとなになってからも、社会や世間、あるいは親を逆恨みしながら、不平、不満タラタラの人生を送る。要はそういう子どもにしないこと。そういうことを知ってもらいため、私はこの原稿を書いた。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 教えていて一番、虚しさを感ずるのは、いわゆる、ドラ娘、ドラ息子に接したときである。このタイプの子どもは、たとえば料理人が、丹精(たんせい)こめて作った料理を、食い散らすようなことを平気でする。いくらお金のためとはいえ、がまんするにも限度がある。 そこで私のばあいは、(つまりBW教室では)、小学生以上の子どもについては、紹介のある人以外は、入塾を認めていない。実際には、小学生になってから入ってくる子どもは、ほとんど、いない。 こうしたドラ息子、ドラ娘になるかどうかの分かれ道は、年中児から年長児にかけてある。つまりこの時期の指導が、きわめて重要。 で、今、この原稿を読みなおしながら、なぜN君はN君のようになってしまったかについて考えている。が、そのN君は、たしか、小学2、3年のときに、私のところにやってきたのではなかったか。決して責任のがれをするわけではないが、私のところへきたときには、すでに、手のほどこしようがないほどのドラ息子になっていた。 それにこのN君の話は、今からもう10年以上も前の話である。なぜ4年前に、そのN君のことを書いたのか、よくわからない。多分、何か、いやなことがあって、そのうさ晴らしのために、この原稿を書いたのだと思う。自分の生徒のことを、こうして悪く書くのは、私のやり方ではない。それに今、読みかえしても、どうも、あと味が悪い。 削除することも考えたが、これも、私の(一部)。このままこの原稿を、ここに残しておくことにする。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●「女」になる子どもたち(これも時代の流れ?) 女子の性体験は、16歳がピークだという。それはそれとして、その子どもがセックスを経験しているかどうかは、男の教師なら、すぐわかる。「男を見る目つき」そのものが、ほかの子どもと違う。ものの言い方や考え方が、「男」をなめた感じになる。「今度のテストは、がんばったか?」「フフフ、いいじゃん、どうでも……フフフ」と。 Tさん(中3)が、大きく変化したのは、中学2年の夏ごろだった。ある日爪を見ると、マニキュアをしたあとがついていた。眉にソリを入れ、しかもかすかだが口紅をしていることもわかった。Tさんは、明らかに「おとなの世界」で遊び始めていた。どういう形で遊んでいるかは、私にはわからなかったが、携帯電話を始終大切そうに持ち歩いていたから、そういう方面で遊んでいることは、察しがついた。 こう書くとTさんのことを、不良(?)と思う人がいるかもしれないが、そういうことはまったく、ない。頭もよかったし、勉強もまあまあできた。家庭もごくふつうだった。いや、両親が別々に外車を乗り回していたから、平均的な家庭よりもずっと裕福だったかもしれない。いつかTさんが、「おやじのマンション」と言ったのを覚えている。父親はマンション経営もしていた。そのTさん、性格も明るく、何かにつけて、大声でよく笑った。 が、この種の問題は、止めて止められるものではないし、親に言えば、かえってやっかいなことになってしまう。男の「カン」だけで、子どもの指導はできない。そこで私は何度かTさんに、アドバイスを試みた。「同年齢の男の子とつきあったら」と。しかしTさんは、同年齢の男子を、「ガキんちょ」と呼んだ上、「あんなガキんちょたち、つまんない」と。そしてこの傾向は、Tさんが中学3年生になるころには、もっと激しくなった。まさに遊びまくっているといった感じになった。もうそのころになると、筆箱の中の指輪類を隠そうともしなかった。私が「これは何だ?」と、指輪の一つをつまんで声をかけると、「いいじゃん」と、あやしげな目つきで、それを私の手からパッと取り返したりした。もしその場だけのやり取りを見た人がいたら、どこかのスナックか、バーでの男と女の会話だと思ったかもしれない。私自身がドキッとするほど、Tさんの目つきは「女」のそれになっていた。 こういうケースを、あなたならどう考えるだろうか。またどうTさんを、どう指導したらいいと考えるだろうか。あるいは、そもそも指導する必要があるのだろうか。ないのだろうか。男と女では、判断のしかたも違うだろう。ある人(女性)は、「親のほうから相談があるまで、放っておくしかないわね」と言った。また別の人(女性)は、「それも時代の流れでしょうか」と笑った。私は男だから、もう少しシビアな見方をするが、正直言って、まったくわからない。ただ言えることは、Tさんは今、高校2年生だが、今は何ごともなかったかのように、ごくふつうの学生として、学校に通っている、ということだ。いやいや、男と女の関係などというのは、もともとそういうものかもしれない。セックスを楽しむことを、悪と決めてかかるのも、正しくないのかもしれない。それぞれの子どもは、それぞれの方法で、おとなになっていく。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 少し前だが、道で、男子高校生の落としたサイフを拾ったことがある。中を見ると、その学生証のほかに、コンドームが2つ、入っていた。 それを見て、そのサイフを交番へ届けるのが、バカ臭くなった。それでそのサイフを、落ちていたところの近くにあった自動販売機の上に、のせた。 今は、そういう時代である。で、この話を、私の生徒(当時、女子高校生)にしたら、その生徒は、こう言った。 「先生、あのね、放課後の教室って、ラブホテルみたいよ」と。「学校の先生は、何も注意しないのか?」と聞くと、「だって、先生はこないもん」と。 こういう問題でカリカリする、私のほうが、おかしいということになる。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
最前線の子育て論byはやし浩司(07)
Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●ズケズケ言う子どもたち(教師の威厳はどこに?) 「先生、口、臭いから、あっち向いていてよ。ああ、臭い臭い」と言った子ども(小6女子)がいた。もともと多動性のある子どもだった。頭の回転はキリキリと早いが、一貫性がなく、ものの考え方が浅い。幼児のころは、無頓着、無遠慮、無関心などの特徴も見られた。小学校の高学年になってからは、症状も落ち着いてきたが、ズケズケとものを言うクセは残っていた。 それはそれとして、私はそう言われたとき、喜んでいいのか不愉快に思っていいのか、一瞬、迷った。そしてその子どもは、いい子なのか悪い子なのか、迷った。さらに私とよい関係にあるのかそうでないのか、迷った。あえて私の判断はここには書かないでおくので、皆さんで判断してほしい。ただ言えることは、こういうふうにものをズケズケと言う子どもが、ふえているということ。そしてそれを民主的になったと喜んでいいのか悪いのか、このところわからなくなってきたということだ。 口が悪いのは、しかたない。今時の子どもは皆そうで、先生に向かって、「ジジイ」とか「クソジジイ」と言う子どもは、いくらでもいる。冗談だとわかっているから、それほど気にならない。問題は、相手が気にしていること、あるいは気にしそうなことを、ズケズケと言う場合だ。しかもスレスレのことを言い、またそれを言い合うことを、親しみの表れと誤解しているような場合だ。どこかテレビの低俗番組のお笑いタレントのようだが、今は、そうでない子どもをさがすほうがむずかしい。 最近の子どもは、先生に対して、畏敬の念をなくしたとよく言われる。それはその通りだが、こういうとき子どもの側ばかりが問題になる。しかし教師の側にも問題がないのか。学校レベル、あるいは教育委員会レベルでもみ消される、教師によるハレンチ事件は、あとを断たない。授業にしても、参観用の授業と普通の授業が、天と地ほど違うことを、子どもたちなら皆、知っている。また教育、教育と言いながら、自分たちが選別されていることを、子どもたちは感じ取っている。しかもこの傾向は、高学年、さらに中学校になるほど、強くなる。ズケズケとものを言う子どもは、こういうスキ間をねらって生まれる。私「臭いか?」子「臭い」私「そうか。ありがとう。このところ、女房もそれを教えてくれなくてね。君のおかげで、恥をかかなくてすむ」子「もうかいているでしょ」私「そうだな。申し訳ない。これからも臭かったら、臭いと言ってよ。なおすから」 子「わかりゃ、イーの。わかりゃア」 私が子どものころは、そういうことを言いたくても言えなかった。回ってきた先生が、鼻クソをポタリと机の上に落としたこともある。しかし私は黙って、それをがまんするしかなかった。そういう時代がよかったのか悪かったのか、それも私にはわからない。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 管理能力という言葉がある。この管理能力には、行動の管理能力、精神の管理能力、情緒の管理能力などがある。 ここでいう「ズケズケ言う子ども」というのは、行動(言動)の管理能力に欠ける子どもということになる。言ってよいことと悪いことの判断にうとい子どもということになる。たとえば多動性のある子どもには、同時に、多弁性がよく見られる。このタイプの子どもは、相手の気持ちもかまわず、言いたいことを、そのまま口にする。そのため、それによって相手がキズつくということが、よくある。が、その一方で、こうした子どもには、ウラがない。つまりそれだけ、心の中が、わかりやすい。 教師と生徒の間ではともかくも、親子や兄弟の間では、言いたいことを言うが、信頼関係の原点である。それがないと、信頼関係そのものを、築くことができない。 そこで重要なことは、(言うべきことは)言う。しかし自分の心の中で処理できるような、(言わなくてもよいこと)は言わない。そういう判断を的確にするということ。またそういう判断のできる子どもにするということ。 ただし一言。「アッ、風が吹いた」「カーテンが揺れた」式の、底の浅い、軽薄な言動については、そのつど、たしなめること。(はやし浩司 子供の多弁性 多弁性 子どもの多弁性)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司 ●しつけの時期(だらしなくなる子ども) 4、5歳ごろに一度、決められたことに忠実になる時期がある。母親が花を切っていたりすると、「先生がねえ、お花、切っちゃダメって、言っていたよ」と。あるいは食事をしながらテレビを見ていたりすると、「パパは、この前、食べているときは、テレビを見てはダメと言ったじゃない」と。この時期をうまく利用すると、しつけがしやすい。しかしそれが「頂点」。この時期の過ごし方が悪いと、どういうわけだか、子どもはだらしなくなる。具体的には幼稚園児より、小学生。小学生より中学生のほうが、概して、だらしない。学校の周囲を見ても、一番空き缶やゴミが多いのが、中学校だ。 先日も街中を歩いていたら、5、6人の男子高校生が飲んだ空き缶を、道路へポイと捨てた。そこで私はこれ見よがしにその空き缶を拾って、近くのゴミ箱に入れてやった。すると高校生たちはすっとんきょうな声を張りあげて、「イーヤーミィ」と声を合わせた。また別の日。どこかの家のまん前で、犬に便をさせていた女子高校生がいたので、私が注意すると、こう言った。「ここ、アンタの家?」と。 理由は簡単だ。世間を知れば知るほど、まじめに生きるのがバカらしくなる。子どもたちは年齢とともに、世間を広げ、それを知る。善か悪かといえば、この世の中、悪のほうがずっと多い。そういう悪の中でうまく立ち回ることを、スレるというが、子どもたちは年齢とともに、ますますスレる。しかもこの傾向は都会ほど強い。そこで私は以前、こんな格言を考えたことがある。「子どもは社会の縮図」と。これは社会に4割の善があれば、子どもの中にも4割の善。社会に4割の悪があれば、子どもの中にも4割の悪が育つという意味だ。社会を是正しないおいて、どうして子どもを是正できるか。よい例が自然教育。おとなたちが一方でさんざん自然を破壊しておいて、子どもたちに向かって、「自然を大切にしましょう」は、ない。少し話はそれるが、私は禁煙運動を精力的にしてきたが、息子の一人がどこかで喫煙を覚えたのを知って、その運動はやめた。自分の息子が吸っているのに、他人に向かって、「タバコをやめましょう」は、ない。反論もあろうかと思うが、私はそう考えた。 一方、まじめな子どももいる。ある日一緒にバスを待っているとき、「ジュースを買って飲もうか」と声をかけたら、「私はこれから夕食を食べるから、いい」と言って、断った女の子(小4)がいた。そこで私は自分なりに、いつどのように子どもが分かれていくのか観察してみたことがある。子どもは、いつ頃からだらしなくなるか、と。その結果得た結論が、冒頭に書いた事実である。4、5歳ごろ、である。 この時期までにしつけをうまくして、それに合わせた思考回路をうまく作ってあげると、子どもはまじめになる。一方、その時期をだらしなく過ぎると、子どもはだらしなくなる。ほかにもいろいろな要因があるが、そういうことだ。そして一度だらしなくなってしまうと、なおすのが大変難しい。身についたシミのようなもので、なかなか落とせない。だからこそ、この時期のしつけが大切なのだ。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) ジュースを断った女の子については、よく覚えている。ただ、ここで(小4)と書いたが、(小3)だったかもしれない。名前を、Aさんと言った。 で、そのAさんと、それから10年くらいしてから、それについて話しあったことがある。そのときAさんは、オーストラリアの大学に留学していた。が、Aさんは、「覚えていません」と。「そんなことありましたア?」と。ケタケタと笑っていた。 そのAさんが、私にこんなことを頼んだ。「いつか結婚するとき、結婚式に来てくれますか?」と。私は、一も二もなく、「いいよ」とだけ、返事をした。つまり私は、Aさんを、子どものときから、全幅に信頼していた。その信頼感は、あの自動販売機の前でできたものだと思っている。 ただ残念なことに、Aさんは、そのままオーストラリアに居ついてしまった。今は、オーストラリア人の男性と結婚して、パースに住んでいるという。(はやし浩司 子どものしつけ まじめな子供 まじめな子ども)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●肩書き人間(悪しき学歴人間) 私のいとこの義父に、国の出先機関の長をしていたのがいる。死ぬまで、長の名札をぶらさげて生きていたような人で、本人が「自分は偉いのだ」と思うほど、世間は相手にしなかった。葬式から帰ってきた母は、こう言った。「あんなさみしい葬式はなかった」と。 老人が老人社会へ入るためには、過去の肩書きを捨てなければならない……らしい。過去の肩書きにこだわっていると、周囲の者が近づかない。恐れ多いからではなく、そういう人とつきあっていると、疲れるから。が、こういう人たちにはそれがわからない。どこへ行っても、「私は尊敬されるべきだ」というような態度をとる。 戦争をはさんで教育を受けた人たちというのは、とくにこの傾向が強い。「立派な社会人になる」ことイコール、善と、徹底的に叩きこまれている。ここで言う立派な社会人というのは、言うまでもなく「肩書きのある人間」をさす。あるいは「肩書きを見せただけで、相手がひれ伏す人間」をさす。 実際、この日本は肩書きのある人は、それだけで得をする。一方、肩書きのない人は、せっかくその力があっても、社会に埋もれてしまう。肩書きのある人は、それはそれでいいと思うかもしれないが、一方でそうでない人を、いかに虐げているか、それを忘れてはならない。仮にあなたはいいとしても、あなたの子どもはどうだろうか。あるいはあなたの孫はどうだろうか。あなたがもっているような肩書きを手にすることができるだろうか。 人間の価値は、肩書きではなく、何をしたかによって決まる。こんなわかりきったことが、この日本で住んで、生活しているとわからなくなる。先のいとこの義父も、同年齢の人と会うたびに、「あなたは何をしていましたか」と聞いていた。よほどそのことが気になるらしく、自分より立場が上だった人にはペコペコし、そうでない人に向かっては、胸を張った。年下の人に向かっても、少しでもできが悪そうに見えたりすると、「君は、算数が何点ぐらいだったかね」と聞いていた。あるいは「こんなのは、簡単な計算で解けるよ。こんなのもわからないのかね」と言ったりした。唯一の趣味といえば、新聞や雑誌への投書。毎日のようにせっこらせっこらと書いては、新聞社や雑誌社へ送っていた。たいてい自画自賛で、読むに耐えない文章だったが、私の母は「偉いもんだ」と言っては、その記事を人に見せていた。 その人はその人で、懸命に生きてきたのだろう。彼とてその時代の価値観に染まっただけだ。かく言う私だって、私の生きた時代の流れに染まっている。彼がまちがっているということにもならないし、私が正しいということにもならない。あるいは次の世代の流れが正しいということにもならない。ただ私の立場で言えることは、こうした悪しき肩書き人間は、世界では通用しないということ。それだけではないが、それも含めて、こういう過去の流れをここで止めなければならない。私のいとこの義父には悪いが、肩書きで自分の人生を見失ってはいけない。……と私は思う。(以上、01年記「子育て雑談」) (付記) 権威主義の人は、電話のかけ方をみればわかる。動物的なカンで(?)、相手が自分より(上)か(下)かを判断する。そしてそれに応じて、電話のかけ方が、まるでちがう。(上)の人には、ペコペコし、(下)の人には、威張った言い方をする。 こうした権威主義が家庭に入ると、親子関係そのものを破壊する。親にとっては居心地のよい世界かもしれないが、子どもにとっては、そうではない。その居心地の悪さが、親子の間に、キレツを入れる。 これからは親の権威だけで、子どもをしばる時代ではない。またそれでは、子どもを指導することはできない。(はやし浩司 権威主義 肩書き人間 肩書きで生きる人)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●超辛口教育論(子どもには本物を) 音程がズレたような、チャラチャラしたジャリ歌手の歌う歌を、「名曲だ」と思い込んで、CDやMDを聞き入っている若い人たちを見ると、「かわいそうだ」と思う。「あんな音楽しか知らないのか」と思ってしまう。が、我が身を降り返れば、そうばかりは言っておれない。私たちも中学生や高校生のときは、そういう歌手の歌う歌を、毎日のように聞いていた。 今朝もテレビのチャンネルを入れると、タレントカップルの破局を大げさに報道していた。見るからに知性のひとかけらも感じないようなカップルだが、そんなカップルの破局が、日本中のニュースになること自体、不思議なことだ。男のほうが名古屋駅を歩く様子が報道されたが、報道陣に混じって、若い女性たちがキャーキャーと、声を張りあげていたのが印象的だった。が、私たちだって、同じようなことをしていた。 子ども時代、なかんずく幼児期には、本物を見せておく。画家をしている知人にそのことを話すと、こう教えてくれた。「絵といっても、子どもを圧倒せんばかりの大きな絵がいい」と。食べ物も、飲み物もだ。最近の子どもたちは、おいしい食べ物はと聞くと、ファーストフードのハンバーグ。おいしい飲み物はと聞くと、自動販売機のジュースをあげる。しかしこうした食感覚にしても、いかに不自然なことか。ニセモノばかり見たり、聞いたり、食べたりしていると、子どもは、皆、そうなる。 となると、私たちの時代はどうだったのかということになる。私自身もニセモノばかり見て育った。いや、ニセモノしか、周囲になかった。当時はそういう時代だったように思う。5円で買うラムネにしても、10円で買う駄菓子にしても、味はついていたが、それだけのものでしかなかった。今から思うと、「どうしてあんなものばかり欲しがったのか」とさえ思う。 かく言う私も、高校時代に口ずさんだ歌謡曲を聞くと、たまらないほどの懐かしさを覚える。ただ私の場合、学生時代はずっと合唱団にいたし、その後も、ごく最近までパソコンミュージックが趣味で、自分で作曲したりして、より高度な(?)音楽を楽しむことができた。そういう視点で考えると、どこか損をしたような気分にもなる。人生は長いようで短いし、短いなら短いで、もっと本物に触れておけばよかったという気持ちだ。つまりニセモノに染まっていた時代の自分が、何となく一方で、時間を無駄にしていたようにしか、思えない。 さて、子どもたちはどうか。今、本物を見ているだろうか。あるいは本物とニセモノを見分ける力は育っているだろうか。私はこれについては疑問だ。「たまごっち」というゲームに夢中になっていても、小さな虫を見ただけで、キャーキャーと逃げ回る子どもはいくらでもいた。あるいは「たまごっち」をしている子どもの横で、「殺せ、殺せ!」とはやしたてている子どもはいくらでもいた。さらに「たまごっち」が終わったあと、本物の動物を育て始めたという話しは聞かない。果たしてこのままで、いいのだろうか。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 本物を、いつどうやって見せていくか……。しかし実際には、子どもたちは、親が見せるよりも先に、テレビや雑誌などによって、ニセモノをニセモノと見抜けないまま、それを本物と思いこんでしまう。 そこで大切なことは、「子どもに見せよう」「教えよう」と考えるのではなく、親自身が、自分で本物を見ることではないだろうか。日々の生活の中で、いつも本物だけを見て、それを評価する。またそういう目を養っておく。これは子どものためというより、あなた自身のためでもある。が、だからといって、子どもも本物を見るようになるとはかぎらない。イギリスの格言に、『水場に馬を連れていくことはできても、水を飲ませることはできない』というのがある。最終的に、子どもが自分の世界で、どういうものを見るかは、親の問題ではなく、子どもの問題ということになる。(はやし浩司 本物 本物を見せる)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●教育の裏の、人間ドラマ(女房が妊娠した!) ある日突然、一人の男が私の部屋に飛び込んできて、こう言った。「うちの女房が、妊娠した。どうしてくれる!」と。寝耳に水とは、まさにこのこと。私が驚いて戸惑っていると、その様子から察知したのか、男は急に態度をやわらげ、「すまん、すまん。カマだ」と。話をよく聞くと、こうだった。 私は「幼児教育は母親教育」という信念から、毎日のように母親教室を開いていた。しかしそれがよくなかった。その男の妻は、私の話を聞くたびに、家で「はやし先生が……」「はやし先生が……」と言うようになってしまった。夫であるその男には、あまり愉快なことではなかったらしい。で、そういう最中にその男と妻は、はげしい夫婦喧嘩をした。喧嘩をして、妻が家を飛び出してしまった。その男は、妻が私のところに逃げたに違いないと思った。冒頭の話は、そのときの続きである。 またこんなこともあった。ある日幼稚園の庭で園児を迎えていると、黒塗りの外車がスーッと止まった。そして中から細身の紳士が飛び出し、ツカツカと私のところへやってきて、「貴様が、はやしか!」と。ものすごい剣幕である。私が「そうです」と言うと、いきなり「このヤロウ!」と言って、数発、殴りかかってきた。避ける間もなかった。気がつくと私は、地面にたたきつけられていた。男はそのまま帰っていったが、私にはまったく身に覚えがなかった。かけつけたほかの先生たちが、「どうしたの?」「どうしたの?」と。私は、ポカンとするしかなかった。 すぐにその紳士が、A君という子ども(年長児)の父親であることがわかったが、そこで一人の年配の先生が、「A君と何があったか話してごらん」と。私はA君のことを話した。 「いやあ、A君がいつも忘れ物ばかりするから、昨日も電話して、もう少しけじめのある生活をしてくださいと言いました」と。するとその先生はパチンと手を叩いて、「それよ!」と言った。「けじめ」という言葉が悪かったのだ、と。A君の母親は、その男の愛人だった。何気なく使った言葉だが、その言葉が、A君の母親を大きくキズつけてしまっていた。 ほかにB君という子ども(年長児)が、C君という子どもにいじめられていたから、C君の母親に、それを注意したことがある。私は軽い気持ちで、「何か家庭で不満に思っていることがあるのではないですか」と言っただけなのだが、その父親が、名誉毀損だと騒ぎ始めた。そして何回か抗議の電話がかかってきたあと、私を裁判所へ訴えるとまで言い出した。結局この事件は、私が謝罪する形で決着したが、あと味の悪さだけは、いつまでも残った。 こうした事件を通して、私は多少なりとも、利口になった。毎日開いていた母親教室は、週一回にしたし、使う言葉も慎重になった。もう少し正直に言えば、子どもの教育のことで、出しゃばるのをやめた。相手から聞かれるまで言わないという姿勢をもつようになった。教育、教育と言いながら、その裏では、さまざまな人間のドラマが展開している。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 教育の世界には、『問われるまで、言うな』という大鉄則がある。わざわざ火中の栗を拾うようなことは、してはいけない、と。拾えば、大ヤケドをする。 先日も、ある小学校で、校長と、こんな会話をした。その校長のほうから、こう言った。「あの3年B組、金P先生という番組ね。あれほど、教育現場を混乱させている番組は、ありませんよ」と。 「つまり親たちは、ああいう番組を見て、金P先生のような先生こそが、理想の先生だと思いこんでしまう。そしてそれを現場の私たちに求めてきます。しかし実際には、教育は、そんな単純な仕事ではありません」と。 私も同感である。それはちょうど、ピストルをバンバンと撃ちあうようなシーンを見て、「刑事の仕事というのは、そういうもの」と思いこむのに似ている。現実には、ありえない。もっと言えば、教育の世界は、無数の欲望が複雑にからみ、ドロドロしている。家庭の事情も、千差万別。さらに子育てには、その親の人生観や哲学観がすべてからんでくる。 一介の教師の、人生観や哲学観だけで、解決できるほど、子どもの世界の問題は、単純ではない。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●短気な子ども(引き金は引かない) 短気な子ども、つまりすぐカッとなりやすい子どもというのは、確かにいる。しかしそういう表面的な症状にだまされてはいけない。どんな人でも、短気なときは短気だし、そうでないときは、そうでない。では、何がそうさせたり、そうさせなかったりするのか。 子どもたちを観察してみると、こんなことがわかる。子どもたちはカッとなるときは、ほぼ条件反射的にそうなるということ。何か気にさわることを言われたり、されたりすると、カッとなる。つまりある一定の分野で、いつも緊張感をもっている。そしてその緊張感を刺激されたとき、カッとなる。たとえばある子どもが、「明日の宿題がやっていない」と、心のどこかで思い悩んでいたとする。子どもはそのことを、心のわだかまりにしている。そういうとき、家族の誰かが「宿題はやったの?」と声をかけると、それが引き金となって、子どもはカッとなる。「うるさい!」と。 緊張感のない分野については、カッとなることはない。かなりはげしいことを言われても、子どもたちはそれを冗談ととらえる。心にまだ余裕があるからだ。わかりやすく言えば、短気な子どもはいつも短気というわけではないし、またそうでない子どもでも、痛いところに触れられるとカッとなる。 A子さん(年長児)は、母親が「ひらがなを書いてみようね」と言っただけで、別人のように急変し、そして暴れた。ふつうの暴れ方ではない。母親に向かって手当たり次第にものを投げつけた。 B君(小4)は、父親が何か疑いをかけるようなことを言うと、やはり急変した。「この貯金箱のお金のことだが……」と。B君は、それだけで「自分が(盗んだと)疑われた」と思ってしまった。父親はこう言った。「ふだんは静かで穏やかな様子なのですが、一度そういう状態になると、ピリピリとした雰囲気になります」と。 こうした緊張感は、親子の間、友だちどうしの間、さらには教師と子どもの関係にも生まれる。そしてそれが刺激されたとき、それぞれの立場で子どもは、カッとなる。ひどい場合には、キレる。 もっともこれだけで、子どもたちが「キレる」原因を、すべて説明することはできない。しかし大半の子どもたちが、「勉強」という言葉に強い反応を示すのも事実で、親が「勉強しなさい」と言っただけで、カッとなる子どもはいくらでもいる。つまりそれだけ「勉強」に対してわだかまりや、あるいは緊張感をもっているということになる。あるいはそれ以前の段階として、抑うつ感をためこむ。 子どもがカッとなったら、そんなわけで、子どもがどういう分野で、どういうように緊張感をもっているかを判断する。もしそこに何らかのわだかまりを感ずることができたら、そのわだかまりにはできるだけ、触れないようにする。要するに引き金を引かないようにする。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 情緒が不安定な子どもというのは、それだけいつも、心が緊張状態にあるとみる。その緊張状態にあるところに、不安や心配が入りこむと、その不安や心配を解消しようと、一気に、情緒が不安定になる。カッとなったり、グズッたりする。 だから「うちの子は、情緒が不安定だ」と感じたら、何が、その子どもの心を緊張させているかを、観察、判断する。(はやし浩司 情緒 子どもの情緒 子供の情緒 情緒不安 情緒不安定)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●ふえる睡眠障害(寝る前は興奮させない) 年長児の子どもたち、10人に聞いてみた。「君たちは、恐い夢を見るか」と。すると、その中で3人が、「見る!」と答えた。「死体の夢を見る」「ワニに食べられる夢を見る」「迷子になった夢を見る」「ロボットに追いかけられる夢を見る」「誰かに食べられる夢を見る」など。 この答には驚いた。私は幼児というのは、恐い夢を見ないものだとばかり思っていた。見るにしてもときどきで、しかも朝になれば忘れてしまうものだ、と。しかし子どもたちは、あたかもその朝見た夢であるかのように、ワイワイと言って、それを説明してくれた。 睡眠中というのは、本来、もっとも心身ともに、リラックスした状態になる。またそうでなければならない。特に子どもの世界ではそうで、もしそうでないというのなら、どこかに問題がある。 この話とは別に、睡眠障害になる子どもがふえている。「夜更かしする」「朝、起きられない」「夜中に起きる」「なかなか寝つかない」など。夜驚症(夜中に狂人のようになって、大声をあげたり、暴れたりする)や、夢中遊行(ねぼけてフラフラとさまよい歩く)になる子どももいる。わかりやすく言えば、静かに眠って、ぐっすり休んで、爽快な気分で朝を迎えることができない子どもがふえているということだ。私の実感では、約50%の子どもに、その傾向が見られる。恐い夢を見る子どもを含めたら、もっと多いかもしれない。 原因は、日中のストレスだとよく言われるが、私はもっと身近な問題にあると思う。これはあくまでも「思う」というレベルの話だが、その一つがテレビであり、テレビゲーム。 子どもにとっては、睡眠前の数時間には、特別の意味がある。特に年少の子どもほどそうで、この時間、子どもを興奮させたりすることは禁物。心を少しずつ落ち着かせ、やがて睡眠へと導いていく。少なくともごく最近まで、人間は過去数10万年間、そうしてきた。が、それが乱れた。子どもたちは寝る間際まで、テレビを見ている。テレビゲームをしている。しかしこの時間帯に興奮させれば、その睡眠そのものが乱される。根拠はないが、こんなことは常識だ。幼稚園児でも、平均して午後八時半前後には床につく。しかし平日でも、幼児向け番組は、午後5時~7時台に集中している。午後七時~九時台には、一応、おとな用とはなっているが、小学生でも見たがるような番組が、目白押しに並んでいる。こういうものを野放にしておいて、「うちの子どもは、なかなか寝なくて困る」は、ない。 子ども、特に幼児には、日没後は、静かな生活を大切にする。そして静かな眠りに入るための準備をさせる。そのために、一つの方法として、テレビのスイッチは切る。もちろんテレビゲームなど、言語道断。眠る間際まで、「やっつけろ!」「殺せ!」「倒せ!」と叫んでいて、どうして静かな眠りに入ることができるのか。ある子ども(小5男児)は、真夜中にガバッと起きて、テレビゲームをしていた(姉の話)。もちろんこういう症状が見られたら、即刻、子どもからゲームを遠ざけるようにする。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 私も、最近は、午後8、9時以後は、ビデオ類などを見ないようにしている。この時間帯に一度、脳ミソを興奮させると、そのまま、寝つかれなくなってしまう。そしてさらに一度、眠りそこねてしまうと、今度は、午前0時過ぎまで、眠れなくなってしまう。(時には、午前2、3時まで寝つかれないこともある。) 子どものばあいも、同じと考えてよいのでは……。とくに子どものばあいは、就眠儀式(ベッド・タイム・ゲーム)のあり方に注意する。子どもは、眠る前、毎晩、同じこと(儀式)を繰りかえす。そのしつけに失敗すると、睡眠不足を引き起こし、さまざまな症状を見せるようになる。(はやし浩司 子供の睡眠 睡眠不足 就眠儀式)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●塾ブルース(10%のニヒリズム) 塾を開くのに、認可も許可もいらない。届出も必要ないし、資格もいらない。もしあなたさえその気になれば、明日からだって塾は開ける。塾は通産省の職業区分では、サービス業になっている。 こう書くと、塾は簡単な商売だと思う人がいるかもしれない。事実その通りだが、それだけに競争もはげしい。毎年雨後の竹の子のように塾は生まれ、そしてつぶれていく。10周年記念ができる塾は、何割もない。さらに20周年、30周年記念ができる塾は、10パーセントもないのではないか。現在、ほとんどの個人塾はつぶれ、残っているのは、中、大手規模の進学塾か、チエーン化された塾だ。 塾は、通産省ではサービス業になっている。そのことは冒頭で述べたが、塾でしていることは、教育ではない。指導である。中に「教育だ」とがんばっている塾教師がいるが、がんばらなければならないところに無理がある。少なくとも世間は、教育機関とは認めていない。 その塾。毎年あちこちの私塾会に誘われて顔を出すが、酒が入り始めると、本音が出てくる。おもしろいのは、むしろこちらのほうだ。昼間は「新学力観の問題点とは……」と論じていたような教師でも、「塾教師なんて……」と話し始める。そういうところで取材した話をここで書くのも気が引けるが、たとえばこんなことを言う。「塾教師が教え子の結婚式に呼ばれることはまずないよ。いくら苦労した生徒でもね」とか、「中学が受かったとたん、ハイさよならね。あとは塾へ来たことそのものを、隠す」とか。 この世界には「10%のニヒリズム」という言葉がある。いくら「指導」に専念しても、全力投球はしない。全力投球すれば、キズつくのは、結局は塾教師。どんなに専念しても、最後の10%は自分のためにとっておく。生徒に裏切られても、キズつかないためだ。 もっとも10%のニヒリズムを意識する教師は、まだ誠実なほうだ。たいていの塾教師はもっとドライ。「生計のため」と、はっきりと割りきっている。むしろこういう塾のほうがわかりやすいし、今の世の中に受ける。手のこんだ料理よりも、ファーストフードのレストランの料理のほうがおいしいと思う人は、いくらでもいる。 おまけに塾教師には、当然と言えば当然だが、保障はまったくない。退職金もなければ、年金もない。30年勤めても、ハクなどつかない。明日病気になって倒れれば、それで塾はおしまい。収入もそれで途絶える。こういう世界から、学校の先生をながめると、本当に学校の先生は恵まれていると思う。いろいろたいへんだろうとは思うが、それでも恵まれている。そうそう学校の先生にそんなグチをぶつけた塾の教師がいる。そしたらその学校の先生は、こう言ったという。「くやしかったら、学校の教師になればよかったではないか」と。「私たちは教育に生きる。あんたたちは教育で生きる」(塾教師1氏談)とも。 一見気楽な商売(?)に見える塾の世界だが、もの悲しいブルースは、毎日のように聞こえてくる。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 本当に自由な教育というのは、「塾」でこそ、可能である。しかしその自由な教育をすれば、その塾は、あっという間につぶれる。 そこで本当に自由な教育をするためには、長い時間をかけて、塾教師は、コツコツと、信用と実績をつみあげるしかない。いきなり自由な教育、というのは、土台、ムリ。反対の立場で考えてみれば、それがわかる。 ある日いきなり、あなたの近所に塾ができた。自由な教育をするという。そういう塾に、あなたは、自分の子どもを預けるだろうか。預けることができるだろうか。子どもを預けるということは、親にとっても、それほどまでに覚悟のいることなのである。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●代償的過保護(自分のために子どもを愛する) 過保護は過保護だが、親の支配欲を満たすためだけの過保護を、代償的過保護という。いわば過保護モドキの過保護のことになるが、外見上は、一般の過保護とは区別がつきにくい。 ふつう過保護には、そうするだけの理由、つまり心配の「種」がある。病気ばかりしていたから、子どもを運動面や食事面で過保護にするなど。しかし代償的過保護には、それがない。このタイプの親は、「親に甘えてくれる子どもがいい子ども」と、とらえる傾向がある。つまり子どもを管理する一方、子どもには依存心をもたせる。そして結果として、子どもを自分の支配化に置く。Tさんも、そんなタイプの母親だった。Tさんは、こう言った。 「息子(27歳)の結婚相手は、私が選んであげます。ヘンな女にくっつかれると、財産を食いつぶされますから」と。そして息子が好きになった女性との結婚に猛反対して、それをつぶしてしまった。今でも息子の帰宅がちょっとでも遅れたりすると、それをくどくどと叱っている。 Tさんが恐れているのは、子どもの自立だった。自立して自分から去っていくことだった。こんなこともあった。息子が高校三年生のときである。息子が県外の大学に進学したいと言ったのに対して、Tさんは、反対。そして私のところへ来て、こう頼んだ。「先生のところへ来週にでも息子をよこしますから、よく説得してやってください。先生の言うことなら聞きますから」と。そして帰り際に、「今日、私がここへ来たことは内緒にしておいてくださいよ」と。 このタイプの親に共通しているのは、他人に心を許さないこと。自分の子どもすら信じていない。言いかえると、自己中心性が強く、わがまま。その上、気が小さく、おくびょう。「自分」というものがあるようで、どこにもない。Tさんも、いつも世間体を気にしていた。「もっと自分の世界を広くしないと」と、私は言いかけたが、やめた。Tさんは、そのとき、私よりも一〇歳も年上だった。 かつてアメリカの教育者が、日本人の子育て法を観察して、こう批判した。「日本人は、自分の子どもに依存心をもたせることに、あまりにも無関心過ぎる」と。つまり子どもに依存心をもたせながら、平気でいる、と。その結果かもしれないが、同年齢の子どもを比較しても、アメリカ人の子どもは日本人の子どもよりも、一回りおとなびて見える。反対に日本人の子どもは、幼稚っぽい。概して甘えん坊が多い。あの成人式にしても、大半の女の子は、親のスネをかじって、美しい着物を着ているという。成人したという自覚すらない。キャーキャーと式場で騒ぐだけ。 要は子育ての目標をどこに置くかという問題に帰結する。いろいろな考え方があると思うが、「子どもをよき家庭人として自立させる」ということであれば、こうした代償的過保護は、百害あって一利なし。子育ての大敵と考える。(以上、01年記「子育て雑談」)(はやし浩司 代償的過保護 代償的愛 真の愛)(付記) 同じような意味で、私は、よく「代償的愛」という言葉を使う。いわば愛もどきの愛。ニセの愛をいう。つまりは、親が自分の心のすき間(情緒不安、精神的欠陥)を埋めるために、子どもを自分の支配下において、溺愛することをいう。 これは一見、愛に見えるが、決して愛ではない。たとえて言うなら、ストーカーが見せる、身勝手な愛に似ている。相手の迷惑もかえりみず、その相手にしつこく、つきまとう。ストーカー行為を繰りかえす本人は、「愛しているから」と言うが、それは本来の愛とは、まったく異質のものである。 よくある例は、子どもの受験競争に狂奔する親。一見、子どものことを考えているようで、その実、子どものことは、何も、考えていない。だから代償的愛という。(はやし浩司 代償的愛 自分勝手な愛 身勝手な愛 溺愛 でき愛)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司・●親孝行の限界(育ててやったではないか) 親をだます子どもはいる。しかし世の中には、子どもをだます親もいる。だまして、子どもからお金を巻き上げる。そうでない人には信じられないような話だが、実際にはある。そういう親をもっている人に向かって、親孝行論を説いても、かえってその人を苦しめるだけだ。Hさん(40歳)も、その一人。 「就職して以来、給料の何割かを、実家の母に送ってきました。母はいつも、『あんたの代わりに貯金しておいてやるから』とか、『あんたのかわりに故郷を守ってやるから』と言っていました。『先祖を供養せよ』と言って、間接的に、お金を要求してくることもありました。しかしお金はすべて、自分のために使っていました」と。 さらに悲劇は続く。Hさんが父親から譲り受けた土地の権利書を、言葉巧みに取りあげ、そのまま他人に売却してしまった。「もともと死んだ父の土地でしたが、実家を新築するにあたって、私は2000万円、負担しました。そのお金と交換ということで、土地の権利書を受け取ったのです。権利書というのは、それです」と。 結果、親子の縁は切れた。ついで、親戚との縁も切れた。親戚の叔父や叔母は、表面的な様子だけを見て、「親不孝者!」とHさんを責めている。無論、Hさんも苦しんでいる。「しかし母親のことを悪く言うのは、もっとつらい」と。 子どもは親から生まれる。それは事実だが、子どもの側から見ると、自分が生まれてはじめて、親がわかるにすぎない。つまり子どもは親を選べない。このHさんのケースでは、Hさんの母親は自分の息子を、自分の所有物か何かのように考えているのがわかる。昔はこのタイプの親が多かった。しかし一方、子どもの側から見ると、「私は私」であって、決して親の所有物ではない。親は「産んでやったことを感謝せよ」とか、「育ててやったことを感謝せよ」と言う。「ここまで大きくしてやったではないか」とも言う。しかし子どもの側から見ると、そういう親のものの考え方は、重荷でしかない。 自分の子どもにいい子になってほしかったら、まず自分がそのいい子になって、手本を子どもに見せる。これが親孝行の基本だが、こういうHさんのようなケースを見聞きすると、私にはもう言葉がない。もう少し古い世代の人は、「それでも親は親だから、親に頭をさげるべきだ」と言う。しかしHさんという、一人の人間を中心に考えると、それもおかしい。Hさんもこう言う。「私も二人の娘を育てていますが、育ててやっているという意識はどこかにあっても、娘たちにはそれを言わないようにしています。それを言ったら、親として、おしまい。親として当然のことをしているだけです」と。 いろいろ考えてはいるが、これ以上のことは、私にはわからない。ただ言えることは、このHさんのケースを知って以来、私は安易に「親孝行」という言葉を使わなくなった。子育ても難しいが、親孝行も、それと同じくらい難しい。とくに子どもが成人するころになると、それがつくづくとわかるようになる。(以上、01年記「子育て雑談」) (付記) 少し前のこと。まだ電話による相談を受けつけていたときのこと。数日おきに、あれこれと電話をかけてくる母親がいた。 「今日は、学校に呼び出された」「おかげで、パートの仕事ができなかった」 「先日は、近所の看板を倒してしまった」「おかげで、その弁償をさせられた」 「今日は、学校から電話がかかってきて、給食費を請求された」などなど。 私はその電話を聞きながら、「その程度の問題なら、どこの家庭にもあるのになあ」と思っていた。しかしそれを口にすることはできない。その母親は母親なりに、真剣に悩んでいた。 が、ある日、気がついた。その母親は、子どものことをあれこれ問題にしているが、そうではない、と。つまり、その母親にとっては、子育てそのものが、苦痛なのだ。子育てがいやだから、あれこれ問題を自分で作って、それで悩んでいるだけ。あるいは結婚そのものに、問題があったのかもしれない。 つまり大もとに1つの問題があり、それがあれこれ姿を変えて、その母親を悩ませていた。……というような例は多い。 ここでいう「産んでやった」「育ててやった」と言う親も、そうである。どこかに犠牲的精神がともなうということは、すなわち、子育てがそれだけ苦痛であることを意味する。本来なら、親は、子どもにこう言わねばならないはず。 「おまえのおかげで、人生を楽しくすごすことができた。ありがとう」と。 それがあるべき、子育ての本来の姿ということになる。(はやし浩司 子育て 親の恩 恩着せがましい子育て)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●サトシ君(いじめ問題の陰で) サトシ君(中2)は、心のやさしい子どもだった。そういうこともあって、いつも皆に、いじめられていた。が、彼は決して、友だちを責めなかった。背中にチョークで、いっぱい落書きをされても、「ううん、いいんだよ、先生。何でもないよ。皆でふざけて遊んでいただけだよ」と言っていた。 そのサトシ君は、事情があって、祖父母の手で育てられていた。が、その祖父が脳梗塞で倒れた。倒れて伊豆(静岡県)にあるリハビリセンターへ入院した。これから先は、サトシ君の祖母から聞いた話だ。 祖父はサトシ君が毎週、見舞いに来てくれるのを待って、ひげを剃らなかった。サトシ君がひげを剃ってくれるのを、何よりも楽しみにしていたそうだ。そしてそれが終わると、祖父とサトシ君は、センターの北にある神社へお参りに行くことになっていたという。そこでのこと。帰る道すがら、祖父が、「お前はどんなことを祈ったか」と聞くと、サトシ君は、「高校に合格しますようにと祈った」と。それを聞いた祖父が怒って、「どうしてお前は、わしの病気が治るように祈らなかったか」と。そこでサトシ君はあわてて神社へ戻り、もう一度、祈りなおしたという。 この話を聞いて以来、私は彼を、尊敬の念をこめて、「サトシ君」で呼ぶようになった。とても呼び捨てにはできなかった。いろいろな子どもがいるが、実際には、サトシ君のような子どももいる。 今、いじめが問題になっている。しかしいじめられる子どもは、幸いである。心に大きな財産を蓄えることができる。一方、いじめる子どもは、大きく自分の心を削る。そしていつか、そのことで後悔するときがくる。世の中には、しっかりと人を見る人がいる。そういう人が、しかっりと判断する。愚かな人ばかりではない。サトシ君にしても、学校の先生には好かれ、浜松市内のK高校を卒業したあと、東京のK大学へと進んでいる。サトシ君は、見るからに人格が違っていた。 自分の子どもが、学校でいじめられているのを見るのは、つらいことだ。しかし問題は、いつどこで親が手を出し、いつどこで教師が手を出すかだ。いじめのない世界はないし、人はいじめられながら成長し、そしてたくましくなる。つらいが、親も教師も、耐えるところでは耐えないと、子どもがひ弱になってしまう。今はこういう時代だから、ちょっとした悪ふざけでも、「そら、いじめだ!」と、親は騒ぐ。が、こういう姿勢は、かえって子どもから自立心を奪う。もちろん陰湿ないじめや、限度を超えたいじめは別である。しかしそれ以前の範囲なら、一に様子を見て、二にがまん。三、四がなくて、五に相談。親や教師ができることといえば、せいぜい、子どもの訴えることに、とことん耳を傾けてやることでしかない。子どもの肩に手をかけ、「お前はがんばっているんだよ」と励ましてあげることでしかない。それは親や教師にとっては、とてもつらいことだが、親や教師にも、できることには限界がある。その限度の中で、じっと耐えるのも、 親や教師の務めではないかと、私は思う。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 人は、ドン底に落ちると、2つのタイプの人間に分かれる。そのときから、徹底した善人になるタイプと、徹底した悪人になるタイプである。どちらの道を選ぶかは、紙一重。 そこまで深刻な問題ではないにせよ、子どもの世界でも、同じようなことが起きる。いじめを受け、それをバネに、ここに書いたサトシ君のようになる子どもと、同じように、今度は反対に、いじめる側に回る子どもである。「いじめられる前に、いじめてやれ」という考え方である。 そういう意味では、いじめる側の子どもが、すべて「悪」とは言い切れない。(もちろんいじめは、悪いことだが……。)抑圧されたうっぷんが、長く蓄積されて、それがいじめに転化するということも、子どもの世界では、よくある。 それにいじめる側は、それを(いじめ)と認識していないケースも、多い。軽い遊びか、ふざけのつもりで、それをする。しかしいじめられる側にとっては、そうではない。ちょっとした相手の言動を、おおげさにとらえてしまう。そういうケースも、多い。 さらに「A君がいじめる」と言うから、学校の先生に相談して、A君を近くから排除してもらう。すると今度は、その子どもは、「B君がいじめる」と言い出す。そこでまた今度は、B君を近くから排除してもらう。が、つぎに今度は、その子どもは、「学校の先生がいじめる」と言い出したりする。そういうケースも、少なくない。 これを「ターゲットの移動」という。つまりその子どもは、もっと大きな心の問題をかかえていて、それが原因で、学校へ行きたくないだけである。それがわからないから、親や先生は、子どもの言うことに、振りまわされてしまう。そういうケースも、多い。 ここに(いじめの問題)のむずかしさがある。(はやし浩司 いじめ いじめの問題)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●教育の「陰」の部分(作られる私たち) 教育には教えて教える部分と、教えずして教える部分の二つがある。前者を「陽」の部分とするなら、後者は「陰」の部分ということになる。たとえばこの日本で教育を受けていると、都会へ出て、大企業に就職することが大切なことで、反対に、田舎に残り、農業をすることは、つまらないことだという意識を植えつけられてしまう。さらに集団の中で、肩書きをもち、名誉や地位を得ることは大切なことであり、反対に集団から離れて、一人で生きることは、変わり者のすることだという意識を植えつけられてしまう。これが教育の「陰」の部分であり、そういう意識が大きな流れとなって、子どもたちの将来像を形づくる。 こうした教育の「陰」の部分は、外国の教育と比べてみると、それがよくわかる。たとえば軍事政権が幅をきかせているような国では、当然のことながら、子どもたちは軍人になることイコール、理想の未来像ととらえる。戦前の日本を例にとるまでもない。マルコス政権下のフィリッピンもそうだったし、今のベトナムもそうだ。一方、オーストラリアでは、自然保護団体の職員の地位が、日本のそれとは比較にならないほど高いし、欧米では福祉団体の職員の地位が高い。この日本では、戦後、一貫して「金儲け」イコール、善という社会観が定着している。私たち団塊の世代は、就職先といえば、一にも、二にも、商社や銀行、あるいは大企業を考えた。 教育されるのは、子どもたちばかりではない。親もまたそうで、たとえば子どもが不登校を起こしたりすると、親ははげしい絶望感に襲われる。この日本では集団から離れることは、恐怖以外、何物でもない。しかしそういう集団性とて、教育の「陰」の部分に過ぎない。幼児のときから、幼稚園の先生は、こう言う。「(幼稚園を)休むと、遅れますから」と。かくして幼稚園や学校は、行かねばならないところという無意識の意識を植えつけられる。そういう子どもが親になり、それを代々繰り返すうちに、今の日本ができた。 問題は、いつどのような形で、その「陰」の部分に気づくか、だ。気づいた段階で、教育に対する考え方が、一変する。「私は私だ」と思っているあなただって、「作られた私」を、あなたの中に発見する。たとえば私の父は、「(天皇)陛下」という言葉を耳にしただけで、いつも体をブルブルと震わせていた。その父とて、結局は戦前の教育で、そのように「作られた」だけなのだ。 さて、あなたはどうだろうか。あなた自身を冷静にながめてみてほしい。あなたの中に巣くう、あなた自身の価値観を、ながめてみてほしい。あなたは今、子育てをしながら、どのような価値観をもっているだろうか。そしてそれは、あなた自身が自分で考えて手にした価値観なのだろうか。それとも、昔、いつかどこかで、植えつけられた価値観なのだろうか。ひょっとしたら、あなたが「私の価値観だ」と思っている価値観は、その「陰」の部分によって作られた価値観かもしれない。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) このところ、日本人の意識そのものが、大きく変わりつつある。旧来型の出世主義から、実力主義へ。それに権威主義も、音をたてて崩れ始めている。そういう意味では、ここに書いたことは、実情には、合わなくなっているかもしれない。あくまでも、参考に。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(06)
●教育の皮肉(教育の原点) 家庭教育では、子どもは使えば使うほど、いい子になる。忍耐力も育つし、生活力もつく。そしてその上、親の苦労のわかる子どもになる。 子どもは突き放せば突き放すほど、自立する。「あなたの人生だから、あなたはあなたで、勝手に生きなさい」という姿勢を、親がもてばもつほど、子どもはたくましくなる。 子どもに期待をしなければしないほど、子どもは親の期待を超えた子どもになる。「私が老人になっても、子どもたちにはめんどうをみてもらわない」と言う人がいるが、そういう人ほど、また子どもたちの愛を一身に集めている。 一方、家庭教育では、子どもは手をかければかけるほど、またお金をかければかけるほど、ドラ息子化する。生活がルーズになり、自分勝手になる。 子どもは溺愛すればするほど、わけのわからない子どもになってしまう。あるいは親に反発する。そうでなければ超マザコンタイプの子どもになってしまう。 子どもに期待をかければかけるほど、子どもはどんどんその期待からはずれ、親の望む方向とは別の方向へ進んでしまう。あるいは親の過剰期待の中で、子どもは窒息してしまう。 皮肉と言えば、これほど皮肉なことはない。親たちがよかれと思ってしていることが、かえって裏目、裏目に出てしまう。なぜか。私はその理由の一つとして、人間には本来、いじってもよい部分と、そうでない部分があるように思う。たとえば人間の自立に関する部分はいじってはいけないし、いじればいじるほど、子どもの自立は遅れる。つまりそういう部分は、人間が「教育」を意識する、ずっとはるか昔から人間に備わっていた「力」だと思う。庭にやってくるスズメにしても、実にたくましい。犬の目を盗んでは、ドッグフードを盗んでいく。 となると教育とは何か、ということになる。そこで一のヒントとして、スズメの話を続ける。このスズメは、山バトがやってきても、まったく逃げない。しかしモズがやってくると一斉に逃げ出す。モズは肉食だ。そこでスズメをよく観察してみると、「逃げる」という行動は、親から子へと代々教え継がれていることがわかる。親鳥が逃げ出すと、間髪を入れず、子スズメたちが逃げ出す。そしてやがて子スズメたちはモズがやってきたら、逃げるということを学習する。 わかりやすく言えば、教育とは、先人の知識や経験を、子どもたちに生きる武器として与えること、ということになる。またその視点を忘れて、教育はありえないし、またその視点からはずれた教育は教育ではありえない。たとえば歴史教育にしても、原爆の悲惨さを教えるのは教育であっても、○○年△△条約成立などという年号を子どもに暗記させるのは、歴史教育ではない。教育がそういう視点に立ちかえったとき、教育が本来どうあるべきかがわかるのではないだろうか。 家庭教育は、あくまでもその一部に過ぎない。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) 今、このエッセーを読みかえしてみても、「まったく、そのとおり」と思う。そういえば、冬になったというのに、ここ1、2年、そのモズが私の庭に来なくなった。どうでもよいことだが、ふと、今、そう思った。 また20年来つづけてきた、スズメの餌づけだが、それについては、今年から、やめた。鳥インフルエンザの問題もある。が、それ以上に、やってくるスズメの数が、あまりにも多くなりすぎた。昨年当たりは、数十羽ずつに分かれた群れが、ひっきりなしに私の庭にやってきていた。 朝早く、1~2キロの餌を庭にまいたり、餌台にのせるのだが、午前中には、それがきれいになくなってしまった。しかしこういう餌づけは、結局は、野鳥のためにはならないのでは……。野鳥が、人間に依存するようになり、野鳥が野鳥でなくなってしまう。 それがやっとわかった。それでやめた。私自身は鳥が大好きで、庭に鳥がいないと、さみしいのだが……。(はやし浩司 忍耐力 自立 子どもの自立 教育の原点 教育の目的)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●新学力観という、観点(役に立つ教育) 「地面に立てたポールを利用して、太陽の高度を調べるにはどうしたらよいか。図解して説明せよ」という問題がある。文部省が実施した「新学力テスト問題」の一つだが、中1年生での正解率は、たったの10・4%。しかしこんなことは、教育が始まる以前から、人間には常識だった。昔の人間は、皆、太陽の位置や影の長さで時刻を知った。今の子どもたちは、そんなことも知らないのかということにもなるし、裏を返せば、今の教育は一体、何を教えているのかということにもなる。 教育の基本は、「将来、子どもたちが生きていく上で、役にたつ知識や経験を、分け伝えること」ではないのか。そういう視点がないと、受験教育に代表されるように、教育がただ単なる点数稼ぎのための道具にされてしまう。もっと言えば、教育が人間選別の道具にされてしまう。ちなみに中学生にこう聞いてみればよい。「君たちは、なぜ勉強するか」と。大半の子どもたちは、こう答える。「高校へ入るため」「大学へ入るため」と。親にしてもしかり。勉強をしない子どもを叱るとき、「そんなことでは、いい大学へ入れないぞ」と叱ることはあっても、「将来、必要な知識が身につかないぞ」とは言わない。こうした教育がさらにいびつになると、幼稚園で掛け算の九九を暗記させたり、漢字の読み書きを教えたりするようになる。 一方、これは当然のことだが、子どもたちはその必要性を感じたとき、実に生き生きと自ら学習し始める。私はときどき、「お金儲けごっこ」をするが、そのときもそうだ。それはこうして遊ぶ。 まず子どもたち(年長児)に、紙で作ったお金を渡す。そしてそれで折り紙を買わせる。大小さまざまな大きさの折り紙があって、それぞれ値段が違う。子どもたちはその買った折り紙で、いろいろなものを作る。絵を描く子どももいる。で、それができたら、今度はこちら(教師)が、そのできたものを買いあげてあげる。じょうずにできたのは、高い値段で。そうでないのは、低い値段で。あとはこれを繰り返す。ときどき、ほかの子どもが作ったものを、別の子どもに売ってあげることもある。20円で買いあげたものを、40円で売りつけたりすると、子どもたちは「ずるい、ずるい」と言うが、「これが資本主義の原理だ」などと難しい言葉で言ってやると、たいてい静かになる。さらに慣れてくると、子どもたちどうしで、ものの売買をし始めるようになる。 こうした動機づけがあると、あとは放っておいても、子どもたちは自ら、足し算や引き算をするようになる。多い少ないの判断も、そして損得の判断もできるようになる。さらに「労働することの喜び」もわかるようになる。 文部省の新学力観では、「知識の獲得量ではなく、自分で考え、表現する力を重視する」というもの。私はこれには大賛成だが、ただし一言。こういう指導が全国一律になされるところにも、問題がある。皆が同じように自分で考え、表現するようになったら、それこそ、この日本はどうなる。そんなことも頭に入れておいてほしい。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) 日本の教育は、全体としてみると、将来、その道の学者をめざす子どもたちにとっては、きわめて効率よく、かつ体系的にできている。理由は、わかりきっている。教科書が、その道の学者たちによって、作られているからである。 たとえば英語という科目にしても、将来、英語の文法学者になるには、たいへん効率よく、体系的にできている。(最近は、こうした考え方が、大きく変わりつつあるが……。) しかし今、将来、学者になる、あるいはなりたいと言っている子どもは、いったい、何%いるのか? また日本の教育には、「子どもたちに実用的なことを教えるのは、悪」と考えているフシすら、見受けられる。しかしどうして実用的であっては、いけないのか。アメリカでは、中学校の数学の時間に、小切手の使い方を教えている。 ここで「将来、子どもたちが生きていく上で、役にたつ知識や経験を、分け伝えること」と教えてくれたのは、オーストラリアのM大学で、教授をしている私の友人である。(はやし浩司 日本の教育 実用的な教育 子どもの学力 子供の学力 新学力観)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司・●一つの暴論(教育革命論) これはあくまでも暴論だが、学校は午前中だけでやめたらいい。午後は、生徒の自由にする。そしてそれぞれの特性に合わせて、塾へ行けばいい。何も学習塾や受験塾だけが塾ではない。ピアノ教室、料理教室、工作教室、釣り教室、水泳教室、フランス語教室、ダンス教室など。学校の中に、塾を呼びこんでもいい。その分、月謝は割安にする。 原則として文部省は、学校の運営管理だけに口を出す。教科書検定は廃止。一方、受験指導は、それを「よし」とする、業者に任せればいい。生徒の答案用紙を採点するのは、しかたないとしても、順位をつけ、進学校へ割り振るなどという行為は、教育者を名乗る教師のする仕事ではない。 また学校の敷地の3分の1には、樹木を植えさせる。校庭には、緑の芝生をしきつめる。管理は、授業の一つとして、子どもたちに任せる。また校舎は今後、完全なバリヤーフリー構造にして、身体障害者や知的障害者を差別することなく入学させる。そして子どもたちどうしで、互いにめんどうをみあう。 教師のする仕事は、「教える」ことではなく、「引き出す」こと。子どもたちの特性を見極めながら、その特性に応じた指導をする。具体的には子どもの特性に応じたカリキュラムを組んであげる。読書が好きな子どもは、毎日でも読書ができるようにしてあげる。皆が皆、算数ができなくてもいい。算数ができない子どもは、算数ができる子どもを尊敬し、ピアノがひけない子どもは、ピアノがひける子どもを尊敬する。互いに皆が、それぞれの立場で相手を認め合う。 そうそうA中学に優秀なスペイン語塾があれば、B中学やC中学からも、自由に越境受講できるようにすればいい。そうすればもっと多様性が広がる。また基礎学力(算数の基礎、読み書きなどの基礎)については、単位制を導入して、義務教育機関中に終了すればよいとする。クラス担任制度は廃止して、生徒の責任者制度を導入する。その責任者(教師)が、それぞれの子どもの指導について、責任をもって指導する。必要に応じて、一日中、行動をともにしてもよい。 高校、大学も基本的には、子どもの多様性に合わせて、多様化する。高校や大学にスキー学部があってもいいし、釣り学部があってもいい。文学部も、作家部、読書評論部などに分ける。経済学部も、起業部、ベンチャービジネス部などに分ける。もちろん一方に、アカデミックな学問を探求する学部があってもいい。哲学や数学の分野で、すぐれた才能を示す子どもについては、それはそれとして伸ばす。 これは暴論だが、しかしもし実行したら、それはまさしく教育革命というにふさわしい。長い間、鎖国と封建制度の中で苦しめられてきた子どもたちにとっては、まさに革命。自由を求めた革命。が、あなたはそれでも今の教育制度がいいと思うか。もしそうならあなた自身の子ども時代を思い浮かべてみてほしい。あなたは心の中で、どんな学校を求めていたかを、だ。力のない子どもの革命を助けるのは、あなたしかいない。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) この原稿を書いてから、4年になる。が、実は、こうした(流れ)は、すでに世界の常識になりつつある。ドイツやイタリアでは、学校外教育が、ますますさかんになりつつある。カナダでも、そうだ。「教育は学校で」という発想そのものが、もう古い。 ただしこの日本で、教育を自由化するには、1つの条件がある。まず、学歴社会を是正すること。それをしないで、自由化すれば、進学塾だけが、学校外教育ということになってしまう。(はやし浩司 教育の自由化 学歴社会 教師の責任)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●学歴信仰は、迷信?(有M文部大臣への反論) 大学の教授は、高校の先生より、エライ。高校の先生は、中学の先生より、エライ。中学の先生は、小学校の先生より、エライ。小学校の先生は、幼稚園の先生より、エライ。少なくとも、大学の教授は、幼稚園の先生より、エライ。誰しも、心の中でそう思っている。こういうのを学歴信仰という。 家計がひっくり返っても、親は爪に灯をともしながら、息子のために学費を送り続ける。が、肝心の息子様はそんな親の苦労など、どこ吹く風。少しでも仕送りが遅れたりすると、ヤンヤの催促。それでも親は、「大学だけは出てもらいたい」と思う。そしてそれが「親の務めだ」と思う。こういうのを学歴信仰という。 浜松にもA高校からD高校まで、ランクがある。やっとの思いでD高校へ入れそうになると、親は「C高校を」と希望する。そしてC高校が合格圏に入ってくると、今度は「A高校。それが無理なら、何とかB高校を……」と希望する。親の希望には際限がないが、そういう思いが、誰にでもある。こういうのを学歴信仰という。 新聞記事だけなので、有M文部大臣の発言の真意はわからないが、文部大臣が、母校のA高校へ来て、「学歴信仰があるというのは迷信」と述べたとか(99年2月)。つまり「日本には学歴信仰はない」と。東大の総長という学歴の頂点に立ったような人が、しかもその信仰の総本山の、そのまた法主の立場にある有M文部大臣が、そういう発言をするところに、日本のこっけいさがある。学歴信仰がなかったら、誰も、受験勉強などしない。誰も自分の息子を塾や予備校に通わせない。もし本当にないのなら、成績に関係なく、東大の学生を入学させたらいい。あるいは文部省は、学歴に関係なく、役人を雇ったらいい。 学歴のある人には、学歴は不要だ。しかし学歴のない人は、それを死ぬほどほしがる。お金と同じだ。金持ちが、いくら「お金では幸福は買えません」と言ったところで、その日のお金に困っている庶民には、説得力はない。私もある時期、自分の学歴にしがみついて生きていた。特にこの教育の世界ではそうで、もし私に学歴がなかったら、私の教育論になど、誰も耳を傾けてくれなかっただろう。反対に肩書きや地位がないため、いかに辛酸をなめさせられたことか。 話は変わるが、ニュージーランドのある小学校では、その年から手話を教えるようになったと言う。教室の壁には、手話の仕方が描いた絵が、ペタペタとはってあった(テレビ番組より)。理由は、その年から、聴力のない子どもが入学してきたからだという。こういう姿勢、つまりその子どもに合わせて、学校が自由にカリキュラムを組むという姿勢の中に、私は学校の本来、あるべき姿を見た。反対にもし日本の小学校で、こういう身体に障害のある子どもが入学してきたら、教師や父母は、どのように反応するだろうか。さまざまな問題が起きるであろうし、その起きる背景に、学歴信仰がある。天下の文部大臣にさからって恐縮だが、文部大臣ももう少し庶民の側におりて、ものを考えてほしいと思う。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) この原稿を書いた時点(01年)と今では、障害児に対する考え方が、大きく変わってきた。15年ほど前のことだが、ある小学校(静岡県)で、1人の身体に障害のある子どもを入学させようとしたことがある。そのとき、「そういう子どもが入ってくると、子どもたちの勉強の進度にさしさわりが出る」と、反対運動を起こした親たちがいた。テレビなどでも、報道されたので、覚えている人も多いと思う。 たった15年前には、日本はまだそういう国だった。が、今、そんな反対運動をすれば、反対に、その親たちが袋叩きにあうだろう。日本の教育というより、親たちの意識が、たしかに今、変わりつつある。(はやし浩司 学歴信仰 学校神話 受験カルト)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●不気味な思考回路(ポケモン現象) 一時期よりは下火になったが、いまだにポケモンは根強い人気を保っている。年齢的には幼稚園の年長児から小学2、3年生児が、そのピーク。私の調査でも、約80%の子どもたちがハマっていたことがわかっている(98年はじめ)。 一度こういう世界ができると、「ポケモンを知らない」とか、「ポケモンなんて、つまらない」などと言おうものなら、それだけで仲間はずれにされてしまう。当時あの「♪ポケモン言えるかな」という歌を、どこまで歌えるかが、その子どものステイタスを決めていた。たとえばその歌を途中までしか歌えなかったりすると、その子どもは「バカ」というレッテルをはられてしまった。 問題は、そのハマリ度だ。好きとかファンというレベルならまだしも、中には熱狂してしまう子どもがいる。現実とゲームの世界が区別できなくなってしまう子どももいる。こうなるとゲームとは、もう言えない。信仰だ。しかもカルトだ。ある子ども(小3男児)は、親に叱られると、いつも「♪ポケモン言えるかな」を心の中で歌っていたという。また別の中学生は、毎夜、空に向かって、超能力を授けてもらうよう、祈っていたという。そうでなくても、大半の子どもは、あの黄色いピカチューの絵を見ただけで、興奮状態になってしまった。 今はまだよい。今は、まだゲームの世界に収まっているから、よい。しかしもしポケモンが思想をもったらどうなる。たとえばサトシが、「子どもたちよ21世紀は暗い。一緒に海へ入って死のう」などと訴えたら、どうなる。それに従ってしまう子どもが続出するかもしれない。ポケモン、いや一連のポケモン現象には、そういう危険性が潜んでいる。 それにもう一つ、心配なことがある。幼児期に一度、こうした思考回路ができると、以後、何かにつけてその思考回路に沿って、ものを考えるようになるということだ。迷信を信じやすくなったり、カルトにハマりやすくなったりする。低劣な運命論やバチ論を振りかざすようになるかもしれない。ある妻は、狂信的なカルト教団に身を染め、夫に向かってこう言い出した。「あんたと私は、前世の縁で結ばれていなかったのよ。それを正すためには、信仰の力が必要なのよ」と。もしあなたの妻がある日突然、そんなことを言い出したら、あなたはそれに耐えることができるだろうか。こんな例もある。 ある教団では手術そのものを禁止している。私がそのことをその教団に確かめたら、「禁止はしていないが、熱心な信者なら手術を拒否します」ということだったが、ともかくもそういうことだ。そしてその結果として、一人の子どもが交通事故で死んだ。子どもの母親が熱心な信者で、手術をがんとして拒否したからだ。が、悲劇はそこで終わらなかった。この事件で孫を失った老人はこう話してくれた。「今は、息子夫婦とも断絶しています。それまでは愛だとか、平和だとか、信仰もそれほど悪いものだと思っていなかったのですが……」と。私にはこれ以上のことは何も言えないが、もしあなただったらそうするか。それを一度考えてみてほしい。ポケモン現象にはそんな一面も隠されている。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) カルト教団と戦うのも、疲れる。本当に疲れる。彼らは、その信仰に、命をかけている。かたや私の方は、そこまではしない。命をかけてまで戦うということはしない。が、この(ちがい)が、結局は、カルトをのさばらせてしまう結果となる。 私は、当時、まだカルト教団と戦っていた。で、そうしたカルト教団のもつ、カルト性というか、危険な側面を、あのポケモン・ブームの中に見た。子どもたちは、狂信的なまでに、ポケモンに夢中になっていた。 そこで私は「ポケモン・カルト」(三一書房)という本を書いた。 が、反響というか、抗議の嵐は、すさまじかった! 今でも、その世界では、「トンデモ本」として酷評されている。どこか「?」な人たちに、「トンデモ本」と酷評されることは、たいへん名誉なことではないか。 このエッセーは、そういうときに書いた。いくら酷評されても、今でも私は、自説をひっこめるつもりは、まったく、ない。(はやし浩司 カルト カルト教団 ポケモン・カルト)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司・●わからぬフリをする(うちの子は、どうですか?) 子どもの情緒障害、専門的には脳の機能的障害には、軽重の程度の差がある。重い場合は別として、軽い場合には、ふつう児との境があいまいで、そのため指導が難しい。いろいろなケースがある。たとえば自閉症にしても、それと明らかにわかる子どももいるが、「どこか心を開かない」「勝手な行動をして、どうも心をつかめない」という程度の子どももいる。かん黙児にしても、外の世界ではまったくしゃべらない子どももいれば、ふとしたきっかけで黙りこくってしまう子どももいる。私にしても、それぞれ何10例もの子どもたちを直接指導してきたが、その私でもいまだに迷うことが多い。いや、判断を誤ることはまずないが、親に言うべきかどうかで迷う。「もし万が一にもまちがっていたら……」という思いと、「治療法も用意しないまま、診断だけをくだすことはできない」という、二つの思いの中で迷う。言えば言ったで、親に与える衝撃ははかり知れない。 だから親は、子どもがどこか変わった症状を示したりすると、子どもを叱ったり説教したりする。「どうして静かに落ちつけないの」とか、「皆の前で、もっとハキハキ、しゃべりなさい」とか。しかし脳の機能的障害というのは、そういうものではない。子ども自身がコントロールできない、脳の奥深い部分で起こる。そして次に親は、その矛先を、教師に向けてくる。「先生の指導が悪いから、こうなったのだ」と。教師がやりきれない気持ちに襲われるのは、たいていこんなときだ。 が、教師は知らぬふりをして教える。そういう知識はないという前提で、教える。少なくとも親のほうから、「どうしてでしょうか?」という質問があるまで、そうする。……こう書くと、無責任な教師のように思われるかもしれないが、教育には、はっきりとわからなくてもいいことは、山ほどある。あるいはわかっていても、わからないふりをして教えることは山ほどある。たとえば子どもの知能や、家庭問題。性格や気質など。その子どもはそういう子どもなのだということを納得した上で、教える。仮に情緒に問題があるとしても、ふつう児として自然に扱ったほうが、その子どもにとってはよいということもある。意識すればするほど、逆効果になる。 そうそう、教師が一番いやがる会話を教えよう。何がいやかって、親に、「うちの子、どうでしょうか」と聞かれることぐらい、いやなことはない。「うちの子、最近、いかがでしょうか」と聞く人も多い。親というのは先生と顔を合わせると、たいていそう言うが、言われたほうは答えようがない。親は軽いあいさつのつもりでそう言うのだろうが、何をどの程度答えるべきか、その返答に困ってしまう。私の場合、そういうふうに聞かれたら、たいてい、「おうちではいかがですか?」と聞きなおすようにしている。そうすると、相手の聞きたいことがわかる。私「おうちではいおかがですか」親「最近、家の手伝いをしなくて困っています」私「ああ、そのことですね」と。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) 「問われるまで、答えない」……それが、教師の間の不文律にもなっている。いくら子どもに問題があっても、教師の側から、それを指摘してはいけない。中には、それを正しく受け取ってくれる親もいるが、ほとんどの親は、その瞬間から、狂乱状態になってしまう。 で、最近の教師の傾向としては、こういう言い方をするのが、通例になっている。「一度、専門医に相談してみられてはいかがですか?」と。あとの判断は、親がすればよいという指導のし方である。 一見、無責任にみえる指導法だが、現状では、それもやむをえないのではないか。(はやし浩司 子供の問題 育児の問題 子供の心の問題 教師の対処法)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●溺愛ママ・ブルース(溺愛は愛ではない) 子どもを溺愛する親は、珍しくない。たいていは親側の情緒的欠陥が原因で、親は子どもを溺愛するようになる。ある母親は、息子(小6)が、修学旅行に行った夜、一睡もせず泣き明かした。また別の母親は、やはり息子(中3)が初恋をしたことについて、はげしい嫉妬心を燃やした。 こうしたケースで特徴的なことは、溺愛している母親は、それを「親の深い愛」と誤解している点にある。ある母親は臆面もなく、こう言った。「息子(高1)の汚れた下着を見ていると、いとおしくて、頬ずりしたくなります」と。つまりそうすることが、親の鏡というわけである。中に生きがいのすべてを、子どもに注いでしまう人がいる。考えることといえば、明けても暮れても、子どものことばかり。毎月、子ども(幼稚園児)の成長記録を、小冊子にして発行している人もいる。こういう人は、「子どもは私のすべて」と公言してはばからない。 しかし溺愛は、「愛」ではない。代償的愛ともいう。つまり自己の支配欲を満たすために、子どもを愛する。あるいは自分の心のスキ間を埋めるために、子どもを愛する。つまりは親の身勝手な愛に過ぎない。子どもを愛するということは、子どもが巣立っていくのを見守りながら、じっとそのさみしさに耐えることにほかならない。もっともこう書いたからといって、溺愛が悪いというのではない。もちろん笑っているのでもない。ただ私がここで言いたいことは、親が溺愛すればするほど、子どもの「核」形成が遅れるということだ。核というのは、子どものつかみどころをいう。その年齢になると、その年齢にふさわしい「つかみどころ」ができてくる。しかし親が溺愛したりすると、そのつかみどころがわからなくなる。全体にその年齢に比して、幼い印象を与えるようになる。が、それだけではすまない。 子どもはその年齢ごとに、ちょうど蝶がカラをぬぐようにしてカラをぬぎながら、成長を繰り返す。しかしその段階で溺愛などが原因で、カラをぬがないと、そのツケはあとへあとへと回される。しかもあとになればなるほど、その衝撃は何10倍も大きくなる。はげしい家庭内暴力につながることもある。「俺を、こんな俺にしたのは、オマエだ!」「許して、お母さんが悪かったわ」と。そうでなければ、そのまま子どもはマザコンタイプの子どもになっていく。30歳になっても、40歳になっても、親離れできない。これは極端なケースだが、結婚してからも実家へ帰るたびに、母親と風呂へ入ったり、一緒に寝ている男性がいた。そういうふうになる。 自分自身の中に「溺愛」を感じたら、子育てから遠ざかる。しかしこれは簡単なことではない。唯一方法があるとすれば、母親であることを忘れ、妻であることを忘れ、ついで女であることを忘れ、一人の人間として、自分のしたいことをする。そしてその反射的効果として、子育てから遠ざかる。もちろん自分自身に情緒的欠陥があれば、それと闘う。(以上、01年記「子育て雑談」) (補記) マザコンになるのは、何も男児だけとはかぎらない。女児も、マザコンになるケースは、多い。しかも女児(女性)のマザコンのほうが、男児(男性)よりも、強烈になりやすい。女性のばあい、実家に帰って、母親といっしょに風呂に入っても、だれも、おかしいと思わない。(男性だったら、それだけで、大問題になるが……。)そういうスキをついて、女性は、男性よりも、より強烈なマザコンになる。 さらにファザコンというのも、ある。自分の父親を偶像化する。「オレのオヤジの悪口を言うヤツは、許さない」と、公の場所で、叫んだ男性(50歳くらい)がいた。 でき愛は、「愛」ではない。自分の心の欠陥を埋め合わせするために、親は、子どもをでき愛するようになる。ご注意!(はやし浩司 溺愛 でき愛 子どもの成長 子供の成長 子供の心の発達 心理)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●スポイルされる子どもたち(忍耐力のない子ども) アメリカ人の友人が、「日本の子どもたちは、100%、スポイルされている」という。わかりやすく言えば、「ドラ息子、ドラ娘だ」と言うのだ。そこで私が、「君は、どんなところを見て、そう言うのか」と聞くと、彼は、こう教えてくれた。 「ときどきホームスティをさせてやるのだが、食事のあと、食器を洗わない。片づけない。シャワーを浴びても、あわを洗い流さない。朝、起きても、ベッドをなおさない」などなど。つまり、「日本の子どもは何もしない」と。反対にアメリカへ、ホームスティしてきた高校生が、こう言って驚いていた。「向こうでは、明らかに不良と思われるような高校生でも、家事だけは手伝っていた」と。 日本人は、子どもを使わない。「子どもに楽な思いをさせるのが、親の愛だ」と誤解しているようなところがある。だから生活感がない。「水はどこからくるか」と、年長児たちに聞くと、「水道の蛇口」と答える。「ゴミはどうなるか」と聞くと、「おじさんが持っていってくれる」と。あるいは「お母さんが病気になると、どんなことで困りますか」と聞くと、「おとうさんが、やってくれるからいい」と答えたりする。 こんな話をある講演会で話したら、一人の母親がこう質問してきた。「何をやらせればいいのですか」と。話を聞くと、「掃除は、掃除機でものの30分ですんでしまう。買物といっても、食材は、食材屋さんが毎日、届けてくれる。料理のときも、台所の周囲でうろうろされると、かえって迷惑だから、テレビでも見ていてくれたほうがいい」と。 子どもを使うということは、家庭の緊張感に巻き込むことをいう。親がせんべいを口にして、寝そべりながら、「玄関の掃除をしなさい」は、ない。子どもを使うということは、親がキビキビと動き回り、子どももそれに合わせて、キビキビとすべきことをすることをいう。たとえば次のようなとき、あなたの子どもはどういう反応を示すだろうか。 あなた(親)が重い買い物袋をさげて、家の近くまでやってきた。そしてそれをあなたの子どもが見つけたが……。さっと子どもがやってきて、あなたを助ければ、それでよし。しかしそ知らぬ顔で、自分のしたいことをしているようであれば、家庭教育をかなり反省したほうがよい。 よく誤解されるが、子どもの忍耐力は、「いやなことをする力」をいう。台所の生ゴミを手で始末できるとか、寒い夜に隣へ回覧版を届けることができるとか。一日中サッカーをしているから、忍耐力があるということにはならない。その子どもは好きなことをしているだけである。その忍耐力がないと、子どもは学習面でも伸び悩む。勉強するということには、どうしても苦痛がともなう。その苦痛が乗り越えられないからだ。またそれ以前の問題として、生活力が身につかない。友だちの家からタクシーで、あわてて帰ってきた子ども(小6女子)がいた。話を聞くと、「トイレが汚れていて、そこで用をたすことができなかったからだ」と。そういう子どもにしないためにも、子どもは使って使って、使いまくる。子どもが2~4歳のときが勝負で、それ以後になると、このしつけはできなくなる。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) ここに書いたアメリカ人というのは、浜松市に住んでいた、R・ケリーという人だった。4、5年前にアメリカへ帰っていった。で、一度、彼の家を訪問したことがある。すばらしい御殿のような家だった。半地下室には、卓球ルームまで作ってあった。 彼が日本へやってきたのは、52歳のとき。ある店で、ぼんやりと外をながめていたとき、私の方から声をかけた。以来、10年近く、つきあった。 すばらしいアメリカ人だった。彼の送別会には、300~400人近い人たちが、ホテルに集まった。この原稿を読んでいるとき、それを思い出した。ここ1、2年、音信がないが、今ごろは、どうしているだろうか? Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※●崩壊家庭の中で(ゆがむ子どもの心) 荒れた自分の家を、得意げになって見せていた子ども(小3男児)がいた。敷きっぱなしになった破れたふとん。その周囲に散乱するティシュペーパー。割れた窓ガラス。汚れた台所に、ゴミの山。一定の限界を超えると、子どもの心から「家庭」とのつながりが消える。ふつうなら、「家庭の恥ずかしい部分は隠そう」という意識が働くが、そういう意識がない。当然、心も荒れる。ものの考え方が粗野になり、他人の心の動きに鈍感になる。 いわゆる「家庭崩壊児」はこうして生まれる。家庭が本来あるべき家庭として、機能していない。こうした拒否的な環境で育った子どもは、心に深刻なキズを負うことがわかっている。こんな子ども(高1男子)がいた。いわく、「台風で壊れる家を見ていると、楽しい」と。そこで私が「本当に楽しいのか」と聞くと、「おもしろい」と。さらに「それが君の家だったら、どうするのだ」と聞くと、「もっと楽しい」と。 このタイプの子どもは、「世間に迷惑をかける」ということに、たいへん鈍感になる。真夜中にマフラーをはずしたバイクを、バリバリとふかしても、それが悪いことだという意識がない。あるいは路上にビンを叩きつけて割っても、それが悪いことだという意識がない。むしろ人に迷惑をかけることを楽しむようなところがある。善悪を判断する中枢部分が、変調をきたしているためと考えるとわかりやすい。仮に立ち直っても、その影響は一生続く。俗に言う、ヒネクレ症状というのが、それである。夫「こんなところに、サイフを置いてはダメだ」妻「あんただって、この前、ここに置いたじゃ、ない」夫「だから、ここに置いてはダメだ」妻「自分だって、ここに置いたクセに、何よ!」 このところの不況で、程度の差こそあるが、このタイプの子どもがふえている。平気で自分の家族や家庭の恥を口にするから、わかる。「うちの父ちゃんね、毎晩、エロビデオを見てる」「ママね、パパの稼ぎが少ないから、苦労してるよ」「パパが本を投げつけて、ママが頭にけがをした」など。 家庭崩壊を子どもに経験させてはいけない。これは子どもを妊娠したときからの、親の義務のようなものだ。が、それでも……というのであれば、これはもう個人の問題ではないように思う。福祉とか、福祉社会というのなら、老人や障害のある人に、こういうタイプの子どもたちも含めるべきだと、私は思う。客観的に見て、そういう心配のある子どもは、行政による手厚い保護が必要だ。親の理解と協力が期待できない以上、そうするしかない。 家庭崩壊を経験した人は不幸だ。結婚しても、「よい家庭を作ろう」という気負いばかりが先行して、結局は失敗しやすい。あるいは結婚そのものができない。子どもをつくっても、うまく子育てができない。頭の中に「家庭像」や「親像」がないからだ。繰り返すが、家庭崩壊だけは子どもに経験させてはいけない、……と思う。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) ……とは言っても、思うがままにならないのが、生活。だれが、自ら不幸になることを望むだろうか。そんな人はいない。 ただいくら貧しくても、「心」だけは、見失ってはいけない。とくに、子どもの前での、夫婦げんかは、タブー中のタブー。はげしい夫婦げんかは、子どもに、極度の緊張感と恐怖感を与える。それが子どもの心にキズをつける。ときに、トラウマとなり、その子どもを生涯にわたって、苦しめる。が、それだけではすまない。 このトラウマには、副作用がある。 やがて時間をかけて、親子関係を破壊する。世代連鎖する。そのトラウマが大きければ、その子どもが多重人格性をもつこともある。激怒したようなときに、まったくの別の人格になってしまったりする。 幼児期においては、すねたり、ひがんだり、ぐずったりしやすくなる。人格の「核」形成が遅れ、善悪の判断にうとくなることもある。 子どもは、心安らかな家庭環境の中で、親の愛情をたっぷりと受けながら育つのがよい。何度も書くが、絶対的な信頼関係、絶対的な安心感、この2つが子どもの心をはぐくむ二大要素と考えてよい。 「絶対的」というのは、「疑いすらもたない」という意味である。(はやし浩司 夫婦喧嘩 夫婦げんか 家庭崩壊 崩壊児 子供の心理 絶対的な安心感)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司・●信頼関係を大切に(先生の悪口はタブー) 子どもの前では、先生の批判、悪口はタブー。子どもが悪口を言ったとしても、「あんたが悪いからよ」と言ってすます。もし問題があるなら、それは子どものいないところで、また子どもとは関係のない世界ですます。あなたが先生を批判したり、悪口を言ったら、子どもは学校で、その先生に従わなくなる。私にはこんな経験がある。 幼稚園で教えていたころ、まったく私の指示に従わない子ども(年長女児)がいた。ある日その子どもに、「どうして言うことを聞かないのか」と聞くと、その子どもはこう答えた。「だって、先生は、本物の先生ではないでしょ」と。この話には余談がある。 このことを当時の園長に告げると、私はそれほど気にしていなかったのだが、その園長は激怒して、その母親に即刻、電話をした。そしてこう怒鳴った。「何てことを子どもに教えているのですか! あなたがそんなこと言ったら、指導できないでしょ!」と。当時はまだこういう気骨のある園長が、あちこちにいた。 「子どもにこの話は、先生には内緒よ」と言うことは、「先生にこの話をせよ」と言うのと同じ。子どもが言った先生の悪口に、相槌を打つということは、あなたが先生の悪口を言ったのと同じ。子どもは先生に、こう言う。「ママもこう言っていた」と。仮に子どもが言わなくても、先生にはそれがわかる。どういう形であるにせよ、あなたの「思い」は、必ず先生に伝わる。子どもというのは、自分の心を隠すことができない。先生は先生で、この種の話には敏感に反応する。裏を返して言うと、子どもの前では、先生をたてる。「あなたの先生は、すばらしい先生よ」「先生のような立派な先生に、あなたが教えてもらえて、とてもうれしいわ」と。 教育は信頼関係で成り立つ。中には「お金(税金)を出しているのだから」という思いからか、教育を自動販売機のように考えている人がいる。あるいは今では、先生より、特に幼稚園の先生より、高学歴の人が多い。そういう人は、どうしても先生を下に見る。こういうものの考え方は、その信頼関係を破壊する。教師だって人間だ。自分を信頼してくれる人には、その期待に応えようとするし、そうでない人には、熱意そのものが沸いてこない。いくら相手が子どもとわかっていても、時と場合によっては、「このヤロー」と思うこともある。そうなったら教育そのものが成りたたない。 たいへんきわどい話をしてしまったが、そうでなくても難しいのが最近の教育。親と教師が信頼しないで、どうして教育ができるというのだろう。問題のある教師がいるのも事実だが、もしそうであるなら、冒頭にも書いたように、子どもとは関係のない世界ですます。一番よいのは、直接、その先生と交渉することだ。今の制度の中では、教育委員会に相談すると、どうしてもおおげさになってしまう。校長に訴えるとしても、校長は今、校長というよりは事務長に近い。アメリカのように教師を選ぶ権利が親にあれば別だが、日本にはそれがない。ない以上、やはり直接交渉がよい。勇気がいることだが、それが一番よい。……と私は思う。これはあくまでも私個人の一意見だが。(以上、01年記「子育て雑談」)(付記) 今でこそ、保育士というのは、一定の地位を確立しているが、35年前には、そうではなかった。私が「幼稚園で働いている」と言っただけで、ほとんどの人は、「あの林は、頭がおかしい」と言った。 そんなわけで、私は、幼稚園の内部では、自分の過去を隠し、幼稚園の外では、自分の職業を隠さねばならなかった。 また保母というのは、「母」、つまり女性にかぎられていた。「保父」が生まれたのは、私が30歳になったころ。現在の保育士という名称になったのは、さらにあとのことである。 ここに書いた園長というのは、恩師の松下哲子先生をいう。すばらしい先生だった。
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(05)
2006年、明けまして、おめでとうございます!1月4日(水曜日)号をお届けします。……といっても、このあいさつを書いているのは、今日、12月5日(月曜日)です。マガジンでは、こうして約1か月先の原稿を書いています。こうすることによって、たとえば、3~4日のスランプ状態になったようなときでも、みなさんのところへ、途切れることなく、マガジンを配信することができます。で、実は、この3、4日ほど、ほとんど原稿を書きませんでした。いろいろ、忙しいことが重なったこともあります。1泊ですが、ワイフと旅行も楽しみました。が、今日は今朝から調子がよく、朝の7時半から目標の、20枚分の原稿を書くことができました。今、時刻は、午前10時45分です。少し荒っぽい原稿かもしれませんが、今年も、こうしてみなさんのところに、マガジンをお届けできることを喜んでいます。みなさんのご健康とご多幸を、心より念願しています。今年もよろしくお願いします。 浜松市 はやし浩司(追伸)年賀状は、HTML版のほうに、載せておきます。************************++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(010)【子育て雑談】++++++++++++++++++++++++4年前(01年)に書いた原稿を、改めて読みなおしています。そのままそれを紹介しながら、(補記)の部分で、あれこれ訂正、修正を加えてみたいと思います。こうして読みなおしてみると、たった4年前の私ですが、どこか過激で、どこか反骨的なのがわかります。とくに進学塾に対する意見は、強烈です。なぜこのような原稿を書いたかについては、いろいろな背景がありますが、「これも私」と思い、ここにコメントをつけて、再掲載することにしました。 はやし浩司 2005年12月10日(土)++++++++++++++++++++++++●敬語と日本の文化論(フレキシブルな日本語?)子どもに向かって、「産んでやった」とか「育ててやった」とか言う人がいる。妻に向かっては、「食わせてやる」とか「養ってやる」とか言う人がいる。Y氏(52歳)がそうだ。息子(27歳)と娘(22歳)がいるが、子どもは子どもで、「産んでもらった」とか「育ててもらった」とか言っている。さぞかし窮屈な家庭だろうと思いきや、Y氏の妻は妻で、「夫のおかげで生活できます」と言っている。そのY氏の妻が私の家にやってきて、こう言った。「ウチのダンナなんか、冷蔵庫から牛乳を出して飲んでも、それを冷蔵庫に戻すことすらしない。だから夏なんか、あっという間に牛乳が腐ってしまう」と。話を聞くと、Y氏は結婚して以来このかた、トイレ掃除はおろか、トイレットパーパーの差し替えすらしたことがないという。家庭というのは、そういうものらしい。それでうまくいっているなら、「あなたはまちがっている」などと言う必要はない。言ってはならない。が、こういう人に限って、私に猛烈に反発してくる。「君は日本のよさまで否定するのか!」。Y氏はこう言う。「日本では上の人を敬う。英語には敬語すらない。外国では、親でも先生でも、『ヘイ、ユー』と言うではないか。そういう国が、本当に理想の国なのか」と。 こういう人に出会うと、気が遠くなるほど、間に距離を感ずる。順に反論してみよう。人間の上下意識を支えるのが、権威。「偉い人は偉い」という権威である。理由など、ない。日本人は、平安の昔からこの権威を徹底的に叩き込まれている。「男は上、女は下」「親は上、子は下」という、日本独特の男尊女卑思想や親意識もここから生まれた。こうした文化は、日本独特のものであることは認めるが、それが「日本のよさ」になるかどうかは別問題である。少なくとも、日本を一歩外へ出た外国では、通用しない。 次に敬語の問題。英語に敬語がないというのは、ウソ。「ユア・マジェスティ」とか「ハイ・エクセレンシー」とかいう言い方はある。「サー」という単語にしてもそうだ。日本語よりはるかに少ないというだけだが、そのかわり、彼らはそれなりの人に対しては、ていねいな言い方をする。仲間どうしだったら、「ハイ」かもしれないが、それなりの人には、たとえば「このようにお会いできる特権を、私の喜びとします」などいうような言い方をする。むしろ日本語に敬語が多いのは、平安の昔から、きびしい身分制度をとってきたことによる。敬語があることを、必ずしも喜んでばかりはおられない。また敬語というのは、人間関係を飾る道具として使われる。あくまでも飾り。だから敬語を使うから相手を尊敬しているということにもならない。使わないから尊敬していないということにもならない。私などいつも生徒に、「ジジイ」とか、「バカはやし」とか呼ばれている。しかしそのほうが互いに心を開いているから、ストレートな人間関係を築くことができる。気も疲れない。 最後に何も、アメリカや欧米が理想の国だとは思っていない。日本は日本だ。しかしここで大切なことは、世界に理解される日本であるか否かということ。もし日本が今までのように、東洋の島国でよいというのなら、それはそれで構わない。しかしそれでよくないというのなら、日本の常識を外国へ押しつけるか、あるいは日本は世界の常識を受け入れるしかない。あるいは英語の敬語を発明して、それをアメリカ人に押しつけるというのもよい考えだ。しかしそれができないというのなら、日本を少しでも外国の常識に近づけるしかない。私はそう考えるが、あなたは私の意見をどう思うか。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記)日本語は、よい意味では、よりフレキシブル(=柔軟性のある)な言語ということになる。いろいろな言い方ができる。その点、反対に中国語などは、ガチガチしている。そんな印象を受ける。たとえば「私はあなたを愛する」は、中国語では、「ウォー・アイ・ニー」となる。が、それだけ。 しかし日本語のほうでは、「私ね、愛しているわ」「私は、愛しているよ」「ぼく、愛しているかも」「ぼくさア、愛しているね」などと、いろいろな形で、微妙な表現ができる。 敬語についても、そうで、これまたさまざまな言い方ができる。しかしそのさまざまな言い方ができるという部分で、日本語は、より複雑になってしまった。そしてそれが、時をおいて、学者たちの間で、話題になったり、問題になったりするのでは? ところで、この文の中で、「君は日本のよさまで否定するのか!」と私は書いた。それを言ってきたのは、実は、女性である。当時は、まだ生々しい話だったので、「男性」とかえた。その女性の年齢は、35歳くらいではなかったか。で、そのあと、その女性から、手紙まで届いた。しかし内容は、支離滅裂。まるで文章になっていなかった。だから「返事を書くまでもない」と思い、電話で返事をすることにした。 しかし電話口に出た男性(その女性の夫)は、電話口で、ただ「すみません」「すみません」と言うだけで、その女性には、電話をとりついでくれなかった。どういう事情になっていたのか、今でもよくわからないが、多分、その男性(夫)も、その女性(妻)に手を焼いていたのかもしれない。(はやし浩司 敬語 日本語 日本語の問題 言葉)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●壮絶な家庭内暴力(余計なことは、言うな) T君は私の教え子だった。両親は共に中学校の教師をしていた。私は7、8年ぶりにそのT君(中2)のうわさを耳にした。たまたまその隣家の人が、私の生徒の父母だったからだ。いわく、「家の中の戸や、ガラスはすべてはずしてあります」「お父さんもお母さんも、廊下を通るときは、はって通るのだそうです」「お母さんは、中学校の教師を退職しました」と。私は壮絶な家庭内暴力を、頭の中に思い浮かべた。 T君はものわかりのよい「いい子(?)」だった。砂場でスコップを横取りされても、そのまま渡してしまうような子どもで、やさしく、いつも柔和な笑みを浮かべていた。しかし私はT君の心に、いつもモヤのような膜がかかっているのが気になっていた。 よく誤解されるが、幼児教育の世界で「すなおな子ども」というときは、「自分の思っていることや考えていることを、ストレートに表現できる子ども」をいう。従順で、ものわかりのよい子どもを、すなおな子どもとは決して言わない。むしろこのタイプの子どもは、心に受けるストレスを内へ内へとためこんでしまうため、心をゆがめやすい。T君はまさにそんなタイプの子どもだった。 症状は正反対だが、しかしこの家庭内暴力と同列に置いて考えるのが、「引きこもり」である。家の中に引きこもるという症状に合わせて、夜と昼の逆転現象、無感動、無表情などの症状が現われてくる。しかし心はいつも緊張状態にあるため、ふとしたきっかけで爆発的に怒ったり、暴れたりする。少年期に発症すると、そのまま学校へ行かなくなってしまうことが多い。このタイプの子どもも、やはり外の世界では、信じられないほど「いい子(?)」を演ずる。 そのT君について、こんな思い出がある。私がT君の心のゆがみを、お母さんに告げようとしたときのことである。いや、その前に一度、こんなことがあった。私が幼稚園の中にあった自分の教室で授業をしていると、T君はいつもこっそりと自分の教室を抜け出し、私の教室へ来て、学習していた。T君の担任が、よく連れ戻しに来た。そこである日、私はT君のお母さんに電話をした。「私の教室へよこしませんか」と。それに答えてT君のお母さんは猛烈に激怒して、「勝手に誘わないでほしい。うちにはうちの教育方針というものがあるから」と。しかしT君はそれからしばらくして、私の教室へ来るようになった。家でT君が、「行きたい」と、せがんだからだと思う。私は以後、一年半の間、T君を教えた。 しかしその「ゆがみ」を告げようとしたとき、お母さんはこう言った。「あんたは、黙ってうちの息子の勉強だけをみていてくれればいい」と。つまり「余計なことは言うな」と。 子どもの心のゆがみは、できるだけ早い時期に知り、そして対処するのがよい。しかし現実にはそれは不可能に近い。指摘する私たちにしても、「もしまちがっていたら……」という戸惑いがある。「このまま何とかやり過ごそう」という、事なかれ主義も働く。が、何と言っても、親自身にその自覚がない。知識もない。どの人も、行きつくところまで行って、はじめて気づく。教育にはどうしても、そんな面がつきまとう。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) このT君は、今でも強く印象に残っている。その後、どうなったかについては、知らない。私はそのT君をとおして、自分の「すなおな子ども論」を、頭の中で完成させた。 従順で、先生の指示にそのまま従う子どもを、すなおな子どもというのではない。心の状態と、表情が一致している子どもを、すなおな子どもという、と。いやだったら、はっきりと、「いやだ」と言う。それを表情や言葉にして、ストレートに表現できる。そういう子どもを、すなおな子どもという。(はやし浩司 家庭内暴力 すなおな子ども 素直な子供 すなおな子供)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司・●21世紀の子育て論(悪しき画一平等主義) 頭のいい子どもは、本当に頭がいい。遺伝子が違うかと思うほど、頭がいい。数年前東京のA中学へ入ったD君も、また昨年同じ中学へ入ったN君も、そうだった。彼らは小学5年のときには、すでに中学3年程度の英語と数学をマスターしてしまっていた。と言っても、特別のことを教えたわけではない。教科書とノートだけを与えておけば、自分で学習していまう。教える側からすれば、これほど楽な生徒はいない。ポイントだけを、それこそ雑談混じりに教えれば、それですんでしまう。 一方、そうでない子どももいる。教えても教えても、ちょうどザルから水がこぼれるように、教えたことが消えてしまう子どもだ。S君もそんなタイプの子ども(中2)だった。たとえば英語の単語でも、一時間かけて数個覚えるのが、限度。しかも次の週にはそっくり忘れてしまっていた。 誤解がないように申し添えるが、私は午前中は幼稚園の教師を勤め、午後は中高校生の塾を開いていた。幼稚園の給料だけでは生活できなかったので、当時の園長と話し合ってそういうふうにさせてもらった。だから一日の流れの中で、私は幼児から高校3年生まで、見ることができた。結果的にそれがよかった。私は幼児を教えながら、いつも「この子どもはこうなるだろう」という予測をしながら教えるようになったし、またそれができるようになった。反対に中高校生を見ながら、「この子がこうなったのは、幼児期のどのあたりに問題があるのか」を考えながら教えるようになったし、それがわかるようになった。 結論から先に言えば、人間の能力は平等ではない。平等であるという前提で教えるから、話がおかしくなる。これも誤解があるといけないので申し添えるが、ただし優劣があるというのではない。先に書いたD君やA君は、たまたま勉強という分野にすぐれた能力を発揮したが、それがすべてではないということだ。D君は運動がまったくダメだったし、N君も、絵がまったく描けなかった。一方勉強ができなかったS君は、学校をサボって、近くの公園でゴルフばかりしていた。もし運動や絵画が主要科目ということになれば、D君やN君は、確実に落ちこぼれということになっていたであろう。そのS君にしても、高校を中退したあと、プロゴルファーの道を歩んだが、25歳そこそこの若さで、100万円以上の月収を手にしていた(85年当時)。 こうした子どもたちを見ていると、問題はもっと別のところにあるように思う。D君にしても、N君にしても、いつも「学校の勉強はつまらない」と言っていた。S君もそうだ。そしてD君もN君も、そしてS君も、結局は学校とは離れた世界で、自分を伸ばすしかなかった。しかしこれはたいへんなエネルギーを要することだ。「能力は平等だ」を歌い文句にしている現在の教育が、一方でこういう子どもたちを生み出している! 繰り返す。子どもの能力は平等ではない。だからそういう前提で、今の学校教育を再編する必要があると思う。またしなければならない。もうあの画一平等主義は、21世紀の日本の実情に合っていない。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) ここに書いたことは、すべて実話である。こうした子育てエッセーを書くとき、気をつけなければならないのは、登場する親や、子どもたちが、だれであるか、それを絶対にわからなくすること。その周辺の人が読んでも、わからなくすること。 が、ここに書いた、D君にしても、N君にしても、彼らの名前の頭文字を、そのままとった。S君については、本名は、M君である。この「悪しき画一教育」については、そのあとも、何度もテーマとして、エッセーを書いた。 で、それから4年。今、学校教育は、急速に変わりつつある。恐ろしいほどの変化と言ってもよい。先生たちの意識も、それに合わせて変わりつつある。いわゆる学校教育そのものが、従来の「画一型」から、多様性をもった、「個性尊重型」に変わりつつある。 と言っても、日本の教育が変わりつつあると考えるのは、正しくない。日本の教育は、戦後、あまりにも(世界の常識)に背を向けすぎていた。それがここにきて、急速に欧米化し始めたと考えるのが正しい。つまり、世界の標準に近づきつつあるということ。またそういう視点で日本の教育をながめないと、日本の教育のこの変化を、正しく理解できない。(はやし浩司 画一教育 教育の欧米化 個性尊重 子どもの能力 日本の教育)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●教育界を吹きすさぶ、むなしい風(目標をなくした教育) できない子どもがふつうになっても、親は「効果があった」とは言わない。ふつうになればなったで、親は「もっと……」と言う。できないままであれば、親は、「効果がなかった」とか、「あの先生はダメな先生」とか言ったりする。できる子どもについても同じ。少しでも成績がさがったりすると、親は大騒ぎする。考えてみれば、こんなむなしい仕事はない。こうした現象は、算数の世界でよく見られる。 計算力というのは、訓練で伸びる。幼稚園児でも掛け算の九九を暗記したり、あるいは小学一年生でも、計算を即座にしたりする子どもがいる。そういう子どもの親は、「うちの子どもは、算数の力(=考える力)がある」と思う。しかし計算力と、算数の力は別。基本的な力がないと、やがてメッキがはがれるように、算数の力は低下する。こういうとき教師は一番、苦労する。親のきびしい視線を、子どもを通して痛いほど、感ずるからだ。 教育、教育と言いながら、親の意識の中にも、「育てる」という意識がない。教育とは、勉強を教えること。子どもの側では勉強をすること。そしてその目的はと言えば、「よい学校に入り、よい大学を出て、よい会社に入社するため」と考える。だからどうしてもそこに成績至上主義がはびこる。成績がよければ善。成績が悪ければ悪、と。こうしたものの見方は明治時代以来、日本の伝統的な教育観として定着している。あの夏目漱石の「坊ちゃん」の中にも、職員会議の席で一人の教師が、「我が校の実績も着実にあがってきております」と発言するシーンがある。この場合、「実績」とは、大学への進学率をいう。 私は一度、ある塾連盟の機関紙にこんな記事を書いたことがある。「何だかんだと言ったところで、日本の教育の柱は人間選別ではないか。もしこの教育界から受験をはずしたら、塾など、あっと言う間につぶれてしまうでしょ。学校教育だってあぶない。もし塾が本当の教育とやらをしたいのなら、受験科目とは関係ない科目で、生徒を集めてみればいい」と。ふつうならあちこちから反論が殺到するが、このときばかりは何も反応がなかった。塾教育そのものを、まっこうから否定したからだ。 話をもとに戻すが、今のような教育体制を続ける限り、この教育界から、この「むなしさ」は消えない。そしてこのむなしさがある以上、教師にやる気など、出てこない。だからいくら外部の人間が教育改革を叫んでも、絵に描いた餅で終わってしまう。考えてみれば昔はよかった。教育がわかりやすかった。進学率を高めることが、教育の目標だった。しかし今は、その目標がない。現場の教師たちが、何に向かって努力したらよいのか、それがわからなくなってしまった。へたに創意工夫をすれば、隣のクラスの父母から文句を言われる。「どうしてうちのクラスでは、してもらえないのか」と。そうそう毎日のように子どもたちを近くの公園へ連れていき、そこで授業をしていた先生がいた。しかし親たちの反対で、あっという間にやめになってしまった。「そんなことすれば勉強が遅れる」と。 創造力豊かな子どもを育てるといったところで、教師自身にそれが許されていないのに、どうしてそれができるというのだろうか。(以上、01年記「子育て雑談」)(補記) ごく最近(05年夏)でも、こんなことがあった。 ある小学校に、オーストラリア人の英語教師が派遣されてやってきた。で、そのオーストラリア人教師が、自分の生徒たちを、近くの公園へ連れて行こうとしたとき、教頭が、それにストップをかけた。「授業は、教室でするように」と。 そのオーストラリア人の教師は、私にこう言った。「野外授業は、オーストラリアでは、みなやっている。当たり前の授業なのに、どうして日本では、だめなのか?」と。 その学校には、その学校なりの、いろいろな事情や規則があったのだろう。「事故でもあったらたいへん」と、その教頭は考えたのかもしれない。オーストラリア人の教師は、こう言った。「オーストラリアの子どもたちの遊びを教えたかったのに……」と。 だからといって、私は、全面的に、そのオーストラリア人の教師の言い分を認めたわけではない。日本人には、「土俵」という考え方がある。「土俵では、相撲のルールに従え」と。そこで私はそのオーストラリア人の教師に、こう言った。「本当に自由な教育をしてみたいと思ったら、英語教室を自分でつくり、生徒を自分で集めること。そこで好きなことをすればいい」と。 この私の考え方は、少し、保守的かな?(はやし浩司 教師の自由 教育の自由 教師のやる気 自由な教育)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+
2024年12月29日
-
最前線の子育て論byはやし浩司(04)
最前線の子育て論byはやし浩司(008)●タイ人拉致は、でっちあげ(?)++++++++++++++++ジェンキンスさんが、自著の本の中で、タイの女性も拉致されたと書いたことについて、K国の中央通信は、「でっち上げ」と主張している。しかし世の中には、ウソで書ける話と、書けない話がある。++++++++++++++++ またまたあのK国が、とんでもないことを言い出した。ジェンキンス氏が、自著の本の中で、実名をあげながら、「タイから拉致された女性がいた」と書いたことについて、「タイ人の拉致は、でっちあげ」と。読売新聞の記事を、そのまま紹介する(12・5・読売新聞)。+++++++++++++++ K国のK国中央通信は2日、拉致被害者の曽我ひとみさんや、夫のチャールズ・ジェンキンスさんらが明らかにした、K国によるタイ人拉致問題について、「でっち上げ」と主張した。 K国がタイ人拉致問題に言及するのは、はじめて。同通信は、ジェンキンスさんを、「我が国で長い間、特別待遇を受け、幸福に過ごしたにもかかわらず、日本では虐待を受け、苦労したなどと言っている」と非難し、著書でタイ人拉致問題を指摘したことについて「我々は信ぴょう性のない、ざれ言だとしか思っていない」としている。 +++++++++++++++ ジェンキンス氏は、本の中で、タイ人の女性について、実名(アノーチェ・パンチョイさん)まであげている。そしてその後の調査で、その女性が実在し、かつK国と関係の深いマカオのホテルを舞台にして、行方不明になっていることもわかった。 世の中には、ウソで書ける話と、書けない話がある。 サンケイ新聞の記事は、つぎのように伝える(11・29)。+++++++++++++++++●「タイ人」、マカオでも 大韓機事件と拉致事件の接点は、拉致被害者の田口八重子さんで、大韓機事件の実行犯、金賢姫元死刑囚の日本人化教育係をさせられていたことが捜査当局の調べで判明している。さらに、最近明らかになったマカオでのタイ人拉致事件の舞台にも、大韓機事件との接点があった。 タイ人女性のアノーチェ・パンチョイさんは78年7月、仕事先のマカオから拉致された疑いがもたれている。「Sホテル」で働いていたアノーチェさんは、日本人を名乗る男に観光ガイドを頼まれ、消息を絶った。男はK国工作員とみられる。 韓国当局は金元死刑囚が84年9月、「蜂谷真由美」名でこのホテルに一週間滞在したことをつかんでいる。田口さんから日本人化教育を受けた1年半後のことだ。 これまでの調べでは、ホテルを出た金元死刑囚は、大韓機事件で服毒自殺したもう一人の実行犯、「蜂谷真一」こと、金勝一工作員とマカオで合流する。二人は西側社会への順応訓練の一環でマカオに現れたのだ。 ホテル周辺には西側情報機関が「K国の工作拠点」とする貿易会社、「朝K貿易公司」があり、ホテルにはたびたび工作員が出入りしていたことが確認されていた。+++++++++++++++++ 何ゆえに、こうまでK国は、強引に、拉致事件を否定するのか? どう考えても、K国の主張には、無理がある。K国中央通信は、こうも書いている。「我が国で長い間、特別待遇を受け、幸福に過ごしたにもかかわらず……」と。 「幸福かどうか」は、本人自身が自覚すること。「幸福だった」と決めつける強引さにも、ただただあきれるばかり。 一連の拉致事件には、K国の最高責任者がからんでいる。それはもう疑いようのない事実である。だからこそ、K国は、こうまで強引に、拉致を否定する。それに日本人や韓国人の拉致については、それなりの言い訳も通る。しかしタイ人となると、そうはいかない。K国の威信は、一気に崩壊する。(すでに粉々に崩壊しているが……。) 言うなれば、現在のK国は、劇画マンガのような国と言ってもよい。何もかもが、現実離れしている。この「でっち上げ」説もそのひとつ。しかしそういうバカげたことを言えば言うほど、今度は、横田めぐみさんのニセ遺骨問題が、ますます国際社会で認知されることになる。そういうことが、まるでわかっていない(?)。 金xxさん、悪あがきは、もうやめなさい!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●韓国経済++++++++++++++++++++ますます中国に傾注する韓国。米韓同盟は、事実上、すでに崩壊している。しかし自由貿易圏内で貿易をしながら、反米、反日を唱えれば、どうなるか?そんなことは、ほんの少しだけ冷静に考えれば、わかるはず。+++++++++++++++++++++ 韓国銀行の発表によると、「実質国民総所得(GNI)の伸び率が、3四半期連続で、0%台にとどまっている」(12月2日)という。 昨年まで、韓国の国民総所得は、3・8%の伸び率で推移していた。ところが、05年度に入ってからは、「第1四半期(1~3月)の0.5%、第2四半期(4~6月)の0.0%、続いて第3四半期も事実上の横ばいとなっている」という。 つまり、ほぼ0%! 実質構内総生産(GDP)が、昨年よりも、4・5%(第3四半期)の伸び率を示している……にもかかわらず、だ。 つまり、国全体としては、お金を儲けている。しかし、そのお金が、国民に届く前に、どこかへ消えてしまう。そういう構図が、そこに浮かびあがってくる。理由は、今さら、ここに書くまでもない。 韓国の(儲け)が、海外へ、流出しているのである。そしてその理由も、今さら、ここに書くまでもない。「流出」ということは、イコール、「逃避」と考えてよい。 韓国銀行は、こうしたお金を、「損失」と考え、つぎのように伝えている。 「第3四半期における実質貿易損失は、12兆4232億ウォンとなる。今年に入ってから第3四半期までの累積損失額は、32兆8580億ウォンにのぼる」と。 まわりくどい言い方をしたが、韓国人自身が、韓国を見捨て始めている。若者の海外移住には歯止めがかからない。頭脳流出も、深刻な社会問題になっている。その上、国内のお金が、どんどんと海外へ流出している! もう少しわかりやすく説明しよう。 あなたは韓国の企業家である。最先端の電子技術を使って、ある製品を製造している。もちろん輸出もしている。 こうして05年度は、1億円、儲けた。しかしそのお金は、アメリカに留学している自分の子どもに、学費として、送金する。あるいはアメリカにいる子どもを通して、外債を買う。あなたは昨夜も、アメリカに住む息子に、電話でこう話したところだ。 「朝鮮半島で、何かあったら、パパも、そちらへ逃げて行くからな」「お前は、そちらの大学を卒業したら、そのままアメリカに残れ」「韓国へは戻ってくるな」と。韓国では、ここ数年、毎年、1万4000人前後が、アメリカを中心として、海外へ移住している。海外定住をめざした留学生も、02年末までに、34万人を越えた。そのため、外貨の流出も、大きな問題になっている。(仮に韓国で大学を卒業して学位を取得しても、アメリカでは通用しない。そのため、アメリカへ移住しても、単純肉体労働につくケースがほとんどだという。) ご存知のように、今、韓国では、一部の大企業のみが、巨額の経常黒字をあげている。その代表的なものとして、S電子工業や、H自動車工業がある。 しかしこれらの企業は、いわゆる「国策企業」であり、国の保護を徹底的に受けている企業である。(国営とまではいかないが、しかし民営とは言えないという点で、「国策企業」と呼ばれている。) が、何よりも深刻なのは、「海外定住をめざした留学生も、02年末までに、34万人を超えた」という事実。日本の人口に換算すると、約120万人ということになる。 もし日本の若者たちが、120万人も、海外定住を目ざし、日本を離れるようになったら、そのとき日本は、どうなるか? それだけでも、たいへんな社会問題になるだろう。しかも、そういう若者たちは、当然のことながら、多額の外貨をもちだす。そのため韓国政府は、一時期、その持ち出し額(送金額)を制限したほどである。 N大統領も、もう少し、「現実」を見たらどうか。今のN大統領をながめていると、かつての社会党政権を思い出す。やることなすこと、どこか現実離れしている。それに中国に傾注するのも、どうかと思う。N大統領にすれば、すばらしい国に見えるかもしれないが、中国は、そんな甘い国ではない。今のチベットや台湾を見れば、それがわかるはず。 中国の経済状況にしても、「国中が、豊田商事のようになっている」(雑誌「S」)とのこと。ウソ、インチキ、まさに何でもござれ。そういう国をまともに信じて接近すれば、大ヤケドをするのは、目に見えている。 私の知ったことではないが、韓国が再び、デフォルト(国家破綻)するのも、時間の問題。しかしN大統領よ、これだけはよく覚えてよい。 今度デフォルトになっても、日本は絶対に、韓国を助けない。私が、猛反対してやる。日本の国連安保理理事国入り問題については、各国に特使まで派遣して反対した。拉致問題のカギを握る、K国工作員容疑者を、日本側の再三再四の要請を無視して、K国へ送り返してしまった。おまけに、アメリカのブッシュ大統領に、「日本の自衛隊を、イラクから撤退させよ」と、陰で要請までした。 やることなすこと、まず、反日、嫌日。どうぞ、ご勝手に! 日本の投資団が、韓国から引きあげたら、それこそ、韓国は、1日も、もたない。 わかっていますか、N大統領!(05年12月5日記)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●土建業+++++++++++++++++++築15年の家の、屋根と軒天の間の漆くいが、はがれて落ちてきた。見ると、ずさんな手抜き工事。「やはり……」と思ってみたり、「なるほど……」と思ってみたり。このところ、土建業を見る目は冷たい。中には良心的な会社もあるのだろうが……。+++++++++++++++++++ 雨どいが、つまるようになった。そこで調べてみると、屋根と軒天の間につめてあった、白い漆くいが、一部、はがれ落ちているのがわかった。で、そのはがれたところを調べてみると、その奥に、紙くずが詰めてあるのがわかった。漆くいの量を減らすためである。 そこであちこち、漆くいが浮きあがっているところを、手ではがしてみた。今にも、はがれ落ちそうなところもあった。が、そこにも、紙くずが詰めてあった。何という、インチキ工事! 15年という年月を超えて、怒りがムラムラと胸の中に充満してきた。 が、こうしたインチキは、この業界では、常識。ずさんな手抜き工事となると、これまたそれ以上に、常識。その頂点にあるのが、談合問題。今、問題になっている、耐震強度偽造問題にしても、こうした一連の業界の体質の中から生まれた問題と考えてよい。 つまりこの業界、上から下まで、インチキのかたまり。上が上だから、下も下ということになる。たとえば業者に、庭に入れる砂利を注文してみるとよい。業者は、あなたの顔色を見て、値段を決めるはず。あなたが個人の素人とわかると、容赦なく、高額の値段をふっかけてくる。 私も、何度か、業者にそれを頼んだことがある。が、最初に、庭屋に頼んだら、1立方メートル、2万8000円も取られた。つぎに生コン会社に頼んだら、1万6000円。最後に、砕石工場まで直接買いに行ったら、たったの2700円。もちろん最後の2700円には、運搬費用は含まれていない。しかしそれにしても……! こういうことばかりしているから、この業界は、ますます信用されなくなる。もちろんそこで働く人たちも、信用されなくなる。これについて、ワイフは、「田中角栄の列島改造論が原因ではないかしら?」と言った。 私はそれ以前のことはよく知らない。しかし、土建業の「質」が悪いのは、事実。それも年々、巧妙かつ、悪質になっている。こんなこともあった。 山荘の土地作りをしているときのこと。水道パイプの埋設を、一部、業者に頼んだことがある。その部分は、いろいろ事情があって、自分たちでは、できなかった。距離は、17メートルほどではなかったか。 すると彼らはすぐ、設計図とともに、見積書をもってきた。設計図そのものは、たいそうなもので、私はそれを見て、「なるほど、水道工事というのは、こういうふうにするものか」と、感心した。一番底に、砂を20センチ厚で敷いて、その上に水道管を置き、それをさらに20センチ厚の砂でおおったあと、25センチほど、土で埋める、と。工事費は、47万円弱。(山の中の工事だから、そこまでていねいにする必要はなかったのだが……。) しかしできあがったところで、村の住人の1人が怒ってきた。「話が、ちがう!」と。あわてて夜中に、工事現場へ行ってみると、一部、水道管が掘りかえしてあった。私はそれを見て、あ然とした。 水道管は、少なくとも、地表から、45センチ下になければならない。しかし手で10~15センチも掘ると、水道管が見えた。それに砂など、どこにも使ってない! 業者は、私の立会いがないことをよいことに、好き勝手な手抜き工事をしたらしい。翌日一番に、その業者に抗議の電話を入れると、担当の男は、悪びれる様子もなく、こう言った。 「すみません、あの仕事は、うちの下請け業者に任せたものですから。すぐやりなおしさせますから」と。 この「下請け業者にさせた」という話は、ウソである。私はその会社の男が、直接工事しているところを、ちゃんと目撃している。 ……とまあ、不愉快な話を書いたが、この業界では、こういうことが当たり前と考えたほうがよい。またそういう前提で、仕事を頼む。それがいやなら、自分ですること。少なくとも、私は、そうしている。 そしてその原因は、つまりこの業界が、なぜ、こうまで悪質になってしまったかという原因は、談合を頂点とする、官僚、政治家、そしてゼネコン、これら3者の癒着(ゆちゃく)がある。まさにここにも書いたように、上が上だから、下も下ということになる。その「上」が改まらないかぎり、結局は、そのしわ寄せは、私たち、庶民のところにやってくる。つまり泣くのは、いつも私たちということになる。 軒天の下の漆くいを、手ではがしながら、私はワイフにこう言った。「そのときは、ぼくたちを、うまくごまかしたつもりなんだろうけどね」と。【付記】 人間がもつ誠実さというのは、その世界で、熟成されるものと考えてよい。つまりつきあう相手によって、大きく、感化される。……されやすい。 誠実な人には、誠実にこたえようとする。が、不誠実な人と接していると、誠実にこたえようとする力(モーメント)が、働かなくなる。 こんなことがあった。詳しくは書けないので、話を少し改変する。内容に不自然なところがあるのは、そのため。どうか、ご容赦、願いたい。 私はある男性の知人に、ある仕事をしてもらうために、その男性に、100万円を渡したことがある。もちろん、別に、その男性には、礼金として、20万円ほどを渡した。が、その男性は、100万円からさらに、自分の取り分として、20万円を引いて、その先の知人に渡した。 相手の知人は、80万円を受け取ったことになる。その男性は、計40万円を自分のものにしたことになる。 それ以来、私は、その男性を、まったく信用できなくなった。当然である。が、それだけではない。何かにつけ、その男性に対して、ウソをつくのが、平気になってしまった。「誠実でいよう」というブレーキが働かなくなってしまった。 ときどき「会いたい」という電話があっても、平気で居留守を使ったり、ウソの用事を並べたりして、断るようになった。しかしそういうウソをつくのは、私の主義に反する。そこで、私は、その男性とは、距離を保つようにし、やがて別れた。その男性がイヤになったというよりは、ウソをつく自分がイヤになったからである。 自分の中の誠実さを守り、育てるのは、たいへんなこと。(だからといって、私が誠実な人間であると言っているのではない。誤解のないように!)そしてその誠実さというのは、つきあう相手によって、大きく影響を受ける。 だから、……というわけでもないが、つきあう相手を選ぶということは、たいへん重要なことである。わかりやすく言えば、誠実な人間になりたかったら、不誠実な人間とはつきあわないこと。それが親類であれ、兄弟であれ、ひょっとしたら、親子であっても、だ。つきあうとしても、どこかで強いブレーキをかけながら、つきあう。 一度、不誠実な人の世界で、自分を見失ってしまうと、それこそ取りかえしのつかないことになってしまう。さらにそれが当たり前になってしまうと、何がなんだか、わけがわからなくなってしまう。タヌキとキツネの化かしあい……そうなってしまう。 そこで子育ての場では、当然といえば、これほど当然のことはないが、ウソはタブー中のタブーと考える。親は、かぎりなく、どこまでも、子どもに対しては、誠実でなければならない。これは子育ての中でも、イロハ中の「イ」と考えてよい。 きわめて具体的な例として、こんなことがあった。 その家の5歳になる子ども(男児)が、父親の手帳を勝手に机から取りだして、落書きをしてしまったことがある。 それについて、その子どもの母親は、私にこう言った。 「本当は、何でもない手帳だったのですが、これから先、そういうことがあってはいけないと思い、私は、息子にこう言ってやりました。『これはパパが会社で使う、大切な手帳なのよ。それに落書きしたから、パパは、会社で社長に叱られるのよ。罰金を取られるかも知れないのよ』と。息子は、しおらしい顔をして、うなだれていました」と。 私は、その話を聞いて、その母親を信用しなくなった。自分の子どもすら、だますような母親である。私のような他人をだますのは、朝飯前だろう、と、私は考えた。 さらにこれは私の人生訓のひとつにもなっている。私は、不倫を遊びでするような男を、まったく信用しない。(本気で恋愛……というのなら、まだ許せる。あの『マジソン郡の橋』に出てくる、キンケードとフランチェスカのように……。) 自分の妻すらも平気でだますような男である。友人たる私をだますのは、もっと平気なはず。私は、そう考える。 加えて一言。 誠実な世界で、誠実に生きるのは、本当に気持ちのよいもの。すがすがしさすら覚える。そういう世界から、不誠実な人の世界を見ると、悪臭がプンプンしているのがわかる。誠実であるに、越したことはない。(はやし浩司 誠実 誠実論)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●日本語の乱れ+++++++++++++++++たしかに、日本語が乱れている。それはわかる。しかし……。いろいろ議論されているが、どれもどこか的をはずれているようにも、感ずる。本当に、日本語は乱れているのか?+++++++++++++++++ 中学生レベルの国語力しかない学生が、国立大で …… 6% 4年生私立大で……20% 短大で ……35%「大学生の日本語力が低下し、中学生レベルの国語力しかない学生が国立大で6%、四年制私立大で20%、短大では35%にのぼることがわかった」というのだ。調査したのは、独立行政法人「メディア教育開発センター」(千葉市)のON教授(コミュニケーション科学)ら。(注……04年度に入学した33大学・短大の学生約1万3000人を対象に、中1から高3相当の問題を盛り込んだテストを行い、02年度に中高生に実施したテスト結果と照らし合わせて、レベルを判定したという。)たとえば「憂える」の意味を「喜ぶ」と思いこんでいる学生が多いなど、外国人留学生より劣る実態で、授業に支障が出るケースもあるという。同教授は「入学後の日本語のリメディアル(やり直し)教育が必要」と指摘する。その結果、中学生レベルと判定された学生は、5年前に行われた調査と比較して、国立大が0・3%から6%、私立大が6・8%から20%、短大が18・7%から35%と、数年間で大きく増加していることが分かったという。Yahoo・ニュースは、「テストでは『憂える』の意味を問う設問で、『中学生レベル」』と判定された学生の3人に2人が『うれしい』に音感が近いためか『喜ぶ』を選択。『大学生レベル』とされた学生の中でも正答率は50%にとどまり、文字通り"憂える"結果となった」と伝えている。【問題の例】 ☆露骨に(1)ためらいがちに (0%)(2)おおげさに (83.3%)〔3〕あらわに (16.7%)(4)下品に (0%)(5)ひそかに (0%) ☆憂える(1)うとましく思う (16.7%)(2)たじろぐ (0%)(3)喜ぶ (66.7%)〔4〕心配する (0%)(5)進歩する (16.7%) ☆懐柔する(1)賄賂をもらう (50.0%)(2)気持ちを落ち着ける(33.3%)(3)優しくいたわる (16.7%)〔4〕手なずける (0%)(5)抱きしめる (0%)(カッコ内は中学生レベルと判定された学生が回答した割合、〔 〕数字が正解) *小数点計算で合計は必ずしも100にならない(以上、Yahoo ニュースより) 私も、最近の子どもたちが口にする日本語には、かなり問題があると考えている。しかしそれは、個々の言葉の使われ方にあるのではなく、文全体として、問題があると考えている。数日前にも、それについて書いた。「先生、終わったら、どうするのですか?」と言った子どもがいたので、私は、こう答えてやった。「先生は、まだ終わらない。元気でピンピンしている。先生が終わったら、葬式でもしてくれればいい」と。 こうした言い方の代表的なもののひとつに、「先生、オシッコ!」というのがある。「トイレへ行きたい」と言うべきときでも、子どもたちは、「先生、オシッコ!」と言う。だから、すかさず、私は、こう言う。「私は、オシッコではない。人間だア!」と。 で、最初の話題。つまり国語力。 「日本の論点」(04)は、「国語に関する世論調査」(04)の結果について、報告している。そして「誤った敬語を含む例文を、正しいと思う人が目立つ」と。 たとえば…… 「先ほど、中村さんがお話しされたように、この本は、とても役にたちます」(まちがい)→正しくは「お話しになったように」 「先生が、お見えになります」(まちがい)→正しくは「先生が、見えます」 「ご乗車できません」(まちがい)→正しくは「ご乗車になれません」 しかしこうした議論を一巡すると、つまり、あれこれ議論をしつくすと、そこに、ふと、こんな疑念がわいてくる。つまり、これは国語力の問題ではなく、日本語そのものがもつ、欠陥(けっかん)ではないか、と。 たとえば英語で、「I go to Tokyo.」は、 「私、東京、行く」 「東京、私、行く」 「東京、行く、私」と、どんな言い方をしても、意味が通じてしまう。私が住む浜松市では、こうした言葉の間に、(ジャン)(ダニ)を入れる。たとえば、「私、東京、行く」は、「私、東京、行くジャン」と。 こうした言葉としての欠陥は、100年単位でみると、さらによくわかる。この日本では、たった100年前に書かれた文章ですら、辞書なしでは、理解することができない。200年前、300年前の文章となると、さらに、そうである。 流動的というよりも、言葉としての一貫性が、まだ確立されていない。だから今の今も、日本語は、乱れつづけている。 で、問題は、それが悪いことなのかどうかということ。最近では、コンビニ言葉につづいて、オタク言葉、さらにはネット言葉というのも、生まれている。そしてそういう言葉が、表に出てきて、日常会話の中でも使われるようになってきている。 ためしに中学生たちが話している会話に、そっと耳を傾けてみるとよい。多分、あなたは、彼らが、何を話しているか、その意味すらわからないのではないだろうか。たとえば、彼らは、こんな話し方をする。「私、あいつにコクられて、いやだった。だって、フタマタよ。それをXXのヤツ、チクってね。あとは、シュラバ。私には、ラブな人、ちゃんといるのよ。私、マッチョは嫌い。腹筋が、8つに分かれている男なんて、サイテー。頭にきたから、デニルしてね。あとは、シカト……」と。 ついでに、若い人たちの間で、よく使われる言葉について、調べてみた。私が中学生たちから、直接、聞き取り調査したものである。 コクル……告白する。 デニル……デニーズ(レストラン)に行く。 マクル……マクドナルドに行く。 カリパク……借りたあと、返さないで、もっていること。 パクル……盗む。 シュラバ……自分のまずいところを見られること。 フタマタ……浮気のこと。二人の異性とつきあうこと。 チクル……告げ口をする。 パシリ……下っ端のこと。子分的な人のこと。 アリガチ……ありえること。 シカト……無視する。 ラブな人……好きな人。 A(エイ)……手を握るつぎの段階。(つぎに、B、Cへと進む。) マッチョ……筋肉質の人。 もっとも、今の若い人たちは、日常的に、そういう言葉、つまり、「テメエ、殺すぞ」式の言葉を使っている。ドキッとする言い方だが、これも、ごく日常的な言い方で、特別な言い方ではない。が、その一方で、旧来型の日本語を知らないからといって、国語力が落ちていると判断するのも、どうかと思う。 つまり言葉というのは、いつも大衆が先導して決めるもの。そしてその大衆は、いつも、若い世代によって、先導される。つまり一部の学者が、おかしいと言うなら、それを言う学者のほうが、おかしいということになる。「国語に関する世論調査」(04、ON教授ほか)でも、敬語の使われ方を問題にしている。 これについても、「敬語は、日本語の美しさを代表するものだから、守るべき」という意見と、「敬語など、もうどうでもよいではないか」という意見の2つが、するどく対立している。私自身は、めったに敬語など使わない。天皇についても、「天皇が浜松へ来た」と書くことはあっても、「天皇陛下が、浜松へ、おいでになりました」と書いたことは、一度もない。 敬意を表す、表さないということではなく、どこでどのように一線を引くか、それを考えるのが、めんどうだからに過ぎない。いちいちそういうことを考えながら文を書くというのも、たいへん疲れる。それに敬語の底流にあるのは、日本人独特の、上下意識。敬語を考えるときは、いつも、その上下関係を考えなければならない。だから敬語は、無視。大きな流れとしても、敬語は、この先、消えゆく運命にある。 だから「国語に関する世論調査」そのものが、どこか、おかしい。その調査では、「敬語の使われ方がおかしいから、日本語が乱れている」というような結論を出したかったのかもしれない。しかし最近の若い人に言わせると、「今どき、敬語なんて……」ということになる。 だから視点を変えてみたら、どうだろうか。つまりここにも書いたように、個々の言葉の使われ方を問題とするのではなく、文全体として、的確に自分の意思を相手に伝えることができるかどうかという視点で、である。その際、どんな言葉が使われようが、それは問題ではない。 「今日、学校あった」(まちがい)→「今日、学校で、授業がありました」 「これは、パパが建てた家」(まちがい)→「これはパパが、買った家」 「これは、私の学校」(まちがい)→「これは、私が通っている学校」と。 で、反対に、これを調査した、「メディア教育開発センター」のON教授に、こんなテストをしてみたら、どうだろうか。はたして、ON教授は、何点取れるだろうか?【問題の例】☆ムッチョ(1)むっつりしているさま(2)貯金がないこと〔3〕筋肉がモリモリしているさま(4)いやがっていること(5)怒っている様子☆コクル(1)告発する(2)忠告する(3)密告する〔4〕告白する(5)納得する☆カリパク(1)食べ物の名前(2)借りて返すこと(3)カリカリと怒ること(4)道路で座ってものを食べること〔5〕借りて返さないこと☆アリガチ(1)ありがた迷惑(2)ありがとう〔3〕ありえること(4)ありえないこと(5)いらぬ節介のこと☆フタマタ(1)2つのことを同時にすること(2)2人の人と、同時につきあうこと〔3〕浮気すること(4)2つの選択肢のこと(5)いやなこと☆シュラバ(1)喧嘩すること(2)がんばること(3)ここ一番というとき(4)苦労すること〔5〕何か、まずいことがバレること 日本語も、どんどんと変化している。もともと日本語という言語は、そういう言語であるということ。調査では、「憂える」の意味を知らないことを問題にしているが、実際、若い人たちが使わない言葉であれば、それもしかたないのではないか。 さらに一言つけ加えるなら、私自身は、旧世代の人たちは、もう少し、若い人たちに、謙虚であるべきではないかと思っている。繰りかえしになるが、「自分たちは知っている。しかし今の若い人たちは知らない。だから今の若い人たちは、おかしい」という論法自体が、おかしいということになる。どこかものの考え方が、復古主義的? ただし世の親たちに一言。 高校入試にせよ、大学入試にせよ、そこで使われる入試問題は、こうしたどこか頭の古い、旧世代の人たちによって作られている。だから、子どもの(進学)ということを考えるなら、体制に迎合したほうがよい。そのほうが、あなたの子どももスイスイと、学歴社会を生きぬくことができる。 そのためにも、あなたの子どもには、ここに書いたように、正しい言葉で、かつ豊かな言葉で話しかけるとよい。「テメエ、殺すぞ」ではなく、「あなたが、そうすれば、あなたは、私によって、殺されますよ」と。 なお、上から(3)(4)(5)(3)(3)(5)の、〔かっこ〕が正解。(はやし浩司 国語力 日本人の国語力 表現力 敬語 日本語の乱れ はやし浩司 子供の国語力 子どもの国語力)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(009)【近ごろ・あれこれ】●VIDEO「フォーゴットン」を見る パッケージに、「シクス・センス以来の……」とか何とか書いてあったので、借りてきた。タイトルは、『フォーゴットン』。 お金もかけている。ていねいに製作してある。しかし途中から、「?」マークの連続。おおまかなストーリーは、こうだ。 ある母親の1人息子が、飛行機事故で死ぬ。母親は、毎日、息子のことを思い、嘆き悲しむ。しかしある日、母親が、息子が写っているはずの写真を見ると、そこに写っているはずの息子が写っていない。ほかにも、ありとあらゆる場所をさがしてみるのだが、息子に関する思い出の品々が、すべてない。ビデオやアルバムからも、息子に関するものは、すべて消されている。 精神科医に相談しても、「あなたには息子などいなかった。息子がいたと思うのは、幻覚だ」「飛行機事故など、なかった」と、逆に諭(さと)されるしまつ。わけがわからなくなった母親は、ひとりで、息子さがしを始める。 ワイフは、「X-ファイルみたいな映画」と言った。たしかにそうだ。「宇宙人のしわざ」とは、最初から最後まで言わなかったが、宇宙人のしくんだ、しわざということは、見ているうちに、わかる。 では、なぜ、宇宙人は、その息子も含めて、一度に、10人近い子どもたちを、拉致(らち)したかだが、結論は、「親子の絆を試す実験」、だそうだ。つまり子どもを拉致しておいて、親は、どこまでその絆を保つことができるか、それを知るための実験、と。 しかしこのあたりから、「?」マークの連続。宇宙人の男は、その母親のまわりから、つぎつぎと、息子に関する思い出の品々を消していく。が、それだけではない。その息子のことを知る人たちからも、その息子に関する記憶を消していく。 母親が、近所の人に息子のことをたずねても、近所の人たちは、みな、「知らない」と言う。けげんそうな顔をするばかり。 しかしここで第一の「?」マーク。飛行機事故の新聞記事はもちろんのこと、その息子を知る人すべてから、息子の記憶を消すなどということは、いくら宇宙人のしわざといっても、不可能。近所の人たちや、親戚の伯父や伯母は、どうする? 学校の友人たちは、どうする? その友人たちの家族はどうする? 飛行機事故のことを知った、アメリカ中の人たちは、どうする? つぎつぎとそのワクが、無限に広がってしまう。 そういう子どもが、10人以上、である。 最後に、母親から息子の記憶を消すことに失敗したという罪(?)で、その宇宙人の男は、処罰されて、天へと消えていく。(タイトルの『フォーゴットン』は、「忘れ去る」という意味か?) しかし、どうして? たかが記憶を消す実験に失敗したくらいのことで……? またそんな実験をしたところで、どういう意味があるというのか? パッケージには、たしか、二転、三転のミステリーが隠されているというようなことが書いてあったと思う。しかしストーリーそのものは、単純。もう少し何か、ウラがあると期待していたが、そういうものは、まったくなかった。 そのため、★は、残念ながら、1つ。少し前、メル・ギブソン主演の『サイン』という映画も、そうだった。思わせぶりなシーンから映画は始まったが、見ているうちに、やはり「?」マークの連続。とくに、明らかにぬいぐるみとわかる宇宙人との格闘シーンでは、思わず、笑ってしまった。 『フォーゴットン』でも、「宇宙人ともあろう知的生物が、なぜそんなことをしなければならないのか?」という疑問が生まれたとたん、興がさめてしまった。『サイン』のほうは、加えて、実に安あがりの映画という感じもしたが……。 ハリウッド映画の技術力には、ものすごいものがある。それはこの『フォーゴットン』を見ても、わかる。しかしこと宇宙人ものに関しては、知的レベルは、それほど、高くない。つまりハリウッドの映画制作者たちの知的レベルは、それほど高くない。 さあ、今なら、日本映画よ、ハリウッド映画に追いつけるぞ! がんばれ!●金が、グラム、2095円! 25年ほど前、金(きん)を、地金で、x00グラムほど買った。当時、たしか、グラム2300円くらいではなかったか。私にとっては、たいへんな買い物で、それなりに覚悟して買った。 しかしその後、金の価格は、ジリジリと下降の一途。新聞で見るたびに、さがっていった。で、やがて見るのもいやになって、その金の地金は、金庫の一番奥にしまいこんでしまった。 その金。一時は、グラム1000円近くまで、さがった。つまり私はその時点で、買った価格の、半値以上を損したことになる。 しかし、である。ここにきて、金価格が、急上昇。インドや中国での金需要に加えて、円安。今日あたり、1ドルが121円前後で取り引きされている。おかげで、金価格が、グラム、2095円まで、回復(田中貴金属・12月5日調べ)。喜んでいいのか、悪いのか、本当のところはよくわからないが、ひとまず、ほっとしている。 が、残念に思うこともある。当時、金を買いに行ったら、店のおやじが、「林さん、金ではなく、プラチナにしておきなさい。金は、まだまだ埋蔵量が残っていますが、プラチナは、もうありませんから」と。 当時は、金とプラチナの価格差は、ほとんどなかった。ややプラチナのほうが高いかなと思った程度。しかしそのプラチナが、今は、グラム4137円! その価格を見ながら、改めて、ため息。「あのおやじさんの言うことを聞いておけばよかった」と。 まあ、こうした投資は、いわばバクチのようなもの。こういうもので儲けをアテにしてはいけない。儲けをアテにすると、結局は、ヤケドする。あくまでも小遣いの範囲で……というのが、私のモットー。あのバブル経済のころも、多少、株取引で儲けたこともあるが、そのバブルがはじけたとたん、大損。あとで差し引きを計算してみたら、マイナスだった。 (最後に、証券会社が、勧めてくれた株を買ったのがまちがいだった。つまりその証券会社は、いわゆるクズ株を私のような素人に押しつけ、自分は売り逃げた。そういうことも重なった。それで大損をした。ハイ。)●「存在に値しない生き方」 私のワイフが、どこかで、こんな言葉を聞いてきた。「存在に値しない生き方」と。 インターネットでその言葉を検索してみたが、見つからない。ワイフに聞くと、「映画のタイトルじゃ、なかったア?」と。どこか心もとない。しかし私は、この言葉に、ドキッとした。ズバリ、核心をつかれたような気分。 つまり私の周囲には、そういう生き方をしている老人たちが、多い。あまりにも多い。で、私は、「ああは、なりたくない」と、いつも思っている。しかしこのままいけば、私も、ああなる確率は、きわめて高い。私が、そうした老人たちとちがう点は、ほとんど、ない。もう少し正確には、そういう老人たちでも、私の年代の時には、私より、もっとマシな生き方をしていた。 が、どういうわけか、あるときから、人は、その「存在に値しない生き方」になってしまう。どうしてだろう? 体力や気力が衰えるためだろうか。知力や行動力、それに好奇心が衰えるためだろうか。が、それだけでもないような気がする。 何か、もっと大きな作用が働いて、老人は老人ぽくなっていく? そしてだれの目から見ても、「存在に値しない生き方」になってしまう。 が、これではいけない。老人というのは、人生の大先輩である。その大先輩が、これから生きる、つぎの世代の人たちのために、生きるヒントを何も伝えることができないというのは、どう考えても、おかしい。その存在感がないというのは、どう考えても、おかしい。 これは私にとっても、たいへん大きなテーマである。老後は、すぐそこまで迫ってきている。ぼやぼやしているヒマなど、ない。 さあ、どうしよう?、……と考えたところで、今日の原稿書きは、おしまい。はやし浩司は、これからも考えつづけるぞ!Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司***********************++++++++++++はやし浩司
2024年12月29日
-
●最前線の子育て論byはやし浩司(03)
●失敗にめげず、前に進め!++++++++++++++++++ある女の子(小6)が落ちこんでいた。学校で、何か、あったらしい。そのとき、ふと、私は、あのスティーブンソンの言葉を思い出した。『私たちの目的は、成功ではない。失敗にめげず、前に進むことである』である。++++++++++++++++++●私たちの目的は、成功ではない。失敗にめげず、前に進むことである ロバート・L・スティーブンソン(Robert Louise Stevenson、1850-1894)というイギリスの作家がいた。『ジキル博士とハイド氏』(1886)や、『宝島』(1883)を書いた作家である。もともと体の弱い人だったらしい。四四歳のとき、南太平洋のサモア島でなくなっている。そのスティーブンソンが、こんなことを書いている。『私たちの目的は、成功ではない。失敗にめげず、前に進むことである』(語録)と。 何の気なしに目についた一文だが、やがてドキッとするほど、私に大きな衝撃を与えた。「そうだ!」と。 なぜ私たちが、日々の生活の中であくせくするかと言えば、「成功」を追い求めるからではないのか。しかし目的は、成功ではない。スティーブンソンは、「失敗にめげず、前に進むことである」と。そういう視点に立ってものごとを考えれば、ひょっとしたら、あらゆる問題が解決する? 落胆したり、絶望したりすることもない? それはそれとして、この言葉は、子育ての場でも、すぐ応用できる。 『子育ての目的は、子どもをよい子にすることではない。日々に失敗しながら、それでもめげず、前向きに、子どもを育てていくことである』と。 受験勉強で苦しんでいる子どもには、こう言ってあげることもできる。 『勉強の目的は、いい大学に入ることではない。日々に失敗しながらも、それにめげず、前に進むことだ』と。 この考え方は、まさに、「今を生きる」考え方に共通する。「今を懸命に生きよう。結果はあとからついてくる」と。それがわかったとき、また一つ、私の心の穴が、ふさがれたような気がした。 ところで余談だが、このスティーブンソンは、生涯において、実に自由奔放な生き方をしたのがわかる。17歳のときエディンバラ工科大学に入学するが、「合わない」という理由で、法科に転じ、25歳のときに弁護士の資格を取得している。そのあと放浪の旅に出て、カルフォニアで知りあった、11歳年上の女性(人妻)と、結婚する。スティーブンソンが、30歳のときである。小説『宝島』は、その女性がつれてきた子ども、ロイドのために書いた小説である。そしてそのあと、ハワイへ行き、晩年は、南太平洋のサモア島ですごす。 こうした生き方を、100年以上も前の人がしたところが、すばらしい。スティーブンソンがすばらしいというより、そういうことができた、イギリスという環境がすばらしい。ここにあげたスティーブンソンの名言は、こうした背景があったからこそ、生まれたのだろう。並みの環境では、生まれない。 ほかに、スティーブンソンの語録を、いくつかあげてみる。●結婚をしりごみする男は、戦場から逃亡する兵士と同じ。(「若い人たちのために」)●最上の男は独身者の中にいるが、最上の女は、既婚者の中にいる。(同)●船人は帰ってきた。海から帰ってきた。そして狩人は帰ってきた。山から帰ってきた。(辞世の言葉)Hiroshi Hayashi++++++++++Nov. 05+++++++++++++はやし浩司●ウィルスが、130個! 長男が新しいプリンターを買った。「パソコンショップへ行く」と言うので、ついて行った。 長男は、パソコンでゲームをするのが趣味。で、長男があれこれパソコンを選んでいる間、私は、ウィルス駆除ソフトを購入。買いに行くとき、長男が、「前のウィルス・チェックソフトは、期限が切れたので、今は、使ってない」などと、のんきなことを言っていた。それが、気になった。それで購入した。 で、家に帰って、プリンターは、簡単に取りつけられた。手伝った。しかしどうも、動作が重い。パソコンが、勝手なことばかりしているといった感じ。 そこで先ほど購入してきた、ウィルス・チェックソフトを、インストール。アプデイトして、さっそく、検査。 その間、私は居間に帰り、いとこが送ってきてくれた柿を食べる。雑誌を読む。ワイフと話す。 やがて長男が居間にやってきた。どこか暗い表情をしている。「どうだった? ウィルスは発見できたか?」と声をかけると、「130個も発見された……」とポツリ。 よほどショックだったらしい。 私は、しかし思わず、笑ってしまった。「130個だってエ~!!」と。「大半は駆除したが、残りは、隔離した」と、長男。またまた笑ってしまった。「あのなあ、たった1個でも、たいへんな問題だよ。ウィルスによっては、パソコンの起動そのものを、おかしくしてしまう。それが130個だなんて……、ハハハ」と。 もっともそのパソコンは、ゲーム用のパソコン。ウィルスが入っていたところで、実害はないが、しかしそれにしても……! 130個とは! 私だったら、たった1個でも、リカバリー(再セットアップ)してしまうだろうに……。Hiroshi Hayashi++++++++++Nov. 05+++++++++++++はやし浩司●晩年論+++++++++++++++++このところ、生きる気力が薄れてきた?そんな感じがしないでもない。+++++++++++++++++ HIVの陽性者になっても、すぐ死ぬとはかぎらない。適切な治療をすれば、10年、20年と、生きながらえることができる。要するに、発症を抑えるということだそうだが、私は少し前、この話をあるドクターから聞いたとき、「では、私はどうなのか?」と考えた。 私は現在、満58歳。一応平均寿命で計算すれば、あと20年※は生きられることになる。しかしその20年間、ずっと健康というわけではない。その前日まで元気で、その日ポックリと死ぬというふうには、いかない。多分、これも平均的な老人をみるとわかるが、その前、5~10年は、闘病生活をすることになる。ということは、私がまあまあ元気なのは、これから先、長くても、10~15年ということになる。つまり立場は、HIVの陽性者と、どこも違わない。 が、20代の若い人が、HIVの陽性者になったら、人生を悲観する。私だったら、悲観して、頭がおかしくなっただろう。しかし今、私は、同じような立場だが、それほど悲観しない。この違いは、どこからくるのか。 これはあくまでも私のばあいだが、もし神様がいて、私に、もう一度同じ人生を繰りかえせと言ったら、私は、多分、断るだろうと思う。今の思考状態のまま、青春時代にもどれるなら話は別だが、しかしあんな無知で、無学で、未熟で、未経験な、動物のような世界にもどれと言われても、困る。とくにあの高校時代は、ごめん。あの高校時代にもどるくらいなら、死んだほうが、まし。本気でそう思っている。 そういう自分の心理を分析してみると、いろいろ気がつくことがある。まず、生きる気力そのものが、薄れてきたこと。変化や冒険よりも、静かな安定を望むようになってきている。行動に、融通がきかなくなってきている。行動範囲が、狭くなってきている。今まで経験した範囲のことで、それを繰りかえすことはできるが、その範囲を超えると、とたんに、不器用になる。「それではいけない」と思うこともあるが、それよりも大きな力が、私に働くようになる。 こうした変化は、たとえば人間関係にもあらわれる。一度、その人との人間関係がこじれると、修復しようという気力そのものが、生まれてこない。むしろ、こちらから積極的に、切ってしまうこともある。多分、それは、時間に限りを感ずるためではないか。「もう、ムダにする時間はない」という思いが、私をして、そうさせる。 あとは、居直りが強くなる。「私は私だ」と。中には私のことを、よく思っていない人がいる。(そういう人は多い!)しかしこのところ、「そう思いたければ、勝手にそう思え」と考えるようにしている。ここでも、あまり修復しようという思いは、生まれてこない。そういうことをするのがめんどうというより、そういうことをしている時間がない。ヒマがない。 ……で、こうした自分自身の老人性と、どう戦うか、である。そのときポイントとなるのが、やはり健康である。体の健康もさることながら、心の健康である。この年齢になると、心も病みやすい。そういう人は、いくらでもいる。いや、すでに私の心も病んできるのかもしれない。今のところ、多分、だいじょうぶだとは思うが、心の健康を守ることが、老人性と戦うひとつの方法ではないか。恩師のT先生は、「(老人性と戦うには)、新しい情報を入れることです」と言ったが、私もそう思う。常に、新しいことに興味をもち、それにチャレンジしていく。そういう前向きな姿勢が、心の健康を保つ。 体の健康は、これは適切な運動をすることで守る。心の健康は、毎日、前向きな生き方をすることで守る。なるほど! ……と、自分で感心していては、しかたないが、今、そういう結論に達した。 話がどんどんと脱線してしまったが、要するに、平均寿命とか、老人性とか、そういうことは考えてはいけない。晩年論も、くだらない。もともとそういうものは、人間が勝手に決めた尺度にすぎない。私は、いつでも、どこでも、何歳になっても、私なのだ。だから私は、HIVの陽性者になった若い人のようには、自分の人生を悲観しない。する必要もない。とにかく毎日を、ただひたすら燃焼させて生きていく。それだけのこと。(この原稿は、2年前に書いたものを、書き改めたものです。)●40歳は青年の老齢期であり、50歳は老年の青春期である。(ユーゴー「断片」)※厚生省が「1999年簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は、女性が83.99歳、男性が77.1歳、男女平均で80.55歳) +++++++++++++++++++++++++++++++++++はやし浩司●依存心+++++++++++++++++俗に言う、甘えん坊。依存性の強い子どもというのは、たしかにいる。その依存心について、一考。+++++++++++++++++ 依存心の強い子どもは、独特の話し方をする。おなかがすいても、「○○を食べたい」とは言わない。「おなかが、すいたア~」と言う。言外に、(だから何とかしろ)と、相手に要求する。 おとなでも、依存心の強い人はいくらでもいる。ある女性(六七歳)は、だれかに電話をするたびに、「私も、年をとったからネエ~」を口グセにしている。このばあいも、言外に、(だから何とかしろ)と、相手に要求していることになる。 依存性の強い人は、いつも心のどこかで、だれかに何かをしてもらうのを、待っている。そういう生きざまが、すべての面に渡っているので、独特の考え方をするようになる。つい先日も、ある女性(六〇歳)と、北朝鮮について話しあったが、その女性は、こう言った。「アメリカが何とかしてくれますよ」と。 自立した人間どうしが、助けあうのは、「助けあい」という。しかし依存心の強い人間どうしが、助けあうのは、「助けあい」とは言わない。「なぐさめあい」という。一見、なごやかな世界に見えるかもしれないが、おたがいに心の弱さを、なぐさめあっているだけ。総じて言えば、日本人がもつ、独特の「邑(むら)意識」や「邑社会」というのは、その依存性が結集したものとみてよい。「長いものには巻かれろ」「みんなで渡ればこわくない」「ほかの人と違ったことをしていると嫌われる」「世間体が悪い」「世間が笑う」など。こうした世界では、好んで使われる言葉である。 こうした依存性の強い人を見分けるのは、それほどむずかしいことではない。●してもらうのが、当然……「してもらうのが当然」「助けてもらうのが当然」と考える。あるいは相手を、そういう方向に誘導していく。よい人ぶったり、それを演じたり、あるいは同情を買ったりする。「~~してあげたから、~~してくれるハズ」「~~してあげたから、感謝しているハズ」と、「ハズ論」で行動することが多い。●自分では何もしない……自分から、積極的に何かをしていくというよりは、相手が何かをしてくれるのを、待つ。あるいは自分にとって、居心地のよい世界を好んで求める。それ以外の世界には、同化できない。人間関係も、敵をつくらないことだけを考える。ものごとを、ナーナーですまそうとする。●子育てに反映される……依存性の強い人は、子どもが自分に対して依存性をもつことに、どうしても甘くなる。そして依存性が強く、ベタベタと親に甘える子どもを、かわいい子イコール、できのよい子と位置づける。●親孝行を必要以上に美化する……このタイプの人は、自分の依存性(あるいはマザコン性)を正当化するため、必要以上に、親孝行を美化する。親に対して犠牲的であればあるほど、美徳と考える。しかし脳のCPUがズレているため、自分でそれに気づくことは、まずない。だれかが親の批判でもしようものなら、猛烈にそれに反発したりする。依存性の強い社会は、ある意味で、温もりのある居心地のよい世界かもしれない。しかし今、日本人に一番欠けている部分は何かと言われれば、「個の確立」。個人が個人として確立していない。あるいは個性的な生き方をすることを、許さない。いまだに戦前、あるいは封建時代の全体主義的な要素を、あちこちで引きずっている。そしてこうした国民性が、外の世界からみて、日本や日本人を、実にわかりにくいものにしている。つまりいつまでたっても、日本人が国際人の仲間に入れない本当の理由は、ここにある。●人情は依存性を歓迎し、義理は人々を依存的な関係に縛る。義理人情が支配的なモラルである日本の社会は、かくして甘えの弥慢化した世界であった。(土居健郎「甘えの構造」)Hiroshi Hayashi++++++++++Nov. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(005)【寸又峡温泉にて】(05・11月x日)●金谷で…… 今日は、寸又峡温泉にやってきた。「すまたきょう・おんせん」と読む。東海道線の金谷(かなや)で下車。そこから大井川鉄道に乗って、千頭(せんづ)でおりる。金谷から千頭までは、SL。その千頭から寸又峡までは、バス。 金谷から千頭まで、SLで、1時間10分。千頭から寸又峡まで、バスで40分。朝方は曇り。小雨模様だったが、金谷へ着くころには、青空が見えた。金谷で、だれかが、「あら、晴れてよかったわ」と言ったのが耳に入った。 それから今度は、SL。蒸気機関車。秋の紅葉のシーズンには、ピークを過ぎたという人もいたが、水色の空にはえて、赤や黄色の紅葉が、色あざやかに輝いていた。 「ぼくは、若いころ、秋の紅葉がこんなにも美しい思ったことがない」と言うと、ワイフが、「年をとると、自然の美しさがわかるようになるのかもね」と笑った。 その金谷で、30分ほど、過ごす。写真を何枚か、とる。●SL SLといっても、当然、古い汽車。ボロボロといった感じ。「昔は、こんなだったのかな」と思いつつ、どこかおっかなびっくり。座席は狭いし、それに汚い。洗面所には、「使えません」の張り紙がしてあったが、張り紙がしてなくても、だれも使わないだろう。使い古した便器のような感じがした。私「ぼくが高校生くらいのときは、SLは、日本中を走っていた」ワ「私は、見なかったわ」私「東海道線からは、早い時期に、消えたかもしれない。でも、ぼくにとっては、旅行といえば、SLだった。トンネルを抜けると、みんなの顔が、煙で真っ黒になっていたりしてね」、ハハハ、と。 ときどき石炭を燃やすにおいが、車内にまで入ってきた。が、なつかしさは、あまりなかった。どこかの汚いトイレに入ったような感じ。それが、まだ残っていた。大井川鉄道は、「古い」ということと、「不潔」ということとを混同しているのではないか。あるいは古いことをよいことに、不潔なまま、居なおってしまっている。 やがて汽車は、川に沿って走り出した。美しい紅葉が、つぎつぎと目に飛びこんできた。私は夢中で、デジタルカメラのシャッターを切った。ビデオもとった。 車内では、女性の案内が、ガンガンと流れていた。歌も歌った。バスガイドならぬ、汽車ガイドである。こういうガイドには、好き好きがあるのでは……? 中には、静かな旅を楽しみたいと思っている人もいるはず。しかしそういう人は、少数派。私のような人間は、だまってそれに耐えるしかない。●千頭 千頭へは、もう何度か来たことがある。若いころは、息子たちを連れてやってきた。最近では、数年前に来たことがある。その千頭からは、トロッコ列車が走っている。それに乗ったこともある。 が、今回は、ここからバスに乗る。待ち時間は20分ほど。昼食用に弁当をさがすが、どこも売り切れ。見ると団体客が、旗を先頭に、バス停のほうへと歩いてきた。みな、寸又峡へ向かうらしい。その団体をぼんやりと、見やる。 それをのぞけば、のどかな田舎町。いくつかの飲食店とみやげもの屋。それが街道に沿って、並んでいる。駅前のにぎわいとは対称的に、道の向こうでは、白い光りを浴びて、一匹のネコが、のそのそと道路を横切っていた。 「弁当は売り切れだった」と私が言うと、ワイフは、「向こうへ着いたら、食べましょう」と言った。 今日は、あまり気分がよくなかった。昨夜は、あまりよく眠られなかった。いとこと長電話をしたのが原因らしい。自分では気がつかなかったが、ワイフは、こう言った。「あなた、興奮して、ペラペラとしゃべっていたからよ」と。そのせいか、軽い頭痛が残った。どうやら、睡眠不足性が原因の頭痛らしい。●寸又峡 寸又峡へは、午後2時過ぎに着いた。山間の、まさに「寸又峡」という感じのところだった。山が高く、もう日は、山の向こうに沈んでいた。浜松でいえば、午後4時ごろというところか。 私たちは旅館でチェックインをすますと、そのまま近くの、そば屋へ。その日はじめての食事である。私は、やまめ定食。ワイフは、とろろ山菜そばを頼んだ。横が売店になっていて、そこに立つ、お姉さん(店員さん)が、おもしろい人だった。私「夢の橋までは、遠いですか」店「今からなら、間にあいますよ」私「片道で何分くらいですか」店「30分くらい……。往復で1時間くらいかな……」私「心中するのだから、片道だけで結構です」店「このあたりでは、心中の捜索は、自費ですからね」私「はい」と。 私たちは食事を終えると、そのまま夢の橋へと向かった。●夢の橋 峡谷にかかる細いつり橋を、「夢の橋」という。定員は、10人ということだったが、谷間には、強い風が吹いていた。それだけでも、ブランブランと揺れる。そこへ足を踏み入れると、さらに揺れる。 私が先。ワイフが、それにつづく。やっと1人が歩ける程度の、細い板。その板の上を歩く。高所恐怖症の私には、たまらない。ゾクゾクとした恐怖感が、足の裏から伝わってくる。 しかしうしろのワイフを見ると、私よりも、もっとこわがっている。前にも1人女性が歩いていたが、橋の途中で、かがみこんでしまっている。こうなると、おもしろくてしかたない。それとわからないように、橋を揺らしながら、歩く。ハハハ。 しかし私とて、こわい。足元ばかり見ていると、手元の様子がわからない。一応、手すりになった細いワイヤをつかんでいるが、ところどころで、それが橋をつりあげる板と結ばれている。その板のところで、足ならぬ手がとられて、思わず、ころびそうになる。 ゾーッ! そしてまたゾーッ! この繰りかえし。 やっとの思いで、反対側へ。美しい景色を楽しむ余裕はない。が、着いたとたん、谷間の美しさが目に飛びこむ。それがどのように美しいものであったか……。 百聞は一見にしかず……ということで、ここに、そのときとった写真を何枚か載せる。●飛Rの宿 泊まった旅館は、飛Rの宿。……という名前の旅館。インターネットで検索して、予約を申しこんだ。1泊1万4000円弱。全体としては、小じんまりとした旅館だが、内部は、どこも広々として気持ちよかった。それに料理が、よかった。 山の中のひなびた旅館ということで、それほど期待していなかった。しかしその洗練された料理に、大満足。おいしかった。久しぶりにご馳走を食べて、胃のほうがびっくりしたよう。考えてみれば、ワイフと2人だけで、こうして旅行に出るのは、珍しい。 私が、「何年ぶりかな?」と聞くと、ワイフは、あっさりと「4年ぶりよ」と。4年ぶり! 改めて、「4年」という数字に驚く。こういう数字は、女性のほうが、よく覚えている。フームと言ったきり、つぎの言葉が出てこない。家庭サービスを、私は、かなりサボっていたようだ。 「ようし、来年からは、毎月、旅行しよう」と私。「毎月は、無理よ」とワイフ。しかしそれにしても、4年ぶりとは……! 私にも結構、古風なところがあるようだ。夫としての責任感を、強く覚えた。申し訳ない気持ちにかられた。●インターネットでの検索 今では、宿屋も、インターネットで簡単に検索できる。今回も、そうした。しかし、HPだけで選ぶと、失敗する。HPでは、やたらと豪華に見えても、実際には……?、という旅館も多い。 1つの方法としては、その温泉街全体が載っているHPを見るというのがある。そういうHPでは、宿泊代が、1つの目安になる。たいていのばあい、旅館の序列や格式、内容によって、宿泊代が決まる。当然のことながら、宿泊代の高い旅館ほど、よい旅館ということになる。 寸又峡温泉にも、大小、さまざまの温泉宿が、10~15軒ほどある。しかし本気で(?)、営業している旅館となると、3、4つ程度にしぼられる。実名を出して恐縮だが、「奥大井観光ホテル翠紅苑」は、★が、3つ。「湯屋・飛龍の宿」が、★が、2つ、というところか。あとは、宿泊予算と相談して決めたらよい。 私とワイフは、温泉街を歩きながら、「ここにしなくてよかったね」「今度来るときがあったら、この旅館にしよう」などと、話した。●温泉温泉は、内湯と、露天風呂の2つがあった。湯の中で、体にさわると、軽くヌルっとした感じがする。私は、夕食前に1回。夕食後に1回。そして朝早く起きて、1回、計3回も、入った。 が、ほかにすることはなし。小型のノートパソコンをもってきたので、それを開いて、文章を書く。ワイフは、BS放送を見る。で、結局、風呂から帰ると、そのまま、寝ることにした。ワイフが、「まだ9時よ」と言った。私は、「ぼくは、睡眠不足だから、ごめん」とあやまった。 こういう旅行先でワイフを見ると、別人のように見える。毎日見慣れているはずなのに、おかしな気分だ。それにゆかた姿のワイフは、珍しい。ムラムラと……(後略)。 「お前さあ、今夜は、きれいに見えるよ」と声をかけると、「あら、そう」と言った。●朝 朝食は、8時ということになっていた。バスは、8時40分に出る。散歩から帰ると、そのまま朝食。そしてチェックアウト。私たちはバス停に向かい、そこで列をつくって、バスのドアが開くのを待った。 団体客と一般客が混ざって立った。そのときのこと、うしろのほうから、7、8人の男女が、大柄な男を先頭にやってきた。道路の中央を、ドヤドヤといったふうな感じでやってきた。そしてそのまま、私たちの前に立とうとした。朝から酒を飲んで、酔っぱらっているふうだった。 私は、2度、3度、「並んで待っていますと」と声をかけた。が、男たちは、無視。バスのドアのところに立とうとした。そこで私は、キレた。さらに大きな声で、こう言った。 「団体客も、一般客も、並んで待っているんだぞ。ちゃんと、うしろに並んだらどうだ!」と。 態度の大きな男だった。しゃべりかたは、関東地方特有のベラメエ調子。どこかの金持ちか、政治家といった風体だった。すると、その男のうしろについていた女が、「そんなに怒らなくてもいいでしょ!」と。 今度は、私が無視した。男が、もどって、私たちのうしろにつこうとしたからだ。 あとで私は、ワイフにこう言った。「ぼくはね、ああいうとき、がまんしないよ。言いたいことがあれば、サッサと言って、それですます。がまんしていると、ストレスがたまるからね」と。●帰途 今度は、寸又峡から千頭までは、バス。千頭から金谷まで電車。少し待てばSLが走るということだが、SLは、もうごめん。 金谷から浜松までは、JRで。午前中までには、自宅へ帰ってくるつもりだったが、列車が何かの事故で遅れた。 帰りの電車の中で、私は眠った。眠りながら、山々の紅葉の夢を見た。夢のような景色だった。途中、少し目を開くと、ワイフも、こっくりこっくりと、うたた寝。寸又峡からのバスの中で、ワイフとこんな会話をした。 「春から夏にかけては、山々の緑は、みな、同じ緑だよね。でも、秋になると、みな、色を変える。人生を季節にたとえる人もいるけど、秋というのは、人生で言えば、晩年。その晩年に、それぞれの人が、最後に、自分の色で、美しく輝くんだよね」と。 さあて、私は、どんな色になるのだろう。赤や黄色ならいい。しかしひょっとしたら、赤サビ色になるかもしれない。そんなことを考えていたら、また眠ってしまった。 のどかで、楽しい旅だった。(おしまい)Hiroshi Hayashi++++++++++Nov. 05+++++++++++++はやし浩司●おかしな日本語 最近、子どもたちの日本語が、おかしい。本当に、おかしい。昨日も、小4のクラスで、こう言った子どもがいた。 「先生、終わったら、どうするのですか?」と。 その子ども(女の子、Oさん)は、「先生、今やっている問題が終わったら、私は何をしたらいいですか?」という意味で、私にそう言った。それはわかる。しかし、何という、日本語! そこですかさず、私はこう言ってやった。 「あのね、先生が死んだら、葬式でもしてくれれば、先生は、うれしいよ。でも、まだぼくは、終わらないよ。元気で、ピンピンしているからね」と。 すると、このところやや反抗的な様子を見せ始めているKさんが、こう言った。「先生は、ふざけてばかりいる」と。私「何も、ふざけていないよ。君たちの話す日本語がおかしいから、そう言っているだけだよ。もう少し、きちんとした日本語を話してほしいからね」と。 そこで私は、いくつかの例を出してやった。 「たとえば、『今日、学校、ある』と言うだろ。それだって、『今日は、学校は、休みではありません。授業があります』と言うべきだ。学校が、消えたり、現われたりするわけないからね。 ほかに、夏になると、『今日、プールがあった』と言う子どもがいる。しかしそのばあいでも、『今日は、水泳の授業があった』というべきだ。プールが、消えたり、現われたりするわけではないからね」と。 さらにこんな例も出して説明してやった。 「よく、『先生、オシッコ!』という子どもがいる。そういうときは、ぼくは、『先生は、オシッコではない。人間だ』と言ってやるよ。いいかな、そういうときは、『私は、トイレに行きたいです』と言わなくてはいけない」と。 すると、最初の女の子が、ムキになった。「そんな言い方、いちいちしないわよ。それに今は、国語の時間ではない! 私は算数が勉強したいの。よけいなこと、教えないでよ!」と。私「国語の時間ではない、だって? 算数だって、国語の一部だよ。計算問題だけが、算数ではない。文章で書かれた問題を解くのが、算数だよ。それは君のまちがいだよ」と。Oさん「だって、意味が通ずれば、いいじゃん」私「しかしそんな話し方ばかりしていると、文章が書けなくなるよ。たとえば、『これは私の学校』などと、外国の人に言ってごらん。その外国の人は、びっくりするよ。『これは、君の学校か』ってね。そういうときでも、『これは、私が通っている学校です』と言う。正しくはね」と。 英語の世界では、日本語の世界とは反対に、単語だけの会話を、たいへん、嫌う。たとえば、「何、食べる?」「うん、ラーメン」という言い方は、英語では、しない。英語では、「あなたは、何を食べたいですか?」「私は、ラーメンを食べたいです」と言う。きちんとした文章で会話をするのが、ふつう。ふつうというより、当たり前。 単語だけ並べて会話をすると、大学教育の場では、すかさず、注意される。「あなたは、文章(センテンス)で、会話をしなさい!」と。ふつうの世界でも、単語だけで応答したりすると、「学のない人」と、判断される。 日本語は日本語と、居なおるのもよいが、少なくとも、正しい言い方とは、ほど遠い。その(ほど遠い)状態で、日本語そのものが、ますます、おかしくなってきている。よい例が、バラエティ番組に出てくる若者たちの会話である。 「ドヒャー、ヤルー!」 「スゲエ~。オレもイッチョ、ヤッカ~」 「アホッ、オマエ、アホカ?」と。 そしてKさんには、こう言った。 「君は、小説を書いているね。小説を書く人は、日ごろから、正しい言い方を身につけておかなくてはいけない。でないとね、意味のわからない日本語を書くことになるよ。自分だけわかればいいという文章は、文章ではないよ」と。 そして最後に、こう言った。「今、ぼくが言っていることが、まちがっていると思う人は、即刻、この教室から出て行きなさい!」と。 とたん、クラスは、シーンとした。そして、いつものレッスンがまた、始まった。【追記】 その翌日のこと。またまた、こんなハプニングがあった。 このあたりでは、「ケチ」のことを、「ケチンボウ」という。おかしな日本語だ。どうやら方言のようなものらしい。 しかし、それにしても……! その言葉を、今日、小5のOさんが、使った。何かの拍子に、Oさんが、「先生は、ケチンボウね」と。 あまりの言葉に、瞬間、息が止まった。そしてこう言った。「もちろん、毛・チン棒だよ」と。 とたん、クラス中が、爆笑のウズで埋まった。私も、「ますい」「まずい」と思いながらも、そのウズに巻きこまれてしまった。私「あのねえ、若い、君のような女性が、口に出して使うような言葉じゃ、ないよ」O「どうして、だめなの?」私「その言葉は、セクハラ言葉だよ」O「ケチンボウがア……?」私「ほら、また、使ったア!」と。 ワハハハ、ゲラゲラ、ワハハハ……。O「でもね、ママに、ケチンボウと言っても、ママは、笑わないわよ」私「もういいから、その言葉を使ってはだめ!」O「どうしてダメなの?」私「もう、いいから、その言葉を忘れて勉強しなさい!」O「先生は、考えすぎよ」と。 あとで家に帰ってから、そのことをワイフに話すと、ワイフも、こう言った。「あら、浜松の人なら、みな、その言葉を使うわよ」と。 それにしても、ギョッとする言葉ではないか。浜松の人には、それがわからないかもしれないが……。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司●6か国協議の崩壊 6か国協議が、崩壊の危機に立たされている。日米韓vs中ロ北の図式から、韓国が、日米から離脱。日本も、アメリカとは、距離を置く姿勢を見せ始めた。つまりアメリカだけが、孤立。 こうなると、何が、6か国協議か?、ということになる。今朝(12・1)のサンケイ新聞は、つぎのように伝える。+++++++++++6カ国協議 空洞化への序曲 きしむ日米と韓、協力ついに終焉(しゅうえん) 【ワシントン・樫山Y夫】北朝鮮の核開発をめぐる日米韓の三国調整グループ(TCOG)の枠組みが、以前からきしみをみせていたが、さきの6か国協議での開会が見送られたことで、名実ともに終止符が打たれた。日米と韓国の思惑の違いを克服できなかったことが、最大の原因だった。TCOGは6か国協議の根幹をなす枠組みだっただけに、その崩壊について、「6か国協議空洞化につながるおそれがある」(米国の朝鮮問題専門家)という懸念が台頭している。+++++++++++ こういう場で責任のなすりあいをしてもいけないが、孤立しているのは、アメリカではなく、実は、この日本である。それを忘れてはいけない。はっきり言えば、K国の核兵器など、アメリカにとっては、痛くもかゆくも、何ともない。 もしK国がアメリカに核でおどしをかければ、K国は、1時間で、廃墟の国と化す。「石器時代にもどる」と説く、評論家もいる。しかもアメリカは、原子力潜水艦1隻で、それができる。 しかし日本にとっては、そうではない。今のK国と、対等に戦争するだけの力は、ない。もし核兵器でおどかされれば、日本は、手も足も出せない。憲法上の制約というより、士気そのものがちがう。それ以上に、今の日本人は、あまりにもその緊張感に欠ける。 こういう状況の中で、どこのだれが、K国の核兵器問題を、解決してくれるのか?、ということになる。本来ならその責任を負うのは、中国もしくはロシアなのだが、この両国が、K国の肩をもっている以上、もう、どうしようもない。韓国にいたっては、「核開発など、もうどうでもいい」といったカンジ。 が、この日本にも責任がないわけではない。中国の北京に視点を置いてみると、それがよくわかる。 日本列島のあちこちにアメリカ軍の基地がある。原子力潜水艦や空母が、その周辺で、ウロウロしている。最新鋭の戦闘機が、四六時中、飛びかっている。中国に言わせれば、「何が、K国の核兵器だ!」ということになる。「日本は核武装していません」といくら叫んでも、その論法は日本の外では、通用しない。 かたや、そのアメリカとの関係も、ギクシャクし始めている。沖縄からのアメリカ軍の移転についても、何ひとつスンナリと、いかない。アメリカにしてみれば、「もうバカ臭くて、やっていられない」という状況になりつつある。「どうして、アメリカが日本など、守らなければならないのか」というのが、アメリカの本音ではないか。 ……といっても、これは日本とアメリカがしくんでいる、ポーカーフェイスの疑いがないわけでもない。日米間のきしみを、演出することによって、中国とK国の間に、キレツを入れる作戦である。今ごろ、日本のK首相と、アメリカのB大統領のとの間で、こんな会話をしているかもしれない。K首相「今、日本が、アメリカベッタリの姿勢を見せると、かえって中国とK国が結束してしまいますよ。そこで、どうでしょう、一応、ここでは、日本は、アメリカとは一線を引いているという姿勢を見せては……? 拉致問題を解決してくれたら、経済援助をすると、におわせるという作戦です」B大統領「うむ、それはいい考えですね。日本が、アメをちらつかせる。で、拉致問題が進展したところで、さっと手を引く。あいつら、あわてるだろうな、ハハハ」と。K首相「そうですよ。『そんな約束、したっけ?』と、とぼけて見せればいい。とぼけは、日本人の得意芸の1つですよ」B大統領「しかしね、絶対に、核開発問題が解決するまで、ビタ一文、K国に渡してはダメだよ。わかっているね、K首相」K首相「よ~く、わかっていますよ、B大統領。どうか、ご心配なく」と。 で、韓国は、相手にせず。 つづくサンケイ新聞は、つぎのように伝えている。++++++++++++++ TCOG崩壊の最大の原因は、6か国協議を通じて、韓国が議長国の中国、ロシアに傾斜、北朝鮮への柔軟な姿勢を打ち出したことによる。これによって日米との対立が鮮明となり、共同声明のとりまとめが困難になったためだ。 米国は韓国の姿勢に変化が見られない限り、「開いても意味がない」として、復活には消極的といわれる。その場合、今後の6か国協議では、日米対中韓露の対立の図式が、いっそう鮮明になる。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司最前線の子育て論byはやし浩司(006)●注意する 電車の中で騒がしい人。大声で話しあっている人。 順番を待つというルールを守らない人。 道路にゴミを捨てたり、ツバを吐いたりする人。 信号を守らない人。 電車の中で、大きな声で、携帯電話をかけている人。 駐車場でないところに、車を止める人。 病院で騒いでいる子どもをもつ、親。 私が講演しているとき、ずっと、しゃべりっぱなしの人、などなど。 こういう人たちを注意するには、コツがある。(1)にこやかな笑顔を絶やさないこと。(2)一応、下手に出て、お願いするという形をとること。(3)「すみませんが……」と話しかけて、「よろしくお願いします」で終わること。(4)早めに注意すること。(5)相手がムッとしてきたときは、頭をさげて無視すること。(6)余計な理由などは、言わないこと。 「早めに注意すること」というのは、がまんしている時間が長くなると、それだけ、ストレスがたまってしまう。そのあと、うまく注意できなくなってしまう。こちらが興奮状態になるのは、まずい。おだやかな口調で、注意することができなくなる。 だから気がついたら、早めに、サラッと注意するのがよい。 そしてここが重要だが、こうした注意には、練習が必要だということ。夫や妻を相手に、何度か、練習してみるとよい。いきなり本番、というのは、まずい。私のばあいも、何度か練習したあと、実際、電車の中で、試してみた。 最初のころは、心臓がドキドキしてうまく注意できなかったが、回を重ねるごとに、うまくできるようになった。今ではたいてい、相手の人は、「あら、すみません」「わかりました」と、引きさがってくれるようになった。こちらのもつ、雰囲気が重要。 が、それでも相手が、ムッとしてくることもある。しかしそういうときでも、こちらは過剰に反応してはいけない。もう一度、「よろしく」と言って、頭をさげる。そうしてサラッと視線をはずす。 あとは無視。それで自分をなおしてくれればよし。それでも、なおしてくれないようなら、あきらめて、その場を去る。反論したり、深追いしてはいけない。言うべきことは言う。しかし、それですます。 概して言えば、外国人のばあいは、みな、笑顔で従ってくれる。とくに欧米人は、そうである。そういうふうに注意したり、注意されたりするのが、習慣的になっているせいではないか。 概して言えば、権威主義的な日本人は、ムッと不愉快な顔をする。これは注意されることによって、プライドがキズつけられたと思うせいではないか。 また注意するときも、うるさかったら、「静かにお願いできませんか」とだけ言えばよい。「まわりの人に迷惑です」とか、「そんなことをすれば、汚くなります」とか、そういう理由は言ってはいけない。理由を並べると、どんな人でも、ムッとする。 だから単刀直入に、言うべきことだけを言って、すませる。 ところで昨日、乗った電車も、騒々しかった。が、私は、注意しなかった。相手が、80~90歳の、おばあちゃん連中だったからである。ワイフが、「みんな耳が遠いのよ」と言った。だから私たちは、別の車両に席をかえた。そういうこともある。Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司【人間の誇りとは……】++++++++++++++++++++2002年の1月に、つぎのような原稿を私はこんな原稿を書いた。今、改めて、それを読みなおしている。++++++++++++++++++++●私はユネスコの交換学生だった 1967年の夏。私たちはユネスコの交換学生として、九州の博多からプサンへと渡った。日韓の間にまだ国交のない時代で、私たちはプサン港へ着くと、ブラスバンドで迎えられた。が、歓迎されたのはその日、一日だけ。あとはどこへ行っても、日本攻撃の矢面に立たされた。私たちを直接指導してくれたのが、金素雲氏だったこともある。韓国を代表する文化学者である。私たちは氏の指導を受けるうち、日本の教科書はまちがってはいないが、しかしすべてを教えていないことを実感した。そしてそんなある日、氏はこんなことを話してくれた。●奈良は韓国人が建てた? 「日本の奈良は、韓国人がつくった都だよ」と。「奈良」というのは、「韓国から見て奈落の果てにある国(ナラ)」という意味で、「奈良」になった、と。昔は「奈落」と書いていたが、「奈良」という文字に変えた、とも。現在の今でも、韓国語で「ナラ」と言えば、「国」を意味する。もちろんこれは一つの説に過ぎない。偶然の一致ということもある。しかし結論から先に言えば、日本史が日本史にこだわっている限り、日本史はいつまでたっても、世界の、あるいはアジアの異端児でしかない。日本も、もう少しワクを広げて、東洋史という観点から日本史を見る必要があるのではないのか。ちなみにフランスでは、日本学科は、韓国学部の一部に組み込まれている。またオーストラリアでもアメリカでも東洋学部というときは、基本的には中国研究をさし、日本はその一部でしかない。●藤木新一の捏造事件 一方こんなこともある。藤木S一という、これまたえらいインチキな考古学者がいた。彼が発掘したという石器のほとんどが捏造(ねつぞう)によるものだというから、すごい。しかも、だ。そういうインチキをインチキと見抜けず、高校の教科書すら書き換えてしまった人たちがいるというから、これまたすごい。たまたまその事件が発覚したとき、ユネスコの交換学生の同窓会がソウルであった(1999年終わり)。日本側のOBはともかくも、韓国側のOBは、ほとんどが今、大企業の社長や国会議員をしている。その会に主席した友人のM氏は帰ってきてから私の家に寄り、こう話してくれた。「韓国人は皆、笑っていたよ。中国や韓国より古い歴史が日本にあるわけがないとね」と。当時の韓国のマスコミは、この捏造事件を大きく取りあげ、「そら見ろ」と言わんばかりに、日本をはげしく攻撃した。M氏は、「これで日本の信用は地に落ちた」と嘆いていた。●常識と非常識 私はしかしこの捏造事件を別の目で見ていた。一見、金素雲氏が話してくれた奈良の話と、この捏造事件はまったく異質のように見える。奈良の話は、日本人にしてみれば、信じたくもない風説に過ぎない。いや、一度、私が金素雲氏に、「証拠があるか?」と問いただすと、「証拠は仁徳天皇の墓の中にあるでしょう」と笑ったのを思えている。しかし確たる証拠がない以上、やはり風説に過ぎない。これに対して、石器捏造事件のほうは、日本人にしてみれば、信じたい話だった。「石器」という証拠が出てきたのだから、これはたまらない。事実、石器発掘を村おこしに利用して、祭りまで始めた自治体がある。が、よく考えてみると、これら二つの話は、その底流でつながっているのがわかる。金素雲氏の話してくれたことは、日本以外の、いわば世界の常識。一方、石器捏造は、日本でしか通用しない世界の非常識。世界の常識に背を向ける態度も、同じく世界の非常識にしがみつく態度も、基本的には同じとみてよい。●お前は日本人のくせに! ……こう書くと、「お前は日本人のくせに、日本の歴史を否定するのか」と言う人がいる。事実、手紙でそう言ってきた人がいる。「あんたはそれでも日本人か!」と。しかし私は何も日本の歴史を否定しているわけではない。また日本人かどうかと聞かれれば、私は100%、日本人だ。日本の政治や体制はいつも批判しているが、この日本という国土、文化、人々は、ふつうの人以上に愛している。このことと、事実は事実として認めるということは別である。えてしてゆがんだ民族意識は、ゆがんだ歴史観に基づく。そしてゆがんだ民族主義は、国が進むべき方向そのものをゆがめる。これは危険な思想といってもよい。仮に百歩譲って、「日本民族は誇り高い大和民族である」と主張したところで、少なくとも中国の人には通用しない。何といっても、中国には黄帝(司馬遷の「史記」)の時代から5500年の歴史がある。日本の文字はもちろんのこと、文化のほとんどは、その中国からきたものだ。その中国の人たちが、「中国人こそ、アジアでは最高の民族である」と主張して、日本人を「下」に見るようなことがあったら、あなたはそれに納得するだろうか。民族主義というのは、もともとそのレベルのものでしかない。●驚天動地の発見! さて日本人も、そろそろ事実を受け入れるべき時期にきているのではないだろうか。これは私の意見というより、日本が今進みつつある大きな流れといってもよい。たとえば2002年のはじめ、日本の天皇ですらはじめて皇室と韓国の関係にふれ、「ゆかり」という言葉を使った。これに対して韓国の金大統領は、「勇気ある発言」(報道)とたたえた(1月)。さらに同じ月、研究者をして「驚天動地」(毎日新聞大見出し)させるような発見が奈良県明日香村でなされた。明日香村のキトラ古墳で、獣頭人身像(頭が獣で、体が人間)の絵が見つかったというのだ。詳しい話はさておき、毎日新聞はさらに大きな文字で、こう書いている。「百済王族か、弓削(ゆげ)皇子か」と。京都女子大学の猪熊兼勝教授は、「天文図、四神、十二支の時と方角という貴人に使われる『ローヤルマーク』をいくつも重ねている」とコメントを寄せている。これはどうやらふつうの発掘ではないようだ。それはそれとして、が、ここでもし、「百済王族か、弓削(ゆげ)皇子か」の部分を、「百済王族イコール、弓削(ゆげ)皇子」と解釈したらどうなるか。弓削皇子は、天武天皇の皇子である。だから毎日新聞は、「研究者ら驚天動地」という大見出しを載せた。●人間を原点に 話はぐんと現実的になるが、私は日本人のルーツが、中国や韓国にあったとしても、驚かない。まただからといって、それで日本人のルーツが否定されたとも思わない。先日愛知万博の会議に出たとき、東大の松井T典教授(宇宙学)は、こう言った。「宇宙から見たら、地球には人間など見えないのだ。あるのは人間を含めた生物圏だけだ」(2000年1月16日、東京)と。これは宇宙というマクロの世界から見た人間観だが、ミクロの世界から見ても同じことが言える。今どき東京あたりで、「私は遠州人だ」とか「私は薩摩人だ」とか言っても、笑いものになるだけだ。いわんや「私は松前藩の末裔だ」とか「旧前田藩の子孫だ」とか言っても、笑いものになるだけ。日本人は皆、同じ。アジア人は皆、同じ。人間は皆、同じ。ちがうと考えるほうがおかしい。私たちが生きる誇りをもつとしたら、日本人であるからとか、アジア人であるからということではなく、人間であることによる。もっと言えば、パスカルが「パンセ」の中で書いたように、「考える」ことによる。松井教授の言葉を借りるなら、「知的生命体」(同会議)であることによる。●非常識と常識 いつか日本の歴史も東洋史の中に組み込まれ、日本や日本人のルーツが明るみに出る日がくるだろう。そのとき、現在という「過去」を振り返り、今、ここで私が書いていることが正しいと証明されるだろう。そしてそのとき、多くの人はこう言うに違いない。「なぜ日本の考古学者は、藤木S一の捏造という非常識にしがみついたのか。なぜ日本の歴史学者は、東洋史という常識に背を向けたのか」と。繰り返すが一見異質とも思われるこれら二つの事実は、その底流で深く結びついている。(以上、2002年1月記)++++++++++++++++++ 今朝(05年12月2日)の朝刊によれば、またまた奈良県の明日香村のカヅマヤマで、石積み石室古墳が見つかったという。 中日新聞は、「百済王族?」と「クエスチョンマーク」をつけて報道している。時期は7世紀後半、40~50代の男性埋蔵か、と。 「被葬者は渡来系か」と題して、前園・奈良芸術短大の教授は、つぎのように語っている。 「土を焼いて作った朝鮮半島の「せん」を使った石室を意識した構造で、被葬者は天武天皇の客人だった、百済王昌成(こうだらのこきししょうじょう)ら、渡来人の人物がふさわしいのでは。丘陵の斜面を削り墳丘を築造する立地条件は、高松塚古墳など、ほかの終末期古墳と一致するが、規模が大きく、「せき(=石へんに、専の文字)」を積んだ、特殊な石室をもつ点が特徴だ」と。 奈良県の明日香村の西南部には、7~8世紀の終末期古墳が密集している。大半が天皇家に関係があるとされる。 中でも、天武、持統天皇陵は藤原京の中軸、朱雀(すざく)大路の延長線上にあり、そこから南約3キロのエリアを天武天皇一族が、「聖なるライン」として築いた墓域とみる説が有力(同、新聞)。 この周辺に、あの高松古墳、キトラ古墳もある。(カヅマヤマと、キトラは、距離にして、1・5キロほど。)今回発見された古墳も、まさに百済や高句麗の様式をまねたもの……というより、百済や高句麗の様式そのもの。そこで前園教授は、「被葬者は渡来人か?」と。日本人の墓とするには、あまりにも無理があるからである。 日本の天皇は、「ゆかり」という言葉を使って、当時は、大問題になった。しかしこの事実ひとつだけを見ても、日本の天皇家と、朝鮮半島は、密接に結びついている。どうして日本の聖域の中に、百済からやってきたと思われる渡来人の墓が、こうまであるのか。また天皇陵の様式にしても、どうしてこうまで百済、高句麗の様式と酷似しているのか。 この先のことは私にはわからないが、再び、私は、あの金素雲氏が言った言葉を思い出す。 「証拠は仁徳天皇の墓の中にあるでしょう」と。仁徳天皇の墓の中には、何かしら、巨大な謎が隠されているらしい。(はやし浩司 カヅマヤマ古墳、キトラ古墳 百済 高句麗 弓削王子 金素雲)Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※最前線の子育て論byはやし浩司(007)【2005年を振りかえって……、思いつくまま】+++++++++++++++++++++マガジンでは、いよいよ今年の最終号になります。(この原稿を書いているのは、12月2日ですが……。)明日は、大晦日(おおみそか)ということになるでしょうか。気分は、そんなわけで、もう大晦日。今年1年を、あれこれ振りかえってみます。+++++++++++++++++++++●無事 昨日(12・1)、1等が3億円のジャンボ、年末宝くじを、30枚買いました。それを買うとき、ワイフが横で見ていて、「当たるわけないわ」とさかんに言っていました。が、しかし、当たります。絶対に、当たります。明日は、その3億円を、私は、手にします。どうか、どうか、ご期待ください。 で、当たったら、どうしようかと、今、悩んでいます。多分、当たったことは、だれにも言わないだろうと思います。もちろん息子たちにも……。しばらくワイフとこっそりと現金をながめたあと、え~と、そこから先が、私にもわかりません。 今年も、ハッとさせられるような危うい場面は、何度かありました。が、今日(12・2)まで、今のところ無事、過ごしてきました。12月31日までこのままなら、それが私にとっては、特等賞ということになります。 3億円は、ただのお金ですが、(無事)というのには、その3億円以上の価値があります。どうか、来年も、家族ともども、みな、無事に過ごせればと願っています。 ……と書きながら、やはり、当たればいいなと思っています。お金は嫌いではありません。●2006年 2006年にしたいことは、たくさん、あります。旅行もしたいし、仕事もバリバリしたい。今は、パソコンが、メインの趣味になっていますから、さらに性能のよいパソコンが、ほしいです。それでいよいよ本格的なビデオ編集をしてみたいです。 そのためP社のビデオカメラを、今、ねらっています。毎晩、カタログをながめながら、「どうしようか」と迷っています。デジタルカメラを買ったばかりだから、すぐには無理と思いますが……。 もちろん健康も大切にしたいです。これからもずっと、自転車通勤を欠かさないようにします。1週間に10単位と決めています。1単位というのは、30分間、自転車に乗ることをいいます。 あとは食べ物には、ますます注意を払いたいと思います。●誠司が日本へ! 年末には、二男が孫の誠司(孫)と奥さんを連れて、日本へ来るかもしれません。昨夜、連絡がありました。 毎年、さみしくなる一方のクリスマスと正月。しかしもし誠司がくれば、パッと明るくなるはず。それからもうすぐ2人目の孫が、男の子か女の子か、わかるそうです。ワイフは、女の子を望んでいますが、多分、また男の子でしょう。 我が家は男系家族なのです。 それにしても、最近、誠司が、どこか、アジア人ぽくなってきました。少し、ほっとしています。いつも私のHPのトップページを飾ってくれているのが、その誠司です。●マガジン 2006年も、マガジンの発行に明け暮れることになりそうです。目標は、1000号! とにかく、やるしかないのです。今さらあきらめて、おめおめとあとへ引きさがるわけにはいきません。 世の中には、私のようなバカがいても、よいのです。(自分でも、バカなことをやっていると、よく思います。) 悪いばかりではありません。頭の体操になります。それに写真を取るという趣味も、身につきました。毎日、デジタルカメラをポケットに入れて歩いています。それと、本屋へ行っても、あれこれ幅広く、本を読みあさるようになりました。これもよいことです。 もともと好奇心が旺盛で、多情多感な人間でしたが、マガジンを発行するようになってから、さらにそれに拍車がかかったというわけです。……といっても、全体から見ると、ほんの一部にすぎませんが……。つまり私が関心をもっている世界は、全体からみると、限られた世界にすぎないということです。 で、一言追加。 カメラをもって歩くというのは、よいことですね。「美」を見る目が、鋭くなってというか、敏感になりました。それにヒマさえあれば、よく出歩くようになりました。2006年は、2005年以上に、あちこちへ出かけ、パチパチと写真をとりたいです。(私のデジタルカメラは、バシャ、バシャと音が出るように設定してあります。無音にすることもできます。ピッ、ピッという音にすることもできます。しかしやはり、バシャ、バシャという派手な音のほうが、気持がよいです。) ●年末、年始 今年は、もし二男夫婦と誠司が来れば、楽しい年末、年始になります。が、まだよくわかりません。この時期は、航空運賃も、割高だし、それに混んでいます。 もし来なければ、例年のように、どこかさみしく、どこかものわびしい年末年始になりそうです。子どもたちが小さいころは、ウスまで買って、モチつきまでしました。門松も、自分たちで作って立てました。一応、ひと通りのことはしました。 が、息子たちも、みな、巣立ち、夫婦2人だけになると、そういうことをするのもおっくうになります。で、だんだんと、こうなってしまったというわけです。 まあ、のんびりと、家で、ビデオでも見ながら過ごします。 初詣(はつもうで)といえば、正月の3が日にするのが、ふつうですが、私たち夫婦は、混雑したところが嫌いです。だから、年末に、初詣の先取りをしたりします。多分、この原稿がみなさんの目に届くころには、もう初詣をすませていると思います。神様も、気にしないだろうと思います。とくにご利益(りやく)がほしいとも、思っていませんし……。 そういえば、このところ神社などへ行っても、手を叩いて、頭をさげるだけです。若いころは、「~~できますように」とか、「~~が手に入りますように」とか言って、手を合わせたものですが……。今は、手を叩いて、頭をさげるだけです。●家族 浜松へ流れてやってきたときには、私は、まったくのひとりぼっちでした。その私がワイフと知りあい、あとは、とにかく、2人だけで、ここまでやってきました。 たまたま昨日(12・4)も、ワイフとこんな会話をしました。「ぼくたちは、だれの助けも借りず、よくここまでやってきたね」と。ワイフはワイフで、「無我夢中だったから……」と言います。 ホント! ときどき、自分で、自分に感心することがあります。(かなり、自己愛者ぽいかな?) こういう状態を、「幸福」と言ってよいのか、どうか? 今のこの世界では、平凡な生活を送れるということだけでも、感謝しなければならないのかもしれません。 感謝します。ハイ! ただひとつ、心残りなのは、ぼくたちは、結婚式をしていないこと。そのお金がなかったというよりは、収入の約半分は、実家へ仕送りをしなければなりませんでした。当時は、まだ、そういう時代でした。●05年 05年という年が、思い出の中で、どういう年になるかは、まだ、よくわかりません。04年や、03年があまり印象に残っていないように、恐らく、05年も、それほど印象に残らないまま、終わってしまうのではないかと思います。 今年は、何をしたのかな? 今年は、何ができたのかな? ……今は、そんな思いでいます。そしてこの時期、毎年、同じことを思います。「来年こそは!」と。 しかしそういうふうに思うのも、どこか疲れました。どうせ何も、できないし……。放っておいても、地球は、太陽のまわりを、回りつづけるのです。どこが最初で、どこが終わりということもないのです。 だからやはり、朝起きたら、そのときから、懸命に生きるしかありません。結果はあとから、ついてきます。そしてその結果は、どういうものであれ、前向きに受け入れるしか、ないのです。 とまあ、またまたむずかしい話になってしまって、ごめん。今日は、むずかしい話は、しないようにと、心がけているつもりなのですが……。 ともかくも、正月に、それほど、こだわらなくてもよいのでは……というのが、今の思いです。季節ごとの、その間にある、休日程度に思えば、よいのではないのかな。とくに私の年齢になると、「年齢」そのものが、わずらわしくて、しかたありません。 どうしてこんなものに、みなが、こうまでこだわるのか、よくわかりません。「ぼくには年齢は関係ない」といくら、心の中で叫んでも、まわりの人は、平気でこう言います。「林さんも、今年は58歳ですね。もうすぐ還暦ですね」と。 真の自由を手に入れるためには、この年齢からも、解放されなければなりません。……とまあ、またまたむずかしい話になってしまいました。ごめん。***************************【正月の予定】1月2日号のマガジンは、お休みします。多分、1月4日号から配信することになると思いますが、今のところ、あくまでも予定です。来年もよろしくお願いします。(まぐまぐ版・マガジンは、予定どおり、配信をつづけます。)このところ、原稿書きをサボっています。本来なら、今ごろは、1月6日号の配信予約を入れなければならないのですが……。今は、スランプかな?、という状態です。ともあれ、今年は、これでおしまい。読者のみなさん、この1年間、マガジンの愛読(多分?)、ありがとうございました。どうか、よい新年をお迎えください。今年は、これで失礼します。はやし浩司******************************Hiroshi Hayashi++++++++++DEC. 05+++++++++++++はやし浩司※
2024年12月29日
全10612件 (10612件中 1-50件目)