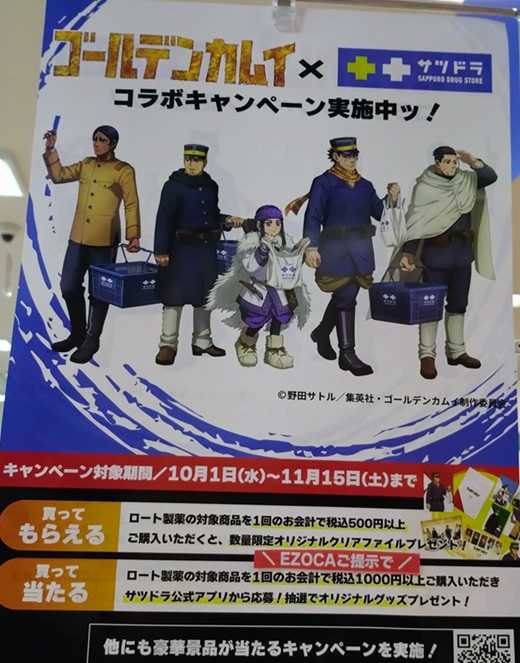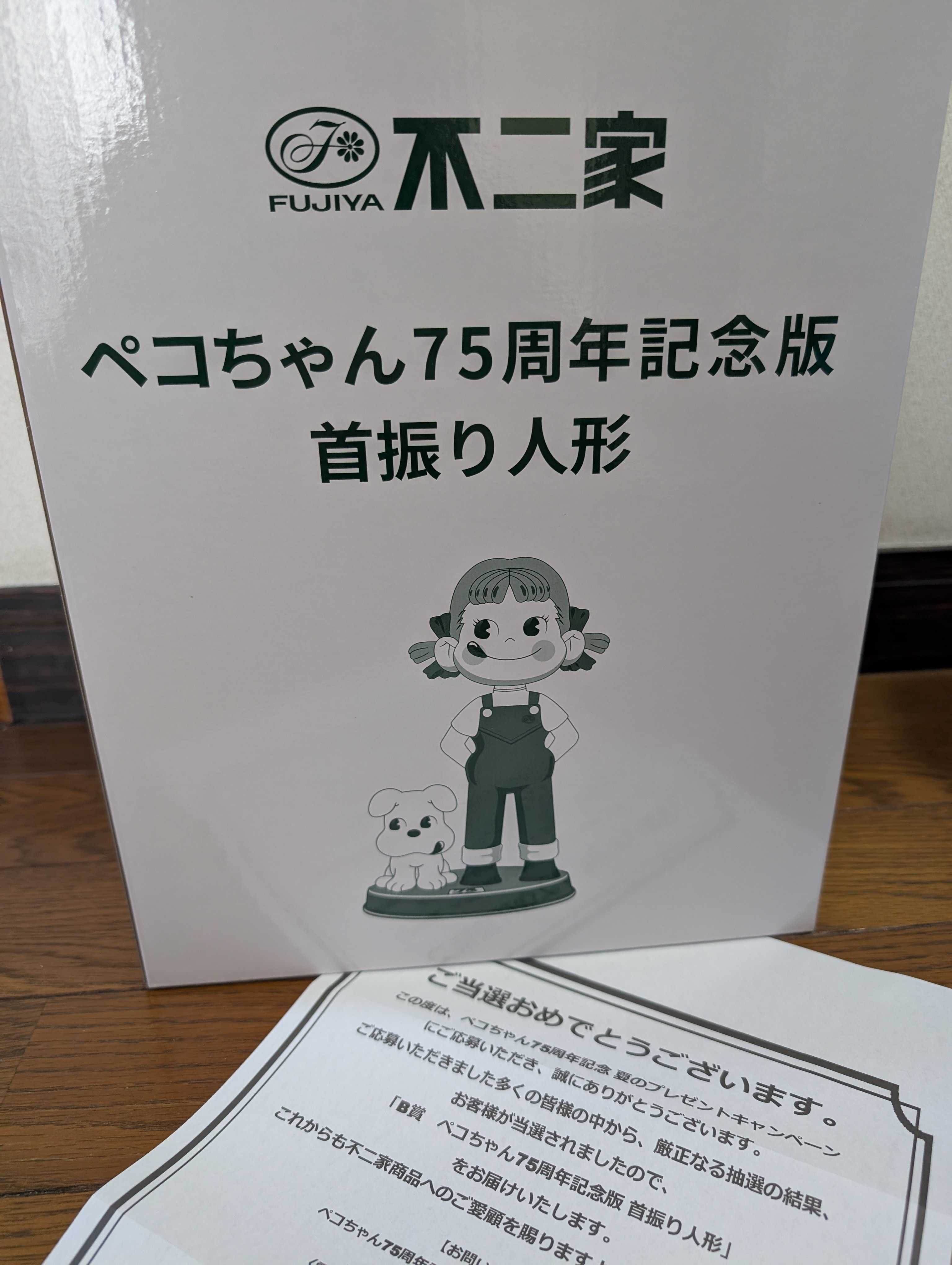2025年07月の記事
全58件 (58件中 1-50件目)
-
戦後体制への憤懣
戦後体制への憤懣日本会議の源流となったのが新興宗教・生長の家に出自を持つ右派の政治活動家だったとするならば、現在の日本会議を主柱的に支えているのが、伊勢神宮を本宗と仰ぐ神社本庁を頂点とした神道の宗教団体である。いくら生長の家出身の活動家らが熱心かつ執拗だとはいっても、彼ら自身が巨大な運動力や資金力を持っているわけではない。この点において宗教団体としての神道と神社界には、けた外れの動員力と資金力と影響力がある。いまも全国8万を超える神社があって各地に根づき、その大半を傘下に収める神社本庁は、日本の宗教界でも比類ないほどのパワーを持っている。しかも明治維新から第二次世界大戦が敗戦によって終結した1945年まで、国家が管理した国家神道体制の下、神道神社は国家による手厚い庇護を受けた。そして天皇中心主義や軍国主義体制を強力に裏支えし、無謀な戦争への人びとを駆り立てていく駆動装置のひとつにもなったのである。国家神道にかんする名著として知られる村上重良「国家神道」(1970年、岩波新書)は、その国家神道のあらましと問題点について簡潔にわかりやすくまとめている。同書から関連部分を抜粋してみたい。〈明治維新から太平洋戦争の敗戦にいたる約八〇年間、国家神道は、日本の宗教はもとより、国民の生活意識のすみずみにいたるまで、広く深い影響を及ぼした。日本の近代は、こと思想、宗教にかんするかぎり、国家神道によって基本的に方向づけされてきたといっても過言ではない〉〈国家神道は、民族宗教としての神社神道を、二〇世紀半ばにいたるまで固定化した、時代錯誤の国境制度であった。こんにちの日本における、政治と宗教をめぐる問題の基底には、国家神道がつくりだした、前近代的で歪んだ政教関係の遺産があり、神社神道もふくめて、日本の諸宗教は、国家神道によって、近代社会に対応する自主的で創造的な自己展開を阻まれてきた〉〈国家神道は、世界の宗教史のうえでも、ほとんど類例のない特異な国教であった。それは、近代天皇制の国家権力の宗教的表現であり、神仏基の公認宗教のうえに君臨する、内容を欠いた国境であった〉そんな国家神道はしかし、日本の敗戦によって80年近い歴史に一応は幕を降ろした。敗戦日本が受諾したポツダム宣言が第10項で、言論や思想の自由とともに信教の自由などの基本的人権を確立するように要求していたからである。これを受け、GHQは日本を占領した直後の1945年10月、「政治的社会的及び宗教的自由に対する制限除去」の覚書を発し、治安維持法などとともに戦前の宗教団体法も廃止されることになった。また同年12月にGHQは、いわゆる「神道指令」を発した。計4項から成る同指令は、国家神道が「国民を欺いて侵略戦争に誘導するために意図」されたもので「軍国主義や過激な国家主義の宣伝に利用」されたと断じ、「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止」などを命じて国家と神社神道の完全分離が目指された。さらによく1946年の元日、天皇が年頭にあたって勅書——俗に「人間宣言」と呼ばれる勅書を発し、「天皇を以て現御神とし、且日本国民を以て他の民族に優越せる民族にして、延て世界を支配すべき運命を有す」というのは「架空なる観念」などと自ら断じた。そして同年11月3日、信教の自由や政教分離の原則が明確にうたわれた現行憲法が公布され、天皇を求心点として国教化されていた戦前の国家神道は葬り去られたのである。 だが、日本の右派勢力や神道神社界の中には、戦後体制への憤懣と戦前体制への憧憬、回帰願望がくすぶりつづけた。英語圏における現代天皇制研究の第一人者として知られるケネス・ルオフ(米ポートランド州立大学教授、同日本センター所長)は、2003年に発表した名著『国民の天皇——戦後日本の民主主義と天皇制」の中で、戦後における神社本庁などの動向を次のように分析している。〈日本が独立を回復してから数十年の間、神社本庁は政治体制とイデオロギーを復活させる足がかかりとなる施策を強く支援してきた。米国製の憲法に象徴される戦後体制を拒否しながら、戦後、主として(1)政教分離を定めた憲法第二〇条の廃止もしくは別の解釈の確立、(2)皇室崇敬の教化——を目標に掲げてきた。そして日本の四七都道府県にまたがる支部を通じて、8万以上にのぼる神社の活動を統合している。神社本庁はまたいくつかの関連団体を支援しているが、その中には神道青年全国協議会や全国敬神婦人連合会なども含まれており、これらの団体は紀元節復活運動と、それ以降の政治運動で大きな役割を果たしていた〉 【日本会議の正体】青木理著/平凡社新書
July 31, 2025
コメント(0)
-
2025年参院選の分析
2025年参院選の分析参政党の躍進について・自分たちの生活が苦しいのは全部、日本在住の外国人のせい→日本人ファースト・子どもを産めない女性を敵視する・陰謀論がはびこるのは物価高が影響している・維新の会は自己責任論を主張(新自由主義)・生活が苦しいのは自己責任ではないと、国民民主党と参政党が選挙演説で訴える→世代間分断維新の会から票が約1000万票溶け落ちる ↓ ↓ ↓ 参政560万票 国民民主党500万票 保守党200万票(合計1250万票) ・れいわ新撰組が共産党の票を食う・自己責任論から「年寄りのせい」「女性のせい」「外国人のせい」・維新の会は大阪でしか勝てない。26万票減らしている。(京都で勝っているが、それは前原維新の会協同代表はもともと京都に地盤がある) ・国民民主党・玉木代表は手取りを増やそうとキャッチコピーで選挙性を戦ったが、このキャッチコピーは裏を返せば「年寄りを殺せ(尊厳死を認める法案)」、「ミソジニー(男性優位)」である。 ・東京都知事選で石丸現象が起こったが、それは、藤川晋之助(選挙プランナー、故人)が仕掛けたものである。選挙における必勝のノウハウを確立した。 ・自民党支持者は日本人ファーストで、行き場を失った岩盤支持層が参政党、国民民主に投票をしている。・自民党から溶け落ちた、岩盤支持者(安部支持者)・の1000万票は参政党に500万票、国民民主党に500万票、移行している。 以上が、参政党、国民民主の躍進の内訳である。リベラル政党は蚊帳の外であった。【関西学院大学法学部 富田教授の分析】
July 30, 2025
コメント(0)
-
臆する心からは何も生まれない
臆する心からは何も生まれない 天下分け目の戦いといえば、「関ケ原の合戦」が名高い。だが、江戸時代の歴史家・頼山陽は「『小牧の合戦』こそが、徳川氏が天下を握るべき武家として天下に認められた戦い」(『日本外史——幕末のベストセラーを「超」現代語訳で読む』長尾剛訳)と見る▼時は点勝12年(1584年)、現在の愛知県で繰り広げられた「小牧・長久手の合戦」。羽柴秀吉の軍勢は約11万。対する徳川家康・織田信雄連合軍は乾坤一擲の大勝負に出る。膠着状態の中、秀吉がしびれを切らすのを待って出陣。大軍ゆえ動きが遅い秀吉軍を、機動力で勝る家康軍が打ち破った▼数字だけで見れば、家康軍に勝ち目はまったくない。しかし、最期まで「攻める心」を持ち続け、マイナスをプラスに変えた。臆する心からは何も生まれない。どんなに条件が厳しくとも〝必ず勝つ〟と決めることで、一切の突破口は開かれる▼いわんや、われらには法華経の兵法がある。師匠への誓いがある。「いよいよはりあげてせむべし」(新1484・全1090)と進めば、破れぬ壁など断じてない▼さあ、今いる使命の本舞台で、歴史回転の広布劇を刻もう。挑むべき最大の敵は、常に自分自身である。(当) 【名字の言】聖教新聞2024.10.11
July 30, 2025
コメント(0)
-
政界の〝谷口雅春信奉者〟たち
政界の〝谷口雅春信奉者〟たち 国民主権の放棄と天皇主権、現行憲法の破棄と明治憲法体制への復古。一読すればわかるように、頭がクラクラするほど復古的かつファナティックな主張ではあるが、こうした政治思想や谷口の教えは戦後日本の右派に脈々と受け継がれており、右派系の文化人ばかりか政界主流の与党幹部、財界人らにも幅広く信奉されてきた。文化人の谷口信奉者の代表格は三島由紀夫だが、三島はこの『占領憲法下の日本』によせた推薦文で谷口をこう絶賛している。〈谷口雅春師の著書『生命の實相』は私の幼時、つねにやめる祖母の枕頭に並んでゐた。燦然たる光明の下に生命の芽の芽生えるその象徴的デザインは、幼い私の脳裏に刻まれたゐた。それから四十年、にわかに身辺に、谷口師に私淑してゐる人たちを見出すやうになったのである。つい先頃も、「生長の家」の信仰を抱く二三の学生が、私の自衛隊体験入隊の群れに加わつたので、親しく接する機会を得た。これらは皆、明るく、真摯で、正直で、人柄がよく、しかも闘志にみちみちた、現代稀に見る好青年ばかりであった。そして、「もし日本に共産革命が起きたら、君たちはどうする?」といふ私の問に、「そのときは僕らは生きてゐません」といふ、もっともいさぎよい、もっともさわやかな言葉が帰つてきた。これだけの覚悟を持ち、しかもかういう明るさを持った青年たちはどうして生まれたのだらうか(略)。かれらは谷口雅春師に対する絶対の随順と尊崇を抱いてゐた。私はどうしても、師のおどろくべき影響力と感化力、世代の差をのりこえた思想と精神の力を認めざるをえなかつた。私どもがいかに理論をもつて青年を説いてもむなしいのである〉(原文ママ)また、中央政界で谷口思想に憑かれた大物政治家の代表格が鳩山一郎であろう。鳩山は1954年から約2年間、首相として政権を率い、日ソ国交回復などを成し遂げたが、首相の座に就く前に脳出血で倒れて闘病生活を余儀なくされたことがあった。この際、鳩山は谷口の『生命の実相』を熱心に読んで感銘を受けたらしく、谷口と共著の形で、『危機に立つ日本——それを救う道』なる教団パンフレットに近い著作を発表、挙句の果てには『生命の実相』を「新時代のバイブル」と絶賛するほどだった。前出した大宅壮一の「谷口雅春論」もこれを取り上げ、谷口と鳩山をこんな風に辛らつに皮肉っている。〈〝神さま業〟は一度味をしめたらやめられない(略)。人間の無知と盲点の存在するかぎり、その上にアグラをかいておればいいのである。一方で出ていくものがある代わりに、新しいカモを続々やってくる。最近の最上のカモは何といっても鳩山一郎である。(略)谷口と鳩山の共著で、「危機に立つ日本」と題するパンフレットまで出ていて、鳩山は〝生長の家〟の宣伝に百パーセント利用されている〉(前同)意外なところでは、ハト派と知られた元首相・三木武夫も自民党幹事長時代の1964年、生長の家が政治結社・生長の家政治連合を結成した際、この式典に参加して祝辞を述べるなど谷口とは近い関係にあった。生前の三木を知る自民党の元参議院らによれば、三木は学生時代に肺を病み、その際に谷口の『生命の実相』に触れて感銘を受けていたのだという。政界の右派に位置づけられる大物政治家の中では、元首相の中曽根康弘も谷口に信を寄せていたらしく、行政管理庁長官時代の1982年5月、参院委員会の答弁でこう発信している。「私は年来、民族が持っておる根源的なエネルギーというものをひじょうに重要視してきておる人間なのであります。それで生長の家というのは、『生命の実相』等を読んでみましても、キリスト教あるいは仏教あるいは神道を融合した一つのお考えが新しく展開されておりました、その背後にあるものは、やはり一つの生命哲学と申しますか、そういうようなものに近いものではないかと拝察しておるのであります」中曽根にかんしては、妻も生長の家の活動に深くかかわっていたらしい。ただ、これらはいずれも少し眉に唾をつけつつ受け止めた方がいいかもしれない。強力な集票力を目当てにして政治家の宗教団体に近づいたり媚をうったりすることはしばしばあることで、それがどこまで本気なのかを推し量るのは難しく、推し量ることにはさほどの意味もない。実際、中曽根が総理総裁として与党・自民党を率いていた時期、選挙時の公認候補選定をめぐって成長の家にきわめて冷淡な態度を取り、生長の家が政治から距離を置く契機にもなっているのだが、これについては後述したい。このほか、近年の中央政界で谷口信奉者であることを公言している人物にはやはり日本会議のメンバーや関係者が圧倒的に多い。その代表的人物が日本会議国会議員懇談会の会長を務めている衆院議員の平沼赳夫、生学連出身の衛藤晟一、あるいは現在、自民党政調会長を務めている衆院議員の稲田朋美らもいるが、これも章をあらためて記すことにしよう。 【日本会議の正体】青木理著/平凡社新書
July 29, 2025
コメント(0)
-
近江上布伝統産業会館㊥
近江上布伝統産業会館㊥文化と地域デザイン研究所代表 松本 茂章国際見本市など海外展開に挑む2017年の9月だった。筆者は海外における日本文化の発信に関心を持ち、調査のためにパリのショーケースを訪れた。そこで「近江の麻」でつくられた財布等の小物を見つけ、滋賀県の麻織物に関心を持った。パリから早速「帰国したら訪問したい」とのメールを送った。以降、近江上布伝統産業会館事務局長の田中由美子や同店舗責任者の西川幸子と交流してきた。西川は京都産業大学外国語学部フランス語学科を卒業後、京都の和装小物問屋に就職。同社がパリの手芸専門店と提携したリボン専門店に勤務した。時おりパリに主張私的刷した。1996年から1年間、仏南部のトゥールーズの語学学校に留学。出産に伴い退職したが自宅で手芸を続けた。同会館のアマチュアクリエーター事業に応募して出品。店の運営や商品開発の経験を買われて2012年に店舗責任者に就任した。同会館は14年以降、海外展開に挑む。西川によると、24年2月には二のなどの世界的な見本市「プルミエール・ヴィジョン」に初出店を果たし、ヘンプ(おおあさ)の生地などを出品した。「欧州ではSDGsが盛んで天然素材が人気。麻の中でもヘンプは水や肥料が少なくでも育つ。化学肥料を必要としないので土壌汚染の心配がない。環境にやさしい素材として麻が注目されている」(西川)これまでもパリの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出品した経験を有する。かつては麻製小物を販売していたが、近年は生地の引き合いも増えてきた。欧州ブランドから注文が届く。「近江上布の名前が世界的に知られることで、手織りする職人さんの励みにもなる」と西川は言った。日本の「伝統的工芸品」は生活習慣の変化などから国内需要が減少。しかし海外で注目されており欧米などでの新展開に大きな可能性を秘めている。(敬称略) 【文化遺産とまち41】公明新聞2024.10.20
July 29, 2025
コメント(0)
-
苦境を乗り越える力となるもの
苦境を乗り越える力となるもの 明治時代、河川の整備は社会の喫緊の課題だった。政府は、海外から多くの土木技師を招いた。その一人がオランダ出身のヨハネス・デ・レイケ。30年もの間、日本に滞在し、大阪を流れる淀川などの改修を担当した▼事業は順風の中で進んだわけではない。当時は階級意識がまだ根強く残り、職人出身だった彼は、周囲から軽く扱われた。他国の技術による誹謗中傷にも苦しめられた▼困難に打ち勝つ力となったのが、親友の存在だった。親友は整備事業の計画や設計など、事あるごとにデ・レイケにアドバイスした。デ・レイケが愛妻を失った時には、真心の励ましを送った。2人の書簡のやり取りは、34年にもわたって続いた(『日本の川を甦らせた技師デ・レイケ』(草思社)▼後世に残る事業の道程には、思うに任せない事態がある。その時、支え合い、励まし合える仲間の存在は、苦境を乗り越える力となる。(略) 【名字の言】政教一致2024.10.19
July 28, 2025
コメント(0)
-
必要な依存が自立を助ける
必要な依存が自立を助ける 「必要な依存が自立を助ける」。著書『こころの処方箋』(新潮文庫)で、そう指摘するのは心理学者の河合隼雄氏。人は、互いに助け合って生きている。「依存を廃して自立を急ぐ人は、自立でなく孤立になってしまう」と◆「自立とは依存先を増やすこと」。そう発信しているのは、東京大学先端技術研究センターの熊谷普一郎教授。脳性まひで手足が不自由となり、電動車いすを利用する自らの体験に基づく考えだ◆東日本大震災の時、教授は5階にある職場から逃げ遅れた。エレベーターが止まったからだ。他の人は、はしごや階段を使って避難できた。だが、教授には避難を可能にする〝依存先〟がなくなっていた◆教授は感じた。世の中のほとんどのものは健常者向けに作られている。その便利さに依存している事実を意識することなく健常者は暮らしていける。自立とは、どんなものにも頼らず生きていることではない。依存先をたくさん持っていることなのだ◆教授は心から思った。「自立は依存しないことではなく、依存できるものを世の中に張り巡らせることだ」「これは障がいの有無にかかわらず、全ての人に通じる」と。(佳) 【北斗七星】公明新聞2024.10.19
July 28, 2025
コメント(0)
-
谷口雅春の才覚と手腕
谷口雅春の才覚と手腕 1930年に生長の家を創設した怪人物・谷口雅春は、もとをたどれば出口なおが創唱した大本教の信者だった。本名は谷口正治。生まれは1893年11月。出身地は兵庫県八部郡鳥原村(現・神戸市兵庫区)。地元の中学を経て早稲田大英文科予科に進んだが、本科に進んで間もなく中退し、紡績工場勤務などを経て大本教入りした。早大予科時代には直木三十五や青野末吉、西條八十といった著名文筆家と同期で、谷口自身、文才に恵まれていたらしく、大本教でも機関誌の編集などで頭角を現した。だが、まもなく大本教から離脱し、糊口をしのぐ方法として1929年に個人誌『生長の家』を発刊、「病気の治療」や「人生苦の解決」などに効果があると評判を呼び、購読者を増やして一挙に軌道に乗せていく。この経緯や背景について評論家の故・大宅壮一が1955年、『文藝春秋』に発表した「谷口雅春論」が興味深い。大矢らしい皮肉たっぷりの筆致で喝破しつつ、谷口という人物と生長の家の本質を端的に捉えているからである。一部を引用してみよう。〈金をもうけるといっても、彼(引用者注・谷口雅春のこと)としては文筆によるほかはない。それのこれまでの経験からいって、たまに単行本を出すぐらいでは生活が安定しない。個人雑誌という形で好きなことを書いて、一定のファンを獲得し、これを少しずつでもふやして行くことを考えたのは、初めから手持ちのファンが若干あったからである。大本教にいたころの彼は、〝手紙布教〟という役を担当していた。これは各種の名簿によって、これはと思う人物に目星をつけ、あなたのこれまでの生涯の中で興味のある話があったら、世間に発表したいと思うから知らせてほしいという手紙を出す、少しでも地位のできた人間は、だれでも自分の過去を語りたい欲望を持っているものだから、感激してすぐ返事をよこす、するとまた折返し、彼の書いてきたものに対する感想を書いて送る——といったような方法で、文通を行っているうちに、相手をうまくおびき寄せて信者にしてしまいのである。男では軍人、女では未亡人が一番この手にかかりやすい。谷口は大本教でこれを長くやっていて、そのコツをつかんでいるし、大本教の信者を横取りして、谷口個人のファンにしてしまったものも少なくない。これは従来属していた宗教から独立して一派を開くものがいつでも使う手である〉〈かくて一サラリーマンのヘソクリで細々とはじめた個人雑誌「生長の家」は、次第に、〝生長〟していって、昭和九年(引用者注・1934年9月)には、資本金二十五万円の株式会社光明思想普及会として新しく発足するころまで行ったのである〉(いずれも大宅「谷口雅春論」より。旧仮名遣いや旧漢字は現代仮名遣いと新字体に改めた) したがって生長の家は創設からしばらくの間、みずからを宗教団体とは位置付けず、「教化団体」と称していた。会員も「信者」ではなく「誌友」。戦前の宗教団体法にもとづいて宗教団体となったのは1940年のこと。あくまでも株式会社として谷口がつくった光明思想普及会は雑誌『生長の家』のほか『白鳩』、『光の泉』、総合雑誌『いのち』など数種を発行し、新聞に大きな広告を載せては「誌友」を急速に増やした。特に戦中は戦争遂行を全面賛美して教勢を拡大し、機関誌の発行部数は80万部を突破した。また生長の家の公称によれば、現在までの総発行部数は1900万部にも達するという。つまり、機関誌や出版物を次々に発効して信者に購入させ、大儲けするという宗教的手法——昨今の新興宗教が常套手段としている手法をいち早く確立したという点において、怪人物・谷口雅春の才覚と宗教経営の手腕は大したものだったというべきなのだろう。また、神がかり的な教祖の多い新興宗教団体のなかにあっては谷口は一応、文才のあるインテリであり、出版宗教という教団成り立ちの性格上、信者にも一定以上の知識層が多かったのも特徴といえば特徴だった。この点は、生長の家から熱心な政治活動化を輩出した遠因ともいえる。その生長の家の教義をごく簡単にいえば「万教帰一」。すべての正しい宗教は元来、唯一の神から発したものであり、時代や地域によってさまざまな宗教として真理が唱えられてきたが、根本においては一つである——そんな理屈のもとに仏教、神道、儒教、キリスト教から心霊学、果ては米国のニューソートやクリスチャン・サイエンス、フロイトの精神分析までをごっちゃ混ぜに取り込んでいると言われていて、大宅壮一は前出の「谷口雅春論」で生長の家を「カクテル宗教」「宗教百貨店」と揶揄した。これに対して成長の家や谷口側は「百貨店には一流の商品がならんでいて、市井の小売店よりも優良品がそろっていますように、そこには真理なる生粋の優良真理を抜粋して陳列してある」「デパートにはよい商品が集まっている。その伝でいうなら、生長の家には各宗教の真髄だけが結集されていることになる」などと主張、これも大宅に「自ら〝百貨店〟であることを認め、他の宗教を専門店、いや、〝市井の小売店〟あつかいしている」と皮肉られている。また、なんといっても「病気の治癒」や「人生苦の解決」こそが生長の家の信者の獲得の最大手段であった。それを支えたのは、谷口の著書『生命の実相』や『甘露の法雨』などに記された次のような独特の〝理論〟である。〈物質は畢竟「無」にしてそれ自身の性質あることなし。これに性質を与うるものは『心』にほかならず。『心』に健康を思えば健康を生じ、『心』に病を思えば病を生ず〉〈物質は無い。われわれが病気であるというのは、われわれが病気だという観念波動を送り出している状態にすぎない。ただあるのは『健康の観念』または『病気の観念』ばかりであります〉その上で谷口は、〈病的思想が無くなれば病気が無くなる。病気が無くなれば病気の治療に要する一切の費用がなくなる〉と唱え、こう訴えるのである。〈わが言葉を読むものは、あうぃんうぃの実相を知るが故に一切の病消滅し、師を超えて永遠に生きん〉つまり、谷口の著書を熱心に読むだけで病が癒り、これこそが奇跡の神癒だ——そういう〝理屈〟であり、実際に病が治ったという信者が殺到して教勢は急拡大していたというのだが、本書における私の目的はこうした生長の家の教義を分析したり論評したり批判したり、あるいはそのバカバカしさを皮肉ったりするところになるのではない。したがって生長の家の成り立ちや宗教的協議にかんするはなしはこのあたりにとどめ、戦後日本の右派活動や日本会議の「源流」にもなったという谷口の政治思想や生長の家の政治活動に話題を移そう。 【日本会議の正体】青木理著/平凡社新書
July 27, 2025
コメント(0)
-
—スイス—今なお残る美しい景観
—スイス—今なお残る美しい景観吉村 和敏(写真家)皆さんは、スイスにどのようなイメージを持っているでしょうか。アルプスの雄大な山々、麓ではヤギやウシたちが草を食み、死んだ空気に包まれた美しい景色——。そんなハイジの世界が広がっているのでは、と僕自身も思っていました。しかし、素朴な村というよりは、もっと歴史のある立派な街が多い。そんなスイスの美しい村を紹介したく、近著『「スイスのもっとも美しい村」全踏破の旅』(日経オリジナル ジオグラフィック)を出しました。スイスには四つの公用語があり、それぞれ異なる文化圏を持っています。それぞれの文化を感じさせる〝いかにも建物〟が多く、自分たちの文化を大切にしています。例えば、レマン湖を中心とするフランス語圏では、ブドウ園が広がるフランスの農家の雰囲気。イタリア語圏では教会のスタイルにイタリア文化を感じます。ドイツ語圏では、ロマンチック街道で見るような気の柱が特徴的な木組みの建物が。最後のロマンシュ語圏はハイジのイメージです。印象的だったのは本の表紙にも使ったポスコ・グリンです。山の中で景観としてもまとまりがあります。しかも、昔ながらの伝統・文化を大切にしている。いまだに昔ながらの暮らしぶりが色濃く残っているのですが、中でも、この地を開いたヴァルザー人の歴史や文化を伝える博物館が素晴らしい。このような博物館や資料館が各地に整備され、それぞれの歴史や文化に触れることができます。 スイスで感じるのは交通の便の良さ。険しい山の上であっても、公共の交通機関で行けてしまう。国内の鉄道網が充実していて、電車で行けないような奥地であっても、基本的にバスが通っています。いままで出した「美しい村」シリーズの時より、観光客も行きやすいのではないでしょうか。しかも、村の中が綺麗なのも日本と似ているかもしれません。住人の一人一人が、この村で暮らすことへのほっこりを持っています。薄くしい村で暮らしたいと思っているから、景観を壊すような開発はしない。一人一人の想いが強くないと、こういうまとまりのある景観はできないんです。ただ、建物の外観は昔のままですが、中は最新にアップデートされています。あったかいし、トイレも最新のもの。パソコンも使えて、暮らしやすいと思います。つまり、景観は守っていくけれども、暮らしは良くしたいというわけ。だから、100年後にもこの景観が保たれるのではないでしょうか。もうひとつの特徴は、地産地消を大事にしているところ。住民の皆が村の中でもモノを買う努力をしている。例えばアーレスハイムに有名な精肉店があります。お客さんがひっきりなしに来るし、従業員も元気いっぱいで活気にあふれています。こんな店があちこちにあるんです。スーパーなどの量販店もありますが、地元で買う方が多いんです。現実のスイスには、多くの日本人が知らない魅力が満載です。ぜひとも、ゆっくり散策するような感じでページをめくり、それぞれの村を旅してもらいたいと思います。=談 よしむら・かずとし 1967年、長野県生まれ。繊細な風景写真、息遣いが伝わってくるような人物写真の人気が高い。主な作品に「『スイスのもっとも美しい村』全踏破の旅』(日経ナショナル ジオグラフィック)『CAROUSELELDORADO』(丸善出版)などがある。 【文化Culture】聖教新聞2024.10.17
July 26, 2025
コメント(0)
-
〝自分の心の壁〟を破ること
〝自分の心の壁〟を破ること今月、開業60年を刻んだ東海道新幹線は、起工式から開業まで約5年半という「短期決戦型プロジェクト」だった。〝東京五輪までに間に合わせる〟〝安全性を損なわない〟。この二つを勝ち取るのは難事業だったに違いない▼〝二つの手立てを見つけなければ物事は「できる」と言えるが、「できない」と断言するには全方法の可能性をつぶさねばならない〟とは当時、技術長を務めた島秀雄氏の持論だった。そんな氏が書き残している。「〝出来ません〟と断ることはアッサリと云ってのけるのはどう云うことだろう」(高橋団吉著『新幹線をつくった男 島秀雄物語』小学館)と▼物事に取り組む前から「私にはできない」「どうせ無理」と、挑戦を拒む人もいる。中にはもっともな理由がある場合もあろう。だが、否定的な固定観念や思い込みから、不要な〝限界の壁〟を自分でつくっている場合もある ▼限界突破への第一歩は〝自分の心の壁〟を破ること。「仏法は勝負」の結果を左右する最大の要素は〝環境や他人〟以上に〝わが心〟である▼「強い自分をつくった人が真実の勝利者です。幸福者です」との師の言葉を胸に、きょうも進もう。自身に生き抜き、かけがえのない人生を自分らしく勝ち開こう。(代) 【名字の言】聖教新聞2024.10.14
July 26, 2025
コメント(0)
-
創価学会へのライバル意識と危機感
創価学会へのライバル意識と危機感 初代会長の故・牧口常三郎らによって1930年に創立された創価学会は、戦後の1955年に初めて地方議会へと議員を送り、よく1956年の参院選では3人の議員を当選させた。そして1960年、池田大作が第3代会長に就くと政界進出の方向性をますます強め、1961年には「公明政治連盟」を結成、1964年11月には公明党の結成大会を開き、大量の議員を一挙に政界へと送り出しはじめた。1965年7月4日の参院選では11人当選、同7月23日の東京都議選で23人当選、1967年1月の衆院選で25人当選、1969年12月の衆院選では47人が当選し、公明党が第3党に——。この勢いを見れば、生長の家をはじめとするライバル宗教団体が危機感を募らせたとしても不思議ではない。(略)谷口雅春率いる生長の家政治連合(生政連)を結成して政界進出を本格化させ、日本の宗教団体の中では圧倒的な保守本流である神社本庁も1969年に神道政治連盟(神政連)を結成、自らの意に添う政治家を育て、支える活動に乗り出した。神社本庁を中軸とする神道神社界は現在の日本会議を支える大きな柱であり、神政連にはその主義に賛同する超党派の国会議員でつくる神政連国会議員懇親会も存在して政界に隠然たる影響力を保持している。(略) ——そうして生長の家は1964年に生政連を立ち上げたわけですが、早大生の静稀さんたちが属していた学生連(生長の家学生会全国総連合)というのは、その下部組織ということになるのですか?「違います。生長の家では、生長の家の真理を基盤としつつ、いろいろな分野に出て活躍すべきだという考えでした。だから政治家の集まりが生政連。他に芸術家の集まりや教育者の集まりもあって、大学生が学生連、高校生は生高連(生長の家高校生連盟)もあって、それぞれが一応は独立組織なんです」——なるほど、その生学連や生高連が全共闘運動に対抗するために活動し、いまから考えると実に多士済々な右派学生運動を排出しましたね。現在の日本会議を事務総長として取りまとめている椛島有三氏はその代表的な一人です。「ええ。地方議会にもそういう人たちはたくさんいるし、学者だと憲法問題で長く活躍している百地君もそうですね」——日大教授の百地章氏ですね。集団的自衛権の行使容認に踏み切った安倍政管の安保関連法制をめぐり、憲法学者としては数少ない合憲論を唱えたのが百地氏でした。日本会議国会議員懇談会の枢要メンバーでも、例えば安倍政権の首相補佐官に就任し、首相のブレーンともいわれる衛藤晟一・参議院議員も出身の大分大学で全国学協の運動に参画していました。「そのほかに高橋史郎君もそうです。僕が生長の家の学生道場にいた4年間、彼とは一緒でした」——日本会議の役員を務め、復古的な家庭観を唱える「親学」の提唱者の明星大教授・高橋史郎氏ですね。ほかにもたくさんいるでしょう。日本会議の政策委員で、安倍政権のブレーンとされる伊藤哲夫氏も。「日本政策研究センターの伊藤君ね。彼はお兄さんが生長の家本部に勤めていました。僕もお兄さんにいろいろ指導されましたね」 「日本会議の大本は生長の家」 ここでもう一度、補足をしておきたい。日本会議やその周辺にいる生長の家出身者にかんしては、前章で類似の情報を記述したが、故人の侵攻や宗教的な属性に関する事柄は本来、それ自体を批判したりあげつらったりすることがあってはならないのはもちろん、情報自体が極めてナイーブかつ注意深く扱われるべきものである。しかし一方、戦後日本の右派運動や日本会議の実態を検証するため、生長の家とその信者の具体的な動きは欠かせない情報でもあり、これを記述することは十分な公益性があると私は考える。また、ここで記したことは、すでに大半が公にされているものであり、実際にはこのほかにも戦後日本の右派運動や日本会議の内部、周辺に多くの成長の家出身者がいる。さらに戦後日本の右派運動と成長の家の関連性について言うなら、三島由紀夫の「盾の会」に参画し、1970年に陸上自衛隊市谷駐屯地で三島とともに自刃した森田必勝も、1960年に日本社会党の委員長・浅沼稲次郎を殺害した山口二矢も、生長の家を率いる谷口雅春の思想に深く共鳴していたとされる。日本の保守政界の多数の重鎮たちも谷口思想の信奉者だった。それほどに成長の家が戦後日本の右派運動に刻み込んだ足跡は深く厚く、本書の主題である日本会議も例外ではない。鈴木邦男へのインタビューに戻る。 ——鈴木さんにとって、生長の家というのはそういう存在なんでしょうか。「生長の家というのは当時、僕ら右派学生にとって、『宗教』という以前に、『愛国運動をやっているところ』だと思っていました。でもご存じのとおり、成長の家はずいぶん前に政治活動からは一切手を引いていました」——ええ。だというのに学生時代、生学連などで活動していた人々が今も熱心に政治活動に取り組んでいるのはなぜなのでしょうか。「みんな真面目なんですよ。特にいま、日本会議に関わっている生長の家出身の人たちなんて真面目です。だって、親が生長の家に入っていた人が大半で、親の薦めで高校生や大学生の錬成会に入った人だったんですから親孝行ですよ。普通、親から宗教団体の集まりに行けなんて言われたら反発するでしょう。それを素直に聞くというのは、やっぱりみんな素直ないい子ばっかりなんです。だから、自民党の先生方からも好かれるんです。それに、彼らにはきちっとした運動能力がある。普通、右派の活動家というのは事務能力なんてないんですよ。その点、彼ら(生学連出身の人びと)は学生時代に培ったノウハウを持っている。椛島君なんかがその典型でしょう。ただ、みんな宗教団体の別動隊だと思われるのをすごく気にしていました。それは椛島君たちもそうでした」——どうしてですか。「だって、宗教団体といったら、それだけで取り上げられなくなってしまう。そういう目で見られたくないと考え、生長の家出身だとなかなか明かさなかった、でも、やっぱり生長の家は大きいですね。日本の戦後の右派活動の中でも占める位置が大きい」——そうですね。実際、椛島氏たちが中心になってつくった生長の家系の全国学協があって、その派生団体が今も日本会議を支えています。ならは、日本会議の源流も生長の家だとみることもできると思うのですが。「ええ、僕もそう思います。日本会議の大元は、生長の家だと」 【日本会議の正体】青木理著/平凡社新書
July 25, 2025
コメント(0)
-
右派人士を網羅した「国民会議」
右派人士を網羅した「国民会議」 日本会議は1997年5月30日、いずれも有力な右派団体として知られていた2つの組織——「日本を守る国民会議」と「日本を守る会」が合流する形で産声をあげた。(略)まずは前者の「日本を守る国民会議」である。これは、いわゆる「元号法制化運動」などに取り組んだ団体を発展解消する形で1981年10月に誕生している。この「国民会議」の運営などに深く関わり、かつては自民党を代表する右派としての名をとどろかせていた元参議院議員の村上正邦(労相、自民党参議院会長などを歴任)のもとを訪ね、経緯を聞くと、往時を率直に振り返ってくれた。私の先輩ジャーナリスト・魚住昭による村上への聞き書き「証言・村上正邦——割れ、国に裏切られようとも」(2007年、講談社刊)の内容などを合わせ、以下、村上の証言を紹介していきたい。「私たちが天皇ご在位50年(1975年)の奉祝行事、それに続く元号法制化運動に成功し(元号法制定は1979年)、せっかく結集した組織が解散してしまうのはもったいないと、そういう声が出ましてね。そこで新たなテーマに取り組む国民会議を作ろうという話になって、財界や政界、学会、宗教界などの代表が中心になって800人ほどが集まって、それで『日本を守る国民会議』を結成したわけです」発足当時の議長には、外交官として国連大使を務めた加瀬俊一が選ばれ、右派論客としても知られるようになっていた作曲家の黛敏郎が運営委員長として全体を取り仕切る形をとった。事務方を総括する事務総長に就いたのは明治神宮権宮司の副島廣之。まもなく議長職は黛敏郎が引き継ぎ、一時は日本の右派運動の中心的存在として様々な活動に取り組んだ。代表的なもののひとつが1986年、同会議が主張し、復古調の歴史観が大きな波紋を巻き起こした高校日本史教科書『新編日本史』の編纂作業などであったろう。参考までに、「国民会議」の活動に役員などとしてかかわった面々を列挙すれば、次のような人物の名をあげることができる(カッコ内は主な肩書、故人を含む)。宇野精一(東大名誉教授)、清水幾太郎(学習院大学教授)、小堀桂一郎(東大名誉教授)、江藤淳(評論家、東京工大教授)、香山健一(学習院大学教授)、村松剛(筑波大学名誉教授)、加瀬英明(外交評論家)、村尾次郎(歴史学者)、瀬島龍三(伊藤忠商事会長などを歴任)、井深大(ソニー名誉会長)、石井公一郎(ブリジストンサイクル相談役)、塚本紘一(ワコール創業者)、武美太郎(日本医師会会長)、小田村四郎(元行政管理事務官、拓殖大学総長)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、百地章(日大教授)、大原康男(国学院大学教授)……。分かる方には分かるだろうが、いずれも新旧の右派人士を網羅するような顔ぶれであり、文字通り学会、財界、そして宗教界や政界右派が総結集したと評しても過言ではない組織として「国民会議」は存在していた。 〝宗教右派〟が結集した「守る会」 一方、後者の「日本を守る会」である。こちらは「国民会議」に先立つ1974年、主に右派系の宗教団体が中心となってつくられた。いわば〝宗教右派組織〟といえる。元自民党参議院議員・村上正邦は、こちらの団体にも「国事対策局長」としてかかわり、設立経緯をよく知っていた。その村上によると、血清の発端となったのは臨済宗僧侶の朝比奈宗源だったらしい。鎌倉・円覚寺貫主などもつつとめた朝比奈は、政治家・尾崎幸雄やキリスト教社会運動家。賀川豊彦らと「世界連邦運動」などを広げた経歴を持つ。村上の証言である。「朝比奈さんはもともと平和運動に熱心だったんですが、あるとき伊勢神宮に参拝して〝天の啓示〟を受けたそうなんですね。それで、以前から付き合いのあった明治神宮の伊達巽宮司や富岡八幡宮の富岡守彦宮司、そして谷口雅春といった方々に『守る会』を作ろうと声をかけ、その輪が広がって各宗教団体の指導者や思想家、文化人も加わって『守る会』が結成されたというわけです」村上のいう谷口雅春とは、新興宗教団体「生長の家」の教祖である。1983年、兵庫県に生まれた谷口は、戦前の1930年に生長の家を創設した怪人物であり、戦中は「日本精神の権限」を訴えて軍部の戦争遂行に全面協力し、信者を急速に増やした。戦後の一時は鉱床信者数が300万人を超えるほどの教勢を誇り、1964年には政治結社として「生長の家政治連合」——略称「生政連」を立ち上げて政界進出も図っている。つまり生長の家は、きわめて右派色の強い巨大新興宗教団体であり、一時は現実政界とも密接なつながりを持っていた。実を言うと村上正邦に自身、かつては生長の家の全面バックアップを受けて自民党から参院選に出馬し、当選を果たした〝生長の家直結〟の政治家であった。この「守る会」の結成に、生長の家の教祖・谷口雅春が大きく貢献したことは重要な意味を持つ。したがってこの点は、もう少し正確に前後関係を確認しておきたい。次に引用するのは、「守る会」の設立に尽力した富岡守彦の跡を継いで富岡八幡宮の宮司となった澤渡盛房が1985年、これもまた生長の家出身者でつくる右派団体「日本青年協議会」の機関紙『祖国と省年』(同年8月号)に寄せた文章である。少し長くなるが、生長の家という新興宗教と新党系の宗教団体が戦後日本の右派運動の源流に脈打っていることを知るため、ぜひお読みいただきたいと思う。〈昭和四十八(引用者注・1973)年〉ごろのことだった。富岡八幡宮先代富岡盛彦宮司は神都伊勢神宮の宿舎で鎌倉・円覚寺派朝比奈宗源官長と同宿の際、どちらからともなく日本の現状を憂える話題に及んだことがあった。(略)このお二人がこれから行動を起こそうという時に真っ先に考えた事は、かけがえのない明治神宮の神域を拠点に活動しておられる伊達巽明治神宮宮司の協力を頂くことが絶対に必要だった。この方は富岡宮司からの呼びかけによって快諾が得られた。そして、有識者歴訪が始まるのであるが、最初にお尋ねしたのが生長の家の谷口雅春総裁であった。私は当時鞄持ちとして富岡宮司に従うことが多かったが、世相を歎じ、宗教審の渙発を論じ、談論風発、精神運動の必要を断じて三ツ巴の論談が展開されたことは云うまでもない。その時である。『生長の家の二つや三つぶっ潰れても、祖国日本が本来の姿に立ち戻るためにはそれもやむを得ない、私たちはそのような覚悟と固い決意で成長の家を拠点とした宗教運動に精進している。協力を惜しまないどころか、生長の家の活動そのもののめざすところはそこにある』という力強いことばが谷口総裁の口から迸り出したのであった。まさに愛国者の箴言だった。これに力を得た両大人はそれから手分けをして目指す有識者を説き廻って遂に昭和四十九(引用者注・1974)年四月二日、明治記念館における「日本守る会」の発足につながるわけである〉(原文ママ) 神道系の中心的存在というべき明治神宮。そして、戦後日本の右派運動に大きな影響を及ぼした谷口雅春率いる巨大新彊宗教・生長の家。その双方のトップに右派系の宗教人が声をかけ、双方から分厚いバックアップを受けて発足した「守る会」——。この構図は、繰り返しておくが、今もなお脈々と受け継がれている。つまり日本会議という存在の背後には、神社本庁を軸とする新党系宗教団体と成長の家の陰が組織的にも、人脈的にも、そしておそらくは資金的にも、べったりとはりついている。これについても詳しく後述することになるから、ここではとりあえず記憶にとどめておいていただきたい。 【日本会議の正体】青木理著/平凡社新書
July 25, 2025
コメント(0)
-
映画 ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ
映画 ジョーカー:フォリ・ア・ドゥホアキン・フェニックスが、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』で、初めてのことに挑戦した。続編への出演だ。40年にわたるキャリアで、フェニックスは一度も同じキャラクターを演じていないのだ。だが、前作の続きでありながら、新たなアプローチをするこの続編に、フェニックスは大きな興奮を覚えたという。この映画かかける意気込みを聞いた。(映画ジャーナリスト 猿渡由紀) ストーリー誰かに愛されることを、人生でずっと願ってきたアーサー(フェニックス)。そんなある日、ジョーカーの熱烈なファンだというリー(ガガ)が現れた。一方で、複数の殺人罪で起訴されたアーサーには、裁判が迫っている。アーサーの弁護士(キャサリン・キーナー)は、虐待を受けて育ったアーサーについて、彼の頭の中にジョーカーという別の人格があることを主張する。 殺人容疑で収監中の男謎の女と出合った彼の運命は…主演のホアキン・フェニックスに聞く5年前の『ジョーカー』の公開時、トッド・フィリップス監督は、凝れば独立した映画だとし、続編の可能性はまるで匂わせていなかった。しかし、実際には、前作の撮影現場で、「もし次を作れるとしたら」と、想像を巡らせていたのだという。「冗談半分での会話だったよ。いや、トッドは冗談のつもりだったようだが、僕は本気だった。このキャラクターについて、まだ語れることがあるように感じたから。そうしたら、トッドと(共同脚本家の)スコット・シルバーが想像のしなかった素晴らしい脚本をかいでくれたんだ。1作目で起きたことに敬意を捧げつつ、新しいことをやってみせる。オリジナルな脚本を。やらないという選択肢はなかったね」 続編に出演するのはキャリア初「制作過程に大きな満足を感じた」 舞台は、2作目のラストから、間もない頃。アーサー(フェニックス)は、複数の人物を殺害した容疑で収監されている。そんなある日、同じ建物の中で音楽セラピーを受けているリーという女性に出会った。リー役に抜擢されたのは、フィリップスがプロデューサーを務めた『アリー/スター誕生』で初主演を果たしたレディー・ガガ。フェニックスとガガは、昔のミュージカルの名曲や、スティービー・ワンダーのヒット曲を、数々の歌を歌う。ジョニー・キャッシュの伝記映画『ウォーク・ザ・ライン/君に続く道』でも歌ったが、その時とは違う難しさがあった。「『ウォーク・ザ・ライン』では、ジョニー・キャッシュのような歌い方をする必要があった。人は、彼がどんなふうに歌うかを知っている。でも、アーサーがどう歌うのかは、誰も知らない。それは大いなる自由でもあり、プレッシャーでもあったよ。それに、今回はライブで歌うものと違っていたね。難しいことはたくさんあったが、トッドが連れてきてくれた、音楽の分野の優れた人たちが、手助けしてくれた。僕たちはみんな同じゴールを目指していたよ。これを正統派のミュージカルにするつもりは、誰にもなかった」1作目では、キャリア初のオスカーを受賞した。それは特別な思い出だ。「努力をつぎ込んだものが人々に受け入れられ、評価されるというのは、すてきなこと。だけど、それで何かが変わったかというと、ノーだ。僕は今も、作る過程が素晴らしいものになったかどうかで、成功を判断する。今作でも、トッドのような優れた人と、最高にクリエーティブな体験をさせてもあった。この映画がどんな結果になるのかは分からないけれど、制作過程について、僕は大きな満足を感じているよ。◇配給=ワーナー・ブラザーズ映画。 【エンタメ】公明新聞2024.10.12
July 24, 2025
コメント(0)
-
はにわ
はにわ東京国立博物館主任研究員 河野 正訓国宝指定50周年挂甲の武人5体が結集この秋、東京国立博物館では約50年ぶりとなる大規模な埴輪展を再際します。埴輪は、3世紀半ばから6世紀にかけて、古墳時代の墓(古墳)に立てられた造形物です。亡くなった古墳の主を鎮魂するため、さらに古墳を聖域として守るため、さらに古墳を聖域とし守るための飾りとして、埴輪は用いられました。その埴輪の代表作として知られるのが、東京国立博物館が所蔵する「埴輪 挂甲の武人」です。造形的にも優れており、頭から足先まで甲冑で覆われ、弓と大刀を持ち、背中には矢いれ具を背負います。これほどフル装備した武人は他になく、埴輪として日本で初めて国宝に指定されました。今回の特別展は、挂甲の武人が国宝に指定されてから50周年をお祝いするために企画しました。この挂甲の武人は、群馬県太田市の窯で焼かれたもので、兄弟のように似ている、同一工房作の埴輪が4体あります。5体中4体は群馬県外の博物館にあり、遠くはアメリカのシアトル美術館で収蔵されています。今回、史上はじめて形態体が結集するという特別な機会を作ることができました。さて、東京国立博物館が所蔵する挂甲の武人は、近年の調査研究により全身を彩色していることがわかりました。赤・白・灰と塗り分けられていたという、埴輪のイメージを一新する成果が出ましたので、色彩したレプリカの埴輪も制作し、特別展で初のお披露目展示をいたします。この特別展は「はにわ」では、他にもご注目いただきたい点がたくさんあります。踊る埴輪として親しまれている「埴輪 踊る人々」について近年ファンドレイジングでご寄付をいただき、解体修理を行いました。踊る埴輪は、挂甲の武人とは対極といえる、ユルい埴輪です。埴輪の特徴として、表現が退化する方向で変化する傾向があります。埴輪作りが終わりを迎える頃、究極的に退化したのが躍る埴輪なのです。デザイン的に優れていますので、埴輪といえば踊る人々をイメージする方も多いことでしょう。その修理後の初お披露目もさせていただきます。なお、ここ30=40年くらい、この埴輪は踊っておらず、片手をあげて馬を引いていた人物がモデルではないかとみる説が出てきております。この人物が何をしているのか想像しながら、埴輪をご覧いただければ幸いです。 古墳時代を想像する楽しみ 埴輪は人だけではありません。土管のような円筒埴輪が最も多く、家や器材、動物などがあり、古墳時代の風景を今に伝えてくれています。各種の埴輪は、それぞれ役割を与えられて作られ、5世紀以降は物語を構成するかのように人や動物などがまとまって群像を形成しています。そのストーリーについて研究者によってさまざまな解釈が与えられ、謎めいているのが埴輪の持ち魅力の一つなのでしょう。全国各地の博物館を代表する埴輪が、この秋には東京国立博物館に、冬から春にかけては九州国立博物館に結集いたします。空前絶後の規模の埴輪展にお越しいただき、日本列島で独自に発達した古墳文化に直接触れてください。(かわの・まさのり) 【文化】公明新聞2024.10.9
July 24, 2025
コメント(0)
-
努力は戦略的に
努力は戦略的に作家 伊東 潤本が売れないにもかかわらず、昨今なぜか小説家志望者は激増し、その逆に読者の数は下降線をたどっている。作家になりたい人はなぜか楽観的で「私だけは大丈夫」「なんとかなるさ」「私は運が強い」の三点盛りで突っ走る。確かに、なにごとも否定的に考えることはよくない。確かに昭和の頃は、「何とかなるさ」で成功した人が山ほどいた。その理由は単純で、あらゆる業種、業界、市場が経済成長によって拡大の一途をたどっていたからだ。しかし経済成長が鈍化し、人口減社会が目前に迫っている今、「なんとかなるさ」は通用しなくなっている。こうした時代こそ、みずからの限られた時間を成長産業に振り向けねばならない。私のいる出版業界で言えば、小説家よりも脚本家を目指したほうが、より将来性あると言える。これまでの映画化作品は劇場用映画化テレビドラマだけだったが、動画配信サービスの登場によって作品数が激増し、脚本家が足りなくなってきている。とくに『SHOGUN 将軍』の大ヒットにより、歴史ドラマはブームになっていくと言われている。しかし歴史のことをよく知る脚本家は少なく、斬新な解釈の歴史ドラマを生み出していくのは至難の業だ。私も若ければ脚本化をめざすのだが、連載の予定が二年先まで詰まっている身としては、このまま小説家として突っ走るしかない。しかし若い人は違う。やる気次第で衰退産業から成長産業へ乗り換えられる。起業するにしても、成長産業で勝ち組を目指したほうが成功確率は高まる。しかし先を見据えることで、まったく新しいものが見えてくる。人生は一度きりだ。同じ努力をするにしても、戦略的に努力してほしい。 【すなどけい】公明新聞2024.10.11
July 23, 2025
コメント(0)
-
ケストナー没後50年
ケストナー没後50年詩人 藤田 晴央詩や児童文学を通じて、市民の視点で社会に警鐘エーリッヒ・ケストナー(1899~1974)は『飛ぶ教室』『エーミールと探偵たち』『ふたりのロッテ』などでドイツを代表する児童文学作家として知られているが、もともとは詩人として出発した人である。1928年の第一詩集から32年までに四冊の詩集を刊行し、多くの読者を獲得していた。しかし、1933年5月、ナチスがドイツ各地の図書館から「反国家的」な図書を持ち出し、広場に積み上げて燃やす「焚書」がなされ、ケストナーの本も燃やされた。そんなケストナーに「列車の比喩」という詩がある。その一部分を紹介する。「ばくらはみな同じ列車にこしかけ/時代を旅行している/ぼくらは外を見る ぼくらは見倦きた/ぼくらはみな同じ列車に乗っている/どこまでか 誰も知らない/(略)/行きさきは車掌も知らない/列車は黙って出てゆく/突然けたたましく汽笛が鳴る!/列車は徐行してとまる/死人がゾロゾロ降りる」『人生処方詩集』(小松太郎訳)これは、ナチス台頭機に書かれたもの。ケストナーは個人も国家も言葉鮮やかに風刺した。その詩には、人権を尊ぶモラルへのこだわりがあった。ケストナーには大人のための長編小説『ファビアン』がある。ワイマール共和国末期のベルリンを背景に、主人公ファビアンを通して「時代」をシニカルに描いている。台頭期のナチスの支持者も登場して左右が対立する混沌とした政治状況の中でファビアンは自己の進む道を模索する。「同時代の人々がロバのように強情に、後ろ向きに歩いているのが見える。奈落が口をぽっかり開け、ヨーロッパの全国民が堕落するのを待っている」(丘沢静也訳)。「あとがき」の一文である。この本が出された後、ヨーロッパはまさに「堕落」していく。ケストナーは強烈な反体制の運動家ではなかった。多くの詩人・作家が亡命していく中、ナチス支配下のドイツでの出版を禁止されながらも自国にとどまり生きのび、著作は隣国スイスから出版した。そこには、風刺詩人としてのしたたかな精神があったように思われる。ケストナーの児童文学の諸作品に通底するのは自由を奪う息苦しい社会への批判である。どの作品にも、母への愛情が色濃く流れている。その立ち位置はいつも、貧しかった少年期にあり、彼はいつも、危うい立場の「市民(ピュルガ―)」の側に立っていた。そのような市民の一人としてケストナーは、戦後も絶えず社会に警鐘を鳴らし続けた。一昨年文庫版が出た『終戦日記一九四五』は、1945年のドイツは五銭前後の日々を描いた貴重な記録だ。敗戦までのナチス党員の残虐な行為、彼らの顔色をうかがう一般市民、逃げ帰ってくるドイツ兵の惨めさ、それまでドイツの占領国だった人々の手のひらを返すような対応などを語る描写は皮肉に満ちていて、国外に亡命していては書けない鋭い人間観察の虚として、第一級の文学作品となっている。今年はケストナー没後50年。押し寄せるファシズムに対してモラルを軸に詩や児童文学を通して警鐘を鳴らし続けた作家ケストナー。放射能汚染や地球温暖化への対応、軍事力強化や福祉充実の行方など問題が山積みの今、わが国の進もうとしている道の先に「奈落」が口を開けていないかどうか、ケストナーの言葉に救われるものは大きい。(ふじた・はるお) 詩集『夕顔』で三好達治賞を受賞。評論集など著書多数。2024年思潮社から『現代詩集文庫・藤田晴央詩集』が刊行。青森県弘前市立郷土文学館運営委員長。 【文化】公明新聞2024.10.11
July 23, 2025
コメント(0)
-
創価学会は人々をつなぎ社会に「安定」をもたらす
創価学会は人々をつなぎ社会に「安定」をもたらすインタビュー 日本大学教授 西田 亮介さん「イメージ政治」——政治資金問題や政治家によるパワーハラスメントの報道もあり、政治への不信が強まっています。現在の政治状況について、どう捉えていますか? 日本における政治不信は、ある種の社会的な「諦念」「諦め」になっています。いまでは、世論調査で支持政党を尋ねても、最も多いのは「特に支持している政党はない」という回答で、〝本当の第一党は無党派層〟と言われることもあります。しかし、こうした状況は、今に始まったことではありません。内閣府が継続的に行っている「社会意識に関する世論調査」では、国の政策に民意が反映されているかを問う項目があります。昭和の時代から最近まで一貫して、「反映されていない」という回答が多数を占めています。一般に多くの国民は、政治について施策の詳細まで知ることは少なく、メディアなどの情報を通して、政策の良し悪しを判断していると考えられます。近年は、政治的な決定や洗濯において、「イメージ(印象)」が強く影響を及ぼしており、政治家もイメージ重視です。私はこうした状況を「イメージ政治」と呼んでいます。人びとは、政治において、必ずしも実態とは合致しないイメージを重要視しているのです。そして、政治や行政もまた、そうした印象重視の環境に対し、過剰に適応しています。つまり、政策の「中身」を吟味するよりも、パッと見て〝良さそうだ〟と感じる「イメージ」が偏重され、政治が動きかねない状況です。最近は、インターネット上の動画などで話題になった政党や政治家に、大きな注目が集まりがちです。政治家の側も、あらゆるネットメディアに登場して、イメージを発信することに力を入れており、実際にそれで一定数の支持者が集まることもあります。政治について腰を据えた議論が少なくなり、イメージばかりが重視された結果、どうなったでしょうか。私は「耳を傾けすぎる政治」が現れたと考えます。効果や合理性よりも、可視化された「わかりやすい民意」に安置に身をゆだねる政治の在り方です。もちろん政治は、民意に耳を傾けるべきです。しかし、民意は常に正確であるわけではなく、合理性や効果に基づいた批判や提案をするとも限りません。自由民主主義の社会においては、表現の自由があり、正確でないとしても、民意が表現される権利は守られるべきです。だからこそ、誤った認識に基づく民意に対しては、政治は安置に身を委ねることなく、責任を持って対話を重ねることが求められます。合意に至らない場合は説明を尽くし、特には説得を試みたり、決断したりすることも必要です。しかし、「耳を傾けすぎる政治」は、こうした対話や説明を省略します。ワイドショーでの評判や、インターネットでの対話など、とにかく「わかりやすい民意」に、脊髄反射的に「反応」しようとします。それは実のところ、一貫性もなく、聞いているふりをしているだけの政治です。今、日本はかつてのような経済成長は期待できず、地域のつながりも希薄になり、先行きの見通しも立たない社会になってきています。こうした不安に覆われた社会において、「イメージ政治」や「耳を傾けすぎる政治」が強まっていくことには、危うさを感じます。 生活とつながる——諦めやイメージ偏重が強まる中で、私たちは政治にどう関わればよいのでしょうか? 主権者を育み、まっとうな政治参加を促すためには、政治教育が必要です。現在も見直しは進められていますが、真正面から「政治教育をどうするか」ということを、もっと議論するべきだと思います。たとえばイギリスでは、政治学者のバナード・クリックによって「市民性教育」が提唱され、中等教育の必修科目になっています。またヨーロッパでは、選挙権を与える年齢を16歳に引き下げようとする運動も広がっています。一方で日本には、こうした政治教育や運動は、ほぼ見当たりません。学校教育では、民主主義の理念や、衆議院・参議院の定数などを教えることはあっても、具体的な政党名や政策を挙げて、現実政治の知識を学ぶ機会は、ほとんどありません。また家庭でも、食卓を囲んで政治を議論するような場面は、あまりないでしょう。例外なのは、創価学会の皆さんかもしれません。以前、学会青年部のイベントに招かれた際に、学会員の過程では、選挙や政治の話を頻繁にすると聞きました。そういう環境があることは、良いことですね。 「隠れた多数派マジョリティー」として「国民益」の実現に寄与 ——創価学会第2代会長の戸田城聖先生は、「青年は心して政治を監視せよ」と教えました。この言葉は、私たちが政治にかかわる上で、重要な指針になっています。 私はこれまでも、創価学会の皆さんが公明党も含めた政治に対し、きちんと意見する姿を見てきました。それは良いことだと思います。一方で、社会全体としては、多くの人が現実政治について知識が乏しい状況です。もちろん、教員の地位を利用した選挙運動や、特定の政党に偏った教育は認められません。その上で、学校教育において創意工夫を凝らして、現実の政党や政策について理解するための授業が造られていけば、それが日本の民主主義の底上げになるのです。そうした政治教育を行うための共通認識と環境づくりが必要だと考えています。何も難しいことではありません。まず知っておいてほしいことは、ただ一つです。それは、「政治は私たちの生活と密接に関係している」ということです。政治が自分の生活に関わらないと考えるのは、端的な間違いだからです。さまざまな仕事やビジネスの在り方は、「業法」と呼ばれる法律によって定められています。例えば、鉄道会社がダイヤを変更するときは、国土交通省に届け出なければなりません。また最近、国立大学の授業料の値上げが議論されていますが、その引き上げ額は文部科学省で決められています。こうしたルールを変えるためには、政治家が動いて、法律を変える必要があります。つまり、政治や行政でしか解決できない課題があるということです。政治への不信が「諦め」に近い状態にある今、自分たちの生活と政治はつながっていると認識できれば、まずそれだけでも十分でしょう。たとえ短い時間であったとしても、政治に「目を向ける」といいうことは、政治へのかかわり方として大切です。 政教分離の誤解——これまで、創価学会と公明党の関係について、憲法第20条の「政教分離」の原則に反するかのような誤解・曲解に基づいて、いわゆる〝政教一致〟批判も繰り返されてきました。 日本絹布における「政教分離」は、統治機構(政府が特定の宗教を排除・弾圧したり、優遇したたりしないことを定めたものです。国民の自由な信仰や、宗教団体の政治活動を阻害するためのものではありません。故に、「政治と宗教は関わるべきではない」と捉えるのは、誤った認識です。つまり、政教分離にまつわる批判は、憲法リテラシー(情報を読み取る力)の低さの問題ではないでしょうか。キリスト教が広く普及したヨーロッパでは、宗教政党が当たり前のように存在しています。例えばドイツには、「キリスト教民主同盟」や「キリスト教社会同盟」という政党があり、与党になったことがあります。また、イギリスのように国境を定めている、政教一致国もあります。ともあれ、本来、政治がめざすべきは「国民益」の拡大です。しかし現実には、政府が考える「国家益」は、必ずしも「国民益」と合致するわけではありません。国家と国民の間に利益の違いがあるならば、両者をつなぎ留める役割が必要になります。現代の創価学会は、学会員にとどまらない幅広い生活者の要望を救い上げ、政治につなげており、広く国民益を実現する役割を果たしています。 宗教の役割——創価学会は宗教的価値観を基に、平和・文化・教育など、幅広い活動を行っています。学会が、日本社会の中で果たすべき役割とは何でしょうか? かつて日本でも、職能団体や労働組合、地域コミュニティーなどが、国家と個人を結ぶ「中間集団」として機能していました。宗教団体もその一つです。宗教は、人びとに心理的な安らぎや、自分を承認してくれる居場所を提供し、それらを通して社会に安定をもたらす社会的役割を担っています。しかし、現代では中間集団の多くは、活発ではなくなっています。そうした中で、創価学会は会員数も多く、分厚い中間集団です。また、収去団体の多くにおいて、設立初期に社会との摩擦が少なからずあるものですが、現在の創価学会は社会と調和し、安定して存在しています。これは、他の新興宗教との大きな違いだと思います。戦後の日本社会は、経済状況が基盤となって、人びとのつながりを支えてきました。けれど、今の日本は、今後の急激な経済成長、国際競争力の向上などを見込むことが難しい状況です。少子化や高齢化も進んでおり、近年は物価高にも直面しています。厳しい状況は、十数年からから100年単位で続く可能性があります。こうした苦難の時代において、経済以外で、人がつながり、自分の存在を承認され、孤立を防ぐ居場所が重要になってきます。宗教や宗教的連帯は、巧く機能すれば日本社会の不安定性に対抗する足掛かりになるといえるでしょう。宗教社会学は、社会と宗教は、お互いに存立する基盤を提供しあってきたと説明します。ゆえに、社会と共存できない宗教、つまり破壊的な宗教は、許容されません。その点でも、数十年にわたって、社会との安定的な関係を持っている創価学会は、他に類を見ない存在だといえるでしょう。私は、創価学会を「隠れたマジョリティー(多数派)」と考えています。会員の多さや多様さを包含する、その存在は実は多数派です。「隠れた」というのは、存在感が大きいにもかかわらず。その活動内容が一般にもあまり知られていないという意味です。だからこそ、創価学会の皆さんには、より積極的な活動を社会に発信し、コミュニケーションすることを期待したい。インターネットが登場する以前は、マスメディアが人々をつなぐ役割を担っていました。しかし、現在はテレビを通して、多くの人が共通の話題や情報に触れていました。島市、現在はネットが中心になり、どんな情報やコンテンツを見ているかは、人によってさまざまです。共通性をもったコミュニケーションが賺しくなり、時代はあまりにも多様になっています。そうした多様性が大きく進んだ社会においては、人々をつなぎ合わせる機能が、希少な価値を持ちます。その意味でも、創価学会は日本の社会の中で、重要な役割を果たす存在だと考えます。 にしだ・りょうすけ 1983年、京都府生まれ。日本大学危機管理部教授。東京科学大学特任教授。慶應技術大学院博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。専門は公共政策の社会学。情報と政治、ジャーナリズム等を研究。著書に『17歳からの民主主義とメディア授業』(日本実業出版社)、『コロナ機器の社会学』(朝日新聞出版)など多数。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」】聖教新聞社2024.10.10
July 22, 2025
コメント(0)
-
網膜の中の風景
網膜の中の風景東京大学名誉教授 安藤 宏太宰治は「一つの約束」というエッセイの中で、世の中にはついに誰にも知られることなく終わってしまう事実のあることを強調している。昔、船の理が難破して海に放り出され、やっとの思いで灯台にしがみつき、窓をのぞいたところ、そこには灯台守一家の楽しいだんらんが繰り広げられていた。もしも自分が助けを求めたら、その団らんは壊れてしまう。そう思って躊躇した瞬間、大波が押し寄せ、船乗りはそのまま海に吞み込まれてしまった、というのである。もちろんこの事実を見たものはだれもいない。けれどもその船乗りの思いを言葉にして伝えることにこそ、文学者の責務がある、というのである。この話は我々に、フィクションとはいかなるものについて、しみじみと考えさせてくれる。人は日々、せわしなく生きているが、決して損得勘定だけにきゅうきゅうとしているわけではない。無意識のうちにふと顔を見せる一瞬のためらいやとまどい。そうしたものの中にこそ、人間が気弱な「真実」が隠されているのではないか。これをすくい取り、想像力によって言葉に置き換えて見せることに、文学の使命があるのだろう。ちなみに太宰は同じ題材を「雪の夜の話」という短編でも扱っている。それによれば、難破した水夫の眼の網膜には、灯台守の一家の美しい団らんが残されていたのだという。一人の人間の網膜には、それまで見てきた数多くの、かけがえのない情景が蓄えられている。ただふだん、それを忘れてしまっているだけなのだ。ふと立ち止まり、心の中の映像に思いを馳せてみると、おそらくそこには、置き忘れていたさまざまな宝物が隠されていることに気づくことだろう。実は「思い出す」という行為は、人間だけに与えられた素晴らしい特権なのかもしれない。 【言葉の遠近法】公明新聞2024.10.9
July 22, 2025
コメント(0)
-
共に〝歓喜の生命〟へ
共に〝歓喜の生命〟へ循環器内科医 山下智子さんやました・ともこ 大阪府内の循環器内科で副部長を務める。1984年(昭和59年)入会。大阪市在住。副白ゆり長。関西ドクター部の誓春会副責任者。 「心こそ大切」を胸に刻むドクター 「心こそ大切なれ」(新1623・全1192)——医学生の頃から愛用する〝大切なパートナー〟であり聴診器に刻んだ御書の一節です。どんな多忙で、大変な時でも、この言葉に触れると、医師になった原点を思い返すことができます。そして、夢だった医師という職業に就けたことへの感謝の思いが湧いてきて、「さあ、もうひと頑張りしよう!」と決意を新たにすることができるのです。私の原点、それは中学1年の時、悪性リンパ腫で、45歳で若くして亡くなった父との思い出の中にあります。 人生を生き抜く小学6年生の時に父が入院。お見舞いに訪ねても、父は苦しい表情一つ見せず、笑顔で迎えてくれました。医師になった今だから分かりますが、当時の父は、つらい治療の真っただ中はずです。苦しくないわけがありません。けれど記憶にある父の姿は、少しもそれを感じさせませんでした。父は生前、私に手紙を書いてくれました。「お兄ちゃんと二人でお母さんのことを頼みます」「体に気をつけて」そして、「智子なら絶対に大丈夫」——今でも、手紙を読み返すと、最期まで家族のことを想い、病と闘い生き抜いた父の姿が浮かんできます。そんな父の人生は、幸福で充実したものであったにちがいないと私は確信しています。こうした経験はそのまま、医師として働くうえでの私の信念につながっています。担当する循環器内科で主に診るのは心臓。生死に直結する臓器です。病因まで救急で運ばれて、治療により一命をとりとめ元気に退院される方もいれば、心臓に病を抱え終末期医療に臨む患者さんも少なくありません。患者さんと共に、生死に向き合わせていただくこの仕事に、誇りと深い使命を感じています。持てる力のすべてを患者さんのために使いたい。その一心です。例えば、終末期にあってなお患者さんが、〝自分の人生を生き抜く〟姿は、ご遺族にとっても、悲しみを乗り越えていくために、とても重要なことです。自身の経験からみても、間違いないと思います。ただ、そうした個々人に寄り添う医療の体制を作ることは、実はとても大変なことなのです。ご本人の意向を最大限に尊重しつつ、看護師、社会福祉士、ケアマネージャー、理学療法士、薬剤師、管理栄養士……多職種の方々と綿密に連携を取らなければなりません。苦労は多いですが、信じる理想の医療を目指して、奮闘しています。どんなに時代が進んでも、AI(人工知能)には、「人が人を想い、関わっていく」ことの代わりは務まりません。一人の人に向き合う医療は、これからの時代、より一層、求められていくことでしょう。 その〝人〟を見るかつて、ある患者さんに言われてハッとしたことがあります。「僕の先生は、山下先生しかいない。どうかお願いします」せわしなく日々が過ぎていく医療の現場。ともすると、病気だけを診るのが診療になってしまいがちです。しかし、患者さんは皆、不安を抱えて来院されます。病気を診るだけではなく、そのひと〝人〟を見て、その〝心〟に同苦し、寄り添うことが、患者さんにとって、どれほど大事でしょうか。その一歩は、患者さんを診察室に呼ぶ時の第一声から。少しでも安心していただけるよう、はつらつと明るい声で呼ぶように心がけています。すると、ありがたいことに@山下先生に会うだけで治ったような気がする」「先生の声が一番元気で気持ちがいいわ」といっていただけることも多く、「声、仏事をなす」(新985・全708)との御聖訓に頷くばかりです。日蓮大聖人は、「蔵の財よりも身の財すぐれたり、身の財より心の財第一なり」(新1596・全1173)とも仰せです。〝命の現場〟にいるからこそ、心の財——どんな苦難にも負けない勇気や心の強さ、生命の輝きが、どれほど尊いものであるかを実感します。多くの方をみとる中で、最期の瞬間には、その人の人生が凝縮されていると感じます。ただただ感謝を述べられる方、穏やかな表情の方……。患者さんが一人でも多く、仏法に説かれる〝歓喜の生命〟で生涯を飾ってほしい——日々、そう祈り、まずは私が〝歓喜の生命〟を漲らせながら、「目の前の一人を大切に」との学会精神で診療に当たっています。現在、大阪府内の病院に勤務しながら、心臓の超音波検査に関わる研究を進め、医学博士号の取得に向けて、論文作成にも挑戦しています。〝妙法の医師〟として大事なことを教えてくださった、池田先生、学会の同志には感謝しかありません。先生が示された「生命の世紀」の開拓者として、人びとを希望の光で照らす医師として、さらに精進していきます!***************************************山下さん教えて健康長寿のために、日頃から何を意識すればよいのでしょうか?健康長寿のためには、身も心も健康であることが重要であるといえます。まず、体の面からいえば、生活習慣病の発症リスクを軽減させる生活が望ましいです。具体的には、日常的な運動、バランスの良い食事、質の良い十分な睡眠が大切です。それに加えて、規則正しい生活のリズムをつくることで、体に不調があっても気付きやすくなり、結果的に早期の受診につながります。また、心と体は深く関連していますから、体の調子を整えることで、心のゆとりも生まれます。そうすると、新しいことに挑戦する活力や、困難を乗り越える勇気が湧いてきます。これが心の健康です。さらに、「〇〇さんと約束した」「○○のために」というような、生きる目的や目標、信念を持っていらっしゃる方は、強い生命力を発揮されることが多いと感じます。*************************************** 【紙上セミナー「心こそ大切」を胸に刻むドクター】聖教新聞2024.10.8
July 21, 2025
コメント(0)
-
牧口先生「創価教育学体系」〈第2篇〉(1930年11月)㊦
牧口先生「創価教育学体系」〈第2篇〉(1930年11月)㊦ 社会の荒波から子どもたちを守り抜く教育は幸福な人生を歩み通すための礎 北海道で教師生活をスタートした牧口先生が、『創価教育学体系』を発刊する30年以上も前(1897年)に、経済的に困窮する過程の子どもたちと日常的に接していた時の体験を踏まえて、力説した言葉がある。「皆、等しく生徒である。教育の眼から見て、何の違いがあるだろうか」「たまたま、垢や塵に汚れていたとしても、燦然たる生命の光輝が、汚れた着物から発するのを、どうして見ようとしないのか」「(社会の中で過酷な差別がある)この時代にあって、彼らを唯一、庇護できる存在は教師のみである」(趣意)この北海道での教師時代に抱いた信念は、その後、東京でさらに強固なものになった。貧困家庭の児童たちのために開設されたミカサ尋常小学校に、1920年6月から校長として赴任した時には、病気になった児童の家に見舞いに行って自ら世話をしたほか、家庭の事情で食事が満足にできない子どもたちのために学校給食を実施した。また、白金尋常小学校に校長に転任した翌年に、関東大震災(23年9月)が起きた時には、牧口先生の提案で、古着などを集めて被災者に送る活動が行われた。その結果、子ども用の古着類が2900点も集まり、小学校の卒業生などから以前に使用していた教科書などが4000冊以上も寄せられた。秋の夜風が冷たくなる中で、心細い思いをしていた子どもたちにとって、届いた衣類がどれだけうれしかったことか。学用品を含めて家財の大半を失う中、授業に欠かせない教科書を再び手にできたときの安心感は、どれほど大きかっただろうか。被災の影響で転校してきた9人の児童にも、学用品が配布されたという。そうした温かな配慮に包まれながら、子どもたちは授業の再開を迎えたのだ。 『創価教育学体系』で牧口先生が教育の目的に関し、「子供たちの成長と発展が、幸福な生活の中で終始できるようにするものであらねばならない」(趣意)と訴えていた箇所がある。ここにある「終始」という表現は、教育について机上で考えているだけでは、決して出てくる言葉ではないだろう。〝自分が縁してきた児童をはじめ、全ての子どもたちが幸福な人生を歩み通せるようにしたい〟という現場の教育者としての切なる祈りが、文字となって紡ぎ出され、書籍に留められたものだと思えてならない。若き日の牧口先生が、北海道で先ほどの文章を発表していたのと同じ時代——19世紀末のアメリカにおいて、牧口先生の教育理念と響き合う主張を行った哲学者がいた。『創価教育学体系』でも言及されている、ジョン・デューイである。1988年に発刊された『学校と社会』で、デューイは次のように呼びかけた。「今日わたしたちの教育に到来しつつある変化は、重力の中心の移動にほかならない。それはコペルニクスによって天体の中心が、地球から太陽に移されたときのそれに匹敵するほどの変革であり革命である。このたびは子どもが太陽となり、その周囲を教育のさまざまな装置が回転することになる」この教育における〝コペルニクス的転回〟を、戦前の日本で進めようとしたのが、牧口先生にほかならなかったのだ。ジョン・デューイ協会元会長のジム・ガリソン博士は、池田先生とのてい談で、牧口先生の功績をたたえてこう述べた。「私は、創価教育に関する牧口会長の理念を研究するなかで、多くのことを学ばせていただきました。いまでは、牧口会長は、デューイに匹敵する、そして時にはデューイを凌駕する貢献をされたと思っています」「デューイは、すでに民主主義への道を順調に歩みつつあった国で研究を進め、きわめて有利な環境にいましたが、これに反して牧口会長は、軍国主義という背景のなかで、実に見事な教育理論を構築されたのです」 牧口先生が校長を務めた小学校に通っていた女性が、当時を回想して述べた証言がある。「身体の弱い私は、雨の日は学用品と薬袋一式と傘と大変でしたが、一生懸命歩いていると、牧口先生が『何か持ってあげよう』と言葉をかけてくださいました」「雪の降る日は、高歯(歯の高い下駄)に雪が詰まり、校門の前で雪をはたいていると、先生がそれを見て、『こうしてとるのだよ、ほらよく取れるでしょう』とやさしく言って、トントンと軽くたたいて雪を落としてくださいました」(趣意)そんな心と心が通い合う瞬間こそ、牧口先生にとって紙幅の時だったに違いない。長年の夢であった『創価教育学体系』が発刊された時、牧口先生の胸に去来したのは、こうしたときの子どもの笑顔であり、将来、『創価教育学体系』の理念が受け継がれて、子どもたちの幸福を第一の目的に掲げる教育が広がることへの強い期待ではなかっただろうか。『創価教育学体系』のケースと扉には、ランプに灯された日が光を放つ姿が描かれている。その絵柄が象徴するように、子どもたちの幸福のために教育に情熱を注ぐ人々がいる限り、子どもたちへの笑顔は社会で輝き続けるに違いない——と。 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史を創るはこの船たしか—第14回— 聖教新聞2024.10.8
July 21, 2025
コメント(0)
-
牧口先生「創価教育体系」〈第2篇〉(1930年11月)㊤
牧口先生「創価教育体系」〈第2篇〉(1930年11月)㊤現在における教育の目的は、果たして確立していると考えられるのか。また、確立しているとすれば、その目的は万人が等しく賛成し、承認するものであるのかどうか。それは、数々の疑問が残されているところであり、実に日本の教育界の重大事である。目的が確立していなければ、方法の設定が不可能であることは、目的なしに射た矢が的に命中するとは考えられないことから察することができよう。(中略)ある論者は(教育の目的は)国家のためと言い、またある人は父母のためという。しかし、それは果たして子どもを愛する父母の純真で率直な希望なのであろうか。真に子供を愛する父母であるならば、決して子どもを自分たちの幸福の手段とは考えないだろう。(中略)(江戸時代の町奉行の)大岡忠相による裁きで、実母と養母が一人の子どもの取り合いをした話はその好例である。一方は、子どもを奪うことが第一義で子どもの生命を顧みなかったのに対し、他方は、子どもの生存を第一義に考えて取り戻すのは第二義だった。教育を受ける子どもたちに社会が捕るべき態度は、まさに父母がこのように子どもにたいしたのと同じ関係であるべきだ。一方の利益だけを重視して、子どもたちをそのための手段とみなすことは、結局のところ、(社会と子どもたちの)双方を共に破滅の縁に追いやることになる。◇教育を受ける子どもたちが、幸福な生活を遂げられるように(生き方を)教え導くのが教育である。教育者や教育を望む父兄などが、自分の生活面での欲望を満たすために子どもたちを手段とするのではなく、子どもたち自身の生活(に関わるもの)を教育活動の対象としながら、子どもたちの幸福を図ることをもって、教育の目的とするのである。言い換えれば、子どもたちの成長と発展が、幸福な生活の中で終始できるようにするものであらねばならない。(哲学者の)ジョン・デューイ氏が、(教育の在り方に関して)「生活のために、生活において、生活によって」と言ったのは、教育者である我々にとって味わうべき言葉である。(『牧口常三郎全集』第6巻、趣意) 校長として日夜書きためた思想の結晶弟子の奮闘で成就した大著の発刊 1930年11月18日に発刊された、牧口先生の『創価教育学体型』第1巻——。より多くの人々に読んでほしいと思いから、当時の教育書としては廉価に抑えられていたにもかかわらず、装丁には金箔で刻印された文字があった。表紙と背表紙に記された書名と、著者である「牧口常三郎」の名前である。当時の日本は、前年(1929年10月)に起きたニューヨーク株式市場の大暴落の影響で、(昭和恐慌)と呼ばれる経済危機が深刻化していた。そうした時勢の中で、採算を顧慮しないような価格での発刊を目指すこと自体、牧口先生も「無謀」と感じた程だった。その上で、あえて費用がかかる金箔の文字が使われたのは、発行の全責任を担った戸田先生の〝師の大著を何としても荘厳したい〟との一念があったからではないかと思えてならない。そもそも『創価教育体系』の発刊は、戸田先生の陰の苦労亡くして、成就を見ることができないものだった。牧口先生が書きためた膨大な草稿の整理を一手に引き受けたのも、発刊を支援するための資金を捻出したのも、戸田先生にほかならなかった。1930年6月に戸田先生が出版してバストセラーとなった参考書の『推理式指導算術』の収益なども、「創価教育体系」の発刊資金に充てたとみられている。戸田先生はなぜ全てをなげうって、牧口先生の大著の発刊を成し遂げようとしたのか。師恩に応えたいとの一心に加えて、牧口先生と同様に、子どもたちを取り巻く厳しい状況を改善しなければならないと痛感していたことも、大きかったのではないだろうか。経済危機をはじめ、社会が不安定になった時に荒波に容赦なくさらされ、翻弄されるのは常に子どもたちである。その現実を、教育者である牧口先生と戸田先生は肌身で感じていた。牧口先生が『創価教育学体系』の緒言に記した、「一千万の児童や生徒が修羅の巷に喘いでいる現代の悩みを、次代に持ち越させたくないと思ふと、心は狂せんばかりで、区々たる毀誉褒貶のご時は余の眼中にはない」との思いを、戸田先生は誰よりも深く知っていたのだ。 この『創価教育学体系』第1巻において、牧口先生が京菊の目的を論じる際の大前提として強調したのは、子どもたちを国家や社会といった何かのための手段にすることはあってはならないとの一点だった。江戸時代の町奉行・大岡忠相の名裁きとして伝えられていた〝子どもを巡って争う話〟に触れ、牧口先生はこう述べた。「一方は、子どもを奪うことが第一義で子どもの生命を顧みなかったのに対し、他方は、子どもの生存を第一義に考えて取り戻すのは第二義だった。教育を受ける子どもたちに社会がとるべき態度は、まさに父母がこのように子どもにたいしたのと同じ関係であるべきだ」(趣意)と。長年にわたって抄育現場で子どもたちと接し、一人残らず幸福な人生を築いてほしいと名がって教育に情熱をすすいできた牧口先生にとって、子どもたちを手段化するようなことは、断じて許せないことだった。しかし、そうした牧口先生の存在を疎ましく思う人によって、『創価教育学体系』を発刊する前から、牧口先生を白金尋常小学校の校長職から追い落とそうとする動きが起きていた。1930年の2月ごろ、戸田先生が経営する時習学館で行われた深夜に及ぶ師弟の語らいの中で「創価教育」という名称が誕生した折に、牧口先生は戸田先生にこう語ったという。「戸田君、商学校長として教育学説を発表した人は、いまだ一人もいない。わたくしは白金小学校長を退職させられるのを、自分のために困るのではない。小学校長としての現職のまま、この教育学説を、今後の学校長に残してやりたいのだ」『創価教育学体系』の草稿の多くは、牧口先生が「日常生活の間に往来する思想の涓滴(けんてき)の散逸を恐れて、書き採って置いた」と述べているように、子どもたちに接する日々の中で体験しては反省し、煩悶しては思索してきた〝思想の滴〟を、多忙に流されることなく、反故紙などにメモ書きしたものだった。一つ一つの紙片に記した言葉が子どもたちの幸福への道を開く礎となり、後進の教育者にとっての道標になることを願い、ひたすら書きためたのだ。戸田先生が草稿の整理を引き受け、メモ書きの一つ一つに何年に目を通したときに胸に迫ってきたのは、教育思想の先見性もさることながら、子どもたちや後進の教育者に対する牧口先生の想いの深さではなかっただろうか。 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史をつくるはこの船たしか—第13回— 聖教新聞社2024.10.7
July 20, 2025
コメント(0)
-
近江上布伝統産業会館㊤
近江上布伝統産業会館㊤文化と地域デザイン研究所代表 松本 茂章約1000点の生地や麻織物を扱う滋賀県・琵琶湖の湖東地区は麻織物の産地である。同県麻織物工業協同組合が運営する近江上布伝統産業会館(愛荘町)は、旧・愛知郡役所1階で商品販売・製品開発・体験を行っている。店舗等の面積は161平方㍍。旧郡役所は1922(大正2)年に建築された歴史的建物である。2020年に旧会館が現地に移った。上布とは麻織物のこと。店舗責任者の西川幸子は「麻織物の魅力にひかれて遠方からお越しくださる方。レトロな建物に魅せられて入館される方など様々。2020年には9000人を超える来館者数を記録しました」と笑顔で語る。店内には約1000点の生地と製品が展示・販売されている。一角には上布の地機織機6台、簡単な織機2台が置かれ、来館者も機織り体験ができる。日本古来の麻には大きく分けて二つの種類があるそうだ。「苧麻」(ラミー)と「おおあさ」(ヘンプ)でらる。西川は「伝統工芸の中で、ヘンプの機織り体験が可能なのは全国では当館だけ」と話した。同会館事務局長の田中由美子によると、同店舗で販売するほか、全国各地の展示会・実演体験催しなどに主張しており、年間売上額は2000万以上に達するという。生産の場であることも特色の一つだ。作務衣を着た職人さんが機織りを実演し、来館者の体験も指導してくれる。手織りに加え、昭和40年代の機械織機(シャトル織機)が稼働しており、24年9月に訪れた際には「グアシャカ」の音がリズミカルに聞こえてきた。手織りの「近江上布」は「伝統的工芸品」である。伝達法に定められ、計算大臣が指定する。23年10月現在、全国で241品目が指定されている。とはいえ、近江上布の生産量は限られ、製品の多くは機織りで、この場合「近江の麻」と呼ばれる。(敬称略) 【文化遺産のまち40】公明新聞2024.10.6
July 20, 2025
コメント(0)
-
スイスのもっとも美しい村を巡って
スイスのもっとも美しい村を巡って写真家 吉村 和敏歴史と文化、個性輝く「世界一豊かな国」2015年に発足した「スイスのもっとも美しい村」には、現在、49村が登録されている。24年春、スイスは「世界で最も美しい村」連合の承認を受け、フランス、ベルギー、イタリア、日本、スペインに次ぐ6番目の加盟国になった。スイスの登録村をすべて訪れて写真を撮る——。そんな壮大な目標を掲げた私は、22年夏にフランス語圏から旅をはじめ、翌年にはドイツ語圏、イタリア語圏、フランス語圏を巡り、約2年半かけて全踏破を成し遂げることに成功した。特に印象に残った三つの村がある。一つはパステルカラーで色分けされた家屋が軒を連ねるル・ランデロン。宗教改革の時代、村人たちは古い信仰を頑なに守り、プロテスタント領にあるカトリックの飛び地として存在していたという。村内にあったバイオリン工房の扉を開けると、弦楽器職人クロード・ルーベさんが日本からの旅人を歓迎してくれ、この美しい村で制作活動を行うことになった経緯を語ってくれた。ソーリオは、標高1090㍍の山の中にひっそりと位置していた。集落の周りに緑輝く草原が広がり、背後に多くの登山家を魅了してきたブルガリア山系の名峰がそびえ立っている。画家ジョヴァンニ・セガンティーが愛した地でもあり、三部作「生・自然・死」の「生」の舞台として知られている。彼が見て、感じて、描いた風景を間近にしていたらたまらなく贅沢な気分になり、日本人が思い描く「アルプスの少女ハイジ」のイメージはこんな感じかもしれないと思った。食文化の大切さを教えてくれたのがサン=トゥルサンヌだ。この村は中世の頃に織物をはじめとする手工業で栄え、今の時代は地産地消に力を入れていた。村人たちは、地元産の肉、魚、野菜、乳製品、飲料を村内の商店で購入し、消費する取り組みを積極的に行っている。宿に併設するレストランで食べたソーセージやチーズがあまりにも美味しく、いつかまたこの地を再訪しようと心に誓った。スイスと言えば、アルプスの雄大な山並みの麓で山羊やウシたちが長閑(のど)に草を食む、自然を中心とした牧歌的なイメージがある。しかし、各地に点在するどの村にも、深い歴史と文化、宗教があり、建物のつくりや装飾、食文化にも個性が満ちあふれていた。厳選された村々を旅して地元の人たちと接していると、この国が「世界一豊かな国」と称される理由が何となく解ってくる気がする。同時に、移動の途中で何度も目にしたアルプスの名峰が、より美しく、より輝きを持って見えてくるのだった。(よしむら・かずとし) 【文化】公明新聞2024.10.6
July 19, 2025
コメント(0)
-
良い夢を見るために
良い夢を見るために公認心理士 立田英子さんまつだ・えいこ 公認心理士。臨床心理士。東洋大学社会学部社会心理学科教授。専門は臨床心理学、パーソナリティ心理学、健康心理学。夢の専門家としてメディアに多く出演。著書に『夢と睡眠の心理学——認知行動療法からのアプローチ』(風間書房)、『一万人の夢を分析した研究者が教える今すぐ眠りたくなる夢の話』(ワニブックスPLUS新書)など。 ☝ポイント① 気がかりなことは〝棚上げ〟してみる② 「悪い夢」と「悪夢」の違いを知ろう③ 〝光や音〟〝掛け布団〟なども関係する 〝オリジナル映画〟最近、どんな「夢」を見ましたか?人が見る夢は千差万別ですが、直近のインパクトの強かった出来事や、気がかりなことが登場する傾向があります。私たちの脳は、日々、五感で得た情報を記憶しています。情報量は膨大で、記憶したことは、その人なりの経験則に基づいて、整理整頓されているといわれています。その分別作業は就寝中に及ぶことも少なくありません。作業中に、脳の中の記憶のかけらがランダムにつなぎ合わされ、脳の中のスクリーンに映像化されたものが夢の正体です。意識と無意識にある記憶の情報が入り交じった、自分だけの〝オリジナル映画〟とでも言えましょうか。睡眠中には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」が約90分周期で交互に訪れます。レム睡眠の最中は、脳は起きているのに近い睡眠状態になり、私たちが長編大作の夢を見るのは、たいていレム睡眠です。夢は、生活環境の影響を受けます。幼児から90代までの1万人以上に調査してきましたが、年齢層によって〝最近見た夢〟の特徴は異なります。10~20代では「学校」「アルバイト」「友人」「推し(好きな有名人)」、30~60代は「仕事」「家族」などが目立ちます。70代以降になると、旧友や亡くなった家族と知人が多く出てくることも分かっています。 悩みや体調の影響悩みや不安を抱えていると、楽しくなかったり、苦しかったりする「悪い夢」を見やすい傾向があります。とはいえ、葛藤を抱え、悪い夢を見てしまうことすべてが、心の健康に悪影響なわけではありません。起きた時に辛い気持ちにはなりますが、それは、脳が問題を好転させようと頑張っている〝しるし〟だからです。ある芸人の方は、舞台に立つと、披露する内容を忘れてしまう夢をよく見ていたそうです。良い夢ではないかもしれませんが、夢の中でプレッシャーや不安といった感情を処理しているのです。また、〝より良い芸の披露のための予行演習〟をしているのに近い状態だと言えます。不安の中で悪い夢を見たとしても、悲観するのではなく、物事に真摯に取り組む自分を認め、前向きな気持ちで夢を捉えていってほしいと思います。注意が必要なのは、体調が関係していて悪い夢を見る場合です。溺れる夢を頻繁に見る、ある水泳部の高校生がいました。楽しく練習に通い、タイムに問題があったわけでもありません。調べていくと、蓄膿症で通院中であることがわかりました。息詰まりによる睡眠中の息苦しさが、夢に関わっていたようなのです。また、小さい頃から、風邪をひいて体調が悪くなると、決まって同じ夢を見る方もいました。こういったケースでは、まず病気の治療や体調を整えていくことを優先する必要があるでしょう。夢の原因となる日常の課題はすぐには解決できず、対処する手はあるのか、と思う方も多いのではないでしょうか。一つは、悩みを〝棚上げ〟する方法です。気がかりなことを抱えたまま寝るのではなく、いったん気持ちを切り替えるのです。好きな音楽を聴いたり、アロマを活用したりして、リラックスするのがいいでしょう。それでも、もんもんとするときは、誰かに相談してみるのもよい方法です。人に話すことで、心が軽くなる場合があります。 「悪夢」には注意心理学では、「悪い夢」と「悪夢」は別物と考えます。先述した悪い夢の場合、楽しくない夢ではあるものの、朝まで眠り続けられます。一方、悪夢は、忘れたいのに忘れられない記憶により、途中で目が覚めてしまう特徴があります。また同じ夢が繰り返し登場する時には、トラウマ(心的外傷)が関係している可能性があります。悪夢が続くと不眠になりやすく、うつ病などを引き起こしかねません。精神医学的には、悪夢は「睡眠障害」のひとつとして認識されています。そのため、大人のみならず、子どもが見た場合も、夢のないようにきちんと耳を傾け、原因を探って対処することが重要です。治療法の一つとして、「イメージ・リハーサル・セラピー」があります。悪夢の筋書きを〝ハッピーエンド〟に変える認知行動療法です。日本では、「悪い夢」と「悪夢」への認識が乏しく、悪夢が〝たかが夢のことでしょう〟と軽く捉えがちです。しかし、本人が夢を見るのがつらいと悩んでいるとしたら、心療内科や睡眠外来などを受診するように勧めましょう。 睡眠環境の改善を夢は、精神面の悩みや体調とともに、入眠前の心身の状態も関係します。よい夢を見るためには、次の点に留意し、睡眠環境を整えておきましょう。〈光や音〉外部の光や音は、できるだけ遮ります。間接照明を活用するなど、くつろげる空難が、よい夢を見るためのポイントです。〈掛け布団〉重い掛布団だと、重いものがのっている夢を見るなど、夢に影響するケースがあります。重過ぎず、心地よい掛布団を使うとよいでしょう。〈トイレ〉尿がたまった状態で入眠すると、「トイレ」や「水」にまつわる夢を見てしまいかねません。就寝前は、きちんとトイレに行くようにしましょう。自分なりの〝入眠のルーティンング(日課)〟をつくっておくことも、良い夢を見るために大切です。健やかな生活と睡眠を心がけながら、良い夢に彩られる秋にしていきたいですね。 夢日記のススメ自分が見た夢を日記に付けていく「夢日記」。ノートの見開きを1日分として、左のパージに「その日に見た夢」と「前日に現実に起こった出来事」の半分ずつ書きます。右ページには、「今晩見たい夢」を記します。夢の記憶は目覚めた瞬間から薄れていくため、夢を見た直後に書くのがポイント。夢日記を見返すと、気になっていたことや不安に感じていたことなどが明白になります。自分の心の状態を知るとともに、夢であると自覚しながら夢を見ること(明晰夢)ができるようになるかもしれません。 なぜ〝金縛り〟に遭うの?体が疲れ過ぎかつ脳が興奮していると、入眠直後、脳は覚醒しているのに、筋肉が弛緩して急速に力が抜けていきます。すると、体がまひした状態になって動けなくなるのです。これが〝金縛り〟のメカニズムといわれています。「誰かが体の上に乗っている」などの体験をした人もいるかもしれませんが、これは心霊現象ではなく、頭はさえているのに、体が思うように動かないため、押さえつけられているような圧迫感を覚えることが原因です。こうした幻覚を「入眠時幻覚」と言います。金縛りにあった時は、落ち着いて指先や目を少し動かしたり、ゆっくりと呼吸してみたりしましょう。金縛りから解放され、自由に動かすことができるようになります。 【健康PLUS+】聖教新聞2024.10.5
July 19, 2025
コメント(0)
-
新発見の絵巻
京都・嵐山で世界初公開伊藤若冲新発見の絵巻福田美術館 学芸課長 岡田 秀之果物や野菜をみずみずしく70代で、色彩豊かに描く伊藤若冲(一七一六~一八〇〇)は、江戸時代中期に京都で活躍した画家。京都の中心にある錦小路の青物問屋の長男として生まれ、二十三歳で家業を継ぎましたが、四〇歳頃に家業を弟に譲って画業に専念し、八十五歳で亡くなるまでの多くの作品を残しました。昨年、福田美術館の所蔵となった伊藤若冲筆の(果疏図巻)。本作はもともとヨーロッパの個人が所蔵していましたが、昨年オークション会社を通じて入手した作品です。約三メートルの絹地におよそ五十種以上の果物や野菜が描かれた巻物です。一般的に、黄色や淡い赤色などは赤外線による退色や修理の時に使う水によって失われやすいのですが、二百年以上たった今でも淡い黄や緑、赤などが奇跡的に残っており、果物や野菜のみずみずしさが感じられます。本作の最後に記された署名に「米斗翁行年七十八歳画」とあり、また巻末に付けられた跋文が書かれた時期から、本作が描かれたのは寛政二年(一七九〇)以前と推定されています。七〇歳の若冲が描いた着色作品自体、数が非常に少なく、しかも本作の様な巻物仕立てで絹に彩色された絵は、同時期に描かれた重要文化財の《菜虫普》(佐野市立吉澤記念美術館蔵)しか確認されていません。しかも、本作がこれまで一度も過去のオークション図録や展覧会図録に掲載されたことがない未確認の作品であり、極めて貴重な発見だと言えるでしょう。また、注目すべきは本作の巻末に書き添えられた跋文の存在です。記した若冲に多大な影響を与えた盟友で相国寺の僧侶であった梅荘顕常(大典)(一七一九~一八〇一)。そこには「果物や野菜の形を極め、色も備えた神のごとき才を宿した作品」であり、三〇年前から若冲と大典と交流していた「大阪の森玄郷からの依頼で制作され、玄郷が亡くなった後、その子ども・嘉続(「かぞく」もしくは「よしつぐ」)が梅荘顕常のもとを訪れ依頼した」ことなどが書かれており、親しかった若冲屁の想いと政策の経緯が判明する貴重な資料です。この大典の跋文には「寛政庚戌十二月十一日」に書いたとあります。「寛政庚戌」は寛政二年(一七九〇)で、若冲はこの年に数え年で七十五歳になります。しかし、本作に書かれている若冲の年齢は前述のとおり「七十六歳」です。これまでも若冲の署名の年齢と実年齢の間には差があることが指摘されていましたが、本作を描いた時点で少なくとも実年齢に一歳加算していたことが判明しました。わずか一歳の差ですが、伊藤若冲研究にとっては大きな進展です。十月十二日から福田美術館で開催される展覧会では《果疏図巻》を世界で初めて公開し、同時に福田美術館が所蔵する若冲作品およびその三〇点と若冲の同時代に活躍した曽我繍白や円山応挙の作品も併せて展示します。本展が若冲の芸術世界をより深く理解し、その魅力を存分に感じ取れる機会になれば幸いです。(おかだ・ひでゆき) 【文化】公明新聞2024.10.2
July 18, 2025
コメント(0)
-
献血の不足補い、有事の備えにも
献血の不足補い、有事の備えにも科学文明論研究者 橳島 次郎人工血液の開発研究今年7月、奈良県立医科大学が、以前から研究と試験を進めていた人工血液を、自施設で製造し新たな臨床試験を行えるようにしたと発表した。血液は生命の維持に不可欠な多くの機能を担うが、その中で最も重要なのは酸素を全身の組織に運ぶことである。人工血液の開発研究は、血液の中で酸素を運ぶ役割を果たす赤血球の代替物を作ることを中心に行われてきた。今回、奈良医大が製造するのは、赤血球の主要成分で酸素と結合するタンパク質であるヘモグロビンを、保存期限切れで廃棄予定の献血から抽出・精製し溶液にして脂質のカプセルに詰めた。人口赤血球製剤だ。血液型がなく誰にでも輸血でき、長期保存し備蓄できるという。医療の現場では、輸血用の血液製剤を安定的に確保し供給することが不可欠である。だが近年、少子高齢化などが原因で、輸血用血液をまかなってきた献血が減り、特にへき地や、災害などの非常時に、血液の確保が困難になる事態が予想されるようになった。人工血液は、輸血用血液の不足を補える代替物として、実用化が待たれている。自然災害だけでなくテロや武力紛争などの有事への備えとして、民間人だけでなく自衛隊員の医療の支えにもなるもので、防衛医科大学などでも研究開発が行われている。人工血液の開発の歴史は古く、1960年代から研究が続けられてきたが、実用化はなかなか実現しなかった。海外の臨床試験では、投与された被験者に起こる有害事象として、通常の輸血と同様のアレルギーや炎症反応、発熱などと並び、血管収縮による血圧の上昇が深刻であるとの結果が出ている。さまざまな人工血液製剤候補の臨床試験が積み重ねられてきた米国でも、国(食品医薬品局)が認可したものは、まだない。今回、奈良医大が着手する臨床試験は、最初の段階として健康な成人を対象に、投与する人口赤血球製剤の量を増やしていき、輸血の標準分量まで安全に達することができるかどうか確かめることを目標としている。実際に患者に投与して安全性を確かめる次の段階の試験に進めるのは、まだ先だ。また、製薬企業ではなく、一医大で医師が主導する臨床試験なので、医療用製剤として認可にこぎつけたとしても、多くの医療現場に生き渡らせるために、より規模の大きな製造・保存と搬送・供給のシステムをどう作れるかが、さらなる課題になる。人工血液の実用化に向けた一歩となるのか、期待を込めて見守りたい。 【先端技術は何をもたらすか—30—】聖教新聞2024.10.1
July 17, 2025
コメント(0)
-
帝国アメリカがゆずるとき
帝国アメリカがゆずるとき玉置 敦彦 著 同盟が持つ不思議な力学二松学舎大学教授 手賀 裕輔 評 11月のアメリカ大統領選に世界の注目が集まっている。孤立主義的で近視眼的な行動をとりトランプ氏が大統領の座に返り咲くことを懸念する声が支配的だ。しかし、トランプ氏の主張は多くのアメリカ人の本音でもある。なぜ、我々が犠牲を払ってまで海の向こうのよその国を助けねばならないのか、こうした主張に頷くアメリカ人は多いし、それは今に始まったことでもない。それでも、アメリカは冷戦期に結んだ同盟を今に至るまで維持、拡大してきた。それがアメリカの望む国際秩序を形成する上で必要だったからであるが、「尾が犬を振る」の喩えのように、ときに超大国アメリカは同盟相手の中小国に振り回され、譲歩を行ってきた。こうした同盟が持つ不思議な力学を説き明かしたのが本書である。戦後アメリカは自らにとって望ましい「リベラルな国際秩序」を支えるための制度として、同盟を形成した。著書によれば、「非公式帝国」アメリカが各国と結んだ同盟は、国力差の大きな非対称同盟であり、それは独自の力学を内包していた。超大国たる手動国(アメリカ)は、追従国(中小国)が同盟から離反することの内容繋ぎ止め(校則)、勝手な外交・軍事行動をとらないよう誓約し(行動抑制)、そして同盟のコストを共に分担すること(負担分担)を求める。その過程で主導国は圧力を行使したり、譲歩を行ったりする。著者が提示する同盟の提携理論によれば、主導国による圧力行使と譲歩の選択を左右するのは、追従国の国内状況であるという。追従国内には、権力を握り、主導国との同盟を利益とみなす提携勢力とこれに反対する抵抗勢力が存在する。この提携勢力がどのくらい役に立ち信頼できるのか(信頼性)、そして提携勢力の統治は安定しているのか(安定性)これらの要因が主導国の行動を決定するという。もし主導国が追従国の提携勢力は信頼できず、当地も不安定だと見なせば、圧力が選択される。他方で、提携勢力が信頼でき、安定している場合には、その対応如何によって圧力と譲歩を使い分ける。主導国にとって難しいのは、自分たちの要求が引き金となって提携勢力が不安定化するような場合だが、その場合、提携勢力が配慮すべき相手かどうかが主導国の判断の分かれ目となる。配慮すべき提携勢力に対しては、主導国は譲歩し支援を提供する。見本では、アメリカとの同盟管理についての議論になると、とかく相手の懐に飛び込む打とか、交渉技術の巧拙が強調されがちである。もちろんそれは重要ではあるが、非対称同盟が持つ力学を踏まえ、より巨視的な視点からアメリカとの付き合い方を考える必要性を本書は示唆している。最期に付言すれば、本書の実証部分は、膨大なアメリカの実証部分は、膨大なアメリカ政府の外交文書を地道に渉猟し、丹念に読み込んだうえで書かれている。実証に関しては既存の歴史研究のみに依処する理論研究も多い中で、著者の真摯な姿勢には敬意を表したい。◇たまき・のぶひこ 1983年生まれ。中央大学法学部准教授(国際政治学)。東京大学法学部卒業。博士(法学)。専門は同盟論、日米関係史、アジア太平洋国際関係。 【読書】公明新聞2024.9.30
July 17, 2025
コメント(0)
-
山代二子塚国史跡指定100周年
山代二子塚国史跡指定100周年—島根県立八雲立つ風土記の丘—全国的に珍しい出雲地域の前方後方墳 島根県の古代史といえば『出雲国風土記』に記された国引き神話、あるいは荒神谷遺跡(出雲市)や加茂岩倉遺跡(雲南市)から出土した、大量の青銅器を思い起こす人も多いだろう。だが、師赤軍のフィールドミュージアムとして活用する「島根県立八雲立つ風土記の丘」がある松江市南港では、島根が全国に誇る古墳も多く知られている。その頂点に立つのが山城二子古墳塚だ。ふつう古墳時代の豪族の墓といえば、「前方後円墳」だが、山代二子塚は墳丘長94㍍、まわりの溝も含めると復元全長150㍍にもなる6世紀最大の「前方後円墳」である。1924年12月に国の史跡に指定され、また、翌年4月刊行の『島根県史』第4巻において、考古学史上初めて「前方後円墳」と呼ばれたことでも名高い。そして、山代二子塚の周辺には大小さまざまな前方後円墳が分布している。前方後円墳流星の時代に築かれた前方後円墳は、古墳時代社会の王道だったのか、異端だったのか——。 古墳時代史物語る出土品獅噛環頭大刀などを展示 この秋、島根県立八雲立つ風土記の丘では、島根の前方後円墳に注目した特別展『王と前方後円墳』を開催している。展示資料数は130点とささやかな規模ながら、出雲で最古級の前方後円墳である雲南市松本1号墳(3世紀)から出土した鏡、邑南中山B-1号墳(4世紀)が出土した鉄製のヨロイ、朝鮮半島からもたらされた松江市岬山古墳(6世紀)の獅子噛環頭大刀といった金属製品のほか、前方後円墳からの出土ではないものの、この土地の古墳時代史を物語る土器や埴輪が集う。とりわけ、7世紀後半以降に出雲国府が営まれた意宇川沿いには、5世紀の有力首長が居住していた痕跡が発見されているが、ここでは朝鮮半島からもたらされた土器が多く出土している。中海を介した対外交渉を司った在地有力首長の存在がうかがえる。そうした地理的役得の結晶であろうか、御崎山古墳や岡田山1号墳では、朝鮮半島や中国大陸に期限する刀が出土しており、全国的にみても屈指の集中密度を誇る。このほかにも、山代二子塚から本格的に始まる出雲型子持壺をもちいた墓前祭祀や、6世紀後半の古天神古墳(県史跡)に始める出雲型石棺式石室の築造は、前方後円墳を築造した集団の異端性を説明するに十分な質と量がある。ただし、それと同時に、被葬者の格の違いを古墳の形や大きさで表現する体制そのものは、一般的な前方後円墳の社会と同じだ。そこに、出雲東部の前方後円墳がもつ「王道」と「異端」の両側面が凝縮されているかのようだ。もちろん正解はわからないが、「調和のなかの個性」という表現が、より実態に近いかもしれない。そうした広域の共通性と差異を捉えつつ地域の歴史を活写することこそが、地域に根差し、地域に愛される博物館が果たすべき使命なのである。 【文化】公明新聞2024.9.28
July 16, 2025
コメント(0)
-
コク
おいしさとコクの関係女子栄養大学教授 西村 敏英イコールではないどのような食べ物をおいしく感じるかは、人それぞれ。同じメニューを頼んだとしても、その評価は食べる人によって微妙に違います。実は、食べ物のおいしさは、素材によって決まる客観的要因だけでなく、食べる人の食習慣、食文化、価値観などによって変わってきます。例えば、「おふくろの味はおいしい」などと言いますが、これは、幼い頃から食べ慣れている塩加減や風味付けをおいしく感じているからなのです。そんな「おいしさ」について、皆さんにも感じてもらいたく、近著『おいしさの9割はこれできまる!』(女子栄養大学出版)を出しました。近年、食べ物の味わいとして「コクがあっておいしい」という表現をよく聞くようになりました。この「コク」というのはどのようなものなのでしょうか。美味しさを表現する言葉には、意味があいまいで間違った使い方をされているものが少なくありません。「旨み」なのか「うま味」なのかで、意味が異なります。旨みというのは、甘味、酸味などと同じく5味の一つ。それに対して、うま味は食べ物がおいしいことを指します。同じように、「味」と「味わい」はどうでしょうか。味というのは5味の総称。そこに香りや食感を加えたものが「味わい」になるのです。 味わい決める1要素 嗜好によって変わるコクという言葉は、おいしい時に使われます。しかし、コクがあるからといって、おいしいとは限りません。それは個人の嗜好によるカラです。コクがあっても強すぎておいしくない場合、「濃い」「くどい」などと表現するのではないでしょうか。このように、おいしい場合にしか使われないため、「コク=おいしさ」と勘違いされてきたわけです。「コク」というのは、おいしさを表現する言葉ではなく、味わいを決める1要素なのです。コクのある食べ物は、味や香り、食感など、さまざまな刺激が複雑に絡み合って、深みを感じます。逆にコクのない食べ物で感じる刺激は単純です。複雑さを増すためには、加熱処理、熟成処理、発酵処理などを行います。これらによって味や香りに複雑さが生まれます。広がりは、その味わいが口腔内に拡がる強さです。口腔内いっぱいに広がることで、強い味わい、濃い味わいと感じるのです。最後の持続性は、口の中に入れたときの余韻がどれだけ続くかです。刺激時間が長いほど、持続性が良く、いつまでも味わいが口腔内に残ることになります。ただ、コクの強さは強ければ良いというものでありません。濃い味わいがいつまでも続いてしまうと、しつこい感覚となり、逆に、おいしさを損ねてしまうことにもなりかねません。 味と香りを混同私たちが、食べ物を味わう時に、おいしさをどのように判断しているでしょうか。まず、食べる前からはじまります。この食べ物を食べようか、やめようかというもの。色や形、匂いなどで、まず。食欲をそそるかどうかを判断しているはずです。次に食べた時に感じるのは、味や香り、食感などです。味には5味があって、甘未、苦味、酸味、塩味、うま味があります。そして複雑さに重要なのが「香り」です。実は、多くの人が味だと思っているのは、口に入れた時に難じる味と香り(口中香)の両方なのです。だから、花をつまんで食べると、香りがしないので、何を食べているかが分からなくなります。例えば、牛肉、豚肉、鶏肉は、多くの人が食べ分けるでしょう。しかし、鼻をつまんで食べてみてください。口中香がなくなると、違いが途端に分からなくなってしまうはずです。食感については、感触と温度があります。例えば、とろみは味わいの持続時間を延ばすため、コクを増すことで知られています。しかし、とろみが強すぎると、ドロドロ状態になり、嫌味にもなりかねません。逆に清涼飲料水のように、爽やかさを求めるものは、とろみがない方がすっきりと感じるはずです。普段から、食べ物に集中して、意識して食べるようにすると、味覚と嗅覚は鍛えられます。それによって食べることの楽しみも変わってくるのではないでしょうか。味、香り、食感、コクと、そんな指標を軸に、自分なりのおいしさを追求していってもらいたいと思います。=談 にしむら・としひで 女子栄養大学教授、広島大学名誉教授。広島大学教授、日本獣医生命科学大学教授を経て、現職。「食肉と健康」「食べ物とおいしさ」について研究。2010年に食べ物のおいしさの要員である「コク」を定義し、世界に発信している。著書に『おいしさの9割はこれできまる!』『食品のコクとは何か』などがある。 【文化Culture】聖教新聞2024.9.26
July 16, 2025
コメント(0)
-
今が勝利の節目を刻む時
今が勝利の節目を刻む時 朝の通勤途中、長袖シャツや上着を身に着ける人を多く見かけるようになった。駅のホームでいつもと同じ場所に立っていても、真夏は炎天下だったが、昨今は近くに立つ大木の影が足元まで延びている。夕暮れ時が早まり、夜は涼しさを感じる。秋が来たなと思う▼季節には節目や変わり目がある。暦の上で秋を認識する以上に、わが身と心で、これまでとは違う変化を捉える方が、季節の移り変わりを深く実感できるのではないだろうか▼御書に「夏と秋と、冬と春とのさかいには、必ず相違することあり。凡夫の仏になる、またかくのごとし」(新1488・全1091)とある。人生にも“変わり目”がある。試練に直面し、宿命転換と境涯革命をかけて信心に奮い立つ時、その前進を阻もうと三障四魔が必ず競い起こる。ここで「仏法は勝負」と、一大決戦に挑めるかが、大きな“変わり目”となる▼日蓮大聖人は先の御文に続けて、障魔の出現に「賢者はよろこび愚者は退く」と仰せである。“今が勝利の節目を刻む時”と一念を定めて打って出ることが、人生を開く“変わり目”となる▼実りの秋である。気高い志を持ち、たゆみない信心の実践で、成長の喜びを存分に体感する季節にしたい。(城) 【名字の言】聖教新聞2024.9.25
July 15, 2025
コメント(0)
-
作家はつらいよ
作家はつらいよ歴史作家 河合 敦五十歳のとき作家として生計を立てようと決意し、二十七年務めた教員を退職。しかし、出版の世界は厳しい。出版不況は危機的な状況で、「二〇二三年度 国語に関する世論調査」では、本を月に一冊も読まない人が六割を超えたという。このため出版業界の売り上げは右肩下がり、印刷される本の初版部数も減る一方だ。小説は創作だから書くのに時間がかかり、年に数冊出版するのが限度。幸い私は講演会やテレビなどの仕事をいただいているが、とても物書きだけで暮らしていけないことがわかる。では、江戸時代の作家たちはどうだったのだろうか。江戸時代、作家に対して原稿料は支払われていなかった。もちろん、印税というものもない。版元は執筆者を遊里で饗応し、それが謝礼がわりだった。作家の多くは武士だったり、裕福な町人だったりするので、これで十分だったのである。しかし山東京伝の黄表紙や洒落本が一万冊あまりも売れるようになると、版元は大もうけできるので、蔦谷重三郎が同業の鶴屋喜右衛門と相談し、京伝に原稿料を支払うことに決め、二社で彼の作品を独占したという。ちなみに、『南総里見八犬伝』を書いた曲亭馬琴や『東海道中膝栗毛』を書いた十返舎一九辺りが原稿料だけで生活した最初の専業作家だといわれている。ただ、人気作家でも楽な暮らしはできなかった。印税がなかったからだ。いくら増刷しても作家がもらえるのは最初の原稿料だけ。だから作家は次々と作品を書き続けてなくてはいけなかった。たとえば馬琴は少なくとも二百数十冊の本を書いており、一九も売れっ子になってからは毎年二十冊以上の本を刊行し続けている。いまも昔も、作家は生きていくのに大変な職業だったわけだ。 【言葉の遠近法】公明新聞2024.9.25
July 15, 2025
コメント(0)
-
清少納言『枕草子』の真実
清少納言『枕草子』の真実京都先端科学大学 国際学実研究院 教授 山本 淳子 中宮定子との美しき絆中学生の頃、私は清少納言が好きではなかった。『枕草子』に登場する彼女があまりに自慢げだったからである。例えば、よく知られている「香炉峰の雪」の章段。中宮定子から「少納言よ、香炉峰の雪、いかならむ」と声をかけられて、清少納言は御簾を高く上げる。すると定子は笑い、周囲は清少納言を褒める。「香炉峰の雪」は唐の白楽天の漢詩の句で、続は「簾を撥(かか)げて看る」。漢詩に通じた定子はこの詩句を踏まえて清少納言は阿吽の呼吸で定子に応えた。それは確かに素晴らしいことなのだろうか。自画自賛が鼻に付くと感じ、思春期の反発を覚えたのだった。確かに『枕草子』には、清少納言が才覚によって定子に褒められる逸話がいくつもある。当時、教養の頂点にあった漢文の知識を持つ高い知性。それをその場に合わせて表現する当意即妙な機知。高貴な存在から評価される喜び。『枕草子』にはそんな作者の自己顕示欲がちらついている——それは私だけでなく、多くの読者の抱く印象ではないだろうか。だが、研究者となってじっくりと『枕草子』を読むに至って、私の清少納言への印象は変わった。彼女にとって大切なのは、自分自身より定子との絆だと分かったからである。先の「香炉峰の雪」の段で、清少納言は同僚たちから褒められる。しかしそこで同僚たちは「私たちだってその詩句は知っている」と言っている。清少納言の知識は定子後宮では珍しいものではなく、彼女は博識で評価されたのではなかった。では、みなはなぜ彼女を褒めたのか。清少納言が御簾を高く上げたからである。白楽天の詩には「香炉峰の雪は簾を撥げて看る」とある。この「撥げて」とは「はじく」という意味である。白楽天は簾のすぐ近くの床に寝ていた。だから簾の下をはじいて雪を見たのである。しかし清少納言は御簾をはじかず、高く上げた。それは、御簾から遠く離れて部屋の奥にいる定子に雪を見せるためである。ていしから「香炉峰の雪、いかならむ」と言われ、清少納言は一瞬考えたのだろう。そしてそれが「詩句を答えよ」という知的クイズではなく、「雪が見たい」という意味であることを悟った。だから、詩句の言葉とは違う行動をとった。それが当たっていたので、定子は笑い、同僚たちは清少納言を褒めた——「ミスを高く上げなど、思いつきもしなかったわ」「定子様にお仕えする女房はこうでないとね」と。どんな時も主人の意思を測り、それに沿って行動しようとする姿勢を評価したのである。『枕草子』は、定子が政変によって窮地に陥った時に書き始められ、定子に献上された。定子の死後は、定子の思い出を世に留めるために加筆された。定子の生前はその心を慰め、死後はその魂を鎮めるために、忠義の部下・清少納言が心を砕いた作品なのである。 やまもと・じゅんこ 石川県金沢市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。2007年、『源氏物語の時代—一条天皇と后たちのものがたり』でサントリー学芸賞を受賞。著書に『古典モノ語り』(笠間書院)、『紫式部ひとり語り』(角川ソフィア文庫)、『紫式部日記と王朝貴族社会』(和泉書院)など。 【文化】公明新聞2024.9.25
July 14, 2025
コメント(0)
-
脳卒中の原因になる
脳卒中の原因になる殿様枕症候群高い枕を使うことで、脳卒中の一因である「特発性椎骨動脈解離」の発症リスクが高まっている状態を「殿様枕症候群」といます。この症候群の原因と予防につながる枕選びのポイントを、快眠セラピストの三橋美穂さんに聞きました。 高さ12㌢以上でリスクが3倍「高さ12センチ以上の枕」は、特発性椎骨動脈解離を起こすリスクが高くなることが国立循環器病研究センターの最新研究で分かりました。特発性椎骨動脈解離は、首の後ろに血管が裂けてしまうことで脳卒中を引き起こします。枕が高いほど発症割合が高く、固い枕ほど関連が顕著でした。睡眠中の7~8時間、首の血管が圧迫され続けるため、硬くて高い枕が首の血管を傷めるのは、想像できます。15~45歳の脳卒中患者の約10%は特発性椎骨動脈解離が原因となっており、それが高い枕に起因しているケースが多いといいます。数割近くは感覚障害やまひなどの後遺症が残ったり、場合によっては命を落とすことさえあるそうです。病名にもなっている殿様枕とは、時代劇に出てくる侍が使っている高い枕のことです。筒状の袋の中にそば殻や綿を詰めたものを、木製の台座の上に乗せた枕で、箱枕ともいいます。江戸時代に男女ともに髷を結うようになり、だんだん凝って派手になって行きました。その髪型を維持するために高い枕が必要となり、首を支える箱枕が誕生したといわれています。健康や寝やすさよりも、髪型を優先したわけです。 寝返りしやすいものを選ぶ殿様枕症候群を予防するためには、枕選びが重要となります。体に合う枕は、自分が思っているより、かなり低いケースが多いです。例えば、「いつも肩が凝っている」「首にくっきりとしたシワがある」「横向きばかりで寝ている」「寝ている間に枕を外してしまう」という人は枕が高すぎる可能性があります。枕を選ぶときは、まずあおむけで合わせるのが基本です。枕を肩にピッタリつけて当て、首から後頭部にかけてどこにも圧迫感がなく、頭の収まりがよいものを選びます。リラックスして立っているときにも保てるようにすることが大切です。仰向けで合わせたら、横向きもチェックしましょう。枕の中央が仰向けように低めで、枕の両サイドが少し高くなっていると、仰向け状態からゴロンと寝返りをして、ちょうど横向きになったところが高いので、肩の圧迫がなく楽に眠れます。横向きになる時注意したいのは、緊張して真横90度にならないことです。枕のフィッティングするとき、私が「横を向いてください」と言うと、体の下に腕がくる人が多いのですが、実際にはそうなりません。睡眠中は筋肉が緩むので、肘は軽く曲がり、腕は前に出ます。体の力を抜いた状態で確認しましょう。お店で選ぶ場合、使用ベッドの硬さと、自宅で使っている敷寝具の硬さの違いを考慮する必要があります。自宅の方が柔らかい場合、体全体が沈むので、お店で試した時と枕の高さが変わることがあるからです。 【健康プラザ】公明新聞2024.9.24
July 14, 2025
コメント(0)
-
「この国のかたち」に込められた思い
「この国のかたち」に込められた思い司馬さんが古書として発見した『統帥綱領・統帥参考』という本があります。もとの二分冊だった原本は敗戦のときに焼却されたので、司馬さんが入手したのはその復刻版です。公刊されたものではなく、参謀本部所属の将校しか閲覧を許されなかったという、いわくつきの秘密文書で、統帥権がどういうものであったかのかを如実に語っています。司馬さんは『この国のかたち』で、『統帥参考』より次の記事を引用しています。 『統帥権ノ本質ハ力ニシテ、其作用ハ超法規的ナリ。(原文は句読点および濁点なし)』(一、6「機密の中の〝国家〟」) さらに、国務はすべて憲法の規定により、各担当の国務大臣が責任を負いますが、統帥権はこの範疇でないことが記されています。 「従テ統帥権ノ行使及結果ニ関シテハ、議会ニ於テ責任ヲ負ハズ。議会ハ軍ノ統帥・指揮竝之ガ結果ニ関シ、質問ヲ提起シ、弁明ヲ求メ、又ハ之ヲ批評シ、論難スルノ権利ヲ有セズ。(原文、ルビなし)」(同前) 日露戦争のときは軍の失敗を議員が論難しました。しかし昭和期になると、軍の失敗を批判すれば「天皇の軍隊に対して文句を言うのか、不忠者!」となってしまう。明治期の日本は、議会が君主権を監督するというヨーロッパの標準の形が進んだ国家の姿だと理解し、それを忠実に真似するのが正しい立憲国家の姿だと思ってやってきました。ところが、日露戦争後はヨーロッパさえもいくらか見下し始めます。真面目に議会を育てて立憲国家を運営していくという考えが希薄になって行きます。そもそも、いばっていられるのは誰のおかげなのか、日露戦争世軍が頑張って勝利したからこそ一等国になったのだ、憲法や議会ではなく軍こそが国家の偉力の中心なのだ——という自意識があり、国民もその考えに傾いていってしまったのです。こうして、明治人が苦労してつくりあげた日本国家は暴走を開始し、滅びに向かっていきます。司馬さんは自分を「走る棺桶」の戦車に乗せて殺そうとした国家の正体について、このようにしてみずからあぶり出しました。しかし、それを小説にして発表することはできませんでした。その代わりに語ったものが『「昭和」という国家』のもとになった「司馬遼太郎 雑談『昭和』への道」であり、書かれたものが『この国のかたち』なのだと思います。司馬遼太郎という小説家のすべてをひとつの本にして見立てるならば、長大な最後の「あとがき」にあたるものが、『この国のかたち』なのではないかと思います。なぜ敗戦に至ったのか——という自身への大きな問いを終生持ち続けて、それに誠実に答えた司馬さんの言葉であり、過去に対する総決算が『この国のかたち』なのです。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 13, 2025
コメント(0)
-
第二章 イェール大学 二十
第二章 イェール大学 二十 興味深いことに、三人とも欧州の出身である。石原は山形県鶴岡、板垣は岩手県岩手郡沼宮内村(現岩手町)、大川は山形県酒田に生まれている。三人とも一八八五年から八九年の生まれだから両親は戊辰戦争の苦難のさなかを子供時代に生き抜き、明治の御世になってからは薩長独裁体制のもとで冷や飯を食らわされてきた世代ということになる。そのことがひときわ気になるのは、朝河自身も似たような経験を経てきたからだ。父は福島県の二本松藩士として戊辰戦争を戦い、身内を数多く失って敗北した上に、主家も所領を取り上げられた。幸い父は代用教員の職を得て、立子山小学校の校長にまで立身したが、一八七三年に生まれた朝河らの立身は狭く閉ざされていた。明治政府のもとでは、戊辰戦争で逆賊とされた奥州諸藩の出身者は政界、官界、軍隊などの多くの分野で薩長出身者の後塵を拝することになった。朝河が東京実業学校(現早稲田大学)を首席で卒業した後、アメリカに留学する道を選んだのは、このまま就職しても差別の壁を打ち破ることは難しいと考えたからだ。しかも維新の趨勢が決した後に、薩長両藩が奥州の諸藩に理不尽な戊辰戦争を仕掛けたことに対する憤りは大きく、彼らが牛耳る国で生きることを潔しとしない反骨心も少なからずあった。そうした心情は石原や板垣、大川らにもあったはずである。陸軍大学校などでどれだけ優秀な成績を収めても、通常の方法では陸軍や参謀本部の中枢に席を得ることはできない。むしろ有能さと反骨心をうとまれ、関東軍の様な辺境に追いやられるばかりである。(それなら関東軍をもって満州国を独立させ、外圧を仕掛けて日本という国家そのものを改造すればいいではないか)石原らがそう決意し、満州国をもって日本を吞み込む計画を立てていたとしたらどうだろう。事は関東軍による暴走などではなく、関東軍による日本乗っ取り計画である。その根幹には明治政府の不正に対する怒りと怨念があるために、彼らは革命的な確信をもって日本の体制を壊しにかかるに違いなかった。 【ふたりの祖国43/安部龍太郎】公明新聞2024.9.21 柳条湖事件かねてから関東軍高級参謀板垣征四郎 (いたがきせいしろう)大佐、同作戦主任参謀石原莞爾 (かんじ)中佐らが中心となり、満蒙領有計画が立案されていた。1931年の三月事件の経験や、排外熱の高揚を踏まえて関東軍は、参謀本部第一(作戦)部長建川美次 (たてかわよしつぐ)少将をはじめ軍中央部と連絡をとりつつ、9月18日夜10時半、奉天郊外の柳条湖村で満鉄線路を爆破、これを張学良軍の仕業と称して軍事行動を起こした。張学良軍の宿営北大営 (ほくだいえい)と奉天城への攻撃から始まり、翌日には奉天市をはじめ満鉄沿線の主要都市を占領した。さらに吉林 (きつりん)への出兵を機に、9月21日には朝鮮軍が司令官林銑十郎 (せんじゅうろう)中将によって独断越境、戦火は南満州全体に拡大した。事件勃発 (ぼっぱつ)直後、不拡大方針をとった若槻礼次郎 (わかつきれいじろう)内閣も22日の閣議では、独断越境という統帥権干犯を追及せず、他の軍事行動とともに既成事実を追認、予算支出を承認した。24日には日本軍の軍事行動の正当性と今後の不拡大方針の声明を発表し、政府は事件を公認した。[君島和彦]
July 13, 2025
コメント(0)
-
統帥権と帷幄上奏権
統帥権と帷幄上奏権国家が統帥権の暴走を許してしまうのは、昭和になってからのことです。明治期は、元勲・元老がいて、彼らが集団指導の体制を取り、明治憲法下の調整をおこなっていました。国家権力の中枢には、政府・議会・軍部の三要素がありますが、昭和期にはいると、統帥権の独立を振りかざした軍部が幅を利かせるようになります。その傾向が最初に出たのは、海軍の軍縮が国際的な課題となったときでした。軍縮を進めようという民政党政府に対し、郡だけでなく、右翼や政友会までもが統帥権を犯しているという言い方をして抵抗しました。「統帥権違反」ではなく「統帥権干犯」です。つまり、法律違反と言えないものを、あたかも法律に違反しているかのように言いました。この言葉は、北一輝がつくったと言われています。なお、北は大正・昭和前期の国家主義者で、社会主義に傾倒し、『日本改造法案大綱』というものを書いて、当時の陸軍の青年将校たちに大きな影響を与えました。のち、二・二六事件の黒幕とされ、処刑されます。この場合、統帥権を干犯したものが、統帥権主義者よりもずっと愛国者だったのは間違いありません。なぜなら、軍縮をしなければ日本とアメリカの間で建艦競争が始まります。そうなると、産業力・国力に優るアメリカに日本は抑え込まれ、対抗しようと無理に軍事予讃をとれば、日本の産業・経済の発達はさらに遅れます。だから、貿易をすることでアメリカと仲良くして、お互いに海軍の建艦競争をやらないようにする——というのが本当の愛国者のやり方であり、国策上の正解です。しかし、軍縮を進めれば、艦長=中将になれるはずだった人はなれなくなり、多くの軍人が予備役に編入されて退役し、収入が激減します。いきおい、軍縮を主張する人間は嫌われてしまいます。だから、まっとうなことを言う人は海軍内で出世できなくなりました。統帥権は、天皇が軍隊を率いる権利なので、解釈しだいで無限に何でもすることができました。帷幄上奏という特権が、陸軍参謀本部、海軍例部という、統帥を管轄する機関に与えられます。帷幄というのは、天皇の前に垂れている御簾=すだれのことで、帷幄上奏権は、直接天皇に会いに行って、すだれをとおして意見を述べたり、相談したりする権限のことです。軍隊は天皇のものでしたから、陸軍や海軍が天皇と直接軍の行動について相談しあって、余人を介さないというので、どこが悪いかという権限なのです。これにより、軍人が首相でさえ知らないところで天皇に合い、意見を述べることができます。しかも、政策や作戦が間違って悪い結果になったとしても訴追されることはありません。 「このことから、統帥権は、無現・無謬・神聖という神韻を帯びはじめる。他の三権(立法・行政・司法)から独立するばかりか、超越すると考えられはじめた。さらには、三権から容喙もゆるされなかった。もう一ついえば国際紛争や戦争を起こすことについても他の国政機関に対し、帷幄上奏権があるために秘密にそれをおこすことができた。となれば、日本国の体内にべつの国家——統帥権日本——ができたともいえる」(『この国のかたち』四、85「統帥権(四)」 神がかりの統帥権が戦争を始めるのですから、その恐ろしさを司馬さんは訴えるわけです。 【「司馬遼太郎」に学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 12, 2025
コメント(0)
-
武士が見たペリー来航
武士が見たペリー来航横浜市歴史博物館主任学芸員 小林 紀子 体験・見聞を日記や手紙で今から170年前の嘉永7(安政元、1854)年、日本に再来航したペリーが横浜に上陸し、幕府との交渉を経て日米和親条約が結ばれた。一方この時、幕府の大名たちに江戸湾の海防(海岸防備)を命じており、多数の藩士たちが沿岸各所に派遣された。横浜市域では、金沢(金沢区)周辺を地元に陣屋を置く武州金沢藩が警備したほか、神奈川宿(神奈川区)に明石藩、本牧(中区)に鳥取藩が横浜応接所の警衛を担った。警衛に従事した武士たちの中には、自身の体験や見聞した情報を日記や手紙に記した者たちがいた。小倉藩医の桐原鳳卿もその一人である。桐原は嘉永7年2月6日に江戸藩邸を出発し、3月14日に帰着するまでの約1カ月間、横浜近くの大田村(西区・中区・南区)の陣所に滞在した。「横浜日記」と題された桐原の私的な日記には、この間の小倉藩の動向、自身の仕事や生活。ペリー一行の様子などが綴られており、みずから描いた、あるいは写したとみられる図も掲載されている。 江戸湾警衛の実態鮮やかにペリーが横浜に初上陸した2月10日、桐原は小倉藩の一員として横浜応接所に赴き、上陸したペリーをはじめ艦隊員たちの容姿や服装などについて事細かく観察した。ペリー一行が応接所に入った後は、友人の裏が奉行所よりき・日高大夫とともに外国人の様子を見てった。そこで桐原は、外国人の医師と名刺交換をした。医師は親しく手を握ってきて、振り払おうとしてもなかなか放してくれなかったという。応接所の外で、桐原以外にもこうした交流が生まれていたことは想像に難くない。また2月27日の日記には、外国人が神奈川、保土ヶ谷宿などを徘徊しているという噂に対し、海上生活が長いので、そぞろ歩きたくなるのだろうと、彼らの心中に思いを馳せるような記述も見られる。桐原がたびたび外出しているのも興味深い。日記には、来訪した知人と天神山(西区)から異国船を眺めたり、近隣の村や史跡を訪れたりした記事が見られる。中でも野毛(中区)には記事にあるだけでも3度訪れている。野毛には湯屋や料理や、酒屋、茶亭などがあったようで、桐原は入浴や飲食を楽しんだ。もちろん藩医としての職務もこなした。日記からは大田村滞在1週間頃から日増しに多忙になったことが読み取れ、薬が不足し、2度も神奈川宿まで買い足しに赴いている。しかしながら3月に入り、ペリー一行が横浜を去り、江戸へ戻れるという噂が立つと、病気のものも順調に快方に向かったという。慣れない土地での長期滞在によるストレスが、藩士たちの病気の一因となっていたことも想像できる。このように「横浜日記」からは、警衛の最前線の現場の実態が鮮やかに浮かび上がってくる。こうした同時代の記録は他にもいくつか知られているが、いまだ各地に眠っている資料もあるだろう。今後さらに事例が積み重ねられていけば、ケリー来航というよく知られた歴史が、より豊かに彩られていくことだろう。(こばやし・のりこ) 【文化】公明新聞2024.9.20
July 12, 2025
コメント(0)
-
友岡雅弥X
友岡雅弥X 基本的に、ことばの本当の意味で、大乗と言えるのは、龍樹の 中観派と般若経経典群であり、そこに、「マサラ・ムービー的盛り」を施した『法華経』の嘱累品までかな。 他の「大乗」経典は、むしろ、「根本説一切有部」の流れの後継に近い。 ただし『法華経』の安楽行品と普賢品は、ヘイト 大聖人の御書は、「法理」のエビデンス・アプローチではなく、「希望」のナラティブ・アプローチとして読んだらいいと思う。 日蓮大聖人も池田先生も「教え」を説いたのではない、 「希望」を語ったんです。 僕は、明確に「日蓮本仏論者」だけど、「久遠元初の仏様」という仏教ではない、日蓮正宗的一神教ではなく、旃陀羅が子として生まれ、犯罪者として遇され、掘建て小屋で門下の手紙に涙し、最後は置いて行く馬のことを心配しながら亡くなる、1人の人間を、人生の模範としようと言う「日蓮本仏論者」 もう一つ、何度も書いてるんやけど。 僕、日蓮本仏論者ですけど。 ばりばりの。 なんで「法華経の智慧」を読む!と決意してる、とか言ってるのに、「本仏」とやらにこだわるのかなぁ。 そういう日蓮正宗的考えを破るためのものなのに。 僕は、明確に「日蓮本仏論者」だけど、「久遠元初の仏様」という仏教ではない、日蓮正宗的一神教ではなく、旃陀羅が子として生まれ、犯罪者として遇され、掘建て小屋で門下の手紙に涙し、最後は置いて行く馬のことを心配しながら亡くなる、1人の人間を、人生の模範としようと言う「日蓮本仏論者」 「文底秘沈」なんて、バラモンの秘密主義だし、中古天台の台密。 それを、「とりいだし」「誰にでも出来る形」で命がけで、広めようとしたのがのが大聖人と違うの。 だから、大聖人は、「文上開示」 「文底」とか「久遠元初」に拘る人がいるけど、平成の宗教改革の意義がほんとに浸透していなかったんだなぁと思います 「文底」釈というのは、「久遠元初」とかいう、「絶対神的日蓮」的、「文上浮遊」的なものではなく、 「今、私は何をすべきなのか」の姿勢。 修行者が酒場に入れば 酒場が彼の修行場になるが、 酒飲みが修行場に入れば そこは彼の酒場となる ——エジプト生まれのスーフィー、ズーン・ヌーン もちろん飲酒のことと違いますよ。 「私」が何をするか、という話 ずっと「文底読み」という「皮相浅薄読み」の訓練受けて来られているので、しんどいですね 『法華経の智恵』のテーマが、「文底釈とは、人間釈である」だったことが、ほとんど忘れ去られてしまっているのは、とても残念。
July 11, 2025
コメント(0)
-
数学で読み解く音楽
数学で読み解く音楽中島さち子(数学者、ジャズピアニスト)「創造性」「自由性」が共通自然をどのように捉えるのか前提を疑って考える音楽と数学、多くの人はまったく別のものと考えているかもしれません。でも、古代ギリシャ時代から続くリベラルアーツ(一般教養)では、数学、音楽、天文学が同じように重要視されていたんです。数学を代数と幾何学に分けて、数の学問が「代数」、形の学問が「幾何学」、そして、動く形の学問が「天文学」、動く数の学問が「音楽」だったのです。美しい世界の調和、宇宙の真理などを探ろうとする、その一つの方法が、数学であり音楽であったわけです。世の中の不思議なこと、どうしてこのようなことが起きているのか、そこを解明しようと証明が生まれ数学に、それを美しさとして捉えようとすると音楽になるんです。当時は、この四つの学問を通じて、世界の在り方を知ろうとしたのでしょう。数学と音楽には「創造性」と「自由性」があります。まず創造性ですが、どちらも、自分なりの視点でものごとを捉えたり、自分なりの法則を考えたりする。そこがすごく面白いのです。二つ目の自由性は、ちょっと視点を変えることで、今まで思いこんでいた世界とは全く違う景色が見えてくるところです。音楽にしても、同じような演奏であっても、ちょっとした音程の揺らぎによって、音が共鳴し合って大きさが変化します。数学にしても同様です。三角形の内角の和は180度だと教わってきたでしょう。でも、地球の様な球体の表面に描かれた三角形の内角の和は180度より大きくなります。 子どもにも大人にもこうしたら良いものが作れると教えられて、できるようになる。それはAIなどの機械にも可能です。でも人間は、自由にモノを見て、作り出していける。そこには大きな違いがあるように思います。人間の感覚はすごいんです。完成で美しいモノをつくろうとすると、無意識のうちに、何か数学的にみても美しい構造になっている。それを読み解いたのが、私の近著『ヒット曲のすごい秘密』(青春新書)です。名曲やヒット曲を聴いている時、その多くの場合、その背後にある曲の構造には目を向けません。でも、ちょっと理性を働かせて、なんでこの音楽にはこんなに気持ちがいいんだろうと考えてみてください。すると、あの曲と、この曲は似ているな、などと気付くはずです。全部が同じではなくても、何となくもの悲しさが共通しているとか。でも、少し違う部分があるから、この曲は物悲しいだけでなく、そのあとに楽しくなるんだと。そんな新しい聞き方ができるようになると、別の面白さが見えてきて、自分でも作れるかもしれないと思える。そうなるといいなと思っています。音楽の研究は、子どもにもできるし、大人になっても楽しめるものです。時間があったら、自分の好きな曲について探ってみてはいかがでしょうか。 生活の中にある揺らぎ皆さんは手毬歌を知っているでしょうか。有名な「あんたがたどこさ」は、実は途中で表紙がどんどん変わる変拍子になっています。手毬歌だから、鞠を衝く動作がしやすい拍子が基本だと思われるかもしれません。でも、突然3拍子になったり、2拍子になったりするのです。鞠をつくだけでなく、足の下をくぐらせる動作が入ります。このタイミングで拍子が変わっているのです。この変化が、鞠つきという遊びをおもしろくしているのです。最初から最後まで4拍子の曲だと、4回に1回足を回すだけの単純な動きになってしまいます。それが3拍子や2拍子に変化することで、足を回しタイミングに緩急ができ、より楽しい遊びになっているのです。数学は、物事を単純化し抽象化する子で、本質をとらえてきました。でも、実際の世界はそう単純ではありません。デジタルの感覚だと、1と2の間には何もありませんが、実際には無数の数があるます。それは整数の数より多いといわれています。そんな不思議なことがたくさんあるのです。実は数学の最前線の研究は、揺らぎを取り入れた確率論になってきています。同じように、揺らぎを生かした音楽が見直されてきています。文額は元々、歩く、スキップするなど、普段の生活の中から生まれてきました。そこには、自然に対する祈りだったり、揺らぎがあるんです。そんな揺らぎを生かした音楽、例えば和楽器の笛の音などにヒントがあるかもしれません。そこから、これまで正しいと信じられてきたことが崩れて、新しい世界が広がっていくと、面白いと思います。=談 なかじま・さちこ 大阪生まれ。数学者、ジャズピアニスト。高校2年の時に、国際数学オリンピックで金メダルを獲得。大学時代にジャズと出合い、ジャズピアニストに。現在は株式会社「steAm」代表。著書に『ヒット曲のすごい秘密』『人生を変える「数学」そして「音楽」』『知識ゼロからのSTEAM教育』などがある。 【文化Culture】聖教新聞2024.9.19
July 11, 2025
コメント(0)
-
鬼胎の正体「統帥権」
鬼胎の正体「統帥権」近代日本を滅ぼしたドイツのこの薬物注射が、その後どのようにして日本という人体を蝕んだか。その仕組みを、司馬さんは特定していきます。原因物質は、ドイツ服に付着していた「統帥権」でした。統帥権とは、軍隊の最高指揮権を表し、大日本帝国憲法の一一条に定められています。統帥権は、天皇が持っている陸軍と海軍を指揮する権限で、具体的には、陸軍の参謀本部と海軍の軍令部が直接天皇とつながって、軍隊を運用する権限のことです。前述のように、日本軍はドイツから参謀本部というシステムを輸入しますが、そのために「軍の統帥権は国家の外側、君主の対外にある」という統帥権が自己増殖し、手が付けられない国内国家をつくり、ついには日本を崩壊させてしまった——というのです。司馬さんは『この国のかたち』で次のように語ります。 「統帥権とは、(中略)『軍隊を統べ率いること』である。/(中略)英国やアメリカでも当然ながら統帥権は国家元首に属してきた。むろん統帥権は文民で統御される。/軍は強力な殺傷力を保持しているという意味で、猛獣にたとえてもいい。戦前の、その当水機能を、同じ猛獣の軍人が掌握した。しかも神聖権として、他から嘴はいれば、『統帥干犯』として恫喝した」(四、85「統帥権(四)」「明治憲法はいまの憲法と同様、明快に三権(立法、行政・司法)分立の憲法だったのに、昭和になってから変質した。統帥権がしだいに独立しはじめ、ついには三権の上に立ち、一種の万能性を帯びはじめた。統帥権の番人は参謀本部で、事実上かれらの参謀たち(天皇の幕僚)はそれを自分たちが〝所有〟していると信じていた。/ついでながら憲法上、天皇に国政や統帥の執行責任はない。となれば、参謀本部の権能は無限に近くなり、どういう〝愛国的な〟対外行動でもやれることになる」(一、4「〝統帥権〟の無限性」) 司馬さんは、前章でふれたように、明治という時代を江戸時代の収穫時期ととらえました。が、昭和前期という時代をよく見ると、その収穫した実が腐ってく過程にも感じられます。腐敗の原因は、明治にあったのです。日本を「鬼胎」にした正体——それは、ドイツから輸入して大きく育ってしまったもの、すなわち「統帥権」でした。要するに「統帥権があるぞ」と言い立てることで、軍が帝国議会や一般人を超越した存在となり、統帥権が一人歩きをして、軍が天皇の言うことさえも聞かなくなっていくという仕組みです。軍の統帥権の実際の運用にあたっては、当然のことながら、政府と議会がチェックする必要がありました。まずは政府内閣が命令・人事で、そして予算決定権がある議会が、予算審議で軍隊を統御しなければいけませんでした。しかし、日本の場合、軍の統帥に関する予算について議会が主導権を持つことはありませんでした。さらに言えば、政府、内閣さえも軍の統帥権の外に置かれていきます。明治憲法下で、軍を抑えられるのは法による支配=人知をやっていた維新の功労者=明治国家のオーナーたち=元老でしたが、彼らが次々と世を去り、昭和になって、西園寺公望という元公家の老人ひとりになると、元老による軍統帥権の統制も利かなくなっていきました。明治国家の基本姿勢は、議会の意見は聞くが、最終決定権はない、というものです。軍の統帥に関する決定権は全て天皇にあると軍部は主張しました。ところが、実際には、天皇自身が決められるわけではありません。軍の中枢を挿す部課局が決定します。軍はその結果を天皇に上奏(報告)するだけで、天皇の意志をしばしば無視して押し切りました。このように統帥権は、昭和に入ると、やがてバケモノのように巨大化していきました。そして日本は迷走をはじめました。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 10, 2025
コメント(0)
-
日常的に個人が監視される未来も
日常的に個人が監視される未来も科学文明論研究者 橳島 次郎人工知能による生体情報の活用㊦前回、日常生活を送るなかで身近な機器から収集された多様な生体情報を人工知能が学習し解析する技術を紹介した。心拍、血圧、呼吸数などの他、睡眠関連音や脳波などから生活や健康の状態を把握するためのものだが、このお技術は全く別の使われ方もされる。今年5月、ヨーロッパ連合(EU)で、世界初の包括的な人工知能技術の規制法が、成立した。この法律では、人勧侵害につながるリスクが極めて大きい人工知能の利用法を特定し、禁止する措置としている。その禁止事項の一つに、公共の場所でのリアルタイムのリモート生体認証による個人識別を法執行目的で行うことに人工知能を使ってはならないという一項がある。監視カメラやインターネットにアップされる大量の画像情報から顔認証を人工知能により瞬時に行い、犯罪者などを補足することが想定されている(切迫したテロの防止や重大犯罪の容疑者の特定のためなどは例外として許容)。この禁止事項が示すように、大量のデジタル生体情報を人工知能に解析させる技術は、治安目的の監視技術にも利用される。使われる生体情報は、顔面や指紋、声紋などの他に、前回見た、睡眠関連御宿の生活音声データやヘッドハンドの健康機器から得られる脳活動データも、個人識別に利用する研究が行われている。そうした日常生活で集められる生体情報データを通して、心身の状態や活動などにかかわるプライバシーが常時監視の下に置かれる未来が来るかもしれない。膨大なデータの学習を通じて、人工知能が生体情報の特性から個々人の不満や攻撃衝動の高まりやすさなどを識別することが考えられる。例えば、暴力犯罪を起こす性向を脳波の特徴と関連付ける研究が行われている。その研究結果を人工知能に学習させ、収集された脳波データを解析させれば、「この人は反社会的行動を起こす可能性が高い」などと判断される可能性がある。EUの人工知能規正法は、個人が犯罪を行うリスクを正確の特徴などの身に基づいて評価する人工知能システムの利用は禁止するとしている。治安のためだけではなく、職場や学校などの管理のための監視もありうる。EUの人工知能規正法は、職場や教育機関において人々の感情を推測する人工知能システムの利用も禁止対策に挙げている。日本でも政府が人工知能の公的規制について検討を始めたところだ。EUが法で禁じた対象についてそう対応するか、きちんと決めてほしい。 【先端技術は何をもたらすか—29—】聖教新聞2024.9.17
July 10, 2025
コメント(0)
-
池田先生「第38回本部総会」での講演(1975年11月)㊦
池田先生「第38回本部総会」での講演(1975年11月)㊦民衆こそ「歴史の底流」を形づくる主役生命尊厳を基盤に恒久平和への大道を 池田先生は1975年11月の本部総会で、創価学会の根本目標は日蓮大聖人の仏法を広宣流布することにあると再確認した一方で、学会の社会的使命について次のように語った。「この広宣流布、仏法拡大の運動それ自体、現実社会において、もっとも本源的な人間復興、生命尊厳の確立の戦いであることはいうまでもありません。そこからさらに一歩、仏法をもった社会人の集団としての社会における責任、また目標はどこにあるかと言えば、生命の尊厳を基調とした文化の興隆にあると言えるのであります」その上で、「世界恒久平和の実現こそ、われわれのめざすべき大道」と宣言したのだ。この挑戦の基軸として池田先生が強調したのは、対話の実践に加えて、歴史の底流を粘り強く形づくる漸進主義と、民衆がその主役であるとの点だった。漸進主義については、いかなる時代の荒波に帆損なわれない金剛不壊の生命の輝きで社会を潤すことを説いた涅槃経の一節を踏まえ、こう論じていた。「時代は刻々と動いていく。天候の推移と同じように、晴れのときもあれば曇りのときもある。これからも、あるときは、暴風雨に遭遇するような場合もあるでありましょう。要はそうした変転に一喜一憂することなく、絶えず原点を凝視しつつ清浄な軌道へと引き戻していく力が、人びとに備わっているかどうかであります。「そうした本源的な力を、民衆一人ひとりの心田に植え付けていくところにこそ、宗教のもっとも根本的な使命がある」人間と人間との生命次元での触発をとおし、平和と共生の地球社会を建設していく労作業こそ、迂遠の様でももっとも豊かな道であるというのが、池田先生の信念だったのだ。 また、民衆が歴史創造の主役であるとの点については、「大海の一滴も衆流を備え、一海も万流の味をもてるがごとし」(新1527・全1121)の一節を通し、こう訴えていた。「大海といっても究極するところ一滴の集積にほかならないし、その一滴に大海のいっさいが含まれているのであります。たった一つの如意宝珠であっても、いっさいの宝を生み出す無限の価値があり、一丸の薬に万病を癒す効果がある」と。希望の未来を目指して一人一人の起こす行動が、仏法の示す方程式に照らし、どれほど大きな波動を広げていくのか——。その使命の大きさを信じ、共に前進しようと呼びかけたのだ。この池田先生の信念は、終生変わることはなかった。2017年の提言では、SGDs(持続可能な開発目標)を巡って、同じ方程式を提起していた。「青年が、今いる場所で一隅を照らす存在になろうと立ち上がった時、そこから、周囲の人々が希望と生きる力を取り戻す足場となる、安心の空間が形づくられていきます。その安心の空間に灯された『共に生きる』という思いが、そのまま、国連が目指す『誰も置き去りにしない』地球社会の縮図としての輝きを放ち、同じような問題に苦しむほかの地域の人々を勇気づける光明となって行くに違いないと、確信するのです」新型コロナウイルス感染症の世界的流行やウクライナ危機の影響もあり、その進捗が遅れる中で、SDGsに対して冷笑的な意見が一部でみられる。しかし私たち創価学会は市民社会の一員として、気候変動をはじめとする人類共通の課題への認識を広げ、「誰も置き去りにしない」との誓いの連帯を築くために、SDGsの取り組みを後押ししてきた。1975年の本部総会で先生が述べた、「もはや未来の時代に対しては、こうした地道な努力しか方法はない。もしこれを冷笑するようでは、その人はいったい人類社会の今後にいかなる方法を持って臨むのかと、私は反問したい」との言葉に脈打つ精神が、創価の民衆運動の矜持にほかならないからだ。 池田先生とトインビー博士との対話から半世紀以上がたった今、博士が着目した創価の民衆は192カ国・地域に滔々と流れる大河となった。本年2月、ベルギーのブリュッセルにある欧州会議の施設内で、池田先生の追悼行事が行われた際、ローマクラブのサンドリン・ディクソン=デクレーブ共同会長は、先生の功績を称えながら、こう呼びかけた。「私たちは今、分岐点に立っています。人権を否定し、自然や地球の存続を脅かす政治的な動きの拡大を目にしています。その一方で、民主主義や自由、平和が失われゆくことに抗する仏教的ヒューマニズムの萌芽が、社会の中で確かに見られます。だからこそ人間革命の流れを強めていかねばなりません。その責任は他のだれでもなく、私たち一人一人にあるのです。人間革命を他者に呼びかけ、力づけることを継続していく。これこそが池田氏の精神を受けついていくことであり、氏に敬意を表することになるのです」国際政治における出来事だけが、人類の未来を左右するのではない。私たち民衆の日々の行動が、窮極において歴史をつくる「水底のゆるやかな動き」を生み出していることを深く確信して、前進していきたい。 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史をつくるはこの船たしか—第12回— 聖教新聞2024.9.17
July 9, 2025
コメント(0)
-
池田先生「第38回本部総会」での講演(1975年11月)㊤
池田先生「第38回本部総会」での講演(1975年11月)㊤時代は刻々と動いていく。天候の推移と同じように、晴れのときもあれば曇りのときもある。これからも、あるときは、暴風雨に遭遇するような場合もありましょう。要はそうした変転に一喜一憂することなく、あわてず原点を凝視しつつ正確な軌道へと引き戻していく力が、人びとに備わっているかどうかであります。それは、生命のバネ、バイタリティーであるといってもよく、そうした本源的な力を、民衆一人ひとりの心田に植え付けていくところにこそ、宗教のもっとも根本的な使命がある。創価学会の社会的役割、使命は、暴力や権力、筋力などの害的拘束力を持って人間の尊厳を犯し続ける〝力〟に対する、内なる生命の深みよりハッスル〝精神〟の戦いであると位置づけておきたい。(中略)仕事をするには時間がかかる。人間対人間の触発をとおして、自他の生命をみがきあげるという開拓作業が、一朝一夕に成就しうるものではありません。だからこそ、結果としてもたらせるものは、いかなる風説にも朽ちることのない金剛不壊なる生命の輝きなのであります。もはや未来の時代に対しては、こうした地道な努力しか方法はない。もしこれを冷笑するようであれば、その人はいったい人類社会の今後にいかなる方法を持って臨むのかと、私は反問したい。(中略)一般に「行き詰った時は原点に戻れ」と言われますが、人間にとって原点とは〝人間らしさ〟〝人間の尊厳性とは何か〟ということ以外にはありえない。その意味から私は、人間と表とした民衆中心主義こそ、来るべき世紀への道標でなくてはならないと考えている一人であります。私共は、その視点から、誰人とも話し合っていきたい。◇一致点を見いだすことも有意義であり、不一致点を見いだすこともまた有意義であります。ともかく、思慮深い判断と先見性が要求される時代にあって、徹底して人類の根本的な原点に立った対話を進めていきたいものであります。(『新版 池田会長全集』第1巻) トインビー博士が寄せた学会への期待人類の結束を目指して「対話」に挑む 究極において歴史をつくるものは、新聞の見出しの材料となるような華やかな出来事でも、政治的・経済的事件でもない。普段は目に見えないが、歳月を経た後で大きくその姿を現してくるような、「水底のゆるやかな動き」である——。これは、歴史家のアーノルド・J・トインビー博士が、人類史を巡る探求を続けるなかでたどりついた、「時間の遠近法」に基づく洞察である。その博士が、現代における「世界的出来事」と着目していたのが創価学会の存在だった。博士は、1972年4月に発刊された池田先生の小説『人間革命』の英語版に寄せて、次の言葉を綴っていた。「戦後の創価学会の興隆は、たんに創価学会が創立された国(日本)だけの関心事ではない」「創価学会は、すでに世界的出来事である」「日蓮は、自分の思い描く仏教は、すべての場所の人間仲間を救済する手段であると考えた。創価学会は、人間革命の活動を通して、その日蓮の遺命を実行しているのである」と。以前から、博士は大乗仏教に関心を抱いていた。1967年の訪日などを通じて、大乗仏教の豊かな可能性を現代に蘇らせた創価学会への認識を深める中、池田先生との対談を切望するようになったのである。1969年9月、その思いを記した博士の書簡が池田先生の下に届いた。その後、準備が進められ、池田先生が1972年5月と73年5月の2度にわたり、ロンドンにある博士の自宅を訪れる形で、のべ40時間に及ぶ対談が実現したのだ。対談の最終日、テレビのニュースでは、ソ連のブレジネフ書記長が西ドイツを訪問し、ブラント首相と会談したことが大々的に報じられていた。このニュースが話題となった時、博士は毅然と言った。「政治家同士の対談に比べ、私たちの対談は地味かもしれません。しかし、私たちの語らいは、後世の人類のためのものです。このような対話こそが、永遠の平和の道をつくるのです」 時々の政治的な動きも見過ごせないが、それに一喜一憂しているだけではいけない。「後世の人類のため」という深い次元に立って歴史の底流を堅実に形づくる努力が絶対に必要である——。それが、トインビー博士の晩年の強い思いだった。だからこそ博士は、一切の対談を終えて池田先生を見送る時に、こう言い残したのだ。「私は、この対話こそが、世界の種文明、諸民族、諸宗教の融和に極めて大きな役割を果たすものと思います。人類全体を結束させていくために、若いあなたは、このような対話を、さらに広げていってください」池田先生はその言葉を胸に、博士から紹介を受けた世界の識者との対話に臨んだ。1973年11月には科学者のルネ・デュポス博士と、1975年5月にはローマクラブの創立者であるアウレリオ・ペッチェイ博士と出会いを結んだ。また、トインビー博士が憂慮していた米ソ関係や中ソ関係の改善を願い、中国への初訪問(74年9月)に続いてソ連(74年9月)を初訪問し、コスイギン首相と会見した。さらに、中国を再訪問して周恩来総理と対談し(74年12月)、時を置かずしてアメリカにも赴いた。キッシンジャー国務長官と会談した5日後(75年1月18日)、国際的なメディアのAP通信がある記事を全世界に発信した。池田先生が3カ国の首脳と相次いで会見したことに触れながら、創価学会について紹介した記事である。小説『人間革命』の英語版にトインビー博士が寄せた文章にも言及しつつ、記事は次の言葉で結ばれていた。「絶望と幻滅の社会の中で、小さな組織であった創価学会は高い理念を掲げ、理念達成に強い確信を持っていた。これを裏付けるように、戦後三十年で、創価学会は現在の組織へと大きく発展したのである」と。そして1月26日、記事でも予告していた通り、グアムの地でSGIが発足したのだ。こうした新しい飛躍の時を迎える中、創価学会の基本精神と社会的使命について池田先生が宣言したのが、同年11月9日に広島で行われた第38回本部総会での講演である。それは、トインビー博士の逝去(10月23日)から間もない時期に行われた講演でもあり、博士が「世界的出来事」と着目した創価学会が何を目指しているのかを、改めて明確に示すものでもあった。 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史を創るはこの船たしか—第11回— 聖教新聞2024.9.16
July 9, 2025
コメント(0)
-
「国家病」としてのドイツへの傾斜
「国家病」としてのドイツへの傾斜 「明治二十二年の憲法発布のときは、陸軍はまったくドイツ式になってしまっていた。/ドイツ式作戦思想が、のちの日露戦争の陸戦において有効だったということで、いよいよドイツへの傾斜がすすんだ」(同前) 明治の軍人を規定していた最も特徴的なものは、リアリズムや合理主義ではなく、経験主義や実験主義だと思います。ドイツが勝ったからそっちの方がいいというもので、現実に実験されたものを信じるというやり方です。そしてドイツの文化やシステムを取り入れたわけですが、彼らはまだ江戸人がドイツの服を着ているだけでよかった。司馬さんに言わせると、「自国を客観視するやり方も身に付いていた。」(同前)そうです。では、ドイツ色が濃くなった昭和の軍人はどうだったか。 (昭和の高級軍人は、あたかもドイツ人に化(な)ったかのような自己(自国)中心で、「独楽のように理論だけが旋回し、まわりに目を向けるということをしなかった」(同前) もちろん、これはドイツの文化が悪いということではありません。司馬さんはそのあたりにも留意しています。 「以上はドイツ文化の罪ということでは一切ない。/明治後の拙速な文化導入の罪でもなかった。/いえることは、ただ一種類の文化を濃縮駐車すれば当然薬物中毒にかかるということである。そういう患者たちをにぎられるかどうかは、日本近代史が動物実験のように雄弁に物語っている」(同前) 昭和の軍人はドイツを買い被っているけれど、本当のドイツを知っている人はいない。ドイツ系者というのが「一種の国家病」だったと、司馬さんは強い調子で批判しています。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 8, 2025
コメント(0)
-
平和と公正をすべての人に
平和と公正をすべての人にインタビュー ジャーナリスト 小山美砂さんこやま・みさ 1994年、大阪府生まれ。広島市在住。元毎日新聞記者。2022年7月、『「黒い雨」訴訟』(集英社新書)を刊行し、第66回JCJ賞を受賞。広島を拠点に、各被害の取材を続ける。 〝いつまで〟被害が続くのか分からない——そこが核兵器の恐ろしさ 「黒い雨」訴訟とは——最初に、「黒い雨」訴訟につて教えてください 「黒い雨」とは、1945年8月に、広島、長崎での原爆投下後に降った雨です。火災のすすなどによって雨は黒く汚れ、放射性物質を含んだ雨をおびた多くの人たちが健康被害に苦しみました。「川が黒く染まり、死んだ魚がたくさん浮いていた」という証言もあります。しかし、黒い雨によって被害を受けた住民たちは、長く救済の「対象外」となりました。黒い雨の降雨地域が狭く限定され、その外にいた人たちは「被爆者」として認めらなかったのです。当然、この〝線引き〟に対して住民たちは怒り、憤りました。援護対象の拡大を求める運動が続けられましたが、その声は長く退かれてきました。2015年、広島で黒い雨を浴びた住民たち64人(最終的には84人)が、広島県と広島市を相手取った訴訟を起こします。実質的には、国に援護対象を拡大するように迫った訴訟——これが「黒い雨」訴訟です。結果、原告である住民84人全員が「被爆者」として認められる全面勝訴。その後、黒い雨被爆者への救済は拡大しました。『「黒い雨」訴訟』の執筆を始めた当時、裁判の判決がどうなるか、正直分かりませんでした。でも、もし裁判でまけてしまったら、長く苦しんできた人たちの想いは形に残らなくなってしまう。〝この事実を書き残さなければ〟。そんな思いで、取材をかさねました。 〝認められない〟痛み——「黒い雨」被害の取材をするようになったきっかけは、なんだったのでしょうか? 大学卒業後、新聞記者として、広島で多くの被爆者の方を取材するようになりました。でも、「黒い雨」被害のことを、初めはよくわかっていませんでした。私自身、爆心地近くの被爆と比べて、どこか軽視してしまっていたのかもしれません。また、制度や背景などが複雑で、何となく遠ざけてしまっていた面もありました。そんな中、黒い雨被爆者との出会いがありました。ある人がこう語っていたんです。「黒い雨の問題ってね、貧乏との戦いでもある。病気で十分働けなくなって、お金が残るはずがない。国が勝手に戦争をして、病気だらけの人生を放っておいた」。また、ある人は「どれだけ訴えても、原爆のせいだって認められないなら、もう、はよ死んだ方がいいと」。その言葉にハッとしました。原爆投下から70年以上がたってもなお、身体も、心も、暮らしも壊され、苦しんでいる。「被爆者」とさえ認められず、援助も受けられない。「核兵器って言うのは、人をこんな状況に陥らせてしまうのか……」。そう痛感しました。どこまでが原爆の〝被害者〟になるのかが分かりづらいのが、核兵器による被害の難しさであり、恐ろしさです。被爆者として、〝認められないこと〟事態が痛みを生んでいる。また長崎では、国が定めた地域の外で原爆にあった人は、「被爆体験者」とされ、被爆者と同じ支援を受けられずにいます。今月9日、その一部の人たちを「被爆者」と認める地裁判決が出ました。しかし、「黒い雨」を浴びた人たちや「被爆体験者」には、原爆投下から間もなく80年がたとうとする今でも「被害が証明できないなら、被爆者として認められない」ということが起きてきています。でも、それでいいのか。「疑わしきは切り捨て」ではなく、「疑わしきは救済」される世の中であってほしい。実は私自身、高校時代、学校に行かなくなってしまった時期がありました。また、新聞記者時代には、心の不調で退職も経験しました。〝社会から置き去りにされてしまっているような感覚〟を経験したからこそ、この問題を放っておけなかったのかもしれません。何よりも、救済されていない被害者がいるかぎり、被害が過小評価され、問題の深刻さから目をそらすことになってしまう。だから私は、爆心地から離れた場所で、「黒い雨」によって被害を受けた人たちの事業を記録することで、核兵器の脅威を伝えられるのではないかと思っています。 SDGsど真ん中——フリーになってからも、広島を拠点に各被害の問題に取り組まれています。今、力を入れておられることなんでしょうか? グローバル・ヒバクシャの取材ですね。核実験や、核兵器の製造の過程などで被ばくし、苦しんでいる人は、国外にも多くいます。9月1日から11日にかけて、カザフスタン共和国へ取材に行きました。カザフスタンにはかつて、旧ソ連の「セミバラチンクス核実験場」という世界最大規模の実験場がありました。450回以上に及ぶ核実験が繰り返され、多くの人が被爆し、今も健康被害に苦しんでいます。「すべての各被害者を救済するために何が必要なのか」を探ることが、今回の取材の目的の一つでもありました。一方、カザフスタンは国際社会で核廃絶の議論をリードする国のひとつです。来年3月に行われる核兵器禁止条約の第3回締約国会議では議長国を務めます。同条約には「核兵器による被害者の円音環境回復」、そのための「国際協力・援助」の項目があり、この分野なら、日本も貢献できるのではないかとの声があります。SGI(創価学会インターナショナル)も協同されていますね。 ——SDGsには「誰も置き去りにしない」という基本理念があります。 核兵器の茂田井って、SDGsのど真ん中だと思うんです。今回のテーマ16以外にも密接にかかわっています。もし核兵器がひとたび使用されてしまえば、3「すべての人に健康と福祉を」や、11「住み続けられるまちづくりを」、14「海の豊かさを守ろう」、15「陸の豊かさも守ろう」などの目標も達成が困難になってしまいます。また、核抑止の考えがある限り、16「平和と公正をすべての人に」は達成できないのではないかと思います。核抑止の考えって、自国や同盟国が核兵器を持つことで、自国の安全を守るという発想ですよね。それって誰かを傷つける、被爆させるかもしれないということが前提になっているように思うんです。実際に、核兵器を維持するために多くのグローバル・ヒバクシャが生み出されている。そうして守られている平和って、本当の平和なのか。そういった議論が、SDGsの達成にも、平和の実現のためにも必要だと思います。 ——核兵器の問題を身近な課題として捉えるには? 「現在も続いている問題だ」と認識することが大事なのではないでしょうか。それは、「核兵器が今、約1万2000発存在している」というだけではなく、実際に今も、「核兵器による被害で苦しんでいる人たちがいる」ということです。被害が認識されていない限り、〝ヒバクシャの体験〟として「伝承する」段階にも入らない。だからこそ、まずは「知ること」自体が大きな一歩ですし、始められることなのではないでしょうか。また、そうして学んだことを「忘れないこと」。まずは、情報を発信している人のSNSをフォローしてみて、時にはそれをシェアしてみる。それだけでも、立派なアクションだと思います。 【SDGs×SEIKYOO】聖教新聞2024.9.14
July 8, 2025
コメント(0)
-
民主主義を機能させるため
民主主義を機能させるため「政治の監視」が市民の役割インタビュー 立命館大学 山本 圭 准教授 嫉妬から捉える——山本准教授の近著は『嫉妬論』です。現代政治理論などを専門とする准教授が、「嫉妬」をテーマに取り上げたのはなぜでしょうか。 政治思想の分野で、ここ50年ほど盛んに論じられているのは、『正義論』を著したジョン・ロールズに端を発する、規範的な政治哲学です。「正義とは」「平等とは」と追い掛け、望ましい社会の在り方を模索していく議論が、近年の主流になっています。しかし、正義や平等、あるいは民主主義のあるべき姿を模索する一方で、現実にはそうした理想がうまく機能しなかったり、社会に受け入れられなかったりということも多くあります。格差を是正する、本来であれば望ましいはずの諸政策に、「ずるい」「納得がいかない」など、不満の声が出ることもあるわけです。こうした不満の背後にはきっと、人間の非合理的な感情があるのではないか。なかでも、最も厄介なのが嫉妬感情であり、この嫉妬を掘り下げることで、麗しく語られてきた正義や平等、民主主義を、別の仕方で捉えることができるのではないかと考えました。例えばロールズ自身が『正義論』の中で、嫉妬について二つのセクションを割いて論じています。嫉妬感情は、正義の構想を揺るがしかねないものだと、彼は重く考えていました。ロールズ以前にも、さかのぼれば古代ギリシャのプラトンをはじめ、多くの哲学者が嫉妬感情を題材にしています。 他人との比較——人間はなぜ、嫉妬してしまうのか。嫉妬されやすい人は、どういう人なのか。身近なこの感情に関して、どのような理解が可能性でしょうか。 アリストテレスが論じたように、人間は誰に対しても嫉妬するわけではなく、むしろ近しい人に嫉妬心を抱くとされています。確かに、自分より待遇の良い隣人をねたむことはあっても、どこかの大富豪を妬む人は少ないでしょう。つまり、嫉妬感情は、比較可能なもの同士の間に生じるものだと言えます。私は、比較それ自体が悪いとは考えていません。他人と比べ、他人の目を通して自分を見つめることで、自分の価値をはかることができる。そこから生まれる嫉妬感情についても、ある意味では人間のさがだと言えるでしょう。なかでも、自分よりすぐれた他者と比較して妬んでしまう「上方嫉妬」は、容易に理解できますし、ある程度は仕方がないと思えるものです。一方、より厄介なのは「下方嫉妬」です。自分より劣位にある人と比較し、抱く嫉妬感情のことです。例えば日本では、生活保護受給者への過剰なバッシングが、たびたび起こります。一般的に、社会保障の充実は、社会全体の福利を向上させる望ましいものであるにもかかわらず、〝自分は苦労して働いているのに……〟との嫉妬心が、弱い立場の人々に向けられていく。他にも、最近の学生たちは、授業の出欠確認を取ってほしいとよく言います。あまり大きな声では言えませんが、私が学生のころは、授業に行かないことも多くあったのでこれには驚いています。理由を聞くと、出席せずよく単位を取る人が許せないようです。これも、他人が自分の水準にまで上がってくるのが我慢できないという意味では、下方嫉妬に近いかもしれません。自分の損得には影響ないはずなのに、他人が利益を得ることを受け入れられない。そんな下方嫉妬が、社会を生きづらくしている一因であるように思います。 分断された社会をつなぐ少しの寛容さと歩み寄り 不可解な感情——嫉妬と民主主義を、「同じ土壌から生まれた双子のようなもの」と述べられているのは、どのような点からでしょうか。 まず、歴史からみても、両者は切っても切れない関係性にあります。民主主義の故郷とされる古代ギリシャに、「陶片追放(オストラシズム)」というユニークな制度がありました。都市国家アテナイ「オスコラトン」と呼ばれる陶器のかけらに、追放しようと思う物の名前を書いて投票場所に投げ込む。ある一定の役票総数を超えれば、最も多く名前を書かれたものが、10年間、追放されるという制度です。その目的については、独裁者になり得る人物を追放し、民主的な平等を保つための制度であったというのが、教科書的な説明です。一方、キルケゴールなど一部の哲学者の間では、別の解釈もなされていきました。陶片追放は妬みの対象になった人物を追放するための制度であり、いわば「民衆の嫉妬のはけ口」だったというものです。民主主義を維持する制度に、すでに嫉妬心が刻印されていたというこの見方は、両者の関係を考える上でとても示唆的です。また、理論的に考えても、民主的な社会は嫉妬が渦巻く社会と言えます。民主主義では平等が中心的な価値になります。しかし、どんな社会であっても完全な平等というのはあり得ず、少なからず差異は生じます。そして嫉妬が比較を条件とするとすれば、相手との差が縮まれば縮まるほど、その差がより気になって比較が生じ、嫉妬感情が孕んでいくのです。そう考えると、嫉妬は民主的な社会で不可避な感情であり、どうにかなくそうとするよりも、どう付き合うかを考えることがより現実的な選択肢と言えます。 現代の挑戦——政治思想の文脈において、民主主義はどのように語られてきたのでしょうか。 意外なことに、民主主義が現在のように肯定的なものとして語られるようになるのは、ここ2世紀ほどです。18世紀ごろまでは、ほとんど例外なく否定的に捉えられていました。民主主義に対する懐疑の中心には、大衆への不信があります。素人が政治の担い手になれるのか、と。そうした大衆批判の代表はプラトンですが、彼にとって、師匠のソクラテスを死に追いやったアテナイの民主制は、「衆愚政治」にほかなりませんでした。政治は一般市民ではなくエリートや知識人に任せるべきだとの見方は、大きな影響を及ぼし、20世紀前半には、大衆を教え導く指導者に強い関心が向けられました。しかし、第2次世界大戦中のファシズムや全体主義の経験から、指導者中心の民主主義議論は勢いを失っていきます。代わって持ち上げられたのが、市民や市民社会でした。参加民主主義、熟義民主主義、闘技民主主義といったさまざまな民主主義の在り方が、市民を主体として論じられ、現代に至ります。ポピュリズムが台頭し、既存の政治体制への挑戦が突き付けられている近年は、一般市民が政治に参加するから悲惨な事態になるのだといった批判が、再び噴き上がっています。アメリカで、ポピュリスト的な指導者に呼応して、支持者から連邦議会議事堂を襲撃した事件は、その象徴でしょう。こうしたこともあり、これまでの土台も大きく揺らいでいます。「民主主義が望ましいのは当たり前」ではなくなり、「名でそれでも民主主義が望ましいと言えるのか」というそもそも論が、盛んに論じられるようになっています。 担い手になる——民主主義の土台が揺らぐ時代にあって、市民が政治の担い手となって行くために、大切なことは何でしょうか。 政治参加には、さまざまな形があります。一般的には「政治参加=選挙での投票」と想起されますが、選挙だけが参加のすべてではありません。NPIやNGO活動、ミニ・パブリックスのような議論の場、街頭デモなども、政治参加の重要な要素です。政治学者のキャロル・ベイトナンは、家庭や職場における意思決定への参加を重視しました。さらに身近な例では、住んでいる地域の町内会、子どもが通う学校のPTAなどへの参加も含まれます。身の回りで、多様な意思決定のプロセスに関わることで、市民としての関心を広げ、より多くのレベルの意思決定である政治についても、公正に判断できるようになると考えられています。かつての日本には、政治と個人を仲介する様々な中間団体が存在していました。地域のコミュニティーなどで、日常的に政治家との接点があり、陳情する回路も今よりもあったように思います。しかし、今では中間団体の多くは衰退し、その結果として、近年はSNSを通じて個人と政治家がダイレクトにつながっている。この傾向が、ポピュリズム政治の背景にもなっています。健全な政治参加の機会をとりもどしていく上でも、中間団体の再生は大切だと考えます。一人一人が政治に対してできることは、限られるかもしれません。自分が選挙に行っても何も変わらない、という学生もいます。私は、投票に行くことで、自分が一票を投じた政治家がどんな仕事をしているか、多少なりとも関心を持てるようになるのでは、と語ります。政治に対する自分の態度が、少しだけでも変わる。それが次の選挙にもつながっていきます。他方で、選挙によって統治者にお墨付きを与えるだけでは、人びとは一日限りの主権者にとどまってしまう。フランスの思想家ピエール・ロザンヴァリンは、権力者にお墨付きを与えるだけの「聖人の民主主義」ではなく、民主主義を実質的に人々の手に取り戻す、「行使の民主主義」に移行することが必要であると説きました。政治家がどのような仕事をしているかを知ることです。しかし現代は、日々流れてくる膨大な情報によって、大切なことすら埋もれがちです。昨今政治資金問題をはじめ、追及すべき点については忘れないことが重要です。政治を監視し続けるのが市民の役割だと考えます。確かに、政治家は強い影響力を行使します。しかし同時に、政治家の言動や振る舞いは、有権者の期待や振る舞いを少なからず反映します。ゆえに、政治家を問うとは、市民一人一人の態度を問うことでもあるのです。政治とは、政治家と支持者の相互作用によって成り立つものであることを、意識することが大切でしょう。 「水を差す存在」——今後の政治への展望を押しいて下さい。 民主主義を活性化し続けるためには、本来、意見や価値観をたがえる者同士の対立が不可欠です。野党(Opposition Party)の「Opposition」とは「対立」であり、批判するのが野党の仕事であるわけですが、近年は、活発な対立や批判は人々に歓迎されず、野党も魅力的に映っていない。批判がうまく機能しないこうした状況を、私は懸念しています。一方、多くの国で分断が深刻化する時代にあって、いたずらに対立をあおる議論も考えものです。今のアメリカ大統領選がまさにそうですが、対立する陣営の間にほとんど対話が成立せず、お互いに罵倒するばかりでは、やはり民主主義はもたないように思います。批判は大事ではあるのですが、同時に、相手が、民主主義の歴史で大切にされてきた態度でもあるのです。対立ではなく、いかに「つなぐ」ことができるのか。完璧にわかり合おうとして歩み寄り続けると、かえって疲弊し、摩擦や衝突が生じてしまうのは、例えば家族のような親密な関係でも同じでしょう。でもそこで、「僕の意見は少し違うけれど」と言いながら、相手の言い分を受け止め、無理に同意を強いない。味方によっては妥協とも思えるそんな寛容さが、多様化する時代には大切かもしれません。政治においても、合意か対立かという二分法には収まらない議論の在り方が考えられないか。それは例えば、法案の修正協議に置けるように、大枠には賛成しつつもゆすれないところでは「ちょっと待った」と水を差すような振る舞いのことです。こうした「水差し」は、支持者向けのパフォーマンスとしては弱いため、あまり評価されませんし、ニュースにもなりにくい。しかし、こうした「水を差す存在」こそが、民主主義を健全に駆動させるために、ますます重要になってくるのではないでしょうか。 やまもと・けい 1981年生まれ。立命館大学法学部准教授。名古屋大学大学院国際言語文化研究科単位取得退学。博士(学術)。岡山大学大学院教育学研究科専任講師などを経て現職。専門は現代政治理論、民主主義論。著書に『嫉妬論』(光文社新書)、『現代民主主義』(中公新書)、『アンタゴニズム』(共和国)、『不審者のデモクラシー』(岩波書店)、共編書に『〈つながり〉の現代思想』(明石書店)、『政治において正しいとはどういうことか』(勁草書房)、訳書に『左派ポピュリズムのために』(ジャンタル・ムフ著、明石書店、共訳)などがある。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」】政教分離2024.9.13
July 7, 2025
コメント(0)
-
60年前のパラリンピック
60年前のパラリンピックノンフィクション作家 稲泉 連 現代のパラ五輪での選手たちの活躍ぶりは、60年前に開催され亜、1964年の東京大会とは隔世の感があります。当時の様子については五輪の史料はたくさん残っていますが、パラ五輪については非常に少なく、調べていくうちにも、さまざまな疑問が浮かんできました。一つは、当時の障がい者スポーツはどのような位置付けだったのか。また、そこに出場した人は、どのような人たちだったのか。そもそも日本でパラ五輪を行うことが、当時の社会において、どのような意味を持っていたのか、などなどです。パラ五輪は元々、ストーク・マンデビル大会として、脊髄損傷による車いす使用者の大会として始まりました。スポーツによるリハビリ効果が期待され、彼らが出場する大会が出発点だったのです。それが60年の歳月を経て、現在のように変化していったわけです。イギリス人医師・グッドマンに師事しスポーツの効果を実感した中村裕医師が中心となり、東京五輪と同時期に東京パラ五輪を招致しました。当時の大会は2部制となっていて、第1部は脊髄損傷の車いすの人たちが集うストーク・マンデビル大会として、第2部で肢体不自由の人たちや視覚障がい者の大会が行われました。この両方を合わせてパラ五輪なのですが、そこにはスポーツによる「いい効果」を障がい者全般に広げたいという、中村さんたちの視点があったように思います。当時の日本では、障がい者が社会の中で自立するという視点は希薄でした。障がい者自身の、注目されることを嫌い、表に出ることを避けていた人が多かったようです。しかし、日本でパラ五輪が開催されることになり、状況に変化が生じていきます。開催国である日本からは、全ての種目に選手を出さなければならなかったのです。そこで、各地の療養所などから競技の経験もない人たちが集められました。中には、日本語のルールブックを大会の1週間前に読んだという競技もあったほどです。それでもパラ五輪は、出場した選手たちに大きな変化をもたらしました。目立つ変化は、開会式では恥ずかしがって下を向きがちだった日本人選手たちが、閉会式の頃になると、笑顔で前を向くようになったこと。参加して選手のだれもが、海外の選手たちの明るさに触れて変わっていったと証言しています。大会の中で自由に生活を楽しんでいる外国人選手たちと交流したことが、その後の自分たちの生き方を変えていくきっかけになったのです。 社会を変えていく転換点に外人選手の姿に触れ変わった 特に選手たち一人一人の証言は、すごく印象的です。彼らがどうしてけがを負ったのか、そこには当時の社会的な背景があります。戦争でケガを負った傷痍軍人、高度経済成長の中で無理な開発などでケガをした人、障害を負った経緯はさまざまですが、それが診療所の中でどのような思いで生活していたのか。彼らの個人史には、当時の日本社会の姿が反映されているのです。また、彼らは日本の障がい者スポーツや障がい者の自立に向け、その後、それぞれ役割を果たしていくのですが、その接点となる場所にパラ五輪があるのです。その意味でも、出場した選手たちの証言に引きつけられるのです。当時、障がいは個人の問題だと考えられていました。だから療養所で過ごすのが当たり前だと。しかし、そうではない生活をしている外国の選手たちを目にしたことで、実は社会に出ていけないバリアがあり、それは社会的な問題だと分かったのです。そんな「気づき」が、その後の障がい者政策を変えていくスタート地点のひとつにもなったので。もちろん、まだまだ課題は多く残されていますが、そこに当時のパラ五輪の意味はあるように思います。グッドマンが最初に表現した『失ったものを教えるのではなく、できることを教える』という言葉は、今でも障がい者スポーツの精神の原典です。走り幅跳びのように健常者以上の記録を出す選手も出てきたパラ五輪。そこには勝敗だけではない何かがあるように思うのです。 いなずみ・れん 1979年、東京都生まれ。ノンフィクション作家。2005年、『ぼくもいくさに征くのだけれど 竹内浩三の詩と死』で第39回大矢壮一ノンフィクション賞を最年少受賞。主な著書に『「本をつくる」という仕事』『日本人宇宙飛行士』『サーカスの子』などがある。 【文化Culture】聖教新聞2024.9.12
July 7, 2025
コメント(0)
-
「刹那主義」のすすめ
「刹那主義」のすすめ東京大学名誉教授 安藤 宏最近、あまり見かけなくなった風景だが、街の先頭には高い煙突があって、鉄のはしごを素人が上るとき、絶対にしてはいけないタブーがあるそうだ。上っている途中で下を振り返ること、がそれである。バットを逆さに立てて見下ろすような風景に思わず足がすくんでしまい、怖くてそれから先、一段も登れなくなってしまうというのである。ついでに言えば、まだどれくらいあるのか、てっぺんを見上げることもしない方がよいそうだ。あまりの距離に絶望して、足がすくんでしまうというのである。これはある意味では人生そのものの譬喩でもある。いたずらに来し方を振り返って感傷にふけったり、これから先、やらなければならないことを遠望したりするのは避けた方がよい。するべきことはただ一つ、ひたすら目の前にあるハシゴ段を、着実に、一つずつ登っていくだけなのである。実はこれは私自身のスランプ克服法でもある。やるべきことがあまりに多くて絶望的になったり、将来に対する漠然とした不安に襲われたときは、まず、目の前のできるだけ小さな課題に全力を集中することにしている。明日までに何をやらなければならないか、そのためには今日の夕方まで、あるいはお昼までに何をしなければならないか、時間をうんと短く区切って、目の前の小さな課題に没頭するのである。まず身近にある小さな充実感を大切にするということ。ひとまずやり切った、というささやかな達成感を大切にするということ。どうもそのあたりに人生の幸福のカギが潜んでいるらしい。私は、あえてこれを「刹那主義」と名づけている。目の前の刹那の喜びを享受できない人に、大いなる喜びを手にする資格はない。幸せの青い鳥は、実はごくごく身近なところにあるのである。 【すなどけい】公明新聞2024.9.11
July 6, 2025
コメント(0)
-
「ドイツ服」の落とし穴
「ドイツ服」の落とし穴このことに司馬さんも気づいていたはずで、「この国のかたち」に「ドイツへの傾斜」という章があります。 「日本は、周知のように、十九世紀もなかばすぎてから、異質なヨーロッパ文明を受容した。それも植民地化によるものではなく、みずからの意志によってそのようにした」(三、50) それが他の国々とは違うと司馬さんは指摘します。植民地になりたくないからヨーロッパ文明を受容したのであり、なかでもいちばん軍事的に強い国家の法制度を入れたということになります。 「明治維新をおこして四年目(一九八一年)に、プロセイン軍がフランス軍を破ったことが大きい。/在欧中の日本の武官は、目の前で鼎の軽重を見てしまった。/彼らはドイツ参謀部の作戦能力の卓越性と、部隊の運動の的確さを見、仏独の対比もした。その上、プロセインはこの勝利を基礎にして、連邦を解消してドイツ帝国を作った。ほんの数年間、明治維新をおこした日本人にとって、強い感情移入をもったということはいうまでもない」(同前) 大日本帝国憲法についても同様です。当時のドイツはヨーロッパでは後進的な国で、市民社会がまだできておらず、君主の権力が非常に強いものでした。それが当時の指導者・伊藤博文たちは、日本の国情によく似合っているようにいるように思えたのです。ヨーロッパという名の憲法国家のブティック(洋服屋さん)に日本人が入ってみたようなものです。どの服が似合うだろうかと思ったら、その当時、ドイツという服を着ているのがいちばん華々しく、自分の体にも合いそうでした。ちょうどいいと、試着室でプロセイン・ドイツの服を着てみたところ、これがなかなかピッタリでした。天皇や政府と言った頭や上半身の大きな当時の日本の体つきに合っていたのです。指導者の中には大隈重信や学者の福沢諭吉のように「イギリスの服の方がいい」と、言い張った人もいました。しかし、伊藤博文たちは「だめだ」と言って、大隈を政府から追いだし、結局、ドイツ服を買って帰りました。そして、天皇の国家がドイツ服を着て大日本帝国を名乗ったのです。ところが、このドイツ服には落とし穴がありました。この服に合わせた軍隊ブーツ(軍靴)が、なんと一度はいたら死ぬまで踊り続ける「赤い靴」だったのです。日本は軍事国家になって踊り続け、右足の陸軍、左足の海軍という足を切り落とされるまで止まらなかったという、恐ろしい結果になった——というのが、昭和に至るこの国の歴史です。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本の歴史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 6, 2025
コメント(0)
-
多様性を失っていった日本
多様性を失っていった日本 明治国家はその草創期には陸軍はフランスに、海軍はイギリスに学ぶという多様性がありました。しかし軍部も、そして国家制度自体もドイツのスタイルを導入してつくり上げられていきます。最も顕著なのが参謀本部です。ドイツはときに、国家が軍隊を持っているのではなく、軍隊が国家を持っていると言われるほど、軍隊が国家を動かしているととらえられていました。それをわざわざまねたのですから、軍隊が国家を左右して破綻に至ったドイツと同じ運命をたどるのは自明とも言えます。私は、明治一四年の政変のころ、日本が国家モデルの目標を急速にプロセイン・ドイツへと移した時期に、悪魔の下となる菌が植え付けられたと考えています。明治一四年の政変とは、一八八一年にイギリス流の国会を開設し、憲法制定を急いだ大隈重信らを、対立する伊藤博文らが追放した事件です。大隈はイギリスをモデルにした、国会が内閣総理大臣を出したりする、国会中心の政府を作るという考え方でしたが、伊藤博文はいちいち国会に諮っていては急速な近代化もできないし、天皇の権力、ひいては藩閥の権力も弱くなってしまうので、その声を急速に国力を強めていたポロセイン・ドイツの帝権と、それを支える軍や役人が国会の議決成して、国会の意見を参考にするだけで国政を行い得るというプロセイン・ドイツ型の国家をつくりあげていきました。結局、この一四年の政変の後に、伊藤のプロセイン型が選ばれることになるのですが、近代日本は、その後幸せな潜伏期をしばらく過ごすものの、日露戦争の戦勝がもたらした「傲慢」という名の疲れから激しく病を発症してしまった——というのが、日本という国を診察したときの、私の所見です。 【「司馬遼太郎」で学ぶ日本史 歴史のパターンが見えてくる】磯田道史/NHK出版新書
July 5, 2025
コメント(0)
全58件 (58件中 1-50件目)