2025年09月の記事
全58件 (58件中 1-50件目)
-
能登で生きること㊦
能登で生きること㊦フォトジャーナリスト 渋谷 敦志暮らしを支える基層一つの縁が次の縁をよび1月の20日から2月2日まで金沢市のギャラリーで写真展「能登を、結ぶ」を開催した。能登出身者や在住の方々が来場し、地震の震災体験、胸の内にあった言葉や思いを語ってくれた。自らの仕事が試される瞬間であり、背筋が伸びるような緊張感もあったが、「記録に残して切れて、ありがとう」という言葉に、「次は能登で」と語る自分がいた。それほどに能登に思いを寄せた一年だったと感じる。わずかな手掛かりと直観を頼りに訪れた能登だったが、行く先々で出会った人々は過酷な環境の中でも僕を快く受け入れてくれた。一つの縁が次の縁をよび、出会いは不思議に広がった。「能登の豊かさを守ることと日本の存在意義を守ることはつながっているんです」そう熱く語ったのは、珠洲市で炭焼き業を営む大野長一郎さんだ。自身で4基あった窯は全て崩れた。2年、23年に続き3度目の被災だった。「向き合えば向き合うほど遠のいていく」と空しさをふと吐露したが、「やめる気はない」と前を向いた。能登の里山佐藤見さんの象徴ともいえる「白米千枚田」には自身で無数の亀裂が入った。千もの田んぼを復旧するのに何年かかるか分からない。それでも、棚田を管理する「白米千枚田愛耕会」の堂下真紀子さんの思いはぶれることがない。「お金を出して業者に修復してもらうんじゃなくて、耕す人の思い、一日一日の営みが復興につながっていく過程が大事だと思うんです」昨年は120枚の田んぼを修復し、田植えと稲刈りには多くのボランティアも訪れた。農業以外にも、物づくりや祭りのことを考えている人に多くであった。一人一人が、自分の置かれた場所で、自分にとって大切なことに取り組み、ふるさとを絶対に復活させるんだと力を合わせていた。 復興へつなぐ耕す思いその強さはどこか優しく ほころびから見えた可能性震災は、過疎や高齢化、人手不足と言って、能登が以前から抱える問題をあらわにした。だが、そんなほころびから僕の目に見えてきたのは、その地域の限界と裏腹にある、まだ力を出し切っていない可能性だった。その土地に深く根付く生業や、いざという時に命を守り合う人のつながり、長年涵養されてきた自然と調和する暮らしなど、能登がもともと持つ力がそこにはたくさんあった。前途は確かに多難だ。でも、こんな時だからこそ、能登の暮らしを下支えしてきた基層の部分に目を向けようと思った。「能登はやさしさ土までも」と言われる。しかし、それは、決してやさしいとは言えないのとの厳しい環境を生き抜くなか、生まれたものだったのではないだろうか。人々が助け合い、支え合う以外に生きようはなかった。人間の意のままにならない自然は行くたびも人々に苦難をもたらしたが、それは同時に、人々の強さとやさしさを育み、恵みをもたらした。それが能登で生きることを根っこで支えている。だから、能登の人は強い。そして、その強さはどこかやさしい。1年間、通い続ける中で見えてきたことだ。これからも僕の能登通いは続く。そして、この土地を、悲しい場所としてではなく、人々が力を合わせて守った場所として、後世に伝えていければと思っている。 しぶや・あつし 1975年、大阪府生まれ。大学卒業後、フォトジャーナリストとして街道。99年、MSFフォトジャーナリスト賞を受賞。アフリカやアジア、南米で紛争や災害、貧困問題の取材を続ける。著書に『まなざしが出会う場所へ』『回帰するブラジル』『僕らが学校へ行く理由』などがある。 【文化・社会】聖教新聞2025.2.4
September 30, 2025
コメント(0)
-
受容には心理的・法的課題も
受容には心理的・法的課題も科学文明論研究者 橳島 次郎人工知能の人間化前回、生体工学技術を使って人型ロボットを生きた皮膚で覆い、外観だけでなく発汗や傷の修復などの生体機能を持たせて人間に近づける研究を紹介した。生成AIの登場で、ロボットに搭載される人工知能も人間化が進む。人間と同じような受け答えをし、人間が書くような文章をかき、絵まで創作できるようになった。そんななか、一昨年1月、国際科学し「ネイチャー」が、生成AIを論文の共著者にすることが認められるかが議論されているとの論説を出した。生成AIは、下調べや論文の下書きに使われたりするだけでなく、研究の本体をなすデータの作成にも使われる。「ネイチャー」の生地が紹介したある論文は、生成AIに米国医師資格試験を受けさせた成績について評価した内容で、使われた人工知能プログラムを研究に貢献した共著者に入れているという。今後、人工知能によってデータを解析し、新たな研究の方向や論点などを得ることもできるようになり、貢献度が一層高まると予想される。昨年のノーベル化学賞のタンパク質のこうぉう予測を行う人工知能プログラムの発明に与えられたのは、それを表す象徴的出来事だ。この人工知能プログラムは、生命現象の研究を進めるのに大きく寄与している。さらにそんな人工知能を全会とりあげた、人間に近づいたロボットは気持ち悪がられ、受け入れられないのではないのではないかという懸念だ。この現象は「不気味の谷」心理現象と呼ばれる。ロボットの外観を人間に近づけていくと、不気味だと感じ、受け入れ度がグッと低くなる谷底が生まれるというのだ。人間化を追求してこの谷にはまり込んでしまったら、ロボット技術と関連産業の停滞を招く恐れもある。人間化を進めたロボット・人工知能に、どういう法的地位を与えるかも問題になる。人間に近づくと単なる物ではなくなるということだ。人間と同等の高度の人工知能を持つロボットを故意に損傷させたら、器物破損ではなく傷害罪に問うべきだろうか。動物愛護法には動物殺傷罪がある。ロボット愛護法が必要になる日が来るだろう。 【先端技術は何をもたらすか—36—】聖教新聞2025.2.4
September 30, 2025
コメント(0)
-
戸田先生「方便品寿量品講義」(1958年2月)㊤
戸田先生「方便品寿量品講義」(1958年2月)㊤われわれは絶対に化学を否定するわけではありません。いいものだけれど、科学が発達すると、ただちに人類の幸福を増す、という考え方を否定するのであります。(中略)われわれの幸福というものは、ほんとうの生命の哲学がはっきりしてこそ、初めて得られるのであります。◇われわれには、みな執着があります。(中略)執着が無かったら、この世の中はバラバラになってしまいます。政治も経済も教育も文化もなくなります。学校の先生が教育に執着がないから、勤務にいかぬとしたら大変でしょう。執着を執着として明らかにみればいいのであります。その執着を明らかに見せてくれるのが御本尊であります。みんなに執着があるから、味のある人生が送れるのであり、大いに商売に折伏に執着しわれわれの信心で、その執着が自分を苦しめないようにし、自分の執着を使い切って、幸福にならなければならないのであります。◇(法華経の方便品で説かれる)「諸の著を離れしむ」とは、先に述べたごとく、文底の仏法では「緒の著を明らめしむ」と読むべきであります。釈迦仏法においては、いろいろな執着は発展を妨げるものとして、阿羅漢や縁覚の境涯になるのに執着を断ち切る修行をしたのであります。しかし、末法における日蓮大聖人の仏法では、意味がちがってまいります。末法今時においては、執着を離れてはいけないのであります。日蓮大聖人は、御義口伝の薬王品の項に「離の字は明(あきらむ)と読むなり」とおおせられているように、執着を離れさせるのではなくて、執着を明らめて使いきる境涯になればよいのであります。(中略)「この執着をするには、こういう理由があるのだ」と、明らかにみていけば、執着がいくら強くても、執着を捨てる場合にしても、はっきりしてまいります。ただ、なんでも執着を離れるという教えは、末法の仏法にはないのであります。(『戸田城聖全集』第5巻) 教学の研鑽を通し 信心の背骨をつくる先師の殉難の地で法華経の精髄を講義 1951年5月3日に第2代会長に就任した戸田先生が、青年部の育成とともに、重点的に取り組んだものは何か——。教学の研鑽を通して、学会員一人一人の〝信心の背骨〟をつくりあげることである。その最初の布石として、会長就任式の場で発表されたのが、御書講義などを担当する「講義部」の設置であった。9月には名称が「経学部」に改められ、体制も強化された。学会員のだれもが、日蓮大聖人のブ報の精髄を学んで信心を深めていけるように、研鑽の過程が5段階に整備されたのだ。特筆すべきは、講義の大半を戸田先生が自ら担当したことである。会合や座談会への出席に加え、「大白蓮華」の原稿の執筆もある中で、多いときには週に3回、講義に全力を注いだ。このうち、新入会員を対象に行われたのが、法華経の方便品と寿量品の講義だった。「一級講義」と呼ばれたもので、講義が一通り終了するたびに新たな受講者を迎える形で、繰り返し続けられた。当初、東京・西神田の学会本部が会場となっていたが、受講者が急増するなかで、1953年9月からは、千数百人を収容できる豊島公会堂(当時、東京・池袋)で開催されるようになり、仙台や大阪でも行われた。講義の様子について、池田先生は小説『人間革命』第7巻でこう記している。「(方便品の講義は)一回、一時間半を要したのであったが、受講者にとっては、一瞬のうちにすぎたと言ってよい。聴き終わったあと、彼らの心身は、さわやかで、軽かった。朝夕、読誦する経文に、にわかに力と情熱が加わったことは、言うまでもない」「受講者は、たぐいまれな温かい彼のユーモアの日常の労苦を、一瞬、忘れ、思わず仏法の極理に、直々に対面した思いをするのであった」戸田先生は、「一級講義」をはじめ、200回以上にわたって豊島公会堂に足を運んだ。当時、豊島公会堂から歩いて数分の処に、戦前は思想犯などを収監する東京拘置所が置かれ、戦後は〝巣鴨プリズン〟と呼ばれた施設が残っていた。戦時中、牧口先生と戸田先生が獄中闘争を貫いた場所である。牧口先生が1944年11月18日に生涯を閉じた〝殉難の地〟に思いを馳せながら、戸田先生は、豊島公会堂出の毎回の講義を通して、学会員の心に希望を灯し、広布前進へのうねりを巻き起こしていったのだ。 戸田先生が、新入会員のために6年以上にわたって繰り返し行った、方便品と寿量品の講義——。その大要をまとめた書籍が発刊されたのは、戸田先生が58歳の誕生日を迎えた1958年2月11日。逝去の2カ月前に当たる時期でもあった。後に池田先生が、「たんなる理論的説明ではなく、一人一人を納得させ、それをバネにして苦悩をはね返させ、広々とした境涯を教えたい、人生の大いなる道を開かせてあげたい——こういう慈愛と智慧の名講義であった」と振り返っていた通り、それはまさに、日蓮大聖人の仏法の幼帝を分かりやすい言葉で語りながら、一人一人が苦悩を乗り越える力を奮い立たせる源泉となっていたのである。講義の中で「執着」について論じた箇所も、戸田先生がそうした甚深の思いを込めて、人間が毎日の生活を送る中で絶えず湧き起ってくる煩悩や執着に対し、どう向き合うべきかを指導したものにほかならない。法華経の方便品に、「令離諸著」という言葉がある。〝釈尊は無数の方便を用いながら、不幸の原因となる諸々の執着から離れるように、衆生を教え導いてきた〟と説かれる一節にある言葉だ。例えば、初期仏典の「ダンママダ」には次の教えがある。「一つの木を伐るのではなくて、(煩悩の)林を伐れ。危険は林から生じる。(煩悩の)林とその下生えとを切って、林(=煩悩)から逃れたものとなれ」このような教えに象徴されるように、初期仏典においては、煩悩や執着から離れる道を説く言葉が多くみられた。しかし、末法に於いて日蓮大聖人が説いた仏法の肝心は、煩悩や執着を断ずることにあるのではないと、戸田先生は訴えたのだ。法華経の薬王品にある「離一切苦」の言葉に対し、大聖人が「『離』の字をば『明らむ』と読むなり」(新1076・全773)と教示していたことを踏まえ、方便品の(令離諸著)の言葉についても、〝諸の著を離れしむ〟ではなく、〝緒の著を明しめむ〟と読むべきであると、強調したのである。(㊦に続く) 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史を創るはこの船たしか—第27回— 聖教新聞社2025.2.3
September 29, 2025
コメント(0)
-
伝えたい自然といのちの尊さ
伝えたい自然といのちの尊さ小説家 塩野 米松「おはなし 絵本」シリーズを刊行春、山の麓の水たまりにはぎっしりとしたカエルの卵が産み付けられています。しばらくたてば、オタマジャクシがいっぱい。川岸にふきのとうをとりに行って浅瀬をのぞき込めばメダカたちが群れをなして泳いでいます。ベランダに置かれたプランター。春に咲いたチューリップの球根は掘り出し、そのままにしてあったものです。夏の雨上がりの後に見たら、緑色の若い芽が点々と。オタマジャクシやメダカは水から生まれてくるのかしら。植物は土から。子どもの頃はそう思っていました。後になって水だまりに卵を産んだのはお母さんガエル。メダカは水草に産み付けられた卵から、植物の種は風に乗って飛んできたのだと知りました。それでも、じゃあお母さんガエルはどこで生まれたのかな。風に乗ってきたタネにはどんな草から来たのかしら。たくさんの本を読み、少しずつ知識を得たつもりでしたが、いのちってどこから生まれてくるのか不思議のままでした。ずいぶん前に出会った長良川の職猟師さんは「魚は川から湧いてくるんじゃ、親父もじいさんも言うておった」と。一昨年大阪の阪南市の港で会った老漁師は「魚は梅雨の頃にアマモの林から湧いてくる」と自信たっぷりに教えてくれました。皆さん、魚を捕って生きた人達です。魚のことなら何でも知っている名人達です。彼らが体験してきた実感なのです。私は思いました。地球に最初の生命が出現したとき、確かにいのちは湧いて出てきたに違いないと。宇宙から隕石に乗ってきたかも、あったかい海の中で奇跡が起きたのかも。いずれにしろずっと遠い昔に湧いで出て、今に至るまでつながって、こんなに多くの命があふれているのです。 生命誕生のふしぎや驚きを描く絵本は心に通ずる秘密の通路 この驚きを子どもたちに伝えたいと思って「塩野米松のいのち わくわく おはなし絵本」のシリーズを考えました。絵本は、驚き、感ずるもの。絵本は心に通ずる秘密の通路です。シリーズの構成、文は主に私が担当しました。昨年10月に出した『ワニくんがやってきた!』(飯野和好・絵・翻案)は、まこと君の通う子ども園にワニの子が入園してきました。縁はいのちのお祭りみたいなところ。さあ何が起きたのでしょうか?11月に刊行したのは『くじらのいるこみち』(はたこうしろう・絵)。郊外の住宅街に一カ所だけ土の道がありました。ほんのわずかな道ですが、雨の後には空を写す水溜りができます。引っ越ししてきた女の子はそこで驚きを!残りの3冊の刊行はこれから。今年3月に『わく』(村上康成・絵)。このシリーズの核心になる本です。いのちが海や山や空から、心からわき出してきます。その後に、都会の小さな公園が舞台の『いっぽんのき』(松木春野・絵)。山姥の12人の娘が世界中からお母さんのところに集まって森の生きものたちと大宴会。その日は12月12日。『やまんばの12人のむすめ』(小沢さかえ・絵)と続きます。ご期待を。 (しおの・よねまつ) 【文化】公明新聞2025.2.2
September 29, 2025
コメント(0)
-
多様な人を「橋渡し」する
多様な人を「橋渡し」するつながりが幸福をつくるインタビュー 米ハーバード大学公衆衛生大学院 イチロー・カワチ教授社会関係資本——カワチ教授の専門である「社会疫学」は、社会全体の健康をどう守るかを研究する学問です。そこでは、生活習慣といった個人の選択だけでなく、人々の健康が左右されることが説明されます。その視点から、新型コロナウイルス禍を経験した現代社会を、どのように捉えておられますか。 各国の新型コロナウイルスの感染者数や死者数には、大きな格差がありました。例えば、アメリカ合衆国の死者数は訳120万人であり、他国に比べても非常に多いです。アメリカの状況の要因は、①所得格差大きいこと、②ソーシャルキャピタル(社会関係資本)が不足していること、にあると考えらえます。1点目に、所得格差は健康にとって有害です。格差が拡大すると、貧困層には、社会から取り残されたという「相対的な剥奪感」が生じます。こうした感情は、希望を奪い、いかりや不満、絶望感を生みます。相対的な剥奪感によって欠乏状態の真理に陥ると「現在バイアス」が増大します。これは、未来について計画的に考えるよりも、目先の利益を湯煎する傾向です。それによって、喫煙や間食、過剰な飲酒などの生活習慣に陥りがちになり、健康が損なわれます。さらに重要なのは、格差は、貧しい人々だけでなく、所得が高い人も含めた社会全体の健康状態に悪影響を与える可能性があることです。格差が大きいと、社会インフラへの投資が低下し、心理的な悪影響も生じ、その〝ツケ〟を社会の全員で払わなければならなくなります。例えば、コロナ禍の中においてアメリカは、まず貧困層が多いエリアで感染が広がりました。アメリカのような格差社会では、貧困素状態にある人々は、適切な医療サービスを受けることも難しいのです。すると、感染者が増え続け、結局は地域全体のリスクが高まり、富裕層にも感染が広がりました、2点目にあげたソーシャルキャピタルは、人とのつながりを通して得られる至言のことです。「絆」「お互いさま」「情けは人のためならず」等々、日本語にはソーシャルキャピタルのイメージを表する言葉が多くあります。日本には、近所同士で助け合う土壌があったのだと思います。そうした地域のつながりや信頼感を基に、人を思いやる協調的な自信と地域全体の財産になる——これがソーシャルキャピタルです。ソーシャルキャピタルが高い地域では、密なネットワークと通じて、健康によい情報がより早く伝達され、助け合いや精神的なサポートなどの資源を得ることができ、健康が促進されます。例えば、コロナ禍の当初、日本では法的な強制力を使わずとも、多くの人が自発的にマスクをつけたり、人の多い所へ外出を避けたりする行動をとりました。一方で、コロナ禍のなかでは、外出や人との交流が減り、世界的にソーシャルキャピタルが大きく低下したと考えられます。今では日本でも、かつてのような地域のつながりは減り、経済格差も広がっており、健康への影響が懸念されます。 マシュマロ実験——格差問題を解決していくための一つの要素として、カワチ教授は「教育」を挙げています。人々の健康のためには、いつ頃に、どんな教育の取り組みが求められるでしょうか。 アメリカで、幼少期に充実した教育を受けた子どもたちと健康の関係を、十数年にわたって追跡調査した研究があります。その結果が、早期に教育を受けると、大人になってからも喫煙率や肥満率が低く、過度の飲酒などの習慣も少なく、収入も安定し、健康水準が高いことが分かりました。特に、3歳から4歳くらいまでの早期の教育に、効果があります。教育といっても、文字や語学を教えたり、国旗や地図を覚えたりといって、知識を増やす勉強のことではありません。大切なのは、子どもの自己抑制(セルフコントロール)の能力や実行力などに関わる教育です。心理学者のウォルター・ミシェルが、4歳児を対象に行った「マシュマロ・テスト」という実験があります。子どもの目の前にマシュマロを置き、「スッタフが戻ってくるまで食べるのを我慢できたら、ご褒美としてもう一つあげる」と伝えます。と伝えます。そうして子供を一人で部屋に残し、何分我慢できたかを観察しました。結果、実験に参加した子どもの25%が、2分以内にマシュマロを食べてしまいました。一方で、10分以上待てた子どもも25%ほどいました。子供たちが16~18歳になった時に再度調査をすると、我慢強かった子どもたちは、成長してからも誘惑に負けず、自己抑制力が高いことが分かりました。誘惑に負けない力は、健康的な生活にとって重要です。タバコやドラッグなど、健康を害するものに手を出さなくなるからです。早期教育で、自己抑制力や我慢強さなどが身に付けば、将来にわたって、健康的な生活を贈れます。そのために必要な教育は、知識を身に付ける勉強ではなく、よく食べ、よく遊び、良く寝ることなど、人間として生きる上で基本的なことです。例えば、家族で一緒に食事をして「いただきます」「ごちそうさまでした」ということも、大切な教育の一つです。お風呂に入り、歯を磨き、就寝前には絵本の読み聞かせをする。幼稚園や保育園に通っていれば、先生のいうことを聞いたり、他の子どもたちと一緒に遊んだりするでしょう。そうした他者との関りが、早期の教育的取り組みとして大切です。 一人一人の〝小さな努力〟が社会全体の健康を生み出す 結束と橋渡し——カワチ教授は、健康には「人間関係」が欠かせないと指摘されています。人とのつながりは、どのように健康に寄与するのでしょうか。 これまでの研究で、人とのつながりが強いと健康になり、人間関係が希薄だと健康が悪化することが分かっています。人間関係が健康を促進するメカニズムを3点、説明します。ます、①人間関係がその人の行動を決める側面があります。例えば、結婚すると、男女ともに野菜を食べる量が増えたという調査結果があります。友人や家族、同僚、近所の人など、自分がつきあう人や集団によって、知らない間に自分の行動が影響を受け、健康にも影響するのです。次に、②人と関わること自体が健康につながります。人と交わることで保たれる運動能力や認知機能があり、それらは筋肉と同じように、使うことで維持・強化されます。そして、③つながりから生まれる支援の力があります。人間関係をつうじて、物理的な手伝いなどを含む「モノ」や「健康にとって有益な「情報」、哀しいときに慰めてくれるといった「感情的なサポート」などを得ることができ、それらが健康に寄与します。これらは個人同士の関係が元になっていますが、さらに話を広げ、地域やコミュニティーなど集団全体のつながりや結束力に目を向けると、先に述べた「ソーシャルキャピタル」になります。 ——コロナ禍において、日本ではマスクを着用しない人への過度の非難を浴びせられると、「自粛警察」と呼ばれる過激な言動もありました。結束力としてのソーシャルキャピタルには、そうした負の側面もあるのでしょうか。 集団の結束力が強い社会では、マスク着用などの規範が広がりやすい半面、そうした規範に従わない人への強い反対が生じることがあります。当時、日本では新型コロナの感染者になった人のうわさが広がり、苛めの対象になったというニュースもありました。こうした結束の強い社会のダークサイト(影の側面)と向き合うために、ソーシャルキャピタルの二つのタイプについて考えたいと思います。まず、地域のつながりという意味で、私たちが普段から頼っているのは、「結束型(ポンディング)」のソーシャルキャピタルです。これは、同じ地域に住む家族や友人、近隣の人々とのコミュニティー野つながりによるものです。しかし、地域の中で困難な課題が生じた時、おなじコミュニティーに限定された結束型のソーシャルキャピタルだけでは、地域の課題を解決することが難しい場面が多くあります。そうしたときに求められるのが「橋渡し型(ブリッジング)」のソーシャルキャピタルです。これは、異なるコミュニティーが橋渡しを行って、資源のある地域から支援を提供することなどを指します。例えば社会には、品温艘、人種的マイノリティー(少数者)、移民、障がいがある人、高齢者など、ソーシャルキャピタルが不足しがちな脆弱僧があります。そこに橋渡しするようなネットワークが必要なのです。 宗教の役割——創価学会では毎月の座談会に、年齢や職業、人種といった差異を超えて、老若男女が参加しています。またコロナ禍の中で、対面御会合が開けなかった時期には、若い世代が中心となって、高齢の方々にもオンライン会議のやり方を伝えるなどして、会員同士がつながることができるように工夫しました。 素晴らしいですよね。それが、まさに橋渡し型のソーシャルキャピタルです。留意すべきは、社会において、ソーシャルキャピタルにも格差があるということです。社会的なマイノリティーなど、ソーシャルキャピタルにアクセスできない集団も多くいます。そうした人たちを、どうやって社会に包容していくか。置き去りにせず、つながっていくために、橋渡しをすることが求められます。そうしたソーシャルキャピタルを醸成するものの一つとして、宗教団体が発揮する役割もあります。アメリカでは、かつてはキリスト教の境界が、そうした役割を果たしていましたが、今では習慣的に教会に通う人は減ってきています。また、ある調査では、白人の75%が「友人の全員が自分と同じ白人」と答えており、人種を越えた交流が少ないことが浮き彫りになりました。一方で、アメリカの創価学会では、あらゆる人種の会員が一緒に活動していると聞きました。異なる人種の間を橋渡しするソーシャルキャピタルを、対面の活動によって築いているというのは、すごいことだと思います。 ——創価学会には、自分の生命や境涯を変革し、人間として成長する「人間革命」という思想と実践があります。また仏法では、いかなる物事も、たった一つでは成立せず、すべては互いに依存し、影響しあって成り立つこと「縁起」と説きます。環境が古人の健康を左右する一方で、一人一人の意識や行動の変革も、社会や環境に影響を与えるのではないでしょうか。 その通りです。社会疫学の視点からも、一人一人が小さな努力を重ねることで、社会全体が健康になるということが言えます。地域などの集団全員の健康リスク少しでも下げる取り組みを「ポピュレーションアプローチ」と呼びます。市民への啓発活動や、健康的な生活習慣の促進、法制度の整備などを通して、そこに住む人々が健康のために少しの努力をすることで、社会全体の健康状態が良い方向に動きます。そうした取り組みによって、やがて国家規模で医療費が下がることも分かっています。今、欧米では、健康や幸福を表す「ウェルビーイング」という概念が注目されています。この内容を見て、私が懸念しているのは、西洋の個人主義的な視点が強調されている点です。一部では友人と過ごす時間などの話も出てきます。多くは瞑想をした方がよいなど、個人的なことがらについて語られています。その点では、すべてが相互に関係しあうという仏教の縁起の考え方は、非常に優れていると思います。自分自身が良い行動をすれば、きっと相手も良い行動をとってくれるはず——そうした他者や社会への信頼感があれば、人は小さな努力を起こせるはずです。自分だけの健康や、一人だけの幸福といったものはないのだと思います。一人一人の小さな良い行動によって、自分も、地域も、そして社会さえも健康になっていくのです。創価学会の皆さんが世界各地で実践していることは、自分自身や周囲の人、さらに地域社会の健康にとって、良い効果をもたらしていると考えます。 Ichiiro Kawachi アメリカ・ハーバード大学公衆衛生大学院の社会行動科学学部長・教授。1961年、東京生まれ。12歳でニュージーランドに移住。オタゴ大学医学部を卒業し、同大学で博士号を取得。内海として同国で診察に従事。92年からハーバード大学公衆衛生大学院の教壇に立ち、2008年より現職。著書に『社会免疫学』(大修館書店)、『いのちの格差は止められるのか』(小学館新書)など。米国医学研究所(IOM)、米国科学アカデミー(NAS)のメンバー。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」】聖教新聞2025.1.31
September 28, 2025
コメント(0)
-
伝統文化にデジタルを導入
伝統文化にデジタルを導入工程を省いて安価に伝統工芸や文化にデジタル技術を取り入れる試みが広がっている。背景には、担い手不測の解消や技術の継承、ファンの裾野を広げたい思いがある。伝統的工芸品産業振興協会(東京都港区)によると、伝統的工芸品の生産額と従業員数は1991年バブル経済崩壊後から減少傾向にあり、現在は下げ止まった状態だ。同協会産地支援部長の河井隆徳さんは市場縮小の背景を「生活様式の洋風化に加え、必要最小限のもので暮らす意識が広がった」とみる。若い世代が工芸品の使用体験に乏しいことも大きい。そのため工芸品の良さが分からず、購入意識も湧かない。デジタル化によって安価に制作でき、より広い世代にファン層が拡大することが期待される。河井さんは「デジタルを採用して安く売ることができ、間口が広がるのはいいこと。ただ、省いた高弟など、安価にできる理由を客にきちんと説明することが大事だ」と話す。今日、加賀と並び三大友禅の一つ、東京友禅を製作する「ユキヤ」(横話)。手描き友禅をデジタルで複製する「some-pri(ソメプリ)」を2019年に始めた。作家が原画を手書きし、スキャナーで取り込みポリエステル生地や木綿などインクジェットプリンターで染める。量産でき、証券に一枚ずつ染める場合の5~10分の1の価格にできる。「従来は『かわいいけど高価で買えない』という声が多かったが、ソメプリ導入で若い客が増えた」と大野深雪社長は手応えを感じている。図案はTシャツや靴、壁紙でも展開し、「デザインを気に入った友禅を知ってもらえる」(町田久美子取締役)機会にもなっている。 後継育成と技術継承ファンの裾野広げる一助にも 作法をAR(拡張現実)で確認南部鉄器のタヤマスタジオ(盛岡市)では、19年に発売を開始した、若手職人が手がける鉄瓶「あかいりんご」が、入手まで10か月待ちのヒット商品になった。代表の山田貴紘さんは、営業職を経て「現代の名工」の父・和康さんに師事。父が30年かけて習得した制作の全工程を3年目の若手にも経験させる。これまでは高弟の一部を数年かけて習得していたが、全工程を経験することで、自分がつくっているとの実感を得やすい。それが、一人一人のやりがいにもつながっているという。この育成法を可能にするのは、デザインの工夫と人工知能(AI)の活用だ。鉄器表面は凸凹が特徴だが、その型を作るには熟練の技が必要。そこで、「あかいりんご」では技術の差が出にくい滑らかな表面にした。さらに和康さんの思考法をAIに学習させ、学術的知見もひも付けてデータ化。作成中に欠陥などが出た際に、キーワードから解決策を学べる仕組みも取り入れている。「父の技術に、一つでも二つでも積み上げて発展させたい」と貴紘さん。茶の湯の作法をデジタル化したのは、ソニーコンピュータサイエンス研究所(CSL)の京都リサーチ(京都市)だ。数寄屋建築の茶室を研究室内に作り、天井に張り巡らせたセンサーで部屋のなかを写し、3次元の点の集まりで表示する。例えば、茶の先生の所作を記録し、AR(拡張現実)グラスを使ってさまざまな角度から繰り返し確認できれば、技能の習得に役立つ。「3次元アーカイブで、俗人的な技能や芸術を未来に残すことができる」と麿本純一リサーチディレクター。茶菓子のデザインを人間とAIで共作するなど、茶の湯文化を進展させる試みも。麿本さんは「テクノロジーは効率化だけでなく人間の暮らしを豊かにすることもできる」と期待を込める。 【文化Culture】聖教新聞2025.1.30
September 28, 2025
コメント(0)
-
古代の城と明治の砲台が共存
古代の城と明治の砲台が共存城郭ライター 萩原さちこ金田城今から約1350年前、大和朝廷が九州北部を中心に造った古代山城の一つです。633年、白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗した日本(倭)は、同盟を結んでいた百済の貴族に指導を受けて国防のため古代山城を築いたとされます。『日本書紀』によれば、九州と朝鮮半島の間にある津島(長崎県)に金田常が築かれたのは667年のこと。防衛目的の防人(兵士)が置かれ、通信手段の狼煙台が設置されたと記されています。古代山城の特徴は、土塁や石塁が谷ごとに包み込むように山の峰や斜面に巡らされていることです。北九州の古代山城では土塁が大半を占めますが、金田常の城壁はほぼ石塁。なんと、現状で総延長2.3㌔の石塁が確認されています。その壮大さもさることながら、残存ども古代山城の中でトップクラス。浅茅湾南岸の山城に築かれており、穏やかな黒瀬湾、浅茅湾と石塁との共演もたまりません。四つ見つかっている城戸(城門跡)も見どころです。一ノ城戸や三ノ城戸では、ほぼ垂直に剃り達石塁の底部に排水溝(水門)が残り、現在でも機能しています。全国でも類を見ない特筆点は、古代山城と明治時代の砲台の共存です。山頂付近に近づくと、突如として砲台跡や弾薬庫跡など近代の片鱗が現れます。日露戦争時、山頂吹き因だけが改変され「城山砲台」として再利用されたのです。浅茅湾の占拠を狙うロシアに対し、明治政府は湾内に幾つも砲台を造り備えました。浅茅湾に突き出す金田城も、絶対に押さえておきたい重要地だったのです。1200年後にべつの目的で再利用されるとは、さすがは国境の島・対馬とうならされます。登城道が歩きやすいのも、明治時代に陸軍が整備した軍道だったからです。緩斜面が続く計画的な道筋、馬車が通るための見事な一定幅。岩盤を大胆に削り込んだ、強引ともいえるほどの完璧な道筋です。切石を敷き詰めた排水路も設けられ、対策も完璧。陸軍の緻密な仕事ぶりに、当時の情勢や技術力、価値観をうかがい知ることができます。 【日本全国お城巡り】公明新聞2025.1.30
September 27, 2025
コメント(0)
-
札幌農学校とウィリアム・ペン・ブルックス
札幌農学校とウィリアム・ペン・ブルックス日本大学工学部准教授 赤石 恵一クラーク博士の後継者として数多くの人材を指導昨年、自著『札幌農学校校長ウィリアム・ペン・ブルックス:生涯とその時代』(北海道大学出版会)を上梓した。ブルックス(1851~1938)は1877(明治10)年に来日した御雇外国人で、「Boys, be ambitious!」の訓示で有名なクラーク博士の教え子である。クラークは当時、マサチューセッツ農科大学という母国アメリカの一振興大学の学長でありながら、学校設立のため開拓使に招かれて札幌に渡った。学校は「Sapporo Agricultural College(札幌農学校)」と名付けられて、クラークがその「President(教頭)」となった。ブルックスはマサチューセッツ農科大学5期生の首席である。クラークに見込まれて札幌農学校教授となり、専門のほか植物学、英語、討論や演説も担当した。クラーク離札後は付属農園の長を引き継いで、後に教頭心得も務めた。北海道農業の近代化にも尽力している。その偉功によりにより帰国時には勲四等旭日小綬章を受勲した。著書のタイトルは当初、まったく違うものであった。「札幌農学校教授」という肩書は後から加えた。ブルックスの地名度は高いとは言い難い。その功績は大きかったが、クラークほどの劇的さはなかった。それは無理からぬことであった。クラークは来札時、既に50才、母国ではまだ稀有だった学術博士(Ph.D.)であり、先述のごとく大学長であったほか、南北戦争で活躍した大佐でもあった。それに比し、ブルックスは大学を出て間もない一青年でしかない。来日25才。最年長の学生との年齢差は4年ほどしかなかった。しかし、およそ8カ月半しか札幌にいなかったクラークスと異なり、ブルックスは1年余りの長きにわたり在職した。その間、内村鑑三、新渡戸稲造といった日本近代を彩る綺羅星のごとき学生を指導、大山巌、パークス、バチェラー、モースなど、都市化する札幌を訪れる政治家や外交官、宣教師や御雇外国人らと数多く交わる機会を得た。日本はブルックスにとり成長と立身の地でもあったのである。帰国後、ブルックスは母校マサチューセッツ農科大学の教授となり、ドイツ留学の上Ph.D.を取得して学長代理を務めるなど恩師クラークと同じキャリアをたどった。札幌の教え子はその後も折に触れ文通し、その訪問を常に歓迎して大学で公演させるなどした。札幌を去って遥かのちの919(大正8)年、マサチューセッツ農科大学勤務30年祝賀会の席上で札幌時代をこう振り返っている。「日本における個人的な関係や機関から得られた支持という観点から考えれば、私は何一つ不自由することがありませんでした。望めばすべて望みどおりになりました。しかし、勉学を共にした学生、特に日本における学生を思うとき、私は最も幸運に恵まれていたと感じます。皆、入念に選抜され一途で、どこをどう見ても模範そのものでした。彼らの成功は、私などの力によるものというよりはむしろ彼らの資質によるものなのです」札幌農学校在職時、ブルックスが教鞭を執ったと思われる建物が今も札幌に残る。「時計台」1回、入り口を入って左側は農学・植物学級教室であった。2階にはベンチに佇むクラークの像が設置されている。いつの日か教壇に立つブルックス像が見られるであろうか。 あかいし・けいいち 1971年、群馬県生まれ。早稲田大学第一文学部卒。博士(文学)。専門は英語教育。 【文化】公明新聞2025.1.29
September 27, 2025
コメント(0)
-
秀吉は経済的統一者
秀吉は経済的統一者信長の意志は、そのまま秀吉がうけついだ。大坂首都案に関するかぎり秀吉は創業者ではなく信長の模倣者にすぎなかった。ただ積極的な模倣者で、いわゆる山崎合戦で光秀を討つや、天下はまだ海のものとも山のものともわからぬというのに、はやくも大坂付近の自侍や大百姓に沙汰をくだして築城を命じている。秀吉個人の城としては近江の長浜城や播州姫路城があったが、かれはそこへはかえらず、大坂城ができるまでのあいだ戦場付近の天王山の宝寺を城塞化してそこを仮の根拠地にしていた。大坂の築城は、「天下普請」といわれた。天下の総力をあげて築くということであろう。普請奉行は石田三成、浅野長政、増田長盛の三人で、都市づくりをする街衢奉行は片桐且元、長束正家、堀秀正であった。巨石のほとんどは讃岐(香川県)からはこんだ。大筏を組み、巨石を水中につりさげて比重をかるくし、あるいは巨石のまわりに無数のあき樽を結び付けて浮力をつけ、このような石はこびの舟筏が内海をわるように往来していたとき、秀吉自身は各地に転戦している。竣工一年後に秀吉は住み、二年後にはほぼ工事は終わっていたというから、大規模の人数を集約的につかうという点で史上最初の才能であった秀吉ならではのことであろう。その規模の壮大さと建築の巧麗さは同時代のヨーロッパ文明をしのいでいる、と宣教師たちは自国に報告した。ただこの城の運命は、秀吉一代で終わる。その規模の大きさは、大坂冬・夏ノ陣にこもった人数を見ても想像がつくであろう。当時大坂にいた英国商館長リチャード・コックスの日記では十二万と推定し、大坂御陣山口休庵噺では十二、三万、そのうち女が一万といっているから戦闘員の数だけでもこんにちの中都市の人口ほどであった。九州を席巻していた薩摩の島津氏が豊臣時代に降り、もとの薩日隅三州にとじこめられたために財政の方途がたたなくなった。島津義久は豊臣家の行政担当幕僚である石田三成にそうだんすると、三成は、「いや、それで十分やっていけるはずです。経済というものがまったくかわってしまったことをあなたはごぞんじないから、心配なさるのです」と、くわしく説明した。三成が説いたのは豊臣政権の成立によって日本史上最初の全国経済というものが成立した、ということであった。それ以前の日本は地域経済しかなく、それぞれの大小名の領内での自給自足経済でしかなかったが、秀吉の天下統一は、政治的統一といういじょうに経済的統一という性格が濃厚で、その全国統一の中心機関の役割を、秀吉の構想によって大阪城下の問屋がはたすことになった。これによって薩摩の島津家は国内で生産される米や物産のあまった分をことごとく大坂に送り、市を立て、現銀化し、その現銀をもって大坂で必需品を買い、国もとに送る。三成はそれを説明しただけでなく、それにともなう実務的なこと——送金法、米の販売法、帳簿の作成仕方——などまで教えた。三成がそういう税制や商業的実務になれていたのは、かれやかれの同僚である豊臣政権の政務長官長束正家が近江人であったからであろう。近江ではすでに複式簿記にちかいものが存在していたという説があるほどである。このようにして大坂という都市は、豊臣政権下のわずか十数年のあいだに運命的な機構と機能の原型をつくりあげてゆく。 【歴史を紀行する】司馬遼太郎/文春文庫
September 26, 2025
コメント(0)
-
アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方
アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方語られる次期大統領の若き日々最初が第45台、バイデン大統領を挟んで今月に2度目、第47代アメリカ合衆国大統領になるドナルド・トランプの若い日が語られる。〝アプレンティス〟を直訳すれば〝新米、見習生〟と言ったところか。監督は「ボーダー二つの世界」がカンヌ国際映画祭の「ある支店」賞を受賞したアリ・アッパシ。次期大統領を相手にこんな暴露的内容の映画を撮って大丈夫なの?とみているこっちが不安になってくる。(だからこそ面白いのだけど……)スリリングな映画の誕生だ。20代の彼、ドナルド・トランプ(セパスチャン・スタン)は不動産業者の父が黒人の入居を断ったせいで政府から訴えられ、副社長だった息子のドナルドは破産の危機に直面していた。少々弱気で、ここに描かれる若い日の繊細な彼からは今日の大胆、傲慢な彼からは想像もできないが、財政界の実力者が出入りする高級クラブの最年少会員になった彼は、やり手で悪名高い弁護士ロイ・コーン(ジェレミー・ストロング)に弁護を依頼して彼の出した「100%言うことを聞く」という条件をのんだ。その結果、彼に気に入られて多くの教えを受けるうちに教えたコーンもあきれるほどの変貌を遂げていく。攻撃目標は攻めまくる。絶対に自分の非を認めるな。コーンからそんなことをたたき込まれるうちにドナルド自身は手掛ける事業の面白さに魅了されて大胆さが生まれ、そこからさらに事業は拡大されて、もはやコーンもあきれる怪物が誕生することになった……という話。(映画評論家 渡部祥子) 【スクリーン】公明新聞2025.1.14
September 26, 2025
コメント(0)
-
日蓮は凡夫なれば過去を知らず
日蓮は凡夫なれば過去を知らず 日蓮の著作とされる「諸法実相抄」に、過去・未来・現在という仏教の視点を踏まえて書かれた次の文章である。 日蓮は、其の場に住し候はねども、経文を見候すこしもくもりなし、又其の座にもやありけん。凡夫なれば過去を知らず。現在は見へて法華経の行者なり、又未来は決定として当詣道場なるべし。過去をも是を以て推するに、虚空会にもやありつらん。 法師品第十以降、釈尊滅後の『法華経』弘通の使命を付属するという『法華経』の中心テーマが展開される。その虚空(空中)での儀式(虚空会)に、果たして日蓮が参列していたのかどうか、自問する場面である。そこで日蓮は最初に、「日蓮は凡夫であるから過去のことは分かりません」と切り出す。この書が書かれたのは、出流罪を経験し、小松原で襲撃されて頭に傷を被るとともに、左腕を折られ、龍口刑場での斬首を免れ、終には佐渡に流罪となっている最中のことである。その事実を見れば、「現在は目に見えて法華経の行者である」ことは間違いないと断ずる。そうであるならば、未来は必ず覚りの場((bodhi-manda)、「同上」漢訳)に赴いて覚ること(当詣同上)は間違いないであろう。現在と未来がそうであるならば、過去には虚空会にもいたのであろう——ち、過去は最後に出てくる。それも「ありつらん」と、古文で言う現在推量系を用いた遠慮深げな言葉で締めくくっている。三世という時は、現在が重視されるから(過去→未来→現在)の順番で列挙されるが、日蓮は、「過去を推する」のに、〈現在→未来→過去〉という順番で論じている。仏教の時間論にかなった事故省察である。過去から現在の自分を権威付けしようとする人たちとは格段の違いである。 法華経は選民思想に非ず もしも、日蓮が過去から決まっていたなどと言ったら、それは〝選民思想〟になってしまう。一切衆生の平等を説く『法華経』に選民思想などあるはずがない。日蓮は、過去から現在の自分を意義付けるのではなく、現在の生き方によって過去に意義付けをなしている。この関係は、我々にも適用されよう。我々が地涌の菩薩であったのかどうか、真剣にいくら考えても答えは出てこないであろう。今・現在の生き方によって、「過去には虚空会にもやありつらん」と感得するしかないのだ。これも、現在における過去への意義付けである。「私は釈尊の生まれ変わりでsる」と主張する人物が、かつて私の知る限りでも同時に五人もいた。そのうちある二人は、「お前はブッダの生まれ変わりなんかではなく、四国のタヌキの生まれ変わりだ」などと意地汚くののしり合っていた。私は、彼らに集まってもらい「我こそは本物のブッダの生まれ変わりだ」という討論会を開いたらいいと思っていた。きっと、醜い罵り合いが始まり、取っ組み合いの喧嘩になるであろう。その姿を見て、本当のブッダの生まれ変わりであるかどうか、判断すればいい。仏教は現在を重視するのであって、過去から現在の自分を意義付けすることはない。過去から意義付けをするのは、現在の自分に自信がないからであろう。大事なのは、過去において誰であったかということではない。現在、人間として何をやっているか、どのような尊い生き方を貫いているからである。それは、原子仏典の『サンユッタ・ニカーヤ』で「生まれを訪ねてはいけない。行いを訪ねよ」(中村元訳)と釈尊自身が語っていたことである。◇ ◇以上、日蓮、あるいは仏教の時間論を概観してきたが、それは、冒頭に紹介した中村元先生の「仏教の思想は時間論といってもいい。それは〝今を生きる〟ということなのだ」という言葉につきつと言えよう。〝今を生きる〟ということが重視されるということは、必然的に「誰が」「どこで」ということも重要になってくる。仏教で説かれる心理は、「いま」「ここ」にいきるこの「わが身」を離れてはありえないのである。死後や、はるかかなたの別世界に楽園を求めることも、人間離れした絶対者を頼させることもないのである。 【日蓮の思想「御義口伝を読む」】植木雅俊/筑摩選書
September 26, 2025
コメント(0)
-
輪廻とは仏教思想に非ず
輪廻とは仏教思想に非ず 日蓮の時間論を概観してきたが、その視点に立って、これまで巷で語られていた宿業論を見てみると、まったく違った風景が見えてくるのではないか。輪廻と業(カルマ)は、仏教の思想だと思っている人が多いが、そうではない。紀元前六、七世紀のウパニシャッド(奥義書)に登場した。それをバラモン教が、バラモン(司祭)階級を絶対的優位とするカースト制度を正当化するために利用した。バラモンと生まれるのも、シュードラ(隷民)や不可触民のチャンダーラ(旃陀羅)と生まれるのも、過去世の業の善悪によると一方的に決めつけた。このようにインドの社会通念となっていた輪廻と業を、釈尊は倫理的な意味に読み替え、現在から未来へ向けて善い行いと努力するように強調した。原始仏教では、人の貴賤は「生まれ」ではなく現在の「行い」によって決まると説き、「バラモンと言われる人であっても、心のなかは汚物にまみれ欺瞞にとらわれている」「チャンダーラや汚物処理人であれ、努力精進に励み、常に確固として行動する人は、最高の清らかさを得る。このような人たちこそバラモンである」などと階級を無条件に上位とする差別思想を批判した。 過去の事実は変えられないが意味は変えられる 繰り返しになるが、原始仏典では次のような時間論が強調された。 過去を追わざれ。未来を願わざれ。過ぎ去ったものは、既に捨てられた。未来は未だ到達せず。現在のことがらを各自の状況において観察し、動揺せず、それを見極めて、その境地を拡大させよ。ただ今日なすべきことをひたむきになせ。(『マッジマ・ニカーヤ』) 前世のことなど言われても誰もわかりはしない。そんな過去のことにくよくよして生きるのは愚かである。仏教は現在を重視した。現在の自分は、はるかな過去からの行い(業)の総決算としてある。けれども、その行いの内容は知る由もないし、過去にあった事実は変えようがない。しかし、現在の生き方によって過去の〝意味〟は変えられるのだ。最近、原稿をかいていると、街角で街頭インタビューするNHKの「街録」というテレビ番組の音声が聞こえてきた。「あなたの忘れることのできない言葉は?」といった質問に、山口県の棒高校の卒業生が、野球部員の時、大きな失敗をしてずっとくよくよしていたそうだが、監督に言われた言葉が忘れられないと言う。それは、「過去にあった事実は変えることはできないが、現在の生き方によって過去の〝意味〟は変えられるのだ』と言われたことだった。「どこかで聞いたことだな」と思っていたら、妻が「これは、あなたが書いてたことじゃない!」と叫んだ。拙著『今を生きる仏教100話』(平凡社新書)の第二十五話に書いたことが、そんなところで生かされていたことを喜んだ。極端に言えば、過去をどのように見るかは、解釈にしか過ぎない。バラモン教はカースト制度を正当化するために過去を悪用した。棒教団は、過去の先祖が地獄で苦しんでいるなどと人を不安に陥れて、その隙に付け込んで工学の寄付をさせた。仏教は「無畏施」(畏れなきことの施し)と言って人の不安を取り除き、安心させることが目的だったのだ。仏教の名を騙り、人に不安に陥れ、恫喝して布施を強要することがあるやに聞いているが、もってのほかである。仏教は、基本的に現在から過去と未来を捉えることを説いた。忌まわしい過去を引きずって現在を生きるか、あの過去があったからこそ現在こうなれたとするかは、現在の生き方次第である。大乗仏教とが、「自らの悪業は、悪業に苦しむ人々を救済するために自ら願って身に受けた(願兼於業)」と主張したのも過去の〝意味〟の現在における主体的転換であった。『維摩経』に登場する天女が、不退転の菩薩の境地に達していて、女性の姿をしているのは、世間で蔑ませている女性を救済するために、自ら願ってのことであるということが、主人公である在家の菩薩によって明かされる。女性として生まれたが故に女性の苦しみを理解できる。だからこそ、女性を救済できるのだという意味が込められている(植木訳『サンスクリット版 維摩経 現代語訳』、二四〇頁)。大乗仏教とは、身に受けている悪条件の〝現在〟を主体的に受け止め、他者救済の原動力に転じたのである。 【日蓮の思想「御義口伝を読む」】植木雅俊/筑摩選書
September 25, 2025
コメント(0)
-
新訳『ドリトル先生』刊行
新訳『ドリトル先生』刊行原文の面白さ伝わるよう新味加え東京大学教授 河合 祥一郎理想的な生き方を教える人物像「ドリトル先生」シリーズ(ヒュー・ロフティング/全12巻+番外編)を夢中で読んだ人は多いだろう。動物の言葉が話せるという設定の物語だが、単に動物と仲良くなれるのが楽しいだけではない。一番の魅力は、理想的な生き方を教えてくれるドリトル先生の生き方にある。ドリトル先生は、お金というものを一切気にしない。「丈夫な体をもち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かにに笑って……東に病気の動物あれば言って看病してやる」というものにドリトル先生はなっているのだ。困ったことにもたじろがず、英国式ユーモアをもって、思ったことを必ずやりとげる。それも、世界じゅうの動物たちの無償の愛とサポートを得て、どんなことでもなしとげてしまう——「そういうものに私はなりたい」と、読者が思うのは当然だろう。実を言えば、先生がお金の心配をしなくても、家政婦役のアヒルのガブガブが代わりに心配してくれるので暮らしで行けるのだが、そこはご愛敬だ。先生の家には、個性豊かな動物たちがファミリーとして暮らしていて、愛と信頼で先生を支えている。その一方で、先生が舟に乗って大冒険をすれば、世界じゅうの動物たちが先生を助けに駆けつけてくれる。いわば自然の大きな力が味方なのだ。人間界の瀬古瀬こした欲望や価値観を脱して、みんなたくましく生きることの大切さ、楽しさを教えてくれる、それが「ドリトル先生」シリーズの最大の魅力だと言えるだろう。子供の頃に「ドリトル先生」シリーズを夢中で読んで生物学者になった有名人も数多い。日本では福岡伸一がまず挙げられるし、『利己的な遺伝子』などの著作で有名な進化生物学者リチャード・ドーキンスもそうだ。ドーキンスは特に、悪者をやっつけるドリトル先生の船を何千羽ものツバメが引っ張ってくれる『ドリトル先生の郵便局』がシリーズの中でも最高だと絶賛している。そもそも作家のヒュー・ロフティングは英国人として第一次世界大戦に従軍した際に、けがをした軍用場が治療も受けずに銃殺されるのを見て大いに心を痛め、動物の言葉が話せて動物を助けてあげられる医者がいたらいいのにと夢想して自分の二人の子どものために物語を書き始めたのだった。エコロジーや共生が謳われる現代こそ、「ドリトル先生」の意義はますます大きいと言えるだろう。 児童向きは完結し大人向けも刊行中長らく井伏鱒二訳が親しまれてきたが、角川つばさ文庫から児童向きに私の新訳が残寒観光(番外編と未邦訳作品も含め)完結しており、さらに二〇二〇年からは角川文庫から大人向けにシリーズの刊行を始め、昨年秋に『新訳 ドリトル先生と秘密の湖』まで刊行した。新訳では原文から忠実に訳し、井伏訳の「オランダボウフウ」を原文通り「パースニップ」にしたり、井伏訳の「おやつのパン」を原文通り「マフィン」としたりするなど、イギリスの文化をそのまま伝えた。また井伏訳では、先生が航海に出るときに登場した船乗りが自分のことを「じょうぶなたらい」(stiffikit)で立派な船員であると新聞にあると言うが、新訳では「立派な船員としての証明書(タティフィケト)のロンドンなまりであると読み取って訳したり、原文にある言葉遊びを日本語で楽しめるように工夫したりするなど、大幅に新味を加えて原文の面白さをそのまま伝えるように努めた。愛と夢と冒険がつまった「ドリトル先生」シリーズをぜひお楽しみいただきたい。(かわい・しょういちろう) 【文化】公明新聞2025.1.27
September 25, 2025
コメント(0)
-
野球、光放つ歴史
野球、光放つ歴史 「所作の活発にして生気あるはこの遊戯の特色なり」。俳人正岡子規が『松羅玉液』に記した「ベースボール」(「正岡子規」所収/筑摩書房)の一文だ◆記したのは1896年。野球に熱中し、図入りで解説も載せている。だが、すでに野球はできぬ体に。前年、喀血し神戸の病院に。当時、治らぬ病のケッカくだった。年後、34歳で世を去っている◆子規は「野球をわが国に広めた功績は大きい」と後世評され、特別枠で日本の野球殿堂に。片や阪神・淡路大震災から30年を控えイチロー氏がどう野球殿堂入り。日を置き米国でアジア人初の野球殿堂へ。満票まであと1票だった結果に、「不完全な中で自分なりの完璧を追い求めて進んでいくのが人生だと思う」と◆2000年冬に渡米。翌年から10年連続の200本安打など数々のメジャーリーグ記録を打ち立てた。オフになればオリックスの本拠地だった神戸に戻り練習。「神戸に対しては、選手を続けるしか恩返しできない」と45歳まで、メジャーで戦い続けた◆米国の野球殿堂にはフランクリン・ルーズベルトの手紙がある。戦争で試合中止論が広がる中、大統領だったルーズベルトは「野球を続けることが最善」と書き送った。道を開いた大統領、イチロー氏と、病を押し文を綴った子規。光放つ歴史である。 【座標軸】公明新聞2025.1.26
September 24, 2025
コメント(0)
-
外来の神格が仏・菩薩として仏教に取り込まれた
外来の神格が仏・菩薩として仏教に取り込まれた 『法華経』の序品を読むと、弥勒菩薩は過去世において、「求名」(名声を追い求めるもの)という名前で呼ばれ、怠け者で、利得を貪り、自分のために説かれたブッダの教えもすぐ忘れるといった不名誉な人物として描かれている。弥勒菩薩は、イランのミトラ(mitra)神がマイトレーヤ(maitreya、弥勒)菩薩として仏教に取り込まれて考え出されたものであったが、釈尊に代わるブッダとして人々に待望されていた。「第六章 人間離れした諸仏・菩薩への批判)でも触れたように、『法華経』は、当時の弥勒菩薩待望論に対して痛烈な皮肉を盛り込んでいたのである。久遠実成による諸仏の統一大乗仏典が編纂される一世紀以降には、このように外来の神格が仏・菩薩として仏教に取り込まれることが起こった。それに伴い、西洋の一神教的絶対者のような宇宙大で永遠だが抽象的な如来(法身仏)が考え出され、本来の仏教の人間観・ブッダ観とは異なるものになる傾向が出てきた。その代表が、ゾロアスター教の最高神アフラ・マズダーに起源をもつとされる毘盧遮那(nairocana)仏である。『法華経』が編纂される頃(紀元一世紀末~三世紀初頭)には、このほか過去・未来・現在の三世にわたり、また四方・八方・十方の全空間において多くの仏・菩薩の存在が想定されるようになった。それに対して、歴史的に実在した人物は釈尊のみであった。釈尊以外の仏・菩薩は、「神が人間を作ったのではなく、人間が神を作ったのだ」という西洋の言葉と同様に、人間が考え出した架空の人物である。極端に言えば、コミックや映画などで活躍する「スーパーマン」や、「スパイダーマン」「鉄腕アトム」などの架空のスーパーヒーローと同じである。こうした傾向に対して、『法華経』は「それらは、いずれも実在しない架空の存在にすぎない。架空の人物にどうして人が救えるのか?」とむげに否定することなく、「それらの仏・菩薩は、久遠以来成仏していた私(釈尊)が、名前を変えて種々の国土に出現していたのであり、それらはすべて私であったのだ』と説くことによって歴史上の人物である釈尊に収束させ、統一した。仏の統一ということでは、化城喩品第七で釈尊を中心としてその八方に、東方の阿閦仏、西方の阿弥陀仏をはじめとする十五仏を配することによって、また見宝塔品第十一で十方のあらゆる世界から諸仏を釈尊の下に参集させることによって、諸仏を空間的に釈尊に統一した。それに対して如来寿量品第十六は、諸仏を時系列の中で釈尊に統一したと言える。 【日蓮の思想「権義口伝を読む」】植木雅俊/筑摩選書
September 24, 2025
コメント(0)
-
自然を巡る作品が多数
自然を巡る作品が多数ミシュレの哲学に学ぶ中央大学名誉教授 大野 一道昨年は、フランスの歴史家ジュール・ミシュレ(一七九八—一八七四)の没後一五〇年である。膨大な『フランス史』、『フランス革命史』等の歴史書のほか、同時代の社会問題を扱う『民衆』、『学生よ』、『女』や、『鳥』、『虫』、『海』、『山』といった自然を巡る作品を書いた彼は、「地球における人類史」、つまり自然全体の中での人類の営みを跡付けしようとしたのだ。そうした仕事は、フランスではアナール派と呼ばれる人々へと受け継がれ、政治史、経済紙、文化史等の枠を超える新しい歴史を今日生み出している。「宗教的不公平は政治的不公平」の根拠となると彼は述べるが、歴史の中での宗教と政治のかかわりに注目する。中世ヨーロッパでは、カトリック教会内部のヒエラルキーが、封建社会のヒエラルキーの裏付けとなっていたし、多くの戦争が宗教的対立から生じていた。『フランス史』でも異教徒への十字軍や、異端への激しい闘いが語られている。ユダヤ教やキリスト教等の啓示宗教では、紙か悪魔か、善か悪かという二項対立で世界が捉えられるからだ。正義と信じる「絶対理念」を掲げて、それにそぐわぬものを断罪し抹殺しようとする傾向は何も宗教だけではない。フランス革命ただなかの革命は内部でも生じていた。 あらゆる生命体が人間の兄弟 ミシュレは『魔女』のなかで、紙に背いた者への球団、弾圧を活写する。中世に在っては髪のいる天上世界を忘れさせる美しい一輪の花にさえ、悪魔の誘いを見るといった倒錯が生じていた。彼によれば、境界から断罪された悲惨な状況を逃げ出し、山野にある大いなる自然、この美しい台地との交わりに救いを見出したのが魔女たちだった。自然の復活はルネサンスの特徴でもある。フランス革命では、人間の内なる自然の要求が前面に出されるだろう。『民衆』では、ヒトは社会的分化や差別化を受ける以前の生まれ落ちた瞬間、すべからく民衆であり、あらゆる生命体と共通する存在だとされる。つまりヒエラルキー的縦構造ではなく、平等という横構造が主張される。さらに『虫』、『鳥』等では、彼らにおける親子愛や仲間愛が観察され、宇宙に内在する大いなる魂のようなものさえ予感される。ミシュレはあらゆる生命体が人間の兄弟なのだと信じる。『人類の聖書』では、キリスト教的一神教以外への世界へ、とりわけ古代インドへと思いが向けられ、そこにあったすべての生が連なり繋がっているという感覚に共感する。そして次のように述べる。「インドから八九年(=フランス革命)まで光の奔流が流れ下ってくる」と。つまり万人の価値における平等を認める古代インド的原理によって、裏打ちされねばならないということだ。強烈な自我により世界を支配する西洋的原理への、「ハハナルダイチを忘れた」者たちへの異議申し立てであろう。こうした彼の思想に、大地(=地球)の未来を守るため、今学ぶべき事は多々あるだろう。(おおの・かずみち) 【文化】公明新聞2025.1.24
September 23, 2025
コメント(0)
-
子どもを育む遊び場
子どもを育む遊び場東京科学大学准教授 北村 匡平限定され進化や発展がない現代の公園は、私が幼かった頃とは、まったく異なる姿になっています。遺残から、子どもを連れて行ったときに感じていたことですが、特に2000年代になって、公園での禁止事項が増え、注意書きや年齢制限のシールをあちこちで見かけるようになりました。空間の近い方、遊具の配置など、遊び場として魅力が乏しく、窮屈な空間になっているのです。今では、子どもたちを公園に連れて行っても、「大人は入らないでください」と張り紙があり、親は遊び場から排除され、周りで見守るしかありません。子どもたちにしても、年齢別に、6歳以下、6歳から12歳、12歳以上と、遊ぶゾーンが湧けられ、兄弟一緒に遊ぶことができないのです。僕らが子どもの頃、1980年代、90年代の公園は、もっと自由で楽しかった。だから、最初は窮屈だなというくらいにしか感じなかったのですが、実は子どもたちにとっても面白くない空間になっています。子どもの遊びというものは、遊び場によって変化します。何もない広場であっても、子どもたちは新たなことを発見して、いろいろな遊びを生み出していきます。でも、遊具は豪華なのに子どもたちがつまらなさそうにしている公園では、すべての遊具で一通り遊んだら終わり。子どもたちは別の公園に行きたがります。遊びの変化や発展がないのです。 ハザードとリスクの違い公園で子どもたちを遊ばせている時、こんなことがありました。6歳から12歳用のトランポリンに、小さい子が入ってきたのです。きっと、お兄さんたちが飛んでいるのを見て楽しそうだと思ったのでしょう。でも、そこにいた子どもたちは、「小さい子がこっちに来ているよ」と親に言い付けました。確かに小さい子どもが入ると、けがをするかもしれません。でも、本当は子ども同士で遊んでいても、小さい子が来たら、けがをさせないように気にしながら遊ぶ。そういう経験によって、心も体も形作られていくのではないでしょうか。それをトラブルがないようにと、一切排除してしまうのは、遊び場自体をものすごくつまらないようにしていると思います。確かに、小さい子どものところに硬いボールが飛んできて、危ないなと感じたこともあります。命にかかわるような危険(ハザード)と、ちょっとして危険(リスク)は、分けて考えるべきです。リスクを取り除き過ぎると、子どもたちが自由に挑戦できない、つまらない空間になってしまうからです。以前、青森県にある富士見湖パークという公園ですごくいい光景を見ました。かなり宮で高さのある滑り台がありました。頂上からスッと滑れる子はまれで、大体は統べるか滑らないかで迷います。その時も20分ぐらいでしょうか、一人の子どもがちゅうちょしていました。でも、親はずっと待っているのです。ともすると「滑れないんだったら早くあきらめて次の場所に行こう」と言ってしまいがち。でも、子どもが行くのかいかないのか、自分の限界に挑戦しようとする気持ちを大切にしていたわけです。そうした「見守る」「待つ」「手放す」という関わり方が大事なのではないのでしょうか。それを我慢できずに介入してしまう。それが問題を悪化させているように思います。 見守る、待つ、手放す豊かに遊べるように その国の文化や思想を反映公園の遊具による事故は、90年代に社会問題になりました。訴訟に発展し、遊具メーカーや公園を設置した自治体が訴えられたのです。その結果、2000年代にかけて、危険度が高いとされた、箱型ブランコや回旋道具が撤去されています。また、遊び方を指定したシールが貼られるようになり、年齢別ゾーニングも行われるようになりました。こうした公園のあり方は、国によって全く違います。その子にも文化や思想を反映していると言ってもいいでしょう。例えばドイツでは、公園自体が巨大な砂場。そこに木製の遊具が設置され、自然に触れる遊びを重視いているのが分かります。水を出しっぱなしにして、子どもたちが泥んこになって遊んでいるのです。大人も一緒になって遊具で思いっきり遊んでいます。デンマークでは、アドベンチャー・プレイグランド(冒険遊び場)発祥の地であり、知育遊具やアート遊具が多い。こう考えると、日本の公園はよくない方向に行っているように思います。まずは大人の意識を変えていくこと。何か問題が起きた時、親はすぐにクレームをつける。公園側は、それが怖いから、危険なことができないような対策をする。社会全体が、面倒なこと、トラブルになるのが嫌だから、先回りして安全で危険な関りがないような空間にしているのです。子どもたちの遊び方が豊かになるように考え、想像力を刺激するような自由な公園が増えるといいと思います。=談 【文化Culture】聖教新聞2025.1.23
September 23, 2025
コメント(0)
-
風格漂う石垣の名城
風格漂う石垣の名城城郭ライター 萩原 さちこ丸亀城全国の城ファンも納得する石垣の名城です。JR予讃線の車窓から見える姿はまさに石垣の城塞。ヨーロッパの古城のような風格さえ漂います。階段のように幾重にも高石垣が連なり、その上に江戸時代から残る天守が鎮座します。石垣は、累計で日本一の高さを誇ります。本丸まで四段に重なり、山麓から頂上までの高さは60㍍以上。標高66メートルほふぉの山に、曲輪(区画)をひな壇上に配置しているため、それを囲む石垣や建造物がおのずと密集し、石垣が折り重なって見えるのです。反り返りの美しさや、屏風のような屈曲が織りなすバランス日の魅力です。大手門から三の丸に続く150㍍の坂道は見返り坂と呼ばれ、坂下へすらりと伸びる石垣の美が楽しめます。城内最高の三の丸北側の石垣は圧巻です。築城したのは、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の下で乱世を生きた生駒親正です。1597年、讃岐17万石を与えられた親正は高松城を本城とし、西讃岐を抑える支城として丸亀城を築きました。1615年の一国一城令により、丸亀城は廃城に。本来ならばこの城の歴史は終わるのですが、丸亀城は異例の復活を遂げます。お家騒動(生駒騒動)により讃岐が分割されたのを機に、1641年に丸亀藩が立藩したのです。5万石で丸亀藩主となった山崎家治は、1643年から丸亀城を現在の姿へと大改修。現在みられる大半の石垣を積んだのは家治と考えられます。現存する三重三階の天守は、山崎家断絶後の1658年に入った京極貴和が、1660年に築きました。天守の鬼瓦や丸瓦には、京極家の家紋・四つ目結紋が輝いています。天守代用の御三段櫓として建てられた天守は、現存天守の中でも最小です。しかし、小さな天守を少しでも大きく見せるためか、さまざまな工夫が凝らされています。正面にあたる北面は、左隅に出窓のような張り出しを設け、素木の格子をつけてデザイン性をアップ。二重目には唐破風、南面には千鳥破風を飾り、華やぎを添えています。 【日本全国お城巡り26】公明新聞2025.1.23
September 22, 2025
コメント(0)
-
つねに天才が発見した
つねに天才が発見した大阪という都市はすでにその存在そのものが数奇であるといえる。たとえば歴史のうえからながめても、大坂が大阪になる以前、この土地を通過した者は幾百万をこえるだろうが、この地政学的価値を発見した者は数人しかいない。その数人はことごとく天才の名を負うている。その名についてはあとでのべる。とにかく日本の(あるいは世界の)どの都市にくらべても都市としての立地条件のよさは、大阪はあるいは最高かもしれない。その価値は、まず日本列島のやや西寄りの中央に位置しているということであろう。ついでに琵琶湖という巨大な貯水池をもち、淀川が天然のパイプをなし、河流で数百万の人口をうるおしうること。さらには後背地(センターランド)がひろく、地味が豊沃で、食糧の供給力が大きいこと。さらにそれらを総和してもうわまわるほどの価値は大阪湾と瀬戸内海であろう。風浪から船舶をまもるだけでなく、瀬戸内海という自然の回廊にまもられつつやがては外洋に向かってひらけ、その航路は大阪湾によって日本列島の各地をめぐり、あるいは神戸港によって世界に通じている。虚心にみればたれが考えても首都は大阪であるべきであった。ところがこの最高の地政学的条件の地が首都にならなかった(ときにはなる。しかしすぐほろぶ)のはふしぎなほどであり、世はリクツどおりにはゆかず、そのゆかぬという機微のなかにこそ、歴史が充填されているようにおもえる。この稿は、それについて書く。ふるいむかしはべつとして、この湾の摂津沿岸を首都にすることを最初にやったのは平清盛であった。かれはいやがる公卿たちを武権によって強引に京をひきはらわせ、大阪湾の沿岸につれてきた。福原遷都である。もっとも福原といえばいまの神戸で、おなじ摂津ノ国とはいえ、大阪(当時大阪という地名はない)でない。しかしかりに四捨五入しておく。清盛というひとは日本史上の権力者として最初にあらわれる商業感覚のもちぬしで、対中国貿易を考え、港のある場所にこそ首都であらねばならぬとおもった。しかし遷都ほどなくかれは死に、都はふたたび京にもどされ、やがて平家そのものはほろぶにいたるから、平家にとって福原遷都ほど縁起のわるいものはないといわるにいたった。その後数百年、大阪湾のまわりを発見する天才はあらわれていない。このあたりはよし・あしのはえるにまかせたただの磯くさい田舎で、近畿の他の地帯にくらべでも人家が多かったわけではなかった。平安から鎌倉期にかけては現在の大阪市の都心あたりはワタナベとよばれていた。大阪のもとのよびなは渡辺であった。渡辺党という二流程度の武士団が住んでいた。日本の姓のなかでもっとも多い姓のひとつである渡辺姓はここを発祥としているが、要するにそういう渡辺のあらしごとどもが河口であみを打ったり、湿田を這いずりまわって田植えをしていた半農半漁の地帯で、どういう権力者もここを天下統治の根拠地として感がいたことはない。そういう種類の知性的頭脳はまだ歴史に出現しない。最初に出現するのは中世末期である。本願寺興隆の基礎をひらいた蓮如がそれであった。戦国百年のうち、蓮如ほどの組織力と宣伝力をもった人物は絶無であろう。その戦略的感覚はのちにあらわれる織田信長に匹敵するかもしれず、その城郭設計の能力にかけては当時の二流の武将になどは足もとにもおよばなかった。蓮如が武将の家にうまれていたらどういうことになったであろう。しかしかれは肉食妻帯僧の家にうまれた。たまたまその家が親鸞を家祖としていた。親鸞からかぞえて八世の孫にあたり、貧窮のなかで成人した。今でこそ親鸞といえば日本史上の巨人だが、蓮如の少年のころはまったく埋没された名であったにすぎない。親鸞はその生存中、「親鸞ハ一人ノ弟子モモチ候ハズ」と言い、思想として教団を否定しただけでなく、その死後、その教徒は叡山から執拗な迫害をうけつづけたため京の一隅で衰微しきっており、妻子を相手に親鸞念仏をとくいわば町の説教所のようなものにすぎなかった。つまり本願寺派親鸞によって興ったのではなく親鸞の教団否定の遺訓を無視してこの宗祖の名をかつぎまわった蓮如によって興ったのである。蓮如はその八十四年の生涯で六、七十人の子をうませ、二十七人成人したといわれるほど精力家だったが、そのなみはずれた体力で天下を布教してまわり、各国各郡各村に講を組織し、ついにはそれまでにかつてなかった民衆の全国組織を完成した。 【歴史を紀行する「政権を亡ぼす宿命の都〔大阪〕】司馬遼太郎/文春文庫
September 22, 2025
コメント(0)
-
能登で生きること㊤
能登で生きること㊤人々のまなざしの先 フォトジャーナリスト 澁谷 敦志能登半島地震の発生から1年余り。今なおその復興は途上にあるが、フォトジャーナリストの渋谷敦志さんはこの間、被災地に通い、能登の人と土地の撮影を続けてきた。昨年12月には『能登を、結ぶ。』(ulus publishing)も出版。「能登の豊かさを守ることと、日本の未来はつながっている」と語る澁谷さんに、写真と共に能登に寄せる思いを語ってもらった。 大切な何かが置き去りに能登半島地震(2024年)の発生から2週間余りの1月17日は、僕は輪島市の朝市通の現場にいた。その日はくしくも阪神・淡路大震災が起きた日。目の前の光景がかつて神戸でみた被災地と重なった。当時、報道写真家を目指していた僕は、被災地に飛び込み、不遜にもそこで衝撃的な写真を撮り、写真家として認められたいと意気込んでいたが、大きく破壊されたまちに驚愕し、一枚も撮ることなく現場を去った。その悔しさや己の無力さ、撮ることの逡巡は今もつきまとう。それでも、記録が残らなければ、何も起こらなかったことになってしまう。そうさせまいと意を決し、焼け野原となった朝市通にカメラを向けた。12月に『能登を、結ぶ。』を発刊し、再び朝市通を訪れた。建物がすべて撤去された被災地には、ただ更地だけが広がっていた。それが復興への一歩かもしれないが、もやもやした気持ちを抑えることはできなかった。大切な何かが置き去りにされている、そんなわだかまりが心の中で渦巻いていた。「復興は進んだ」「遅れている」といった議論のはざまで、零れ落ちる人生を拾い上げ、再生への道筋を照らす仕事はまさにこれからだと、荒涼とした風が吹く跡地で自らに言い聞かせた。そして、震災直後から目にした能登の人々の「強いまなざし」を思った。 海があり、山があり、小さな畑がこの風景の一部になりたい そこに伝えるべきものが発災後、能登に入ったのは1月2日。日本赤十字社の救護チームに同行し、活動を記録するのが役目だった。初日は、道路の断裂や土砂崩れで思うように被災地に入れず、その遠さに打ちひしがれた。それでも、3日に輪島市の門前町、4日に穴水町、5日には珠洲市までたどり着くことができた。その時点で一番懸念されていたのは、外浦の孤立状態にある地区だった。しかし狼煙や折戸の避難所を尋ねると、人々はただ救護を待つのみではなく、食材や飲み物、灯油などを持ち寄り、独自に感染症対策を施しながら、苦境をしのいでいた。東日本大震災の時もそうだったが、災害対応力は田舎ほど強い。折戸から先は徒歩での移動を余儀なくされた。隣の高屋を目指す道中で一人の女性と出会った。高屋町の吉田華子さんだ。巨岩が塞ぐ道路のわきを自転車で分け入り、ガソリン10㍑とコンロのガス管15本を積んだ自転車で、崩壊した崖を乗り越えようとしていた。彼女にそこまでさせるものは何だろう。吉田さんは「高屋に大好きな人たちがいるから」と答えた。その言葉に心が震えた。そして、そのまなざしに心をわしづかみにされた。この残酷に破壊され地も、彼女のような人がいる。そのまなざしの先に何があるのか。それを伝えるだけでも、自分が能登を撮る意味はあるのではないか。そう心を仕向け、僕が能登の取材を続ける決意をした瞬間だった。発災から半年が過ぎた7月、高屋町の畑で吉田さんと集落の女性たちを撮った。海があり、山があり、そのあいだに小さな畑がある。そこで集落の人がおしゃべりし、土をいじる。「高屋のこの風景の一部になりたい」と吉田さんは話していたが、僕が追い掛けてきたもの、伝えるべきは此れだ、とすとんと胸に落ちた。この一枚の写真につまっている、能登の明日の日々を確かにするもの。それを写真で表し伝えていきたいと思うから、『能登を、結ぶ。』は生まれた。 しぶや・あつし 1975年、大阪府生まれ。大学卒業後、フォトジャーナリストとして活動。99年、MNFフォトジャーナリスト賞を受賞。アフリカやアジア、南米で紛争や災害、貧困問題の取材を続ける。著性に『まなざしが出会う場所へ』『回帰するブラジル』『僕らが学校に行く理由』などがある。 【社会・文化】聖教新聞2025.1.21
September 21, 2025
コメント(0)
-
バイオ技術で近づく外観、生体機能も
バイオ技術で近づく外観、生体機能も科学文明研究者 橳島 次郎ロボットの人間化昨年6月、東京大学の研究グループが、人の細胞から作った活きた培養皮膚で覆われたロボットの顔を作成したと発表した。人間の皮膚を支える生体組織を模倣し人工素材にしっかり貼り付けられる手法を開発した成果だ。この先端技術により、今あるシリコンゴムよりも人間に近い外観と、排熱(発汗)などの生体機能を備えた人型ロボットの開発につなげられるという。この研究グループは3年前に、同じく人の細胞から培養した活きた皮膚で覆われていたロボットの指の開発に成功したと発表している。切り傷をつけても、コラーゲンの絆創膏を貼ると人間の皮膚のように治すことができたという。さらに同じ研究者を含む別のグループは、一昨年末に、筋組織から培養した骨格筋で動く二足歩行ロボットを作成したと発表している。生きた皮膚で覆われた筋肉を備えたロボットが出来上がる日が来るだろう。こうした生体組織と人工素材を融合させたバイオハイブリッド・ロボットの利点は、機械仕上げではまねできない生き物の優れた運動能力や防御と修復の能力を持たせられることだ。生体組織はエネルギー効率が良く、運動消費が機械より少なくて済むとも期待される。バイオハイブリッド・ロボット技術は、人間の医療(傷んだ皮膚や筋肉の修復、再生など)にも応用できるという。生体内の状態に近い筋肉組織を作る技術は、連載第13回で取り上げた培養肉開発にも応用できるともいう。ただバイオハイブリッド・ロボットの開発はまだ研究段階で、実用化にはほど遠い。特に、生体組織維持のための栄養分とエネルギーの補給をどのように行うかという独特の技術的問題がある。すでに人工知能技術と機械工学技術を組み合わせて、人間が行う作業をうまくこなし、人間に近い表情を浮かべて受け答えができる人型ロボットの開発が進んでいる。そこに生体工学技術まで加わって、見た目や触った感じまで人間に近いロボットが生まれるかもしれない。機械であるロボットを、どこまで人間に近づける必要があるだろうか。連載17回でみたように、日本人は西洋人に比べ、機械人間である人型ロボットへの抵抗が少ないといわれてきたが、生きた皮膚まで備えたロボットには薄気味悪さを感じ、日本人でも抵抗が強くなるかもしれない。そうした社会心理面に配慮しつつ、バイオハイブリッド技術をどこまでロボット工学に応用する必要があるか、検討すべきだ。 【先端技術は何をもたらすか—35—】聖教新聞2025.1.21
September 20, 2025
コメント(0)
-
最新研究「睡眠の謎」㊦
最新研究「睡眠の謎」㊦今日のポイント時間の確保を優先して柳沢教授ノーベル賞級といわれる、睡眠に関わる物質(オレキシン)を発見した医師・柳沢正史教授(筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構長)。前回に引き続き、すべての人が関係する〝睡眠〟の、知られざる最先端研究を語ってもらいました。 〖よく眠ると洞察力も向上〗睡眠は、日中の記憶を選別し、必要なものを定着させます。また、通常の言語化できる記憶の他に、「技能記憶」「マッスルメモリー」と呼ばれる、体で覚える記憶も、睡眠時間が少ないと定着しづらくなります。また、睡眠をしっかりとった被験者は「洞察力」が高まり、睡眠不足の被験者は低くなったというドイツの研究もあります。条件によっては3倍の差が生まれました。クリエーティビティーが向上し、朝起きた時に〝気付き〟を得られる確率が大きく高まるのです。 〖子供の能はねるほど発達〗子供の睡眠時間(平日)が増えると、脳の認知機能を担う海場は発達し、容積が増ええます。子どもに必要な睡眠時間は、9歳で10時間、15歳で8時間45分といわれています。子供の睡眠不足は、海馬の発達を阻みます。学力面から考えると、受験への影響など、人に依っては一生のハンディにつながることも起こりうるでしょう。 〖20代が夜型のピーク〗「朝型」「夜型」という言葉がありますが、これは年齢で大きく変化します。ドイツとスイスで5万5000人を調査した大規模な研究があります。それによると、子どもは朝方ですが、思春期から夜型になり、20歳代が夜型のピーク。その後は朝方に戻っていきます。ですので、高校生・大学生は本来、朝早く起きない方がよいといえます。早起きすると、夜型体質のため「尾曽根速雄喜」となり、最も大事な〝睡眠時間〟が減ってしまうからです。現実的には、登校で早起きする分、早く寝て、時間を確保することを心がけてください。 〖覚醒を促すオレキシン〗脳の〝覚醒〟を保つ物質が、私たちが25年前に発見した「オレキシン」です。日中での突然眠気に襲われ、〝居眠り病〟といわれる「ナルコレプシー」という病は、オレキシンを作る細胞の消失が原因です。現在、オレキシンの働きを〝抑える〟ことによる不眠治療薬(睡眠薬)が実用化されています。既存の薬と比べて「依存症」「リバウンド」が少ないため、〝必要な時だけ飲んで、簡単に卒業できる〟薬です。大切なレム睡眠も抑制しない、はっきり言って、とても良い薬です。今、私たち筑波大学の睡眠研究機構では、約1万匹のマウスを使った、世界最先端の大規模な実験を行っています。〝睡眠に関わる物質や遺伝子の発見〟につながる可能性のある、とても重要な研究です。睡眠は、本質的に個体レベルの現象なので、実験は大変です。睡眠から覚醒はすぐ促せても、覚醒から睡眠には簡単に誘導できないことも、睡眠研究を難しくしています。その半面、仮設や予測を立てずに進める探索的研究の余地があり、とてもワクワクします。 依存症の少ない睡眠薬も登場 〖不眠の65%は〝睡眠誤認〟〗不眠症の治療で大切なのは、個人の〝睡眠の質〟です。しかし、睡眠の質を客観的なデータで測ると、本人が自己申告する質とは大きく異なっているケースがあります。これを「睡眠誤認」と呼びます。私たちは、筑波大学発のベンチャー企業(S‘UIMIN)を立ち上げ、おでこにシール状のセンサーを貼るだけで、睡眠時の脳波を自宅で測定できるデバイスを開発しました。測定値がクラウド上に集められ、個別の「睡眠レポート」を分析します。すると、不眠を自覚する人の65%が睡眠誤認していました。ある40代の女性。常に不眠に悩んでいるといい、「昨晩も朝4時まで眠れませんでした。時計を見たので間違いありません」と訴えます。しかし、前の晩の脳波を確認すると、4時頃を含む複数の時間で中途覚醒は見られるものの、実際はかなり良質の睡眠がとられていました。この女性は、客観的には健やかに眠っていることを丁寧に説明することで、睡眠に対する不安は消え、不眠の訴えもなくなりました。レム睡眠時に無呼吸イベントが多発している人もしばしば見つかります。抱き枕を使って横向きにナムル時間を増やすことで、睡眠時かむ呼吸が軽減しました。高血圧の治療は、手軽に毎日測定できる、「家庭用血圧測定器」の登場で、〝教科書〟が書き換わりました。客観的な値を自覚することで、血圧は下がる」と言われるまでになりました。睡眠も、脳波で〝見える化〟することで同じようなイノベーションを起こせればと考えています。この脳波の検査は、全国300以上の医療機関で申し込める他、簡易体験もできます。自分の睡眠は、自分では客観的には分かりません。手前みそですが『いまさら聞けない 睡眠の超基本』という本を出しています。分かりやすい本ですので、興味がある方は、ぜひ読んでみてください。 〖時差ボケ生む週末の寝だめ〗睡眠不足の借金(睡眠負債)を返すには約4日かかります。「平日の睡眠不足を、週末に寝だめで解消する」は、無理な注文なのです。さらに、睡眠中央時刻(入眠時刻と気象自国の中央の時刻)が、平日と土日とで大きくずれることはマイナスです。中央時刻が4時間ずれれば、4時間の「社会的時差ボケ」が発生します。日本と中東の自さと同程度の時差ボケを、自ら作り出しているのです。時差ボケは簡単には解消しません。私も1週間ほど米に欧州から帰ってきたばかりですが、まだ時差ボケが続いています。私は睡眠学者として「紺屋の白袴」ではいけないと思い、普段から事情が許す限り、午前0時に寝て7時に起きる規則的な生活習慣を守る努力をしています。 【医療MedicalTreatment】聖教新聞2025.1.20
September 19, 2025
コメント(0)
-
雪と生きる雪を生かす
雪と生きる雪を生かす雪先案内人 伊藤 親臣さん雪国の知恵の結晶背丈よりも高く雪が降り積もり、長く厳しい冬が続く雪国。今期の降雪量は北日本や日本海側では平年より多く感じます。時に〝やっかいもの〟になる雪ですが、先人たちは、雪の力を生かした雪国独自の生活様式や文化をつくってきました。その一つが「雪室」です。雪室とは、冬に降り積もった雪を蓄え、雪の冷たさをじょうずに生かした「天然の冷蔵庫」のこと。雪と共に生きる雪国の知恵の結晶です。古くは日本書紀にも記載されており、電気冷蔵庫が普及する1960年代後半まで、雪国の各地で利用されていました。しかし、衛生基準の厳格化と電気冷蔵庫の普及とともに、雪との向き合い方が変わりました。便利さ故に、「雪と共に生きる」から「雪と距離をとって生きる」ようになり、雪の利活用は衰退しました。結果、雪は人間の暮らしを制限する〝やっかいもの〟として扱われるようになったのです。雪に関する技術のほとんどは、雪害対策のために用いられました。それが近年、省エネや再生可能エネルギーへの意識の向上とともに、雨が〝冷やす〟ためのエネルギー(冷熱エネルギー)として注目されています。ターニングポイントは2002年のシンエネ法の改正。この時、雪は新エネルギーとして明確に位置付けられました。まさに「克雪(之の克服)」から「利雪(予期の利用)」への一大転換です。 クリーンエネルギー雪は毎年、自然がつくり出す冷熱エネルギー資源であり、二酸化炭素を排出しない純国産のクリーンエネルギーです。雪をエネルギーとして活用する方法は、主に食品などを低温貯蔵する「雪冷蔵」と、建物の空調などに使われる「雪冷房」に分けられます。雪冷蔵、雪冷房を行うためには、大量の雪を長期的に備える「貯雪庫」を造ります。いうならば、断熱性を備えた『現代版の雪室(天然冷蔵庫)』です。雪室は電気冷蔵庫とは明らかに異なります。電気冷蔵庫では通常、設定温度に対してプラスマイナス2~3度を繰り返します。この温度差が食品にはストレスになりますが、雪室は年間を通して、ほぼ0度を保つので温度ストレスを与えます。さらに、雪室に貯蔵した食品には次の効果があります。低温純化(低温糖化)——食物が自ら凍結を防ぐために、含有するデンプンを透過させるので、甘味が増します。鮮度保持——低温高湿度の環境は乾燥や細胞のお灸を抑えるので、新鮮さが長く保たれます。雪室氏貯蔵したコメは年中、新米状態です。酸化防止——低温下では酸化反応の速さが鈍るので、酸化による食品の劣化が進みません。不快臭の低減——不快な臭いの成分を抑えるだけでなく、不快臭の生成も抑制するので、食品の風味が向上。雪の表面には空気中のごみやちり、有害物質を吸着する性質があります。2002年、新潟県上越市内の小学校で世界で初めて雪冷房が導入されました。私もシステム設計に携わりました。以来、公共施設のほか、米穀販売会社や酒造会社などが雪冷房・雪冷蔵設備を導入し、大小合わせて全国200カ所以上に設置されています。 スノーフードバレー構想私が進める利雪技術の研究開発は、雪と共に生きた先人の知恵を現代にふさわしい形でよみがえらせ、雪国を豊かにしていく取り組みです。雪室を中心とした雪の利用者を通して、地域資源を見直し、雪貯蔵品を特産品に成長させるとともに、雪国の魅力発信に努めています。例えば現在、行っている「雪室留学」。日本各地で生産された食品を雪国に輸送し、雪室で熟成させて高い付加価値を与えます。それを需要に応じて国内外に供給する仕組みです。食品だけではありません。低温保管が必要な衣料品にも対応できます。網の目のように物流が発達している現代では、雪国が「低温倉庫のハブ(地域の拠点)」、ひいては「日本、アジアの食糧庫」として発展する可能性を秘めている私は思います。IT産業が盛んなアメリカ西海岸がシリコンバレーとなったように、雪国に雪を利活用する産業が盛んになれば「スノーフードバレー」が実現するのではないでしょうか。雪による熟成、貯蔵、感想など、雪の可能性は、まだまだ追及する価値あるものばかり。私たちが雪の性質を理解し、その力を生かすことができれば、雪国にももっと新しい産業が生まれていると思います。雪国のある小学校に出前授業に出かけた際、児童に「雪が溶けたら何になる?」と聞きました。大人なら「水になる」と答える人が多いでしょう。ところが、児童は「春になる!」と。私は、今の時代にふさわしい雪国の生活様式や文化をつくり、雪国にお希望の春を届けていきたい。人間が雪に寄り添い、雪と上手に付き合うことで、雪は〝空から降る宝もの〟になるのですから。 いとう・よしおみ 1971年、愛知県生まれ。室蘭工業大学大学院工学研究科博士後期課程修了。工学博士。日本雪工学会理事。東京農業大学客員教授。〝雪のエンジニア〟〝利雪アドバイザー〟として、食品などに付加価値を与える雪冷蔵庫など、現代にマッチした利雪施設の開発・普及に尽力。著書に『空からの宝ものが降ってきた! 雪の力で未来をひらく』(旬報社)など。 【環境】聖教新聞2025.1.19
September 19, 2025
コメント(0)
-
第八十七 和辻哲郎と「法華経」
第八十七 和辻哲郎と「法華経」 哲学者・和辻哲郎博士が『法華経』の研究所を残していたことを知る人は少ないであろう。それは、「法華経の考察」と題して雑誌『心』(一九五六年十、十一、十二月号)に掲載されたが、一冊の単行本として出版されたことがなかったからだ。晩年の和辻は、病床にあって、死を予期しつつも弛むことなく精力を込めて探求し続け、『心』に掲載された「阿毘達磨論について」「煩悩の分析」「ミリンダ王問経と那先比丘経」などとともに、「法華経の考察」に雑誌掲載後も加筆増補を行っていたが、未完の遺稿となっていた。それらの遺稿の校訂を中村元先生が手がけられ、和辻博士没後二年目の一九六二年に出版された『和辻哲郎全集』(岩波書店)第五巻の後半に「仏教哲学の最初の展開」として収録された。「法華経の考察」は、その中の後編「大乗経典にいたる仏教哲学の展開」の第二章として収められている(四八六~五六八)。和辻博士は、初めは西洋の思想や文化を研究しておられたが、二十九歳を境にして日本の古代文化の研究を始められた。日本文化の研究は、仏教の理解なしには行われえないということに気づいて、仏教思想を源流から研究することに取り組んだ。その研究の第一弾が『原始仏教の実践哲学』であり、それが学位論文となった。宇井伯壽博士は、その諸について「その優れた力作なる点においてはすでに学界の驚異とまで激賞せられ、影響を及ぼせることも多く模倣者を出すほどに認められた」(『印度哲学研究』第四巻、三五二~三五三頁)と記している。中村先生は、「日本では〔中略〕文献学的研究のほうに主力が注がれているので、〔中略〕思想的研究は数少ない。これは全くユニークなものである」と、その全集五巻の「解説」に記している。多くの仏教学者たちが、伝統的な視点にとらわれがちであったのに対して、和辻氏は思想としてのアプローチをしておられて、大いに刺激を受けた。東京大学教授の木村泰賢氏と論争を繰り広げ、仏教学者たちを驚愕させたという。私も、〝思想として〟仏教を研究することを目指していたので大いに刺激を受けた。ただ、久遠実成の釈尊を「法身仏」としていることは、私と意見を異にするが、(第五十五話「法身如来は形容矛盾」を参照)、その思想としての仏教へのアプローチは参考になった(和辻博士の考察内容については、全集第五巻を読んでほしい)。何よりも、その「第二章 法華経の考察}の冒頭で阿辻博士は、『法華経』が仏教伝来、最も広く知られ、祖先の間でポピュラーで民衆に親しまれていたことから書き始めている。そのことを示す具体例として、日本人のだれもが知っている牛若丸、後の源義経についての、南北朝から室町時代初期に成立したといわれる軍記物語『義経記』に描かれている義経と武蔵坊弁慶との出会いの場面を紹介している。牛若丸というと、今日の五条大橋で弁慶と戦って、負けた弁慶が家来になった……という話を我々は聞かされてきた。その大筋は、同じだけれども、それ以外のことが書いてあったというのだ。あと一振りで千振りの大刀が集められるというので、弁慶が五条天神近くの築土のほとりで待ち受けている。そこへ牛若丸が笛を吹きながらやって来て、弁慶が切りかかる。しかし、一晩目は逆に太刀を取り上げられ折られてしまう。二晩目は、清水坂の上で待っていて、今度は長刀で挑みかかったけれども、軽々とかわされた。牛若丸は近くの観音堂へ入り込む。それを追っかけて行ったら、そこにはお経を読んでいる人が大勢いた。それは『法華経』であった。大勢の中で、牛若丸は女性の衣装で衣をかぶっているから、見分けがつかない。弁慶は後ろから一人一人ついて牛若丸を探し回る。見つけると、牛若丸が持っていた経典を奪い取って、一緒に『法華経』を読誦し合った。その場面を『義経記』から引用すると、 御曹司の持ち給へる御経を追つ取って、ざつと開いて、「あはれ御経や、御辺の経か、人の経か」と申しける。されども返事もし給はず、「御辺も読み給へ、我も読み候はん」と言ひて読みけり。弁慶は西塔に聞こえたる持経者なり。御曹司は鞍馬の児にて習ひ給ひたれば、弁慶が甲の声、御曹司の乙の声、入り違へて二の巻半巻ばかり読まれたる。参り人の永夜撞きもはたはたと鎮まり、行人の鈴の声も止めて、これを聴聞しけり。万々世間澄み渡りて尊く心及ばす。 弁慶は、御曹司(源義経)が持っていた経を奪い取ると、ざっと開いて、「なんと経ではないか、お主の経か、それとも他人の経か?」と尋ねた。義経は返事をしない。弁慶は「お主もお経を読め。わしも読もう」と言って読み始めた。弁慶は比叡山西塔に名の聞こえた『法華経』を受持する者であった。御曹司は鞍馬寺の稚児であって経を習っていたので、弁慶の高い調子の声と、御曹司の低い調子の声が、入り混じって第二巻の半分ばかりを読んだ。参詣していた者たちが一晩中鳴らす鐘の音も次々に鎮まり、仏道の修行者も鈴の音を止めて、二人の読経に聞き入っていた。読経の声はすみずみまで澄み渡り高貴で心の思いも及ばないほどであった。しばらくして、帰ろうとする御曹司を引き留め、弁慶は太刀を求めて勝負を挑んだ。散々に打ち合った末、打ち負かされた弁慶は牛若丸の家来になった——という話である。その描写は、和辻博士が指摘しているように、二人の「勝負よりむしろ法華経読誦の方に作者が力を入れている」それを読んで、和辻博士は、次のように感想をのべている。 明治の中ごろに生まれたわたくしたちは、牛若丸と弁慶との五条の橋における出合を、ぜんぜん法華経などと関係なしに教えられた。だから、大人になってからずっと後に、初めて『法華経』を読んだ時、この法華経合誦の描写を見て、実に驚愕に近い印象を受けたのである。〔中略〕弁慶は比叡山の西と塔の持経者であり、牛若丸は鞍馬の寺で教育を受けたのであるから、彼らがお経のうちの最もポピュラーな法華経を知っていたからと言って、少しも不思議なことはない。しかるにわたくしどもが日本おとぎ話において読まされた牛若丸や弁慶は、法華経などとはまるで無縁の人であるかのようにわれわれの心に印象づけられていたのである。 和辻博士は、これに続けて、さらに次のように記している。 これは何も牛若丸や弁慶に限ったことではない。われわれが明治時代に受けた教育は、全体にわたって法華経などと縁のないものであった。現にわたくし自身は、法華経の内容について何一つ知ることなしに大学を、しかも文科大学を、卒業することができたのである。 このように、日本の教育の偏りと、自らが『法華経』に無知であったことを反省する言葉を綴っている。その実態は、明治の教育に限らず今も変わっていない。私もそれを読んで、日本の文化、文学、芸術に与えた『法華経』の影響について学ぶべきだと痛感した。 【今を生きるための仏教100話】植木雅俊/平凡社新書
September 18, 2025
コメント(0)
-
阪神・淡路大震災から30年
阪神・淡路大震災から30年災害を〝わがこと〟とする想像力 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から、きょうで30年となる。大都市を襲った直下型地震は、老朽化した建物の倒壊など甚大な被害をもたらし、多くの尊い命を奪った。一方でこの時の教訓は、災害の備えや復興の在り方を見直すきっかけとなってきた。南海トラフ地震、首都直下型地震などの大規模災害がそう遠くない将来に起こるとされている今、過去の災害の記憶をどう未来に生かすべきか——。大震災当時、京都大学防災研究所教授で、現在は震災伝承施設「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」のセンター長を務める河田惠昭氏に聞いた。(聞き手=水呉裕一) インタビュー阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター河田 惠昭(としあき)センター長必死の救出現場でのテレビ取材——阪神・淡路大震災が起きた日、河田センター長はNHKのニュース番組で、被災地から実況中継で災害現場の状況を伝えておられます。30年前の1月17日をどのように振り返りますか。 あの日、突き上げるような激しい揺れで跳び起きました。午前5時46分のことです。私は、大阪市北区のマンション3階の自室で、幼い娘を挟んで妻と川の字になって寝ていました。自身に備えて家具をクローゼットの中に入れるなどの対策をしていたため、災害はほとんどありませんでした。しばらくして、NHK大阪放送局から午前10時のニュース番組に出演してほしいとの依頼があり、テレビ局に向かいました。その時はまだ被害の全容が分かっておらず、限られた情報の中で話したことを覚えています。その後、テレビクルーに同行する形で被災地に入ったんです。最初に向かった神戸市東灘区では、倒壊した家に閉じ込められた住人を助け出そうと、多くの人が必至で屋根瓦を剝いていました。この状況を撮影してよいのかと逡巡しましたが、「災害の様子を全国に伝えてほしい」とその場の人々に言われ、取材を続けました。東灘区役所で区長にインタビューしたときは、区長室に30代半ばの男性が祖母の遺体を抱えて入ってきて、「どこに安置すればよいでしょうか」と相談に来た場面に遭遇しました。区長がその場で安置所を決め、職員に指示を出していました。まさに現場は待ったなしの状況でした。その後、兵庫・芦屋市の被災地を回っていた最中に、偶然にも近くにNHKのテレビ中継車が止まっていることが分かりました。夜のNHK総合テレビで実況中継することが決まり、撮影した映像を放送するとともに、被災地で何が起きているかを話しました。 南海トラフ地震に備えるために——河田センター長は震災後から毎日、被災地を回って調査をされたそうですね。どのような思いで現場を歩いたのでしょうか。 ただ無力感でいっぱいでした。一生懸命に災害研究をやって来たのに、いざというときに被害を軽減させる何の役にも立てなかったことが、悔しくて仕方がありませんでした。被害に遭った方々に聞き取り調査したときのことを今でも思い出します。2階建ての一軒家に2世帯5人で暮らしていた家族からは、こんな話を伺いました。その家では、おじいちゃんとおばあちゃんが1階で生活し、幼稚園児の女の子は「今日は、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に寝る」と言って、その比に限って1階に下りていったそうです。翌早朝の地震で天井が落ち、その子だけが犠牲になりました。「何で自分が死ねへんかったんやろ」——残された家族の言葉が忘れられません。このほか、被害者に話を聞くと、だれもかれもが悲惨な経験をしていまいました。災害研究は、どこまでも実践的でなければ意味がない。私はこのことを痛いほど実感しました。当時、地震学者での間では、阪神・淡路大震災を〝南海トラフ地震〟と位置付けていました。いずれもっと大きな地震が起きることを考えると、私はこの災害から学ばなければいけないと思いました。そして現場を歩いてみると、家も道路もめちゃくちゃですが、その壊れ方は場所によってそれぞれ異なる特徴があることが分かりました。被害が出た原因を部分的にでも見落とすことがあってはならないとの覚悟で、その後もすべての被災地をしらみつぶしに調査して回ったんです。 手を取り合った被災地での歩み——災害の研究のほか、被災地の復旧や震災の記憶の継承にも尽力してきた河田センター長は、現在の復興の姿をどのように見ていますか。 当時の被災状況を思い起こすと、街は想像以上の復興を果たしたと思います。これは、特定のだれかではなく、被災地に関わるありとあらゆる人々が手を取り合い、復興を目指してきた結晶に他なりません。私がそう実感するのも、足を運んだ被災地で、復興のために尽力する人々を見てきたからです。阪神・淡路大震災から、ちょうど1年後、震災の教訓を未来へ残すこと目的とした「メモリアル・コンファレス・イン神戸」というイベントを開催しました。この会議の特徴は、参加者を地震の専門家に限らず、一般公募したことにあります。私自身、イベント実行委員会の幹事長を務めましたが、委員会に集ったのは、被災者をはじめとする市民や行政関係者、研究者、技術者、企業人など、あらゆる分野の人々が80人。イベント参加者は、1000人を超えました。お好み焼きソースなどを製造する会社の社員が参加すると聞いた時には、〝こんな人まで参加してくれるのか〟と驚きました。その社員は自社工場で被災した状況にあって、地域の今後の発展を考え、同じ場所で再建するべきか、それとも移転すべきかを真剣に悩んでいました。もし私が研究だけに専念していたら、こうした人々の悩みをじかに聞くことはなかったでしょう。当事者の生の声を聴くことで初めて認識する課題もあります。当然のことですが、被害の影響は被害に遭った地域に関わる全ての人に及びます。復興に踊無上で、その地域にタス触る人々が、立場や分野を超えてつながり、互いに知恵を出し合わないと、必ず支援の手から零れ落ちてしまう人が出てしまいます。このイベントは2005年まで毎年、それぞれの立場で得た教訓や、抱える課題を共有しながら復興を目指して開催してきました。10年を一区切りとして「災害メモリアルアクションKOBE」と名称を変え、実行委員も次世代に引き継ぎ、今も大震災の教訓を発信し、次の災害に備える活動を続けています。 復興を果たしてきた連帯の力命をつなぎ止める 人の優しさ 防災の習慣化が身を守る対策に——阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」でも、展示などを通じて震災の記憶を伝える活動を続けておられますが、教訓を未来に生かすためには、どのような視点が大切だと思いますか。 災害を〝わがこと〟と捉えることです。阪神・淡路大震災の際に行った聞き取り調査を思い起こしても、同じ災害に遭っていながら、誰一人として同じ体験をしている人はいませんでした。住んでいる場所や置かれている状況も異なるため、いざというときに〝自分ならどうするか〟と想像し、自分で行動することが求められます。防災において、どこまでも大切なのは自分の命は自分で守るという姿勢です。それがどうも、今の社会には、自分の命が危険にさらされことへのリアリティーに乏しく、他人任せになってしまっている人がいるように感じます。自分の「命」を守ることを考える上で、たとえば「健康」という言葉に置き換えてみるとどうでしょうか。自分の健康を維持するために、食事や運動、睡眠などの生活習慣に気をつけている人はとても多いと思います。防災に求められる考え方も全く一緒です。私は仕事柄、上京することが多いのですが、新幹線に乗る時は、必ず飲み物と駅弁を買って乗車します。事故など新幹線が止まったら、簡単には運転再開しませんから。また上京した際には特に、災害時の停電に備えて、電子ロックのコインロッカーは使わないようにしています。こうしたルールを生活主観の中で定め、地震をトレーニングしていく中で、不測の事態に陥ったときにも対応できる自分自身になっていけると考えます。 〝関連死〟を防ぐ人とのつながり——教訓を単なる知識としてではなく「自助」の心を育む糧にすることは必要ですね。南海トラフ地震などの大規模災害が起こるといわれる今、河田センター長が懸念していることはなんでしょうか。 人と人とのつながりの希薄化してることです。他人に干渉していないことを是とする社会の風潮の中で、「共助」の働くつながりが弱まっていくことを懸念しています。いざ災害が起きた際に、いくらボランティアの人に協力してもらっても、日常的なつながりのある人との支え愛に勝る安心感はありません。多少〝お節介〟になるぐらいがちょうどいいんです。実は、昨年3月に出る予定だった南海トラフ地震の被害想定の更新結果が、まだ発表されていません。避難生活の疲労やストレスなどが原因で亡くなる「災害関連死」の推定ができないからです。昨年の元日に能登半島地震が起きましたが、11月に能登の関連死の数が、熊本地震の数を上回り、今も増え続けています。震度6弱以上の地域に住んでいた人は能登半島地震が17万人、熊本地震が148万人と、被災者の絶対数がこれだけ違うにもかかわらずです。避難所の居住環境や医療体制など、改善できることは全部やろうと努力していますが、根本的な解決にはいてっていません。被災すると、人は肉体的でなく、精神的にも傷つきます。見えない〝心の傷〟は簡単には治りません。単に時間が解決してくれるものでもないと思います。この30年の復興を振り返る中での実感ですが、そうした〝心の傷〟を追いながらも、生き方を変えることができた人や、何かを信じることができた人、〝災害に負けてたまるか〟と前を向けた人は幸せになっているように思います。そうした人々が前を向けるようになったのも、人との関りや励まし合いがあったからにほかなりません。目の前の一人の苦しみを〝わがこと〟として、困っている人がいれば声をかけて寄り添う。想像を絶する被害が出るであろうと災害に際して、そうした「人の優しさ」は絶対に必要です。阪神・淡路大震災から30年というときに当たり、改めて一人一人が災害への備えを振り返るとともに、今の社会委の風潮を見つめつつ、未来に起こる災害の被害を想像して、自分には何ができるかを考えてもらいたいと思います。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」】聖教新聞2025.1.17
September 18, 2025
コメント(0)
-
スケッチの楽しみ
スケッチの楽しみ山田 雅夫(建築家)なぞり描き、1色濃淡描くための感覚を身に付ける「気がする」を「描ける」に木になる建物や風景をスケッチとして残すのは楽しいもの。写真とは異なり、描いている間、ずっと対象を向きあうことになります。しかし、シャッターを切ればいいだけの写真と比べると、描く作業にはちょっとしてコツが必要です。例えばリンゴ。一見すると誰にも描けそうに思えるはず。でも、実際に描いてみると、ずれたり歪んだり、どうして描けないんだろうと思うことでしょう。実際、私の教室に来る生徒さんたちも、だれもが簡単に描けそうな気がすると、声をそろえて言います。でもやってみるとうまくいかない。この、「描けそうな気がする」を、「描ける」に持って行くためのトレーニングがあるのです。そのために近著『決定版 スケッチ練習帖 3週間ドリル』(あかり舎)を出しました。ポイントは「なぞり描き」と「1色濃淡」です。以前、スケッチの第一歩として、縦横2本の線で描く長方形と、そこに内接する陀円を描く練習を提案しました。これは自分が描きたい線を、実際に描くための練習です。今回は、そこから一歩進んで、物の形を捉えるための「なぞ描き」、立体感を出すための「1色濃淡」です。 自由に動かせるような手に思っている絵が描けない要因にいくつかあります。一つは、頭の中で描きたいものが組み立てられていない場合。例えば、海岸線の風景をj見た時に、どこを省略して描くのか。印象的な浜辺を描くのは難しいものです。でも、そこに一艘の小舟があるとどうでしょうか。波間に漂っていても、浜辺に引き上げていても、小舟を中心にすることで、絵が引き締まって見えるはず。このような構図は、センスにもよるかもしれません。しかし、描いてみようと、その景色に引かれたのには、何か理由があるはず。シンボリックな建物があった、海の中の小舟が印象的だったなど。そう言う者を中心として、構図を考えるのは、写真と同じです。ただ、絵の方が余計なものは描かなくて済む自由さがあります。もう一つの要因は、頭の中で作り上げたイメージを、紙に描けないことです。実は、私たちが思っている以上に、手は自由に描けないもの。自由に動かせるようにするには、スポーツと同じようにトレーニングが必要なのです。そのための「なぞり柿」です。 自然がつくる曲線は美しい皆さんは、富士山を見たことがあるのでしょうか。実際に見たことがなくても、テレビや写真などで見たことがあるはず。富士山の絵を描けるでしょうか。富士山の稜線は、一見すると直線で結ばれているように思えるかもしれません。実は、ひもなどを吊るしたときにできる「懸垂曲線」でできています、しかも、皆さんが思っている以上になだらかで、雄大さを感じるはずです。このように、自然が生み出したカーブは、何度でも手で描く練習をすると、美しさが実感できると思います。果物のリンゴにしても、独特な形をしています。いろいろな曲線がつながってできているので、形を捉えるのが難しい。だから、頭の中ではリンゴの形が分かっているのに、手で描くのが難しいのです。「なぞり描き」を繰り返すことで、こうした物の形のパターンを理解できるはずです。また、立体感を出すためには濃淡が重要です。ギリシャ神殿の柱を思い浮かべてください。白い円柱の表面に、さまざまな意匠が掘り込まれています。これをいくら細かく描いたとしても、単なる模様にしか見えません。しかし、影のグラデーションをつけると、立体的な形が瞬時に浮かび上がってきます。実際の形をどのように捉えて、どのように描いていくのか。絵は感性を描くものだと思われています。しかし9割以上は描き方の説明がつくもの。多くの人に、手軽にスケッチを楽しんでもらえたらと思います。=談 やまだ・まさお 1951年、岐阜県生まれ。都市設計家、速描スケッチの第一人者。つくば科学万博の会場全体設計者、横浜みなとみらい地区の事業化案作りにも携わる。首都圏のカルチャーセンターで、スケッチや絵画講座が人気に。著書に『スケッチ練習帖』『スケッチは3分』など多数。 【文化Culture】聖教新聞2025.1.16
September 17, 2025
コメント(0)
-
大村益次郎
大村益次郎司馬遼太郎氏の数ある作品の中でも、歴史家の磯田道史氏が〝最高傑作と語る『花神』を40年ぶりに再読。幕末期に活躍した維新十傑の一人、大村益次郎の物語だ◆生まれたのは200年前の1825年。緒方洪庵の適塾で医学や蘭学を学んだが、長州の桂小五郎に軍略的才能を重用され、四境戦争(長州征伐)で攻めてくる幕府軍を撃破。戊辰戦争を勝利に導き、新政府の近代兵制を進めた◆大村は、戦いに勝つという一点で徹底した合理主義を貫いた。磯田氏は『「司馬遼太郎」で学ぶ日本史』の中で、『花神』では日本人の形式主義というものが存分に否定されています。合理主義の反対は不合理主義……多くの場合、不合理を生み出しているのは、言ってみれば形式主義なのです」と◆花神とは中国の言葉で〝花咲かじじい〟を意味する。時代の転換期に彗星のごとく現れて、枯れ木に花を咲かせるように新たな道を開いた源だろうか。「常識を発達させよ。見聞を広くしなければならぬ。小さな考えでは世に立てぬ」との明言が伝わる◆国内外の情勢が混迷を深める激動の時代だからこそ凝り固まった古い考えに縛られてはならない。見聞を広く深く、そして清新な息吹で前に進みたい。(祐) 【北斗七星】公明新聞2025.1.15
September 17, 2025
コメント(0)
-
最新研究「睡眠の謎」㊤
最新研究「睡眠の謎」㊤今日のポイント〝黄金時間(ゴールデンタイム)〟は存在しない柳沢教授人生の3分の1の時間を費やし、日々の健康に直結する睡眠。ノーベル賞級といわれる、睡眠に関わる物質(オレキシン)を発見した医師・柳沢正史教授(筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構長)に、最先端の睡眠額を語ってもらいました。 〖レム睡眠も深い眠り〗睡眠は、現代神経科学最大のブラックボックスの一つです。「脳を持つ生物は、外敵に気付きにくくなる〝意識のオフライン化〟を、なぜ毎日行うのか」「何が動物の〝眠気〟をもたらし、制御するのか。そもそも眠気の実態とは?」例えば、身体運動を行うと、よく眠れることはみなさんご存知でしょう。この理由も、いまだに解明されていません。なお、都市を重ねると、深い眠りができにくくなることは自然です。高齢者で「深く眠れなくなった」ことをおかしいと悩むことは、かえって不安で眠りが悪くなりかねず、睡眠障害の入り口に立つことになります。寝てすぐ訪れる「ノンレム睡眠」は眠りが深く、夜の後半に増え鮮明な夢を見る「レム睡眠」は眠りが浅い、とよくいわれます。しかし実際には、レム睡眠も深い眠りで、心身の健康のために重要であることが分かっています。睡眠に「ゴールデンタイム」はないのです。 〖悪い夢は見た方が良い?〗夢の中身は、ストレスの大きい内容が多いといわれます。一方、それは現実に起こってしまったときの〝耐性〟をつけている可能性も指摘されています。悪い夢を見た時は、〝予行演習〟ができたととらえて、「見ておいてよかった!」と思いましょう。 〖夜の光は有害〗体内時計を調節するのは、目の奥にある網膜神経細胞です。その細胞が光(ブルーライト)を検知すると、脳は朝だと捉えて体内時計をリセットします。夜に目に入る明るい光は、睡眠学的には〝有害〟でしかありません。夜のホルモンといわれ、眠りを誘うメラトニン。その分泌中に眠れば深い眠りになりますが、日中は、ほぼ分泌されません。また、眠りを誘う〝深部体温〟の降下も日中にはありません。残念ながら、夜勤の人がぐっすり眠ることは、生物学的には困難と言わざるを得ません。 徹夜した脳は〝酩酊〟と同じ 〖日本人は最も寝ない国民〗経済協力開発機構(OECD)の統計では、日本人の睡眠時間は、欧米の平均より1時間以上も短く、最も少ない7時間20分程度。〝世界で最も寝不足な国民〟といえます。日本人は〝昼間の眠気〟は普通だと捉えますが、奥州では、体調不良の兆候だと認識されます。国民1人当たりの国内総生産(GDP)の値と睡眠時間との関係を調べると、生産性の高い国は、押しなべて睡眠時間が多い。一方、日本人は1理当たりのGDPの値もそれほど高くなく、睡眠時間が極端に少ない。睡眠を削って働いても、経済的な豊かさにつながっていないのです。なお、昔から日本人の睡眠時間が少なかったわけではありません。平均時間は、1960年の調査では、今より約1時間多かった。しかも平均就寝時間が早く、今よりずっと〝早寝〟の国民でした。働く世代の睡眠時間が絶対的に短い現代の日本社会では、睡眠時間の質を論ずる前に、睡眠時間の確保が優先です。 〖睡眠時間が短いと病みやすい〗睡眠時間が短くなると、病気にかかりやすくなることは強いエビデンスがあり、医学的に確立されています。特に、「うつ病などの精神疾患」「メタボリック症候群」などにかかりやすくなります。睡眠時間が〝不規則〟になっても、循環器系疾患等のリスクが高まります。また、高齢者を12年追い続けた外国のデータによると、レム睡眠が「5%減るごとに〝総死亡率〟が、13%上昇した」「1%減るごとに、認知症リスクが9%高くなった」と報告されています。脳は、睡眠時間が減るほど能力が落ちます。97年に出た有名な論文によると、徹夜明けの農のパフォーマンスは酩酊状態(血中アルコール濃度が0.1~0.2%)と同程度です。慢性的な寝不足は、どうでしょうか。20~30年代に行った実験研究では「4時間睡眠×6日」「6時間睡眠×10日」は、どちらも徹夜明けと同じ能力に堕ちました。 〖性格も悪化する?〗睡眠が減ると〝性格〟も悪くなります。アメリカでは、冬時間から夏時間(サマータイム)に移行する一日は、国民全体の睡眠時間が1時間減る日です。実はその一日は、ドネーション(寄付)の金額が毎年減っているという研究があります。人間という生物の〝利他的行為〟が抑制される日だといえます。また、社員のどのような要素に門買いがあると、企業の〝損失コスト〟が高くなるかを推計した、経済産業省の研究があります。それによると、「肥満」「運動」より、「睡眠」に問題があった場合が、損失コストが約10倍も高くなりました。睡眠に問題があると、仕事の持落ちベーションが下がったり、ストレスで人間関係が悪化したりするからだと推測されています。さらんは〝社員が睡眠時間を長く取れている企業ほど、利益率が高い〟と言う研究も発表されています(慶應義塾大学商学部・山本勲教授の研究)。 〖寝ない大人は横に育つ〗「肥満でない男女が、4時間睡眠を2週間続けると、どうなるか」を研究したデータがあります。興味深いことに、1日の摂取カロリーが約300㌔㌍増え、内臓脂肪が11%も増えていました。逆に、肥満気味の人が睡眠を1日1時間増やすごとに、カロリー摂取が1日当たり1500㌔㌍。減るという報告もあります。「寝る子は育つ」ということわざがありますが、「寝ない大人は横に育つ」ということです。太り気味の人は、十分な睡眠を取ってください。 メディカルトピック💊血圧、正しく測らないと…正しい方法で血圧を測らないと、数値が高くなって高血圧の護身につながる恐れがあるとの研究結果を、米ジョンズ・ポプキンス大学の研究チームが米医学誌に報告しました。米国新造協会のガイドラインでは、測定時は上腕に幕「カフ」を心臓と同じ高さにし、腕はテーブルなどに置きます。18~80歳の133人を対象にした実験では、手を膝に置いただけだと収縮期血圧(血圧の一番上)が3.9(単位は㎜Hg)、腕をぶら下げた支え無しだと同6.5、測定値が高くなることが分かりました。同ガイドラインでは他に、背もたれに背中を当てることや、足を組まずに両足を床に付けることなどを求めています。 【医療MedicalTreatment】聖教新聞2025.1.13
September 16, 2025
コメント(0)
-
視力維持や皮膚の健康に不可欠
視力維持や皮膚の健康に不可欠女子栄養大学短期大学部 助教 新木 由希子ビタミンA 今月からは脂溶性ビタミンを取り上げます。その名の通り油に溶ける性質を持ち、ビタミンA、D、E、Kの4種類が知られています。今回は、ビタミンAを紹介します。ビタミンAは、視力の維持や皮膚の健康に不可欠なビタミンで、レチノールやレチナール、レチノイン産などの総称です。β(ベータ)カロテンは、小腸上皮細胞でビタミンAに効率よく吸収されるため、「プロビタミンA(ビタミンA前駆体)とも呼ばれています。ビタミンAには、大きく分けて二つの形態があります。動物性食品に含まれるレチノールやレチナールと、植物性食品に含まれるβカロテンなどのカロテノイドです。不足した場合、夜間の視力が低下する夜盲症などの症状が現れます。一方、取り過ぎれば肝臓に蓄積され、頭痛や筋肉の不快感といって副作用を引き起こす可能性があり、注意が必要です。ニンジンやカボチャ、ホウレンソウなどの緑黄色野菜は、βカロテンを豊富に含み、食卓にいろどりを添えてくれる食材です。効率よくビタミンAを摂取するためには、油と一緒に食べることがポイントです。野菜を油でいためたり、サラダに油を使ったドレッシングをかけたりすることで、食事の中で吸収率を高められます。 ニンジンとガボチャのヨーグルトサラダ〖材料=2人分〗ニンジン120㌘、塩小さじ1/6、水、レモン汁各小さじ1、カボチャ80㌘、ヨーグルト大さじ、マヨネーズ大さじ1、塩小さじ1/8、こしょう少々〖作り方〗1、 ニンジンは皮をむき、千切りにする2、 1に塩と水を加え、混ぜながら、しんなりさせる。3、 2を絞り、レモン汁を加えてよく混ぜる。4、 カボチャは1.5㌢角に切り、電子レンジ(600W)で2~3分加熱して冷ます。5、 残りの食材でドレッシングを作る。6、 3と4を混ぜて器に盛り、5をかける。 【Vitaminの効能10】公明新聞2025.1.12
September 16, 2025
コメント(0)
-
第22回 細胞から見た病気
第22回 細胞から見た病気福岡山王病院 病理検査部長 土屋 正文さん 生命の基本単位から捉えた人体の調和と混沌病気の原因は何か。それが正確に分からなければ適切に治療することはできません。御書に、「病の原因を知らない人が病気を治療しようとすれば、病はますます倍増する」(新1241・全921、通解)とある通りです。その病気の診断をするのが、わたしたちの病理医の仕事で、具体的には、採取された細胞や組織を顕微鏡で観察し、異常や疾患を診断しています。なぜ細胞を見ると病気がわかるのでしょうか。素おれは細胞こそ生命の基本単位で、複雑に思える人体も37兆個という細胞の集まりだからです。そして大ざっぱな言い方かもしれませんが、病気は、その多くが「細胞が痛むこと」で治療は「細胞を治すもの」であり、「傷んだ細胞を取り除くこと」であるからです。 身体の四つの要素顕微鏡で観察される人体の臓器や組織は通常、とても美しい調和の世界です。しかし、そこにウイルスが入り込んだり、がんなどの腫瘍ができたりすると、その調和が乱れ、混沌の世界が生まれます。調和と混沌——これは病理学が専門であるカナダ・モントリオール大学元学長のルネ・シマー博士が、池田大作先生とのてい談『健康と人生—生老病死を語る』で指摘した点でもあります。この時、シマ―博士の〝細胞内の調和に何らかの変化が起こり、カオスの状態になる。そこに病が発生する可能性があると考えています〟との発言を受け、池田先生は〝仏法も調和と不調和という視点から生命現象をとらえています〟と語り、「四大」という考え方を紹介されました。「四大」とは、「地」「水」「火」「風」のことで、仏法では、これら四つの要素で見ん体は形づくられ、その調和が乱れる時に病になると説いています。「地」とは「固さ」を表し、形を保持しようと記さ用のこと。人体では、骨や、皮膚、筋肉のことです。「水」とは「湿り気」のことで、ものを摂め、集める作用。主に血液、体液のことです。「火」とは「熱さ」のことで、ものを熟成させる作用。発熱や体温、消化作用、またエネルギーの働きなども「火」に当たります。「風」とは「動き」で、ものを増長させる作用を指します。私たちの体内では呼吸、新陳代謝のことです。もちろん、四大は、現代医学とは異なる体系です。しかし、私は、この仏法の考え方は、生命の傾向性をとらえていると思います。というのも、細胞が病気になることを考えると、不思議とこの四つに対応できるからです。 酸素がなければそもそも、細胞はどのように説きに痛み、〝病〟となるのでしょうか。細胞が損傷する原因は、細菌やウイルスによる感染、自己免疫の暴走、遺伝子の異常、廊下、放射線など、さまざまなものが考えられますが、最もダメージを受けるのは、酸素に関連するものです。細胞は、取り入れた酸素をもとに細胞内のミトコンドリアでエネルギーを生成し、自らを修復したり、周囲の細胞とやり取りしるためのタンパク質などを合成したりして、生命活動の源にしています。ですから、酸素がなければ生きていけません。酸素は血管を流れる赤血球を介し、各器官に運ばれますが、何らかの原因でその流れが遅くなったり、血栓などで血管がつまったりすると、酸素が不足し、細胞が傷んでしまうのです。またミトコンドリアがエネルギーを生み出す際、副産物としてつくられる活性酸素も、細胞に悪影響を与えることが分かっています。加えて、そのミトコンドリアに異常が生じても、酸素を使ってエネルギー生み出すことができず、やはり生きていくことはできません。この血栓などによる梗塞を「地」、血流の流れが滞ることを「水」、ミトコンドリアの以上による影響を「風」と捉えれば、「四大」が乱れることで細胞が病んでしまうのです。また「火」ということに関連し、老化現象を説明することもできます。実は、一つ一つの細胞は、分裂できる回数が決まっており、分裂を終えた細胞や、傷んでしまった細胞は、排除される働きが備わっています。しかし、老化した細胞の中には、そのはたらきを阻止する酸素を出すものがいて、排除されない場合があるのです。そればかりでなく、最近の研究では、この牢か細胞から炎症を引き起こす物質が産生され、周囲の細胞を傷つけてしまうことが分かっています。「火」の乱れといえるでしょう。 「ちょきん」が大切生きている以上、細胞の老化や損傷は避けられません。しかし、たとえ一つの細胞が傷ついたとしても周囲の細胞がそれを治し、支えてくれる働きがあります。その働きは、わたしたちの食事、睡眠、運動とも密接につながっていることから、自分の生活を見直すことが大切です。しこで、お勧めしたいのが「ちょきん」です。「貯金」を思い浮かべる方もいるでしょうが、今回、強調したいのは次の二つです。一つは「貯筋」、つまり筋肉を蓄えることです。腕や足など、筋肉を鍛えると大きく発達しますが、これは細胞が分裂して増えるのではありません。細胞自体が大きくなっているのです。この筋肉細胞は、先ほどの四大の乱れを鍛える作用があります。例えば筋肉細胞が発達すると、血流が良くなり、老廃物が取り除かれることで、梗塞を防ぐことができ、筋肉細胞から発せられるマイオカインという物質には、がん細胞の異常増殖を抑制する働きもあります。これは「水」と「地」の調和を保つ働きでしょう。またミトコンドリアが増殖し、古いミトコンドリアを取り換える力にもなります。これは「火」の調和に相当するでしょう。さらに前進の代謝を挙げ、脂肪を分解して敗亡を若返らせる働きがあり、これは「風」の調和に当たります。一般的には、「体力の本体は筋肉」といわれています。激しい運動は活性酸素を増やすので、無理は禁物ですが、筋肉を鍛える体操や運動を心がけたいものです。 「地」「水」「火」「風」の乱れが病に仏法の四大と対応する細胞損傷の原因 規則正しい生活を二つ目は「貯菌」です。これは、良い腸内細菌を蓄えることです。私たちの身体は無数の微生物が共存し、中でも腸内細菌は、高血圧や肥満、不眠の解消、認知機能の改善など、わたしたちの健康をさまざまな角度で支えていることが分かっていました。一例として、難病である潰瘍性大腸炎は、健常な人の腸内細菌を移植することで、その症状が改善されることが報告されています。こうした効果をもたらす「貯菌」にも、四大の乱れを整える作用があります。「地」「水」という観点では、動脈硬化を防いで血流を良くし、「火」という点では、感染症から身を守る免疫細胞の力を強めつつ、過度な炎症を抑制し、「風」という点では、酸化を防ぐ機能を高めることが分かっています。このほか、細胞自体が若返るオートファジー(自食作用)を促進させたり、ホルモンを生成して脳に送り、心を安定させたりする「脳腸相関」の重要性も知られています。腸内細菌をバランスの良いものにするためにも、野菜や根菜類、海藻類といった食物繊維が豊富な食材を日常的に摂取すること、また良質な睡眠が腸内環境を整えることから、規則正しい生活を心がけることも大切です。 心身のバランスを整える学会活動は健康長寿の力 「貯筋」も「貯菌」もその上で、この「貯筋」も「貯菌」も、調和の中で成り立っています。例えば、筋肉細胞が発達すると脂肪細胞は減りますが、適度な脂肪細胞は必要です。というもの、健康な脂肪細胞は血圧や血糖値を低下させ、血管壁の修復にも寄与する有益なホルモンを分泌しているからです。ですので、脂肪を落とすために運動することはよいことですが、過度な運動や絶食などで落とし過ぎてはいけません。しかし、反対に、脂肪細胞が多くなり過ぎても、人体に悪影響が出てしまう場合があります。多くの進行大腸がんなどでは、その周囲に脂肪が多量に付着していることが分かっています。これは生活習慣病に伴う「内臓脂肪」と呼ばれているものですが、その肥大した不健康な脂肪細胞からは、血管を収縮したり、血栓を形成したりする有害なホルモン分泌され、腫瘍の発生につながってしまうと考えられています。一方、腸内細胞を、大きく分けて「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」といった三つで構成されますが、善玉菌の割合が全体の2割程度であると、悪玉菌や病原性細胞の増殖を味方につけて、良好な腸内環境がともたれるようです。善玉菌の代表格は乳酸菌ですが、いくら健康のためといえ、乳酸菌ばかり摂取していると、腸内細菌のバランスが崩れてしまいますので、食事も、さまざまな腸内細菌が育つよう、多彩な食材を摂取することが大切になるのです。また「貯筋」はしかっりできているので、「貯菌」はおろそかにしていい、というものではありません。人体は、さまざまなものが密接にかかわりあっているので、運動はもちろん、食事も睡眠も含めて、生活リズム全体で総合的に工夫していくことが必要です。天台大師は「摩訶止観」で〝「火」が強くなって「水」を破ると、「火」の病気にかかる。反対に「水」が大きくなって「水」を破ると、「水」の病気にかかる〟と、そのバランスの大切さを教え、修行の時間を不規則な生活になったり、健康であることを過信して寒暖差を気にせずに過ごしたりする生活態度を戒めています。御書にある「四大順ならざるが故に病む」(新1359・全1009)とは、このことで、仏法はバランスの良い生活を教えているのです。 四菩薩の行動こそ御書には「四大」に関連して、上行・無辺行・浄行・安立行という四菩薩の一面を論じている部分があります。「御義口伝」の「火は物を焼くをもって行とし、水は物を浄むるをもって行とし、風邪は塵垢を払うをもって行とし、大地は草木をもって行ずるなり」(新1046・全751)との前後です。かつて池田先生は、この御文を通し、わたしたちが信心をしていく上での大切な心構えを指導されました。浄行菩薩の働きを「火」と対応させ、〝先頭に立つ人々の心に勇気と情熱の炎を点火し、皆の進むべき道を照らすリーダーと生き抜いていこう〟と。次に無辺行菩薩を「風」と対応させ、〝風が塵やホコリを払うように、いかなる困難をも吹き飛ばして、自由自在に活躍していくのだ〟。また、浄行菩薩を「水」と対応させ、〝濁世の真っただ中に飛び込みながら、とうとうと流れる水のごとく、常に清らかな境涯で周囲にも清浄な流れを広げていこう〟。最後の安立行菩薩を「大地」と対応させ、〝多様な草木を育む大地のごとく、全ての人をどっしり支え、励ましの栄養を送っていこう〟。そして、この四菩薩のすべてに「行」の字が含まれていることは意義深く、「行動」を貫いてこそ仏になることを教えているのだ——と。上行菩薩、浄行菩薩のところで先生が教えられた「率先の気持ち」や「清らかな心」をもって行動することで、脳内ではセロトニンが分泌されますが、これは自立神経を整え、細胞が働きやすい環境となることで、心身両面の働きを安定させる力になります。また無辺行菩薩のところで教える「風の前の塵なるべし」との心によってストレス物質として知られるコルチゾールの分泌が抑えられ、細胞の大敵と夏活性酸素の発生を抑制することができます。そして、安立行菩薩のところで教える、「人のために」との行動によって、ストレス軽減や免疫力アップ、そして細胞の若返りに効果のあるオキトシンという物質が分泌されることが期待されます。また私たちの日々の学会活動は、細胞の健康で言う点で見た時も、大変に友好なものだと私は思います。 先駆の魂を忘れず私たち九州の創価学会員が大切にしている魂——それは「先駆」です。いかなる戦いにおいても先頭に立ち、さまざまな困難を乗り越えながら勝利の歴史を築いてきました。この心意気こそ、四菩薩の省人に通じるものだと思います。そして、こうした道を率先して歩いてこられた先輩方が、都市を重ねても若々しく活躍する姿を見るたびに、先駆の生き方を貫いていく中に健康長寿の秘訣があると感じてきました。学会創立100周年となる2030年に向け、希望の未来を開く「世界青年学会 飛翔の年」が幕を開けました。私たち自身も常に挑戦の心を忘れず、地域の同志と共に、新たな民衆勝利の先駆の歴史を打ち立ててまいります。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」■創価学会ドクター部編■】聖教新聞2025.1.10
September 15, 2025
コメント(0)
-
生命のヘビのヒミツ
生命のヘビのヒミツ帝京大学教授 濵田 陽悠久の昔から世界の「生きた尺度」小学生の時に与えられた文房具には定規が入っていた。いろんな線を引き、座標を描き、そうしたものが基準であると思うようになった。何か、直線で、固く、動じないものがこの世界を理解する根底になると。けれども、里山へ、森へ足を踏み出せば、定規の代わりに折れた枝をひろって、っ子の世界には様々な形が満ちあふれていると感じることができる。そして、その背後に、動く者の気配を覚える。その代表が、ヘビだろう。ハリー・ポッターを知るわたしたちは、筆箱に定規の代わりにヘビが入っていたら、と想像することも自由だ。サン=テグジュペリも『星の王子さま』の冒頭で、大人にはまるで帽子にしか見えない、像を丸のみした大蛇の絵を描いている。古から人は、この世界の、いろいろなところに、動き、自在に姿を変える何かがあると感じてきた。世界最古のヘビの化石が出土し、縄文土器にヘビの生命力が象られ、芦原中津国との呼ばれた日本列島には、水田稲作が伝わる前、いたるところにヘビが棲んでいた。這う、食むなどの御言説のある蛇は、四つ足に足歩行、車輪では分け入ることができない茂みや水中にまで環境適応し、生態系のバロメーターにもなっている。この太古の地主から、先人たちは、地貰いなどの民族習慣により、地を受け継いだという感覚をもっていた。 日本各地の神話・物語に登場 ヘビといえば、恐ろしい、と思考がストップしてしまう近代的偏見から、今年こそ自由になってはどうだろう。脱皮や独から古代人はヘビの生命力を感じてきたのだ、というような、ありふれた解説の向こう側へ分け入ってみよう。ヘビの化身である大物主の神は、大国主の、農耕による国造りをサポートしたという。列島の環境を知り尽くしている存在として理にかなった神話だ。ある夜、オオモノヌシは、妻になったモモドヒメの櫛箱に隠れていて、本来の美しい姿を見せるも、驚いて声を上げた姫に誇りを傷つけられ、三輪山に還った。姫は落胆し、腰を落としたが、そこに突き立っていた箸に刺さって亡くなってしまった。葬られたのが邪馬台国の卑弥呼の墓とも推定される、日本最古の巨大前方後円墳、箸墓古墳だ。美しい三輪山は、とぐろを巻いた邪神そのものの姿だとも伝えられてきた。豊かなユーカラ(叙事詩)をもつアイヌやヘビをマームン(神のもの)と呼ぶ琉球、そして、ヤマタノオロチの龍邪様(セグロウミヘビ)の出雲の列島各地の神話・物語には、わたしたちが、生死を超えて生成し続けるものとして、この世界を見ようとするヒントが秘められている。直線から、曲線へ、円、楕円、山のような三角錐にもなるヘビは、定規のない悠久の昔から、生きとし生けるものの新参者である人が、この世界を理解しようとするときの、「生きた尺度」となってきたのだ。(はまだ・よう) 1968年生まれ。京都大学博士(人間・環境学)。現在は、賀川豊彦記念松沢資料館客員研究員、法政大学国際日本研究客員所員。日韓次世代学術フォーラム運営委員、国際日本文化研究センター協同研究院。 【文化】公明新聞2025.1.10
September 15, 2025
コメント(0)
-
国立公園の魅力を発信
国立公園の魅力を発信 海女小屋や火山散策…「ならでは」をブランド化 男子禁制を破る体験政府が2030年に訪日観光客6000万人誘致を目標に掲げる中、豊かな自然や景観を誇る国立公園の魅力も見直されている。全国35カ所の国立公園の中には高度経済成長期に整備された宿泊施設が老朽化した所もあるが、地域の時性を生かした「ならでは」の体験で新たな観光需要を掘り起こそうとする動きが加速している。伊勢志摩国立公園(三重県)では、海女文化が観光の「キラーコンテンツ」。海女が暖を取る小屋を模した施設では、60年以上海に潜ってきた野村礼子さんが海女仲間とともに、取れたての伊勢エビやアワビ、魚を囲炉裏端で焼き、訪れた人たちに振る舞う。男子禁制だった海女小屋の体験について、運営する兵吉屋社長の野村一弘さんは初めて迎えた外国人観光客から興味津々の様子で質問攻めに遭ったことが忘れられない。「海女の魅力を考えてもらい、観光の商品になると思った」と振り返る。ストーリー性のある体験は人気が高く、累計利用者数約20万人の約3割はアジアを中心とする外国人観光客だ。親子3世代で香港から訪れた女性は、3000年以上の海女の歴史を知り驚いた様子。「自国にはない文化が新鮮で魅力的だった」と、海女姿での記念撮影を堪能している。 立ち入り禁止区域に入る一方、火山、森、湖の風景が特徴の阿寒摩周国立公園(北海道)は普段は人が入れないエリアなどに着目。約7000年前に形成された火山群「硫黄山」(アトサヌプリ=アイヌ語で「裸の山」の意)」)でのトレッキングツアーが目玉だ。硫黄採掘で地域を支えた山は落石事故で長く立ち入り禁止だったが、認定ガイド同行を条件に入山を許可。全国の山を巡っている芳賀肇さんは夫婦で参加し、「生きている噴気孔を間近で見られたのは貴重な体験だった」と語る。また、夜は宿で過ごすことが多い温泉地の阿寒湖畔には、自然とアイヌ文化、デジタルアートが融合した新たな夜観光「カムイルミナ」が誕生。シーンに合わせて光が変化し、音楽が奏でられる「リズムシティック」と呼ばれる杖を手に参加者が暗闇の森を歩き、アイヌの叙事詩を基にしたストーリーをたどる。ストーリーや音楽は地元のアイヌ民族の協力で作られたオリジナル。周辺の宿泊施設では体験チケットがセットの宿泊プランを販売する。参加者は、その足で土産店などを訪れる。阿寒アドベンチャーツーリズムの山田英智さんは「人が間に血出てくる気脚気となり、地域の活性化にもつながっているのではないか」と話している。 観光地増加で課題も環境省は2016年に国立公園のブランド力を誘客につなげる「満喫プロジェクト」をスタート。環境客と地域の双方にメリットがある「持続可能な公園」を目指した取り組みは成果を出す一方で、観光客増加に伴う新たな課題も生んでいる。ポロジェクトに取り組んでいる伊勢志摩国立公園では、美しいリアス式海岸で知られる英虞湾が一望できる横山展望台を中心に再整備した。スロープやカフェを設け、24年度の来訪者は40万人超で過去最多の見込み。1人当たりの滞在時間も増加している。ただ、展望台は最寄駅から約4㌔離れており、観光客の9割以上が車利用。近隣駐車場の周辺に安岐町の車が渋滞し、ごみのホイ捨てなどマナーの悪化もみられるようになった。「人が来過ぎても気持ち訳すごせない」と同公園管理事務所の拓殖規江所長。駐車場の優良可やシャトルバス運行などの対策を検討しているという。伊勢志摩国立公園は96%を民有地が占める「地元の人の生活が丸ごと入っている公園」であることが特徴で、地域の理解がなければ「関係者と協力し、地道にプロジェクトを進めていきたい」と話している。 【文化Culture】聖教新聞2025.1.9
September 14, 2025
コメント(0)
-
日本一平和な現存天守
日本一平和な現存天守城郭ライター 萩原さちこ宇和島城宇和海に面してリアス式海岸が続く穏やかな愛媛県宇和島市。その宇和海に突出した標高約80㍍の丘陵に築かれているのが宇和島城です。現存の宇和島城は、1596年から藤堂高虎が築きました。加藤清正や黒田官兵衛などと並び、築城名手として知られる人物です。大きな特徴は、五角形の縄張り(設計)。現在でも城下を歩いていると、方向感覚を失います。さすがは築城名人・高虎とうなされます。かつては城の大半が宇和島海に面して海磁路で、二辺は宇和海に、三辺は堀に囲まれていました。すべての堀は埋め立てられていましたが、現在でも本丸から宇和島港が望め、海域の立地を実感できます。見どころの一つが、全国的にも貴重な古い石垣です。藤兵衛丸や本丸側面の石垣が高虎時代のものと考えられます。隅角部の算木積みも、まだ未成熟。荒々しい石垣は風情たっぷりです。築造時期を考慮するとこれほど高い石垣は珍しく、高虎はかなり先駆的な技術をもっていたようです。江戸時代から残る天守は、全国に現存する12棟のうち、最も穏やかで平和な天守と言えます。この天守は、1666年頃に宇和島伊達家2代の伊達宗利により建造されました。太平の世に建てられたため、防衛の工夫はありません。明るく開放的な天守入り口にも、屋敷の玄関のような歓迎の雰囲気が感じられます。広々とした空間に格式の高い大きな唐破風があしらわれ、柱には宇和島伊達家の三つの家紋が刻まれています。天守の壁面には弓矢や鉄砲を放つ「狭間」がなく、床面を張り出させて敵を頭上から攻撃する「石落とし」もありません。内部も広々としていて、軍事施設というよりは住まいのような雰囲気。御殿や家屋のようなつくりで、階段の手すりは木材が丁寧に仕上げられています。全国の天守には千鳥破風の内部を「破風の間」という射撃や監視の空間にすることがありますが、宇和島城の天守にはそれもなく、戦うことを前提にしていないことがわかります。 【日本全国お城巡り24】公明新聞2025.1.9
September 14, 2025
コメント(0)
-
悠久なる南洋との交流
悠久なる南洋との交流島根県立古代出雲歴史博物館 専門学芸員 岡 宏三出雲の「龍蛇さん」かつて出雲では、十一月(旧暦では十月)になると連日木枯らしが吹き荒れた。十月を神無月ともいうが、出雲地方では諸国の神々が参集されるから神在月という。出雲人は時雨れる空に神々の到着を感じ取り、「お忌み荒れ」と呼んだ。神々が滞在されている間は、物音をたてて議(はか)りごとの妨げにならぬよう、歌舞音曲を自粛し、特に神々が諸国へお帰りになる日(神等去出)の夜は屋外に出ることさえ忌み慎んだ。なので神々をお迎えした出雲大社や佐太神社(松江市)などの諸社で行われる神有祭を「お忌みさん」ともいう。「お忌み荒れ」になると、出雲の沿海に「龍蛇さん」(西南諸島以南に生息するセグロウミヘビ)が海流に乗って漂着する。室町時代の謡曲「大社」は神在祭を題材とする。神々が参集するなか、海龍王が黄金の小筥の中の小龍(龍蛇)を社前に捧げると、大社の大神が出現し、大平の世と福寿をかなえよう、と告げる筋立てである。龍蛇は神々の先導役・海上安全・火難水難の神とされているが、この謡曲では、幸せと富をもたらす存在であるとも位置付けているのだ。確かに南方の海のかなたからは、悠久の昔から富がもたらされていた。出雲大社の背後の山の裏側、日本海に面した猪目洞窟遺跡から、約二〇〇〇年前、弥生時代後期の男性の人骨が出土している。この人物が腕輪として身に着けていたゴホウラ貝は、奄美大島以南で採取される貝で、特定の位置にあるもののみが装飾品とする貴重品だった。大社から車で西へ約五〇キロの場所に、大航海時代の頃、世界有数の銀の産出量を誇った世界遺産・石見銀山がある。数年前、銀山領の港として栄えた温泉津の町の入り口から「石敢当」が出土した。中国の福建省を発祥とする、丁字路の突き当りなどに立てられた魔よけの石で、沖縄・鹿児島両県に広く分布する。琉球国王を中継とする中国交易ルートによってもたらされた習俗である。「石敢当」は両県以外でも東北地方にまで分布するが、どれも幕末・イン代以降に立てられたものなのに対して、温泉津の石敢当は江戸時代前期までさかのぼる。かつ「来龍」「進宝」など縁起の良い文句も刻んであり、招福の願いも込められていたことがわかる。龍蛇が出雲に到達するまでのルートをさかのぼっていくと、はるか太古の昔から脈々と続いていた、南洋諸島、さらには大陸との、壮大な交流の軌跡が浮かび上がってくるのである。(おか・こうぞう) 【文化】公明新聞2025.1.8
September 13, 2025
コメント(0)
-
戦後80年見極める社会のかたち
戦後80年見極める社会のかたち 制度の根幹見つめる必要性戦後に区切り、国の在り方議論へ政治学者 御厨 貴さんみくりや・たかし 1951年、東京都生まれ。東京大学卒業後、東京都立大学、政策研究大学院大学、東京大学先端科学技術研究センターなどで教授を歴任。政府の有識者会議委員も多数努める。 「戦後という捉え方に区切りをつけ、これからの時代を表す新しい言葉を創る時期に来ている」——。日本の近現代史に詳しい政治学者で東京大学名誉教授の御厨貴さんは、日本をどんな国にしていくのか、皆で真剣に考える必要性を痛感している。 失われた〝歴史顧みる痛み〟政治家や市民の証言を記録するオーラル・ヒストリー研究の第一人者。戦後政治家のさまざまな証言を思い起こし、中曽根内閣で官房長官を務めた後藤田正晴が自衛隊の海外派遣を阻止した事例を挙げる。台湾から復員した後藤田には「二度と戦争をしたくないという強い思いがあった」と振り返り、「戦争を知らない世代が政治家になり、歴史を顧みるときの痛みのようなものが失われてしまった」と指摘する。明治から昭和の初期まで、日本は戦争を繰り返しました。「日清戦争、日露戦争、第1次世界大戦、満州事変など、ほぼ10年おきに戦後が新しい戦後に置き換わった」。日米安保体制にも支えたれた先の大戦以後、戦火を交えずに済んでいるが、「若い世代は先の戦争実感がなく、体験者は今後も減っていく。戦後何年という時代の捉え方にそろそろ良区切りをつける時期だ」とし、世代を超えて抜本的に国の在り方を考える重要性を訴える。複雑さを増す内外情勢も背景にある。ウクライナや中東の戦争では「むき出しの憎悪で、人権保障など普遍と思われていた価値観が揺さぶられている」。安全保障や危機管理を考える米だが、、フェイクニュースがあふれ、冷静な議論の土台が失われつつある。「戦後80年で到達した大変な事態」との認識を示す。 許されない課題の先送り満州事変までの数年間は「政党内閣が曲りなりに続いた」ものの、ただ一人の元老が天皇に首相候補を進言する不安定な仕組みだった。首相の選出システムを制度化しておけば、その後の軍部の台頭はなかったかもしれない」ひるがえって現在でも、議院内閣制をどう維持するかといった視点が欠けているという。「自民党が永続的に続くものと思われているが、機能不全を起こすこともあり得る」。安易な楽観論を戒め、社会や制度の根幹を見つめる必要性を説く。御厨さんは、天皇の退位に関する政府の有識者会議の座長代理もつとめた。安定的な皇位継承が危ぶまれ、「このままでは皇室が途絶える可能性がある」と安倍晋三首相(当時)に伝えると、「危機が来たら日本は必ず神風が吹く」と返ってきた。「振るった答えにびっくりしたが、目に見えている課題を先延ばしにするのは許されないはず」と言い切る。「陛下(現上皇さま)が退位され、また続くはずだった平成が終わったのも一つの変わり目になる」とみる。戦前と戦後で日本は大きく様変わりしたが、昭和天皇は相変わらず在位していた。「『昭和100年』で振り返るのも特別なイメージがあるから。天皇と元号が強く結びついた最後の時代になるだろう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・深まる分断、増す不透明感——新しい時代へ紡ぐ言葉を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・聞き手がいて語り手が生まれる「対話」から繋がる記憶哲学研究者 永井玲衣さんながい・れい 東京都生まれ。2024年、『水中の哲学者たち』で「わたくし、つまりNobody賞」を受賞。他の著書に『世界の適切な保存』など。 哲学研究者の永井玲衣さんは、学校や企業を舞台に、さまざまな人たちと『哲学対話』を繰り広げる。相手が当たるエピソードを「聞いて、語り継ぐ」という実戦でもある。扱うテーマは多様だが、戦争の記憶継承という試みも重要な位置を占める。 答えのない問いを中心に「哲学対話」では、10人前後の参加者が車座になり、地震の考えや想いを順番に話していく。「なぜ死ぬのが怖いのか」「大人って何か」といった根源的なものから、何気ない日常の疑問まで題材は多岐にわたる。「のびのびと表現でいるよう」人が話している間はさえぎらないのがルール。学校や企業のほか、寺社、美術館などでも開催し、子どもから高齢者まであらゆる世代が参加する。「どうしたら人とつながれるか」という問題意識を抱いて約10年、永井さんは『哲学対話』を地道に続けてきた。「日常のもやもやには哲学の種が埋まっていて、政治的、社会的な問題もはらんでいる。人は集まると競い合うが、答えのない問いを置くことでつながれる」地、体感をもって強調する。対話の基本は、向き合う相手に関心を持ち、意識を集中して話を「聞く」ことだ。しかし、近年その機会が失われていると指摘する。SNS隆盛の現代では、断片的な情報が一方的に流れ込み、相手の意見を打ち負かそうとする人があふれる。「人の話を聞けないメディア」が、終わりのない欧州、そして分断を生む。『個人のアイコンが記号に見え、取り換えの利かない『人間』が向こう側にいることを忘れてしまう。私たちは一人の人間が生きていることを忘れずにいられるかを試されていると、危機感を口にする。 戦争の体験 継承の場もロシアのウクライナ侵攻を埋め、若手写真家八木咲さんと、戦争について対話をする場を設ける「せんそうってプロジェクト」を始めた。「若者は『戦争を知らないから語ってはいけない』と後ずさりするが、そうすると高齢者が減っていく名で戦争の記憶が断絶してしまう」という懸念からだ。プロジェクトで「わたしのせんそう」と題した対話が持たれた際には、「おばかカラオケに行くたびに軍歌を歌った」といったエピソードが語られる。だれかの話をきっかけに、若い世代に何かしらの思いでに行き当たる。「戦争は日常の中にも残っており、話してみると意外なかかわりがあったと気付く。自分の言葉を発見していく時間で、『私も戦争について語っていいんだ』と言って帰る人もいる」昨年6月には広島でも対話の場を開いた。「聞き手がいて、始めて語り手が生まれる」という意純粋な思いがある。語られる戦争体験談は、聞き手の中に固有の経験として残り、そこから一つの継承が始まる。そして「聞き手もまた、語り手になり得る」。伝え聞いた体験をまた確かに話すことで、記憶がつながっていくと信じている。 【戦後80年 見極める社会のかたち】聖教新聞2025.1.7
September 13, 2025
コメント(0)
-
牧口先生「創価教育法の科学的超宗教的実験証明」〈第一章〉(1937年9月)㊦
牧口先生「創価教育法の科学的超宗教的実験証明」〈第一章〉(1937年9月)㊦ハーバード大学で21世紀の宗教を展望人間を強く善く賢くする役割が重要牧口先生が「創価教育法の科学的超宗教的実験証明』で論じたのは、教育の課題だけではなかった。後半部分を中心に、日蓮大聖人の仏法への言及からみられるように、牧口先生の問題意識の核心は、子どもたちの幸福にとどまらず、全ての人々が幸福な人生を歩むための道筋を明らかにすることにあったからだ。当時の日本の支配者であった〝国家のための教育〟の方針に徹底して抗い、『創価教育学体系』という独自の教育理論を世に問うただけでも、牧口先生は孤立無援に陥っていた。それに加えて、宗教団体は国家の統率下に置かれ、信教の自由が制限されていた時代にあって、宗教に関して真正面から論じることは、火に油を注ぐ幼な行為であった。牧口先生はその状況を十分に承知しながらも、一歩も退かずに、同署の「はしがき」で地震の覚悟をこう綴ったのだ。「教育の改良に取り組むことが、すでに膨大な計画にあるのにもかかわらず、宗教の問題にまで深入りするのは〝蟷螂が斧を以て隆車に向かう〟に等しいと見なされ、それまで理解者だった人々まで遠く離れていくかもしれない。しかしそれでこそ、法華経に説かれる(『猶多怨嫉』『況滅度後』のような)予言が的中することになり、ますます革新を強くして毀誉褒貶を顧みず、(自ら信ずるところを)大いに訴えねばならないと思います」(趣意)と。*この難題に取り組む覚悟を持って牧口先生が同書で追及しようとしてのが、「科学的」な実験証明であり、「超宗教的」な実験証明であった。まず、創価教育学が本当に普遍的な価値を持つのかについては、実験証明の焦点を次のような形で説明した。——〝どのような人でも、教育に関して同一の原因をつくることができれば、同じような結果を出せる〟と言う普遍的妥当性があることが、科学的な証明として欠かせない。創価教育学会の同志が、国語やチリなどの狂歌で出した成果に関して共通する法則が分かれば、それを適用することに依って他の教科でも実験証明できるはずだ——。こうした形での検証とは別に、宗教に関しては体験を踏まえた新しい形での検証が必要になると、牧口先生は考えた。そこで重要なのは、科学的な検討に堪えられるだけでなく、〝その宗教が、現在と未来にわたって幸福と安穏を保証する力を有している〟と、人々が信じることができるような実験証明でなければならない、と。19世紀にマルクスが述べた言葉に由来する〝宗教は阿片〟との見方に対して、奥の既成宗教が惰性的な存在となったままで、正面から弁明する方途も持たずに無気力になっていると、牧口先生は感じていた。この宗教一般に対する旧来の認識を打ち破るような、宗教理解のための新しい枠組みが求められるとして、牧口先生はその実験証明の在り方を「超宗教的」と名付けたのである。それは仏法の概念を踏まえた方法で、第一に「信」(師匠とするに足るような人の言葉を信じること)、第二に「行」(教えられたとおりに実践し、自らの体験によって価値の有無を証明すること)、第三に「学」(その理由について経文や道理を通し、見極めていくこと)、の三つの段階を経て宗教の進化を検証するというというものであった。*このようにして教育革命と宗教革命の旗を完全と掲げた牧口先生は、1943年7月、戸田先生とともに投獄された。その半世紀後(93年9月)、池田先生は「21世紀文明と大乗仏教」と題する講演をハーバード大学で行い、牧口先生の問題意識を現代に引き継ぐ形で、宗教の要件について論じた。「果たして宗教をもつことが人間を強くするのか弱くするのか、賢くするのか愚かにするのか、善くするのか悪くするのか、という判断を誤ってはならない」と訴えた上で、大乗仏教に脈打つ宗教的な力用について、次のように強調したのだ。「仏教は観念ではなく、時々刻々、人生の軌道修正を為さしむるものであります」「あらゆる課題を一身に受け、前意識を目覚めさせていく。全生命力を燃焼させていく。そうして為すべきことを全力で為しゆく。そこに、『無作三身』という仏の生命が瞬間瞬間、湧き出だしてきて、人間的営為を正しい方向へ、正しい道へと導き励ましてくれる」と。講演の結びで池田先生が呼びかけた「二十一世紀の人類が、一人一人の『生命の宝塔』を輝かせてゆくことを、私は心から祈りたい」との思いは、今、192カ国・地域で活動する世界の創価学会のメンバーによって厳然と受け継がれている。時流に迎合すて耳当たりのよいことばを語るのではなく、あえて〝苦い種子〟となって未来に遺ることを選ぶと獅子吼した牧口先生——。その精神は、21世紀の地球に「人間教育」の大輪を咲かせるとともに、「人間のための宗教」による豊かな実りをもたらしているのだ。連 載三代会長の精神に学ぶ歴史を創るはこの船たしか—第26回— 聖教新聞2025.1.7
September 12, 2025
コメント(0)
-
牧口先生「創価教育法の科学的超宗教的自実験証明」〈第一章〉(1937年9月)㊤
牧口先生「創価教育法の科学的超宗教的自実験証明」〈第一章〉(1937年9月)㊤日蓮大聖人の言葉に、「病の起こりを知らざる人の病を治せば、いよいよ病は倍増すべし」とある。このことは、現在、日本で起きている教育制度改革の論議にも、適切に当てはまる命題ではないだろうか。日本の教育制度は、明治維新から70年近くの間に欧米文化の直訳や輸入で出来上がきたが、その中で弊害となっている面を取り除いて、他の面での大きな功績を永遠に残すためには、病の原因の深くさかのぼって根底から治療しなければならない。ところが、そのようにはせず、やみくもに枝葉末節に手を入れて外見的な体制を整え、その場を取り繕うようにしてきたために、今日、大きな困難に直面することになった。(中略)今や日本の現在の社会は、政治も経済も道徳もその他の生活も行き詰っている。(その中で)病根はすべて人材の欠乏にあると気づき、教育を改良して将来の禍根を除去する必要があると目覚めるまでになってきた。しかし(対応は)、国民健康保険制度の導入といった程度の、物質面からの部分的な改善にとどまっており、根本となる人間精神の在り方に関わる立て直しを考えるまでには及んでいないようである。それは、あたかも画竜点睛を欠くに等しいといえよう。◇我々は(少しばかりの提言をするために)、本書を提供するにあたって、単刀直入に、(創価教育法による実験の)課題として現れた成績をありのままに記述した。読者の方々は(それらの実権を)直接的に観察する代わりに、この記述を読むことを通して、忌憚のない評価をしていただきたい。また、そのような結果が生じた原因について明らかにすることによって、検討が進められ、対策が追及されることを望む者である。◇昔であれば首が飛ぶであろうと思われるほどの大胆で率直な提言を、恐れずに行うだけの自信を持っているのには、それ相応の深い根底があることを看破してほしい。些細な冥利のために行ったのでないことだけでも、認識してもらいたいと切望するのである。(『牧口常三郎全集』第8巻、趣意)遠い将来を見据えて苦言を語り残す「教育のための社会」築く挑戦を!牧口先生が1937年9月に著した『創価教育法の科学的超宗教的実験証明』——。それは祖「創価教育学体系」の発汗後に書き上げられた小冊子であり、晩年まで発表を続けた多くの論文を除いて、最期の単行著作となるものだった。自らの思索と実践の集大成となる著作を出すにあたって、牧口先生はその信条を「はしがき」にこう綴っていた。「甘い果実のように賞味されて、その場限りになるよりも、苦い趣旨の役目を果たして、たとえ吐き出されたとしても、遠い将来に役立つように残すことが、我々に与えられた使命ではないだろうか」(趣意)と。当時は、美濃部達吉の天皇機関説に対する国会での弾劾演説(35年2月)を機に思想や学問への圧力が高まっていただけではなく、日中戦争が勃発(37年7月)して間もない頃である。牧口先生も、「四十年間の没頭、四面楚歌の裡にある」と自ら述べていたように、厳しい状況に置かれていた。子どもたちに幸福の種に教育の改善に没頭して、独自の教育理論を確立したものの、なかなか理解の輪は広がらなかったからだ。牧口先生の学説を実践する教師たちが成果を上げてきたことを紹介しながら、「人間教育において一定の軌道が見つかり、百発百中の普遍的方法が確立されるならば、人類の幸福のために、令眼視すべきものではない」(趣意)と述べ、社会での公正な議論を求めたのである。「昔であれば首が飛ぶであろうと思われるほどの大胆で率直な提言を、恐れずに行うだけの自信を持っているのには、それ相応の深い根底があることを看破してほしい」(趣意)と。ここで言う「深い根底」には、万人の幸福のための法理を説いた日蓮大聖人への核心があったことはもとより、当時30代だった戸田先生が成し遂げた教育実践への絶大な信頼があったと思えてならない。戸田先生が発刊した『推理式指導算術』に対し、牧口先生は自らの学説の「唯一最大の価値の証明」と称賛するとともに、戸田先生が開いた塾についても「私立小学校時習学館」とあえて表現していた。牧口先生は、創価教育に基づく学校を創設する構想を描いていたが、時習学館はその先駆けにほかならないとして、弟子の挑戦を〝かけがえのない希望〟として受け止めていたのだ。*同書の前半では教育を巡る課題を論じているが、注目すべきは、第一章の冒頭で日蓮大聖人の「種々御振舞御書」の次の一節を掲げていることである。「病の起こりを知らざる人の病を治せば、いよいよ病は倍増すべし」(新1241・全921)当時の教育改革は、行き詰まりの根本原因を見極めようとせず、枝葉末節の部分ばかりに手を入れようとしていた。それが状況を悪化させていることに対し、仏法の洞察を踏まえながら問題提起を行ったのだ。加えて牧口先生が懸念していたのが、教育改革に対する社会への関心が低いことだった。その背景として、牧口先生は次のような点に目を向けた。一つは、社会において分業化が進み、それぞれの分野の関連性が複雑になる中で、人々が目前の仕事に忙殺されて、物事を全体的に見渡して考えることができなくなっていること。もう一つは、実際の結果に基づいて証明すれば、教育問題は理解しやすい面もあるはずなのに、膨大な知識による形で説明しようとするために、かえって人々の理解を難しくさせてしまっていることである。残念ながら、牧口先生の懸念は社会で真摯に受け止められなかった。しかもこの傾向は戦後も基本的には変わらず、教育改革もその場しのぎの対応が続く面があった。時を経て、こうした混迷を打破するために、池田先生が2000年9月に発表したのが、「『教育のための社会』目指して」と題する提言だった。現代における教育改革論議に対して、「〝特効薬〟を求めるあまり、長期的展望を描いた対症療法的な改革にならぬよう留意すべき」と指摘する一方で、池田先生はこう呼びかけた。「〝社会から切り離された教育〟が生命をもたないように、〝教育という使命を見失った社会〟に未来はありません。教育は単なる『権利』や『義務』にとどまるのではなく、一人ひとりの『使命』にほかならない。——そういう社会全体で意識改革していくことが、全ての根本であらねばならないのです」と。つまり、21世紀の教育を見据えて最重要の焦点となるのは、教育を社会の一分野として埋没せずに、あらゆる人々が使命感をもって「教育のための社会」を築くことにあると訴えたのだ。 連 載三代会長の精神に学ぶ歴史をつくるはこの船たしか—第25回— 聖教新聞2025.1.6
September 12, 2025
コメント(0)
-
弱さとおろかしさ
弱さとおろかしさ 物事は両面からみる。それでは平凡な答えが出るにすぎず、智慧は湧いてこない。いまひとつ、とんでもない角度——つまり天の一角から見おろすか、虚空の一点を設定してそこから見おろすか、どちらかしてみれば問題はずいぶんかわってくる。 『夏草の賦 上』*「人の世の面白さよ」庄九郎は具足をつけながら、からからと笑い、つぶやいた。人は、群れて暮らしている。群れてもなおお互いに暮らしていけるように、道徳ができ法律ができた。庄九郎は思うに、人間ほど可憐な生きものはない。道徳に支配され、法律に支配され、それでもなお支配され足らぬのか神仏まで作ってひれ伏しつつ暮らしている。 『国盗り物語 二』*人は、いつも、自分をさまざまな意識でしばりあげている。見栄、てらい、羞恥、道徳からの恐怖、それに、自分を自分の好みに仕立て上げている自分なりの美意識がそれだ。それらは容易に解けないし、むしろ、その捕縛のひと筋でも解けると、自分の全てが消えてしまうような恐怖心をもっている。 『風の武士 下』*(人はおれを利口なやつとよんできたが、人間の利口など、たかが知れたものだ、囚われになれば、どう仕様もない)官兵衛が心から自分をあざける気になったのは、入牢して十日ほど経ったときである。(知恵誇りの者がたどりつくのはたいていこういうところだ)知恵者は、道具でいえば刃物のようなものだ。手斧で板を削り、のみで穴をうがち、鋸で木を切る。道具でもって家も建ち、城も建つ。なるほど偉大なものだが、しかし板にちっぽけな古釘が一本入っていたりするだけで刀はかけて道語はだめになってしまう。(知恵など、たかが道具なのだ)播州でおれほどの智者はいないとひそかに思っていたことが、なんだかばかばかしくなってきた。 『播磨灘物語 三』*織部正は、その長い反省で一度も蹉跌ということのなかった、稀有の幸運児である。人柄も円満で、ほとんど、きずというものがなかった。惣内によれば、織部正は、おそらくそういう自分の人生や性格というものに、この歳になってようやく反逆を覚え、むしろきずやいびつのなかにこそ、美しさがある。 『人斬り以蔵』(「割って、城を」)*「人間をごぞんじない」継之助は、色のあわい、鳶色の瞳を大きくひらいていった。人間はその現実から一歩離れてこそ物が考えられる。距離が必要である。刺激も必要である。愚人にも賢人にも会わねばならぬ。じっと端座していて物が考えるなどあれはうそだ——と継之助はいった。『峠 上』*「別あつらえの人間など、どこの世にいる。ただの人間だから、おたがい自分をもてあまして苦労している。 『峠 上』*「人は、その長ずるところをもってすべての物事を解釈しきってしまってはいけない。かならず事を誤る」 『峠 下』*人間の厄介なことは、人生とは本来無意味なものだということを、うすうす気づいていることである。古来、気づいてきて、いまも気づいている。仏教にしてもそうである。人間王侯であれ乞食であれ、すべて平等に流転する自然政体のなかの一自然物にすぎない、人生は自然界において特別なものではなく、本来、無意味である、と仏教は見た。これが真理なら、たとえば釈迦なら釈迦がそう言いっ放しで去ってしまってゆけばいいのだが、しかし釈迦は人間の仲間の一人としてそれは淋しすぎると思ったに違いない。『ある運命について』(「富士と客僧」) 【人間というもの】司馬遼太郎著/PHP文庫
September 11, 2025
コメント(0)
-
第三章 日蓮の時間論
第三章 日蓮の時間論 中村元先生は、「仏教の思想は時間論と言ってもいい。それは、〝今を生きる〟ということだ」と話されていた。筆者は、学生時代に物理学を学んでいたこともあって、時間論に興味があった。その観点でこの「御義口伝」を読むと、日蓮の時間論と思しきところが多数散見された。その中から代表的なものとして寿量品廿七箇の大事」の中の「第三 我実成仏已来無量無辺等の事」を見てみよう。 第三 我実成仏已来無量無辺の事御義口伝に云く、我実とは釈尊の久遠実成道なりと云う事を説かれたり。然りと雖も当品の意は、我とは法界の衆生なり、十界己己を指して我と云うなり。実とは無作の三身の仏なりと定めたり、此れを実と云うなり、成とは能成・所成なり。成は開く義なり。法界の無作の三身の仏なりと開きたり。仏とは此れを覚知するを云うなり。已とは過去なり。来とは未来なり。已来の言の中に現在は有るなり。我れ実と成けたる仏にして、已も来も無量なり無辺なり。百界・千如・一念三千と説かれたり。百千の二字は、百は百界、千は千如なり。此れ即ち事の一念三千なり。今、日蓮等の類い南無妙法蓮華経と唱え奉る者は、寿量品の本主なり。(以下、略) 寿量品のあらすじ① 従地涌出品第十五で大地の裂け目から無数の地涌の菩薩が出現した。それを見て圧倒された弥勒菩薩(マイトレーヤ)菩薩の疑問に応えて、寿量品第十六が展開される。その最初の部分のあらすじを要約する。まず、冒頭で釈尊が、次のように語っている。「良家の息子(善男子)たちよ。あなたたちは、如来の真実の言葉を信じなさい」と三度にわたって語りかける。それに対して、弥勒菩薩をはじめとする菩薩たちは三度、説法を懇請する。それに続いて以下のことが語られる。「一切世間の点の神々や人間、および阿修羅たちは皆、今の釈迦牟尼(シャーキャムニ)仏は釈迦(シャーキャ)族の宮殿を出て出家し、伽耶(ガヤー)の都城から遠くないところにある覚りの座(道場)に坐してこの上ない正しく完全な覚り(anuttara-sanmyak-sambodhi、阿耨多羅三藐三菩提)を得たと思いこんでいる。しかしながら、良家の息子たちよ、私が、実に仏となってからこれまで、無量無辺の百・千・万・億・那由他劫という遥かな時間が経過しているのだ。譬えば、五百・千・万那由他・阿僧祇(=5×10の87乗)という無数の三千大千世界(十億個の世界)を磨り潰して微塵(原子)にして、それを東の方の五百・千・億・那由他・阿僧祇という数の国々を過ぎるごとに一粒の微塵をおいていって、全ての微塵を尽くしたとしよう。その多くの世界の微塵を置いたところも、置かなかったところも、さらにまた合わせて微塵となして、その一つひとつの微塵を一劫(筆者の計算では10の24乗年)とすると、私が仏になってから経過した劫の数は、それよりもさらに百・千・万・億・那由他・阿僧祇劫も多いのである。成道した時から今に至るまで、私は常にこの娑婆(サハー)世界にあって説法し、教化してきた。また、他の世界の百・千・万・億・那由他・阿僧祇の国々においても衆生を導き、利益をもたらしてきた、その間、私は燃燈仏などの如来について説き、それらの仏が涅槃に入るということを説いたが、それはすべて私が方便(教化の手立て)として考えたことなのだ。良家の息子たちよ、もしその衆生が私の所にやってきたときには、私は仏の眼によって彼らの真などの能力の優劣を観察して、救済すべき相手に応じ、所に応じて自分の名前を変えていること、寿命の大小があることを説き、また「出現しては、涅槃に入るであろう」と言い、種々の方便を用いて勝れた奥深い教えを説いて、衆生に歓喜の心を起こさせてきたのである」◇ ◇この御義口伝で論じられる、「我実成仏已来無量劫百千万憶那由多阿僧祇……」(植木訳『梵漢対照・現代語訳 法華経』下巻、二二四頁)という一節は、以上の文脈の中に出てくる。 十界己己の我ら衆生が無作の仏 この「我実成仏已来無量無辺」の一部から日蓮の時間論が展開される。この一節は、一般的には、 我実に成仏してから已来(このかた)無量無辺なり。 と書き下され、「私が成仏してから、これまでに無量無辺の遥かな時間がたっている」というほどの意味で用いられている。 日蓮は、「我実成仏已来無量無辺」を構成しているそれぞれの文字について、次のように意味付けを行っている。まず初めの「我」と「実」について、「我」という主語は、釈尊のことであり、「実」、すなわちその釈尊の真実とは何かというと、それは五百塵点劫の久遠の昔に成道していたこと(久遠実成道)であるとされる。それが、「我実とは釈尊の久遠実成道なりと云う事を説かれたり」というところである。ただし、この一節は『昭和定本 日蓮聖人遺文』と要法寺版『御義口伝抄』では、「我とは、釈尊の久遠実成道なり」となっていて、初めの「実」の文字が欠落している。これでは、「我=釈尊」「実=久遠実成道」の対応関係が失われてしまう。従って『日蓮大聖人御書全集』の「我実とは釈尊の久遠実成道なり」を参照した。ところが日蓮は、これは表面的なとらえ方であるとして、「然りと雖も当品の意は」と断って、寿量品本意は何かといえば、「我とは法界の衆生なり。十界己己を指して我とは云うなり。実とは無作の三身の仏なりと定めたり」と言い換えている。すなわち、寿量品の意図するところは、「我」とは釈尊に限定されるのではなく、全宇宙(法界)に存在する衆生のことだという。「衆生」とは、広い意味では一切の行きとして生きるもののことだが、狭い意味では人間のことである。十界論的に言えば、十界のおのおのを指して「我」と言っている。これは、仏教が特定の人を特別扱いすることはなく、釈尊であれ、衆生であれ、「法」(dharma)の下に平等であるとする原始仏教以来の精神に基づくものである。また、「実」について言いえば、その「法界の衆生」、あるいは「十界己己」の衆生が本来、無作の仏であるということが、本来の仏教にとっての生命の真実であり、是こそが「実」であると言うのだ。 成とは開く義 以上の「我・実」に続いて、「成・仏・已・来」のそれぞれの文字に対して日蓮が与えた意味は次のように並べることができる。漢訳との対応を考えて、それぞれの感じが行頭に来るように配列してみる。 我とは法界の衆生なり。十界己己を指して我と云うなり。実とは無作の三身の仏なりと定めたり。此れを実と云うなり。成とは能成・所成。成は開義なり。法界が無作の三身の仏なりと開きたり。仏とは此れを覚知するというなり。已とは過去なり。来とは未来なり。已来の言の中に現在は有るなり。我れ実と成(ひら)けたる仏にして、已も来も無量なり無辺なり。 「我」というのは宇宙(法界)に存在する衆生のことであり、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天・証文・独覚・菩薩・仏の十界おのおのの衆生を指して「我」と言っている。次の「実」というのは、その「法界の衆生」、あるいは「十界己己」が本来あるがままの仏(無作の仏)であるということが、本来の仏教にとっての生命の真実であるという。すなわち、寿量品で明かされる如来とは、我々のことであり、我々こそがその主人公であるということを一貫して主張している。「成」は、動詞として「能成」と「所成」の二つの側面からとらえられている。他動詞に「能」がつくとお能動的な主体を意味する。「所」がつくと受け身となる。すなわち、「~するもの」と「~されるもの」のいうことだ。「能・所」を挙げることによって、何かの行為には必ず「する側」と「される側」の両面がともなっていることを示している。この「成」という文字について日蓮は、「成は開義なり」とし、「成る」ではなく、敢えて「開く」と読み替えている。「成」は普通、自動詞として「なる」と読む。ところが「なる」と読めば、日蓮の仏法においては正確さを欠くことになる。例えば、「成仏」という言葉は仏典の漢訳において早くから用いられ、定着してしまっている。そのため、日蓮も著作の随所でそれを用いている。これを、文字通り「仏になる」と読むと、現在の凡夫としての自分を全否定して、まったく別の人格になることによって成仏するということになってしまう。これでは、「総論 南無妙法蓮華経とは」(七八~七九頁)で訓述した「厭離断九の仏」となってしまい、「九界即仏界」「因果具時」の成仏、「即身成仏」とは程遠いものになる。だから、日蓮は敢えてここで「成」の読み方を変えている。すなわち、「成は開義なり」とした。「仏になる」のではなく、「仏を開く」という表現であるべきだというのだ。人間離れした特別な存在になる日必要はなく、自己に秘められたものを開き現すことによって、現在の自己に即して、凡夫の儘で成仏するという意味だ。それをどのように開くのかといえば、「法界が無作の三身の仏なりと開きたり」である。全宇宙が、あるいは小宇宙とも言うべき自己の生命が、無作の仏であると開くというのだ。とすると、「能成」、すなわち「成(ひら)く側」は、法界の衆生、すなわち我々自身のことであり、「所成」、すなわち「成(ひら)かれるもの」が、無作の仏ということになる。「能」と「所」は、「成(ひらく)」という行為において一体のものであり、我が身に無作の仏を開くことである。無作とは、後述するように「はたらかず・つくろわず・もとの儘」ということだから、「無作の仏」とは、三十二相といった特殊な姿を具えるような荘厳身ではなく、執着や妄想を離れた凡夫のあるがまま(真如)の仏ということであろう。現在の自己に即して、凡夫のままで人間として成仏するということだ。失われた自己を回復し、真の自己に目覚めることによる人格の完成である。「無作の仏」といっても、それは自己に「成(ひら)く」べきものとしてあるのだから、「仏」というのは、それを成(ひら)いて覚知した人のことをいうのである。だから、「仏とは此れを覚知するを云うなり」となる。仏であるか、衆生であるかという違いは、それを画ししているか、していないかという違いがあるだけである。サンスクリット語のブッダ(buddha)が、「目覚める」という意味の動詞の語根ブッドゥ(√budh)から造られた過去分詞で、が、「目覚める」という意味であることに通じている。仏であるか、衆生であるかという違いは、それを覚知しているか、していないかという意味があるだけである。『諸法実相抄』で日蓮は、 迷悟の不同にして生仏異なる。 と言っているが、迷っているか、覚(悟)っているかという違いによって、「生仏」、すなわち「衆生と仏」の違いがあるということであって、同じことを言っている。この「生仏」を「いきぼとけ」と読まないように注意していただきたい。「ブッダ」とは、「目覚めた人」「覚った人」「覚者」ということであって、釈尊の固有名詞ではない。普通名詞である。しかも、原始仏典でしばしば複数形の「ブッダー」(buddha)が用いられている。釈尊も荷を特別扱いすることはなかったのである。「法」と「自己」に目覚めれば、だれでもブッダ(仏陀)であったのだ。ここにも、〝法の下の平等〟をうかがうことができる。 已来の言の中に現在は有る 以上のことを踏まえて、「已とは過去なり、来とは未来なり。已来の言の中に現在は有るなり」として、ここから時間論が展開される。「已来」は熟語として、「(過去のある時点より)このかた」「(~から)ずっと引き継いて」を意味する。ところが日蓮は、独自の時間論を展開するために一文字ずつ区切って意味付けしている。「已」というのは、「すでに」と読み、過ぎ去ってしまったことであって、過去を意味する。「来」というのはこれから来ることであって、まだ来ていない未来を意味すると言うのだ。この一節に示される時間論は、過去といい、未来といっても、現在のことにすぎないということである。時間といっても、今・現在しか存在しない。過去も、未来も、観念の産物である。過去といっても、過去についての「現在」における記憶であり、未来といっても、未来についての「現在」における予想・期待でしかない。所詮、現在である。その意味で、過去といい、未来といっても、現在を抜きにしてはあり得ないのだ。『開目抄』に「心地観経に曰く」と断って、 過去の因を知らんと欲せば、現在の果を見よ、未来の果を知らんと欲せば、現在の因を見よ。 という一節が引用されているが、これも、過去や未来が、現在を離れてどこかに客観的にあるのではないことを言っている。あるのは今・現在のみであって、常に「永遠の今」だというのだ。 已も来も無量無辺 こうした時間論を踏まえた上で、一念三千の自受用身を自己に体現し、我が身を「無作の仏」と覚知したときのことを、日蓮は、 我れ実と成(ひら)けたる仏にして、已も来も無量なり無辺なり。 と結論している。この読み方と、これまでの、 我れ実に成仏してより已来(このかた)、無量無辺なり。 という読み方と比べると、違いが明らかである。両方とも、漢字だけを順に拾って読むと、 我実成仏已来無量無辺 となって同じだが、後者のほうは、成仏したのは遥かな過去の一時点であって、時間的に現在とは大きく隔たりがある。前者は、現在の瞬間において我が身を無作の仏と成(ひら)くことにより、過去の未来の意味が、現在の瞬間において無量無辺に開けてくる。瞬間即永遠、宇宙即我と開けてくる。というような意味になる。過去の時点ととらえる考え方は、因果を時間的に隔たったものとしてとらえる因果具時の発想である。此れだと、因が劣り果が勝れている(果勝因劣)という前提で、劣った因から勝れた果を目指すということになり、現在の凡夫としての自分(院)を否定して、未来に特別な存在(火)になるということで、現在という時点の意義が薄れてしまう。それに対して、日蓮の考え方は因果具時であり、時間的隔たりの中で因果をとらえず、現在という時間において仏因と仏果をとらえるので、現在という時間こそが重要な意味を持ってくることになる。 現在の瞬間に永遠を開く 「我れ実と成(ひら)けたる仏」が立っているところは、今・現在である。それは、現在の瞬間に生命の本源たる久遠を開いていることである。その現在の生命は、時間的に過去と未来を含んでいるわけで、現在における歓喜の充満と、意味の輝きで、過去(已)と未来(来)が「無量無辺」に開けてくるのだ。「無量無辺」とは、時間的な観点から言えば、「瞬間即永遠」ということになる。空間的な観点から言えば、「宇宙即我」「自己の宇宙的拡大」ということを言ってもかまわないと思う。以上述べてきたように、時間というのは、実は今・現在しか実在しない。瞬間、瞬間が、常に「今」の連続である。我々は、連続する「現在」において生きている。それなのに、無明によって妄想や執着が生まれ、時間の観念が形成される。そして、今・現在の重みに気づかずに、過去や未来にとらわれてしまいがちである。過去に辛く忌まわしい経験をして、それを忘れることができない人は、過去を引きずるように過去にとらわれながら、「現在」を生きてしまいがちである。あるいは、「現在」をいい加減に生きながら、未来に夢想を描いて「現在」を生きている人もいる。あるいは、過去の栄光に酔いしれて「現在」を生きている人もいる。いずれにしても、過去や未来という妄想に生きていることに変わりはない。過去にあった〝事実〟は変えることはできないが、過去の〝意味〟は変えられる。それは、現在の生き方いかんによる。未来も現在の生き方いかんによる。仏教は、原始仏教以来、一貫して現在を重視してきたのである。日蓮が言うのは、今現在という瞬間に、生命の本源としての無作の仏の生命を成(ひら)き、智慧を輝かせる。そこに、瞬間が永遠に開かれるということだと思う。哲学者の梅原猛氏(一九二五~二〇一九)が、 『南無妙法蓮華経』ととなえる題目は、いわば永遠を、今において、直観する方法なのである。 「紀野一義・梅原猛著『仏教の思想12 永遠のいのち〈日蓮〉』、270頁」 と言ったのは至言である。また、哲学者の三木清(一八九七~一九四五)が、二十歳の時に「友情——広陵生活回顧の一節」と題する小分の末尾に記した次の言葉は示唆に富んでいる。 現在は力であり、未来は理想である。記録された過去は形骸にすぎないものであろうが、我々の意識の中にある現在の過去は、現在の努力によって刻々に変化しつつある過去である。一瞬の現在に無限の過去を生かし、無限の未来の光を注ぐことによって、一瞬の現在はやがて永遠となるべきものである。 原始仏典の『マッジマ・ニカーヤ』においても、釈尊は現在の重要性を次のように語っていた。 過去を追わざれ。未来を願わざれ。およそ過ぎ去ったものは、すでに捨てられたのである。また未来は未だ到達していない。そして現在のことがらを、各々の処においてよく観察し、揺らくことなく、また動ずることなく、それを知った人は、その境地を増大せしめよ。ただ今日まさに為すべきことを熱心になせ。 (中村元訳) このように、仏教が志向したのは、〈永遠の今〉である現在の瞬間であり、そこに無作の仏の命をいかに開き、顕現するかということだったということを日蓮は主張しているのであろう。以上のことを踏まえると、成仏とは、この「我が身」を離れることではなく、今自分がいる「ここ」を離れることでもない。要するに、「今」「ここ」にいるこの「我が身」に無作の仏を開き、具現するということである。これに対して浄土教は、「今」ではなく「死後」、「ここ」(娑婆世界)ではなくて「あちら」(西方十万億土)、「我が身」は不浄なものであり脱却されるべきものとしている。これは『法華経』だけでなく、原始仏教の本来の人間観、人生観、国土観とは全く逆行するものであり、日蓮は、この点を鋭く批判したのである。以上、日蓮の時間論を見てきたが、中村先生は、「インド思想史」の講義でカーラ・ヴァーディン(時間論者)に言及された折、「道元の時間論は永遠性を見ているが、歴史性がない。それに対して、日蓮の時間論は永遠性に立脚するとともに歴史性があります」と話されたことがあった。確かに道元は、抽象的な形而上学的時間論に偏っているのに対して、日蓮の場合は、永遠性に根差しつつも『法華経の行者』として現実への関りを重視する歴史的な時間意識に満ち満ちていると言えよう。 【日蓮の思想「御義口伝を読む」】植木雅俊/筑摩書房
September 11, 2025
コメント(0)
-
一念の全体像と心の自由度
一念の全体像と心の自由度 以上の十界(および、その互具)と、十如是、三世間を融合的に組み合わせて「三千」(=10×10×10×3)という数字を満たして「一念三千」が体系化された。三千の数によって、心の働きの具体相、種々に生起しては変化するその結果、一念が主体だけでなく環境にまで遍満しているという在り方——といった一念の全貌が包摂される。けれども、それは可能性としての全貌であって、偏狭なことの場合は、現実として三千という数を満たすことはない。六道輪廻している人は、実際生活では六界が具足しているのみで、六×六=三十六界で、十如是を加味して三百六十如是、三世間を考慮しても「一念千八十」にしかならない。心(一念)の自由度は千八十(=6×6×10×3)である。三悪道に取り込まれているときは、「一念二百七十」で、自由度はわずか二百七十(=3×3×10×3)である。もっと心の不自由な人は、その数はさらに少なくなる。もっとも不自由な地獄界にとらわれている人は、なかなかそこで抜けきれず、最も極端な場合には、現実的には他の九界と互具することなく、一界互具して一界で、十如是と三世間を加味しての「一念三十)、自由度は三重(=1×1×10×3)でしかない。さらに地獄界で束縛され、がんじがらめになって、衆生世間や国土世間の空間が広がり限りなくゼロに近ければ「一念十」ということあり得る。自由度はたったの十(=1×1×10×1)という不自由さである。そういう具合に、生命の変動可能な領域は限りなく小さくなる。その意味では、一念三千の三千は、一念(心)の自由度を最大値を示すものと理解できよう。ここまで読んできて、心の自由度を大きく左右するのは、十界すべてが自由自在であるが、それとも不自由であるのかにかかっていることに気づかれるであろう。(略)十界が自由自在であることを日蓮は、この『御義口伝』で「十界同時の成仏」と表現していた。その構造を図顕したのは、十界曼荼羅であると理解される。妙楽大師は、そのことを『法華文句記』巻一下において、次のように記している。 若し三千に非ざれば、摂ること遍からず。若し円心に非ざれば、三千を摂せず。(大正蔵、巻三四、一六七頁) 「三千」という数は、一念の稼働領域の全体を示すものであり、それによって一念の全体像を把握することができるが、現実的には何も欠けたもののない円融円満の自由自在の心であって初めて、実際に一念が「三千」という数を満たすことができるのである。その時のことを、妙楽大師は『金剛錍論』において次の言葉で示している。 実相は必ず諸法、諸法は必ず十如、十如は必ず十界、十界は必ず身土なり。(大正蔵、四六巻、七八五頁下) 一念の真実の姿(実相)は必ず諸法という具体的な事物・現象を持って現れ、その諸法は必ず十如是という因果の理法にのっとって現われ、十如是は必ず十界という心の働きとして現れ、その十界の境涯は自己の身体(身)に閉ざされてあるのではなく、我が身の存在する環境(土)にまで拡がっている。妙楽大師は、そのことを『摩訶止観輔行伝弘決』巻五で次のように述べている。 当に知るべし、身土一念の三千なり、故に成道の時、此の本理に称うて一身一年、法華委に遍し。 (大正蔵、巻四六、二九五頁下) これは、天台大師智顗によって体系化された「一念三千」が体現されたときに開ける境地である。我々が、覚りに達した時、「身土」(身体と国土)にわたる一念三千という「「本理」(根本の真理)にかなって、私たちの身体も一念三千に遍満している(一身一念、法界に遍し)ということを覚知できるというのである。このことを日蓮は、『一生成仏抄』で、 十界三千の依正色心、非情草木、虚空刹土、いずれも除かずちり(塵)も残らず、一念の心に収めて、此の一念の心、法界に遍満す。 と述べ、主体と環境(依報と正報の依正)、物質と精神(色心)、非情(心を持たないもの)の草木、国土(刹土)、さらにはミクロ(塵=原子)とマクロ(虚空=宇宙)にまで遍満する一念の雄大さを説いている。そうなると、「自受用身」とは、南無妙法蓮華経という智慧の光明によって十界・三千の全てを輝かせ、生命の自由度が最大に達している人のことだと理解できる。それは、何も特別な姿をしている必要はない。三十二相・八十種好などといった特殊な身体的特徴なども必要ない。こうして、「色相荘厳」のように、人間離れした姿形を飾り立てた{尊形}は否定される。そして、人間としてのありのままの姿であり、凡夫の身のままであって、我が身に一念三千の当体を開けば「自受用身」となるのである。これは、いわゆる「尊形」という考えとは無縁であり、それを伝教大師最澄(七六七~八二二)は、「無作の三身」と称している。それは、作為的に得られたものではなく、本来のおのずから具えていた人格を開き現わした仏という意味である。「出尊形の仏」と言われているのは、「仏様然」として、いかにも立派そうに外見を飾り立てた姿とは無縁であることを意味している。神格化したり、人間離れしたものに祀り上げたりしたのは、釈尊滅後に登場した、いわゆる小乗仏教(説一切有部)であった。本来の仏教では、『尊形』など全く説かれていなかった。凡夫の当体、本有のままの仏という在り方が説かれていた。それは言い換えれば、「第三章 日蓮の時間論」で述べる「はたらかず・つくろわず・もとの儘」という無作本有の仏ということである。もっと分かりやすく言えば、最も人間らしいブッダ(目覚めた人)と言えよう。以上のように「自受用身」「一念三千」「出尊形の仏」「無作の三身」ということについて、種々に論じてきたが、こうした言葉が示すものは、「今、日蓮の類い南無妙法蓮華経と唱え奉る者、是なり云云」と日蓮は明言している。南無妙法蓮華経と称えるのは、失われた自己を回復し、真の自己に目覚め、人格の完成のためであると日蓮は言っているのであろう。 【日蓮の思想「御義口伝を読む」】植木雅俊/筑摩選書
September 10, 2025
コメント(0)
-
才能と仕事
才能と仕事 「人の一生はみじかいのだ。おのれの好まざることを我慢して下手に地を這いずりまわるよりも、おのれの好むところを磨き、そのことのほうがはるかに大事だ」 『峠 上』*「人間の才能は、多様だ」と、継之助はいった。「小吏にむいている、という男もあれば、大将にしかなれぬ、という男もある」「どちらが、幸福なのでしょう」「小吏の才だな」継之助はいった。藩組織の片すみでこつこつと飽きもせずに小さな事務をとってゆく、そういう小器量の男にうまれついた者は幸福であるという、自分の一生に疑いももたず、冒険もせず、危険の縁に近づきもせず、ただ分をまもり、妻子を愛し、それなりで生涯をすごす。「一隅ヲ照ラス者、コレ国宝」継之助は、いった。叡山をひらいて天台宗を創設した伝教大師のことばである。きまじめな小器量者こそ国宝であるというのである。 『峠 上』*竹中半兵衛の才能は、栄達への野心をすてたところに息づいていた。錯綜した敵味方の論理的状勢や心理状況を考えつづけて、ついに一点の結論を見出すには、水のように澄明な心事をつねにもっていなければならない、と官兵衛には考えている。囚われることは物の判断にとって最悪のことであり、さらに囚われることの最大のものは私念といっていい。それを捨ててかかることは、領土欲や栄達欲が活動のばねになっている小領主あがりの武士にはなしがたいことなのである。しかし半兵衛は奇跡のように、平然と保っていた。『播磨灘物語 三』*「人には得手と不得手がある。英雄にも愚者にもそれがある。それを看ぬいて人の得手を用いるがよい。また人にはかならずいやなところがある。たとえば残忍、欲深というのはひとのいやがるところであるが、そういう人物ですら長所があり、それを新設にみてやらねばならない」 『世に棲む日日 一』*人間の才能は、大別すればつくる才能と処理する才能のふたつにわけられるにちがいない。西郷は処理的才能の巨大なものであり、その処理の原理に哲学と人格を用いた。『歳月』*人は、その際室や技能というのはほんのわずかな突起物にひきずられて、思わぬ世間歩きをさせられてしまう。『ある運命について』(『胡蝶の夢』雑感)*人間は人なみでない部分をもつということは、めずらしいことなのである。そのことが、ものを考えるばねになる。 『十六の話』(「洪庵のたいまつ」)*「藤兵衛、人間はなんのために生きちょるか」と、竜馬は膳ごしにいった。「事をなすためじゃ。ただし、事をなすにあたっては、人の真似をしちゃいかん」世の既成概念をやぶる、というのが真の仕事というものである、と竜馬はいう。だから必要とあれば大名に無心をしてもよい。 『竜馬がゆく 三』*「仕事というものは、全部やってはいけない。八分まででいい。八分までが困難の道である。あとの二分はたれでも出来る。その二部は人にやらせて完成の功を譲ってしまう。それでなければ大事業というものはできない」 「竜馬がゆく 八」* 小人という西郷の用語は己を愛する者という意味である。「……であるから相手がたとえ小人でもその長所をとってこれを小職に用いればよく、その才芸を尽くさしめればよい。水戸の藤田東湖先生もそのようなことをいわれた。小人ほど才芸のあるもので、むしろこれを用いればならぬものである。さりとてこれを長官に据えたり、これに重職をさずけたりするとかならず国家をくつがえすことになる、決して上に取り立ててならぬものである」 「翔ぶが如く 三」 【人間というもの】司馬遼太郎/PHP文庫
September 9, 2025
コメント(0)
-
唱法華題目抄④
唱法華題目抄④現代語訳教学部編第6段 法華経をどのように信じたらよいか(御書新版12㌻6行目~11行目・御書全集8㌻18行目~9㌻4行目) 問6 無知の者の法華経の信仰は質問するはじめに知恵ある人がお話になったこととして申し上げたのは、結局は、来世のことが疑わしいので、良し悪しを申し上げて、お伺いしたいためだった。その教えなどは、とても恐ろしいことなのだと私には思われます。一文字も知らない我々のような者は、どのようにして法華経を信仰すればよいのでしょうか。また、心構えについては、どのように思い定めていけばよろしいのでしょうか。 答6 答者への疑いをただす答える。この私が申しあげたことも確かなことだとお思いにはならないのでしょうか。その理由は、このように申し上げるのも、天魔である坡旬〈注1〉や悪鬼などが私の身に入って他の人の良い教えを非難しているのではないかとお思いになっているのではないでしょうか。一切のことは、賢く見るのが知恵ある人なのではありませんか。…………〈注1〉〖天魔である坡旬〗御書本文では「天魔坡旬」。「坡旬」は、魔の名前。サンスクリットのパービーヤスの音写。「悪い者」の意。 第7段 法華経は意味が明瞭な経典(御書新版12㌻2行目~17行目・御書全集9㌻5行目~10㌻3行目) 問7 智者の言葉を疑う質問する。もしこのように私が疑っているとしたら、私は愚かな人であり、多くの智慧ある人の言葉を疑い、そうかといって信じるものもなく、空しく一生を過ごしてしまうことになるのでしょうか。 答7 法を依りどころにせよ、人を依りどころにするな答える。私(釈尊)の遺書〈注2〉には「法(真理)を依りどころにしなさい。人を依りどころにしてはならない」〈注3〉とお説きになってしまいますので、今日の通りに説かないのであれば、どれほど素晴らしい人があったとしても、信用してはならないのではないでしょうか。また、「意味が明瞭な経典〔了義経〕を依りどころにしなさい。意味が不明瞭な経典〔不了義経〕を依りどころにしてはならない」〈注4〉と説かれていますので、愚かな者であっても釈尊が一生のうちに説いてすべての教えの順番の前後や、教えの浅深を識別できない以上は、意味が明瞭な経典にお従いください。意味が明瞭は経典も、意味が不明瞭な経典も、どちらもたくさんあります。小乗の経典である阿含経は意味が不明瞭な経典であり、(これと比較すれば)華厳経・方等部の経典・涅槃経・浄土教を説く観無量寿経などは意味が明瞭な経典である。また、(法華経以前の)40年余りのさまざまな経典は、法華経などを比較すれば意味が不明瞭な経典であり、法華経は意味が明瞭な経典である。涅槃経を法華経と比較すれば、法華経は意味が明瞭な経典であり、涅槃経は意味が不明瞭な経典である。大日経を法華経と比較すれば、大日経は意味が不明瞭な経典であり、法華経は意味が明瞭な経典である。それ故、40年余りのさまざまな経典と涅槃経を押す手になって、法華経を師匠としてお頼みなさい。法華経を、国土、父母、太陽や月、大海、須弥山、大空や大地のようなものとお考えください。(法華経以外の)他の経典を、関白・大神・公卿から庶民に至るまでの全ての人々、(太陽や月以外の)星々、(大地に生える)草や木のようなものとお考えください。私たちの身は、釈尊から遠く離れた時代に生まれて悪行ばかりしている愚かな者であり、能力も劣り、教えを受ける資格のないものである。(一方)国王は臣下よりも人を助けるものであり、父母は他人よりも我が子を慈しむ者であり、太陽や月は他の星々よりも闇を照らすものであり、(それらと同様に)法華経が我々の機根に対応しないなら、まして他Kの経典では救うことは困難であるとお考えください。また、仏である釈尊と、阿弥陀如来・薬師如来・多宝仏・観音菩薩・勢至菩薩・普賢菩薩・文殊菩薩などの全ての仏と菩薩たちは、我々に慈悲をかける父母であり、これらの仏や菩薩たちが衆生を教え導く慈悲の究極の教えを、ただ法華経にだけとどめられているとお考えください。(法華経以外の)ほかの経典は、悪人や愚かな者、能力の劣る者、女性、六根のはたらきを失っている者〈注5〉などを救う秘伝の方法を、また説き顕してはいないとお考えください。法華経が他のあらゆる経典よりも優れている理由は、ただこのことにあるのです。ところが、今の時代の学者たちが、法華経は他のあらゆる経典よりも優れていると称賛しながら、しかも、釈尊から遠く離れた時代の者の機根には対応していないと言っているのを皆が信じているが、(それらの学者たちが)どうして謗法の人ではないと言えるでしょうか。ただ一言で謗法の人であるとお答えを定めきってください。結局、法華経の文字を破り裂くなどしたとしても、法華経の本質が破壊され悪業と比較して、(法華経を)遠ざけるように言ったとしても、人々はその言葉を用いるはずがない。ただ、(法華経と)似たような権教の教えによって(法華経を)遠ざけるように言う時にこそ、人は騙されるのだとお考えください。…………〈注2〉〖仏の遺言〗涅槃経を指す。涅槃経は釈尊が亡くなる直前に説かれたとされる。〈注3〉〖「法を依りどころにしなさい。人を依りどころにしてはならない」〗御書本文は「法に依って人に依らざれ」(依法不依人)、値版強(北本)巻6の如来性品愛4の3(南本では四依品第8)の文、「法」はさまざまな意味を持つが、涅槃経では、「法」とは仏を常住不変のものにする法性(真理そのもの)であると説明しており、「法(真理)」と訳した。〈注4〉〖「意味が明瞭な経典……してはならない」〗前注と同じく涅槃経(北本)巻6の如来性品第4の3(南本では四依品第8)の文。〈注5〉〖六根の働きを失っている者〗御書本文は「根失」。六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)のいずれかの機能を欠いていること。 第6段 釈尊の真意である法華経を誹謗する念仏(御書新版14㌻1行目~16㌻16行目・御書全集10㌻4行目~11㌻14行目) 問8 法華経の修行と称名念仏の比較質問する。ある智慧のある人は以下のようなことをお話になりました。「40年余りのさまざまな経典と8年間〈注6〉の法華経は、成仏に関しては、法華経以前〔爾前〕の経典は実践ガム賺しい修行(難行道)であり、法華経は実践が容易な修行〔易行道〕です。」(しかし)極楽世界に生まれることに関しては、同じく、(どちらも)実践が要因修行です。法華経を書写したり読んだりしても、十方世界にある浄土や阿弥陀仏の国土に生まれるはずである。観無量寿経などの経典を用いて阿弥陀仏のお名前を唱える人も、極楽世界に生まれるはずである。ただ(修行する者の)機根や(仏との)一縁の有無によるだけなので、どちらがどうと争ってはならない。ただし、阿弥陀仏のお名前を唱えることは、だれもが実践しやすいと思って、日本中で行いなれていることなので、法華経などの他の修行よりも(実践が)容易なのである」このようにお話になっていたが、どうなのか。 答8 法華経は仏の真意が説かれた経典答える。あなたがおっしゃった教えは、そのようであるかもしれません。また、世の中の人々も、多くの人はそれを道理であると思っている印象を受けます。ただし、私自身はこの主張に対しては疑わしく思っている。その理由は、前に申し上げた通り、釈尊から遠く離れた時代の凡夫は、智慧ある人といっても頼りにはならず、世の中あげて、昔の時代の智慧ある人には及ぶはずがないからである。(一方)愚かな者といっても、経典や論書の文が根拠としてはっきりしている場合は、軽んじてはならない。そもそも、無量義経は、法華経を説くための序文〈注7〉である。そうであるのに、釈尊が初めて覚りを開いた場所(寂滅道場)(での説法の開始)から、今の(釈尊は)いつも霊鷲山にいる」〈注8〉と言われている霊鷲山で説かれた無量義経に至るまで、その年月・日数を詳しく数え上げると、40年余りである。その間に説かれた経典を挙げると、華厳経・阿含経・方等部の経典・般若経である。それらで述べられた教えは、三乗〈注9〉や五乗〈注10〉が学習する教えである。修行のための時間を結論して、「菩薩の多くの劫にわたる修行(歴劫修行)を述べた」〈注11〉と言い、随自意(釈尊自らの意志に基づくもの)と随他意(他人の意向に従うもの)とを分けて、これらを随他意であると述べ、40年余りのさまざまな経典と(法華経の)8年間に説かれることが、言葉は同じでも意味が違うことを結論して、「言葉は同一でも、意味はそれぞれ異なっている」〈注12〉と説いている。成仏に関しては別として、極楽世界に生まれることに関しては一つあるはずである、とは思えない。(釈尊は)華厳経・方等部の経典・般若経などといった究極的で最も優れた大乗の経典や、たちまちに覚りを得る教えや段階的に覚りを得る教えなど、全てを「まだ真実を顕していない」〈注13〉と説かれた。これら分量の多い諸経典でさえ、「まだ真実を顕していない」という経文に含まれないということがあるだろうか。その上、それぞれの経典だけを挙げているのではなく、はっきりと年月・日数まで出しているのだからなおさらである。そうであるから、華厳経・方等部の経典・涅槃経などに説かれる〝阿弥陀仏によって極楽世界に生まれること〟が、「まだ真実を顕していない」との経文にあたることは、もはや疑いない。観無量寿経に説かれる〝阿弥陀仏によって極楽世界に生まれること〟にかぎって、どうして「険しい道の妨げが多いからである」〈注14〉との経文に含まれないことがあるだろうか。もし、随自意の法華経に説かれる極楽世界に生まれることを、随他意の観無量寿経に説かれる極楽世界に生まれることと同じものとして、(どちらも)実践が容易な修行だと結論し、しかも〝実践が容易な修行の中でも、観無量寿経に説かれるⒷ念仏によって極楽世界に生まれることは、さらに実践が容易な修行である〟と主張されるなら、権教と実教を混同する過失があり、謗法である。その上、一滴の水がだんだんと流れていって大海となり、一粒の地理が積み重なって須弥山となるように、だんだんと、権教の経典を用いる人も実教の経典を用いる人も権教の経典へと退くようになる。こうして、権教の経典を用いる人が次第に国の中に充満するなら、法華経に随喜する心も起こらくなり、国の中に翁がいないように、人に魂がなくなるように、法華経や密教経典〈注15〉を用いる寺院が荒廃し、善神たちや竜神〈注16〉などの、あらゆる聖人が国を捨て去ったなら、悪鬼はきっかけを得て乱れ入り、爆風が吹いて五穀も実らず、疫病が流行して、人々が大量に亡くなることになるだろう。今から7、8年ほど前までは、「(念仏以外の)他のさまざまな修行では永遠に極楽世界に生まれることはできない。善導和尚が「(雑行を行って心が純粋ではないものは)千人のうち一人も極楽世界に生まれることができない〔千中無一〕」と結論なさった上、「選択集」〈注17〉には「(念仏以外の)他のさまざまな修行は投げ捨てよ。(他の修行を)行う者は、暴漢の集団である〈注18〉と記されている〉などと、好き放題に言って、強く訴えていた。それに対して、この4、5年が過ぎた後には、「選択集」のように人に勧める者は、謗法の罪によって師匠も信者も両方とも無間地獄に堕ちるにちがいないと、経文に記されている」という教えが出現した様子がある。それに対して、はじめは念仏の修行者たちは全員がそれを不思議に思った上、「念仏を唱える者は、無間地獄に陥るにちがいない」などと口汚く騒いでいましたが、「念仏の修行者は無間地獄に堕ちるにちがいない」という言葉によって智慧がついて、おのおのが「選択集」に詳しく目を通した。そうすると、確かに(「選択集」を)謗法の書物とみなしたのだろうか、「仙人のうち一人も極楽世界に生まれることができない」という間違った教えを口にせず、他のさまざまな修行でも極楽世界に生まれることができるということを、どの念仏の修行者も主張している。しかしながら、ただ言葉の上で認めているだけで、心の中は相変わらず元の「仙人のうち一人も極楽世界に生まれることができない」という思いである。在家の愚かな人は、(念仏の修行者の)ない芯が謗法であることを知らないで、〝穂家のさまざまな修行でも極楽世界に生まれることができる〟という言葉に騙されて、「念仏の修行者は法華経を誹謗していないのに、〝法華経を誹謗している〟と聖道門〈注19〉の人が言っているのは、不当なことである〉と思っているのではないか。そのような人は、ひたすら「他のさまざまな修行では、千人のうち一人も極楽世界に生まれることができない」と言う人よりも、謗法の心が勝っている。(このように念仏の修行者は、内心とは裏腹に所業を行次てもよいと主張し、念仏には)問題がないということを人に知らせて、島も念仏だけを再び弘めようと画策しているのである。これもすべて、天魔のもくろみなのである。…………〈注6〉〖8年間〗『法華玄義』巻5条では、釈尊が72歳のときに法華経を説き始めたという伝承を紹介している。また、『法華玄義釈籖』巻11や『法華文句記』巻4下では、釈尊が覚りを開いてから42年後に法華経を説いたという菩提流支『法界性論』(現存しない)の説を引いている。釈尊は80歳で亡くなったので、これらに基づいて、天台教学では、法華経を説いたのは8年間とされている。〈注7〉〖序分〗経典の導入部にあたる部分。無量義きょうは、法華経を説くための準備として直前に説かれた経典(開経)と位置付けられた。〈注8〉〖いつも霊鷲山にいる〗法華経如来寿量品第16の「常に霊鷲山 及び余の諸の住処に在り」(法華経491㌻)に基づく。釈尊は、人々に仏法を信仰させるために私の姿を示すが、実際には霊鷲山で存在し続けているという趣旨の文。霊鷲山は、法華経をはじめ多くの経典を説いた舞台とされている。〈注9〉〖三乗〗声聞・縁覚・菩薩のこと。二乗(声聞と縁覚)に菩薩を加えたもの。〈注10〉〖五乗〗三乗に人・天(神々)を加えたもの。〈注11〉〖「菩薩の多くの劫にわたる修行を述べた」〗無量義経説法品第2の文(法華経32~33㌻)。無量義経より前に説いた経典では、きわめて長い時間にわたる修行を説いていたという趣旨の文。〈注12〉〖「言葉は同一でも、意味はそれぞれ異なっている」〗無量義経説法品第2の文(法華経32㌻)〈注13〉〖「まだ真実を顕していない」〗御書本文は「未顕真実」。同じく無量義経説法品第2の文(法華経29㌻)。釈尊が覚りを開いて、無量義経を説くまでの40年余りは、長州の意向に合わせて説法してきたが、真実の教えはまだ説いていなかったという趣旨。〈注14〉〖「険しい道の妨げが多いからである」〗御書本文は「留難多きが故なり」。無量義経より前の経典は、覚りに通じる真っすぐな道ではなく、妨げの多い険しい道のようなものであり、いくら修行しても覚りを開くことはできないという趣旨の文。〈注15〉〖法華経や密教経典〗御書本文は「法華・真言」。「災難興起由来」や「立正安国論」での用法から考えて、法華・真言はそれぞれ、宗教ではなく経典を指すと解した。〈注16〉〖竜神〗インドの想像上の生き物ナーガのこと。蛇を神格化したもの。〈注17〉〖「選択集」〗法然の著作「選択本願念仏集」んこと。阿弥陀仏の誓願に基づく称名念仏(南無阿弥陀仏と称えること)こそ、極楽世界に生まれるための最高の修行であると説いている。〈注18〉〖他のさまざまな修行は投げ捨てよ。行う者は、暴漢の集団である〗「選択集」の取意。〈注11〉〖聖道門〗浄土教(浄土門)以外の仏教のこと。 大白蓮華2025年1月号
September 9, 2025
コメント(0)
-
丸馬出を駆使した鉄壁の防御
丸馬出を駆使した鉄壁の防御城郭ライター 萩原 さちこ諏訪原城諏訪原城(静岡県島田市)は「丸馬出」で知られた城です。「馬出」とは、虎口(出入り口)の前に置かれた、前線基地であり防御拠点にもなる区画のこと。半円形の馬出を丸馬出といいます。諏訪原城には、丸馬出とそれを囲む堀が幾つも良好に残っています。近年は整備が進み、その規模や構造がさらにわかりやすくなりました。城全体の設計も楽しめ、戦国時代を土づくりの城を初めて訪れる方にもお勧めです。大小五つの丸馬出を駆使して虎口を複雑化した、巧妙な設計が特徴です。馬出を二つ重ねた「重ね馬出」を配置することで鉄壁の防御を生み出しています。敵が歩きやすそうな直線路も、道幅を狭めて敵を1列にし、射撃面を増やして効率よく狙い撃ちできるよう工夫。横堀も駆使されていて、感嘆の連続です。敵の動きや城兵の迎撃法をシュミレーションしながら歩くと、どう守り、どう戦おうとしているのかが分かります。諏訪原城は、駿河から徳川家康領の遠江へ侵攻した武田勝頼が、1573年に馬場信春に命じて築かせました。駿河と遠江の国境、大堰川の誓願にあり、大井川下流域と聞く川に挟まれた牧之原台地の北端近くにあります。当時の大井川は牧之原台地に沿って流れ、背後は河川と断崖に守られていたようです。築城の目的は、大井川沿いの防御線、徳川方の拠点である掛川城などのけん制、高天神城攻めの前線基地としての機能でしょう。武田方にとって、遠江攻めの重要な橋頭堡だったはずです。翌年に崇天神城を攻略すると、兵站基地としての役割を担いました。しかし、1575年に長篠・設楽原の戦いで勝頼が大敗し形勢は逆転。諏訪原城はすぐさま家康に攻略され、徳川方の城へと大改修されました。丸馬出は武田氏の城によくあるため、丸馬出が多用された諏訪原城は武田の城の代表例とされてきました。ところが近年の調査により、ほとんどの丸馬出は徳川方が築いた可能性が高くなりました。上書きされた歴史があるのも、諏訪原城の面白さです。 【日本全国お城巡り23】公明新聞2024.12.26
September 8, 2025
コメント(0)
-
腎臓の主要な働き
腎臓の主要な働き「一番好きな臓器はなんですか? 出会った人からそう問われるのは比較解剖学を専門とする東洋大学の郡司芽久助教だ。研究対象は筋肉や骨格の構造。でも、解剖学と聞いて内蔵の研究だと誤解されるらしい◆もちろん臓器に思い入れはない。なのに、いつもなぜか腎臓が思い浮かぶのだとか(『キリンのひづめ、ヒトの指 比べてわかる生き物の進化』NHK出版)◆腎臓の主要な働きの一つは血液中に溶けている尿素を集め、体外に排出すること。血液の中には老廃物の尿素だけでなく、赤血球や分解前のタンパク質など、生命活動に必要かつ重要な物質も数多く含まれている◆さまざまな物質が溶け込んだ血液の中から大事なものだけを取り出す。いわば、ごみ処理場のような役回りで、あまり日の目をみない。だが、どの臓器よりも複雑かつ精緻な構造をもち、淡々と役割を果たす。助教は、それが腎臓に引かれるゆえんだと◆わが身を振り返れば肺や心臓も休むことなく命を支えている。ささいなことで自分にがっかりしたり、落ち込んだりする筆者。そんな時にこそ誇りに思いたい。機能する限り決してへこたれない〝彼ら〟と共に歩んでいることを。(佳) 【北斗七星】公明新聞2024.12.25
September 8, 2025
コメント(0)
-
ギャンブル規制強化を
ギャンブル規制強化を〝携帯電話はポケットの中のカジノ〟英国の医学誌ランセットの姉妹誌「ランセット・パブリックヘルス」の委員会は、商業ギャンブルの国際的な広がりが健康や福祉にもたらす悪影響に懸念を表明、規制強化を提言しました。世界保健機構(WHO)のほか11カ国の専門家でつくる同委員会の提言によると、オンラインを利用したカジノやスポーツ賭博は近年、急速に拡大。世界で約4億5千万人がギャンブルの影響にさらされ、このうち8千万人はギャンブル依存症や問題のあるギャンブルを経験しています。また、新しい分析ではオンラインのカジノやスロットを利用する大人の16%、青少年の26%、また、スポーツ賭博を利用する大人の9%、青少年の16%に、ギャンブル依存症の恐れがあると推測しています。委員会共同議長のヘザー・ウォードル英グラスゴー大学教授は「ギャンブルというと、ほとんどの人は伝統的なラスベガスのカジノや宝くじを思い浮かべるが、人々を誘い込む最新技術を活用した巨大テクノロジー企業とは、思いもしない。いまや携帯電話を持っている人は誰での1日24時間、ポケットの中のカジノにアクセスできるようになった」と危機感をのべています。商業ギャンブルは、多額の借金を負わせるだけでなく、心身の健康問題や人間関係の破綻、自殺や家庭内暴力の可能性、犯罪の増加や雇用の喪失にもつながるとされています。インドネシアの研究者は「インドネシアではギャンブルは違法だが、オンラインギャンブルの取引量が近年爆発的に増えている。国内の法執行機関ではこれら国際サービスのアクセスを規制することができない」として、国際協調による規制強化の必要性を訴えています。 【医療 最近の話題から】聖教新聞2024.12.23
September 7, 2025
コメント(0)
-
仏教は一神教的絶対者を立てず
仏教は一神教的絶対者を立てず ところが、インドは陸続きであったことから、イランの方から在外の神格が仏教に取り込まれることが起きた。クシャーナ王朝(一世紀半ば~三世紀半ば)の頃に高まったマイトレーヤ菩薩として仏教に取り込まれたことに依っている。それに伴い、西洋の一神教的絶対者の永遠だが抽象的な如来(法身)が考え出され、本来の仏教の人間観・ブッダ観とはかけ離れたものになる傾向が出てきた。ゾロアスター教の最高神アフラ・マズダーに起源をもつとされる毘盧遮那(vairocana)仏である。中村元先生は、「西洋においては絶対者としての神は人間から断絶しているが、仏教においては絶対者(=仏)は人間の内に存し、いな、人間そのものである」(『原始仏教の社会思想』中村元選集決定版、第一八巻、二六一頁)と言われた。仏教では本来、人間からかけ離れた絶対者的に見すえた人間主義であり、人間を〝真の自己〟(人)と、人間としてあるべき理法(法)に目覚めさせるものであったのだ。日蓮も、それと同じ思いで「出尊形の仏」「無作の三身」という言葉を引用して用いたのであろう。しかし、既に述べたように、「三身」という表現は、本来の仏教から逸脱であり、筆者は基本的に用いないことにしている。「無作の三身」を「無作の仏」と表記しても何の問題もない。日蓮は、『御義口伝』において、三身の具体的内容には何もこだわっておらず、伝教大師が用いた「無作の三身」という表記を採用しているだけのようだ。以下、本書の解説においては、どうしても「無作の三身」という言い方を用いなければならない場合を除いて、「無作の仏」とすることを断っておく。 【日蓮の思想『御義口伝を読む』】植木雅俊/筑摩選書
September 7, 2025
コメント(0)
-
「人」と「法」の関係の逸脱
「人」と「法」の関係の逸脱 天台大師が、「三身即一身」「一身即三身」と言って三身を融合させようとしたり、「報中論三」、すなわち報身が根本であって、そこに三身が具わっていると論じたりしなければならなかったのも、余計なことがなされたことで生じる無理を繕おうとしたものだとしか思えない。このようにして考え出された(法身・報身・応身)の三身に、それぞれ〈真理・智慧・肉体〉という意味付けも行われたようだが、これも後付けのこじつけでしかない。二身論や、三身論などといった余計なことを考え出さず、「人」と「法」の関係のままでいれば、すっきりとしていた。ところが後世になって、普遍的真理であった「法」が人格化されて、宇宙そのものを身体とする「法身如来」(法身仏)という特別の存在にされてしまい、各自が体現すべきものとしてあった「法」が、崇め、すがるべき対象にされてしまった。その法身如来は、我々の現実世界とはかけ離れた存在であり、一神教的絶対者と類似した構造になる。そうなると、仏教本来の「人」と「法」の関係性が崩れてしまう。仏教では、「依法不依人」(法に依って人に依らざれ)として、依るべきものは「人」ではなく、「法」とされていたのにもかかわらず、その「法」を「法身如来」として「人」にしてしまったのである。それは、もはや仏教とは言いえないのである。仏教はそのような絶対者的存在を立てることはないのであって、「法身如来」は、仏教を本来の思想を逸脱したものである(詳細は橋爪大三郎・植木雅俊著『ほんとうの法華経』、三二三~三二四頁を参照)。その一神教的絶対者と我々との間に、「預言者」のような介在者が割り込んでくると、その人は特権階級になる。仏教は、そのような絶対者や、特権階級を必要とせず、「人」と「法」の関係として「法」(dharuma)の下に、釈尊も例外とせず、あらゆる人が横並びとなる平等思想を説いていたことを知るべきである。 【日蓮の思想『御義口伝を読む』】植木雅俊/筑摩選書
September 6, 2025
コメント(0)
-
〝三身如来〟の問題点
〝三身如来〟の問題点 日蓮が引用した伝教大師の著作の一節に「無作の三身」という言葉があった。この『御義口伝』には、この言葉がしばしば出てくる。これは、歴史的な背景があって用いられているが、「三身」という言葉は、本来の仏教からすれば、適切でないものであることを指摘しておかなければならない。法身・報身・応身の三身論が登場したのは、釈尊滅後八百年を経過した四世紀ごろのことで、その二百年ほど前には二身論が先行していた。釈尊が八十歳で亡くなったということで、〝有限の仏〟に対する〝永遠の仏〟という議論が展開され、法身如来(法身仏)という考えまでに発展する。「法身」と漢訳されたのは、パーリ語のダンマ・カーヤ(dhanma-kaya)でその語が、紀元前二世紀ごろの『ミリンダ王の問い』(Milinda Panha)に登場する。アレクサンドロス大王のインド遠征(紀元前四世紀末)の後、西北インドに住み着いたギリシア人の子孫であるミリンダ(弥蘭陀、ギリシア名=メナンドロス)という王様が、インド人の仏教僧ナーガセーナ(那先)との対談で、「ブッダの存在を示すことができますか」と尋ねた。ナーガセーナは次のように答えた。 既に入滅してしまった世尊を、「ここに居る」とかといって示すことはできません。けれども、世尊をダンマ・カーヤによって示すことはできます。ダンマ(法=真理)は世尊によってとき示されてきたものであるからです。 このダンマ・カーヤは、後の大乗仏教の言う「法身」「法という身体」という意味ではない。カーヤに「集まり」という意味があるので、「法の集まり」というほどの意味である。釈尊は、「法」を覚ってブッダ(目覚めた人)となった。その「法」は、人間として在るべき理法、真理のことで、あらゆる人にも開かれている。釈尊は、自らをブッダたらしめたその「法」を「経」として残した。それがダンマ・カーヤ、すなわち「法の集まり」と称されている。「人」と「法」の関係としては、「総論 南無妙法蓮華経とは」(三七頁)で詳述しておいた。釈尊自身は、自分のことを永遠の存在だと思ってほしいなどと考えてもいなかった。釈尊自身がそうであったように、「人」としてめいめいの「自己」と「法」をよりどころとするように、〝遺言〟していた。その考えが、『大パリニッパーナ経』において、入滅を間近にした釈尊によって「自帰依」「法帰依」として説かれていたのである。「法」が釈尊の後継者であり、師であり、よりどころである。そこには、〝永遠のブッダ〟などの出てくる余地など存在しないし、必要なかった。 【日蓮の思想『御義口伝』を読む】植木雅俊/筑摩選書
September 6, 2025
コメント(0)
-
団塊の世代が75歳以上に——介護「2025年問題」
団塊の世代が75歳以上に——介護「2025年問題」にどう対応淑徳大学 結城 康博教授に聞くゆうき・やすひろ 1969年生まれ。淑徳大学卒、法政大学大学院修了。政治学博士。研究分野は社会保障論、社会福祉学。ケアマネ―ジャーなどを経て現職。著書に『介護格差』(岩波新書)など。要介護者 急増の可能性人手不足で支援届かぬ恐れ現場の実態——介護を巡る現状は結城康博教授 今年8月時点で介護が必要な要介護・要支援の認定者数は約718万人に上っており、65歳以上に占める割合は約20%だ。統計的に75~79歳と比較すると倍以上に高まる。人口の構成上、一番多い団塊世代が全員75歳以上になるということは、来年以降、要介護者が急激に増える可能性があるということだ。高齢者の単身世帯が増えていることも心配の一つだ。単身者は家族による在宅介護ができない。1人暮らしの在宅介護者もいるが、要介護3以上になると、認知症も伴う場合が多く、非常に大変だ。また日本は、「保証人社会」であり、家賃や介護保険、入院の契約時に保証人がいないとサービスが使いにくい。結果、社会で生きづらくなる。 ——介護の現状は結城 訪問介護を代表として、人手不足が進んでいる。訪問介護は有効求人倍率約14倍(昨年度)で、地域によっては非常に人数が少なくなっている。介護保険をと花押としても、契約してくれる事業者がおらず、要介護認定を受けてもヘルパーが来てくれないといったことが既に起きている。厚生労働省によると、こうした事態を防ぐには、介護職人数が26年度には約240万人、40年度には約272万人必要だとしている。毎年の着実な増加が欠かせない。 ——人手不足の原因は。結城 まず労総市場の資金水準に介護業界が追い付いていないことが問題だ。人口減少社会で、どの業界も人手が足りていない。そうした中で、介護業界は他の産業に比べて依然として給料が低いのが現状だ。社会的に賃上げの流れが起きているが、今年の中小企業の賃上げ率が約4%だったのに対し、介護報酬改定による介護業界の賃上げ率は2.5%だった。また、人口減少だけでなく少子化も進む中で、そもそも人がいない。介護業界全体で若い人を受け入れる体制づくりができていないことも人材不足の要因となっている。ベルの角度では、ハラスメントの問題もある。介護サービスの利用者のうち、肌感覚では10~15人に1人の割合でハラスメントをしている。介護業界に人が集まらないのは、そうした要因が複雑に絡み合っている。 求められる施策人材確保への賃上げ重要介護福祉士医療行為の拡大検討 ——求められる対応は。結城 介護報酬をあげるなど介護事業者の処遇改善を進めることが重要だ。介護政策の充実、特に介護人材対策に大きく投資し、賃金を全産業並みにすることが求められる。賃金が上がることで介護業界へのイメージも良くなる。一方で現役世代が働きながら家族らの介護を行う「ビジネスケアラー」が増加することが予想される。ビジネスケアラーへの支援では、介護休業などの制度が充実してきているものの、最終的にはプロのヘルパーや施設に関わってもらわなければ、仕事と介護の両立はできない。介護の「楽しさ」や「やりがい」などの啓発活動を通じて、介護従業者を増やし、育成していく取り組みも不可欠だ。 ——そのほかには。結城 資格自体の見直しも必要だ。地域で医療ニーズの高い要介護者が増えていく状況下では、医療行為ができる介護福祉士がもっと重要になる。現状は、たんの吸引や経管栄養しかできないが、医師の指示も能登で駐車や点滴、導尿といった、例えば准看護師レベルの医療行為ができる介護福祉士の新しい資格を創設すれば、それに見合った待遇改善にもつながるのではないか。 ——当事者や家族、周辺の人たちが意識すべき点は。結城 現時点では介護業界に外国人労働者が多く入ってくる見込みは立っていない。事業者側からすると、人手が足りない状況では、介護する人を誰でも受け入れるというわけにはいかない。つまり介護する人を選ぶ可能性があるということだ。大事なことは、要介護者やその家族も顧客権利意識を持つのでは核、選ばれるための「支えられじょうず」になることが求められる。その意味では今後、介護を受ける側のマナー講習のような取り組みも必要になる。さらには、そもそも介護されなくても済むように健康で過ごす各自の努力も必要だ。そのためには日ごろから社会参加を促し、いろいろな人とつながりを持って行くことが重要になる。 社会で支える体制構築を来年以降制度改革へ勝負の10年 必要な視点——介護政策の在り方や政治に求めることは。結城 国民全体で、「介護なくして、日本の社会、経済は持たない」というコンセサス(合意)をつくり出すことだ。何も対策を講じなければ、親の介護で働けなくなる介護離職者が一気に増える。50代、60代の管理職矢部寺bb社員が、介護のために仕事をやめざるを得なくなる。離職を回避できたとしても、十分な働きができない。そうした層が増えてしまえば、日本経済自体に大きな打撃となる。だからこそ、社会全体で介護を支えるための政策にお金を回すことが求められる。介護政策とは一種の労働政策だ。社会を維持するための〝インフラ政策〟と言ってもいい。介護への投資で介護職の賃金をアップさせる。ビジネスケアラーには、安心して介護しながら仕事もできる環境をつくる。介護人材を確保する仕組みを整える。こうした施策を副詞的な側面だけでなく、社会全体を支えるインフラ的な視点で議論してもらいたい。 ——人口の3分の1が高齢者になる「35年問題」もあるが。結城 35年には、団塊の世代が全員85歳以上になる。85歳以上の要介護認定率は5割以上と言われているので、来年から、必要な手立てを講じる「勝負の10年」となる。そのためには社会保障全体の仕組みも見直し、大改革をしていく必要がある。現役世代がどんどん減っていく中で、高齢者が高齢者を支えるという世代内で助け合いも大切になってくるだろう。10年と言っても残された時間は少ない。介護保険制度を維持していくための〝勝負〟が今こそ必要だ。公明党がその先頭に立ち、存在感を発揮することに期待したい。 外出や友人と会うなど社会参加が多いほど要介護リスクが提言——。日本福祉大学の健康社会研究センターが今年5月に発表した調査によると、ここ10~20年の65歳以上の高齢者について、社会参加の増加によって、要介護認定の発生リスクが低下していることが分かった。同調査では、2010年度の高齢者2万2522人と、16年度の高齢者2万6284人をそれぞれ3年間かけて追跡。双方のグループ外出や人とのつながりなど社会参加で介護リスク減で要介護2倍以上の認定を受けた割合を比較した結果、65~74歳の前期高齢者では、16年度の要介護発生リスクが10年度と比べて25%低下、75歳以上の後期高齢者では、27%低下した。低下した要因に関しては、外出や友人と会うといった社会参加する機会が全体的に増えたからだと分析。社会参加に要介護認定の発生リスク低下に関連している可能性があると結論付けている。 【土曜特集】公明新聞2024.12.21
September 5, 2025
コメント(0)
-
自身の強みを意識しよう
自身の強みを意識しよう作家 伊東 潤若い頃は好きな作家ができると、その人の著作ばかり読んでいた。それで気づいたことは、どの作家も作品によって当たりはずれがあることだ。当時は「そんなものかな」と思っていたが、作家になってからは自分はそうなってはいけないと思い、どうしたらハズレをなくせるかを考えた。その結果、たどり着いたのは、「自分の強みから離れない」ことだった。それには、まず自分の強みを定義せねばならない。それで書評家の方に自作の強みを尋ねると、「合戦の臨場感かな」という答えが返ってきた。私の場合、歴史小説の戦国ものから始めたからだ。その後、別の時代を描くことになり、何を題材にするかを考えた末、選んだのが「合戦の臨場感」を生かせる古式捕鯨という題材だった。そして『巨鯨の海』という作品に結実させた。それからは、この方法論で様々な分野に挑戦していった。偶然だが、自分の人生のキャリアチェンジにも強みを重視してきた。私はビジネスマン時代、誰かに仕事の一部を託すのが嫌だった。大きなプロジェクトでも、自分で全てをやりたいと思った。それで自分には自己完結の仕事が向いていることに気づき、作家へと転身した。作家ほど自己完結性の高い仕事はないからだ。これも自己完結という強みを見つけたからにほかならない。こうしたことは、だれにでも適用できることだ。自分の強みを客観的に把握し、それを外さない仕事をしていく。ないしは、仕事そのものを自分の得意な領域に引き込んでいく。「上から仕事を課されるので無理」と言うなら、自分でコントロールできる仕事に移ればよい。そのくらいの覚悟がなければ、自分の強みを仕事で生かすことはできないだろう。 【すなどけい】公明新聞2024.12.20
September 5, 2025
コメント(0)
全58件 (58件中 1-50件目)
-
-
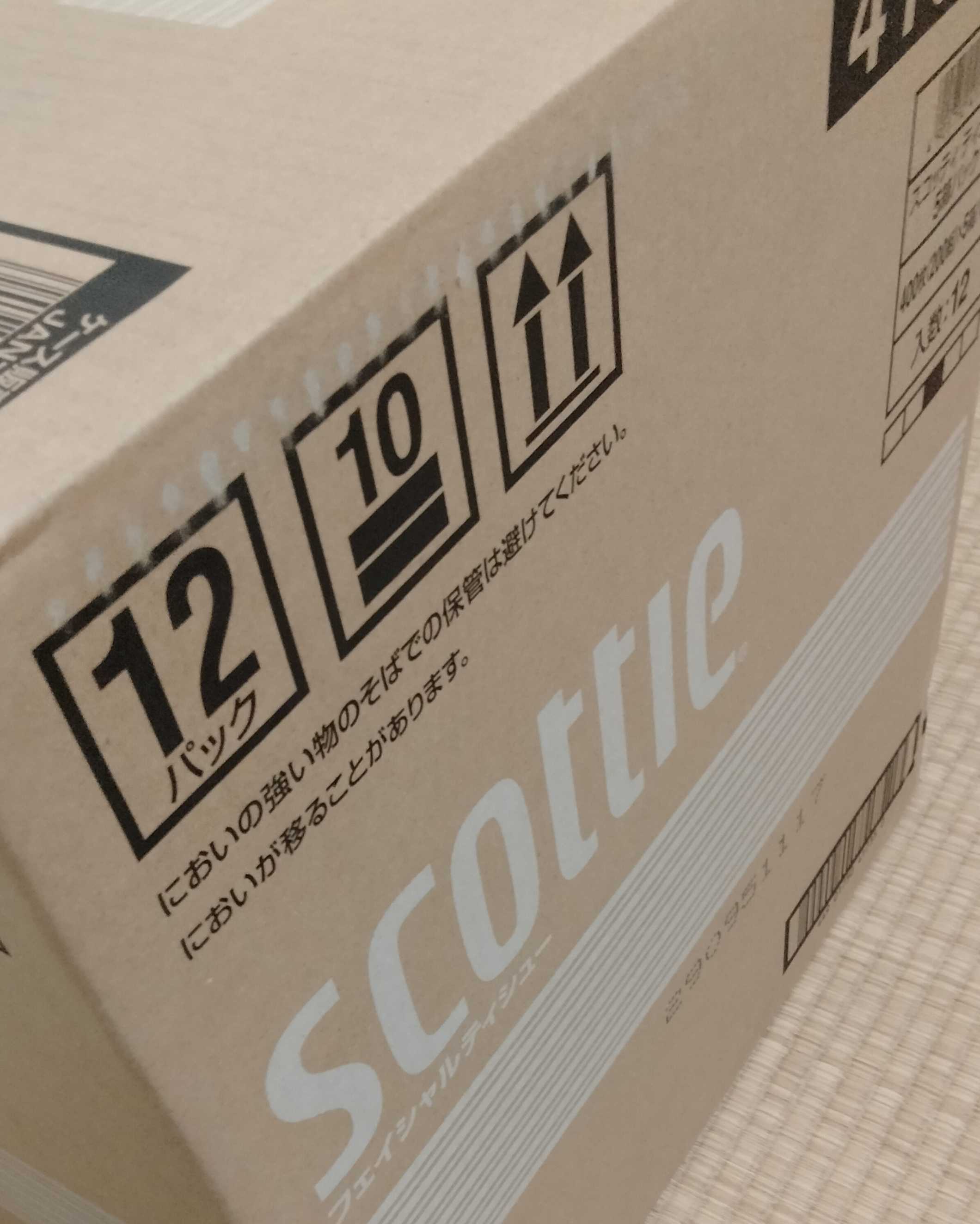
- 株主優待コレクション
- マツキヨココカラ:京都で:ノンアル…
- (2025-11-15 18:27:26)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【2025年11月】お買い物マラソ…
- (2025-11-15 11:01:26)
-
-
-
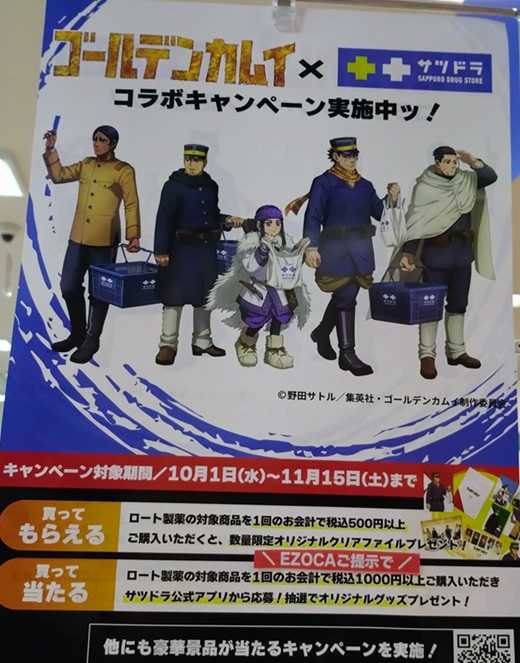
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-







