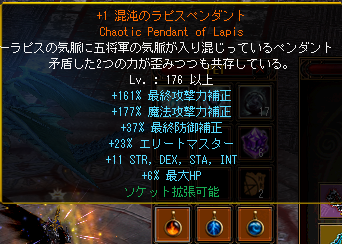2009年11月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

歯ぐきが腫れて痛い・・・(T_T) 行きつけの歯医者さんで見てもらうことにした
先週の木曜日ぐらいから左の上の歯が痛み出した。触ってみると、歯ぐきの外側が腫れて膨らんでいる。しばらく様子を見ていたが、よくならないので行きつけの歯医者さんで見てもらうことにした。歯医者さんは平日は午前9時30分から午後1時まで、午後は午後3時から午後7時までの診療だ。今日、月曜の朝。診療の始まる前の午前9時15分ごろ電話した。症状を簡単に言うと、「午前中はどうですか?午前11時からならOKですよ」と言うので予約した。行ったのは、兵庫区にある「くれもと歯科医院」だ。くれもと歯科医院_01くれもと歯科医院_01まず、歯ぐきの腫れている歯のレントゲンと、口全体のレントゲンを撮ってもらった。その上で、お医者さんに診断してもらった。定期的に歯石を取ってもらっていたので、「今まではどうもなかったのですが、だいぶん悪くなっているうようですね」と言われ、レントゲンを見て口腔の中を見てもらった。歯の根の元に細菌が入って膿ができているとの事。その影響で、歯の骨も細くなっていると言われました。実際に、ペンの先のカメラで撮影した歯ぐきの映像、レントゲンを見せてもらって、「歯の根の半分が黒っぽくなっています。ここに細菌が入って骨を溶かしているんです」と説明があった。とりあえず、膿を取り出して腫れがひくか様子を見ますとの事。どうしても腫れがひかないようでしたら、歯を抜くしかありませんね。それで、歯ぐきに麻酔をしてもらい、歯ぐきを切開して膿を出してもらった。その後、歯科衛生士さんに、その歯の部分の歯石を取ってもらい、切開した歯ぐきの消毒をしてもらった。その後、お医者さんから説明があり、しばらく様子をみます。1週間後にまた来て下さい。痛み止めの薬と消毒用のうがい薬を出しておきますとの事でした。うがい薬と「とんぷく」いろいろ説明がありましたが、もらって帰ってきて、袋をあけてみたら・・・。消毒用と説明のあった「うがい薬」は、ごく普通のうがい薬の「イソジンガーグル」だ。「とんぷく」用としてもらった「痛み止め」の薬も、ごく普通の痛み止めの「ボルタレン」だ。歯ぐきの腫れが引くのは時間薬でしょうが・・・。そう言いながら、炎症には悪いと決まっているお酒を今夜も飲んでいます・・・(^^♪
2009年11月30日
コメント(2)
-

三宮のイルミネーション エコ・エンジェル2009
JR三ノ宮駅の南側にイルミネーションが出現している。”エコ・エンジェル”と銘打って、発光ダイオードを使ったイルミネーションだ。エコ・エンジェル_02エコ・エンジェル_05エコ・エンジェル_03エコ・エンジェル_01エコ・エンジェル_04 エコ・エンジェル_08エコ・エンジェル_06三宮駅南エリア(神戸市中央区三宮町・雲井通・小野柄通周辺)の2階歩行者用デッキを中心に、LED20万球による、総延長約1,000mに及ぶデッキ回廊イルミネーションです。【エコ・エンジェル2009(YouTube)】
2009年11月29日
コメント(0)
-

広島から東城・帝釈峡までは列車の旅。もちろん、東城から神戸までも列車です!
広島から東城・帝釈峡までは高速バスがあるようです。値段も早さもそちらの方がリーズナブルなのですが・・・。でも、今回は、あえて列車の旅を楽しみました・・・【11月20日】広島駅から岡山駅までは新幹線です。駅を出てすぐに見えてくるのが、新しい広島市民球場です。広島カープの本拠地です。新広島市民球場_01新広島市民球場_02岡山駅で新幹線を降りて、在来線に乗り換えです。岡山駅は南北になっていて、東側(海側)が新幹線です。新幹線の西側に在来線のホームが並んでいます。一番手間に、伯備線(新見・米子方面)のホームがありました。特急やくも号_01特急やくも号_02やくも17号 岡山 15:05発~新見 16:06着です。特急やくもが入線してきます。特急やくも号_04島根県の出雲市行きです。特急やくも号_05可愛いキャラクターですね。特急やくも号_06 特急やくも号_07やくもの車窓から・・・。特急やくも号 車窓_01特急やくも号 車窓_02新見駅で芸備線に乗り換えです。芸備線 下り_01東城駅止まりの普通電車です。新見 16:12発~東城 16:48着です。芸備線 下り_02車窓からも、晩秋ですね・・・。芸備線 下り_03芸備線は、ワンマンカーでした。芸備線 下り_04東城駅手前で、ちょうど夕日が沈んでいきます。きれいな夕焼けでした。芸備線 下り_05東城駅_01夕闇迫る東城駅です。上帝釈行きのバスを1時間ほど待ちました。帝釈峡を満喫した後、また東城駅から乗ります。【11月21日】東城駅_02新見行きの普通電車です。これも、ワンマンカー。備後落合発で、東城は15:07分発です。新見には15:42に到着。芸備線 上り新見駅から岡山駅までも、今度は普通電車でした。備前片上行きです。新見始発で、15:50発~岡山に17:25に着きました。伯備線 上り_01総社の手前で、みごとな夕焼けになりました。伯備線 上り_02予定より2時間ほど、早く岡山駅に着いたので途中下車して、噴水広場を見てきました。きれいにライトアップされていました。噴水広場_07噴水広場_06噴水広場_05噴水広場_01噴水広場は、僕が中学生の時、35年以上前・・・。岡山大学病院に入院していた時に初めて見ました。
2009年11月28日
コメント(0)
-

帝釈峡の神石民俗資料館 縄文時代の遺跡&虎屋旅館
帝釈峡の神龍湖畔に神石民俗資料館がある。縄文時代の遺跡資料から、江戸時代、神楽の資料まで展示されている。【11月21日】帝釈峡 神石民俗資料館_12縄文時代の石のやじり。帝釈峡 神石民俗資料館_02時代は下って、大和朝廷の時代の須恵器です。帝釈峡 神石民俗資料館_01天然記念物のオオサンショウウオのはく製です。帝釈峡 神石民俗資料館_03特産の和牛。神石牛の頭の骨。帝釈峡 神石民俗資料館_05牛のミイラです(7ヶ月の胎児)。帝釈峡 神石民俗資料館_06キツネのはく製もありました。帝釈峡 神石民俗資料館_10神楽のお面などもありました・・・。帝釈峡 神石民俗資料館_08帝釈峡 神石民俗資料館_07さて、帝釈峡で泊まった旅館は映画「寅さん」の撮影舞台ににもなった「虎屋旅館」だ。虎屋旅館虎屋と角屋旅館_02お隣の「角屋旅館」と共に、上帝釈では人気の旅館になっている。泊まった旅館の窓からの帝釈天・永明寺と紅葉。虎屋旅館 紅葉帝釈峡の名前の由来にもなる、帝釈天・永明寺です。帝釈天 永明寺最後は、旅館の料理の紹介・・・虎屋旅館の料理メインは、ベニマスのお刺身と塩焼き。それに天婦羅です。虎屋旅館 神石牛のステーキそれに、神石牛のステーキがつきました。部屋も、メインの8畳に6畳の脇部屋、そしてベランダ。それに、洗面所とトイレとお風呂が付いている。かなりリッチなお部屋でした。お値段はさすがに、11,000円しましたヨ。最後に、岡山駅から乗った特急「やくも」など、列車の旅を紹介しなければなりません。
2009年11月27日
コメント(0)
-

帝釈峡の遊覧船で紅葉の残りを楽しむ・・・
帝釈峡の遊覧船乗り場に行くと・・・。「今出るところです。急いでください」!チケットを買って、あわてて乗船口まで降りていった。13時の便だった。【11月21日】帝釈峡 遊覧船_02帝釈峡観光が本格的に始まったのは、1924年(大正13年)に帝釈ダムが完成して、神龍湖が出来てからの事。その前は、数軒の農家が点在する山奥だったそうです。その数軒の農家の一軒でしょうか?遊覧船から見えました。帝釈峡 遊覧船_03紅葉のなごりです・・・帝釈峡 遊覧船_05帝釈峡 遊覧船_07帝釈峡 遊覧船_08帝釈峡 遊覧船_04岩肌がむき出しでそそり立っています。帝釈峡 遊覧船_06神龍湖の中に島が浮かんでいます。蓬莱山といいます。神龍湖の一番端には帝釈ダムがあります。帝釈峡 帝釈ダム_01帝釈峡 帝釈ダム_02ダムの堰堤の幅がわずか40mというのは珍しいそうです。ダムの奥にある岩盤は「太郎岩」と言われ、ダムを設計した速水太郎の名前を取ったそうです。帝釈峡 帝釈ダム_03帝釈峡 遊覧船_11紅葉(もみじ)橋の下をくぐります。帝釈峡 遊覧船_13桜橋です。帝釈峡 遊覧船_09神龍橋です。帝釈峡 遊覧船_12帝釈峡 遊覧船_14帝釈峡 遊覧船_15遊覧船も楽しんだあとは、ちょっとタイムスリップしてみます。神龍湖畔に「神石民俗資料館」があり、縄文時代の遺跡から神楽のお面まで展示されています。
2009年11月26日
コメント(0)
-

帝釈峡の広島自然歩道を歩く・・・ 登りはかなり急な坂\(◎o◎)/! でも紅葉の残りが見れました!
電車とバスで来たのだから、この際と自然歩道で神龍湖まで歩くことにした。ニジマスの養殖場のところから遊歩道は通行止めになっている。養殖場の前に「中国自然歩道」の看板が・・・。「高低差150mあります」と書いてあります。覚悟して歩いてくださいねってことですね。帝釈峡 自然歩道_01帝釈峡 自然歩道_02神龍湖駐車場まで3.2km・・・帝釈峡 自然歩道_03自然歩道の登口。ここから、延々と木組みの階段と坂道が続きます。もう頂上かなと思わせておいて道が曲がっていたり・・・。一旦平坦になったかと思ったら、また坂道が続いたり・・・。本当の頂上までに着くのに20分あまりでした。実際は、もっと時間がかかったような感覚です・・・。ああしんどかった (#^.^#)・・・帝釈峡 自然歩道_04右に曲がれば、スコラ高原。神龍湖は左手です。ここからも、アップダウンはそこそこありましたが、そこそこ平坦な道です。自然歩道でも、以外に紅葉を楽しむことができましたヨ!自然歩道 紅葉_01自然歩道 紅葉_02自然歩道 紅葉_04地面に笹の群生もありました・・・自然歩道 笹途中に、人家があるところを通過します。帝釈峡 自然歩道_05ほどなく、眼下に赤い橋が見下ろせます。ここからがまた急な坂道。でも、今度は目的が見えているので足取りは軽くなります・・・。坂道の高度差も、上帝釈の側と比べると半分ぐらいのようです。神龍湖側に下りてきて、最初に出会う橋。神龍橋です。帝釈峡 神龍橋_01帝釈峡 神龍橋_03神龍橋の下を走る遊覧船・・・神龍橋からの遊覧船_01神龍橋からの遊覧船_02帝釈峡 紅葉橋_01神龍橋をすぎて、ほどなく紅葉(もみじ)橋が見えてきます。帝釈峡 紅葉橋_02紅葉橋のたもとに遊覧船の乗船口があります。紅葉橋を渡って、トンネルをぬけてみやげ物街を通って行くと桜橋に行きます。ここからまた、神龍橋に戻って行けます。帝釈峡 桜橋_03帝釈峡 紅葉橋_03桜橋からは、紅葉(もみじ)橋を望むことができます。神龍湖の橋を満喫したところで、遊覧船を楽しみます・・・。
2009年11月24日
コメント(0)
-

晩秋の帝釈峡にやって来た それなりに秋の雰囲気を楽しめました!
晩秋の帝釈峡にやって来た 紅葉は終わっていたが、それなりの雰囲気が楽しめました・・・【11月21日】上帝釈の虎屋旅館に泊まって、朝の8時す過ぎから散策をはじめました。帝釈峡入口帝釈峡散策01それでも、紅葉がところどころで楽しむことができました。帝釈峡 紅葉_01帝釈峡 紅葉_03渓流も楽しめました・・・帝釈峡 渓流_01帝釈峡 渓流_03帝釈峡 渓流_04帝釈峡の主なスポット。雄橋(おんばし)です雄橋01雄橋03帝釈峡のきっての急流。断魚渓(だんぎょけい)です。断魚渓01断魚渓谷02帝釈峡の神龍湖までの遊歩道は途中で通行止めになっています。本来なら、素麺滝や雌滝(めんたき)への遊歩道があったのですが、がけ崩れで通行止めになっているのです。かわりに、自然歩道を歩くことで神龍湖まで行くことができます。
2009年11月23日
コメント(0)
-

やっぱり 月に水はあった! エルクロスが観測したそうです!
NASAの月探査観測船、エルクロス(LCROSS)が月に水を観測したそうです。LCROSS 2【月探査衛星 エルクロス(LCROSS)の中継映像見ました! 】の、続報です。NASA 月に水あった 【ワシントン=時事】米航空宇宙局(NASA)は13日、月に水が存在することを示すデータを得たと発表しました。10月に無人探査機「エルクロス」を月面に激突させた際に生じた大量の噴出物を分析した結果、水の存在を確認しました。NASAは90リットル相当の水分が噴出物に含まれていたとしています。 水の存在は、将来の有人月探査で月の水を電気分解し、水素をロケット燃料に、酸素を宇宙飛行士の呼吸用として利用できる道を開くことになります。 NASAはこれまでの観測で、月の極地域には大量の水素が存在していると判断。月の南極付近のクレーター「カベウス」に太陽光が当たらない「永久影」があり、その部分に的を絞って10月9日、エルクロスを時速9000キロ近い猛スピードで激突させました。舞い上がった500トン(推定)の噴出物を分光計などを使って分析。噴出物が太陽光にさらされて水蒸気が生じたことが分かりました。 クレーターの地表温度はマイナス200度まで下がるといいます。NASAは「永久影付近の地下で数十億年間、水が氷の状態で保たれているなら、太陽系の進化の解明につながる」と期待を膨らませています。 米航空宇宙局(NASA)の無人探査機「エルクロス」が10月9日、月面に衝突してから20秒後に撮影された月面の噴出物(枠内中央白い部分)(NASA提供・時事)「しんぶん赤旗」日刊紙 2009年11月15日付NASAのホームページでも紹介されています。LCROSS Impact Data Indicates Water on Moonエルクロスの衝突のデータは、月面上の水の存在を観測した。
2009年11月19日
コメント(0)
-

今年も、ボンジョーレ・ヌーヴォーが解禁! 早速楽しんだヨ!
本日(11月19日)、フランスの地域限定ワイン、ボンジョーレ・ヌヴォーが解禁になった!ボンジョレ・ヌーヴォー2009_01近くの、ファミマで売っていたので、早速買った!最近は、ペットボトルのワインを売っているようだ。これもそれだった。ALBERT BICHOT (アルベール・ビショー社)BEAUNE(ボーヌ)産、BOURGOGNE(ブルゴーニュー)地域、FRANCE(フランス)商品名:BEAUJOLAIS NOUVEAU(ボンジョレ・ヌーヴォー)ボンジョレ・ヌーヴォー2009_02ボンジョレ・ヌーヴォー2009_03美味しく、いただきました。お先に!!【ボンジョレ・ヌーヴォー2009】(紹介ページ)
2009年11月19日
コメント(0)
-

紅葉と渓谷を満喫した後は、食い気と温泉だ!
昼飯抜きで、天滝を歩いていたので、さすがにおなかがすいた。 【11月14日】その前に、天滝の登口にあった句碑。宮田砕花歌とある。調べてみると芦屋市宮川町の詩人のようだ。青雲に ひびきとよみて 落ちきたる天瀧なりと こころつつしむ天滝渓谷 句碑天滝の下にあったテストハウスで食事をした。ひらべ定食川魚の「ひらべ」の塩焼きと、地元、筏産たかきびを使用した「きびうどん」とのセットです。「ひらべ」は、うまく焼いてくれているので、骨ごと食べることができました。うどんも美味しかった (^^♪おなかがいっぱいになった後は、今度は温泉。養父(やぶ)市の旧大屋町から旧養父(やぶ)町にむけて走り、「但馬楽座」の「やぶ温泉」に入りました。なんと、道の駅に温泉や宿泊施設があるのです。天然やぶ温泉_01天然やぶ温泉_02天然やぶ温泉_03500円で入ることができました。天然やぶ温泉_04天然やぶ温泉_05露天風呂はありませんでしたが、サウナはありました。無色透明の温泉で、すこし”ぬるっと”する感じです。広い湯船で、ゆったり、のんびりできました。
2009年11月17日
コメント(0)
-

天滝に行くまで、渓谷と紅葉の中を歩いていきます!
天滝に行くまで、すばらしい渓谷と紅葉の中を歩いていきます。 【11月14日】普通にあるいて40~50分かかるそうです。今回、紅葉や渓谷の写真をじっくり撮りながら行ったので、お昼の12時すぎから登りだして、たっぷり2時間ちかくかかりました。天滝に着いたら午後2時を回っていました。天滝でゆっくりして、下りるのは比較的早く下りてきたのですが・・・。それでも、ところどころで写真を撮るので下まで下ってきて天滝レストランに入った時は午後3時30分を回っていました。天滝案内03【ごみ、空き缶、たばこを捨てる人は入山禁止】天滝案内04環境保護の協力金100円です。天滝案内05途中には、もちろん街灯などないので、夕方からの登山は危険です。僕が、今回山を下りてレストランで食事をしている時、午後4時前ですが・・・。やって来た家族ずれが天滝まで1時間かかると聞いてびっくり。今から登るのは暗くなるので危ないですよと言われて帰っていきました。天滝渓谷_02天滝渓谷_04天滝渓谷_05天滝渓谷_07天滝渓谷_08滝や渓谷だけでなく、紅葉もきれいでした!天滝渓谷 紅葉_02天滝渓谷 紅葉_07天滝渓谷 紅葉_05天滝渓谷 紅葉_03天滝渓谷 紅葉_08雨の降った後だったので、渓谷の水の量はハンパではありませんでした。ものすごい勢いで流れていましたよ。
2009年11月16日
コメント(0)
-

養父市大屋町の名瀑 天滝の紅葉を見に行った!
養父市大屋町の名瀑 天滝の紅葉を見に行った! 【11月14日】日本の滝100選にも選ばれている落差98mの滝だ。天滝と紅葉_02天滝と紅葉_05天滝と紅葉_07天滝と紅葉とカメラレディ女性の方も、滝の撮影にこられていました。天滝三社大権現_01滝のすぐそばには、天滝三社大権現という祠があった。天滝三社大権現_03祠には、ありがた~い? お札があって、お賽銭箱にお金を入れて頂いて帰ることができる。天滝までの遊歩道で、思いっきり渓谷と紅葉を楽しむことができましたヨ!
2009年11月15日
コメント(0)
-

ご近所の銭湯 湯あそびひろば つかさ湯
たまには、広い湯船につかりたい!と、1ヶ月に1~2回は利用するご近所の銭湯 つかさ湯湯あそびひろば つかさ湯_01以前、紹介したかもしれませんが・・・。のれんが気に入って、改めてのアップです。のれんも、季節ごとに変わる・・・湯あそびひろば つかさ湯_02写真は、11月7日ののれん・・・。【クリックすると、大きい画面が開きます】湯あそびひろば つかさ湯_03お昼の2時から深夜1時までの営業。朝風呂もやっていて、朝の6時から午前10時まで。定休日は毎週木曜日。朝風呂は、木曜の朝はやっていて、翌朝の金曜日の朝はお休みだ。ご近所はもちろんのこと、かなり遠くからも入りに来てくれているようです。
2009年11月13日
コメント(0)
-

近鉄奈良から神戸三宮へ直通!
奈良観光の後は、近鉄奈良から快速急行で神戸三宮へ直通で帰った!近鉄奈良駅_01近鉄奈良駅のビルです。近鉄の路線図です。クリックすると大きい画面が開きます。近鉄奈良駅_04ホームにすでに電車が入っていました。座れませんでした。「大和西大寺」で多くの人が降りましたが、そんなにたくさんの人が降りると予想していなかったので、座り損ねちゃいました。「難波」まで座れないと思っていたのだが、そうでないと分かったので、次の大きい駅の「学園前」でちゃっかりと座りました。でも、便利になったな・・・
2009年11月12日
コメント(0)
-

ついでに薬師寺も見てこよう! 修理中の国宝の東塔を見て、吉祥天女に会った!
唐招提寺に行ったついでに、薬師寺も見てこよう!解体修理前の東塔も見ておきたい! (11月7日)距離的にはあまり離れていないので、歩くことにしました。1dayキップがあるので、バスに乗ってもいいのですが・・・。唐招提寺前のお休み処でコーヒーを頼んで待っていると、バスの時間までだいぶんあるのにバスが通過。本来なら15分前に来ているはずのバスのようだ。ということもあって、バスを待つより歩いたほうが早いなということでの決断です。薬師寺・北門薬師寺の駐車場と反対側の北門からはいりました。いわゆる裏口です。薬師寺・金堂ぐるりと回って、改めて金堂の正面と向き合います。薬師寺は、天武天皇により発願(680)、持統天皇によって本尊開眼(697)、更に文武天皇の御代に至り、飛鳥の地において堂宇の完成を見ました。その後、平城遷都(710)に伴い現在地に移されたものです。(718)ということで、唐招提寺より古いお寺なのです。薬師寺・東塔_01薬師寺・東塔_02右手には、解体修理が始まる東塔に足場が組まれています。薬師寺・西塔左手には、西塔がすっくと立っています。薬師寺・金堂の灯篭_01金堂の正面には灯籠が立っています。薬師寺・金堂の灯篭_02薬師寺・金堂の灯篭_04参拝の方々が、お線香をあげて、お願いごとをしていました。薬師寺・金堂 焼香_02金堂の堂内は撮影禁止だけど、外からなら大目に見てくれるようです。薬師寺・金堂アップ_02中央は、薬師寺の名前の由来どおりに、薬師瑠璃光如来が座っています。白鳳時代の仏像です。国宝に指定されています。薬師寺・金堂アップ_03右手に立っているのは、日光(にっこう)菩薩。薬師寺・金堂アップ_04左手に立っているのは、月光(がっこう)菩薩です。ひねった腰が魅力的ですね。薬師寺・講堂金堂の北側にある大講堂。金堂より大きい建物です。時代が下って、天台宗や真言宗のような密教と違って、僧侶の修行がお寺の主な役割の時代。修行の場である講堂の方が、本堂である金堂より大きいのは自然のなりゆきだったのでしょう。秋の特別公開ということで、国宝の吉祥天女画像を公開していました。薬師寺・宝物展_01別料金、500円が必要ですが、訪れた日(11月7日)は無料公開日だったので、あまり抵抗なく入ることにしました。歴史教科書に載っていて魅力を感じていた絵画なのでぜひ見たいと思いました。実物は、以外に小柄な絵画です。保存状態がよくって、緑や赤の色がよく残っています。黒っぽくなっているのは、青か紫の色でしょう。A4サイズの複製画を売っていたので、思わず買って帰りました。500円です。クリックすると、大きい画像で開きます。無料休憩所内に、本尊の台座に描かれている、玄武(北)、青龍(東)、朱雀(南)、白虎(西)のレプリカがありました。薬師寺・金堂の玄武など_04薬師寺・金堂の玄武など_03薬師寺・金堂の玄武など_02薬師寺・金堂の玄武など_01たっぷり、国宝を堪能して、西の京を後にしました。薬師寺東口バス停薬師寺東口のバス停から近鉄奈良駅まで帰りました。後から気が付いたのですが、近鉄の西の京駅から乗って西大寺で乗り換えた方が早かったでしょう。でも、奈良で夕食でちょっと一杯やって帰りたかったので、近鉄奈良駅までバスで行って結果的によかったのではないでしょうか・・・。
2009年11月11日
コメント(0)
-

唐招提寺 詳しい解説
唐招提寺を参拝した時にもらったパンフレット。唐招提寺についての詳しい解説があった。せっかくなので、紹介します!唐招提寺 伽藍案内この寺の概説ここは奈良市五条町。奈良の郊外といった感じだが、都が奈良にあった1200年前は、平城京右京五条二坊に当り、いわば首都の中心街区であった。西紀759年(天平宝字3年)天武天皇の皇子新田部親王の旧邸地を賜ってここに唐招提寺が創建された。唐の国から来朝した鑑真和上の招提-み仏のもとに修行する人たちの場という意味を寺名として掲げる。別に建初律寺とも称するが、これは中国四分律の南山宗による戒律を軸として教学に励むわが国最初の律寺ということである。今も日本律宗総本山として仰がれている。開山唐僧鑑真和上(過海大師)は大唐国揚州大明寺の高僧。わが聖武天皇の寵招に応え、授戒の師として来朝することになったが、七五四年(天平勝宝六年)東大寺に到着するまで十二年間、前後五回に及ぶ難航海に失敗したにも拘らず、初志を曲げず、奈良の都に着いた時は両眼を失明していたほどである。かくて大仏殿の前に戒壇を設け、聖武・孝謙両帝をはじめ、わが国の多くの高僧たちに授戒した。すでに仏教国家の形態を整えていたわが国が、画竜点晴の実を挙げたのは、まさに大和上の功績である。このことは中学校の教科書にも出ている事績だが、ひとり仏教史の上だけでなく、ひろく天平文化に及ぼした影響は計り知れざるものがある。まことに日本の大功労者であった。東大寺戒壇院を退いて当寺を建立し、在すこと四年。763年(天平宝字7年)5月6日、76歳をもって寺内に示寂した。弟子たちが師の大往生を予知して造った和上の寿像(乾漆・国宝)は、山内開山御影堂に安置され、毎年6月6日(5月6日を新暦6月6日に当てる)御忌当日を中心に前後約一週間開扉されるが、「若葉しておん目の雫拭はばや」と詠じた俳聖芭蕉ならずとも、像前に襟を正して感動を禁じ得ぬのである。その和上の御廟は御影堂の東に隣接する林中に静まっている。仏教文化華やかだったあのころに輩出した高僧たちの名は、史上おびただしく遺っているが、さて、それらのお墓は、たまたま出土品によって明らかとなった行基菩薩の墓所のほか他に例を見ず、残後1200年問香華を絶たずお詣りされてきたのは、ひとりここ和上の御廟あるのみである。ところがこの寺にも盛衰幾変遷がある。方四町の境内に輪奥の美を競い、さらに西山に四十八院を構えた往時、鎌倉時代の戒律復興に盟主覚盛上人の中興、あるいは近世における東塔や堂舎十数宇の退転、廃仏殿釈の嵐などを経験してこんにちに至る。今もとより創建当初の盛んさはないとはいえ、なおよく擁する国宝十七件、重要文化財二百余件、まこと天平文化の大群落であり、かって「海東無双の大伽藍」「絶塵の名刹」と称せられたゆえんを目のあたりに偲ぶことができよう。伽藍の案内開祖鑑真和上壬百年遠忌を機とする寺観復興事業として、天平様式に再建された南大門の正面、堂々雄偉の金堂を仰ぐ。わが国現存最大の天平建築であり、天平金堂唯一の遺構として君臨するもの。その豊かな量感、ダイナミックな立ち姿、息を呑んで感嘆久しうするのみである。大棟を飾る風雪千二百年の鴟尾の簡潔な美しさ、「大寺のまろき柱の月かげを土に踏みつつものをこそ思へ」(会津八一)と詠わしめた大円柱の放列は遠くギリシャの神殿を想起させよう。本尊乾漆盧舎那仏、薬師如来、千手観音、梵釈二天、四天王など創建以来の天平のみ仏います内陣の厳粛さは、そこに盲いた大徳鑑真和上が今も礼拝瞑想中かと、われらも粛然たらざるを得ない。圧倒されそうな強烈な芸術性の発揮である。毎年中秋の月の夜には、この金堂を開扉して諸尊に献灯される観月讃仏会の行事もあって、餐客たちも秋露とともに法悦に濡れるのである。金堂のうしろに続く講堂は、奈良仏教の上代寺院がいずれも学問寺の性格を濃厚にしていた関係上、講莚聴問の場であったが、この建物は和上の創立に際して特に宮廷から平城宮の東朝集殿を賜って移築したものであることに注目したい。平城宮跡百ヘクタールは今は一屋すら留めぬ草原と化したが、幸いに一棟ここに移築されたればこそ、もって当時の宮殿の片鱗をうかがうことができるのである。その遺重性はただ天平建築たるだけのものでない。堂内には本尊弥勒如来(鎌倉時代)持国・増長二天(ともに奈良時代)を安置する。金堂・講堂を結ぶ伽藍中心線の東側には、境内唯一の重層建造物舎利殿(鼓楼)が軽快に建つ。もと和上将来の三千粒仏舎利を奉安した由緒を持つ鎌倉建築で、今では毎年五月十九日のうちわまき会式(中興忌梵網会)に当って、古式ゆかしい可憐なうちわ(宝扇)を参詣者に撒き頒つ場として親しいなつかしさを思い起す人も多かろう。中興上人覚盛大悲菩薩追善のため、上人の薫陶を受けた法華寺の比丘尼たちが霊前に供えたうちわを、有縁者に授けたことに発端する儀式で、宗祖鑑真和上の開山忌舎利会(前出六月五日・六日)、解脱上人始めるところの釈迦念仏会(十月二十一日ー二十三日)とともに、当山の印象的な法要として、山内全域に静かな雑踏を見せる日である。舎利殿に東隣する長大な建物が三面僧房東室の遺構(鎌倉時代)で、南半分は解脱上人釈迦念仏会の道場(礼堂)に改造されている。僧房は上代寺院が全寮制の学問寺だったことを示す名残りで、かっては多くの律僧たちが戒律きびしい起居をしたところである。さらにその東の二つの校倉。南が経蔵、北が宝蔵となっている。ともに遺存例少ない天平校倉で、殊に経蔵はこの寺創始以前、新田部親王の邸宅があったころの遺構だから、七五六年成立の正倉院宝庫よりさらに古く、わが国現存最古の校倉として記憶されるべきである。宝蔵北側の石畳を東に歩を進めると、奥まったところに高床式の収蔵施設新宝蔵がある。山内に襲蔵する文化財の、更に完壁な保存を期して先年竣工したもので工芸・絵画・経文類のほか、処を得ずして講堂内に仮安置されていた破損仏もここに移された。これらは彫刻史に特に唐招提寺様式という範疇を設定して重視される一群である。一般的に喧伝されている名宝如来形立像もこのなかにある。すでに仏の役目を終って破損彫刻となったこの立像の伸びやかな美しさの魅力を味わいたい。さて鑑真和上御廟の西、境内のたたずまいひとしお清寂ななかに宏大な殿宇が望まれるであろう。南都興福寺旧一乗院門跡の宸殿遺構を精密に復原移築された古建築で、平安貴族の邸宅とその生活様式をうかがうべき好箇の資料として稀少価値きわめて高い。今では大和上の尊像を安置する御影堂とし、一山後学あげて宗祖のいますがごとくお仕え申している。和上の尊像は前述の如く6月6日開山忌当日を中心に約一週間開扉される。この御影堂震殿に昭和五十年東山魁夷画伯が揮毫奉納された障壁画「山雲」「濤声」なども、和上像開扉とともに公開される。一方、伽藍中心線西側には鐘楼と戒壇がのこされている。鐘楼に懸るのは平安期の梵鐘だが、これには「南都左京」という後世の追刻銘があって、歴然たる「右京」五条の地を誤刻したことがわかる。ほほえましい思い違いではある。戒壇は石造三段の豪壮なもので、和上が東大寺に創めた戒壇院の土造のそれとしばしば対比されるのである。こちらは江戸末期の祝融に禍されて外構を失ったが、雨露に堪えて粛然たる厳格さはひしひしとわれらに迫り、おのずから襟を正さしめるであろう。このたび最上層にインド・サンチーの古塔を模した宝塔を奉安し、周辺も整備して授戒場としての面目を一新した。以上は拝観者のみなさんの比較的たやすく目に触れ得るものについて概説した。それも近来の旅行形態に鑑み、当山内での所要時間を1、2時間と見込んでの案内であってみれば、もとより委曲をつくすこともできぬのはけだし止むを得ぬ。その上、この案内記では繁を避けて境内諸堂諸尊のそれぞれに一々国宝・重要文化財の表記を省略したが、これは嘱目ほとんどがそのいずれかに該当するためである。いずれにせよこの古刹唐招提寺伽藍の整う美しさは予ねて世上に喧伝されていよう。まことに四時趣きを改めて詩情こまやかである。わけても若葉・青葉の色が山内を埋めつくすころは、宗祖と中興両大徳の忌日ともめぐり合って感傷するによく、境内随所に咲きこぼれるる萩の盛りのころは、遠く和上の故郷揚州を偲びながら、頭を垂れて、低徊久しうすることができる。もし狭霧立つ朝の夢幻にも似たほのかな気配と、落陽に染まる天平の彊の壮麗を知るならば、風趣は一だんと深く古都の古刹の雰囲気はいよいよ昂揚されるのである。右のほか江戸末期に惜しくも雷火に失った東塔のあとや、旧二坊大路沿いのいわゆる西山四十八院あと付近(廃大日堂の本尊大日如来坐像-平安初期1は現在新宝蔵に移座)あるいは四至の東を限る秋篠川界隈の散策など、情感きわめて深く、かくて半日を清らかに過ごすことができよう。しばらくは、観光客でごったがえすでしょうが・・・。落ち着いたごろに、また寄ってみたい所です。
2009年11月10日
コメント(0)
-

唐招提寺 金堂の解体修理 落慶法要が終わって、一般公開! 早速見に行った!
唐招提寺。約9年間におよぶ、金堂の解体修理が終わって、さきほど落慶法要が行われた。11月4日から一般公開された。正倉院展と合わせて、早速見に行った!実を言うと、2年前に解体修理中とは知らないで行った時は、ご本尊は講堂に安置されていた。今回、改めて、金堂とご本尊を正式に見ることができるということでわくわくという思いで行った!唐招提寺 伽藍案内唐招提寺の入口、南大門。観光バスが着たのか、たくさんの人がならんでいます。唐招提寺・南大門9年間の解体修理の終わった金堂です。唐招提寺金堂_01瓦もほとんどが葺き替えられ、シビも新しくなりました。唐招提寺のシビ_02唐招提寺のシビ_01ギリシャのエンタシスを思わせる柱の傾きも修理されました。唐招提寺金堂_02金堂の奥の、舎利塔と講堂。講堂は僧侶が修行したところです。唐招提寺・講堂と舎利殿_01唐招提寺・講堂_02金堂や講堂の東側には礼堂があり、参拝客が目の前の宝堂や経堂を眺めていました。唐招提寺・礼堂東室_02宝堂と経堂唐招提寺・宝堂と経堂唐招提寺・宝堂唐招提寺・経堂ともに、校倉造として貴重な建物です。さて、唐招提寺の建立に係わった鑑真の像が安置されている御影堂(みえいどう)を見てきました。唐招提寺・御影堂_02厳かな雰囲気がします。続いて、鑑真のお墓です。唐招提寺・鑑真御廟の塀唐招提寺・鑑真御廟のコケ_03鑑真のお墓の前にはコケが生えている広場がありました。唐招提寺・鑑真御廟鑑真のお墓(御廟)です。唐招提寺・鑑真御廟と供養塔ろうそくの灯った灯篭。同じ灯篭が、鑑真のいた中国の大明寺にあるそうです。日中友好の灯りですね!
2009年11月10日
コメント(0)
-

奈良・正倉院展を見に行く! 奈良・斑鳩1dayチケットを使った!
奈良に正倉院展を見に行った。合わせて、9年間の金堂の解体修理が終わって、落慶法要が行われ11月4日から一般公開されている唐招提寺も見て来たい!11月7日(土)、久しぶりの休みを使って行って来た!近鉄が発売している、奈良・斑鳩1dayチケットが使える。奈良・斑鳩1dayチケット_01神戸沿線からは、阪急・阪神・山陽から乗って、近鉄の奈良市街は乗り降り自由。奈良交通のバス、生駒山のケーブルも乗り降り自由だ。最寄の阪神の駅は西元町。1dayチケットは元町駅からなので、通勤定期で西元町から元町まで行き、一旦改札を出て、窓口で「1dayチケット」を買ってまた改札を入った。阪神なんば線直通特急で阪神尼崎まで行き、阪神なんば線に乗り換えた。近鉄奈良駅まで直通だ!近鉄奈良駅の改札を出ると、「正倉院展」の前売りチケットを売っていた。1000円のところを900円で買えた!正倉院展_01下調べでは、近鉄奈良駅から正倉院展の奈良国立博物館まではバスがあるのだが、みなさん歩いているようなので僕も歩くことにした。距離にして800mぐらいだったので・・・奈良の鹿_03奈良の鹿_02途中に、鹿に会う事ができました (^^♪御即位20年記念第61回正倉院展会期:10月24日~11月12日正倉院展_05いきなり、「30分待ち」の立て札!正倉院展_02正倉院展_04正倉院展_06入口前のフロワーを蛇行して入っていきました。見どころは・・・。紫檀木画槽琵琶(したんもくがそうのびわ)四弦の楽器・琵琶。螺鈿の装飾が美しい。桑木木画棊局(くわきもくがのぎきょく)寄木細工の碁盤。伎楽面 呉女(ががくめん ごじょ)伎楽でかぶるお面。朱の唇、白い顔、薄紅のほおなどに、唐美人の少女の面影が見えます。緑牙撥鏤把鞘御刀子(りょくげばちるつかさやのおんとうす)象牙の小刀楽毅論(がっきろん)光明皇后直筆の書花氈(かせん)フェルトの敷物平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)螺鈿飾りの鏡。夜光貝を切った白い螺鈿や赤い琥珀、べっ甲のタイマイなど高価な素材を使って、花びらやつぼみ、葉などを表現している。子日目利箒(ねのひのめとぎほうき)天皇の儀式用の玉飾りの箒子日手辛鋤(ねのひのてからすき)天皇の儀式用の鋤金銀花盤(きんぎんかばん)花形の足つき大皿。唐で流行した花形の角をもった鹿が描かれている。縁は色ガラスや水晶のかざりがぶら下がっている。白石鎮子 青龍・朱雀(はくせきのちんす せいりゅう・すざく)大理石のレリーフ。これ以外にも、皇室で日常的に使われていたと思われるテーブルクロスとか、伎楽の舞をする人の下着とかも展示。奈良時代の課税対象となった住民台帳なども展示。「出雲の国」なども出てきて、平城京の支配の範囲が垣間見られる。台帳の中身をみると、男10人、女12人・・・。などと、男女ほぼ同じ人数。時代が下って、課税対象の男性をごまかすために極端に女性の多い台帳とは違い、まだまだ健全な時代だったんだなと思えます。僧侶の写経の記録もあります。何枚書いていくら、何字書きミスったら何枚分を差し引くとか、事細かく記載されています。記載をチェックする僧侶については、チェックミスが何箇所あれば、何十枚分を差し引くとか、より厳しくなっています。残っている書物も、はっきりいって下手な筆跡も多くあります。普通の博物展と違って、いろいろ面白いものもありますヨ!
2009年11月09日
コメント(0)
-

キャナルガーデンのオブジェが冬バージョン、雪だるまに変わっていた!
パソコン部品の買い物に、ハーバーランドに行き、キャナルガーデンに寄った時・・・。オブジェが電飾の雪だるまに変わっていた!キャナルガーデンの雪だるま_03後ろから見たら、こんな感じ。キャナルガーデンの文字が光っています。キャナルガーデンの雪だるま_02ホワイトバランスを、白熱電球に変えて撮ってみました!キャナルガーデンの雪だるま_04より見た目に近い色感覚になりました。キャナルガーデンの雪だるま_05キャナルガーデンの雪だるま_06買ってきたのは、LANケーブルの延長用コネクタとLANケーブル。職場の模様替えでパソコンを移動。LANケーブルが届かなくなったため、延長用のテーブルタップならず、LANケーブルを繋いで延長する必要があったわけだ。LANの延長用コネクタ(RJ-45コネクタを2個、直接繋いだもの)とLANケーブル(3m)それぞれ500円ぐらいだった。無事、パソコンはネットワークにつながった!
2009年11月06日
コメント(0)
-

新開地のアートヴィレッジセンター drowning room
drowning room新開地のアートヴィレッジセンターでの企画展示。神戸ビエンナーレの協賛企画である。アートビレッジセンター_02drowning roomArt Initiative Project Exhibition as media20092009年10月31日(土)~11月23日(月・祝)大崎のぶゆき・田中朝子・冨倉崇嗣・中川トラヲ・森本絵利入場無料(12:00~20:00 最終日は17:00まで火曜日休館)http://kavc.or.jp/art/aip神戸アートビレッジセンターIF・KAVCギャラリー、lroom/B1・KAVCシアター、スタジオ3他 神戸ビエンナーレ会場(関連企画のみ) 神戸アートビレッジセンター(KAVC)では「Exhibitionasmedia2009(メディアとしての展覧会)『drownillgroom』」を開催します。本企画は、アーティストとアートセンターが企画立案から実施までを共同して行う、アートイニシァティヴ・プロジェクトです。タイトルの「drowningroom(ドラウニングルーム/溺れる部屋)」とは、今回の出品アーティストの共通点として挙げられる、内面へと向かう思考性から浮かび上がった言葉、「drown」(=溺れる、夢中にさせる)とスペルが似た「draw」(二描く)からなる熟語「drawingroom」(=応接間)から導かれました。 本展ではアーティストの遊び心によって企画構成された応接間が出現します。また、彼らが見せること以上に楽しむことを目的とした作品が展示空間の随所に点在します。その他広報物のアートディレクションや関連企画など、主体的に展覧会創りに参加します.本プロジェクトを通して、アーティストの空想力や眼差しが創る新たな展覧会のカタチを提案できれば幸いです。drowning room 1drowning room 2drowning room 3drowning room 4
2009年11月05日
コメント(0)
-

「沈まぬ太陽」見てきました! 見ごたえある3時間半だったなあ!
11月2日の夜、山崎豊子原作の『沈まぬ太陽』を映画化した「沈まぬ太陽」を見てきました!沈まぬ太陽案内見たのは、18時50分からの回。終わりは22時25分でした。3時間22分の大長編ですが、最初からぐいぐいと映画に引き込まれ、その長さを感じさせませんでした。 1960年代、航空会社の労働組合委員長の恩地。公共交通の安全確保のためと社員の賃金と労働条件改善のために献身する。その恩地が、10年近く中東やアフリカに左遷。帰国後、航空会社の飛行機が群馬県御巣鷹山に墜落した大惨事で遺族係を務める。その後、新しく就任した会長に抜擢されて会長室室長として働く・・・。 1960年代の左遷先のアフリカ、御巣鷹山の墜落現場の惨状と追われる対応・・・。映画の出だしで、その20年の時間がクルクルと交錯して、ぐいぐいと引き込まれていきます!恩地が、労組委員長として、社員の労働条件とともに公共交通としての安全運行を追求したこと。御巣鷹山事故で、遺族の方々の心に思いをはせ、親身に対応する恩地。テーマに「命の尊厳」があるといいます。御巣鷹山事故で子どもや孫、全員を亡くして天涯孤独となった老人。最愛の夫を亡くして、子どもと2人残され、アルコール中毒になった妻。そのリアルな人生に向き合う恩地の人間性がほとばしります。ラストシーンで、アフリカの大地に沈む大きい太陽。真っ赤に染まった空。雄大な自然。力強い生命力。よし、行こう! って感じさせます。沈まぬ太陽 間合いでも、さすがに3時間30分は長いのですので、途中、10分間のトイレ休憩があります。ご安心のほど・・・。
2009年11月04日
コメント(0)
-

唐招提寺の大修理が終わって、今月4日から一般公開される
唐招提寺の10年にも及ぶ平成の大修理が終わって、今月の4日から一般公開される。 世界遺産に登録されている唐招提寺(奈良市五条町)の金堂(国宝)と3仏像(国宝)の10年におよぶ大修理が終わり、11月1日から落慶法要がおこなわれ、4日から一般公開されます。大修理で、なにが明らかになったのでしょうか。岡清彦記者唐招提寺001【大修理が終わった金堂、(屋根上部の両端にあるのは)装飾用の鴟尾(しび)】【屋根を支える丸柱】天平建築の力強さ満ちて 唐招提寺は、中国・唐の高僧、鑑真(がんじん、688~763年)が来日し、奈良時代の天平年間に創建に着手した寺です。 境内には、金堂、講堂、鑑真和上像などの国宝や鑑真の墓などがあり、1200年前の静寂な雰囲気をたもっています。 金堂は、奈良時代のものとしては、唯一現存するものです。 井上靖の小説『天平の藍(いらか=瓦)』や松本清張の『球形の荒野』の舞台にもなり、全国から多数の人が訪れます。 唐招提寺の近くに住む直木孝次郎大阪市立大学名誉教授(古代史)は、仏像を安置する金堂のたたずまいをこう語ります。 「鴟尾(しび)を上げた寄棟造りの大屋根は、ゆったりとした傾斜を描き、太い丸柱の列ががっしりとささえて微塵(みじん)もゆるぎがありません。天平建築の力強さに満ちています。その剛毅(ごうき)さに、鑑真和上の精神を感じます」 鑑真は奈良時代、仏教の戒律を授ける僧侶として日本に招かれました。 鑑真は、中国・上海近くの揚州の大明寺から日本に渡航をこころみますが、ベトナムの近くまで船が流されるなど5度も失敗。12年かけて6度目の753年に日本に到着します。その困難な渡航から盲目になったといわれています。聖武上皇らに戒を授けました。唐招提寺003【講堂】【経堂と境内のコケ】大震災を機に 金堂は、高さ約16メートル、東西約28メートル、南北約15メートルという巨大なもの。阪神・淡路大震災(1995年)を機に、大修理が必要になりました。 大修理を担当した奈良県文化財保存事務所唐招提寺出張所主任(当時)の植田哲司さんが語ります。 「4万数千枚の瓦をささえる屋根の重さで、柱が内側に倒れる“内倒れ”がおきており、最大で121ミリも傾いていました。危険な状態でした。金堂の構造を補強する必要がありました」 2000年1月から、大修理が始まりました。 瓦をすべて下ろし、柱を全部解体する金堂の全面解体。仏像を安置する基壇の発掘調査。盧舎那仏(るしゃなぶつ)、薬師如来、千手観音の3仏像の修理―。 「金堂は、平安、鎌倉(2回)、江戸、明治、平成の各時代、合わせて6回修理されていますが、大修理は、江戸と明治につづくものです。今回の大修理は、今後300年間は、修理の必要がなくなるほどのものです」技術の発展か 植田さんが今回の大修理で注目するのは、江戸時代に屋根を高くするために、屋根裏につくられた「小屋組」(屋根を支える骨組み)です。 「時代をへることに建築技術が発展しました。今回の大修理で、小屋組をどのようにしてつくったのかという構造が初めてわかりました。小屋組で、屋根を約2メートル高くできたのです。屋根が一段と大きくなり、どっしりとした重量感あふれる現在の姿になりました」5メートルを超える巨大な千手観音。政策当初は、千本の手があったといわれますが、現在は953本。(「飛鳥園」提供)創建年代の手がかり得た 金堂の創建年代は文献になく、長い間、学者の間で論争になってきました。奈良時代中期の天平年間という説と、奈良時代末期から平安時代(794年に京都に遷都)初期の延暦年間(782~806年)説などがあります。40年ほどの幅がありました。 鑑真が、現在の唐招提寺の地である新田部(にたべ)親王の旧宅跡をもらいうけたのは759年(天平宝字3年)です。 鑑真は、まず平城宮の東朝集殿を移築して、講堂にし、僧侶に戒律を説きました。伐採781年 今回の大修理で、奈良文化財研究所の光谷拓実氏が、木材の年輪で伐採年を調べる「年輪年代法」で調査。樹皮が残っていた3本の垂木(屋根を支えるための木材)は、781年に伐採されたことがわかったのです。創建年代の手がかりが、初めて科学的に明らかになりました。植田さんは、「垂木は天井に近いところの木材であり、金堂は780年代に完成したと思います」と語ります。 奈良芸術短期大学の前園実知雄教授は、もう少し新しいと考えています。 「金堂の創建に着手したのは790年代で、完成したのは塔の建設に着手(810年)した前ではないでしょうか」 前園さんは、奈良県立橿原考古学研究所に在籍していた当時、長年にわたって唐招提寺の発掘調査をしてきました。金堂の周辺から、修理のさい、傷んで廃棄された瓦が大量にみつかっています。 「金堂創建時と特定できた瓦は、平城京内の西大寺や法華寺、薬師寺などでも見つかっています。770~780年ころの瓦です。しかし、金堂の創建時の瓦は、手法の粗雑さからもう少し時代を下げたほうがいいと思います」前園さんがもう一つ根拠としてあげるのが、3体の仏像の一つ、薬師如来の手の中から見つかった銅銭(隆平永宝)です。796年に鋳造されたものだからです。 前園さんは、鑑真の思想から唐招提寺伽藍の創建順を推定します。 「寺院は、通常、金堂から建造しますが、鑑真は戒律を教えるのが目的で渡航しました。最初に、講堂を移築し、僧侶に戒律を教えました。その後に食堂(じきどう)、僧房、金堂、塔の順でつくったのでしょう」唐招提寺005 posted by (C)きんちゃん唐招提寺006 posted by (C)きんちゃん日中友好の懸け橋唐招提寺 松浦俊海長老 10年におよぶ金堂の大修理が終わり、感慨ひとしおです。鑑真和上は、命がけで日本に渡航をこころみた、いわば中日友好のさきがけとなった人です。 昨年5月、中国の胡錦濤主席が唐招提寺を訪問され、和上のお墓に私といっしょにお参りしました。お墓の前の灯籠(とうろう)と同じものが、中国の大明寺にもあります。森本孝順・元長老が兄弟の灯篭として寄進(1980年)したものです。温家宝首椙が日本の国会演説(07年4月)で、両寺の灯籠がともっていることにふれました。小さな明かりは、中日友好のシンポルです「しんぶん赤旗日曜版」2009年11月1日付けに紹介・・・。ぜひ、行ってみたいですね。
2009年11月01日
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1