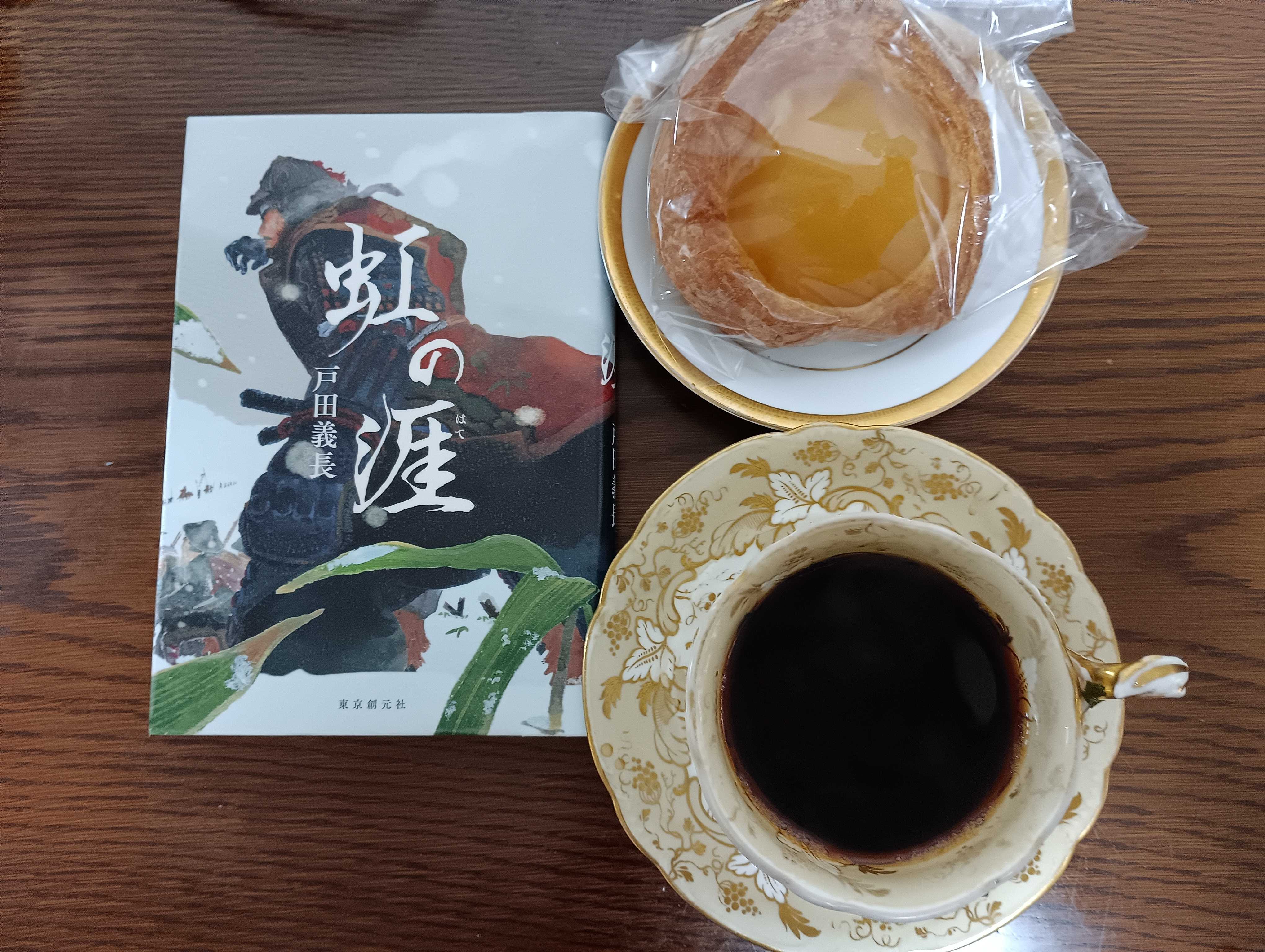2016年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

高田崇史『QED 諏訪の神霊』
高田崇史『QED 諏訪の神霊』~講談社ノベルス、2008年~QEDシリーズ第15弾です。 それでは、簡単に内容紹介と感想を。―――1997年10月。 住宅地で、留守にしていた家の庭で、近所の男が殺害されていた。現場には、串差しにされた白兎の死体もあった…。 同じ住宅地で、さらに事件は繰り返される。いずれも、現場近くで動物の死体が見つかることとなる。 * 1998年のゴールデンウィーク。桑原崇と棚旗奈々は、二人で御柱祭を見に行くこととなった。現地では、桑原の中学時代の同級生や、シャーロキアンの緑川の妹とも合流し、御柱祭、御頭祭など、諏訪大社にまつわる謎に挑むこととなる。諏訪に巧妙に張られた結界の真相とは。――― 今回も面白かったです。諏訪大社はなぜ上社、下社(いずれも2社ずつ、合計4宮)に分かれているのか、御柱祭、御頭祭の意味についての諸説がはらむ矛盾とは、そしてそれらの意味とは……。御柱祭についてはテレビで見たことがある程度ですが、本書の謎の提示は実に刺激的で、そしてそれへの解釈の提示はまさに圧巻です。
2016.06.25
コメント(0)
-

多田哲『ヨーロッパ中世の民衆教化と聖人崇敬―カロリング時代のオルレアンとリエージュ―』
多田哲『ヨーロッパ中世の民衆教化と聖人崇敬―カロリング時代のオルレアンとリエージュ―』~創文社、2014年~ 著者の多田哲先生は、中京大学国際教養学部教授です。本書は、先生の博士論文を元にした一冊です。 手元にある先生の論考として、多田哲「キリスト教化と西欧世界の形成」堀越宏一/甚野尚志編『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房、2013年、15-37頁 があります。 さて、本書の構成は次のとおりです。―――序第一章 先行研究の状況と本書の立場第二章 『一般訓令』(一)―文書的性格・構成・内容・目的第三章 『一般訓令』(二)―成立事情第四章 司教区への民衆教化プログラムの普及第五章 民衆の宗教生活に関するオルレアン司教およびリエージュ司教の把握第六章 オルレアン司教区およびリエージュ司教区における民衆教化プログラムの展開第七章 オルレアン司教区およびリエージュ司教区における私有教会第八章 オルレアン司教区およびリエージュ司教区における聖人崇敬の概要第九章 オルレアン司教区の聖人崇敬(一)―司教座都市における聖十字架崇敬第十章 オルレアン司教区の聖人崇敬(二)―司教座都市における聖アニアヌス崇敬第十一章 オルレアン司教区の聖人崇敬(三)―農村部における聖マクシミヌス崇敬第十二章 リエージュ司教区の聖人崇敬―農村部における聖フベルトゥス崇敬結論補論 「民衆教化」とは何かあとがき初出一覧注史料・文献目録略語一覧索引地図――― 本書の中心は、オルレアンとリエージュという二つの司教区で民衆教化がいかに進められたかを明らかにするケーススタディです。前提として、先行研究を整理して本書の立場を明確にした上で、王国全体に発せられたシャルルマーニュによる『一般訓令』の背景・内容を分析し、また両司教区の概要を論じています。 先行研究整理では、民衆教化に関する総合的な研究から、カピトゥラリア(条項に分かれた法令)、説教、民衆教化の担い手といった個別的研究まで、カロリング期を中心としてどのような研究が行われてきたたが幅広く紹介されており有益です。 『一般訓令』に関する分析では、起草者として誰が携わっていたかという議論が興味深いです。また、『一般訓令』を受けて、民衆教化に関して各地の教会会議でどのような決議がなされたかもふれられ、その影響も示されます。 個人的に最も興味深かったのは、第四章から第六章までの概要的な部分です。『一般訓令』を中心とした王国の民衆教化理念が、教会会議や国王巡察使といった制度により普及していきます。また、両司教区で、民衆教化に関する課題は何だと捉えられていて、また具体的にどのような点を強調しながら民衆教化プログラムが進められたかを論じます。特に興味深いのは、民衆に最も近い立場である教区司祭が、何を尊重し、どのような内容を説教すべきとされたか、また彼らを監督する立場である司教はそのためにいかなる手法をとっていたか、という分析です。 聖人崇敬を利用した民衆教化については、比較的無名の聖人を、有名な聖人を引き合いに出しながらその功徳を強調するという手法、たとえ元々無名の存在でも、遠くに遺体のある有名な聖人よりも、身近に遺体のある聖人の方が民衆の崇敬を集めやすかったといった点が指摘されます。 カロリング期にいかなる手法で民衆教化が進められていたかを明らかにする良書だと思います。
2016.06.22
コメント(2)
-

高田崇史『QED~flumen~九段坂の春』
高田崇史『QED~flumen~九段坂の春』~講談社ノベルス、2007年~QEDシリーズ第14弾にして、初の連作短編集です。今回は、以前の記事を(一部修正の上)再掲します。―――「九段坂の春」年代)1981年(昭和56年)主要人物)桑原崇(九段坂中学2年)事件)女医殺害事件、桜の枝で首を刺された男事件概要)千鳥ヶ淵で同級生の桑原崇と偶然出会った鴨志田翔一は、その直後、桜の木の下で、彼に桜の花を突きつけてくる酔っぱらいに出会う。その酔っぱらいが、とつぜん血を吐いて、絶命したのだった。歴史上の謎)『万葉集』巻第一・20-21番、額田王と大海人皇子の、「蒲生野の唱和歌」。「袖」「紫」という言葉の再解釈。…桑原崇、五十嵐弥生「北鎌倉の夏」年代)1984年(昭和59年)主要人物)棚旗奈々(雪ノ下女学院高等部1年)事件)鎌倉宮境内にて、管理人の不審死事件概要)鎌倉宮に、不審な明かりが見える、その正体は人魂だ、幽霊だという噂が広まっていた頃、不審な明かりの正体を突き止めようとした管理人が死亡。外傷なし、死因不明だった。歴史上の謎)楠木正成は湊川で本当に死んだのか?…上田壮(桑原崇?の影響)、須藤真司(鎌倉湘南大学附属高校2年)「浅草寺の秋」年代)1984年(昭和59年)~1985年(昭和60年)主要人物)小松崎良平(吾妻橋高校3年~名邦大学文学部社会学科1年)事件)浅草寺裏手の公園にて、男女の心中(?)事件概要)浅草寺裏手の公園で、会社員佐藤真太郎と江川奈緒美が、抱き合って死亡していた。事件の担当は、岩築竹松。岩築の甥、小松崎に、一応(?)つきあっている江川優里から連絡が入る。姉がまるで心中のような状況で死んでいたが、佐藤という男は、姉が付き合っていた男ではないという。歴史上の謎)待乳山聖天、浅草寺の背景…出雲谷、鴨志田翔一(真土山高校3年)「那智瀧の冬」年代)1991年(平成3年)主要人物)御名形史紋(紀伊和歌山大学大学院所属)事件)ボートに乗った、体中が火傷したような男の死体事件概要)福森麗奈は、高校のときからの習慣で、朝に熊野灘を見に行った。ところが、その朝は、海岸に壊れかけたボートが半分乗り上げたまま揺られていた。中には、真っ赤に腫れた男の死体があった。…男は、人から多くの恨みをかっているような人物だった。歴史上の謎)天狗…「私」の母、御名形史紋――― それぞれ、独立した事件でありながら、微妙にリンクしあっていて、最後には4つの物語がすうーっとつながります。…が、暗澹たる気持ちが残ります。 QEDシリーズの主要メンバーの4人が、過去にもうちょっとで知り合いになりえていたというのを、なんだかにこにこしながら読み進めました。そして、「那智瀧の冬」は別として、他の3章では、それぞれのメンバーの初恋(?)が描かれています。ほろ苦いですね…。 最も印象的だったのは「九段坂の春」です。あの桑原さんが、現在の雰囲気はもちろんあるのですが、それでもしっかり中学生の感じです。五十嵐先生が、桑原さんにとって本当に大きな存在だったのですね。
2016.06.15
コメント(0)
-
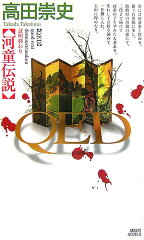
高田崇史『QED 河童伝説』
高田崇史『QED 河童伝説』~講談社ノベルス、2007年~QEDシリーズ第13弾です。それでは、簡単に内容紹介と感想を。――― 神山禮子のアパートの近く、河童が出るという噂のある川のそばで、彼女と接点のある男性が殺された。なぜか、その左手は切断されていた…。さらに、彼女の職場と取引関係のある製薬会社の関係者が被害者となる事件が続く。 一方、棚旗奈々は、桑原崇たちとともに野馬追祭を見に行くこととなっていた。彼女たちも禮子のアパート近くでの事件を知っており、自然と(?)話題は河童のことに。いくつもの名前をもつ河童の正体は。きゅうりが好物、頭の皿が乾くと死ぬなど、彼らに与えられた特性の意味とは。――― これは面白いです。サスペンスフルなプロローグから興味をひきつけられる事件、製薬会社をめぐる問題点、そして支離滅裂ともいえる河童に与えられた特性の意味など、魅力的な謎やテーマがふんだんにつまっています。崇さんの師匠(?)ともいえる人物も登場し、楽しい1冊です。
2016.06.01
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1